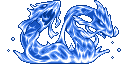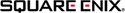灰色の隠者 魔術講師代行
──支都ルアムザ外区 封歌の庭園──
『外区』と『内区』の狭間に近い位置に、ルアムザの建造物の中では珍しい平屋の建造物がある。細い通りに面した正門は細い蔦に彩られて緑色。その合間に『封歌の庭園』という文字が木製のプレートに刻み込まれているのが微かに見えた。
どこかのんびりとした雰囲気をもつその敷地へと足を踏み入れると、庭を掃除していた初老の女性が刻まれた皺をより深くして貴方に挨拶。
「お早いお着きでしたね。ではどうぞこちらへ」
・
封歌の庭園は、『内区』に近い位置にはあるが基本的には『外区』の人間、それも子供達を主に受け入れているという、比較的珍しい魔術学院のようだった。
「それでですね。貴方には私のお手伝いをしていただきたいの」
小さな応接間に置かれたソファーに座る貴方に、老女が小さな杖を携えて戻ってくる。
「もう私も年でしてね、これでも昔は一端の召喚師を気取っていたものなのですけれど、魔術を試すなんてもう何年ぶりかしら」
貴方は首を傾げる。ならば、今までここで教鞭を取っていたのは一体誰なのか。建物の中をここまで歩いてきてみたが、生徒らしき子供達が数人いるだけで、教師らしき人間は一人も見当たらなかったが。
「いえ、ずっとこの庭園で子供達に魔術を教えてくれていた腕の良い魔術師の方が一人がいらっしゃったのですけど、ここ数週間前から突然連絡が途絶えてしまって……」
老婆はほとほと困り果てたような表情で呟く。
「お家の方にも何度か窺ってみたのですが留守のようでして。ですから、仕方なく私が、と。ですが、もう私は殆ど術式を扱えるような身体でもありませんし、講義の内容を実践して示すことは殆ど出来ません」
だから、こちらの出番、ということか。
「では、早速参りましょうか」
・
召喚師らしい老女がゆっくりと黒板に文字を書き、教える魔術の内容をこちらが簡単に実践してみせる。そういう形式で授業は進んでいく。
部屋に居るのはまだ十歳程度と思われる子供達だ。皆真剣な様子で老女の話に聞き入っている。
「──となります。では、皆さんもためしてみてください」
老女が簡単な小動物を呼び出すための印章を生徒達に試してみるよう促す。すると、あちらこちらで空中にほのかな光が灯り始めた。どうやら空中に印章を描くための基礎的な技術は既に教わっているらしい。
と、その時。
「せんせー!」
声と共に、一人の少年が得意げに立ち上がると、空中に少々複雑な印章を描き始める。
「ぼく、勉強してこんなのも呼べるようになったんだよー」
満面の笑みを浮かべて少年が描き終えた印章。それは大型の四足獣を呼び出すための印章──だったのだが、その一箇所に致命的とも思えるミスがあった。
みしり、と。
宙に穿たれた印章が、嫌な音を立てて一度だけ振動する。
(──まずい)
そう思った瞬間、印章を形作っていた光の軌跡がぐにゃりと歪み、まるで生き物のように跳ね上がった。
生徒達の驚きと悲鳴の声が交錯する。
召喚の魔術印章の記述に失敗した場合、稀に発生する現象だ。描いた印章自体に呼び出そうとした存在の概念が宿り、意思をもって動き始める。この場合、命を持った印章は召喚師の制御は受け付けなくなり、召喚しようとしていた存在の性質や形状などをトレースするように独りでに動き始める。
これが無害な小動物などなら問題はないのだが、目の前にいる虹色に近い輪郭線のみで構成された化け物の姿は……
(……明らかに肉食)
軽く溜息。
貴方は素早く武器を引き抜くと、その化け物が生徒達に襲い掛かる前に攻撃を仕掛ける!
battle
不確かな印章

あの後。子供達を怪我させる事なく、呼び出された化け物を何とか打ち倒したまでは良かったのだが、その後が大変だった。派手に荒れた教室の中で泣き喚く子供達。部屋を片付け、子供達を落ち着かせた頃にはもう夕刻に近い時刻になっていた。
「本当に、助かりました」
庭園の正面門近くで、深々と礼をする老女に見送られ、貴方はその場を後にした。
殆ど授業らしい事は出来ず、報酬を貰っても良いものなのだろうかとも思わなくも無いが、先程の化け物を退治した謝礼と取るのが妥当か。
灰色の隠者 都内警邏手伝い
──支都ルアムザ テトラクレスロード──
支都ルアムザ。都の中央で交わりつつ真っ直ぐに伸びる八本の大通りを、円状の細い街路が何重にも包み込む。ルアムザという都の形状を簡単に表すならばそうなる。直線に伸びる大通りを『縦の街路』とするならば、円を描く通りは『横の街路』といえるだろう。
街はこの縦と横の街路によって幾つかの区域に分断されており、一般的に都の中心地から三横路以内を『内区』、それより外を『外区』と称する。内区は貴族、旧貴族達の邸宅や彼等を相手にした商店、そして五王朝やグローエス国の運営等を司る重要施設などが密集しており、その中心には五王朝を象徴する巨大な宮殿『ロベルアムザ』が存在する。対して外区は一般市民達が暮らす領域であり、彼等を対象にした雑貨などを取り扱う商店や食堂、そして住居等が広がる。また、グローエス国のみならず五王朝を守護する王朝師士団の本部なども設置されている。
今回、ルアムザの斡旋公社から受けた依頼は、『外区』で最近多発しているという連続通り魔事件に備えるための、場当たり的な人員増強だ。
警邏の時刻は、その通り魔事件が頻繁に起きているという深夜から早朝まで。
都にはかなりの数の衛士と雇われの冒険者達の姿があり、実際に通り魔が出たとしても、衛士か冒険者かのどちらかと鉢合わせになるのは確実とも思える程だった。
(……しかし、これでは)
その通り魔とやらに少しでも物を考える頭があれば、この厳戒態勢が解かれるまでは行動を起こす事はないだろう。そして、何れ厳戒態勢が解かれるのを待ってから犯行に及ぶ筈だ。現在のこの措置は抑止力としては役に立つとは思うが……根本的な解決にはなっていないようにも思える。
が、それはこちらが気にする類のことではない。とにかく、自分達は自分達に振られた仕事を忠実にこなすだけだ。
・
徐々に東空の縁が赤く染まり始める。朝の気配だ。
別段、これといった事件も起きず、退屈極まりない一夜ではあったが、文句をいう相手がいる訳でもない。
貴方は軽く欠伸をかみ殺すと、一旦衛士詰め所へと戻ることにした。
──支都ルアムザ テトラクレスロード──
翌日。どうやら昨日も通り魔事件が起きたらしい事を衛士詰め所で聞く。
話によれば事件現場に居合わせ、通り魔とやりあった冒険者が居たらしいのだが、見事返り討ちにあい、他の衛士達が現場に辿り着いた頃には、夜の街路に無残な姿を晒していたらしい。
衛士達は勿論のこと、部外者である雇われの冒険者達の間にも、通り魔に対する怒りに近い感情が浸透していた。
・
真夜中の街路。暫く共に進んでいた冒険者と分岐路で別れ、数歩道を進んだその時。
ざっ、と。
荒々しい風が背後で巻き上がる音が聞こえた。反射的に横へと跳ぶ様に移動しながら背後を振り向き、武器を引き抜いた貴方の眼前で、先程別れた冒険者が強烈な空気の渦に巻き上げられて空へ跳ね上がり、そして酷く鈍い音を立てて地面に激突し、街路に酷く赤い花を咲かせた。びしゃり、と響いた音の先には、片手に木製の杖を携えた一人の男が力なく立っているのが見えた。
(あの杖は……純白樺の杖か)
純白樺の杖。中位から上位の魔術師が使う杖として知られているものだ。
彼が噂の通り魔なのかは知らないが……今、眼前に立っている男が魔術師であり、そして極めて危険な存在であることは一目で判った。男の虚ろな瞳は何も映しておらず、貴方の姿を認めた彼は機械的な動きで手に持った杖を振るい、風を巻く魔術を操る!
battle
憑依された魔術師

魔術師に致命傷を与えると、一瞬だけ瞳に色が戻る。彼は何事かを呟こうとして──そのまま息絶えた。
と、路地に倒れた魔術師の懐から、不気味に輝く灰色の首飾りが転がり出る。
貴方は何気なくそれを拾い上げ、月光に透かし見る。
それはうっすらとではあるが、不気味な色合いの影を纏っているようにも見えた。
灰色の隠者 盗賊狩り
──ディステュート通り・ルアムザ依頼斡旋公社──
「はいはい。この依頼は……盗賊狩りですね。そのままです」
手続きを取ってくれた暢気そうな女性がのんびりと呟く。
「えっとここから少し遠いんですが、テュパンの北の方にシランって街ありますよね。そこから『夜霧の谷』という場所に行けるんですが、何でもそこに、近傍の街道で盗賊行為を行っている者達のアジトがあるという情報が手に入ったそうなんですが」
そこでうーん、と彼女は首を捻る。
「なら、士団でも派遣して駆逐しちゃえば良いと思うのですけど、多分、国の方も人手が足りないんでしょうね。今は『現出地形』の封鎖とか国同士の小競り合いで忙しいですし。普通はテュパンの公社で掲示されるような依頼が、近場のこっちに廻されるくらいですし」
独りうんうんと頷くと、改めて貴方に話し掛けてくる。
「で、お願いするのは『夜霧の谷』を住処にしているという盗賊達の討伐。無理なようでしたら盗賊達が実際に『夜霧の谷』を根城にしているかどうかを確かめてきてください。何かしら証拠になるような物件をこちらに持ってきて頂ければ、報酬の方はお支払いしますので」
──夜霧の谷──
薄暗い霧が深く深く立ちこめる。色は灰。それも鈍い黒が混じった重苦しい色だ。
街道を離れ数時間。大地に穿たれた深い切り込み、角のきつい斜面を下り、谷底へと降りた。
まだ真昼に近い時刻である筈なのに視界は極めて悪い。霧が空からの光を遮り、拡散して、谷底にまで届かない。空を見上げれば薄暗い円が朧気に浮かんでいるのが微かに見える。まるで月のようだが、あれが太陽。
『夜霧の谷』の名を持つこの霧深い峡谷は、元々霧が良く発生する場所ではあったのだが、その頃はせいぜい朝時に霧が張る程度だった。だが、『虹色の夜』以後発生した『現出』の影響により地形自体はそのままに本来この土地が持っていた特徴だけが特化され、終始霧の海が漂い全てを覆い尽くす今のような状態になったのだという。
何気なく視線を巡らせる。こんな最悪の視界の中でも微かに見える岩々は、猛々しく伸びて尖り、行く手を阻んでいる。
「へー。こんな状態になっても、一応みんな生きてるんだねぇ」
肩の上に腰を下ろしていたリトゥエが指差す方向をみれば、霧の狭間に微かに動く影が幾つか見えた。
「……こっちのこと、狙ってるね」
少し緊張した調子でリトゥエが呟く。貴方はゆっくりと武器を引き抜き立ち止まり、岩陰から飛び出してきた影を迎え撃つ!
battle
荒猫


流石にこのような環境のため餌となるようなものが少ないのか、血走った目つきで谷をうろついている亜獣達の姿が多く見られた。
霧の中を歩きながら、今回の方針について考える。目的ははっきりしている。ルアムザの斡旋公社で受けた、この谷を根城に活動しているらしい盗賊達の討伐依頼。その遂行。
獲物を探して谷を徘徊する亜獣達から身を隠しつつ、依頼書に書かれていた盗賊達の住処とやらを探すため、谷を彷徨い歩く。
「……ねぇ、【NAME】。このまま探してても埒あかないんじゃないかな」
ひょいとリトゥエが顔を出す。
「うろついてる化け物達はなんか殺気だってるし、視界も悪いしさ。私もそれなりに霧は見通せるけど、あまり見つけられる自信ないよ」
ならば、谷への進入ルートに張り込んだ方が効率が良いだろうか。
貴方は顎に手をやり、思案する。
「うーん。でも、いくら入り込む場所が少ないって言っても三つはあるし、それに盗賊連中が独自のルートを使ってるって可能性も無い? だいたい、ホントにこの谷に盗賊達の住処があるかどうかも怪しいし」
リトゥエは次々と問題点を指摘するが、盗賊達の住処の有る無しまで疑い始めては何もできない。それに、このまま無計画に谷を探索し、遭遇した亜獣達と殴り合いながら進むよりは、谷へと至る小街道部などの危険の少ない場所で待ち伏せた方が安全かつ堅実だ。
「んー、それもそかなぁ。それじゃさ、二手に分かれよーよ。私は飛べるから西側の山道あたりを張ってる。見つけたら取り敢えず後つけてって、連中の住処調べてからそっちに報せに行くよ。貴方は街道の方任せていい?」
異論は無かった。リトゥエにこちらが張り込む位置を細かく伝え、彼女とは霧の中で別れる。
貴方は霧の中へ消える小さな妖精を見送ってから、谷を南へと歩き始めた。
「はやく、はやく!」
既に深夜ともいえる時刻。空に昇り夜を照らす筈の月は薄雲に遮られ、周囲は暗く闇色に閉ざされている。こちらを先導するように飛ぶリトゥエの羽が散らす淡い燐光が、唯一に近い光。
向かうのは『夜霧の谷』の中程に開いているという洞穴だ。リトゥエが言うには崖の上から細い岩棚を伝って進めばそこに辿りつけるらしい。昼間に谷を調べたときはそのようなものは欠片も見つからなかったのだが。
「でも、見るからに『盗賊でげす~』って連中がそこに入っていくのみたもん!」
前方からリトゥエが怒鳴り返してくる。……どうでもいいが「でげす~」は止めて欲しい。
・
リトゥエが示した細い岩棚を──灯り無しで歩くという暴挙を行いつつも──何とか渡り切ると、確かに、丁度人独り入り込めそうな程度の穴が岩壁に開いている。どうやらリトゥエが嘘を言っていたというわけではないらしい。
慎重にその穴の中へと身を躍らせると、物音を立てぬよう、奥へと進んでいく。
縦横二メートルほど、何とか立って歩ける程度の洞穴を暫く進むと、奥から話し声と──小さく灯されている明かりが見えた。
岩陰から、奥の様子を伺う。そこには数人の盗賊達と──灰色の長衣を着込んだ老人の姿があった。どうやらそのどちらも洞穴から入り込んできた【NAME】達の事には気づいていないようだ。
何やらぼそぼそと話し合っているようだが、そんなことはどうでも良い。さっさと盗賊達を締め上げ、仕事を終わらせる事にしよう。
──夜霧の谷 灰色の隠者──
「…………」
盗賊たちを切り伏せ──その感触が酷く奇妙な事に思わず貴方は眉根を寄せる。
「人形を切り捨てて楽しいかね」
老人の呆れたような声。それは【NAME】の真後ろから聞こえた。
「──!」
無言の叫びをあげて飛び退き、武器を構え直す。その仕草に老人はくつくつと笑い──倒れ伏す盗賊達に視線をやって、その笑みを苦笑に変える。
「まったく、折角の手駒を。まだまだ彼らには使い道があったというのに。
……仕方ない、今度はあなた方に私の手足となっていただこう」
老人は薄気味の悪い笑みを浮べ、懐から何かを地面へ投げ捨てる。
硬質の岩肌に転がったそれは、数瞬も経たずに武装した骸骨戦士へとその姿を変えた。数は二体。こちらを囲むような位置に動き、ゆっくりと武器を構える。
「では、始めましょうか」
いつの間にか携えていた杖を老人が振り下ろす。
同時に、二体の骸骨戦士達が一斉に襲い掛かってきた!
砕けた二体の骸骨戦士達を前に、老人は少し感心したような表情を浮かべた。
「ふむ、なかなかやるようだ。もう少し、真面目にお相手した方が宜しいかな」
呟き、老人が左手を前に差し出す。すると、その手の中に巨大な書物が出現した。
びしり、と周囲の空間が凍りつく。
書物から沸き出す強大な力が周りの存在概念を圧倒する。あの書物が何なのかは判らないが──明らかに危険だ。少なくとも、今の自分達が太刀打ちできるものではない。
「……おや」
力に圧倒され、身動きすらとれずにいた貴方を見て、老人が唐突に首を傾げる。同時に、書物から溢れていた力が呆気なく消滅した。
「その首飾り──ルアムザでの『手』を切ってくれたのも君等だったのか」
老人が杖を振るうと、先日手に入れた『灰色の首飾り』が空中に浮びあがる。
「面白い。『昂壁の翼』の腰抜け共以外に敵対存在が居なくて退屈していたところだ。今、君等を私の人形にするのは簡単だが、それではつまらない」
杖を懐に仕舞うと、老人は盗賊達の死体に近づき、彼らが持っていた奇妙な石を拾い上げる。
「もっと力をつけるといい。またいつか出会ったとき、私と対等に戦えるだけの力を」
言って、老人は高らかに笑うと、一瞬にしてその場から姿を消した。
灰色の隠者
──銀嶺岩窟墓地──
銀嶺山脈の東端を廻り込むように延びるウスタール大街道を進む。
巫都ラケナリアと副都オルノルンとを結ぶこのルートの中間地へと辿りつく。夕闇の赤の中、街道の周囲を覆う木々の隙間から、まだ真新しく見える巨大な共同墓地らしきものがちらりと見えた。
人里からも離れたこんな場所に、何故このような巨大な墓地があるのか。いつものようにリトゥエに尋ねてみたのだが、
「そんなことまで判んないよ……」
といった答えが返ってきた。
そこに折り良く、一人の行商人らしき男が通りかかる。
呼び止め、墓地についての事を尋ねてみたところ、どうやらあの墓はオルス国で数年前に起こったという内乱の戦没者達を弔う場所として作られたものらしい。そして噂によれば、ここ数ヶ月ほど前から戦いで命を落とし葬られた者達の躯が土の中から外へと這い出て、墓地周辺を徘徊する姿が確認されているという。
「だから、あんた達もさっさとここ通り過ぎちまった方が良いよ」
言って、男は足早に立ち去った。
「……なんかやばそうな所みたいだね」
男の背中を見送りながらリトゥエが呟く。確かに、あまり長居しているとロクでも無いことに巻き込まれそうだ。さっさと立ち去ることにしよう。
──と、その時。どん、という重く鈍い音と共に、視界の片隅に映っていた男の身体が唐突に横へ吹っ飛んだ。同時に道端に広がる森から幾つもの黒い影が飛び出し、男に取りつく。
血飛沫が舞った。
「【NAME】!」
リトゥエの声を聞くまでも無く、貴方は男に群がる影──恐らくは犬か、狼か──を蹴散らすために走り出す。
「ァアア!」
しかし、森から鈍い唸りと共に新たな影──腐乱した死体の群が姿を現し、道を塞ぐ!
グール達を始末し終えた貴方の周囲を、先程商人を襲っていた犬達が取り囲んでいる。既にあの男がどうなったのかは言うまでも無かった。
こちらの隙を窺うように周りを囲む犬達と睨みあいを続ける。既に逃げられる状況ではなく、あとはどちらが先に仕掛けるかといった一触即発の状況だ。
──と、その時。
「近くで『手』の気配がしたと思えば……また君等か。『灰色の首飾り』、まだ持っていたのかね」
唐突に、何も無い虚空から声が響き渡り──そして、灰色の法衣を着込んだ老人が空間から染み出すように姿を現す。
「うわ、また出た……」
リトゥエが呻き、貴方の背後へと隠れる。
老人はそのまま音も無く街道に降り立ち、手を軽く振ってみせた。すると、その仕草に従うように周りを囲んでいた犬達が背後に下がる。
「どれ、あれから力をつけ──おや? 種を、持っているのか?」
老人は【NAME】の背嚢を透かすように見据え、呟く。
「リカステやガレクシンで私の実験体を狩っていたのも君だったのか。くく、面白い。面白いな」
くつくつと一頻り笑うと、老人は袖の中から二つ程、『夜霧の谷』で見た小さな骨のようなものを地面へと投げ捨てる。
「ならば、どれだけ力をつけたか、見てやろう。それ、レカ・ステフ・アゴルミィ・クリフ」
それは一瞬にして骸骨戦士の形態となり、手に持った武器を構える。
「種を持っているというのなら、それも使わせてもらうぞ。レカ・アゲニィ・アゴルミィ・ニバス」
老人が呟く言葉が終わるか終わらないかというタイミングで、【NAME】の背嚢がびくりと脈動する。慌てて背嚢を投げ捨てると、そこからずるずると不気味な蔦が這い出し、獲物を探すように蠢く。
「こんなところか。……では始めるとしよう。できるだけ楽しませてくれよ」
老人は手に持った杖を掲げ、両眼を糸のように細めた。
「ここで、敗れるのか……」
老人が小さく呻き、膝をつく。
老人の身体が、手に持っていた本と共に何の前触れもなく砕け、塵となって果てた。
「……なんだったんだろ、結局」
その様をリトゥエと二人、呆然と眺める。
老人が一体何を画策していたのかは知らないが──とにかく、それを打ち砕くことに成功したようだ。
灰色の隠者 ヨファイオの影
──ヨファイオの影──
深い緑と河の透明との狭間、所々緑色の領域からはみ出し河を侵食している枝などを切り払いつつ進む。
移動を開始して数時間。
大水蛇が出るという区域は係留所から更に西に進んだ位置にあり、まだまだ先は長いのだが。襲ってくる亜獣や行く手を遮る木々に気をとられ、思うように歩を進めることが出来ない。
やはり無理にでも水路を選んだほうが良かったのだろうか。
「とかいっても今更仕方ないでしょ。もちっと前向きに行こ。前向きに」
などとリトゥエは言うが、実際その区域に大水蛇が出たとしても、船が無ければ結局はどうにもならないのではないかという気もする。
(少々短絡過ぎたか)
思い、嘆息。
もう少し事前準備か、情報収集に努めた方が良かったのかもしれない。
時間が経過し、夜ともなれば道程は尚更厳しくなり、一部の亜獣達の動きも活発化するだろう。このまま歩を進めていても大した成果は得られそうに無いし、これは辺りが暗くなる前に引き揚げた方が賢明かもしれない。
──引き返そう。
そう、貴方がリトゥエに告げようとした時。
「……むにゃ。何、あれ?」
貴方の肩上でうつらうつらと船を漕いでいたリトゥエが、目を瞬かせて前方の一点を指差す。釣られて視線をそちらへと向けるが、これといった物は──。
「いやほら、あそこ見えない? あの樹と樹の向こうでなんか動いて、あ、やば! 【NAME】、隠れて!」
声を抑え、しかし鋭い調子での警告に、貴方は慌てて身を伏せた。
一体どうしたのか。
既に身体を半ば透明にさせているリトゥエに問い質すと、彼女は先程示していた方向をじっと見つめつつ呟く。
「亜人……それも蜥蜴人[ディリザード]の集団かな。私達には気づいてないみたいだから、【NAME】。そこの影からなら顔出しても大丈夫。見てみて」
言われた通りに見れば確かに、リトゥエの示す場所でちらちらと動く青色の人影があった。
蜥蜴人は、ヨファイオ周辺を生息域をする亜人の一種だ。一時はそれなりな勢力を誇り、周辺地域に住む人々と色々といざこざがあったと云うが、グローエスが派遣した師士団の力によって彼等はその縄張りを大きく縮小する事となった、らしい。
そこまでの情報を記憶から引っ張り出した貴方は、思案するようにふむと唸る。
(……この辺りを縄張りをする、人とは少々良好ではない関係の者達、か)
──もしかすると、最近このヨファイオ上流を通る人の船を襲うという大水蛇と、彼等蜥蜴人達の間には何らかの係わり合いでもあるのではないか。
「あー。【NAME】、冴えてるかも。そう云えば蜥蜴人達って、水棲の生き物を自分達の遣いにする事が良くあるんだった。種族的にそう云う風な力が備わってるとか何とか……」
リトゥエの台詞に、貴方は成程と頷く。となると、ではどうすべきだろう?
何か良い案は無いだろうかと、ふわふわと傍で浮いている妖精に話を振ってみると、彼女は眉根を寄せて腕組み。
「うーん。まずあの連中が本当に大水蛇と関わりあるのかが今のところ判んないから、それを確かめてみるのが良いんじゃないかな?」
その辺りだろうか。
しかし、それをどう確かめるべきか。今までの経験や噂からすると、蜥蜴人達と会話での交渉を行い情報を引き出すのはまず無理だろうし、後は彼等の後をつけてその動向を探るくらいしか思いつかないが。
「私もそれ以外無いかなーって思うけど……あ! 動き出した!」
リトゥエの言葉に蜥蜴人達の方へと慌てて気を戻すと、先程までは動きを止めていた蜥蜴人達がこちらが居る場所とは逆の方角へと移動し始めていた。
意外とその動きは速く、このままぼんやりとしているとあっという間に見失いそうだ。
「ど、どうしよ、【NAME】。追いかけるなら急いで行かないと直ぐ見失っちゃいそうだけど。でもあんまり迂闊に近づいていくと、もしあいつ等が後ろに意識を向けた時に逆に私達の事がバレちゃうかも」
確かにそうだが、迷っている時間も余り無さそうだ。
兎に角急いで追いかけるか、それとも少しばかり様子を見つつ追いかけてみるべきか。
・
既に辺りは夕暮れを過ぎ、暗く染まりかけている。
ヨファイオ河上流周辺を埋める森の一角に身を潜めた貴方は、河辺に輝く松明の光の下をじっと眺めていた。
松明を手にしているのは、先程まで自分達が追っていた蜥蜴人達。だが、そこにいるのは彼等だけではない。河の向こうから現れた者、河岸を伝いやってきた者、森の別方向からやってきた者。見ている間にあれよあれよと数は増えて、既に三十以上の蜥蜴人達があの河縁に集まっていた。
一体、彼等は何のためにこの場所へと集まっているのか。その疑問は、つい先程解消された。
「……いやぁ、見事に当たったね、【NAME】」
貴方の肩上で、声を落として呟かれたリトゥエの言葉に、貴方は無言のまま頷く。
視線を岸から河の方へと移せば、そこには全長十数メートルは下らない巨大な水蛇の姿があった。
蜥蜴人達は先程から、水の中から僅かばかり出ている背に乗せられた荷物を抱え、陸の方へと運び出す作業を続けていた。
恐らく大水蛇の背中に乗せられていた荷物は、恐らく彼等が襲った交易船から略奪してきた物品だろう。これであの蜥蜴人達が大水蛇とつながりがある、というのはこれでほぼ確実となった。恐らく蜥蜴人達が飼い慣らした大水蛇を使ってヨファイオを通る船を襲っているのだろう。
「だけど、ここの蜥蜴人連中があの大水蛇を使ってるってのは判ったけど……でもどうしたもんかな。この状況だと流石に大水蛇退治ってゆーのも……」
リトゥエの躊躇うような、怯むような言葉は尤もな物だ。
明らかに多勢に無勢。
個人または少数戦力が基本である冒険者が相手に出来るような雰囲気では全く無い。
(これは下手に動かず、観察に徹した方が良さそうだ)
さっさと引き返すというのも何だ。兎に角、情報収集に専念する事としよう。
そう思い、貴方は取り敢えず河の中から頭と胴の上部のみを見せている大水蛇達の方へと何気なく視線を移し──。
見てはいけないものを、見たような気がした。
「は?」
思わず呟き、改めて今視線が通り過ぎた場所へと気を戻す。
一際大きな水蛇の頭の上に立つ、一つの影。
まず、その影は他の蜥蜴人達と比べ、そのシルエットが異質だった。
蜥蜴人達はその生活習慣上大仰な衣服は好まず半裸に近い姿であるため、シルエットは自然と丸みを帯びたものであるのに対し、その影は頭部が三角の形に奇妙に尖り、ゆったりとした長衣は明らかに蜥蜴人達では用いられぬ型の物。つまり、人の衣服──それも典型的な魔術師が為す輪郭だった。
だが、それだけでは驚くには値しない。
問題は、下方の松明の光に煽られて見えたその衣服の色が黒と白の中間、つまり灰色に統一されており、そして右の手には通常では有り得ない程に巨大な、しかし数度確かに見た覚えのある本を手にしていた点にあった。
その外見に一致する人物を、貴方はただ一人だけ知っていた。
しかし、
(……馬鹿な)
こう呟かざるを得ない。
あの老人、確かに、銀嶺山脈の墓地で粉々となって散った筈。なのに何故ここに居るのか。貴方は愕然とその人影を見つめる。
と、水蛇の頭上から蜥蜴人達の方を眺めていた影の頭部がゆっくりと動く。
三角形のシルエットが揺れ、その縁の下から覗く奇妙に輝く眼光が貴方の隠れている場所を真っ直ぐに突き刺した。
「────」
瞬間、息が詰まる。
眼を見開き固まった貴方に、帽子の鍔下で輝く光が僅かばかりの笑みの気配を作り、そして奇妙な形の杖を携えた左の手を一度大きく振った。
と、同時。
「あ……え?」
耳の直ぐ傍で、リトゥエが驚きの声を上げた。
もくもくと陸揚げの作業を続けていた蜥蜴人達が一斉に動きを止め、貴方が隠れている方へとぐるりと身を廻したのだ。
「まさかバレた? な、なんでいきなり!?」
彼等は全員がこちらの位置をはっきりと認識しているかのように、それぞれ作業を切り上げ、武器を手に持ち、ゆっくりと貴方の隠れている場所へと向い、動き始める。
(まさか……)
先程、人影が取った杖振る行動。それが、今この場にいる蜥蜴人達全てに対する何らかの指示、もしくは命令の類であったという事か。
しかし、蜥蜴人達は先程からそれぞれ個々に作業を行っており、水蛇の頭の上に居たあの影に気を払っていた者は殆ど居なかったように思えた。なのに、杖を一度だけ振るという動作で、場に居る蜥蜴人達が一斉に反応した。
という事は、何らかの術式的な支配命令系統が、あの影と蜥蜴人達の間で既に出来上がっていると見るべきか。
「【NAME】、来るよ!!」
リトゥエの警告に、貴方は戦いやすい位置へと素早く身を移動させながら、愛用の武器を構える。
最も近くに居た蜥蜴人達の一団が突っ込んでくる。前衛三人に、後衛一人。御せぬ数ではない。貴方は迎撃の為に腰の高さを落とし、先頭の蜥蜴人が手にした大棒を振り上げる動作に合わせて、必殺の技法を叩き込む!
何とか最初に襲い掛かってきた蜥蜴人達を打ち倒すが、多勢に無勢なのは変わりない。
この状況で、今は大水蛇の傍でこちらを笑みと共に眺めているあの男が手を出してくれば逃げる事すら難しくなるだろう。
「【NAME】! 次が来る、もう逃げよ!?」
叫ぶリトゥエは既に遠く、逃げの態勢に入っている。判断としては間違っていないが、しかし先程の蜥蜴人達の速度を考えれば逃げ切れるかどうか怪しい。とはいえこのままやり合っていても状況は悪化するだけだ。
(──大きな技法を放って一度相手を退かせて、その隙に逃げる!)
移す行動を決め、手にした武器を握り締めた瞬間。
「…………」
大水蛇の頭上に立ってこちらを眺めていた老人の手が一度だけ動き、その掌に握られていた奇妙な形の杖の先端が、貴方の周りを包囲し始めていた蜥蜴人達に向けられる。
同時に、ぴたりと。
蜥蜴人達全員の動きが停止した。
そして突然身動ぎ一つしなくなった蜥蜴人達を唖然と見る貴方の耳に、
『今日はこの辺りにしておこうか』
空気を介さず、直接届いてきたかのような。
まるで直ぐ傍で囁かれているような程の近さで、老人の声が響く。
「何、この声!? え、でもこれって……あれ? ウソ」
水蛇の上に立つ影に気づいていなかったらしいリトゥエが戸惑うような声を上げる。その様子を見るに、どうやら彼女にもこの声が聞こえているようだ。
『お遊びだったとはいえ。銀嶺でこの身を砕かれた借り、このような形で返すのは詰まらぬしな。開龍を為した後、改めて遊ぶとしよう。それまでにもっと力をつけておくといい』
大水蛇の頭上に立つ影が、杖を横に大きく振る。その仕草に操られるかのように、貴方を囲んでいた蜥蜴人達がその包囲を解くと、貴方をさっぱりと無視して先程まで続けていた作業へと戻っていく。
貴方はその様子を呆気に取られて眺めていたが。
『それ、命が惜しくば去るがいい』
響いた声に、貴方は我に返る。
どうやら、あの大水蛇の上に立つ影──遠目から見える衣服と、そして聴こえる声の質から判断するに、恐らくはテュパンの谷や銀嶺の山脈墓地で顔を合わせた魔術師の老人──は、今この場にいる蜥蜴人と、そして川に浮ぶ大水蛇達を完全に掌握しているようだ。
その彼が見逃す、と言っている。ならば今この場から大人しく立ち去れば、取り敢えずは危険な無くトホルドの街まで戻れそうではあるが。
(……しかし、逃げて良いのだろうか?)
あの老人。一度は確実に倒し、しかし何故か今この場にも存在する異質な者。それを見逃して良い物か。
「……【NAME】、今は、逃げた方が良いと思う」
そんな貴方の迷いを払うように、肩上に立つリトゥエがはっきりと告げてきた。
「今のこの状況じゃ、無理だよ。見逃してくれるっていうなら……逃げるべきだよ、ここは」
言ってリトゥエが見るのは、大水蛇の背から荷物を陸に運び込んでいる蜥蜴人達の姿だ。たとえ老人相手に互角の戦いが出来るとしても、あの数の蜥蜴人達を相手にして生き延びるのはまず不可能だろう。
──勝ち目は無いのだ、ならば退くしかない。
貴方は一度眼を伏せた後。身を翻す事無く、大水蛇の上からこちらを見下ろしている影を睨んだまま、ゆっくりとこの場を後にする。
『そう言えば、まだ君達には名乗っていなかったか』
老人の姿が視界から消える間際に、そんな声が届く。
『私の名はニビト・ブラームス。この名を覚えるか忘れるかは勝手だが、私が君に名乗ったという事実だけは忘れぬように』
・
夜のヨファイオに輝く松明の光が、完全に見えなくなる。そこまで離れて、貴方は漸く人心地がついた。
しかしリトゥエは未だ難しい表情のまま腕を組み、じっと蜥蜴人達が作業を続けているであろう河辺の方向を睨んでいる。
「それにしても、なんであのお爺さんが生きてるのよ……。あの声、確かそうだよね? 【NAME】」
貴方は無言のまま頷く。声と──暗がりでははっきりとは判らなかったが、あの輪郭と手にした巨大な本。その特徴は銀嶺山脈で相対した術師と一致している。それだけでは良く似た別人、という可能性もあったが、届いていた言葉は明らかにあの老人でなければ流れが繋がらぬ物。
蜥蜴人と大水蛇。
そして、その二つを手足のように扱う、一度は倒した筈の老人の存在。
一体彼等──いや、彼は何を目的として行動しているのか。
……兎に角、今は街に戻って身体を休め、その後ゆっくりと考えてみる事にしよう。
灰色の隠者 藍鱗と碧鱗
──西ヨファイオ河──
グローエス南部に位置する街トホルドから、南の属国オルスへと至る道を歩く。
歩を進めるごとに足裏に感じる硬い感触が心地いい。丁寧に舗装された石畳の道は、五王朝全土をくまなく結ぶウスタール大街道の特徴だ。
そのまま歩き続けて数時間。徐々に周囲の景色に緑が混じり始める。西ヨファイオ河が近づいてきた証拠だ。
・
ヨファイオの南の岸から北の岸を繋ぐ百メートルほどの巨橋の根元付近に、ヨファイオ河を行き来する船が停泊する大規模な係留用の施設がある。名をオイビア係留所と言う。
河には既にしっかりとした橋が掛かっているため、係留所には南北の岸を往復する渡し舟といったような類の船は一切無く、係留している船の大半は長く東西伸びるヨファイオの河を利用しての物資運搬を主目的とする船だ。ここに大規模な係留所が作られたのも、大街道ウスタールを利用して物資の運搬が迅速かつ容易に行うことができるから、という理由らしい。
だが、大水蛇による襲撃事件は未だ解決しておらず、係留所で停泊する船舶は以前と同じく多い。中には一度引き返した後大きく迂回し、大水蛇が出没されるという地域を避けて通っている船もあるというが、迂回せずに進む場合と比べ数十倍もの時間と相応の危険が伴う為に容易く選択できる手では無く。中には大水蛇からの目こぼしを期待してそのまま河を進む者達も居るが、命からがらといった様子で係留所まで引き返してくる船も少なくない。
つまるところ、この西ヨファイオを利用した輸送路は今も半ば死んだ状態のまま、という事だ。
・
そんな鬱屈した状況の中、船乗り達が憂さを晴らすべく集まる場所。オイビア係留所にある宿兼酒場の一角で、貴方は小さなテーブルの上に並べられた安い料理を片付けつつ、テーブルの縁に腰掛けた紫髪の妖精に向けて小声で話し掛ける。
内容は、前回このヨファイオ河の奥に足を踏み入れた時に出くわした連中についてだ。
「取り敢えず、大水蛇を遣った蜥蜴人達が今回の騒動の犯人ってことでいいんだろうけど……」
問題は、その蜥蜴人達の影にまた別の存在が居た、という事だ。
腕組みしつつの貴方の呟きに、リトゥエは手に持っていた干し葡萄の粒をもぐもぐと頬張りながら頷く。
「だよねぇ。あの時の蜥蜴人達の動きはどっかおかしかったし、多分あのお爺さんが胡散臭い仕掛けで何かしてるんだろうけど。普通に人の術式であれだけの数の存在操るのは難しいから、なんかのでかい印章陣──は無いか。後は精神操作の力がある神形、魔導器って線か、専用の魔術品か寄生生物を使ってとかそんな処かなぁ」
リトゥエの言うとおり、あの時出くわした蜥蜴人達の様子は明らかに尋常ではなかった。まるで老人の指示に従うだけの操り人形のような。
その事から推測するに、今回ヨファイオで起こっている事件は蜥蜴人自身の意思ではなく、あの老人、ニビト・ブラームスの指示によって引き起こされているという可能性が高い、と。
「あくまで推測、だけどね。ていうか、蜥蜴人達は昔に今回よりももっと規模の大きい事件起こして、その時人間に徹底的にやられちゃってるから、こういう事やると最終的にどうなるかってのは判ってる筈だもん。この辺に居る妖精の子達にも聞いたけど、前は動向調査みたいな感じで軍の連中とかが定期的に蜥蜴人達の集落を廻ってたって聞いたし、蜥蜴人達がその事を忘れてるって訳はないと思う」
それは初耳と貴方は目を瞬かせて、あれと首を傾げる。
国の方から蜥蜴人達の動きを掴む為に人を派遣しているのならば、今のこの状況は何だ?
「虹色の夜」
リトゥエは短く一言呟いて、香草の包みをはむりと一口。指先についた汁を舌でしゃぶりつつ貴方を見上げて言葉を続ける。
「人が足りないんだよ。平時なら兎も角、亜獣に現出地形にって今は何処もかしこも危険や異常だらけで、目に見えるそっちに人が割かれちゃって、それ以前から行われていた警戒行動は疎かになっちゃってるみたい。ヨファイオ周辺はあまり現出の報告が無いからほっとかれてるんじゃないかな」
そんないい加減な事で良いのかとも思うが、五王朝各所で発生している変事の内容と規模を考えるに、現出が発生していない処に人員を割きたくないというのも判る気はする。
「まぁ、軍人ぽくない人とかならちょくちょくそっちのほうに向かってくの見かけたとは聞いたけどね。──ああ、あと今日初めて会った妖精の子がちょっと詳しく話してくれたんだけど」
包みの最後の一欠を飲み込むと、リトゥエは少し表情を引き締める
「暫く前に、ここから結構離れた場所にある蜥蜴人達の大集落で何かあったみたいなの。詳しくは判んないんだけど、ある日を境にそこ一帯の土地概念が少しだけど歪んで、あと空気の質が替わったって言ってた。何があったのか詳しく調べようとした子もいたらしいんだけど、近づくと圧迫されるというか気分が悪くなるというか、そんな感じになるらしくて断念したって」
(土地概念の歪み、か)
傾向としては現出の発生時に良く言われるものだが。
「私もそうじゃないかなって思って詳しく聞いたんだけど、その子が言うにはそこまで強烈な感じじゃなかったって。せいぜい人の術式で場が歪んだ程度って」
「…………」
「で、その事件の後から、そこの集落に住んでいた蜥蜴人達の様子が途端に変わって。他の場所──ここの係留所の上流にあるっていう別の蜥蜴人の大集落にいきなり攻め込んで、そこを占領しちゃったんだって」
前にリトゥエが聞いてきた『藍鱗と碧鱗の部族が何だかごそごそやってるみたい』という話の詳細が、それか。
「うん。まぁ、最初聞いたときはたまに衝突って話だったんだけど。……それでね。異変のあった大集落が藍鱗の部族の中心地で、その攻め込まれて占領された大集落ってのが碧鱗の部族の中心地だったらしいんだけど、碧鱗の方は不意打ちだったし、大集落に居た者は殆ど全滅。残りは散り散りで別の場所にあった小集落に移って立て直そうとしてるって話なんだけど、藍鱗の連中は碧鱗の大集落を拠点にして、一つ一つ碧鱗の集落を潰していってるんだって」
血生臭い話である。右側に置かれた皿に手を伸ばそうとした動きが思わず鈍る。
「後、その大集落を占領した藍鱗の連中は、集落に近づいてくる存在には問答無用で攻撃しかけてくるらしんだけど、問題はその大集落が河の近くにあるらしくて──」
河の上流を抜けようとする人間の船が大水蛇に襲われるというのも、その『集落に近づく者を問答無用で攻撃』という流れの一環か。
「──正解。それでね、何で唐突にこんな事になったのか判らないって、この事を教えてくれた妖精の子達は話してたんだけどさ。……この状況を作ったのって、多分」
恐らくは、あの老人。
灰色の影を纏う魔術師、ニビト・ブラームスの手によるものだろう。
「…………」
貴方とリトゥエは、至った結論に思わず黙り込む。
暫くの間、周囲の喧騒だけが貴方とリトゥエの間を無遠慮に通り過ぎ、
「──ねぇ、【NAME】」
先に口を開いたのはリトゥエだった。彼女は難しい表情のまま貴方に視線を合わさず、声だけを寄越してくる。
「あのお爺さん、前にちゃんと【NAME】がやっつけたよね?」
「…………」
そう。その筈だ。
あの老人は、あの銀嶺山脈麓にあった墓地で自分が確かに倒した。手応えは確かで、その消え様も見届けた。
なのに、何故彼はこの河に在るのか。
「それに、あのお爺さんが蜥蜴人──藍鱗の連中を使って動いてるとして、一体どういうつもりでこんな事してるんだろ?」
リトゥエは眉根に皺を寄せて首を捻るが、そもそも自分達とあの老人には大した接点が無い。顔をあわせた回数は前回の件を入れても三度。言葉も両手で数えられる程度しか交わしておらず、これではニビトの思惑など読みようがない。
肩を竦めつつ貴方がそう返すと、リトゥエは「だよねぇ」とばかりに溜息を吐く。
「で、まぁ今判ってる事はこれくらいなんだけど、【NAME】、これからどうするの?」
問われ、貴方は椅子の背凭れに深く身を預けて、ふむと唸る。船によるヨファイオの通行を邪魔する大水蛇。その水蛇を操るのは蜥蜴人で、その蜥蜴人を操っているのが恐らくあの老いた魔術師。解決を目指すならばあの魔術師を何とかするか、彼の手足となっているらしい蜥蜴人を軒並み退治するか。大水蛇を打つという手もあるが、水蛇が居なくなれば蜥蜴人達が自ら妨害を開始するだろうし無駄手間だろう。兎に角被害を小さく片付けようとするならば頭を叩くのが常道だが、そもそもニビトと一対一の状況になったとして、果たして勝てるものなのかどうか。前回は勝つ事ができたが、あの時の老人の動きには明らかな油断があった。彼が手にしていた巨大な本も、袖口に忍ばせていた杖もその力を発揮していない。もし、それらの力が全力でこちらに向けられていたならば。
「…………」
その辺りの事を考えると、正直今回の件はここで手を引いた方がいい気がする。そもそも、大水蛇の件は仕事として依頼を受けて動いているわけではない。好奇心と正義感、それに功名心等が合わさった結果としての自発的な行動だ。故に、自身の手に余ると判断したならさっさと手を引いたとして誰からも責められる事では無い、むしろ冒険者としては正しい行動と言えるだろう。
──藍鱗と碧鱗──
ここまで関わって引き下がるというのも面白くない。多少なりとも関わったからには、やはり行ける所まで行くのが冒険者というもの。
にやりと笑いそう告げる貴方に、リトゥエは半ば呆れたような感心したような顔をして、
「相変わらず無茶というか何というか……。まぁ、それはいいとして、具体的な行動方針はどうするの?」
言われ、貴方はとんとんとこめかみを数度叩く。
リトゥエがヨファイオに住む妖精達から得た情報で、それとなく現在の状況を掴む事は出来たが、しかし妖精達はあくまで外側から見ていた者の言葉であり、これだけではやはり情報が足りない。もう少し内情を掴んでおく必要があるように思える。
「ふむ。確かにね。しかし内情かー。その辺の情報を得るのに手っ取り早い手段といえば──」
内部に居る者をとっ捕まえて情報を吐かせる。
「──台詞取られた」
恨めし気な顔でこちらを見やるリトゥエに小さく笑いながら謝罪し、続きを促す。そんな貴方の態度に不満そうにしつつも話を再開する辺り、やはり彼女は生粋のお話し好きらしい。
「それで、えーと。前みたいにあの御爺さんやら大水蛇が出てきちゃうとアレだけど、上手く単独か少人数行動取ってる蜥蜴人達相手なら、捕えるのも難しくないかもね。まぁ、話してくれるかどうかは判んないけれど」
正直なところ望み薄と言わざるを得ないが、他に何か案があるのかと言われると、
「うーん。妖精の子達も空気が変わってから近づくの嫌がってるし、人間達はそもそも蜥蜴人達の動きが怪しくなってるって事すら気づいてないよね? となるともう伝聞での情報収集は限界で、あとは私達が直接動いて情報を得るしかない訳だからー」
あれやこれやと立ち止まって考えていた処で状況が好転する事はない、と。
「一応、妖精の子達にもう少し詳しく調べてみてって言ってはあるけど、力の弱い子達だから無理強いはできないし、宛てには出来ないかも」
となれば、善は急げか。早速彼等を探し──行く前に、眼の前の料理を片付ける事にしよう。
貴方は手早くフォークを動かし料理を口の中に放り込む。少々冷え始めているが、そもそも味を気にして頼んだ料理でもない。気にせず食事を続ける。
「でさ、蜥蜴人達を捕えるとして、あいつ等が居そうな場所の宛てとかあるの?」
既に満腹なのか、料理に手をつける様子も無く、テーブルの上で忙しなく動くフォークの先端を手持ちぶたさに眺めていたリトゥエが、ふと顔を上げた。
(宛て、ねぇ)
最後の一口を果汁で軽く味付けされた水で胃の中へと押し流しながら考える。
明確な宛てがある訳ではないが、係留所で聞いた人々の噂や己の経験、そして先程のリトゥエの話を総合するに河の上流へと向かえば彼等と遭遇する確率は高いだろう。少数の蜥蜴人達を狙うという方針で行くならば、彼等が占領しているという大集落からは多少距離の置いた辺りで、周辺を巡回する蜥蜴人に襲撃をかける、といった辺りが無難な手か。
碧鱗の小集落とやらを廻ってみるという手もあるが、そもそも位置が不明だし、彼等は突然襲撃された側。魔術師の影響を受けた藍鱗の部族の状況についての情報を持っているとは思えず、それ以前につい最近同族に襲われ、その後知らぬ異種族の人間がやってきたとして、果たして友好的な会話をする気になるものなのかどうか。明らかに否であるし、そういった者達を無理矢理捕まえて話を聞くというのも筋が違うだろう。
淡々と話す貴方に、リトゥエはふむと小さく頷く。
「なら、狙いは藍鱗の連中に絞るとして……大水蛇に遭うと厄介だから、河縁通るのは避ける?」
いや、大水蛇を見つけたとしても、そこで河から離れれば良いだけだから問題はあるまい。あの水蛇が陸地を行く様を見たことはないし、もし河から上がってこれたとしてもあの巨体だ。木々が邪魔する陸ではそう速くは動けまい。
「え? そうかなぁ? あれだけでっかいと、その辺の樹なんてバリバリ吹っ飛ばして進んできそうだけど」
「…………」
そう言われると自信が無くなってきた。
少々情けない顔になった貴方を見て、リトゥエは擽るような声で小さく笑うと、
「まぁ、下手に目印の無い森の中を進むよりは迷い難いし、その利点も考えると河縁進んだ方が良いかもね」
そこまで言って、小さな妖精の身体がひらりと宙へと浮ぶ。
「取り敢えずさ、ここであれこれ話してても始まらないし、行きましょ?」
頷き、貴方も席を立つ。
河に沿って上流へ向かうとして──前回あの老人と遭遇した辺りまで行けば、その間に彼等の一集団とくらいは出くわすだろうか?
・
等と考えつつリトゥエを伴い酒場を出ようとしたところで、
「あら、もう出るの?」
今正に店の中へと入ろうと出入口を潜りかけた白衣の女性と鉢合わせした。レリエルである。
自分達が酒場で食事を取る間、彼女とは別行動を取っていたのだ。レリエル曰く、この酒場にはヨファイオ特産料理である……何かの魚の串焼きが無いとか何とか。眼の前に立つレリエルが口に咥えている木の串恐らくはその料理の名残だろう。
彼女は店に入るのを止めて数歩後ろへ。貴方はその隙間を抜けて店の外へと出ると、レリエルが自分の横に来るのを待ってから、先程酒場で決めた方針を彼女に話す。
「うーん。術式で操られている者を捕えて情報を引き出す、というのは少しばかり難しいぞ? 恐らく強力な精神矯正がされているから、言葉や暴力で吐かせるというのは難しいだろう」
それは判ってはいるが、裏を返せば、それを解呪さえ出来れば情報を引き出すのは容易いという事ではないか。忠誠や信念などなく、さらには自分が操られていたという事を知れば口も軽くなるというものだろう。
「で、誰が解呪するの?」
「レリエル以外に居ないでしょ」
貴方の肩上で、何いってんのと呟くリトゥエに、レリエルは両手を広げておどけてみせる。
「前に話した事は無かったっけ? あたしは学士や印章、機甲術士としてはそれなりの自信はあるけど、術士としての才は二流かそれ以下だよ。蜥蜴人の大集団を纏めて操るような魔術師の術を、専用の印章石や陣無しで破るってのはまず無理」
「そ、そうなの?」
「うん。まぁ、蜥蜴人達を操ってる術が、大人数を一度に操るために個々の術式自体は甘く組み立てられてる可能性もあるから、絶対に解けないとは言わないけど」
「……そこに望みを託すしかないって訳ね」
「申し訳ないけどね。【NAME】君も、そこのところは覚悟の上で宜しく」
少々残念な話であるが、今のように、彼女が自分にとって何の利益も無いであろう旅に付いてきてくれるというだけでもそもそも有り難い話なのだ。礼を言いこそすれ、責めるような話では全く無い。
「そういってもらえると助かるね。じゃ、行こうか」
彼女の促しに頷きで答えて、貴方は歩を速くする。目指すは河の上流だ。日が出ている間になるべく距離は稼ぎたい。そう勢い込んで進んでいたが故に。
「しかし、ニビト・ブラームスか。前に、何処かで聞いた覚えがある気がするんだけど……」
後ろを歩くレリエルの、そんな小さな呟きが耳に入る事は無かった。
・
一度辿った道であるせいか。昼頃に係留所を出て、日が暮れる前には一応の目的地であった前回大水蛇と蜥蜴人達の集団と出くわした場所まで辿り着く事が出来た。が、
「うーん、今回は出会わなかったね」
自分たちの目的はこの場所に何事も無く辿り着く事ではなく、蜥蜴人──それも青い鱗を持った連中と出会う為だ。既に位置としてはヨファイオの上流と言っても良い地点。ここから更に上るか、それともこの周辺を重点的に探し回るかの二択となる訳だが。
どうしたものかと首を捻り、ふと、リトゥエが険しい顔で河の上流方向を睨んでいるのに気づく。
「いやね、前来たときはあれこれあって気づかなかったけど、あっちの方、かなり空気が違うっていうか、土地概念に歪みが見えるわ」
どうした、と声を掛けた答えがこれだ。
しかし、その土地概念が云々という話は別の大集落の話ではなかったか。ここの上流にある大集落とやらは、元は碧鱗の部族の集落である筈。確か、空気がおかしい云々は藍鱗の部族の大集落の話だと。
「あの子達はそう言ってたんだけどね……。それよりもこれ、人の術式がどうこうってレベルじゃないような……」
リトゥエは暫くぶつぶつと呟いていたが、結論がでないのか。勢いをつけて顔を左右に振ると、
「あれこれ考えてても仕方ない。取り敢えず【NAME】、動きましょ。どうする?」
言われ、貴方は先程まで考えていた今後の選択を思い出す。
(上流に進む? いや、しかしここは……)
リトゥエが感じている異常も気になるが、今回の目的はあくまで蜥蜴人の捕縛だ。下手に彼等の集落近くに踏み込み、大集団に追い掛け回されるという展開は避けたい。当初の目的通り、この辺りで少数行動を取っている蜥蜴人を探し出し、奇襲をかける事としよう。
「了解。なら、一度散開する? 纏まって探すのは効率悪いし」
リトゥエの提案に当然とばかりに頷く。羽を持ち、空中からの俯瞰が可能なリトゥエはこういう時には頼りになる存在だ。河の周囲には深く木々が茂っており、上からの見晴らしがそう良い訳ではないが、やはり地べたを這いずり探し回るよりは有効な手段となりうる。
「ん。それじゃ行くけど、【NAME】もちゃんと探すのよ?」
釘を指すように告げて肩上から飛び立ち、木々の狭間を抜けて去っていく小さな妖精を見届けた後、貴方は気合を入れて背嚢を抱え直す。確かにこういう場でのリトゥエは頼りになるが、それに甘えっぱなしというのも癪に障る。こちらも出来うる限り頑張るとしよう。
・
などと勢い込んではみたももの。
「【NAME】君、どうだ? 見つかった?」
がさがさという草葉を払う音と共に姿を現したのはレリエルだ。貴方が首を横に振ると、レリエルは「お仲間か」と小さく息を吐いて貴方の隣に並ぶ。
「やっぱりこういう時はリトゥエちゃん頼りになっちゃうね──って、お?」
と、辺りを見渡していたレリエルの視線が木々の間で止まる。どうかしたのかとそちらを見れば、貴方が居る場所に向かってかなりの速度で飛んでくるリトゥエの姿があった。
「リトゥエちゃんお帰り。その様子だと収穫アリかな?」
レリエルが伸ばした手を軽く蹴って勢いを殺し、ひょいと何時もの定位置である貴方の肩上に停止したリトゥエは、
「……んー」
しかしレリエルの問いに何ともいえない微妙な表情を返す。
「あれ? 収穫ナシ? てっきり蜥蜴人が見つかったから急いで帰ってきたものだと思ったんだが」
「いや、居た事には居たんだけど……ちょっと、不意打ちなんて無理というか拙い状況っぽかったというか」
「リトゥエちゃんにしては珍しく歯切れの悪い物言いね」
「うーん、まぁ、その、取り敢えず行ってみれば判ると思う」
軽く首を傾げて訊ねるレリエルに、リトゥエは渋い顔のまま呟く。貴方はレリエルと顔を見合わせるが、その間にリトゥエはひらりと空中に舞い上がると先導するように森を飛んでいく。
「ふむ。あの子が行けば判るというなら、大人しく従ってみようか。行くよ、【NAME】」
とんとんと愛用の長銃で己の肩を数度叩いてから、レリエルはリトゥエを追って走り出す。貴方にしても異論は無い。彼女等に遅れぬように後に続いた。
そのまま暫く森を駆け、傾斜のきつい坂道を登って然程高さの無い崖上へと出る。眼下には獣道よりも多少マシといった程度の細道があり、そこで、
「────」
青の鱗と、緑の鱗。二つの鱗を持つ蜥蜴人達が入り乱れ、戦いを繰り広げていた。
・
「不意打ちは出来るかもしれないけど、一匹捕えて逃げるとか無理だよね。この状況だと」
貴方の肩上に止まるとそう呟くリトゥエ。戦況を見る限りでは、確かに彼女の言う通りだった。これで、せめて二つの集団が互角か、緑の鱗の側が多少優勢程度ならば付け入る隙もあるかもしれないが、実際の戦況は碧鱗側が圧倒的な劣勢のようで、半ば逃亡状態に近い。そもそも彼等の装備と動きに差がありすぎた。追い詰める誰もが手に槍か杖、弓を持ち、声を発する事も無く凄然と攻撃を続ける藍鱗の側に対し、碧鱗の側は武器を持つ者は数える程しか居らず、殆どの者は怯え逃げ惑っている。完全な掃討戦だ。
「……酷いね、これ」
「確かにね。青い鱗が藍鱗の部族なんだろうけど、動きに熱が無い。成程、確かにこれは完全に精神的な制御を受けてる。じゃなきゃ、こんな一方的な状況であんなに冷静に動ける訳ないよ」
唸るような声音でリトゥエが呟き、レリエルが溜息交じりに呻く。
恐らく碧鱗の側には非戦闘員が多く混じっている。何とか全滅に至っていない理由は、恐らく武器をもつ碧鱗の蜥蜴人達の腕前が、追い縋る藍鱗の戦士達を大きく上回っているからだろう。が、常に殿を務め、藍鱗の蜥蜴人達からの攻撃を凌いでいる彼等の消耗は激しいらしく、遠目でもその動きが怪しくなってきているのが判る。矢が迫り、槍が迫り、一人の碧鱗の戦士を捉える。一度捕まればもう逃げることは適わない。他の仲間達も己に肉薄する刃を凌ぐのに精一杯で、血を噴き動きを止めたその蜥蜴人の助けに入る事も出来ず、間も置かずに放たれた無数の追撃が彼を串刺しにする寸前。
逃げる碧鱗の集団に紛れていた一つの影が、するりと身を翻した。
「あれは──」
影の姿を見て、レリエルが驚きの声を上げる。
その間にも、走り出た影は手に持った何かで空中に光線を描き、そして。
「──!」
響き渡った言葉は、術式を発動させるための『宣言』たる一声。
同時、空間に刻まれた印章の輝きと共に、寸での処まで迫っていた死の刃が、吹き荒れた風の渦に払われた。
目前にまで迫っていた藍色の者達を押し返したその影が、未だ収まらぬ風に衣服をはためかせながら面をあげた。
白髪の混じった髪に、皺のある顔つきからしてそれなりに歳を経た男。一瞬、あの灰色の魔術師かとも思ったが、しかし服装や姿形は全くの別人だ。そして、
(何処かで、見たような──?)
ほんの僅かな既視感。
それを補うように、貴方の隣に立っていたレリエルが声を上げた。
「──バッケン導師! 何をやっているんですっ!」
その叫びが届いたか。崖下で手にした短剣を構え、藍色の蜥蜴人達と相対していた彼は一瞬こちらへと視線を送り、目を見開く。
「レリエル君か!? 済まない、少し力を貸して欲しい。彼等を逃がしたいんだ! ────!」
彼はこちらに向けて大声をあげた後、傍に居る碧鱗の者達に何事かを叫ぶ。それに呼応するように碧色の戦士達の動きが変わり、怪我を負った蜥蜴人を庇うように後退を始める。
それを見た藍色の蜥蜴達が逃がすものかと動き出すが、しかし彼等の動きを押さえ込むように男が印章を描き、生み出された閃光の槍が青い鱗の蜥蜴人を打ち据えて吹き飛ばす。
「ええい、アーバンヘイムから戻ってきた後、また居なくなったと思ったらこんな処に居たのかあの人は。【NAME】君、悪いけど手伝って。あの人はウチの──昂壁の導師格の人なんだ!」
彼女はそれだけ言うと、長銃を構えて狙撃の態勢に入る。
一体どういう状況なのかいまひとつ判らないが、兎に角あの魔術師の男を助けた方が後々話が上手く進みそうだ。
貴方は武器を抜き、崖上から身を躍らせる。壁面を適度に蹴りつけて速度を落としつつ着地し、魔術師──レリエルはバッケンと叫んでいたか。彼の懐に入ろうと踏み込んでいた蜥蜴人の一匹を技法で弾き飛ばす。
「助かります。左は君に。右は自分が」
言って、バッケンが動く。短剣が素早く空中に印を描き、それを見た藍鱗の蜥蜴人達が彼の動きを止めようと動き出すが、しかし崖上から飛来する銃撃が蜥蜴人の動きを阻害。その間にバッケンの術式が成立し、生み出された光の槍が彼等に突き刺さる。
そこで負傷した右手側の蜥蜴人達をフォローするように、左手側の蜥蜴人達が身を移そうとするが、それを妨害するのが自分の役目だ。貴方は一気に彼等の懐に飛び込むと、己の技法を敵集団に向けて全力で解き放つ!
振るった一撃が蜥蜴人を吹き飛ばす。既に倒した数は十を超えて、辺りには打ち伏した蜥蜴人達の身体が転がっている。最初に碧鱗の蜥蜴人達を襲っていた者達は粗方倒し終えたが、森の向こうから次々と新手が現れ切りがない。恐らく、近くにあった碧鱗の集落を襲った戦力が、大立ち回りを繰り広げる自分達を潰す為に徐々にこの場所に集結しつつあるのだろう。
レリエルと貴方のサポートを受けて十分な集中を経て放たれた儀式技法が、周囲の蜥蜴人達を軒並み弾き飛ばす。しかし、その影から新たな蜥蜴人達と、その更に薄暗い影を纏った異質な気配を放つ巨体が、地を揺らしつつこちらに迫ってくるのを認めて、魔術師の男バッケンが冷静に呟く
「そろそろ退き時ですね」
彼は崖上に居るレリエルに手で合図を送ると、次いで貴方に目配せして走り出す。
確かに、退くならば今だ。先程の儀式技法も、その為の隙を作るための一撃だったのだろう。
運良く儀式技法の被害から逃れたらしい蜥蜴人の放った矢を捌きつつ、貴方はバッケンの後を追った。
・
「それで、何がどうなってこんなことをしてるんです、バッケン導師? 貴方の専門は呪草煎法でしょうに!」
「いや、その呪草煎法研究の一環で久々にこっちに来たら、何だかあれやこれやと色々巻き込まれてこんな感じにですね。いやいや全く、実戦なんて久しぶりですよ──っと危ない」
「その色々巻き込まれて、の辺りに関する詳しい事情を、お聞きしたいところ、なんですが──ったくしつこいな! リトゥエちゃん、後ろからついてきてる連中、何とかなんない!?」
「無茶言わないで! 数が多すぎるよ! ……っと、このまま直進ヤバイ! 回り込まれてる、右、右行って!」
「右!? 道無いんだけど! ええい、【NAME】君先陣宜しく!」
そんな無茶苦茶な、と言いたくもなるが、飛び込まなければ逃げ場が無い。兎に角技法を放って強引に草木をぶち抜きながら、道を作ってそこを走る。
「やっぱりこのままじゃジリ貧ですねぇ。どれ、この辺で二手に分かれますか」
「二手、ってどう分かれるの?」
「自分一人と君達、若しくは自分と妖精のお嬢さんと、他の人達、かな。ヨファイオはよく調査で足を運んでいたからね。自分ひとりでなら、上手く追手をまけるような場所が無くも無いんですよ。だからこっちになるべく彼等をひきつけて、頃合を見て身を隠します。そうすれば──とっとっと、ええと、なんでしたっけ。ああ、そうすれば無事に全員逃げ切れる可能性は高いでしょう。そこの妖精さんを貸していただけるなら成功率はさらに高まりますね」
「……うーん。【NAME】、どうする?」
問われて、走りながら考える。取り敢えず、今の状況のまま逃げ続ければ何れ捉まるのは必至だ。そして逃げるのに必死でこちらに代替案など無い。となれば、彼の案に乗るしかない。
「判りました。では妖精さん、こちらへ──っと!」
「仕方ないなぁ──って、うわっ!?」
バッケンの方へと移動しようとしていたリトゥエの目の前を、巨大な炎の塊が通り過ぎる。地に落ちたそれは大きな火炎の花を咲かせて、貴方達とバッケンとの間を遮った。
「ああもう熱い! ちょっと待ってて、今そっちへ!」
「いや、この火を利用すれば上手く──妖精さんは彼等と一緒に! 丁度良いです、ここで分かれましょう!」
「導師、大丈夫なのですか!?」
「なぁに、任せておきなさい。上手く逃げ切って状況が一段落着いたなら、オイビア係留所から真っ直ぐ北へ、三本河を越えた先にある大岩に来て下さい! 自分も碧鱗の彼等の無事を確かめてからそちらへ向かいます。では!」
炎の向こうで、バッケンはこちらに向けて軽く手を上げて、そしてその手に握った短剣で炎を切る。その動作に合わせてまるで命を持つかのように、彼の周りを包む炎が舞い踊り、そして盛大な爆炎を生む。
「ほ、ホントに大丈夫なの、あれ!?」
あまりの派手さにリトゥエがレリエルの肩に張り付いて叫ぶが、レリエルは涼しい顔のまま走り出す。
「たとえ呪草煎法専門といっても、一応は導師級の──下手をすれば司位にも至ろうかという位の魔術師だ。その本人が大丈夫と言うんだから大丈夫だろう。さ、【NAME】君も、今のうちに行くよ!」
否という理由など無い。貴方は頷き、この場から脱するべく彼女の後を追った。
灰色の隠者 封龍珠
──西ヨファイオ河──
オイビア係留所から真っ直ぐ北へ、三本河を越えた先に、目を見張るほどの大岩がひとつ。その上に、一人の男が座していた。
「無事だったようで何よりです。レリエル君。それに、そちらの妖精憑きの君も」
彼は貴方とレリエルがやってきたのを察して、被った帽子を僅かに挙げて軽く挨拶をしてくる。
妖精憑きという言葉に、貴方の肩上に座るリトゥエが一瞬顔を顰めるが、
「……突っ込むと話がズレそうだから今は止めとく。それより、オジサン何者なの? レリエルの関係者、で良いんだよね?」
最後の台詞は自分達の隣に立つ、白衣に身を包んだ眼鏡の女性に向けたもの。彼女、レリエルはとんとんと肩上で長銃を弾ませつつ口を開く。
「バッケン導師。ウチの──『昂壁の翼』に所属してる高位の魔術師だよ。あたしとは専門も所属も違うけど、導師格の人だからね。それなりの面識はある」
「レリエル君は印章と機甲。自分は呪草や考古術学が専門だけど、一応術式関係でも導師の格を持ってるからね。その繋がりでの指導で幾度か、といった処ですか。で、君は……」
男が術式を併用してひらりと大岩から降りると、こちらの顔を見て少し考える仕草の後。
「確か、アーバンヘイムで使いに来てくれた冒険者君ですよね。どこかで見たような、と思っていたんだ」
(アーバン、ヘイム)
その言葉で思い出す。
以前、公社で受けたレリエルからの依頼に、大空洞で連絡が途絶えていた調査団を探してくれというものがあった。
あの時に出会ったのが、この男だったと。すっかり忘れていた。
「取り敢えず挨拶はこの辺にして……それより導師、これは一体どういう事なんです? 先程は蜥蜴人達と行動を共にしていたようですけど」
早速のレリエルの問いに、バッケンは少し困ったような表情を浮かべる。
「実際の処、自分もなし崩し的に巻き込まれたクチでして、どうと明確には答え辛いのですが……まぁ、自分の知る限りは話しましょう。歩きながらで構わないかな?」
別段異論はない。貴方が無言で頷くと、
「有り難い。では行きましょうか」
バッケンは一度顎を引いてからざくざくと獣道を歩き出す。貴方は慌ててその背を追った。
・
「でも、歩きながらって何処行くのさ?」
鬱蒼と茂る木々を裂いて歩く魔術師の傍に、リトゥエがふらりと飛び上がる。
「生き残った碧鱗の者達が集まっている村です。いつ襲撃を受けるか判らないような状況ですから、あまりそこを空けたくないんですよ。戦える者は、もう殆ど残っていませんから」
「……そんなに、状況悪いの?」
「残念ながら」
途中拾った枝と懐より取り出した短剣でもって草と木を払いながら、バッケンは暗い調子で語る。
「碧鱗の部族の大集落が襲われてからは、もう一気にね。今となっては、自分達が向かっている集落以外はほぼ全滅と言ってもいい程です。当然の話ですけれど、元々そのような大規模な侵略行動に対応できるような備えがあった訳ではありませんから、ああも本格的に──それも、あのような状態の者達に攻められては、どうしようもない」
「碧鱗の部族の方は、今どのような方針で動いているのです?」
最後尾に立つレリエルが、周囲警戒のためか時折後ろに視線を走らせつつ訊ねる。バッケンは僅かに左右に首を振り、疲れの混じった声を漏らした。
「方針、と言えるようなものはありませんね。部族の上の者達は最初の大集落への襲撃で殆ど亡くなってしまったらしくて、行動はバラバラ。抵抗どころの話ではなくて、逃げ延びるのがやっと、と言った処です。一応自分やある程度戦いの出来る蜥蜴人達が集まって各集落を回って避難させてはいますが、それも焼け石に水。それに、今避難場所に使っている集落もいつ見つかるか。残念ながら、このままでは全滅は免れないでしょう」
「全滅、って……。そんな虱潰しにされてるの?」
「虱潰しですね。どういう手を使っているのかは知りませんが、自分が知らない程に小さな集落の位置すらも把握し、襲撃していると聞きます。実際、先程君達と出会ったのも、その小さな集落に住む達を避難させる手伝いを頼まれた時でしたからね。正直、今避難場所として使っている集落も、いつ彼らに襲撃されてもおかしくない状況です」
「徹底してるなぁ……」
そんな会話を聞きながら、貴方はバッケンの後に続いて小さな沢を跨ぎ、更に森を進む。
方角は北西。ヨファイオの中では河が少なく、逆に森が濃い地域。人が訪れる事は殆ど無く、蜥蜴人達の姿もあまり見られない場所だ。深く茂る木々は人々の進入を阻み、河を欠いた土地は水を源とするヨファイオの蜥蜴人達を遠ざける、という事なのだろう。
だが、そんな場所にある避難地とやらも、バッケンは安全では無いという。それ程までに藍鱗の者達の襲撃は隙が無いのだろうか。
「そういえばさ。オジサン、蜥蜴人達からお手伝いを頼まれるとか、仲いいんだね。人間なのに」
リトゥエのふと思いついたように発せられたその言葉は、貴方も不思議に思っていた事だ。
人間とヨファイオの蜥蜴人達の関係はあまり宜しいものではない。これはグローエスに暮らす者達の中では一般常識にも近いものだ。なのに、このバッケンという導師は碧鱗の部族の者達と共に行動し、しかも彼らに助けを請われる程に信頼されているらしい。
対し、バッケンは少し照れたように顎髭を撫でる。
「最初のうちは酷いものでしたけれども、根気良く彼らと接触している間に、ね。幾つかの呪草煎法を彼らに伝えたりもしましたし。こちらとしても彼らと交流を深めておけばこの辺りの特殊な呪草を手に入れるのが楽になりますし、それに彼らからの許可を得なければ近づく事すら難しいモノがありましたから、まぁそれなりに必死に頑張った結果ですよ。目的があるから近づいた訳でして、そう褒められたものではありませんね」
「……難しい、モノ? 蜥蜴人達が何か遺跡──芯形機構を聖地の変わりにしていたとか、神形か魔導器かを神器としていたとかですか? でも、そんな話は翼では一度も聞いたことは……」
ぶつぶつと呟くレリエルに、バッケンは慌てて首を横に振る。
「ああ、そんな大層なモノじゃありませんよ。いや、大層なモノで“あった”と言うべきでしょうか。所謂考古術学に置いての資料と言いますか、そうですね。皆さん、『封龍珠』というものをご存知ですか?」
「…………」
全く無い。
貴方は無言を答えとして、視線を後ろ、最後尾のレリエルに向ける。が、彼女も数度眼鏡を叩いた後、ふるりと首を横に振った。意外な事に彼女も知らないものらしい。
「んー、封龍珠? ええと、かなり昔に聞いたことがあるような……?」
そんな中、頼りない呟きを漏らしたのはリトゥエだ。彼女はバッケンの帽子の鍔に体重を感じさせない動きで座り込み、何かを思い出すように虚空を見上げ、
「あ、思い出した。……でもこれってホントに昔の──私じゃない記憶の域だよ? 堕ちた準芯竜や、それに近い亜竜や龍種の、『肉体』ではなく『格』を押さえ込むために作られた珠。その位の竜種になると、肉体だけを拘束する技を仕掛けても効きが薄いとかで、同時に概念的な封印を行う時に使われてたモノとかだっただっけかな?」
「それを、蜥蜴人達がもっていた、と?」
レリエルの言葉に、バッケンは軽く頷いてみせる。
「軍や翼の一部の人間の間ではかなり前から知られている話ですけれどもね。ヨファイオの蜥蜴人達は、その珠の管理を役目として存在する者達だという説もあるくらいですし」
「その……どう聞いても封龍珠とやらがとても大層なモノに聞こえるのですが」
苦笑しつつ呟くレリエル。
「ていうか『芯なる者』達が竜を相手にする時にたまーに使ってた奴だから、貴方たち人間の視点では明らかに神形器とか魔導器とか、そういう類に属するモノだと思うんだけど」
リトゥエの方も今ひとつ納得行かないのか、微妙な表情で頬をぽりぽりと掻く。
「…………」
貴方にしてみても同意見。
しかし三方からの胡散臭い目を向けられても、バッケンは然してひるんだ様子も無く。上から垂れ下がってきていた蔦を器用に切り裂いて道を整えながら声を返してくる。
「まあ、そのままの状態で残っていれば大層なモノでしょうが、どうもヨファイオの蜥蜴人──少なくとも碧鱗の部族で保管されていたものは既に使用済みらしくてね。既に用を成さない単なる珠になっているとの話なのですよ」
「単なる珠、ですか?」
「ええ。軍が昔蜥蜴人達の反乱を抑えに派遣された際に、ある程度の事は調べられていますからね。間違いはないと思いますし、自分が見た時もそれはもう力を殆ど失った只の珠にしか見えませんでした。どうも封龍珠というモノは一度しか使用できないもので、彼らが崇めている品は既に一度使われ、それで力を失った珠である。故に危険性も価値も然程無い──というのがその時の調査団の報告に残されてました。翼で全く知られていないのもこの辺りが原因でしょうね。魔術的見地からみて価値は低く、故に翼の者達にしてみればどうでもよい品、という事。実際自分も魔術師ではなく考古術学的な視点でのアプローチのためですし」
腰辺りの高さまである太い木の根を身軽に登りながら、魔術師は淡々と答える。フィールドワークを主としていたのか、バッケンは魔術師にしてはかなり体力がある方らしい。この悪路の中でも、その動きに陰りが殆ど見えない。
そんなバッケンの帽子の鍔の上で、リトゥエが小さく首を捻る。
「でも、やっぱりこう、危なそうじゃない? 確かに封龍珠は一回こっきりで使い捨ててた気がするけど……でも竜種の『格』を取り込んだ封龍珠は、その竜の意思を内に秘めているようなものだから、結構危ないモノのような……」
竜種は、現世界に生息する生き物の中でも随一とも呼べる力を持つ種族だ。
特に芯竜ともなれば、正に神が如き力を持つとされる存在。それと比べて準芯竜や龍種がそれより数段落ちるとしても、絶大な力を持つ事には変わらない。その『格』を内に封じ込んでいるというのなら。
「バッケン導師。藍鱗の部族──いえ、ニビト・ブラームスの狙いはその珠なのでは?」
自分と同じ結論に達したのか。レリエルの発したその問いに、バッケンは小さく唸る。
「……それも確かに考えはしたのだけれども、少なくとも自分が見る限りでは珠の内にそういった強い力が宿ってるようには見えなかった。珠という型に封じられた竜の格がその形を維持できなくなって弱まってるという可能性もあるけど、それにしては珠から感じる力が小さすぎる。軍の調査報告資料では、恐らくこの珠は使用はされたものの、封印には失敗して、不完全な形で格を取り込んだのではないかと──ん?」
唐突に。
今まで一定のテンポを殆ど崩さず、淡々と獣道を歩き続けていたバッケンの足が止まる。
振り返った彼は、笑みのない顔でこう訊ねた。
「ニビト・ブラームス? どうしてその名前がここで」
「──あ」
と、思わず声が出た。
そういえば、自分が持っている情報を彼に話していない事を思い出す。藍鱗の部族の裏に、あの灰色の魔術師が居る事を。
「って、オジサン藍鱗の連中の裏に誰が居るか知らなかったの? ていうかこの名前に心当たりあるの?」
「いえ……藍鱗の蜥蜴人達の動きから、何者かが背後で糸を引いている事くらいは気づいていましたが、それが誰かは……まさか、ブラームス氏がそうだと? 根拠は?」
貴方は自分と灰色の隠者──ニビト・ブラームスと名乗る老人との間で起きた事件とそれに纏わる出来事を簡単に彼に話す。霧の谷での遭遇。各地で見た死して動く存在と奇妙な種子。銀嶺で一度彼を倒した事。ヨファイオでその倒した筈の老人とまた出会った事。そして、彼に付き従う藍鱗の部族の事を。
「…………」
バッケンは暫く無言のまま顎に手をやり、じっと何かを考えていたようだが。
「ニビト・ブラームス氏は、過去に『昂壁の翼』に上級魔術師として籍を置いていた人間です。専攻は異封と召喚、それに死操。当時の翼の中でかなりの腕を持つ魔術師として知られ、特に死操に関しては極めて高い技術を持っていましたが……五年ほど前に『昂壁の翼』でちょっとした事件を起こしましてね」
「──ああ、それでか!」
「わぁ、な、何!?」
と、そこに突然声を挙げたレリエルに、リトゥエがびくんと小さく跳ね上がる。
「っと、リトゥエちゃん御免。いやね、どこかで聞いたことがあると思っていたんだ。今の導師の話で思い出した。ニビト・ブラームス──翼内で外法に手を染めて、弟子や部外者を使って人体実験を繰り返してたらしくてね。それが発覚した時に、身柄拘束の為に派遣された衛士や魔術士を皆殺し。その後『貯蔵塔』に逃げ込んで、そこから持ち出した魔導器を使って出張ってきた上位魔術師達と大立ち回りした挙句、追跡者の手を振り切ってまんまと失踪したっていう、翼きっての大罪者だよ」
「……あのお爺さん、そんな無茶やってたの?」
「あたしは直接関わってなかったから詳しくは知らないけど、その時はかなり大きな騒ぎになってたな。持ち出された魔導器も結構力の高いもの持ってかれたって聞いたし。確か──」
「ニビト・ブラームス氏が持ち出した魔導器は幾つかありますが、特に拙いものは二つですね。『四界の杖』と『虚枠書本』。自分も事件の時に借り出された魔術師の一人でしたが、この二つには梃子摺らされました。召喚補助、概念変換の四界の杖と、結界補助、時空制御の虚枠書本。それを同時に使われるとね。正直、逃げてくれて助かったとあの時は思ったものでしたが……【NAME】君、確か君は種子がどうこう、と言っていたか?」
バッケンの問いに貴方は無言で頷く。奇妙な生物に埋め込まれていたあの奇妙な種子。銀嶺で戦った時は、その種子から伸びた植物と戦った事もあった。
「……彼の研究の一つがある程度完成したという事か? 盗み出した魔導器の力を借りれば、その応用で藍鱗の部族の者達を今のように……」
バッケンは暫しぶつぶつと呟いていたが、貴方達の視線に気づいたか、ふと顔を上げると少し言葉に迷ったように視線を彷徨わせて。
「済まない。兎に角、予想以上に拙い状況であるのは判りました。まあ、彼が藍鱗の部族を操って碧鱗の部族の集落を蹂躙している理由はやはり判らないままだが……そうだな、もしかしたら彼だけが知る何かが」
あるのかもしれない。
そう続く筈のバッケンの言葉は、
──怒、と。
遠くより響いてきた、地を揺らす程に強く低い音によりかき消された。
続いて、周囲の木々に止まっていた鳥や獣達が一斉に動く気配。そこかしこで葉が揺れ、ざわつく森の影の中で多くの鳥達が空に上がる姿が掠めた。
「な、何!?」
びょん、とバッケンの鍔で飛び跳ねたリトゥエが、慌てて貴方の傍へと飛んでくる。首下に巻きつく細い身体を手で押さえながら、貴方は状況を把握しようと意識を研ぎ澄まそうとして。
──轟、と。
木々の向こう。揺れた葉々の合間で、黒く太く濃く澱んだ独特の波動が、空を裂いて走るのが見えた。
その光景は、闇の属性を凝縮した概念の放出でよく見られるものだ。森の一角より伸びて宙を貫いた黒色の波動は、かなりの距離がある筈の貴方達が居る場所にまで、その力の残滓を届かせる。黒色の波が辺りを僅かに打ち、肌にびりびりとした小さな痛みを残す。
「っ──痛~ぅ!」
小さな妖精の身には、ああした強い概念は毒だと聞く。リトゥエがぎゅっと身体を縮こまらせて貴方の首にしがみつく。
「あの方角は……いかん!」
と、突然バッケンがそんな事を叫ぶと、先程までとは比べ物にならない速度で森を走り出した。
「導師!? どうしました!?」
レリエルの叫びに、バッケンは一瞬だけ振り返り、
「今の音と、概念放出、そのどれもが──自分達の向かっている場所、碧鱗の集落がある方角から飛んできています! 彼らに、何らかの危険が迫っている可能性が高い! 急ぎます!」
言って、バッケンはそのまま更に速度を上げて走り出す。その動きは明らかに貴方やレリエルの事が考慮されていない動きで、
「ッ、ええい。【NAME】君、走れるね? 行くよ!」
このままモタモタしていたら確実に置いていかれる。レリエルの焦った声に貴方は頷きを返し、既に茂った草葉の向こうに消えかかっているバッケンの背中を追って全力で駆け出した。
・
息を切らせながら、深く濃い森の中を懸命に走る。
そんな貴方の耳元を、先程届いた波による痛みがまだ残っているのか、小さく弱々しい声音でこんな言葉が通り過ぎる。
「でも、あの強い単一概念の直線放出──あれはまさか、吐息[ブレス]?」
──封龍珠──
走り始めてから、どれ程の時間が経ったのか。
ただ先行くバッケンの背中を全力で追いかけて、そしていきなり森が拓け、広がった視界。そこで目にした光景に、貴方は短く呟き息を呑む。
「これは」
そこは、かつては村であったのだろう。
だが今、ここは村ではなく、一つの戦場──いや、虐殺の場となっていた。
無感情に走る藍色の影と、地に伏せ倒れる碧色の影。蜥蜴人達特有の高い叫びと時折響く爆音。家屋は崩れ、辺りには火が弾けて、所々が白く、黒く、煙っている。
「……酷いな、これは」
貴方の背後から声。少し遅れていたレリエルが追いついたらしい。彼女は銃を取り出しながら辺りを一度見回し、
「状況は一方的か。【NAME】君、バッケン導師は? 見失った?」
問いに貴方は無言のまま頷く。森、それもヨファイオの森に慣れたバッケンの動きは早く、途中からは半ば見失い、その後貴方は殆ど勘頼みの状態で森を進んでいた。恐らく先にこの村へと辿り着いている筈だが、しかし何処に居るかまでは判らない。
「【NAME】、レリエル! 前、前!」
──と、貴方の首にしがみ付いてたリトゥエが慌てた声をあげる。
その焦った声に慌てて彼女の指差す方を見れば、藍色の鱗を持つ蜥蜴人達の集団が、どこか機械的な動きでこちらに走ってきている。手にした武器の先端にべっとりとこびりついた血の量から察するに、既に何人もの碧鱗の蜥蜴人達を屠っているようだ。
集団の中には、今までみた蜥蜴人達よりも身体が一回りほど大きく、立派な武器防具を身につけた者も居る。恐らくは指揮者格。どうやら、今回の襲撃はかなり力を入れたものであるらしい。
「問答──出来るような相手でもないか。【NAME】、行くよ! あいつらを蹴散らして、導師を探す!」
崩れた家屋の影や道の向こう、森の外れから次々と現れる蜥蜴人達。その全てを相手にするには明らかに敵の数が多すぎ、こちらの手が足りない。貴方達は半ば追い立てられるような調子で村を走る。
正面から振り下ろされた棍棒をするりと避けて、すれ違いざまに一撃。前を塞いでいた蜥蜴人達の一団を突破して更に走る貴方の目の前に、
「居た! オジサ~ン──ってうわぁ!?」
壁の壊れた家の向こう。帽子を被り、短剣を握り締めこちらに背を向けた魔術師の姿を認めてリトゥエが声をあげ、そして次の瞬間、彼が身構える先に見えたその存在に、驚きの声をあげる。
「これは……」
殿を務めていたレリエルが、それを見て僅かに息を呑む。
壊れた家の影からゆっくりと身を起こしたのは、骨のみで形成された巨大な竜だ。
不死生物か、魔導体か。どちらにせよ明らかに自然の摂理に沿った存在ではないその化け物は、全身に纏う黒色の澱みを揺らしながらバッケン、そして貴方とレリエルを見下ろす。
(この気配……)
先程見た、空を裂く黒い力。それと同種の気配が、この骨の竜から感じられた。
あの力を発したのがこの竜ならば、油断していい相手ではない。貴方は骨竜から視線を外さぬまま、バッケンの傍へと走る。
「オジサン、無事!? こいつ何なの?」
リトゥエの問いに、バッケンはこちらには視線を寄越さず声だけを返す。
「どうやら、君達の言っていた事は本当のようですね。先程ブラームス氏らしき人物と会いました。彼が蜥蜴人達を操って碧鱗の部族を襲っていたという話も、当人から聞きましたよ」
「うげ、あのお爺ちゃんも来てるの? 何処?」
「集落の奥へ。追おうとしたのですが、あの竜に止められましてね。どうやら、あれもブラームス氏の操る力の一つのようです。死操による技なのか、『四界の杖』の力による召喚術なのか。以前手合わせした時には、あのような竜を手駒としていなかったと思うのですが──、?」
バッケンの言葉が止まり、一瞬だけ視線が辺りを走る。
「何やら、蜥蜴人達も増えてきたようですね。殆ど囲まれています」
「それは……恐らくあたし達が引っ張ってきてしまった分かと。申し訳ありません」
「謝られる類の話ではありませんよ。それより、この場を切り抜けるために力を尽くすとしましょう。ほら、来ますよ?」
バッケンが声だけで正面を指し、何かに備えるように僅かに腰を落として短剣を肩の高さに構える。
肉を持たぬ骨の竜。その白い大顎がぱっくりと下に開き、その奥から果てしなく黒く濃い、不透明で形持たぬ何かがせり上がってくるのが見えた。
「【NAME】! 吐息が来る、避けて!」
竜種の力の象徴、吐息[ブレス]。
たとえ骨のみの歪んだ存在となっていても、それを放つ力は残っているらしい。
「──ッ!!」
音も無く。黒色の一閃が、身構える貴方達へ向けて放たれた。
圧倒的なまでに統一、凝縮された力の一閃。
奔る黒の概念の渦。
その直撃を受ければ、脆弱なる人の身など容易く砕け、崩滅する。
貴方とレリエル、そしてバッケンは素早く左右へと飛び、その一撃を寸での処で避けた。側面を抜けて後方へと抜けていく力の波は、背後でこちらの様子を窺っていた蜥蜴人の一団や、並ぶ家屋、そして村外の森を次々と舐め、その全てを闇色に染めて砕いていった。
それを見届け、貴方は一瞬だけ安堵の吐息をつく。
「くぅ、っつ!」
と、そこでぎゅぅ、と貴方の首にしがみ付いていたリトゥエの身体が、硬く縮んでいる事に気づいた。
先程の一撃。直撃はしていない。しかし吐息が直ぐ傍を通るだけでも、彼女の身体にはかなりの負担が掛かるという事のようだ。
(リトゥエは、)
下がらせた方がいいか。貴方は未だ痛みで身体を強張らせているらしい、リトゥエに一度この場から離れるように告げる。
「でも……ああもう、判った、御免」
彼女は少しの躊躇いの後、貴方の首から離れてふわりと空中へと上がっていく。
それを見届ける間も無く、バッケンがするりと貴方の傍へと近づき、蜥蜴人の集団の中から飛んできた光の矢を短剣で逸らしつつ囁く。
「【NAME】君。君はどちらの相手が好みです?」
バッケンの視線が、ゆっくりとこちらに向かって歩いてくる骨竜と、少し距離をとってこちらを包む無数の蜥蜴人達を順々に通り過ぎる。
(どっちもやだなぁ……)
思わず本音を呟きたくなるが、そういう訳にも行くまい。
「出来れば、君にあの骨の竜を任せたいところなのですが。先程戦ってみた感触からすると、どうも術式に対してかなりの耐性を持つようでして、少しばかり相性が悪い」
バッケンは魔術師だ。属性概念に対抗する力が強い相手と一対一となれば、殆ど勝ち目はないだろう。
「──つまり、銃術のあたしと【NAME】があの竜を相手する以外、この場を切り抜ける道は無い、と」
「申し訳ない話ですが、そういう事です」
「はぁ」
レリエルは長銃の具合を確かめるように一度長銃の各所を手で触れてから、貴方に視線を送る。
(仕方が無い、か)
貴方は武器を構え、一歩。骨竜の方へと踏み出す。
それを確認すると、バッケンは無言のままこちらに背を向け、辺りを囲み攻撃のチャンスを窺っている蜥蜴人達に向けて短剣を掲げ、宙に印章を切り始める。役割分担は決まったと言う事だ。
(……さて)
果たして、勝てるかどうか。
貴方が見上げる先、大きく開かれた骨竜の口蓋の奥で、黒く濃い力の波動が凝縮していく!
battle
形骸の竜

黒い淀みによる繋がりが絶たれ、骨の竜がその形を失って単なる骨の塊へと姿を変える。
同時に背後から強烈な光。バッケンの放った儀式術式が最後の蜥蜴人達に向けて放たれ、彼らを纏めて吹き飛ばした。
「やった、か」
呟き、緊張していた意識を、長く息を吐く事で休ませようとして、
『これは驚いた。不完とはいえ、四界を用いた骸の竜を壊したか。存外やるようだ』
響く声。
弾かれるように顔を上げれば、地面に転がり山となった骨竜の残骸、その頂点に、黒と灰色の交じり合った影が一つ。虚ろに揺れるその影は日の光の下にあっても姿をはっきりと現さず、まるで影が人の形を取っているかのよう。左の手にある奇妙な形状の杖と、脇に挟みこまれた巨大な本。そして右の手に掴まれた血に染まる鈍い白色の珠だけが確かな形を持っていた。
「ニビト・ブラームス」
その名を呟いたのは、いつの間にか貴方の直ぐ近くにまで移動してきていたバッケンだ。彼は手に短剣を握ったまま、油断の無い姿勢で、ゆっくりと灰色の人影に話しかける。
「その珠、本当に目的はソレだったのですか」
バッケンの視線の先には、人影が手にした珠に向けられていた。あれが、バッケンの言っていた碧鱗の部族達の宝、封龍珠なのだろう。
『ああ。藍鱗の連中と同じく大集落に祭ってるだろうと最初に襲ったのだが、無いのは予想外だった。お陰で無駄に時間と手間を食う事になった』
「判らないな。先程も問いましたが、そこまでして封龍珠を求めてどうするというのです。ヨファイオの蜥蜴人達が祭っていたのは既に使われた封龍珠。既に何かを封ずる力は失われ、単なる珠となっている筈のものでしょう」
『はは。使用されていない封龍珠など求めて何とする。竜の格を秘めたこの珠こそが私の求めるものだよ。確かに、珠という型に押し込められて格を歪まされたままでは、力を形と成す枠すらも失って内に残る力の発現など到底不可能だが』
影色の手が揺れて、その内にある白色の珠が僅かに掲げられる。
『竜という形を得て始めて力を持つモノならば、その竜というカタチにもう一度格を流し込んでやれば、そのカタチに沿って格は矯正され、力は蘇る。理屈としては簡単なものだな』
バッケンが眉を顰め、僅かに首を傾げる。
「……馬鹿な。竜の張りぼてか、近い存在の合成生物でも使うのですか? そのようなもので竜種の格を受け止められぬ事くらい、貴方なら判るでしょう。それに、珠から感じられた力の弱さから考えれば、恐らくその封龍珠は不完全にしか格を取り込めていない。たとえ封が解けたとしても満足な力は」
バッケンのそんな呟きに、人影の気配が僅かに呆れの含んだものに変わる。
『気づいていないのか? ……まぁ、説明するのは簡単だが、ここで話してしまうのも些か趣が無いか』
くつくつと陰の篭った笑い声が辺りに木霊する。
『藍鱗の部族の大集落。そこでちょっとした式の準備を行っていてな。必要な品もこれで全て揃い、やっと次の手順へと進める事ができる。私が何をするつもりなのか。それを知りたいのならそこへ来るがいい。私の自慢の式だ。見物客が居ないと言うのも些か味気ないしな』
僅かな笑みの気配を語尾に残して、辺りに散らばる骨と影の姿がゆっくりと薄らいでいく。
「逃がしは──」
しない。その言葉と共にバッケンが短剣で宙に素早く印章を記述。それに導かれて理粒子が蠢き、消え行く影に向かって力が炸裂する。
強烈な輝きと、それに伴う爆風。
だが、その光と風が晴れた後には何の痕跡もなく。バッケンの小さな舌打ちが、彼の放った術式があの灰色の影を捉えられなかった事を示していた。
・
崩れた家屋。血に塗れた地面。篭る火の匂い。あちこちで倒れ付す、二色の鱗の蜥蜴人達。
一人の魔術師により生み出された凄惨な光景の中。貴方達はただ無言で、既に何も無い一点。あの灰色の隠者が立っていた場所を睨む。
『私が何をするつもりなのか。それを知りたいのならそこへ来るがいい』
彼の言葉が脳裏を過ぎる。
藍鱗の部族の、大集落。
そこで一体、ニビト・ブラームスは何をするつもりなのか。
「……追いましょう。彼には禁忌というモノが無い。同じ魔術師として見過ごせぬ存在です」
バッケンは険しい表情のまま、貴方を見る。
「【NAME】君、レリエル君。巻き込む形で済まないが、手伝って欲しい」
灰色の隠者 双頭が昇る時
──西ヨファイオ河──
灰色の隠者、ニビト・ブラームスの後を追い、貴方達とバッケンはヨファイオの河縁を進む。
目指すは藍鱗の大集落。位置はオイビア係留所の上流にある碧鱗の部族の大集落を更に北へと抜けた先だ。蜥蜴人と骨の竜の襲撃を受けて壊滅した碧鱗の部族の小集落を離れた貴方は、一度係留所まで戻り態勢を整えた後、大集落を目指した。
その途中。標となる碧鱗の大集落があった場所を通りがかることになったのだが。
「……何これ」
貴方の肩上に止まっていたリトゥエがふわりと浮き上がり、辺りを気味悪そうに見回す。
眼前に広がっていたのは、森の中、水辺の傍にあって、何故か荒涼とした印象を与える風景だった。
そこかしこに樹で組み上げられた家があり、生活用具があり、所々に食料が積み上げられている。だが、そこで暮らす人だけが足りない。まるで集落に住んでいた者が丸ごと神隠しにあったような、そんな印象だ。
「確かここって、藍鱗の部族に攻め込まれたんだよね」
前にそう言ったのは、確かリトゥエ自身だったと思うのだが。
「え。いや、そう言われるとそうなんだけど……ていうか、確かにあっち、村の隅っこのほうだとそんな気配はあるんだけど」
貴方の言葉に、リトゥエは戸惑ったように答えて首を傾げる。
「でも、にしてはここに残ってる血の気が少ないっていうか、何ていうんだろ、別の気配が強いっていうか、正直、あんまり気分が良くない。空気が悪いって感じじゃなくて、ここに溜まってる何かが……」
「その正体は、恐らくこれですね」
今までじっと黙り込んでいたバッケンが、地面をとんとんと突く。
「地面に巨大な印章陣が描かれた後があります。もう力を失い、消滅しかけていますが。レリエル、読み解けますか?」
「…………」
バッケンが後方を振り返る。気づけば、レリエルは一人。貴方達とはかなり離れた場所でしゃがみこみ、集落全体の地面を見回している。
「何かの、補助。融解、崩滅……転換? 駄目ですね。全てを読むのは無理です。既に殆ど消えかかっている上、私達の使う印章の系統とは異なる要素がいくつか入ってる。これは、多分」
「──象形ですか」
「の、極めて簡素なもの。それとの合成式ですね。……となると、恐らくは」
顔を上げたレリエル。その言葉の続きは聞かずとも判るのか。バッケンは己の顎を軽く撫で、苦々しく顔を顰める。
「神形か、魔導器の固有印章陣──多分、“犠牲の転換”か。彼の持ち出したモノの中に『四界の杖』という魔導器があります。あれが持つ真の力を発揮するには、確か杖の内部に記されている印章陣を展開する必要がある筈です。この場所に残っている気配は、それのモノでしょう」
独り言のような声音で呟かれた言葉に、リトゥエがひどく嫌そうな表情を浮かべる。
「犠牲の、転換? ……なんかこう、凄い物騒な響きがするのは気のせいかな?」
その問いに、バッケンは小さな溜息と共に頷いた。
「気のせいではありませんよ。“犠牲の転換”は、印章陣内に居る命ある者を纏めて崩滅させて、その砕けて無形となった概念残滓を“贄の力”として『四界の杖』に回収し、魔術行使の際の力に変換する機能です。印章陣内に存在する有機生命全てに作用し、取り込まれた場合は身体すらも砕けて消え去ります。大集落の住人の殆どは、この印章陣の犠牲になったのでしょう。……成程、大集落から逃げ延びた者が極端に少ないのはこれのせいか」
そんな危険な印章ならば、今こうして大集落の中に居る事自体危険なのではないか。
貴方は泡を食って訊くが、バッケンは「いえ」と短く首を振る。
「既に力は失われていますし、それに“犠牲の転換”の印章陣は、資料を読んだ限りでは、少しでも精神的な抵抗があれば飲み込まれない。強制力は然程無かった筈です」
「え? でも、じゃあおかしくない? 藍鱗の部族が攻めてきたときと同時に使ったか、その後にでも使ったとするなら──」
碧鱗の蜥蜴人達が抵抗する意思を持っていなかったとは思えない。争った様子が然程無い事から、この印章陣で不意を打ったのではないかと、そう推測したわけだが。
「確かに精神的抵抗があれば飲み込まれないのですが、肝心の精神を操作されていた場合はまた話が別ですから。特に存在概念自体が元々人間より不安定な亜人種相手なら、恐らくは意識混濁か、睡眠状態にでもしてしまえば印章の効果に飲まれてしまったでしょうね。そして、ブラームス氏は翼でも上位の魔術師の一人として数えられる」
腰を上げて貴方達の傍へと歩いてきたレリエルが、バッケンの言葉を引き継いだ。
「それほどの術士なら、眠りの魔術のひとつやふたつ朝飯前という事。この集落全域を覆う眠りの雲を生み出すことすら容易だろうね」
広範囲の睡眠魔術で大集落に暮らしていた蜥蜴人達の意識を失わせてから、“犠牲の転換”の印章陣を展開し、食らったと。バッケンとレリエルの結論はその辺りに落ち着いたらしい。
「で、えーと……」
困ったようなにバッケンとレリエル、そして辺りの様子を順々に見て、リトゥエは心底引きつった顔で、己の頬を掻きつつ呟く。
「つまり、ここで判ったのってこんな感じ? 要するに“あのお爺さんが今、めちゃくちゃ強い力を持ってる”って事? タダでも強いのに」
「もしくは、その蜥蜴人達の命を利用して生み出された力を使って、何か大きな術式を行使するつもりである、といったところですね。“犠牲の転換”で集めた力は所詮は無形ですから、その力を使わずとも徐々に拡散していき、消滅していきますので。だから、まず目的を据えて、その達成のための手段として大事を起こす前に使用されるのが常でした」
「それって──うへぇ」
げんなりと、品なく舌を出して呻いてみせるリトゥエ。貴方にしてみても同感である。
全く、厄介な話だ。場に居る者全員が、深々と溜息をつく。
「……まぁ」
一番最初に気を取り直したのは壮年の導師だった。
「ここでこうして話していても仕方ありません。藍鱗の大集落の方へ急ぎましょう」
あの灰色の魔術師が、一体何をしているのか。
そしてその行為が悪しき物であった場合、果たして自分達で止められるのだろうか。
確信など無い。だが、ここまで来たのだ。今更逃げる訳にも行くまい。
貴方は覚悟を決めると、村を抜けて北──藍鱗の大集落があるという方角へと足を向けた。
──死を越えし者──
藍鱗の部族の大集落。その跡地には、ほぼ更地に近い光景が広がっていた。
そこに在ったであろう建造物や、生活を支える品々、暮らす人々の断片がほんの微かに残るだけ。何も無い、と言っても間違いではないその地には巨大極まりない印章陣が刻み込まれて、走る印自体が放つ輝きのお陰で、場は眼も眩むほどの光に包まれている。
「ちょ、ちょっとこれってヤバくない!? この印章陣って、まさか──」
リトゥエが連想したのは貴方とほぼ同じものだろう。
蘇るのは、つい先程通りがかった碧鱗の大集落。
そこに刻まれていた巨大な印章陣は、バッケンやレリエルの推測では村に暮らす蜥蜴人達を丸ごと食らう程のもの。それが今ここで再度展開され、行使される寸前なのではないか。
だが、銃を構えたまま周囲の地面に素早く目を走らせたレリエルは頭を振る。
「いや、あれとはかなり質が違う。多分“犠牲の転換”の印章陣とはまた別物だ。でも……」
彼女の視線が、遠く集落の向こうに向けられる。
「なんていう規模。それにこの式。水と──それに、死生? こんなもの、今まで見たこともないぞ」
大集落の枠すらも越え、周辺の森すらも食いながら刻まれた印章陣。足元でまるで脈打つように明滅する光の印からは、今まで見たことも無いほどの力に満ちて、今にも臨界に達して噴き出す間際。そんな気配が感じられた。
「レリエル君、【NAME】君、急ぐぞ! 印章陣に力がどんどん満ちていく。もう発動が近い! この陣が持つ意味は判らないが、その前に」
この術を構築し、行使しようとするあの男。ニビト・ブラームスを倒すしかない。
揃って頷き、先を行くバッケンを追うように貴方は走る。目指す先は、既に見えている。集落跡地、その中央付近に浮かぶ、二つの影。
一つは宙高くに浮かび、四肢を大きく伸ばした骨の竜だ。骨と骨の間を不気味な色合いの蔓が幾重にも絡まり伸びて、それぞれの骨をしっかりと支えていた。
そしてもう一つは、
『来たか』
灰色の隠者、ニビト・ブラームス。
竜より少しばかり下の高さ。支えも無く空中に浮かんでいた人影は、走り寄るこちらの存在を迎える様に振り返った。
下から立ち上る印章の光に煽られ、今まで不自然なまでに黒色の陰に隠されていた部分が露になっている。
その姿がはっきりと見える位置にまで駆け込んだ貴方は、その異様さに気づく。
長衣と帽子の隙間から覗く色を失い窪んだ瞳。光に満ちたこの場にあって、地を這う煙のように男の身体に纏わりつく黒色の影。露出している肌の色は青く黒く、生気など微塵も無い。
「貴方、まさか」
耳元、呆然と呟かれるリトゥエの声が小さく貴方の鼓膜を打った。
「──“死を越えし者”」
・
『研究の成果、というやつだよ』
青白い顔に笑みを浮かべ、落ち窪んだ両の眼が、貴方達の姿をゆっくりと捉える。
『君らは確か見た事があるだろう? “死生の芽”。死しても生を得る秘術の種。全く、昂壁の馬鹿共が邪魔をしなければもっと早く完成していたものを』
僅かに頭を振る。同時に彼の片頬、皮膚の下でずるりと何かが這ったように見えた。
右に杖、左に本を抱える両の手。指先、爪の先よりちらちらと見えるあれは、恐らくは植物の蔓。ブラームスの言う通り、どこかで見た記憶のある、あの怪しげな蔓に良く似ていた。
『しかし、快適だよ。この身は。人という枠を脱すればこれほど自由に力を揮えるようになるとは正直思っていなかった』
笑い。正に愉快といった調子で彼は両腕を広げ、高らかに音なき声を張った。
「……驚いた。あれ、本当に死んでるのに、生きてる。“死を越えし者”なんて見るの、ホントに久々だよ」
強張った声が耳元から聞こえる。リトゥエだ。
「存在概念が拡散せずに肉体の内に留まってて、しかも意識まで保ってる。ヤバイよ、あれ。鬼とかとは別の意味で危ない、凄く。あれは人としてみちゃダメ。あいつが言ってるように、その枠から外れた化け物として見て」
彼女の言葉に頷き、改めてブラームスを見る。
灰と黒の混じったその姿。内側から漏れ出してくる気配は、銀嶺山脈で戦った時と比べてまるで別物だ。恐らくあの時、ニビト・ブラームスという名の人間は死に、同じ名前の人ならざる“死を越えし者”が誕生した、という事なのだろう。
『さて、約束通り来てくれた事であるし、私が何をするつもりなのか話してやろうか』
そして笑いを収めたブラームスは、そんな事を言い出す。確か、碧鱗の部族の小集落で出会った際、その様なことは言っていた。だが、
(そんなもの)
この目の前に広がる状況。今にも何か大変な事が起こるのが明白な状況で、わざわざ彼の長話を聞いて時間を無駄にする必要などない。
動こうとする貴方。だが、それより一瞬速く、一歩後ろに立っていた影が貴方の横をすり抜けた。
「──話など不要です。何故なら」
バッケンが両の袖口から二本の短剣を取り出すと、空中に印を描きつつブラームスへと駆け寄る。
「貴方の目論見は、ここで潰えるからです!」
鋭い叫びと共に、バッケンは二つの短剣でもって鋭く正確に印を切る。同時に、短剣の切っ先に強い理粒子の光が生まれ、それは瞬く間に巨大な槍となってニビトに向けて、
『そう死に急ぐなよ。折角話してやろうというのだ』
打ち出される直前。
ブラームスが手にした杖を鋭く振る。その先端から生まれた四つの光は巨大な円を描き、その内側から四つの影が飛び出した。
影の二つは骸骨の騎士、残り二つはどす黒い血で全身を染めた巨大な蜥蜴人だ。骸骨の騎士はバッケンが放った光の槍を払い、蜥蜴人は走り寄るバッケンの前に着地すると、正に人外の速度で手にした武器を振るう。
バッケンがその攻撃を懐より取り出した新たな短剣で凌ぐ事ができたのは、正に偶然以外の何物でも無いだろう。だが、所詮は短剣だ。衝撃全てを殺すことなど到底敵わず、彼の身体は大きく後方──貴方が立っている辺りにまで吹き飛ばされた。
「……く」
「導師、無事ですか!?」
レリエルが銃を構えたまま彼の傍へと駆け寄る。短い呻きと共にバッケンは何とか身を起こすが、衝撃が抜けきらないのか動きは鈍い。
『大して長い話でもない。たとえ僅かでも、それだけ生が伸びるというのだ。有り難い話だろう? お前は確か……バッケン、だったか』
その様を愉悦と共に眺めてから、灰と黒の二色で構成されたその男はゆっくりと語り出す。
『何をするか、か。そんなもの、既に使われた封龍珠を捜している時点で直ぐにわかるだろう。この珠に封じられし龍──サンサーラを蘇らせ、それを己の駒とする。それ以外にあるものかね?』
こんな話を大人しく聞いてる場合ではない。
武器を構え、走り出そうとする貴方だったが、視界の片隅で動く何かに気をとられ、動きを止める。
「そんな事、出来るはずが無い──!」
貴方の立つ位置から少しばかり前方で、何とか腰を上げて叫びを返すバッケン。その片手が、貴方に動かぬようにという合図を送っていたのだ。
何か、策があるのか。
『出来る筈が無いと。そう考えるのは、知識と力が足らぬ証拠だ。このヨファイオの地で討たれ、川となりし龍、サンサーラは、二つの頭、二つの命で一つの存在となる龍でな。故に』
宙を浮かぶブラームスの直ぐ隣に、二つの珠が円を描くように回転している。その珠からは淡い輝きが漏れていた。
『サンサーラの格を封じ込むには、二つの珠が必要だったという事だ。それぞれ一つでは単なる石でしかないが、こうして二つ、重なり合わせれば一つの格として成る事となる。一つずつ調べ、その力を測ったとて全く無駄なこと』
「馬鹿な。軍の──昂壁の翼の調査団が、その程度の事を調べない筈が」
『無論、調べたな。と言っても、彼らが調べたのは私が用意しておいた何の変哲も無い石を、だが』
貴方のほうへと向けられていたバッケンの片手が、ブラームスの視線から隠すようにして刻んでいた密やかな印象記述。それがほんの僅かな時間、止まる。
「……驚きました。まさか、それ程前から下準備をしていたのですか」
『下準備、とは少し違うな。ヨファイオの封龍珠の仕組みを知ったのが、丁度その時だったからな。当時、調査団を率いていたのはこの私でね。お陰で、もっとも早くその事に気づくことができた。あの頃の私には力も技も足りなかったが、今の私には』
地面から湧き上がる輝きに照らされながら、灰色の魔術師は両の腕を広げてみせる。
『この不死なる身と、死生の芽。そして“四界”と“虚枠”がある。無数の蜥蜴人共を吸いし“贄”の力を用いれば、たとえ魔導の珠とはいえ、その封を開くことは可能だ』
「で、でも、そんなの開封してどうする気!?」
貴方の肩に硬くしがみついたまま叫んだリトゥエの声は、場に立ち込める緊迫した空気故か、半ば裏返っていた。
「それ、それだけじゃ、単に珠の封印を解いただけじゃ、中に入っていた概念がそのまんま外に溢れるだけで、直ぐに辺りに散って無くなって──って、まさか、それをその“杖”に!?」
喋っている途中で気が付いたのか、リトゥエは老人の持つ“四界の杖”を指差して顔を引きつらせる。
“四界の杖”が持つという固有能力は、ここにくる途中の集落跡でバッケンから聞いていた。生者の概念を砕いて集め、それを“贄”と呼ばれる力とするもの。それはつまり、あの珠に秘められている竜の格とやらも、吸い込み、力に変える事が出来るのではないか。
そんなリトゥエの指摘に、灰と黒の魔術師はしかし、くつくつという笑いと共に首を横に振る。
『それも悪くないがね。しかし“贄”の補給など何処ででも出来るが、龍の格となると話は別だ。貴重な龍の概念が単なる無形の力に堕ちるのは勿体無い。だからこうして、わざわざ手間と暇をかけて式を行っているのだよ。過去の遺物を掘り起こし、その形を取り戻させるために、な』
ニビトが貴方達から視線を外し、背後を振り返る。彼の後ろに浮かぶのは、全身に怪しげな蔓を絡ませて形を保つ骨の竜だ。
「……過去の、遺物」
鸚鵡返しに呟かれた言葉に、ブラームスは視線をこちらに戻す。
『ああ。掘り出すのが文字通り骨だった。蜥蜴人共をわざわざ操ったのも、これを探し、掘り出させるためが殆どよ。蜥蜴人共の伝承と翼にあった文献では、ヨファイオの何処かで朽ち果てた事は判っていたが、その詳しい位置までは掴めなかったからな。サンサーラの亡骸、これほど格を取り戻すのに相応しい素体など無かろうよ』
「翼に、文献? 私が目にしたものの中に、こんな龍についての文献など」
『ある筈も無い。とうの昔に、私が処分したからな。はは、まだ目録の改竄はバレていないのか。あそこの管理も相も変わらず間が抜けているな』
「……全く、隙が無い人だ」
『そうでもない。全てに隙が無いならば私は翼を出てはいないし、このような身体にもなってはいないからな』
バッケンの悔しげな呟きに、ブラームスは笑みを深くして答える。
そんな会話の間にも、ニビトの傍に浮かんでいる二つの珠の回転速度が上がり、放つ光の輝きが増していくのが判る。それに合わせて地面に描かれた印章陣が脈動し、宙に浮かぶ骨の竜に異様な気配が宿り、更にはブラームスの左手に収まる巨大な本の頁が捲れる速度が上がる。
彼はこちらに長々と話をする間にも、着実に術式を進行させているのだ。
このままでは、拙い。
その事を訴えようと、僅か前にしゃがむバッケンに視線を移して、
「…………」
後ろに回されていた彼の片手が刻んでいた印章は、既に完全な姿で宙に浮かびあがっている。そして仕事を終えた指が三本、こちらに向けて立てられている事に気づいた。
『では、そろそろ頃合か』
指が一つ伏せられる。
ブラームスは左手に持っていた本を宙へと離すと、右手に持つ杖の先端、纏う奇妙な揺らぎに向けて指先を当てた。
指が二つ伏せられる。
彼の左手が複雑に動き、空中にどろりとした印を刻む。その仕草に合わせて場の空気が一段と重くなり、地の印章陣の輝きが一際と増した。
指が三つ伏せられる。
ブラームスの傍に浮かんでいた二つの珠に細い亀裂が無数に走り、一部が音を立てて剥がれたその瞬間。
「“裁きとなれ、呼雷嵐[サンダーテンペスト]”」
バッケンの叫びが場に轟き、空中に生み出される無数の光点。
生み出された光はそれぞれが耳を裂くような爆音を上げて、地面へと向けて一直線に太い雷を落とす。その全ての輝きの直線状には、今正に術を完成させる印を刻みかけたブラームスの姿があった。
『────』
彼の死したる身体を貫いた雷の槍は、合わせて十の数を超えた。
生命力に優れた巨人や、鬼種でさえ打ち倒す儀式技法。
だが、その全てを受けて尚、宙を浮かぶブラームスが地に伏す事は無く。彼の身を僅かにふらつかせ、高度を落とす程度の結果しか生み出さなかった。
「そんな、無茶苦茶な──って、【NAME】!?」
傍で呻いたリトゥエの声が一気に遠のく。肩上にあった気配も同時に消えた。何故なら、バッケンが三本目の指を折ると同時に、全力でブラームスへと向けて駆け出していたからだ。
バッケンによる雷嵐の一撃。それはあの死を越えし者にほんの僅かなダメージしか与えられなかったのかもしれない。
だが。
(こちらが近づくくらいの隙は!)
まるで獲物を狩る獣。地を這うようにして駆ける貴方に向けて、ブラームスの杖が動く。だがその動きは明らかに鈍い。先程バッケンを迎撃した骸骨の騎士と血色で染まった蜥蜴人が、貴方の進路を塞ごうとするのが視界の片隅で見えたが、貴方の直ぐ後ろについたレリエルが、彼らを牽制するように銃を放つ。
この好機を逃せば後は無い。ここで、決めるしかない!
「はあああッ!」
僅か数瞬の交差。
レリエルの銃撃にも怯まず前に出てきた邪魔な障害物を蹴散らし、杖より生まれる四界の魔術を掻い潜り、放つ。
開放された技法の力が黒と灰の魔術師の肩口を捉え、炸裂する。魔術師の外套が弾け、その下の青い肌と肉、そして不気味な蔓を散らす。
届く。
己の手が、魔術師の身体に傷をつける事が出来た。
ならば、もしかすれば、このまま奴を倒すことも、
『何を思い上がっている』
「──が、!?」
ブラームスの肩。大きく抉られた肉の内側から瞬く間に這い出した蔓が、貴方の首を掴んだ。
絞められる。思い、拘束を解こうと手を蔓に回す間もなく。小柄とも言っていいブラームスの、しかも肩の傷口から生えた蔓。女の細い腕ほどの太さも無いそれに貴方の身体は容易く持ち上げられ、大きく一度振り回されると、その勢いのまま凄まじい速度で投げ飛ばされる。
「ぐ、う」
その先に居たのはレリエル。彼女は反射的に銃を手放すと貴方の身体を受け止めようとして、しかし勢いを殺せず、共に大きく後ろへ──バッケンとリトゥエの直ぐ傍にまで飛ばされ転がる事となる。
「【NAME】! レリエル! だ、大丈夫!?」
「……くそ」
今のが、恐らく唯一の好機。しかし、その間に貴方に出来た事はブラームスの肩を飛ばす程度。しかも、その傷さえ、
『ふむ』
貴方の技法により抉られた筈の肩口。そこから伸びた蔓がまるで飛んだ肉を補うように纏まり、ゆっくりとその姿を変化させる。失われた皮と肉を、彼の身に巣食う蔓が補完していく。
『少しばかり大人しくしていろ。直ぐに構ってやる』
杖が振られ、同時に貴方達の周りを囲うように四方形の輝く壁が生み出される。
「と、閉じ込められるよ!」
貴方の肩に捕まったリトゥエが怯えたように叫び、痛みによるものか顔を顰めて身を起こしたレリエルが、その輝く壁を見て小さく舌打ちする。
「絶対領域[フォースフィールド]の変形か……。この術式、効果時間は短いけど、とにかく硬いんだ。無理に突破するには余程の神形か魔導器の補助でもないとまず無理だぞ」
「で、でも、それじゃどうするの!? このままじゃ」
「どうするって……こんなもので塞がれちゃ」
悔しげに呟かれるレリエルの言葉の続きは、言われずとも判る。
もう、打つ手がない。先程の好機を活かす事が出来ず、そして今は四方を塞がれ、ブラームスに迫ることも、逃げることすらもできない。リトゥエはばたばたと慌て、レリエルは歯噛みし、バッケンは未だ立ち上がらずに顔を伏せたまま。
『さぁ、蘇り、取り戻せ。サンサーラよ』
正に最悪の状況。そんな中、高々と響く宣言。
それに合わせ、ブラームスの隣に浮かぶ二つの珠が完全に砕け、そこから無形の力が溢れ出す。
眼に見えるものではない、だが、確かにそこに在るのが判る。感じられる。
そんな力が珠から生まれ、そして瞬く間に形を失って空中へ消え去りかける前に。
ブラームスの持つ杖がその力を掬い上げるように動いて、そして杖の先端に宿っていた“贄”の力ごと、後方に浮かぶ骨の竜へと叩きつけられた。
・
地面に描かれていた印章陣がその役目を終えて沈黙し。
連なる骨が形作る輪郭に沿うように、消え去りかけていた力がその形を取り戻し、再生する。
龍の目覚めが、今。
──双頭が昇る時──
水で形作られた巨大な蚯蚓。
そんな表現が良く似合うモノが、森の彼方此方から唸るような低音と共に立ち上がり、うねりうねりと空中をのたくりながら飛んでくる。大きさは小さいもので幅数メートル、巨大なものなら十数にも及ぶ程。その全てはヨファイオに伸びる河川から生まれたものだ。
それら全てが目指す先は、灰色の魔術師の背に浮かぶ骨の竜。空を飛びやってきた水の流れは竜の骨にぶつかるとその姿を変化させ、骨に張り付き絡まるように動くと纏まりを解き、その骨の形に沿って身を整える。その様は、宛ら水で出来た肉だ。
四方より伸びた無数の水の手が、竜の骨を支え、その身に水を流し込む。ヨファイオの河川から吸い上げられた水が、龍の肉となり、手となり、爪となり、鱗となり、鬣となり、髭となり、目となり、角となる。水で創り出された二つの頭が僅かに揺れて、開かれた顎から濃い水の概念と、不死存在特有の穢れ腐った概念の残滓が零れ落ちる。
それはもう、単なる骸竜とは呼べないだろう。
──双濫龍サンサーラ。
系統は異なるものの、最も芯竜に近いと呼ばれる“龍”の格を持つ存在が、ここに蘇った。
・
『はは、全く。すばらしい力だな。そして、我が“死生の芽”の効果もしっかりと残っているようだ。それ、龍よ』
ブラームスが、杖を手にした腕を僅かに前へと振る。その仕草、そして杖の先端に宿る力の揺らぎに従うように、宙浮かぶ巨龍が、未だ四方より繋がれた河川との接続はそのまま、ずるりと空中を泳ぎ、彼の近くへと移動する。
「……まさか、完全に制御下に置いてるのか?」
呆然とレリエルが呟く。
「確かに、召還術では支神霊みたいな上位存在を従えることも可能だけど、あれは完全な制御ではなく、あくまで契約だ。操っている訳じゃない。でも……」
隠者の手が動く。それにあわせて、水の龍の身体も動く。爪が開き、顎が開き、身がうねる。その様は、まるでブラームスの手の内にある人形が如く。
『同調はほぼ完璧か。だが、まだ身体が完全では無いな。動きも少しばかり硬いが──それも直に慣れるか。目の前の遊び相手と戯れるうちにな』
言葉と共に、ブラームスの窪んだ両の眼が貴方達を捉えた。
「…………」
──これは、拙い。
それは判る。既に自分達の周囲を塞いでいた絶対領域の壁は消えている。
ならば逃げ出すべきだ。少なくとも、今この状況、この状態で戦うのは拙い。あの龍と魔術師に勝利する。その結末に至る道筋が微塵も見出せないこの状況では。
だが、
『どれ、サンサーラよ。昂壁の馬鹿共を食らいに行く前の余興だ。その力、断片とはいえここで見せてみよ』
逃げ出す間など与えぬとばかりに、無慈悲に告げられる声。
不死たる隠者の下。河の化身たる大龍は、地上から凄まじい勢いで水を吸い上げながら、二つの頭をゆっくりと擡げる。その顎の奥で、ぐるぐると濃縮された水の概念が渦を巻く!
battle
昇る双つの龍

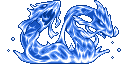
死ぬ。
仰向けに倒れ、指一本すら動かす力も残っていない貴方の脳裏を、その一言が過ぎる。
暗く閉じかけた視界の中、ぼやけたリトゥエが縋り、こちらに何か叫んでいるのが見えたが、一体何を言っているのか。聞こえている筈なのに、意味を成す言葉として聞き取れない。直ぐ傍には、懸命に立ち上がろうと身体を震わせるレリエルの姿が見えたが、しかし力尽きたか、がっくりと上体が折れて動かなくなる。
倒れた彼女を越えた向こうには、大小二つの影が見えた。小さな影が大きな影に向けて僅かに右手を掲げ、それに従い大きな影が高度を上げて、後ろへと控える。次いで、掲げた右の手に握られた杖の先端に色違いの四つの輝きが生まれ、徐々に力を増していく。
あの光が、自分の命を絶つ力。
それが理解できていても、しかしもう貴方の身体には避ける術も、防ぐ術も無い。
(……ここまでか)
声にならぬ呟き。それを残して、貴方は静かに両目を閉じる──間際。
ざくり、と。
右の耳元に、地を抉り刺さる何かの音が聞こえた。
一体何だ。殆ど途切れかけていた意識を繋ぎ止め、視線だけを横へと向ける。
そこには、煌々と輝く刀身。柄の衣装には見覚えがある。バッケンが使っていた、あの短剣だ。眩い光が、ぼやけていた貴方の五感を明瞭にする。
短剣からの輝きが貴方とリトゥエ、レリエルを包み込み、
「私が時間を稼ぐ! その間に、この事を昂壁の翼へ伝えてくれ! 灰色の隠者が死を越え、古の水龍を従えたと!」
バッケンの叫びが聞こえ、同時に短剣に宿る輝きが炸裂し、視界全てが白一色に埋め尽くされた。
・
地面に刺さった短剣二つが、音も無く崩れ去る。弾けた光が消えた頃には、既にその場に【NAME】の姿も、レリエルの姿も無かった。
『転移術か』
その様を見届け、ブラームスは小さく鼻を鳴らす。
『私があの妖精憑きを嬲るのも構わずに延々と何かを練っているから、一体どんな攻撃を仕掛けてくるのかと期待していれば、なんと。逃がす算段とはな』
期待外れ。そんな心情を隠すことなく、彼は残った一人、こちらを睨みながらゆっくりと立ち上がる男を眺める。
『それで。お前はどうするのか、バッケンよ』
問いに、バッケンは無言。ただ浮かぶブラームスへと向かい歩を進める。
『ほう』
呟き、血色の失せた老人の顔に、呆れの混じった表情が浮かんだ。
『この龍。そして私の技。それを前にして、足止めと?』
「ええ」
一言。そこに込められた意思に、ブラームスはふむと頷き、呆れの色を消す。
『力の差を読めぬわけではないだろうが──ま、良いだろう。ここ暫くロクな者と手合わせしていなくてな。お陰で、この間は腑抜けていた隙を突かれてこの様よ。もっとも、この姿となる“ついで”という意味もあったがな。昂壁の導師ともなれば、それなりには楽しませてくれるのだろう?』
「勿論。敵う、とまでは言いませんが、彼らが翼へ戻るまでの時間程度は稼いでみせましょう」
言って、立ち止まる。ブラームスとの距離はおよそ三か四メートル。術士同士の戦いという視点で見れば、その距離はもはや至近といってもいい。
『ならばその間、龍には存分に“肉”を吸ってもらうとするか』
ブラームスの視線がバッケンから離れ、傍らに浮かぶ巨龍に向けられる。釣られて龍を見上げれば、確かにその身体は先程よりも更に巨大になっている。龍に繋がった水の柱が脈動する度、龍の内に宿る力がどんどんと増し、そして凝縮されていく。
「────」
反射的に、バッケンは袖口から引き抜いた短剣を、浮かぶ龍へと投げつける。術式によるものか、短剣自体が持つ力によるものか。刀身から黄金色の光を弾かせながら、一直線に龍へと疾った。だが、
『おっと』
ブラームスの左手より差し出された巨大な本。独りでに開いた本の内側から光が弾け、短剣と龍の間に半透明の壁を生む。短剣に宿った輝きはその壁に突き刺さり、貫く際に失われて、ただの尖った金属の塊と化した短剣は、龍を形作る水の流れに容易く弾かれ、飲まれ、消えていった。
『手は出させんよ。お前はここで龍が力を整えるまで、私の暇つぶしに付き合ってもらおう。昂壁の懐かしい連中とやり合う前の肩慣らしよ』
「…………」
投擲の姿勢のまま、バッケンは鋭い舌打ちを零す。自分がブラームスと戦う間にも、龍は力を蓄えていく。これでは、本当に足止めの役しか果たせそうに無い。
『じっくりと遊んで、じっくりと殺してやろう。期待せよ、バッケン』
言葉と共に、彼の右手がこちらに向けられる。
ブラームスの持つ“四界の杖”。既に“贄”の力は殆ど失せているものの、僅かに残るその力でさえかなりのものだ。それより生み出される術式の直撃を受ければ、容易く致命傷となるだろう。
懐から新たな短剣を引き抜きながら、バッケンは薄く息を吐く。
果たして、どれだけ彼の動きを止められるだろうか。死力を尽くしたとて、自身があの“死を越えし者”を下せるとは思えない。
短剣を逆手に構え、バッケンは空に浮かぶ隠者を見上げる。
杖の先端に輝く四つの光。次の瞬間襲ってくるであろう術式の四連撃をどう捌くか。その事を考えながら、せめてと思考する。
(……レリエル君達が無事翼に辿り着くまで、持たせられると良いのですが)
降り注ぐ炎、氷、雷、そして闇の概念による連続術式。
迫る四つの力に、バッケンは光走らせた短剣を掲げ、迎撃の術式を組み上げる。
灰色の隠者 昂壁の簒奪者
──昂壁の簒奪者──
「以上、ですか」
「何と云いますか、恩を仇で返されるとは正にこの事ですね」
「だから云っていただろうが! あの時、奴を見逃すべきではなかったのだ! あの外法の男はいずれこの翼に、いや、五王朝に対して厄を齎すと!」
「……ふむ。恩ねぇ」
「あら。イネル師、何か異論でも?」
「いや。なにが『見逃すべきではなかった』のかとね。あの時の我々の状況をそう思い返せるのは流石としか云いようがない」
「何が言いたい!」
「見逃す、ではなく見逃してもらった、だろう? 声高に叫んだところで過去は変わらないという事だよ。五年前、君が云うところの臆病風に吹かれてニビト・ブラームスの追跡を真っ先に打ち切ったのはベリデート師ではなかったかな? 君も兄弟子の言い分に納得して矛を下げただろうに。君は自分と身内を責めて何が楽しいんだ?」
「あ、あの時は──大体、お前がそれを言えた義理か!? あの時塔の管理を務めていたのはお前の」
「……お、お二方! ここはひとまず押さえて……」
「あら、ゼーベンさん。ここは下手に口を挟まない方がよろしいのでは? あの事件の後、ニビト・ブラームスの追跡を任されていたのは貴方の研究室でしょう? なのにこれまで一つの痕跡も発見できずに。私達がここまで後手となった原因は貴方にあるといっても間違いではないのですよ?」
「それは、その……」
「予算も回さず、人も貸さずによくもそう吠えられるものだ。元々大した規模でもない彼の研究室に、更に圧力をかけ続けていたのは何処の誰かね? そもそも、てっきり君等は『彼を見つけられては拙い』と、そう考えていたものだと思っていたが?」
「き、貴様、何をいうか!?」
「イ、イネル師、あまり……」
「大体だ。当時にあの男、ニビト・ブラームスが研究していた“死生の法”。その研究の為の資金と資材を裏から回していたのが──」
「皆さん」
「…………」
「皆さん、静粛に。今は過去の事で言い争っている場合ではありません。私達はこれからの手を考えるために、こうして集まったのですから」
「確かに、カエンサル殿の言う通りではあるな。少し控えるとしよう」
「──しかし、だ。責任の所在は重要だとは思うがね。導師バッケンがヨファイオで奴を発見したとき、すぐさま翼に連絡を通してくれれば、このような状況にはならなかったのだが」
「本当にね。導師バッケンといい、レリエル上級研究員といい。大師の直弟子という立場が、そういった自惚れを招くのかは知りませんが」
「さてね。少なくとも、君等の態度を見る限りでは、自惚れが大師の直弟子にのみ生まれるものではない事は判るが」
「……口の減らない男」
「兎に角だ! 今回の件についてはバッケン、レリエルの行動に問題があったのはお前も反論できまい」
「幾らでも出来るが、これ以上話を引き伸ばすのはカエンサル殿に悪い。話を続けたまえよ」
「ッ……なら、そうさせて頂く。──今回、我々が考えた案はこうだ。“天落の星座”を使う」
「「…………」」
「大きく出たものだね。秘奥印章陣を使うなど、大師がこの場に居られたならば一体なんと云われるか」
「仕方がないでしょう? 龍種が相手。更に、あの男には二つの魔導器がある。ともなれば、手は限られます。国から対重討伐指定存在専門の護法を借り受ければ話はまた変わるでしょうけれど、たとえ縁が切れたとしても、あの男が一時とはいえこの翼に席を置いていたのは事実。他の組織に解決を任せるようでは示しがつかないわ」
「これ以上無様な姿を見せては、今後の翼の運営にも差し支えが出る。今回の件は我々の力で片をつけねばならない。たとえ秘奥を使ったとしてもな。この点に関してはイネル師も異論はあるまい?」
「残念ながらね。ついでに言うなら先程責任がどうこうという話をしたのはアレかね。僕等に印章陣を敷く時間を稼げと?」
「ふふ、察しが良くて助かるわ。印章陣の記述式開封、展開、記述は私達の研究室に属する人員で行います。イネル師、ゼーベン師、クンティール師は指導している下の研究室からも人を募って、ニビト・ブラームスの足止めをお願いします」
「セラエ師、そ、それは余りにも! ……カエンサル殿、このような配置は……」
「そうですね。私の眼で見た限りでは、秘奥印章陣の使用も、その配置も問題はないように思えます」
「カエンサル殿!?」
「ゼーベン君、落ち着きたまえよ。確かに、実働、実戦の経験がある人材となれば、僕等カドモル派の人間が前面に出ない訳にはいかないんだ。残念ながらね」
「で、ですがっ」
「そう謙遜せずとも良いだろう。ゼーベン師の召喚術式は私も一目置いている。きっと君の教え子ならばあの龍の動きを止めることも造作ない。なんでも、一人際立った才を持つ術士が君の研究室に入ったんだって?」
「それとこれとは話が違う! 大師が組み上げた秘奥、その式を貴方達だけが独占するつもりですか!?」
「あら、本音がでましたわね」
「ッ、く」
「……ふん。こういった機会でもなければ、直弟子ではない我々は触れる事すらままならぬ代物だ。お前達があの龍とやりあう間に、じっくりと調べさせて頂く」
「全く。このような事態となっても、頭にあるのは大師が遺されし秘術と己が派閥の利権かね。度し難い」
「お前が言えた──」
「勿論、僕も込みでの意見だよ。まぁ、僕等らしいといえば僕等らしい話だけどね。カエンサル殿も、大師の秘奥にご興味が?」
「まさか。皆様もご存知の通り、私は大師の遺された遺産にも、翼の争いにも興味はありません。ただの外からの助言者。故のこの立場です。今回の件は、そうですね。天秤の調整と考えていただければ」
「天秤ねぇ……? 正直、最近の僕等はそちらの方々に散々虐げられてる気がするのだけれど、客観的に見るとそうでもないのか?」
「あら。人聞きの悪い」
「それだけ、カドモル・ウォン・レインという名は強い力を持つ、という事と考えていただければ」
「厄介な話だね」
「それよりも、ニビト・ブラームスの件について、話を進めます。彼の龍に対抗するため、秘奥印章陣を使う。ここまでは宜しいですか、皆様方?」
「「…………」」
「結構です。では、細かい詰めに入りましょう。エンペール嬢、四から十一までの資料をこちらへ」
「──────」
「────」
「──」
・
「ただいま、っと」
昂壁の翼の上級研究員に与えられる一室。そこで無言のまま部屋の主を待っていた貴方達は、開いたドアを潜り聞こえた声に顔を上げる。
「レリエル! ね、どうだったの、ていうか、どうなりそうなの!?」
一番に飛び出したのはリトゥエだ。小さな妖精は貴方の肩上から飛び上がると、忙しなくレリエルの周りをぐるぐると回り始める。
「とと、リトゥエちゃん落ち着いて」
「いや、落ち着いてる場合じゃないでしょ!? あの龍、私達がこっちに移動してる間もどんどん気配が増してて、今じゃ凄い事になってきてるよ!? 私達──妖精の間でも騒ぎになってきてるし、それにこっちに、ルアムザの方に段々近づいてきてるし!」
「らしいね。翼も遠見の術式でしっかり監視してて、その辺りの事も聞いた。姿を全く隠しもせずに、巨大極まりない水の龍が空を泳ぐ様はなかなか壮観だって」
何を暢気な、と貴方は呆れ混じりに呟く。あれ程の存在が街を襲うとなれば、たとえ軍が出張ろうと大なり小なり被害は免れないだろう。壮観だとか云っている場合でもなかろうに。
そんな苦言に、レリエルはひょいと肩を竦める。
「別に暢気になってるつもりはないけれどね。一応、翼はもう対応に動いてるし。うちの爺さん方はどうも、あの龍を真正面から叩き潰すつもりらしい」
「叩き潰すって……そんなの、龍種相手に人間がマトモにやりあったらどれだけ被害がでるかわかんないよ!? それに、あのお爺さんが持ってる魔導器もあるし、下手に近づくと、」
「マトモにはやるつもりはないだろうさ。ていうか、上の方々はどうも『もののついで』にお相手するつもりのようだよ」
「はぁ!? 何それどういう事?」
「それは──」
「レリエルサマ?」
と、そこで暢気な調子で口を挟んだのはカミオだ。
「なにやり剣呑な空気。何か問題事でも起こりますれば?」
相変わらずの珍妙な口調で訊ねてくる青年。表情には焦りや緊迫の色など無く、平時通りののんびりとした気配。そういえば、部屋に戻ってから誰も彼に事情を説明していなかったことを今更ながらに思い出す。
「ち、ちょっと。カミオ、貴方まだ気づいてないの? 貴方なら感じるでしょ、ほら、南の方に何か全然気配隠してないバカでかい概念判んない!?」
「はぁ」
リトゥエは息を巻くが、カミオの反応は鈍い。
「ま、状況整理も兼ねて始めから話すか。カミオが理解してくれるかはあんまり期待してないけどね」
・
「とまぁ、こんな処だな」
今までの流れ。貴方が体験した幾つかの事件と、ヨファイオでの一幕。そして昂壁の判断と、対応策。レリエルは淡々と話し終える。レリエルの予想通り、カミオの反応は説明が終わった後も変わらず鈍いままであったが。
「……にしても印章陣? そんなので、あの龍を何とかできるの?」
小さな顎に手をやりつつ、リトゥエが怪訝な声を出す。
あの龍とニビト・ブラームス。それらに対抗するために昂壁の翼が持ち出したのは、印章陣による大規模魔術だという。
昂壁はブラームスの目標がここ昂壁の翼であることを理解しており、その迎撃のための大規模印章陣の準備を既に始めているのだという。
「確かに、人間の使う実記述したでっかい印章術式が強力だってのは知ってるけどさ、でも、相手はあの龍だよ? ヨファイオの河川全てを根っこにした化け物相手に、印章陣一つで何とかなるもの?」
「少なくとも、上の爺さん方はそう考えてるみたいだね。まぁ、話によれば“天落の星座”を引っ張り出すらしいから、それ故の自信ってとこだろうけど」
(“天落の星座”……?)
聞いた事も無い単語に、貴方は素直に首を捻る。リトゥエなら知っているかとそちらに視線を投げるが、彼女も貴方と同様らしく、訝しげに眉を寄せている。
「何よそれ。なんかの暗号?」
「大師──カドモル・ウォン・レインの遺産の一つ。昂壁の翼の虎の子だよ。重討伐指定存在や攻城兵器向けに軍に流されてる印章陣“天落の星々”の原型。“天落の星々”は“天落の星座”の規模をとことん縮小して簡略化したものだって話ね」
レリエル曰く、その“天落の星々”と呼ばれる印章陣でも、並の重討伐指定存在ならば屠ることも可能なのだという。そして今回持ち出すのは、それの本物。威力の方も、当然数段上と予想できる。
「成程ね。……ていうか、そんな強烈な印章陣があるなんて聞いたこと無いけど」
「そりゃね。翼にしてみれば大師が封じた禁忌の秘奥って代物だし。お陰で上の爺さん達は大張り切りだよ。大義名分が出来たってね」
大義名分とはつまり、その禁忌の印章陣を表立って使う口実ができた、という事か。
このような緊急時に、と渋い顔で呟いた貴方に、レリエルは苦笑を浮かべる。
「正確には『秘奥印章陣を己が目で見て、記述する事ができる口実』だけどね。あの印章陣は普段は何十もの封がされていて、普段なら調べることすら叶わない代物でね。大師が凝らした無数の秘術を内に持つ特級品。だから、大師から直接教えを請うことが出来なかった連中にしてみれば、正に宝の山というべきものなのよ」
「呆れた話ねぇ……。それじゃ、あれ? レリエルはこれからすぐその印章陣の構築作業に加わるのかな」
確かレリエルは印章関係が専門の筈だ。ならば己の本領を存分に発揮できる流れになった、という事か。
リトゥエの呟きにそう納得しかけた貴方だったが、しかしレリエルは浮かべていた苦笑を更に強くして首を横に振った。
「いや、今回のあたしは貧乏くじだよ。ブラームス氏が絡んでいる判った時点で直ぐに報告しなかった件についてあれこれと言われてね。ブラームス氏とあの龍がここへ来るまでの時間稼ぎに回された」
「じ、時間稼ぎって、どうするのよ!」
「昂壁の翼の中でもそれなりに実戦経験のある者と、あと長距離、遠隔術式や召喚術が得意な者を集めて、極力人的被害は出さない形でニビト・ブラームスと龍を牽制する、って事らしいね」
「……うへぇ。てか、大丈夫なのそれ」
「どうだかねぇ。あたしは少々責任がって話だから、前の方立たされちゃうかも。まぁ、取り敢えずは──」
そこでレリエルは一度言葉を切り、表情を改める。
緩みの無い、真剣な顔と視線。それを貴方とリトゥエに向けて、そしてこう告げた。
「【NAME】君、それにリトゥエちゃん。流石にこの先まで君達に付き合ってくれってのは言えない。だから、一度ここで別れようか」
「…………」
貴方とリトゥエの視線が一瞬だけ交差する。
どちらが問うか。その押し付け合いは貴方に軍配が上がり、リトゥエが小さな溜息と共に口を開く。
「本気でいってるの、それ?」
「ああ」
レリエルは短く頷いた。
「一度戦って、あの龍の力は知ってるわけだしね。この先は個人ではなく、昂壁の翼がニビト・ブラームスを相手にする事になる。だから君等が危険を負う必要はもう無いといってもいい。そして今からあたしが動くのは、あくまで昂壁の翼の一員として、だ。そして君は昂壁の翼の一員ではない。云いたい事、判るかな」
──判る。彼女はつまり、こう云いたいのだ。
もう状況は個人のレベルを超えて、一介の冒険者である【NAME】が居ても居なくても、状況に大した変化は無い域にまで大きくなってしまっている。
だから、居ても居なくても同じだというなら、無駄なリスクを負って自分に付き合う必要はないと。そう云う事だろう。
簡単に云えば、切りのいい今、こちらが手を引きやすいように水を向けてくれたという事。
「…………」
「で、どうかな? 【NAME】君」
改めて問われ、貴方はじっとこちらを見るレリエルに口を開く。
──どうするも何も、
今更問う事でもないだろう。最後まで見届ける気がないのならば、もっと前の段階でとっくに手を引いている。
貴方が肩を竦めながら努めて軽くそう言えば、レリエルは複雑な笑みを浮かべて、助かると頷いた。
表情の奥には、僅かな安堵がある。多少は頼りにしてくれていると考えていいのか、それとも巻き添えは多い方がいいということなのか。思ったままに口に出せば、
「さぁ、どっちかね」
と、はぐらかす様に笑う。そんな様子に、傍で見ていたリトゥエは呆れたような吐息。
「そこは素直に頼りしてるっていっときゃいいのに」
「ならそういう事にしておこうか」
改めて皆で笑い、そしてリトゥエが小さく咳払い。
「で、ええと。レリエルに付き合うって形なら、私達はあのお爺ちゃんの足止めを手伝うって事でいいの?」
「そうなるけど、あたし達だけで足止めする訳じゃないから、その辺はね。さっきも言ったけど、翼で戦闘経験のある術士を集めて編成した集まりに、あたし達も混ざるって形になる」
貴方はふむと唸る。昂壁の翼の術士。戦いの最中、脇を任せるに足る者達なのだろうか?
「少なくとも歴戦の勇士って訳じゃないね。といっても、実際脇に居るのは使役する亜獣とか魔導生物とかだと思うが。術士は前にはでやしない。のんびり安全圏から高みの見物ってところでしょ。下手な術式を使ったところで、あれだけの概念存在相手だと牽制にもなりはしないし」
「なんか頼りになりそうに聞こえないんだけど」
「実際の所はあたしも判らないがね。使役獣の働きは多分あたし達はすぐ傍で見ることになるから、戦ってみれば良く判るんじゃない? 私達、多分前面に出されるから」
「……そうなの?」
「幾らなんでも、誰も接近せずに牽制するってのは難しいからね。あたしは罰も込みだから、多分そっちに回されると思う。──で、【NAME】君達は準備、大丈夫? 実はもう召集始まってて、今すぐにでも下に降りないとダメなんだけど」
ずいぶんと急だと一瞬思ったが、その思いつき自体が愚かなものだったと直ぐに否定した。
実際、猶予はないのだ。貴方の頷きに、レリエルは立ち上がると、カミオに視線を送る。
「カミオ。本当は余り人には見せたくないんだけど、背に腹は変えられない。力を貸してもらう」
「喜びまして。あとカミオではなく──」
「貸してもらう、カミちん」
カミオは返答はせず、ただ笑みのまま深く一礼した。
・
その男は、ギンナム・ラシャ・オルシスと名乗った。
翼から選出されたニビト・ブラームスを足止めする役を担った者達は、大きく三つの集団に分けられるらしい。それはレリエル曰く、連なる研究室の違いという話であるらしいのだが、その大きな三つとは別に、一つの小さな集団があった。他の者達とは、明らかに毛色の違う気配を纏った彼等。装束は学士然としたものではなく、ある者は旅慣れたものであり、ある者は戦い慣れた衣服。帯びる装備も同調誘導器のみではなく、剣や短槍、弓や斧を持つ者までいた。この小さな集団こそが、レリエルとそして貴方が属することになる集団だ。他の三集団とは異なり、実際にニビト・ブラームスと水龍の眼前に身を置き、戦う役目を担った者達。その長が、ギンナムという名の男だった。
中年から壮年の境。小男と云ってもいい彼が身に纏うモノは、先程挙げたような動きやすいものではなく、そこいらの術士にありがちな長衣にトネリコの長杖。だが、その動きや身体のこなしは隙が無く、昂壁の翼の敷地内、各塔の間に挟まれた中庭に立つ姿は、その小さな体躯に似合わぬ不思議な存在感があった。
「いやはや。レリエルのお嬢さんがこちらに加わってくれるのは驚きでした。貴女の噂は聞いていますよ。そちらの冒険者の方もね。色々とご活躍なされているようで」
褪せた前髪の奥から、細い眼がレリエルと貴方を順に見る。それはこちらが持つ力がどれ程のものかを測ろうとする、冷静で、硬質な視線だ。言葉遣いは多少慇懃ではあったが、その眼からは友好的な色は無い。ならば、敵意を示す色があるのかといえば、それも無い。ただ、意思を介さず自分達を見定めようとするだけの視線に、貴方は僅かにたじろぐ。
対し、レリエルの方はといえば、そんな男の視線を意に介した風も無く。逆に何処か探るような眼をギンナムに向けて、口を開く。
「あたしとしては、貴方が『前衛』の長だという方が余程驚きなんだけどね、オルシス上級研究員殿。貴方、ゼーベン師の研究室に所属してる術士でしょう? それも司位の使い手──召喚司って聞いてる。それなのに、どうして『前衛』の長なんてものに収まっているのかね」
翼内での立場はほぼ対等であるのか。レリエルはいつも貴方と話しているものと同じ口調で彼に問う。
召喚士は元々前に出る者達ではない。攻撃を受けない後方から使役獣を扱い、敵を倒す。それが彼等の流儀だ。今回の相手である龍は安全圏と予想されている位置が目視外とされているため、他の三集団は数百メートルから数キロという距離をとって布陣し、そこから使役獣や多人数による儀式技法で超長距離攻撃を行うとされている。当然、ニビト・ブラームスと直接対峙する役を担う小集団の中には、彼のような召喚士らしき者は見当たらない。術士らしき者達も居るには居るが、その装備を見る限り生粋の術士ではなく、技法と術式を併用する戦士に近いのだろう。だというのに、その長となる者が召喚士であるという。レリエルの疑問も尤もだ。
「いやはや。答えは……そうですね。単純に云えば好奇心、ですかね? 他存在を招き、縛り、操る。その技を突き詰め、極めるのが召喚士というものです。方法は我々の式とは異なりますが、しかし龍種を支配下に置く程の御技。身近で見たいと考えるのは自然な事かと思いますがね」
「リスクとつりあっていないような気がするがね。他の召喚士の方々は高みの見物のようだけれど?」
「その辺りはまぁ、価値観の相違、いや、優先順位の違い、という事で納得していただければ。別段長になどなるつもりはなかったのですが、『前衛』に回った人間の中で一番立場が高いのがワタクシと貴女で、二者択一だったようですね。……と言いますか、あまり世間話をしている場合でもないのですが、話を進めて宜しいかな?」
「ああ。すまない、続けてくれ」
レリエルの言葉に頷き、ギンナムは淡々と話し出す。内容は現在彼が得ているニビト・ブラームスの情報。それは先程レリエルが説明してくれた事と被る内容もあったが、幾つか新しい情報も存在した。
その中のひとつが、自分達を逃がすためにヨファイオに残った昂壁の翼の導師、バッケンについての情報だった。
結論からいえば、彼は死亡したという。
龍やニビト・ブラームスが残した痕跡を探るためにヨファイオへと至急向かった軍と翼の調査隊が、彼の亡骸を回収したらしい。
(──死んだ、のか)
呆気のない。実感が湧かない。そんな意味の言葉が、最後に見た彼の姿と共に、幾つも脳裏を過ぎる。
思わず黙り込む貴方達であったが、ギンナムはその空気を払拭しようとしたのか、それとも全く気にするつもりもないのか。周囲の者達に声をかけて先に昂壁の翼の正門まで移動するよう指示すると、改めてこちらへと視線を寄越す。
「時間もありませんので、以後の──細かい動き、合わせについては移動しながら話しましょう。早々に出ますが、宜しいですかな?」
「ん、……ああ」
気を取り直すための数泊の間の後、レリエルが僅かに伏せていた顔を上げた。
「あたしは構わないが……【NAME】君、君の方は本当に大丈夫か?」
そう、先程は訊いてきた事をもう一度確かめてくる。ギンナムも貴方に眼を向け、補いの言葉を続けた。
「恐らく、戦いは長丁場になると思います。貴方は昂壁の翼の人間ではありませんから、急ぎの御用があるのでしたら、それを済ませていただいた後で合流して頂いても構いません。勿論、悠長にしている時間はありませんがね」
そこまで云われると、確かに一度彼等と離れ、あれこれと準備を整えたほうが良い気がしてきた。
彼等の言に甘える事にして、一度ルアムザへと戻る。そう告げた貴方に、ギンナムは表情を変えず一つ頷き。
「現在、ニビト・ブラームスはトホルドとルアムザを繋ぐウスタールの大街道に沿ってこちらへと移動してきています。道は現在軍が封鎖作業に入っているようですが、貴方のことは彼等に話をつけておきましょう。……そちらの妖精さん?」
「ひっ!? は、はい!?」
突然、声と視線を向けられて、貴方の肩上で隠匿結界を張り、息を潜めるようにじっとしていたリトゥエが、びくぅと文字通りに飛び上がり、悲鳴じみた声を上げた。
耳元での突然の叫びに顔を顰める貴方と、青い顔のまま背筋を伸ばして自分を見る妖精に、ギンナムは少々困ったような表情。
「……いやはや、そう驚かれても困るのですが。まさかワタクシ達の眼から本当に逃れられると思っていたわけでもないでしょう?」
「う、あ、うん。まぁ、そうだけど……でもいきなり話振られたから、その」
喋っていいのか悪いのか。それが上手く判断できていないのか、リトゥエはつっかえつっかえの答えを返す。
「驚かせたことは謝りますがね。それで、ワタクシが何を云いたいかというと、軍の方々に『妖精を連れた冒険者が現れたら、ワタクシ達の隊にまで通すように』と伝えておきます。ですので」
「ん。合流するときは、私は身を隠さずにしろってことね」
「そういう事です。では、レリエルのお嬢さん、参りましょう。……と、そちらの方は」
ギンナムは貴方とレリエルの後ろに立つ人影に声を掛ける。
「レリエルのお嬢さんの連れ合いですかね。それとも、冒険者殿の?」
「あたしの連れだ。共に行く。それ以上の詮索はご遠慮願う」
「ご遠慮願いまするば」
レリエルの言葉に合わせて、カミオが声を挙げる。彼を見るギンナムの視線が、一瞬だけ酷く鋭く輝くが、しかしそれは文字通りの一瞬。直ぐにその気配は消えて、薄い笑みがそれを蔽うように浮かんだ。
「いやはや、何とも興味深い方に見えますが──まぁ、よろしいでしょう。レリエルのお嬢さんの云うとおり、今は詮索するべき時でもない。では、行きましょう」
ギンナムは背を向けて歩き出し、レリエルとカミオがその後に続く。
「……にしても、何だかホントに大事になってきたねぇ」
しみじみとした調子で呟くリトゥエに、貴方は深々と息を吐きつつ頷く。
取り敢えず、折角得た時間だ。
一度街へと戻り、十分に戦いの準備を整えてからレリエル達と合流することにしよう。
・
──昂壁の翼。
あの五つの塔により構成される王朝の知識が集う地を離れて、既に五年もの月日が流れていた。
高き空の上。足元に莫大な量の水でもって身を形成する龍を従え、死してなお生きるというカタチを持ったその老人は一人、朧な記憶に身を委ねる。
いずれ、と想定はしていだ。だが、あの時。あの場面で、この身となるのは考えていなかった。
故に、“死を越えし者”と成った彼の身には、老人自身が前もって考えていた以上の問題を抱えていた。
そのひとつが、記憶だ。
『まさか、ここまで欠けるとはな』
気づいたのは、ヨファイオで“死ぬ以前”に続けていた作業を再開したとき。己の記憶に、思い出せぬ部分がぽつりぽつりと存在してることに気づいた。
ある物事について。ある出来事について。それらが丸ごと思い出せなくなる訳ではない。ただ、それらを構成する要素に、不自然な“欠け”が生まれるのだ。まるで己を記した本に無数の虫が食らいつき、決して塞げぬ穴を開けていくように。少しずつ、だが確実に、知識と、そして記憶が欠け始めていた。
最も愕然としたのは、五年前。己を貶めた当時の師達。その姿と名前を思い出そうとして、すっぽりとそれが抜け落ちている事に気づいた時だ。
彼等に対する、怨恨。
その念は変わらず、この“芽”が張り巡らされた胸に深く強く、燃え盛っているというのに。
『恨む対象……更には、何故という動機となる部分すらも、失われるか』
欠ける記憶。その選択に、己の意思は全く介しないらしい。少しでも意思が関わりを持つというなら、五年前の事件に関する記憶は、決して失われることはなかっただろう。或いは逆に、思い入れの強い記憶ほど、速く失われていったのか。
どちらにせよ。気づいた時には、既に五年前の事件の記憶は半ば薄れ、朧な印象のみが残る形骸と成り果てていた。
記憶が欠けていく事に気づいたとき、すぐさま手は打った。お陰でその速度は緩まったが、しかし完全に止められてはおらず、他にも問題は数多い。
“死を越えし者”と。
ヨファイオで対峙した冒険者が連れていた妖精は、自分をそう呼んだ事を思い出す。青を越えて黒にも至りかけた、皺の濃い顔に苦い笑みが浮かぶ。
たとえ死を越えられたとしても、ただそれだけでは何も成す事はできない。死を越え、更には生きていた頃の全てを手に入れ、そしてその先へと進む事の出来る身。それを得てこそ、文字通りの“死を越えし者”と成りうる。
『ままならぬよな』
失われたものはある。だが、代わりに力は得た。文字通り生者では耐え切れぬ程の力を。
そして己が身を焦がすのは怨嗟の炎。既にその根となった筈の出来事もまともに思い出せぬというのに、只炎だけが燃え盛り、思い出せぬが故にその火の勢いを抑える術を見い出せない。
この炎が失せる時、それは即ち。
『──奪い、壊した時のみか。あの塔を』
呟き、手にした魔導器を振る。
足元の龍──あれから凄まじい量の水を吸い上げ、既に数百メートルにも及ぶかという規模にまで膨れ上がった龍が、老人の仕草に従い、動き出す。
その時、龍と同期した意識に大きなズレを感じ、老人は小さく舌打ちを零す。
ヨファイオを発つ前。戯れ交じりに相対した昂壁の翼の導師。あの男が最後に放った短剣の影響だ。
こちらの隙を窺い、そして己が身を犠牲にして、あの男は一本の短剣を龍に投げ込んだ。所詮は短剣一本とそれを見逃したのだが、結果がこの同期の不調だ。
導師如きと甘く見た。幾ら力を得たとしても、それに胡坐をかけば容易く足元を掬われる。
『全く。理解はしていても、なかなか直るものではない』
自嘲の呟きと共に、老人は北西を眺める。
遠見の式などは使わない。遠く地平の向こう。見えぬ空と大地の境界の先に、己が目指す場所がある。
『さて……。我が力、どこまで届くか見極めさせてもらうぞ、昂壁の翼よ』
灰色の隠者 星を待つ道程
──グローエス領 ウスタール大街道──
「あれが……」
支都ルアムザから古き街トホルドへと続くウスタール大街道上。貴方は空を見上げ、小さく呟く。
距離にしておよそ二キロ。薄く雲が掛かる青空の中を、より濃い青の色がゆっくりと泳いでいた。
「ええ、双濫龍サンサーラです。いはやは、あそこまで強大な竜は、ワタクシも初めて見ます。流石龍種。最も芯竜に近い亜竜と呼ばれるだけはありますね」
応えたのはギンナム。貴方が訪れた時、彼は一時的に戦列を離れて休息を取っている処で、ついでとばかりに状況の解説を買って出てくれた。
「全くだ。ヨファイオで出くわした時とは比べ物にならないほど強力になっていた。あたしも何度か牽制に出向いたけど、下手に正面に出ると、少しミスするだけで即死だな、あれは」
貴方の横を歩くレリエルが、手にした符のようなものにあれこれと何事かを書き記しながら、溜息混じりにそう零す。
「あれはなかなかで手強い相手なございましてでしたなぁ」
その後ろから続く声は、どこかのんびりとしたもの。カミオである。どうやら彼もレリエルについてあの龍と戦ったらしい。口調自体は暢気なものだが、話している内容自体は、龍の凄さを語るもの。彼のような何処か外れた者達でも、あの龍の評価はかなりのものであるらしい。
「……はてさて、ここまでの話はご理解頂けましたかな、冒険者殿」
少し先、先導する形で歩いていたギンナムが、目だけを貴方のほうへと向ける。
──大まかな作戦は、翼でギンナムやレリエルとの話に出ていた通り。
本陣となる昂壁の翼の術士団がはるか後方、ルアムザの近郊付近に陣取り、“天落の星座”の印章陣を記述、起動準備中。彼等の準備が整うまで、残りの者達が龍を牽制し、時間を稼ぐ。単純なものだ。
細かいのは、龍を牽制する集団内での割り振りである。
龍と対する集団は分けて二つの系統、実質的には四つの集団が存在する。
ギンナムやレリエル、そして貴方が割り振られたのは、その集団の中でも『前衛』とされる集まり。前衛は文字通り、前に出て戦う者。あの数キロという距離を開けても、容易くその姿を確認できる大龍に近接し、戦う役を担った集団が一つ。
残る三つは『後衛』の集まり。前で云わば戦士として戦う力を持たない者達──翼で純粋培養された戦闘経験のない術士や、主に後方超長距離からの支援技術を持つ者がそこに収まっていると、建前の上ではそうなっている。後衛はそれぞれ連なる研究室によって分かれており、龍の進行方向から正面、右正面、左正面、という位置に、一定の距離を維持しつつ展開しているらしい。途中、大街道を移動している際に出くわした集団は、恐らくこの内の正面に展開されている一団なのだろう。
後衛の集団が何をするかといえば、主に使役獣を使っての前衛の補助と、そして複数人によって編み上げる大規模儀式魔術の行使である。印章陣を併用した儀式魔術は極めて高い威力を誇るが、しかし着弾位置すらも陣の中に組み込んで構築する必要がある。故に今回の龍のような常に移動する対象に向けて行使するのは不得手としており、それを補うには前衛による龍の誘導が必要なのだと。
「研究室という系統で分けただけに、三つの集団はあまり密な連携が取れているとは云いがたくてね。今までの感じから見ると、どうもそれぞれの集団が好き勝手に使う魔術を決めて、好きな位置に打ち込んでるぽいね」
「何それ。効率悪すぎない? ってことは、同じ場所に同じ魔術が三つ被るとかある訳?」
うげー、とリトゥエは渋い顔。しかし、召喚司は口元だけ笑みを作って首を振る。
「いや、同地点に複数の儀式魔術が被ると、どちらの魔術も発動自体が無効化される可能性がありますので、彼等も着弾位置と効果範囲だけはある程度他の集団の式を見つつ、被らないように調整しているようですな」
「多分、自分達が組んだ魔術が発動しないのだけは耐えられないって事だろうね」
「いや、遊びじゃないんだからさ……。魔術士ってみんなこうなの?」
「基本的には翼の外なんて殆ど出ない連中ばかりだしね。実験気分が抜け切れてないのさ。自分の術がどれだけ綺麗に動くか見たいってのは重要な事なんだろう」
「といっても、龍の進行方向に上手く儀式魔術を置けなかった場合は結局無駄になりますから、後衛の方々もそれはそれで必死のようですな。先程から、あちらの方々の指示の声が煩くて敵いませんよ」
レリエルは視線は手元にある符に向けたまま、まるで他人事といった調子で答え、ギンナムは己の耳についた飾りを弄りながら顔を顰める。よくよく耳を澄ませば、その飾りからは何やら人の話し声が聞こえてくる。どうやら、あの飾りは他の集団からの通信を受ける為の道具らしい。
「とまぁ、そんな感じで、ワタクシ達のやる事は、龍の足止めと、ニビト・ブラームスの牽制、あと儀式魔術の効果範囲への龍の誘導、といったところです。それで冒険者殿には、主に足止めと誘導──つまり、龍との対峙を主に行ってもらうつもりです」
「…………」
その言葉に、貴方は思わず眉を寄せる。あの、これだけの距離があると言うのに肉眼で確認できる程の馬鹿でかい龍を相手にするくらいなら、まだあの老人の牽制役の方がはるかにマシではなかろうか。
「それ、なんか【NAME】が貧乏くじ引いてない?」
じっとりと視線を細めてギンナムを見るリトゥエだが、しかしそれに応えたのはギンナムではなく、
「ああ、それはそうでもないよ。あたしも、【NAME】君はサンサーラ相手が良いと思う」
まだ何やら符にあれこれ文字を書いているレリエルだ。
「というか、【NAME】君ではブラームス氏の相手が難しいんだ。君、専門の長距離射程技法とか、高水準の対術式技法とか使えないだろう? 冒険者だし、ギルドで教えられる役割に沿った汎用的な技法しか習得していないだろうし。所謂倒し倒される戦いでなくて、時間稼ぎや牽制を目的とするなら、力よりも技に優れた連中を割り当てたほうが安全で、確実なんだ」
「いやはや。適材適所、といっていいのかはワタクシにも判りませんが、割り当てとしてはそう外したモノではないでしょう。納得いただけますか?」
ここで納得できないといった処で状況が変わる訳でもないだろう。貴方は吐息と共に頷き、改めて空に浮かぶ龍を見上げる。
見れば、龍の頭部付近で、何か小さな影が動き、更には時折光のようなものが走っているのに気づいた。
(……何だ?)
一瞬疑問に思い、しかし直ぐに自己解決する。あの小さな影が自分達の仲間、所謂『前衛』の者達なのだろう。
「『本陣』からの報告を聞く限りですと、“天落の星座”の準備を整えるには、大体ですが後十回前後ローテーションを繰り返す必要があるでしょうかね」
当然ではあるが、前衛の者達は常に全員が龍と、そしてニビト・ブラームスと対峙し続けている訳ではない。前衛を二手に分けて、休息と攻撃を繰り返している。1ローテーションが一時間として、後十時間。太陽の位置から考えて、丁度日が暮れる辺りだろう。
「因みに、今までの龍の移動速度から計算すると、あと五度程龍の前進を阻止しないと、“天落の星座”準備終了前に、龍がその印章陣構築地点に辿り着く事になります。こうなってしまえば何もかもが御終いですね」
「……なんで龍の進行路上で用意してんのよそんなもん」
「ああ、それあたしも気になってた。オルシス氏はその辺りの話は聞いているのか?」
問いに、ギンナムは小さく肩を竦める。
「さて。上の方々が考えることはワタクシには何とも。ルアムザ近郊という位置から考えて、誰に対してかは知りませんが、何らかの威力効果を狙ったとも考えられますが、この辺りの事を我々が考えたところで今更どうなるものでもないでしょう」
「そりゃそうだけどさ……」
「まぁ、やれるだけやるのみですな。そろそろワタクシ達の休息時間も終わりですので、冒険者殿もワタクシ達と同じタイミングで動いてもらうことにしましょう。正確には貴方は翼の人間ではありませんから、そこからの行動自体は自由にして頂いて結構です。自己判断で動いてください」
「ああ、それで思い出したが」
と、そこで漸くレリエルが手元から顔を上げる。
「【NAME】君、流石に単独で龍とやりあうのはキツいだろう。だから……そうだな、あたしかカミオが君に付こう。君は自分と一緒に動く者を誰か一人を選んでくれ」
──星を待つ道程──
「よし、出来た。【NAME】君、これを持って行け」
差し出されたのは、先程からレリエルが何やら書き込み続けていた符だ。
「大跳躍の術式が仕込んである。この術式を駆動した状態で飛べば、力の加減次第だが最高で数十メートルは跳べる」
何でこんなものを。
(……いや)
そうか、と貴方は考え直す。
自分は龍を相手にする、という事になっているが、その対象は現在上空を遊泳中。それもかなりの高度だ。こういった策無しでは、武器を届かせることもままならぬ、という事なのだろう。
「上手く龍の身体を足場に使ったりすれば、地面に足を着かずとも戦い続けることも出来る。本当なら常時飛行が可能な道具でも貸し出せれば良かったんだが」
「いやはや、その辺りの品は翼所属の者達が使ってましてね。冒険者殿にまで回す余裕が無かった。申し訳ないが、その符で何とか立ち回って頂きたい」
こういった品があるだけでもマシである。貴方は礼と共にレリエルから符を受け取る。
「一応ワタクシの声を受信するための術式も仕込んでありますので、指示の声が聞こえたならばそれに従って欲しい。先程話した儀式魔術の件もありますのでね。──では、いきましょうか。サンサーラもかなり近づいてきたようですし」
ギンナムの視線を追うように貴方も遠くに見える龍を見上げる。確かに彼の言う通り、その濃い水色の巨体は先程よりもかなり近づいてきている。距離にしておよそ、一キロか、五百メートルか、その辺りか。
「冒険者殿は今回は実質初めての手合わせとなるでしょう。符の使い勝手も確かめる意味もありますし、あまり無理はせぬよう──そうですね、龍の側面から、あまり気を向けられぬように攻撃して、具合を掴むと良いでしょうな。ワタクシはニビト殿の相手に出向きますが、一応貴方の動きにも気を配っておきます」
告げて、小男は手にした杖を掲げて印章を描き、召喚の宣言を高らかに告げる。円状の印章の中から現れたのは翼持つ四脚の大獣。彼はその背に飛び乗ると、跨るではなくその背に立ち、
「では、お先に失礼」
そんな言葉を残して、空高く飛び去っていった。
「……じゃあ、あたし達も行くか」
遠ざかっていく影を見送った後、レリエルが己の長銃の調子を確かめるように一度構えてみせる。
「とりあえず、ペアは先刻決めた組み合わせで。一組が右、もう一組が左側面から行くよ」
・
サンサーラの側面へと回り込みつつ、貴方は懐に仕舞われた大跳躍の符を握り締める。
符に込められた術式が駆動し、同時に貴方の両脚に濃い力が溜まっていく。更に、自分の身体全体にも僅かな理粒子が纏わりつくような感触。簡易重力制御か、風圧無効か、その辺りの能力だろう。この様子なら、脚にたまっていく力を加減無く発動しても、そう酷いことにはなるまい。
「……さて」
移動中にギンナム、そして他の者達から聞いた情報を思い出す。
狙うは龍の横、なるべく頭部に近い位置だ。龍の気を引く事に成功すれば龍の進行方向を多少調整する事が出来る。更に上手くいけば、龍の意識を完全にこちらに向け、暫く動きを止めることも可能だろう。
だが、龍の気を引くためには、当然なるべく頭に近い位置を攻撃しなければならない。自分が合流する前に戦っていた『前衛』達の話によると、あの龍の胴部には痛覚、触覚と呼べるものがないらしく、頭付近の部分を攻撃しても全く反応がないのだ。そのため、龍の動きに干渉するならばどうしても頭部、若しくは頭部付近に攻撃する必要があるのだが、龍の頭部に近づくという事は、口から吐き出される竜の力の結晶、吐息を受ける可能性も高まるという事だ。真正面から挑む場合と比べればその危険性は格段に下がるが、しかし前腕から伸びる水の爪が届く範囲でもある。十分に注意して挑まねば、容易く命が失われる事になる。
「…………」
油断などしていい相手ではない。
極限まで戦いに意識を集中し、貴方は符の効果によって脚に溜まった力を解放。大きく地面を蹴った。
battle
双濫たる古の死龍
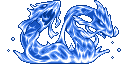
龍の腕。その先端、四指の一本が音も無く伸びた。
正確には、指の先、爪に当たる部分が、だ。
長さにして約二十メートル。一瞬にして伸びたその爪が、貴方目掛けて振るわれる。
「──!」
その大きさ故か、龍の動き自体は鈍重だったのが貴方の命を救った。龍に対する攻撃を終えて落下していく貴方のすぐ真上を、水色の切っ先が通り過ぎていく。腕の動き自体は酷くゆっくりとしたものだったが、その爪の先端部ともなれば衝撃波すら生まれそうな程の高速となっている。爪の動きに沿って空気が巻き込まれ、爪自体は貴方の身体を捉えなかったものの、渦を巻いた風の流れに呑まれて豪快に吹き飛び、態勢を整える間もなく地面に叩きつけられた。
「か、く」
身体が衝撃に痺れる。しかし、寝転がっている場合でもない。貴方は懸命に四肢を震わせ、何とか立ち上がろうとして、
『聞こえますか』
懐から響いた男の声に動きを止めた。
『そろそろ交代の時間です。頃合を見て一時後退してください。くれぐれも、下がる際に隙を突かれぬよう』
声の主は、恐らくギンナム。確か、レリエルから渡された符に、彼の声を伝達するための術式も仕込んであるという話を思い出す。
(下がれ、か)
タイミングとしては丁度良い。
貴方は何とか立ち上がると、龍の興味がこちらに向いてない事を確認してから走り出した。
・
前回の敗北時に受けた傷を癒しつつ、遠目に戦いを見守る。
戦況は芳しくない。『前衛』の抵抗も虚しく、龍は前進を続けていた。
早く、戻らなければ。
そんな焦りの中、貴方は力を取り戻す事に専念する。
・
『──と、皆さん、待ってください』
再度龍に対する攻撃を仕掛けようとしてた貴方の耳に、術式経由でのギンナムの声が響く。
『本陣の方から連絡が届きました。どうやら、準備が整ったようです』
ここで云う本陣とは、今まで儀式魔術で援護してくれていた『後衛』という意味ではない。
つまり、それは。
『“天落の星座”の構築が終了したそうですな。早急に、術式効果範囲外にまで退避せよ、との事です。日が落ちきると同時に、印章陣を駆動させるそうで』
貴方は空を見る。
気づけば既に日は完全に傾いて、広がるのは夜に近い空。肝心の太陽は既に地平の彼方に半ば以上が埋まっていた。
「ていうか、ちょっと急がないとヤバくない? って、ととと!」
貴方は龍に向かっていた足を強引に止め、バランスを失って落ちかけたリトゥエを片手で拾い上げつつ、今まで走ってきた道を逆走し始める。
『効果範囲は1キロと伝えてきていますが、“天落の星座”の詳細は向こうも完全には把握していない筈ですね。最低でもそこから五百メートル、欲を言えば更に1キロは離れるべきです』
無茶を言う。
高速移動、飛行の術式が可能な術士ならそれも容易いだろうが、こちらは単なる冒険者だ。そんな贅沢なものは、
「【NAME】、貰った大跳躍の符を使えば!」
ああそうか、と頷き、懐に手を入れて力を込めた。
大きく上方へと跳ぶ力を与えてくれるこの符の力を、横へと向けて使えば、普通に走るよりは多少はマシになるだろう。
身体に、脚に宿った力を溜め、そして地面を蹴る。
土が大きく抉れる感触を後方に感じながら、貴方の身体は大きく前へと跳んだ。この速度なら何とか1キロは稼ぐことができそうだが、それ以上は厳しいか。
貴方は舌打ちと共に再度地面を蹴り、そして最後に一度、後ろを振り返る。
「…………」
自分は出来得る限りのことはした、持てる力は出し切った。そんな実感はある。
しかし、空を泳ぐ龍の姿に、陰りのようなものは見つけられない。特別な力も無い個人の力で何とかできる相手ではない、という事なのだろう。
後は、昂壁の翼の秘奥とやらがあの龍に通じるかどうか次第、か。
──灰色の隠者──
空泳ぐ巨龍の頭部。その上に、灰色の長衣に身を包んだ、黒の影を朧に纏う老人が立っていた。
彼は後退していく昂壁の者達を余裕の視線でもって見下ろす。
今まで彼等が退くのに合わせ、超長距離から儀式魔術による多種の攻撃が行われてきた。今回も、あと暫くすれば何かの術式がこちらの進路に向けて打ち出されてくるだろう。
そこまで読めているのだ。避けようと思えば容易い。
だが、彼はあえてそれを正面から受け、そして力で持って捻じ伏せ、乗り越えてきた。
己と、龍が持つ力がどれ程のものなのか。
そして抗すべき相手、昂壁の翼との間に、どれだけの力の差があるのか。
それを確かめるかのように。
『この程度なのか?』
五年前に離れ、そして己が越え、下そうとしていたもの。
あれ程に固執していた場所。
それがこの程度のものだったというのか。
失望が、欠けた記憶の隙間に染みていく。
身の奥で盛る炎。既に火種すらも欠けたそれを吹き消すためのこの戦いであったが、果たして、このまま彼の塔を折り蹂躙したとして、それでこの炎が消えるのかどうか。
『いや』
消えぬとしても、それでいいのか。
自分の中にある薄れた感情を、老人は褪めた視線で分析する。
──まず、昂壁の翼を潰し、奪う。
それこそが、次の段階へと進むための契機となる。
自分はそのように認識していて、そして、こう考えるようになった理由等はもう二の次なのだと判っていた。
『…………』
内に埋没していた意識を、外へと向ける。
既に時刻は夕から夜に入る頃。少し前まで地平の彼方に見えていた太陽の欠片は姿を消し、その残滓ともいえる赤色が空の一部を焼くのみだ。暗く閉じかけた地平の一角には、支都ルアムザと、そして目標である昂壁の翼の姿が微かに見える。
そろそろ、昂壁の翼のみでは抑えきれなくなったと判断し、軍が行動を開始する頃だ。
師団が投入されるか、それとも護法を持ち出してくるか。どちらにしても、邪魔をするならば叩き潰すのみだ。五王朝の護り手たる護法。手合わせする相手としては申し分ない。彼等を蹴散らす事ができたならば、昂壁のみならず、この国すらも蹂躙する事が可能だろう。
『さて、どれ程のものなのか。なかなか先は見えぬものよな』
くつくつと篭る様な声で嗤い、黒と灰色が入り混じった老人は空を見上げ、
『────』
目を見開いた。
・
天空より、光纏う星が墜ちた。
一つではない。全て合わせて、三十七。
輝きは光跡と轟音を従えながら夜空を射る矢となり、その全てが龍泳ぐ空間を目指す。
龍と、その周辺の空域に降り注いだ星は、地面に辿り着く前に巨大な白色の華を咲かせた。
一つの星が生み出した光の空白は、直径にして約百メートル。
三十七の白円が連なり、抉り取り、そこに存在していた夜の黒と、龍の水、それを容易く白の一色に塗り上げた。
空を喰らった白の光。その輝きが残っていたのは時間にして十拍程だろうか。
光が失せた後。
あれ程強大な力を誇り、絶対の存在と思われた巨龍の姿は無く。
彼の龍が自身を構成する為に従えていた膨大な量の水が、その拘束を解かれて、力なき大粒の雨となって降り注ぎ始めた。
・
昂壁の翼が誇る秘奥印章陣、“天落の星座”。
事前に通達されていた印章陣の効果範囲外ぎりぎりの位置で、貴方と、そして後退時に合流したギンナムは、降り注ぐ星光の嵐によって龍が砕け散っていく様を見ていた。
あれ程強大な存在であった水身の大死龍が、その力を更に上回る力によって完膚なきまでに叩き潰される、その様を。
「……終わった、のかな?」
貴方の首元にしがみついていたリトゥエの呟きに、僅かな疑問の色が混じっているのは、目の前で繰り広げられた光景があまりにも現実離れしていたが故だろう。
だが、先程の出来事は現実だ。
龍の身体は砕けて、圧縮されていた膨大な量の水が解け、豪雨となって辺りに降り注いでいる。龍の主であったあの老人、ニビト・ブラームスも、龍が完全に崩滅する程の力の奔流の只中にあったなら、その痕跡も残さず消滅しているに違いない。彼が持っていた魔導器が残っているかどうかは、微妙なところか。神形器や魔導器は、己に課せられた役目が満たされぬ限り失われる事は無いモノだとは聞いているが、それにも限度があるだろう。
これで終わったと。そう判断していた貴方がつらつらとそんな事を考えていた時。
「いやはや……驚いた」
水の嵐の中、貴方の傍にいたギンナムの声が僅かに震えていた。その事に、貴方は驚きと共に彼を見る。
ギンナムは遠く空の一点を見据えて、半ば茫然と呟いた。
「流石は“死を越えし者”と云うべきか、それとも手にした魔導器の力故なのか。……まだ、存在していますな。彼は」
「────」
彼の指差した位置。龍が存在していた場所よりも更に高空に、微かな点が見える。貴方の視力ではそれを正確に把握することは出来なかったが、
「何あれ、マジで!? あんなの食らって何で生きてるのさ!」
同じ位置を見上げて叫んだリトゥエの言葉が、その点の正体を正確に表してくれた。
まさか、あの龍すらも跡形も無く砕かれる光爆の群の只中にあって、無事とは。化け物──そんなありふれた言葉で括って良いものか迷ってしまう。
「どうやら、先程の“天落の星座”があの規模の癖に単体対象の術式であったらしい、というのもありますが──それでもよくもまぁ、人の形を保っているものだ。絶対領域を行使したか、存在概念の相をずらしたのか。ともかく……龍を失った今、彼にここで退かれては、ワタクシにしてみれば少々都合悪い」
そう呟き、空を睨むギンナムの顔からは、普段浮かべている何処か皮肉げな笑みは掻き消えて、ただただ酷薄な色だけが浮かんでいた。
彼の表情と、目つきに貴方が小さく息を呑む間にも、ギンナムの左手が目にも留まらぬ速度で動き、右の手に持った杖の柄尻で地面に複雑な印章を描く。
「冒険者殿、その上へ。彼を追い詰めます!」
「追い詰める、ってあんな遠いところに居るのを、一体どうやって!?」
貴方もリトゥエに同意する。支給されていた大跳躍の符の力を借りても、あの位置にまで飛び上がるのは難しいだろう。
対し、ギンナムは僅かな苛立ちを見せながら地面に描いた印章を指し示す。
「ですので、この術式で一気に行きます。──早く! 間に合わなくなる!」
「っ」
ギンナムの剣幕に押されて、貴方はびくりと身を竦めたリトゥエを伴ったまま、反射的に彼の描いた印章の上へと移動する。
貴方が印章の上へと乗ったのを確認すると、ギンナムもその上へ。そして印章の中心点に杖を突き、じっと空の一点を見つめると。
「“舞い上がれ、上昇爆風[アップバースト]”!」
ギンナムがそう叫ぶと同時。
──轟、と視界が跳んだ。
「ぐ、」
瞬間、身体が重力から解き放たれ、そして下方から生まれた爆風により、貴方とギンナムの身体が凄まじい速度で空へと弾かれる。
いきなりの展開に反応も出来ず、貴方は只生み出された力によって常識外の速度で空を駆け、そして。
『ぬ、ぅ!?』
宙高く。
砕けていく己が僕、その残滓を茫然と見下ろしてた灰色の魔術師の眼前へと辿り着く。
『お前達は──』
「“支え無き大地よ来たれ、空中浮揚[レヴィテイション]”!」
更にギンナムが素早く術式を起動。空中に生み出された架空の地面に足がつく。眼前には、突然の強襲に驚愕の表情を浮かべる老人の姿がある。
あの“天落の星座”の後に、間髪入れずの襲撃だ。老人の反応は明らかに鈍い。
更に今までの戦闘、そして先程の“天落の星座”によるものなのか、その身体には無数の綻びが見え、纏う忌まわしい気配もヨファイオで対峙した時ほどではない。
今ならば。
(──行けるか?)
そう思考する間にも、貴方は構えた武器に力を込める。今は躊躇うような場面ではない。ギンナムが生み出した透明の床を蹴り、一気に踏み込む。
「ニビト殿、お覚悟を!」
背後。ギンナムの叫びと共に輝きが走り、何か強大な気配が顕在化する。恐らくはギンナムが高速召喚した彼の使役獣のものだろう。その気配は貴方の上を飛び越えるようにして灰色の魔術師へと襲い掛かり、
『たわけが、見くびるなよこの私をっ! “閉じよ、封印の檻[シールドケイジ]”!』
老人の右手が閃き、魔導器『四界の杖』がその力を発揮する。生み出さたのは光り輝く大檻。飛び掛った使役獣──細身の四足獣を閉じ込めたその檻は一瞬にして縮み、中に封じた獣をこことは違う空間へと封じ込めた。それは常識では考えられぬ技である。他人の使役する召喚獣を、強制的に自分が支配する領域へと閉じ込めたのだ。
しかし、老人が召喚獣に意識を向けたお陰で、貴方は一気に彼との距離を詰める事に成功した。
『──く、』
短く、老人の声が耳を掠める。左の手にある書物が開き、その中から飛び出すのは彼によく似た幻の人影。目くらましかと思考するが、しかし幻から感じるのは本体に勝るとも劣らぬ力の気配。
このまま飛び込むのは危険。
そう一瞬思考するが、しかし貴方は短く頭を振る。
今こそが、“死を越えし者”を──灰色の隠者を討つ、唯一の機会。
そう信じ、貴方は身に秘めた力全てを武器に込め、目の前の影に叩きつける!
ブラームスが持つ魔導器に、貴方の渾身の一撃が突き刺さる。
「な」
『、に』
貴方と、老人。二人は目の前で起きたその出来事に驚愕の声を漏らす。
老人が貴方の攻撃を防ぐために掲げた魔導器たる杖。その一部が、貴方の攻撃により砕けたのだ。
そして、杖の内側から強烈な光が生まれ、爆発した。
「────」
貴方はその光をまともに浴びて吹き飛ばされ、更にはギンナムが作り出していた偽物の足場も砕けて落下。同様にブラームスも杖から手を離し、大きく吹き飛ばされる。
爆発によって貴方達と距離を取る事に成功したブラームスは、殆ど崩れ去った身体を何とか維持しつつ、落下していく貴方と、そして遠く地平の先に僅かに見える五つの塔を、流れていく視界に収める。
『く、はは。そう……これだ。これでこそ……己の……いや、だが、まだだ……また……いずれ……』
響く声は徐々に擦れ、同時に老人の身体も夜空の黒に溶けるようにして消えていった。
・
「ふんぐぐぐぐぐ! ふをー! ふをー!」
貴方の衣服を捕まえて顔を真っ赤にしたリトゥエが、そんな声を漏らす。
正に必死の形相でそんな呻き声を出す。
(……不細工だなぁ)
彼女を見上げ、貴方は何となく思ったままを呟いてみると。
「うるさいよ、うるさいよ! 何? 【NAME】、それ私に、手を離せっつってるわけ!?」
すみません口が過ぎましたリトゥエ様。
「判れば、宜しい。ってよいしょっと」
リトゥエは鷹揚に頷いてから、貴方の服を掴み直す。
灰色の隠者が持っていた魔導器の爆発。それに吹き飛ばされ、高々度から落下した貴方は、追いついたリトゥエが全力で支えてくれなければ、地面に叩きつけられて綺麗な赤い花を咲かせていた処だった。
「っていうか、そろそろ地面、近くなってきた?」
下を見る。どうやら地面までそろそろ数メートル、という高さまで降りてきていたようだ。サンサーラを構成していた水が降り注いだお陰であちこちに小川や巨大な水溜りが出来ており、なかなか酷い状況ではある。
「じゃ、そろそろ離すよー」
その声に頷いて、貴方はぬかるんだ地面へと着地。先程の爆発と、そして戦いの影響か身体を支えきれず、思わず膝をいてしまう。
泥にまみれてしまった膝に顔を顰めながら立ち上がり、そして細く、緊張を解くための吐息をついた後、空を見上げた。
「…………」
「多分、逃がしちゃったね、あのお爺さん」
貴方の無言をどう取ったのか。いつもの定位置、貴方の肩上に着地したリトゥエがそんな事を言う。
確かに逃がしてしまった。
だが、“死を越えし者”の自身を再構築する力がどれ程なのかは判らないが、あれだけダメージを与えておけば暫くはロクな活動はできまい。
「ていうか、正直もう係わり合いになりたくないよね、あんなの」
心の底から、といった風なリトゥエの感想に、流石の貴方も今回は同意の吐息を零す。個人であの“死を越えし者”を相手にするのは正直無理がありすぎる。後は彼と因縁のあるらしい昂壁の翼の者達か、軍の連中が何とかして欲しい処である。組織という形でもって戦って、漸く対等に戦えるレベルの存在。あれは、そういったモノなのだろう。
そんな化け物を相手にして、何とか五体満足で生還できた。
それだけでも上々の結果、といってしまっても良いのではないだろうか?
(まぁ、これだけ頑張って、報酬が無いのが玉に瑕なんだけれど)
昂壁の翼辺りから、何か貰えないか交渉してみるべきだろうか。
雨も止み、澄み切った夜空を見上げながらつらつらとそんな事を考えていると、
「──にしても【NAME】。貴方、なんか身体が光ってない?」
「は?」
突然のリトゥエの声に、貴方はすぐ傍にある彼女と顔を見合わせ、そして自分の身体を見下ろした。
「…………」
見てみると、確かに彼女の言う通りだった。
先程の魔導器から爆発した輝きが、身体にまとわりついて残っているような感覚。薄ぼんやりとしたその光は徐々に消えつつあるが、しかし身体の芯に灯った穏やかな熱のようなものは失せる様子も無い。
「て、それってもしかして」
リトゥエがじっとりと目を細め、まるで内側を覗き込むように貴方の身体を凝視する。あまりに真剣な様子に何となく居心地が悪くなり、彼女から顔を背けようとしたその時。
「やっぱり。【NAME】、貴方の身体に、先刻の魔導器が内包してた概念が染み込んじゃってる」
概念が染み込んだ。詳しい意味は判らないが、
(やはりそれって、拙いんだろうか)
引きつった顔で己が身体を見下ろす【NAME】。リトゥエは両腕を組んで小さく唸った。
「どうだろ。あの魔導器の存在目的次第だけど……取り敢えず、【NAME】の存在概念にちょっと色がついちゃったのは確かだと思う」
つまり、どういう事なのか。
要約を求めた貴方に、彼女は苦笑気味の表情で頬を掻く。
「──貴方、少し人の枠から外れたかも?」
うへぇ。
思わず呻き、改めて自分の身体を見る。確か、『四界の杖』は強力な召還術補助能力と、更には他の存在概念を吸収するような力を併せ持っていた筈だ。目で見た限りでは、消え始めた光以外におかしな部分はないが、見えないところでおかしな事になっている可能性はある。
恐々とする貴方だが、しかしその心配も一瞬だ。
「おーい、無事かー!?」
遠くから声が掛かる。顔を上げれば、それは先程まで肩を並べて戦っていた『前衛』を努める術士達だ。一様に笑顔を浮かべる彼等に、貴方は大きく手を振り応える。
(……まぁ)
あれこれと考えても仕方ない。
今はこの勝利の喜びを、彼等と共に分かち合う事としよう。
・
勝利に沸く昂壁の集団。戦いの最後に灰色の隠者と剣を交わした者として、盛り上がる彼等に囲まれ、もみくちゃにされている貴方。
そんな騒ぎから外れ、一人静かに己が手にあるモノへと視線を落とす者がいた。
彼等の長を務めた召喚司、ギンナム・ラシャ・オルシスである。
「……さて」
その手にあるのは、先端の一部が砕け、輝きを鈍くした一本の杖だ。
神形、魔導器は条件を満たさぬ限り決して失われぬ物とは言われているが、このように欠けたり、若しくは破壊されたりという事は普通に発生する。その姿形が失われぬという訳ではなく、存在自体が失われないという意味なのだから。故に元は剣だったものが今は単なる宝石の形となっていたりという事も良くある話である。
五年前、昂壁の翼から灰色の隠者が持ち去った魔導器の一つを撫でながら、彼は口の端を僅かに上げる。
「いやはや、ここまで上手くいくとはね。確かに、『前衛』を申し出た時には、あわよくば、と考えていましたが──こうも都合良く、ワタクシの手の中にやってくるとは」
喉に詰まるような声音で彼は笑い、空いた手を己が袖内に突っ込むと、そこから一枚の紙片を取り出す。
そして余す隙間無く、びっしりと印章が刻まれたその紙を、彼は誰の目にも留まらぬうちに杖の柄に貼り、巻きつけた。
紙は一瞬にして溶けて、杖の表面に沈み込む。紙に記されていた無数の印象が柄の表面で一瞬輝き、そして跡形も無く消滅。紙片が杖に貼り付けられたという痕跡は、完全に消え去った。
「……今は、まだ。ですが、その刻が来れば、役に立ってもらいますよ──『四界の杖』よ」
呟かれた声は小さく。
龍が散らした水の概念が強く残る大地に吸い込まれ、そして誰の耳にも届く事無く消えていった。