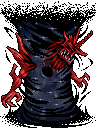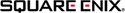真なる楽園 (ルートA)嶺渦の大禍鬼
――真なる狼鬼の宿地──
――今回は上手く事が運んだが、次はどうなるか判らない。
そんなイェアの発言がまさか呼び水となった訳ではあるまいが。キルーザム狼咆洞穴へと移動した【NAME】達は、状況が当初の予想とは異なっている事を悟る。
狼咆洞穴についての情報はノエルとウィースルゥインが保持する重ねた記憶からのものなのだが、今回の洞穴の状況は、彼女達が持つ記憶のどれとも一致しない、強い鬼気が溢れた場となっていた。それは、洞穴の入り口に辿り着いた段階で既に一般の兵達でも判る程のもの。何せ、入り口から中を覗き込めば判るのだ。
まるで幽霊のように僅かに身体を透き通らせた狼達が、手ぐすねを引いて【NAME】達が洞穴内に入ってくるのを待っていたのだから。
「一体また、なんでこんな事に……」
イェアが頭痛を堪えるようにこめかみを押さえながら、嘆きの声を出す。
流石に、そんな状態の洞穴の中に素直に突っ込んでいくわけにも行かず。【NAME】達は洞穴前でこれからどうするかを話し合っていた。
「中から、凄いやる気を感じる」
そんな事を言い出したのは、洞穴の方をぼんやりと眺めるウィースルゥインだ。
「今まで、ノエル達がここを通るときには、一度もこんな事、無かった」
「はい。大抵は、洞穴内の途中にある地下へと続く脇道に入った辺りからこの気配が強くなって、ああいう狼達の迎撃が増えてくるような感じだったとわたしは思います」
「入り口あたりに居るのは、この穴に普通に棲んでる、亜獣達ばっかりだったよね」
「ですが、今は地下に居るはずの狼――あの凍った湖に浮かんでいた狼の鬼種の気配が、この外にまで吹き出ている程です」
ノエルが言うように、洞穴の中から外へ向かって、強い歪な概念を宿した強風が吹いている。穴を通り吹き抜ける際に聞こえる音は、何処か遠吠えを思わせた。
「ええっと、確か洞穴の奥に居るでかい狼の鬼が、その小さい狼達を率いているボスで、アタシらはコレを倒しに来たって事でいいのよねん」
「ノエルやウィーちゃんのお話では、狼は殆ど洞穴の奥で眠りに近い状態にあり、そこへと居たる道中には狼の眷属は現れるものの、そう数は多くない、という話だったのですけれども……」
「この様子では、眠っているどころか、眷属達を使い、寧ろ我等を待ち構えている形に近いな」
「わたしの感知でも、狼鬼が覚醒状態にあるのが確認できています。強い歪みが、洞穴の奥で脈動しているのが判りますから」
「何故都合悪く今回だけ……」
頭を抱えるイェアに、先刻から話だけ聞いていたオリオールが口を開く。
「今回だけ、今まで何度も重ねてきた過去とは違う。そういう事であるのなら、原因は単純に、僕等のせいである、という事になるんじゃないかな」
「わたくし達?」
「そう。だって、過去繰り返してきた事と今とでもっとも違うのが、僕等の行動だからね。その中から推測を立てるとすると、ブランタンハリアの大禍鬼ブムドゥと、ここの大禍鬼……カンファートだったかな。この二体が何らかの形で繋がっているような存在で、ブムドゥが封じられた事でカンファートが明確な“危機”を知って迎撃するための準備を整えた、とか。まぁ、間の部分の予想は色々立てられるけれども、最後の結果の部分は変わらないのだから、どうでもいい話ではあるけれどもね」
自分で予想を言っておいて、それをどうでも良い事と直ぐに切って捨ててみせるのがオリオールらしいとは思うが、しかし彼の言う事は確かにもっともだ。
考えるべきはこうなった理由ではなく、この状況をどうするか、である。
「とはいえ、キルーザムの洞穴って殆ど一本道の構造なのよねん?」
「うん。途中下に行く分かれ道以外は、ずっと広いまっすぐ」
「そのような地形で待ち構えられているとなれば、小手先で崩すのも難しかろうな」
リゼラの言葉に、軍部隊を指揮する二人が深々と嘆息する。
「正面突破、しかありませんわよねぇ……」
「盾並べて槍突き出して、後ろから術式と弓で釣瓶打ちかしらん。相手が狼となると一度切り込まて乱戦になったらもう大変よ? しかもあれ、普通の狼なの?」
対し、ノエルはじっと洞穴の奥を見定める。その瞳には独特の、人ならざる者の色が混じり、その先に居る存在を精査しているようだ。
「……単体での規模は雲泥の差ですが、存在概念の形は大禍鬼カンファートのものとかなり類似していますから、その分身体に近いものだとわたしは推測します。実体は持っていますが半ば概念存在に近いですね」
「まさかミスティック系? アストラルほどじゃないけど面倒なやつじゃないのん……」
「ううん。もっと弱いよ」
ウィースルゥインの言葉はわかりやすいが、しかしその分言葉が足りない。
それを視線で問うと、彼女は少し考えるように間を置いて、
「狼の鬼が、そうね。自分の毛の一本で作ったみたいな分身。だから、数は多いけど、形はふわふわしてるし、ちょっと殴ったらすぐ壊れちゃうと思う」
「それ、ウィーちゃん基準でちょっと殴ったら、じゃないでしょうねん」
「んー? うーん。みんななら頑張って殴ったら直ぐ壊れるくらい」
多少判りやすくなった。
「……何にせよ、標的の狼鬼含めて待ち構えられているのは確かで、そうなると事前にわたくし達が用意していた印章陣などをじっくり記述して準備してから攻撃を掛けるという手筈は到底無理で、けれどもここまできて出直すという選択肢はもうありませんわ」
「ならば結論は、こやつら全てを斬り伏せるか」
「不本意ながら、強行突破して力尽くでの撃破を目指すしかないでしょう。【NAME】さん達に、何時も以上の負担を掛ける事になりますが、もう謝りはしませんわ。覚悟して、宜しくお願いいたします」
全員が、ただ一度頷くだけで意思を統一する。
「兎に角、こうなっては最後は【NAME】さんに全てを託す形となりますから、そこまでの道は、わたくし達軍の方で死力を尽くして道を開きます。内部はほぼ一本道に近い大洞窟。広いとはいえ。数十人が常に横に並べるほどのものではなく、陣形はどうしても縦長の列になりますわ」
「そして最前列が常に狼達と戦う役となるわねん。となると、その指揮しないと駄目だしアタシは前か」
「我も、そちらに回ろう」
「そりゃ心強いわ。取り敢えず、大盾並べて陣形組んで、疲労や負傷状況見ながら列入れ替える感じでいくわ」
「では、わたくしは中央で全体の状況把握と、指揮を努めます。あと、ウィーちゃんはもしものときの切り札として、わたくしの傍に詰めていてくださいな」
「【NAME】と一緒がいい」
「今回ばかりは、そこは曲げてお願い致します」
「むー」
無表情ながら不満げな声を出すウィースルゥインを「鬼との戦いの時は一緒ですから安心してくださいな」と宥めて、そして視線を残る二人へと向ける。
「術士や弓兵、遠隔兵器は全て後列に回します。敵の布陣と地形を考えると後方から攻められるという可能性は低いですから。ノエルはそちらでフォーレミュートによる援護を行ってください。ハマダン様は、念のため後方の警戒をお願いします」
ノエルは無言で頷き、オリオールも短く「了解だ」と答える。オリオールの装備は遠隔攻撃に適したものでは断じて無いが、しかし多対多の正面衝突の戦闘に付き合えるようなものでもない。取り敢えず比較的安全な場所で用心をしてもらうという、幾分彼の立場も配慮した配置といえるだろう。
それらを一通り割り振った後、イェアは【NAME】の方へと振り向く。
そういえば、自分の役目を何も言われていない。
「【NAME】さんは遊撃として、今決めた配置の中で自分が必要だと思うところにいってあげてくださいな。多分貴方は、わたくし達が何か決めてしまうより、貴方自身の考えて動いてもらったほうが良い結果を齎すでしょうから」
【NAME】としては勝手に担当を割り振ってくれた方が楽なのだが、彼女が何故このような形にしたのかも判る。
自分の考えた布陣に見落としがあるかもしれないという不安が、誰かに補い助けて貰いたいという気持ちに繋がっているのだろう。
「…………」
【NAME】はイェアが提示した人員の割り振り、そしてこれから突入する洞穴で、どのような戦いが起きるのか。
それを自分が思い付く範囲で考えながら、何処の組の補助に入るかを告げた。
【※前衛組に参加を選択した場合】
【NAME】は前列組に参加する事に決めた。
・
【NAME】は最前列の兵士達と共に、襲い掛かってくる狼達を真っ正面から迎撃する役目を買って出た。
兵士達は前列にて大盾を構えて狼が陣に喰い込んでくるのを防ぎつつ、隙間から槍や剣で応戦するという形を取っていたが、【NAME】はそういう中にいては己の力を発揮出来ない。故に、その列の外へと飛び出して背面に軍部隊の最前列を置き、凡そ半周を狼達に囲まれる形での戦闘を続けていた。
斬り伏せ、蹴り倒し、打ち据える。その間にも、奥から凄まじい量の狼達が、一直線に軍部隊目掛けて突進してくる。その数は十や二十ではきかない数で、とてもこの洞穴に元々棲息できていた数とは思えなかった。
しかも襲い掛かってくる狼達の身体は半ば透けていて、物理的な攻撃がいまひとつ通りづらい。術式を併用し、概念的な力を通した技法でなければ完全に破壊する事は難しく、半端に破壊された狼は暫くするとダメージを回復させてしまう。一体一体が手強い訳ではないが、兎に角厄介な相手だった。
その時、中列のイェア達から伝令が届く。
彼女の見立てでは、この狼達は大元の大禍鬼と比してあらゆる能力を大きく落とす代わりに、ほぼ無尽蔵に生み出す事が可能な存在なのかも知れないという。洞穴に侵入してから既に【NAME】達はかなりの数の狼を退治しているが、数が減っているようには見えず、実際イェアやウィースルゥイン、ノエルによる観測では、場に満ちる陰性存在概念の量は全く減っていないどころか、寧ろ増えてさえいるという。砕いた狼達の欠片が寄り集まって、新たな一匹の狼に化ける。そんな現象も所々で確認されているという。
事前にノエルやウィースルゥインが言っていたように、この狼達は大禍鬼が【NAME】達を迎え撃つために一時的に造り出した存在なのだろう。
「ということは、時間を掛ければ掛ける程不利というわけねん……」
「無限の雑兵とは、つまらぬ上に煩わしい。【NAME】、疾く行くぞ。このような下らぬ事に、刻を浪費するなど我慢ならぬ」
「あ、ちょっと杜人クン!? そんな一人で突出しちゃ駄目だって……ったくっ! 総員、続くわよ!」
リゼラと【NAME】が先陣を切る形で、ある程度の数の狼達を一気に倒すと、流石に狼達の密度が薄くなる。押し寄せる狼の波が、凪とまでは行かないが、小波程度になったのだ。
その、波がある程度収まっている隙に、疲労した最前列を控えていた次列に入れ替えながら前進するが、そうした陣形の組み替えを移動中に行うような急ぎ方をしても、然程も進まぬうちに遠吠えのような音が聞こえ、新たな狼の大波が、また洞穴の奥からやってきて切りが無い。
しかし、そんな状況だからといって、立ち止まっていては押し切られる。兎に角進んで進んで、大元である大禍鬼を倒さねば、この戦いは自分達の敗北になる。それは誰もが理解している事だった。
【NAME】達は次々と襲い掛かってくる狼達を薙ぎ倒しながら、更なる進軍を続ける。
位置は、そろそろ洞穴の中頃。地下の湖へと続く、脇道が存在する地点に近付きつつあった。
湖へと続く脇道は、更なる地下へと続く大道だ。下りの道へと入れば、奥より殺到してくる狼達の数は更に増し、加えて新たな変化も現れる。
向かってくる狼達の中に、赤と青、特徴的な毛色を持つ大狼が混じっていたのだ。
いち早くそれに気づいたリゼラが、手にした剣の刃を払いながら迫る二匹の大狼を見据え、
「親玉……という程では無いが、他の狼達よりは手強そうだな」
「総員、気をつけなさいなっ! 何してくるか判らないわよん! ……って、外見で大体判るわよねぇあれ……」
まぁ、口からモロに炎や冷気の煙が漏れ出しているので、その通りの攻撃が飛んでくる可能性は極めて高いだろうと【NAME】も結論付ける。
「そんな訳で、あいつらとぶつかりそうな奴らは、ちゃんと耐熱耐冷の術式仕込みなさい!」
今からかよ!? という叫びが兵士達の間で走る中、狼達の群れは正面から兵士達にぶつかる。そして二匹の狼はその脇から回り込むように、壁を跳ね蹴って盾を構える兵士達の脇を狙おうとしてくる。
だが、事前にその動きが確認できていたならば、食い止めるのは容易い。【NAME】やリゼラ、そしてノクトワイが素早く動き、二匹の動きを制するように刃を向ける!
炎と氷。相反する力を操る狼をどうにか退けた【NAME】達は、更に洞穴を更に進んでいく。
その間も、狼達の襲撃は途切れることはない。疲労と負傷、消耗が重なり、最前列の入れ替わりも激しくなっていく。素人目の【NAME】から見ても、現状の隊列を維持しての前進はかなり厳しくなってきている。遠からず、最前列が崩れ、陣形は破綻し、乱戦となるだろう。そうなれば、被害はこれまでとは比べものにならないほどに増し、隊自体が壊滅する事も有り得る。
故に、後はもう時間との勝負だ。こちらが破綻するのが速いか、それとも最奥に居ると思われるこの狼達の親玉である大禍鬼の元に辿り着くのが先か。
遠く洞窟の先には、僅かにだが、その終着を示す景色が現れつつあった。
地下道の終着点と思しき場所。湖面が凍り付いた大きな地底湖らしき場所へと到着すると、狼の襲撃がついに途切れた。理由は不明だが、取り敢えず危機的状況は切り抜けたと言って良いだろう。
ようやく一息つき、そして改めてその場を見渡した【NAME】達は、地形の異常に驚く。
確か、ノエル達の話によれば、氷の張った湖の上に巨大な狼――大禍鬼カンファートが浮かんでいるという話だったのだが、この場にそれらしき姿は無く、代わりに凍結した湖面の中央に、巨大な割れ目――凍った地面に穴が空いていたのだ。
遠く、氷の手前からではその穴の奥がどうなっているのか把握する事が出来ない。中を覗き込むならば、氷の上を進み、その穴に近付く必要があるだろう。
「……見た感じ、アタシ達が乗った程度じゃ割れそうもない分厚さに見えるけど……」
「割れ目のところから測るに、あれ厚さ1メートル以上は余裕でありますわよね。なら百人乗っても大丈夫、だとは思いますけれど」
「あの奥から、凄まじい鬼の気配が漂ってきているのは感じます」
「何かがあの奥にあるのは確かだ。しかし同時に、我等がここまでやってきている事も、あの奥に居る何者かは理解しているだろう」
「ということは、アタシ達は完全に待ち構えられてるって事だけど……困ったわねん。いざ氷の上に乗ったところで下から何か仕掛けられたらどうしようもないし」
「では、遠隔からあの穴の中に攻撃を叩き込んでみますか? 角度的に、あの下がどうなっているのか把握できませんけれども」
「効果の程は定かじゃないけど、相手の領域に迂闊に入り込むよりはマシでしょうね。では、術士隊を全て前へ。あの穴目掛けて、術式攻撃を放ちます」
指示に従い、後方から術士や遠隔、攻城級の兵器を携えた一団が前へと出て、氷に開いた穴の奥目掛けて攻撃準備を始める。
その時、である。
「――――」
下方から立ちのぼる強い鬼種の気配とは別の何かが、ぞり、と何処かで蠢くのを感じた。
しかし、【NAME】に判ったのはそこまでだ。何が、何処で。それが判らず、ただ身を低くしながら、正体を探るべく全周へ向けて意識を向ける。
そして【NAME】がソレを見つける前に。
「――警告! 上ですっ!」
叫ぶようなノエルの声は、しかし、その別の何かが動き出すよりも僅かに遅い。ノエルの声に上を確認する前に、色濃く暗い炎を纏った巨大な狼が地面へと落下し、攻撃準備をしようとしていた術士部隊へ目掛けて、全身から黒色の炎を吹きだし、浴びせたのだ。
「【NAME】っ! 行くぞ!」
爆音と悲鳴が響き、多くの兵士達が黒色の炎の風に吹き飛ばされる中。翠色の光を引いた小柄な影が間髪入れずに狼に斬り掛かる。放たれた剣線が、新たな被害者を生む事を防ぎ、そして後手として放った【NAME】の攻撃が、大狼を術士部隊達の傍から弾き飛ばす。
これで、狼と軍部隊との距離をどうにか離す事が出来た。その間に部隊を立て直すべく、イェアが声を張るのが聞こえる。
「前衛陣は前へ! 後衛陣を守りなさい! 襲われたのは……二と五、六番隊? 後退しながら被害確認、報告を! 残りは戦闘補助に回ってください!」
【NAME】の一撃により大きく吹き飛ばされた狼鬼だが、ダメージ自体は殆ど通っていないようだ。奇襲の結果が芳しくなかったのか、ぐるると不満げな唸りを上げて、こちらの様子を窺っている。
「……こいつが、この洞穴の主っていう大禍鬼ってワケ?」
「いえ」
背後、兵を整えながらのノクトワイの呟きに、黒銃を手に援護射撃の姿勢に入ったノエルが首を横に振る。
「大禍鬼はもっともっと強大な存在です。あれは恐らくその眷属。それも、先程まで戦っていた一時のものではなくて……」
「もっとちゃんと造ったものね。自分の一部をしっかりと分けて生んだ、本当の眷属。だから、さっきまで戦ってたやつとは、全然違うよ。気をつけて」
ウィースルゥインの言葉に、オリオールが「確かにね」と呟く。
「要するに、今のこのシチュエーション自体が、あの狼が奇襲を成立させるための一つの罠だったのだろうね。穴に興味を惹かせ、下から大禍鬼が気配を放ち、そして眷属は……天井辺りで身を隠していたってところかな」
「最もこちらが注意を払っていない、ある意味油断していたタイミングでやられましたわね。全く、流石上位の鬼といいますか、頭が回りますわ」
「けれど、杜人クンと【NAME】が直ぐさま対応してくれたおかげで助かったわ。もしアレがなかったら、後衛陣が軒並みやられれてたかもだし」
対し、リゼラは忌々しげに後方を一瞥し、
「そうやって口を動かしている暇があるなら、早急に動け。戦う気がないのであれば、我と【NAME】だけで片を付ける。――【NAME】、来い」
「ああん! ちょっとまってちょっとまって!」
と、制止するノクトワイの声を無視して、リゼラが一気に前に出る。その無造作とも思える単独での前進は、後に【NAME】が続くであろう事を確信しての動きだ。
そんな背中を見せられては、こちらも動かぬわけには行かない。軍部隊は未だ混乱が収まっていない。ならば自分達で片付けられるならそうした方が良いだろう。
黒い炎が吹き荒れ、熱風がとぐろを巻く。それを身軽に躱して剣閃を飛ばすリゼラの隣を摺り抜けて、【NAME】も己の技法を大狼目掛けてぶつけていく。
【※後衛組に参加】
【NAME】は後列組に参加する事に決めた。
・
前列組が狼達を駆逐していく様子を、【NAME】とオリオールはぼんやりと眺めていた。
陣形と狼達が前方から現れてくる関係上、後列には狼が殆ど来ない。ノエル達が援護射撃を飛ばす様子を、あまり敵味方の判断が効くような超長距離攻撃が可能な技法も術式も持たない【NAME】とオリオールは、ただただ彼等の後ろをついていくだけという気楽な立場となっていた。
更なる地下の湖へと続く脇道へ入ると、前列組が赤と青の体毛を持つ二匹の狼と交戦状態に。彼等が赤青の狼達の対処に集中する事で、他の狼達の対応に穴が埋まれ、外壁を走るようにして後列組に襲い掛かってくる狼の一団が現れる。
「このまま前衛の連中に任せきりで終わるかと安心していたのだけれど、どうやら僕等も働かないといけないようだよ」
「わたしは先刻からずっと頑張って援護しているのですけれど……」
ノエルの不満の声にえらいえらいと彼女の頭をぽんぽんと叩いてから、【NAME】は武器を素早く構え、迎撃の態勢に入る。
後列組は遠距離からの援護を重視した人員配置となっている為、実際に接敵した状態での戦いに慣れているのは【NAME】達他数人の護衛しか居ない。中に入り込み、掻き回されると大きな被害が出る可能性が高い。回り込んできた数は相当な数だが、その全てを食い止めねばならない。
「敵を倒すのは正直苦手だけど、時間を稼いだり、動きを止めたり程度なら僕でもどうにかなるかな。じゃ、やろうか、【NAME】」
襲い掛かってくる狼の群れは左右。右にオリオールが進み出るのを見て、【NAME】は左へ。壁を疾駆し、半ば落下するように速度をつけて襲い掛かってくる狼達目掛け、【NAME】は手にした武器を振り上げる。
battle
咆哮の先兵

【NAME】達が散発的に襲ってくる狼達を処理している間に、前衛は上手く人員を輪番で回しながら狼達を正面から押しのけていき、遂には終着点と思しき凍てついた湖の景色が、遥か前方に見える位置にまで来ていた。
「いよいよ、本番か。大禍鬼カンファート、勝てる相手なのかな」
「……正直な処、不安です。過去の記憶に於いて、あの狼鬼が本気になった姿とわたし達が戦ったことは一度もありませんから」
だからといって、今更戦うのを止めて逃げ出しますという訳にもいかない。
何れだけ強大な相手であろうと、勝ちの目を探り、見つけ、引き寄せるしかないのだから。
「そうですね、【NAME】。わたしも、きっとあなたの役に立てるよう、頑張りますから」
「健気なものだね。まぁ、僕としても死にたくはないし、出来うる限り、手助けはさせてもらうよ」
地下道の終着点と思しき場所。湖面が凍り付いた大きな地底湖らしき場所へと到着すると、狼の襲撃がついに途切れた。理由は不明だが、取り敢えず危機的状況は切り抜けたと言って良いだろう。
【NAME】達が取り敢えず到着したかと隊列の後尾付近で一休みしていると、何やら前方が騒がしい。一体何かあったのだろうか。
「行ってみますか?」
ノエルの問いに頷いて、【NAME】とノエル、そしてオリオールは凍てついた湖の手前で何やら話し込んでいるイェア達の輪に加わる。
何の話をしているかと問えば、彼女等が指差す氷の張った湖の光景を見て、成る程と頷く。
確か、ノエル達の話によれば、氷の張った湖の上に巨大な狼――大禍鬼カンファートが浮かんでいるという話だったのだが、この場にそれらしき姿は無く、代わりに凍結した湖面の中央に、巨大な割れ目――凍った地面に穴が空いていたのだ。
遠く、氷の手前からではその穴の奥がどうなっているのか把握する事が出来ない。中を覗き込むならば、氷の上を進み、その穴に近付く必要があるだろう。
「……見た感じ、アタシ達が乗った程度じゃ割れそうもない分厚さに見えるけど……」
「割れ目のところから測るに、あれ厚さ1メートル以上は余裕でありますわよね。なら百人乗っても大丈夫、だとは思いますけれど」
「あの奥から、凄まじい鬼の気配が漂ってきているのは感じます」
「何かがあの奥にあるのは確かだ。しかし同時に、我等がここまでやってきている事も、あの奥に居る何者かは理解しているだろう」
「ということは、アタシ達は完全に待ち構えられてるって事だけど……困ったわねん。いざ氷の上に乗ったところで下から何か仕掛けられたらどうしようもないし」
「では、遠隔からあの穴の中に攻撃を叩き込んでみますか? 角度的に、あの下がどうなっているのか把握できませんけれども」
「効果の程は定かじゃないけど、相手の領域に迂闊に入り込むよりはマシでしょうね。では、後ろにいた後衛陣を呼んできましょうか」
と、イェアが兵士達に指示を出そうとしたその時、である。
「――――」
下方から立ちのぼる強い鬼種の気配とは別の何かが、ぞり、と何処かで蠢くのを感じた。
しかし、【NAME】に判ったのはそこまでだ。何が、何処で。それが判らず、ただ身を低くしながら、正体を探るべく全周へ向けて意識を向ける。
そして【NAME】がソレを見つける前に。
「――警告! 後ろです!」
叫ぶようなノエルの声は、しかし、その別の何かが動き出すよりも僅かに遅い。ノエルの声に上を確認する前に、光輝く冷気の帯を纏った巨大な狼が、【NAME】達が進んできた道から突如現れ、完全に油断し休息を取っていた後尾列の者達目掛けて、全身から白色の氷刃を吹きだし、浴びせたのだ。
「【NAME】っ! 行くぞ!」
風切りの音と共に血飛沫が舞い、悲鳴が木霊する。多くの兵士達が白色の凍てつく暴風に吹き飛ばされる中。翠色の光を引いた小柄な影が間髪入れずに狼に斬り掛かる。放たれた剣線が、新たな被害者を生む事を防ぎ、そして後手として放った【NAME】の攻撃が、逃げ惑う後列の人員に襲い掛かっていた大狼を遠くへと弾き飛ばした。
これで、狼と軍部隊との距離をどうにか離す事が出来た。その間に部隊を立て直すべく、イェアが声を張るのが聞こえる。
「前衛陣は反転! 後衛陣を守りなさい! 襲われたのは……二と五、六番隊? こちらへ退きながら被害確認、報告を! 残りは戦闘補助に回ってください!」
【NAME】の一撃により大きく吹き飛ばされた狼鬼だが、ダメージ自体は殆ど通っていないようだ。奇襲の結果が芳しくなかったのか、ぐるると不満げな唸りを上げて、こちらの様子を窺っている。
「……こいつが、この洞穴の主っていう大禍鬼ってワケ?」
「いえ」
背後、兵を整えながらのノクトワイの呟きに、黒銃を手に援護射撃の姿勢に入ったノエルが首を横に振る。
「大禍鬼はもっともっと強大な存在です。あれは恐らくその眷属。それも、先程まで戦っていた一時のものではなくて……」
「もっとちゃんと造ったものね。自分の一部をしっかりと分けて生んだ、本当の眷属。だから、さっきまで戦ってたやつとは、全然違うよ。気をつけて」
ウィースルゥインの言葉に、オリオールが「確かにね」と呟く。
「要するに、今のこのシチュエーション自体が、あの狼が奇襲を成立させるための一つの罠だったのだろうね。穴に興味を惹かせ、下から大禍鬼が気配を放ち、そして眷属は……通り道で身を隠して、こちらが気を抜くのを待っていたって訳だ」
「もっともこちらが注意を払っていない、ある意味油断していたタイミングでやられましたわね。全く、流石上位の鬼といいますか、頭が回りますわ」
「けれど、杜人クンと【NAME】が直ぐさま対応してくれたおかげで助かったわ。もしアレがなかったら、後衛陣が軒並みやられれてたかもだし」
対し、リゼラは忌々しげに後方を一瞥し、
「そうやって口を動かしている暇があるなら、早急に動け。戦う気がないのであれば、我と【NAME】だけで片を付ける。――【NAME】、来い」
「ああん! ちょっとまってちょっとまって!」
と、制止するノクトワイの声を無視して、リゼラが一気に前に出る。その無造作とも思える単独での前進は、後に【NAME】が続くであろう事を確信しての動きだ。
そんな背中を見せられては、こちらも動かぬわけには行かない。軍部隊は未だ混乱が収まっていない。ならば自分達で片付けられるならそうした方が良いだろう。
白い風が吹き荒れ、冷気が刃となって渦巻く。それを身軽に躱して剣閃を飛ばすリゼラの隣を摺り抜けて、【NAME】も己の技法を大狼目掛けてぶつけていく。
【※中央組に参加】
【NAME】は中列組に参加する事に決めた。
・
隊列の中央となる位置は基本的には極々安全だ。更に言うなら、護衛としてここに居る場合、非常に暇な場所と言える。
共に居る、部隊の長を務めるイェアの方は大忙しだ。前衛を務める部隊が狼達と死闘を繰り広げる様子を心配そうに眺めながら、時折ノクトワイが見えていない部分をフォローする指示を出したり、前列交代の予定を組んだり、後衛陣の援護射撃をどう行うか指定したり、その間に狼達の存在についての検分を行ったりしている。
【NAME】としては皆が戦っていたり、色々な仕事をしている中、ただウィースルゥインと二人、ぼんやりイェアの横で立っているだけしか出来ないというのは、非常に心苦しいものがあった。
同じ立場であるウィースルゥインも同様の思いを抱いているのだろうかと、ふと視線を向けると、彼女は単に【NAME】が自分を見てくれた事が嬉しかったのか、表情は変えないまま、じっと【NAME】を見返して身体を上下に揺らす。全く気にしていないどころかむしろ機嫌が良さそうですらあった。
そうこうしている間に、軍部隊はどんどんと洞穴を進み、地下の目的地へと続く脇道へと突入。赤と青の特徴的な色を持つ狼を相手する際には多少梃子摺りながらも、大きな被害は無く、遂には大禍鬼カンファートがいる筈の凍てついた湖へと辿り着く。
しかし、そこで待っていたのは。
「湖が割れて、穴が空いてる……? それに……大禍鬼が、二匹ですの?」
「違うわ。あれはカンファートじゃない。カンファートの分け身」
ウィースルゥインの言葉に、イェアは怪訝と彼女を見る。
「あのさっきから襲ってきていた狼もそれという話じゃありませんでしたっけ?」
「あれは気配だけを捏ねてつくった幻みたいなもの。でもあの二匹は違う。わたしの髪から生まれる子達に近いけど、もっとはっきり分かれてる。自分の身体を分けた“子”に近いわ」
だから、気をつけて。
そう続けたウィースルゥインの言葉が終わる前に、二匹が大きな動きを見せた。
まずは突進。そして、前衛の部隊と衝突寸前からの大跳躍である。天井にまで届くほどに飛んだ二匹の狼は、身を回して天井を蹴って速度を上げて、一匹は黒い炎、一匹は白い氷を纏いながら、守りの薄い隊列の中列、後列目掛けて落下してきたのだ。
鈍く破裂する音と、砕け切り裂く音。二つの音が二箇所から生じ、同時に悲鳴と血飛沫が舞う。近接戦闘が行える兵士達は主に前列に集め、中、後列は術士や弩弓兵、戦闘訓練を受けていない学士などが集められていた。そんなところに飛び込まれては、一方的にやられるしかない。
「イェア!」
「判っていますわ! ウィーちゃんは黒い方、【NAME】さんは白い方を対処してください! 急いでっ!」
battle
対狼の禍鬼

【※分岐終わり】
「成る程ねぇ」
二匹の大狼が、【NAME】達の手により滅びていく。砕けていく身体は黒と白の煙となって消滅し、後に残ったのは巨大な狼の爪が二本。
「自分の爪を使って生み出した眷属、か。手強いのも道理よね」
そう独りごちるように呟いてから、ノクトワイは後方を振り返る。
不意を突かれ兵士達にかなりの被害が出たものの、幸いというべきか死者までは出なかった。【NAME】達は負傷者の治療を行いながら、改めて場の調査を開始する事にした。当初の穴への先制攻撃を仕掛けるという手は、後列に固まっていた術士達や遠隔攻撃手達の被害により不可能となり、であるならば直接近接部隊が穴の様子を確かめるしか手がなくなったからだ。
慎重に氷の上を進み、中央に開いた数十メートル級の巨大な穴を覗き込む。
すると、意外な事が判った。
ここは当初、その姿形から氷の張った湖と思われていたのだが、実は湖ではなかったようなのだ。厚い氷の下には凍っていない湖水ではなく、更なる地下へと続く洞窟が存在していた事が判明する。どうやらこの氷の床は、その道を隠すための氷壁であったらしい。
そして、続く洞窟の奥から感じる鬼種の気配は、ノエルやウィースルゥイン曰く、過去に【NAME】が氷床の上で戦った狼鬼カンファートと形は同じものながら、その強さは比べものにならない程に増しているという。
「本当なら、軍部隊もつれていきたいところですけれど……」
イェアは振り返り、軍部隊の様子を窺う。
まずこの場所までやってくる間延々と狼の群れと戦い続けた上に、先刻の奇襲が重なって、前衛後衛共に消耗が激しい状態だった。負傷者も多く、戦闘不能に近い者達も居る。
この洞穴での戦いが作戦の終わりではなく、まだ先に大きな戦いが残っている事を考えると、彼等は治療や休息に専念してもらう方が良いだろう。
「てなわけで、こっからはアタシ達だけでどうにかするしかないわねん」
【NAME】達は用心しながら氷の穴を下り、続く洞窟の更なる奥へと進んでいく。
――嶺渦の大禍鬼──
そうして辿り着いたのは、横に広く、しかし縦には然程の高さも無い、鍾乳洞のような空間だった。
その最奥に、大きな楕円の窪みがあり、そこにくるりと身を丸めるようにして、一匹の狼がやってきた【NAME】達に鋭い眼光を向けていた。
――こいつが、カンファートか。
【NAME】は内心の呟きと共に、武器を改めて構え直す。
その間に、身を横たえていた狼も立ち上がる。その大きさは、成る程、ノエルやウィースルゥインが先程の狼と比べて“もっともっと強大な存在”と言うわけだと納得する程のもので、先程術士達十数人を腕の一薙ぎで払った狼の、更に数倍以上の体躯を持っていた。立ち上がった狼の背はもはや天井すれすれに近いほどで、【NAME】からすると見上げる程に大きい。
【※前衛組に参加を選択した場合】
更に、巨狼の背後からは、別の大狼が一匹、そろりと身を起こす姿も見えた。先刻戦った大狼が黒炎の狼だとするなら、こちらは白氷の狼とでも言うべきか。カンファートに似た力を宿す大狼は、回り込むような動きで【NAME】達と一定の距離を保つ。
【※後衛組に参加を選択した場合】
更に、巨狼の背後からは、別の大狼が一匹、そろりと身を起こす姿も見えた。先刻戦った大狼が白氷の狼だとするなら、こちらは黒炎の狼とでも言うべきか。カンファートと似ていながらも異なる力を宿す大狼は、回り込むような動きで【NAME】達と一定の距離を保つ。
【※中央組に参加を選択した場合】
しかも、両の前脚の先、四本の爪の内一本がそれぞれ砕けて、渦を巻いた欠片が新たな化生――先刻倒した筈の白黒二匹の大狼を新たに生み出す。
「……これは、堪りませんわね」
その様子を見て呻くような声を漏らしたイェアの言葉は、その場に居る皆の内心を代弁していた。
【※分岐終わり】
そして暫く、誰も身動きしない緊迫の間を経た後。
カンファートは【NAME】達を見下ろすと口蓋を浅く開き、息を吸う動作を取った。その動きに併せて、空間に満ちる空気が、狼鬼の元へと吸い込まれていくのが判る。
「――来るわ」
小さく、ウィースルゥインが呟く声が聞こえたと同時に。
大禍鬼カンファートは、歪んだ氷結の概念に満ちた力を、圧縮した暴風という形で【NAME】達目掛けて放つ!
[BossMonster Encountered!]
カンファートが持つ力は大きく分けて二つ。氷結の力と風操の力である。
あらゆる攻撃は全てが氷結の結果に繋がるもので、受ければ凍り、躱せど凍てつく。そして守りはその氷結の力を混ぜ合わせた風の結界を使い、迂闊に手を出すと氷結してしまう事も含めてその防御力は絶大という他無く、正に大禍鬼の名にふさわしい、化け物染みた存在であった。
しかし、そんな相手であっても、【NAME】達は負ける訳にはいかない。
なぜならこの先には、カンファート以上の敵が待っているのだから。こんなところでやられてしまうようでは先は無い。
大禍鬼相手に地力で戦うとなった時、もっとも力になってくれたのはウィースルゥインとノエルの二人だ。彼女達は元々、対大禍鬼の戦闘集団として調整が行われていた過去を持つ。今はその頃より大きく在り方は変わっていたが、特に“人形”であるノエルに搭載されていた機能が、この場面で大きく効いてきていた。
狼鬼が放つ、歪な概念を用いた氷結と風操の力。それを、ノエルは短い時間ながらある程度破ったり、防いだり、封じたりする事が出来たのだ。
これを上手く活用し、要所となる場面でウィースルゥインとリゼラという高い火力を持つ者が集中する事で、【NAME】達はカンファートを徐々に徐々に追い詰めていく事に成功していた。
そして、あらゆる御膳立てが整ったタイミングで、【NAME】が己の持つあらゆる力を乗せた一撃で以て、カンファートの身体を二分し、更なる追撃で砕き、破壊したのだった。
・
形を失い、散っていく大禍鬼の存在概念。イェアは封縛印章石群を取り出すと素早く空中で展開させてから、ウィースルゥインを呼び寄せる。
既にもう、一度は成功した手順だ。ウィースルゥインが干渉を行って印章石群内に仕込まれた術式を駆動させると、広がっていた石群達からこれまでとは比べものにならない程の光が放たれ、その光が指向性を持って集まり、うねり、波となり、今まさに砕かれ空間に掻き消えようとしていた存在概念を拾い集めると、それらを抱えて石の中へと戻っていく。
後には、主を失い代わりに静寂を新たな主とする事になった鍾乳洞と、そして過去に狼鬼が呑み込んだものの取り込む事が出来なかったらしい、一本の武器が地面に転がっているだけだった。
これで無事、作戦の第二段階は成功となった。主たる狼鬼を失い、洞穴の中も一気に安全になっている筈だ。
「後は洞穴を抜けて、“城”を目指すだけですわ! あともう一息――頑張りましょう!」
真なる楽園 (ルートB)嶺渦の大禍鬼
――固独たる化身──
――先に、キルーザム狼咆洞穴の狼鬼を討つ。
【NAME】がそう宣言した通り、決定した進軍のルートは、ロームフーネ無空峡谷からザルナルバック月光丘陵を経由し、キルーザム狼咆洞穴へまず至るというものだった。
峡谷は単純な一本道。ただ前進し、谷底や側壁の棚に棲息する亜獣達の襲撃を迎撃するだけだ。突進する四足獣の群れ、舞い降りる大鳥や翼竜の牙、側壁の亀裂より奇襲してくる肉食獣。それらを慎重に対処しながら、軍部隊は着実に前進していく。その道中に不安定な所は一切なく、【NAME】は指揮を執るイェアの隣で、兵士達が奮戦する様子を応援するだけで良かった。
そんな状況が終わりを告げたのは、谷の終着点となる場所が近付いてきた辺りからである。
暴風を身に纏い、縦穴となった空間の宙空にて留まりこちらを見下ろす巨大竜――アルンカリア。
軍部隊の近接系兵士はそもそも武器が届かず、弓や弩による遠隔攻撃、個人の術式攻撃などは竜が備える硬質の鱗どころか、アルンカリアが纏う烈風の壁を破ることすら出来ず、容易く弾き飛ばされるだけだった。
こちらからの攻撃は一切通じず、そして竜からの攻撃は、纏う風を解いて放たれる竜巻の渦に、竜種が得意とする風の概念を圧縮した吐息[ブレス]。更には切り裂く風を纏う四肢の爪が軍部隊に襲い掛かる。
一時の撤退。イェアとノクトワイがその判断を下すのは、交戦を開始してから数十秒も経たぬ間だった。
アルンカリアは追撃を行ってはこず、それ故に部隊の態勢を立て直すのは容易ではあったが、しかし直ぐに再戦を挑むには、初交戦時の結果がまずすぎた。
どうしたもんかと皆が顔を突き合わせて悩む中、手を挙げたのはウィースルゥインだ。その片方の手には、驚いたノエルの腕が掴まれている。
「皆が困ってる。だから、私とわたし――ノエルが、何とかする」
「ちょ、ウィースルゥイン!? どうするつもりですかっ?」
どうやらノエルのほうはさっぱり判っていないまま引っ張り出されたらしい。慌てて問う彼女に、藍色の髪の少女はきょとんと見返し、
「わたしが落とすから、ノエルは“勉強”通りに、アレで翼を撃って。後は」
ウィースルゥインの瞳が、するりと動く。その先には、他の皆と同様に驚きの顔を浮かべた【NAME】の姿が映っていた。
「【NAME】がやっつけてくれる。……よね?」
そして【NAME】は、ウィースルゥインが敵としてではなく味方として戦う姿を――“固独”の大禍鬼として、想像していた以上の力を発揮する様を、間近で見る事になったのだ。
[BossMonster Encountered!]
少女が数多の存在と共に在り、万象の力を持つことは知ってはいた。
しかし、それに加えて更にもう一つ。
彼女が持つ全く別軸の力を、【NAME】はこの場に至ってようやく目撃する事が出来た。
それは、イェアが“固独”と名付けた、過去に存在した幾つものウィースルゥインにはなく、今ここに居るウィースルゥインだけが得ている特性だ。
その特性を端的に表すならば――攻撃を含めた他者からの干渉を拒み、大きく弱体化ないしは無効化する事ができるのだ。
自分の存在概念にあらゆる要素を内包するが故、己が世界の内で存在全てが完成してしまっており、だからこそ固定され、独立していた在り方は、超常地形の象徴とも言える強大な存在達の力すらも、殆ど寄せ付けない。
ノエルとの件でその完全さは崩れ、他存在との接点を持ち、そして流動する自己を得たとしても、それは未だ、僅かながらの事でしかない。少女が持つ、存在としての極めて高い独立性は揺らぎは生まれつつも未だ健在であり、他者からの接触――物理的概念的問わない様々な攻撃を、彼女は自分の世界には届かないものとして無効、あるいは大幅に弱体化させる事が出来るのだ。
「うわぁ……どうなってんだありゃ……」
と、近くでその様子を眺めていた兵士が、唖然と声を上げるのが聞こえたが、【NAME】としても似たような感想だった。
峡谷の最深部。縦長の穴の中程にて、巨大竜の周りを覆う、圧縮され白色に染まる烈風の渦巻。その中を、ふわりと浮かんだウィースルゥインの小さな身体が、まるで何事も無く突き進んでいくのだ。
あの強烈な風の力は、既に【NAME】達は散々味わっていた。殆どの攻撃を弾き飛ばす、まるで高速回転する鋼のような代物の筈だ。だというのに、少女はその風の渦を、この世にそもそも存在していないかのような態度で擦り抜けていく。
そうして、彼女の姿が風の渦の中へと消え去り、見えなくなって数瞬の後。
「えい」
そんな軽い掛け声に反し、ご、と鈍い音――近い音で言い表すならば、巨大な岩石を勢い良く硬質な地面に叩き付けたような音が響き、渦巻く形で固定されていた風が解放され、四方八方へ、まるで爆発するような形で破裂した。
全方向へと放たれる、衝撃波のような暴風。突然生じたそれに、見守っていた殆どの者達が派手に吹き飛ばされる中、
「ノエル。撃って」
「はいっ!」
気づかぬ間に腹這いの姿勢で黒銃フォーレミュートの狙いを定めていたノエルが、衝撃波の向こう側に姿を現した巨大竜、その両翼目掛けて二度、引き金を絞る。
放たれたのは、【NAME】がこれまで見慣れていた光条ではなく、得体のしれない様々な力が圧縮され、球の塊となったかのような、不気味な気配を発する弾丸だった。
射撃された二つの弾丸は、今までの理粒子を圧縮加速して放つ光条よりは遥かに低速。しかし、今縦穴の中で吹き荒れている風の力や、暴れ狂う概念の波。それらの影響を全く受けず、いや逆にそれらを弾に吸い込むようにしながら真っ直ぐに進み、全身を露わにしたアルンカリアの両の翼に着弾する。
次の瞬間、竜が絶叫をあげる。威嚇や誇示、攻撃のための咆哮ではない。弱々しく、痛みと衝撃に苦悶する悲鳴の絶叫だ。
それも当然だろう。ノエルが放った二つの弾丸は、着弾した竜の十数メートルはあろうかという翼二枚を、円形にえぐり取るように、完全に消滅させたのだ。
破裂した風が、ようやく収まり始める。そしてつい先刻まで圧倒的な力を誇り、軍部隊を退けていた巨大竜が、今は無残な姿を傾がせて、そして無様に地面へと墜落していく。
地響きのような音を放って、アルンカリアが地面に叩きつけられて、のたうち回る。もうその姿に先刻までの強者の姿は無い。後は止めを刺されるのを待つだけの存在でしかなかった。
「やった! ウィースルゥイン、成功ですっ!」
「うん。簡単」
立ち上がり、両手を上げて喜ぶノエルに、空中から降りてきたウィースルゥインがその両手に手を合わせ、互いに笑みを交わし合う。
そこだけを切り取れば極めて微笑ましい遣り取りであるのだが、彼女達の向こう側で未だ苦しげに身をうねらせる竜の姿と合わせると、空恐ろしさすら感じる光景だった。
あれが、ウィースルゥインの“固独”の力。
そして、ノエルが“人形”として振るう力。
そのどちらもが、人の身では達する事の出来ない超常的で、圧倒的な力であり、谷を統べる暴竜が纏う渦風や、その先の超常地形を統べていた、歪なる音色を力として放つ奏者の強烈な概念攻撃に対しても同様と言えた。
[BossMonster Encountered!]
【NAME】とウィースルゥイン。そしてノエルの三人は、あっさりとその歪な奏者の本体であるところの巨岩を破壊し、夜の丘を埋め尽くしていた狂気が薄らいでいくのを感じながら、この“丘”に立ち入ってからの流れを思い返す。
・
暴風の竜を打ち倒した【NAME】達が次に訪れた場所。短くは“丘”――正しくはザルナルバック月光丘陵と名付けられた超常地形が持つ特性は、既に過去行われた【NAME】とオリオールの探索によって、大まかに割れている。
その特性を極々単純に言い表すなら、昼は安全、夜は危険だ。
太陽が出ている間は、真なる亜獣達の楽園とも呼ばれるエルツァン島の中に居る事すら忘れてしまう程に平穏な世界が広がり、そして太陽が地平に落ちて姿を消すと、今度は逆に凶暴極まる亜獣達が我が物顔で歩き回る、正に人々が想像するエルツァン島そのままの危険な世界が姿を現すのだ。
当初、部隊は昼間に丘を進み、夜に陣を構築して敵襲に備えるという方針を採っていた。
しかし、それは直ぐに逆転する事になった。夜間はほぼ常にそこかしこから現れる亜獣達の襲撃を受け続ける事になり、陣形の内側にいた休息予定の兵士達すら一睡たりともできないような惨状となったからだ。
それ故、昼間に十分な休息と準備を行い、そして夜の訪れから朝の始まりの間、跋扈する亜獣を薙ぎ倒しながら前進を続けるという手法に変更された。
しかし、それでも夜間、特に深夜帯に出没する亜獣達の強さは群を抜いており、下手をすると大鬼、禍鬼にも匹敵しようかという強さを持つ亜獣達が、群れを成して襲い掛かってくる事もあるのだ。
一日、一日と過ぎる毎に部隊の疲労は増し、負傷者も増えてきた。一時は陣の内側に亜獣の侵入を許し、補給物資が損害を受ける事もあった。
――このままではまずい。
何らかの打開策を考えねばならないのは皆の間で一致する意見であり、当然部隊長たるイェアもノクトワイと何度も話し合い、その方法を模索していた。
そんな時、である。
「あの音の原因を探し出し、優先して叩くという手が良いのではないかと、わたしは考えます」
「あいつらをやっつけちゃえば、きっともっと、夜が静かになるわ」
そう進言したのは、ノエルとウィースルゥインの二人だった。
「……音?」
首を傾げるイェアに、ノエル達も同様に首を傾げる。
「聞こえませんか? 日が暮れて、夜になって、月が空に昇っている時だけ響く、あの笛の音」
「ああ……言われてみればそんな音がちらっとしてたような気がしますわね。てっきり気のせいかと深く考えていなかったのですけれども」
「あと、歌う声もする。私、知ってるわ。あれが、この場所の歪んだ夜を生む奏者達だって」
そして彼女達の話が続いていく程、聞いているイェアの顔がどんどんと険悪になっていき、
「ちょっと待ってください。つまり、こういう事ですか? 今、この“丘”で発生している昼と夜の二面性……特に夜に凶暴な亜獣がばんばん湧き出てくるのは、貴女達の言う存在が元凶であり、それをどうにかしたらこの状況は直ぐにでも解消される、という事ですの?」
「うん。そう」
「少なくとも、その傾向は弱まると、【NAME】が奏手を討伐した後の記憶から読み取れるとわたしは考えます」
「…………」
その答えに、ふるふるふる、と顔を伏せたイェアが、何かを噛み締めるように震え、しかし耐えられなかったようで爆発した、
「――それを! ――先に! ――言ってくださいな! あなた達、陣地でそんな話一度もしなかったじゃないですのっ!」
「……そうでしたっけ?」
「したと思う。ただ、あまり強い存在じゃないって言ったら、『じゃあ別にどうでもいいですわね、どうせ“丘”なら戦わずとも通り抜けられるでしょうし』って」
そこで、今まで黙っていたオリオールが挙手までしてから話に加わる。
「というか、その辺りの事は【NAME】と僕がここを探索した際に似たような話をして、予測としてそういう可能性もあると一応報告したと思うのだけど……」
「…………」
【NAME】も無言でイェアの方を見る。
集中する視線。ノクトワイが、苦笑と共に口にする。
「あー、部隊長殿? 皆こんなこと言ってるけど?」
「……御免なさいでした……その、すっかり忘れておりました……」
少し離れた位置で成り行きを見守っていたリゼラが、心底呆れた風に、深々と吐息をつく音が聞こえた。
・
ウィースルゥインとノエルが言うには、歪の奏者を倒すのはそう難しい事では無いらしい。
奏者の攻撃方法は、主に音波を利用した概念破砕。しかし、常人ならば到底耐えられないであろうその攻撃に対して、
「そんなものなんて、私に通じやしないもの」
あっさりとウィースルゥインはそう言ってみせる。
むしろ厄介なのは、その音の出所とされる場所に到着するまでの道中だという。
目印として大岩が存在する場所――オリオールが過去に予想していたこの土地の要の一つ――が、そもそも夜にしか明確に出現しないらしい。昼間は大岩の存在が安定しておらず、在るか無いかが不確かになり、見つけるには相応の運を要すると。
つまり、確実を期するならあの危険な夜に音の出所を探り、そこへと移動せねばならないのだ。
最初は軍部隊をそこまで移動させるという案も考えられたのだが、それはウィースルゥインが不要だと断言し、ノエルも同意した。自分達二人でも十分――保険として【NAME】が居ればもう万全だ、と。
そうして夜に軍部隊を置いて出発した三人は、襲い掛かる亜獣達を薙ぎ倒しながら音の出所まで移動し、見つけた大岩の上にて出現する大小三つの影と対峙した。
歪な音を奏でる人影と、従う妖魔が放ってくる攻撃を往なし、反撃によって大岩の上より吹き飛ばし、ひらりと動いたウィースルゥインが奏者の動きを、続く【NAME】が二体の妖魔の動きを押さえる。
「ノエル」
「――行きます!」
そうして確保された射線。
構えた黒銃フォーレミュートから放たれる、陰陽相克、万象の力が圧縮された弾丸が、奏者達の“本体”である大岩を打ち砕いたのだ。
その瞬間、丘中に立ち込めていた歪な気配は見る間に遠のき、暴れていた亜獣達の姿も、まるでその存在が幻であったかのように薄れて消え去っていく。
後に残ったのは、日中と同じ、平穏な丘陵の風景。空に浮かぶ月は、いつのまにか優しく仄かな輝きを灯す半月へと、その姿を変えていた。
・
“谷”と“丘”。二つの超常地形を何とか潜り抜けた軍部隊は、まず一つ目の目的地であるキルーザム狼咆洞穴の入り口へと辿り着く。
大口を開けた大空洞。それを前にして、イェアとノクトワイは洞穴侵攻についての最後の詰めを行っていた。
キルーザム狼咆洞穴での作戦内容は比較的単純なものだ。というよりも、洞穴自体が非常に簡単な構造であるため、少なくとも道中部分に関しては小手先の技を使いようがなく、ただ隊列を組み、洞穴内に棲む亜獣や鬼種などの危険生物を排除しながら進む以外の選択肢がないのだ。
勿論、終着点にて存在する大禍鬼に対しては相応の準備を行っているが、それにしてもノエルとウィースルゥインから得た過去の戦いの記録から、大禍鬼が操る力をある程度推測し、その対抗策を用意してあるというだけの話。
それ故、いざ今ここで頭を使う部分と言えば、長く伸びる隊列の何処に誰を配置するかという程度の事でしかない。
軍部隊自体の列構成にはそれ程迷う所はない。少数の斥候が先頭となり、続いて敵と直接相対する近接系兵士で構成された前衛組、その後ろが全体指揮と負傷した前衛の治癒を主とした補助を行う中衛組、そして後方から角度を取っての遠隔攻撃で火力支援を行う後衛組に分ける、といった程度の話だ。前衛組に人数を多めに配分し、その中で分隊列を構成。消耗度合いによってそれを順次ローテーションさせて治癒休息補充などを行う、スタンダードな戦法である。
問題は、【NAME】達軍内でも特殊な立場や強力な戦闘力を持つ人員を、どう配置するか、である。
相談の為に集まった皆の中で、イェアが【NAME】の方に一歩踏み出し話し始める。
「内部はほぼ一本道に近い大洞窟。広いとはいえ、数十人が常に横に並べるほどのものではありませんし、陣形はどうしても縦長の列になりますわね」
「亜獣の回避は難しい地形だし、何より狼鬼の子分みたいなのが一杯いるんだっけ?ならアタシは最前列で指揮しないと駄目か」
イェアの言葉を引き継ぐように、己の髭をぴんと弾いた男の方に、小柄な少年が近付く。
「我も、そちらに回る。後方からの挟撃が生じにくい場であるなら、戦力は前面に集中した方が良かろうよ」
「そりゃ心強いわ。取り敢えず、大盾並べて陣形組んで、疲労や負傷状況見ながら列入れ替える感じでいくわ」
「では、わたくしはその後ろで全体の状況把握と、指揮を努めます。後は、遠隔攻撃組を並べて……ノエルもこの辺りで……【NAME】さんとウィーちゃんはもしもの時の戦力としてわたくしの近くで待機、と。まぁ、こんな感じでしょうか。あ、ハマダン様は前方斥候にご協力を」
「了解だ。ただ、むしろここで考えるべきは、どう動くべきか、だろうね」
オリオールの言葉に、イェアはこくりと頷く。
「洞穴を統べる主である狼鬼の居所へ、一気に詰め寄って相手に対策を練る間や増援を送られないようにするか。それとも無理はせずに慎重を期して、極力消耗や相手の過剰な反応を誘わないようにするか」
「どちらが良い、とは一概には判断しづらいと、わたしは考えます」
淡々とノエルが告げると、ノクトワイも頷き、
「まあ、この人数で強行軍とかやっても速度は知れてる上に、兎に角纏めて戦う事になるから色々無理は出てくるでしょうね。それでも、大禍鬼の不意をつけたりするかもしれない。逆に慎重に行く場合は順番の殲滅戦になるでしょうから進むのは比較して楽になるでしょうけれど、大禍鬼にはじっくりと準備されて迎え撃たれる可能性はあるわねん」
「全てはカンファートの出方次第、という事か」
リゼラの簡潔な言葉は正に核心で、イェアも苦い顔つきで髪に手櫛を通す。
「何れだけこちらを侮ってくれるかどうか、という所ですわね。ノエルやウィーちゃんのしてくれた過去の話では、【NAME】さん相手にかなり“舐めた”態度を取っていたようですが、だからこそ対応が読み難い、といいますか。速攻を掛ければ完全な不意をつけるかもしれませんし、慎重に進んでも大した手を取ってこないかもしれない。要するに、どちらだろうと同じ、と」
「勿論、その逆も有り得るのよねん」
「まぁ……そうではありますけれども。とはいえ、どちらかに決めて進めた方が良いのは確かで、結果についてはもう、殆ど運任せになりますわね」
だから、と間に挟み、
「という訳ですので、【NAME】さんに決めて貰えます?」
「?」
いきなり話を振られて、きょとんと目を瞬かせてしまった。
何故そんな決定を自分に振ってくるのか。【NAME】が生まれた疑問そのまま言うと、
「もう何度かお話ししてる事ですけども、やっぱり大禍鬼を相手にする際に要になるのは【NAME】さんな訳でして。なら、わたくし達が決めた流れで【NAME】さんが苦労するような展開になるより、【NAME】さん自身で選んで貰った方が、どういう形になるにせよ納得していただけるかな、と」
単に責任をこちらへぶん投げているだけな気がしなくもないが、実際、主力として戦う事になる人間が、有利だと考える流れで作戦を進められるなら、その方が良いのも確かではあるのだ。
「…………」
これから突入する洞穴を、兎に角速度重視で行くか、安全重視で行くか。
正直に言ってしまうと、単なる道中の話だ。どちらを選ぼうと大禍鬼相手に大した差が生じるようにも思えない。
故に、【NAME】は然程深くは考えず、自分が好みの戦法をそのままイェア達に伝えた。
――荒ぶ禍風を断って──
【※強行軍で行くを選択した場合】
【NAME】達は強行軍で進む事に決めた。
・
――さっさと進んでさっさと殴ってさっさとおさらばしてしまおう。
そんな旨の【NAME】の発言に従う形で、軍部隊は可能な限り速度を上げて、洞穴内の進軍を行う事に決めた。
といっても、戦闘部隊のみではなく半非戦闘員等の人員を含めた大人数での進攻であるため、せいぜい駆け足程度の速度だ。しかし、巨大な洞窟の中を、盾と槍を構えた兵士達を前面に置いた一団が、一斉に突き進んでいく様は、相当な迫力を生み出していた。
当然ながら、そんな形で突然現れた闖入者達に慌てふためいたのは、洞穴内に元々棲息していた亜獣達や、洞穴の更に地下に棲むという大禍鬼の眷属と思しき狼達である。ある者は逃げだし、ある者は威嚇し、ある者は勇敢にも牙を向くが、しかし盾と槍で組み上げられた壁に容易く阻まれた。
【NAME】達はそんな彼等の反応など一切気にせず、前列に敷いた強固な編成によって存在する障害を押し流すように、ずんずんと奥へ突き進んでいく。
その順調な流れが変化したのは、洞穴の中程。下方へと続く脇道辺りに到着した辺りでの事だ。
そこで奥から現れたのは、赤と青の色彩を放つ二匹の大狼である。
この狼二匹が高く遠吠えをする。それを境にして、これまでは混乱しきり、【NAME】達に押されるままであった敵の様子が、がらりと変化した。
「指揮……というより、威圧か煽動……? 狼だけでなく、亜獣達の動きも変わりましたわ! 皆さん、ご注意を! ここで纏めて、戦いになりますわよ!」
イェアの警告の通り、これまでは殆ど逃亡を続けていた亜獣や狼達が、明確な戦意と共に、軍の突進に対して立ち向かう動きを見せ始める。
こうなると、今までの勢いだけで押していく形は危険だ。強引さを逆手に取られ、生じた隙を突かれて逆襲されかねない。
最前列で指揮していたノクトワイもそれを察したのか、素早く進軍停止の指示を出し、陣形を状況に合わせて変化させながら、亜獣と狼の大群となった敵と対峙する。
黒銃を構え、照準を前方に据えながら、ノエルが僅かに首を捻りながら呟く。
「……相手をする数自体に変化はありませんけれども、こうして纏められた分、時間は短縮出来たと考えるべきでしょうか?」
その時間の短縮に、果たして意味があったかどうか。
現状では判断がつかないところが問題ではあるが、何にせよ、ここで大きな一戦をせねばならないのは間違いないだろう。
【NAME】は愛用の武器を引き抜くと、戦いの前に緊張する兵士達の間を抜けて、ふらり、と前へと進む。
「あ、【NAME】さん!? 待って、ここはわたくし達軍の部隊に任せていただいても――」
そう、遠くで叫ぶイェアの声を無視して、【NAME】は最前列に居た二人――ノクトワイとリゼラに軽く声を掛ける。
「あらら。来ちゃったのん?」
「このような状況にあって、彼奴が後ろで日和っているような性か」
そして隣にまで上がってきた【NAME】に、リゼラは一瞥すらくれず、ただ言葉だけを寄越してくる。
「お前が来たのであれば、後は目の前の敵を倒すだけか。――征くぞ、【NAME】よ」
「あーもー! アナタ達だけで決めないのっ! 行くわよん、全軍攻撃開始!」
あれだけの数を一遍に相手にするとなると流石に厳しい。お互いが全滅するまでの殴り合いとなれば、果たしてどれだけの時間と消耗が生じるか判ったものではない。
故に、【NAME】を代表する高戦力の者がまず敵の頭であった大狼二匹を倒し、敵の動きが乱れたところを盾槍構えた兵士達が一気に突き破って敵集団の向こう側へと抜けることで、【NAME】達は洞穴の奥へと進む事に成功した。
「……にしてもこれ、こんなに無理して急いでいく必要あったのかしらん……」
剣を鞘に納めながら、ノクトワイはそんな事を呟くが、全く以て今更な話だった。
必要不必要の判断が出来なかったからこそ、行動にブレが生じないように取り敢えずの方針を定めて動いたのだ。それを後であれこれと口にしたところで何の意味も無い。
ただ、
「残党として後方に敵を残したままの進軍ですから、少々不安を残す形にはなりましたわね……」
イェアは既に突破した後方を心配げに振り返っている。
大狼二匹を倒した事で敵集団の指揮系統は完全に崩壊したらしく、少なくとも通り抜けた【NAME】達を今すぐにも追ってくる亜獣や狼は居ないようだが。
「ま、大物の相手を前にして、雑魚に無駄な力を使わずに済んだという意味では、十分に有用じゃないかな。要は、もし奴らが追ってくるにしても、その前に狼鬼を倒せば良いのだろう?」
そんな風に軽い調子で話すオリオールだったが、イェアは神妙な顔で首を横に振り、
「いえ、ここ一本道で最後は行き止まりですから、結局戻る時に戦う事になるのではないかと……」
「あー、言われてみればそうだね」
「…………」
全員、思わず黙り込むが、先刻言った通り一度選んでしまった結果だ。今更後悔してもどうなるものでもなく。気持ちを切り替えて前へと進むしかなかった。
そんな【NAME】達の正面には、狼鬼カンファートが座すると思われる、脇道深部の広間――凍てついた湖の姿が見え始めていた。
【※慎重に進軍するを選択した場合】
【NAME】は慎重に進軍する事を決めた。
・
洞穴内を慎重に進軍していく事にした【NAME】達は、順番に出現する亜獣達と戦っていく事になった。
まず現れたのは洞穴に本来棲息する亜獣達の集団だ。突然現れた人の大集団に、一部の亜獣達は逃げ出すが、多くは自分達の縄張りに入り込んだ邪魔者に対し、攻撃の姿勢を見せてきた。
そして次に出現したのは狼の群れである。驚く程の数の狼の群れが、【NAME】達の進軍を留めるように現れ、襲い掛かってきた。
最後に、下方へと続く脇道へと降りてきた時に現れたのが赤と青の、二色の体毛を持つ大狼に率いられた集団だった。彼等はリーダーである二匹の狼に従い、連携して【NAME】達を攻撃してきたのだ。
これが全て、連携して襲ってきていたなら脅威であっただろう。
しかし、それぞれがバラバラに向かってきたのであれば、話は違ってくる。
【NAME】達は武器を構えると、堅実な立ち回りを心がけながら襲ってくる敵を順々に捌いていく。
そして【NAME】達軍部隊は、立ち塞がった敵全てを悉く蹴散らしていった。
「まぁ、この程度であれば、無理に急いだりせず慎重に戦ってけば大した被害も無く倒せるわよねん」
「何より、ある程度どこに何が棲息しているかはウィーちゃんのお陰で割れていますからね。一度に大挙して、となると流石に厳しいですが、こうやって順番に戦っていくならば、梃子摺る相手ではありませんわ」
部隊を束ねる二人の発言に、【NAME】も同意の頷きを返す。どうやら、自分の選んだ方針は間違いではなかったようだ。
そして、都合三度の襲撃を問題無く処理し、地下へと続く洞穴の脇道を進んでいた【NAME】達の正面には、狼鬼カンファートが座すると思われる、脇道深部の広間――凍てついた湖の姿が見え始めていた。
【※分岐終わり】
下方に凍り付いた湖が広がる巨大な空間へと辿り着くと、まず目に付くのが湖の中央にて浮かぶ、巨狼の影だ。
――あれが狼鬼カンファートか。
そう呟いたところで、【NAME】はうん? と首を傾げる。
良く良く見ると、浮かぶ狼の姿が、うっすらと後ろに透けている。広間全体に力自体が強く満ちているのは感じるのだが、けれどもその在処がどうも、あの狼が浮かぶ場所と一致しないような気がするのだ。
しかし、【NAME】の感覚では、それ以上詳しく見極められない。
ではどうするか。【NAME】は、傍でさあやるぞとばかりに氷の上に浮かぶ狼に向かって身構えていた少女二人に話を向ける。
この二人であれば、しっかりと精査しようとすればこの場に存在する概念の状況や流れを、詳しく把握できるのではないか、と考えたのだ。
自分の中で生じた曖昧な疑念を、どう話せば他人に上手く伝わるのか。【NAME】は苦労しながら彼女等に話をする。
ノエルとウィースルゥインは一度お互いの顔を見合わせてから、【NAME】の方へと振り向くと、
「取り敢えず、あの狼の存在概念を詳しく精査すれば良いのですか?」
「変なところ、探すの?」
取り敢えず、大雑把には伝わったようだ。
【NAME】が頷くと、二人は時間にして一分程の間、揃ってじーっと、無言で正面を睨んだり、辺りを見回したりすると、揃って首を捻った。
「……どうも、狼が浮かんでいるあの場所ではなく、湖の下に、巨大な陰性概念が存在しているように、わたしには感じます。ウィースルゥイン、あなたはどうですか?」
「うん。浮かんでるの、あれ本物じゃないよ」
「……つまり、氷の下にカンファートの本体が存在していて、あれは幻、という事ですの?」
話を聞いていたらしいイェアの割り込みに、二人はうーんと考え込む。
「全然嘘、でもないみたい」
「湖の上に居る狼の姿からも、相応の存在概念を感じます。ですがその下に、同質で、もっと強大な存在概念が存在していて、そちらから上の狼の姿へ、力が供給されているように見受けられます」
「……成る程ねぇ」
対し、イェアとノクトワイは顔を見合わせて話し込む。
「となると……対狼鬼用に仕込んできた術式は、全部下の奴にぶち込んだほうが良さそうですわね」
「上の狼と、下の存在の繋がり次第って感じだけど、そうねぇ……上の狼をウチら軍の部隊で相手してる間に、少数が湖潜って下の奴を叩く形にしてみる?」
「でも、水中戦は流石に想定していませんわよ!?」
「水中……?」
と、そこでウィースルゥインは首を捻った。
「この下、何もないよ? 空っぽ。ほら」
氷面の上にウィースルゥインが上がると、その拳をとんと付けて、少しの間を空けてそこから離れた。
すると、彼女が拳を付けていた場所、湖面に張った氷の面に拳大ほどの穴が空いており、そこを覗き込んだイェアが絶句する。
「もしかしてここ、湖の氷面が凍り付いたわけではなかったんですの!?」
慌てて【NAME】も覗き見れば、一メートル程の氷の床の向こう側には、凍っていない水ではなく、角張った岩肌――つまり、洞穴の他の場所と同様の地面が広がっていたのだ。
「これなら、話は楽に進みそうねん。こっちで上の狼相手にして、気を引いている間に」
「【NAME】さんやわたくし達、あと仕込みを持ってきてる学士の子達が氷の下に潜り込んで、その先に居るであろう本体を叩く。――これで行きましょう!」
真なる楽園 (ルートB)坤濁の大禍鬼
――真なる泥鬼の宿地──
――今回は上手く事が運んだが、次はどうなるか判らない。
そんなイェアの発言がまさか呼び水となった訳ではあるまいが、ブランタンハリア山岳回廊へと移動した【NAME】達は、状況が当初の予想とは異なっている事を悟る。
短く“山”と称されていたその場所は、過去、オリオールと共に訪れた際とは地形の構造レベルで変化しており、山岳回廊を形作っていた特徴的な十の山も、その殆どが姿を消してしまっているような有り様だった。
当然、【NAME】達が以前に作った地図は全く当てにならず、それを元にしてイェアが組み立てていた作戦も、そのまま実現させる事はほぼ不可能となった。どうやら自分達という敵がこの地に訪れる事を、山に宿る鬼は既に把握し、対抗するために地形自体を変化させたようだ。同じ鬼であるカンファートの崩滅の顛末を如何なる手段を使ってか知り得たのだろう。
――ここは一度仕切り直すべきか。
そう提案するも、イェアは首を横に振り作戦の続行を決める。
既にこの行軍は撤退も停滞も出来るものではなく、進む以外に成功は有り得ないものだ。どうにかこの状況を乗り越え、ブムドゥを討伐するしかないのだ。
イェアはそう語り、そして作戦も大筋としては予定に沿った形で進めると告げた。状況は変化してはいるが、結局やる事は一つ。鬼をこの土地から切り離し、そして討伐して封じるだけなのだから。むしろこちらを敵として認識し、鬼の存在がより明確化している今の状況の方が、存在の分化自体はやりやすいかもしれないとも。
ではどうするか。その問いに、イェアは鈍い汗を額に浮かべながら、じっと考え込む。その間、【NAME】達も彼女の様子を固唾を呑んで見守った。
そうして暫くの後。
「でしたら、こうしましょう」
イェアが即興で変更した案を示す。
「事前の作戦では部隊を分けて各地に配置して土地概念へと直接干渉する印章陣を記述し、一箇所に歪みを集めて鬼を顕現させるという流れになっていました」
しかしもう、この作戦は使えない。土地概念に対する干渉行為、しかも具体的な操作を伴う行為は非常に難度が高く、ある程度その土地に対する事前情報がある事が前提だ。地形が丸ごと、土地概念のレベルにまで変化が生じているとなると、事前に意図していた結果を導き出せる確率は万に一つも無いだろう。
だが、地形自体が今のように変動し、“荒れている”状態であるならば、それを逆手に取る事で、近い状況は生み出せるかも知れない。
「今回は、最も歪みが大きい場所に直接赴き、そこで前もって用意してあった干渉制御用の印章陣複数を片っ端直接転写、土地概念に宿る歪みを制御するどころか暴走させて促進させ、それでもって鬼をより確かに、明確な形で顕現させる――過程は逆ですが、生み出す結果は同じな筈ですわ」
これが彼女の新しい案だった。
但し、この手法を採る場合、自分達に対して敵意溢れる土地を進み続け、歪みの中心地にまで辿り着いた後、そこで強大な鬼を急ぎ顕現させる事になる。そのため、事前に準備していた対鬼種の用意などは殆ど使用出来ずに、全く弱体化していない大禍鬼と、真っ向から戦わねばならなくなるという。
「厳しい戦いになりますし、被害も相応に……いえ、そもそも勝てるかどうかも怪しいかもしれません。ですが、現状、これ以上の状況を生み出す流れが思い付きませんし、そして時間を掛けている暇もありません。時を与えれば与えるほど、相手の守りは堅くなるでしょうから。――他に、何方か良い案があるというのでしたら、発言してして頂いても構いませんが、どうです?」
問い掛けに対して、皆は無言を通す。イェアの作戦には多々強引な部分が見受けられたが、しかし彼女の案以外のものを提示できるかというと否という他無く、であるならば、部隊の長を信じて動くのがもっともマシな選択肢だろう、と。
・
軍部隊は一団となって、もっとも大きく歪んでいるように見える一つの山――唯一、過去の記憶と同様の姿を残す、第七山を目指し進軍を開始する。
その際の隊列は、以下の通りとなった。
先頭には、ノクトワイ率いる主力部隊がつき、斥候先導役としてオリオールが入る。彼が持つ経験と知識により、目的地までより安全なルートを選択して貰おうという思惑からだ。
中央には、本陣として長にして指揮者のイェアと学士などの戦闘に向かない人材、また物資などを運ぶ輸送部隊が置かれた。彼女等には遠隔攻撃や感知能力を持つノエルが付き添う。
後尾には、後方からの奇襲に備えるため一部に近接重視の精鋭部隊をいくつか置き、その中で高い戦闘力を持つリゼラを隊長として据えた。過去には敵対したこともあるキヴェンティの若長と、常駐軍の兵士達。その相互理解に多少の問題は存在しているだろうが、命の遣り取りとなる戦いの中でならばそう問題にはなるまいとの判断だった。
そして、浮遊に近い移動行動が可能なウィースルゥインは、定位置を定めずに全体で危険な状況となった場所の助っ人や、概念感知の能力と高位置からの視野を活かした周囲警戒を行う役を任される事となった。
既に幾度かの戦いを経て、ウィースルゥインも完全に部隊の主力として活用し得る存在と扱われるようになっていたのだ。
そんな中。【NAME】の行動は自由裁量で好きに動いて良い、とイェアからは伝えられていた。
「貴方はわたくしの指示で動くよりも、貴方自身の考えて動いた方が、きっと皆に良い結果を齎すでしょうから」
と、厚く信頼されているとも、面倒だから投げられたとも取れる曖昧な指示であったが、勝手にして良いというのならば、勝手に最適と思われる行動をするだけだ。
部隊の中で、それぞれがどういう配置についているのかは判った。
では、自分はそんな彼等のうち、誰の所に行くのが最善なのだろうか?
【※ノクトワイ達と最前線へを選択した場合】
【NAME】はノクトワイ達と最前線へ向かう事に決めた。
・
山中を進み、歪みの最も濃い場所を目指す。
その目標を掲げて進軍を開始した軍であったが、当然ながら凄まじいまでの反攻に遭っていた。
完全に軍部隊を敵と定めた大禍鬼ブムドゥは、この土地自体に半ば同化している存在である。
故に、その力の影響範囲はブランタンハリア山岳回廊全体に及んでおり、【NAME】達の動向に関してもほぼ把握されているとみて間違いない。
つまりは、次から次へと、鬼の尖兵たる泥人形達が送り込まれかねない状況だった。
進軍を続ける【NAME】達、その最前列にて戦い続ける兵士達の前には、引っ切り無しに泥の人形が現れ、時には自分達が立っている真下や背後からも現れる。所謂盾と槍による“壁”を構築し維持出来る環境ですらなく、最前列の兵士達は比較的手軽に扱える武器を手に持ち、半ば乱戦に近い状況で泥人形達を打ち倒しながら先へと進み続けていた。
「少し、進む方向を左手側へズラした方がいいね。恐らくこのままいくと、地形を利用して囲まれるかもしれない」
「うん? ……あー、成る程。流石ハマダン様。そういった状況を見抜く眼は、本当に頼りになります」
「褒めたところで何も出ないよ。……というか、君が普段周りに話している口調に慣れていると、物凄い違和感があるね」
「その辺りはもう慣れていただくしか。ただ、左となると……」
「泥人形達が既に生まれ始めている。あれが完全に出現する前に、急いで叩いた方が良いだろうね」
「あの数となると、3連戦くらいにはなるでしょうね。……皆、行ける?」
問いに、彼に従う兵士達は無言。しかし、それぞれの顔には強い意気が感じられた。それを見てノクトワイはくくと笑い、
「じゃ、【NAME】はアタシと先陣ね。一気に行くわよん!」
刃についた泥を払い、駆け出すノクトワイ。その後を続きながら、【NAME】は進行方向の相手を見定める。
数は相当だ。泥人形の集団は、確かにノクトワイの言う通り、大まかに三つに分断されている形だ。これを各個に撃破出来るか、それとも合流されてしまうかで、戦況の有利不利は大きく変わる。速攻を掛けると即決したノクトワイの判断力は、流石という他無い。
前方のノクトワイが手にした剣が鋭く走らせ、泥人形を数体、纏めて斬り断つ様子が見えた。
負けてはいられない。【NAME】も手に持つ武器に力を込めて、新たに生じようとしていた泥人形に攻撃を仕掛ける!
山岳回廊は地形単位で大きく変化しており、既に道と呼べるものは消失している。獣道すらない状態だが、しかし本来は地表に生える樹木などもその変動に巻き込まれる形で大きくその姿を変えるか或いは消失している為、寧ろ移動速度という面でのみ語るのであれば、以前よりも上になる程であった。この辺りの事を考えるに、大禍鬼ブムドゥはあまり賢い存在ではないのだろうと、身も蓋も無い感想を抱く。
「そりゃまぁ、土地概念と半ば同化してる泥の巨人らしいからねぇ。元々がどうだったかは知らないけれども、今はもう知能なんてものは殆ど無い、殆ど衝動や反応だけで動いているような存在なんじゃないかな」
新たに現れようとした泥人形の頭部を蹴りながら、オリオールはそんな自分の推測を話す。
「だから、大きな罠とか、そういうものについてはあまり警戒しなくて良いとは思うよ。けれど、戦力比を見て退くとかそういう頭を使う動きをする可能性も低いだろうね。……まぁ、その辺りはどうでも良い話で、今問題なのは」
「隊列が殆ど意味を為してないってとこよねん。ただまぁ、どうも下から出てくる連中ってあんまりこう、集中的に出てくるわけじゃなくて気紛れに湧いてくるって感じなんだけど……」
「さっきは後列側で出たって報告、イェア嬢の方から来てたっけ?」
確か隊列の遥か後方で何やら騒いでいた様子は、【NAME】達が居る最前列からでも確認できてはいたが。
「その前は中央に派手に出てたそうよん。今、隊長殿とそのお付きの学士連中が対抗の術式組んでるからもうちょい待って、だってさ」
対抗。どうにか出来る方法を既に思い付いているのか。
【NAME】が少しの驚きと共に言うと、
「アタシ達が今歩いてる部分だけ、術式で地面を固めるだか造るだかして、“山”の土地概念から切り離された道を作るとか、なんかそんな話してたわねぇ。……あ、来たわよん」
イェア達が居る中央付近で光柱が立ち上がり、それと同時に、丁度【NAME】達が居る辺りの地面までが、淡く輝く光の幕で覆われる。
幕は【NAME】達が前進する動きと合わせるように前へと移動し、そして確かにその幕の範囲内であるならば、泥人形達が出現する事はなくなった。
「おお、こりゃ便利」
「一気に楽になったわねん。あとは、前から出てくる連中を叩きのめして進むだけか」
イェア達が展開した地面を覆う光の幕により、少なくとも下からの不意打ちが生じる可能性が大きく減じた。
この為、隊列が明確に機能し始め、進軍速度は大幅に加速する――と思いきや、そう上手くは行かなかった。
「……改めて考えてみると、こうなる可能性も十分に有り得た、と言えるかもしれないね」
「そりゃ今まで下から出てくるのが減った分、他の場所から出てくる分が増えるわよねん……」
歪みの中心、第七山を目指す【NAME】達に立ち塞がるように現れる泥の眷属達は、最初の泥人形だけではなく、もっと巨大な、泥の巨人とも言うべき者達が出現するようになっていた。
【NAME】やオリオールの記憶の中にある大禍鬼ブムドゥと同等、とまでは行かないが、それを二回りほど小さくした程度の巨人が、今も【NAME】達目掛けてゆっくりとやってくる。遠目からだと遅く見えるその動作も、尺の違いによる錯覚だ。実際目の前までくると判るがかなりの速度で、部隊の進行方向を変える程度では避けられない。
「来るわよ! 第四列、戦闘態勢!」
正面からやってくるそれに対し、既に一から三までが交代し、今最前を努めている四番目の部隊が、ノクトワイの合図に従い、巨人との戦いに身構える。
「全く、切りが無いね」
横で印章石の残りを確認しているオリオールの言葉に頷きながら、【NAME】も戦いに参加するべく、泥で汚れた武器を拭い、迫る巨人へと向けた。
battle
巨鬼の偶身
「【NAME】」
泥の巨人をようやく処理し終えた辺りで、ふわりと空中から着地する白と藍色を纏う人影があった。
やってきたのはウィースルゥインだ。これまでは上空でふわふわと隊列の各地を移動して様子を確認し、イェアに報告を送るような仕事をしていた筈だが。
「イェアに言われたの。前の方が大変そうだから、【NAME】を手伝ってあげてって」
その言葉に感激したのは【NAME】の横に居た男二人である。
「流石気が利く! ……というか、この調子でやってると前が破綻するの、ちゃんと把握してくれてたみたいねん」
「正直そろそろ、僕が戦いに混ざるのは厳しいような戦況になってきているから、交代人員は全く持って有り難いと言わざるを得ないな」
――いや、オリオールが後ろに下がって良いなどという話は一切出ていないが。
【NAME】が真顔で言うと、オリオールは暫く固まり、
「……本気かい?」
「本気も何も、ルート選定はやってもらわないと駄目ですから、前には居てもらわないと困りますよ。ついでに言わせてもらえればですね。この猫の手も借りたい状況で、一人後ろに下げるとか有り得ないでしょう」
ノクトワイの冗談気の全く無い言葉に、オリオールはがっくりと肩を落とした。
ウィースルゥインの加入により大幅に戦力が上がり、進軍速度も大幅に加速する――と思いきや、またもそう上手くは行かなかった。
「なんか! 滅茶苦茶増えてきてない!? いくらなんでも、ここまで出てくるなんて想定してないわよっ!?」
「そうなの?」
「そうだねぇ……。というか、前がもう巨人だらけじゃないか」
「人形やなんか腕みたいなのも増えてるし! せっかくウィーちゃんが来てくれても、途端にこんな増えてちゃ逆に進めなくなっちゃうわ!」
ノクトワイがわいのわいのと騒ぐのも仕方が無い状況だった。
最前衛を構築する列順の輪番は既に三周目に突入している。そろそろ第七山の目視も可能かという辺りにまでやってきている筈なのだが、その道を塞ぐ泥の眷属達がこの数では、碌に前へと進めない。
そんな中、
「ただ、妙と言えば、妙だね」
ぽつりと、目を眇めて呟いたのはオリオールである。
他の皆が懸命に戦う中、彼は少し下がって戦線から距離を置き、迫る敵の動向をじっと観察する。
「ちょっと! ハマダン様! 適当な言い訳付けて休まないでくださいよ!」
「いやいやそうじゃないよ。ただ、これは……そういう事なのか? なら、もしかすると一つ、良い案を思い付いたかもしれない」
そう、独りごちるような言葉を漏らしたオリオール。その視線は、ウィースルゥインを後ろの守りとして置き、泥の眷属と戦いを繰り広げる【NAME】に向けられていた。
・
端的に言えば、オリオールの予想はこういうものだった。
「つまり、君達が泥の眷属達を引き付けているんじゃないかと、そう思うんだよ」
【NAME】か、もしくはウィースルゥイン。泥の眷属達は神出鬼没であり、今はイェアの術式の影響によって真下からの出現は封じられているものの、そこ以外の場所には自由に出現できる。だというのに、最前列に対して泥の眷属達が殺到するのは何故なのか。それがオリオールの疑問の始まりだった。
勿論、こちらの前進を止めようとするなら正面から当たるのが常道ではあるのだが。それにしても他の方向、隊列の他の場所への襲撃が殆ど無いのが妙なのだと。
そうして迫ってくる泥の眷属達の所作を眺めるうち、出現時の彼等が標的としているのが主に【NAME】であると見切ったのだ。地上に出現した後、他の者達からの干渉を受けたりしてその標的が変わる事はある。しかし、土から姿を現すその瞬間、彼等が注意を向けているのは常に【NAME】――あるいはその後ろを守っていたウィースルゥインに対してなのではないか、と。
この推測が正しいか否か。確かめるのは簡単である。
取り敢えず【NAME】とウィースルゥインを本隊から離し、泥の眷属達の動きを観察すれば良いだけだ。
「成る程……。二人分の戦力低下は惜しいですが、当たれば大きい。試してみる価値はありそうですね」
「だろう? ただ、もしこの予測が間違いではなかった場合は、【NAME】やそこの彼女に泥の眷属達が殺到する事になるがね」
しかし、その時はこちらも身軽だ。別に戦う必要も無く、逃げ回っていればいいだけなら、何とかならなくもないだろう。
【NAME】がそう答えると、「剛胆だねぇ君は」とオリオールは苦笑いを浮かべ、
「何はともあれ。それを試すにはまず、今迫ってきているアレをどうにかしてからとしようか」
言って、視線を前へと戻す。その先を追えば、これまで幾度か出現していた泥の巨人が、何と三体。同時に現れ、こちらに向かって迫ってきていた。
巨人を断ち割ると同時に、【NAME】とウィースルゥインは崩れていく巨人達を突き抜けるようにして、軍部隊から離れていく。
「どうかな?」
全力で走る【NAME】の後方を、とん、とん、と木を蹴る勢いだけでついてくるウィースルゥインの声に辺りを見回せば、
――当たり、か?
そろそろ軍部隊の影が見えなくなる程度に離れた訳だが、しかし自分達を包む泥の眷属達の包囲は先刻までと然程変わらない。次々と生じる泥の人形、イェア達の術式の範囲から離れたが故、地面から足元を狙うように伸びてくる巨腕。そして前方にて盛り上がる影は、泥の巨人が出現する兆候だ。
この状況から考えるならば、オリオールの推測はほぼ当たりと見て良いだろう。
後は、もう一つ、調べる事がある。この結果次第では案外この後の対応は変わってくる。
「次は、どうするんだっけ」
ウィースルゥインの問いに、【NAME】は武器を振るいながら簡潔に答える。
【NAME】とウィースルゥイン、二手に分かれて、泥の眷属達の出方を見る。敵が両方を標的と定めているなら直ぐに合流し、片方のみなら狙われていない方は軍部隊に戻って彼等の援護に戻る。
「私だった時は、言われた通りにすればいいんだよね」
頷いて、そして丁度やってきた分かれ道。十メートル級の巨大な岩を境にして、【NAME】とウィースルゥインは左右に進む道を替えた。
すると、【NAME】の方へ突っ込んできていた泥人形の数が露骨に減り、そして逆側、ウィースルゥインが移動していった方向ではざわざわと様々な泥の化身が生じる気配が見える。
どうやら、ブムドゥはウィースルゥインが持つ独特の気配に刺激されて、攻撃の手を集中させていたという事らしい。
泥人形の襲撃がほぼ収まり、【NAME】が足を止めてそちらを眺めてみると、森の中から小さな白色の影が空へと上がっていくのが見える。事前に、もしウィースルゥインが標的であった場合は、一定の高さにまで空中に上がり、そこから適当に逃げ回って注意を引くだけで良いと伝えてあった。泥の眷属達は所詮は泥で出来た存在。土の重量で空へと飛んだ彼女を追うのは難しく、泥の手や槍を飛ばしたところで、ウィースルゥインが持つ“固独”の特性を貫く事は出来まい。
これで大きな障害は無くなった。後は、この隙に第七山へと進み、全ての準備を済ませてブムドゥを顕現させるだけだ。
第七山へ向かう軍部隊へ合流すべく、【NAME】は急ぎ踵を返した。
【※リゼラ達と後方警戒へを選択した場合】
【NAME】はリゼラ達と後方警戒へ向かう事に決めた。
・
隊列の後尾へと回った【NAME】は、リゼラと、そして軍の兵士達十数人と共に、周囲を警戒しながら黙々と隊列の後に続いていく。
聞こえるのはさめざめと降る小雨の音と、黙々と歩く皆の水気を含んだ足音。そして遥か前方から聞こえてくる戦いの喧噪だけだ。
「前は、かなり大変そうですねぇ。うちらはこんな調子でぼけっとしてるだけで良いんですかね?」
兵士の一人が、そう話しかけてくるが、ここにいる面子に振られている仕事は部隊後尾の警戒である。
隊列の後方は、主に学士等の直接的な戦力とは数えがたい非戦闘員や輸送物資、それらを運搬する者達が多く存在する。もしこちらに亜獣や泥の眷属達が現れた際、自分達が居なければ大きな被害が出るだろう。いくら敵が来る様子がないからといって、勝手に持ち場を離れて援護に回る訳にもいかない。
そのような旨の言葉を返すと、その兵士も「まぁ、ですよねぇ」と納得顔で頷く。
「ただ、一応うちらって今回エルツァンに来た部隊の中でも結構な腕前の連中が揃ってるとこでしてね。だからそれが、半ば遊兵相当になってるってのが自画自賛ながら勿体ないというか」
そういう兵士達は、確かにその立ち振る舞いには相応の強者らしき気配がある。とはいえ、あくまで兵士として卓越した腕を持っているという話であり、人外の力を持つといった特別な者達という訳でもないのだが。
しかし、そんな彼等を隊の殿に配置したイェアにも、彼女なりの理由がある筈だ。実際、ここに居る兵士の数は、それ程多くはない。前方で激戦が繰り広げられる事を前提に、少数の精鋭だけを後方の警戒に置き、他の戦力は全て前に注ぎ込むと、そういう戦術なのだろう。
勿論、話を振ってきた兵士もその事は判っているのだろう。だからこれは、単なる世間話。【NAME】や、そしてもう一人と交流を持とうとする程度の意味合いしか持たない会話だ。
問題は、【NAME】は兎も角としてもう一人、キヴェンティの少年は、そうしたある意味判りきった会話はあまり好まないという事だった。
実際、【NAME】と兵士が話している間も、リゼラは一言も口を挟むことは無く、そもそも聞いているのかも怪しい態で、鋭い目つきを周りに並び立つ木々へと向けていた。
そんな様子を見て、兵士は軽く肩を竦めてみせる。【NAME】は苦笑しながら、軽い身振りと小声で、彼はこういう会話は好まない事を伝えようとしたその時、
「お前達、何を悠長な事を言っている。そろそろ来るぞ」
「……は?」
いきなりの鋭く、しかし短い言葉に、兵士はぽかんと呆気に取られる。
一瞬、何を言われているのか判らず、しかし、直ぐに兵士の表情は引き締められたものへと変わった。それは、周りで話を聞いていた他の兵士達も同様だ。その少年の示唆は、自分達にそろそろ働かねばならない状況が生じる――つまり敵が来るという事なのだから。
そんな彼等に、イェアは短く指示を出す。この場の兵士達の指揮を任されているのはリゼラだ。キヴェンティの頭ではあるが、軍部隊兵士とは無縁どころか過去には敵対関係にあった彼を一隊の長に据えるというのは思いきった方針であるが、リゼラも、そして兵士達の方も、然して気にしている様子は無かった。リゼラは元々そのようなことに頓着する質ではなく、兵士達もこれまでの戦いからリゼラの強さと為人をある程度認識している。隊の長としての役割をこなすのに、少年は十分な力を持っていた。
「部隊は半分に分ける。我はお前達の内情は知らぬ。故、内訳はお前達で決めよ。左右にて散れ。【NAME】と我はこの場にて対応する」
「了解しました。……ですが、杜人殿。そろそろ来るのは判りましたが、一体何が来るので……?」
「周囲の鬼気が増した。警戒せよ、地面だけではない、他からも来るぞ」
「……他?」
会話しながらも兵士達は部隊を二手に分け、それぞれ列を囲うように左右に散る。
その様子を追っていた【NAME】は、彼等が横へと動いていく際に、その周囲に立っていた木々が、不自然というしかない、まるで意思をもつかのようにうごめき、兵士達に襲い掛かるのを見た。
慌てて迎撃する兵士達に、思わず援護に入ろうと【NAME】は動きかけて、
「何処へ行くつもりか、【NAME】」
止める声に、リゼラの方を振り返れば、隊列の真後ろから次々と泥人形が現れて【NAME】達の方へと手を伸ばし、そして彼等の合間に立つ木々も、まるで泥人形達の動きを援護するかのように、こちらへ向けて伸長させた枝を鞭のようにしならせて攻撃してくる。
「お前はここ、正面で我と共に、彼奴等の相手だ。――抜かるなよ?」
「これは、長くなるな」
短く、そう呟いたリゼラの言葉に、【NAME】は内心同意するしかなかった。
泥人形達は単体では然程強い相手ではないが、倒しても倒しても次から次へと現れ、そして枝を伸ばし攻撃してくる木々は、外見上は普通の木と殆ど見分けが付かず、移動こそしない為一定の距離さえ取ればその攻撃は届かなくなるが、その頃にはまた別の近くに生えた木が、こちらに対して攻撃を仕掛けてくるようになるのだ。
つまり、襲ってくる木に限って言うならば反撃するだけ無駄で、ただ凌ぐしかない。泥人形の方はより状況は酷く、凌ぐだけでなく、倒せるだけ倒していかねば総数が増えて、何れ押し切られてしまう事になるだろう。どちらも、厄介な相手だった。
隊列後方の左右に展開した兵士達は流石自賛するだけあって良く働いており、見事な壁となって敵の攻撃を隊列の内側へと通さないよう留めている。
「根本を断たねば収まらぬが、それを目指し前へ進むのが今の我等の道行だ。であるならば、性には合わぬが暫くは守りの一手を貫くしかあるまいな」
泥人形の首を一撃で刎ねながら、リゼラは淡々と呟く。
【NAME】は隊列の前方を見るが、未だ目的地である第七山は煙る小雨の向こうで、霞む姿すら見出す事は出来なかった。
「…………」
リゼラの言う通り、長い戦いになりそうだった。
――真なる泥鬼の宿地──
「…………」
泥人形、そして動く木々の攻撃を延々と捌きながら、前へと進む軍に続いていた【NAME】達であったが、徐々にだが襲撃の頻度が下がっていき、ついには新しい泥人形も、木々が動き出す事もなくなった。
理由は判らないが、どうやら一段落ついたようだ。
そう判断し、安堵の吐息と共に武器に付いた泥を払った【NAME】は、隣で戦っていたリゼラがぴたりと身動きを止めて、硬直しているの事に気づいた。
どうかしたのか、と彼を見ると、リゼラは遠く、浅い斜面となっていた現在地から山側の方向を暫く睨むように見ていた。その先にある何かを、見定めようとするかのように。
一体何がと【NAME】も同じようにそちらを見るが、木々に覆われた視界は狭く、何も見出す事は出来ない。
ただ、何か小さく、地響きのような音が遠くから響いてきているような気がした。
(……これは?)
思い、そして解答を内で得る前に、隣に居たリゼラは大きく息を吸うと、隊列の中央目掛けて
「――後方より警告! 総員、前方へ50メートル! 急ぎ詰めよ! 左方より流水が来るぞ!」
そしてリゼラは素早く走ると、荷車の後ろに回り、全力で押し始める。
突然のリゼラの行為に、部隊全員が一瞬虚を付かれて固まったが、しかし少年が必死に荷車を押して少しでも前方へと移動させようとしているのを見て、慌てて動き出す。身軽な者は急ぎ前へと走り、力ある者達は荷車等の大荷物や動きの鈍い者を拾い上げて前へと進む。隊列の最前列では泥人形達との戦闘は続いているようで、前へと詰められる隙間はそれほど多くはない。横に脹れ、半ば隊列が円形になる程に変化した時。
山側となる斜面から突如現れた濁流が、轟音と共につい先程まで隊列の後尾組が居たあたりを突き抜けていく。
岩や、木、土の塊。それらが混じり合った鉄砲水が、まるで【NAME】達を狙っていたかのように通り過ぎる。更に、その高速で流れていく泥水の表面が一瞬膨れ上がり、そこから矢のように飛び出してきた影が、半ば茫然とその様子を眺めていた【NAME】達の不意を突くように襲い掛かってくる!
【NAME】達が立つ場所ぎりぎりを通り過ぎていく濁流は、その水面を矢のように飛び跳ね、【NAME】達に襲い掛かってきた影達を処理する頃には、すっかり収まっていた。
鉄砲水から飛び出し襲ってきたもの。斬り捨て、地面に転がったそれは、泥で出来た魚を模した化生。つまりは、これまで襲ってきていた泥の眷属と同様の代物だった。
そして、
「これは……」
「おいおいまたかこれ……?」
ざわざわと兵士達が騒ぎ始める。理由は簡単だ。先刻と同様の地響きが、またどこかからし始めたからだ。
「大禍の鬼ブムドゥは、土地そのものと同化している。ならば先刻の木と同様、この唐突な鉄砲水も、奴から我等に対する攻撃の一つであろうな。心せよ、お前達。我等は、この地そのものと戦っているのだと」
リゼラがそう語る間に、地響きが大きくなっていく。今度はリゼラが指示を出す前に、中央のイェアから通達が来た。前進の停止。見れば、先刻まで泥の人形達で溢れていた隊の前方には、何の影も無くなっている。どうやら、泥の眷属達の消滅が、先刻のような泥の水流による攻撃の前兆となっているようだ。
「前列は十分に警戒を! 水流がくると同時に、泥の眷属が飛び出してきますわ!」
【NAME】達の様子を確認していたらしいイェアが、素早く追加の警告を飛ばすのが聞こえた。
「……この調子では、目的地に辿り着くのはまだまだ刻が必要なようだな」
ブムドゥが一度水流を起こす度に、部隊の進行に大きな影響が出る事になるだろう。リゼラの言葉に、【NAME】は全くと溜息と共に返すしかなかった。
泥の眷属による波状攻撃と、時折襲う水流による分断攻撃。それらを受け続けた軍部隊は大きく疲弊していった。
しかし、それでも着実に目的地である第七山への距離を縮め続けた【NAME】達は、ようやく、その姿が前方彼方に見える程度にまでやってきた。
後は第七山の周囲にて準備を行い、第七山を起点にしてブムドゥを顕現させるという流れになるのだが、当然ながらというべきか、この山岳回廊の中で最大の歪みを持つ第七山に近付けば近付くほど、現れる泥の眷属は強力なものへと変化していた。
特に、第七山が見える位置にまで近付いた辺りで出現するようになった、地面より生える泥の巨大な腕の化生。これが他の泥の眷属――泥の大巨人よりも手強い存在であった。
その腕単体が、泥の巨人と同等に近い大きさを持つ上、兎に角力が強く、そして動きが速いのだ。泥より生えた腕という存在である故、移動能力は無いのだが、何せその腕をぐるりと一度旋回させるだけで、周囲全てが薙ぎ払われる。手で握られれば容易く身は潰れ、そのまま投げられれば彼方まで飛ばされる。秘めた陰性概念の強さも他より上で、放つ歪みは術式にも似た効果を及ぼす。鬼種の格で表すならば禍鬼級には十分届くほどの難敵だった。
これが次々と、生えては消え、生えては消えを繰り返すのだからたまったものではない。進軍途中からイェア達学士が展開した、地面より泥の眷属達を生じさせないようにする結界術式を破って出現まではしないのが辛うじて救いとなっていた。もし、隊列の真中にこれが出現する事があれば、部隊は一瞬にして壊滅していただろう。
腕をどうにか破壊し前へと進み、更に現れる腕を破壊し、前へと進む。それを繰り返し続けた軍部隊は、ようやく第七山の麓に近い泥の川縁へと辿り着く。
後はここで、術士学士達が印章陣を展開し、第七山の歪みを加速させてブムドゥを顕現させるだけ、なのだが。
「もう少し、安全圏を広げないと、印章陣の準備なんてやってられないわねん……」
「ええ。他の泥のお化けはともかく、あの泥の腕は兎に角長いですから、もう少し距離を取らないと、奥にまで手が届いちゃいます」
既に軍部隊の列は形を変えており、イェア達が敷く泥の眷属が地面から出てこれないようにする結界を中心にした円陣へと変化している。隊列の各地に散らばっていたノクトワイやオリオール、ノエル達と一旦合流した【NAME】達は、ノクトワイとイェアから新たな指示を得る。
「と言う訳で、結界の範囲を広げますが、それをするにはその範囲内にいる泥のお化け――特に土から直接生えたままの腕の化け物は全て処理しないとなりませんわ」
「アタシとハマダン様は隊の右に生えてる腕をやるわ。ノエルとウィーちゃんは左側お願い。【NAME】達はそこ以外――大分担当広くなるけれど、アナタ達二人なら、行けるでしょ?」
「引き受けよう」
【NAME】が返事をする前に、リゼラが短く答え、そして即座に動き出す。相変わらず、判断と動きが速い。【NAME】は慌ててその後を追った。
通り過ぎていく木々の合間、兵士達を狙おうと動く巨大な腕の数は三本。距離的にはかなり離れているが、泥腕の長さから考えると互いに連携が可能な配置だ。
素直に行くのは危険。そう判断する【NAME】であったが、
「纏めて狩る。征くぞ」
言い捨て、こちらを置いていくかのように速度を更に上げるリゼラに、【NAME】は呆れと感心が入り交じった吐息を一つこぼしてから、彼に劣らぬ速度で、【NAME】達の存在に気づき迎撃の動きを取り始めた泥腕達に襲い掛かる!
結界の範囲内にあった泥腕を全て破壊し終えた【NAME】達は、学士達が全ての準備を終えるのをただ待つ。
合計にして九つ。加えてそれらを制御するための複数の印章陣。それら全てを用意するには相応の時間が必要であり、【NAME】達はその間、結界の外より湧いて出て襲い掛かってくる泥人形達と戦い続ける必要があった。
結界の範囲が広がった事が理由なのか、純粋な地形的な問題、あるいはこちらが想像しえない何かがあるのか。ここまでくる間、何度か襲ってきた濁流による攻撃が来なかったのが数少ない救いだった。あれが印章陣を準備している最中に叩き込まれていたなら、作戦はあっさりと瓦解していただろう。
そうして、暫くの時間が過ぎた後。円陣の中央に描かれた巨大な印章陣の上に立つイェアが、拡声の術式を併用して叫ぶ声が聞こえた。
「印章陣、一番から九番まで、総駆動! ――出ますわよっ!」
【※イェア達の護衛に回るを選択した場合】
【NAME】はイェア達の護衛に回る事に決めた。
・
部隊の長を務めるイェアは、当然ながら隊列の中心。隊列の全てが確認でき、指揮する事が可能な上で、尚且つ最も安全と考えられる場所に位置取っていた。 指揮者が前線に出て、もし何かがあったら隊の瓦解は確実だ。故に、当然の配置であり、そしてそんな彼女をもしもの時の襲撃から守る護衛役が必要なのも、また当然の話であるのだが。
「【NAME】さん、暇そうですわね」
そう話しかけてきたイェアは、視線すらこちらに向けてはおらず、各所からくる伝令や上空のウィースルゥインの報告を受け、細かい指示を伝え、時には拡声術式を併用して直接伝える作業を続けていた。そんな忙しい中、横で生あくびをしていたのがばれていたのは驚きだった。
一応護衛として近くに居るとはいえ、邪魔をしないようにと彼女に一度も話しかけずにいたこちらに対しても、彼女はある程度の気を向けてはいたらしい。
「退屈でしたら、ノエルと一緒に前衛の方々の援護でもやっていて頂いても構いませんわよ? ただ、一応わたくしの護衛役を申し出てくれたのですから、それを完全にほっぽり出す勢いで前線まで行かれても困っちゃいますけれど」
あくまで、ここから術式などを使った遠隔攻撃での援護ならしていても良い、という事らしい。
実際、【NAME】とイェアが居る位置から少し離れた場所にて展開している、主に弩弓や弓兵を集めた部隊の中で、一人荷車に積まれた荷物の更に上に立って射角を確保し、前方目掛け黒銃フォーレミュートの引き金を引き続けているノエルの姿もある。彼女に混じってそうした行為に勤しむのも、戦況をより良い形へ持っていくのならば悪い選択肢では無いのかもしれない。わざわざ隊列の中央に突如敵が襲撃を掛けてくる可能性も低いだろう。
そう、【NAME】が判断した時。全く真逆の結果が、突如として生じる。
最初に起きたのは真下からの地響きだ。そして強烈な陰性質の概念が、イェアや【NAME】が立つ位置へと急速に集まってくるのを感じた。
「――――」
隊列中央に居た全員が、何かの前兆を思わせるその変化に、ぴたりと動きを止めた。
だが、その中で唯一。【NAME】だけは、目の前に居たイェアの腰に腕を引っかけると、全力で後方へと投げ捨てたのだ。
「ちょ、あ、えーっ!?」
一体何が起きたのか、何をされたのかも、いまいち理解出来てない表情を浮かべたイェアの身体が数メートルほど飛んでいき、近くに居た兵士が慌てて彼女を受け止める。
その次の瞬間。先刻までイェアが居た場所――つまり【NAME】の目の前に、直径にして数メートルはあろうかという巨大な拳が、地面から凄まじい勢いで突き上がったのだ。
現れたのは、泥で出来た巨大な腕である。伸ばされた腕の長さは十メートルを優に超える巨大なもの。どうやら、直接こちらの部隊の頭を狙ってきたらしい。 まさかそのような事を相手が理解していたとは意外だったが、今はそんな事を感心している場合ではない。突き上げによる初撃が躱された泥腕は、ぴんと伸びたその身を、ぐねりと捩じ曲げ、振るような動きを見せる。
――まずい。
その前動作から、泥腕が次に何をするのかは明白だった。ぐるりと、腕が生えた場所を基点に大きく振り回すつもりなのだ。
泥腕が現れたのは隊列の中央。周囲には非戦闘員や主に遠隔武器を手にした者達、更には物資を運ぶ荷車などもいくつか存在している。突然現れた泥腕に茫然と動きを止めている者達が殆どの中、この腕がそのようなアクションを行えば、大惨事という他無い結果が生じるだろう。
急ぎ、武器を引き抜くと眼前の上目掛けて、ありったけの力を込めて技法を放つ。
相手は泥ながら、相応の手応えが返り、攻撃を仕掛けようとしていた泥腕が大きく揺れて、その動きが中断される。
しかし、これで一安心などと言える状況ではなかった。何故なら、他の場所でも同様の揺れが生じ、陰性概念が集中していく気配を感じたからだ。
その数は更に二つ。地面が揺れて割れ、新たな腕が二本生じる。ここでようやく状況を飲み込んだ者達が応戦や待避の姿勢を見せ始めるが、どちらも動きが鈍い。
「――ッ」
小さく舌打ちしながら、【NAME】はイェアと、そしてノエルの名を叫ぶ。状況を打破するには彼女達の力が必要だった。
その声にまず応えたのはノエルである。彼女は前方へと向けていた黒銃の照準を素早く移し、
「牽制します! 【NAME】はその間に、各個に撃破を!」
黒銃から放たれた光条が、周囲へ攻撃しようとする泥腕達の動きを制するように突き刺さる。三つの標的、それぞれの状態を見ながら、的確に放たれる黒銃の狙撃は、泥腕の直ぐ傍に居た者達が待避するだけの時間を稼いでいく。
そして、
「迂闊でした……。術士、兵士達は急ぎ対応を! 射撃武器は十分な射角を取って、広範囲の術式は控えなさい! 味方にも被害が出ますわ! あと、学士達は、後方へ一旦後退を! 最低、わたくし達が立っている場所の安全を確保します。術式の準備を始めなさい!」
イェアは実戦には向かぬ学士達だけを集めて状況に対処する為の術式を組むつもりであるらしい。確かに、このまま次から次へと隊列の真中から泥の眷属が湧いてきては、隊列の意味自体が消失する。
そしてイェアは【NAME】の方へと振り向き、
「【NAME】さん! 申し訳ありませんが、ここはどうか、宜しくお願い致します!」
言われるまでもない。何せ自分は、彼女の護衛としてここに居たのだから。
「……派手にやられましたわね」
地中より伸びた三本の腕。【NAME】はノエルの補助の元、それらを各個に撃破していったが、全くの被害を出さずに全てを終わらせるという訳には流石に行かず。
幾人かは泥腕の攻撃に捕まり負傷し、物資の幾つかも荷車ごと破壊されてしまっていた。物資に関しては、もうこのまま投棄していくしかないだろう。
「今、後ろに下げた学士達に、急いで術式を組ませていますが、完成までにはもう少し掛かりそうですわ。取り敢えず、このまま進軍を止めていては、今も戦い続けている前衛組の負担が大きくなります。兎に角、前進を再開しましょう」
その術式が駆動できる状態になるまでは、今回のような唐突な襲撃を警戒する必要があるという事か。
「的確にわたくしが居る場所を狙ってきたあたり、警戒というよりは、更なる襲撃が当然あると考えるべきでしょうね。心苦しいですが、副隊長から前衛に回している兵士のいくらかを中央に回して貰います。流石に、近接戦闘をこなせる要員が【NAME】さんだけでは、負担が大きすぎますから」
――最初に思っていたよりは、何やら厄介な状況になってしまったものだ。
【NAME】がついた深い溜息の音は、未だ降り続ける小雨の音と、進軍を再開した兵士達の足音に紛れて誰にも届かずに消えていった。
――真なる泥鬼の宿地──
その後も、隊列中央を標的とした泥の眷属の襲撃は幾度か発生していた。
流石に二度目以降ともなれば、軍部隊も相応の警戒と心構えが出来ている。前衛側からの応援人員もあり対処は迅速かつ順調に行われたが、しかしそろそろイェアの配下である学士達が、一定範囲内の土地から泥の眷属が生じるのを封じるという術式を完成させようという時。まるでそれを察知しているかのように、一際大きな襲撃が行われた。
「……結構、一気に来ましたわね」
地面が沸き立ち、現れるのは泥の人形、泥の巨人、そして泥の巨腕だ。巨腕が持つ存在概念は、泥の巨人よりも強固で陰の気が濃く、鬼種としてみるならばこちらのほうが上位である。その巨腕の眷属は、どうも報告を聞く限りでは部隊前列にて進軍を食い止めようとしている集団の中では存在が確認されていないという。
要するに、どういう基準による判断かは判らないが、この隊列中央に眷属を集中するべきと、山岳回廊の土地に根付く大禍鬼は考えているようだった。
「数は多いですが、この二波を防ぎさえすれば、術式は完成させられますわ! 皆さん、全力で対応を!」
学士達が組み上げたという術式は、少なくとも隊列中央を標的にして行われていた襲撃に対しては、極めて大きな効果を齎した。
術式の効果は、一定範囲内の地面に対して干渉を行い、土地概念を切り離して掌握。術者の制御下にある独自の大地へと変化させるというものだ。術式としてはかなり大仰なもので、更に術式は常時駆動を求められる。故に学士達は術式を輪番にて交代しながら維持しつつ移動を行うという無茶を強いられる形となったが、隊列中央は疎か、前衛組も足元からの襲撃という事を気にせずに良くなった分、進軍速度は大幅に上がる事となった。
そうして、【NAME】達はようやくにして、地形自体が大きく変化したブランタンハリア山岳回廊にて、唯一以前の姿のまま残されていた第七山に辿り着く。
その周囲は泥の濁流によって封じられ、立ち入る事は難しいが、イェアが言うには、別に中へ入り込む必要はないという。その周辺にて印章陣を構築し、山自体に干渉を掛ける形となるため、寧ろ後の事を考えれば山の中に入る方が危険であるらしい。
これ以上歪みに近付かなくて良いというのは有り難い話ではあったが、しかし状況は依然厳しい。度重なる襲撃により軍全体の消耗が激しく、更に未だ攻撃が続く中、ブムドゥを完全顕現させる為に幾つもの印章陣をここで準備しなければならないのだ。
【NAME】はイェアの護衛という役目であるため、殆ど戦いには参加出来ない状態で、術式の構築と同時に学士達へと指示するイェアの傍に付き、遠くで行われている皆の奮戦を眺めているしかできない。
じりじりと時間が過ぎて、各部隊から被害報告も多く入るようになってきていた。
まだか、まだか、と待ち続ける中。
ようやくイェアが面を上げて、遠くの隊員にまで聞こえるように、拡声術式を併用して大声を上げた。
「皆さん、お待たせしました! 今より大禍鬼ブムドゥの顕現作業を行います!」
【※ウィースルゥインと遊撃を選択した場合】
【NAME】はウィースルゥインと遊撃を行う事に決めた。
・
「でも、【NAME】は飛べるの?」
「…………」
行動を決め、一通りウィースルゥインに喜ばれた後。彼女の率直な質問に、【NAME】は思わず黙り込む。
言われてみれば、彼女は空中に浮かんで移動することで自由に部隊内を移動出来るからこそ、遊撃と全体補助、そして全体警戒の役目を任されていたのだ。
ならばウィースルゥインと同様に空中を移動出来なければ、共に動く事など出来ないし、逆にウィースルゥインが【NAME】に合わせて地面を歩いて移動するのはその利点全てを台無しにする事になる。
――どうしよう。
我ながら迂闊な選択をしてしまった。
これは今から別の所のフォローに変更しようか、と頭を抱える【NAME】だったが。
「取り敢えず、今あるところのお手伝いしてから考えよ」
全く建設的な意見に、反論もない。
ウィースルゥインは多少の高度を取ってふわふわと、【NAME】は兵士達の間を苦労して割っていきながら、まずは最前線になるであろう前列の援護へ入る事にした。
到着した頃には、既に戦いの真っ最中であった。
正面から現れる亜獣、そして泥の眷属。オリオールの先導の元、ノクトワイの指揮により現れるそれらを撃破していく。
「それじゃ、やろうか」
ウィースルゥインの言葉に頷き、【NAME】も愛用の武器を構え、彼等に混じり、繰り広げられる戦いに参加していく!
「なんつーか……思ったより激しかったわねん」
「僕なりに、楽に進める上で、敵が少ない、それらが両立できるルートを選択しているつもりなんだが、確かに遭遇率が高いね。特に、泥の亜獣達」
オリオールの言葉に、皆が頷く。
「倒せないという程ではないんだが、襲撃の頻度が進む度に上がっている。勿論、歪みの強い場所を目指して向かっているのだから当然だという解釈はできるのだけど……」
冒険家は、どうもしっくりこないという風に首を捻るが、答えは出ないようで、結局肩を竦めて話題を打ち切る。
「取り敢えず、先に進むとしよう」
「そうねん。止まってても仕様が無いし。――あ、そうだ、【NAME】」
? と首を傾げると、ポンと紙片を押しつけられる。
「列の真ん中に居る隊長殿へこれ渡しといて。いまんところの状況の手控え。あと、そろそろ正面以外から敵が来る可能性も考えられるから、暫くそっちで警戒しといてあげて」
了解、と【NAME】は紙片を受け取って、列の移動を開始しようとする。
だが、人の波と逆へと移動するのはなかなかに厄介だ。元々人が通れるほどの道もない場所を進んでいる。避けるというのも難しく、素直にイェア達が来るまで立ち止まって待っているべきか、と考えていると、突然、背中に妙な重みを感じた。
「一緒に飛べば直ぐよ」
真後ろから声。視界の隅で揺れる髪。胴に回された両の手はしっかりと前で結ばれている。その手、その髪、その声。組み合わせれば誰かは判る。
どうやらウィースルゥインが背中にくっついているらしい。そう認識した時、ふわりと、自分の足裏が地面から離れるのを感じた。
本当に、一緒なら飛べるらしい。
それは判ったのだが。
「「…………」」
すれ違っていく兵士達が向けてくる視線が兎に角痛かった。
前衛から離れ、伝令がてらイェア達の居る隊列中央付近の援護と警戒に回ってみる。
すると、【NAME】達が丁度そちらへ移動すると同時に、タイミングが良いのか悪いのか、泥の巨腕や巨人が周囲の地面から生え、イェア達に攻撃を始めようとしていた。
――こちらに移動したのは正解だったか。
そう思いながら、【NAME】は素早く彼女等の救援に入る。
隊列の中央となると、本来は攻められ難い場所だ。それにしては、敵の攻撃が激しい。
飛び散った泥で汚れた顔を拭いながら、イェアが怪訝と眉を顰める。
「泥鬼が、わたくし達人間の隊列の意味――中央に指揮をするわたくしが居ると狙いを付けて攻撃している、というのは考えづらいのですが……」
例えばこれが亜獣や肉食動物などであれば、獲物として狩るために集団の中で弱いと思しき者達に攻撃を集中させようとするのは判る。
しかし相手は大禍鬼の眷属である。その目的は兎に角こちらの殲滅だろう。どうせ全てを殺すつもりであるのならば、わざわざ中央に戦力を集中させるような小手先の行動を取るというのも妙な話だ。
「取り敢えず、相手の勢いはどうにか弱まってきたようです。あまりここばかりに【NAME】さん達を引き留めるのも他の場所に悪いですから、別の場所の援護にも行ってあげてくださいな」
確かに、イェアの言う通り敵の襲撃は一旦収まっている。一応、何かがあれば直ぐに中央に戻れるよう意識しながら、【NAME】達は彼女の指示に従う事にした。
前列、中列、と来たのだから、残るは、
「後ろ、行くの?」
ウィースルゥインの言葉に、【NAME】は短く頷いた。
「【NAME】。それに、彼の娘子も一緒か」
迎えたのはリゼラだ。周りには一時的に彼の指揮下に入っている兵士達が、周囲を警戒しながら目礼だけを飛ばしてくる。
【NAME】とウィースルゥインはリゼラの傍に着地すると、彼にこれまでの後列の状況を訊ねる。すると、リゼラはつまらなさ気に肩を竦め、
「万事何事も無く、だ。何やら前方で煩く騒いでいるらしいのは見えていたがな。何故かこちらには泥の巨腕どころか、泥人形すら現れぬ。相手にしたのは、せいぜいが幾匹かの亜獣程度で――」
と、そこでリゼラの言葉が途切れる。少年の足が止まり、目が細められる。彼の周りで警戒していた兵士達も、その雰囲気を強い緊張に変化させていた。
彼等の変化の理由は、【NAME】にも判る。
「これが、前で暴れていた泥腕の鬼とやらか。一つ一つはそれ程では無いが、この数となると油断は出来ぬか。お前達、攻める必要は無い。互いが互いの足元を守れ。その間に、我と【NAME】で始末を付ける」
勝手に面倒な仕事を回された気がするが、しかしそうする事がもっとも被害無く、そしてスムーズに処理出来るであろう事は【NAME】にも理解出来ていたため、異論無く武器を構える。
「杜人の方。私は?」
「お前は上にでも浮かんで、兵士共の助けをしてやれ。我等には構うなよ。邪魔になる」
「むんー」
少し不満そうな声を上げながらも、ウィースルゥインはふわりと高度を上げる。泥腕の鬼は地面からその手を伸ばす。つまり高度を取れるウィースルゥインは非常に有利な存在だ。地上に張り付かせるよりも上から援護をさせたほうが有用なのは語るまでもない。
「ではやるか、【NAME】よ。それにしても――」
リゼラは一瞬、【NAME】の顔を見上げて判るか判らないか程度の小さな笑みを作り、
「――まるでお前が、我等の退屈を紛らわせるために、この鬼共を連れてきてくれたかのようだな」
それは恐らく、彼流の冗談だったのだろう。言った瞬間、既に少年の姿はそこにはなく、銀色の刃が跳ねるように前方へと走るのが見えた。
しかし、【NAME】は少しの間、彼の動きを追えずに固まってしまう。
彼の冗談。しかしこれは、本当に冗談であったのだろうか、と。
リゼラの言葉を聞いてから、【NAME】は戦いながらも、よくよく、鬼の動きを観察する事にした。
すると、気づいた事が一つ。今まで何故気づかなかったのかと呆れてしまう程に、泥の鬼達の動きに特徴があったのだ。
「……もう」
地面から空中へ。伸ばされる複数の手を、ウィースルゥインが煩わしげに髪の先で貫き、枝別れとすることで破裂させる。彼女にとっては己の身に触れさせる事すらさせない、まさに雑魚相手の戦いであるのだが、しかし彼女が狙われる頻度が、他の者達と比べると雲泥の差なのだ。ウィースルゥインを上へと逃し、そしてリゼラから偶然の示唆を受けたからこそ、一目で判った。そして、鬼達が出現するパターンについても、そこを起点にして考える事で直ぐに答えが出た。
理由までは判らないが、
(こいつらが狙っているのは……ウィースルゥインか?)
成る程、自分達が前列、中列、後列と移動していく度に鬼が襲ってくる訳である。狙われているのがウィースルゥインなら、自分達が移動した先で鬼が襲ってくる流れになるのも当然だ。
【NAME】は近くに戻ってきていたリゼラに、手短にその予想を話すと、彼は浅く吐息をつき、
「あの娘子を、軍部隊から一度離して逃げ回らせろ。そうすれば、一気に状況は進む。しかし、恐らくは大丈夫であろうが念のためだ。【NAME】、お前はついていってやれ」
その言葉に、【NAME】は小さく笑ってしまう。
普段、ウィースルゥインには突き放したような言葉ばかりの彼であるが、やはりそれなりに、ウィースルゥインの身を案じてはいるらしい。
【NAME】にそれを察せられたのに気づいたか、彼は渋面のまま小さく舌打ちすると、
「急げよ」
短く伝えた後、未だ現れる泥人形へと向かっていった。
「【NAME】。何処行けば良いの?」
ぶらんとウィースルゥインに抱きかかえられる形で空中を移動していた【NAME】は、背中からの声に、取り敢えず軍部隊から離れて、あとは適当にぶらぶら、と非常に無計画な指示を出す。
だが、言われたウィースルゥインの方は別段気を悪くする風でも無く、むしろ嬉しそうに身体を揺らすと、背中から抱きつくように掴まえている【NAME】の身体を持ち直しながら、ふわふわと軍部隊とも、目的地である第七山とも違う方向へと進んでいく。
下方、意識を集中すると、葉茂る木々に隠れた地面が時折泡立ち、陰性質の概念が【NAME】達の移動する方へ目掛けてどんどんと集まってきているのが感じ取れる。
どうやら、先刻の予想は大当たり。この土地に巣くう泥鬼の意思は、少なくとも軍部隊全員よりも、ウィースルゥインと【NAME】の事を脅威と認識しているらしい。
その判断の正否は兎も角、【NAME】達としては非常に有り難い状況だ。【NAME】達の作戦は、軍部隊が大量の印章陣を用意し駆動させることで大禍鬼を現世界に顕現させ、土地概念と切り離す事をまず最初の目標としている。それが出来るのは自分達ではなくイェアと彼女が指揮する学士術士の部隊だけだ。
これまでの大きな問題として考えられていたのが、複数の印章陣を大禍鬼のお膝元、もっとも歪が集中している第七山付近にて記述展開しないといけない部分だ。これを【NAME】達が囮となることで大禍鬼の注意を彼等から逸らせるならば、成功率は大幅に上がる。
「なら、一杯暴れた方がいいんじゃないかな?」
言われてみるとその通りなのだが、しかし流石に注意を引きつけすぎると自分達の身が危なくなる。空中という比較的安全圏を彷徨き回る程度でも大丈夫だろう、と【NAME】が言うと、背後の気配が、少し不機嫌そうなものへと変わる。
「【NAME】。私は、もっと【NAME】の役に立ちたい。わたしは一杯一杯、そう願ってた。だから私も、一杯一杯、そう思ってるの。だから、危なくないようにとか、気にしなくていいよ。ううん、もっと、危ないこと、私にしてくれていいから」
回された腕に、く、と小さく力がこもるのを感じた。
「安心してね。私が、ちゃんと貴方を、守ってあげる」
「…………」
思わず苦笑してしまう。視界の端で揺れる藍色の髪が、こちらの身体を、おっかなびっくり、触れたり、巻き付いたりするのも、彼女の言う守るという意思の表れなのだろうか。
彼女の提案。それ自体は、そう間違ったものではない。自分達に注意を向けさせ、こちらのリスクを高めることで、軍部隊のリスクは逆に大きく下がるだろう。それは確実に、泥鬼の顕現と討伐という目標に近付く。問題は、どの程度派手に暴れるとどの程度大禍鬼の気が惹けるのか。要するに、自分達の力でどうにか収められる範囲が読めない、という所だが。
「大丈夫。きっと、私と貴方なら、鬼がそのまま来ちゃっても、勝てちゃうよ」
そう軽々しく言うウィースルゥインだが、本音を言えば、【NAME】も同意見であったりもするのだ。
【NAME】はくく、と喉を鳴らすように笑ってから、ウィースルゥインに一つ指示を出す。
――大禍鬼がこちらを放っとけないくらいに、盛大なのを一発、真下にくれてやれ、と。
「ん」
変化した藍色の髪先は合計五つ。偽りの竜の顎から放たれた黒弾が、地面を十メートル単位でえぐり取り、その後の爆発でその五倍近くの土地を更地へと変える。
それを見届けてから、【NAME】と彼女が地面へと降りる。すると、強烈な震動と共に平らになった地面が波打つように歪んで、そこから今まで以上の泥の形代が姿を現す。
泥人形。泥腕。更には、泥の大巨人。数は正に無数で、瞬時に数えきれるような量ではない。
「豊作ね」
或いは大漁か。
【NAME】達をぐるりと囲み込む泥造りの存在は、全身から害意を発し、背中合せで立つ【NAME】達に襲い掛かってくる!
「そろそろ、みんな準備終わったかな」
右の振りで泥人形を切り裂き、左の振りで泥腕を割り断ち、正面へと突き出した藍の髪の大鳥が、大巨人の頭を吹き飛ばす。
それらの動作をこなしながらのウィースルゥインの質問に、同じく泥の眷属達を蹴散らしていた【NAME】は木々の向こうに見える山を見据える。
過去に調べた十山の中で、唯一残る第七山。その周囲の詳細までは見えないが――所々でぼんやりと、印章の輝きが放ち始めているのが辛うじて見える。
終わったかどうかは判断し難いが、しかしそろそろ自分達は戻り始めても問題は無いように思う。
何せ、ここに現れた泥の眷属達は、もうその殆どを二人で処理してしまったからだ。
「なら、後は放っておいて、行こ」
どん、と背中に抱きつかれる感触。続いて、ふわりと身体が空中へと浮かぶ。下方から、残された泥の眷属達が放つ泥槍の群れが飛来するが、その全ては、ウィースルゥインがたなびかせる藍髪の守りを突破出来ない。
「ちゃんと、ノエル達が安全にお仕事できてたら、いいんだけど」
それについては、行ってみないと判らない。背後から泥の眷属達から追い掛けられている身としては、出来ればこちらが合流すると同時あたりに印章陣が駆動し、大禍鬼ブムドゥが顕現してくれると有り難いのだが。
そう思っていた所に、正面、目指す第七山の下方で、発光する弾が上空高くへと連続して放たれるのを見た。
あれは恐らく、
「準備出来たよ、っていう事かな?」
であるならば、遠慮無く急いで戻った方が良さそうだ。
【※分岐終わり】
――坤濁の大禍鬼──
【※リゼラ達と後方警戒へを選択した場合】
地形自体が大きく変化したブランタンハリア山岳回廊にて、唯一以前の姿のまま残されていた第七山。その周囲は泥の濁流によって封じられ、立ち入る事は難しいが、イェアが言うには、別に中へ入り込む必要はないという。
その言葉の通り、軍部隊は山の縁にて幾つもの印章陣を展開し、それぞれに術の要たる学士が陣の中心に立って駆動させる準備を終えていた。
印章陣の数は合計にして九。本来の作戦では十あるという山の各地に一つ仕掛け、土地概念に対して干渉を行う印章陣であったという。その全てをこの一箇所、第七山にて駆動させる。それぞれの印章陣は、単独で一つの機能をこなすよう設計されていた。それを同時に、同じ場所目掛けて駆動させれば、当然ながら想定されていた効果は発揮されない。ただこの場にて生じるのは、合計九つの干渉を同時に受けて、元々山岳回廊の中で最も歪みが強いとされていた場所に、更なる混乱、術を行使するイェア達ですら想像出来ない程の大きな乱れが生じるであろうという事だけだ。
そして、それ程の歪みが一点にて集まるというのであれば、
「一番から九番まで、総駆動! ――出ますわよっ!」
【※イェア達の護衛に回るを選択した場合】
用意された印章陣の数は合計にして九。本来の作戦では十あるという山の各地に一つ仕掛け、土地概念に対して干渉を行う印章陣であったという。その全てをこの一箇所、第七山にて駆動させる。それぞれの印章陣は、単独で一つの機能をこなすよう設計されていた。それを同時に、同じ場所目掛けて駆動させれば、当然ながら想定されていた効果は発揮されない。ただこの場にて生じるのは、合計九つの干渉を同時に受けて、元々山岳回廊の中で最も歪みが強いとされていた場所に、更なる混乱、術を行使するイェア達ですら想像出来ない程の大きな乱れが生じるであろうという事だけだ。
そして、それ程の歪みが一点にて集まるというのであれば、
「一番から九番まで、総駆動! ――出ますわよっ!」
【※ウィースルゥインと遊撃を選択した場合】
【NAME】とウィースルゥインが第七山に辿り着くと、事前の推測の通り、軍部隊は山の縁にて幾つもの印章陣を展開し、それぞれに術の要たる学士が陣の中心に立って駆動させる準備を終えていた。
ウィースルゥインに抱えられた形で、【NAME】は術を駆動させるイェア以外の面子が集まっていた、山の際ギリギリの場所に着地し、彼等と合流する。
場に用意されていた印章陣の数は合計にして九。本来の作戦では十あるという山の各地に一つ仕掛け、土地概念に対して干渉を行う印章陣であったという。その全てをこの一箇所、第七山にて駆動させる。それぞれの印章陣は、単独で一つの機能をこなすよう設計されていた。それを同時に、同じ場所目掛けて駆動させれば、当然ながら想定されていた効果は発揮されない。ただこの場にて生じるのは、合計九つの干渉を同時に受けて、元々山岳回廊の中で最も歪みが強いとされていた場所に、更なる混乱、術を行使するイェア達ですら想像出来ない程の大きな乱れが生じるであろうという事だけだ。
そして、それ程の歪みが一点にて集まるというのであれば、
「一番から九番まで、総駆動! ――出ますわよっ!」
【※分岐終わり】
術の要。九つの印章陣を監督し、効果が同じタイミングで現れるよう調整する印章陣を一人操作していたイェアが、号令と共に己の鉄腕を地面に叩き付け、描かれた印章を駆動させる。
立ち上がる光は無数。同時に生じたそれらは、全く同一の瞬間に第七山を包むように突き刺さり、包み込む。
同時に、山岳回廊全体が蠢動し始めた。
「成功か」
小さく、傍に居たリゼラが呟く声が聞こえた。
概念の感知に対し優れた力を持つ者ならば、今、この山岳回廊の土地に存在する歪みが、【NAME】達の目の前に聳える山を“出口”として吹きだそうとしているのが判るだろう。極限まで歪んだ概念は空間にひずみすら生み、そこから膨大な量の陰性概念が吐き出され始めている。イェアが講じた策が、見事に機能した結果である。
そして時間にして数十秒。
最初は微震程度の揺れが、今は立っているのも難しい強震となり、更には大きな地鳴りが響き始めた辺りで、唐突に、目の前の光景が一変した。
【NAME】達の眼前にあった巨大な山が丸ごと消滅し、以前にも見た泥の湖――いや、泥の海へと一瞬で変じたのだ。
そして、そこからは事前の話通り、これまで見た事も無い程の大きさを持つ泥の巨人――大禍鬼ブムドゥが、轟音と共に立ち上がる。
「……さて、ここまでは上手く行きましたが、問題はこの先ですわ。本来、わたくし達学士が対泥鬼用の印章陣を使ってブムドゥを弱体化させる予定だったのですけれど」
「……もしかして、問題があるのかな」
天すら覆うかという巨大さを持って身を起こす大巨人。それを引きつった顔で見上げるオリオールの言葉に、イェアも同様の表情を浮かべて、
「わたくしが使った印章陣のような、ブムドゥの全てを引き出すための術式の補助に、術士や学士の殆どを注ぎ込んでしまったもので。当初の予定と比べると、せいぜい三割……いえ四割? 取り敢えず、やれるだけやってみますわ。――十一番から三十番まで印章陣駆動! 余力は無しです、全て今ぶち込みなさいなっ!」
イェアの合図を皮切りに、待ち構えていた全員が一斉に動き始める。
事前に準備していた術士部隊が、印章陣を併用した儀式術式を次々に駆動させ、泥の海から這い出そうとしていた巨人に対して様々な効果を発揮する。その多くは補助的なものだ。巨大化を止めるべく無数の輝く綱が巨人の身体を縛り、凍てつく杭が四肢に喰い込み、高熱の岩が空から降り注いで泥の形を変えていく。それら全ては巨人に対して明確なダメージを与えられないものの、綱を破り、杭を砕き、岩を弾く行為に力を割いているのか、巨大化の速度は大幅に弱まった。
そこへ、イェアが別の印章陣を駆動させる。すると正面、広がる泥海の表面から急速に水分が奪われて、干からびて硬質化していった。ブムドゥまで【NAME】達を送るための道を作ってくれたのだ。
「皆さん、行ってください! あまり、長くは保ちません! この術式が効いている間に倒せないと、泥の海に飲み込まれますわよ!」
「全く、シビアな話ねぇ……。とはいえ、やらなきゃどうしようとも全滅なら、やるしかないんだけどさ。【NAME】、ハマダン様。あと他の皆も、準備いいかしらん?」
今更準備が出来ていないなど言えるような状況か。
冷静に【NAME】が突っ込むと「そりゃそうだわ」とノクトワイは髭を揺らして笑い、
「ならアンタ達、覚悟決めなさい! アイツの泥の身体――概念の膿が全部無くなるまで、叩いて叩いて叩きまくるわよっ!」
[BossMonster Encountered!]
battle
坤濁の大禍鬼

ブランタンハリア山岳回廊という土地を構築する概念に根付き、延々と力を蓄えてきたブムドゥ。
今、完全に形を成したそれは、溜め込んでいた力全てが大禍鬼という姿で現れたものであり、今までとは比べものにならない程の力を振るう代わりに、無限とも思える再生、創生能力は失われていた。この土地と不可分であった頃は破壊したとてただ土地に戻るだけであったが、完全に顕現し土地から離れた今であるなら、少なくとも顕現した分を破壊しても土地に戻ることは無く、この場にて散じていく。つまり、今は殺す目が存在している。
しかし、である。
「呆れるくらいタフねっ! つーか、あんだけ攻撃してるのに殆ど姿が変わってなくないっ!?」
「いやはやまったく、並の大禍鬼ならもう二、三回は倒せるほどのダメージは入っていたように思えたんだがね」
「完全に再生しているのではないようですが、損傷した分を内部の泥で補填して回復していると、わたしは判断します」
つまり、こちらの攻撃による痛手は確実に受けてはいるのだが、それを外見に反映させない程度に、その内側に余力を残している、という事か。
【NAME】の解釈に、分析の言葉を述べたノエルが冷静に頷き、隣のノクトワイとオリオールが露骨に肩を落とす。
「この調子でやってると、時間切れは確実よねん……。ちょっとーっ! 隊長殿ーっ! 後どれくらい時間あるかしらーっ!」
「もう無理ですわー! あと数分っていうかそろろそ戻る兆候が出始めちゃいますーっ!」
遠くからの半ば悲鳴のような返答に、その場の全員が顔を見合わせて、代表としてオリオールが口を開く。
「状況は完全に末期的だが、どうするね?」
そしてこういう場において、解法を的確かつ端的に示すのは往々にして“杜人”と呼ばれた少年だった。
「どうするも何もあるものか。やることは一つ、鬼を断つ事以外あるまいよ」
「……いや、それが出来なかったから今こうなってるんじゃないのん?」
「所詮、あれは歪みが形を持ったものだ。ならばその存在概念を保つための器がある。それを保てぬようにしてしまえば、身は崩れ、単なる陰の塵となろうよ」
少年は、ふん、と小さく鼻の奥を鳴らし、
「力を一点、一瞬に集中せよ、という話だ。これまでの連携した動きではなく、それぞれがもつ最大の力を同時にアレに叩き込め。特に、娘子等よ」
リゼラが鋭く視線を走らせたのはノエルと、そして少し宙に浮かんだ位置で話には参加せずにただこちらを眺めていたウィースルゥインだ。
視線を向けられてノエルは少し身を固くし、逆にウィースルゥインは「なぁに?」とばかりに寄ってくる。
「この場にいる者のうち、【NAME】を除いて最も大きな力を振るえるのがお前達だ。故に、お前達が使える力で最大のものを、あの鬼に放て。お前達はただその事に集中するだけで良い。他の者は、此奴等の技に合わせよ。我の見る限り、その程度の技量はあろうが?」
「アタシ達はまぁ、出来なくもないでしょうけど……ウィーちゃん達、うまくできそうなの?」
言われて、ノエルは戸惑ったように口篭もる。しかし、その背中にとんと小さな影が寄り添った。
「大丈夫よ。わたしと私が力を合わせたら、あれくらい一発なんだから」
「……いや、もしそれが本当ならさっさとやって欲しかったんだけど……」
オリオールの心底からの言葉は、近くで話が聞こえていた兵士達も含めた皆が思う事であったが、やる気になってくれたのならばそれに水を差すつもりはない。
「それじゃ、ノエル。あれをやろう。私達の“双色”」
「……それを、今、ですか……?」
「うん。もし必要な時に出来なかったら困るから。今のうちにね」
「…………」
二人は何事かを話し合った後、お互い正面から抱き合う姿勢で、ふわりと空中に舞い上がった。
「あの子達、何するつもりか判る人いるのん?」
ノクトワイの問いに、ほぼ全員が首を振る。例外は既に彼女達が行うであろう攻撃に合わせる為の準備動作を始めているリゼラくらいだった。
空中に舞い上がった抱き合う二人の少女。その藍色の髪と、くすんだ黄金の髪が、凄まじい勢いで伸び始めると、彼女等の頭上にて大きな球状の渦を作った。巨大な藍と金の二色の渦は、暫くぐるぐるとその場で回転を続けた後、
「「行って」」
揃う声。それを合図に、渦から放たれた鋭角を持つ髪の帯が、泥の大巨人の全身を滅多刺しにした。しかも、突き抜けた髪は更に変化して向きを変え、再度巨人に突き立ち、突き刺さり、巨人の身体を双の色の帯で覆い尽くしてしまう。
これまでならばブムドゥは己に巻き付く全てを力で引きちぎり、その拘束から逃れていたが、今回は身体に多重に喰い込んだそれを容易に解くことは出来ずにいた。しかも髪の帯とブムドゥの身体が触れている場所からは、じゅうじゅうとまるで焼け焦げているかのような音を放っていた。
その様子を、【NAME】達は唖然と眺める。
「……おいおいおい。何なのあれ」
「ウィース……ウィーちゃん嬢が普段使ってる変形する髪の力を、ノエル嬢も使えるのか。それも化身として動きを任せるのではなく、自分の意思で、望むような形で」
「しかも相乗効果か知らないけど、威力がめっちゃ上がってるわねん。あれだけで倒せない?」
確かに、帯に包まれたブムドゥの身体は徐々に縮み始めてはいる。
しかし、ノクトワイの希望的観測を前に、首を横に振る者が居た。
「いや、無理だ。あれでは足りぬ。よく見よ。あの髪は永久に伸びている訳では無い。ところどころで動きが止まり、それを切り捨て、新たな髪にて突き刺している。つまり、完全に押し込むには弱い」
リゼラの言葉通り、よくよくブムドゥを覆う帯を見ていると、一定まで伸びきった帯は勢いが止まり、そこから逆にブムドゥの陰性概念に取り込まれるようにして消失してしまっている。そこを補うように髪の渦から新たな髪帯がブムドゥを覆うが、徐々にだがブムドゥの身体が縮小していく速度が下がっているようにも見えた。
「故に征くぞ。ここで崩滅させねば我等の負けだ」
「……言われてみればそういう話だったわねん。――全軍、総攻撃! この瞬間、可能な限りの力をブムドゥに集中させよ!」
ウィースルゥインとノエル、二人からの攻撃をどうにか食い止めているという状況のブムドゥに対し、【NAME】達が更に攻撃を加えれば、形勢は当然ながら大きく傾く形となった。
多種の術式や技法が放たれ、次々と泥の巨人を削り取る。それが更に髪帯からの侵食を加速させる形となり、ブムドゥは己を形作っていた陰性概念を失い、その身を小さくしていった。
そして、そろそろ力が尽きてきたのか、ノエル達が放つ髪の勢いが衰えて、突き立つ帯が綻び、解け始めた頃には、ブムドゥの身体は以前見た大巨人程度――せいぜい10メートル程の姿へと縮んでいた。
「――――」
ここまで来れば、後は止めを放つのみだ。
一歩。既にイェアが叫んだ時間制限に近付きつつある中、彼女が駆動させていた術式の効果が失せ、滑りを取り戻し始めた泥の海面を、【NAME】は術式を併用して強く蹴り飛ぶ。
瞬く間に距離を詰め、巨人の真上にまで飛び上がった【NAME】は、己が武器に持てるあらゆる力を込めて、緩慢に頭を上げようとする巨人を、上から下へと、真っ直ぐに撃ち断った。
それが、ブムドゥという鬼種が、この世にて存在を許される境を越えた一撃となった。
生じた泥の海が、元の山へと瞬く間に戻っていき、これまで幾度も再生を繰り返した巨人が、もう何の手を下す必要も無く、指先から渇き、ひび割れ、そして砕けていく。
これが終わり。ブムドゥを構成する存在概念が、崩壊し、滅していくのだ。
・
形を失い、散っていく大禍鬼の存在概念。イェアは封縛印章石群を取り出すと素早く空中で展開させてから、ウィースルゥインを呼び寄せる。
既にもう、一度は成功した手順だ。ウィースルゥインが干渉を行って印章石群内に仕込まれた術式を駆動させると、広がっていた石群達からこれまでとは比べものにならない程の光が放たれ、その光が指向性を持って集まり、うねり、波となり、今まさに砕かれ空間に掻き消えようとしていた存在概念を拾い集めると、それらを抱えて石の中へと戻っていく。
後には、霧雨失せて常に空を薄暗く覆っていた雲も途切れ始めた山並みと、そして過去に泥鬼が呑み込んだものの取り込む事が出来なかったらしい、一本の武器が地面に転がっているだけだった。
これで無事、作戦の第二段階は成功となった。主たる泥鬼を失い、無茶苦茶な変化を続けていた地形も、取り敢えずは現状の形で落ち着く形となるだろう。地形としてはむしろ以前よりも単純な構造になっている程だ。これから更に別の目的地へと向かわねばならぬ身としては有り難い
「後はこの山脈を抜けて、“城”を目指すだけですわ! あともう一息――頑張りましょう!」
真なる楽園 最後の休息地
――最後の休息地──
“山”と“洞”。二つの超常地形でそれぞれ大禍鬼を撃破し、その存在概念を無事確保した【NAME】達は、最後の目的地であるところの“城”を目指す。
そして進む毎に穏やかになっていく風景の中、幾日かの行軍を経て一つの小さな丘の上に辿り着いた時。
見下ろす先にようやく現れたのが、この未踏の島に於いては場違いとも思える、所謂戦時防衛のための“城塞”ではなく、独特の装飾を施された“宮殿”に近い造りの白亜の城――有り得ざる城クナハ・クリサの姿だった。
・
その丘は丁度良く、城の外観をある程度視認できる程度の距離があったため、イェアはまずこの丘に一時の野営陣を設置。これまでの長旅で溜まった疲れや傷を癒やしながら、“城”攻略のための調査と準備を開始する事にした。“城”の周辺はこれまで【NAME】達が通過してきたようなエルツァン特有の超常地形とは違い、他の地域――エルツァン内で表すなら沿岸部の土地概念の歪みが少ない場所となっており、故に腰を据えてじっくりと攻める余裕があると判断しての方針だった。
そうして数日の休息と準備の時間を経て。
少し離れた位置で、超巨大な印章陣の準備を進める学士部隊を横目に見ながら、【NAME】はイェア達と最後の打ち合わせを行っていた。
「それでは簡単に、まずおさらいと、あと出発前には省いた細かい部分の説明を行っていきましょうか」
有り得ざる城クナハ・クリサの奥にあると思われる、“鬼芯の檻”へと続く道。それを抜けた先に存在する、檻を形作る柱の一つと“鬼喰らいの鬼”は同化している。それを討伐し、尚且つ“巻き戻し”を発生させない事が今回の目的だ。
まず最初に、道を通るための筋を付けなければならない。
もし“鬼芯の檻”に続く道を隠し塞いでいる“封印”を破壊してしまった場合――例え“封印”の守護者と目される“芯なる者”の眷属、護竜リンドヴルムを討伐出来たとしても、状況の“巻き戻し”が発生してしまう事は、ウィースルゥインが垣間見た過去の記憶から既に判っていた。
檻へと下る道を塞ぐ“封印”や守護者を含めて、“芯檻”の内の一つ、という構造なのだろう。
では、どうすれば良いのか。
これに対してイェアが考えたのは、“封印”を破壊しない程度に干渉してリンドヴルムを呼び出し、更に城の外へ誘い出した上で弱らせ、現在外で記述構築中の大型印章陣にて捕らえ、一時的に動きを封じる、という作戦だった。
リンドヴルムは“役目”を定められている場合、それを実行する間はただでも高い能力が更に強化され、加えて尋常ではない再生能力を発揮させる事が知られており、更に先刻話した通り、崩滅させればそれ自体が“巻き戻し”のトリガーになる可能性も考えられていた。故に、リンドヴルムに対しては討伐ではなく封縛を狙い、護竜の動きを止めている間に“鬼芯の檻”へ精鋭部隊が突入。シンラを発見討伐、総員の撤退が済んだ後に時間差で封縛を解く、というのが一連の流れだ。今、学士達が数日掛けて地面に記述している超巨大な印章陣が、そのリンドヴルムを封じるための代物だという。
「――という、作戦なのですが。何方か異論、ないしはもっと別の良策がある、という方はいらっしゃいます?」
既に準備は進めているため、一応意見は聞きますが変更はまず無いですよ、という程度の意味合いの問いに、場に居たほぼ全員が首を横に振る。強烈な再生能力を持つ守護竜を倒さなくて済むのなら、それに越したことは無い。
問題は、この印章陣でリンドヴルムの動きを止める事が本当に可能なのか。
そして、印章陣による封縛が解けた後、リンドヴルムがどう動くかだ。
当然生まれた皆からの疑問に、イェアは考え考え答えを返す。
「少なくとも後者については、役目を持つリンドヴルムはそれに縛られていますから、封印の守護を放り出してまで、立ち去ったわたくし達をわざわざ追ってくるという事はないと思われますわ。……もっとも、封印にちょっかいを掛けた奴らは地の果てまでも追いかけて八つ裂きにしろ、なんていう命令を受けている可能性もないではないですけれども。もう、その場合は仕様が無いと割り切って、死力を尽くして戦うなり、全力で逃げ出すなりするしかないでしょうね」
出来ればそんな展開になりませんように、と皆が何とも言えない顔で黙り込む。
「前者についても、正直な処やってみないと判らない、という所が多分にあります。今回用意している印章陣は、過去の文献に残されていた対護竜用の印章陣――といいますか、ある伝承内こういう仕組みの印章陣を使ってリンドヴルムを封じる事が出来た、と記されていたものを、今のわたくし達の技術で強化しつつ再構築したものですわ。ただ、あくまで過去の資料でしかありませんから、全てが真実かどうかは定かではありませんし、まあぶっちゃけいうと盛られてる可能性大ですので、うまくいくかどうかは神のみぞ知る、と言ったところでしょうか。ただ、多人数で常時駆動させ続ける、儀式構造を持つ封縛印章陣としては最大規模ですから、これで駄目なら他の何でも大体駄目だと思われますわ」
「結局のところは、今出来る範囲で最善は尽くしたと、そういう事かしらん」
「そう思っていただければ」
ノクトワイの問いに短く答えてから、イェアが話を次に進める。
「リンドヴルム封縛成功後は、軍部隊の多くはそのままリンドヴルムの監視として残します。今回の印章陣は一度発生させれば効果が持続する種類ではありませんので、常に外から力を注ぎ続けなければなりませんわ。うちの学士、あと兵士の方々の中でも術士としての技も持つ人達にも、印章陣の維持に代わる代わる参加していただく形になります。これに、護衛兼監視として他の兵士の大半を置いて、残りは“城”の確保を行っていただきます。もし印章陣が破綻すれば、なんとか彼等だけでリンドヴルムを押さえてもらう形になりますわね。そして肝心の“鬼芯の檻”への突入方法についてですが……」
「そういえば、“封印”を具体的にどう破るのか。それを聞いてないね」
がじがじと焼いた肉を囓っていたオリオールが口を挟む。“城”周辺は亜獣達も比較的通常の動植物に似たばかりであったため、狩りをして手に入れた、久々の持ち込み携帯食以外の食べ物である。
「破壊してしまうと“巻き戻し”の原因となる、という事でしたら、正規の手段で“封印”を解く、というお話になるのでしょうか?」
軽く味をつけた湯をすすりながらのノエルの問いに、イェアはぱたぱたと手を横に振った。
「残念ながら、正攻法――お城の中心にある大祭壇から繋がる各部屋に、エルツァン島の各概念に染まった供物を置くという形は、今回は使えませんの。リンドヴルムが出てこない範囲で一通り調べてみた感じですと、それで封印を一時的に緩める事で道となる八つ目の扉の通行が可能にはなるんですが、その時、通る者自体の存在概念に干渉して、檻が存在する世界と近しい形に一時的に変質させるという手順が入るようで……」
イェアは【NAME】以外の面子に順々に視線を巡らせ、
「多分、【NAME】さんだけなら行けるとは思うのですが、わたくしやノクトワイ様みたいな普通の人や、ウィーちゃんやノエルみたいな色々と普通じゃない人達はその干渉に適合できないか、そもそも弾いちゃうかしちゃって、問題が出てきてしまうと思うんですの」
「なら、突入する人を減らすのん? 最低、【NAME】だけ入れるならシンラをどうにかは出来る……という過去は一応あったんでしょ?」
「それだと失敗した過去と変わりませんわ。最低でも、印章石群二つを担いだわたくし、後ウィーちゃんとノエル、リゼラさんも可能であれば欲しいところです」
「……それ、僕とかノクトワイ氏はどういう扱い?」
「居ても居なくても。副隊長はむしろ残って頂いた方が兵員指揮の観点から良いくらいですけれど」
「折角ここまで来たんだから、アタシも見てみたいところなんだけどねぇ……。“鬼芯の檻”に、“鬼芯の残骸”。大体、“同加”の大禍鬼すらアタシ満足に見てないのよん? そんなんじゃ、何しにこの島まで来たのかわかんないじゃないの」
何を観光気分丸出しな、と白眼を向けられるノクトワイだが、彼は気にした風も無く笑い、
「んで? そこんところどうにかする方法も、一応考えてはいるんでしょ?」
対して、イェアの反応は思った以上に鈍い。
「考えてないわけではないんですけども……“芯なる者”か、その教えを受けてた辺りの人間が残したもの相手なると流石に。一応、干渉出来そうな術式を幾つか組んではみましたけど、根本的にわたくし一人の同調力じゃ出力不足の可能性が多々……」
「私がやってみる?」
と、そう声を出したのは今までこれといって表情を作らず、働く学士達の動きを眺めていたウィースルゥインだ。話を聞いていなかったという訳ではなかったらしい。
だが、こちらの提案に対してもイェアは難色を示す。
「ウィーちゃんが直に何かすると逆に“封印”が派手に反応するか、もしくは素通りさせてしまう可能性もありそうですし……」
「そういえば、シンラもホイホイ中に入れてる訳だから、案外大禍鬼相手だとザルなのん? この“封印”」
「目的……といいますか、対象が違ったんだと思います。この造りですと、破壊しようとする意思が無い、実体を持たない存在辺りでしたら、案外あっさり中に入れるんじゃないでしょうか。あと、“鬼喰らいの鬼”の場合は土地概念経由での移動でしょうから、そもそもここを通過していったかどうか不明ですし」
「役に立たないわねぇ……」
「取り敢えずは、【NAME】さんのゼーレンヴァンデルングと同じで、ウィーちゃんはわたくしの術が駄目だった場合の保険としてお願い致します。やり方を考えれば、もしかしたらうまく相乗効果を生み出せるかもしれませんし……」
「そう」
「ちなみに、“封印”をどうにかできて、“鬼芯の檻”の世界に入り込んだ後は、殆どもうぶっつけ本番で行き当たりばったりで行きます」
一気に作戦が雑になった。
思わず【NAME】が突っ込むと、「と言われましても……」とノエルは心底困った顔になり、
「そこからはノエルやウィーちゃんの証言が曖昧だったり抽象的すぎる部分が多くて、作戦の立てようがないんですの。取り敢えず中の柱とシンラが一体になってるところだけは判っていますから、それを探して、徹底的に、痕跡も残さないほどに崩滅させて、その後にわたくしが持ち込んだ印章石群二つで、その穴を埋めればお終いですわ。上手く行けば、ですけれども」
「…………」
これで話は終わり、と半ば放り投げるように手を広げてみせたイェアに、【NAME】達は暫く無言で視線を交差させる。
彼女が言う事ももっともではあるのだが、可能であるならもう少し、何らかの対策を立てておきたいところだった。
「えーっと、取り敢えず檻に向かうメンバーは、ここの七人……でいいのよねん?」
「そのつもりです。最低限の戦闘能力と役目、あと異界に対する耐性あるいは対策を施す余裕があること。そして状況の真相について大まかに把握していること。以上を条件に選出すると。わたくし、ウィーちゃん、ノエル、ノクトワイ様、ハマダン様、リゼラさん、そして【NAME】さん」
「じゃ、最低でも隊列……というか敵と戦うときの主力を決めておいた方がいいかもしれないわねん」
「同意する。七人は邪魔だ。敵と相対するなら、実際に刃を交える者は多くとも三手までとせよ。それ以上は互いの立ち回りが干渉し、逆に動きが鈍る。残りは左右に構えて敵の移動を押さえるか、後衛として補助をさせよ」
戦いの話になると、これまでほぼ無言であったリゼラがすらすらと指示を出してくる。
そして、一息間を置いて彼が視線を向けたのは【NAME】だ。
「【NAME】よ。この中では、お前が全ての要だ。故に、お前が共に戦う上で必要だと、そう判断する者を二名選べ」
「あと、選んだ子達がやられちゃったりして動けなくなった時用に、どうメンバーを入れ替えるかも決めといた方がいいわねん」
対して、【NAME】はむぅ、と考え込む。二人の言いたいことは判るのだが、一つ疑問が湧く。
――ちなみに、自分がやられた場合の替わりは?
と【NAME】が訊ねると、全員から「【NAME】がやられたらもうそれで作戦失敗だからどうでもいい」とばっさり切られた。
どうやら、決めないと話が終わらないらしい。
「…………」
居並ぶ六人。
自分を見る彼等の顔をぐるりと眺めてから、【NAME】は彼等と共にどう戦っていくか。その順番を考える。
「まぁ、【NAME】が誰でもいいという事なら、僕達の方で勝手に決めてしまってもいいけどね」
「だが、薦めはせぬ。万全を期すならば、お前が最適と思う形に我等を配し、使ってみせよ。後に悔いたとて、取り返しはつかぬ故な」
責任重大だ、と軽く溜息をついてから、少しの思考の間を置いて【NAME】が出した答えは――。
真なる楽園 激甚たる護竜
――激甚たる護竜──
“封印”をゼーレンヴァンデルングで完全に破壊してしまうと、リンドヴルムの状態に拘わらず“巻き戻し”が起きてしまう可能性が高い。
それを避けるべく、イェアが術式で“封印”を破壊しない程度に干渉を行って、その守護者であるリンドヴルムを誘い出し、城の外へとおびき寄せる。
これが、最初の予定であったのだが。
「……む、ぐぐ」
城内の空間は特殊であり、外観との関連性を無視した大円の空間に、八方の部屋と繋がる巨大な祭壇を配した構造をしていた。イェアはその祭壇の前で、事前に用意していた術式を幾つも駆動させ、“封印”に対し干渉を行おうと四苦八苦していた。
しかしイェアに加えて、外で印章陣の準備を行っていた学士達数人の救援を得ても尚、人の技による封印への干渉は難しいらしく、“封印”を構築している大祭壇はうんともすんとも言わない。
というより、イェアが用意した術式自体は問題無いようなのだが、齎す効果の力、そもそもの出力が足りないようなのだ。
「これ見てると、何となくぶん殴ったら開きそうな気がしてくるんだけどねぇ……」
そう呟くノクトワイが見るのは、城内最奥、八つ目の扉である。ここが、“鬼芯の檻”へと降りる為の入り口であるらしい。
しかし扉という形で存在しているものの、この“封印”は位相要素も含めた概念的な結界であるため、その扉を破壊する等という物理的な方法での解決は不可能。手段としては今イェアが行っているようなやり方か、あるいはゼーレンヴァンデルングの力を借りるかという話になるのだが、先刻の話の通り、後者の手法は勢い余って――という可能性も十分考えられ、イェアとしては出来れば避けたい方法だった。
難儀するイェア。結局、今居る者達のなかで一番概念的な力が強い存在――ノエルとウィースルゥインに、術式の駆動部分だけを任せてみる事になった。
イェアが構築し維持した術式に、二人が力だけを思い切りぶっ込むと、過剰なまでの出力を発揮した術式は瞬く間に限界を超え、焼き切れて砕け散る。しかし一瞬であっても発揮した力は、明確な効果を現した。
“封印”が一気に揺らぎ、その揺らぎから滲み出すように、七色の輝きを放つ別の位相領域の口が開いたのだ。
「――!」
強大な咆声と共に現れるのは、護竜リンドヴルム。空間を割り裂くようにその巨体を現世界に顕現させると、七色の光を伴い、翼を大きくはためかせる。
「総員、外まで撤退ーっ!」
イェアの叫びに従い、全員が全力で外へと駆け出す。兎にも角にも、リンドヴルムを外へ――仕掛けた印章陣にまで誘き寄せなければ話にならないからだ。
城の外へと次々と人が飛び出し、そして最後に殿を務めていた【NAME】とイェアが、恐る恐る城外から門を窺う。
「……さて、次の段階としてはリンドヴルムが外まで追ってくるかどうかですが、確率としては精々20%くらいと踏んで――あ、来た! 来てます来てます! 総員兎に角距離を取ってくださいな! 対策無しで戦ったりしたら、びっくりする程あっさり死にますわよっ!」
そして、城内という狭いエリアから外の広大なエリアへと移動したリンドヴルムは、空を縦横無尽に飛び回り、“封印”に対して干渉を仕掛けてきた【NAME】達に攻撃を仕掛けてくる。飛行能力を持つ護竜に取って、閉鎖空間から解放された今は、明らかに地の利を得た状態だった。
しかしこちらも単独で戦う訳では無い。軍部隊から無数の弓や術式が巨竜を覆い、傷は負わせられないながらも、自由な動きを阻害し、牽制の役割を果たしてくれる。
(……これならば)
どうにか出来るかもしれない。
何より、倒す必要は無いのだ。ある程度弱らせてから、イェア達が仕掛けた印章陣の罠へと追い込めば良い。それだけならば、難しいながらも不可能な事ではない。
しかし、
「く、来るぞ!」
警戒とも悲鳴ともつかない声が上がるのが聞こえた。
リンドヴルムが、幾つかに分かれて展開している兵士部隊の一つに標的を定め、その大翼を羽ばたかせたのだ。
翼の奥から外へと、歪な七色の光が渦巻くように広がり、そして翼を振り下ろすと同時、七色に輝く風の渦となって放たれる。
「対概念防御! 三番術士隊前へ!」
指示と共に複数人の術士――それも防御結界が専門である結界士[シーリングスフィア]達が急ぎ前へと出る。
印章石と高性能の同調誘導器を併用した高速駆動。一瞬で構築された光鱗の壁が兵士の一団を守るように聳え立つ。
だが、“芯なる者”の最高の眷属。伝説にも近い強存在であるリンドヴルムを前にして、彼等が造り上げた結界は薄板程度の守りにしか成り得ない。護竜の両翼が放った七色の風は結界士達が結んだ守りを瞬く間に穴だらけにし、前へと出ていた術士達諸共、兵の一団を散り散りに吹き飛ばしてしまう。
例え薄板とはいえ、障害は障害。全くの無駄ではなく、風の威力は多少弱まっていたようだが、それでも致命傷はどうにか免れる程度のもので、風の乱打を浴びた一団は殆どが戦闘不能に陥っていた。
たった一度の攻撃。しかも竜種の本領である吐息[ブレス]ではない攻撃に対し、防御手段を講じていて尚あの被害なのだ。時間を掛ければ掛ける程、被害は大きく、そして援護は乏しくなってくるだろう。特にリンドヴルムの動きを止めるための印章陣やそれを駆動させる学士達に被害が及べば、作戦は一発で瓦解する。
ならばやはり迅速に。
軍部隊の助けが得られている今のうちに、一気に勝負を決めなければいけない。
【NAME】がそう覚悟を決める間に、リンドヴルムが新たな動きを取った。
一度大きく空へと上がった巨竜が、身を逸らし、喉を膨らませ、大きく顎を天に掲げる。
「――――」
拙い。その思考が、【NAME】を含めた軍部隊の全員の間に走る。
竜種最大の武器。リンドヴルムが操るのは七つの概念を圧縮放射する吐息[ブレス]で、一つ一つの力は芯竜属のそれには及ばないが、単属性ではなく七種の力の奔流であるそれは完全な防御手段を講じるのが難しい。基本としては攻撃動作から射線を推測しての回避、可能であるならば攻撃動作前にそれ自体を潰すのが一番の対策となるのだが、相手の位置が悪い。届くのは投擲武器か長射程の術式で、しかも今から撃ったとて吐息の妨害になるとは思えず。
(これは、駄目か)
と、せめて何処へ飛んでくるかを確認してから回避すべく上を睨んでいると、大翼を広げ顎を掲げる護竜の更に上方、妙なものが浮かんでいるのが見えた。
その場には不似合いな、小さな人影だ。風に煽られ、長くたなびくのは藍色の髪。
「えい!」
一体いつの間に移動していたのか。ウィースルゥインが高く上げた足をリンドヴルムの頭目掛けて振り下ろすと、どういう理屈で生じているのか理解し難い、不可思議な歪みと共に形を失い無形の理粒子と化した飛沫が散り、竜の喉元にて圧縮されていた概念の塊が、こぶりと溢れるように口元から漏れる。
そして、
「今っ!」
以心伝心。完全にタイミングを合わせて放たれたノエルの黒銃による銃撃が、ほんの一瞬硬直したリンドヴルムの身体を捕らえた。
放たれたのは概念圧縮の球弾ではなく、輝き走る光条だ。理粒子砲としてのフォーレミュートの弾速は、光の速度とまではいかないものの、大型弩弓が撃ち出す矢の速度程度ならば悠々上回る。しかし、理粒子が銃身内で圧縮解放される際の概念変動や照準作業、更には引き金を引いてから実際に発射されるまでにラグが存在する為、それらを総合的に鑑みれば回避や防御はされやすい。リンドヴルムが吐息の前動作中であったのに加えて、ウィースルゥインの攻撃が入り、完全に虚を突かれ態勢が崩れた状態でなければ、ああして直撃させるのは難しかっただろう。
思わぬタイミングで受けた二度の衝撃に姿勢を崩し、溜め込んでいた吐息を顎端から散らしながら落下していくリンドヴルム。しかし地面に墜落するまでに姿勢を整えようとしている。このまま見逃せば、直ぐに空へと戻ってしまうだろう。
故に、今。ここが勝負所だった。
【NAME】は全力でリンドヴルムが落ちていく場所目掛けて走り、空駆ける竜を地面に引き摺り降ろすため、更なる追撃を狙う!
[ExtraMonster Encountered!]
叩き落としたリンドヴルムをどうにか印章陣上にまで押し込めば、後は総力戦となった。
各人の攻撃の後、止めの【NAME】の攻撃に合わせて、イェアが指揮する学士部隊が合図に従い印章陣を駆動。立ちのぼる強烈な光の網が、リンドヴルムを絡み取り、地面へと縛り付け、動きを封じる。漏れ出す七色の輝きが印章陣から伸びる網を引きちぎろうと波打つが、網はまるでその光を逆に取り込むようにして己を強化し、より強靱にリンドヴルムを縛り上げていった。
それを見届けながら、戦いで乱れた髪をどうにかなでつけながら、イェアが感慨深い声を出す。
「リンドヴルムと人との戦いは幾度かありましたから、ある程度の対処法も伝わっているんですのよね……。例えばあの七色の力に対するものとか。まぁ、吸い込みすぎると逆に印章陣の方が力を制御しきれなくなって自壊しちゃうんで、だからこその時限制限付きのという話なのですけれど」
役目を持つリンドヴルムは、強力な不死性と無尽蔵とも思える力を発揮する。その設計思想は、神形器が己の役目を定め限定することでその能力を尖らせ、高めるのと似た方向性を持っており、創造主である“芯なる者”が好む手法の一つなのだろう。それを逆手に取った術、という事だ。
「あの状態になれば、印章陣の駆動状態さえ維持できれば、暫くは何とかなる筈ですわ。後は任せて、わたくし達は先へ急ぎましょう」
軍部隊にリンドヴルムの対応を任せて、【NAME】達は城内に戻る。
リンドヴルムが外へと出ているため位相領域の口が開いており、それによって封印自体にも微細な歪みが生じていた。これは事前の予想には無かった展開だ。上手く利用すれば、封印に傷を付けずにその奥へと潜り抜ける事が出来るかもしれない。
「……といっても、もうわたくしの同調力では無理なのは判ってるので……ウィーちゃん! 後ノエルも、わたくしの術式をフォローしてくださいな!」
「了解しました」
「ん」
イェアが構築し、ノエル、そしてウィースルゥインが力を注ぐ事で術式が駆動する。
大祭壇自体は沈黙したままだが、輝く八つ目の扉に生まれていた揺らぎが大きくなり、“封印”が更に緩んでいくのが判る。そしてその向こう側に、フローリア諸島の奥に隠され続けてきた檻の世界が垣間見えた。これならば、どうにか向こう側へ渡る事も出来そうだ。
【NAME】からすると、過去に辿り着いた事がある世界だが……。
「“鬼芯の檻”が構築されている場所は、固有の小世界として存在していると考えられていますが、その中で五感が受け取る感覚は、場所――というよりも状況や人個人の感性によって変化する程にあやふやなものです。だから、一度経験があるからといって、それを基準として心構えをするのは危険ですわ。なるべく心に柔軟さを持って行きましょう」
忠言としてはまさに道理。
イェアの言葉に頷いてから、【NAME】は皆を一度見渡して、号令を掛ける。
ここからが、戦いの本番。自分達の力だけで道を切り開いていかねばならない、正念場だ、と。
真なる楽園 紅い三日月の庭
――紅い三日月の庭──
降りた先に広がっていたのは、藍と紫が混じり合う空に紅の三日月が輝き、真っ黒な地面が只々広がる不気味極まる世界だった。
そこでは亜獣は勿論、小動物はおろか、植物も苔の欠片すら見当たらない。まるで生あるもの全てを拒むかのように、命の気配が全く絶えた空間は、さながら地獄。あるいは冥府。連想されるのは、そんな場所だった。
そんな中で動くものは唯一。瘴気のような薄暗い塊が人の姿を辛うじて模したような、朧な四肢と胴を持つ巨大な人影だった。
その姿は、【NAME】と、そしてオリオールには何処か見覚えのあるものでもあった。僅かな思考の後、直ぐに思い至る。
イールシック地下都市遺跡の最奥。“芯檻”の遺跡で見た、あの謎の巨人である。
勿論、完全に同一という訳では無い。特に、巨人が放つ気配のようなものは完全に別の質を持っており、今この地で彷徨う影は、兎に角陰質の気――上位の鬼種が放つものよりも更に強力であるが、しかしどこか纏まりには欠ける。そんな、見る者に不確かで不気味な感情を強く抱かせる存在だった。
数は群れる程ではないが、単数ともいえない。荒涼とした空間に、大きな巨人の影が点々と、まるで亡者のように当て所も無くさまよい歩いている。
しかし、それは【NAME】達がこの地へ足を踏み入れるまでは、という話であったようだ。
【NAME】達が巨人の存在を確認したように、その巨人達も自分達が彷徨う黄昏の世界に異質の存在概念――命を持つ存在が現れたことに気づいたようだった。
距離が違い巨人達から、動きが変わる。最初はゆっくりと、しかし次第に速度を上げて。まるで餓鬼が久方ぶりの餌を見つけたときのように、【NAME】達目掛けて迫ってくる。
「なんか問答無用で明らかにやる気満々って感じだけど……。平和的な交渉どころか、そもそも会話がが成り立つような相手には到底見えないわねぇ」
「ならば斬り滅ぼせば良いだけの話であろうよ」
「ですが、あの巨人一体でも、大禍鬼に届こうかというくらいの、存在としての力を感じます。そう容易く済むような事ではないとわたしは考えますが……」
「確かに、僕でも感じるくらいの毒々しい気配を撒き散らしてるね。でも、言ってみればそれだけのようにも見える。個を明確に形作る核すらなく、ただ曖昧に模した、存在概念の塊でしかないと考えるなら……」
「だからこそやりづらいところもあるでしょうが、それ以上に崩す方法もいくらでも思い付きますし、そもそもあんな姿でしかないなら、案外打たれ弱いという可能性も高いですわ。ウィーちゃん? ちょっとびゃーっと一発カマしてみていただけます?」
「ん? んー。出来るかな」
言われて、ウィースルゥインがふわりと前へと出ると、もっとも間近に迫っていた巨影目掛けて、軽く髪を振ってみせる。
すると、髪の先端から一瞬長大な爪を持つ腕が生まれ、次の瞬間には生えた四つの爪が数十メートル程の距離まで伸びて、迫る巨人の身体を文字通りに繊切りにした。
「出来た」
おー、と本人すらびっくりしているような声。見てる側からしても予想外な上に強力な攻撃すぎて素直に驚いてしまう。
だが、彼女が行ったのは結果としてみれば物理的な斬撃だ。例え四つの線にて分断したとして、あの黒い靄で出来ているような巨人ならば直ぐに元に戻ってしまうのではないか。
そう、誰もが思い、成り行きを見守っていたのだが、
「……意外と効いてるね」
「思っていたより戻りが遅いですわね。というか、あまり戻れていないと言いますか。どうやら、本当に打たれ弱いみたい」
「それなら、動きが止まってるうちにさっさと処理しちゃった方がいいかしらん」
言って、ざっとノクトワイが鋭く前へと出る。同様にリゼラも無言のまま彼と同様に進み出た。やはり二人とも戦士としての高い力量を持つが故に、好機と判断したとき決断から行動に至るまでが兎角速い。【NAME】もその彼等の後を追おうとして、
「警戒を! 反撃来ますっ!」
後方から唐突に飛んだノエルの声に、駆け込んでいた二人は迷わず反応。間髪入れず真横へと跳ねる。
彼等が一瞬前まで居た場所へ、渦を巻き形を整えようとしていた巨人の影から何の前動作もなく黒霧の波が飛んだのだ。
「気をつけて下さい! 相手は人の形を模してはいますが、中身はやはり陰性概念の塊でしかないようです!」
「成る程。素直に人の形に添った攻撃が飛んでくるって訳じゃないという事か。って、今何で判ったんだい?」
「概念的な存在の動き、流れを見ていけば、ある程度どう動くかは、確実ではありませんけれど推測出来るので……。特にあれは陰性質、鬼種の存在概念と同種のものですから、今のわたしの――“人形”としての力を十全に発揮出来るようになったわたしの感知能力なら、精細に観測する事が可能です」
「よし、ならそれを軸に対応しましょう。ノエルは敵の状態を監視して攻撃の気配があれば警告出してくださいな。それを聞いたら各個で回避を。攻撃の速度自体はそれ程でもないようですが、恐らく直撃したらかなりまずいと思って下さい」
了解、と短く告げて、【NAME】は武器を引き抜き改めて巨影を見定める。
このレベルの相手に正面切って戦えるとなると、自分、リゼラ、そして辛うじてノクトワイ辺りとなるか。残りの面子は主に援護という形での参加となるだろう。
そう考えていた【NAME】の隣に、ひょいと小さな影がやってくる。
「【NAME】。やるの?」
上目遣いに小さく問うのは、藍色の髪の少女だ。
若干戸惑いながらも頷くと、そう、と彼女も頷き、
「じゃあ、私もやるね。今度はちゃんと、よく効きそうなものを出せるように頑張る」
ざわざわと、彼女の意志に反応して長い長い髪が蠢き、その中で幾つもの存在の影が生まれては消えていく。
その様子は心強くもあるが危なっかしさもあり、果たして止めた方が良いものかと考えてしまうところもあるのだが、
「【NAME】、呆けておる場合か! もう次の巨人も迫ってきている! 合わせろ、疾く滅するぞ!」
鋭い声に前を見れば、既に声の主は翠色の光を身の内から放ちながら、矢のように前へ飛び出していた。
「ちょっ! 早い! 早い! 【NAME】、フォローいくわよっ!」
慌てて駆け出すノクトワイに、【NAME】も気持ちを即座に切り替え、巨人へ攻撃を行うべく彼の後に続く。
【NAME】達は近寄ってくる巨人をどうにか討伐しながら進んでいく。
「推測するに、ですね」
戦いを続けながら、そう前置いてのイェアの言葉は、この巨人の影達は、鬼芯の残滓が、その形骸を倣い仮初めの形をもったものであるという。イールシックの遺跡で見た巨人と似ているのは、恐らくそういう事なのでしょうね、と。
つまり、この瘴気で形作られた巨人のようなものは、過去に猛威を振るい、フローリアにて封じ散じたという鬼芯属の幻影であるといえるのではないか。そんな話であるらしい。
もっとも、本来の鬼芯の強大さと比すれば塵芥に等しい存在であり、謂わば鬼芯属が生み出す単なる気配が自然と形を模し、力を持って襲ってきているのではないか。それだけ、鬼芯属は規格外の存在である、という事なのだろうが、
「……それはそれで妙な話だね」
そう、首を捻ったのはオリオールである。
「妙、ですか? 要は、既に鬼芯属は消滅しているからこそ、その残りかすから大禍鬼の出来損ないみたいなのがぽこぽこ出来てるんじゃないかって話なのですけれども。結構、この予想自信ありますわよ?」
「いや、そこじゃなくてね。ここは確かに“鬼芯の檻”なのだろうけれども――」
そこで言葉を切ったオリオールが指差すのは、遥か前方。荒涼とした空間の中にあって唯一存在感を放つ物体だ。
点々と、円を描くようにして七本。黒色の地面に突き刺さり、天の月へ目掛けて真っ直ぐに聳えるのは、六角の凄まじく巨大な柱の群れだ。
その姿。規模こそ大きく違えど、似たようなものをやはり過去に見た覚えがあった。
エルツァン島の周囲、海中より伸びていた柱である。あれと比べると遥かに巨大ではあるが、形状や外から見た質感は非常に酷似している。
「あれが多分、“檻の櫺子”に相当するものじゃないかな。だからここは一応“檻の外”のに当たると思うのだけれども、そこに、封じられて消滅したという鬼芯属の気配が、形を持つ程に漂ってるというのもおかしいだろう。……というか」
遠くを睨むオリオールの顔が、嫌そうに歪む。彼の目線を追って柱を眺めた【NAME】達も、彼の表情の意味を理解し、やはり似たような顔つきになった。
「感知しました。七本の柱のうちの一つから、影の巨人が持つものと同質の気配が、際立って多くこちら側へ漏れ出していると、わたしは判断します」
「漏れる、じゃなくて、噴き出してるね」
「……そこの娘子共が見たという過去では、同加たる大禍鬼は“鬼芯の檻”に立つ柱と一つになっていた、という話であったな」
その言葉を聞き、ノクトワイは髭の先を摘みながら唸る。
「シンラが檻の柱とくっついて檻の中にまだ残ってた力を取り込んでるから、柱の機能にも問題が出て、そっから外の方にまで漏れ出してる、って感じかしらん。……何というか、取り敢えず目指す場所はっきりとしたわねん」
「はっきりはしましたけれど……つまりこれって近付けば近付くほど、陰性概念が濃くなって、影の巨人が生まれてる可能性も高いって言う事で……」
「…………」
厄介、という言葉が心中に浮かぶ。
影の巨人達自体は反射的な行動しか取らない上、手当たり次第に攻撃するため時には影同士が互いを攻撃しあう事もある程だ。倒す事自体はそう難しくはない。
だが、持っている力そのものは上位の鬼種にも劣らぬ程なのだ。もし攻撃をまともに喰らえば相当なダメージを覚悟せねばならず、慎重な立ち回りが要求される。
結果として、体力や精神の消耗は免れず、これから檻と一つになった大禍鬼との戦闘を控えた身としては、極力戦いになるのは避けたい相手なのだが。
「取り敢えず、対シンラで要となるのは【NAME】さんです。なので、影の巨人は極力彼以外の面子で対処していく事にしましょう。柱へ辿り着くまでは、臨時の編成で……そうですね。前衛をノクトワイ様とリゼラさん、左右からわたくしとオリオールさんでカバーしますから、【NAME】さんは後方でノエルと一緒に居て、もし彼女に危険が迫ったときだけ動いていただくだけで構いませんわ」
イェアの指示に、皆が銘々に答えてそれぞれの位置取りを行う中。
「……私は?」
「ウィーちゃんは……ええと、正直どう戦えるのか見てていまいち良くわからないから、好きに動いちゃっていいのかなぁ……」
「わかった。好きにやるから、任せて」
言って、ふわりと上空に浮かび上がったウィースルゥインは、靡く髪から様々な化生の姿を生み出しながら、新たにこちらへ迫ってくる巨人達に対して攻撃態勢に入っていた。
妙にやる気な様子に、大丈夫かな……とイェアと二人で視線を交わし合うが、純粋な戦力としては、【NAME】を除いて評価すれば彼女はこの集団の中でも随一といって良い存在である。結構なムラっけがあるとはいえ、今はだからと欠いて戦っていけるような局面ではなかった。
「それでは皆さん――行きますわよっ!」
イェアの号令の下、【NAME】達は前進を開始する。
――藍から紫に染まる空。
紅の三日月の下、遠くに聳える七本の柱の一本からは、瘴気を思わせる不気味な霞が、濛々と広がっていた。
真なる楽園 柱芯の大禍鬼
――柱芯の大禍鬼――
そうして、【NAME】達は辿り着く。
身体の半分を柱の黒に埋め込んだまま、その影──“鬼喰らいの鬼”と呼ばれた大禍鬼シンラは、身構えて立つ【NAME】達を虚ろな両眼で見下ろしていた。
神形が奏でる鈴鳴りの音は、しゃらしゃらと連なる程の勢いで【NAME】の耳朶を打つ。眼前に存在する鬼の強大さ、そしてこの世界に於いても類を見ないほどに強大で強固な“封じ閉じ込めるもの”に対して、強く反応を示しているのが伝わってきた。
シンラは以前、二匹の“大禍鬼”を取り込み、己の力を強化させていた。
その二匹の存在概念はゴディバでの戦いの折に【NAME】とゼーレンヴァンデルングの斬撃により断たれ、失われた。
だが、今眼の前にあるその姿。黒の柱と一つとなったその身体からは、二匹の“大禍鬼”を取り込んでいたときと同等か、それ以上の力を感じさせた。
「……一応、方針の復習をしておきます」
小さく喉を鳴らしてから、イェアが緊張に掠れた声で話し始める。
基本の路線はシンラを崩滅させ、空いた柱に封縛印章石で捕らえた大禍鬼の存在概念で穴埋めするというものだが、シンラは特性として“同加”の力を持つため、前回のような肉体を滅ぼした程度で印章石の存在概念を解放するとそれと“同加”して復活してしまう。その為、今回は徹底的に、完膚無きまでに崩滅させねばならない。
静かな【NAME】の号令の元。一同は、柱芯の大禍鬼との戦いに挑む。
[ExtraMonster Encountered!]
battle
柱芯の大禍鬼
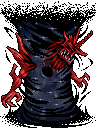
柱と同加し、既に鬼という形すらも失いかけていたシンラを、まさに柱ごと、【NAME】の一撃が討ち滅ぼす。
だが、それだけでは足りない。更に幾度も幾度も、【NAME】達はその痕跡塵一つ残さぬように入念に叩き潰した。
そして大きく大きく抉られた柱。そこに残ったシンラだったものの、最後の残り滓。それを消し去ろうと【NAME】が武器を振りかぶった正にその時、四色の輝きが溢れ、そこから不定形の化生が溢れるように召喚され、遮られる。
「“四界の杖”の力っ!? その姿になってまで、まだ残していたというのか!」
オリオールの驚く声。この場に耐えきれなかったのか、呼び出された存在はどれもが歪み、直ぐさま存在が崩壊していく。だが、その隙に残り滓はえぐり取られた柱の、辛うじて残っていた奥の部分を削り取り、その向こう側――つまりは鬼芯の檻の内側と、空間が繋がった。
「――――」
変化は、一瞬にして明確に起こった。
残り滓としか思えなかったその存在に、檻の内側に封じ込まれていた濃厚極まりない、極陰質とも言うべき存在概念がまるで磁力の極に吸い寄せられるようにして集まり、形を持ち始めたのだ。
最初の礫であったシンラの存在概念は、一瞬にして呑み込まれ、どんどんと、どんどんと。長き封印により分解され、形無き陰性概念となり漂っていたものが、個として、生まれていく。
「【NAME】さんっ! いけない! 止めてください!」
「撃ちます、避けて下さい!」
イェアの悲鳴のような叫びと、ノエルの切羽詰まった警告が重なる。
身を横へと流した【NAME】の直ぐ傍を、強い陽性――これまでは見る事の無かった地母としての概念が強く込められたフォーレミュートの砲撃が走り、今まさに生まれようとする何かを削り取るが、しかし、核となったシンラの存在概念には届かず、直ぐに概念の集合が再開される。
「……誤算です!」
その様を見て、イェアが絶望に染まった声を上げる。
「もうシンラという鬼種が自己を保てぬ程になった状態で、鬼芯が分解され、けれどまだ完全に浄化されていない場所に飛び込めば、分解されていた存在概念がそれを核に集まって、姿を取り戻そうとする――過去にありえた姿、この世界に存在するあらゆる者に対する破壊者、鬼芯属の姿にっ!」
――まさか、復活するというのか。
多数の芯属が力を合わせ、人を含めたあらゆる生物を用いてようやくこの地に封じた芯属、鬼芯属が。
「ううん」
しかし、首を小さく横に振る者が居た。
「あれは違う。だって鬼芯はもういないから。だからあれは幻。“同加”の鬼が、希った主の幻を背負ってるだけ」
「鬼芯属にはならない、という事ですか? ……でも、あれは」
「何にせよ、まだはっきりとした形も取れてないっていうのに、先刻戦った大禍鬼よりも遥かに凄まじい気配を持つように僕には見えるんだが」
それも、時間が経つ毎に存在の強さが増していっている。
このまま再現なく周りの陰性概念を取り込んでいくとするなら、鬼芯属になろうがなるまいが、最終的には手に負えない存在になるのは明白だった。
吹き付けてくる強烈な歪の風に負けぬよう、大きく息を吐いて武器を構え直した【NAME】の隣に、す、と人影が立つ。
「ならばやる事は明白だろう、“神形の使い手”よ。手に負えなくなるというのならば、手に負えなくなる前に全く斬り断ち、崩じ滅せば済む話。まさか、先刻の戦いで力尽きた訳ではあるまいな」
そんな弱音が吐ける状況ではないだろう、と返すと、今度は逆側に二人やってくる。
「ったく、アタシは本来監察役だってのに、こんなトコまできてこんな化け物相手にしないと駄目だなんて、やんなっちゃうわねん……」
「それについては僕も似たようなものだが、しかし今から逃げ出して助かる確率は万に一つもないだろう。秘蔵も秘蔵、とっておきの印章石を引っ張り出してはみるが、さてどれだけ通じるやら」
口ではそう言いながらも、その目には強い戦意があった。
続けて【NAME】の左右の腕に、そっと添えられる手がある。
「……大丈夫です。【NAME】」
「もしもの時は、わたし達が頑張るから」
右は軍服の娘。左は薄布の娘。強張った決意の顔と、無表情の中に真摯さを秘めた瞳が【NAME】を見上げる。
そして最後に、背後から。
「【NAME】さん、やりましょう! あれさえ……あれさえどうにか出来れば、わたくし達の勝利ですっ!」
力強い言葉に頷き、【NAME】は改めて正面を見据え、一歩、戦いの火蓋を切るべく踏み込んでいく。
真なる楽園 繊と背負うもの
――“繊と背負うもの”──
過去に、“繊”というものが居たのだという。
その名を知るものは、今も昔も殆ど居ない。何故なら、その存在を呼称するのに名が必要だと、誰も考えなかったからだ。
そのものは、あらゆる者達からただ、“鬼芯属”と呼ばれた。
世界に存在する、あらゆる者の反存在。
己と同じ陰性質の存在概念を持つ存在すらも破壊しうる、基盤となる世界自身にとっても害なし仇なす、絶対の消失者。
それ故、鬼芯は一世の内に二柱と存在する事は無く、そのものの名について疑問に思う者は居らず、“繊”が動く度に躰の各所より生まれた、直系とも言える子らの中でも更に僅か。一握りの鬼の子達のみが、その名を知っていた。
ただ、誰がその“繊”という名を付けたのか。
それは誰も知らない。子達も、そして“繊”と名を持っていたその存在すらも。
“繊”は全てと反する者。在り方は全くの異質であり、人が言うところの心や意識のようなものも持ち得ないのだ。
だからそれを知るのは、名をつけたものただ一つだけ。
鬼芯属を生み出した、この世界そのものだけだった。
あらゆるものを破壊し、世界すらも壊すとされる鬼芯属であるが、それを生み出すのも、やはり世界そのものである。
世界が己の内側に存在する存在達により、基盤の部分から崩壊の危機に瀕したとき。世界が自己の消滅すら厭わずに生み出す、地母種とは同種の目的ながら、正反対の過程を求めて生み出される抗体。それが鬼芯属である。
当時は芯属達――特に“芯なる者”達の力が正に栄華を極めた時代。それ故に生じた歪みが、その歪みが彼の鬼芯を生み出した。
鬼芯は生み出されたときから多くの存在を喰らい、歪め、壊し続けた。それが、生まれた意味だったからだ。
しかしそれも、いつかは力尽きる。
破壊するための抗体として生まれたとしても、他の者達は言ってみれば生きるために、創造するために世界から生み出された存在。
そんな中で、たったひとつで逆らい、全てを壊し尽くせる筈がない。
事実、この世界が生じてから鬼芯属が誕生する事は幾度かあれど、世界が滅びたことは一度たりともない。
いつかは止められ、いつかは破れる定め。
役目を全て果たすことなく、いや、それを織り込まれた上で生み出されるのが、鬼芯属という――この世界において最強の力を持つ芯属の正体であった。
ではその彼とも彼女とも判らぬものに、世界は何故“繊”という意を持つ名を送ったのか?
例え全てを滅ぼそうとするものであれ。
例えそれを成し遂げられず滅ぶものであれ。
世界にとっては、己から生まれたものの大切な一つに過ぎないのかもしれない。
――汝、柔らかなり、しなやかなり、強かなりて。
生死繋ぐ筋となり、世の均衡を保つ糸となるように。
・
「“繊”。あれはそれを背負う者」
「……“繊”?」
短く呟いたウィースルゥインの声に、反射的に声を返す。
「そう。“繊”。私達の始まり。鬼芯が一つだけ壊さず、自分の中に持っていた、ただ一つのもの。鬼芯を示す、ただ一つの言葉」
「どういう意味を持っているのですか?」
「知らない。鬼芯も知らなかったし、私達――大禍鬼も知らなかった。でも、“鬼喰らいの鬼”は、それを背負うつもりみたい」
「そりゃまた大層な話だね。とはいえ、鬼芯そのものになれるってわけじゃないんだろう?」
「無理。私達は――大禍鬼は鬼芯から生まれるけれど、鬼芯とは別のものだから。だから例えほんのちょっとの私達が、どれだけ鬼芯の存在をかき集めても、鬼芯の存在概念をかぶった私達にしかなれない。あいつが夢見た鬼芯の幻しか背負えない。鬼芯は、それだけ私達とは違うものなの」
安心していいのか判断しがたい話だ。
対し、鼻を鳴らしてウィースルゥインの言葉を切り捨てたのはリゼラである。
「そのような要領を得ぬ定義なぞどうでもいい。悠長に話をしている間に、アレはどんどんと力を吸い、より強大なモノへと変ずる。【NAME】、お前が動かぬなら、我が先に行くぞ」
彼の言う事はもっともだ。
【NAME】は右手に武器を構え、左手は首飾りを握る。
ちりんちりんと鳴り響く音は、脈動するように【NAME】の身体に力を注ぎ込んでくるが、しかしいつぞやのように、明確な意思と共に形を変え、【NAME】の剣としての姿となる気配は見せない。
大禍鬼を核とし、鬼芯の幻想を纏おうとするあの存在は、流転の神形が斬るべき者では無いのか。それとも、
――今はまだ、機ではない、という事なのか?
どちらにせよ、このまま放置していると手が付けられなくなる事は明らかだ。幸い、強大化していく――ウィースルゥインの呼び方に従うならば、“繊と背負う者”は、こちらを敵としてまだ捉えてはいないのか、大きな動きを見せてはいない。
【NAME】は仲間の内の二人に呼び掛けると、檻の内側にて浮かぶ“繊と背負う者”に、戦いを挑む!
battle
“繊と背負うもの”

無数とも言える攻撃と防御の最中。【NAME】が放ったある一撃を境に、“繊と背負うもの”の様子が更に移り変わる。煙る紫と黒の霧のようなものが、ゆっくりと、しかし確かに、一つの形を作り出そうとしている。
漂う鬼芯の存在概念を吸収することによって行われていた再生と増殖が、【NAME】達の必死の攻撃により遂に間に合わなくなり、“繊と背負うもの”の状態が、イェアの望んでいた姿へと変化し始めたのだ。
「……どうやら、届いたようですね」
それを見て、イェアの緊張を孕んだ声が響く。
「現れますわよ、“繊と背負うもの”の本当の形が。皆さん、自分が持ちうる全ての力を、今ここで!」
そのようなこと、言われるまでもない。
【NAME】達はそれぞれ武器を構え直し、鬼芯の継承者が見せる最後の姿を捉えるべく、黒と紫の向こうへと目を凝らす。
【NAME】達の攻撃が、ようやく“繊と背負うもの”の核心に届き始めたという事なのか。
それとも、単に集められ、満たされた陰性概念が、ソレと姿を為す程にまで溜め込まれたという事なのか。
これまで何処か不安定に揺れ動いていた“繊と背負うもの”の姿が、漸く一つの形に固定され始める。
「ここまで攻撃して、ようやっとか……」
疲労の色が隠せないオリオールの呟きに、【NAME】も熱くなった身体を冷ますように深く、息を吐く。
眼前に起きている変化は、“繊と背負うもの”が一つの存在として、この世界の上で存在が安定し始めた証拠だ。
砕かれた大禍鬼が背負った幻想とはいえ。この世に在るものを悉くを滅する役目を持つ、生きとし生けるもの達全てにとっての敵が、生誕を迎えようとしているのだ。
「――――」
身体が戦慄く。本能が叫ぶ。
あの存在は、たとえ己が命を賭してでも、討ち滅ぼさねばならないものだと。
あれは、正真正銘の鬼芯属ではない。とはいえ、その器となり、化身となりえた存在を、この“鬼芯の檻”の外へと出すわけにはいかない。今はまだ檻の柱に囚われているが、その縛りからもじきに解放されるだろう。そうすれば、大禍鬼どころではない、周囲のあらゆる存在を無差別に崩滅させようとする、災厄の権化ともいえる者がフローリア諸島に解き放たれるのだ。
現世に顕現した鬼芯の化身は、まず城を喰らい、兵を喰らい、竜をも喰らい、島を喰らい、際限なく喰らって喰らって喰らって喰らい尽くすだろう。
その破壊と消滅の手が一体どこまで及ぶのかは判らないが、しかし少なくともこのフローリアには、この鬼芯の化身を止められる者は居るまい。
遂には鬼の姿となった“繊と背負うもの”。その姿は、二重に絡まるようにして形を保っていた。下方には過去のシンラの姿を彷彿とさせるもの。その上部には、それより遥かに巨大な、恐らくは過去の鬼芯が形を保っていた頃の姿。掲げられた両腕。その先で新たに渦巻く陰性概念の塊は、まるで闇色の新星を思わせた。
「でも」
その様に圧倒されていた【NAME】の隣で、小さく身近な声が届く。
「大丈夫。その為に、私とノエルが居る」
どういう意味かと視線を向けると、その逆側に、新たな気配がそっと寄り添うのを感じた。
「対鬼芯属として設計されていた“人形”であるわたしや、元々鬼芯を親とし、他に様々な助力を得ている彼女なら、あの星の輝きも、何とか出来るかも知れない」
一息。間を置いて、ノエルは真っ直ぐに【NAME】を見上げる。
「――忘れないでください。ここに居るのは、あなただけじゃない」
【NAME】は無言のまま武器を構え、そして一瞬、周囲を見回す。
皆が、自分を見ていた。彼等の視線が込める感情はそれぞれだが、けれどもそのどれもが、【NAME】を鼓舞し、応援してくれているように感じた。
浅く、笑うような吐息。
それだけで、重圧に縛られかけていた心も、疲労で萎えそうになっていた身体も、まるで羽が生えたかのように解き放たれて、軽くなった気がした。
「――じゃあ、行こうか」
そんな風に。
まるで皆と散策にでも出るような気軽さで、【NAME】は現世界屈指の存在相手に、最後の一歩を踏み出した。
集められ、凝縮され、形を与えられていた残滓。鬼芯として成り立っていた存在の壁を突き破った先に見出した、小さな小さな別種の存在概念。
“繊と背負うもの”の核ともいえる、大禍鬼シンラの存在の欠片。
皆の死力を尽くした助けを得て、【NAME】はようやくそれに辿り着いた。
「――――」
爪先ほどもない、小さな点。それに向かって刃を通すと、“繊と背負うもの”が、まるで本当に幻の存在であったかのように、一瞬で消滅した。
――勝った。
そう【NAME】が自覚する前に、後方から叫ぶような声が響く。
「い、いけない! まだ準備がっ」
その声と、そして周囲の空間に生じ始めたこれまで感じた事も無いような奇妙な歪みが生まれ始めるのを見て、【NAME】は思い出す。
“繊と背負うもの”の化身は、まだ檻との繋がりを維持していたままであった。その為、化身が消滅する事によって檻の不全が明確となり、予想通りそれを解決するための“巻き戻し”が生じ始めたのだ。
「間に合って!」
イェアは慌てて印章石群二つを取り出し、その存在概念を解放するが、しかし“繊と背負うもの”の化身となったシンラが開けた穴は、大禍鬼二匹分の存在概念程度では埋めきれず、一時、巻き戻しの速度は弱まるものの、その流れを完全に留める事は出来ない。
「……そ、そんなっ!」
愕然とした声が、場に居る者達皆にその結末を告げる。
イェアの策は、失敗したのだ。
――このままでは、また巻き戻されて全てが終わってしまう。
絶望の空気が広がり、終わりの予兆が皆の身を縛り続ける。そんな中で、するりと。まるで前もってこうなることを知っていたかのように、一切の戸惑いなく前へと進み出た二つの影があった。
先頭に居た【NAME】の隣を、その影がすれ違うとき。
「大丈夫です」
「私達が、何とかするから」
軍服の娘ノエルと、薄布の娘ウィースルゥイン。左右からの声に、【NAME】は目を見開く。
何とかする。何とかする? この状況を?
「一体、何をするつもりですのっ!?」
背後から、焦りを帯びたイェアの叫びに、二人は歩みを止めないまま、淡々と語る。
「簡単な話です。足りないのならば、補えばいい。ウィースルゥインは鬼としての特性を強く持つ存在で」
「ノエルは私の手足。私の力を自分の中で高め、取り入れて使う“人形”よ」
「だからわたし達二人が、檻として取り込まれてしまえば、きっと」
「カンファートとブムドゥでは足りなかった分に、私達の分を足してしまえば、きっと」
「「“巻き戻し”は、止められる」」
二人の言葉には、明確な覚悟の色がある。恐らくは、前々からこうする事も考えていたのだろう。
「――そんな」
それに対し、イェアは、迷い故か、一瞬声を詰まらせてから、それでも叫ぶ。
「そんな犠牲を払うくらいならっ! このまま素直に“巻き戻し”を受けてやり直すべきですわ! 例えもう一度ここに至る道がどれだけ険しくても――」
「もう一度なんて、もう有り得ない。そういっていたのは、イェア。あなただったと、わたしは覚えています」
「……っ」
続く言葉を封じられ、息を詰まらせるイェア。その間に、二人は柱の真中にまで辿り着き、そして【NAME】達に振り返る。
ウィースルゥインは、浅く目を閉じ、全てを受け入れた表情を見せ、そしてノエルは泣き笑いにも近い顔で、【NAME】の顔を見上げて、
「だって、これこそがきっと、わたしと私が、【NAME】やイェア――皆の役に立つ一番の方法。……そう。わたしが探していた“役目”なんだって思うから」
「――――」
反射的に声が飛び出す。ふざけるな、やめろ、馬鹿を言うな。焦りで混ざり合った感情のせいで、それらは明確な言葉にすらならない叫びとなった。
そんな【NAME】に一つ、微笑みだけを残して、二人の少女が柱に空いた穴の中央で、お互いの身体を絡ませ合う。
「だから、始めましょう。“双色”」
すると彼女等を包み込むように伸び始めた二色の髪が、止めようとした【NAME】達を柱の外へと弾き飛ばし、そして穴を完全に埋めるように広がっていったのだ。
それはさながら、藍とくすんだ金の色を持つ繭。
柱の穴に根を張った繭は、徐々に柱の色と一体化して、見分けがつかなくなっていく。柱自体が持つ存在概念に倣うように、ウィースルゥインとノエルが混じり合ったかのような存在概念を持つ双色の繭が、柱そのものに変化しているのだ。
確かに、これならば。
柱に開いた空白は塞がれて、“巻き戻し”からは免れるかもしれない。
だが、だがだ。
――こんな終わりを、認められるものかっ!
髪によって吹き飛ばされ、地に伏した姿からその様子を見上げた【NAME】は、全力で手にしていた武器を突き立て、それを支えに立ち上がる。
その武器が、吹き飛ばされた際に手放した己の愛用の武器ではなく、いつのまにか首飾りから変じていた金色の輝き放つ剣となっていても、【NAME】はその事にすら気づかない程、頭に血が上っていた。
やるべき事は、単純だ。
選択としては誤りかも知れない。だが、その誤りを正すつもりが、欠片も浮かんでこない。
一歩、二歩、そして三歩。踏み出す毎に速度を上げて、【NAME】は駆け出す。
今、自分達を拒絶し、弾き出そうとした双色の繭目掛けて。
真なる楽園 楽園の果て
――狭間の少女達──
【NAME】達を柱の外へとはじき飛ばし、柱のえぐれた部分に対し、藍とくすんだ金の髪を広げてそれを塞ぎ、一体となる繭を作ろうとする二人。
だが、そんな馬鹿馬鹿しい真似を、まんじりと見守ってやるつもりは、【NAME】にはさらさら無かった。
既に同化現象は始まっている。広がった髪は彼女達の身体であり、心でもある。それを傷つけると彼女達にもダメージが、と叫ぶイェアを全く無視して、【NAME】は金色の輝き放つ剣を片手に、柱の中へと一人飛び込んでいく。
繭の中は、さながら地獄ともいうべき環境だった。己の存在を捩じ曲げ、異質極まるもの――それも鬼芯の概念に晒され続け続けたそれと同化する作業。それによって引き起こされる感覚は、もう痛みという言葉では片付けられない代物。存在が感じうる全ての刺激を同時に突きつけられているようなものだった。
繭の中に入った【NAME】には、彼女等が今現在、味わっている感覚が、伝播するように響いてくる。あくまでも、今【NAME】が感じているのは伝わってきたもの。実際に彼女等が感じているのはもっと強く、激しい刺激である筈だ。
(……何処だ!)
目の前に広がるのは、全身を苛んでくる金と藍の色だけ。蠢くそれらは、入り込んだ【NAME】をどうにか外へと押しだそうと動いている。
ただこれが単なる拒絶であると、そう感じられるのならまだ割り切れるというのに。
伝わってくる刺激の中から、彼女等の想いも伝わってくるのだ。
「あなたが」
「貴方が」
「「この苦しみを味わう必要なんてない」」
と。
「――――」
湧いてきた感情は様々。
だが、もっとも強く、明確に己の中に表れた感情は、怒りだった。
自分でも判る程に、理不尽とも思える理屈が頭を駆け巡り、それが止まらない。
まだ生まれて幾年も経っていない、人ですらない、自分の足でろくに立つ場所も定められない。
そんな子供二人が、保護者に向かって何が苦しまなくて良い、だ。
冗談も大概にしろと、余りの刺激故に凶暴になっていく思考のまま、【NAME】は繭の中を乱暴に泳いでいく。
繭がこちらを押し出そうとする動きの流れから、もう彼女達が居る場所は判ったも同然だった。押してくる方向に逆らえば、そのまま二人の元へと行き着く。
――何故、何故と。
強くなっていく刺激。全身をあらゆる種類の痛みが襲うような感覚に混じって、叫ぶような思考が飛んでくるが、そんな問いにはもう、返答をする気すら起きない。
思う事は一つだけだ。
二人をここから引きずり出して、思い切りひっぱたいてやる、と。
battle
狭間の少女達

繭と化した髪の渦を黄金色の刃で裂き、その奥にて収まっていた二人の身体を強引に掴んで、【NAME】は最後の力を振り絞って、柱の外へと放り投げた。
しかし、
「――っ」
無理矢理双色の繭を突き破り、彼女達を柱の外へと放り投げた反動で、逆に【NAME】自身が柱の裏側――檻の中へと転がり落ちてしまった。
落下する身体。そこは檻の外側や柱の中とは、比べものにならぬ程の強烈な陰性概念が空間に満ちていて、同化者である【NAME】の存在すらも変質させようとしてくる。
“繊と背負うもの”が檻の内に残っていた陰性概念の多くを吸収した上でまだこれだというのだから、本物の鬼芯属の強大さを実感せざるを得ない。
流石に、これは終わったか、と一瞬考え、いや、と【NAME】は強く首を振り、強く強く訴えかける。
その対象は、今この手の中にて収まる剣。神形器ゼーレンヴァンデルングだ。
流転ではなく円環。流れ進むではなく戻り回る繋がりは、この神形にとって忌むべきものであるはずだった。
今までは己を密かに主張をし、自分に力を貸してくれながらも、しかし沈黙を続けていた神形器。
つまりそれは、自分の意思を表に出し、本領を発揮する場面を今か今かと待っていたからに他ならない。
鬼芯属すら封じ込め、分解したという、世界でも類を見ない程の“封じ閉じた”場所。
それに閉じ込められた形の今であるならば、彼の神形器が己の役目を自覚せぬ訳がない。
(……さあ、目を覚ませ!)
【NAME】の渾身の叫びに、答える鈴音が一つ。
――そう。認めるわ。
ゼーレンヴァンデルングの声は、今まででもっとも明確に、耳元で届く。
――ここが私の“役目”の地。
――これが私の全てが果たされる場所。
そんな意味の言葉と共に、強烈なイメージが【NAME】の頭の中に叩き込まれる。
それは、神形が意図する、この状況の解法であった。
本来、檻は、芯なる者が編み出した秘奥の芯形機構に加え、他の芯属の手も加えられたもの。それは絶大ともいえる力を持ち、如何な神形器であっても容易く打ち破れるものではない。
だが、今ならば。
“繊と背負うもの”と化したシンラによる穴が開き、そこにイェアが二匹の大禍鬼の概念を叩き込んで、更にはウィースルゥイン達が繭を施し変質させた今ならば。
自分が檻の内側から柱そのものに突き立ち、持ちうる全ての力を注ぎ込めば、檻自体の完全な破壊までは難しいかもしれないが、生む輪を接ぎ変える程度は出来る。
これまで生じた“巻き戻し”は、檻が持つ保全機能の一環だ。しかし、その保全機能がそもそも動かせない程にまで“芯檻”を破損させてしまえば、“巻き戻し”は起こりえない。そして、これを己の“本来の役目”と認め、全ての力を解放した自分ならば可能だ、と。
全ての力の解放。それはつまり、道具としての終わり。
神形器ゼーレンヴァンデルングの――生物に例えるならば死を意味していた。
「……っ」
逡巡する【NAME】に、鈴の音が優しく鳴り響く。
――私は“役目”を帯びて生まれて、それを為す為の道具よ。
――だから、全うして絶えるのは器としての誉れ。
――そしてそれを目の前にして逃すのは、生き恥を晒すのと同じ。
――貴方を、一時であれ私の持ち主だと認めていた事。
――それが誤りだったと、私に思わせないで。
「…………」
その言葉に、【NAME】は覚悟を決めるしかなかった。
――だから、唄って。
──私を紡ぐ、流転の詩を……。
神形の願いに、【NAME】は過去に幾度も紡いだ唄を捧げる。
そうして生じたのは、これまで見た事も無い程に長大で、金色の輝きを放つ大剣だ。
それを【NAME】は両の手で掲げて、そして一瞬過ぎる感慨を経て、勢い良く振り下ろす。
それだけで、柱の一本――エルツァン島を要としていた柱そのものが、完全に消滅した。
――楽園の果て──
柱を破壊し、檻の外へと脱出した【NAME】達は、イェア達と合流し、“鬼芯の檻”から“城”へと戻る道をひた走る。
その間、イェア達にゼーレンヴァンデルングの事を話すと、暫しの絶句の後、
「檻ごと破壊されたら、この世界どころか、エルツァン島すら危ないですわよ!?」
彼女の言う通り、内から外に対しては全くの無反応であった“封印”を潜りどうにか“城”にまで戻った【NAME】達は、エルツァン島全体が大きく震動を始めている事を知る。
「色々な施設や、“城”の存在から察するに、エルツァン島は恐らく“鬼芯の檻”の管理地として造られていた島なのだと思われます。だから、ゼーレンヴァンデルングが檻自体を派手に檻を破壊してしまったら、島の方にも影響が出る可能性が凄く高い。特に、“鬼芯の檻”の柱は、“芯檻”の構造から逆算するに、フローリア諸島の各島の土地概念と連結して生成されたものと考えられますから、その中の一本――恐らくエルツァン島と繋がっていた柱をあんな風にぶった斬ってしまったら……」
「……つまりそれって、この島自体が崩壊する、という事かい?」
「有り体に言えばそうです。少なくとも、固有の独自空間をまるで重複するように島内に展開していた力は無くなるでしょうから、それらが重複してエルツァン島上に展開されて、無茶苦茶な状態になるのは確実ですわね。こんな状態で、島の土地概念が崩壊せず保たれたなら逆にびっくりですわ」
「その辺の理屈はまぁ置いといて、結局どうすりゃいいのん?」
「脱出! 全力で島から脱出ですわよー! そんな土地概念同士のカチ合い現場なんかに巻き込まれたら、人間なんてひとたまりもありませんわ! 撤収ですてっしゅうっ! というか、この“城”自体も崩れ始めてるじゃありませんのっ!」
イェアが叫ぶと同時に、“城”内に詰めていた兵士達がわーと外へと飛び出す。
そして【NAME】達は外でリンドヴルムを相手していた軍部隊と早々に合流。リンドヴルムはこの震動が始まった時点で、既に封じられていた印章陣の内部で姿を解き、消滅していたらしい。恐らくは“鬼芯の檻”が復元不能なまでに壊れ、任じられていた“役目”そのものを失った事で、この世界にて顕現を続ける意味も失ったのだろう。あの個体は、もう二度と、この世界に姿を現す事はあるまい。
だがそんな事に気を回している状況では全く以て無かった。
物資その他必要最低限のもの以外を放置して、【NAME】達は全力で島の外側、近場の岸目掛けて移動を開始する。島を包んでいた特性はもう完全に失われており、ほぼ全景が正常に見通せる状態だ。“城”の位置が比較的沿岸部に近くて助かった。もし内陸であったなら、恐らく岸に辿り着く前に、様々な土地概念の氾濫に巻き込まれて助からなかっただろう。
エルツァン島の特性も急速に失われていった為、内海にて待機していた軍船とも即座に連絡がつき、近隣の浜にて総員を回収、エルツァンより脱出する。
上陸回収用の小舟から船上へと昇り振り返ると、エルツァン島はもう過去のものとは全く違う様相を見せていた。
無数の地形が重なるように現れては消え、砕け、混じり合い、そして飽和して泥のようになり、最後には崩れてはまた別の形が現れる。
完全に、土地として壊れてしまっていた。あれではもう長くは保つまい。島としての形も、果たしてどれだけの間保てるのか。
短い間ではあったが、皆で協力し、探索を続けた場所。
それが砕け、壊れていく様を、皆は複雑な気持ちで見守る。
と、そこへ、ちりんと聞き慣れた小さな音。
――それじゃ、お別れね。
最後に、鈴音と共にゼーレンヴァンデルングの別れの声が【NAME】の耳に届いた。
――私が斬れる、全ての糸を今から断つ。
――短い間だったけれど、ありがとう。
――さようなら、【NAME】。
思わず言葉に詰まる。
「…………」
彼の神形に、己の名を呼ばれた。それは最初で最後の事だったように思う。
そして、それを合図とするように、エルツァンと呼ばれた島は全てが光の粒となり、まるで存在自体が幻であったかの如く、消滅していく。
島を覆うが如く何本も立ち上る光の柱は、まるで檻のようであり、それがあっさりと消え去った後には、凪の海しか残らない。
その光景は、フローリアの根に存在した、あの“鬼芯の檻”の行く末を示しているようにも思えた。
全てを見届けて、【NAME】は静かに実感する。
これで本当に、全てが終わったのだと。
真なる楽園 ささやかな午睡
――ささやかな午睡──
砂浜の上を、細波が音を立てて駆け上がっては引いていく。
エルツァン島の崩壊から、相応の月日が流れた後。仲間達と無事にエルツァン島から生還した【NAME】は、アノーレの港町、ポロサにて宿を借り、これといって何をするでもなく。時折こうして近くの砂浜に降りてきては、ぼんやりと海を眺める日々を送っていた。
そんなある日。
いつものように海岸から遠く海を眺めていた【NAME】の元に、二人の訪問者がやってきた。
「こんにちは、【NAME】」
「ご機嫌は如何でしょうか。これは、イェアからの差し入れです」
軍服ではなく、仕立ての良い町娘の装いをしたノエルと、そして彼女と良く似た、けれども色彩は異なる衣装を纏ったウィースルゥインの二人である。
二人は現在、イェア預りの軍属として、彼女の所で生活している。より正確には、【NAME】がポロサから動こうとしないため、取り敢えずそちらに預けられている形だ。ウィースルゥインは当然として、今ではノエルも完全に人の枠を離れた力を持つ存在となってしまった為、そろそろ軍という組織の中に居るのは危険であると、イェアから【NAME】に保護者役を移譲したいと打診を受けているのだが、【NAME】はその答えを保留している状態だった。
ちなみに、エルツァンから無事に生還した後。この二人には散々に折檻し、しっかりと教育を施してある。
掲げられたのは葡萄酒と乾酪が入った網籠。それを受け取り、ちゃんと礼の言葉を返したつもりだったのだが、対する二人の反応は今ひとつ芳しくない。
「まだ、元気が無いようだと、わたしは判断します」
「うん。困ったね」
と、言われても自覚が無いのだが、しかし改めて今の自分を昔の自分と比べてみると、そういう判断になるのも間違ってはいないのかもしれない。
素直にそう答えると、いよいよ彼女達はしょんぼりした様子で、小さく肩を落とすばかりだった。
その後、彼女等と話したのは、他の皆の様子だ。
白衣の学士、“先生”のイェア・ガナッシュは、エルツァン島での出来事を報告資料に纏める仕事に未だ掛かりきり。何時終わるか知れない作業量と、確実に正気を疑われかねない内容に、二重の意味で頭を痛めているという。最近は果実酒以外の酒にも手を出すようになり、ノエルが苦言を呈する事も増えたという。
髭面の伊達男、“海月”のノクトワイ・キーマ・フハールと彼が率いる部隊は、無事任務を終えたということで原隊に復帰。しかし、彼自身は然程の時も経たない間に、その姿を消した。当初は様々な憶測が立てられ、捜索隊なども編成されたりもしたのだが、それらも程なく打ち切りとなった。ノエルが最近レェアから聞き出した話によると、そもそも彼の名前と立場は偽のものであり、その本性は別の“六家”からフローリアの情勢を把握するために派遣されていた諜報員であったという。レェアは最初から彼の素性を知っていたらしいのだが、別に誰かに言う事でもなく、あとで上手く使えるかも知れないと秘密にしたままだったとか。その彼が消えたという事は、つまりノクトワイが“六家”から指示されていた仕事――諜報員としての仕事はやり終えた、という事なのだろう。何を探り、見届けるためにここに居たのかまでは、流石のレェアも把握してはいなかったようだが。
「でも結局、使い処を窺ってる間に色々終わっちゃって、そのままって訳。本人は色んなものを見て帰っちゃったけどね。……ずるいなぁ」
とは、レェアのその時の言葉をそのまま再現したものだ。因みに、同じ姉妹でもイェアは全く知らなかったらしく、それを聞いてびっくりする程ショックを受けていた。
そして、命脈と共に在る女、“女賢者”レェア・ガナッシュ。こちらはノクトワイとは対照的に、アノーレの四大遺跡事変が終わった後も、以前と変わらぬ形でのんびりと、しかし影では色々と、人ではなくなった自分にしか出来ない作業なり、研究なりを続けているようだ。
“杜人”のリゼラ・マオエ・キヴェンティがエルツァン帰還後に少し様子が変わったことに対しても、「少年がちょっぴり大人の経験を自分の知らないところでするのって、少し妬けるね」などと宣い、少年の顰め面をより深くさせていた。あの調子では、彼の年頃で眉間に皺が刻まれてしまいそうな程である。
壮年の博士、“冒険家”のハマダン・オリオールも、ノクトワイとほぼ同様のタイミングで、こちらは正式に皆に別れを告げてから、東行きの船に乗ってフローリアを去った。
彼が追ってきた“四界の杖”と、彼が持ち込んだ神形器の結末。
その両方を見届けた彼にとって、フローリア諸島で成すべき事は全て終わったという事なのだろう。
別れの挨拶自体既に済ませていたのだが、彼は同職の探検家カール・シュミットの顛末について、多少なりと思う所があったようだ。今後の自分の冒険者としての在り方を、見直してみるのも良いかも知れないと、そんな話をしていたのを思い出す。
そして話は、復興がようやく軌道に乗り始めたアノーレの事へと移り、そして消滅したエルツァンと時を同じくし、別の場所に新たな島の影が現れたという話も出てきたという。エルツァン島が消失し、“鬼芯の檻”が恐らくはそれに近い状況になった事で、このフローリアも更なる変化の兆しを見せていた。ノエルとウィースルゥインが今回こうして【NAME】に会いに来たのも、この話をしてやる気を出して貰おうとしているのは、既に【NAME】も判っていた。
しかし、それは【NAME】としてはもう知っている話でもある。とうの昔に、似たような目的の下、イェアから話を聞いていた。以前までの自分ならば、我先にとその情報を追っていたところだろう。
それでも、何故か不思議と動く気にはなれない。自分でも理解出来ないその感覚。曖昧なままの自分の心に手を伸ばしていくと、近しい言葉が一つだけ浮かぶ。
――待っているのだ、と。
その時、何かが耳に届いた気がした。
「――――」
耳慣れたものではなかった。誰かの声でもなければ、何かの音でもない。況してや、鈴鳴りの音では断じて無い。
ただ、訪れを知らせるために、既に何かを発する力すら持たぬものが、せめてもの力で訴えた、声無き声だった。
そんな声に惹かれて、【NAME】は視線を移す。直ぐ傍の浜に、丁度一つ、大きな波が打ち寄せて、そしてゆっくりと引いていく。
その後に、燦めく何かが浜辺に残されているのを見た。
「【NAME】?」
ノエルに呼び掛けられた気もするが、耳に入らなかった。【NAME】は波打ち際に駆け寄り、掛かっていた砂を払い、目を凝らす。
それは、いつか見ていた、いつも見ていた、首飾りの破片だった。
「…………」
無言のまま拾い上げ、そして握り締める。
もう鈴音が耳元で響く事も、身体に力を満たしてくれる事もない。首飾りの半ば以上は失われ、残る部分もぼろぼろで、今にも崩れ落ちてしまいそうだ。
けれど、本来の剣の姿ではなく。
まるで自分の手元に収まる為に、仮初めの首飾りの姿で戻ってきてくれた事に、言葉に出来ぬ感慨が湧く。
それは意識もせぬまま、一つの滴となって砕けた首飾りを濡らした。
・
永き時を、閉塞を穿ち、流転を断つために在った勇ましき剣の神形は、今ようやく。
その役目を終えて、ささやかな――けれども終わりのない午睡を得たのだ。