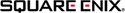![]()
みんなdeクエスト 那由多の道と異界の扉
- 真なる楽園 在りし日に縋る孤独の手
- 真なる楽園 解けて凝る清濁の在処
- 真なる楽園 ふたり立つ境の際
- 真なる楽園 秘中の暁
- 真なる楽園 識別の朝
- 真なる楽園 折合の昼
- 真なる楽園 愛顧の夕
- 真なる楽園 決断の夜
- 真なる楽園 幕引きの導
- 真なる楽園 (ルートA)坤濁の大禍鬼
真なる楽園 在りし日に縋る孤独の手
――在りし日に縋る孤独の手――
その頃には、わたしにとってわたしとの繋がりは掛け替えのないものになっていた。
わたしはわたしの世界を通して、長く長くあらゆるものを知った。あやふやだったいろいろなものが、今はくっきりと見えるようになったと感じる。自分の気持ちの動き、心の流れを捕まえて、言葉に出来るようにもなった。
けれどわたしの周りにあるものは、それでも全てが形のない、色のない、熱のない、褪せたものばかり。
はっきりと見え、感じるのは、わたしに触れて繋がった時に見えるものだけ。
わたしが思い出す古い出来事。
わたしが辿る誰かとの旅路。
それを眺めるとき、世界が形と熱を持ち、色と音を放つ。
だから今も透き通った鏡越し。わたしはわたしの歩みを見つめ、確かな情景に身を委ねる。
そうして長く、長く。ただただ、わたしが見る光景を眺めていると、自分の中に小さな疑問のようなものが生まれた。
いつも、わたしはわたしを見ていた。大切なわたしの夢。だから忘れる事はない。なのに――どうもわたしは、何もかもを忘れてやり直してしまうようだった。
島を訪れ、島を進み、そして城へと辿り着き、また島を訪れる。わたしはそれを、ずっとずっと繰り返し続けている。
島を歩いて、いろいろなものを通り過ぎて、最後に城の門を潜る。その後は大抵よく見えなくなって、そして気づけば島まるごとが、少し前の形に戻っている。島を包み込むように立つ、大きな棒のようなもの。その内側だけが、くるりと元の姿に塗り替えられてしまう。
その時、わたしを通じてわたしにも何かが触れてくる事に気づいていたけれど、感触はとても弱くて、わたしが何かをする前にそれはいなくなって、そして全部が元に戻っている。
最初は気にしていなかった。けれど、今のわたしにとっては少し邪魔だった。
あの弱々しい感触が、わたしが全てを忘れてしまって、ずっと同じ事ばかりを繰り返すようになっている原因だと思うから。
忘れてしまうこと。それについてはどうでもよかった。だって、わたしは覚えているから。わたしはわたしなのだから、わたしが覚えているならそれは平気。
でも、同じ事をこの先も繰り返し続けるのは、少し残念を感じる。
わたしの旅。
色々な風景を見て、誰かといっしょに進む道。
それはまだ、わたしにとって新鮮なものではあったけれど、そろそろもっと別の、あたらしいものも見てみたい。
昔の事のように、もっと色々な出来事を見て、感じてみたい。
そうすればきっと、ずっと。
わたしはわたしの違うところを見知る事で、もっとわたしになれると思うのだ。
けれど、どうすれば良いのかなんて判らなくて。
だからわたしは、ただわたしが望む事を続けるしかなくなってしまう。
わたしに触れれば触れるほど、何もなかったわたしが、どんどん何かを得ていくのを感じる。
温かくて、鮮やかで、嬉しくなる。
幸せになって、そして恋しくなる。
自分の周りにあるどうでもよいもの。それらを押しのけて、わたしはまたわたしを求めて歩き出す。
どこにいるかなんて、直ぐに判る。だってわたしとわたしはそういうものだから。
そうして、わたしはわたしを見つける。共に居る誰かの姿も少しだけ見える。彼の背中を眺めるだけでも、わたしの心は安らいでいく。
わたしの旅を眺める時、この事が一番の愉しみだった。わたしとわたし以外に色が無く、形もよくわからない世界の中で、彼の姿だけはなんとなく判るのだ。
それはわたしに気づいた時とは少し感じが違うけれど、それでも誰かが在ると感じられるのは新鮮で、そしてとても安心できる。
わたしにとっての彼とは、つまり寄る辺なのだ。
眺めるだけでも安らぐけれど、わたしと繋がれば、その心地が更に深くなる事をわたしは知っている。
だから見つけたわたしへ、わたしは繋がりを求めて手を伸ばす。
――そうして、形ない指先がそろりとわたしに触れた。
すると花が咲くように世界が色に包まれ、わたしも確かなわたしになっていく。
その事にわたしはまた嬉しくなって、もっともっとと手を伸ばす。
知り、触れて、なぞる程に。
わたしとわたしの世界は同じになっていく。
わたしとわたしの姿形は同じになっていく。
鏡合わせに立つわたしへと、広げる掌。重なる境は波紋を残して、触れた際から溶けては混じる。
――さあ、また微睡の中でわたしを見ましょう。
鏡の向こう、向かい合わせに立つ瞳の中に、わたしの世界を見つけようとして。
わたしの瞳が、真っ直ぐわたしの姿を定めている事に気づいた。
眼前に見えるわたしの唇が震えて、喉が動く。囁くような声音は、わたしが聞く初めての声で、
「見つけた」
驚きで、手が離れた。
「……見つけた」
次の超常地形へと向かう途中。顔を掌で覆い、膝を折ったノエルは呻くような声音でそう呟いた。
前方、数歩ほど先行していた【NAME】が、こちらの様子に気づいて振り返り、窺うように声を掛けてくる。戻ってこようとする【NAME】に「大丈夫です」と短く応えて、ノエルはゆっくりと立ち上がる。
【NAME】から見れば、先刻の自分の動きは立ちくらみのように見えただろう。
しかし、実際は違う。強烈な現実感を伴う幻が己の意識にのみ生じる現象――幻視が、ノエルの身を襲ったのだ。
多くは睡眠中に、夢として視る事が多い幻視であるが、それ以外の時、つまり起きている時にも発生する事はあるようだ。自分が日中に遭遇するのは初めての経験だったが、しかし“いつかのノエル達”が警告してくれていたお陰で、そう混乱せず無く受け入れる事が出来た。
それどころか、常に気を張り、用心していたのが功を奏したのだろう。遂に、幾人かの“いつかのノエル”が示唆していたその存在を、一瞬、僅かながらも見定める事に成功したのだ。
恐らくは快挙といえる事の筈なのだが、実感は薄い。何せ、今のノエルからすれば、この一連の出来事は確たる証拠が一切ない、自分の中でだけ生じる妄想じみた事柄だったからだ。しかも長い時を経ての達成という話になるとはいえ、ノエル自身には長い時とやらの記憶がない。これで達成感を得よというのが無理がある。
だが、これまで視た幻が伝えてきた言葉に、相応の信憑性が生じているのも事実だ。
(眉唾物と、そう思いたかったところですが……)
全くの妄想の産物と断ずるのは、もう難しい。
エルツァン島に渡ってから、少しづつ生じるようになった幻視。
初めてノエルが視たそれは、幻視とやらの詳細らしきものを延々と考え、訴え続ける自分を追体験する――という代物だった。
面食らったものの、島で暮らし、そして【NAME】の“鬼喰らいの鬼”討伐の旅に同行するようになってからも頻繁に現れる幻は、確かに最初や、それ以後にも時折視るようになった“幻の中の自分”が伝えていたものと一致する事柄で、単なる夢と斬り捨てる訳にもいかなくなった。
ノエルの記憶にないノエルが語るもの。それらは幻によって、ところどころ内容に突飛な推測が混じったり、情報の量に差があったりしたものの、大筋は同様のものだ。
曰く、
『ノエル・ガナッシュは己と、そして全く知らない何者かの過去を、幻として視ている』
と。
そう、どうやら自分が視ている幻は、全てが過去の出来事であるらしいのだ。
例えば自分が歩んでいるこの“鬼喰らいの鬼”討伐の旅において、その先と思しき未来の光景や、同じ場面の別の選択を選ぶ自分を幻として視る事がある。
だが、“いつかのノエル達”が積み重ね得た結論は、それら全てが過去に辿った旅路の記憶であるのだそうだ。
ならば何故多重化し、まるで未来すらも視ているような記憶として現れるのか。それについても、“いつかのノエル達”は大凡結論といえるものを既に見出していた。
要するに、ノエル・ガナッシュが――いや、エルツァン島に存在するほぼ全ての物事が、ある時を境に、環を描くようにして元の形に巻き戻っているのだ、と。
(確かに、考えてみればそういう話になるのでしょうけれど……)
俄に信じがたいが、同時に納得出来る話でもあるのだ。
自分が視ている現在、そして未来と思しき幻とは、つまり過去に存在していて、しかし上書きされ失われた自分。ループし続けるノエル・ガナッシュが辿った道筋であるとするなら、幾つもの可能性が同時に存在しつつも大きな逸脱はない――“どれも有り得そうな未来”となっているのも判る話だ。島にやってくる以前の幻はそうした多重化が一切発生していない点も、この推測を補強していた。
そしてどういう理由によるものかは判らないが、自分はその塗り替えられた筈の過去の記憶を、幻として垣間見ているのではないか、と。
最初にこの推測に辿り着いた“いつかのノエル”は、それを証明するべく一つの手を打った。彼女はその発想をした段階から以後、延々と、常にその事を頭の片隅で思考し続け、更にもしこの思考を幻として視た者が居たならば、自分と同様の事をしろと伝えたのだ。
結果が今である。島内の状況を再現する幻視において、“幻視についてある程度の共通認識を持つノエル”と“幻視についての共通認識を殆ど持たないノエル”のどちらが現れるか。今と過去では、その比率が大きく変化しているのだ。
今のノエルと、恐らくはループの初期と思しきノエルの幻では、認識している状況、幻視に対しての情報量が格段に違う。初期の自分の場合、幻視についての認識が甘いノエルばかりを幻として視ており、得られる情報は殆ど無い状態。突然の幻視に混乱し、ただただ憔悴するばかりの者達が殆どだった。
対し、今のノエルが視る多くの幻の中では、幻視についての知識や考えを持ち、解決のための試行錯誤をしている自分が居た。幻の程度の話で語るならば、今の自分が体験しているものの方が遥かに再現の度合いがきつく、心を塗り替えてくる力が強い。それでもどうにか、表面上は何事も無く保っていられるのは、正に幻から得られた知識の差、心構えの違いによるものなのだろうと思う。
環のように巻き戻り、繰り返す自分の記憶。それらが延々と蓄積され、それを幻として視ているとするならば。
この知識を“次のノエル”へと伝え続ける事が出来れば、それは全てが過去の出来事だという証明であると同時に、未来の自分への助けとなり、解決へと向かう道標にもなり得るだろう。その時の自分はそう考え、今の自分はそれを正しく受け取る事に成功している。繰り返される過去の蓄積であるならば、“知識を持つノエル”はこの先どんどんと積み重ねられて、逆に“知識を持たないノエル”の存在は少なくなっていくのだろう。
ただ、そうして知識を受け継がせる方法を編み出した今であっても、この現象自体が一体何であるのかという部分については殆ど手探りのままの状態だった。 むしろ、問題点は二つに増えている。
最初は幻視だけで済んでいた話であったが、今はもう一つ、巻き戻りという問題が増えている。
幻視については兎も角、巻き戻りについては自分だけの話には留まらない。誰かに、例えば旅の道連れである【NAME】に相談する事は幾度も考えたのだが、
(上手く、説明出来る自信がない……)
如何せん、形となる証拠のようなものが一切ないのだ。更に言えば、これから“鬼喰らいの鬼”との対決を前にした【NAME】に、こんな自分でも理解し難い話を聞かせる気にもなれなかったし、何よりこんな話をしたところで、解決の手掛かりになるようなものは全くもって無いのだ。聞かされたところで困るだけだろう。
“いつかのノエル達”の思考や行動を参考にすると、多くの自分はエルツァンでの旅の最後に辿り着く場所――城のような場所にその原因があると考えているようだった。しかし、自分を含めたこれまでのノエル達は誰一人として、その城の中の出来事を幻として視た者はいないようで、中に何があるのか、何が起こるのかは謎に包まれたままだ。逆にいえば、これが幻視と巻き戻りに何らかの関連性があると示唆しているように思えなくもないが、推測の域は出ないだろう。
また、幻視についても疑問は多く残っていた。
状況をある程度認識できるようになったからこそ生じる疑問。何故そんな事になっているのか、そして何故幻として過去の記憶を見るようになったのかという疑問だ。
これまでの自分は、幻視について多くの推測を重ねてきた。それらは幻視を介して過去から今のノエルへと伝えられてきてはいるが、しかしその伝達方法はかなりの運任せであるのは否めず、そもそも何故そうなっているのかが判っていない。酷く断片的なものであったり、大きな飛躍があったり、欠けた情報による予想であったりで、過去の自分の苦労が窺える。
ただ、そういった数多の自分が考えを続けてきた結果、ある程度の共通認識のようなものが出来上がりつつあった。
それは、
「誰かが、わたしに幻を見せている――あ」
思わず声に出た言葉に反応し、先行く【NAME】が怪訝と振り返るのが見えた。ノエルは首を左右に振って何でも無いと伝え、彼の後に続く。
場所はなだらかな草原。亜獣の気配は薄く、暫くは安全そうだと判断し、ノエルは歩きながらまた思考に没頭する。
己が視る幻が、外的要因によるものであるという推測は、比較的速い段階で生まれていた。それもそうだ。過去には自己診断が出来ない故、“人形”としての機能異常によるものかと戦々恐々していた自分も居たが、これだけ繰り返した記憶を受け継ぎ、そしてついさっき“見つけた”ノエルからすると、もうその線はないだろうと確信出来る。
ヒントとなったのはやはり、あの未知の幻達だった。
ノエル自身が関わる幻とは完全に一線を画す、奇怪で異常極まる不可思議な幻視。あれが自分の中から生じたものとは到底思えない。とするならば、その出所は己ではなく別にある、と考えるのが当然だろう。
あれらは完全な妄想の産物にしては、少しばかり方向性が整いすぎている。内容自体はノエルの想像を絶するようなものばかりであったが、けれどもその中に、“これはこういうもの”という大まかな傾向のようなものが存在するのだ。
そして、自分が幻として視るものは基本的に“記憶”であるとするならば、あの幻も同様に、何者かの記憶であると考えるのはそう的外れなものではない筈だ。
つまり、あの四つの記憶が、ノエルに幻を視せている存在の正体に繋がるものだ、と。
だが、そこまで思い至った辺りで、幾多のノエルの思考は完全に止まってしまっていた。
ノエルが味わった四種の未知の記憶。それらは全て、主体となる者が別であったように思えたからだ。そもそも、者であったのかすら確信が持てず、何より情景が異質すぎてまともな情報を得る事も出来ない。モノによっては多少理解が及ぶ幻もあったが、それにしても、今ノエルが置かれている状況とは全く繋がりを見出せず、完全に行き詰まってしまっていた。
まずは正体を掴むのが優先すべき事だとは判っていたが、それについても方法が思いつかず。何か別の切っ掛け、別の尻尾を掴むしかない状態で、長い間状況が停滞していたのだ。
しかし今。ノエルは運良く、そしてようやく、求めていた別の尻尾とやらを見つける事に成功したのだ。
こうして順々に状況を考えていくと、先刻は全く感じなかった達成感のようなものが、じわじわと胸の奥に沸いてくる気がする。確かにこれは大きな前進だと、そう思える。
(ですが……)
迫る白昼夢の気配。幻に埋め尽くされそうになる自分の全て。その切り替わりの刹那に見出した、今まで気づく事の出来なかった何かの存在。それを、ノエルは一瞬ではあるものの捉える事が出来た、見つける事が出来た筈だ。
けれど、その姿を今改めて思い返すと、沸き上がってくるのは解答ではなく疑問でしかない。
何故ならば、現実と幻覚の狭間。どこでもない場所でノエルに向けて手を伸ばしてくるその姿形は、
「わたし……?」
線が細く、色の薄い髪を伸ばした、表情の少ない娘。
それは自分自身の鏡写し。殆ど寸分違わぬ己が、能面じみた顔の奥に歓喜を偲ばせて、こちらの手に手を重ねて握っている姿だった。
どう言う事なのか、という疑問しか湧かない。解決に一歩近付いたと思ったら、いや、確かに一歩前へと進んだのだが、しかしその先には更なる分岐が存在していたような、そんな感覚がノエルを襲う。
自分が、この幻を見せている? いや、そんな訳がない、とノエルは小さく首を振る。少なくとも、“いつかのノエル達”は今のノエルと同じ立場の筈だ。そこに更なる別種の自分が、このような超常的な干渉をしてきているというのは流石に入り込み過ぎているというか、いまいち納得がし難く、その上、
(あのわたしとは違う記憶の事を考えれば、正体がわたしだというのは妙ですし……)
そうなると、ノエルに似てはいるが、しかし別物。或いは、ノエルに化けた何者か、辺りが候補となるだろう。そして少なくとも接触するこちらに対し、人の姿のようなものを取って、そして感情のようなものを向けている事は判った。この情報だけでも、正体の候補は大きく絞る事が出来た。これは十分に進展といえるだろう。
もっとも、その進展は僅かであり、解決には程遠いとしか言いようがないが、少しずつ、確かに、歩みを進めていく他無い。
今、ノエル達が使っている伝達方法は、自分の先に存在するであろうノエルが、偶然この事を知り考えているノエルを幻視する事で成り立つ、極めて不安定な代物だ。
今回ノエルが得た発見も、本当は別のノエルが既に得ていて、しかし後のノエル達にはあまり伝わらずに埋もれてしまった情報であるという可能性も十分に有り得るのだ。
また、幻視によって情報が伝わる確率を高めるために、旅している間は常時これらの事について思考をする必要があり、例えば今のような単なる移動中は色々と考えを進める事が可能だが、超常地形に入ったり敵と戦ったりしている間はこれらの情報を頭の片隅で思い浮かべているだけで精一杯で、得た情報を纏める事すら難しくなる。状況の進展が遅々としているはこの辺りの事情が大きく影響していた。
だが、遅々としていようが、今のノエルにはこうして状況を探り、進めていくしかない。幸い、ループの中に閉じ込められているらしい自分だ。時間は恐らくたっぷりある。ならばこうして得た情報を蓄積し続けていけば、いつかノエルが、きっと解決の口に手を届かせてくる筈だ。
「…………」
と、そこまで考えて、ノエルは思わず足を止め、神妙な顔つきで視線を泳がせる。
何か、重要な事を見落としているような気がしたのだ。
所々欠けながらも、何とか受け継がれているノエルの記憶。幾重にも残る自分の残骸。それらを、ある基準を元にして並べていくと、何か、先刻の自分の楽観を覆すようなものがある――ような気がしたのだが。
そのままじっと数秒、ノエルは黙考を続ける。しかし何も思いつかない。
以前から薄々感じていた事だが、自分の発想する力の無さは自分でも驚く程だった。ノエルは酷く情けない気持ちを抱えて深々と溜息を一つつくと、駆け足で少し離れてしまった【NAME】との距離を戻す。さっき心配させたばかりなのだ。これ以上、彼に無用な気を遣わせたくはない。
(この先は、次のわたしに任せましょう――)
無責任ではあるが、他の誰かの手を煩わせるならこうは考えない。どうせ同じわたしがやることなのだ。ならば任せてしまっても良いだろうと、ノエルは何処か甘えるような気持ちでそう結論付ける。
と、前を歩く【NAME】がこちらへと振り返り、前方を指差すのが見えた。示す先には、新たな超常地形の姿が揺らぐように存在していた。
どうやら、物思いに耽る時間はこれまでのようだ。ノエルは愛用の黒銃を構え直して、彼の傍へと駆け寄っていく。
――後のノエルは、この記憶を視て思う。
既にこの時点で、自分は彼女の姿を正しく捉えると同時に。
近付く終わりの兆候すらも、薄々感じ取っていたのだと。
真なる楽園 解けて凝る清濁の在処
――解けて凝る清濁の在処――
無数の記憶の洪水が、己の中で溢れるように流れていく。
押し寄せる感覚の再現。切り出された情景と感情。その中に、自分へと訴えかける声が混じっている事に気づいたのはいつ頃からだっただろうか。
大海に放り出された木の葉の如き感覚を味わいながら、空より降る雨粒の数を数えるような。そんな感覚の中、いつ終わるか判らぬ時間が続き、そして。
「…………」
目が覚めた。
割り当てられた天幕の中は、まだ暗闇に閉ざされている。力の入らない腕でどうにか上体を持ち上げて、ノエルは深く息を吐いた。
近くに用意してあった水桶を引き寄せて、掛けてあった布を水につけて絞り、身体を拭く。ひやりとした感触が、己の正気をどうにか取り戻してくれる。全身に張り付いていた鈍い汗を全て拭き取ると、服を着ることもせず、そのまま顔を伏せて自分の内側を探る作業に入る。
気が狂うかと思える程の数多の光景。その中に点々と差し込まれている声は確かに自分のものであり、自分に向けて放たれた訴えだった。それらをどうにか聞き取り、意味を解く事で、今、ノエルは己の身に起きている現象を、大掴みにではあるが把握しつつあった。“この状況”に陥って直ぐの頃の自分はさぞかし混乱しただろうが、今の自分は当時の自分よりも遥かに多くの先人、幾多の彼女達が懸命に残してくれた声がある。その多くは悲痛であり絶望の感情を伴っていたが、それでも彼女達はいつかの自分が“この状況”を読み解き、そして解決に導く事を祈ったのだ。
そうして、これまでに残されてきた声を最も多く捉え、そして起きている“この状況”の分析にようやく成功した彼女は、一つの結論に愕然とする。
(もう……限界が来てる)
彼女が今のような奇妙な状況に陥ったのは、このエルツァンの島へとやってきてたった一日後の事だ。それから幾度も、既視感という言葉では片付けられない程の強烈なイメージが意識を奪い、眠る時には、現実としか思えない程に実感を伴った夢がいつ終わるとも知れず続くのだ。今こうしている自分が現実であるという事も、浮かぶイメージや夢の合間に差し込まれた自分への伝言によって、どうにか区別が出来ているという有り様だ。要するに、そうした声が紛れていないならばこれは本物だと勘違いしてしまう程に、その現象は強烈なものとなっていた。
それだけでも十分に問題なのだが、より悪いのが、どうやら自分の知らない自分が伝えてくる始まりの時期、そして陥る状況は、時を経る毎に早まり、症状自体も急速に酷くなっている事だ。どうやら最初の頃は精々印象に残る夢の記憶程度のもので、当時の自分は暢気に予知夢か何かかと勘違いしていたようだが、何の事は無い。それは予知などではなく、全ては己が過去に辿った記憶であるのだと、今ならば判る。数多の自分が伝えてくれた情報のお陰だ。
現状は、既に末期的だという自覚があった。
平常の態度を繕うことすらままならず、イェアや【NAME】、軍部隊の皆から訝しげな目を向けられている事も判っていた。まだ【NAME】は“鬼喰らいの鬼”討伐の旅に出発すらしていないというのに。
恐らくもう、今の自分では彼の旅に同行する事は不可能だろう。
そして“次の自分”には旅への同行どころか、自我を保ち、状況を認識する余裕すら残されないかもしれない。
「……なら」
喉を震わせながら、息を大きく吸い、そして吐き出す。
その一連の動きで、覚悟を決める。自分が陥ったこの状況にけりを付ける覚悟を。
正直に言えば、まだ準備が整っていない。いつかの自分達が残してくれた情報は膨大ではあったが、彼女等の多くは、現象についての知識を持っていたが故に“時間はたっぷりとある”と誤認していた。その油断が響いた。如何に解決に導くかという部分においては、まだ策が十分に立てられてはいないのだ。
現状では勝算は低く、見込みも薄いだろう。可能であればもう少し、対策と呼べるものを用意して挑むべきなのだ。
けれども、もう猶予がない。ここで仕掛ける以外にないように思えた。
脱ぎ捨ててあった衣服を纏い、用意してあった装備を身につける。時折意識を奪うかのように再現される記憶を抑え込みながら、ノエルは天幕を出ると、篝火の光を避けつつ陣地の外へと向かう。
何処へ向かうべきか、というのは、今のノエルにとってはそれほど深く考える必要はなかった。自分をこのような状況に追い込んでいる相手の素性は、未だ全く以て判らないままだ。しかし、彼女がノエルの事を望み、ノエルに触れて繋がろうとしている事は、もう嫌という程に知っていた。であるならば、こちらが望んでさえやれば、向こうは直ぐにでも手を伸ばし、自分を己の世界へと取り込もうとするだろう。ある程度の状況を把握する事が出来た今ならば、簡単に導き出せる結論だった。
だが、彼女との対決に、他の皆を巻き込むわけにはいかない。実際巻き込むものなのかはわからないが、もしやという可能性もある。時折幻視する、己のものではない過去。それが彼女に由来するものであるならば、彼女が秘める力はこれまでノエルが見知った存在の中でも最上に位置する。だからノエルは一人で何者かと対峙すると決めたのだ。こうすれば、どのような結末になろうとも、害を受けるのは自分だけだから。
【NAME】と共に“鬼喰らいの鬼”討伐に向かう前に気づく事が出来た――既に終わりが間近に迫った彼女だけが採れる選択肢だった。
陣地を離れ、夜の闇に包まれた海岸を進み、眼前に広がる森を見る。エルツァンの超常地形たる“霧の森”の入り口。そこを前にして、彼女は一度だけ背後を振り返り、告げる。
「行ってきます」
誰に向けてとも定めず呟いた声は、やはり誰の耳にも届く事無く。
森の中へと飲み込まれていく彼女と同じように、夜の闇に僅かに凝り、そして解けるように消えていった。
早朝。常駐軍が島の岸近くに敷いた陣地は、複数の天幕とそれを囲うように設置された柵によって構成されている。並ぶ天幕の内の一つで目を覚ました【NAME】は、まだ眠気の残る顔をこすりながら、のそりと外へと這い出る。
エルツァン島の空気にも、大分身体が慣れてきた。軍部隊の陣設営も一段落付き、“鬼喰らいの鬼”討伐の旅への準備も大分進んでいる。そろそろ、出発の日取りを決めても良いかもしれない。そんな事を考えながら、一先ず朝食の配給を受けるべく歩き出そうとした丁度その時。【NAME】の元へと、息を切らせてやってくる者が居た。
エルツァン島探索の為に派遣されたアラセマ常駐軍の部隊内では珍しい、白色の学士服に身を包んだ女性。隊の一応の長である学士イェア・ガナッシュだ。
兎に角全力で走ってきたのだろう。肩は乱れた呼吸に合わせて大きく揺れて、普段ならば美しいと評しても良い長く伸ばした銀髪は、今は方々に乱れて酷い有様だ。
一体そんなに慌ててどうしたのかと問えば、息は荒いながらも明瞭な答えが返ってくる。曰く、
「ノエルが、行方不明に、なったん、です……っ」
「…………」
全く想像していなかった発言に、一瞬絶句する。穏やかではない話だった。
そもそも行方不明と早々に判断して良いものなのか。単に私用で一時的に陣を離れたという可能性はないのか。
そんな【NAME】の当然とも言える疑問に、深呼吸してようやく落ち着いたらしいイェアは、眉根を寄せたまま首を振る。
「私用って、こんな危険だらけの無人島で一体どんな私用があるっていうんですの」
確かにそうだ。行方不明という言葉をわざわざ使ったからには、イェアには既にそう断言できるだけの情報があるのだろう。
「あと……こう言っては何ですけれども、あの子はまだ、自分一人では満足に動けない子です。【NAME】さんは、気づいてはいませんでしたか? あの子は誰かから指示を受けない限り、自分から一人になろうとはしない事に」
そうだっただろうか? 【NAME】はこれまでの事を思い返してみるが、いまひとつはっきりそうだという記憶が思い当たらない。
だが、言われてみれば共に旅をしていた間、彼女が自分の傍を彼女自身の都合で離れるという場面に遭遇した記憶は殆どない気がする。ノエルが自分の意志で強く何かをしようとする様を見たのはただ一度、レェアの仇であるイルギジド・マイゼルを追うと告げたあの時くらいか。
「それに、エルツァンに来てからあの子の様子は少しおかしかった。ノエル自身は必死にそれを隠そうとしていたみたいですけれど、嘘や取り繕いが出来る程、あの子は人としての経験を積んでいませんからね……」
そこについては、思い当たる事は多々あった。
エルツァンに到着し、野営のために陣地を造った頃あたりだろうか。ノエルと幾度か話す機会があったのだが、どうにも受け答えが覚束無い様子で、会話が噛み合わないどころか、その事にノエル自身が気づいていないような時もあった程だ。
それを訝しんではいたものの、【NAME】の方も“鬼喰らいの鬼”討伐の仕事を任されその準備に追われていた事もあり、彼女への配慮や注意を完全に怠ってしまっていた。軍部隊の長を務めるイェアにしても似たような状況だったのだろう。【NAME】とイェアは、互いに苦虫を噛み潰した顔を浮かべ、深々と息を吐く。
「……取り敢えず、今急いでノエルの捜索を行う準備をしていますが、【NAME】さんは予定通り、“鬼喰らいの鬼”の討伐に向かってください。ノエルは、わたくし達の方で探しますのでご安心を。今回、貴方のところにこうしてやってきたのも、ノエルはこちらでどうにかするという事と、彼女を旅に連れていくことは出来ないという事をお伝えしておきたかっただけですから」
ばっさりと切り捨てたような物言いをするイェアだったが、その顔には苦渋の色が滲んでいる。
彼女ともそれなりの付き合いだ。彼女の立場も、言外にどう考えているかも多少は判る。本来ならば藁をも縋りたいところなのだろうが、そういう気持ちを抑えられるのも彼女だ。アノーレでも、実に姉の事を信じてはいたが、しかし自分の立場を捨ててまで姉を助けるような真似はしなかった。姉と同じく奔放ではあるのだが、しかしその質は異なるのだ。自分に課せられた責任を放り投げない。それは美徳といえるものではあるが、故に取り返しがつかない結果を招いたこともあるだろう。
だから【NAME】はこう告げた。自分にも協力をさせて欲しい、と。
「それは……認められません」
対して、イェアの反応は予想していた通りのものだった。
あれこれと理由を付けて拒絶し、最後には部隊の長からの指示という態で、こちらに命令してくる。だが、【NAME】はその全てに対して全く同じ文言――それでも自分にも協力させて欲しいという言葉だけで返した。
理屈も何も無い、完全なごり押しである。
だが、今このような場所で、このような状況であるのなら、恐らくこの手がもっとも効く。
そんな【NAME】の予想を証明するように、
「――判りました、わ」
押し問答は10分も立たずにイェアが折れる形で決着が付いた。
彼女自身、本音を言えば猫の手も借りたい筈なのだ。加えてここは上役など誰も居ない土地で、見咎めるものも、被害を被る者もいやしない。ならば勝負は時間の問題でしかない。
「本当に、強引ですわね、あなたは」
イェアは何処か呆れたような苦笑いで、深々と溜息をつく。けれどもその表情の底に安堵の色も見えて、【NAME】は自分の強引な物言いが間違ってはいなかった事を再確認した。
【NAME】は一度咳払いをして場を改めると、次の段階に話を進める。
これでようやく肝心のノエルの捜索についての話が出来るようになったが、しかし、いざ探すとなると、まずどう動くべきか。その辺りイェアはどう考えているのだろうか。
【NAME】が問うと、イェアは眉根を詰めた険しい顔で呻くように声を漏らす。
「ん……それについては、正直なところあまり良い手が無くて。急ぎ軍の方で相応の戦力を確保した捜索隊を複数編成して、全周囲に対して探索を行うつもりですけれど、やはり大分動きが遅くなりますわね。本来ならば速度重視で手分けして探し回るのが一番早いのですが、何せここはエルツァン島ですもの。内陸の超常地形は勿論、沿岸ですら完全に安全が確保されているとは言い難いですし……」
そんな場所に、様子のおかしいノエルが一人で彷徨っている事を考えると、かなり絶望的な心地になる。
「けれど……【NAME】さんが手伝ってくれるなら、もっと違うアプローチが可能かもしれませんわ。【NAME】さん、今すぐ出立は可能ですか?」
未踏の島内奥地へ入り込むなら話は別だが、ノエルを捜索するべく周辺地域に向かう程度の話ならば、流石に今すぐには厳しいが多少の時間さえあれば準備は終わるだろう。
【NAME】が答えると、イェアはこくりと頷き、
「でしたら、準備が整い次第わたくしの所に来て頂けますか? ノエルを見つける手掛かりとなる品をあなたに預けます。【NAME】さんはそれを使って、単独での強行探索を行って下さい。数が一つしかなくて、わたくしが使って探すつもりだったのですけれど、貴方が参加してくれるなら、貴方が使った方がきっと有用ですわ」
成る程と【NAME】は頷く。そういった物があるのならば、確かに軍の兵士を部隊として編成し大人数で移動するよりも、身軽で戦闘力もあり、そして特殊な土地での旅にも慣れている人間に一任した方が確実かつ迅速だろう。
「【NAME】さん。……どうか、ノエルの事を宜しくお願い致します。あの子を、助けてあげてくださいな」
否やはない。不安な面持ちを向けるイェアに、【NAME】は安心させるように深く頷いてみせた。
真なる楽園 ふたり立つ境の際
――固独の景象――
一人、そこへ訪れた少女は、己の鏡と対峙していた。
この地へと派遣された常駐軍部隊内での規律では、決して単独では踏み込んではならぬとされた島の内陸。異質極まる超常地形と凶悪な亜獣が跋扈するそこをたった一人で抜ける不安と恐怖は、過去ならばいざ知らず、足元すら覚付かぬ今の少女にとっては極めて大きなものだ。
だが、それでも彼女は歩を止める事無く、目指す場所――ただただ自分だけを見つめ、掻き回す視線の主が立つ場所へと辿り着いた。それを成し遂げた力の源は、自分と繋がっているこの謎の存在と、今すぐにでも明確な決着をつけねばならないという決死の意志だった。
幻惑に眩む意識。模糊と揺らぐ五感。今にも自分を失いそうになりながら、少女はしかし毅然と面を上げる。
「決着?」
対し、相対する者――もう一人の自分は、その能面のような顔に微かな揺らぎを見せた。自分以外ならば読み取れないであろう揺らぎが示す感情は、疑問だ。
「そんなもの、要らないの」
声は耳から届いたようであり、己の内から生じたようでもあった。言葉と共に、心の内に意味が産まれる。鏡の思考が己の思考に混ざりあい、もう一人の自分の考えが伝わってくる。
――何故ならば、そもそも決着を付けるべき相手など存在しないのだ、と。
あなたはわたしであり、わたしはあなた。そして自分以外の全ては要らないものだ。主観となる自分と、客観となる自分。喰らいつく螺旋。互いを捉えて観察するその二つが存在しうるならば、世界はそれで完結できると。
だが、その答えは少女にとって認められないものであり、そして過ちの結論であると断ずる事が出来るものであった。
目の前に立つ“それ”は、自分に対して疑問を覚えた。即ちそれは、今目の前に居る“それ”が自分とは別個の存在としてある事を示し、だからこそ互いの存在を認め、観察する事が可能なのだ。
しかし現状が進行すれば、今の少女は確実に失われる。少女が長くない時間と僅かな人々と交流する事で得た人格が虚しく消えるだけなのか。それとももう一人の自分と完全に混じり合い、別の何かに変わるのか。判らないが、どちらの結末を辿ったとして、己の鏡たる彼女が望む結果が得られる事は無いだろう。
だが、そんな理屈よりも、まず拒絶が先に来るのだ。
違う。
違う。
違う、と。
私が見て聞いて知って感じた出来事、私が得た記憶は、私だけのもの。それを誰かと共にするつもりはない。
彼女が見て聞いて知って感じた筈の出来事、彼女が得たのであろう記憶は、彼女だけのもの。それを己のものだと感じたくはない。
そう、そうだと改めて念じる。何が己の鏡か、と。そんな筈は無い。懸命に目を凝らす。眼前にて浮かぶのは無数の力の奔流を従えた白色の体躯。風ならぬ風を受けて靡く長い髪は藍と黒の境界だ。姿形で語るならば、自分と自分は、いや、ノエル・ガナッシュとその少女は似ても似つかない。それすらも、今ようやくにして気づく事が出来た事実。
逆らわねばならない。決別せねばならない。
目の前で揺らぐ少女。その前に立ったときから生じていた正体不明の重圧は、目の前の少女に対して敵意を向ければ向けるほど強くなる。まるで自殺しようとする意志を身体が拒絶するかのようだ。
しかし、彼女が己へと伸ばす手を払い押し返さねば、イェアを始めとした軍の皆や“先生”たるレェア、そして【NAME】の元に帰れない。それだけは認められない。既に半ば溶け掛けた心でも、絶対に厭だと強く願える。
「っ、ぅ」
泥のように萎えた手足に、仄かな火が灯るのを感じた。震える手が黒銃の銃口をゆっくりと上げていく。少女の周囲で渦巻く気配は、【NAME】に同行しこれまでノエルが遭遇した様々な強存在の何れとも似通っており、そして何れとも違う奇妙で、同時に強大極まるものだった。そんな存在に、果たして自分の銃による攻撃が通用するのか。ちらりとそんな疑念が心の奥に浮かぶが、だからといって諦めるという選択はこの場においてはありはしない。
構え終え、照準を定めたノエルは、黒髪の少女目掛けて銃の引き金を引く。黒銃フォーレミュート。印章術と機甲術の併用により生み出されたこの銃の全力射撃は、“先生”が持つ銃と同系統の、弾丸として装填した印章石を燃料に駆動する純理粒子砲だ。出力が相手の存在概念を圧倒出来れば、例え実体を持たない概念存在であっても滅する事が可能だが、しかし逆に出力が足りなければ砲撃の方があっさりと弾かれる。
その結果は、無情という他無かった。
至近とも言える距離から放たれた光条は、少女の身体に触れるどころか、彼女の周囲を渦巻く無形の気配の一つすら貫けずに、四方に散って消えていく。
「どうして?」
薄く首が傾げられた。こちらを眺める少女の視線には不可解なものを見るような色があった。
絶望の呻きが、口奥から漏れる。己が扱える最大の攻撃があっさりと無効化された事実は、状況の終わりを示すのに十分なものであったが、だからといって折れる訳には行かない。
無駄だと知りながらも次の弾を装填する。知らぬ間に、頬が濡れている事に気づいたが、それを拭うこともない。
「ぅああああっ!!」
漏れ出た叫びが、新たに発した光条の結果を変える事など有り得る筈もなく。同様の結果を前に、少女の身体がふわりと前へと進み出す。
「判らない。どうして拒むの?」
「厭だと、わたしが、思うから、です。あなたは、わたしではない。わたしは、あなたではない、わたしじゃ、ない。そう、わたしは、おもいます」
少女が近付くほどに、重圧が増す。返答するための喉も上手く動かない。何時の間にか立っている事も出来ず、ノエルは蹲りながら、けれども顔だけは伏せず、近寄ってくる少女を見上げる。
「証拠は、あります。わたしがいやだと、あなたには伝わっていない。それが、違い。わたしと、あなたの」
「だから、もっと知りたい。あなたとわたしを。それで、お互いだけを見て、お互いだけを触れて変えるの。そうすれば」
「……駄目、です。何故、判らないのですか。違うからこそ、なのに。なにもかも、同じになってしまえば……」
「だから、教えて?」
焼けるような熱さと、凍えるような冷たさ。それを併せ持つ感触が、頭を撫でるように触れた。
「やめ――あ、ぁ」
それだけで、ごっそりと何かが吸い込まれ、そして挿し入れられた気がした。これまで感じていた幾多の既視感が、より明確な実感を帯びた記憶として蘇る。
これまでに、幾度もこの黒髪の少女と出会っていた事。
これまでに、幾度も【NAME】と共に安らかなる岸辺を発ち、真なる亜獣達の楽園を旅した事。
そしてこれまでに、幾度もあの有り得ざる城の奥で、全てを無にしてきた事も。
潮の岸辺で、霧の森で、風の峡谷で、雷の湖で、鋼の地下で、月光の丘で、泥の山脈で、凍える洞窟で、繰り返した旅路の景色、繰り返した戦いの記憶が幾重にも重なって蘇り、今の自分を塗り替えていく。
「ああ、そう。うん、そう。わたしは、あの時、こう思っていました。わたしは、その時、そう思っていました」
もうノエルは自分がどういう姿で居るのかすら良く判らなくなっていた。歩いているのか、走っているのか、戦っているのか、眠っているのか。今の感覚が、差し込まれた無数の記憶に押し出されて、酷く希薄になっていく。唯一、少女が謳うように呟く声だけは、辛うじて記憶の中に紛れる形で届いてくる。理由の判らぬ高揚感、多幸感、充実感。それを把握し、ああとノエルは唇を戦慄かせる。何故少女の声だけが届いていたのか判った。自分が、彼女と同じになったからだ。
「ほら、こんな風に。そう、こんな風に」
自分と自分。二重に重なって聞こえる言葉と共に、自分達を囲う世界が失われ、過去に見た、想いの景象に塗り潰されていく。
少女はもう、それが現実であるのか記憶であるのかも判断出来ず、新たな涙を一筋こぼす。
――ごめんなさい【NAME】。もう、わたしは。
そう願った理由すらも、記憶の渦に埋もれ、見えなくなっていった。
姿を消したノエルを探し出す。
そう決めたならば、もう迷いは無用だ。【NAME】は陣中央の広場にて部隊の編成指揮を行っていたイェアにその事を告げてから、常駐軍の陣を後にする。
その手には、別れ際にイェアから渡された小さな印章石がある。ノエルがいつも被っている帽子に取り付けられている飾り。それに施された術式を探知するためのものだ。
受け取った時に、こんなものがあるのならば直ぐノエルの居場所が判るのではと呆れた【NAME】だったが、イェアが深い嘆息と共にその場で印章石を駆動させ、石が何の反応も見せない事に成る程と苦笑するしかなかった。イェア曰く、元々の感知距離が数百メートルも無い上に、エルツァン島という土地概念単位での変質、断絶が多発しているような場所では距離関係なくまともに感知出来るかどうかも怪しいという。この仕組み自体は昔、まだノエルが目覚めて間もない頃、彼女が迷子になった時を考えて仕込まれていたもので、エルツァン島のような異常環境下での使用を想定したものではないらしい。
「ですので気休め程度のものですけれど、無手で探し回るよりはいくらかマシでしょうから」
言いながら印章石を【NAME】の手の中に収めたイェアは、そのまま手を握って離さず、どうか宜しくお願いしますと深々と頭を下げる。その様子からは深い心配の念が伝わってきて、【NAME】は直ぐにノエルを見つけて戻ると、自分でも信じていない言葉をどうにか吐き出す事しか出来なかった。
陣から離れて海岸沿いに少し移動した【NAME】は、イェアに教わった通りの文句を告げて、印章石を掲げてみせる。
込められた術式が駆動し、石が一瞬淡い輝きを帯びるが、しかし光は直ぐに失せて、そのまま完全に沈黙する。どうやら、この周囲には居ないようだ。
とはいえ、それ程遠くに行っているとも思えない。常駐軍内で捜索隊を編成していたイェアも同じ考えであったようで、まずは概念的な断絶が確認されている内陸の危険地帯は避けて、陣が敷かれた近隣地域を全方位で探すと言っていた。陣に隣接する島内の超常地形二箇所、霧の森と風の峡谷は軍内の斥候の他に【NAME】やオリオールからの報告、更にはイェア自身の調査によりある程度の地形把握は行われているが、やはり大人数、それも人の捜索を行うには少しばかり厳しいところだ。ならば近場の捜査は彼等に任せ、自分は超常地形の探索に向かった方が良いだろう。
印章石を懐にしまい、【NAME】は視線を内陸へと向ける。陣地が存在する沿岸域から直接向かえる超常地形は霧の森と風の峡谷の二つだ。捜索するならば谷の方が捜索範囲自体は狭まって楽だが、ノエルがそちらへ向かう可能性はあまり高くないようにも思える。根拠は単純な話で、単なる距離の問題だ。霧の森へは内陸に進めば直ぐだが、風の峡谷へと入るには岸を暫く進む必要がある。彼女にそちらへと向かう明確な目的があったなら別だが、ただ迷い込んだという可能性ならば霧の森のほうが高い。
とはいえ、陣内から突然行方不明になった者が無目的というのも考えづらいが。
(そもそも、何故、というところが判らないままなのか)
兆候らしきものはあったが、それを踏まえても突然としか言いようのない失踪。まだ理由が判ればそれを頼りに探すという事が出来るのだが、それを知るのは姿を消した本人のみだ。
現状出来るのは足で探す事だけである。海岸周辺の探索は他の者達に任せるならば、自分が行くのは霧の森か風の峡谷のどちらか。判断すべき情報はほぼないならば、
(近場から、か)
結局は運任せだが、迷って立ち止まっているよりは遥かに建設的だ。何より、時間が経てば経つほど無事に見つけられる確率は下がっていく。ノエルの姿が確認されたのは未明の頃合い、陣の中をよろめくように歩く彼女の姿を見たという夜番の兵の証言が最後だ。彼は小用か何かだと思い、別段気にも留めずに見逃したとの事だが、責める事は出来ないだろう。あくまで彼等の役目は外敵に対応するためだ。そんな時間に内から外へと出て行く人間の存在を考慮しろという方が無理がある。
だが、兵士の証言自体は至極ありがたいものだ。彼の話から推測するなら、ノエルは恐らくはその頃に陣の外へと出て行ったのだろう。何時、何処へ、何の為に。内の一つが埋まったのだ。
だが、この情報により導き出せる推測は、あまり喜ばしくないものだった。兵士がノエルの姿を見たと言う時刻に彼女が陣から出たのならば、もう相応の時間は経過している事になる。もし島の内陸に入っていたら、いや、沿岸付近を彷徨っていたとしても、亜獣の集団に一度か二度は襲われていてもおかしくない。普段のノエルならばある程度の亜獣相手なら一人で渡り合ってみせるだろうが、何せここは“真なる亜獣達の楽園”だ。確認されている亜獣は、他島とは質の異なる者達も多い。加えてノエルが本調子ではない事も考えれば、果たして今も無事でいるのかどうか。
「…………」
頭を振り、意識を切り替える。考えても暗い想像が過ぎるだけで、何の進展もないのだ。立ち止まるよりは動く。兎に角、今の自分に出来るのは極力急ぎ探し回る事だけだ。
【NAME】は一度呼吸を整えると、島の内陸、鬱蒼と茂る木々の合間から薄い霧が漂う森の中へと身を躍らせた。
霧に包まれた森を走り始めて、どれ程の時間が経ったのか。
過去にエルツァンを訪れた探検家カール・シュミットの手記において、ナリア・バータ霧眩森林と名付けられたその土地は、濃淡の差はあれども全域が常に白色の霧に包まれており、更には昼夜の概念すらもないという。時間の経過は疎か地形の把握すらも難しい、捜索という行為には至極向かない場所だった。森に入って早々、これは先に峡谷を回るべきであったかと後悔した【NAME】であったが、結局はノエルがどちらに居るのか次第である事を考えれば、あまり意味の無い話かと思い直し、ただ霧の森を走り回る。
時折、霧が亜獣の形を持ち襲い掛かってくるが、【NAME】はもう立ち止まることすらなく斬り捨てる。定期的に目印を配置し、イェアから譲られた印章石を駆動させ、無反応であることを確かめてからまた移動。それをもう幾度繰り返したのか。目印を打つ作業がそろそろ三桁の大台に乗るかという回数に至ったとき。
「――――」
目を見張る。
もう殆ど惰性に近い動きで駆動させた印章石が、ほんの僅かではあるが反応を示したのだ。
石を凝視し、続く反応を待つ。だが、それ以上の反応を石は見せず、まさかと【NAME】は焦る。てっきりこの印章石、対象を感知しならば位置なり方向なりを示してくれるものだと勝手に思っていたのだが、
(これだけか!)
石の反応が判るか判らないかという極めて微弱な事を考えると、その強弱で距離程度は把握可能なのだろう。そしてその差を把握すれば方向を割り出す事は可能な筈だが、折角見つけたというのに無駄な作業を強いられているという感が強い。焦れた気持ちを持て余しながら、【NAME】は石を片手にその場を中心にして八方に移動し、どちらに移動した時により反応が強まるかを確認しようとするが、どの方向に移動しても、反応自体は殆ど変化が無い。
ならば考え得る可能性としては、距離での強弱ではなく、単純に感知した反応自体が極めて微弱だからこそ、印章石の反応も微弱であるという線か。
もしそうだとするならば、一気にノエルの居場所の絞り込みが難しくなる。【NAME】は一瞬暗澹とした気分になるが、しかし直ぐに気持ちを切り替える。
少なくとも、この近くに居る事は確実になったのだ。今までのそもそも霧の森に彼女がいるのかどうかすら判らなかった時と比べれば格段の前進である。印章石の感知範囲は数百メートル程度と聞いた。視界を遮る霧に包まれた森の中では全域を見通す事は出来ないが、虱潰しに探していくという方法が現実的に可能な範囲だ。後の不安は、
(ノエルが無事かどうか、か)
あくまで印章石が捉えるのは、ノエルが身につけていた帽子の飾りである。所有者の生死を保障してくれるものではない。だからこそ、可能な限り早く見つけるべきだった。
そして、石を駆動させた状態のまま、【NAME】は捜索を再開する。今までのような印章石の探知だけを当てにしたやり方ではなく、森の中に目を凝らし、ノエルの姿を探すという地道な探し方だ。時折石からの反応が途切れ、その時だけは彼女が居る場所から遠のいたらしい事が判るが、それによって位置を逆算するのは霧の森の地形の複雑さから難しい状況だった。気持ちは急いているというのに、実際の捜索の手はむしろこれまでと比べて遅々としたものになっているようで、生まれる落差によって余計に苛立ちが募った。
遮る枝葉を裂き、窪地を確認しながら潜り抜け、洞のある大樹の傍を通る。大きな木だ。これは目印として使えそうだと、僅かに進む足を緩めて大樹を見上げた【NAME】は、広く枝張り葉を茂らせた瑞々しい姿に、雷気を纏う死して枯れ果てた姿が重なるように現れて、驚きで固まった。
幻か、と目を凝らすが、しかし姿は一定には留まらない。二つの大樹が移り変わり、重なって現れては消えて、そしてまた重なる。そしてその変化は大樹だけに留まらず、周辺の風景にすら波及し始めた。
【NAME】が居たのは、霧に包まれた森の中だ。しかしその風景の上に、別の景色――紫色の空に染まった雷気を纏う湖と、視界を遮るものない広大な丘陵、そしてまるで天蓋を持つような形状の峡谷ががぶれるように現れる。始めは薄く幻のように見えていた三つの新たな景色は、それぞれが溶けるように混じり、最終的には四つの情景が重なり合う、異質極まる状況へと変化した。
空は濃い紫の色。辺りは強い風によってうねる霧に包まれ、足元には立つことが出来る湖が、まるで丘陵のような凹凸を描いて広がる。先刻まで【NAME】が走り回っていた霧の森も異常な場所だったが、今【NAME】の前に出現した代物に比べれば随分普通な場所であったように思う。正直に言って、今目の前にある光景は幻覚が白昼夢の類であるようにしか見えなかった。
一体いきなり、どうしてこんな状況に。
茫然と立ち尽くしていた【NAME】は、ふと、奇妙な光の気配を感じて、その出所に視線を向ける。
光を放っていたのは、手の中にあった石だった。これまで霧の森を走り回っていた間、ほんの微かな光を反応として発しているだけだった印章石は、今は強い明滅を放って震え、捉えた目標へと所有者を導くように引っ張る。
生じた状況の変化と、印章石の突然の反応。それに関連性があるのかは判らないが、ノエルの存在を探知する石が顕著な反応を示してくれるのは有り難い。突如現れた異常な風景に対する戸惑いを払い、今やるべき事を思い出させてくれる。
【NAME】は印章石の導きに従い、最初はゆっくりと、続いて急いで走り出す。恐ろしいことに、足場へと変じた湖水は、まるで舗装された煉瓦道のような硬質の感触を足裏に伝え、先刻まで木々で覆われていた場所を突っ切っても見えない何かに激突するような事はなかった。つまり、少なくとも視覚触覚に限った幻覚の類ではないようだ。
五感、精神丸ごとが幻覚かそれに類する現象に囚われたという話ならば別だが、正直な感想を言えば、まだそちらの類であった方がマシに思える。今目の前で起きている現象は、土地概念の歪み程度の話で収まるレベルではない。もしこんな事が現実として起きているのならば、それはもう世界の在り方の塗り替えに近いだろう。
唐突に地形が全くの別物に変化するという事象は、昨今では東大陸の国で“現出”と呼ばれる形で生じたらしいが、話に聞くそれにしても、今【NAME】の目の前で起きているそれよりは控えめであったように思う。
強風の中であっても晴れない霧のお陰で見通しは悪く、この湖の丘がどこまで続いているのかすら判らないが、もしこの風景が延々と遙か彼方まで続いていたならと想像すると、背筋が凍るどころの話ではない。自分がただ旅をしている中で突然こんな状況に陥っていたなら、恐らくはもっと混乱し、どうすれば良いのかすら思いつかず、ただ立ちすくんでいたに違いない。
だが、今はノエルを探すという目的があり、そして標となるものが手の中にあった。成すべき事があり、その為の道標があるならば、少なくともそれを達するまでは、自分が置かれた状況について考えずにいられる。ある種逃避に近いが、だが間違ったものではない。ノエルもこの謎の状況に巻き込まれているのであれば尚更だ。
と、そこまで考えて、【NAME】はふと思う。
この現象が、ノエルの突然の失踪に関係している可能性について。
「…………」
ほんの少し思考して、【NAME】は直ぐに頭を振る。確かに状況としては重なっているが、繋ぐための情報が一切欠片すらないのだ。もし関係があったとしても、今の【NAME】からすれば推測する事すら難しい。もしそれが判る者が居るとすれば、ノエル当人くらいだろう。ならば結局は、彼女を見つけ出すという事が最優先される。
――無事でいれば、良いのだが。
もうすっかり見慣れた、表情の薄い、軍服の少女の姿を脳裏に浮かべる。
最初に会った頃はまるで能面のようだと思っていたものだが、共に旅をする間に抱く印象も変わっていった。
それは【NAME】がより深く彼女を知ったからなのか、それとも旅をする間に彼女が変わっていったのか。
きっと、両方なのだろう。
そんな感慨に耽っていた時、突如周囲に強大な気配が複数、こちらを囲むように現れた。
吹き抜ける風から渦巻くように。霧の中から染み出すように。湖の底から沸き立つように。紫の空から響く笛の音と共に。
生じた四つの影は、それぞれが風を纏う竜、霧を吹き散らす竜、雷を帯びた竜、そして道化染みた鬼の姿となり、それぞれが【NAME】の移動を封じるように、四方を遮る形で位置取る。
(……どういうつもりだ?)
四方を囲んだまま、しかし攻撃までは仕掛けてくる様子のない四つの影。【NAME】は彼等に視線を走らせながら、訝しげに首を捻る。
どうやら、相手はこちらに積極的に害を加えるつもりはないようだが、しかし一歩動きを見せようとする度に、威嚇し、牽制するような態度を見せる。
要するに、こいつらの目的は【NAME】を闇雲に襲う事では無く、単にこの場に留める事であるようだ。
だが、【NAME】としてはそんなものに付き合っては居られない。何せ目的はノエルを探し出すこと。それを果たす為には、こんなところでじっとしている訳には行かないし、何より、
(こういう連中が、こういう態度で現れたという事は)
こちらの目的をある程度解し、そして止めようと考える何か、あるいは何者かが存在している。それは、先刻まで【NAME】が持ち得なかった、この奇妙な現象とノエルを結びつける重要な情報の一つでもあった。
そこまで判れば、話は早い。
【NAME】は笑みすら浮かべながら、愛用の武器を構えて躊躇無く、大きく前へと足を踏み出した。
天従の継承




重なる空間が解けて消える。どうやら出現した影の化生が、生じた空間の源となっていたようだ。
霧と雷、風を纏う三体の影竜、そして歪な鬼の影を消し飛ばすと、重なっていた風の谷、雷の湖、笛鳴るの丘の風景が消し飛び、しかし新たな風景が重なるように生じ始めるのを感じる。
油断は出来ない。そして立ち止まっている訳にも行かない。
印章石の反応を見定め、それが指し示す方へと、【NAME】は走り続けた。
それから幾つかの景色が重なり、根源と思しき影を退けながら前進を続ける。進む毎に生じる景色の濃さは強まり、現れる影の力も増しているのを感じる。
その力が、一体どこまで高まっていくのか。急く心の片隅にそんな不安が過ぎった時。
風景が決定的に移り変わり、同時にそれは生じた。
立ちのぼるのは城塞。顕現したのは実在信じ難き様相を保つ有り得ざる城だった。
そして驚く【NAME】の眼前で巨大な城門の奥から飛び出すように現れたのは、先刻戦った三体の竜の数倍はあろうかという大きさを持つ、一対の翼を備えた巨竜の影だった。
「……っ!」
感じるのは強烈な風と、周囲全てを圧倒するかのような凄まじい力の波動だ。【NAME】は風から身を守るように腕を掲げながら、唸るような歯噛みの音を溢す。
天に顎を掲げて、大気は疎か大地すら揺るがす程の雄叫びを上げた後、竜の影は両の翼をはためかせて巨体を空中へと舞い上がらせた。
翼が動く度に巻き上げられ、吸い寄せられる風は、竜が放つ根源の概念に染め上げられて僅かな色を帯び、竜の周りに薄い七色の繭を造り上げる。その威容は、この世界に於ける単体最強種とも称される芯属の一つ――芯竜属を連想させた。
両の眼光が、城門の前にて身構えた【NAME】に向けられる。
「――――」
一瞬細く、竜の眼が眇められたのが、果たして何を意味するものだったのか。
それを想像する間も無く、巨竜は大きく首と、そして一対の翼を仰け反らせる。明確な、力を溜めるための予備動作。竜の動きに従うように、周辺の理粒子が唸りを上げて翼の中や竜の口蓋の奥へと吸い込まれ、七色の繭も解けるように広がって個別の球へと姿を変える。
竜種の力の象徴たる、根源の吐息。加えて、別種の力が放たれようとしている気配も感じる。先刻相対した化け物と同様の、実体ではない影のみの竜とはいえ、集まっていく力の流れ、竜の影自体が持つ存在概念の強さは相当なものだ。
――吐息が来る前に。
仰け反り力を練る竜の口蓋から、力の奔流が撃ち出されるより速く、奴の動きを制する。
そう思考するよりも先に、【NAME】の身体は既に技法を練り上げて、空に浮かぶ巨影目掛けて攻撃を開始していた。
芯影の虚竜

影であれども、強烈な存在感を放つ巨大な竜。振るわれる鉤爪は地面や城を構成する壁を溶けるように切り裂き、更に渦となって巻く風にも破壊の力を纏わせる。
嵐のような猛攻。それを辛うじて掻い潜った先にて待ち受けるのは七色の光の交差だ。一条一条が強烈な属性を帯びた概念攻撃であるそれをどうにか耐えきったところへ、巨竜は満を持して吐息を放とうとする。
だが、その一連の流れは【NAME】にとっては予想通りのものだ。竜の吐息が切り札であると、そう判っているならば対処は可能である。それは戦闘が始まる前から認識していた事。
撃たれてしまえば、喰らえば終わり。
地母の種が操る象形よりも更に原始的な、存在の根源に繋がる竜の吐息。概念的な攻撃力の高さは折り紙付きだ。例え正しい竜種ではない影の存在であれ、戦闘の最中に垣間見た吐息の力は絶大という他無かった。
ならば、撃たれる前に、喰らう前に。
放たれる機会が判っているなら、その前に倒してしまえば良いだけだ。勿論、容易な事では断じてないが、これまで数多の敵を屠ってきた【NAME】にとっては、出来ない事ではない。
「――っ!」
言葉にならない、鋭い気合の声と共に満を持して踏み込と、溜めた力を一点に集中させ、放った。
反った喉笛、それを縦に切り裂くのは黄金の輝きだ。光の交差を防御しつつ組み上げ、凌いだと同時に放った大技法は、影の大竜を飲み込み一撃で滅ぼした。
竜の姿を形作っていた影が、四方へ霧散する。すると先刻と同様に、生じていた景色――巨大な城塞も跡形も無く消し飛び、続いてまた別の風景が現れる。
しかし、今度はこれまでとは違い、何処かの景色が重複して存在するような類のものではなく。
「……これは」
呻くような声が漏れた。
見覚えがある。だが、己の目で見たものとは細部が違い、そして以前、とある事情により焼き付いた彼の老人の記憶で見たものともまた細部が違う。
出現したのは、周囲に黒色の森を従えたなだらかな丘。その丘の縁、森との境界に立つ形となっていた【NAME】は、丘の上に存在するそれを茫然と見る。
暗褐色の外壁を持つ、何処か無骨な印象を見る者に与える、錐台状の巨大な建造物。
その建物自体には見覚えはない。だが、建物が崩壊し、残骸となった後の姿は幾度も見ている。だから、あれが何なのかは、直ぐに想像がついた。
――【NAME】の目の前に現れたのは、“凍え穢れし”と呼ばれるようになる以前。
崩壊し、廃墟となる前の四大遺跡が一つ。在りし日の、ゴディバ遺跡の姿だった。
――二人立つ境の際――
そこは訪れる者は誰も居ない、入り込める物は何も居ない、閉じた地底湖の境。
わたしは仰向けになって湖面に浮かび、緩やかな波紋を起こしながら天井を見上げている。
幾つも、幾つも、幾つも。
繰り広げられるのは無数の光景。巡るような万華鏡。一片一片に想いが宿り、それらが僅かな見方の違いによってその形を次々に変化させていく。
わたしは延々と続く記憶の欠片を、ただ望洋に眺め続けるだけのものになっていた。
身体はもう無い。己を記す形は無い。手足の感覚は失われ、耳は音を捉えず、鼻は匂いを伝えず、目はなにものも写していない。
揺蕩っているのは身動きしない心の塊だけ。だから届く光景は、空から染み込んでくる数多の記憶だけだった。
心に映し出される記憶の数々は、どれも全てがわたしのもの。
島へと渡る夜に空を見上げた記憶。木の下の学び舎で物語を綴じた記憶。失われた場所で雲が瞬く間に晴れていく記憶。いつかの港で彼と出会った記憶。皆と最初に食卓を囲んだ記憶。二人に抱きしめられた記憶。
そして、初めて目を覚ましたときの、雪と風に包まれた彼女が、驚愕の表情でわたしを覗き込んでいる記憶。
思い出せなかったわたしの始まりすらも、そこでは記憶の一片として、容易く視る事が出来た。
どれもこれも、わたしには大切で、そして幸いの記憶だった。
勿論、中には苦しみを伴うものもあった。
幾度も襲う幻に心を病む記憶。向けてはならぬ人に刃を向ける記憶。親にも等しい人の命が絶えていく記憶。胸を痛めてけれども諦めに微笑む人の記憶。
けれど、その多くには望みがあった。その多くには願いがあった。
だからわたしは、生まれた悲しみも拒まず、幸せの延長として受け入れる事が出来た。
――本当に?
ふと気づくと、傍に誰かの気配がした。
気をそちらへ向けると、わたしの隣に誰かが立っているのを感じる。
湖面に横たわり、天を見上げるわたしとは違い、その誰かは、湖面に立ってわたしをじっと見下ろしていた。
――本当に?
本当に。
再度の問いに、わたしは想いだけで答えを返す。
すると、わたしの心にその誰かは軽く爪先を引っかけて、
――そう。ならこれもそう?
裏返された。
波を打つ湖面。見上げていた心が、見下ろす形へと反転する。
湖上の天から、湖底の地へ。心の向きがひっくり返ると同時に、視えていた世界も裏返った。
透き通った湖中。見える景色に違いはなく、見える記憶に違いはない。
幾つも、幾つも、幾つも。
繰り広げられるのは無数の地獄。血塗れの万華鏡。一片一片に死が宿り、それらが僅かな見方の違いによってその形を次々に変化させていく。
生死が等しく生まれあらゆる価値を無にする記憶。想像を絶する戦場にて陰陽問わずあらゆる命が尽きていく記憶。幸福と晏然の象徴が血塊に伏せ結晶へと変わる記憶。希望に縋る賢者が己が身を愚者へと堕とす記憶。
その多くが認め難い。その多くが信じ難い。
だからわたしは、有りもしない目を閉じて頭を振る。こんなものは見えない。わたしのものではないと。
――本当に?
本当に。
叫ぶように想いを返す。
すると、わたしを見下ろす誰かは悲しげな吐息を一つこぼして、
――ならこれも、あなたは捨ててしまうのですか?
背中を、強く踏みつけられた。
沈む。わたしの心が、湖に沈んでいく。
澄み切った湖中にあって、嵐のように渦巻く凄惨な記憶の群れを通り過ぎ。
沈んで、沈んで、沈み続けたその底で。
わたしは、始まりを見たのだ。
原型を留めたゴディバ遺跡。
仮初めの通路を進み、幻の階段を下る。構造自体はごく単純で、しかもご丁寧に遺跡内部を区切る隔壁は一方だけが解放されている状態になっていた。
先刻までとはまるで逆。妨害どころか、案内されているかのような錯覚を覚えながら、【NAME】は急ぎ足で遺跡の奥へと進む。
そうして辿り着いたのは、遺跡の地下に存在した広大な空間だった。
球形を描く大空間の中に、支えも無く浮かぶ円形平面の床。床へと至る道筋は、【NAME】が下ってきた宙に穿たれるように停止した半透明の薄板で出来た階段のみだ。
階段を下り切り、床面へと着地する。床には薄く輝く線が同心円状に刻まれているが、過去に【NAME】が訪れた遺跡――例えば場衝機構の最深部のように、その線から強力な力のようなものは感じ取れない。象形が刻まれている訳ではなく、単なる装飾、あるいは目印としてのものであるようだった。
そしての同心円の中央に。
少女と少女は、絡み合うように存在していた。
「――――」
床の中心。円の中央。そこには半ばから砕けた巨大な器があり、少女達は台座部分に腰掛けるようにして蹲っていた。
二人の内の一人は、忘れようもない彼女。【NAME】が探し続けていた彼女の姿だ。
軍服を着込んだ線の細い娘。名はノエル・ガナッシュ。アノーレ島からの付き合いである、最初はまるで人形のようで、今はもう人形とは括れない程の想いを見せてくれる少女。
そしてもう一人は――少なくとも【NAME】からすれば一度も見た事が無い少女だった。
姿形、その面影自体は人の少女のものだ。
しかしその在り方は、物理的な視覚だけでなく、ある程度存在の形を見抜く力を持った【NAME】から見ると、異質であり異様、不気味極まる存在だった。
何故なら、少女はその小さな体躯に、【NAME】が知る様々な強存在の概念を内包していたからだ。
一つは生命を司る源に根付く力。
一つは陽に満ちた世の理を営む力。
一つは陰に満ちた世の理を壊す力。
一つは細やかながらもあらゆる可能性を秘める力。
それらが、本来ならば相反する存在概念すらも他の概念が橋渡しし両立する形で同居しているのだ。それは極めて歪で、ある種平等であり、奇跡的とも言える在り方だった。
少女はノエルを抱え込むようにしながら、その視線は現れた【NAME】に向けられる事無く、緩くノエルの方へと向けられている。しかし、彼女の周りに存在する何もかもは違った。少女の周囲を渦巻く力の奔流は仮初めの空間に歪みすら与えるほどに濃密に漂い、その動きには意志すら感じさせる程だ。しかもそれらが帯びる意思の気配は全て、【NAME】へと向けられている。穏やかではない、招かれざる客を排除しようとする気配。僅かなりと感じ取れる意思は、完成された世界を汚す塵を払うかの如き、厳格で、そして容赦のないものだ。
その意思をもっとも色濃く反映していたのは、広がるようにして漂う彼女の長く豊かで美しい髪だ。波打つように揺れる髪は、途中からその姿を髪ではなく別のものへと変化させていた。ある一房は獣であり、ある一房は竜であり、ある一房は鳥であった。それらは全てが姿を模した存在特有の概念を宿しつつ、【NAME】に対して強烈な警戒と害意を向けていた。恐ろしいのは、それらが模したものでありつつも、その在り方自体は本物と寸分違わぬ事だった。万化百獣、一度たりとも留まらぬ程在り方を変化させながら、どの姿であれ真に迫る。髪の先端より竜の頭が顔を覗かせれば、それは正しく竜種の化身であり、口蓋の端から漏れ出すのは紛れもなく根源を宿す竜の吐息が溢れたものだ。
加えて、少女の周囲に点々と存在していた歪みにも変化が生じる。時間を経る毎に深まっていった歪みはまるで渦を巻くような形へと変化し、その変化は更なる形――不気味な気配を発する大きな球体の形を保つ。姿を得た球体は、まるで外敵から少女達を守るかのように、彼女等の周囲をくるくると旋回し始めた。
それら全てが、変わりなく自分に敵意を向けてくる。その精神的重圧は並大抵のものではなく、歴戦の【NAME】であっても武器を構えつつそれ以上の前進を躊躇う程だ。
しかし、こうして留まっていても何の解決にも至らないのも確かだった。
彼女達の状態が容易に視認できることから判るように、【NAME】が立つ床の端から床の中央までの距離は然程遠くはない。だが、その距離が遠い。【NAME】は気を図るように油断無く少女達の周囲に視線を走らせるが、何せこの場所は自分と彼女達以外には何も無い。髪が変化した化生。浮遊する球体。どれもが【NAME】を注視し、注意を外す要因は無い。幸い、彼等に護られた少女自身はこちらに一切の注意を向けている様子は無いが、何にせよ感じる危機感は相当なものだった。
手の中にある武器の柄を握り直しながら【NAME】は考える。
目的は明快だ。あの少女に囚われているらしいノエルを取り返す。
ではどうするか。手段は多数あるが、現実的なのは大きく分けて二つだけだ。
交渉か戦闘か。
可能であれば交渉で済ませたいが、しかし少女の様子を見ているとその望みは薄いように思えた。
実際、【NAME】は諦観と共に声を掛けてみるが、やはり少女が反応を示す様子は無く、同時にノエルにも声を飛ばしてみるも、彼女の方も反応を示さない。遠目には薄く目を開き、呼吸もしているように見えるが、揺れる瞳は虚ろで定まらず、少女と見つめ合う形でありながらもその視線が交わっている風には感じられない。死んではいないが、正気を保っている状態ではないようだ。
ノエルの様子を見る限りでは、直ぐに命の危険が差し迫っている訳ではないものの、悠長にしている余裕もないように見える。
「…………」
覚悟を決める。
武器を改めて構え直し、【NAME】は正面、数十歩程の距離を経て座る少女を睨む。
踏み込めば十中八九、彼女の周囲で蠢く者達が一斉に襲い掛かってくるだろう。それらの攻撃全てをいなして、少女の腕からノエルを奪い取る。
(……奪い取る?)
一瞬で考えた策に、【NAME】の中で疑問が生まれる。
自分は何故、奪い取るなどという生温い方法を選んだのか。あれだけの明確な敵意が集う中に飛び込むのだ。懐に飛び込めたのならば、恐らくはこの現象の大元と思しきあの異質な少女に対し、致命の一撃を狙うのが常道である。あれは幼い少女の姿をしてはいるが、その中身は別物だ。それは十分に判っている。たかが姿形に惑わされるならば、自分はこの場この地に辿り着く以前に、疾うの昔に息絶えているだろう。
では何故、無意識にその選択を避けたのか。
考えて、案外あっさりとその答えに行き着いた。
「――――」
辿り着いたのは、既視感だった。
少女の姿、少女の在り方が、【NAME】が以前に見知った、自分ではない者の最後と重なったのだ。
そういう事かと、【NAME】は切迫した状況も忘れて、気が抜けたような嘆息を吐く。
何故思いつかなかったのか。あの時、あの記憶を掘り起こしたときには、あんなにも確かに覚えていたのに。
眼前にてノエルを捕らえる彼女の正体に、【NAME】はようやくにして気がついた。そうして成る程と思う。ノエルを捉え、偽りのゴディバにて佇むのも、彼女の素性を考えれば当然と言えるものではあった。
幾つもの存在が重なり合った少女。それらの存在の中で、【NAME】が知り、そして既に名を世に知られた者はたった一つ――鬼の名しかない。
だから今、凍え穢れる前のゴディバに座する彼女の名を呼ぶのならば、恐らくはこれが最も相応しいだろう。
――古き正統なる大禍鬼が一。
“天従”のウィースルゥインと。
同時に、彼の老人が残した想いが蘇る。それを知った時の、【NAME】自身が抱いた気持ちもだ。
ああでも、と、【NAME】は苦みと共にその気持ちを振り払う。
悪いが、彼女は自分の“身内”に手を出したのだ。
その報いは、相応に受けて貰おう。
「――ふ」
浅く短い吐息と共に、心が振り切れるのを感じる。意識は軽やかに、戦いへと臨む己に切り替わった。
僅かにしゃがみ、そして勢いを発条として跳ねた。床を蹴り、走る。少女の左右、髪が唸りをあげて変化し、【NAME】目掛けて殺到する。【NAME】は走る速度は落とさぬまま、武器を振りかぶって素早く技法を組み立てる。
作戦は変わりなく、しかしより明快になった。少女の僕を全て殴り倒し、そして少女すらも殴り倒して、ノエルを取り戻す。それだけだ。
距離が詰まる。獣の力が、鬼の力が、地母の力が、それぞれ【NAME】に殺到してくる。
あらゆる者であるようで、しかしそのどれとも違う未知の在り方を見せる彼女――ゴディバ遺跡の主であった鬼を名残として持つ存在と、【NAME】は今、刃を交える。
白雉の少女



――自分の泣き声が、まるで他人事のように耳に届いた。
溢れる涙で視界は眩み、光が反射して周りは良く見えない。
そんな中で、朧気に映る二つの影があった。
「ようこそ世界へ、僕らの愛し子よ」
一人は、正面からこちらの覗き込むようにしている男の気配。
「貴方は、こんな時でも相変わらず素っ気ないのね」
一人は、後方から自分を包み込むように抱えている女の気配。
「君の無感動ぶりの方がどうかと思うが」
「感動してるわ。とても」
「知っている。だから“ぶり”だと言った。君は、表情に出ないだけで案外と情緒に富んでる」
「貴方だって、私の事を言えるような人じゃないでしょ?」
「互いに、理解があって結構だと思う」
「……そうね」
物静かで、深い情を感じる言葉が交わされて、けれどもその会話は直ぐに止まる。
響く泣き声の中。二人の視線が自分に注がれているのを感じる。
「このままなら、どれだけ保つと思う」
「判らないわ。私だって、昔の伝承や、噂話として聞いていた程度の知識しかないもの。その中じゃ、無事に育つ事もあれば、そもそも生まれることすら出来ない話も一杯あった」
「となると、もう後は天のみぞ知る、か」
「天を自然の摂理と捉えるなら、そちらに望みを託すのは難しそうだけどね」
「離れたとは言え、君だってそれを司る一員だろう」
「離れれば、もう一員ではないわ。そんな私から生まれた子だもの。恵みを受けられる筈はないし、だからほら、この子はこんな有り様なのでしょうね」
「……どうにかするよ。してみせるさ。準備はしてきたつもりだ。君の事も、必ず」
「私はいいわよ。覚悟して、こうしているんだもの」
「僕の覚悟が出来てない。だから君も、彼女も。どうにかなってもらわないと、僕が困る」
「勝手ね」
「今更だよ」
その言葉を最後に男の姿が消えて、小さな自分とその身体を抱える女だけ残される。
ゆらゆらと淡く揺れる自分の身体。木霊していた泣き声は、その揺らぎに飲み込まれるように収まっていった。
泣く事で疲れたのだろう。結局視界は晴れないまま、煙るような眠気が意識に靄を掛けていく。
「でも、嬉しいものね」
そんな自分の耳に、囁くように届いた声音は、少しの悲しみを帯びながらも至極優しい、慈しみに満ちたものだった。
耳元に、気配が近付く。閉じかけた意識、未だ歪んだ視界。
その中で近付いた女は、泣き笑いの顔に強い決意と願いを秘めて、こちらを見ていた。
「よく聞いてね。そして忘れないで。私と彼の、大切な貴女」
これはわたしが生まれた、始まりの記憶。
「貴女が貴女だと示してくれる、大事な大事な貴女の名前。それは――」
――これはわたしがわたしになった、初めての記憶。
人、鬼、地母、そして翆霊。
無数の在り方を宿す少女の周囲で生じる超常現象。髪が変化し生じる眷属とも取れる化け物。そして環境を変化させる奇怪な球体。それら全てを掻い潜った【NAME】が放った一撃は、しかし彼女に傷一つつけられず呆気なく霧散した。
傍にノエルが居るからと多少の加減はしたとはいえ、並の亜獣や鬼種ならば跡形も無く滅ぼす程の力を込めた技法の一撃。それが彼女の身体に触れると同時に、まとった理粒子、破壊のための力学的なエネルギーが、根こそぎ奪われていくのだ。
少女の身体に打撃の結果が生まれず、代わりにその周りに浮かんでいた球体の一つが、まるで風船の方に弾けて消滅したのを見て、【NAME】は小さな呻きと共に大きく距離を離す。
どうやらあの球体は、彼女に害なす力を受け取り、肩代わりする力があるらしい。
そうなると厄介だ。どう攻めればその守りを突き崩す事が出来るのか。
「…………」
【NAME】は迷いながら、窺うように少女の姿を睨む。
と、その時、少女に変化が起きていた。
より具体的には、少女達と表現すべきだろう。いつの間に正気を取り戻していたのか。少女に抱きかかえられ、今までぴくりとも身動きを見せていなかったノエルが、彼女にすがりつくような恰好で、必死に何かを訴えかけていた。
「だめ、です」
はっきりしない、苦しげで掠れた声。けれどもその声は、離れた【NAME】の耳にも辛うじて届いた。
「その人は、わたしの、大切な人。だから、駄目。それに、見たでしょう? あなたは、わたしじゃないって」
ノエルの言葉に、少女の様子にも変化が生まれた。
【NAME】が襲い掛かっている間ですら微塵も態度を変えず、ただ茫とノエルを見下ろしていた少女の視線が、直ぐ傍のノエルの瞳へと向けられる。
「わたしはあなた。だから、あなたはわたし」
「そうじゃない。……そうじゃないんです!」
答えにノエルはぶんぶんと頭を振る。
「あなたも、あの記憶を見たでしょう!? わたしも見たんです! なら……それならば判るでしょう!? わたしの名前は、ノエル・ガナッシュ! そして、あなたのっ」
一拍。言葉が途切れて、ノエルは一度大きく息を吸い込むと、叫ぶ
「あなたの、名前は、――――ですっ!」
そうノエルが叫んだ瞬間。
【NAME】達の周りに存在していた遺跡の光景全てが、まるで硝子細工のように砕け散った。
――産まれ落つ万象の雛――
細かな結晶。燦めく粒子となって、仮初めの世界を構築していたものが粉々に砕けていく。その光景はある種幻想的な美しさを醸しだし、【NAME】は目を奪われる。
だが、その姿は正に一瞬、刹那の間だ。世界を別の在り方へと塗り替え、更にはそれを維持し続けていた力は、もう今は感じられない。だから砕かれた輝きも、本来この地を支配していた土地概念にあっという間に飲み込まれて、乳白に近い濃厚な霧の中に消えてしまう。
後に残ったのは、この場所の本来の姿。濃い霧に包まれた森の様相と、消耗した様子の軍服を着た娘。そして、そんな彼女から一瞬たりとも視線を外さず凝視している、薄布を身に纏った少女だけだった。
少女の様子も、さっきまでとは一変していた。
姿形自体にはそう変化は無い。だが、広がり変化していた髪は元の長さらしい彼女の腰程度に留まり、周囲に生じていた空間の歪みようなものも完全に消え去っている。そして何より、少女が放つ気配の質が、大きく変化していた。
先刻までの彼女は、溢れ出る陰陽の力を、より強い生命の流れで引き留め、人の形にどうにか押し込めているような。いつ崩壊してもおかしくない、切羽詰まった気配を放っていた。
だが、今は荒れ狂うような強い存在概念達はすっかりと鳴りを潜め、それまでは殆ど感じ取れなかった気配――【NAME】にとっては身近である人間の気配が、それら静まった力と上手く結びつき、安定した形を維持しているように感じられた。
そんな彼女の姿からは、ついさっきまで感じていた強烈な危機感は想起されない。
勿論、つい先程まで少女の周囲で荒ぶっていた力が完全に失せたわけではない。少女の内側には、未だ膨大な力が存在しているのを感じる。だが、それが直ぐにこちらの危険には繋がらない事も判る。少なくとも、ここから自分に害が及ぶ流れになったとしても、十分に対処可能な猶予はあると、【NAME】の冒険者としての勘が告げていた。
正直な処、何故いきなり少女の様子が変化したのかは判らない。だが、今の彼女相手ならば、どうやら戦闘以外の選択肢が取れるようにも思えた。
【NAME】は小さく息を吐き、身構えを僅かに崩しながら、少女二人の様子を改めて窺う。
件の少女は、己の掌をじっと見るような姿勢のまま動く様子は無い。そしてもう一人の方はといえば、
「……【NAME】、どうして」
少女の傍で、茫然とこちらを見るノエルの表情には、幾つもの感情が綯い交ぜになって浮かんでいる。
一目で見て取れるのは、強い後ろめたさだ。その奥に、深い安堵と僅かな恐怖があるのが判る。
「【NAME】には、絶対に迷惑を掛けないようにって、だから、一人で……」
途切れ途切れにそんな事を言う彼女に対し、【NAME】は深々と溜息をつく。迷惑を掛けないようにと勝手に行動した結果がこれか、と言いたくなる気持ちは多分にあったが、ここでそれを口にしたところで、ノエルが更に萎縮してしまうだけだろう。
先刻までなら至極遠く感じた距離。それを今はたった数秒、容易い仕草で詰める。近付く【NAME】に対し、ノエル以外に反応する気配はなく、彼女の隣でぼんやりと立っている少女の髪もそのまま、何ら動き出す様子はない。それを一瞥で確認してから、【NAME】はノエルの正面に立つと、無言で片手を挙げた。
こちらを見上げていたノエルの瞳が、怯えとも覚悟とも付かぬ曖昧さで閉じられる。僅かに衝撃に備えるかのように身を縮こまらせているのは、どうやら叩かれるとでも思っているらしい。
意外と彼女の“先生”達は体罰主義だったのだろうか。【NAME】は気の抜けた笑みを浮かべて、
「あ」
そのままぐりぐりと、乱暴に彼女の頭を撫で回した。
戸惑いの表情を浮かべたノエルの頭が左右に揺れる。なすがままで目を瞬かせる彼女に、【NAME】は改めて大きく吐息を溢した後、心底からの言葉を漏らす。
――無事で良かった、と。
その気持ちは確かに伝わったのだろう。ぐらぐらと揺れていたノエルの顔が強張って、そして次の瞬間には泣きそうに歪んでいく。
「ご、ごめん、御免なさい。【NAME】、わたしは、でも」
頭に乗った手を振り払うくらいの勢いで、ノエルは焦って言い募る。そんな彼女の反応は、最初に出会った頃とは本当に別人のようだ。微笑ましくはあるが、しかしだからこそ、今回のような事になってしまった面もあるのだろう。
取り敢えず落ち着け、とぽんぽんと軽く叩く。すると、彼女は殆ど力を込めずに置いた掌に、己の額をこすりつけるようにして、
「――ありがとう、ございます」
震える声で、けれども確かに伝わるようにと懸命に努力をした声。その状態で、ノエルは何処か浸るように暫く身動きを止めてしまい、【NAME】は段々気恥ずかしくなってくる。
そして、はっきり言って全く状況が判っていないこちらに対してちょっと状況の説明を、とそんな要求をしたところで、彼女の両肩に移動させていた手の甲に、何かが添えるように触れた事に気づいた。
しっとりとした感触。反射的に意識がそちらへとズレると、大きな二つの瞳と正面からぶつかる。触れていたのは、小さな掌。いつの間に位置を移していたのか、先刻まで自分の掌をぼんやりと眺めていた少女は、その手を【NAME】の手の甲へと伸ばし、視線は真っ直ぐ、凝視するように【NAME】の顔に向けられていた。
少女の視線は、これまでのように何処を見ているかもはっきりしない曖昧なものではなく、明確に【NAME】の姿を捉え、認識していた。
その証拠に、少女の唇は小さく震えて、
「――【NAME】。私も」
ん、と二人の間を割り込むようにして、藍色とも紺色とも取れる綺麗な髪に覆われた頭が突き出された。
「…………」
意味が判らない。
いや、意味は判る。何を求められているかも判る。だが、何故彼女からそういう要求をされているのかが判らない。
「ん」
催促するように揺れる頭。その向こうに見えるノエルの顔も、突然割り込んできた存在に対する驚きで完全に固まってしまっていた。
少女の頭越しに、【NAME】とノエルは無言で視線を交わす。しかしどちらの顔にも困惑があり、欲する答えは得られないまま。
「んー」
三人、妙な体勢で暫く固まり続ける事となった。
森に立ち込める霧は、時に固まり、亜獣の姿を取って襲い掛かってくる事がある。
丁度今がそうだった。【NAME】達から数メートルほど離れた位置。木と木の間に、霧がうねるように蟠る兆候を見た。【NAME】のこれまでの経験では、ああいう動きを見せた場合、暫くすると霧が濃く集まり、化け物の姿となって生じる事が殆どである。
【NAME】は先んじてそれを討つべく武器の柄に手をやり、腰を浮かそうとする。だが、それよりも速く反応するものがあった。
少女の、豊かな髪の一房、である。
ゆらりと浮かび上がったそれは、先端を一瞬のうちに鳥の姿へと変えると、まるで矢の如く霧の蟠りを穿った。
突き刺さった髪の先端から、霧が環を描いて抉られる。しかしそれだけでは終わらない。毛先から更に放たれたのは、強烈な存在概念の圧だ。存在概念の強度に物を言わせ、他の存在を強引に押さえつけ、押しつぶす。理粒子干渉による概念攻撃等とは、根本的に違う代物だ。少女の毛先から放たれた力によって、霧の集合であった部分は黒と青の中間に近い色の結晶が飛沫へと塗り替えられて、そして次の瞬間には砕け散る。
伸びていた髪が元の長さへと戻り、ついさっきまで今にも霧の化け物が生まれそうな兆候があった場所には、もう何も、霧すらも存在しない円状の空白が、ぽっかりと残っているだけだ。
その間も、少女自身は一切の身動きなく、倒れた大樹の上に腰掛けて、じっと【NAME】の方を見つめたままである。
ただ、彼女の髪だけが、この場の邪魔するなとばかりに、霧の化生が現れる前にその兆候ごと消し去ったのだ。
「…………」
一連の動きを若干の冷や汗混じりで見届けた【NAME】は、浮かし掛けた腰を切り株の上へと戻すと、視線を横へと移した。
「――と、わたしが把握している状況は、今話した通りなのですが……」
倒れた大樹と、切り株。その間に存在する大きな根っこの上に腰掛けていたノエルは、窺うように【NAME】の方を見ていた。
対して、【NAME】は腕組みしたまま、うーむと唸るしかない。
恐る恐る、突き出された頭を撫で回した後。
【NAME】は少女に敵意や害意はないと判断し、取り敢えず話し合いの場を持つことにした。
という以前に、まず【NAME】には現状に対する情報が殆ど無かった。何せ、朝に突然ノエル失踪の話を聞かされ、慌てて捜索に出れば妙な現象に巻き込まれ、その中心となる場所でどうにかノエルを発見出来たものの、そこには何やら得体の知れない少女が居り、ノエルはそんな彼女に囚われるような形で正体を失っている状態だったのだ。
一先ず一触即発な状態は回避されたものの、【NAME】からすれば疑問だらけのこの状況。何らかの説明が欲しい所だった。
そんな【NAME】の要求に対し、おずおずと答えてくれたのはノエルだった。彼女についても、そもそも何故突然居なくなったのかなど疑問は尽きない。【NAME】はどう話したものかと迷い、言葉を選びながら話すノエルの説明を辛抱強く聞き続けたのだが。
(……はっきり言って無茶苦茶に過ぎるというか)
延々と繰り返される旅路。無数に交差する他者との記憶。存在の混同による同一化。そして、それに抗うための対決。
【NAME】の感覚からすると、彼女が語る話は夢物語にも近いものだった。
だが、その話には完全な妄想とも言い難い、筋とも言えるようなものの存在が感じられるのも確かだった。【NAME】には一つ、彼女が言う“それ”と思しき存在について知っている事があり、何より今こうして、ノエルが意識下で繋がり、そして感じ取っていたらしい“それ”が、目の前に形を持って存在しているのだから。
【NAME】の視線を受けて、大樹の上に腰掛けた少女が一つ瞬きする。
「何、【NAME】?」
短い問いに、いや、と【NAME】は反射的に誤魔化しかけて、うん? と首を傾げる。
そういえば何故彼女は、こちらの名前を知っているのだろう、と。
生まれた疑問をそのまま口に出してみる。正直、答えは期待していなかったのだが、相手の反応は普通の人間と変わらないほどに速く、そして真っ当なものだった。
「だって、私はわたし。今はもう、違うけれど」
少女の視線が、僅かに逸れて、ノエルの方を見る。その視線をノエルは硬い表情で受け止めて、
「……つまり、あなたはわたしの記憶を今も保持していると?」
問いに、少女は少し視線を落として己の内側を探るような間を置いて、
「それだけじゃない。私は、あなたそのまま、殆ど変わりないと思う」
その答えに、ノエルの表情がさっと険しくなる。
「ですから、あなたはわたしではないと――」
「それはもう、判ってる。私とノエル、あなたは違うもの。それは、あなたが教えてくれた」
対して、少女の表情は静かなまま。その面持ちは、出会った頃のノエルの姿を連想させた。
「でも、今の私は、きっとあなたそのまま。……だって私は、あなたに触れたとき、生まれたようなものだから」
「生まれた……ですか?」
戸惑うような声を漏らすノエルに、少女は素直にこくりと頷く。
「うん。こうしてお話ししている私は……私が覚えてる誰かの形を、そのまま真似てるだけ。けれど、その形の内側にあるものは全部、あなたから貰ったものしかない。今の私は、あなたが持っていた心で動いてる。あなたが知っていた事。あなたが定めていた事。あなたが感じていた事。あなたが想っていた事。それをあなたが私に見せて、教えてくれたから。私は今、こうしてあなた達とお話が出来てる」
これが、あなたの名前を知っている理由、と少女は【NAME】に視線を戻して告げる。
それに【NAME】が何か反応を返す前に、ノエルが険しい表情のまま口を開く。
「……あなたは、結局、何なのですか? 私の中にも、あなたの記憶のようなものは残っています。けど、その殆どは普通の人間が辿るような記憶ではありませんでした。それに、全部が全部、あなたのものだとも思えない」
続けてノエルが語ったのは、彼女がまるで現実の出来事のように体験したという幾つかの記憶だ。
それらは、端から聞いている【NAME】からしても繋がりが見出せず、加えて言えば人間が体験するような記憶ですらないように思えた。
だが、そう思えるというのに。
【NAME】には、ノエルが話す記憶の光景と繋がる存在について、思い当たりがあった。
そもそも、彼女を最初に見たときから、その正体については大凡の見当がついていた。だからこそ、ノエルが語る記憶の光景と彼女との関連性についても容易に見出す事が出来てしまう。
しかし、彼女本人はどうなのだろうか。もし彼女が自分の存在について良く判っていないのであれば、この自分の中にある推測を伝えるべきか、伝えざるべきか。
そんな【NAME】の逡巡は、杞憂に終わる。少女は能面のように一切の表情を変えず、淡々と答えた。
「それは全部、私のこと」
少女の小さな手が、胸元に添えられる。そこに、目に見えぬ何かがあるように。
「私には、その頃の私の心は無いから、それはずっと、良くわからないものだったけど。でも今の私なら、少し判る。それは、私だったものの事だって。生まれる前の、私達の事だって。だから、言える」
「…………」
「その全部が、私だって」
意味を解しづらい言葉。ノエルは眉根を寄せた表情で少し考え込み、そして困ったような、何処か縋るような視線を【NAME】に向けてくる。
ノエルからすると、少女の言葉は至極判り難いものだろう。
だが、ノエルとは違い、とある一件について知る【NAME】からすれば、何となく理解出来る事がある。
要するに、この少女は何処かを境にして、一度完全に死んだのだろう。
肉体が、ではなく、精神が。
だからノエルと偶然に繋がった時に、彼女は彼女の言う通り、ノエルを元にして彼女はそこで生まれたのだ。
そして彼女は、今の自分が、当時の自分とは随分と違う事を自覚している。今の自分が、幾つもの自分が寄り集まったものである事も自覚している。
その自覚は、きっと残酷なものだ。彼女自身が、そう捉えはしないだろう事も含めて。
「…………」
脳裏に、いつかの老人の姿が過ぎる。
彼が、終ぞ見る事が出来なかった結末。見知らぬ誰かに託した儚い宝物。
それが、どのような縁によるものか。今、こうして目の前に居る。
きっと、その姿、その在り方は、老人が最初に目指していたものとは大きく異なっているのだろう。
彼はその事を、嘆くだろうか。悲しむだろうか。
あるいは、喜ぶのだろうか。既に心すらも別のものとなった孫娘の形骸、新たな生を受けた万象の雛を見て。
「……【NAME】?」
と、名を呼ばれて、【NAME】は物思いから覚める。
気づけばノエルが傍によって、心配そうにこちらの覗き込んでいた。
「どうしました? もしかして、先刻の戦闘で何か?」
いや、さっきの戦闘での影響どうこうという話ならば、半ば譫妄状態に陥っていたノエルの方が怪しい。彼女の話を信じるならば、どうやらエルツァン島にやってきてから今までずっと何らかの精神干渉を受け続けていたという話だし、一度その辺りについてイェアに検査をしてもらった方が良いだろう。
【NAME】がそう言うと、ノエルはむ、と小さく唸って表情を消す。
「……イェアは、やはり心配していましたか……?」
心配どころか現在進行形で大迷惑を掛けたままである筈だ。何せエルツァン常駐の軍部隊を動員してのノエル捜索を今も行っている最中だろうし。
そんな【NAME】の言葉に、ノエルの顔色が蒼白に近くなった。
「【NAME】! は、はやく戻りましょう! これ以上、わたしの為に皆様の貴重な時間を割かせる訳には!」
なら最初から失踪などしなけりゃいいものを、という正論は、今言ったところであまり意味はないだろう。そんな事も思い付かないほどに思い悩み、思い詰めていたという話なのだから。
だから今するべきは、必死にノエルを探しているだろうイェアに無事な顔を見せてやる事だ。
ノエルが転がっていた黒銃を拾い上げ、傍に戻ってくる。【NAME】も切り株から腰を上げて、霧の森から海岸線へと出るルートを考える。ノエルを探すためにかなり闇雲に歩き続けた上に、途中からは奇妙な空間に囚われていたせいで、今居る位置も方角もあやふやだ。正直な話、ここから陣に戻るのはかなり手間な気がする。【NAME】は暗澹とした気分で、視線を動かし、
「…………」
倒れた大樹の上。少女はじっとこちらを見ている。表情はないが、瞳の奥には、窺うような気配がある。そういう所は確かにノエルに似ていた。
「――あ」
【NAME】は彼女に声を掛けようとして、言葉に詰まった。
そういえば、彼女の名前を、自分はまだ正確には知らないのだと。
確か戦っている最中。ノエルが彼女に向かって名前を叫んでいたのは覚えている。しかし、戦いの最中であったせいなのか、その肝心の名前の部分について、はっきりと聞き取れなかったのだ。
傍で、急かすようにこちらを見上げていたノエルに【NAME】が訊ねると、彼女は一度目を瞬かせてから、少し眉根を寄せて難しい表情を作る。
「あの子の、名前ですか……」
ノエルは少し困ったように、【NAME】と少女へと視線を行ったり来たりさせる。
何か、言い淀むような問題でもあるのか。
【NAME】が訝しげに問うと、ノエルは「問題、といえば問題ではあるのですけれど」と前置き、
「――――です」
「……?」
何か、甲高い音の羅列のようなものが聞こえた気がした。
首を捻った【NAME】に、ノエルは浅い嘆息をつくともう一度口を開こうとして、
「――――」
別の場所から、先刻と同じ不思議な音がした。
音の出所は、倒れた大樹の上。座る少女の、唇からだ。
しかし、響いた音は、人の喉から発せられたとは思えぬ、奇妙極まる音だったのだが。
【NAME】が戸惑いも露わに二人を交互に見ると、ノエルの方はその反応に納得の頷きを一つし、少女の方は唇が薄い笑みの形をつくる。
「これが、私の名前。ノエルが思い出させてくれた、私が私であるための名前」
「地母の系統に伝わる習わしの一つ、だそうです。地母種達は己の役目を示す“通名”、呼称として使う“俗名”の他にもう一つ。自分という存在概念の形を維持するための形を音程を定める“真名”を持っていると。先刻の音は、彼女の真名です」
――地母の系統。
その言葉に、【NAME】は驚きと共に納得も得る。
焼き付いた老人の記憶の中で感じていた不足。先刻の少女との戦いで感じていた想定外の力。それが、地母の系統という言葉で繋がった気分だった。
「真名は本来は秘するもの。こうして発音する事自体が稀で、わたしも彼女と繋がって、彼女の記憶を見ていないと声として出せなかったと思う程なのですが、……【NAME】、どうでしょうか?」
無理だと返す。まず聞き取ることすら満足に出来なかった。
真名は無理だが、流石に名前がこれだけしかないという事はないだろう。何か別の、それこそ“俗名”とやらを教えてもらえないか。
そんな【NAME】の当然の提案は、少女の浅い左右の首振りで却下される。
「私の記憶の中で、名前について残ってるのは、それだけ」
少女の言葉に、【NAME】は軽く顎に手を当てて思案する。
幾つもの在り方が共存する彼女。その中で、“人”であり“地母”である彼女を示す名は、それこそ彼の祖父すらも知らなかった。今回、ノエル達が見つけた名以外はもう、覚えている者はこの世には居ないだろうし、ノエル達が見つけた名にしても、普段呼ぶには使わぬ特別な名前である。
そして“翆霊”としての彼女の名は、そもそも存在しない。彼の老人が少女に施したのは命脈の力による施術。繋がり現世に引き出された翆脈に名などがある筈も無い。
ならば残るは“鬼”としての彼女の名。これは、恐らくフローリアに滞在する人間ならば知らぬ者は少ない。それ程に知れた名が存在する。彼女がその力をも宿す存在であるならば、この名で呼ぶのも偽りではないだろう。
だが、やはり惑いがある。
名とは存在を定義するものだ。【NAME】が見る限り、今は“人”の形を主として存在している彼女をその名で呼ぶ事が、延いては“鬼”を呼ぶ事にはならないだろうか。
少女を見て、【NAME】は逡巡する。そんな【NAME】を、少女の方はじっと見つめ続けている。
その真っ直ぐな視線を受け止めながら。【NAME】は彼女が最初にこちらの名を呼んでからずっと、自分から殆ど目を離さずにいることに気づく。
瞳に宿るのは、直向きな感情だ。殆ど初対面にも近い少女。それも、明らかに尋常ではない存在である彼女に、そのような目を向けられる事には、どうにも戸惑いが先につく。
二重の惑い。そんな【NAME】の内心を見抜いたのか。少女は無表情を少し笑みの形へと崩すと、とん、と大樹を蹴った。
ふわりと髪が広がり、【NAME】の方へと小さな体躯が近付いてくる。美しく波打つ髪の動きに、【NAME】は暫し見惚れて、
「む」
鈍い声が漏れた。
飛んできた身体が、【NAME】の頭を包み込むようにしてしがみついたのだ。細い両の足がこちらの脇を挟み、腹が視界を塞ぐ。頭の左右に感じるのは回された腕の感触だろう。何処かひんやりとした体温が、【NAME】の上半身を包むように伝わってくる。
「え……。あ、えっ?」
横から完全に動転した声が聞こえたが、それに【NAME】が何か言葉を返す前に、上方から淡々とした声。
「あなたがしたかった事を、かわりにやってあげた」
「――っ!」
息を吸う悲鳴、とでも言えば良いのか。そんな声が横から上がるのを聞きながら、【NAME】は視界が回復するのを悟る。べったりとくっつく形になっていた腹が、少し距離を取ってくれたのだ。見上げれば、直ぐ傍に無表情な少女の顔があり、
「あなたが決めてくれるなら、何でもいい。わたしはそれくらい、あなたの事が大好き。だって、私もそれくらい、あなたの事が大好きだから」
少し判りづらくて、しかし少し考えれば意味が判る言葉。
隣に立つノエルが顔を伏せる気配を感じたが、それについては極力反応しないのが情けというものだろう。【NAME】は意識して正面にいる彼女以外の事を考えないようにする。
無垢に飛びつき、今は見下ろすようにこちらを眺めている少女。その背後に見える、少女が先程まで座っていた大樹の幹は、彼女が座っていた形にえぐれていた。その現象は彼女が意図したものなのか、無意識下のものであるのか。判らないが、しかしこうして【NAME】と彼女が触れている部分には、何ら異常は見受けられない。その事を如何に解釈するべきなのか。
(きっと、彼女は)
今、内包する全ての存在を含めて、彼女なのだろう。
であるならば、この逡巡も不要なもの。そして唯一他者に知れた名があるならば、それを使うことこそがきっと彼女の安定にも繋がる筈だ。
「――ウィースルゥイン」
呟いた言葉に、息を飲む気配。それは正面の少女からではなく、隣に居るノエルからだ。
しかし、構わない。構う必要はない筈だ。それを示すように、見下ろす少女は表情を一切変える事無く、けれど少しだけ頭を俯かせて、
「判った。それが、昔の、そしてこれからの私の名前」
こつんと額が当たる感触と共に、【NAME】は少女――ウィースルゥインが己から身を離すのを感じた。
「二人とも、戻るの?」
ふわりと宙に浮かび上がった少女からの問いに、【NAME】は頷く。するとウィースルゥインは「そう」と短く頷き、少しの間を置いて話しだす。
「……私は、あなた達をまだ見ていたい。だって、わたしがはっきり見えるのは、まだあなた達だけだから」
少女の視線が、ここで初めて【NAME】から外れる。隣に立つノエルが、少し緊張で身体を強張らせるのを感じた。
「ノエル。わたしを私にしてくれた人。あなたは私に、まだあなたの姿を見せてくれる?」
「…………」
ノエルは険しい表情で少女を睨み
「これまでのようなやり方でしたら、きっぱりお断りさせていただきますけれど……違うのですよね?」
「だって、あなたは私じゃないから。ただ、見せて欲しいだけ。近くで、あなたを」
「でしたら……構わないと、わたしは思います」
渋々といった調子で頷くノエルに、ウィースルゥインはこくりと頷き、視線を【NAME】に戻す。
「【NAME】も、いい?」
見る事自体にとやかく何かを言う気は無いが、そもそもどうやって、どういう風に、という疑問がわく。どうも彼女の言い方だと単に同行したいだの監視がしたいだのという風には聞こえないのだが。
そんな【NAME】の問いに、ウィースルゥインは小さく首を傾げる。
「ただ、見ているだけ。多分、私になった私は、もう前みたいな事は出来ない。だから、見ているだけ」
少女は空中で丸まるような仕草で停止する。その身体が、次第に薄らぎ、周囲の景色に徐々に塗り潰されていくように感じた。
身体の変化に気づいたのだろう。ウィースルゥインは自分の身体を見下ろし、少し自嘲するような笑みを浮かべる。
「言った途端にこれだから。意識してしまうと、やっぱり駄目みたい」
「……どういう事です? 大丈夫なのですか?」
「今まで私は、真っ暗で、何も無い場所に居た。でも、あなたに出会う事で、そこから明るい場所に出てこられるようになった。あなたや、あなたに関わる人達を視ていると、私もあなた達に見えるようになる。今は、これまでよりもずっとはっきりしているけれど、まだ慣れないみたい……」
少女は膝に顔を埋めるようにして、何処か眠そうに独り言のような口調で呟くと、一瞬、視線を上げて【NAME】とノエルの方を見る。
「だから、あなた達の事。また、夢の中で見せてね。これからは、呼んでくれたら、会いに来るから。だから……またね?」
最後はもう、囁くような声音で。
あらゆる力を秘めた少女は、霧の中に染み込むように消えて、後には【NAME】とノエルの二人だけが残された。
「……【NAME】、聞いていますか?」
聞いています。
霧の森から、常駐軍の陣が存在する島南側の海岸を目指す。その道すがら、【NAME】は延々とノエルの繰り言を聞いていた。
「さっきのあの人が言ったこと。したこと。あれは、わたしには一切関係が無い事だとわたしは主張します」
はい、そうですね。
「ですので、【NAME】は先刻の件は一切忘れて、記憶の外へと追いやるべきだとわたしは思います」
既に追いやっているのに同じ話をされるせいで何度も記憶が蘇ってしまいます。
投げやり気味に答えると、ぐ、と詰まるような声を最後に何も話しかけてこなくなった。
むしろ、そこまで気にされる方が逆にこちらも気を遣うのだが、
――その辺りの機微は、まだまだ彼女には早いのだろうか。
などと考えながら、【NAME】は同時に別の事も考える。
何を考えているかといえば当然、先刻出会ったあの少女についてなのだが、それ以外にも幾つか、気になる話もあったのだ。
それは、ノエルが見続けていた記憶と、過去の彼女達とやらが立てた一つの仮説だ。
曰く――自分達は延々と、このエルツァン島の旅を繰り返しているという。
「…………」
ノエル・ガナッシュが昨今――彼女の感覚でははるか昔から――感じていた異変の発端がウィースルゥインであり、そしてノエルの感想やウィースルゥイン本人の発言を元に推測するならば、ノエルが見続けてきた自分の過去の記憶とやらは、ウィースルゥインの中に蓄積されてきたノエルの記憶、という事になるのだろう。
ウィースルゥインがノエルという存在を常に注視し、その在り方全てを模倣しようとしていた結果、ウィースルゥインに過去のノエルの記憶が蓄積し、そして未来のノエルの方にその蓄積されていた記憶が逆流していた。そんな理屈だ。
と、するならば。
つまりあのウィースルゥインという少女は、ノエルを――そして可能性としては【NAME】含めたエルツァン島に存在している全てを含め発生しているらしい巻き戻しから、完全に独立した存在であると考えられる。その意味でも、あの少女は極めて重要な、正に状況の鍵となり得る存在だった。
本人は、こちらが呼べば会いに来るなどとえらく気軽な感じで言ってはいたが、実際に今少しばかり内心で呼びかけてみても無反応なあたり、果たしてどれだけ信用出来る話なのか怪しい。そもそも、彼女は大禍鬼の存在概念を身に宿しているという極めて危険な存在であり、ノエルに対して強烈な干渉を行い続けていた前科がある。そんな存在をどれだけ信用できるかと言えば、
『あなたが決めてくれるなら、何でもいい。わたしはそれくらい、あなたの事が大好き。だって、私もそれくらい、あなたの事が大好きだから』
「……【NAME】。今、妙な事を考えているようにわたしは感じましたが」
横からのじっとりとした視線を受けて、【NAME】は若干の引きつり笑いで誤魔化す。
ただ、ああ告げてきた彼女の、言葉だけではない、その奥に存在する心情の真摯さについては、確かに【NAME】の胸にまで届いていた。
だから、信用には足ると、【NAME】は考えていた。もっとも、ああいう形で育まれた彼女の精神自体が、鬼種が本性として持つ衝動に飲まれるという可能性も、十分に有り得る話ではあるのだが。
(……何にせよ)
エルツァンにやってきてからそれなりの時間も経過し、他の同行者達と共に幾度か調査を行った結果、色々と知り得た事もある。
今回のノエルの件も含め、一度これまで得た情報をまとめて突き合わせ、イェア辺りと今後について話をする時間を設けた方が良いのかもしれない。
特に今回、ウィースルゥインに出会えたのは大きな進展であるように思えた。彼女を上手くイェアと会わせる事が出来れば、色々と状況が好転するかもしれない。少なくとも、多くの情報が得られるのは確かだろう。
問題は、人の形をとってはいるものの、その存在自体は明らかに人と異なる異質な彼女と、どう引き合わせるか。ウィースルゥイン本人は、ノエルに近い人物となら大丈夫かも、みたいな曖昧な事を言っていた気がするが、その言についてもどれだけ信用できるのやら。
だが、これまでバラバラに存在しているように見えた色々な要素が、徐々に一つの形を示し始めたような、そんな予感がする。
「――【NAME】、見えました! 森の終わり、海の青色です!」
隣、ノエルが前方を指差しながら、こちらを見上げてくる。その表情には先刻までの不機嫌さは無く、明るい安堵の色しかない。
そんな彼女に頷きを一つ返して、【NAME】は薄れてきた霧の向こう、木々の合間から覗く青の色に向かって駆け出す。
垣間見えた光明は、まるでこれから自分達が進む道をも照らしてくれる標のようだった。
真なる楽園 秘中の暁
――秘中の暁──
海近く故か、吹く風が思いの外強い。
天幕の出入り口となる垂れ布を捲り外へと出ると、潮気を含んだ空気が首筋を撫でるように通り抜けて、日中ではあまり感じる事の無い、ひやりとした肌寒さを覚えた。
「…………」
浅く身体を震わせて吐息を一つ。反射的に襟元を正してから、【NAME】は未だ濃い暗闇が広がる軍陣地の中をゆっくりと歩き出す。
時間は夜。恐らくは未明から明け方といった辺りだろうか。もう少し時が進み、地平の向こうから朝の気配が昇ってくる頃にもなれば、各々の天幕でも動きが生まれるのだろうが、今はそれらの気配もなく、周囲は深い静寂に包まれている。この陣地に於いて、今が最も静かな時間帯だと言ってしまっても良いだろう。
点々と設置されている篝火が弾ける小さな音を聞きながら、【NAME】が向かっているのは陣地の外だ。
こんな夜番の兵以外の誰もが寝静まっているような時間に、一体何をしに行くのかと言えば。
(様子を見に――或いは注意をしに、という事になるのか)
内心と共に漏れ出す吐息は嘆息に近い。呆れとまでは言わないが、またか、という印象は拭えなかった。
イェアから遠回しに相談を受けての今回の件であるが、彼女の話から推測を立て、目覚める時間を少し前倒しして気を張っていたら案の定。妙な気配、独特の違和が陣地の外――内陸の超常地形群とは異なる場所で生じているのを感じ取ったのだ。しかも、その気配は【NAME】にも多少の覚えがあるもので、イェアの心配が少なからず的中している事を裏付けてもいた。
とはいえ、イェアから相談を受けた手前、違和を感じたという話だけで終わらせる訳にも行かず。実際に気配の出所へと赴き、“彼女達”が具体的に何をしているのか確認し、ついでに多少釘を刺す程度はせねばならないか、と二度寝という甘美な誘惑を振り切っての出発だった。気が向かない事この上無いが、しかし仕方が無いと言えば仕方が無い。恐らく、自分は彼女達――より厳密に言えば“彼女”を抑える事が出来る、数少ない存在であるだろうから。
そんな事を考えながら、【NAME】は歩を進める。陣地を囲う簡易の柵、その小さな門となる場所で暢気に立ち話をしていた夜番の兵二人へ声を掛け、イェアから外出の許可がある旨を話し、彼等に見送られる形で陣地の内から外へと出た。
捉えた気配は未だ消えてはいない。それを確かめ、辿る形で海岸を進んでいくと、徐々に陣地にて焚かれている火の光が遠のいて、代わりに夜の空を彩る星の光が周囲を照らし始める。眼前に広がるのは打ち寄せる波の音だけが響く浜辺の姿だ。軍陣地近隣の海岸では棲息亜獣の掃討を既にほぼ完了させており、身の危険を感じるような気配は全く無く、【NAME】は気楽に浜辺を歩いていく。日中の間は時折海、或いは内陸から亜獣がちらほらと現れるそうだが、夜間に於いては極めて稀だという。夜番を務める兵の数が、陣の規模に対してあまり多くない理由も、この辺りに起因している。
それでも完全に夜番を廃止しないのは、最低の警戒は維持するという意味もあるが、どちらかといえば規律や習慣を守るための一環という意味合いが強いのだと、実質的な軍部隊の指揮を執っているノクトワイが話していたのを思い出す。確か、人里から切り離された場所で多人数での集団生活を行う際には重要な要素だ云々という話だったが、単独、あるいは少数での行動を常とする身としては今ひとつ理解しづらい部分ではあった。集団を統べる立場、特に危険と隣り合わせの場での指揮を執るともなれば、一冒険者には想像もつかない複雑なあれこれがあるのだろうと、適当に納得して話を聞き流した記憶がある。
但し、そんな油断が許される――ある程度の安全が確保されているのは、陣地とその周辺に限った話だ。
軍陣地を遠く離れて、その姿、焚かれる篝火が完全に見えなくなる辺りからは当然、話が違ってくる。地形は単純な砂浜から鋭い岩肌を持つ磯が混じり始め、徐々に見通しも悪くなり、幾つかの物陰では潜む存在の気配を感じる。獲物であるかを見定める、窺いの視線が複数向けられているのも直ぐに判った。
が、今の【NAME】は、そのような些細な事に気を向けるつもりはない。懐を弄り、握り締めるのは既に身に着ける事にも慣れてきた首飾り。器にて眠る神形の意志に覚醒の気配は無い。エルツァン島に入ってから僅かにその眠りが浅くなり、そして自分へと流れ込む力が強くなっているのを感じてはいたが、この流転の神形が己が役目と認めた際に放つ強烈極まる力を知る【NAME】からすれば、今の状態は目覚めと呼ぶには程遠い。
(程遠いが……)
それでも、神形との繋がりによって齎された力を利用すれば、この磯の一角を丸ごと塞ぎ周囲と分断しつつ隠匿する規模の結界を感知し、そして破るのはたわいもない事ではあった。
人は疎か、意志すら持たぬ存在をも拒み、隠れようとする世界の区切り。目で見るだけでは周囲と殆ど差異の無い迷彩を施したそれを、【NAME】は気軽な動きで破壊しようとして――しかし、寸でのところで動きを止めた。
よくよく、目の前に存在する結界を見据える。結界が持つ隠匿と分断の力。その奥に、僅かな相のズレを感じ取ったのだ。
世界の相をズラして固定し、別個のものとして成り立たせる結界――細かく分ければ派生位相式結界とも呼ばれるそれは、定め区切った場の内に外とほぼ同様の土地概念を写し、現世界と分離した小世界を構築する。相の差によって現世界からの影響を受けないようにする為のものであると同時に、結界内にて構築した位相領域内の事象を現世界に漏らさないようにする為の方法である。
そもそも結界術式とは場を仕切り、隔絶するという機能を基本として成り立つ代物であるが、位相を絡めた結界術式は、境界を作り区切った上で場の在り方を制御するという、基本的な結界の手法に加えてもう一段、別軸の隔離手段を組み込んだ多重構造を持つ。こうする事で、現世界を模した結界内での出来事を位相領域内での出来事として処理し、結界を解く際にはその世界を完全に切り離して消去。現世界に全く影響を与えないように出来る。派生位相式の結界は、外から内よりも、内から外への影響を抑える事に重点を置いたものだと言えるだろう。
ただしそれは、迂闊に結界を破壊してしまうと、構築されていた位相領域が何の前置きも無く現世界に重なるように展開され、中で生じている何かがそのまま外側へ現れる形になる、という事でもある。
基本的に、現世界を元にして人が単独、或いは少人数で構築できる位相結界は、場の土地概念に極々僅かなズレを生じさせて造り上げる、極めて弱く小さなものだ。破壊した結果、位相領域が現世界側に重なる事になったとしても、瞬く間に現実の在り方に呑み込まれる形となる。しかし、その瞬きという一間、場がどのような状態になるのかが想像し難く、何より“中に居る筈の彼女達”がどうなるかが読めない。今の状況で、選ぶべき手段ではないだろう。
となれば、思い付く残る手段は、結界の中に入り込んでみるくらい。普通の人間であるならば純粋に破壊するよりも数段難度は高い行為ではあるが、逆に己が相を変化させる事が出来る者であるなら、位相を用いた結界に入り込む事はそう難しくはない。
そして都合良く、【NAME】は――より正確には【NAME】と共にある己には、“同化者”としての力があった。それを利用すれば、不可能という程のものでもない。例えばこれがもっと大規模で、もっと異質な結界であるならば話は別だが、この世界はそれらと比べれば遥かに単純で、簡易的なものだ。何とかならない事もない。結界自体も、隠匿、分断という基礎的な効力は十全に発揮されてはいるが、細かいところの造りが甘い。取り敢えずの知識で取り敢えず仕立て上げてみたような代物で、これならば少しの工夫で結界を誤魔化せるだろう。
ただ問題は、中がどうなっているのか全く判らない事と、結界を形作っている力が、【NAME】が知る様々な強存在が混じり合った、強烈かつ不安定極まるものである所だった。結界内に入る事は出来るだろうが、その中でどういうズレた世界が構築されているのかが読めない。流石に土地自体が丸ごと別物になっているというのは考えづらいが、何せこの覚えがある気配の主、常識があるのかどうかが未だはっきりしていない。恐らくあると信じたいが、その常識に則った結果が結界を敷こうという判断に至ったのなったのならば、それはそれで中がどうなっているのか怖くなる。
「…………」
眉根が寄る。逡巡の時間は大凡10秒。覚悟というよりも諦めに似た気持ちで、【NAME】は不定理粒子を使い己の身体に僅かに干渉。ほんの少し、目の前に存在する結界内の相に己の相を寄せ、結界に触れた。
内と外、その相違を判じて拒み弾く構造を持つ結界の境は、内の相を持つ【NAME】を、するりと結界の内側へと招き入れる。目の前の結界は、モノ自体は強烈な力を下地にした豪勢な代物ではあったが、造り自体は先程述べたように非常に拙いものだ。上等、或いは一般の術士であるなら仕込むであろう多重の判断、防御の処置などは一切無く、【NAME】の身体は簡単に、結界内に構築されていた位相領域の中にて存在を確定させる。
一瞬ぐにゃりと歪んだ視界が、直ぐに正常なものへと戻る。結界内の風景は、外と殆ど同じでありながらも多少の差異があった。具体的には磯辺ではなく砂地の海岸の風景が展開されていたくらいで、天候や昼夜に関しては外そのままだ。遮るものの殆ど無い、月明かりが照らす浜辺の景色。それをぐるりと見渡していた【NAME】は、少し離れた場所に二つの人影が立っている事に気づく。
人影の正体は、【NAME】が予想していた通りの二人だった。【NAME】は一つ溜息をついてから、彼女達に声を掛けようとして、
「じゃあ……いきます!」
「待って、誰か来た」
「――は? 誰か? って、え、【NAME】? あっ、危ない、危ないですっ!」
物凄い勢いで何か飛んできて爆発した。
暫くの間を置いて。
結界の中に居た“彼女”達――アラセマ常駐軍に所属する兵でありながら、特殊な素性を持つ“人形”の娘ノエル・ガナッシュと、先日の出来事により縁を持った、幾多の概念によって成り立つ鬼ならざる大禍鬼ウィースルゥインの二人に対し、【NAME】は事情の説明を求めていた。
因みに、反省の意を示す正座で見上げる少女二人を前で苛立たしげに立つ【NAME】の姿は、先刻の爆発によって砂まみれ傷だらけである。放たれ爆発した力の質の異様さと規模からすれば、この程度で済んだのは正に僥倖と言えるものなのだろうが、だからといって全く以て有り難くはない。
座る二人の内の片方、何時もの軍服を着込んだ娘の方は、身体を縮こまらせるように俯きつつも、時折窺うようにこちらを見上げてくる。その様子からは兎に角強い後ろめたさや罪悪感らしきものが滲み出ている。爆発で吹っ飛んだ【NAME】を看護していた時は謝り通しで、その時よりはまだ落ち着いている様子だったが、代わりに深く落ち込んでいるようだ。
対してもう一人、薄布を纏った程度の藍色に近い髪を長く広げた少女の方は、同様に正座してはいるものの背筋はまっすぐに伸びて、【NAME】を見る視線に怯みや澱みは一切無い。更に言えば反省しているような様子も別に無く、寧ろ【NAME】を見上げる瞳はどこか嬉しそうですらあった。
【NAME】からの質問に対する受け答えも、今見せている態度がそのまま反映されているような形で、ノエルは謝罪の言葉以外は口篭もることが多く、ウィースルゥインは素直で言葉も明瞭ながら、内容が若干おかしかったり端的過ぎたりで今ひとつ要領を得なかった。
彼女達曰く、どうも二人で定期的に“勉強”をする為、こんな時間にわざわざ陣地の外で会う事にしたそうなのだが、妙な話だと【NAME】は首を捻るしかない。
ただ会って話をするだけであるならば、未明に陣地の外で会わずとも、彼女達二人だけになる方法はある。ノエルは天幕を個人で利用しているし、ウィースルゥインは正に神出鬼没だ。未だ在り方に不安定さを残す彼女は、それ故の便利さも有しているらしく、互いに存在を認識している相手であるならば、その傍に任意で出現する事ができるようなのだ。人目を気にするという話ならば、その力で直接天幕内に出現して会えばいいだけである。勉強をするにしても、こんな人気のない場所にご大層な結界を拵えてやるものではないだろう。
「それじゃ、駄目なの」
そんな【NAME】の疑問を、ぼんやりとした表情でこちらを見る少女が、しかしはっきりとした言葉で断ずる。
何故、と返せば、
「だって、【NAME】。あなたはさっき自分がどういう目に遭ったのか、もう忘れたの?」
「…………」
虚を突かれた気分だった。勿論忘れてはいない。しかし、今のやりとりと繋がりがあるとは全く考えていなかった。
つまり、“勉強”という言葉からこちらが連想しているものと、実際行っているものがズレていたのだ。先刻自分が喰らった謎の力の爆発が、彼女等の“勉強”の産物だというのか?
【NAME】の我知らずの呟きに、ウィースルゥインは少し考える間を置いてからこくりと頷き、
「多分、そう。これはノエルの――」
「――ま、待って! 待って下さい!」
と、突然ノエルがウィースルゥインの方に飛びついて、彼女の口を手で塞いだ。鬼種の少女はいきなりの事に目を瞬かせたが、ノエルの考えは伝わったようで素直にその口の動きを止めたようだ。
だが、そのような行動をすれば、当然【NAME】の意識はウィースルゥインからノエルの方へと移る。
――何か、ウィースルゥインに話されてまずい事でもあるのか。
ばつの悪そうな怯えた表情でこちらの様子を窺うノエルに、【NAME】がいつになく険しい顔と視線を向ける。元々引け目がある風だったノエルはそんな【NAME】の態度に怯んでしまい、顔を伏せて、自分が口止めしている相手に助けを求めるようにちらちら見る始末。
対し、ウィースルゥインは薄い表情のまま小さく首を傾げて、
「【NAME】を困らせたくないなら、ちゃんと話す方が良いと思う。嫌われるよりも、叱られる方が悲しくないもの」
「……う」
何処か諭すような雰囲気すらある少女の言葉が深く心に刺さったのか。ノエルは呻くような声の後、伏せていた顔をどうにか【NAME】へと向けて、怖ず怖ずとした調子で話し始めた。
――簡潔に纏めると。
彼女達がやっていたのはノエルが持つ“人形”としての力を活用するための訓練、であったらしい。
ウィースルゥインとノエル。今に至る経緯は紆余曲折し、その在り方も大きく形を変えてしまっているが、元々、二人の素性には繋がりがあった。
ウィースルゥインは、“天従”と呼ばれる他存在と繋がり従える力を持つ大禍鬼として。
ノエルは、その鬼を核として造られた芯形機構の端末である“人形”として、である。
今のウィースルゥインは、過去に大禍鬼として存在していた時とは殆ど別物と呼んでも良い状態にあり、あらゆる種の様々な特性を得た代わりに、鬼種として本来持っていた固有の特性である“天従”の力は殆ど失われ、逆にイェアが“固独”と称する程の強力な独立存在性――他存在との非干渉性質を持つに至った。
しかし、以前にウィースルゥインとノエルの間で起きた顛末からも判るように、ウィースルゥイン専用の端末として造られたノエルに対しては、弱まった“天従”の力が未だ効力を発揮したままだったのだ。
そしてこの事は、想定されていた力の源を得られず不完全な“人形”であったノエルが、漸くにして本来の性能を発揮出来るかもしれないという可能性に繋がるものでもあった。
現在のウィースルゥインが持つ多様な強概念と、それに由来する様々な力。
ノエルが彼女との間に歪ながらも確保した繋がりは、どうやら時を経る毎に徐々にではあるが太く、深くなっているらしく、しかも互いの存在を認識し明確に切り分ける事が出来るようになった今では、以前よりもお互いを悪影響なく理解できるようになっていた。
その過程で、ノエルは己の内蔵された元々は鬼の力を引き出す為だけに使われる筈の機能を利用する事で、今のウィースルゥインが持つ別種の力すらも僅かながら、より判りやすく使いやすい形として変換し、発揮できる事に気づいたのだ。
これが上手く使えるようになれば、ノエルの戦闘能力は格段どころか今までとは別の次元――高位の鬼種相手でも相応に渡り合える程に高まるかもしれない。
しかし、生まれてこの方そんな機能を使ったことなど一度もなかったノエルだ。力の制御は極めて不安定な状態で、取り敢えずは力の源であるウィースルゥイン本人と共に、軍の皆に迷惑の掛からぬ陣地の外で更に結界も準備し、その中で取り込んだ亜獣等を相手に、己の本来の力の使い方を手探りで研究していたのだ。
――つまり、これが彼女等のいうところの“勉強”であった、と。
「以上、です……」
一通りを話し終えたらしいノエルが、恐る恐るという風に【NAME】の方を見上げてくる。
「…………」
対して、【NAME】は頭痛を堪えるようにこめかみを押さえて、改めて深く吐息をつく。
何かこそこそやっているらしい、というのは判ってはいたが、彼女達の行動は思った以上に危険なものだった。成る程、自分やイェアに言えない訳だと【NAME】は納得する。
「……御免なさい。この前の事もありましたから、皆に話すと、止められるかもしれないと、そう思ったら、言い出せなくて。それに、練習も最初は失敗ばかりで制御出来ずに暴発してしまう事もあって……だから、余計に。特にイェアには、これ以上、心配を掛けたくないって……」
あまりの言葉に、【NAME】は一瞬怒鳴りそうになる。
心配を掛けたくないも何もあるものか。何故自分が今、こうしてノエル達の様子をわざわざ観に来ているのかといえば、イェアから相談を受けたからこそなのだ。既に一度、ノエルが陥っていた状況を見抜けずに失敗をしたイェアだ。当然、ノエルの事にはこれまで以上に気を払っている。今回見せているノエルの妙な動きについては当然イェアもある程度把握していて、だからこそ心配し、けれども自分には隠そうとしているノエルの心境も考慮して、わざわざ【NAME】に相談しに来たのだ。そんなイェアを知っているだけに、ノエルの言葉と行動は至極浅慮に思えた。
大体、ウィースルゥインとの件でも、一人で溜め込んだ末に行動を起こした結果が、エルツァン島の軍部隊を巻き込んだ捜索行に発展したというのに、まだ反省してなかったのか。アノーレ島での彼女はそういう態度を殆ど見せなかった気がするのだが、最近は何処か視野の狭い、衝動的ともいえる行動を取る事が増えたように感じた。
人が経験を積み、変化をしていくのは当たり前の事だが、良い変化もあれば、悪しき変化もある。
今回の事は、その悪い部分が強く出ているように思えて、【NAME】は表情厳しく、縮こまるように身を竦めるノエルに言葉をぶつけようとして、
「あまり、怒らないであげて」
隣から、そう取りなすように口を挟んだのは、ウィースルゥインだ。
何時の間にか立ち上がっていた彼女は、【NAME】の衣服を引っ張るようにして意識を自分の方へと向けようとする。
「それだけ皆や、何より【NAME】。あなたの役に立ちたかった。だって、ずっと、わたしはあなたの事を助けられなかったから。あの時も、あの時も。わたしは直ぐに動けなくなって、あなたが怪我をしながら頑張るところ、ただ遠くで見ているだけだった」
訥々と。【NAME】に向けて紡がれる言葉は、一体誰が辿った記憶なのか。
「ま、待って、それは――」
少女の背後で、ノエルが動いて彼女の言葉を止めようとするが、しかし薄布を纏った少女は一度振り向いて、掌を浅くノエルに向けるだけでその動きを逆に抑えてしまう。
そして改めて【NAME】を見上げた彼女は、またゆっくり、平坦ながらも僅かなりと情が感じられる声で、話し始める。
「あの時のわたしでは、あなたの力になれなかった。でも、今は私が居る。だからわたしは――ノエルは、皆を困らせても、心配させても、叱られても、やらなければならない事を、やろうとしている。もしちゃんと出来たなら、きっとあなたの力になれる筈だから。……この気持ちだけは、【NAME】も判ってあげて」
「…………」
それはつまり、反省はしていてもまたこうした行動を取るかもしれないという意味でもあったが、しかしこちらの怒気を大きく削ぐ言葉でもあるのは確かだった。
物言いとしては、ずるいと言っても良いものだ。要は貴方の為だという免罪符を翳す事で情に訴えて意気を逸らしているだけなのだが、厄介なのはこれがその場限りの言葉ではなく、全くの本心で言っているらしいのが伝わってくる所だ。
(狙っての台詞、ではないとは思うが……)
見下ろす【NAME】の窺うような視線にも、万象を宿す少女は一切の怯みを見せることなく、むしろ自分を見てくれている事に満足を得ているかのように、ただただじっと目を合わせてくる。
以前、彼女が言っていた事を思い出す。自分は記憶の底から取り敢えず拾い上げた仮初めの人格の中に、ノエルが持っていた知識や経験、情動を詰め込んだだけの存在でしかないと。
だが、まだ明確に意識を持つようになってから然程も時間が経っていないはずなのに、ウィースルゥインの立ち振る舞いはとても落ち着いていて、【NAME】とノエルの感情の遣り取りも齟齬無く理解出来ているようだ。少なくとも、今彼女の後ろで不安げに動きを止めて成り行きを見守るノエルと比べると、彼女の方が遥かに泰然として、成熟した心を持っているようにしか見えない。
見えないが、しかし事実として彼女が生まれたのはごくごく最近。そんな彼女に、こうして諭されてしまっては、流石に語気荒く叱りつけるような気も失せてしまう。
けれども、だからといって彼女達がやっている事を見逃すというのは難しかった。
純粋に、危険なのだ。これは彼女達の心意気や信用などでどうにかなるものではない。ノエルを保護する立場であるイェア――そして勝手ながら二人に対し保護者のような立場を自認していた【NAME】としても、おいそれと許可できるものではない。
――取り敢えず、二人だけでやるのは危険なので今後は止めるように。
そう【NAME】が通達すると、ノエルはがっくりと肩を落として丸まってしまう。ウィースルゥインは先刻ノエルの意気を強く代弁していたが、ノエル自身としてはどうやら大分心が折れていたらしい。
ノエルが己の力や素性についてあれこれと悩んでいたのは、多少なりとも知っている。それを思えば、ただやるなと、そう頭ごなしに禁じてしまうのは【NAME】としても望む事ではない。
――では、どういう筋で落とし所とするのが良いか。
【NAME】が腕を組んで続く言葉を考えていると、気づけば【NAME】の傍に居た筈のウィースルゥインがノエルの隣へと移動しており、耳元でこしょこしょと何かを吹き込んでいた。
訝しむ【NAME】の前で、何かを言われたノエルがふおお、と【NAME】の方を凝視しながら身を膨らませるように慌ててみせる。一体何言われたの……と不安になったが、しかしそうした妙な態度を見せたのも一瞬だ。
ノエルはウィースルゥインに一度頷きを見せてから、意を決した様子で【NAME】の方を向き直る。
「でしたら、【NAME】。わたしは、貴方に、お願いがあるのですが」
その目には強い逡巡がありながらも僅かな期待も混じっていて、思わず【NAME】は身構えてしまう。
「わたし達ふたりだけでは問題があるというのなら、次からは貴方に、わたし達の“勉強”を見てもらえれば、とわたしは思うのですが……」
「…………」
僅かに考えて、それで全く問題が無い事に気づく。冷静に考え直してみると自分の憤りも、イェアの心配も、全てはノエルが一人で暴走し、自分達の手が届かないところで致命的な事になるのを恐れていただけなのだ。問題があるとすれば、こんな深夜に起き出して付き合うのは辛いという程度の事だが。
「やっぱりイェアには心配を掛けたくないですから、知られないようにこの時間のまま続けたいのですけれど……」
――いや、イェアにはあからさまに怪しまれて滅茶苦茶心配を掛けているが。
「え。……えっ!?」
引きつった声を上げたノエルに、【NAME】はそもそも自分がここに来たのもイェアから相談を受けたからである事を話すと、ノエルの表情は殆ど泣きそうなまでに崩れてしまった。全く、表情豊かな娘になったものだと【NAME】は思わず笑ってしまう。
そんな彼女の横には、過去のノエルを思わせるような表情の薄い少女が、固まってしまったノエルの代わりに【NAME】に問うてくる。
「なら、この時間じゃなくても良いけれど……それなら【NAME】は、わたし達の“勉強”、一緒にしてくれるの?」
否という為の目立った理由はもう失せてしまった。
これまで無意識に込めていたらしい肩の力を抜くと、僅かな笑みと共に【NAME】が頷く。
「「――っ!!」」
すると、目の前では嬉しそうに顔を見合わせる微笑ましい少女が二人。その様子は――どちらが姉に見えるかは脇において――まるで歳近い姉妹のようにも見える。
彼女達の在り方からすれば当然なのかもしれないが、最初の出会いからの経緯も考えれば、良くもまぁここまで健全な関係になったものだと驚き半分納得半分。
――兎にも角にも、仲良きことは、美しきかな。
少しの面倒事が増えたが、決して無駄な事ではない。実際、ノエルがウィースルゥインの力を借りられるようになれば、大きな助けになるのは間違いないのだ。
「【NAME】、これから宜しくお願いしますねっ」
声を弾ませ、小さな笑みを見せる軍服の娘は、本当に、最初に出会った頃とは別人のようだった。
真なる楽園 識別の朝
――識別の朝──
芯海の東西に存在する二つの大陸を股に掛け、あらゆる土地を旅してきたという冒険家――ハマダン・オリオール。
彼ならば、ウィースルゥインのような特異な存在を相手にしても、比較的隔意無く受け止めてくれるのではないだろうか。また、似たような存在についての知識を持っているかも知れない。
【NAME】にとって、ウィースルゥインは直近の危機をもたらす存在とは思えなかったが、未知の集合であるのは確かだ。彼女自身意識せぬ災厄が、唐突にその身から生じる可能性もある。彼の幅広い知見を借りて、万象を身に宿す彼女についての何らかが知れるならば、有り難い話である。
そう考えた【NAME】は、彼とウィースルゥインの対面の場を設けることにしたのだ。
朝方。初対面の場所としてオリオールが選んだのは、軍陣地内に用意された彼用の天幕ではなく、陣地の外を出て暫く内陸側へ進んだ先。島の超常地形の一つである森――ナリア・バータ霧眩森林の境界付近という、中々に危険度の高い場所だった。
何故こんなところを選んだのか。問いに対するオリオールの返事は、
「まぁ、一番は用心、二番は適応の把握。こんな感じと思って貰えばいいよ」
二番目についてはいまいち理解しがたいが、一番目は判りやすい。
オリオールには当然、ウィースルゥインについての説明は一通り終えている。彼に求めているのは、より正確にウィースルゥインという存在を把握する為の意見だ。だからこそ、【NAME】は己が持つ情報を可能な限り彼に提供したつもりだった。
姿形は人間の少女ではあるが、それ以外の部分については全く以て人とは異なる、これまで【NAME】が出会ってきた者達の中でも際立って特殊な存在。一つでも危険と考え得る要素を複数併せ持ち、その中には鬼種――しかもただの鬼種ではなく、その最高位に近い大禍鬼の存在概念すらも内包する者。
客観的に考えれば、用心するのは当然である。むしろ、事情を知っても気味悪がらず、こうして顔合わせを承諾してくれるというだけでもマシというものだろう。少なくとも、オリオールはウィースルゥインを知ろうという姿勢を見せてくれている。それだけでも、事前に【NAME】が期待していたところは十分満たされていた。
ただ、この場所が用心に繋がるというのはどういう事なのか。
「それ程深い理由がある訳ではないがね。【NAME】から聞く限り、その子はかなり存在として不安定であるように思えたから、こうした土地概念に大きな歪みを持つ地形の近くであるならば、何をするにしろ使い出はあるかなと、その程度の話さ。逃げる際に使うも良し、反応を見るにも良し。……ま、大した事じゃない。単なるもしもの備えでしかないから、気にせず状況を進めてくれ。それで、肝心のウィースルゥイン嬢は何処に?」
問いに、【NAME】は少し時間を、と返してから、目を閉じ、内心で訴えかける。
ウィースルゥイン。地母の脈を継ぎ、人の身を持ちながら、翆獣の祝福すらも得た、古の禍々しき鬼。
彼女の存在は、出会った時から今に至る僅かな間に、少しづつであるが変化が生じている。最初の内は主にはノエルからの強い呼びかけに応じる形で、ノエルの直ぐ傍にて姿が生じるという流れだった。しかし今では、ノエルだけではなく【NAME】の呼びかけにも反応するようになっていた。
強く彼女の名を念じ、呼び出す意志を込めることで反応し、【NAME】の近くに出現する。この変化はウィースルゥイン曰く、「ずっとノエルだけ視えていたところに、【NAME】の事も視えるようになった」という事であるらしい。
何も無い暗闇の中で、ノエルという光を見つけて、その光が照らし出す世界を眺める。これが、まだ存在としては不安定であり、現世界から隔絶されている少女の普段の在り方だったのだが、そんな彼女の世界にもう一つ、小さな光が灯ったのだ。
ただし、ノエルという存在を経由せず、ウィースルゥインの感覚のみを通して視える【NAME】の姿はひどく朧で、見失うことも多いという。【NAME】が彼女を呼び出す場合は、ウィースルゥインが【NAME】の姿を捉え、尚且つそちらへと彼女が意識の焦点を向けていれば漸く繋がるという程度でしかなく、ノエルから呼び出す形と比べて精度はかなり低く、呼び掛けても全く反応が返ってこない時も多々あった。
これについては、そもそも【NAME】との間にある程度の繋がりが生じている事自体が異常だ、というのがイェアの見解だ。ウィースルゥインとノエルの間にある繋がりは、元々の彼女達――“天従”の大禍鬼とその“人形”という間柄だからこそのもので、【NAME】との間にそのような関係性は欠片も存在しないのだから。
なのに何故、【NAME】との間にも繋がりが生まれたのかといえば――ウィースルゥイン自身から、【NAME】へと向けられている関心の強さが全てなのではないか。「推測でしか語る事は出来ませんけれど」と前置いた上でのイェアの言であったが、それを聞いた当人が「そうかも」とあっさり返していた辺り、取り敢えずそういう事と納得する他無い。
要するに、現状【NAME】とウィースルゥインが僅かなりとも繋がっている事自体が既に奇跡的な結果であり、今後その精度が上がっていく可能性は薄いだろうという話である。もっともこれも、ウィースルゥインの知覚が今より広がっていけばまた大きく状況が変化するかもしれず、結局この先どうなるかは未知数という益体もない結論に落ち着くのだが、今現在、普通に【NAME】が彼女を呼び出した場合、成功率はせいぜいが三割程度だろう。
ただ今回は、オリオールとの対面の場を用意した上で、わざわざ現場にて彼女を呼び出すという方法を取っているのだ。ここで失敗するようでは話にならない訳で、
「待ってたよ。あなたが、私を呼んでくれるのを」
【NAME】の背後で、何かが生じる気配がした。
小さな声。振り向けば藍色に近い髪が大きくたなびいて、その奥にて少女の立ち姿が音もなく姿を現す。【NAME】の呼び掛けに応える形で、ウィースルゥインがこちらの世界にてその存在を確定させたのだ。
このあっさりとした召喚の成功には当然理由がある。単純な話だ。ウィースルゥインが、彼女の世界で【NAME】の姿を常に捉えるのは難しい。だから最初から決まった時間の間、自分を探して視ていてくれと伝えておいただけの話だ。ただその場合、彼女が最も好むノエルとの繋がりから意識を外さずを得ない為、あまり長時間お願いできるものでもないのだが、こうした約束の時間に呼び出すという形であるならば、十分に許容されるものだった。
もっとも、最初からノエルを経由するなり、あるいは事前に試行を繰り返して彼女を呼び出しておけば良いという話でもあるのだが、まずオリオールの方の準備を整えてから彼女を呼びたかった事に加えて、“後々の流れ”を考えて、今回はこの手法を取ることにしたのだ。
大きく広がった長い髪が纏まり、表情の薄い顔が【NAME】の方へと向けられる。
「おはよう、【NAME】。それで、私に会わせたいという人は、どなた?」
彼女にも、大まかに話は通してある。といってもオリオールに対してとは違い、彼女には単に会わせたい人が居るという程度しか伝えてはいないが。
ウィースルゥインは【NAME】の背後に出現した為、正面に居たオリオールは【NAME】の姿が壁となって見えないらしい。ウィースルゥインが表情を変えないまま、ひょこと身体を傾ける動きに合わせるように、オリオールの方も一つ咳払いを入れてから笑顔を作り、
「初めまして、お嬢さん。それは僕の事だよ、ウィースルゥイン嬢……で良いのかな?」
問いに、ウィースルゥインは上体を傾けたまま小さく頷く。
「そう。私の名前はウィースルゥイン。だから、そう呼んで」
「了解した。ではお返しに僕の自己紹介、といくべきなのだろうけれど……【NAME】から聞く限りでは、どうやら君はノエル・ガナッシュ嬢の知識や経験をそのまま受け継いでいるそうだね。なら、既に僕の事についても知っているのかな?」
笑顔を維持したままそう続けるオリオール。彼の言葉の意図は判りやすい。まずは【NAME】が提供した情報が正確であるのかどうかの判断を、実際に己の目で見て行おうというのだろう。このオリオールの言動は、偏見や伝聞に縛られない彼の流儀を示すものだ。【NAME】は素直に感心していたのだが、訊ねられたウィースルゥインの反応が何故か芳しくない。彼女は表情は変えないまま、じっと笑顔で固まるオリオールの顔を眺めた後、
「……判らない。おじさん、どなた?」
「あ、あれっ? というかおじさん!? まだそんな歳じゃないよ僕はっ!」
話が違うとばかりに狼狽えるオリオールに、抱いた感心が一発で吹き飛んだが、【NAME】からしてもウィースルゥインの返答は予想外で、驚いたように彼女を見るしかない。
オリオールはエルツァン島探索からの同行とはいえ、ノエルと共にアノーレでも幾度か顔を合わせた仲だ。ノエルの過去を知り、またエルツァン島でのあらゆる活動を眺めてきたウィースルゥインが判らないというのはどういう事か。
【NAME】が慌ててウィースルゥインに訊ねると、彼女は「……んー?」と眉根を寄せて、己の記憶を辿るように暫く動きを止めると、
「……思い出した。ノエルの撃った銃を変な避け方してた変なおじさん」
「酷いな!」
本当に酷かった。
ウィースルゥインは、嘆くオリオールと若干引いている【NAME】の様子を交互に見て、少し困ったように小首を傾げる。
「ん……。あまり強くなさそうなのに、なんだか偉そうで、なのに【NAME】やイェアも信用していて、だから少し好きじゃないみたいだけど、ノエルにとっては本当に、どうでもいいおじさんだったみたい。だから名前も、うまく出てこない。んん……ハマタ……ハンマダ?」
「ハマダン・オリオールだよ! あの子、僕の事をそんな風に捉えていたのかっ!? あとおじさんやめて!」
言われてみれば、ノエルとオリオールは殆ど接点が無かったか、と【NAME】は思い出す。
一応、ノエルがオリオールに言及するときは、ハマダン様などと敬称付けして呼んでいたような記憶はあるし、別段彼女がオリオールに何か思うところがある態度を取っていたようには見えなかったのだが、まさかこういう形でオリオールに対するノエルの心象が露呈する形になるとは。
とはいえ、あくまでこれはウィースルゥインという別個の人格を通して、過去のノエルの経験を思い返した際の感想。ノエルが無意識下でオリオールに対して抱いていた形のない印象を、ウィースルゥインが言葉として無理矢理拾い上げたものだろう。なので実際に、ウィースルゥインの言う通りの印象をノエルが持っていたかというと、また少し違ってくるのだろうが、
(あくまで“少し違う”程度……だよなぁ)
解釈の違いの範囲で収まってしまう辺りがやはり無情。そう感じずにはおれない【NAME】であった。
そんな行き違った始まりを見せたオリオールとウィースルゥインの初対面だったが、この程度の事で憤慨し、気分を害するオリオールではなく。直ぐさま気を取り直した彼は、改めてウィースルゥインに話しかけていく。
最初は当たり障りのない質問や現状確認。続けて少し踏み込んだ問いをしたかと思えば、まるで世間話のような話題を挟み、そこから相手の興味を惹くように自分の経験を絡めた話へと持っていく。ノエルを通してしか今の世を知らないウィースルゥインからしてみれば、オリオールの語る様々な旅の話はとても興味深いものだったのだろう。話が続くに従って、オリオールに対して見せていた何処か胡乱な様子は失われて、彼の話を熱心な様子で聞き入るようになっていた。
ただ、オリオールが気分良く己の冒険譚を語るのを、ただただウィースルゥインが聞くだけの場というのは、【NAME】が望んでいた形とは大分ズレている。それも当然オリオールは判っている筈で、つまりこの流れは、彼からの「もう終わっても良いよ」というサインだ。
【NAME】はオリオールの話が一段落するのを確認してから、そろそろ時間なのでこの辺りで一旦お開きにしようと伝える。
「時間?」
きょとんと首を傾げるウィースルゥインに、【NAME】は今日のオリオールとの対面の後にイェアとも会う約束をしている事を話した。
既にウィースルゥインはイェアと幾度か顔を合わせており、イェアからはウィースルゥインが知る様々な情報を聞き出すため、可能であればいつでも自分のところに連れてきて欲しいと頼まれている。今回もその一環としての約束だった。
ウィースルゥインが持つ情報は、エルツァン島を取り巻く特異な状況を把握する上で極めて重要なものであったが、ウィースルゥインの記憶の在り方は非常に複雑であり、その記憶を汲み取り解釈し言葉へと変える為の彼女の意識は未だ形を持って間も無い。故にウィースルゥインからの聞き取り作業は非常に根気が必要なものとなっており、得た情報の分析整理を兼ねた休憩を挟み、何度かに分けて行う事になっていた。
イェアとの聞き取り作業には、大抵ウィースルゥインをこちらへと呼び出した【NAME】かノエルが付き添う。慣例に従うならば【NAME】が彼女と共にイェアの所へ向かう形になるのだが、今回それは避けたかった。
【NAME】は少しオリオールと話したい事があるので、ウィースルゥインだけでイェアの元へと行ってくれないかと頼む。
「……んー」
対して、ウィースルゥインの反応は芳しくない。オリオールとの話を途中で遮られたのに加えて、一人でイェアのところに向かうというのは彼女にとってはあまり気が進むものではないのだろう。実際、イェアとウィースルゥインの会話は主にイェアがウィースルゥインに延々質問を続ける形になるので、彼女からすれば不快でこそないものの、あまり楽しいものではない。【NAME】やノエルが一緒にいるならばそれも許容出来るが、といったところなのだろう。
勿論、【NAME】にしてもこういう反応が返ってくるのは考慮の上だ。ノエルには話を通してあるので、彼女と合流して一緒にイェアのところへ向かってくれと頼む。また、その後のノエルの時間も余分に確保してあるので、休憩がてら彼女と遊ぶなり何なりしても構わない、とも。
「うん。それなら」
無表情の奥に僅かな喜色を滲ませて、ウィースルゥインは小さく頷くと、オリオールへ短く別れの挨拶をしてから、早速とばかりに身を翻して軍陣地の方へと消えていく。ふわりと、まるで風に乗る薄布のような身軽な動きで少女の姿が遠のき、そして霞むように薄らいでいった。
その様子を、【NAME】とオリオールは暫し無言で見送った。
「彼女、一人で行かせても大丈夫なのかい? 全く知らない兵士があの子を見つけたら、相当な騒ぎになりそうだけれども」
オリオールの疑問はもっともだが、【NAME】はその点は大丈夫と気軽に応える。
まず、今の彼女の存在は、まだこの世界においてはっきりと確立されていない。存在として未だあやふやさを残す彼女は、【NAME】やノエルが乞い、互いに存在を認識し合う事で現世界へと姿を現すが、しかしその姿が万人に認識出来るものなのかというと、そうではないのだ。
「……ああ、そんな事も言っていたな。確か、君かノエル嬢がその存在についてを示唆してみせないと、そもそも彼女を認識する事が出来ないと」
――より正確には、認識しづらいというだけではあるのだが。
何も知らない者が彼女の姿を捉えるのは難しいが、それにも個人差があり、特殊な才を持つ者や勘が鋭い者が見れば、偶然認識できたり、或いは幽霊を見たような感じで知覚できる場合もある。ただ、それについてもウィースルゥインの方が一切己の存在について気を払っていない場合に限った話で、彼女の方が望めば、【NAME】やノエルであってもその存在を認識するのが難しくなる程度に気配を消す――要するに、こちらの世界から己の姿を消すことも出来る。例え軍陣地の中に入り、兵士達の間を通っていったとしても然う然う気づかれるものではない。
そして更に言えば、彼女は“自分が兵士達に見つかっては問題がある”事を認識している。だから、大丈夫な筈だった。
【NAME】がそう言うと、オリオールは感心とも呆れともつかない笑みを浮かべて嘆息する。
「そういう所がまぁ、あの子の一番特別なところなのかもしれないな」
「……?」
どういう意味だろう。
【NAME】が視線だけで問うと、
「【NAME】、君が期待する通り、僕は人成らざる人……というか、まあ人の姿を取りながらその枠からは外れているような存在に出会った事は何度かある。例えばそうだね、人の姿を模して暮らす鬼だとか、或いは古の時代そのまま生きてきた亜人だとか。竜種と人の間の子や、他概念世界の住人と存在概念が混じり合ってしまった人、なんてのにも会った事はあるし、後は地母の眷属と深い縁を持った騎士……というのもこの範疇に入るのかな」
話しながら、オリオールは近場にあった折れ木の株によっこらせと腰を下ろす。
「色々な、特異な素性を持った連中と会ってきたけれど、彼等はその大抵が、自分という存在がどういう者なのかを客観的には認識出来てないか、或いは自分が今のこの世、人間社会に於いてどういう立ち位置にあるのかを上手く把握出来ていなかった。そもそも人間社会と接点を持たずに生きていたり、偶発的な結果そういう存在になってしまったりとかで、そうなるのも当然という場合も多かったけれどもね」
そんな中で、
「ウィースルゥイン。あの子の存在は僕がこれまで出会ってきた中でもそうは居ないくらいに特殊だ。あれ程に複雑な形を持っているのに、人の姿を保ち、人の心を保っていて、更にはそんな自分を冷静に俯瞰して認識し、取り巻く人々との関係性すらも相応に把握出来ているなんて。一つ一つを満たしていた人達はそれなりに居たけれど、これ程多くを満たしていた子は中々居なかった。あんな存在でありながら、自分を理解して、しっかりと人の社会を知り、それを踏まえて行動できるなんて子は、正に奇蹟の産物といってもいいかもしれないね」
そう語るオリオールの様子には、本心からの感心の気配があった。
ウィースルゥインは、その生い立ちからして極めて特殊な存在であるのは【NAME】も理解していたが、しかし彼女の心については、【NAME】はあまり意識していなかった。鬼、翆霊、地母、そして人間。それらが混ざり合った在り方は特別ではあったが、彼女が宿す精神については、少々突飛で表現が乏しいところはあるものの、あまり特別なところはないものだと。
そんな【NAME】の意見に、オリオールは「そう考えられるのは、本当に幸運だと思うよ」と苦笑いを浮かべる。
「特別ではないというのが特別だという話さ。正直言って、僕は彼女が現れてその姿を目にした瞬間、全力でこの場から逃げ出そうかと思ったよ。こんな一つ爆発すれば僕の命なんてあっさり消し飛ぶような存在を相手なんてしていられない、とね。さっき話している間も、足が震えて仕方無かった」
「…………」
純粋に驚いて、【NAME】はオリオールの顔をまじまじと見る。
彼がウィースルゥインと話していた時の様子を思い出す。いつも通りの平常な態度。敵意は見せず、むしろ好奇心が勝るような態度は、【NAME】が想像し期待していたそのままの彼で、【NAME】は流石オリオールと胸をなで下ろしていたのだが。
【NAME】が素直な感想を言うと、オリオールはおかしそうに軽く肩を揺らす。
「ははっ。まぁ、好奇心があったのは正解だがね。けれど恐怖や最大限の警戒をあの子に対して向けていたのも確かだよ。もし彼女が何らかの動きを見せるようであったなら、僕が持ちうるあらゆる技能を用いて対応するつもりだったし、ちゃんとその備えもしてあった。……といっても、所詮僕が出来る事なんて高が知れてるけれど」
オリオールがひょいと右手を振ると、指の間に袖口から転がり出た印章石達が挟まれる形で収まり、また手を振るとその石が消滅する。手品師のような器用さだった。あれが、彼の言うところの“備え”だったのだろう。
「別に、あの子に敵意があったわけじゃない。ただ、どのような動きを見せても、出来うる限りで対応できるようにしていただけさ。僕の経験則から行くと、彼女のような特別な存在を前にするならば、しておくべき心構えだったからね」
そんなオリオールの吐息混じりの言葉は、【NAME】が彼に対して期待していたものだ。
【NAME】が彼にウィースルゥインを会わせた理由。それは、彼の経験から、ウィースルゥインのような存在に対しての忌憚ない意見と知識を得ること。そして、ウィースルゥインと今後も支障ない関係を続けていく上での助言を貰うためだ。偏りのない姿勢を心がける、観察者としての視線を持つオリオールならば、参考になる話が聞ける、と。
改めて、オリオールにその趣旨を伝える。
「ん? ああ、あの子を一人でイェアのところに行かせたのも、彼女に直接聞かせ辛い事でも僕が言いやすいようにするためか」
訊ねられて、【NAME】は一応は、と返す。
ウィースルゥイン本人から聞いた情報から推測するに、現世界上に実体を持っていない時のウィースルゥインは、主にノエル、時には【NAME】の感覚と重なり、間借りするような形で現世界の状況を把握しているらしい。逆に実体を持った場合はあくまで実体が持つ五感が全てで、そういった感覚を間借りする力は大いに弱まるという。だから今回は取り敢えず【NAME】の方でウィースルゥインを呼び出した上で、ノエルを餌にして彼女をそちらへ釣り出した。この場にノエルを連れてこなかったのは、オリオールがよりウィースルゥインとの遣り取りに集中できるようにするための配慮だった。
「えらく気を回すものだ。それだけ、あの子の事が気に入っているのかい? 【NAME】」
言われて、【NAME】は首を捻る。
気に入っている、というよりも、彼女がどうにかうまくやっていけるようにしたいという、どこか責任感にも近いものが原動力のように思えた。
ウィースルゥインという、万象とも呼べる在り方を宿す少女が生まれた経緯。その断片が、過去の旅路の終着点で心に焼き付いたが故だろうか。
「まぁ、悪い事ではないさ。むしろ彼女のような存在にとって、導く手のあるなしは凄く重要な事だよ。それを自認する誰かがちゃんと居るならば……僕がこれまで経験したような、良くない結末からは少しは遠のけるかもしれない。僕が君に何か伝えられる事があるとするなら、そんな出来事についてくらいだろうか」
物騒な言葉に、【NAME】は反射的に身構える。
僅かに強張ったこちらの顔を見て、オリオールは「そこまで警戒はしなくていいよ」と言うが、しかしその顔には何処か苦みを伴う笑みが浮かんでいた。
「先刻言ったように、僕は過去に色々な……人とは違う人、というのが近いかな。人の姿はしているけれども、ちょっと違うところがある人々と会った事がある。勿論、ただ知っているだけだったり、一度会って話して終わりだったり、そんな程度の間柄でしかない人達も居たけれど、中にはそこそこに、関係を持った人達も居た」
ただまぁ、とオリオールはそこで小さく言葉を作り、間を挟む。
「……大体は、あまり良い結果、良い関係を生む事は出来なかったな。その形も、彼等の素性や環境によって違いはあるけれど、多くはすれ違い、認識の齟齬、後はそもそも、存在として異質である事からくる迫害や嫌悪。色々あったけれども、雑に纏めて言ってしまえば、異質な要素が周りとの対立を生んで、そして孤立し、人から離れるか、離される。そういう結末になる事が多かったように思う。……参考になるかは判らないけれども、その辺の事を、もう少し詳しく話してみようか」
続けてオリオールが語るのは、過去に彼が出会った異質な者達の結末だった。
鬼種として織り込まれた役目を放棄し、人の中に溶け込んで暮らそうとした者は、逆に鬼種の在り方を奉ずる異教の人の手により、堕落した者として刈り取られた。
竜種と人の間にて生まれ、深奥の森を守護していた部族の戦士は、竜の身体を求めるも竜にはなれず、人の心を求めるも人にはなれず、常に相反する己を愁い、その命を自らの手で絶った。
白天の翼を身に宿し黒狼と関わり得た娘は、運命の気まぐれで得た力を他者より敬われ、或いは恐れられ、それを嫌って人の世から距離を取った。
そして、
「多分、この話が【NAME】、君に一番聞かせた方が良いものかもしれない」
そうして彼が始めたのは、とある“人形”の話だった。
「僕の知人に学士が居てね。あるとき、彼女の所に冒険者が一人の人形を持ち込んだそうだ。それは文字通りの人形ではなくて、少し違う意味での人形――“芯なる時代”とか、ああいう古い時代のいつかに造られたような、所謂役目の為に造り出された、人の姿を持っているけれども人ではない何か、という意味での“人形”だ。その子は遺跡の奥で眠っていたのだけれど、目覚めたときに不具合か何かが起きたらしくてね。本体自体は問題は無かったそうだが、自分が造り出された役目も、本来なら植え付けられている筈の記憶も無く、身体を動かしたり他者と意思疎通を行うための基礎的な部分すらも存在しない、真っ新に近い状態だった」
そこで言葉を区切り、窺うようにこちらを見るオリオールの視線に、【NAME】は彼が何を言いたいのかを悟る。
――君も、それに似た存在を知っているだろう、と。
「人形を持ってきた冒険者も、持ってこられた学士も、どちらも人が良いものだから、その人形を放り出しもせず面倒を見始めた。学士は人形の事を調べ、不完全だった基礎的な機能を復旧させて、何も知らない人形に色々な事を教えて――」
どう表現すべきか。少しの迷いを経て、彼はこう続けた。
「――心の庭を造った、と言えば良いのかな。そして冒険者は人形を連れて旅をして、様々な体験をさせた。庭に光と水をやったのさ。最初は碌な受け答えもできず、本当に人形のようだったそれは、色々な事を吸収してそれを肥として、その庭に小さくても綺麗な花を咲かせた。……可愛いものだったよ。受け答えは幼子のようだったけれど、ちゃんと感情も見せるようなって、冒険者にも、学士にも、よく懐いていた」
「…………」
オリオールが語る話は、所々ウィースルゥインに繋がるところもあった。しかし大部分に於いて、探検家が出会ったという“人形”は、別の彼女も連想させるものだった。
だからこそ、話の続きを聞くのが、少し怖くなった。
「ただ、学士も、冒険者も。人形が生まれながらに定義されていた目的の部分を、あまり重要視していなかった。終わりから遡れば、これが最大の過ちだったのだろうね」
何故なら、これまでオリオールがしてくれた話は大抵、こうした幸福の情景の後に、その破綻が語られるからだ。
「彼等曰くその切っ掛け自体は偶然という話だったが、何れ起きるべきして起きた事であったと、そうも言っていたか。詳しくは知らないが、どうやらその人形は大勢の敵と戦う事を想定して造られたモノだったらしくてね。冒険者と同行していた際に巻き込まれた大きな戦闘で、眠っていた人形の“役目”の部分が目覚めてしまったそうだ。それからはもう、あっという間だ。僕も見ていたが、その子の中で育まれていた心が、凄まじい勢いで毟られ、刈り取られていった」
オリオールは今までしてきた話と同様、淡々とした調子で語る。それは自分が直に見てきたであろう過去の出来事に対して、何の感慨も抱いていないようでもあれば、一切の感傷を封じるために意識して取っている態度のようにも見えた。
「元々、その人形は戦闘に関する事のみで、頭の中の全てを満たすように設計されていたそうだ。人形として定められた本領が起動していなかった頃に、空いていた部分で造られた庭は、学士や冒険者、それに人形本人の懸命の努力も虚しく押し流されて、花が咲いていた痕跡すらも無くなった。後には本当に、ただ戦う為の人形が残ったそうだ」
そこで一度。オリオールは深々と吐息をつく。
「……この話の何が一番酷いかというとね。戦う事だけしか無くなった人形は、最終的には自分を目覚めさせ、ずっと可愛がってくれていた学士や冒険者の事すら思い出せなくなって、単なる駆逐すべき敵と認識するようになったって事だ。最後には冒険者が、己の手で暴走した人形の始末をつけたと、そう聞いたよ」
「…………」
口の中に苦い何かが広がるような錯覚を覚える。
本当に、嫌な話だ。彼女と境遇が全く同じという訳ではない。だから同じ結末を辿る訳ではない。けれども共通点は確かにあって、だからこそ連想してしまうのだ。もしかしたら、こうなるのかもしれないよ、と。
こちらの表情を見て、自分の言いたいことはしっかりと伝わってたと理解したのか。オリオールは口を少し歪めた顔で【NAME】を眺めて、
「後、この話で僕が君に示しておきたいのは、今ウィースルゥイン嬢には人らしき心があって、それによって力が律されているとはいえ、その心も己が存在の根源から来る衝動に対しては無意味であるかもしれない、という可能性だ。あの子を信じるな、とは言わないけれども、気をつける事だけは、忘れない方が良いと思うよ」
それについては、【NAME】も最初から判っていた事だ。大丈夫だと頷くと、オリオールの方も頷きを返してくれた。
「取り敢えず、僕の経験から話せる事はこんなところだろうか。……ただ、長々と語りはしたがね、これらは結局、僕が経験した話でしかない。君は、様々な事を経験した僕の知識を借りたいと、そういったけれども、一つこれだけは言っておきたいかな」
あくまで僕個人の考えだから、軽く聞き流す程度でも構わないけどね。
そう前置いて、しかしオリオールは少し身を正してから、真っ直ぐに【NAME】を見据えて告げる。
「――経験は、未来に備える助けになるけれど、選択の判断材料にはならない。多くの事を経験し、多くの現実を知る程に、それを元にして物事を判断する事は出来なくなる。知る事で、色々な出来事に対処出来るようにはなるけど、逆に何かを選ぶ事は難しくなるんだ」
「……?」
いまいち、理解が及ばない。
怪訝と見返すと、オリオールは更に言葉を続ける。
「何故なら、相反する現実がある事を――殆ど変わりのない条件であっても、ほんの少しの要因、人の目でなんて到底読め解けない何かが混ざるだけで、選択の結果が全く別のものになる事を知ってしまうからだ。例えば、僕が先刻話した、人の中に紛れて暮らしていた鬼種の話。今、僕がした話の中では、その子は人の手によって殺されたけれども、実は全く問題無く、人の社会の中で平穏に暮らし続けている鬼種が存在する事も、僕は知っている。上手く行かない現実ばかりの話をしたけれども、逆に上手く行った現実だって、確かに存在した筈なんだ。同じ選択をもう一度しても、少し何かの歯車がズレただけで、違う現実が顔を出すなんて平気で起きる。それくらい、この世はいい加減だって、僕は考えている。だから、君がするべきは――」
多くのものを見て来たからからこそ、どんな現実も起こり得る可能性はある。
身を以てそれを感じたのであろう探検家は、静かに、しかし力を込めて語る。
「――自分が望んだ未来へ至る為の判断をし、そして結果どういう終わりを迎えたとしても、悔やむ事がないよう心の中で始末を付けて欲しい。望むべきを識り、後悔には別れを告げる。勿論君も、そんな事は理解した上で僕に意見を求めたのだろうけれど、確認として、言わせて欲しい」
「…………」
彼の意気に呑まれて、【NAME】は思わず黙り込んでしまった。
そんなこちらの態度に、少し自分の語りが気恥ずかしくなったらしい。「やれやれ、僕も口煩くなったものだ」とオリオールは自嘲するように笑ってから、どっこいせと立ち上がる。
「これは確かに、おじさんと言われるのも仕方が無いのかもな。【NAME】は、どう思う?」
どうもこうも。
座るときにはよっこらしょ、立ち上がるときにはどっこいせと言い始めた時点で駄目ではないだろうか。
「……あー」
率直な感想にがっくりと身を折るオリオールを眺めながら、【NAME】はオリオールがしてくれた色々な話を、ゆっくりと頭の中で咀嚼する。
――望むべきを識り、後悔には別れを告げる、か。
ウィースルゥインに限らず、異質な在り方、不自然な在り方を持つ者には、やはりそれ故の歪みが何らかの形で現れる。オリオールの経験談は、その事を示唆してくれていた。
そして【NAME】が取るべきは、それをただ徒に避けようとして視野を狭くする事ではなく、まず自分が望む事を見据えて、そこへ辿り着けるように広く道を求め、後々に悔いを残さぬようにする事だ、とも。
「…………」
具体的な何かが見出せた訳ではない。けれども、こうしてオリオールに意見を求めたのは、決して悪い選択では無かった。
薄く掛かっていた靄が晴れて、今まで見ていなかったところへも視界が拓けていく感覚を得ながら、【NAME】はそれだけは確信する事が出来た。
真なる楽園 折合の昼
――折合の昼──
エルツァン島探索を取り巻く状況は、一つの契機によりゆっくりと、しかし大きな変化を見せつつあった。
積み重なった偶然の産物――奇蹟とも思える運命の巡りにより現れた万象の雛ウィースルゥインは、今後の探索を進める上では当然として、“鬼喰らいの鬼”討伐、更にはエルツァン島の秘密にも迫る、重要な要素になり得る存在だった。
だから【NAME】は少しづつ、彼女を軍部隊の上層に会わせる手筈を進めていた。可能であれば、明確な協力者として表に出せる程にまで彼女を馴染ませる事が出来れば、とも考えていた。
その一環として、まずは部隊を指揮するイェア、ノクトワイと彼女を引き合わせて少しずつ交流を深め、ウィースルゥインが持つ情報を彼女等に提供させる。それによる成果は確かで、最近イェアが延々と天幕に籠もり何事かの計画を裏で進めているらしいのも、恐らく彼女から多様な情報が齎された故の事だろう。
しかし、そんな風にウィースルゥインと他者との交流を促していた【NAME】だが、例外として彼女を出来るだけ近づけさせないようにしていた者達が居た。
常駐軍部隊が設営した陣地から少し離れた場所にて独自の野営陣を敷き、イェアからの要請を受ける形でエルツァン島の探索行を手伝う、フローリアの原住民達、キヴェンティの一団である。
彼等キヴェンティは、鬼種の撲滅を部族内の為来りとして長く受け継いできた者達だ。特に今回、エルツァン探索行に協力してくれたキヴェンティ達の長であるリゼラ・マオエ・キヴェンティは、その思想の急先鋒とも呼べる存在だ。四大遺跡事変の際には、封じられた鬼を命を賭して討つ事も辞さない程、鬼種の討伐に対して強い信念を持っていた。今回の参加については“女賢者”レェア・ガナッシュからの要請である部分も大きいのだろうが、“鬼喰らいの鬼”の跡を追うという部分も彼の判断に大きな影響を与えたのは明白だった。そして当然、彼の部下とも呼べる者達も、似たような考えを持つ者達が多いだろう、とも。
対し、ウィースルゥインは大禍鬼である。
勿論、彼女の在り方はこれまでの様々な経緯により、ただ単純に鬼であると言えるような存在ではなくなっている。むしろ表面上からは、鬼としての要素は殆ど見出す事が出来ない程だ。
しかし、彼女を構成する存在概念は確かに、鬼種の象徴とも言える陰性質の概念が不可分な形で存在している。ある面から見れば人であり、地母であり、翆霊であると同時に、やはり鬼としての形も残してはいるのだ。それも、かなりの比重を占めるものとして。
イェアの見立てによると、今のウィースルゥインという存在を大まかに表現するならば、命数尽きた地母と人の子を基礎として、強大な大禍鬼の存在概念をそこへ流し込み、それを命脈の力でもって繋ぎ合わせる事で一つの命の姿を成している、というものだった。
つまり、肉体や精神的な部分ではなく、あくまで概念的な視点で見るならば、ウィースルゥインはやはり、鬼としての要素が強い存在なのだ。
そしてキヴェンティ達は、島外からやってきた【NAME】達よりも、そうした概念的な性質を気取る力、特に鬼に関わるものに対し長ける者が多い。技法術式のような、汎用性を求めた体系的な力は持たないが、翆霊を始めとした彼等固有、彼等独自の能力を持ち、その事が一人一人の個性を伸ばすものに繋がっているが故、という部分もあるのだろう。
そんな彼等がウィースルゥインを見て、即鬼種と判断し刃を向けてくるという事も有り得ると考えれば、キヴェンティ達とウィースルゥインを出来る限り会わせないようにしていた自分の選択は間違ったものではないと、【NAME】は考えていた。
しかしそれは、間違いではないだろうが、恐らくは正解でもないのだ。
そうして逃げ続けていても、いつかは限界が来るだろう。勿論上手くやれば彼等とウィースルゥインを一度も会わせずに全てを済ます事は可能なのかもしれないが、偶発的な遭遇からの戦闘にでもなってしまえば、それで多くの事が終わってしまう。軍が鬼と協働している事実は、邪推や誤解の元になり得るだろう。それが軍とキヴェンティとの間に決定的な不和を齎す流れも、十分に予想出来た。
であるならばやはり、事前に話をつける――せめて、彼等の長に話を通しておくべきだ。
そう結論付けた【NAME】は、リゼラにこれまでの事情の大筋を伝え、彼女との面会の場を用意する事にした。
それが果たして、どのような結果に繋がるか。ある種の覚悟を、己の内で定めながら。
昼を過ぎた海辺の景色は、常とは異なる様相を見せていた。
空の徐々に覆い始めているのは、エルツァン島沿岸部では珍しい暗雲である。まだ雨の匂いはしないが、行き交う厚い雲の隙間から、時折稲光と、鈍く響く音が聞こえてくる。直ぐに、という事はないだろうが、恐らくは一刻程もすれば大粒の雨粒が視界を埋め尽くす事になるだろう。
エルツァン島に雨雲が訪れるのは、【NAME】がここへとやってきてから数える程しかない事だが、その全てで土砂降りの雨となっている。出来れば降り始める前に、用件を済ませておきたいところだった。
「【NAME】」
背後。小さな呼び声に、【NAME】は僅かに視線を向けて返事とする。
砂の浜から岩の浜へと変化していく間。半ば浮かぶような足どりでこちらの歩みについてくるのは、薄布を纏い、藍色にも近い長い髪を翻す少女だ。見上げてくる独特の光彩を持つ瞳には、目を合わせた【NAME】の顔が映っている。
「どこへ行くの? キヴェンティの人達が居るのは、あっちでしょ?」
今日の目的は既に彼女――ウィースルゥインに教えてある。ウィースルゥインは人の枠を大きく外れた存在であるが、しかし人格は人とあまり変わりなく、記憶も彼女と繋がりを持っていたノエルとほぼ同様のものを持っている。それ故、彼女自身が一度も足を運んだ事も、誰かから教えらた事もない筈のキヴェンティ達が居す位置を普通に把握しており、今【NAME】が向かっている場所が、キヴェンティ達が作った野営地とは別の場所である事も判っていた。
疑問に答えるのは簡単だ。別に隠していた訳でもない。単に、面会の相手であるところのリゼラが、別の場所を指定したからというだけの話である。
「? なら、どこに?」
更なる問いには、答える必要を感じなかった。もうすぐに、そこへと着くのだから。
前方に現れたそれは、巨大な岩だ。一体どういう縁でそこに転がる事になったのか。半ば地中に突き刺さる形で存在するその岩の大きさは、地上に出ている部分だけでも数メートルの高さを持っていた。そして大きな岩の頂点には、座して海を眺める一つの人影があった。
【NAME】とウィースルゥインが、岩の傍へと近付く。さて声を掛けるべきか、それとも岩の上へと上がるべきか。迷ったところで、姿勢良く胡座を組んでいた人影が、すくと立ち上がる。
「――来たか、【NAME】」
短く告げて、こちらへと振り向くのは面差しにまだ僅かな幼さを残す少年。エルツァン島探索に同行したキヴェンティ一団の長であり、マオエと呼ばれる氏族の若長ともされる、リゼラ・マオエ・キヴェンティだ。
日頃から厳しい気配を纏わせる少年だったが、今日は一段と、その気配を強くしていた。鋭い眼光が見下ろす先に、【NAME】の姿は既に無い。彼の視線は【NAME】の後ろに居る少女へと向けられていた。
少年は次の言葉も、身動きも生まず、暫し場を無言が支配する。
「…………」
この状況は、あまり宜しくない。【NAME】は息苦しさを感じて、取り敢えずそれを崩す事を考える。まずは取り敢えず、互いに自己紹介でもさせるべきか。
しかし、【NAME】が一歩前に進んで言葉を発しようとするのを、背後から袖引く動きが止めた。
振り返ると、ウィースルゥインがこちらを見上げて、小さく首を横に振る。
「いい。私がちゃんと話す」
彼女の言葉に驚いて思わず固まった【NAME】の横を、ふわりと一歩、軽い動きで少女の影が通り過ぎて、そして未だ岩上にて無言を保つ少年に、ウィースルゥインは小さく礼の姿勢を取る。
「こんにちは。そして、初めまして、リゼラ・マオエ・キヴェンティ。私の」
一瞬、少女の言葉が途切れた。
「私の名前は、ウィースルゥイン」
「――は」
それを聞いて、少年がようやく新たな動きを見せた。浅く、詰めていた息を吐き出すような笑い。続いて、彼の奥から険の気が増すのを感じた。
「ウィースルゥイン。天従の大禍。我を前にし、その名を己とするか、娘子よ。お前は我等キヴェンティが、如何なる使命をもって生きる民かを知らぬのも無理はないが――」
「ううん」
短く。
リゼラの言葉を、ウィースルゥインの声が遮った。
「知ってるの。杜人の方。あなた達がこの“古戦場”を護るために、そして残された鬼をことごとく斬るために、今まで生きてきた人達だって。そう、あなた自身が語ってくれたこと、私は知ってる」
リゼラの視線が、一瞬、【NAME】の方へと向く。その動きは、恐らく事前に【NAME】がリゼラに話しておいた、ウィースルゥインの現状を思い返した故の動きだろう。
彼女には、ノエル・ガナッシュとしての記憶がある。より正確には、彼女が正しく己の記憶として認識出来たものが、それしかない。だから、ノエルを通して経験したリゼラとの遣り取りも、ウィースルゥインはまるで己の体験であるように覚えているのだ。
ならば、と少年の視線がより鋭くなる。
「その上で大禍鬼の名を語るとするなら、お前は我が刃にて崩じ滅される為にここへとやってきたのか。であれば今すぐ、その望みを叶えてやるが」
少年の手が、腰に吊された二本の剣の内の一本に伸びる。鍔際から鳴る硬質の音に一触即発の気配を感じ、慌てて【NAME】が間に入ろうとするが、
「違うの」
曇りも怯みもない明確な否定は、その【NAME】の動きすらも止めてしまった。
「この私の名前は、今の私を示すための言葉。【NAME】が、私を私なのだと記してくれた言葉。あなたが言うように、これは昔の私、鬼だった私が持っていた名前だけど、今の私にとっては違う。だから、あなたがどう感じたって、私はこれが私の名前だって言う事を、やめたりなんかしない」
もし止めてしまえば、多分、きっと。
「あなたが本当に斬らないといけない私になってしまうから」
「…………」
そこで言葉を切り、殺気すらも孕んだ睨むようなリゼラの視線を、ウィースルゥインは微動だにせず受け止め続ける。もう、【NAME】が間に入っていけるような空気では無く、ウィースルゥインの言葉に、リゼラがどのような反応を返すかが全てだった。
一拍、二拍と時が過ぎ、海の向こうから湿り気を含んだ強い風が一度吹いて、収まる頃。
「お前自身の心根が如何なるものか。それを示そうとする意気は、確かに伝わった」
少年が放っていた鬼気が、まるで演技であったかのようにすっと引いたのだ。
そして、とん、とリゼラの足裏が岩肌を蹴る。小さな動き。しかし少年の身体はふわりと空中を舞い、【NAME】達の前方、大凡5メートル程の間を開けて着地した。
続けて彼は、大きく両の足を前後に開くと、重心を前に、深く身を伏せた姿勢を取った。そして両の手、片方は剣の鞘に、片方は剣の柄へと伸びていく。
「ならば次へと移ろう」
それは剣を抜き放ち、相手を断ち斬るための構えだ。先刻まで少年が見せていた険の気配は失せたままだが、しかしリゼラが見据え、刃の矛先としているのは明らかにウィースルゥインだった。
少年が身を更に縮め、身体に力と発条を溜め込んでいるのが判る。鞘と刃の間からは独特の光彩、翠を思わせる輝きが、たなびくように漏れ出しているのが見える。単なる斬撃、彼が普段行う高速の連斬ではなく、概念存在などを相手する際に時折用いる、命脈の力を引き出して敵を撃つ力とする技の前兆だった。
間に割って入るべきか。逡巡する【NAME】に、リゼラがちらりと目を向ける。
「【NAME】、以前お前は我に訊ねたな。彼の翁が求めた結末。それが目の前に現れたなら如何にするか、と」
「…………」
言われて、思い出す。今居るこの場所で、過去に彼と行った遣り取り。その最後にて自分が彼に行った問いが、【NAME】の脳裏に過ぎる。
確かあの時。リゼラは、このような事を言っていたか。
――己自身の目で、その在り方を正しく見極め、そしてどうするのかを定める、と。
【NAME】の呟きに、リゼラは「然り」と返し、
「眼では見せて貰った。言葉でも見せて貰った。では最後に、我が手で――いや、我に授けられた翆なる力を以てして、其奴が如何様な娘であるのか。見極め、定めてやろう」
そして少年は改めてウィースルゥインへと視線を戻し、
「行くぞ娘子? 神妙にせよ」
「どうぞ、杜人の方」
対して、ウィースルゥインの方はあっさりと返す。あまりの無警戒な態度に、【NAME】はウィースルゥインが状況を認識出来ていないのかと思わず彼女の顔を覗き込むが、それよりも早く、リゼラの方が動いた。
刹那、空から強烈な光が走った。もう真上までやってきた雲から雷が生じたのだ。陽を遮られて薄く翳っていた周囲を一瞬、白色の光が埋めて視界を焼く中。リゼラの一連の行動と結果を【NAME】は辛うじてその眼に捉える。
そして雷による視界の焼き付きが収まる頃には、リゼラは既に5メートルという距離を縮め、長剣を鞘から大きく抜き放った姿勢で静止していた。
ごろごろと腹に響く雷音が尾を引くように轟く中、【NAME】は起きた状況を再認識する。
刃を放った少年は、ウィースルゥインとの距離をたった一度の踏み込みで大きく詰めてはいたが、しかし、刃の切っ先が届くまでには至っていなかった。彼が鞘より走らせた剣先は、ウィースルゥインより手前、大凡掌の間を空けた空間を斬り上げる形で裂いただけだった。
しかし、リゼラが放とうとしていた剣撃は、単なる刃で斬るだけのものではない。剣に纏わせたのは世界の基盤、この世の生命の根源ともいう力だ。それを放ち、存在を打ち据える事で敵を滅ぼす。彼が剣にその力を通すだけで、触れた異質な存在は爆発するように吹き飛ぶのを幾度か見た事はあったが、今回は通すだけではなく、溜め込んだ力を無形の奔流としてウィースルゥインに放ったのだ。
白色に染まる視界の中、鞘に溜め込まれていた翠色の力は、剣という封を抜かれ、刃の流れに誘われるようにして、正面で身動ぎも見せずに立つ少女に叩き付けられた。その様は、桶に汲んだ水をぶちまけるかのような激しさで、少女の姿は翠色の爆発に呑み込まれて一瞬完全に見えなくなる程だった。
しかし、雷による白色と命脈の力による翠色。場に走った二つの閃光が消えた後には、
「…………」
全身を仄かな翠色に輝かせたウィースルゥインが、五体満足どころか傷一つすらないまま、ぼんやりと立っていた。
ウィースルゥインは自分の身体が薄く放つ発光を不思議そうに見下ろしていたが、眼前、リゼラが振り切った刃を鞘に収め、残心を解く様子に気づき、顔を上げる。
姿勢を戻す少年からは、全てを終えたと、そんな気配が漂っていた。
「もういいの?」
ウィースルゥインの問いに、リゼラは言葉も無く、頷きだけで返す。
「これで、あなたには私が判ったの? 私だって、まだ全部が見えてない、私の事」
「お前が己自身の中に何を見出そうとしているのかは知らぬが、我が求むる事は知れた。だから終わりだ」
――今の行動で、一体何が?
【NAME】が問うと、リゼラは「簡単な話だ」と呟き、
「我が見極めねばならぬ事はただ一つ。この娘が斬るべき存在か否か。それのみだ。故に我は、我等が我等たる源の力を用いて、その娘の在り方を問うただけの事。命脈の力を受けて、滅びるか綻びを生むようならば、此奴はこの世の命として正しくはない者と定め、全く斬り断つつもりであった。――だが」
リゼラの視線がウィースルゥインの姿を眇めて捉え、【NAME】も彼女を見る。
彼女の全身から放たれる翠色の輝きは、先刻リゼラが練り上げていたものとは違い激しさはなく、ただウィースルゥインの身体を包み込み、護るような優しく穏やかな気配を持っていた。
「命の脈が不安定な地という事もあるが、我が“孔”より導きし翆なる力、それに屈するどころか拒みすらせず、逆に受け入れ取り込み、己のものとして従えて見せた。その身に宿す祝福は、翆なる獣の僕たる我等キヴェンティが授けられたものよりも純粋で強い。単なる呪いにより縛られ得た繋がりではこうは行くまいよ。……つまりこの娘は、我等が主たる存在に対し、我等よりも近しい場所に居るのだと、そういう事だ」
そう締めくくったリゼラの声には、普段の覇気が欠けているように思えたが、それも彼の言が本当であるなら判らない話ではない、と【NAME】は同情する。要するに、ウィースルゥインの方が、自分達が敬い奉る存在に好かれている、という話なのだから。
しかし、ウィースルゥイン当人としてはその辺りの事は今ひとつ把握出来ないままであるらしい。彼女は僅かに首を傾げるだけで、ただただ自分の望む事を伝える。
「良く判らないけれど、あなたは、私と、仲良くはしてくれるの? それとも、やっぱり嫌いなまま?」
「……仲良くする理由が見渡らぬ。そもそも好悪について語った記憶は無いが」
そう言いながらも、態度からは厭気が滲み出てみて、リゼラにしては珍しい態度だと【NAME】は内心思う。
と、そんな心の動きを見透かされたのか、彼は「それより」と鋭い視線を【NAME】の方へと向けた。
「【NAME】よ。お前からの頼み、全く受け入れよう」
苦々しい態度を隠さず、リゼラはそう告げる。
彼の言う頼みとは、事前に【NAME】がリゼラに対して要請していた、ウィースルゥインという存在をキヴェンティ達の内で周知させ、問題無く許容されるための手回しだ。長たるリゼラの触れがあれば、スムーズに事が進むと考えての依頼だった。
リゼラのその答えに、【NAME】は深々と安堵の吐息をつく。ウィースルゥインを助力者として迎えるにおいて、もっとも対処が難しいと考えていたのがこの点だったのだ。リゼラが認め、許容してくれたという事実は、最難関を無事に越えた事を意味する。
しかし、本当に良いのかと【NAME】は改めて訊ねてしまう。リゼラが鬼種の討滅に対して並々ならぬものを持っているのは、これまでの付き合いからはっきりと感じていたからだ。今のウィースルゥインは全く純粋な鬼種ではないとはいえ、鬼としての要素を確かに残した存在であるのは否定できない事実なのだ。
だが、
「良いも悪いもあるものか。是非もないとは、正にこの事よ。……【NAME】、お前は少し、我の事を見誤ってはおらぬか?」
リゼラの返答は、少し想像とは違ったものだった。
「お前が懸念するように、我はこれまで鬼を斬る事を一とする態度を取ってきていた。が、それはあくまで、我等キヴェンティに定められた役目であるからだ。我は鬼を斬る事自体を、絶対としているのではない。我等に授けられた使命、延いては我等の祖を生んだ翆獣たる主の意志を、大事としているのだ」
「…………」
彼の言葉に対し、ああ、と【NAME】は素直に得心する。
その理屈であるならば、今、翠色の輝きに満ちた姿で立つウィースルゥインの存在は。
「この娘子は、“迷の民”の祈りにより導かれたものとはいえ、我等が主が認め、我等以上の繋がりを以て在る者だ。ならばこれを斬ると判ずる者こそが、翆獣の僕としては許されざる者となるだろう」
片方の手を耳元にやりながら、頭痛を堪えるような顔つきで、リゼラは深々と嘆息を吐く。口ではそう言いながらも、ウィースルゥインを見るリゼラの眼は恨めしげだった。少年の視線を受けて、先刻リゼラに刃を向けられた時には微塵の変化も見せなかったウィースルゥインの顔が、少し怯んだように歪んだ。
「なんで、そんなに嫌なの? 私、あなたに何もしてない。それに、ノエルもあなたとの事、気にしてた。あなたから、疎まれてるって。だから私も、あなたに嫌われると気になる」
拗ねたような困ったような言葉に、リゼラは苦い顔のまま唸る。
「諄い。別にお前を嫌っている訳では断じてないし、あの器の娘とて同様だ。寧ろあの娘に関しては、気を配っているというのが正確なところだ」
「なら、何故?」
続けて問う少女に、【NAME】も確かに、と助け船を出した。リゼラがウィースルゥインに見せる態度は、【NAME】からしても彼の言葉とは多くのズレがあるように見えた。その理由については、やはり少し聞いておきたい。
だが、リゼラとしても誤魔化しているという訳ではないらしい。どう言えば伝わるかと、少し言葉を選ぶように間を置き、
「此奴自体に思う所がある訳ではない。ただ、此奴の事を考えると、様々な面倒事が頭を過ぎるというだけの話だ」
――面倒事?
鸚鵡返しに呟くと、少年は短く頷く。
「然り。我等キヴェンティから見れば、この娘は忌子どころか、神子にすらなり得る存在だ。その内面に、役目とは相反する鬼の因子を残すというのにな。例えば、キヴェンティとしての己を未だ確固として持てておらぬ未熟者からすれば、この娘の在り方は迷いの元でしかないだろう。それらを正し導き、律するのが長の務めとはいえ、大事を前にして、そのような事に気を回さねばならぬのは、煩わしいという他なかろう」
成る程、と【NAME】は頷く。実感を伴うかは別として、彼がどういう事情で今のような態度になっているのかは判った。
判ったが、しかしこの話でウィースルゥインが納得するかというと、それはまた別の話であり、
「それなら、私と、仲良くしてもいいと思う。あなたの事、私に見せてくれても良いと思う」
「断る。言ったであろうが。仲良くする理由が見出せぬと。【NAME】よ、お前が相手をしてやれ」
「【NAME】は、一杯相手してくれてる。ノエルも」
「ならばそれで満足せよ。我を巻き込むな」
「うー。もっと、見える人達の事、知りたいのに」
不満げな声を上げるが、しかしそれ以上の踏み込みは諦めたようだった。
それを見届けて、リゼラはようやく解放されたとばかりに深々と吐息をつく。
「……全く、あの翁も厄介な土産を残していったものだ。死してなお、我らにあれ程手間を掛けさせた上で、更にこのような娘子を置いていくとはな……」
実感が籠もった声音で独り言のように呟いてから、彼は【NAME】の方へと向き直ると、
「【NAME】よ。改めて、お前の頼みは聞き届けた。キヴェンティの内については、我が責任を持って、そこな娘を受け入れられるように手を打っておく。故にお前は、お前が出来る事を、憂い無くこなすといい」
同時にそれが、彼にとっての別れの挨拶でもあったのだろう。
リゼラは【NAME】達の隣を通り過ぎると、後はもう振り返る事も無く。島の岸辺と超常地形の狭間に設けられたキヴェンティ達の野営地へと歩いていった。
「あの人の事、もっと良く、知りたかったけど」
ウィースルゥインは少ししょんぼりとした様子だった。
この少女が、他者にこうも明確な接触を望むのは、案外珍しい。相応の好奇心はあるが知っていたが、それはノエルや【NAME】という存在を経由して発露される場合が多く、例外はイェアくらいのものだったのだが。
【NAME】が何気なくそういうと、ウィースルゥインは【NAME】を見上げて、
「ノエルが、時々気にしていたから。あの人は、“先生”と一緒に居る事が多かったでしょ。だから」
「……ああ」
成る程、と納得する。
ノエルにとってガナッシュの姉妹は親にも等しい存在で、リゼラはその片側と親しい。
だからノエルはリゼラの事を多少なりと意識しており、それがウィースルゥインにも移った結果が、彼女のリゼラに対する興味に繋がっていたと、そういう話だ。
残念ながら、リゼラとウィースルゥインの交流は失敗に近い終わりになってしまったが、リゼラがウィースルゥインを許容し、キヴェンティ達に働きかけてくれるようにするという【NAME】が当初に抱いていた目的は、無事達成する事が出来たのだから、今回の会合自体は成功といっても良いだろう。
「次に会ったら、もう少し、お話しできるかな……」
んー、と考え込むウィースルゥイン。どうやら、あれだけリゼラに拒絶された後だというのに、全く堪えていないらしい。
次は正真正銘、リゼラと彼女の間を取り持つ為の場を用意してあげるのも良いかもしれない。純粋な善意という部分も勿論あるが、リゼラがああいう態度を露骨に見せるというのが珍しく、面白いというのもあるし。
ウィースルゥインの事をこちらに丸投げするつもりらしいリゼラに対し、仕返しとも言えるような事を考えながら。【NAME】はウィースルゥインを連れて、帰路に着く。
既に空は曇天。
ごろごろと唸るような音が鳴る頻度も増えている。雨が降り出す前に、さっさと軍陣地に戻るとしよう。
真なる楽園 愛顧の夕
――愛顧の夕──
「ノクトワイ先生のぉー! ウィースルゥインちゃん着せ替え教室っ! 開っ! 催っ! withノエルちゃんっ!」
「わー」
「…………」
口髭を綺麗に伸ばした美丈夫(自称)の熱いシャウトに対し、少女が二人。ぱちぱちと手を叩く方と、恐ろしいまでの無表情で微動だにしない方という、対照的な反応を見せていた。
何だろうこの空気。その間に挟まる形で立っていた【NAME】はリアクションに困り、口元を横に引きつらせながら無言を保つ。
場所は常駐軍陣地の中央部付近に立てられた大天幕の一つ。主に、衣料品関係を収めた物置として扱われている所である。普段は兵站係が時折やってきては必要なものを引っ張り出す以外に訪れる者は殆ど居ない場所なのだが、今日はなんと四人もその天幕にやってきていた。
何をしに来たのかと言えば、それ程深く語る事もない話である。先刻のノクトワイの宣言通りの事をやりに来ただけだった。
事の発端については長くなるかもしれないので、中点を挟んで語る事にする。
ウィースルゥインとノエルを連れてノクトワイのところで世間話をしていたら、二人の服装が味気ないとノクトワイが突然ご立腹。
オンナの子ならオサレよオサレ! という流れから、なんやかんやでこうなった。
短かめで済んだ。日頃からこれくらいの量でまとめたいところである。
因みに、衣料品物置として使われている大天幕に居るのだが、ここに置かれている服自体は使わない。フェイントだった。
正確には、最初は「けれども服がぁーっ! 少女用の服がないのよぉーっ! なんでもってこなかったのアタシぃーっ!」とノクトワイがくねくね懊悩し始め、終いには妙な唸り声を上げながらほっほっと左右に反復横跳びしだし、それを見たウィースルゥインが新手の遊びなのかと不思議な顔をしながら後ろで真似する様子を【NAME】とノエルは気味悪がりながら眺めていたのだが、そうした謎アクションに飽きたノクトワイが次に取った行動が、この天幕への移動だった。
恐らくは支給用衣料の保管庫代わりとなっていたここならば、オサレな服の一着や二着くらいあんだろという雑な思考の元に【NAME】達を引っ張って移動したのだろうが、冷静に考えれば軍隊用の支給衣服が突っ込まれているだけの場所である。似たようなデザインの味気ない服や造りの荒い下着、靴や手袋に防寒具などがあるだけで、到底ノクトワイのファッソン精神を満たしオサレパワーを迸らせるようなものは置いている訳が無かった。
早々の企画倒れな雰囲気濃厚となった着せ替え教室であったが、案外口髭のおっさんは折れなかった。流石自前で幼女用の衣服を取りそろえていると口走るほどの熱意溢れる漢だけある。彼は溢れるバイセクシャルコミュニケーションを全力で用いて、数少ない女性兵士達のところから彼女等がぽつぽつと持ち込んでいた私物を借り受け、更には一部の特殊な男性兵士の方々からも幾つかの用途不明なアイテムを強奪し、この天幕の中にそれなりなオサレアイテムを取りそろえてしまったのだ。
当然ながら、そんな大仕事を行ったのだから、時間は相応に過ぎていた。【NAME】達がノクトワイの元を訪ねたのが昼前だったのだが、今はもう夕暮れも近づき、陣地内は夕食の準備で皆がそわそわし始めるような時刻である。その間、【NAME】達は何もやることなく天幕の中でぼんやりと待っているだけで退屈この上なかったのだが、しかしノクトワイに付き添おうかと提案しても彼に強行に拒否され、しかしなら帰ると言っても今度は泣いて止められたため、我慢して時間を過ごすしか無かった。
これでノクトワイがかき集めてきた自称オサレアイテムが見ていて頭が痛くなるような悪趣味なものだったなら、本当に今日という日は何だったのかと自問しつつ終える事になったのだが――。
「はい、次出来たわよーん。どぉ? どぉよこれ?」
仕切りを払い、奥から出てきたのは、背中が大きく開いたドレスを纏った少女だ。
「…………」
細身の身体を彩るのは白色の絹布。袖口には豊かなひだが設けられて、よくよくみれば至る所に細やかな刺繍が施されている。素材や装飾自体は質素だが、しかし丁寧かつ繊細な仕事で造られた良品であることは【NAME】にも直ぐに判った。
よくこんなものを、どうなるかも判らない秘島探査の旅に持ってきたものだ。そう驚きの感想を漏らす【NAME】に、ノクトワイは深々と嘆きの吐息をついた。
「【NAME】ーっ。そこは違うでしょ! ここは、ノエルのかわいさを全力で褒めるとこよん! ほらほら、こんなにかわいいのにっ! 見なさいよこのうなじっ! 普段と比べて色気五割増しくらいになってんでしょっ!? あと背中、ほれずびゃーっとっ!」
「――っ!」
両肩持たれてぐるりと反転。背中をこちらへ見せる形になったノエルの、腰辺りから首筋までが丸々【NAME】の前に晒される。ひう、とノエルが喉奥から妙な音を立てて、むき出しになった肌がほんのりと赤く染まっていくのが判る。
「綺麗。あと大胆」
そう短く評したのは、【NAME】の横に座っていたウィースルゥインだ。こちらはこちらで着飾っているが、今ノエルが着ているものとは違い、もっと幼児趣味的な色合いが強い、子供らしいものだ。編み込んで飾った髪も愛らしさをアピールする方向性で、ウィースルゥインが本来持っている神秘性などが大きく減じているかわりに、これはこれで独特な魅力のようなものを放っている。
「んふふ。でしょーっ? まぁ、ノエルちゃんはちょっと肉付きが薄いから腰とかアレとかアソコとかちょいちょい手を加えてあげないとダメだけど、元は良いからねぇ、なんというか、盛りがいがあるというか」
「やめっ! そういう事言うの、止めて下さいっ!」
わたわたと慌てるノエルの顔は、先刻は僅かに赤みがかる程度だったのが、今はもう耳まで赤くなっている。その様子をくすくすと楽しげに見守り、
「ほら、ウィーちゃん。あなたもこっち、おいでなさいな。二人で並ぶと、また映えるわよん」
「そうなの?」
「ええ。アタシにオサレになった二人のカワユイところ、見せて欲しいわねん」
「判った」
ふわりとウィースルゥインが移動して、ノエルの背中に抱きつくように絡まる。
ノエルの衣装がシンプルで白色であるのに対し、ウィースルゥインが今着ている衣装は豪華で黒色。それが並ぶことで対比として一つの形になる。
元々、手当たり次第に集めてきた服の一つである筈なのに、こうしてまるで対のものであるかのように見せる手腕は、確かにオサレの先生を自称するだけある。【NAME】は呆れと感心が混じった感情で、隣にやってきたノクトワイを見上げる。二人を見る彼の表情はとても満足げで、心なしか肌もつやつやしていた。本当にこのオッサンはどうしようもないな、と【NAME】は身も蓋も無い感想を抱きながら吐息をつく。
そうする間に、着飾った二人は、広い天幕の中央で手を取り合って、拙いダンスを踊り始める。
簡単なステップ。簡単なスナップ。
それを少し離れた位置で眺め、「イイっ! イイわっ!」と身体をぐねんぐねん捻って悶えていたノクトワイだったが、
「――で、実際の所どーする気なの? あの子」
と、唐突に素のテンションで聞いてきた。
一瞬戸惑い、しかし直ぐに気を取り直す。誰のことを問うているのかは判る。ウィースルゥインについてだ。
どうするも、放っておく訳にはいかないから取り敢えず目の届く範囲にいてもらっている、と答える。多くの異質を備えた異形。【NAME】達が見逃し、或いは取りこぼしてきた出来事を記憶する者。恐らく、彼女という存在は、自分達の目的を達成する上で大きな鍵となる筈だ。しかし、どう扱うかと問われると、正直困る。助力者として有用であるのは間違いないが、果たしてそう扱っても良いのか。特に彼女が持つ力については、危険性の方が先につく故の戸惑いがあった。
そんな【NAME】の答えを聞いて、ノクトワイは少しの間無言。困ったように頭を掻いて、彼はこう言った。
「もう少し、ちゃんと考えてあげたほうがいいわよん。面倒みて、守ってあげるならそうする。出来ないなら、ちゃんとアナタが、始末を付ける」
「…………」
――始末。
ノクトワイが言わんとしている事は理解出来る、のだが。
「一番やっちゃダメなのは、放り捨てる事。それは、判ってるわよねん?」
それは勿論の事だった。
仏頂面で頷く【NAME】に、ノクトワイはふふんと髭を揺らす。
「なら結構。それが判ってるなら、後はしっかりゆっくり考えなさいな」
言って、ノクトワイはぽん、と肩を叩いて話を終わらせると、ウィースルゥイン達の方へと絡みに行く。
彼女達二人をからかうように、気軽に話しかけるノクトワイからは、先刻【NAME】に一瞬見せた厳しい様子は微塵もない。その切り替えの鮮やかさは流石だが、食えない男という印象も同時に強くなった。
そんな【NAME】の視線に気づいて、ノクトワイはにやりと笑みを浮かべて振り返ると、
「ほら、【NAME】ーっ! アナタ、結局二人の服の感想、言ってあげてないじゃないの! この子達待ってるから、ちゃんと聞かせてあげなさいな!」
「…………」
プレッシャーの掛かるフリをしてくれる。一瞬恨めしげな視線をノクトワイへと向けたが、しかし彼の隣でこちらを見る二人の様子に、意識が直ぐに持って行かれる。
慣れない服を着て慣れない表情でこちらを見るノエルと、表情は薄いながらも期待感を乗せて窺うような視線を向けるウィースルゥイン。
――さて、どういう言葉を贈るべきか。
色々な事を考えながら、【NAME】は彼女達の傍へと近付いていった。
真なる楽園 決断の夜
――決断の夜──
その夜。
【NAME】がイェア・ガナッシュの天幕を訪れると、そこには二人の先客が居た。
「【NAME】?」
軍服の娘と、薄布の少女。ノエルと、そしてウィースルゥインである。
二人は普段イェアが事務に使っている長机の前に椅子を並べて座っており、やってきた【NAME】に気づいて振り返る。
「あら、いらっしゃいませ、【NAME】さん」
そしてその奥、机を挟んだ対面では、白衣を纏った学士、この天幕の主であるイェアが笑みを浮かべて立ち上がるのが見えた。
「【NAME】さんが来たという事は、結構時間経ってたんですのね。――と、ああ、ノエルとウィーちゃんは今日も長々と付き合わせてしまいましたし、もう解放しますわね。ありがとう、二人とも」
感謝の言葉に、ノエルは表情を少し曇らせて僅かに首を横に振る。
「いえ、わたし達の方こそ、イェアにうまく伝えられなくて、申し訳ありませんでした。もう何度もやってる事なのに、慣れなくて」
「それについては仕方ありませんわよ。特にウィーちゃんの方は、こうして会話して、意思疎通が出来るだけでも凄い事なんですから。ねぇ、ウィーちゃん?」
「……?」
イェアからにこやかに声を掛けられたウィースルゥインだが、しかし一瞬戸惑ったように動きを止めた。
「……ああ、うん。……そうかな?」
少しの間を置いて、何かに気づいたようにぎこちない声を出し、その後でようやく返事する。
因みに、ウィーちゃんとはウィースルゥインの愛称である。元はノクトワイが提唱したもので、それを気に入ったイェアも好んで使っているのだが、ウィースルゥイン本人はこの愛称をあまり気に入ってはいない。より正確に表現すると、そもそも自分が呼ばれていると認識する事が難しいようだった。先程のイェアからの問いに対して反応が鈍かったのも、その辺りに起因している。
ウィースルゥイン、という言葉を、彼女は今の己を示す名と定義した。
それは一般的な“名付け”とは少し方向性が異なる。他者が個を示すためのものではなく、本人が個を明らかにするためのもの。ウィースルゥインは自分の在り方を名という形によって定める事で、不安定で不確かな己の拠り所としているのだ。
だから、愛称という文化にはいまいち馴染めないのも当然の話だった。それを認める事は、定めた己の揺らぎにも繋がりかねないからだ。
勿論、イェアの方もそれを理解しているのだが、改める気はないようだった。
理由は明快で、ウィーちゃんの方がかわいくて呼びやすいのと、こうした大雑把な遣り取りを許容し行えるようになる事が、彼女の精神の成長にも繋がる、との考えからだという。
自己の確立は当然出来るものとして、そこから凝り固まらず、広い視野を持てるように。
生まれたばかりと言っても良い彼女に課すには、少々ハードルの高い要求であるように思えたが、間違いだと断ずる程でもなく。【NAME】は傍観という形で、彼女等の遣り取りを見守っていた。
「では、わたし達は帰ろうと思います。行きましょう、ウィースルゥイン」
「ん」
ノエルの促しに、ウィースルゥインも素直に頷いて立ち上がる。
だが、そう言った筈のノエルが動き出さずに、何やら思案するような顔つきで暫く【NAME】の方を見た。
何だろう、と少し首を傾げてノエルを見返すと、
「これから、【NAME】はイェアとお話をされるのですか? でしたら、飲み物……果実酒は確か切れていましたから、お茶の用意をしておきましょうか」
どうやら、気を遣わせてしまったらしい。
若干悪い気もするが、有り難い事は確かだ。礼を言う【NAME】に、ノエルはほんの少し笑みを見せて頷くと、天幕の隅に置かれた棚に向かおうとする。
今【NAME】達が居る天幕は、イェアが普段事務作業を行う際に使っているもので、来客用の設備も一応用意されている。といってもここは軍の野営地で、訪れるのは基本身内のみだ。あるのは数人分の杯と、飲料水を溜める瓶のみ。沸かすための火もない。イェアが果実酒を常飲しているため、あまり気を払われていないのだ。
その為、この環境で茶を淹れるとなると単に茶葉を水に突っ込み、自然に味が移るのを待つ形となるが、そんな時間を掛けていてはそもそも来客も帰ってしまう。なので、色のついた水を飲んでいるのとあまり変わらない程薄い茶が出てくる事になるのだが、それでも何も無いよりは遥かに有り難い。
が、
「あー、えっと、ノエル。ちょっと待ってくださいな」
所々、考え込むような声音で、イェアがそれを留めた。
「今日はちょっと特別に、わたくしが直々に【NAME】さんにお茶を淹れてあげようと思ってますの。だから、ノエルももう寝ちゃって構いませんわよ?」
「……イェアが、ですか?」
「ですわよ?」
怪訝な顔で固まるノエルに、イェアは少し不満そうな顔。「わたくしだってやろうと思えばそれくらいできますし」と返すが、ノエルの表情は訝しげなままで、
「イェアがやろう思うのが珍しいと、私はそう思ったのですが……」
「酷い! でも間違ってはないかも!」
間違ってないのか、と呆れながら二人の遣り取りを眺めていた【NAME】だったが、その視界の中で、ウィースルゥインが小さくノエルの袖を引くのが見えた。
「ノエル。いいから戻ろう?」
「え? ですが」
突然、予想してない方からの言葉に、ノエルが戸惑う様子を見せる。
しかしウィースルゥインはそんな彼女の態度を意に介さず、【NAME】とイェアを交互に見てから、改めてノエルの方へと視線を戻し、
「それは多分、作った理由。ただ、二人だけで、お話ししたいんじゃないかな。だから、戻ろ」
「…………」
ノエルがぱちぱちと二度程瞬きする程動きを止めた後、恐る恐るイェアを見る。
対するイェアは、浮かべていた笑顔を微かに引きつらせていた。どうやら、図星らしい。そして【NAME】が図星と気づいたように、ノエルもその事に気づいたようだ。
「……そう、だったのですか。す、すみません、わたし、気がつかなくて……」
「ああっ! こちらこそ御免なさいねノエルっ、遠回しに言っちゃったせいでなんか変な風になっちゃって……」
怖いくらいの無表情、まるで出会った当初の頃のような顔つきで意気消沈するノエルに、イェアがあたふたと慌てる。ウィースルゥインの指摘は間違いだと嘘をつく余裕すら無い程の慌てぶりだった。
「ていうか、ウィーちゃんが判ってたのがびっくりですけれど、そういう事は面と向かって言っちゃ駄目ですわよ!」
「駄目だったの?」
「う……ウィースルゥインがちゃんと判ってたのに、私は判ってなかった……。私の方がずっと長く人と暮らしてるのに……」
「ああっ! ノエル! ほらウィーちゃん、あなたこういう機微も理解できてるなら、ノエルがダメージ受けるのも判るんじゃありませんのっ!?」
「そうなの? 私なら気にしないから。ノエルも気にしないと思った。私なら、教えてくれた方が嬉しいから」
「う、うーん。そっか……根っこのところは同じでも、それを使って考える“カタチ”が違うから、もう個人としてはノエルとウィーちゃんは大分違う感じになってるんですのね。勉強になる……ああいやいや、今はそういう話ではなくてですね」
「イェア。わたしはお邪魔だと思いますので、今すぐ出て行きますね。ごめんなさい……」
「あ、ちょ、ノエル! ノエルーっ!」
大騒ぎだった。
――結局。
その後、落ち込むノエルをあれやこれやと元気づけ、気持ちを持ち直させるのに結構な時間を要してしまった。
【NAME】からすると、ノエル達をその場に残るのを認めてしまった方が早かったのでは、という気もしたのだが、
「実際、誰にも聞かせたくないってくらいの秘密の話をするつもりもありませんでしたから、一緒でも良かったのですけれどね。でも、やっぱりこんな時間まで付き合わせてしまったのは確かですし。保護者の立場としては、こちらの都合でこれ以上の夜更かしをさせるのは、認められませんわ。……今更な話ではありますけれど」
既に二人が立ち去った後。
天幕の出入り口となる垂れ布を眺めながらのイェアの言葉は、庇護の想いと、己に対するふがいなさ、後ろめたさが混じり合った、複雑な色合いを見せていた。
先刻までの流れから、イェアがお茶を淹れるというのはてっきりノエル達をさっさと帰すための嘘だと認識していたのだが、驚いた事に、彼女は自らの手でお茶を用意し、淹れてくれた。
最初はイェアも実際にやるつもりなどなかったのだろう。しかし、ノエルの自分に対する心証を悟り、こりゃいかんと奮起してみた、といったところか。
手の込んだ準備をし、わざわざ外で湯を貰ってきて運んできたりと、普段やり慣れていない者特有の手間の掛け方をしていたところが、有り難くもあり、微笑ましくもあり。
彼女の性格を考えれば恐らくは一過性の反抗でしかなく、今回限りの気まぐれで終わるのが勿体ないが、そこは仕方無いと諦めるべきだろう。
「では改めて、【NAME】さん。こんな夜更けにわざわざ来て頂いて、申し訳ありません。はい、お詫びにどうぞ」
そうしてようやく茶が出てきたのは、ノエル達が天幕を辞してから更にかなりの時間が経った後だった。
イェアお手製の茶は、ノエルが時折葡萄酒が切れている時に出してくれるものと比べると、そもそもの茶葉の質自体が雲泥の差だった。こういう辺境の野営地で頂けるような代物ではなく、本来は歓待の席で出すような上等なものなのだろう。聞けば、確かに高級なものだとの事だった。私物として適当に持ち込んだ物の中に紛れていたらしい。
味自体も相当なものだ。この前の出来事、リゼラと料理の腕を競い合った件での事もあり内心戦々恐々していたのだが、よくよく考えてみると、イェアは少々特殊な味覚をしているものの別に際立って不器用という訳ではない。単に飲食に対して興味が無いため、料理についての知識や上達への欲求が足りなかったというだけなのだ。
そしてそれは、前回の件でノクトワイから指導を受けたことにより、ある程度の改善が成されている。学士という職業柄か、極力得た知識に沿って物事を行おうとする為、素人特有の突飛な思いつきなどを割り込ませる事もなく。上等な素材を使い、真っ当な作法に従うのなら、出来るものもは当然、相応の代物に仕上がる。当たり前と言えば当たり前の話だ。
茶を幾度か口に含み、程よい渋味を暫し味わってから、【NAME】はイェアに今日の用件を聞く。取り敢えず夜の遅い時間に来て欲しいと、大雑把な伝言を受けてやってきただけで、何故自分が呼び出されたのかは聞いていないのだ。
イェアは自分用の茶を淹れ終えると、席に座り直してから話を切り出す。
「ちょっと今、最後の詰め……といえばいいのかな。今後どうするかを最終的に決める、山場のようなところに差し掛かってまして。だから一度、【NAME】さんがこれまでエルツァン島で経験した事を、改めて聞かせて欲しいなと、そう思って」
「…………」
ふむ、と【NAME】は腕組みし、椅子に深く座り直す。
【NAME】達がウィースルゥインと出会い、彼女が軍陣地に出入りするようになってから、何やら頭を悩ませている事には気づいていたが、このイェアの言葉で悟る。どうやら島での行動方針について迷っていたらしい。
しかし、自分が経験した事全てとなると、またなんとも話が長くなりそうな要望で、少しばかり億劫というか、気が重くなった。
そんな内心が表情に出てしまったのか、イェアがあははと苦笑する。
「全部が面倒でしたら、簡単な雑感でも構いませんわ。ただ、あの子。ウィーちゃんについては、出来れば詳しく、【NAME】さんの見解も込みで、一から知っている事を話して頂ければと、思ってますの」
(ウィースルゥインについて、ねぇ……)
言われて、考える。
実際のところ、【NAME】自身と彼女との間に縁は余り無い。ノエルとウィースルゥインが繋がり、交流を経て、その末に対時するという一連の流れの中、【NAME】は最後の結末に介入したというだけの話なのだ。だから、何故彼女が自分達と共に居る事を望む状態になったのか、という経緯については、正確には良く判っていない。ノエルから大まかな説明を受けたものの、正直当事者ではない人間が聞いてもいまひとつ理解が及ぶような内容ではなく、そういった事も含めて考えれば、やはり自分はあまり彼女を知らない、という結論に落ち着く。
【NAME】が彼女について知っているのは、別の流れ――リゼラと共に島の各地を巡った一連の探索行で得た情報くらいだ。
そしてそれらについては、既に【NAME】が話せる事は全てイェアに伝えてあった。なので、今更新しい何かを求められても、中々に難しい。
そう答えた【NAME】に、イェアは困ったような笑みを浮かべて、
「んー、それはまぁ、そうなのですけれども。今、ちょっと新たな状況……というかあの子達に変化が生じまして」
――変化?
怪訝と首を傾げると、白衣の彼女は少し考え込むような表情を浮かべ、「変化というよりは、進展、でしょうか」と呟く。
「ウィーちゃん、最初の頃は、【NAME】達がエルツァン島で延々と繰り返しているという旅について、最後の部分は良く判らないって言ってたでしょう?」
【NAME】は短く頷く。その話は、ウィースルゥイン本人から聞いた覚えがある。
確か、島の最奥にある“城”のような場所に至る辺りで大抵繋がりが途切れてしまい、そこから先の出来事はウィースルゥインも良く判らない、と。
「それが最近、その“城”に入った後の記憶を、断片的にですけれども思い出せたりする事があったみたいで。どうもウィーちゃんとノエルが、前よりもしっかりした自分を維持しながら繋がりを深くしている影響が、そういうところにも出始めてるようなんですの。混ざり合わずに互いを視る事で、よりはっきりと物事が見えるようになってきたとか」
だからもう一度改めて、ウィースルゥインの事についての情報を洗い出しておきたい。そして、新たにウィースルゥインから齎された情報を、過去の情報を再精査しながら纏めておきたい、というのがイェアの考えであるようだった。今回、【NAME】にもう一度話をしてくれと頼んでいるのもその一環、という事らしい。
何か見落としがないか、新たな発見を導き出せないか。それを確認するための再度の聴き取り。
一からまた話をするのは少々骨の折れる作業ではあるが、それがイェアの助けになる、それも“山場”とやらを越える鍵となるのならば、強硬に拒絶するほどの事でも無い。何より、
(美味しいお茶も、入れて貰った事だし)
【NAME】は承諾の頷きを返すと、エルツァン島での出来事を一から思い出しながら、時にはイェアからの質問に答える形で、ゆっくりと語っていった。
――それから。
時間にして、さて、どれだけ経過したのか。
天幕の中に居るため外の様子から察する事は出来ないが、恐らくは深夜から未明に差し掛かった辺りで、【NAME】の話はようやく終わった。
「ふーむ。んー……」
聞き終えたイェアは、椅子に深くもたれかかって、暫く天幕を見上げたまま、微動だにせず何事かを考えていた。
とにかく話せる事は話した、と満足感すら得ていた【NAME】であったが、しかし果たしてこちらの話から何か改めて見出せる事があったのかどうか。
【NAME】が身動きを止めた彼女を黙って見守っていると、イェアはがばりと唐突に身を起こす。
「よし、決めました」
何を、と問うと、彼女は真剣な表情で【NAME】を見据え、
「【NAME】さん。――貴方にお願いしていた“鬼喰らい鬼”討伐の件、一度取り消させていただけませんか?」
「…………」
面食らう。
――それは、“鬼喰らいの鬼”の討伐を諦める、という事なのだろうか?
誤解がないよう、確認の意味を込めての【NAME】の問いに、イェアは「まさか」と首を振る。
「ですが、今わたくし達が選んでいる選択肢……【NAME】さんだけに任せる形じゃ、多分駄目なんだと思います。新しくウィーちゃんから聞いた事、“城”での顛末を考慮するなら、きっともう一段、別の方法が必要なのだと」
それを聞いて、【NAME】は前々からの疑問をようやく口にする。
ウィースルゥインが新たに思い出したという“城”についての話。それを、【NAME】はまだ聞いていなかった。具体的には、一体どういう事になっていたのか。それを聞かねば、彼女がどういう思考を辿り結論に至ったのか、いまいち話が掴めないままだ。
【NAME】の問いに、イェアはああ、と目を瞬かせて、
「あの子が言うには、【NAME】さんは島の最端に位置する“城”で、大きく二通りの流れを辿るそうです。一つは、城奥に存在する封印を破壊し、それと同時に現れる“竜”と戦う流れ。もう一つは、封印を解除して、そこから更に別の場所へと向かう流れ。ただ、どちらの流れを辿るにしても、結末はほぼ同じになるようですわね」
――巻き戻し、か。
【NAME】が呟くと、イェアはこくりと頷く。
「のようですわ。最初のパターンで出現する竜は、ウィーちゃんはノエルから外見や能力について聞いた感じですと、芯竜属やその系譜の亜竜ではなく、恐らくは“リンドヴルム”と称される類の守護生物だと思われますわ」
リンドヴルム。
聞いた事の無い言葉に首を捻ると、イェアは「あれ、ご存じありません?」と瞬きし、
「旧時代――“芯なる時代”辺りの知識を持ってる学士の間なら結構知られている類の存在ですわ。冒険者の方々もご存じの人はそれなりに居たのですけれど……西大陸限定なのかな。ええと、簡単にお話ししますと、リンドヴルムは“芯なる時代”の最後期に良く使われていた、最高級の汎用型概念戦闘生体。簡単に言えば“芯なる者”の凄く強い召使いってところですわ。色々とバリエーションがあるんですけど基本は芯竜をモチーフにして造られていて、こう、ばっさばっさと翼で飛び回って、口から吐息[ブレス]をがーっと」
イェアは両の手をわさわさ振りをながら、口をあーんと開いてみせる。
が、【NAME】が無言で彼女を見つめていると、段々恥ずかしくなってきたのかこちらから視線を外してこほんと咳払い。
「えー。まあ、兎に角リンドヴルムはそういう存在ですわ。主に拠点防衛用として設計されていて、本領は他概念世界間に存在する奈落の子を迎撃する為のものだそうですけれど、“芯なる者”達はもうちょっと広く活用していて、芯形機構や自分達の居所の防衛といった重要な場所の守護者としても配置していたようです」
要するに、遺跡でよく見る警備用の亜獣や機種、魔導生物の最高品みたいなものだろうか。
我ながら雑な解釈だが、と思いつつの【NAME】の言葉に、しかしイェアは「大雑把に言えばそんな感じですわね」とこれまた雑な同意を返してきた。
「で、そういう一地点を守るという役目のせいで、今の時代まで生き残っていたものも幾つか居て……まぁ、そのせいで色々と有名なんですの。“芯なる者”達が使う最高位の眷属としては珍しく、文献等の資料だけで確認された存在じゃなくて、実際に遭遇した記録も結構あって……まぁ、凄いですわよ、被害例。普通に軍隊が出張ってやられてるパターンもありますし、過去には街どころか国まで燃やしたリンドヴルムも居たとか言われてますわね」
で、その凄まじく危険な存在が“城”に居るのは確か、という話なのか。
「ついでに言えば、【NAME】さんが戦う相手にもなるようですわね」
「…………」
げんなりと、苦虫を噛み潰したような顔になってしまう。
“鬼喰らいの鬼”とまた戦わねばならないというだけでも気が滅入るというのに、そんな厄介な相手とも戦闘になる可能性がある――ウィースルゥインの言をそのまま信じるならば、既に戦ったという過去が存在するとは。
「とはいえ、“鬼喰らいの鬼”も正直大概な相手の筈ですし、それを倒した【NAME】さんであれば戦えない相手ではない……実際に、ウィーちゃん達の記憶では、【NAME】さんはその竜すら下しているそうですから。本当に、流石ですわね、【NAME】さんは」
そう褒めてくれるイェアに、【NAME】はだけれども、と口を挟む。
――竜を倒せたとしても、その結果が巻き戻っているようでは、意味が無いのではないか。
【NAME】の言葉に、イェアは表情を険しくして頷く。
「ええ、全くその通りですわ。ウィーちゃん達が確認した二通りの流れの内のもう一つ、“封印”を解除し、その奥へと向かった【NAME】さん達は、赤い三日月が浮かぶ空間で、“鬼喰らいの鬼”を見つけ、戦いとなる。【NAME】さん、この場所について、思い付く事があるのではありませんか?」
イェアの問いに、【NAME】は隠す必要も感じず、ただ思ったままを答える。
過去に聞いたその名に倣うならば、そこは恐らく――“黒い切り株の向こう”だ、と。
「わたくしも、そう考えてます。リンドヴルムが守護するような“封印”が存在するのなら、多分その“城”は、“鬼芯の檻”へと続く正式な道があるのだと思いますわ。この地、エルツァンには“鬼芯の檻”の前身となるものが存在する。【NAME】さん、覚えていらっしゃいます?」
頷く。
オリオールと共に巡った、カール・シュミットの軌跡を辿る旅。その終着点で見た、芯形機構の事だ。
その名は曰く、“芯檻”。
「これは推測ですけれど、エルツァン島は鬼芯属をフローリアに封じる“芯檻”という大術式を構築する際の要となった場所なのでしょうね。だから前身の実験施設があり、そして島全体を包み侵入を拒む結界があり、更には最奥に檻へと繋がる道と、道を塞ぐ封印と守護者が居る。“鬼喰らいの鬼”がエルツァンを求めたのも、鬼芯の檻へと向かうためだったと考えられますわ」
アノーレで【NAME】の手により討たれ、しかし身体を砕かれながらも己の崩滅を防ぎ逃げ去った大禍鬼シンラ。
エルツァンへ向かったという痕跡は掴めていたものの、その目的までは判らないままであったが、ここに来てその事についても目星がつくようになってきたのか。
だが、シンラはどうやってエルツァンがそのような場所であると知っていたのか。そして鬼芯の檻に向かって、一体何をするつもりだったのか。
ウィースルゥインは、それすらも過去の記憶として見ていたのだろうか?
【NAME】の問いに、イェアは軽く肩を竦めて、
「流石にそこまでは。ただ前者については、遺跡に封じられる以前から知っていたか、或いは島に漂う陰性概念の流れを読めば判る事なのかもしれませんわ。鬼種は人よりも遥かに高い感知能力を持っていますし。そして後者については」
イェアは一瞬口篭もり、言葉を選ぶような間を置いて、
「ウィーちゃんが辛うじて視た記憶の中では、シンラは赤い月が浮かぶ暗闇の空間に並び立っていた、巨大な柱の一つと一体化していたそうですわ。アノーレで、【NAME】さんがノエルと共に戦った時よりも、更に大きな力を持つ存在となって」
「…………」
その発言を、【NAME】は己の内で吟味して、そして自分なりの解答を出す。
つまり、鬼芯の檻と同化する事で、自分との戦いで失った力を取り戻す。それが“鬼喰いの鬼”の目的であった、と。
「断言は出来ませんけれど、結果としてはそうなっているようですわね。あと、これが重要なのですが……その鬼を無事に討伐する【NAME】さん達の姿も、ウィーちゃんには見えたようです」
「…………」
それは、本来ならば喜ばしい事実なのだろう。
しかし、今、自分達がこうして島の軍陣地にて“鬼喰らいの鬼”討伐について話しているという現状を考えると、それはあまり朗報とは言えないものだった。
何故なら、自分達が最初に想定していた目的を無事達成したとしても、その全てが巻き戻り、無に帰すという事を示していたからだ。
【NAME】が表情を暗くした事に、己の危惧が正しく伝わった事を理解したのだろう。イェアは疲れの色濃い苦笑を浮かべる。
「【NAME】さんにお願いしていた“鬼喰らいの鬼”討伐の依頼を一度取り下げる、というのはこれが理由です。【NAME】さんだけでは――少なくとも以前のわたくし達が選んだ方法では、この状況を打破できない。“鬼喰らいの鬼”を討伐出来るかもしれません。けれど、それすらも無かった事にする巻き戻しが止められない。だから別の、或いは更なるアプローチを模索します。【NAME】さんが、先刻話してくれた色々な事は、わたくしに大きなヒントを与えてくれました。だから」
イェアはそこで一度言葉を切り、
「少し、わたくしに時間を下さい。巻き戻しが起きる理由について、推測は出来ています。これも、【NAME】さんのお話のおかげですわ」
【NAME】は驚きで僅かに目を見開く。
己がした話の中で、今自分達の身に起きているらしい時間の巻き戻しの理由になるような点などあっただろうか?
慌てて記憶をひっくり返す【NAME】に、イェアはくすりと小さな笑みを浮かべた。
「【NAME】さん、イールシックの地下都市遺跡で、巨大な幻と戦った時、最後に自分が何をしたのか、ちゃんと話してくれたじゃないですか。それですわよ」
――最後?
言われて、思い返す。確かあの時、出現した巨大な幻身と戦い、最後にカール・シュミットの姿をなぞる形で、芯形機構を制御していた台座目掛けて攻撃を放ったのだったか。
それをそのまま呟くと、イェアは大きく頷く。
「つまり、そういう事なのではないかとわたくしは考えますの。巻き戻しは、“芯檻”を構成する柱に損傷を受けたとき、あるいは檻へと向かうための“正しい道”に施された“封印”が破壊された時などに、機能不全を復旧させるために芯形機構が起こす現象なのではないか。わたくしは、そう予想していますの」
「――――」
考える。
ウィースルゥインは、巻き戻しという現象は【NAME】が“城”へ向かった後に起きる、と言っていた。
そして“城”では、自分は“芯檻”を構成する柱と同化したシンラを倒す、または檻へと続く道を閉ざす“封印”を破壊しリンドヴルムと戦う事になる。後者については含んで判断するべきかは悩ましいところだが、確かに“芯檻”に関わる要素に対し、破壊行動を取ってはいるのだ。
イェアの言は突飛な発想ではある。本人が言うように予想の範疇をでるものではない。
しかし、有り得ないと、大きく否定する材料も見当たらなかった。
――時を巻き戻す。
そのような事がもし起きるとするならば、島まるごとを使い、芯属の中でも最大の存在ともされる鬼芯属を封じた芯形機構の力によるものだとするのは妥当――というよりは、フローリアの根源にも関わる最も強大なそれに理由を求める以外、時を巻き戻す等という馬鹿げた事象と釣り合いが取れるようなものが存在していないのだ。
ただ、存在していないからといって、それが原因と断じても良いものか。確かに、候補として考えるならば十分に有り得るものではあるが。
結局、反論も出来ず、しかし同意も出来ず。
難しい表情で黙り込んだままの【NAME】に、イェアは小さな苦笑を浮かべ、
「【NAME】さんがそういう反応をされるのも判りますわ。わたくしも、明確な証拠のようなものがあっての予想でもありませんし。けれど、賭けてみても良い、とは思ってもいます。巻き戻しのトリガーとなるようなものが、現状の情報ではこれくらいしか思い付かない、というのがより正確ではあるのですけれど……」
その点については、【NAME】としても同意だった。結局、これまでと同じ方針で動いていては前に進めないのならば、兎に角別の方向を模索し、色々と試してみるしかない。幸い、状況は失敗しても巻き戻されるのだから。試そうと思えば何度でも試せるのだから。
【NAME】がそういうと、机を挟んだ先の学士は表情を険しくさせる。
「いえ、然う然う気楽に出来るものではありませんわ。何せ、今の形――ウィーちゃんがわたくし達のところへ来てくれるという状況自体が、今回限りという可能性もあるでしょうし、失敗した後、その成果が後へと引き継がれるかどうかも判りませんもの」
「……ああ」
思わず呻き声が出た。理屈としてはそうなるのか、と【NAME】もこめかみを押さえる。
肝心の巻き戻しとやらが発生した時、果たしてどの時点の自分達に巻き戻されるのか、それすらもウィースルゥイン以外は把握出来ないのだ。
「まぁ、ウィーちゃんが教えてくれればそこでどうにかなるでしょうけれど、出来れば、今回の一度の試行でカタをつけたいと、そう考えてます。何せ、差し迫ったという程ではありませんけれど、悠長にしていてもよい状況ではないようですし」
浅く息をつきながらの彼女の言葉は、何とも含みのある言い回しだった。
巻き戻しという状況に巻き込まれているのであれば、時間的猶予はむしろ無限に近いほどにあるのではないか。
そんな【NAME】の言葉に、イェアは硬い顔で首を横に振る。
「【NAME】さん、わたくしとリゼラさんが料理対決したこと覚えてますわよね」
頷く。
「あの時、食材の調達を行うために何度かアノーレ島の方と遣り取りして、輸送の船を寄越してもらったりしたのですけれど、そこで改めて気づいた事があるんです」
天幕の隅に纏めてあった紙束の中から何枚かを引き抜き、イェアはばらりと机の上に広げる。
【NAME】が視線を走らせると、それらはアノーレにあるアラセマ常駐軍部隊と連絡を行った記録であるように読めた。
イェアはその紙のうち、サインの横に書かれた数字をとんとんと叩く。
「日数の辻褄が合わないんですの。それまで、精々あちらには定期連絡くらいの文を送る程度だったので気づくのが遅れてしまったんですけれども、今回の件で本格的にむこうと遣り取りした事と、ウィーちゃんの話を繋ぎ合わせる事で、その違和感が明確になった、と言いますか。判りやすくいうと、ですね」
浅く吐息。イェアの顔に浮かぶのは憂鬱な気配。
「どうも、エルツァン島の内と外では、時間の流れが違うみたいなんですのね」
「…………」
それは、ウィースルゥインが言っていた時間の巻き戻りという奴の影響で、時間にズレが生じている、という事なのだろうか。
【NAME】が神妙に呟くと、意外な事に、イェアははっきりと首を横に振った。
「勿論それもある、とは思うのですけれど、それ以前に、外と内……というか、このエルツァン内での時間の流れ自体が、そういった巻き戻り関係なく不定みたいなんですの。ウィーちゃんの話をそのまま受け止めて考えるのでしたら、わたくし達は何度も同じ時間を過ごして、その分だけ島の外との時間がズレていく、という感じになりそうなのですけれど、そもそも巻き戻しが起きる以前の段階で繋がりがおかしいらしくて」
例えば、そうですわね、
「わたくしがアノーレに食糧の輸送をお願いする連絡を行って、それが承認されて、輸送の船が近海にやってくる。最低でも数週間か、下手すれば数ヶ月は掛かるような作業が、その半分以下で行われていました。しかも、諸処で掛かっている時間が、どうも安定してないんですの。単なる伝言の行き来で一週間以上掛かったかと思えば、準備完了の連絡が来た数時間後に到着の知らせが来るというのは流石に不自然ですわ。この事から判るのは……」
――つまり、場面場面で時間の進みが、遅くなったり早くなったりしている?
口を挟むと、学士は顔をしかめたまま頷く。
「と、考えるのが自然ですわね。これに加えて、ウィーちゃんの言う巻き戻りが発生してるみたいで、所々妙な遣り取りになってる箇所もあります。ただまぁ何にせよ、内と外で結構な時間の差が出始めてるのは確かで、しかもこの時間の動きが不定であるとするなら、出来うる限りこの状況を打破しないと、もしかしたら極めてまずい事になる可能性も十分考えられますわ」
例えば、と問うと、イェアは厭味のある笑顔を浮かべ、
「何せ、なぜそうなっているのかが判りませんからね。もしかしたら、ここで過ごした一日が、外での一年に相当するほどの歪みが突然生じる可能性もないではない訳でして。誰にも話してませんでしたけれど、実際既に、外と内では結構な日数、時間のズレが生じていますし」
「…………」
知りたくない事実だった。成る程、イェアが出来る限り解決を急ごうというのも判る話だ。
取り敢えず、話は判った。が、では具体的にどうするのか。
【NAME】の問いに、イェアは表情を改める。
「先程の話に戻ります。少し、わたくしに時間を下さいな。今、先刻お話した推測を元に、巻き戻しの切っ掛けと定めた二つの要素をどうにかしながら、“鬼喰らいの鬼”を崩滅させるための方法を考えていますの。封印を破壊せず、竜をどうにか抑えて、そして柱を損傷させずに“鬼喰らいの鬼”を討つ。それが出来ないなら、巻き戻しが生じないように、芯形機構を騙す方法を」
――そんな事が、果たして出来るのか。
思わずそう問うと、イェアは自身の胸に掌を当てて、畏まって【NAME】を見た。
「お任せくださいな。一応ですが、当てはありますわ。先刻の【NAME】さんのお話で、島の状況がどうなっているのか、かなり正確に把握できるようになりました。だからこそ思い付く事もあります。それに、あなたが話してくれたウィーちゃんの事も、随分参考になりました」
やっぱり、と言葉を挟み、白衣の学士は呟く。
「――あの子の力を借りれば、可能かもしれない」
その言葉に、【NAME】は片眉を顰めた。
ウィースルゥインは、確かに多くの強存在の力を内包する。しかし、彼女がその力を全て使いこなせるかというと、それは否という他無い。
【NAME】がウィースルゥインと初めて遭遇した時には、彼女が内に秘めた力の奔流と刃を交えはした。だが、あれが彼女の意志の元に振るわれたものだとは到底思えず、その印象は、戦いの後にウィースルゥインと幾度か行動を共にした後でも変わっていなかった。
後の遣り取りで判った事だが、ウィースルゥインはノエルの記憶と知識を持つ故に、人が扱う術式について多少の覚えがあるようだった。しかしウィースルゥインが内に持つ力は人のものとは完全に別種で、それに関わる力は、殆どが無意識で発揮されているように見えた。
実際、本人に訊ねてみた事もあるが、答えは「あまりよく判らない」という頼りないものだ。彼女の曖昧な説明を【NAME】なりに解釈するに、本人が意識しづらい生理反射や、本来自分が持っていない筈の器官があるような感覚に近い、という事だった。故に彼女が持つ特有の力の部分を要として作戦を考えるのは、高いリスクを伴う筈だ。
これらの事は、先刻話をした際にも伝えてあった事だが、それをイェアは忘れていないだろうか。
念のために問うと、「安心してくださいな」と彼女は笑った。
「わたくしだって、あの子とはそれなりに顔を合わせたつもりですから。それを踏まえて、のお話ですわ」
ならば良い、と【NAME】は素直に引き下がる。ウィースルゥインが軍陣地に出入りするようになって、ノエルを除けば恐らく最も接触し交流しているのはイェアだ。その彼女が良いと考え、そして【NAME】が示した懸念も考慮済みだというならば、これ以上【NAME】が言う事は何もなかった。
その【NAME】の様子を確認して、イェアは一つ深呼吸を挟んだ後、ゆっくりと言葉を続ける。
「……取り敢えず、考えている方法を遂行する為の準備と、計画の詳細。それが完全に固まり次第、今回の探索行に参加している者全員を対象とした、説明の場を設けるつもりです。その時は【NAME】さんにもお伝えしますから、必ずご参加くださいな。……ウィーちゃんも、そのとき皆に紹介してみるつもりです」
それは、と【NAME】は一瞬口を挟みかける。
イェアの言う計画とやらが、ウィースルゥインの助力を必要とするものであるなら、彼女を重要人物数人以外とも引き合わせるというのも判る話だ。
しかし、その対象が全員となると、意味合いが少し違ってくる。
ウィースルゥインの事を、軍部隊の全員が見知っている状況を、イェアは求めている。
それはつまり、
「あなただけじゃありませんわ。総員を以て、状況を打開する――今わたくしが計画しているのはそういう作戦です。だからどうか、【NAME】さん。ご期待を」
「…………」
自分やウィースルゥインを含め持てる全ての戦力を動員して、“鬼喰らいの鬼”の討伐――そして巻き戻しからの脱却を狙う、総力戦を行うつもりなのだ。
見上げてくるイェアの瞳が放つ強い覚悟の色から、【NAME】は彼女がこの作戦に賭けるものの大きさを、ひしひしと感じていた。
届く細波の音が、耳朶を優しく撫でていく。
青みがかった円より降り注ぐ光に照らされて、遠く小さな白波が幾重も重なり砕けていくのを、巨大な岩の上で膝を抱えて座る彼女は、ただ茫と眺めていた。
生まれては消える。
生まれては消える。
打ち寄せる波の音と共に、殆ど変わりの無い反復がただただ積み重なっていく。
その押しては引く海の営み、延々と繰り返される光景に、ささやかな安らぎを得るようになったのは、さて、いつ頃からだったか。
何気なく思い記憶を辿るが、明確な理由のようなものも、発端の時期もはっきりとしない。身体と心両方に溜まった疲れと、そして時刻故の細やかな眠気が、深く考える事を妨げてくる。
暫くの思考の後。どうでも良い事か、と彼女は思い返すを止めて、薄く瞼を閉じた。
視界が暗闇に落ちる事で、響く波音が際立つ。定期的に、ざざ、と寄せる音を、彼女は耳だけではなく全身で感じ取り、その律動に身を委ねると、浅く漂うようだった眠気が、段々とその主張を強めていくのを感じた。
何だかもう何もかもが面倒で、ここで一眠りしていこうか。
そんな思いつきに流されてしまおうかと迷っていた時、そんな彼女を呼ぶ声が響いた。
「ノエル」
という声に、半ば微睡みの中にあった意識が覚醒する。
彼女――ノエルが眼下を見ると、そこには、夜の闇に半ば溶けかけた長い黒髪を、海より吹き寄せる風に流されるままにして立っていた少女、ウィースルゥインの姿があった。
「片付け、終わったけれど。戻る?」
「ううん。もう少しここにいるつもり。あなたはどうする?」
「付き合う。良い?」
「どうぞ」
短い遣り取りの後、浜に立っていた少女の身体がふわりと浮かび上がる。
ノエルが今座っている大岩は、高さにして数メートルはあろうかという代物なのだが、ウィースルゥインはその高さを一切苦にせず、一息の跳躍で岩上に座るノエルの隣へと音も無く移動。空中で停止し、ゆるやかな動きで前転を一度挟んだ後、彼女は巻いた髪をまとめるように手で押さえながら腰を下ろした。
この場所は以前、ウィースルゥインが【NAME】に連れられ、キヴェンティの若長と面会した場所だ。ウィースルゥインが存在を知り、それをノエルに伝えた結果、この大岩は二人の密かなお気に入りの場所となっていた。
夜の何気ない時間。若しくは“勉強”の後などに、ここで暫しゆったりと海や空を眺めながら、ウィースルゥインと話をしたりして時を過ごす。この時刻ならば、キヴェンティの若長――リゼラ・マオエ・キヴェンティと顔を合わす事も無いだろうとの考えからだ。
今日も、流れとしてはいつもと変わらない。イェアの天幕を辞した後、落ち込んだ気持ちを切り替えるため、ウィースルゥインと共に“勉強”をする事にした。彼女に結界を敷いてもらい、その中で一時間か、二時間か。【NAME】とイェアに見せてしまった間の抜けた失態を取り繕うように、自分の内に秘められていた機能を扱うための訓練を続けた。今は、それを終えての一休みの時間だ。
そのまま暫く、二人は言葉を作ること無く、夜の闇と細波の音の中で静かに身を置く。
「ねぇ」
ふと呼び掛けられて、ノエルは浅く首を傾げてウィースルゥインを見る。
「何でしょうか?」
覗き見た彼女は、視線をこちらには向けておらず、ただ遠く、海彼方に霞む雲の欠片を眺めたまま言葉を続ける。
「考え事?」
端的。
その一言に尽きる問いにノエルは少し驚いて目を瞬かせて、そしてどうだろうと自問してみる。
「……考え事。んー、どうでしょうか」
視線をウィースルゥインと同じく海の彼方へと向けてみる。
上空では風が強いのだろうか。浮かぶ雲は見て判る程の速度で流れていく。雲の形が徐々に変化して千切れ、散っていくまでの間、ノエルは己の中を掘り下げる。
これといって、明確に何かを考えていたつもりはない。だが、問われて改めて考えてみると、幾つか心に引っかかっている事があった。
「そう、ですね。ウィースルゥイン、あなたの調子はどうですか?」
「私? そうね」
少しの間。するりと、彼女は手を己の長い髪に絡ませる。
「まだはっきりとはしないところはあるけれど、段々、自分が確かになってきた気がする。こうして貴方の隣に座って、岩の冷たさ、風の流れ、波の音、月の光。どれも……うん、私の感覚が、私が感じたものとして、受け止めてる。だって、ほら」
腕に沿うように螺旋を描いた黒色の髪が、吹いた風に煽られて解け、そのまま背後へと流れていった。その髪の動きはごくごく自然で、彼女が正しくここに在り、この世界の影響を受けている事を示している。
ウィースルゥインは、ちゃんと、この世界に居るのだ。
「ね? それに、視える人も増えてきたよ。物知りなおじさん。髭が素敵な人。杜人の方。それに、いつも槍を研いでる仏頂面のお兄さん。ご飯の時に騒がしいお姉さん達。岸の岩の影で寝てばっかりのお爺さん」
「……なんだか、予想外の人達が増えているようにわたしには思うのですが。接触とか、してません?」
「ううん。だって、困るでしょう? だからしてない。私はわたし。今の私が、ここの人達に知られるとうまくいかなくなるかもしれないって、判るから」
「なら良いのですけど。そうか、あなたはわたしを受け継いでいるのなら、そういう事もしっかりしているのですよね」
「うん。まぁ、偶に声とか掛けてみたけど」
「接触してるじゃないですか!」
一瞬でも信用した自分が馬鹿だった。
慌てて怒鳴るが、ウィースルゥインは涼しい顔で首を捻る。
「物は試しよ。私の声が――伝えたいという心が、私を知らない存在に届くかどうかの試し。結果は届かなかったから、問題はないでしょう?」
「……届かなかった、のですか」
「ええ。すこし反応する人も居たけれど、空耳という形で片付けられてた。やっぱり、あなたや【NAME】みたいな、明確に視える人を挟まないと、まだここにはっきりとは居られないみたい」
「そう……」
小さく呟くと、ウィースルゥインの顔がこちらを向く。
「貴女がそんな顔をするような事じゃない。大丈夫よ。私が知る人が、私を知る人が、増えれば増えるほどに、私はここで“ウィースルゥイン”になる。それはもう、判っている事だから」
時間が解決する事であり、そもそも【NAME】かノエルか、それこそイェア達でも良い。誰かがウィースルゥインを皆にまとめて紹介し、周知してしまえば即座にどうにかしてしまえる話。それを、ノエルはイェアから聞いていた。
それをしていないのは、【NAME】とイェアが、その前にある程度の段階を踏んでおこうと考えているからだとも。
確かに、ウィースルゥインは極めて異質な存在だ。それを軍の内で受け入れるには、相応の下準備なり、口合わせなりが必要なのはノエルにも判る。また、ウィースルゥインからしても、少しずつ自分の在り方を定めていく時間が必要だろうとも。
それを考えれば、
「大凡、問題は無く状況は進んでいると、そう受け取っても良いのでしょうか」
「私については、そうね。むしろ、私は貴女に驚いたけれど」
「わたし?」
「ええ。だって、私の事、心配してくれていたのね。最初は、私が貴女を視る事も、嫌がっていたのに」
「……あれは、だって」
口篭もると、隣に座る少女が喉を鳴らすように笑う。表情は薄いままだが、それでも彼女の感情は伝わってきて、ノエルは更に困ってしまう。
最初に彼女と遭遇し、互いを絡ませ溶け合い、そして戦って、明確に“分かれた”。
それ以後、それなりの時間を彼女と共に過ごした結果、ノエルの中での彼女は――恐らくは人でいうところの“双子の姉妹”に近い存在であると、そう捉えるようになっていた。
能力は違う。在り方も違う。しかし記憶の多くは共有され、意思の動きすらもある程度は読み通せる。
近しき他人。違いはあれども似通った者。それは正に双児の関係だった。
少なくとも、今のノエルにとって、ウィースルゥインという存在は多少なりとも気を掛けるべき対象であり、それを本人から指摘されても、明確に否と答え繕う気にもならない相手となっていた。
「それで? 私の事だけを考えていた訳でもないでしょ?」
未だ笑みを含んだウィースルゥインの声に憮然としつつも、ノエルは話を続ける。
「勿論です。といいますか、あなたの事についてはほんのちょっとです」
「うん。判ってるから話続けて?」
「……何なんですかその妙に余裕ある態度は。はぁ……ええと、ああ、自分の事です。わたしの、力について」
ノエルは自分の手を翳し、確かめるように指先を動かす。
「ウィースルゥイン。貴女が持つ色々な力。それをわたしも段々と扱えるようになってきたな、と。そんな実感をようやく得られるようになってきたと、そう思っていたんです。これならきっと……【NAME】の助けになれる」
ウィースルゥインとの“勉強”の中で、自分に眠っていた“人形”としての力が、大きく開花していくのを感じていた。それも恐らくは本来の自分に設定されていた性能以上のものとしてだ。
大禍鬼の力を受ける器としての機能を、ウィースルゥインが持つ他のあらゆる強存在の力をも引き出すものとして使う。
結果、本家本元よりは幾分劣化しているとはいえ、たかが“人形”が操るには埒外とも言える多彩な能力を行使出来るようになっていた。身体能力もあらゆる部分が向上し、これまでは鬼の強い陰性概念に晒されると影響を受けてしまっていた不安定さも一切なくなった。
自分が大きく、一つの機能として完成していくのが判る。今の自分なら、【NAME】の隣に立って戦う事に迷いを得る事もない。
内心の充実感に我知らず頷いていると、
「ノエル、凄いよね」
「は?」
ぽつりと返された声に、ノエルは怪訝と首を捻る。
確かに、自分は“人形”としてこれまでと比べて大きな力を持ったという自覚はある。
だが、
「……あの、これ貴女から間借りしているだけの力なのですが。それを借りている本人から凄いと言われましても」
そう。結局の所、今の己は“人形の主”たるウィースルゥインあってこそなのだ。その力の供給元から感心されても困る。
対して、ウィースルゥインは何処か拗ねたような鼻息を漏らし、
「だって私、ノエルみたいに、うまく使えない」
「使っているではないですか。先刻の結界だって、わたしでは構築できない優れたものだと、わたしは思いますが」
「ああいうのじゃなくて。私が、本当に持っている私の力。なんとなく、判るようにはなってきたけど」
ウィースルゥインの視線が背後に流れる。
風に揺れる彼女の長い髪。その先端の一部がゆらゆらと揺れて、時折獣の姿になり、そして消える。
「これだって、何でこうなるのかよく判らないし。私が元々持っていた私の記憶の中で、私はもっとはっきりと、私の力を使っていた。でも、今の私はそれが上手く動かせない。だから、ノエルは凄い。私が使えない私を、ノエルは引き出して使ってる」
「……そうはいっても、わたしに元々存在していたらしい機能に、貴女が持つ力を流し込んで無理矢理行使しているだけですから、そう褒められたものでもないのですけれど」
「でも、多分イェアは、私が私の、今の私だけが持つ力を必要にしているみたいだから」
「…………」
話の方向性が、少し変わったのを感じる。
ノエルはどう答えるべきかと少し考え、しかしその間に、ウィースルゥインが更に言葉を続けた。
「ノエル。貴女はイェアが準備してるお話の事、考えてた?」
「……はい。主に今日、【NAME】がああして呼ばれていた事について、ですけれど」
細波の中。ノエルが意識せずに考えていた大凡を占める部分がそこだった。
イェアが最近進めている大規模な計画については、ノエルは多少、ウィースルゥインはそれなりに大きく絡む形で話を聞いている。
その計画は、ノエルとウィースルゥインが近頃見通せるようになってきたあの記憶――“城”での出来事を受けて立てられたものだという事も。
「【NAME】が呼ばれたという事は、もう計画も実行段階に移ってきた、という事なのでしょうけれど……ウィースルゥイン、あなたが依頼された話、ちゃんと問題無く進みそうなのですか?」
「難しい。さっき言った通り、まだ私は、うまく使えないから。でも、それはイェアもわかってるから、どうにかすると思う」
考え考え話すウィースルゥインの言葉に異論はなかった。確かに、イェアならばどうにかする手段を考えるだろう。
しかし、
「ずっと、考えてはいるんです。本当に、あの方法でどうにかできるのかって」
「……んー。イェアの考えは間違ってはいないと思う」
ただ、それは。
「イェアの知っている事が全てなら。後、“足りる”かどうかも話は別になる」
「…………」
彼女の言葉に、ノエルは黙り込み、畳んだ膝頭に顔を埋める。
ノエルとウィースルゥインは、自分達が断片的に知り得た“城”以降の事柄を、可能な限りイェアに伝えていた。
しかし、それはあくまで可能な限り。
うまく自分達で拾い上げ、明確に言葉とする事が出来なかった事柄というものも確かに存在しており、当然、それはイェアには伝わっておらず、知っているのはノエルとウィースルゥインのみだ。
欠落している情報。それが、イェアの計画に影を落としているのかどうか。それはノエルにも、ウィースルゥインにも、はっきりとは判らない部分だ。
加えて更に一つ。“足りる”かどうか。
イェアの計画の骨子。巻き戻しを回避するための“誤魔化し”の部品。それが果たして、誤魔化すに足るものなのかどうか。
「ウィースルゥイン」
「何?」
本当に、こうすべきなのだろうか?
一瞬の疑念を、しかし振り払う。月明かりに照らされたさざめく海を見据えたまま、ノエルは強張る舌を動かし、言葉を続けた。
「もし“足りない”場合、わたしでどうにか出来ると思いますか?」
問いに、暫く反応は無かった。
視線を隣へ向けると、珍しくウィースルゥインの顔に表情が浮かんでいる。
酷く、渋い顔だった。
「そういうやり方は、取るべきじゃない。それは、私の記憶が教えてくれてる。きっと、あなたが大事に思う人達、皆が悲しくなる」
「…………」
「それに、あなたくらいじゃ足りない。あなたで足りるくらいなら、あの鬼達でも足りる。もしどうにかしようとするのなら、もっと強く、もっと大きなものがいる。例えば」
ウィースルゥインはそこで一度言葉を区切り、そして表情を普段のフラットなものに戻す。
「難しい。取るべきじゃない。それは判ってる。でも、私はわたしだから、そう考えるわたしも否定しきれない」
「ウィースルゥイン……」
「わたしでどうにか出来るか。それは判らない。けれど――私達なら、多分出来る」
ノエルを目を見開いて彼女を見る。
こう言ってしまって良いのか。それを認めてしまって良いのか。瞬間、幾つもの逡巡が生まれたが、しかし全てが押し流された。
自分の求める結末がより確かになる。その安堵に比べれば、それらは全く軽いものだった。
「良いのですか?」
「良いも悪いも無い。言ったでしょう? 私は私。だけど、その私を作ったのはあなたなの。だから貴女の想いは、私も持ってる」
「……ありがとう」
深く、溢れるような感謝の言葉で、もしもの約束は結ばれた。
ノエルは胸中にある想いと、そこから生まれる覚悟を自覚し、こう呟く。こう呟くしかなかった。
「自らの犠牲を是とする。やはりわたしは、“人形”なのだと。……そう、思います」
真なる楽園 幕引きの導
――幕引きの導──
近頃、エルツァン島探索を行う常駐軍部隊が拠点としている、島沿岸部に造られた野営陣内の雰囲気は、大きく変化していた。
より具体的にに表現するならば、軍部隊が行っている活動の方向性が変わってきた、というべきだろうか。
これまで、島に派遣されたアラセマ常駐軍部隊は、謂わば地固めのような作業を堅実に進めてきた。
最初に探索の拠点とするべく島沿岸部に野営地を設営して、その周辺に棲息する亜獣を総員で以て徹底的に駆除。陣地の安全を確保し、島内での足場を確固たるものとした後、隊員の中から諜報に長けた者を集めた斥候部隊と、精鋭からなる探索部隊を複数編成。それらを状況に合わせて適時投入していくことで、自分達の掌握圏をじりじりと伸ばしていった。
用心に用心を重ねた慎重な探索計画である。その進展は、お世辞にも敏速とは言えないものだったが、しかし、一歩一歩着実に、立ち止まる事なく状況を前へと推し進めた。エルツァン島探索部隊の長を努める学士、イェア・ガナッシュの立案により行われていたのは、そんな調査活動だった。
だが、近頃はどうもそれまでの方針とは明確なズレが感じられる動きが増えてきていた。
まず、探索隊を編成、派遣する頻度が目に見えて減少し始めた。
また、探索行動の減少に反比例するように、軍陣地内での内務が増えていき、それも設営した天幕群の解体や物資の整理処分等が主となっていた。
特にここ数日は、沖に停泊する船舶へ、島内に備蓄されていた物資や収納した天幕の多くを引き上げる作業も行われるようになり、一部の兵達の間では、軍はこの真なる亜獣達の楽園の探索を諦め、島から手を引くのではないかと、そういう噂も生まれ始めていた。
そんな、少しばかり浮き足立ち始めた兵士達の間に、一つの報が伝わる。
探索部隊の隊長であるイェア・ガナッシュ。そして彼女の補佐役の副隊長を務め、兵員の実質的な指揮も行っているノクトワイ・キーマ・フハール。謂わば隊の要といえる二人の連名によるその指示は、今日の夕餉の後、調査部隊に所属するほぼ全員を、陣地の中央――既に大天幕群の撤収が半ば終わり、ほぼ何も無い空き地となっているそこへ集めるように、というものだった。
呼集の対象となる面子は、今まで沖の船にてほぼ別行動を取っていた者達や、常駐軍部隊とは別の場所に拠点を定めて活動しているキヴェンティの一団すらも含まれ、エルツァン上陸時に行われた最初の集まりよりも多くなる計算になる。
この指示に、殆どの兵士達が少なからずの動揺を見せた。
それだけの人数を集めるというのなら、余程重要な、この部隊の進退に関わる話が行われるのは間違いない。
ならば以前からの懸念通り、エルツァンからの撤収を報せる為の集まりなのかではないか?
作業を進めながら、様々な噂話をする兵士達。そんな中で一人、知らせを伝え聞き、逆に気を引き締める者が居た。
――いよいよ、か。
【NAME】は小さく独りごちる。
兵士達とは違い、【NAME】には思い当たる事があった。
“固独”たる万象の雛。ウィースルゥインが自分達の元に現れてからずっと、イェア・ガナッシュが水面下で進めていた、この繰り返される状況を打破するための策。
それがようやく始まる事を、【NAME】は悟ったのだった。
「…………」
静かなざわめきが満たす陣地の中で、【NAME】は空を見上げる。
天にて浮かぶ太陽は既に地平へと傾き始めて久しく、辺りは徐々に茜色へと染まりつつある。直に、夕食の準備が始まるだろう。それが終われば、伝えられた会合の時間となる。
コルトレカンの港でノエルと出会ってから――より深く遡れば、ランドリートの島でオリオールと遭遇した時から続く、長い長い芯海での旅路。
その幕を引く導が示される時は、もうすぐそこにまで近付いていた。
日は既に地平の向こうへと消えて、場が月と星、そして篝火の光で照らされるのみとなった時間。
陣地中央の広場では、沖にて停泊する船や歩哨担当者を除いた軍部隊員のほぼ全員が集められていた。
彼等に対し、部隊の上層部であるイェアとノクトワイが部隊の今後についての説明を行う、というのが今回の集まりの趣旨であるらしい、とは、【NAME】がここへと来る際に近くを歩いていた兵士達が、ぼそぼそと話し合っていた噂だ。
場にはキヴェンティ達の姿もあり、兵士達の集まりからは少し距離を置いて全員が姿勢良く座し、その最前列には彼等の長であるリゼラ・マオエ・キヴェンティの姿もある。オリオールやノエルは、イェア達の補助をするべく彼女等の傍であれこれと話しながら、時折背後の天幕などに出入りする等して準備を進めていた。
そうして、暫くの時間が経った頃。
「では、今から皆様に、重要なお話をしようかと思います」
集まった皆を前に、何処か緩い調子で始まりを告げた彼女が、続けて提示してきたものは、兵士達の間で噂されていたエルツァンからの撤退指示などではなく、寧ろ真逆と言っても良い代物だった。
その内容自体は、至極判りやすいものだ。
「取り敢えず、下準備が全て終わりましたので、これより当部隊はほぼ総員でもって島の内陸へと侵攻し、エルツァン島に逃走したと思われる“鬼喰らいの鬼”を討伐する作戦を行います。今日は、その事前説明の為の場を、こうして設けさせてもらいました」
大方の予想とは完全に相反する発言に、集まった兵士達の間で大きな響めきが起きた。
しかし、それは直ぐに収まる。殆どの者達からすれば、彼女の宣言は成る程と、腑に落ちるものだったからだ。
最近行っていた、陣地を解体し物資を整理する作業は、兵士達の間では島から撤収するが故だと考えられていた。
だが逆に、目的を達するために総力で島へと入るという場合であっても、この陣地は確かにもう不要のものなのだ。
沖の船へと回収された物資類は、持ち運びの難しい大型の天幕や設備、予備の武具などが多く、食糧類や簡素で軽量な天幕、更には陸地での輸送に使う道具類などはそのまま残されている。
言われてみれば確かに気づく。これは撤退ではなく、進軍のための用意だったのだと。
「――――」
それを知り、これまで何処か意気消沈気味であった兵士達の雰囲気が変わる。
当然だろう。今まで自分達が行っていたのは地味な調査作業のみで、もしかするとそれだけで終わりかもしれないと思っていた。そんな所に、ようやく自分達が本来任せられていた筈の作戦が行われるというのだから。
彼等の一瞬の戸惑いは、直ぐに沸き上がるような歓声に変わった。
「……あら」
そんな兵士達の様子にイェアは少し面食らったようで、表情は笑みのまま少し口を引きつらせて、逆にノクトワイは予想通りとも言うように腕組みしてこくこくと頷く。
「ほら、部隊長殿。固まってないで説明説明」
「あ、ああ、はい。ええと……それでは今回の作戦の概略に入る前に、まず皆様には現在わたくし達と、そしてそちらの――」
イェアの視線が、【NAME】の方へと向く。【NAME】が立つ位置は、イェア達とも兵士達とも距離を取った、篝火の間の暗闇に紛れるような位置。基本的には部外者であるため、配慮してそういう位置取りをしていたのだが、イェアの方は目敏くこちらの存在を把握していたらしい。
イェアの視線に誘導されるように、場の者達の多くが【NAME】の方を見、「神形の……」だの「……遺跡の事件を解決したっていう」などとぼそぼそと小声で遣り取りする声が耳に入る。居心地悪く、【NAME】は反射的にイェアの方へとひらひら手を振り、夜の闇に紛れるように更に数歩下がる。
その様子に、イェアは【NAME】の厭う気配に気づいたらしい。
「あー、すみません、話振ってしまって。えっとまぁその、【NAME】さんやあと、そちらのオリオールさんや、キヴェンティの方々のご協力で把握出来た、エルツァン島内の状況についてを一通り確認させて頂きたいと思います。……ノエル、あれ持ってきてくださいな」
そうして、一度裏手に残されていた一つの天幕から出てきたノエルが広げたものを見て、兵士達はまた驚く事になる。
彼女が持ってきたのは、大雑把ではあるもののエルツァン島のほぼ全域を埋める地図だった。
――エルツァンの島内は、無数の異質な地形が、不定の繋がりを持って存在する。
探索初期にイェアはそう解釈し、事実、カール・シュミットの手記と実際の探索結果では、地形の繋がりは必ずしも同一のものではなかった。
しかし、【NAME】がオリオールやリゼラと共に幾度か島の深部まで入り込み、そしてウィースルゥインが幾度も見た【NAME】達の軌跡の情報を取り入れると、少なくとも今現在この時に於いては、島内の各地形の繋がりをほぼ確定出来ると、イェアは考えた。そうして完成したのが、ノエルが皆に対して広げてみせた地図である。
その製作には【NAME】も協力していたため存在は知っていたが、軍内では精々“森”と“谷”の調査が終わり、その先に手を伸ばそうかという進展速度であった筈で、それを認識している兵士達にとって、目の前に提示された島内全体に及ぶ地図は、驚愕に値するものだろう。
当然、彼等からすると唐突に出てきた代物に、疑念を覚える者もいる筈だ。しかし口に出すことはない辺り、普段緩くはあれどもさすがは軍隊という事なのだろう。言葉にならないざわめきを僅かに溢すだけで、部隊の長の続く言葉を待つ。
ただ、以降の話の流れがある程度読める【NAME】からすると、その沈黙も長くは持つまい、と思うしかないが。
「さて、一応見て判るとは思いますけれども、これが現在把握しているエルツァン内の地形構成です。方角についてはかなり当てにならないので、まぁわたくし達が今居る海岸が島の最南端にあると仮定して記述しています。存在する地形は大別して六箇所」
彼女は、伸縮する細い棒をしゃきりと伸ばして、地図の下方から地形を示す大円を順番に突いていく。
「この海岸から繋がっているのが“森”と“谷”の二つ。ここから“森”と繋がっているのが“湖”で、“谷”と繋がっているのが“丘”になります」
繋がりを示すように、イェアは大円と大円の間を棒の先端でつつと滑らせる。
「因みに、“森”と“谷”は隣接しているように見えますが、実際は接点はありませんわ。空間的な断絶があって、その先には進めないようになっています。この辺の事は、探索活動に参加されていた方は直に見ているのでご存じの事かと思います」
その言葉に、兵士の幾人かは浅く頷くだけだ。兵士達の興味は、その先に記された地形群にあった。何故なら、現在、軍内での調査が進んでいるのはその二地形のみで、隣接していると思われる“湖”や“丘”に関しては、一部の斥候部隊が短い時間足を踏み入れ、侵入地点の周辺を軽く捜索した程度であったからだ。
兵士達の興味を知ってか知らずか。イェアは普段の調子と変わらず、淡々と地図についての説明を続ける。
「そして“湖”からは“丘”の他にも“谷”へと繋がるルート、“丘”からは“湖”と“森”、更に“洞”に繋がるルートが確認されていますが、この幾つかは不可逆――つまり行く事は出来ますが戻る事が出来ないようになってると考えられます。最後に“山”と“洞”が、互いに行き来可能であるのも確認済みです。各地の接続としてはこんなところでしょうか」
「要は、島内にある地形がどう繋がってるかがある程度判ったんで、それを踏まえて島内に各地形を配置してみたって程度の地図なのよねんこれ」
ノクトワイの補足に、イェアは短く頷く。
「これに、各地の地形と直接繋がる“地下”と、“山”と“洞”から行ける“城”を合わせた合計八地点が、今確認できているエルツァン島の全てとなります。先刻副隊長が仰った通り、一応、島内の大きさに合うように大雑把な感じで地形を割り当てて描いてますけれども、それぞれの地形の大きさは可変で……まぁそれぞれ独自の世界が島の中に隣り合って存在していると認識してもらえれば良いと思いますわ。これでも、わたくし達の活動については殆ど問題のないものですから」
そしてイェアは長棒を、ノエルが掲げ持つ島の地図の最上部に近い位置をつんと突いた。
「で、今回わたくし達が目指す場所は、今居る海岸からほぼ反対側の位置に存在するここになります。この目的地を便宜上“城”と呼称しますが、この場所には古代期に構築された封印が存在し、わたくし達の討伐目標たる大禍鬼はその封印を潜り抜け、その奥にて潜伏している、という所までは判っていますわ」
「つまり、我々はこれから侵攻のために部隊を再編し、“森”経由か“谷”経由、どちらかのルートを使って島を進み、この“城”に向かうという事ねん」
「但し、この封印には守護者が存在する事も判っています。名はリンドヴルム――皆様の中には知っている方もいらっしゃるかと思います」
言葉を切り、イェアが窺うような表情を向けると、兵士達の間で明確な反応が起こる。「リンドヴルムってあのお伽噺とかで出てくるアレかよ」だの「いやいやちゃんと記録として残ってるでしょ」だの「俺婆ちゃんがリンドネタでめっちゃ怖がらせきて小便漏らしたの思い出したわ」だのと、やはり少し普通の反応とはズレている気がしたが、【NAME】としては自分が知らなかったことの知名度の高さにちょっと驚くと同時に、彼等がリンドヴルムの名を出されても怯んだ様子も見せない事に尚驚く。
「勿論、リンドヴルム相手に正面から殴り合うにはわたくし達だけでは到底無理ですし、何よりリンドヴルムの討伐がわたくし達の目的ではありませんので、そこはどうにか、上手く躱す方法を考えてはおります。ここについてはわたくしの部下達の方で準備はさせてますし、本番前に改めて詳細説明を行いますので、省いて話を進めますわね」
「といっても、それなりには戦う事にはなるでしょうから、一応心構えだけはしておくようにねん」
「「はっ」」
締めるようにノクトワイが言うと、瞬時に腹に力の入った返事が重なった。普段緩く見えても兵士としての練度はやはり相当なものだなぁ、と改めて【NAME】が感心する間に、イェアの話が再開される。
「取り敢えず、今回の作戦を単純に説明すると、わたくし達軍部隊の戦闘員が総出で島へと入り、超常地形を抜けた後でリンドヴルムと、そして“鬼喰らいの鬼”と戦う……という話になるのですが、実際のところはもう少し面倒だったり、対応の為の遠回り、あとその関係で、非戦闘員に属する方々にも同行をお願いする感じになります。先刻のリンドヴルムの件でも、うち所属の学士の子達を連れて行く必要があるんですけど、あの子達はあんまり戦闘経験とかありませんから、兵士の皆さんに半ば護衛してもらう形で進軍していく事になると思います。お手間を掛けることになりますが、必要なことですので、どうか宜しくお願いします」
「ルートの方も、どちらか片方を通ってさっさと“城”に行く……って訳にもいかないんだっけ?」
「はい。えーっと……」
イェアは視線を僅かに虚空へ向け、少し考えるような仕草を挟む。
「実は、“城”に施されている封印をどうにかする時、事前に必要なものがありまして。非常に大きくて強力な存在概念を、二つほど、どこかから調達してこないと駄目なんですの。エルツァン島の超常地形にはそれぞれ、土地毎にその地を象徴するような強力な個体が棲息しているのが確認されているのですが、その中で“洞”、そして“山”には特に強力な、大禍鬼級の者が存在しているのが判っています。ですから」
ノエルは地図上、上から二列目に存在する丸二つをとんとんと順番に叩き、
「“谷”あるいは“霧”ルートから島へ侵入した後、“湖”ないしは“丘”を経由してから、“洞”と“山”の両方を周り、ここに棲む大禍鬼二体を撃破、崩滅させ、その存在概念を封縛する必要があるんですの。そこで捕らえた存在概念を使って……あー、その、“城”の封印をどうにかします。あと、これはここに集まってる皆様に謝っておきたいところなのですが……」
イェアが少し口篭もりながら、言いづらそうに言葉を続ける。
「軍部隊での活動はそこまで――存在概念二つを回収して“城”到着後、リンドヴルムを対処するまで、となります。それ以降、封印内に潜伏すると思われる“鬼喰らいの鬼”に対しては、最初の方針通り、【NAME】さん、あと一部の概念干渉に対して高い耐性を持つ人員か、防御手段を持つ者、あと、わたくしと副隊長もそちらに参加して討伐部隊を編成。少数で封印内に潜入し、“鬼喰らいの鬼”の討伐を狙います。皆様にはその間、“城”の確保と、リンドヴルムの対処を継続してお願いする形になると思います」
そんなイェアの言葉に、場に集まっていた者達からの明確な反応は無かった。
正確には、感情を表に出さぬようにした結果、無反応という反応が返ったというべきか。
うっすらとした落胆。或いはやはりという納得。仕方無いという割り切り。そして微かな安堵。それらが静かに、沈黙を形無く彩る。
対し、ノクトワイはにやにやとわざとらしい笑みを見せて、
「要するに、アナタ達の仕事は“鬼喰らいの鬼”と戦う主力を如何に消耗させずに“鬼喰らいの鬼”の元へと送り届けるかって事。それでも結局、幾つかの場面――例えば土地の主みたいな大物や、リンドヴルムとの戦いとかだと、結局【NAME】に出張って貰う事になるでしょうねん。その辺をアタシ達だけでどうにか出来るなら、一丁前にヘコんだり怒ったりってのもアリなんでしょうけどねん。実際の実力を考えりゃ、むしろ英雄殿の露払い役っていう光栄なお役目だと思いなさいな。アナタ達だって噂くらいでなら知ってるでしょ? あそこの彼が、ほぼ単身で大禍鬼を何度も狩ってるって話」
またこちらに視線が集中して、【NAME】はいよいよ居心地悪く、小さく肩を竦めて誤魔化した。
確かに、戦績としてはそうなるが、それは幾つかの“反則”を用いて更には状況が味方したが故であって、それこそ独力で導いた結果な訳では無い。だからあまり持ち上げられると、どうにも居た堪れない気になるのだが、かといって今は強硬に反論して、話の流れを滞らせる場面でもなく。【NAME】としては、ただただ黙る以外にない。
そこへ、イェアが自分達に注目を戻すようにぱんぱんと二度ほど手を叩き、
「有り体に言えば、ノクトワイ様の仰る通りとなりますわ。わたくし達の主となる仕事は、【NAME】さん達を護衛しつつ“洞”と“山”へと赴き、そこに潜む大禍鬼を弱体化する策を講じた後、【NAME】さん……というか、大禍鬼と渡り合える実力を持つ人員を主力として置き、軍部隊はその補助をする形で戦闘を行う事になります。そして、討伐後に鬼を封縛するのですが、それには特別の印章石が必要で――ええと」
イェアはごそごそと地面に置かれていた荷物袋を漁ると、拳大の燦めく石を細鎖で繋げたものを持ち上げる。
「このように、こちらも既に準備済みです。存在を小規模の位相世界へと封じる、大型の封縛印章石複数個を術式を使って連結する事で、一つの封縛印章陣として駆動するようにしたものですの。鬼種が持つ陰性存在概念が、個としての形を解いた時のみに特化とした調整を施す事で、本来ならば到底不可能な大禍鬼級の強大な存在概念の封縛を可能にしていますわ。合計二つ、用意が終わっていますから、【NAME】さんが大禍鬼を崩滅させた後、これを使い、崩れた存在概念を封縛します」
「確かこれ、普通の封縛印章石とはちょっと扱いも違うんだったかしらん?」
「先刻言ったとおり、対象を弱らせるだけじゃなくて、存在自体を砕いて、崩滅させないといけませんわね。あと、駆動に莫大な同調力――より正確には概念干渉力が必要ってところですけど。まぁ、そこについてはちゃんとあてがありますのでご心配無く。存在概念を確保し、“城”のリンドヴルムを無力化出来たなら、後は“鬼喰らいの鬼”討伐を行います。これに成功するか、あるいは失敗し“鬼喰らいの鬼”討伐部隊が全滅した場合は、速やかに島の外周部へ移動後、沖にて停泊する船と連絡を取るなり、位置を報せる照明術式を使うなりで合流、撤収してください。成功失敗問わず、エルツァン島での活動は、今回の計画で終了と、そう考えて下さい」
そこまで一気に話して、イェアはふぅと軽く息を吐いた。
「今後の活動計画は、大まかに説明するならば以上の流れとなりますが、皆様の中で、これまでお話しした作戦についての疑問点について、何かありますでしょうか? 無いようでしたら、具体的な部隊編成、進行日程、行動計画の話に移りたいと思うのですが」
イェアのその問いに、場に集まった者達は、しんと静まりかえった。
それは、疑問が無いが故の沈黙ではないのは、少し離れた位置に居た【NAME】には直ぐに判った。
兵士達の間で、それぞれ窺うような気配がある。誰が代表して、皆の心の中にある大きな疑問を口にするのか。それを窺うための間だ。
多数の視線が行き来しあい、そして最終的に一人の男に集約された。集まる兵士達の前列にどかと座ったその男は、髭面の中年。部隊の中では小隊の一つを束ねる役につく者だったか。
「……一つ、質問の許可を頂きたいのですが、宜しいでしょうか」
「発言を許可します。どうぞ」
「隊長殿は、そこまで詳細な島の情報を、一体どのように取得し、そして作戦立案の根拠となりうるものと判断されたのでしょうか? 失礼ながら言わせていただきますと、到底通常の手段で手に入れられる範囲の情報量を超えているように、自分には思えます」
「…………」
問いに、イェアは近くの何人かの人物に目配せをしてから、改めてその兵士に向き直る。
「貴方の質問はもっとも……というより、わたくしとしても恐らく皆様が疑問に思われているのも判っていますわ。わたくし自身も、逆の立場であるなら一体何処から島の奥地にあのリンドヴルムが居るだの、封印をどうこうする方法がだの、大禍鬼の存在概念を捕らえられる印章石群の準備なんて出来たんだって思いますもの」
だから当然、それには相応の理由が存在している。
それこそが、
「実は、このエルツァンという島をよく知る、協力者を得る事が出来たんですの」
「協力者……ですか?」
ぽかん、と髭面の兵士は声を上げた。
その反応は、他の者達にも共通するもので、例外は【NAME】のような以前から事情を知る者と、そして恐らくイェアやリゼラ達から事前に話を聞いていた、キヴェンティ達や一部の学士達に限られた。
この結界に守られたほぼ未踏の島だ。
真なる亜獣達の楽園とも呼ばれ、人は当然、文化持つ亜人の集団すら見当たらないこの島において、協力者を見つけた、というのは正に寝耳に水ともいえる話だったろう。
そして【NAME】は、ここでか、と自分の中に緊張が走るのを感じる。
イェアは事前に言っていた。今後の作戦が滞るため、軍部隊員達にも彼女を――万象の雛たる“固独”の大禍鬼を紹介するつもりである、と。
ならば、今がつまりその場面であるのだろう。
だが、【NAME】には聞いていない部分があった。
一体彼女を、どのように説明するつもりなのか、だ。
何せ、ウィースルゥインはあらゆる存在を内包する人ならざる異質の者。しかもその在り方は、人の姿を基本としているが、存在概念的には鬼種の要素がもっとも強い存在だ。
更には、名前からしてウィースルゥインである。
今この場にいる者達は皆、アノーレ島のアラセマ常駐軍部隊所属だ。四大遺跡事変の事も知っている。その流れで、過去にゴディバに封じられていた大禍鬼の名を覚えている者も、少なくはないだろう。ここでその名を素直に出せば、果たしてどういう反応が返るのか。あまり想像はしたくない。
さて、その辺りをどのように配慮するのか。全て隠すのか、それとも全て明かすのか。隠すならばどうその存在に理由を付けるのか、明かすならばどうその存在を協力者として認めさせるのか。
そう【NAME】が考える間に、イェアが近くに居たノエルに指示をし、ノエルは天幕の中へと入っていく。どうやら、既にウィースルゥインはあの天幕の中にて呼び出され、出番を待っている状態だったのだろう。イェアからすると、今回の質問は想定内のもので、このタイミングで彼女を紹介すると決めていたのだろう。元々、あの質問をした兵士自体がサクラであるという可能性すらある。
そして天幕が開き、ノエルに手を引かれて、薄布を纏った少女が姿を現す。
この地においては場違いという他無い年頃の少女。年季の入った軍服を纏う者達の中で透けるような薄布を纏っただけの身体が一歩、前へと歩く度に、長い長い藍色の髪が、風も殆ど無いというのにまるで生きているかのように靡き、その先端は妖しげな曲線を描く。
その様は、純粋な美しさだけではなく、この世のものならざる異質さ、異様さを、見る者に強く印象づけた。
彼等の心が、初めてウィースルゥインの姿を目にした驚きから、その常人とは明らかに異なる気配に対して、嫌悪、或いは恐怖の感情を催す前に。
イェアが彼女が素早く彼女の隣に立って親しげに両の肩を抱いてみせると、
「この子は、エルツァン島の象徴であり、それを守る事を役目とする妖精……つまりこの島に宿る地母種ですわ。名前は、ウィーちゃんといいますの!」
「――――」
満面とも言える笑みを見せて声を張ったイェアに、【NAME】は素直に思う。
――これは、巧い。
この世界に存在する代表的な強存在、芯属の一種として考えられている地母種は、人との対話も可能な異種族である。状況によっては人に協力してくれる余地を持ち、更には人に似た姿を取る事もあると伝承にて知られている。彼女達ならば、唐突な協力者としても人々に受け入れられる土壌があるのだ。
何より、ウィースルゥインの中には確かに、地母種としての要素も存在しているのだ。一部嘘が混じっているが、完全な嘘というわけではない。
兵士達が「地母……芯属?」と虚を突かれている間に、イェアは畳み掛けるように言葉を続ける。
「えっとですね、本当の名前はもっとこう地母種さんっぽい……“羽衣に翻る女王”とかそんな名前? なのですけど、ちょっと長いのでウィーちゃんです! 【NAME】さん達が島の深くを探索している時に偶然彼女と出会って、その時に意気投合して、わたくし達に協力してくれるようになったんですの!」
――滅茶苦茶強引に話を持っていってるが大丈夫かこれ。
と、事情を知っている【NAME】は感じるが、先入観無しだとそうでもないのか? と首を捻る。その間にもイェアの話はどんどん続く。
「ウィーちゃんが言うには、“鬼喰らいの鬼”がこの島にやってきて、“城”の奥で何かしはじめてから、この島全体の土地概念に何時も以上の物凄い歪みが出てきていたみたいで。それをどうにかする為に“城”近くでうろうろしてたそうなんですけれど、封印の守護者であるリンドヴルムに邪魔されて、困っていたところを【NAME】さんに出会ったと。そうですよね? ウィーちゃん?」
「…………。うん、そう。私は地母種。この島から生まれた地母種よ。困ってたから、【NAME】と協力する事にしたの」
気づくか気づかないかという間の後、殆どイェアの言葉をそのまま発するウィースルゥイン。打ち合わせをやってないのかと心配になる遣り取りだが、しかし強引ではあれ、話自体の筋は確かに通っているのだ。
地母種とは、大禍鬼とは真逆の存在。土地や自然の概念より生じてそこに根付き、その安定と平穏を望む妖精種の長たる者達だ。
イェアは彼女を、この島から生じこの島を維持するために存在する地母種とした。それはつまり、エルツァン島のあらゆる事情に通じている事を意味し、そして外部からその島の安定を脅かす存在――イェアはこれを“鬼喰らいの鬼”と定義した――に敵対する者でもある。つまり敵の敵は味方、という納得のし易い構図を造り出していた。
「それでですね。【NAME】さんが連れてきたウィーちゃんとお話をして、この島について多くの情報を得ました。今回の地図にしても、作戦にしても、“城”の封印にしても、この子がいなかったら全く判らないままだったんです。本当に、感謝してもしたりないくらいで」
この部分の話は全くの事実であるあたり、果たして事前に考えていたのか、それとも今アドリブで考えて話しているのか。
どちらにせよ、兵士達が持つ疑問に対しての答えとしては十分なものであるように思えた。こういう想定外の助力者がいなければ、先程イェアがぶち上げた情報や計画は到底立てられないのは明白だからだ。
であるならば、もう彼女の言を信用するしかない。勿論、訝しさを心に残した者はいただろうが、しかしそれも、十分内に呑み込める程度のものだった。
何故なら、
「それじゃ、ウィーちゃんの方から、皆様に挨拶、お願いできますか?」
促しを受けて、一歩。ウィースルゥインが兵士達の方へと進み出る。
「……みなさん、初めまして」
小さく、淡々とした、しかし確かに人の言葉を彼女は兵士達に向け、そしてぺこりと頭を下げた。
在り方は化け物の域。心はまだ生まれたばかり。それでありながら、彼女には人との遣り取りに対する知識は持ち、それに倣う素直さと賢さがあった。
表情は薄い。けれども、その瞳の奥には獣ではなく化生でもなく、人に近い意思の色が宿っている。それは、この夜の暗がりの中であっても、目を覗き見た兵士達にならば伝わるものだった。
彼女は広場に集まった皆を見渡す。多くの兵士達、キヴェンティの一団、学士や、普段は船の上で活動し、殆ど陸に上がってこない者達もいる。その殆どは彼女の事を知らないだろう。しかしウィースルゥインの方は、ノエルや、そして【NAME】を通じて見知っている者達が殆どだ。
そんな彼等に対し、ウィースルゥインは少し考える間を置いて、話し始める。
「私のお願い。島を守るために鬼を倒す。その力を貸してくれるという貴方達に、まずお礼を言わせて。そして、約束します。私が持つ力も、貴方達を助けるために使うから。だから」
イェアが口早に告げた嘘八百に従うようにそこまで話してから、ウィースルゥインは僅かに目を伏せ、そして面を上げる。無表情だった顔は僅かに、真剣味を帯びた硬さを宿し、
「だから、どうか――私の事を認めて、私が居る事を許してください。そうすれば、私はみなさんと一緒に居られると、そう思うから」
その訴えは、イェアの作り話から生じたものではなく、ウィースルゥイン本人が持つ願いに近いものなのだと、【NAME】には判った。
未だ、この世界との係わりを安定して持つ事が出来ないウィースルゥイン。それは酷く観念的な要素でありながら、ウィースルゥインという存在にとって極めて重要で影響の大きいものだ。ノエルを通じ、あるいは【NAME】を通じてでしか、今までこの世界には触れられず、そして実体を得ても、他者から存在を認識される事自体が難しい。そんな環境で暫く過ごしてきて、今ようやく、イェアが彼女に用意した舞台がやってきたのだ。ここで、彼等がウィースルゥインという存在をどれだけ強く認識し、覚えてくれるかで、ウィースルゥインの今後の在り方は大きく変わるだろう。
果たして、兵士達の反応がどうだったかと言うと。
「……かわいいな」
「うん。かわいい」
「なんつーの? ノっちゃん以外で、久々に女の子らしい女の子を見たような、この新鮮なキモチ」
「うちの女衆、男モドキか魔性か研究馬鹿の三択だからな……」
「いやまぁ、地母さんだし正しくは女の子ではないんだろうけど……あれ? 妖精さんって性別あるんだっけないんだっけ? てか地母さんって保母さんみたいでソソるね?」
「何いってんのお前?」
この部隊の男連中は多くがノクトワイ麾下の緩い連中であるため、反応も緩いこと極まりなかったが、しかしこれといって問題視はしていないように見受けられた。
女性陣は多くがイェアの部下である学士達で、こちらはウィースルゥインの存在を事前に知らされていた者達が多かったのか、反応は静かである。
例外としては、学士以外の者達で、
「みんなー。ノッちゃんが二人に増えたわよー」
「これまた弄りがいがありそうなのが来たねっ! もうちょっと早く来てくれてたら色々遊べたのにっ!」
「見てよあの髪と肌。あれが妖精? 妖精のツヤってやつなの? アタシも妖精になれねーかな……」
「やだよアンタみたいなゴツい妖精。夢壊れるわ」
こちらも多くがノクトワイ麾下であるためノリが軽く、やはり気味悪がられている雰囲気はないようだったというか、ノっちゃんってまさかノエルか。兵士達の間で交わされる会話の中で、それが一番驚いた。
そんな彼等の反応を、ウィースルゥインはどう受け取ったものかと掴みかねて、半ば固まってしまっていたが、その両肩に、ぽんと手が乗る。
「取り敢えず、大丈夫みたいですわよ。――ねぇ、皆様! この子の事、受け入れてくださいますか?」
イェアが声を張ると、場に居る者達から歓声にも似た声があがり、そして拍手が響く。
「ありがとうございます! 良かったですわね、ウィーちゃん」
「うん。……うん」
こくり、こくりと表情は薄いままながら噛み締めるように頷いて、ウィースルゥインは改めて周囲に向かって小さく黙礼をした。
それ以降の内容は、軍の人員割り振りや指揮系統の整理など、部外者である【NAME】が聞いていても把握しづらい話題へと移ったため、【NAME】は一度離脱し、時間をある程度潰してからまた戻る事にした。キヴェンティ達も同様のタイミングで引き上げていったようだが、彼等も今回の件ではどう動くつもりなのだろう。キヴェンティ達はあくまで軍の協力者としてやってきている為、その指揮下には入っていない。リゼラが行動の全てを決めている筈だが、果たして彼はどう考えているのか。あとで顔を合わせることが、聞いておくのも悪くないように思えた。
自分に割り当てられた天幕にて軽く休息を取ってから広場に戻ると、頃合いとしては丁度よかったようだ。軍内での作戦会議は一先ず終わったようで、兵士達がそれぞれ散っていくところだった。
【NAME】はその流れに逆らって、会場となっていた広場の中央へと歩いていく。
案の定、というべきか。そこにはイェアを始めとした、【NAME】にとっては見慣れた者達が集まっていた。
ノクトワイ、ノエル、オリオール、リゼラ、そしてウィースルゥインである。
逆に、兵士達の姿は既に殆ど無い。一部は、ウィースルゥインに興味深げな視線を向ける者達も居たが、話し掛ける事もなく、そのまま立ち去っていく。
それを意外と思う【NAME】に、イェアは先刻の長話の疲れが出ているのか、浅く吐息をつきながら、
「有り体に言えば、遠回しに人払いをさせて頂きました。これから少し、わたくし達だけで認識の一致を行っておく必要がありましたので。ノエルに【NAME】さんを呼んできていただこうかと思っていたところでしたけれど、良い所で戻ってきてくださって助かりましたわ」
――認識の一致、か。
【NAME】は小さく、彼女の言葉の一部を反芻する。
結局の所、今回の作戦に於いても、やはり最終的には【NAME】を代表とした、少数による攻略が必要な場面が存在する。先刻行われていた作戦説明は、主に軍部隊兵士に対しての説明という意味合いが濃く、その部分についての話はほぼ省かれていたり、【NAME】達にならば判る嘘も紛れ込んでいた。兵士達への説明としてはあれで十分だが、しかし自分達にとっては足りないものだ。
ならば後で当事者達の間で改めて話をするつもりなのだと受け取り、兵士達への話が終わる辺りを見計らってこうして戻ってきた訳なのだが、他の面子にしても自分と同様の解釈をして、こうして居残ったのだろう。
「じゃ、僕等だけの内緒話を始めようか。……といっても、殆どのところは別に誰かに聞かれてもそう困るものでもないとは思うけどね」
そう口火を切ったのは、オリオールだ。
「先刻の、話を聞いていた限りでは、【NAME】を要として“城”の奥に居るというシンラを少数精鋭で倒す、という流れは変わらないようなのだけれど、それで大丈夫なのかい? ただ倒すだけでは、結局“巻き戻り”とやらが発生して、また最初に戻されるのだろう?」
この場に居る者達には、既に“巻き戻り”等のウィースルゥインから得た様々な情報は一通り話してある。
全員が信じているかどうかは別として、それを前提としてイェアが行動を組み立てているというのは、一応の共通認識にはなっていた。
それ故の彼の問いに、対するイェアは普段の柔らかい雰囲気は影を潜めている。彼女は考え込むように眉根を寄せたまま、少しの間を置いて返す。
「正直に言ってしまいますと、大丈夫と断言出来ない程度に不安はありますわね。先刻の説明では、二体の大禍鬼級の鬼が持つ存在概念を封縛して、それを使って“封印”の方をどうにかすると話しましたが、実際のところ、それがシンラを討伐した際に起きるであろう“巻き戻り”に対しての策ですの」
どうも先程の説明では所々はっきりしない物言いであったのは、そもそもの用途が嘘だったから、という事か。
【NAME】が呟くと、「まぁそういう事です」と少し照れたように笑う。
「それで、今回の作戦の肝は、二種の大禍鬼を概念的に封じ、それをシンラ討伐時に生じる“柱”の欠損に対して穴埋めとして用い、“芯檻”が基本機能として備えている“事象の巻き戻し”による機能回復を摺り抜けよう、というものですわ。同じ大禍鬼、同種の存在概念でもって欠損を補填すれば、“柱”の欠損が生じたという部分を誤魔化せるのではないかと、そういう考えに基づくものです」
そのアイディアは、以前からイェアがあれこれと悩んでいた事に対する一つの解決策だった。
確かに、彼女が想定していた状況が大凡正しいものであるのなら、そう的外れなものでもない、上手く行く可能性がある手法のようにも思える。
だが、【NAME】を含め、場に居る者達の表情は、どうにも冴えない。その皆の内心についてもある程度理解出来るのだろう。イェアは僅かに苦笑し、
「ただ、皆様も薄々感じてはいらっしゃるでしょうけれど、これには色々と問題……と言いますか、本当に可能かどうか判らない、不確かな部分が多分にありますの」
「試しようも無い事ですから、一度やってみないと判らない、という事ですね」
「有り体に言うとそうなりますわ。兎に角情報が伝聞に次ぐ伝聞って感じで、わたくし自身が観測した情報というのがさっぱりありませんから、もう殆ど山勘というか、まぁこれなら多分いけるんじゃありませんの? 的なノリで決めていくしかないと言いますか。個人的には不本意極まりないのですけれど、かといって他にやりようもないですし……」
ノエルの言葉に、イェアは頭痛を堪えるようにこめかみに手をやりながら嘆息する。今回の作戦を計画したものとしては、
「そもそも、大禍鬼を二体も倒して、その上で存在概念を封じ込めるってのが既にハードル高いわよねぇ」
心の底からの言葉、という風にノクトワイが重々しく告げる。
「ウチの連中だってそれなりに鍛えてるし、連携や武装についても相当の域に達してるっていう自信はあるけれど、それでもあまり戦いに慣れてない子達まで連れながら、大禍鬼級の相手ってのは流石に無理よん。そりゃ、牽制とか、時間稼ぎとか、それくらいなら巧く立ち回れば出来なくもないし、ある程度ダメージを与えるくらいなら可能かもしんないけどさ。崩滅――つまり身体に加えて概念的な完全崩壊に持ってくってのは流石にね」
「そこに関して、後、他の地形で確認されている霧や風、或いは雷の竜のような大物に対しては、やはり【NAME】さんに大きな負担を掛ける事になると思います。……御免なさい、【NAME】さん。前に、あんな見得を切りましたのに」
彼女が言っているのは、以前の夜。彼女から今回の計画についての話をうっすらと聞いた時の事だろう。確か、貴方だけには戦わせない、と。そんな宣言だ。
対して、いや、と【NAME】は短く首を横に振る。
あの域の、特に大禍鬼級相手となると、闇雲に並の兵士を突っ込ませたところでどうにもならない事は、既に幾度も相まみえた経験を持つ【NAME】自身がよく判っている。まず、相応の武器や加護等の特殊な力があるのが、彼等を相手にする際の最低条件だ。自分にしたって、神形の加護に加えて、“同化者”という、ある意味反則染みた力があるからこそ、半ば単独で渡り合えているのだ。
単純に、援護や亜獣の処理を任せる事が出来、大禍鬼との戦いにのみ集中できる環境を用意してくれるだけでも、これまでと比較すれば随分と楽になるだろう。その点だけでも全く心強い助けと言える。
それに、イェアはこちらに大きな負担を掛けると言うが、彼女が先刻説明していた作戦内容を聞いていた限りでは、軍部隊の方ももかなり攻めた姿勢を取っているのは判っている。
まず非戦闘員を含めた相応の規模の部隊で、島内の超常地形に侵入するという行為自体が、かなりのリスクを伴うものだ。戦力的な面でもそうだが、人が多ければ食糧物資の確保も難しく、他にも様々な問題が生じる筈だ。
これ以上を求めるどころか、本当にあそこまで出張って大丈夫なのかと、【NAME】の方が心配になる程だった。
そんな事を自分なりの言葉で話すと、ノクトワイが苦笑いしながらイェアを見て、
「それについてはねぇ。【NAME】ちゃんには悪いけどアタシの方で幾らか口挟ませて貰って、これでも最初の予定よりは大分手を緩めさせてもらってんのよん。最初は“森”や“谷”に居るっていう大物の相手も軍だけでやるみたいな計画だったんだから」
「わたくしとしては、行けるかな、とは思ったんですけれど……」
「無理だってば。というか、もし行けたとしても多分かなりの被害が出るわよ。そうすると、肝心の“山”や“洞”、そして最後の“城”でまともに動けなくなるかもしれない。ウチらが頑張らなきゃならないのはそこなんだから、その前で戦力を減らすわけにはいかないわん。……まぁその反面、終盤――“山”や“洞”辺りはかなり無理してるというか、下手すりゃかなりの被害が出る可能性もある感じになってるのよねぇ……」
「そこについては、前にお話しした通り、譲れませんわ。事前にわたくし達が策を巡らせれば、確実に戦いは楽になって、【NAME】さんの負担は大幅に軽減出来ますし。変更は、ありません」
その遣り取りから、どうやら以前から二人の間で軍戦力をどう使うかやり合っていたらしいことが伝わる。
イェアの強情な様子に、ノクトワイはがりがりと頭を掻き、話の方向を少しだけ変える。
「本当なら、“城”での大一番に戦力をぶつけたいから、そこまで兵力の消耗は控えたいところなんだけど、これ別の相手を封じるって流れは無理なのかしらん? せめて、“山”か“洞”どちらか一方だけとかで、後の一つには森や谷の主を捕らえるとか」
「わたしにある記憶の中でも、その二つの地形に存在する主よりも、他の地形で遭遇した主達の方が力が弱いように感じます。そちらならば、それ程大きな被害なく崩滅させられると思います」
「でしょ? これどうかしら、部隊長殿」
ノエルからの援護を受けて、名案とばかりにイェアの方を見るが、しかし彼女は深く首を横に二度振る。
「……駄目ですわ。大体、今わたくし達の所にある材料で造り出せた封縛印章石群もあの二つが限界で、それにしたってウィーちゃんが持ってる力を多少なりと借りられたからこそ、どうにか完成できたものですし。設計も燃費度外視で組んだせいで必要な理粒子干渉量が膨大すぎて、あの子の力を借りないと多分駆動させることすら出来ない、不良品紛いの代物なんですのよ?」
言われてみれば、複数の封縛印章石をただ鎖で繋いだだけのようなもので、大禍鬼の存在概念を封じ込めるというのだから、各所で無理が出ているのも当たり前ではあるのか。
「でもだからこそ、その二つには可能な限り、強大な存在概念を持つ者を捕らえたいんですの。不確かすぎる事だから、出来る限り、その不確かさに対応しておきたい。失敗しても“巻き戻し”でやり直しは効くのかもしれませんが、今、ここまで造り上げた“状況をやり直す”事は出来ないんです」
「今回の策の要、妥協できないポイント、という所かな」
ふむ、と鼻の奥を鳴らしながらのオリオールの言葉に、白衣の学士は今度は大きく頷く。
「ええ。ブランタンハリアとキルーザム、二つの超常地形の主は、“城”を除くエルツァン島の全地形の中で双璧となる力を持つと、ウィーちゃんは認識していますわ。ですよね?」
「うん」
話を振られて、今までずっとぼんやりと立って皆の顔を窺っているだけだった少女はこくりと頷く。ちゃんと話自体は聞いていたらしい。
「あそこの二匹は、特別みたい。大禍鬼みたい、じゃなくて、多分本当に大禍鬼なんじゃないかな。捕まって、造られた世界に括り付けられた鬼」
「まぁ、僕の方も“山”の鬼には会った事があるけれど、あれは本当に尋常ではなかったね。それでも確か、全力の姿ではないという話なのだろう?」
【NAME】とオリオールは、カール・シュミットの件で“山”の調査を行った経験があった。
そこで泥の大巨人と対峙し、あれがブムドゥであるという事なのだが、後でイェアに顛末を話したところによると、あれですら、鬼としての全てを表に出した状態ではないらしい。
「わたくしの推測ですと、そうなりますわね。土地概念全体に存在概念が融合しているような状態になっていて、“山”のあらゆる場所に出現でき、そして幾らやられてもそれは“山”の中から伸ばした身体の一つでしかない、というのが多分“山”の泥鬼――ブムドゥと記されていた鬼の状態ですわ」
「であるならば、其奴を斬るには山を斬るしかなくなるが。如何様にするつもりか」
これまでは腕組みし、ずっと黙していたリゼラが漸く口を開く。戦いの話となると途端に気が入るのが彼らしい。
対して、イェアの方は事前に考えていたのか、すらすらと返答する。
「土地の概念を精査して、もっとも陰性概念が強く生じている場所に術を打つ事で、土地概念と鬼の存在概念を明確にし、全てを顕現させてから切り離して討伐する、というのが常道と考えますわ。今回もそれに則った準備をこちらのほうで行っていますから、リゼラさんにはただ出てきて敵を斬っていただければ、それで結構ですわ」
「ならば良い。話を続けよ」
満足な答えが聞けたのか、彼はそうそうに話をきりあげ、また目を閉じて動きを無くす。
その態度に、先刻までは向かい合ってやり合う形になりかけていたイェアとノクトワイが、毒気を抜かれたように顔を見合わせて苦笑し、けれども直ぐに表情を引き締める。
「勿論、ノクトワイ様が仰りたい所も十分に判っています。けれど、それであっても、この形でお願いしたいんです。大禍鬼シンラはアノーレで身体を失い逃亡を図った身ですが、“鬼芯の柱”と繋がる事で元の状態に回復どころか、以前より力を増している可能性すらあります。封縛印章石群に封じる存在概念は、最低でも彼以上の量の存在概念を有し、“芯檻”が持つ照査機構を騙せなければ、シンラを倒せたところでまた全てが水の泡。だから、どれだけ被害がでる事になろうとも、ここだけは譲れません」
「…………」
暫く無言、彼らしくない仏頂面でイェアを見下ろしていたノクトワイだったが、大きな吐息の後、表情を緩める。
「兵を実質預り指揮する身としては、どうにか反論したいところだけれども、全く納得出来ない意見という訳でも無いのが辛いところよねぇ」
「……申し訳ありません。ノクトワイ様」
「ま、いいわよん。実際の所、これまで地味な活動続きで兵士達のフラストレーションが溜まってたってのもあるしね。勝ちに行く戦なら、どいつもこいつもやる気は出すでしょうし、やられたらやられたで運が悪かったと割り切りもつくでしょ。それについては変更無く進めるとして、次は……」
「“城”に到着してからについては、如何されるのでしょうか、イェア」
ノエルの問いに、イェアはこれまでの態度とは一転、むーんと気のない様子で腕組みをする。
「んー、そこについてですが、正直今ここであれこれ話しても多分忘れちゃうだろうから後でいいかなーとも思ってるんですよね」
そんな雑な、と思わず声に出たが、「いやだって」とイェアは前置き、
「“城”付近に到着した時点で一度簡易の陣を形成して、休息と“城”攻略……というか対リンドヴルムの下準備をやらないといけませんから。結局そこで会合の場をまた造るので、そこでいいかなと」
「イェア嬢の手間を考えるとそうなるのかもしれないが、例えば不慮の事故で途中で君が戦線離脱した場合は考えているのかい、それは」
「あ、それもそうですわね」
相変わらず、ところどころで脇が甘い。
「といっても、ここに居る方々用にはあまり話すこともないんですよね。大雑把に説明しますと、まず封印を刺激してリンドヴルムをこちら側に呼び出してから、ぶったたいてある程度弱らせた後で捕まえます」
「つ、捕まえる? あの護竜をかい?」
「まあ捕まえるというか、時間制限つきで動き封じる感じになりますけれども。“城”の外でわたくしが学士の子達と一緒にえっちらおっちら……そうですね、学士全員で常時術式駆動を維持して、数時間……ギリギリ半日くらいは持たせられる束縛術式を準備しますから、それでリンドヴルムを取り敢えず足止めします。護竜自体が“芯檻”のシステムに含まれている場合を考えると、崩滅を狙うのは危険ですし、そもそもあの竜をそこまで追い込むのが大仕事ですから。取り敢えず一瞬でも全力で叩いて、相手が怯んだところにその術式で引っかけて動きだけ止めて、その間にわたくし達が封印を抜けて“鬼芯の檻”へと降りるという手順になります」
「肝心の封印を抜ける方法はどうなってるのん?」
「正規の手段があれば何事も無く、それこそリンドヴルムが出てくる事も無く通れるようなんですけど、その辺りの情報がはっきりしなくて。取り敢えず、リンドヴルムが出てくる際に位相領域の口が封印上に開く筈で、その影響が封印自体にも出る筈ですから、そのあたりの歪みを利用して、どうにか摺り抜けるようわたくしの方で干渉してみる……という感じを考えてはいますが、はっきり言うと自信がないので、もしかすると【NAME】さんや、あとはウィーちゃんの力を借りてゴリ押しする事も考慮してます」
「……大丈夫なんでしょうか」
非常に雑な話に、露骨に不安げな顔つきになったノエルがそう呟くが、イェアとしてももう割り切るしかないという心境のようで、
「大丈夫だと思いたいですわね。“城”の中以降の話になると、ウィーちゃんやノエルの情報もう曖昧さ五割り増しくらいになりますから、もう殆どそんな感じで展開を組み立てるしかなくなるんですよねぇ……。こんな話、兵士の皆様にはとても出来ませんわ」
「結局、そこから先は行き当たりばったりの出たとこ勝負、というところかな」
「取り敢えず、その辺りの話はまた後で考えるとして、今は“城”までの移動と、大禍鬼の討伐に全力を尽くすとしましょう。【NAME】さんには、道中の大物相手の時以外は、基本休んでいていただいて、ここぞというときに出張って貰いますから、他の皆はそれまで頑張って、【NAME】さんの手を煩わせないよう頑張りましょう」
了解、と皆が返す中。ノエルとウィースルゥインの二人が、互いを確かめるように視線を交わした後、一歩前に出てくる。
? と見返すと、
「“森”や“谷”、あと“湖”や“丘”にいる、強い相手。それの相手を、私とわたし……ノエルに任せても、いいよ?」
「……あなた達だけで、どうにかするつもりですか?」
表情厳しく、イェアが問い詰めると、ノエルは少し怯むように後ずさるが、しかし踏みとどまり、しっかりと顔を上げて告げる。
「出来るかどうか、わたしには判断が出来かねます。けれども、わたしと私……ウィースルゥインは、【NAME】と共に彼等を相手にした記憶があります。だから彼等が何処に潜み、どう動き、そしてどう攻撃してくるか。それを知ってます。それに」
ノエルは小さな手を掲げると、その周りの空間がぐらりと揺らぐ。その様子に、【NAME】、リゼラ、そしてイェアの表情が鋭くなる。彼女の掌の周囲で渦巻く無形の力は、陰性質を帯びた概念を圧縮したものだ。
「その力……“人形”としての力、ですか」
「はい。ウィースルゥインを主とすることで、わたしが持っていた対鬼種存在としての機能の多くが解放されました。あと、この力とフォーレミュートを併せて活用することで、自賛となりますが、私の戦闘力は大幅に高まったと判断しています。出来ればそれを、本格的な戦いに――“鬼喰らいの鬼”との戦いの前に試しておきたいと、そうわたしは思っています」
「あと、私も頑張るよ。ノエルと練習して、私も力、ちょっと使えるようになったから。ノエルを、【NAME】を、私を見てくれたみんなを、ちゃんと助けられるように」
「…………」
対し、イェアは気難しい顔で黙り込む。その心情を、【NAME】は手に取るように理解出来た。
彼女等の言いたいことは判る。そして彼女等を戦力として計算出来るならば非常に状況が有利になる事も判る。けれども、その判断を下しがたい。
それはまったく、【NAME】も同様の事を感じていたから。
だからこそ、イェアが最終的に下す決断も、【NAME】が抱くものと同じであるだろうと思えた。
そして、イェアはふっと表情を緩める。
「わたくしにとってあなたも、そして貴女も。今では大事な存在です。やはり危険の矢面に立たせるのは抵抗があります。でもだからといって、ここで貴女達の想いを無駄にするようでは、それこそ保護者……いえ、養育者失格でしょうね」
「……なら」
「許可致します。けれども、あなた達だけでは駄目よ。ちゃんと、【NAME】さんと一緒に戦う事。それならもし駄目だったとしても、きっと彼がなんとかしてくれますわ」
こっちに振ってくるかー、と一瞬思う【NAME】だったが、実際の所この面子の中で最も戦闘力が高いのは自分だ。単純な戦技という話で区切るならノクトワイ、翆獣の力と常識外の域にある剣技体術を持つリゼラも相当なものだが、それでも神形の力も含めあらゆる要素を加味すれば、自分が面倒を見るのが適任なのだ。
「【NAME】、宜しくお願いしますね」
「駄目そうだったら、助けてね?」
双方からの声に、【NAME】は改めて、了解と頷きを返すしかなかった。
「よしっ! じゃまぁ、大体決めるところも決まったことだし、景気づけにアレやりましょうかアレ!」
「アレ?」
突然調子を上げたイェアの声に、全員が怪訝と見る。そんなところで彼女はびっと自分の手を前へ突き出して、
「ほら。一致団結して、えいえいおーって奴です! わたくし、大抵根暗な連中とぶちぶち顔付き合わせて本読んだり書いたり術組んだりばっかりでしたから、こういう大作戦って初めてなんですの。だからそういうの、ちょっと憧れてたりして!」
「……結構、そういう子供っぽいところあるよな、イェア嬢は」
「暗に年齢の割にとか思ってません?」
「ないよないない。ほら」
ぽん、と伸ばされたイェアの手にオリオールの手が重ねられ、
「でもま、アタシもこういうの好きよん。特に今ここに居る面子ってほら、軍隊としての集まりじゃなくて、そういうの関係ない、色んなとこからの寄り合いみたいなとこあるでしょ? だから……そうね、仲間って感じがして、ならこういうのもお似合いっていうか、悪くはないんじゃないかって思うのよ」
更に、ノクトワイの手が重ねられる。
それを見て戸惑ったのはノエルだ。眼前で重ねられていく手を見て、彼女は理解に苦しむように小さく眉根を寄せて、
「あの、これは何をどうするものなのでしょうか?」
「大きな事をやる前に、一緒に居るみんなで手を合わせて、最後に掛け声で心を合わせて、仲良くなるための儀式よ」
「わたしが知らないのになんでウィースルゥインが知ってるんです!?」
「有名」
横からの言葉に目を見開くノエルだったが、「ほら」と小さな手が乗せられると、恐る恐る自分も手を重ねる。
そして、更にその上に、意外な手が伸びる。これまでの話し合いの間も一歩引いた態度を取っていたリゼラの掌だ。
彼がこういう流れに素直に乗ってくるというのは意外と言う他無く、全員が彼を凝視すると、片耳を煩わしげに押さえた少年は、忌々しげな嘆息でだけで返す。
「せねば、あれやこれやとお前達が手を打ってきてこの場が終わらぬからな。ついでに煩く騒ぐ奴もいる。……兎に角、早々に済ませよ。残るはお前だけだぞ、【NAME】」
そうして、手を重ねて待つ彼等六つの視線が、迎えるように【NAME】の方を見た。
「――――」
前へと進み出て、繋がる手に、自分の掌を重ねる。
見合わせる顔には、先刻までの話し合いの中であった不安はもうない。大事を前に気持ちを合わせる儀式と、ウィースルゥインは言っていたが、確かに景気づけとしては丁度良いものなのかもしれない。
「それじゃ、いきますよーっ! “鬼喰らいの鬼”討伐、絶対成功させましょうっ! それ、えいえい、おー!」
叫ぶイェアに、皆はそれぞれの態度で、けれども確かに声を合わせて、重ねた手に力を込めた。
――進撃する者達──
イェアから今回の計画が軍全体に告知されてから数日後。部隊はいよいよ、島内に広がる超常地形群への進軍を開始する事となった。
総員は結局百を優に超える数、全体の八割程が参加する事となった。キヴェンティ組は、長たるリゼラ・マオエ・キヴェンティによる、
「この戦では、お前達の出番はもうない。船にて我の帰還を待て」
との沙汰に従い、沖の船にて待機中となっている。リゼラ曰く、翆霊の顕現が上手く行えない島内の領域では、彼等は逆に足手まといになる可能性が高いと判断した、という事らしい。
侵攻部隊が構成する隊列は、方形と円形の中間。所謂戦地に赴き、そこで戦陣を組むという訳ではなく、ほぼ常戦の態勢が求められるため、部隊集団外縁に戦士、その後ろの円に術士を配置して中央に非戦闘員や指揮人員、物資輸送の荷車などを配置し、全周からの襲撃に対応する形だ。非常に身動きの取りづらい構成と言えるが、しかし今居るエルツァンの海岸地帯ならば兎も角、内陸の超常地形へと入れば、いつ如何なる方向から攻撃を受けることになるのか判らない。移動時には一般的な縦長の隊列を組むのは非常に危険だった。
事実、亜獣の存在が少ない海岸地帯であっても、既に解体を終えた陣地跡を離れて暫く進むと、各所で亜獣の気配が生まれ始める。こちらが大集団であるため、亜獣達は警戒し襲ってくることは多くはないが、しかし警戒を解かぬまま距離を保ち、威嚇を続ける者達もおり、それらが襲撃へと変化する前に事前に潰しておくべく、外辺の兵士達が幾度か小隊を組み、亜獣達を追い払うという流れが先刻から続いていた。
【NAME】は本来であるならば陣形の中央、イェア達指揮集団に同行するように、と言われていたのだが、兵士達が実際どの程度動けるものなのか、見ておきたいと、その場をそっと離れ、亜獣討伐の為に陣を離れた小隊の後に付いていく事にしたのだ。
軽く速度を上げて、先に向かった兵士達の後を追う。彼等が討伐に向かったのは海より上がってきた水棲亜獣の群れだ。海から上がってきたところまでは確認していたのだがそこからの動向が掴めないため、牽制として派遣された形である。
【NAME】が現場に到着すると、彼等が近付いた事が刺激となったのか、はたまた最初から襲い掛かってくるつもりだったのか。小隊は既に亜獣達の群れとの戦闘に移っていた。
戦況としては、小隊側が優勢に見えるが、しかし亜獣側の数が案外と多い。恐らく術式で感知した時から更に海より上がってきた亜獣達がいたのだろう。
背後から大声を上げ、加勢に来た事を告げながら、【NAME】は海から上がってこようとしていた亜獣へと向かいっていく。
だが、
「大丈夫です、英雄殿! こちらの処理はもう終わりましたであります」
「自分らもそっち行くんで、一緒にやりましょうぜ!」
「というか超必殺技見せてくださいよ超必殺技! 一撃でこう、敵を纏めて消し飛ばすビームみたいな奴! それで大禍鬼一発で沈めたんでしょ!?」
そんなもんないよ、いや、あるにはあるけど今出ないよ。
「あるの!? マジで?」
ゼーレンヴァンデルングの力を解放しての大剣撃とか大雑把に言うとそんな感じだったしなぁ、と思いながら、【NAME】は素早く武器を引き抜き、全力で追従してくる兵士達と共に亜獣への攻撃に移る。
破るべき障害






「流石英雄殿! 有り得ないくらい強いでありますな!」
「いや俺等がめっちゃ先行して蹴散らしたし、英雄殿別にそれほど戦ってなくない?」
「あたし超必見たかったのになんであんたらそんな張り切っちゃったの? 馬鹿なの? 殺すよ?」
三者三様の態度を見せる小隊の兵士達だったが、しかしそんな巫山戯た遣り取りを交わしながらも、その実力自体は【NAME】からみても相当だ。このレベルが部隊兵士の平均であるならば、エルツァン島内に出現する強力な亜獣達相手でも十分に渡り合えるだろう。
改めて考えてみると、彼等は“谷”や“森”に立ち入り、探索調査をしっかりこなしている兵士達なのだ。ならば沿岸部に現れる亜獣程度ならば対処出来るのも当然で、
(――こちらが、彼等を見誤り、侮っていた、という事か)
これを、自分が持つ力に自惚れていたが故と考えて良いものなのかどうか。
判断しがたいが、何にせよ、これからは彼等の事も共に戦う者として、任せるところは任せられる――つまり相応に信頼出来るのだと思えるようになったのは、大きな収穫だろう。
もっとも、それは超常地形内にて出現する並程度の亜獣相手ならばであって、上位の相手をする際に、彼等の力を全面的にあてにするのは難しい。
――任せられるところは任せられる。
それは逆に言えば、彼等だけには任せられないような場面は確かに存在する、という事なのだから。
兵士達と共に部隊と合流する頃には、既に島の内陸に存在する超常地形へと続く入り口付近へと近付きつつあった。
想定された進軍のルートは、イェアが最初の説明で言っていた通り二種類。
一つはナリア・バータ霧眩森林からカリッサ灼雷領域を抜け、ブランタンハリア山岳回廊、キルーザム狼咆洞穴を経由し、最後に有り得ざる城クナハ・クリサへと至るルート
一つはローム・フーネ無空峡谷からザルナルバック月光丘陵を通り、キルーザム狼咆洞穴を潜った後にブランタンハリア山岳回廊へ向かい、こちらも最後に有り得ざる城クナハ・クリサへと辿るルート
本来はこの二通りの他にも、島内各地の超常地形と直接繋がるイールシック地下都市遺跡を使うという手があり、こちらを使うならばほぼ直接狼咆洞穴と山岳回廊に向かう事が可能と、大きなメリットが存在する。
しかし、地下都市遺跡の構造が複雑である為、ノエルやウィースルゥインの記憶を又聞きする形ではどうしてもルートの選定が難しく、かといって人を派遣し調査を行うには広大すぎて時間が足りない、更には地下の通路であるため大人数での移動には適さない、等の判断から、選択肢から除外されている。
そして提示された二つのルートのうち、どちらを進むか。
これは、数日前の会議の後、イェアから直接どちらにするべきか意見を訊かれ、その時の答えがそのまま、部隊の方針として採用されていた。
【NAME】としては、そんな決め方で良いのか? と疑問に思ったものだが、白衣の学士曰く、
「わたくし達であれこれ助けられるような段取りは付けましたけれど、結局【NAME】さんが正面切って戦うみたいな形になってしまいましたから。なら、“山”の泥鬼か、“洞”の狼鬼か、【NAME】さんが先に戦いやすい方を選んで貰うのが一番かな、と。……何だか、自分で言ってて悲しくなってきましたけど」
【NAME】だけに、負担は掛けさせないように。
そう、あれこれ計画を練っていた結果がこれなのだから、彼女が意気消沈するのも仕様が無い話ではあるが。
何にせよ、ルートの選択権は完全に【NAME】に移譲されて、そしてあの時、自分はこう答えた筈だ。
確か――。
真なる楽園 (ルートA)坤濁の大禍鬼
――固独たる化身──
――先に、ブランタンハリア山岳回廊の泥鬼を討つ。
【NAME】がそう宣言した通り、決定した進軍のルートは、ナリア・バータ霧眩森林からカリッサ灼雷領域を経由し、ブランタンハリア山岳回廊へまず至るというものだった。
最初の霧煙る森については、【NAME】やオリオールによる調査に加え、軍部隊内でも複数回の調査が行われていたため、多くの情報は既に割れている。そんな状況であっても、一部に非戦闘員や学士等をも含めれば三桁規模の人員による進軍は、相応の困難に見舞われた。
ナリア・バータで特に厄介だったのは、霧により生じる亜獣の発生が、半ば神出鬼没に近い点だ。
高い概念的な感知能力を元々備えているノエルやウィースルゥイン、リゼラ以外の者達にとって、霧の亜獣の出現は術式による補助が無ければ顕現する前動作を掴む事が出来ず、殆どの場面で不意を打たれる形となってしまう。そういった事例が何度か起き、小さな被害が出始めた辺りで、学士や術士達が隊列の中央にて術式を駆動させて警戒を行い、守るように囲む兵士達が彼等の指示を受けて霧の獣を対処しつつ森を進む、という形に落ち着いた。イェアが事前調査の情報や術式、機甲具などを活用し、極力霧の薄い場所を選ぶ事で霧の獣との遭遇率を下げようと努力していたが、何せ人数が人数だ。想定通りのタイミングで移動出来る筈もなく、中々上手くはいかない。
結局、霧の森での活動には既に慣れていた【NAME】や、概念感知に優れたノエル、気配を読む事に長けたリゼラ等が隊列中を走り回って対処を続ける事で、綱渡りに近い状態での行軍を続ける事となった。
状況としてはかなり厳しいものであったが、しかし前進自体は着実に行われており、
――このままの調子であれば、どうにか大きな被害を出さずに森を抜けられるか?
そう、皆が楽観し始めた頃。
隊列の先頭付近にて現れたのが、ナリア・バータ霧眩森林の主とも言える存在だった。
それは、霧の身を持つ巨大な竜の化生。過去にエルツァン島の調査を行ったという彼の探検家も遭遇したというそれは、ユクォンフーと名付けられていた。
ユクォンフーは竜身を持つ者のご多分に漏れず、強烈な霧状の吐息[ブレス]を放つ。それは単なる霧ではなく、強烈に圧縮された概念の奔流だ。竜種の放つ吐息は炎、氷、雷など、そのものを打つけられた際にその力に沿った結果――例えば炎傷や凍結、感電等――を負うものもあるが、それらはあくまで副次的効果と言える。
彼等が放つ吐息の本質的な攻撃力は、超密度に凝縮、圧縮された存在概念を叩き付け存在概念を破壊するところにあり、何の対応策も持たぬ並の戦士や術士がそれを受ければ、為す術も無く己の存在概念を塗り潰され、人としての在り方を失い崩れ去るしかなくなるだろう。
急ぎ、相応の力を持つ者が対処に向かわねば、兵士達に大きな被害が出る。しかし、ノエルやリゼラ達は遠くの位置に居り、イェア、ノクトワイは部隊指揮を行う必要があるため、前に出て戦う訳にもいかない。
立ち向かえるのは、比較的近くに居る自分だけだ。
「――――」
【NAME】は素早く判断し、動揺する兵士達の脇を抜けて、隊列の先頭、今にも兵士達に襲い掛かろうとしていた霧の竜の前へと飛び出していく。
だが、意外な事に、そこには先客が居た。
【NAME】がやってきた事に気づいて、その人影が振り向く。長い紺とも藍ともとれる不思議な色合いの髪が靡いて、その向こう側から現れたのは、薄布を纏った少女――ウィースルゥインだった。
彼女が立つのは、兵士達よりも前方。彼等と竜の境の位置に居る。どうやら、ユクォンフーを一人で相手するつもりであったらしい。
「【NAME】? 来たの?」
何処か場違いな緊迫感の薄い問い掛けに、戦うときは自分が一緒に居る時だけだと約束しただろうと、武器を構えて彼女の前へと出ようとする。
流石に、ほぼ無手に近いウィースルゥインを前面に出すのはまずかろうという判断からだった。
「うん、そうだったね。なら私と二人でやろ?」
しかし、通り過ぎた筈の彼女の姿は、【NAME】の真横を維持したままだった。視線を向ければ、【NAME】と並走する形で、彼女はどこか嬉しそうな様子でこちらの顔を見上げていた。
「ふふ、【NAME】と一緒にするのって、はじめてだね。ちゃんと役に立つから、見てて」
そして【NAME】は、ウィースルゥインが敵としてではなく味方として戦う姿を――“固独”の大禍鬼として、想像していた以上の力を発揮する様を、間近で見る事になったのだ。
[BossMonster Encountered!]
異を嫌う霧主



少女が数多の存在と共に在り、万象の力を持つことは知ってはいた。
しかし、それに加えて更にもう一つ。
彼女が持つ全く別軸の力を、【NAME】はこの場に至ってようやく目撃する事が出来た。
それは、イェアが“固独”と名付けた、過去に存在した幾つものウィースルゥインにはなく、今ここに居るウィースルゥインだけが得ている特性だ。
その特性を端的に表すならば――攻撃を含めた他者からの干渉を拒み、大きく弱体化ないしは無効化する事ができる能力である。
自分の存在概念に、あらゆる要素を内包するが故。彼女はこれまで、己が世界の内で存在全てが完成してしまっていた。
だからこそ固定され、独立していた在り方は、超常地形の象徴とも言える強大な存在達が放つ力すら殆ど寄せ付けなかった。
ノエルとの件でその完全さは僅かに崩れ、他存在との接点を持ち、そして流動する自己を得たとしても、それは先刻の言葉通り、未だ僅かながらの事でしかない。
少女が持つ、存在としての極めて高い独立性は揺らぎは生まれつつも未だ健在であり、他者からの接触――物理的概念的問わない様々な攻撃を、彼女は自分の世界には届かないものとして無効、あるいは大幅に弱体化させる事が出来るのだ。
白濁とした飛沫。雪崩のような勢いで噴き出すそれを、ウィースルゥインは全く無視し、竜の注意を引いてみせる。そうなれば、後は簡単だった。【NAME】は素早く背後へと回り込み、渾身の一撃を放てば、竜はあっさりと霧散した。拍子抜けした面持ちで佇む【NAME】に、傍へとやってきたウィースルゥインは言葉無く、ただ小さく微笑みを見せるだけだった。
――どう? ちゃんと役に立ったでしょ?
そう、言外に告げるように。
そして霧の森を無事に突破し、続いて雷が支配する湖畔を通り抜けようとした軍部隊は、湖の中央に佇む小島より襲来した巨蛇と対峙する事になったのだが、白金の巨蛇が操る大雷のような強烈な概念攻撃に対しても、彼女の特性は同様の結果を齎すのだった。
[BossMonster Encountered!]
固を厭う雷蛇



迸る雷撃は、周囲あらゆる場所に突き刺さり、空気が裂ける轟音と、超高熱による焦痕を大地に刻んでいく。
その勢いは凄まじいという一言では表現しきれぬ程で、黄白に輝く大蛇――バルタフアと呼称された存在の周りは、まるで雷の嵐が常に吹き荒ぶような有り様だった。
とてもではないが近づける状況ではなく、軍部隊は結界を得手とする術士集団を前に置いて距離を取り、雷撃を捌く事で精一杯。そして戦闘巧者たるリゼラやノクトワイにしても己の間合いにまでは近づけず、完全に足止めされている。【NAME】ですら、あらゆる加護を総動員してどうにか雷撃を捌きながら、己の攻撃を雷蛇に届かせているような状態だった。
対して一人。その雷の嵐を、ものともしない者がいた。
閃光の雨が支配する宙を浮かび進むのは、藍色の髪を靡かせた少女。大禍鬼ウィースルゥインは、ゆっくりと、しかし一切速度を緩める事なく、バルタフアの傍へと近付いていく。
何百どころか、何千にも及ぶ細い稲光。それらが、向かってくる少女目掛けて矢の如く放たれる。
しかし、その光は彼女の姿を摺り抜けて、宙空に白色の残光を刻むだけだ。ウィースルゥインの身体には焦痕どころか、何らかの衝撃を受けた様子すらない。
「……無茶苦茶だ」
思わず声が溢れ出る。
すると、どうやらその呟きが聞こえていたらしい。空を行くウィースルゥインが、下方、【NAME】の方へと浅く振り向くと、
「これは、当たり前の事。だって、私の世界に、この子の姿はどこにもないもの」
邪気のない微笑み。それだけを【NAME】に残して、ウィースルゥインはそのまま雷蛇の正面へと立つ。
己の雷撃が通用しないことを悟ったバルタフアは、その顎を開き、彼女を噛み砕こうと試みる。だが、その一噛みも、彼女の身体を摺り抜けてしまうのだろう――そう考えていた【NAME】は、バルタフアの閉じようとした顎が、まるで鋼鉄の塊を噛んだかかのように、ウィースルゥインを咥える形で、がちりと動きを止めるのを見た。
「だけど、今。私はあなたを認めた。だから、あなたの力は私に届く。けれど――」
バルタフアの上下の顎を受け止めていた藍色の髪が更にたゆたい、先端があらゆる獣の姿に変化する。
そして、
「――私の力も、あなたに届くわ」
大気が黄金の輝きとなって、轟音と共に爆ぜる。
弾けるように四方に飛んだ藍色の獣達が、バルタフアの頭部を内側から貫き、粉々に破壊したのだった。
――無数の強存在を宿し、完結した世界で生きてきた万象の雛。
“固独”の大禍鬼ウィースルゥイン。
彼女という存在の強さと、そして危うさを。目の前で改めて感じる【NAME】だった。
“森”と“湖”。二つの超常地形を何とか潜り抜けた軍部隊は、まず一つ目の目的地であるブランタンハリア山岳回廊の入り口へと辿り着く。
厚い雲に覆われ、薄暗く閉じた空。煙るような霧雨が、山に茂る木々の葉を重くしならせる。その風景は陰鬱な空気を生み、一時の休息を取っていた【NAME】達の身に、じわりと纏わり付いてくる。
今居る場所は、山岳回廊の中で最も低い第二山の頂付近。各々、適当な場所で腰を下ろしながら簡易食を口にし休息を取っているのだが、いまひとつ疲れが取れていく気がしないのも、この景色と雰囲気が大きな要因の一つだろう。
そんな中、【NAME】は今後の軍の作戦内容についてを思い出していた。
“山”での作戦方針は、既に出発前にある程度は聞かされている。
以前の【NAME】とオリオールによる調査、そしてノエルとウィースルゥインが共有する過去の記憶に従うならば、少なくとも今現在のブランタンハリア山岳回廊は、十の山で構成された群山地帯であると考えられている。
そしてブランタンハリアという土地に根付いて半ば一体化し、未分化状態にある大禍鬼ブムドゥを完全に崩滅させるには、まずブムドゥを個として土地から切り離すのがもっとも簡単、かつ対処のしやすい手段だとイェアは考えているようだった。
その為の方法として彼女が計画したのが、まずこの固有地形の特徴である十の山のうち八ないし九箇所に、それぞれ複数人の術士によって駆動する大型の印章陣を設置する。印章陣は土地概念に対して干渉を行うもので、それを同時に駆動させる事で、山岳回廊全体の土地概念に混じる歪み――陰性質の概念を、残された一つの山目掛けて押し出すというもの。
一箇所に押しつけられた陰性質の概念は当然飽和現象を起こし、そして偏りを持って飽和した概念は現世にそれを元とした実体を生む。これまでも何度も見てきた、上位鬼種が顕現する際のプロセスである。これを、山岳回廊全体に仕掛けようというのが今回の作戦の基本案だ。
勿論、問題は多々ある。
まず各地に印章陣を設置する為、軍部隊を細かく分散しなければならない。それぞれ印章陣記述を行う学士を含んだ小部隊を、この超常地形にて個々に活動させるのは、かなりのリスクを伴った。以前の【NAME】が行った探索報告により、ブランタンハリア山岳回廊に棲息すると思われる亜獣は、他所よりも幾分か弱い種が多いと見られているが、問題は山自体に根付くブムドゥが生み出す手――泥の人形や巨人達である。彼等に目を付けられると、軍兵士達が幾ら手練れとはいえ、かなり厳しい状況に追い込まれる事になるだろう。
また、各小部隊が印章陣の設置に成功したとして、それはあくまで前段階でしかない。本番は、印章陣の干渉によって顕現するブムドゥとの戦闘だ。
これまで、【NAME】はブムドゥの欠片である泥人形、そしてブムドゥの本性とも信じていた泥の湖から立ち上がる大巨人とも交戦してきた。
しかし、イェアが言うにはあの大巨人ですら、大禍鬼ブムドゥの全てが顕現した姿ではないというのだ。
彼女が推測するに、全てが顕現する際には、山一つが丸ごと泥の湖ならぬ泥の海へと変じ、そこから超巨大な巨人が現れる事になるという。
そんなもの相手に勝てるのか、という疑問は当然浮かぶが、
「いつ、何処に出ると判っているのなら、まぁ色々と準備は出来ますもの。山に仕掛ける印章陣にも弱体化させるための構造を仕込んでありますし、現場の方でも色々と、可能な限りの術式を仕掛けてフォローします。実際の戦闘力自体は、【NAME】さんが以前に戦ったという状態よりも多少強い程度には押さえ込めるんじゃないでしょうか」
とは、先刻作戦開始前の打ち合わせを行ったときのイェアの言である。
ちなみに、【NAME】はその時に軍部隊が印章陣を各地に展開する時間を稼ぐための陽動と、そしてどの山が鬼種顕現に適しているかを調査する役を任されていた。
鬼種を顕現させるには、元々陰性概念が一番強く出ている歪な土地が適しているのだが、その山が何処にあたるのかが、現状見分けられていないのだという。
【NAME】とオリオールがこの場所を調べた際に、歪が強い場所として割り出したのは第四と第七山。つまりそのどちらかを選ぶのが最適となるのだが、第四山の方では以前、【NAME】が姿を現したブムドゥと交戦し、それを打ち倒している。その時、第四山自体から発していた強烈な歪な気配が大きく減じていたのを確認しているのだ。
その減少が、一時的なものであったのか。それとも、既に元に戻っているのか。或いは逆に、反動として前以上に歪みが強くなっているのか。
それを確認するというのが、今回【NAME】に任されたもう一つの任務だった。
「陽動は、なるべくブムドゥの気を引くように、目につくもの全てに攻撃を仕掛けるみたいなノリでガンガン進んでくれたら、土地と繋がっているブムドゥが勝手にそちらに意識を向けると思われるので、あまり気にせず【NAME】さんの何時もの調子でやって頂ければ大体大丈夫だと思われますわ」
普段どう思われているのかと疑問に思う発言だったが、面倒なので敢えて突っ込まず受け流す。
「第四山の調査にしても、直に行ってみれば大体すぐ判ると思うので、大雑把にでも判断できればさっさと戻ってきてもらって大丈夫です。一応第七山前提に作戦は組み立ててありますから、あくまで保険ということで」
そういって貰えると気楽で良い。兎に角暴れ回るほどイェア達の危険度が下がるという事ならば、まあ可能な限り張り切ってみるとしよう。
ただ、流石に一人でやるのは戦力面で、というより、ブムドゥの気を引くほど暴れられるかという部分で不安が残る。
【NAME】は、誰か随伴に連れて行けないかとイェアに持ちかけると、彼女は腕組みして唸り、
「ん、うーん……。わたくしは当然として、ノクトワイ様も各部隊の総合指揮者として居て貰わないと駄目ですし、あとリゼラさんは亜獣の生息数が多いと思われるルートを通っていく部隊の先遣討伐をお願いしていますからこの三人以外になりますわね。だから、ノエル、ウィーちゃん、ハマダン様の何方か一人でしたら、どうにか人員組み替えでカバー出来ると思います」
その三人から、陽動兼調査の戦力として向く人材となると、果たして誰か。
【NAME】は然して考える間も置かず、一人の名前を口にした。
――その機先を征く──
【※ノエルと行くを選択した場合】
【NAME】はノエルと共に行く事をイェアに伝えた。
【NAME】とノエルは、軍部隊が各山にて行う印章陣記述を邪魔されない為の陽動兼、第四山の確認調査としてそちらへ単独で向かう事となった。
移動の間、【NAME】達はこれといった狙いを定めずに技法や術式を放ち、周囲に自分達の存在を誇示しながら移動していった。するとそれまで遭遇していた敵の多くは単なる亜獣であったのが、段々と泥で出来た人形に入れ替わっていく。この山全体がブムドゥと通じているというのなら、自分達が派手に動けば動くほど、ブムドゥが反応を示し、対応のために泥の人形を生み出して差し向けてくるのだ。
これは同時に、ブムドゥの意識が自分達に集中し始めている事も意味し、他の者達への注意が逸れる事にも繋がる筈だった。
――どうやら、陽動は順調のようだ。気合いを入れて、もっと派手に暴れながら進むとしよう。
【NAME】が傍らに居る少女にそのような事を告げると、彼女は構えた愛用の黒銃をじっと眺め、少しばかりの思案の後。
「もっと、という事でしたら、フォーレミュートの弾を変更するべきだとわたしは考えます。少し時間を下さい」
共に行くことを選んだ軍服の娘が、移動しながら自分の抱える黒銃をごそごそと弄る。
しかし弾を変えるとはいうが、そもそもその銃、実弾を撃ち出すものなのだろうか。大体が光条で、偶に実弾のようなものを撃っているような気もするが。
【NAME】が思った疑問をそのまま口にすると、
「切り替えが出来るんです。基本的には理粒子砲ですから、弾は不要なのですけれど、一応小口径の実弾も発射可能です。あと今は、本来実弾を装填する枠に、別のものを入れていますから」
彼女が力を込めた手の中で生じるのは、複数の色が渦を巻いて留まる、歪な球状の物体だった。
見た目も不気味だが、それが秘める概念的な力も、【NAME】から見れば極めて不気味な代物だ。何せ、陰と陽、生と死、相反する概念が、渦を巻いて一つとなっているのだ。
しかし不気味であり、不自然ではあったが、そんなものを何故彼女が生み出せるのかという理由については、直ぐに思い付いた。
これは、“人形”たる彼女が、“主”たる存在から引き出した力なのだと。
「ウィースルゥインが持つ力を、わたしが持つ能力を使って抽出したものがこれです。色々と二人で“勉強”をして、使い方を模索していたのですが、結局はこうして――」
ノエルは渦巻く球体をフォーレミュートの弾倉に叩き込むと、彼女は手近な標的――何時の間にかこちらに大挙して押し寄せてきていた泥人形の群れに向けて、引き金を引く。
放たれた弾丸が、泥人形達の中央で着弾すると同時。
渦巻き圧縮された無数の概念が一瞬で膨れ上がって炸裂し、その範囲内にあった泥人形達は疎か、木々や土すらも、えぐり取るようにこの世界から消滅させた。
球が秘めていた圧倒的なまでの強度を持つ存在概念によって、範囲内に存在していたあらゆる存在概念が打ち負かされ、砕かれたのだ。
「どうですか? あんまり数は無いのですけど、効果的な場面でこれを使って地面ごと吹き飛ばしていけば、きっとブムドゥもわたし達を脅威に思う筈です。――わたし、【NAME】の役に立てそうですか?」
彼女にしては珍しいはっきりとした笑顔で聞いてくるノエルに、【NAME】は若干引きつり顔のまま頷くしかなかった。
何はともあれ、陽動としての仕事は十二分に果たせそうだ。
えぐり取られた地面のそこから、先刻以上の速度で出現を始める泥人形達を見て、【NAME】はそう確信した。
巨人の眷属




ノエルと共に、陽動として襲い掛かってくる亜獣達や泥人形を派手に薙ぎ倒しながら山を進み、無事に目的の第四山へと辿り着いた。
浅い泥の川を渡り山に入ると、これまで執拗に襲い掛かってきた泥人形の姿がめっきりと減り、遭遇するのは元々棲息していたのであろう亜獣ばかりとなった。
山の様子も随分と違う。以前来たときには地面全体が泥濘んでいたのだが、今ではしっかりと硬い土になっている。【NAME】が意識を集中し、場の空気を感じ取ってみても異常な気配は少なく、極めつけは、
「計測終了しました。この第四山内の外縁から中心部付近へと進むほど、土地概念の歪みが小さくなっているようです。また、山の境で周囲の土地概念との大きな断絶が存在しています。これのおかげで、第四山は以前【NAME】さんが正した土地概念の影響が未だ強く残っているようだとわたしは判断します」
元々、概念感知に優れていたノエルであるが、“人形”としての機能がより明確に扱えるようになった今ではその能力にも磨きが掛かっている。その彼女がこういうのだから間違いはないだろう。
結論としては、【NAME】が大禍鬼を討伐した戦いの影響によって山の土地概念の歪みは静まっており、それは今も維持されて、更には他の山との繋がりも薄くなっている、と。
それを考慮するならば、第四山を鬼の顕現の場とするのは難しいと、そう判断するしかないだろう。
【※オリオールと行くを選択した場合】
【NAME】はオリオールと共に行く事をイェアに伝えた。
【NAME】とオリオールは、軍部隊が各山にて行う印章陣記述を邪魔されない為の陽動兼、第四山の確認調査としてそちらへ単独で向かう事となった。
「こうしていざ出発をしてから訊ねるのもどうかと思うが、一応聞いておこうか」
天候が少し変化し、霧雨から小粒の雨へと変化していく山中。近場に居た亜獣目掛けて適当に技法をぶっぱなし、ついでに山の木々や地面すら抉るように追い打ちを掛けていると、【NAME】の隣で半眼のままその様子を眺めていた冒険家が、非常に冴えない顔で声を掛けてくる。
今頑張ってブムドゥの気を引こうと陽動してる最中なんで話は後でいいかなぁと言う【NAME】に、「いやいやちょっと待って」と言葉を続け、
「なんでまた、僕を選んだんだい君は。自慢じゃないがね、僕は戦闘能力とか派手に戦うとか、そういう類の事には全く向いていない人材だよ? むしろ、戦いを避ける方に自信があるくらいだ。大体、陽動で派手に動けと言われても、僕が修めているのは精々小剣と護身用の格闘術くらいで、そりゃ印章石っていう奥の手はあるけど、これ陽動でおいそれと使っていたら直ぐに無くなってしまうんだが?」
それについては、まぁ何となくそうかなとも思ってはいたのだが、他の二人を軍部隊から連れて行くくらいならば、この無精髭の冒険家でも構わないかと思っただけの話なのだ。
亜獣を一通り吹き飛ばし終えた【NAME】は、そそくさと移動を開始し、オリオールもその後に続く。目立つ動きが求められる陽動役だという話を聞いている筈なのに、オリオールの動きは相変わらず油断無く、気配を消すような独特なものだ。意識してのものではなく、もう殆ど身体が覚えてしまっている動きなのだろう。
【NAME】も判っていた事であったが、全く以て、こういう役には向かない人材である。
「で、理由くらいは聞いてもいいものかな」
別段、秘密にするような理由でもない。オリオールの再度の問いに、【NAME】は小雨によって湿り気を帯びた前髪を軽く払いながら、その疑問に答える。
単純に、【NAME】から見た軍部隊の戦力配分の問題だった。
陽動に連れて行って構わないと言われた三人。この内、ウィースルゥインは、ここに辿り着くまでの二つの超常地形を抜ける間に見せた姿から、誰もが頷くほど、類い希なる力を持っているのは皆が判っていたし、【NAME】もその事をしっかりと認めていた。複雑な仕事を任せるのは流石に不安が残るが、例えば自衛戦力のような単純な使い方であれば十分に力を発揮出来る。
そしてノエルにしても、そのウィースルゥインを“主”として設定した事で、彼女の素性――鬼芯やその眷属達、陰性概念存在と戦うために造られた“人形”の機能が解放されており、以前までの彼女と比べるとあらゆる部分で能力が向上している。その上、黒銃フォーレミュートの火力や修理された防御機能を持つ黒球の能力も合わさって、その戦闘能力は軍部隊内では既に別格、【NAME】やウィースルゥイン、リゼラと同等に扱っても遜色無い程の力を有するようになっていた。
その二人に対し、オリオールはといえば本人が言う通り、護身レベルの武器と、隠し玉らしい印章石が幾つか使える程度。その戦闘能力は軍内の平均的な兵士達とそう変わりないか、下手するとそれ以下だろう。
そんな中で、これからイェア達は山岳回廊の各地に散り、印章陣を設置して回るという、危険な任務を行わねばならない。また、一時の拠点として置いた第二山頂上の陣についても、何時何時、亜獣やブムドゥの尖兵たる泥の化生に襲われるとも限らない。
であるならば、可能な限り軍内に高い戦力を持つ者を残しておきたいと考えるのは当然であり、
「つまり、僕が一番抜けても影響が無いから連れてきた、ということか」
正解! と親指を掲げて彼に振り返ると、オリオールはがっくりと肩を落としていた。
「何が辛いって、全く否定ができないところだよね。……ただ、君の判断自体は正直どうだろうとは思うよ。結局の所、陽動が派手であるならば、他の部隊にブムドゥの意識が向く可能性が低くなるという話で、そういった動きが出来ない僕を連れてきたという事なのだから」
それについては、まぁ、自分が頑張るしかない、と【NAME】は答える。自分の選んだ事の責任は、自分で取ってみせると。
だから先程からは、【NAME】としてはかなり自分の制限を外した勢いで、陽動となる行動を行っているつもりだった。その成果は、周囲の土地から感じる妙な圧迫感、視線のようなものから、全くの無駄ではないらしいことも判っている。
ただ、これで足りているのか、という疑念は晴れないままではあるが。
「……まぁ、僕の方でも、出来うる限り役目は果たさせてもらうさ。こういう場面でしか使えないような印章石も、幾つか無いでは無いしね」
言って、オリオールが一つの印章石を取り出し、短い文句と共に遠く前方へと放り投げると、周囲の空間がくくと歪み、そしてそこから染み出すように泥の化生が複数現れる。
「場の土地概念に干渉して、陰性質概念を抽出し鬼種を召喚するっていうだけの印章石なんだが、やっぱりここで使うと、泥鬼の概念の方が吸い出されて、そっち側の化け物が出てくるね」
だが、この場所の土地概念と一体化した鬼の気を引くという意味では、十分に役に立つ石であるように思えた。
「ま、使い道も思い付かなかったからアレ一つだけどね。ほら、折角呼び出したんだから、あれを景気よく吹き飛ばして、より大禍鬼の気を引いてみせるとしよう」
巨人の眷属



オリオールと共に、亜獣達は極力回避し泥人形相手も適当に捌く形で山を進み、無事に目的の第四山へと辿り着いた。
浅い泥の川を渡り山に入ると、これまで執拗に襲い掛かってきた泥人形達の姿がめっきりと減り、遭遇するのは元々棲息していたのであろう亜獣ばかりとなった
山の様子も随分と違う。以前来たときには地面全体が泥濘んでいたのだが、今ではしっかりと硬い土になっている。【NAME】が意識を集中し、場の空気を感じ取ってみても異常な気配は少ないように感じる。
「イェア嬢の予想の中では、一番可能性の高い結果という形になったね」
オリオールの言葉に【NAME】は頷く。彼女は言っていた。第四山の調査はあくまで保険であり、本命は第七山と据えて作戦を立てていると。
つまり、イェアはこの場所の陰性概念が以前並か、あるいはそれ以上の規模に膨らんでいる可能性は低いと考えていたのだろう。
「ま、一度正した歪みが前以上に集まるには、周囲の土地の構造が相応に歪みやすく、しかも溜まりやすいものになっている必要があるし、加えて前に来てから今日までの間にそれだけ溜まりやすいものであるなら、以前僕等が来たときにはもっと凄い事になっていただろうからね。長く長く、誰も訪れる事なく変化が少なかったであろうこの場所で、一つ大きな正しを行ったのであれば、何か大きな理由でもない限りは然う然う激しい歪みが生まれる筈がない」
結局のところは事前のイェアの予想通り、以前での戦いの影響によって土地概念の歪みが静まっており、ここを鬼の顕現の場とするのは難しい、という結論になるか。
「で、いいんじゃないかな。後はこの事をイェア嬢に伝えれば、次はいよいよ本番――鬼との戦いだ。……今回は軍の人達もいることだし、僕は後ろで見物しているだけで大丈夫だろうか」
イェアの事だから、やはりオリオールにも何らかの仕事は割り振ってくるのではないだろうか。
【NAME】がそういうと、オリオールは「あまり前に出ないで良い仕事なら良いのだけれどもねぇ」としみじみ呟き、
「取り敢えず、今回頼まれていた役目は無事完遂だ。急ぎイェア達の所に戻るとしようか」
彼女達の方でも作戦は進めている筈だ。一応戦闘面での要とされる自分が遅れると、イェア達の作戦進行にも影響が出てしまう。オリオールの言う通り、用は済んだのだから早めにイェア達軍部隊が待機している場所へ帰るとしよう。
【※ウィースルゥインと行くを選択した場合】
【NAME】はウィースルゥインと共に行く事をイェアに伝えた。
【NAME】とウィースルゥインは、軍部隊が各山にて行う印章陣記述を邪魔されない為の陽動兼、第四山の確認調査としてそちらへ単独で向かう事となった。
「力いっぱい、暴れればいいの?」
ウィースルゥインのその問いに、【NAME】は正直なところ答えに窮した。
これが万象の力を宿す彼女でなければ間も空けずに頷いたところだろう。
しかし、先刻の“森”と“湖”での戦いにおいてウィースルゥインの圧倒的ともいえる力を見せつけられた後では、彼女のいう“力いっぱい”が一体どれ程の事象を引き起こす事になるのか、全く持って読めないのだ。
だから【NAME】は暫しの思案の後、自分が使える中でも比較的強力かつ広範囲な技法を使い、こちらに近付きつつあった亜獣の群れに叩き込む。
盛大な力の炸裂の後、亜獣の群れは悉く吹き飛び、更には生えていた木々の幾つかも折り曲げ、薙ぎ倒す程の結果が生まれる。
――これくらい、かなぁ?
攻撃を放った余韻として浅く息を吐いてから、【NAME】はその様子を表情無く眺めていたウィースルゥインに、大体これくらいの威力の攻撃を適当にばらまいてもらえれば良い、と伝える。【NAME】としてはかなり派手に打ち込んだもので、これほどの規模であれば数回もやれば、土地概念に対する影響からそこと繋がる大禍鬼も反応を示してくるはずだ。
すると、ウィースルゥインはこくりと頷き、
「判った。じゃあさっきのをばらまくね」
言って、ざわりと、彼女の髪が蠢いて、その先端から生じたのは四羽の大鳥だ。途中から千切れ、独立する藍色の大鳥となった髪は、そのまま翼を畳んでくるくるとその場で横方向に回転し始めると、
「行って」
短い号令と共に、鳥達が四方に射出され、畳まれていた翼が十メートルにも広がる。高速に回転しながら直進する鳥の翼は、当然周囲の地面や木々に触れる事になるのだが、翼はそれらを一瞬にして切り刻みながら暫く直進し、そして最後に鳥ごと大爆発を起こした。
爆発の術式などが起こす空気の振動音が全く無い、異質で耳障りな音を立てながら、藍色の大円球が生じて消滅した後には、ごっそりと半円状にえぐり取られた地面だけが残った。その直線上には切り刻まれ、薙ぎ倒され、掘り返された木々と土の凄惨な跡が刻まれ、それが合計四つ。【NAME】が指示をだして30秒もせぬ間に生じたのだ。
「どうかな。もっとする?」
「…………」
――自分が見せた攻撃よりも数段上な上に、それが三発くらい余計に発生してませんかね。
【NAME】が絶句していると、ウィースルゥインは少し困ったように僅かに眉根を寄せ、
「足りなかった? なら別の感じにするね」
次にざわめく彼女の髪の先端が造り出したのは竜の頭だ。あれは既に幾度か見た事がある。本物の竜種のような吐息[ブレス]を放つ、さっきの鳥よりも更に派手な攻撃である。
【NAME】が慌てて彼女を止めようとするが、竜の動きが速い。どうやら彼女なりに加減をするつもりだったらしく、攻撃として放つ概念を凝縮する過程をある程度省略したのだろうが、そのせいで発射速度があがり止めるのが間に合わない。
ご、と鈍い音と共に放たれた吐息、強烈な概念の流れはまるで鉄砲水のように山肌を削り取り、その進行方向にあった全てのものを薙ぎ倒して飛んだあげく、最後には遠くに見えた岸壁に突き刺さってそれすら削り、更に壁を抉る際に一部が飛沫となって飛び散って更に削る範囲を広げた事で、その周囲一角を丸ごと崩してしまった。
遠くで響く轟音を聞きながら、ウィースルゥインが「これくらいだった?」とばかりに窺うような上目遣いを見せてくるのに、【NAME】はもう何度も頷いて、これ以上は不要と答える。
ウィースルゥインが放つ力の殆どは、己が宿す極めて豊富かつ高い強度を持つ存在概念を利用したものだ。それ故、【NAME】が使う技法術式のような、理粒子による現象結果によって行う攻撃よりも、遥かに概念的存在に対し効果的で、そして目立つ。
そんなものが立て続けにこの場所に叩き付けられたのだ。当然ながら、ブランタンハリアの土地に根付く大禍鬼に対しては強烈な訴え掛けとなるのは想像に難くなく、
「わ。一杯」
【NAME】達が立つ地面が鈍い震動を始め、周辺から強烈な陰性質の概念が自分達の下に集まってくるのを感じる。それは【NAME】が過去に大禍鬼ブムドゥと対決した時にも匹敵する程のもので、ウィースルゥインの行動がどれ程のアピールになったのかが判るものだった。
そうして現れたのは、凄まじい数の泥人形と、そして泥の巨人達だ。時折、ブランタンハリアに流れる泥の川などで発生している事を見掛ける事もある巨人が、それも複数である。
――これは、確実にやり過ぎたな……。
囮としての役割は十二分に果たせた気がするが、これ程の数と強さの敵を相手にする事になるのは想定外だった。しかも、自分達は第四山へ行く途中なのだ。こいつらと戦いながら、あるいは全滅させて第四山まで移動せねばならない。
「…………」
「なに?」
若干恨めしい気持ちでウィースルゥインを見下ろすが、彼女はこちらの意図が理解出来なかったのか、小さく首を傾げるだけ。
まぁ、責めてどうなる話でも無い。それに、ウィースルゥインが居てくれるならば、これだけの相手であっても、そうそうやられる事はあるまい。
――とはいえ、厳しい戦いなるのは避けられそうにはないが。
【NAME】は、隣の彼女に、泥の眷属を倒しながら移動を開始すると告げると、少女は「わかった」と短く告げて、髪をうねりと波立たせる。
それを見届けてから、【NAME】も改めて武器を構える。
泥人形達の数は今まで見た事も無いほどの多量、その背後からはこちらに迫る巨人の姿が見える。
まずどれから倒し、次にどう動くか。それを考えながら、身体は勝手に前へ、襲い来る敵を討つために動き始める。
巨人の眷属






ウィースルゥインと共に、目に付く亜獣や次々と沸いてくる泥人形、更には大型の泥巨人すらも滅茶苦茶に吹き飛ばしながら山を進み、どうにか目的の第四山へと辿り着いた。
山に入ると、これまで執拗に襲い掛かってきた泥人形達の姿がめっきりと減り、遭遇するのは元々棲息していたのであろう亜獣ばかりとなった。どうやら、以前での戦いの影響によって土地概念の歪みが正されたまま、半ば他の場所から隔絶された土地となっているようだ。
となると、やはり事前のイェアの予想通り、ここを鬼の顕現の場とするのは難しいと、そう考えるのが妥当だろう。
「なら、私が一杯力を使ったら、ここの山も他の場所みたいにゆらゆらするようになるのかな?」
――明らかに面倒な事になりそうだから止めなさい。
慌てて制止する。陰性質の歪みが土地概念に存在していないのであれば、わざわざ印章陣を置いて干渉を行う必要すら無いのだ。第四山に関してはこのまま放置して作戦を進めても何ら問題は起きないだろう。
「なら、もう用事はおしまいなの?」
少なくともここへ来た目的は果たしたと言えるだろう。陽動についても、正直言ってやりすぎなくらいやりまくったのでそこも問題はない筈。あるとすれば、帰り道でも先刻のような猛攻を受けると、結果としてイェア達の所に泥の眷属達を引き連れていく事になってしまう点くらいか。
「じゃあ、そっと帰ろうか」
幸い、この山に入って以降、泥人形達の襲撃はない。この山の土地概念に鬼の気配も感じない事から、どうやら大禍鬼は【NAME】に一度やられてから、第四山に対して一切手を伸ばしていない事が判る。つまり、ここでの自分達の動きは気取られていない筈で、ならば極力気配を消して山から出れば、大禍鬼の感知にひっかからずに移動する事が出来る。
――と、そう考えるのは流石に希望的観測が過ぎるか、とも思うが、しかしやれることといえばそれくらいしかない。
【NAME】は自分が知る中で気配を断つ、存在を消すような類の術式を掛けながら、山の外を目指ながら歩きつつ、視線を横に向ける。
「……?」
それを感じて、見上げてくるウィースルゥイン。ゆらりゆらりと揺れる長い髪は時折気紛れのように姿を変化させ、身体から漂うあらゆる存在が混じり合った気配は、まるで大花が虫や鳥を誘う濃厚な香り、或いは獣が己を誇示するために放つ匂いが如く、強く辺りに撒き散らされている。
これをどうにかしない事には、流石に土地に根付く存在相手に気取られないようにイェア達が構えた仮の陣地まで戻る、というのは不可能な気がする。
【NAME】がそれについてどうにかならないかと彼女に問うと、
「……あまりしたくないけど、出来るよ」
そうなの? と【NAME】が目を瞬かせると、ウィースルゥインは「そう思われてるのは、少し嬉しいかもしれない」と薄い表情を僅かに笑みの形にして、
「まだ、私はこの世界にちゃんと溶け込めていないから。だから二人きりの今なら、【NAME】。貴方が私の事を忘れるようにしてくれたら。まるで居ないように、意識すらしないようにしてくれたら。私はこことの繋がりが保てなくなって、元の、あの場所に戻っちゃうと思う。そうしたら、多分もう、誰にも気づかれない……気づいてもらえないわ」
「…………」
【NAME】は思わず顔を顰める。
案としては、確かに悪いものではない。現状ではその選択以外にはないだろう。
しかし、ウィースルゥインが過去に彼女が居たという世界――今も半ばそこに居るという世界に戻ることを、あまり快く思っていないのは【NAME】も感じていた。
だから必要な事とはいえ。彼女からの提案であるとはいえ。
彼女にそれを頼むのを、そして彼女が告げた事を自分が行うのは、確かな抵抗があった。
けれども、ウィースルゥインの方はそんな【NAME】の態度に小さく首を横に振り、そして今度はより明確に、笑みを作ってみせた。
「その事を、貴方が忘れてしまっていたくらい、私の事、ちゃんと見てくれているのは、判ってるから。だから、いいよ。少しの間くらい、大丈夫」
逆に、彼女に気を遣われてしまっているようでは世話は無い。
【NAME】は謝りの言葉を変えそうとしてしかし途中で飲み込み、礼の言葉に切り替えてから、頭の中を、意識を切り替える。
目を閉じ、感覚を遮断し、意識を空にする。そうして十秒、二十秒、三十秒とすぎて、一分程の後に目を開き、感覚を解放すれば、そこには山の中、一人佇む【NAME】の姿があった。
後は何も考えず、とにかく急いでイェアのところへと戻るだけだ。変に何かを考えると――いや、この思考自体がもう既に危険だ。
【NAME】は半ば何かに追われるように走り出し、極力速く、第四山を離れてイェア達のところへと帰る事だけを考えた。
【※分岐終わり】
――陽動となる行動は第四山へ到着するまで、との指示は事前に受けていた。
帰り道で暴れるとイェア達が待つ場所にまで泥鬼の注意を引きつけることになるため、帰りは極力気配を消し、交戦を避けながら山中を進み続けた【NAME】は、ようやく軍部隊が一時の拠点としている山の頂に帰還した。
「お帰りなさい、【NAME】さん。第四山の方、如何でしたか?」
出迎えたイェアに事の次第を報告すると、彼女は最後まで聞き終えてからこくりと一つ頷き、
「ご苦労様でした、【NAME】さん。ではブムドゥを誘導する場所は予定通り、以前の【NAME】さん達の探索で強い歪みが確認されていたもう一つの山――第七山で変更無しとします。【NAME】さん達が派手に暴れてくれたおかげで、他の山への各部隊の移動と、印章陣の展開は滞りなく進んでいると報告が来ています。彼等がブムドゥに目を付けられる前に、わたくし達も急ぎ、第七山へと向かいましょう」
しかし第七山は【NAME】とオリオールの調査時には周囲を泥川で囲われており、山へと入る道すら見つけられなかったのだが。
その辺りについての対策は存在するのか。【NAME】が問うと、彼女ははて? と首を捻り、
「別に第七山自体には入りませんよ? わたくし達はその川の前――山の周囲に陣を敷いて、攻撃準備を済ませる予定です。だって多分、作戦が成功した場合は山が丸ごと巨人に変容するでしょうから」
――え、そんなでかい巨人が出てくるの?
「恐らくは」
素で訊ねると、イェアの方も全くふざけた様子もなく返してくる。どうやら冗談ではないらしい
「正確には、泥の湖がそれくらい広がって、中からブムドゥが出てくるという流れでしょうけれど。何にせよ、山中に入ってしまうと逆にそれに飲まれて危険かと思われますわ」
「…………」
勝てるのかなぁこれ、と一気に先行きが不安になるが、しかし続くイェアの言を信じるならば、彼女達軍部隊が準備する様々な術式などで、巨人の力は相応に弱まるとの話だ。今はそれをあてにするしかない。
今更、後に退けるような状況ではないのだ。
相手がどのような強大な存在として現れたとて、全力を以てして叩き潰していくしかないのだから。
――坤濁の大禍鬼──
第七山への境界となる泥が濁流となって流れる川を前に、軍部隊はこれから始まるであろう大一番を前に、様々な準備を行っていた。
その多くは術式の準備だ。大禍鬼級といった強存在を相手にする際、人の枠に収まる一般的な装備と技量の兵士が立ち向かう場合、物理的な火力――対個人規模の武器や技法で戦いを挑むのは、基本的には自殺行為の類とされる。それ故、要は術式、それも地面などに印章を記述構築した上、数人の術士が力を合わせて駆動させる、印章陣による術式攻撃が主となる。近接武器を持つ兵士達も、その術式の加護を得る等の補助を得ることで多少なりと攻防の力を増す事が出来、それに対大型生物や攻城級の兵器を活用すれば相応に戦えるようにはなるのだ。
ただしそれも、ある程度は戦いになるレベルにまでどうにか戦力を誤魔化せるというレベルの話であり、援護や一時的な守りを受け持つ程度の役割をこなせる程度でしかないとイェアは言う。
一般的な想定として、大禍鬼級の相手をする際に必要と考えられる人員や物資が、今この場には一割も無いのだ。元々中隊規模の人員を、更に各山にて泥鬼を顕現させる為に分割しているのだから、そこについてはもうどうしようもないという。
結局、【NAME】に代表される力持つ者が、どれだけ戦えるか。それが今回の戦いの勝敗を決するのは間違いない。
――今のわたくし達は、あくまで状況を有利にし、敵を弱める、【NAME】の助けをする程度にしかなれない。
幾度か、似た話をイェアからされているが、そう告げる時の彼女は何時も、何処か悔しげな顔だったのを思い出す。
しかし今、全ての準備を終え、集まった皆を前にして開始を告げようとするイェアの表情には、そんな後ろめたさを感じさせるような弱さはない。
これから現れるであろう、強大極まる存在相手に向かって、戦え、と。そう指示しなければならない人間が、そのような顔を他者に見せる訳には行かないのだ。
「では、そろそろ始めましょう! 各地の皆さんに通達。印章陣を駆動させ、土地概念に干渉を始めてくださいなっ!」
複数の伝達手段を併用しての指示が、各種に飛ぶ。
歪みの強いこの場所では、術式による情報伝達がかなり阻害される。高強度の遠隔伝信術式を駆動させながら、同時に発光、発煙術式などを使って、視覚的な合図も同時に行う。指示は問題無く各地に伝わり、各地の山にて強烈は光が空へ立ちのぼり、続いて地面が蠢動し始めた。
「成功か」
小さく、傍に居たリゼラが呟く声が聞こえた。
概念の感知に対し優れた力を持つ者ならば、今、この山岳回廊の土地に存在する歪みが、【NAME】達の目の前に聳える山という一点目掛けて押し寄せるように集中していくのが見えただろう。イェアが講じた策が、見事に機能した結果である。
そして時間にして数十秒。
最初は微震程度の揺れが、今は立っているのも難しい強震となり、更には大きな地鳴りが響き始めた辺りで、唐突に、目の前の光景が一変した。
【NAME】達の眼前にあった巨大な山が丸ごと消滅し、以前にも見た泥の湖――いや、泥の海へと一瞬で変じたのだ。
そして、そこからは事前の話通り、これまで見た事も無い程の大きさを持つ泥の巨人――大禍鬼ブムドゥが、轟音と共に立ち上がる。
「さあ、今ですわ! 一番から二十番まで、印章陣駆動! 残り三十五までは補助として適時駆動、それ以降は詰めの場面で使いますわよ!」
イェアの合図を皮切りに、待ち構えていた全員が一斉に動き始める。
まずは事前に準備していた軍部隊が、印章陣を併用した儀式術式を次々に駆動させ、泥の海から這い出そうとしていた巨人に対して様々な効果を発揮する。直接的に攻撃するものもあれば、動きを縛るもの、弱めるもの、あらゆる種類の力がブムドゥに対して放たれ、その動きを弱めていった。
更に、広がる泥海の表面から急速に水分が奪われて、干からびて硬質化していく。これも軍が仕掛けた術式の一つの効果であるようだ。
「そんじゃ、気合い入れていくわよんっ!」
そして、実質の戦闘部隊指揮を行うノクトワイの号令が轟き、満を持して【NAME】達が巨人目掛けて突撃を開始する。
[BossMonster Encountered!]
坤濁の大禍鬼

あらゆる方向から、大小様々、無数の技法と術式が、重なり聳える泥の大巨人を打ち据えていく。
まるで山が立ち上がったかと錯覚させるほどであったその巨体は、幾度も幾度も、挫けず武器を振るい術式を放つ【NAME】達の猛攻によって、大きくその姿を減じさせていた。
「【NAME】よ。そろそろ機だ。支度せよ」
鋭い声はリゼラのもの。彼は動きを止めて構えを変え、大技を放つ態勢に入る。その仕草は度々彼が見せた強烈な交差二連撃、“古の月[エンシェントムーン]”の構えだ。
どうやら彼が一気に勝負を着けるつもりらしい事を悟り、【NAME】は周囲に攻撃を合わせるよう伝える。
全員が持てる最大規模の攻撃を一気に放ち、巨人が広がる泥の海を利用し身体を再生するより早く、全てを破壊し、崩滅に導くのだ。
「ここで決めます! 総員、全火力攻撃!」
イェアの指示に従い、兵士達が個々に大技を放つための前動作を始め、術士達は多人数による儀式系術式の準備に入る。
そして次の瞬間、同時に放たれた幾重もの力が、ブムドゥの身体をこれまで以上の勢いで削っていく。
特に三人、リゼラが斬撃と突撃の交差による光吹く双撃。ノエルのフォーレミュートに強度の存在概念を圧縮して封じ放つ、理粒子砲――というよりは竜種の吐息[ブレス]に近い、概念干渉砲の一撃。そしてウィースルゥインの“固独”の特性による、単なる接触によって生じる存在の拒絶消失。それらが大禍鬼を形作る殆どを吹き飛ばし、後には身長にして10メートルにも届かない、泥の巨人が残った。
「――――」
一歩。既に軍が駆動させた術式の効果は失せ、滑りを取り戻し始めた泥の海面を、【NAME】は術式を併用して強く蹴り飛ぶ。
瞬く間に距離を詰め、巨人の真上にまで飛び上がった【NAME】は、己が武器に持てるあらゆる力を込めて、緩慢に頭を上げようとする巨人を、上から下へと、真っ直ぐに撃ち断った。
それが、ブムドゥという鬼種が、この世にて存在を許される境を越えた一撃となった。
生じた泥の海が、元の山へと瞬く間に戻っていき、これまで幾度も再生を繰り返した巨人が、もう何の手を下す必要も無く、指先から渇き、ひび割れ、そして砕けていく。
これが終わり。ブムドゥを構成する存在概念が、崩壊し、滅していくのだ。
「ひゅー。ホントにやれたわねぇ」
その様を眺めて、肩に剣を担いだノクトワイが、自分でも信じられないという風に呆れ気味の声を出すのが聞こえた。
彼の剣は土色で汚れ、もう殆ど切れ味を残しておらず、姿も泥だらけ。傷も少なからず負っている様子だ。それは他の兵士達にしても、そして【NAME】にしてもほぼ同様の有り様でもあった。
そこへ、後方で指揮を執っていたイェアが、ぐったりとした様子でこちらに歩いてくる。彼女にしても、後方にいたとはいえ巨人の放つ泥槍の射程は十分に届く位置。怪我はないようであるが、所々泥に塗れ、顔には疲労の色が濃い。
「まったくですわ……。あれだけ用意した印章陣もせいぜい足止めか補助の足しになるかで、こんなの、【NAME】さん達が居なかったら即破綻じゃないですかもう……って、そんな事言ってる場合じゃありませんでしたっ! 封縛封縛っ! ウィーちゃん、ちょっとこっちきてーっ!」
「……ん? んー」
散り砕けていく鬼の気配に、イェアが慌てた様子で鎖に繋がれた石群を持ち出すと、宙に鋭く印章を切る。鎖の根を中心に石群が浮かび上がって広がり、薄暗く曇っていた印章石がそれぞれ輝きを放ち始めるが、
「うわーやっぱりわたくしの力じゃ全然駆動させるまで足りてないっ! ウィーちゃん、あれに力ぶち込んで!」
「……どんな?」
呼ばれて寄ってきたウィースルゥインが、曖昧な言い方で急かしてくるイェアに首を傾げる。
「どんなって……わたくしがあの石に組んである術式は把握できます!? 出来るなら、それに同調して干渉――兎に角、なんか動きそうな感じの力をテキトーにお願いしますっ! 急いで!」
「む。むー」
端から聞いていても呆れる程の雑な指示に、当然ながらウィースルゥインは困ったらしく、珍しく表情を明確に曇らせて浮かぶ石群を見る。
これ大丈夫か、というか、ここまでやって存在概念の確保に失敗とか、笑い話にもならないぞ、と【NAME】達がはらはらしながら見守っていると、
「こんな感じかな?」
呟いて、ふわりと石群の傍に飛び上がったウィースルゥインが、鎖の中央を指先で弾く。
すると、広がっていた石群達からこれまでとは比べものにならない程の光が放たれ、その光が指向性を持って集まり、うねり、波となり、今まさに砕かれ空間に掻き消えようとしていた存在概念を拾い集めると、それらを抱えて石の中へと戻っていく。
後には、元の姿を取り戻した山と、砕け散った泥鬼の僅かな断片だけが残された。
「……これで良かった?」
「完璧ですウィーちゃんっ! もう大好き!」
イェアの大喝采にウィースルゥインは先刻とは別の意味で困って、眉根を寄せて小さく首を竦めた。
こうして、ブランタンハリア山岳回廊の主とも言える存在であった大禍鬼ブムドゥは、完全に滅び去った。
その存在概念は封縛印章石群にて封じられ、兵士達には相応の被害は出たものの死者を出す程でもなく、今回の戦いは完全な勝利という形で幕を閉じた。
――最後はどうなるものかと思ったが、ブムドゥとの一連の戦いについては案外楽に終わった気がする。
そんな【NAME】の感想に、薄暗くも強烈な輝きという相反する光を帯びた石群を、ふわりと宙から降りてきたウィースルゥインから受け取ったイェアは、神妙な顔つきで首を横に振る。
「何いってるんですの。全然楽じゃなかったじゃないですか。最初も最初から、【NAME】さんに殆ど単独で囮みたいな真似させたの、もう忘れちゃったんですの?」
「…………」
ああいう役はいつもの事過ぎて、本当に忘れていた。
【NAME】の反応に、イェアは「本当にこの人は……」と頭を抱えて溜息をつく。
「事前の情報と下準備。更にこれだけの人数であらゆる攻撃法を揃えて待ち受けても、【NAME】や、ウィーちゃん達があれだけ頑張ってくれてようやくなんですのよ? 【NAME】さんって、どうも自分の苦労を甘く見積もるクセ、ありません?」
「……?」
そんな事を言われて、しかし【NAME】としては首を傾げるしかなかった。
実際、これまで【NAME】が経てきた戦いと比較すると、多くの人達から様々な助けが得られていた分、今回はいつもより心強く戦えたというのは事実なのだ。だから、別に間違った事を言ったつもりはなかった。
それもこれも、イェアや皆が全力で手を貸してくれたからこそ案外楽に終わったのだと、そんな感謝の念から出た言葉なのだから。
【NAME】がそういうと、む、とイェアは眉根を寄せて、怒ったような顔で固まる。
「そういう事、恥ずかしげもなくきっぱり言わないでくださいな。慣れてないものだから、どう返したらいいのか、判らなくなっちゃいますわ。と、兎に角!
この次のキルーザムでも同様に上手く行くかどうかは判りませんから、油断せず、気を引き締めてくださいな!」
語気強く言ってくるりと顔を背けた彼女に、ああ成る程、照れてたのかと素直な感想を口に出すと、
「だから! そういうことはっきり言わないでくださいな! ……あーもー! 【NAME】さんの馬鹿!」
本サイト内コンテンツの一切の転載を禁止いたします。