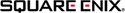真なる楽園 至る幻、芯檻の縮尺模型
――イールシック地下都市遺跡――
イールシック地下都市遺跡。
エルツァン地下に存在する巨大な遺跡群は、中央に存在する都市部以外にも無数の通路を広く張り巡らせて、エルツァン島各地の地下にその網を伸ばしている。
だが、改めて考えてみると、それも奇妙な話だと【NAME】は思う。
これまでの旅の経験から、エルツァンという島の内部はそれぞれ独立した土地概念を持つ、極めて異質な世界の集合体となっている事が判っていた。それぞれの土地と土地は、多くが明確な“境界”と言えるものを持っており、互いが干渉し合わないような構造となっている。土地同士の繋がりすらも、状況によっては不安定になっている程なのだ。
しかし、そのような環境において、イールシック地下都市遺跡の地下通路網は、多くの地域と繋がりを維持したままなのだ。それも“境界”越し――一歩踏み込めば瞬時に周囲の環境が切り替わるような形ではなく、“地上から地下へと続く通路”として、物理的に繋がった状態で、だ。
もっとも、それらの場所から繋がっている通路が、地下にて物理法則に則った形で存在しているかと言われると、【NAME】とオリオールが観測した限りでは否というしかなかった。例えば比較的近い地点にて存在していた通路二つが、入口を基準に考えて地下内で交差するような方向に伸びていたとしても、実際通路に入ってみるとそういう構造にはなっていない、という風に。どうやら地下道路群はエルツァン島の各所に入口を繋げてはいるものの、いざ“地下”へと入れば、それぞれの入口との距離、配置を全く無視した独自の通路網を“地下”内で構築しているらしい。
侵入した細道から、所々に設置されていた通気口などを伝って通路と通路を渡り続けた結果。【NAME】とオリオールはどうにかカール・シュミットが辿ったであろう大通路に行き当たることに成功していた。
「エルツァンの土地は状態が極めて不確定だ。地形、天候、環境はおろか時間すらも安定しない。だが、イールシックの通路網は、その多くの場所と繋がる口を持ち、保ち続けたままだ。“谷”や“森”に繋がっているのは既に確認済みで、今僕等が歩いている“山”からのルートもある。更にカール氏の手記を信じるならば、“洞”――キルーザム狼咆洞窟に繋がる通路も持っている筈だ。もしかすると、“湖”や“丘”にも、僕等が見つけられていないだけで、地下道路網の入口が存在しているのかも知れないね」
これまで見つけてきた通路とは、明らかに毛色の異なる巨大な通路。そこを歩きながら、オリオールは淡々と話す。
前方には、小さな男の背中。カール・シュミットの幻影は、この大通路に入ってから殆ど途切れること無く存在し、大通路を奥へと歩いていく。
「そんな風に、歪んだ環境を持つあらゆる土地と繋がっているのだろうけれども、地下自体には他の土地のような歪な環境や、陰性質の鬼の気配がない。地下通路と地下都市。機種が多く潜むという話だけれども、言ってみればそれだけの場所で、エルツァン内陸の地形の中では唯一といって良い、正常な場所だ。つまり、イールシック地下都市遺跡は、エルツァン内陸に存在する地形の中では、少し特殊な位置づけにある場所なのだろうね。これだけでも、多くの何故という疑問が生まれ、憶測が出来るけれども……」
通路に機種の気配は無い。
かつかつ、と硬質の床を靴裏が叩く音と、オリオールの話し声だけが響く。
「これまで発見されてきた中で、今僕等が歩いているような巨大な通路が存在した、という話は聞かない。殆どは人数人が通れれば良い程度の細道ばかりで、ここのような――」
一瞬、オリオールは上方、左右と視線を振る。
「広い道はどうやら例外――特別な通路であるらしい。となると、気になるのは」
何故そのような特別な通路が必要であったのか。
そして、その特別な通路の先には一体何があるのか、か。
【NAME】が言葉を引き継ぐと、オリオールは大きく頷いて、
「ブランタンハリアで遂に一人となり、当然負傷もあっただろうね。そんなカール氏が疲労困憊の中、この道を辿り、そして何を見て、如何にしてエルツァンの外へと脱出するに至ったのか。エルツァンの土地の中でもどうやら特別な場所であるらしい地下都市遺跡の中で、更に特別な通路の先に、彼は何を見て、そして僕等は何を見るのか」
笑い、
「わくわくするね。これぞ正に探して検める――“冒険”という奴だよ」
そうして、【NAME】達は大通路の末端に辿り着いた。
・
地下都市遺跡、と。
そう呼ばれるのは当然、張り巡らされた地下通路網の中心に、都市にも似た形状の地下遺跡が存在していたからだ。
しかし、大通路を進んだ先。【NAME】達が辿り着いた場所はといえば。
「……何だろうね、ここは」
大通路の先に存在していたのは、兎に角だだっ広い逆凸形の空間だ。
高さは数十、横は一辺数百メートルはあろうかという長方形。その床部分は中央から半分ほどが中窪の状態となっており、上段と下段の二段構造となっていた。
上段区画は殆ど何も無い。四方に、壁に接する形で小さな塔のようなものが建っているのが見えるが、それ以外に目につくものは無い、至極がらんとした空間だ。カール・シュミットの手記にあったような、地下都市を思わせる建造物もなければ、機種達の姿も見当たらない。ただ、上段部の床部分は所々が大きく砕けており、寸断されている場所が多いようだ。
そんな上段区画に対して、下段区画は猥雑な構造となっているようだった。複数の壁が、上から見れば格子に近い形で配置されて場所を区切っており、その内部には用途のはっきりとしない多数の資材が、雑に積み置かれているのが見える。そんな中で、中央を経由する形で大きな十字路が真っ直ぐに通っているのが印象的だ。
上段と下段の境となる縁には、所々に鋭角の巨大な出っ張りが伸びているのが判る。出っ張りは壁の内側から外へとスライドする形で伸びていて、構造から察するに、恐らくその出っ張りは上段と下段を区切り封鎖する事が出来る隔壁が、半端な形で留まっている状態なのだろう。
そして下段区画の中で一際目立つのが、中央に見える十字路の交点部だ。広く取られたその場所は、床が独特の形状となっており、特に目を引く。
「取り敢えず、あの目立つ真ん中に行ってみよう。あの床が何なのか、気になるしね」
異論は無い。オリオールの提案に頷いて、【NAME】達は移動を開始した。
上段区画を中心目指して進み、下段区画へと降りる方法を探す。暫くの捜索の後、下方へと伸びる階段を見つけ、それを辿り下段区画へと降りる。
上段区画と異なり、下段区画は上から見た時の印象そのままだ。空間は複数の大きな壁で仕切られており、所々に巨大な金属の塊などの資材らしきものが積み置かれていた。
壁は所々が可動式となっているらしく、開いている場所を通れば、隣接するエリアに移動出来る。中央へと行くルートは、上から見たときに既に把握していた事に加えて、カール・シュミットの幻影が頻繁に現れるため、道に迷う心配が無い。【NAME】達は幻影の動きに従って移動し、下段区画中央へと続く十字路の一本へと出た。
と、そこで周囲に異変を感じ、【NAME】は立ち止まる。
まず耳に届いたのは鈍い起動音。蹲った状態のまま動かず、機能停止しているかと思われた機種が、【NAME】達の接近を感知したのか、突如その身を起こす。
「……これまでと違って、どうやら下には未だ稼働状態の機種が存在するらしいね」
面倒そうな声音で呟きながら、オリオールが腰裏の鞘から小剣を引き抜くのが見えた。
自分達目掛けて武器を構えて迫る彼等に、【NAME】は己の得物を手に取り対抗する。
battle
主無き兵士達


機種を撃退した【NAME】達は、道をそのまま辿って下段部中央、十字に交差する道の交点に辿り着いた。
遠目からでは良く判らなかったが、実際に真上までやってきてみれば、そこが一体どういう構造になっているのかが判った。つまりこれは、
「アレの小型版、かな」
オリオールが見ているのは、今いる場所から若干の上方。空間の上段区画と下段区画の境から半端な形で出っ張る隔壁の一部である。
隔壁はどうやら全部で四枚あるようなのだが、その一枚、<青または赤>のラインが各所に入った壁は、既に開かれた状態であるらしく、床部は残る三枚で構築されていた。
この隔壁の向こう、下方には恐らく何かあるのだろう。
だが、それを調べる必要まであるのか? と首を捻ったところで、【NAME】達の前に幻影が過ぎる。
イールシック地下都市遺跡で初めて見る、カール・シュミットの幻影。それはなんと、隔壁の中に沈み込んでしまった。
「……ということは、カール氏がここに訪れたときはこの障壁は開いていて、彼はこの奥」
がんがんと地面を蹴り、
「隔壁の向こう側へと移動していった、と?」
つまり、カール・シュミットの消息を追っている自分達は、どうにかしてこの隔壁を全て開き、ここの下方に何があるのかを確かめねばならなくなってしまった、のだが。
「しかし、一体どうやって開ければ良いのかな、これは」
「…………」
周囲に、隔壁の開閉に使えるようなものは見当たらない。
しかし、開けられないということは流石にあるまい。何せ過去、カール・シュミットが障壁の向こうに降りたのだから。
「……兎に角、調べられるだけ調べてみるしかないか。何処かにこの隔壁を操作するための装置がある、と考えるのが利口だが」
さて、肝心のそれが何処にあるのやら。
【NAME】はぐるりと周囲を見渡す。周りは壁で覆われて殆ど見えないが、しかし上方は広く開いており、上段部分だけはよく見える。
そこでやはり目につくのは、四方に配置された塔状の建物だ。
「宛となるのはあれくらい、だよな。手がかりくらいはあるかもしれない。行ってみるだけ行ってみようか。……しかし、似たような塔が四つとなると紛らわしいな」
適当に番号でも付ければ区別はどうにかつくだろう。
「それもそうか。ではあれを1――」
オリオールが時計回りに四つの塔にそれぞれ数字を振り、
「として、さて、何処から行こうか」
そもそも、そこまでの道が繋がっているかという部分もある。下段部は所々が色つきの隔壁で閉じられており、通行不能になっている場所があるのは上から見ていて既に判っている。確か、ここから移動出来そうな塔は<1または3>番の塔だけの筈だ。
下段区画中央。地面の一角に存在していた四枚の大隔壁は、既に全てが開かれている状態だった。
その壁の向こうに存在していたのは、遙か下方へと続く巨大な穴だ。
「これはまた……どこまで続いているのかね」
縦へと伸びる空洞を見下ろして、オリオールは呆れたように呟く。
カール・シュミットの幻影が隔壁を越えてその下へと消えていった事から、隔壁の向こう側には下へ降りられる空間がある事は想像がついていたが、こうも深い穴が存在しているとは思わなかった。
穴は六角形。幅は30メートル程だろう。壁部の各所に取り付けられてる照明は未だ死んではおらず、穴の中は薄暗くはあるも完全な闇には閉ざされていない。しかしそんな状態でありながらも、【NAME】達の目にはその底が何処にあるのかを見通す事が出来ない。100メートル、200メートル。いや、もっと深いだろうか。穴の中央には螺旋の縁が入った金属の光沢を持つ巨大な柱が突き立っているが、その下部がどうなっているのかも、【NAME】の視力では正確に把握する事はできなかった。
「確か、カール氏の幻は、ここから下へ降りていった筈、なんだけれど……」
大穴を覗き込みながら、オリオールが腕組みする。
素直に考えると、この穴に飛び降りた、という事になるのだが、それは、流石に。
「カール氏の足跡を追ってきた身とはいえ、ここから底の見えない穴に飛び降りるというのは、どうにもぞっとしないね」
底がどうなっているかは判らないが、多少の衝撃緩衝材があったとしても死は免れないような高さだ。術式を使って落下速度を落としながら降りる、という手も考えられたが、しかし穴底がどういう状況が判らない状態でそうするのもやはり危険な気がする。
「何か、もっと安全な方法は無いものか――あ、あれか?」
と、オリオールが穴の縁の一点を指差す。そこにあったのは、穴の縁から下へと真っ直ぐに並んで取り付けられた把手だ。横に指先から肘程度、手前に掌程の長さを持つ把手は、外壁に一定間隔で据え付けられて、それは穴の奥へと伸びていく。
「これを梯子代わりに伝っていけば、下まで降りられるんじゃないか?」
早速とばかりにオリオールが把手に足を掛け、手で握り、するすると数段下に降りて、その具合を確かめる。把手は外壁と完全に一体化しており、加えて老朽化しているという様子もない。
「大丈夫そうだ。【NAME】、これを使って降りてみよう」
・
把手は無事穴の底まで取り付けられており、【NAME】達はそれを伝ってどうにか穴の底まで降りる事が出来た。
「……いやぁ、流石にきつかったね」
【NAME】が把手を離して穴底に足を突くと、先を行っていたオリオールが両の手を振りながら苦笑いする。正確な時間までは判らないが、穴の縁からこの底まで、移動に使った時間は分単位では済まないものだったように思う。見上げてみれば、上から差し込む光の円はかなり小さい。最初に見積もった深さ以上であったのは確かだろう。
全身の筋肉が強張っているのを感じ、【NAME】もオリオールのように身体を解すために両の手足の筋を引っ張るように伸びをする。
「で、ここが最奥、という事になるのだけれど……」
ぐるりと周囲を見渡す。
【NAME】達が足をついている床部分は、どうも穴の底よりも一段程高いようだ。床自体が分厚い台座のようなものであるらしい。一体何故と、疑問に思い、そして気づく。
中心から上へと伸びる巨大な柱。その底部は、今【NAME】達が立つ床部分と接合具を挟んで一体化されており、
「……成る程ね。本来はこの床が、昇降機としての役割を持っていて、柱はそのための基部か」
何らかの方法で操作することにより、床が上下に移動し、恐らく上の各所に残されていた資材を上から下へと運んでいたか、若しくは下から上へと運ばれたものが、残されていた資材であるのか。どちらにせよ、
「ここが終端、という訳ではないようだね。ほら、【NAME】、あそこを」
オリオールが視線を向けたのは、側面。上から見た時は暗闇と角度故に判らなかったが、穴の底部には更に横方向へと伸びる穴があったのだ。
そしていつの間に現れていたのか。幻影の男が、恐る恐る穴の奥へと消えていく姿も見えた。
その影の後を追って、【NAME】とオリオールは僅かな高さを持つ台座から飛び降り、高さは然程でもないが横幅は大きく取られた半円形状の通路へと入る。
天井と側壁に二列づつ、合計四列の灯りの列に照らされた道は、先刻の予想を証明するように完全な物資運搬用であるらしく、内部には資材を運ぶためのレールや機器等の残骸が残されていた。【NAME】達はそれを避けながら道の奥へと進んでいくと、案外と道の終わりは早くやってきた。
「これはまた、凄いね」
終端に聳えていたのは、これまでとは比較にならない程に頑丈そうな、積層の巨大障壁だ。
しかし、この障壁はこれまでのものとは違い、障壁の傍に開閉用と思しき装置が用意されているのも直ぐに見つける事が出来た。
「さて、後は動かす事が出来るかどうか、なのだけれど……」
あるのは大きなレバーが一本、ボタン式のスイッチが四個。レバーは上方に引き上げられた状態で、ボタンは幾つかが点灯状態。
順当に考えるならば、レバー操作で開くという辺りなのだろうが。
「そんな処だろう。では早速――」
レバーの大きさは、両手で掴んでようやく動かせるかという代物だ。オリオールは把手部分を握ると、体重を掛けて一気にレバーを降ろした。
その瞬間、強烈な警報音が地下通路に響き渡り、周囲の照明が仄かな白色から強烈な赤色へと変化する。
「……あれ? 間違ったか?」
と、オリオールは暢気な様子で微動だにしない隔壁と、いきなり派手な様子になった周囲を見回すが、しかし余裕があったのはそこまでだ。
がしゃん、と。
風切り音を伴い、天井付近から巨大かつ硬質な何かが複数落下してきたからだ。
「機種かっ!」
【NAME】とオリオールが振り向き身構える。
その視線の先。上方より落下してきたそれは、筒状の身体から無数の銃器を伸ばした、見るからに危険な大型機種だった。
「で、結局どう操作するのが正解だったのかな……」
襲い掛かってきた巨大機種を撃破した後も、警報音は鳴り止まない。余りの音と、そしてぎらぎらと光の強弱を変化させる照明にあてられて、いい加減頭がくらくらしてきたところだ。出来ればさっさとこれを収めて欲しいとこらだが。
【NAME】の愚痴に、オリオールは困ったように腕を組む。
「と言われてもどうしたものだかね。【NAME】、何か良い方法思いつくかい?」
思いつく訳がない。
だが、レバーを操作するのが外れだったのなら、他の要素を触ってみれば解決するのではないか。
【NAME】は装置に近付くと、闇雲にボタンをぽちぽちと押してみるが、しかし何の変化もない。
ならば、思案する。しかし鳴り響く音と慌ただしい光の動きに、上手く集中できない。
「…………」
もう色々と面倒くさくなってきた。
【NAME】は投げやりな気持ちでレバーを一度元の位置に戻すと、ボタンに拳を数度叩き付けた後、更に装置自体を蹴りつけてから、止めとばかりに思い切りレバーを下へと叩き込んだ。
すると、がこん、と鈍い音が響き、隔壁が一枚、一枚と開き始める。
「ええー……?」
その様子と【NAME】の顔を、オリオールが何とも言えぬ渋い顔で交互に見るが、まぁ、開いたから良いのではなかろうか、と【NAME】は涼しい顔で受け流した。
――試顕領域エルツァン――
鈍い音を響かせながら、積層式の巨大隔壁がゆっくりと開いていく。
重なっていた複数枚の壁は回転するように動いて、隔壁の向こう側が【NAME】達の目の前に晒される。一体この先に何があるのか。期待と共にそちらを見た【NAME】は、現れた意外な光景に目を瞬かせた。
隔壁の向こう側には、また別の隔壁が存在していたのだ。
開かれた隔壁をくぐった【NAME】は、辺りを改めて見回す。前方には今開いた隔壁と同種のものが固く閉ざされた状態で存在しており、隔壁と隔壁との距離は大凡10メートル。左右上方に視線を遮るものは無く、幅そのままの空間が、緩やかな曲線を描く金属質の壁に沿って、ただ奥へと伸びていく。所々に点々と小さな照明の灯りが存在しているが、視界は明瞭とは言い難く、細部がどうなっているのかまでは良く判らない。
だが、それだけの情報でも判ることはある。つまり、
「円蓋の中に、またもう一つ、サイズの小さい円蓋が存在しているのかな」
顎に手をやり、呆れたような声音で呟いたオリオールに、【NAME】も短く頷く。恐らく大小二つのドーム状の壁が存在し、自分達は今、その境目に居るのだろう。
「今越えてきた壁の分厚さだけでもかなりのものだった筈だけど、その内側にもう一つあるとはね」
話しながら、オリオールは一瞬背後、開かれた状態の巨大な隔壁を流し見る。
「……厳重というか、念入りというか。僕もこれまで色々な場所に入り込んできたけれど、ここまで徹底しているところはあまり見た事がないな。そもそも、ここに来るまでの間も、結構な数の封鎖用らしい壁があったろうに」
言われてみれば、と思う。
ここに降りてくる間も既に、少々やり過ぎではないかと思えるくらいに隔壁が用意されていた気がする。例えば上方にあった逆凸状の空間では、上段区画と下段区画を遮る大隔壁に加えて、下段区画は各所を塞ぐ可動壁まであり、中央に存在した更なる地下へと降りるための縦穴にしても、入口は四重の隔壁でもって閉じられていた。
過剰とも思える隔離構造を持つ場所。
それには当然ながら、設計段階でそうするだけの何かがあった筈で。
「問題は、何を遮るために用意されていた隔壁なのか、という事だよね……。可動式ということは、何らかの緊急時を想定したものなのだろうけれど」
素直に考えれば、開閉可能な隔壁を用意する理由は大きく二つに分けられる。
一つは外部からの侵入や、攻撃に対するための備えだ。
「これが外から内への干渉を防ぐための構造であるなら、その殆どを既に潜り抜けてきた今の僕等にとってはそう気にするような事じゃなくなる。むしろ奥にはそういった防御に護られた何かがあるという事だから、この先にあるものに色々と期待が出来るところだ。所謂城の宝物庫とか、そういう類だ。――けれども逆に」
これが外から内への攻撃に対する備えではなく、内から外への動きに対する備えであったなら。
「この奥に存在するであろう何かを封じる為の用意と考えられる。単なる火災とか、そういった不意の事故に対応するためにしては仰々しすぎる。緊急時、もしくはそれに類するような状況に際して、決してそれを外に漏れ出さぬようにする為の設計なんだろう。もっとも、それが何なのかは、現状では全くもって想像はつかないが――」
もしも前者の理由ではなく、後者の理由であった場合。
気になるのは、これまで通過してきた道筋に存在する隔壁の状態だ。
可動式の隔壁は、その殆どが閉じた状態となっていた。目の前にある積層式の隔壁然り、背後の隔壁然り、縦穴へと入るための隔壁然り。そもそも上方に存在していた資材置き場らしい空間へと続いていた大通路にしても、ブランタンハリア山岳回廊に存在していた入口部分はこれまた隔壁で閉じられた状態であったのだ。
例外は資材置き場の上段区画と下段区画を遮る隔壁だが、それについても完全な開放状態ではなく、中途半端に展開された形で停止していた。その不自然な姿は、閉じる途中であった隔壁が、何らかの問題によって動きを止めた結果ではないか、とも。
「その辺りを考慮に入れると、要するに今の状況は、既に想定されていた緊急の事態とやらは起きたか、もしくは起きると判断された後の状態なんじゃないかな。で、これまでの造りから推測すれば、まぁ外からの侵入に備えるためというよりは、内からの何かを抑えるための物と考える方が自然だろうね。何せ、隔壁を開くための装置が、外からやってきた僕等が操作出来る場所にあった訳だから」
確かにその通りだ。外敵の侵入への対策として用意されていたものなのならば、例えば縦穴上部を塞いでいた四重隔壁を操作するための機器が、縦穴の上方に存在しているのはおかしい。
「…………」
そこまで話して、【NAME】とオリオールは正面へと視線を戻す。
目に映るのは、閉じた状態を維持する二つ目の積層隔壁だ。恐らくはイールシック地下都市遺跡の、最深と思しき場所へと続く扉。
然して深く考える事無く、ただ幻を追ってこうしてやってきてしまったが、先刻の推測の通りならば、この向こうには一体、どれ程の危険が存在するというのか。多数の機種を使役したであろう、この遺跡を造った何者か――推測するならば旧時代に芯属から直接知恵を授けられた人間達か、はたまた芯属自らの手によるものか。そんな彼等が危険視し、囲った何かがここにあるのだろう。
見れば、隣に立つオリオールは顔に不敵な笑みを浮かべてはいるものの、その顔色はあまり良くない。恐らくは自分も、似たような顔色になっている事だろう。
――はっきり言ってしまえば、厭な予感しかしない。
率直に呟くと、「いや本当にね」と隣からは心のこもった声が返り、
「……正直、この奥に何があるのかを確かめるのは怖いよ。好奇心はある。興奮もしている。けれども同時に、同じくらいに恐ろしくもある。この感情を無視する者は、探検家として、冒険家として、長生きは出来ない。それは今までの経験から十分に判っている。でもほら」
オリオールが、【NAME】のすぐ隣を指差す。
反射的にそちらを見れば、ふわりと。半ば透き通った幻の人影が、【NAME】の傍を通り過ぎて真っ直ぐに前へ、正面の隔壁へと近付いていく。
既に見慣れた、カール・シュミットの幻影。
だが、その姿は、幻であっても判る程に傷つき、疲弊していた。身につけていた装備類も殆ど失って、片腕は力なく下へと降ろされて、脚は引き摺るようにしか動かず、遅々とした歩みだ。
しかし、血と泥に汚れた彼の顔には、既に過去の幻影で見たような恐れや怯えの色はない。ある種の覚悟――己の行く末が死である事すらも呑み込む。そんな覚悟を得た者の顔だ。
幻はそのままゆっくりと、しかし着実に。立ち止まっていた【NAME】達を置いて先へ――閉じられた大隔壁の向こうへと消えていく。立ち止まる気配どころか、戸惑う気配すら見せない。これまでと同様、カール・シュミットが過去にここを通り抜けた時には、この隔壁は閉じられてはいなかったのだろう。
と、【NAME】と同様に幻影の背中を見送っていたオリオールが、小さく溜息をつく音が聞こえた。
「例え一人になったとしても、いや、一人になったからこそ、カール氏は先を進むことを望んだのかな。……まぁ、何にせよ、同業としては彼に負ける訳にはいかない。今は多分、恐怖を殺して進むときだ。それに、彼がどうやってこの奥地から生還したのかという疑問もあるしね」
言われてみればそうだ。
彼がこの場所まで単独でやってこられたのは、隔壁が開いていた事に加えて、機種との遭遇も殆どなかったからだろう。先刻【NAME】と戦闘を繰り広げた警備役らしい機種達も、あくまで閉じた隔壁を無理に開こうとする者に対して出現したのであれば、そもそも隔壁が閉じていなかったであろうカール・シュミットが通過した際に反応しなかった可能性はある。
だが、ここにやってきて、それから一体どうしたのか、という疑問は確かにある。
記録によれば、カール・シュミットはこの後エルツァンを脱し、アノーレへと戻っている。しかし、先刻の幻影を思い返せば、瀕死という域には至ってはいないものの負傷と疲労の蓄積は一目で判る程のもので、エルツァンの地形を単独で抜けられるような様子ではなかった。
ならばこの隔壁の向こう側か、もしくは今【NAME】達がいる二つのドームの隙間を辿れば、少なくともエルツァンの沿岸へと脱出できるようなルートが存在する筈なのだが――本当にそんなものが都合良く存在しているのかという疑念が、どうしても拭えない。
手記に手がかりでもあれば良かったのだが、何故かカール・シュミットはブランタンハリア以降の経緯を手記には一切残していないため、参考に出来るものが何も無い。
(いや、それ以前に……)
過去にカールが訪れた際には開いていたらしい隔壁が、今は閉じている。それは見逃せない事実でもある。
少なくとも、カール・シュミットがここに辿り着いたとき、もしくはその後に、この場所の隔壁が閉じられるような出来事が起こったという証明になるからだ。
「それを知るためにも、ここで怖じ気づいてはいられない。彼が何を見たのか。それを見届けるこそが、僕が定めた“冒険”だからね。少々の……いや、大層な危険であれ、それは許容の範囲だよ。はっきりと言ってしまえば、一人で来ていたならば引き返しているところだ。けれども今は」
そこで彼は言葉を区切ると、笑みと共にこちらを見る。
「フローリア諸島の幾多の事件を解決した英雄殿が一緒に居る訳だしね。きっと大丈夫だろう」
――あまり宛にされても困るのだが。
無責任な発言に、【NAME】は吐息と共に肩を落とすが、しかし【NAME】としてもここで引き返すつもりはなかった。
何故なら、先程から僅かにではあるが感じるのだ。
胸元に収まる首飾りが、静かに、しかし確かな音を立てて、反応している事を。
「では、ご開帳と行こうか。といっても、装置はさっきと同じようなのがあるけれども、結局どうするのが正解なのかね」
オリオールは二枚目の隔壁傍に近づき、横に備え付けられていた大きなレバーに手を伸ばす。
「取り敢えず、先刻の【NAME】の真似をしてみようか。……また機種が出てきたら宜しく頼むよ」
そういって、オリオールは適当にボタンを叩いた後、がつんと蹴りを一発入れてからレバーを叩き降ろした。
【NAME】は新たな機種が出現しないかと素早く周囲に気を配るが、しかし何かが現れる気配は無く、逆に、
「……あれ、開いた」
ごうん、と腹に響く音を立てて、隔壁がゆっくりと動き出す。
「まさか、本当にあの手順が正しい操作法なのかね……」
流石にそんな筈はない、と思う、のだが。
「まぁいい。取り敢えず、開けた向こうから突然有毒ガスが噴き出すとか、呪いの霧が飛び出すとか、凶暴極まる化け物が出てくるとか、十分に有り得る話だ。気を引き締めていこう」
化け物は兎も角、呪いや毒なんていきなり言われてもどう対処したものか。
半ば投げやりな気分になりながら、【NAME】は開いていく隔壁の向こうへと目を凝らした。
隙間から差し込むのは白色。【NAME】は一瞬その白さに目を眩ませて、堪えるように瞼を閉じて、そしてゆっくりと開いていく。
そうしている間にも、複雑に重なり合った扉は音を立てて開いていき、その奥に存在しているものが、【NAME】達の眼前に広がる。
――イールシック地下都市遺跡の、恐らくは最奥となる地。
そこに存在していたのは、上層の地下都市部とは全く質が異なる、術的な気配が色濃く漂う場所。全面の壁、床にびっしりと紋様が刻まれたドーム状の広大な空間と、その中にて上方へと突き立つ柱の群れだった。
・
完全に開放された隔壁。その隙間は五メートル四方ほどだ。開かれた口を潜り、【NAME】達は半球の内部へと足を踏み入れる。
「……これはまた、凄まじいな……」
オリオールが上ずった驚きの声を上げるのも判る。
円蓋の内部は半径数百メートル規模の広大なもので、その中央部付近で巨大な柱が合計にして七本、無秩序に突き立っている光景もかなり異様だが、何よりも漂う空気が独特なのだ。
空間全体に広がっているのは、これまで通ってきた地下都市とは明らかに趣が異なる気配。ちりちりと肌が粟立つような感覚と、意識が圧迫されるかのような雰囲気は、狭い場所で多種の強力な術式を行使した際に生まれやすいものだ。単純に言えば、場に存在するあらゆる理粒子が活性化している状態である。
その理由については、簡単に想像がついた。
近場を見渡すと、兎に角目につくのが巨大な紋様である。壁も床も、素材の判別もつかぬ、滑らかで硬質なもので造られており、ほぼ全面にびっしりと複雑な意匠の紋様が刻み込まれている。白色を帯びて明滅する紋様。その内側から感じられる力はまるで溢れるようで、それが空間にまで作用しているのだろう。
既に、オリオールはその一つに対して身を折るようにかぶりついており、
「……これは、印章[シギル]じゃないな」
膝を付き、それに軽く指を這わせたオリオールは、眉根を寄せて唸り声を上げる。
「む、ぅう……恐らくは象形[グリフ]……なのだろうけれど、ただの象形ですらないな。【NAME】、ほら、ここを見てくれ」
オリオールが指を差した場所に目を移す。
そこは紋様の先端部だ。蔓のような形状の一端を構築している部分。それを良く良く目を凝らしてみれば、どうやらただ単純に床を一線でもって彫り込まれたわけではなく、細かく小さな紋章の列が、線となって存在している事が判る。つまりは巨大な一つの象形として存在しながら、その実、無数の微細な象形としての役割、力を持って存在しているのだ。
象形とは、主に芯属達が操った絶大な力を持つ紋様術式である。人が操る、印章による術式よりも遙かに強く、多彩な力を持つそれは、小さな一紋様ですら熟練の術士達によって組み上げられた印章陣や印章機構を上回るという。
その象形が、
「これだけの広さを持つ空間に、びっしりと刻み込まれているとはね……。ここまで徹底した象形記述がされている場所は、数多の芯形機構[グリフコンバータ]でも稀だよ」
――芯形機構。
確か、過去の“芯なる時代”に芯属達が造り上げた、象形を内包して力を行使する大型具や建造物の総称で、アノーレ島に存在した“四大遺跡”もその分類に入るのだったか。
「ああ。兎に角、この場所は凄まじい力を秘めた芯形機構であることは間違いない。しかも死んでない。駆動こそしていないが、まだ機構内に組み込まれた術式は生きたままだよ、これは!」
感心と感激に染まった声で、オリオールはまた床の紋様に張り付いて、ああだこうだと呟き続ける。
しかし、彼が判ったのもそこまでだ。
【NAME】もオリオールも、こういう古代の術式についての知識はそれ程でもなく、況してや象形を用いた芯形機構ともなれば完全な門外漢だ。肝心の部分とも言える、この場所が一体何のために造られた場所なのか。つまり、芯形機構としてどのような機能を持つのかという要が判らないままだった。
オリオールは嘆息と共に立ち上がり、
「こうして這いつくばっていても話は進まないか。【NAME】、取り敢えず手分けしてここを一通り探索してみよう。もしかしたら、もっと判りやすい何かが見つかるかもしれないし、それにカール氏の幻影が見つかれば、彼がこの場所で何をしていたのかが判る筈だ」
探索という点には異論は無いが、しかし別れて個別に行動しても大丈夫なのだろうか?
【NAME】の問いに、オリオールは気難しげな顔で唸るが、
「どうだろうね。機種らしき姿は見えないし、亜獣についても同様だ。敵が現れて、という状況にはならないようには思える。けど、僕には良く判らないが、この場所は大分概念的におかしい感じなのだっけ?」
言われて、【NAME】は少し迷いながらも頷く。
理粒子の活性もそうだが、土地自体の存在概念がかなり歪であるように感じる。単純な陽性質、陰性質に偏ってるという話ではなく、どうにも不自然な形で安定しているように思えるのだ。
予想でしかないが、この場所に刻み込まれた象形のどれかが、そうした状態に土地概念を固定化しているように感じるのだが、それがどう発展し、そして危機に変化しうるかまでは【NAME】には判らない。象形で制御されているというのならば、概念飽和による異存在の発生という可能性も薄いとは思うのだが。
そんな【NAME】の感想に、オリオールはふーむと唸り、
「まぁ、大丈夫ということにしよう。万一僕が何か危ない相手と遭遇したら、一目散に君の処まで逃げてくるから宜しく頼む」
……本当に大丈夫なのだろうか。
口元を引きつらせながらそういうと、オリオールはどんと己の胸を叩き、
「なぁに、僕の逃げ足の早さを甘く見てもらっては困るよ。これまで僕が冒険家としてやってこれたのは、敵を単に倒すことだけじゃなく、如何に相手を眩まし、捌いて、戦いを避けるかという技能を磨いてきたからだよ」
威張るような事だろうか、と【NAME】は一瞬笑いかけて、いや、それは十分に威張れることなのだろうと思い直す。
確かに彼の言う通りなのだろう。彼は冒険家だ。その目的は秘境を踏破する事であって、敵を倒すために旅をしている訳ではない。ならばその戦闘技術は如何にして己の危険を減らし、生き延びるかに特化するべきで、それを考えれば彼の力は全くもって正しく誇れるものであるのだろう。
「では、僕は壁沿いに進んで、ここ以外の出入り口が無いかを探ってみるから、【NAME】はあれの様子を探ってきてくれないかな」
そうしてオリオールが指差すのは、広間の中央に並び立つ巨大な柱の群れだ。
遠目から見ると黒色の柱にしか見えないが、果たしてあれは何なのか。ここから眺めているだけではさっぱり判らないし、近付いても判る気がしない。どうも、似たようなものを何処かで見たような気がするのだが、はっきりと思い出せないままだ。
まだ冒険家として活動してきたオリオールのほうが知識の面で優れている筈で、あれを調べるのに適している気がしてならない。役割を逆にした方が建設的なのではないだろうか、と【NAME】は手を挙げて提案したが、しかし、返ってきた答えといえば。
「あー、うん。確かにそれは一理あるのだけれども。長年の経験によるものか、どうにも厭な感じがしてね。あそこに近付くと、何か起きそうな感じがひしひしとしていて」
「…………」
もしかして、手分けして探索しようと持ちかけたのも、この流れに持っていくための布石か。
「いや、それについては冗談抜きだけれどもね。実際、力が必要となりそうな場面では君に任せるべきだろうし、何より気になってるんだろう?」
そういって、オリオールはとんとんと胸元を指で叩いてみせる。彼のアクションの意味は、【NAME】には正しく伝わった。オリオールは、こちらが持つ神形が反応している事に気づいていたのだろう。
「さっきから、ちょくちょくと神形器を触っているみたいだったからね。それに、視線も定期的にあちらに向いていたようだし」
完全に見抜かれている。こういう場にあっても他者を洞察する余裕を維持しているのは感心すべき事ではあるが、見抜かれた【NAME】としては若干恨めしく感じるのも致し方ないだろう。
確かに、オリオールの言う通り。先刻から首飾りの形を取った神形が、微かながらも反応しているのだ。明確な意思を示す程に目覚めた訳ではないものの、鈴を転がすような小さな音が、興味の度合いを示すように、ちりん、ちりんと【NAME】の耳を擽っている。
――流転を司る神形、ゼーレンヴァンデルング。
その存在が、こちらからの訴えに対しての反応ではなく、周囲の状況を感じ取って、神形自ら反応を起こす。それはつまり、意思持つ神形が断つべきと判断しうる対象が、この場所に存在しているかもしれないという事だった。
・
一先ず【NAME】と別れたオリオールは、背後、中央にて乱立する柱へ向かって歩いていく【NAME】に、一瞬だけ視線を送る。
オリオールの私見では、この芯形機構は未だ生きた状態を維持しており、何かを切っ掛けにして駆動状態に入る可能性も十分にあった。そしてその切っ掛けを作る役目は、自分ではなく【NAME】であるだろうとも。
「神形器と芯形機構は設計思想は違うけれども、同じ“芯なる者”の手による場合が多いから、何らかの形で干渉しあう事が多いんだよね。上手く、良い反応を引き出してくれると良いんだが……」
こんな、半ば偶然に期待した方法しか思いつかない自分が、少しばかり恨めしい。東大陸で得た知己の中には、こういった芯形機構に関して造詣深い者達も何人か居た。中には芯形機構のような“芯なる時代”の遺跡に加え、機種やそれに連なる技術を応用した機甲の技に優れた学士もおり、もし彼女がこの場に居てくれたなら、きっともっと的確な方針を示してくれただろうとも思う。
わざわざ東大陸に区切らずとも良い。フローリア諸島に滞在している人物であれば、例えば機構学者[グランコレクター]にして“女賢者”の異名を持つレェア・ガナッシュがこの場に居れば、芯形機構を一見しただけでもある程度の当たりはつけてくれたのだろうが、残念ながら彼女は遙か海の向こうである。
(イェア嬢も、一応は遺跡研究の専門家ではあるらしいけれども……)
彼女の様子を思い出し、オリオールはうーん、と腕を組む。
今回のエルツァン島探索の軍指揮を務めるイェア・ガナッシュも、姉であるレェアと同じく、アラセマでは名の知れた“螺旋の理”出身の学士である。印章術式については高い知識を持つとも聞くし、腕や頭が姉と比べて劣るという訳では勿論ないのだとは思うが、どうも彼女は野外調査や実地研究向きではないように感じる。恐らく彼女は資料を揃えて机の上だけで完結するタイプだろう。
それが悪い事だとは言わないが、今のような状況で、経験から来る閃きのようなものが欲しい場面となると、正直彼女の出番がないように思える。
身に染みて判っていた事だが、世の中、なかなか都合良くは行かないものだ。
浅い溜息を一つついて、オリオールは思考を切り替える。
「……さて、では僕も出来る事をしようか」
先刻、【NAME】が懸念していたように、いつ不慮の事態が生じてもおかしくない事を考えれば、本来ならあまり単独行動は取るべきではないのだが、万が一、危険な状況が生じた際の逃亡経路だけは先に見つけておきたかった。勿論、来た道を戻るというのが最も簡単な手ではあるのだが、
(カール氏が訪れた後に、隔壁が全て閉まっていたというのがね……)
そこから推測するに、何らかの状況が発生した際に、隔壁が自動で閉まるようになっている可能性がある。そうなれば、ここから脱出するにはあの多重構造の隔壁をこじ開ける必要が出てくる訳で、そのような状況に陥るのは極力避けたい。故に別経路の脱出ルートを――という事なのだが、よしんば他に脱出ルートがあったとしても、そこが隔壁で封鎖されない保障はなく、むしろそこも隔壁によって封鎖される確率は高いだろう。つまりは殆ど気休めに近い行動ではあるのだが、こうした用心の積み重ねが、もしもという時の生存率を高める事をオリオールは知っていた。
オリオールは円蓋の縁を歩きながら、もし別の脱出口があるとするならばどこかを考える。今居るのは二つの円蓋の内側となる場所だ。ならば、側面からの脱出ルートを探るならば内側からではなく、外と内の境の空間に移動して探した方が早いだろうか?
一度広間の外へ出ようか。そう考えて身を翻しかけたオリオールは、振った視界の片隅に、ふと気になるものを見つけた。
それは上方。曲線を描く外壁の、中頃辺りだろうか。繋ぎ目が殆ど見出せない、硬質で滑らかな壁が続く中で、大きな窓のようなものが数個、横に並ぶ形で取り付けられていたのだ。
それを見上げて、オリオールはふむと小さく唸る。
ここは地下だ。外光を取り込む意味での窓に存在価値はない。換気が必要な場所とも思えないし、何より換気として使う場合、あのような半端な位置に少数取り付けたところで然したる効果は望めないだろう。
ならばあの窓の用途は内から外を見るためか、もしくは外から内を見るためのもの、という事になり、取り付けられた位置を考えるならば、外側から円蓋の内部を見下ろす形で広く確認するためだと推測できる。
「……となると、あそこに部屋でもあるのかね」
内部に存在する巨大な芯形機構。それを観察できる位置に存在する部屋となると、重要度はかなり高いように思える。もしかするとこの場所についての情報が得られるだけではなく、芯形機構自体を操作出来るような機器が存在している可能性もある。最低、構造図でも見つかれば、文字がさっぱり理解出来なくても脱出ルートを探す際の役にも十分立つだろう。
問題は、どうやってそこへ向かうか。
窓の位置は軽く見積もって10メートルは上方。滑らかな壁は手を掛けるような場所などなく、何より反るような曲線だ。内側から窓がある場所まで登るという選択肢はありえない。
となると、残るは外側から、という事になる。ここは二重の円蓋で囲われた構造になっているのは、既に判っている。そして窓が存在するのは内側の円蓋であり、ならば窓の外側に部屋が存在すると過程するなら、それは内と外、二つの円蓋の境界となるあの隙間の空間に存在している筈だ。もしかすると、そちらから上方へと登るための手段があるかもしれない。
勿論、そのようなものは存在せず、全く別のルートからのみ移動出来るか、そもそも部屋など存在しないという可能性も拭えないが、
「ここは思考よりも、まずは行動する場面かな」
一人小さく呟いて、オリオールは踵を返す。まずは侵入口へと戻り、そこから円蓋の外側へと回って、窓があった場所の直下へと行ってみる。そこに何かあれば良し。登るための何かがあれば尚良し。何も無ければ――最初の目的、別の脱出路の捜索に戻るとしよう。
・
重い扉をどうにか開けて、オリオールは己の身体をその向こうへと引っ張り上げた。
その先にあったのは、扇状の横長い小部屋だ。室内には複数の椅子や机に、様々な機器が取り付けられている。円蓋内部と違い、象形などが刻まれた部分は殆ど無く、上層の地下都市で散見されるような機械類が多く詰め込まれていた。
手近な機械――複数のレバーやボタン、半透明の板に触れて、そのどれもが何の反応も示さないのを確認してから、オリオールはぼりぼりと頭を掻く。
「……当たりではあったけれども、結果は外れかな、これは」
あれから円蓋の外側へと移動したオリオールが、窓が見えた地点の真下付近に回り込むと、そこには数人が乗れるほどの昇降機が存在しており、上方を見れば、昇降機のレールが延びた先には、円蓋の外側に出っ張るような形で壁が膨らむように存在していたのだ。
どうやら、先刻の予想における“尚良し”の展開であるらしいと、オリオールはその時笑みと共に一人頷いたのだが、しかし肝心の昇降機がうんともすんとも言わない。諦めて昇降機のレールを手掛かりに壁を登り、扉を強引に開けて部屋に入り込むという作業が必要になってしまった。
そうした苦労の末に、どうにか部屋へと辿り着いたのだが、
「機械類は全て完全に動作を停止してるし、図面らしきものも無し。所々に象形はあるけれども、それも用途は不明、か」
書類のような現代的なものが存在している筈もなく。せめて機器のどれかが動作してくれていれば、そこから断片的ながら情報を得ることも出来たのだろうが、ここまで反応なしとなると、もう単なる意味の無い物でしかない。
オリオールはがこんがこんと適当なレバーを掴んで上下させながら、どうしたものかと思案し、
「……そういえば」
以前、知人に聞いた話を思い出し、オリオールは改めて室内の捜索を始める。
今度は闇雲にではなく、目的を持って。主に探るのは、機械類に存在する差し込み口のような部位だ。一つ、二つ、三つ。室内にある機械を順番に探っていくと、最後の一つでようやく目当ての物を発見する。
「あった。確か、これだ」
一抱えほどの大きさの、長方形の機器。その使い方は全く判らないが、今はそこは重要ではない。オリオールはその機器の側面に刺さっていた平たい金属の板のようなものを、するりと引き抜いた。
独特の光沢を持つ板は、中程から複雑な紋様がびっしりと刻まれている。それを眺めて、オリオールは己の記憶と一致している事を認めて良しと頷く。
この板は、機種の類が多く存在するような、機甲文化を強く残す遺跡で時折発見されるもので、一見単なる板にしか見えないが、内部には多くの情報が封じ込められているのだ。
もっとも、その情報を把握するには特殊な方法なり、専用の機器なりが必要となり、今のオリオールにはそのどちらも持ち合わせていない。しかし、持ち帰り、後で調べる事は可能だ。最初に望んでいたものとは少し異なる形となってしまったが、完全な空振りに終わるよりは遙かにマシな結果だろう。
板の上面に大きな走り傷があるのが不安を誘うが、贅沢は言ってられない。それを大事に背嚢の中へと仕舞い込んだ。
「後は、イェア嬢がこれを解析する技術を持ち合わせているかどうか、か。……どうか頼みますよ、“螺旋の理”の学士殿」
呟きながら、オリオールは身体を起こすと背嚢を背負い直す。取り敢えずここにはもう用はない。最初の目的であった、脱出ルートの捜索に戻るとしよう。
思い、出入り口へ向かって歩き始めたその時。
背後。複数の窓から、強烈極まる光が部屋の中へと差し込んできたのだ。
一体何だ、と驚き振り返って、窓の傍へと駆け寄ったオリオールは、
「な――」
窓の向こうに見えた光景に、呻くような声を漏らす。
円蓋の内側。並び立つ柱の群れ――その中央に、全長数十メートルはあろうかという巨大な化物の姿があったのだ。
オリオールと一旦別れた【NAME】は、彼の指示に従う形で、広間の中央に並び立つ大柱群へと向い、歩いていた。
中央に近付けば近付くほど。場に満ちる独特の気配は、強く、色濃くなっていくように思う。
「…………」
どうにも、厭な感じだった。
歩む速度はどうしても緩んでいくが、しかし精々が数百メートルの距離しかない。【NAME】は程なく、広間の中央付近に到着する。
広間の中央に立つ大柱は、大きさや太さ自体はほぼ同一ながら、それぞれ位置も向きもバラバラに床から天井へ向けて突き立っていた。その数は、合計で七本。乱立する黒柱の林の中に入り込んだ【NAME】は、その一本の傍へと近寄った。
聳える。そんな言葉が似合う威容を前にし、【NAME】は迷いながらも掌を黒柱に触れさせてみる。
反応は、ない。凹凸のない滑らかな肌触りと、ひんやりとした感触が掌に伝わるだけだ。
掌を離して柱を見上げ、【NAME】はふーむと考え込む。
この黒色の柱自体に、何か仕掛けがあるのは確かなのだろうが、やはり近付いてみても、触ってみても、全くもって判らないままだ。こうして間近にして判った事といえば、床や天井に描かれているような象形が、どうやらこの黒柱にも刻まれている事くらいだ。何故遠くからでは気づかなかったかといえば、刻まれてはいるものの、床や天井にあるものとは違って光を放ってはいないせいだ。つまり、この黒柱に刻まれている無数の象形は、現在その力を発揮していないか、発揮出来ない状態にあるのだろう。
となると、柱に固執してみても別段何かが起きる事はないのか?
僅かな思案の後、【NAME】は軽く、胸元の首飾りに手を当ててみる。
反応は……僅かにあった。首飾りの姿を取った神形器の意思。それはどうやら、この柱自体に向けられてはいるようなのだが、例えば強力な封印や結界等を前にした時にこの神形が発する強烈極まる破壊の意志ではなく、どこか窺うような、確かめるような。そういう類の、興味や疑いに近い感覚を向けているように感じる。
だが、【NAME】に判るのは精々がそこまでだ。伝わるとはいえ、人ならざる物の思考を完全に理解するのは難しく、その望みを解決しようとするならそれ以上。そもそも、解決するなどというつもりがあったかどうか。
何にせよ、【NAME】は柱に対してこれ以上のアプローチが思いつかなかった。勿論、武器でぶん殴るなり、神形を試しにぶつけてみるなりという行動が一瞬脳裏に浮かんだことは否定できないが、しかし相手は芯形機構。それを実行した結果、とんでもないことになる可能性もある。止めておいた方が無難だろう。
――で、どうしたものかな。
柱を見上げたまま、後ろに歩く形で距離を取った【NAME】は、改めて辺りを見渡す。
上面を閉じる円蓋。真っ平らな床面。全方にて輝く、強大で無数の象形。どうやら床に刻まれた象形は、それぞれの柱を中心にして連なり歪んだ線を作って囲うように描かれているらしい事に気づく。例えばガナッシュの姉妹のような研究者ならば、その辺りを熱心に追求していくのだろうが、生憎と【NAME】からするとだからどうしたという感想しか沸いてこず。
元々の性根の問題なのか、基礎知識を持たない故に興味が惹かれてないのか。出来れば後者であってくれた方が他人からの印象は良いだろうなと、苦笑いしながらまた視線を巡らせて、
「――ん?」
と。
視界に一瞬、人の影が過ぎった。
慌てて振り返る。見間違いかと思ったが、確かにそこに人影はあった。
全身に傷を負い、憔悴した男の姿。カール・シュミットの幻影だ。
幻影の居場所は広間の中心点。彼はそこに片膝をつき、床を覗き込むような姿勢で動きを止めている。
(そこに何かある、のか?)
他の場所と変わらぬ、単なる床でしかない。そう結論づけかけて、【NAME】は反射的に首を横に振った。
いや、違う。カール・シュミットの幻影が座り込む手前の部分だけ、僅かに他より上方へと迫り出して、僅かな段差を作っている。
一体彼はあそこで何をしているのか。【NAME】は慌てて幻の傍へと駆け寄る。それ程距離があるわけではない。十秒と掛からずその場所へと辿り着いた【NAME】は、既に消え去った幻影が見ていたものを見下ろす。
小さく指先程度、他の部分よりも盛り上がっているのは横二メートル、縦一メートル程の範囲だ。切り取られた長方形の中には、他の場所に描かれているような小さな紋様の複合が巨大な紋様を形作る独特の象形ではなく、上部には横書きの小さな文字列が綴られて、下部には大きな象形が一つだけ刻まれていた。
上部の文字は、恐らく象形ではなく、この芯形機構が造られた際に使われていた言語なのだろうが、【NAME】には全く読めない代物で、何が書かれているかは判らない。
それを暫く見下ろして、【NAME】はどうしたものかと息を吐く。
確か、カール・シュミットの幻影はこの床を覗き込むように身を折って、そして消える瞬間、己の掌を何処かに当てていた気がする。
掌を当てるような場所。そう考えて、目についたのは下部に刻まれた大きな象形だ。その象形は他の床や壁面にあるものと同様、淡い輝きを放ち、未だに力を失っていない事を示している。幻影の位置関係から推測するに、彼が触れたのは恐らくこの象形である筈。
「…………」
一瞬の迷いの後、【NAME】は恐る恐る、その象形に手を重ねてみた。
その瞬間。
【NAME】の頭の中に、言語を介さずにただ直接、意味のみが叩き込まれた。
だが、それでは人は正しく意味を理解出来ない。頭の中に強引に差し込まれた意味の塊を、【NAME】はどうにか言語として分解し、咀嚼する。
それは、強引に言葉に変換するならば、こういう意味合いのものであった。
『形象素体の接触を確認。取得情報を元に想定存在を形象。――これより“芯檻”の試顕を開始します』
改めて、その意味を認識すると同時。
円蓋内に存在する全ての象形が強烈な光を発し、【NAME】の視界は正に純白に染め上げられた。
「――――」
反射的に目を閉じて、それでも突き抜けてくる暴力的な光の嵐を、【NAME】は両の腕で顔を覆うことでどうにか凌ぐ。
象形が放った閃光が収まったのは、数秒の後だ。腕の隙間から溢れる光が、ゆっくりと弱まっていく。しかし、弱まる光と反比例するように、これまで円蓋の中に漂っていたあの奇妙な気配が、【NAME】の前方で爆発的な勢いで増していくのも感じていた。
存在が、形になっていくのを感じる。形を持った存在が、その力と、強烈極まる害意を、周囲に存在するあらゆる者へと向け始めているのを感じる。
腕を下ろし、瞼を開くのが、恐ろしい。
自分の目前で、何が現れようとしているのか。それを確かめるのが恐ろしい。
だが、目を閉じたままではいられない。既に光は収まっている。傍ではあの大禍鬼も斯くやという、凄まじく濃厚な存在概念を持つ何物かが蠢いているのも判っている。
微かに震える喉を動かして、息を吸い、そして吐く。
それで腹は決まった。
腕を解き、瞼を開き、【NAME】は真っ直ぐに正面を見る。
そこには全長数十メートルはあろうかという、朧な白色の身を人に近い形で維持した、巨大な幻身の姿があった。
battle
芯檻の縮尺模型

化物の姿は、鋭角の巨人という大枠を保ちながらも、状況によって自在の変化を見せた。
時には腕を数倍にまで巨大化させて振り下ろし、時には頭部を霧のように解いてこちらの攻撃を無効化し、時には身体の一部を切り離してそれを力の源とした強力な概念干渉を行う。
その在り方は、肉体に縛られた存在では到底不可能と思えるものだ。
しかし繰り出される一撃の重さ、動く度に空間で渦巻く大気の流れと、軋み削られた床面を見れば、この敵が肉体を持たぬ幻ではないのも判る。
そこまでの情報から【NAME】が思いついたのは、一般には半概念存在と呼ばれる者達だ。
正しい意味での“生来からの己の肉体”は持っていないが、近いものを己の器として用意し、それを自分の存在概念の拠り所とする類。
これなら、目の前の相手が持つ特徴にある程度合致する。陽性、陰性問わず、概念飽和現象によって生まれる妖精種や鬼種の中にこういう類の存在が居る他、死して肉体を失った後、残った存在概念が他人の肉体に宿る――端的に言えば幽霊に取り憑かれた場合も、分類としてはこれに該当するだろう。
しかし、今【NAME】が相手をしている虚ろな巨人は、これまで見てきた半概念存在達とも少し毛色が違うように思えるのだ。
濃密極まる存在概念によって、元々現実として形を持っていない筈の存在が、物理法則にまで影響を与える程の密度を持った結果。
世界から生じた反発によって、あたかも存在して見えるようになった虚空の姿――それがきっと、今自分が戦っている奇しき幻の存在の正体なのだろう。
「っ、【NAME】っ! どうにかなりそうかいっ!?」
荒れ狂う無形の力。その奔流をどうにか掻い潜り、一旦大きく距離を取った【NAME】は、遙か後方で声を上げるオリオールに一瞬視線を送る。
この規模の相手となると、オリオールの戦闘力は殆ど宛に出来ない。それが自分で判っているからこそ、彼はこちらの戦いの邪魔にならぬようかなりの距離を置いた状態で、完全な援護行動に徹してくれていた。
(どうにか、か……)
先刻のオリオールの声を、口の中で反芻する。
敵は確かに圧倒的な存在ではあるが、しかし幾多の修羅場を潜り抜けてきた【NAME】からすると、手も足も出ないという程の相手ではない。
だが、決め手に欠けるというのも事実だ。ついさっき交わした一連の攻防では、かなり良いところまで化物を追い込んだという手応えはあったのだが、如何せん相手は半ば幻のような存在だ。殺す、滅するという域にまで持っていく事は出来ず、既に今はその時与えたダメージすら見出せないような姿に戻っている。幾ら概念のみの存在とはいえ、こちらの技法、術式を絡めた攻撃を受け続けているのだ。その力が削られていない筈は無いのだが、しかし少なくとも【NAME】の目には幻身の姿が大きく損なわれているようには見えず、逆に自分の身体に蓄積する疲労と負傷は確かな実感としてあった。
このままではまずい。
何か状況を変える一手を考えるか、若しくは全力での逃亡に移行するか。このまま戦い続けて消耗し、どちらの手も選べなくなる状況に陥ることが最悪の状況だ。幻の化物から放たれた、直接的な概念干渉攻撃による無形の波動を回避しながら、【NAME】は起死回生の手と、逃げを打った際の最も安全な行動を同時に考える。
と、その時だ。
「――【NAME】っ!! 左手正面、十時方向!」
後方からのオリオールの叫びに、【NAME】は素早くそちらに視線を走らせる。
【NAME】が戦場としているのは広間中央、七本の巨大な柱に囲まれた場所だ。立ち上がった巨大な化物、その右足の傍で、輪郭を歪ませた幻の人影が、床を転がるようにして走っていく姿が見えた。
動かない腕、引き摺る足。それでも全力で幻の人影は床上を這って進むと、広間のまさに中心――【NAME】が、そして先程のカールの幻が触れた台座に寄りかかり、そして。
「――――」
消えていく幻。彼が何をしたのか、【NAME】は正確に判断できた訳ではなかった。
しかし、【NAME】はこれを光明の一手であると認識し、行動を開始する。少なくとも、状況を変化させるための行動になりうる筈だと。
化物が踏み込み、【NAME】目掛けて槌状に変化させた手を高速で打ち下ろす。落下の途中で不自然な加速が掛かったそれは、白色の衝撃波を放ちながら【NAME】目掛けて文字通り発射されてくる。【NAME】はその一撃を、躊躇すること無く前へと駆け出すことで回避。背後では叩き付けられた幻身の手が弾けて砕け、ただ触れるものを圧する力の波となって迫ってくる。
それに何の対策もなく飲まれれば、まるで竜巻か渦潮に揉まれたような状況に陥るだろう。【NAME】は走る速度はそのまま、手にした武器に力を籠める。純粋な技法では概念的な力のみに対抗する事は難しい。明確な理粒子干渉を行い、変質した事象を背後直ぐ傍まで迫った力の波に叩き付けた。
意味づけされた理粒子と、意味づけされていない理粒子の塊がぶつかり合い、互いを押しのける形で相殺し合う。力の波の一角が割れて、【NAME】の左右を圧迫感が通り過ぎていくが、【NAME】はそれに一切の意識を向けず、ただ前へと走る。
目指すは、幻影が取りついていたあの台座である。
化物が生じた切っ掛けがあの台座に触れた事であるならば、それをどうにかするのも、あの台座に対して何かを行えばいいのではないか。
台座が近付く。しかし、そこへ至るまでには、化物のすぐ傍をすり抜ける必要がある。既に幻身は先刻の一撃により砕いた腕を修復し、足元へと駆け寄ってくる【NAME】目掛けて、のしかかるような動きで身を倒してきている。
走り抜ける――間に合わない。
回避は――既に遅い。
ならばと、【NAME】は走る動きを止めて、靴裏を硬質の床に滑らせながら、大きく足を開いて僅かに腰を落とす。上方を見れば、凄まじい圧力を伴って、白色に近い力の塊が落下してくる。そのまま押しつぶされれば、その濃密極まる存在概念の圧に屈して、こちらの人としての形を維持する存在概念など容易く崩滅に追い込まれるだろう。
しかし、逆に攻撃を仕掛ける状況だと考えれば、これ程絶好の機会は無い。相手は回避運動も取る事無く、まるで己の身を晒すかのような仕草で、しかもわざわざ相手から近付いてきてくれている。
ならば後は簡単だ。
一撃。全力を込めた一撃でもって、彼の幻身を貫き、突き抜ければいい。
問題は時間だ。必要となる威力を生み出すための術式を組み立てる時間。技法を練り上げる時間。それが果たして足りるのかどうか。
だが、迷っている時間も無い。【NAME】は瞬時に、己の中で最も強力な技を行使するための準備を始める。
幻身が落下してくる。猶予の時間はもう数秒とない。予備動作を行う毎に自身の内側で力が溢れて、手にした武器へと伝播していく。変質した理粒子が周囲を光の粒となって舞う。満ちた力が、爆発の時目掛けて加速する。
しかし、
(間に、合わない?)
寸前で気づいた。技が成立するより、幻身が落下する方が、僅かに早い。
だが、もうどうすることも出来ない。【NAME】は目前まで迫った力の圧に刹那の絶望を感じつつも、しかし諦め動きを止める事なく、渾身の一撃を放とうとして、
――そう。止まらないで。
――そうすれば、貴方は。
加速した。
腕を一気に上へと振り切る。間近。定義された技法の動作が、世界に干渉する力を、攻撃という形に変換し、威力として炸裂させる。
幻身の背より吹き上がるのは独特な黄金色の輝きだ。それは本来、【NAME】が選び放った技法が持つ効果にはないものだ。その理由について、思い当たる節はあったが、しかし【NAME】はそれに思考を回している余裕はない。
化物の胴に開いた大穴を潜るように、【NAME】は全力で跳躍する。技法を用いた跳躍により大きく高度を取った【NAME】は、その着地点――台座目掛けて放つための技法をまた編み始める。
果たして、あの台座に一撃を加えること。それが正しい行動なのかは判らない。
だが、幻の彼は。カール・シュミットは、ボロボロの身体をどうにか起こして、無事な片手に愛用の武器を握り、そしてなけなしの力で振り上げて、振り下ろしていた。
ならばきっと、その行動は正しいのだろう。
理由という程の明確なものはない。単に、彼がそれだけ必死な様子でした行為が、全くの無駄であったとは思いたくなかったからだ。
跳躍が上昇力を失い、僅かな滞空の後、落下を始める。
【NAME】が放った一撃は、予想以上に幻身に対してダメージを与えていたらしく、幻身は仮初めの人型を半ば崩したような状態のまま、動きを再開できていない。【NAME】の動きを邪魔するものはなく、【NAME】は十分な時間を得て練り上げた力を、一切の躊躇も無く、落下点にあった台座目掛けて叩き付けた。
芯形機構の要と思しき部位である。所詮人の身の攻撃では、破壊どころか傷を付けられるかどうかも怪しい。実際、【NAME】が放った一撃は、台座の表面に刻まれた無数の象形の輝きを変化させるだけに留まった。
だが、続けて起こった出来事は、状況を一変させるに十分なものだった。
「これは――柱がっ!」
遠く、オリオールが驚きの声を上げるのが聞こえた。
台座に刻み込まれた象形の列が強烈な輝きを放つと同時、広間中心部に建つ七本の柱が強烈な光を放ち、空中に無数の象形を展開し、積層させ始めたのだ。
目に映るのは、兎に角強烈な光の乱舞だ。柱から放たれる光に加え、その柱に連なるように生まれた象形の円陣、方陣がそれぞれ色の異なる光を放ち、更には床面に刻まれた象形も強烈な輝きを放つのだ。視界の全てが極彩色に塗り潰されたような感覚に陥る。耳に届くのも、何かが高速で回転するような甲高く耳障りな音だけで、元々空間に満ちていた濃い理粒子の気配も、その光や音が強まるのに比例してどんどん高まっていく。
五感の殆どが潰されたような形となって、【NAME】はもう立つことすら出来ず、床に膝を付く。光で埋め尽くされた視界の中で、辛うじて見えたのは、空中にて象形の陣に全身を砕かれた幻身が、それぞれ七本の柱の中へと吸い込まれるように消えていく様子だけだった。
その後、一体何が起きたのか。【NAME】にはもう良く判らなかった。
ただ、一際強烈な閃光が視界を覆って、続いて失われる見当識。そして一瞬の間を置いて、一つ残ったのは奇妙な浮遊感だ。
それらが収まったと思った時には、【NAME】は何故か水面に叩き付けられていた。
「が、ごぼ」
光に包まれていた筈の視界が、突然濃い青色へと変わり、四肢に粘るような水の圧力がまとわりつく。
一瞬の混乱から脱し、濡れた服や重い装備に四苦八苦しながら、どうにか水面に顔を出した【NAME】は、荒く息をつきながら、周囲を見渡す。
水面は波に揺れて、【NAME】の顔を幾度も水で覆う。舌に乗った水は塩の味で、どうやらここが海である事は判ったが、
(海……海だって?)
つい先刻まで、自分は地下の遺跡にいた筈なのに、何故海に。
状況が掴めず、【NAME】は辺りを闇雲に見回す。空は濃い藍色に包まれて、地平の彼方のみ赤く焼けるような色に染まっている。視界の一方には陸地らしき影が見えて、その隅には微かに、火の光らしきものが見える。見えた地形には僅かに覚えがある。ここはどうやら、常駐軍の陣が存在するエルツァンの海岸線だ。見知っている場所が直ぐ近くにある事を認識し、【NAME】はまた混乱しかけていた思考がある程度落ち着いていくのを感じた。
「っ、ぷぁ――っ!!」
と、波間に見慣れた髭面が浮かび上がるのが見えた。どうやらオリオールも、自分と同様の目に遭っていたらしい。
取り敢えず、現在位置と、そして旅の道連れが一応は無事であった事は確認出来たと、【NAME】は深く安堵の吐息をつく。
だが、その一拍の間の後、浮かんでくるのは疑問だ。
結局、遺跡に存在していたあの芯形機構は何だったのか。現れた化物の正体は。そして自分は、何故こんな場所に放り出されたのか。
恐らくは誰に問うても答えの無い疑問。それを抱えて、【NAME】はまた一度大きく吐息をつくと、知らず下方に沈んでいた視線を上げて、
「――――」
遠方に見えたそれに、【NAME】は思わず息を呑む。
海の中から空へと向かって聳えているのは、高さ数十メートルはあろうかという巨大な柱だ。
それを暫し無言で見上げて、【NAME】は成る程と内心で呟く。
――どうも既視感があったと思ったら、こういう事か。
あの地下都市の最奥にて存在した柱と、そしてエルツァン島の周囲に点在するという海中より突き出た柱。
その形状も規模も、全くもって同一のものだったのだと。
・
その後。
エルツァン島の海岸に存在する、常駐軍の陣内。オリオールの天幕を訪れた【NAME】は、彼が遺跡最奥にて何時の間にか回収していたらしい資料を、専門家であるイェアに解析して貰った結果をオリオールから聞くことになった。
資料は古すぎたせいか破損していた部分が幾つかあり、結果読み取れない部分は多々あったものの、あの謎の地下大空間が何のためのものだったのか、その大筋は判明したらしい。
――結局の処、あれは何だったのか。
単刀直入に訊ねた【NAME】に、オリオールは「早急だねぇ」と苦笑する。
「でも、そうだね。確かにこういうことは端的に言ってしまった方が逆に判りやすいのだけれど……」
オリオールはふーむと【NAME】を見据えたまま、顎を軽く捻ってみせて、
「【NAME】。君はフローリア諸島がどういった経緯でここに存在しているのか。その話は聞いた事があるかな」
そう問われて、確か、と思い返す。
脳裏に浮かぶのは、空想の草原と大樹の根に寄り添うように建つ小屋の中だ。
アノーレ島に存在する“四大遺跡”の一つ、ノイハウス遺跡にて、当時はまだ生身の姿を持っていた女賢者レェア・ガナッシュによる昔語り。彼女による芯海の物語はかなり大雑把なものではあったが、概略程度は何とか覚えている。
確か、フローリア諸島は鬼種の根源ともいえる芯属、鬼芯属[ヴァルラギータ]と争うための戦場として用意されていた場所だった、という話だったか。
【NAME】がそんな空覚えの答えを返すと、
「そこまで判っているなら十分だよ。ならそれを踏まえて、あの場所が一体何を目的にしていた場所だったか。その話をしようか」
――そうして始まったオリオールの説明は、以下のようなものだった。
【NAME】達が、そしてカール・シュミットが辿り着いた、地下都市遺跡最奥の半球型空間。
あれは強大極まる鬼芯属を封じ込めるため、複数の芯属が協力して組み上げたという特殊芯形機構、“芯檻”の駆動実験をするための場であったらしい。
半球の広間の中央付近に乱立していた柱達がその要となるもので、膨大な量の存在概念をそれぞれの柱に分割して宿し、循環させながら浄化変換した一部を外部端子となる別の柱へと移して放出。その繰り返しによって封じた存在の力を徐々に徐々に減少させていく――そんな構造を持つ芯形機構なのだと。
それに関連し、島の周囲に存在していた柱が何であったのかについても推測が立つようになったという。あの柱は、イールシック地下施設に存在していた柱とそれぞれ連動しており、先刻の説明の中での放出用の端子としての役目に加えて、芯形機構から発揮される力の効果範囲を定義する、もしくは力を広く発揮させるための中継点としての機能も持っていたのではないか、というのがイェアの予想だった。
要するに、【NAME】とオリオールは芯形機構が駆動させた何らかの術にとって、“異物”として、その効果範囲の外側へ、あるいは柱を経由して外側へとはじき飛ばされたのだと。
また、今回の件でカール・シュミットの謎についてもある程度は予測がつく形となった。
ブランタンハリアからイールシックと、ほぼ単身の状態であった彼が如何にしてエルツァンの外へと脱し、アノーレへ辿り着く事が出来たのかは、つまり芯形機構の発現により【NAME】達が海に放り出された時のような事が、カールの身にも起こったのだろう、と。但し、カールは【NAME】達のようなエルツァン島沿岸すぐ傍、あの柱の傍ではなく、もっと遠く、アノーレにも近い位置に飛ばされたのだろうが。
それが何故なのかという処までは、流石に理由が思いつかないという。カールがイレギュラーなのではなく、【NAME】達が柱のすぐ傍に転移した事自体が偶然である、という可能性もあるとか。
そして、これまでのエルツァンの旅の間、なぜカール・シュミットの行動だけが幻として出現していたのかという疑問についても、一つの解答が出た。
イェアの解釈では、カール・シュミットが芯形機構の駆動に巻き込まれたのがその原因だったのではないか、というものだった。
イールシック地下に存在した芯形機構は、エルツァン島全体に対して干渉を行う程のものだ。故に、その力が行使された際に、共に居た彼の存在概念が、エルツァン島自体の土地概念に取り込まれ、焼き付けられる形となったのではないか、と。ブランタンハリアやイールシックで他地域より多くの幻影を見掛けたのも、滞在していた時間と焼き付きが発生するまでの間隔が短かったから、辺りが妥当な推測ではないかとも。
(あれ? それってつまり……)
そこで話を締めくくったオリオールに、【NAME】は新たに生まれた疑問を口にする。
【NAME】とオリオールも、同様の条件で芯形機構の力に呑み込まれて、外へと放出されたのだ。
ならば、これからは【NAME】達の幻影もエルツァン内で頻繁に発生する事になる、のだろうか?
「今のところ、軍の調査人員から、それらしい報告は聞いていないけどね。そもそも、カール氏と僕等では状況が結構違うだろうから、一概に同じ状態になるとは言えないんじゃないかな。何せ、カール氏があの幻の化物を倒せたとは思えないし」
確かに、と【NAME】は頷く。
あの幻の強さは、下手をすると大禍鬼に匹敵するか、それ以上の力を持っていたように感じる。単身、しかもボロボロであったカール・シュミットでは戦いにすらならない筈だ。恐らくは明確な戦闘となる前に芯形機構が駆動し、難を逃れたのだろう。
「何せ、強大な芯属達の中でも単体で最強ともされた鬼芯属だ。それを封じるためのテストケースともなれば、芯属達も相応の存在を用意したんだろうね。……しかし、その理屈で考えると、あのイールシックの遺跡は芯属達が直接作った都市跡、という事になるのかな? でも、これまで僕が見てきた“芯なる者”の工房とは趣がかなり異なるし、あれはどちらかといえば“古賢属”の……ふむ……ということは、彼等の流れを汲む人……“機種”についても……」
ぶつぶつと、頭を伏せて考え込むオリオール。
その様子を見て、【NAME】は何となく厭な予感を覚えて、そっと彼にばれぬよう立ち上がり、天幕を後にしようとする。
だが、あと一歩というところで間に合わない。
「よし、【NAME】っ!」
オリオールはがばりと顔を上げると、引きつった表情で天幕に手を掛けたまま固まる【NAME】に嬉々とした笑みを浮かべて、
「どうだろう、新しい“冒険”の話があるのだけれど、聞いてくれるかなっ!?」
「…………」
――全力で、お断りします。
真なる楽園 所生みの遺跡が記す形
──ナリア・バータ霧眩森林──
【NAME】満身の力による一撃を受けて、幻の竜がその身の多くを砕かれて動きを止めた。
しかし致命に至るものではなかったようだ。竜は直ぐさま散った霧をかき集め、元の姿に戻ろうとする。
堂々回り。そんな言葉が脳裏に浮かぶが、だからといって攻撃を止めるわけにもいかない。【NAME】は小さな舌打ちと共に、続けて技法を放とうとして、
「――上出来だ、【NAME】よ」
短く呟く声が、【NAME】の直ぐ傍を通り過ぎていく。
「後は我が詰めよう。控えよ」
そんな言葉を置き去りにして、地を滑るように走った小柄な影は、周囲の霧を取り込み始めた竜へと瞬く間に肉迫。正に電光とも表現できる剣閃でもって、再生する竜の身体を更に切り刻んでいく。
宙断つ速度は一足四斬。目で追う事も難しい速度で放たれる刃の群れは、一息の間に竜の再生と損傷を拮抗させ、続く一息で再生の速度をあっさりと上回った。
線と点、角と曲。縦横無尽の剣線は、敵の外側より内側へと走り、手、足、翼、頭、尾、そして最後には胴へと至る。
十を数える頃には、斬り、突き、断ち続けられた霧の竜は己の姿を完全に失って、小さな白い球体を残すのみとなっていた。
それは殆ど固体に近い、濃密な霧の集合体。リゼラは頼りなく浮かぶ球体目掛けて切っ先を掲げ、止めとなる突きの構えを取る。
だが一歩前へと踏み込んだ瞬間。
「――――」
彼の動きがほんの僅か、不自然に止まった。
一体何が、と【NAME】が思う間に、リゼラは突きを再開する。しかし、その刹那とも言える間が、結末を変えた。少年の刃が届く前に、球体が破裂するように砕け、白色の風を八方へと放って消えてしまったのだ。
リゼラは暫し、眇めた目で白球が浮かんでいた空間を眺めていたが、構えていた剣を払う仕草を挟んで鞘に収めると、一度足元を撫でるように手を伸ばしてからこちらへと歩いてくる。
――これで終わった、のだろうか?
既に少年から威勢は消え失せており、辺りを見渡せば既に立ち込めていた霧も殆ど姿を消して、風景は平穏な森に近いものへと変化してはいるが、戻ってきたリゼラの表情は冴えない。
【NAME】は問うていいのか迷いながらも声を掛けると、リゼラは少し迷うように口を閉ざした後、
「……一先ずは、これで終わりだ。渦を成していた力は核を失い、形を持ち集った歪は散り薄れ、天地に解けた。今の我では、これ以上の正は出来ん。本来ならば、あの核に刃を通して歪みを変じて正し、更には力のみを宿す形として残す事も出来たのだが」
そこで言葉を切って、リゼラは不服そうに己の手元に視線を落とす。
少年の手の中には、握り拳ほどの大きさを持つ丸い石が一つ。
先程、地面に手を伸ばしていたのは、その石を拾い上げるためかと【NAME】は納得するが、しかし何故そんな石をわざわざ拾ったのかまでは判らない。
「我としたことが、これに気を取られて機を逃した。全く、妙な知識がつくと、肝要なところでつまらぬ枷になって敵わぬ」
忌々しげに言って、リゼラは石の表面を【NAME】に見えるように傾ける。
覗き込み、じっくりとその石を見ていると、気づく事があった。それは、
「もしかしてそれ、印章石かい?」
そう声を作ったのは、もう一人の連れ合いであるところの探検家、ハマダン・オリオールだ。
霧の竜との戦闘時は、強敵相手に正面切って戦うのは厳しいと、距離を取っての援護に徹していた彼だったが、何時の間にか傍に移動していたらしく、【NAME】の隣で同様にリゼラの手元を窺うように身を曲げていた。
彼は眉根を寄せたまま、ふむと唸り、
「石自体の力は既に失われているようだけれども、その表面の刻印、確かそれは印章[シギル]のものだね。……にしても凄いな。リゼラ少年、君、剣だけじゃなくて印章も扱えるのかい?」
賞賛の声に、しかしキヴェンティの少年は苦い表情を変えぬまま、浅く首を振る。
「翆獣に連なり、命脈と繋がる我等キヴェンティが、何故お前達が扱う迂遠な手法について深く学ぶ必要がある。そも詳しいならば、石の力が失われている事に直ぐさま気づいただろう。付け焼き刃の知識と、戦闘慣れしておらぬ輩からの不要な忠告のお陰で、この石の存在を認識し、一瞬ではあったが警戒してしまった。先刻のは、故の失態だ」
成る程と、【NAME】は頷く。
あの白色の球体目掛けて刃を突き入れようとした瞬間、地面に転がっていた石が印章石である事を見抜いたが、しかしその効果や力がまだ残っているかまでは瞬時に判断できなかった。だから一瞬だけ動きが止まってしまい、結果、切っ先が届く前に球体の消滅を許してしまった、と。
それは判ったが、
「……不要な忠告?」
あの場面で、他者からの忠告など無かった筈だが。
「お前達にしたとて詮無い話だ。流せ」
首を捻ったオリオールと【NAME】に、リゼラは片耳を抑えながら苦み走った顔つきで吐き捨てるように言う。霧の竜を正しく処理する事が出来なかった事が理由なのか、リゼラはかなり不機嫌なようだ。これ以上追求すると怒り出してしまうかもしれない。【NAME】はオリオールと顔を見合わせ、更なる追求を諦める。
「……にしても、ここに印章石があるというのは少しばかり妙だね。少年、その石もう少し見せてくれないかな」
別段石自体に興味があった訳ではないのか、リゼラは無言のまま、石を無造作にオリオールの方へと投げ寄越す。
受け取ったオリオールは、石の表面、刻印の跡が残る場所に顔を近づけ、目を細めて凝らすように見始めた。
妙、とは一体どう言う事だろうか? 印章石自体はそう珍しいものにも見えないのだが、何か特殊な力を持つ石だったりするのか。
【NAME】の疑問に、オリオールは「ああいや、そっちではなくてね」と小さく笑みを挟み、
「僕等からすれば印章石というのは身近なものだけれどもね。先刻の少年の話でもあったように、そもそもこのフローリアは長く外界と切り離されていた場所で、加えて僕等が今いるのはエルツァン――ほぼ未踏の地といえる訳だ。そんなところで、使用済みの印章石が見つかるというのは不思議だと思わないかい?」
「……ああ」
言われてみればそれもそうだ。他の島々でならばまだ判らないでもないが、未だ強力な結界に包まれたエルツァン島の中で、近代の術式系統により生み出された印章石があるというのはおかしな話だ。力ある石に印章を刻むことで現象を導く技術はかなり古くから存在していたというが、それも“芯なる時代”に届こうかという程の昔ではない。そしてこのフローリアは、あの女賢者が語った推測を真実とするなら、少なくともその“芯なる時代”が終わる前までには閉ざされていた筈。なのに、そんな場所で印章石が見つかるというのはどういう事なのか。
勿論、自分達と共にやってきた軍人や、エルツァン探索の先駆者であるところのカール・シュミット探検隊、それ以外にも、偶然この島に辿り着く事に成功した者達が使った物、という可能性も十分に考えられるが。
そんな【NAME】の推測に、オリオールはふーむと考え込むように己の無精髭を撫でる。
「軍の調査隊はまだここまで到達出来てない筈だし、カール・シュミットの手記に森でこんな遺跡を見つけたなんて記述も無いから、あるとすれば三番目、過去に偶然辿り着いた誰かの物……という事になるのだけれど、正直なところ考え難いところではあるね。まぁそれについても謎だけど、何より不思議なのが……」
オリオールは石から目を離すと、小さく肩を竦めてみせて、
「この印章石、どうも効果は隠匿結界を形成するもののようでね」
その言葉に二重で驚く。効果についてもそうだが、印章を見ただけで効果を見分けられるオリオールにも驚いた。戦闘時に術式を使う素振りを殆ど見せていなかったので、そういった事は守備範囲外と思っていたのだが。
「術式の才能はからっきしだけど、印章石の方は良く使うからねぇ。ほら」
ばらり、と五指の間に小さな印章石を挟んで笑ってみせる。まるで手品師のような仕草に、【NAME】は思わず苦笑してしまうが、リゼラはそんなオリオールの態度など全く無視し、
「隠匿結界。姿隠しか? それとも忌み地か?」
「忌み地? ……ああ、人払いの事かな。種類としてはどうやら両方のようだよ。認識に対する存在偽装と、近付く他者の精神に作用して遠ざける効果の併用。範囲を指定する印は……あった。広めだね。大凡数十メートルといったところか。量産品ではなく一品物。それもかなり上等な代物だね」
「力を失った原因は?」
「石に刻まれた刻印に多少の欠損が見られるが、これが主な原因ではないね、単にこの石に宿っていた力が全て消費されただけのようだ」
リゼラは小さく鼻を鳴らし、自身の顎先に親指を当てて暫し思案するように固まり、
「印章石とは、どの程度持つものなのだ?」
「んー、基本はそれぞれの石が持つ固有の貯蓄量と術式の消費量で決まる。僕も専門家ではないから、石に刻まれた術式全ての構造まで判る程じゃない。なので、断言はできないけど、そうだね。この大きさの石で、この遺跡を包む程度の大きさなら……常時駆動で精々一月くらいは。ただし、限定的な駆動――例えば接近者が現れた時のみ結界を形成するようなものならば、駆動状態となった時間次第でいくらでも伸びるだろうね。探知のみ生きている状態で、一度も隠匿結界を構築していない状態を続けていたなら、十数年は楽々持つんじゃないかな」
つまり、当てにはならない、と。
「石の駆動時間から、設置された時間を逆算するのは難しいね。それに刻印の欠損は石の消耗を無為に加速させる場合もあるから特に。ただ、少なくとも判るのは、この遺跡に何者かが訪れるのを避けたいと、そう考える誰か――それも、僕等が知り得ない誰かがこのエルツァンに訪れていた、という事かな」
ふむ、と【NAME】は唸る。
カール・シュミットという前例があるのだ。ならば彼等以外にも、自分達より以前にこのエルツァンへ渡る事に成功した者が居るのも有り得ない話ではない。
ただそうなると、派生して無数の疑問が湧いてくる。
先に島へと渡った誰かが居るというのならば、それは一体何者なのか。
印章石を扱っているのならば少なくとも人、それも原住の民キヴェンティではなく、三大陸の何れかから渡ってきた人間ではある筈だ。
後は渡ったタイミング。可能性としては諸島が開放された十年前から生じるが、当時はエルツァン島に手を回している余裕など無い。精々がコルトレカンの状況が安定し、アノーレの調査開拓が始まった数年前辺りからと考えるのが妥当だろう。
そして何よりの疑問は、その何者かは、一体何故この森の遺跡に対して隠匿結界を残していったのか。
当時は無人の秘境であろうエルツァンにおいて、遺跡を他者から隠匿しようとしたのは何故なのか。島内での拠点として利用するべく、あの霧の化け物達の襲撃を避けるために結界を構築した、という推測は出来るが、
「果たしてどれ程の効果があったのかはちょっと判らないな。何せ、肝心の印章石が今では機能していない訳だしね」
印章石は基本的に使い捨てで、そうなると同じ石を使っての実験を行うことも出来ない。その辺りの真相は闇の中となりそうだ。
【NAME】とオリオールは、その謎の人物に対してあれこれと思考を巡らせるが、ふと気づくと、リゼラの姿が近くにない。
あれ、と視線を巡らせると、彼は既に遺跡を離れ、周りを囲う木々の中へと歩き始めていた。
「っと、少年? ちょっとちょっと待ってくれ!」
慌てて声を掛けたのはオリオールだ。リゼラはそれに反応して足を止めて振り返る。その表情にはもう先刻までの不機嫌さはない。
「どうした、探検家。まだ何かあるのか?」
「いや、どうしたって……。リゼラ少年も、気にはならないのかい? さっき色々聞いてきたのに」
対し、リゼラは一瞬視線をオリオールの方へと移し、
「今、我等が持つ情報だけでは到底結論なぞ出せまいよ。ならば考えるだけ時間の無駄だ。既に、我が任ずる責のために【NAME】の手を煩わせている。“鬼喰らいの鬼”討伐の役目は一刻を争うものではないが、しかし悠長にしていて良いものでもあるまい」
「あー、まぁ、それはそうなんだが。……その発言の後に話すのは少々腰が引けるが、少し良いかな、二人とも」
オリオールは両の手を上げて、窺うように視線を左右に振る。
【NAME】とリゼラが無言で続きを促すと、オリオールはこほんと一つ咳払いをし、
「提案なんだが、少しばかりここの遺跡を調査する時間を僕にくれないだろうか? 多分この遺跡、今見えている部分だけの代物じゃない」
続けて彼が言うには、オリオールが過去に行った幾多もの冒険の旅の中で、これらと良く似た遺跡“芯なる者”の遺産たる象形駆動用建造物、芯形機構[グリフコンバータ]を発見した事が何度かあるのだという。そして、この類の芯形機構は本体となる部分が地上では無く地下に存在する場合が多いのだと。
「――と言う訳で、だ。恐らく何処かに地下部へと入るための出入り口が存在する筈なんだ。それを探すための時間が欲しい」
「存在したとして、その先に【NAME】の目的に関係するものであるとは思えぬが?」
リゼラはそう言いながら、こちらに問いの視線を向ける。
“鬼喰らいの鬼”の気配は歪な霧が薄くなった今でも近辺で感じる事はない。もし遺跡に地下部が存在したとしても、そこに“鬼喰らいの鬼”が居る可能性は低いだろう。
「まぁ、それについては否定できない。けれど、印章石を設置していった誰かについてだけではなく、君が拘ったあの霧の竜が、何故この場所に生じていたのか。その理由を確かにする事は出来るかもしれない。そうすれば、リゼラ少年。君の仕損じについて、もしかしたら挽回できるかもしれないよ?」
オリオールの言葉に、リゼラは沈黙のまま不快げに眉を寄せるだけ。
否定はない。つまり、それこそが答えだ。
確かに今、竜を打ち倒した事により霧は晴れて、土地に漂う歪んだ気配も多少落ち着いてはいる。
だが、完全に失われてはいないのだ。一度は晴れた霧もまた暫くすればこの場所を覆い、静まった歪みも時間と共にまた強くなっていくだろう。それは、木々の隙間から徐々に這い出してこようとしている乳白色の霧の影や、胸元の神形器を通して伝わってくる土地概念の状況からも判る。リゼラの剣は、この地に渦巻く歪から生じた“結果”を斬ったが、しかしそれが生じる“原因”や“過程”にまでは届いていない。
それは、歪みを正す事を任じ、こちらに助力まで求めた彼にしてみれば、明らかな残心となる事柄だろう。
「全く。賢しく言を操るものだな、探検家。秘境を巡るよりも、口を動かし人を回す事を生業としたほうが良いのではないか」
皮肉げな言葉に、オリオールは小さく肩を竦める。
「そちらはどうにも性に合わなくてね、謹んで辞退させていただくよ。それで、リゼラ少年は認めてくれるのかな?」
「我に問う事でもあるまい。頭は【NAME】、今の我はその力であり剣だ。力は、剣は、意も言も持たぬものだろう」
「その割りに、先程は剣の方が頭を引っ張っていたように見えたがね?」
「なに。頭が当然選ぶ筈の道を、剣が先導してやったまでのこと。ならばそれは同じ事だろうよ」
すまし顔でそう告げて、リゼラは鷹揚に腰を下ろす。
「では、早々に済ませるがいい、探検家よ。理解しているだろうが、晴れた霧は幾許かで戻る。刻限はそれまでとせよ」
宣言するように言い切って、リゼラは返事も待たずに両の目を閉じた。早々に休憩に入ったらしい。
どうやら彼の中では、既にオリオールによる遺跡調査は行われるものとなっていたようだ。これがつまりは、彼の言うところの“先導”というやつなのだろうか。
オリオールがお手上げとばかりの両の掌を上に向けてこちらを見るが、【NAME】としては引きつり気味の苦笑を返すくらいしか思いつかなかった。
・
「それじゃ、【NAME】も休んでいてくれ。何せ霧の化け物達の相手は殆ど君らに任せていた訳だから、ここくらいは真面目に働かせてもらうよ」
とまで言われ、実際、霧の化け物との連戦により身体に疲労が蓄積していたのは確かで、【NAME】はこれといって反論はせず、座して目を閉じ動かないリゼラの近く、長い年月による劣化でひび割れ欠けた石段の上に腰を下ろす。
オリオールはまず直ぐ傍にあった円形台状の大型構造物を調べる事にしたらしい。背負った荷物の中から用途の判らない道具や印章石などを取り出して、ひっつけたりかつかつと叩いたり、時折印章石を駆動させたりしている。【NAME】からすると具体的に何をしているのかさっぱり判らず首を傾げるしかないが、遺跡調査の玄人ならばあれで色々と判ることもあるのだろうと、半ば投げた気持ちで考える。
(それにしても……)
周囲、祭壇を思わせるような形状の遺跡を見渡して、【NAME】は、またか、とげんなり呟く。
アノーレからこちら、芯形機構とやらばかりに出くわしているような気がする。しかも、中に入ると大抵碌な目に遭わない上に、収穫と言えるようなものが手に入った記憶があまり無い。
今回も、上手く行けば芯形機構の内部へ突撃、という流れになりそうなのだが、正直な処、進入路が見つからないでいてくれた方が有り難い程だ。確かに先刻の印章石の持ち主についてや、霧の竜がまるでここが居所であるかのように振る舞っていたのも気にはなるが、
(明らかに道草だよなぁ)
エルツァンの奥地へと踏み込み、あの“鬼喰らいの鬼”を探し、倒さねばならない状況の中、こんな寄り道をしている余裕などあるのか、と。
暇つぶしに、そんなぼやきにも似た思考を声として出してみたところ、返ってきた反応はこうだった。
「僕からすると贅沢な話だがね。これ程までに芯形機構が残っている場所は、東西大陸合わせてもそうそうないよ? あの“虹色の夜”ですら、芯形機構ごと現出したパターンは稀だ。僕のような探検家は言うに及ばず、レェア嬢達学士にとっても、このフローリアは夢のような場所だろうね。冒険者である君にとっても、それは同様だと思うんだけどな」
流石は一流の探検家である。回答もまるで冒険野郎の見本のようなものだ。
対して、
「我がこれまで見てきた“芯なる者”が残した遺物は、その多くが自然の摂理を無用に曲げ、命脈の理法を弄ぶものであった。この地の芯形機構が同様の代物であり、未だに力を有した状態であるならば、速やかに破壊するべきであろう。とはいえ、現状優先すべきは“鬼喰らいの鬼”の必滅の方ではあろうがな」
「いや、壊されるのは困るかなぁ。まだ駆動可能状態なのはわからないけれども……」
恐る恐るオリオールが言い添えるが、それにリゼラが全く反応を示さないところが少し怖い。
ただ、二人とも“らしい”答えではあり、納得できるところもあった。もっとも、それが自分の意見へと反映できるものなのかというと首を捻るしかないが。
そんな会話を続けながらも、オリオールの作業は続く。円形台状の構造物、その上部を調べ、前面に移り、側面、そして後面へと。そうしている間にも周囲の森からは徐々に霧の気配が忍び寄り、リゼラが薄く目を開けてそちらを確認する様が見えた。どうやら終わりの時刻は近いようだ。果たしてオリオールはそれまでに何かを見つけられるのだろうか。見つからなければ有り難いというのは確かに本音なのだが、いざその可能性が見えてくると残念にも思えてくるから不思議だ。
が、そんな【NAME】の懸念もどうやら無駄なものであったようだ。
「……こいつだな」
そう呟く声が聞こえて、【NAME】が視線をそちらに向けると、大型構造物の根元にてしゃがみ込んでいたオリオールが、くいくいとこちらへ手招きしているのが見えた。
「【NAME】、少年。来てくれ。見つかった」
「…………」
無言のまま、立ち上がったリゼラが歩き出し、【NAME】もその後に続く。
オリオールが探っていたのは円形台状の大型建造物の一辺、上方に尖塔のような外見の突起を備えた部分の裏側だ。どうやらその下部を掘り起こしたらしく、オリオールが見下ろす先の地面は一メートル程沈んでいる。そこから顔を出していたのは上部に存在する建造物とはそもそも材質自体が異なる、ひび割れどころか傷すら見当たらない、硬質で滑らかな平面だった。
それを見て、【NAME】は成る程と納得する。少なくともこの遺跡は本体が地下にある、という話については信憑性が出てきた。
が、肝心の入り口は何処なのだろうか。確かオリオールはそれを探していたのではなかったのか。
【NAME】が怪訝とオリオールを見ると、彼は困ったように笑い、
「だから、ここが侵入口ではないか、っていう話なんだけど……」
いや、どう見ても壁では?
「と思うかもしれないけれど、ほらここを」
言って、オリオールは掘られた穴に半身を下ろすと、露出した壁の一点に指をあてて、つつ、とずらす。
彼の指が辿った場所。そこには、気をつけて見ればようやく判る程度の僅かな切れ目があった。曲線を描き、丁度オリオールが掘った地面の下部を掠めるようにして走った切れ目は一メートルほどの真円を作っている。
オリオールはこつこつと円の内側を手の甲で叩き、
「調べてみたところ、この向こう側が空洞になっているみたいでね。恐らく円の内側部分が蓋になっていて、ここを潜って中へ入れるんじゃないかと」
オリオールの発言に、【NAME】は成る程と小さく声を漏らす。
確かに、この細い切れ目は壁と扉との境目と見る事も出来るかもしれない。だが、
「如何にして開く」
端的なリゼラの言葉に、オリオールは「問題はそこでね」と頬を掻く。
「表面に手が引っかけられそうな部分はないし、かといって押し込んでみても……」
両の手を円の内側に乗せて、オリオールが力を込める。しかし、壁は僅かたりとも動く気配を見せない。暫くうんうんと唸りながら押し続けていたが、深く吐息をついて身を離すと、お手上げとばかりに両の手を広げてこちらを見る。
「とまぁ、この通りでね。奥に空間があるのは確認出来ているから、ここさえどうにかしてしまえば中へ入れる筈なんだけど」
どうにか、と言われてもさてどうしたものか。【NAME】は眼下の壁を取り敢えず眺めてみる。
そういえば、オリオールはこの遺跡に良く似たものを以前にも見つけていたという話を思い出す。その時は一体どうしていたのだろうか。
「前に見つけた遺跡も、こういう場所に入り口があったんだけれど、地下部分も殆ど壊れた遺跡だったしね。こんな蓋なんてものはなかったんだ。それを考えれば、この先に存在している遺跡は生きた遺跡である可能性が高くて、色々と期待は出来るんだが」
どうやら過去の知識は役に立たない状況であるらしい。
この円形の内側部分を蓋であると仮定し、加えてここが“芯なる時代”の遺跡であると考えるならば、開く手段として思いつくのは物理的な手段ではなく、術式、それも象形[グリフ]を使うようなものだろう。だがそんな手段は人の手には余る。故に正攻法ではなく、絡め手か、力技でもってどうにかするしかないが。
「とはいえ絡め手を使おうにも、こんなもの相手だと、どう絡めればいいのかすら思いつかないな」
溜息混じりのオリオールの言葉に、【NAME】も同意するしかない。
暗号があるなり、象形が描かれているなり、鍵穴のようなものがあるなり、そんな取っかかりすらも存在しないのだ。単なる壁に、境界となる円線が走っているだけでは捻った手など思いつかない。
ならば、残る手段は一つ。力技しかあるまい。
「正直、そちらも望み薄だとは思うが、まぁ、やってみるしかないか」
オリオールが穴から這い上がると、ひょいと懐から複数の印章石を取り出し、幾つかの文言を唱えながら穴の中へと放り込む。
爆発、衝撃、轟音が連続で生じるが、煙が晴れた後には、無傷の壁が残るだけ。オリオールはその結果を見て大きく息をつきつつも、新たなら印章石を取り出し、
「【NAME】、君からも頼む。合わせて行ってみよう」
文言と共に印章石が投げ込まれる。その発動と同時に、【NAME】も武器を振るい、術式を穴目掛けて叩き込んだ。
先刻以上の衝撃と爆音が辺りに轟く。だが、
「……駄目か、これは」
流石は芯形機構本体部への出入り口を塞ぐもの、というべきか。多重の攻撃を受けても壁は全くの無傷で、境目に僅かなズレすらも発生していない。やはり、芯形機構相手に力押しというのが無理があったのだろう。
もう諦めるか、と投げやりな気分になりかけたところで、
「ならば我が試そう」
と、それまで下がった位置でこちらの遣り取りを眺めていたリゼラが、己の片刃半剣をすらりと抜き放ちながら前に出る。
「試す……って、まさか斬るつもりかい?」
「以外に如何にする」
オリオールの驚きの声に、リゼラは当然とばかりに返す。
だが、“芯なる時代”由来の超硬質素材相手に、剣による切断で挑むのはいくらなんでも厳しいのではないか。下手をすると、リゼラの剣が刃こぼれどころかぽっきりと折れてしまう可能性すらある。
止めた方が、と【NAME】とオリオールが声に出す前に、リゼラは身を深く沈めると、一拍の間を置いて地を蹴り、そして剣を一閃させた。
跳躍からの、大上段。
一切の歪みの無い太刀筋が、穴底に掠めるかという位置まで走り、
「――案外と、容易い」
そんな、何処か意外そうな声音を合図に、円の中心に縦の一本線が刻まれて、続けてその線を境に壁が音を立てて奥へと沈み込み、落下。その向こう側が露わになっていく。
はまりこんでいる状態ではわからなかったが、分断された壁の厚みはどうやら掌以上はあるようだった。それをたった一太刀で断ち割るとは。
「「…………」」
【NAME】とオリオールは暫しあんぐりと口を開けて固まっていたが、いかんいかんと首を振って気を取り直す。
リゼラが剣を払い、鞘へと戻す間に、【NAME】とオリオールも穴の中へと下り、断たれた壁の向こうを覗き込む。どうやら奥はオリオールの予想通り広い空間となっており、更なる地下へと続く入り口――下方へ伸びる巨大な階段が存在していた。無茶苦茶な方法ではあったが、取り敢えず遺跡の地下へと続く道への侵入口は確保できたようだ。
では早速――と階段へと向かいかけた【NAME】であったが、それを止める声があった。
「【NAME】。一応確かめておくが、本当に良いのかい?」
何が? と首を捻ると、「いやほら先程の話」とオリオールは苦笑し、
「君、言っていたじゃないか。こんな寄り道をしていていいのか、って」
ああ、確かに、言ってはいた、と【NAME】は思い出す。
「さっきは色々と強引に話を進めてしまったけれども、君が本気で芯形機構の探索が嫌だというのなら、流石に僕も無理強いはしたくない。リゼラ少年の言う通り、“鬼喰らいの鬼”の件の方が、優先順位として上であるのは当然の話ではある。まあ遺跡の奥が気にはなるけれども、地下部が僕の推測通り存在したと、その確証が得られただけでも十分……とは言い難いけれど、慰みにはなるしね」
「先刻も言った通り、頭はお前だ、【NAME】。心思うがまま、決めるといい」
続けてのリゼラの言葉に、【NAME】はうーむ、と唸る。
【NAME】の意識としてはやはり道草という感覚が強く、加えて芯形機構に対しての良い印象の無い。
とはいえども、折角入口を見つけたのだ。ここまできて素通りというのは、やはり冒険者として勿体ない気もするのだが。
──場衡機構“霧眩”──
遺跡地下の調査を行う。そう決めた【NAME】達は、分かたれ生まれた壁穴を潜り、その向こうに存在していた縦横数メートルの折り返し階段を慎重に降りていく。
光源となるものは階段の壁面に点々とつく小さな灯りのみで、視界は良好とは言い難い。
それに加えて、
「……っ、何だろうね、この感じは……」
口元を抑え、呻くように呟くオリオール。その額には鈍い汗が光っている。
階段を降っていくごとに、周囲に立ち込める空気は異質さを増していた。単なる土地概念の歪みや、陰性質の存在概念といった、既に【NAME】にとっては慣れた気配だけではなく、もっと別の、より力強く、より原始的で、そして暴力的ですらある強い気配が、階下より漏れ出してきているのを感じる。それは圧すらも伴うもので、ただ階段を歩いているこちらの存在自体に強い負荷を掛けてくる。
「前に似た遺跡に入った時は、こんなきつい感覚は全然無かったんだけれど、やはり生きた遺跡と死んでいる遺跡では別物ということかな……」
浮かんだ汗を拭う動きも力なく、僅かな光源に照らされた顔色はお世辞にも良いとは言えない。様々な事情に加えて、神形の加護も僅かなりと得ている【NAME】からすれば強烈ながらも単なる圧力として感じる程度のものだが、オリオールにとってこの環境はかなり強い毒となり得るものらしい。
対して、もう一人の同行者であるところのリゼラの方はといえば、普段と然程変わりない様子に見える。【NAME】達の少し後方。鋭い目つきのまま、何か考え込むようにしつつも淡々と階段を降る姿は、調子を崩したような様子など微塵も無い。そもそも彼はキヴェンティ――翆霊を操る、一般的な人間よりも概念的な存在と繋がりを持つ者達だ。こういった環境に対してもある程度の耐性を持つのだろう。
(それにしても……)
単なる概念質の偏りとも、極端な飽和とも違う、独特の気配。
一体この気配が何なのかまでは掴めないものの、全く知らない未知の感覚ではないようにも思えた。これそのものではないが、以前にも似たような、強烈な力の波を感じた記憶があるのだ。
それが何時、何処であったか。
思い出そうとする【NAME】の背後で、小さく呟く声が聞こえた。
「――“命脈”か、これは」
リゼラの呟きに、【NAME】は過去のとある出来事に思い至る。
アノーレの四大遺跡。そこで【NAME】が繰り広げた戦いの中で、大禍鬼という蓋を失った命脈の力が氾濫するという現象が生じた事があった。
強烈な光の波。触れれば身も心も泡となって押し崩されるような圧倒的という他無い力の奔流。
今、この場に漂う気配はそこまで強力なものではないが、質自体は同一のものだ。
確かに、と頷く【NAME】の隣で、オリオールは疲労の色濃い顔を上げ、
「命脈――リゼラ少年達キヴェンティが崇める芯属の大元の事、だったかな。以前その筋の専門家から軽く話を聞いた事はある。世界を構成する概念の生と滅、骨子部分を司る大きな流れ、という程度で、詳しいところは良く理解できなかったけれど……」
「お前達“迷の民”がどう捉えているかなど知らぬ。が、ここに漂っている力は確かに命脈のものだ。それも、“孔”の向こうに存在している、概念という生を経ておらぬ、ただ純粋な命脈の飛沫。それがこの場に――地上に満ちるあの歪な気配と混じり合わず、同時に存在しているようだ」
リゼラの言葉に、はぁ、とオリオールは疲れの交じった声を漏らし、
「僕の調子が悪いのも、その気配に当てられたからかな。にしても、命脈って、そんなほいほいと気配として感じられるものなのかい?」
「そのような筈があるものか」
リゼラはばっさりと斬り捨てるように言う。
「命の脈とは、世の根にて脈打つ源。我等キヴェンティとて、命脈を感じ、繋がり、身に“孔”を得られる者は限られる。このように、力そのものが形無く表へと漏れ出すなど異常という他無い。そもそも、この島自体の土地は狂い、命脈を正しく追えぬ程であったというのに、この場においてはまるで命脈そのものに繋がっているかのように、容易く近しく感じ取れる。……だが」
訝しむように折れ曲がった階段の下方を見る。
重なる階段の列は視界を遮り、奥底に何があるのかまでは見通す事は出来ない。
「やはり妙だな。命脈はつまり命の流れよ。形無き力が現世に現れたとて、何らかの代がなくば直ぐさま散り消えるか、その場の土地概念に馴染み、変質する。例えばこの遺跡の中ででも漂っている、あの霧の気配と混じり合う筈だ。なのに何故、このように分かたれた形で、尚純粋な姿を保っている? それに、命脈の気配は残っているというのに、“孔”の存在自体は感じられぬ。我の“孔”を持ってしても、命脈の枝に触れる事も能わぬ。近しいというのに、届かぬとは、一体どういう事だ……?」
続くリゼラの声は半ば独り言に近いものへと変化し、そして浅い吐息と共に止まった。
「まぁいい。この遺跡の要にでも至れば、その因となるものも判ろうよ。――行くぞ、【NAME】よ」
言って、後尾に居たリゼラが【NAME】達を追い抜く。【NAME】は慌ててその後を追おうとして、
「ま、待った! 二人とも、この気配は――ぐっ」
オリオールが制止の声を上げようとして、しかし苦しげにその身を折る。
原因は【NAME】にも直ぐに判った。周囲を埋める無数の気配の内、陰性質の歪みの気配が先刻よりも一段と高くなっている事に。
それを合図とするように、薄く張るように漂っていた霧の濃度が徐々にだが明確に高くなっていく。霧は、宿す歪みの気配も地上部に漂っていたものと同質のものだ。下方、先頭に立つリゼラの正面、階段と階段を繋ぐ踊り場にて白色の塊が二つ、【NAME】が警戒の念を覚える前に、霧の身を化生の姿へと変化させていく。
現れたのは動物を模したものではなく、純粋な影だ。霧の身を持ち立体を得た人影は、こちらの行く手を塞ぐように並び、威嚇じみた動きで両の腕を広げた。
「霧の影。それも、外のものよりも陰が強いな」
リゼラが、面倒そうに呟きながら無言で剣の柄に手を伸ばし、そして一瞬、視線を後方へと飛ばす。
釣られてそちらを見れば、上方からは別の霧の塊が一つ。人影へと変化していくそれは、リゼラと【NAME】が先に進むことで後尾となったオリオールに手を伸ばそうとしていた。
「ぅ、ぐ……っ」
狙われる形となったオリオールは、どうにか立ち上がり腰裏に備え付けた小剣を抜こうとしているものの、その動作は常と比べれば格段に遅い。霧の影もオリオールの動きから狙い易しと察したのか、素早く霧の爪先をオリオール目掛けて振り下ろそうとしていた。
――これは、拙い。
あのままでは、オリオールの命は無い。彼を守るべく、【NAME】は武器を引き抜きながら慌てて階段を駆け戻ろうとする。
と、その脇をするりと、
「構わぬ。【NAME】よ、そちらはこやつに任せよ」
鋭い声と共に、赤色の熱を持つ何かが摺り抜けていくのを感じた。
「“孔”は命脈の力に届かずとも、この地にこれ程の命の飛沫が残されているのならば」
細く、赤い、細糸のような線。それは見つめる【NAME】の前で、瞬く間にその姿を変化させていく。
「それを我が“孔”に通し、その形を現世にて焼き示す事も容易い」
一本であった線は揺らめく度に二又、三又へと分かれ、薄い身は厚く太く変化し、九又となる頃には、燃えさかる鱗を備えた大蛇の姿となっていた。
生じた九つの口蓋から溢れるように炎を噴き出すその威容は、【NAME】の記憶に焼き付いていた。アノーレの島にて幾度か戦った存在。杜人のリゼラが従える、翆の霊。
その名は、
「――さぁ、我が孔より生まれし翆の顕『九継』よ。久方ぶりの戦だ。存分に喰らい、その身を滾らせよ」
階段の下より生じた霧の人影は【NAME】とリゼラが討ち滅ぼし、階段の上より生じた霧の人影は九継が燃やし尽くす。
九継が発する熱量はかなりのもので、離れた位置で戦っていた【NAME】にも十分に感じられる程だった。当然、近くに居たオリオールにとってはより強烈であったらしく、時折、
「ぅを、ちょ、あつっ! あついあつい!」
という悲鳴染みた声が聞こえていた。叫びに交じって、きゅーきゅーと甲高い声も聞こえていた気がするが、あれは九継の鳴き声か何かなのだろうか。アノーレで戦った時はそんな声を出していた記憶はないのだが。
一戦を終えた【NAME】とリゼラの元に、同じく霧の化生を倒し終えたらしい九継がひらひらと戻ってくる。先刻まで身に纏っていた激しい炎は既に失われており、淡い熱だけを残した赤く輝く鱗をリゼラに甘えるようにすりつけてから、その身をリゼラの背後へと移す。すると九継の影に隠れる形となっていたオリオールの姿が目に映った。冒険家は壁に寄り掛かるようにして階段に座り込んでおり、
「……いやぁ、全く、死ぬかと思ったよ」
【NAME】達の視線を受けて、引きつった声と共におどけたような笑顔を見せるが、その顔色は目に見えて悪い。まさか九継と霧の化け物との巻き添えでも喰ったのかと声を掛けるが、彼は力なく首を振る。
「そちらは単に熱いだけで済んだよ。単純に、気に当てられただけだ。ただ……、ぐ」
両の膝に手を突いて、ゆっくりと身を起こす。その仕草は明らかに辛そうだ。
命脈の化身たる九継と、歪の気配が顕在化した姿である霧の人影との戦い。それがすぐ傍で行われていたのだ。症状が悪化するのも当然だろう。
(これは、流石に……)
彼を連れて先へ進むのは厳しい。
【NAME】が迷った末、声を掛けようと口を開き掛けたその時。
「探検家よ」
と、背後からリゼラの声。
続く言葉が半ば判っているのか、深い嘆息と共に彼を見るオリオールに、リゼラは端的に告げる。
「これ以上は諦めよ。足手まといどころか、死ぬぞ」
「…………」
対し、オリオールは一度、歯を噛み締めるように口元を振るわせて、
「判った。後は君達に任せよう」
けれどもすんなりと、了承の言葉を返した。
あれ? と【NAME】は素直に思う。常の彼の態度を考えれば、ここはもっと粘るものかと考えていたのだが。
と、オリオールの視線が【NAME】の方へと動き、
「意外かい? 僕がこうも簡単に引き下がるというのは」
表情に出ていたのだろうか。【NAME】が己の顔を思わず撫でると、オリオールは青白い顔ににやりと笑みを浮かべた。
「僕が長年探検家としてやってこれた最大の理由と自負しているのが“引き際を弁える”という部分だ。踏み込んでいける場所、踏み込んではいけない場所。その見極めを誤った同業があっさりと命を落とす様は、これまで嫌という程見てきているからね。……そして私見では、ここは恐らく僕が踏み込んではいけない場所だ。この先へと行けば、君達は兎も角、僕は生きては帰れないだろうと、そう感じている」
オリオールは鈍い動きで背嚢の位置を調整すると、改めてこちらに向き直る。
「……では、僕は戻るよ。探索の成果は、軍の陣地で聞くとしよう。良い結果を期待しているよ」
果たして、何が見つかれば良い結果となるのか。【NAME】からすると少々不明なところであったが、彼がこちらの無事を祈ってくれているのは伝わる。【NAME】は笑みと頷きをオリオールに返して、
「ならば此奴と共に行け」
と、リゼラは片手をすっとオリオールの方へと掲げた。
すると、リゼラの後方に控えていた炎蛇を構成する九つ首の一つが分離し、ゆらゆらと踊るようにオリオールの傍へと移動していく。
「お前も本調子ではなかろう。霧の化が生じたならば、其奴を頼れ。遺跡の外までならば、どうにか持つ筈だ。命脈の力が不調の原因ではあろうが、護衛の役は十分果たす。ここを出るまでの辛抱と思え」
「……それはまた、有り難いね」
傍で泳ぐように周回する炎蛇をおっかなびっくりの表情で眺めるオリオールに、炎蛇は任せろとばかりにきゅいーと声を上げてみせた。
・
九継の一頭を連れたオリオールと別れて、時折出現する霧の化け物との戦闘を挟みつつ、階段を下り続ける事暫く。
長い階段の終端に至った【NAME】とリゼラは、そこから繋がっていた短い通路を経由して、円筒状の巨大な広間へと辿り着く。
広間を構成する円の横幅は半径10メートル程。床の中心には大きなシャフトが一本通されており、どうやら床が昇降機としての機能を持っているらしかった。広間へと入る道は、今【NAME】達が歩いてきた小通路の他にもう一つ別の通路があるようだが、そこの口は随分と上方に存在していて、今【NAME】達が居る通路の口が床から一メートル程の高さにあるのに対し、もう一つの口は床から五メートル近くは上にあった。壁は床が持つ昇降機としての機能の邪魔をしないためか突起一つ無い滑らかな造りで、壁伝いにその入口まで昇るのは難しいように思えた。床の昇降機能を使う事が前提の構造なのだろう。天井部までは10メートルもないように見える辺り、上にある通路口の位置が、この昇降機で移動出来る最上位置かと【NAME】は内心頷く。
視線を移す。床の中央付近、シャフトの傍には台座のようなものが見える。恐らくあれが昇降床の操作装置なのだろう。つまり、さっさと通路口から昇降床へと下り、あの装置をあれこれと触って昇降機を操作し、遺跡の更なる奥を目指す――というのが以上の事から思いつく今後の行動、となるのだが。
「…………」
そう思いながらも、【NAME】は未だ通路口に立ち止まったまま、円筒状の広間を見下ろす形で固まっていた。
どうしても、通路口から昇降床へと降りる気にならない。
その理由は極々単純なものだ。広間内には、まるでミルクのようなこれまで見た事も無い程に色濃い巨大な霧が、ぐるぐると渦を巻くように存在していたのだ。
広間の中央から伸びるシャフトの周辺、床より数メートル程上方にて浮かぶ霧の大塊。今までの経験から察するに、あの渦巻く巨大霧は【NAME】達が広間へと下りると同時に、その姿を変じ、襲い掛かってくるだろう。
生じる姿がどういうものとなるかは想像がつかないが、あれ程の量の霧だ。地上の森で遭遇した霧の竜か、それ以上の化け物へと変化する筈だ。
だからこそ、【NAME】はどうしても踏ん切りがつかず、ただ広間を見下ろすことしか出来なかった訳だが、
「――何をしている、【NAME】」
そんな後ろ向きな【NAME】の迷いを、リゼラが意に介する筈も無い。
「戦いの準備が出来たなら言え。次第、下へ降りるぞ」
彼は短く言い捨てると、鞘からさっさと長剣を抜き放ち、既に戦う気満々で下方――いや、広間にて浮かび渦巻く霧の塊へと意識を向けている。
「…………」
頼もしいといえば頼もしいのだが、即断即決が過ぎる。もう少し戦いを避けるという方向に考えを進めてくれないものだろうか。
とはいえ、今のこの状況ではリゼラの態度が正しく、先に進むにはあの霧と戦う覚悟を決めて下へと降りる以外に手は無い。
通路口から昇降床へと飛び降りた【NAME】は、周囲の変化に驚く。
まず目についたのは明るさだ。円筒の広間の壁や床を、白色の光線が編み目のように走って全体を照らしており、昇降床中央に配置されていた操作装置も各所が淡く輝いて、立てられた板の表面には無数の絵や模様が表示されている。どうやら、円筒空間から繋がっていた通路の先で見つけた三つの装置を動かした事で、停止状態にあった昇降床が機能を取り戻したようだ。
装置に駆け寄り、縦板表面に浮かんだ図と模様を見る。模様は古の時代の文字か何かなのだろう。全くもって解読できないが、しかし図の方は何を示しているのか直ぐに判った。中央には長方の四角があり、これが恐らく現在居る広間だ。その上部には赤色の横線が点滅していて、昇降床の位置を示しているのだろう。長方形は横に幾つかの区切りの表記があり、それぞれ外には横方向に一本線が伸びている。それは終端が丸い点となっており、線の数は三つ。推測するならば、これまで【NAME】が移動し、起動させた大型装置があった場所だろう。成る程成る程と【NAME】は頷くが、これだけでは、既に自分が確認してきたものばかりだ。もっと他の、新たな場所に繋がるところは無いのかと改めて図を眺めると、
「……あった」
長方形の下線が点線になっており、その更に下に溝のような形で四角く空間を示す図が存在している事に気づいた。何故その部分が光の線ではなく溝でのみ描かれているのかは判らないが、円筒広間の最下部の床と、その下に何かがあるのは判った。自分達が今から向かうとすればここだろう。
問題は、そこへ至るための方法だ。
【NAME】は装置の各所に視線を向ける。通路の先で見つけた装置と同様、ここも機甲技術を基礎にしたものであるらしく、自分にも扱えそうなスイッチやレバー類は幾つか存在しているが、どれがどういう機能を持つものなのかは推測しか出来ない。手当たり次第に触っていけばある程度は判るだろうが、予期せぬ事態が生じる可能性もある。それを考えれば迂闊には触れず、【NAME】は中途半端に手を伸ばした状態で逡巡するように固まる。
が、
「【NAME】よ。あまり迷っている暇はないぞ」
背後。リゼラの言葉に振り返れば、宙にて渦を巻く霧の帯が、一点に集まり、形を成していく光景が見えた。それは既に見慣れた光景と言えるものだったが、しかし、これまでとは明確に違う部分があった。集まっていく霧の量、密度が、格段に濃く、強くなっているのだ。昇降機が機能を回復した事が原因なのかは判らないが、今から出現するであろう霧の化生が、先刻幾度か戦った大鬼よりも更に強力なものであるのは確信できた。
戦いとなれば装置に触っている余裕などない。そして戦いが始まればこの装置が巻き添えを受けて破壊される可能性もあるだろう。ならばその前に、可能な限り操作しておくに限る。
【NAME】は意を決し、手当たり次第に操作を開始する。
まずは装置下部に取り付けられたスイッチを叩く。外壁に開いた通路口にて隔壁が降りる音。違う。
続いて別のスイッチに触れる。昇降床がゆっくりと回転を始める。これも違う。
本命、装置側面から伸びている巨大なレバー。握り、動かそうとしてみるがびくともしない。何かロックでもかかっているのかとレバーの根元部分を見てみるがそれらしきものはなく、はてと視線をレバーの握り手部分に移せば、そこにボタンが一つ取り付けられている事に気づく。押すと、装置上部より突き出た表示板に浮かぶ長方形の中に新たに青線が加わるのが見えた。そのまま、レバーに力を込める。あっさりと動いた。最上段にて固定されていたそれを、勢い良く下げる。
かち、かち、と小気味よい音と共にレバーが段階的に下がり、最初は赤線と同じ位置にあった青線もその動きに併せて長方形の下方へ移動し、最後、長方形下線の点線に重なるところで停止。同時に、レバーも何かに引っかかったかのように動きが止まる。
ここまでしか下がらないのか、と【NAME】はレバーから手を離しかけて、
「…………」
そこでふと、装置上面に取り付けられた複数のスイッチの内、一つの枠線が点滅している事に気づく。先程まではこのような状態にはなっていなかった筈だ。
【NAME】は少しの思案の後、そのスイッチに触れた。すると、かくんとレバーが一段階下がった。続いて縦板に表示されていた長方形の下方に光が走り、新たな空間がより明確に表示される。
その変化に、【NAME】が驚きでレバーを握る手を緩め、ボタンから指を離した瞬間、がこん、と床の下方より何かが外れるような音が響き、昇降床がゆっくりと降下を開始した。
床が下へと降りていく速度は、今までの霧の大鬼の重量によって下降していた時よりも緩やかなもので、これが本来の昇降機が持つ速度なのだろう。
だが、そんなゆっくりとした下降も、直ぐにまた先程までと同様の――いや、先程以上の落下速度になりそうだと、【NAME】は既に身構えるリゼラの横に並びながら考える。
流れていく内壁を背景に、渦を巻いて集う霧の塊が、ようやくその姿を実体化させる。
現れたのは、これまで何度も戦ったものと同じ鬼面の巨人だ。
しかし、その身は一回りは大きく、輪郭はより確かとなり、内から溢れる陰性概念の強さも段違いに増していた。
大鬼が昇降床へと着地する。強烈な振動が床を揺らし、内壁とシャフト部から軋むような耳障りな金属音が響き渡り、緩やかであった下降が速度を大幅に増す。その速度はこれまでの大鬼の重量が生み出したものよりも速く、下降というより落下に近い。
「……拙いかもしれんな」
リゼラが小さく呟いたその理由は判る。このままの勢いでは、最下の終点に辿り着いた時に昇降床自体が強烈な衝撃を受けるだろう。途中で速度を強制的に落とす機能もあるかもしれないが、この昇降床自体を降下させている大重量を想定しているとは到底思えない。
「ならば、急ぎ砕くしかあるまいよ。――行くぞ、【NAME】よ!」
少年が鋭く袖を振るうと、そこからするりと転び出た赤糸が、素早くその身を九頭の蛇へと変化させた。
九つの口から放たれる炎弾を援護とし、一気に距離を詰めるリゼラ。大鬼もその動きに反応し、両の腕を振り回して応戦する。
こちらも傍観している場合では無い。己の武器を改めて構え直して、【NAME】は正面にて繰り広げられる戦いへと飛び込んでいく。
battle
飽霞の大鬼

九継の炎弾の嵐により大鬼の守りを削り取ったところを、リゼラの刀が一閃でもって断ち割り、生まれた隙目掛けて【NAME】が全力の一撃を叩き込む。
防御の手をこじ開けられた状態で直撃に晒された大鬼は、流石に身体を維持することが出来なくなったのか、堪らず霧の塊へとその身を崩そうとする。しかしこれまでとは違い、鬼は霧の渦へと姿を完全に戻す事が出来ず、ぐずぐずと揺らぐような歪んだ鬼の姿、不定型な霧の塊のまま、降下速度を落とした昇降床の上で醜く蠢いていた。
「……ふむ」
その様を一瞥し、リゼラが視線を僅かに鋭くする。
「より歪を強く、濃く、多く宿した事で、不確かなる霧の身ではなく、確かな鬼としての存在に傾いたか」
であれば、とリゼラが一瞬きの内に鬼の傍へと近接すると、するりとその身に刃を突き立てる。
リゼラが突いた刃は翆の色を宿しており、その輝きは瞬時に鬼の身全体へと波及すると、次の瞬間には強烈な光と共に消滅。後には、突き出された刃だけが残っていた。
一体何がどうなったのか。残心を解いて戻ってくるリゼラに視線を向けると、
「翆片憑依[ティルベイズ]の応用だ。命脈の力を宿した刃を彼の身に通し、その上で力を解いて放っただけの事。正しき形、正しき代を持つ者にはただの生命の波でしかなく、歪んだ形、歪んだ代、そもそも形すら持たぬもの相手ならば生命の波は取り込まれて逆に糧にすらなる。だが、あのような歪みとしても不安定な状態となった存在相手ならば、ああして強烈な波として放てば、在り方自体を歪みに取り込まれる前に塗り替えて、消し去る事が出来る。……理解出来たか?」
「…………」
出来たような、出来ていないような。
何とも鈍い表情を返す【NAME】に、リゼラは小さく笑い、
「何にせよ、これだけ理解出来れば良い。――あの幾度もしつこく我等の前に現れた大鬼成す霧は、今、我等の手により払われたとな」
確かに、円筒空間に立ち込めていた強烈な陰性概念の気配は急速に薄れつつあった。この様子ならば、少なくとも暫くはこの円筒空間にて霧の化け物が生じる事はあるまい。
「後は、この先に何があるか、か。【NAME】よ、この更に下方に新たな道があるというのは間違いではないのだな?」
リゼラの確かめに、多分、と頼りなくも答える。昇降床の中央部に設けられている操作装置。その上部に取り付けられた表示板の中では、昇降床の位置を示しているらしい赤線は、既に円筒空間を示す長方形最下部の更に下、新たに拡張された部分へと至ろうとしている。最下部を示していた点線部が、これまで自分達が降りてきた中で最も下となる場所であるのは、外枠より外へ伸びた通路の線から推測出来ている。ならばそこから下へ行くことが出来れば、取り敢えずは新たな場所へ移動出来たという事になる筈だが。
そうこうする内に、赤線が点線より下方へと移動する。上へと通り過ぎていく際に見えた内壁に、格納された壁の縁らしきものが見えた。どうやら表示板の点線、最下層の床となっていた部分は、可動式の隔壁であったらしい。
昇降床はそのままゆっくりと、しかし確実に下降を続ける。可動隔壁より下の区域の壁には光の線が無く、照明の灯りすら無い状態で、光源となるのは【NAME】達が乗っている昇降床の部分のみ。上方に見える、これまで居た円筒空間を示す光の円がどんどんと遠のいていき、せいぜい月程の大きさとなったところでようやく、昇降床はその動きを停止させた。
動きを止めた昇降床の正面には、円筒空間にて通過したものとほぼ同等の規模の通路口が一つ。覗き込めば、その奥は更に下方へと降りる為の螺旋階段が続いていた。
【NAME】は早速階段を降りようと身を乗り出して、思わず身体を硬直させた。下方から噴き出してきた強烈な気配に、身体が反射的に拒否反応を示したのだ。
「如何にした、【NAME】よ」
突然動きを止めた【NAME】にリゼラは怪訝と首を傾げて、硬直した【NAME】の横から螺旋階段を見下ろし、
「……歪の気配が濃い? いや、それだけではなく……命脈や、正しき存在の力すらも、溢れるように満ちているのか?」
暗闇の中、険しい顔つきで呟く。
「先刻、大鬼を成した歪を正したというのに、これ程の歪みが未だ残るとはどういう事だ。本来、土地に繋がる歪みは広く連なりを持つものだ。そして我等が倒したあの霧は土地自体に根付くものの筈。なのに何故、一切弱まる気配無く、むしろ先刻までより強い歪みがこの奥に存在している。何故だ?」
リゼラは考え込むような表情で暫し黙り、続いて耳に軽く指を当てるような仕草を取って、
「――別口、だと? しかし……命脈の気配も、いや、そうではあるが、有り得るのか……?」
ぶつぶつと小声で何事かを呟いた後、リゼラは傍に立つ【NAME】に鋭い視線を向ける。
「ここで止まっていても始まらぬ。【NAME】よ、降り、何があるのかを確かめるぞ。恐らくはここより下、先刻よりも更に強い歪み……いや、多種の力の飽和が生じている筈だ。可能であれば、守りを施せ。甘く見れば、我等とて先刻の冒険家のような事にもなりかねん。心せよ」
──所生みの遺跡が記す形──
昇降機を下りた【NAME】達は、そこから続く長い螺旋階段を更に下り、遺跡最奥と思しき場所へと辿りついた。
階段の終端に存在したのは、円形の床と天井を持つ小広間だった。円柱を輪切りにしたような構造となっている部屋の内側にはびっしりと、淡く明滅しながら光る紋様が描かれており、その全てが強く膨大な力を秘めた象形。室内には上層で時折見た機甲技術が絡んだ装置類は一切存在しておらず、純粋な象形のみで構成された空間は、人の手には負えない、超常的な雰囲気を強く漂わせていた。
とはいえ、そうした広間の雰囲気なり、造りなりを詳しく把握する余裕は、この時の【NAME】達には余り無かった。
何故ならば、地上や遺跡の上層部とは比べものにならない程に濃厚で、そして雑然とした気配の渦が、この広間を埋め尽くしていたからだ。
「……たかだか歪な霧の発生源、というだけでは片づかぬな。一体どれ程の力が、この空間に集まっておるというのだ」
眉尻を上げ、視線険しく宙を見据えるリゼラの言葉には強い疑念が見えた。異質な存在の感知や理粒子の動きの察知については、多少なりと自信がある【NAME】としても、彼と同様、室内の状態については思うところはあった。
この広間に満ちているのが、単なる陰性質の概念――つまりは鬼種の存在の種となる歪んだ存在の気配だけであるならば、ある意味話は簡単なのだ。しかしここに満ちているのはそれだけではない。様々な形に変質した理粒子が、ただ強く、この部屋に留まっているのだ。
それは自然な妖精の気配であったり、それは野を生きる動植物の気配であったり、それは歪みから出でた鬼の気配であったり。
全く繋がりの感じられない様々な存在の気配が、この然程大きくもない部屋の中に不自然に押し込められているような、そんな感覚だ。
共通しているのはただ一つ、それらは全て生命を宿した存在の気配だという事。この広間には無数の生命の気配だけが、姿無く、まるで残滓のようにこびり付いていた。
「…………」
これが、一体何を示しているのか。
遺跡――芯形機構が力を発揮した結果がこの状況なのだろうが、しかし【NAME】が判るのはここにそんな異常な気配が強く漂っている事だけで、それが何を齎すものなのかが判らない。まさか、そんな気配を生み出すためだけの芯形機構という訳ではあるまい。
どういう事かと、懸命に【NAME】が考え込んでいる間に、状況に変化が生じた。
広間に漂っていた複数の力。その気配の内の一つが、急速に活性化を始めたのだ。
増していくそれは、既に【NAME】にとっては馴染みとなったもの。陰性質を秘めて歪んだ濃霧の気配だ。
はっきり視認出来る程の濃い霧が、何も無かった空間からにじみ出すように生じ、続けて複数の渦となって宙に蟠り、一点に集まって厚みを増してその身を明確な形へと変化させていく。
そうして現れた存在は、
「ほう」
形を成した霧塊の姿。それを見て、リゼラが小さく声をあげた。
現れたのは地上――ナリア・バータ霧眩森林にて幾度も戦った、あの竜だ。細部は多少異なり、放つ力の密度や質も違うが、しかし存在としての大枠は同一のものと言って良いだろう。
それがなんと、
「……三体、か」
呻きながら、【NAME】はリゼラから少し距離を取る。選んだのは守りではなく攻めの姿勢だ。部屋はそれ程広くはない。ならば一箇所に固まって互いに背後の死角を補うより、ある程度の距離を取って空間を抑え、そもそも竜に背後を取られないようにした方が戦いやすく、味方同士の巻き添えも発生し難い。数的には不利――九継を加えても精々互角であり、それを考えると常道の策とは言えないが、相手が疲労とは無縁の霧の化生である事を鑑みれば、最初から守勢を選ぶのはデメリットが大きい。強気に攻めて、こちらの体力が尽きる前に一期に押し切り、崩滅を狙う方が勝率は高い筈だ。
だが、問題も当然ある。敵は高い再生能力を持ち、一体でも完全に屠るのに梃子摺った相手だ。それが同時に三体となると、果たして押し切れるのか。不安という名の蛇が一瞬頭を擡げるが、
「この奇妙極まる環境故、何が来るかと身構えておったが、現れたのがお前達とは。甚だ以て拍子抜けよな」
そう、全く意に介さない少年の声が、内心の蛇の頭を問答無用で叩き潰す。
「今度こそ、お前達全ての存在を我が刃にて正してやろうぞ。――さぁ、行くぞ、【NAME】よ!」
笑みすら浮かべ、長剣を鞘から引き抜き飛び出すリゼラ。その様を見せられては、不安に駆られている場合ではない。
三つの竜頭、開かれた喉奥から濃密な白色が渦を巻くのが見えたが、リゼラ、そして【NAME】も、退くという選択肢は思い浮かばなかった。
交差する白色の霧柱。その間隙を縫うようにすり抜けた【NAME】とリゼラは、そのまま霧の竜へと走り寄ると、それぞれの武器を、吐息を放ち動きを止めた竜の身体目掛けて叩き付ける!
【NAME】とリゼラ、二人の攻撃を続けざまに受けた三匹の竜が、それぞれ大きく身体を歪ませた。
それを好機と見たか、九継が喉元を大きく膨らませ、動きを鈍らせた竜達目掛けて巨大な炎弾を放つ。
膨大な熱量が空間に溢れ、多少離れた位置に居た【NAME】にも濃い熱の圧力が感じ取れた。直撃すれば纏めて崩滅を狙えるほどの強烈な一発。だが、竜達は身を器用に細め、くねらせるようにして炎球の上方を潜って回避し、更なる追撃を嫌うように高度を取ってみせる。
回避された炎弾が側壁に当たり凄まじい爆風を四方に発生させ、部屋の中の大気が荒れる。あれ程の炎弾の直撃であっても壁は傷すらついておらず、熱風だけなのは幸いだ。もし壁が砕かれ破片が混ざるようであれば面倒な事になっていただろう。【NAME】は態勢を崩されぬように重心を低くしつつ、上方へと位置を移した竜達からは視線を外さない。
竜達は天井付近で蜷局を巻くように動いて、【NAME】とリゼラの攻撃により歪んだ輪郭を修復している。天井の高さはこれまで辿ってきた遺跡内の部屋と比べれば低いが、しかしそれでも人の背丈と比べれば数倍の高さを持っている。直接攻撃を届かせるには厳しい位置だが、ここで押し切らねばまた元の状態へと戻ってしまう。【NAME】は技法を上へと放つべく、身を深く屈めて力を溜め込む。
と、宙で渦巻く竜の姿に、小さな違和感を覚えた。
絡み合う三体の竜。それは互いの欠損した存在概念を融通しあい、受けた損傷を回復しているのだと思っていたのだが、それぞれの竜達の喉が少しづつ膨張し、口蓋からは煙のような霧がうっすらと漏れている事に気づく。
――まずい。
悠長に距離を測っている場合ではなかった。竜は回復だけではなく、同時に攻撃の準備も進めていたのだ。【NAME】は急ぎ技法を駆動させるべく身を動かそうとするが、それより速く竜の三つの首が絡み合い、仰け反り、先刻の九継のように喉を膨張させる。開かれた口の奥では濃厚な陰性概念が白色の渦をつくるのが見えた。
間に合わないと、そう判断した【NAME】は一瞬で意識と動作を切り替えた。躊躇いは即座に死に繋がる。それはこれまでの冒険で散々学んできた事だ。前動作により半ば駆動を始めていた技法を強引に身を振って打ち消し、回避を試みる。
今にも放たれようとする吐息。竜の狙いは真っ直ぐに自分目掛けてだ。宙へと攻撃を放つために動きを止めていたのを狙われたか。身を横へと跳ねさせようと足裏に力を込めるが、地を蹴る動作へと入る前に、竜の顎が振り下ろされるようにこちらへと向く。竜の放つ霧の吐息は、これまで見たものは直径一メートルほど。しかし今回は三体同時だ。純粋に三倍と見積もるならば、回避のための移動は少なくとも二メートル、出来れば四メートルは欲しいが、着弾までにそれほどの距離を稼げるとは到底思えない。
とはいえ、流石に今から行動の変更は難しい。半ば絶望的な気分になりながら、しかし【NAME】は諦めることなく足指に力を込めて身体を横方向へと飛ばし、
「――遅い」
そんな声と共に、絡み合う三つの竜の頭が同時にブレた。
吐息の行方を確認するべく視線を竜に向けたままだった【NAME】は、その視界の端から飛来した小柄な影――天井を滑るように走り、抜刀したリゼラの一撃が、竜の首を纏めて薙ぐのを見た。
横殴りに近い剣撃を受けた竜の首は切り裂かれるまでには至らなかったものの、大きくその動きを乱す。続けて吐き出された霧の奔流は、当初の目標であっただろう【NAME】の位置目掛けてではなく、くねり暴れる竜頭の動きに追従するように、部屋の床を無秩序な軌道で舐めていく。
床面に当たった霧の吐息は怒濤の如く周囲へと散る。間際を横切った吐息の線、押し寄せる白色の飛沫が持つ陰性質の力は急速に弱まっていたものの、それでも十分に驚異的だ。横へと強引に飛んで崩れた姿勢のまま、更なる跳躍を無理矢理行って、その波に呑まれることをどうにか避ける。
と、そこへ上方から爆音の連続が轟く。
何事と顔を上げれば、リゼラの横薙ぎを受けて身を捩らせていた三体の竜の全身が、無数の火弾の炸裂に包まれていた。天井へと降る緋色の豪雨。その主は、炎蛇の翆霊たる九継だ。先刻放った大玉が避けられた事を考慮してなのか、九継は九つの首から小規模の火弾を連続で吐き出して、回避の隙間を生じさせる事無く竜の身体に次々と炎を着弾させていく。
勿論、その一発一発の威力は低い。実際、炎の弾はほぼ全弾が竜の身体に当たっているが、その霧の身体が弾ける様子も縮小していく気配もない。
しかし、生じる衝撃は無効化できていない。間断なく着弾し破裂する炎の花は、三体の竜を天井に張り付けにする。竜の吐息が細く弱り、終わりを告げた後も、炎の蛇は攻撃を続けて、
「【NAME】、詰めよ!」
そう叫ぶ声。天井を駆けて竜をすれ違いざまに斬り、その勢いのまま床へと着地したリゼラの言葉に、【NAME】はようやく己の役目を認識した。
そうだ。九継が何故直接的なダメージを与えられない攻撃を続行しているのか。それは三体の竜の身動きを抑え込むためであり、誰かが止めを刺すためのお膳立てでもあるのだ。
リゼラは先刻放った攻撃で大きく距離を取っている。ならば、この場で追撃を放てるのは三体の竜の傍にいる自分だ。
一度は中断した技法を再度駆動させる。放つ力は持てる最大のもの。高低の差はあれど標的は九継の炎により天井に射止められた状態だ。避けられる心配はなく狙いを定める必要もない。
深く強く。限界まで張り詰めさせた力。それを、武器を振り上げる動作と共に一気に開放させる。
【NAME】の動きに従って空間の理粒子が唸りを上げて変質し、破壊の力が天井目掛けて立ち上がり、三体の竜を丸ごと呑み込んだ。
・
竜を形作っていた陰性概念が砕け消失した後も、精々その分の陰性概念が失われただけで、部屋の中に立ち込める奇妙な気配に大きな変化は生じなかった。
まるで空間自体が奇妙な熱を持っているような、不思議な圧力。それを感じながら、【NAME】達は改めて部屋の中の探索を開始する。
とはいえ、探すような所など殆ど無かった。元々然程大きくもなく、目につくようなものがある訳でもない部屋だ。特徴として存在するのは床や壁に描かれた象形だけで、それにしても門外漢である【NAME】には調べようがなく、それが何なのか、どうにか出来るものなのか、何もかもが判らない。出来る事と言えば、適当に部屋の中を彷徨き回り、壁や床に触れてみたりする程度。恐ろしいほどに滑らかな、一体どんな素材で造られているのか見当もつかない壁の表面は、先程自分達が繰り広げた激しい戦いなど全く感じさせない。霧の竜による吐息。九継の巨大火炎弾。リゼラや【NAME】の攻撃。それらは時には壁を、時には床に当たった筈だが、見たところ傷一つ存在しないのが恐ろしい。
「【NAME】よ」
と、部屋の隅で壁に手をつき、引きつった表情を浮かべていた【NAME】は、名を呼ばれて振り返る。
部屋の中央に立つリゼラがこちらを見ていた。彼は【NAME】が視線を向けたのを確認し、小さく手招きをする。
何か見つけたのだろうか。【NAME】が彼の傍へと近付くと、少年は手にした片刃の剣の先端で、床の一点を示す。
リゼラが指したのは部屋の中心点から数メートルほど脇に外れた地点。そこには大きな象形が円を描くように連なって刻まれている。それ自体は他の床や壁と同様である、が。
「……?」
怪訝、と【NAME】は眉根を寄せる。
単純にそれだけではない。淡く発光する象形。その輪郭が、他の場所に描かれた象形よりも妙に複雑なのだ。いや、複雑、というよりも……、
「印章?」
思わず呟いてリゼラを見ると、彼は目を細めた常の仏頂面で頷く。
「床に描かれた象形を使いながら、そこに継ぎ足すことで別の印章を造り出しているようだ」
ほう、と息を吐いて、【NAME】は改めて床面を見る。
象形の淡い光を利用するように、重なる形で描かれた印章は、部屋の中心を真中とした直径にして凡そ四メートルの印章陣として描かれていた。最初に見たときは元々この床に刻まれていた象形の一部かと思っていたのだが、言われて見てみればこの中心部だけは妙に紋様の密度が濃く、床に浮かぶ紋章の中には、効果は理解出来ないものの見覚えはあるものは幾つか存在していた。
成る程ね、と頷いてから、とすると、これはどう言う事だと考える。
この遺跡に入る前に、オリオールも交えてした会話。それを思い出せば、この“芯なる時代”の遺物たる芯形機構の最奥で、印章という比較的近代の技術の痕跡がある。ならばそれは、
「遺跡を隠す呪いを用意していた何者かが描いた代物なのだろうよ。もっとも、我にはこれが一体どういう力を持ったものであるかはとんと判らぬがな」
暗に、お前は判るのかとリゼラの視線が問うてくるが、【NAME】が持つ印章の知識は戦闘時に行使する一般的な空間記述用の印章を幾つかといった程度で、何よりこういった複数の印章を場に刻み込み陣として機能させる類の大術式は、印章単体だけ理解出来てもその全体の機能を察する事は至難だ。その筋の専門家でもなければ不可能だろう。
【NAME】の答えに、リゼラは不機嫌そうな顔つきのまま小さく鼻を鳴らし、
「どうだろうな。専門家と言えども何でも判るという訳では無いようだぞ。いや、そもそも専門ですらないの――」
ぶつぶつと独り言のように呟いて、途中、耳鳴りを堪えるように片方の耳を抑えると、表情を更に苦く歪める。
リゼラの妙な様子に、【NAME】がどうかしたのかと訊ねるが、しかし少年は短く首を振り、
「気にするな、こちらの事情だ。――話を戻すが、もし専門家が居たとしても難しかろう。あの辺りを見てみよ」
と、リゼラが抜いたままの剣先で新たに指し示したのは部屋の中央一メートル程の範囲だ。何かあるのかとそちらを意識して見ると、
「……薄い?」
他の場所よりも、印章を形作る部分が極端に薄く、半ば掠れるようになっている。円形の印章陣、その中心部を一メートルの太さの線が横切ったかのような形。
「ああ。どうやらこの印章とやらは」
リゼラが身を浅く屈めると、指で床の一部――印章が刻まれている部分をなぞり、指の表面を【NAME】に見せてくる。
彼の指先には、淡く光る粉のようなものが僅かに付着していた。
「理石を原料とした発光顔料が使われている……らしい。大陸の金持ち術士が使う贅沢品……だそうだ」
ほう、と【NAME】は感心する。よくそのような事が判るものだ。そもそもリゼラはキヴェンティ、そういった大陸の知識など殆ど持っていないだろうに……って、何故に伝聞調?
【NAME】がはてと首を捻ると、リゼラは普段以上の苦み走った顔つきとなり、
「だから気にするなと言っているだろうが。流せ」
「…………」
これ以上追求すると本当に怒り出しそうなので【NAME】は大人しく口を噤む。
リゼラは煩わしそうな嘆息を一つついてから、視線を【NAME】から己が指した部屋の中央へと向けて、
「印章の陣はその全体を見て術の構成を把握し、駆動する流れを掴み、結果を推測できる……のだそうだ。それは軽い欠損程度ならば経験で補えるものだそうだが、このように、印章陣の半分程、それも要となる中心を含めた部分が読み解けなくなっている状態では、専門家とてその効果をはっきりと把握するのは難しい……とな」
リゼラはこつこつと床を歩き、中心に近付く。印章の掠れた部分をその足裏が踏むが、掠れは悪化する事もなくそのままだ。
「床がこの堅さだ。彫り込む事も出来ず顔料を使ったのだろう。聞けばこの顔料、原料が理石であることからそれ自体にある程度術式で手を加えることが可能だそうでな。当然、外的要因による劣化や剥離諸々に対する処理も施されているらしく、余程の事が無ければこのように損なわれる事はない……という話だ」
ならば、何故。
当然の疑問に対し、リゼラは剣の峰の部分で自身の肩をとんとんと叩きながら、
「思い出せ。先刻、そのような呪いの力など吹き飛ばすような強烈な吐息が、丁度この辺りを薙いでいただろうが」
「……あー」
合点がいった。【NAME】は額に手をやり、気の抜けた声を漏らす。
そうだ。あの霧の竜との最後の遣り取り。上方から下方、つまり床目掛けて叩き付けられた、陰性概念の塊ともいえる霧の吐息。それは“芯なる時代”の産物たるこの遺跡の床や壁には一切の影響を与えなかったが、人の手で多少の概念的な守りが施された程度の顔料では到底耐えられない代物だろう。掠れた状態でもまだ床に残っているのが不思議なくらいだ。
あの竜の吐息の幅が大体一メートルであった事を考えれば、成る程、色々と符合する。
「何にせよ、結果は変わらん。我やお前ではこの呪いの図の全容を読み取る事は出来ぬし、それは他の者が居たとしても同様であろうよ。我等がこの地で知り得た事は、遺跡の構造と、遺跡が未だに健在である事。そしてこの要と思しき場所には正体の知れぬ妙な気配が残っており、件の何者か――恐らくは術士が、ここで過去に何らかの呪いを執り行っていた事、くらいか」
そう言えば、この場所に漂う他所では味わったことがないような奇妙な気配。これは一体何なのだろうか。リゼラの口ぶりからすると、彼もそれについては何の答えにも行き着いてはいないようだが。
そんな【NAME】の呟きに、リゼラは暫し視線を彷徨わせた
「我に判るのは、過去にこの場所にて命脈への“孔”――それもかなり巨大な“孔”が開かれ、しかし今は閉じて失われている事だけだ。この遺跡全体に漂う命脈の気配とは、“孔”が開いた際に満ちた命脈の力の残滓なのだろうよ。そして、それは先刻我等が対峙した霧についても同様だ。【NAME】、お前も判っているだろう。外とは違い、この遺跡の中ではあの霧は無限に生じる存在ではないと。寧ろこの地自体は上よりも安定した場所ですらある」
問い掛けに、【NAME】は若干迷いながらも頷く。リゼラの言は、【NAME】も薄々感じていた事だ。
例えばナリア・バータの森。あそこで霧の化生を退治し、その存在概念を崩滅へと導いたとしても、土地自体に根ざした歪みは新たな陰性概念を産み、それはまた霧となって姿を現す。土地の在り方自体が歪んでいるため、形を持った歪――謂わば鬼種を打ち倒したとしても根絶やしにする事は出来ないのだ。
しかし、この遺跡の中は、どうやら違うらしい。
例えば遺跡に侵入した当初に降った階段。あそこで幾度か霧の化生と遭遇した訳だが、倒せば倒すほど、その場に満ちていた陰性の気配は小さくなっていき、それは縮小することはあれ、時を置いて元に戻る事も、増大する事も無かった。
例外は昇降床を備えた円筒空間で幾度も出くわした霧の大鬼であったが、あれにしても途中までは完全に崩滅させる前にその身を解かれ、止めを刺し損ねていただけであり、最後に相対した際に大鬼がリゼラの一撃により完全に崩滅してからは、その気配を全く消失させていた。
加えて言えば、遺跡内のそれぞれの場所にて生じていた歪の霧は、それぞれが繋がりを持たず、独立して存在していた。本来、土地に根差し、連なりを維持して生じた陰性概念は、此方が損なわれれば彼方がそれを補うように流れる、まるで水が如き動きを成すことが多い。しかしこの遺跡に漂う歪みの霧は、そういったものを一切持っていないように見えた。先刻の水で例えるならば、それぞれが繋がり得る程の水の供給が受けられる、水溜まりとして個々存在しているような状態か。
この事から考えれば、つまり、
「少なくとも今に於いて、この遺跡は霧の歪を生む源ではなく、我等が崇める翆なる脈を穢す場所ともなってはいない、という事だ」
呟く彼の口調は何処か忌々しげだ。その気持ちは判らなくもない。彼はこの遺跡が地上の歪み、歪の霧の出所と見込んでいたのだろう。しかし、それは外れた。例えばここを破壊したとしても、地上の状況は恐らく変わらない。何故なら部屋の内に刻まれた無数の象形は未だに強い力を保ってはいるものの、その力自体は一切発揮していないからだ。芯形機構が、己の刻まれた象形の力を存分に振るっている状態であったなら、リゼラは――それが可能であろうかどうかは脇において――この部屋を、この遺跡を、破壊しようと動き出していただろうが。
リゼラは浅く息を吐き、刃を一度払うように走らせてから、ゆっくりと鞘に納める。
「ここで“孔”を繋ぎ、命脈を穢し、何が行われていたのか。気にはなるが、残念ながらそれを追う手立てが我にはない。この地に残された命脈や、霧の歪み、他にも幾多の気配が、何を起因として生じたものであるかもな。……残る我等に出来る事は、ここで得た情報を、極力あの冒険家に伝えて慰みとしてやる程度か。もしかすれば、あの男が何か思いつく事があるのやもしれんが……さて、望みは薄かろうな」
言われて、そういえばとオリオールの事を思い出す。九継の一頭と共に外を目指していったが、果たして無事に陣地へ帰還できたのだろうか?
今更ながらとも言える問いに、リゼラは小さく肩を竦める。
「さてな。遺跡の外までは九継がついていたが、それ以後は知らぬ。気になるのならば、急ぎ戻るが良かろう。もうこの地に用も無いしな」
言って、リゼラは螺旋階段の出入り口へ向かい歩き出す。足取りは淀みなく、既にこの遺跡に対する興味の殆どが失せているようだ。何とも割り切りが早い。【NAME】は置いていかれぬように慌てて彼の後を追おうとして、
「――――」
ふと、視界の隅に何かが過ぎった。
立ち止まり、振り返ってその正体を探る。部屋の隅近く。淡い光の紋様が無数に浮かび上がる床面。その中で一瞬捉えたのは拳ほどの立体物だ。床が輝いているからこそ、その光が上方へと伸びるのを遮っていた物体が、異物として認識出来たのだ。
【NAME】はその物体に近寄ると、少しの思案の後、慎重に拾い上げる。
その形状は、一言で言えば奇妙。類似する存在が即座に思いつかない。素材は半透明の結晶にも似たもので、円形盤の側面と片面から親指程の太さの六角柱が伸びているような構造。柱はそれぞれが円形の輪でもって繋がれており、輪と六角柱にはびっしりと紋様が浮かんでいる。六角柱は円形盤から合計七本伸びていたが、その内の外側三本は途中で色が濁り、紋様も滲んで歪んでいる。元々そうなっていたのか、それとも先刻の戦闘の巻き添えでも喰らったせいなのか。掲げ、目を凝らして刻まれた紋様がどういうものかと見定めようとしていると、
「何をしている、【NAME】よ」
不審な動きをしていた【NAME】の気づいたのか、リゼラが戻ってくる。【NAME】が振り返ると、リゼラの視線は【NAME】の顔から手元にあった結晶の立体物へと落ち、
「――っ」
突然、リゼラが片側の耳を抑えて、表情を思い切り顰めて頭を傾けさせる。その仕草は、まるで耳元で誰かに叫ばれたかのようだが、しかしここに居るのは【NAME】とリゼラのみ。【NAME】は怪訝を通り越して不気味なものを見る表情でリゼラの様子を窺うが、しかし彼は直ぐに態度を平時のものへと改めると、
「見せてみよ」
別段、断る理由もない。【NAME】が素直に差し出された手に立方体を落とすと、彼は何処か胡乱げな視線でそれを眺めた後、
「……これが思わぬ手掛かり、いや、アレの言を信じるならば、用意された手掛かりか。破損がどの程度影響を及ぼすかは判らぬが、空身で戻るよりは遥かに良い」
そして【NAME】の顔を見て、珍しくほんの少しの笑みを浮かべた
「急ぎ戻るぞ、【NAME】。その品をアレの妹――軍を率いる学士の娘に調べさせ、駆動させる事が出来れば、もう少し何かが判る……という話らしいぞ」
だから、なぜ最後に伝聞調になるのか。
真なる楽園 虚ろの姿が伝えるもの
──虚ろの姿が伝えるもの──
エルツァン島の海岸沿い、軍の陣地内に存在している天幕群の中の一つ。エルツァン島に派遣、常駐しているアラセマ軍部隊の長、“先生”の異名を持つ学士イェア・ガナッシュが居所としている天幕にて、【NAME】はようやく一連の話を終えた。
ナリア・バータ霧眩森林での竜との戦い。思わぬ遺跡の発見と、謎の印章石から生じた謎の上陸者の存在。遺跡内部での戦いと、深部での顛末。見た光景、感じた気配、それらを出来うる限りの言葉を尽くして、【NAME】は場に居る者達に伝えたつもりだった。
天幕の中に居るのは、【NAME】を除けば合計四人だ。
「はぁ、それはまた、何とも大変でしたわね……」
そう、どこか気の抜ける返事をしたのは、【NAME】が座る客用の椅子の正面。机を挟んで椅子に座る白衣の娘。この天幕の主である、イェアだ。
「うーん……途中で離脱出来て良かったとするべきか、遺跡の最奥に辿り着けず残念と思うべきか、迷う流れだねぇ……」
続けて、苦笑いにも似た表情でそう言うのは、天幕の脇に置かれた戸棚に腰掛ける壮年の男、ハマダン・オリオール。
「…………」
天幕の入り口脇。両眼を閉じて立ったままのリゼラ・マオエ・キヴェンティは、【NAME】と共にこの天幕に入ってから未だ沈黙を保ったままだ。
そして、最後。
「【NAME】」
座る【NAME】の正面に立って名を呼んだのは、軍属の衣装を身に纏った細身の少女。ノエル・ガナッシュだ。彼女の表情の薄さは何時もの事ではあるのだが、どうもこちらを見下ろす視線が、常よりも温度が低いように感じる。
若干気圧されながらも、何? と見上げると、
「あなたの今回の任務は、早急に“鬼喰らいの鬼”の存在を探し当て、その討伐を行う、というものだったとわたしは認識していたのですが。……一体何を寄り道されているのですか?」
そんな言葉と共に、ずい、と差し出されたのは木製の杯だ。若干荒い動きで、杯の中身が波打つように揺れている。
【NAME】は誤魔化すように笑って受け取ると、一気に杯を煽った。口から喉へ伝わっていくのは清涼な茶葉の香りだ。果実酒が中心のここで茶というのは珍しい。予想外の味に目を白黒させていると、正面、ノエルは表情を変えぬまま、浅く吐息をつき。
「……ただでさえ、あなたは危険な任務についているのですから。それ以外の事に、わざわざ首を突っ込むような無茶は必要無いと、わたしは考えます。……きっと、わたしが言っても無駄な事、あなたは聞いてはくれないのでしょうけれど」
淡々とした口調。平坦な表情。けれども、紡がれる言葉には何かを抑えるような間があり、上方からこちらに向けられる視線は、怒る、責めるというよりも気遣いの色が強いもので、だから余計に居心地が悪くなる。
何事も言い返せずに【NAME】が黙っていると、見下ろす視線が一瞬途切れて、手の中にあった空の杯が取り上げられる。顔を上げれば、ノエルは机の傍へと戻り、新たな茶を淹れ直そうとしているところだった。無意識に吐息をつくと、視線の隅で、オリオールが苦笑を濃くして会釈するのが見えた。確かに、今回の件の発端はオリオールの提案によるものだ。だからこその謝罪なのだろうが、ならば直接助け船を出してくれても良いだろうに。恨みがましい目を返すと、オリオールは露骨に視線を逸らすだけだ。
「……えっと、それで、【NAME】さん」
と、机を挟んだ正面から声が掛かる。イェアは細い手先を頬に当てて、視線は虚空、未だ何か考え込んでいるような仕草で、しかし声だけは【NAME】へと飛ばしてくる。
「今、【NAME】さんからしていただいたお話の中で、幾つかは推測としてわたくしが答えられる事はありますが……何から聞きます?」
流石“先生”――というべきなのだろうか。何とも心強い答えだった。
だが、何から、と問われると、【NAME】はううん? と口篭もってしまう。というより、そもそも【NAME】自身があの遺跡に用があって潜り込んだ訳ではなく、半ば流されて入ってみた形に近い。遺跡の中で疑問に思う事も幾つかあったが、それにしても然程興味がある事柄でもないのだ。
「あ、なら僕から訊いてみてもいいかな」
と、詰まった【NAME】の様子を察してか、オリオールがひょいと手を挙げる。【NAME】があっさり譲ると、彼はにこやかに笑い、
「まずは、あの遺跡について。僕も幾度かああいうのと似た遺跡に入り込んだことはあるんだがね。結局何を目的とした芯形機構だったのか、まだはっきりさせられてないんだ。一応、ある程度の機能は掴めてるんだが。イェア嬢に論があるならば、是非とも聞いてみたい」
その言葉に、イェアは少し驚いたように目を瞬かせる。
「あら。それに関しては、既に西大陸の学院では分類定義までされてますわよ」
「え」
膝に肘をついてたオリオールが、かくんと姿勢を泳がせた。
愕然の表情を浮かべたオリオールに気づいて、イェアは少し慌てたように両の手を振った。
「ああでも、それについて認められた統一見解が出たのは、ハマダン様が東大陸に渡ってからでしたし……仕様が無い事かも?」
拙いフォローに、オリオールは誤魔化すように頭を掻くしかない。
「……実地調査に偏向しすぎて、業界の情報収集が疎かになっていたかな。で、西の方ではあのタイプの遺跡はどういう扱いになってるんだい?」
「“場衡機構”と、そう呼ばれてますわね」
――場衡機構?
【NAME】が鸚鵡返しに呟くと、イェアの視線がこちらへと向く。
「ええ。他の大陸では知りませんが、西大陸ではもっとも多く存在が確認されている類の芯形機構です。代表的なのは北方竜皇山脈のゼルバトーリア遺跡、ワーゼルフィン共同体フラタ区内のペルパトハ地下嶺園の二つが有名ですわね。あと、最近ではモーハス、イェハック、シオラ、ヴィヴォマの四大聖地内にも、同様の芯形機構が存在している事が各学院でのみ情報公開されてますわね」
全く聞いた事の無い名称が次々と並ぶが、いちいちそれについて訊ねて話の腰を折る程愚かでもない。【NAME】は適当に聞き流しながら、何時の間にか直ぐ傍に立っていたノエルが差し出す杯を受け取り、小声で礼を言う。彼女は小さく頷くと、続けて別の杯を持ってオリオールの元へ。だが、オリオールは近くに立ったノエルの事にも気づかないようで、ただ深々と嘆息をつき、
「ほぉ……いや、感心してる場合じゃないな。それで、機能の方は正確に判明しているのかな? まぁ、名前から何となく想像はつくが……っと、おお、済まない、頂くよ」
無表情ながらも若干不機嫌を交ぜたノエルの視線にようやく気づいて、オリオールは慌てて杯を受け取る。その様子をイェアはくすりと笑いながら見届けて、
「でしたら、大方はご想像の通りだと思いますわ。場衡機構は、“芯なる者”が周辺総合環境の大規模改変と微細調整を行うために用意した、極々基本的な芯形機構だと、そう考えられています」
「だろうね。ああでも、そうか。土地概念のみの改変ではなく、環境を含めた変更か。……しかし、それは改変という表現でいいのかな?」
「流石、鋭い」
イェアは目を細めて、口角を僅かに上げる。
「ええ。改変というよりは、土地の創造と、上書き。それに近い働きを持つそうです。“芯なる者”達は単独でも十分土地の在り方を作り替える力を持っていたと言われていますが、そんな彼等でもやはり一から土地を造り上げるとなれば、正確な設計図、膨大極まる理粒子操作、そして大量な象形記述という、“芯なる者”達にとっても個人で行うには難しい……というよりも面倒な作業を必要とした。それを確実に、負担無く行うために、この芯形機構を用意したのではないかと考えられていますわ。ですので、このエルツァンの異質極まる土地の中に、場衡機構が存在していたというのは、ある意味当然の事と言えるかも知れませんわね」
確かに、あの遺跡がそういう機能を持つものであるならば、エルツァン内の土地がそれぞれ独特の、際立った特性を持つ地形になっているのも理解出来る。
「場衡機構は大きく中枢区画と拡張区画の二つに分かれています。その内、中枢区画は芯形機構の芯の部分。生み出す環境の設計図や、実際に創造を行うための象形のみで構成された区画で、ここはどの場衡機構も殆ど同じような外見――円形の小部屋となっているそうです。これは、先程【NAME】さんからして頂いたお話とも一致しますね。逆に、拡張区画が担当するのは核となる象形の効率的運用、安定動作、予備構造その他色々、芯形機構の制作者であった“芯なる者”それぞれが好きなように造るので、各場衡機構で全く別物になっている事が多いそうですわ。それで――」
「――待て。レェアの妹よ」
「……? リゼラ、さん?」
と、そこで口を挟んだのは今まで入り口の横で黙りを決め込んでいた少年だ。
エルツァンへとやってきたキヴェンティ達の長は、薄く開いた片の目だけでイェアの方を見定め、
「やはり姉妹というべきか。貴様の話は姉に似て、無駄が多い。要点を絞れ」
「ひ、ひどっ!」
「というか、僕としてはその辺りの話は色々興味深いんで長話どんとこいという所なんだけれど」
苦笑しながら口を挟むオリオールに視線すら向けず、リゼラは煩わしげに鼻を鳴らす。
「ならばお前達だけで後で存分にやると良い。レェアの妹、先に我の問いに答えてみせ――」
「どうぞ」
そこへ、ずい、と少年とイェアの間を遮るように杯が突き出された。
「…………」
リゼラの剣呑な視線が、横へとズレる。果たして場の空気を判っているのかいないのか、杯を突き出した姿勢のノエルは、無表情のまま、少年の顔を見返す。
「リゼラさん!? あの、ノエルには悪気がないんで、怒らないであげてくださいね! 穏便、穏便にお願いしますわ!」
イェアが大慌てで叫ぶ中、リゼラはそのまま無言でノエルの顔を眇め見た後、突き出された杯を手に取る。するとノエルは僅かに頭を下げて、とことこと机の傍へと戻っていく。
その、少なくとも表面上はあまりに頓着のない動きに毒気を抜かれたか。リゼラは離れていく背中を見ながら浅く吐息をついて、僅かに表情を緩めると、改めてイェアの方へと顔を向けた。
「まず一つ聞く。レェアの妹よ。貴様の言う――場衡機構か。それは命脈へと繋がるための“孔”を開く力を持っているのか?」
「“孔”を開く――命脈への接触という意味でしょうか? ……ええと、モノによりますが、殆どのものは備えていたと資料にはありました。“芯なる者”達は当然、芯属の一つである翆獣種と、それが源とする命脈の存在を把握していましたし、生命を含めた現世界の環境を操る上で、命脈への干渉は重要な要素を占めますから。それを省く事は考え難いでしょうね」
「ならば二つ聞こう。歪んだ霧が無数に漂うあの森を場衡機構が生み出したというのならば、それを元の姿に戻す手立ても場衡機構にあるのか?」
「ありません」
即答して、しかしイェアは少し首を傾げる。
「いえ、あるといえばあるのですが、わたくし達には不可能ですわね。場衡機構の中枢区画に刻まれた象形を書き換えて、元あった環境をその場で再構築するというものですから。本来、場衡機構は土地概念が生み出すであろう正負含めた在り方すらも計算して環境を構築します。つまり今、あの土地に霧の歪が存在しているのは、そもそも場衡機構自体に、そういった存在が生まれるような設計が用意されていたと考えるのが妥当でしょう。……尤もそれは、場衡機構による環境形成後に、外的要因による環境の変化が生じていなければの話ですが」
「では三つ聞こう。場衡機構の内側に漂っていたあの妙な気配は何だ。場衡機構であるならば、どの遺跡でもあのような気配が――命脈の残滓が強く残るものなのか?」
「……それについては、実際に行っていないわたくしには何とも答えづらいのですが、一度でも駆動した痕跡のある場衡機構では、そういった環境構築を行った際の残り火……残り香……まぁ、リゼラさんがいうような残滓が、大なり小なり残っている事はあるそうです。ただ、概念的な防御に長けている人間でなければ入れない程の濃厚な気配が残っているという話は、わたくしは聞いた事がありません」
そこまでの答えを聞いて、ようやくリゼラは少しの間を置く。
僅かに思案するように開いていた片眼を少し閉じると、今度は両眼を開いてイェアを見据える。
「すると四つ聞こう。人の身でありながら、彼の遺跡に刻まれた象形を印章の陣で以て僅かなりとも制御し、古代に届く大呪を施す。そのような事、可能であるのか?」
問いに対し、イェアは唸るような声を間に挟み、
「常識的に考えるならば不可能……な筈です。象形――特に“芯なる者”が扱う象形は、彼等と比べれば矮小な人の存在概念ではどうしても制御が出来ません。扱うには、象形自体の規模を極めて縮小化し、簡略化した上で、更に別個の概念を制御存在として介して使うことで、道具という形に貶める必要がありますわね。これがつまりは、通称ではなく狭義的な、本来の意味での神形、魔導器に相当するのですが、芯形機構に用意されているのはそのどちらもされていない、言ってみれば本来の象形です。象形の劣化物である印章を使ってこれをどうにか出来るならば、わたくし達も苦労は致しません」
その答えに、リゼラは僅かに首を傾げ、視線を鋭くさせる。
「常識的に考えれば不可能、という事は、非常識的に考えるならば可能と、そういう事か?」
「……まぁ、色々と無茶な前提条件をクリアしていれば、出来なくもない、とは思いますけれども……」
「どのような?」
端的なリゼラの追求に、白衣の学士は腕組みして考え込む。
「ええと……まず、卓越した印章術の使い手である事が第一。続いて、その行使を補助し、記述した印章の格自体を象形が扱える程の高位へと押し上げるための器が必要でしょう。端的に言えば、先刻例に挙げたような神形、魔導器の類ですわね。あと、術士が求むる結果が、扱おうとする象形の示す力の方向性と似通っていれば大分楽になります。そして、これが要で、一番重要な部分なのですが」
イェアはそこで言葉を切り、呼吸を一度挟むと、
「――人の枠を逸脱する事。これが絶対の条件です。先刻言った通り、“芯なる者”の象形とは、単なる人間からすれば次元自体が違う代物と言いますか、どうしても存在概念の格が足りません。だから“芯なる者”の象形を操ろうとするならば、何らかの方法で、何らかの存在に、逸脱する必要がある。そう考えられてますわ」
「人ならざる者。成る程、ならば、そうだな」
呟いて、リゼラが視線を動かす。イェアから横へ僅かにズレたところで、少年の視線は止まった。その先に居たのは軍服の少女だ。
「例えば、そこに居る“鬼の呪われ子”のような、か?」
「……っ」
リゼラの言葉に、ノエルは小さく息を呑み、僅かに表情を強張らせる。
彼女が確かな動揺を表に出すのは稀だ。だからこそ、鬼の子という言葉は、今のノエルには強く響いたのだと察する事が出来た。
「リゼラさん! それは、流石に言葉が過ぎますわよ!」
と、流石保護者と言うべきか。先刻までの何処か押され気味な受け答えをしていたイェアが、一変して鋭く声を飛ばす。
【NAME】も、反射的にリゼラへ振り返る。視線が険しくなっているのは自覚出来たが、抑える気にはならなかった。
リゼラは己を見る【NAME】とイェアを順に一瞥して、そして軽く自分の耳を抑えるように触れて、
「――確か、ノエル、と言ったか? 許せ、確かに口が過ぎたようだ」
問われて、ノエルはほんの僅かに目を見開くと、そのままぴたりと暫し固まる。ああいう時の彼女は判りやすい。どういう反応を返すべきか判らず、困っているのだ。
そのままノエルは数呼吸の間微動だにしなかったが、震えるように声を絞り出し、
「……は、はい。謝罪は、受け入れました。以後、どうかお構いなく」
こくりと頷きだけを返して、リゼラはまたイェアを見返す。
「それで、どうなのだ。返答は?」
「ノエルは……試したことが無いから実際どうかは判りませんけれど、可能性としては半々というところではないでしょうか。もっとも、これは素養的な話で、ノエルは知識も何もありませんから、現実的には不可能ですけれども」
「つまりは、人でなくなれば良い、と」
「ええ。勿論、下位存在に落ち込んでしまうのは意味がありませんが、同格か上位の存在へと存在概念を変質させることが出来れば、象形に手を届かせることも可能かもしれません。あと、言っては何ですが、ノエルよりも相応しい存在を、リゼラさん、あなたは身近に知っている筈ですわよ?」
「……ああ、言われてみればそうだな。アレの普段の態度を知っていると、どうもそんな連想が――っ」
と、リゼラは唐突に言葉を切ると、暗みを払うように首を振った。
一体突然どうしたのかと、【NAME】達は怪訝な顔でリゼラを見るが、彼は心底面倒くさそうな顔で杯を持たぬ手をひらりと振り、
「気にするな。何時もの事だ。そして、これまでの問答で大まかな理解は出来た」
「え、まだ僕、碌に状況を把握できてないんだけど……」
愕然としたオリオールの声を無視して、リゼラは続けて言葉を作る。
「それでは、最後の問いだ。――【NAME】、お前も何を悠長にしている」
完全に油断しながら茶を口に含んでいた【NAME】は、いきなり話を振られてぶっと咽せた。
【NAME】は咳き込みながらリゼラを見ると、少年は頭痛を堪えるようにこめかみに指を当てながら、
「忘れたか、惚け者が。あの遺跡で手に入れたものを、早々にレェアの妹に渡せ」
「? 【NAME】さん、何か見つけたんですか?」
きょとんとした顔でこちらを見たイェアに言われて、【NAME】はああと思い出す。そういえば、イェア達に話したのは遺跡の最奥で竜と戦い、そこで何者かの印章陣を見つけたまでで、帰り際に拾った奇妙な物体についてはまだ話していなかった。
【NAME】が足元に置いていた背嚢から、一つの立体物を取り出した。
大きさは拳ほど。円形の水晶盤のようなものに、合計七本の六角棒が取り付けられた不思議な形状の物体だ。各所に紋様――後で詳しく見てみたところどうやら印章らしきものが刻まれていたのは確認できたのだが、一体どういう用途のものなのかは判らぬまま。これを見つけた当初、リゼラは確かイェアにこれを見せれば良いと、一体どういう根拠によるものか全く判らぬ事を言っていたが、果たして本当にそれで良いのだろうか。
不審に思いながらも【NAME】が長机の上にその立体物を置くと、リゼラを除いた三人がそれを覗き込む。
果たして、
「飲み物を注ぐ椀の台座に使えそうです。とても安定しそうだと私は思います」
一人素っ頓狂な感想を零すノエルだったが、除いた二人は驚きに目を見開いてその物体を凝視する。
「これは――」
「何でまた、こんなところに。【NAME】、君、これが何だか知っているのかい?」
――いや、判らなかったからこうして見せている訳だが。
勿論、水晶にも似た素材に印章が刻まれているのだから、恐らくは印章石のような術式を駆動させて何らかの効力を発揮する類の代物である事くらいは見当はついているが、しかしわざわざこのような複雑な形状に加工されている印章石というのは見た記憶が殆どない。
そんな【NAME】の言葉に、オリオールは大仰に首を振って見せて、
「こいつは、所謂機甲具――それも機甲と印章術式の術式を組み合わせる事で生まれる、最先端の代物だよ」
「ですわね。効果の方は確か、一定範囲の空間の震えと、一定範囲の平面情景を微細な印章情報列として簡略化し、記録する。それは任意の機会で再現することが可能で、情景は平面の映像として、震えは音声として再現する……だったかな。最初に造られたのは東大陸なんですけれど、今では西大陸の学院の間でも幾つか同様の機能を持つものが造られていますわね」
「……器の台座ではないのですね」
何処か残念そうに立体物を眺めるノエルを全員が一瞬見てから、音も無く視線を逸らす。
「それで、【NAME】さん。あなたはこれを、遺跡の最深で見つけたということですの?」
頷くと、「こいつはまた」とオリオールが浅く歯を見せて笑う。
「これのお陰で、一気に対象を絞れたね。内輪に見ても、遺跡に隠匿結界を仕掛け、そして機甲具を残していった人物がエルツァンにやってきたのは三年……いや、二年前の間に収まるだろう」
「ええ。それも一硝六点一制式は西大陸では殆ど使われていない、フォータニカ発祥の方式ですから、多分西側ではなく、東側からやってきた方でしょうね」
「……となると、常駐軍のフローリア開放政策の事を考えれば、もっと最近にやってきたと見ても良いだろうかね?」
「そこまでは何とも言えませんけれど。そもそも、このエルツァンに乗り込んだということは、エルツァン島の周囲に存在するあの結界を抜けてきたという事です。あれを突破できるような方であるなら、アラセマによるフローリアの封鎖などそもそも有って無いようなものでしょうし」
言われてみれば、そういう事になるのか、と【NAME】は小さく唸る。
【NAME】が神形の力を使って一時的に払い、潜り抜けたエルツァン島全体を包む強大な守りを、機甲具の所持者は少人数、もしくは単独で摺り抜けた事になる。彼の探検家カール・シュミットがエルツァンへと踏み入ることが出来たのは偶然だという話だが、対して彼等の場合もそれと同様であったと見て良いのかどうか。
「何にせよ、だ」
と、そこで戸口の横に立っていたリゼラが、預けていた背を天幕の支えから離してこちらに歩いてくる。
「この機甲具が、遺跡の奥へと入り込んで印章陣を残した誰かが残したものであるというのなら、内に残された記録を今ここで再現してみれば判る事も多くあるだろうよ。そして、レェアの妹よ。貴様ならばこの機甲具を駆動させる事ができるのではないか?」
机の上に置かれた機甲具を手に取り、リゼラはイェアへ向かって差し出す。受け取った彼女は眉間に皺が残るほどに強く、睨むように機甲具を眺め、
「……はっきり言うと、難しいと思います。ほら、この部分を見て頂けます?」
と、イェアが指差したのは突き出た七本の柱の内の三本。半ば辺りから色を失って、紋様が滲むように消えている部分だ。
「記憶の為の印章が不自然な形で失われてますわ。恐らく、記憶が行われた後に何かこの部分が失われるような状況が発生したのでしょうけれど……【NAME】さん、心当たりはありませんか? この感じですと、多分記録が行われた後に、何らかの強烈な存在概念に当てられて、欠損してしまったんだと思うのですけれども」
問われた【NAME】は、機甲具を拾い上げたときの状況を思い出す。部屋の中央から少し離れた場所に、無造作に転がっていた機甲具。改めて考えてみると、そんな中途半端な場所で無造作に置かれているのも妙だ。これが記憶装置であり、そして遺跡を訪れ印章陣を描いていた人物が残したものだとすれば、もう少し判り易い場所、例えば部屋の中央などに置かれているのが普通な気もする。
と、そこまで考えて、【NAME】は思い至る。確かめるようにリゼラを見ると、彼も同様の事を考えていたのか、顔を苦く顰めていた。
「あの時の、竜の吐息か」
「竜、ですか? ええと、確か遺跡の中でも霧の竜と戦いになったんでしたっけ?」
問いに頷き、【NAME】は続けて語る。
最奥の部屋で行われた三匹の霧竜との戦い。その時、竜が吐き出す強烈な陰性概念を秘めた霧の吐息は、部屋の中を幾度も縦横した。部屋中央部に描かれていた印章陣も、竜が放った吐息により損なわれしまったのだ。そして機甲具についても、元々あのような代物をわざわざ部屋の隅の床にて無造作に転がしておくとは考え難く、
「竜の吐息で吹き飛ばされたとするのが妥当であろうよ。もっとも直撃であれば形すら残っていなかっただろう。精々が、吐息の飛沫に押し出された程度だろうがな」
「つまり、印章の欠損はそのせいって事ですか……うーん」
「イェア。貴女の知識でも、機甲具の駆動は難しいのですか?」
ノエルが少し意外そうな気配を纏わせて問うと、イェアは「駆動させるだけなら簡単なんですけれどもね」と息を吐き、
「一硝六点一制式については以前に資料で見た事がありますから扱える事は扱えると思います。けれども、何せ情報記憶がされていた印章が失われていて、この欠損部分についてはどうやっても復元は不可能ですわ。少々の破損でしたら、情報補完を行う事も可能ですが、これは二割、下手をすると三割近くが失われています。後、それ以外の部分でも所々異常が見られますし、再生そのものがが正常に出来るかどうかも怪しいですわね。……ええと、確か……」
イェアは円形盤から突き出た七本の六角柱の内、中央の一本に触れると、少し力を入れて押し込みながらくるりと右へと回す。すると、六角の柱の外殻六面が開くように展開し、その内部より小さな操作盤らしきものが飛び出した。
「フォータニカはどちらかといえば機甲技術が先行している国ですから、一硝六点一制式も機甲技術がメインで、制御系もこんな感じになってるんですよね」
飛び出した操作盤は細かく複雑そうで、知識がない【NAME】からすると一体どう触ればいいのか見当も付かない。
「……それ、どう見ても僕等だけじゃ再生できなかった気がするんだけど、機甲具を残した人はどういうつもりで置いていったんだろうか」
オリオールにしても同様であったらしく、そんなもっともすぎる発言が飛び出し、イェアも少し苦笑する。
「これは機甲具の状態確認用のものなので、再生自体は特定文句の宣言とかでも可能ですけれど、まぁ、少なくとも相応に印章術やそれに類する知識がある人を対象としていたか、そもそも自分達用に使っていた物を置き忘れていったか、といったところでしょうね。……で、えーっと、記憶内容の精査……状況確認……自動補正はなしか……」
その後、イェアはぶつぶつと呟きながら操作盤と向き合うこと暫く。
「うん。これで、何とか、再生自体は出来る……とは思いますけれども」
顔を上げたイェアの表情は何とも冴えない。やはり問題があるのだろうか。
「欠損部分や異常部分の補完をやってると終わりそうにないので、取り敢えず問題部分は切り捨てて、再生だけは出来るようにしてみました。ですので、記憶された状況がわたくし達に把握出来るレベルで再現されるかどうかは、正直難しいようにも……」
「言い訳は不要だ。疾く駆動させよ」
「うう、リゼラさんきつい……」
呻きながら、イェアは機甲具を地面に置くと、短く何事かを発してから、その場から離れる。
すると機甲具の突き出た六本の柱に刻まれた紋章が光を放って上方へと広がり、縦横二メートル程の淡く光る幕となって空間を区切った。続いて機甲具の硝子状の円盤部が輝くと、区切られた空間の内部で風景が歪み、別のものへと変化していく。
数秒の間の後、そこに現れたのは薄暗く殺風景な部屋の一片だ。光の幕に映し出された平面の情景。光源は下方と上方からの淡い光のみで、所々に輝きを放つ紋様の姿が見える。【NAME】には見覚えのある風景。霧の森の地下にあった遺跡、その最奥に存在した部屋の景色そのものだった。
だが、
「……やっぱり、大分無理がありますわね……」
イェアが苦い声で呻くのも判る。
平面の幕上にて展開された風景は、一時たりとも安定を見せない。時には小さく、時には大きく歪み、一瞬の間に完全に消滅したかと思えば次の瞬間にはまた姿を現す。そんな不安定さだ。また、同時に再生される音についても雑音が激しい。殆ど物音がしていないであろうその場面に於いても、機甲具からは時折ざりざりと耳障りな音が響いている。
「何だか、目がしぱしぱします」
「確かにね。まぁ、映像として再生されているだけでも儲けものと思うとしよう」
両眼を手で押さえてぐりぐりと擦るノエルの様子が微笑ましかったのか、オリオールは彼女を見て小さく苦笑し、そのまま視線をイェアの方へと向ける。
「で、まさかこの映像だけで終わり、という訳ではないのだろうけど、この機甲具、どの程度の時間記録できるものなのかな?」
「わたくしが聞いた中で最高の記憶量をもつものでも、最大で三分程ですけれど、これはもっと性能の低いもので、見たところ大体20から30秒くらいのようですわね。今東大陸の学院で使われているものの主流が大凡一分と言われていますから、恐らくは旧式のものか試作物の類なんでしょうけれど……あ、来た」
言葉を切って、イェアは静かにするようにと周りの者達に仕草だけを見せる。
光の平面を形作る枠内に入ってきたのは、老境の域にある男の姿だ。映像が頻繁に乱れるため、はっきりとした顔立ちを見定めることは出来ないが、髪も髭も真白。長衣を纏い、手に同調誘導器らしき杖を携えた姿は見るからに術士のものだ。男の背後には合計八つ、拳大程の大きさの玉がふわふわと支えもなく浮かんでおり、歩く仕草に合わせ、常に彼の背後に在るように位置を器用に変化させる。玉はそれぞれ色持つ光を強く放っているようなのだが、映像の乱れや色相の荒れ具合のせいで、それが正確にはどんな色なのかを見定めることが出来ない。
平面の中央に移動した老人がこちらへと向き直る間、枠内に新たな人影が増える事はなく、どうやらその場に居たのは彼一人きりであるようだ。
老人は真っ直ぐに視線を正面へと向けて、一拍。歪む姿形の中、口があると思しき部位が歪むのが見えた。
一体何を伝えるつもりなのか。【NAME】達が固唾を呑んで耳を澄ます中、続けて聞こえてきた声は。
「 を 見出 。幸 感 する。ワ の は 」
「……あー」
「これは……」
「……ん」
場に居た者達から、不快さを堪えるような呻きや、失望の色濃い溜息が多方から漏れた。溜息までは零さなかったものの、【NAME】にしても全く同じ気分だった。
再生開始時のほぼ無音状態の時ですら妙な雑音が混じっていた事を考えれば、それとなく予想出来た事ではあったが、機甲具により再現された音声は大半がひび割れ、歪み、時には途切れ、意味を汲み取るのが難しい代物だった。
【NAME】がイェアやオリオール達と何とも言い難い顔を見合わせる間に、再生はあっさりと終了する。その時間はイェアの見立て通りの大凡30秒。
「……取り敢えず、繰り返し見てみましょうか」
イェアが機甲具を操作して、記録を反復させる。
巻き戻される映像。再現される異音。映像に殆ど動きはない。情報源となりそうなものはほぼ音声のみだ。意識を耳に集中させて、どうにか老人が話す言葉を聞き取ろうとする。
再現される情景と音の状態は始まりから終わりまで一定の水準ではなく、序盤は所々の短音は把握できるレベルであるのだが、中盤の欠損が酷く、音どころか映像すらも数秒単位で消失する程だった。逆に終盤部は比較的状態が良く、短文程度ならばどうにか判別理解出来るようにも思えたが、あくまで比較すればという話であり、明確に聞き取れたとはお世辞にも言えないものだった。
二度目、三度目、四度目。
五度目の繰り返しが終わったところで、イェアは立ち上がると再生を止めた。機甲具を手に取り振り返った彼女の表情は、頭痛を堪えるかのように顰められている。
「はぁ……。兎にも角にも、音声の部分が大幅に欠損しているのが痛いですわね。……どなたか、読唇の心得がある方、いらっしゃいます?」
無言の返答に、イェアは「ですわよねぇ」と小さく吐息をつき、
「取り敢えず、情報をまとめましょうか。ええと、まず先刻のお爺さんのお名前は、ええと、何て仰ってましたっけ……バイォー?」
「……ムァーヴルじゃないか?」
「……オトルさんではないか、とわたしは考えますが」
雑音を省いて推測するに、ビールと聞こえたような。
「「…………」」
それぞれの意見がバラバラだった。リゼラを除いた四人は一瞬顔を見合わせて固まり、
「で、では気を取り直して……ええと、確か自分が何処からやってきたかについてもお話しされていたようにも思うのですけど、どう聞こえました? わたくしは東の大陸より船を使って、とかそんな風に聞こえたんですが」
「確か西の海からどうこう、と言っていなかったかな?」
「南の港、と仰っていたようにわたしには思えましたが」
これも歪んだ音を強引に変換して考えると、宝を使い海上を飛んだとか何とか。
「「…………」」
それぞれの意見がバラバラだった。四人は鈍い汗が伝うのを感じながら視線を絡ませ合い、
「戯れ言で遊びたいのなら、我が居らぬ時にやれ」
「ああっ! リゼラさん、待って! 帰るの待ってくださいな! っていうか冗談じゃありませんって、大まじめですわよわたくし達!」
「……ならば、不明瞭な所はそもそもの思案から外せ。終わりの部分なら、幾つかの言葉はそれなりに聞き取れたのではないか?」
確かにそうだ。音声部分の多くは途切れていたり、異音に変換されていたりしていたが、しかし後半を過ぎると徐々に明瞭となっていき、最後の方はある程度ならば言葉として聞こえるようにはなっていた。
それを要約すれば、
「ご老人が終わり付近で言っていたのは確か、あの遺跡で行ったらしい大術式とやらが失敗した事と」
「それによってあの場所が非常に不安定な状態になって、術の再行使が不可能になったから、エルツァン島にある別の場衡機構に向かう、でしたっけ?」
「他にも何か仰っていたように私には思えましたが、良く聞こえませんでした」
オリオール、イェア、ノエル。三人の発言は、【NAME】の認識とほぼ一致していた。
得られた情報は少ないという他無い。しかし、判る事は確かにある。
「……つまりは、あの場所に満ちていた強い異質は、やはり部屋に残されていた印章陣――あの翁が齎したらしい術式によるものか」
リゼラの不快げな言葉に、イェアは短く頷く。
「なのでしょうね。話し振りから推測すると、お爺さんはちゃんと自分が何をしていたかとか、何故こんな機甲具を残していたのかとかも、色々と話していたように思えるんですけれども」
「残念ながら、その辺りの話は記録の真ん中あたりの、軒並み失われたところにあったようだね」
間が悪いというか何というか。
【NAME】達はげんなりと顔を見合わせるが、一人、リゼラはそんな事には頓着する様子はなく、淡々と言葉を続ける。
「しかし、レェアの妹よ。先刻貴様は、人の身では芯形機構の象形は扱えぬといっていたな。では、この状況はどう説明する」
「だから失敗したのでは? ……ああでも、そうですわね。例え失敗だったとしても、場に変化は生じているのか。だから、あのお爺さんの印章陣は、象形の制御には失敗しているけれども、接触や干渉には成功している……?」
「印章陣だけの力で、という可能性はないのかい?」
「んー、わたくしは描かれていた印章陣を見てませんからその辺りは何とも……。ただ、遺跡全体に及ぶほどの広範囲の土地概念変質を齎すような術式、しかも失敗の副作用による影響がそこまで広がるようなと考えると、印章陣の規模的に有り得ないような気がしますわね。そこまで大きな影響を持つものならば、多人数によって駆動させる、数十メートル以上の大印章陣の類でないと」
「となると、ご老人はさっきイェア嬢が言っていた条件をある程度はクリアしていると考えていいのかな……?」
何処か恐る恐るといった様子のオリオールの言葉に、場は暫し沈黙する。
イェアが上げた条件は三つ。極めて高い技量を持つ術士であり、神形器や魔導器に匹敵する代物を所持し、尚且つ人の枠から外れた存在である事。
その条件を満たした者が、エルツァンで何かを――絶大なる力を持つ“芯なる者”の象形を利用して何かを成そうとしているのだ。それは、何ともぞっとする話だった。類似する存在として思い浮かぶのは、アノーレで戦いを繰り広げたあの召喚司だ。あれと同等の人物が、自分達の知らぬ間にこの島を訪れ、何かをしていた。一体何を? 恐ろしさを煽るのは、この何をしているのかが判らないという所も大きかった。
「ああ、いやいやいや! 失敗はしてるんですから、全部の条件を満たしている訳じゃない筈ですわよ! ……多分」
「でも、イェア嬢。印章陣を個人で記述している辺りからもう術士やとしてはかなりの腕前の持ち主であることは確定だろうし」
「それに、男性の後ろに浮かんでいた物体も気になります。映像が荒く、はっきりとは確認できませんでしたが、あれは単なる同調誘導器とは考え難いと私には思えます」
「う、うーん……、参りましたわね。まさか、“鬼喰らいの鬼”以外に、こんな厄介な闖入者が島に紛れているなんて。しかも、何より面倒なのはこれ、既にあのお爺さんは目的の術式を各地の場衡機構で試しまくった後、という可能性が高い事なんですよね……」
イェアが戸惑うのも判る。
老人の目的が見えない事と、老人が描く印章陣の効果が判らないせいで、果たして放っておいて良い事柄なのかどうかも判断が出来ないのだ。
「わたくし達の目的は“鬼喰らいの鬼”の討伐が主ですわ。けれど同時に、エルツァンの調査や探索、安全確保の役割を期待されているのも確かです。その観点から考えれば、件のお爺さんが一体何をしていたのかを確かめるのは優先度の高い案件ではあるでしょう。けれども……」
「まぁ、色々と、難しい状況ではあるね」
口篭もるイェアをフォローするようにオリオールが言葉を足して苦笑する。イェアは困ったような顔でこちらとリゼラを交互に見ていた。
向けられた視線の意味を【NAME】は暫く考えて、ああ、そうかと気づく。
――適任者が、自分達しか居ないのか。
【NAME】の様子から察したか、「そういう事だよ」とオリオールが言葉を続ける。
「ご老人が他の場衡機構で行ったであろう術の影響で、内部の環境、概念状況が大きく変質している可能性がある。それを考えると、軍の兵士は勿論の事、僕やイェア嬢、あとは海月殿のような普通の人間では、少々荷が重い。遺跡の中に立ち入るのがまず難しいだろうね。勿論、色々と準備や無理を通せば可能ではあるかもしれないけれども……」
「残念ながら、この陣地にある物資では付け焼き刃の対策しか出来ませんし、そのような状態で手を出すのは寧ろ危険が増すだけでしょうね。あと、ノエルに関して言えば」
視線を向けられて、軍服の少女は伏し目がちに声を落とす。
「……今も、守りを得てようやくという私では、そのような場所では足手まといにしかなれないと考えます」
僅かに俯いた拍子、帽子の先に取り付けられた小さな飾りが揺れる。見慣れたそれは、彼女を概念的な干渉から守るための品だ。以前に聞いた話を思い出す。ノエルはその特殊な素性故に、外的な強度概念に影響を受けやすく、特に陰性質の概念干渉には極端に弱い。それを踏まえれば、ノエルが失格であるのは明らかだった。
要するに、老人の後を追って他の場衡機構へと赴くには、概念干渉に対して根本的な強い守りを持つ者である必要がある。
例えば、神形との係わりを持つ【NAME】であったり。
例えば、翆獣との繋がりを持つリゼラであるならば、可能なのだ。
「我とすれば、むしろ願ったりの状況だ。彼の者が我等が崇める命なる脈に触れ、何を成すつもりであったか。翆の眷たる者として、それを確かとせねばならぬ。……が」
悠々と話しながら、リゼラは唐突に言葉を切り、視線を向けたのは【NAME】の方だ。
「今の我は、お前の刃としてここに居る。故に、判断はお前に任せよう」
――いきなり話を振られても困るのだが。
【NAME】としては戸惑うしかない。ここまでの話から、件の老人に対する興味は多少なりと湧いてはいる。湧いてはいるが、しかし思い出すのは霧の大鬼や霧の竜達との戦闘だ。あのような危険が待ち受けていそうな場所にわざわざ飛び込む程かと言われると、首を捻るしかない。
「勿論、無理にとは言いません。ですが、エルツァン島の歪な地形を巡り、場衡機構を探り当て、その内部へと立ち入る事が可能なのは、ここでは【NAME】さんとリゼラさんのお二人しか居ません。だから、あくまで可能であればお願いしたいと、その程度の話であると認識してくださいな」
「…………」
暫くの沈思の後、余裕があれば、という何とも消極的な返答でお茶を濁す。気乗りしていないこちらの態度を察してか、オリオールが同情気味に笑い、
「出来うるなら僕が替わりたいくらいなんだけれどもねぇ」
【NAME】としても可能であれば替わってもらいたいところだったが、そういう訳にも行かない。
深々と嘆息し、そして、はてと考える。
他の土地に存在する場衡機構――といわれても、思い当たるような建物を見つけた記憶が一切無いのだ。
「まだ他の場所の遺跡では、隠匿結界の印章石の効力が切れていないって事じゃないかな」
オリオールに言われて思い出す。霧眩森林で発見できた遺跡も、あそこに構築されていた隠匿結界が失われていたからこそ見つけられたものであったのだと。
だが、そうなると一体どうやって新たな場衡機構を見つければいいのか。
「その対応については、一応わたくしの方で用意してあります。ハマダン様が、隠匿結界を構築していた印章石を事前に持ち帰っていてくださったので、それを使った物を、ね」
イェアは天幕の隅にて乱雑に置かれていた荷物の中から、一つの石を取り出して戻ってくる。
それは以前に霧の森でリゼラが見つけた印章石だ。そういえば何処にやったのか気にしていなかったが、知らない間にオリオールが持ち帰り、彼女に渡していたらしい。
だが、以前の姿そのままという訳ではない。石はよく見れば一つではなく、二つの石が重なる形となっており、色を失った一つ、【NAME】の見覚えある石の裏側に、別の印章石がもう一つ、張り付くように存在していた。
これは? と視線だけで問うと、イェアは両手を腰にやり、胸を張るように身体を揺らす。
「わたくし特製の、結界破りの印章石です! この石と同系統の隠匿結界を感知し、対抗術式を展開する機能を付与してみました。これを使えば、隠匿結界という存在の方を拾い上げる事で、あのお爺さんが隠したであろう場衡機構も芋蔓式に発見出来るという寸法ですわ!」
自信満々、得意げに言い放つ彼女だが、それを茶化す気にはなれなかった。確かに、この状況に於いて彼女が付加した機能は極めて有効だ。
おー、とばかりに拍手をすると、イェアは素直に笑みを深めて、嬉しそうに頬を染める。
「ただ、感知範囲は広く見積もっても半径数百メートル程度ですから、結局これを持ってエルツァン島の中を歩き回らないと駄目っていうのは変わらないのですけれども」
「…………」
付け足された言葉に一気にテンションが下がるが、それでも何も無いよりはマシだろう。
「場衡機構は多分それぞれの地形に存在してはいたのでしょうけども、現存してるかどうかは判りませんしね。ただまぁ、無理に当たりをつけるならばナリア・バータから直ぐ移動出来る地形を虱潰しにしてみるしかないかなぁ、と思います」
そんな不確かな発言と共に手渡された石を、【NAME】は背嚢に仕舞いながら浅く溜息をつく。
“鬼喰らいの鬼”の討伐だけでも厄介だというのに、追加でこのような役目を任されるとは。
あくまでこちらの自由意志に任せた上で可能であれば、という前置きがある分、多少気が楽ではあったが、しかしと横目でリゼラを見れば、
「では、【NAME】よ。遺跡の捜索を始めるならば我等のみで陣を出る。他の者は連れてこぬよう、注意せよ」
と、こちらに任せるという発言をした割りに、場衡機構を探し出して老人の足跡を追うという流れが、彼の中では当然であるようなのが若干辛い。
――とはいえ、確かに。
先刻までは色々と渋ってみせてはいたものの、結局の所、【NAME】自身も気になるところではあるのだ。更に言えば、危険であるからという理由が、自分にとってそれ程躊躇う根拠にはならない事も。
その辺りの事を考えれば、成る程、リゼラがあのような態度を取るのは、こちらの事を案外深く理解しているからなのかもしれないと、【NAME】は内心苦笑しつつ思うのだった。
真なる楽園 円輪の轡が封ずる形
――場衡機構“灼雷”――
カリッサ灼雷領域。稲光が時折走る、雷気に満ちた危険な湖の縁を用心しながら歩いていた時。突然、何かが強く振動するような感触を覚え、【NAME】は慌てて身動きを止めた。
懐を探り、取り出す。振動の正体は、二つの石を無理矢理一つに重ね合わせたような、奇妙な形をした印章石だ。
エルツァン島の探索と“鬼喰らいの鬼”討伐。二つの任を帯びて島に派遣されたアラセマ常駐軍部隊を束ねる学士イェア・ガナッシュが、島の何処か、隠匿結界にて隠されているであろう芯形機構――正確には“場衡機構”と称される遺跡を見つけ出す為に用意してくれた品である。
その石が反応を示している。つまりそれは、近くにあの年老いた術士が敷いたであろう隠匿結界が存在し、同時に結界の内側には場衡機構が存在している事も意味していた。
「【NAME】よ。見つけたのか、件の遺跡を」
声を掛けてきたのは、今回の旅の同行人である年若い――幼いと言っても良い年頃の剣士、リゼラだ。今回のエルツァン渡航に参加したキヴェンティ達を率いる、“杜人”の名を持つ少年の問いに、【NAME】は無言で頷く。正確には、遺跡ではなくそれを隠しているらしい結界を、ではあるが。
もっとも、印章石によって知る事が出来るのは周囲に隠匿結界が存在している事のみで、詳細な場所までが判る訳ではない。印章石が感知できる範囲はイェアの言を信じるのであれば半径大凡数百メートル。幸い、四方の内の一方は湖で、常時雷気を発する湖の底に遺跡が存在するとは考えたくない、というよりもし場衡機構が存在していたとしても、そのような場所に隠匿結界を張る意味が見出せないので除外。そして残る三方の内の二方は岸辺で見晴らしは良く、移動の手間もかからない地形となっている上、片方は先刻歩いてきたばかりだ。そちらに結界が存在しないのは確定と考えていい。実質的に探索が必要な場所は、進行方向となるもう一方の岸辺沿いに加えて、湖とは逆方向の一方、針葉の森となっている地域くらいだろう。
印章石の反応を頼りに、【NAME】はまず岸辺をそのままなぞる形で暫く歩く。すると、印章石の反応はある場所を境に全く無くなり、ただの石ころに戻ってしまった。
――ならば、森側か。
どうやら、遠のいてしまったらしい。方向転換し来た道を戻り始めると、推測通り、また石が振動を再開する。
結界との距離が近付くほど振動が強くなるような、距離を測る力でもあれば楽なのだが、この印章石に付与されているのはあくまで同種の隠匿結界が感知範囲に引っかかれば振動を返す効果でしかない。また、結界破りの力にしても、その結界の範囲内にまで辿り着かねば効果を発揮しないという代物だ。隠匿結界までの残り数百メートルの距離は、自力で詰めるしかなかった。
探す側からすれば少々面倒な話ではあるが、あの短い時間で結界の探知と解除という二つの力を備えた印章石を用意出来た事がまず異常なのだ。これ以上の機能を期待するのは、流石に高望みというものだろう。
それに、詳細な距離までは掴めないものの、結界破りが可能となる範囲――結界自体に接触する事が出来れば、印章石に刻まれた紋様が輝きを放つという。結界の範囲は確か数十メートルという見立てであった筈だ。虱潰しに探していくしかないが、砂漠の砂粒の中から宝石を拾うような気が遠くなる程の話でもない。【NAME】は然程気を張ることもなく、湖の傍を離れて森の中へと立ち入る。
森の中は苔草の少ない、比較的視界の良い環境となっていた。湖が近いわりに土には湿り気がなく、空気はひんやりとしている。並び立つ樹木は全てが針葉樹で、立地からすると若干不自然にも思える。雷気を放つ湖だけではなく、こういった近隣の何気ない地形に対しても、場衡機構による土地改変の影響があるのだろうと解釈して良い環境なのかどうなのか。判断が難しいところだった。
そのまま暫く歩いていると、後方、殿を務めていたリゼラから声が掛かる。
「【NAME】よ。あの術士が残した結界は、確か忌み地の力を持つといっていたか?」
――忌み地。そういえば、以前リゼラは人払いの効果の事をそんな風に呼んでいたか。
【NAME】が何気なくそう呟くと、リゼラは僅かに頷く。その間も、彼の視線は森の各所へと油断無く向けられている。
「我等キヴェンティにも、同様の力を生む術はある故、理解は出来る。だが、対処についても同様と考えて良いのかと、疑問に思ってな。どうなのだ?」
どう、と言われても、リゼラ達キヴェンティが言う忌み地の対処法を知らないので、何とも一概に答えづらいものがあった。取り敢えず、【NAME】は自分が知っている人払いの結界についての事を歩きながら話す。
人払いの結界とはつまり、特定範囲に対する本能的な警戒感、忌避の念を生物に抱かせる精神干渉の類だ。この精神干渉とは直接的に干渉してくる物から、五感に作用するような物まで様々であるが、その殆どは人払いの結界が存在すると認識しているならば効き目は薄いとされている。当然だ。行きたくないと何となく感じるような場所、避けた方が良いと思える要素がある場所へ、逆に踏み入っていけば良いというだけの話なのだから。特に、今回はある程度の場所が限定出来ている上に、結界自体の直接効果範囲に入る事が出来たならば印章石が反応を示す。ならばそもそも人払いの力が自分達に効果を及ぼす前に、印章石が反応する筈で、
「我等がわざわざ対処を考える必要すらない、と。そういう訳か」
先取りしたリゼラの言葉に、【NAME】は頷き一つを返す。
【NAME】がこの森に大して用心せず入ったのもそれが理由だ。気をつけるべき点はそれ程無く、亜獣の存在に警戒しつつ、森の中を一通り歩き回れば発見出来る、若干面倒ではあるが容易い作業。話によれば、結界は人払いの他にも誤認による隠蔽の機能――つまり遺跡のある場所に足を踏み入れていても、その存在を気づく事が出来なくなるような力があるという事だったが、これも結界を破ってしまえば無効化出来る。結界破りの印章石を持つこちらからすればあってないようなものだった。
そんな事前の予想の通り、【NAME】達が森を歩き出してそう時間も掛からぬうちに、印章石が淡い輝きを放つ。印章石が秘めた結界破りの力が発揮出来るようになった合図。隠匿結界に触れた事を示す合図だ。それを意識してみると、確かにほんのわずか、何となく行く気になれない、そんな方角が存在しているように感じる。つまりこれが人払いの結界の力であり、そちらの方向に目を移しても他の場所と全く違いがないように見える事が恐らくは認識干渉、誤認させる力の効果なのだろう。
【NAME】は立ち止まると、石を掲げて小さく喉を鳴らす。背後のリゼラはこちらの動作から状況を把握したのか、同じく足を止めて、何事も発する事無く周囲を警戒し始める。相変わらず察しが良くて助かる。そう思いながら、【NAME】は手にした石へ宣言の言葉を告げた。
印章石の駆動を行う際、一般的に所持者の素養は不要とされる。印章石に刻み込まれた印章術は、所持者が備える理粒子同調能力ではなく印章石そのものを通じて世界に干渉し、事象を発現させる。知っておくべきは、その術式を駆動させるための方法のみで、主流として使われているのは定型句による発声方式だ。イェアから預けられた印章石もこの方式を採用していた。注意すべきは正しき発声。極力はっきりと教えられた言葉を唱えれば、印章石が強烈な光を放ち、周囲の空間を白の輝きで埋め尽くした。
「――――」
瞼を閉じていても透けて感じる程の強い光は、五秒程で徐々に弱まり、消えていった。
輝きが失せたのを感じ、【NAME】が恐る恐る目を開けると、眼前、印章石を駆動させる前は単なる森であった筈のそこは、ぽっかりと開けた空き地となっており、存在していた針葉の木々の代わりに、古びた白色の大石で構築された建造物群が、ひっそりと建っていた。
半ば朽ちかけた建造物群は、完全に同一のものではないものの、以前に霧眩森林で見たあの遺跡と良く似ている。
「どうやら、当たりのようだな」
後方、リゼラの言葉に肯定の頷きを返しつつ、【NAME】は空き地へと出ると、遺跡の傍へと歩みを進めた。
多少の用心をしつつ、【NAME】は遺跡を一通り見て回る。亜獣の気配は無く、調査は手早く進んだ。やはり、地上部の遺跡の構造は以前見た場衡機構とほぼ同じで、ならば侵入口も同様であると調べてみれば、その推測通り、中央に存在した円形台状の大型構造物の下部に、地下へと続く階段を塞ぐ大蓋が見つかった。
「またこの覆いか」
見下ろして、呆れたような声音でリゼラが呟く。
そういえば、森に存在した場衡機構でも、出入り口は似たような蓋で塞がれていた。これも場衡機構という芯形機構が共通して持つ構造の一つなのだろうか、と【NAME】は何気なく呟くが、
「いや、それは違うな」
意外な事に、リゼラからははっきりとした否定が返ってきた。
そう言うからには、彼には根拠があるのだろう。流れで訊ねると、少年は「簡単な話よ」とつまらなさ気に前置き、
「素材からして、地上にあるこの痛んだ建物とも、この下に存在するだろう地下のものとも異なるからだ。以前、刃を通したからこそ判る。恐らくは、この蓋は遺跡を隠していた忌み地、姿隠しの仕掛けと同様、あの翁が残したものであろうよ。だからこそ――苛ッ!」
リゼラの気合いの声が短く走り、鞘から跳ねた銀光が、違わず蓋のみを真っ二つに斬り断つ。長剣を回転させ、鞘に収める動きに合わせるように、蓋が分かたれ、落下していく様子は、見ていただけのこちらからしても壮観な光景だった。
「このように、容易く断ち切れる訳だ。……何を呆けている。行くぞ、【NAME】よ」
と、【NAME】が感心している間に、リゼラは蓋の向こう側に存在していた階段を早々に下り始めていた。【NAME】も慌ててその後ろを追う。
中へと入ると、むっと、絡みつくような濃い気配が外へと這い出してくる。様々な要素が混じり合い、密度を上げた、ただただ濃密な気配。それは以前場衡機構に入った時と同様のものだ。【NAME】は慌てて意識を集中し、己の身に防御を施す。見れば前方、先を行く形になっているリゼラも、その全身が淡い緑色に包まれていた。やはりオリオールやノエル達を連れてこなくて良かったと、そう考えながら【NAME】は先行く少年の後に続く。
目指すは、芯形機構の最深部。以前にも見た、あの象形だけが存在する殺風景な小広間だ。あの術士の老人がそこで何らかの印章術を行っていたならば、今度はその情報を正確に持ち帰る。その為の道具はイェアから預かっていた。老人が前回残した機甲具を可能な限り修理したものだ。それを使い、印章陣の姿を像として正しく写し取る事が出来れば、印章を専門として扱うイェアならば印章陣が持つ効果を解読する事が出来るかもしれない。
問題は、遺跡の最奥に何事も無く到着できるかどうか。
そして、最奥にて前回のような化け物が待ち受けていないかどうか。
これまでの経験からどちらも望みは薄いなと思いつつ、【NAME】は地下へと伸びていく階段を溜息混じりに降りていった。
・
体感にして大凡四半刻が過ぎた頃。階段は唐突に終わりを告げて、通路は平坦なものへと変化した。
正面へと伸びていく道は真っ直ぐで、分岐点は一切無い。縦横は三メートルあるかないか。周りを囲う壁や天井、床は滑らかな金属質で、両の壁には小さな光源が一定の距離を置いて配置されていた。
仄かな輝きが照らす通路を、【NAME】はただ黙々と道を歩き続ける。会話をする気はあまり起きなかった。何故なら、ナリア・バータで見つけた遺跡の内部と同様の奇妙で強い圧迫感は、階段を降り始めた時よりも強く、厚いものになっていたからだ。神形やその他諸々の加護を相応に受けている【NAME】だ。体調を崩す程の影響を受けることはなかったが、しかし精神に掛かる負担は確かにあり、それが無駄口を叩く余裕を失わせていた。
そのままどれ程前へと進んだだろうか。ようやく一本道が終わりを告げる。通路の終端。その先に存在していたのは、左右へ緩やかにカーブしながら伸びていく分かれ道だ。構造としては、恐らくドーナツ状の管型通路。規模は大きく、先程歩いてきた通路と比べれば十倍以上はある。直線通路から円形の管型通路への接続口は、管型通路の中程の壁にあった。管型通路へと身を移した【NAME】達は、湾曲する壁を滑り、通路の下部へと降りる。
「【NAME】。気づいているか」
と、そこへ背後からリゼラの声。一瞬そちらへ視線を移せば、彼の袖口から赤い紐のようなものがするりと身を宙へ泳がせる姿が見えた。リゼラの翆霊“九継”だ。【NAME】にはいまいちはっきりと感じ取れなかったが、どうやら前回の霧の森にあった場衡機構と同様、この遺跡の中でも命脈の力が強く残ったままになっているらしい。
宙を泳ぐ九継の姿が、身をくねらせる毎に一頭、一頭と増えていき、見る間にその姿を九つの頭持つ大炎蛇へと変化させた。九つ首の蛇は、本来の姿となった身体を解すようにぷるぷると頭を好き勝手な方に伸ばしてから、その向きを全て一方向へと定める。
九継と、そしてリゼラ。20の瞳が凝視するのは、管型通路の上部。天井付近にて不自然に走る稲光だ。最初は不定期に、しかし【NAME】が見上げる間に定期的に。高速で明滅し始めた稲光は、一拍の間を置いて大きな稲光の渦となり、そして次の瞬間には雷で出来た身を持つ化生となって、空中にて実体化する。
「……ッ!」
先刻のリゼラの問いは、この事か。
【NAME】が慌てて武器を構える間に、化生は生じた質量に従うようにして、通路の下方に居る【NAME】達目掛けて落下してくる!
【NAME】が深く息を吐いた。その背後では、リゼラが拍子抜けしたように小さく鼻を鳴らし、くるりと手にした剣を回す。
既に、周囲は静寂に満ちている。襲い掛かってきた雷の化生を悉く蹴散らした後だ。
「さて、【NAME】よ。ここから如何にする」
呼吸すら乱さず刃を鞘へと収めたリゼラが、こちらへ視線を向けることすらなく問うてくる。
(……どうする、か)
内心呟きながら、【NAME】はぐるりと辺りを見渡す。
今居る場所は巨大な管状通路の底部だ。通路は前後に伸び、それぞれ緩やかにカーブしている。前後両方の通路が同方向へと湾曲している事から考えるに、恐らくこの管状通路は環の形状になっているのだろうと推測出来たが、あくまで推測。実際どうかは歩いてみないと判らない。
視界を上へと回す。先刻は激しい稲光が走っていたため意識の外にあったが、改めて天井を見ると、丁度真上の位置に巨大な模様が描かれている事に気づいた。その模様は印章や象形といった、どちらかといえば文字に近い代物では無く、純粋な絵だ。真上に描かれていたのは赤の鳥。そのまま視線をズラしていくと、一定間隔ごとに、天井に色の異なる絵が描かれている事に気づく。通路自体は殆ど代わり映えしない中、天井の絵だけは色が違うのは有り難い要素だった。どれだけ移動したかの目印として使えそうだ。
そして直ぐ傍、道が曲がっていく側に存在する壁を内壁とするなら、逆に存在する外壁の側。その中程には小さな穴が見える。遺跡の外へと続く通路口だが、場衡機構の最奥、中枢区画を目指している身としては、そちらへ移動するという選択肢はない、
一通り見回し終えて、【NAME】は改めて考える。
選べる選択肢は、大して存在しない。思いついて二つだ。
ゆるりとカーブしていく通路の、どちらかに進んでいくかという単純な二択である。
(取り敢えず、通路が環状であると仮定して……)
【NAME】は身体を、先刻定めた内壁側へと向ける。
管状通路の下部にて、【NAME】はふと足を止め、何気なく辺りの様子を確認する。
通路はその幅からして10メートル以上は悠々ある程の巨大なものだ。伸びる道筋も延々と長く、しかも通路内の構造は殆ど代わり映えがない為、どれだけ歩いたのか一見して把握しづらい。
数少ない目印となるのは、天井部に描かれた大きな模様だ。最初は遠く小さく見えるだけであった紅の魚の絵も、今は真上に近い位置にあり、その巨大な姿を輪郭までくっきりと見ることが出来た。
と、見上げていた模様の周囲に、ぴしりと、青白く稲光が走るのを見た。
「…………」
厭な予感。
それを明確に自覚する前に、稲光は急速に発生頻度を増していく。そして一際大きな稲光が走り、天井付近で大きな渦を造ったと同時、光の渦は雷の身を持つ化生となって空中にて実体化。そのまま、生じた質量に従うように、通路の下方にて身構える【NAME】達目掛けて落下してくる!
「さて、【NAME】よ。ここから如何にする」
襲い掛かってきた雷の化生を悉く蹴散らした後。呼吸すら乱さず刃を鞘へと収めたリゼラが、こちらへ視線を向けることすらなく問うてくる。
(……どうする、か)
内心呟きながら、【NAME】はぐるりと辺りを見渡す。
延々と続く管状の道――と半ば思い込んだままであった【NAME】は、遠く視線の向こう、カーブしていく道の端にて、行く手を阻むように聳える巨大な壁を見つけた。
どうやら、管状通路の端に辿り着いたらしい。取り敢えず【NAME】は行き止まりの方へと歩み寄ってみる。
眼前の壁は管状通路を垂直に断ち割るような形で真っ直ぐ聳えており、色々と調べてみるも、正面の壁の向こう側へと抜けられる扉のようなものは一切見当たらない。純粋に、完膚無きまでに、通路はここで終端となっているようだった。
但し、側面の壁――曲線を描く通路の内周側となる壁の一箇所が、他の場所とは異なる構造になっていた。
幾重にも重なった壁が開かれて、奥へと続く大きな口を開けている。どうやら可動式の隔壁が開放状態となっているようだ。管状通路内と違い照明となるべきものは殆どないらしく、開いた大穴の向こうは良く見通せない。だが、その先にはこれまでの管状通路とは別種の空間が広がっていて、そして場衡機構の深部――中枢区画へと繋がっている事も直ぐに理解出来た。
何故ならば、
「……気配の圧が格段に濃いな。森の遺跡の奥、あの紋様だらけの部屋へと続く階段で味わったものと同じ類のものだ」
背後、片眉を寄せて穴の奥に広がる薄闇を睨むように見たリゼラの言葉は、【NAME】が感じたものをそのまま表現したものだった。
開かれた隔壁の向こう側から漂ってくる、様々な気配が混じり合った独特で強烈な気配は、霧眩森林に存在した場衡機構の最奥から漂ってきた気配と全く同種の代物で、規模としてはむしろ前回よりも強い程だ。ならば、この穴の先に、目指す遺跡の中枢区画――幾多の象形が刻み込まれた小部屋が存在していると考えるのは間違ってはいない筈である。
「何にせよ、だ」
呟き、前へと一歩進むリゼラの手は、浅く柄頭に添えられて、いつでも刃を鞘から抜き放てる姿勢に変化していた。
「喜べ、【NAME】。ようやく終わりが見えた。後はこの穴をくぐり、気配の流れを手繰るのみだ」
少年はそのまま【NAME】の隣へと並ぶと、表情は普段の不機嫌そうな顔のまま、視線だけを一瞬こちらに向ける。その両眼には、強い戦意が宿っていた。
「……無論、これ程の濃密な気配が渦巻く場所へと赴くのだ。前回と同様かそれ以上の歪が、形を得て我等の前に現れる可能性は高い。奥へと進むのならば、相応に、身と心を構えてからとせよ」
――円輪の轡が封ずる形――
開かれた隔壁を潜り、遺跡を構築していた管状環型通路の中心部に到達した【NAME】は、そこに存在していた昇降機を操作して、下方へと向かう。
それより先は、事前にイェアから聞いていた話の通り、霧の森の遺跡で見たものと似たような構造となっていた。昇降機で移動可能であった範囲の最も下の位置まで降りると、底部には更なる地下へと続く螺旋階段があり、渦を巻くように伸びていく長い長い階段を降り終えれば、無数の象形が壁や床、天井に刻まれている以外何も無い、殺風景な広間に辿り着く。この部屋こそが、【NAME】が目指していた場所。場衡機構の中枢区画である。
後は、部屋の中を調べ上げて、場衡機構を隠匿する結界を敷いていた老人の痕跡を探し出すだけ、なのだが。
――そう簡単にはいかないか。
内心呟きつつ、【NAME】は己の得物に手を伸ばす。意識は他方、広間のあちこちで生じ始めた異変に向けられている。
広間に立ち込めていた気配は、森の遺跡の深部で味わったものよりも更に濃い。【NAME】は自分達が広間に足を踏み入れたと同時、揺れた大気が連鎖的な反応を産んで、雷気を帯びた陰性質の概念が急速に膨張し始めるのを感じていた。それは無数の稲妻という現象となって現実に姿を現す。ぱちぱちと弾けるような音と共に、地上では湖の岸辺、地下では円環通路の天井部などで既に見慣れた、禍々しい気配を帯びた光の亀裂が至るところで走っていく。
そして【NAME】が用心深く武器を構える間に、状況は更に変化する。最初は無秩序に発生していた稲光は次第に纏まりを産み、それは中空の三点にて渦を巻いて飽和し、雷気は空間に満ちる色濃い生命の力を陰の気質に絡め取る形で実体を取った。
現れた姿は、今度は霧の竜ではなく、雷の竜だった。前回は霧で、今回は雷。理由は何となくは判る。遺跡の上に存在している地形が、場衡機構による土地改変によって生み出されたものであるならば、遺跡内にその概念が色濃く残っていてもおかしくはない。また、性質問わず強度の概念飽和によって生じた存在は、現世界上で同等格の存在概念を持つ姿に倣う場合が多いと聞く。その理屈を信じるならば、目の前にて生じた化生は竜種に相当するほどの概念規模を持つという事なのだろう。何故前回訪れた遺跡と同様の三匹の竜が生じたのかまでは判らないが、判ったところでどうなるものでもないと、【NAME】は半ば脱線しかけた思考をこれから始まる戦いに向けて切り替える。
と、そこへ鋭い声が掛かる。
「【NAME】――気づいているか」
そう短く強い声を発したのはリゼラだ。
こんな派手な現れ方をした竜に気づかない筈も無いだろう。【NAME】が少年を訝しげに見ると、少年の視線は一点、雷の竜にではなく、広間の中央へと向けられていた。
釣られてそちらを見れば、彼が何に注意を促していたのかは直ぐに判った。
広間中央付近の床には、中心点から円状に広がるようにして巨大な印章の陣が描かれていたのだ。それも、【NAME】が以前見たような欠損したものではなく、完全な姿のものが。
加えて、その陣の中央には、これまた見覚えのある品が置かれているのも確認できた。円盤の端から六つの柱が伸びた機甲具。どうやら老いた術士は霧の遺跡と同様にこの場所でも何らかの術式を行おうとし、そしていつか訪れるかもしれない誰かに対して、機甲具を使った伝言を残したらしい。以前手に入れたものとは違い、遠目に見た限りでは破損している様子もない。あれならば、きっと老人が残そうとした言葉を全て正しく聞く事が出来る筈だ。
しかし、機甲具を回収しようと近づきかけた【NAME】を遮るようにして、空中に生じた三匹の竜が身体を動かす。雷で出来た身体からは時折稲光が竜の形から漏れ出すように走り、文字通りの光の速さで周囲の床面を打った。
古代、“芯なる時代”に造り上げられたであろう部屋だ。裂けるような音が鳴り響くだけで、壁や床には傷どころか焦げ痕すら残しはしないが、一つの稲光が広間の中央付近に落下し、それによって衝撃波でも生じたのか、近くに置かれていた機甲具が跳ねるように吹き飛び、転がっていくのを見て、悠長にしている暇はないと判断する。機甲具もそうだが、広間中央の床に描かれた印章陣にいつ被害が及ぶかも判らない。遠目に見た限り、余剰の稲光が直撃した程度では消えてはいないようだが、この間のような陰性概念を凝縮したような攻撃を受ければ、人の手によって描かれたに過ぎない印章陣は容易く消滅してしまうだろう。
「竜を疾く討ち滅ぼし、アレを無事に手に入れる。――行くぞ!」
返事をする間も惜しい。【NAME】は稲光を纏って泳ぐ三匹の雷竜目掛けて、攻撃を始める!
竜が口蓋を開く。黄金色の喉奥から迸るのは雷の奔流だった。
強烈な一閃は横薙ぎに走り、【NAME】は身を低くして直撃を避ける。頭上を横切る凄まじい雷気。全身の産毛が逆立つような感触と熱の圧力が一瞬で通り過ぎる。
気づけば、全身が淡い輝きを放っているのが判った。神形による守りが生じているのか、それとも別の力が反応した結果なのか。しかし自分の状態を正確に把握する時間も惜しい。【NAME】は身を屈めた姿勢で身体の発条を溜め込むと、地面を蹴り、一気に竜との距離を詰める。
雷身の竜は、ナリア・バータの遺跡で遭遇した霧身の竜よりも手強い相手であった。何より、その身体が雷で出来ているのが問題だ。攻撃を仕掛けるために近付くだけでも危ない。物理攻撃の影響が薄いのは霧の竜も同様であったが、今回の相手は攻撃する事自体が危険だ。身を構成する溢れんばかりの雷気は、触れるだけで鎧などの防具を素通りし、こちらの身体を貫き、焼いてくるのだ。
離れすぎては攻撃が届かず、しかし近付きすぎれば雷竜が無秩序に放つ稲光や、攻撃時に散った雷の飛沫に飲まれる可能性が生じる。
駆け出し、竜との距離を縮めた【NAME】であったが、普段よりも数歩、距離を取った位置から放った技法は、身を捩じるようにして後方へと下がった竜に届かずに空を切る。
舌打ちと共にもう一撃、と踏み込みかけたところで、横から膨れ上がる気配。
「――ッアアアァ!」
本来の竜種とは違う、甲高い独特の咆哮が響く。向けられた害意を感じて攻撃を諦め、強引に後ろへと身を飛ばした。すると眼前を、左手方向から飛来した大爪が薙ぐようにしてすれ違っていく。
竜が三匹居る事も厄介だった。一匹だけに意識を集中させる事が出来ず、瞬時の判断が難しい。安全重視の立ち回りを取るのが最も重要ではあったが、だからこそ追い込みが足りず、決定打に欠ける展開となっていた。
二匹目の竜は続けて【NAME】目掛けて体当たりを仕掛けようとするが、その身体は突然生じた爆発によって大きく離されていく。
リゼラの翆霊、九継が放った炎弾だ。九継は【NAME】の傍にふわりと浮かび、要所で炎弾を吐き出すことで戦闘をサポートしてくれていた。
一瞬、背後に視線を向ける。そこでは残る一匹の竜と一対一で戦いを繰り広げるリゼラの姿があった。
九継はリゼラの翆霊である。本来ならば主であるリゼラと共に戦う事で九継は最高の性能を発揮出来るのであろうが、九継はリゼラの元へと移動することなく、【NAME】の近くに控え、戦闘時にどうしても生じる隙を補うような動きをしてくれている。恐らくはリゼラがこちらに気を遣い、翆霊に対してそういう命令を下しているのだろう。
素直に感謝すべきか、甘く見るなと憤るべきか。
迷うところではあるが、然程も時間が経過していない雷竜達との戦いの間、既に幾度も炎蛇の助けを受けた事を考えれば、彼の判断は正しかったのだろうと思う他無い。
と、視界の隅に映っていたリゼラの動きが変わる。これまでは防御一辺倒だったところが、一気に攻めの姿勢へと変わったのだ。
突撃してくる竜を回り込むことで回避したリゼラは、身体を回転させながら抜剣。独楽のような動きを取りつつ更に身体の軸を捻り、最上段から竜の身体を長剣で叩く。
生じたのは独特な破裂音。
刃が竜に触れた瞬間、翠色の爆発が生じ、竜の巨体が凄まじい勢いで吹き飛ばされた。身体の半分ほどを爆発で失った竜は、爆風に流されるように宙を泳ぎ、他の二匹の竜が留まる場所で停止する。
大幅な欠損により三匹目の竜の動きは鈍り、しかし他の二匹がその竜をかばうように前へと出てくる。所詮雷で出来た架空の身だというのに、ああした仲間を守るような動き、連携を取るところも、竜達が手強い理由だった。
対して、リゼラはえぐり取られた竜の身体から飛び散る雷撃を避けるために一度大きく距離を取った後、遠のく竜の動きに注視しながら【NAME】の傍へと歩いてくる。相対していた竜を圧倒した割りに、その表情は冴えない。仏頂面のまま【NAME】の横へと並ぶと、彼は忌々しげに息を吐き、
「我が内にて溜めに溜めた翆なる脈を刃に通し、打ち込んだ末があの程度よ。やはり我の剣と彼奴等は相性が悪い。“古の月”を以てすれば悉く滅する事も可能やもしれぬが……そもそもが我が手を下すより、【NAME】。お前に任せるのがより誂え向きであろうな」
――いや、何かこちらが向いているような事があったか。
彼の発言にいまいち納得がいかず、【NAME】が怪訝と見返すと、
「少なくとも我よりは向いておろうが。何より、霧の森の遺跡で竜の止めを担ったのはお前だぞ」
呆れ混じりに言われて、【NAME】としても困る。あれはリゼラよりも自分の距離が竜に近かったからだ離れていたからではないか。
「ならば言い方を変えるか。お前、あの三匹の動きを全く封じ、我が一撃にて崩滅出来るよう御膳立てをする事が出来るか?」
「…………」
黙ると、リゼラは「そういう事だ」と言い残して前へと出る。
「適当に追い込んだ挙げ句、大技を撒き散らされて前回の二の舞を演じる訳にもいかぬ。我と九継で、今より奴らの身動きを……そうだな。十数える間に止めてみせよう。【NAME】、お前はその間に、あの三竜を纏めて滅する技を整えよ。反する合間も与えず、一息で潰す。機会は一度と思え」
――そんな短い時間で、あの厄介な竜達を抑える事が出来るのか?
【NAME】が言葉の真偽を確かめる前に、リゼラは一刀を肩に担ぎ、もう一刀を腰から抜き放つと、前方にて浮かぶ三匹の竜目掛けて駆け出していく。
「九継、解けよ!」
リゼラの叫びに反応し、九頭の蛇がゆらりと身を立てる。三竜目掛けていつもの炎弾を放つのかと九継を見た【NAME】は、九つの頭を持った大蛇であったそれが、九つの身体を持つ大蛇へと変化した事に目を見張る。以前、オリオールと一緒に霧の森の遺跡に降りた際、一人戻るという彼に、九継から分離した一匹が付いていった事があった。今回の変化はその延長だ。炎蛇の九又に分かれていた部分から全て切り離され、九匹の大蛇となった九継は、三匹の竜を取り囲むように位置取り、一斉に炎弾を放ち始める。
回避する間を完全に潰した上で、九方向からの炎弾の嵐。強烈な陰性概念の塊であり、雷で姿を維持する存在である化生に対して、九継の攻撃は損傷を与えるには幾分弱い。特に本来なら九頭であるところを分割している今では、吐き出す炎の量も九分された状態だ。
しかし、動きを封じ、位置を固めるという意味では、一箇所に集中して炎弾を放つよりも囲うようにあらゆる角度から炎弾を叩き込む方が遥かに有効だ。それを示すように、三匹の竜は炎弾が爆発する際の衝撃に押されて空中の一点で抑え込まれていった。
勿論、炎の弾は常に位置を変えて九つの角度から放たれているが、空中に浮かぶ竜の逃げ場所を完璧に塞ぐには流石に足りない。生じた隙間から、三匹の竜はどうにか炎弾の包囲網の外へと逃れようとする。
だが、それを阻止しようと動く、もう一つの力があった。リゼラだ。
炎の華と雷の飛沫。轟音と衝撃波が連なり弾ける空間を、小柄な少年の影が飛ぶように走る。例えば、連続で爆発した炎弾の影から、身体をくねらせて下方へと逃げようとする雷竜。リゼラはその前へと一瞬で身を移すと、淡い翠色の光を放つ右の長剣を振るい、鼻頭を叩き潰して動きを制する。かと思えば、少年の姿は次の瞬間には天井に張り付いており、翻した左の腕、握られたもう一本の剣が、上へと浮かびかけていた別の雷竜を薙ぎ、炎弾の嵐の中に叩き落とす。
時には九継の炎弾を自らの近くに落とし、生じた爆風すら利用して変幻自在に立ち回る様は、人の業の域を超えているようにも思えた。
「――【NAME】、何を呆けているっ!」
しかも、それだけの動きをしている合間に、一瞬であれどもこちらの様子を窺う余裕があるのが恐ろしい。【NAME】は慌てて技法の駆動準備に入る。
過ぎた時間は既に五つ程。ならば残る時間は指示に従うならば半分だ。五節系は厳しいが四節規模の滅質技法ならば余裕はある。身構え、見据え、力を溜める。視線の先、炎弾と剣線の嵐に包まれた三匹の竜は、もうその身体を伸ばすことすら出来ない程に押し込められている。リゼラと九継の攻撃がそこで留まる事はなく、更に五秒が過ぎる頃には、竜達はさながら一つの球体であるかのような状態へと追いやられ、最後、仕上げとばかりに放たれた九発の炎弾と二対四線計八斬の刃が閃くと同時、
「【NAME】!」
再度の叫びは、止めを促す合図だ。
躊躇う理由は何もない。炎弾の嵐が止み、少年の姿が竜の傍から消える。抑えが消え失せ、自由を取り戻した竜達が動き出すその前に。
十分に練り上げ、高めた大技法を、【NAME】は一息で撃ち放った。
・
広間の中で高まっていた陰性概念が、満ちていた雷気と共に急速に薄れていく。しかし、それだけだ。雷の竜を造り上げていた分の陰性概念が【NAME】の一撃によって崩滅し失われただけで、それ以外の、無秩序であらゆる要素を内包した気配は未だ広間に強く根付いたままだった。
だが、雷の竜を全て排除したことで、当面の危機は去ったのも確かだ。加えて、今回は霧の森の遺跡とは違い、部屋の中央にて床に刻まれた象形をなぞり拡張するように描かれた印章陣は殆ど欠損無く、残されていた機甲具についても多少衝撃を与えてしまった事もあったが少なくとも外見上は無傷のままで、件の竜を撃破する事が出来たのだ。
床に転がっていた機甲具を拾い上げて、リゼラが戻ってくる。と、彼の視線が【NAME】の手元で止まった。
「【NAME】よ。それは以前に手に入れたものか?」
問いに、【NAME】は頷く。【NAME】の手の中にあったのは、リゼラが回収してきたものとは別の、霧の森の遺跡で手に入れた機甲具だ。
円盤外縁から伸びた六本の柱のうちの幾つかが故障したものではあったが、今回の目的を果たすためならば十分とイェア・ガナッシュに持たされていたのだ。
【NAME】は機甲具を構えると、教わった操作を行う。中心の柱を捻って展開させて操作盤を露出。それに苦労して指を這わせる。
定型句による宣言を使えば声だけで操作出来るとの話だったが、それが判らない【NAME】は機甲部分を使って操作するしかなかった。
機甲具が記録状態になった事を確認すると、【NAME】は機甲具の円盤部分を下に向けて、床に描かれた印章陣を端からゆっくりと映していく。手っ取り早く全景を取って終わりにしたかったが、それをするには【NAME】の身長は三倍ほど必要になっただろう。
リゼラは既に常態となっている不機嫌そうな顔のまま、【NAME】の作業を暫し眺めて、
「成る程な。絡繰りでもって印章陣を像として残せば、この地に立ち入る事が出来なかったレェアの妹も同様の光景を見る事が出来、印章陣の内容を直に読む事が可能となるか」
そういう事、と【NAME】は呟いて、機甲具の記録状態を解除する。
破損した状態の機甲具は記録時間が大幅に減少している上、音声の記録がほぼ不可能となっているらしいが、こうして印章陣を映すだけならば大した時間が掛かるわけでもなく問題にはならない。
展開していた操作盤を格納すると、【NAME】は手にしていた機甲具とリゼラから渡された機甲具、二つを背嚢の中に仕舞い込む。
後は、イェアの元にこれらを持ち帰り、皆で検分してみるだけだ。
「問題は、あの絡繰りに残された虚ろの姿が、我等に何を語るかどうか、か」
リゼラの呟きに、【NAME】は苦笑と共に頷く。
印章陣、それもこれだけ大規模かつ高等な印章陣となると、その機能を正確に読み解くのはかなり難しい作業であるらしい。
ならば、この地に訪れ、術を施した老人自身が残した言葉の方に期待を掛けるのも当然と言えるだろう。
「では、もうここには用も無い。早々に去るぞ、【NAME】よ。お前にとっては気にもならぬものなのかも知れぬが、このあらゆる力が混沌と在る地は、我であっても些か堪える」
【NAME】にしても異論は無い。これ以上この強い気配に満ちた場所に居続けるのは【NAME】にとっても疲労が溜まる。さっさと脱出するに越したことは無い。
短く了解の言葉を返して、【NAME】は言葉通り足早く先を行く小さな影の後に続いた。
真なる楽園 過去の決意が目指すもの
──過去の決意が目指すもの──
薄暗い部屋の中で、一人。背を浅く丸め、力無く立ち尽くす老人の姿があった。
白色の髪と、白色の髭。長く伸びた二つに艶はなく、砂漠のように渇き、くすんでいる。僅かに落ちた肩、曲げられた首筋からは身体に蓄積された疲労の気配が濃く滲み出ており、顔色は血の気を失って土気色に近い。
年経て枯れた老木を思わせる姿の中で、唯一、両眼だけが爛々と強い生気を帯びて輝いていたが、しかし他の部分との不均衡さが、老人が纏う不気味な雰囲気を際立たせる形となっていた。
そんな彼の正面には、円盤の縁から六本の柱が突き出た立体物があった。その場所の情景と音を、小さく短く切り取り、記憶する機甲具だ。そして機甲具の傍には、無残に砕けた球体が一つ、水晶を思わせる素材を四方に散らして転がっている。
既に、この場所で老人が成そうとした事は終わっていた。
結果は判っていた事ではあったがやはり届かず、しかし最後の足がかり、逆転の一手とも言うべきものを掴む事も出来た。後は、それに己の全てを賭して、望むべき未来を引き寄せるだけだ。
それが、どれだけ確率の低い未来であろうとも。
だが、その前にやらねばならない事がある。必要な事であるかどうかは判らない。意味があるのかどうかも怪しい。全く不要の結末となれば、それが最も幸いであるのは確かだろう。
しかし、そんな結末が訪れないであろう事は、老人自身が一番良く判っていた。
だからこそ、出来うる限りの希望を残しておく。今から行う作業は、その為の種を蒔き、芽となる事を期待するものだった。
「――この地、この場に、ワシの意志に触れる知恵と力を備えし貴方が訪れた幸運を、ワシは深く感謝をしよう。どうか、この老い耄れめが残す言葉を、最後まで聞いていただきたい」
枯れた喉を震わせて、老人はどうにか言葉を紡ぐ。僅かな時間。恐らくは己の手から離れた未来を、身も知らぬ誰かに託すべく。
「ワシの名は、マイオトール。過去にはフォータニカの栄えある守護機士の末席に名を連ねた事もある、機甲師にして魔術師、隠者にして死霊操士じゃ――」
・
「これはまた、随分と様子が変わっているね……」
「そう、ですわね」
再生された映像を前に、オリオールとイェアが、若干声を詰まらせながら呟き合う。
エルツァン島の端、東と西の海岸線の狭間にある、アラセマ常駐軍の陣地内。エルツァン島に派遣された軍部隊の長を務める学士、イェア・ガナッシュが居所とする天幕では、【NAME】がカリッサ灼雷領域にて発見した場衡機構の最奥で手に入れた機甲具の駆動作業が行われていた。
天幕の中に居るのは、以前、ナリア・バータ霧眩森林に存在した遺跡探索後、見解を聞くためにイェアの元を訪れた時と同じ面子だ。天幕の主であるイェア。遺跡について興味津々であったオリオール。旅に同行していたリゼラ。そしてイェアの身の回りの世話も受け持つノエル。
と、【NAME】が最後に目を向けた人物――中に居る者達に葡萄酒注いだ杯を配っていたノエルが、長机の傍に立っていた【NAME】の前に立った。差し出された杯を受け取って、軽く目礼だけをすると、ノエルはこくりと頷いて、そのまま【NAME】の隣に収まる。既に視線は正面、機甲具が映し出す光景へと向けられていた。
【NAME】も釣られるようにそちらを見る。機甲具より漏れ出した光によって構築された淡い色の幕。そこに表示されているのは以前にも一度見た老術士の姿である。しかし、機甲具の状態によるものなのか、単純に記録映像の時間差によって生じたものであるのか。彼の様相はオリオール達の言うように、以前の映像で見た時と比べて大きく変化していた。
まず印象に残るのが、全身から漂う極度の疲労、衰弱感だ。まるで死地に片足を踏み入れているかのような姿で、映る表情は死相すら浮かんでいるように見える。長衣から覗いた首や四肢は骨や筋が浮かんで見えるほどに細く、再現された肌の色相は土気色にも近い。
「でも、考えてみればこうなるのも当然かも知れませんわね。幾ら優れた術士とはいえ、これ程のお年を召した方が、恐らくはたった一人でエルツァン島へと渡り、異質極まる土地を旅して、更には芯形機構の奥底にまで至る。ただの人の身であれば異常を来す程の概念の歪みの中、地図なんてある筈もなく、食料すら満足に確保できていたのかどうか」
考えてみれば、確かにそうだ。エルツァンへの初上陸を果たしたとされるあの有名な探検家カール・シュミット達でさえ、集団でエルツァンに辿り着きながら碌な調査を行う事も出来ず、放浪の末にほぼ全滅という結果で幕を引いたというのに。
対して、マイオトールと名乗った老人はエルツァン各地を恐らくは単独で探索し、そこに存在した複数の場衡機構を見事に探し当て、更には遺跡の最深部にて何らかの術――それも象形を絡めて取り込もうという大術式を行おうとしていたのだ。
彼が歩んだ旅路の過酷さは、【NAME】達がこれまでこなしてきたエルツァン行以上のものであったのは想像に難くない。ならばあれ程までに消耗、衰弱するのも無理からぬ事だと言えるだろう。
ふーむ、とオリオールが鼻から大きく息を吐き、
「ただ、そうなるといよいよもって、ご老人が無理を押して一体何をしていたのかが気になるね」
「それは当然ではあるが、そもそもだ」
と、天幕の端で両腕を組んだままだったリゼラが口を開く。
「この術士、動きから察するに、ここに己の望みに適うものがあるのだと把握して行動しているとしか思えぬ。しかし貴様等“迷の民”は、この島についての情報を今現在まで殆ど持ち得ていなかったのではなかったか?」
細く鋭い視線を向けられて驚いたのか、イェアがびくんと肩を揺らした後、口元に手をやって考え込む。
「その筈、ではあるのですけれども……。といいますかこのお爺さん、さっきフォータニカって仰ってましたよね?」
「フォータニカといえば、大陸の中央から東端にまで至ろうかという国土を持つ、東大陸の一大国家だ。という事はやはり、マイオトール氏は東大陸からフローリアにやってきた、という事になるね」
これについては、以前の推測を裏付けする結果といえた。
しかし、だとすると余計に理解が難しくなる。【NAME】にも判る話だ。何故ならば、
「おかしな話ですわね。フローリア諸島の詳細部――中継地として開放されていたランドリート島以外については、東大陸側には殆ど情報は伝わっていない筈なんです。ですので、マイオトールさんがフローリア諸島、特にエルツァン島についてわたくし達以上の情報を持っている可能性は、まず無いと思うのですけれど。同じ東大陸出身者であり、常駐軍の内部に喰い込み、四大遺跡の鬼を次々と従えていたあの“彼”ですら、エルツァンについての情報は殆ど持っていなかったと思います。何せ、島の探索を受け持っていた、つまりこの島について一番詳しいであろう常駐軍の方でも、エルツァン島内部の様子は碌に確認出来ていませんでしたから」
今エルツァン島調査の指揮を執っているイェアは、フローリアに駐屯するアラセマ常駐軍内の中でも相応の地位にある立場だ。その彼女が知らない事ということは、軍では本当にエルツァンについての情報は殆ど持っていなかったという事になる。そしてフローリア調査を率先して行っていた彼等が把握していないという事は、他の誰もがそれ以上の事を知らないという事にも繋がる。
「となると、考えられるのはマイオトール氏はあくまで推論による情報の組み立てによって、エルツァン島に彼が目的とする何かが存在すると当たりをつけていたか、もしくは――」
思案顔で唸るイェアに、【NAME】の脇に控えていたノエルが小さく手を挙げた。
「わたし達とは全く別口の情報源から、エルツァン島についての情報を得ていたのではないかと、わたしは考えますが」
「んー、まぁ、わたくしもその辺かなーとは思うのですけれども……」
ノエルの言葉に、イェアはこくりと頷きながらも、浮かべた表情には怪訝の色がある。
「でも、どっちにせよしっくり来ないというか、行き当たりばったりな話ですわね。推論にしても、別の角度から情報を得ていたのだとしても、それを信じて動くのは、少しどころか凄く無茶で無謀な行為としか言いようがないですし」
イェアは、未だ機甲具により映し出されたままの老人の映像を指差す。今、映像は再現を途中で停止させた状態にある。微動だにしない老人の姿を前にして、イェアは感心とも呆れとも取れる吐息をつき、
「わたくし達姉妹が軍の要請に従ってこちらに来た時も、えらく無茶な選択をしたものだと思っていたものですけれども、このお爺さんには負けますわ。ランドリート島以外への渡島がアラセマ出身者以外の方々に開放されたのは極最近の話ですが、マイオトールさんが残されていた印章石の状態を見る限り、それ程直近で渡ってこられたようには思えませんし。恐らくは開放以前に密航でフローリアへとやってきて、そのままずっと隠れて行動されていたのでしょう。何の組織の手助けも受けずに、単独で」
「それ程に、無理を通してやってきたのなら」
ノエルが考え考え、途切れがちに言葉を紡ぐ。顔つきは常の無表情ながら、僅かに寄った眉根が彼女の思案の深さを伝えてくれる。
「この方は、己の身を顧みぬくらい大事な何かを、ここで成そうとしていたのでしょうか? 例えば、“先生”やリゼラさん。それに、軍団長や、あのイルギジド・マイゼルのように」
軍装の少女の言葉に、場に居る者達は皆暫く沈黙する。
「……彼等と一纏めにして語っていいかは判らないけれども、少なくとも自分を含めた様々なモノを賭けて、何かをしていたのは確かだろうね」
「というか、あの人達と同じレベルの事をやろうとしていたと考えると、色々と頭が痛くなりますわね……。誰も彼も、碌な事してないじゃありませんの」
確かにそうだ。げんなりと呻くイェアに、心底同意して【NAME】は頷く。
対し、名をあげられたリゼラは、軽く右の耳を抑えるような仕草をしながらイェアや【NAME】を睨みつけるが、しかし一つ深く吐息をつく事で内心の怒気を抜き、
「我等があの時成そうとした翆脈顕現は至極貴い行為であるのだが、貴様達“迷の民”の理解及ばぬ事であるのも、既にアレとの遣り取りで学んでいる。――兎にも角にも、だ」
杜人と呼ばれる少年は、嫌気を隠す事無く言葉を続ける。
「こうして話していても埒があかん。さっさと絡繰りの像を先へと進めよ。そも、この翁の言葉を聞けば解決する事が多くあろうが」
「それもそうですわね。じゃあ、再現を続けましょう。残りの時間は……ええと20、いえ25秒くらいかしら」
「……短いねぇ」
オリオールが肩を竦めて苦笑いで呟く。彼がそんな態度を見せる理由は理解出来る。最初の名乗りの部分だけでも既に10秒近くを消費している事を考えれば、続く言葉の内容次第では、もしかすると大して情報を得られないのではないかという疑念は当然だ。
同様の予想を立てているのか、地面に置かれた機甲具の傍にしゃがみ込んだイェアの表情もあまり冴えない。
「正直なところ、これだけの残り時間で一体何を伝えられるのか、色々と不安になってきましたけれども。……取り敢えず、最後まで聞いてみましょうか」
イェアが展開された状態のままになっていた機甲具の操作盤を弄ると、幕に映り込んだ老人の像が動き始め、機甲具からはくぐもった声が再生される。
『これまで、ワシは幾度も幾度も失敗を繰り返してきた。最初の過ちは……あの鬼が眠る遺跡じゃな。ワシの過信と迂闊により得た結末に容赦はなく、長く存在した猶予も大きく削り取られた。だが、失敗を経た故に得る事が出来た知識、得る事が出来た方法で以て、別の道を辿る事が出来たのは僥倖とも言えるだろう』
ご、と老人が咳き込む。大きく肩が揺れて、掠れるような耳障りな呼吸音が暫く響く。
『新たな道はより苦難の道でもあった。この島にて所生みの遺跡が多く存在する事を知ることが出来たが、しかし一度の失敗にて地の在り方は大きく揺れて、使い物にはならなくなる。幾ら八宝があるとはいえ、命の理に触れる象形に手を伸ばすのは容易い事ではなかった』
「……八宝? ああ、この後ろに浮かんでいる――」
「オリオールさん、静かに」
イェアの鋭い声に、オリオールは肩を竦めて口を閉じる。そうする間にも、マイオトールは苦しげな様子のまま語りを続けていた。
『だが、今。ここで八宝が一を犠牲にする事で、解を得た。ワシは残る最後の所生みの地となる月光の丘、太陽と月が瞬く交差する丘陵にて、その解に持ちうる全てを注ぐ。故に、どうか。この記憶を見ている貴方に願う事がある。どうか、ワシの望みがどのような結末を辿ったのか、それを――』
そこで、映像と音声が唐突に途切れてしまった。
「…………」
皆、訝しげに顔を見合わせる。
――まさか機甲具の故障だろうか?
【NAME】達が視線をイェアに集中させるが、彼女も他の者達と同じく怪訝な表情を浮かべて首を捻っており、
「んー? ちょっと、もう一度最初から流してみましょうか」
イェアがごそごそと機甲具の操作盤を触ると、先刻の映像がもう一度始めから再現される。しかし、終わりは同じだ。マイオトールが言う望みとやらが語られる前に、映像と音声はぷっつりと途切れてしまう。消えていく光の幕を前にして、イェアが深々と溜息をつく音が聞こえた。
「どうやら、時間切れのようですわね。これが記録できる時間の限界だったみたい。……確かに、改めて見てみると最初に見積もった分くらいの尺はちゃんとありますわね、これ」
言われてみれば、名乗りの部分から20から30秒程で終わっているようには思えた。
だが、そうなると記録されている話が至極半端なところで途切れているのは何故なのか。
「率直に考えると、マイオトールさんは記録時間を把握せずに話を続けていた為、話の途中でぶつ切りになった、という事でしょうか?」
「…………」
ノエルの素朴な調子の言葉に、場に居る全員が何とも言えぬ沈黙を返す。
まさか自分で用意した機甲具の記録時間を把握していなかったなど有り得ないだろう、と一瞬思うが、あの老人の憔悴ぶりを思い返すと、そうした些細な過ちをしてしまってもおかしくはないという気もしてくる。
加えて、
「あと、話していた内容がまたなんとも判りづらいというか、聞く人に伝える気がないというか……」
「……まぁ、マイオトール氏もかなり切羽詰まっていたようだし、その辺りも含めて仕方無いんじゃないかなぁ……」
などとイェアとオリオールが微妙な顔つきで言い合う中、一人リゼラだけは既に平常の表情へと戻っていた。彼は浅い吐息を間に挟むと、
「何を惑っている。既に必要な情報は得られただろう。聞けばあの翁は――月光の丘であったか、そこで最後の術を施すつもりだというではないか。後はそこへ我等が向かえば、翁が成そうとした事の結果が判る。失敗であればこれ以上我等が追う必要はなくなり、成功であればそこに何らかの成果がある。ならば我等は行くだけで良い。それだけの話であろうが?」
――確かに、それはそうなのだが。
相変わらず思い切りの良い決断をするリゼラに、【NAME】は困り顔を向ける。これが彼だけの旅であるのならば、他人事として無責任に応援するなり何なり出来るのだが、自分も恐らく同行する流れになるのだろう事を考えると、そういう訳にも行かない。
結局、老人が何をするつもりだったのか判らないままだ。彼が何かをした結果が成功失敗問わず存在している場所へと赴くのは、色々と度胸がいる。何せ、これまで脚を運んだ二つの遺跡では、どちらも最深部にて竜の姿を取った化生との戦いになっている。もし竜達が老人の施した術式を原因として発生しているならば、今回もそれと同等、いや、それ以上の存在と出くわす可能性があるのだ。出来れば事前に可能な限りの情報を集めておきたいというのは当然の思考だろう。
というような趣旨の発言を【NAME】がすると、イェアは腕組みをして唸り、
「【NAME】さん達が戦ったという竜についても、実際に印章陣と係わりがある存在なのかも良く判らないんですよねぇ。竜という姿を取っていたとの事ですけど、話を聞いた限りだと、概念的な在り方は寧ろ鬼種に近い存在のようにも思えますし。……そこを追求、というか状況の関連性を正しく切り分けるためにも、せめてお爺さんが何をしていたのかの推測くらいは立てておきたいところですけれども」
「とはいえ、なぁ。何ともあやふやな、抽象的な言い回しばかりで、意味を読み取るのも難しいね」
イェアの言葉に対し、オリオールがふーむと腕組みをして考え込む。
「大雑把に解釈すると、マイオトール氏は色々な遺跡を回って何かの術を延々続けてきたが失敗続きで、けれどもカリッサにあった遺跡で成功する目処が立った、という話でいいのだろうか」
「なのでしょうけれども、肝心の何故こんな海を越えた島にまでやってきたのかとか、そもそもどういう効果の術を実験していたのかとか、そういう話が一切ありませんでしたわね……」
「機甲具の記録時間を考えれば、それも仕方無い事なのではと私は考えますが。事実、今回の件についての話だけでも記録時間は既に越えているのですから」
ノエルの言う通り、その辺りの話が入っていたならば、老人の言う“願い事”の段に辿り着く前に記録は途切れていただろう。
「仕様がありませんわねぇ。でしたらこちらの機甲具から情報を得るのはもう諦めて……」
イェアは己の白とも銀とも取れる長い髪をくるくると指に巻きながら、ふと【NAME】の方を見る。
「【NAME】さん、お願いしていたもう一つの方、渡していだだけます?」
彼女が何を望んでいるのかは直ぐに判った。地面に展開していた機甲具を片付けていたイェアに、【NAME】は背嚢の中から取り出した別の機甲具を手渡す。
【NAME】が渡した二個目の機甲具は、雷の湖の遺跡の最奥、中枢区画に残されていた印章陣を記録したものである。印章陣の正常な全景を手に入れる事が出来れば、印章術、特に印章陣に代表される印章記述の専門家である自分ならば、陣が持つ機能、駆動させる術式の内容を読み解ける可能性があると、彼女から密かに頼まれていたものだった。
【NAME】の説明を聞いて、オリオールはふむふむと頷き、
「成る程、ご老人の残していた機甲具に情景を記憶する力があるというのなら、それを利用してこういう使い方も出来る訳か。上手くやったものだね」
「……はっきりいって面倒だし疲れるし読み取れるか自信ないのでやりたくないんですけれど、折角【NAME】さんに撮ってきてもらった事ですし、何とか頑張ってみようと思います。やりたくないんですけれど」
余程厭なのか二回やりたくないと言いながら、イェアは機甲具の記憶再現操作をすると、急いで長机の前へと戻る。
再現される映像は、【NAME】が記憶してきた印章陣だ。一括ではなく分割して撮影された印章の陣を、イェアは視線を光の幕に向けたまま、机に置かれた荒い紙に描き写していく。場面が変わり、新たな印章陣が浮かび、描き写す。それを数度繰り返して機甲具が停止すると同時に、イェアは大きな溜息をついて、深々と椅子に腰を下ろす。
「で、出来ました……。で、ええと、次は解読……」
印章陣の全景を写し取った大紙。それを隅から隅へと、食い入るように視線を走らせること暫く。面を上げたイェアは、露骨に顔を引きつらせていた。
「んー、これは……何とも」
「何だいその反応。もしかして、何かまずいものとか?」
オリオールが訊くと、イェアは表情はそのまま、机の上に置かれた大紙を見下ろして、呻くように堪える。
「まずい、というか、やばい、というか、普通なら禁じられてる類、といいますか」
うわぁ、とオリオールと【NAME】は苦い顔を突き合わせて、ノエルは無表情のまま驚いたように目を瞬かせ、リゼラは常の不機嫌そうな顔をより顰めてみせる。
「如何な代物だ。話せ」
リゼラの険のある言葉に促されて、イェアは「断片的な解釈からの推測ですが」と前置いてこう話を続けた。
彼女曰く、描かれていた印章陣に類似する既存の術式を挙げるならば、それは人体を含めた混合癒着生物生成のための術式であるという。
勿論、解読しきれない部分は多々あり、それだけの効果しか持たない印章陣ではないと思われたが、しかし主となるのがその部分であるのは確かで、ならばあの老人は、場衡機構という土地や環境を改変する象形の力を印章陣にて捩じ曲げて、生物――それも恐らくは人間を絡める形で適用しようとしていたのだろう、と。
生命を持つ存在に対して莫大な力で干渉しようとしていたのだから、命の脈、生命の理を司る命脈の力を利用しようとしていたのは自明で、命脈の気配が強く残っているというリゼラの指摘も、成る程、当然といえる話であった。
「纏めると、こういう事かな」
話を終えたイェアの後を引き継ぐように、オリオールが言葉を続ける。
「マイオトール氏は、自分、もしくは他者に対して他の生物の存在概念をつなぎ合わせる事で、別種の存在を産みだそうとしていた、と」
「印章陣の他の部分から察するに、独立した別個の存在を単に継ぎ接ぎするだけのキメラではなく、存在を境界無く混ぜ合わせて、新たな――上位の存在を誕生させようという試み、だったのでしょうね」
「…………」
既に何度目かの沈黙は、これまでとは違い、重苦しく、そして僅かな緊張感すらも漂わせるものだった。
「……一気に、片手間で調査するには過ぎた話になってきましたわね、これは。要は、あのお爺さんは“鬼喰らいの鬼”が持っていた能力に近いものを、別の研究法で実現しようとしていた、という事なんでしょうか」
「僕は直接見てはいないけれども、“同加”のシンラ……だったかな? 存在を喰らって力に変えるのだったっけ?」
オリオールはそもそも四大遺跡の事件に殆ど関わっていない。だからこその覚束ない言葉だったが、イェアはこくりと頷く。
「ええ。あらゆる存在を己が内に取り込み、同じ存在として加える能力。だから“同加”。ただ、シンラが持っていた力は、あくまでシンラという存在に他の存在が取り込まれるという形を取ってますの。対して、こちらの術式の方はそういった主や従の関係なく、複合する他存在を混じり合わせて全く別個の在り方を生み出そうというもののようですわね」
「……それは、何が違うのでしょうか?」
ノエルが素直に首を捻る。【NAME】としても同じ疑問があった。二人の視線を受けて、イェアは「んー」と細い指先で顎先を撫でて、
「“鬼”という在り方は維持したまま、存在概念だけを銜え込み増していくか。それとも元々の在り方すらも放棄して、多種の存在と混じり合うか。この違いですわ。前者の場合ならば何をどれだけ取り込もうとも鬼種として在り続けますが、後者の場合は鬼種ですらなくなる可能性も有り得る。そもそもの在り方の変質すらも許容する、という事です」
「レェアの妹御よ」
と、そこまで黙って話を聞いていたリゼラが口を開く。
「つまりそれは、対象が人ならば、人の枠を越えた別の存在に変化する、という事か?」
「そうなります……ね……」
答えかけて、イェアの表情が端から見ていても判るほどに硬化していく。そんな彼女の様子に追い打ちを掛けるように、リゼラが話を続けた。
「貴様、以前に言っていたな。象形を直に操るための条件とやらを」
「……覚えていますわ。確かに、お話ししました」
その話は、【NAME】も覚えていた。
“芯なる者”が操る紋様、絶大な力を秘めた象形を操るには、幾つもの条件がある。
そもそもの術に対する知識。補助するための道具。象形が持つ力と目的の相性。そして最も重要なのが、人の枠から外れる事だ、と。
リゼラが指摘しているのは、恐らくこの最後の部分だ。
「あの翁が行おうとしている事は、それに繋がる術であると考えられぬか」
「……本末転倒、という気はしますが、断言も難しいですわね。印章陣を使って象形を僅かなりと操る術式の開発は、あくまで象形の直接干渉や掌握を行えるような存在へと生まれ変わるための前準備でしかなく、より大きな力を使うための前座である、というという事ならば、筋自体は通りますけれども……」
言葉を途切らせると、イェアは何とも言えない表情で首を捻る。その隣で、オリオールが何とも呆れた表情で掌を掲げてみせ、
「人で無くなってまで、やらねばならない事なのかな、それは。僕からすると、全く以て理解し難い事だけども。人は人のまま、その摂理に沿って生きるべきだとは思うがね。そこから外れなければ成し得ない事というのは、そもそも人の手に余る所業だろう。……と、思うんだが、皆はどうかな」
話を振られて、場に居る者達はそれぞれの反応を見せた。
最初に答えたのはノエルだ。
「私は、人ではないそうです」
淡々とした無表情で、まず彼女はそう呟いた。
「私は本来、鬼の力を受けて鬼と戦うための存在として造られたと聞きました。そしてその在り方に従うならば、私が今、こうして皆様方の前で生きることは、己が造られた際に定められた枠からはみ出す行為だと、私は考えます」
「ちょ、ちょっと、ノエル。貴女、そんな風に考えてましたの?」
イェアが慌てたように口を挟む。
対して、ノエルは常の硬質な表情を、最近は時折見せるようになった柔らかなものへと変化させて、首を小さく横に振った。
「けれども私は、今の自分を否定したくはありません。それは、今の私を信じ認めて、共に居る事を選んでくれた方々を拒絶する事に繋がりますから。私は、私を信じてくれた方々に応えたい。だから、己が生まれた定めを乗り越えようとする人を責めたくはないと、私はそう思っています」
と、何処か噛み締めるように告げるノエルに、イェアが深く安堵の吐息をついて、そして半眼となって視線を横へと向ける。
「だ、そうですわよ、ハマダン様」
「そういうつもりで言ったわけじゃないんだが、失言だったのかなぁこりゃ……」
オリオールがぼりぼりと己の頭を掻き、居心地悪げに身じろぎする。
彼がそういう態度を取る気持ちも判らないでもない。オリオールの見解とノエルの考えは正反対に近いもので、取りようによってはオリオールの言はノエルの在り方を責めているようにも聞こえる。勿論、オリオール自身にはそのつもりまではないのだろうが。
「……あー、と、そうだ。少年はどう考えているんだろうか? 君達、キヴェンティからすると、こういう行いはどう捉えているのかな」
半ば誤魔化すような調子でオリオールが言うと、両腕を組み、むっつりと黙り込んでいたリゼラが、不快そうに薄目を開き、
「どうもこうもあるまいよ。あの遺跡で命脈の力が強く残っていたのも、翁が施した術式の名残と思えば納得はいく。“芯なる者”とやらの紋様をどうするかなど、我からすれば気に掛ける事でもないが、我等が崇める命脈に対してそのような歪な行為のために触れるなど、許されざる事甚だしい。翆獣の理を弁えず、奉る心も持たずに、命の節を貶め、ただ目的が為に利用しようとするなど不届き至極よ。あの破天荒極まるレェアでさえ、少なくとも生命の道理は弁えていたぞ」
だが、と間に挟み、
「経緯はどうあれ、そうして生まれた命そのものの罪過については、どうであろうな。命の在り方を己が目で見定めてみねば、確かなことは言えぬ。歪な由にて生まれたからといって、命の姿形までもが歪んでいるとは限らぬ。――例えば、そこの娘子のようにな」
「…………」
リゼラが視線を向けた動きに釣られて【NAME】もノエルを見ると、彼女は大きく目を見開いたまま完全に固まってしまっていた。リゼラからそんな事を言われたのが余程意外だったらしい。
そのまま微動だにしないノエルを暫し眺めて、リゼラは小さく鼻の奥を鳴らすように笑うと視線を移す。
「それで、レェアの妹御。貴様はどうなのだ。彼の翁やアレと同じ術士であるならば、その遣りように僅かなりとも惹かれるところはあるのではないか?」
少年の問いは揶揄するようでもあり、そして見定めるようでもあった。
問われたイェアはといえば椅子に深く背を預けると、視線をふらふらと天幕の上へと揺らしながら言葉を作る。
「わたくしからすると、倫理面の話以前に、お爺さんの行動はそもそもの危険度が高すぎて論外、といった所ですわね」
「ほう。“迷の民”の中でも貴様等のような連中は、危険などものともせぬ人種かと思っていたが」
面白がるようなリゼラの言葉に、イェアは小さく肩を竦めて口元の端を釣り上げる、
「それは目的を達成するためには必要な、負うべきリスクであると判断でき、尚且つ成功の目が見えていればこそ、ですわ。確かにわたくしも学士の端くれです。自身の知的好奇心を満たすためには、少々の無茶も許容する性格だと自分で理解はしています。けれど、あんな術式を自分に行使すれば、どんな影響が生じるか読めたものではありません。主と従すら定めず、存在すらも崩すほどの手法です。まず己の人格が維持出来るかどうかが怪しいでしょう。そうなれば、次の段階をなんて話では無くなりますし、わたくしには半ば自殺行為にしか見えません。そんな愚手に、己の全てを賭けようとする程博徒ではありませんし、切羽詰まってもいませんわ」
そこまで言って、彼女は眉根を寄せて首を捻る。
「……ただ、これ程の印章陣を作り出すような方が、そんな当たり前の事を理解出来ていないとも思えないんですよね。だからどうも、しっくり来ないというか」
「では、彼の翁には別の目的があると貴様は言いたいのか?」
本人も確固たる証拠のようなものがなく発言しているのだろう。リゼラの問いに、イェアは「判りません」と言葉を濁す。
「もしくは、妄信を貫いてしまうほどに、何かに追い詰められているのか、といったところでしょうか。もしわたくしがマイオトールさんとお話しが出来たなら、全力で止めるところですけど……それは不可能な話でしょうし」
「残念ながら、彼がこのエルツァンを訪れたのはかなり以前の事だろうしね」
オリオールが戯けた調子で両の掌を掲げてみせる。
結局の所は、オリオールの言う通りなのだ。マイオトールは既に彼が言う“望みの結末”を、とうの昔に迎えた後なのだ。ここで自分達が彼の行いを肯定しようが否定しようが、もう然したる意味はない。
【NAME】達に出来る事は、それこそマイオトールが伝言で伝えていたように、彼がようやく見つけたという解が、どのような結果を生み出したのか。それを確認しに行く事だけだった。
「何にせよ、マイオトールさんは、最後の遺跡で自身が持てる全てを注ぎ込んだと思われます。ですので、遺跡に立ち込めていた強い気配が彼の術式の影響によるものであるのならば、【NAME】さん達が前回、前々回と訪れた遺跡よりも、強く濃い形で残っていると思われます。当然、遺跡中枢区画も同様でしょうね」
リゼラがふん、と小さく鼻を鳴らす。
「最初の遺跡では霧、次の遺跡では雷。場衡機構が生み出した土地の持つ歪みの要素を、そのまま引き継いでいると考えるのが自然ではあるが。何が出るかは、遺跡がある土地の状況次第か」
「ご老人は何と言っていたかな。確か――太陽と月が瞬く交差する丘陵、だったか。……確か、以前にカール・シュミット氏の手記を軽く流し見させて貰ったときに、それらしき丘の記述を読んだ気がするが。【NAME】、確かめてみてくれないか?」
言われて、【NAME】は荷物の中から借り受けていた古ぼけた手記を取り出す。
過去にエルツァン島を旅した探検家、カール・シュミットが残した手記である。暫くページを捲り、それらしき記述を探す。太陽だの月だのという部分に合致するところは無かったが、しかし手記の中に存在していた丘陵はただ一つだったことから特定は簡単だった。
彼が残した記録の名称にならうならば、そこの名は“ザルナルバック月光丘陵”。禍々しき月の光の下、狂気を帯びた亜獣達が跋扈し、不気味に輝く光の結晶が漂う危険極まる場所であるらしい。
――こんな所に足を運ばねばならないのか。
【NAME】は思わずげんなりと顔を顰める。本音を言えば遺跡の調査どころか丘陵にすら近寄りたくない気分だったが、そんな【NAME】の内心を察してか、イェアが申し訳なさ気な顔をこちらへと向けてくる。。
「最初の頃でしたらそれでも構わない、と言えたのですけれど、これまで判明した事柄を考えれば、遺跡の状況を確認しておかない訳にも行きません。軍の方で調査を行えれば良かったのですけれども、多分遺跡の中へはわたくし達のような普通の人間では、立ち入る事すら難しい状況でしょう。ですので、わたくしとしても貴方に頼り切りで心苦しいところなのですけれど、今回は正式な要請という形で、貴方に“ザルナルバック月光丘陵”に存在すると思われる場衡機構の調査をお願いさせてください」
深々と【NAME】に向かって頭を上げたイェアは、身体の向きを少し横へとズラして、また頭を深々と下げる。
その先に居るのは、腕を組み、天幕の支え柱に背を預けていた小柄な少年だ。
「そしてリゼラさん、どうか、【NAME】さんの手助けをお願いできませんか? 情けない話ですが、頼れるのは、【NAME】さんと貴方だけなんですの」
「代われるものなら代わりたいところだけれどもね。残念ながら僕には荷が重すぎるようだし……」
横から口を挟んだオリオールが、視線を隣、【NAME】の傍に立つノエルの方へと向ける。
彼女も、無表情は常のままだが、その瞳の奥に何処か無念そうな色を揺らがせて、
「申し訳ありませんが、この件については私も【NAME】の役に立つことは出来ないと判断します」
「とまぁ、そんな感じでね。僕等からもお願いしたい。可能であれば、少年。【NAME】と共にまた遺跡の調査に向かってくれないだろうか」
頭を下げたまま動きを止めているイェア、そしてオリオールとノエル、最後に【NAME】の方を順々に見て、リゼラは仏頂面のまま緩く息を吐く。
「……何を勘違いしている。そも、我にしてみれば貴様等に頼まれずとも、翆の眷として、彼の翁が命の脈を如何に触り、何を成すのか、それを確かめ、正すために動いている。これは以前にも言った筈だ。そして同様に、この島に於ける我は【NAME】の剣でもあるとな。【NAME】が向かうと言うのならば、付き行く事に否はない」
「あ、ありがとうございます!」
「礼を言われる事でもない。言葉で説くのは我ではなく、【NAME】の方であろうが」
煩わしさも隠さず手で払うような仕草で、リゼラは話をこちらへと向けてくる。が、イェアの方は「大丈夫ですわよ」と微笑み、
「だってわたくし、【NAME】さんの事は信じてますもの。この方は、どんな困難な事にも負けずに立ち向かえる、強くて、立派な人だって」
「…………」
そんな浸るような顔つきで持ち上げられても、こちらとしては困るしかない訳だが。
【NAME】はうんざり半分気恥ずかしさ半分の心地で、誤魔化すような苦笑を浮かべるしかなかった。
・
常駐軍のエルツァン島探索計画について打ち合わせをするというイェア達に別れを告げて、【NAME】は自分に割り当てられた天幕を目指して陣地を歩きながら考える。
取り敢えず、現段階で得られるだけの情報は得られた。
老いた術士マイオトールが向かったのは“ザルナルバック月光丘陵”の場衡機構。待ち受けるのは、マイオトールがこれまでの遺跡で施してきた印章陣の最終形だ。
その結果が失敗であれば、遺跡の内部はこれまで以上に強烈な気配の圧に満ちていると考えられ、術の中心となっているであろう中枢区画では、他の遺跡で遭遇した霧や雷の身を持つ竜の化生を更に上回る存在と遭遇する可能性が高いだろうと思われた。
そして、もし成功していたのであれば。
先刻のイェアが読み取った情報に従うなら、象形という“芯なる者”の力を借りて生み出された、多種の生命の存在概念を混じり合わせた何者かが誕生している筈だ。
対策を練るという意味では、もう少し詳細な情報が欲しかったところだが致し方ない。兎に角、これまで以上の危険が待ち受けていると、そう考えて気を抜かずに遺跡を調査するしかないだろう。
「先刻は、何なりとごねていたようだが」
と、内心で今後の予定を考えていた【NAME】は、突然の声に驚いてぴたりと脚を止める。振り返れば背後、数歩距離を置いて、小柄な少年が立っていた。
彼は向けられた【NAME】の顔を見て、軽く口角をあげ、
「レェアの妹の天幕を出れば、もう意識はすっかりと遺跡の探索へ向けて切り替えているか。ならば最初から、やる気を見せてやれば彼奴等の気を揉ませずに済んだものを。案外と意地が悪いな、お前は」
言われて、【NAME】はそんなつもりではなかったのだが、と困ったように笑うしかなかった。
実際、天幕を出るまでは乗り気では無かったのだ。だが、いざ一人になって考える時間が出来ると、意識は確かに、リゼラの言った通りに如何に丘陵の遺跡を探し出すか、遺跡の地下には何が待つのか、そんな事に向けられている。これはもう、単純に未知なる物に対する冒険心でしかなく、謂わば職業病にも近いものだった。
そんな曖昧な感覚を素直に言葉とすると、リゼラの表情は流石に呆れたようなものへと変わった。
「あの探検家といい、よくもまぁ、それだけの心持ちで軽々しく動けるものだと感心はするがな。我等キヴェンティのように、確固たる使命を帯びて生き、暮らしている訳でもないというのに、ただ己の心が示すがまま、命を賭し、前へと進む。お前達は標無き“迷の民”ではあるが……」
そこで僅かに言葉を切ると、少年は小さく鼻を鳴らし、僅かな笑みを見せる。
「だからこそ、如何な暗闇の中にあっても真っ直ぐに、歩みを止めぬ力を備えているのだろう。――もっとも、それ故か明らかな過ちの道筋を選んでいても、決して歩みを止めぬ頑鈍な者達も多いがな」
そうして、少年は【NAME】の隣を通り過ぎ、軍の陣地を離れる方へと歩いていく。行く先は、恐らく陣より少しばかり離れた所にあるキヴェンティ達の野営地だろう。
遠ざかる少年の姿を何気なく見送っていると、彼は一瞬振り返って【NAME】を見る。垣間見えた顔には既に笑みの色はなく、常の鋭く険しい表情に戻っていた。
「旅の準備が整えば、我を呼べ。あの翁が残した最後の土産がどのようなものか、この目で確と見届けに行くとしよう」
真なる楽園 禍つ秘の記憶が示す形
――場衡機構“月光”――
昼と夜。日と月。かつてカール・シュミットの探検隊に属し、ここで命を落としたとされる人物――ザルナルバックという名をつけられたこの丘陵は、明と暗の境界を経ることで環境を一変させる。
夜が狂気に満ちた多種の亜獣達が跋扈する危険極まる時間とするなら、逆に昼は穏やかな日差しと爽やかな風が吹き抜ける平和に満ちた時間と言えるだろう。
故に、月光丘陵にて探索行動を行うならば、可能な限り日中の間に行うべきだと気づくのに、然したる時間は掛からなかった。
早朝から暮れに掛けて、ぐるりと円を描くように連なる丘を幾つも越えてみたものの。【NAME】が持つ印章石――マイオトールと名乗った老人の隠匿結界を探知出来る特別な石は、何ら反応を示す様子は無かった。
――今日の収穫はなし、か。
と、【NAME】は少しばかり気落ちしながら探索を切り上げ、合流地点を目指して移動を再開する。
旅の連れであるキヴェンティの若長、リゼラ・マオエ・キヴェンティとは、今は別行動を取っていた。日中に危険が少ない事が判明した時点で、二手に別れて探索を行う方が効率が良いとの判断からだ。
リゼラは印章石を所持していないため、隠匿結界を正確に掴むことは出来ないが、彼が言うには、
「そもそも忌み地の技、身隠しの術とは、そこに在る事が確かではない時こそ、十全に働く代物だ。既に種が割れているならば、お前が持っている石が無くとも、怪しい場所くらいは見通してみせよう。もっとも、相応に近付かねば流石に厳しかろうが」
との事で、ならばと手分けしての探索となっていた。
丘陵はそれ程広大な地形という訳ではなかったが、似たような山と谷がなだらかに延々と続くような構造となっており、あまり目印になるようなものもない。障害物のようなものも視線を遮るものもないため、単に見渡し、移動するだけであるならば楽な場所だが、虱潰しに歩き回る場合は、己の現在地やこれまで確認してきた地点の把握がし辛く、案外と面倒な場所でもあった。
実際、合流地点と定めた場所へと戻ろうとしている今でも、若干道に迷いつつある。確か、頂上に一本木が立つ丘を合流の場所と定めていたと思うのだが、周囲を見回してもそれらしき丘が見当たらない。
あの一際高い丘の向こう側だっただろうか、とそちらへと歩を進めようとした【NAME】は、視線の先、目指した丘の頂上に、小さな人影が立っている事に気づいた。
もう見慣れた感のある、腰に二本の剣を差した小柄な少年の姿。アノーレ島に住まうキヴェンティ達の若長を務めるリゼラは、こちらに背を向ける形で腕組みし、遠くへ視線を向けている。
これは運が良い。わざわざ合流地点へと向かう手間が省けた。
今居る場所は丘陵の谷部、少年が立つ丘の頂上まではそれ程の距離もない。【NAME】はゆっくりと丘を登り、リゼラの傍へと移動する。背後から声を掛けると、リゼラは一瞬こちらへと視線を向けて、
「【NAME】、か」
僅かに目を見開いているのは、こちらの存在に驚いたからか。
傍に近づくまで気づかないとは、常に周囲に気を配る彼にしては珍しい。
【NAME】がそういうと、少年は呆れたような表情を見せて、
「お前こそ、ここまで来て何も感じてはおらぬのか。レェアの妹御から渡された石に、一切の変わりはないのか?」
どういう意味だ、と一度首を捻って、【NAME】は直ぐに彼の言の意味に気づく。
――まさか、隠匿結界の存在を感じ取ったのか?
「正確には、結界の方ではないがな。あの雑多で濃く、厚い生命の気配が、あちらから漂ってきているのが判らぬか」
言って、リゼラが見るのは下方、彼が先刻から視線を向けていた、丘と丘の間にある谷間だ。
なだらかな丘と同様、緩やかな窪地となっているそこは、一見して何の変哲もない場所としか思えなかった。
だが、リゼラにそう言われてから改めて見直してみると、何も無い草原に時折微細な歪みのようなものが走り始め、そして五感を研ぎ澄ませてみれば、
――確かに。
これまで探索した場衡機構に漂っていたものと同種の気配が、僅かにではあるが今【NAME】達が立つ丘の上にまで届いていた。
しかし、遺跡の地下で感じたあの気配が地上にまで、更に言えば隠匿結界の外にまで漂ってきているというのは意外だ。これまでの遺跡二つでは、地上部にまでその気配が漏れ出ている事など無かったのだが。
そんな事を【NAME】がいうと、隣に立つ少年も首肯する。
「理由についての想像は出来なくもないが、それよりも直に確かめた方が早かろうよ。行くぞ、【NAME】」
声を掛けて、リゼラが丘を降っていく。【NAME】もその後を追うと、懐に仕舞い込んでいた何かが微細に震える感触が伝わってくる。隠匿結界を捉える力を持つ印章石が、その存在を報せるべく震えているのだ。印章石の感知範囲は確か数百メートルという話だったが、石が反応を示す前にリゼラは既に気配を察していた。イェアの持たせてくれた印章石の性能が悪いのか、それともリゼラの気配を掴む能力が高すぎるのか。何にせよ、目指す窪地に隠匿結界が存在するのは間違いないようだった。
丘を半ばまで降った辺りで、【NAME】にも周囲の気配が持つ異質さをはっきりと感じられるようになっていた。
正面、複数の丘の谷間となる窪地は未だに何の変哲も無い草原のままであったが、場を支配している異質な気配に対し広がっているのは平凡極まりない風景で、それが明確な違和を生み出している。そして違和の存在を把握した上で目を凝らせば、窪地の景色は徐々に歪み、その奥に隠されていた何かが僅かに垣間見えるようになった。
隠匿結界とは、忌避の植え付けと認識の偽装である。故に、そこに何かが在ると理解しているならば、結界の効果は大幅に弱まる。
このまま窪地の中心にまで行き、暫く意識を集中して周囲を調べれば、隠匿結界を己の力だけで破る事も可能だろう。誤認の力は所詮、感覚を誤魔化す力でしかない。気を配り、五感の真否を見極めることが出来れば、得られた偽りに対する小さな綻びは偽装全体へと波及し、隠匿結界が見せる幻の認識を全て覆す事が出来るだろう。
だが、イェアより渡された印章石が持つ結界を破る力を使えば、そんな手間も不要である。
丘を降りきり、窪地に辿り着いた時点で、印章石は振動だけではなく、淡い輝きを放ち始めていた。その変化は印章石に仕込まれた結界破りの力が使用可能の状態になった事を示していた。
結界破りの力は、以前に一度駆動させた経験がある。認識影響を与えている範囲内で印章石に仕込まれた術式の力を発揮させれば、場を覆う偽りの景色を容易くはぎ取る筈だ。
【NAME】は余裕を持って、印章石を窪地の中央へと向けて掲げ、設定された定型句を正確に唱える。
瞬間、印章石に込められた術式が駆動を開始し、石から放たれた強烈な光が、平野の窪地を白の輝き一色で埋め尽くす。
「――――」
瞼を閉じていても透けて感じる程の強い光は、五秒程で徐々に弱まり、消えていった。
輝きが失せたのを感じ、【NAME】が恐る恐る目を開けると、何も無かった丘の合間となる窪地には、古びた白色の大石で構築された建造物群が出現していた。半ば朽ちかけた建造物群は、完全に同一のものではないものの、以前に森や湖の近くで見たあの遺跡と良く似ている。
しかし、明確な違いが一つあった。
「濃いな」
一言リゼラがそう漏らした通り、隠匿結界が消滅した故であるのか、窪地に立ち込めている異質な気配の圧は、先刻までよりも数段その度合いを高めていた。
属性や性質を問わない、あらゆる力を秘めた強い気配。幾多の生命の気配が混ざり合って、まるで熱を帯びているかのような錯覚すら覚えるほどの圧。森や湖の遺跡で例えるならば、地下部の中枢区画へと向かう辺りで感じた気配の強さだ。それが中枢区画から離れた遺跡の地下部どころか地上部にて漂っているとするならば、果たして地下部や、その奥となる中枢区画では一体どれ程の圧力、濃度を持つ気配となっているのか。
そして気配の原因が老人が施した術式によるものであるならば、気配の濃度が強いと言うことはそれだけ、老人の術式が強力なものであった事も示している。もっとも、それが老人の行いの結果までもを示しているのかどうかは判らないが。
「それも、中へ入れば知れる事だろうよ。見たところ、遺跡の造りはこれまでと変わらぬようだ。ならば、地下へと降りるための入り口がある場所も、そう違いはあるまい」
リゼラの言葉に頷いて、【NAME】は半ば朽ちかけた遺跡の中を進む。
目指すは、遺跡の中央に存在していた円形台状の大型建造物の裏側だ。これまで【NAME】達が巡ってきた場衡機構と同様の構造であるならば、そこに地下区画へと続く侵入口がある筈だからだ。
果たして、大型建造物の裏側、その下部へと目を向けると、確かにそこには過去立ち入った場衡機構と同じ、遺跡地下へと降りる為に侵入口が存在していた。。
しかし、
「覆いは無し、か」
ぽっかりと開いた地下へと続く口を見下ろして、リゼラは確認するように呟く。
これまでの二箇所、霧の森の遺跡と、雷の湖の遺跡。二つの場衡機構の入り口は全て、硬質の蓋によってみっちりと塞がれていた。だが、この丘陵の遺跡には大蓋が存在せず、開かれた穴の奥に存在する階段と、両壁に取り付けられた照明具が照らす淡い光の点線が既に見えている状態だ。
何故、この遺跡にだけ蓋が存在しないのだろうか?
【NAME】が怪訝と首を捻っていると、隣で険しい目つきを下方の侵入口へ向けていたリゼラが振り向き、
「以前話した事を覚えているか、【NAME】」
曖昧な物言いに、【NAME】は眉根を寄せる。どうもこの少年は時折言葉が足りていない。それだけでは判るものかと答えると、
「森の遺跡、湖の遺跡、どちらでも見たあの覆いは、元々存在していたものではなく、術士の翁が何らかの術を用いて塞いだものであろうとな」
言われて、前にそんな話を聞いた事を思い出す。確か、雷の湖にあった遺跡の地下部へと入り込もうという時であったか。
少年曰く、蓋となっていたものの材質が、遺跡の各所で使われているものとは根本的に異なるとか何とか。故に、侵入口を塞ぐ蓋は後にこの地を訪れた術士マイオトールが用意していったのだろうという推測が成り立つと。
「そうだ。そして、ここには覆いが存在していない。これまでの遺跡と比べ気配が外へと強く漏れ出しているのも、覆いが無いことが一つの理由として考えられるやも知れぬな」
どうだろう、と【NAME】は首を捻る。
――たかが蓋一つで、気配などという模糊とした代物を閉じ込められるものなのだろうか?
リゼラとしても確証あっての話ではないのだろう。微妙な【NAME】の反応を意に介した風もなく、
「さて? 我とて埒外の話だ。事実そうであるかは判らぬ。だが、術士がわざわざ用意した封なのだ。何らかの意味があったのは間違いなかろう。だからこそ、この遺跡には覆いがない事にも、何らかの理由がある筈だ。……考えられるとするならば、そうだな。大凡三つか」
リゼラの呟きは、【NAME】が推測していたパターン数と一致していた。
一つは、マイオトールが遺跡を立ち去る際に蓋の用意を忘れていたという、極々単純な可能性。
推測としてはお粗末極まる物だが、そうであるという可能性を全く除外できない類のものでもある。
もう一つは、マイオトールにとってこの場所で蓋をする必要性が無かったという可能性。
これについては、これまでの遺跡で何故蓋が用意されていたのかを正確に把握した上で推測せねば結論を出しづらい。情報が足りない自分達からしてみれば、真否を考える判断材料にそもそも欠けると言わざるを得ないだろう。
そして最後の一つは――マイオトールが未だに遺跡の外へと出ていないという可能性だ。
これまで、マイオトールが場衡機構地下への侵入口に用意していた蓋は、開ける事を全く考慮していないみっちりと隙間無く封をする形の、正に蓋である。
ならば当然、蓋を設置するのは自分が遺跡へと入り込んでいる間ではなく、そこから立ち去る時であった筈だ。
とすると、この遺跡の侵入口に蓋が存在していないのは、蓋をする必要が無かったからではなく、まだ遺跡の内部にマイオトール自身が残っているからだ、という理屈も成り立つ。
もしそうであるならば、既に相応の月日が流れた今、マイオトールが遺跡内部で未だに術式を行っているという可能性は極めて低く、ならばつまり、あの老人はこの遺跡にて命尽きたのだと考えるのが妥当だろう。
遺跡内で何らかの事故に遭ったか、それとも己の命が失われる事を前提とした忌術に挑んだのか。――過去の遺跡で老人が残した伝言から察するならば、可能性としては前者よりも後者の方が高いようにも思えた。
ただ、こうしてあれこれと推論してみたところで、はっきりこれだと断言出来る程の材料が今の自分達に無いのも事実である。
結局のところは、
「何であれ、我等の行動に変わりはない。遺跡の最奥へと立ち入り、己が目で確かめれば良い話だ。それがどのようなものであったとて、あの術士が為そうとした結末がこの地にある事には変わりあるまい」
泰然とした態度でリゼラは言い切り、そして侵入口の上縁に手を掛けてから、横目で【NAME】の方を見る。
「行くぞ【NAME】よ。外にこれ程気配が漏れ出ているのだ、恐らく、遺跡の内にて蔓延る歪も、以前の二箇所とは比べものにならんだろう。心して掛かれ」
・
【NAME】にとって、三箇所目となる場衡機構。
侵入口を潜り、細く下方へと伸びる階段を降り始めたところで、【NAME】とリゼラは直ぐにその違いに気づいた。
「……これは、生きているのか」
呟くリゼラの視線は、【NAME】と同様、階段の壁や天井部に向けられていた。
森と湖、二箇所で見つけた場衡機構は、芯形機構としての機能自体は維持していたものの、内部に組み込まれた象形や機関、そして中枢区画に存在する象形陣自体は駆動していない、いわば待機状態であった。
しかし、階段の天井、壁、天井にて脈動するように走る光線と、階段の先、まだ見えぬ奥地から届いてくる不可視の力の波動が伝えてくれる。
この場所は違う。この遺跡は停止も待機もしていない、芯形機構としての力を十全に駆動させている、リゼラの言うところの生きている状態なのだと。
そして、それが原因なのかは判らないが、侵入時のリゼラの予想通り、遺跡の地下部はこれまでの場衡機構とは比べものにならぬ程に、陰性の存在概念に傾いていた。
視界のそこかしこで小規模な歪みが生じ、鬼という形の実体を取りかけては、しかし不完全な状態で止まり、消えていくのが見える。土地概念の歪みが飽和し、それによる存在の顕現化が生じる前に別の地点で新たな飽和が生じ、その影響を受けて他方の顕現化が邪魔をされる。そんな連鎖的な現象によって、遺跡内部は鬼種が大量発生し続ける事なく、ただ歪を弱めぬまま維持し続けていたようだ。恐らくは、過去に多数の鬼種が生じ、それらが相打つなり自然消失するなりし続けた結果生じた小康状態なのだろう。
だが、そのバランスも【NAME】とリゼラというイレギュラーが立ち入った事で崩れてしまったようだ。
【NAME】達の前方より三点、そして後方よりそれ以上の数の強い歪みが生じて、ゆっくりと形を成していく。それは先刻確認していた小規模で留まり消滅するものではなく、見る間に肥大化し、しかし明確な実体を持つことなく、ただの影で形作られた存在として空間に蟠った。
暗黒の渦、空間に開いた闇。そんなものが、ゆらりゆらりと引き寄せられるように【NAME】達の方へと近付いてくる。その姿に生物としての気配はなく、意思すらもないように思えたが、しかし闇の奥から周囲に撒き散らされる強烈な害意、向けられる敵意の感覚に疑いようがなく、少なくとも自分達の障害となりうる存在である事は確かなようだった。
「全く。身体どころか、依り代や概念の因すらなく個として存在を維持出来うるとは。この地が持つ歪み、世の理に対する“芯なる者”の不作法さは、“迷の民”共が言う四大遺跡に立ち入った時に身に染みていたつもりであったが……」
前方に向かって身構える【NAME】の背後で、後方より近付く影に刃を向けながら、リゼラは小さく舌打ちをする。
「霧の獣といい、雷の化生といい、僅かなりとも実体があれば、我が刃でもって全く切り裂いてやるものを」
リゼラが苛立たしげに唸るのも仕方の無い話だ。
何せ場衡機構では彼の得意の剣技が通じ辛い相手が多い。今、自分達に迫ってくる影も、ただ剣で斬るだけでは恐らく厳しい。物理攻撃よりも概念系、術式攻撃が有効な相手だろう。
「翆なる脈を刃に通し、破裂させる手もあるが、それをやるには些か狭いか。なれば――」
少年が、ふらりと袖を振る。
「来たれ、我が翠なる顕たる“九継”よ。貴様の盛る焔の顎にて、あの闇を燃やし尽くしてしまえ」
すると、袖口から外へと転び出た赤色の線が瞬く間に膨れ上がって、火の粉を散らす九つ頭の大蛇となって階段の後方を塞ぐように姿を現す。頭の一つがくるりとこちらを振り向くと、リゼラの促しに「くぁー」と外見に似合わぬ不思議な音を出してから、後方より迫ってきていた形持つ影へと襲い掛かっていく。常ならば炎弾を吐き散らして敵と戦う九継であるが、縦横二メートルあるかないかの細い階段上で既に彼我の距離が間近となれば、近接攻撃を仕掛けた方が速いという判断だろう。
背後に湧いた無数の影は、リゼラ――より正確には九継が抑えてくれる。
ならば自分は、前方に出現した影を蹴散らせば良いだけだ。
階段の下方にて渦を巻きながら迫る無形暗色の化生。蠢く影の細腕が複数、こちらを取り込むように伸びてくるのをしっかりと見据えながら、【NAME】は己の武器を勢い良く振りかぶり、先端にまで通した力を一息に解放する。
一度襲われてから後は、正に立て続けだった。
あれが皮切りになったと言うべきか。最初に発生した影の化生を討ち滅ぼしたと思ったら、もう次の瞬間には傍から新たな気配が沸き立ち始め、それを倒したと思ったらまた次と切りが無い。
生じる影の化生は攻撃は通じ辛いものの、力強さも無ければ俊敏さにも欠け、獰猛な戦意がある訳でも無ければ狡知な挙動をする様子も見受けられない。漫然と夜の火に誘われる虫のような動きでこちらに迫ってくるだけで、多少面倒ではあれ、手強い相手という程ではなかった。
だが、次から次へと切れ間無く出現されると流石に厳しい。立ち止まって迎え撃っていては延々進むことが出来ないと、【NAME】は影との戦闘を続けながら階段を降りていく。
連続する影の襲撃が終わりを迎えたのは、階段を降り切り、大きく開けた空間に飛び出した時だ。
辿り着いた場所は、斜めに傾いた広大な長方形の空間、その上方部の壁から突き出るように伸びた大床の上だった。
四角状の床は十数メートル四方はあろうかという大きなもので、囲いは存在せず、縁には操作盤らしきものが取り付けられた機構装置もあり、形状や細部は異なるものの、霧の森にあった遺跡に存在していた昇降機に近い。どうやらここは、巨大な昇降機の搬器部分となる平面床の上であるらしい。
霧の森の遺跡にあった昇降機との違いは、シャフトが垂直ではなく斜め方向へと伸びている事と、二本の大きなガイドレールが籠となる昇降床を支えている事。つまりは垂直ではなく斜行型の昇降機なのだ。
そしてシャフト内の空間に、歪んだ存在の渦――陰性概念の飽和現象などの気配が無い事も、違いとして挙げられるだろう。勿論、既に【NAME】にとっては場衡機構の特徴とも思えるような、あの圧迫感すら与える強烈な生命の気配や、在り方としての歪さから生じる土地概念の澱みのようなものは感じられたが、それらが鬼種の顕現へと通じる程に高まる様子は見せていない。
――それが偶然であるのか、それともシャフト自体に仕掛けが施されている結果なのか。
【NAME】が何気なく呟くと、隣、顕現させていた九継を赤色の糸へと戻し袖内に納めたリゼラが、小さく肩を竦めるのが見えた。
「偶然の筈もなかろうよ。【NAME】、お前、この遺跡に漂う気配の流れ……いや、そこまでは行かずとも、大まかな分布、位置による強弱のようなものは読み取れているか?」
いや、と首を振る。【NAME】に判るのは、せいぜいが自分の周囲に立ち込める気配の強さや質程度だ。不定理粒子に関わるものであれば話は別だが、この遺跡に漂う気配はそちらの系統とは異なるものだ。残念ながら、同化者としての能力が役に立つような状況ではない。
「では、判らぬか。ならば背後を見よ」
促されて振り返れば、先刻【NAME】達が走り降りてきた階段へと続く口が見えた。その奥では影の化生がまだ泡立つように生まれ続けていたが、彼等が平面床の方まで出てくる気配はなく、複数の影がお互いを喰い合うように動いている。先刻まで、まるで誘蛾灯に惹かれる虫のようにこちらへ迫ってきていたというのに。
「今我等が居るこの傾いた空間内は、ある程度の土地概念の整調が行われているようだ。いや、整調というよりは、歪みを他方へと誘導する仕組みか。だからこそ、あの影達はこの場所に入ることも出来ず、ああして蟠っているのだろうよ。これも、遺跡が生きているからこその力であろう」
呟くリゼラの視線は、斜めに傾いた状態の側壁部に向けられていた。滑らかな金属質の光を放つ壁部には導管が複雑に走っているが、その奥には淡い輝きが灯った紋様が浮かんでいるのが見える。既に見慣れた、“芯なる者達”が使ったとされる力持つ文字――象形の姿だ。緩やかに明滅するそれからは、波打つように強い力が放たれているのを感じる。残念ながらその具体的な力までをも理解する事は出来なかったが、少なくとも刻まれた象形が、己の持つ力を発揮している状態にあるのは何となく察することが出来た。
「何にせよ、この場所が安全であるのは確かと言えよう。もっとも、ここより繋がる他方においては、この空間に存在していたであろう歪を押しつけられた形だ。先刻の階段と同様か、それ以上に歪んだ環境になっているであろうがな」
「…………」
先行きが暗いが、ここが休息地点として使えるのは有り難い。【NAME】は一つ深呼吸を挟んで先刻までの戦闘の余韻を吐き出してから、床の縁に設置されていた装置に近付く。
備え付けられていた操作装置は、機関の仕組みとしては霧の遺跡にあったものと然程違いは無いようだ。台座から伸びた硝子状の板と、幾つかのボタン。但し、霧の遺跡にあった装置は側面に昇降操作を行うためのレバーが存在していたが、ここにはそれはなかった。
硝子板に表示されている文字は殆ど読めなかったが、描かれた図形は簡単に類推できた。
縦長の平行四辺形、その縦線には所々に区切りの線があり、線と線の間にそれぞれに番号が振られていた。そして最上の区切り線が入った部分は点線で左右が繋がれた状態となっている。
要するに、区切り線が昇降機の停止位置を示し、点線が現在の搬器――今【NAME】達が立っている昇降床の場所を示しているのだろう。番号は、取り敢えず階層とでも考えればいいのだろうか。
区切り線は合計五本。番号らしき文字は上から順に一から五まで振られている。現在地は、この図に従うならば零階層目という事になるだろう。
と、そこへぐるりと周囲を見回っていたリゼラが【NAME】の傍へとやってきた。眉根を寄せて、硝子板に浮かんだ映像を睨むリゼラに【NAME】が視線を向けると、彼もそれに気づいて【NAME】の方を見、
「軽く辺りを調べてみたが、周りは壁しかない。唯一あるのは、我等が通ってきた階段へ通じる口のみだ。床と壁の合間には、人一人潜れる隙間すら見当たらぬ。遺跡の更に奥を目指すならば、この装置を操り上手く床を動かすか、或いは床自体を突き破り自力で降りていく必要があるぞ」
後者の手段はぞっとしない。
とはいえ、装置を操作するにしても、一体どうすれば動くのやら。
前々回の遺跡で昇降のために使ったレバーがないとなると、あとは台座に用意されているボタン類のみとなるのだが、しかしそれらに触れてみても昇降床が動き出す気配はなく、硝子板に映る図形の周りに走る、文字や数値らしきものの羅列が細かく変化したりする程度だ。
どうやらボタンは外れであるようなのだが、では一体どうすればいいのか。
うーむ、と唸りながら、【NAME】が何となく表示板の図形を指で弾いてみせると、がくんと昇降機が振動し、続いてゆっくりと下方へと移動を始めたのだ。
鈍く滑車が回る音を立てながら、搬器が下方へと移動していく。下方から上方へと流れていく壁を眺めながら、隣に立つリゼラが浅く息を吐き、
「成る程な。触れればそこへ移動するという訳か」
彼の言の通り、先刻何気なく【NAME】が指で弾いた図形の場所、三本目の区切り線の所で昇降機はゆっくりと停止した。そこでは、床の周囲三面は先刻までと同じ金属質の壁に囲われたままであったが、残り一辺はぱっくりと大きな口を開けており、その先には広く長い一本の通路が奥へ奥へと伸びている。ここと同様、通路の側面には象形らしき紋様が幾つも浮かんでいるのが見えるが、その輝きはどこか仄暗く、通路全体を覆う不自然な暗闇を払い切れておらず、上手く通路内を見通す事が出来ない。
一言でいえば、不気味な通路だった。外見的にもそうだが、実際に感じる気配自体が宜しくない。通路から漂ってくるのは強烈な歪みの気配だ。今居るシャフト内が比較的正常な空間になっているためか、通路にて蠢く気配は際立って歪に見えた。
流石に、直ぐさまその通路へと移動する気にはなれず、他の場所はどうなっているのかと【NAME】は硝子板に触れて、別の層へと順々に搬器を移動させる。三から四と降りて、通り過ぎていた二、そして一の層へと移動してみたが、構造自体は全ての層でほぼ変わりは無かった。それぞれの階層では一本の大通路が奥へと伸びている形で、そしてその通路はこのシャフト内とは比べものにならない程の歪んだ気配に満ちている事。
「……覚悟を決めて、何れかの通路を進むしかないようだな」
腕組みして呟くリゼラに、【NAME】は小さく頷く。
問題は、何処の層の通路へ進むかだ。
それぞれの階層に存在する通路は、構造自体は何れもほぼ同じで、気配も同様に強い歪みに満ちていたが、その状態には僅かな違いがあるように思えた。その違いの中で一番判り易かったのが、色彩の傾向だろう。最初の3層目では通路を埋める暗闇は僅かに紫と黄色に傾いており、今居る最後となった1層目ではほんの少し赤色に傾き、所々は赤銅の明るさにも近付いている。気配の質も層毎に違いがあるようだが、しかしそれが一体どのような意味を持つまでは判らず、進むべき道を選ぶための判断材料としては些か頼りない。
「これまでの遺跡の造りから読むのであれば、中枢区画は遺跡の深い場所にあるとするのが自然だ。なれば、真っ先に最下の層を進むのが無駄の無い行動となる。が……」
硝子板に表示された図形の下部に、リゼラは指を当てるか当てないかの位置で停止させ、リゼラは言葉尻を濁す。普段から不機嫌そうな表情の多いリゼラだが、今は眉根を深く寄せて、半ば睨むような目つきを硝子板に向けている。
彼の懸念は、何となく判る。
第一から四層と、最下層である第五層。
先刻、一通りの層へと移動しようとした際に第五層を飛ばしたのは、何も忘れていた訳ではない。
第四層辺りに降りた際、シャフトの最奥――つまり件の第五層があると思しき付近から、凄まじい気配が立ち上っている事に気づいたからだ。
その気配は、単なる陰性概念というだけではなく、今まで【NAME】が見知った幾つもの力が無秩序に混じり合ったもので、兎に角危険な気配である事だけは判る。これまで培ってきた冒険者としての経験が、最下層に何の対策も用心も無く下りるのは自殺行為に等しいと告げていた。
リゼラはそのまま暫く無言で硝子板を睨んでいたが、表情を緩めると細く吐息をつき、
「判断しかねる。如何にするかは、【NAME】。お前に任せよう」
丸投げされた。
反射的にげんなりと顔を歪めると、対しリゼラは薄く笑みを作り、
「なに、その結果如何様な目が出ようとも、お前を責める事は断じてない。信頼故と思え」
全く口当たりの良い言葉だが、元々この少年は世辞を言う類の人間でもない。真実、そう思っているのだろう。
両眼を閉じて操作盤の傍から離れる少年を苦笑しつつ見送って、【NAME】は視線を正面の硝子板へと戻す。
「……さて」
何気なく呟いて、【NAME】は改めて思案する。
取り敢えず、何れかの層の通路を進み、その先を確かめるという方針は確定として。では考えるべきは何処の通路から、という話となる。
最下という位置に加え、あれだけ露骨な特別さを醸し出しているのだ。五層が遺跡の深部へと繋がっているのはまず間違いないようには思えるが、厭な予感がして仕方が無いのも確かだ。
結局のところは、その予感を無視して五層へと降りるか、あるいは一先ず他の場所を巡り様子を見る妥協の行動を取るかという二択になる訳だが。
選ぶとするならば、さて、どうするべきか。
鈍い音を立てながら、搬器となる平面床が傾いた縦穴の奥へ奥へと降りていく。
第四層の境を越えてから既に随分と下降を続けているが、操作装置の上面に取り付けられた硝子板の表示は、未だに変化を見せない。これまでの第一から第四までの階層はほぼ等間隔であったため気づかなかったが、どうやら、硝子板に浮かんだ図形はシャフトを実際の寸尺に合わせて描かれた縮小図ではなかったようだ。
そして深く潜っていくに従い、これまで比較的正常な状態に保たれていたシャフト内にも、既に慣れたものとなった強い生命の気配と歪な陰性質の気配が漂い始める。恐らく、シャフト内に仕組まれているらしい環境を清浄化するための力でも抑えきれない程に、第四層以降の空間が劣悪なものとなっているのだろう。事実、シャフトを囲う壁の内側に刻み込まれた象形部分は、第四層から上の階層の時よりも強い輝きを放ち、明滅の鼓動も速くなっている。それでも、壁を覆う象形の隙間からは、まるで染み込むようにしてあの特徴的な気配が忍び寄ってきているのが判る。【NAME】達が乗る昇降床にも複雑な紋様の象形が浮かび上がり、まるで床面全体を覆うような輝きを放っていた。
「気配の強さだけで測るならば、これまで巡ってきた場衡機構中枢の凡そ倍、といったところか」
隣に立つリゼラの表情は、普段よりも更に険しい。
【NAME】にしても、これだけの強い気配や歪みというものは殆ど経験したことがない。過去の経験で言えば、命脈が溢れ出る寸前の四大遺跡深部や、幾つかの明確な異界の雰囲気に近く、そこで感じた根本的な異質さ、強大さに比べると等級は些か下がる。だが、それらのように状況の要因がはっきりしている訳でもなく、ただ場所に気配や歪みがこびり付くように残り続けて、今なお薄れる様子を見せないというのは、何より不気味さを感じさせる。
「大禍鬼に比類する鬼種が生じてもおかしくない程の歪だ。これが、遺跡の最奥に辿り着く前から漂っているとなると、ならば最奥では如何程のものとなっているのか。あまり考えたくはないな」
出来れば、この昇降機の最深部が、そのまま遺跡の中枢区画である事を祈る他無いが。
「そうした期待は裏切られるのが常ではあるが――何にせよ、そろそろ気構えをせよ、【NAME】。壁が途切れるぞ」
リゼラの言葉が終わる間際、視界が一気に開けた。
搬器を支えるガイドレールが取り付けられた壁を除いた三辺が無くなり、現れたのは巨大な広間だ。軽く見積もって縦に50、幅は200メートル程の、縦に短い円筒の空間。その上方の縁から斜めに降っていく形で、【NAME】達は空間の下方へと移動していく。
まず目を引いたのが、広間内に広がる風景の異質さだ。
遺跡の地下に存在し、金属質の床、壁、天井に覆われている空間に重なるようにして、夜の闇に閉ざされた空と、なだらかで小さな丘陵群が同時に存在していたのだ。
歪な夜と緩やかな丘の群れという組み合わせは、この遺跡の外に広がるザルナルバック月光丘陵の光景を思い出す。恐らくは幻影か、それに類するものなのだろう。映し出された空も丘陵も淡く透けており、その向こう側に本来存在する壁や床が見え隠れしている。加えて、床面に広がる丘陵はそもそもの寸尺がおかしい。広間内に丘陵が収まるように、全体が縮小されているのだろう。
そしてもう一つの特徴して挙げられるのが、天井部分より広間の中心へ向けて、四方から捻れるように伸びている巨大な四本の導管である。
遠目からでは正確には把握しづらいが、幅は数メートルもあろうかという太いもの。それぞれ、赤、青、紫、緑の四色に塗り分けられた導管の先端は、大きく喇叭状に開かれている。果たして何の為にあるものなのかはさっぱり読み解けないが、全く意味の無いオブジェという訳でも無いだろう。
「このような場所も、以前に訪れた遺跡には無かったものだな。部屋の基礎は過去に訪れた中枢区画に似通ってはいるが、規模が数段違う」
リゼラの呟きに、【NAME】は確かにと頷く。この遺跡自体が、他とは異なる大規模なものであったのか、それとも中枢区画はまた別に存在するのか。出来ればここが中枢区画であって欲しいが、それはそれで、前回、前々回で刃を交えた竜の化生以上の存在が出てくるとしか思えず、どう転ぼうとも厄介な状況になるのは目に見えていた。
【NAME】が深い嘆息をこぼす合間に、搬器は徐々に速度を落とし、広間の床面上にゆっくりと停止する。
位置は広間の中心と外壁の丁度中間あたり。それぞれの距離は大凡にして50メートルといったところだろうか。広間全体には不自然な暗闇の気配は無く、幻影の夜を彩る星々の淡い光が広間の中を照らしているが、その程度では広い部屋の全域を照らす事など出来る筈もなく、殆どの場所は薄暗い闇に閉ざされている。空に月でも出ていればもう少し話は違うのだろうが、どうやら新月であるのか、空に月の白円の姿はなく、中天付近に一際黒い円の縁らしきものが見えるだけで、強い光源となっているのは、【NAME】達が立つ昇降機の搬器から放たれる光のみだった。
昇降床に描かれた象形の光は、今はでは上方へと立ちのぼる程になっており、放たれた輝きの幕が、床の上部を守るように覆っている。これ程の強烈な力を発揮せねば、広間を埋め尽くしてる今にも飽和しかねない程の強烈な気配の圧と、その中で弾ける時を待つ歪んだ概念から搬器を守る事が出来ないのだと考えると、流石に空恐ろしい気分になってくる。
「……さて」
と、傍で身動く気配に振り向けば、昇降床の外側に広がる風景を睨むように見つめていたリゼラが、浅く吐息を付いて腕組みする。
「ただこうして辺りを見回していても話が進まぬが、何の策もなくこの外へと出るのも同様に気が進まぬな」
全くだった。碌な目に遭う気がしない。
うんざりと同意する【NAME】に、リゼラも小さく頷き、
「どうせならば、一息にこの地に蠢く歪みが丸ごと形を得てくれるならば、それを打ち倒すだけで済む故、面倒が無くて良いのだが。問題は、階段を降りてきた時のように細々と小出しにしてきた場合か」
【NAME】としては、まだそちらの方が楽な気もしたが、良く良く考えるとこの広い部屋を探索し、まずここが中枢区画であるのかどうか。マイオトールが目指し術式を行う地として選んだ場所であるのかを確かめねばならない事を考えると、確かに引っ切り無し襲い掛かられるよりはまとめて処理出来た方が結果楽なのかもしれない。
もっともそれは、この猛烈極まる気配が集まり結晶となった存在に勝つ事が可能であるならば、という条件が付くが。
「そも如何様な存在が生じるかも想像するに能わぬとなれば、考え得るは如何様に動くか、か。【NAME】、ここで優先するべきは何かは判るか」
見上げてくる視線に、【NAME】は少しの思案の後に答える。
第一に、この場所が目的地であるかどうかの確認を行わねばならない。方法としては、この場所に彼が残した印章陣があるかどうかを探すのが、一番手軽で確実な方法だろう。
とはいえ、今自分達が居る広間は、過去の遺跡にて辿り着いた中枢区画とは比べものにならぬ程に広い。印章陣を探すにも、相応の時間が必要となるだろう。
また、広間の床部分には縮尺された丘陵の光景が被さるように広がっているため、本来の床の状況が確認しづらく、加えて言えば、その規模の違いは、この場所が中枢区画ではないという可能性にも繋がっているようにも思える。
ならば、印章陣自体を探し回るよりも、ここから更に奥へと続く道筋が無いか調べる事を優先した方がまだ建設的かもしれない。
そんな【NAME】の回答に、リゼラはふむと頷き、
「とするならば、ここでの戦闘は極力手短に済ませるか、もしくは戦いながらであっても部屋の捜索を行い、奥へ向かう道筋を見つけた時点でさっさと先へと進んでしまうのも手であろう。もし、中枢区画が別に存在するのであれば、そこでまた新たな戦闘となる可能性もある。なれば、ここで全力を出すのは些かまずかろうよ」
何とも厭な予想であったが、現実味のある想像なのも事実だった。
【NAME】は疲れの交じった溜息をつきながら、己の武器の具合を確かめる。隣のリゼラも、二本差した腰の鞘から一本の長剣を引き抜き、逆の手を振って九継を顕現させる。
「では行くぞ、【NAME】よ。守りが施されたこの場より一歩外に出れば、一気に負荷が掛かる。くれぐれも、備えを忘れるなよ」
言い捨てて、リゼラが搬器の床から勢い良く外へと飛び出す。
輝く幕から少年の身体が外へと出た瞬間、全身が翠色の炎で包まれたかのように、盛大な光が飛び散った。続けて外へ出た九継の身体も、一瞬空中にて縫い付けられたように固まり、動きを止めるのが見えた。それ程までに、この広間を埋め尽くす気配は濃密なものであるのだろう。
「…………」
一つ、呼吸を置いてから、【NAME】も後に続く。
実の所、命脈の加護を得ているリゼラや、そもそも命脈の断片であり概念的な存在である九継よりも、【NAME】の方がこういった環境に対しての対抗能力は高い。そもそもの素性に加えて、今は神形器から強力な守りの力も得ているからだ。
外へと出た瞬間、全身に強烈な圧迫感が掛かるが、それも元々自分が持つ“同化者”としての力に加えて、流転の神形が齎す守りにより、その大半を受け流す事が出来た。
但し、だからといってこの場所で普段通りに動けるかと言われれば、そう簡単には行かないようだ。己の在り方自体が気配に侵されて歪められるような事は無いが、それらは確かな重圧となって、こちらの動きに制限を掛けてきていた。身体の動きが常より鈍り、五感に乱れが走るのは避けられなかった。
昇降床から広間の床へと降りる。足は緩やかな丘を貫いて、その奥に存在する硬質の床を踏みしめていた。どうやら、床の上にて展開されていた丘陵の光景は単なる幻でしかないらしい。
もしこの丘陵が実際に姿を持っていたのならば、至極歩きづらい地形であった事だろう。全く以て有り難い事実であった。
「……さて、まずは何処へと向かうか。【NAME】よ、何か案はあるか」
改めて辺りを見回しているリゼラに問われて、【NAME】は素早く思案し、二つの候補を出す。
一つは、取り敢えず側壁へと移動してみる案。この広間から別の場所へと続く道が存在するのであれば、出入り口がある可能性がもっとも高いのはそちらである筈だ。外壁をぐるりと回って調べてみるのは至極妥当な行動と言えるだろう。
もう一つは、広間の中心地点の確認だ。広間の形状や、天井から突き出ている奇妙な導管の配置からして、この広間の中央には何かの役目があるように感じられた。それを知るには、取り敢えずそちらに向かってみるのが良いだろうという、単純な判断によるものだ。
と、そんな風に答えながら、部屋の中央付近へと視線を向けた【NAME】は、
「…………」
広間の中心。四本の導管が口を向けた宙空の一点に、幻影の夜空の中で丸く浮かんでいた一際黒い影が、まるで落下するように移動していく姿を見た。
夜の闇の中から抜け出すように生じた不気味極まる黒色の球体は、四つの導管が向ける喇叭の先にて留まると、ぬるりとその輪郭を泡立たせる。
――瞬間、広間全体に向けて、強烈な害意が放たれた。
「どうやら、早々にお出ましのようだな」
表情を強張らせて固まっていた【NAME】の視線を追って、そちらに顔を向けたリゼラが、淡々と呟いて身構えるのが見えた。戸惑う様子など一切見せず、直ぐさま状況に対処するため意識を切り替える様は流石という他無い。【NAME】もそれに倣って、深い溜息一つで気持ちを切り替える。
その合間にも、黒色の球体は更なる変化を続けていた。
空中にて蠢く影の円に幾重もの波が走り、そこから這い出すようにして、四肢持つ大影の化物が姿を現した。四本の導管からは濃密な気配の固まりが大影目掛けて吹き付けられて、影はそれを身に取り込んで、更に巨大に、存在を明確にさせていく。顕現の流れは、過去の遺跡で遭遇した竜の化生とは全くの別物だった。
そして遂には月より溢れ落ち、床へと身を落とした大影の化物は、【NAME】達の方を正確に捉えて、喉を反らして高らかに、この世の生物とは全く一致しない名状しがたき咆哮を上げる。
偽りの新月の夜。
【NAME】達は正しき暗闇の中でなお暗い、黒月の光から生じた異形――外より来る者と対峙する。
battle
月光の焼跡

その影は、あらゆる形状へと変化する無秩序の獣だった。
時には腕を無数に生やし、時には真円の球体へと移り、時には汚泥の波へと変わる。だが他者を呑み込み、喰らう事を第一とする影の在り方に変化はなく、【NAME】とリゼラは、貪欲に迫る大影の攻撃を紙一重の所で躱し続けながら、攻略の糸口を探り続けた。
それを見つけたのは、数えて十九度目の変化の終わり際。リゼラの言葉が切っ掛けだった。
「気づいたか、【NAME】よ」
三本の渦潮となり、【NAME】の身体を取り込もうとする流れからようやく脱し、一息ついていた【NAME】は、それを補助するために剣を振るっていたリゼラが傍に戻ってきた時の言葉に、怪訝な顔を返す。
「あの黒の化物、何れだけ姿を変えようとも、必ず一部、球の姿を残したままとなっている箇所があるようだ」
――つまりは、それがあの大影の核ではないか、という事か。
【NAME】が即座に答えると、リゼラは視線は大影へと向けたまま、浅く頷く。その先では、影の化物がまた新たな形態へと変化しようとしていた。
「ならば、後はそれをどう暴き、どう砕くか、か。【NAME】よ、お前は止めの役か、囮の役か、どちらを望む」
「…………」
――出来れば、止めの役が嬉しいなぁ、と思うのですが、どうでしょうか。
恐る恐るリゼラの方を窺うと、少年はどうも理解しかねるといった表情でこちらを見返し、
「むしろそちらの方が厄介であると思うのだがな。まぁ良い」
言い残し、少年の姿が消える。気づいた時には、リゼラの刃が大影の周囲を光となって走り、続けて幾重もの翠色の爆発となって弾けた。そこへ、上空に身を移していた九継からの炎弾の雨が追い打ちとして降り注いで、大影の身体を削り取る。
しかし、相手は所詮影だ。攻撃による痛み、怯みなどは無縁の存在である。影はリゼラ達に連撃により生じた欠損など気にもせず、その動きを攻撃の為に変化させる。空中に浮かぶ九継、そして床面へと着地したリゼラ目掛けて、飛び散った影を弾丸のように丸め、霰のように撃ち出したのだ。
九継が懸命に身をくねらせて避け、リゼラは縋るように迫る弾丸を飛び退り、刃で弾きながらどうにか凌ぐ。しかし影の弾丸は切れ間無く放たれて、遂には命中した九継の身体が大きく揺らぎ、リゼラの方は防御しつつも押し込まれ、壁際に半ば縫い付けられた状態で動きを止められてしまう。
そんな中、大影が彼等に止めを刺すべく、形態を更に変化させた。
変わろうとした姿は、恐らくは大鉈だ。揺らぐ影の巨刃、平面の長板となった身を大きく縦へと振り上げ、まずはリゼラ目掛けて振り下ろさんとする。
「――――」
だが、【NAME】はそこに勝機を見た。
大影の傍へと一瞬で間合いを詰めた【NAME】は、振り下ろされようとする大鉈の根元――丸く不自然に膨らんだ箇所目掛け、リゼラが飛び出してからじっと練り上げ続けていた技法の一撃を、全力でもって叩き込んだ。
最初に得た感触は、弾力だ。ぐ、と球の中に放った力が沈み込み、押し返されるような感覚。
しかし、直ぐにそれは失せて、続けて貫き、弾けるような爽快な手応えが返ってきた。自分の攻撃が、破壊の力を正しく発揮したのだ。
だが、その事に喜ぶ感情を自覚するより早く、
「何をしている! 直ぐに退けっ!」
リゼラの警告の叫びに、反射的のその場を全力で飛び退けば、【NAME】の一撃によってまるで水風船が破裂するかのように、莫大な量の影の飛沫が八方へ弾け飛んだのだ。
【NAME】は体勢を崩しながらも、もう一歩、更に一歩と地面を蹴るように下がる事で、どうにか飛沫の圏外へと出ることに成功する。
「っ、は……ぁ」
詰めていた息を、深く吐き出す。眼前では、飛び散った影の塊が、在り方を維持出来ずにゆっくりと溶け始めている。
その影の飛沫の一片一片が、先刻まで自分達に襲い掛かってきた、触れれば肉体どころか在り方すら溶かされそうな程の害意に満ちた、黒色の泥である。もし、ほんの僅かでも反応が遅れていたならば、自分は弾けた飛沫にあっけなく呑み込まれていただろう。
九死に一生。そんな気分で茫然と固まっていた【NAME】のところへと、リゼラが薄れていく影の様子を用心深く確認しながら歩いてくる。向けられた表情は呆れに満ちたもので、
「だから言ったであろうが。止めの方が、むしろ厄介であるとな」
「…………」
こうなるのが判っていたならば、先に言って欲しかった。
・
偽りの月より這い出て幻の丘陵へと降り立った、大影の化け物。
それをどうにか討伐する事に成功した【NAME】達であったが、あれだけの莫大な量の影が消滅したというのに、広間を埋める気配が劇的に変化する事はなかった。
未だ広間の内には奇妙な幻影が浮かんだままで、広間を埋め尽くす気配の圧にも、歪みにも大きな変化は無い。そもそも、あの化け物がこの地の陰性概念の飽和によって生じた――つまりは鬼種の類であるのかどうかも、今となってははっきりとしなかった。
「気配にかわりがないのであれば、またいつ先刻のような化け物が生じるかも判らぬ。急ぎ、調べを済ませるぞ」
リゼラの言に頷いて、【NAME】は改めて広間の捜索を開始する。
まずは側壁をぐるりと一周、入念に調べて回るも、部屋の周囲は滑らかな金属質の壁が延々と続くだけで、他の場所へと移動するための通路口は勿論、隠し通路の痕跡のようなものも見当たらなかった。
ならばと、広間の中央へと移動した【NAME】は、その床部分一体が他の所と微妙に造りが違う事に気づく。丘陵の幻影によって視線を遮られていた為、それに邪魔されずに確認するべく、地面にへばりつくように視線を下げた【NAME】は、成る程こうなっていたのか、と納得の声を漏らす。
「如何にした、【NAME】よ」
と、傍へとやってきたリゼラに、【NAME】は今見た光景、広間中心の床部がどうなっているのかを簡潔に告げた。
――要するに、この部分は更に地下へと降りる為の昇降床になっている、と。
リゼラがふむと唸り、【NAME】と同様に身を屈めて幻影の向こう側に存在する床の状態を確認し、身を起こす。
「成る程。雷の泉の遺跡で使ったアレか。とすると、動かす為のものは――」
リゼラが視線を動かすと、直ぐにぴたりと停止する。その先には、丁度幻の丘陵の膨らみに重なるように存在していた操作用の装置らしき台座があった。確認すると、台座の構造自体も以前に見た記憶のあるものだった。どうやら、設計が共通であるらしい。
「しかし、そうなると、ここより更に下方に中枢区画があるのは確実と、そう考えても良いのか」
「更に言えば、ここを降りればまた新たな戦闘が発生する可能性がある、と」
「…………」
そうとは言いきれないのではないか、とは思うが、否定できる材料も今ひとつ見つからない。先刻の影の化け物は過去の遺跡に於ける竜の化生に相当するものではなかったとすると、この昇降床の先に、そうした存在が居る可能性は十分に有り得た。
先刻、派手な戦闘を繰り広げたばかりだというのに、更に大物との戦闘か、懊悩する【NAME】を横目に、リゼラは操作用の装置の方へと近付くいていく。
「今更何を躊躇っているか。これまでの迂遠な旅路の結末が、ようやく直ぐ傍まで来ているのだ。我とお前の力があれば、征せぬ相手などそうは居るまいよ。さっさと覚悟を決めて――」
と、装置を操作しはじめたリゼラであったが、昇降床はうんともすんとも言わない。暫く静止し、矯めつ眇めつした後。彼は表情を消して【NAME】の方へと振り返り、
「さあ、これを操ってみせよ。……我には、どうも絡繰りの類は良く判らぬのでな」
――禍つ秘の記憶が示す形――
それより先はもう、過去二度辿った道筋の再現でしかなかった。
昇降床を操作して移動可能範囲の最下へと降りると、そこには更に地下へと降りる為に螺旋階段の口があり、蜷局を巻いて底へ底へと伸びていく階段を降り続けた先には、無数の象形が刻み込まれている以外は何も無い、殺風景極まる部屋があった。
見紛うような風景ではない。こここそが【NAME】達が目指していた遺跡の最奥、場衡機構の中枢区画だった。
「…………」
しかし、その部屋へと足を踏み入れた瞬間。同じ中枢区画といえども、ここが過去のそれとは全くの別物である事に気づかされる。
まず、場に立ち込めている気配が違った。
中枢区画に降りてくるまでは、あれ程に濃密で雑多で、そして荒れ狂っていた気配の圧は、部屋の中には一片たりとも存在していない。加えて、過去に竜の化生が生まれる要因ともなっていた歪な気配――つまり概念の陰性質な偏りすらも感じ取れなかった。
また、部屋の全面に刻み込まれている象形の状態も大きく異なっていた。
これまでの場衡機構では、中枢区画に刻まれていた象形は何れも、輝きこそ失ってはいないが象形自体の持つ力は発揮されていない状態――いわば待機に近い状態であった。
しかし、ここに存在する象形達は、まず状態が一律ではなかった。壁や天井、中心より離れた位置に刻み込まれた象形は強い明滅を繰り返している状態で、待機どころか駆動状態にあると見ても良い程だ。
だが、部屋の中心点から一定の半径内に刻まれていた象形は一切の輝きを失い、床の色とほぼ同色に解け込んだようになっていて、そこからは微塵の力も感じ取れない。つまり、象形として持っていた力を全く失っている状態であるようだ。
――そして、最後にして最たる違いとして。
部屋の中央には、ぼんやりと人の姿が浮かんでいたのだ。
「…………」
螺旋階段の終端から部屋の中へと入った【NAME】とリゼラは、緊張を隠す事無くその正体を確かめようと目を凝らす。
象形の輝きが失われているためか、周囲より薄暗くなっている部屋の中央。そこで僅かに床から浮遊して佇んでいる人の姿は、【NAME】達にとって見覚えのあるものだった。
「――マイオトール、か」
短く、囁くように呟いたリゼラの言葉は、【NAME】が連想していた名前と同様のものだ。
今は目深に被った頭覆いに遮られてその顔は窺えないが、纏う長衣、携えている大杖、そして彼の周りに浮かぶ七つの玉が、遺跡の深部で手に入れた機甲具が映し出した、【NAME】達が後を追っていた老術士の姿に結びつく。
しかし、記憶にある姿と全てが同一である、という訳でもなかった。より正確には、その在り方が異常、というべきか。
まず、床より足ひとつ分ほど宙に浮かんで留まっている姿が異常。服も含めて身体から色が半ば失われ僅かに背後が透けているのが異常。何より、彼を構築している存在概念が異常だった。放つ気配が、健全な人間のモノでは断じて無い。
近い存在をあげるとするならば、死霊の類だろうか、と【NAME】は考える。
姿形は老人のものではあるが、あそこに浮かんでいる姿は肉を備えた実体であるようには到底見えなかったからだ。
死して肉体を失い、しかし強い残念を抱いていたり、土地概念の変質に巻き込まれる等の特殊な状況が重なった場合に、その者の存在概念が崩滅にまで至らず、現世界に無実体のまま留まってしまう事がある。それが俗に霊と呼ばれる存在だ。括りとしては概念存在に属する不死体の一分類、という形になるだろう。
その内、生前の精神性をほぼ完璧に維持している場合は、精神体という若干方向性の異なる名称が与えられる。アノーレの四大遺跡にて出会った学士レェア・ガナッシュのような者は、正確にはこの辺りの分類に含まれる。中には、肉体すらも何らかの手段で取り戻し、“死を越えし者”という不老不死を体現するに至った者も居るというが、ここまで来ると実在が確認されたのはごく僅かな例のみで、半ば伝承の存在に近いだろう。
逆に生前の精神性を正しく維持出来ていない場合は、それを霊体、死霊等と呼称する。そこから、生前の断片的な感情などだけを残し、それに従って害を及ぼすような存在は怨霊、などとあれこれと細分化されていく事になる。
これらを踏まえて考えるなら、部屋の中央にて浮かぶ人影は、所謂霊として分類できる存在だろう。
何故ならば、人影は【NAME】達が部屋に入ってきてもこれといった反応をみせないまま、僅かに俯き、頭覆いで顔を隠すような体勢で、ただぼんやりと空中に浮かび続けているだけだからだ。
健常な精神と、周囲を認識出来る何らかの知覚。それらを備えているならば、侵入者に対して友好なり、警戒なりの態度を示してしかるべきだろう。そういった反応が無いという事は、少なくともあの存在は真っ当な意識、精神を持つとは言い難いように思えた。
「……さて、どう判断したものか」
視線は中央に浮かぶ老人の姿に向けたまま、リゼラは窺うようにこちらに声を飛ばしてくる。
「【NAME】よ。お前の見立てを聞かせてくれるか」
問いに、【NAME】は先刻考えていた事をそのまま話し、逆に、リゼラの見解を問うた。自分とは違う、キヴェンティという視点から見た解釈というのも聞いておくべきだろう、との考えからだ。
対し、リゼラはふむ、と小さく唸り、
「大凡はお前の所見と変わらぬ。加えて言えば、あの翁からは鬼の気は殆ど感じられぬ。これまでの場所で、我等が討ち滅ぼしてきた竜の化生に相当する存在があの者、という訳でもないようだ」
リゼラの言う通り、人影からは陰性質の概念が放つ独特の気配が全く無い、とまではいかないが、過去に遭遇した記憶のある霊的存在と比べるならば非常に薄いものだった。
誕生の際から概念存在である者達とは違い、肉体を持つ種から概念のみの存在へと転じた者は、一様に概念的に不安定な存在である場合が多く、環境に在り方を左右されがちだ。格の低い霊体の多くが周囲に害を為す存在となるのも、土地概念の微細な歪み、陰性質の偏りから影響を受けて、その性質を陰なる気質――つまりは鬼の性質へと変化させてしまうからである。
この事から考えると、今、【NAME】達の前に存在している存在は、そうした外環境からの影響を受けない程に強固な存在概念を保ったままの、特別な霊体であると言えるだろう。
だが、しかし。
「あのような姿になることが、翁の目指すものだとするならば、失望したという他無いがな」
リゼラの不機嫌そうな言葉は、程度は違えど【NAME】の内心と通じるものだった。
大陸から遠く離れた島にまでわざわざ足を運び、封じられた真なる亜獣達の楽園へと渡り、更にはそこに点在する幾多の芯形機構の最奥にまで潜り込み、そうして目指した結果があのような姿だとは、流石に思えない。
思い出すのは、軍の陣地でイェア達と話した予想だ。
マイオトールは、芯形機構の象形を用いて何かを成すつもりなのだろう、と。
彼が用意していた印章陣を読み取ったイェアは、マイオトールが己の存在を別のモノへと変換しようとしていた節がある、とも言っていた。人体を絡めた、他存在との融合。彼が用意していた術式とは、そんな代物であったという。
だが、今、目前に浮かんでいるそれからは、他の存在と混じり合っているような気配は全く感じられない。
肉体は明らかに損なわれてはいるが、その在り方は人の概念のみがこの場所に焼き付いているかのような、純粋な霊体だった。イェアが解釈した印章陣の効果から考えれば、その結果として生じた存在と見るには、どうにも違和感が残る。
「つまり、あれは失敗した結果であるのか、もしくは――」
至る過程の中であの姿となり、そこから更に術式を駆動させた後なのか、という話になるだろう。
部屋の中心部に刻み込まれている象形から光が失われている事から察すれば、結果の如何に拘わらずマイオトールが象形に対する干渉自体には成功したと見るのが正しいだろう。
ならば、象形を完全に操る条件の一つである、“人の枠から逸脱する”事。それを満たす為に己の在り方を霊体へと変えて、そこから更に違う何かを目指したか?
そんな【NAME】の推測に、リゼラは暫く黙然とし、
「……有り得る話だが、確証も無いな。調べようにも、これまでのように印章陣が残っているようにも見えぬ」
リゼラの視線は、部屋の中央の床上に向けられている。彼の言う通り、色を失った象形の周りには、過去二度の遺跡で見たマイオトールの印章陣は見当たらない。術式の行使によって消滅したのか、始めから存在していなかったのか。遠目からでは痕跡を追う事も難しかった。
――となれば、後残るのは。
この場にて起きたであろう現象の証拠となるものは、あの中央にて浮かぶ術士の姿のみ、となるが。
「して、如何にする? どうやら、あちらからは動く気はなさそうではあるが、かといって声を掛けて通じるような様子にも見えぬな」
となれば、後は近づき、反応を見るしかないだろう。いっそのこと先制攻撃を仕掛けてみるという手もあるが、そも自分達はあの老人を追い、何をしているのかを確かめにここにやってきた身だ。それに対して問答無用で攻撃を仕掛けるというのは些か筋が違うように思える。
【NAME】はリゼラに視線で合図を送った後、ゆっくりとした足取りで、部屋の中央へと歩いていく。
「鬼気はない。が、それだけの話でもある。怠るなよ、【NAME】よ」
背後からのリゼラの言葉に、【NAME】は振り返らぬまま頷く。
武器に伸ばした手を引っ込めぬまま、じりじりと距離を詰めていく事暫し。
床を仄かに照らす象形の輝きが失せた領域、部屋の中心点から凡そ10メートル程の距離に足を踏み入れた瞬間。そろそろ細部まで確認出来る程になった人影に、明確な変化が生じた。
僅かに斜めに向けられていた体が、こちらへゆっくりと向く。同時に、彼の周囲にて無秩序に浮かんでいた七つの宝玉が連なる環を造り、回転を始めた。
速度は徐々に上がっていき、比例するように宝玉が放つ輝きも強く、明確になっていく。その変化によって判ったのは、宝玉それぞれに色の違いが存在する事だ。
先刻までは殆ど無色半透明に見えていた七つの宝玉は、紫紺、深緑、紺碧、漆黒、深紅、黄金、そして月白の輝きを強めると共に、その内側から強烈な力の気配を放出し始める。
放つ力の質は、存在概念を内に秘めた鉱物である理石のものと似ていたが、力の規模は段違いだ。強烈な炎気、雷気、水気などが、それぞれの宝玉から今にも形を得て溢れんばかりに高まっていくのを感じる。師位の術士が数人掛かりで組み上げる大術式でようやく生み出せるような、そんな規模の力が、一つ一つの宝玉の内側で満ちていく。それが外へと放たれれば、凄まじい威力の攻撃となるだろう。
【NAME】は足を止めると武器を引き抜き、相手の出方を窺うように宙空のマイオトールを注視する。
宝玉の環が更に回転し、老人の足元から空気が撓むように吹き上がる。手にした大杖は真っ直ぐにこちらに向けられ、先端に浮かび上がった印章の紋様目掛けて、杖全体から強い理粒子の流れが生じるのを感じた。【NAME】からすれば慣れた気配、術式を行使する際に生まれる理粒子干渉の流れであるが、霊体が印章術式を操るというのは例外が過ぎた。術式を組み上げ、理粒子の干渉を行うには、相応の精神力が必要とされる。思考、意思、そういったものが無ければ、術式を構築し、駆動させるのは不可能だ。
――ならば、あれは霊体ではなく精神体なのか?
そんな一瞬の疑念は、しかし生じた風に煽られて頭覆いが外れ、露わになった老人の顔を見て早々に失せた。
年老い、色を失った男の顔には表情と呼べるようなものは欠片も無く、開かれた瞳はまるで玉を埋め込んだかのように白い。掲げられた手の動きも、どこか糸で引き上げられたかのような不自然さで、そこには到底、マイオトール自身の意思のようなものを見出せなかった。こちらに対して身を向け、術を行使しようとする姿も、単に自分が彼が感知しうる範囲に入り込んだからこその反射的な対応であるように感じた。
――だが、そのような精神状態であるならば、一体どうやって術式を構築しているのか?
「どうした。何を惑っている」
と、横から剣を構えたリゼラの姿がずい、と視界の隅に入ってくる。後方に控えていた筈だが、状況の変化を見て直ぐに前へと出てきたらしい。その横では、彼の袖口から零れた赤糸が、九又に分かれて巨大化していく様子も見えた。
少年の問いに、【NAME】は先刻の疑問を手早く話す。すると、彼は僅かに片眼を細めて考えるような素振りを見せた後、
「あれは、過程であるのだろう」
「……?」
極めて端的な返答に、【NAME】は思わず彼の方を振り向き、凝視してしまう。意味が判らなかった。
【NAME】が向ける視線と表情からこちらの内心を察したのだろう。リゼラは視線を一切正面の老人から逸らすことなく、足りない言葉を補っていく。
「あの術士は、“芯なる者”の力を使い、何かをしようとしていた。しかし“芯なる者”が残した力ある紋様を扱うには、己を人ではないものへと変化させねばならぬ、という話であったな」
頷く。それを気配だけで把握したのか、リゼラは話を続ける。
「翁が残していた陣は、その力ある紋様――象形を内に含めたものであった。そして、それを動かすべくこれまで他の遺跡で幾度も試し、失敗し、そしてこの場所で最後の覚悟と共に挑んだという。ならば、あの姿は」
「――ああ」
成る程、と納得する。
軍の陣地にて、イェアはこんな予想を立てていた。マイオトールは印章陣を使って己の身を別の存在と融合して人の枠から外れ、それによって象形を操る程の格を持つ存在になろうとしていたのでは、と。
だが、良く良く考えてみるとそれはおかしい。その印章陣が象形を絡め、それを拡張するように描かれていたものならば、順序が逆なのだ。肝心の印章陣を駆動させるための格がそもそも足りていない、という話になってしまう。
だから彼は、象形の力などを借りず、これまで【NAME】達が見た印章陣とは違う方向で、己の存在を別のもの――恐らくは概念のみの存在へと変化させようとしたのだろう。
だが、己の在り方を変化させるような術式など禁忌に属する代物だ。それを知りうる知識があり、禁忌を侵すという覚悟があろうとも、司位の術士が入念な準備や最上級の補助道具を用意した上で、幾人もの師位級の術士の力を借りてようやく可能か、という域の御業である。それを独力、しかも全く補助も期待出来ないような状況で行おうとするならば、術式自体を限界まで簡略化し、余分な部分を削ぎ落とさねばならないだろう。
つまり、マイオトールは自身が構築した印章陣を駆動させるためだけの存在――術式の行使以外は何もかもを切り捨てた己へと、その在り方を変質させたのだ。
「だから、あれは過程であり、そして残滓でしかないのだろうよ。我等に対して敵意を見せる理由までは流石に判らぬが、単純に、生前にこの地が大切な場であると認識していた名残が、他者を排除しようという行動に繋がっているのやもしれぬな」
その辺りは正に怨霊に近しい反応で、霊体らしいと言えなくもないが。
「何せよ、どうやらあちらはやる気のようだ。身も心も失い、且つ近付く者に害を為そうとする者に掛ける情けは微塵も無い。――手向けだ、【NAME】。微塵の名残も無く、現世から崩し、滅するぞ」
リゼラが刀剣を構え直し、僅かに腰を落とす。彼の見据える正面では、回転する七つの宝玉が【NAME】達に目掛けて小さな紋様の陣を幾重も重ね、まるで照準のように狙いを付けていた。その陣の内側から生じようとする力は、今まさに自分達に向けて膨れ上がろうとしているように見える。
正直、戦いは避けたいというのが【NAME】の本音であったが、マイオトールがこの場で行っていたであろう術式の詳細や、その結果を手繰ろうにも、現場の上にて居座るマイオトールの存在が邪魔だ。何を調べようとするにも、まずマイオトール自身を片付けねばならない。それも、手加減などという事は不可能だ。相手は霊体、行動原理は極力単純化されてはいるが、説得も力で押さえつけるのも難しい。それを止めるには、完膚無きまでに攻撃し、在り方そのものを消滅させるしかないだろう。
と、そんな事を考えていたとき。
視界の何処かで、強烈な光が瞬いた。
「――っ! くるぞ、【NAME】!」
一瞬、息を呑む間を挟んだ後、リゼラが鋭く叫んで大きく横へと跳んだ。反射的に、【NAME】も逆方向へと飛び退れば、その直ぐ傍を通り過ぎるように黄金色の閃光が貫いていく。
一瞬間を置き、空間が裂けるような耳障りな音が走った。光が通り過ぎた空間が一瞬で高熱を持ち、【NAME】は慌てて更に横へとステップを踏んで、生じた熱の圏内から辛うじて脱出しながら、黄金の閃光の出所を探る。
見誤るような状況ではない。閃光を放ったのは、老人の周囲に浮かぶ七つの宝玉の一つだった。回転する七つの内、一つの宝玉、黄金の色を放っていた宝玉が今大きく輝きを減じており、こちらに向けて連なるように展開されていた紋様の陣が、スライドするようにズレながら消滅していくのが見えた。
続けて、宝玉の列が回転し、別の宝玉が最前へと来る。今度は深紅。こちらへ砲塔を向けるように紋様の陣が重なって発生し、一際宝玉が強い輝きを放った。
瞬くような赤色の輝きが一度走り、続けて宝玉から深紅の閃光が放たれる。
今度は、先刻のような目ですら追えぬ速度を持つ光の槍ではなかった。まるで吹き付けるように放たれ、渦を巻いて広がる炎の嵐だ。速度自体は目で見て回避が行える程度のものであったが、精々幅一メートル程の光線ではなく、太さ三メートル以上、更に発射点となる宝玉から放射線状に広がるような形状の炎が、こちらへと迫ってくる。【NAME】とリゼラ、二人分かれたような立ち位置となったにも拘わらず、両者を飲み込む事も十分可能な広がりだ。
「【NAME】、お前はそちらから回れ! 我は右より挟み込む!」
炎を裂けるため、更に左へと走る【NAME】の耳に、突き抜けていく火炎の流れの向こうからそんな叫びが聞こえた。
案としては至極真っ当。マイオトールが持つ宝玉七つが、どれもこのような儀式技法にも匹敵する強力な大術式を放てるのならば、距離を取ることは極めて危険だ。そのまま、宝玉からの攻撃の連射を受ければ、近付く事すら出来ず一方的な防戦を強いられる事になるだろう。
であるならば、挟撃にて相手の意識を分断しながら距離を詰め、どちらかが懐へと飛び込んで勝負をつけにいくのは全く正しい。
突き出すように溢れた炎の波が、横への薙ぎの動きへと変わる。向きは【NAME】から見て右手方向。つまりはリゼラが居る方向だ。彼からすれば厳しい状況だろうが、逆に【NAME】は一気に楽になった。リゼラが炎の海に呑まれる前に、【NAME】がマイオトールに肉迫し、宝玉の操り主であるマイオトールに攻撃を仕掛ければ、宝玉が吐き出す炎も動きを止める筈だ。
【NAME】は身を屈め、暗く輝きを失った象形が刻み込まれた床を蹴って加速する。
別の宝玉が一つ、自分の方へと照準らしき紋様の陣を展開し始めるのが見えたが、しかし遅い。既に距離は残り五メートル。あと数歩踏み込めば、近接する間合い。宝玉の砲撃よりも早く、こちらの攻撃が届く。
勝利を確信しながら、一歩、更に踏み込んだところで気づく。身動きを止めていたマイオトールの大杖の先端から、何時の間にか虹色に輝く細い紐のようなものが零れ、床に広がっていた事に。
「――――」
突然生じた状況に、顔が歪む。
【NAME】とマイオトール。二人の間に残された数メートルという距離の狭間で、床上に渦巻いていた虹色の紐がむくりと立ち上がり、【NAME】の行く手を遮ったのだ。
虹色の紐が描くのは、大剣を担いだ人型の戦士の輪郭だ。身長はほぼこちらと同じ。広く足と思しき部位を開き、大剣を模した輪郭を背後に振ると、突撃しようとした【NAME】を迎え撃つように薙ぎ払った。
強引に足を止めた【NAME】の胸を掠めるように、虹色の輪郭が走った。辛うじての回避に成功した形だが、しかし、突撃の勢いは完全に崩されてしまった。
輪郭の戦士は振り抜いた勢いを溜めるように殺すと、更にもう一撃を放つために身体を前へと沈み込ませる。同時に、先刻からこちらを照準に捉えていた宝玉から、瞬くような紺碧の光。
「呵――ッ!」
そこへ轟いた裂帛の声は、驚くべき事に上方からだった。右手の方へと払われる炎の柱。それを天井を蹴りながら飛び越す形で、白色の人影――リゼラが大上段に振りかぶっていた刃を斬り下ろす。
標的は、真っ直ぐにマイオトールの頭頂。だが、飛びかかってきたリゼラの存在には【NAME】より早く気づいていたのか、こちらに向けられていた宝玉の照準、そして輪郭の大剣を振るおうと構えていた戦士の動きが変わる。宝玉から放たれた強烈な水流と、強引に身を捻って振り上げられた輪郭の刃が、リゼラの剣線とリゼラ自身を受け止め、後方へと弾き飛ばした。
かわりに、【NAME】には大きな猶予が生まれた。可能であるならばここでマイオトールに仕掛けるべきだったが、しかし練り上げていた技法は既に解けてしまっている。今から瞬質技法にて攻撃したとて、大した傷は負わせられない。そう判断した【NAME】は、仕切り直す意味を込めて、空中にて身を回して後方に着地したリゼラの傍まで一気に後退する。
「……全く、宝玉と術士のみかと思えば、更に従者が増えるとはな。謂わば盾の奥に弓と術士という構えか」
忌々しげに言い捨てたリゼラの表現は、今相対する彼等の組み合わせを的確に表していた。
床にて次々と立ち上がる輪郭の戦士達が盾としてこちらの近接を防ぎ、その間に弓である宝玉が狙い撃ちにしてくる。肝心の主といえばその奥で不動であり、こちらは壁を倒し、弓を潜る事でようやく手を届かせることが出来る遠い存在だった。
「あの虹の化生を造り出しているのがマイオトールだというのならば、どれだけ倒そうとも無駄だ。大元を断たねばならん。如何に守りを崩し、要を直接狙うかを考えるしかなかろうな」
もっともな話ではあるが、それを実現するには一体どうすればいいのか。
そう話す合間にも、輪郭の戦士達の向こうで、宝玉が新たな紋様を表示し、光による攻撃の照準をこちらに定めようとしていた。
「我と、そして九継」
一瞬、リゼラの視線が上へと向く。見れば、天井付近に張り付くように九頭の炎蛇が待機し、こちらと敵の様子を窺っている。
「我等が陽動に回る。どうにか盾と弓、守と攻に間隙を作ってみせよう。【NAME】、お前は機を待ち、我等が生み出した隙を突き、あの術士を崩滅させよ。出来るな?」
「…………」
果たしてリゼラ達が無事にこなせるのか。そしてもしこなせたとして自分がその隙を活かせるのか。
二重の意味で確信が持てなかったが、しかしこの場を切り抜け、生き残るためにはそれを為さねばならない。
【NAME】が頷く。前方、回転し浮かぶ宝玉の内の一つから紫紺の輝きがあふれ出すのが見える。猶予は無いと、そう判断したのはリゼラも同様だったのだろう。彼は浅い吐息のみを残して、その場から掻き消えるように駆け出す。驚くべき速度で、宝玉の照準を避けるように曲線を描いて走り込むリゼラと、それを援護するように天井から火弾を放つ九継。宝玉の内の一つが漆黒の輝きを放ってそれらを防ぎ、紫色の光が宙をうねるように走りながらリゼラを狙う。少年と九頭蛇、老人の霊と彼が従えている宝玉と輪郭の戦士達。その絶え間ない攻防に対し、消極的な干渉でもってリゼラ達を補助しつつ、【NAME】はじっと勝機を窺う。
「そういう事か!」
殺到する輪郭の戦士達の刃を凌ぎ切り、宝玉から放たれる六色の閃光を掻い潜り、マイオトールとの距離を至近にまで詰めた【NAME】が放った、正に死力の一撃。
それがマイオトールの身体を何の手応えも無く摺り抜けたところで、【NAME】の決死の突撃を補助するべく動き回っていたリゼラが、そう愕然と声を漏らすのが聞こえた。
だが、【NAME】にはその意味を問い質す余裕も無い。
技法を打ち切った姿勢のまま硬直する己の位置は、敵の懐の中である。霊体どころか、単なる幻像であったかのようなマイオトールの姿は、【NAME】が巡らせる視線の中、背後でこちらを術式で打ち抜くために手を掲げており、そこからは変質していく理粒子の気配が強烈に沸き上がる。同時に、彼の周りで環を描いて巡る七つの宝玉が、秘めた力を自分に放出しようとしている気配も明確に感じた。
彼我の距離、双方の体勢、攻撃が生じるまでの残り時間。
それを考えれば、躱せる状況ではなく、致命の一撃を避ける事すらも至難に思えた。
だが、ここで諦める訳にも行かない。【NAME】は何とかこれから身体を襲うであろう無数の攻撃に対するダメージを軽減するべく無理矢理身を動かそうとし、
「九継! そのまま行けっ!」
そんな叫びが耳に届くと同時、予想外の方向からの衝撃と共に、視界が派手に横へと吹っ飛ばされた。
「――が、ぐ」
頭が強烈に揺れた。全身が軋み、肺から空気が押し出される。続いて、身体の側面が熱く焼かれるような感触が走ったが、それはすぐ後の床に叩き付けられ、勢いそのままごろごろと転がる衝撃によって直ぐに記憶の外へと追い出された。
十回転に届かない辺りでようやく身体が止まるが、受けた衝撃のせいで満足に呼吸することも出来ない。
一体何が起こったのか。
ようやく身に受けた衝撃の余波が抜けきり、眩み歪んでいた視界が、正常な像を結び始める。どうにか身を起こそうとした【NAME】の視線の中では、床に転がったままの自分目掛けて殺到しようとする輪郭の戦士達が、側方より走り込んできた白色の人影が放った翠の光により横薙ぎに払われる様が辛うじて見えた。
「生きているか、【NAME】よ」
数歩、【NAME】の方に背を向けたまま、飛び退るようにして近付いてきたリゼラからの問いに、【NAME】は何とか、と絞り出すような声で答える。
「ならば結構。九継の献身も報われよう」
その言葉と、そしてようやくはっきりとしてきた視界の中、リゼラが見据える前方にて、七つの宝を従えて浮かぶ人影の足元で砕けていく炎の残骸に、【NAME】は自分がどのようにして助かったのかを理解する。
リゼラの翆霊である九継が【NAME】を横から突き飛ばし、入れ替わりとなる形で、七つの宝玉と、そしてマイオトールの術式による攻撃を一身に受けたのだ。床にて広がる炎からは、既に九つの頭を持つ大蛇という姿を見いだす事は出来ず、その炎も瞬く間に小さくなって、最後に僅かな火の粉を散らして消滅してしまった。
――九継は、死んでしまったのか。
半ば茫然と、消えた炎の名残を見つめていた【NAME】だったか、視界の隅、こちらへ僅かに振り向いたリゼラが僅かに嘆息するのが見え、
「気に病む程の余裕があるならば急ぎ立て。翆霊とは“孔”より出でる命の形でしかない。謂わば呼ぶ度に生まれ、還る度に死に行く者よ。もっとも、砕き絶えた今も、この場には僅かなりと九継の存在が残っておる。これが完全に消え去るまでは、また九継を喚び出すことは叶わぬが」
つまり、“孔”の持ち主であるリゼラが存在している限り、九継は身体が粉々に破壊されようともまた新たに喚び出す事が可能だが、しかし再出現させるにはある程度の間が必要、という事か。
「然り。……なに、もう彼奴の種は割れた。後は九継が居らずとも、我とお前で何とか出来よう」
立ち上がり、身構えようとしていた【NAME】は唖然とリゼラを見る。これまでの戦いの中で、何処にそんな要素があったのか。むしろ、マイオトールの霊体に攻撃が通じないことが判明したのだから、状況はより悪い事が判明したのではないか。
そんな【NAME】の言葉に、リゼラは軽く肩を竦めて、
「単に、我等が見誤っていただけの話よ。あの老人の姿がマイオトールであると、そう認識していたのがそもそもの間違いだ」
「……?」
どういう意味か。眉根を寄せた顰め面で固まる【NAME】に、リゼラは視線だけである一点を示してみせる。
彼が見たのは、老人の霊体の周囲を回る七つの宝玉――そのもっとも後ろに配置された、月白の輝きを放つ宝玉だ。
「あの七つの宝玉の内、一つだけ。一切攻撃も防御にも使われていない。だが、宝玉自体からは強い力が放たれているままだ。あれ自体は、今も恐らく、内側に秘めた力を発揮している状態なのだろう。だが、奴の姿にそれらしき変化はない。という事は、だ」
――つまり、今【NAME】達が見ている彼等の常態。それを根本から形作っているのが、あの宝玉である、と?
言葉尻を引き取って【NAME】が問うと、リゼラは浅く頷く。
「妙だとは思っていたのだ。何の依り代もない単なる霊体にしては、在り方がどうも安定しすぎているとな。あそこに浮かんでおる翁の姿は、正しく幻像よ。その本体、マイオトールが己の存在概念を変じた対象が、霊体ではなく宝玉であったとするならば、成る程、陰性質の概念に然う然う汚されぬ事も合点がいく」
で、あるならば、
「崩滅させるならば、あの宝玉自体を狙えば良い。弱点が判れば後は楽なものだ。虹の化生は、まだ然程の数も戻ってはおらぬ。今ならば、容易く割れようよ」
そんな単純に行くものなのか、と【NAME】は首を捻るしかない。
九継は戦線離脱、こちらにしても先刻受けたダメージがまだ抜けきっていない。万全の状態でどうにか押し込んでいた相手に、この戦力でどうにかなるのだろうか、と。
対し、リゼラは軽く鼻で笑い、
「――一太刀。それにて済むと判っているならば、そう難しい話ではない。どれ、【NAME】よ。今度はお前が、少しばかり奴の動きを止めてみせよ」
「…………」
無茶を言う。
しかし、リゼラに何らかの勝算があるらしい事も理解は出来ていた。逆にこちらにはそういったものが無いのだから、彼に賭ける方がまだ状況が好転する可能性があるだろう。
武器を構え直し、マイオトールに向かって駆け出す。宝玉がぐるりと周り、数を減らしはしたものの未だ数体は存在する輪郭の戦士が、行く手を阻もうと動き出す。
――さて、動きを止めるにはどうしたものか。
これといって思いつく事が無かった【NAME】は、接敵する前に適当な大技を練り上げると、照準や効果などは一切考えずに適当に輪郭の戦士達目掛けて撃ち放つ。
大雑把な爆発が生じ、輪郭の戦士達が吹き飛ぶ。案外マイオトールまでのルートは簡単に開いたな、と暢気に考えた【NAME】の視線の先では、居なくなった輪郭の戦士達の間から、宝玉による射撃が今まさに放たれようとしている様が確認出来た。
「あ、まず」
幾ら受けたダメージが完全に抜けきっていなかったとはいえ、流石に動きが短絡過ぎた。宝玉の輝きは三つ。同時に三本の光線から狙われているのだろう。そんな中、確かにリゼラが示していた月白の宝玉は一切の身動きを見せておらず、よくこんな事に気づいたものだなどと、場違いすぎる感想が浮かぶ。色々と諦めてしまったが故の現実逃避だろうか。
次の瞬間、三つの宝玉が強烈な光を瞬かせ、それぞれが秘めた概念を吐き出す。それを【NAME】は碌な回避運動もせずにただ見届けようとして、
「伏せよ、【NAME】」
それよりほんの僅かに早く聞こえた声に、身体が反射的に従う。
膝が砕けるような形でかくんとその場に身を折った【NAME】の頭上を、何かが割り裂く感覚が走り、
「“翳ろ――古の月[エンシェントムーン]”」
短く静かな、そんな声音が耳朶を打つと同時。
半月の断層が【NAME】の頭上を横に斬るように生じ、放たれた三つの閃光の出所となる宝玉はおろか、他の三つの宝玉も巻き込んで真っ二つに断ち割るのが見えた。より正確には、最奥に浮かんでいた一つの宝玉を守るために、断層上に存在していなかった宝玉達が割り込んだのだ。
幾つもの硝子細工を地面に叩き付けたような甲高い音を背景に、分かたれた三つの閃光が【NAME】のすぐ傍を突き抜けていく。その結果に【NAME】が驚きの声を挙げる前に、更なる何かが、また【NAME】の頭上を貫いていった。
先刻の一撃が線であるならば、次に放たれた一撃は点だった。
翠色混じりの光撃が、先に横へと割った空間に対して突き立つように刺さり、その一撃は【NAME】の真正面、マイオトールの幻像の背後に半ば隠れるような位置取りに身を移していた最後の宝玉へと叩き込まれる。
月白の宝玉に光撃が突き刺さり、一瞬だけ耐え、しかし僅かな罅が生まれ、それが瞬く間に全体へと走り、そして砕け散った。
――その瞬間。
これまでの六つの宝玉が破壊された時とは、全く違う現象が生じた。
まず、月白の輝きが、広間全体を埋め尽くす程の強さで炸裂した。
「っ」
視界全てを白の一色で彩るくらいの強烈な光の炸裂と共に、耳の奥を掻き毟るような甲高い音が鳴り響き、【NAME】は思わず目を閉じ、耳を塞ぐ。
しかし、数秒で収まると予想したその現象は直ぐには消えず、音も収まる様子がない。
目を閉じていても瞼を貫いて眼球に突き刺さる光の炸裂と、頭の中で木霊する反響音。
【NAME】は頭を抱え込むようにその場で蹲って、どうにかその異常極まる状況に耐えようとし、
「……え?」
そんな声が、喉奥から零れた。
閉じていた瞼の裏で、まるでこちらの意識に焼き付けてくるかのように、無数の、これまで【NAME】が見た事も無い光景が映し出されていく。
耳に響く音にも、変化が生じていた。反響する音とは別に、無数の人の声が重なるように頭の中で広がっていく。
同時に、胸の奥に幾つもの感情が、唐突に、まるで何処からか植え付けられたかのように、溢れてくる。それはこれまで自分が抱いた経験のあるものもあれば、ないものもあった。良感情、悪感情。抱いたこともない思考。知るはずもない知識。そんなものが、光と反響音で漂白された【NAME】の意識に、五感に、次々と焼き付けられていく。
その現象が、あともう少し続いていたら、恐らく【NAME】は耐えられなかっただろう。
だが、その丁度境目というタイミングで、唐突に光と音が消え去った。
「…………」
完全に、頭の中が空白になっていた。
三つ呼吸を置いて、【NAME】はようやく、自分の状態を把握する。
最後の記憶にあった己の体勢は、確か両の耳を抱え込んで蹲る、というものだった筈だが、今の自分は仰向けに大の字の状態となって、茫然と天井を眺めていた。
目端から、涙が流れた痕を感じる。【NAME】はこめかみを抑えながら上体を起こし、次に目頭をもみほぐしながら、深く息を吸い込み、そして吐き出す。
――今、自分に何が起こった?
思うのは、それだ。慎重に、状況を思い出す。
マイオトールの霊体との戦闘。リゼラの勝算。それを活かすべく前へと出た【NAME】は、輪郭の戦士達を蹴散らすも宝玉の狙撃による危機に陥り、しかしその隙を逆に利用する形で、リゼラが宝玉達を全て破壊。そして最後の、先刻まで戦っていたマイオトールの本体とリゼラが見積もった宝玉が砕け散った時、
「――――」
炸裂する光。鳴り響く反響音。
その中で、自分は一体何を見た?
断片的な筈なのに、幾つもが重なり合っている、見た事も無い光景と感じた事も無い感覚、そしてそれに連なるように付随する未知なる思考の重層。
それを恐らく、近い言葉で言い表すならば。
「……誰かの記憶、か?」
呟かれた声は、自分のものではなかった。
驚きに顔を上げると、数メートル程離れた場所で剣を片手に立ち尽くし、同じく驚いたような顔でこちらを見るリゼラの姿があった。
・
既に、広間には静寂しかない。
場衡機構の最深部。探し求めた老人がここで形として残したものは、力を失った象形と、彼が術式の仕掛けとして用いた道具だけだった。
彼が己の存在を賭して駆動させたと思われる印章陣は、僅かな痕跡を残すのみで到底読み取れるようなものではなく、【NAME】が知る事が出来たのは、ただ奇妙な焼痕を広間の中央に残しているという、どのような解釈が出来るのかも不明な一点のみだった。
後には、もう何もない。彼の術式が――象形という“芯なる者”の力を利用しようとする程の大きな何かを起こす筈の大術式が、一体どんな結果を生み出したのか。その答えを導き出せるようなものは、何も。
「……【NAME】、そろそろ行くぞ」
既に、螺旋階段へと続く出口付近に立っていたリゼラが、こちらに声を掛けてくる。
可能な限り、自分とリゼラで出来る調査はしてみたつもりだった。しかし、結果はといえば全くの無駄骨としか言いようのない結果だった。
【NAME】は頷くと、一度改めて部屋の中を見渡す。
もう、この場に用事はない。恐らく訪れるのはこれで最後となるだろう。
【NAME】は何気なく、最後に部屋の中央へと視線を向けて、
「――――」
一瞬、見知らぬ視点の風景が重なるように過ぎる。
部屋の中心から緻密に描き込まれた、まるで絵画の一つかと思える程に美しい印章陣。その中心にて背中を曲げて、祈るように頭を垂れる誰かと、その先で横たわる誰か。
だが、その幻視も一つの瞬きで消え去る。
【NAME】は僅かに頭を左右に振ると、既に先に行ったリゼラを追って、広間を後にする。
全ての来訪者が去り、大気が完全に静止する。
広間は、本当の静寂に包まれた。
真なる楽園 彼方の宝玉が辿る果て
──彼方の宝玉が辿る果て──
リゼラを探し、【NAME】はエルツァン島沿岸に設けられた常駐軍陣地の近くに存在する、キヴェンティ達の小さな野営地へと足を運んだ。
しかし、彼が常の居所としていた天幕では、その入り口にキヴェンティの戦士が一人控えているだけで、中は無人。どうやら、主は不在であるらしい。
仕方無く、側仕えの役割も務めているであろう若い男に、彼等の主の行方についてを訊ねる。普段、碌に会話をしたこともない相手であったが、彼はあっさりとリゼラの行く先を教えてくれた。その応対は、普段常駐軍の兵士達がしている噂話――キヴェンティ達の取っつき難さから想像していたものとは少し違っていて、有り難いものの若干拍子抜けした感は否めず。
そんな【NAME】の態度から内心を察したのか。続けて口を開いた彼曰く、どうもキヴェンティ達の間では、四大遺跡での件も然る事ながら、コルトレカン島にて関わった事件も妙な形で伝聞として伝わっているようで。
加えて、彼等からすると己の主となる幼き若長と対等に近い友誼を結んでいるようにも見え、結果、どうやら自分は、キヴェンティ達の中ではそれなりに畏敬の念を抱かれているらしい。
何とも言えない居心地の悪さを覚えながら、話をしてくれた戦士に別れを告げて、【NAME】はキヴェンティ達の野営地を離れ、先刻の男が教えてくれた場所へと向かう。
リゼラが向かった先は、海岸線を暫く歩いた先にある大岩の上であるとの事だ。最近の彼は、そこに一人で向かい、何か考え事をしている事が多くなったという。
「…………」
少しばかり、思い当たる節はあった。そうした時間が増えたのは、何も彼ばかりではない。【NAME】とて、同じであったからだ。
リゼラと共に赴いた、三つ目の場衡機構。
まだ、あの場所で見た情景を自分の中で上手く整理できていない。常駐軍の陣地に帰還した後、探索結果についてイェア達に一応の報告は行ったが、それもあくまで簡易のものに留めてもらっていた。
キヴェンティ達の野営地が存在する森の境界を潜り、【NAME】は海岸へと出る。
そろそろ夕の刻限に入ろうかという頃合。赤く染まり始めた空と海の風景に混じり合うように、岸に転がる巨岩と、その上に座り彼方を眺める少年の姿を見つけた。
「――【NAME】か」
巨岩に近付き、声を掛ける前に、振り向かないまま少年の声が【NAME】の耳に届く。気配と足音だけで存在を気取り、何者かを特定してみせる。一人佇み、物思いに耽っているようでいて、その鋭さは普段通りのままであるようだ。
【NAME】も大岩の上へと移り、彼の隣に何となく腰を下ろす。少年が向ける視線の先には、赤く輝く大円が、そろそろ海の端へと沈み始める景色があった。【NAME】も暫し無言でその様子を眺めていると、隣から声が掛かる。
「して、何用か。今から“鬼喰らいの鬼”を討つための旅に出る、という話か? もう日が暮れようかという今より出立とは、少々時が悪い気がするが」
それもある。もっとも、出発するならば少なくとも明日にはなるだろうが。
旅の同行を頼む話は、用件の内の一つでしかない。【NAME】が今日、彼の元に訪れたのにはもう一つ、別の理由があった。
――あの時。
思い出すのは、月光の丘陵の地下。最後の場衡機構、未だに生きた芯形機構の最奥にて遭遇した七宝を操る幻像との戦いと、その決着の際に起きた、まるで走馬灯のように意識に過ぎる無数の光景、無数の意思。――恐らくは、何者かの記憶についての事だ。
砕け散った宝玉から発した光が消え去った時。確かリゼラも、彼らしくもない茫然とした様子であったように思う。ならばあれは、自分と同じようなものを見ていたのではないか、という疑問だ。彼が呟いた言葉は、【NAME】の心中にあったものと全く同じであったからだ。
【NAME】がそのような事を問うと、リゼラの視線がようやくこちらへと向けられる。
「……【NAME】、やはりお前も、視ていたのか」
頷く。
だが、あれを視た、といって良いものなのか。それすらもはっきりしない。
あれはまるで、一人の人間の半生を、たった僅かな数瞬に込めて、意識に焼き付けられたかのような感覚だった。
複数の光景、複数の情景が折り重なるような形で記憶されて、それを上手く分解して理解できないのだ。ただもやもやと、重く密度の濃い何かが頭の中に留まっている、居心地の悪い感覚が消えてくれない。
そんな風に【NAME】が語ると、リゼラは少し目を見開いてこちらを見、
「成る程、上手いたとえをするな」
そうして、少し考えるように視線を泳がした後、
「……であるならば、だ。我とお前で、その記憶についてを補い合い、組み立ててみる、というのはどうだ。一人で形なきものを掘り返すよりも、言葉を介し、二人の意識と思考でもって再構成すれば、この乱雑に積み重ねられた状況の塊も、確かな人の生の記憶として並べ直せるやもしれぬ」
確かに、と【NAME】は息をつく。
少なくとも、個々で考え込むよりは、互いに話し、情報を客観的に見ていけば、もう少し把握しやすい形にする事が出来るだろうし、そもそもリゼラと自分が見たものが同じものなのか、それとも違うものなのかを知る事も出来るだろう。
【NAME】とリゼラは、岩の上で身を正し、互いに向かい合う。
行うのは自身の記憶に焼き付けられた、他者の記憶を検分していく作業だ。
「では、始めるとしよう。――あの七宝の光が、我等に何を残そうとしたのか、それを知る為にな」
・
年齢を考えれば、恐らくこれが最後の遠征となるだろう。
後を継ぐであろう副官に、守護機士としての教えを徹底的に教え込み、最後には皮肉混じりの礼を言われながら見送られて、久方ぶりの自室へと戻った自分の元に、これまた久方ぶりの相手からの手紙が来ていた。
一人息子からである。
自分と同様、研究肌の性質を持っていたが、こちらが何故か荒事主体の軍人になったのとは対照的に、息子はごく普通に研究者としてのレールに乗って学院へと入り、そして実地研究主体の学士となった。王都セーリエンからは遠く離れた国境の僻地に居座り、そんな辺境の地に見合った何やら地味な研究を続けているらしいという噂を聞いてはいたが、とうの本人から手紙が来るというのは、さて何年ぶりだろうか。
部屋の掃除は、どうやら誰かがしていてくれたらしい。本棚や机に椅子、研究用の道具や機甲具に、宝玉や硝子細工といった調度品も綺麗に磨かれていた。
然したる埃も積もっていない椅子を引くと、封を手早く切って中身に目を通す。
親愛なる、から始まり、適当な時候の話が続き、しかし本文は短い。息子らしい、簡潔な手紙であったが、しかしその本文が中々の衝撃を齎した。
『いい人が見つかりました。ここで、一緒になろうと思います。学院には戻れそうにないので、済みませんが後の事を宜しくお願いします』
「…………」
少なくとも、妻が生きていて、セーリエンで共に過ごしていた頃は、余所のお宅と比べれば親孝行な良い息子だと思っていたのだが。
机に肘を突き、頭痛を堪えるようにこめかみを揉む。最近気になっていた白髪が、更に増えそうな状況だったが、しかし、口元は僅かに緩んでいるのも自覚できた。
嫁を娶り、子を産み、家族を作る。
その様を親に見せてくれる事が一番の親孝行だと、今は亡き両親が自分に告げた台詞が、今になって胸を突いた。
「……全く、親不孝者がっ!」
雷雨の中。途中の村で買い取った馬を走らせながら、そんな言葉が口からついてでるのを止められなかった。
泥濘んだ細道は、既に馬で走るには厳しいものだ。実際、馬の持ち主であり息子の家までの道も教えてくれた村人から、そこに馬で行くのは危険だと止められた程だ。
だが、悠長に向かう気にもなれなかった。懐には、長らく音沙汰のなかった息子からの手紙が仕舞い込まれている。
それは、危急を告げる手紙であり、後を託す手紙でもあった。
一体何があったのか。そのような状況であっても簡潔な文面でしか送ってこない息子が恨めしい。よくこのような文才で学士になどなれたものだと呆れる他無いが、そもそも嫁を貰ったという手紙を寄越してきた後、学院との繋がりも断っていた訳だから、そもそも学士としての適性も無かったのかと溜息をつくしかない。
森の合間に伸びた道を馬は走る。近隣の村から、息子が住むという小屋まではそれなりの距離が存在していた。村の住民の話では、息子はその小屋でひっそりと暮らしており、時折村へとやってきては、薬士や施療士紛いの事をしたり、見た事も無いような不可思議な衣服などを持ち込んで金や食料などと交換していたらしい。村の者の中には、その小屋へと出向いた者も居たようではあったが、大抵応対するのは息子であろう男のみで、他の住人の気配はするものの、顔を合わせたことはないという。息子は元々愛想が悪い方でもないので村人達にはある程度受け入れられていたようだが、やはり若干距離を置かれていたのは確かなようだった。
ただ、気になるのは、村人達は息子の姿しか見た事が無い、という部分だ。
「あの手紙が嘘だったという事は考えたくもないが……」
あれから、もう十年を超える年月が流れている。いつかは連れてくるだろう、もしくはいつかは自分を呼ぶであろう、そう思い待ち続けての今である。まさか、息子の居場所を知る機会が、助けを求めるものであるとは思いも寄らなかった。
そこでようやく森が開け、目的地と思われる小屋の姿が見えた。馬から飛び降りると、手早く手綱を結びつける。もどかしいが、この雷雨だ。放置する訳にも行かない。外套はじっとりと雨を吸って重い。これまでの長旅での疲労が、老いた身体を鈍く蝕んでいるのを感じる。身を包む装備が相応の相手に対処するための機士装備であるのも問題だった。セーリエンから走ったところで、直接的な害に対抗するには遅すぎるというのに。そう言った判断が出来なくなっているあたり、もう守護機士としては生きていけないだろうと考えながら、小屋の扉をゆっくりと開き、中へと入る。
合計して、三つの部屋しかない小さな家だ。家の扉からはそのうちの一つの大部屋の内しか見えず、他の二部屋は独立していた。
一つの部屋は、寝室だった。そこには大小二つの寝台があり、大きい方は二人が一緒に寝られる程の大きさだ。少なくとも、息子は誰かと住んでいた事が確かめられて、情けない吐息が漏れた。
だが、安心できたのはそこまでだった。その寝台の内の一つ、毛布に包まれるように何かが横たわっている事に気づいたのだ。
息子が送ってきた手紙の内容が思い出される。機甲具を展開するかどうか迷い、しかし場からは害意もなにも感じられない事から、そこまでの用心は不要と思い直す。
毛布を、慎重に捲る。その下に存在していたのは、
「……結晶?」
形状としては菱形に近い。大きさは凡そ人と同じ程度の、鈍色の結晶が、寝台の中に収まっていた。
拍子抜けと、疑問。両方が胸の内を占めたが、考えたところで何か思いつく訳でもない。今自分がしなければならないことは息子の安否の確認と考え、その場から離れる。
続くもう一部屋へ入るための扉を開けたところで、足が凍り付いた。
室内自体に、大きな問題は無い。恐らくは施療用の部屋なのだろう。部屋のあちこには薬品や薬草、煎ずるための道具や術式を使うための同調誘導器などが置かれている。
ただ、その部屋の下から、強い術式の気配が漂ってきている。しかもこれは、自分の経験に従うならば余り良い類の気配ではない。
床を調べると、案の定、地下へと続く縦穴があった。下ろされていた縄梯子を伝い下へと降りていくと、途中から穴の側壁に印章が刻み込まれている事に気づく。
厭な予感が増す。床一面ですらなく、側面、上面、丸ごとに印章を刻み込む、部屋単位の印章陣は、一人身の術士が身に余る大術式を行使するために良く使う、手間暇重視の代物だ。
つまり息子は、それ程の術を、わざわざ自分の小屋の地下に穴を掘ってまで使おうとしていたのだ。
一体何をしていたのか。
縄梯子の終端から手を離し、地下の小部屋に降り立つ。灯りは無い。真っ暗に閉ざされた空間。機甲具を素早く起動させると、狭い室内全体を、白色の輝きが照らす。
目にした光景に、深い溜息が零れた。
「本当に、親不孝者が」
床に刻まれていたのは赤色の印章陣。その中央にて腐蝕し、虫の湧いた亡骸が一つ、己の胸を刃で貫く形で突っ伏している。印章陣を軽く読み解けば、その効果はそれとなく知れる。絶対領域[フォースフィールド]の系譜に連なる禁術、生命停滞の術式。命を代償にして命の流れを静止させる術式だ。
「……そして、初めまして。恐らくは、ワシの孫娘殿」
そして倒れる亡骸の前には、淡い赤色の輝きに包まれて眠るまだ幼さの残る少女の寝姿があった。
正に、目の回るような日々だった。
息子の手紙に記されていたのは極めて短文の内容でしかなく、まず孫娘がどのような状態にあるのかを把握する作業が先となった。
しかし、これがまた難しい状況だった。孫娘の状態を静止させている術式がまずフォータニカにおいては禁術の類である。見つかれば、タダでは済まない。そのため、孫娘の存在は慎重に隠蔽した上で、ほぼ独力、もしくは事情を明かさずに情報を集め、解法を探さねばならなかった。
既に守護機士としては引退し、隠居同然の暮らしから一転。過去に培ったあらゆる縁故を活用できるだけ活用し、あらゆる資料、道具を、貸室に集めさせ、黙々とそれらを読みふけり、調べ、そして宛が見つかればそこへと足を運ぶ。
孫娘の状態は、比較的早い段階で知る事が出来た。彼女を救助した際に見つけたあの結晶が大きなヒントとなってくれた。同時に、何故息子が自分に嫁、そして娘に最後の時まで会わせようとしなかったのも、何となく知れてしまった。
だが、そこから先が中々進展しない。孫娘自体には強力な停滞の術式が施されているため、時間的猶予はあるが、しかし何年と掛けて良い代物でもない。なにせ、唯一彼女を救う事が出来るであろう自分が、もういつちょっとした病で逝ってしまってもおかしくないのだ。他に託せる誰かが居ない現状、頼りは自分だけである。まだ動ける内に、どうにか解決してしまいたかったが、ある程度、どうすれば良いのかという方針は纏まったものの、如何せん、それを実現するのに適した道具と、適した場が見つからない。
幾つかの手段を試し、目処が全くたちそうにないと諦め、机に突っ伏す。
もう思いつく場所、現存する手は殆ど試し終えて、五里霧中の状況にあった。
ぼんやりと、机の上に積まれた資料を手繰る。東の果ての深き森の伝承。西の大陸に伝わる竜皇の噂。違う違う、どれも違う。思い、捲って、ごく最近運び込まれてきたその資料に目を通したところで動きが止まる。
虹色の夜。あらゆる不可思議、異質な景色、そして過去に存在したかのような遺跡が突如現れるという謎の現象が、大陸の西の端、グローエス五王朝にて起こっているという噂。
そして亜獣達の楽園。東西二大陸の間に存在する諸島は、人の手が未だ分け入らぬ秘境であり、そこには過去に人の手によって滅ぼされ絶滅した筈の亜獣や、古の“芯なる時代”の遺物が今にも生きた形で残っているという。
資料を詳しく読み込む。どちらについても、強く気を引く部分が見つかった。賭けるのであれば、もうここしかない。
確か、と記憶を漁る。守護機士時代、各地を飛び回っていた経験から、様々な場所に隠れ家を用意していた。グローエス五王朝内にも、確か幾つかそんな場所があった筈だ。今もそれが無事かどうかは判らないが、流石に全滅という事はあるまい。
机の上に手を伸ばす。資料に隠れるような形となっていたそれは、月白の色合いを持つ宝玉だ。父より受け継いだそれは、先祖が芯形機構に入り込んだ際に手に入れた強力な魔導器でもあった。問題は、本来この宝玉は単独ではなく八つを組み合わせて扱う代物であるという点。既に他の七つは失われていたという話であったが、資料によれば、どうやらこれに良く似たものが、虹色の夜にて現出した地より確認されているらしい。
まずは、それを手に入れて、然る後、亜獣達の楽園へと乗り込む。フローリアと呼ばれるその諸島は、西大陸にある一国、アラセマ皇国による封鎖が行われているらしいが、その程度、誤魔化しはいくらでも出来る筈だ。元々、機甲士としてよりも術士としての力量の方が上であった身だ。その本領を発揮すれば恐らくは容易い。
「……待っていなさい。直ぐに、元気にしてあげよう」
視線の先。光に包まれて眠るように目を閉じた少女は、微動だにしないままだった。
「何と言うことだ……ッ」
入念な準備。周到な用意。万全を期した筈の術式は、間抜け極まる勘違い、根本からの見通しの甘さにより、完膚無きまでに失敗した。
アラセマの調査団からの介入を嫌い、唯一その手が未だ入っていなかった島の北に存在していた芯形機構を舞台として選んだ。だが、その遺跡の奥にて封じられていた鬼種の特性を見極めるという、ごく基本的な行為を見過ごしたのだ。
結果が、この始末である。
彼女を抱えて、遺跡の外へと飛び出す。背後からは恐ろしいまでの気配。遺跡の奥にて繋がっていた、あの凄まじい力が噴き出していく。話には聞いていた、資料では見知っていた。しかし、自分が直に目にすれば、それがどれほど強大で、そして貴いものなのかが改めて判った。
だが、その貴き力が、自分の過ちによって今、狂っていく。それは耐えがたく恐ろしい感触だった。もし自分が一人だけであったなら、今すぐあの場所に舞い戻り、如何にこの狂える状況を食い止めるかに全力を尽くしていただろう。
だが、そうする訳にも行かない理由があった。手放せないものが今の自分にはある。
抱えている手が、歪なる概念に触れて爛れていくのを感じる。自然と沸き上がる恐怖、嫌悪、忌避感。当然だ。大いなる禍々しい鬼。健全なる陽性の概念に属する存在である人の身であるならば、今すぐにでも放り捨てて、一目散に逃げ出すべき存在。
しかし、そうする訳には行かないのだ。
何故なら、彼女を託されたのだ。例え失敗したとしても。例え想像する中で最悪な状況に陥ってしまったとしても。
自分が、彼女を見捨てる訳には行かなかった。
背後より、風が吹く。心が凍り付く程の冷気を帯びた風。晴れていた空が急速に閉ざされていき、白色の雪が渦を巻き始める。
その光景はまるで、自分と彼女の未来を暗示しているかのように思えた。
翆なる存在と、その眷属。
それを、自分はこの島に来て初めて知ったように思える。
東の大陸にも、そういった場所はいくつかあった。世界の基盤、大地の底や空の上、目に見えぬ場所を走るという命の脈。それを崇める者達も居たように思う。
だが、この島にて暮らす人々のように、敬虔であり、真摯でも、そして純粋でも無かったように思う。実際、キヴェンティと名乗った彼等は、自分が知る者達とは違い、驚くべき事に命脈の飛沫を己の形に合わせて顕現させるという力すら授けられていた。
彼が喚び出す翆なる獣達は何れも神秘的で独特な美しさがあり、自分はその姿に魅了された。いや、姿というよりも、その存在自体が持つ生命としての力強さに圧倒されたと言っても良いだろう。その時ばかりは、己と孫娘が置かれた危機的としか言いようのない状況、急速に失われていく猶予時間への焦りを忘れることが出来た。
そんな彼等との時間を過ごす内、思いついた事が一つだけあった。
彼等が持つ、翆なる獣を喚び出すよりも更に深く、命の脈と繋がる力。もしかすると、この方法を使えば、自分の失敗により招いた終わりが近付く彼女の状態を、全く別のモノへと変えることが出来るかもしれない。
だが、それはある意味祈りであり、願いでしかない。自分が感じた、生命というものに対する根源的な畏れ、敬い、偉大さ。それが、もしかすれば万事あらゆる事を救ってくれるのではないかという、他者に結果を丸投げするという、研究の徒を自称する者が口に出すには憚られるような代物だった。
それでも、と。
思わずにはいられない。
案としては、悪い手ではない。祈りや願いどうこうを置いておいて、利用するという視点で考えるならば、これ以上の手は存在しないだろう。
ならば、それを利用するためには、一体どういった方法、場所、そして準備が必要なのか。
自分の愚かな失敗により、長く残されていた筈の時間は、もう目に見える程に僅かとなってしまった。
その僅かな時間を少しでも損なわぬよう、急ぎ、しかし今度こそは過たぬよう、考えを巡らせていく。
「ここが、ワシの終わりか」
部屋全面が象形に刻まれたその部屋は、自分の一人息子が息絶えていたあの地下室を連想させた。
そんな中で、今から自分がやろうとしている事を考えると、全く、血は争えぬものだというしかない。
床には、既に印章陣を描き終えてある。象形を含める形で記述された印章の陣は、我ながらそら恐ろしいまでの出来映えだ。もっとも、悲しいかな、その結果を確認する事が出来ないのだが。
手の中にある月白の宝玉に手を添える。反応し、動き出す宝玉の数は六。純白の宝玉は、前回の遺跡での実験で壊してしまったが、しかしその時の失敗により、今回の方法を思いつく事が出来た。これまで何故失敗してきたのか。象形を操る条件は満たしていると思っていた。八宝という補助道具。術士としての技量。駆動を行うための補助印章陣。そして術者の格。
問題は、どうやら術者の格であったらしい。八つの宝玉を使うことで誤魔化せると踏んでいたのだが、どうやら宝玉達の出力が足りないことが前回で判ったのだ。無理矢理に高めた結果、宝玉の一つが砕けてしまった事で、それが判明した。自分が以前から所持していた宝玉と、グローエスにて手に入れた七つの宝玉は、同型の存在であるように見えて、実際には違うもの――正確には性能が落ちた模造品であったらしい。
だからこそ、今回はやり方を変える事にした。今度のやり方は、アノーレの島で出会った彼等が誉れとしていた手段を見本にしたものだ。これならば以前のように失敗することはないだろう。
印章陣に膝を折る。陣の中央には、既に孫娘の姿がある。封印は、印章陣の中に解除の術式も仕込んである。上手く駆動すれば、その途中でこの拘束も解けるだろう。
目を閉じて眠る彼女を、暫し眺める。
自分が見るであろう、最後の姿。それを瞼に焼き付けるように、ただじっと見る。結局、彼女が目を開いた顔を見る事も、彼女がどんな声をしているのかも、知る事なく終わりを迎える。その事について、寂しく思いはすれ、悲しく思う事は無いが、しかし心残りがあるとすれば、まず第一に彼女のこれからが見届けられないことと、
「……結局、お前が何て名前なのかを、知る事もできないのか。全く、つくづく親不孝者が」
泣き笑いの表情で毒づいて、そして手を組み合わせると、頭を垂れて、祈りを捧げる。
こうして真摯に、何者かに祈りを捧げるという行為をするのは、初めてかもしれない。
――どうか、どうか。命を統べる貴き獣。命を象する三つ足の獣よ。どうか。
この子に、祝福あれ。
・
「……はぁ」
深く、吐息を漏らし、【NAME】は姿勢を崩すと岩の上にごろりと寝転がった。
見上げた空は、既に濃紺の闇。話し始めた頃に見えていた太陽の赤は影も形も無く、夜の闇は方々に散る星の瞬きと、三日月を描く白い月によって照らされている。視線を移せば、常駐軍の陣が焚く夜番の炎が見えるが、既に寝静まっているようでそれ以外の光は見えない。時刻としては、恐らく真夜中を過ぎて未明に近付いた辺りだろう。夕暮れ時から始めて、焼き付けられた記憶を分解し、構築し、そして繋げて一連の流れを造り上げるまで、結局それだけの時間が掛かってしまった。
だが、時間を掛けただけの甲斐はあった。マイオトールが歩んだ道筋、彼の思惑の大枠はほぼ把握する事が出来たのだから。
「――つまるところ、こういう話か」
既にだらけていた【NAME】とは違い、未だ姿勢を崩す事無く、ただ口元に手をやって考え込んでいたリゼラが、虚空に向けていた視線の焦点を、寝転ぶ【NAME】の方へと結ぶ。
「あの翁がこれまで遺跡の奥で残していた呪いの痕は、息子の忘れ形見を救うためのものであった、という事か?」
恐らくは、そうなのだろう。受け取った手紙の断片的な内容と、記憶の主――マイオトールの当時の思考から読み取れば、間違いはあるまい。
これまで【NAME】達が見てきた状況の中で存在したどうにもしっくり来ない部分が、この情報によっていくらか解消されたような気がする。印章陣の対象が己ではなく、差し迫った状況にある別の誰かだというのであれば、印章陣の効果についてや、老人の無茶極まる所業についても多少の理解は出来た。
ただ辿った記憶の中では、マイオトールが救おうとしていた少女が、一体どのような状況に陥っていたのかまでは判らなかった。
彼の感じていた焦燥感、そして求めた解決手段が極めて大がかりなものであったことから、余程危険な状態――それも単なる病では収まらないようなものに身体を蝕まれていたのは確かだろう。記憶の中で最初に現れた時から、少女には既に強力な封印、守りが施されていた事を考えれば、途中の遺跡で起きた失敗による影響以前の段階で、既に彼女は相応に異質な存在であった事が示されているように思えた。
「遺跡、か」
と、【NAME】の言葉を引き継ぐように、リゼラが険しい表情で呟く。
「【NAME】、お前は確か、あの遺跡に覚えがある、と言っていたな」
リゼラがどの場面を指して言っているのか、それを少し考えてから、【NAME】は若干覚束無い心地でありながらも頷いた。
――老人が辿っていった流れを、単純に記していけば、こうなる。
東大陸にて息子から危急、もしくは後を託すような類の手紙を受けて向かった先で、マイオトールは孫娘と思しき少女を見つける。
彼女には何らかの問題があり、マイオトールはそれをどうにかするための情報収集と研究に没頭。その結果、八つの宝玉という道具と、古の芯形機構が生きた状態で現存する可能性の高い、フローリア諸島の存在を知り、道具をどうにか調達した後、一人フローリアへと渡る。
フローリアへと渡った後の記憶は大きく間が空いており、次の場面では既に何処の遺跡の中から脱出する際の記憶。この時、懸命に地下から這い出してくるマイオトールが連れていた少女は、これまでの場面で見たものとは別種の封印により全身を固定されており、更にその姿は所々が人と異なる形へと化けていた。
その後、マイオトールは現地で更なる調査研究を続け、別手段での解決策を模索。その舞台となり得る別の芯形機構を求めて未踏のエルツァンへと渡り、最終的には月光の遺跡にて最後を向かえるのだが、この中でリゼラが言っているのは、マイオトールがフローリアに辿り着いて最初の記憶――遺跡より命辛々といった様子で飛び出してくる場面の事だ。
全身に傷を負った老人が、強烈な波動を放ち崩壊していく遺跡から異形と化した少女を連れて逃げていく様子に感じた、妙な既視感。
改めて考えてみて、判る。正確には、遺跡に見覚えがあったのではなく、その風景に見覚えがあったのだ。
そう、あれは――アノーレ四大遺跡の一つ。最北の雪の地に埋もれ、朽ちた“天従”の遺跡、凍え穢れしゴディバのものだった。
だが、細部は違う。遺跡から脱出したマイオトールの視界に映っていたのは、何処にでもあるような丘と、下方に広がる林だけ。【NAME】が常の光景として知る風雪の気配は、彼が脱出した遺跡を中心にし、今正に空へと立ちのぼっていくところだった。
「…………」
そこまで考えて、【NAME】はむくりと身を起こす。
焼き付けられた記憶の風景と、ゴディバ遺跡について過去に誰かから聞いた話が、ここで結びつく。
――常駐軍が正式にフローリア諸島へと派遣される以前。アノーレの北部にあるゴディバ遺跡で謎の爆発が生じ、それ以後、カンクゥサ山地より以北は氷雪に閉ざされた極寒の地へ変化してしまった、と。
そこで、くく、と喉を鳴らすように笑う声が聞こえた。
視線を移すと、リゼラが軽く片耳を手で押さえるような仕草をしながら、苦い笑みを浮かべている。
「とすると、やはりそういう事になるのか。レェアがゴディバの位置を特定し、調査を始めようとした段階で丁度ゴディバの爆発が起こり、アレは現地の土地概念が完全に変質しきる前にどうにか現地に入り、そこで、あの鬼に遣われし娘――ノエルといったか。彼女を見つけたという話であったが、つまり、アレは先を越されていたという訳だな」
自分達が見たあの光景は、これまで話にだけ聞いていた、過去にゴディバ遺跡で起きたという原因不明の大爆発――正にその現場であった、という事か。
「これについては、レェアとて初耳の話であっただろうな。我等も関わったあの四つの遺跡での事件の発端となったゴディバ遺跡の爆発と、そこから生まれた世の乱れが、まさか件の翁の手によるものだったとは。全く、縁とは思わぬところで繋がるものだ」
全くだ、とは思うが、正直なところ、それだけの情報では話が先に進んだ気がしない。
具体的には、マイオトールはゴディバにて何をしようとして、そしてどんな結末を辿ったのだろうか?
【NAME】の呟きに、リゼラはふむ、と顎を軽く撫でやり、
「前に我等が聞いた、翁の残した伝言があるだろう。あの中に、近しい言葉があったように思うが」
言われて、【NAME】は記憶を探る。思い出したのは、二度目の伝言だ。
最初の失敗。鬼が眠る遺跡。あの話か。
「とはいえ、それだけではやはり何を行っていたかまでは判らぬが……そうよな。あの娘の様子から判断するのであれば、恐らくは」
リゼラの表情が、一際険しくなる。
だが、続くリゼラの言葉をある程度予想出来ていた【NAME】は、リゼラがそんな顔つきになるのも仕方が無いだろうとも思う。
術式による加護を得ながら走る老人、揺れる視界の中、彼が抱えた少女の姿は曖昧な映像としてしか確認できない代物だったが、しかしそこから漏れ出してくる強烈極まる陰の気質と、老人が感じていた戦慄と恐怖の記憶は、【NAME】の心にもしっかりと刻み込まれていた。
始めから、そうするつもりだったのか。
それとも、図らずもそうなってしまったのか。
どちらであるのかは判らないが、マイオトールはゴディバの遺跡で、恐らくは。
「――鬼と、娘を繋げたのであろうよ」
吐き捨てるように告げたリゼラの表情は、苦々しいとしか言いようのないものだった。
アノーレの四大遺跡とは、大いなる禍つ鬼を要として用い、陰なる存在の極みであり、世界に存在するあらゆるものの敵である芯属“鬼芯属”に対抗する術を模索した芯形機構である、という話だった。
ガレーには“同加”。ノイハウスには“現創”。ヴィタメールには“百封”という力を持つ大禍鬼が封じられ、遺跡にはそれぞれが保有していた力を利用するための仕組みが施されていた。【NAME】も、四大遺跡事変の折、幾つかを己の身で体験した事があった。
当然、ゴディバの遺跡にも、その奥には大禍鬼が封じられていたのだろうが、【NAME】がゴディバを訪れた際には、その鬼らしき存在を確認する事が出来なかった。【NAME】より先行し、ゴディバの大禍鬼を確保するため動いていたであろう召喚司イルギジド・マイゼルにしても、当時の彼の話を思い起こすならば、遺跡にて大禍鬼を見つける事は出来なかったらしく、過去にゴディバを訪れたであろうレェア・ガナッシュも、ゴディバ遺跡の要となっていた大禍鬼についての話はしていなかったように思う。
ただ、どんな大禍鬼が封じられていたか。それについては、聞いた覚えがある。
“天従”のウィースルゥイン。そんな名前の大禍鬼だ。
その鬼種が、ゴディバの遺跡から消失していた理由は杳として知れないままであったが、今、思わぬ形で、行き先についての有力な候補が現れてしまった。
レェアや、イルギジド、そして【NAME】がゴディバの要となっていた鬼と遭遇しなかったのも当然だ。何故なら、既に遺跡から去っていたのだから。
「成る程な。それ以後の記憶の中で、娘の封印が四肢の拘束すら施された強力なものへと変わっていた理由がこれか。失敗だと言うわけだ。人と鬼を繋げて、人の方が在り方を保てる筈もないだろうに」
愚か極まる、とリゼラが呟き、【NAME】の同意の言葉を返そうとして、
「……?」
いや、と首を捻る。確かに、老人が抱えた少女からは凄まじい程の鬼の気配が漏れ出ていた。加えて、その姿形にも大きな揺れが生じ始めているのも見た。
しかし、人という形は保っていたように思える。確かに気配は違う。存在の形も揺らいでいた。だが、基礎が人であった事は間違いがないように思えた。そう、例えば“同加”のシンラが他者を飲み込んだ際、姿形自体は鬼の姿のままであったように。
【NAME】がそんな事を呟くと、リゼラは怪訝と半ば睨むような視線を【NAME】へと向ける。
「【NAME】、お前はこう言いたいのか。あの娘は、大禍鬼という存在を逆に己の内に取り込んでいる、と」
そこまでは【NAME】にも判らなかったが、しかし、少なくとも外見上は、あれは鬼ではなく、少女のままであったように思う。概念的にも、大禍鬼に相応しい凄まじい陰の気を放ってはいたが、それ程の気配を生み出しながらも、姿の変化は僅かで収まっていたのだ。
肉体とは、存在の器である。そして人の器を硝子の容器とするならば、繋がれた大禍鬼の存在とは、熔解した鉄にも等しい。なのに、そのようなものが注ぎ込まれても、少女は少女としての外見を保っている。異常な光景ではあったが、焼き付けられた記憶が正しいものだとするならば、事実として認めるしかない。考え得る可能性としては、マイオトールが何らかの方法を用いてそんな結果を導き出した、くらいしか思いつかないが、一体どうやってそんな真似をしたのかも同様に思いつかない。わざわざフローリアという海向こうの島に当たりを付け、苦労をして渡ってきた程なのだ。遺跡の奥に封じ込められた大禍鬼を上手く利用するための算段が彼にはあったのだろうと納得する他無い。
「では、何故翁はそれを失敗と呼んだ」
完全に押さえ込めていないから失敗、もしくは、もっと別の答えを導き出そうとしていたから失敗。この辺りではないか。
【NAME】の考え考えの答えに、リゼラは腕組みし、両の眉根を寄せて暫く無言で固まっていたが、
「……戯言、とも言い切れぬか。だが、翁にとってその状況が良しきものではないのは確かであろうな。以後の記憶では、マイオトールは常に強い焦燥を得ていたように思える」
それについては【NAME】も否という気はない。
その後、マイオトールはアノーレの島で様々な調査を続けていたようだ。主には四大遺跡と、そして島に暮らすキヴェンティ達について。それらの場面では、マイオトールはいつも焦りに支配されていた。時折、彼の視界の中に入る少女は、結晶の中に閉じ込められているような姿だったが、内側から漏れ出す気配、少女の姿形の変容は、時間が経つにつれて進行しているように見えた。マイオトールが焦りを覚えるのも仕方無い事と言えるだろう。
当時の彼の思考については、複雑すぎて断片的にしか把握できない。
概念の均衡。地母と大禍鬼。陽と陰。命の根源へ繋がる伝承。翆なる者達との接触と遺跡の根源の力。どれも単語としては理解出来たが、深い部分での理解が及ばない。
判ったのは、マイオトールが命脈という存在について関心を抱いたのは、どうやらこの時であったようだ、という事だ。
彼はキヴェンティ達が崇める姿と彼等の解釈から、命脈という存在の偉大さを知り、同時に自分の目的にとって極めて重要なものであると悟り、それを元に、新たな方法を考案する。八つの宝玉を改めて用い、芯形機構の力を利用して行う大術式だった。
しかし、命の脈へと繋がる機能を持っていた四大遺跡は一つは崩壊し、他の三つにしてもその影響を受けて極めて不安定な状態に陥っていた。それ以前に、四大遺跡について深部に鬼が封じられている事を考えれば除外する他無い。
ではコルトレカンか、はたまたランドリートか。しかし、彼の記憶を遡るならば、当時のランドリートには既に多くの移民が暮らしており、コルトレカンの方では条件に合致するような芯形機構を発見出来なかったらしい。生きてさえいれば、芯形機構としては非常に俗な代物である場衡機構であっても十分に条件を満たせる筈であったが、肝心のそれが見当たらない。
しかし、今からフローリアを離れるような時間的猶予も無い。故にマイオトールは、最後に残されていた島に希望を託して、エルツァンへと向かった。
後の顛末については、【NAME】達が追った彼の足跡とそう変わりはない。
見つけた芯形機構にて、その深部の象形を利用した術式を行使しようとして失敗。一度術式の場として使用した場所では土地概念が大きく乱れて使い物にならないため、一つの遺跡で一回、まるで使い捨てにするかのようにマイオトールは遺跡を巡り、そして雷の湖にて象形を操るための足りなかった条件を満たす方法に気づいて、月光の丘にてそれを満たして、そして【NAME】達が見た記憶は終わりを告げた。
細部については、欠けている部分はいくらかあるものの、マイオトールという人物が辿った一連の流れについては、大凡の理解が出来たような気はする。特に、動機に関しては、こう言ってはなんだが非常に判りやすく、共感のしやすいものではあった。
「…………」
しかし、である。
疑問の全てが解消されたわけではない。一番の疑問としては、
――マイオトールが救おうとしていた彼女は、結局どうなったのか?
それが、最後まで記憶を並べてみても、判らないままだった。
せめて、最後にマイオトールの術式がどうなったのかを見届けられたならばまだ良かったのだが、残念ながら、マイオトールは己が成そうとした結果を、最後まで見届ける事無く消滅した。
推測になるが、彼は自身を宝玉の一つと同化し、その宝玉を介して印章陣を駆動させたのだろう。これが、象形を直に扱うための条件である“人の枠を超える”ための、マイオトールが選んだ方法だったのだ。
故に、彼の記憶はそこで終わりだ。
人としての在り方を失い、宝玉の一部となったマイオトールにはその後は無い。石に五感はなく、石に心はない。石に刻まれていた彼の記憶を辿ったとて、それより後に生じた結末を知る事は叶わないのだ。
マイオトールが、いつか訪れるかもしれない誰かに残した伝言。自分が辿った結末を、恐らくは見届けて欲しいと、そう続けたであろう言葉を律儀に拾う義理も無いのだが、彼が残した様々な情報が、迂闊に放置して良い問題では無い事を告げていた。
だが、ならばどうすれば良いのか、という所で思考が止まってしまう。知らねばならない。だが知る為の手段がもう存在しない。
八方塞がり。そんな気分になった【NAME】は、隣に座るリゼラに何か思いつく事はないかと話を振ってみるが、少年の反応もあまり芳しいものではない。
「……さて、な。あの月光の遺跡の中で、我等がそれらしき存在と遭遇する事はなかった。だが、最奥の場にて、その者の亡骸が残されていた訳でも無かった。今の我等に判るのは、それだけであろうよ」
だが、とリゼラは少し迷ったような間を置いて言葉を続ける。
「あの術士が、遺跡の奥にて行おうとしていた呪いについては、我の目でみれば、多少なりと推測できなくもない」
【NAME】は驚きで目を見張る。
リゼラ達キヴェンティにしてみれば、マイオトールが扱うような印章陣についての知識は殆ど無いだろうに、とそんな事を言うと、彼は浅く首を横に振り、
「逆だ。我等キヴェンティであるからこその推測だ。どうやらマイオトールはアノーレでの失敗の後、キヴェンティ達と多くの係わりを持っていたようだ。我には奴と交流を持った記憶がないが、当時我等の元にはレェアが入り浸っておったからな。警戒し、接触の対象として外したのであろう」
レェア・ガナッシュ達が一応は正規の調査隊なのに対し、マイオトールは謂わば密航してきた身である。避けるのも当然と言えるかも知れない。
「キヴェンティと交流を持っていた時の彼奴の記憶から辿れば、マイオトールは翆なる脈について強い敬畏を抱いていたように思える。だからこそ奴は、我等が命の脈に救いを求めたのだろう」
救い、とは、つまり。
「“孔”より命脈の片を喚び、それに救いを求める。……レェアの妹御が言っていた、他の命を絡めるという行為にそもそもの違いはないな。【NAME】、お前に判りやすく例えるのであれば、人と鬼が繋がった存在に、更に翆霊のような存在を結びつける事で安定を図ろうとしたのだろう」
「…………」
絶句する。そんな、継ぎ接ぎどころか濃い味を中和するために更に別の濃い味を突っ込むような真似をして、上手く行くものなのか。
そんな呆れきった【NAME】の反応に、リゼラの方も何処か頭痛を堪えるよな表情で僅かに頭を振り、
「判らぬよ。この推測が正しいのかも含め、結末を知る者は誰も居らぬのだからな。判っているのは、マイオトールが最後に呪いを行った場所に、件の娘の姿は無かったという事実だけだ」
少なくとも、遺跡の最奥にはマイオトールの幻像と、彼が所有していた宝玉しか存在していなかった。あったのは、広間中心部の床面に残っていた強烈な焼け跡――思い返せばあれば、人の形をしていたように思う。
それがマイオトールが助けようとした者の成れの果てであるのか。
それとも、彼が行使した大術式の影響によって生じた、成否に関わりのない焼痕であるのか。
「状況を考えれば、どちらも有り得るとしか言えぬ。故に、ただ心構えをしておく他なかろう。もし、あの娘が今も生きているとするならば、このエルツァンの何処かを、独りで彷徨っているのであろうしな。それが、人であるか、鬼であるか、或いはもっと別の何かと化しているのかは判らぬが」
「…………」
彼の言葉に、【NAME】は起こしていた身をまたごろんと、岩の上へと横たえる。
視界に映るのは星が散る夜の空の光景。そこから僅かに首を巡らせれば、島の内陸、茂る木々の影が見える。それより以降の光景は、ここから見える景色と、実際に中へと踏み入った場合では全く異なるものであることを、既に【NAME】は知っている。幾つもの特異な地形が不自然に繋がる形で存在しているのがエルツァンという島だ。外から見える姿は偽りのものといっても過言では無い。それぞれの土地は強い歪な土地概念によって構築された極めて危険な場所であり、それぞれの地には、先刻話に出た大禍鬼も斯やという力持つ存在が蔓延っている。それらを踏まえて考えてみると、彼の四大遺跡の一つに封じられていた大禍鬼と繋がる存在が、島の何処かにいたとしても警戒しこそすれ、絶対の脅威という程でもない気がする。もっとも、どのような存在になっているのか自体が判らないのだから、そういった甘い見積もりや、逆に不必要なまでの警戒自体が不要であるようにも思えたが。
――我ながら、度胸が据わってきたものだ。
苦笑する。色々な存在の助けがあるからこそとはいえ、まさか自分がここまで強くなるとは、過去には想像もしていなかったが。
と、そこで視界の隅で白い影が立ち上がる姿が映った。
リゼラは、まだ寝転がったままの【NAME】を見下ろすと、
「そろそろ戻る。【NAME】、今日の会合は久方ぶりの有意義な時間であった。礼を言おう。そして、出発は明日で良いのだな?」
一瞬、何を言っているのかと首を傾げて、ああ、と思い当たる。そういえば、旅の同行を頼みにも来ていたのだった。
こくこく頷くと、少年も一つ頷きを返してから、身軽に岩の上から飛び降りる。僅かな音も立てず着地する様を、【NAME】はごろりと仰向けになった姿勢で見送り、そこでふと、彼に聞いてみたい事を思いついた。
そのまま歩き出そうとするリゼラの背に、【NAME】は問い掛けてみる。
――もし、その存在と今後出会う事があったなら、どうするのか、と。
「どうする、か」
少年の動きが、少しの間止まった。
「我等キヴェンティにとって、鬼とは全く断つべき存在だ。それが翆なる我等が獣より与えられた、キヴェンティの使命よ。故に、鬼であるならば、如何にと問われるまでもない」
僅かな沈黙。それを経て、ゆっくりと話し出したリゼラの言葉は、【NAME】の予想通り苛烈なものだった。
が、
「命脈を捩じ曲げて生まれた存在など許しがたい。だが、“迷の民”たるあの翁が、どのような願いを内に秘め、どのような捧げをもってして、我等が主に祈ったか。それを、我は知っている」
リゼラが語るその場面は、【NAME】の記憶の中にも確かにあった。
正に彼が最後を向かえる直前。少女を印章の陣の中央に横たえて、膝を折った老人が黙然と頭を垂れる光景。
自身が見届けられぬ事を理解して、少女がこの先辿る運命を、どうかどうかと願う心は、切々と【NAME】の心にも刻み込まれていた。
「もし我が前に、彼の者が現れたならば。それを忌まわしき鬼、歪んだ命脈の塊として斬り断つか。或いは、愛されし人の子、望まれた命脈の化身として認めるか――」
【NAME】に背中を見せたまま、幼い少年は歩き出す。
去って行く背中はそのまま振り返る事無く、静かにこう言葉を紡いだ。
「――それは、我が眼にて其奴の在り方を正しく見極めてから、定めるとしよう」
真なる楽園 疎かに迷う灯の夜
――疎かに迷う灯の夜――
――例えるならば“それ”は、地底深くにて静かに潜む、太古よりあらゆる環境から切り離されてきた、誰も知る者のいない湖だった。
そこはあらゆる干渉から隔絶された場所。生けるものは何一つ居らず、大気は僅かに揺らぐ事すら無い。降り積もった数多の死が、長い時を経て大地へと変じた後。無数の必然と偶然の重なりによって生じた空白に、土と岩の隙間から染み込み伝った水が溜まり続けて湖という形を得たもの。
洞の中程までを埋める湖の面は、閉じた情景を鏡のように写し出す。一切の振れがなく、極限まで透き通る水面に描かれた景色は精巧で、まるで湖の中にもうひとつの世界が存在しているかようだ。見る者が見れば心打たれる、至極美しい光景と言える代物だが、しかしそこはそもそも誰も居ない、一筋の光すら入り込まぬ暗闇の中。価値を見出す者は疎か、存在を知る者すら居ないそれは、全く意味を為さぬものでしかないだろう。
外では世界が様々に流転し、あらゆる出来事が起きている。
しかし、湖はその全てから孤立していた。
微動だにせず佇む洞の情景。その様子を同様、微動だにせず映す湖面。変化は一分足りとも訪れず、上下に伸びる二つの風景はただただそのままの姿で在り続ける。だから湖は、己が本来水であることすら忘れて、ただ世界を映したまま、静止した時を過ごし続けた。
それから一体どれ程の時間が過ぎたのか。いや、“それ”にとって時間という概念は存在していなかった。だからその発端を認識した時、初めて“それ”は始まりを知り、時が動くものである事を知ったのだ。
発端はたわいのない出来事。洞窟の天井から溢れ落ちた、一粒の小さな水滴のようなもの。
ただ水滴が落ちて波紋を生んだ時。湖面を境に広がる二つの世界、上下に伸びる相似の風景が異なる撓みを見せた事で、“それ”は己が内に写した世界と己が外にある世界が別のものである事を認識したのだ。
小さな波紋は巨大な湖の面に環となって広がり、静かな反射、散乱を経て消えていく。二つの像が元の姿を取り戻し、あらゆるものが動きを止めるが、しかし“それ”にとってはもう、世界は静止したものではなくなっていた。
世界の頂点では、尖った鍾乳石の先端で、徐々に大きくなる水の玉が揺れている。“それ”は湖面に新たな水滴が落ちるのを、じっと待ち続ける。“それ”はもう、待つという事を知っていた。
水滴が落ちる。上と下。両の頂点から中間の面へと目掛け、等速の二つが近付いていくのを認識しながら“それ”は思う。
湖の境界から伸びる、二つの風景。
そのどちらが本物であり、そして自分はそのどちらに触れられる存在なのだろうと。
・
「これくらい、でしょうか?」
独りごちて、ノエルは脇に積み上げた枝を数本、目の前でちろちろと燃える炎に焼べていく。
ぱちりと、弾ける音が響き、新たに入れた枝に火が移って、弱まっていた焚き火の勢いが増す。しかしその内の一本は妙に火の回りが悪く、出る煙も他のものより多いように思えた。
「…………」
そういえば、と思い出す。初めて“先生”達と野営をした時、焚き火を行う際の注意点として、薪に用いる木は乾燥した枯木を使うように、と教えられたのだ。生木は水分が多いため、火のつきが悪く、ついたとしても煙が兎角酷くなるので焚き物には向かないと、そんな話だったか。
今回、薪として木枝を集めてくれたのは【NAME】だ。殆どはちゃんと枯れたものであったが、どうやらその中に生きた木の枝があったらしい。旅慣れた【NAME】がその辺りの木を適当に伐採してそのまま持ってくるとも思えない。恐らくは拾った枯れ枝の中に、折れて間も無いか湿気ったものが偶然紛れ込んでいたのだろう。
未だもくもくと煙を吐く枝を引き抜いて軽く踏み消した後、ノエルは浅く息を吐いてから視線を戻す。
燃える火の上で、木組みの枠に引っかけられた鉄鍋が小さな音を立てて揺れている。鳴る音の正体は鍋の中に入れてある印章石だ。鍋を覗き込めばくつくつと沸騰する湯の底で輝くそれが見える。
この石は水質浄化のために必要な複数の術式を同時駆動させるべく、一つの石に印章を多重刻印したもので、これがあれば汚水や概念変質した水であっても、一応という前置きは付くが飲料水として利用が可能になる。旅の道具としては非常に有り難い品だが、複数の術式を組み合わせる事で望む効果を生む類の印章石は、素体となる石の質や印章記述を行う術士に要求される技量の関係で、稀少かつ高価だ。個人で手に入れるには難しく、今ノエルが使っている石にしても、本来ならばエルツァン探索を行う常駐軍部隊内で共有して使うために用意されていた一つである。“鬼喰らいの鬼”を捜索し討伐するまでどれだけの時間が掛かるのか、出発時には全く見積もりが出来ない状況であった事から、最低限水は確保できるように、と部隊長を務めるイェアの厚意により譲り受けたものだ。
水と食料はどちらも旅には必要不可欠なものであり大荷物になりがちだが、その片方の現地調達が容易になるのは非常に有り難い。ノエルは感謝の念を遠く離れた海岸に居る筈のイェアに送りつつ、鍋から沸いた湯を円筒の器に移すと、そこに軽く湯煎して溶かしておいた蜂蜜を垂らす。揺らして混ぜて、一口、二口。熱と甘みを口の中で転がしてから、ノエルは敷いた厚布の上に座り直し、左右の布をくるりと身体に回して蹲る。
今居る場所は深い森の中だ。刻限は大凡未明。周囲は枝振り良く高く伸びた木に覆われて、昼間であっても薄暗い場所である。夜ともなれば星の光が所々に瞬くのみで、焚き火が照らす朱色の外は、濃い色の黒色に覆われて殆ど見通せない状態だ。日が出ている間はそうでもなかったが、夜もすっかり深まった今では、気温もかなり下がっている。湯を沸かしていたのも暖を取るためだ。エルツァン島内を分断し、固有の環境を構築する超常地形群の中には、昼夜の概念が存在していないような場所もあり、明るいうちはここもそうではないかと期待していたのだが、残念ながらその予想は外れる結果となってしまった。
身の奥に流し込んだ熱が外側へと広がっていくのを感じながら、ノエルは厚布の合わせを握って寄せて、僅かに身を焚き木へと近づける。
見張りの交代は、もう暫く後。天上に見える大星の一つが、森の木々影に入るまでだ。星のズレと体内時計から割り出すに、あと二時間か三時間程だろう。見上げた視線を前へと戻すと、焚き火の向こう側では、外套を身体に巻き付けて地面に転がっている【NAME】の姿が見えた。
揺れる炎の合間に見える寝姿は、ノエルにとってはもう見慣れたものである。そして見慣れているからこそ、これまでの旅路による疲労が、【NAME】の身に確かな形で積み重なっているように感じられた。
当然と言えば当然の話だ。島の岸辺から今居る森に辿り着くまでの道程は過酷極まりないものだった。場所場所による強烈な気候変化や異常現象に加え、次々と出現する亜獣達。中には大禍鬼にも匹敵するかという大物も居り、それらを打ち倒しながらの強行軍だ。戦闘時には精々牽制か補助止まりの、殆どおまけに近い働きしかしていない自分でも消耗はかなりのもので、いくら経験豊富な冒険者であり、神形の力をも得ているとはいえ、常に前線に立ち、それらと正面切って戦い続けていた【NAME】が疲れていない筈がない。しかも、彼にはまだこの先、“鬼喰らいの鬼”と刃を交えるという本来の役目があるのだ。
(もっと、休ませてあげられれば、良いのですけれど……)
既に“鬼喰らいの鬼”の気配はノエルも掴んでいる。恐らくはこの森を抜けた先、もう直ぐ傍といって良い距離に、あの鬼が居る筈だ。
全てを決する戦いの時は近い。だからこそ今、彼の力になれるのなら、何でもしてあげたかった。
でも、とノエルは背を丸めて、肩を抱えるように回した腕の中へ己の顔を埋める。
何でもしてあげたい。けれども、もう自分が彼の役に立てるような事は何もないのだと。
概念異常や陰性概念存在を、常人とは違う形で感知し認識できる自分の力は、“鬼喰らいの鬼”を探索する際には意味のあるものだが、状況は既にその段階を過ぎている。後に待っているのは“鬼喰らいの鬼”との戦いである。そしてその場面に於いて、先刻まで利点となっていた“人形”としての特性は、今度は悪い影響を及ぼしてしまう。
鬼種との親和性が高く、しかし本来ならば存在する筈の“主”が居ない不安定な状態の自分。対する相手は、その“主”と同種の格を持つ存在である。もし大禍鬼がこちらに対して干渉をしてきたならば、抵抗する事が出来るかどうか。【NAME】の役に立つどころか、迷惑を掛け、足を引っ張ってしまう可能性の方が遥かに高いのだ。
「…………」
炎の中で小さく木枝が弾けた。その様子を陰鬱な瞳で眺める。
エルツァンの岸辺で、【NAME】が自分の事を望んでくれたのは嬉しかった。抱いたこの気持ちが確かに、“嬉しい”というものなのだと信じられたのは、自分が意識を持つようになってからそう何度もあった事ではない。それ程に、嬉しかったのだ。だからあの時は、半ば熱に浮かされるような形で彼の誘いに乗ってしまった。
だが、いざ“鬼喰らいの鬼”との戦いが目前に迫った今となってみれば、当時のような高揚は微塵も無く、不安がひたひたと、周囲の闇の中から自分の傍へと忍び寄ってくるように感じる。
怖い。恐ろしい。知らず、肩へ回した手に力がこもる。
鬼種と戦う事自体は、別に平気なのだ。もっともこれは、大禍鬼と対等に戦える自信がある等という話ではない。例え自分の力が全く及ばず一息で殺されようとも、やはりこうなったかと納得を覚えて死ぬだけだろうという、そんな褪めた認識故のものだが。
しかし、ただ自分が死ぬだけならともかく、誰かの、それも【NAME】の障害となるかもしれないという推測は、震え叫び出したくなる程の恐怖と焦燥を煽った。
思い出すのは、アノーレ島の各地で大禍鬼と対面したときの強烈な圧迫感。そして雪降る遺跡で召喚司から受けた身の毛もよだつ程に忌々しい、しかし抗いがたい束縛と支配だ。特に、完全に身体を操られて【NAME】に銃口を向けた時に感じた絶望的な気分は、今でもはっきりと心に焼き付いていて離れない。
それを、もう一度味わうくらいならば。
(今の、うちに)
引き寄せられるように、視線が傍に置いた愛用の黒筒に向く。意識せず伸びていく手指が視界に入った。自分でも驚く程に震えている手がじりじりと進み、金属の光沢を放つ銃身の表面へと届いて、
「――っ」
指先から伝わったひやりとした感覚に、ノエルは我へと返った。
まるで弾かれたように手を引っ込める。何時の間にか呼吸を止めていたらしい。荒く息を吐くと同時に、どくどくと心臓が脈打つのを感じた。先刻まで感じていた夜の冷気は失せて、鈍い熱と粘るような汗が全身から滲む。
――今、わたしは一体、何を考えていたのか。
半ば茫然としながら、一度、二度、と深く呼吸をして気分を落ち着かせようとするが、手の震えは未だ治まらない。片手で持っていた器をどうにか口元に運び、既に温度が下がった中身を飲み込む動きで、どうにか身体のざわめきを治めようと努める。
ぎゅっと目を閉じて縮こまり、暫く。ようやく身と心が落ち着いてきた事を自覚して、ノエルは目を開けて深い吐息と共に身体を弛緩させた。
思い詰めているという自覚が苦笑と同時に沸き、ようやくいつもの自分の思考が顔を出す。ここで“その選択”を取るのは合理的ではない、と。やるならばもっと後。可能であれば、敵を巻き添えにできれば尚良いだろう。更に言えば、【NAME】と同行するのを鬼と遭遇する寸前までとし、自分は彼の帰りをその場で待つという方針もある。これならば、少なくとも【NAME】の背中を撃つという事態は無くなる。
ただ、やはり共に最後まで、という気持ちが自分の中にあるのもノエルは認めていた。理由については、それを頭の中で探ってみても明確な根拠が見当たらない。利点は然程浮かばず、逆に欠点は次々と浮かぶ。なのにそうしたいと思う気持ち。不可解極まるが、そういった考えこそが人を人たらしめると、過去に“先生”が語っていた記憶がある。ならば、自分にそのようなものが生まれたのも、ある種の成長だと捉える事は出来るのだろう。
だからといって、許容できるものでは到底無いが。
(せめて、わたしが“人形”として正常なら、こんな心配も要らないのに)
ノエルは眉根を寄せたまま、諦観と共に細く息を吐く。
アノーレ島に存在していた四大遺跡は、そのどれもが鬼種の力を利用して鬼芯属に対抗する手段を模索する、ある意味毒を持って毒を制する理念で建造された芯形機構だ。その遺跡の一つ、ゴディバにて発見されたノエルも、当然それらの流れを組む形で生み出された存在だった。
ゴディバ遺跡自体はレェアが調査に入る前にその殆どが吹き飛んでおり、詳細な調査は不可能な状況であったそうなのだが、断片的に残されていた情報だけでも用途や機能の推測が容易な程、単純な構造を持った代物であったらしい。
レェア達の推測が確かならば、自分は芯形機構によって封印制御された大禍鬼との繋がりを得て、その力を身に充たして戦う存在なのだという。
一般には陰性概念の飽和により生じるとされる鬼種は、物理的な肉体よりも、己を形作る概念自体に在り方を依存している場合が多い。それ故、概念的な攻撃は肉体という器を持つ鬼種相手でも、単純な物理攻撃より有効な攻撃手段となる。
だが、大鬼や禍鬼、それ以上となる大禍鬼格のような上位鬼種を相手にする場合、それを形作る存在概念が強固すぎるが故に、外部からの概念的な干渉に対して高い抵抗力を発揮するようになる。要するに、有効であることは変わりないのだが、存在としての格が上がるほど、有効打に持っていくまでの敷居が高くなっていくのだ。
そしてゴディバ遺跡で行われていたのは、この敷居を低くするための対策だと考えられていた。敵と同様の陰性概念を持つ存在を用意して代わりに戦わせれば、その者が操り放つ攻撃も陰性質を帯びたものとなるため、上位鬼種が持つ、質の異なる概念攻撃に対する抵抗、反発作用が弱まるのではないかという、そんな思惑によるものだ。
鬼と繋がり、鬼と等しくなり、しかし鬼と戦う“人形”――それが自分だ。
製造時に想定されていた力が十全に発揮出来る状況ならば、これから始まる“鬼喰らいの鬼”との戦いは、己の本領が発揮出来る場だと言っても良いだろう。
しかし現実は逆だ。要である鬼種との繋がりを得ていない状態では、“人形”として本来持っている対鬼種の機能の殆どは働いていない。更に“主”となる鬼種がまだ登録定義されていない為、一定以上の陰性質を持つ強存在を前にすると、身体がそれを“主”となる存在であると誤認、誤作動を起こしてしまい、加えて、それらを受け入れる為に人為的に用意された穴を利用されれば、外部からの干渉を抵抗無く直接的に受け取ってしまう。
根本的な部分での不全が原因なのだ。出発前は【NAME】に己の在り方に逆らってみせると大見得を切ってみせたものの、現実的に可能かと改めて考えてみれば、望みは薄いと言わざるを得ない。
しかし、ではどうすれば良いのかと考えると、答えは全く見当たらなかった。その不全を解決できるような手段は欠片も思い浮かばず、ならば結局割り切るか、諦めるか。どちらかしかないように思える。
ちらちらと瞬き揺れる炎を眺めながら、そんな事をぼんやり考えていた時。
「……?」
知らず僅かに伏せ気味になっていた顔を上げて、ノエルはきょろきょろと辺りを見回した。
妙な気配を感じたのだ。
人とは異なる“人形”の感知に引っかかったそれは、これまでノエルが感じた事が無いような不可思議なものだった。
まず、気配が現れては消える。場所自体は大きく変化はないようなのだが、感知したと思った数瞬の後には、もう弱まり、薄れるように消えて、そしてまたふとした拍子に現れる。生じる気配の質自体も独特だ。完全な未知の気配というわけではない。これまでノエルが旅してきた間で感じた様々な存在の気配の中に、一致するものはあった。だがその気配が独特なのはそこではなく、幾つもの既知の気配が一つの形となって存在している事にあった。基礎となるのは強い陰性概念。それに、複数の存在の気配が一体となっているように感じる。一瞬考えたのは複数の生物の要素を組み合わせた合成亜獣だったが、しかしその類は各々の要素が独立した気配を生じさせる事は無い。他に思い当たるものといえば、
「やはり、鬼種……でしょうか?」
根となっている気配が陰性に偏りを持つ概念。となれば、鬼種の類と推測するのが妥当だ。鬼種の誕生については、世界の在り方が揺らぐ事で陰性概念の飽和が起きて生まれるのが主とされるが、それとは別に、元々は別の存在であったものが、何らかの要因により存在概念を陰性質に傾かせてしまう事で鬼と化す妖魔化、或いは妖鬼化と呼ばれる現象がある。今、自分が感じた不安定で奇妙な気配は、妖魔化の過程にあるものと考えるならば納得できなくもない。それ以外の可能性としては、他存在を取り込むような力を持つ鬼種が同化作業の真っ最中であるという線も有り得るが、不自然な気配の明滅を考慮するならば、そちらよりも鬼種へと変化する途中故に気配がはっきりしないのだという推測の方が真実味があるように思えた。
何にせよ、
「確かめる必要はある、とわたしは判断します」
単なる気のせいか、遠く離れた場所に存在するものの気配であるならば良いが、近場に居る場合はあまり良くない。
ノエルは小さく呟いて、傍に置いた黒銃を手に取り静かに立ち上がる。
しかし、一瞬動きが止まる。相手は恐らくは鬼。先刻の逡巡がまた頭を覗かせる。感じる気配は断続的で、明確な判断は出来ないが規模や強度自体は大きなものではないように思える。これまでの経験から考えればこの程度の相手ならば大丈夫である筈だ。そもそも、犬鬼や豚鬼、喰人鬼程度ならば全く無視できるし、大鬼や禍鬼のような位の鬼種でもそうそう問題は起きないのだ。
視線を動かす。外套に包まり眠る【NAME】の顔を少しの間眺めて、ノエルは意を決して眉根を詰める。単なる懸念による警戒で彼を起こすのは忍びない。どうせこの先自分が役に立てる事など殆どないのだ。ならば今くらいは【NAME】のためになりたい。
ノエルは照明用の石を取り出すと同時に、黒銃の下部に取り付けてあった丸い玉を一つ切り離す。僅かな振動音を立てながらふわりと浮かび上がったのは、自立しての行動が可能な補助機甲具だ。元々は看護用のものを地点防衛にも使えるように改良したもので、内蔵された印章石を駆動させる事で治癒と障壁の展開が可能であり、加えて簡素な攻撃能力も持つ。以前、コルトレカン島で【NAME】と初めて出会った時に破壊され、暫くそのままだったのだが、エルツァン渡航時に補充されたのだ。数は一つだけではあるが、眠る【NAME】を一時的に守るだけならばこれでも十分だろう。
「宜しくお願いします」
何となく告げると、その言葉に反応した訳では無いのだろうが、ゆらりと玉が空中で揺れる。愛らしさを感じて小さく笑みを作ってから、ノエルはその場から離れた。
焚き木が照らす範囲の外へ出ると、一気に視界が暗くなる。同時に冷気が忍び寄るように手足に絡み、一度緩んだ緊張が戻ってくる。手元の石が生み出す灯りは淡く限定的だ。どうにか足場を照らしつつ、通りがかる木の幹などに目印をうちながら、ノエルは用心深く森を進む。
時折立ち止まり、意識を集中して気配を探る。状況は出発前と余り変わらない。不定期に生じては薄れる気配。距離も規模も掴みづらいままで、どうにか方角は割り出せる程度だ。一瞬背後を振り返り、焚き木の灯りが遠く森の狭間に見える事を確認してから、ノエルは歩みを再開する。いくら鬼らしき存在の気配を感じたとはいえ、この暗闇の中あまり遠くまで一人で移動するのは危険だ。焚き火の火が完全に見えなくなるまでに何らかの成果を得られなければ引き返した方が良いだろう。
そう心に決めて森を更に進むと、これまで鬱蒼と茂る木々に塞がれていた視界が僅かに開けた。横倒しになった木の幹がまず視界に入り、続いて上方に広がる夜空が目に映る。どうやら大樹が朽ちたかして折れ、周囲の木ごと倒れた結果生まれた小さな空き地であるようだ。
空を塞ぐ木の葉が無いため、星の光がそのまま届いて視界は他の場所より明瞭だ。ノエルは半ば反射的な動きで暗闇の中から明るい空き地へと出る。
と、その瞬間。
あの気配を、直ぐ傍で感じた。
「っ」
息を詰めて、素早く視線を動かす。幸い、視界は良い。ノエルは直ぐに気配の主と思しき存在を見つけた。
枯れて横倒しとなった木の上に、染み出すようにして白色の靄が揺れて、それが見る間に人らしきものの形へと変ずる。現れたのは、まるで幽霊が如く虚空に浮かぶ、淡い白色の輪郭だった。
純粋に驚き、ノエルは両眼を瞬かせる。鬼種か、亜獣。つまりは凶暴な化け物の存在を想像していたノエルは、完全に不意を突かれた形だった。こちらに背を向けるようにして生じた影は、明らかに人の姿、それも自分とそう変わらぬ体躯の小柄な少女のように見えた。
以前、【NAME】から聞いた事を思い出す。エルツァン島では、過去にこの島を訪れた者の幻が残像のような形で見える事があると。今、目の前に現れた少女の姿も、その類であるのだろうか?
【NAME】の話では、あくまでそれは幻影でしかなく全く無害なものだと言っていた。確かに、敵意のようなものは感じない。しかし眼前の少女から漂う気配は、単なる幻と片付けられない程に異質なものだった。姿形は、透けた人の影でしかない。だが、ノエルの“人形”の感知を持ってしても、在り方を正確に認識する事が出来ない。それ程までに、眼前にて浮かぶそれの気配は不定で、複雑に入り組んでいた。
最初に感じた陰性質の概念はそのままに、それ以外の存在概念がまるで万華鏡のように切り替わる。瞬き一つを経る間に、その気配は一度は人のようになり、一度は鬼のようになり、そして次々と、揺らぐように、更なる別の存在を思わせる気配に変わる。姿形はただの朧気な少女のもでしかないというのにだ。
「…………」
あまりの事に警戒も半ば忘れ、茫然と見上げる視線の先で、浮かぶ少女の身体がゆっくりと回る。細い指先が円を描き、絹糸のような長い髪が翻り、そして色の無い相貌がノエルの方へと向けられた。
何も捉えていない茫洋とした瞳が虚ろに流れて、ノエルの姿を横切ろうとしたその時。
唐突に焦点がぴたりと結ばれて、二つの黒瞳の中に、自分の姿が映り込むのが見えた。
「あなたは――」
少女の唇が、僅かに震える。瞳の中に映る己の唇が、僅かに震える。
「――誰?」
問いが重なった瞬間、ノエルは己というものを失った。
・
「…………」
瞼の裏に強い白色の刺激を感じて、【NAME】はゆっくりと目を覚ました。
鈍い眠気が頭の奥に蔓延り、意識と身体の動きを阻害する。続いて感じた身体の側面からの痛みと冷えは、半ば土の上に直で眠るような状態になっていたからだろうとぼんやり考える。身を包む外套はある程度の冷気は防いでくれるが、ある程度という範疇を出るものではない。もぞもぞと身動きし強張った身体を解そうとしていたところで、あれ? と首を捻る。
視界の上方に、妙な物体が一つ浮かんでいた。黒色に塗られた球体。色は違うが形自体には見覚えがある。確かノエルの所有する機械の一つだ。以前に一度【NAME】が破壊したものだが、アノーレでの四大遺跡の件が片付いた後、時間に余裕が出来たイェアが新たに作り、ノエルに渡していたのを覚えている。【NAME】の視線を感じたのか、丸い球体は中央に小さく取り付けられた硝子状の部分をこちらに向けて、くるりと僅かに身を傾けてみせる。
それと目を合わせて、暫く。
「……?」
気づいて、【NAME】はがばりと外套を剥ぎ取るようにして身を起こした。
ようやく頭に血が巡ってきたような感覚。既に周囲は淡い陽光に照らされて、それは濃紺から薄青へと変化を始めていた。つまりは夜が終わり、とうに朝となっている事を示していた。確か、約束では朝を迎える前にもう一度見張りを交代する筈だったのだが、まさか寝過ごしたか。
見張りを務めていてくれている筈のノエルを探し、【NAME】は辺りを見渡す。しかし、焚き火は既に消えており、その傍に軍服の少女の姿は無い。かわりに、黒色の球体が【NAME】の動きに追従するように位置を変えるのが見えただけだ。
まさか、と厭な予感が頭に過ぎる。
交代の時間から大きく過ぎている事に加えて、この場に彼女の機甲具が、恐らくは眠るこちらの警護用に残されていた事を考えれば、例えば単なる用足しのような小事でここから離れた可能性は低い。彼女が見張りを務めている間に何かが起きて単独でここを離れた後、未だ戻っていない。そう考えるのが自然だ。
急ぎ探すべきだった。【NAME】は慌てて立ち上がると、装備の状況を手短に確認した後、まだ闇が完全に晴れていない森の中へと飛び込もうとして、直ぐ傍に並ぶ木々の一本に、身体を寄りかからせるようにして立つノエルの姿を見つけた。
身なりに変化は無く、何か怪我をしているようにも見えない。少なくとも、危急の大事に巻き込まれた訳では無かったらしい。【NAME】は深く安堵の吐息を付きながら、彼女に声を掛けつつ近付いたのだが、
「……?」
反応が鈍い。木の幹に肩を預けるような姿勢で身動きをみせず、【NAME】の言葉はまるで聞こえてすらいないようだ。傍に立ってもこちらに顔や目線を動かす様子すらない。
窺うように改めて名を呼ぶと、ようやくノエルの顔がこちらへと向く。
「【NAME】?」
確かめるような声。目が二度、三度と瞬くと、霞が掛かったように濁り定まっていなかったノエルの視線が、ようやっと焦点を結ぶ。
「おはようございます、【NAME】。……? あ……もう、朝ですか」
ふるりと首を振って周囲を見、ノエルは少し茫然と、驚いたように声を漏らす。
――まさか、目を開けたまま寝ていたのか? こんな場所で?
【NAME】が呆れたように訊ねると、少女は傍に転がっていた黒銃を引き寄せるようにしながら、
「……そう、なのでしょうか?」
といわれても、【NAME】としても答えようがない。未だぼんやりとしたままに見える彼女を見ていると、寝起きと判断するのが一番近いような気もするが、しかしと【NAME】は背後に一度視線を送る。
ふわふわと浮かぶのは黒色の球体。ノエルがあれを配置していたということは、ただ焚き火の傍で周囲を警戒しているだけでは済まないような状況が発生していたと推測出来るのだが。というよりそもそも、何故こんな所に一人で居たのかが判らない。寝てしまうにしてももう少しマシな場所や体勢というものがあるだろうに。
そんな事を【NAME】は話すが、対するノエルの答えはやはり曖昧だった。彼女は眉根を寄せて記憶を探るように視線を彷徨わせるが、
「ええと、確か……火が弱まってきたところで薪を足して、その後……近くで物音がしたのでそれを確認して、それから……」
そこまでぶつぶつと呟いた後、困った顔でこちらを見る。どうやら思い出せないらしい。【NAME】が深々と溜息をつくと、ノエルは少し消沈したように頭を下げる。
「申し訳ありません、【NAME】。良く、覚えていなくて」
ああいや、と【NAME】は首を振る。確かに先程は焦らされたが、結果は何事も無かったようだし、何より長時間眠る事が出来たのは少し有り難かった。どうやら自分では気づいていなかったが想像以上に疲労が溜まっていたらしい。きっとノエルがこんな場所で居眠りしてしまったのも同様の理由故ではないだろうか。
そんな話をすると、ノエルはこちらの意図を察してくれたのか、「ありがとうございます」とまた一度頭を下げて、木の幹から身を剥がす。暫く自身の身体の状態を確かめるように掌を閉じたり開いたりし、最後にこくりと小さく頷く。
「体調に問題は無いようです。では、出発の準備をしましょう。“鬼喰らいの鬼”の所在はこの森を抜けた先、という話でしたね」
恐らくは、と頷く。距離は然程もない。つまり彼の鬼との決着は今日中につくだろう。それを前にして少し締まらない一日の始まりとなってしまったが、気を取り直して行くしかない。
【NAME】は荷物を纏めるべく消えた焚き火の傍へと戻る。と、背後からノエルが付いてくる気配がしない。振り返ると、ノエルは顔だけをまだ暗闇に半ば閉ざされた状態の森の奥へと向けていた。
どうかしたのか。問うと、少しの沈黙が間に挟まり、
「……いえ、多分、何もありません。行きましょう、【NAME】」
不明瞭な、自分でも良く判っていないような声音で呟いて、ノエルは視線を切るとこちらの傍へと歩いてくる。
彼女が見つめていた薄闇の奥。【NAME】の目には、そこはただ静かな森の風景が広がっているようにしか見えなかった。
真なる楽園 幸せに惑う重ね日の誘い
――幸いに惑う重ね日の誘い――
有象無象。今まで知らずにいた感覚が目覚めていく事すら、“それ”は正しく認識できなかった。
世界を満たすあらゆる事象と己。この二つを区別する殻を持たずにいた者は、己の変化を把握するどころか、そもそも事象の区別、存在の区別すら出来ない。だから“それ”は形持つ身でありながらまるで形無き身であるように、長らくあらゆるものと関わりなく、故に一切の変わりなく、漂うように存在してきたのだ。
関わりがないからこそ形を成すことが出来ず、形がないからこそ関わりを得ることが出来ない。
外れた摂理から導かれた“それ”は、生まれた時からそのようにして在り、だからこそ生まれた時から不変のままであった。
けれども今、その孤立し関われぬ存在に、指を届かせる者が現れた。
より正しくは逆。“それ”が唯一他者と捉えられる存在が、“それ”の世界に触れてきたのだ。
明確な異なるもの。だからこそ“それ”は、貪欲にその異なるものに触れ、なぞり、味わった。それを一度、二度と為す度に、“それ”は今までの“それ”とは別のものへと変化していった。
“それ”は関わりを得る事で形を成していき、“それ”は形を成すことで新たな関わりを得ていく。
これまで区別できなかった己と事象が次々と分離していき、“それ”は唯一触れる事が出来た存在を基準にして、急速に一つの個として成立しはじめていた。
垣間見たのは記憶。描き出されたのは心象。
辿る経験が人格を成し、認識が自他を主観によって定義していく。“それ”の上を流れ通り過ぎる情報は、“それ”に一つの大きな痕を刻むに十分なものだった。
だが、その激流は正に一時の事でしかない。
触れ合ったのはほんの僅かな時間。気づけば繋がりは解けて、また“それ”は何物とも関われぬ在り方に囚われる。得られた無数の刺激を細部まで分解し、味わい、己が内に取り込めば、これまで自分がどれ程冷め切った世界に居たのかが判る。
そして、一度熱を知れば、それを求めずにはいられない。
まだ生まれたばかりの“それ”にとって、明確な思考というものはまだない。情動を自覚し、認識する程に心が形を持っていない。
ただ、焼き付けられた存在の形。“それ”が初めて触れる事が出来た、他者が齎す数多の感覚とまた繋がりたいという、光に誘われる蝶の如き原始的な反応に従い、“それ”は探るように己の手を広げていく。
触れるものはこれまでと同様の、区別が付かぬものばかりだ。僅かなりと形を得、知と識を得た“それ”であっても未だ在り方は不定なまま。彩りを持ち、熱を放つ、判り、感じ取れるのはあの時繋がった者の気配だけだ。
だからこそ、探し出すのはそれほど難しい事ではない。
もう澄んだ静寂ではなく、万葉がざわめくように揺れる世界を泳ぐように進み、あの気配を追い求める。
そうして“それ”は触れて、繋がり、そして夜の終わりと共に解けた。
・
覚えの無い夢の感覚。具体的に何を見ていたかは思い出せず、ただ重い夢の印象だけが、頭の芯にこびり付いていた。
「ん、う」
喉の奥で小さく呻きを溢しながら、ノエルはゆっくりと寝台から身を起こす。
昨日は普段よりも早く床についた筈だが、全身に鈍い倦怠感が残っている。意識は目覚めてはいるが、身体はまだ眠っているかのように反応が遅い。寝付きも寝起きも良い方だと自認しているノエルにとっては、戸惑いの残る朝だった。
探るように身体のあちこちを動かしてみるが、明確な不調の原因は思いつかない。となると、身体面ではなく精神面、例えば先刻見ていたらしい、既に思い出せない夢の内容が、身体の動きに影響を及ぼす程のものであったとか、その辺りだろう結論付ける。
(……夢、ですか)
見たのは久しぶりな気がする。自分が今の自分として目覚めた当初――“女賢者”として知られるアラセマの学士レェア・ガナッシュによりゴディバ遺跡の奥に保管されていた停滞殻から連れ出され、本格的に覚醒して間も無い頃は睡眠する度に様々な夢を見ていたのだが、暫くすると全く見なくなったのだ。“先生”曰く、夢というのは、起きている間に得た記憶を、眠っている間に整理していく過程で生じるものなのだそうだ。当時の自分は活動の基礎となる基本情報を整理し、長期記憶へと定着させる作業を行っていたため夢を頻繁に見、そしてそれが終わったから夢を見なくなったのではないか、という話だったか。それが事実なのかどうかは、推論を立てたレェア本人も断言は難しいねと笑っていたが、当時の自分は成る程と納得していた覚えがある。
久方ぶりの夢。普通の人はよく見るものらしいのだが、ノエルが夢を見た記憶はそれこそ明確に目覚めてからの最初のうちだけであったし、レェアの推論もあり、自分が人とは違う“人形”であるが故にもう夢を見ることはないのだろうと勝手に思い込んでいたのだが。
それが、今になって夢を見るとはどういう事なのか。今感じている妙な倦怠感と関連づけて考えるならば、
(この不調を報せるものだった、とかでしょうか?)
夢を見たから身体がどうも重いという訳ではなく、不調故に夢を見た、という考え方だ。
しかし、先刻自己診断した限りでは身体に具体的な問題のようなものは感じられない。一般的な表現をするならば、しっかりと寝た筈なのに昨日の疲れが取れてないという感じだ。精神面での不安定から来たものであるという話なら判らなくもないが、だとするならそれについてはある程度は仕様が無いようにも思える。何せ今居るのは自分が目覚めてから殆どの時間を過ごしてきたアノーレ島ではなく、ほぼ未踏の地とも言える“真なる亜獣達の楽園”エルツァン島である。不安を抱かない方がおかしいだろう。
ただ、見た夢が不調の呼び水となる類の内容だったかというと、そうでもなかったように感じる。
夢の印象自体はあやふやな割りに妙に重いものだったが、強く残っている感情の中には、胸に染みるような温かさがあった。陰性ではなく陽性のイメージを生むそれを、自身の不調を報せるメッセージであったと受け取るのは難しく、逆に一体どんな夢だったのかと興味が湧く程だった。
しかし、どうにか記憶を掘り返そうとしてみても、具体的な部分ははっきりとしない。
夢とは現実には起こりえなかった出来事をも、整理の過程で頭の中に蘇らせるものであり、細部まで記憶に留めておくのは難しいものだと聞く。実際体験してみると納得できる。所々の情景と、そして大雑把な印象は思い出せるが、それが明確な像を結ばない。像を結ばない故に記憶に対して焦点を明確にしづらく、結果思い出した筈の情景や印象すらも霞のようにあやふやになってしまうのだ。
何か、切っ掛けのようなものでもあればと思うが、そんな都合の良い物がタイミング良く見つかる筈もなく、ノエルは浅い嘆息と共に、夢の回想を諦めた。
そうしている間に、感じていた気怠さもゆっくりと解けていく。慣れない事態に少し戸惑ったものの、どうやら大事に至るものではなく一時的な不調であったようだ。
短く安堵の息を吐いて、ノエルは寝台から離れ身支度を始める。
自分に割り当てられた天幕は、他の皆が使っているものと比べれば一回り小さいが、一人で使っているため使用可能面積自体は広く、不都合を感じる程ではない。簡易ながら寝台が存在するのも一人で使っているからこそ出来る贅沢だ。最初は断り、共用の天幕でも構わないと言ったのだが、イェアから自分の素性も含めて一人の方が良いだろうと言われ、成る程と受け入れた形だった。
髪を軽く梳かして乱れを直し、軍服を纏う。洗顔もしたいところであったが、まだ真水の確保が安定していない状況ではそれも難しく、諦めて布で手早く拭って済ませる。現在はアノーレより持ち込んだ水や海水を術式による浄化を施して何とか賄っているが、エルツァンに派遣された人員は同行してくれたキヴェンティ達も含めれば結構な数だ。生活用水として使える水源の確保は急務で、東の海岸沿いでは海に至る小川が発見されており、その調査結果次第ではもう少し真水も気軽に使えるようになるという話だが、今は我慢する他無い。
帽子の位置を整えてから、天幕を出る。通り過ぎようとする夜の気配を切り裂くように、赤色の強い光が海の向こうから上がってくるのが見えた。眩しさに、ほんの少し目を細めながら、ノエルは陣の中を歩き出す。
日の出からまだ然程時間も経っていない頃合いだが、他の天幕では人々が身動きする気配が感じられ、陣地の中央付近に並ぶ天幕群からは既に炊事の煙が上がっている。危険地帯での野営であることから日が暮れてからの活動は極端に制限されるため、朝の活動が早くなるのは当然の話だ。
ノエルは真っ直ぐ食料の配給が行われている天幕に向かうと、火の前で大鍋を回していた兵の一人から、干肉が入った湯の椀を二つ受け取る。これが今日の朝食だ。葡萄酒は断った。今から行く場所にはそれは大抵常備されているものだからだ。
向かうは、エルツァン調査を行う部隊の長であるイェア・ガナッシュが居る天幕である。彼女の起床の手伝いと朝食の運搬は、ノエルが毎日担う仕事の最初の一つなのだ。
炊事を担当していた兵に頭を下げ、野太い声に見送られてノエルは歩き始める。イェアは事務用と自室兼寝所として二つの天幕を所有している。役目と時刻を考えるならば寝所の天幕に向かうのが普通だが、ノエルは事務の天幕へと足を向ける。理由は簡単で、イェアがわざわざ寝床に戻って眠る事はあまり無いからだ。昼間は自室兼寝所の天幕で指示などを行い、夜は集中できるという理由で事務用の天幕に籠もり、面倒なのでそのままそこで寝てしまうことが多いのだ。なのでまずは先に事務用の天幕を覗き、そこに居なければもう一つの天幕に向かうと言うのが一連のパターンとなっていた。
通りすがり、朝食の配給を受けに歩く何人もの兵士とすれ違い、皆が掛けてくる声にノエルは少し口篭もりながら短く言葉を返していく。あまり馴染みの無い人に突然声を掛けられるのにも、段々と慣れてきた。
エルツァン調査の部隊は、常駐軍の余剰兵力を纏めた混成部隊だ。イェアと共にスライドする形で異動してきたガレー常駐部隊の者達も居るが、副隊長を務めるノクトワイが連れてきた者達や、全く別の部隊から派遣されてきた者達もおり、隊内の空気は同じ常駐軍部隊でもガレーの頃とは大分趣が違う。色々と話しかけられ、こちらが戸惑う程に親しい雰囲気で踏み込まれる事もままあった。
これまでノエルが彼方此方で見聞きし学習した“人間の関係性”に照らし合わすと、恐らく自分は彼等から“気に掛けておくべき子供、或いは娘”と捉えられているようだった。対し、ガレーの部隊内では、自分が遺跡から発掘された人ではない存在だと知っている者が殆どだったため、良く言えば配慮し気を遣っている、悪く言えば不気味がられ距離を置かれているようなところがあったように思う。
こういう事に気づいたのも極最近の話だ。イェアの元、ガレーで暮らしていた時はそういう扱いが普通なのだと考えていたのだが、【NAME】と同行し、様々な事を経験した結果、過去の自分の扱いというものが何となく判るようになっていた。
とはいえ、状況が客観的に認識出来るようになっただけで、どちらが良かったのかと判断出来る程ではない。
得た知識を使って俯瞰すれば、今の状況の方が健全なものなのだろうと解釈する事は出来る。だが、客観的に見ればそう判断出来るというだけで、当事者である自分がどう思っているかと問われたならば、良く判らないと、そう答えるしかない。過去の自分の在り方を思い返せば寂しさのようなものを感じなくもないが、今のようにあれこれと話しかけられたりすると対応で迷い、困惑する事も多かった。一つの事柄に対して生じる幾つもの感情を、時には合わせ時には切り分け、評価し比べ、解釈する。それが、まだ上手くいかない。
――物事には全て善し悪しがある。それを可能な限り把握した上で、更に己が内に用意した物差しで測るべきだよ。
まだ目覚めたばかりの頃、レェアはそうノエルに教えてくれたが、物事を把握するための視野は昔より広がったものの、まだ物差しとやらが不確かなままだという自覚がある。その認識は、ノエルを酷く憂鬱な気分にさせた。
自分の周りに居る人々は、皆、その物差しをしっかりと己の内に備えているのをノエルは知っている。
親代わりであったレェアやイェアは勿論、エルツァン渡航の際に少しだけ話をした副隊長や、海を越えてこの島へとやってきた探検家の男性。キヴェンティの者達を率いてやってきた、自分よりも背の低い少年に、そして【NAME】。皆、それぞれが持つ物差しに従って、今回のエルツァン行に参加しているように見える。
省みて、自分はどうだろう。
考えると、ただただ状況に流された結果であるように思えた。何かを選んだ訳ではなく、皆の決意に付き従うようにここへとやってきただけだと。
出発前、エルツァン島へと渡る人員を決める際、イェアからは参加を取りやめた方が良いのではないかと聞かれた事がある。対して自分は明確に拒絶をした記憶があるが、それを己の決断だと言えるような自信が、ノエルには無かった。
あの時の心情を今思い返すならば、ただ怖かっただけなのだろう。一人、アノーレに置いていかれるのが。
「…………」
そう考えた時、早く自分も【NAME】達のようにならねばならないという焦燥が、強く身を焼く。
今はまだ許されている。だが、それに甘えていては、自分は何時まで経っても彼等と同じ所に立つことは出来ない。判らない事だらけの現状でも、それだけは明確に認識出来た。
彼等が持つ物差し。それは謂わば“拘り”であり“意地”のようなものなのだろう。ある意味では利己、我欲とも呼べるものか。己を強く持ち、己の価値観を持つ者。だからこそ、ここぞという時に迷わず、惑わされず、己が正しく望む事を勝ち取りに行けるのだ。
自分にはきっと、それがない。理由については幾つも思い当たるが、一番は単純に経験不足からくる未熟さとなるのだろう。積み重ねたものがないからこそ、土台が弱く、確固たるものがないのだ。
勿論、全く何に対しても執着が無いとはノエル自身も思ってはいない。だが、他者から客観的に納得の出来る理由を提示されれば、自分は恐らくその執着を諦めてしまうだろう事も、薄々は判っていた。今はこちらの曖昧な想いを汲んでくれる人達が周りに居るため、そのような流れにはなった事はない。が、もしその人達が望まないような願いをこちらが抱いた場合、ノエルの希望は簡単に潰される事になるだろう。
そして、直ぐ目の前に一つ、丁度それに近い流れになると思われる問題が迫ってきていた。
(……“鬼喰らいの鬼”の討伐)
それは、今回のエルツァン渡航の主目的である。
どのような作戦を採るのか、具体的な話は全く聞いていないが、しかし討伐の要が【NAME】となるであろう事は、彼と旅を共にしてきたノエルにとっては当然の話であった。
問題は、自分がそんな彼等の助けになれるのかどうか、だ。
不完全な“人形”である今の状態では大した戦闘能力もない上に、概念的な歪みや干渉、特に鬼種が基盤とする陰性概念に対しての耐性が低い。四大遺跡でもイェアが用意してくれた小道具を使っても影響は完全には免れず、大禍鬼を前にした時には行動に大きな問題が生じる程だった。そんな自分が、土地概念が大きく変容した超常地形が連なるエルツァン島の調査や、その奥に居るという“鬼喰らいの鬼”討伐に付いていけるのかどうか。
こちらの素性を知っているガレーからの兵士達や、長を務めるイェアから遠回しに気遣われているのは感じていたし、エルツァンに渡ってきてから回される仕事も主に陣地内での活動に限定されているように思う。
この扱いから考えれば、自分は後詰めですらない後方支援要員の一人として数えられているのだろう。
そしてそれはつまり、“鬼喰らいの鬼”討伐の中核となるであろう【NAME】と共に行き、彼の助けになるという希望は叶わない事を意味する。
不満がないといえば嘘になる。だが、その扱いはもっともだとノエル自身も感じていた。だから仕方無いと思えるし、諦めてもしまえる。希望とは言ったが、相反する気持ちもあるのだ。助けとなるべく同行したというのに、足手まといになってしまうという恐怖はやはり根深い。
(――もしここで私に“意地”があるなら)
それでも、と逆らう事も出来るのだろうか?
自分を含めた皆が、必ず良い結末に向かえる選択ではないだろう。けれどもきっと後悔は無い筈で、今感じている重く鈍い感傷を払うに足るものであるように思えた。
もっとも、今のノエルにその“意地”はない。もし皆にこの事を話せば、「そんなものなんて無くていい」と言う人達も居るかもしれない。だが、ノエルにとってそれは望むべきものだった。確かに、強い拘りや偏った価値観による行動は、悪い方向に働く事もあるのだろう。でも、己の在り方に従い選ぶという行為自体が、ノエルにとってはとても眩しいものに見えるのだ。
過去に一度、それに近い選択を自分も出来た事がある。四大遺跡での旅の中、“先生”の仇を討つと定めた時の事だ。
だが、あの時にしても、もし周りの者達――例えば【NAME】から否と言われていたならば、自分はどうしていただろう?
それでも一人で出来ていたかといえば、自信はない。結局自分の中からは、その程度の志しか生まれてこないのだ。
所謂気の持ちよう一つで変わる事なのかも知れないが、なかなかに難しい。自分自身の事も良く判っていない者にとっては尚更だった。
周りの人々から向けられる気遣いや、優しさ。厚情と呼べるものが己に向けられている幸いを知り、感じられるようになった今だからこそ、それに応えねばと意気込む気持ちだけは強くなる。けれど、結果に繋がる道筋はなかなか見当たらず、あったとしても時間が必要なものばかりで、だから余計に焦れて、そして落ち込んでしまう。
「…………」
知らず、溜息が零れる。どうしようもない思考に身体が引き摺られて、いつの間にか足も止まってしまっていたようだ。ノエルは浅く首を振って気を取り直すと、目指す天幕へ歩みを再開する。
エルツァン島の海岸に設営した常駐軍の陣地は、半径百メートルを超える程の規模のものだが、炊事用として用意された天幕付近からイェアが使っている天幕の場所までは直線にして数十メートルも無い。深く物事を考えないようにただ歩く事に集中すれば、直ぐに目指す天幕の前へと到着する。手の中にある二つの椀、その中身はまだ温かいままだ。それを確認してから、ノエルは天幕の垂れ布を潜り、中へと入る。
「イェア。いらっしゃいますか?」
「……ぅ、んげ」
天幕の奥から変な声が聞こえた。そちらを見ると、適当に並べた荷物の上にシーツ代わりの布を一枚掛け、その上で毛布ごと丸まるように固まっている物体が一つ。身体を抱え込むようにして眠っているイェアだ。毛布の端から見える衣服は普段の白衣のまま、銀に近い髪は荷物の端から零れるように地面に流れて、毛先が土の上で緩やかに渦を巻いている。
ノエルにとっては見慣れた寝姿で、これといって感想も浮かんでこない。持ってきた朝食を事務に使っている長机の上に置くと、丸まるイェアの傍に寄って、
「起きて下さい」
「ふぎゃ」
すこーんと寝台代わりとなっていた荷物の一つを抜くと、その上で丸まっていたイェアの身体が敷布ごとごろんと転がり落ちた。腰を強か打ったらしく、イェアは涙目で両腕を背中に回したまま上体を起こし、
「あたたたた……、ぁあ? ……ああ、ノエル、おはようございます」
「おはようございます、イェア。朝食はそちらです。葡萄酒はまだ残っていると判断して頂いてこなかったのですが」
「……んあー?」
腰を押さえたまま顔を顰めていたイェアは、ノエルの起こし方に別段文句を言う事も無く、くあ、と小さなあくびと共に天幕の隅を指差す。
「……あー、そっち。そっちの方に昨晩放り投げたようなー」
「何をやっているのですか」
細く息を吐いてそういうと、イェアは決まりの悪そうな誤魔化しの笑みを浮かべ、
「いや今後の方針とか、その辺りで色々と詰まっちゃっいまして、勢いでつい。流石“真なる亜獣達の楽園”と言いますか、いざ上陸してもそこからがまた険しいと言いますか……。取り敢えず、ご飯食べましょうか」
「はい」
転がっていた瓶を拾い上げ、こちらは卓上に置かれたままだった杯に中身を注ぐ。幸い、栓はされており飲み干しもされておらず、濃い色の液体が杯一杯になる。そうしている間にのそのそとイェアが起き上がって席に着き、ノエルも手近な椅子を引いて座る。個人利用の天幕だが、主の役柄上来客が多く、予備の椅子は幾つかあるのだ。
「うー、あっつ。あー、目が覚めますねこれ」
ずずず、と湯気を放つ椀の中身を啜りながら、イェアがほんわかと顔を緩ませる。それを見ながら、ノエルも続いて椀に口をつけた。舌に残るのは湯の熱と微かな塩気、あとは臭みの残った肉の味だけである。保存食として持ち込んだ大量の干肉を湯で茹で溶かしただけの代物なのだから、当たり前といえば当たり前の話であるが。
イェアはこの飾り気も栄養も味も乏しい代物に全く不満がないようだが、彼女以外の兵士達からは酷く不評らしい。ノエルとしても、不満は無いがかといって満足しているかと問われたら素直には頷けないという評価だ。炊事担当の兵士はせめて野草が使えればとぼやいていたが、同時にまだそうした調査が行える段階に達しておらず暫くは無理だろうとも言っていたか。因みに、アノーレ島から大量に持ち込んだ食材の中には干肉の他にももう一つ発酵させた魚があったのだが、そちらは味にクセがありすぎるため、一部の兵士達以外は誰も手を付けていないという状況である。
昼や夜に頂くものとしては物足りないけれども、朝の寝起きに胃に入れるものとしてはそう悪いものではない。今ノエル達が居るエルツァン島の沿岸は朝方に冷え込むことが多く、そんな中でこの温かな食事は身も心も解してくれる。事実、イェアの天幕へとやってくる間に感じていた心の落ち込みは、身の内に染みた熱に押し出されて大分マシになったように思えた。
「ふふ。ノエルも少し、気が緩んだようですね」
「……はい」
言われて、頷く。気づけば、こちらを見るイェアの顔には僅かな気遣いの色が見えた。どうやらこれまでの些細な遣り取りの間に、自分の気持ちの沈みを見抜かれていたらしい。
「それで、どうですか。わたくしに話してみて、解決しそうなお話ですか?」
色々と言葉を抜かした曖昧な問い掛けではあったが、意味は確かにノエルに伝わった。
けれども、ノエルは純粋に困るしかない。他人に相談してもどうしようもない話だという気もするし、何よりイェアに話すと自分の中にある曖昧な望みを知られ、逆に止められてしまうかもしれない。それが怖かった。
結局、ノエルは少しの逡巡を経て、
「良く判らないと、わたしは判断します。けれど、それとは別に、イェアに話しておいたほうが良い事はあります。……夢を、見ました」
「夢、ですか」
ずずず、とイェアは椀の中身を傾けながら、鸚鵡返しに呟く。その視線は僅かに虚空に向いて、思案の気配がある。
「んー、てっきり貴女が夢を見るのは起動時の基礎情報取得状態の時だけと思ってたのですけれど……、ノエル、身体に異常とか、あります?」
「今朝は起床時に身体の反応が普段よりも鈍いように感じました。今は正常です」
「その程度だと何とも言いづらいですわねぇ。別に貴女、身体のつくり自体はそうわたくし達と違いがありませんから、それくらいの不調は許容範囲ですし。ノエル、ちょっとこっちに来なさいな」
呼ばれて、傍に近寄ると、目や口の中を覗き込まれ、幾つかの術式、更には機甲具で身体の節々を調べられる。胸元から頭を離したイェアは気難しげに唸り、
「熱、脈、心音、どれも正常域の範囲内。身体的には明確な体調異変は無いように思えますね。ただ、概念的に少し変な兆候が出てる感じ」
「概念的、ですか」
「ええ。……といっても、貴女の場合は元々あまり安定してないから、これも正常の範囲内と考えてもいいのかもしれないけれど」
服を直しながら、ノエルは小さく首を捻る。“人形”の機能として他存在の概念状態感知、認識などは備えているが、実は自己診断は出来ていない。より正確には、その機能は存在するものの役に立たない状態なのだ。
なにせ“主”がいない“人形”はその時点で存在として既に異常なのだ。自己診断機能の処理が初期の初期で異常と判断して止まり、次の段階に進んでくれない。だからこうしてイェアが確認してくれるのは非常に有り難いのだが、問題はそれが判っても、ではどうすればいいのかという所が判らない点か。
イェアは硝子をはめ込んだ機甲具越しにこちらを見やり、気難しげに眉根を寄せて唸る。
「むー。見た感じ、揺らぎ――というか何か色々紛れこんでますわね。ノエル、貴女エルツァンに来てから陸の方に上がったことあります?」
「いえ……一度も」
島に来てからノエルに回されていた仕事は、主に陣地の設営や維持、伝令などの雑事である。なので、エルツァンの沿岸地以外の場所に足を踏み入れたことは無い。
ノエルの応えに、指示を出している当人であるイェアも「ですわよねぇ」と首を傾げ、
「エルツァン島内は土地概念が強烈に歪んだ超常地形の集合体。それは、これまでの事前調査でもう判明してる事。でも、その外側に存在する島の沿岸地や近隣海域についてはそれほど大きな概念的歪みはなくて、それこそ他の島とあまり差は無いかむしろここの方が安定してるくらいなんですよね。内陸の方に入って、それで何らかの影響を受けた結果という話なら判りやすいのですけれど、入ってないとなるとそっちの可能性も低いし……」
うーん、とイェアは暫く考え込むが、これといったことは思いつかなかったようで、肩を竦めてみせて、
「存在概念については、明確な異常というほどの振れ幅でも無いですし、取り敢えず様子を見るという事にしておきましょう。夢については、最近ノエルは【NAME】さんにくっついて色々経験していましたから、得た情報が過多になってその整理のために夢を見た――辺りが無難な推測かしらね」
「……納得出来るとわたしは思います」
存在概念の異常については不安はあるものの、夢については成る程と頷けるものだった。
神妙な顔で言葉を返したノエルに、イェアはひらひらと手を振って笑い、
「まぁ、あまり気に病まないようにね。こういう事って、深く考えるほど悪化しちゃうものですから。わたくしも最近眠りが浅くってもー大変ですわよ心労で」
夜中まで葡萄酒片手に仕事をしていれば眠りが浅くなっても仕方無いのでは、という台詞はどうにか喉の奥に留めて、ノエルは器に残った既に殆ど熱の失せた湯を飲み干す。
確かに、気にしていたら治る類のものでもないのだからあれこれ考えても仕方の無い事だ。切り替えて、今日の仕事をこなすとしよう。
何時もの流れでは、こうして朝食を二人で取った後、朝会が無い日はノエルが部隊内各所へ活動予定等の伝達へと向かう形となる。イェアから幾つかの紙片と命令内容を受け取り、ついでにもう一つの天幕に洗濯物が溜まっているのでどうにかしてという依頼を受けてから、使い終えた食器を重ねて天幕を辞する。
「そうだ、ノエル。一応伝えておきますね」
少し真面目な声音で呼び止められて、ノエルは天幕の出入り口で歩を止め、イェアの方へと振り返ろうとしたその時。
「――――」
一瞬、くらりと視界が歪んだ。
そして次の瞬間、頭の中にどっと、数多の光景がひっくり返るように広がっていった。
「う」
呻きが漏れる。突然意識を埋めるように溢れ出たそれは、恐らく夢だ。今日の朝、思い出そうとして思い出せなかった夢の記憶。それが、断片的ではあるが唐突に蘇ったのだ。
取っかかりとなったのは、今のイェアの言葉だろう。そう、あの言葉。そっくりそのまま、同じ言葉を、夢の中で聞いた覚えがあるのだ。
――いや、夢の中、だったのだろうか?
薄暗い天幕の中。椅子に座ってこちらを若干見上げるようにしている、少しの緊張を帯びたイェアの顔。目に映る光景全てが、蘇った記憶の一つと一致する。
丁度、ここなのだ。この場所、この日、全く同じこの光景の中、イェアは続けて、こう告げるのだ。
『【NAME】さんが今日、“鬼喰らいの鬼”討伐に出発されるそうです。その前に、ノエル。少し、彼とお話ししてきたらどう?』
「…………」
一語一句、まったくの同じ言葉がイェアの口から生まれて、ノエルは目を見開いてイェアを見返す。
だが、そんなノエルの内心の驚きなど伝わる筈もなく、イェアは妙なノエルの態度にきょとんと首を傾げて、
「ノエル? どうしました? ……もしかして、今はあまり会いたくない? でも、出来れば無理をしてでも会っておいた方が良いと思います。“鬼喰らいの鬼”討伐の旅は、恐らくは極めて危険なものになるでしょうから」
続いた言葉、これは記憶に無い。
その事に身体の硬直が解けて、知らず詰めていた息が漏れる。
だが、彼女の問い掛けに引き摺られる形で、また別のイメージが脳裏に過ぎる。別の光景。別の邂逅。その時の会話は疎か、自分がどのような感情を抱いたのかすら、染み出すように再現される。
「……いえ、大丈夫です。それには及ばないと、わたしは判断します」
「及ばないって……。“鬼喰らいの鬼”の手強さ、それにエルツァン島がどれ程危険かは、貴女も判ってますわよね? いくら【NAME】だって、もしもという可能性も」
「そうではなく、……いえ、何でもありません。了解しました、イェア。早朝の庶務が済み次第、彼のところに向かいます」
「結構です。なるべく、急いだ方が良いですわよ」
上手く説明できる気がせず、内心の混乱を誤魔化すように話を終わらせると、ノエルは一礼し、天幕を出た。
並び立つ天幕の間を足早に歩きながら、ノエルは先刻生まれた不可解な心の動きをどうにか抑えようと、ぎゅっと胸元に手を押し当てる。
焼けるような期待と、凍るような不安。これはきっと、本来ならイェアから【NAME】が出立するという話を聞いたときに、自分の心を埋め尽くすものだったのだろう。だが、今のノエルの胸の中には、それとは別に不可解な既視感が強く渦巻いていた。
夢の記憶、であった筈だ。
なのに、この鮮明さ、正確さ、克明さは何だ。
先刻、イェアによる誘いを断ったのも、理由がある。何故なら、別にわざわざ【NAME】に会いに行く必要は無いのだと知っていたからだ。
簡単な話だ。今から朝の仕事を一通り終えて、そしてイェアから言いつかった洗濯物の処理をしようとする途中で、自分は【NAME】に出会うのだから。
そしてその後、自分は僅かな不安を感じながらも、凄く嬉しくて、幸せで、満たされるような心地になるのだ。
「…………」
覚えている。覚えている? いつ? 何処で?
夢とは、こういうものだっただろうか。違う筈だ。少なくともノエルが知る限りでは、夢とはただの過去の記憶の整理であるという話だ。だから夢とは、既に得ていた知識や光景、それらを秩序無秩序問わず頭の中で組み合わせる事によって生じる、刹那的なものと考えるのが相当だろう。
しかしこれは、どうもそういう類とは違うように思える。ノエルが持つ知識で近い言葉を当てはめるなら、予知と呼ばれる物に近いだろう。その中でも将来起きるべき出来事を夢として事前に見る――予知夢という奴だ。
だが、何故そんな事がいきなり出来るようになったのかがさっぱり判らなかった。占いや先見の手法を習った事など一度もないし、“人形”としての機能にも、そんなものは無い。そもそも、本当に予知であるのかすら判らない。
自分の中に、断片的に、良く判らない記憶がある。そしてそれは恐ろしいまでの現実感を持っているのに、実際に体験したという覚えは無いものが殆どだという。
端的に言えば異常な状況だった。今の己の状態を冷静に判断するならば、
「狂ったのでしょうか、わたしは」
どうだろう、と自問するが答えは出ない。単に狂っただけであるならば、先刻のイェアの言葉をほぼ正確に予見出来ていた事が謎だ。いや、狂っていなかったとしてもその点は謎のまま残る事になるが。
(取り敢えず、確かめるしかない、でしょうか)
少しずつ、可能な範囲から。
良く判らない部分は多い。だが、少なくともこの妙な記憶、不可思議な既視感が、本当に現実のものであるのか。それは次の機会ではっきりとする事が出来る筈だ。
手元にあるイェアから預かった紙片を届けて、そして任された他の仕事も終えた後、イェアの衣類の洗濯を行う。
その途中で彼に出会わなければ、この妙な記憶は単なる気のせいで済ませることも出来るだろう。先刻のイェアとの会話は偶然と、そう強引に切り捨ててしまえばいい。
(けれど、もし……)
記憶の通りに出会ってしまったら。
それは、どう解釈すれば良いのだろう?
「…………」
イェアの天幕へと向かう間にあんなに悩んでいたというのに、まさか更なる悩み事が増えるとは。
――この新たな悩みが、どうか気のせいで片付きますように。
願いながら、ノエルは小走りに天幕の間を進んでいった。
・
そして、数時間後。
願いも虚しく、夢の記憶として刻まれていた光景そのままの場所で、ノエルは【NAME】と出会ってしまった。
内心の動揺を押し隠しながら【NAME】と話をして、そこでノエルは彼が自分を深く望んでくれている事を知った。それは夢として断片的に体感していた事ながらも、やはり凄く嬉しく、幸せで、満たされた気持ちになったのだ。
少し前まではあれ程思い悩んでいたというのに、一度踏み込まれて請われただけで、直ぐに彼と共に行く事を是としてしまうのだから、我が事ながら現金という他無い。
結局のところ、駄目だという理由をあれこれ並べようとも自分は【NAME】の力になりたいのだ。
これが望んでいた“意地”と呼べるものに至っているかは判らないが、どうやら自分自身が気づかないうちに、【NAME】という存在を強く心の中に住まわせてしまっていたようだ。その比重は、多分育ての親である二人の学士にも等しいだろう。
だが、だからといって不安が無くなった訳ではない。むしろ懸念となる事は増え、不安はより増してしまった状態だ。
(……わたしは、どうしてしまったのでしょう)
得ていた既視感、夢と思しき記憶通りに【NAME】と出会った事で、自分の記憶にある光景が、単なる夢でしかないという可能性も、ほぼ無くなってしまった。
もしこの経験に無い記憶が予知に類する――つまりは未来を示すものであるなら、それを任意に引きずり出し、読み解く事が出来れば、あらゆる場面で物事を有利に運べるような気はするが。
(けれど、そんな都合の良い代物なのでしょうか?)
そうは思えなかった。正体は全く想像がついていないというのに、ただその確信だけはノエルの中にあった。
予感がする。いや、正確には伝わってくるのだ。これは予知などという便利なものではなく、もっと別の、より危険な何かへと繋がるものだと。
記憶の合間合間に差し込まれる、警戒を促す感情。場面場面の事象、それに連なる感情の動きの中に、危機を想起させる心の動きが常に感じられる。刻まれる危機感は記憶の場面とは繋がりが全くなく、だからこそ共通する違和としてノエルの意識にまるで痼りのように残っていた。
何かに対して警告を促している。そんな感覚だが、判るのはそこまでで、そしてこれだけではどうしようもない。
「…………」
先に行くと去っていく【NAME】。自分の事すら正しく把握出来ず、時には銃口すら向けた歪な“人形”を――それでもと望んでくれた大切な人。
もうすっかり見慣れた背中を目で追いながら考えるのは、そんな彼にこの不安定で情けない状態を悟らせず、心配させず、そしてどうやって力となるか――それだけだった。
真なる楽園 浅き夢見る無白の瞳
――浅きに夢見る無白の瞳――
――ふと、懐かしい夢を見た。
その記憶は、確かわたしにとっての原風景であったように思う。
己というもの。心というものを明確に持つようになったのは、果たしていつだっただろうか。
人に近く、しかし人ならぬ者。通常の生物であるならば誕生し、幼少を経て成長し、完成へと至るのが正しき姿なのだろうが、何せ造られた身であるならば話が別だ。
生まれた時から肉体面では殆どの成長を終えた状態となれば、普通の範疇には括れない。勿論、精神面に置いても、与えられた役割をこなせる程度のものは製造過程で付与されてはいたようだが、話に聞く限りでは、どうやら目覚めた当初は外からの刺激に対して殆ど反応を返さない、文字通りの“人形”のような状態であったらしい。
島の北の外れ。当時既に風雪に閉ざされつつあった“天従”の遺跡から連れ出され、そして島の南西端に位置するそこに運ばれてから暫くの間は、肉体としては生きてはいるものの、心自体はまだ生まれていない。そんな状態だったそうだ。
実際、その話に従うならば初めて目を覚ました場所は凍えた遺跡の地下である筈なのだが、当時見た筈の目覚めの光景は、未だに思い出せないままだ。
記憶として残る最初の光景はここ。彼女達二人が当時の居所としていた、遺跡傍の仮設住居であった。
機甲具含めた様々な道具、資料が雑多に積み上げられ部屋の中、視界の正面、覗き込んでくる二人の“先生”の姿。
巷の間で“先生”の異名を持つ彼女と、後に「あなたの“先生”だ」と自称した彼女。疲労や諦観が滲んでいた表情が、明るい驚きと笑みに変わっていく様子は、今でもはっきりと思い出せる。
本来であれば、“人形”は停滞殻から起動する際に各種の必要な情報などが刻印付けされ、最低限の自律性を保った人格が形成されるものだという。だが、半壊どころか全壊にも等しい遺跡から掘り出され、何より要たる遺跡と鬼種が揃って存在しない状況での起動である。正常な起動手続きが行われる筈も無く、当時“人形”の異常に気づいたレェアは、妹であるイェアと共に、本来なら刻印付けされる筈であった情報をどうにか後付けしようと四苦八苦していたらしい。その瞬間から意識が生まれた身としては実感しがたいが、自分が遺跡で目を覚ましてから外部の刺激に対して反応を示すようになるまで、どうもかなりの時間がかかっていたらしく、古の時代の産物については相当の知識を持つ学士二人も、その頃には半ば諦めかけていたと、後に本人達から聞いた。
深々と吐息して、腰を下ろし、けれど気の抜けた微笑みで自分を優しく見るレェア。
逆に張り付くように近付いて、僅かに涙を浮かべた笑顔で色々と口早に話しかけてくれたイェア。
当時はただ、彼女達によって刷り込まれた定型対応で応えるしか出来なかったが、今にして思えば、二人が向けてくれた異なる笑顔は、深く強く、心の中に染みていった記憶がある。
心が動くという事。感情というものが、どういうものであるのか。
それを問われた時に、真っ先に思い出すのがあの笑顔であり。
そして、それを見た自分が彼女達に返した定型の動き――形ながらのぎこちない笑みを浮かようとした時、同時に己の内側で生じた微細な意識の波は。
きっと、自分の心が初めて生んだ鼓動。本当の意味での目覚めを得た、小さな合図だったのだろう。
それは大事な大事な、わたしだけの最初の記憶。
――そんな事を、成る程と思い返して。
“それ”は、この出来事を始まりと定義して、そこから繋がっていく記憶を、自分のものであると認識する事にした。
・
彼女の面影が遠のいて、夢の中での微睡からゆっくりと目覚めていく感覚。一先ずの終わりを感じ、“それ”は残念を抱きながら、また何も見えず聞こえぬ虚ろの中へと戻っていく。
今の“それ”には、何かを残念と思える程の心、意識と呼べるものが生まれつつあった。
移ろう無数の幻像。重なり合い、混じり合った記憶の羅列。取り留めなく、流れるような在り方の共有は、最初の頃のような拙く短い触れ合いではなく、長く深い繋がりを保つ異なる形へと変化している。
最初は一方、“それ”が手を伸ばして触れ、ただただ貪るように弄るものだった。だが今は互いに、いや、相手を鏡と見立てるようにして、他方の世界が描く光景を、無秩序ではあるが緩やかに眺めるようにもなっていた。
但し、その鏡合わせの繋がりは対等なものではなく、釣り合いが取れたものでもなかった。
接触は片側である“それ”の手により行われているというのに、“それ”自体には、自己という形がそもそもからして希薄だった。
故に、彼女との微睡の邂逅を続けるにつれて、“それ”は己の内にあった筈の世界よりも、鏡合わせたる彼女が夢見て思い返す記憶を、己の正しき世界だと認識するようになっていった。
生まれた心とは、彼女の心象を写す事で焼き付けられたもの。
生まれた意識とは、彼女の成長をなぞる事で形作られたもの。
結果、本来ならば“それ”が正しく留めるべきであった記憶を、“それ”はまるで雑音であるように、等しく価値の無い存在の塵であると目を向けず。
逆に、繋がりを得ることで垣間見た彼女が持つ幾つもの記憶を、“それ”はまるで己のもののように、次々と味わっては自分の世界として溜め込んでいく。
鏡合わせとなった彼女が、“それ”が無価値と断じた世界の光景を、悲嘆と共に見せつけられている事にも気づかずに。
・
――甘く見ていた、としか言いようがない。
深夜の夜営の最中。ノエルは眠る【NAME】から少し距離を置き、物陰にしゃがみ込むと、じっと身を丸めて耐えていた。
「……う、ぐ……ぇ」
内臓がひくつき、喉が焼けるような感覚。嫌悪感を催す臭いが逆流し、嘔吐として零れる。地面にぼたぼたと吐き出されるものの中に固形物は無く、大半は胃液だ。それでも幾度も幾度もえづき、もう中身は何も無いというのに身体は中々落ち着いてくれない。
そのまま数分が過ぎ、ようやく身体の反応が収まる。全身に鈍い汗を感じ、ひやりと身体が震えるのを感じた。汗を拭かねば身体が急速に冷えて体調を崩すかもしれない。そんな事を考えるが、しかし半ば意識が朦朧とした状態の今では動く気にもなれず、近くにあった木の幹に身体を預けて、ただ息を整える。
「…………」
今居る場所は島の内陸、超常地形の中間地に広がっていた小さな林だ。エルツァン島の超常地形は境界線を越えると明確に土地の傾向が切り替わる場合が多いが、中にはそれほど極端に変わらない場所や、干渉地ともいえる比較的安定した地形が間に存在している事がある。今自分達がいるのはその類だった。
焦点を合わせる気力もなく、暗闇に包まれた木々の間に視線を彷徨わせながら、ノエルは半ば茫とした意識のまま考える。
エルツァン島へとやってきた後。【NAME】と共に“鬼喰らいの鬼”討伐の旅を始める辺りから、奇妙な状況を幻視するようになっていた。
状況、である。単なる幻の映像には留まらず、場面におけるあらゆるもの――感覚や感情すらもが再現されるのだ。幻視とはいったものの、正確には視るだけで収まる話ではなかった。
殆どの場合は寝ている間の夢としてだったが、時には今さっきのように起きている時ですら唐突に襲ってくる、強烈な現実感を伴う幻の数々。幻の内容は幾つかの種類に大分出来、それぞれが異なる形でノエルを苦しめていた。
比較的マシなのは、ノエル自身の記憶にある光景――つまり自分の過去らしき光景が再現された場合だ。これは過去にあった出来事の再現であるとはっきり認識できる分不安は薄く、むしろ懐かしい記憶が今に正しく蘇る感覚は、過去の己を見直す切っ掛けにすらなってくれた。
問題は、過去ではなく今、もしくはそれ以後となる未来と思しき情景が現れる時だ。
要するに、全く記憶に無いエルツァンを旅する己の姿が幻として生じるのだが、この時、エルツァン島へとやってくる以前となる過去の幻とは異なり、様々な状況が幾つも幾つも、重なるように表現されるのだ。
例えば、過去の記憶を幻として見た時、それらは基本、ノエルの記憶から生まれたノエルの記憶通りのものだった。
発生する出来事、変化する光景、自分の行動。それらは全て同じ経緯を辿り、幻や夢というよりも、単なる過去を正確に回想する形として現れる。
しかし現在若しくは未来――エルツァン島に辿り着いた後の光景を幻視した場合は、事情が大きく異なった。似たような状況から、全く別の選択、別の行動を取る幻が幾つも重なるように展開されるのだ。
中には、己が死に至る幻も幾つかあった。だが現実にそのような状況に陥ったかと問われれば、今こうして旅を続けている事から判る通り、否である。近い状況に遭遇しても傷一つすら負わず切り抜ける事もあれば、そもそもそういう状況に遭遇しない事もままあった。ノエル自身がそんな状況を避けるような行動を、積極的には取っていなかったとしてもだ。
また、既に“鬼喰らいの鬼”らしきものの気配を掴む事に成功し、旅の終わりが近付いている筈の今だというのに、これまで見た幻の中には、通った記憶の無い不可思議な特性を持つ土地を、“鬼喰らいの鬼”の気配求めて探し歩いている場面もあった。
この故判らぬ幻覚が、一つの未来を示してくれるものであるならば確かに役には立っただろう。
だが、遭遇する兆候すら無い状況も次々と紛れ込むようでは、それはもう予知ではなく、まさに幻、あるいは妄想に近い産物と言うほか無い。
しかし厄介なのは、近しい未来、或いはほぼ正確な未来を視る事もあるのだ。それで救われた事もあったし、的中しなかった幻にしても大きく外れた突拍子の無いものとは言えないものばかりで、それによって推測できる情報もあった。だからこそ、単なる幻と安易に断ずる事も出来ず、未だ悩まずにはいられない。
とはいえ、悩みの種ではあるものの、これについては精々扱いに困るという程度で収まる話でもあった。
時には己の死すら幻視する。それは体験としては強烈なものなのだろうが、それは“自分の体験”として十分に飲み込めるものだ。受け止める事自体はそう難しい話ではない。
本当の問題――より切実で、そして今のノエルに極度の負担を掛けている要因は、別にあった。それは、
(……“わたし”ですらないもの)
ノエル自身の過去、現在、未来らしき記憶に混じって、どうも自分には全く関わりの無い――己の中から生じる筈もないような類の記憶が、恐ろしいまでの現実感を伴って現れる。ついさっき、ノエルが味わったものもそれだった。
記憶――と表現したものの、それが本当に記憶であるのかすら、ノエルにははっきりとは判らない。少なくともノエル自身がこれまで得てきた経験や、そもそも持つ人格、周囲を形作る環境から導き出せるような物ではなかったからだ。
これまで見た事も無い光景。
それまで得た事も無い感覚。
内側から溢れる衝動は異質という他無く、独りでに行われる思考はノエルの認識と理解の範疇を超えていた。
それらの記憶を体感する時、単なる状況だけが再現されるだけでは済まず、己すらもノエルではない別の“何か”になるのだ。
しかも、その“何か”は視る情景によって異なり、一定ですらない。
時には身を焼く程の衝動が、時には何も考えられぬ程の空虚が、時には内から溢れる程の慈愛が生まれ、圧倒的な勢いで心を満たしていく。
それはまだ人格というものを得て然程の時を過ごしていないノエルにとって強烈極まりない経験であり、毒というしかない代物だった。
(あれは、一体……)
垣間見る無縁の幻は、全くの出鱈目な内容ばかりという訳ではなく、大凡四つの系統に分ける事が出来た。
命が満ちる大地の底で、あらゆる生死を看取り続ける無為の視線。零れて戻る命の流れは、貴い筈の営みとはこれ程矮小でたわい無いものなのだと見せつけてくる。
自然を尊ぶ宝石の庭で、迷い込んだ男に惹かれ野に下る女の足音。幸いに満ちる心の様は、対して至るべき望みすらも満足に見出せない己の未熟を明確にさせる。
陰と陽が争う戦の地で、惑い逃げる者達を千切り喰う巨躯の咆哮。思うまま征服する力は、これまで味わった事ない他者を従え弄ぶ暴力的な甘美でもって溺れさせようとする。
そして忌まわしき気に包まれた部屋で、薄く輝く光を通して倒れ臥す誰かを見やる虚ろな心。零れ出す血が床に広がっていくにつれてあらゆる情動が死んでいく。
どれも心を酷く苛むものだったが、最後の情景が格別に辛い。閉じて失われていく感情に引き寄せられて、ノエル自身の心も凍っていくのだ。
始めから失われているのならばまだ耐えられる。だが、この状況における自分は、最初悲しみや嘆き、様々な強い感情に支配されているというのに、時を経る毎にそれが萎び、枯れて、失われるのだ。
己の内に強く在った筈ものが、急速に損なわれていく。
それを我が事として味わう辛苦は凄まじく、状況から解放された後も影響が深く鋭く心に突き刺さる。
今日見た情景は三番目に連なるもので、夢から覚めた後は強烈な忌避感や嫌悪感が全身を支配し、暫く吐き気や震えが止まらなくなる程だが、それでも最後の光景よりは幾らかマシだった。
最後の光景は己というものをもう一度取り戻すまで身動き一つ取れなくなるような有り様で、しかもどうにか立て直した後も、幻を視る前の自分と視た後の自分が、何処か違うものであるかのように感じる。これまでの短い経験で培ってきたノエル・ガナッシュという形が、視る度に少しずつ歪められ、崩されていくようだった。
「…………」
こうして現状を再認識してみると、取り返しがつかない事が自分の中で起きているのが実感出来てしまう。
「わたしは」
怖い。怖い。一体自分は、どうしてしまったのか。どうなってしまうのか。これまで抑え、堪えていたものが、噴き出すように溢れてくる。
暗闇の中、ノエルは幹に顔を伏せるようにして涙をこぼす。己の変容も恐ろしいが、何よりこれから、“鬼喰らいの鬼”という強大な相手に挑む事になる【NAME】に、無駄な負担を掛けてしまう事が恐ろしかった。
何故こうなってしまったのかすら想像もつかないのだ、解決する為の手を模索する事も到底叶わない。
今出来るのは、どうにかこの状況を【NAME】に知られないようにする事だけだ。泣いている場合などではないのだ。目元を拭い、昂ぶりかけた心をどうにか落ち着かせようとする。
生まれたばかりの頃は、まるで湖面のように凪いでいた自分の心は、今ではこんなにも千々に乱れるようになってしまった。“先生”達であればこの変化を成長などと呼ぶのであろうが、今のノエルにとっては厄介極まりないものだった。
「…………」
ノエルは何とか心を静め、じっと闇の向こうを睨むようにしながら考える。解決の方法は欠片も思いつかないが、状況の整理は行っておくべきだと、自分の理性的な部分が訴えている。それに、今日は二つばかり“収穫”があった。それをしっかりと検める必要がある。些細な事であれ一つずつ確かめ、それを解決の糸口に変えていくしかないのだ。
(一つは……)
己を蝕む未知の光景。こちらに関してはノエルには打つ手立ては無い。正直もう何が何だか判らず、ただ翻弄されるしかないように思えた。
だが、もう一つの光景――ノエル自身が関わる記憶について、少しばかり思うところがあった。
この不可思議な夢が、どういう理由によって生じるようになったのかはやはり判らないままだ。だが、エルツァン島にて旅する自分の記憶の中で、今と同様、夢の情景に苛まれている場面が再現された時。どうも今のノエルとは、視えるものの状態や精度、それを受け取るノエル自身の認識に、場面場面でかなりの違いが存在するのだ。
夢幻として顕現する状況については、ある程度の定型が存在しているらしい事には、比較的はやく気づいていた。例えば視える未来はエルツァン島内を旅しているものにほぼ限られ、そして旅する土地にしても未見のものがあるとはいえ精々が五種類程度に収まる、といった風にだ。時間についてもほぼ同様で、エルツァン島へと到着し、【NAME】からの誘いを受けて、“鬼喰らいの鬼”を探す旅をしている期間は最大でも七日から十日辺りまでに限られ、夢の中の自分が把握している日数も大体がその間となっていた。この二つの要素を組み合わせて考えれば、エルツァン島内での超常地形の数と、軍の陣地を出発点として見た場合の各地形配置程度は読み解く事が可能である。実際に、【NAME】とノエルが辿ったルートもその枠から外れたものではなかった。
要するに、無数の可能性が重なって見えはするが、現れる可能性は単なる場面を切り取っただけのものではなく、そこに至るまでの現実的な道筋がちゃんと用意されているという事だ。
例えば霧の森、或いは風の峡谷を旅している時は大抵が陣地を出発して直ぐの頃合いで、凍えた洞窟や草原に聳える城に辿り着く辺りでは“鬼喰らいの鬼”の気配を掴み、もう旅も終わりに近付いている、という具合にだ。これらについては例外はほぼ存在せず、つまりノエル・ガナッシュが歩む未来として確定していると言える部分なのだろう。
だが、幻視の認識については、そうした時系列とも呼べるような流れから完全に逸脱し、独立していて、一切の関連性が見出せないのだ。
まず、そんな夢すら視ていない自分。数える程の夢しか見ずに予知夢と信じ込んでいる自分。昼夜問わず幾度も幻を視て殆ど己を失いかけている自分。それらが、再現される幻の中では先程の時系列を全く無視して存在していた。幻視する状況すら発生していないらしいノエル・ガナッシュと、強烈な幻視体験により不調の極みにあるノエル・ガナッシュが、同じ霧の森を旅している場合もある。夢についての状況は時々によりバラバラで、それぞれの場所や時間から法則性を導き出すことが出来ないのだ。
しかし、一切の法則が存在しない、という訳ではない。今の自分と同じように、夢について思考する数多の自分。彼女達には一つの共通点があった。
それは、どの夢の中でも「夢で視た自分よりも、今の自分の方が状況が悪い」と考えているのだ。
確かに、夢の中のノエルが、夢で視たノエルを当時の自分自身と比較する時、夢で視たノエルよりも状況が悪いという場合は見当たらないように思えた。良くても精々同じ程度。実際、今のノエルもそう考えている。今の自分が最も多く夢を視、そして最も明瞭且つ最も深刻な影響を受けている、と。
勿論、精神的に今より参っている自分というのも垣間見た夢の中に存在してはいたが、その夢の中の自分が晒されている状況は、今のノエルからすればマシに思えるものばかりだ。大抵、失調の原因は他の要因が絡んだ複合的なものだった。
また、もう一つ別に気づいた事があった。
エルツァン島内の奥地に相当する場所まで入り込んだ今の状態でも、時折、既に通過した筈の土地の情景を視る事がある、という点だ。
これまで、再現される過去の記憶は全て一通りであると考えていた。実際、エルツァン島に渡ってくるまでの記憶が再現された場合はそうなっていた。
だが、エルツァン島内での事は、過去と思しき状況すら、幾つもの可能性が重なった状態で現れるようなのだ。
つまりこれは、今ないしは未来の光景は確定していないが故に幾つものパターンとして再現され、逆に過去は確定しているが故に一通りの形でしか再現されない、という今までの捉え方を否定するものだった。
これに、先程の幻視を解釈する自分達の共通点を加えると、何かが導き出せる――ような気がするのだが。
「…………」
暫く頭を働かせてみるも、何も思いつかない。ノエルは深々と溜息をつく。
これまでの幻視経験により精神的に極めて不調であるというのも勿論あるが、そもそもノエルはこういう閃きを要求されるような事柄は苦手だった。自分が“人形”であるからだ、と言い訳したくなるが、単に適性や経験不足からくる未熟故だろうとノエル自身も薄々は判ってはいた。
【NAME】や“先生”達に相談できれば、きっと良い推論なりを示してくれるだろうが、もう“鬼喰らいの鬼”との対決も迫った今、考え事の種を増やすわけにもいかない。
ただ、この気づきは大きな前進であるように思えた。きっと、もっと時間や精神的に余裕のある自分であるなら、この情報から今より建設的な思考をする事も、
「――――」
と、そこまで考えて、ノエルは一つの小さな思いつきを得た。
エルツァン島内に限り、現在過去未来関係なく多重の光景として再現される幻。
幾多の幻が生み出す行く末は刹那的なものではなく、それぞれに確かな流れを持っていたが、その流れの中にあって、幻視に関する状況だけは一連の流れから完全に逸脱しているように見えた。
(でも、その幻を視るわたしの状況こそが……)
多重に存在する光景、並列で有り得る未来、島の海岸を起点として無数に枝別れする可能性――と思われていたもの対し、明確な“順序”を与えうるものなのではないか?
今までノエルが、今ないしは未来に起こりうる可能性を示した幻と、そう解釈していたものは、実は――。
「……これは、でも……」
この発想から思考を加速させる。
勿論、今自分が陥っている状況の解決に至るようなものではない。しかし、ノエルの中に生まれた推測をどうにか証明し、更に後に伝えることが出来れば、恐らく“次からのノエル達”はかなり先へと進みやすくなる筈だ。
証明と伝達。二つの要素は、同時に満たせると直ぐに結論付ける。伝達が成立した時点で、証明も成されるだろう。但し、確実性は極めて乏しい。雑で力技ながらも策自体は思いついたが、これが成功するかどうかは今の自分には判らず、殆ど全てを後に丸投げするようなものだ。
でも、
(今のわたしには、解決できなくても)
ノエルが得た思いつき。これを後に伝え、後に続く者達が皆この方法を倣ってくれたなら、恐らく状況は一つ先の段階に進むことが出来る。
もっともそれは、今こうしている自分には全く意味のなさないものではあるのだろうけれど。
でも、いつかの自分が、この奇妙な状況を打破する為の切っ掛けとなり得ると思えば、僅かな慰み、小さな救いにはなってくれる。
「……うん」
小さく頷き、ノエルは立ち上がる。
この茂みに飛び込んだ時とは、心の状態が大きく変わっているのが判った。ほんの小さな事でも状況を知り、そして望みを繋ぐという事がこれ程に心を強くするとは思いもしなかった。
ノエルは夜営の場に戻りながら、常に心の隅で思考し続ける。
間断なく繰り返されるのは現状を示す訴えであり、後の自分へと送る警告であり、そして更なる前進を求める希望の声だ。
これを常に、恐らくはもう間近に迫っているであろう終わりの瞬間まで発し続ければ、きっとほんの僅かであれども確率は高まる筈だ。
――まだ存在し得ない未来のノエルが、この思考を行い続けるノエルの姿を幻視し、体感し、そして更に後のノエルへと広げていく可能性が。