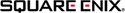真なる楽園 恥も外聞も無いとは正に
――恥も外聞も無いとは正に──
エルツァンでの探索行に、誰の助けを借りるか。そう考えた時、ふと脳裏に浮んだのは──。
「…………」
口髭を蓄えた奇矯な態度の男、ノクトワイ・キーマ・フハール。
さて……どうなのだろう。本当にあの男に同行を頼んで良いのだろうか?
・
ノクトワイの居所となっているのは、エルツァンに構築された野営陣の端に張られた特徴的な天幕だ。
彼が大草原攻略時にも使っていた、他と比べて少し大きい造りの天幕。その何が特徴的なのかというと、一言で言えば色である。
桃色。凄く桃色なのだ。
一体どんな染料を使ったのかと疑問に思うほどの、くすみのない桃色。ヴィタメール遺跡攻略の際にも使っていた代物だと聞いていたが、それから今回のエルツァン島探索までの間に、手入れが出来るような暇があったとは到底思えない。だというのに、それでも眼前に輝く桃の色は、まるで着色したばかりかと疑う程の瑞々しさで、周囲に建つ味気ない天幕群の中で、文字通り異彩を放っていた。
正直、中に入るのはおろか近付く事すら躊躇う外見の天幕であるが、ノクトワイに旅の同行を頼むにはここを訪れるしかない。副長という役職故かノクトワイがここに居る事は少なく、大抵は何処かに足を運んでいる事が多いのだが、野営陣内をあちこち歩き回って彼の所在を聞いて回った結果、どうも今は運悪く、ノクトワイは己の天幕に戻っているらしい。
近付けば近付くほど感じる色彩の強さ。目が眩み、圧迫感すら覚える桃色だった。この中で寝泊まりしているノクトワイは、一体どういう神経をしているのかと心底疑問に思いながら、【NAME】は天幕出入り口の垂れ布に手を掛けて、中の様子を覗き込む。
と、そこには意外な光景が広がっていた。
「ですから、どうかお願いします! 後生のためにもどうか!」
「う、うーん……。っていうか先生ちゃん、後生って良くそんなの知ってるわね。それ、環の国辺りの考え方でしょ」
天幕の中にいたのは二人。一人は予想通りの、【NAME】が目当てでやってきた人物。ノクトワイ。そしてもう一人は銀髪白衣の女性。エルツァンに派遣された軍の取り纏め、長の役割を担う軍属の学士、イェア・ガナッシュだった。
騒いでいるのは主にイェアである。彼女は何やら凄い勢いでノクトワイに頼み事をしているようで、ノクトワイはたじたじになっているようだ。
(……ふむ)
話の内容までは判らないが、取り込み中であるのは確かで、しかも何やら揉めているらしい。
忙しいようなら誘うのを止めておこう――というか、ここで首を突っ込むとこちらに飛び火してきそうな。そんな嫌な予感がした【NAME】は、中の二人に気づかれぬよう、無言で捲っていた垂れ布を戻そうとした、のだが。
「――あ、【NAME】さん! 丁度良いところにっ!」
見つかった! 逃げろ!
一切事情が判っていない状態だというのに頭の中に走る理由無き警告。それに従い全力で天幕から離れようとした【NAME】だったが、垂れ布から手を離し、天幕より離れようと身を翻した瞬間には、普段からは想像できぬ速度で駆け寄ってきたイェアに、むんずとばかりに服の裾を掴まれていた。
身体にイェアの重量が掛かり、前へと進む力は阻害。逃げるには、掴まれたイェアの手を振り払う必要があるが、
「な、なんで逃げるんですのーっ! いくらわたくしでも流石にその態度は傷つきますわよ!?」
と、半分泣きが入った声音で言われると流石に手荒に振り払う気は失せた。
だが、イェアの妙な勢いには、不気味さ、というよりも、嫌な予感を覚えずにはいられない。本心を言えば聞きたくはない。聞きたくはないが、しかしこうなっては聞かないと状況が進まなそうだ。
【NAME】は覚悟を決めると、一体イェアはここで何をしていたのかを訊ねる。
「えっと、実はノクトワイ様に、ほら。この前わたくしがリゼラさんに喧嘩をふっかけられた件。あれの対決のための準備を、ノクトワイ様にお手伝いしていただきたいな、とお願いに」
ああ、そういえばそんな事もあったな、と【NAME】は思い出す。
以前、ノエルの誘いで軍の定例会議――という名のお悩み相談の場に顔を出した際、ひょんな事からイェアとリゼラが料理の腕を争う展開になったのだ。
その時は大差でリゼラが勝利を収め、その後改めて双方十分な用意を整えた上での再決戦、という流れになっていたが、
――本当にやるのか。イェアに勝てる目とか微塵も無いだろうに。
「やりますわよっ! というか【NAME】さん、流石に言い過ぎではありません!?」
確かに、と【NAME】は素直に謝るが、
「いやでも、先生ちゃんには悪いけれど、実際の話【NAME】の言う通りだとは思うけどねん」
追い打ちは天幕の奥。小さな座椅子に座ったノクトワイは、若干呆れの交じった顔で【NAME】の言を肯定する。
「大体ね。先生ちゃんだって内心では判ってるでショ? リゼラ君の方はあれ、料理をする事が生活の一部として身についてる類よ。対して先生ちゃんは、そういった類の事は殆ど人任せにしてきた引き籠もりの研究馬鹿なワケだし」
「もう少し言い方! 言い方に気をつけてくださいな!」
「一意専心な生粋の研究者なワケだし」
「ああ、いいですわね、そんな感じでお願いします!」
と、半ば自棄気味にイェアは叫んだ後、はぁーっと一気に暗くなる。
「……それはわたくしもですね。判ってはいます。自分の腕前では、多分あの子の足元にも及ばないって。あの時だって、もう味の加減はおろか刃物の持ち方すら危うくて、一応料理の形になったのだってかなりの幸運の結果だって」
それならば、と【NAME】が言葉を続ける前に、
「でも! でもですね! あんな感じで勝負を挑まれて、何もせずにただ座して敗北、死を待つなど出来ましょうかっ! ならばどのような手を使ってでも、せめて一太刀、いえ、逆に切り伏せてみせる――それが大人の女というものですわ!」
「ああ、女としての最低の矜持ってそういう」
がーっ、と吼える背後、至極納得したように頷くノクトワイに、イェアが物凄い速度で一瞬振り返り、
「そこ、黙ってくださいな! ――というわけで、【NAME】さん! ここでわたくしと出会ったのが運の尽き。ノクトワイ様と一緒に、あなたもご協力していただきますわ! これは連隊長命令ですので、拒否権無しです! ノクトワイ様も!」
暴走してるなー。
猛るイェアを前にして、【NAME】は深い諦めの表情を浮かべて思う。最初にイェアに会ったとき、自分に対して酷く遠慮がちに依頼をしてきたあの頃が懐かしい。
とはいえこれも、そもそものお願い自体がたわいもない事であるのに加えて、自分と彼女がある程度の関係を築き、打ち解けてきたからこその強引さなのだろうが。
と、そこでノクトワイがひょいと手を挙げる。
「いやね、アタシ個人としちゃ別に先生ちゃんのお手伝いしてあげるってのが嫌ってワケじゃないのよ?」
「……え? ですけれど、さっきまでお願いしていたのに、一向に頷いてくださらなかったじゃありませんの」
「だって、ねぇ?」
と、ノクトワイは困ったようにこちらを見る。
彼の戸惑いが何なのか。少し考えて、【NAME】は直ぐに思い当たった。
そうだ。自分とノクトワイは、一応審査員の一人という事になっていた。再度行われるという料理対決は、前回と同じく【NAME】、ノクトワイ、オリオール、ノエルの四人を審査員として行う、という話であった筈だ。
だというのに、一方の要請に乗り、その準備に肩入れするような真似していいのか、と。そういう迷いだろうか。
【NAME】がそう言葉を作ると、「ま、そんなとこね」とノクトワイは頷く。
「そもそもの審査員が二人常駐軍、一人が外の国の人、一人が冒険者って割り振りで、有利不利で言えば杜人クンがかなり不利なワケだし。それに加えて、お手伝いまでやっちゃうっていうのは流石に不公平かなーって、そう思うのよねん」
「……う、それは、そうかもしれませんけれど」
至極真っ当なノクトワイの論に、若干イェアは怯むが、
「で、ですけど! そもそも有利だの不利だの、贔屓がちゃんと働いているなら、最初の勝負の時にわたくしが勝ってないとおかしいですわよねっ!?」
「……そこに気づいたか……」
ちっ、と小さく舌打ちするノクトワイ。
その態度を見て、イェアはいよいよ勢いづく。
「それに、手伝いに限って言えば、今度はリゼラさんだって他のキヴェンティの方達の力を借りて準備する筈ですから、わたくしだってどなたかに手伝ってもらって準備しても問題ない筈ですわ! というわけで、決定! 【NAME】さんとノクトワイさんは、わたくしと一緒に食材の調達を手伝っていただきます!」
「「……はぁー」」
【NAME】とノクトワイは同時に深々と溜息をつく。
一瞬視線を合わせて、もう少し粘る? と無言で問い掛けるが、もう諦めて手伝った方が色々早く済むでショ、という気配が返ってきて、まあそれももっともだと、【NAME】とノクトワイは短く了承と答えを返す。
斯くして【NAME】とノクトワイは、隊長殿の指揮の下、彼女の料理対決の下準備を手伝う事になってしまった。
・
「で、具体的には何をすりゃいいワケ? 先生ちゃんが作る料理の味見でもすりゃいいのん? それとも杜人クンところの情報収集とか?」
「違いますわ。わたくし、あの後色々と考えたですの。前回リゼラさんにわたくしが負けた原因について」
「純粋な腕の差じゃないのん?」
「それも一因! 一因としてありますが! もっと大きな、重要な部分がありますの!」
「いや、そこが最重要だった気がするんだけど……ああ、御免なさい御免なさい、ほら、先生ちゃん、涙目にならないで先続けて?」
「もっとも重要な部分。――それは、食材ですわっ!」
ああ、うん、まぁ、ねぇ。
【NAME】は前回の料理の内容を思い浮かべながら、確かにそれはある、と頷く。
何せ、前にイェアが作った代物は、彼女が軍の糧食として用意したものを主な材料としていたのだ。つまりは二種類の乾物である。調味料などで手を加えようにも限界がある。
対し、リゼラが出してきた料理はエルツァン島内で取れる新鮮な動植物を素材としたもの。確かに、調理という工程を経る前の段階で既に大きな差があったと言えよう。彼女の言は、そう的を外れたものではない。
(それらが揃ったからといって、調理がまずければどうにもならない訳だが……)
しかし勝負の土台の部分で負けていれば、同じ舞台に上がる事すら出来ないのも事実だ。
「成程ね。ということはつまり、アタシ達は杜人クン達キヴェンティみたいに、エルツァン島内で使えそうな食材を確保してきて欲しいって事? でもそれ、結構ホネよ? アタシや【NAME】にはそんな知識はないし。頼むなら、ハマダン様の方がまだ目があるんじゃないの? あの人の冒険家の肩書きは伊達じゃないし」
「それについては大丈夫です。軍の島内調査――あとは沿岸警備で得た情報を元に、わたくしの方である程度の当たりをつけてありますので。ほら、これを見てくださいな」
ばさりとイェアが広げたのは、駐屯地を中心としたエルツァン島の大まかな地図だ。島の中の部分に関しては殆どといって良いほど何も書き込まれておらず、駐屯地の両岸と、そこから続く森、そして谷の一片しか情報は無いが、海上と、陣の北側傍の地形については比較的広く、細かに情報が書き記されている。
イェアはまず、とんとんと地図上の二箇所、海上の一点と、西側の海岸から北上した先にある谷の隅を指し示した。
「取り敢えず、この二箇所。そこで、エルツァン外で発見されている、とある亜獣達と類似する形状を持つ存在を確認したという話を聞いています。それらは珍味――高級食材としての価値を持つと記憶しています。もし、この地点で確認された亜獣が、エルツァンの外で発見された存在と同種、もしくは近似種であるなら、同様に食材として利用する事も可能である筈ですわ。そして」
続けて、イェアは陣から北東となる森の奥。書き込まれた地形の境界を越えた、更に奥の位置へと指をずらす。
「残りの一箇所。この周辺で、亜獣の目撃報告とは違いますが、少しばかり気になる情報がありまして。こちらは前者二箇所と違って、まずはその情報の確認と、地形の探索調査からとなりますが、わたくしの推測に間違いがなければ、ここで更にもう一つ、重要な食材が得られると踏んでますの。――纏めますと、【NAME】さんとノクトワイさんには、この三箇所にてわたくしの食材調達をお手伝いしていただきたいと、そう考えています」
イェアが指し示した三点の内、陸の二点については、カール・シュミットの手記に簡単な記載があった記憶がある。谷はロームフーネ無空峡谷、森はナリア・バータ霧眩森林と呼称されていた地形だ。
しかし、手記に記されていた内容に、イェアが目当てとしているような亜獣についての情報は全く無かった気がする。とある亜獣と似た形状と言われても、では具体的にどんな外見の亜獣であるのか。それが判らない事には捜索は厳しい。
そんな疑問は、当然ながらノクトワイも持ったらしく、
「ええっと、まぁ、場所は大まかには判ったけどさ、そこで何を狩るなり採るなりしてくりゃいいワケ? アタシらだけだと大雑把に姿形だけ言われてもわかんないわよん?」
当然の意見に、イェアはこくりと一度頷いて、
「そこはわたくしも同行しますのでご安心を」
「――え、先生ちゃんも? 大丈夫なの?」
彼女の言に、ノクトワイと、そして【NAME】も驚く。
曲がり形にも、というのは少々憚られるが、イェアは一応このエルツァン探索の軍部隊の長を務めている人物である。そんな者が、ほいほいと陣を離れて危険地帯に足を踏み入れるというのは許されるのか。
ノクトワイの言葉に続けて、【NAME】もそんな事を指摘するが、対するイェアは物凄く澱んだ目になり、
「部隊管理についてはある程度落ち着いてきましたし、わたくしが少々の時間離れていても問題は無いでしょう……というか、そもそもわたくし、あんまり皆さんに頼られてませんし……どうせ居なくなったところで誰も気にしませんし……糧食不評だったみたいですし……」
「ああ、ええっと……」
元々の部隊内での扱いに加え、この間の定例会議に参加した身としては、「そんな事は無い」と直ぐさまフォローするのも白々しい。どうしたもんかとノクトワイに視線を向けるが、彼は諦めなさいなとばかりに首を横に振るだけ。
そうしてイェアは暫くぶつぶつと「どうせ人望ないですわよ」だの「この歳でお付き合い経験なくて悪かったですね」だの、何やら関係ない事まで小声で呟き続けた後。完全に思考が脱線している事に気づいたか、頭をぶんぶんと左右に振ると、
「ま、まぁ、そんなワケでわたくしも同行するとして。――まずは、ここを攻めようかと思ってますの」
とん、と改めて彼女が指差したのは、地図の南方。海上だ。
東エルツァン海岸の沖。岸からはかなりの距離を置いた先である。
「海――ってことは、魚介類なのかしらん? でもそこ、なんというか……」
ノクトワイが言葉に詰まるのも判る。
海のど真ん中なのだ。一体、どうやってそこに行くのか。
「勿論、船を出しますわ」
【NAME】の疑問に、あっさりとそう言ってのけるイェア。
つまりは、自分達がエルツァンまでやってきた時に乗った、あの軍船を使って沖に向かうというのか?
「……いや、流石にこんな私的な事に船使うのは厳しいと思うんだけど。先生ちゃん、あの規模の大船って動かすのも一苦労って当然判ってるわよね?」
「え? ああ、勿論、そちらではなく別の船を準備しますわ。その辺りはお気になさらずに」
「別の? いや、先生ちゃん、別の船ったって、あとあるのは……」
「――っと、お二人の協力が得られると決まったなら、わたくしの方の準備も急がないといけませんね。ではお二人とも、わたくしは先に失礼させていただきますので、準備が終わり次第、東エルツァン海岸線のこの辺りまで来てくださいな。そちらにて改めて、細かい打ち合わせと参りましょう」
と、広げていた地図をさっさと丸め、慌ただしく天幕から出て行こうとするイェア。
切り替えの早さに追いつけず、え、あー、と言葉も出ぬままその様子を見送る【NAME】とノクトワイだったが、彼女が天幕から出て行く間際に、ようやくノクトワイが声を飛ばす。
「ちょ、ちょっとお待ちなさいな! それで結局、アタシらは何を相手にするワケ!?」
その問いに、イェアは「言ってませんでしたっけ」と呟いて、
「まず標的は大鯨獣。つまりは、鯨狩りですわ」
――え? 鯨? マジで?
返事にぽかんと動きを止めていた間に、イェアは「急いで準備をしませんとー」とさっさと部屋を飛び出してしまう。
残されたノクトワイと【NAME】は、この先どうなるのかと暗澹とした顔を見合わせ、
「「…………」」
深々と溜め息を交差させた。
――取り敢えずは、相応の準備を整えた後。
ノクトワイと共に、“東エルツァン海岸線”に足を運んでみるとしよう。
真なる楽園 先生、世界を釣る
――先生の手法・海編――
軍の野営陣を離れて、【NAME】達は海沿いに東へと進む。
東エルツァン海岸線。正にそのままとしか言いようのない名称が付けられたその場所は、島内の他地域と比べれば危険度が低い場所と考えられていた。
軍が進めていた調査の結果によれば、エルツァン島は、内陸に踏み込めば“地形や空間の非連続性”という特性が発揮されて、周囲とは隔絶された独特かつ危険な地形、生態が構築される。だが、例外として島の外縁となる沿岸部だけは、そういった独立した特異性が生じず、ごくごく普通の海辺として存在しているのだとか。
事実、【NAME】が今歩いている浜の景色は、他の島々のものと殆ど変わりはなく、“真なる亜獣達の楽園”――フローリア諸島においてもっとも危険とされる島を歩いているとは思えぬ程だ。
もっとも、浜辺としての地形を持つのは野営陣とその東西――距離にして数キロ圏内のみであり、他はほぼ断崖絶壁。加えて、確認されている亜獣も内陸よりはマシだが他島と比べれば危険度の高い種ばかりで、沿岸経由ならば容易く島一周出来るというような話では全く無いのだが。
そうして暫く海岸を進み、指定された場所へとやってきた【NAME】とノクトワイ。そこには既に、印章石による動力機を搭載した小型船に乗るイェアの姿があった。
「――っと、あら?」
半ば砂浜に乗り上げる形で泊まっている船の上。何やらごそごそと俯き加減で作業をしていたイェアが、立ち上がって【NAME】達の方に振り返る。彼女は少し不満げに吐息を付き、
「遅いですわよ、お二人とも。わたくし、待ちくたびれました」
「え?」
思わぬ言葉に、ノクトワイと二人、首を捻る。
「いや、アタシ達結構あれから間を置かずに来たつもりだったんだけど……」
「わたくしなんてとっくの昔にここで待機して、お二人がくるまでずっと待ちぼうけだったんですから。ほら、そこ見てくださいな」
言って彼女が指差した先。船の傍には、海岸地帯に生息している水棲系亜獣達の死体が多数、固まりとなって転がっていた。
「ここでお二人待ってる間、こんなに亜獣達が襲ってきたんですのよ。これから鯨狩りなのに、機甲兵器の無駄遣いをする羽目になってしまって散々です」
「……えー?」
取るものも取り敢えず急いできた、とまで言うつもりはないが、そこまで彼女を待たせる程、余計な事を間に挟んだ記憶は無いのだが。
(イェアが早く来すぎなんじゃないの……?)
(よねぇ……?)
などと、口には出さずにノクトワイと視線だけで会話する。
「というかネ。別に軍陣地内の岸辺で待ち合わせしていればそれで良かったんじゃないのん? そこなら亜獣に襲われることも無いだろうし」
もっとも過ぎる意見に、しかしイェアは首を横に振った。
「問題ありますわよ。この船が動いてるところを他の人達に見られたら、皆さんきっと何事かと思われるでしょうし」
そんなイェアの言葉に、ノクトワイは怪訝と彼女が乗る船をしげしげと見て、「うげ」と声を詰まらせる。
「先生ちゃん、その船、緊急時専用の奴じゃないの。特注の印章石使ってるから制限なり限界時間なりがあって、ここぞって時にしか使えないって言ってなかったかしら」
「今こそが、そのここぞという時ではありませんの?」
「…………」
ド真面目な調子で返されて、【NAME】とノクトワイは暫し絶句。
「いや、それは流石にどうかと――」
「さて、【NAME】さん達も到着した事ですし、早速出発しますわよっ! まずは沖に出て手頃な魚型亜獣を確保します。ほら、はやく乗ってくださいな!」
――駄目だこりゃ。
そんな思考を視線だけで共有させてから、【NAME】とノクトワイは粛々と船に乗り込む。
船は小型とはいえ、乗員数10人以上の代物である。【NAME】とノクトワイ、そしてイェアの三人が乗っただけでは殆どが空いた空間となるのだが、しかし、その半分ほどは印章石がはめ込まれた鈍色の鉄の塊で占拠されていた。
それが何か。推測は出来る。機甲師《マシーナリィ》が使う機械仕掛けの武器、機甲兵器の類だろう。
だが、判りやすく銃口や槍のような突起がついてるものは兎も角、その殆どは素人目には用途がさっぱり不明なものばかりだ。
「あら、【NAME】さん、その子達が気になりますの?」
そんな【NAME】の怪訝な視線が目に留まったのか、イェアが何処か嬉々とした様子で話し出す。
「全部、目的の鯨さんを仕留める為の道具ですわ。特にわたくしが欲しい鹿の子やかぶら骨の部分を上手く採取するのは大変ですから、幾つも機甲具が必要で。ほら、これとか――」
と、彼女はいそいそと愛用の品らしいそれらの説明を始めたのだが、専門用語が多すぎて殆ど理解が出来ない。
しかし、ここでわざわざ素人の自分にも判るように――などとお願いするのは愚の骨頂。更なる説明地獄が続くのは自明である。【NAME】は彼女の説明を遮ると、ただ自分がこれから何をすれば良いのか。これから自分達は何をする予定なのか。それだけを訊ねた。
一応、事前に“鯨狩り”という話だけは聞いていたが、具体的にどうするのかという部分はさっぱりなのだ。というより、本当に“鯨狩り”をするつもりなのかを確かめておきたかった。先程は、何やら手頃な魚型亜獣を確保、などと言っていた気がするのだが。
対して、自分愛用の品々についての語りを強引に切られたイェアは少し不満そうな顔を浮かべるが、彼女としても、これからの事についてはちゃんと話しておかねばとは思ったらしい。即座に気を取り直し、
「勿論、今日のわたくし達の目的は、大鯨獣を狩る事です。けれど、それを達成するにはまず、大鯨獣が好物としている魚の、そのまた好物である魚を確保しなければなりませんの」
「…………」
何だか凄く回りくどい事を言われた。
「つまりは、結局、最初に何をするワケ?」
わざわざ挙手を挟んでのノクトワイの質問に、イェアは「ですから」と前置いて、
「先刻お話しした通り、まずは最初のお魚の確保です。という訳で、早速沖に出ることにしましょう。――お二方、しっかり掴まっていてくださいな!」
と、こちらの返事も待たずに、イェアが船の後部に取り付けられた大型の機械に手を突っ込む。
そのままイェアがごそごそと手を動かすこと数秒。船の推進装置と思しき機械の隙間から、淡い輝きが漏れ始める。機械に内蔵されていた印章石に火が入ったのだ。
続けて、機械が外殻を展開。内部より無数の印章を空中に描き出すと同時、浜辺に乗り上げる形となっていた船体が、地面を抉るような勢いで旋回する。輝きと共に船全体を覆うのは、揺らぎを伴う空気の圧だ。それを感じて、【NAME】は察する。この船の推進能力は、術式機構を使った大気制御によって得られるのだと。
そして推進装置から別種の音が響く。上方に向けて開かれた穴から、装置の内部へと空気を吸い込む吸引音だ。展開された複数の印章陣が更なる光を放ち、数拍の間を置いた後、装置後部から強烈な無形の圧が放たれる。内部に溜め込んだ空気を圧縮したものを勢い良く後方へと吐き出すことで、地面から僅かに浮遊する形で制止していた船は強烈な推進力を得、正に弾かれるように前へ――沖目掛けて飛び出した。
「ぬぉ!? ちょ、先生ちゃん、もうちょっと抑えて抑えて!」
全身に掛かる強烈な空気の圧と水の飛沫。慌てて船の縁に掴まるノクトワイの声を聞きながら、【NAME】も身を伏せて身体を船外へと持っていかれないようにする。
推進機能の特性故か、船は海面の上下差に敏感に反応する。波を割るというより波の上を跳ねるように進む船内は、まるで荒馬の上が如き様相だ。船内の各所に刻まれた印章の力によるものか、積み込まれた機甲兵器は船と接着しているかのように微塵も揺るがないが、残念ながら乗員にまでは効果が及ばないらしい。強烈な上下の揺れと、速度による前方からの圧力。四肢を伸ばし、その二つに懸命に耐えていた【NAME】は、
「さぁー! 待ってなさいなーっ、バーウスバーナーっ!」
と、船体後部の推進装置上にて仁王立ちになって叫ぶイェアの姿を見て愕然とするのであった。
・
「で、あんだけ派手に飛び出した後にこれ?」
「……まぁ、そうですの」
沖に出て十数分ほどの荒々しい船旅の後。
【NAME】達三人は、船に積んであった釣り竿を片手に、静かな水面に糸を垂らす作業に入っていた。
釣り糸の先端には、イェアが持ってきた特製の練り餌。既にこのポイントに到着して一時間以上が経過しているが、一切掛かる気配はない。
「というか、ね」
漸く糸を巻き終えて、ノクトワイはよっこらせと竿をあげた。針の先端に取り付けられた餌の様子を見て、問題が無い事を確認してから、再度海に投げ入れる。
「そもそも開幕からあんなに飛ばす必要なかったんじゃないのん?」
「……いや、ちょっと無駄にテンションあがっちゃってました。ごめんなさい」
普段から余裕のある態度を崩さないノクトワイらしからぬ、責める色の濃い口調に、イェアは肩を竦めて己の竿を揺らす。
ノクトワイの機嫌が悪いのは、先刻のイェアの無茶な操船のせいだ。単純に言えば、船酔いである。平地から海へと上がっていきなりあのような状況に放り込まれては已む無しである。【NAME】とて、本調子とは言い難い。二人、青い顔を並べて竿を振る。残るイェアが全く平気な様子なのが恨めしい。
「それにしても」
「ごめんなさい。ごめんなさい」
「まだ何も言ってないわよ」
「え? ああ、ごめんなさい」
「はぁ……。まぁいいわ。で、それにしても、よ」
ちょんちょん、と竿を揺らしながら、ノクトワイは続ける。
「なんというか、一匹もお魚が引っかからないんだけど、本当にここでいいのん?」
「はい。ここで間違いありません」
あっさりとそう返されると、次の言葉が続け辛い。【NAME】は間を埋めるように糸巻きをぐるぐると回す。
竿の握りの部分に取り付けられた糸巻きはかなり大型のもので、収められる糸の長さは優に100メートルを超える。そして現在、糸巻きはその大半を吐き出していた。つまり海底近くにまで針を落として、魚が掛かるのを待っている状態なのだが、これだけの長さとなると、竿から手に伝わる微細な力や糸の張りで当たりを察知するのは難しい。
「アタシも釣りの経験はそれなりにあるから言わせてもらうけど、これ、多分魚自体がここにいないと思うのよねん。だってこう、餌つついてくる反応すらないし。先生ちゃんの指示通りに、なるべく底に届くようにはしてるけどネ……」
ノクトワイは反応がないと言っていたが、【NAME】からするとその反応すら全く感知できる気がしない。
この地点に到着してから【NAME】がやっている事と言えば、適当に練り餌のついた針を海に投げ落としては、魚が食いついてくれるのをただ茫と待ち、定期的に針を海から引き上げる。後は、イェアの指示があれば取り付けた練り餌を交換する事くらいで、何とも歯がゆい、釣りをしているという実感が湧かない状況が続いていた。本当にこれでいいのだろうか、とそんな考えが頭の中に擡げてくるのも宜なるかなと言った所ではなかろうか。
――取り敢えずは、餌か、もしくは場所を変えた方が良いのではないか。ここまで一匹も掛からないとなると、確かにノクトワイの言う通り、魚がそもそも居ないか、もしくは餌の選択が間違ってるとしか思えない。
糸巻きを動かしながら、【NAME】がそのような話をイェアにすると、返ってきたのはこんな答えだった。
「それはそうですわ。だってそれ、釣るための餌ではありませんもの」
「は?」
ノクトワイと【NAME】、声が被った。
「え? いや、ちょっと先生ちゃん、待ちなさいヨ。ならこれ、つまり撒き餌なワケ? でも、それならこうして針に付けても……」
「いえ、撒き餌でもありませんわよ、それ。近い表現でいうと……毒?」
「毒!?」
糸を巻き終えて、丁度針先に取り付けた餌の状態を確かめようとしていた【NAME】は、思わぬ言葉に練り餌に触れようとしていた手が止まった。
「ああいえ、人間には無害ですのでご心配無く。わたくしが目当てとしている魚に特に効く毒……というよりは、その魚が嫌うとされている素を練り込んだものですわ。それを魚の生息域である海底付近で溶かして撒き散らす事で――」
「……ああ、何か、上がってきてるわね」
ノクトワイが船から身を乗り出し、海中を覗き込んでそんな事を言う。
【NAME】も倣って海を見ると、海中の奥から多数の魚影がゆっくりと浮上してくる様子が見えた。
その様子を眺めながら、【NAME】は成程と頷く。細かい理屈は判らないが、取り敢えずの流れは判った。つまりは、先刻からの自分達の行動は、魚を釣り上げるためではなく、魚を海底から海面付近へ誘導させるためのものだったという事か。
「正解ですわ、【NAME】さん。花丸あげちゃいます!」
にっこり笑って指をくるくる回してみせるイェア。そういう仕草を見ていると、彼女が“先生”と呼ばれているのも何となく判る気がする。
が、そんな朗らかなイェアに釣られる様子もなく、ノクトワイは頭痛を抱えるようにこめかみに手を当てながら、
「……ええと、先生ちゃん? ならアタシ達、なんで結構な時間わざわざ針に糸付けて竿振ってたワケ?」
「そっちの方が気分出るじゃありませんか。ただ練り物だけぽぽいと投げ込んであとは待ってるだけじゃ、退屈でしょう? それに一応、針を付けておけば偶然お魚に引っかかるかもしれませんし」
「…………」
いや、魚が寄ってこない練り物をつけてるのだから、針に魚が掛かることは――少なくとも目当ての魚が掛かることは万に一つもないのではなかろうか。
他にも色々と、突っ込み処が多々ある発言であったが、いちいちそれを指摘する気も失せたのか、ノクトワイは深々と溜息をつく事で言葉にせずに吐き出し、
「で、釣りじゃなかったってのは判ったけどさ。これからどうすればいいのかしらん? 魚が海面付近まで上がってくるとして、それを網かなんかで掬えばいいワケ? 網とかあったっけ?」
ノクトワイの言葉に船内を見回すと、大網らしきものはいくつか積み込まれているのは確認できた。だが、【NAME】がそれに手を伸ばす前に、イェアが否定の言葉を飛ばしてくる。
「いえ、網でわざわざ掬う必要はありませんわよ。なにせ、わたくし達のお目当ては、ほら」
イェアが指差す先では、海底から上がってきた魚影が海面を飛び越え、空中へと勢い良く飛び出す様子が見えた。
大きさは大人の腕一本ほど。口は鋭く突き出て開かれ、その隙間からは鋭い歯が突き出ている。全体の形状は魚に近いが、しかしよくよく見るとその細部には単なる魚らしからぬ奇妙な部位が確認出来た。
「水棲の魚型亜獣の一種ですわ。基本は海底を回遊してる種なんですが、好物の魚は海面付近を泳ぐ小魚でして。とはいえ性質自体は凄く攻撃的で見境無し。特に刺激されて興奮した今でしたなら――」
直ぐ傍の水面が次々と弾け、そこから飛沫と共に跳ね上がった無数の魚が、船上に立つ【NAME】達目掛けてその口蓋を大きく開く。
「――このように。わざわざ釣るまでもなくあちらから来てくれるという寸法ですわ」
ノクトワイが腰に佩いた剣の柄に手を伸ばし、イェアは機甲兵器を手に立ち上がり、そして【NAME】は己の武器を素早く構える。
「ささっと捕まえて、次のステップに入りますわよ」
頷く間もなく、【NAME】は迫る魚達目掛けて鋭く技法を叩き付けた。
飛ぶように水面を跳ね、こちら目掛けて襲いかかる魚達の群れ。
しかしその戦闘能力は然程高いものではない。何せ水面から飛び出し、突撃してくるだけだ。出現地点が読みづらいというのはあるが、しかし反応さえ間に合ってしまえば、食いつかれる前に打ち落とすのは容易である。個体として見れば他島の亜獣達と比べれば強力だが、戦法が一辺倒であるならば梃子摺る程の相手ではない。
【NAME】はそれらを悉く迎撃し、船上に魚を転がす。ノクトワイ、そしてイェアの周囲にも、打ち落とされた魚達がびちびちと身体をくねらせていた。その大半は、外見に大きな傷がない状態だ。イェアの指示もあり、ノクトワイは剣の峰で、イェアも右の手に取り付けた巨大な擬腕で払う形で、飛びついてきた魚が傷つかぬように打ち落としていたのだ。
魚達の襲撃が一段落ついた頃。イェアは肩あたりから腕一本を覆うように取り付けていた機甲兵器を外し、船上に転がった無数の魚達の見定めを始める。魚型の亜獣達はどうやら陸上での活動能力は一切持っていないらしく、ごく普通の魚と同様、鰓と思しき器官を開閉させるだけで、もはや反抗の気配もない。イェアはそれらを険しい顔で眺めて、
「えーっと、取り敢えず元気そうなのはこれとこれとこれ……くらいですわね。後は、この第十一番私設機甲具――名付けて“えいえい大釣りくん”にぽぽいっと」
中から比較的傷が少なく、元気の良さそうな魚十数匹ほどを、船内に積み込まれていた機械類の一つ――四角い形状で、内部に海水を張った鉄塊の中へと放り込み、残りはそのまま海に戻してしまった。
海へと戻った魚達は、既にこちらに襲いかかる気力も尽きていたらしく、そのまま海の底へと逃げるように消えていく。イェアお手製の毒の効果がまだ残っているような気もするが、いちいち気に掛けてやる義理もないかと【NAME】は意識を海中より離す。
「で、ここからどうするの、先生ちゃん」
剣身についた海水を丁寧に拭っていたノクトワイが訊ねると、イェアは水を張った鉄塊、彼女が言うところの“えいえい大釣りくん”の中で泳ぎ始めた魚達の状態を確認しつつ、険しい顔で腕組みし、暫しの間。
「んー、少し心許ないですが、まぁ、大丈夫ということにして、次の段階に進みましょう」
次、と言われて、海岸でのイェアとの会話。今回の鯨狩りの流れについての説明を思い返す。
確か、大鯨獣が好物としている魚の、そのまた好物である魚を確保しなければならないと言っていたか。
つまり、本番の大鯨獣とやらを引っかけるための魚、その好物である別の魚を今確保できた。そんなところか。
となると、次の段階は、
「まずは移動ですわね。一度、島の内と外を隔てる概念境界付近まで出ます。そこで、今取った魚を餌に、大鯨獣の好物とされる“雷狩魚”を釣り上げますわよ」
――先生、誘き釣る――
エルツァン島沖合。出発地であった東エルツァンの海岸線は遙か遠く、島の全景すら一目で確認出来る程に離れた場所に、一隻の船が浮かんでいる。
【NAME】が放ったゼーレンヴァンデルングによる一撃の影響が未だに残っているらしく、島を覆うようにたゆたう影の帯は大きく歪んで、不確かに明滅している。【NAME】達を乗せた船は、その影の境界付近にまでやってきていた。
「そういえばこれ、中から外へは簡単に出られるのん?」
距離にして数十メートルほど。船首に立ち、前方にて揺らぐ半透明の影を眺めながら、ノクトワイは背後、船尾に取り付けられた推進装置を準備稼働状態に移行させていたイェアに問い掛ける。
推進装置の展開していた外殻の幾つかが格納されて、光が弱くなる。それを見届けてから身を起こしたイェアは、遠くに見える影を眺めて、うーん、と渋い声を出す。
「簡単には出られませんわね。例えば、今のわたくし達がこの船で外に出るのは難しいと思います。もちろん、【NAME】さんがもう一度ゼーレンヴァンデルングを使うというなら話は別ですけれど」
「ふーん? じゃあ逆に聞くけど、それって【NAME】の神形器を使わなくても、頑張れば外に出られるってコト?」
続けての問いにイェアは僅かに小首を傾げ、
「んー、そうですねー。必要なのは、大出力の印章機構、それを利用した術式構築者と、その行使者。この辺りでしょうか?」
船尾を離れて、船内に積まれた幾つかの機械の内、内部が槽となっている鉄塊――“えいえい大釣りくん”を覗き込みながら、続く答えを返す。
「大型魔導船の動力を利用すること前提で、師位相当の能力を持つ結界回りに熟知した術者が四、五人いれば、これといった被害もなく行き来は出来ると思います。例をあげれば、わたくし達がエルツァンへと渡るときに使用した船で、わたくしの部下か、ノクトワイ様の部隊の術士の手を幾人か借りれば。逆に、今のわたくし達ですと、印章機構の方はどうにかなりますが、境界をすり抜けるための術式の構築が難しくて、甘く見積もっても九割以上は失敗、という感じになりますわね。――よいしょ」
掛け声に合わせて鉄塊の側面から伸びた把手に手を掛けると、体重を掛けてそれを下ろす。鈍い音と共に鉄塊の表面に亀裂が入り、スリットが生じる。イェアはそこに手を当てて表面部を取り外し、内から出てきた掌大の操作盤に五指を合わせた。
「ちなみに、その術無しであれ通ろうとするとどうなるのん?」
「推測ですが、あの影……といいますか歪みは、概念的な相の差が、視覚として捉えられる程となった結果と思われます。ですので、概念的に……どう言えば一番近いのかな。弱い。いえ、複雑? まぁ、何にせよ、ある程度の大きさを持つ個体が通り抜けようとした場合は、弾かれるような感じで押し戻されるのではないかと」
「ふぅん。要は、壁みたいな感じなのね。……ってか、先生ちゃん、さっきから何やってるの?」
「なにって、準備ですわよ。えーっと。それそれ」
上面、開いた大口から中の様子を覗き込みつつ、側面の操作盤を操るイェア。一体何をやっているのかと【NAME】も顔を近づけて中を覗き込んでみると、海水が詰まった鉄塊の内部では、内壁から伸びてきた機械の腕に捉えられ、身体に糸を差し込まれている魚の姿があった。
「後は、っと」
イェアが更に操作をすると、鉄塊の下部から四本の足が生え、身を左右にがくがくと揺らしながら船の端まで移動し、船の縁に引っかけるような状態で静止する。
それを端から眺めていたノクトワイは、まさかという口調で訊ねる。
「“先生”ちゃん、もしかしてそれって……」
「勿論、釣りの準備です。ちなみにコレは“釣り竿”ですわ」
どう見ても鉄の塊である。
そう突っ込もうとした【NAME】の口を遮るように、がこんと鈍い音と共に“えいえい大釣りくん”の側壁が割れて、中に貯められていた海水ごと、捕まえていた魚達もだばだばと落下していく。海に戻された魚達は慌てるように海の底目掛けて泳いでいくが、それぞれの身体から伸びた細い鋼鉄糸は、鉄塊の下部に開いた小さな穴に繋がっている。その内部からは糸を吐き出す小さな音が鳴り続けていた。
それを見て、ノクトワイは己の口髭を摘みながら、感心したような吐息を零す。
「はぁん。成る程、泳がせ釣りね」
言われて、【NAME】は思い出す。確か、漁法の一種で、生きた魚を餌として使い、それを喰らう魚を釣る、主に大型の魚を狙う場合の手法だ。
「でもって、機能としては確かに“釣り竿”なのね、ソレ。見た目は兎も角」
「まぁ、仕掛けと言った方が通じが良いかもしれませんね。手近な機甲兵器に生け簀と釣り機能を適当にブチ込んだだけですんで、外見については多めに見ていただければ。それでも全自動で操作はやってくれますし、後はタウスが掛かってくれるのを待つだけなのですけれども」
――タウス?
聞いた事も無い言葉に首を捻ると、イェアは海の様子から目を離さないままこくりと頷き、
「ええ、タウス。“雷狩魚”の異名を持つ大魚亜獣ですわね。前に哨戒からこの付近で発見したって報告を貰っていたんで、居るならこの魚を餌にして釣れる筈なんですけれど――っと!」
突然、海が黄金色に輝いた。
弾ける雷気が、海を伝染するように走り、浮かび上がる気配が服や髪を逆立たせる。何事かと警戒心も露わに身構える【NAME】とノクトワイだったが、イェアは歓喜の表情を浮かべ、
「掛かりました! 大当たりですわっ!」
「早いわね!」
まだ魚を海に戻して数分も経過していないというのに。
驚くノクトワイと【NAME】に、イェアは周囲にて荒れ狂う雷の網を前にも平然と首を振り、
「タウスは、餌に使った魚達が海底と海面を移動するところを狙って捕まえますから、むしろ直ぐ掛かってくれないと困っていたところです」
「それは判ったけど、この雷は一体何よ!?」
「タウスが持つ電撃能力ですわ。狩りの時や、外敵との戦闘時に、タウスは体内から周囲へ強力な雷撃を放つんです。だからこその“雷狩魚”という異名な訳ですね。先刻からバチバチしっぱなしなのも、食いついた魚に糸がついてたものだから、焦っての事だと思いますわ」
言われてみれば、“えいえい大釣りくん”から伸びた糸は強く張って、ギリギリと糸を巻き上げる耳障りな音も響いている。仕掛けた釣り餌に食いついたのだから、当然そこから釣り上げの作業に入っているのだろうが。
(それって……)
「つまり、今からその雷連発してくる魚が下から浮かび上がってくるって訳!?」
【NAME】の想像を補うようなノクトワイの叫びに、イェアはにこやかに微笑んで、
「その通りです。さぁ、【NAME】さん、ノクトワイ様、戦闘の準備を!」
「そういう事は先言っといてよね! アタシだって相応の準備ってもんがあんだから!」
叫びながらノクトワイが抜刀し、【NAME】が慌てて武器を構える中。
海中から、強烈な雷気と共に巨大な魚影が浮かび上がってくる!
「……予想以上にでかかったわね、これ」
紐に繋がれ、後方にぷかぷかと浮かぶタウスの姿を船尾にて眺めながら、ノクトワイが呆れたような声を出す。激戦を終えて船上にて座り込んでいた【NAME】は、全くだと頷いた。
雷を伴い、海中から姿を現したタウス。その大きさは【NAME】達が乗る船を上回り、下手をすると鰭の一撃で転覆されかねない程だった。“えいえい大釣りくん”から伸びていた糸は特別製の鋼鉄糸だったとはいえ、よく引き上げられたものだと感心するしかない。糸の強度も然る事ながら“えいえい大釣りくん”自体の力も相当なものだ。これでタウス自体の動きも封じてくれたならもっと評価できたのだが、残念ながら海面まで引き上げられたタウスは暴れに暴れ、ノクトワイと【NAME】は船上にて弾ける雷撃を潜り抜けての大立ち回りを繰り広げる羽目となってしまった。
戦闘自体は、【NAME】とノクトワイが的確にタウスの体力を削って一通り弱らせたところで、それまで船を転覆されぬよう操船に専念していたイェアが、相手を一時的に麻痺させ、動きを止める機甲兵器を使用。それの効果が発揮するまでタウスを抑え込む形で、比較的スムーズに、タウスを死なせず捕獲する事が出来た。
「で、この馬鹿でかい魚を捕まえて今回の目的は達成――って訳じゃないのよねん?」
「勿論!」
勢い良く返事をしたのは、船の状態を確かめていたイェアだ。彼女は一通り見終わったのか吐息と共に身を起こすと、
「これは前座ですわよ前座。大体、タウスは食用として使える部位が殆ど無い魚ですし」
「これが前座て」
「大体、最初に言いませんでしたっけ? 大鯨獣が好物の魚をまず捕まえるって。大鯨獣は、このタウスが大好物……といいますか、これを目標に餌探しをしているらしくて。なので、大鯨獣の回遊ポイントにこのタウスを引っ張っていけば、大鯨獣を誘導するのも容易、という訳です」
「……それってつまり、大鯨獣さんってのがこの船と同じくらいのサイズなタウスを余裕でパクつけるくらいでかいって事よねん」
「はい」
「無理じゃね?」
心底げんなりと呻くノクトワイ。それに関しては【NAME】も全くもって同意見でこくこくと幾度も頷くが、イェアはそんな【NAME】達の様子をさらっと流して、
「では、いきますわよー。目指すは、大鯨獣の姿が目撃されたエルツァン沖の東端です!」
声と共に、船の推進装置を稼働させた。
――先生、世界を釣る――
やってきたのは、エルツァンを覆う概念境界の東端付近。イェアが言うには、大鯨獣は概念境界沿いに島の周囲をぐるぐるとスローペースで回遊しており、推測によれば大鯨獣が現在居ると思しき場所がこの周辺であるらしい。
「大鯨獣に関しては、かなり早い段階で海域哨戒を行っていた兵士達からその存在について報告があがっていました。ノクトワイ様もご存じですよね?」
船とタウスを繋いでいるのは“どっこい太巻きくん”から吐き出されている大紐だ。イェアはそれを緩めながら、ノクトワイに話を振る。ノクトワイは少し考え込んでから、
「あー。もしかして、合同探知で見つけてた陰性質の大型亜獣反応? もしかして、アレを狙ってるわけ? ってか、陰性概念って話だったから正直鬼種だと思ってたんだけど、鯨なの?」
「恐らく。大鯨獣のような超大型の亜獣は、生息域の土地概念が陰性質に偏っていた場合、食事などの際に得たその性質を体内に取り込んで本体自体も陰性質に偏る傾向がある、というのが研究で判っていましたし。あの後哨戒での目撃例などを照らし合わせて、正体は陰性質に変化した大鯨獣――バーウスバーナである、と」
「そんな亜獣、聞いた事無いけど……。【NAME】はある?」
問われて、【NAME】は素直に首を振る。少なくとも、フローリア諸島では聞いた覚えはない。
「あら、そうですの? 芯海では結構目撃されてる大型水棲亜獣の一種で、亜獣なんてフローリア諸島以外でそうそう見掛けませんから有名な部類だとは思うんですけど。あと、さっきのタウスとかも」
件のタウスは、未だ麻痺が解けておらず、身動きもせず海に浮かんでいる。“どっこい太巻きくん”から伸びる大紐から伝わる術式が、タウスの身体を硬直させているのだ。先程から大紐は“どっこい太巻きくん”からどんどんと吐き出されており、それに併せて【NAME】達が乗る船とタウスとの距離も離れつつあった。これもイェアの操作によるものだが、一体どういう意図があるのか。その説明はまだされていない。
ノクトワイは作業を続けるイェアから視線を外し、
「……有名ねぇ。それ、ハナから亜獣とかに興味もってる人達の間で有名とかじゃないのん? アタシはこっち来るまでは亜獣なんてのとは縁無かったし、アラセマに居た頃もお仕事は基本陸だったからなぁ」
【NAME】にしても、海はそもそも範疇外だ。単独で行動する冒険者にとって、船という足が必要な海での活動は縁遠い。そんな【NAME】とノクトワイの反応に、「一般的にはそんなものなんですのねー」と頷き、
「まぁ、亜獣といっても、見た目は基本的に鯨と変わりませんわね、勿論多少の差異はありますけれど。特徴といえば、亜獣特有の……他生物との混合要素と、若干の概念干渉能力くらいですか。性格は普段は大人しい方で下手にちょっかいを掛けない限りは人が乗ってる船には寄ってきませんけど、その巨体と、水流操作の能力の影響で、漁船の仕掛けが破壊されたりとか、不慮の事故で転覆したりとかはありますね。大きさが大きさですから」
「で、そんな相手を今から狩ろうってのね。……正直言って、こんな船とこんな人数で鯨狩りが出来るとも思えないんだけど、大丈夫なのん? 話聞いてる限りだと、滅茶苦茶でかそうなイメージなんだけど。ってか、そもそもそんなでっかいのがこんな大して水深もなさそうな場所に居るわけ?」
「大鯨獣の知名度が高い理由の一つが、人の生活圏に近い、浅瀬の方まで寄ってくる事が多いからですので。基本は外洋を回遊しているらしいのですけれど、彼等が好む“雷狩魚”タウスの行動範囲がかなり広いので、タウスの気配に釣られて陸地周辺に近付いてくる事もあるみたいです。――あ、ちなみにサイズは、わたくし達がエルツァン島に来るときに乗っていた船と同程度と思っていただければ」
「でかくないっ!?」
というか無理じゃない? それ無理じゃない?
ノクトワイと共に、【NAME】は討伐するのは不可能ではないかとイェアに訴えるが、彼女はまぁまぁと掌を翳し、
「勿論、策はありますわよ。所詮、相手は海の生物。しかも海中である事を前提とした巨体とその構造である筈ですわ。だから、そこから離し、わたくし達の舞台にまで大鯨獣を引き上げてしまえば勝機は十分にある筈です」
「……いや、引き上げるって、こんな小船でどうしようってのよ」
「どうするかは、今から見せて差し上げますわ。というわけで、本番、行きますわよぉー!」
イェアが“どっこい太巻きくん”を操作すると、巨大な巻尺に似た構造の“どっこい太巻きくん”から空中に漏れていた印章が消え、中央部に埋め込まれていた印章石が輝きを失った。
それと同時に海面を走る、膨大な電の帯。“どっこい太巻きくん”が駆動させていた術式が停止した結果、タウスが行動を開始したのだ。
唐突に術式による麻痺から解放されたタウスは、状況を把握出来ずに混乱しているのか、正に最大出力といった様子で雷撃を四方八方へと散らしながら海面をのたうつ。距離を取り、術式を停止させたとはいえ、“どっこい太巻きくん”から伸びた大紐による拘束はそのままだ。紐による束縛は、タウスの全身を縛るように施されている。タウスは満足に泳ぐことも難しく、束縛から逃れようと海面上で身をくねらせながら、ただ闇雲に周囲へと雷撃を放ち続ける。
空中のあちこちで裂けるような音が連続で響き、満ちた雷気によるものか全身の毛が逆立つような感覚を味わう。
「なんか凄い事になってるけどーっ! これ、こっからどうすんの!?」
「暫く放置ですー! 後はタウスに大鯨獣が食いついてくるのを待つだけですわ!」
間断なく続く音に負けぬよう怒鳴りに近い声を上げたノクトワイに、こちらも叫ぶような声でのイェアの返答。
「ほ、ホントにこんなので寄ってくる訳っ?」
「以前に見た資料が本当なら、大鯨獣はタウスが持つ雷気を感じ取る力を持っている筈ですわ! なら、発見報告があるこの場所で、タウスの雷撃を誘発させ続ければ、きっと――来たっ! ほら、見てくださいな!」
雷撃により激しく荒れ狂う海面に怯まず、イェアが身を乗り出して指を差す。
大紐による拘束から逃れようと派手にのたうつタウス。その下方より、更に巨大な影が海中から浮かび上がってくるのが見えた。海面が大きく盛り上がり、タウスが突き上げられるような形で半ば空中へと押し上げられる。
今にも盛り上がった海が割れて、そこから姿を現した何者かが、タウスを一呑みにする――と思われた、その瞬間。
「さあ、逃げますわよ! 全速力っ!」
「え?」
前回と同様、船上からの戦いになるのかと悲壮な覚悟と共に身構えていた【NAME】とノクトワイは、突然の言葉に肩透かしのように身を崩した。
だが、そんな二人を全く無視して、何時の間にか船の後部に移動していたイェアは、船の推進装置を全力稼働。外殻が全解放され、中に収められた印章石が今までにない程の強い輝きを放つと同時、船は大紐によって繋がれたタウスごと、弾かれるような勢いで移動を開始した。
突然襲いかかってきた前方からの圧力に、【NAME】とノクトワイは危うく船から振り落とされるところだったが、【NAME】は固定された機甲兵器に手を引っかけ、ノクトワイは転がりながらも船の縁を掴まえることでどうにか耐える。そこへ、更に襲いかかってくる上下の振動。海面を跳ね飛ぶように進む船から落とされないよう懸命に掴まる。
「おおお! ちょ、先生ちゃん、どういうこと? 戦うんじゃないのっ!?」
「いや、こんな小船であんなの相手にどうやって戦うんですか」
「…………」
予想外の常識的な返しに、逆に黙り込んでしまう【NAME】とノクトワイ。
「一撃で沈められちゃいますって。だからこうして、最低でも大鯨獣を岸にまで誘導して、陸地で戦闘出来るような状況を整えないと」
「……ああ、成程」
振動に揺さぶられながら、ノクトワイの納得したような声を聞く。【NAME】としても得心がいった。先刻の「わたくし達の舞台にまで引き上げる」とはこういう意味か。
しかし、
「って、そんな都合良く釣られてくれるのん?」
そうだ。大鯨獣を陸地にまでおびき寄せる事など出来るのか。いくらタウスという餌があるとはいえ、そうそう上手くいくものなのか?
【NAME】とノクトワイの疑念に、しかしイェアは後方を振り返り、
「大鯨獣は兎に角タウスに――といいますか、タウスの雷撃に目が無いんですの。だから、こうしてタウスを喰われる前に引っ張っていけば――ほらっ!」
彼女の視線を追うように船の後方を見れば、大紐に拘束されたまま、高速で船に引き摺られるタウスと、その後方から追い迫る巨大な海面の盛り上がりが見えた。大鯨獣は未だ海中から姿を現してはいないが、しかし立ち上る水柱からその大きさがどれ程のものか想像するのは容易い。そして速度の方も相当なものだ。印章機構を推進器として持つ魔導船の全速力に、全く引けを取っていない。しかし、追いつけるほどの速度は出せないらしく、距離自体は全く縮まっていないのは幸いだ。もし追いつかれていたならばあっという間にタウスごと、自分達の船も呑み込まれていた事だろう。
「後は、どうにか岸まで逃げ切って、そこで勝負ですわ。よし、見えたっ!」
跳ねるように海を進む船の前方に、エルツァン島の姿が映る。船の圧倒的な速度故か島は見る間に近付き、そして船は全くの減速を掛ける気配も無く、一直線にエルツァンの海岸線目掛けて突き進んでいく。
「ちょ、先生ちゃん! 速度緩めて速度!」
「緩めたら追いつかれちゃいますし、大鯨獣に警戒されるかもしれないからダメです! このまま一気に陸に上がりますわよ!」
「ああんもうっ! 【NAME】、衝撃に備え――あがががががっ」
ノクトワイの言葉が終わる前に、船はざんざんと岸に乗り上げて浜辺を派手に滑る。それとほぼ同時に、推進装置から甲高い音が響き、内蔵されていた印章石が砕けて溢れ落ちた。どうやらここまでの逃亡劇の間に限界まで酷使された結果、過負荷に耐えきれず、壊れてしまったらしい。推進装置が構築していた術式が解け、船を包んでいた空気の圧も消滅。地面に船体を衝突させた船は、その勢いに抗しきれず、【NAME】達乗員や積み込まれていた機甲兵器などを撒き散らしながら崩壊した。船から放り出される瞬間、慌てて積み込まれていた機甲兵器の一つ――機械仕掛けの巨大な腕を取り付けたイェアが素早く印章を空中に刻んだ瞬間、吹っ飛ぶ速度が大幅に弱まった。恐らくは彼女が術式を駆動させたのだろう。しかしそれでも完全に勢いは殺し切れず、【NAME】は砂地の地面を派手に吹き飛ばす形で、ごろごろと数度転がる。
くらくらと揺れる視界。身体の節々に走る痛みを堪えて立ち上がれば、【NAME】の左右にはそれぞれ、全身が砂まみれになったノクトワイとイェアが、
「ったく、無茶苦茶だわっ!」
「うーっ、まともに顔面から突っ込みましたぁ……」
と騒がしく身体の砂を払っているところだった。その様子から、どうやら大きな怪我を負ったという事はなさそうだ。
そこまで確認して、【NAME】は海から響いてくる地響きのような音に慌ててそちらを見る。そうだ、自分達はタウスを餌に、大鯨獣を陸に引き上げようとしていたのだ。船は壊れた。積み込まれていた機甲兵器の内、タウスを束縛していた“どっこい太巻きくん”は既に壊れて、中身を派手に晒した状態で傍に転がっている。そして絡まった大紐の先には、陸に打ち上げられ、既に電気を放つ事も出来ない程に弱った“雷狩魚”と、今正にそれを喰らおうとする大鯨獣の姿があった。
「――って、ちょ、これでかすぎじゃないのっ!?」
ノクトワイが悲鳴をあげるのもわかる。
海を割り、大鯨獣が岸に乗り上げる形でその巨体の全てを地上へと晒す。全長10メートルなどでは到底収まらない、大型船舶にも迫るかという姿。先刻からの地響きは、この巨大な獣が、地面を削り滑ってくる際の音だ。水と土。二つの波を造りながら、大鯨獣は一呑みでタウスを浚い、そしてそのままの勢いで、【NAME】達の居る方へと突っ込んでくる。迫る黒色の巨体は、まるで動く山のようだ。
――これを倒すのか?
流石に無理があるのではなかろうか、そうイェアに訴えようと口を開き掛けて、
「さー、わたくしの食材のために、全力で倒しますわよ!」
やる気ありすぎじゃないですかね。
内心そう突っ込む間にも、大鯨獣は地を削りながらこちら目掛けて突っ込んでくる。
「迎撃ですわ!」
いや無理でしょう。
【NAME】はノクトワイと視線で意思を交換しあうと、イェアの襟首をむんずと掴み、全力で横方向への回避を敢行。
「あれ、ちょっとー!?」
と、慌てたようなイェアの声を無視して【NAME】はどうにか大鯨獣の突進を避けきり、側面へと回り込む。イェアの予想通り、陸に打ち上げられた形の大鯨獣は、突進の勢いが収まれば後は碌に身動きが出来ないようだった。これならば案外どうにかなるのかも。そう、楽観的な予測を立てた【NAME】であったが、
「【NAME】、海の方!」
ノクトワイからの警告の声にそちらを見れば、打ち上げられた大鯨獣の尾が上下に動く仕草に併せて、海水が無数の柱となって立ち上がり、まるで宙を泳ぐ蛇のようにうねり、そして、
「来るわよ!」
大鯨獣目掛けて攻撃を仕掛けようとしていた【NAME】目掛けて落下してくる!
battle
封じられた海の王


「…………」
「……いやぁ。まったく」
海岸にて転がる二つの人影。ずたぼろになった【NAME】とノクトワイは、大の字の姿勢のまま、先刻の戦いを回想していた。
大鯨獣バーウスバーナとの戦闘は、正に死闘を極めた。陸に打ち上げられた大鯨獣は殆ど身動きができない状態となっており、攻撃自体はし放題。しかし、巨大すぎる鰭はただ上下させるだけでも強烈な一撃となり、身体を僅かに偏らせ、ひっくり返すだけでも十分な脅威となった。逃げ遅れ、押しつぶされれば確実に戦闘不能になっていただろう。更には、大鯨獣は水を操る力を持っており、海水を練り、操り、固めて、時には口から水流として打ち放つ事で、【NAME】達を翻弄した。これらの対応には、イェアが用意していた機甲兵器による防御が欠かせなかった。イェアの機甲兵器は印章石を内蔵し独自の強力な術式を展開するものが殆どで、イェアはそれらを惜しみなく投入した。その結果、【NAME】達は大鯨獣の操水を抑え込みながら着実にダメージを与える事に成功し、そしてつい先刻、ようやくとなる止めの一撃を、大鯨獣の脳天に叩き込むことに成功したのだ。
「で、こんだけ苦労した結果が、アレってのがねぇ……ってか」
ぐったりとしていたノクトワイが、ゆっくりと身を起こしながら視線を遠くへ向ける。
「臭いわね、本当に」
呻くような言葉に、【NAME】も無言で頷く。
ノクトワイの視線を追えば、そこには大鯨獣の亡骸が、半ば解体された形で存在していた。
鯨の身体は鰭や尾などは丁寧に分解され、腹は大きく開かれて、そこから熱を持つ内臓が外へと掻き出されている。悪臭の原因はそこからだ。血と消化物が混じり合った独特の臭いは、そのサイズ故か強烈極まりない。
そんな中で、血まみれの白衣を着込んだ人物が、せっせと作業を続けている。顔をマスクで覆ったイェアは機械仕掛けの巨大な腕の先端に、また別の刃物状の巨大な機甲兵器を取り付けて、ばっさばっさと内臓を解体。偶に、
「おー、カラギモ発見。やっぱおっきいですわねー」
などと感心したような声が届いてくる。
既に大鯨獣に止めを刺して結構な時間が経過しているのだが、鯨の解体作業はまだまだ終わりそうにない。正直なところ、この悪臭に加えて全身血と海水と砂まみれな事もあり、さっさと軍の陣地に引き返して身体を綺麗にしたいのだが、ほっといて帰ってしまっていいものなのだろうか。取り敢えず、最初のイェアの依頼自体はこなしたとは思うのだが。
そんな【NAME】の呟きを聞いて、ノクトワイも全くと頷き、
「おーい、先生ちゃーん! アタシ達、もう帰っちゃっていいーっ!? 色々汚れちゃったから綺麗にしたいんだけどーっ!」
大声で叫ぶと、鯨の内部に入っていたイェアがひょいと顔を出してマスクを外し、
「後の作業はわたくし一人で大丈夫なんで、先に戻っていただいても結構ですー。一応、今回手伝って戴いたお礼ということで、そちらの――」
イェアの右の腕に取り付けられた巨大なアームが、ひょいひょいと少し離れた場所に並べられた大鯨獣の鰭や尾を指差す。
「適当に好きなのを持ち帰っちゃってくださいなー。わたくしが必要なのはもっと別の部位ですんでー」
言葉に従い、【NAME】とノクトワイはそれらの部位を矯めつ眇めつ眺める。
「……【NAME】、これ要る?」
どうかなぁ。
渋い顔を見合わせる。取り敢えず、折角貰えるのだからと持ち運びしやすいものは持ち帰ってみる事にしたが、何というか、苦労に対する実入りというものがいまいち釣り合っていない気がしてならない。
適当に鯨の肉などを抱え、帰路につこうとする【NAME】達。と、そこへ鯨の内部に戻り掛けていたイェアが、ふと思いついたように声を飛ばしてきた。
「あ、そうだ。次はロームフーネに卵を取りに行く予定なんで、準備と休息が終わりましたら、お二人でそちらまで来てくださいねー」
「…………」
【NAME】とノクトワイは、更に表情を渋くして身動きを止め、そして深々と溜息をついた。
――取り敢えずは、相応の準備を整えた後。
ノクトワイと共に、今度は“ロームフーネ無空峡谷”に足を運んでみるとしよう。
真なる楽園 先生、卵を盗んで走り出す
――先生の手法・谷編――
西エルツァン海岸線から北上した先に広がる、アーチ状とも三角状ともいえる独特な形状を持った峡谷。
カール・シュミットの手記に従うならばロームフーネ無空峡谷と呼称された場所へとやってきた【NAME】とノクトワイは、その入り口、海岸線から峡谷へと入る口の前で待っていたイェアと合流した。
「よくぞ参った、我が精鋭達よっ!」
「……何その成切り、ふざけてるの」
「テ、テンション低いですわね」
ノクトワイの返しが予想外だったらしく、ポーズまで決めていたイェアが途端におどおどと弱気になる。
対し、ノクトワイは色濃く疲れが残った気配を漂わせながら、
「いやそりゃね。この前の鯨狩りはえっらい苦労させられたし、その後のお願いとやらでばんばん時間取られるし。で、続けて今回でしょ? そりゃ対応もおざなりに――」
「あー! わーわー!」
と、うだうだと文句を続けようとしたノクトワイを遮るように、イェアがノクトワイの前に移動してばたばたと両手を振る。
「それダメ! ダメですわよ、ノクトワイ様!」
しー、しー、と口に指を当てるイェアに、ノクトワイは暫し眠たげな視線を投げて、
「……ああ。えーっと、で、今回は何すりゃいいのん?」
何やら強引に話題が変わった気もしたが、【NAME】がそれを指摘する前に、慌てた調子でイェアが言葉を繋ぐ。
「前回は流石に【NAME】さん達に無理させすぎましたんで、今回は簡単なお手伝いをお願いする予定です。さくっと説明しますと……卵泥棒ですわね」
卵泥棒。
鸚鵡返しに呟いて、【NAME】はふむと考える。
予想できる展開としては、これからロームフーネの峡谷に入り、そこに生息する亜獣の卵を巣から盗み出す。そんな感じだろうか。
それをそのまま口にすると、イェアはこくりと頷き、
「正にその通りですわ。これなら楽だとは思うのですけど」
「何だか、普通に簡単そうで、逆に警戒しちゃうのはなんでかしらねん。もしかして、竜種の巣に入り込んで卵盗むとかそういう展開じゃないでしょうね?」
「あー、一応翼竜の存在が確認されてるんで、【NAME】さん達が宜しければ、そちらの卵でも良いと言えば良いんですけど……」
不可。凄く不可です。
ぶんぶん首を振ると、イェアは「ですよねー」と半笑いになり、
「今回の標的は、オーメルスゾーンという四足の草食亜獣の卵ですわ」
話しながら、イェアは地面に下ろしていた巨大な鉄製のアームを持ち上げると、左右の腕にそれぞれ取り付ける。鯨退治の時には右腕のみだったが、今日は二本、両腕分を用意していたらしい。
「オーメルスゾーン……。これも、この前の大鯨獣と一緒で聞いた事無いわネェ? どんな亜獣なのん?」
「そうですね。フローリア諸島では今まで確認されていませんし、他の地域でも最近確認されたという情報はありませんから、ノクトワイ様がご存じないのも無理からぬことかと思います。オーメルスゾーンは旧時代の記録に残っていた亜獣で、実際に存在を確認されたのは“芯なる時代”が終わって暫くの短い期間だけだったそうです」
歩きながら話しましょう。
そう告げて、イェアは峡谷の中へと足を向ける。【NAME】とノクトワイも、それに続いた。
「にしても、そんな古い記録良く残ってたわねん。っていうか、先生ちゃんも良く覚えてるものね、そんなの」
「フローリアに出向って話になったときに、学院にあった亜獣関係の資料は片っ端から当たりましたからね。東大陸の“虹色の夜”で現れたという亜獣達については厳しいですけれど、それ以外、それ以前に確認された亜獣についてなら、それなりに語れるつもりです。で、そのオーメルスゾーンなんですけれど、生物としてはごくごく普通の草食獣で、大きさも一メートル以下の、その程度の亜獣です。既存の動物に例えるならば、小型の河馬か犀といったところでしょうか。特殊な能力のようなものも全くありません。特徴といいますか、性質のようなものはありますが、そのサイズでならば別段気にする必要は無いでしょうね」
「……それ、亜獣なの? ってか、よくそんな平凡極まりない亜獣の情報が資料として残されてたわね」
「分類としては亜獣、ですわね。資料として残っていたのも、一応理由はありまして。まぁ、色々とかみ砕いて説明しますと、卵がすっごい美味しいんだそうです。記録として残すほどに」
「あー」
ノクトワイが気の抜けた声を漏らす。それは、イェアからすれば見逃せないだろう。
「とまぁ、そういう訳でして、これからオーメルスゾーンの巣に向かいます。場所の方は、一応もう確定させてますんで、直ぐに着くとは思うんですけれど」
その発言に、【NAME】は少し驚く。現在、軍の調査範囲は主に海洋と左右の海岸沿い、そして野営地の北側を主に進めていた筈だ。内陸に相当し、土地概念的にも独立した領域であるロームフーネ無空峡谷には然程手を伸ばしていないと思っていたのだが。
そんな【NAME】の感想に、イェアは僅かに苦笑を浮かべて
「流石に、先遣の支隊くらいは派遣してますわよ。勿論無理はせず、極力戦闘は避けて、安全を十分に確保した上での情報収集に専任させる形で、ですが」
「まぁ、そんな感じで人を回していても、碌に情報が手に入らないばかりか、負傷したり、行方不明になったりってのもちょくちょく起きてるんだけどね」
ノクトワイがそう続けて、小さく溜息をつく。
彼等が苦い様子を見せるのも判る。エルツァンの海岸や、野営地の北側は言ってみればエルツァン島の外縁のような場所で、その本性はここのような内陸の特殊地形にある。その調査に人を派遣した結果がこれでは。
「それでも、生息している亜獣の情報や、大まかな地形の情報については多少なりとも手に入ってきまして、そうして得られた情報の中に、わたくしの知るオーメルスゾーンとほぼ同様の外見を持つ亜獣と、その巣の位置があった、という訳ですわ。――ええっと、確か、こっちです」
谷の底。乾き果てた土の上を歩いていたイェアが、転がる大岩を幾つか乗り越え、片側の崖の壁沿いに歩み寄る。そこには深く亀裂の入った巨大な隙間があり、その向こう側には、どういう自然現象によって生じたものか、迷路じみた谷道の通路が存在していた。
イェアの先導に従い、亀裂の中に足を踏み入れる。先刻までと違い谷の上方は広く開いているため、道は明るく視界は良好だ。イェアの後に【NAME】が続き、そして殿をノクトワイが務める。背後からはきょろきょろと周囲を見回すような気配があり、
「支流の跡とか、そんな辺りかしらね」
「どうでしょうか。エルツァン島の地形は、経年による変化という自然形成の基本概念から逸脱している可能性が高いですから、もっと別の要因による可能性も考えられますけれど」
「じゃあ何なのよん?」
「……それについては、判りかねますが。わたくしの方で確認しているのは、この谷道は枝状の細かい行き止まりと広い空間の組み合わせになっていて、オーメルスゾーンの巣はその行き止まりのどこかにあるらしい事。それと――」
唐突に。
言葉を切り、イェアがぴたりと立ち止まる。肩より腕全体を覆うように取り付けられた機械の擬腕から、僅かな駆動音と共に小さな印章が光と共に漏れ出し、上部に取り付けられた印章石が輝きを放ち始める。若干身を屈めたその背から漂うのは緊張だ。
イェアのその様子から警戒の意識を周囲に飛ばした【NAME】は、両側の崖の上方、壁に走る凹凸の影に隠れるように、ゆっくりとこちらに迫ってくる脅威の姿を察した。
「谷道では、オーメルスゾーン以外に危険な亜獣――主に大長虫の類が多数生息する、という話だけですわ」
「……成る程ねん」
背後にて、ノクトワイが一息で抜刀する気配。
それが契機であったかのように。崖の上方にて機を窺っていたらしい巨大な蛇達が、一斉に【NAME】達目掛けて落下してくる!
「ある意味楽よね。上から落ちてきてくれるのって」
ノクトワイが笑みすら零してそう呟く間に、彼の手が鋭く閃き、新たに落下してきた大蛇の身体が斜めに断ち切られる。
「そうですの? わたくしからすると、やりづらくって仕方無いのですけれど……」
そうは言いながら、イェアは機械に覆われた両の腕を上空に掲げて、ふ、と浅く息を吐く。
続いて、機械の掌、伸びた指先が更に枝のように分かれて、その先端がそれぞれ、空中に複数の印章を描く。
そうして生まれるのは術式の駆動だ。理粒子の飛沫と共に指先から放たれた無数の炎弾は、次々と落ちてくる蛇達の身体を的確に捉え、熱と共にはじき飛ばしていく。
全然やりづらいようには見えない。
【NAME】がそんな素直な感想を零すが、イェアは両腕を掲げたまま「いやいや」と首を振り、
「この“マッシモ鉄腕くん”は基本的にはパワー重視と言いますか、肉弾戦は掴みや打撃メインで、術式補助についても小技じゃなくて大技用の奴でして。こういう柔らかくて細長い、にょろにょろしたの相手には向いてないんですよねー」
などと言いつつ、鋼の指先から放たれる術式は蛇達をどんどんと駆逐していく。鯨狩りの時も薄々感じていたのだが、機甲師としてのイェア・ガナッシュは、自分が想像していたよりも数段優秀な戦士であるらしい。
「って、【NAME】。ぼーっとしてたらダメよ。上上」
後方からの忠告に、ああと視線を上げる。降ってくるのは二匹の蛇。空を滑る。そんな比喩が似合うほどの素早さ、独特の軌道で降ってくるのは亜獣としての特殊な能力を発揮した結果なのだろう。
しかし、その程度の事に惑わされるならば、この真なる亜獣達の楽園に辿り着けてはいない。一瞬でその軌道を見切り、僅かなステップでもって蛇の噛みつきを躱して、返す動きで二匹の蛇の頭部を一度に砕く。
「ヒュー」
「さすがですわね。【NAME】さん」
前後からの賞賛に、肩を小さく竦めることで答えて、己が武器を収める。蛇の襲撃は【NAME】が処理した二匹で最後だ。
「では、肩慣らしも終わったことですし、本番と参りましょうか。確かあそこに、オーメルスゾーンの巣が一つあるという話ですので」
言って、イェア前方。遠くに見える、曲がりくねった谷道から枝分かれした行き止まりを指し示した。
――先生、草食獣の卵を追う――
「…………」
枝別れした谷道の行き止まり。
所々に転がる大岩や、削れ崩れた壁の影などを経由し、身を隠しながらそこへと移動した【NAME】達は、眼前にて身を埋める巨体を前にして、暫くの沈黙を続けていた。
重苦しい空気。三人の態度はそれぞれ違う。【NAME】は眉をしかめて未だこちらには気づいていない大獣の姿を眺め、ノクトワイは乾いた笑みを浮かべてイェアの方を見、イェアはだらだらと鈍い汗を流しながら視線を斜め下に向けている。
沈黙を破ったのは、ノクトワイだった。
「ねぇ、先生ちゃん」
「……はい」
「ちょっと確認しておきたいんだけど」
「……どうぞ」
「さっき先生ちゃん、今回標的の亜獣について、こんな事いってなかったかしらん。一メートル以下の河馬だか犀だかって」
「……言いましたね」
深く、一度大きく溜息を挟んでから、
「どうみても! どう少なく見積もっても! 五メートルは超えてんですけどっ!」
「ノクトワイ様声っ! 声大きいですわっ! 見つかりますから!」
「そりゃ大きくもなるわ。犀ってか象でしょあれ」
「で、ですわね……」
ようやく現実を見つめる気になったのか、イェアはうーんと唸りながら遮蔽物としていた岩の影からひょこんと顔を出し、
「た、確かに外見はオーメルスゾーンなんですよね。でも、サイズが一回りどころか、五回りくらい違う。先遣隊の人達は極力亜獣とは距離を置いての調査に徹してたから、大きさについては大雑把にしか把握してなかった。あと、わたくし自身が亜獣の外見の特徴だけを聞いて、大きさの方を確かめてなかったのが原因……なのでしょうね」
ごめんなさい、とこちらに小さく謝るイェア。
とはいえ、【NAME】からすると謝られたところでどうなるものでもない。取り敢えずはイェアには早く気を取り直してもらって、ここからどうするのかを決めて貰わねばならない。
【NAME】がその事を遠回しに伝えると、
「う、あ、そ、そうですわね。ええっと……」
イェアはあたふたと視線を彷徨わせた後、大きく一度深呼吸を置く。
「うん。推測でしかありませんが、恐らくこの亜獣はオーメルスゾーンの亜種なのだと思われます。大きさは異なりますが、それ以外の情報はほぼ一致していますので。なら、卵についても同様に、文献通り美味である事が期待出来ます」
「って事は、予定通りに進めるってワケね」
「はい。ただ、オーメルスゾーン自体がここまで巨大であると、卵を強奪するにも一筋縄ではいきません。オーメルスゾーンの性質は基本至極臆病ですが、子がかかわると途端に勇猛になる。少し語弊がある言い方かもしれませんけれど、子煩悩なんですの。また、特性として猪のようにとにかく突進して敵を退けようとする癖があるのですが……」
「あんなデカいのに全力で突進されたら洒落にならないわよ」
ノクトワイの言葉に、【NAME】も全くだと頷く。前回の鯨狩りでは、オーメルスゾーンとは比べものにならない程の巨体による突進を受けた身だが、あれは一度きり、しかも十分に対応する時間があっての事だ。陸上生物による突進の場合は話が随分と違ってくる。
「はい。ですので、不意打ちといいますか兎に角驚かせるなりで相手を混乱させて、対抗するよりも逃げる選択肢を取って貰うようにするのが良いんじゃないか、と」
「出来るなら、そりゃそっちの方がいいんでしょうけれど、大丈夫なの?」
「……多分。術式で徹底的に目くらまし、その上で精神干渉を仕掛けて、更に【NAME】さん達に襲撃してもらう。これだけ重ねれば、多分逃げ出してくれるとは思うのですけれども」
どうでしょうか。そんな風に伺いの視線を向けてくるイェアに、【NAME】は一瞬ノクトワイと顔を見合わせてから、頷く。手としては、そう間違っているとは思えない。ノクトワイの方も同様に考えていたらしく、異論は出てこなかった。
そんな二人の反応に安堵したのか、イェアは少し表情を緩めて微笑み、
「よし。なら、早速始めましょう。十秒後に精神干渉、そこから更に五秒後に炎系の幻覚と、大気干渉による破裂音を作ります。そこに合わせて突撃を掛けてくださいな。かなり大きな音が出ますんで心構えの方、お願い致します」
告げて、イェアは両の腕の機甲兵器“マッシモ鉄腕くん”を展開させ、直ぐさま術式の構築を始める。両腕の印章石が輝きを放つのを見届けてから、【NAME】は武器を引き抜き、岩陰から飛び出す準備を始める。
そうしている間に、まず一つ目の術式が駆動。枯れ草で組まれた巣の中で身を屈めていた巨大な獣が、有りもしない何かを求め探すように首を左右に振り、立ち上がる。何処か朦朧としているのは、イェアの精神干渉が上手く影響を及ぼしている結果だろう。
そこへ二つ目の術式が駆動。突然、巣全体が炎に包まれて、続けて鼓膜を貫くような甲高い、しかしびりびりと肌や腹に響いてくる破裂音が立て続けに鳴り響く。
二重の出来事に、亜獣は悲鳴にも似た鳴き声をあげて、上体を反らして両の前足を高く空ぶらせた。素人目に見ても判る。亜獣は完全に混乱していた。イェアの策がものの見事に嵌まった形だ。
「行くわよ」
鋭く短い声に、【NAME】は我に返る。そうだった、混乱させて終わりではない。ここから詰めに入るのが自分達の仕事だった。
【NAME】は武器を構えながら、一気にオーメルスゾーンとの距離を詰めていく。ここで重要なのは、決して正面から仕掛けないこと。自分の存在を顕示すること。そして逃げ道を示してやることだ。難しい仕事ではない。油断さえしなければ、事は簡単に成功するだろう。
術式によって鳴り響く破裂音に負けぬように強い雄叫びを上げながら、【NAME】とノクトワイは慌てふためく亜獣目掛け、その逃亡を促すための攻撃を開始する。
battle
命守る大獣

事前の予想通り、オーメルスゾーンを追い払うことにはあっさりと成功した。
精神干渉による混乱の助長をした上で、視覚と聴覚に対する刺激を与え、更に人間による襲撃だ。幾ら巣を守っていた亜獣と言えど、ここまでお膳立てをされては逃げ出してしまうのも責められないだろう。
「で、後は卵を回収して終了だわねん」
「ええ。さっきのオーメルスゾーンが戻ってくる前に、さっさとお暇してしまいましょう」
イェアの促しに頷いて、【NAME】達はオーメルスゾーンの巣に改めて足を踏み入れる。
巣の大きさは凡そ五メートル超。先程のオーメルスゾーンが身を屈めてはまり込めば丁度良いサイズだ。そしてその巣の中央には、オーメルスゾーンの卵が四つほど、密集するように転がっていた。これで卵が無かったら肩透かしも良い所であったが、どうやら運が味方をしてくれたらしい。恐らくは、先程のオーメルスゾーンはこの卵の産みの親であったのだろう。
あとは、これを持ち帰れば良いだけ、なのだが。
「…………」
眼前の卵を見下ろし、【NAME】達は暫し無言で固まる。
卵に対し、三人の心に過ぎる印象はただ一つ。それを口に出したのはノクトワイだった。
「なんつーか、その」
「ええ。言いたいことは判りますわ」
「それでも言うけどさ。うん、その――卵、でかくない?」
「…………」
でかい。
直径にして一メートルはないものの、50センチ以上は確実にある。しかも、試しに持ってみると異様に重いのだ。
「そりゃそうですわよねぇ……。成獣があんな大きさなんですから、卵もそりゃ大きくなってますわよねぇ……」
「卵の大きさと成体の大きさはあんまり繋がりない場合もあるけど、これに関しちゃ関係あったんでしょうね。先生ちゃんが知ってるオーメルスゾーンだと、卵の大きさどんくらいだったの?」
「駝鳥程度だったと思うんですけれど。今回、ダブル“マッシモ鉄腕くん”つけてきたのも、卵の持ち運びの為ではあったんですが……」
言って、イェアは腕の側面に付けていた籠を取り出す。蓋が開かれた籠の中は衝撃吸収用の素材が敷き詰められていて、彼女が想定していた、せいぜい全長10センチほど、掌程度の大きさの卵であれば、その籠の中に卵は上手く納まったのだろう。だが、残念ながら目の前にある超巨大卵が相手となると、籠の中に一つ入れる事すら残念ながら不可能。
「で、どーすんのよ先生ちゃん」
「どうって……。抱えて持っていく以外に方法はありませんわよ」
(抱える、と言われてもなぁ)
イェアの言葉に、【NAME】は困ったように頭を掻く。いくら大きいとはいえ、抱えることすら不可能という程の代物ではない。イェアの言う通り、抱えて持ち帰る事は可能であるのは確かだろう。
しかし、この大きさの卵を抱えた場合、両腕、ないし片腕は確実に塞がれることになる。それは、亜獣達の楽園であるエルツァン島においては危険極まる行為だ。亜獣達に襲われた場合、迎撃の反応は確実に遅れるし、下手をすれば卵が割れてしまう場合もあるだろう。触ってみたところ、卵の殻はかなりの強度を持つように思えたが、しかし抱えた状態から地面に投げ捨てても大丈夫かと言われると自信が持てない。その程度の強度である。
「諦める、っていう方針は?」
「ありませんわ。ここまで来て手ぶらで帰っては、何の為にきたのか判りませんもの」
「ならどうするのん? あんまり迷ってる時間はないわよ」
ノクトワイの言葉に【NAME】も頷く。先刻巣を守っていた亜獣は混乱させて追っ払っただけなのだ。落ち着けば直ぐにここへ戻ってくるだろう。その時、己の巣を荒らしている自分達を目撃すれば、一体どういう行動を取るかは火を見るより明らかである。どうするにせよ、早急にここから離れねばならないのは確実なのだ。
イェアはほんの僅かな黙考の間を置いて、閉じていた目を開く。
「卵は全てもっていきましょう。ノクトワイ様と【NAME】さんはそれぞれ一つを、わたくしは二つを運びますわ」
「……よ、欲張りねぇ」
「念のため、ですわよ。で、最低でも一つは持ち帰る事を優先。途中で亜獣と遭遇した場合は、【NAME】さんかノクトワイ様、もしくはその両方が、卵を破棄して迎撃してくださいな」
つまり、イェアが抱える二つを優先して行動する、という事か。
「はい。わたくしはこの」
イェアの両腕に備わった鋼の腕が、彼女の操作に従って繊細に稼働する。
「“マッシモ鉄腕くん”でそれぞれ一つずつ、卵を確保します。鉄腕くんは強力な荷重制御の術式を仕込んでありますから、この程度の重量物でしたら然程わたくしの運動性に影響を与えず持ち運ぶことが出来ます。ですので、運搬役のメインはわたくしで、お二人はその護衛をお願いします」
「作戦としては妥当なトコね。じゃ、その方針で行きましょ」
了解、と頷き、【NAME】は適当な卵の一つに手を回し、ぐっと力を込めて持ち上げる。
……重い。
「これは、きついわねん」
同様に卵を抱えたノクトワイが、【NAME】と同じ感想を漏らす。正直言って、これを抱えて走るのはきつい。腕の自由が無くなるという事を考慮にいれれば、ろくな速度が出せないだろう。
対し、イェアは二つの卵をひょいひょいと気軽い調子で脇に収めてみせる。そのまま歩く速度も普段通りだ。鋼のアームに仕込まれた荷重制御の術式とやらはかなり上等な代物であるらしい。
イェアは【NAME】とノクトワイの方へと振り返ると、一瞬の間を置いて、
「では、作戦開始、ですわ」
告げる。
その言葉に頷いて、【NAME】達は元来た道を急ぎ戻り始めた。
――先生、卵を盗んで走り出す――
最初は順調だった。
何せ、オーメルスゾーンの巣までやってきた道を遡っているだけなのだ。途中に遭遇した亜獣は既に全て掃討している。ならば帰りの道で亜獣に遭遇する可能性が低いというのも道理だろう。【NAME】達は巨大な卵を抱えたまま、一切亜獣達と遭遇すること無く谷道を抜け、無空峡谷の本道とも言えるアーチ状の谷の底へと出る事に成功した。
「案外、このまま何事も無く陣地まで戻れたりするかもしれないわねん」
等と軽口を叩くノクトワイに、同意の頷きをしようとした矢先。
無空峡谷の底に、鈍く、しかしはっきりと。
複数の大獣達が立てる、重量感溢れる足音が響き始めたのだ。
「……これ、は」
ロームフーネは天井が半ば閉じられた、円蓋に近い構造を持つ峡谷だ。故に響く音は木霊し、反響し、増幅される。足音はその数を特定できぬ程に連なって、【NAME】達の耳を打つ。
その数は判らない。だが、足音がどちらから来るかは何となく察せられた。
北側だ。【NAME】達が目指す、軍の野営陣がある方角は南である。それ故、進行方向からではない、のだが。
「すんごい嫌な予感がするわね……。ちょい、先生ちゃん。これどう思う?」
口元を引きつらせて笑うノクトワイから話を振られたイェアは、強張った顔をじっと、谷の北側に向けて、
「【NAME】さん、ノクトワイ様」
「なによん」
ノクトワイは軽く返事をし、【NAME】は視線をイェアに向ける。
「申し訳ありませんけれど、お二人が持っている卵は諦めて貰う事になりそうです」
「いや、別にアタシはこれ欲しかった訳でも無いし、先生ちゃんがそういうなら別にそれでいいけどねん」
気軽に告げて、ノクトワイは抱えていた卵をぽいと放り出す。オーメルスゾーンの卵の殻は想像以上の堅さを見せて、地面に落下した後も割れずにそのままころころと暫し地面を転がった。その様子を確認しても不安は拭えず、【NAME】は少し迷った後、そっと地面に卵を下ろす。
イェアが、自分とノクトワイに卵を諦めろと言った理由は何となく判る。つまりは最初に決めた作戦をより確実に果たすための前準備だ。
そうしている間にも、地響きのような足音は音量を増し、その音の持ち主がどんどんとこちらに近付いてきているのが判る。峡谷の北側に視線を移せば、土煙と共に、多数の巨大な影が、恐ろしいまでの勢いでこちらに走ってくる様子が微かに見えた。
三人、それを暫し眺めて、
「取り敢えず」
「うん、取り敢えずね、ねん」
「ええ、取り敢えず、ですわね」
三人、そう言葉を続けて、
「「逃げましょう」」
一言。
告げて、同時に峡谷の南側、西エルツァン海岸へと続く峡谷の出口を目指して、全力で走り出す。
今までのような加減をした走りではない、文字通りの全力疾走である。
先頭はノクトワイ。普段は飄々とした身のこなしが基本の彼だが、いざ本気となればしっかりと根の張った力強い姿勢となる。安定したストライドで、後に続く者達に対して走りやすい道を示してくれる。
続くイェアは、明らかに走り慣れてない様子の、なよなよとした芯の無い走り方であるが、その速度自体は大重量の卵二つ抱え、金属製の巨大な擬腕を両腕に取り付けているにも拘わらずノクトワイとほぼ同等である。機甲兵器である擬腕を使い、身体強化や荷重、大気制御の術式によって補助をしているのだろう。 そんな二人の後を、置いて行かれぬように懸命に追いかけながら、【NAME】は一瞬背後を振り返る。後方から迫ってくる地響き、連なる足音。その正体は既に判っている。視線の先には、全長五メートルを超える巨大な亜獣の群れが、一直線にこちら目掛けて走ってくるのが見えた。その先頭に立つのは、先刻【NAME】達が追い払ったあの個体である。思い出すのは、イェアによるオーメルスゾーンの解説だ。曰く、子がかかわると物凄く勇猛になる、子煩悩な性質だ、と。
つまりは、こういう事だ。
【NAME】達により巣から追い払われたオーメルスゾーンは、峡谷に生息する仲間達に助けを求め、自分を襲い、巣を荒らし、そして今卵を持ち去ろうとする【NAME】達への逆襲に戻ってきたのだと。
当たり前の事ではあるが、四足獣の全力疾走に対し人間が速度で勝ることはまずない。特に相手が亜獣であれば尚の事である。逃げる【NAME】達と、後方より迫るオーメルスゾーンとの差は見る間に縮んでいく。
「これは、ちょっと、逃げ切れない、気がするわねん」
「卵を、二つ、残してみた、んですけれど、完全に、無反応みたい、です、わね」
確かに、【NAME】とノクトワイが持っていた卵を置いた場所を、既にオーメルスゾーン達は通り過ぎているように見えるが、その勢いが弱まった様子は微塵も無い。
「やっぱり、先生ちゃんが、二つもってるのが、ダメなのかしらん」
「それか、卵の事は、もうどうでもよくなっていて、わたくし達に、兎に角逆襲をしたいと、それだけになっている、とかですか」
「調べるために、先生ちゃんだけ、別方向に、分かれて逃げるってのは、どうかしらん?」
「いえいえ、わたくし達の、目的を達成するには、卵を持っていない、ノクトワイ様が、ここで立ち止まって、オーメルスゾーン達を、食い止めてくださるのが、もっとも最適な、方針かと」
「うふ、うふふ」
「くす、くすす」
などと前行く二人が不気味に笑い合う間にも、オーメルスゾーンはどんどんと距離を詰め、既にその姿形がはっきりと見える位置にまで近付いてきていた。
限界が近い。戯れの会話を続けているイェアとノクトワイに、そろそろ手を打つべきだと告げると、不気味に笑いながら睨み合っていた二人はころりと態度を変える。
「【NAME】さん、ノクトワイ様。お二人ならば、どの程度持たせることが、可能ですか?」
「立ち止まって、迎撃したなら、一瞬で伸されるわね。但し、逃げながらの牽制なら、上手くやれば、それなりに削り取れるんじゃ、ないかしらん。【NAME】は、どう思う?」
全力で走りながらの途切れ途切れの会話は、内容を頭に染み込ませるのも少し苦労する。問われた内容を理解し、内心で検討し、答えを出す。
【NAME】が出した答えは、回避重視で立ち回るならば、怒れるオーメルスゾーン達を上手く翻弄し、その足を緩めるくらいは可能だろうと。稼げる時間は――大凡30秒。
その答えに、イェアは暫し無反応。後方の足音が更に高まり、こちらの姿を視界に捉えたオーメルスゾーン達が更に速度を上げた気配を感じる。何らかのアクションを取るならば、ここが限界点。そんなタイミングで、イェアがようやく口を開く。
「でしたら今から30秒、オーメルスゾーン達をその場で足止めしてください。その間に、わたくしは対策を行いますわ」
告げて、イェアが唐突に立ち止まった。両の擬碗で地面を突くような姿勢で砂埃を上げて急停止するイェア。
「ちょ――先生ちゃんっ!? ああんったくもーっ、もうちょっと先に言いなさいってば!」
駆け抜けかけていたノクトワイは慌てて身体を傾けて、そのまま勢いを横へと逸らす。走る勢い自体は殺さずに向きをぐるりと回転させて、崖の壁を蹴り、反転を終えて着地。そのまま走り、停止したイェアの横をすれ違って、突進してくるオーメルスゾーンの集団に、真っ正面から突っ込んでいく。
【NAME】も即座に反応した。イェアが停止を始めたのを見た瞬間、傍に立っていた岩目掛けて飛び上がり、側面から両の足で岩を踏みつける事で走る勢いを相殺。溜め込んだ力を発条のように解放して岩を蹴り、今度は逆方向、ノクトワイと同じくオーメルスゾーン達を正面から抗する形で走り出す。
「ったく、【NAME】! 無茶はしないようにね!」
それはこちらの台詞である。
ノクトワイの言葉に内心でそう返しつつ、【NAME】は自分目掛けて全力で突進してくる亜獣の弾丸、その弾道を一瞬で見切り、紙一重で回避しつつも確実に攻撃を加え、後方に居るイェアへと突進が向かわないようにする。そんな位置とタイミングを計り、即座に実行に移していく。
一回避、一攻撃。取る度に、続く行動の枠は制限されていく。オーメルスゾーンの群れの数は両手の指では数え切れない程だ。止まる気配のない突進の連続。回避し、すれ違いざまに攻撃し、次の突撃を回避し、すれ違いざまに攻撃する。その連鎖の限界は推測で八回。それ以上は半ば運頼みとなるだろう。そしてイェアが告げた30秒を満たすには、その運頼みの域に到達してなお、暫くは持たせる必要がある。
(できるのか……?)
一瞬の迷い。だが、それに引き摺られ、躊躇う余裕など既に無い。
30秒。それだけを稼げと言われ、自分はそれに是の行動を返したのだ。それを今更迷うなど、愚かしいにも程がある。
そんな思考を瞬間で振り捨てて、【NAME】は眼前の脅威に集中する。
――やってみせる。
その意思だけを胸に、【NAME】は手にした武器に力を込めた。
30秒という時間がいつ経過していたのか。それを認識出来たのは、可能な限りのオーメルスゾーンを地面に転がした後。完全な手詰まりの状態となって、今正にオーメルスゾーンの突進を身に受ける間際となったタイミングだった。
最初に走ったのは、上空目掛けて駆ける強烈な閃光。
続いて起きたのは、岩が砕け散り破壊される轟音。
そうして導かれた結果は、ロームフーネの峡谷を覆う天蓋の崩落だった。
上方から落下してくる大量の岩は、その真下に居たオーメルスゾーンと、そして【NAME】達に降りかかる。【NAME】に襲いかかろうとしていたオーメルスゾーンが、首筋に直撃した大岩と共に頽れ、更に落下してきた岩に押しつぶされていく。他のオーメルスゾーン達も次々と同様の運命を辿っていった。
しかし、助かった、と思える状況では断じてない。続けて降り注ぐ大岩は、ご丁寧に【NAME】を避けてくれる訳では無いのだ。
自分目掛けて落ちてくる数メートルはあろうかという尖った岩をぎりぎりで回避した先には、細かい石の礫の雨だ。細かいとは言え、一つ一つは拳大ほどもある鋭角の欠片だ。鋼鉄製の鎧を着込んでいたとしても相応のダメージは免れない。その上、礫の雨の向こう側に、天井のアーチを作っていた巨大岩の一部が崩れず丸ごと落下してくるのが見えた。サイズは目測でも十メートルは超える。物理的に人が耐えられるような質量ではない。これは駄目かと、【NAME】は半ば覚悟を決める。
が、そこに別の救いが来た。
「【NAME】さん、これを!」
叫ぶ声は後方。そちらへ振り返った【NAME】は、彼女――焼け焦げたような鉄の両腕を分離したイェアが、急いで投げて寄越してきた何かを反射的に掴む。
『“それは何物も拒む境。絶対領域《フォースフィールド》”』
瞬間、響いた文言は手の中の石からだ。印章が刻み込まれた石は、砕け散ると同時に強烈な光を放ち、空間に己が身に刻まれていたのと同じ印章を映す。
それは、術式が封じ込められた印章石だ。動力として用いる印章石ではなく、石自体に術式を刻み仕込む類の特別な印章石。これにより使い手は術式に対する自身の力量、理粒子干渉能力に左右されずに刻まれた術を行使する事が可能となる。だが、そもそも印章石として機能しうる石材が貴重な上、石単体で術の駆動が出来るようにする場合は、印章石の特性を刻み込んだ術専用とし、尚且つ一度きりの使い捨てにしなければならない。更には発動する術自体も不安定になる場合が多く、効果や時間が一般の術者が操る術式より劣る場合が殆どだ。石はあくまで動力としてのみ使い、術式構築は外部装置に任せたり、同調誘導器の補助要素として組み込んだ方が、費用対効果は遙かに優れていると言えるだろう。
だが、今、この場面のように。緊急時の備えとして使うならば、極めて有用な品である。
駆動したのは、西大陸の召喚士《サモナー》達が主に使う、領域結界術の一つだ。召喚獣を捕獲し、格納し、喚び出す。その為に研鑽された領域操作の術から派生して生まれた界絶の術式は、結界守護者《セイクリッドテリア》などが扱う正統な領域結界術系統と比べ、非常に尖った性能を持つ。
効果時間は極めて短く、熟練の術者でも十秒と維持できない。しかし、その防御性能は絶対だ。世界を切り取り断絶する。相の操作の域に至るその術は、結界の内と外を隔てる事によって他者への、そして他者からの接触を完全に遮断する。破るには正に世界構造にすら手を届かせる程の強力な概念的力が必要だ。単なる物理的な衝撃――例えば巨大な岩石の直撃など、その結界はものともしない。
もっとも、その効果時間は限定的だ。落下してきた石礫、そして巨大岩の落下による衝撃を耐えたとしても、巨大岩にのしかかられたままでは、結界が消滅した時点で終了である。【NAME】は自分の現在の状況を確認し、困ったように頭を掻く。このままでは、寿命がたった数秒伸びただけである。
――なに、これ。
だが、そんな些細な結界にすら反応して、小さな鈴音が胸元から響く。微かながらもはっきりとした、否という意思が、所持者たる【NAME】に伝わってきた。
閉塞を疎い、静止を拒む。境を切り裂き、封じを穿つ。流転を根源とする神形器の、ごくごく僅かな、半ば微睡みの中に沈んだままの覚醒。
しかしそれでも、この窮地を脱するには十分だ。
――かこわないで、わずらわしい。
りん、と一つ、音が鳴る。瞬間、胸元の飾りが小さな刃へと変化した。
生まれた刃は、ほんの少しだけその身を傾ける。その極小の動きのみで、流転の神形器は【NAME】を包む絶対領域を一瞬で無効化。そしてまた直ぐに元の姿へと戻ろうとする。
だが、それだけで戻られては困る。
【NAME】は胸元にぶら下がる刃を即座に手に取り、素早く上へと振った。振りかぶる間も惜しく、腕を上げ、手首を捻る。振り終える頃には、既に刃は小さな飾りの姿へと変化していたが、しかし払った動きに沿って宙を走ったほんの僅かな黄金の輝きは、【NAME】を押しつぶそうとした巨大岩を、粉々にまで爆砕させた。巨大岩は渦巻く粉粒の靄となり、無害な塵となって周囲に広がっていく。
「……は」
――助かった。
天蓋の崩落が収まり、地鳴りのような音が引いていく。【NAME】は腕を掲げた姿勢のまま、深く安堵の吐息をついた。
・
ノクトワイと二人。仕事を終えて元の場所へと戻ると、イェアはまだ地面に座り込んで作業を続けていた。
「……あ、おかえりなさい。どうでした? 大丈夫でした?」
こちらの存在に気づいて振り返るイェアに、【NAME】とノクトワイは手にした二つの卵を見せる。
「無事よん。ほぅら二つともー」
確かにノクトワイの言う通り、その手にある巨大な卵は傷一つ無い。オーメルスゾーン達の全滅に成功した【NAME】達は、逃げる際に手放した卵の回収に向かっていたのだ。オーメルスゾーン達は故意か偶然か、手放された二つの卵を踏みつけること無く通り過ぎていたらしい。
「良かった。でしたら、その二つは【NAME】さんとノクトワイ様の分としてお納めくださいな。それが今回のお仕事の報酬、という事で。わたくしが使う分はこの二つで恐らく足りると思いますし」
言って、イェアは傍に置かれた二つの卵に視線を向ける。【NAME】とノクトワイの活躍故か彼女が持っていた卵も全くの無傷だった。
「……いや、こんなでかい卵貰っても処分に困るんだけど……。ってか、二つじゃ足りないでしょ? またどうせこの後……」
「ノクトワイ様ーっ!」
慌ててばたばたと手を振るイェア。ノクトワイは「あー、はいはいごめんねごめんね」とあやすように手を振り苦笑いを浮かべるが、一体何の話なのか、隣で聞いていた【NAME】は首を捻るしかない。
取り敢えず、この卵は自分のものとして取り扱ってもいいのだろうかと問うと、
「ええ。煮るなり焼くなり、好きになさってくださいな。何にせよ、無事で良かったですわ。正直もー駄目かと思いましたもの」
実感を込めた言葉に、【NAME】とノクトワイも頷く。
「いやまさか上からあんなもん降ってくるとはねぇ。先生ちゃん容赦なさすぎじゃないかしら」
「ちゃ、ちゃんと絶対領域をそちらに回したじゃないですか。わたくしとしてもかなり出費の激しい策だったんですから手加減してくださいな」
「あー、まぁねぇ。で? そっちの方はどうなの?」
ノクトワイの視線は、座り込んだイェアの前に置かれた二つの擬腕に向けられていた。
イェアが身につけていた機甲兵器“マッシモ鉄腕くん”。無空峡谷の天蓋を崩落させた一撃は、この両腕から放たれたものだった。内蔵した印章石から限界まで力を引き出し、複数の術式を同時駆動させて放った光の奔流は非常に強力であったが、しかし本来この機甲兵器が想定している使い方とは異なっていた事も重なって、過負荷による動作停止状態となってしまっていたのだ。イェアは先程からその修理を行っていたのだが、
「……片方は、完全に駄目ですわね。印章石が完全に砕けちゃってるのもありますけど、機械部分も部品が結構溶けちゃったり、弾けちゃったりで。これはもう骨組みの所から組み直さないと駄目かも」
「換えの部品とかある訳なのん?」
「そもそも、これ自体が予備のつもりでしたから。アノーレ……いえ、本国から部品取り寄せるか、いっそ戻るか。それくらいしないと無理ですわね。もう一機の方は――」
片方を手に取り、右の腕にはめ込む。今までより明らかに動きがぎこちないが、しかし内蔵された印章石は光を保ち、装甲板の可動や印章陣の空中展開もどうにか行われている。
「こんな感じで、普通に使う分にはなんとかなりそうですわ。陣に戻ってオーバーホールすれば、普通に使う分には問題ないでしょう。“マッシモ鉄腕くん”はわたくしの主兵装ですから、両方とも駄目になってたら厳しいところでした。これからまだ、ナリア・バータ霧眩森林の方に出向かないと駄目ですのに」
「……あー、そっか。まだ一箇所、採りに行かないと駄目な食材があったんだっけ」
心底げんなりとノクトワイが声を漏らす。
最初にイェアが話していた食材調達の為に赴く予定の場所は、確かに三箇所だった。一つは海、一つは谷。そして最後の一つが森だ。
「もうはっきりいってしんどいんですけど……。鯨のお肉と、この卵でも十分じゃないの?」
「だーめです! 最後のが色々誤魔化すために凄い重要なんですのよ!」
え、誤魔化すの?
「ごほん! 失言でした! お料理に彩りを添えるのに凄い重要なんですのよ!」
物はいいようだった。
白けた視線を向ける【NAME】に気づかないふりをしつつ、イェアは大袈裟な動きで動作不良となった“マッシモ鉄腕くん”と卵二つをどうにかこうにか抱え、
「という訳で、次はナリア・バータの探索です。陣地に戻って、休息と準備。わたくしの方も色々と整備や用意がありますので、ある程度はゆっくりしていただいて構いませんわ。その後、東エルツァン海岸線とナリア・バータ霧眩森林の境界にて合流としましょう。これで、よろしいですわね?」
「…………」
「お返事は?」
「……りょーかい」
ここまで手伝って投げ出すというのも収まりが悪い。
色々と諦めたノクトワイの返事に合わせて、【NAME】も小さく手を挙げることでその意を示す。
――取り敢えずは、相応の準備を整えた後。
ノクトワイと共に、今度は“ナリア・バータ霧眩森林”に向かうとしよう。
真なる楽園 先生、秘境の美果を求めて
――先生の手法・森編――
「──この森は、霧の森だ」
「どうしたの先生ちゃん、いきなりキメ声出して」
「いや、何となく。カール・シュミットの手記の書き出しが、そんな感じだったなーって思い出しまして」
「あー。アレ、前に最初の方だけ見せてもらったけど、文章はかなり酷かったわねん。全部そんなノリで書かれてんの?」
「前半はまだ余裕あるんでそんな調子なんですけども、後半は別の意味で凄いですわよ。悲惨というか、末期というか、そんな感じで。読んでみます?」
「……遠慮しときます。ってか、まぁ、そらそうよね。カール・シュミットってエルツァンの奥の奥まで入り込んじゃったんでしょ? 入口でこんな感じなのに、その奥となれば一体どうなってんだか、考えたくもないわ」
「それも仲間をどんどん失いながら、ですから。四つ目の地形あたりまではまだ正気を保っている風なのですけど、それ以降からは段々内容が断片的になっていって。最後に書かれている場所も、どうやら以前に訪れたどこかの地形に再度赴いているようなのですけど、妄想も色々交じっているみたいでもう何が何やら……」
背後で繰り広げられるそんな会話に耳を傾けながら、【NAME】は木々の間を埋める濃霧を掻くようにして進んでいく。
ナリア・バータ霧眩森林。
東エルツァン海岸線から直ぐ北へと進んだ場所に広がる大森林だ。【NAME】はイェアの食材調達の手伝いという形で、ノクトワイと共にこの森に足を踏み入れていた。
森は常に乳白色の色濃い霧で覆われており、侵入者達の歩みを妨げる。先頭を行く【NAME】の視界は数メートルも無い。用心深く前方を確かめながら、草木を払うようにして進んでいく。【NAME】からするともう方角も位置も判らなくなっている状態で、本当にこちらに進んでいいのか。それすらも理解できてはいないのだが、
「【NAME】さん、少し進路がずれてますわ。もう少し左手。ええと、20度ほど左の方向でお願いします」
と、背後からの指示は非常に細かい。【NAME】は言われた通りに足先を左へ20度――と思しき角度へと逸らし、歩みを再開する。
一瞬後ろを振り返る。三人の隊列は、先頭が【NAME】、後尾がノクトワイ。挟むようにイェアという形だ。当然、真後ろにはイェアが居るのだが。
「……? どうされました、【NAME】さん?」
不思議そうに首を傾げる白衣。服装は普段通りだ。右の腕に嵌まった“マッシモ鉄腕くん”も陣地での整備を終えて通常運転。前回左腕に装備していたものはやはり直せず倉庫の奥に放り込まれる形になったそうだが、もう一本は分解整備をするだけでどうにかなったらしい。
が、それ以外に前回と大きく異なる点が一つ。
それは、顔面を丸々覆っている巨大な布製の仮面である。仮面は紐を後頭部まで回してくくりつけるような構造となっており、呼吸器となる口と鼻に密着する部分には瘤のような袋がぶら下がり、目の部分には透明な硝子が二枚。表情はまったく窺えず、硝子越しに辛うじて目だけが見える程度だ。
装いとしては極めて不気味である。当初、待ち合わせの場所でこれを被ったイェアと出くわしたときは何事かと思ったものだが、彼女曰く、
「これは今回のナリア・バータ探索のために突貫で用意した第零十九番私設機甲具、名付けて“くんくんここ掘るくん”ですわ。これを使うことで、目標物の位置と、ナリア・バータの霧の状態、両方を感じ取れるようになるんですの」
との事。
因みにこの時、両手を前にあげつつくいくいと動かしたイェアの仕草は犬っぽくて中々にかわいらしいが、残念ながら顔面のマスクが色々な意味で台無しにしていた。
そんな事を思い出して、非常に残念な気持ちでイェアの顔を見ていると、こちらの内心を察したのか硝子越しのイェアの瞳が半眼となり、
「【NAME】さん。変な事考えている暇があったらさっさと進んでくださいな。ナリア・バータの霧は、どうも静止していると意思ある者の想念を感じ取りやすくなるみたいですから。常に動いている場合と止まっている場合では、その発生率に大きな差が……あー」
と、お小言じみた言葉を続けようとしていたイェアが、気の抜けた声を出して視線を【NAME】から横へとずらす。
何事かとその視線の先を追った【NAME】は、乳白色の霧が所々でより濃く留まり、塊のようなものを形成し始めていた。それは、カール・シュミットの手記や、ナリア・バータでの先遣調査を行っていた兵士達からの報告にもあった現象だ。
簡単に言えば、霧が亜獣を造り出す前兆。
「……仕方ありませんわね。【NAME】さん、戦闘準備を。ノクトワイ様は後方警戒を宜しくお願いします。どうも、一度発生し始めると前後左右からどんどんと次が湧いてくるようですので」
「りょーかい。さっさと前を掃除して脱出しちゃいましょ」
「とはいえ、この霧の中を駆け抜けるというのも危険極まりないんですけどね……」
まったくだと同意しつつ、【NAME】は己が武器を構える。その隣には、右に取り付けた機械の腕を展開させながら、左の手にて宙に印章を描き始めたイェアが立つ。
そうしている間にも、前方に浮かんだ霧の塊は更に変化。多彩な亜獣――それも軒並み狂暴そうな形状をもつそれらへと姿を変えた。
「侵入者の深層意識から脅威を読み取り形とする、という話でしたけど……」
隣に立つイェアが少しばかり首を傾げる。
「わたくしたち、あの程度の相手なら容易く退けられる自信、ありますわよね?」
確かに、とは思う。あれ以上の存在と対峙した事は幾度もあった。脅威を読み取るというのであれば、もう少し危険な相手が――それこそあの、黒い切り株の向こうや芯形の遺跡で死闘を繰り広げた鬼達が形となって現れてもおかしくはないと思うのだが。
「ちょっとー! んなこたどーでもいいからさっさとやっちゃってよ! 後ろからも霧が溜まってきてるわよっ!」
二人、疑問に動きを止めていたところに、背後からの急かす声。
「う。と、取り敢えずさっさと片しちゃいましょう。考えるのはその後ですわ」
告げて、イェアの右腕が駆動音をあげながら前方へと向けられる。展開した鋼の指先が空中に複数の印章を刻み、内蔵された印章石がそこに力を流し込む。放たれた術式は雷撃の嵐だ。走る無数の稲光が霧の獣を貫き、その姿を霧散させる。
その様子を横目に見ながら、【NAME】も構えた武器に力を込めて前へと踏み出す。
この程度の相手ならば、余程油断しない限り負ける事は無い筈だ。手早く打ち倒すとしよう。
「振り切れた、というところですかしら」
鋼の腕の装甲を展開させ、中に溜まっていた熱を外へと逃がしながら、イェアはもごもごとマスクの口元を動かす。
霧の化け物の戦闘能力はかなりのもので、姿の原形となった亜獣と比べても数段上の力を持っていた。しかし、【NAME】とイェア、そしてノクトワイの手に掛かれば下す事自体は容易かった。
問題は、その霧の化け物は身体を破壊されても直ぐに霧の塊へと戻り、また亜獣の姿を取り戻そうとする事だった。
暫くの戦闘の後、完全に撃退することは不可能と判断した【NAME】達は、適当な亜獣を破壊して突破口を開くと、その場からの離脱を選択。この方針転換は功を奏し、多少の追跡は受けたものの比較的簡単に離脱する事に成功した。
額に手を当てて後方を眺めていたノクトワイは、にやりと笑みを浮かべて振り返り、
「大体、やり方も判ってきたわねん」
「ええ。とにかく同じ場所には留まらない。霧の塊が生じ、そこから亜獣が生まれた場合は適当に相手をしながらさっさとその場から離脱を図る」
「逃げるが勝ちってトコかしら。霧の化け物を退治するのが仕事ってんなら別だけど、今のアタシ達は別件だしね。ただ、問題はあるけどね」
かりかりと頭を掻くノクトワイ。彼が何を問題視しているのかは簡単に判る。霧のせいで視界が悪く、逃げ辛いのだ。特にここは深い森の中。ただでも足場が悪く、更には霧で覆われているときた。全速力で駆けるのは難しく、もし他の者達と逸れてしまえば合流も難しい。そもそもこうして霧眩森林を問題無く歩けているのも、イェアが持ってきた機甲具の力が大きい。もし彼女と逸れてしまえば遭難は免れないだろう。
「で、こっからどっち行きゃいい訳?」
ノクトワイの問いに、懐から取り出した円盤――第六番私設機甲具“くるくる座標くん”を見て、そして鼻を鳴らすような仕草と共にマスクの瘤を揺らしたイェアは、
「恐らくはこちら、ですかしら」
言って、ひょいと一方を指差す。
そちらに視線を向けてみるが、ただただ他の場所と同様、その先には草木と濃い霧があるだけだ。獣道すらない。進むには、正に分け入るつもりで行かねばならないだろう。
【NAME】とノクトワイは暫しそちらを眺めて無言の後、
「……にしても、本当にソレ、信用しても大丈夫なのかしらん?」
ノクトワイの言葉に頷きながらイェアを見るが、彼女はマスクの顔をゆらゆらと左右に揺らしながら、
「大丈夫大丈夫。余裕ですわよ余裕。どーんと大船に乗った気でいてくださいな! 段々、この森の霧についても判ってきましたし!」
「そう言われると逆に心配になるわっ!」
マジで大丈夫なのかな?
【NAME】とノクトワイは不安一杯でイェアを見るが、ここで立ち止まっていても仕方無いのは確かだ。またいつ霧の塊が生じるとも限らない。兎にも角にも移動は始めた方がいいだろう。
【NAME】は武器で遮る枝葉を払いながら、イェアが指し示した方向へと移動を開始する。
――先生、秘境の美果を求めて――
細かいイェアからの指示に従い、時には右へ、時には左へ。進行方向を変えながら、【NAME】達は霧の森を進んでいく。
「……なんか段々、霧が更に濃くなってきた気がするわねぇ」
そんなノクトワイの呟きは、【NAME】も薄々感じていた事だった。
元々濃かったナリア・バータ特有の霧は、暫く前から更にその濃度を増し、今はもう数歩前すら見通すのも難しい状況だ。
「気がする、ではなくて実際に濃くなってますわよ。今、周期的にはこの辺りは森の中で一、二を争うほどに霧が濃い状態になってますもの」
「……周期? え、そんなもんまでもう判ってんの?」
「一応、先刻から直に観測情報を蓄積してますからね。その為の機甲具もそれなりに持ってきてますし。なぜそうなっているのかという原因までは判りませんけれど、多少の法則性程度は」
「なら、なんでアタシ達、そんな霧が超濃くなってるところをわざわざ通り抜けてんのかしら」
「さっきまでの予想だと、ここは今一番霧が薄くなる場所だったんですけど、どうも少しズレてたみたいで……」
「霧について段々判ってきたって発言はどーなったのよん」
「め、面目ないです……」
イェアが何かを喋る度に、先程から背中に僅かに掛かる重量感。理由は、逸れないためにイェアがこちらの服を掴んでいるからである。振り返っても、最後尾にいる筈のノクトワイの姿すら朧にしか確認出来ない。それ程の濃い霧である。ここまで視界が悪化すると、霧の亜獣達が生じる兆候すらも視認できない程であり、それを警戒して極力急ぎ足で進もうとはしているのだが、それも度を増した視界不良により上手くは行かない。焦る気持ちは、場に居る皆に共通したものとなっていた。
兎に角、霧の獣の気配は見逃さないように。そして、地面の障害物に足を取られないよう。それを気をつけつつも、限界まで急ぐ。
そのような事に意識を取られていた【NAME】は、突然、周囲の木々が怪しげにざわめいた事に気づくのが遅れた。
「【NAME】、しゃがみなさいなっ!」
鋭い声に、殆ど反射的な動きで身体が反応する。身を伏せようとした、というよりも半ば腰砕けの状態で身体を下へと落とした【NAME】の真上。霧を切り裂く飛沫と共に、銀色の線が走る。撫でるような円線は霧を綺麗に割り、更には上方、傍の木枝より伸びてきた蔓を、その先端の刃のような突起諸共切り飛ばした。
「亜獣っ!?」
イェアの慌てた声に、【NAME】はその正体を悟った。注意深く周囲を見れば、例え濃い霧に囲まれていようとも判る。周囲の木々、その身に巻き付くように、狂暴な形状をした蔓草が這い回り、【NAME】達目掛けてその仮初めの頭を擡げていたのだ。
迂闊だった。霧という存在に完全に気を取られ、通常の亜獣が存在しうる可能性を完全に除外していた。
「こら、【NAME】、早く立ちなさい! 次が来るわよっ!」
蹴り飛ばすような声に、【NAME】は慌てて立ち上がる。まるで矢のように飛んできた蔓草の先端が、ぐさぐさと土に突き刺さる音に冷や汗が出る。ここまで視界が悪くなると、単なる蔓状の植物亜獣でも十分な脅威だ。【NAME】は素早く傍に居るイェア、ノクトワイの方へと身を寄せると、互いの死角を補うように背合わせの陣形を取った。
「どの程度の範囲に蔓が展開しているのかが判らないのが面倒ですわね」
「普段なら片っ端からぶった切っちゃうところだけど……」
そう呟くノクトワイに、【NAME】は否と伝える。
動かずにこの場に留まっている程、霧の化け物の発生率が高まる事を考えれば、取れる手段は殆ど無く、基本軸は一つしかない。
「取り敢えず、移動。後は前に進むか後ろに進むか、くらいよねん」
そしてどちらを選ぶべきかと言えば、前しかない。
【NAME】はイェアに目的地の方角を訊ねる。イェアは暫くの沈黙の後、
「……多分、あちらですわね」
と、霧に包まれた一方を指差す。目を凝らしてどうにかそちらを見通そうと努力してみるが、地面がどのようになっているかまではさっぱり判らない。
(出たとこ勝負、か)
【NAME】は諦めの吐息をつくと、続いて気合いを込めるために大きく息を吸い、そして止める。
力を溜める気配。それはイェアとノクトワイにも伝わった筈だ。だから【NAME】は何も告げず、全力で走り出す。
ひゅん、と風切りの音を立てて、蔓草がしなる音。【NAME】は視線すらくれず、迫る音に合わせるように武器を掲げて、弾き、そして走った。
視界が殆ど閉ざされている状態での全力疾走など、そうそう維持出来るものではない。
体感で精々百歩ほど。木の根を飛び越え、大岩を蹴り、地面に着地した【NAME】は、そこから更に踏み出そうとしたところで土の窪みに靴先を引っかける形で転倒した。ぐるりと視界が回転し、視界の半ばが草葉で埋もれる。まずい、まずい。内心そう連呼しながら、【NAME】はどうにか身を起こそうとする。転がったままでは、上方、樹木を伝って身を伸ばした蔓の亜獣からの攻撃の餌食である。衝撃で軋む身体の悲鳴を無視し、【NAME】はどうにか立ち上がるが、
「…………」
来ない。
武器を構え、来るであろう攻撃に備えていた【NAME】であったが、攻撃は一向に来ない。【NAME】は傍に聳える樹木達をじっくりと眺め、その身に蔓を巻き付けていない事に気づいて、は、と浅く息を吐く。どうやら、蔓の亜獣の縄張りから脱する事には成功していたらしい。
「【NAME】さーん! どこですかーっ! あとついでにノクトワイさまもー!?」
「ついでって先生ちゃん酷くないーっ!?」
と、反響するように叫ぶ声が【NAME】の耳に届く。全力で走る途中、イェアやノクトワイとも逸れる形となってしまっていたのだが、取り敢えずどちらも無事なようだ。
取り敢えず【NAME】も大声で返事してから、イェア達の姿を探そうとぐるりと視界を回し、木々の間、霧の向こうにちらちらと動く彼女達の服や髪の色を捉え、そこでようやく気づく。
霧が、薄れているのだと。
・
「つまり、予想位置がちょっとズレてたってこと?」
「そうなりますわね。なので、少し横に移動したらこんな感じだったって事で」
イェア、ノクトワイと合流した【NAME】は、彼等の話を聞きながら森の中を進む。
先刻までは一寸先は霧といった状況であったが、今はうっすらと掛かる程度で、霧というよりは靄に近い状態となっている。イェア曰く、ここからはもう目的地付近に近付くまで、霧はこのもっとも薄い状態を維持するという。
「どうもナリア・バータの霧は、実は一定の秩序を持ってまるで呼吸するように濃度を変化させているみたいなんですの。只、分布図を作ってみた感じだと幾つかの箇所では濃度が非常に濃い状態で維持されていて……推測ですけど、その辺りにこの森が霧に覆われている原因か、それに繋がるような存在があるのではないかと思われます」
「……てか、移動中によくそこまで分析出来るわね」
「まぁそこは“先生”の異名も伊達じゃない、という事で。元々はわたくし、こういう実地での土地概念の解析とか、自然分析の方が得意なんですのよ。ただ、姉の方が毎度毎度フィールドワークで外ばっかりだったから、かわりにわたくしが内にこもった作業ばっかり回されるようになっちゃったんですけれども」
「なんか先生ちゃん、こういっちゃ悪いけど、貧乏くじばっか引いてない?」
「それを、いわないで、くださいまし。ほんきで、へこんでくるんで」
硝子の向こうで若干涙目を浮かべて訴えるイェアに掛ける言葉も無く、【NAME】は焦りながら別の話題を振る。
そういえば、最初はこの三箇所目の食材探索だけは情報がかなり曖昧だった記憶があった。亜獣の目撃例があった訳でもなく、ただ彼女は気になる情報がある、といっていただけだ。
今回こうして、イェアの指示に従い森の奥へとずんずん分け入っている訳だが、では一体何を探しに来ているのか。その疑問は解決されていないままだった。
流石に、そろそろ何を探しに来ているのか、その説明くらいは欲しい所だ。そう【NAME】が言うと、イェアはマスクをもごもごと動かし、
「まだ、あるとは決まった訳では無いんですけれども、このマスクが、その“臭い”を感知してまして。だから、あると、そう推測して、わたくし達はその臭いを辿り、こうしてその根元に向かって移動していますの」
「……また言い回しがややこしいわねん。もうちょっと噛み砕いて」
【NAME】が思った事をノクトワイがストレートに指摘すると、イェアはうーんと腕を組み、
「要は、先遣としてここに入った兵士達の報告の中に、わたくしが欲しかった食材が持つ“臭い”を微かに嗅ぎ取ったという話を聞いたんですの。だから、その“臭い”の発生源をたぐっていけば、きっとその食材がある筈だと、そういう訳ですわね。このマスクは」
とんとんと自分の顔を覆う布を指で叩き、
「漂ってきたその“臭い”を些細であれ嗅ぎ取り、その出所を探り、そして防ぐために改良を施した機甲具ですわ」
成る程、と【NAME】は頷く。つまりイェアが先刻から移動方向を迷わず指し示す事が出来たのは、彼女がかぶったマスクが【NAME】達が感じ取れない“臭い”とやらを嗅ぎ当てているからだ、と。
「正解ですわ。臭いは段々強くなってきて、そろそろ【NAME】さん達にも判るくらいになってくると思います。目的の場所は、もう直ぐです。【NAME】さん達も覚悟をしておいてくださいな」
「はいはい、りょーかいよん。……ん?」
ん?
何となく、聞き捨てならない言葉がところどころにあったような気がするのだが。
【NAME】とノクトワイ、合わせるように首を傾げるが。
「ほら、急ぎますわよー!」
と、何時の間にか先を行く形となっていたイェアに急かされ、追求のタイミングを外された二人は、まぁいいかと口を閉ざしてその後を追った。
――その選択が間違いであった事を、【NAME】とノクトワイはこの後直ぐに身をもって体感する事になるのだが、それは正に後の祭りであった。
――先生、毒々狂花にご執心――
突然、濃密としか言いようのない香りが、【NAME】の鼻腔を貫いた。
鼻に忍び込んできたその感覚は、まるで流動物のようだ。鼻の奥からぬるりと、喉奥にまで入り込んだその臭いは、【NAME】が知覚出来る範疇を超えていた。言葉としては表現できない、暴力的で根源的な、ただただ一言、“臭い”としか表現できない何かが、【NAME】の思考を焼き尽くす。
視界が瞬く。舌が痺れる。肌が粟立つ。鼓膜が軋む。一つの刺激が五感を狂わせ、その想像を絶する感覚に、【NAME】は溜まらず意識を手放した。
「ききき、きましたわーっっ!!」
が、真横で放たれた大絶叫に、手放した筈の意識が戻った。
マスクの奥の瞳を歓喜に輝かせたイェアの隣では、鼻を押さえて身を折ったノクトワイが、目を白黒させながらうめき声を漏らしている。
「な、が、な、なに、この、ニオイ……!」
ノクトワイも、【NAME】と同様の“臭い”を体感しているらしい。彼は目からは涙、鼻からは鼻水をだらだらと零して普段の洒落た髭男ぶりが影も形も無いような様相となっていたが、恐らく自分も似たような状態になっている事は想像に難くなく、【NAME】はその事には言及せず、どうにかこうにか、隣でくねくねと未だ歓喜のポーズを取っているイェアに訊ねる。
一体この臭いは何なのか、と。
「勿論、これがわたくしが求めていた臭い――“黴爛果”ブラウパーザナップの臭いですわ!」
「黴爛果っ!? あの、伝説のアレ、かっ!」
知っているのかノクトワイ。
視線だけで彼に問うと、ノクトワイは鼻と口を手巾で覆いながら立ち上がり、
「アタシでも知ってる、有名な奴よ。西の方じゃ山の奥地とかで稀に発見される、現存してる数少ない亜獣の一種よ。有り得ない程に強烈な臭いで感覚を持つあらゆる生物を自分の周囲から取り除く植物系亜獣。鬼種すら道を譲るって言われる極めつけで、その臭いの一芸だけで“芯なる時代”から今まで生き残ってきたって言われる恐ろしい――ってうおーっ、口と鼻塞いでも目っ! 目からくるっ!」
目を覆ってじたばたと暴れはじめたノクトワイ。【NAME】も痺れるように痛む目をどうにか開け、どうにか身体を立て直す。足が子鹿のように震えている。まさか“臭い”だけでここまでのダメージを受けるとは。これまで幾多の逆境を潜り抜けてきた【NAME】であったが、このような状況は初めての経験だった。
そんな、正に死地の中にある心地で立ち上がった【NAME】は、
「大丈夫ですかー? お二人ともー?」
直ぐ傍で、身体をちょこんと傾けてこちらを覗き込むマスク面を見て、先刻、ここへやってくる前の彼女の発言が脳裏に蘇り、そして繋がる。
成る程。彼女の言う「覚悟を決めろ」とは、そして「防ぐ」とは、この臭いに対しての事であったのか、と。
謀ったな、と言わんばかりの刺すような視線を前に、イェアは若干たじろぐように身を泳がせて、
「いや、だって、マスクは一人分しかありませんでしたし、わたくしが被らないと機甲具として使うのは難しいですし……その……許してくださいましね!」
暫く迷った後、色々と吹っ切れたのか、くねっと身体を捻り、こーんと自分の頭を叩くポーズを取るイェア。
「…………」
これはもう一発ぶん殴っておくべきであろうか、とイェアが軍内で人望無いという話に心底納得した【NAME】であった。イェアが言う事自体はもっともである分、余計に怒りのぶつけどころがなく、溜まった憤懣がついついイェアに向いてしまう。
怒りの笑顔、のような表情を浮かべてイェアを見る【NAME】に、彼女はだらだらと首筋から冷や汗を流しながら、
「え、ええっと……あの、それで、ですね。取り敢えずこの“臭い”から脱するためには、ブラウパーザナップを討伐しないと駄目な訳なのですけれど」
「……ほっといて“臭い”の範囲に出ちゃいえば脱出できるわよねん」
と、答えたのはノクトワイである。ようやく目の痛みに慣れてきたらしい彼は、苦労して【NAME】達の傍へと移動し、
「ブラウパーザナップは確か、移動能力は殆ど持たない亜獣だもの。だからその“臭い”の範囲外に移動すれば、それで完全に無害よん。“臭い”から逃れるだけなら、討伐する必要なんてないわよね?」
「え? あ、えーっと、それはそう、なんですけれども。ほら、わたくし達、一応食材を取りにきた訳でして……」
「そうね。折角ここまで来た訳だし、そこを放棄するのもどうかなってアタシも思うわ」
「ですよね!」
「けどね、一人安全圏で指示してるだけの人に従う必要もないかなーっ、とも思うわけなんだけども。【NAME】もそう思わない?」
思う思う。
頷きながら、【NAME】はがしりとイェアの右肩を掴まえる。対し、ノクトワイは左の肩にその掌を乗せた。
イェアは戸惑ったように左右に首を振り、
「アレ? いや、アレ? えっと、どういうことでしょうか?」
「つまりね。もう無事にブラウパーザナップの居る場所まで到達できたのなら、その“臭い”を感知する機甲具を操作する必要も無い。操作をする必要が無いなら、そのマスクを脱いでも別に大きな問題は生じない。そうよね?」
そうです。
「そうじゃないですーっ! わたくしが“臭い”を直に嗅がないといけなくなっちゃうじゃないですのーっ!」
「そこはホラ」
上に立つ者として、諦めていただかないと。
「止め、ちょ、あーっ、ぬが、脱がさないでください! やだ、いやーっ!」
・
「さて、ここからが本番ね。【NAME】、準備はいいかしらん」
問い掛けに、【NAME】は隣に立つノクトワイに頷く。その顔の半分はイェアからぶんどったマスクを半分に裂いたもので覆われている。【NAME】の顔には残る半分が。当然隙間があり、口元に付けられていた瘤――中身は微弱な消臭効果を仕込んだ小さな印章石を大量に仕込んだものだった――の効果も非常に薄くなっており、“臭い”に対する防御効果は殆ど無くなっている。
しかしそれでもいい。これでも十分。さっきよりすごいマシ。
【NAME】とノクトワイはそんな意思と共に並び立ち、すちゃりと武器を構える。先刻はイェアにあれこれと言ったものの、流石にここまできて逃げ出す程に臆病ではないのだ。
「…………」
背後で轟沈しているイェアには視線を一切くれずに、【NAME】は前方の巨大な亜獣を見る。
「ブラウパーザナップの攻撃手段は、まず従えた蔓草」
その形状は、波を打つように生えた一本の樹木だ。伸びた枝や根には、先刻遭遇した植物系亜獣のようにざわざわと動く蔓が巻き付いており、近付いてきた【NAME】達を警戒するように揺れている。
「そして、花ね」
視線を樹の中心に向ければ、そこには不相応な程に巨大な果実が一つぶら下がっていて、周囲には毒々しい色合いの無数の花が咲いている。芯は葯ではなく円い口のような空洞。その中は見通せないが、緩い風に煽られる度、そこから“臭い”の塊がこちら目掛けて襲いかかってくる事から、あの花が“臭い”の出所であるのは間違いないようだ。
「花から出てくる“臭い”は、本格的な危機を察知するとタダでも強烈なそれを別の――色々と神経的に喰い込んでくる類のものに変化させるって話よん。対策なしに喰らうと洒落にならないけど、どうにか耐えなさい」
「…………」
いや、そんな事を戦う寸前に言われても困ります。
思わずノクトワイに視線を向けるが、言った本人もその無茶ぶりは理解していたらしく、
「無理よねぇ。アタシも、相手がこいつだって知ってたら事前に色々用意してたんだけどね……本当に先生ちゃん、なんでそれを最初に言っとかないのか」
多分、言っていたら自分達がついてこないか、マスクを最初からかっぱらわれると思っていたからではないでしょうか。
「……そぉね」
「うー。あー。くさい、くさいですー。うあーん。たすけておねーちゃーん」
背後から響く呻き声を完全に無視して、【NAME】とノクトワイは視線を正面に向ける。
「それじゃ、いくわよん」
軽い合図。続けて、ノクトワイがその場で浅い跳躍をする。
髭の剣士が次に起こす行動は判る。その勢いを利用して屈伸からの加速だ。そろそろ彼の剣の癖も馴染んできた。恐らくは正面から挑む事は無く、左右へと身を振りつつ迂回し、辿る先は横。狙うは花弁の茎であろう。
それを理解しているからこそ、【NAME】は彼が動き出すより早く、正面から前へと出る。搦め手を活かすには、陽動役が重要だ。【NAME】は気合いの声と共に真っ直ぐに飛び出して、樹の亜獣の注意を自分に引きつけて囮となり、しかしあわよくばその中心に一撃を叩き込もうと、全力で地面を蹴った。
「おーい、先生ちゃーん」
「…………」
「ちょっと。そろそろ起きてー」
「……ぐす。ぐすぐす」
まるで亀のように四肢をたたみ込み、俯せになって身動きしなくなっていたイェアは、ノクトワイの何度かの呼びかけに、ようやく反応をしめす。
ぐずったような声を上げて伏せていた顔を起こしたイェアは、覗き込むノクトワイと【NAME】を見上げ、
「おふ、おふたりとも、酷いですわよぉ」
「いや、酷いのは主にそっちだと思うんだけど、……ああもう、悪かったわよ。悪かったからほら、泣き止みなさいな。いい歳こいてなんつー顔晒してんのよアンタ」
「歳のこというな」
「はいはい御免なさい御免なさい。ってか別に気にするほどの歳でもないでしょうによ」
「うるさいです。……ぐす」
普段の態度とはかなり様相の違う、まるで子供のような仕草と口調でぐしぐしと顔を擦りながら、イェアはようやく身体を起こして辺りを見る。
「……あ」
動いていた視線が止まる。彼女が見ているのは正面。既に【NAME】とノクトワイの手によって息絶えた“黴爛果”ブラウパーザナップである。臭いの元であった花はノクトワイの剣により全て斬り飛ばされ、樹を守るように蠢いていた蔦は【NAME】の技法でもって排除されている。後に残ったのは幹を折り裂く程に深々と刻まれた斬撃痕と、その上でゆらゆらと揺れる巨大な果実である。
「“黴爛果”ブラウパーザナップが有名なのは、その“臭い”もそうだけど、もう一つ。樹が実らせる果実の味と、そして香りにある。花が齎す暴力的な“臭い”とは異なり、その果実が薫らせるのは柔らかな“香り”。それはあらゆる料理が持つ彩りを増す、最高の添え物である――だったかしらん?」
「その通り、ですわ」
イェアはゆっくりと既に息絶えたブラウパーザナップに近付くと、その実を抱くように掴み、もぎ取った。
彼女は暫し、抱きかかえた果実に埋めるように顔を寄せると、小さく嘆息。そして、
「お二人とも」
くるりと振り返り、深々と礼をした。
「これにて、わたくしのお願いは終了です。本当に、お手数を掛けました。これまでわたくしの無茶なお願いにお付き合いしてくださって、本当に、ありがとうございます」
「…………」
唐突に寄越された真摯な言葉に、【NAME】は単純に面食らって、言葉を詰まらせる。
そんな【NAME】に小さく笑みを向けながら、ノクトワイはひらひらと手を振り、
「まったくね。アタシも【NAME】も、何の得にもならないのによくこんなトコまで付き合ったもんだわ。人に情けを掛けるのも大概にしとかないと駄目よねん」
茶化すような返しに、イェアはわざとらしくむくれるような顔を一瞬作って、けれども次には力の抜けた笑みとなり、改めて頭を下げる。
「お二方のご協力は、決して無駄には致しません。勝負の日には必ず、皆にあっといわせるような料理を用意してみせますわ」
言われて、そういえばと気づく。
あの約束から結構な日数が過ぎている。具体的な日付を聞いていなかったのだが、一体リゼラとの勝負はいつに行われるのだろうか。
【NAME】がそんな事を口にすると、イェアはこくりと頷き。
「ええと、もう明日、ですわね」
「明日!?」
思わず声が出た。
「……【NAME】がそんなにびっくりするのって珍しいわねん」
横からのそんな声を無視して、【NAME】はイェアに本当に大丈夫なのかと訊ねる。
食材探しを勝負の前日までやっていたのでは、肝心の料理の部分についてどれだけ対策が進んでいるのか、全くもって怪しいように思えた。前回のイェアの料理を思い出すに、そもそも彼女の料理の技能は然程――いや、全然高くないように思えた。食材を揃えることで確かに舞台を整える事は出来るだろう。しかし、舞台を整えただけでは駄目なのだ。舞台の上で見せるもの。これがしっかりとしていなければ、勝負の土台が作れたとしても結局は同じ結果にしかならない。
そんな【NAME】の心配に、イェアはにっこりと微笑みだけ返して、
「大丈夫ですわよ。なんせわたくしにはこの果実がありますから」
「?」
どういう意味だ、と首を傾げる【NAME】に、隣に立つノクトワイが頭痛を堪えるようにこめかみに手をやり、
「さっき言ったでしょ。ブラウパーザナップの果実は料理が持つ彩りを増す最高の添え物だって。要するにそれ、言い換えれば」
「この果実が持つ香りは七難を隠すって事ですわね」
つまり果実の香りで誤魔化すという話か。
呆れたように呟くと、イェアは言葉では答えずに暫くくすくすと笑って、
「まぁ、【NAME】さん。色々心配していただいているのは判りますけれど」
イェアはそこで言葉を切ると、少し身を正して、
「先刻言いました通り、わたくしに協力してくださったあなたを裏切るような真似は決して致しません。それだけは、お約束しますわ。ですからどうか――」
――楽しみに、していてくださいな。
そう告げて、彼女は踵を返す。
「さぁ、戻りましょうかー。えーっとまずは霧の配置確認して一番帰りやすいルートを……って、あーっ! “くるくる座標くん”壊れてるっ! っていうかそもそも“くんくんここ掘るくん”がっ! ああいや、帰るだけならなんとか“くるくる座標くん”だけでも……」
何やら不吉極まる発言が聞こえ、大丈夫かいなと思いながら彼女の後を追おうとした【NAME】は、ちょい、と肩をつつかれて、動きを止めた。
振り返れば、髭面が意味深な笑みを浮かべてこちらの耳元に寄ってくる。
思わず、ひぃ、と息を呑んだが、
「【NAME】、先生ちゃんのコト、いまいち信用できない感じ?」
こそりと言われて、【NAME】は暫しの迷いの後、頷く。
確かに、先刻の彼女の発言はとても真摯で、その言葉だけでも信じてしまえるような、そんな力があった。だが言葉と想い、それを除いて客観的に考えると、彼女がこれまで確保した食材を使用したとしても、まともな料理が出来るとは正直思えなかった。何事も、熱意だけでどうにかなるものではないのだ。
そんな【NAME】の言葉に、ノクトワイは「まぁ、【NAME】の意見ももっともよねん」と頷き、そしてこう続けた。
「今日の夜の、そうね。月が空の真上あたりに来る頃。野営地に戻ったら、それくらいの時間に、一の十四番の天幕に来てみなさいな」
一の十四番。一は、野営陣の中心である大天幕群に属する天幕である事を指す。そして十四番。十番台の天幕は確か、
(……炊事用?)
怪訝とノクトワイを見直すと、彼はにやりと笑い頷いて、一度【NAME】の肩を叩いてから身を離す。
「斜め四十五度の角度で、はーっ! あ、直りましたわ! ……ってあれ? お二方、何されてるんです? もう帰りますわよー」
イェアの呼ぶ声が聞こえ、先にノクトワイが「はいはい」と返事をしながら気軽な動きで歩いていき、先刻の話がどういう意味なのかと追求するタイミングを逸してしまった。
(今日の夜の、一の十四番、か)
【NAME】は先行く二人を暫し眺めて、浅く一度首を振った後、その背を追って歩き出した。
真なる楽園 海月・先生の壮絶お料理道
――海月・先生の壮絶お料理道――
冴え冴えとした空には幾多の星々と、円を描く月の姿。
雲の影一つ無い今日の夜は殊更に澄み渡っていて、星の姿も、月の姿も、闇の中にくっきりと際立つような輝きを放っている。
「…………」
細く、息を吐く。
割り当てられていた多人数用の天幕をそっと抜け出た【NAME】は、暫くそんな空の様子を眺めてから、ゆっくりと陣の中を歩き出した。
野営陣は浅い静寂に包まれている。ところどころに焚かれた篝火から溢れる薪の弾ける音と、宿泊用の天幕から漏れ出す兵士達の小さな話し声や寝息が、海から届く細波の音と絡み合って【NAME】の耳に届くが、さくりさくりと砂地を踏む己の足音を紛れさせる程のものではない。
陣地の隅では、遠くちらちらと火が瞬く様子が見えた。その傍には幾人かの人影らしきものもあった。夜番を務める兵士達だ。ここはエルツァン、真なる亜獣達の楽園である。野営陣周辺は亜獣の姿が殆ど確認されていないとはいえ、警備に手を抜けるものではない。
とはいえ、その警戒は主に外に向けていれば良いものだ。夜番を担当する者達の姿は基本、陣地の隅の方ばかり。陣の中には人の姿は殆ど無い。中天に至った月の位置が示すのは、今が既に深夜を過ぎて未明に入り始めた刻限だという事。兵士達の殆どは、明日の日の出と同時に始まるそれぞれの仕事に備えて眠りについている。所々、騒がしい気配を放つ天幕もあったが、それでも控えめに、灯りすらも灯されていないものが殆どだ。
そんな中に、一つ、例外ともいえる天幕があった。
陣の中央広場に接する位置に張られた大天幕。その外縁を包むように張られた天幕群の内の一つだ。一の十四と、そんな番号が縫い込まれた天幕の内側からは、煌々と灯りが外へと漏れだし、更には騒がしい音、加えて煙のようなものまでが外に立ち上っていたのだ。大天幕周辺は宿泊用の天幕があれば、誰かが騒がしいだの眩しいだのと怒鳴り込んできそうな程の様相であった。
今までの物静かな野営陣の様子を半ば楽しむように歩いてきた【NAME】は、視界に入ったその目的地を暫し唖然と眺める。
と、一の十四の天幕の近くに立ち、手持ちぶさたにしていた兵士が一人。棒立ちしていた【NAME】に気づいて、てくてくと寄ってくる。
その様子に多少の警戒心が湧き、立ち去るべきかという選択肢が脳裏に浮かぶ。しかし、【NAME】としても別に何も悪いことをしている訳では無い。夜間の出歩きについて軍の間で何らかの取り決めがあったとしても、そもそも【NAME】の立場は軍属ではなく、金銭契約による傭兵関係ですらない、乞われてやってきた客分に近い立ち位置だ。咎められる謂われは無い、と寄ってくる兵士の顔を毅然と見返す。
兵士は【NAME】の傍まで近づいてくる、何やら非常に申し訳なさそうな顔で、
「アー、その、なんだ。多分ここのテントに色々と思うことはあるだろうが、上からの命令でな。出来れば見なかったことにして、黙って立ち去ってくれるとありがた――って、ありゃ? あんたは……」
と、兵士は目を細めて【NAME】の顔を確かめるように覗き込み、
「おお! あんた、アレか。ウチの隊長とイイ仲の冒険者か!」
ウチの隊長。イェアの事だろうか。
隊長という役職からその名前を口にするが、兵士は違う違うと首を振り、
「学者先生の方じゃねーよ、ノクトワイ隊長の方だっての! 俺はほれ、ガレー組じゃなくて、キヴェンティの対処に行ってた部隊の出身だからさ。……って、おい、どうした?」
「…………」
いきなりの不意打ちすぎる言葉に、【NAME】はがっくりと膝を付く。
――まさか、ノクトワイと、イイ仲だと、思われて、いた、とは。
『確かに、【NAME】とアタシって結構シンミツなナカよねん。最近ずっと一緒に旅してたし。ウフーン』
などという幻聴が聞こえるほどの強烈なショックに見舞われ、【NAME】は暫く身動きが取れない状態に陥った。
ようやく立ち直ったのは、兵士にぺちぺちーんと両頬を張られた辺りだ。
「目覚めたかよー? ってか、なんだよねみーのか?」
いやいや、大丈夫大丈夫、ちょっと精神的に凄いダメージ喰らっただけ。
そう返して、【NAME】はどうにか身体と心を立て直す。未だに衝撃が抜けきらず膝が笑っているが、まあ多分きっと大丈夫。
(で、ええと、なんだっけ)
あまりのことに会話の流れが記憶からぶっとんだ。
暫く記憶を漁り、ああ、と兵士が何を言ったのか思い出す。見なかったことにして、立ち去れ、だったか?
【NAME】がそう呟くと、しかし兵士は何故か首を横に振った。
「いや、そこはもういーんだよ。だってお前、あの冒険者でいいんだよな?」
どの冒険者か。ノクトワイとイイ仲の冒険者か。
突っ込むのも恐ろしく、【NAME】は肯定も否定も出来ないまま、引きつった顔で固まる。
「あれ? 違うのか? ほら、“四大遺跡事変”を治めた英雄殿。神形器持ってる冒険者」
それなら自分。正に自分。間違いなく自分である。
こっくこっくと頷くと、「んだよ、間違えたかと思ったじゃねーか」と笑い、
「フツーの連中なら色々と口止めして追い返さないとならんところだったが、お前は別だよ冒険者。学者先生じゃなくて、うちの隊長からちゃんと指示でてる。『【NAME】が一の十四番の天幕に来たら、ささっと中に入れてやってねん』ってな」
・
そうして通された一の十四番の天幕自体は、炊事用として設計されているため広く、通気性の高い構造となっていた。しかし本来広い筈の天幕内は多数の炊具と火や水を扱うための設備で埋められており、中に居る人影は、その中央にて半ば埋もれるような状態で作業を行っていた。
中央に配置されていたテーブルの一つで、刃物片手に慎重に魚を捌いているのは白衣に前掛けを身につけた女性だ。その背後には、口髭を撫でながらぷるぷる震える刃物の先を眺める長身の男の姿。
女の方は、自分が今まさに切り裂かんとする魚の状態に完全に気を取られているらしく、天幕の垂れ布を捲って中に入ってきた【NAME】に一切気づく様子がなかったのだが、男の方は直ぐさま顔を上げて【NAME】の方を見て、や、とばかりに片手を挙げた。
「おや、【NAME】。ちゃんと来たのねん」
「――え? 【NAME】さん? って、みきゃーっ!」
ピュー、とばかりに、魚の身を抑えていた方の手から血を噴き出させた女性――イェアは、慌てて術式で止血を施してから、恐る恐る、といった様子で【NAME】の方を仰ぎ見て、
「【NAME】、さん、あの、どう、して?」
どうして、ここに居るのか、という事なのだろう。
主な理由は当然、ノクトワイに指示されたからであるのだが、それを口に出して良い物だろうか。
だが、【NAME】がついノクトワイに向けてしまった視線から、イェアは答えを聞く前に事情を察したらしい。アタシ知りませんよとばかりに顔を背けてわざとらしく口笛を吹くノクトワイに突っかかる。
「ノ、ノクトワイ様っ! まさか、言っちゃったんですのっ!?」
「まーほら、【NAME】も先生ちゃんの壮言大語に凄い心配そうっていうか、胡散臭そうにしてたじゃないの。だからその疑念をこう、払拭させるにはこれがいいかなー、とね」
「い、言いたいことは判りますけど、もう明日対決って時に教えなくてもいいじゃないですのーっ! せっかく本番で【NAME】さんを驚かそうと思ってましたのに! っていうか」
突然、イェアは身を翻すと、だだだと【NAME】の横を走り抜けて天幕の外へと顔を出し、
「こらーっ! オーリスさん、なんで【NAME】さんを通しちゃってるんですの――え? ノクトワイ様から別件指示? 俺一応そっちの所属だから逆らえない? いや、いやいやいや、今の指揮系統ならわたくしの方が目上ですわよ、優先はわたくしの方――は? ノクトワイ様からガレー組の女の子紹介してもらえる約束? ちょ、ま、ウチの子に先を越させたら――あ、いや、手を付けたら、わたくし本気で怒りますわよ!? って、あーもー、待ちなさいなっ! 逃げるなー」
と、イェアの声が遠のいていき、暫くの間の後、心底疲れた顔で戻ってきた。
「先生ちゃんおかえりなさぁい」
「ノクトワイ様。後で、どういう事か、しっかり聞かせていただきますからねっていうか、その両刀っぷりなんとかなりませんの」
「いやぁねぇー。アタシの愛は老若男女誰に対しても向けられるのよん。あでも、メインはやっぱり少年少女ねん」
「……駄目だこの人。いつか何とかしないと……」
両手をこめかみに当て、心底疲れの交じった溜息を零すイェアに、ノクトワイはくつくつと楽しげに笑ってみせて、
「ほら、そんな事より、【NAME】の相手をしてあげなさいな。さっきから所在なげにしてるわよん」
いきなり話を振られて、【NAME】は戸惑ったように視線を彷徨わせた。そんな態度を見せていたつもりは一切無かったのだが、端から見ればそう映っていたのだろうか。
と、そうして揺れた視線が、こちらをばつが悪そうに見上げるイェアと搗ち合う。イェアの瞳が、少し迷ったように彷徨って、
「えっと。つまりはこういう事なので大丈夫、という話なのでした。はい」
そうして浮かべた笑みは些細な悪戯が見つかった子供のような表情であった。
・
――つまりは、こういう事らしい。
イェアは、【NAME】とノクトワイに食材調達を頼んだ件とは別に、ノクトワイに対して料理についての手ほどきを頼んでいたらしい。どうも常駐軍内の間では、ノクトワイはそれなりの美食家であり、そして彼自身もそれに相応しい料理の腕前を持っているというのは有名な話であったらしく、それを知っていたイェアは、今回の勝負のためにノクトワイから指導を受ける事にしたのだという。
そうしてイェアは、日中は普段通り、いや普段以上のペースで軍務をこなし、そうしてひねり出した時間を機甲兵器その他の調整整備に当てて、更には【NAME】達と共に食材の探索で大立ち回り。そしてそれが終わって野営陣に戻ってからは、ノクトワイの指導の下、深夜まで料理の修業を行っていたのだ。
「まぁ、料理の練習をやっていた時はもう少し早く終わったんですけどね。今日は特別で、明日の下準備を朝までやるつもりですわ」
そう言って、イェアは少し照れたように笑う。
それでも、もう少し早く、という表現だ。今は既に未明。そろそろ明け方も近付いてくる頃合いである。ならば普段は真夜中辺りまで料理の練習をしていたのだろうという話になる。
よくよく、笑うイェアの顔を眺めてみる。そうして真剣に観察してみるまで、彼女の表情、その各所に現れた疲労の痕跡に全く気づいていなかったことに、【NAME】は複雑な心境となった。目の下に刻まれた隈を誤魔化すために施された化粧。その存在を、今の今まで見逃していたのだ。
【NAME】が己をじっと見つめ、そして痛々しげな表情となったことで、その内心を察したのだろう。イェアは今度は困ったような、それでいて呆れるような顔になり、
「【NAME】さん、それは無用な考えですわ。だってこれは、わたくしがわたくし自身で決めた労苦ですから。多分に勢いがあったのは否定できませんが、自分でこうしようと。選んだ結果故の事です。【NAME】さんが気づく必要も、そして気づいて何かをしようと思う必要も、全くもってありはしませんわ。よゆーです、よゆー」
「…………」
その発言を、水臭いと。
そう思う程に、彼女との関係は何時の間にか深まっていたのだろうか。自分の事である筈なのに、【NAME】はそれを上手く判断できなかった。
元々は浅い関係であり、そして今もそう、多少打ち解けたようでありつつも、一定の距離を保った間柄。そんなつもりでいたのだが、いざこうなってみると、妙な苛立たしさ、もどかしさのようなものが内心を微かに過ぎるのだ。
そんな風に【NAME】が思う間にも、イェアは更に言葉を続けていく。
「というか、ですね。わたくし自身もなんで自分がこんな事をしているのか判ってないところもあったんですけど、今こうして話をしていて、一つだけ。はっきりしてきた事があります」
ぴ、と一本。イェアは指を立ててみせて、
「どうもわたくし、あの子が自分に喧嘩を吹っかけてきてくれた事が、凄く嬉しかったみたいなんです」
あの子。そう言われて思いつくのは、一人だけだ。
リゼラ・マオエ・キヴェンティ。“杜人”と呼ばれる、マオエ氏族の若長。幼いとは裏腹の大人びた物腰と態度、しかし年齢相応ともいえるような熱のようなものを秘めた少年。
「へぇ。一体なんでまた?」
テーブルに凭れるような体勢となったノクトワイが、興味深げに訊ねる。【NAME】にしても、イェアのその心の動き方には気を惹かれた。
そんな二人からの視線を受けて、イェアは己の心の内を浚うように少し視線を彷徨わせて、
「多分、あの時。リゼラさんが初めて、わたくしという人間に対して、何らかの干渉をしてくれたんだと思います。リゼラさんが、一体どういうおつもりであんな発言をしていたのかまでは判りませんけれども」
「あー、一応、あの妙な煽りっぷりが、普段の杜人クンらしくないってのは気づいてたんだ。割りに、凄い必死に反論してた気がするんだけど」
「あ、あれは、レェアの事とか、色々引き合いに出されて……。でも、少しして落ち着いたら、直ぐに判りました」
「まーそりゃねぇ」
ノクトワイは軽く笑って、一瞬【NAME】の方を見る。アナタもそのへんは判っていたでしょう、と。
それについては【NAME】も同意見であり、そしてイェアも同じであるようだった。
「これまで事務的な、最小限の会話だけしかしたことはありませんでしたけど、それでもいきなりあんな風な感じでお話しをされるような子ではないというのは感じてはいました。……そもそも、あまり言葉を費やすという事を好まれていないような、そんな雰囲気がある方だと思っていたのですけれど」
イェアの感想に、【NAME】も同感の頷きを零す。
リゼラと対面し、会話した経験は幾度かあるが、あの少年は興味が無いもの、価値が無いもの、そう断じた相手に対しては自分から関係を持つ事をしない。良くも悪くもばっさりと、竹を割ったような質の持ち主なのだ。そんな彼が、この間のイェアとの会話のように、無駄に気を逆なでするような言葉を吐き続けるというのがそもそも異常なのである。
何かが、あるのだろう。だがその何かがさっぱり判らない。
「でも、それはそれで今回の事は良い機会かなって、そう思ったんです。あの子がわたくしと……そうですね。喧嘩? そんなものをしたいというのなら、わたくしも思い切り全力でそれに乗ってあげて、……まぁ出来れば、ですけれどもあの子をぎゃふんと言わせて。それをとっかかりに仲良くなって、今回の事の理由を聞いたりして。それで、それで――」
イェアはそこで僅かに目を伏せ、思い描いた光景に耽るように、けれどもじっとその未来を信じるように頷いて、
「――あの子と、姉の事とかも色々、お話したいなって」
そういうイェアの瞳は気力に満ちていて、そしてそんな前向きな態度を見せられると、先刻あれこれと躊躇っていたのが馬鹿馬鹿しく感じる。
――ここは一つ、強引に行くべきだろう。
そう判断した【NAME】は、無言で軽く、己の服の袖をまくってみせた。
「あらん」
「……【NAME】さん?」
ノクトワイが面白そうに、イェアが驚いたように【NAME】を見る。そんな二人に、【NAME】は気軽に告げた。
――イェアの料理勝負の下ごしらえを手伝おう、と。
【NAME】の提案に対する反応は対照的だった。ノクトワイが深い笑みと共に親指をあげてみせたのに対し、イェアは心底戸惑った様子で、おっかなびっくり、【NAME】とノクトワイを上目遣いで交互に見る。
「え、でも……その……良いんでしょうか?」
「先生ちゃん、アタシにこんだけ手伝わせといて、【NAME】に対しては遠慮してみせるってどーいう事なの……」
「いや、でもでも、【NAME】さんですし。ノクトワイ様は、はっきりいってどうでもいいですけど」
「はっきり言いすぎじゃないの!?」
「でも、【NAME】さんは、その……ノエルが……うーん」
それでも戸惑う様子のイェアに、【NAME】は段々と焦れてきて、彼女の背後に回り込むとその両肩を掴み、
「きゃっ! 【NAME】さん!?」
慌てる彼女をずんずんと押して、元居たテーブルの前。未だ捌きかけのまま放置された魚の前へと連れてくる。良くやった、とばかりに笑うノクトワイに、【NAME】も笑みだけで返し、そして困ったような顔で見上げてくるイェアには、大丈夫と。以前、彼女に言われ続けた言葉を今度は【NAME】が告げる。
【NAME】の言葉を、イェアは僅かに目を見開いて受け止めて、
「……そうですね」
力が抜けた笑みを浮かべ、こくりと頷いた。
「ではその言葉を信じて、甘えさせていただきます。――【NAME】さん、どうかわたくしを手伝ってくださいな」
畏まりました。学者先生殿。
――その不器用な手管の結末――
その日。野営陣は、早朝から妙な空気に包まれていた。
より正確に言えば、妙な匂いがある場所から漂ってきていたのだ。
一般の兵士達が異常を察知したのは朝食の配給の時だ。いつもの萎びた食事を目当てに、死人のような足取りで大天幕に群がってきた兵士達は、炊事用として用意されている一つの天幕から、久しく嗅いだことの無い匂いが漂ってくるのに気づいた。
漂ってくる匂いは、明らかに肉や魚、野菜等が茹でられ、焼かれ、炒められている時のものだ。しかし、それはおかしい。兵士達も既にエルツァンへやってきてそれなりの時を過ごしている。連隊長を務める学者先生が、碌な食料を持ってこなかった事は既に身に染みる程わかっているのだ。炊事用の天幕も一つで足りる程度にしか手を加える余地が無く、四つ以上用意されたうちの三つは半ば放置状態の荷物置きとなっていた筈。だというのに、これはどういう事なのか。
疑問と、それ以上の食欲を煽る匂いに釣られ、天幕の中を覗き込もうとする兵士達。しかしその天幕の前には、連隊の班長を務める男――オーリスが部下達を引き連れて仁王立ちし、一切通さぬとばかりに円陣を組んでいた。
まるで、天幕の中には一切の立ち入りを許さぬ、そこにある匂いの元は自分達のものだ――そんな風にも見て取れる態度に、集まった兵士達は気色ばんだ。中にあるものが何なのかはまだ判らないが、しかし隠し、独占するつもりならばそれ相応の何かがあるのだろう。それも、凄く、美味しそうな匂いのする何かが。
となれば、これまで魚の発酵乾物で食い繋いできた兵士達からすると我慢できるものではない。上役二人の緩い性格のせいもあり、その部下達も軍人としては箍が外れやすい方だ。今までの環境のせいもあり、そこを退け、中を見せて、俺等にも喰わせろ、独り占めは許さんぞ、と一気に熱くなっていく。
だが、そんな周囲の状況に対し、集団の中心にて囲まれ迫られる形になっていたオーリスは、平然とした態度を崩さなかった。
「確かに、今、この天幕の中では、普通の――いや、高級とも言える食材を使っての料理が行われている」
オーリスはその緊迫した状況にもかかわらず白けきった表情を浮かべ、「だが落ち着けお前ら、冷静に考えろ」と前置きし、こう告げた。
「――中で料理してるの、学者先生だぞ?」
「…………」
暫くの沈黙の後。
――あれ、それって要するに罠じゃん?
――喜び損じゃないかしらこれ?
――つまりは匂いだけで結局メシマズじゃないの?
呟きが各所から漏れ、暴動寸前かとも思える程に熱くなっていた場の空気が、一転して急激に冷めた。そんな反応にオーリスはうんうんと頷き、
「一応俺らも先生の指示があったからこそ、こうやって朝もはよから通せんぼしてる訳だがな。本音を言えばさっさとメシ貰いにいきたい。だからお前等がここの番を変わってくれるというなら交代してもいい。……どうだ?」
窺うような視線に、場に居た者達は皆露骨に顔を逸らす。そして一人一人、「無駄足こいた」だの「期待させないでくださいよ」だの「配給貰うの遅れたじゃないの」だの「行きおくれめが」だのという声と共に、のろのろと鈍い足取りで大天幕の逆側、食事配給が行われている天幕へと歩いていく。
こうして、野営陣の兵士達を一時沸き上がらせた匂いは、早々に兵士達にとって関係の無いものとして斬り捨てられる事になったのだ。
最後に立ち去った兵士の後ろ姿を見届けて、オーリスは満足げに笑い、
「はっはっは。さすがは名高き学者先生だ。名前を出しただけでこれとは。正に効果は抜群――ごっ」
前のめりに吹っ飛んだ。
その背後からは、にょきりと伸びる細い足。そしてばっさーと垂れ布を捲くって現れたのは、徹夜明けのせいか顔色悪く、髪が乱れたイェアだ。
「っつーか待てや最後! 最後関係無いじゃありませんのっ! 行き遅れてない、行き遅れてないですわよわたくしっ!」
天幕など外と内とを布一枚隔てているだけ。外の会話は中には丸聞こえだ。彼女は手負いの獣の如く吼えるが、しかし既に兵士達は立ち去った後であり、遠くからはがやがやと、食事を受け取るために並ぶ兵士達の声が聞こえてくるのみだ。
未だふーふー唸るイェアの隣から、ひょいと顔を出したのはノクトワイだ。口髭の伊達男も同じく徹夜明けの筈だが、その身だしなみには一切の歪みは無く、表情に多少の疲れと眠けが漂っている程度だ。彼は毛を逆立てるイェアを見て、軽く吐息をつき、
「実際、先生ちゃんまだ若い筈だし、本人が自分からそんな事言ってた訳でも無いのに、段々そんなキャラが軍の中で定着してきたわよねん」
「やめてっ! そういう怖い事言うのホントにやめてください! 泣いてる子だっているんですよ! 主にわたくしが!」
頭を抱えながら身を左右に振るイェア。
(悲惨な……)
同じく天幕の中に居た【NAME】も、冗談では無く若干涙目になっているイェアに流石に同情してしまう。
そんな中、蹴り倒されていたオーリスが「まぁまぁ抑えて」と立ち上がり、
「でもこれで、料理勝負の時まで他の連中に邪魔されるって事は無くなると思いますよ。確か、昼過ぎって話になってましたっけ?」
イェアはじろりとオーリスを見やり、鬼の形相を浮かべたまま、
「……ええ。昼食時を過ぎた辺りで、リゼラさんとも話がついています。場所は大天幕ですわ」
「ならまぁ、大丈夫でしょう。学者先生に、隊長、あとそっちの冒険者も。安心して時間まで準備していてください。……あー因みに、俺等もそれにご相伴預かれるんですかね?」
恐る恐る、半笑いで訊ねるオーリスに、イェアはにっこりと至極女性らしい満面の笑みを浮かべ、
「なにせ料理しているのはわたくしですから、オーリスさん達のお口には合わないと思いますので――ぜったいにっ! あげません! 大人しく魚の乾物でも囓ってなさいな!」
「報われねーなぁ……」
天を仰ぐオーリスであったが、自業自得だろうと思うしかない【NAME】であった。
・
そして時間が過ぎて、約束の刻限。
大天幕の中。前回定例会議を行ったその場所では、前回とほぼ同様の面子が顔を合わせていた。
前回と違うのは大テーブルの上が綺麗に片付けられて、そこに多種の工夫を凝らした料理が溢れかねない程に乗っている事と、
「にしても、少しばかり意外でしたわねん?」
「そうだろうか?」
入口から見てテーブルの奥側。イェアの料理を並べていたノクトワイの声に、その逆、テーブルの手前側。リゼラの料理を並べるオリオールは、小さな笑みと一緒に首を傾げてみせる。
大天幕の中にいるのは【NAME】、イェア、ノクトワイ、ノエル、オリオールの五人だ。まだ最後の一人、リゼラは顔を出してはいない。イェアとノクトワイ、そして【NAME】が運んだ料理をテーブルに並べていた時、多くの料理を載せた台車と一緒にオリオールが一人やってきたのだ。曰く、「リゼラ少年は今少し準備中で、かわりに自分が彼の料理を運んできた」と。
テーブルの上に並べられた自分の料理に、最後の施しをしていたイェアも、少し不思議そうな顔だ。
「まさかハマダン様が、リゼラさんのお手伝いをされていたとは思いませんでした。……よく、彼が認めてくれましたわね? 勝手なイメージですが、そういった提案はきっぱりお断りされるような方だと思ってました」
「いやぁ、実際結構大変だったよ」
オリオールは笑みのまま、手にしていた大皿を最後、テーブルの中心付近に置く。子豚に似た獣の姿焼きだ。焼きたてであるらしく湯気が目に見える程である。
「けれども、イェア嬢が【NAME】やノクトワイ氏の協力を得ていたのは早い段階でわかっていたからね。なら僕くらいは彼の助けにならないと不公平かな、と頑張ったのさ」
「ああ、えーっと、そこは、そのぉ……」
暗に責めるような彼の言に、イェアは露骨に視線を泳がせる。ノクトワイの方は肩を竦めて、
「とはいえ、アタシ達が手を貸さないと単なる前回と同じ結果になるのは目に見えてましたしね。結果としては、そちらにハマダン様が入る事で良いバランスになったんじゃないか、と」
のうのうとそう言ってのけるノクトワイに、オリオールは苦笑いを浮かべ、
「そうでもないよ? 一応手助けすることを認められたとはいえ、料理の方では彼の力になれたかというと大きく疑問が残るしね。そもそも彼からすれば、どうもバランスや勝ち負けというのは――」
「口を閉ざせよ、探検家。お前はどうも口が軽い」
「――おっと」
わざとらしく口元を抑えるオリオールの背後から、小柄な人影が姿を現す。キヴェンティ、マオエ氏族の若長リゼラは、いつも以上の仏頂面で天幕の中を一瞥し、テーブルの空いた場所に手にしていた大きな草包みを置き、結びを解く。中身は潰して蒸した芋に似たもので、所々には黒や赤などの色彩が見えた。甘い匂いが解けるように広がって、「ぐ、やはり手強い」とイェアが呻くような声を上げるのが聞こえた。
地面に座しかけて一瞬動きを止め、不機嫌さを増した顔でテーブルの椅子に座り直したリゼラに、オリオールは全く気兼ねなく声を掛ける。
「それで、もう準備は終わったのかな? かなり無理をしていたようだけれど、大丈夫かい?」
「諄い。そもそもお前には関係の無い事だ。構うな」
ぴしゃりと断ち切られて、オリオールは大袈裟に手を挙げて、そして【NAME】達の方に肩を竦めてみせる。
「…………」
【NAME】達はそんな遣り取りに、怪訝と視線を交わし合う。気づいたのは自分だけかと思ったが、イェアとノクトワイの態度を見るに、彼女達も違和感を覚えたらしい。
リゼラが持ってきたあの料理が、最初にオリオールが言っていた準備中の料理であった。という話ならば納得はできる。だが、それを持ってきた上で「準備が終わったのか」と訊ねるのはどういう事だ。
「……何か更に隠し球でもあるんでしょうか」
「……いやでもこれ以上なんか持ってこられたら流石にキツイわよ」
「……今でもこっちがちょっと負けてる感じすらありますからね」
などと、顔を寄せ合ってぼしょぼしょと相談するが、答えは出ない。
と、そこへ、
「あの」
呼びかける声。先刻から一人、配膳を手伝う事も無く、ただ椅子に座ったままテーブルに展開されていく様々な料理に釘付けになっていたノエルだ。
黒銃も持たず、帽子もかぶらず、普段以上に身軽な装いの彼女は、声を挙げたものの視線は全くテーブルの料理から動かさず、
「まだ、食べてはいけないでしょうか」
いつものノエルの平坦な口調。
しかし、【NAME】達には判った。今発せられたノエルの言葉には、彼女の内心が強く籠められていた事を。
「……ノエル、あなた、随分食いしん坊になりましたわねぇ」
呆れたようなイェアの声。場に一瞬、緩やかな空気が流れて、
「確かに」
短く、少年が発した声に、緩んだ空気が直ぐさま緊張した。
「既に互いの料理は並べ終えた。それで相違ないな?」
「それはわたくしの台詞なのですけれど、リゼラさんがそういうのでしたら、恐らくはそうなのでしょうね」
どうやら、リゼラは更なる料理を準備していた訳ではないらしい。イェアの返事は歯切れの悪いものであったが、リゼラはそれについては言及せず、テーブルに置かれていた食器に手を伸ばしながら告げる。
「――では、競い合いを始めるとしよう」
それに倣うように、【NAME】達も食器を手に取り、並べられた無数の料理達を味わい始めた。
・
事前に決められていたルールは、このようなものであった。
集められた審査員と、そして料理者本人達。それぞれに一票ずつが与えられて、食後にどちらの料理が良かったか、手持ちの票を投じて優劣を計る。そんなルールだ。前回と同じ人員のみが集められているため、審査員は四人。そして料理人は二人。つまり票は合計六票だ。三対三となれば引き分けとなる数であり、前回の対決がああいう結末で終わったことを考えると、きっちりと勝敗を分けるために一人誰かを呼んでくるという案も最初はあったのだが、
「不要だ。増やす必要は無い」
というリゼラの発言に押し切られる形で、現状の人数のままとなった。料理人二人分についても意味はあるのかという話にはなったが、これについては、
「ちゃんとどちらが優れているのか、わたくし達が理解して、それを形として示す事が大事ですの」
というイェアの発言が尊重される形で導入される事となった。
そんな事を思い出しながら、【NAME】はテーブル上の料理に更に手を伸ばす。
イェアの料理は、前回のものとは全く毛色が違った順当かつ豪華なものだ。料理の基礎をノクトワイから学び、珍味ともいえる食材を、種類は少ないながらも豊富に使い、更には飽きがこないように趣向を凝らした料理の数々は、見ては楽しく、食べても美味しいと、付け焼き刃ながらも作り手の真剣さが伝わる心地の良い代物だった。
対して、リゼラの料理は前回の延長線上にある料理達。「素朴で充実」というイメージはそのまま、それを大きく伸ばし、広げたような品揃えとなっていた。イェアの料理とは違い、少ない素材に芸を凝らしたようなものではなく、前以上に多種の食材を使ったものが多く、味もそれぞれが個性的。食べる側での好き嫌いが大きく影響するのは致し方ないものの、そんな当たり外れを楽しめるような品々となっていた。また、時折イェアの料理にも似た、アラセマからの移民が作るような料理が混ざっているのも面白い。
そんな事を考えながら料理を口に運んでいた【NAME】は、ふと、テーブルを囲う皆の様子を窺う。
「いやぁ、しかし久しぶりのまともな食事だね」
「ですねぇ。今までの乾物地獄から脱出できてこんなにうれしい事は無い……」
「僕も粗食に慣れてはいるけれど、流石にあの魚の乾物だけで食いつなぐのはね……」
テーブルの向い側では、男二人が嬉しそうに料理をそれぞれのペースでがっついている。話を聞いている限り、どうも彼等はイェアの用意していた魚の乾物が余程苦手であったらしい。その魚を用意したイェアに当てつけるような台詞を続けながら、半ば咽び泣くように料理を口に運んでいる。
「ふむ」
最初はテーブルの下座側に腰を下ろしていたリゼラは、場所を移して上座付近へと回り込み、淡々と、しかし噛み締めるようにイェアの料理を食べ続けている。やはり彼もあれだけ煽った手前、イェアの料理にはそれなりの興味を持っていたのだろうか。思い、眺めていると、
「……?」
彼の輪郭に、一瞬淡い輝きが宿ったような気がした。
瞬きする。すると、既にもうその輝きは無い。見間違いだろうか、と首を傾げてリゼラの姿を改めて確認するが、別段それ以降奇妙な様子は無く、【NAME】は直ぐに興味を失った。ただ、ほぼ無表情で料理を食べ続けていたリゼラの顔が不満そうな仏頂面となり、そして雑音を遮るように片側の耳を抑えていたのが印象に残った。
「もふ。もふもふ」
横で表情を殆ど変えず、発言も碌にしないまま小さな口に次々と料理を突っ込むノエルの様子に少し引きながら、【NAME】も釣られるように手近な料理に手を伸ばした。
対象は、傍にあったリゼラの料理。最後に彼が持ってきた、ふかした芋を潰したような料理だ。イェアの料理は既に作り始める所から知っているせいか、味は問題無いながらも新鮮味が無いが、しかしリゼラの料理は見かけから想像出来る味とは全く異なるものが多く、「一体これはどんな味なのか」と、わくわくするような気分を味わえる。
「…………」
ぴりりと舌に走る痺れのような辛味を味わいながら、【NAME】は一瞬、横で繰り広げられる男二人の小芝居に顰め面を浮かべながら、リゼラの料理ばかりを口に運ぶイェアを見て、申し訳ないと内心謝る。
テーブル上の料理はその大半が場に居る者達の胃に入り、宴はそろそろ終わりに近付いている事を示していた。
・
「では、そろそろ決を採るとしようか」
満腹後の気怠い空気が支配していた大天幕を、オリオールののんびりとした声が引き締める。
「イェア嬢の料理が良かった、と思う者はあちら。リゼラ少年の料理が良かった、と思う者はそちら」
大雑把に片付けられたテーブルの上にて、空の皿が二つ並べられる。【NAME】から見て左がイェア。右がリゼラだ。
「票は、それぞれが食事に使っていたナイフを替わりにしよう。では、まず一票」
仕切るが故の責任か、まずオリオールが己のナイフを皿に添えた。ナイフが置かれたのは左――イェアの方だ。
「……あの」
「何かな、イェア嬢」
「ハマダン様、リゼラさんの手伝いをされていたんですよね?」
「そうだけど、別にだからとそちらに入れなければならない約束をした覚えはないからね。僕の好みで言えば、イェア嬢のものの方が良かった、というだけの話だよ。やはり、僕からすると“珍しい味”という方に気が惹かれるからね」
言って、オリオールは席に腰を下ろす。どうやら彼からの評価を得る為のもっとも重要なポイントを、イェアは的確に突いていたらしい。
「それでは、次の方、どうぞ」
オリオールはそう促すが、しかし他の者達は暫し無反応。沈黙が一瞬場を埋める。
どうしたものかと、【NAME】は視線を走らせ、様子を窺う。イェアは未だテーブル上に残されていた一つの皿を迷うようにつついたまま動かず、ノクトワイは困ったように頬を掻いて、リゼラは両眼を閉じて腕を組み、時折何の拍子に眉根を寄せて身じろぎしている。
そして最後の一人。隣に座るノエルに視線を送ると、彼女も何故か自分を見ていた。視線がまともにぶつかり、心構えができていなかった【NAME】は思わず怯む。そんな反応に、対するノエルは不思議に思ったらしい。
「どうされましたか、【NAME】?」
問う声に促されたか、他の者達の視線が自分に集まる。
(……なんというか、この流れだと)
まず自分が票を入れなければならないような、そんな空気になってしまったようだ。
【NAME】は一瞬戸惑って、しかしそんな必要も無いかと割り切った。どうせ単なる料理対決。それも、一度は入れた相手にもう一度入れるだけだ。躊躇う必要も無い。
思い、【NAME】はテーブル上に載せられていた自分のナイフを、静かにリゼラの方に置いた。
「ほぅ」
とオリオールが呟き、ノクトワイが顎を撫でる。イェアががっくり肩を落とすのが微かに見えて、何とも申し訳ない気分になったが、しかし自分の素直な感想がこれだったのだから仕方が無いと思い直す。
重みのようなものが一気に取り除かれた気分になって、【NAME】はすっきりした気分で椅子に座り直す。
と、
「では、私も」
からん、と音が鳴った。目を開けば、【NAME】が置いた皿の上に、更なるナイフが転がる。誰のものかと視線を向ければ、皿にナイフを落とした姿勢を取っていたのは隣に座っていたノエルだ。
「うぅ~」
イェアが唸るような声を上げて、悲しそうにこちらを見る。
「……あの、【NAME】さん、ノエル。わたくしのお料理、どの辺りが駄目でしたの?」
問われて、今それを答えて良いものかと迷った【NAME】であったが、
「こちらの方が色々と面白い、そう私は思いました」
「面白い……料理対決で面白さで負けるとは……」
ノエルは端的にそう言うが、色々と言葉は足りないものの、【NAME】の感想も彼女とほぼ同様のものだった。イェアの料理は美味の食材を選りすぐり、それに手を加えた派生系ばかりの料理で、美味いことは確かなのだが、味に広がりがなかったのだ。
対して、リゼラの料理はその真逆とも言えるもの。そして、今【NAME】達は魚の乾物という常に同じモノを食べ続けてきた身だ。純粋に刺激に飢えていたところに、リゼラの出してきた料理は覿面に響いたのだ。それらは正に面白い。楽しく食べられるものであり、【NAME】達に暫く欠けていたもの。これに抗うのはなかなかに難しい。
そんな【NAME】の補足を聞いて、イェアは「なうー」と椅子の背もたれに身を預けた。
「つまり、私の方針自体が最初から間違っていたって事ですかー」
「それでも、純粋なおいしさ、という意味で語るなら、やっぱこっちだとアタシは思うけどね」
と、そんな言葉と共に、最後の審査員のナイフが皿の上を滑った。自分の皿に置かれたナイフを、頭を抱えていたイェアは半眼で見て、続いてその主であったノクトワイを睨み、
「……お情けで入れられても困ります」
対し、口髭の男は肩を竦めてその視線を逸らした。
「そのつもりは無いわよん。というか、ちと杜人クンの方は気になる点があってね」
「ほう。気になる点、とは?」
オリオールの興味深げな声に、ノクトワイは腕組みをしてうーんと唸り、
「杜人クンの料理の中に、妙なのがまじってたのよね。なんていうか……浮いてる料理。アタシ達の国の、ってか、キヴェンティの料理っぽくない奴。あれのせいで、どうも纏まりがないっていうかね。味付けが先生ちゃんのと似たような感じになってたから、特に比較できるようになっちゃって、そのせいで先生ちゃんの料理の方が良いかなって、そんな印象になっちゃったの」
言われて、確かにそんな料理があったと【NAME】は頷く。それはノエルを除いた他の者達の認識の中にもあったらしい。皆の視線は一点。丁度イェアが未だ自分の目の前に置いていた皿の料理に向けられる。
あれが、そうだ。違和感の残る料理。イェアがああして手元に一つ残していたのも、恐らくはその違和感の為だろう。
「……しかし、これはまた綺麗に票が割れたものだね」
テーブル上を眺めてのオリオールの言に、【NAME】もそちらを見る。空の皿二枚。その上に置かれたナイフは二本ずつだ。審査員は四名。その全員が既に票を入れたことになる。
残るは本人達。イェアとリゼラがその結論を下すしかないが、こちらも同様に二人で二票だ。互いが自分に票を入れれば、それで結局は同じ。引き分けとなる。二人とも、自分の料理に自信があったこそのこの二度目の対決だ。当然、票は自分に入れるだろう。ならば同数引き分け、また勝負は持ち越しとなるのか、それとも引き分けで納得してくれるのか。そして持ち越しとなった場合、また自分とノクトワイはあの食材調達に付き合わされるのか。
そこまで考えて、椅子の上でげんなりと脱力していた【NAME】は、ぐぬぬと唸り声を上げていたイェアが、そのナイフを――リゼラの皿に置く姿を見て慌てて身体を立て直した。
「先生ちゃん?」
皆の意外という思考。それを代表するように問い掛けたノクトワイの声に、椅子から立ったイェアは小さく深呼吸をして、そしてせいせいしたように笑ってみせた。
「だって、仕方がありませんわ。わたくし、気づいてしまいましたから」
「気づいたって、何にかな?」
オリオールが、少し身を乗り出すように問う。
「この料理の事、ですわ。わたくしもお食事している間ずっと気になっていたんですけれど、先刻のノクトワイ様のお話でようやく、何が気になっていたのか、それが判りました」
「ほう。それは有り難いね」
イェアの答えに、オリオールは笑みを深くする。
「僕もね、リゼラ少年があれらの料理を作っていたとき、どうにも気になっていたんだ。何故彼はあのようなものを作るのか。いや、作れるのか、とね。その答えをイェア嬢が教えてくれるというのなら有り難い」
そんなオリオールの言葉に、イェアは笑みの質を変化させてこう応えた。
「だって、あの料理。あの味付け。あれは、わたくしの姉の――レェアのものなんですから」
イェアは椅子に腰を下ろすと、自分の目の前にある料理に手を伸ばす。
「懐かしい。これ、わたくし達がまだ子供の頃に、練習していた料理ですわね。わたくしも姉も当時はうまく作れなくて諦めたのですけれど」
そして一口。
「そう。完成すれば、こんな味。姉がノエルを拾ってきて、二人で相手をしていた時に、レェアが振る舞ってくれたものの一つですわね。結局わたくしは諦めてしまっていたのに、レェアは隠れて一人でちゃんと作れるようになっていて。あの時はわたくし、散々煽られたものですけれど」
今となっては、それも懐かしいと。彼女は囁くように零した。
「と、言うわけで、ですね」
そしてイェアはこう前置き、テーブルの対面。未だ目を閉じ腕組みしたままの少年を見た。
「わたくしの負け。それで結構ですわ、リゼラさん。貴方が、どういうつもりでこのような状況を作り、そしてこんな料理をわたくしに用意してくれたのかは判りませんが、ただ、わたくしは、凄く」
そこで言葉を切り、
「嬉しかった。――ありがとうございました」
深々と礼をする。
それに対し、リゼラの反応はといえば、片眼を浅く開いて頭を垂れるイェアを睨み、深く吐息。
「勝手に負けを認めるな、レェアの妹よ」
リゼラは腕組みを解くと、己のテーブルにあったナイフを手に取り、かつんと刃をイェアの票となる皿に当てて転がし――そして別の新しいナイフを手に取ると、それを続けて同じ皿に転がしたのだ。
「――は?」
きょとん、と目を瞬かせるイェア。見ていた【NAME】達にしても同様だ。一体どういう意味の行動なのか。いきなりの事に驚く一同にリゼラは元の姿勢に戻ると、
「レェアの妹よ。今回の貴様の料理には、我が期待していたものがあった。だからだ」
「はぁあ?」
意味が全く判らない。
リゼラが一本のナイフをイェアの皿に置いた事まではまだ理解できるが、しかし新しいもう一本。それはどこから湧いてきたというのか。
「あの、杜人クン? できればもう少し、判りやすく説明をしてくれると有り難いのだけど」
「……というか、そもそもですねっ!」
ばん、と先刻までの殊勝な態度は何処へ行ったのか。いや、その反動とでもいうものなのか。イェアが勢い良くテーブルを叩き、
「リゼラさん、貴方、何がどうしたくてこんな事をしてるんですか!? わたくしにいきなりケチを付けてきたかと思えば、いきなりこんな、姉の事を思い出させるような料理を出してきたり。それでいて、我の期待していた料理だったって――じゃあわたくしは、一体何を貴方に期待されてたっていうんですのっ!」
問い詰める。そんなイェアの言葉に、リゼラは至極不機嫌そうな顔を浮かべて、細く息を吐き、
「願われたのだ」
「願われた?」
鸚鵡返しの言葉に、リゼラは頷く。
「貴様の姉に、願われたのだよ。あの我が儘が、今の妹の料理の腕前を知りたい、とな。この間の寄り合いの折、貴様が起こした食の問題を知って、愛しの妹御の将来が心配になったのだそうだ。そのナイフは、アレが入れた票だと思え」
「はぁああ? え? あれ? リゼラさん、もしかして今もまだ、姉と繋がってる状態なんですか? いや、でも、前に……」
そう。イェアが混乱するのも判る。確か以前、ノイハウスの遺跡でレェア本人が言っていたではないか。
『エルツァンの島は兎に角土地概念の歪みが並じゃなくて、私みたいなのが外側から干渉するには厳しい場所でね。あの中では時の歩みや因果すらも歪むっていう話で、身体の顕現が出来る出来ない以前に、意識を向こうへ繋ぐのも不可能なのよ。だから、残念だけど今回はお留守番』
と。
【NAME】が慌ててそう言うと、リゼラは深く頷き、
「そうだ。エルツァンは命脈の流れすらも歪み、掴み切れぬ土地よ。我が翠霊たる“九継”すら、その姿を満足に取ることもままならぬ。半ば亡霊に近いアレにしてみれば、姿どころか、意識を保つことも難しいだろう」
「なら、一体どうやったんだい?」
興味津々、といった様子のオリオールの問いに、リゼラが視線を向けたのは、何故か【NAME】だった。いきなりの事にたじろいだ【NAME】であったが、その視線は【NAME】ではなく、その胸元に向けられている事に気づいた。
「神形の使い手。お前がエルツァンという島の囲いを揺るがせた時。やはり心配になったと、あの馬鹿は我の“孔”目掛けて、自身を無理矢理繋げてきてな」
「む、無茶するわねぇ」
焦ったようにノクトワイ。確かに無茶な話だが、最初は自分で無理無理といっていたのにいざとなると勢いでどうにかしようとする辺り、あの女賢者らしいとも思えた。
「だが当然、島の内部の土地概念はねじ曲がり、命脈を辿る事も難しい。我という基点を捉えた状態であっても、その姿を顕現させる事などやはり不可能だった。が、どうも感覚だけを、我と同期する事で得る状態に持っていく事には成功したようでな」
と、それまで黙っていたノエルが、小さく首を傾げて、
「つまり、“先生”は、貴方がここで得た感覚を共有している状態で存在してる、という事でしょうか?」
「今は少し違う。アレの意識が、我と同調した状態で、我の中に存在しているのだ」
「それって、要するに……」
「先刻から、指示が煩くて敵わん。常ならば精々が時折意思を交わす程度であるのだが、今回、料理を深く味わうために、アレとの同調を深くしてな。それ故、暫し準備に時間が掛かった」
腑に落ちた。リゼラが最初に遅れてきた理由。準備と言っていたのは、その事だったのか。
「えーっと、ちょっと待ちなさいよ」
そう言って、ノクトワイが手を広げると、うんうん唸りながら言葉を続ける。
「つまり。杜人クンは最初の会議の時、さっさと帰るっぽい態度を見せてたのにいきなり先生ちゃんにケチ付け始めたのも、それが理由?」
「無論だ」
「料理対決に持ってったのは、先生ちゃんの料理の腕前が今どんなもんか知りたかったって事?」
「あれでは不十分と駄々を捏ねられ、本気の料理が味わえるように舞台を整えろと騒がれた」
「……はーっ」
呆れたような声を漏らすノクトワイ。これまでのリゼラの振る舞いは彼らしくなく、それが謎となってこびりついていたのだが、蓋を開ければこんな話。ある意味、リゼラらしい理由によるものだったのだ。
一同の反応はそれぞれだ。オリオールは苦笑気味に椅子に深く腰を下ろし、視線だけは面白そうにこちらを窺っていて、もう完全に傍観の態勢だ。彼の興味があった部分は既に明かされたのだから、その態度は当然だろう。ノエルの方はいまいち何を考えているのか判らない表情で、ぼうとリゼラの方を見ている。彼女が敬愛する女賢者が、彼を通して自分達を感じているという話に、何か感じ入る事でもあったのだろう。
そしてイェアは、唖然とした表情のまま固まっていて、
「ええと、待ってください。では、リゼラさん。姉ではなく、貴方がわたくしに期待していたものとは、一体なんだったのですか?」
「貴様に期待していたのは」
そこまで呟いて、珍しく、リゼラは口篭もるように動きを止めて、
「期待していたのは、レェアの妹――いや、イェアと言ったか――お前が、我の料理に見出したもの。それと同じものだ」
「……それって」
ぽかんと、リゼラを見るイェアに、少年は気難しげに顔を顰める。
「我にとっても、あの味付けは、懐かしいものだ。それをこの異境の島で、別の者の手から味わえると期待するのは――ぐっ」
突然、リゼラが耳を抑えるような仕草で声を止めた。その様子に、ぴんと来るものがあった。要するに、彼がこういう態度を見せていた時は、
「もしかして、レェアが何か?」
「――む、う。そんなに自分の料理が恋しいというのならいくらでもと……意識が繋がるというのは、厄介極まりないな」
至極苦々しくそう告げて、嘆息。そしてリゼラは立ち上がると、
「何はともあれ、イェアよ。勝負は貴様の勝ちだ。故に、以前の食にかかわる我の言動は全て取り消そう。そうだな、貴様の料理は、レェアの作るものよりも幾分か優れ――む、ぐ」
言葉の途中で耳を抑えるリゼラ。
「なんか、完全無欠っぽかった杜人クンが一気に身近になってく気分がするわねん」
「あの歳で尻に敷かれる様を見せられるのは同情せざるをえないね」
「“先生”と常にお話ができるというのは羨ましいと、私は思います……」
三人はそんな様子を好き勝手に論評するが、一人、イェアだけは立ち去ろうとした背中に声を掛ける。
「あの、リゼラさん? 一つ教えていただいていいでしょうか」
まだ何か話す事があるのかと、足を止めて訝しげに振り返るリゼラに、イェアは恐る恐る訊ねる。
「リゼラさんは、どうして。今回のお料理で、レェアの料理をまぜてくれたんですの? もしレェアに事前に教わっていたとしても、きっと貴方が作るのは、凄く難しかったと思います。なのに」
リゼラは眉根をいよいよ寄せて、
「貴様にはかん――っぐ、早く術を解かねばたまらんな」
また何事かを叫ばれたらしく頭痛を堪えるような仕草で暫し唸ってから、リゼラは諦めるような吐息と共に振り返ると。
「……貴様が、姉の事を近しく感じられれば良いと、そう思ったからだ。長らく、直には会っていないのだろう?」
「――――」
その答えに、イェアは暫く茫然とリゼラの方を見て、
「う、うううっ!」
ぐぐ、と震えを堪えるように身を縮めて、妙な唸り声を発し始める。
一体どうした、と【NAME】達はおろか、言い捨てて立ち去りかけていたリゼラすら様子を窺いかけた瞬間。
「なに? なにこの良い子っ! かわいすぎじゃないですのっ!」
弾けるように叫んだ後。
イェアはテーブル横を勢い良く駆け抜けると、あまりの唐突な反応に全身を強張らせて固まったリゼラ目掛けて体当たり。
「ひゃー! レェアがお気に入りにするのも判りますわっ! 最初はあの少年趣味がとか思ってましたけどっ!」
「――ぬ、お、おい! やめ、止めろっ! 貴様等、姉妹揃って抱き癖でもあるのかっ!?」
普段のリゼラならば一撃で引き離す事も、そもそも突進を往なすことなど朝飯前であろうに。無様に地面に転がりじたばたと蠢く様子を、【NAME】達は苦笑いのまま、微笑ましくも白けた様子で見守る。
「ま、これで一件落着って感じなのかしらね」
「丸く収まったというのは確かではあるね」
「今日は凄く美味しかったと私は思います。また、機会があれば是非、料理対決というものを行っていただきたいです」
「絶対にノゥ。また食材調達からやらされたら今度こそ死ぬわよアタシ達」
ノクトワイと【NAME】、二人でタイミングを合わせてぶんぶんと首を横に振って、そして皆で声を揃えて笑った。
――取り敢えずは、これでこの間の定例会議から引っ張っていた問題は、ひとまずの区切りがついた形か。
【NAME】が言うと、男二人はそうだなとばかりに頷き、しかし、一人ノエルだけがかくりと首を傾げた。
「いえ、あの時の定例会議で問題になっていたのは、イェアの料理の腕前や、リゼラ様との諍いでは無く――兵士達の間で生じている食料についての不満、という話であったと私は記憶しているのですが」
「……あー」
わざわざ挙手してノエルの発言に、他の三人から何とも言えない吐息が漏れた。
そういえばそうだ。後々話がもつれた部分がまるで主のような気分になっていたが、大本はそこであり、解決しなければならないのもそこだった。
「今回のお料理対決で、何か役に立ちそうな事とか、ないかしらん」
「ないだろうね。リゼラ少年達キヴェンティの食料調達方は、軍のような大集団を賄えるには厳しいものだし、イェア嬢の料理にしても食材の調達に関しては至極大変だったらしいのは、先刻の【NAME】達の反応で判るよ」
ノクトワイの苦し紛れの言葉を、オリオールはざっくりと斬り捨てる。
結局、食料の問題に関しては解決法は非常に限られているのだ。自給自足が難しいのだから、後取れる選択といえば一つ。アノーレから新たに食料を輸送してもらうしかない。
しかし、問題は多い。まずアノーレは未だ“四大遺跡事変”での混乱から抜けきれず、食料の追加輸送が可能であるかが不透明である事。加えて、輸送に掛かる時間だ。
「今からアノーレに一旦戻るために沖に待機させてる船を動かして、島を包んでる境界を潜って、ポロサに帰還。そこから指定食料の調達を行って、運搬、積み込み、そして戻る。……どんだけ少なく見積もっても数週間はかかるわよね、これ。そもそも、調達自体が出来るかどうか」
それまで、魚の乾物生活か。
今日、豪勢な食事を堪能してしまったが故に、その未来予測はあまりに辛い。隣に座るノエルの、無言無表情ながらも発散される強烈なしょんぼりオーラは目も当てられない程だ。
さてどうしたものかと、一同黙り込む。そこへ、軽い調子で下方から声が飛んできた。
「ああ、その件については」
リゼラを思いきり胸の中に仕舞い込んだ状態で、イェアはぽきゅんと顔を上げて、
「皆さんからそんなお話があったあの日のうちに、アノーレの方に伝令を送りましたので問題はありませんわ」
「いつの間にっ!?」
「いや、ですから皆さんとお話をした日に」
「そういう意味じゃなくて! ってか、船動かしてないでしょ!? どうやって!」
「小型の魔導船に術士を何人か乗せて境界に干渉した後、私の“鳩”をアノーレに飛ばしてもらう感じで」
「“鳩”……あれ、まだあったのねん」
「ええ。あ、因みに物資の調達はカナード様がかなり無理に融通してくださったみたいで、もう輸送船は境界を越えて、沖で待機していた船と合流。今荷物の積み替え作業を行っている筈ですわ。幾つかの食料は先行させていた小船で、もう昨日の段階で到着してますわよ」
「聞いてない! って、何かどっから湧いてきたのかわかんない調味料やら食材やらあったのはそういう事だったのっ!?」
などと、とぼけた遣り取りをするイェア達。それを眺めて、オリオールは苦笑と共に【NAME】の方へと振り返り、
「つまりは、全部一段落と、そういうことなのかな?」
――話を聞く限りでは、そういう事になるのだろうか。
イェアとノクトワイが口論している間に、ようやっとイェアの束縛から脱したリゼラが、頭痛を堪えるようにその場から逃げ出そうとし、しかし普段からは想像できぬ程の鈍い動き故に、更にイェアに掴まって引き倒される。
そんな様子を見ながら、【NAME】は改めて今日の料理対決の後片付け――天幕の隅に詰み置かれたままの食器類を洗うために椅子から身を起こす。
「ですが、どうも変なのですよね」
そこで、ふと、思いついたような。
リゼラを抱えた状態のまま。誰に聞かせるつもりもない、まるで独り言のようなイェアの呟きが、【NAME】の心に妙な印象を残した。
「距離を考えるなら、島間の移動には最低一週間。島の境界を揺るがせるのにも数日はかかる筈ですのに……何故、こんなに早く着いたのでしょう?」
真なる楽園 冒険家は手引きとなる
――冒険家は手引きとなる──
エルツァンでの探索行に、誰の助けを借りるか。そう考えた時、ふと、ランドリートの島で共に旅をしたあの冒険家の男の姿が脳裏を過ぎった。
こういった未踏の地に、冒険家としての経験豊富な彼が同行してくれるなら心強い。
しかしそこまで思いついて、【NAME】は「はて」と眉根を寄せる。今回の作戦に同行しているとは聞いたが──そういえば姿を見た記憶が無い。一体どこにいるのか。
・
オリオールの所在を探して、【NAME】はてくてくと野営の陣を歩き回る。
最初はオリオールに割り当てられているという天幕に向かったのだが、中は様々な資料や道具等が乱雑に積み置かれていただけで無人。その後、陣中央の広場やイェアの天幕、キヴェンティ達の居所にも足を運んだが全て空振りで、手がかりを求めて通りすがった兵士達に片っ端から声を掛けてみた結果、海の方へと一人歩いていく彼の姿を見たという情報を得た。
野営陣の直ぐ傍に存在するエルツァンの海岸は、その殆どが比較的遠浅の地形となっている。多くは砂地ではなく岩場となっており、そして海に濡れた岩は良く滑る。【NAME】は足元に気をつけながら、オリオールの姿を探して磯を歩く。
捜索の場所は何せ海岸。視線を遮るものが殆ど無い場所だ。直ぐに見つかるだろうと高を括っていた【NAME】であったが、実際に見つけられたのは一時間近く過ぎた後。オリオールが磯に並ぶ大岩の間に出来た幅五メートル程の窪みにすっぽりと、まるで隠れるように座り込んでいたのが原因だ。
そこは若干海際から離れた場所であった為、地面の湿り気はそれ程でもなく、おかげで足を滑らせる心配はせずに済みそうだったが、岩場だけに凹凸が多く、巨大な岩の間だけあって日光が遮られて薄暗い。躓かぬよう用心しながら窪みに降りると、近付くこちらの気配を察したのか、しゃがみ込んで何やら作業をしていたオリオールがふと顔を上げて【NAME】を見る。
「おや、【NAME】。一体こんな処で何を?」
それはこちらの台詞である、と言葉を返しかけて、座り込んだオリオールが周囲に広げている物を見て、彼が何をしていたのかを把握する。
岩の上に置かれていたのは、硬めの草で編み込まれた籠と木で出来た細身の銛。しゃがみ込んだオリオールの前には、その辺りに転がっていた石を集めて組み上げて作ったらしい囲いがあり、その周りには細枝の串で貫かれた魚が数匹、囲いの中で燃える火に炙られてじりじりと音を立てていた。
――つまり、オリオールは一人で魚を獲っていたらしい。
納得の吐息と共に傍まで歩いてきた【NAME】へ、オリオールは小岩で挟む形で立てられた木串を一本手に取る。
「折角だし、君も食べるかい? 裾分けだ」
断る理由も無く、【NAME】は差し出された串を受け取った。程よく焼けた魚からは食欲をそそる香ばしい匂いが漂っているが、色合いが若干毒々しい。見るからに警戒色なのだが、果たして食べても大丈夫なのか。
そんな事を考えながら訝しげに魚を眺める【NAME】に気づいたか、オリオールは微かに笑い、
「背鰭に毒があるようだけど、そこ以外は大体大丈夫だよ。鱗も処理してあるし、そのまま齧り付いて貰って構わない。ああでも、ワタは避けた方がいいかもね」
おおう、と何気なく背鰭に触れようとしていた手を引っ込めて、【NAME】は慎重に魚に口をつける。これといって味付けがされているわけではなく、せいぜい塩気を僅かに感じる程度なのだが、妙に美味しく感じる。はぐはぐと魚を食べながらそんな感想を伝えると、
「いや、それは単純に配給の食事に舌が慣れてしまっていたせいじゃないかな」
オリオールの返しに、【NAME】は「あー」と半ば呻きに似た声を零して頷く。
エルツァン島にやってきてからの食事は、軍からの配給で賄われている。それらはアノーレ島にて事前に準備し、船に乗せて運んできたものであり、保存食として加工した物が主だ。加えて、イェアが用意したという食料はどうにも癖が強く、品揃えもお世辞にも良いとは言えないもので、それらに慣れている状態ならば、単なる魚を焼いたものであっても美味しく感じるのは当然だ。
オリオールは普段から野営陣から姿を消す事が多かったが、その間、こうして釣りや狩り等をして、皆が配給の食事のみでひもじい思いをする中、一人腹を満たしていたのだろう。
「……待った待った。少し誤解があるよそれは」
成る程成る程、と頷きながら魚を口に運んでいると、オリオールが慌てた様子でそんな事を言ってくる。
【NAME】としては別に誰かに告げ口するつもりもなく、むしろ自分も彼を真似て食生活の改善を図ろうと考えていたくらいだ。そんなに焦って言い訳しようとしなくても大丈夫なのだが。
【NAME】がそんな趣旨の言葉を返すと、「いやいやそれ本当に誤解なのだけれど」とオリオールは苦笑いを浮かべる。
「僕が普段陣の方に居ないのは、周辺地域の探索に出ているからだよ。そもそも、今回だって別に魚を獲る為だけにこっちへ来たって訳じゃないしね」
「…………」
【NAME】は無言のまま、オリオールの顔と彼の目の前でぱちぱちと音を立てる焼き魚を交互に見る。そんな仕草から【NAME】の心中を察したオリオールは苦笑を深くし、
「確かに、これを目の前にしてだと説得力は無いかも知れないけれど、本当にそうなのだから仕方無い。……そうだな。一応常駐軍の部隊も、イェア嬢の指揮の下でエルツァン島の探索調査を進めているのは【NAME】も知ってるかな?」
勿論、と頷く。
合わせて、エルツァン島へと派遣された常駐軍部隊を束ねる立場にある学士、イェア・ガナッシュの探索方針として、エルツァン内陸部への侵入は事前に立案された調査計画に沿う場合に限り、特に無断、単独での行動は厳禁。例外として許されているのは、イェアが直接指示をした先遣の任務を帯びた者達と、“鬼喰らいの鬼”討伐の役目を担う自分のみ、という話であった事もしっかりと記憶していたが。
そんな【NAME】の冷静な言葉に、オリオールは「あー」と視線を微かに泳がせて、
「その部分は少し脇に置いてもらうとして……。取り敢えず、だね。イェア嬢がエルツァン島の探索調査の為に立てた計画の方を僕も一応事前に見せてもらって、問題は無いと助言した口なのだけれど、あの計画は良く言えばとにかく慎重に、人的物的被害を最小限にするべく安全面を極端に重視して組まれたものなんだ。だから先遣の支隊は別として、本隊となる主力の調査部隊が負うリスクは、予測しうる範囲内でだけどほぼ下限に近い辺りまで下げられてる。彼女が立てた計画は、それ程良く出来たものなんだけど、安全第一で組み立てた影響が他の処に出ていてね。如何せんその分……」
少し言葉を迷うようにオリオールは腕を組み、首を捻るが、しかし続く言葉は想像がつく。
「まぁ、有り体に言えば遅いんだ、調査の進みが」
危険を排するとは、つまり未知を探り不備を潰すことだ。入念な準備と丹念な調査。それを緻密な計画に基づいて実行すれば、着実かつ安全にエルツァンの土地を暴いていく事は出来るだろう。
だが、それに比例して必要とする作業と調べるべき場所は増え、時間は大きく消費される。いわば安全を時間で買っている状態だ。それ自体は悪手では決してないのだろうが、
「現在の、エルツァン島調査ではなく“鬼喰らいの鬼”討伐を主目的とした部隊が取るべき手としては、あまり良いものではないね」
“鬼喰らいの鬼”の追跡は、彼の鬼が現在どの程度の危険性を有しているのかを判断する為の確かな情報がなく、その優先順位は曖昧だ。だが、決して低く見積もって良いものではない事は、事情を知る多くの者達の間では共通認識となっていた。例外は“女賢者”レェア・ガナッシュくらいで、彼女だけは「別に放っといても大した事ないんじゃないのー?」などとだらけた発言をしていたが、現在の彼女は軍内での発言権どころかそもそも肉声を伝える手段すら持っておらず、直接それを聞いていた【NAME】やイェアも余りに適当な発言故にそれを外部に漏らすことはなく、結果彼女の主張は完全に流される形になっていた。
そんな状態であったため、少なくともアラセマ常駐軍内では、エルツァンへ向かった“鬼喰らいの鬼”は悠長に対応して許される存在ではなく、放置など以ての外。出来うることなら早急に発見し、そして可能であれば討伐すべき存在とされていた。
ならばエルツァン島へと渡った軍部隊の長が取るべき作戦は、暢気な安全策ではなく、もっと攻めの姿勢でなければならない筈なのだ。
「もっとも、僕やノクトワイ氏も彼女が立てた計画に是と答えたのだから、あまり言えた義理ではないけれどね」
その事が判っていて、何故オリオールはイェアの調査計画を認めたのか。
理由については、既に【NAME】はイェアから話を聞いて知っていた。
「そう、結局軍は“鬼喰らいの鬼”討伐という極めて危険かつ重要な任務を君に丸投げした。だから、無理に危険を伴う行動方針を採る必要はなく、地道で慎重な調査を行う形でも問題はないと、そういう事だ」
「…………」
何処か皮肉気にオリオールは言う。
それに対し、【NAME】は何か言葉を返そうとして、しかし結局は口を開かず黙り込んだ。
イェアから説明された今回の作戦方針、“神形器”を持つ自分を主力とした少数をエルツァン島奥に送り込むという案については、苦肉の策とはいえそれなりに理に適ってはおり、【NAME】自身も納得して引き受けたものだ。それが軍にとって徒死となると判っていての要請であったのか、それとも今までの実績と過度の信頼による期待を込めた依頼であったのか。今更それについてあれやこれやと問い質すつもりはなかった。
そんな【NAME】の反応に、オリオールは少し険の混じっていた眉根を揉むようにして緩めて、軽く頭を下げる。それは“鬼喰らいの鬼”に纏わる話についての謝罪ではなく、
「済まない。少し露悪が過ぎたね。その件について君に責めてもらったところで、僕の気分が軽くなるだけで、他には何も解決はしないのだから」
オリオールは囲いに手を入れると、新たな串を二本引き抜き、一方をこちらに向ける。最初に受け取った一本分を既に食べ尽くしていた【NAME】は、遠慮無く渡された串を受け取る。刺さっているのは先程と同じ種類の魚。少し小振りだが、背鰭が先に取り除かれていてこちらの方が食べやすそうだ。
そうして二人、新しい魚をもぐもぐと口にして、
「っと、ああいけないいけない。そんな話をしたかった訳ではなくて、だ」
はっ、と話の途中であった事を思い出して、オリオールが魚から口を離す。
「要するに、軍の調査計画は堅実ではあるが至極ゆっくりとしたものだ。それはそれで結構な事ではあるのだけど、正直な話、それに僕も付き合わされるというのは中々我慢を強いられるものでね」
話すオリオールの表情には、にやりと何処か不敵な笑み。
「はっきり言ってしまうと、このフローリア諸島という場所は、僕が来る前に想像していたよりも少しばかり退屈な場所だったんだ。ランドリートはせいぜいが土地概念の変質程度。コルトレカン、アノーレと渡ってはみたけれども、土地としての面白さはむしろランドリートの方が上だったと言っても良いかも知れないね。【NAME】、君は色々と珍しい出来事に出くわしたようだけれど、残念ながら僕はそういう運には恵まれなかったし」
残念だ、と本気で残念そうな様子を見せるオリオール。
いや、コルトレカンやアノーレで、そんな羨ましがられるような目に遭った覚えは一切無いのだが。形もあやふやな化け物や、数多の鬼種を相手に死闘を繰り広げ続けた記憶しかない。
【NAME】はげんなりとした気分で異論を唱えるが、オリオールは笑って取り合わず、
「で、だね。そんなフローリアの旅だったんだが、この島に来て少し認識が変わった。どうもエルツァンはひと味違う、中々に刺激的だ、とね。僕が足を踏み入れた経験のある場所で比較するなら……そうだね。グローエスの“現出”地形の数々に、西大陸北方の至境“芯竜盈地”。後は東、環の国の“八生門外”か。あの辺りの滅茶苦茶さには流石に劣るけれども、アラセマが誇る召喚四大聖地の要区や、フォータニカで見つけた翆獣種の寝所、それに大陸圏界“樹海”の入口あたりに近い雰囲気はあるように思うよ」
と、若干興奮気味に説明されたのだが、【NAME】からするとその大半は聞いた事もない地名で、全くもってイメージが湧いてこない。知識としてあるのはグローエス五王朝の“現出”現象あたりか。しかしそれも“現出”自体がそもそも多種多様な土地概念変質、置換、合体現象の総称であり、その規模は上は空飛ぶ大島出現から下は無限に水が湧き出る小穴の出現と振れ幅が大きく、一体オリオールがどれを基準に話しているのかさっぱり判らない。
「……んー? そう言われるとイメージを伝えるのが難しいな。まあ、単にここで僕が言いたいのは、兎に角このエルツァンという島は、久々に僕の好奇心……言ってみれば冒険家心を擽るような場所だな、と。それだけの話ではあるのだけれどね」
ふむ、とその発言を吟味し、最終的にオリオールが何を言いたかったのかを考える。
――つまり、軍のエルツァン調査ペースが遅すぎて付き合ってられないので、己の冒険家心という名の単なる好奇心を満たすために、軍の取り決めである単独侵入禁止という話を無視して好き勝手にエルツァンを歩き回っていた、と。
こうして端的に纏めると、この男、どうしようもない輩であるように思えてくる。
【NAME】が歯に衣着せずにそう呟くと、
「はははっ! いや、全くその通りだ! うんうん、確かに我ながらどうしようもない人間だな! ははっ、良いな【NAME】!」
オリオールは気分を害すどころか、逆に大声を上げて気持ちよさそうに笑い出した。
そういう反応が予想外。戸惑う【NAME】に、ようやく笑いが収まったらしいオリオールは、ひゅうと一息ついて、
「はは、最近どうも僕の“冒険家”という名前が売れている処にばかり行っていたせいか、そういう至極真っ当な指摘をしてくれる人が少なくなっていてね。そんな自己中心的な行動を許容するどころか褒めそやしたり感心したりするような人までいる始末だ。【NAME】はどうやらまともな感性を持っているようで安心したよ。とはいえ、元々僕は軍の人間ではないし、あくまでオブザーバーとして協力しているだけだから、軍内での指示に従う理由もないのだけれどね」
笑顔でぱんぱんと肩を叩かれるが、何が彼の琴線に触れたのかいまいち理解出来ず、【NAME】は口元を引きつらせて曖昧な呻きを漏らすしか出来ない。
暫くすると落ち着いたのか、オリオールは笑顔を引っ込めると片手に持ったままの魚をもりもりと囓りながら、
「ま、そういう訳でね。一昨日は“谷”、昨日は“森”、そして今日は“磯”を、色々と僕の視点で冒険をしていたと、そういう訳だ。これはその際偶然に得た戦利品だね。……もう一本要るかい?」
まだ二本目が食べ終わってないので無理です。
丁重に断ると、オリオールは大袈裟な仕草で肩を竦めてみせ、
「それは残念。思っていたよりたくさん捕れたからね。君が来てくれて助かったと言えば助かったかな」
と、また囲いの中に手を入れて、残っている串二本程を火から離すオリオール。彼は魚の焼け具合を確認してから、囲いの石をそのまま崩して火を消去。どうやら焼き魚は残り二匹で終わりらしい。
(……そういえば)
その様子を何とはなしに眺めながら、【NAME】は思う。
オリオールは先刻“磯”を冒険していたと言っていた。つまりは先刻まで【NAME】が歩いてきた、何の変哲もない岩場の海岸である。
果たしてそれは、彼の好奇心や知識欲を満たす“冒険”たり得たのか。そんな疑問が湧いたのだ。
それをそのまま言葉としてぶつけると、オリオールは少し考えるような表情となり、
「うーん。少なくとも食欲を満たす冒険にはなったね?」
「…………」
「冗談だよ。まぁ、君の言うとおり、この海岸自体を探検しよう――などと思って足を運んだ訳ではないのは確かだよ。おっと、別に魚獲りが主目的であった、という事でもないから誤解の無いように」
してないので早く話を続けてください。
【NAME】が感情を殺して呟くと、「冷めてるなぁ、今時の子は」とじょりじょり己の顎を撫でる仕草で一拍間を置いて、
「ここに来た第一の目的は、一言で言えば答え合わせだよ」
――答え、合わせ?
【NAME】が鸚鵡返しに呟くと、オリオールはこくりと頷き、
「若しくは、証拠探し。間違い探し……だと少し意味が違ってくるかな?」
と言葉を足してくれたが、いまいち要領を得ないままで、【NAME】は怪訝とオリオールを見返す。すると、じっとこちらを見ていたらしいオリオールと真正面から目が合った。
一瞬怯んだ【NAME】であったが、オリオールは別段気にした風もなく、こちらの顔を見たままぽんと何か思いついたように手を合わせる。
「そういえば思い出したよ。【NAME】、今は君が持ってるんだっけ?」
「?」
何を? と首を捻ると、オリオールは食べ終わった魚の串をぽいと放り捨てて、開いた両手で妙な仕草をする。左手が何かそれなりな大きさのものを掴む形で止めて、右の手は人差し指と親指を寄せて左右に振るように動かす。
その手振りが示すもの。考えて、思いついたモノをそのまま呟いた。
「手帳?」
「正解。イェア嬢から聞いたのだけど、君が今、あの手記を持っているんだろう? ほら、アラセマの探検家で、最初にエルツァンに足を踏み入れたっていう……名前なんだったかな。カール、までは覚えているんだが……」
考え込むオリオールに、【NAME】は懐に仕舞い込んであった革張り表紙の古ぼけた手記を取り出しながら呟く。
――探検家カール・シュミット、と。
対し、その言葉がトリガーとなって思い出したのか、オリオールは「おおっ!」と歓声を上げ、
「そうそう、そんな名前だった! いやぁ、実はこちらへ来る前に一応、イェア嬢にそれを読ませてもらっていてね。地名やら地形の情報、特徴等は一通り頭に叩き込んだつもりだったのだけれど、肝心のタイトルをド忘れするとはね。年は取りたくないものだ」
で、この手記がどうしたのだろうか?
【NAME】の疑問に、オリオールは「単純な話だよ」と前置き、
「要するに、僕はその手記に書かれていた事が本当なのかどうか。それを自分の目で確かめようとしていた、というだけの話だ。だから――」
――成る程。答え合わせ、という事か。
・
「持っているなら丁度良い。少しばかりその手記を貸してはくれないだろうか。流石にそろそろ記憶が曖昧になってきていてね。出来ればその手記を改めて読み直して、情報の補正をしておきたい処だったんだ」
とのオリオールの言に、焼き魚の施しを受けた手前、無碍に断る訳にも行かず。【NAME】がイェアから借り受けた貴重品の手記は、今隣で歩く男の手の中に収まっていた。
食事をしていた大岩の間から離れて、魚籠と銛を担いだオリオールと磯を歩く。行く先は海岸沿いを常駐軍の陣がある方へ。陣まではそれ程離れておらず、海岸にほど近い場所に張られた天幕の群れが遠目にでも確認出来る程度の距離だ。
歩きながらオリオールは手記を捲り、独りこくこくと頷く。
「ふーむ成る程、道理で見つからなかった筈だ」
一体何がだろうか。
「捜し物が、だよ。やはり軽く一読しただけで記述の細部まで記憶出来る程、僕の頭は優秀ではないようだ。どうも、“始まりの場所”はこちら側の“磯”ではなく、野営陣を間に挟んで反対側の“浜”であったようだね」
だから、一体何を探しているのだろうか。
「先刻言っただろう? この手記の記述が本当であるのか。その証拠となるものを探しているんだよ」
その返答に、【NAME】は「はぁ」と吐息にも近い曖昧な声を零す。
――探検家カール・シュミットの手記。
当然、イェアから古ぼけた手帳を受け取った際、【NAME】も直ぐさまその中身に目を通してはいた。何せその手記は自分がこれから踏み入り、超えていかねばならぬ未知の場所についての情報が記載されている筈。貴重極まりない情報収集源であり、この先の命綱とも言えるものだ。本来ならば軽く扱うなど以ての外で、熟読玩味すべきもの。
だが、最初の数頁辺りまでなら大きな問題は無かったのだが、先へと読み進めていく内、【NAME】はこの手記に対して持っていた最初の認識を大きく修正する羽目に陥った。
色々と複合的な理由はあるが、それらを纏めて簡潔に言うならば、こうなるだろう。
――この手記はどうもあてにならない、と。
最初の数頁には、手記の持ち主である処のカール・シュミット氏による彼の経歴とエルツァン島へと旅立つ事に至った経緯、そして彼の仲間達についての略歴が記述されているのだが、その合間合間に差し込まれる自画自賛と自己顕示描写の嵐。そして読み手にとっては一番興味がある筈の、如何にしてカール達がエルツァン島へと辿り着いたかについての、驚くべき程の記述の少なさ。綴られる空虚な美辞麗句の合間にたった数行、それも極々抽象的な表現で書かれているだけで、もうこの段階で読み進めるのが苦痛に感じるような代物だった。
が、これはまだまだ序の口である。以降、エルツァン内に存在する地形一つ二つほど超える間は、まだどうにか探検日記という体裁を保っている。だが、三つ四つと進み、探検隊が半壊し始めた頃には、断片的な単語や妄想じみた現実離れした描写、文字と判別することも難しい記号や図形めいたものが不定期に書き綴られているだけで、読んでいる方の正気が試されるような代物となっているのだ。
それでもどうにか、集中して読み解けばどういう内容が書かれているのか判らなくもないのだが、しかしそれだけの苦労を賭して解読した代物が、果たして正しい情報であるのか。それが一切判らない事を考えると、真面目に解読しようとする意欲も失せる。何せ、カールがエルツァン探索への意欲に満ち溢れていたであろう最初の数頁ですら、読み手が一読して虚言であると判るような描写が交じっているのだ。それを考えれば、追い詰められていたであろうエルツァン島内探索時の記述に、どれ程の信憑性があるのか甚だ疑問だった。
と、【NAME】はカール・シュミットの手記に対してそんな評価を下していたのだが。
「いや、それ程軽んじるものでもないんじゃないかな。個人的には、かなり参考になる部分もある手記だと思うよ」
二大陸に名を轟かせる高名な冒険家殿は、そんなどうしようもない筈の手記に有り難い擁護の言葉を下さったのだ。
意外、と驚く【NAME】に、オリオールは少し思案するように顎に手を当てて、
「むしろ、気に入っていると言っても良いかもしれないな。強い功名心と探求心、それに状況がどれだけ悪化しようとも諦めない意志を感じる。それは僕らのような職種の人間にとってはとても重要で、そして好ましい素質だよ。このカールという人はかなり良い探検家だったんじゃないかな」
と、想像以上の高評価なのだが、【NAME】からすると首を捻らざるを得ない。少なくとも、手記に関しての部分は納得しがたいものがあった。
――序盤はまだしも、後半以降については弁護のしようがないだろう。まず読めないし、意味判らないし。
そんな【NAME】に対し、オリオールは手にした手記をぺらぺらと捲りながら、
「そうでもないと思うがね。例えば……こことか」
開かれた頁は、奇っ怪な図形が頁一杯に描かれたもの。訳判りません、と降参の諸手を挙げた【NAME】に、
「これは恐らく通った道筋のメモだろうね。二頁ほど前に、新しい場所に入った事と、犠牲者の名前……後これは追跡者、逃亡、かな? そうあるから、続く頁は多分逃げながら辿ったであろうルートを彼なりの方法で綴った……何?」
「…………」
いや、もういいです、と【NAME】は肩を竦めてオリオールから視線を外す。
ここは流石冒険家、同業の思考を読むのはお手の物、と感心するところなのだろうか。それとも単にこちらの察しが悪いだけなのだろうか。出来れば前者であって欲しいなぁと願いつつ、【NAME】は話を変えるべく改めて訊ねる。
――結局、自分達は今、具体的に何を探して海岸を歩いているのか、と。
その問いに、オリオールは簡潔に答えてくれた
「探しているのは、船の残骸だ。それも、古いもの。例えばそう、これくらいの年代のね」
言って、オリオールは手にした手記を軽く上下に振ってみせる。
それがどういう意味なのかくらいは【NAME】にも判る。オリオールが海岸で探しているのは、つまりフローリア諸島が発見され、島々の調査や入植が始まろうとしていた頃に、エルツァンを覆い護っていた結界を幸運にも潜り抜ける事に成功した探検隊――カール・シュミット達が乗っていたであろう船の残骸だったのだ。
「そもそも、だ。イェア嬢から聞いた話によると、このカール・シュミットの手記は、当たり前の話ではあるんだけど最初は至極信憑性の薄いものとして取り扱われていたらしいんだ。昔はカール・シュミットの手記ではなく、“夢日記”とか呼ばれていたらしい。夢、妄想の類だとね」
話しながら、【NAME】達はざくざくと海岸を歩く。常駐軍の陣はそろそろ目前に近い位置だが、立ち寄ることはしない。目指すは陣を挟んだ反対側の海岸だ。
「何せ当時は……いや、【NAME】が神形器で干渉をするごく最近まで、エルツァンの結界を越えて島に上陸するなんて到底不可能と言われていたらしい。そんなところへ行って帰ってきたと主張する重傷の探検家が現れたところで、そうそう信用される筈がない。しかも証拠となるのは、彼が所持していた手記のみだというのだからどうしようもない。カールは自分の船も、仲間達も、何もかも失って、手記と身一つでアノーレの海岸に流れ着いたと、そう主張していたからね」
陣地を通り過ぎる際、警邏や海に用事がある兵士達とすれ違う。既に【NAME】もオリオールも大半の兵士達とは顔合わせは済んでいる。軽く目礼や身振りで合図し、別れる。
陣を離れて、挟んで逆側の浜辺へと入った。そこで、【NAME】はふと思いついた疑問を口にする。
カール・シュミットという探検家は一人エルツァンを脱出し、生還することに成功したという。
ならば、それからの彼の人生はどういうものだったのだろうか?
そんな素朴な問いに、オリオールは兵士達に向けて浮かべていた笑みをすっと消し、
「残念ながら、アノーレ漂着時に負っていた傷が元で早くに亡くなったそうだよ。エルツァン島探索についても結局認められる事はなく、カール・シュミットは身も心も病んだまま、身寄りも知人もいない場所で一人でね。その後、カール・シュミットの手記は本国の学士筋から相応の信憑性があるとの評価を受けて、彼がエルツァンに辿り着いたという話もある程度は信じられるようになったのだそうだけど、それでも確かとされた訳ではなく、加えて言えばカール当人が認められぬ失意のまま亡くなった事にもかわりはない」
「…………」
手記の中、序文では意気盛んな文章を綴っていた人物が、そのような末路を辿る。何とも無常な結末だ。
「一人で孤独に亡くなった。それは、探検家や冒険家なんてものを生業にしている人間ならばある程度覚悟はしている事だとは思う。けれど――自分が確かにある場所へ、誰も到達していなかった場所へと至った事。それを誰にも信じてもらえなかったという事実は、本当に同情せざるを得ない。未知の場所へと赴くとき、そこで得られる経験は確かに自分一人だけのものだ。それがあれば他人に認められなくとも構わない。そういう類の人達も居るだろう。僕も、どちらかといえばその部類だ。けれど、他人に認められたいと、そう訴えてた人の声が、けれども誰にも届かなかった。それは凄く悲しい事だと思う」
小さな嘆息が、隣を歩く男の口から溢れる。
「だから、今僕がこうして、自分の冒険心を満たすと共に、カール・シュミットという人物が記した足跡を辿り、彼が経験したと記した事柄が本当であるのか。それを確認したいと考えている。取り敢えずその手始めが、今回の船の残骸探し、という訳なのだけど……」
そうして言葉を区切り、オリオールが足を止めた場所は、予定の“浜”一帯だ。
「カール・シュミットが上陸した場所についての記述は本当に僅かだ。島の恐らくは南側から結界に触れたこと。船は破壊され、その残骸に掴まる形でエルツァンの砂浜に打ち上げられたこと。荷物の殆どはその時失われたこと。ヒントとなるのは精々この程度か」
エルツァンの南側から突入し、岸に流されたというのなら、【NAME】達がエルツァンへと侵入した経路と殆ど変わらないという事になる。つまり、もしカール・シュミットの手記が真実であるならば、調査隊の陣地周囲に広がる海岸の何処か、それも砂浜となっているどこかという事だ。東西の海岸線の内、砂浜となっている場所は幾つかある。その中で、オリオールは今いる“浜”に狙いをつけていた
その理由はといえば、
「エルツァン周辺、特に境界内の陣地周辺の潮流についてはかなり豊富な情報が既に纏められてるからね。それにほら、【NAME】、あれが見えるかい?」
言って、オリオールは沖の方向を指差す。
【NAME】が彼の指し示した場所を見ると、そこには海の中から一本。細く巨大な柱のようなものが上へと突き出ているのが見えた。
岸からその柱まで大凡で300メートルほどはあるだろうか。それなりに距離があるため、柱の大きさは正確には読み取れないが、恐らくは高さ30メートル、太さ5メートルは超えているであろう代物だ。
見たところ、自然物ではなく何者かの手による人工物に見えるが――推測するならば“芯なる時代”に造られた遺跡の一種なのだろうか?
「さて、そこまでは判らないけれど、聞くところによればエルツァン島の周囲にはあれと同じようなものが七本、等間隔で突き立ってるのだそうだ。それで、どうもあの柱が海流に影響を与えているらしくて……よしんば何かが流れ着くなら、ここの周辺になる可能性が一番高いとそう考えられるんだ」
と、オリオールが愛用の背嚢から取り出した紙束を見ながらそう言う。
さて、そう上手く見つかるものだろうか。
流石にこの広い浜辺で、古い船の残骸を探そうというのだ。もし残骸が残っていたとしても簡単には見つから――、
「あった」
――早いな!
と、思わず突っ込む間に、オリオールは岸からそれなりに離れた場所で無造作に積み上げられた木板の残骸を拾い上げる。
「何せ、荷物が海に流されたらしいからね。取り敢えずの拠点を作るのに使える材木をかき集める必要がある。ならば自分達が乗ってきた船の残骸は当然使うだろうし、そういった拠点を作るならば波に呑まれぬように海からはある程度距離を取り、しかし島内の亜獣を警戒して内陸には入りすぎない位置に集めようとする。それが丁度ここであった、と。……ふむ」
オリオールは手にした板きれの表と裏をじっと眺めて、
「間違いない。これは、人の手による加工品だ。そして、この腐蝕ぶりからして、僕等と一緒にエルツァンに入った常駐軍由来のものでもない、と。そして自然に流れ着くにしてはここは陸側すぎる。ならば導き出される結論は――この木材こそ、かのカール・シュミット探検隊が乗船していた船の残骸である」
誰に告げる風でもなくオリオールはそう言って、一つ深呼吸を置き、
「これで、カール・シュミットという探検家が、エルツァンという島に辿り着いた。その事実を、僕等は確かに知る事が出来たんだ」
・
「そうだ、【NAME】。僕からちょっとした提案があるのだけど」
陣へと戻る途中。木材の一つを手の中で転がしながら、オリオールは隣を歩く【NAME】にそう話しかけてきた。
一体何の話だろう。【NAME】が視線だけで問うと、
「先刻の通り、僕は軍の動きや……あと君の“鬼喰らいの鬼”討伐の役目とは別に、自分の“冒険家”としての活動を行うつもりだ。それは、さっき君から借りた手記。その主が辿った足跡を追い、確かめるという件が主となる」
既に手記は【NAME】の手に戻っている。オリオールはあの手記の全てを頭の中に記憶した、と言っていた。先程、手記の持ち主の名前すら忘れかけていた事を考えると俄に信じがたい話だが、本人がそう言い張るのだから、もうそれ以上こちらから言う事はない。次に忘れたので手記を見せてくれと言われても覚えてるから不要ですよね、と返すくらいだろう。
(……というか)
君の“鬼喰らいの鬼”討伐とは言うが、そもそもオリオールは東大陸の某かから彼の鬼――と同化した輩――を退治するためにやってきたのではなかったか? そちらを完全にほったらかして大丈夫なのだろうか?
ふと疑問に思い、その事を問い質すと、オリオールは「うむー」と露骨に視線を外し、
「……それに関しては、きっぱりと言わせてもらうなら僕の手には余るよ。所詮僕はしがない一冒険家でしかないしね。戦闘に関して言えば、せいぜい二流の腕前だ。大禍鬼のような大物相手ともなれば、殆ど力になれないだろう。元々、僕の手に負えないようなら手を引いても良いとも言われているしね。申し訳ないけれど、【NAME】の力で何とか蹴りをつけてほしい」
こちらに丸投げかーとも思うが、しかしオリオールの言う事にも一理はあるのだ。オリオールは冒険家としての知識や能力が優れているのは確かなのだが、本人が言うとおり、戦闘については他の同行者候補達より数段劣るというのも確かであるのだ。そんな彼に無理強いはし辛い。
「まあ、君が僕の助力を借りたいというのなら出来うる限りの努力はするけれどもね。……で、そう。話の続きだけれど、僕がそうして君に力を貸すように、君も気が向いたらで構わないのだけど、僕に力を貸してくれないだろうか。“冒険家”として挑む、エルツァンの旅に、ね」
ふむ、と【NAME】は考える。
それはつまり、オリオールと共に“鬼喰らいの鬼”の討伐を目指してエルツァンの奥地へ入り込むのではなく、エルツァン自体を探検しようという話なのだろう。今まで【NAME】がやってきたような旅と同じように、目指す地形に赴き、探索を行い、目的を果たして、そして帰還する。そんな旅だ。
「一応、先刻伝えたように、今回の僕の“冒険”の目的として、あの手記を据えようと思っている。過去のカール・シュミット氏が歩んだ軌跡を確かめる冒険だ。あの手記の記述については、ただ読むだけでは不可解な部分も多々あったからね。それを現地に赴く事で解き、補完し、それが本来どういうものであったのかを確かめる。そんな旅にしたいと思っている。特に、手記の後半部分についてはかなり引っかかるところもあるからね。その違和感の正体も確かめられたなら僥倖なのだけど。勿論、手記の流れ通りに進めるのが難しいことは判ってはいるから、ある程度は端折って進めるつもりだ」
そこでオリオールは言葉を切り、【NAME】の方を見る。
「という感じなんだけれど、どうだろうね?」
どう、と言われても中々答えづらく。【NAME】はうーむと声を上げて黙ってしまう。
オリオールの冒険。それに付き合うのは、普段ならば全く吝かではない。だが、今自分は“鬼喰らいの鬼”討伐の役目を任されている身だ。そんな自分が、彼の個人的な冒険とやらに時間を割いて良いのかどうか。
そんな【NAME】の迷いに対し、オリオールも「全くその通りではあるけどね」と苦笑する。
しかし、
「でも、僕の旅は実質的にはエルツァンの各地を回るものになると思う。それはつまりエルツァンに存在するという各独自地形に対して調査を事前に行って、“鬼喰らいの鬼”を目指す道筋についての知識を仕入れるという結果に繋がる。エルツァン島について何も知らない状態で、“鬼喰らいの鬼”を探して、ずんずん進む無茶なスタイルよりは、時間は掛かるけどより安全な手段にはなると思うのだけれど、どうかな?」
「…………」
目を閉じて、少しの逡巡。しかし、オリオールの発言が理に適っているのも判る。そして何より、【NAME】自身もオリオールが行う“冒険”とやらに興味が出てきた、という部分もあった。
一つ頷き、目を開く。そしてこちらの返事を待っていたオリオールに、【NAME】は承諾の答えを返した。
対し、オリオールは満足げな笑みで大きく頷き、
「そうか、ありがとう。素直に言ってしまうと、僕一人ではエルツァン島の亜獣相手は厳しいと思っていたところなんだ。だから君が力を貸してくれるというのは至極有り難い。――改めて、宜しく。」
伸ばされた手。【NAME】はそれを応えて強く握手を交わした。
「じゃあ陣に戻って、準備を整え次第、早速冒険に向かうとしようか」
そう晴れやかな様子で告げるオリオールに、【NAME】は最初の目的地、冒険の舞台となる場所は何処かと訊ねる。
「ふむ。では、まずここに向かってみようか」
オリオールの手がするりと伸びて、【NAME】がまだ手にしたままだった手記の頁を捲る。
一、二、四、八、十六。次々と捲られて、そして停止し開かれた頁には、塗り潰された黒の円形と、書き殴りの蚯蚓文字が乱雑に記されていた。
頁数からして恐らくはカール達の探索行の中盤。端々に書かれた文字はどれも読みづらく、唯一、【NAME】が解読する事が出来た文字列は、
「手記曰く、“紫の空と荒れ枯れた木々の元に広がる、雷気を帯びた死の大湖――カリッサ灼雷領域”へ」
真なる楽園 出会う幻、照明の証明
──カリッサ灼雷領域──
その一歩を踏み出した時。霧深い森が唐突に終わり、周囲の風景が一変した。
【NAME】達の眼前に広がっていたのは、草木の枯れた赤茶の土地と、離れた場所からでも感じられる程の強い雷気を放つ、巨大な湖だ。満ちる雷気は湖だけに留まらず場全体にまで溢れ、時折稲光が地上や空中へと駆け走る様は、見る者の危機感を否応なく煽った。
――このまま歩みを進めて良いのか。今すぐ踵を返すべきではないのか。
突如現れた異質な地形に、【NAME】は思わず身を硬直させるが、しかし【NAME】の後ろをついてきていた冒険家は、小さく口笛を吹くと、
「これはどうやら当たりのようだね」
躊躇う事も無く、飄々とした様子で【NAME】を追い抜き、禿げた大地に足を踏み入れる。
そんな彼を止めるべきかと一瞬迷い、【NAME】は頭を振る。躊躇のないオリオールの動きは恐らく正しい。確かに危険であるかもしれない。だが、ここで止まって、況してや戻ってどうするというのか。第一、目の前の光景には引っかかるものがある。思い出すのは、野営陣でオリオールから聞いた話。
「“紫の空と荒れ枯れた木々の元に広がる、雷気を帯びた死の大湖”――残念ながら空の方は雲に閉ざされて見えないが、あの湖を見る限り、ここが今回の目的地と、そう考えて良さそうだね」
オリオールの言葉に、【NAME】も頷く。
要素の大半は一致してる。ここが彼が求めていた“冒険”――探検家カール・シュミットが記した手記を検めるという旅の、最初の目的地である“カリッサ灼雷領域”なのだろう。
ならばここで怖じ気づくのは情けない。彼の“冒険”に付き合うと一度は決めたのだ。自分がするべきことは危険を避けることではなく、危険と向き合い、対処し、切り抜ける事だろう。
気持ちを切り替えて、【NAME】も赤色の地面に歩を進める。つい先程まで居た森とは、漂う空気の感触からして違う。足裏から感じる土の感触は僅かな粘りを帯びて、鼻には硫黄に似た臭いがまとわりつく。ランドリートなどでも土地概念の変質により大きく地形が変化している場所はあったが、こうも極端ではなかった。
オリオールは興味深げに周囲を見渡し、
「それぞれの場所が完全に独立し、独自の環境を構築している。状況としては“現出”に近いね」
“現出”。確か、暫く前に東大陸で発生したという現象だったか。
「うん。あちらは既存の土地に対して別の地形を上書きするような感じだったけれど、こっちはどうも……」
オリオールは背後、自分達が今まで歩いてきた霧の森へと振り返る。
【NAME】も釣られる形でそちらを見る。森と湖、その境はまるで線引きされたかのように明確だ。が、よくよく見ると、
「!?」
驚く。時折、向こう側に見える森の姿が霞み、消えるのだ。まるでそこには本来何も無いかのように、一瞬だけ空白の景色が過ぎる。直ぐにまた森の姿が見えるようにはなるのだが、不気味な現象である事には変わりない。
一体これは、とオリオールの方へと振り返るが、彼は肩を小さく竦めて、
「流石の僕も、はっきりどういう事かと答えられないよ。ただ……そうだね。カール・シュミット氏の手記によれば、本来この“カリッサ灼雷領域”には、野営陣の西の浜から繋がる“ロームフーネ無空峡谷”から移動できたそうだ。だが、僕等が通ってきた“森”は……」
野営陣の東。東エルツァン海岸線から内陸へと入った先に存在していた“ナリア・バータ霧眩森林”から、自分達はこの場所へとやってきた。西と東。そのどちらの地形からも辿り着けるというのなら、“湖”はその中間にあり、自分達は森を西方向へと進んだと考えるのが妥当だが。
「西に進んだ記憶、あるかい?」
はっきり言ってしまえばない。そもそも方角が明確に判るような状況でもなかったからだ。茂る木々と深い霧。方位を知る手がかりは碌に無い状態での手探りの移動だ。西に進んでいたなど断言できない。
だが、結果として“湖”に出たのだから、自分達は西方向に進んでいたとするのはそう間違ってはいない筈だ。
そう言う【NAME】に、オリオールは一度頷きつつも、
「ただそれは“谷”から見て“湖”が東方向にあればこそ、だよね。残念ながら、手記によれば“湖”は“谷”を北西側に抜けた先にあった、との事らしい」
「…………」
そんな事書いてあったか、と手記を取り出しページを捲る。
“ロームフーネ無空峡谷”についての記述は“ナリア・バータ霧眩森林”と同様、手記の前半にある。この辺りの記述内容はまだ日誌に近い体裁を保っており、カールによる地形についての考察、推論に突飛な飛躍が多いものの、後半と比べれば至極まとも。特に今、こうしてエルツァンに居る自分達が眼前の状況と照らし合わせて読めば、何が書かれているのか理解するのは容易い。
直接的に北西と書かれてはいない。だが、カール達の“谷”での活動の記録と、そして自分達が知る情報。それを掛け合わせれば、確かにカール達は北西方向から谷を脱出し、雷の湖に辿り着いていた事が判る。
しかしそれでは、手記の記述と、自分達が辿った状況が噛み合わない。それ程大きな矛盾ではなく、無理に理屈をつけようとすればつけられてしまう程度の事ではあるのだが、やはりどうもしっくり来ない。
どこか情報に誤りがあるのか、それとも何かを見落としているのか。
「取り敢えず判るのは、地形同士の繋がりがおかしいって事くらいだね。もしかしたら、先刻僕達は“森”から“湖”へ移動する事が出来たけれど、もう移動出来なくなってるという可能性もある。例えば今見たような、森の姿がふとした拍子に消えた瞬間、とかね」
「…………」
言われてみれば、そうだ。
森が霞んで消えて、空白となったあの瞬間。もしそのタイミングでひょいと境界を渡っていたなら、一体どうなるのか。
ごく普通に森の中へと戻るのか。それとも何も無い場所に放り出されるのか。はたまたオリオールの言うように移動すること自体が?
「試してみたい、という好奇心はあるけれど……僕のこれまでの経験では、こういう類の事象に対して迂闊に踏み込むと、大抵取り返しのつかない展開になりがちだ。止めておいた方が利口だろうね」
言って、オリオールは背後の森から視線を外すと、【NAME】に目配せしてから慎重に歩き出す。
「ただここで覚えておくべきは、手記と実際に僕等が歩んだ道筋に何らかの矛盾が生じたとしても、それが即座に手記の虚言であるとは決めつけられない、という事だろうか。イェア嬢も言っていたんだが、どうもエルツァンという島は、その在り方からして不安定な代物のように思えるんだ。だから例えば、カール・シュミットが上陸した時には事実であった事柄が、年月を経た今となっては嘘となってしまっている。そんな事も、どうも最初に想像していたよりも多くありそうな気がするね」
それは、オリオールの“冒険”の目的を考えれば、なかなか厄介な状況に思えるが。
数歩遅れる形となった【NAME】からの感想に、オリオールは「全くだよ」と笑い、
「だからこの“湖”での調査も、ある程度割り切って行うつもりだ。そもそも僕等に出来るのは見て、探して、そして感じる事くらいだ。本当は色々と追っていきたい部分はあるし、この湖について独自で調べてみたい気持ちもあるけれど……今回は、目的を一つだけに絞ろうと思っている」
間を置くように、オリオールは小さく息をつく。【NAME】が視線だけで続きを促すと、冒険家は正面に広がる湖を眺めながら、ぽつりと溢すように答えた。
「――カール・シュミットがこの場所に抱いた心残り。それを、僕等の目で確かめようと思う」
・
カール・シュミットの心残り。それはこの場所で失った仲間についてだった。
彼が残した手記。カリッサ灼雷領域について記述されていた頁は、湖についての大雑把な地図と各所に残されたメモ書きという体裁であったが、その後の頁には湖を離れる事になった顛末と、その後悔についてが記されていた。
湖に関するメモは走り書きに近く、【NAME】にはその殆どが読めないような代物だった。しかし、湖から脱した後に書かれたのであろう、続く頁に記述された文章はその限りではなく、曰く。
「時間は夜。畔から離れた場所で休息を取っていた探検隊の面々は、何処かから響いてきた悲鳴で目を覚ます。灯りを手に天幕から飛び出したカール達は、夜番を務めていた面子の姿が無い事、そして先刻聞こえた声がその人物――カリッサのものである事に気づく。直ぐに彼女を探そうとしたが、しかしその瞬間、探検隊は何処からかやってきた亜獣による襲撃を受ける。亜獣はそれまで湖周辺にて遭遇した事のないもので、更には運悪く襲撃を受けた直後に灯りを失ったカール達は、視界不良の中、正体もはっきりと判らない亜獣達の攻撃から逃れる事に専念する他無く、そのまま這々の体で湖を脱出する。カリッサを残して、ね」
オリオールは開いていた頁を閉じ、手記をこちらに差し出す。それを受け取りながら、【NAME】はつまりと考える。
カール・シュミットの後悔。それは、ここに自分の部下を一人置き去りにしたという点か。
「色々と自己弁護やカリッサを含めた部下達への愚痴は書き込まれているが、根っこのところはそうだね。もしかしたら、自分達が逃げ出さなければ彼女と無事合流できたのかもしれない。カール氏はそう考えていたようだ。少なくとも、逃げ出した事で彼女が生存出来る道を完全に閉ざしてしまった、とね。……この頃の探検隊はまだ致命的な破綻を迎える前だから、仲間を悼むという気持ちが残っているようだよ」
若干皮肉げな表情でオリオールはそう語る。
カール・シュミットの探検隊は、最終的にはリーダー以外は全滅という末路を辿る。オリオールの言う通り、そういった失った仲間についての記述は、手記の全体を通してみるとあまり多くない。探検隊にとって、仲間を失う事はごく有り触れた事象でしかなくなってしまい、カール達自身も如何にこの異質な世界から生き延びるかに思考の全てを費やす他無く、既に脱落した者達について考える余裕など失われていくからだ。
ふむ、【NAME】は頷き、そして少しの間を置いて首を捻る。
それは判ったが、ではどうすれば良いのだろうか? 先刻オリオールはカール・シュミットの心残りを確かめる、と言ってはいたが、具体的には一体何を。そもそも、カールの探検隊がエルツァンを訪れていたのははるか過去だ。今、こうしてやってきた自分達に何が出来るというのか。
そんな【NAME】の疑問に、オリオールは苦い表情で頷き、
「うん。出来る事はない。けれど、確かめる事は可能だ。例えば、カリッサ女史の結末。そして突然現れたという見知らぬ亜獣の正体、とかね。流石に、何故カリッサ女史が仲間達が居る天幕から離れていたのかまでは難しいだろうけど、彼女の遺品程度は見つけられるんじゃないかと思っている。出来るなら、カール氏の代わりに弔いをしてあげたい。今回の僕の“冒険”は、エルツァンの島を探索するというよりも、カール氏の足跡を追うという側面の方が強い。だから、彼が見たものを自分達が確かめるのは勿論の事、彼が見損ねたもの、取り落としてしまったものも、可能ならば拾い上げていきたいんだ」
成る程、とは思うものの、オリオールが上げた二点だけでも中々に面倒な仕事であるように思えた。
カール・シュミットがエルツァンを訪れていたのはフローリアの調査が始まった初期から中期にかけてだ。数年、下手をすれば十年近く前の話となる。果たしてその痕跡が今も残っているのかどうか。以前、浜辺にてカール達が使ったと思しき船の残骸を見つける事は出来たが、今回は個人の痕跡。それも行方不明となった者の痕跡だ。容易く見つけられるとは到底思えない。
見知らぬ亜獣の正体についても同様だ。カール達にとっての見知らぬ亜獣を探す――それはつまり、彼等が把握していた亜獣についてを理解していなければならない訳だ。しかしそのような事は、知りようがない気がする。【NAME】が読めなかった湖についてのメモ書きに、その辺りの事も記述されているのなら話は別だが。
「いや、残念ながら湖で遭遇した亜獣については殆ど書かれてはいないね。あるにはあるが、せいぜいが、ほら、あんな感じの」
ふと、オリオールが一方を指差す。
その指が示す方へと視線を移した【NAME】は、こちらに向かって猛然と進んでくる亜獣達の群れを見た。
「雷気を帯びている以外は、これといった特徴もない亜獣だね。勿論、エルツァンに住む亜獣だ。その力はかなりものだろうけれど、しかし強力であるかと言われるとそこまででもない。そんな存在だ」
などと、暢気に話をしている場合でもないだろう。迫る亜獣達は、明らかにこちらを敵、若しくは獲物と認識している。
【NAME】が一歩前に出て武器を構える。オリオールも合わせるように腰の後ろに差した小剣を引き抜きながら、
「カール氏とその仲間達は色々と問題はあれども、その戦闘技量においては相応のものを持っていたようだ。手記の中では敗北し、逃げ回るという結末ばかりであったようだけれども、ああいった並程度の亜獣達相手ならば、難なく退けていたんだろう。僕等も、負けないように頑張るとしよう」
言葉が終わる。その瞬間、オリオールが身を深く屈める。飛び出す為の前動作。それを察し、【NAME】も迫る亜獣達目掛けて勢い良く踏み込んだ。
探索の基本は、まず拠点となる場所の確保である。オリオールはそう語った。
【NAME】とオリオールはまず近隣を見て回り、地面が比較的しっかりしていて、視界が広く、しかし自分達の居場所は周囲から物陰となりうる。そんな地点を探す事にした。湖からある程度離れた場所、という点も外せない。何故なら時折湖から迸る稲光が、湖の外側、陸地の表面を激しく撫でていくのを確認していたからだ。いつあんな雷の一撃が襲ってくるかわからない場所に拠点を構える訳にはいかない。
途中、遭遇する亜獣達を蹴散らしながら進む。カリッサの湖周辺の土地は殆どが泥濘んでいて、適した場所を探し当てるのにはかなり苦労しそうだ、という【NAME】達の予想に反し、そこは意外と早く見つかった。
場所は地面にめり込んだ岩の上面。更に二方向、地中から地表へと別の大岩が伸びていて、周囲からの視線を多少防いでくれていた。岩に触れたままとなる環境は体温を奪われやすく、拠点として考えるとあまり良い場所ではない。だが、赤く禿げた泥濘の地面から漂う臭気はあまり心地のよいものではなく、極力そこに接していたくないという欲求の方が勝った形だ。
二辺の岩の出っ張りや周辺で確保した枯れ木などを使って覆いを張り、大荷物などをその下に置いて取り敢えずの身軽となる。他者というものが存在しないであろうこの地では盗難に気を配る必要がないのが有り難い。勿論、亜獣に荷物を漁られる可能性もあるため、その点だけは考慮する必要がありそうだが。
「【NAME】は、あまりこういった作法の経験はないのかい?」
軽い新鮮さを感じていたのを見抜かれたのか。
岩の上。座して粗い紙を広げていたオリオールからの問いに、【NAME】は頷く。【NAME】のこれまでの旅は、ただ突き進み、到達し、そして帰還する。そんなものだった。何処かに腰を下ろし、そこを基点にじっくりと地形を探索しようとする。そんなスタイルは取った記憶が殆どない。
【NAME】の答えに、オリオールは呆れとも感心ともつかない笑みを浮かべ、
「それはそれで凄いとは思うけれどもね。身一つであらゆる場所を突き進める。そんな自信の表れだろうから。とはいえ、僕のような人間がついていくには少々厳しいのも確かだ。特に捜し物となるとね。悪いけれど、今回は【NAME】も僕のやり方に合わせてくれると助かるよ」
別段不服があるという訳ではないのだ。勿論、と【NAME】は頷き、そしてここからの動きについてを訊ねる。
対して、オリオールは顎に手をやり小さく唸ると、
「んー、定番だとここを基点に周辺地形を確認していって地図作成……という流れになるんだけど、エルツァンという島内に限っていえば、この方法はどうなんだろうね」
何か、気になる点でもあるのだろうか。
「気になる、というより、意味があるのかどうか、といった処だね。イェア嬢が指揮している常駐軍の方でも、エルツァンの探索調査を進めているのは【NAME】も知っているよね」
頷く。イェアは【NAME】に“鬼喰らいの鬼”討伐の役目を託してはいたが、かといって全てを投げ出すというつもりはさらさらなく、彼女達の出来る範囲でエルツァンという秘境へ手を伸ばそうとしている。自分だって軍の陣地に滞在していたのだ、それくらいは流石に判っている。
「うん。それで、軍が調査で得た情報は、僕もいくつか貰ってはいたのだけれど、それを見た限りで言うならば、エルツァンという場所では、どうも地形自体が少なからず変化するものらしい」
「……?」
言っている意味が今ひとつ理解出来ず、【NAME】は怪訝と眉根を寄せる。
地形が変化する、というのは多かれ少なかれどこでも有り得る自然な現象だと思うのだが。
そんな【NAME】の内心の感想を読み取ったのか、「いやいやそういう意味ではなくて、ね」とオリオールは首を振り、
「例えばそうだね。誰かがとある場所で川を見つけたとしよう。彼はそこに川があると記憶してその場を離れ、陣地に帰って報告した。その後、彼は大して間も開けず、自分が歩いたルートをそのまま辿って川があった場所へと移動してみた。けれどもそこにあった筈の川は跡形もなくなっていて、単なる岩場になっていた。……そんな感じでね」
「…………」
それは、確かに異常である。成る程、地形が変化するとはそういう意味か。
だが、とも思う。
この島にやってきてから自分達が拠点としていた海近くの平地や、東西に延びる海岸。そこで、オリオールが言うような大きな地形の変化とやらを感じた記憶は一切無かった。
それに、海岸に隣接していたナリア・バータ霧眩森林やロームフーネ無空峡谷。そして今自分達がいるカリッサ灼雷領域についても、それらの名称の元となったのであろう“森”や“谷”、“湖”については変化無く存在しているように思える。
そんな【NAME】の指摘に、オリオールは素直に頷く。
「うん、それについては全くその通りだ。イェア嬢とも話してはいたんだけれど、どうも今僕が言った変化はエルツァン島の内陸に存在している土地――さっき僕等がここに来るときに通ったような境界で独立している場所に限定された話でね。外側、少なくとも海に面した場所においては、その特性が発揮されていないようなんだ。後、土地それぞれが持つ根っことも言える部分。そこについても不変であるらしい。つまりナリア・バータは霧深い森であり、ロームフーネは空を塞がれた峡谷であり、そしてここカリッサは」
赤茶け禿げた土地の中央に、雷気を帯びた大湖を持つ場所である、と。
「その要素は変わらないまま、けれども細部は揺らぐように変化する。その揺らぎは、主に長短――地形自体の伸縮に影響する場合が多いようだけれど、中には先程上げた例のように、地形自体が別物になっている場合もあるようだね」
はぁ、と【NAME】は思わず気の抜けた返事をしてしまう。
無茶苦茶な話もあったものだとは思うが、確かに、オリオールの言が本当であるのならば、詳細な地図など作ったところで探索の役には殆ど立つまい。何せ、それが短時間で変化してしまうのだから。
だが、気になるのはオリオールが目の前に広げている紙だ。彼は先程から片手に筆を持ち、大小様々な模様と文字をその紙の上に走らせていた。それは【NAME】からすると、【NAME】達がこの“湖”に侵入してからこの拠点と据えた岩の上へとやってくるまでの間に確認した地形や、遭遇した亜獣に関する情報に見えるのだが。
それに先刻の話。地形の細かい変化とやらが頻繁に発生しているのであれば、遙か過去にこの地に訪れた筈のカール達の痕跡や、その仲間の遺物がそのまま残っている可能性は極めて低いのではないか? これは今回の“冒険”においてはかなり致命的な要素であるように思える。
対し、オリオールはそれを否定すること無く、大きく頷く。
「それも全くもってその通り。ただ、望みも一応あってね。この土地変化の発生については、どうもある程度のルールがあるのではないか、というのがイェア嬢の推測なんだ。……そうだね、先刻の例をそのまま使うとすると、例えばある人物がそこに小川が存在したことを確認したとする。この時、その人物がそこに居る限り、その地形には変化は発生しない。彼がその場所から少し離れてから戻ってきたとしても恐らくは同様。けれど、彼が一度その土地自体――つまりさっき僕等が通ったような土地と土地を区切る境界を越えた場合はその限りではない、という風にね」
……つまり、今、自分達の状況に置き換えるとするならば、この“湖”から外へ、例えば隣接する筈の“森”へと移動しない限りは、土地の状態は変化しないままである、と?
「仮説でしかないけどね。正直、僕には今ひとつ理解が難しい話であったけれども、イェア嬢が言うには、エルツァンの土地にとって外部からの侵入者というのは完全な異物であり、同時に種でもある、と。だからその存在を受け入れる際に世界は形を変えて、その存在が世界を観察する事で状態が固定されるのでは……とかどうとか、そんな話だったか」
「…………」
何を言いたいのかさっぱり判らない。というかどんな理屈だ。
そんな【NAME】の内心はそのまま表情に出ていたらしく、【NAME】の顔を見たオリオールは少し吹きだし、
「僕からしても似たような感想だけれど、まぁ、何が言いたいかというと、その理屈を信じるなら、この“湖”はカール氏が去ってから、殆ど形を変えていない筈だって話だよ。これが望み、という訳だ」
そうだ。エルツァンの外部からやってきたのはカール達を除けば自分達と軍だけ。そして軍の調査の手は未だ“谷”と“森”までしか伸びていない。つまり、この“湖”に限っていえば、侵入者は恐らく自分とオリオールだけ。ならば変化は一度だ。勿論その一度の変化で捜し物が失われている可能性はあるが、しかしそれは高い確率ではない筈だ、と。
「加えていえば、僕等がここから他の土地へと移動しない限りは、この場所の地図を細かく作っていくのも無駄にはならない。もっとも、たった一度きりの探索にしか役に立たない使い捨てだ。それを考慮すれば、やはり地図を作るにしても、調査の状況を埋める程度の大雑把なもので良いとは思うけれどもね。その点、カール氏が手記に綴ったアレは、絶妙の代物だったとは思うよ」
うんうんと頷くオリオール。彼は広げていた紙を軽く払ってから丸め、立ち上がる。
「……さて、ではそろそろ捜索、始めようか。結局は足を使って、まずはカール氏達が襲われたという場所を探すことになる。そこが判れば、後はその周辺を地道に捜索すればカリッサ女史の痕跡を見つける事も出来る筈だよ」
問題は、そこを見つけられるかどうか。未だ変わらずこの“湖”に存在しているかどうか、か。
「それに関しては祈るしかないね。幸い、探検隊が休息を取っていたという場所についての記述はそれなりにある。カリッサ灼雷領域の中では珍しい林の中だそうだ。もっとも、林とはいえ枯れ木のものでらしいけどね。後、湖からはそれ程離れていない場所でもあるようだね」
禿げた土地が大半のこの場所で、その情報は大きな手がかりとなり得る。湖畔に沿って歩いて行けば何れ見つけられるという事だ。
だが雷を帯びた湖の傍を歩くのは相応の危険があり、更にはそれで湖を一周して見つからなかった場合は、先刻の懸念の通り、カール達が休息で使った場所自体が無くなっているという事になる。
「まぁ、ここであれこれと考えていても仕方無い。何はともあれ、まずは動くとしよう。そうしなければ、状況は何も進まないからね」
行こうか、という促しに従い、【NAME】とオリオールは大湖周辺にある筈の林を求めて歩き出した。
・
捜索を始めてまず感じたのは、湖自体の大きさだ。体感にして数時間。距離にして大凡10キロ以上を軽く歩いた筈なのだが、湖を一周どころか半周すらしていないように感じる。その基準は湖の中央付近に見える小さな島の影。そこから聳える巨大な樹が造り出すシルエットからの推測である。到底頼りにならない曖昧な基準ではあるが、そう間違ってはいない筈だという実感はあった。オリオールも似たような認識であるらしい。
「せめて、太陽でも見えていたならもう少しまともな判断もできるのだがね」
恨めしげに空を見上げるオリオール。曇天は変わらず、分厚い雲が太陽の位置を完全に隠している。
「……にしても、この“湖”にやってきて、拠点を作って、そこからこうして捜索を始めて、もう結構な時間が経過してる筈なんだが、天気は兎も角として、明るさまでこうも変わらないとなると、あの話についても信憑性を帯びてきたな」
一体何の事だ。
【NAME】の疑問に、オリオールは空を見上げたまま、
「先刻した話の続きになるけど、エルツァン内陸に存在する土地は、それぞれを境にして本当の意味で独立した、別個の世界として構築されているのかもしれない。そしてそれは、天候はおろか、天行すらも独立して動いているのでは、という話さ。少なくとも軍の調査では二箇所。“森”は夜という概念が無く、“谷”は昼夜の周期が普通よりも長いのではないか、という調査結果が上がってきている」
「…………」
無茶苦茶な話だ、とは思うが、この“湖”に来てから一向に周囲が暗くなる気配が無い事を考えると、少なくともこの場所に於いては昼間が常よりも長いように思える。もしかしたらここも、“森”と同様に夜が存在しないのだろうか。
「いや、それはないとは思う。何せ、カール氏達が襲われたというのが」
ああ、そういえば夜に、という話であったか。
「出来れば余裕がある内に湖を一周するか、一度諦めて拠点に戻るかを判断すべきなのだろうけれど……難しいね。多分半分に近いところまでは移動しているとは思うんだが。……【NAME】は、どう思う?」
立ち止まってのオリオールの問いに、数歩前を進んでいた【NAME】も歩を止めて、振り返りながら考える。
オリオールの言う通り、判断に悩むところだ。疲れについてはまだ気にするレベルには達していないが、この先の道程がどの程度あるのかが読み切れないため、このまま進んでいいのかの判断がつかない。湖が単なる円形であるならば話はまだ簡単なのだが、距離を離しつつも岸沿いに移動している事を考えると、そのうねり方次第で移動距離は大きく変化するからだ。
――どうしたものかな。
思い、何か判断の材料となる情報はないかと【NAME】は辺りを何気なく見回して、
「――――」
こちらを向くオリオール。その背後に見える湖の岸に、ぽつんと。
一つの人影が立っているのが見えたのだ。
「……? 【NAME】、どうかしたかい? 僕の顔に何か?」
口を開けて驚きのまま固まった【NAME】。自分に向けてその顔を向けているのかと、オリオールは訝しげにぺちぺちと己の頬を摩る。
そんなオリオールに【NAME】は呆けた顔のまま左右に首を振り、ゆっくりと背後、湖畔に見える人影を指差す。
オリオールはそれに従い背後へと振り返り、
「……人?」
呟く声に、【NAME】は頷く。
そこに立っていたのは確かに人だった。湖の岸までの距離は歩幅にして大凡100歩分。詳細を見分けられるほどの近さではないが、しかし人の姿である事を確かめられない程の遠さでもない。
人影はこちらに背を向けて、湖を覗き込んでは時折妙な動きで何かを避けるように飛び退り、しかしまた湖の傍へと戻るという動作を繰り返している。
「「…………」」
暫くその様子を観察してから、【NAME】とオリオールは思わず顔を見合わせる。
あれは恐らく人だ。亜獣ではない筈。人型亜獣という可能性もあるが、遠目から見えるその背中、纏う衣服は人のそれであり、また人の姿を装う上位存在特有の強烈な存在感、威圧感というものも感じない。気配という点で語るなら、むしろ普通の人よりも小さい気がする。何せ、その存在に気づいたのがついさっきであるのがその証拠だ。
だが、しかしそれは奇妙である。
ここに人は居ない筈だ。エルツァンに上陸した人間は、部外者である自分とオリオール、そしてキヴェンティ達以外は皆軍人であり、その装備は軍配備のものだ。だが、遠くに見えるその人影の装備は、軍のものでも、況してやキヴェンティ達のものでもない。強いて言うならば、直ぐ傍に立つオリオールが身につけているものに近い。
ならば一体、あれは何者なのか。
「…………」
【NAME】とオリオールは、同時に視線を遠くに見える人影に戻す。
影は未だに、先刻と似たような行動を繰り返していた。湖を覗き込み、そして跳ねるように後ろに下がって、また湖の傍に戻っていく。
「――うん?」
その瞬間、オリオールが訝しげな声を上げて、遠く目を凝らす。
人影がまた湖に近付き、覗き込み、そして跳ねて後ろに下がって、
「あ」
オリオールが何に対して訝しんだのか。【NAME】もそれに気づいた。
後ろに跳ねて、湖の傍へと戻る。その二つの動作を繋ぐ際、人影の姿が霞み、まるで瞬間移動したかのように立ち位置と姿勢を変化させていたのだ。
そして行われる動きは、ぴったり先刻と全く同じ動作。人影は先程から延々とその動きを繰り返していた。
暫くそれを眺めた後、まずオリオールが身体の緊張を解き、【NAME】もそれに倣う。
何となく、判る。あれは恐らく、危険な存在ではない。そして恐らく、重要な存在でもない。あれは只の、
「……幻影?」
【NAME】の呟きに、オリオールも頷く。
「確かめてみよう。湖の傍に近づくのは危険ではあるけれど、今は踏み込む場面だ」
湖から走る雷は、今も時折陸へと向けて伸びている。それに警戒しながら、【NAME】とオリオールは湖畔で同じ動作を繰り返す人影に近付いた。
直ぐ傍まで来れば、もう見間違う事はなかった。
それは、人の姿ではあったが、しかし人ではないものだ。
まず、その人物には影がなかった。姿は僅かに透けていて、身体の輪郭は時折激しくぶれる。そして湖に近付き、覗き込み、離れる。この一連の動作の、終わりと始まりが繋がっていない。
その在り方は、肉体を失ったものの存在自体は未だ現世に残っている、所謂概念存在として残った人の残滓――幽霊に近いものに見えたが、近いだけで同一ではない。
ここにはきっと、何も無い。ただ繰り返し、同じ動きを取るだけの幻の像でしかないと。そう感じた。
「【NAME】、どう思う?」
どう、と言われても、曖昧すぎて何とも答えづらい。
答えづらいが、しかし直ぐ傍で自分達の存在を全く無視し、同じ動きを延々と繰り返す姿。それを見て、推測できる事が一つだけある。
どういう理屈で、何が原因で、幻の像がここに残っているのかは判らない。
判らないが、この幻の像のモデルが誰であるのかは何となく察する事が出来た。
オリオールに良く似た、つまり一般的な探検家の装備を身に纏った男。小柄ではあるが、がっしりとした体つき。顔は僅かに痩けて、目はぎょろりと大きく。壮年を過ぎて、老境にも近づき始めているようにも見えるが、しかしその瞳の奥にはぎらぎらと、まるで若者のような熱意が滾っている。
多分、彼がそうなのだ。
この幻の主が、きっと、
「――カール・シュミット、なのか」
そうオリオールの呟く声が合図になったかのように。
幻は次第にその像を薄く霞ませて、空間に溶けるように消えていった。
──出会う幻、照明の証明──
以後。
【NAME】達は岸沿いに大湖を周回する間、幾度もその男の幻影を見る事となった。
ある時は武器を構え、【NAME】達には見えぬ何かと戦う姿を断片的に。
ある時は手記を持ち、立ち姿のまま何事かを手記に書き込む様子をそのままに。
幻影は【NAME】達が特定地点に一定距離まで近付くと生まれ、そしてある程度同じ動作を繰り返した後、消えていく。消えた幻影は、一度その場を離れた後、暫くの時間を置いて再度訪れるとまた発生する。その間隔は一定ではなく、また確実でもないらしく、数分程度の間でまた発生する事もあれば、かなりの時間を挟んでも幻影が再発生しない場所もあった。
それらの検証も続けながら湖を一周し終え、拠点に戻った【NAME】とオリオールは、一時の休息を挟んだ後、岩の上に地図を広げてそれを覗き込んでいた。
粗い紙に描かれているのは、湖の形状と、幻影を確認した地点や位置、情報などだ。
「……ふむ」
オリオールは小さく唸ると、指先を地図の上方へと動かす。
「幻の像が多く確認されているのは、今僕等が居る拠点を南側と考えた場合、その真逆。北側から西にかけてに集中しているね」
あの幻がカール・シュミットのものであり、そして幻が過去、彼がここで取った行動をそのまま再現しているというのならば、つまりカール達は湖の北から西側付近で活動していたという事になる。
「だけど、湖を一周した限りでは、手記にあったような林を見つける事は出来なかった」
“湖”は視界の良い場所で、視線を遮るものが殆ど無い。だからこそ、林の存在を見逃したという事は考えづらく、それが示すのは林自体が既に“湖”から消滅しているという事実だ。
それは最初に想定していた標が既に失われている事を表しており、本来ならば致命的とも言えるものだ。しかし今は、新たにカールの幻影という新たな目印を使って補う事が可能だった。
出現する幻影は、その全てが同一人物のものだった。一体何故、カールと思しき人物だけ、その行動が幻としてこの場所に残っているのか。その理由は全く理解できず、推測すらも出来ない状態であったが、しかし【NAME】達にとっては至極有り難い現象であるのは確かだ。
「となると、兎に角湖の北から西辺りに当たりを付けて歩き回るしかないか。……どうせなら、カール氏以外の幻影も現れてくれれば良かったのだけどな」
他の者達の幻影も現れてくれたならば、そしてその中にカリッサ女史のものがあれば、より発見も容易になったのだろうが。
「まぁ、そこまでねだるのも贅沢というものか。取り敢えずは今のところ確認出来ている幻影の中から、もっとも新しい――カール達が“湖”を離れる事になった事件に近いか、その場面を再現しているものを探し出して場所を絞り、彼等を襲ったという亜獣や、カリッサ女史の痕跡を探してみよう。……そういえば、【NAME】」
地図を覗きながら、途中見た幻影のなかでどれがもっとも新しいものなのかを考え込んでいた【NAME】は、名を呼ばれてふと顔を上げる。
「君、確か湖の中央にある島。あそこから何かを感じる、と言っていたっけ?」
言われて、ああ、と思い出す。
大湖の周囲を回る道中の間に幾度か。首から提げた飾りを伝い、小島の方から何らかの気配が漂ってくるのを感じていたのだ。それらはあの“鬼喰らいの鬼”や、他の大禍鬼が放っていたような確固たる陰の質を持つ気配ではなかったが、強く、歪な気配があの島から広がっているのを感じていた。
【NAME】がそう言うと、オリオールは小さく唸り、
「本来ならば、そちらの方も少しばかり探りを入れておくべきなのだろうけれど……、しかし、ねぇ」
呟いて、オリオールは視線を下方、広げられた地図へと落とす。
地図には湖の形状が大略に近い形ながら描かれており、中央に島らしき円がある。だが、湖の岸と島が繋がる線は存在していない。湖中央に浮かぶ島は正しく島であり、湖の岸から陸地で繋がっていないのだ。
漂う歪な気配。その正体を確かめるには、強烈な雷気が迸る湖中を泳ぐか、湖上を出来合いの船で渡るかの二択しかなく、そしてそのどちらも恐らくは自殺行為だった。
「今回はやはりそっちを調べるのは諦めて、最初の目的を達成する事を考えた方が良さそうだね」
それについては異論はない。幻影、という新たな要素が出てきたことで、【NAME】の興味もどちらかといえばカール・シュミットを追う方に向いていた。
「で、だ。僕の予想では、こことここ、そしてこの辺りで見た幻影が怪しい」
言ってオリオールが指し示したのは地図の北西。三点密集して発生していた幻影は、湖からかなり距離を取った場所にあり、地図に書き記されたメモによれば、幻影の一つはただ地面に座して、時折手に持った何かで地面を引っ掻くようにしながら、一点をじっと見つめている幻影。残る二つは、何かと戦っているような幻影だ。
「ここに残っていた幻影は、他の場所での戦闘の幻影とは少しばかり雰囲気が違ったように見えたんだが、【NAME】はどう思った?」
言われて、【NAME】は思い出そうと暫し眉根を寄せて考え込むが、果たしてどんなものだったか、いまいち上手く思い出せなかった。何せかなりの時間を歩き詰めて、幻影は数にして20近くを見たのだ。メモ書きだけでは直ぐに内容を思い出せるものではなかった。
そんな【NAME】の態度から悟ったのか、オリオールは苦笑しながら地図をくるりと丸め、
「では、またそこに行ってみようか。本当なら一度ここで夜を明かしてから、と考えていたんだが……」
オリオールはひょいと上方の覆いから顔を出して空を見る。未だ、曇り空は昼間の明るさを保ったままだ。
「けれど、少し陰りが出てきたようにも見えるね。この感じなら、あちら側に到着する丁度良いタイミングで日が暮れてくれそうだ」
いや、夜になってしまうのはまずいのではないだろうか。暗くなれば、探索行為は困難となり、亜獣との戦闘も不利に、危険になる。
そんな【NAME】の感想に、オリオールは「まあ普通ならそうなんだけれど」と笑い、
「ただ、気になる事があってね。カール氏達が襲撃されたという見知らぬ亜獣っていうのは、要するにその辺りに起因するのかな、とね」
そして【NAME】達は準備を整え、拠点を発った。
最小の荷物だけを持って出発した前回とは異なり、夜間での行動、休息も視野に置いた今回は荷物が幾分か増えていたが、道筋自体は既に一度辿ったものであったため行程自体はスムーズに進み、問題無く目的の場所に辿り着く。経過時間も大凡の予想通り、雲越しに差し込む光はかなり弱まっており、夜の気配が急速に迫り始めているのを【NAME】も感じる事が出来た。
「……それで、この幻影なのだけれども、どう思う?」
【NAME】とオリオールの前に生じた男の幻影は、先程から一定の動きを繰り返し、繰り返し行っている。
手にした何かを掲げて足早に歩きながら、辺りを懸命に見回して、しかし突然後方に仰け反り、尻餅を突き、そのまま逆の手でぶんぶんと何かを打ち払うような動きを見せながら後ずさる。そんな様子だ。
それは確かに、他の場所で見た戦闘時の幻影とは様子が異なるものだ。何というか、地に足がついていない、覚束ない様子なのだ。
これ以外にも一つ、既に別の幻影を見ていたが、それもこれと似たような態度だった。完全に慌てた風で、地面に蹴躓きながら走り逃げる。そんな幻影だ。
何故この二つだけ、こんなにも動きが悪いのだろうか。
その理由を探るように、【NAME】は目の前の幻影の動きを観察し、ああ、と気づく。
他の戦闘時らしき幻影と、今見た二つの幻影。その違いが判った。
前者の幻影は、しっかりと敵を見据え、それに対して攻撃や防御を行っているのに対し、後者の幻影は完全に視線が揺れて定まっていない。それが示すのは、
「敵が、見えていない?」
そう呟くと、オリオールは満足げに笑ってみせた。
「やはり、そう見えるよね。この幻と、さっきの幻。この二つでは、カール氏は完全に敵を見失っている。顔は探るように左右に振られて、武器を持っているであろう手も、闇雲に払うだけ。そして、こんな視線を遮るものが何も無い場所で何故敵を見失っているのか。それを考えれば、理由として思いつくのはあまり多くはない」
襲ってきた敵が透明の身体を持つものであった、という可能性もあるが、より妥当な予想はこうだろう。
――つまり、このカール氏は敵の姿を捉えられない程の暗闇の中で戦っているのだ、と。
そんな【NAME】の言葉に、深く頷くオリオール。
「この幻影のカール氏は、夜に亜獣との戦闘を行っていた。そしてカール氏が“湖”から逃亡することになった戦闘も、夜に発生したものだ。この二つを安易に繋げるのは短絡的かもしれない。だが、カール氏は相応の経験ある探検家だ。エルツァンのような危険な場所で、夜という状況に行動を開始しているとは到底思えない。だからこの幻影の氏は、きっと望まざる戦闘を強いられた結果なのだと僕はそう考える。そしてそんな状況に陥っているという事は――」
オリオールは、この周辺がカール達探検隊が見知らぬ亜獣とやらに襲われた現場であると、そう考えているのか。
だが、と【NAME】は辺りを見回す。
広がるのは他の場所と変わらぬ赤茶けた大地。やはりカール達が休息の場所として選んでいたという林の姿は見当たらない。
「強引な解釈だとは思うけれど、こういう形ならどうだろう。林自体は地形の変化により消滅した。けれども、幻影自体は変わらぬまま、ここに存在していた、と。もっとも、ここに存在している幻影が、ここでカール氏が取った行動を再現しているという保障もないのだけれどね」
とはいえ、その辺りを疑い始めると、この幻影を状況の証拠として考えるという行為が無駄に等しいものとなる。幻影が手がかりとなる事を前提とするならば、そこは無理矢理にでも納得し、疑問は呑み込んでしまうべきだろう。
「で、この辺りが襲撃の現場だと想定するとして……すると近くにカリッサ女史の痕跡かあり、そしてカール氏達を襲った亜獣が生息しているという事になる。僕の予想では、女史の痕跡は兎も角、亜獣の方は今は見つけられない気がするのだけど、もしかしたらという事もある。取り敢えず、完全に日が暮れるまで捜索をしてみる事にしようか」
所々【NAME】に理解しがたいところはあるものの、オリオールの提案自体は妥当なものだ。了解と頷いて、【NAME】とオリオールは周辺の探索を始めた。
といっても元々視界を殆ど塞ぐ物のない平坦な場所だ。大して気をつけて探すような処もなく、捜索は手早く、しかし得られる物もなく進む。途中、亜獣達と遭遇し戦闘になる事もあったが、現れた亜獣達は“湖”の他の場所で出くわした者達と大した差はなく、そしてカリッサの存在を示す証拠となるようなものを見つける事も出来ず、夜はゆっくりと近づいていった。
・
そして夜。
空は未だ厚い雲に覆われたままで月星の光など届くはずもなく、周囲を包む暗闇の色は濃い。そんな中、【NAME】達は事前に用意しておいた松明を片手に捜索を続けていた。
範囲は幻影を中心点に半径大凡500メートル。灯りを用意してあるものの視界が優れているとは到底言い難い状況だ。探索の歩みは遅く、最初に決めた範囲を見て回るだけでもかなりの時間を消費してしまったように【NAME】には思えた。
しかし、
「……どちらも外れ、か」
一通り回り終え、探索の中心点まで戻ってきた【NAME】は、呟くオリオールに小さく頷く。
夜の暗闇の中という事もあり、カリッサの痕跡を見つけるという点においてはあまり期待していなかった。だが、もう一つ。カール達を襲ったという亜獣らしき存在と遭遇できなかったのは、先刻のオリオールの予想が外れた事を示す。勿論、探索が足りない、偶然その亜獣がこの付近に居なかった等の可能性も考えられるが。
【NAME】達は一時の休憩を取るため、その場にて改めて火を起こし、それを囲みながら次の行動を思案する。
亜獣の捜索が空振りに終わったのは正直なところ痛い。既に湖周辺は一周し終え、一通りの探索は終えた形だ。加えて夜行性という可能性にも賭けてみたがそれも外れとなると、当てがもうない。件の亜獣が極めて少数の、かつ縄張りが極めて広い類であるという場合も考えられるが、もしそうならば見つけるのは正に至難という話になってくる。
「いや、少数……というのは無いと思うんだけれどね」
と、半ば弱音に近い【NAME】の言葉に対し、オリオールは眉根を寄せて首を振る。その手には、カール・シュミットの手記。彼はそれに視線を落としながら、
「手記での記載を信じるならば、カール氏を襲った亜獣はどうやら複数であるらしい。いや、描写からすると多数、というのがより近いのかな。ほら、ここ」
開かれた頁。“湖”を脱出した後にカールが記したと思われる部分には、彼等は唐突に、幾多の攻撃を、間断なく受け続けたらしき事が書かれている。
それを素直に解釈するならば、確かにオリオールが言うような、単独や少数ではなく、多数で構築された群れに襲撃を受けたと考えるのが妥当だ。
しかし、【NAME】達がこれまで“湖”を探索してきた中で、そのような集団と遭遇した事は一度もない。夜という、カール達が襲撃を受けた際の同一と思しき条件、同一と思しき場所を整えても結果は同じだった。ならば、そもそもその亜獣の集団自体が現存していない、もしくは存在していないと解釈するのもそう間違ったものではないのでは。
「んー、君の言う事ももっともだとは思うけれどもね、だけど、出来ればその結論で話を終えてしまうのは避けたいんだよ」
何故、と短く問うと、オリオールは表情を僅かに苦笑に変えて、
「それは僕が探検家だから、だよ。探して検める事が僕の生業だ。けれど、今はまだ探す事も検める事も完全には出来ていない」
その言に、【NAME】は首を捻る。
【NAME】からすると、かなり探し回った気がするのだが、オリオールとしてはまだまだ足りないという事なのだろうか。
しかし、当てにしていた要素が空振った今となっては、残る手段は本当に“湖”全体をしらみつぶしに探し回るという選択肢だ。それは余りにも効率が悪いように思えるが、そういう手段こそがオリオールの言う探し検める事、という話だと?
そんな若干否定的な【NAME】の反応に、オリオールはいやいやとまた首を振る。
「単純に、その当てが的外れだったのではないかって話さ。勿論、完全にという話ではなくて、もっと見落としていた要素があるのではないか、と。そういう事」
見落としていた事?
「うん。僕も今手記を読み返していて気づいたんだけど、僕等はさっきカール氏達が襲われたという状況をなるべく再現して探索を再開したつもりだった。けれど、よくよく見ると一つ、大きく違う点がある事に気づいたんだよ」
言われて、【NAME】はオリオールから受け取った手記を改めて読み直す。
だが、そのような点は見当たらない。勿論、人数といった部分は違うが、その辺りは調整の仕様が無いので除外するとして、それ以外の点、例えば夜、例えば場所、であるような処は極力合っている筈――、
「あ」
「ん、気づいたかい?」
これがオリオールの気づきと同様であったのかは判らない。ただ、気になった部分は一つだけあった。
それは、灯りに関する点だ。
就寝中、遠くからの悲鳴を聞いたカール達は、灯りを手に寝床から飛び起き、外に出たという記述がある。そして、その後に襲われた彼等は早々に灯りを失い、夜闇の中での戦闘を強いられることになった。
ここが妙だ。何故なら、
「例えば僕等がさっき使っていた松明。これが彼等の使っていた灯りであるならば、寝床からこれを持って飛び出すというのは少し無理があるよね」
所謂洋燈を使っていたという可能性も考えられるが、
「あれならばそうおかしくはないけれど、基本的には油を燃やす類の物だ。襲われて破壊されたとしても、そう直ぐに消えるというものでもない。火を使った照明は大体はそうだ。取り落としたところであっさりと消えてしまう類ではない」
で、あるならば、カール達が灯りとして使い、そして襲撃を受けた際に真っ先に失ったそれは、
「――輝石か、もしくは照明印章、照明術式。輝石は効果が短くて長期探索で使うにはあまり向いたものではないし、術式はそもそも使える者は限られる。となると、それらの縛りが無い照明術式を仕込んだ印章石を使っていたと推測できる」
照明の印章を刻み込んだ石。比較的高価な代物ではあるが、しかし便利な道具であるのは確かだ。カール達は相応の腕前を持つ探検家達だったと聞く。ならば、それらを普段から常用していたと考えてもおかしくはないのか。
「それで、だ。よくよく読んでみれば、彼等が襲撃すぐに灯りを失った、というのも妙だよね。カール達が持っていた灯りは一つではない筈だ。何せ姿がないカリッサを探そうとしていたんだからね。灯りは多ければ多いほど良い。なのに」
なのに、彼等は亜獣と遭遇して直ぐに全ての灯りを失い、亜獣の姿も碌に確認できない状況に陥っている。それは、亜獣達が彼等の灯りに対して率先して攻撃を仕掛けている事を意味していた。
これが何を示すのか。【NAME】がオリオールを見ると、彼は笑みを浮かべて、
「それじゃ、早速実証に移るとしようか」
言って、オリオールが服に取り付けられた無数の物入れ袋の中から大きな石を二つ取り出し、その一つを【NAME】の方へと投げ寄越す。流石著名な冒険家というべきか、あまり一般的ではない照明の印章石も普通に常備していたらしい。
「使い方は判るかな?」
照明の印章石。ものによって発動の手順は違ったりもするが、大まかには同じだった筈だ。
石には印章が刻まれており、【NAME】がそれを指でなぞる。すると石自体が発光を始めた。どうやら発声による術式駆動の促しが不要な種であったらしい。それを見届けてから、オリオールも自分の手の中にある石を発光させてから立ち上がる。
「では第二幕と行こう。出来れば、これが当たりである事を祈るよ」
頷きながら、【NAME】も立ち上がる。手の中に灯る輝きは、松明のような直接的な火の光とは違い強烈ではないものの、遠く、染み通るように闇を貫いて、視認できる領域自体は松明よりも広い。探索自体は松明を使っていた頃よりは楽に進められそうだ。
後は、果たして亜獣を見つける事が出来るかどうか。
そう考えて、【NAME】は違うかと首を振る。正確には、亜獣がこちらを、こちらが持つ印章石の輝きを見つけてくれるかどうか、か。
【NAME】は期待と共に夜の闇の向こうを見渡し、そして先行して歩き始めたオリオールの後に続いた。
・
結論から言えば、オリオールの推測は見事に当たりであった。
だが、
「まさか、湖からとはなっ!」
毒づく叫びは途中で途切れ、鞘から抜き放たれた小剣の刃が、印章石によって照らし出された光を反射し輝くのが見えた。
その亜獣が現れたのは、印章石の灯りを携えた【NAME】達が湖の畔に近寄った時の事だった。光が湖を照らして僅かな間の後、湖面が泡立ち始めた事に気づいた【NAME】達が何かの反応を示すより先に。湖の中から、複数の何かが飛び出し、こちら目掛けて殺到してきたのだ。
まるで矢のように飛び出してきた何か。姿も満足に視認できないほどの速度で突進してきたそれは、オリオールが持っていた印章石目掛けて次々と突撃するとあっさりとそれを砕いた。同時に、【NAME】の持つ印章石目掛けてもまた別のそれが突撃してきたが、しかしその攻撃に対しては辛うじて【NAME】の反応が間に合い、どうにかその突撃の直線上から印章石を逃すことによって回避。それにより、照明を失い夜の闇に取り残されるというカール達の二の舞になる事はどうにか避けられ、結果、その正体を確認する事に成功した。
襲いかかってきたのは、鰐口を持つ細長い大魚。今まで“湖”では見た事も無い類の存在だった。それも当然。何故なら、【NAME】達は湖の中に目を向けたことはなかった。強烈な雷気を帯びた湖は、触れることさえ恐らく危険。故に、近付く事はあれども調べるという考えは殆ど無かったのだが、
「……考えてみれば、当然か。“湖”の周りをあれだけ探し回って見つからなかった亜獣というのなら、居場所としてもっとも可能性の高いのが」
湖の中に棲息している亜獣であるという可能性だ。
そこから飛び出してきた亜獣は、一直線に岸に立つ【NAME】達に突進してきた後、空中で勢いを弱めてくるりと身を翻す。滑るように宙を泳ぐ姿は単なる魚とは思えぬものだ。どうやら湖の中を普段の住処としつつも、陸上で、いや、空中で活動する事も出来る類であるらしい。
と、そんな事を考える間も無く、新たな気配が湖の方から膨れ上がる。湖面が泡立ち、飛沫を飛ばして跳ね上がる大魚。そして逆側からも、空中で姿勢を整えた魚が加速し、突進を開始する気配。その狙いは全て、【NAME】が持つ印章石に集中していた。
突進の速度は強烈だ。動きが直線であるため回避するための動作自体は即座に思いつくが、それに身体がついていけるかどうかは別問題。【NAME】は半ば体勢を崩すような形でどうにかその突撃の矢群を避ける。前のめりの、駆けるような動き。身体の直ぐ傍で亜獣が高速ですり抜けていく気配が伝わり、衣服を通り越して皮膚に焼けるような、痺れるような感触を残していく。どうやら、魚達は己の身に雷気を帯びているらしい。
湖から飛び出した新しい影は、【NAME】の直ぐ傍を通り抜けた後、最初に現れた魚達と同様に空中に滞空。最初に現れた魚達も、湖の中には戻らず湖上にて体勢を立て直し、改めてこちらに突撃するタイミングを見計らう動きを見せる。それだけでも亜獣の数は倍近くになったというのに、湖の中から更に別の気配が上がってくるのを感じる。
――そして、その全てから狙われている。
【NAME】は己の手元に向けられる無数の意識を認め、背筋が凍るのを自覚した。
「【NAME】! 一旦湖から離れるぞ!」
否も無い。少なくとも、この場所は危険だ。新手が収まる様子が無い。
【NAME】が先行して走り出し、オリオールが後に続く。後方からは追ってくる亜獣の気配があり、時折その気配が強く膨れ上がった瞬間、唸るような風切りの音と共に突進が来る。
大魚達が空中を移動する速度はどうやら【NAME】が走る速度とそう変わらないようで、そのままならば距離自体は大きく変わらない。
だが、大魚達はどうやら短時間での強烈な加速が掛けられる能力を持つらしく、それを使った突進が行われる際には一瞬で距離を詰められ、そして襲い掛かられる。
その狙いは、一貫して【NAME】が持つ印章石に向けられており、この窮地を脱するならばこれを手放してしまうべきか。そう逡巡する瞬間もあったが、カール・シュミットがその後も亜獣達と戦闘を続けていたらしい事を考えると、自ら灯りを放棄するという選択肢はないと結論付ける。
「戦うにしても、有利な場所で行うべきだが……どうしたものだろうね、っと!」
後ろに続く形となっていたオリオールは、後方に注意しながら、突進してきた大魚に合わせるように手にした小剣を振るう。剣の刃と魚の鰐口が噛み合い、硬質の音と共に魚の身体があらぬ方へと跳ねて吹き飛ばされていく。様子を窺うように振り返った【NAME】に、痺れを払うかのように手をぷらぷらと振ったオリオールは軽く笑って見せ、
「亜獣の狙いが君の印章石だと判っていれば、迎撃も簡単……とは僕の技量ではとても言えないけれど、できなくもないね」
そして、オリオールはふと思案するように表情を真剣なものへと変える。
「……そうか。あの亜獣の狙いが兎にも角にも印章石で、今のような攻撃を闇雲に行ってくると考えるなら、案外、一網打尽にするのも難しくはない、のか?」
一体何を思いついたのか。
【NAME】が訊ねる前に、オリオールは走る速度を上げて【NAME】の隣に並走すると、
「ここから暫く真っ直ぐ進んだ先に、大きな枯れ木が一本だけ残っている場所があった筈だ。そこから湖を見て左手側。そちらに確か大きな窪地になっているところがあったと思う。覚えているかい?」
逆に問われて、【NAME】は懸命に記憶を掘り返す。
似たような平坦な地形ばかりの“湖”周辺であったが、所々にそういった地形があったのは覚えている。それがこの近くだったかどうかは【NAME】からすると定かではなかったが、確かにオリオールが言うような窪地があった事自体はどうにか思い出せた。それは窪地というよりも穴に近く、高低差も10メートルはあろうかというもの。傾斜がきつく、底がどうなっているのかは軽く覗き見た程度で済ませた筈で、半ば沼に近い状態になっていた記憶がある。
――で、その窪地がどうしたのだろうか?
そう言葉を作ろうとして、【NAME】は一瞬息を止める。
オリオールの思いつきが何なのか。それを【NAME】もようやく察した。背後より迫る亜獣の習性を利用するなら、成る程、それは適した場所だ。
【NAME】の表情の変化を見てオリオールもそれ以上言葉を作る事なく、【NAME】達はそのまま亜獣達の追撃を凌ぎながら進み、目的地の窪地へと到着する。
半ば滑り込むように、窪地の縁で足を止めた【NAME】とオリオールは、後方より追ってくる、空中をまるで水の中であるかのように泳ぎ迫る大魚の群れを一瞥し、
「それでは【NAME】、どうぞ」
促しに頷いて、【NAME】はひょいと、手にした印章石を窪地の底目掛けて放り投げると、オリオールと共に素早くそこから離脱する。
続いて起こった状況は、これまでの魚達の行動からすると至極想像しやすいものだ。
窪地に投げ込まれた印章石へと、追って来ていた魚の大群が次々と突撃していく。加速し、矢のように印章石に食らいつく亜獣の突撃は凄まじく、印章石は数撃と耐えられずに破壊されたが、既に突撃の体勢に入っていた魚達は砕かれた印章石へ止まること無く殺到していく。その先に、先行していた大魚達が窪地の底、沼地となった地面に突き刺さり身動き出来ない状況にあるにも拘わらず、だ。
結果、砕かれ粉々となった印章石が光を完全に失う頃には、【NAME】達を追いかけていた亜獣の殆どは窪地の底で仲間の突撃をその身に喰らうか、地面に突き刺さり抜け出せない状態となり、
「いやぁ、ここまで綺麗に策がハマると気持ちが良いね」
物入れ袋から取り出した別の石を軽く叩き、その衝撃で灯った光でもって窪地の底を見下ろしたオリオールは、そう満足に笑った。
オリオールが新たに持ち出した石は、照明の印章石ではなく、輝石と呼ばれる発光物だ。一般的な冒険者にとって、灯りとして馴染み深いのはむしろこちらである。
【NAME】としても、オリオールと同じ気分だ。淡い輝きで照らされた穴の底の様子は、中々に爽快感がある。
「後は……」
背後を振り返るオリオール。釣られる形で【NAME】も振り返れば、どうやら窪地の底で醜態を晒す仲間達から遅れを取り、結果助かっていたらしき亜獣が数匹、【NAME】達に鰐口を向けながら空中を泳ぐ姿があった。
その様子からは強い戦意が感じられ、どうやら退くつもりは無いらしいのを察する。
「まず残りの彼等を退けてからにするとしようか」
先刻とは状況が大きく変わった。この程度の数ならば、後れを取る気はしない。
オリオールが小剣を構え直し、【NAME】も己の得物を亜獣達に向ける。その動作が引き金であったかのように、宙を浮かぶ大魚達は、【NAME】達目掛けて雷気を散らしながらの突撃を敢行する。
襲い掛かってきた大魚を難なく倒した後。窪地の底を覗き込んでいたオリオールは、新たな石を物入れ袋から取り出した。
「さて、では止めといこうか」
表面に描かれた印章を手慣れた様子でなぞり、何事かを呟きながら投げ落とされた石は、底に接すると同時に四方へ炎を吹き出して炸裂し、窪地の底を火の海へと変える。そして爆発した炎は一瞬では消えることなく、地面にへばりつくように持続し、盛る火の向こう側では未だ息があった大魚達が炎に炙られて身を捩り焦がす様子が見えた。
オリオールが使ったのは、炎熱系の術式が刻まれた印章石。火炎弾[ファイアボール]のような即時爆発する術式と、土地に対して炎を持続させる術式を複合したものなのだろう。
炎はそのまま数分近く維持されて、ようやく収まった頃には、窪地の底に突き刺さっていた大魚達は全て焼け焦げた状態で息絶えていた。
「……流石にやり過ぎたかな」
いや、妥当なところではないか。加減をするような場面でもなし。
そんな【NAME】の感想に、「まあそれもそうなのだけども」と頷き、
「出来れば腹の足しにでもするつもりで、面倒だからと一気に焼いてみたのだけど、どうも火が強すぎたような気がしてね。これは原型が残ってるかどうか……」
(……ああ、そういうつもりだったのか)
逞しい、と苦笑する【NAME】を置いて、オリオールは輝石片手に窪地の底へと降りていってしまう。窪地の傾斜はきつく、視界は夜故輝石があれども不明瞭。しかも印章石による術攻撃を仕掛けたとはいえ、未だ生き残っている魚が居るかもしれない。流石にその行動は迂闊すぎないか、と【NAME】が注意を促そうとするが、
「さて、まともに食べられそうなものは……と、流石にまだ熱いな!」
という気楽そうな声が底の方から聞こえてきて、どうやら杞憂かと小さく吐息。比較的安全に下へと降りられる場所を見極めながら、オリオールに続いて窪地の底へと降りる。
まだ炎が消えて間もないためか、確かにオリオールの言うとおり、窪地の底は強い熱が籠もっている。特に靴底越しから感じる地面の温度はかなりのものだ。気をつけていないと靴自体が焼け溶けてしまいそうだ。
強烈な熱に焼かれたせいか泥濘んでいたはずの地面は乾燥し、踏み込めば軽く砂となって砕けるような感触。土に突き刺さっていた大魚達の残骸もあったが、殆どは炭に近い状態だ。もしかしたら生き残っている大魚も居るかもしれないと用心のために降りてきた【NAME】であったが、その必要は無かったらしい。
先行して降りていたオリオールは難しい表情で地面を見下ろし、炎によって焼かれた大魚の状態を見ていたようだが、暫くの後、残念そうに吐息をつく。
「これはどれも無理そうだ。もう少し火力の弱い石を使えば良かったかな……」
心底名残惜しげに言うオリオール。本気で食べてみたかったらしい。
【NAME】は流石に呆れて、そもそもの目的を見失ってはいないだろうかと問うが、対してオリオールは心外そうに目を瞬かせ、
「いや? だって今回の目的はほぼこれで達成できたようなものだしね」
「…………」
そうだろうか? と【NAME】は素直に首を捻る。
今回オリオールが定義した“冒険”の目的は、カール達を襲った亜獣の正体の解明と、彼等の仲間であったカリッサ女史の消息という二つだ。
だが、それは二つの目的のうちの一つがようやく判ったという程度。まだもう一つを調べる作業が残っているのではないか?
そんな【NAME】の指摘に、オリオールは苦笑いを作りながら、
「と、僕もさっきまで思ってはいたんだけれどね……」
言って、ひょいと地面の一角を指差す。
「ほら、あれを見てくれないか」
彼が示したのは、窪地の底のちょうど中央。抉るように開いた穴だ。大きく何かが破裂し、それによって出来たらしい痕跡。オリオールが先刻投げ込んだ印章石が落下した場所だ。
一体そこに何が、と覗き込んだ【NAME】は、爆発によって捲り上げられた土の中からひょこりと顔を出しているソレを見て、渋い顔で黙り込んだ。
そこにあったのは、完全に白骨化した人の死骸だ。
爆発の影響を受けてかその半身は砕け、吹き飛んではいたが、残る半分は人の骨の姿を保ち、地表に姿を見せていた。
エルツァンは未踏と言っても良い場所だ。そのようなところで、明らかに人と思しき遺体が見つかったという事はつまり、それは唯一の先人たるカール・シュミット探検隊の一員のものと見て間違いはあるまい。
勿論、人型の別種族――亜人のものという可能性はあったが、爆発の影響で四方に散った残骸の中には、焼け焦げてはいるものの原型を留めた、恐らくはこの遺体が身につけていたものであるらしき品もあり、オリオールはその一つを拾い上げて、
「この武器の造りとか、西大陸由来のものだし、確定と考えてもいいだろう。っと、あつつっ!」
手袋越しでも感じるらしい熱さに、オリオールは慌てた仕草で武器を地面に落とす。硬質の音を立てて転がる武器は、あれだけの熱に晒されていても大きな変形も損傷も見当たらない。元々の品質がかなり高いものであったのだろう。加えて西大陸の製法による武器であるならば証拠としては十分だ。
「この亡骸が、“カリッサ灼雷領域”という名の由来となったカリッサ女史、なのだろうね……」
呟き、土に埋もったまま半壊し、無残に焼け焦げた白骨を見下ろして、感傷に浸るオリオール。
「…………」
「…………」
「…………」
白々とした【NAME】の視線に、オリオールは表情はそのまま、鈍い汗を流しつつ振り向く。
「……何かな?」
――いや、カール・シュミットがここに一人残してしまった後悔の象徴であるカリッサの亡骸をこうも派手に吹っ飛ばしておいて、よくそんな表情が出来るものだな、と。
「仕方が無いだろう!? いや、僕だってまさかここにカリッサ女史の遺骸があるとは思わなかったんだよっ! 昼に調査したときには、影も形もなかっただろう!?」
確かにそうなのだ。
この窪地を見つけたのは夜になる前。“湖”を一周している時の事だ。その時、窪地の縁から底となるこの場所を見下ろしたときには、人骨や遺留品などは一切見つからなかった。推測となるが、カリッサはこの場所にて命を落とした後、周囲の斜面が崩れ、土が底に積み重なるような事が起きたのだろう。その結果、カリッサの遺体と持ち物は地中に埋まる形となり、見逃してしまったのだ。今回、この場所でカリッサの白骨を見つけられたのは、複数の偶然が重なった故の幸運だった。
もっとも、その幸運を引き込むために、死者を弔うどころか冒涜するような行為を、図らずもする事になってしまった訳だが。
オリオールは深々と溜息をつくと、
「償い、というつもりはないけれど、取り敢えずはカリッサ女史を弔おう。元々、そのつもりできたのだし。【NAME】、済まないが手伝ってくれるかな。こんな場所ではなく、もう少しマシな場所に運んであげたい」
それについては別段異論は無いが……そういう作業は夜が明けてからのほうが捗るのではないだろうか。
【NAME】の指摘に、オリオールはそれもそうかと頷き、
「では一度ここを離れて、朝になってから亡骸を引き上げる作業を始めるとしよう」
了解、と窪地の上を目指して斜面を登り始めたオリオールの後に【NAME】も続く。
と、そこでふと疑問が湧いた。
「まだ何か?」
――結局のところ、カリッサ女史の死因は何だったのだろうか?
【NAME】の問いに、オリオールは登る手足の動きを止めて、ふむと一つ鼻を鳴らすと、
「これまで得た情報を繋げて考えれば、探検隊の夜番を務めていたカリッサ女史は、何らかの理由で照明の印章石を手に湖の傍に近づいた。可能性として高いのは、亜獣の気配を感じての巡回か、用足し辺りか。それで、この時に、湖から僕等を襲ってきたあの大魚が印章石に惹かれて現れ、カリッサ女史を襲撃。即座に印章石を破壊されたであろう彼女は、暗闇の中、大魚の攻撃に碌な対処も出来ず、悲鳴を上げながら闇雲な逃亡を続けた結果――」
この窪地に落ちた、と?
「若しくは、ここに隠れてやり過ごそうとして適わず、こう、真上から、大魚の突進が槍衾状態で、ざくざくと」
「…………」
「将又、無事に逃げ切る事に成功し、ここを拠点にしてどうにか生き延びてカール氏達が捜索に来てくれるのを待つも、食料が尽きてそのまま、とか。……まぁ、色々と想像は出来るけども、死の主要因という点で語るなら、カール達と同様、亜獣による襲撃を受けた為、という事になるのだろうね」
最初に手記を読んだ際に一番最初に思いつくような原因そのまま、といった処か。
「意外性は無いというのは僕も認めるところだ。ただ、今回の冒険でそれを確かめ、ついでに想像ながらもその流れを掴めたのは、個人的には収穫だったかな。何故カール達が唐突に襲われたのか、という部分については、ほぼ解明できたと思う。【NAME】も……大体想像がつくよね」
言われて、【NAME】はこくりと頷く。
原因を作ったのは恐らくカリッサだ。彼女が湖に近付き、手にした照明の印章石によって大魚達を陸へとおびき寄せてしまった結果、彼女を探してやってきたカール達の印章石に大魚達が更に釣られる形となったのだろう。
「判ってしまえば、対策なんていくらでも取れる事だ。けれど、未知の場所を探検する者にとっては事前に知るという事自体が不可能で、なのにそれは容易く命取りになり得る。……他人事ではないよね、本当に」
そう深刻な口調で言いながらもオリオールの横顔はどこか不敵で、その様子は彼がこれまで様々な秘境に挑み踏破した経験を持つ、三大陸有数の冒険家である事を再確認させるものだった。
・
カリッサの亡骸と、爆発によって散らばっていた遺品を可能な限りかき集めた【NAME】達は、それをとある幻影の真下へと運び、一部の使える武具を除いた全てを埋めることにした。
“湖”の周囲に幾つも残るカール・シュミットらしき男の幻影。その中で、【NAME】達が選んだ幻影はじっとその場に仁王立ち、湖を眺め続ける。“湖”周辺で見つけた幻影の中で、もっとも静かな姿を取るその幻影の傍ならば、カリッサも安らかに眠ることが出来るだろう。そんな判断からだ。
冥福の祈りを捧げた後、【NAME】達は“湖”の拠点へと戻り、手早く荷物を纏める。このまま冒険の継続は行わず、一度常駐軍の陣に休息と補給、報告を兼ねて帰還する予定だった。
丸めた天幕を背負ったオリオールは、ぐ、と大きく一度伸びをして、
「……さて、これで取り敢えず今回の“冒険”は無事終了だろうか。大成功……とは言い難いが、及第点以上は付けられる内容ではあったかな」
案外と評価が厳しい。最初はかなり無茶に思えた目的二つを、ほぼ達成する事が出来たのだから、もう少し良い点数をつけても良いと思うのだが。
【NAME】の言葉に、オリオールは若干口元を引きつらせて、
「それについては、主に僕の方がね。まさか“心残り”を晴らす旅で、その心残り自体を半分吹っ飛ばしてしまうとは……」
「…………」
言われてみれば。
「ま、まぁ、そちらは後で僕だけ心底反省しておくとして、だ。――そろそろ次の“冒険”についても話しておこうか」
そんな物言いをするという事は、既にオリオールの中では次の目的について決まっているのか。
【NAME】が訊ねると、彼は大きく頷く。
「次の目的地は――“ザルナルバック月光丘陵”。そこで僕等は、カール氏が最後に遭遇したという奇妙な光の塊。その正体を探ろうと思う」
真なる楽園 夢歩く幻、昼夜表裏の境
──ザルナルバック月光丘陵──
“谷”を抜けた【NAME】達の前に広がるのは、視界を遮るものの殆ど無い広大な丘陵地帯。それはこれまで進んできた峡谷とは全く異なる風景だ。
あちらが荒れた強風と乾き痩せ禿げた土地で構成されていたのに対し、こちらは穏やかな微風と適度な湿りを帯びた肥えた草原が広がる。その差異は驚く程で、
「いやぁ、この“境界”を抜けたときの環境の変化は、やはり感動的だね」
隣、額に手を翳して前方を見渡すオリオールは楽しげだ。そんな彼の心境は【NAME】にも分からなくはない。エルツァンの内陸地形特有の、土地と土地の境を越えた瞬間に、かちりと世界が切り替わるようなあの感覚。現象としては極めて異質であり、不気味でもあるが、しかしその明確な変化を小気味良いと感じる部分も少なからずある。特に、切り替わった先の風景が何処か暢気なものであった今回ならば尚のことだ。
そうして、【NAME】達は眼前に広がった新たな景色を暫し眺めて、
「ただ、妙ではあるな」
と、唐突にオリオールが訝しげに首を捻る。
はて何か妙なことでもあったか、と【NAME】は隣に立つ彼を見る。エルツァン内でのこういう極端な地形の違いは、既に“湖”を探索したときに判っていた事だ。今更妙だと思う事でもあるまい。
そんな【NAME】の指摘に、オリオールは首を横に振る。
「エルツァン島の中でこういうなだらかな丘が続くような地形は、僕等の今回の目的地であった“ザルナルバック月光丘陵”のみだったと思うのだけど……」
ならば、ここがその場所ではないのか?
単純に【NAME】がそう答えると、彼は腕を組んで気難しげに唸り声を上げる。
「ここが目指していた“丘”だとすると、手記の内容とは大きく感じが違っているように見えるんだよね。【NAME】、“ザルナルバック月光丘陵”についての部分、覚えているかい?」
言われて、【NAME】は確認のために手記を取り出す。カール・シュミットが遺した、エルツァンに関する記録。“ザルナルバック月光丘陵”の記述は、手記の前半にある。それを改めて確認した【NAME】は、オリオールが何を言いたかったのかを悟る。
手記の記述によれば、その丘陵は歪で陰湿な気配に満たされ、狂気に満たされた亜獣達が無数に闊歩する極めて危険な場所で、カール達探検隊は強大な力を持つ亜獣達に幾度も襲われ、多くの被害を出したという。
が、今目の前に広がっている景色はといえば、
「そんな雰囲気や、亜獣の気配は感じるだろうか?」
「…………」
今自分達が居るのは丘陵の入口。奥へと進めばまた雰囲気が違ってくるのかも、と考えはしたが、そもそもなだらかな丘が遠くまで続く場所だ。視界を遮るものは殆ど無く、遠くまでよく見える。そして視線を遠くに飛ばしてみても、手記にあるような雰囲気もなければ、亜獣達が蠢いているような気配も感じられない。胸元にある首飾りを手繰れば、僅かに陰性質の――鬼種に由来する気配を感じるような気もするが、それは他の場所でも感じるような代物で、むしろそれらに比べれば酷く弱いようにも思える。
手記にある描写とは明らかに違う。ならばここは“ザルナルバック月光丘陵”ではないのか、という話になるが、
「でも、手記によれば“丘”の特性を持つ地形は一つしかないんだ。勿論、カール氏が足を運ぶことのなかった未知の土地が存在し、今僕等が居る場所がそこである、という可能性もあるにはあるんだが……」
自分でそう言いながらも、オリオールとしてはどうも納得しがたいものらしく。彼は気難しげな顔つきで、そろそろ中天に近付こうかという太陽が齎す、ぽかぽかとした陽気に包まれた丘を、睨むように見据える。
取り敢えず、ここであれこれと考えていても仕方が無い。実際に丘の奥へと足を踏み入れてみれば、手記通りの場所であるのか、それとも違うのかがはっきりとするのではないだろうか。
【NAME】の提案に、「それもそうだな」とオリオールは表情を緩め、
「では、早速探索を始めるとしよう。ここが“ザルナルバック月光丘陵”であるのなら、なぜ手記と状況が違うのかを調べなければならないし、逆に違うのならば新たに別の“丘”を探し直さねばならない。どちらにせよ」
――面倒な話だ。個人的には、別の場所へと移動する必要の無い前者であってくれた方が楽ではあるが。
率直な【NAME】の感想に苦笑しながら、オリオールが先行して歩き出す。【NAME】もその後に続いた。
・
そうして【NAME】達は本格的に丘陵の中へと入り込んだ。
体感にして一、二時間ほどの探索。大雑把な地図を作りながら、それを目安に幾つかの丘を越える。緩やかな上下の傾斜は四方に広く伸びて、終端はなかなか見つけられない。これまでのエルツァンでの旅の経験から予想するに、“丘”という土地の終わりとなる境界が何処かに存在している筈だが、それは遠目に見て認識出来るものではない。少なくともこの土地が、二つ、三つ程度の丘で収まらない広さである事は判ったが、収穫と言えばその程度だ。
「で、それなりに奥までは来たと思うのだけれど、遭遇する亜獣はといえば……」
とある丘の頂。呟くオリオールの視線の先には、小さな亜獣の影が複数。彼等は身体を寄せ合いながら、懸命な様子でこちらに突撃してくる。
その姿形からは、カール・シュミットの手記にあったような狂暴さは到底感じられず、エルツァンの海岸で遭遇するような亜獣達にも遙かに劣る、【NAME】からすれば手慰みで片付けられる程度の亜獣にしか見えなかった。
勿論、それは見た目だけであり、実際は凄まじい戦闘能力を持つという可能性もあったが、既にここに来るまでに数度、似たような亜獣達と戦闘した経験から推測するならば、
「……ランドリート辺りで出てくるような亜獣だよな、あれは」
と思われるが、もしかしたらという事もある。
【NAME】は無言で武器を抜き、距離を詰めてくる亜獣達と相対する。あの亜獣が強ければ良い等と、普段ならば決して考えないような事を思いながら。
battle
草原を喰う者

残念ながら――というのは少しばかりおかしな話であったが、襲ってきた亜獣達は、【NAME】の一撃であっさりと蹴散らされてしまう程度の強さだった。
追い返され、背を向けて草原の中に消えていく亜獣達を暫く眺めた後、【NAME】とオリオールは戸惑いの表情で顔を見合わせる。
「……やはり、ここは僕等が探していた“丘”とは別の場所なんだろうか?」
答える言葉が思いつかず、【NAME】は腕を組み考え込む。
どうも、妙な場所ではあるのだ。これまでエルツァンを旅した経験を基準にして考えるなら、ここは逆の意味で異質な場所といえるだろう。
あまりにも平和すぎるのだ。牧歌的とも言える風景。穏やかな気配。脆弱な亜獣達。どれもが、亜獣達の真なる楽園であるエルツァンという島での“普通”から外れている。
だが、それ以上の何かが思いつく訳でもない。違和感はあるのだが、それだけ。加えて、それが自分達の目的地としている“丘”に繋がる要素であるのかと言われると疑問だ。接点はないように思える。
結局の処。
オリオールの言う通り、ここは“ザルナルバック月光丘陵”ではないと、そう結論付けるのが妥当なのだろうか?
【NAME】の独り言のような呟きに、オリオールはうーむと唸り、
「何か、裏がある。それは僕も感じてはいるんだけど、その裏を暴くための手がかりがないのも確かなんだよね。……兎に角、もう少しだけ探ってみて、これといった発見が無ければ、別の場所に移動してみよう」
下手な考え休むに似たり。気にはなるが、しかし今回の目的はまず“ザルナルバック月光丘陵”を探す事だ。この場所の違和感について調べるのはまた別の機会でも良いだろう。
「次は、あちらの丘に向かってみようか。“谷”との境界を基準に考えれば、あの辺りで」
オリオールの言葉に頷き、【NAME】は丘の頂を降りていく。
一瞬、空を見上げる。晴れ晴れとした空は、徐々に青色から赤色へと変化を始めており、柔らかな日差しを注ぐ陽の円が、じりじりと地平へと近付いていくのが見えた。
遠くまで広がる草の原が、次第に黄金色へと焼けていく。
その色の合間に、一瞬。
「……?」
【NAME】は、白く朧に揺れる何かを見たような気がした。
だが、一度の瞬きでそれは失われて、後には風に戦ぐ草の波が残るだけ。
「【NAME】? どうかしたかい?」
先に行くオリオールが、動きを止めたこちらに気づいて振り返る。
「…………」
じっと目を凝らして草原の一点を見つめてみるが、変化はない。
何かの見間違いだろう。少しだけ考えて、【NAME】は何でもないと首を横に振り、オリオールの後を追った。
──ザルナルバック月光丘陵──
「……まさか、こういう裏があるとはね」
訪れた変化に、オリオールは唖然と声を漏らす。
つい先刻まで思い悩んでいた、この丘に潜んでいるであろう裏の側。それはあっさりと、【NAME】とオリオールの前に姿を現した。
見る間に沈んでいった太陽。その片鱗すらも地平の向こうに下り、周囲が完全に夜の帳に包まれた――そう【NAME】達が認識したと同時。
一瞬。視界に映る景色全てが、霞むように揺れた気がした。
丘陵に吹いていた穏やかな風がぴたりと止まり、動きを失った大気は一段、粘るように重さを増す。
そしてゆっくりと、しかし、明確に。
これまで感じる事のなかった暗く、歪で、荒々しい気配が、染み出すように丘陵を侵し始めている事に気づく。
太陽が沈んだ方角とは真逆の地平から、煌々と輝く冴えた白色の円が顔を出す。真円を描く月は驚くに巨大で、目に見えて判る程の速度で空を昇っていく。中天へ近付くにつれ強くなっていく青白い光。それに比例するかのように、丘陵を覆う気配は加速度的に鈍く、重く、そして狂おしく変化していった。
夜を示す空の色は、藍でも紺でも黒でもなく、暗い紫。丘の姿自体はそのまま、さっきまで感じていた長閑な雰囲気は完全に消え失せて、今この場所を満たしているのは異質で陰質な、エルツァンの島では有り触れた“普通”の気配だ。
もっとも、その度合いはこれまで辿ってきた“谷”や“湖”のような場所に漂う気配を大きく上回っていたが。
「成る程。“月光丘陵”とはそういう事か。カール氏も上手く名付けるものだね」
【NAME】と共に空を見上げたオリオールは、乾いた笑みを浮かべながら呟く。
「つまり、こういう事だ。“ザルナルバック月光丘陵”は、昼と夜でその在り方を大きく変化させる、そういう特性を持つ場所なんだろう。そしてカール氏率いる探検隊は、夜の丘陵に辿り着き、そしてほら、あそこに居るような――」
オリオールが指し示すのは前方。
【NAME】達が立つ丘の頂に向かって、亜獣達の集団が凄まじい勢いで駆けてくるのが見えた。
疾走する亜獣達の顔に正気の色はなく、激しく動く四肢からは血の飛沫が散っている。見開かれ血走った瞳は【NAME】達を捉え、そこからは強烈な害心が垣間見えた。
「――まるで月の光で気をやられたかのような、極めて凶暴な亜獣達に襲われ、被害を出しながらもどうにかここを脱出した。夜が明けるのを待たずにね。だからカール氏にとってこの場所は、あの空を覆ってしまう程の異形の月が支配する狂気の丘陵――昼夜表裏の裏側だけしかない場所だった、と。昼の姿を見ていた僕等と、夜の姿を見ていた彼等で、情報が噛み合わない訳だ」
などと、暢気に語っている場合ではないだろうに。
既に迫る亜獣の群れは間近だ。【NAME】は己の得物を引き抜き構えながらオリオールにも迎撃の準備を促すが、冒険家は向かってくる亜獣の凶相ぶりを引きつった顔で眺め、
「……正直、あれほどの亜獣相手なら、僕は後ろに下がって戦いは全て君に任せた方が、むしろ邪魔にならなくて良いんじゃないかと思うんだが……どうだろう?」
はっきり言ってそんな気もしなくはない。が、こちらだけ危険の矢面に立たされるのは単純に気分が悪い。元々はオリオールの“冒険”なのだから、そちらも相応にリスクを負ってもらわねば不公平だろう。
【NAME】が半眼を向けて言うと、「……ごもっとも」とのっそり腰の後ろに結びつけた小剣の鞘に手を伸ばす。
「仕方無い、僕なりに君の足手まといにならないよう、気をつけて動いてみるとするよ」
引き抜く音が響くと同時に、既に眼前にまで迫った亜獣が、大きな吠え声と共に地を蹴る。
互いの力が交差する最中。
【NAME】の耳には微かに、笛の音のようなものが届いた気がした。
battle
宴溺れる大鬼


襲い掛かってきた亜獣の討伐に成功した【NAME】達は、そのまま怖じけることなく、凶暴極まる獣が無数に闊歩する丘陵の探索を再開した。
夜の丘にて繰り広げられる光景は、カール・シュミットの手記にある描写ほぼそのままだった事から、取り敢えずの第一段階、ここが“ザルナルバック月光丘陵”であるかどうかについてははっきりさせる事は出来た。特に、夜になってから出現するようになったカール・シュミットと思しき幻の姿が決定的だった。昼の間は一切見る事のなかった幻が、夜にだけ現れる。それはこの丘陵は昼と夜では在り方自体が大きく異なる場所である事を示しているようにも思えた。
ここが“丘”である。それを確信できた【NAME】達の探索は、次のフェーズ――今回の“冒険”の主な目的であるところの、カール達が見たという光の塊を探すものへと移行していた。
カールの手記によれば、この月光に覆い尽くされた丘陵に侵入した探検隊は、気が触れたかのように際限なく暴れ回る亜獣達と遭遇し、丘陵のあちこちを逃げ回る羽目になったらしい。そして多くの被害を出しながらも、丘陵をようやく脱出できるかというところで、これまで“丘”で出くわした狂気に包まれた亜獣達とは毛色の異なる、淡く輝く奇妙な光の塊に遭遇したのだという。
光る塊は、他の亜獣達のようにカール達に対して積極的な攻撃を仕掛けてくることはなかった。そして探検隊の一員であった術士――ザルナルバックの見立ては、この光の塊は丘陵を構成する土地概念と何らかの繋がりがあり、もしかするとこれを破壊すれば、丘陵を支配する狂おしく不気味な気配を払う事が出来るのではないか、というものだった。
だが、それに従い光の塊を破壊しようと攻撃を仕掛けたカール達は、光の塊からの思わぬ反撃を受ける。光の塊は他の亜獣達のようにカール達を襲う事はしなかったが、しかし戦闘能力が全く無く、そして無抵抗な存在ではなかったのだ。この反撃により、提唱者であったザルナルバックは死亡。更に戦闘による騒ぎに反応し他の亜獣達が乱入してきたことから、カール達は光の塊の討伐を断念し、ただ犠牲者を出しただけで何の成果も得る事無く“丘”を離脱する事となる。
光の塊を探し、正体を確かめ、可能であるなら破壊をし、その結果どうなるかを知る。
これが、今回のオリオールの“冒険”の目的だった。
この目的を達成するには、まず光の塊が実在するのかどうか。存在するのならば、一体何処に居るのか。それをまず明らかにしなければならない訳だが。
「――っ!」
新たに襲ってきたのは人型の巨体が三体。喰人種に似た外見を持ってはいたが、【NAME】が知るそれらより二回りほど身体が大きく、膂力もそれに比例するように高い。逆に知性は欠片も感じさせず、動きは獣以下だ。一切の欺瞞動作の無い直線的な攻撃は、破壊力は抜群ながらも見切るのは容易い。振りかぶり、振り下ろし、薙ぎ払い。轟風を伴って迫るそれらの攻撃を紙一重で避け、相手の要所に対して攻撃を入れる。どれだけ身体能力に優れようとも、関節や腱を断ってしまえば動きは目に見えて鈍るものだ。勿論、超常的な回復能力を持つものが多い亜獣相手では、それも一時の効果しか期待出来ない事が殆どではあるが、一瞬であれ有利状況を作る事が出来ればそのまま押し切れる。痛みを完全に無視して暴れ回る喰人鬼に対しそのまま連続で攻撃を叩き込み、一気に三体沈ませた【NAME】は、深く吐息をついて緊張を解く。
丘陵に夜が訪れてから、これで何度目の交戦であったか。既に両手の指で数え切れない程であるのは確かだ。
夜の丘陵を徘徊する亜獣達は、他の地域のそれとは明らかに行動指針が異なる。異質な存在である亜獣であるが、その習性については一般の動植物達とそう大きな違いはない。捕食、縄張り維持、危険防御行動、遊戯。だが、この月光丘陵を徘徊する亜獣達はそれらの分類に一致しない、無差別な害意、戦意に支配されているように見える。他者を探し、他者を攻撃する。そんな意思に支配されているかのようだ。故に、他の場所と比べて亜獣達と戦闘になる可能性が非常に高い。カール・シュミットの手記を最初に読んだときは、なぜこれ程多数の亜獣に襲われているのかと疑問に思ったが、実際に自分が同じ状況に陥ってみれば、成る程こういう事であったのかと納得する。
が、納得できたからといって、状況が改善する訳ではない。
この頻繁に亜獣――それも無謀な戦意に支配された亜獣達との戦闘が発生しうる場所を、ただ闇雲に歩き回って光の塊を探すというのは愚手が過ぎる。先にこちらの体力、精神力が尽きるのは明白だ。だからせめて、光の塊を探す上での何らかの当てがあればまだマシなのだが。
と、【NAME】が喰人鬼三体と戦っている間、別の小鬼一体の相手をしていたオリオールが、激戦を窺わせる様子で戻ってくる。そんな彼に【NAME】が考えていた事をそのまま話すと、小剣にこびり付いた血油を拭っていたオリオールはぐりぐりと己の顎を撫で、
「……当て、か。そうだね。光の塊とやらがザルナルバック氏の言うような土地概念自体に繋がりを持つ、いわば概念的な存在であるのなら、【NAME】。君の力でそれらしいものを感じ取る事はできないだろうか? 眠っているとはいえ神形の担い手である君なら、概念的な存在に対する感知能力は、常人よりも多少なりと上がっている、とは思うのだけれど」
オリオールの予想はそう間違いではない。確かに、そういった良く判らない存在を感じる力は以前よりは増しているようには思える。
が、それは酷く曖昧で、頼りにならないものである事も判っていた。エルツァン島の何処かにいるという、あの強大な“鬼喰らいの鬼”の気配を、未だ明確に感じ取る事が出来ないというのが、その証拠だ。
丘陵内においても、土地自体に蔓延る鬼の気配のようなものは僅かに感じ取れるのだが、その位置までは漠然としていて掴めない、そんな状態だ。光の塊とやらがどのような気配を持っているかも良く判らない状態で、それを感じ、察する自信は全くもってない。
そういう【NAME】に、オリオールはうーんと唸り、
「別にそう、特定の何かを追う必要はないんだ。例えば、そうだね。この丘陵の何処かに、他とは何処かズレた気配を感じさせる場所とか、そういうのは無いかな? それくらいの差異だけでも、手がかりにはなり得るんだけど。後は……夜になってから響いてくる、妙な音の出所について、とか」
音。
その言葉に、【NAME】はオリオールにもあの微かな笛のような音が聞こえていた事を知った。
――オリオールは、あの音について既に何か判っているのだろうか?
対して、
「まさか。僕にもちゃんと聞こえてはいるけどね。あれも怪しいとは思うんだが……カールの手記の中では、一部に記述がある程度で、特に光の塊と繋がりがあった風でもなくて、どう扱ったものかと困っている。まぁ、それは横に置くとして、だ。どうだろう【NAME】。一度集中して気配の方を探ってみてもらえないだろうか」
自信はないが、しかし他にこれといって手がある訳でもなく。そしてやるならば亜獣を倒したばかりの今のうちだ。周囲の安全が一応は確保されている今のうちでなければおちおち集中も出来ない。
【NAME】は己の首から提げた飾りに手を当てて目を閉じ、意識を集中させた。
視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚。それを全て遮断し、本来ならば持たざる筈の感覚が、何かを捉えるのを待つ。
「…………」
暫くの間を置いて、【NAME】はゆっくりと目を開いた。
「どうだろうか? 何か感じられたかな」
オリオールの問いに、【NAME】は考え込みながらも浅く頷く。
広く、丘陵全体に広がる歪な雰囲気。各所から立ち上がり暴れ回る、荒々しく凶暴な陰性の気。その中に紛れるように、幾つか特徴的な違和のようなものを感じることは出来た。
だが、
「……複数、かい?」
そう。違和感を覚えたのは複数の箇所。それも、感じるのはどれも別種の違和だ。
一つはここより北方。今居る場所から二つほど丘を越えた先に見える小さな点。他の場所よりも僅かに大きな丘の頂付近で、遠目に見える影は、恐らくは巨大な岩か何かだろう。そこから波紋のようなものが周りに広がっていくようなイメージを得る。
もう一つは、ここより少しばかり西。複数の丘に囲まれた、窪地のようになっている場所だ。そこでは丘陵の各所で騒がしく蠢く凶暴な気配が妙に密集しているようだった。
最後は南だ。自分達が丁度この丘陵に入り込んだ辺り、つまりこの“丘”と“谷”を結ぶ境界の近辺。そこでは、この土地を覆うように広がっている歪な気配が集中し、濃くなっているように感じた。
このうちのどれかが当たりか、もしくは全てが外れか。
一通り全て回ってみるべきだろうか、と【NAME】はオリオールに問うが、意外な事に、彼は首を横に振った。
「この調子では、回れるのは精々が一箇所、というところだろう。【NAME】だって、自覚はあるだろう?」
「…………」
無言で頷く。夜に突入してから、まだ大した距離を移動していないにも拘わらず、戦闘回数はかなりのものだ。しかも、現れる亜獣達はどれもが手強い。既に蓄積された疲労は身体の各所に影響が出始めている。まだ致命的な状況に至るものではないが、この状況で三箇所を巡ろうとすれば恐らく数十戦近くをこなす必要が出てくるだろう。流石にそれは身体が持たない。
「なら、絞るしかない。まぁでも、安心していいよ。大体、何処が当たりかは【NAME】の話を聞いて判ったからね」
笑みを浮かべてそう告げるオリオールに、【NAME】は素直に驚いた。【NAME】からすると、光の塊の所在に繋がるような情報はこれといってなかったように思えたのだが。
「いや、これまでの情報を組み合わせれば大まかには判る。【NAME】が上げた中でもっとも可能性が高いのは、多分ここだ」
オリオールの手にある、これまでの探索状況が描かれた地図。その中で彼が指差したのは、
「……入口?」
自分達が丘陵に入って最初に居た場所。言ってみれば、既に探索を終えた地点である。なのに、そこへもう一度戻る、と?
怪訝と【NAME】はオリオールを見るが、彼は【NAME】の視線を全く気にした様子もなく、軽く肩を竦めて、
「理由については、歩きながら話すよ。あまりここに長居して、また別の亜獣に襲われるのも楽しくない。取り敢えず、移動を開始しよう」
──夢歩く幻、昼夜表裏の境──
道中、オリオールが語ったのは、こんな話だった。
「それ程複雑な話ではないよ。単なる状況の分析と、その中でもっとも自然と思われる流れを推測した場合、境界の近くがもっとも可能性が高い場所だろうと、そう思っただけさ」
思考の道筋は判ったが、理由の説明になってないような気がする。
【NAME】がそう突っ込むと、オリオールは「ほら、手記にもあっただろう?」と指を一本立てて、
「カール氏は“丘”を脱出する寸前に光の塊と遭遇し、そして敗北後には直ぐさま“丘”を脱出した――とね」
ああ、と言われて直ぐに気づく。
脱出する寸前。失敗しても別の場所へと逃げられた。
それはつまり、光の塊と遭遇したときには既に、土地の境界となる場所付近に居たのだと考えるのが自然だ。
「で、【NAME】が違和感を覚えた場所の中で、境界の近くにあったのが最後の一点であった、と。もっとも全域で境界が存在している場所を確定させていたわけではないから、西にあった窪地は兎も角、北のポイントについては同様の条件である可能性もあるのだけれど」
ならば何故。
「それについては、【NAME】が言っていた違和感の種類を比べてみて、かな」
あの話については、した【NAME】からしてもはっきり判っていない状態で語った、至極主観的で曖昧なものだったと思うのだが、それを真に受けて大丈夫なのだろうか。
【NAME】は苦笑しながらそう言うが、オリオールはいやいやと首を振る。
「そうでもないよ。ある程度納得出来るところはあったしね。例えば……そうだね。西のポイントで感じた密集する気配とやらは、そのまま多数の亜獣達が集まって大乱闘でもしてたんじゃないかと。他の解釈をするにも、どれも光の塊とは一致しないものだったから、ここは第一に外して良い」
近場だからと、【NAME】としては一番最初に回るべき場所として考えていたのだが、どうやらそれを口にしなくて正解だったらしい。
「残るは北と南のどちらか、という話になるのだけれど、北から感じたのが波紋の広がり、南から感じたのがこの場所を埋めているこの……厭な気配。それが濃くなっている感じだとするなら、まぁ後者の方が可能性は高いだろう」
「……?」
どうしてそうなるのか。
「これも、カール氏が残した情報からの判断だけどね。ザルナルバック氏が残した光の塊に対する見立ての話があっただろう? 彼は光の塊をここの土地概念自体に繋がりを持っているような類であると考えた。ならばそれ相応の理由というものがある筈だ。例えば、丘全体に広がる気配、この陰性質の歪みの塊であるような存在だった、とかね」
成る程、と【NAME】は頷く。
だが、北のポイントから感じた気配、この土地全体に広がっていくような感覚も大きく違いはないように思えたが。
「まぁね。ただまぁ、そちらについては別の予想があってね。多分そこが、ほら、あの音の出所なんじゃないかって思うんだ」
今も時折耳に届く、歪んだ笛の音。それの大本があの場所だというのか。
「波紋のような、という【NAME】の言葉からの推測だけれどね。ただ、それは脇に置くとしても、カール氏の手記にあった光の塊との接点は、やはり南側の方が強いように思う。それに、南は確実に“丘”の境界に近いところが重要でね。取り敢えずそこが外れであったなら、そのまま境界を抜けてこの“丘”から離脱できる」
その発言に、【NAME】は少し驚く。空振りだった場合は今回の“冒険”を諦めると?
「流石に長時間の探索が出来るような場所ではないだろうし、一度出直しだね。“湖”のように腰を据えるのにも向かない土地であるように思えるし。【NAME】も気づいているだろう? “丘”全体を覆うように包んでいる気配と、それに笛の音。あれはきっと、全ての存在に狂気を植え付けるものだと」
「…………」
それは何となく感じてはいた。夜が始まってから精神を圧迫されるような感覚がずっと続いている。恐らく、長い時間ここに滞在するのは危険だ。
「もっとも、その可能性は低いとは思うけどね。なんせほら」
オリオールが指差した先。
【NAME】達がここにやってきて最初に登った丘の頂に、夜の闇の中でも辛うじて見える程度の淡い輝きを灯した光る塊が複数、ふわふわと漂っているが見えたからだ。
・
光の塊と、カール・シュミットの手記にあった通り、単純にそう呼んではいたが。
実際に目の当たりにすると、それは光の塊というよりも。
「……氷の結晶に近いのかな、これは?」
ふわりふわりと丘の頂に浮かんでいたのは、内部に淡い輝きを宿した、半透明の結晶体だ。
もっと近づき、詳しく観察してみたい誘惑はあったが、
「成る程、ザルナルバック氏がああいった見立てをするのも判るな。まるで気配が形を持っているかのようだ」
結晶とその周囲には、異質な気配が濃厚に漂っており、それは空間の歪みとして視認出来る程のものだった。“丘”全体を包んでいる空気が、この丘の上で滞り、溜まっているかのような印象。しかもその濃度は、【NAME】達が見ている間にもどんどんと増していき、そして一定まで達すると、
「結晶が、生まれた?」
濃密な気配の中心にて、白色の破片が生じてちきちきと音を立てて固まり、新たな結晶と化す。同時に、空間に満ちていた気配は一時的にではあるが大きくその濃度を薄めた。
その一連の流れを見て、オリオールはははぁと声を漏らす。
「なんだ、そういう事か。直に見てみれば、一発だったな」
一体どういう事か。
訊ねる【NAME】に、オリオールは肩を竦めてみせて、
「ほら、つまりアレだよ。今は鬼種の発生が頻繁になったフローリアで冒険してきた【NAME】なら、何度かこれに似た現象を見た事がないかい? 陰性質の概念を固め、集め、そしてそれを形に成す――概念の飽和による存在の顕現化」
「……ああ」
声が漏れた。
それは確かに見た事がある。もっとも記憶に残っているのは、アノーレ島の四大遺跡ガレーで、イェア・ガナッシュが見せてくれたあの儀式だ。
要するに、今目の前で起きているのは――鬼種誕生の瞬間なのか。
「もっとも、見たところあの結晶は鬼種とはまた違う類の存在のようだがね」
そうなのか? と思わず【NAME】は問う。
ああいった状況で生まれてくるのは大概が鬼種であった記憶があるのだが。
「僕も詳しく知っている訳ではないし、学士や異種の友人からの受け売りになるけど、どうも概念飽和による存在の顕現化ってのは、何も鬼種に限った話ではないらしいからね。例えば、対存在である妖精だって、その誕生経緯は同じだと聞くよ」
ならば、今目の前で増えていく結晶は妖精の類である、と?
「……それとはまた違う気がするね。どうも無機質的というか、意思が感じられない存在に見えるし。概念の飽和によって生まれた存在は大抵、その過剰な概念が持つ特性を継承した、意思持つ存在として生じるそうなのだけど……」
そこで言葉を切って、オリオールは前方に見える結晶を見る。
ふわふわと浮かぶ光の群れは、ただ空から降る月の光を取り込み、反射させながらそこに浮かんでいるだけで、それ以上何か行動するような様子はない。
「まぁ、密集した土地概念の飽和によって生じた何かである、としておくのが妥当だろう。……で、見ているだけでは始まらないのは確かだし、そろそろ次に行かねばならないんだが……」
オリオールの言葉に、【NAME】は今回の“冒険”の目的を思い返す。
光の塊が実在しているのか。光の塊の正体は一体何なのか。光の塊を破壊すれば何が起きるのか。
前者二つは、既にある程度確証が持てた。となると、残るは一つとなるわけだが、
「カール氏の一番の“心残り”が、光の塊の討伐だ。ザルナルバック氏の考えが正解であったのか。それを知るためにもさぁ、張り切って始めてくれていいよ、【NAME】!」
「…………」
完全にこちらにぶん投げる態勢のオリオールを、【NAME】は三白眼で睨む。
「ま、まぁ、ぶっちゃけて言ってしまえば、光の塊を破壊してどうなるかという予想はついてはいるのだけれどもね。でも、やはり“心残り”を晴らしてやりたいという気持ちはあるんだ。だから申し訳ないが、【NAME】。少しばかり頑張ってはもらえないだろうか。ほら、あそこで見ているカール氏のためにも、ね」
オリオールが指差す先には、疲れの色濃い男の幻影が、じっと丘の頂を眺めているのが見えた。
だが所詮は幻影。過去の幻である。それに見せてやるためだけに、わざわざこちらに攻撃を仕掛けてきている訳でもない相手に戦いを吹っかけるというのは、凄まじく無駄な労力である気がしてならない。加えて、オリオールが完全に戦闘をこちらに任せるつもりらしいのが癪で仕方無い。
せめてオリオールも戦えと強要すると、最初は渋っていたものの直ぐに折れた。
「……確かに、僕の“冒険”に付き合わせている訳だから、言われると弱いんだよね」
ただ、僕が付き合っても何の得にもならないと思うんだがなぁ、という愚痴は無視する。戦力としてではなく、こちらだけ貧乏くじを引かされるのはお断りだというだけの話なのだから。
諦めの吐息と共に、武器を引き抜く。頂上へと数歩踏み込めば、場に満ちた濃厚な気配が、侵入してくる【NAME】を押し返してくるような錯覚。光の結晶が、ゆらりと揺れてこちらの動きに反応するかのように近付いてくる。
「相手は半概念存在だ。手記の記述を信じるなら、攻撃手段は純粋な概念干渉のみで物理防御は捨てて良いけど、属性に縛られていないせいか攻撃種自体は多彩なようだから注意を。顕現化自体はしている筈だから、物理攻撃も一応通じる筈だよ」
口早に告げられるオリオールの助言に頷きながら、【NAME】は己の思考と身体の動きを戦闘用のものに切り替えていく。
【NAME】の一撃を受けて、半透明の結晶が硬質な音を立てて砕け散った。
しゃり、と硝子が擦れ合うような涼やかな音。それを耳元で聞きながらすり抜けて、【NAME】は流れるような動きで次の結晶へと迫る。
結晶が淡い光を明滅させ、その清廉で美しい姿からは想像もつかない程の、どす黒い、固形化した闇の塊弾が吐き出される。
数は無数。方向は無差別。故に回避行動は難しく、【NAME】は結晶攻撃のために準備していた技法を、迫る弾の迎撃に当てる。武器に伝わる感触は、鈍い土を殴ったようなものに近い。砕け散った闇は小さな紫電を周囲に走らせながら消滅していく。闇の塊弾はそのまま着弾すれば触れた範囲をそのままえぐり取る。既に丘頂上の地面は闇弾によって造り出された穴だらけだ。直撃を受ければかなりのダメージを覚悟せねばならないが、しかし理粒子による干渉を僅かなりと行えばその威力は急激に損なわれて消失する。光の結晶が繰り出す主攻撃への対処法を早い段階で見抜けたのは僥倖だった。それも、
「【NAME】! 右から来るぞ、気をつけろ!」
右手に小剣、左手に複数の印章石を構えて叫ぶオリオールの見識のお陰である。確かに彼が言う通り、オリオールの戦士としての技量は高いものではない。だが冷静な思考と経験に基づく洞察力、状況判断力は折り紙付きだ。状況次第では、ただ腕が立つだけの相棒よりも遙かに有り難い存在といえるだろう。
【NAME】が右手からの攻撃――直線的な光線に対して回避する合間に、オリオールは手の中の石を投げつけ、結晶に対する牽制を行う。印章石による術式攻撃は、その石自体に秘められた力が物を言う。彼が投げた石は指の間で挟める程度の小石だ。駆動する術式は弱い空間整調。本来ならば気分を改める際に場の清めを行う程度の、極々弱い力しか持たないものだ。しかし駆動した術式が広げた空間に捕われた結晶体は、びりりと震えるようにその動きを止める。歪みの飽和から生まれたばかりの結晶は、未だ顕現化して間も無く、その存在自体が安定していない。だからこそ、小石程度の印章石が駆動させる術式の影響すらもダイレクトで受ける。勿論これが空間整調の術が籠められたものでなければそう上手くは働かなかっただろう。この辺りの状況を瞬時に見極めるセンスが、オリオールにはあった。
そうしてオリオールが作ってくれた間を利用し、【NAME】は正面の結晶へと一気に距離を詰める。結晶の奥が明滅し、新たな力がわき上がる。だがそれが外へと形を成す前に、振り上げた【NAME】の一撃が、生まれようとした力ごと結晶を破壊。そして返す動きで右へと身を飛ばした【NAME】は、振り上げた腕をそのまま下ろし、術式による影響が解けて動きを開始したばかりの結晶を叩き壊した。
しゃりしゃりしゃり、と空中に砕かれた結晶が舞い散る音が響く中。武器を振り下ろした姿勢のまま、暫し動きを止めていた【NAME】は、詰めていた息を深々と吐き出すと、その全身から力を抜いた。
「お見事」
ぱちぱちと拍手するオリオールに、【NAME】は軽く手を挙げて答えた後、改めて周囲を見渡す。
結晶は既に全てが破壊されて、場に満ちてた歪な気配もその殆どが消え去っていた。また、徐々に気配が集まってくるような雰囲気を感じなくもなかったが、それは直ぐに起きる事でもないだろう。
取り敢えずこれで、課せられた役目。光の塊を破壊する、という仕事はこなした訳だが。
「…………」
【NAME】はもう一度視線を周囲へ、先刻よりも遠くへと向ける。
この丘の頂上に満ちていた気配自体は薄まってはいる。だが、“丘”自体を包み込む歪んだ気配自体には何の変化がないように思えた。
オリオールからすると、この状況はどう見えているのだろう。
拍手しながら傍に歩いてきたオリオールにそれについての意見を訊くと、
「え? ああ、最初の予想通り、別に何の影響も与えていないんじゃないかな」
は? いや、ザルナルバックの見立てを信じるなら、光の塊を倒す事で何か変化が、という話だったのでは?
【NAME】が焦って問うと、オリオールはあははと笑い、
「そこについては、単なる見立て違いだよ。例えばそうだな。君の主張がそのまま通るとするなら、大きな川で概念飽和が発生して、川の妖精が生まれたとする。この時、川の妖精を退治したら、大きな川に対して何か変化が起きるのか? という話だよ」
起きないの?
「顕現化した時点で、ある程度存在としては切り離されるからね。その妖精は恐らく川の守護を続けるだろうけれど、妖精自体に何かあったとしても、それ自体では川に対して何の影響もでない。それで、これを今回の件に当てはめると」
光の結晶という形で顕現化した時点で、存在概念としてはこの場所と繋がりを持つものの、光の結晶に対して何かをしたところで、この場所自体に影響を与える事は出来ない、と。
「破壊する事で概念を消失させた結果、というのを影響に分類するのなら、影響を与える事にはなるけれどね。今みたいに、結晶を全部破壊したらこの丘が多少すっきりしたみたいに。でも、その程度でしかないという事だ」
「…………」
それが判っていたなら、何故先に言わない。
恨みがましい視線から、こちらの内心を悟ったか、オリオールは焦るようにぽりぽりと頬を掻く。
「あくまで、目的は探り検める事だから。予想はできても、実際にやってみたら違う結果が生まれる場合もあるし、それに」
それに?
【NAME】が鸚鵡返しすると、彼は苦笑を浮かべて、
「カール・シュミット氏が辿った軌跡を追う――それを主眼とするならば、やはりこの“心残り”は、しっかり形として見せてあげたかったんだ。……例え、残念な結果であろうとも、ね」
一瞬、オリオールの視線が彼方へ逸れる。
丘の中腹。草原の中に一人立ち、丘の頂上へと視線を向けていた男の幻影は、既に無く、
「……あれ?」
と、釣られてそちらに目を向けた【NAME】は、丈の短い草原の中から小さく飛び出す棒のようなものを見た。
気になり、その傍へと移動して草原を分ける。するとそこには、
「誰かの装備品、か」
打ち捨てられていたのは、主に武器と防具だ。雑に投げ捨てられたらしく、武器は半ば地面に突き刺さり、防具は留め金などが全て外された状態で地面に転がされていた。
その中の一つを手に取り、矯めつ眇めつしていたオリオールは、
「ほぅ」
小さく唸ると、防具の一部に指を当ててこちらに見せる。
そこには小さく人名らしき文字が刻まれており、表記通りに読むならば、
「――ザルナルバック。どうやらこの装備は、ここで亡くなったとされる彼の遺品であるらしい」
成る程と頷いて、しかし【NAME】は怪訝と辺りを見回す。
装備だけがあり、彼の遺体らしきものがない。それはどういう事だろうか、と。
そんな疑問に対して、オリオールは苦い笑みを浮かべて、
「つまり、“湖”の時とは違い、ここでのカール氏は自分の部下を自分の手で弔えたと、そういう事なのだろうね」
・
その後、【NAME】達は新たな亜獣に遭遇する前にと、素早く“丘”を脱出した。既に一度通過した経験のある場所から境界を跨ぎ、“谷”へと戻った【NAME】達は、一度態勢を整えるべく、駐屯地へ目指して歩き出す。
「流石に今回はきつかったな……」
呟くオリオールの身体からは何時もの精力的な雰囲気が無い。全く同意だと【NAME】も頷くが、
「――で、じゃあ次の“冒険”についての話なのだけれど」
切り替え早いな! と、オリオールの発言に心底驚く。というか、まだやるつもりなのか。
【NAME】が呆れた風に、遠回しにもう終わりでいいのではないかと主張してみるも、オリオールの方はといえば「まだまだやるつもりだよ」と全く通じていない返事。
「とはいえ、残るところは最後の核心になりそうな部分だし、他に比較的どうでもいい謎は……」
おい。今、わざと核心外してるとかどうでもいい謎とか言ったか?
「言ってないよ? で、そうだね。次はあそこについての記述が本当なのか。それを確かめてみようか。【NAME】、手記を頼む」
【NAME】の真顔の突っ込みを笑顔で躱しながら、オリオールは【NAME】にカールの手記を取り出すよう促す。
渡した手記をぺらぺらと捲り、止めた頁は後半を過ぎた辺りだ。
「場所は“何処かのエルツァン海岸線”だ」
何処かって何処だ。
【NAME】の当然極まる疑問に、しかしオリオールは開いた頁を見ながらうーんと考え込むように首を捻る。
「それが、判らないんだ。手記に書かれた内容から判断するなら、少なくとも僕等が知る、陣地の周辺に広がる東西のエルツァン海岸線ではない。これと一致するような描写が一切ないからね。もっとも、先刻の“丘”のような例もある訳だから断言は出来ないけれど、それでも確率としては極めて低い筈だ」
その判断を信用するならば、手記に書かれた海岸線とやらへ辿り着くには、エルツァン内陸に存在する地形からそこへ繋がる場所を探さねばならない、という話になるのだろうか。
東西のエルツァン海岸線から、そのまま海沿いにぐるりと島を一周出来るなら話は楽なのだが、
「残念ながら、どちらの海岸も途中で崖なりなんなりでそのまま岸沿いを進んでいくのは難しいしね。船を使って、という方法も採れなくはないけれど、ただ海からのアプローチは、これまでの情報から考えると多分無理だろうね」
それはどういう意味だろうか。
「単純に、船で見て回った場合、陣が置かれているあの海岸以外に、砂の浜辺がないんだよ。けれど、手記にある“何処かのエルツァン海岸線”とやらは、明らかに砂浜だ」
「…………」
常識的に考えるなら、カール・シュミットが到達したという“何処かのエルツァン海岸線”とやらは存在していないか、もしくは陣周辺に存在する砂浜の過去の姿、という事になる。
だが、これまで【NAME】がエルツァン島を探検する中で体験した、島の中で発揮されている異常なルール。そのルール上でならば、島の外から見て存在しない筈の砂浜に、島の内からなら辿り着ける。そんな有り得ない事象も十分に起こりうる事を、【NAME】は、そしてオリオールは既に知っていた。
「取り敢えず、次の目的地はこの“何処かのエルツァン海岸線”としよう。ヒントとなる情報は殆ど無い。取り敢えず“谷”と“森”。それ以外の地形に足を運んで、そこから別の海岸線へと降りられる道が無いか。探してみるしかないだろう」
どうやら、次は今まで以上に場所を探す事自体が面倒な話になりそうだ。
「因みに、そこで僕等が何を調べるかというと、この海岸でカール達探検隊のメンバーが多数死傷したらしくてね。その原因がなんなのかを突き止める予定だ」
「…………」
もう見つからなくても良いんじゃないだろうか、それ。
真なる楽園 弔う幻、真実は奇なり
──北エルツァン海岸──
思案の末、【NAME】は一先ず“鬼喰らいの鬼”については後回しとし、今回はオリオールの“冒険”に注力する事にした。
決断は下した。ならば後は躊躇わず行動するのみだ。【NAME】とオリオールは、早速共に海岸へと降りて調査を開始する。
まずは、海岸についての概略を把握する。海岸はそれ程大規模なものではなく、見える範囲でその全域が収められる程度の広さだ。浜は砂地。幅は1キロに届かない程、奥行きも然程ではなく50メートルくらいで、浜との境界は森の緑で線引かれていた。
しかし海の様子を確かめると、少しばかり奇妙な、違和感のようなものを覚える。常駐軍の陣が置かれた海岸とは、どうも趣が違うように感じるのだ。
その疑問に、オリオールからこんな海岸がエルツァン島に存在していたという話を軍の方は把握していないという話を聞く。既に軍はエルツァン島沿岸を船を使って全周し、島への上陸が可能な地形は一箇所――軍が陣を構えるあの海岸しかないと把握しているというのにだ。
つまり、今自分達が居る海岸は、海側からでは確認できない場所だという事になる。
「位置としては、ここまでの移動経路から考えれば島の北側にある筈だとは思うのだけど、そもそもこの海岸が、本当にエルツァン島の外縁を構築しているかどうか自体が疑問だね」
どういう意味だろう。
「この浜も、あの海も、これまで島の中で見てきたような、独立した性質を持つ土地と同一の代物なのではないか、というお話だ」
「ああ」
成る程、それならば島の外側からこの海岸が確認できないという話も判る。ならば、もしかすると海を泳いで暫く進んでいけば、
「海の途中に境界があって、そこを抜ければ唐突に陸地に打ち上げられるかもしれないね」
「…………」
想像すると凄まじくシュールな光景だ。
口元を引きつらせる【NAME】に、オリオールも似たような顔つきで笑い、
「それが真実であるのか。確かめてみたい気持ちはあるけれど、君に“鬼喰らいの鬼”討伐を一旦延期してもらって付き合わせているんだ。まずは最初の目的を達する事だけに注力するとしよう」
了解、と【NAME】は頷き、そして話を要の部分へと向ける。
――果たして、この場所はカール・シュミットの手記にあった海岸と同じ場所なのだろうか?
「君はどう思う?」
問われて、【NAME】は肩を竦めて首を振る。
カール・シュミットの手記において、この海岸についての記述があるのは後半を過ぎ、手記の終わりにも近い位置だ。この場所へと辿り着く前の段階で、既にカール達は心身共に限界に近い状態にあったらしく、手記の内容も極めて抽象的、断片的なものになっている。手記を取り出し、海岸について描かれている頁を開いて確認するも、そこに書かれているのは砂の浜と、二枚貝のようなものの絵と、死についてを繰り返す文字のみだ。
絵の方は単純化されたものであるが故か何処か牧歌的な雰囲気すらあるのに対し、文字の方は書かれた内容もそうだが文字自体も何処かおどろおどろしく、どうも絵と文字のイメージが一致しない上に、元々の情報量が少なすぎる。もし特定できるとするならば、
「判るのは、砂浜と貝、か。砂浜は一致しているのだから、もう一つ。貝を見つけられれば良い、という話になるのだろうけれど」
――しかし、貝くらいどこの浜にでも居るのでは?
【NAME】の指摘に、オリオールは短く頷く。
「居るね。だから加えてもう一つ。カール氏が死んだと綴るような何かがあれば、という事になる。要するに、もう一つの目的である、カール達に一体何があったのか。それに相当するようなところを見つけられれば当たり、という訳だ」
先に手記と同じ場所なのかを見極めてから、詳しくここで何があったのかを調べる。そうすることで無駄手間が省けると思ったのだが、先にカール達が遭遇した出来事の痕跡を見つけなければ、そもそも場所の特定自体ができないとは。
小さく溜息をついた【NAME】は、いや待てよ、と気づく。
もしここがカール達の辿り着いた浜であるならば、アレが見えるのではないだろうか。
これまでも何度も見た姿。カール・シュミットと思しき男の幻影だ。
「……ああ、言われてみればそうだね。それを見つけられれば、確かに十分な証拠になり得る」
ふむ、と小さく鼻奥を鳴らして、オリオールは一度辺りを見回し、
「これまでの経験では、あの幻は僕等が近付くと姿を現す事が多かった。となると兎に角ここを虱潰しに歩き回ってみるのが良いか。幸い、それ程広い場所じゃない。直ぐに確かめる事が出来る筈だ」
早速、始めるとしよう。そう言って歩き出すオリオールに【NAME】も続いた。
・
幻影は【NAME】達が近付く事で現れる。それはこれまでの経験から判っていた事だ。故に、幻影が存在するかどうかを確かめるには、各所を歩き回る必要があった。
幻影を発生させるために近付かねばならない範囲はそれ程広くはないが、しかし狭いという程でもない。発生する地点から十数メートルも近寄れば十分であるのは経験上判っていた。なので、【NAME】達はそれを計算に入れつつ浜辺をぐねぐねと、正に虱潰しにするようにしながら、同時に手記の記述にあった貝と該当するようなものがないか、地面を確認しつつ歩いていく。
と、内陸から海岸のギリギリまで移動した時だ。
「【NAME】、来るぞ」
短いオリオールの警告。既に【NAME】も気づいている。武器を手に取り、構えるのは海側だ。
波打つ海面を、大きく割るようにして姿を現したのは、数匹の亜獣だ。その姿形は見覚えがある。常駐軍が陣を構える海岸で時折確認されている類の亜獣だ。
しかし、
「少し、様子が違うようではあるね」
オリオールの言う通り、外見は似通っているが、細部や動き、内側から溢れる気配はより荒々しく、手強い印象を与えていた。東西エルツァンの海岸線で相手をした亜獣達と同等だと甘く見れば、痛い目に遭うだろう。
「もっとも、エルツァン内陸に出てくる亜獣達程でも無いように見えるけれど、だからといって油断する必要もない。気を引き締めていこう」
オリオールの言葉に頷く間に、亜獣達は明確な害意を放ちながら距離を詰めてくる。
それに対抗するべく、【NAME】は武器持つ手に力を込めて、一歩、強く砂を蹴って前へと進み出た。
多少手強くはあったが、倒せない相手ではない。【NAME】は手早く一匹、二匹と片付け、そして最後の亜獣に止めを刺す。
背後では、オリオールも相手していた一匹を丁度仕留めた処のようで、小剣を一度鋭く振ってから腰裏の鞘へと戻していた。
「……にしても、奇妙な話だね」
亜獣達の亡骸を見下ろし、オリオールは首を捻る。
「この海岸に出てくる亜獣も、精々この程度の強さだ。土地の特性としても、単なる海岸にしか見えない。それほど際立った危険性があるような場所ではない筈なんだが、カール氏はここで多くの死者を出したとだけ書いている」
ふーむ、と【NAME】も腕を組む。
オリオールが何を言いたいのかは判る。カール・シュミットの探検隊は、相応の力量を持つ者達の集まりだ。それは、これまで彼等の足跡を辿った自分達が遭遇した様々な危険を考えれば明白だ。被害者を出しつつも、全滅までには陥らずどうにかそこを切り抜けてきた彼等の力はかなりのものである筈で、その事を考えるなら、今自分が戦ったような、陣周辺の海岸で出る亜獣に毛が生えた程度の強さしか持たない相手に、後れを取るとは思えないのだ。
そうなると、やはりカール達が辿り着いた海岸はここでは無いのか、という話になるが。
「……どうだろうね。取り敢えず、結論は海岸全域の調査を終えてからにしようか」
異論は無い。もしかしたら、新たな何かが見つかるかもという可能性はある。
歩き出すオリオールに、【NAME】も無言で従った。
・
そうして、時間にして一時間程で海岸の探索は終わった。
元々、見晴らしが良く障害物もない場所だ。ただ歩き回るだけであるなら大した時間を取ることもない。途中、幾度か亜獣と遭遇したものの、最初に出くわしたような亜獣達と大した違いは見受けられず、手記にあったような貝の姿も無ければ、カール・シュミットの幻影を見つける事も出来なかった。
海岸の終端。砂浜と岩場の境界に立ったオリオールは、眼前に聳える切り立った崖を前にし、ふーむと唸る。
「流石に、この崖を越えていく訳にもいかないし、結論づけるなら、ここはつまりは“外れ”であった、という事なのかな?」
問いに、【NAME】も少し思案してから、同様の結論を得る。
証拠となるようなものが何も見つからなかった現状を考えるなら、そう判断せざるを得ないだろう。
【NAME】がそう答えを返すと、暫し、場を沈黙が埋める。
小さく、オリオールが溜息をついて、
「……【NAME】には悪いことをしたね。折角“鬼喰らいの鬼”の痕跡を見つけたっていうのに、わざわざそれを取りやめてこちらの調査に回った結果がこれでは。申し訳ない」
オリオールのせい、という訳でもあるまいし。謝られるようなものでもないだろう。
淡々と返すが、オリオールはしかし苦笑を深めて、
「まぁそれでも、ね。やはり、僕の“冒険”に付き合わせた結果でもあるし。……それにしても、ここが外れとなると、では一体カール氏は何処の海岸に辿り着いたのだろうね。正直な話、僕の直感はここ以外にないと告げていたのだけれど――ん?」
と、ぐるりと視線を巡らせていたオリオールの動きがぴたりと止まった。
「【NAME】。あれを」
オリオールが指差したのは、砂浜の向こう。切り立った崖の下に広がる、半ば海に沈んだ岩場の中だ。
そこにぽつりと、海の中に半分身を埋めるように、人影のようなものが立っているのが見えた。
影の外見には、見覚えがある。あれは、
「カール・シュミット……か?」
これまで幾度も見てきた、幻影の男の姿だった。
幻の男は、腰まで海に浸かった状態で、渋い表情で空と崖側を交互に見やり、そして暫くの後にゆっくりと崖に向かって歩いていくと、そのまま消えてしまった。
影が消えていった場所は、海岸の縁に立つ【NAME】達からするとどうなっているのか確認出来ない。【NAME】とオリオールは何も言わずに顔を見合わせてから、合図も無くざぶざぶと、二人海の中へと分け入る。
そうして、幻影が立っていた場所へと移動した【NAME】達は、幻影と同じように崖側を見、
「……成る程ね」
オリオールが溢した納得の呟きは、【NAME】の内心と同様のものだった。
幻影が消えていった場所。ほぼ垂直に聳える崖の下方にぽっかりと、幅にして十数メートル近い巨大な空洞が開いていたのだ。
──弔う幻、真実は奇なり──
洞窟の中へと入れば、もう疑いようがなかった。この場所こそが、カール・シュミットが辿り着いた海岸だったのだと。
崖の側面に開いた大穴の中は、真っ直ぐの一本道だ。洞窟の内部はひんやりとしており、風が通っていく気配は無い。内部は下面が海水に満たされている状態で、その深さは大凡膝丈。海水の向こうにはごつごつとした岩の地面が見える。凹凸は大きく、気をつけて歩かねば足を取られて転倒してしまう事も有り得るだろう。足が半ば海水に浸かった今の状態ならば特にだ。
そんな洞窟の中で目を引いたのが、海水に半ば埋もれるようにして存在する、白色扇状の巨大な物体。緩やかな流線形を持つそれは、有り体に言えば二枚貝だ。 大きさにして2メートル強はあろうかという巨大貝。その姿は洞窟の各所で見る事が出来、そしてこれこそがカール達がこの場所にやってきた事を示すものだった。
「カール・シュミットの手記にあった貝とは、つまりこれの事なのだろうね」
内の一つ。洞窟の縁を背にして、どんと鎮座している白色の巨大貝。少し高い位置にあるお陰で、完全に地表へ露出している状態のそれを靴裏で踏みながら、オリオールは眇め見る。
カール・シュミットの手記に描かれていた白色の貝。確かに、こうも大きなものであるなら、特筆に値する代物ではある。
白色貝は殻をぴったりと隙間無く閉じていて、微動だにしない。恐らくは岩場に固着する類の貝なのだろう。貝の表面には無数の傷や汚れ、付着物などがあり、 この姿のまま長い期間一切動いていないように見える。生きているなら、当然外へと管を出して外部の何らかを餌にするのだろうが、今は自分達が傍に居るせいか、それとも死骸であるのか、殻は閉じたまま僅かたりとも開く様子はない。
オリオールは足を貝の表面から下ろし、ふむと唸る。
「栄養のある堆積物が溜まるような地形でもないここに貝が複数棲息しているという事は、この洞窟は潮が満ちれば恐らく完全に海の中へと没するのだろうね。そして、カール氏達は、あの幻の様子からすると」
オリオールが視線を横へとずらす。向けた先は洞窟の中央。そこには、海水に膝下を埋めながらもするすると、何の障害も無い速度で歩いていく幻影の男の姿があった。
「水が完全に引いた状態。つまり干潮の時にこの洞窟に入ったのではないかと考えられるね」
にしても、カールは何故こんな洞窟の中に入っていったのだろうか?
「さて、そこまではね。単なる好奇心か、それとも休息場所を探していたのか。【NAME】、洞窟の外で見掛けた幻影の仕草、覚えているかい?」
貝が陣取る高台から降りたオリオールは、ざぶりと海水を割りながら洞窟の奥へと歩き出す。【NAME】もその後に続きつつ、彼の問いに記憶を掘り返す。
洞窟の外。岩場の中に立っていたカール・シュミットの幻影は、空と洞窟を交互に見比べていたような気がする。
「空の様子を確かめて、洞窟の中に入った。そこから連想できることと言えば、まぁ、単純に」
雨、か。
「うん。雨を避けるためにこの洞窟に入って……そしていざ入ってみれば、意外と奥行きがある事に気づいて、どんどん奥へ進んでいったんだろうね」
そう話す間に、先行していた幻影が消滅するが、洞窟はまだ奥へと続いている。入口から差し込む光はもうかなり遠のいて、行く手は薄暗い闇に包まれていた。 足場が悪い事もあり、そろそろ照明がないと危険かもしれない。そう【NAME】が思う間に、かちりと硬質の音と共に、先を行くオリオールの手元に淡い光――輝石の輝きが灯るのが見えた。
「海岸でカール氏の幻影を殆ど見る事がなかったのは、外に滞在していた時間自体が単純に短かったから、という辺りが順当か。何にせよ」
手にある光を掲げ、洞窟の奥を照らす。続く一本道は、奥へと進むに従ってその幅を狭めているようだ。入口部分は海からの侵食により削られたものなのか十数メートルと広いものだったが、今【NAME】達の前に伸びる道は、既に十メートルを切る程の幅となっている。
「カール氏達がこの先へと進んでいった結果が、手記にあった死の記述に繋がっているというのなら。その真相を探るためにやってきた僕等も同様に、この洞窟の奥へと行かねばならない。……気が滅入る話だけれどもね」
全くだ、と【NAME】はも毒づく。
つまりこの先に、既に残り少なくなっていたカール・シュミット探検隊に止めを刺すような程の危険が待っているという事になるのだから。
「救いは、カール氏達と違い、僕等はこの先――もしくはこの洞窟自体に大きな危険が存在する事が判っている点か。ここまで歩いてきた限りでは、鬼種や、強力な亜獣の気配のようなものは感じないけれども。【NAME】はどうだい?」
振り返っての問いに、【NAME】は首を横に振った。
エルツァン島内の他の地域のような強烈な陰性質の気配も無ければ、大きな土地概念の歪みすらも感じない。陰性質の気配が無いという事はつまり、格の高い鬼種もここには存在していないという事になる。勿論、鬼種がその気配を取り繕っているというのなら話は別だが、
「そもそも、外から誰かがやってくる事が稀だろうエルツァンで、気配をいちいち隠す手間を掛ける必要性も思いつかないから、そこについてはあまり警戒しなくてもいいんじゃないかな」
その理屈に従うならば、この洞窟には際立った危険――少なくとも単体で強大な力を持つ鬼や亜獣は存在していない事になるのだが、そうなるとカール達が見舞われた死に繋がる事柄とは、いよいよもって何だったのか、という話になる。
最も可能性が高いと思われた、強力な鬼ないしは亜獣の襲撃を省くとするなら、次に思いつくのは自然現象、事故あたりだ。現場をこの洞窟と想定すると、予想出来る状況といえば、
「……満潮による洞窟水没での溺死か、地形的な問題――例えばこの洞窟の何処かでぽっかり地面に穴が開いていて、不注意でそこに落下したとかそういう類のもの。あと思いつくのは、洞窟の奥に毒の空気溜まりがある、辺りか」
オリオールが上げた例は、どれも妥当な処だった。特に満潮による水没は容易に想像出来るし、毒気溜まりでの死も洞窟探索では良く聞く話だ。もっとも、その両方が、という事は然う然う無く、地形的に可能性が高いのは溺死の方だろう。
だが、だ。
「洞窟を一通り調べて、これといったものが見つからなければ、探検隊から出た死者の原因は満潮による溺死と考える事になりそうだけれど……それは正直、どうにも納得しがたいものがあるよね」
呟くオリオールに、【NAME】も同意の頷きを返す。
カール・シュミット達はかなりの経験を積んだ探検家の集まりと言って良い。そんな彼等が、満干による洞窟内の水位変化を考慮せずに行動している筈がないのだ。
「やはり、他に要因があると考えた方がまだ納得がいく。だから、何かが、この洞窟にあるとは思うのだけれど……」
ざぶり、と海水を割りながら、オリオールが止まっていた歩みを再開する。
彼の手の中から溢れる光は洞窟の奥を僅かに照らすのみで、広がる闇の向こうに何があるのかは未だ謎のままだ。
果たして鬼が出るか蛇が出るか。
【NAME】は武器の柄に手を置きながら、先行くオリオールに続き、歩き出す。
・
洞窟の行き止まりは、案外と早く訪れた。
入口から100メートル程進んだ辺りで、徐々に細くなっていた道が突如広がり、大きな楕円形の空間に繋がっていた。そこが、洞窟の終端だった。
空間の広さは大雑把に見積もって30から50メートル程だろうか。楕円の広間はそこで行き止まりとなっており、広間に繋がる道は、【NAME】達が歩いてきた一本道のみ。
そして中に存在していたのは、無数の貝、貝、貝だ。棚状になった段差の上にぎっしりと、大きさにして1メートルを超える巨大貝がひしめく姿は不気味でありつつも、壮観であり、幻想的ですらあった。
「これはまた、凄い数だね。群棲地にでもなっているのかな、ここは」
呆れたような声音で広間の中の様子を眺めるオリオール。
床面に浅く海水が張る中、【NAME】はその光景に驚きながら、一体どれだけの数の、どのような貝が居るのか。生まれた好奇心そのまま、楕円の空間の中へ足を一歩踏み入れて、
「――?」
突然、目の前に現れた幻に、【NAME】とオリオールは固まるように動きを止めた。
出現した幻は、いつもの男の姿。だが、気になったのはその男が見せた動作である。
これまで洞窟を歩いてきた時に見た幻影の多くは、男は慎重な様子で洞窟の中を確かめながら奥へ奥へと進んでいた。
しかし、今【NAME】達の前に姿を現した幻影は、正に必死とも言える形相で、【NAME】達が歩いてきた一本道を、半ば転がるような勢いで走り戻っていくのだ。
(どういう事だ……?)
遠ざかる幻の背中を、【NAME】と唖然として眺めていたが、
「……ん?」
と、隣で似たような顔つきで幻影を見ていたオリオールが、怪訝と声を漏らすと両眼を鋭く細め、凝らす。
「あれは――」
オリオールの視線の先。幻影が転倒し、何か直ぐ傍に向かって叫ぶように口を大きく開き、そして武器を何度も振る仕草をするも、結局は諦めてまた走り出す。そこで幻は解けるように消滅していったのだが、
「【NAME】」
振り向くと、オリオールは神妙な顔つきで、ぴんと指を一本立ててみせ、
「先刻、僕が言ったことなのだけれど」
何の話だろうか。怪訝と見返すと、オリオールはほら、と言葉を続ける。
「気配を隠す必要がないから、警戒しなくても良いという話」
それが何か?
何が言いたいのかが判らず首を捻ると、オリオールは自嘲するような湿気た笑みを浮かべて、
「取り消す事にするよ。……そうか、至極辛抱強く、尚且つ普段の消耗を抑えられる狩人であるなら、エルツァンであっても、気配を消し、そして待ち伏せる意味はあるのだろう。【NAME】、あれ、見えるかい?」
オリオールが指差したのは、先刻の幻が転倒し、何事かを叫んでいた場所だ。所詮は幻影。声までを再現することは出来ないのか、何を叫んでいたまでは把握できないが、しかしそこでカールに何かが起きた事だけは判る。
あそこに何かあるのか、とオリオールの指先を辿るが、そこには白色の巨大貝が一つ、ぽつんとその身を横たえているだけ。
一体あれがどうかしたというのだ。ここまで来る途中、同じような貝は何度も確認しているではないか、とオリオールに抗議しかけて、【NAME】はその白貝の合わせ目から外へと飛び出た何かに気づき、口を噤む。
閉じられた二枚貝の隙間。貝の内側から外側へと飛び出ていたのは、細い鎖鉄をつなぎ合わせたものだ。武器防具に関しては馴染みのある【NAME】には直ぐに判った。あれは、鎖帷子として使われるものの断片であると。
「――――」
そこから、一気に様々な事が繋がった気がした。
恐る恐る、広間を振り返る。
広い空間を埋めるように、無数の貝が、みっちりとその合わせを閉じ、微動だにせず沈黙している。
だが、良く良くそれらを順番に眺めていくと、所々に、痕跡があるのだ。
例えば手前の棚の一番奥にある巨大な貝の表面には、半ば朽ちかけた槍が突き刺さっていたり。
例えばもっとも傍に並んだ三つの巨大貝の内、左のものの表面には、普通に考えれば有り得ないであろう、まるで炎に焼かれたかのような焦げ痕があり、そして周辺にはまるで背嚢の中身をぶちまけたかのように、様々な品の残骸が散らばっていたり。
先刻の幻影。目の前に転がる幾つかの痕跡。そして手記の顛末。
それらを結びつければ、導き出される結論は、極々単純なものだ。
――つまり、洞窟に侵入してから既に幾度も見掛けている巨大な貝達こそが、カール達を窮地に陥れた元凶である、のだろう。
勿論、それはあくまで状況証拠のみだ。【NAME】達がここまで来る間、巨大貝のどれもが、一切身動きをみせないまま沈黙している。自分の勘違い、若しくは巨大貝達が活動停止状態にある。そういう可能性もある。
しかし、しかしだ。
もしも、この巨大貝達が推測通りの、極めて危険な狩猟者であるのならば。
今の自分達は、その巣穴の奥地にまで、ほいほいと入り込んでしまっている状態なのだ。
【NAME】はすぐ傍にある、貝殻の合わせ目から鎖を垂らしたまま微動だにしない巨大貝に視線を向けたまま、オリオールに提案する。
今すぐここから離れた方が良い、と。少なくとも、早急に、この広間からは離れるべきだ。
「手遅れになる前で良かった。【NAME】、今すぐここから――」
「――ガギ! ガギギガギガギギっ!」
「なっ!?」
突然鳴り響く、硬質な何かを激しく擦り合わせたような耳障りな音。
一瞬、何処から発生したのか判断できなかった程の大音は、目の前の巨大な白貝から生じたものだ。波打つ貝殻の口が、左右に、高速に揺れて、そこから凄まじい音が洞窟内に反響する。
そして僅かな停止、一拍の間を置いて、ばくんと、白貝の片側が開き、貝の中身が【NAME】の目の前に露出する。一般的に、貝殻の内部には本体――軟体の身体がある筈なのだが、そこにあったのは無数の触手と、それに埋もれるようにして貝の内側で転がるのは、
「骨……っ」
無数の骨と、正体が特定できぬ何かの残骸だ。それは繊維であったり、鉄であったり、石であったり。判然としない色々なものが、貝の内側で触手と共に蠢いていた。
「【NAME】、逃げるぞ! どんな攻撃をしてくるのかは知らないが、所詮相手は貝だ、離れてしまえばどうということは――」
オリオールの声が、驚きによって途切れた。【NAME】も眼前に生じた光景に、ぽかんと口を開けて固まる。
「動いたっ!?」
逃げ出そうとした【NAME】達の慌ただしい動きに反応するように、半ば海水に埋もれる状態であった白色の巨大貝が、唐突に浮き上がったのだ。
貝の下部から支えるように突き出たのは、こちらも無数の触手のような物体。それらはびたびたと洞窟の床を埋める海を割り削るように動き、巨大な貝の身を素早く前進させ、そして開かれた貝の殻を水平に広げたまま、その身を高速で回転させた。
波打つ貝殻の先端が、ふぉん、と低音を伴いながら洞窟内の大気を裂く。鋭く走った先端は、寸でのところで回避した【NAME】の傍を通り抜けた後、背後、洞窟の岩壁をまるで飴のように切り裂いた。
ぐるぐると数度、勢いのままに回転し、そして停止する。足踏みするように貝の下方から伸びた触手が蠢動し、開かれた貝の口が勢い良く閉じて、
「ガギガギガギギ――」
波打つ合わせ目を擦り合わせ、強烈な音を出す。
身の毛がよだつような異音。こちらを威嚇でもしているのか、と【NAME】は身構えながら考えるが、
「――ガギ――ガギギギ」
まるでその音に呼応するかのように。
洞窟の別の場所から、似たような音が複数、木霊となって聞こえてきた事に気づいて、【NAME】は己の推測を改めた。
これは威嚇ではなく――合図だ、と。
「……【NAME】。あれを」
オリオールが指差す先、【NAME】達がこれまで歩いてきた洞窟の一本道。その各所に点々と身を沈めていた白色貝達が、次々とその下部から触手を伸ばし、身体を浮かび上がらせる様子が見えた。貝の口がむずむずと開き始め、下方の触手が波打つように動き、目の前でまた大きく口を開いて回転を始めた貝のように、行動を開始しようとしている。
「これは、まずいな……」
短く、オリオールが呻く。
ここまでの道中、見掛けた巨大貝の数は十の指では足りない。その全てが、動きだし、こちらを標的と定めたのであれば、【NAME】達は洞窟から脱出する為には彼等全てを相手せねばならない。
いや、それだけで済めばまだマシだろう。何せ、今【NAME】達の傍に存在する広間では、その白色貝が正に無数に横たわっているのだ。
「…………」
【NAME】は一瞬、視線をそちらに飛ばす。まだ、広間の方では大きな変化はない。だが、それもまだという前置きがあっての事だ。
視線を前へと戻す。先刻、先端による一撃を放ってきた大貝は、【NAME】とオリオールの退路を塞ぐように洞窟の中央に陣取り、ゆっくりと、広間の方へと押し出すように、こちらとの距離を詰めてくる。
その背後には、別の巨大貝が二つ、下部より生えた触手を蠢かせながら迫ってくるのが見えた。
「全く、巣に餌を追い込む親さながらだな。……【NAME】、突破できそうかい?」
他に道はないのだ。できるできないではない。やるしかないだろう。
「心強い言葉だね」
好きでこんな発言をしている訳でもないのだが、毒づいたところで状況は改善しないのだから仕方無い。前向きに行くしかあるまい。
【NAME】が一度の嘆息を置いて、心と身体を戦闘状態へと切り替えると同時。視線の先、ばくんと開かれた貝の先端が、鈍い風切りの音と共に【NAME】目掛けて放たれる。
高速で迫るのは鋼の刃にも匹敵する鋭角の脅威だ。これを受けるという選択は、直ぐにでもこの場を脱するべき状況である事も加味すれば愚手の極み。走る先端、その下方を潜るように避けて、そしてそのまま貝の後方、洞窟の入口目掛けて走り出そうとする。
が、
「ぅお、っと!」
背面、オリオールが悲鳴にも似た声を上げて後ろへ下がるのを見て、すり抜けるという選択肢を捨てる。【NAME】が前方へと進んだのに対し、オリオールは後ろに下がってしまった。つまり分断された形で、ここで自分だけが走り出せばオリオールは取り残される形となる。オリオールの戦闘に関する力量は高い方ではない。だが、逃げるという事に限って言えば、彼の腕前はかなりのものだ。オリオール自身が自分の強さを理解しているが故、それを補う術に長けている、というべきか。純粋な破壊、攻撃ではなく搦め手による攪乱を得手としているのだ。だから彼を残して逃げたとしても、恐らくは大丈夫、だとは思うのだが。
「…………」
僅かな逡巡の後、【NAME】はすり抜け、走り去ろうとしていた動きを止めて、身を翻し、己の武器を振る。逃げるのは、傍の一つ、そして迫る二つの貝を破壊してからでも遅くは無いだろう、と。
貝の先端は未だ回転したまま。数瞬と待たず、武器を振りかぶるために上方へ伸ばした【NAME】の胴を真中から薙ぐだろう。
だからそれよりも速く。
技法により力を乗せた一撃を、露出したままの貝の内側目掛けて叩き付ける。
三体の巨大貝の猛攻をどうにか潜り抜けた後。【NAME】とオリオールは全力で洞窟を駆け戻る。
丁度潮が引いていくタイミングであった事が幸いし、洞窟に入った時は膝下辺りまではあった水深は、既に踝を濡らす程度にまで下がっていた。お陰で本来の姿ともいうべき形態となった巨大貝達からの襲撃も、回避と逃亡に全力を注ぎ込んだ【NAME】達の足を、完全に止めるまでには至らない。
何せこちらも必死だ。触手という足を使った巨大貝の移動速度は、その姿から想像できる速さの倍はあった。もし途中、一体相手であっても本格的な交戦状態となっていたならば、それを倒す前に別の巨大貝達に次々と追いつかれ、そのまま数の力によって押しつぶされていただろう。
息が苦しくなるほどの全力でもって洞窟を駆け抜けた【NAME】とオリオールは、勢いそのまま、外界を照らす陽光の下に飛び出し、海辺の際まで一気に走る。
そして恐る恐る背後を振り返り、洞窟の奥、光が完全に届かない薄闇の向こうから、あの白色の巨大貝が奇怪な音と共に出てこないことを確認して、深々と安堵の吐息をついた。
・
「……つまりは、こういう事なのだろうね」
洞窟を離れた【NAME】達は、岩場を抜けて、海岸に戻る。サクサクと砂に足跡を付けながら歩く先は、この海岸へと入ってきた時に使った獣道だ。
「カール氏達探検隊は、海岸へとやってきた際に雨に降られて、雨宿りの為に洞窟へと入った。その流れで洞窟の調査を開始した彼等は、最深部のあの広間に入った処で、本性を現した貝達の襲撃を受けて、多数の被害者を出した、と」
手記には確かに貝が描かれてはいたが、まさか死因自体がその貝によるものだったとは。
「実際に襲われていなければ、僕等も想像できなかっただろうね」
苦く笑うオリオールに、同意の嘆息を漏らす。実際に戦ってみると、白色の貝の戦闘力は見掛け以上の代物で、エルツァンの他所でこれまで遭遇してきた難敵達に勝るとも劣らない程のものだった。それがあれだけの数だ。カールの探検隊が多くの死者を出したというのも頷ける話だろう。
今回の“冒険”の目的が、あくまでカール達に何が起きたのかを探るもので良かった。あの白色貝達と、まともにやり合わねばならないような目的であったなら、こちらも被害無く切り抜けるという訳にはいかなかっただろう。
「ただ、少し無念に思う事はあるね。あの幻影でのカール氏の様子を考えれば、彼は洞窟から脱出した後、二度と現場に戻る事はなかっただろう。きっと、置いていった仲間達の事を――」
と、言葉の途中で、オリオールの歩みがぴたりと止まる。そろそろ海岸を離れ、獣道へと入ろうかという位置。彼は一点、砂浜と森の境となる場所に視線を向けていた。
どうしたのか、とそちらを見ると、
「――幻」
そこに居たのは、もう見慣れた男の幻だ。
地面に片膝を突き、祈るような仕草で固まる男の幻影。彼はそのまま暫く身じろぎすらせず動きを止めて、そして立ち上がると大気に解けるように消えていく。
後に残ったのは、彼が祈りを捧げていた先。僅かな山を作る土の盛り上がりだ。その頂には武器が一本、証のように突き立てられて、傍には古びた防具が並べられていた。
幻影となった男が、過去にそこで何を造ったのか。想像はつく。
傍まで移動した【NAME】とオリオールは、暫し無言でそれを見下ろして、
「彼なりに、弔いは済ませていたか。ならば、僕等が余計な事をする必要は無い、のかな」
オリオールは短く、四柱信仰者の間で使われる印を切り、【NAME】は浅く目を閉じて黙祷する。
虚構の海から、緩やかな風が吹いてくる。祈りの時間は、その風の流れが完全に収まるまで続いた。
・
「次が、いよいよ手記の最後となる部分――最後の“冒険”という事になる」
獣道を辿り、帰路へとつく最中。オリオールは真剣な様子でそう告げる。
「場所は、ブランタンハリア山岳回廊。ここで、カール・シュミット探検隊は、隊長以外の全ての人員を失い、消滅する」
――つまり、そこで彼等は全滅したのか。
言葉通りに解釈し呟いた【NAME】に、しかしオリオールはいんやと首を振った。
「それが少し違う。何故なら隊長を務めるカール・シュミット氏は、その後、無事にアノーレに帰還する訳だからね。けれども、手記はその山で最後の隊員――ブランタンハリアを失ったところで、実質終わりを迎えるんだよ」
そこまで言って、彼は意味深に言葉を切ってこちらを見る。
「…………」
オリオールが何が言いたいのか。何を謎と定めているのか。それを察する事が出来ないほど、【NAME】は鈍くはない。
「当然、疑問が生まれるよね。一人となったカール・シュミットは、それから一体どうしたのか。彼の足跡は、そこからアノーレ島までの間、殆ど空白となるんだ。手記ではブランタンハリアから脱出する顛末すら書かれていない」
先を歩いていた探検家が振り返る。その顔には、深い笑みが浮かんでいる。
「これまでの“冒険”は、正直なところ余興さ。僕が本当に探り検めたかったのは、この部分なのだから」
そして彼は前へと向き直る。その歩みは、先程よりも幾分か早い。
「――さあ、早く戻るとしよう。そして準備を整えたら、“冒険”を始めよう」
真なる楽園 導く幻、有り様を知りて
──ブランタンハリア山岳回廊──
眼前に広がるのは、煙るような雨が降り続け、全体が白く霞がかった山々。今は天霧によって隠されて確認する事は出来ないが、途中までの斜面は緩やかであるが、頂付近からは鋭く上へと伸びる特徴的な形状を持っている筈だ。
【NAME】は視線を、上から下へと移す。
今居る場所は山岳を形成する一山の中腹。下方から響いてくるのは怒濤を思わせるような音だ。
連なる山の合間に流れるのは、水ではなく泥の大川である。それは激しくうねりながら分かれ、山という宮殿を囲う回廊のように続く。木々の隙間から勢い良く流れていく土色を眺めながら、【NAME】は拠点として定めた場所に転がる大岩の上に座り、一時の休息を取っていた。
ここはブランタンハリア山岳回廊。
カール・シュミットの手記によってエルツァンを知り、探索する者達の間では、単に“山”とも呼称される地。エルツァン内陸に存在する固有地形の一つである。
彼の手記においては、白色貝達の洞窟があった海岸を経由して辿り着いた場所であり、手記の最後にカール率いる探検隊が訪れ、そして終わりを迎えた場所でもある。
ふと思い立った【NAME】は、仕舞い込んでいた手記を背嚢の中から取り出す。
ぺらぺらと頁を捲り、開いたのは手記の最終盤だ。頁の位置としては手記全体の五分の四辺り。これ以降の頁は空白が続き、最後の頁に、探索を終えてアノーレに帰還したカール・シュミットが後に追記した、一連の探索行に対する結文があるのみ。実質、エルツァンについて書かれた最後の部分となるのが、このブランタンハリア山岳回廊についての記述である。
未だ山岳を覆うように降る雨はさめざめと、小雨というよりは霧雨に近い。座る岩の上方には、枝を折り曲げ葉っぱを湿らせて垂らす樹木の屋根が存在するも、大気自体を湿らせる繊細な霧雨相手では頼りなく。開かれた手記が僅かにではあるがしっとりと重みを帯びていく。あまり、手記にとって良い環境ではない。【NAME】は焦りのようなものを覚えながら、素早くブランタンハリアについての記述を再確認していく。
といっても、見るべきところは殆ど無い。
カール・シュミットの手記は、その記述時期により大きく内容が異なる。前半部は比較的真っ当な、読者にとっては理解しやすく情報も多いのだが、終盤に近付くに従い、手記の内容はどんどん抽象的、あるいは狂気的なものへと変化していく。特に最後、全ての仲間を失ったとされるブランタンハリアについての箇所は、雨、山、泥。そして巨大な鬼という単語が羅列され、最後にここで己を除く全ての人員が失われ、エルツァンという島と、この探索行を決めた過去の自分に対する怨嗟の書き殴りがあるだけだった。
だが、そんな内容であっても、やはり参考になる情報というものは存在する。それは鬼という言葉だ。
「……と、【NAME】。もう戻っていたか」
声を掛けられ、手記から視線を上げると、転がる小岩をとんとんと避けながらこちらに歩み寄るオリオールの姿があった。
「で、そちらの方はどうだった?」
背負っていた荷物を張られた天幕に放り込みつつの問いに、【NAME】は先刻終えた探索の成果を端的に話す。
第三山中腹までを終えて、見つけた幻影の数は三。発生位置は山の南方から反時計回りに沿って伸びていた獣道に二つ、第六山の方へと向かう谷へと下る谷に一つ。可能な限り、地形についての情報とその位置は小紙にまとめてはおいた。それをオリオールに渡す。
続けて、オリオールに首尾は? と訊ねると、彼は手に持っていた大紙を石の上へと広げて、
「第五、第八の、人が行ける範囲での探索は終わったよ。結果はこんな感じかな」
――早くないか?
こちらが山一つ、それも中腹までをようやく回り終えたのに対して、既に二つの山の探索を終えているとは。これが秘境踏破に慣れた冒険家本来のペースなのだとしたら、普段はこちらのペースに合わせて、かなり進行を遅らせているのだろうか。そんな事を思いながら、【NAME】は広げられた大紙に視線を移した。
・
既に、【NAME】達がブランタンハリア山岳回廊に入って十日以上が経過していた。
オリオールが広げたのは、自分達が“山”に入ってから作り始めた地図である。ブランタンハリア山岳回廊は、これまで通過してきたエルツァンの特殊な地形の中でもかなり広大な場所だった。その調査を始めるにあたって土地の全容を把握するために、山岳を構成する山々の数や配置などを書き記した地図を作ったのだ。何せ、合計して十の山が連なる山岳地である。大雑把な地図を作成するだけでも数日という時間を必要とした。
そして土地の構成をある程度把握した【NAME】達は、“冒険”を次の段階へと移す。
オリオールが定めた調査目標。それは、ブランタンハリア山岳回廊におけるカール・シュミットの幻影の捜索である。
「何せ、手記から得られる情報が少なくて、カール氏達に何が起こったのか殆ど判らない。けれど、これまでの“冒険”の経験から、あの幻影を見つける事が出来れば、カール氏の動向はある程度知れる。僕等に出来るのは、出来うる限りカール氏の幻影を探して、それによって彼がここでどういう行動を取ったのか。それを辿っていくしかない、のだけれど……」
探索範囲が広域であるため、極力亜獣などの危険存在との遭遇を避けるようにしながら、【NAME】とオリオール、手分けしての捜索をする事にした。この方針は現段階では成功と言っても良い成果を残しており、一週間近く経過した今では既に第一、第二、第六、第九、第十の五山については山頂付近へと続く絶壁地帯を除く、人が立ち入れそうな――つまり疲弊しきっていたであろうカール達が立ち入れそうな――場所の捜索は完全に終了。他の山についても、今回で第三の大部分と第五、第八の調査が終わった形だ。残る手つかずの山は第四と第七山となるが、この内の第七山については山と山の境を流れる泥川を渡れるポイントが現状見つかっておらず、実質、残された調査可能な山は第四山のみという事になる。
――それにしても。
【NAME】は以前見たときに書き込まれていた幻影確認箇所に加えて、オリオールが新たに書きつけ、更に【NAME】のメモにより追加された点を眺め、ふーむと考え込む。
地図を見て、気づく事がある。それは、
「多いね」
オリオールがぽつりとこぼした端的な言葉は、【NAME】の内心と同じものだった。
これまで“湖”や“丘”、“海岸”やそれ以外の場所でも時折確認してきた、カール・シュミットらしき男の幻影。それらは精々、一地形に対して数箇所、多くても十数程度といったところだった。
だが、ブランタンハリアでは既に数十もの幻影が確認でき、更に幻影の発生箇所にも大きな偏りがあるのも直ぐに判った。
「特に多いのが第二、第六、そして第九か」
オリオールが指で密集する点をなぞる。幻影の存在は、過去、カールがその場所に存在していたことを示す。つまり、その軌跡を辿れば、幻影の発生地点は線として繋がっていくのが当然だ。進む指先は、第九山の端から始まり、外縁を沿って隣接する第一、第二、第三と進んでいった後、第六を経由し、
「……ここで、途切れる?」
第六山の縁。他山との隣接地。泥川の境にて点によって作られた線は途切れてる。
線が伸びていた方向にあるのは、第四と第七山の境界だ。
「【NAME】。第六山の――この場所で見た幻影、覚えているかい?」
問われて、思い返す。第六山は“冒険”の第二段階に移った際、最初に探索した山だ。途切れた線。泥川の境界に存在していた幻影は何かに後方から襲われている最中らしく、周囲に声を張るように口を動かしつつ泥川が流れる方向へと走り、途中で消滅するというものだった気がするが、あまりはっきりと思い出せない。
何故なら、
「あの時、確か対岸に見えていたよね……」
泥川の向こう、第四山と名付けたその場所では、泥濘んだ地面から生えるように、無数の泥人形達が徘徊している様子が見えていたからだ。そちらに大半の気が向けられていて、いまいち幻影について思い出せないのも致し方ないところだろう。
それに、山岳回廊の中心付近に位置する第四、そして第七山近辺からは、どうにも厭な気配を強く感じるのだ。
漂う気配は“山”中を覆う歪な気配と同種のものだ。但し、他と比べてその強さが違う。それは山と山の間を流れる濁流からも時折感じるもので、大抵、そういう時は川の中から泥で出来た巨人のような存在が、ずるりと身を擡げていたりするのだ。
それらを考えると、第四、第七山ではもしかすると、泥に纏わる存在が他の山よりも多く出現する、一際危険な地域なのかもしれない。
などと【NAME】が思考する間に、オリオールはとんとんと地図の一点を叩き、
「第九山で見たカール氏達の幻影の進行方向から、移動順は先刻の移動順で確かな筈。そして幻影の態度を思い起こすなら、カール氏達は恐らく第六山から第四か第七、どちらかの山に向かったのだろうと考えられるね」
しかし、その途中には泥の大川があった訳だが、あそこを渡っていったのだろうか?
【NAME】の見立てでは、そう易々と渡れるような代物ではなく、何者かに追われていたからといっておいそれと飛び込めるものでもないような気がしたのだが。
「そうだね。泥川が当時も存在していたのなら、もしかすると追っ手から逃げるために川に飛び込んで、その時に全滅したという流れも考えられるし、もしかすると当時は川自体が存在してなかったという可能性もある。だが、何にせよ――」
――現地に足を運び、もう一度、改めて状況を検分してみる必要があるだろう。
【NAME】が引き継ぐように言葉を作ると、オリオールは大きく頷いて広げていた地図を丸め、
「では、早速向かうとしよう。【NAME】、準備の方は大丈夫かい?」
こちらよりも、戻ってきたばかりで碌に休息もしてないだろうオリオールの方が大丈夫なのか。
そんな心配の言葉に、オリオールは口元を深く笑みの形へと曲げて、
「この程度、気にする必要も無いよ。なんせ僕はまだまだ若いしね」
「…………」
一瞬何か言葉を返そうとして、しかし【NAME】は賢明にも口を噤み、天幕内に放り込んだ荷物をまた抱え直すオリオールの後に続いた。
・
オリオールの先導に従い、【NAME】は泥濘みの多い山道を行く。途中、幾度も亜獣らしき存在を察知したが、先行くオリオールが的確に制止と移動の指示を出し、それに従う事で遭遇を次々と回避していく。
それは職能としての危険察知や隠密行動に近い技術だが、オリオールのそれは二つの技能を複合した上で己の経験を加味し、更に数段高めたような代物であるように思えた。
このような技術を持っているなら、普段も使ってくれて良いだろうに。そうすれば、色々と楽になった場面があったのだが。
思わずそんな愚痴が漏れた【NAME】に、オリオールは苦笑しながら首を横に振る。
「単純に、今回は一度地形を把握しているから出来る事だよ。後、気配を消しやすい環境であるからこそ、という部分もある」
それは確かに、と【NAME】は納得する。下方から響く濁流の音と、山を包む霧雨。この二つを有効活用する事で、ここまで遭遇回避が行えているのだろう。
「……で、そんな事より【NAME】。見えてきたよ、件の場所が」
オリオールの言葉に顔を上げれば、目に映ったのは第六山と四、七山との境となる谷だ。そこには幅20メートルはあるだろう大川が横たわっており、濁った泥水が勢い良く流れていく。
【NAME】達はそのまま斜面を下り、谷川の傍へと近寄る。
「幻影の動きを見る限りは、やはり川の向こうに渡ったと考えるのが妥当だけれど――ん?」
と、オリオールが言葉を切り、怪訝、と一瞬片眉を深く寄せて、
「【NAME】、あれを!」
慌てた動きで指差す先は、川向こうの第四山側だ。その川縁から、全力で山の斜面へと走っていく幻影の後ろ姿があったのだ。
幻は泥川の中から一切速度を変化させる事無く駆けて、まるで川など無かったかのような様子。そのまま、幻が木々の向こうへと消えていくのを見送って、オリオールは【NAME】の方へと振り返る。
「……あの動きを見ていると、どうやらカール氏がここに来ていたときは、川自体が存在していなかったようだね」
しかし、カール・シュミットの足跡を追っていくのならば、自分達はどうにかこの川向こうにある第四山側へと移動せねばならないのだ。
――どうしたものかな。
【NAME】は川の縁へと近付き、流れる泥水の勢いを確かめるが、直ぐに判断出来た。少なくとも、この川を歩きないしは泳ぎで渡る事は不可能だと。
「それについては僕も同意見だ。……んー。なら、上から行ってみるかい?」
上? と【NAME】が首を捻ると、オリオールは自分の荷物の中から縄を取りだしてくるくる回してみせる。
「これをあちら側の木に投げて引っかけて、もう片側をこちら側の木に結び、伝って渡る、という方式なのだけど」
成る程、不可能ではないだろう。だが、あまり現実的ではない気もする。
【NAME】が簡潔に感想を言うと、冒険家は「まぁねぇ」と苦笑を浮かべた。
「本来なら渡河の際の命綱として使う方法だし、それもあまり安全な策じゃない。完全に上を伝っていこうとするなら、余程丈夫な木にひっかけないと駄目な訳だけれど、この距離だとそう上手くはいかないだろうしね」
けれど、
「ならばどうする? カール氏は第四山へ入ったのはもう確実だ。ならばどうにかして、この川を渡る方法を考えなければならないのだけど、別に思いつく方法、何かあるかい?」
川を安全に渡る方法は思いつかない。
だが、第四山へと入る方法は思いつく。
「ほぅ?」
驚いたように両目を見開くオリオール。だが、【NAME】からすると、単にオリオールが川を渡るという事に拘りすぎているだけなのだと判っているだけに苦笑するしかない。
別段、勿体ぶるような話でもない。【NAME】はさっさと結論だけを言う。
――ここからではなく別の、泥の川が存在していない場所を経由して第四山へ入れば良い、と。
・
「……いや、確かに視野が狭くなっていたね。そうか。単に遠回りすれば良いだけの話ではあった。僕としたことが、目の前の事象だけに囚われてしまうとは。全く、間の抜けた姿を見せてしまった」
移動するのは第二山。【NAME】達が居た第六山とは、第四山を挟んで真逆に位置する山だ。
第二山と第四山の境には唯一、泥の川が存在していない地点があるのは、既に初期の地図作成時に判っていた。【NAME】が提案したのは、そこを経由して第四山へと侵入しよう、という話だ。
オリオールがそれを選択肢として思いつかなかったのも、判らないでもない。
まず、大幅な遠回りになる事は確かで、そして加えて、別の大きな問題が一つ。
「ただ、【NAME】。川を渡らずに第四山へと入る場合、僕等が見つけられた場所はあの一箇所しかないよ?」
先行していたオリオールが、前方を指差し振り返る。眼前、第二山と第四山の間に広がっているのは川ではなく、大きな沼地である。
どろどろと、粘りを帯びた泥塊が、山の間を横たわるように広がる。この沼自体については、それほど渡る事は難しくない。底無し沼という訳ではなく、精々膝丈程度に足がめり込むくらいだ。
しかし、この場所の問題はそこではない。
沼の各所では、時々巨大な泡が生まれ、その泡は大きく膨らむと人型へ変化し、泥の人形となる。生まれた泥人形は、暫く徘徊した後、また泥の沼に沈むようにして消滅していくのだが、
「前にここを通り抜けようとした時の事を思い出すね。確か、一斉に僕等に襲い掛かってきたっけ、あれ」
当時の事を思い出すのか、口元を引きつらせて笑うオリオールに、【NAME】は肯定の頷きを返す。
第四山の調査を行おうと、この泥沼を抜けようとした際。それまで無反応だった泥人形達が一斉に自分達へと襲い掛かってきたのだ。
所詮は泥人形。動き自体は極めて鈍いものであったが、しかし泥人形達はその身体から泥の塊を変質させて放つ力を持っており、【NAME】達は足を泥に取られた状態で遠隔攻撃の嵐に襲われるという、非常に好ましくない形に追い込まれた。
結局、その時は第四山へ入る事は諦め、飛び交う泥槍を払いながら大急ぎで沼地から撤退する事になった。別段、当時は第四山へと強いて入る理由も無かった為、無駄に強行突破する必要がなく、だからこその選択であった訳だが。
「“冒険”を達成するためには、今回は逃げる訳にはいかないのだけれど、【NAME】、何か良い作戦はあるかい?」
作戦、という程のものではないが、方針はある。
極力急ぎ、立ち止まらずに泥の沼地を抜ける。泥人形達がこちらに反応し、襲ってこようとも、相手をするのは直線上。進行方向に存在する障害となりうる泥人形のみとするべきだ。
【NAME】がそう告げると、オリオールはにやりと笑みを浮かべて頷く。
「一気に行くとしよう。【NAME】、準備の方は良いかな?」
小剣を抜き放ちながら問うてくるオリオールに、【NAME】は言葉では答えず。己の武器を手に握り、身を深く、己の発条を溜め込むように沈める。
「では、スタートだっ!」
叫ぶオリオールの声に合わせて、【NAME】が先行するように前方へと身を飛ばした。
即座に、ずぶりと足が沈み込む。絡みつく泥の感触を、【NAME】は蹴り飛ばすようにしながら足を動かす。背後にオリオールが続く気配を感じると同時、周囲に存在していた泥人形達もこちらに反応する素振りを見せ始める。
だが、その動き自体は鈍い。どろどろと半ば崩れた身体をこちらに向ける様はゆっくりとしたもので、振り返るまで恐らくは数秒。更に攻撃姿勢に入るまで更に数秒の猶予が存在するだろう。
もし足場が普通の平地であるならば、泥人形達が攻撃を仕掛けてくる前に走り抜けられただろうが、生憎と膝下まであろうかという泥を分けながらの疾走だ。攻撃が始まる前に渡りきることは難しいだろう。
加えて、
「正面! 新しい泡が生まれるぞ!」
オリオールの警告の通り。【NAME】達の進行方向にて、新たに複数の泡が生まれるのが見えた。
それらはまるで【NAME】達の行く手を塞ぐように膨らみ、盛り上がり、そして泥の人型へと変化していく。
「――っ!」
方向転換、という言葉が一瞬脳裏を過ぎったが、それは愚手と一息で斬り捨てる。最初の方針通り、行く手の泥人形は処理、それも最速最短の手で処理するのが選択肢としては最善の筈だ。
短い舌打ちと共に【NAME】は己の武器を握る手に力を込めて、眼前、己目掛けて泥の腕を伸ばす人形達に叩き付ける。
行く手を遮る泥人形達を悉く破壊し、後方から迫る泥の槍の追撃を潜り抜けた【NAME】達は、第四山への侵入にどうにか成功する。
だが、いざ立ち入ってみて判明した事だが、第四山は他の山とは土地の質が大きく異なっていた。
まず、全ての土地が泥濘みの中にあるように緩く、踏み込みに力が上手く入らない。そして、そんな土地であるなら本来は生育しないであろう樹木が、ごくごく平然と根を張り、上方へと枝葉を茂らせている。土地自体がどこかちぐはぐで不自然なのだ。
「僕の経験では、こういう類の地形は危険だよ。歪に傾いた土地概念が、本来ならば土地からは切り離されている筈の、土地上に存在している他存在を取り込んでしまってる。あまり長居していると、僕等の存在概念も土地概念の影響を受け始めるよ」
もしそうなってしまった場合、下手をするとこの土地から離れられなくなるか、こちらの存在概念自体が不安定になり、自身を維持出来ずに崩滅する可能性もあるという。
流石にそういう結末は遠慮したいと、【NAME】は急ぎ山の中を進むのだが、それを遮るのが泥濘の地面から次々と生じる泥の人型達だ。
「いやはや、てっきりあの沼地だけかと思っていたら、まさか第四山全域で出てくるとはね。しかも、こちらに敵意を向けたままと来た」
最初は、オリオールの技能による遭遇回避を期待したのだが、彼がこの場所についての地理に疎いのに加え、そもそも第四山の泥人形達は【NAME】達が近付く事で反応して生じるという代物であったらしく、相手の感知前に行動を制御して逃れるというオリオールの技能は全く通用しない相手である事が早々に判明し、頓挫した。
良く良く考えてみれば、最初の調査の際に第六山の川岸に第四山を見たとき、泥人形達が多数存在していたのを確認していたのだから、第四山がそういう環境であると予想する事もできたのだが。
ただ、予想が出来ていたからどうなる、というものでは無かったのも確かだ。カール・シュミットがこの第四山に入ったというのなら、それを追う身とすれば結局は立ち入らねばならぬ場所なのだから。
「【NAME】、そろそろ到着だよ」
正面より沸いた泥人形が、動きを始める前に一撃。沼地と違い、足場は緩いながらも速度を大幅に削がれる程の悪環境ではない。ならば進行方向に居た相手ならば、動き出す間に蹴散らす事は容易だ。振り切った腕を戻す合間に【NAME】は数歩前へと駆けて、木々の間から身を外へと飛び出させる。
拓けた視界。そこに姿を現したのは、以前見た泥の川だ。但し、見える風景は違う。前回は対岸として見ていた場所に【NAME】は滑り込むように着地する。
「……さて、ここからようやく、カール氏の幻影を追う作業の再開か」
そうなるのだが、と【NAME】はこの先の進行に懸念を抱く。
最初に考えていたよりも余裕が無い状況だ。常時こちらを付け狙うように発生する泥人形の存在に加え、土地概念による干渉の不安もある。悠長に第四山中を歩き回り、カール・シュミットの幻影が発生する場所を洗い出していくのは難しいだろう。第四山を脱出する際には、またあの沼地を抜けていかねばならないことを考えれば、疲労が大きく蓄積していないうちに捜索を打ち切って脱出し、態勢を整えてから再開。このスパンを複数回行うことを前提とする必要もあるのではないか。
冷静に【NAME】はそう指摘すると、オリオールの方も同様に考えていたのか間髪無く頷き、
「可能な時間は……多めに見積もってもあと一、二時間、といったところか。この、常時敵が湧き出してくる環境は精神的にも肉体的にも流石に厳しい。【NAME】、戦闘に関しては君が要だ。だから厳しいと感じたときは、直ぐにでも申告してくれ。その段階で直ぐ脱出に移ろう」
了解、と返して、【NAME】とオリオールは残り少ない時間を惜しむように幻影の捜索を開始する。
捜索を始めた当初は、この厳しい状況の中で幻影が見つからなかった時はどうしよう等と考えていた【NAME】であったが、
「……多いな」
短くオリオールが呟く通り。
第四山にて出現するカール・シュミットの幻影は、他地域と比べて多く出現していた第六山などよりも更に多いものだった。
泥川の縁から内側に入った時に見つけた一つから、殆ど続けて五つ、一瞬途切れて四つ、三つ、四つと、殆ど繋がった幻影として現れ、カール・シュミットが過去にこの場所で取ったであろう行動を、そのまま幻としてトレースし続けていた。
「何故ここだけ、こんなにもカール氏の幻影がくっきりと残っている? その理由はなんだ? この場所の土地概念が大きく歪んでいるからか? しかし……」
そう、ぶつぶつとオリオールが呟くのも判る。
確かに不思議だ。この第四山が大きく土地概念が歪んでいる場所なのは事実ではあるのだが、しかしこれまでの“冒険”の旅の間、このような土地概念の歪みを持つ場所が一つもなかったかと言えば答えは否である。“湖”や“丘”では、ここに匹敵するか、それ以上に歪んでいる場所も存在していたように思う。
しかし、そこではこのようにはっきりと、連続した形で幻が存在している事は無かった。
何か、理由があるのか。理由があるとするなら、一体どんな理由があるのか。いや、理由などなく、単なる偶然なのか。
答えのない疑問を胸に、泥の化け物を次々と破壊しながら、【NAME】達は山の奥へ奥へと進む。
標となる幻影の男の姿は、その殆どは逃げ惑う様子で、時折仲間に何かを叫んだり、助け起こすような仕草も見られ、彼がこの地でどれ程追い詰められていたのかが垣間見える光景であったが、
「まだ、全滅している訳ではないのだよね。彼の動きから推測するなら、まだカール氏は幾人かの仲間と共に居る筈だ」
そう。まだ、カール・シュミットは一人ではない。探検隊は、隊の形を維持しているのだ。
と、するならば、この先に、カールが仲間達全てを失うような何かが存在しているのだろうか?
「――【NAME】っ!」
一瞬意識を物思いに沈めかけていた【NAME】は、オリオールの注意を促す声にはっと顔を上げる。
先行する形で走っていた幻影が、唐突に足を止め、茫然と前方を見たまま固まったのだ。
一体何を見たのか。
【NAME】達が立ち止まる幻影と同じ位置にまでやってきた時、周囲の木々が唐突に失せて、眼前の視界が大きく拓けていくのを感じた。
「っ!?」
それは突然の変容だった。
木々に囲まれた薄闇から、雨空の下での薄い光の中へと移り変わる。
その下にて存在していたのは、泥で出来た巨大な湖だ。ついさっき、たった数歩前までは存在すら感知出来ていなかった湖が、突如として眼前に出現した。
唐突極まる現象に、呆気に取られる【NAME】達が新たな反応を起こす前に。
泥の湖面全体が突然ぐらぐらと泡立ち、そして次の瞬間――湖を形作っていた泥全てが、頭、首、肩、腕、胴となって、上体を立ち上がらせたのだ。
──導く幻、有り様を知りて──
――山岳回廊の中心にて現れた、泥の巨人。
その存在についての情報は、断片的ながら事前にカール・シュミットの手記から得てはいた。そして、山岳回廊を探索する道行きの間、それらしき存在を見掛けてもいた。
だが、今目の前に出現したそれは、【NAME】が想像していたものと比べ、一回りどころか二回り、いや、三回りは強大な存在であった。
「っ」
見上げ、我知らず息を呑む。
出現した巨体は、果たしてどれ程の大きさか。現れたのは上半身のみであるというのに、既に湖周囲の木々を優に超える程だ。泥で形作られた姿は不確かでありながら、しかし人としての型は維持したまま半身を完全に起こし、そして頭部、落ちくぼんだ二つの空洞を、遙か下方にて固まる【NAME】達へと向ける。模した眼窩の奥では、仄暗い赤色が瞬き揺れているのが微かに見えた。
これまで山岳回廊を探索する間、【NAME】はこの泥の巨人に近い存在を幾度か見る事はあった。
それは谷を流れる泥川の中からであったり、山を削る崩れの中からであったり。
多くは一瞬の間で、巨大な人という形を失い泥の中へと身を崩していくような存在だった。共に旅をしていたオリオールが一度も見た事がないと言っていた程の、まるで幻のような存在。だが、神形の所持者となったが故か、歪な気配を察する事に敏感となっていた【NAME】は、見逃すこと無くその存在を捉え、認識出来ていた。
だからこそ、【NAME】は“山”を探索するうち、何れあの泥の巨人と戦いになると、
(ある程度の覚悟は決めていた、のだが……)
今、目の前にて聳える巨人は、その時見たものと比べ数倍以上の大きさだった。加えて、鬼気――鬼種特有の陰性質に傾いた独特の気配が、凄まじい勢いで噴き出して、不可視の嵐となって辺りに吹き荒れる。
途中で見た巨人を基準として、下手に覚悟を決めていてしまっていたため、その差によって生じた動揺は大きかった。
「……成る程、こいつが君の言っていた、そしてカール氏の手記にあった巨人――いや、鬼種か。僕は初めて見るが、なんとまぁ、ここまでとはな」
そう呟くオリオールの声も、流石に震えが交じっているように聞こえた。
山岳回廊の初期調査を行っていた頃。野営での世間話として、オリオールに時折泥の巨人を見掛けた話をした時を思い出す。
その時のオリオールの見立てでは、【NAME】が見掛けたという泥の巨人は、この山岳回廊という土地自体が強く持つ歪んだ泥の概念が、形として外部に漏れ出しかけていた場面なのではないか、というものだった。
つまり、その巨人は土地そのものであり、化身。土地自体に深く結びついたまま、それが飽和という形で出現するのは、最上位以外の妖精や鬼種に見られるものだ。だが、山岳回廊のそれは、土地との分化が明確には行われず、密接に繋がったまま現れては引っ込むという、独特の形態を維持しているのではないか、と。
直ぐ傍に存在していた幻影が、【NAME】達と同様、空を見上げるような態勢のまま、音もなく消滅していく。オリオールは一瞬、視線を幻が存在していた場所に走らせて、
「つまりはこれが、カール氏の探検隊を全滅させた元凶だというのか……?」
そこまでは判らない。
しかし、こちらに向けて巨大極まる腕を掲げ、振り下ろしてくるその存在を退けなければ、自分達がそれを確かめる事も、そして生きてここから帰ることも出来ないのは確かだった。
動揺し、固まっていた身体が、迫る危険に反応して動き出す。
「――――」
天を覆い、そして塞ぐ。風が巻き込まれて唸る音。周囲に落ちた影の暗闇が急速に太くなっていく。
広げられ、落下してくるのは巨人の大掌だ。回避は既に間に合わない。ならば残る助かる術は、
――吹き飛ばす。
短い思考と共に、【NAME】は正に決死とも言える一撃を、降ってくる泥の圧目掛けて打ち放つ。
まるで山のような巨人。
その姿が、【NAME】の渾身の一撃を中心に受けて砕け、ただの泥の塊へと返っていく。
輪郭を失った泥が、形を無くし、巨人という体を失う。泥水に戻ったそれらは地面へと戻り、元の湖の姿へと変化して、そして。
「消えた?」
風景全てが大きく歪み、一瞬の後。眼前から、湖の姿は失せて。
後に残ったのは、泥濘の山の斜面と、そこから伸びた木々の群れだけだった。
「……一体、何だったのかね」
そう呟きながら地面にへたり込んだオリオールの姿が視界の端に映る。彼も一応泥の巨人との戦いに参加してくれてはいたが、正直に言ってしまえば殆ど役に立っていなかった。ただ、オリオール自身も己の力量では【NAME】と巨人との戦いに割り込めないのは判っていたのだろう。極力、サポートという形で邪魔にならぬよう、しかし僅かなりとも手伝えるように立ち回っていたのは流石だと言う他無い。もっとも、そのような弁えた動きであっても、時折巨人の攻撃に巻き込まれかけていて、真っ向から巨人と戦っていた【NAME】の方が気を揉むような場面も幾度かあったのだが。
「恐らくは最初の予想の通り、あれがこの土地と繋がり生まれた鬼の一種……なのだろうけど、あの消え方だと、崩滅出来たという感じではなさそうだ」
それについては、【NAME】も同意見だった。
最後に放った一撃。手応え自体は十分あったが、しかし歪の塊を砕いたという、そんな開放感、爽快感のようなものが一切なかったのだ。形として生まれていた、この地が持つ歪み。それは【NAME】という打撃を受けても砕き正されず、ただ土地の内側へと押し返されただけ。
「でも、全くの無駄、という訳ではなかったようだね」
ぬ、と年齢を感じさせる掛け声と共に立ち上がり、小剣にこびついた泥を払いながらこちらに歩いてくるオリオールに、【NAME】は無言で頷く。
巨人を正しい意味で倒す事は出来なかった。
だが、この戦いの勝利が、状況に良い変化を齎したのは確かだ。何故なら、周囲からは泥人形の気配も、そして第四山に満ちていた歪な気配も大きく減退していたからだ。
少なくともこの場において、危険度は大幅に下がったといって良いだろう――【NAME】は深々と、安堵の吐息をつく。
そして、
「……ん?」
と、傍で視線を周囲に回したオリオールが、ふと一点で動きを止めた。
「【NAME】、あれを」
オリオールが指し示したのは、前方。つい先刻まで巨大な湖を形成していた場所に存在していたのは、大きな崖だ。そしてその下方にて、逃げ込むように走るのは、既に見慣れた男の姿。カール・シュミットの幻影だ。
幻影は、今居る位置からは影となる方へと消えていく。【NAME】とオリオールが慌ててその後を追った。
距離はそれ程離れている訳ではない。ぐるりと回り込む形で軽く斜面を下り、木々の間に伸びた泥濘みの獣道を抜け、崖の下方、幻影の男が消えていった場所の手前までやってきた【NAME】達は、目の前に現れたそれに驚く。
――これは……洞窟? いや、通路か?
崖の下部から斜め下に存在していたのは、縦横10メートル以上はある巨大な穴だ。それも、自然に作られたものではない。綺麗な四方に切り取られた穴、その側面は岩肌などでは決してない、金属製の滑らかな光沢を持っていた。
「地下都市の通路、か」
突然の言葉に、【NAME】は隣のオリオールを見る。
「――“イールシック地下都市遺跡”。エルツァンの各地に存在している地下通路から入る事が出来る巨大都市跡だよ。カール氏の手記にも記述があった筈だが、覚えていないかい?」
言われて、ああ、と思い出す。
確か、手記の序盤にそんな内容の部分があった。そこには多数の機種が潜んでおり、迷い込んだカール・シュミット達は彼等の襲撃に遭い、命辛々逃げ出したとかそんな話だったか。
【NAME】の言葉にオリオールは「大体はそんな処だね」と頷き、
「そしてどうやら、カール氏はブランタンハリアからここを通って、またイールシックに入っていった、という事なのだろうね。――ほら、あのように」
【NAME】とオリオールの視線の先。
巨大な通路の奥では、薄闇の中から染み出すように、小柄な男の後ろ姿が生まれていた。
現れた男の影は、通路をふらつくような足取りで進んでいき、そして、
「……ん?」
そこで【NAME】達はある事に気づき、小走りで大通路の奥へと入る。
入口から中へと、凡そ数十歩入り込んだ処で、【NAME】は目の前を塞ぐ壁に手を当てて、小さく呟く。
「行き止まり?」
そう。
通路はそこで行き止まりになっていた。上面から生えるように降ろされた隔壁が、大通路を途中から完全に寸断していたのだ。
そして、カール・シュミットの幻影は、その壁がまるで存在していないような様子ですり抜けて、向こう側へと消えていってしまった。
つまり、それは。
「カール氏がここを通った時、この壁は存在していなかった、という事なのだろうね」
彼の後を追うにはこの壁をどうにかしなければならない。
だが、【NAME】は周囲を確かめるも、この壁をどうにかできそうなものは見当たらず。壁に手を当て、人力で持ち上げようとしてみるも、その重さは凄まじいものでぴくりとも動かない。
いっそ破壊するか。思い、武器を手に取り身構えるが、
「止めた方が良い。恐らくこの壁、僕等の腕一本よりも厚みがあるよ」
というオリオールの言葉に、【NAME】は溜息をついて肩の力を抜いた。
今は己の胸元で沈黙する彼の神形の力を借りればもしや、という気もするが、そもそもあの存在はこの程度の事に力を貸してはくれないだろう。
しかし、そうなるとここからどうすれば良いのだろう?
途方に暮れた顔で暫く壁を眺めた後、【NAME】はオリオールを見る。
探検家は【NAME】と同様、心底困ったという顔で正面を塞ぐ隔壁を見つめていたが、
「……何にせよ、カール氏がイールシックに入ったという事が判った。そして、今の僕等にこの壁をどうにかするような手段はない。ならば」
オリオールは壁から視線を外すと、【NAME】に決意の表情を向けて、
「別の侵入口から、この大通路へと至る道を探してみよう。幸い、イールシック地下都市遺跡への侵入経路は複数ある事は既に判ってるからね。その内のどれかから入り込み、外からではなく内側から、カール氏の存在を探してみよう」
成る程、と【NAME】は納得する。少なくともこの大壁をどうにかすることに固執するよりは余程良い案であるように思えた。
――ならば早速、イールシック地下都市遺跡へと入る別の場所を探すか?
そう訊ねた【NAME】に、オリオールは首を左右に振った。
「ここまでの連戦に加えて、あの巨人との戦闘もあったんだ。僕もそうだが、特に君の疲労の蓄積はかなりのものだろう。それに、今は収まったとはいえ、泥人達の発生がまたいつ復活するかも判らない。一度第四山から拠点まで――いや、常駐軍の陣まで戻って十分な休息と準備を整えてからにした方が良いだろう」
そう言われてみれば、と言葉にされたことで【NAME】は今まで気づかなかった疲労が全身に鈍く、重りのようにのしかかっている事に気づく。
「では一度戻ろう、【NAME】。――申し訳ないが、最後の“冒険”は延長戦に突入だ」