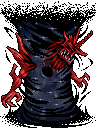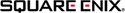真なる楽園 安らかなる岸辺
──真なる楽園へ──
アノーレ島の南西端の町、ポロサ。その港にやってきた【NAME】は、出航の準備を続ける大船の群れを眺めつつ歩いていた。
【NAME】がここへ足を運んだ理由は一つ。大禍鬼を追うという常駐軍から、正式に協力の要請があったからだ。イェア・ガナッシュが何処からか得た情報を元に常駐軍の術者達が詳しく走査を仕掛けた結果、“真なる亜獣達の楽園”があるとされる位置で、鬼が空間に残していた歪みが途切れたという。
“真なる亜獣達の楽園”。エルツァン島と呼ばれるそこは、フローリアを構成する大島のうち、唯一未調査のまま残されている島だ。島全体を覆うように独自の理が働いており、上陸するのも容易ではないとか。だが、それでも常駐軍はあの鬼を追い、そして討つつもりらしい。
今ここに居るのは、ノイハウスでのレェアとの会話の後に散々迷った末の結果だ。危険ではあるが、神形器を使い“鬼喰らいの鬼”を倒しきれなかったが故の義務感も多少ながらある。それに未知の島というものに対する好奇心が特に強かった。自分の身を第一にしない選択は冒険者としての寿命を縮める事になるのは理解しているが、だからといって容易に好奇心を押し殺せるのなら、そもそも冒険者などしていない。
港を歩きながら、常駐軍からの要請が来た時の話を思い出していた【NAME】は、知らず港の北にある広場へと辿り着いていた。そこへ、
「お、来たわねん」
と、声を掛けられて、はっと無意識に下を向けていた面を上げる。広場の東、港と町を繋ぐ石造りの階段に、口髭の男が腰掛けてひらひらと手を振っていた。
──ノクトワイ・キーマ・フハール。
彼も今回の件に絡んでくるのだろうか。【NAME】が彼の方へ近づくと、ノクトワイの笑みが深くなる。
「いやいや。今回の作戦ってばエルツァンの調査も兼ねてるからかなり総動員でねぇ。アタシも出張ることになっちゃって。指揮取るのが先生ちゃんってのは聞いてる?」
それは常駐軍からの協力要請が来た時に聞いていた。こくりと頷くと、ノクトワイはそこで僅かに笑み、
「じゃあほら、あのコ達が来るってのは?」
男が顎先で示した方向を見ると──。
「……キヴェンティ」
【NAME】は僅かな驚きの声でそう呟いた。ノクトワイが示した先にいた一団は、白を基調とした衣服に身を包んだ独特の雰囲気を持っていた。所謂、キヴェンティだ。彼らは周囲に人間を近づけさせない特有の空気を生み出しながら、ポロサの港の一角を埋めていた。
そして集団の先頭には、小柄な少年が一人立っている。腰に長剣を提げた少年の名はリゼラ・マオエ・キヴェンティ。彼は【NAME】とノクトワイに気付いて、遠く海の彼方へ向けていた視線を、ノクトワイとその脇に立つ【NAME】に向けた。
「はぁ~い」
それを受けて、ノクトワイがリゼラに向けてひらひらと気の抜けた調子で手を振る。しかしリゼラは何の反応も見せず、【NAME】達からすっと視線を外した。
「あら、嫌われてるわね」
苦笑しつつ【NAME】を見上げるノクトワイ。
あの少年の性格から考えると、彼にとってノクトワイのような性質の軽い人間はあまり好ましい相手では無いだろう。笑う【NAME】に、ノクトワイは僅かに肩を竦めた。
「どうやったんだか知らないけど、先生ちゃんはキヴェンティ達の協力まで取り付けたらしくてねぇ。今回の作戦に同行するってね。まぁ、杜人クンの性格から考えると、彼から先生ちゃんに申し出たっつー可能性もあるけど──」
と、突然言葉を切り、ノクトワイは【NAME】の後方へと視線を動かす。何かあるのかと、【NAME】が振り返ろうとしたところに。
「【NAME】。こちらにいらっしゃったのですね」
小さいが澄んだ声が響いた。声の主は背に黒銃を背負った小柄な人物。ノエル・ガナッシュだ。宿の部屋に居ないと思ったら、先に港へと来ていたらしい。
「や、ノエルちゃんも元気そうねぇ」
座り込んだまま手を挙げて挨拶するノクトワイに、ノエルは律儀に居住まいを正すと一礼。
「ご無沙汰しております。ノクトワイ様」
「いやぁねぇ、様づけなんて他人行儀に。親しみを込めてノーたんと呼んでくれてもオッケーよん」
「お断りします」
「……ちぇ。で、アナタがこっちに来たということは、アレ?」
曖昧な問いに、しかしノエルはこくりと頷く。
「わたし達が割り振られている船の準備が整いました。乗船のご案内をさせていただきますので、こちらへ」
・
風は適度に吹き、海は極めて穏やか。だが、船員達の方は大騒ぎを続けていた。何でも、既に眼に見える位置にあるというエルツァンの島へどうやっても辿り着けないのだという。島の見える方角へと進んでいる筈なのに、見える島との距離が一向に縮まらないのだと。
エルツァンの島は色々と伝説に事欠かない。今回のような事象も、彼の島を目指し挫折した者達が歌った噂話の一つとして良く聞くものであったが──いやはや、実際出くわしてみるとなかなか感慨深いものがある。
船に乗り込んでいる常駐軍の者達はどうすれば島へ辿り着けるのか、喧喧囂囂といった調子で議論を続けていたが、こちらとしては単なる乗客気分。操船は船の専門家に、行動指示は軍の方にお任せと言う事で、【NAME】は船尾付近の縁に背を預けて昼寝と洒落込んでいた。
──と。
座り込んでいた【NAME】の身体の上に影が差した。閉じていた眼を開き上を見れば、今回の作戦で指揮を取るイェアの下で働いている筈のノエルが、こちらを覗き込むようにして立っていた。
「【NAME】。お話が」
【NAME】が表情だけで内容を問うと、ノエルは僅かの沈黙の後。
「あなたにこの件を何とかしていただきたいと、イェアはそう言っています」
この件、この件、と【NAME】は首を傾げて小さく呟き、思い当たる。船首が指す先に見えるあの島へ近づけないのを自分に何とかしてくれと、イェアはそう云ってきているのか?
(……無理だろう)
そんな事を突然言われても困る。慌てて身を起した【NAME】だが。
「詳しいお話はイェアから直接お聞きください。船室のほうへご案内します」
【NAME】の言葉を封じるようにノエルは丁寧に言って、浅く一礼した。
・
そして十数分の後。【NAME】は何故か船首に備え付けられた衝角の先端に立っていた。背後に意識を向ければ、甲板に立つ船員、兵士、そしてイェアやノエル達の視線が、こちらの背中に集まっているのを感じる。
何でこんな事に。内心呟き溜息をつきながら、イェアの居室での会話を思い出す。
「色々調べた結果ですけれど、エルツァンの島が持つ固有の概念と、他の地域との概念との差。それが一種の結界に近いモノを形成して、今わたくし達が行く道を閉ざしているようですの。本来なら、高位の術者を集めて境界を揺らがせて騙し騙しですり抜けるのがベターなのでしょうけど、かなりの時間が掛かりますし。だから──【NAME】さん。あなたが譲り受けた神形器で、お願いできませんか?」
お願いできませんか、と言われても、【NAME】としてもあの神形器を自由自在に使いこなせるというわけではない。大抵の場合は、神形器からこちらへ干渉してきた時に限られる。
首だけ回して後ろを振り返れば、イェアがにこやかに笑って小さく手を振ってきた。ついでに、周りの者達からも応援の声があがる。
(あまり期待されても困るのだが──)
やるだけはやってみるか。そう意思を決めて、【NAME】は首から提げた飾りを手に取った。
──りん、と。
同時に、耳の奥で小さく鈴鳴る音が聞こえた。
(いける、か?)
首飾りを握る手に力を込める。鳴る鈴音がより強くなり、飾りの奥から半ば眠ったような虚ろな声が響きだす。
──感じる。
手の中にある飾りがふるりと揺れた。
──蟠る場。澱む波。滞る風。
同時に、【NAME】は首飾りの感覚を僅かに共有する。前方、エルツァンの島が見える方角を、僅かながらも色濃く沈んだ影が包んでいるのが見える。
──これを、斬りたいの?
少女の声で響く問いかけに【NAME】は頷き、肯定の意思を返す。すると、飾りの奥から満足げな気配が生まれた。
──なら、使って。私のカタチを望んで。
望む。
そう届く声に従い、【NAME】は首飾りから長剣の形状へと変じたゼーレンヴァンデルングを握った。
神形器の変化に背後から起こるどよめきと歓声を耳にしながら、【NAME】は剣を上段に構えると、一拍。そして勢い良く振り下ろす。
──同時、神形に秘められた力が弾けた。
剣身が空間を断つ動きに合わせ、大気が高い音を立てて爆ぜ、正面へと飛ぶ。
振るわれた神形から生じた力の奔流は膨大。撃ち放たれた無形の衝撃は、独特の破砕音を上げながら凄まじい勢いで海上を駆けると、遠い前方にたゆたっていた影の幕へと突き刺さり、その一部を音も無く吹き飛ばした。
その様を遠目に眺め、【NAME】は背後を振り返る。
これが正解なのかは判らないが、自分に出来ることは取り敢えずやった──筈だ。後は、その結果を判断できるであろう人物に問うしかない。
「船長、動力を起してくださいな! 土地概念の境界に大きく揺らぎが出来ました。今なら島へ辿り着ける筈ですわ」
振り返った先、イェアが声を張って指示を出すのを聞いて、【NAME】は小さく息をついて肩の力を抜いた。どうやら上手く行った、と考えて良いらしい。
後は、船を操る者達の仕事だ。剣から首飾りの形状へと戻ったゼーレンヴァンデルングを懐に仕舞うと、船員達の讃辞の声などを適当に受け流しつつ船尾へと移動。甲板の縁に身を預け、昼寝と洒落込むことにした。
目覚めた頃には、船はエルツァンの島へと辿り着いている事だろう。
そう気楽に考え、【NAME】は両の眼を閉じた。
──安らかなる岸辺──
上陸してからの軍の動きは兎に角素早かった。運搬作業。周辺偵察。野営地の選定、設営を滞りなく進め、既に陣はほぼ完成。今は海岸近くの開いた空間に今回の作戦に携わる人間達を集め、部隊の上層部が決定した項目を下の者へと伝達中だ。
広場に円を形成して立つ常駐軍の者達。そんな彼らの中央には、ノクトワイとイェアの二人の姿があった。
「────」
「はいはい。……で、だね。島内探索の隊分けと進行予定は今言った通りねん。残ったオーリスの部隊はこの野営と船の維持。南周り第三班のカリンの部隊と二半単位で交替ってことでヨロシク」
「────」
「んいんい。……あと、三周目の合同探知で沖に強度陰性質の大型亜獣が何種か確認されてるから、そっちの警戒怠っちゃだめよん。船やられたらまー色々とキビシイことになっちゃうから、任務としては探索行く連中より責任重大ってこと、よくよく理解しときなよ」
隣に立つイェアが小声で指示した内容を、彼女の斜め一歩前に出たノクトワイが伝える。今回の作戦での立場は、確かイェアが連隊の長を務め、ノクトワイはその補佐という形になっているらしいが、集まった部下達を指揮する二人は立場がまるで逆に見えた。軍外の者であるイェアより、実働の軍人達にはそれなりに人望のあるノクトワイが指示を出した方が物事がスマートに進む、ということなのだろう。
「いよっし、んじゃ解散。今回の任務の重要性と危険性。それをちゃんと認識して動くよーに。以上!!」
ノクトワイが一際声を上げて、ぱんと手を叩く。それを合図として、広場に集まっていた兵士達がそれぞれの役目をこなす為に散っていった。
そんな彼らの動きを他人事の如く眺めていた【NAME】であったが、己が立つ方へイェアとノクトワイが揃って歩いてくるのに気付いて視線を戻した。二人は【NAME】の傍へと歩いてくる間、だらだらと会話中。大した距離があるわけでもないので、会話の中身は丸聞こえだ。曰く。
「あーったく、メンドクサイわ~。えらい長々喋って喉乾くしさ。別に先生ちゃんが直接命令しても変わんないと思うんだけど」
「そうでもありませんわ。わたくしほら、元々軍外の人間で学士ですし、それに女ですから。立場その他が上という事になってはいましても、やはり多少なりと反感を持つ方もいらっしゃるでしょうし。それに、ノクトワイ様って兵の人達の間ではとても人気があるんですのよ。人望があるっていうのでしょうか?」
「ジンボーって……何でこんなテキトーにやってるのにそーなるのかねぇ。──ねぇ?」
最後の「ねぇ?」は、既に彼の目前といって良い位置に居た【NAME】に向けられたものだ。彼のこういう軽いながらもソツの無い態度が位的に下層の者達に人気がある理由──そして同時に、恐らく上層の者達からはあまり好ましく思われていない理由になっているのだろうが、それもいちいち口に出して言う事ではない。【NAME】は取り敢えず肩を竦めて誤魔化した。
「あららツレナイ。……ま、いいわ。で、今回本命の【NAME】には詳しい話はしたの?」
本命という言葉に何となく不吉なものを感じたが、こちらが反応を返す前に、問われたイェアが小さく首を振って答えた。
「いえ、今からする処ですの。といっても、大してお話しする事などないのですが。ノクトワイ様もお付き合いされます?」
「アタシはパース。もうちっと話詰めとかないといけないとこもあるし、あと、杜人クン達も実際どう動くつもりなんだか、その辺の事もね~。ま、用があったら呼んで。それじゃね」
ノクトワイは気軽に言うと、ひらりと手を振り去っていった。
その背を何とはなしに見送っていた【NAME】に、横からイェアの穏やかな声が掛かる。彼女はにこりと笑うと、
「一先ず、わたくしの天幕へ場所を移しましょうか、【NAME】さん」
【NAME】に告げて、先導するように歩き出した。のんびりと歩く彼女の後を追おうと一歩踏み出して、
(本命ねぇ……)
ふと、先刻のノクトワイの言葉を思い出す。やはり、自分の持つ神形器、ゼーレンヴァンデルングの力を主軸として常駐軍の部隊は動くつもりらしい。
だが、【NAME】とて自由自在に神形器を使いこなせるわけではない。【NAME】は他人に気付かれぬ程度の小さい溜息をつくと、首元の飾りを無意識に弄りながら、先行く彼女の後を追った。
・
フローリアは四つの大島と無数の小島によって構成された諸島だ。今まで【NAME】が旅してきたランドリート、コルトレカン、アノーレはその内の大島に分類される島々であり、エルツァンもその一つとして数えられる。
諸島発見後、各島の地質や危険性等を調べる為に送り込まれてきたアラセマ皇国の調査団は、ランドリート、コルトレカン、アノーレと三つの島の調査を終えた後、最後となったこの島エルツァンを調査しようと上陸を試み──それが叶わず、彼らは島の調査を断念した。彼らは幾度もエルツァンの島へと船を走らせたものの、先刻【NAME】達が遭遇したような異常現象に見舞われ、結局、調査団は島に上陸することが出来ずに放置された。
フローリア探索の第一陣となった彼ら調査団が引き上げ、ランドリートへの入植と芯海での中継都市化、そしてコルトレカン、アノーレの入植と話が進んだ後も、何度か調査部隊は編成されてエルツァンへと送り込まれたが、結局彼らは一度足りともエルツァンへ上陸することは出来ず。コルトレカン、アノーレの調査や治安維持に梃子摺っていたアラセマは、エルツァンの利用を初期の段階で放棄。島は完全な秘境として残され、以後島についての様々な噂が乱れ飛ぶも、その真相は誰も知らないという状況が長く続いた。
が、そんな停滞した状況を多少ながらも打破した者達が存在した。アラセマの探検家カール・シュミットと、その仲間達で構成された民間の調査隊だ。
カール達は侵入者を拒む島の力から偶然にも逃れることに成功し、エルツァンへの上陸を果たす。そして半ば全滅に近い状況ながら、最も近い大島であるアノーレへと帰還した彼は──生還したのは長であるカール一人だった──エルツァンという島について多くの情報を記した手記を残し、息絶えた。
彼の残した手記。その中で、カールはエルツァンという島が他の島とは完全に一線を画す特殊な、危険な場所であると記していた。
手記から読み取れるエルツァン島の特殊性の内、まず挙げられるのが亜獣や鬼を含む危険生物の異常なまでの数だ。その数はアラセマの討伐軍が派遣される前のコルトレカンやアノーレを遥かに上回るとされ、エルツァンが“真なる亜獣達の楽園”と呼ばれる所以ともなった。
次いで、各地形の特殊性と、それぞれの空間の不連続性。そして、島内発生事象の非現実性と、時間進行の不確実性だった。
所謂禍鬼、大鬼、そして大禍鬼。鬼種の中でも高位に位置する存在がそれぞれの地形を支配し、一つの地形が一つの世界に等しい形で存在する。地形と地形の繋がりが希薄であるため島内を地図として起す事もできず、島内で発生する様々な現象は、手記の内容を信じるならば全て異質。
当然、このカールの手記は彼の内でのみ生まれた単なる妄想の産物であるという可能性もあったが、エルツァン島についての詳細な資料は彼の手記以外になく、故にそれが嘘かどうかの判断すら出来ない。ならば取り敢えず全て真実という前提で見た方が建設的、という考え方らしい。
「と言う訳でして、これがカール・シュミット氏が残した手記ですわ。貴重品ですので大切に扱ってくださいね」
歩きながら島についての概略を語るイェアに連れられ、合わせ革で作られた天幕の一つに入った【NAME】は、そこで古ぼけた手記をぽんと手渡され、素直に慌てた。
その正否は問わないまでも、島についての情報が記された唯一の品を、ほぼ部外者に等しい冒険者に貸し与えるというのはどうなのか。
「ちゃんと写しはありますし、それに今回の件ではわたくし達はあくまで補助要員ですから。やはり主力となる方にはしっかりと情報を提供しておきませんと」
申し訳なさげに告げられた「主力」という言葉に、【NAME】はやはりかと深々と溜息をついた。
そんな【NAME】の態度に、イェアはどこか諭すような調子で続ける。
「わたくし達常駐軍の方でも島の探索は行います。ですが、大鬼、禍鬼クラスなら兎も角、上位の大禍鬼や、わたくし達の標的であるあの“鬼喰らいの鬼”と遭遇した場合、探索を主とした小隊単位では討伐はおろか……情けない話ですが、逆に全滅させられる可能性の方が高いでしょう」
故に、少数での探索を行うことが出来ない。かといって大人数で纏まっての探索行動となれば、動きは当然鈍く、効率は悪くなる、と。
【NAME】がイェアの言葉を奪うようにそう呟くと、彼女は神妙な表情のままこくりと頷いた。
「数は無くとも、罠となる大型の印章陣を念密に仕掛けるといった事をすれば何とかできなくもないですが……探索時での遭遇戦等となればそのような事は不可能ですし。それに上陸して軽く調査をしてみて判ったのですけれど、兎に角この島は土地概念の歪みが酷くて、地面や空間に式を記述しても正常に働くかどうか」
そこで彼女は小さく首を左右に振って息をつく。
「ですので、上位の鬼種と対抗しうる力を持つ神形器、その所有者であるあなたが如何に早く、そしてどこまでエルツァンの深部に入り込む事ができるか。それが全てになりますの」
イェアの物言いに、【NAME】は少々の苛立ちを混ぜて反論する。自分が持つ神形器ゼーレンヴァンデルングはそんなに都合よく扱えるものではないと。神形器自身の意思が、己の力が振るわれるに値する状況か否かを判断し、そして是と判じた時のみ秘めた力を解放して所有者に預ける。それが短い経験の中で得たゼーレンヴァンデルングの理だ。
「ええ、神形器の扱い辛さについては、ワイゼ──いえ、ハマダン・オリオール様から窺っております。ですが、それでも頼らざるを得ないのが現状です。わたくしはこの陣の指揮統括の役がありますので動けませんが、他の者でしたら二名程、同行者として自由に連れて行っていただいて構いません。ノエルは勿論ですが、ノクトワイ様や今回同行してくださったハマダン様。それにキヴェンティのリゼラ様も、あなたからの要請があれば御力を貸してくださる筈です」
ノクトワイ様がここを離れるとちょっと指揮がやりづらくなるのですけど、と添えるように呟いた。
「…………」
【NAME】は己のこめかみをとんとんと指で数度叩いて、沈思する。
彼女の言いたいことは判る。
未知の島で、目標の探索を兼ねた目的地も曖昧な行軍。島内での危険度は高い故に迂闊に少数の部隊に分ける訳にもいかず、しかし大人数で固まっていては自然と移動速度も低下し、探索にも向かない。ならば少数の精鋭を選抜して単独で島奥へと派遣するのが良策という流れなのだろう。
鬼に対する感知能力の高いノエルや、【NAME】が所持するゼーレンヴァンデルングの異常概念の感知能力。ノクトワイやリゼラの高い戦闘能力と、オリオールの特殊地形に対する知識。少数によるフットワークとそれらの特殊技能の相乗があれば、もしかしたら──と。つまりはそういう事だ。
(だが……しかし)
幾らノクトワイやリゼラが並の実力ではないといえ、たった二人の増員で、事前情報など殆ど無いエルツァンの島奥へと分け入り、そしてあの“鬼喰らいの鬼”を探し出して討つ。
(──厳しいな)
アノーレで戦った時の手応えから推測するに、今回エルツァンへと渡った兵士達全員と合同で戦ってもあの鬼にもう一度勝てるかどうか微妙だというのに。
眼の前に立つ女学士は、そんな【NAME】の意見に頷きつつも、
「無理を言っているのは重々承知していますわ。ですがあの“鬼喰らいの鬼”が、ただ身を隠すためだけにこの島へと移動したとは到底思えない。きっと何か思惑があっての行動だと思うのです。そしてそれが、わたくし達にとってどういう影響を及ぼすものなのかは判りませんが──手を拱いている間に何もかもが手遅れになってしまう。それだけは絶対に避けたいの」
深く深く頭を下げて、彼女は告げる。
「だからどうか──【NAME】さん、どうか宜しくお願いします」
そんなイェアを眺めて顔を顰めて僅かに呻き、そして【NAME】は今日何度目かの溜息をついた。
真なる楽園 力の霧欠
──ナリア・バータ霧眩森林──
その森林には、乳白に近い霧が立ち込めていた。
霧は驚く程に色濃く、どろりとした粘性さえ帯びているような錯覚に陥る。
──この森は、霧の森だ。
森へと足を踏み入れる前の天候は曇天であったが、たとえ晴天だったとしても、はたまた豪雨であったとしても、この森から霧が晴れることは無いという。【NAME】がイェアから借り受けたカール・シュミットの手記にはそう記されていた。
エルツァンの岸から森の中へ。ほんの僅かに足を踏み入れた辺りで【NAME】は立ち止まり、白色の霧に包まれながら手記のページを捲る。
カール・シュミットの手記は、極々単純な構成で書かれている。移動と新たな地形に関する記述、そして顛末。その繰り返しだ。元は単なる日誌に近いものなのだから当然と言えば当然だ。尤も、手記の中盤以降からは謎の多い、妄想じみた内容へと変化するのだが。
カールが率いる探検隊は、【NAME】達アラセマ常駐軍が上陸した地点からはかなり西へと離れた位置に漂着したらしい。それ故なのか、この霧の森に関する部分は岸に近い割りに手記の前半ではなく、丁度真中にあたる位置に書き込まれていた。
彼は手記の中で、この森を“ナリア・バータ”と名付けていた。
カールの探検隊は霧より生まれた多数の化け物と、彼らが練り合わさって現れた霧の竜との戦い、そして貴重な仲間を失っていた。竜が吐き出す霧の吐息、それに混ざっていた強力な毒で身を侵されたのだ。
死亡した隊員の名はナリア・バータ。手記に記された地形名の殆どは、そこで失ったカールの仲間の名がつけられていた。
ぱらぱらと流し読んで頭の中に大まかな内容を記憶していた【NAME】は、最後に書かれた彼の結論と思しき文章を見て目をとめた。
『この森に立ち込める霧は、侵入者の深層意識から脅威の対象となる存在を引きずりだして、我々の世界へと顕在化させる』
そして、
『森の主は霧の竜だ。あの猛々しき竜の姿が、この森を支配する力の原型なのだろう』
【NAME】は手記を閉じて、一息。改めて、眼前に広がる木々の群れと、そして漂う乳白の霧を見た。
・
「【NAME】。気付いているか」
──と、唐突に言われて、【NAME】はその声の主である少年、リゼラ・マオエを見た。
「霧に混じる歪みが強くなっている。そろそろ来るぞ」
少年が視線だけで指し示す方向。漂う霧の所々に、濃密な霧の塊が発生しているのに気付いた。
そして塊はゆっくりと浮遊しながら【NAME】が立つ場所へと近づき、次第にその形を凶暴な獣の形へと変化させ始める。
その様を眺めて、【NAME】はふむと唸る。どうやらあれが自分が持っている脅威の対象であるらしいが、正直単なる亜獣にしかみえない。
【NAME】の感想に、背後の少年は静かな表情のまま武器を抜き、言葉を返す。
「簡単だ。恐怖となる対象、ではなく、敵となり仇となりえるカタチ、であるのだろう。単なる探検家であったカール・シュミットとやらには、全ての亜獣は恐怖の対象であるだろうからな」
なるほどと呟きながら武器を抜き、構える【NAME】の動きに合わせて、霧で形作られた亜獣達も行動を開始する。【NAME】達を排除する行動を。
さすが元が霧というべきか。
兎にも角にも、打撃による攻撃の手応えが薄く、原型となった亜獣よりは数段強い。周りに漂っていた霧の塊は一通り砕き終えて取り敢えずの安全は確保したが、これで打ち止め、という訳ではないだろう。
戦闘で上がった息を整えて、武器を仕舞う。そこへ少し離れた位置にいたリゼラが剣を収めながら戻ってくる。
「我の剣とは相性が悪い。『九継』を迎え入れれば早いのだろうが──命脈が掴めぬ」
リゼラが吐き捨てるように呟く。冷静な少年にしては珍しく、言葉の内に僅かな苛立ちの色が見えた。恐らくは、自身の分身ともいえる翠霊を呼び出せぬ歯がゆさからだろう。
そんなリゼラを眺めながら、【NAME】は森を歩く間定期的に弄っていた首飾りから手を離す。僅かに共有した神形器の感覚を信じるならば、この森には“鬼喰らいの鬼”の気配は無いように思えた。
【NAME】はその事を仲間に告げて、ならばさっさとこの森からは脱し、別の地形へと向かうべきかと提案するが。
「この方角の更なる奥に、地を統べる命の力の渦がある」
霧の奥を見据えたまま、リゼラがそう呟いた。
少年の言葉に、【NAME】は首を傾げる。先刻も彼はそのようなことを言っていたが──その命の力とやらが、ゼーレンヴァンデルングの感覚では嗅ぎ取れぬ、“鬼喰らいの鬼”の気配を指すのだろうか。それとも全く無関係の何かを示すものなのだろうか?
リゼラは僅かに顔を伏せて、思案するように口元に手をやる。
「判らぬ。土地概念がもう少しでも正常ならば命脈の力を借りて詳しく探ることも可能であろうが、この島の概念異常は並ではなくてな。──この先に、森を取り巻く力の中心となる渦が見える。それしか判らん」
己の眼で確かめるしかない、という事か。
森の奥の奥。リゼラの先導で辿り着いた先に広がっていたのは、砕けて崩れ、しかし具えた機能を失う事無く動き続ける遺跡群だった。
「なるほどな」
それを眺めて、【NAME】の数歩前で立ち止まっていたリゼラが苦味のある声で呟き、後ろに立つ【NAME】へと振り返る。
「【NAME】。済まないが、どうやら無駄足を踏ませたようだ。これはあの大禍鬼とは全く無関係の──“芯なる者”が遺した芯形機構[グリフコンバータ]の成れの果てだ」
確かに彼の言う通り、広がる風景の中に“鬼喰らいの鬼”が居る気配などない。しかし──兎に角、概念の歪みが酷い。今にも別の鬼種が発生してもおかしくない程だった。
あまり長居はしない方が良さそうだ。そう判断し、その場から離れようとした【NAME】を、
「──待て。油断するな」
濃厚な霧に包まれた遺跡群を凝らすように見ていたリゼラが、静止の声をあげた。
振り返った【NAME】は少年の視線を追い──そこに先刻出くわした化け物のように霧で身体を構成した巨大な竜が、【NAME】達の方へと宙を滑る様な動きで迫ってきているのが見えた。
(あれは……)
カールの手記に記されていた霧の竜──か。
「来るぞ、【NAME】」
腰に差した長剣を引き抜きつつ、少年が冷静な声を飛ばす。【NAME】が慌てて武器を構える間に、竜は瞬く間に迫り、そして【NAME】達目掛けて襲い掛かってくる!!
[BossMonster Encountered!]
battle
森従える霧主

竜が繰り出す爪の嵐を掻い潜り、連打。竜の肩から首に掛けて集中的に攻撃を加え、身を吹き飛ばす。
しかし竜は遺跡から生み出される霧を身の内に取り込みその傷を修復。しかも身体を修復前より大きく、より正確な姿へと変化させていく。
(拙いな……)
その様を見て【NAME】は怯むように一歩下がり、戦闘の熱で浮いた額の汗を拭った。
しかし、リゼラは剣を中段に構えたまま逆に一歩進み、修復を終えて動き始めた竜を睨む。
「あの竜はこの森に蠢く歪な力が最も明確に顕現した姿だ。ここに残る力は歪な理、歪な命だ。そして自らを正す意思もない。ならば討つべきだ。我等キヴェンティはその律を全とする。手を貸せ、【NAME】よ」
かといって、こんな処で無駄に体力を消耗するのはあまり良策とはいえない。
では、どうするか。覚悟を決めて徹底的にやり合うか──
「ならば行くぞ【NAME】!! 我等が命の理を持ってして彼の力の歪みを正す!!」
意気強く放たれた言葉と共に、少年の身体が一瞬沈み、次の瞬間弾かれたように飛び出した。
そこへ凄まじい咆哮。
同時に、先刻より巨大になった霧竜の口蓋から、莫大な量の霧が打ち出される。その目標は全力で走り出したリゼラだ。
少年の小さな身体が、打ち寄せる白の波に飲まれて消える──その瞬間。
「苛──ッ!!」
気合の声と共に少年の持つ長剣が閃き、その切先に乗せられた斬り裂く概念が空間を断ち、彼を飲み込もうとした霧の流れすらも二分。真っ二つに断たれた竜の吐息は、それぞれ少年を避けるように後方へと流れて弾けた。
「【NAME】、何をしている!!」
と、霧の吐息によって荒れた大気の向こうからリゼラの叱責が届く。
確かに、ぼんやりと見ている場合ではない。【NAME】も武器を構え、リゼラの後を追って走り出す!!
[BossMonster Encountered!]
battle
森従える霧主

竜が周囲の霧を取り込み再生する前にリゼラが竜の身体へと張り付くと、正に電光とも表現できる剣閃でもって霧の身体を切り刻む。そしてリゼラの攻撃が竜の修復能力を上回り、最後には殆ど固体に近い程の濃密な霧が詰まった白い球体が一つ残るのみとなった。
リゼラはその球体の中心に一度刃を通し、そして小さく何事かの文句を呟くと、そのまま刺した剣を抜いた。
「これが、この森が持っていた力の結晶だ」
リゼラはそう呟くと、ひょいと球体を投げて寄越す。【NAME】は慌てて受け取った。
辺りを見渡せば既に立ち込めていた霧は晴れて、平穏な森の風景を取り戻している。
「無駄を取らせたな、【NAME】よ。“迷の民”であるお前には判らぬだろうが、目の前にある歪を放置するというのは気分の良いものではなくてな」
剣を収めながらの詰まらなさげなリゼラの声に僅かに苦笑しながら、【NAME】は改めて首飾りへと手をやる。
森に立ち込めていた歪が多少静まり、神形器が知覚できる範囲は先程より広がっているものの──やはりあの鬼の気配は感じられない。
ならば、やはり森を脱し、島の更に奥へと入り込む必要があるか。
真なる楽園 白風の鬼珠
──ロームフーネ無空峡谷──
【NAME】は首飾りに手をやると、握り、意識を集中させる。ほんの僅かに同調した神形器の感覚が──この峡谷に奇妙な力が吹き抜けているのを捕えた。
一体、何の気配か。あの“鬼喰らいの鬼”が発するような凶暴なものではないが、しかし何処かしら影のある、鬼が放つものによく似た気配であるのは確かだった。
詳しく知ろうと意識をより集中させてみるが、そんな【NAME】の意思など全く無視するように、返って来る感覚はあやふや極まりない。
──と、そんな【NAME】を邪魔するように、ガァ、と枯れた鳴き声が空から響く。見上げれば、【NAME】の真上を円を描くように飛ぶ鳥の群れ。
どうやら、峡谷を滑空する鳥達に目をつけられたようだ。天より細く差す照明など不要という鳥とは思えぬ動きで、上空を舞っていた彼らは【NAME】に向かい真っ直ぐに滑降してくる!!
上空より滑空し、地面すれすれの位置から飛び掛ってくる鳥達を全て打ち捨てた【NAME】は、詰めていた息を吐いて、そしてふと気付く。
谷を抜ける風。それに、奇妙な気配が混じっていることに。
【NAME】の脇を通り過ぎる風は緩やかながらも不可思議に巻き、谷底に奇妙な流れを作っている。
「この風は──嵐竜のものだな」
そう呟いたのは先導していたオリオールだ。風の流れだけでそんなものが判るのかと、【NAME】は訝しげに彼を見ると、男は僅かに苦笑。
「まあ、微妙に違う気配が混じってる気もするけど──多分確かだよ、特徴的だし。それに何度か戦った事もあるからね」
そこでオリオールは表情を真剣なものへと変える。
「でも、この先に嵐竜が居るというなら、このまま下を進むのは拙いな。空中に留まられるとこちらの攻撃が届かなくなって厄介だし……【NAME】、上に登るかね?」
言って、彼が指で指し示したのは、崖の中程にあった大きな岩棚だった。
岩棚の上への登攀。これ自体は大した問題も無く終わった……のだが。
「──う」
眼前に広がった光景に、【NAME】は息を呑む。
丁度【NAME】達が顔を出した岩棚の上に鎮座していたもの。それは巨大な巣だった。しかも普通の鳥が作り出すような生易しい代物ではなく、峡谷に住む翼竜のもの。
更に巣の主は御在宅であらせられ、その上【NAME】の存在にも気付いたようで、伏せていた顔をゆっくりと上げてこちらを見ている。
「あー、これは迂闊だったかー」
などというオリオールの気の抜けた叫びを聞きながら、己の縄張りに踏み込んできた人間達を払うために身を起した翼竜と対峙する!!
battle
力強き翼竜

竜を手早く打ち倒した【NAME】達は、峡谷の更に奥、風の中心へと向かい歩を進める。風は不気味に唸り、棚の下方を見れば、谷底の砂を巻き上げて風は黄銅の流れとなっている。
──と、その風に乗り、時折獣の遠吠えとも思える声が聞こえた。気のせいか、とも思うが。
「本番だな。そろそろ近いぞ」
オリオールの呟きに、【NAME】は眉を顰める。確かに、今までの様々な戦いで【NAME】が培ってきた、冒険者としての勘とも呼べるもの。それがこの峡谷の奥、力持つ風の向こうに何かが居る事を伝えてくれる。
薄い土色に染まった景色の中、【NAME】は僅かに足を止めて考える。
本来ならば、そういった気配を感じたなら避けて通るか戻るべきなのだろうが、少なくとも【NAME】の判断ではこの谷に脇道など無く、そして戻ったとしても別の道が見つかるとも思えない。
結局は、進むしかないか。
溜息をつこうとして、しかし風に混じる土埃に気付いてそれを止めると、【NAME】は改めて足を動かし始めた。
奥へ奥へと進むごとに、峡谷を抜ける風は強さを増し、既に暴風と呼んでも差し支えの無い程に達していた。
だが、その風に屈して引き返す訳にもいかない。巻き上がる土埃に遮られ、視界の殆どを塞がれた状態のまま。【NAME】はただ黙々と谷を進む。
──と、唐突に視界が晴れた。
無意識に伏せていた顔を上げて周りを見れば、そこは円の形に削り取られた巨大な広場。
その広場の中央には、峡谷に吹く力ある風を操り、渦の形として纏う巨大な嵐竜の姿があった。
己が身に白く濁る程の強風を帯びたその竜は、自らの住処に侵入してきた無粋な輩の存在に気付き、その両眼をゆっくりと向ける。
竜と自分達の高さはほぼ同等。これならば、武器を届かせることも可能か。【NAME】は満を持して武器を引き抜き、身構える!
[BossMonster Encountered!]
battle
嵐という暴君

全力を込めた一撃が竜の喉元へと突き刺さり、弾けた。風が爆発的に吹き荒れて、竜は断末魔の悲鳴をあげた後、激しい音と共に倒れ伏した。
風が消えたことにより視界が晴れ、【NAME】は改めて周囲を見渡す。広場は行き止まりに近く、しかし竜が浮んでいた場所の背後に聳える切り立った崖。その一部が崩れており、それによって出来た段差を上手く選べば峡谷の上へと抜けられそうだ。
少なくとも、竜を倒したことによってこの場所に漂っていた気配は消えた。と云う事はやはりあの鬼はここには居ない。
ならば次のステージへ。【NAME】は正面に聳える崖へ向かい、ゆっくりと歩き出して──。
「お待ちください」
止められた。振り返ると、ノエルが僅かに眉を寄せて息絶えた竜の姿を見ていた。
「あの竜……何か、あります。中に、あれは──」
鬼の気配、か?
しかし【NAME】が持つ首飾りは全く反応しない。つまり、ノエルの感性には引っ掛かるがゼーレンヴァンデルングにしてみれば取るに足らない程度のもの、か。
そこで、【NAME】より先に進んでいたオリオールはふむと唸ると、
「なら捌いてみるか?」
気軽に言って、己の腰に刺した小剣を掲げてみせる。鉄を上回る硬度を持つ鱗に包まれた巨竜をそんな小さな剣で捌けるのか、と【NAME】は疑問を口にするが。
「そうでもない。わざわざ鱗の上から刃を立てる必要も無いからな、まぁ見てると良いよ」
・
「こんなものだろう。──で、多分あれじゃないかな。見てくれ」
鮮やかな捌きぶりで竜の腹を綺麗に開いて見せたオリオールは、ある一点を指差した後、素直に場所を譲る。替わりに【NAME】とノエルが前に出て竜の腹の中を覗き込んだ。
生臭い血の色と臭いに染まる竜の体内。その中に、握りこぶしほどの大きさの白色の球体が埋まっているのが見えた。
「これ、です。恐らく、竜が操っていたあの歪な風の力。その源がこれなのだと、わたしは考えます」
「では、改めて行こうか」
オリオールの声に【NAME】は頷くと、白色の球体を背嚢に放り込み、そして正面に聳える崖へ向かってゆっくりと歩き出した。
真なる楽園 焼けつく雷碑
──カリッサ灼雷領域──
湖の中心にあったのは、島の真中に立てば端から端までを一度に見渡せる程度の大きさしかない、小さな島だった。
そして、雷満ちる湖の中にぽつんと残されたその島の上にあるのはたった二つ。島中央の僅かに丘となった場所に立つ巨大な枯れ木と、それに巻きつく雷身の蛇だ。
胴の太さだけでも人間の大人では到底抱え切れそうにない巨体を持つその蛇は、自分の住処に入り込んできた闖入者たる【NAME】を見据え、絶え間なく放電を繰り返す頭部をゆっくりと起こす。
対して、【NAME】は深い溜息をつく。
この場所一帯を支配していた気配の主が、今眼の前に居るこの蛇のものであると──つまり、【NAME】の目的である“鬼喰らいの鬼”の気配ではない事がはっきりとしたからだ。
しかも雷で身を纏う大蛇が、愚かにも彼の縄張りへと足を踏み入れた【NAME】を素直に逃がしてくれるとは思えない。それ故の溜息だった。
そんな【NAME】の諦念に反応したかのように、蛇が枯れ木から身を離す。樹から地への移動ではなく、樹から宙へ。蛇は空中を泳ぐように漂い、そして爬虫類らしく大きく顎を開くと、喉奥から細く高い鳴き声を一つ上げた。
響く声に空気が揺らぎ、それに誘われるように湖の雷気が空中へと立ち昇った。生まれた黄色の輝きは島の周囲に網となって広がり、それによって【NAME】は己の退路を塞がれた事を知る。
(……やるしかない、か)
空中をうねる雷の大蛇を見据え、【NAME】は無言のまま武器を抜いた。
[BossMonster Encountered!]
一際高く跳躍した【NAME】は、蛇の鼻面に全精力を込めた一撃を叩き込む。
だがすれ違い着地した【NAME】は、背後からの空気が裂ける高い音を聞き、肩に走った強烈な痛みに苦悶の声を上げた。大蛇の放った雷撃に身体を打たれたのだ。
しかし、ここで足を止めれば一巻の終わり。雷の衝撃で痺れ感覚を失った身体に鞭打ち、無理矢理横へと動かす。傷の痛みに大蛇が身をくねらせる度に飛び散る雷の飛沫。それを寸での処で避けると、練り上げた技法の攻撃を打ち上げるように繰り出した。
裂帛の気合と共に打ち出した力。返るのは、会心とも言える手応え。
見れば、黄色に染まる蛇の胴が、【NAME】の一撃によって真っ二つに千切れ飛んでいた。
二分された蛇の後部は激しい音を立てて地面へと落下し、暫く暴れた後に動きを止め、残った頭部もふらりふらりと力無く空中を泳ぐと、島を離れて雷気帯びる湖へと身を落とし、そのまま静かに湖の底へと沈んでいった。
その様を見届けて、【NAME】は身を折るとかっと息を吐く。雷に貫かれた身体は痺れ、殆ど言う事を聞かない。
(少し──休むか)
そのような状況ではないのは判っているのだが、いい加減身体が限界に来ていた。
【NAME】はそのまま大の字に倒れ、背に当たる土の感触を味わいながら、深く深く息を吐き、両眼を閉じた。
・
「【NAME】。お目覚めですか?」
──いつの間にか眠っていたらしい。
傍らから掛けられた声に、【NAME】は僅かに両眼を開く。空を埋めていた暗雲もいつの間にか消え去り、月と多くの星々が瞬く曇りのない夜空が高く広がっていた。そしてそんな空を背景に、ノエルが【NAME】を覗き込むようにして見ている。
「先程の大蛇との戦闘から、四時間以上経過しています」
まるで独り言のような調子で呟かれるノエルの言葉を聞きながら、【NAME】は寝転んだまま動かずに夜空と彼女を眺めて暫く。軽い声で勢いをつけてひょいと身を起こすと、状態を確かめるように身体を動かしてみる。大蛇との戦いでの傷や疲れが完全に失せたとは到底いえないが、多少は楽になったように思えた。
呼吸ひとつの間を入れて、ぐるりと視界を一巡。
あの雷を纏う大蛇を屠った影響なのか。湖水や大気に満ちていた強烈な雷気は薄れ、先刻までの異常な空間は、何の変哲も無い物静かな夜の湖畔へ移り変わっていた。島上に緑が無く、あるのは中央に立つ巨大な枯れ木一本というのは風景としては寂しいものがあるが、まあそれも仕方あるまい──などとぼんやりと考えた処で。
「【NAME】、少し宜しいでしょうか?」
ノエルの問いに、疑問を乗せて彼女を見た。するとノエルは島中央に立つ枯れ木。それを指差して告げる。
「あの木の根から、小さいものですが歪な気配を感じます。鬼か、それに類する気配とわたしは推測しますが」
どうされますか? という視線に、【NAME】はまだ半分眠りの中にあった意識を静かに覚醒させる。
(──まだ何かあるのか?)
正直、これ以上の戦闘は勘弁して欲しいところだが、かといって調べぬまま放置するという訳にもいかない。【NAME】は手だけで後ろをついてくるようにノエルに指示し、歩き出す。
生まれた警戒の念は消さずに、【NAME】はゆっくりと枯れ木へと近づく。傍まで移動してみて気付いたことだが、枯れ木は遠目から想像した以上に大きかった。最初に見たときはあの大蛇が巻き付いていたため、然して気にしていなかったが、大人数人が手を繋ぎ幹を囲んだとしても、恐らく両端に位置する人同士の手が届かない程だ。
一歩、一歩と近づき、周囲に動きが無いのを確認してから、また進むのを繰り返す。枯れ木との距離はゆっくりとではあるが確実に縮まっていき、そして木の根にまで何事もなく辿り着いてしまった。
「…………」
拍子抜け、という訳ではないが、気が抜けたのは確かだ。そこへ、
「その裏から、感じます」
と、後ろをついてきていたノエルが言う。彼女は【NAME】の横をすり抜けると、根と根に挟まれ陰となっていた部分で立ち止まり、振り返ると【NAME】を見た。
──そこに何かあるのか。
【NAME】も根を乗り越えノエルに近づくと、彼女が指す陰の中を覗き込んだ。
根に半ば埋まるように置かれていたのは、深い藍の色を持つ掌大程の大きさの碑石だった。その表面には何かの文字が刻まれているが、【NAME】にはその意味を掴む事ができなかった。少なくとも、アラセマやキヴェンティの人間が使う文字ではなく、魔術などの技法使用の補助に使われる印章[シギル]とも異なるものであるのは確かだが、それ以上のことは判らない。
これがノエルの言う気配の出所だろうか。
見たところ、強い波動のようなものは感じるが邪悪な力がどうこう、というような雰囲気は無い。振り返りノエルに視線だけで訊ねれば、彼女は無言で頷いてみせた。
「ですが、【NAME】はこれをどうされますか?」
問われて、迷う。取れる選択肢といえば、破壊し捨て去るか、持ち歩くか。その二つか。
取り敢えず拾い上げ、その処理をどうするかは後で決める事にする。
(あとは……)
【NAME】は改めて懐に手をやると、神形の首飾りへと触れ、意識を集中する。辺りに立ち込めていた歪の気配が消えたお陰で、飾りと共有する感覚の範囲は広い。だが、それでも“鬼喰らいの鬼”の気配は感じられずに終わった。
やはりこの地にあの鬼は居ない。
ならば、次の地形へ──エルツァンの島の更なる奥へと踏み込まねばならないか。
真なる楽園 揺るぎの秘石
──イールシック地下都市遺跡──
建物の出入口から外へと出る。当然、周りの景色は建物へ入る前のものと同じなのだが、漂う雰囲気が全く異なっていた。
静ではなく、動。
建造物の中より現れ、寂れた道路を滑るように走る群れは武装した機械兵器達。彼らは真っ直ぐにこちらへ向かって移動してくる。
ここに居ては危険。兎に角場所を移そうと【NAME】は走り出し──しかし建物の影から現れた巨体に行く手を塞がれた。
それは今までのような対人を主としたものではなく、もっと大型の存在と対峙するために作られたと思しき巨大な機械兵器だった。
暫し呆気に取られて動きを止めた【NAME】の様子にも油断は示さず、その巨大な機械は胴の側面に取り付けた巨大な杭打ちの先端を、無機質な動きで【NAME】へと向ける!!
[BossMonster Encountered!]
battle
生誕の場護る

大型の機械兵器を何とか撃破するも、その戦闘に消費した時間は少なくなく。道路を走っていた機械兵器の群れは既に眼前とも言って良い位置にまで近づいてきていた。
このままでは拙い。が、【NAME】がやってきた通路がある方向は既に大量の機械達で埋め尽くされて、そちらへ戻るのは不可能だった。【NAME】は仕方なく、先に何があるかも判らぬ方角へとがむしゃらに走り出す。
兎に角空間の縁を目指して走り、そして聳える硬質の壁まで辿り着いた【NAME】は壁面に手を付いて、今度は壁とは平行に走り出す。その先にどこかの通路へ繋がる口があれば、助かる可能性はある。
迫る機械達を振りきり、すり抜け、走り続ける【NAME】。そろそろ体力の限界──といったところで。
見えた。壁に開いた扉と、その奥へ続く通路。開いた扉の上部には、○と黄の光が点灯している。
(助かる、か!?)
【NAME】は全力で駆けて通路へと飛び込み、通路の奥から機械達の気配が無いことに安堵。そして、背後を一度だけ振り返って自分を追ってくる機械の姿を確認してから、通路の奥へと駆け出した。
真なる楽園 大禍石の破片
──ザルナルバック月光丘陵──
夜に昇る月の輝きには不思議な力が宿るという。それは太陽が齎す陽性の力ではなく、どこかしら陰の質を帯びたものであり、故に歪な概念を持つ存在に僅かながらに働きかけ、その在り様を微妙に変化させる。
この丘に夜のみ現れ、暴れ狂う亜獣達にはその影響が顕著に現れている、ということなのだろうか。
そんな事を考えて、しかし【NAME】は短く首を振る。原因などどうでもいいのだ。それより丘陵を徘徊する亜獣に見つかるか見つかるまいか。それのほうが重要だ。無駄なことに意識を向けて、周囲の警戒を疎かにする訳にはいかない。
丘を彷徨う無数の凶暴な気配、それを見切り、気配と気配の間をすり抜けるようにして【NAME】は進んでいく。
眼を血走らせ、恐ろしい速度で走り抜けていく狼の群れをやりすごし、安堵と共に【NAME】は周りへ視線を飛ばして、そこで短い草の原でのみ構成されていた丘陵の中で一つの異質を見た。
緩やかに上下する草原。幾つもある丘のなかで、一際大きな山を作っている丘の頂点に映る奇妙な影。訝しげに眉を寄せて、目を細めて凝らせば、どうやらそれは巨大な岩であるのが判った。
空からの月光を受けて仄かに輝く大岩をじっと眺めていた【NAME】は、僅かに思案し、そして己の首から下げた飾りを手に取った。
「…………」
なるほど、あれか。内心呟いて、【NAME】は表情を疑念から確信、そして緊張へと変化させた。
大岩から感じる異質は、丘を渦巻いている多数の気配に比べれば微弱──なように思える。しかし、丘陵全体を覆うように働いている奇妙な気配。【NAME】が離れた位置から丘陵を眺め見たときに感じたあの微弱な鬼の気配の大元が、あの岩であるように思えた。大岩から染み出すようにして漏れる気配が丘全体に充満して、それが夜になると現れる亜獣達にも干渉している。
各所から感じる亜獣達の常ならざる気配に混じり、あの大岩から漂うのが“鬼喰らいの鬼”に近しい気配なのかは判断できないが、少なくともあの丘の頂点に聳える大岩が、丘陵が持つ異質の元凶であるように思えた。
──ならば行くか。
小さな可能性でも確かめておく必要はある。
【NAME】は武器を片手に、岩立つ丘の頂上へと足を向けた。
・
丘の頂上を目指して緩やかな傾斜を登り、暫く。足を止めた【NAME】は、眼の前に転がる──いや、突き刺さった大岩を見上げた。
岩の大きさはかなりのもので、高さは【NAME】の身長を優に超えて、大型の亜獣などよりも更に高い。7メートルを超えるか超えないか、といったところだ。高さに合わせて──ということでもないのだろうが幅の方もかなりのもの。形状は縦向きの楕円を半ばまで地中にめり込ませたような印象だ。
そして岩の頂点には、一つの人影が立っていた。
人影はまるで道化師のような衣装を纏い、手には長い笛を携えている。その姿は人に似ているが、纏う気配は極めて異質で、しかも強大だった。影の傍には二匹の小さな妖精の姿があり、彼女達は道化の肩にしなだれかかるような格好で浮んでいる。
道化の影が、ふと顔を僅かに下へと傾ける。
見上げた【NAME】と、見下ろす人影。二人の視線が絡まった。
夜の影に紛れてその顔は殆ど見えないが、しかし黄金に輝く両眼が自分の両眼を捉えるのを、【NAME】ははっきりと感じた。
そこで瞳が笑い──影は手に持った笛を口へと運んで。
そして、吹いた。
「────!!」
吹き出され、奏でられたのは音ではなく、破壊の波動。強烈な破裂音と共に大気を割りつつ、放たれた力は【NAME】目掛けて一直線に飛ぶ!!
[BossMonster Encountered!]
笛が呼ぶ破裂は奏者たる道化の影から扇状。距離は離せば離すほど回避は難しくなる。【NAME】は兎に角距離を取られぬよう全力で近づき、そして防御は捨てて攻撃と回避に集中する。
放たれる破壊の波を正に紙一重といった間合いで避け、そして密着に近い状態からの一撃。
(──取った!)
【NAME】は勝利を確信する。道化師の身体に食い込んだその攻撃は、手応えこそ何故か薄かったものの、明らかに相手の息の根を止める致命となる一撃だ。
しかし道化の手が全くダメージを負っていないような自然な動きで笛を口元へと持っていく仕草を見て、【NAME】は全力で横へと飛んだ。
「────!!」
真横を通り抜ける破裂の音色。回避できたことに安堵しつつも、【NAME】は困惑と動揺の中で道化を見る。相手の胴体は【NAME】の一撃を受けて殆ど吹き飛び、失われていた。しかし道化師の動きに鈍りは微塵も無く、寧ろその身より放たれる歪な気配はより増して【NAME】を圧倒した。
(どういうことだ……?)
身体を損傷しても極普通に動く。これはまだいいが、纏う気配や力にわずかでも陰りが見えないというのはおかしい。それに、先刻の胴への一撃に殆ど手応えと言えるようなものが返ってこなかった事も奇妙だ。まるで、幻影か木偶人形を相手にしているような感覚。
そこまで考え、【NAME】は一つの結論に思い至る。
──この道化は、あくまで代理の存在なのだと。
(ならば……)
近くにあるもので、本体として推測できるのは一つしかない。
道化の影が動き、口を寄せた笛から再度破壊の調べが奏でられる。【NAME】はその波動を視線すら寄越さずに避けると、手にした武器に渾身の力を込め、振り上げ、そして叩きつける。
今まで争っていた道化師にではなく、その隣で【NAME】達の戦いを見守っていた大岩へと。
ごぎ、と硬く低い音が響き、岩の表面が砕けて飛び散り、そして僅かながらではあるが八方へと亀裂が走る。同時にがくんと、道化師から感じていた強い力の気配が弱まるのを感じ、【NAME】は己の推論が当たったことを確信した。
後は簡単だった。正に渾身の力を込めた攻撃を二度、三度と叩き込んで岩を破壊すれば、道化の影から力の気配は完全に失せて、呆気なくその身を空中へと霧散させた。
・
徐々に朝が訪れつつあることを、【NAME】は地平に近い空の色から悟った。
疲労により地面に投げ出していた身体に力を入れると、身を起こす。何気なく視線を周囲へと巡らせると、先刻破壊した大岩の破片が周りに派手に散らばっているのが目につく。
【NAME】は何気なくその岩の一つを拾い上げると、手の中で転がす。岩からは僅かながらの異質な気配が染み付いているのを感じたが、しかしそれも暫くすれば消えるだろう。何とはなしに背嚢の中にその岩を放り込んでから、【NAME】は立ち上がった。
取り敢えず、この丘で感じた気配は“鬼喰らいの鬼”のものではなかった、という事は確かめられた。
ならばもうここには用は無い。
【NAME】は新たな地へ続くだろうと思しき方角を己の感性だけで決めると、ひょいと一度背嚢を抱え直してからゆっくりと歩き出した。
真なる楽園 大禍鬼の指
──ブランタンハリア山岳回廊──
雨の中、草を飲み込み木々を倒して斜面を這い寄る泥の巨人。その動きは一見、先刻と変わりは無いように見える。
だが、こちらがあの巨人に放った攻撃には、僅かながらであるが手応えはあった。同時に、その動きが多少なりとも鈍っていることも。たとえ泥の身体でも、それを維持し回復させる為の力が必要だということだ。
ならば、相手の力を削りきれば勝機はある。勝機はあるが──しかし、それまでこちらの体力が持つかどうか。
そうして迷う間にも巨人の攻撃を避ける為、距離を取る為に動くことによって体力は消耗する。ここで戸惑い勝機を逸するよりは、それに賭ける方がまだ悔いが無い。
無意識に首飾りを弄る。が、反応は鈍く、奥に眠る気配はまどろみの中にある。まだ己の出番ではないと、そんな風に。
──こうなったら、とことんやり合うか。
【NAME】は僅かに苦笑を残して首飾りから手を離すと、逃げる足を止めると覚悟を決める。
そして【NAME】は振り返り、間髪入れずに横へと跳躍。一瞬前まで居た場所に泥の塊が駆け抜けるが、【NAME】は一切意に介さず、泥の巨人の懐へと飛び込み、攻撃を叩き込むために動く!!
[BossMonster Encountered!]
battle
回廊の巨鬼

腐った果物を纏めて叩き潰したかのような音。
それは【NAME】の技法による攻撃を受けて、泥の巨人の頭部が弾け散った音だ。身の全てを泥で構成しているらしく、破裂した頭から飛び散るのは泥の塊のみ。それらは雨に濡れた木々に降り注ぎ、どろりと地面へ滴り落ちた。
頭部を丸ごと失った巨人の動きが、そこで漸く目に見えて鈍る。
(──好機!)
恐らく、これを逃せば次は無い。
【NAME】は雨に濡れ湿りを帯びた地を蹴って巨人の懐へと飛び込むと、鋭い連撃を放つ。全力に等しい力を込めた攻撃を、しかも間断無く打ち放った。息もつかず繰り出される技法を受けて巨人の泥の身体が弾け、瞬く間にその形を失っていく。
【NAME】の一撃が巨人の腕を飛ばし、肩を剥ぎ、腰を散らして、足を削ぐ。限界を超えて酷使された身体が悲鳴をあげ、無呼吸での長時間の行動に意識が狭窄し始める。だが、ここで動きを止める訳にはいかない。
残ったのは巨人の胴体。最後の一撃とばかりに、詰めていた息と共に気合の声を張り上げ、【NAME】は止めとなる技法を泥の巨体の中心へと叩き込んだ。
──ど、と。
腹に響く音が振動として伝わり、そして確実な手応えが【NAME】へと返る。巨人の胴が派手に四散し、形を失い、単なる泥の飛沫となって周囲に広がった。
「ふ、は──っ」
身を折って膝に手をつくと肩を激しく上下させて荒れた息を整える。
(何とか……なったか)
思いつつ、最後に大きく息を吐いてから、【NAME】は顔を上げて巨人の居た場所を見る。そこにあるのは形を完全に失った単なる泥の塊であり、独りでに動き出すような気配も、ましてや【NAME】に襲い掛かってくるようなこともない。
と、そんな泥の塊の中に、一つだけ異なる色彩を見つけて【NAME】は歩み寄り、それを見る。
泥に塗れて落ちていたのは、歪に折れ曲った巨大な指だった。
明らかに人間のものではなく、恐らくは──鬼種のもの。これが、先刻まで戦っていた巨人の本体ともいえるべきものなのだろうか。指からは別段奇妙な気配が漂っているという雰囲気は無く、既に力の殆どは失っていると判断。【NAME】はそこで改めて安堵し、そして気付いた。
自分の身体が凄まじく泥だらけであることを。
「…………」
どうしたものか。こんな場所で洗濯をする訳にもいかないし──雨が泥を洗い流してくれる事に期待するしかないか。
苦笑しつつ、【NAME】はそこで懐の首飾りへと何気なく手をやる。先程触れた時にはすぐさま巨人の気配を捉えて同調を断ったため、もう一度改めて周囲を探ろうと思ったからだ。
【NAME】は大して期待もせずに神形器の意思に働きかけて数秒。
「……え?」
──感じた。
あの“鬼喰らいの鬼”が放つ独特の気配。それを、ごくごく弱いものながらも確かに感じた。
(場所は……)
遠い。少なくとも、この山脈の内にある気配ではない。だが、感じ取った気配は確かな標となって、【NAME】に進むべき道を示してくれていた。
「…………」
あの鬼と戦う。その事が俄然真実味を帯びてきた。
果たして、今の自分が“鬼喰らいの鬼”と対峙し、あの化け物を打ち倒すことができるのか?
【NAME】はその方角を見据えて、ほんの僅かに逡巡する。だが、それも一瞬だ。
迷いを消し、表情を正すと内なる覚悟を視線に乗せて、【NAME】は歩き出す。
山脈の向こう側。“鬼喰らいの鬼”の気配漂う地へと。
真なる楽園 凍りつく理
──キルーザム狼咆洞穴──
空間に渦巻く力の波動。その濃度は凄まじく、まるで肉眼ででも捉えられるかのような錯覚まで感じる程。【NAME】はその吹き荒れるような力の渦に当てられ、その空間へ足を踏み入れるのを躊躇い、歩を止めていた。
地下へと降る道の終端は、巨大な地底湖となっていた。天井には鋭角に尖る岩柱が幾つも並んで垂れ下がり、下方にはかなりの量の水が溜まっている。だが、その水は液体ではなく固体。正確には氷だ。
この空間を統べるのは、凍てついた水の舞台上に浮ぶ大きな影。湖のほぼ中心に近い位置で浮ぶ、常識では考えられないほどの巨体を持つ狼だった。
褪せた蒼の体毛に身を包んだ狼の体長は、遠くから眺めた限りでの推測で述べるなら最低5メートルといったところ。軽く背を丸め頭は僅かに垂れた姿勢で、四肢は余分な力無く下方へと伸びているも、その足先は固体となった湖水に触れてはいない。
狼が身に秘めた特性なのであろう。浮ぶ巨大な身体からは、何もかもを凍えさせようとする力ある冷気が漏れ出していた。空間を引き締め、湖水を凍らせたのは恐らくその力によるものであろうが──。
(しかし、これはまた……)
呻きつつ眺め、観察し、そして【NAME】は知った。洞穴を駆け抜けていた、力の音を伴う風が生まれる理由を。
両眼を閉じて身動きすらしない巨狼が行う、ただの呼吸。それが正体。
あの空中に浮び身動きもせず、まるで眠っているかのような狼が、生きる為の生理的な形として行っているのであろう動作。彼の存在にとっては意識するまでもない、極々些細である筈のその動作が行われる度、空間が振るえ、歪み、軋み、音が生まれる。そして狼の吐息から漏れ出た力の概念は大気に流れを作り出して、風へ。独特の音と力の気配を載せた風は、凍りついた地底湖から【NAME】が歩いてきた道を伝い、洞窟の上方へと流れていく。
洞穴を駆け抜ける咆声が生み出される過程。それを茫然と眺めて、【NAME】はただ思う。
──この獣を相手にするのは危険だ、と。
ただ遠くから眺めただけでも、少なくとも二つの事は確認できる。あの存在は“鬼喰らいの鬼”では無い。そして、秘める力は彼の鬼と同等か、それ以上であると。
手に負える相手であるなら、後々の憂いを断つ為に退治を行うべきかとも考えていたが、そのような馬鹿げた話が通じるような存在ではない事がびりびりと肌で感じられた。途中、打ち倒してきた二匹の狼からは鬼に似た気配を感じたが、今遠く湖上に浮ぶあの巨大な狼からは、紛う事なき鬼の気配、それも“大禍鬼”と呼ばれる程の力を持つ強大な鬼達の気配と合致していた。
そこまで考え、【NAME】が思う言葉は一つ。
(逃げる……)
そう、逃げるべきだ。迂闊に手を出して良い相手ではないのは容易に知れた。
【NAME】が持つ力の最たるもの、懐に秘めた神形器の力を引き出すことが出来たならもしや、という事も考えられるが、【NAME】の切り札様は気まぐれだ。かといって、独力で相手をするとなるとかなり、いや、非常に厳しいように思えた。
ならば長居は無用。迅速にこの場から離脱すべし。
思い、僅か一歩。後ろへ踏み込んだと同時。遥か遠くに見える狼。その片側の眼が僅かに開かれたように見えて、そして次の瞬間には。
「──な」
正に唐突。視界に映るものの殆どが、一瞬にして別のものへと変化していた。
慌てて首を振り、周囲を確認。何処に居るかは即座に判った。自らが踏み締めている地面、暗色のごつごつとした岩肌であった筈の足場が、いつの間にやら平らで半透明な白色を持つものへと変わっていた。
つまり、これは。
(……引き寄せられた?)
先刻まで立っていた場所から、氷張る湖上までの距離は100歩以上の幅。それを一瞬にしてゼロにされて、あまりな状況の変化に【NAME】の思考は音を立てて停止。
しかし上方から見下ろされる視線を感じて、身体は自然と。顎をあげて、額を後ろへ。視線の主を確かめるべく顔を上へと向けてしまう。
「…………」
先刻までは閉じていた筈の狼の両眼が薄く開かれて、自分を見ていた。美しく輝きつつも冷め切った狼の瞳に射竦められ、僅かに動き出していた思考がとどめを刺されるが如く再度停止。
人の頭を超える大きさを持つ眼が、闖入者たる【NAME】を値踏むように見る。一分、二分、三分。視線に囚われ、【NAME】はほんの少し動くことも出来ぬまま時間は過ぎる。いや、実際には一瞬の事だったのかもしれないが、強大な存在に威圧された【NAME】には、世界を平等に流れる時間の動きなど掴めるはずも無い。
そしてどれだけの時間が過ぎたのか。
一つの変化が、【NAME】の呪縛を解く
「────」
にい、と巨狼の身を持つ鬼の口元が歪む。それが合図。
本能が発する限界までの警告が、【NAME】の硬直を解いた。動きは全速。手は武器の柄に、足は距離を取るべく凍る湖を蹴った。
同時に、狼鬼が動き出す。ただ、己の前に現れた奇妙な存在の生きるという力。それを見定めるが如く。
[BossMonster Encountered!]
battle
洞穴の巨鬼

「く、ぁあ、あ──!!」
悲鳴ともつかない声をあげて、狼鬼が放つ有象無象の攻撃を凌ぐ。既に位置は湖上ではなく岩場の上。鬼の一撃が空間を薙ぎ、岩を容易く削り、破壊の力を波紋の如く周囲へと撒き散らす。それを受ける動きは思考によるものではなく、今までの経験によって身体に覚えこませた条件的な反射による回避運動。己の存在概念に組み込まれた技法の全てを駆使して受け、払い、弾き、避け、そして。
「──あああああっ!!!」
一撃。
ただ一度の攻撃を、狼の皮を被った常識外たる存在に向けて放った。
怒涛の如く押し寄せていた攻撃を隙間を縫っての一撃。当然満足な態勢、状況下で放ったものではなく、そのような攻撃が、強大という文字を体現する狼鬼に致命的なダメージを与えることなど有り得ない。
──しかし。
「…………」
鬼の攻撃が、それを境に止んだ。
驚いて、【NAME】はぽかんと動きを止めた狼の顔を見上げる。
巨大極まりないその顔に浮んでいた表情は、人の感情で言い表すならば恐らくは「喜」の色だ。こちらの攻撃が効いた様子は微塵も無い。
だが、狼は何故かそのまま【NAME】に背を向けて、僅かに空中を浮んで湖の上へと身を移すと、【NAME】がこの地底湖に足を踏み入れた時と同じ姿勢を取って、両の眼をゆっくりと閉じた。
もう、狼が動くことはなく、あとは狼の呼吸が生む大気の流れが定期的に周囲の気配を揺るがせるのみ。
(……はて)
どうしたことか、これは。
茫然と狼を眺めていた【NAME】は、武器を構えたまま数瞬の思案。そして出した結論は。
「見逃してくれる、のか?」
呟くも答えは無い。
だが、後方へ一歩二歩下がってみても、先程のように湖の上へと引き寄せられることはなかった。
(それならば……)
安堵。深く深く安堵の吐息を一つついた後。
【NAME】は正に全速力といった調子で疾走。正に脱兎の如くその場から逃げ出した。
・
兎に角全力。
途中、何が居たかや何があったかなどは全く考えず、一秒でも早くあの狼の居る地底湖から離れる為、力の限り洞穴を走り抜ければ、いつの間にやら周囲の景色は外のもの。辺りに海の岸は見えず、場所はどこぞの山腹に近い処から考えると、洞窟に侵入したときに見た出口とは別の場所から外へと出たようだった。
荒れた息を整えようとして、そこで疲労を感じて思わず座り込んでしまう。そのまま仰向けに地面へ身を投げ出すと、胸元から首飾りが顔の方へと転げ出してきて、煩わしくそれを払ってから、一息。
と、そこで暫しの間を置いた後。
「そういえば……」
ふと思い出して、払った首飾りへと何気なく手をやった。
【NAME】は大して期待もせずに神形器の意思に働きかけて、数秒。
「……え?」
──感じた。
あの“鬼喰らいの鬼”が放つ独特の気配。それを、ごくごく弱いものながらも確かに感じたのだ。
逸る気持ちを押さえて、意識を改めて集中させる。
(場所は……)
遠い。今居る山の腹を降りた更に先。少なくとも、一時間歩いた程度で辿り着くような距離ではない。だが、感じ取った気配は確かな標となって、【NAME】に進むべき道を示してくれていた。
「…………」
あの鬼と戦う。その事が俄然真実味を帯びてきた。
果たして、今の自分が“鬼喰らいの鬼”と対峙し、あの化け物を打ち倒すことができるのか?
【NAME】はその方角を見据えて、ほんの僅かに逡巡する。だが、それも一瞬だ。
迷いを消し、表情を正すと内なる覚悟を視線に乗せて、【NAME】は歩き出す。“鬼喰らいの鬼”の気配漂う地へ向けて。
真なる楽園 檻の向こう側
──在り得ざる城クナハ・クリサ──
山間の盆地に建つのはいつ誰が造り上げたのかも定かではない古の城だ。
点々と広がる小さな湖の間を抜けて、古城へと近づく。外装は古ぼけ、半ば崩れているが、入口となる正面の扉は未だ健在のようだった。僅かに開いた扉の隙間からは、何とも表現できぬ異質な気配がずるずると漏れ出していた。
城の内部は外見通りのものではなく、酷く滑らかな壁によって作られた半球の構造を持っていた。
その大きさは明らかに異常で、外からみた城の外観を完全に無視している。入口となる正面門は円形のドームの中央、何も無い空間にばっくりとその口を開けており、そこからは外の景色が見えるが、裏側へと回れば入口は姿すら見えず、真横から見れば細い光の線が一本縦に走っているのが見えるだけ。一種の転移門か何かと考えるのが妥当だろう。
円形ホールの中央床部には象形による複雑な陣が書かれており、円の縁となる壁には八つの窪みがある。
窪みはどうやら扉であるらしく、【NAME】が手で触れると壁の一部が音もなくずれて開く。八つの扉の内の七つには奥に小部屋があり、それぞれ独自の概念を凝縮した小世界を構成しているらしいことが、神形の補助を受けた己の感覚が教えてくれた。
残る一つの窪みは他の七つよりも大きなもので、触れて開けばその奥には、捻れた様に渦巻く七色の虹の輝きがあるだけだった。
・
七つの扉の奥に広がる小部屋。それぞれの部屋は固有の力が満ち溢れていた。ある部屋には凍えた力が、ある部屋には霧の力が。別の部屋には雷が溢れ、別の部屋には泥が満ち満ちている。どれも強い力ながらもどこか不安定であり、場を構成する存在概念としては歪な形を持っていた。
そしてどの部屋にもその真中には一つ台座が設置されており、その頂点部には何かをはめ込めるような窪みがあった。窪みの形は部屋によって異なっており、つまりそれぞれに対応する品があると予想できたが──。
七つの小部屋全ての台座に、適合する品を配置する。
力の霧欠。
白風の鬼珠。
焼けつく雷碑。
揺るぎの秘石。
大禍石の破片。
大禍鬼の指。
凍りつく理。
配された禍々しい力の結晶七つは、それぞれの小部屋に漂う歪な力の概念と交じり合い、異質な概念を調律した。
七つの部屋から生み出された整えられた小さな世界の力は、床に描かれた象形を辿ってホールの床全てを淡い輝きで埋めて、中心で一つの光となったそれは【NAME】の身体を経由するように通ってから、八つ目の扉の向こうで渦巻く輝きの中へと伸びていた。光は虹色へと混じり、七色にもう一つの新たな色彩を乗せて八色の渦とする。
そして渦の光度が上がっていき、捩れの中心がゆっくりと解け始めてその向こう側を写し始めた。
輝きの向こうにあるのは──深い闇。
いつか見た黒い切り株の向こうを思い出させる暗く落ちた藍色の空の彼方には、赤色の三日月が映っている。
ぢりぢりと、首飾りの形を取っていたゼーレンヴァンデルングが音を鳴らす。
それはこの虹色の向こう、あの藍の空が広がる異界のどこかに“鬼喰らいの鬼”が居る事を報せてくれたが、同時に鬼芯を封じるという“檻”の存在もはっきりと知覚させてくれた。
「…………」
まだ虹色を超えて“向こう側”へと渡っていないにもかかわらず、強烈に圧迫される精神。
だが、ここで退く訳にも行かない。
【NAME】は覚悟を決めると、一歩、虹の向こう側へと踏み出した。
──檻の向こう側──
深く広がる藍の空。
紅く曲がる三日月。
色無く閉じた地面。
黒く聳える柱の群。
その中で、一際高く伸びる大柱の表面に、一つの影が見えた。
身体の半分を柱の黒に埋め込んだまま、その影──“鬼喰らいの鬼”と呼ばれた大禍鬼シンラは、身構えて立つ【NAME】達を虚ろな両眼で見下ろした。
・
神形が奏でる鈴鳴りの音は、しゃらしゃらと連なる程の勢いで【NAME】の耳朶を打つ。
シンラは以前、二匹の“大禍鬼”を取り込み、己の力を強化させていた。
その二匹の存在概念はゴディバでの戦いの折に【NAME】とゼーレンヴァンデルングの斬撃により断たれ、失われた。
だが、今眼の前にあるその姿。黒の柱と一つとなったその身体からは、二匹の“大禍鬼”を取り込んでいたときと同等か、それ以上の力を感じさせた。
──それは何故か。答えは、神形の助力によって増された感覚が教えてくれた。
この異質な空間、周囲に漂う陰性の概念全てが、柱と混じり合っているあの鬼に向かって流れ込んでいるのが見えた。あの鬼は、“檻”を構成する柱と同化する事によって、この場や“檻”の向こうにあるとされる陰の結晶、破壊の象徴たる芯属“鬼芯属”の気配を己が内に取り込んで、自身の力へと変換させているのだ。
恐らく、シンラの力を持ってしても“檻”を破壊してその囲いの奥へと達する事は不可能だったのだろう。だが奴は“鬼芯”に最も近づく為の次の案として、“檻”自体と同化する事を選んだという事か。
『────』
言葉にもならぬシンラの吠え声が世界に木霊し、そして鬼の周囲に力の概念が収束する。鬼から発せられるのは強烈なまでの害意。そのあまりの強さに、【NAME】は我知らず息を呑む。
鬼の本来の目的を察する事は出来なかったが、シンラが極めて危険な存在であること──そして時間と共にどんどんと力を蓄え、それ以上の存在と化すことだけは理解できた。
「…………」
語る言葉など既に無い。
手に神形を握り締め、【NAME】は檻依の大禍鬼に向かって己が持つ力全てを解放する。
[ExtraMonster Encountered!]
battle
檻依の大禍鬼
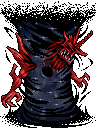
半ば“檻”に埋まり、既に鬼という形すら失いつつあるシンラを、討ち断つ。
まさに死の具現とも言える【NAME】の一撃は、シンラの胸部中央を過つことなく穿ち、その存在を崩滅へと導く──筈だった。
しかし、既に檻と一体化し、生物ではなく単なる力の象徴でしかなくなったシンラは完全には消し去れず、破損したシンラの存在を補填する為に、エルツァンの根を構築する檻が因果を歪め、全てを巻き戻そうとする。
藍色の空が。
黒く溶けた大地が。
浮ぶ三日月が。
そして、檻の彼方にある鬼芯の残滓が。
【NAME】の眼に映るもの全てが一つのうねりとなって流れ、黒色の闇となって何もかもを押し流す。
欠損を逃れる為に過去へ──その要因となった【NAME】を押し流していく……。
・
……ふと気付けば、【NAME】は何処かの浜辺に立っていた。
目を瞬かせて辺りを見回し、遠く浜辺の一角に常駐軍の駐屯地があるのが見え、自分がエルツァンの浜辺、西エルツァンの海岸線に居る事が判った。
──判った、のだが。
「…………」
何故こんな場所にいるのか。
そもそも、ついさっきまで何をしていたのか。
全くと言って良いほど思い出せなかった。
【NAME】は首を傾げて頭の中を探り、しかし何も出てこない事に一つ吐息。思い出せるのは、常駐軍の陣地からエルツァン内部へと探索を始めようとした辺りまでだった。
傾げていた首を逆の方へとまた傾げ、暫し考え込んだ後。
──まぁいいか。
こうして考え込んでいる事自体時間の無駄だ。【NAME】は地面に落ちていた自分の道具──中身が微妙に以前と違っている気がしたが、はっきりと思い出せなかった──を背負い直すと、近くに見える常駐軍の仮設駐屯地へと向けて歩き出した。
真なる楽園 思わぬ事実が彼女を襲う
――思わぬ事実が彼女を襲う──
エルツァンの探索へと入る前。常駐軍が設営した陣の中央、集合地として用意された広場の端で、【NAME】は長椅子替わりに置かれた岩に一人座り、心と身体を休めていた。
喧噪は無い。朝の支度は終えた時刻だ。軍の者達は皆、それぞれの任務をこなすべく、方々に散っている。
一度陣を発てば、今後人心地がつける時間を持つことは不可能に近いだろう。これが最後の休息だ。深く深く弛緩し、そして徐々に、これから先に待ち受ける困難に備え、己を研ぎ澄ましていく。
と、そこにふと影が差した。
視線を上げれば、直ぐ傍に見慣れた小柄な人影が一つ。窺うように【NAME】を見下ろしていた。
「……何だかお暇のように私には見えますが、今日は出発されないのですか?」
揶揄する気配は無い。ただ、事実を確認しているだけのような調子で問いを発したのは、荷物片手のノエルだ。
暇を持て余していた訳ではなく、出発しないつもりだった訳でもない。むしろ、これからの難事に備えての準備の時間だったのだが、外から見た自分は、ただ茫と岩の上に座っていただけにしか映らなかったのだろう。考えてみれば、そう思われても仕方が無いのかもしれない。
認めたものか、否定したものか。【NAME】が曖昧な態度を返すと、ノエルは何かを思案するように暫し視線を外し、戻す。
「でしたら、【NAME】もご一緒しますか?」
「……?」
突然の誘いに、首を捻る。
一体何にご一緒せよというのか。【NAME】が短く問い返すと、ノエルは言葉が足りなかったことに気づいたのか、手元の荷物を揺らしながらこう続けた。
「今から、大天幕の方で定例の集まりが行われるのです。イェアや、ノクトワイ様。助言役であるオリオール様に、今日はキヴェンティの方も参加されると聞いています」
集まり――つまりは、会議だろうか。
視線を僅かに移す。彼女が手に抱えているのは、主に紙束だ。垣間見える図や文字は僅かで内容までは読み取れないが、恐らくは、これまで常駐軍が周辺探索を行って得た情報を纏めたものなのだろう。
それを見て、【NAME】は理解する。“鬼喰らいの鬼”の討伐は任せると言ってはいたものの、やはり彼女達も軍人。丸投げする気は到底無く、自分達で出来る事をやるつもりなのだ。
しかし、そういう会議をやるというのなら、自分を呼んでくれても良いだろうに。【NAME】はそう思う。
やはり情報は力である。特に、未知の場所への冒険、生命の危機に直結しうる危険な地域の探索となれば、重要性は計り知れない。それが事前に得られるならば、極力得ておきたいと思うのは当然だろう。
それに、単なる情報だけではない。イェア達軍が、この真なる亜獣達の楽園探索をどのように進めているのか。取っている手段がどういうものなのかも知っておきたいところだった。自分と彼等。個と集団という違いはありこそすれ、探索を進める上での参考にはなる筈だ。
と、いう風な事を、【NAME】はノエルに対して語ったのだが、
「いえ、あれは」
何故かノエルは、困ったように眉を寄せて、少し口篭もるように言葉を返す。
「そのような、建設的な集まりというものではないと、私は思うのですが……」
「?」
――え、じゃあ何の集まりなの?
怪訝な視線を向ける【NAME】に、ノエルは眉を寄せた顔のまま、微動だにせず固まってしまう。【NAME】が急かさず彼女の反応を待っていると、ふとノエルの表情が緩む方向に変化し、続けて細い吐息。
「こうして説明するより、実際に来ていただいた方が早く、正確に伝わると私は思います」
どうやら、口頭での情報伝達を諦めたらしい。
まぁ確かに、と貴方は頷く。見る事は信ずる事だ。今からその定例の集まりとやらが始まるのだから、それがどういうものなのかとここであれこれ言葉を交わすより、さっさとお邪魔して自分の目で見て把握した方が数段早く、そして確かな選択だろう。
「では、向かいましょう。会議は大天幕で行われますので、そちらへ」
促しに応じて立ち上がると、【NAME】はノエルと共に歩き出す。目指す先は言葉の通り大天幕――この岸辺に造られた野営地の中央にある広場から、陸側の方向に張られた天幕群だ。
大きな天幕を中心に、周辺を複数の小さな天幕が囲うような構造で、他の場所に張られた天幕と違い、寝泊まり用ではなく、軍部隊運営に纏わる要素を集めた場所となっている。周囲の天幕は物資保管や炊飯施設として使われ、中央の大天幕は各種資料や情報の集積、執務、そして会議の場として利用されている、らしい。
らしい、というのは、あくまで【NAME】は伝聞としてしか聞いていないからだ。
エルツァンへとやってきて、最初にイェアから事情と“鬼喰らいの鬼”討伐の作戦を聞いたのは彼女個人の天幕であり、その後はこれといって大天幕へと近付く用事などもなく。あの大天幕群に立ち入ったのは、配給を受けるために複数ある炊事用天幕の一つに数度、という程度。中央の大天幕には近寄ったことすらなかった。
「どうしましたか、【NAME】」
と、隣を歩くノエルに突然話を振られて戸惑う。いや、いきなり、どうしましたと言われても。
「いえ、何だか、その」
そこまで呟いて、また、ノエルはぴたりと表情と口を固まらせてしまう。
「…………」
彼女とも、もうそれなりの付き合いだ。何となく判る。今、彼女の頭の中では、どう言えば相手に自分の感情が正しく伝わるのかと、懸命に言葉を探しているのだろう。
ノエルはその出自か、置かれていた環境故か、口が上手い方とは決して言えない。特に自分が感じた印象など、漠然としたものを言葉として伝えるのが苦手だ。以前は、暫く考えた後に諦め、何でもないと誤魔化すか、良く分からないと放り投げてしまうのが常であったが、
「私には、貴方が何かを楽しみにしている、そんな風にみえました」
今はこうして、自分の中に生まれた印象を、どうにか言葉にしてくれるようになった。それは彼女の確かな成長で、【NAME】は嬉しく思う。勿論、先刻のように彼女の心情が関係しない物事であるならば、容易く説明を放棄したり、または長々と回りくどい言葉を費やして説明してくれたりはするのだが。
【NAME】はその事については何も触れず、ノエルの楽しみという言葉に対し、確かにそうかもしれない、と素直な感想を返す。
野営地の大天幕は、外から見掛けた事は何度もあったが立ち入ってはいない場所だ。中がどうなっているのかという、たわいの無い好奇心を“楽しみ”と表現するのなら、ノエルの指摘は全く間違ってはいない。
それに、イェア達が行うという会議の中身にも興味があった。
ノエルが抱えている紙束は結構な量だ。これだけの情報を元に話し合いをするというのならば、自分にとってもかなり実のあるものになるのではないか――そんな期待を持つのは、至極当然だろう。エルツァン探索の助けとして、イェアからカール・シュミットの手記を借り受けてはいるが、その記述は曖昧なものが多く、しかも古い。常駐軍が今、足で集めた情報の方が、手記よりも遙かに島の現実を捉えた重要なものである筈だ。
などと話を繋いだ【NAME】であったのだが。
【NAME】が言葉を続ける程に、元々表情が薄い筈のノエルの顔が、一見して判る程に曇っていく。
――何か、間違った事を言ってしまったのだろうか。
思わず心配になって訊ねると、ノエルはこちらから露骨に視線を外して、小声でこう返した。
「……いえ。ただ、実際大天幕でどんな話し合いが行われているのかを見ても、あまり幻滅なされないよう、宜しくお願いします」
・
「はい、次の議題ですわー。えっと、キュスター班所属マリエーヌさんからのご意見。『相談です。第二班のクルス君が最近冷たい。どういう事なの? も、もしや浮気とかっ……。“先生”隊長とノクトワイ副長はどう思われます? 問い詰めた方がいいでしょうか。それとも、彼を信じて待った方がっ!?』との事ですがー、皆様、どう思われます?」
天幕中央の大テーブル上。積み上げられた紙の山から抜いた一枚を読み上げ、場にいる者達にそう問い掛けたのは、白衣を着込んだ女性。エルツァン島に派遣された常駐軍の連隊を指揮するイェア・ガナッシュである。
対して、テーブルの左右に座る男ふたりがそれぞれ反応を返す。
「ふむ。クルスといえば、あの少し童顔の彼かい? 以前に、軽く話した記憶はあるけれども」
右側。思い出すように顎を摩るのは、丈夫さ優先の服装に身を包んだ男だ。東大陸よりやってきた冒険家で、今はエルツァン島にやってきた軍部隊の相談役となっているハマダン・オリオール。
続けて、
「いいわよねェあのコ。ソソるわ。今すぐにでも食べちゃいたいくらい」
左側。緩んだ顔で口髭を摘んで笑うのは、洒落た軍装束を纏う彫りの深い顔つきの男。今はイェアを補佐する連隊の副長という立場に収まっているノクトワイ・キーマ・フハールである。
「それにしてもウワキっ! 浮気は許せませんわね! 女の敵ですわ! 今すぐにでも注意しにいきませんと! 早速キュスターさんに通達ですわ! この場合、一体どんな罰則が適切か――」
「……少し良いかな」
憤っているようでいて、何故か楽しげでもあり、そして投げやりにも見える。まるで徹夜明けのような調子で歌うように声を張るイェアに対し、そっと手を挙げて発言の許可を求めたのはオリオールだ。
「って、はい? 何でしょう?」
「一つ聞きたいのだけれど、キュスターさんというのは、南側設営の時に指揮をやってた、髪を右肩側で纏めた凛々しい雰囲気の彼女?」
「そうですがね。何か、気になる事でも?」
替わりに答えたノクトワイの言葉に、オリオールは困ったような笑みを浮かべて、
「気になる、というかね。僕も設営の手伝いをやっていて、その時、世間話をしたんだが。確か彼女から、自分はそのクルス青年と交際をしている、という話を聞いた覚えがあるのだけど」
「「…………」」
「それも、フローリアに来る前からの付き合いだと言っていたよ。ちなみに、クルス青年と軽く話したというのはこの時彼も一緒にいたからで、僕が見る限りではクルス青年の方がキュスター女史に熱を上げているという風に見えたんだが。……これは、どう解釈すればいいのだろうね」
「――つ、つまりクルスさんはキュスターさんという本命が居るというのにマリエーヌさんを弄んでたって事ですか!? 尚更許せません! これは軍法会議ものですよっ!」
「つーかそもそもね」
更にテンションを上げるイェアを押し留めるように、別の方から手が挙がる。
「マリエーヌちゃんにはちゃんと旦那居たと思うんだけど、そこんとこ、先生ちゃん的はどうなの?」
ノクトワイの言葉に、イェアはびきりと引きつるように制止し、そして少しの間の後。
「……えっとぉ……きっとマリエーヌさんは、旦那様と離れてこんな危険な任務に同行する事になって心細かったと思うんですの……。だから、身近にいる男性につい心を寄せてしまうのも仕方無いかなって、わたくし思うんですのぉ……」
「成程成程。先生ちゃんの言いたい事はよぅく判ったわん」
「大略、女性の意見というのは、男からするとある意味至極斬新に聞こえるものだが、これは中でもとびきりだね」
男二人、うんうんと暫し頷き合い、そして真顔に戻ると、
「というか先生ちゃん、完全にネタで言ってるでしょ」
対し、イェアは、へ、と鼻を鳴らし、
「……冗談抜きで言いますと、色恋沙汰なんてわたくしに聞かれても知るかってなもんです。お付き合い経験もないのに。嫌がらせでこっちに話振ってるんでしょうかこのお手紙」
「で、対応は?」
「マリエーヌさんの旦那様にこのお手紙を渡しておきます! ざまぁ!」
吐き捨てるように告げて、ばーん、と手にしてた紙を机の端に聳える山の上に叩き付けるイェア。
「容赦ないわネェ」
「今日のイェア嬢は切れが良いね」
「切れというか暗い情念を感じるわネ」
「そこ! 煩いですわ! さぁ気を取り直して、次のご意見ー!」
「…………」
そんな風に眼前で繰り広げられる会話を前にして、テーブルの隅、彼女達から少し離れた位置に座した【NAME】はげんなりと呻く。
(……何これぇ)
「ですから、言ったでしょう。あまり期待はされぬようにと」
【NAME】が隣に座るノエルと小声で言葉を交わす間にも、会議はだらけた空気のまま進んでいく。
「えー、オーリス班所属のマルクさんから。いつもありがとうございます。で、内容は――『こっち来てから俺の洗濯物がやばい。なんかガビガビすんの。今すぐ打開策』」
「いやアノーレでも酷かったでしょ。なんで慣れてないのこのコ」
「えーっと、あ、この人最近こっちに来た人みたいですわね。それも直ぐに内陸の方に派遣されてたみたい」
「運良いわねぇ。で、打開策らしいんだけど。こういった知恵に関してはハマダン様強そうなイメージがありますけど、どーです?」
「干す場所を考えるしかないんじゃないだろうか。原因は潮風だからね。それが直接当たらないように工夫すれば、多少は緩和されると思うけれども」
「ふむ。打開とは程遠いですけれども、わたくし達から出来る回答としてはその程度が限界になりますかしら」
「まぁねぇ。……そういえば、先生ちゃんの服は結構パリっとしてるわよね」
「そこはホラ。わたくし機甲師ですので。色々とこっち来るときに役に立つだろうと持ち込んだ機甲兵器を流用して、ちょちょいと」
「特権だね」
「貸してあげたらいいんでないの?」
「やー、あくまで個人使用が限界のなんで無理ですわね。残念だなマルク、この機甲兵器は一人用なんだ――みたいな?」
「そんなのやってりゃそりゃジンボーも無くなるわ」
――などと、ダラダラと続く会話が、所謂“定例会議”という代物であるようだった。
何故こんな事になっているのか。三人の間で続けられる遣り取りを適当に聞き流しながら、傍に座るノエルに訊ねれば、彼女が言うにはこんな経緯であるらしかった。
曰く、最初の頃は今後のエルツァン島探索計画等、比較的真面目な話し合いなどをしていたのだそうだ。
だが、ある時、隊の探索進行に遅延が出ている大きな要因の一つとして隊内の士気低下が議題に上り、その原因を探るため、兵士達から広く意見を聞く流れになった。しかし、元々このエルツァン行に参加したのは“四大遺跡事変”の際に比較的被害が少なかった部隊。ガレー遺跡に駐留していた、イェア直轄である外部出向組の学士系集団と、大草原にて展開していた、ノクトワイ指揮するこれまた若干緩い部隊。いまいち規律正しい軍隊の人間という枠から外れがちな彼等から寄せられた意見の多くは、最初にイェア達が想定していた方向性から大幅にずれており、加えて上司も上司でそれらのネタにホイホイと乗っかって反応を返していった結果、現在のようなお悩み相談の場に変化していったのだという。
成程、と一先ず頷く。取り敢えず流れは判ったが、
(……流石に脱線しすぎではなかろうか)
というより、ノエルもそこまで状況を把握しているなら、何故口を挟まずに放置しているのか。
世慣れしておらず比較的流され易いとはいえ、生来の質としては生真面目な部類に入るノエルだ。このような状況になった場合、直ぐにでも修正を試みようとする。そんなイメージがあったのだが。
そんな【NAME】の疑問に、ノエルの答えはこうだった。
「私としても、幾度かそうしようと思った事もあったのですが、この場以外では皆様真面目にお仕事をされていて……私にはあまり理解できませんが、これは恐らく“息抜き”というものであると。そう判断して、口出しを控えていたのですが」
どうも、ノエルなりに気を遣った結果が現在の惨状であるらしい。
彼女がそのように他者に対して気を回すというのも過去からの成長の証のようで微笑ましく映る。
映るが、しかし今回に関してはその判断が恨めしい。もう少し参考になる意見交換の場であって欲しかった。【NAME】はのんべんだらりと話し続ける三人を見て、深々と溜息をつく。
「? 【NAME】さん、どうかなさいました?」
と、物言いたげな態度に気づいたが、イェアが【NAME】に話を振り、オリオール、ノクトワイの注意もこちらに向いた。
丁度良い。【NAME】は先刻ノエルから聞いた話を元に、そろそろ大本の問題に回帰したほうが良いのではないかと口を挟む事にした。
出来ればエルツァン攻略についての話が聞きたいところだったが、これは自分の都合だと自制。まず先に、彼女等が問題としていた、探索進行の遅延理由についての追及を促す。
【NAME】の話を聞いたイェアは「んー、それについては、ですね」と少しの迷いと、何故か不快感のようなものを見せながら、ノクトワイを一瞬見る。
「折角【NAME】さんも参加してくれたことですし、あの話について改めてしてみましょうか?」
「んー、それもそうねぇ。【NAME】、これについてどう思う?」
言って、ノクトワイはテーブル上に積まれた紙束の山からひょひょいと数枚を引き抜き、【NAME】の方へと滑らせる。
紙面に視線を走らせると、そこに書かれていたのは兵士達から上がってきたらしい意見の羅列だ。文体、調子、表現、長短。様々ではあったが、意見については大筋全て同じ事が書かれていた。
端的に言えば、
「食に関する問題、ですわ。【NAME】さん、ここでのお食事について、ご不満はありますか?」
問われ、あー、と【NAME】は苦笑する。思い当たる事は、あったのだ。
「ほら。【NAME】だってそう思ってるみたいじゃないの」
そんな態度を見て、ノクトワイが揶揄するように言うと、イェアが不満と不可思議半々の顔で首を捻る。
「……ご飯、そんなに問題ありました? 一応、必要な量と品は用意したつもりだったのですけれども」
対し、両側の男二人は顔を見合わせて、
「問題は、あるわねぇ」
「うーん。必要な量と品、というのがね……」
言葉を濁す二人に、イェアは意味が判らないと首を捻り、
「? えっと、【NAME】さんも、何か問題だと思われますか?」
問われて、言いづらいながらも以前より感じていた問題点を指摘する。
――元々の量が少ないこともさることながら、品数が少なすぎるのでは、と
「品数、ですか?」
不思議そうに返されて、あ、これ伝わってないなと思いつつも【NAME】は頷く。
「ええっと……量については、確かに常駐軍の立て直しがまだ終わってなかったせいもあって、調達出来た食料は予定よりも若干少なくなってはいますが、それでも一日二食配給出来る分は確保していますし。品数についても、普通はあんなものではないでしょうか?」
それに対して、【NAME】、ノクトワイ、オリオールがぶんぶんと首を横に振った。
「あ、あれー? え、でも飲み物に、保存が利くモノに……」
「その二つだけ用意してどうするのよ先生ちゃん」
「流石にね、積み込んできた飲食物が果実酒に一、二種類の保存が利く乾物類のみ――しかも、一つがあの癖のある味の魚というのは、兵士の皆が不満に思うのも当然だと思うよ」
「つーかアタシ等も不満だわ」
ノクトワイとオリオールの言葉に、【NAME】も実感を込めて頷いた。
【NAME】も既に幾度か軍の食事配給を受けているのだが、その内容が常に同じなのだ。そして、うちの一つが強烈な発酵臭のする魚の乾物――発酵した特製の塩水に漬けたものであり、腐っている訳では無いようなのだが、如何せんその臭いのせいで食欲があまり湧いてこない。加えて、そんなものでも量があればまだ救われるのだが、至極少ないのだ。あれでは肉体労働の兵士達が体力を維持するのは難しいだろう。
三方からの批難に、イェアは「え、でも」と慌てたように呟き、
「美味しいでしょ? わたくし、あれだけでいくらでも働けますけど」
「先生ちゃん、それ完全に自分基準すぎるでしょうに……」
「あと、流石に栄養面でも問題があるね。あれだけでは、短期ならまだしも長期の滞在となれば病気になる者達も出てくるだろう。陣を張り、腰を据えての活動を行う予定だったのなら、食については加工物だけではなく、原料や現地調達も視野にいれた準備をしておいた方が良かっただろうね」
「う、そ、それについてはそうかもしれないですけれど、でも、今更切り替えるとか無理ですわよ。軍の方もそんな余裕ないですし。ノエルも、あれで不満ないでしょう?」
「…………」
「あ、あれ? 貴女、昔はそんな不満な顔してませんでしたよね……?」
「今の私は、【NAME】と共に様々な食物とその味を、知覚し、認識した身です。その経験から言わせていただくなら、この献立を一切変更せず、今後も調査を続けていくのは流石に問題があると、私は考えます」
「あ、あれー……?」
「そもそも、先生ちゃんに兵站任せたのが失敗だったかしらん……。考えてみれば、先生ちゃんって基本引きこもりの研究者で、こういうのって殆どやったこと無かったわよねん」
「あ、あーっ! 酷い! 酷いですわ! わたくしだってちゃんとガレー駐留部隊の管理とかやってたんですのよ!?」
「確かに、島の調査計画については良く出来ていると感心していたけれど、部隊指揮や管理といった部分は何だか適当というか、気分で決めてるところが見え隠れしていたような気がするね。成程、イェア嬢が何に興味を持っていて、何に興味を持っていないか。その差という事なのかな」
「わーん! ハマダン様までっ!? だ、大体お二人わたくしのこと責めますけど、こっちに来る前に今回の計画案に関しては一通り書類に纏めてお二人に確認してもらったじゃありませんの! その時、何も言われてないんですから同罪! 同罪ですの!」
「あら、そうだったかしらん?」
「……はて、記憶に無いのだけれども……」
「ちょ、しらばっくれるとか本気で酷いですわよーっ!」
「いえ、イェア。私の記憶によれば、計画案は言われた通りに書類として纏めはしましたが、ノクトワイ様は直属部隊の指揮、ハマダン様は“先生”――レェアのところへ向かっていたりとお忙しく、結局確認していただかないままであったような」
「「…………」」
――と、そんな遣り取りを断ち切るように。
「馬鹿馬鹿しい」
テーブルから外れた位置。今まで沈黙を保っていた小柄な影が悠然と立ち上がった。
白色の短衣に細身の剣を腰に佩いた人影は、外部からの協力者としてこの地にやってきていたキヴェンティの一団を束ねる少年。リゼラ・マオエ・キヴェンティだ。
彼は鋭利な視線をイェア達に向け、
「彼の鬼を断つための算段。それを話し合うための場であると足を運んだが、どうやら我の勘違いであったようだ」
「う、ぐ。……それは、その」
斬り伏せるような言葉に、この会議の長であるところのイェアが、声を詰まらせる。傍の男二人が自分は関係ないとばかりに視線を逸らすのがいよいよ酷いな、と完全に他人事の態で見ていると、
「――【NAME】よ。お前も、時を無駄にしたな」
突然自分に話を振られて、【NAME】は驚く。どうやら彼も自分と同様、ここで行われている会議についてある種の期待をしていて、更には自分も同じ考えであったと見抜かれていたらしい。
【NAME】が苦笑という形で答えを返すと、それを見たイェアが更に申し訳なさそうに肩を竦める。
「え……。もしかして、【NAME】さんもそういうつもりで参加してくれてたんですの?」
答えづらい。思わず言葉に詰まるが、しかし直ぐに否と言わない時点で、答えは教えているようなものだった。うー、と更に落ち込むイェア。
対して、左右に座るオリオールとノクトワイは、イェアのフォローなり言い訳なりをするのかと思えば、
「まぁ、【NAME】も暇ではないだろうしね。……え? もしかして、イェア嬢は今日も普段と同じ調子で最後まで会議を進めるつもりだったのかい?」
「本音をいうと、いつ先生ちゃんが話を本筋に戻すつもりなのかと思ってたんだけど、ハナから考えてなかったのね」
男二人容赦ない。ノクトワイの方はからかいのつもりで言っている感がある為まだマシだが、オリオールの方は本気で予想外といった風な語り口で、より大きなナイフとなってイェアの後頭部に突き刺さるのが目に見えるようだった。
そのまま、暫くうーうーと唸っていたイェアだったが、頭のスイッチを切り替えたのか突然がばりと身を起こす。
「う、うう……! わ、判りました! 判りましたわ! 話をエルツァン攻略に戻しますから、ちょっと待ってくださいな!」
「不要だ。先刻まで話を聞いている限りでは、碌に進捗がない事だけは理解出来た。ならばこれ以上ここに居る意味は――」
と、断ち切るような言葉を続けていたリゼラが、突然ぴたりと動きを止めた。
口を浅く開いた状態で突然微動だにしなくなった少年に、周りの者達は怪訝な顔を向ける。
「ど、どうしました?」
子供相手だというのに完全に萎縮してしまっているイェアが恐る恐る訊ねると、リゼラはイェアの顔を今まで以上に鋭く睨む。ひ、と愛想笑いに近い顔で固まるイェアだったが、リゼラはそんな彼女の反応を無視して、頭痛を堪えるようにこめかみに手を当て、深い溜め息をついた後。
「――状況が変わった。レェアの妹よ、先刻の話を続けよ」
「え? えっと……」
「続けよ、と言った。貴様等“迷いの民”の食事に関する話だ」
酷く不満。そんな様子で、しかしリゼラはまた同じ場所に腰を下ろす。彼の心中が荒れているらしいのは気配で察せられるが、それでも座る姿勢に戻る際の動きに一切の歪みがないのは流石である。
だが、一度断ち切られた話の流れを、直ぐさま再開させるのは中々に難しい。しかもこのような空気になってしまっていたなら尚更だ。イェアは困ったように皆を見回し、オリオールは思案するような視線をリゼラへ向け、ノクトワイは呆れたような苦笑で場の空気を軽くする事に務める。因みにノエルは今ひとつ状況が掴めていないのか、若干不思議そうな表情で皆を眺めている以外の変化はない。
取り敢えず、この状況、この雰囲気の中から会話を再開するのは少々難しそうだ。そして無言が続けば尚更となる。【NAME】は話の取っかかりとなるものを急いで探して、
(キヴェンティ、か)
そういえば、リゼラ達キヴェンティは、食事に関して一体どう思っているのだろうか。
この疑問は、丁度良い。思いついたまま、座するリゼラに話を振ると、少年は不機嫌そうな顔のまま【NAME】を一瞥し、
「我らには、そのような事情など、全く関わりの無い話だ」
ばっさりと斬り捨てられる。が、ここで話を終わらせてしまうと、また微妙な空気に戻ってしまう。【NAME】は素早く思考を走らせて言葉を続ける。
――しかし、リゼラ達も軍の討伐隊に参加するという形を取っている。ならば、食事面でも軍から供給を受けているのではないか?
「いや、それが受けてないのよねぇ」
そんな疑問に、答えたのはノクトワイだった。
「キヴェンティに対してアタシ達が供給したのはここまでの移動手段だけよ。食事どころか、住居まで全部、キヴェンティは自分達で用意してるわよん」
(それはまた……)
【NAME】は若干の驚きを抱く。
元々、キヴェンティ達と常駐軍の仲は良いとは言えない。なにせ、“四大遺跡事変”時には直接刃を交わした間柄だ。接触を嫌うというのも理解できる話ではある。実際、キヴェンティ達は常駐軍の陣から離れた場所に自分達の野営地を構築して、そこで待機している程だ。
だが、食料の融通程度はされているものだと思っていたのだが。流石に、そこすら手を貸さないというのは問題があるのではないか。
そんな【NAME】の意見に、イェアはぶんぶんと首を横に振る。
「勘違いされては困りますわよ。最初、食料についてはちゃんとキヴェンティの方達の分も用意する計画だったんです。けれど……」
「不要なものだ。近隣に分け入り、野草や果実を得、獣を狩り、手を加える。それで、我らは十分だ」
そう簡単に言ってのけるリゼラだが、現実的に考えれば、それは全く容易な事ではない筈なのだ。軍の一団と比べ、キヴェンティ達は少数。だからこそ現地調達による自給自足が成り立っているのだろうが、しかしここはアノーレとは生態が明らかに異なる、未知の土地エルツァンだ。生息している動植物も、あちらとは様相が大きく違う。キヴェンティ達は、自然と近しき関係を結び生きる集団だ。故に、人の手が入っていない場所で生活するための知識も豊富なのだろうが、それでも、食べられるかどうか判ったものではないそれらを、一つ一つ確かめていくのはかなりの苦労だったろう。
そう【NAME】は感心して言うが、リゼラはまたいつもの調子で淡々と「その程度の事、労苦には含まん」とあっさり返し――しかし、途中でふと、口と表情が固まった。
それはほんの僅かな間で、直接声を掛けて、彼の反応を見ていた【NAME】だけが気づける程の微細な間だ。
故に、そこからリゼラの表情が、彼にしては珍しい揶揄するような薄い笑みへと変化した事への驚きで、直前の不可解な間に対する疑問は、するりと意識の外へと追いやられてしまった。
リゼラはその表情を【NAME】からイェアの方へと映して、
「我らの手によるものと比べものにならぬ、まるで畜生の餌のような代物なぞ口に出来るか。あのレェアであっても、もう少しまともな感性を持っていたぞ」
「な……」
言われて、イェアは目を見開いて絶句し、そしてがたんと立ち上がった。
「ちょ、流石に姉と一緒にされても困りますわっ!?」
「さて? アレは少なくとも、自分に付き従っていた者達への糧食は、我の目から見ても相当の物を用意していたと思うが」
「それは単にあの人が後先考えないでドカドカ盛りまくる性格だからですわっ! 普段からそうでしたもの! そんな調子でやっていたら、絶対に破綻しますわよ!」
「しかし、少なくとも遺跡占拠の際にそのような状況になったという話は聞いていないがな。勿論、糧食が切れたという話もだ。――そもそも、レェアの妹よ」
「な、なんですの」
「貴様、もしや食の味を愉しむ事が出来ぬ類ではあるまいな? 料理も出来ず、味も分からず、滋養を考える事も出来ない。成程、そのような者が糧食を調達していれば、それは当然、下の者達の不満に繋がろうというものだ」
「あ、な――い、いや、いやいやいや、味はともかく、料理が出来ないってなんですか! できます、できますわよ! 当然ですわ!」
「怪しいものだが」
焦った様子で反論するイェアと、表情の変わらぬリゼラ。二人の様子を見ながら、【NAME】は他の面子に視線を投げる。
「…………」
ノエル以外の男二人と視線を合わせた際に得られた共通認識。それは、
(何だか、雲行きがおかしくなってきたような)
話が、妙な方向に転がりつつある。そんな予感である。ちなみに、ノエルだけは興味深そうにただ眼前で繰り広げられる会話を追っている。まだ彼女には会話の流れの善し悪しというものは理解出来ないらしい。
などと考えている間にも、イェアとリゼラの遣り取りは更に展開していく。
「そういえば以前にアレが言ってたな。妹はどうにも味音痴な上に不器用、更には懶婦で、自分が料理を指導しようとも些かも上達せんとな。将来が心配と嘆いていたが、確かに今こうして貴様の様子を見ていると、我もアレの不安が僅かなりと理解できる」
「あ、あの人っ、人の将来とか気にするような質じゃないでしょうにっていうか、あっちも料理の腕はそれ程でもなくて、言うほど差なんて無かった筈ですわ! ああいや、まずそれ以前に、大体リゼラさん! 貴方だってどれ程の料理を作れるって言うんですか!?」
「……あー、そっちに話持ってくとやばいんじゃないの先生ちゃん……」
小声で囁くノクトワイの声は、当然彼女の耳には届かない。
対するリゼラの答えは、ノクトワイや【NAME】が予想した通りのもので、
「少なくとも、レェアの妹よ。貴様が己に付き従う者達のために準備したものよりは上等な料理を出す事は可能だ。――更に言えば、貴様が調理を行ったものよりも上等なものを出す自信もある。アレが言っていた事を信じるならばな」
「い、言ってくれますわねっ……」
「……おー、怒ってる怒ってる」
「彼女にしては珍しいね」
男二人の完全に観客のような感想に、酷いと思いつつも同意する【NAME】。普段は比較的温厚なイェアがこうも沸騰している様子はなかなかに新鮮だった。
だからこそ、続く行動に対する反応が遅れた。
「でしたら、勝負ですわ! あなたとわたくしで、どちらが美味しい料理を出せるか――今すぐに始めますわよっ! 皆さんは、ちょっとここで待っててくださいなっ!」
「「え?」」
と、リゼラとノエル以外の面子が呆気に取られる間に、イェアはそのまま天幕の外へと走り出していってしまった。
止める間すら無かった。ぽかーんと口を開けて揺れる天幕の入り口を眺め固まる一同。
そんな中、一人小柄な影が立ち上がる。
「では、我も用意を始めるとしよう。……さて、何人分用意せねばならぬのかな」
誰に向けてかも判らぬ調子で呟き、その小さな背中が天幕の外へと向かう。その表情には先刻イェアに対してみせていたような嘲る笑みではなく、面倒事を嫌々処理するような、不満と鈍い倦怠感を帯びた顰め面に戻っていた。
そこへ声を掛けたのは、殆ど彼との接点が無い筈のオリオールだ。
「少し良いかな、リゼラ少年」
呼びかけに、少年は足だけを止めた。それだけの反応で良しとしたのか、冒険家はそのまま言葉を続ける。
「君に対してこう言えるほど、僕は君のことを知っている訳ではないのだけど、敢えてこう聞こうか。――一体どうして、こんな君らしくもない真似を?」
対する答えは、嘆息混じりの酷く簡潔なものだった。
「……単なる我が儘だ」
・
そうして幾許かの時間が流れて。
「ど、どうですの!?」
「…………」
二人の料理人を左右に置いた大天幕のテーブルには、大きく分けて二系統の料理が並んでいた。
その系統に対して名前をつけるならば、一つは「拙く少ない」。一つは「素朴で充実」した料理達だ。
前者のものは、料理の基礎すら怪しく、乏しい素材と相性が考慮されていない調味料を雑に用いたあり合わせの代物。あと臭いが酷い。
後者のものは、味付け自体は最低限ではあるが、多様な素材とそれらが持つ味を活かして味に深みを出した代物。あと臭いが良い。
それら全てに口を付けた料理人以外の四人は、淡々と評価を下す。
「杜人クンだわね」
「少年の方に入れよう」
「こちらの方が満足できます」
「…………」
これも慈悲と、【NAME】だけは何の言葉も付け足さず、皆が支持した後者を推した。
そんな皆の評価を前にして。後者の料理を出したリゼラは当然の結果とばかりに一つ頷き、前者の料理を出したイェアは俯いたままぷるぷると肩を震わせる。
「――こ」
「こ?」
顔を伏せて何事かを呻くイェア。それをよく聞き取ろうと皆が少し身を寄せた瞬間、
「こ、こんなの無効! 無効ですわ――っ!」
彼女はばーんと身をテーブルを両手で叩き、絶叫した。
「大体、食材に問題あったし、時間だって無かったしっ! ちゃんと準備出来てたら、わたくしだってリゼラさんの料理なんか足元にも及ばないものを出せますしっ! ていうか、こんなまだ小さな男の子にお料理で負けるなんて、そんな事実有り得ませんしっ! わたくしだって一応、女として最低の矜持くらいはありますわっ!」
「うわぁ……」
気持ちの良いまでの負け惜しみに、ある意味感心する一同。というか、矜持があるというのなら、何故この結果を前にしてそんな台詞を吐けるのか。
だが、そんな言葉に真っ当な反応を返す者がいた。
「ほう」
リゼラである。彼は、イェアの作った料理を一口二口と口に運び、暫し考え込むような間と、小さな溜息を挟んだ後、
「ならば、その準備とやらをしてみてもらおうではないか」
「……え?」
殆ど勢い任せで叫んでいたイェアは、少年のその答えに驚きで目を瞬かせる。そんな彼女に、リゼラは淡々と言葉を続ける。
「お前の料理が本来の実力によるものではないという話は判った。そして我が出した料理も間に合わせであるのは確かだ。ならば改めてもう一度、相応の準備の時間を置いた後に互いの料理を出し合い、その味を競うとしよう。今この場と同じく、この場に居る者達から評価をされる形でな」
「……?」
少年の言葉に、【NAME】はノクトワイやオリオールと視線を交わし合う。
端的に言えば、彼の意図が読めない。リゼラからなされた提案は、場に居る皆が疑問に思うものだった。
イェアの本来の実力――とはいうが、恐らく彼女の力量では豊富な食材や設備、しっかりとした下準備が出来ていたとしてもリゼラの料理に敵うとは考え難い。それくらいの差が感じられた。まさかイェアの先刻の言い訳を真に受けている訳ではあるまいし、それはリゼラとて判っている筈だ。
とすると、何故、という疑問が湧く。
再度の料理の競い合い。それをやる意味が、果たして彼にあるのか。まさかイェアを完膚無きまでに叩き伏せたい、というような幼稚な思考を、あの子供らしからぬ態度を常とするリゼラがするとも思えないのだが、しかし状況を考えると、目的としてはそれくらいしか思い浮かばない。
何とも不可解。考えが理解出来ず、イェア以外の者達が怪訝とリゼラを見るが、少年はそんな皆の視線に一切気を向けた方もなく、ただ正面、戸惑ったように口篭もるイェアを見て、
「如何か」
再度の問い。それは、イェアからすると非常に苦しいものだ。
彼女とて、自分とリゼラ、その差が歴然であることは理解している筈だ。しかし、先刻派手に叫んでみせた手前、リゼラからこう提案されては、彼女曰く女の矜持とやらを捨てないためには、例え敗北が予感できていたとしても、
「の、望むところですわっ! 次こそは、絶対にあなたをぎゃふんと言わせてみせますっ!」
と、答えるしかない。
――こうして、最初の議題そっちのけで、イェアvsリゼラのお料理対決が始まる事になってしまったのだった。