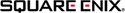少女と黒犬 消えた少女
──消えた少女──
シレネから北西、山裾に広がる森林地帯に足を踏み入れる。
クロテア湖から離れる格好になるためか、この付近で凶暴な生物が出現したという話はついぞ聞かない。
紫峯山や化石の森に近付けばまた違うのだろうが、時折見かける動物も大人しいものだ。無闇に脅かさなければ、向こうから襲ってくることもないだろう。
(……あれ?)
そう思った途端、行く手から走り来る小さな影があった。襲ってくるのか? それとも不意の闖入者に怯えて混乱しているだけか? 今ひとつ判断がつかない。
油断しても怪我をするような相手ではないが、とりあえず応戦の構えを取っておこう。
battle
森の動物達


やがて、前方の木々の隙間にそれらしき建物が見え隠れしてきた。
まだ町を出てから一時間も経っていないはずだ。確かにこれなら、子供でも少し頑張れば歩いて来ることができるだろう。こんな場所に未知の遺跡があったとは俄かには信じ難いほどだ。この上内部に亜獣が出ないとなれば、ピクニック気分で町民が訪れるのも頷ける。
とはいえ……。
【NAME】は周囲を見回した。
林立する広葉樹。鬱蒼とした、という程の密度ではない。陽が射せば充分な明るさがあるし、適度に間隔の空いた木々は奇妙に捩れたりすることもない。天候さえ荒れていなければ、視界はそう悪くないと云える。
再び前方に目を遣る。
木立ちの奥に垣間見える、暗灰色の遺跡。建物は山肌に半ば埋もれるように寄り添っており、土砂崩れでも起きようものなら入口まですっかり埋もれてしまいそうに思えた。塔や楼閣の類は無く、また二階があるようにも見えない。平坦な箱のような造りだ。
目立つようなものではない。だが、かといって全く目に付かない訳でもない。何故こんなものが今まで見つかっていなかったのだろう?
あまりに安全過ぎるので、全く冒険者が近寄らなかったのだろうか。だが、冒険者でなくとも、狩人あたりが少し脚を延ばせば簡単に発見されていたのではないか。
(……考えすぎか?)
勿論、本当に単なる偶然だという可能性もあるのだが……。
もし遺跡の発見に何らかの意図が働いているとするなら、注意する必要があるだろう。
・
考え事をしながら遺跡に歩み寄る。
僅かに開けた遺跡の前の空間には、周囲の木に寄り添うようにして青い天幕がいくつか張られていた。
近くで確認すると、遺跡は“埋もれるよう”ではなく、本当に岸壁を貫いて奥まで続いていることが判る。外から見る限りでは然程大きな遺跡とは思えないが、この造りだと奥行きがどの程度あるのかは見当もつかない。
入口は両開きの扉になっているが、今は開け放たれて数個の岩で固定されていた。
その前に幾人かの人だかり。大半が非常に軽装、あるいは普通の街着のようだから、おそらくシレネの町民グループだろう。何かトラブルでもあったのか、足元に荷物を置いたまま困惑した面持ちで何事かを話し合っている。
「全く……。なんでうちの娘は皆こうなんだ」
中心に立った男が、誰にともなく毒づいた。大柄ではないが、引き締まった身体つきだ。40は過ぎているだろう、一行の中では最年長に見えた。
「やっぱり先生に似たんじゃないですかね……」
栗色の長い髪を後ろで結んだ女性が小声で答える。先程の男に睨まれて、女性は逃げるように荷の1つを運んでいった。察するに“先生”とは彼の事なのだろう。
「僕、さっき中を一通り回ったんだけど、リサリサちゃん見なかったなあ。先に帰っちゃったんじゃないですか?」
若い男が云った。“先生”はむう、と唸っただけで森の方を睨みつける。
「あのー……」
控えめな声が、向かって左手の天幕の方から上がった。
そちらに目を向けると、声の主は帽子を被った金髪の女性だ。天幕の前に置いた座椅子に腰掛け、赤い布を掛けた机に頬杖をついている。机の上には石ころだの首飾りだの、何だか良く判らない雑多な物がいくつも並んでいた。
「私、今日はずっとここに居ましたけど、もしお子さんが一人で帰るようなことがあったら、気付いたと思いますよー?」
それだけ云うと女性は机の方に向き直り、得体の知れない石ころを指先でくるくる回して一人遊びを始めた。
良く見ると、机の上に置かれた幾多のゴミには、それぞれ値札らしきものが付けられている。
(まさか……土産物屋か?)
ひょっとして彼女は、遺跡内での拾得物を個人で販売しているのだろうか。勝手にそんなことをして良いものか――と思いかけたが、良く考えると似たようなことを冒険者は日常的に行っている。この件については深く考えないことにした。
「そうですか、ありがとうございます。じゃ、やっぱり中ですかね。怪我でもしてなければ良いですけど」
「亜獣が出ないとはいえ、ちょっと心配ですね」
荷を纏めながら若い男二人が口々に云う。“先生”は渋面を浮かべたままで押し黙っていた。
「まあ、先生も私もいるから、少しぐらい怪我してもここで縫っちゃいますけどね」
先刻逃げ出した栗色の髪の女性が、歩いで戻りながらクイクイと空中で何かを縫うような仕草を見せた。その言葉振りからすると、どうも先生というのは医者か何かのようだ。
「……中でかくれんぼでもしてるのかも知れませんね」
今まで黙っていた黒髪の若者が、遺跡の壁に背を凭れたまま呟いた。他の面々と違い、この男は一見して装備がしっかりしている。集団から少し距離を置いているところから見て、町民ツアーに同行した護衛役か何かだろうか。
「一人じゃ、かくれんぼも何もないだろう」
医者先生が不機嫌な声で云う。
「オニは私達なんですよ」
黒髪の男が柔和な笑みで答えた。
「ありえますね、それ」と栗色の髪の女性が賛同する。「周りが大人ばかりで退屈だったんじゃないですか。上のお嬢さん達も連れてくれば良かったのに」
「リサだけでも手に余るのに、あれらまで来たら五月蝿くてかなわんよ。とにかく、もう一回中を見てくる」
「じゃ、皆で行きますか」
「そこまでしなくて良いだろう。皆は帰り支度を続けていてくれ。一応ダスター君だけ付き合ってもらおうかな」
「判りました」
“先生”に名指しされ、黒髪の護衛役――ダスターが頷いた。
(……ふうん)
なんとなく立ち聞きする形になってしまったが、おおよその事態は見えてきた。
彼らがどういう経緯で遺跡を訪れたのかは判らないが、帰り支度を始める段になって、同行していた医者の娘が遺跡から出てこない――といったところか。迷子なら結構深刻な事態に思えるが、誰かの云ったように、かくれんぼでもしている可能性はある。
この遺跡は内部も安全だというから然程心配する必要はないだろうが、見つけたら一応外に連れ出した方が良いだろう。
少女と黒犬
──少女と黒犬──
ホール状になった入口を抜けると、十字路に出た。周囲を見回した感じでは、この遺跡は通路とそれに沿って設えた部屋が並んでいるだけの単純な構造に思える。
現在までの処、ネーブブルグ遺跡では亜獣の存在が確認されていないようだが、今後ともそうであるとは限らない。普段どおり、神経を張り詰めて慎重に行動を開始する。
しかし――。
じりじりと通路を進む【NAME】の脇を、例の医者先生が足音も高らかに駆け抜けていく。
(…………)
なんだか、馬鹿馬鹿しくなってきた。この様子だと、本当に何もいないのかも知れない。仮に亜獣が潜んでいた場合、真っ先に襲われるのはあの先生で間違いあるまい。こちらも適当に気を抜いて行くべきか。
・
とりあえず幾つか手近な部屋に入ってみたが、流石に荒らされている。殆どは一見して空っぽで、詳しく調べるまでも無い。
だが、四番目に入った部屋は少し様子が違っていた。
調度品の類は相変わらず全く無い。ただ、部屋の正面にあたる壁面に大きな紋様が1つだけ刻まれていた。人の背丈程の真っ白な円を中心に、周囲を幾重にも複雑な紋様が縁取っている。
(これは……グリフだな)
かつて『芯なる者』が用いたとされる概念異渉紋様。その効果は千差万別で、発揮される力も印章などとは比べ物にならない。
古い遺跡にはつき物だが、壁に刻まれているのは比較的珍しいように思う。多くの場合は床に描かれ、近付くと突然亜獣が召喚されるなど、大抵ろくでもない現象を引き起こしてくれる。
「やはり、それが気になりますよね」
声に振り向くと、外で見かけた黒髪の冒険者が立っていた。確か、ダスターと呼ばれていた男だ。
「私も一応冒険者の端くれですからね、グリフは気になる。でも、どうも動作しないんですよ」
云いながらダスターは象形の前に近付くと、白い円に向かって手を翳した。
確かに、象形は何の反応も見せない。既に機能が死んでいるのだろうか? 【NAME】が近付いてみる。と――。
「え?」
近付く【NAME】に呼応して、模様全体が鈍い光を発した。やはり、まだ機能は失われていないようだ。警戒したダスターは数歩後退し、動き始めた象形の様子を遠巻きに観察する。
円の周囲を縁取る紋様を細かな光の粒子が無数に走り、それに合わせて円の内側に混沌とした色合いが浮かび上がる。
真っ白だった円の中には、水面に墨を流したような濃淡が複雑に浮き上がり、流動する。固唾を呑んで見守る【NAME】の前で、やがてそれは一つの像を結び、静止した。
「何でしょう? これ。どうやったんですか?」
浮かび上がったのは、斜め上から見た殺風景な室内の映像だ。この部屋ではないが、床や壁の具合からして遺跡内のどこかであることが知れる。映像は鮮明だが、実物に比べると色合いが薄く、どこか現実感が乏しい。視点が普段の感覚から外れた位置にある所為かもしれない。
ダスターが再び手を翳したり縁に触れたりするが、何の反応も無かった。
映像は暫くの間止まっていたが、数秒の後、何の前触れも無く切り替わった。今度もまた上から見た部屋の映像。ただ、室内の様子が微妙に違うから、遺跡内のまた別の部屋だろう。
「ああ……監視装置? 珍しいな」
(……なるほど)
一定時間毎に遺跡内の各部屋の様子を映し出すための象形か。確かに珍しい。
基本的に、古い遺跡になるほど人間にとっては意味不明な象形が刻まれている。古い遺跡の主は多く『芯なる者』であり、彼らの価値観や能力が人間とは余りにもかけ離れている所為だ。監視装置のような、人間にとっては実用的だが回りくどい機能のものは殆ど存在しないと云っていいだろう。おそらく、芯属ならばこんなものを作らずとも、身一つで同じ事が実現できるはず。
つまり、この遺跡は比較的新しい。芯なる者の時代より、少し後。より人間に近い存在が築いたものではないか、と考えられる。
「監視用なら、任意の部屋を映すように仕向けられるはずですが……」
ダスターが映像を映し続ける象形の周囲をつぶさに見て回る。
「無理かな。操作するための機構が見当たらないから、直接理粒子干渉しないと駄目か。構造を知らない人間には扱えませんね」
象形への干渉を諦め、【NAME】とダスターは少しの間切り替わっていく映像を漫然と眺めていた。運が良ければ、迷子の女の子の姿が見つかるのではないか、という期待を込めて。
「……妙だな」
幾度目かの映像で、ダスターが呟いた。だが、【NAME】には彼が何に気付いたのか判らない。ダスターは何かを考えるように右手を口許に当てて、映像に見入っている。
また、何度か映像が切り替わった。
「やはり」と、ダスターは何かを確信したようだ。
「部屋が多すぎる。私達が調べたのは大部屋が七つに小部屋が六つ程。なのに、今映った映像は大部屋だけで十を超えてます。この遺跡は思ったよりも広い。……あ」
(おや……)
次に切り替わった映像の中に、少女の姿があった。
これまでと同様の斜め上から見た部屋。青いワンピースを着た少女が隅の方に映っている。
そして……。
「亜獣……?」
少女の向かい側に、黒い犬が寝そべっていた。眠っているのか、死んでいるのか、映像からは判断できない。だが、少女との対比で、犬が結構な大きさであることが見て取れる。
少女はためつすがめつ犬の方に歩み寄り――そこで映像は切り替わった。
「今の部屋はどこだろう。見たことがない」
隠し部屋が無数にあることは確実だ。そのどれか1つに少女は迷い込んだということだろうか。
とにかく、もしあれが生きた亜獣なら非常に危険だ。急いで探し出さなければならない。
・
リサリサは当惑していた。
父親を驚かそうとして隠れる場所を探したのは良いが、どうも変な場所に迷い込んでしまったらしい。彼女が何となく開いた扉の奥に、それは居た。
「犬……。亜獣? 生きてるのかな……?」
死んだように眠る真っ黒な犬。首周りと尾は多少毛量が多く、ふっさりとしている。その精悍な面持ちは狼を思わせたが、リサリサは狼と犬の区別を知らない。彼女がそれを狼でなく犬だと認識したのは、赤みがかった首輪が着けられている所為だった。
床には犬を囲むように青い円が描かれており、円の縁から出たぼんやりとした光が半球状に犬の身体を包んでいる。
部屋をのぞいた時は驚いて息を呑んだリサリサだが、冷静に観察すると、どうも生きているようには見えない。彼女が部屋に入った時も微動だにしなかったし、第一、呼吸している様子が全くない。
よく考えたらここは随分古い遺跡の中なのだから、死体だって原型を留めているとは考えにくい。ひょっとして、精巧な置物か剥製の類ではないだろうか。
一度そう思うと、今度は恐怖よりも好奇心の方が勝った。彼女は元々動物が大好きだったが、家が病院であるせいか、ペットを飼うことが許されない。他の病院では犬を飼っているところだってあるのに、といつも不満に思っていた。
この犬はちょっと大き過ぎるけど、よく見るとなかなか可愛い顔つきをしているような気がする。
少しづつ角度を変えて犬を見つめながら、徐々に距離を詰めていく。近づくにつれ、犬を包む半球がよりはっきりと見えてきた。青みがかった透明な薄い膜で、ほんの僅かな光点が表面を流動している。
「なんか、綺麗……」
何気なく、手を伸ばす。
「あ」
差し出した指先が半球に触れるか触れないか、というところで、それは音も無くシャボン玉のように弾けて消失してしまった。同時に、床の青い円が次第に色を失って消えて行く。
「どうしよう……。消えちゃった」
何か取り返しのつかないことをしてしまったという罪悪感。いたたまれない気持ちになったが、この場を離れようにも脚が動かなかった。
微動だにしなかったはずの黒犬が、燃えるような青白い瞳でリサリサを見つめていたからだ。
・
【NAME】とダスターが遺跡を早足で巡る。
「そこかな」
ダスターが通路の突き当たりの壁を指す。【NAME】が近付くと、予想通り壁に扉が浮かび上がった。
「やはり、そのペンデュラムが鍵のようですね。まさか売店で販売されているとは……盲点でした」
そう。ネーブブルグ遺跡には先の象形をはじめ、間取り上、部屋があっても良いはずなのに扉の無い謎の空間が幾つもあった。
何か進む為の鍵があるのではないか――と、誰もが思っていたが、それが何なのか、どこにあるのか誰も気付かなかった。さっきの監視機能の象形の起動条件を探る内に、【NAME】の持つ『貴賓のペンデュラム』に思い至ったという訳だ。
「そういえば、確かお嬢ちゃんも土産物を物色してたなぁ……迂闊でした」
扉を開いた先は部屋ではなく、直線に続く廊下だった。左右の壁に規則正しく扉が並んでいる。
「この先は全て未知の領域です。手当たり次第に行きましょう」
・
リサリサは恐怖に凍り付いていた。
黒犬が音も無く身を起こす。その体高はリサリサの肩にまで迫っているから、殆ど子牛だ。開かれた鋭い目は炎のように青く輝き、高い知性と強固な意志を思わせる。明らかに普通の犬ではない。亜獣だ。
手を伸ばせば触れられる距離に、それが居る。
やはり、部屋に犬の姿を見た時点で逃げ出すべきだったのだ。そんなことを考えたが、もう遅い。今から逃げ出そうにも、身体が震えて云うことを聞かなかった。走るどころか、この場にへたり込んでしまいそうだ。
それでも何とか気力を総動員し、ようやく少女は数歩、もつれる足で後ろに下がった。
――何だ? この小便臭い雌餓鬼は。
「え?」
突然の声に、リサリサは弾かれたように周囲を見回した。だが、部屋にいるのは自分と黒犬だけだ。
――おつむの回転が鈍い奴だな。声の主なら俺だ。お前の目の前にいるぜ。
今度もはっきり聞こえた。いや、「聞こえた」というよりも、他人の意図を直接頭に書き込まれたような奇怪な感覚だ。そして、「目の前にいる」という声の主は、言葉通りに受け取るなら黒犬、ということになる。
「これ、貴方が喋ってるの……?」
恐る恐る、リサリサは犬に向かって問いかけた。
――厳密にはその表現は不適切だ。俺は自分の発話意図を直接意識下に触れさせているだけで、それをいちいち言葉に直して理解しているのはお前の都合によるものだ。つまり、“喋っている”訳じゃねー。ただし、俺の発話能力は音声同様に周囲にブロードキャストされるので、ほぼ“喋る”と同等の機能を持っている。また、もし俺がお前と同精度の発声器官を持っていたなら、実際に“喋る”ことも可能だったろう。
黒犬は答えて、後肢で頭を掻いた。
「驚いた……。言葉を理解できる亜獣がいるのね」
――恐らくお前より数段多くの言語を理解できるだろう。だが、驚くには値しない。知能の高い亜獣など他にいくらでもいる。連中の多くに言葉が通じないのは、人語を解する必要性が無いからに過ぎない。
「そ、そう。でも……犬だよね?」
――定義による。俺個人としては、家畜と同列に見られるのは心外だ。
「あ、ごめん。違うんだ?」
――いや、広義の犬に含まれることは認めざるを得ねー。キャペルウェイトって知ってるか? 原型からすると、あれが比較的近い。
「へー。キャペルウェイトね。……知らないけど」
――これは俺の持論だが、無知は罪じゃねーぜ。学習を放棄しない限りはな。しかし、起きたら腹が減ったな。
黒犬は暫しリサリサを値踏みするように見詰めてから、不意に何かに気付いたように舌打ちした……ように思えた。
――なんだと……。
言葉と共に、今度は明確な驚きの意思を感じた。
「どうしたの?」
――そうか。前の奴は死んだのか。二重安全機構は今でも有効ってことだ。うぜぇ……。
黒犬がリサリサに向かって数歩詰め寄る。
「え? 何? 何?」
リサリサは思わず後退った。会話に興味を惹かれて意識していなかったが、この犬はその気になれば自分を簡単にかみ殺せる程の存在なのだ。
だが、構わずリサリサに近付いた黒犬は、どこか恭しい様子で頭を垂れた。
――“制約の環”の下において、主命に背かず、身命を賭して御身を御守りすると誓約する。
リサリサはきょとんとした表情で静止した。
「誓約……?」
意味するところは何となく理解できるのだが、余りに唐突で反応に困る。呆けたような少女の様子を見て、黒犬は実に厭そうに付け足した。
――お前が俺の主だ。何なりと御命令を下しやがれ。
「あの……私が、貴方に命令するの?」
――他に誰がいるんだ?
黒犬がリサリサの前に座り込んだ。リサリサは少し思案してから、犬の前で中腰になった。
「じゃあ、お手」
そう云って右手を差し出す。犬の体躯が余りに大きいので、手を出す高さに少し迷った。
――なめてんのか?
黒犬は差し出された少女の掌をちらりと見て、ぽん、と無造作に左前肢を重ねた。
「わ。お利口さんだね」
リサリサは顔を綻ばせ、左手で犬の頭を撫でてみた。
――ふざけた命令出すな。殺すぞ。
されるがままになりながら、黒犬は渋面を作る。
「だって、急に御命令を、なんて云われても困るよ」
――あれは忘れろ。お決まりの手続きみたいなもんだ。大体、命令がない限り『御身を御守りする』なんて決まりもねーから、出鱈目も良いところだ。
「でも、私がご主人様なんだよね?」
――その認識で概ね問題ないが、これは主従関係なんて良いもんじゃねーぜ。“制約の環”と呼ばれる忌々しい呪いだ。人でなしどもの研究成果のな。
リサリサが眉根を寄せて考え込んだ。
「もうちょっと詳しく」
しかし、答える代わりに黒犬は顔を上げ、部屋の入口を向いて警戒の意を見せた。
――誰か来る。……戦闘経験を積んだ人間だ。面倒だな。
「あ。私を探しに来たのかも。どうしよう。説明して解ってもらえるかな?」
ひょっとすると自分は、この遺跡で結構な発見をしてしまったのではないか。そんな気がしていた。この犬はそんなに危険ではなさそうだし、亜獣狩りを生業としているダスターさんでも、話せばきっと理解してくれるだろう。
リサリサはそんな風に事態を楽観的に捉えていた。しかし、黒犬の答えはにべもない。
――説明している間に戦闘が始まる。とりあえず、お前は黙って自分の家に帰るべきだろう。
「え、もうお別れなの?」
リサリサの表情には色濃い落胆が浮んでいた。黒犬の方は淡々として説明を続けた。
――いや、俺の行動はお前に束縛されている。具体的にどういう構造になっているのかは知らねーが、見えない鎖で繋がれているような感覚だ。必要以上に主と距離を取ることは難しい。つまり、お別れはまだだ。
最後の部分を厭そうに告げる黒犬。だが、リサリサの方はそれを聞いて顔を明るくした。
「じゃ、家に来る? でもうち病院なんだよね。ペット飼っちゃいけないって云われてるし」
――仮にペットが許可されていたとしても、俺を家で飼うのは無理があるだろう。近場で人目につかない場所が欲しいところだ。
「あ、それなら家の近くに小さな森があるよ。真ん中は公園になってるけど、周りは木がいっぱいで、道を外れたら誰も居ないと思う。私の部屋二階なんだけど、窓から見えるぐらいの距離だし」
――規模にもよるが、それは使えそうだな。
「雨が降ったら、すっごく大きなナメクジが出るよ。黒いやつ」
――それはどうでも良い。とりあえず、接近中の奴をやり過ごすか。
・
ダスターと【NAME】が幾つめかの扉を開けて、部屋に入る。
幾重にも積まれた何かの荷物。視界を遮る小さな衝立。雑然とした室内の中心に、一人の少女が硬い笑みを浮かべて立っていた。
少女は濃い青色の服を着て、金色の髪を後ろで二つに分けて結んでいる。彼女が問題の迷子、リサリサと考えて間違いないだろう。
「……無事だったか」
ダスターが息をついた。
「あ、えっと……ダスターさん。はは、見つかっちゃった」
少女はどこか悪びれた様子で、にこにこしながらも落ち着きを欠いている。
(……犬はどこへ行った?)
象形に映し出された映像では、確かにあの辺りに黒い犬の姿があったのだが……。実際にその場を見ても、何も無い。床に微かな円形の痕跡だけが残っているが、それが何なのかは見当もつかなかった。
ダスターも【NAME】と同じ疑問を抱いたようで、しきりに室内の様子を気にしている。
「あー、えーと。そろそろ、帰ろうかなー?」
矢鱈と部屋の中に注意を向ける【NAME】達に向けて、無視される形になった少女が云う。
「……妙だな。確かにこの部屋だったと思うが……ここに犬が居なかったか?」
ダスターが少女に問う。
「え? あ、うん。犬が居るように見えたんだけど、触ったら消えちゃったの。ほら、そこ」
指差す先にあるのは、床にある円形の痕跡だった。これもまた何かの象形だろうか。そうだとしても既に機能はしていないと見えて、【NAME】が近寄れど触れど何の反応も無かった。僅かな光すらも認められない。
「ふうん……まあ無事で良かった。しかし、そうするとこのグリフ、何のためのものか良く判らんな……」
ダスターが床の模様を検分しながら呟いた。確かに、ちょっと奇妙だ。しかしまあ、迷子が無事に見つかったのだから深く詮索する必要もないだろう。
【NAME】はダスターと共に少女を部屋から連れ出すと、例の医者先生の許へと送り届けることにした。
・
無事に遺跡から脱した少女は、父親でもある医者にこっ酷く叱られた。【NAME】達が象形の部屋で見た亜獣は結局姿を見せず、何事も無かったかのように一行は町へと戻る。
彼らの遥か後方を黒い犬が追跡していることなど、誰も知る由は無かった。唯一人、黒犬と出会った少女リサリサを除いては。
少女と黒犬 制約と命名
──制約と命名──
憩いの森。周囲の自然から切り離され、ただ人々のくつろぎの為にのみ街中に残された地形。
南北に細長い森は北寄りの中心が切り拓かれて公園になっており、決して深いものではない。それでも一歩敷地内に足を踏み入れれば、そこはもう街の熱気からは隔絶された世界だった。小さな森は街中に孤立しつつも、特有の緑の香りや清廉とした涼しげな空気に溢れ、訪れる人々に充分な潤いを齎している。
この日の早朝、そんな森の一角にリサリサは居た。
中央公園に向かうものとは違う、周遊のための道を歩く。運が良ければ、この付近では野生のリスに遭遇することもあった。リサリサはそれを見つけて追い回すのが大好きだ。けれども、今はもっと別のことを考えていた。新しく友達になった――と彼女は思っている――少し大きめの黒い犬のことだ。
適当に周遊道を進んだところで、立ち止まって周囲を確認する。人の気配は無し。
彼女はそこで唐突に道を外れると、おもむろに森の中へと突っ込んで行った。幾重にも落ち葉の積もった地面を、小走りに進む。
「おーい……」
周遊道が見えなくなる程度にまで進んでから、犬を呼ぼうと声を上げる。大声を出すのは憚られるので、そっと囁くように。森の中はしんと静まり返っているが、こんな声が果たしてどこまで届くのか、甚だ疑問だった。
「どこにいるのー……?」
今度はもう少し大きめの声で呼んでみる。さっぱり加減が判らない。しかも、何と呼べば良いのか判らないから、どうしても曖昧な呼びかけになってしまう。最初に名前を訊いておくべきだった、とリサリサは思った。
だが、心配する必要は無かったようだ。幾らも待つことなく、落ち葉を踏みしめる軽快な足音と共に黒犬が姿を現した。
――そんなに何度も呼ばなくても良い。人間とは聴覚の出来が違うし、そもそも俺にはお前の位置が大体判っている。
「私には全然判らないんだから、不公平だよね。もっと『ここだ!』っていう場所を決めようよ」
毒づきながらリサリサは籐で編まれた籠を地面に置き、自分もしゃがみ込んだ。
――難しい注文だ。余り外輪部に近いと外から丸見えだからな。……で、何だそれ。良い匂いだな。
「ふっふっふ。私が腕によりを掛けた特製のお弁当ですよ。どう? 欲しい?」
――毒見でもさせるつもりか?
「可愛くないこと云うね」
リサリサが包みを開いた。蓋を開けた弁当箱を地べたに置く。中には様々な料理……穀類や麺類すら入っており、犬の餌というより丸っきり人間用のお弁当だ。
――これ、お前が食べるための食糧じゃないのか?
「え? 違うよ。食べて良いよ」
――まあ、喰うだけ喰ってみるか。
黒犬は少しだけ躊躇ってから、弁当箱に顔を突っ込んだ。
「どう? 美味しい?」
少女がわくわくしながら犬の様子を見守っている。
だが、黒犬は何とも微妙な表情を浮かべて顔を上げると、個々のおかずの匂いを嗅いで吟味し始めた。
――これは……なんつー濃い味つけだ。しかも栄養のバランスも悪い。
「ええー?」
リサリサが肩を落とした。黒犬は続いて具体的な問題点をあげつらって行く。
――まず、俺にはこんなに大量の炭水化物は必要ねー。それに妙な味付けしたり火を通しまくったり、骨を取り除く必要もねー。肉食動物は大体そんなもんだ、覚えとけ。
「せっかく作ったのになぁ」
――これ、お前が作ったのか?
「全体の10%ぐらいは、私の作品です」
――殆どゼロに近いな。どうせこのブロッコリあたりだろ。
「ぶぶー。玉子でした」
――大差ねーよ。まあ、それでも腹の足しにならないことは無い。
云ってから、黒犬は覚悟を決めて再び弁当を食べ始めた。リサリサは自分の膝に頬杖をついて、その様子を窺うことにした。
「ね、ちょっと色々説明して欲しいんだけど。この前聞きそびれたから」
――どうでも良いだろ。お前が知る必要は無い。
黒犬は弁当に顔を突っ込んだままで受け答えした。食べながらでも鮮明に意見を述べられるのは、発声と違う利点だ、とリサリサは思う。
「質問するから答えてね。これ、命令よ」
――お前……。何でも訊いてくれ。
「じゃ、まず、なんであんな所で寝てたの? 死んでるのかと思ったよ」
あんな所、とは勿論ネーブブルグ遺跡のことだ。最近発見されたばかりの、亜獣の居ない安全な遺跡。その奥の一室で、彼女はこの黒犬と出会ったのだった。
――あそこは元は研究所だ。鬼を支配して使役するための実験をしていた。俺は初期の被験体の一つだが、研究が次の段階に進んだ時点で用済みになって寝かされたってわけ。
黒犬が面倒臭そうに答える。
「ふーん。鬼を支配って、ペットみたいなもの?」
――少し違う。強力な鬼と友好関係を結ぶのは余程の餌が無ければ無理だし、かといって力ずくで抑え付けるのは更に困難だ。そこで、完全な支配は最初から諦め、小さな力で可能な限り鬼を制御してみよう、というせこい発想の下に生み出されたのが、“制約の環”という忌々しい代物だ。あの研究所の成果物はほぼこれだけと云って良い。
「環ってその首輪のこと? それがあるから命令に逆らえないの?」
――いや、これは単なる飾りだ。環は肉眼では見えない。一般に強い効果を持つ象形ほど図柄も複雑、肥大化し派手に光り輝くもんだが、“制約の環”を構成する象形は極めて小さく、光量も無に等しい。生物に直接象形を刻むのが難しかったのかも知れないし、何か他に理由があったのかも知れない。その辺の細かい事情までは聞いてない。
「へー」
――命令の方は逆らえないのではなく、逆らう気にならない、というのが正確だな。環は主従関係を設定し、主に対して害意を抱いたり、命令に背こうとした場合に痛みを与える。単純だが、多くの生物には効果的に働いた。反復学習で従順になればそれだけ環自体の力は不要になり、省エネでお徳という訳だ。
「痛いんだ……。それは、厭だね」
リサリサは眉をひそめた。
――解ったら気安く命令出すんじゃねーぞ。
「病院で鎮痛剤もらってきてあげようか?」
――当然ながら無意味だ。そんなもので抑制できるぐらいなら、最初から環の存在価値は無い。
リサリサは弁当を食べる黒犬の様子を暫らくじっと見守っていたが、ふと思い付いたことを口にした。
「ね、もし私が『命令に従わなくて良い』って決めたら、痛くなくなるのかな?」
予想外の少女の提案に、黒犬は一瞬虚を衝かれた。食事は一時中断し、少女の真意を計るようにその目を見る。
――そりゃ、良いね。解放してくれたら、お礼にお前を頭から喰ってやるよ。だが、残念なことに不可能だ。
「頭……」
――まず、支配解除の方法をお前が知らない。決めただけじゃ何の意味もない。環に直接干渉して手続きが必要だ。正直俺もどうすれば解除できるのか知らん。
「そっか……」
――そしてもう一つ、暴走防止の為に設定された二重安全機構の問題がある。何らかの原因で支配者が死亡、または支配解除した場合、次に目にした人間を仮の主人に設定する。お前が俺の主人になったのもこれの働きだ。結局、環自体を外せなければ何の意味もない。
リサリサは、初めて会った時に黒犬が『前の奴が死んだ』というような意味の事を云っていたのを思い出した。あれは、“前の支配者”が居なくなったから、次に出会ったリサリサが仮の主になった、という意味だったのか。
これでは、リサリサが黒犬の支配を放棄できたとしても、この犬はすぐにまた別の者によって支配されてしまう。それは抜け出すことの叶わぬ螺旋のようで、なんだか可哀想な気がした。
「なんか、陰湿な仕組みだね」
リサリサは溜め息を落とした。黒犬はこれには答えず、改めて弁当箱に顔を突っ込んだ。
リサリサは少しの間無言で食事の様子を眺めていたが、ふと、大事なことを聞き忘れているのに気がついて口を開いた。
「あ、そうだ。名前は何ていうの? おーいとか何とかじゃ呼び難いよ。私はリサリサ・ネックベット。貴方は?」
――名前か。前の奴には“ワン公”って呼ばれてたな。
「ワン公って……それ、名前じゃないよ。愛の無い環境で育ったのね。だから、そんなに性格が歪んじゃったんだ」
――ほっとけ。
「よし、私が良い名前をつけてあげよう!」
――あのな……お前、俺を何だと思ってるんだ?
黒犬はもう殆ど残っていない弁当にまだ顔を突っ込んでいる。放っておくと弁当箱まで食べられそうな気がしてきた。リサリサは暫く黒犬のそんな様子を見つめてから、おもむろに口を開いた。
「がじちゃん」
――は?
「がじがじお弁当を食べてるから、がじちゃん。うん、良いね。これで決定! どう、気に入った?」
リサリサは小首を傾げ、食事を終えた黒犬の顔を覗き込む。
――なめてんのか?
少女のにこやかな表情に、さっと険の影が差した。
「貴方の名前はがじちゃん。これ、命令よ」
――良い名前だな。突然気に入ってきた。
「でしょ?」
リサリサは満足げに頷くと、弁当箱を手に取り、籐の籠に戻した。なんだかんだと文句を云っていた割に、弁当は綺麗に平らげられていた。
・
「じゃ、時々ご飯持ってくるからね。散歩とかしなくて良いのかな?」
――二、三日食わなくても問題ねーよ。それより、そのままで聞け。
「ん?」
――こっちを見ている奴がいる。お前、誰かに俺のことを喋ったか?
「え……」
リサリサは思わず周囲を見回しそうになったが、何とか自制して小声で話を続けた。
「……喋ってないよ。でも遠くからだと、単なる野犬と動物好きの可憐な美少女にしか見えないんじゃない?」
――動物好きはともかく、残りの要素にはいずれも疑念の余地がある。
「変質者だったらどうしよう。もしかして私ピンチ?」
――いや、全然違うな。かなりの距離を維持したまま近付こうとしない。それが逆におかしい。普通、俺とお前の姿を見てもこれほど警戒することは無いだろう。……おや、離れて行った。
リサリサは立ち上がって周囲を見回した。しかし、一体どこから見られていたのか全く見当もつかない。
「影も形も見えないよ。そんなに遠いんなら、周遊道を散歩してた人かも」
――そうかも知れない。だが、とにかく他人には注意しよう。
「この前も思ったんだけど、ちゃんと皆に説明した方が良いんじゃない?」
リサリサはこれまで多少お転婆な面はあれど、基本的に“良い子”で通してきた。故に、両親にさえ秘密で通すという事がどうにも落ち着かなく感じる。また、そうすべき理由も良く理解できていなかった。しかし、黒犬の返答は簡潔だった。
――止めた方が良い。危険だ。
「そうかなあ。軍の人とかに連絡すれば安全じゃない?」
――“制約の環”や俺の存在が公になれば、それを利用しようと近付いてくる輩が必ず現れる。軍とて例外ではない。可能な限り秘密にするべきだ。
「利用って云っても、できないよね。がじちゃんの主人は私で、それは変更できないんだし」
――お前は負の方面への想像力が欠如しているな。ある意味それは幸せな事かもしれないが。
「がじちゃんは負の方向に思考が捻くれまくってるよね」
――む……。まあ良い。基本的に黙っている方が無難だということだ。
「ふーん。お父さんとかにも云わない方が良い?」
――お前の親父って医者だろ? 学者の類に共通することだが、好奇心が奴らを残虐にする。これまた絶対に知られたくない人種だ。
リサリサは短く息をついた。どうも、この犬は人間不信の嫌いがあるようだ。
遺跡が研究所だった頃には、一体どういう生活を送っていたのだろう。訊いてみようかと思ったが、あまり幸せな過去ではなさそうなので止めておくことにする。
「結局、がじちゃんの事は誰にも云っちゃ駄目なのね……がっかりだよ」
この犬のことを皆に自慢してやりたかった彼女は、少なからず落胆した。せっかく素敵で知的で、しかも意外性のある友達ができたと思ったのに、誰にも紹介できないなんて想定外だ。
「だけど、秘密の友人ってのも、考え方次第では良いかも」
――お前は中心に据えるべき問題を取り違えているような気がするな。そもそも何時から俺とお前が“友人”になったんだ?
「とにかく内緒にしとけば良いんでしょ? なんか、隠れて悪いことしてるような気分になるね」
――事実その通りだ。お前は遺跡での発見を隠蔽し、町に亜獣を匿っているんだからな。だが気にすることは無い。当面我々の安全を優先しよう。
「了解!」
・
【NAME】は特に目的もなく町をぶらぶらしていた。
今日は何の収穫もなく一日を終えそうだったが、時にはのんびりするのも悪くない。
足の向くまま町を歩いていると、森林公園に行き当たった。公園とは云っても、外から眺める分には森にしか見えない。森と水の豊かなシレネならではの、落ち着いた寛ぎの空間だ。
(……おや)
丁度その時、その森から出てくる小さな人影があった。両手で籐の籠を提げ、二つに結んだ金髪を揺らしながら、人影は迷いの無い足取りで街路に消えていく。
あれは……確か、ネーブブルグ遺跡で迷子になっていた少女だ。この近辺に住んでいるのだろうか。
しかし、買い物にしては随分変な経路だ。何か一人で憩いの森に行く用事でもあったのだろうか?
少女と黒犬 化鳥を狩る影
──化鳥を狩る影──
昼下がり、【NAME】は憩いの森を訪れた。
若々しい緑の梢の下、そこかしこに残ったほんの僅かな雨露の湿り。木々の間を風が抜ければ、それだけで昼の熱気はすっかり消え失せて、肌寒いまでの涼しさを感じさせる。これが早朝であれば尚のこと清々しいに違いない。
森の中を巡る周遊道を抜けて中央の公園に足を踏み入れた【NAME】は、大きくひとつ伸びをする。公園の脇には小さな池があり、僅かに波立った水面が日差しを複雑に反射している。その柔らかな光が、目に心地良い。
普段の殺伐とした戦いから解放され、心身ともに清新になる思いだった。冒険者の休暇、といったところか。
しかし、【NAME】のささやかな安らぎは、幾らも続かなかった。
突然の叫び声が森の静寂を打ち破る。見るからに慌ただしい様子で駆け込んできた男が、息も絶え絶えになりながら己の駆けて来た道を指差した。
「化鳥だ! 化鳥が町にいるぞ!」
何事かと集まった数人に向かい、男は肩で息をしながら仔細を説明する。どうやら公園の外、つまりシレネの街中に亜獣がいるらしい。
(……ま、冒険者の休暇はこんなもんだろうな)
独りごちて、【NAME】は自分の眼で鳥の姿を確かめるべく、公園の外へ向かって歩き出した。
・
昼下がり、リサリサは憩いの森の奥で黒犬と会っていた。
「でも、不思議だよね。城壁とかで囲ってないのに、町に亜獣が攻めて来ないなんて」
ふとした疑問を口にする少女。彼女はここのところ手を替え品を替えて食事を作り、黒犬と他愛も無い話をするのを日課としていた。その知識量の差から、自然と少女が生徒で犬が教師のような役割になることが多い。
――当たり前だ。お前は亜獣を、手当たり次第に人を襲って喰うようなモノだと思ってないか?
「違うの?」
――全く違う。そもそも、お前らが亜獣と呼んでいるものは、基本的に芯なる者どもが手を加えた生物のことだ。殆どの場合、元は単なる野生生物に過ぎない。
「そうなの? そのへんの野犬とかも亜獣って呼んだりしない?」
――今はそういう使い方もあるようだが、本来の意味からは外れた用法だ。いずれにせよ、連中が人を襲うのは生きる上で必要に迫られてのことだ。理由も無いのにわざわざ人の町に突っ込んで殺しあうなど、有り得ない。
「ふーん。云われてみれば、そうかも」
――おっと、そういや人間は例外だな。多くの者が自ら亜獣の巣に突っ込んでは、特に意味もなく虐殺を繰り返す。つまり、怯えながら暮らしているのは、実際には亜獣の方だという訳だ。
「なんか、新発見」
リサリサは神妙な様子で頷いた。
と、どこかから叫び声が聞こえたような気がして顔を上げる。同様に黒犬も声の方に注意を向けたのが判った。
視界は周囲の木々にすっかり阻まれ、何が起こっているのかは判らない。遠くで誰かが大声を上げる。化鳥が出た――そう云っているように聞こえた。
「化鳥って云った?」
――そう聞こえたな。
公園の方で人々が小走りに移動する気配。
通常、化鳥と云えばハーピーやその眷属を指す言葉だ。つまり、紛う方なき亜獣。それが、町中に出た……?
「ね、町に亜獣が来たみたいだけど、何で?」
――さあ?
・
憩いの森を出ると、化鳥が出たという現場はすぐに判った。
立ち並ぶ二階建ての民家。その連なった赤い屋根の一つに、紫がかった羽根を持つ人面鳥が止まっている。【NAME】の位置からはまだ結構な距離があるが、家の前の通りは見物人や武器を手にしていきり立つ者で立錐の余地も無いようだった。
(……これは、手を出しづらいな)
こんな場所に亜獣が現れることは滅多に無いので興奮するのは判るが、ああして民家の周囲を人で埋められては、逆に打つ手が限られてくる。
化鳥の方は下の喧騒を全く気にせず、ただ漫然と屋根に止まっている。降りてくるなら応戦も可能だが、ひとまず集団からは距離を置いて様子を見ることにしよう。
・
リサリサは森の外輪部から、木の幹に隠れるようにして外の様子を窺っていた。その背後には、彼女に付き従う黒犬の姿がある。
「ほら、屋根の上に何か居るよ」
リサリサは遠くに見える赤い屋根の一つを指差して、犬の方を振り返った。
――確かに居るな。
「結構うちの方に近いなー。退治しないのかな?」
リサリサは木の幹に両手で縋り、顔だけを出して民家の方に目を戻す。この騒ぎで人の注意はあちらにあると踏んだのか、黒犬も少女の脇まで進み出てきた。
――下から手を出すのは難しい。術式を使えば家が焼けそうだし、あんなに人が取り巻いていては矢を射掛けるのも危険だ。屋根に登って接近戦を挑み、最低でも位置を変えさせるべきだ。
「あんな斜めの屋根に登って大丈夫? 危ないんじゃない?」
――当然危ない。だから皆ああして様子を見ているのだろう。
確かに、手に弓や杖を持った者の姿も見えるが、誰も実際に手を出そうとはしていない。人ごみの中には本職の冒険者らしき姿もあるが、同じく手を出しかねているようだ。
「ね、がじちゃんは足が速いんでしょ?」
リサリサは囁くように、しかし妙に嬉しそうな調子を込めて云った。
――あん? なんだ突然。そりゃ、お前と比べたら大半の動物は足が速いんじゃねーの?
「その大半の動物の中でも、かなり速い方じゃない?」
――どうしてそう思う?
黒犬が民家の方から視線を外し、リサリサの顔を見た。
「キャペルウェイトは目にも留まらぬ速度で動く、って本に書いてあった」
少女の返答に、黒犬は口の端を歪めた。……笑っているのだろうか。
――そんな事、わざわざ調べたのかよ。ま、そこそこ速いとは思うが、目にも留まらぬってのは大袈裟だぜ。
黒犬の語調にどことなく誇らしげな色が宿る。この性格の歪んだ犬でも、褒められるのはまんざらでもないようだ。
「ねえねえ……」
リサリサは民家の観察を完全に止めて、黒犬に向き直った。
――なんでそんなに満面の笑みなんだ?
「良いこと思いついちゃった」
――ふーん。良かったな。
黒犬がリサリサから視線を逸らす。その頭を少女がぐい、と掴んで自分の方に戻した。
「何を思いついたのか訊いてよ!」
――あぁ。何を思いついたんだ?
「この前『隠れて悪いことしてるみたい』って云ったじゃない? そうじゃなくなる方法を思いついたの!」
――ほー。
「つまり、隠れて善いことをすれば良いのよ!」
少女が握り拳を突き上げるように胸の前に翳した。黒犬が仰け反るような仕草を見せた。
――驚いた。ある意味素晴らしい発想だ。それで?
「簡単に云うとこうよ。がじちゃんが一瞬で屋根に上り、一瞬であの鳥を倒して、一瞬で森に戻る。もちろん誰にも見られない程の超スピードで。こうして人知れず町の平和を守るのよ! どう?」
――俺しか働いていないようだが?
「私はマネージャーなのよね」
――色々と云いたい事はあるが、一言で片付けるなら“無理”だ。
「どの辺が無理なのよ!」
――屋根に登るまでは容易い。だが、あの鳥を倒すのに一瞬では厳しい。屋根で本格的に戦闘を始めたら、どんなに眼の悪い奴でも気が付くだろう。
「じゃあ、こんなのは? 一瞬で屋根に上り、駆け抜けざまに鳥を攻撃して、一瞬でここに戻る」
――意味あんのか?
「それで追いかけてきたらさ、森の中で倒しちゃうの」
――挑発で膠着状況を打開するのか。それぐらいなら、まあやれるかもな。ただ、鳥が追って来たら町民も皆ついて来そうだが。
「森の反対ぐらいまで引っ張れば、鳥と人の速度差で何とかなるんじゃない?」
――人が追いつく前に倒して隠れろってか。ま、不可能ではないな。最悪町の外まで走れば良いか。
「よし、それじゃあ命令しちゃうよ! 私は公園のあたりで待ってるからね。頑張って!」
少女は両手の握りこぶしを胸の前に振りかざして気合を入れた。それから、とことこと公園に向かう道を駆けて行く。
――しかたねー。行ってくるぜ。
黒犬は渋々といった様子で命令を受諾すると、現場の様子を観察し、走行経路を頭の中に描き出した。
・
【NAME】は人ごみから少し離れた場所で屋根の上を観察していた。事態は相変わらず何の進展も無いようだが……。
(……ん?)
不意に、化鳥が何かを感じて顔を上げた。続いて、飛び立とうと翼を拡げた――その刹那。
バン、と軽い衝突音がした。けたたましい化鳥の鳴き声と共に、突然大量の羽根が宙に舞う。化鳥は激しくもんどりうってから屋根の半ばまで転げ落ちたが、すぐに屋根を蹴って空中で姿勢を制御し、改めて怒りの声を上げた。
突然の出来事に、下で様子を伺っていた見物人達は困惑の眼差しでお互いを見た。
「何だ? いきなり」
「誰か何か投げたか?」
誰もが理解不能といった声を上げる。
だが、【NAME】はとてつもない速度で屋根を通過した影を目で捉えていた。化鳥の片翼を貫く格好で屋根の上を駆け抜け、隣家を蹴って方向を変え、路地を飛び越えて姿を眩ました黒い影。
それは、犬の姿をしていたように思う。
飛び立った化鳥は暫し中空に留まった後、憩いの森の方角に顔を向け、耳障りな金切り声を上げた。
(……なるほど、そっちか)
いち早くその意図を察した【NAME】は、どよめく群集に先駆けて森へと走った。
これは、誘導だ。
化鳥は先の影を追うつもりだろう。そして、それこそがあの犬の、あるいはそれを使役した何者かの目的と見て、ほぼ間違い無い。だが、何故わざわざ森の方へ?
数秒の後、予想通り化鳥は憩いの森を目指して飛び立った。先に森へ向けて走っていた【NAME】を背後から易々と追い越し、化鳥は明らかな目的を持って一直線に飛び去って行く。
【NAME】は遠ざかる鳥の背を追い、全力で公園へと続く道を駆けた。
・
公園で待つ少女の許へ黒犬が戻った。同時に、例の鳥のものと思われる鋭い声が上空を近付いてくるのが聞こえた。
「やったね! 上手く行ったんだ」
――やったね、じゃねぇ。見られたぞ。目で俺を追った奴がいた。
「えー? 目にも留まらぬ速さで動いてよ」
――あのな。“目にも留まらぬ”ってのは言葉の綾だ。至近距離ならともかく、ある程度距離を取っていれば見えないなんてこたねーよ。大体、俺ぐらいの大きさと質量を持った物体が本当に認識さえできないような速度で動いてみろ。屋根はぶっ壊れるし、発生した乱気流で周囲の見物人みんな吹っ飛ぶぜ。
「失望しました」
――悪かったな。でも普通の人間なら“何かの影”程度にしか認識できてないとは思うぜ。
「そっか。だけど、影を見られたってのも良いかもね」
――何でだ?
「次々と凶悪事件を解決していく謎の影、なんて噂になった方が素敵じゃない?」
――勝手に云ってろ。それより鳥が降りてくるぞ。
公園の上空に姿を見せた化鳥は黒犬の姿を認めると、すぐさま降下して鋭い爪による攻撃を繰り出した。
黒犬は苦も無くそれを回避したが、反撃はせずに慎重に位置取りを確かめる。
――もう少し森の方に避難してくれ。そっちに攻撃されると面倒だ。
「判ってる!」
リサリサは答えて駆け出そうとしたが、大変なことに気付いて立ち止まった。
「うわ! 人が来たよ!」
公園の反対側を指差して大声を上げる少女。彼女の示した先には、駆け込んで来る【NAME】の姿があった。
・
森を抜け、【NAME】は公園に出た。
そこには先の化鳥に加え、黒い犬、それに【NAME】を指差して大声を上げる少女の姿があった。
(あれ、あの子は……)
見覚えのある少女だ。確か、ネーブブルグ遺跡で出会った迷子だ。……待てよ。そういえばあの時、黒い犬も見たような……。
記憶を辿る【NAME】の脳裏に、その時、別の誰かの意識が割り込んできた。
――場所を変えるか?
(……何?)
鮮明に浮かび上がる、何者かの言葉。いや、これは言葉ではなく、意図そのものか?
更に、平然とその声に答えるようにして少女が云った。
「もう遅いんじゃない? これ」
――仕方ねーな。先に鳥を片付けよう。
再び声が響く。まるでそこの黒犬と少女が会話しているかのように思えるが……。詮索は後にしよう。
取り敢えず化鳥を片付ける。声の主が誰であろうと、その点については同意できる。
battle
街を穢す妖鳥

手早く化鳥を始末し、【NAME】は改めて少女と黒犬に向き合った。
さて、どう切り出したものか。まずは声の主を確認すべきだろうか? と云っても、この場にいる顔ぶれから消去法で残るのは一人、いや一匹しか居ないのだが……念のためだ。
しかし、【NAME】が口を開くより先に、再びあの声が語りかけてきた。
――話の前に場所を移動したい。町の連中に見られると色々厄介だ。
思わず【NAME】は黒犬を見た。犬もまた【NAME】を見返している。その身体的特徴は狼に近いが、体躯は普通の狼よりかなり大きい。恐らくはキャペルウェイトか、それに類する存在……つまり、亜獣だ。
如何なる事情の下に亜獣と少女が行動を共にしているのか気に掛かるが、ここに町民が雪崩れ込んできては確かに面倒だ。
【NAME】は声の提案を呑み、人目につかない場所まで移動することにした。
・
――当然理解していると思うが、この声の主は俺だ。目の前の黒い犬だな。
公園を離れ、森の木立に隠れるようにして一行はささやかな会議を始めた。
【NAME】の予想通り声の主は犬だったようだが、当人からそれを告げられると何か感慨深いものがある。人以外の形態を持つ者が、こうして意思疎通を図ってくるのは珍しいことだ。
犬はお座りの姿勢で少女と並んで【NAME】と対面している。その頭は少女の肩の高さにあるから、結構な大きさだ。当然これは肉食獣だろうから、その気になれば少女を食い殺しかねない。正直、危険だ、というのが第一印象だった。
【NAME】の視線に警戒の色が宿ったのを悟ってか、少女が黒犬に縋るような仕草を見せた。
「この子は……悪い子じゃないの。本当よ」
――どうだかな。
黒犬がそっぽを向いた。少女がむっとした表情で犬に鋭い視線を投げかける。
「あのね、人がせっかくかばってるんだから、混ぜ返さないでくれる?」
――誰がいつ、お前にかばってくれなんて頼んだんだ?
黒犬が少女を振り返った。その青白い瞳は、炎のように静かに輝いている。だが、少女の方はその視線を平然と受け止め、全く臆した様子も無い。
「むっかー。大体なんでいつも“お前”なの?」と少女は黒犬に指を突きつける。
「リサリサっていう超可愛い名前があるんだから、それで呼んでよね」
――自分の発言の不気味さを理解してるのか? 俺がお前を何と呼ぼうが勝手だろ。それとも女王様とか主上とか呼ばせて悦に浸るか?
リサリサは一瞬本当に命令を下そうかと考えたが、思い留まった。命令さえすれば黒犬は嫌々呼んでくれるだろうが、それではあまり意味がない。ここで云われるまま命令しては敗北だ。
「可愛くないやつ!」
リサリサが噛み付きそうな顔を見せた。
――それで結構。かばう必要も無くなって丁度良かったんじゃないか?
あ、とリサリサは口に手を当てて、【NAME】の方を見た。自分が何のために話をしていたのか、今頃思い出したようだ。
【NAME】は半ば呆れながら少女と黒犬の問答を眺めていた。
「えっと……これはまあ、親愛の情の表現でして。本当は、良い子なんです」
決まり悪そうに微笑みながら、リサリサは黒犬の頭をなでなでした。
――“可愛くないやつ”だけどな。
「……良いから黙ってかばわれてなさいよ。これ命令よ」
じろりとリサリサが横目で黒犬を睨みつけた。
――ああ、冷静に考えると、かばってもらいたいような気がしてきたな。
「でしょ? 最初からそうしてれば良いのよ」
リサリサは両手を腰に当て、ふん、と鼻息をついた。
(……何なんだ? これは)
一人と一匹の奇妙なやり取りに、【NAME】は気抜けした。
単に仲睦まじいようにも見える。だが、どうも二人の力関係が不自然だ。明らかに黒犬の方が強大な生物なのに、なぜ少女はこれ程気安く接し、尚且つ主導権を握っていられるのだろう。黒犬自体の危険性はともかく、その辺りが気になった。
「ケチがついたわ。とにかく……そう、安全なの。だってこんなに可愛いくて無力な女の子が一緒でも平気なんだもの。退治したりする必要なんて、全然ないと思いませんか?」
少女が上目遣いに【NAME】を見つめた。これは恐らく、意図的な精神攻撃の一種だろう。冷静に考えると彼女の論理展開はやや強引であり、本人もそれを自覚しているが故の行動だと思われる。
「それに、理由があってこの子は私には逆らえないんです。何故かっていうと、制約の環だっけ? 初めて会った時に、二重安全機構? っていうのが働いて……」
――待て! それは教えるな。
何かを説明しようとした少女の言葉を、黒犬が鋭く遮った。予想外の反応に驚いた少女が、ぴくりと身体を震わせる。犬の語気は今までのふざけた調子とは打って変わった強いもので、有無を云わせぬ迫力を感じさせた。
「……どうして? これを説明しないと、納得してもらえないと思うんだけど」
――今は理由は云えない。だが、お前がもう少し賢ければ、自分で思い当たることができるはずだ。
「そうかな……。でも、だったらどうしよう。とにかく私の命令は絶対、ってことで……。ほら、お手だってできるし?」
リサリサが犬に向かって右手を差し出した。一呼吸おいて、黒犬が左前肢を少女の手のひらに重ねる。
確かによく訓練されている……と云って良いものか?
――水を差すようで悪いが、俺にはこの行為が意味が少々計りかねる。
従順にお手をしながらも、黒犬は今ひとつ釈然としない様子だった。
「犬の躾といえば、“お手”が基本なのよ。確かに意味はわかんないけど。反対の肢を乗せるのは“おかわり”って云うのよ」
――飼い主の自己満足かつ、支配関係を明確にするための儀式といったところか。
「お手ぐらいで大袈裟ね。おかわりもやってみようか」
(…………)
なんだか良く判らないが……。
一つ云えるのは、思ったほど危険では無さそうだ、という事だろうか。少なくとも、早急に対処が必要な類の緊迫感からは程遠い。それに、亜獣といえども、意思疎通できる相手を始末するのは余り気分の良いものではない。
結局、【NAME】は少女の熱意に絆される形で、黒犬の存在には目を瞑ることにした。
甘い判断。それが悲劇を生む可能性を孕んでいるとは知りながらも、今はこうしておきたい気がした。憂いの種があろうとも、芽吹く前からそれを摘み取るのは気乗りがしない。あるいは、彼女はこの亜獣と案外上手くやっていくのかも知れない。
もし、そうでなくなった場合には――その時こそ、この亜獣に対処することになるのだろう。
少女と黒犬 紅蓮の鳩
──紅蓮の鳩──
シレネから紫峯山を越えて続く街道、その最初の関門たる山間渓流を【NAME】は往く。
道の右手は遥か下の渓流を望む断崖絶壁で、落ちればひとたまりもない。充分な道幅があると判っていても、自然と誰もが左手の山肌に縋るような形で歩むことになる。一際道が細くなった箇所では鉄の鎖が渡してあり、これを頼りに進むことで己の恐怖心を抑えつける。実際には突風にでも煽られない限り鎖は不要なのだが、谷の高さを知っているとどうしても足がすくんでしまう。そこを越えればようやく谷を渡る吊り橋、山間渓流の中間地点だ。
多くの場合はこの辺りまでに猛禽類の襲撃を受けるのだが、今日は少し違っていた。
「そこで止まれ」
吊り橋に差し掛かったところで、対岸にばらばらと人影が躍り出る。橋の出口を塞ぐ形で集った男達。その中から、紅色の服に白い外套を羽織った剣士が一歩手前に出た。青年と呼べる年齢は過ぎ、壮年の前半といった風体。冒険者と云っても通じるなりだが、どうも同業者では無さそうだ。果たして、男は云った。
「我々は泣く子も黙る新進気鋭の山賊『紅蓮の鳩』。今日よりこの吊り橋では通行料が必要になる」
(…………)
自ら名乗るぐらいだから、本当に山賊のようだ。わざわざ新進であることをアピールする意味があるのか理解できないが、ともかく只では通れそうにない。
「大人しく有り金と荷を差し出すなら良し、さもなくば痛い目を見ることになるが、どうするかね?」
剣士風の男は吊り橋の向こうで大剣を片手に構え、【NAME】に切っ先を向けた。
無論、こんな連中に屈服するつもりは毛頭無い。見た限りでは大した相手でも無さそうだし、ここは逆に痛い目を見せてやるべきだろう。
【NAME】の意を察した男が不敵に笑うと、左手を翳した。後ろに控えた手下から、素早く二名が走り出て吊り橋に乗る。
「降伏する気はないか。ならば、己が不運を呪いながら絶望の内に息絶えるが良い!」
「多少はやるな、アラセマ軍の狗めが。少し本気で相手をしてやりたいところだが……急用を思い出した」
男は剣を納めると、白い外套を派手に翻しつつ背を向けた。
「今日のところはこれで見逃してやろう。だが、次は無いと思え!」
男が駆け出すと、それに続いて『紅蓮の鳩』の一行は見晴らし台へと続く方角へ走り去って行った。
(ふむ……)
【NAME】はその背を見送ってから、暫し思案した。
造作も無く追い払ったとはいえ、あの調子では近い内にまた出現するのが目に見えている。冗談みたいな連中だったが、あれでも山賊だ。場合によっては脅威に成り得る。
【NAME】は吊り橋の上から周囲の地形を確認した。
山賊に相対した者がここから逃げようとすれば、鎖の設えられた狭い道を戻るよりない。通い慣れた冒険者なら問題ないだろうが、ここを通る者が皆そうであるとは限らないだろう。
自分の身一つ守れない者は旅をすべきではない――そういう考え方もあるが、これで誰かが山賊の餌食になったり、更には逃げようとして転落でもされたら寝覚めが悪い。
少々手間だが、【NAME】は一度シレネまで引き返し、山賊の存在を報せておくことにした。
ええと、連中が名乗った名前は何だったか……。
・
シレネの片隅。街中にある南北に長い森の奥で、今日も少女は黒犬と密会していた。
「今回はこれよ!」
ばん、とリサリサが紙袋を突き出した。袋の口を開いて見せると、中にはビスケットらしき物体が詰まっている。
――なんだそれ。人間用の菓子じゃないのか?
「近所のおばちゃんに教えてもらって、犬用のビスケットを作ったのよ。今度は90%私の作品です!」
――急激にパーセンテージが上がったな。
リサリサが地面に皿を置き、袋を傾けた。円形、長方形、棒状、動物型、様々な形のビスケットが皿に注がれる。
黒犬はちょっと匂いを嗅いでから、バキバキと音を立ててビスケットを齧りだした。
「……どう? 紫ビーンズを刻んで入れてみたんだけど」
リサリサは黒犬の側に屈み込んで様子を見つつ、訊いてみた。
――こういうモノを喰うのは初めてだ。栄養価はともかく、優雅なおやつって感じだぜ。
黒犬が皿から顔を上げ、リサリサを見た。
――これは、美味い。
「そ、そうなんだ」
リサリサは何故か心中複雑な様子だった。黒犬は少女が会心の反応を見せるだろうと踏んでいたのだが、肩透かしを食らった格好になる。
――なんだその反応は? 自信の作品じゃないのか。
「うん。実は自分でもひとつ食べてみたんだけど」
――美味かったろ?
「ちょー不味かった! 歯が折れるかと思った。吐いて捨てた」
――不幸な奴だな。矢張り、人と獣が解かり合うことなど有り得ないのか……。
黒犬は無念そうにそう告げて、残ったビスケットに齧りついた。リサリサは紙袋を傾け、皿にビスケットを補充する。
「ビスケットぐらいで大袈裟ね。それより聞いてよ! さっき知ったんだけどね!」
――また亜獣でも出たか。
「え、亜獣じゃないけど……なんで判るの?」
――そりゃ、物凄く嬉しそうな顔してるからな。否応無く思い出させるぜ、あの化鳥の日の事を。
「そ、そう。まあそれは置いといて、町の北の方で山賊が出たらしいの!」
そう告げた少女の顔には、今度こそ間違いなく会心の笑みが浮んでいた。
――お前の考えてることは判るぞ……。
「それなら話は早い!」リサリサが黒犬の背をばふん、と平手で叩いて云った。「今度も頑張ろうね!」
――頑張るのは俺だけだがな。
面倒くさそうに黒犬が云う。リサリサはその頭をぐしゃぐしゃと、力いっぱい撫でてやった。
少女と黒犬 山賊を狩る影
──山賊を狩る影──
【NAME】が渓流に入るより、少し前のこと。照りつける太陽の下、崖の中腹を這う道を一人の少女が歩いていた。
少女は左手を山肌に添えて極端過ぎるほど道の左端に寄り、恐る恐るといった様子で足を踏み出して行く。
「こ、こわ……」
ちらりと右の方に目を向けて、リサリサが呟いた。崖の淵まではまだ大人が何人も並んで歩ける程の距離があり、冷静に考えれば躓いて転んだとしても充分安全な間合いがある。だが、想像力は容赦の無い恐怖を喚起した。この道に差し掛かった時、軽く眼下の渓流を覗いてみた彼女はそこに吸い込まれそうな錯覚を抱き、二度と崖下は覗かないと誓っていた。
少女は視線を左に戻し、次いで崖上を仰いで声を上げた。
「がじちゃん、来てるー?」
彼女の周囲には黒犬の姿はない。だが、少し遠くから彼の意思が返ってくるのが感じられた。
――居るよ。そんなことより、さっさと進め。
「ここ、遠回りでも、もっと安全な道を通すべきだと思うのよね……」
誰にともなくぼやきながら、少女は再び歩き出した。
・
リサリサが吊り橋に差し掛かると、数秒の後にばらばらと人影が対岸に現れた。
「そこで止まりな」
「はい。止まりました」
云われるままに橋の中ほどで止まる少女。その姿を目の当たりにして、出てきた男達は互いに顔を見合わせた。剣士風の男が一歩進み出て、ぽりぽりと頭を掻く。
「あー……お嬢ちゃん、何やってんだ? こんな所で。怪我する前に家に帰りな」
迷子になるにはおかしな場所だが、それ以外にこんな子供が一人で訪れる理由を、男は思いつかなかった。
「あの、失礼ですが、山賊の方ですか?」
「あ、ああ……確かに失礼だが山賊だ」臆した様子も無く妙な問いを返す少女に戸惑いながら、男は答える。「泣く子も黙る『紅蓮の鳩』とは我々の事……」
「ならば、天に代わって成敗致します!」
男の言葉が少女の台詞によって遮られた。年端も行かぬ少女に指を突き付けられ、男は目をぱちくりさせる。
「私じゃなくてこの子が!」
リサリサが左手の指を口にくわえ、指笛を吹いた。がらり、と少女の後方、崖の上あたりに何かの気配。男がそちらに視線を遣ると、遥か頭上から彼を見返す黒い影があった。
「犬……か?」
男は事態を把握できず、呆けたように呟きをもらす。次の瞬間、崖上の影が宙に躍り出た。
まっ逆さまに墜落するかに見えた影は着地の寸前で壁面を蹴り、吊り橋の手前に力強く降り立った。黒犬はそのまま少女の隣まで歩いて止まると、少し見上げる風に彼女の顔を覗いた。
――今の指笛、なんか意味あんの?
「かっこいいでしょ。この日の為に密かに練習しておいたのよ」
リサリサは再び指をくわえて軽くぴーぴー笛を鳴らすと、「涎出てきた」と口を拭った。
――あ、そう。普通に声聞こえてたんだけどな。
「こっちの方が雰囲気出るじゃない」
――然様か。とりあえず、さっさと皆殺しにして帰るとしよう。
駆け出そうとする黒犬。慌ててリサリサがそれを制止した。
「ちょっと待って! 殺人は駄目よ!」
――は? そんじゃどうするんだよ。
黒犬が振り返り、不満げな顔を見せた。
「圧倒的な実力を以って、全員生かしたまま武装解除するのよ!」
――無茶苦茶云うぜ。その後はどうすんだ?
「アジトまで案内させて、建物を完膚なきまでに破壊する」
――いや、それはマジで無理。
「じゃあ、アジトまで案内させて、場所を軍に通報する」
リサリサは渋々作戦を変更した。
――まあ、その辺が落としどころか。お前の腕力じゃ首領一人連行するのも不可能だしな。つーか、最初から軍に全部任せて俺らは帰ってれば良いんじゃねーの?
僅かな期待を込めて、黒犬が提案した。
「駄目よ。規律に縛られた大きな組織は、動きたくても中々動けない。だからこそ、根無し草のような冒険者達が各地で活躍するのよね」
――ち……変なところだけ理屈っぽいな。
「私も将来は冒険者になりたい。看護婦とかじゃなくてさ」
――ああ、それについては賛成だ。お前が看護婦になったところを想像すると、背筋が凍るぜ。
「失礼ね。でも冒険者って良いよね。ダスターさんとか結構格好良いと思わない? 憧れちゃうなあ……って、あ」
如何にもわざとらしい男の咳払いが聞こえて、少女と黒犬は吊り橋の先を見た。
「お取り込み中すまないが、そろそろ良いだろうか?」
「あ、良いです。お待たせしました」
――頼むからもう少し下がっててくれ。この地形はお前を守るには有利だが、絶対とは云えん。
「了解!」
リサリサがとことこ走って遠ざかる。男はそれを見送ってから、剣を黒犬に向ける。
「……お前達が何なのか私には今ひとつ理解できないが、我々は刃向かう者には容赦しない。生かしては帰さん、悪く思うな」
・
数分後、そこには見事に叩きのめされた山賊の一団が横たわっていた。だが、流石に全員の武装解除には至らず、起き上がった者は黒犬を遠巻きにして再び武器を構えていた。
――生かさず殺さずというのは、思ったより骨だな……。
黒犬が呟いた。極度に力を抑えているが故、攻撃を受けた山賊連中にもまだまだ余力がある。だが、それでも見せ付けた実力の差は彼らの戦意を削ぐのに充分だった。
頭領と思しき男が、剣を杖にして立ち上がった。
「ふ……。なかなかやるではないか、良く判らない小娘の飼い犬め。そろそろ本気で相手を……あん?」
男が背後を振り向いた。街道の向こうから新たな手下――禿頭の男が走り寄り、彼に何事か耳打ちする。
「……どうやら、我らが拠点で面倒事が起きたようだ。命拾いしたな。だが、次は無いと思え」
男は肩で息をして、白い外套を派手に翻した。
――こいつ、面白いな。
黒犬は男を攻撃するでもなく、追うでもなく、彼の様子をただ眺めている。戦いの終わりを知ったリサリサは吊り橋を渡り、犬の許まで駆けて来た。
「あの、アジトに帰るんですか? 一網打尽にします」
「うるさいな。ついてくるなよ。ちょっと本気で有事だからな。その犬と遊ぶなら他所でやれ」
剣士風の男が迷惑そうに云って歩き出す。
「冗談じゃなく危険ッスよ。何しろ、鬼が出たッス」
先ほど来た禿頭の男がリサリサに耳打ちし、すぐに剣士の後を追った。
「阿呆が、部外者に教えるな」
剣士が追いついてきた禿頭をばちん、と叩く。少女と黒犬が顔を見合わせた。
「鬼って云った?」
――云ったな。どうする?
「どうしよう?」
一人と一匹に見送られつつ、山賊達は己が拠点に向けて山道を早足に進みだした。
・
【NAME】が山間渓流の崖沿いを歩いていると、どこか遠くから指笛のような音が聞こえてきた。
例の山賊だろうか? 知らず、街道を進む脚が速くなる。
道は次第に細くなり、やがて壁沿いに鎖の繋がれた場所に出る。ここを越えれば、もう吊り橋だ。山賊の姿を探して視線を先に送った【NAME】は、吊り橋の奥に見知った姿を見つけた。
一瞬黒い塊のように見えたのは、犬だ。その側には犬とさして背丈の変わらぬ少女の姿があった。
(あの子は……)
誰なのか考えるまでもない。あの時の迷子、リサリサだ。更に先を見れば、何やら撤退していく様子の山賊たちの背があった。どうも、また余計な事に首を突っ込んでいると見える。
少女は暫しの間立ち止まって何事か犬と相談していたが、やがて前方に声を掛けつつ道を進んで行った。山賊の一味が振り返って何かを叫ぶ。
普通ならこれは緊迫した状況のはずだが、別に少女が誘拐されようとしている訳ではなさそうだ。むしろ、山賊の方が彼女を厭っているように見える。一行は紫峯山の見晴らし台へと続く街道を途中で逸れ、荒れた岩山へと踏み込んで行く。あの子は山賊の砦にでもお邪魔するつもりなのだろうか……。
少女と黒犬 対成す鬼
──対成す鬼──
結局、リサリサと黒犬は山賊を追って彼等の砦まで到達した。
山賊の首領と思しき剣士は何度も彼女らを追い払おうとしたが、実力では敵わず、黒犬の追跡能力を撒くことも叶わず、ついには諦めてしまったようだ。
悪路の果てにようやく行き着いた砦は半ば崩れ落ちた石造りの遺跡を利用したもので、お世辞にも立派なアジトとは云い難い。
「山賊って、随分ぼろっちい処に住んでるのね」
三割がた倒壊した外壁を前にして、リサリサが率直な感想を漏らす。壁の内側は所々草の茂った広場で、中心の建物以外にも、ごく小さな塔が三本程備わっている。
「雨露さえ凌げれば文句は無い。鬼が眠っているとは聞いてなかったがな。とにかくさっさと帰れ」
「鬼が出た、ってそんなに大変なことなの?」
――ひと口に鬼と云っても色々だ。大禍鬼が出たなら大変どころの騒ぎじゃねー。だが、こんな連中が現場でのうのうと生き延びているということは、相手の程度も推して知るべし、だ。
「こんな程度で悪かったな。我々に取っては一大事だ」
剣士は歩きながら黒犬を一瞥した。黒犬は興味深そうに男を見返す。
――最初から疑問だったんだが、お前は俺が何故会話できるのか、とか気にならないのか?
「気にしてどうする? 訊いて欲しいのならそう云ってくれ」
――気付いていないようだから教えてやるが、俺は人間じゃない。
「道理で少し毛深いと思ったぜ。だが正味問題無い。お前らが何か訳ありなことぐらいはすぐ判る。山賊なんかやってる連中は一人の例外も無く訳ありだ。だが、我々はお互いそんなことを詮索したりはしない。重要なのは過去や生い立ちではなく、これから何を成すか、という点だ」
――面白いが、山賊が云うといまいち説得力が無いな。
「我々『紅蓮の鳩』は平和を愛する山賊なのだよ。軍の連中とは愛し方が違うだけだ。例えば、もしお前達が町を追われるような立場になれば、その時は仲間として迎えてやらんこともない」
男は本気とも冗談ともつかない口調でそう云った。黒犬がリサリサを振り返る。
――聞いたか? 良かったな。落ち延びる先ができて。
「そうなったら、私はまるで肥溜めに咲く一輪の花ですね」
「せめて掃き溜めにしてくれないか。肥溜めには花は咲かんだろ」
「……よし、決めた!」
リサリサが唐突に声を大きくした。少女の様子からある種の気配を察した黒犬は、何ともいえない複雑な表情を見せた。
「義によって助太刀します! 私じゃなくてこの子が!」
びし、と少女が黒犬を指差した。
――そうくると思ったぜ。
「別に事情を詮索する訳じゃないんだが、お前達は一体何をやりたいんだ? 我々を殲滅するのが目的じゃなかったのか」
――この娘は馬鹿なんだから仕方ない。それに、突然チカラを手に入れた人間がとち狂うのは良くある事だ。
遠くを見るような目で黒犬が答えた。その表情に浮んでいるのは、諦観の念だろうか。
「まあ、鬼退治をしてくれると云うのなら、我々としては断る理由は無い。私は『紅蓮の鳩』の首領、ルドラ・フランツだ。無論、私とてただ見ているつもりは無い」
「私はリサリサ、この子はがじちゃんです」
「よろしくな、リサガジ」
――勝手に名前を繋げるな。気色悪い。
「照れちゃって!」
顔を顰めた黒犬を見て、リサリサが楽しそうに云った。
――なんでお前まで喜んでるんだ。
「難事件を次々と解決して行く謎の冒険者リサガジ。その正体は、一人の美少女と忠実なる黒犬のコンビだったのだ」
――段々、お前の妄想力に付いて行くのが困難になってきた。
「冗談はその辺にして、内部の様子を見てくるか」
云って、男は己の剣を構えた。黒犬は男の様子を見て、ため息を一つ漏らす。
――正直なところ、お前の実力では足手まといにしかならねーぜ。
「ふん、あれが私の全力だと思ったか。今度は本気だ。相手が鬼なら遠慮は要らん」
――おいおい、本当に本気じゃなかったってのか?
黒犬が目を剥いた。己に相対した者が、それも明らかに格下の者が、手加減をするなどとは考えても居なかった。しかし、どうもこの男は本気なのかふざけているのか、はっきりしない所がある。
「当然だ。我々『紅蓮の鳩』は平和を愛する山賊。人や家畜相手に本気は出さん」
ルドラは薄く笑う。リサリサはそれを聞くと胸の前で両の掌を合わせ、目を輝かせた。
「凄い! かっこいい! 本番では重りを外したりするんですか?」
「なんだそりゃ?」意味が判らない、といった様子のルドラ。「重りなんかつけてたら、腰を痛めるだろ」
リサリサの目の輝きが急速に失われていった。
「……失望しました」
その時、ぐらり、と軽微な揺れが地面を走った。下方から何かが崩れるような音。続いて、助けを求める声が砦の中から聞こえてきた。
黒犬とルドラは外壁を越え、砦の中に踏み込んだ。入れ替わるようにして、中から山賊が二人走って外に出た。リサリサは砦の入口に身を寄せ、外から中の様子を窺った。
建物内の石畳はひび割れ、歪んで波打っている。その一部は崩れ落ち、ぽっかりと穴が開いていた。穴の底は暗く、どのぐらいの深さがあるのか一見して掴めない。
「床が……地下があったとは」
――退がれ。上がって来るぞ。
床下から大気を揺るがす咆哮が響いた。続いて、だん、と建物を震わす振動。次の瞬間、黒犬の言葉通り鬼が眼前に姿を現した。穴の底から軽々と跳躍し、石畳の上に降り立ったのは赤と青、対照的な肌の色を持つ二体の鬼。
鬼達は天井や床、眼前の人間と犬を順次見渡し、冷静に状況を検分している。
「え……二匹……」
外から見ているリサリサが呟きをもらした。
――二匹か。多少骨が折れるが、何とかなりそうだな。
「本当?」
黒犬は相手を観察する。予想通り、大禍鬼や禍鬼のような強烈な存在ではない。赤と青、特徴的な、対を成す二体。おそらくは防御面で相互に得手不得手を補い合うタイプだろう、と見当をつける。
右の青い奴は明らかに物理的な防御が脆弱で、属性防御に特化している。対して左の赤い奴はその逆。ならば、まずは自分のやりやすい相手を無力化してから、残りを片付ける。
――こいつからだ。
黒犬が床石を蹴った。右の青い鬼に向かって矢のように走り、その喉を喰い千切るべく、飛び掛る。
至近距離ならば文字通り目にも留まらぬはずの一撃。しかし全力を籠めた黒犬の攻撃は、鬼の身体を掠めることすら叶わなかった。
――何!?
青い鬼の身体は中心から有り得ない角度に折れ曲がり、黒犬の攻撃を完全に回避していた。なまじ人に似た姿をしているが故に、それは予測から外れた動きだった。
砦の石壁を蹴り、空中で姿勢を整えて黒犬が着地する。攻撃を回避された以上、見せざるを得ない一瞬の隙。その一点を最初から狙っていたかのように、赤い方の鬼が爪を振り下ろす。
砦の暗がりの中に、血飛沫が舞った。
「がじちゃん!」
黒犬は脱兎の如く飛び退り、再び鬼と間合いを取っていた。持ち前の反射神経と強靭なバネで窮地を脱した黒犬だったが、鬼の爪を避けることは叶わなかった。致命傷こそ負わなかったものの、左脇腹から後肢にかけて二筋、大きく肉が裂かれている。あふれ出る血液は黒い毛並みをじっとりと濡らし、てらてらと光らせていた。
――成る程……こいつら、見た目と反対だ。
左前肢に散った自らの血液を舐め取り、黒犬が呟いた。防御の弱そうな青が“技法回避”専門、頭の悪そうな赤が“術式回避”専門。一見して判る防御面での差異は誘いの罠、という仕組み。
ふざけた奴らだ、と黒犬は独りごちた。
体毛を重く濡らした血液が、ぼとりと零れて床石の上に水溜りを作る。
リサリサが声にならない悲鳴を上げた。砦の中に駆け込もうとする彼女を、即座に黒犬が制止する。
――入ってくるな。お前がいると余計にヤバイ。
「でも、血が……」
――黙ってろ。
反射的にそう突き放してから、黒犬は自分の頭に血が上っていることを自覚した。
自分の身体を傷付けられたことに対する怒り。そしてそれ以上に、相手を軽視して見事に術中に嵌った自分の軽率さに対する憤り。
黒犬は一つ深呼吸をして、自制心を取り戻す。これ以上の失態は、それこそ許せない。
――悪かった。一旦外に出よう。
「そうだな。砦が崩れたら危険だ。嬢ちゃんはうんと遠くに行ってろ」
リサリサが無言で頷く。ルドラは二体の鬼に剣を向けたまま、じりじりと後退を始めた。
・
【NAME】は山間渓流を抜けた時点で、街道から外れた。
見晴台の方には向かわず、わざわざ荒れた岩地へと足を踏み入れる。進む先は山頂方面とは反対で、渓流を外側に大回りして麓へ戻るような形になる。
既に山賊達の姿は無い。だが、それと知って観察すれば、岩地に人が歩いた形跡があるのは明らかだった。
岩地に残された痕跡を追って進む内、遠くから誰かの叫び声が【NAME】の耳に届いた。ほんの僅かだが、何かの振動が地面を伝わって来たのも感じる。
(……何だ?)
向かう先は山賊の砦のはず、それなのに、妙に厭な気配を感じる。捩れた概念。穢れた存在。それはまるで、鬼の気配だ。
やがて、荒地の先に半ば崩れた石造りの砦が見えてきた。外壁付近には数人の山賊の姿もあったが、奇妙な事に皆一様に砦の中に注意を向けている。
どうやら、外から接近する者より中を気にしなければならないような事態が起きているようだ。
【NAME】は砦までの距離を一気に駆け抜け、外壁の切れ目に立った。山賊たちは途中でそれに気付いたが、もはや誰も【NAME】の接近を止めようとはしなかった。
壁の内側を見る。
歪んだ石造りの砦。それを取り巻く数名の山賊と、黒く開いた入口に向いて立つ剣士と黒犬。そして敷地の片隅からそれを見つめる少女。
衆目の中、縦に長い砦の入口からソレが無造作に姿を現した。矢張り、先ほど感じた気配は間違いではなかった。鬼だ――それも、二体。
だが、直に姿を眼にして感じるその気配は大禍鬼のような強大な物ではない。この程度なら、人の身であっても充分勝ち目はある。
――よお、また会ったな。
匂いでもしたのだろうか。黒犬が【NAME】の方を軽く振り向いて目配せした。いつも通りの軽い調子だが、犬の身体に刻まれた痛々しい傷は遠目にも良く判った。
「ルドラさん、この人も頼りになります!」
黒犬のその声で【NAME】に気付いたリサリサが、剣士に大声を掛けた。
「加勢なら誰でも大歓迎だ。来るぞ」
ルドラと呼ばれた剣士が背を向けたまま云った。何が何だか判らないが……鬼を前にしてやるべきことは、一つしかない。
battle
対成す鬼


二体の鬼が地に臥した。地面に衝突した鬼の身体は腐肉の如く融解し、湿った音を立てて体組織を撒き散らした。それが形を留めていたのも僅かな時間でしかなく、やがて鬼の肉体は自重で崩れ去るように溶けて広がり、地面に黒い染みだけを残して完全に消え去った。
「がじちゃん! 大丈夫!?」
リサリサが黒犬に駆け寄る。鬼の爪で刻まれた傷からは、まだ血が流れ出ていた。
「おい、誰かこの犬の手当てをしてやれ」
――必要ない。舐めときゃ治る。
「遠慮するな。こんな連中でも応急処置ぐらいはできる。ダフ、お前が良いだろう」
ルドラの指示を受け、禿頭の男が中心の砦とは別の小さな塔へ駆け込んだ。幾らも待たない内に、男は水桶とガーゼを持ってきて犬の傷口に応急処置を施し始める。
傷口を水で洗われた黒犬は顔を顰めたが、特に文句も云わずされるがままになっていた。禿頭の男はこういう処置に慣れているのか、手際良く傷を清め、大量のガーゼを当てて包帯で固定した。
「これで血が止まれば平気だと思うッス。ちょっと傷が深いから、本当は縫った方がくっつきが良いかも知れないッス」
――それこそ必要ない。もう充分だ。
「あの、有難うございます」
「礼を云うのはこっちの方ッス。正直自分達だけではあの鬼の相手はできなかったッス。助かったッス」
リサリサと禿頭が互いにぺこぺこ礼を交し合う。
「そっちの助っ人にも礼を云うべきかな? ……と思ったら、お前はあの時の冒険者じゃねーか。どうなってんだ?」
「どうなってるんでしょう?」
ルドラの疑問に、リサリサも続いて首を傾げた。
(…………)
どうなっているのか聞きたいのはこっちの方なのだが……。
・
【NAME】は今日起こった事態について、ルドラとリサリサから一通りの説明を受けた。黒犬はその間、もっぱら茶々を入れる役に徹していた。
少女が山賊退治を企てたこと。山賊の後を追って砦までやってきたこと。そして、何の脈絡もなく少女が鬼退治を申し出たこと。
説明された少女の行動には一貫性が無く、支離滅裂なものだった。しかし、本人もそう云っているのだから信じるよりない。
ついでに、犬の名前ががじちゃんだという事も教えてもらった。そういえば前に会った時はお互い名乗らなかった気がするので、【NAME】も自分の名を告げておいた。
後はこの山賊砦をどう扱うかだが……。
「それじゃ、私は帰ります。この場所のことは、しっかり通報しておきますから!」
リサリサは臆面もなくそう云った。自分から山賊を襲っておいて後から助太刀し、最後にはやっぱり通報するらしい。
「さっさと帰って軍にでも何でも報せるが良い。場所を知られた以上、どうせこの砦は早晩放棄する」
事実、周囲の山賊たちは誰に云われるでもなくテキパキと動き回り、既に撤退の準備を始めているようだった。
「お嬢ちゃんの方はこれ以上余計な事に首を突っ込まないことだ。お友達がそういう目に遭うのが厭ならな」
ルドラが顎をしゃくって黒犬を示す。包帯を巻かれた犬の姿を見て、少女は小さく肯いた。真っ白だった包帯には、微かに血が滲んで浮き出しつつある。
「ダフさん、がじちゃんの手当てを有難うございました。【NAME】さんも加勢してくれて助かりました」
「気をつけて帰るッス」
「山賊の皆さんもお元気で。もうシレネの近くには出てこないで下さいね!」
リサリサは禿頭を含む数名に見送られながら、黒犬を従えて町へと戻って行く。途中で一度だけ振り返り、大きく手を振った。何人かの山賊がそれを見て手を振り返す。
一見普通のお別れだが、手を振っているのが山賊だということを考慮すると実に間抜けな光景だった。
「我々に向かって『お元気で』は無いだろ」
ルドラは少女の背を見送りながら、思い出したように苦笑して【NAME】を振り向いた。
「あのお嬢ちゃん、ちょっと拙いな。好く云えば無邪気だが、悪く云えば馬鹿だ。あの位の歳で恵まれた暮らしを送ってきたなら仕方が無いかも知れんが、人の悪意に関して想像力が欠如している。例えば、我々が砦に戻ったのは罠だったかも知れない。あるいは、この禿は手当てのふりをして犬に毒を塗ったかも知れない」
「塗ってないッス」
禿頭の男が答えたが、ルドラは無視して先を続けた。
「そうした可能性について、最初から一切考えてもいないのが問題だ。あの犬が保護者をしている間は平気だろうが、まだ何かやらかしそうな気はするな」
そんな事を話している間に、リサリサと黒犬の姿は見えなくなった。何となく少女を見送っていた山賊達も、三々五々各自の作業に戻って行く。
ルドラは無言で軽く片手を上げると、【NAME】に背を向けた。それは別れの挨拶だったようで、彼はそのまま振り返りもせず砦の中へと歩み去ってしまった。
(さて……)
この山賊達を更に追及するという手もあるのだろうが、どうも今ひとつ気乗りしない。元々個人的には然程脅威に感じていなかった所為もあるだろう。砦の所在についてもリサリサが軍に連絡するようだし、それに任せて放置とするか。
実にくたびれ損な結果になったが、とりあえず【NAME】は街へと戻る事にした。
少女と黒犬 過去からの亡霊
──過去からの亡霊──
憩いの森の奥、町の者が訪れることのない死角。そのささやかな安息の地には、今日も少女と黒犬の姿があった。
黒犬は身体の左側を上にして横たわっている。リサリサはその脇に座って犬の身体に手を添えた。
いつもより体温が高い。呼吸も浅いし、時折身体中の筋肉が震えている。
「熱があるし、震えてるよ……ねえ、大丈夫?」
――お前医者の娘だろ? 外傷に対する正常な防衛反応だ。自力で快復できる。
「まだ、血が滲んでる」
山賊に巻いてもらった包帯を解いて、血糊で張り付いた赤黒いガーゼを静かに取り除く。顕わになった傷口はまだ塞がってはいないが、既に僅かに肉が盛ってきていた。
「切り傷は洗った方が良いってお父さんが云ってたんだけど……どうしよう……」
家から勝手に持ち出してきた洗浄用の水が入った瓶や、使い方が良く判らない綿を取り出して少女が戸惑う。
――ほっとけ。この程度なら自然に治る。それよりむしろ、お前に処置される方が怖い。
「薬要る? 病院の人呼んでくる?」
――呼ぶな。逆に殺される。薬もいらねー。
「……痛い?」
――そりゃな。だが俺は人間ほど痛みに敏感じゃないから、お前が想像するような恐ろしい痛さとは多分違う。
「え!?」少女が驚いて目を剥いた。「人と犬って感じる痛さが違うの……?」
――当然違うだろ。人間は特別痛がりだ。後は基本的に強い武器を持つ者は痛みに敏感で、捕食されやすい連中は鈍いのが多いように思う。まぁ単に我慢強いだけかも知れんが。
「へぇー……」
リサリサは少し感心した。自分と他者で痛みの感じ方が違うなどとは考えたことも無かった。傷と痛みの概念は、彼女の中では分かち難く一体化していたからだ。同じ傷を受ければ誰もが同じように痛いのだと、リサリサは深く考えずにそう信じていた。
黒犬が起き上がり、自分の負っている怪我を目で確認する。
「でも、なんで強い方が痛がりなのかな。なんか逆っぽい気がするけど」
――殺傷能力の高い者は、ある程度痛みに敏感でないと正常に生育できない。なぜなら、自分の武器の使い方を覚える過程で自分自身を殺してしまうからだ。戦いの場では痛みが不利になる場合もあるので、強い者が必ずしも鋭敏な感覚を持っているとは限らないが。
「なるほど! こんな事まで知ってるなんて、がじちゃんは博識だね!」
当たり前の知識なのかも知れなかったが、傷の痛みを紛らわす意味も籠めて、とりあえず褒めてみた。
この犬が賢いことは判っていたが、本当に色んな事を知っているとリサリサは思う。日頃からこうした事柄について思索しているのだろうか。それとも、リサリサ自身が特別馬鹿なだけで、みんな当然のように理解している事なのだろうか。
リサリサは黒犬が嬉しそうに自分を馬鹿にするだろうと期待した。しかし、彼の声は明るくはならず、逆に翳を増して返ってきた。
――忘れたか? “制約の環”は痛みで対象を制御する。つまり、これを作った連中は痛みの専門家だ。俺はそいつらとずっと一緒に居たんだ。
「そうでした。周りに先生がいっぱい居たんだね」
――鬼や亜獣の痛みの感覚など誰も知らなかった。それが具体的にどう違うのかを比較するのも、難しい。
「他人の痛みは判らない?」
――その通り。だから連中は実験を通じて知る必要があった。人でない者にどのような痛みを与えれば、効果的に苦しむのかを。そのために随分多くの試行があった。
リサリサは思わず息を呑み、片手で口を覆った。
この犬の過去があまり楽しいもので無さそうな事は気が付いていた。だけど、それが具体的にどんなものだったのかは、全く想像すらしていなかった。
そんな話を聞き出したい訳じゃなかった。そんな事を思い出させるつもりじゃなかった。
リサリサは手を下ろして何かを云いかけたが、それは言葉にならず、また口を噤んでしまう。
――あぁ、要するに……この程度の傷や痛みは全く問題にならないと、そういうことだ。
少女が泣き出しそうな顔を見せた所為か、黒犬は珍しく繕うようなことを云った。
・
【NAME】は憩いの森に幾度目かの訪問を行った。
この森は町民の憩いの場であり、あの時の女の子と黒い犬が隠れ家代わりに使っている場所でもある。ただし、後者について知っているのは今の所、【NAME】ぐらいかも知れない。
今もあの子と犬は、この森の何処かで一緒に居るのだろうか。
(おっと……)
どうでも良いことに思いを寄せながら周遊道を歩いていると、珍しく他人に出くわした。
前方から歩いてくるのは、女性と見紛うような綺麗な金髪を腰まで伸ばした優美な男だった。男は緑を基調にした街着に身を包み、登山者や狩人が好みそうな羽根つき帽子を被っている。
線が細く、余り身体を鍛えている風ではないが、歩き方を見ればある程度の実力は掴める。この男は多分、冒険者か何かだろう。武器を携えているようには見えないから、専門は多分術式か、と見当をつけた。こんな場所でも無意識にそんな観察をしてしまうのは、職業病と云えるかも知れない。
男はゆっくり歩きながら朱色の瞳で森の奥を眺めていたが、【NAME】とすれ違うより前に、不意に立ち止まった。
(は……?)
そして、金髪の男は【NAME】の見ている前で90度右を向くと、そのまま道を外れて森の中へと踏み込んで行った。
・
「だけど、どうしてこんな仕組みになったのかな」
呟くようにリサリサが云った。彼女は乾いた地面を払って腰を降ろし、両脚を手で抱え込むようにして座っている。黒犬の方は彼女と向かい合ってお座りの姿勢で話を聞いていた。
――仕組みって、何がだ?
「環の二重安全機構? ってやつ。主人が居なくなったら手近な人を勝手に認識しちゃうなんて、結構いい加減だよね。私なら最初から『誰であれ人間は攻撃できない』とかにするよ。これでも暴走防止になるよね?」
――連中が皆お前みたいに幸せな奴だったら、そうしたかも知れない。
「駄目なの? 良い考えだと思うんだけど」
――勿論、駄目だ。
「どこが?」
少女の無邪気な質問に、黒犬は素っ気無く答える。
――その仕組みでは、人を襲うのに使えない。また、“食事”にも制限が掛かる。
「え……」
――そうした用途は当然最初から考慮されている。事実、お前も俺を使って人間を襲った。
「あれは!」リサリサは言葉を詰まらせた。「……だって、山賊だったし」
――同じだ。
少女は俯いて唇を噛んだ。あの日取った自分の軽率な行動の意味を、今更ながらに理解した。
そうか。自分は亜獣を駆って、人間を襲撃したのだ。その事実の認識が、今頃になって少女に重くのしかかってきた。
「でもでも、他にもっと良い方法がある……と思う」
――確かにな。恐らく、本当は主人が居なくなった瞬間に絶命するようにしたかっただろう。だが、鬼に対して適用することを考えると、そこまで強烈な効果を発揮するものはまず作れない。そんなことが可能なぐらいなら、最初から行動を完全支配できただろう。だから“制約の環”は次善の策の積み重ねで成り立っている訳だ。
「また、気が滅入ってきた」
――別にお前が滅入る必要ねーだろ。環を作った連中にその脆弱な精神を分けてやりたいな。
「うん……でもさ、その人達って多分もう居ないんだよね? 随分時間が経ってるんでしょ?」
――ん? ああ、確かに、全員死んでるかもな。
「それだと環の外し方はもう判らないって事にならない?」
――なるな。連中の幽霊でも出て来てくれれば解決するんだが。
「ちょっと、気持ち悪いこと云わないでよ」
リサリサが眉をしかめたが、黒犬はさも当然のことであるかのように続けた。
――いや。死者の存在概念が不安定な状態で残るってのは、そこまで珍しい事じゃない。いわゆる概念残滓ってやつだな。
「ええ? やめてよ。本当に?」
――ただ、会話ができる程高度な状態で残ることは通常有り得ない。仮にあったとしても、自然現象ならすぐに不安定になって消える。
「駄目じゃん」
――まあ、率直に云って駄目だな。
そう云いながらも、余り深刻そうに見えないのは黒犬がこの状況を甘受し始めている所為だろうか。だったら良いのだけれど。
リサリサがそんなことを思った時だった。遠くない場所で、がさり、と落ち葉を踏みしめる音がした。
弾かれたように少女が音の方に顔を向ける。傾いた陽の中、木立の中に立っていたのは見た事のない男だった。微かな風が木立を抜け、男の長い金髪をさらさらと梳く。
「あ……」
驚いて立ち上がるリサリサ。黒犬は男を一瞥すると大きく息を吐き、これ見よがしに厭そうな顔をした。
男は目を細めて黒犬に視線を送ると、
「久しいな。息災だったか? “ワン公”」
そう言葉を放った。
・
突然現れ、犬に語りかけた男を見てリサリサは混乱した。
「どうして……がじちゃんの事を……」
男はそれにも答えず、ただ黒犬を見下ろして彼の返事を待っていた。
――お前が近付いているのは判っていた。こんな忌々しい匂いは、あまり無い。
「こんな時は、素直に再会を喜ぶものだ」
――できれば勘違いであって欲しいと祈っていたのだが、どうやら本物らしい。どうなってんだ? 死んだんだろ?
「何故だ? 悪いが至って健康だ。短命な同僚達は概ね土に還ったが」
――お前の寿命が尽きる程には時間が経っていなかったのか。これは、非常に残念だと云わざるを得ない。
リサリサは会話の内容についていけず、ただ目を白黒させて男と黒犬を見比べた。
――だが、生きているなら何故俺の支配を解除している? 実は幽霊だと、今からでも云って欲しいところだが。
「その話は後にしよう」
男はたおやかな手を翳して黒犬の言葉を制し、「この娘は何だ?」と、ようやく犬の脇に居る少女の方を見た。
「あ、えと、私はリサリサ・ネックベットといいます。あの……がじちゃんとお知り合いなんですか?」
リサリサは思い切って男に訊いてみた。
「がじちゃん?」
男が不思議そうな顔で反復した。
――このすかした男はアーデルハーン・メリァルーダという。簡単に説明すると、俺の前の支配者だ。
黒犬が男に代わって説明を加える。男はようやく得心したような表情を浮かべた。
「ああ、“がじちゃん”ってお前の名前か。なかなか素敵な名を賜ったじゃないか。つまり、この子が今の支配者ということか」
金髪の男――アーデルハーンが云った。その名前は、どこかで聞いた覚えがある。リサリサは記憶を辿り、それを思い出した。
「あの……アーデルハーンさんって、遺跡の発見者の?」
リサリサの問いに、アーデルハーンは軽く首肯する。
「そういうことになってるね」
やはりそうだった。初めてネーブブルグ遺跡に遊びに行った時、第一発見者はアーデルハーンという冒険者だというような話を聞いた記憶が、リサリサにはあった。
――待て。お前が遺跡の発見者だと? どういう事か説明してもらおうか。
「構わないが、その前にこの子には外してもらいたい。俺についての情報は余り広めたくないし、第三者が居ない方がお前も素直になり易い」
――まあ、その方が良いだろう。
黒犬はリサリサに首だけを向けて、続けた。
――悪いが今日は帰ってくれ。俺は少しこの糞野郎と話がある。
「良く判らないけど、大丈夫なの?」
リサリサが黒犬に問う。が、間髪入れずにアーデルハーンがそれに応えた。
「心配してくれて有難う。だが、俺はこの犬の扱いに慣れているから問題ない」
――素で云ってるのか? こいつが心配しているのは俺の方だ。
「冗談だよ。犬には少し高度過ぎたかな」
アーデルハーンは口の端を歪めて嘲るような笑みを浮かべている。
――あ、そう。俺もこの馬鹿の扱いには慣れているから大丈夫だ。それより、お前にまでこの男の狂気が伝染すると困る。今は大人しく帰ってくれ。
「了解! 危なくなったらすぐ呼んでね!」
――あのな。俺の危機にお前を呼んで何かの足しになるのか?
「良い子じゃないか、リサリサちゃん」アーデルハーンは失笑した。「心配するな。俺はただ、くじ引きの結果を確認しに来ただけだ」
「……?」
くじ引き?
リサリサには男の云う意味が全く判らなかったが、これ以上追求するのは止めて森を離れることにする。
黒犬に迷惑をかけるのは厭だったし、それに、実を云うと男の朱色の瞳が少し怖かった。
・
「少し変わったな。昔ほど荒んだ感じがしなくなった。あの子の影響だとすれば、良い巡り合わせだったと云える」
少女が立ち去るのを見届けもせず、アーデルハーンは語り始めた。
――お前以下の主人など存在しようが無いから、必然的に巡り合わせは良くなるな。
黒犬が憎まれ口を挟んだが、アーデルハーンは慣れた様子でそれ受け流すと、淡々と先を続けた。
「お前は精神的なバランスに少し問題があった。知識面では優遇されていたが、情操教育が欠けていたせいだな。思春期の少年みたいなものだ。まあ面白いからそれで良いと云ったのは俺なんだが、子供に飼わせるというのは案外良い改善方法かも知れない」
――どこが良い方法なんだ? 俺はあいつの奴隷でありながら、同時に保護者でもあるという困った状況に陥っている。
「それは、素晴らしい」
――頭でも打ったか? 今『素晴らしい』と聞こえたが。
「絶対的な弱者に触れる経験が、お前には必要だった。犬には多少難解だろうが、あの子と接する中でお前が育んでいるのは、ある重要な情念の萌芽だ。人はそれに特別な名前をつけて大切にしている……その呼び名を教えてやろうか? 凡そあらゆる言語において、その情念を表す単語は存在する」
――呆れが礼に来るとはこの事だ。お前のそうした発言にも素敵な名前がついているので教えてやろう。それは“妄想”とか“寝言”と呼ばれるものだ。ただし、これらは特に大切にされている様子はない。
「犬にしては良い切り返しだ」
アーデルハーンは内心で会話を愉しみつつ、努めて淡々と続けた。
「しかし、自身の内面の変化を自覚したことでまた一つお前の感受性は先へと進む。更なる展望を見据えて今の内に忠告してやるが、異種交配は色々と無理があるから止めておけ。猫がアヒルの子を産めないように、あの少女がお前の仔を産むこともまた不可能だ。どうしても試してみたいと云うのなら、別に止めはしないが」
云って、アーデルハーンが薄笑いを浮かべる。黒犬の口の端が引き攣った。
――どうやら、お前は俺に殺されたくてここまで出向いてきたらしいな。
黒犬が四つ足で立ち上がって牙を剥いた。だが、アーデルハーンは些かも慌てることなく、穏やかに眼を細めて微笑を返す。
「冗談だ。からかい甲斐のあるところは変わっていないようで、安心した」
――そんな下らない事を云うためにわざわざ来たのか?
「実は、その通り。今のでもう用件の半分は済んだ。矢張り、お前を弄るのは面白いよ」
――それなら今度は俺の番だ。遺跡の発見者とはどういうことだ?
「言葉通りの意味だ。俺がネーブブルグの扉を開き、その在り処を町民や軍人どもに報告してやった」
――意図を掴みかねるな。遥か昔に廃棄したんだろ? 何故今更戻ってきて『発見』する?
「我々の研究を陽の目に晒したい……という訳ではない。謂わば、一種の遊びだ。敢えて言葉で表現するなら、『芯なる者の気分を味わうため』といった辺りか。知っての通り、“芯なる者”は現在地上には存在しない、とされている。だが、連中の影響は未だに各地に色濃く残っている。その最たるものが、お前達“亜獣”の存在と云えるだろう」
――あーあ。語り始めたよ。
「連中は非常に高度な知識と技術、そして豊かで蠱惑的に歪んだ想像力を駆使して、意味不明な生物を無数に生み出しては無責任に野に放った。何故だと思う? 無論、奴ら自身が楽しむためだ。何を愉しむか。思うに、それは超越的な立場からの観察だ。己の力が及ぼす影響をつぶさに確認しながらも、自身はその外側に立つという形だな」
――くだらねー。
「自らの投じた一石が、鏡の如く澄み切った水面に大きな波紋を広げていく。それを眺めるのは中々の愉悦だ。投じた石が実は爆弾だった場合には、より一層愉しめる」
――お前が好きそうな話だ。つまり俺は、お前が投げた爆弾ってわけか。
「まあ、そんなところだ。ただし、用意したのはお前だけじゃない」
――何?
「くじ引きだと云っただろう? 当然『あたり』と『はずれ』がある。片方は既にあの子が引いた。つまりお前だな」
――ち……。俺は貧乏くじ扱いかよ。
「もう一方も近い内に引かれるだろう。何が出てくるかは、見てのお楽しみだ。多分、お前も立ち会うことになる」
――どうせ『あたり』は後期被験体の鬼だろ。大体予想がつく。
簡単な推測だった。自分より古い被験体は殆ど死んでいる。ならば、もう一方はより後期の被験体――実際に鬼種に環を植え付けたものに決まっている。
それがこの男の云う『あたり』なのだろう、黒犬はそう考えた。ネーブブルグ遺跡の地下には、鬼の為に用意された専用の部屋があったはずだ。
「つまらんな。ほぼ正解だ。ま、後は楽しく観察と行こうじゃないか。これは損得勘定などの介在しない、純然たる好奇心だ。お前にもこうした高度な感情が理解できるだろうか?」
――心底くだらないと思うぜ。
「そう云うな。俺の気紛れが無ければ、お前は目覚めることすらなく、孤独な闇の中で朽ち果てていただろう。そう考えると、お前が今感謝すべき相手が見えてくると思うのだが」
――目覚めたところで、結局俺は環からは逃れられない。
「だが、必ずしもそれが不幸だとは限らない。現にお前は、あの子との主従関係を心地良く感じ始めている」
――またそれか。冗談も休み休み云え。そんなことは全くない。
「本当にそうかな?」アーデルハーンが口許だけで笑って、朱色の瞳で黒犬を見据えた。「では、試してみようか」
――なんだと?
「これが用件の残り半分だ。もしお前が望むのならば、今ここで“制約の環”を外してやろう。お前は自由を得る。もうあの子に付き合う必要は無くなるし、あの子の方にもお前を構う理由は無くなる。お前は何処へなりと勝手に姿を消せば良い。……さて、どうする?」
問い掛けるアーデルハーンの眼差しは、黒犬が遠い昔に見た記憶のままだった。新たな課題を被験体に与え、実験し、観察する者の眼だ。
その眼を見て、黒犬はようやく理解した。この男は、本当に自分の内面を観察する為に来たのだと。
――少し、考えさせてくれ。
黒犬は答え、男から眼をそらす。そして、己の境遇と少女の存在について考えを巡らせた。
・
翌朝、リサリサはいつものように憩いの森を訪れた。
いつもの場所で道を逸れ、いつもの森の奥へと踏み込んで行く。
……そして、いつもの場所に寝そべっていた黒犬に声を掛けた。
「おはよー。くじ引きって何だったの?」
伏せの姿勢を取っていた黒犬は、リサリサの姿を認めてゆるりと上体を起こす。
――おはよう。どうやら俺は『はずれ』のくじだったらしいぜ。
「ええー?」
――あの遺跡には『あたり』と『はずれ』の二匹が居たんだとさ。実にどうでも良い話を長々と聞かされた。『あたり』の方は多分、鬼だ。起こすと匿うのが大変だから、遺跡にはもう近付かない方が良いぜ。特に病院関係者が連れて歩くのには向いてない。お前の親父にもさり気なく教えてやれ。
「ふーん……」
ふと思いついて、リサリサは満面の笑みを浮かべる。
「私は、がじちゃんの方が『あたり』だと思うよ!」
云って、リサリサはばふんと犬に抱きつき、頬を寄せた。
――そりゃどうも。暑苦しいからくっつくな。
「照れちゃって!」
ぼん、と黒犬の背を叩いたリサリサは、ふと真顔に戻って黒犬から身体を離した。
「前から思ってたけど、がじちゃんちょっと獣臭いよね」
――俺が獣臭いのは普通の事じゃないか?
「よし、今度お風呂に入れてあげよう! 傷口染みるかな?」
――いや、傷は平気だが必要無いだろ、それは。
「何で? 気持ち良いのに。知ってるかもしれないけど、この森の南の方に小さい湖があるよ。水浴びでもして来たら?」
――独りで勝手に泳いで来いよ。
ぷいとそっぽを向く黒犬は、何となく落ち着きが無いように見えた。リサリサは回り込むようにして犬の顔を覗き見る。
「……ひょっとして、がじちゃん、お風呂が苦手?」
黒犬は一瞬躊躇するような素振りを見せたが、すぐに開き直る。
――当たり前だ。好きこのんで全身を水に浸すなど、考えられない愚行だ。
「へー。良いこと聞いちゃった。よし、ちょっと待っててよ!」
リサリサが立ち上がる。黒犬の頭を厭な予感がよぎった。
――おい、まさか……。
「タオルとか持って来るから期待してて! しっかり水浴びさせてあげる!」
リサリサは勢いよく数歩を踏み出してから立ち止まり、思い出したように振り返った。
「これ、もちろん命令ね」
そう云ってにっこり笑うリサリサに、はいはいと黒犬は迷惑そうな呟きを返した。
元気良く去って行くリサリサの背後で、黒犬はだらりと地に伏せる。木漏れ日の中で半ばまどろみながら、彼は遠ざかる少女の足音に聞き入った。
少女と黒犬 鬼の眠る場所
──鬼の眠る場所──
ネックベット医院の朝は早い。
まだ外が暗い内から院内の廊下は足音が行き交い、各自が細かく定められた予定をこなして行く。
来院者の多くは亜獣に襲われるなどした負傷者で、その治癒と復帰訓練が医院の柱となっていた。
医師は院長であるテオドール・ネックベットを含めて二名。病床は全部で十六床。
そんな病院の中をリサリサは我が物顔で闊歩する。居住部と病院部を繋ぐ廊下は一応カーテンで仕切られていたが、うんと幼い頃から勝手に両方を行き来していた彼女にとっては、どちらも自分の家の一部でしかない。彼女の二人の姉や妹も同様だった。
「お、リサ。最近妙に朝が早いな」
廊下を歩くテオドール・ネックベットが、近付いてくる娘リサリサの姿を認めて声を掛けた。
「おはよー、お父さん。もうあの遺跡には行かない方が良いよ」
「何なんだ藪から棒に。あの遺跡ってネーブブルグか?」
テオドールは廊下で立ち止まり、娘と向かい合った。
「うん。何ていうか……鬼が居るかも、みたいな?」
「何だそりゃ? しかしダスター君は今日現地に行ってるはずだぞ」
テオドールはネーブブルグ遺跡があるであろう方角に視線を向けて、黒髪の冒険者の姿を思い浮かべた。
彼とは以前遺跡を訪れた際に護衛を引き受けてもらってからの付き合いで、以来テオドールは何度かダスターと会って遺跡について意見交換をしていた。彼は最初は遺跡に対して比較的興味が無さそうな顔をしていたが、シレネで化鳥騒動があった日を境にして態度が変わり、今では随分ネーブブルグに執心している様子だった。
「むむ……どうしよう。病院の人じゃないから良いのかな」
何故かリサリサが困ったような顔をして見せた。そんな娘の姿を見て、ふとテオドールは思い出す。
「あ、そういえばすっかり忘れてたが……先日、リサに訊きたいことがあるとか云ってたな、彼」
「え? 私に?」
不思議そうな表情でリサリサがテオドールを見上げる。
「現地でリサに見て貰いたい物があるという話だったが、まあ今度皆で行った時で良いだろう。……おっと、一人で勝手に遺跡に行ったりするなよ。もう迷子は御免だ」
「一人で行くわけないじゃん。でも、何だろう。私が役に立つとは思えないんだけど」
「確か『迷子になった時に見つけた物』について教えて欲しい、とか云ってたぞ。何か凄い発見でもしたのか?」
「……え?」
リサリサの顔に驚きと不安がない交ぜになった色が浮ぶ。しかし、テオドールはそんな娘の様子には全くお構いなしで続けた。
「やはり、どんな遺跡にも何かしら浪漫が眠っているものだなぁ。予約が入っていなければ今からでも向かいたいところだが……」
廊下で立ち止まったまま、遠い眼で遺跡に思いを馳せるテオドール。通りすがった看護婦がふと彼の姿を認め、つかつかと大股で歩み寄って来た。踏み出す脚に合わせて、彼女の背で一本に縛られた栗色の髪が小刻みに跳ねる。
看護婦はテオドールの背後に立つと、手に持った封書で彼の肩口をぽんぽん叩いた。
「先生、遺跡の浪漫を語るのは休診日にして下さい」
つっけんどんな口調でテオドールにそう告げて、彼女はリサリサに向き直った。少女と目線を揃えるように、少しだけ屈み込む。
「リサちゃん、またね」
「あ、はい」
リサリサは父親を譲り渡す意味を込めて数歩後退して、軽くお辞儀した。
看護婦は天使の笑みを以てそれに応えると、未だ夢の中にあるテオドールの腕を掴み、引きずるようにして彼を連れ去って行った。
・
それから少し後のこと。憩いの森にはいつもの様に話し込むリサリサと黒犬の姿があった。
黒犬は地べたにお座りの姿勢を取り、リサリサの方は持ち込んだ小さな折り畳み椅子に腰掛けていた。
「……というわけで、ダスターさんが頑張って遺跡を調べてるみたいなんだけど、良いのかな?」
――別に良いんじゃねーの。あいつは冒険者って奴だろ? 医者が鬼を連れて歩くのとは訳が違う。
今朝の会話の一部始終を聞かされた黒犬は、さして興味も無さそうに云った。
「そんなもん? 鬼って、ルドラさん達の処に出たような奴だよね?」
リサリサが遠くを見る目で思い出す。
――前にも云ったが、ひと口に鬼種といってもその力や姿は千差万別だ。押しなべて一般人には近寄りがたい存在だが、戦いを本分とするような連中なら欲しいかもな。
「ふーん。あとね、ダスターさんが、私に訊きたいことがあるんだってさ」
――ほー。お前にモノを尋ねようとは、酔狂な奴がいたもんだな。
「それがね、『迷子になった時に見つけた物』について教えて欲しいんだって」
リサリサの言葉に、黒犬が訝るような視線を遣した。
――何?
「これって、何のことだと思う?」
――お前が何か凄い物を拾ったのでなければ、まず俺のことだな。
「だよね。どうしよう?」
――訊かれて逃げ出すのも変な話だから、適当に誤魔化すしかないだろう。
「先手をうって、永久に口を封じちゃうとか」
リサリサが冗談めかして笑みを浮かべる。
――落ち着け。穏便に行こう。そもそも、よく考えると極一部の冒険者は既に俺達のことを知っている。
黒犬は、化鳥や山賊の一件でまみえた【NAME】という冒険者の事を思い浮かべる。一方、その場の勢いだけで会話を楽しんでいたリサリサは、云われるまですっかりそのことを忘れていた。
「そういえば、そうでした。じゃ少しぐらい情報提供しても良いんじゃない? ひょっとしてあの床の模様とか調べてるだけかも知れないし」
リサリサが指先で空中に円を描いて見せた。
――床の模様って、俺が踏んでたあれか? あの象形は今から調べてもあんまり意味ねーぜ。対象を概念的に固定して維持するだけの簡単な機能しかないから、一度停止させると再起動にはまた術式が必要だ。更に外部からの干渉で容易に破壊されるから、使用は外敵が居ないことが前提だ。
黒犬の解説に、リサリサが渋面をつくって見せた。
「もうちょっと簡単に」
――扉を開けると二度と閉まらない冷蔵庫だと思え。
「よく解りました」リサリサが立ち上がる。「よし、ちょっとネーブブルグ遺跡に行って来よう」
――また迷子になるなよ。
「大丈夫よ。当然“一人で”行くわけじゃないし、ね?」
黒犬を見返すリサリサの顔が、いつもの悪戯っぽい笑みに彩られた。
・
昼下がり、ネーブブルグ遺跡を訪れたリサリサがまず目にしたのは、閑散とした広場の様子だった。
一時期それなりに賑わっていた遺跡も今は落ち着きを取り戻したようで、訪れる者もそう多くはないらしい。
かつて遺跡前に幾つかあった天幕は今や軒並み片付けられ、唯一残った土産物屋も今は開店休業状態だった。
遺跡の入口だけは以前と同じように開け放たれて固定されたままだ。
しかし、リサリサは何となく中に入る気にはなれず、広場で立ち尽くしていた。
傍から見ると彼女は一人きりでここに来ているように思えるが、実際には森の中で黒犬と別れたばかりだった。危険に際して指笛を吹けば、すぐに黒犬がやってくる手筈になっている。
建物の内部に入ることは、同時に森で待機する黒犬から距離を取ることを意味していた。流石に、ここで本当に一人ぼっちになるのは心許ない。
とりあえず入口に立って中を覗いてみようか。あるいは大声を出せば、中にいるダスターに届くかも知れない。
そんなことを考えていた時だった。
「おや」
丁度探索を終えた所だろうか。荷一つで遺跡を出てきたダスターが、リサリサを見て立ち止まる。
「あ、こんにちは、ダスターさん」
リサリサは挨拶して、ほっと安堵の息をついた。迷う必要も無かったようだ。そのまま数歩、ダスターの方に歩み寄った。
「……ひょっとして、一人でここまで来たのか? 随分大胆なことをするものだ。君に訊きたい事があったから、丁度良いと云えば丁度良いが」
相手が子供だからか、以前会った時よりざっくばらんな口調だ、とリサリサは思った。ダスターはリサリサの連れを探すように、周囲に視線を巡らせる。
「えと……お父さんからその話を聞いたから」
リサリサは曖昧に笑って誤魔化した。実際は一人で来た訳ではないのだが、それは云えない。
「まあそれは良いか。実はちょっと急ぐ必要が出てきたので、今日あたりお邪魔しようかと思っていたんだ」
え、とリサリサは驚きの声を上げる。
「すみません。お父さんは急ぎじゃないとか云ってて、おまけに今朝までその話自体を忘れていたみたいです」
「ああ、いや、良いんだよ。急ぎになったのはつい先日のことだからね」
云いながら、ダスターは背嚢を地面に下ろした。
「ネーブブルグ遺跡の発見から随分と時間が経っているが、どうやら、近いうちに常駐軍からの調査隊が来るらしい。今更……と思うだろうが、実は未だこの遺跡には秘密が残っている。後から来た連中にそれを持って行かれるのは、少々口惜しいじゃないか。私としては、その前にどうしても確認しておきたかった……何の話かは見当がつくだろう?」
「いえ、実は全然何も知らないんです。すみません」
ぺこりとリサリサが一礼する。
「はは」ダスターが破顔した。「そう云えとでも吹き込まれたのかな。あの黒い犬に」
リサリサは思わず顔を上げてダスターを見、口許を押さえた。
「君が森に犬を匿っていたことは知っている」
ダスターは事も無げに云った。
「多分、今も近くまで来ているんだろう。……そんなに驚かなくても良いさ。ほら、あいつに見覚えはないか?」
ダスターが親指を立てて上を指し示した。
リサリサは空を見上げて、あ、と小さく声を漏らした。その声に被さるように、大きな羽ばたきの音がひとつ。続いて二人の立つ広場を影がよぎった。
「あれは……」
リサリサが上を見たままで呟いた。彼女がそこに見たものは、円く開いた広場の上空を飛ぶ紫色の異物――人の顔を持った化鳥の姿だった。
化鳥は付近を軽く旋回すると、遺跡に近い大樹の梢に止まって枝を大きくしならせる。ばさばさと音を立てて木の葉が幾つも舞い散った。
「君は判りやすくて良いな。君達が退治した鳥にそっくりだろ? でもあれは別の個体だよ。前の奴はアイリーン、こいつはベアトリスと名付けている。次はキャロラインにするつもりだ」
ダスターは飄々と説明した。リサリサはダスターに視線を戻して訊ねる。
「もしかして……貴方のペットなんですか?」
「そうだね。通常、この辺りの街に亜獣は出ない。例外は、冒険者が使役するペットぐらいだ。まあ、お行儀の良い者は街の外で待たせるのが普通だが、完全掌握されている前提で街中まで連れて入ることも、ままある」
「ご、ごめんなさい。私ペットだと知らなくて……」
リサリサは自分がペット退治を行ってしまったことを知り、狼狽した。
「いやいや、それも別にどうでも良いんだよ。アイリーンは私があそこに捨てたんだから。あの一件で、私は君の方が犬を支配しているのだと確信した。そうでなくては、あの犬がわざわざ衆目の前に出てくる理由がないからね。まあ……予想以上に動きが速かったから、目で追うのもギリギリだったが」
リサリサはダスターの意図を掴みかねて沈黙し、俯いて目を逸らす。ダスターは少女の前にしゃがみこむと、彼女の顔を僅かに見上げるようにして云った。
「尋ねたいのは、あの犬を支配するに至った経緯だ」
ダスターは思い出す。迷子捜しをしたあの日、ダスターは【NAME】と共に少女の迷い込んだ部屋に踏み入った。
彼女は犬に触れたら消えたと云ったが、そんなはずはない。彼女が黒犬を手に入れたとすれば、あの時しかない。あそこで何かがあったのだ。
「君はあの時、嘘をついた。今度は包み隠さず教えて欲しい。君があの日、部屋で犬に出会って何をしたのか。如何にして封印を解き、如何にして契約を結んだのか? それを聞きたい」
「えっと……」
リサリサは観念し、最初から全てをダスターに説明した。
妙な部屋に迷い込んだ時のこと。
青い光に包まれた犬を見つけたこと。
自分がそれに触れ、目覚めさせてしまったこと。
“制約の環”のこと。
そして……二重安全機構の働きにより、自分が黒犬の主となったことを。
ダスターは口に手を当てて何か考えていたが、リサリサがそこまで話し終わると、すっと立ち上がった。
「触れただけ? そんなことで良いのか。この手の遺物にしては異様に警戒が薄いな。それに、その二重安全機構ってやつには欠陥がある……。限定的な利用を前提としているのか」
ダスターは殆ど独り言のような調子で云った。
「そうですか?」
「ああ、君は欠点を理解していないのか。だから素直に教えてくれた訳だ。あの犬はそれについて口止めしなかったのか?」
リサリサははっとした。そういえば化鳥騒動の日に【NAME】と出会った時、それを説明しようとして制止されたような気がする。結局リサリサはその理由を聞かずじまいだったので、すっかり忘れていた。
「まあ良い、他の冒険者連中が来たら面倒だし、取り急ぎ下へ向かっておきたい。犬を呼んでおいてもらえるかな。そういう事ができるのかどうか知らないが」
「あの、何を……?」
「まだ直接見てはいないんだが、この遺跡、実はもう一つ支配可能な個体が眠っている。最初の頃はそれ程興味は無かったんだけどね」
ダスターは地面に置いていた荷を背負い、リサリサを遺跡の中へと促した。
「だけど、支配できるのが鬼種なら話は別だ。この機会は、逃せない」
・
ネーブブルグ遺跡へと続く森を歩く内、【NAME】は指笛の音が響くのを聞いた。
……何だか、以前にも似たようなことがあったような気がする。
予感めいたものを感じながら【NAME】が歩き続けていると、不意に藪の中から飛び出してきた者がいた。
咄嗟に戦闘態勢を取ろうとして、その姿に脱力する。半ば予想はしていたが……飛び出してきたのは、一匹の黒い大きな犬だった。
――よう。【NAME】じゃないか。
黒犬の声ならざる意思が、【NAME】の頭に届く。
――遺跡に向かうなら一緒に行こうぜ。土産物屋のねーちゃんが居るかも知れないが、ペットの振りしとけば問題ねーだろ。多分。
云って黒犬は早々に歩き出す。
(また何かやってるのか……)
どうやら今日もリサリサと黒犬は何かに首を突っ込んでいるようだ。
黒犬の同行を断る理由は特に無いので、少しの間【NAME】は彼と一緒に歩くことにした。どうせ遺跡はすぐそこだ。
・
――む? 建物の近くに何か居るぜ。
木立の先に遺跡が見え隠れしてきた所で、黒犬がわずかに歩調を落とした。
付近に潜む動物でも見つけたのだろうか。だが、この犬がその程度のものを警戒するとも思えない。
【NAME】も目を凝らしてみたが、ここからでは陰になる部分が多すぎる。角度によって見える範囲も大きく変わり、遺跡付近といわれても一見して把握することは難しい。
――向かって右奥の樹の上だ。梢の中に色違いが混じっている。
【NAME】の様子を察した黒犬がそう補足した。
云われて姿勢をあれこれ変えながら観察し、ようやく気付く。平坦な遺跡の屋根に被さるように育った大樹、その枝の一つが大きく撓んでいた。生い茂った葉の中に垣間見えるのは、浅紫色の鳥の羽……。
――どっかで見たような鳥だな。
【NAME】と黒犬は、遺跡前の広場に出る数歩手前で立ち止まった。
ここまでくれば、もう相手の姿は明確に認識できた。
遺跡入口を右上から見下ろす紫の化鳥。枝の上には片足で止まり、もう片方の足を持ち上げてしきりに口で咬むようにしている。爪の手入れでもしているのだろうか。普通の鳥なら可愛らしい光景だが、如何せん人面でそれをやられると薄気味が悪い。それに、爪の手入れというのは要するに戦いの準備でもあった。
先刻の指笛の音が再び響く。
ぴくり、と黒犬がその音に反応した。前回とは聞こえ方に少し違いがあり、明らかに建物の中で反響している音だった。
――どうやらあいつは遺跡の中だな。呼ばれてるようなのでちょっと行って来る。あの鳥は……まあお前なら楽勝だろ。任せるぜ。
云うが早いか、黒犬は遺跡に向かう広場を一直線に駆け出していた。
そのまま遺跡内まで突っ切って鳥を無視する算段だろうか。その割に本気で走っているように見えないのは、ただの手抜きか、それとも先日負った傷をかばってのことか。
しかし、それでもほんの数秒後には黒犬は遺跡の入口に辿り着いていた。化鳥は手入れを止めてその様子を見ていたが、特に襲い掛かるような仕草は見せない。
――あれ? やる気のない奴だな。それじゃ遠慮なく先に行かせてもらうぜ。
黒犬が開け放たれた扉を越え、遺跡内に入っていく。彼の後を追うべく【NAME】も遺跡に向かった。
だが、【NAME】が広場に姿を現した途端、紫の化鳥は甲高い声を上げて飛び立った。止まっていた枝は一瞬大きく下に撓み、反動で跳ねて激しく木の葉を舞い散らせる。
(通してくれるのは犬だけか……)
なんとなく疎外感を覚えながら、【NAME】が武器を構える。
大きく翼を広げた人面の鳥が、【NAME】の頭上に爪を翳し、襲い来る!
battle
足止めの化鳥

化鳥を片付け、【NAME】は息を整える。
当然ながら、先に遺跡に入った黒犬の姿はとうに見えない。
さて、余計なお世話かもしれないが、彼の後を追うべきか。
少女と黒犬 狂気の片鱗
──狂気の片鱗──
ネーブブルグ遺跡の地下二階。
薄暗い廊下には早足で歩く黒髪の男と、時々小走りになりながら彼の後をついて行く少女の姿があった。
「あの……どこまで行くんですか?」
リサリサが不安げに男の背に問いかける。
「この奥に螺旋階段がある。その下だ」
ダスターはちらりと少女を振り返ったが、歩調は緩めずにそのまま進み続けた。
リサリサは来た道を振り返り、もう一度指笛を吹いた。早く来て、と心の中で黒犬に呼びかけながら。
・
――お? 迷子じゃなさそうだな。どういう経緯だこりゃ。
やがて、廊下を歩く二人の許に、黒犬の声が届いた。ダスターとリサリサが振り返る。
「あ、がじちゃん来た」
ぱっと顔を明るくして、リサリサが黒犬の方に駆け寄ろうとする。
ちょっと待った、とダスターが素早くそれを制した。腕をつかまれたリサリサは、不思議そうな表情でダスターを見上げる。
「悪いが、その距離を保つように彼に云ってくれないか。私は臆病なんでね」
真面目な表情で黒犬を見ながら、ダスターが云う。リサリサはくすりと笑った。
「大丈夫です! がじちゃんは、とっても物分りが良いんですよ」
「念のためだよ。近くで見るとかなり大きい……まさに亜獣だ。今まで君が喰われずにいたのが信じられないぐらいだよ」
「解りました。がじちゃん、その距離をキープしてね」
――ああ。そりゃ良いが、何故俺を呼んだ? お前、その男にどこまで教えたんだ?
「色々あって、全部お話してしまいました」
少女が舌を出す。
――あそう。ま、用事が済んだなら帰るとするか。
「いや、もう少し待って欲しい」
早々に立ち去ろうとする黒犬を、ダスターが引きとめた。
――あん?
「このまま地下まで三人一緒に行こう。……いや、二人と一匹で、と云うのか?」
――何の真似だ? 誘拐ごっこなら他でやりな。
「君は随分攻撃的だな」
云ってダスターは少女の方を見る。
「一応私を攻撃しないよう命令を下してくれないか。あの犬はちょっと怖い」
「平気ですよ。がじちゃんはもう、命令なんてしなくても人を傷つけるようなことはしないんです」
少女はにこやかに黒犬とダスターを見比べたが、黒犬は何故か微かに悲しそうな顔をした。
「念のため、だよ」
ダスターは無表情に云った。
「はい。じゃあ、がじちゃん、命令よ。ダスターさんを攻撃しないでね」
命令を受け、黒犬は憂いを含んだ瞳でリサリサを見つめた。
――お前……自分の命令の意味を理解してるのか?
問われて、リサリサは僅かに首を傾げた。彼女に代わって、ダスターが答える。
「私が自分の安全に拘るのを許して欲しい。もしかすると君は、その距離からでも攻撃できるかも知れない」
――そんな奴ほっといて帰ろうぜ。
黒犬が云ったが、ダスターはリサリサの腕をつかんだままで話を続けた。
「まあ、そろそろ本題に入ろう。実は、本当に協力して欲しいのは彼女ではなく、君の方だ」
――俺が? お前に?
「君は多分知っているんじゃないかな。この遺跡、最深部に馬鹿みたいに長い螺旋階段があるんだが、その下に開かない扉がある。こいつを使っても開かないんで困っていたんだよ」
ダスターが貴賓のペンデュラムを取り出して見せ、また背嚢のポケットに仕舞いこんだ。
――それは見学者の認証用だからな。最深部は関係者以外立ち入り禁止だ。
「聞いていた通りだな。実はこのところ連日その扉の開け方を調べていたんだが、少し前に妙な奴が教えてくれたよ。あの扉は登録された者、つまり遺跡の元の住人にしか開くことができない、ってね」
――そいつは頭のネジが二、三本飛んだ感じの長髪男じゃなかったか? よく信じる気になったな。
「やはり知り合いか。半信半疑だったが、彼は壁の象形を操作して最下層の部屋の中を見せてくれたんだ。青い光に包まれて、眠っている鬼の姿が見えた。興奮したよ。彼の象形への干渉にも驚いたが、その鬼の美しさに思わず見入ってしまった。それに、君のその反応で確信が得られたよ。扉は本当に開きそうだ」
――誰が手伝うって云った? そのおかしな男を探してそっちに頼め。お前ならあの馬鹿と気が合うだろう。それに、あいつも間違いなく扉を開くことができる。
「残念ながら、それ以来彼の行方は全く掴めない」
ダスターは両手を広げてお手上げの仕草を見せた。
――なら、独りで頑張って扉をぶち壊せ。何日掛かるか知れないが、やってやれないことは無いだろう。
「ばかに非協力的だな。だが生憎あまり時間が無い。それに、君はこの状況では手伝わざるを得ない。そうだろ?」
――どういう意味だ?
「二重安全機構の仕組みには、ちょっと問題がある。特に、この子のように支配者側が弱過ぎる場合にはね」
言葉に不審な気配を感じて、リサリサが不安げに彼を見上げた。その瞬間、ダスターは少女の腕を後ろ手にまわし、強く引き寄せた。
「痛っ」
リサリサは小さく悲鳴を上げて身を捩ったが、腕力が違い過ぎる。めいっぱい力を込めても、抵抗と呼べる程の動きさえできなかった。
「何らかの原因で支配者が死亡した場合、次に接触した人間を仮の主に設定する――」
云いながら、ダスターは空いている方の手で腰の短剣をすらりと引き抜いた。
「……つまり、私が今この子を殺せば、君の支配権は私に移る。そういうことだね」
冷淡に云って、ダスターは更に強くリサリサを引き寄せた。リサリサは刃を見て悲鳴を飲み込み、息を止めて身を硬くした。
「だから、君はこの状況では協力するしかない。だろ?」
ダスターはおどけたような笑みを黒犬に向け、手の中の短剣を弄んだ。
黒犬は身動きはせず、静かにダスターを見返した。その青い瞳に、冷たい敵意の炎が宿る。
――刃を下ろせ。
「ん?」
ダスターが手の動きを止めた。
――そいつの命令に免じて、今は警告に留めてやる。だが、これ以上下卑た真似を続けるなら、如何なる命令があろうと関係ない。
黒犬はダスターを睨む眼に力を篭めた。
――もし次に彼女を傷つけるような素振りを見せれば、即座にお前を殺す。
ダスターが息を呑んだ。
その背を一瞬冷たいものが走ったが、ダスターはすぐに気勢を取り戻す。
「……ハッタリだろ? 仮に命令を無視できるとして、私がこの子の首を切るのにどれだけ時間の猶予があると思ってるんだ。いくらなんでも、そこまで速くは動けまい。もし絶対の自信があるなら、君は既に行動に移っている……違うかな」
――試してみるか?
ダスターは黒犬の眼を見た。その青い双眸には些かの迷いも感じられない。行動の可否はともかく、この犬が真実自分を殺す気でいることをダスターは直感した。
一瞬の沈黙の後、ダスターは短剣を下ろした。
「いや……やめておくよ。怖いからね。支配者の変更にどの程度時間が掛かるのかも私は知らない。あるいは、彼女の死が認識されるまでの時間がね。機能の目的を考えるとまず一瞬で終わるはずだし、君の言葉は十中八九ハッタリだろう、だが確実ではない。それよりもっと平和的に行こうじゃないか。私は君達には大して興味は無いんだ」
ダスターが短剣を鞘に納める。リサリサは全身の緊張を解き、息をついた。
「ごめん……がじちゃん。私、ちょっと馬鹿だったかも」
かすかに震える声で、リサリサは黒犬に向けてそう告げた。少女は恐怖と悲しみの混じった複雑な表情を浮かべている。
――ちょっとではなくて盛大に馬鹿だ。だが、それは最初から判っていた。気にするな。
「だけど、それでもやっぱり、人を殺すなんて云わないで」
リサリサの言葉に、黒犬は目を剥いた。
――心底驚いたぜ。そいつが何をやろうとしたか理解しているのか?
「今のは多分……本気じゃなかったと思う。この人はそこまで愚かではないし、それ程人並み外れた事ができるようには見えないもの」
――前半はともかく、後半は良い洞察だ。こいつはどう見ても小物だからな。
「酷い云われようだな」
ダスターが肩を竦めて見せた。リサリサはダスターを無視して、本心から云った。
「それに、がじちゃんが人を殺すところを、私は見たくないよ」
やれやれ、とでも云いたげに黒犬が息をつく。
――どうやら、お前は俺の想像を遥かに越えるほどの馬鹿だったらしい。
そして、ふ、と黒犬は身体の力を抜いた。ようやく、張り詰めた空気が弛緩したようにリサリサは感じた。
「もう良いから、扉を開けて、帰ろうよ」
「そうしてくれると助かるね。そんなわけで、命令してくれないか。大人しく地下まで行くこと、ついでに、私を傷付けないよう念を押して欲しいね。先導は彼にやってもらおう。道は知ってるだろ?」
リサリサは云われた通りに命令を出し、二人と一匹は揃って遺跡の深部へと歩き出した。
・
【NAME】は遺跡の廊下を早足に歩いていた。
さして複雑な構造ではないが、部屋数だけは多いのでリサリサや黒犬の居場所を探すのは大変だ。
別に追いかける必要もないような気はするのだが、今までのあの子の行動パターンからすると、きっと今回も面倒事に巻き込まれているのだろう。
山賊砦での一件を思い出すまでもなく、そんな確たる予感があった。
それに、今度は何に首を突っ込んでいるのか、という興味も多少ある。【NAME】は手近な扉を次々開け放ち、遺跡の深部へと向かって進んで行った。
・
黒犬に先導された一行が暗く長い螺旋階段を下りると、終着点には真っ黒な一枚の扉があった。
――これだな。実際に入ったことは無いから、本当に開くかどうかは知らねーぜ。
黒犬がダスターを振り返る。ダスターが無言で頷き返した。
一歩、扉に向かって黒犬が距離を詰める。その途端、扉は跡形も無く消失した。
「上出来だ」
ダスターが微笑んだ。
扉の向こうは、大きな広間になっていた。天井も高く、床は遺跡の一階全部を併せたぐらいの広さがある。
まず黒犬が先に広間へと足を踏み入れた。それに続いて、ダスターとリサリサも中に入る。
「この扉、勝手に閉まらないのか? 閉じ込められたら困るじゃないか」
ダスターは扉のあった場所の断面をつぶさに観察しながら云った。
――離れると勝手に閉まるが、内側からは誰でも開けられる。
「ふうん。それなら問題ないな」
云ってから、実際にその通りであることをダスターは確認する。
「さて、それでは、いよいよご対面といこう」
ダスターは、ここに至ってようやくリサリサの腕を解放した。
「あの……私達は」
「君らもそこで待っていてくれよ。どんな鬼なのか興味があるだろう」
それから、ダスターは一人広場の中央に向いて歩き出した。薄い光に包まれてそこに座す、醜い鬼の許へ。
・
――あれは……まさか禍鬼か?
「ほう、こいつは望外の成果じゃないか」
広間の中心で、薄い光の膜に包まれて眠る、土気色の鬼。その正面にダスターは立った。
座った姿勢でありながら見上げる程の巨躯。その身体の大きさに比して足は短く、腹は風船のように膨らんでいる。
だが、醜く太った鬼の姿を前にして、ダスターの顔は上気していた。
「良いね……鬼はこうじゃなくてはいけない。流石に大禍鬼までは期待していなかったが、禍鬼級の奴が支配できるとは、まさしく僥倖だ」
――おい、そいつはやばいぜ。顔見てわかんねーのか? マジで止めとけ。
「子供に完全掌握されている君が云っても全く説得力がないな。先刻、君が本気で怒ってくれたお蔭で逆に“制約の環”や二重安全機構の仕組みが確かなものだと判った」
ダスターが顔だけで振り返って、笑った。
「さて、お目覚めの時間だぞ、禍鬼よ」
ダスターの両手が透明な膜を貫いた。
一度瞬きをするだけの時間で、鬼を包む膜は完全に消えてなくなった。
その瞬間、土気色の巨体が凄まじく膨張したように感じた。
だが違う。膨らんだのは気配だ。薄い膜一枚で遮られていた気配が解放された、それだけに過ぎない。
ただその気配が、空間を侵食する程に重く捩れている。質量すら感じさせる強大な圧力。おぞましい、それは鬼の持つ独特の気配だ。
「素晴らしいな……本当にこんなことが」
乾いた笑いを浮べ、ダスターが両手を広げて鬼を迎えるような格好をした。
開かれた鬼の双眸は真っ白で、何の感情も見られない。
人間が無防備にそれと対峙するなど、正気の沙汰とは思えなかった。
『おはよう。お前が、新しい主、という訳か』
鬼がダスターの姿を認めて立ち上がり、次いで恭しく地に片膝をついた。
リサリサは全身が粟立つのを感じた。黒犬の言葉とは違い、鬼のそれは普通の肉声だった。
だけど人間のものとは全然違う。その声を聞くだけで耳が、心が、冒されていくようだった。
しかし、ダスターはそれも一切意に介さないようだ。
「そうだ! はは……凄いな、これは……。こんなに簡単に、鬼種を掌握できるのか……」
ダスターと鬼の姿を見ながら、黒犬は微かな違和感を覚えていた。
あの鬼は何故“誓約の言葉”を云わずに居られるのだ?
余りに馬鹿馬鹿しいので誰にも教えていなかった事だが、“環”が主人を認定した際には『誓約がどうしたこうした』という下らない台詞を云うことが義務付けられている。
それを云わなければ当然、痛みが与えられる。なのに、何故?
しかし、黒犬のそうした疑念はすぐに忘れられることになる。
「もう良いでしょ? ……私達は帰ります」
リサリサは眉を寄せ、歓喜に満ちたダスターの姿を見て云った。彼は朗らかな表情でリサリサを振り返る。
「まあ待ちたまえ。せっかくだから少し試してみようじゃないか」
「何……を?」
リサリサが、扉の方に後ずさる。
決まってるじゃないか、とダスターが吹き出した。
「鬼の実力を、だよ」
その言葉が発せられると同時に、黒犬が地を蹴った。
鬼には目もくれず、ダスターの首を目掛けて一直線に跳びかかる。だが、次の瞬間、ダスターの首筋を捉えていた黒犬の視界が土気色の壁に遮られた。
防御すら間に合わないはずの速度でダスターに繰り出された牙が、予想外の手応えによって弾かれる。
――こいつ……!!
如何なる術式の為せる技か、あるいはそれが持って生まれた運動能力なのか。醜く太った鬼の巨体が一瞬にしてダスターの前に立ちふさがったのだ。
横滑りしながら着地した黒犬は、頭を斜め下に振って何かを吐き出す。べたりと音を立てて床に張り付いたのは、土気色の肉塊と腐汁のような臭いを発する灰色の血液だった。
――速い。
吐き捨てるように黒犬が呟いた。こいつもやはり、見た目と全然違う。
『犬よ。我が主を傷つけることは、まかりならぬ』
云って、禍鬼は大きく肉を喰いちぎられた己の腕をしげしげと見つめ、逆の手で傷口をぐじぐじと弄り回した。押し出されるように灰色の体液が零れたが、すぐにその傷口が塞がっていく。
黒犬は鬼とダスターから距離を取り、リサリサをかばえる位置まで下がった。広間の出口はすぐ側だが、あの鬼に背を向けるのは危険だ。
鬼の後ろで、ダスターがふう、と大きく息を漏らした。
「一瞬、肝を冷やしたよ。目の前で見ると本当に速いんだな。……だが、やはり鬼と犬では格が違うようだ」
黒犬は無言で鬼の姿を睨みつける。認めたくはないが、ダスターの言葉は真実だった。
「さて、一体どれ程の力を見せてくれるのかな。楽しみだよ。実に、楽しみだ」
ダスターが心底愉しそうに笑んだ。その時、唐突に場違いなノックの音が広間に響いた。
・
【NAME】はやたらめったら長い螺旋階段を下りた。
地の底へと続くかのような、暗く無駄に長い階段の先にあったのは、黒い一枚の扉だ。
もう残った場所はここしかないのだから、リサリサと黒犬が中にいることは間違いない。
扉を前にして【NAME】は思案する。
縁取りや装飾の具合、設えられた位置から総合的に考えると、これは多分『扉』で間違いないのだとは思う。
だが、取っ手が無い。
仕方ないので、とりあえず軽くノックしてみた。
数拍を置いて、何の前触れも無く扉が消失した。同時に、耐え難い歪んだ気配が吹き出し、それに圧される。
扉の向こうには【NAME】を見て驚く少女と黒犬の姿、そしてその奥に見える、あれは――。
(……鬼か)
思ったとおり、また面倒事に巻き込まれているようだ。
「【NAME】さん! ……でしたっけ?」
リサリサが云った。
――よお。来てくれると思ってたぜ。あいつには教えなかったがな。
黒犬が嬉しそうな声を響かせる。
「おやおや、どうなってるんだ」
黒髪の男が鬼の傍らに立ち、広間に現れた【NAME】の姿を見て渋面を浮かべた。
彼は……以前にこの遺跡で会ったことがある。【NAME】は思い出す。
確か、ダスターという名の冒険者だったと思うが……この様子からすると、どうやら鬼の飼い主に転職したと見える。
「困ったな。こんなに早く見つかるのは想定外だ。軽く実力を見せてもらうだけの予定だったのだが、これだけ纏めて相手ができるのかどうか」
ダスターは全く困った様子を感じさせない調子でそう云った。鬼が集った面々を見比べ、不快な声を上げる。
『これは新しい実験か? 随分とまた意味不明だな』
「そんなところだ。寝起きの運動に、そいつらと戦ってみたらどうだ」
ダスターが顎をしゃくって【NAME】を示した。醜い鬼は特に何を云うでもなく、漫然と【NAME】に向かって歩き出した。
「では、始めてくれよ。禍鬼の手による、愉快な血の饗宴を!」
[BossMonster Encountered!]
battle
支配されし鬼

「おいおい、本気を出せよ。鬼の力はそんなもんじゃないだろう?」
殆ど抵抗らしい抵抗も見せずに膝を折った鬼を見て、ダスターが当惑と落胆の入り混じった声を上げる。
鬼の身体に穿たれたいくつもの傷口からは、灰色に濁った体液が一定のリズムで流れ出ていた。
しかし次の瞬間、ぶるり、と傷口が動き、体液の流出が止まった。身体の全ての傷口が別の生き物のように蠕動し、次々塞がっていく。
「ほう、再生するのか。次は是非実力の程を見せて欲しいな」
ダスターは期待の篭った眼で、醜い鬼に声をかけた。鬼は無感動な白い眼でダスターを見返した。
・
ネーブブルグ遺跡の一階。壁に象形の設えられた部屋の中に一人の男が立っていた。
緑を基調にした服と帽子、腰まで届く長い金髪――遺跡の発見者にして黒犬の前支配者、アーデルハーン。
壁の象形には遺跡の最下層の部屋が映し出され、そこに集う人々と土色の鬼の姿を遠く斜め上から見下ろしていた。
アーデルハーンは女のような手をしなやかに象形に翳し、理粒子干渉を行う。円の中で色が混ざり合い、中心に位置した鬼と、その背後に居る黒髪の冒険者をより大きく映し出した。
太った鬼は身体中に受けた傷の再生を終え、今しも立ち上がらんとするところだった。
黒髪の冒険者は歪んだ笑みを以ってそれを眺めていた。今にも拍手しそうな無邪気な喜びぶりだ。
象形を通じて男のそんな様子を見つめながら、アーデルハーンは皮肉めいた笑みを浮かべる。
「残念だったね」
アーデルハーンは額に掛かる髪を軽くかき上げ、愉しそうに独り呟いた。
「そいつは、『はずれ』だよ」
少女と黒犬 饗宴
──饗宴──
遺跡の地下広間に集った面々の前で、ゆるりと禍鬼が立ち上がった。
【NAME】は武器を構え、黒犬も再び飛び掛る構えを見せる。
『我が主を傷つけることはまかりならぬ』
誰に云うともなく、鬼は感情の篭らない声で繰り返した。そして、広間の中央に立つダスターにゆるゆると歩み寄る。
『それは、我にのみ許された行動だ』
「は?」
ダスターが素っ頓狂な声を上げた。
『永き眠りから覚めると空腹が酷い。その上、こう痛みと血の臭いが強くては、食欲が昂進されてかなわぬ』
ダスターの顔が凍りつく。
逃げようとしたダスターに、鬼の右手が素早く伸びる。ダスターの胴体は、鬼の巨大な片手で易々と握り締められた。
「おい、よせよ……」
自由に動く両手を鬼の指にかけ、ダスターが呻いた。
『さあ、我が主よ。お前の苦痛を我に喰わせてくれ。そして“環”による痛みを与えてくれ』
ダスターの両脚が床から離れる。禍鬼が口を開いた。
「や、やめ……」
ダスターが両手を顔の前に突き出した。その片方を、禍鬼が口に差し入れる。
がしゅ。
鬼が口を閉じた。
人のものとは思えない絶叫が、ネーブブルグ遺跡の地下に木霊した。
鬼は暴れるダスターを苦も無くあしらいながら、口の中のものを何度か咀嚼し、嚥下した。そして不満げな声を漏らす。
『なんだこれは。“環”の痛みがまるで向上しておらぬ。真面目に工夫しているのか?』
鬼は肘まで喰いちぎった腕を更に口の奥に進め、今度は肩から胸近くまでの骨を砕きながら勢いよく噛み千切った。
鬼の手に掴まれた胴体の下で、ダスターの両脚がそれぞれ別の生き物のように大きく痙攣した。血が噴水のように噴出し、ダスターは紅いあぶくを吹いて白目を剥く。
『宴の最中に眠ることはまかりならぬ』
鬼がダスターを掴んだ腕で何らかの理粒子干渉を行った。仄かに赤みを帯びた光が、握った手の内から零れ出る。
びくん、と激しく一度全身を震わせて、ダスターが意識を取り戻した。
それを確認した鬼はダスターの身体を高く持ち上げると、今度は片足の先を口に含ませる。
「あ、あ、あ……」
苦悶と恐怖に満ちた瞳でダスターが鬼を、次いで広場に集う【NAME】達を見た。
大きく開かれた鬼の口許は、口紅を塗りそこなった子供のように滑稽に彩られている。ダスターの身体から毀れ出るものが鬼の顔を伝い、土気色の巨体に幾筋もの模様をつけた。
鬼を攻撃するべきか? ……それとも、あの男に止めを刺してやる方が確実か?
【NAME】は僅かに逡巡する。
次の瞬間、黒犬が鬼に飛び掛っていた。無防備に向けられた鬼の背に向けて跳躍し、その左の肩口に喰らいつく。深く咬んだ牙は肉をちぎるには至らず、鬼にぶら下がった格好になる。黒犬はそのまま身体を捻り、更に深く肉を咬みこんだ。
『煩わしい』
鬼は左腕を大きく振るって自分の肉ごと黒犬の牙を外すと、着地した犬を叩き潰すべく、逆の腕を地面に叩き付けた。
ダスターの身体を掴んだままで。
黒犬が間一髪でそれを回避する。振り下ろされた鬼の腕は広間の床を叩き割り、石片と血肉の飛沫を巻き上げた。
表情の乏しい鬼が、きょとんとしたような気配を見せる。
『おや……死んでしまったではないか』
鬼が手を開く。不用意に篭めた力はダスターの肉体を掌の中で押しつぶし、床板を砕いた衝撃は一瞬で彼をただの肉塊へと変えていた。
ぼとり、と赤黒い雑巾のような捩れた物体が床に落ちる。もはや僅かな痙攣さえも認められなかった。
哀れな末路だが、あの鬼が“食事”にどれほど時間を掛けるつもりだったのかを考えると、むしろ幸運だったと云えるかも知れない。
ぐう、と言葉にならない不満の音を鬼が上げる。
だが、部屋を改めて見回した鬼の白い眼は、新たな獲物――広間の床に座り込んだ少女の姿を捉えてしまった。
『おぉ、二重安全機構か。これは良い仕組みよな』
鬼は血の混じった息を吐いた。それは何故か笑いの表現のように感じられた。
『新しき我が主は、小娘のようだ。非常に珍しい……食後のデザートに取っておくべきであろうな』
そう云って禍鬼はその場に座り込み、ダスターだった物体を再び拾い上げて、口にした。
・
リサリサは広間の床にへたり込んでいた。
噎せ返るような臭いが広間に満ち満ちている。呼吸が苦しい。口の中には妙な味を感じる。まるで空気が薄い血の霧に変じたようだ。
逃げるどころか立ち上がることすらできず、リサリサは眼前で繰り広げられる光景を放心して眺めていた。
瞳に映るものの意味を理解しないよう、ただそれだけを努力して。
やがて、鬼がリサリサの方を見て、何かを云った。何を喋ったのかは判らない。リサリサはただ早鐘のように打つ自分の心臓の音と、身体を巡る血の音だけを聞いていた。
黒犬が座ったままのリサリサの服を咥えて引っ張る。
――やべえ。おい、しっかりしろ。
「……ひ……」
黒犬に揺さぶられ、ようやくリサリサの瞳が焦点を結ぶ。
陰惨な光景から眼を逸らし、脇に立つ黒犬を見た。リサリサは何かを云おうとしたが、あごが震え、舌がもつれて言葉を成さなかった。
――逃げるぜ。立てるか?
リサリサは立ち上がろうとしたが、膝に力が入らない。手も脚も、全身が小刻みに震えていた。
――だめだこりゃ。仕方ない、掴まれ。お前を乗せたまま走る。
黒犬がリサリサの正面に回り、できるだけ低く伏せの姿勢を取った。リサリサは黒犬の首に両手をまわし、その背に抱きつくように覆い被さった。犬としてはかなり大きな背だが、牛馬ほどではない。しっかり掴まらないと、簡単に落ちてしまいそうだ。
――もうちょい気合入れろ。全力で首を掴んで、足は俺の身体を挟め。格好悪いとか云うなよ、どうやったって乗馬みたいにはいかねー。
リサリサは無言で頷いて、廻した手に力を篭めようとする。
黒犬はリサリサを背に乗せたまま、可能な限りゆっくりと立ち上がった。なんとか彼女を落とすことなく体を持ち上げたものの、首にかかった少女の腕には殆ど力が感じられない。
――これじゃちょっと速度出すと振り落としちまうな。まー、無理もねーか。
黒犬が【NAME】を一瞥する。
――悪りぃ。後を頼む。
【NAME】は黙って首肯した。あの鬼がどういう眼で少女を見ているのかは、ダスターの末路を見れば明らかだ。まさか残ってくれとは云えない。
リサリサは黒犬の身体に頭を押し付け、目を閉じていた。
「がじちゃん……怖いよ」
すがった手に、ようやく少女が力を込める。
――手を離すなよ。
黒犬が床を蹴った。広間を抜け、螺旋階段を駆け上がる。疾く、しかし、リサリサを振り落とさないよう加減して。
『おお、逃げては実験にならぬではないか。もしや“環”の研究は終了か?』
寒気がするような鬼の声が広間に響き、螺旋階段を上る黒犬とリサリサの許にまで届く。
リサリサは頭を振ってその声を追い出し、必死で黒犬にしがみ付いた。
・
ややあって、寝起きの食事を終えた鬼は、ゆらりと立ち上がった。
全く凄む様子のない、淡々とした態度。しかし、それが酷く忌まわしいものに見える。
【NAME】は土気色の巨体を真っ向から睨みつけ、武器を構える。
やるより無い。
だが、禍鬼は戦いの姿勢をとる【NAME】に数歩ゆっくりと歩み寄ると、なにやら逡巡するような様子を見せた。
『ふむ……』
目の前の敵とその背後にある広間の出口を見比べながら、おもむろに鬼は右手で自らの左腕を掴んだ。二の腕を握りこんだその手に力が篭る。
次の瞬間、灰色の血飛沫が迸った。
(……何!?)
【NAME】は目を疑った。
鬼は自らの左腕を肩から引きちぎっていた。少し持ち手の角度を変えて二、三度腕を引っ張り、溶かした飴のように糸を引く組織を切断する。
ごみでも投げ捨てるように、鬼は無造作に左腕を高く放り上げた。腕は大きな弧を描いて広間を飛び、鈍く湿った音を立てて【NAME】の遥か後方に落ちる。
ちらりと目でそれを確認し、【NAME】は鬼に視線を戻した。
驚くべきことに、たったそれだけの時間で既に鬼の左腕は半ば再生していた。
歪な切断面から新たに生えた、赤子のように小さく滑らかな手。灰色の体液にまみれて濡れたそれが、見る間に膨らんでいく。
(……出鱈目だ)
先ほどの食事で再生力が向上しているのか? まさか常時ここまでの能力が発揮できるとは思えない。
何にせよ、こいつを地上に出すつもりは無い――【NAME】は戦いに意識を集中する。
それが能力だというのなら、二度と再生できなくなるまで、破壊するのみ。
[BossMonster Encountered!]
battle
狂気の禍鬼

鬼の巨体が崩れ落ち、その体組織が半ば溶解した。
だが、それで安心することはできない。【NAME】は次第に形を失っていく鬼の脇に立ち、武器を構えた。
そして、今度こそ再生しないよう、徹底的に、執拗に止めを刺す。
やがてただの肉片と化した鬼を見下ろし、【NAME】は肩で息をしながら数秒待った。
再生の兆しは無い。
【NAME】は安堵の息をついた。これで、終わりだ。
振り返る。
眼前に広がるのは、何の変哲もないまっさらな室内の光景。しかし、そこから受けるのは拭いようも無い強い違和感。
(莫迦な……)
【NAME】は思わず呻いた。
戦いの前に鬼が投げた左腕が、どこにも見当たらなかった。
立ち尽くした【NAME】の耳に、遥か遠方――螺旋階段の上から何者かの咆哮が届く。まるで鬼の声のような、激しい咆哮が。
・
少女を背に乗せ、螺旋階段を抜けた黒犬は遺跡の中を更に駆ける。
――すまん。あの鬼がこれほどの変態だとは知らなかった。
「研究、失敗だね」
鬼から離れ、少し落ち着きを取り戻したリサリサが云った。
――まあ、そんな予感はしていたが、鬼を制御するのはこれっぽっちも成功していなかったようだな。
暫く無言で走る。
「出口だよ! がじちゃん!」
リサリサは両手で犬にしがみ付いたまま、前方に目だけを向けて云った。
――脚がいてーな……傷口が塞がり切らない内に無理したか。
黒犬がちらりと自分の身体に目を遣った。
――悪りぃが、これまでみたいにお前を乗せて移動するのはちょっときついぜ。
「良いよ、歩くから」
リサリサが犬の背を降りようとする。
――くそ……それも駄目だ。
黒犬が背後の暗い廊下の向こうに視線を送る。
リサリサが振り返るより早く、凄まじい咆哮が彼女の耳朶を打った。明らかに階下から発せられているにもかかわらず、空気の振動さえ感じる程の叫び。
……鬼だ。
――どうなってんだ……。
黒犬が少し姿勢を落とし、既に片足を下ろしていたリサリサを、再び自分の背に乗るよう促した。
少女を乗せたことを確認して、黒犬は再び走り出す。
すぐに遺跡を抜けて、森に出た。だが、走る速度は明らかに落ちていた。
血が零れている。先刻の戦いで、かつて鬼に切られた傷口がまた開いていた。
――差が詰められている。……追いつかれる。
後方から、気分の悪くなるような歪な気配が近付いているのが判った。
どうすれば良い?
森の中を走りながら、黒犬は考える。
逆走して【NAME】との合流を期待するか?
あいつがそう簡単にやられるとは思えない。何らかの手段で鬼の方が煙に巻いたのだろう、とは思う。
だが、もしそうでなかった場合、戻るのは自殺行為だ。それにリサリサを連れて戻ることなど、できるはずもない。
ならばリサリサを置いて自分だけ戻るか?
それもまた自殺行為だ。万全の体勢であったとしても、あの鬼と一対一で戦うのは厳しい。
【NAME】が生きていて、尚且つ自分が生きている内に合流できなければ終わりだ。そんな賭けは避けたい。
ならば、どうすれば良い?
黒犬の思考は堂々巡りをする。二人とも生き残る方法を探し求めて。
少女と黒犬 最後の選択
──最後の選択──
背後から近付く歪んだ気配を感じながら、少女を背に乗せた黒犬が森をひた走る。
このまま街まで走り抜ける。
黒犬はそう決めていた。鬼を連れて街に駆け込むなど褒められた行為ではないが、背に腹はかえられない。
だが、血を流しながら走る黒犬の速度は目に見えて衰え、逆に鬼の方は次第に速度を上げていた。
運が良ければ身が持つと思っていたが、甘かった。これでは森を抜ける前に追いつかれる。
――駄目だ。街まで届かない。
追いつかれる。それは二人の死を意味していた。リサリサも黒犬も、それを理解している。そして、最悪の場合どうすれば良いのかを考えていた。
先に結論を出したのは、リサリサの方だった。
「……下ろして」
リサリサはしがみついた犬の背に向かって小さく呟いた。
――なんだと?
「私を下ろせば、あの鬼はがじちゃんを追いかけられないかも」
――駄目だ。俺は逃げられるだろうが、そんなことをすれば間違いなくお前は死ぬ。
「でも、このままじゃ追いつかれるよね」
――まあな。
「そうしたら、二人とも死んじゃうよ。だから……私を下ろして。一人で逃げて」
――ふん……。
黒犬が速度を緩め、リサリサを地面に立たせた。実際の所、彼女を乗せて走るのは限界に近かった。
「隠れてれば、もしかしたら助かるかもしれない……よね」
――いや。あの鬼には制約の環があり、その主人はお前だ。確実に見つかるだろう。そして、見つかったが最後、お前が生き延びる可能性は万に一つも無い。
「もしそうなったら、ルドラさんの処にでも行って。あの人なら少しはマシでしょ」
――あんな山賊だらけの処に行けるか。ルドラに会う前に禿頭が主人になったらどうする。それに……まあ良いか。
リサリサは思わず吹き出した。こんな時に笑える自分が不思議だった。
「だけど、もう、仕方が無い」
――お前は死を覚悟したようなふりをしているが、違う。考えようとしていないだけだ。お前は死から目を逸らしている。それは恐怖からくる逃避に過ぎない。お前みたいな奴が死を受け入れる事などできやしない。ましてや覚悟するなど、絶対に不可能だと断言できる。後から泣いても遅いぞ。考え直せ。
リサリサは、そうだよね、と俯いた。
「本当は……がじちゃんの云う通りだって、解ってる」
云って、気付いた。そうか。さっき笑えたのは、そのせいだ。自分はこれを夢か何かだと、そう思いたがっている。死んでしまえば目が覚めるのだと、そう思いたがっている。
現実感があるままでは、自分の心が耐えられないから。
でも、それを自覚しても、自分の力では結局どうすることもできない。
だから、リサリサはこうすることを決めていた。顔を上げて、黒犬の青い眼を見つめる。
「でも逃げて。……これ、命令よ」
リサリサは命令を下した。せめて、この犬だけはこれ以上傷付けたくなかった。二人とも死ぬか、自分だけが死ぬか。選択の余地など無かった。
だが、黒犬は少女を見返した眼を僅かに細めて、穏やかに告げた。
――逆だよ、それは。
「……え?」
――逃げるのはお前、囮が俺だ。俺が戻ってあいつを足止めするから、お前は街まで走って衛士でも冒険者でもとにかく人を呼べ。二人とも生き残る可能性があるのは、これしかない。……だから、命令は却下する。
「そんな!」
――たまには俺にも命令させろよ。……逃げてくれ。頼む。
云って、黒犬は微かに口許を綻ばせた。その表情の変化はほんの僅かなものだったが、リサリサは彼が微笑したのだと確信した。
黒犬がくるりと向きを変え、遺跡の方へ――鬼の来る方へと走り出す。
リサリサは一瞬後を追おうとして、そうすることが彼に対する裏切りになると気付き、踏みとどまった。
そして、少女は泣きながら街へと続く道を走り出した。
・
【NAME】が遺跡を抜けると、森の拓けた部分に赤い血が零れていた。そして、重なるようにして灰色の体液も。
二色の血液は点々と道に沿って先へと続いている。
シレネに向けて移動しながら、誰かが鬼と戦った痕跡だ。赤い血の主が誰であるかは考えるまでも無い。
【NAME】は血の跡を追って、森を走った。
……遠い。
鬼の方はともかく、そうでない者がこんな距離を、こんな出血で、戦いながら移動できるのか?
疑問と不安をない交ぜにしながら、【NAME】は更に走る。
あとほんの少しで森を抜けてしまう。まさかシレネまで行ったのか、と思ったが、そうではなかった。
森の出口に、鬼が立っているのが見えた。
今や土色ではない。鬼は全身に赤い返り血を浴びた上、流れる灰色の体液が斑に入り混じって二目と見られない醜さを呈していた。
醜悪な巨体の足元には、鬼と比して随分小さな黒い影が横たわっている。
倒れているのは、犬だ。その周囲を染める赤黒いものが、次第に地面に広がっていく。
鬼が振り返る。
喉笛と左目を失った鬼が、残った片方の白い眼で【NAME】を見た。腕や脚で骨まで剥き出しになった傷口が、次々と塞がっていく。
【NAME】は走り込みざま武器を構え、そのまま鬼に向かって更に加速した。
再生の時間は与えない、この一瞬で決着を付ける!
[BossMonster Encountered!]
battle
血に染まる鬼

鬼の巨躯が水平に吹き飛び、樹木を激しく軋ませて血肉を散らし、地に落ちる。
その口から、傷から、どぼどぼと灰色の液体が噴出した。間髪入れず、【NAME】は倒れた鬼の許に駆け寄った。
二度と再生しないよう。
肉の一片すらこの世に残さぬよう。
完膚なきまでに止めを刺した。
・
「がじちゃん!」
街の方角から声が聞こえた。【NAME】が顔を上げると、左右に結んだ髪を跳ねながら走り来る少女と、武器を手にした数人の大人達の姿が見えた。
リサリサは地面を濁す鬼の残滓にも、灰色の血に染まった【NAME】にも一瞥もくれず、真っ直ぐ黒犬の許へと駆け寄った。
震える手で、その身体に触れる。
まだ、生きていた。
けれど、それは本当に“まだ”というだけだった。
呼吸が酷く浅いし、苦しそうな雑音が混じっている。
血と体液は止め処も無く流れ出ている。切り裂かれた傷は内臓にまで達していた。
何をどうすれば良いのか判らなかった。だから、ただ黒犬の傍に座ってその上体を抱きかかえた。
零れ出る血液が腕と地面を伝って、少女の服に染みていく。
――おい……汚れるぞ……。
ようやく届いた彼の意識は、消え入りそうな程に弱々しいものだった。
――これで、良くやったほう……だろ?
黒犬の青い目が、力無く少女に向けられた。
「どうして!?」
嗚咽でリサリサの言葉が途切れた。涙が零れていた。
「だから……逃げてって云ったのに! 命令した! 命令したのに!」
目の前で一つの命が失われつつある。それが判っているのに、何もできない。そんな自分の無力さが悔しかった。
「死んだら駄目! 死んだら絶対許さないから!」
憎まれ口が返って来るのを期待した。だけど、それすらも無かった。
「がじちゃん、いやだよ!」
――――。
黒犬の最期の思いが、リサリサの心に届く。
彼が何かを伝えようとしたことが判った。けれど、それは言葉にする前に消えてしまった。
少女の両手の中で、黒犬の体温が急速に失われて行った。
少女と黒犬 さよならの夢
──さよならの夢──
そして、一週間が経った。
・
ネーブブルグ遺跡の騒動でネックベット医院には数名の者が担ぎこまれたが、それは怪我人ではなく、単に鬼の死骸を前にしてその瘴気にあてられた者達だった。幸いにして重傷者はいない。
例外はダスターという冒険者だったが、彼は“鬼に挑んで敗れた者”として、つまり、良くある事として処理された。
ただ……犬の死骸の側で泣き喚く少女には、少々難儀したようだ。
駆けつけた者は死骸を放置して少女を町に連れ帰ろうとしたが、彼女は絶対にそれを許そうとはしなかった。
結局、少女のたっての願いで、その犬はネックベット医院の側、憩いの森の片隅に埋葬されることになった。
明らかに亜獣と判る死体に拘泥する少女に人々は奇異の眼差しを向けたが、彼女は全く意に介さない様子だった。
そして、そんな少女の事も犬の事も、この数日で綺麗に忘れ去られていた。
人々に取っては既に終わった事件。何も無かったかのように、再び日常が回りだしている。
ただ一人、彼女だけがまだ事件を引き摺っていた。
・
夕暮れの森の中。
憩いの森の周遊道からほんの少し外れた場所に、その墓はあった。
外輪部に近いこの場所からは、木々の隙間から街が見える。見上げれば、梢の向こうには近くの医院の建物が迫っていた。
墓は、土を盛って作った塚に小さな石碑を墓標とした簡単なもの。埋葬された亜獣はその名を知る者さえ殆どなく、参る者となれば少女一人を除いて皆無だった。
【NAME】は事件以来、初めてここを訪れた。深い意味はない。ただ、なんとなく……だ。
だが、驚いたことに、墓には先客がいた。
緑を基調にした衣装に身を包んだ男が、片膝をついて墓前に何かを話しかけていた。
「どうだ、生を全うできただろうか? そうであったことを願うよ」
僅かな姿勢の変化にあわせて、女のように長く美しい金色の髪がさらりと肩から流れ、零れ落ちる。
「はは、くだらない事を気にしてるんだな。だが、死者に許されるのはただ消えることのみ。何者であろうとそれを覆すことはできん」
まるで本当に誰かと話しているようなそぶりだが、周囲には誰もいない。死者の概念残滓を汲んで話している風にも取れるが……流石にそれはあるまい。
「どれだけ長く生きようと、如何に充実した生を送ろうと、死には必ず思い残しがあるものだ。諦めろ」
男が立ち上がり、小さな墓石を見下ろした。そのまま数秒、無言で塚を見つめる。
「……なんてな」
ふ、と男は微かに自嘲の混じった息を漏らした。
「やはり俺には、芯なる者ほど超然と振舞うことはできんようだ」
男は再び墓前に屈み込むと、石碑に右手を当てて少しの間静止し、口の中で何事か呟いた。それからまた立ち上がると、白い花を無造作に放り投げた。
「ついでにそれもくれてやる。せいぜい安らかにな」
花は土の露出した地面に落ちると、二、三度転がってから石碑の手前で止まった。
頃合を見計らって【NAME】も墓に近付く。立ち去り際の男と、【NAME】の目が合った。
朱色の綺麗な瞳。
男は僅かに意外そうな顔を見せたが、特に何も云わずに去っていった。【NAME】の方もまた、無言で男を見送る。
墓前に片膝をつき、【NAME】は石碑を見つめながら黒犬の姿を思い起こした。
(……ん?)
その時、ふと、妙なことに気がついた。
微かだが、墓石に異質な色を見たような気がした。注意深く観察すると、石の表面にごく薄い紋様が浮かんでいる。手を翳して影にしなくては見えない程の、ほんの僅かな光。
円を基調として複雑に入り組んだ曲線は、ゆっくりと色味を変化させながらそれと気付かぬ程の淡い光を放っている。
ごく簡単な何かの印章。いや、これは……。
(象形? ……そんな莫迦なことはないか)
印章の元になった概念異渉紋様――グリフ。それを記述することは、人間にはできない。
振り返ったが、男の姿は既に無かった。
・
夜。
――ああ、また夢だ。
リサリサはそれを認識した。
あれから、何度か似たような夢を見た。「がじちゃんが死んだと思ったのは嘘で、本当は生きている」そんな、夢。
その夢を見るたびに、嬉しくて目が覚めた。
そして、すぐにまた現実を知って、泣いた。
毎日のように、それを繰り返してきた。
死に直面した時は、衝撃の方が強くて理解が追いついていなかった。日が経って、夢を見るようになってから、本当の悲しみが襲ってきた。本物の喪失感を知った。だけど……あまりに繰り返し夢を見るので、もうそれにもすっかり慣れてしまった。
そして、今また少女の前に黒犬の姿があった。
・
周囲に何もない。ただの真っ白な部屋の中。
少女と黒犬が向かい合って立っていた。
「よお。元気か?」
黒犬が口を開いた。
――うん。あれ。声が変かも。これじゃ反対だよ。
「良いじゃねーか。細かいこと気にすんなよ。夢なんだし」
――そうだね。
リサリサは黒犬を見つめて佇んだ。なんだか、いつもの夢と少し違う。
「どうしたんだよ黙り込んで。気色悪いな」
目の前の犬は、本当はもう死んでいる。今日はそれが解っていた。
だけど……それでも構わなかった。それでもやはり、話をしたいと思った。
――ねえ。
声を出そうとすると、代わりに自分の言葉が脳裏に浮かんだ。どうも調子が狂うが、ちゃんと聴こえているようなので気にしないことにする。
――どうしてあの時、逃げてくれなかったの?
「口を開いたと思ったらそんなことかよ。俺が逃げたら、お前が死ぬって云ったろ?」
――それはもう聞きました。
「じゃそれで納得しろ。雄より雌、年寄りより若い個体を残す。これは極めて基本的な生存戦略だ」
――なんか、納得できない。
リサリサは口を尖らせる。
「だと思ったよ。でもま、どっちか片方死ぬとしたら……俺しかねーだろ。どうせ俺は、誰にも求められていない存在だ」
――そんなこと……ないよ。
「それ、慰めてんの?」
――それに、ちゃんと命令したのに、どうして?
リサリサが困惑と後悔の入り混じった哀しげな眼差しを黒犬に向ける。
あぁ、と声を上げて黒犬はばつが悪そうに一旦視線を外したが、すぐにまたリサリサを見返した。
「……云ってなかったっけ? 俺は“制約の環”を外してもらったんだ。お前の命令はとっくに無効だったんだよ」
――え? どうやって?
あの遺跡の関係者はもう誰も居ない……云いかけて、リサリサはすぐそれが間違いだと気がついた。
――あ……! あの時の綺麗な男の人ね?
「その時だな。“綺麗な”は余計だが」
黒犬があっさり認める。
そうだった。憩いの森で出会った髪の長い男、彼は黒犬の前の支配者だと云っていたではないか。ということは、つまり彼は環を作り出した人達の一員だ。
もし環を外せたとしたら、あの時をおいて他に考えられない。
――あれ? でもおかしくない?
リサリサは軽く握った右手を口許にあて、思い出すような仕草を見せた。
「何がだ?」
――水浴びしたのって、あの次の日だったよね? その時、私の命令ちゃんと効いたような……。
「そんな事あったっけ。何か勘違いしてるんじゃねーの」
――そうかな……。でも、外したなら、なんですぐ教えてくれなかったのよ。
リサリサが頬を膨らませた。
「だな。うっかり忘れてた」
――こんなの忘れるわけないじゃん! あ、ひょっとして……。
「……なんだよ」
リサリサは自分の思いつきに自信を得て、意地悪く笑った。
――それを教えたら、もう私と会えなくなると思ったんじゃない?
「んな訳ねーだろ。普通に忘れてたんだよ」
――ふーん。
リサリサは後ろで手を組んで、軽く身を乗り出すようにして黒犬をじろじろ見つめた。
「なんだよそれ。……ま、でもとりあえず元気は出てきたみたいだし、そろそろ帰るかな」
――え。もう?
返事を待たずに、黒犬は少女に背を向けて歩き出していた。
その姿が、少しづつ遠ざかる。
リサリサは走って追いかけようとした。だけど沼地にでも踏み込んだように、足は一向に前に進まない。彼女は必死に走り方を思い出し、左右の脚を交互に動かした。
――待って。行かないで。
黒犬が立ち止まり、軽く振り返る。
リサリサは手を伸ばしたが、指先すら届かない。逆に黒犬との距離は遠ざかったようにすら感じた。いつの間にか、彼女は泣いていた。
「お前は馬鹿だけど、そこそこ良い友人だったよ」
黒犬は少女の姿を優しく見つめて、青い目を細めた。
「……じゃあな、リサリサ」
そして、黒犬の姿は消えた。
・
リサリサは、ベッドの中で目を開けた。
自分の部屋の天井が、滲んで見える。
――がじちゃん。
口の中で、そう呟いてみた。
――大丈夫。
リサリサは半身を起こし、涙を手で拭った。
窓の外に目をやると、幽かに空の端が白んでいる。もう明け方が近かった。
――私は、大丈夫だよ。
いつもの夢を見た後は、胸が潰れるような気持ちになった。
今日のは違う。
これまでに見た夢とは、全然違っていた。
少し時間が掛かったけれど、ようやく私は、彼の死と向き合うことができる。
ようやく私は、彼の最期の思いを受け止めることができる。そんな気がした。
薄く射し込む朝の光の中で、リサリサは軽く目を閉じた。
あの時、言葉にする前に消えてしまった彼の最期の意思。それを、もう一度心に思い描く。
――きっと、こんな感じで良いんだよね?
リサリサはそれを自分なりに理解して、心の中の黒犬に語りかけた。
勿論返事は無い。だけど、彼が生きていたとしても、きっと照れて誤魔化しただろう。
あの時感じた彼の思い、それは間違いなく、暖かいものだったから。