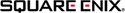リネット 消えた猫
──消えた猫──
特にやる事も無く、村の中をぶらぶらと散歩する。かつてはアラセマの冒険者がうろうろするだけで、つぶてやゴミを投げつけられたという噂がまことしやかに囁かれていたが、今ではそんな事もないようだった。とは云え、村人が突然陽気になるはずは勿論無く、【NAME】は活気の無い静謐とした村の中を、ただ漫然と散策するしかなかった。
ふと、アラセマで療養していたクィナ・センテの事を思い出す。彼女はもう村に戻っているだろうか? もっとも、戻っていたとしても恐らく会うことも無いだろう。センテの一族はコルトレカン島では恐らく唯一の主氏族、重要な儀式には欠かせない存在だ。今頃は“黒い切り株”を再度塞ぐ作業に追われているのかも知れない。
少し寂しいような、手持ち無沙汰のような、曖昧な気怠さに囚われる。周辺で亜獣でも狩っていた方がマシだろうか、とそんな事を思い始めた時――。ふと、視界の隅に動く影を捉えた。見ると、質素な民家の影に隠れるようにして黒猫が【NAME】の様子を窺っている。
(珍しいな……)
シレネやリコルスでは野良猫の類も多く見られたが、思えばサリクトラムで猫を見たのは初めてだ。黒猫は少しの間、警戒心を浮かべた緑色の瞳で【NAME】を見つめていたが、やがてプイとそっぽを向いて歩き出した。スタスタと、すまし顔で黒猫は村の外へと歩いていく。
(……毛並みの良い猫だな)
キヴェンティもペットを飼い始めたのかな――と、そんな事を考えている内に黒猫はさっさと村の門を越えてどこかへ行ってしまった。
・
「あれ?」
茫と去り行く黒猫を見送って立ち尽くす【NAME】の背後から、男の声がした。振り返った【NAME】を見て、魔術師風の男は「やっぱりそうだ」と柔和な笑みを浮かべた。白い猫が甘えるような声を上げて、その足元に付き添った。
左右で色違いの特徴的な瞳に、若干奇妙な魔術師風の服装と、猫……。忘れるはずもない、サンメアリ号で一緒だった猫魔術師リネットだ。
「生きてらしたんですね。良かった。あの船の生存者はもう誰も居ないのかと思ってました」
早口にまくし立てて、彼は【NAME】の手を両手で握ってぶんぶんと振る。どうやらそれは再会を喜ぶ握手のようだ。
しかし、同じ疑問を【NAME】も抱いていた。リネットのそれより、おそらく深く。
(なんで……彼は殺されなかったんだろう)
だが、リネットはそんな理由については興味が無いようだった。あそうだ――と明るい声を上げて、バックパックから何かを探り出す。
「これ、良かったらどうぞ。僕の著書なんですけど」
「この村の書店でも売ってもらう事になったんで、良かったらそっちの方もお願いします」
リネットは期待するような目で【NAME】を見た。どうやら、体験版を渡して残りを店頭で買ってもらう戦略のようだ。愛想笑いをして【NAME】は受け取った本をぱらぱらとめくって見たが、大した内容では無さそうだった。
(これを買うのは余程の物好きだな……)
「ところで、ミネアという女性を知りませんか。実は、僕がコルトレカン島へ渡ったのは彼女を――祖母を捜す為だったんですけど」
立ったまま本をめくっていた【NAME】に向けて、徐にリネットがそう切り出した。
(祖母……?)
「そうです。母方の祖母。僕が生まれて間もなく、家族を捨てて一人故郷へ帰ったらしいのですが……つまり、それがこの島だと聞いた訳です」
リネットは何時に無く真摯な表情をしていた。しかし――。
(……聞いたことは無いな)
首を振って答えた【NAME】に、リネットは「そうですか」と短く嘆息する。
「リコルスから街を回り、縋る思いでこんな村まで訪ねてみましたが――どうも、無駄足だったようです。……帰るよ、ショコラ、ガトー」
足元を振り返って、リネットが呼びかけた。おそらくそれが猫の名前なのだろう。そういえばサンメアリ号を脱出する時、彼は白猫と黒猫を連れていたような記憶があった。
「あれ……ショコラは?」
しかし、彼の呼びかけに答えたのは足元の白猫ただ一匹だった。リネットは物陰を覗きこんだりしながらショコラを呼び続けたが、一向に現れるような気配は無い。
「もしかして一人で餌を探しに行っちゃったのかな……。でも、この辺りで食べ物が採れるような場所、あったっけ……」
リネットが考え込むような仕種を見せる。しかし、猫魔術師のくせに餌不足でペットに逃げられてしまって良いものだろうか。
「とりあえず、僕は執筆活動のため暫くサリクトラムに滞在する事にしたので、もしそれらしき黒猫を見かけたら連絡して下さい」
リネット ショコラを追いかけて
──残された足跡──
ギアス聖域はキヴェンティ達にとって特別な意味を持つ森だ。
従来よりおいそれと侵入の許されるような場所では無いが、今はまた違う意味で立ち入りが禁止されている。ギ・ロの一件で白宝宮に穿たれた世界の境界――“黒い切り株”が未だに存在しているからだ。コルトレカン島のキヴェンティ達は現在、翆獣の僕たる誇りに懸けて“黒い切り株”を再度塞ぐ術式に追われている。当然ながら、見学させてもらうのは無理だろう。
どうせすぐに追い返されるだろうと予想しつつ、【NAME】は森の外輪を覗いてみた。
(ん……?)
何かが目の端に引っかかったような気がして、【NAME】は立ち止まる。
(小動物の足跡か?)
足元を覆う木の葉の間、湿って柔らかくなった黒い地面に、小さな跡が点々と残されていた。注意深く観察しなければ見落としそうな微かなものだ。足跡は消えかかりながらも森の奥へと続いている。
(ひょっとして……ショコラ?)
そういえばリネットの相棒の黒猫、ショコラは未だに行方不明になったままだ。もしかすると、餌を捜し求めてこの森の奥まで行ってしまったのかも知れない。
──ショコラを追いかけて──
小さな足跡を追いかけ、聖域の奥へと侵入することにした。
森に少し踏み込んだだけで、辺りは途端に暗がりに包まれた。黒く捩じれた木々の間を、濃い霧が漂い始める。遠くで、ほぅ――と何かが啼く声が聴こえた。振り返ると、既にもと来た道も白い霧に閉ざされている。薄暗い森の中はまるで別世界のように、外界から孤立していた。
【NAME】は出し抜けに肌寒さを覚えた。
過去ギアス聖域を訪れた際には亜獣の類には遭遇しなかった。神聖な森なのだから、あるいはそれも当然なのかも知れない。だが――。
(……何かいる)
岩陰に蠢く何かの気配を、【NAME】は敏感に察知した。
battle
聖域に潜む影

(何だ、今のは……)
異形の怪物を追い払い、【NAME】は一息ついた。それにしても、こんなものが「聖域」に残っていて良いものなのだろうか――。そんなことを思いながら、束の間の休息に身を任せる。
「誰だ」
突然の、凛とした声。
霧の向こうから現れた小柄な影は、キヴェンティの装束を身に纏った金髪の少女――クィナだった。クィナは【NAME】を見て少し驚いたような表情をつくる。
「“あれ”の様子を見に来たのなら……そんな必要は無いと云っておく。ここは今、僅かだが概念の澱みが生じている。ユーリが向こう側との境界を開いた影響だろうが――無論、貴様が心配するような問題ではない」
さあ帰れ、と云わんばかりの口上を陳べ、クィナは腕組みをする。取り付く島も無いのは相変わらずだが、いきなり斬りかかって来なくなっただけマシだろうか。とりあえず、怪我の調子は良いようだ。
(さて。猫の話を信じてもらえるかどうかだが……)
少し迷った末、【NAME】は正直に黒猫探しの件を説明することにした。
「猫だと……?」
聞く耳など持たないかと思われたクィナが、予想に反して少し考え込むような仕種を見せた。
「待て。貴様には話しておかねばなるまい……。今、リネットという男が『人捜し』の為にサリクトラムを訪れている。当たり前だが、アラセマ人が捜すような人間は本来そこには居ない」
(そりゃ、キヴェンティの村だからな)
「良いか。もし奴の話を聞いて、何か下らない事を思いついたとしても……余計な事を教える必要は無い。それが奴の為でもある」
それだけ云って、クィナは背を向けた。
「猫を見つけたら、早急に立ち去るが良い」
霧の中に消え行くクィナの背中に、【NAME】は小さく感謝した。
リネット 真実の埋葬
──ショコラを追いかけて──
殆ど見分けられないような足跡を懸命に追いかけ、【NAME】は更に聖域の深部へと踏み込んだ。
霧は更に濃度を増し、辺りは夜と見紛うような暗がりに変じていた。唯一の手がかりである小さな足跡も既に判然としない。これ以上の追跡は無理かと、そう思われた時――。
がさ、と落ち葉の擦れる音。
(――居た!)
黒い大樹の根元に、溶け込むようにして黒い猫が佇んでいた。緑色に光る双眸が素早く【NAME】を捉え、猫は動きを止めた。間違いない、サリクトラムで見た黒猫、ショコラだろう。
(……)
そのまま、暫し無言で黒猫と見詰め合う。重要な問題に突き当たったからだ。
(……どうやって、連れて帰ろう)
試しに、持っていた鼠のしっぽを差し出してみた。
動物を懐柔するなら食べ物と昔から決まっている。
ショコラは少しの間【NAME】の様子を窺っていたが、やがて「ニャ」と短く鳴いて近づいてきた。
差し出した餌をショコラがはぐはぐと食べる。幸せそうに眼を細めて食事を取る黒猫の姿はそう――隙だらけだ。
(愚かな。所詮は猫)
捕獲成功――と心の中で勝ちどきを上げて黒猫に手を伸ばす。次の瞬間――。
(何だって!!!)
伸ばした両手が空を掴む。寸前でショコラが身を翻したのだ。しなやかな動きで【NAME】の腕をすり抜けた黒猫は、冷ややかな一瞥を残してすたすた森の出口方向へと歩き出した。相手を甘く見た慢心が、捕獲の失敗を招いたのだ。
反省する【NAME】の方を振り返り、ショコラが立ち止まって短く鳴いた。察するに、『行くぞ』とでも云いたいのではないか。
とぼとぼと【NAME】が後からついて来るのを確認すると、ショコラは再び歩き出した。どうやら、【NAME】を引き連れて帰るつもりのようだ。
──ショコラを連れて──
ショコラを連れて――もとい、ショコラに連れられて【NAME】は森を行軍する。
後はギアス聖域を抜け、リネットの待っているであろうサリクトラムへと戻るだけだ。しかし、たったそれだけの仕事がそれほど容易ではないという事に、【NAME】は気がついた。
ショコラが立ち止まる。
(やっぱり……居たか)
はっきり景色を覚えている訳ではないが、来る時にも通った場所だと直感した。そう……岩陰に潜む何かと戦った、あの場所だ。その者の姿はまだ眼には映らない。けれども、確実にそこには「何か」が――それも、とても厭な「何か」が潜んでいる。
ショコラが「フー」と不機嫌そうな声を上げて、毛を逆立てた。どうやら戦う気満々のようだが、果たして主人無しで戦闘できるのか……。とにかく、ショコラが怪我しないよう充分注意しなくてはならないだろう。
battle
猫を狙う影

なんとか無事に切り抜ける事ができ、ほっと一息つく。この先はおそらくもう安全だろう。後は一気に聖域を抜けて、リネットの待つサリクトラムへ向かえば一件落着だ。
──真実の埋葬──
多少のトラブルはあったものの、なんとか【NAME】はショコラと共にサリクトラムに戻ることができた。
後はショコラを飼い主の許に届ければ万事解決だ。リネットが猫を置いてどこかへ旅立つはずも無い、探せばすぐに見つかるだろう。
正午も近い陽射しの下、閑散としたサリクトラムの村内を歩き回る。程なくして、リネットの姿は見つけることができた。
「ああ、ショコラ!」
無事だったか――と声を上げてリネットが駆け寄って来る。ショコラの方は飼い主に一瞥をくれただけで白猫と何事か挨拶を交わしだしたが、リネットは特に気にした様子もなく良かった良かったと独りごちていた。
「わざわざ送り届けて下さったんですね。ええと……お礼をしたいのですが、ちょっと用ができたので、こちらの方へ」
リネットが歩き出す。何も云わなくても二匹の猫は後ろをついて歩いていた。更にその後ろを【NAME】が追いかける。用と云っても、この村でできるような事は少ない。おそらく件の祖母捜しの続きなのだろう。
主氏族の方と直接話せることになったんです――とリネットは声を弾ませた。
・
「お待たせしました。わざわざすみません」
そうリネットが声をかけた相手は、クィナ・センテだった。彼女は【NAME】を見ても特に反応を示さず、木造家屋の壁にもたれて陽射しを避け、腕組みをしていた。
「構わぬ。一通り話は聞いているが……祖母を捜しているのだったな」
「はい。名前はミネアですが、今思えばそれも偽名だったかも知れません。女神様にあやかった名前で、僕らの故郷では一般的ですし……。あ、あと、外見も多分、年寄りでは無いです」
「……」
クィナの緋色の瞳がちらりと【NAME】に向けられた。しかし、彼女は何を云うでもなく、黙ってリネットの話の続きを待った。
「実は、僕は純血の人間ではありません。ちょっと、変でしょう」
リネットが自分の瞳を指差して苦笑を浮かべる。サンメアリ号で彼を見た時にも気付いていたが、確かに彼の瞳は少し変わっていた。右目が灰色で、左目が朱色だ。
「祖母はどうも亜人だったらしいんです。僕がずっと小さかった頃にもう彼女は行方を眩ましているので、僕自身が覚えている事はあまり多くは無いのですが……とても綺麗な女性だったと記憶しています。きっと長命種だったんでしょうね」
リネットは少し空を見上げるようにして、思い出すような仕種を見せた。
「そう……長い黒髪と、朱色の瞳が印象的でした」
(……え)
リネットの言葉に、【NAME】の心臓が一つ大きく跳ねた。長い黒髪と朱色の瞳を持った亜人の女性――それは、もしかすると『彼女』の事ではないだろうか? リネットは続ける。
「祖父が亡くなったこともあるのでしょうけど……結局、失踪の原因は判りません。故郷に戻る――と、それだけ告げて消えたそうです。それがつまり、コルトレカンの事だったらしいのですが……お願いします、何か手がかりはありませんか?」
リネットの縋るような視線を受け、クィナは瞑して大きく一つ息を吐いた。
「生憎だが……そんな者はこの村には居ない。ミネアという名も知らないし、似た外見の女にも覚えは無い。――これで良いか」
にべもないクィナの答えに、リネットは「そうですか」――と項垂れた。
静かに半眼を開いてクィナがそれを見つめる。彼女の眼差しに、【NAME】は逡巡の色が浮かんだような気がした。一呼吸だけ置いて、クィナが口を開く。
「その女を見つけたとして――どうするつもりだ」
彼女の問いに、リネットは一瞬不審げな顔をして口篭ったが、
「……死ぬかもしれない人を、放って置く訳には行かないでしょう」
それだけ答えて悄然と踵を返した。
「それは、彼女自身の選択だ」
クィナは立ち去るリネットの背に呼びかける。
「自分で選んだ運命ならば、後悔は無いだろう。結果としてその先に何が待っていようとも」
リネットは何か云いかけてそれを押しとどめ、視線を落とす。
「うん……あの人ならきっと、そんな事を云うと思う」
僅かな沈黙の後、でも――とリネットが顔を上げた。
「……それでもやっぱり、諦められなくて」
リネットが苦笑いを浮かべた。
クィナは答えず、それで話は終わりになった。
リネットは【NAME】に向き直り、ショコラの件について簡単にお礼を陳べた。【NAME】も適当に相槌をうってから別れを告げる。
「僕はしばらくシレネに滞在するので、何かあったら訪ねてみて下さい。……まあ、おもてなしはできませんけどね。住宅街の奥で少し入り組んでますが、向かいに猫の看板のお店があるから近くまで来ればすぐ判ると思います」
それからリネットは猫を従え、村の出口に向かって数歩進み、止まった。
「もしかして、本当はもう彼女は――」
やおらクィナを顧みて、リネットはそこで言葉を切る。クィナは無感動な瞳で、黙ってリネットを見つめ返していた。
「……いや、何でも無いです。ありがとうございました」
リネットが二匹の猫を従えてサリクトラムを後にする。ショコラは途中で【NAME】を振り返ると、聴こえるか聴こえないか程度の鳴き声を上げた。たぶん、別れの挨拶なのだろう。
去り行く彼らの様子を、クィナと【NAME】は見えなくなるまで黙って送っていた。
・
――果たして『彼女』がアラセマに渡り、人間と結婚までしていたなどという可能性があるだろうか。考えたところで詮無い事と判っていても、どうしても思考が流れてしまう。
クィナが腕組みを解き、凭れていた壁を軽く蹴って陽射しの中に出た。
「貴様の考えている事は判る……だがそれを確かめる術は無いし、奴にこれ以上憶測を聞かせる必要も無い」
それは、確かにその通りだった。釈然としない風の【NAME】を見て、クィナが鼻でせせら笑う。
「仮令それが真実だったとしても何になる。奴自身が謂れの無い迫害を受けるのが関の山だ。あるいは『貴方の祖母を殺したのは私です』とでも云うつもりか?」
それはそれで一興だがな――とクィナは嗤って、その場を去った。
一人残された【NAME】に出来たのは、気怠い日差しの中をただ立ち尽くす事――それだけだった。