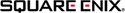神形器 血の跡
──血の跡──
アナナスの路面に、黒い線が残されていた。
その線は何かを引きずったように石畳を伸び、封鎖された多く地下道別口の1つへと続いていた。普段誰も訪れないような町外れであり、発見したのはとりわけ熱心な清掃員だったという。
血の跡。
誰もが口には出さないが、そうに違いないと考えていた。そして、清掃班によって入り口の石蓋が外された時、その考えに間違いが無かったことを知った。
石蓋の下から見つかったのは、鼠に喰い散らかされた死体だった。
・
その日、アナナスの街は殺人の話題で持ちきりだった。
何でも、郊外で死後数日以上が経過した男の死体が見つかったという。どんな手口で、何故殺されなければならなかったのか。人々は眉をひそめながらも、久しぶりの身近な醜聞に心躍らせているようだった。
だが、【NAME】には気がかりな事があった。被害者の名前――所持品や近場の宿の記録などからマイス・ゴートンという名の旅人だと判ったらしいのだが――どうも、どこかで聞いたような気がする。
全く顔が思い浮かばないことからして、おそらく直接会ったことは無いのだろうが……あれは一体どこで聞いた名前だっただろう。
益体も無くそんなことを考えていたからなのか、気が付くと【NAME】はアナナス郊外側の地下道入り口の方へと近づいていた。件の死体が発見されたという、封鎖された入り口の方だ。
曇天の下、血の跡が発見されたという路面に目をやる。勿論、今は清掃班によって「黒い線」は消された上、周囲には立ち入り禁止のロープが張り巡らされている。発見当初に辺りを取り巻いていた野次馬も、今はもう居ない。
こんなところへ来ても仕方が無いと、頭ではそう判っているはずなのだが。何か拭いきれない違和感があった。被害者の名も気になったが、もっと決定的な部分で。
そう、アナナスは清掃が盛んな街だ。人通りのほとんど無い郊外の一角とはいえ、路上の血の跡が数日放置されていたというのは不自然ではないだろうか。偶然、この周囲にだけ誰も近寄らなかっただけか、さもなくば――。
(……隠匿されていたのか?)
そう考え付いたとき、市街とは逆の方向に気配を感じた。
一見するとそれは単なる小さな林のようだった。細い小道が奥へ続いている以外、特に目を惹くこともない――。だが、今、確かに誰かがそちらに入っていったような気がした。
【NAME】は小さな林の奥を注視したまま、考えを巡らせる。
(隠匿結界が張られていたとしたら、その中心はどこだ?)
この地下道の入り口だろうか。違う。ここは既に過去に封鎖済みの場所だ。注意を逸らす結界の中心が、ここであるとは考えにくい。もちろん、死体を中心に隠していた――そういう考え方もある。しかし、【NAME】には他に気になることがあった。
『一部の隠匿結界が誰かに破られた』
ギアス聖域で、ワンはそう云っていた。それが、ここではないだろうか。
それが何なのか……場合によっては、確かめる必要があるかもしれない。
神形器 第二の鏡
──第二の鏡──
[BossMonster Encountered!]
battle
黒の揺りかご

とどめの一撃を受け、黒い肉塊は大気に滲んで崩れ行く。
(今のは……)
間違いない。リコルス港に出現したものと同じ「何か」だった。
ふと、祠の中で何かが光を反射しているのに気付く。次第に後退していく周囲の黒いぶよぶよが消えるのを見計らって中を覗いてみると、そこには一枚の割れた鏡が収められていた。
祠の外観と同じ、三本脚の不思議な獣を模した彫像が、抱え込むようにして鏡を固定していたようだ。今、それは鏡もろとも真っ二つに切断されていた。
先ほどのキヴェンティの男は、これを護っていたのだろうか。
ぽつり、と。
佇んだ【NAME】を追い返すように、雨が降り始めた。
今ここで出来ることはもう無い。一旦引き返すしか無いだろう。
・
「……はい、これで全部です」
むっつりと押し黙って座るネスカートの前に、うずたかく積まれた本の山。新たな一冊をその頂上に乗せて、ケイジュは窓を見た。
「うーん良い雨ですね。雨の日はなんだか心が落ち着いて、読書も捗るでしょう」
「良いからお前も読めよ」
顔も上げず、ネスカートは脇に積まれた本を一冊取ると、机の上を滑らせてケイジュによこした。『コルトレカン伝承1』と題されたその本を受け取ったケイジュは、借り物なんだから丁寧に扱って下さいよ――と云いつつ、ぱらぱらとめくって眺め出した。
「なになに。はるか昔、芯海には何も無かった――起源譚ですか」
「ああ。ユーリ先生に新たに書き下ろしてもらった奴だ。古い歌や伝承の類ってのは……ただの御伽噺である場合も多いが、裏になにかしらの真実を隠している場合もある……ふわぁ~」
「確かに、先日ユーリさんが説明していた話ですね、これ。鬼がどうとか、獣がどうとか」
「うむ……ギ・ロとマギサの詳しい話は2巻を参照……」
云ってネスカートは新たな一冊をケイジュの方へ滑らせる。
「そんないっぺんに読めませんよ。マギサというのが2匹のもう片方ですか」
「ああ」
「さすがにアラセマの調査より詳しいですね、これユーリさんによる記録でしょう」
「ああ」
気の無い返事をするネスカートを、面白くなさそうな顔でケイジュが見る。ネスカートの方は『黒い切り株の向こう』と題された民話のようなものを読みふけっていた。先ほどケイジュが持ってきた一冊だ。
「結局……神形器さえあれば、別に余計な調査は無くても安心なんですよね」
「諦めろ。あれは今、眠っている……多分な。今できることをやった方が良い」ネスカートが本の頁を繰りながら答えた。
「眠るんですか。武器が?」
「言っただろ、ゼーレンヴァンデルングは恒常を厭う流転の神形だ。それ自身の概念も常にゆらぎ続け、いつでも同じ力を揮う訳じゃない。人間が寝たり起きたりするのと同じ感じだ」
「難儀ですね」
「使い手の意思に応じて姿すら変えるというからな……実際に見たことは無いが。しかし、あんなもの盗んでも良いことは無い筈なんだがな」
はい、終了――と云ってネスカートは本を机に積んだ。
「え。もう全部目を通したんですか」
「うむ。大体覚えた。『黒い切り株の向こう』なんかは面白い。お奨めだ」
「あからさまに関係無さそうな題ですね」
「そうでもないさ。キヴェンティは一族の悲願を達成するために、黒い切り株の向こうへ行った――とか、理想郷譚みたいだが、ちょっと変なところがある。まあ、とにかくお前も全部読んでおけよ」
ネスカートは立ち上がり、ぐっ、と組んだ両手を伸ばして体をほぐした。じゃあな――と言い残して、そのまま部屋を出る。
「ああ……」
げんなりした顔で、ケイジュは机に積まれた本の山を見た。
「なんか……鬱陶しい雨ですね……」
神形器 第三の鏡
──第三の鏡──
[BossMonster Encountered!]
battle
黒の揺りかご

とどめの一撃を受け、黒い肉塊は大気に滲んで崩れ行く。しかし――。
(まただ……)
手応えが無い。目の前の黒い物体は確かに消え始めているが、倒した、という感じがしない。おそらくは、まだ完全に体が具現化できていないのではないか――そう思わせる「不確かさ」があった。
だが、確実に以前よりは力を取り戻しつつある。それだけは感じられた。
祠の中には、やはり割られた銅鏡が収まっていた。
これで、3つ目。
誰かが、これを割るために島を徘徊していることは間違いない。油断なく周囲に目を配るが、既にその何者かの姿は無かった。
おそらく、封印されていたと思しき先の肉塊を解放するつもりなのだろうが……。見た限り、「あれ」には高度な知性は期待できない。仮に完全な状態で地上に姿を現したとして、使役することなど到底叶わないだろう。ただ混乱が生じるだけでは無いのか。
(あるいは混乱を起こすだけが目的か……)
いずれにせよ、関わり合いにはなりたくない話だった。
・
「やっと全部読み終わりましたよ」
嬉しそうな表情で、数冊の本を抱えたケイジュが廊下を進む。入りますよ、師団長――と声を掛けてから、突き当たりにある一室の扉を押し開いた。
応接用の机と椅子、その向こうに奇怪な魚をあしらった悪趣味な衝立が見える。最近手に入れた遠方の土産物とやらで、魚はシーラーズという名らしい。珍しいということでネスカートはいたくお気に入りの様子だったが、正直なところケイジュにはどこが良いのかさっぱり判らなかった。
応接用の机の上に持参した本を重ねながら、ケイジュはその衝立の向こう――扉を隔てた隣室に居るであろう師団長に向けて話しかける。
「もう完璧です。フローリアの歴史についてなら何でも聞いて下さい。民話も忌峰の狐憑きから黒い切り株まで、全て暗誦できますよ」
そう、これでユーリから借りたコルトレカン関連の書物は、新たに書き起こしてもらった物も含めて全部だった。事実上、サリクトラムに関して現存する書物には、全て目を通したことになる。
「ところで、アナナスではまた旅人の死体が見つかったそうです。今度はマイス・ゴートン」
無造作に積まれた本を整理しつつ、ケイジュは奥の衝立に向かって話し続ける。
「やはり、サンメアリ号の乗員は既に殆ど殺害されているようですね。それも、総じて一週間以上も前に、です。ちょうど港のギ・ロ騒動の前あたりですが……何か関係があるんでしょうか」
しかし、しばらく待ってみても反応が無い。訝しげな表情で、ケイジュが顔を上げた。
「師団長?」
返事は無い。
「失礼」
古魚の衝立を避けて、ケイジュが奥の部屋――師団長の私室へ続く扉を開いた。
「居ない……」
がらんとした部屋の中、師団長たるネスカート・ワイゼンの姿は、どこにも見当たらなかった。
神形器 仮面の男
──仮面の男──
遺跡の町アナナスを出て、サリクトラムを目指し街道を進む。
島南部の街道とは異なり、討伐の手の薄いこの辺りでは危険な亜獣が多い。適度な休息を取りつつも、常に警戒は怠らないよう進んでいく。
だから、木陰から現れたその男を見たときも、【NAME】は敵と判断して武器を構えたのだが――。
「まてまて。俺もアラセマの人間だぞ」
開口一番、そう云って男は手を振った。
――怪人。
それが、彼を見た第一の印象だった。
がっしりとした体格は戦士を思わせる。だが、肝心の武器を携帯していないし、微妙に高価そうな衣装は格闘にも不向きだろう。冒険者なのか何なのか、今ひとつ判断を下せない中途半端な外見。
そして、何と云っても決定的に怪しいのは、鷲のような怪鳥の仮面で顔の上半分を覆っていることだった。
「ん。なんだ。これか?」
【NAME】の疑惑の眼差しに気づいたのか、男は自分のつけた仮面を指さした。
「なかなかお目が高い。こいつは東大陸の土産物で、『蒼天を断つ翼ラ・ズー』を模した逸品だ」
云って男は口元でにやりと笑って見せる。
「貰った物は使う主義なのでこうして被っている訳だが……まあ、良くあることだな」
良くあるかどうかは疑問だが、この程度の変人ならば冒険者には良く見受けられるのも確かだった。
それに、とぼけたことを云っているものの、その立ち居振る舞いには隙が無い。やはり何か戦闘技術を身に着けているのだろう。
未だ疑いの抜けきらない【NAME】の視線を受けて、こほん、と男が咳払いをする。
「実はキヴェンティの村で色々調べたいことがあったんだが、あの通りの村だからな。二の足を踏んでいたところだ。ここで会ったも何かの縁、ということで、村まで一緒に行かないか?」
確かにサリクトラムではアラセマの人間は歓迎されるとは言い難いが、随分気の小さい話だ。とりあえず敵では無さそうだと判断を下し、【NAME】は同行を承諾することにした。
「ありがたい。俺の名は――」と、男はなぜかそこで一旦言葉に詰まり、
「……ソードだ」
云って右手を差し出した。
自分も名前を告げて握手を交わしながら、【NAME】は妙な事に気付く。ソードと名乗った男の右手は、武器を使い込んだ人間の手をしているのだ。しかし、彼は今丸腰だった。行きずりの人間に対し余計な詮索は無用、とはいえ、少しだけそれが気になった。
考えられる合理的な説明は――。
(武器、壊れたのかな)
それが【NAME】の結論だった。
しばらく無言のままサリクトラムへの道を同行する。
別段おしゃべりが必要とは思わないが、ソードの方はそう考えてはいないようだった。歩きながら、おもむろに話を切り出してくる。
こう見えても俺は、人の縁ってやつを信じる方なんだ――とか、どこかで聞いたような話だった。
「ところで、冒険者なら各地を回っているわけだろう。何か面白い噂話を聞いたことがないかな」
たとえば、とソードは続ける。
「殺すことのできない獣、とか」
【NAME】は足を止めてソードを見た。彼の方も歩みを止めて振り返る。柔和な口元とは裏腹に、鳥の仮面の奥から覗く鳶色の瞳は、刺すような鋭い輝きを持っていた。
(殺すことの、できない獣……)
普通に考えるといわゆる不死体、アンデッドのことを指しているように思えるが――【NAME】の脳裏には別なものが像を結んでいた。
港や森の奥で見た、あの黒い肉。あれは――。
「ほう。何か心当たりでもあるのかな」
返答に詰まった【NAME】を見て、世間話でもするようにソードが云う。
(この男……何を探っている)
だが、詮索はそこまでだった。ソードがサリクトラムの方角に顔を向ける。道の向こうから、近づいてくる何者かの姿があった。
「迎えが来たようだな。続きは後でゆっくりと」
──襲撃の火蛇──
「やはり来たか。アラセマの民よ」
サリクトラムに続く道の向こうから現れたのは、槍を手にした銀髪の若い男だった。その独特の装束を見るまでもなく、キヴェンティの戦士であることは明白だ。
「お邪魔します」
ソードは男に向かって手を挙げたが、その挨拶は男の気には召さなかったようだ。
「参れ、カダ」
男の声に呼応して、青く燃え盛る半透明の蛇が姿を現し、その槍に巻きついた。
おそらく初めて目にするであろう翆霊を前にしても、ソードは全く動じた様子もない。
「なるほど、それが翆霊か。炎の蛇を使役するのは、従氏族ホノエ・マロウ……だったかな」
銀髪の男――ホノエは答えない。
「だが、短気は損気だぞ。俺はしがないただの旅人だ」
ソードは云って、戦う気は無い、というようなアピールをした。
「ふざけるな。今、この時にサリクトラムを訪れる者、それは獣の解放者しかありえない」
ほう、とソードは考え込むような仕種を見せる。
「ではやはり、封印を解いているのはキヴェンティではないのか……」
「妄言を。これまでの封印が解けたことを見ても、アラセマがギ・ロを復活させようとしていることは明らかだ」
ホノエが槍を構える。
「おい。待てよ」
「命脈に背く迷の民よ、遙か彼方、摂理の環の果てに消え去るがいい!」
ソードの制止の声を無視し、ホノエが地を蹴った。
やれやれ――そう云ってソードは右手を天に掲げる。小さく「ウルサ・マヨル」と呟くと、次の瞬間、その手の内には半透明の刀身を持った美しい剣が現れていた。
[BossMonster Encountered!]
battle
誇り高き炎士


召剣――。
既にその剣の姿は掻き消えていたが、ソードは今、戦いの最中に他概念世界から剣を呼び寄せていた。そんなことが出来る人間は、そうは居ない。
(どう贔屓目に見ても“ただの旅人”じゃないな……)
【NAME】の疑惑をよそに、既にソードは倒れたホノエに駆け寄っていた。
「おい。しっかりしろよ」
ソードが倒れたホノエを抱え起こしたが、意識は殆ど無い。
「これだから人の話を聞かない輩は困るな……まだ訊きたいことがあったのに」
ソードが懐から何かの紙を取り出した。
「キヴェンティはこの連中を知っているか?」
半眼を開けたホノエに向かって、ソードが何かを読み上げた。
グンナ・フューニー
マイス・ゴートン
シルギン・テオノール
……
(ああ、これは)
マイス・ゴートン。それはアナナスで先日見つかった、死体の名だ。そして、これらの名前をどこで見たのか、【NAME】はようやく思い出した。
(サンメアリ号から、救助された人間のリストか)
そういえば、自分はあの時、結局名前を書かないままで眠ってしまった。だから、【NAME】の名はそのリストには出てこない。しかし、これを聞かせてソードはどうしようというのだろう。
案の定、ホノエは眉を顰めただけで、答えない。
やはり知らないかな――とソードは云って紙片を収める。
「このまま置いていくのもナンだが、仕方ない」
荒れた街道の脇に立つ楡の大樹にホノエの体を預け、ソードは立ち上がった。
「もうサリクトラムは目と鼻の先だな。念のために訊いておくが、あんたは獣の封印は解いていないだろうな?」
違う――そう云って【NAME】は首を振った。
「そうか。その言葉、信じるとしよう。たとえギ・ロの肉片と出会っていたとしても……星の巡り合わせが悪い奴ってのは居るもんだ。俺はこれからサリクトラムに行くつもりだが――この調子では歓迎してもらえそうもないな。あんたも、準備が必要なら一旦アナナスに戻っても良いぞ」
じゃあな、と言い残して、ソードは迷わず村の方へと歩き出す。
鴇色の翼を備えた一羽の巨大な白い鷹が、大樹の枝からその様子を見送っていた。
神形器 最後の鏡
──最後の鏡──
フローリア諸島の先住民族、キヴェンティの暮らすサリクトラム。
普段は閑散とした村だが、今は門のすぐ内側に人垣が出来ていた。その中心に居るのは鳥の仮面の男、ソードだった。やはりあの格好は衆目を集めているようだ。もっとも、村人達の顔に浮かんでいるのは、好奇というより不審の色のようだが……。
「お。来たか」
【NAME】の姿を認めてソードが振り返った。
「っと、こっちもやっと出てきてくれたな」
挨拶もそこそこに、ソードはまた前に向き直る。どうやら、探していた人物がやって来たらしい。
彼の見つめる先――人垣の向こうから現れたのは、白いドレスを着たユーリの姿だった。
「お久しぶりね、ネスカ――」
「初めましてソードです。その節はどうも」
云いかけたユーリの言葉を遮るように、ソードがそう畳み掛けた。が、
(なんか矛盾した挨拶だな……)
ユーリは暫しきょとんとした表情をしていたが、すぐに悪戯っぽい笑みを浮かべ、
「ではソードさん、お貸しした書物はお役に立ちましたか?」
うんうん、という具合にソードが頷く。
「それはもう。じきにお返しできるはずです。無茶なお願いを快諾してもらって申し訳ない。研究に差し支え無ければ良いのですが」
「いえ。大丈夫ですよ。あの本の内容は、全て憶えていますし」
トン、と人差し指でこめかみの辺りを指し、
「私、暗記は得意ですから」
云ってユーリはにこりと笑った。
「それに、コルトレカンに関する調査も、もう終わりです。ちょうど一通り纏めて本にしようと思っていたところでしたので」
そうですか、と答えながらソードはまた懐から何やら紙片を取り出していた。
何か質問を用意していたのだろう。だが、それは叶わなかった。
「退け」
人垣が瞬時に割れた。一人残ったユーリの後ろから、キヴェンティの少女が歩み寄る。
真っ直ぐにこちらを射抜く、冷たい緋色の瞳。
……間違いない。あの時、サンメアリ号に乗り込んできた娘だ。
「さがれユーリ。その連中は敵だ――それも、恐らく獣の解放者」
淡白にそう云った少女に向けて、ユーリが微笑みを返す。
「それはありませんよ、クィナ様。私が保証します」
「貴様の保証など何の意味もない」
クィナが右手を前に伸ばした。仰向けたその掌から白い大鷲が瞬時に現れ、鴇色の翼を広げて優雅に啼いた。
「ホノエは敗れたようだが私は違う。ここで始末する」
「離れていてください」
後退するユーリに声をかけてから、あんた達は離れなくて良いぞ――とソードは小声で付け加える。
「大丈夫ですよ。慣れてますので」
既に姿の見えないユーリにそう言い聞かせると、ソードは右手を空に翳して、剣を喚んだ。
[BossMonster Encountered!]
battle
緋色の暗殺者


勝負は決したかのように見えた――その時。
キン、という鋭い音が、サリクトラムの村に響き渡った。
「莫迦な……」
膝を付いたままクィナは北――ギアス聖域の方角を向いて呻いた。
「ワンは何をやっている!」
彼女の見つめる先、遠く霞んだ森の彼方に今、緑色の光柱が立ち昇って消えた。
「今のは……まさか」
ソードが呟く。
「獣の封印は解けた」
クィナがソードを睨め付ける。
「もはや貴様らに構っている暇は無い」
云うが早いか、クィナは村の外へと駆け出した。
「あの方角はギアス聖域……やはり白宝宮はそこか。しかし」
クィナの姿を見送りながら、ソードが口に手をあてて考え込む。
「まずい……まずいな。今のままで勝てるのか?」
・
また、あの声が聞こえてきた。
――いやな奴が来る。
この娘が目覚めると、自分の意識が薄らいで行く。
記憶が呑み込まれてしまう。
――あれも壊そう。
何故こんなものを背負い込んでしまったのか。
やはりあの時、選択を誤ったのだろうか。
素直にこれを渡しておけば良かっただろうか。
だがもう遅い。
――使って。
――私を使って。
……煩い。
短剣を模した首飾りを握り締め、ワン・テオは身を起こした。
神形器 朱色の瞳
──朱色の瞳──
日没の風が聖域を駆け抜ける。
静謐な森の中、白く冷たい霧を巻き上げながら、黒い木々の間を吹き抜ける風。
それが今、金属の腐蝕するような異質な臭いを運んでいた。
「仮面ごっこしてる場合じゃなくなったな……」
聖域を前に、立ち止まったソードが軽く嘆息する。
「『ソード』は、ここで終了だ」
云って、鳥の仮面をかなぐり捨てる。東大陸の土産物だったそれが、虚ろな音を立てて地面に転がった。
仮面の下から現れたのは、毅然とした表情の銀髪の男だった。【NAME】の知った顔ではない。
「知り合いにばれたら面倒なんだが……もう関係あるまい。ここから、俺の名前はネスカート・ワイゼンだ」
(ワイゼン……って)
本来、彼の素性など【NAME】にとっては何の意味も無い事だ。だが、ワイゼンの名があれば話は別となる。
ワイゼンといえばアラセマの一級貴族、『六家』の一つ。しかも、名前の第二節にその名を持つということは、六家の直系であることを意味している。それでなくとも、『ネスカート・ワイゼン』がコルトレカン常駐の第六師団の師団長の名であることぐらい、軍属の冒険者なら誰でも知っているだろう。
(冗談……な筈もないか)
「実際に封印を見る前に色々情報収集しておきたいことがあったんだが……こんなに早く破られるとは」
【NAME】の当惑を余所に、ネスカート本人は至って自然体のまま話を続けていた。勿論、冗談を云っている風でも無い。
「さすがに、俺一人ではもう何も出来ない」ネスカートが【NAME】を見た。
「手伝って、くれるか?」
問われるまでもなく、元よりそのつもりだった。とは云え……。
(師団長の暴走、もとい、独走に付き合う破目になるとは……)
そんな前例は、当然ながら聞いたことも無かった。何かの間違いであって欲しいと願いつつ、【NAME】はネスカートと共に腐蝕を始めた暗い森に足を踏み入れる。
目指すは聖域の中心、白宝宮。
・
殺すことのできない獣ギ・ロ。
それがあの黒い肉片の本来の姿。
実体化しつつあるギ・ロを見つけようと思えば、頭の痛くなるようなこの臭いの元を辿れば良い。確実に濃く、強く、いや増していく不快な臭いが、獣の居場所を教えてくれる。
やがて、森が開けた。
円形の広場の中心に、白い影が聳えている。
――白宝宮。
美しい曲線はやはり三本脚の神獣を模っていたが、黒宝宮や紫宝宮と比較すると何倍も大きく、柔らかな月明かりに映えて一層優美さを増している。それは祠というより、宮殿と呼ぶに相応しい姿だった。
入り口に駆け寄ろうとして、【NAME】はそこにうずくまった小柄な影に気が付く。呆けたようにぺたりと地面に座り込んでいる、その影はクィナだ。
首だけを動かしてこちらを見ると、クィナは自虐の笑みを浮かべて云った。
「無理だ」
力なく彼女の指差す先に、それはあった。
宵の薄闇の中にあって更に黒い、蠢く巨大な球体。
無数の切れ目と触手を持つ、おぞましい肉塊。
それは美しい白宝宮の外壁の前にあって、あまりに不愉快な姿として【NAME】の目に映った。
「これが――ギ・ロか」
――トクン。
ゆっくりと、大気が脈を打つ。
「お望み通りの展開だろう。これで満足か」
クィナが、諦観とも取れる薄い笑みを浮かべた。
「馬鹿いえ、こんなモンが出てきて嬉しい奴なんか居るか」
ネスカートが静かに数歩、ギ・ロに近づいた。
「俺達はな……こいつを始末しに来たんだ」
白宝宮の前で肥大化を続ける肉塊を見据えるネスカート。その背に向けて、クィナがぽつりと云った。
「……本当に、お前達では無かったのか」
最初から人の話を聞けよな、とネスカートが呟いた。クィナは自嘲的な乾いた笑い声を上げ、
「何を……やっているのだろうな、私は」
そう云ってうな垂れた。ほんの数刻前は鬼気迫る戦士の貌で剣を交えていた彼女だが、今はとても小さく見えた。
「クィナ・センテ。主氏族の娘だろう」
ネスカートがクィナに半身を向けた。
「背筋を伸ばせ。センテの次期族長がそんな姿を見せたら、村人はがっかりするぞ」
クィナは黙したまま顔を上げ、ネスカートを見た。
「誰にでも間違いはある。自慢じゃないが、俺の場合その程度の事は日常茶飯事だ」
(本当に自慢じゃないぞ……)
ネスカートは不敵に笑って続ける。
「お前にも眼と耳があるだろう。少しはそれを有効に使うことだな。誰でも彼でも『迷の民』などとひと括りにしていては、それは眼も曇る」
さらに数歩、ネスカートは黒い肉塊に近づいた。
「本当に、戦うつもりなのか?」
「ああ。さすがにほっとく訳に行かないだろう、これは」
ネスカートが顎でギ・ロの方をしゃくって見せる。そうしている間にも肉塊は肥大化を続け、周囲の地面をぐじぐじと侵食しつつあった。
「……おしゃべりはここまでだな。行くぞ、【NAME】」
「待て……待ってくれ」
立ち上がり、土埃を払うクィナ。その仕種が、妙に子供じみて可笑しかった。
「今しがた、剣を交えたばかりの相手にこんな事を云うのは変かも知れないが」
一旦言葉を切って、クィナはネスカートを見る。その表情は既に戦士のそれに戻っていた。
「私も、戦う」
「……有り難い」
ネスカートが朗笑した。
――トクン。
ぬらり、と球体に刻まれた無数の切れ目が一斉に開く。
その全てが、朱色の瞳を持つ眼だった。
肉片の時の虚ろな死んだ眼とは違う、強い意思を感じさせる瞳だ。
「来るぞ」
ネスカートが右手を掲げて剣を喚ぶ。
「……セプテントリオ」
神形器 不死の獣
──不死の獣──
[BossMonster Encountered!]
battle
暗黒の瞳

確実な手応えと共に、ギ・ロの体が切り裂かれる。どぷどぶと音を立てて、裂け目からゼリー状の黒い肉が溢れ出した。拍動に合わせて、際限なく流れ出る柔らかな肉が周囲に広がって行く。
「やったか?」
どろどろと広がり続ける肉の沼に膝まで浸かりながら、ネスカートが云った。
「……駄目」
クィナが歯噛みする。
トクン、と肉の海が脈を打つ。次々と周囲に肉瘤が浮かび上がり、裂け目から新しい眼球が生まれでた。
「どうやってこんなもの4つに刻んだんだ、おい」
「昔の話だ、私に訊くな」
黒い肉の沼から脚を引き抜こうとして、クィナが動きを止める。出し抜けに、肉の海が渦を巻いた。
(……!?)
まずい――叫ぼうとしたが、声にはならなかった。
柔らかな流れに足元を掬われ、【NAME】の体は渦巻くギ・ロの黒い海の中へと投げ出される。広がっていた肉の沼が、再び中心に集まりつつあった。
(……このまま取り込むつもりか)
腐臭を放つ黒い肉がうねり、盛り上がって行く。
柔らかく重い肉が【NAME】の全身を包み込んだ。
沈んでいく。
暖かい、暗闇の中へと。
・
聖域の森を駆け抜けて来たワンは、白宝宮を前に立ち竦んだ。
白宝宮を取り巻く広場は今、渦巻く黒い肉によって埋め尽くされていた。中心には、無数の眼球を持った黒い球体が形成されつつある。
「……遅かったか」
憔悴した顔でそう独りごちて、息を整える。クィナや【NAME】が向かっていたようだが、この様子ではもはや助かるまい。
「いいえ、まだ間に合います」
声に驚いて、ワンが振り返る。何時の間にそこに居たのか――ワンの背後には、純白のドレスを纏ったユーリが立っていた。
「良かった。もう来てくれないのかと、心配しましたよ」
ユーリがにこりと微笑みかける。後ろに一歩退いたワンを追うように、ユーリも一歩踏み出した。
「貴方が――犯人ですね?」
「……なぜ、お前がここに」
ユーリは微笑んだまま、その問い返しには答えない。
「さあ、早く助けてあげなさい」
ユーリがギ・ロを指差した。
「今それができるのは、貴方だけです」
増幅と再構成を続けるギ・ロの方に、ワンが数歩、歩み寄る。
「生きてるか、【NAME】」
波打つ肉の球体に声を掛ける。返事は無い。
「受け取れ」
ワンが短剣をあしらった首飾りを外して、右手に持った。
「これが――神形器、ゼーレンヴァンデルングだ」
振りかざし、全力でそれを黒い球体に投げつける。
銀色の首飾りは一条の光となり、再生を続けるギ・ロの体を貫いた。
・
暗闇の中に、【NAME】は浮かんでいた。
暖かい暗黒に全身が包まれる。既に呼吸が出来ていない筈なのに、不思議と息苦しさを感じなかった。上下の感覚すらも失われているというのに、安息すら覚えてしまう。
(眠い――)
手足は柔らかな何かに包まれ、殆ど動かすことができない。寧ろ、動かそうという気にもならなかった。ワンの呼び声を聞いたような気がしたが、もう、どうでも良い。こうしてギ・ロの内側で、永遠に生き続けるのも悪くない……そう思った。
【NAME】の頭を、心地よい痺れが包み込む。このまま何もかも忘れて、眠ってしまいたい。
闇にたゆたいながら、【NAME】は意識の目を閉ざそうとしていた。
――何を、しているの?
突然の声に、【NAME】の意識が揺り戻された。
耳ではなく、直接頭の中に響くような、明瞭な声。
――使って。
少女の声。
いつか……どこかで聞いたようでもあり、初めて聞く声のようでもある。
――私を、使って。
暗闇の中、茫――と銀の短剣をあしらった首飾りが浮かび上がる。本当に己の眼で視ている光景なのかどうか、それすらも今の【NAME】には解らない。
――斬るべきものが、そこに、ある。
斬る……?
そう……。
斬るのだ。
この暗黒が見せる、偽りの安息を斬る。
殺すことのできない獣、ギ・ロを斬る。
――私を、使って。
全身に痺れるような痛みが走り、【NAME】の意識が覚醒した。
剣が、欲しい。
この闇を斬る、光の剣。
ギ・ロを葬る神形の剣が。
僅かの間を置いて、確認するように少女の声が聴こえてきた。
――それが、貴方の望むカタチ?
「そうだ」
答えると同時に首飾りが消え失せた。代わりに、右の掌に現れる重い感触。それを、両手で握りなおす。眼で確認するまでもなく、【NAME】はそれが何なのかを理解していた。
輝く白剣、神形器、ゼーレンヴァンデルング。
残された全ての力を込め、【NAME】は暗闇に神剣を振り下ろした――。
神形器 理由
──理由──
ギ・ロが、破裂した。
神形器の力に内側から引き裂かれ、ギ・ロの黒い肉は千の破片に寸断されて弾け飛ぶ。不完全な状態で残っていた肉の沼はその圧力で巻き上げられ、球体の内側から溢れ出した無数の灼けつく光によって切り刻まれた。
ギ・ロの肉片は飛び散りながらも更に崩壊を続け、白宝宮の壁や聖域の木々に到達する前に、塵と化して完全に霧散した。
一瞬遅れて、【NAME】やネスカート、クィナの身が宙に投げ出される。
そして……拍手の音が、聖域に虚ろに木霊した。
「お見事」
にこやかな表情で手を叩くのは、白のドレスに身を包んだユーリだった。
粛々と木陰から歩み出た彼女は、白宝宮の前まで来て足を止め、【NAME】達を見渡した。その脇には、神形器が先ほどの剣の姿のままで地面に突き刺さっている。
(何故、ここに……)
立ち上がろうとして、【NAME】は地に崩れ落ちた。――力が、入らない。クィナやネスカートも同じように、地面に転がったまま虚脱していた。
「無理に動かないことです。もう少し遅ければ、ギ・ロと同化していても不思議ではなかったのですよ」
ユーリが【NAME】を見る。
「それでなくとも、神形器の力を揮うのは容易なことでは無い筈です」
ユーリは振り返ると、広場の隅で立ち尽くしているワンに目を遣った。
「ワン、貴方も、良く神形器を運んで来てくれました。とても感謝しています」
「ギ・ロの封を解いていたのは――まさか、お前か」
ワンの顔に畏怖の色が浮ぶ。
「そうです」ユーリが微笑んだ。「護り手の方々に見つからぬよう、苦心しました」
(ユーリが、ギ・ロを……?)
霞のかかったような頭で、【NAME】は懸命に考えを巡らせる。まだ、体は思うように動かない。
クィナが、両手で体を支えて上体を起こした。
「……ギ・ロは崩滅した。何を企んでいたのか知らないが……そろそろ諦めたらどうだ」
苦しそうに喘ぎながら、クィナはそれだけ云ってまた浅く息を整える。
ユーリが、くすくすと笑い出した。
「まだ、お解りで無いのですね、クィナ様」
数歩、歩く。その先にあるのは――神形器。
「私がギ・ロを解放したのは、これを持って来て欲しかったからです」
ユーリがゼーレンヴァンデルングの柄に手をかけた。地に刺さったその剣を、彼女は片手で軽々と引き抜く。
「神形器ゼーレンヴァンデルング、ようやく私の許に来てくれましたね」
美しい朱色の瞳で剣を見つめ、ユーリが微笑した。
・
呼吸を整えながら、ネスカートが半身を起こした。
「……では、サンメアリ号の生存者を殺したのも……」
「そう、私です。彼らには悪いことをしました。誰かが神形器を隠している可能性が高いと思ったのですが――まさか、キヴェンティが所持していたとは」
ちらり、とユーリがワンに視線を送った。広場の隅で、ワンは俯いて視線を逸らした。
「……どうやって乗客の名前を」
「それはネス、貴方が教えてくれたのですよ。港で、初めて出会った時のことです。貴方は助かった乗客の名簿を快く見せてくれました」
ユーリは人差し指でトン、とこめかみの辺りを指し、
「私、暗記は得意ですから」
そう云ってにこりと笑った。
「成る程」
やり取りを座って見ていたクィナが、俯いたまま、吐き捨てるように云った。
「結局、私が討つべき相手はユーリ、お前だったという訳だ」
次の瞬間、クィナが地を蹴った。
一瞬にしてユーリとの間合いを詰める。彼女が振り向くより疾く、白刃が一閃し鮮血が宙に舞う――筈だった。
「……莫迦な」
クィナが驚愕に目を見開く。クィナの剣は、ユーリの左手で柔らかく受け止められていた。
刃を素手で止めているにもかかわらず、そこに傷は、無い。
「貴女の力では、私は殺せません」
ユーリが右手の剣を振るい、刀身でクィナを弾き飛ばした。受身も取れないまま、クィナは白宝宮の壁に打ちつけられ、床に崩れ落ちる。こほ、とその口から血の泡が飛んだ。
「キヴェンティは自らそれを認めて、私の事を呼んでいたではないですか。『殺すことのできない獣』、と」
もっともそれは随分と昔の話ですけどね――と付け加えて、ユーリは掴んでいたクィナの剣を手放した。
「一体、お前は……」
依然広場の隅に立ったままで、ワンが云った。ユーリはそれを無視するように、ネスカートに向かって語り出す。
「以前、肉片の名前について話をしましたね。覚えていますか、ネス。ギ・ロについてお教えした時のことですけど」
「……ああ」
「獣の肉片にも、ウィリ、ルフ、レウムといった名前が付けられた――と、そう云いました。これらは、ギ・ロではなくマギサの肉片に付けられた名です。後の一つを記憶している人間は、既に残っていませんが――」
ユーリが悪戯っぽく笑む。
「マギサの肉片に付けられた名前の、最後の一つはユウリ――つまり、私です」
・
「では、そろそろ使わせて頂きますよ。この剣もそれを望んでいます。神形器に触れた者ならば、きっとこの子の声を聞いたのではないですか?」
「壊したい、か」
苦渋の表情でワンが答える。
「もちろん、壊したかったのは、ギ・ロなどではありません。あれの肉片が甦る前から、声は聞こえていたでしょう」
つかつかとユーリが歩を進める。白宝宮から離れ、今は何も居ない広場の中心に立った。
「この子が本当に斬りたいのは、世界の境界を塞ぐ、この聖域。遙か昔、キヴェンティが命脈の力を行使して作り上げた檻の蓋」
ああ――とワンが呻いた。
「“永遠に続く”封印です」
ユーリが剣を翳した。一瞬の後、それは彼女の手の中で一回り大きな、輝く刀へと姿を転じる。――きっと、それが彼女の望んだカタチなのだろう。
「見せて上げましょう。この剣の本当の使い方を」
そしてユーリは、唄い始めた。
・
回れ、運命の糸車
絡まる呪縛を切り
連なる劫罰を断ち
儚き泡沫と散る
贖え、
其の身解くるまで
・
ユーリが神剣を一閃した。
眩い光が聖域の大地を貫き、寸分の歪みも無い正確な円形に切り裂く。
白宝宮の前に穿たれた巨大なそれが、全てを呑み込む深い黒色を持って浮かび上がった。
「この島は、檻です」
剣を手にしたまま、ユーリがその中心へと歩み寄る。
「そして、鉄格子の代わりをしているのが、この“黒い切り株”――。キヴェンティの貴方なら知っているでしょう。“黒い切り株の向こう”に何があるのか」
「……鬼芯属」
「そう、良く出来ました。かつて幾多の芯属と共に、キヴェンティが挙って倒そうとした鬼、つまり私の母とでも呼ぶべき存在です。私は、これから『彼女』を救いに参ります」
そこでふと、ユーリは思い出したように立ち止まる。
「そうそう、云い忘れてましたが……その娘、放って置くと、死にますよ」
白宝宮の壁にもたれてぐったりとするクィナを、ユーリは一瞥した。
「助けるさ」
ワンが即答して、クィナの許に駆け寄った。クィナは「よせ」とでも云うように口を動かしたが、声にはならなかった。
「延命は、命脈の理に逆らう、か。悪いが、俺はそういうことには興味無いんだ」
云って、ワンは両手でクィナを抱え上げた。
「それに……誰かが死ぬって判ってるとき、諾々と見過ごすのが自然の姿とは、俺は思わないから」
「結構。貴方の下した判断は、生物としては極めて正常です」
ワンの腕の中で目を閉じたクィナに向けて、ユーリは話し続ける。
「クィナ様はまだご不満かしら? けれども、貴女達のような小さな存在が命脈の理を気にして生きる必要など、どこにもありはしないのよ。人の生命など、命脈という名の巨大な濁流に浮かぶ一抹の泡にも等しきもの。波に呑まれ、刹那の後には消えて無くなる、それが必定です。泡沫のごとき存在がどう足掻こうと、大河の流れを乱すには至りません。キヴェンティはつまらない儀式で命脈の力の欠片を手に入れた気になっているようですが……そうね、仮令貴女達が全ての存在概念を明け渡したとしても、荒れ狂う水面にほんの一飛沫を上げる程度のものです。結局、ひたすらに死を怖れ、あらゆる手段を使って命を永らえさせる、それが貴女達にとっての自然であり、また本来の姿でもあるのです。……だから貴女もワンのように、もう少し自由に生きてみたらどうですか?」
クィナは反応しない。既に意識を失っているようにも見えた。ワンがかぶりを振る。
「理由は関係無い……俺は、助けたいから、助けるだけだ」
ワンは背を向け、クィナを抱えたまま聖域の森の中に去っていった。
ユーリがそれを見送りながら、目を細める。
「……面白いですね。これだから、私は人間が好きなんです」
それから更に数歩、ユーリが黒い円の中心に進んだ。
「それでは、私もそろそろ行きますね」
緩々と立ち昇る黒い光に包まれながら、彼女はネスカートを顧みる。
「ネス。貴方達にもまだ少し、時間は残されているわ。……追ってくるのでしょう?」
ネスカートの返事を待たずして、ユーリの姿は完全に黒に包まれ、消えた。
後に残された僅かな光の残滓だけが、蛍のように宙を漂う。
「追いかけるさ」
彷徨う光の粒を見つめて、ネスカートが呟いた。
「……止めて見せる」
神形器 夢の終わり
──黒い切り株の向こうへ──
濃い霧に包まれた、黒い木々の立ち並ぶ森を抜け――【NAME】はギアス聖域の中心、白宝宮のある円形の広場に立った。
白く滑らかな曲線が造り出す三本脚の神獣の前には、今、ゼーレンヴァンデルングによって穿たれた穴が黒々と口を開けていた。暗黒そのものであるかのような“黒い切り株”からは、時折、ふつり、ふつり――と、黒い靄のようなものが流れ出て、宙に消えていく。
この“向こう側”に何があるのか、目を凝らしたところで見えるのはただ漆黒の闇ばかりだった。それがあまりにも黒いので、見つめていると中に吸い込まれそうな錯覚に陥ってしまう。
ネスカートはその“切り株”の淵に立っていた。
「準備は良いか?」
ネスカートが【NAME】に向かって尋ねる。――勿論、黒い切り株の向こうへ行き、ユーリと戦う、そのための準備の事だ。
「向こう側には何が待っているか分からない。これが“檻”として造られたものであるとすると、亜獣などが存在する可能性は殆ど無いと考えて良いだろう。……ただ、ひとつ気になる事がある。ユーリがマギサの肉片だとして、残りの3つは何処に行ったのか、という事だ。彼女が今まで単独行動だったことを考えると、コルトレカン島には居ない公算が高い。となると――」
(……その先か)
ネスカートが【NAME】を見て頷いた。
「獣との戦いは鬼のそれと平行して行われていた。こいつの向こう側に紛れ込むことは可能だったはずだ。無論、他島に逃れた線もあるが……今日この時の為に、敢えて残りの肉片を送り込んでいた可能性はある。彼女ならそれぐらいはやるだろう」
確かに、それは考えられることだった。
「理想としては、彼女を追いかけ、倒す。これだけだ。だが、円滑に事が運ぶとは限らない。云うまでも無いが、向こう側に町などあるはずも無い――今の内に、できるだけ準備をしておいた方が良い」
──黒い切り株の向こう──
準備は出来ている――【NAME】は答えた。
結果がどうなろうと、これが最後になるだろう。決意を胸に、【NAME】は“黒い切り株”の中へと、一歩を踏み出す。足の裏には何の感触も無い。落下を恐れたが、体は奇妙な浮遊感を持って支えられた。一歩踏み出すごとに、足の下からは黒い光が湧き上がり、緩やかに纏わりつきながら消えて行く。
そのまま、数歩、中心へと歩き出す。と、不意に、周辺から音が消えた。
視界が闇に包まれた。
・
真の闇。
首を巡らせても何も視えない。
体を動かしても何の抵抗も無い。
何も聴こえず、断続的な耳鳴りだけが続いている。
(――厭だ)
自分自身が闇の一部に溶け込んでしまったような錯覚。この先に世界が開けることを信じて、ただひたすらに闇を漂う。
・
長い時間が過ぎたようでもあり、僅かな時間でしか無かったようにも思う。
不意に、闇の彼方に白い点が現れた。それは加速度的に大きくなり、瞬く間に白の奔流と化して全てを包み込む。突然の強烈な光に、両の眼が刺すような痛みを訴えた。
ゆっくりと、地に足が付くのを感じた。
閉じた瞼の向こうで、光が次第に退いていく。
出し抜けに、身を切るような寒さが身体を襲った。
吹き荒ぶ風音。
目を開く。
体に纏わりついた光の粒が散り、空気に溶け込むように消えて行く。
そして、世界がその姿を眼前に現した。
終わりを告げられた世界。最初の印象はそれだった。
藍色に濁った空に、細く赤い三日月が切り傷のように浮かんでいた。見渡す限りの荒野に生物の気配は感じられず、倒壊した建物の柱が白く疎らな模様を描くばかりだった。廃墟の中を、時折吹き抜ける風だけが虚しく木霊する。
遠く、正面に神殿跡らしき建造物が見えた。
半ば崩壊したその階段を、白い人影が進んで行く。風が彼女の黒髪を梳かし、純白のドレスを揺らした。その右手には、仄かに光る白い刀剣が握られている。
――ユーリ。
彼女を倒せば、全てが終わる。
目指すは白の神殿のみ。
──鬼芯の檻──
白亜の石で作られた吹き曝しの神殿。天井は無く、大きな円柱の殆どは倒壊し、あるいは途中で折れて崩れている。濁った藍色の空には、血のように赤く細い三日月が浮かんでいた。空の色を映じて暗く光る石畳の、その中央には七段の階段。
段の上には左右のつりあがった台座と――。
「ようこそ『黒い切り株の向こう』へ」
純白のドレスを纏い、右手に神形器ゼーレンヴァンデルングを携えた女、ユーリが居た。
「本当に――死の世界という言葉が相応しいですね。とても、寂しい場所」
ユーリが静かに階段を降りる。
「フローリアの島々が“鉄格子”だとすれば、ここはさしずめ“檻の中”。正確にはまだ何層もの鉄格子が残されているのだけれど……私の母たる者は、その中心に在る。彼女の存在概念が完全に消え去るまで、幾星霜を経ても壊れぬこの忌々しい檻に囲まれて。とても酷い話、そうは思いませんか?」
ユーリは立ち止まる。
「だから私は、流転の神形器以てこの檻を破り、彼女を助け出す」
「悪いな。俺達はそれを許す訳にはいかない、確かに可哀想だがな」
音も無く、突き出したネスカートの手に現れる白く輝く一振りの剣。
「そうね。それは初めから判っていたこと。だから……ここで決着をつけましょう」
ユーリは薄く微笑んだ。
「どうかネス――貴方が楽に死ねますように」
[Shape Your Own Destiny!]
battle
殺せない獣

・
最後の一撃。
命に届くその傷を受けて尚、ユーリは、ふふ――と含み笑いを浮かべて見せる。
(まさか……)
更なる再生を予期し、【NAME】は武器を構え直した。
「――残念」
左手で己を抱いて、ユーリが僅かに俯いた。その手の下から、じわじわと綺麗な赤が彼女のドレスを染めて行く。
「貴方達の――勝ちです」
神形器が緩やかに彼女の手から離れ、鋭く床石に突き立った。
そして、ゆらり――と。
ユーリが、地に崩れ落ちた。
──夢の終わり──
雪が舞い降りてきた。
暗い空から、一つ、また一つと白い結晶が地に落ちて消えていく。その様子を、ユーリは仰臥したまま眺めていた。
「綺麗ですね」
言葉と共に、吐息が白くほどけて消えた。薄く白化粧を始めた世界の中で、彼女の周囲だけが赤黒く染まっていく。
「……悪いが、獣の本来の力を取り戻す前に、消えてもらう」
ネスカートが神形器を引き抜く。
賢明な判断です――と、ユーリは空を見つめて、表情も変えずにそう告げた。
ネスカートの手の中で、ゼーレンヴァンデルングは剣の形を失い、ごくごく質素な短刀へと姿を変えた。ほんの小さな刀だが、彼女の命を奪うのにはそれで充分だった。
「……貴女なら、人として生きることも可能だったはずだ。望むなら、永遠に」
何故そうしなかったのかという、それはネスカートの最後の問い掛けだった。
そうかも知れません――とユーリが答える。
「でも……、ずっと――貴方たち人間を見てきて、知っていたから。永遠に生きる必要なんて、無いんだってこと」
変わらず空を見たまま、ユーリは切々と話し続けた。
「本当はもう、生きる事にも倦んでいたのかも知れない。けれど、私にも目標が欲しかった。有限の命を生きる彼らみたいに、私も頑張ってみたかった。そして……何かにうちこんで、終わる生なら、それも良いかな、と思ってた」
ユーリがネスカートを見た。ネスカートは変わらず固い表情で彼女を見下ろしている。ユーリは口の端で笑って見せた。
「――だから、ここで、私の夢は終わり」
「……そうか」
ネスカートが神形器を構えた。
「さよなら」
ユーリが目を閉じた。
音も無く短刀が振り下ろされる。
――今度生まれてくる時は、私も人として。
ネスカートの振り下ろした神形器は正確にユーリの心臓を貫き、溢れ出る光が瞬時に全身を蒸発させた。
血の跡すらも残さず、彼女の存在は完全に消え失せた。ぽっかりと冷たい床石の上に空いた空間を、少しづつ雪が覆い始める。
「帰ろう」
短刀を手にしたまま、ネスカートが立ち上がった。
振り返ることもせず、『こちら側』の黒い切り株へと、【NAME】は歩き出す。
・
聖域は場違いな喧騒に包まれていた。
黒い切り株は、遠巻きにアラセマ軍の衛士らしき集団に囲まれていた。その真ん中に突然【NAME】やネスカートが出てきたのだから、これはもう注目するなという方が無理な話だった。
「師団長!」
長い金髪の、線の細い男が群集から歩き出る。【NAME】の知らない顔だった。
「あ……ケイジュ」
ネスカートがばつの悪そうな顔でたじろいだ。
「貴方という人は……貴方という人は、一体、何を……」
ケイジュと呼ばれた男は、つかつかと肩を怒らせて歩み寄り、
「何を考えているのですか!」
震える声で一喝した。
「……いや、なんというか、自分で確認しないと落ち着かない事ってあるだろ。つまり――」
ケイジュの剣幕に、ネスカートは悪戯を見つかった子供のように尻込みする。
「私が云いたいのは、そんな事ではない!」
ぴしゃりとケイジュが云った。肩で息をしてから、ケイジュは「何故――」と吐き捨てる。
「何故、出かける前に私に一言いってくれないのです! 貴方の命令があれば私は――いや、第六師団の誰であろうと、即座にサリクトラムに向かったのに! 必要とあらば全軍を率いてでも良かった!」
「うお……」
やっぱり黙ってて正解だった――多分そんな言葉を、ネスカートは云い掛けて呑み込んだ。
「そんなに我々は信用がありませんか! それでなくとも、師団長が黙って一人で出て行くなどという事がありますか!?」
至極もっともな意見だった。ひとしきり捲くし立てたケイジュは「ああ……血圧が」と座り込んだ。そのまま、恨みがましい目をネスカートに向ける。
「――しかし、無事に戻ってきたという事はつまり、マギサは既に居ないと……そう考えて良いのでしょうね?」
「あ、ああ……誰に聞いたんだ、それ」
「主氏族クィナ・センテと従氏族ワン・テオです。お二人ともアラセマ軍で身柄を預かっています。“黒い切り株”の後始末も、彼らキヴェンティが行ってくれることになっていますよ」
ケイジュが身をずらすと、後方でアラセマの衛士に囲まれて押し黙っているワンの姿が見えた。
「成る程……アラセマ軍に頼んだのか。彼女の治療」
「そういう事です。そして我々には拒む理由はありません。――『ネスカート・ワイゼンの居場所と引き換えに』という交換条件が無くても、アラセマ軍は彼らを受け入れたはずです」
ケイジュの言葉にネスカートは少し驚きを見せ、何でそいつが俺の名前を知ってるんだ――と云った。ワンはニヤリと笑うと、懐から何かを取り出して見せる。
「自分でそう名乗ってたからな……俺は偶然、樹上でそれを聞いてただけだ」
笑いながらワンが指先で回しているそれは、ネスカートが被っていた怪鳥の仮面だ。ケイジュがそれを一瞥する。
「あんな悪趣味な証拠品まで持って来られては、信用しない訳にも行きませんしね。――おまけに、神形器を隠していたのも彼だと云うじゃないですか。クィナ・センテもそれは知らなかったようです」
「ああ……あれは何故なんだ? 解らなかった」
一同がワンに注目した。
「……アラセマは獣について嗅ぎ回っていたからな。余計な事をして寝た子を起こさぬよう、決定的な武器となる神形器はこちらの手に収めるつもりだった。その為に派遣されたのが俺とクィナだ」
ぽつぽつとワンが話し始める。確かに、彼はサンメアリ号に密航していた。その手助けをしたのが他ならぬ【NAME】だったのだから、間違いない。だが、彼はあの時、神形器は無かった――と、そう云ったはずだ。
「あの船で神形器に触れた時、声が聞こえた。最初は虚を突かれて、自分の意識を失いかけた」
(壊そう、か)
「だが、すぐに気が付いた。こいつが壊したがっているのは、聖域の方なんじゃないかってな。それはギ・ロの復活なんかよりずっと不味い。だから俺は咄嗟に、『武器に見えないような形』を望んで、それを隠し持つことにした。神形器は無くなったと、そう思わせた方が安全だと考えたんだが……間違いだったかもしれないな」
そうでも無いさ――ネスカートは云ったが、それはケイジュの大声で掻き消された。
「ああ! そうだ、神形器。神形器はどうなったんです!?」
「あ――あれね」
興奮したケイジュに、なぜか冷ややかな面持ちでネスカートが答える。
「ゼーレンヴァンデルングが行方不明になったという噂は、既に如何ともしがたい程に広まっています。未確認ですが、フハール家やアスカーン家も動き出しているとの情報も――」
「あほな連中だ」
「何か云いましたか?」
「いや別に。ところでケイジュよ。云い難いことだが」
ネスカートがぽりぽりと顎を掻く。
「神形器な……あれ、壊した。ベルトーチェの婆さんには謝っといてくれ」
「ば……」
ケイジュは何か云い掛けたがその先は言葉にならず、魚のように口をぱくぱくさせた。
「良いんだよ。あれだけぐるぐると持ち主が変わったんだから、さぞ嬉しかったことだろう。一箇所に留まるのは好みじゃなさそうだからな」
うんうんと一人頷きながらネスカートは続ける。
「そんな事より――そろそろ帰らせてくれよ。俺の心は今、柔らかいベッドに倒れこみたいという、その一念で満ち満ちているんだ」
諦めたように、ケイジュがかぶりを振った。
「……そうですね。聖域の外でセタセタを待たせてあります。そちらの方も――」
ケイジュが【NAME】を振り返る。
「【NAME】だ。無下にするなよ。多分、今回一番の功労者だ」
「はい。【NAME】さんもご一緒に、リコルスまで戻りましょう」
歩き出してから、ふとケイジュが再度【NAME】を振り返った。
「これから大変かも知れませんよ……一般には知られなくとも、軍では『獣を斬った者』として有名になるでしょうからね」
・
ギアス聖域を後にして、一行はサリクトラム近くの街道へ出た。
ケイジュの云った通り、そこにはセタセタの一団を従えたアラセマ軍が待機していた。セタセタは騎乗用の数頭と、ほろを張った数台の荷車に分かれている。【NAME】は気楽な荷車を希望したが、凱旋するものはかくあるべし、とネスカートに諭され、騎乗の方へと回された。
鞍を備え付けたセタセタにしぶしぶ跨り、【NAME】はアラセマ軍と共にリコルスを目指し行軍する。霧の立ち込めた薄暗い聖域とは打って変わって、外は眩しい程の陽射しだった。涼しい風が草の香りを運び、【NAME】の頬をくすぐる。荷車に速度を合わせて遅めに進むセタセタの背に揺られながら、ふと――今まで見てきたものは、全て夢だったのでは無いか、と。
そんな事を思う程に、それは平和で、懐かしい風景だった。
・
「ところで……サリクトラムへは何を確認しに行ったんですか?」
徐に、ケイジュが隣を併走するネスカートに尋ねた。このセタセタは中型で二人乗りだ。ケイジュもネスカートも、アラセマの甲冑を着けた騎手の後ろに乗っている。【NAME】も同様にして彼らと併走していた。問われたネスカートはケイジュの方を向くと「大したことじゃないが」と前置きしてから、面倒そうに説明を始めた。
「最初の肉片が現れた時、彼女――ユーリは一片の迷いもなく『あれはギ・ロだ』と断言しただろう。確かに性質から考えて『獣の肉片だ』という判断は妥当だ。流石は専門家、とその時は思った」
「それで?」
ケイジュが先を促した。
「しかし、サリクトラムの伝承に獣は二匹いた。ギ・ロとマギサだ。不完全な状態でも判別が容易な程、獣の情報が正確に残っているのかと、俺は現存する資料を集めてもらって調べなおした。結果はお前も読んだ通り。肉片の特徴どころか、名前すらも完全には伝わっていない。変だな……と、思うだろ」
「……それだけ、ですか?」
「まあ、それだけだ」
ケイジュは、ほとほと疲れ果てたという様子で溜息をついた。
「貴方という人は……本当に、何を考えているのか……」
ケイジュの悲嘆を余所に、一行は高い空の下、心地よい蹄鉄の音を響かせながら朗らかに進んで行く。
・
「渡しておきたい物がある」
まもなくアナナスに着こうかという時、決心したかのようにネスカートが【NAME】に手招きした。招かれたところで手綱を持たない【NAME】にはどうしようも無いのだが、騎手はすぐにそれを察してネスカートの真横につけてくれた。
「実は、ユーリに止めを刺した時、俺は神形器が砕け散ると思っていた。それこそがあの剣の真の役割だと、そう予想していたんだ」
併走しながら、少し声を落としてネスカートは続ける。
「だが、あの剣は壊れなかった。眠りについただけだったんだ。未だ何かの役割を担っているのだとすれば――あれを持つのに相応しいのは、多分俺じゃない」
手を出してくれ――とネスカートが云った。【NAME】の差し出した掌に、ネスカートが何かを取り出して渡そうとする。
「? なんですか、それ」
目ざとくそれを見つけたケイジュが顔を向けた。
「記念品」
ネスカートが手を離す。
ちゃり、と金属的な音を立て、【NAME】の掌に置かれた冷たい感触――。
それは美しい装飾をあしらった、小さな短剣の首飾りだった。