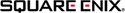みんなdeクエスト 那由多の道と異界の扉
- 神形器 プロローグ
- 神形器 湖畔の町シレネ
- 神形器 隻鬼に挑む者
- 神形器 隻鬼
- 神形器 港の開放
- 神形器 腐蝕の港
- 神形器 最初の鏡
- 神形器 霧の聖域
- 神形器 湖畔の影
神形器 プロローグ
──予兆──
【NAME】は、船に乗ってから何度目かの溜息をついた。
ラースナウアの港を出てから数日。コルトレカン島へと向けて出航した連絡船サンメアリ号は天候に嫌われるような事も無く、ここまで至って順調な航海を続けている。しかし、それとは裏腹に、【NAME】の心中では不満の黒雲がどろどろと全天を覆っていた。
チューチューと小憎らしい声を上げて、頭痛の原因の一端を担う連中が積荷の影から顔を覗かせる。モップを片手に鼠を追い払うが、彼らは再びあちこちで穀物の袋を齧って穴を開けてみたり、掃除の終わった場所に糞をしたりとやりたい放題だ。
そもそも、オリオールの口利きで乗せてもらったは良いが、船賃の代わりに労働を要求されるとは聞いていなかった。甲板の掃除、船室の掃除ときて、今度は食料庫の掃除だ。それだけでも充分頭が痛いというのに、鼠の群れまでオマケに付いてくるのはサービス過剰では無かろうか。
モップを武器に持ち替える。
少し――そう、ほんの少しなら問題無いだろう。喧嘩はご法度だったが、これは掃除なのだし。技法を用いて調子に乗る鼠を追い出してやるとしよう。
頭痛の種


数匹片付けたところで、堰を切ったようにして残りの鼠が流れ出す。一体どこに隠れていたのか、後から後から飛び出しては、階段へ、あるいは壁の穴へと姿を消していった。
こんなに手早く片付くのなら、もっと早く実力行使に移っていれば良かったか――そんな事を考えつつ、鼠の去った平和な食料庫の清掃を再開する。手早く床を片付け、破れた穀物の袋の中身をこぼさぬように移動する。はて、これはどうすれば良いのだろう。適当な袋を探して移しかえておくべきか。
思っては見ても、勝手の判らない船内では中々その「適当な袋」の在り処が見つからない。棚に収めるか壁に掛けるかしてありそうなものだが、矢鱈と積み込まれた樽や木箱の類が累々と壁際に山を為しており、壁も棚も見えたものではない。普通こんな積み方をするものだろうか。
とりあえず、普通このへんに棚ぐらいあるだろう、といい加減な見当をつけて、壁の山を崩しにかかってみる。樽は水が入っているようで重いため、木箱に手を付けてみるとこちらは存外に軽かった。これなら楽々探索可能だ。調子に乗ってどんどん木箱の山を崩していくと――木箱の奥の空間で、一人の男が座ったままひらひらと手を振っていた。

「やあ。どうも」
男は箱山の奥から静かに這い出ると、膝立ちのまま、両手を顔の横に上げてひらひらさせる。いないいないバァ、のようでもあるが、恐らく「戦う気はない」というポーズだと思われる。
(密航者か……)
確かに、見たところ武器を持っている風ではないが――油断しない方が良い。
一歩退いて間合いを取る。男はゆっくり立ち上がると、参ったな、と呟いてぽりぽり頭を掻く。金髪碧眼の、ごく平均的な体格の男だ。多少は鍛えているようだが、この程度なら不意打ちをくらいでもしない限り不覚を取ることも無いだろう。
「不幸だ。船倉は厳重警備と踏んでこっちに来たというのに。なんで技法を使って暴れる掃除係が居るんだろうか」
男はまじまじと【NAME】を見る。
「あんたは正規の兵士じゃなさそうだな。俺は見ての通り密航者みたいなもんだが……ここだけの話、ナイショにしておいてはくれまいか」
しばし黙考する。この男を船の衛士に突き出すのは簡単だが、密航者は場合によっては海に落とされることもあると聞く。自業自得だが、それは何だか寝覚めが悪い。一方、見逃した場合はどうか。格別自分に不利益は無さそうだ。ついでに衛士に突き出す僅かな手間を省いて、すぐさまのんびり休むことができる。――決まりだ。
【NAME】は、深い慈悲の心を持ってこの事をナイショにしてやる旨を男に伝えてやった。
「ありがたい。俺の名はワン・テオだ。あんたは?」
一瞬躊躇するが、後で礼が貰えるかもしれないと思い、本名を名乗っておく。
「【NAME】か。この借りはいつか返すよ」
ワンと名乗った男は、それだけ云うと再び木箱で組んだ山の中へと潜り込む。ついでに奥の壁か棚に麻袋が無いか確かめてもらうと、しばらくして足元に麻袋が滑り出してきた。首尾よく見つかったようだ。
ざらざらと、破れた袋から豆を移しかえる。これで一通りやることはやった。さて、と部屋を後にしようとした【NAME】の背に、ワンの声が掛かった。
「ああ、最後にもう一つお願いがあるんだが」
振り向くと、箱の山の中でワンが床を指差している。
「ここに木箱を戻しておいて欲しいんだが。中からやるのは至難の業なんで」
食料庫の清掃と木箱の城の再構築を終えた【NAME】は、廊下に出て目を丸くした。追い出した鼠が走っているだけならまだしも、廊下ではその鼠達を追いかけて大興奮した猫が右往左往し、更にそれを一人の男が追い回していた。しばし騒動を繰り返した後、猫は鼠の消えた扉の前でじっと動かなくなる。

「お騒がせしております……」
猫の飼い主と思しき魔術師風の男が、面目無さそうに云った。
(この船には猫まで乗っているのか……?)
尤も、ペットを連れている冒険者というのはさほど珍しいものでもない。さしずめ男は調教師の類を生業としており、【NAME】と同じように労働で船賃を払っているのではないだろうか。
男は白猫を抱え上げると、いそいそと扉の奥へ消えていった。
【NAME】は仕事の首尾を船長に報告し、船員用の共同寝室へと戻った。嘆かわしいことに、【NAME】には客室などという上等なものは用意されていない。
船長には鼠が大挙して出て行ったことも――ついでに技法を使ったことも報せておいたが、特に問題視されることもなく、むしろ住み着いた鼠を追い払ったことを感謝されてしまった。この上新たに船倉の掃除あたりを押し付けられたらどうしようかと危惧していたが、そんなことも無く、晴れて今日は休息となった。
だだっ広い共同寝室も今は空っぽのようで、これなら落ち着いてゆっくり休むことができるだろう。自分に割り当てられたハンモックに横たわると、ぼんやりと今日一日の出来事が去来する。
追い出した鼠達は各部屋で一騒動巻き起こしたらしいが、最終的にはその全てがどこかへ消えてしまったと聞く。いい加減な判断の下での行動にしては好結果を齎したと言えよう。今度から清掃には技法、これだな……などと他愛も無いことを考える。
そういえば木箱に埋もれていた彼――ワンは、あの窮屈そうな場所で港まで頑張るのだろうか。それに比べればこの待遇も悪くは無いかもしれないな……。
うつらうつらと船に揺られるうち、連日の疲労も手伝って眠気が押し寄せてきた。ああ、このまま眠っても何の問題も無いだなんて、なんて幸せなんだろう。
……。
……。
それにしても。
脅かしてやったとは言え、一匹残らず鼠が消えてしまうとは――。
まるで、沈没直前の船のようだ……と思った。
──口火──
明けて翌朝。
【NAME】が目を覚ました頃には、既に船はコルトレカン島の近海に迫っていた。甲板に出ると、まだ薄暗い海の彼方、青い島影が小さく水平線に浮いている。あれが――コルトレカン島か。
朝の光が海を照らし、海上は薄い霧に覆われていた。この距離では仔細など判るはずも無いが、やはり陸が見えるということは言い知れない安心感を人に与えてくれる。

「あ。昨日はどうも」
階段を上って甲板に現れたのは、昨日廊下で見かけた猫連れの男だった。昨日の白猫に加えて、今朝は賢そうな黒猫も一緒に連れている。ナァナァと甘ったるい鳴き声を上げる白猫に比べ、黒猫の方は寡黙なようだ。
(猫好きなんだろうな)
そういう偏向した趣味の冒険者は少なくない。こだわりは一種の力となる場合もあるからだ。単なる趣味かも知れないが。
「ああ……えと、猫魔術師なんですよ、僕。知らないかな……マイナーだから」
【NAME】の好奇の視線に耐えかねたのか、彼は黒猫を抱え上げて話し出した。昨日は気づかなかったが、向かい合ってみるとこの男は特徴的な目をしていた。右は灰色、左は朱色――左右で色違いの瞳を持っている。
「ペットと協力して戦うのは普通の調教師と同じだけど、それよりももっと同調力を重視した技法を用いるんです。だから、猫魔術師。……まあ別に猫でなくても良いんだけど、やっぱり相性が」
(猫魔術師ね……)
聞いた事も無い職業だった。少なくともアラセマにはそういった技法を伝えるギルドは無いはずだ。ニコニコ笑顔で話しているが、あんまり信用しない方が良いかも知れない。昨日の密航者と言い、この船に乗っているのは怪しい奴ばかりだな――そう考えてから、きっと自分も他から見れば怪しい奴なんだろう、と気づいて可笑しくなった。
他愛もない会話をして時間を潰す。猫魔術師の彼はリネットという名らしい。女性みたいな名前だ。職業も変わっていれば名前も変わっている。きっと生まれはどこか遠方の国なんだろう。目のことも気になったが、余り詮索しないでおくことにする。
それよりも、今日はお互い非番らしい。どうせ港に着けばまた何かしら手伝いを要求されるのだろうから、今の内にのんびりしておくのが得策というものだ。
朝霧に煙る海はいつしか晴れ、薄い島影も次第に明瞭さを増していた。
不意に、頭上を巨大な影がよぎる。
反射的に振り返り顔を上げると、船の後方に舞う巨大な鳥の姿があった。薄紅色の翼を広げてゆっくりと旋回をはじめる美しい大鷲。――その白い背には、一人の人間が乗っているようだった。
マストの上で見張りが大声を上げる。それに応えるかの如く、船の下部から怒号が響き渡り、重い金属のぶつかり合う音が甲板に上がってきた。武装したアラセマ軍の衛士達だ。
口々に何かを喚きつつ、次々と甲板に衛士が集まってくる。詳しい会話の内容は聞き取れないが、言葉の端々に「敵」や「キヴェンティ」といった単語が認められた。
(単に鳥の背に人が乗っている……というだけの平和な話では無さそうだな)
今ひとつ状況が飲み込めないまま、【NAME】は船室の壁を背にとって油断なく武器に手をかけた。リネットは猫を抱え、船内へと通じる階段で息を潜めて成り行きを見守っている。どうやら、勇敢さは今ひとつのようだ。
衛士の内の数人が巨鳥に向かって弓を射る。が、腕が悪い。船の上ということもあるだろうが、ほとんどの矢は回避運動を取るまでもなく外れていた。
「何をしている、さっさと射ち落とせ!」
大鷲は甲板の衛士の頭を掠めて高速で滑空し、今度は船の前方へと抜けてふわりと浮かび上がる。再びこちらへと方向を転換する鳥の背には、やはり人――それも女性が乗っているようだ。片膝を立て、右手で鷲の背を、左手には小刀を持っている。
大鷲は先ほどよりもさらに速度を増し、急角度で甲板へと向かって一直線に飛来する。衛士達が甲板に並んで槍を構えるが、鳥は全く速度を落とす気配は無い。
このままでは激突する――そう思った瞬間、

「退け」
鳥の背で、女が口を開いた。同時に、巨鳥の姿が女の右腕に吸い込まれるようにして瞬時に消失する。
背に乗っていた女はそのままの勢いで甲板の男達をなぎ倒しながら着地し、哀れな衛士の一人を蹴った反動で自らの体勢を瞬時に整えた。刹那の隙も見せることなく、彼女は倒れた男の一人を盾に取る。
「動くな」とその首筋に小刀を当てた。
「馬鹿な。一人で何が出来ると云うのだ」衛士長らしき男が槍を構える。
「やめておけ。貴様では相手にならぬ」
言い放った女は明らかにアラセマの人間ではない。身に纏った装束には妙な紋様が入っており、両の頬には赤い顔料で線が引いてある。フローリア諸島の先住民族、キヴェンティの一部に見られる特徴だ。その顔には幼さも残るが、キヴェンティの成人は12歳。この娘も、おそらく既に戦士としては一人前のはずだ。
「我が名はクィナ・センテ・キヴェンティ」
娘が衛士長に顔を向ける。その冷たく鋭い緋色の目には一抹の迷いも感じられない。
「神形器ゼーレンヴァンデルングを貰い受けに来た」
多対一の白兵戦を始めたアラセマ軍の衛士達をよそに、【NAME】は甲板と船内を結ぶ階段の真ん中で佇んでいた。上からは戦いの音がひっきりなしに響いてくる。……ということは、つまり衛士軍団はあの娘一人を相手に良い勝負を繰り広げているのだろう。ついでに、人質は無視されたということにもなる。
リネットに手を引かれてここまで戻ったものの、さて、これからどうするべきか。【NAME】の立場からすれば当然衛士に加勢するべきなのだろうが……。
「手を出さない方が良いですよ」
猫を抱えたままでリネットが云った。
「彼女は普通の人間じゃない。変な白い鳥を見たでしょう。あれは“翆霊”です」
(――スイレイ?)
「そう。フローリアの先住民族、キヴェンティ達が行使する力。彼らはその力を得る為に、自分の存在概念の一部を明け渡しているんです。それだけで、いかに強力かつ危険なものか解るでしょう。一見すると普通の生物のようですが……」
確かに、己の存在概念と引き換えというのは穏やかではない。何しろそれは己の根幹を成すモノだ。一部だけとは言え、渡せば失うものが余りに大きい。一歩間違えれば即、死――あるいは崩滅してしまうことだろう。
「あ……僕の猫は、ふつうの猫ですよ」
何を勘違いしたのか、訊いてもいないのにリネットが自分の猫について弁明する。
とにかく、翆霊を相手に戦いを仕掛けるのは危険です――リネットがそう結論付けた時、階下に人の気配がした。
「物知りだな、君達」
見ると、昨日食料庫で出会った密航者、ワン・テオ氏だ。
「お。あの時の掃除係くんじゃないか。お陰様で余計な騒ぎを起こさずに済んだよ。ありがとう」
言いながら、ワンは階段を上がってくる。何故、“余計な騒ぎを起こさずに済んだ”奴が今ひょこひょこと出て来るんだ――?
「ちょっと通してくれよ。上に用事があるんだ」
「上は今――」
リネットの言葉を遮るようにして、ワンがちっちっと指を振って見せた。
「知ってるよ。胡散臭い娘が飛んできただろう」
そのまま【NAME】達の横を抜け、ワンは階段を上がりながら軽く片手を上げる。
「知り合いだ」
背を向けたままでそう云うと、彼は甲板へ出る扉を開いた。濃厚な血と潮の臭いが、船内に流れ込む。
いつしか戦いの音は止んでいた。
甲板は文字通り血の海と化していた。
その中に立つのは、緋色の瞳をした少女が一人。
全身に返り血を浴び、虚ろな目で辺りに転がる屍骸を見下ろしている。
「うーん何だこりゃ。やりすぎだろお前」
ひょこひょことした足取りで赤黒い血溜まりを避けつつ、船室から出てきた男――ワンが、少女に声をかけた。
「適当に騒ぎを起こすだけで良かったのに……殺しすぎだ」
「迷の民にかける情など無い。それより神形器はどうした」ぶっきらぼうに少女が問いを返す。
「いや、それがね……」両手を広げて、参った参った、という仕種を見せるワン。
「警備はしていたが、肝心の船倉は空っぽだった」
「なに?」
少女が声を上げると同時に、うつ伏せに倒れていた衛士の一人が上体を起こした。
「お……生き残りだ。仕留め損ねたな、クィナ」
クィナはそれには応えず、力なく起き上がった衛士を興味無さそうに見やる。
衛士は半ば狂乱気味に声を上げると、槍を構えてワンに向かい、駆け出した。
「君は運が良いな……クィナの方に向かっていたら首が飛んでいただろうよ」
呟くワンの足元には、いつの間にか茨のような植物が張り巡らされ、彼を護るようにして取り囲んでいた。
青い鎧の男 vs 侵入者



ワンに一蹴された衛士は再び甲板に崩れ落ち、放心した表情で呟いた。
「……何なんだお前ら……神形器は一体どこへ……」
「訊きたいのは俺の方だよ。しかし、解ったこともあるな」
ワンは倒れた衛士から目を離し、クィナの方に向き直って続けた。
「衛士連中も知らないってことは、誰かが俺より先に盗み出したってこった」
「乗員を皆殺しにするか」変わらぬ表情でクィナは云った。
「非効率的だな。それに結構強そうなのが清掃員に混じってるぞ」
ちらり、とワンが【NAME】の方を見やる。
「無駄な争いは避けるべきだ。それに――もし盗賊が居たとすれば、とっくに逃げ出している頃合だろう。船上で盗んでそのまま港まで御一緒してたら世話は無い」
クィナは何かを答えようとしたが、言葉は突然の轟音にかき消された。同時に、船全体が左舷に大きく傾斜する。甲板の血溜まりが無数の黒い糸を引き、肉塊の幾つかが転がって海に転落した。
「何だ……こりゃ」
呟くワンの正面――轟雷の如き破壊音を立て、左舷から甲板に巨大な触手が叩きつけられる。
左舷から姿を見せたのは、小島かと見紛う特大の蛸――海嘯獣テンタクルスだった。人間が戦って勝てる相手ではない。
その姿を一瞥すると、「流石にこいつの相手は無理だな」とクィナは右手を翳す。
「――鴇羽」
その腕から滑り出すようにして、先刻の大鷲が姿を現した。
「一旦離脱する」と、それだけ告げてクィナは鷲の白い背に飛び乗った。
「おお。何の躊躇いも無く俺を置き去りにするとは、さすがクィナ」
早々に飛び去るクィナと鴇羽の姿を見送りながら、ワンは甲板に立ち尽くす。
船は左に舵を取りつつ速度を増し、何とか傾斜に抗しているようだが、あんな物がしがみ付いていては長くは耐えられまい。遅かれ早かれ転覆するのは目に見えている。
「後で迎えを寄越してくれるんだろうな……」
ワンの呟きをよそに、連絡船サンメアリ号はゆっくりと海嘯獣の触手に呑み込まれつつあった。
「こっちです」
リネットに導かれ、【NAME】は傾斜した甲板を船尾へと向かう。
海嘯獣の触手は木造の船を蹂躙し、既に各部の構造材を破壊している。このままでは船体が分解するのも時間の問題に思われた。
「海嘯獣は血の匂いに興奮します。すぐに船から離れれば、まだ逃げることは可能なはず……」
可能だろうが無かろうが、逃げる以外に手は残されていない。手近なマストに捕まりつつ、船に備え付けられた小船の縄を解き、脱出の準備をする。
(拙いな……船が保たないか)
絡まる触手の圧力に船体が悲鳴を上げ、甲板に亀裂が走った。
ロープを解き終わると同時に、サンメアリ号の船体は大きく左舷へ傾き――【NAME】とリネットは小船もろとも、荒れ狂う海へと投げ落とされた。
──リコルス港──
子供の声が、聴こえた。
まだ幼い声。けれども、確たる目的を持っている。自分が何者なのかを知っている。そんな印象を与える声。
――早く。
初めて聞く声だった。脳裏に響く声、これは誰だろう。
いや、それよりも……。
自分は今、何をやっているのだったか?
――早く。
船。そう、自分は連絡船サンメアリ号に乗船していた。
奇妙な女が船に降り、衛士は殆ど皆殺しにされた。
更に船は海嘯獣に襲われて……それから。
――壊しに行こう!
少女の言葉につられるように、意識が現実へ引き戻される。
「あ、気が付きましたか」
【NAME】が目を開くと、ぼんやりと白い布の天井が見えた。声の主を探して首をめぐらせる。と、身体の節々に鈍い痛みが走った。
「ここはコルトレカン島、リコルス港の仮設キャンプです。あなたは軍に保護されているんですよ」
そう云ってから、看護婦らしき声は事の顛末を説明してくれた。
あの後――。
船が転覆したことは確かなようだが、結局海嘯獣とサンメアリ号がどうなったのかは、定かではない。多くの乗組員は【NAME】達よりも先に脱出していたようだが、その者達も一様に気を失った状態で海上を漂っていたらしい。場所が外洋で無かったことが幸いし、軍の救命活動は滞りなく行われているそうだ。
「……と、いうことで、軍では救助を確認した人の名前をリストアップしています。具合が良さそうなので、今から貴方にも書いてもらいますね」
半身を起こした【NAME】に、近づいてきた看護婦が紙片を乗せた板を差し出した。
グンナ・フューニー、マイス・ゴートン、シルギン・テオノール……リストに連なる名前の数々は、これまで救助された人物のものだろう。末尾にはリネットの名も記されている。
「ここに自分の名前を――あら、筆記用具はどこへ置いたかしら」
前に書いた人が持って行っちゃったんじゃないでしょうね、などと呟きつつ、看護婦はごそごそと物入れを探り出す。呆とした頭でその様子を眺めていると、天幕の入り口が開かれ、外から兵士らしき影が現れた。
「ちょっと失礼。名簿を借して欲しいのだが」
片手で入り口の幕を押さえつつ、男が云った。
「あ、でもまだこの人は書いてないんですけど」
屈んで道具入れを探っていた看護婦が、顔だけを向けて答える。
「持ち物の検査は終わってるんだろう。良く知らないが、神形器捜索が第一だろうから、大した問題じゃない――とりあえず拝借」
男は【NAME】の手から名簿をひったくると、そのまま外へと引き返していった。
仕方ないなあ、と看護婦が立ち上がって呟く。
「荷物は足元に纏めてありますから、気分が良くなったらもう町の方へ行かれて結構ですよ」
それだけ云い残して、看護婦も天幕を出て行く。
動けないような怪我はどこにも無かったが、それよりも気力が消耗していた。【NAME】は安っぽい寝台に再び横たわると瞳を閉じ、訪れる眠気に身を委ねた。
遭難者の収容された天幕から、少し離れた場所。
リコルス港の片隅に、二人の男の姿があった。
慌しく行き交うアラセマの軍人達からは距離を置き、二人は遠く湾上の救出活動を検分する。とは言え、夜間のこととて右往左往する光を見つめているだけに過ぎない。

「今度は船が沈没か。全く次から次へと忙しい」
大柄な、戦士然とした銀髪の男が呟くように言い、
「が、俺達が来ても結局やることは何も無いな」と締めくくった。
途端に、隣に立っていた神経質そうな男が眉を顰めて向き直る。夜目にも色白で髪も長く、銀髪の男とは対照的に線が細い。だが、彼は毅然たる態度で声を荒げる。
「悠長に構えている場合ですか、神形器が奪われたのですよ!? もはや我々だけの問題では収まりません。ああ……もう……私はベルトーチェ様に合わせる顔がありませんよ」
額に右手を当てて悩ましげな表情を浮かべる。長い金髪が潮風にさらわれ、顔にかかったそれを鬱陶しそうに振り払った。銀髪の方は悪びれた様子もなく、
「別にお前がうちの婆さんと顔合わせる必要は無いだろうが。それに地理的に考えて盗人はコルトレカンへ渡るしか無いんだから、無事に島まで運送できたと云えなくもない」と、安穏とした調子だ。「たかが神形器だしな」
「たかが神形器なんて言い回しは生まれて初めて聞きました。それにどうやったらこれが無事に見えるんです? 行方不明じゃないですか。ワイゼンの名に傷が付きますよ、これは」
「ピリピリするなよケイジュ。どうせ俺達が焦った所で事態は好転しないさ。当面は遭難者の救助を優先するしかないだろう。案外、これで全て上手く行くのかも知れんぞ。紅茶でも飲んで落ち着いてくるか?」
「時々思います。貴方のそのずぶとい神経を少し切り取って、私にも分けて欲しいと」
ケイジュと呼ばれた男が諦めたような面持ちを作った。
「泰然自若と云うんだろ、こういうのは。とにかく、見つからなかったら民間には伏せて捜索かな。しばらくは本国にも秘密にしておく……なんて訳にはいかんかな、やはり」
当たり前です、と即座に答えが返る。
「じゃ、報告書とかその類はケイジュ、お前に一任する。がんばれ」
金髪の男――ケイジュは、ああ……信じられない、と呟いて頭を振った。
夜の海は寒い。救助活動に一区切りつけたアラセマの軍人達は、港に張られた仮設テントの下で休息を取る。
師団長たる銀髪の男とケイジュの姿もその中にあった。二人は向かい合ってテーブルにつき、差し入れの紅茶で暖を取っている。……と、

「あのう、アラセマ軍の方ですね?」
不意に女性の声がした。繊細だが、その声は不思議と港の喧騒の中でも良く通る。
二人が声の方へ首を巡らせると、テーブルの横、ほんの十歩も離れていない場所に小柄な女性が立っていた。腰まで届く真っ直ぐの長い黒髪。踝まである亜麻色の長衣と、袖口に金色をあしらった紫の上着。運動に向いているとは云い難い服装が、いかにも場違いだった。
彼女は心配そうな表情を浮かべ、朱色の瞳は不安げに周囲を窺っている。
「俺はネスカート・ワイゼン。師団長だ」
彼女の姿を認めると同時に、銀髪の男が応えた。彼の方を横目で睨め付けながら、ケイジュは
「貴女は?」と問う。
「私、ユーリと言います。知人の乗った船が沈没したと聞いて、居ても立ってもいられなくて」
「全力を挙げて救出活動中です、ご安心下さい。本格的な捜索は夜が明けてからになりますが、沈んだ場所も近く、この辺りの潮流から見ても助かる確率は高いでしょう。不幸中の幸いでした。それから、諸事情により民間の方は暫く港には――」
入れません、とケイジュが言い終わらぬ内に、
「聞いた話では神形器ですか? それも無くなったとか」
「……誰に、聞きました?」
「サラナ海岸に流れ着いた方が何人かいらっしゃいます。町ではその方々の噂で持ちきりでした。聞いたところでは、キヴェンティがどうとか、神形器がどうとか」
ああ、と呟いてケイジュは天を仰いだ。夜でもあり、天幕に遮られて見えないが、空には巨大な暗雲が立ち込めているに違いなかった。
「ともかくお嬢さん、安心してアラセマ軍に全てをお任せ下さい。貴女の御知り合いは我々が誇りに賭けて、必ずや救出致します。なお、既に救出された者の名簿はあちらでご確認できます」
クスクスとユーリは笑い出し、口元に手を当てる。
「ええ、ありがとう。でも私、お嬢さんなんて言われる年ではありませんの。子供だって居るんですよ」
「なん、ですと? ……結婚……してらっしゃるのですか」
「ええ、夫はもう亡くなりましたけれど」
ユーリは微笑んでそう答える。確かに、彼女の外見は少女と言っても通じる程に若かった。
「それは失礼。しかし……とてもそうは」
「見えませんか? それ、褒め言葉として受け取っておきます」
近づいてきたアラセマの兵士に救助者のリストを渡され、目を通しながらユーリは続ける。
「神形器を盗んだ犯人、見つかると良いですね」
「乗員の救出を優先しますよ」ネスが即答した。
そうね、ありがとう、と再び礼を言い、ユーリは兵士にリストを返した。そこに知人の名はあったのだろうか、表情からは読み取れない。
「ネスさん?」
未だ驚愕と落胆の狭間で揺れているネスに、ユーリが声をかける。
「師団長なんて、もっと怖い人だと思っていました。気さくな方で良かった――本来なら、私など近づくことも出来ないのでしょうに。神形器など物騒な話ですけれど、貴方のような方が指揮を執るなら、きっと安心ですね」
それだけ云うと、ユーリは踵を返した。
「居られましたか?」彼女の後ろ姿に向けて、ネスが声をかける。「貴女の知人」
「ええ」ユーリが振り返る。「ご親切にどうも」
僅かの沈黙の後、挨拶の代わりに柔らかく笑んでから彼女は去って行った。しばしそれを見送ってから、ネスは冷め切った紅茶を口に含む。
「美人でしたね」
茫とする師団長に向かって、ケイジュが云う。
「奥さんへの報告書、私がまとめておきましょうか」
ネスはそれには答えず、拳骨でケイジュの頭を軽く叩いた。
やがて夜が明け、昼過ぎには遭難者の捜索は終わりを告げる。神形器ゼーレンヴァンデルングの行方は杳として知れず、リコルスの港は閉鎖、軍を挙げて全島での神形器捜索が始まる事となった。
神形器 最初の鏡
──最初の鏡──
サリクトラムの村から北に外れた森の中。
『ギアス聖域』と呼ばれるその森は、施された隠匿結界と配された守護の戦士達によって完全に下界から隔絶されている。
聖域の中心に置かれたのは、三本脚の美しい獣を模した優美な祠、白宝宮。
その薄暗い一室に、5つの人影があった。

「一枚目の鏡が割れた」
戸口に立った灰色の短髪の男が呟くように云い、他の4人に視線を巡らせた。
簡素だが独特の流麗な紋様を施された衣装から、彼らがフローリアの先住民族キヴェンティであることが知れる。
興味無さそうな顔で部屋の隅に座る金髪の青年、仁王立ちした屈強な大男、毒々しい緑の髪を持つ小男、そして緋色の冷たい眼をした少女。翆霊との契約による影響か、成人した彼らの髪や瞳の色には統一性が無い。

「アラセマの仕業か?」
緋色の瞳の少女、クィナが訊く。
「判らない。獣の肉片は付近の港に現れた。何者かが追い払うことには成功したようだが」

「逃げられたのだろうな」
「奴らに獣が殺せる筈がない」

「ギ・ロの鏡はあと三枚――」
口々に云ってから、しばし場を沈黙が支配する。

「ふむ……」
と、隅に座って黙していた金髪の青年が静寂を破った。そのまま静かに目を瞑り、
「もう少し細かく刻んで封印すれば良かったのにな」
と神妙な顔つきで続ける。
「慎め、ワン」
緋色の瞳だけを青年に向けて、クィナが云った。ワンの方は全く意に介する様子はないが、クィナもそんな事は最初から了解している。
「已むを得んな。ホノエ、ニケ、ロウは各封印の守護にまわれ」
あれ。俺は――というワンの声を無視して、クィナが続ける。
「誰であろうと構わぬ。鏡に近づく者は総て消し取れ」

「悲鳴が聞こえた……それから化け物が出た、か」
アラセマ常駐軍駐屯地、第六師団本部。
黒塗りの机に両肘をついて手を組み、銀髪の師団長ネスカートは
「釈然としないな」
と続けた。
巨大な円卓には数人の男達が席に着き、各々資料に目を通している。
「そうですか?」
と、資料を見ながらケイジュが答えた。
「私は現場に居た訳ではありませんから仔細は判りませんが――完全に化け物が現れる前から、異状は認められていたようですし。そんなことより、問題はこの化け物の素性ですね」
「黒い肉塊とか云われても困るな」
ええ、と答えてケイジュが紙の束をまとめ、トントンと机の上で揃える。
「ですから今日は、事件の目撃者でもあり、その方面が専門でもある方にお越し頂きました。やはり直接話を聞く方が良いでしょうからね。情報提供者という扱いですが、講義を聞くつもりで臨んでください」
ケイジュは資料を机に置いて立ち上がり、部屋の扉の方へと歩いて行った。
「ではユーリさん、お願いします」

「あれは、ギ・ロの肉片ですね」
部屋に招かれたユーリは円卓の正面に立つと、やおらそう切り出した。
「ぎろ、ですか。初耳です」
合いの手を入れたネスカートを、ケイジュが肘で小突く。余計な口出しはせずに黙っていましょう、ということらしい。
「残念ながらギ・ロについて詳しい書物は現存しません。ただ、サリクトラムの口碑伝承にその名を持つ幻獣の話があります。伝承の筋は単純明快で、むかし翆獣の僕たるキヴェンティ達がこの島で鬼と戦った、つまりキヴェンティというのは、ここフローリア諸島の守護を担う民なのだと、そういう話ですね。曰く――」
遙か昔、フローリアの島々が生まれた時。
強力な『鬼』との戦いがあった。
傷ついた『鬼』からは無数の澱みが零れ落ち、そこから更に多くの魔物が生じた。
コルトレカンに生まれたのは、対照的な二匹の獣。
それらは件の鬼と比すれば無にも等しい存在だったが、人の力では殺すことができなかった。
「……と、この獣の片方がギ・ロと呼ばれていたようですね。獣達は四つに裂かれて尚戦うことを止めず、已む無くセンテの氏族が高位儀式を用いてそれらの肉片を生きたままこの地に封じた――そんなところです」
「なるほど」
「つまり、例の黒いやつがその封じられた肉片の一つではないか、と」
「そういうことです。私の見た限りでは、間違いないでしょうね」
「敵である獣に個体名をつけるのが面白いですね」
ネスカートのその言葉に、ユーリがくすりと笑った。
「個体だけではありませんよ。彼らは自ら裂いた獣の肉片にもウィリ、ルフ、レウムといった名を与えて区別していました。……もっとも現在では全てを正確に伝える人は居ませんが。わざわざ名前をつけるということは、それだけ長い間『獣達』と戦っていた、ということなのでしょうね」
ユーリが部屋を去った後、室内は重い空気に包まれた。
「どうやら、危惧された事態が起こりつつあるようだ」
「やはり『殺すことのできない獣』は実在したようですね」
アラセマが移民を開始した当初から、コルトレカン島ではその噂があった。現地の古村に伝わる不死の獣。実在の確たる証拠は何年も掴めず、既に半ば忘れられていたことだったのだが。
(それが、保険のつもりで神形器を運んでよこした途端にこうだ)
ネスカートは静かに考えを巡らせていた。
長年にわたって隠匿されていたような封印が、自然に解けるとは考えにくい。
ならばそれは、何者かの手によって意図的に破壊されたと見るべきだろう。
しかし……。
「解らんな」
思ったことをそのまま口に出してみた。
「理解する必要など、我々には無いでしょう」
とケイジュが答える。
「誰かが『獣』の解放を狙っている。それだけ判れば充分です。大方、何か狂信的な連中が暴走しているだけのことでしょう」
同席していた者の多くは、それで納得しているようだった。
本当にそうだろうか。
誰かがユーリの云う『獣』を封縛から解放しようとしている、そこまではおそらく間違いないだろう。
……だが、何のために?
わざわざそんな危険なモノを復活させる利点があるだろうか。ケイジュの云うように、狂人の仕業と簡単に片付けてしまうべきなのか。
ネスカートはかぶりを振った。
現時点で答えを出すことはできない。
とにかく、肉片ひとつでこの騒ぎだ。全ての封印が解かれる前に取り戻しておく必要があるだろう。
不死の力に抗する流転の神形――ゼーレンヴァンデルングを。
本サイト内コンテンツの一切の転載を禁止いたします。