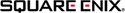オリオール a prologue
── a prologue ──
その島々は、ある筈のない場所から現れたという。
東西南の三大陸の真中に横たわる『芯海』。後にフローリア諸島と呼ばれるようになるその島々が、過去の地図では「何も無い」とされていた海域に出現したのは、今から十年以上昔の話となる。
ランドリート、コルトレカン、アノーレ、エルツァンという四つの大島で構成されるこの諸島には、もう大陸では殆ど見られることの無くなっていた『亜獣』が今も暮らし、誰も足を踏み入れたことも無い遺跡や、異質な概念を秘めた地形が数多く在るとされ、発見当時、大陸で活動する冒険者達の間では『亜獣達の楽園』とも、『最後の新天地』とも呼ばれた。
しかし、この諸島を属領とした西大陸の国アラセマは、諸島に存在する遺跡や発掘される鉱物などによって得られる利益が損なわれるのを恐れ、自国民以外の人間がランドリートの島を除いた三つの島へと渡る事を禁じた。そして慎重に慎重に、未知かつ異質なフローリア諸島の開拓と発展を推し進め、十数年の月日を経てようやくエルツァン以外の島を自らの管理下に置くことに成功した。
幾つかの問題を残しつつも、こうしたアラセマ皇国の篤い保護を受けたフローリア諸島は、このまま順調に発展していくかに見えた。
だが、これは今より数ヶ月前。丁度『東大陸』のグローエス五王朝で発生した『虹色の夜』とそれに類する騒動が一段落ついた頃、フローリア諸島に一つの異常が発生する。諸島ではあまり確認される事のなかった『鬼種』達が、突然その数を増し始めたのだ。
そこから先は劇的だった。鬼種の増加に呼応するかのように、通常ならばそれほど害を及ぼすことの無かった亜人や亜獣達が、突然凶暴化するような事件が多発しはじめる。更に近隣の海と、島を構成する土地概念の異常だ。元々異質な概念を持つ地形の多いフローリアの島々ではあったが、ここ数ヶ月でその異常ぶりに拍車が掛かっている。諸島を構成する島々の内、そういった異質地形が少なく土地概念的に最も強固であるとされたランドリートの島でも、一部の地域に土地概念の異常が発生し、島の北東と南西の二つの地域が封鎖され、侵入が禁止されている状態にある。
その異常により発生する事件を処理し、原因を調査するためにアラセマ本国から正式な軍が諸島へと派遣され、それと同時期に、今までランドリート以外の島では禁じられていた他国民の入島制限も緩められることとなった。そしてその話を聞きつけた三大陸の冒険者達は、『芯海』を越えてフローリアの島へと向かう船に、我先にと飛び乗った。
──【NAME】も、そんな冒険者達の内の一人だった。
・
きっかけは、酷く些細な事だったと思う。
あの左側に立つ男の狡っからい言葉遣いだとか、まだ仕事に慣れてもいない女給に狙いをつけ、執拗にからかう根性だとか。
(こんな筈じゃなかったのだが)
見回し、【NAME】は小さく溜息をつく。都の筋、大通りに面した酒場前は既に人だかりの山脈が円状に聳えている。その中央に立つのは、やさぐれた二人の男と、そして自分だ。
フローリア諸島の外れにある島、ランドリート。それと同じ名を持つ『ランドリートの都』は、諸島外からの船を受け入れている唯一の港であるボーグボーデンを中心として発展した都だ。長い船旅を終え、漸くランドリートの都へと辿りついた【NAME】は、何気なく入った酒場で態度の悪い男二人と出くわした。
油断していたとしか言いようが無い。彼らに少し文句をつけるだけのつもりが、何故か他の席についていた連中が異様に盛り上がり始め、気づいた時には、酒場の前にできあがった闘場の主役へと祭り上げられていた。まさか廻りの人間があれほど争い事に飢えているとは思わなかった。
人の輪で作り出された闘技場の真中に立ち、仕方なく己の武器を構えた【NAME】の脳裏を、都へと向かう船の上で会話した旅人の言葉が掠める。
このランドリートの都では喧嘩はご法度だ。
その旅人曰く、仕掛けた方も受けた方も、ランドリートの治安維持を司る『ランドリート警備団』や『アラセマ常駐軍』に捕まれば営倉行きはほぼ確定だとか。着いた早々ブタ箱直行はできれば遠慮願いたいが、とはいえ、戦いを避けられる状況でもない。もしこの場から逃げ出そうとしようものなら、眼の前に立つ男達よりも、周りを囲む野次馬連中に袋叩きにされかねない。娯楽に飢えた男達の血走った眼がそう訴えている。こうなってしまえば後は──
(とっとと眼の前にいる相手を片付けるしかない)
再度溜息を溢した後、【NAME】は値踏みするように相手の二人を眺める。
戦いというものにおいて、『人数差』というのはなかなかに絶対的で、特に相手が戦闘系の『技法』を習得している場合、一対二の状況を無傷で切り抜けるのは、余程力量に差が無い限りは至難だ。
またつきそうになる溜息を飲み込み、少々の傷を受けることは覚悟する。そして武器を構え、彼らに向かって一歩踏み出そうとした、その時──
「──ちょっと待った」
背後からの制止の声に【NAME】は動きを止め、振り返る。
そこには探検家風の軽装とも重装とも取れる装備を身に纏った、壮年と思しき男が一人。野次馬の集団から抜け出し、人々が作る円の内側、舞台の中へと入ってきていた。
「ンだテメェ、邪魔するつもりかよ!?」
水を差され殺気だった声をあげるゴロツキの片割れに対し、探検家は己の顎を撫でつつ、その意気を削ぐかのような軽い調子で言葉を継ぐ。
「いや、そういうつもりじゃないんだが。ほら、二対一は流石に公平とは思えなくてね。……そっちの君」
【NAME】を指差し、朗らかに告げた。
「僕が君の手助けをしてあげよう。二対二なら釣り合いも良いし、そっちの方が賭けも盛り上がると思ったんだが、どうだろう?」
彼の言葉に、囲う人垣から歓声とも怒号ともつかない声が上がる。よくよくそちらを見てみれば、確かに人波の中に賭けの胴元らしき人物の姿がちらほらと見える。……これは、いよいよもって逃げられそうに無い。
「ええい、いちいちうざってぇ……シモンズ! 両方とも畳んじまうぞ!」
「ウ、ウィッス兄貴!」
周りの異様な雰囲気に触発されたのか、怯えるように武器を構え、向かってくる二人。包む歓声が一気に最高潮にまで達する。
(まったく、いい見世物だ)
内心毒づきながら迎撃の態勢へと移行した【NAME】の耳に、隣に立つ男の気楽な声が届いた。
「ま、僕が見たところ負けはしない。軽く行こう」
視界の片隅に、肉厚の直刀を引き抜く探検家の姿が掠める。──意外なことに、本当に手を貸してくれるらしい。
battle
いつかの二人


【NAME】の攻撃に動きを崩した小柄な男。その隙に彼の側面へと素早く移動した探検家は一足で懐へと飛び込むと、男の脇に肩口を押し当てて気合一閃。
「苛ッ──!!」
ど、と鈍い音と共に小柄な男の身体が吹っ飛び、【NAME】達を囲んでいた人垣に突っ込む。
「兄貴ぃ~!」
返って来る情けない悲鳴に、長身の男は苛立たしげに数度舌打ちし、
「シモンズ! く……っめぇら、覚えてやがれ!」
そんな捨て台詞と共に、探検家に吹き飛ばされ腰を抜かしていた男──シモンズといったか──を抱え、這う這うの体で逃げ去っていく。背を向けて人の波に紛れていく彼らを眺めつつ、直刀を背の鞘に収めた探検家は呆れたように一言。
「もう忘れたよ」
同時に、周囲を包んでいた人々から一際高い歓声と怒号、そして幾つかの胴元らしき人物の間を金が飛び交う。
「君、大丈夫か」
異様な盛り上がりに気圧され、立ち竦んでいた【NAME】は、横から掛けられた探検家の言葉に我に返り、慌てて身体を調べる。大した傷は無い。
(勝ったのか……)
負けることはないだろうと、戦う前、相手の二人を見定めていた時に判っていたものの。事実そうなってみると、やはり嬉しいものだ。
手助けしてくれた探検家に、【NAME】が礼を言おうとしたその時──逃げたゴロツキ達と入れ違うように、その逆方向から人々の叫び声が響く。先程まで響いていたような浮かれたものではなく、どちらかといえば警戒を促すような調子の声に、【NAME】は隣に立っていた探検家と顔を見合わせる。
「なんだ?」
呟く探検家の声に合わせるかのように、人垣が割れる。そこから現れたのは、アラセマ常駐軍の装備に身を包んだ兵士数人と馬上の騎士一人。
「お前達が騒ぎの元凶か」
馬上からの高圧的な声に、探検家が首を捻る。
「どちら様かな?」
「捕らえろ」
問いに答えずに、騎士は言葉短に部下と思しき兵士に指示する。それを聞いた兵士達は無言で手にした短槍の穂先を【NAME】へと向け、左右から油断なく距離を詰めてくる。
(どうしたものか……)
一瞬迷い、そして即決する。明らかに正規の物と思われる軍装に身を包んだ者達。無闇に逆らうのは危険だ。【NAME】は武器を引き、無抵抗を示すために両手を挙げて頭の後ろで組んだ。【NAME】の隣に立っていた探検家も同じ仕草を取り、苦笑気味に呟く。
「しかし、なにやら物騒だね。この程度の喧嘩にもワザワザ君らみたいなのが出てくるのか?」
その言葉に、馬上の騎士は剣呑な声をあげた。
「物騒なのはお前達の方だ。この都で乱闘──しかも『技法』を用いた喧嘩など許される筈も無かろう。牢の中で反省することだ」
騎士の言葉に、【NAME】は、もう今日で何度目かもしれぬ溜息をついた。
オリオール 解放と依頼
── 解放と依頼 ──
例えばの話。
どことも知れぬ島の只中、小さな小さな森の奥に、こじんまりとした一つの家があったとする。
その家の中央には古めかしい木彫りの机があり、その脇には小さな椅子が二つあるとしよう。そして椅子の上には二つの人影がある。
一つの影は教師であり、一つの影は教え子だ。
二人は机を挟んで向かい合い、一人はどこかのんびりとした様子で、一人は少し戸惑った様子で座っている。
「──で、先生」
二つの影の内、より小さい影がその姿に似合った細い──しかし微妙に棘のある声で、もう一つの影に問うた。
「先程のは、一体何の話ですか?」
眉を顰める生徒に、もう一つの影は緩やかな動きで肩を竦めた。
「だから、最初に言ったでしょうに。どこにでも居る冒険者のお話だって」
おどけた返答に、生徒はより険の増した声を出す。
「何故ここで冒険者の話ですか。私はそんな話を聞くために先生の元に居るわけではありません。もう無駄話は結構ですので、早く今日の授業を始めてください」
先生と呼ばれた影は、軽く肩を竦めてみせる。
「つれないわね。というか、気を張りすぎなの貴女は。もう少しこう、肩の力を抜いてだね……」
「力を入れているつもりはありませんが」
間髪入れぬ肩筋張った返答に、先生は小さく苦笑する。
「……まぁ、良いけどね。それに別に無駄話をした覚えはないよ。単純な教訓話」
「教訓ですか?」
「そう。さっきのは『喧嘩するなら常に逃げ道は確保しとけ』っていう話。タメになるでしょう?」
「なりません」
即答。二つの影はそこで暫し沈黙する。
「……で、その後さっきの冒険者がどうなったかというと──」
「まだ続ける気ですか」
呆れたような声音に、先生は朗らかに笑い、
「モッチロン。貴女が泣いて頼むまで話すの止めない」
「…………」
「泣き真似してもダメ。やるなら素で泣いて見せなさい素で」
奇とも嬉ともつかぬ口調に、小柄な影が嘆息する。
「……判りました。先生がお話をするのに飽きてこられるまで、つき合わせていただきます。……でも、せめて次のお話が何の教訓であるかだけでも教えていただけると嬉しいのですが」
慇懃に答える小さな生徒に、机にしな垂れかかるように身を伏せていた影の背中が小さく揺れる。
「くくく。ああ、今度のお話は簡単よ。『その偶然を人は運命と呼ぶか否か』って話。どんなに名の知れた英雄でも、彼や彼女達が構成する物語の全てが必然で始まるわけじゃない。例えば、貴女がここに居るのも、その全てが貴女の意思と力だけで決まったんじゃないのは、判るよね」
「…………」
苦い表情を浮かべて黙る生徒の素直さに、先生と呼ばれる影は喉の奥で笑いつつ、伏せていた身を起して言葉を継ぐ。
「ま、ぶっちゃけて言っちゃえば『運も実力のうち』って奴?」
「ぶっちゃけ過ぎです」
・
このフローリア諸島には、街や都がそれぞれ持つ治安維持機構の他に、アラセマ常駐軍と呼ばれるより上位の──軍隊が存在する。
アラセマ常駐軍と呼ばれる一団は、フローリア諸島を属領とする西大陸の国、アラセマ皇国から派遣されてきた軍隊である。『常駐』というその名とは裏腹に、この諸島に古くから駐留していた軍ではない。ここ数ヶ月ほど前から発生し始めた、フローリアに属する各島とその周辺の異変。それの対処と調査のために、西大陸にあるアラセマ本国から派遣されたのが彼らだ。
アラセマ常駐軍の駐屯地は、フローリア各島に点在する街か村の近隣、もしくはその内にある。ランドリートの都の場合は、都より若干の距離を置いた平地上に設営されている。故に、彼らの駐屯地にある施設の殆どは、突貫作業による急場凌ぎの物で作られた──もしくは仮組みのみで構成されたものであり、牢の方も作りは極々簡素なものとなっている。
そんな出来合いの牢の中。窓も無く床も無く、剥き出しの土の上に、独り【NAME】は立ち尽くしていた。
既に日は暮れているらしい。窓は無いものの、周囲に漂う空気が寒々としたものへと変化したことから、それが判る。
ぐるりと一度だけ牢内の様子を見渡し、【NAME】は暫し思案した後。簡単に結論付ける。
(……逃げ出せなくも無いか)
牢というより、留置所と呼んだほうが正しい。格子は鉄製であるものの接合部は弱く、四方を占める壁も薄い。全力を出せば容易に抜け出せる。
──が。
【NAME】はその考えを体外に吐き出すかのように、すっと息を抜く。
流石にそれは短絡過ぎる。逃げ出し、もし途中で捕まってしまった場合のことを考えると、やはり脱獄には二の足を踏まざるを得ない。大体、こちらはたかだか都内で喧嘩しただけである。わざわざ逃げ出さずとも、それ程時間も掛からずに釈放されるだろう。
そう判断した【NAME】は、湿気た土の上に腰を下ろし、時間が過ぎるのを待つ事にしたのだが。
「おい」
唐突に話し掛けられ、伏せかけていた顔を上げる。
声がした場所は牢の外、簡素ながらも鉄で作られた格子の向こう側だ。そこにはこの牢の番人と思しき、アラセマの兵士用装備に身を包んだ男が立っていた。
男は【NAME】が顔を上げたのを見届けると、格子に掛かった鍵を面倒そうに開き、手招きする。
「出ろ。釈放だ」
……予想外に早い。釈放は少なくとも明日になってからと考えていたのだが。
意外そうな顔を浮かべた【NAME】に、男はむっつりとした表情のまま動きを止めたあと、
「理由は知らん。上からの命令だ。──ほら、とっとと出て来い」
彼を苛立たせても得をすることはなかろう。【NAME】は土の上から腰を上げると、素直に彼の後へと従った。
・
【NAME】は先導する男の後に続き、営倉となる建物から外へと出る。先刻の予想通り既に駐屯地には夜の帳が降り、その中を輝く赤く白い光が点々と、夜に抗うように咲いている。
兵士が向かったのは敷地の中央、常駐軍駐屯地の中で最も大きな施設。その扉を潜り、施設のエントランスへと足を踏み入れた【NAME】は、そこでそれぞれに時間を過ごしていた駐屯地の人間の中に、一人の男の姿を見た。
(あれは……)
都でゴロツキと喧嘩した時に手を貸してくれた、名も知らぬ男だった。
夜となり既に閉じた窓口の壁に寄りかかっていた彼は、【NAME】の姿に気づくと軽く手をあげて挨拶。【NAME】はその仕草に眉を顰めつつ、何故ここに彼も居るのかと訝しげに見やり──ふと気づく。
荷物や服装、剣などの武装が、会った時そのままだった。
(捕まったわけじゃないのか?)
当然ながら、【NAME】の所持品は営倉に入れられる前に全て軍に没収されている。なのに、彼にはそういった雰囲気が無い。とはいえ、会った時に然程気にして相手を見ていたわけでもないので単なる印象だ。気のせいである可能性も高いが。
「【NAME】、で宜しいですね」
──と。
脇からの唐突な声に【NAME】は小さく肩を震わせ、慌てて声のした方へと振り向く。そこには、先程の兵士とはまた異なる、より事務的な衣装に身を包んだ女が、いつの間にか立っていた。恐らくはこの駐屯地に詰める職員か。
彼女は【NAME】が驚きから覚めるのを待ってから、再度問う。
「宜しいですか?」
一瞬何が宜しいのかと迷い──名前の正否を問われているのだと気づく。反射的に頷くと、脇に抱えていた荒い紙を数枚取り出し、【NAME】へ見えるように掲げて示す。
「当常駐軍での手続きはこちらで済まさせていただきました。これにより、貴方はこのフローリア諸島で当軍を補助する者として行動する権利と、当軍駐屯地で幾つかの補助を受ける権利が与えられ、軍が『討伐指定』もしくは『害獣指定』を行った対象を発見した場合、これを撃退する義務が発生します」
そんな勝手に──と言い掛けた【NAME】を遮るように、彼女は間髪入れずに言葉を繋ぐ。
「フローリア諸島での特殊地形探索などをされるおつもりでしたなら、この契約は必須のものです。ご不満でしたら島を去られるべきでしょう」
きっぱりと言われ、言葉に詰まる。その間にも女の説明は続いていく。
「貴方は『第○旅団』の所属で、軍での待遇は『序階士位』相当となります。備品支給などもそれと同等の物を与えられます。詳細については駐屯地の窓口で改めてお尋ねください。
また、貴方はワイゼン家からの推薦という形になりますので、後援を受けた家の名を汚さぬような行動を心がけてください。以上です」
そこまで一気に告げて、職員らしき女は小さく一礼した後、手に持っていた荷物を【NAME】へと差し出す。【NAME】の荷物だった。反射的に出した【NAME】の手に荷が収まったのを確認したあと、小気味良い動きで踵を返すと無言のまま去っていく。一片の隙も無いその振る舞いに、【NAME】は茫然とその後ろ姿を見送るしかできなかった。
そして、漸く我に返ると、まず疑問が頭に浮ぶ。
(──推薦?)
女の最後の言葉に、【NAME】は素直に首を捻る。ワイゼン家といえば、このフローリア諸島を属領としているアラセマ皇国を事実上治める『六家』の一つ。生粋の名家であり、その影響力は国の中心からは遠く離れたこの島でも十分に通じる。そのような家が、何故自分のような流れの冒険者を『後援』する?
そう自問した【NAME】の視界に、一人の男──探検家風の衣装を纏ったあの男だ──が軽く手を振る姿が映る。
(……なるほど)
得心いった表情で頷いた【NAME】を見て、彼は軽く笑みを浮かべて手を挙げた。
「ま、俗にいうところのコネという奴だよ。正直、島に渡ってきた早々こうなるとは思ってなかったが、こちらも大人しく所持品を調べられる訳には行かなくてね」
言って、彼は自分の背嚢を軽く叩いてみせた。
「君のほうの持ち物は大丈夫かい? 無くなっている物は無いか? ここはどうか知らないが、場所によっては金目の物が抜き取られている場合もあるからね」
軽く所持品を調べてみるが、なくなっているようなものは無い。という以前に、無くして困るようなものなど元々持ってはいない。
そんな【NAME】の様子に彼は苦笑しつつ頷くと、
「では、本題に入ろうか」
同時に、男の視線に真剣味が増す。それに気づいた【NAME】も軽く姿勢を正してその視線を受け止めた。
「当然──というかどうかは判らないが、こうして君を出してもらったのには理由があるんだ」
どこか問うような調子の彼の言葉に、【NAME】は無言で頷く。
殆ど赤の他人といってもよい自分を彼が助けてくれる義理など、本来ならば微塵も存在しない。なのに、わざわざ彼の言うところの『コネ』を使って、こちらを釈放するよう軍に呼びかける。先に恩義を与えておいて、交渉をより有利にするのは基本中の基本。つまり、何かこちらに頼みたい事があるのだろう。
だが、アラセマの一級貴族であるワイゼン家に対してコネがあるという程の男が、何故身元も知れぬ冒険者を使おうとするのか。それが【NAME】には判らなかった。
「──の前に」
と、そこで探検家は言葉を切ると、油断なく周囲に視線を走らせ、どこか呆れたような表情で顎を擦る。
「ひとまずここから出ようか。どうも落ち着かない」
その言葉に、エントランスの薄闇の一部が小さく身じろぎするのを、【NAME】は確かに感じた。
・
「君は、どうしてこの島へとやってきたんだ?」
そう問われたのは、既に施設を出て数分歩き、駐屯地の内と外とを区切る柵に近づいた頃だ。
【NAME】は返答に迷い、黙する。一応の恩人とはいえあまり赤の他人に話すようなことでもないからだ。
難しい表情を浮かべる【NAME】に気づき、男は少し困ったような調子で続ける。
「ふむ、少々不躾だったかな。別にそう立ち入った話でなくて、暫く予定は空いているかどうかを尋ねたかっただけなんだが」
少し先を歩いていた背中が立ち止まり、【NAME】の方へと振り返る。
「もし、差し迫った用が無いというなら、一つ僕から提案があるんだ。君も、ランドリートの都にあるボーグボーデン港は、諸島外からやってきた船しか受け入れていないのは知っているだろう? そのお陰で、フローリア諸島に属する他の島へと渡るには、ランドリート島の南東に位置するこの都の正反対、北西の端にある『旅立ちの街ラースナウア』の港まで行かなければならない……ここまで良いかい?」
彼の言葉に、【NAME】は船上で聞いた旅人の話を思い出し、そして頷いた。ランドリートの港は現在飽和状態に近く、故に『客』である外来の船を逃さぬよう、諸島内を行き来する連絡船などは別の街にある港を利用しているとか。恐らく、彼のいうラースナウアがその街にあたるのだろう。
「で、僕はその街に停泊しているコルトレカン島行きの船に少しばかり用事があるんだが、一人でそこへ向かうのは少々危険でね。だから君を道連れにと──まぁ、堅苦しく言えば、君に僕の護衛を頼みたいんだ」
護衛? と問い返すように視線を送ると、彼は軽く頷いた。
「うん。君をこうして外に出すように彼らに頼んだのはこういう理由だ。深くは説明できないが、正直、誰が味方で誰が敵だか判らん状況でね。君は見るからに島外の人間だったし──それに、僕は人の縁というものを信じる方なんだ」
そこでどこか軽い調子で笑った後、男は口調を改める。
「どうだろう。向こうに着けば金の方も、300zid程度なら払えるだろう。何ならコルトレカン行きの船に乗せてもらえるように頼んでも良い。ラースナウアまでは結構な距離があるから、大して美味い話とは言えないかもしれないが……受けてもらえないだろうか?」
暫し迷ったが──結論は簡単に出た。【NAME】は小さく頷き、男に了承の意思を伝える。
嵌められた感が無いでもないが、仕事としてそう悪いものでもない。どちらにせよ、ランドリート島は冒険をするには些か不向きな場所で、一部の冒険者の間では『フローリアであってフローリアでない』と言われている場所だ。本格的な冒険を行うつもりならばランドリート以外の島へと渡らねばならず、その為にいつかはラースナウアへ赴かねばならなくなる。となれば、そこへ向かうついでに報酬が貰えるというこの仕事は、正に渡りに船だった。
「そうか」
【NAME】の返答に、男は満足げに頷き返した。
「では宜しく頼む、【NAME】君──と、まだ名乗っていなかったな」
彼は握手を求めるために差し出しかけた右手を途中で止めて、小さく咳払いする。
「僕の名はオリオール、ハマダン・オリオールだ。東大陸にあるフォータニカという国で、考古学博師を務めている」
改めて差し出された手を、【NAME】は軽く握り返した。
「では、まずランドリートの都へ戻ろうか。細かい話は、移動しながらするよ」
・
常駐軍駐屯地から、都へ。オリオールと名乗った男と【NAME】は、夜に暮れた草地に細く伸びた道筋を、然して急ぐでもなく歩いていく。
「まず、道順について話しておこうか」
【NAME】から数歩前を歩いていたオリオールは、振り返る事無く説明を始める。
「ランドリートの都からラースナウアの街へと向かうルートは、大きく分けて二つある。アンタア東街道から向かうルートと、オーンアム南街道から向かうルートの二つだ。本来なら、ランドリートを包む外環四街道をそのまま進んでいけばラースナウアに着くらしいんだが、今はまぁ、それどころじゃないらしくてね」
笑いでも堪えているのか、オリオールの肩が小さく揺れた。
「アンタアから廻る場合は、希望の平原からポリツェルッツェンの村を北に抜けて、そこから巨岩の荒野を経由してオータの河を渡ればラースナウアに着く。オーンアムから廻る場合は、途中で島中央の山岳に入り、オーンアム間道を通ってマルダの村へと移動する。そこから山中公路を通って北へ向かえばラースナウアに着く。どちらもかなり危険らしいが……どちらかといえばオーンアム南街道からのルートを使った方が楽らしいね」
(楽、か)
【NAME】は、オリオールの言葉に軽く首を傾げる。四つあるフローリアの大島のうち、最も安全であるとされるのがこのランドリートの島だという。ならば、どのルートを通ったところで楽なことには変わりないのではないか。
【NAME】がそう尋ねると、オリオールは唐突に立ち止まって、じっと前方を見据えた後、軽く嘆息。そして疲れの混じった声音で続けた。
「本来ならば安全らしいんだが……聞いたところによると、このランドリートの島でも鬼種や亜獣の動きが活発になってるっていう話でね。かなり治安が悪くなっているらしい。ほら、その証拠に──」
そこでオリオールは言葉を切り、自分達が歩いていた道の先を示す。そこには、【NAME】達の姿を見つけ、『獲物』を狩るために動き出した凶暴な獣の姿があった。
「都の近くでも、こういう類の獣がでるようになってる。島の奥地の方じゃどうなってるか、想像するだけで憂鬱になるね」
確かに彼の言う通り、この島はもう安全な場所ではなくなっているらしい。
【NAME】とオリオールは武器を構え、襲い掛かってくる獣と相対する!
battle
野犬の群れ


獣達を無難に片付け、夜が深ける前に何とかランドリートの都へと辿りつくことに成功した。
──と、丁度都の門を潜ったあたりで、オリオールが【NAME】に振り返る。
「さて……すまないが、僕は少し島の人たちに用事があってね。訊き込んでおかないとならない事があるんだ。でも、そこまで君らに付き合わせるのも悪い。だから、街では別行動ということで構わないか?」
拒む理由も無く、【NAME】は頷く。常に相手のスケジュールに合わせて拘束されるというのは流石につらい。
「判った。ラースナウアへは結構長旅になると思うから……そうだな、この都の近くに『プポルの庭』があった筈だ。腕に自信がないなら、そちらの方で軽く訓練してみるのも良いだろね。……とにかく、僕はそろそろ失礼するよ。都を出る準備が整ったら適当に声を掛けてくれ」
そう告げて軽く手を上げた後、オリオールは振り返る事無くその場を立ち去った。少しばかり大きな背嚢を背負った後ろ姿が夜の都の雑踏に消えていくのを見送った後、【NAME】は背嚢を抱え直しつつ思案する。
(これからどうするかな)
選択肢は意外と多い。
準備も程々に、ラースナウアの街へ向かって旅立つか、それともランドリートの都を軽く観光してみるか。オリオールが言っていたように亜獣の住処に出向いて腕試しをするのも良いし、一度軍の駐屯地へ足を運んでおくのも悪くないだろう。
オリオール 襲撃と疑問
──襲撃と疑問──
例えばの話。
どことも知れぬ島の只中、小さな小さな森の奥に、こじんまりとした一つの家があったとする。
その家の中央には古めかしい木彫りの机があり、その脇には小さな椅子が二つあるとしよう。そして椅子の上には二つの人影がある。
一つの影は教師であり、一つの影は教え子だ。
二人は机を挟んで向かい合い、一人は深く椅子に腰掛けて、一人は気難しげに首を傾げている。
「……先生」
首を傾げていた影がもう一つの影に呼びかけると、どこかだらしなく背凭れに身を預けていた影が小さく動く。
「なぁに」
「このお話には、何の意味があるのでしょう? 本当にただの教訓話でしかないのですか?」
本来なら教訓話ですら無いというのを責めているかのような口調に、先生と呼びかけられた影はくすりと笑う。
「始めにそういった筈だけど。ただの教訓話だって」
「……先生のことですから、もっと別の何かが話の裏にあるものだと思っていたのですが。本当に、それだけなんですが」
「何? 嘘言ってるとでも思ってた?」
「…………」
「本気で泣きそうになってる?」
小柄な影が反射的に動き、だん、と木彫りの机を強い調子で叩く。だが、もう一人の影はその動きを面白そうに眺め、声をあげて笑うだけだ。
「くくっ──まぁ、今はまだね。もう少ししたら、貴女にも判るような話になるから」
その言葉に、立ち上がっていた影の動きが止まる。
「私が、ですか?」
「そ。聞いてて損な話じゃないから。今日のところはお勉強は我慢なさい」
「……『今日のところは』って、一日掛かるんですかその話」
暫し無言。
「で、次は『旨い話には裏がある。痛い目見たくなかったら、迂闊に話に乗るのは止めましょう』って話。正に教訓話ね」
「何だか俗っぽいです」
「実際、俗世の話なんだから仕方ないでしょ。……じゃ、続き行くよ。その時、名も無き冒険者は──」
・
夜。
眼前にようやく村の姿が見え始め、詰めていた息を抜きかけた【NAME】達は、村へと続く道上に、敵意を帯びた複数の人影を認めた。武器に手をかけつつ、【NAME】達は警戒するように立ち止まる。
「何用かな」
一歩前に進み出て問うたオリオールの言葉を無視し、その影達は素早く散開。一瞬にして【NAME】達を取り囲むように動き、徐々に包囲を狭めてくる。
夜の闇に紛れ、その正体は一目では判らないが、彼らの素早く隙の無い動きは、明らかに真っ当な訓練を受けた者のそれだった。
「交渉する気など毛頭なし、か。何とも物騒な賊だね」
彼らの動きを呆れたように眺め、オリオールは嘆息しつつ言葉を継ぐ。
「でも、動きで判るよ。──軍の者だろう、君達は」
オリオールの褪めた声が一瞬だけ彼らの動きを止める。
「どこの家の連中かは知らないが、今は君達に構っている余裕は無いんだけどね。お引取り願えないか」
問いに、影の集団から一つが進み出る。
「申し訳ありませんが──こちらにも立場というものがございますので」
影から響くのは慇懃な拒絶。その態度からも、相手が山賊などとは根本的に異なる者達であることが容易に知れた。
その返答にオリオールは参ったとばかりに頭に手をやり、苦笑。
「……やはり、駐屯地で身分を明かしたのは迂闊だったかな」
苦々しげに呻くオリオールを見やり、【NAME】は密かに溜息をつく。護衛を頼むくらいだから、誰かに狙われているのだろうという程度の予想はしていたが、こういう相手が出てくるのは想像の外にあった。正規とは異なるといえ、軍の集団と事を構えるというのは、あまり楽しい話ではない。
「まぁ、通してくれぬというならば、無理に進むしかないわけだけど」
オリオールは話は終わりとばかりに言い捨てて、腰の後ろに撒きつけた鞘から厚みのある小剣を引き抜いた。そして、背後に立つ【NAME】へと視線だけで振り返る。
「【NAME】君、正面から包囲を突破する。村まで行けば向こうも手を出せまい。──準備は良いか?」
愚問だった。当の昔に【NAME】は戦闘体勢へと移行している。それを確認したオリオールは、視線を前へ──村の方向へと移す。
「よし……では、行こうか」
battle
夜の襲撃者


「いやはや、何とか助かったね」
台詞とは裏腹な「助かって当然」といった調子で呟くオリオールに、【NAME】は返答する余力も無く、小さく頷くだけ。
包囲網の一角を破ることに成功した【NAME】達は、その穴を突いて包囲を脱し、何とか村の中へと逃げ込むことに成功した。
村の中へと飛び込んでしまえば、もう先刻の一団が追ってくることは無かった。村の広場まで無我夢中で駆け抜けた後、荒く息を吐いて乱れた呼吸を整える。
(しかし、何だってあんな連中に──)
襲われねばならぬのか、と問い質すようにオリオールを見れば、彼は、自身が持っていた背嚢を地面に下ろし、苦々しい表情でそれを眺めていた。
(なん、だ?)
──と、【NAME】の視線に気づき、オリオールが慌てたように顔を上げて、地面に降ろしていた背嚢を担ぎ直した。
「とにかく、流石に疲れた。今日はもう休むことにしよう。宿の部屋が空いていてくれれば良いけど、どうだろうね」
オリオールは取り繕うようにそう言って、歩き出す。
「…………」
夜の広場を歩いていくオリオール。【NAME】は、彼の背中で揺れる妙に縦長の背嚢を無言のまま眺め──小さく溜息をついたあと、疲れの滲んだ足取りで彼の後を追った。
オリオール 報酬と出航
──報酬と出航──
例えばの話。
どことも知れぬ島の只中、小さな小さな森の奥に、こじんまりとした一つの家があったとする。
その家の中央には古めかしい木彫りの机があり、その脇には小さな椅子が二つあるとしよう。そして椅子の上には二つの人影がある。
一つの影は教師であり、一つの影は教え子だ。
二人は机を挟んで向かい合ってはおらず、二つの影のうち、より小さい方は机に幾つかの書物を広げ、何やら作業をしている。
その小柄な影を眺め、もう一つの影が呆れたように呟く。
「……何それ」
対する影は、机から顔をあげると手に持っていた本の表紙を、もう一つの影へと見せた。
「これは『芯なる者』と『地母種』の歴史に『古賢属』がどう関わっていったか、ということを記したものですね。前に先生の書室でお借りしたものです」
「うわ」
先生と呼ばれた影は、げんなりとした声音で呻く。
「またツマンナイもの見てるねー。っていうか、それの片手間にこっちの話聞くつもり?」
「只の教訓話ならそれで十分かと」
「言う言う」
だが、生意気な口を利く生徒に怒るような気配も無く、寧ろどこか面白そうな様子で、先生と呼ばれた影は気だるげな調子の言葉を続ける。
「まぁ、仕方ないか。でも、ここから先は貴女も一度は聞いたことがあるだろうし、良いかね。──でも、一応続けるよ」
・
ラースナウアの街の中心にある、一際大きな屋敷。その一室に二人の男が居る。一人は探検家風の装束を纏った男、ハマダン・オリオール。もう一人は、色素の抜けた髪を後ろに流した、既に老境の域に差し掛かった長身の男。二人の間には無骨な事務机があり、その上には細く長い一つの品が置かれている。
「荷の方は確かに」
その品を手に取り、暫し眺めた後。呟かれた男の言葉を聞いたオリオールの肩から力が抜け、安堵の吐息が漏れた。
「……これで役は果たしたかな。そちらに『翼』があるなら、報告の手紙を当主に──ベルトーチェ様へ出しておいてくれ」
「承りました、ハマダン様。大任、ご苦労様です」
深々と頭を下げたあと、男はにこやかな表情のまま続ける。
「……正直にお話しますと、ベルトーチェ様は貴方がこの話を受けてくれるとは考えていらっしゃらなかったそうで、酷く驚いてらっしゃいましたよ」
その言葉に、オリオールはどこか疲れたような笑みを浮かべた。
「断れないよ。フォータニカへの留学は情けで許してもらったようなものだからね」
と、そこで真剣な表情に変わる。
「しかし、もうワイゼン家とは絶縁に近い状態の僕にこういう役を任せるというのは、正直どうかと思うんだが。僕は国を捨てた人間だ」
どこか自虐的な言葉に、男は内心苦笑しつつ口を開いた。
「それだけ、ベルトーチェ様が今もハマダン様を信頼されているということでしょう。先刻の『虹色の夜』の件で、ハマダン・オリオールの名前は西大陸の方にも伝わっておりますよ」
途端、オリオールの表情が苦々しいものに変わる。
「……なんで」
「あの事件の特徴を考えれば自明かと思われます。特に召喚専家はどこもかなり熱心に情報収集を行っておりました」
笑いを含んだ男の声に、オリオールは頭痛を堪えるように頭を押さえた。虹色の夜と呼ばれた事件は、現世界に異世界の異質な概念や化け物が無差別に召喚される大災害だ。召喚術を生業とする家では、確かに興味深い事件だったのだろう。
「この話をしましたら、マウセリア様などはもう酷くお喜びになられて、嬉々として他の方に触れ回っておりましたから。一時期、宮廷の方ではハマダン様が大ブレイク」
「……ブレイク?」
「ええ。大ブレイクでした」
オリオールはとことん苦り切った顔で暫くぶつぶつと呟き、深く溜息をつく。そして自分の想像を払うように頭を数度振ったあと、男の方を眺める。
「しかし、あなたがフローリアに居るとは思わなかった。てっきり家の方に居るものと思ってたよ。こっちに居るのは、兄さんの世話かい?」
「いえ、ネスカート様はそういうった事はお嫌いなようですし。今度軍の方へ入られたワイゼン正家のお嬢様の付き添いです」
「……正家の女性が軍に? そこまで手駒が足りていないのか?」
「そうですね──大きく見れば、やはりハマダン様の仰る通りです。ハマダン様がアラセマを去る前まではそうでもありませんでしたが、今ではアスカーンとフハール家の力が増しておりまして。正直な話、猫の手も借りたい状況です。ベルトーチェ様も頭の痛いところでしょう」
「アスカーンとフハールか……」
オリオールは呟き、ふと何かを思い出したように顔を上げた。
「そういえば、ここへ来る道中、一度軍関係者に襲われた。僕がヘマを踏んだというのもあるが……コレの正体まで掴んでいるのかどうか判らないけれど、第六師団──ワイゼン家のほうで何か怪しい動きがある、ということくらいは他の師団にも漏れていると思う。キヴェンティ……だったか? 軍には彼らと繋がっている者も居る筈だから、気をつけてと兄さんに伝えて欲しい。まぁ、第六師団はワイゼン家の力が特に強いという話だから、取り越し苦労かもしれないけど」
オリオールの言葉に、白髪の男は眉を顰めて小さく唸る。
「できうる限り内密に進めていた筈なのですが──ランドリート島の軍にまで既に伝わっていますか」
内密に進めていたというのに、既に他の師団にまで情報が伝わっている。となると、情報隠蔽は殆ど上手く行っていなかったということになる。
沈黙した男に、オリオールは困った表情で呟いた。
「……これは、もう手遅れかな?」
「そう、かもしれませんね」
オリオールはそこで思案顔のまま暫し固まり、そして視線を机の上の品に移しながら男に問うた。
「あなたも船でコルトレカンへ渡るのか? あなたがコレの護衛につくなら問題もないだろうけど」
問いに、男は「いえ」と短く頭を振った。
「まだ事務作業が残っておりますので。念のため、次の船で移動する予定ですが、それもいつになるやら。コルトレカンへの運搬にはネスカート様から送っていただいた衛士団に護衛を任せます。とはいえ、先程のお話を考慮に入れますと、彼らだけでは少々不安が残りますね──」
そこで、男のどこか窺うような視線に気づいたオリオールは、居心地が悪そうに視線を逸らせる。その様子に、男は嘆息しつつも改めて言葉で問うた。
「ハマダン様はコルトレカンへはお渡りにならないのですか? ネスカート様とはもう長い間お顔を合わせていらっしゃらないのでしょう?」
男の言葉に、オリオールの表情にはっきりとした影色の幕が下りた。
「今さらだ。僕にしてみれば、兄さんに合わせる顔が無いよ。軍から逃げた弟なんてね。いずれは向こうの島へと渡るつもりだけど、会いに行く気はない」
どこか鬱々とした声は、それ以上の言葉を拒絶していた。暫しの沈黙のあと、オリオールは少しばかり強張った顔を解すように軽く頬を撫でる。
「じゃ、用も済んだことだし。そろそろ僕は行くよ」
小さく笑みを浮かべ、男に別れを告げて踵を返す。止める言葉も無く、男は深く頭を下げるだけでそれに答える。
──と、部屋を出ようと扉に手をかけた状態で、オリオールの動きが唐突に止まる。
「ああそうだ」
「どうしました?」
呟くオリオールに、男は訝しげに問うた。すると、オリオールはどこか困ったような表情で振り返る。
「いや、ここへ移動してくる間に冒険者を雇ったんだが、彼に報酬を払わないと。すまないが、そちらに金はあるかな」
照れた様子のオリオールに、男は苦笑しつつ立ち上がる。
「金の方でしたら、こちらへ移る際、家からいくらか預かっております。ハマダン様にお渡しするのでしたらベルトーチェ様もお怒りにはならないでしょう」
「済まない。あと、その冒険者をサンメアリへ乗せてやって欲しいんだが、構わないか?」
それも造作も無い。男は短く頷いた。
「捻じ込んでおきましょう。ハマダン様がコルトレカンへ渡らないというのでしたら、部屋の空きくらいはあるでしょうから。……尤も、船長の性格を考えると、あの部屋にその方が割り当てられるとは到底思えませんがね」
二人、声も無く笑い、そしてそれが収まった後、オリオールは改めて口を開く。
「では、そろそろ行くよ」
「ええ。あと──探し人の件、承りました。この状況ですのであまり人手も出せませんが、出来うる限り調査しておきます」
「頼む。じゃあ、元気で」
「ハマダン様も。あまり無茶をなさらぬように」
・
「ということで、これが報酬だ」
どん、と。部屋の中央に置かれた粗末な机に、アラセマ皇国で使われる金、zidが置かれる。アラセマの属領とされるフローリアでは、この通貨単位が基本だった。
ラースナウアの港の近くにある一軒の宿屋。その二階の一室に部屋を取った【NAME】の元へオリオールがやってきたのは、つい先程の話だ。オリオールは机の横に置かれた丸椅子に腰を下ろし、持ってきた金を【NAME】の方へと差し出す。
「あと、コルトレカンへの船に君が乗せてもらえるように頼んでおいた。名はサンメアリ号。港の一番東側に停泊している連絡船がそれだ。無理矢理頼み込んだから扱いがどうなるか判らないけど、とにかく乗せては貰えると思う。コルトレカンへ向かうつもりならばその船を使ってくれ」
彼の言葉に、【NAME】は金の確認をしつつ、宿の鎧戸を開けて港の方を見る。港の最奥、東の端には、停泊するほかの船よりは明らかに一回りほど大きい巨船が停泊している。恐らく、あれがサンメアリ号か──などと考えつつ金の勘定を続け、確かに300zidある事を確認し終えると、オリオールに短く頷いてみせる。
「そうか。じゃ、僕はもう行くよ。一つの用事は終わったけど、もう一つの用事がまだ残ってるからね。まだ君がこの島で活動するつもりならば、いずれ会う事もあるだろう。その時まで、健やかに生きていけることを願って」
オリオールは小さく手を振ると、【NAME】の部屋から去っていった。
(もう一つの用事……?)
オリオールの最後の言葉に、【NAME】は首を傾げる。それが一体何なのかと、心の中で好奇心という名の蛇が首を擡げるのが判ったが、かといってそういった話を訊けるような間柄でもないし、既に彼は去った後だ。わざわざ追いかけて、呼び止めてまで訊く程のことでもなかった。
……それこそ、どこかでまたもう一度会うことがあれば、その話を訊ける機会もあるだろう。【NAME】はそう判断し、身を粗末な寝台の上へと投げた。