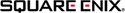![]()
みんなdeクエスト 那由多の道と異界の扉
- 花々からの観察者 商都テュパン a prologue
- 花々からの観察者 ウスタール大街道
- 花々からの観察者 大海神祭
- 花々からの観察者 刻印
- 花々からの観察者 接触
- 花々からの観察者 象形
- 花々からの観察者 護法
- 花々からの観察者 覚醒
- 花々からの観察者 幕間
- 花々からの観察者 妖精
- 花々からの観察者 娼館
- 花々からの観察者 懇願
- 花々からの観察者 月下
- 花々からの観察者 風羽
- 花々からの観察者 虹色
- 花々からの観察者 聖域
- 花々からの観察者 破砕の護竜
- 花々からの観察者 終結
- 花々からの観察者 月夜に咲く an epilogue
花々からの観察者 商都テュパン a prologue
──商都テュパン a prologue──

ある大陸の西南部。大国が乱立する一地方に、グローエス五王朝と呼ばれる連立国家がある。
中央をグローエス、北西をカルエンス、北東をクンアール、南東をオルス、そして南西側に広がる土地を治めているのがテュパン。この五王朝の中で、テュパンは唯一海と面している国である。
通称『南海』と呼ばれるその海上を、留まることなく走る風達は暖かく、強い。
そんな力強い空気の流れを帆一杯に受けて、一隻の船が澄んだ碧色の海に緩やかな波を立てて進んでいく。
木造船の甲板。所狭しと積み上げられた輸送物資に埋もれるようにして甲板の縁から海を眺めていた貴方は、青く高い空から降り注ぐ陽光を遮るように軽く額の高さに手を掲げ、船が進む先を見据える。
見えるのは、真昼の強い陽光に晒されて白く白く染まる街並み。
商都テュパン。五王朝における海の玄関口だ。
船から桟橋に渡されたタラップを伝って、久々の石畳を踏みしめる。文字通り、地に足がついた気分だ。
最後の最後に船を下りたため、既に桟橋に人は居ない。軽く身体を伸ばし、深呼吸。そのままゆっくりと視線を巡らせる。
翠色に近い色彩を持つ穏やかな海。建造物の殆どが白色に塗り固められた街並み。露店が雑多に並び人通りが絶えぬ港沿いの大通り。そして貴方が先程まで乗っていた船。
軽く背嚢を抱え直し、都の方角へと足を向けたその時。
都の方向から、何やら小さな影がまっすぐこちらへ向かって飛んでくる。
(なんだ……?)
反射的に避けようと動いたのだが──貴方の動きに合わせて、影自体も軌道を修正してくる。
がっ、と。
避けきれず、衝突。肩のあたりにちょっとした衝撃が走り──

「ね、ちょっと、助けてよ!」
切羽詰まった声。慌てて視線をそちらへ向けると、肩にしがみつくように張り付いている、体長15センチほどの大きさの、少年とも少女とも取れる人の姿。
その背中からは、細く伸びる薄い膜のような羽が二枚。透明の絹のようにも見えるそれは南海から吹き寄せる暖かな風に吹かれてゆらゆらと揺れている。
「──妖精!?」
「その通り。んで、俺らはそいつにエライ目にあわされた訳だ」
思わず叫んだ貴方の声に、意外な場所からの返答。
前を見れば、恐らくこの妖精を追ってきたらしい、息を切らせた男が二人。手に武器を構え、顔には怒りの形相。


「なるほどな、お前さんがそいつの飼い主かい。んなら、アンタに責任とってもらうか!」
言い捨て、突然襲いかかってきた!
追いかける者


「いやぁ、もぅ、ホント助けてくれるんだもん、ありがと!」
街の大通りを歩く貴方。その頭に張り付いた小さな妖精が、上機嫌で呟く。
にこにこと笑う彼女──らしい──に、貴方は軽く吐息。先程、場の勢いに飲まれて助けたまでは良かったのだが、この妖精、一向にこちらから離れる気配が無いのだ。
その小さな妖精は、こちらが尋ねている訳でもないのに、先程から自分の身の上を延々話し続けている。元々彼女は行く宛もなく五王朝中を旅をしているらしく、このテュパンに訪れたのも気まぐれ以外の何物でもないのだとか。先程男に追われていた事にしても、よくよく彼女の話を聞いてみれば、どうやら先程の男達にしたちょっとした悪戯がバレて、追いかけられていたのだとか。
「だってあいつら、態度でかいんだもん。周りの人達とか嫌がってたし」
妖精は憤慨した様子でぶつくさと呟く。
(少々、悪いことをしてしまっただろうか?)
先程倒した男達の悲惨な様子を思い浮かべ、苦笑。
「でさ、貴方、どこ行く予定なの? 私、何となく南の方行きたいなぁ~、って思ってるんだけど」
と、頭上からさも当然といった風に声が飛んでくる。
貴方はひきつった表情を浮かべつつ、頭の上に乗っかっている妖精に、いつまでついてくる気なのか問いただす。
すると、妖精は小さく唸ってから、ひょいと頭上から前方へと飛び跳ねた。
「いやさ、貴方、こっちにきて間も無いんでしょ? だから私が色々手伝ってあげようかと思って」
言って、羽を揺らし空中でぴたりと停止。
「……っていうか、私って人間の街中に一人で居ると結構目立っちゃてさ。なんか変な人が寄りついてくるし。だったら街に居なきゃ良いんだけど、『お役目』があってそういう訳にもね。だから誰か適当な人にひっついていけば大丈夫かなって──」
逆さのまま両腕を組み、自分の言葉に頷きながらぶつぶつと呟いたあと、一転、有無を言わさぬ調子で叫ぶ。
「ま、色々役に立つと思うからさ! いーでしょ?」
そのままくるりと上下を反転。まっすぐにこちらを見据え、妖精は優雅に一礼。
「私はエルセイドの『月夜に咲く女王』の系譜に連なる観察者、リトゥエ・アルストロメリア。見ての通り、流翼種・フェイアリィ。で、貴方は?」
聞き返され、反射的に名を答えてしまう。
リトゥエは、なんか呼びづらい名前だねぇ、と返してから音も無く宙を移動。とん、と貴方の肩に着地して勢い良く叫ぶ。
「よっし。じゃ、いきましょ!」
花々からの観察者 ウスタール大街道
──テュパン領 ウスタール大街道──
五王朝南西に位置するテュパンという国は、南海に面した弓なりに近い領地を持つ。海との境は大半が砂浜。海岸線に近いウスタール大街道から見える翠色に近い海原は、ひどく穏やかで――

「【NAME】、どしたの?」
大街道を離れ、浜へと歩き出した貴方に気づき、街道の少し先をふわふわと気持ち良さそうに飛んでいたリトゥエが訝しげに戻ってくる。
彼女の問いかけに言葉を返そうとして、口に出すほどの理由が無い事に気づき、苦笑。
単に日差しが暖かかったから何となく水に触れたくなった。そんなところだろうか。
「ねぇ。ちょっとどこ行くのよ?」
ひょいと貴方の肩に降り立ちぐにぐにと頬を引っ張ってくるリトゥエを軽く指で弾いて窘め、改めて海に向かって歩き出した。
遠目からは緑色に見えていた海は、近づくとその色合いを青に近いものへと変えていく。軽く手で海水に触れ、意外と生温い感触に少し落胆する。
海水から手を抜き、周囲を見渡す。映るのは柔らかく押し寄せる波と黄金色に近い海岸。人に襲い掛かってくるような危険な存在の姿は無い。ならば、このあたりで少し休憩を取るのも良いだろう。そう思い、貴方は軽く身体を伸ばした。テュパンから南へ暫く歩き詰めだったため、少々身体に疲れが溜まっていた。
(そういえば……)
テュパンの南。
そこでふと、いつか聞いた言葉を思い出した。
視線を動かす。貴方の立つ場所から少し離れた海の上。海面から1メートルほどの高さをふわふわと浮び、どこか遠くを眺めているリトゥエの姿がある。
『でさ、どこ行く予定なの? 私、何となく南の方行きたいなぁ』
浮んだ言葉は、あの妖精と初めて会った頃のなにげない一言。
「んー?」
見つめるこちらに気づいて、リトゥエが「?」と小首を傾げて見返してくる。彼女の視線から伝わってくる言葉は「なんか用?」だ。
そんな彼女に問うてみる。何故あの時、南へ行きたいと言ったのか。
「へ? あ、ああ、あれね」
意表を突かれたような表情を見せたあと、反射的になのか、リトゥエはこくこくと頷く。
「えーっと、ほら、あっちの方……【NAME】、見える?」
リトゥエは左手を腰に当てて、空いた右手で海岸線の南方向をひょいと指差した。その先を追うと、ゆるりと曲線を描きどんどんと海の方へと迫り出していく陸地、その先端に一つの島があった。
島は他の場所とは異なり緑色が少なく、周囲には何やら細々としたものが張りついているように見える。
「あれが、海の都グラジオラス。干潮の時だけ陸地と繋がる海上都市。私、あそこに行ってみたかったんだ」
指し示していた手を下ろし、こちらへ振り向き楽しそうに笑うリトゥエ。
「あの都ではね、毎週水曜に『海神祭』っていうちょっとしたお祭りがあるんだけど、その中で年に一度だけ特別な日があってね。そろそろ、その『大海神祭』の日なんだよ」
笑みがどんどん濃くなっていく。
「普段の『海神祭』も結構なものらしいんだけど、『大海神祭』の日はもう物凄い大騒ぎになるんだって。五王朝だけでなくて、フィーエルとかラカルジャとか、中には大陸中央のフォータニカみたいなところからわざわざ見にくる人達も居るって聞いたよ」
正直、そんな祭があるという話は初耳だった。貴方は少し感心したようにリトゥエを見る。
「私、あんまし人って好きじゃないけど、でもお祭りとかってやっぱり良いよねぇ。こう、なんていうか、雰囲気がさ、気持ち良いっていうか」
言って、リトゥエはうんうんと独り腕を組んで納得顔。
──と、そこで貴方は首を傾げる。「一度行ってみたい」ということは、この妖精自身は海神祭とやらを一度も見たことがないと、そういう事だろうか?
そう尋ねると、リトゥエは素直にこくりと頷く。
「うん。私、クォルルマルの方からカルエンスとグローエスを廻ってこっちに来たから、南の方はあんまりね。だからさ、、今度の水曜日に私達も見にいこーよ。私がまだ『聖域』を出る前に、南海の方からクォルルマルの森に来てたネレイドの子達に『大海神祭』の噂だけは色々聞いててさ、その頃から行きたい行きたいって思ってたんだ。今ならほら、ちゃんと【NAME】も居るからいきなり誰かに捕まえられるってこともないだろうし」
前は良く襲われたんだよねぇ、としみじみと呟くリトゥエ。確かに、彼女のような小妖精は愛玩用として捕らえられ、他国に高額で売り飛ばされることも多いという。あまり表立って街中をうろつくわけには行かないのだろう。
(初めて会った時も何やら追われていたし──)
内心苦笑しつつ、貴方は軽く頭に手をやって、遥か彼方、南海を吹き抜ける風に霞む島の影を透かすように見据えた。
確かに、年に一度というその機会に折り良くこの土地を訪れたのだ。その『大海神祭』とやらに行ってみるのも悪くないだろう。
花々からの観察者 大海神祭
──海都グラジオラス 大海神祭──
──大海神祭当日、午前。
都の外れ、グラジオラス山の中腹あたりにある寂れた宿で──都の中心部にある宿等は、既にどこも満室だった──部屋を取った後。『マリーベルの道』と呼ばれる勾配のきつい道を下り、グラジオラスの都の中心部を目指す。普段は人通りも疎らなこの急勾配の道も、今日は人いきれが激しい。

「あははっ! これだと、私みたいなちっちゃいのなんか全然目立たないよね。一人で来ても、大丈夫だったかな」
そんな中、はしゃいだ様子でリトゥエがひらひらと空中を踊ってみせるが、周囲の人々は気にした様子もない。彼女よりも遥かに珍しいものが今日はこの都に集まっているのだ。
「すっごいねぇ。人も一杯、亜人も一杯。妖精達も一杯だもん。ほら、あれ、見えるでしょ?」
リトゥエが指差す方向、まだ早朝の斜光が降り注ぐ青く澄んだ空を見上げると、何やら空の一点がちらちらと瞬いているように見える。
「風の子達だよ。普段はもっと高いところに住んでるんだけど、この街の雰囲気が気になって降りてきたみたい」
その瞬きは数度上空を周回した後、都の中心の方へと消えていった。
同時に、どん、と。
都の外輪を巡る街路の方で、腹に直接響いてくるような重低音が轟く。祭の始まりを知らせる太鼓の音だ。小道を歩いていた人々、ある者は音に驚いて立ち止まり、ある者は慌てて都へと駆け出す。
「始礼の儀が終わったみたい。次は……えーっと」
懐から小さな紙切れを取り出すと、それに視線を走らせる。軽く覗き込んでみるが、字が細かすぎるせいでよく見えない。
「午前のメインイベントの……海神招来の儀だね。だからみんな急いでるのか」
呟きながら周囲を見渡し、自分の言葉に納得するように頷くリトゥエ。
(海神招来って……)
何やら、えらく凄まじそうな儀式のような気がするが。
「ああ、海神様って言ってもあれだよ。都の術師が海の概念を擬似的に具象化して、その出来具合で今年の運勢を占うとか、そういう類の物。でも、やっぱ派手な分人気らしくてね。ネレイドの子達と合同でやるから凄いらしいんだわ、出来るモノが。話してくれたネレイドの子は、数十メートルクラスの竜が出来ちゃって崩滅させるのにエライ苦労したとか何とか言ってたけど」
「…………」
滅茶苦茶だ。
「とにかくほら、さっさと都の方に行こうよ。こんな坂道でぼーっとしてても仕方ないしさ」
──正午。
街はどこもかしこも人の群れ。都の大通りが奉納の舞を踊る舞踏師達の為に半封鎖状態となっており、結果、他の街路に人が集まる結果となって、より喧騒が増す。都の中には亜人達の姿も多く、中にはここグローエス五王朝では存在しないとも言われる特異な姿の亜人達も見えた。
当然ながらというべきか、街路沿いにある酒場や食堂、それに類した場所は『混雑』していると一言では片付けられないほどに人が溢れかえっていた。そんな中、『マリスクの水瓶亭』と呼ばれる食堂兼酒場の前に設置された幾つかの椅子とテーブル。その一つにようやく腰を降ろした貴方は、手に持った木製の杯で軽く喉を潤す。
「……はぁ。エライ目にあったねぇ」
手に持った──というよりは抱えた──カップにちびちびと口をつけながら、リトゥエが溜息混じりに息を吐く。中に入っているのは果実酒だ。
実際、酷い目に合った。
あの後、リトゥエの話していた『海神招来の儀』とやらを見物にグラジオラスの中央港、儀式のために専用に設けられた海上祭壇の近くへと移動した。祭壇の中央に集まった数人の術師──恐らくは五王朝内でもトップクラスの──が儀式を始めてたった数分。祭壇の前方、三十メートル程の沖に巨大な水塊が浮かび上がる。そして、通常ならそこから竜だの、魚だの、鳥だの、稀に亜人や人間を模した形に変化していくらしいのだが──
(まさか、爆発するとは……)
今年はそのどれにも当てはまらなかった。空中に浮んだ水塊はどんどんとその大きさを増し、直径五十メートル程の大きさになったあと、大爆発を起こしたのだ。
元々が単なる水であったため、港へ見物に集まっていた者達に怪我人が出たなどという事は無かったのだが──飛び散った海水を諸に被り、その大半がずぶ濡れになるという有様。実際、貴方とリトゥエも降り注ぐ水飛沫をまともに受けて、全身海水塗れだ。既にそれから数時間程経ち、濡れた服もほぼ乾いてきたのだが……手櫛も通らなくなってしまった髪には閉口してしまう。
「あんなんで今年の運勢占えるのかなぁ。なんか国の人たちも大騒ぎしてたしさ。『今年は爆発しました』とか、流石におおっぴらに言えないだろうし」
今年の運勢は『爆発』です。……確かに嫌だ。
「でも、あながち間違ってはないかもね。今の情勢を考えるとさ」
軽く息を吐くと、んしょ、と杯を持ち上げ、果実酒を口に含む。
──それもまた事実だ。『虹色の夜』以後発生しはじめた『現出』により、当初よりは落ち着いたものの、現在でも五王朝内は混乱状態にある。都の、そして王朝の運勢を占うという儀式で、まっとうな結果が出ないというのも仕方の無い事なのかもしれない。
「そいえばさ」
と、唐突にリトゥエが口を開いた。
「軍船が無かったね、港の方」
物思いに耽っていた貴方は、疑問の視線で彼女を見やる。グラジオラスの中央港は基本的に交易船や客船などが停泊する場所であり、その上、今は『大海神祭』。先程の『海神招来の儀』を執り行うという理由もあり、船の進入すら禁じられている筈だ。
「んー、いや、そじゃなくてね。【NAME】も聞いたこと無いかな。『大海神祭』の時にはテュパンの海軍、『蒼穹艦隊』の船が何隻か、毎年一般公開されてるって話」
そういえば、先程通りがかった旅人らしき数人が、そんな話をしていたようなしていなかったような。
「いくら、一般公開が無しになってても、一隻くらいあっても良さそうなのになぁ」
唸りながら首を傾げるリトゥエ。
……この妖精、人間の使う軍船などに興味があるのだろうか?
「うん? いや、別に船自体はどーでもいいんだけど、テュパンの軍船にはね、ネレイドの子達が守霊としてついてる船が幾つかあるの。だから、その子達に最近の海の様子を色々と聞こうと思ってたんだけど──ま、他の子でも別に良いか。今日なら都の近くに来てる子達も居るだろうし」
言って、空になった小さな杯を【NAME】に手渡すと、ひらりと空中に浮かび上がる。
「それじゃ、私、ちょっと沖の方で誰か捕まえて話してくる。えと、夜には宿の方に戻ってるから心配しないでね。それじゃ!」
そのまま軽い動きで身を翻すと、一気に空へと飛び上がる。周囲に立ち並ぶ建造物を飛び越えるとその姿は青色の空に埋もれ、消えていった。
(心配しないで、か)
何とはなしにリトゥエの残していった言葉を反芻する。
あの妖精とは、すっかり旅の道連れといった間柄になってしまったが……これで良いのだろうか?
──夕刻。
祭は最高潮へ。一通りの祝祭儀式が終了すれば、後は無礼講だ。祭自体は午後を少し過ぎたあたりに行われた終礼の儀で既に終了している。
昼頃にリトゥエと別れた後、大通りでの舞踏儀やリヴァッツィオの広場でのバザール、都の外れにある神殿での終礼の儀を見物した頃には既に空も赤く染まり始め、日没の時刻が近いことを知らせてくれる。
と、周囲の人々が皆、南海の方角を見据えて、何かを待っている事に気づく。貴方も街路に立ち止まり、何事かとそちらの方へ視線を送ると──
大空に、大きな光の花が咲いた。
花火、だ。
海上の船から打ち上げられる魔術散光の輝きが、朱、藍、黒が混じり合う空に華やかな彩りを添える。小さな光玉が大空へと駆け上がり、弾け、空に美しい紋様を描き出す度に、詰め掛けた観客から歓声があがる。どうやら都の人々はこれを待っていたらしい。
と、その時。
南海の彼方で一瞬、ちらちらと光が瞬くのが見えた。空を彩る花火の光とは明らかに質の異なる瞬き。
「?」
訝しげに眉を顰め、水平線の彼方へと目を凝らすが──近隣の船が打ち出す魔術散光の輝きに紛れ、よく判らない。
……火線、のように見えたのだが、気のせいだろか。
──深夜。
既に祭は終わり、街にはその残り火が燻るのみ。【NAME】は人ごみを避けるように都を離れ、島の海岸線をのんびりと散策する。いい加減リトゥエも宿に戻っている頃だろうか。思い、そろそろ帰ろうと宿の方角へと足を向ける。
と、その時。
海岸のある一点が、文字通り『ぐにゃり』と歪み──すぐに元の状態へと戻る。
「……?」
歪みが見えた場所は、海と岸との狭間にある、砂に半分埋もれさせた小さな岩の連なり。丁度進行方向にある。
貴方は首を捻り、数秒黙考する。
少し、確かめてみる必要があるかもしれない。
──第七位相守護者 月夜の歪──
歪みが見えた岩陰へと貴方は近づく。一歩、二歩、三歩と進み、その岩陰まであと数メートル程まで近づいて──
「────」
唐突に世界が揺らいだ。
視界が廻り、平衡感覚が失われ、意識が一瞬にして遠退いた。
じゃり、と砂が擦れる音を聞いて、自分が浜に膝をついた事に気づく。
心に喝を入れ、震える足を叱咤して立ち上がり、貴方はその場から離れようと動く。理由は判らない、判らないのだが、
(ここに居ては危険だ)
身体の中の最も根本的な感覚、本能とも呼べるものが、無音の警鐘を鳴らし続けている。
そして、ようやく視線が定まり始めたその時、
──ずるり、と。
岩陰から何かを引きずるような音が響く。貴方は視線でその音の主を追った。
空には煌々と輝く月。降り注ぐ月光は、岩陰から這い出た『それ』をはっきりと照らしだす。
「…………」
何なのだろうか、これは。
貴方の目の前にある物体は、赤とも青ともつかぬ半透明の肉塊。二メートル近いその塊の表面にはぼんやりと発光する印のようなものが浮かび上がっている。
そして肉塊のあちこちからは、人のものらしき足や腕が伸びていて──いや、違う。腕や足はそのままゆっくりと肉塊の中へと沈み込み、
ぶしゅり。
潰れる音と共に、肉塊の中に浮んでいたバラバラの人体が一瞬にして赤の塊に変化し、肉塊の中に溶けていく。
濃厚な血の匂いが、周囲の空気を汚染した。
「!!」
次の瞬間には、塊は元の赤と青が交じり合ったような色へと戻っていく。既にその中には人の姿は無く、身体は先程より一回り大きくなっていた……のだが。
(溶けている?)
見れば、塊の末端部がぶくぶくと泡立ち、徐々にではあるが縮んでいく。そこからは鼻がもげるような異臭が漏れ出しており、漂う血の匂いと相まって激しい嘔吐感に襲われる。
貴方は吐き気を抑えつつ、何とか肉塊から数歩距離を取った。肉塊から離れれば離れる程、周囲の揺らぎが収まっていく。
(……こいつが元凶か)
武器を引き抜き構える。
それが合図だったかのように、肉塊の表面に光る印が強烈な、それでいてどこか暗い色を秘めた輝きを放った!
第七位相守護者

肉塊に渾身の一撃を与えると、その表面の印が爆発的な輝きを放つ。
同時に、強烈な光に思わず顔を背けた貴方の左肩に強烈な衝撃。反動で身体が後方へと吹き飛ばされる。
「がっ!!」
数度地面に跳ね、倒れ伏す。頭を振り、衝撃で遠退いた意識を懸命に取り戻す。
(何か──喰らった、か)
傷を確かめようと自分の肩口へと視線を向けた貴方は──そこに奇妙な焼印を見た。
それは、先程の肉塊の表面に輝いていたものと同じ形の印だった。
(…………)
視線を移し、化け物の方を見れば──肉塊は己を維持していた力が消滅したかのように、どろどろと呆気なく溶けはじめていた。溶けた肉片はそのまま砂漠に巻いた水のように地へと吸い込まれ、その痕跡すら消していく。
貴方が痛みをこらえようやく立ち上がった頃には、化け物がそこに存在した証となるようなものは一切消滅していた。
残ったのは、この耐えようも無い疲労感と──左肩に残された奇妙な刻印のみ。指で軽く刻印をなぞると、言葉では表現できない不気味な感覚が全身を襲った。
「呪い……か?」
……何やら、厄介な事になってしまったようだ。
花々からの観察者 刻印
──刻印──
ふと、気がつくと。
私を包む世界は無音の静寂に満たされていた。
その世界を動かしていた、私。そして私と同じ二人の存在。感じるのはそれだけ。
世界は無数の要素が満ちているけど、それを扱う『皆』が居ない。
私達は寂しかった。
『皆』はどうしたのだろう。彼等が居なければ、私達はここに在る意味が無い。
私と二人は、懸命に『皆』を探した。でも、見つからない。
ある時。もう一人の私は、自分達は『皆』に捨てられたのだと、そう言った。
この私は何を言っているのだろう?
『皆』が居なければ私達は私達でありえないのに。
たとえ、捨てられたとしても、私達は『皆』を探すしかないのに。
そうだ。きっとこの私は壊れてしまったのだ。
ならば処分しなければならない。
私は壊れた私を処分した。
それは違う私の役目だけれど、違う私ももう居ない。
違う私は何もかもに絶望し、独り眠りについてしまった。
でも私は世界の子である竜と一緒に『皆』を探す。
違う私は、すぐに諦めてしまったけど、私は諦めない。
もう一人の私は、もう『皆』は居ないのだと言ったけど、私は信じない。
竜と一緒に、私は探して、探して。
……そして私は、世界の片隅に小さな断片を見つけた。
そうだ、あれが『皆』が居た場所。私は、彼等と共に在るために生まれたのだ。
彼等と共に在らなければ、私が在る意味は無い。
ならば、一緒にならなければ。
私は世界の要素を集め、その断片に注ぎ込む。
私の世界とその断片。繋ぐための印は十二。
今はもう、私と竜、二人だけになってしまったけれど、
それでも私はもう一度、『皆』と一緒に──

「【NAME】! ちょっと、【NAME】ったら!」
ある宿の二階。南の方角に備え付けられた鎧戸から差し込む直射日光を浴びて、貴方はうっすらと目を開く。確か、鎧戸は閉めておいた筈なのだがとそちらへ視線を送ると、逆光の中、仁王立ちしている小さな妖精の姿が見えた。どうやらこの妖精がわざわざ鎧戸を開けたらしい。
ぼんやりと寝る前のことを思い出す。確か、大海神祭が終わった後、この街にやってきたら急に疲れが出て、宿を取ったあと即寝入った。
「やっと起きた。……もう真昼だよ?」
寝台から身を起こすと、頭を左右に振り、意識を覚醒させる。
『それでも私はもう一度、皆と一緒に──』
あれは夢。そう、夢だ。夢の中で聴いた声。
(もう一度、皆と一緒に──)
一緒に、何だというのだ?
「【NAME】? どしたの?」
唐突に動きを止めた貴方を訝ったのか、リトゥエが疑問符を顔に浮かべて貴方の目の前にふわりと浮ぶ。
リトゥエの問いに答えようとして──思い直し、口を閉じる。彼女に夢の話をしたところでどうなるものでもない。取り敢えず「なんでもない」と答え、貴方は寝台から勢い良く立ち上がった。
「ねぇ、【NAME】。それ、どうしたの?」
と、貴方の左肩を指し示すリトゥエ。そこには親指の爪より一回り大きい程度の焼印が刻まれていた。あの『大海神祭』の夜に出会った化物から受けた印。初めは暢気そうな表情で刻印を見ていたリトゥエだが、次第にその表情が強張っていく。
(……なんだ?)
そんな妖精を貴方は訝しげに見やる。どう言えば良いのか。真剣な表情のままじっと肩口を見つめられるというのは、正直気色が悪い。難しい表情で固まっていた小妖精を軽く指で弾いてやると、「きゃん!」という悲鳴と共に小さな身体が景気良く吹っ飛び、寝台で数度バウンドした。
貴方は溜息をつきつつ手早く荷物を纏めると、寝台に転がったままぎゃんぎゃんと文句を言うリトゥエを無視してさっさと部屋を後にする。
「あ、ちょ、ちょっと待っ──」
慌ててこちらに飛んでくるリトゥエを遮るようにドアが閉まり、
「んぎゅぅ!」
何やら蛙を踏み潰したような奇声が部屋の中から聞こえたが、放っておいてさっさと階下に降りる。あの妖精にいちいち構ってると、無駄に時間を食ってしまって仕方が無いのだ。
「はぁぁ、参ったなぁ」
【NAME】が去った後。部屋の中には小さな妖精が一人、寝台に寝転がり、天井を見上げる。背の羽がある為に首だけを上へ向けるような格好で、御世辞にも楽な姿勢とはいえないが、何となく、天井を見上げたい。そんな気分だったのだ。
(ネレイドの子達に聞いてはいたけど……)
リトゥエは内心呟き、あの日の事を回想する。
大海神祭の日、正午を少し過ぎた時分。【NAME】と別れて南海へと赴いたリトゥエは、南海に住むネレイドの妖精達と会い、南海の情勢や『現出』の原因などについての情報を交換した。そして、人間──それも国家指導者クラスの者達──と接触していた彼女等ネレイドの妖精種からもたらされた情報の中には、極めて重要なものが幾つかあった。その内の一つが、この五王朝内に『現出』を発生させている大元となる存在、『位相守護者』についての情報だった。
人間達からの情報によると、彼等が『位相守護者』と呼ぶその存在は、この五王朝のどこかに潜み、『現出』を行うために世界概念の局地的な変異と流動化等を行って、他概念世界に存在していたと思われる地形や存在などを、強引に現世界へと呼び出しているのだという。彼等が何故そのような事を行うのかは一切謎のままだが、その『位相守護者』達の所在についても人間達は既に掴んでいるらしく、『参慧樹』や『カクラの機甲館』等の幾つかの場所で『位相守護者』の存在概念を──微かにではあるが──確認しているらしい。
そして、その時出会ったネレイドの子達によれば、あの大海神祭の日に、南海上で確認されていた『位相守護者』に対し、南海を守護するネレイドのニルフィエ達とその長である『碧に揺らぐ女王』、そしてテュパンの蒼穹艦隊全艦艇が合同で攻撃を仕掛けたのだという。グラジオラスの港にテュパンの軍船が無かったのはそういう理由があったのだ。
守護者一体に対してこの布陣。
しかし、これは大袈裟でも何でもない。『位相守護者』達は元々の存在概念が現世界に住む自分達とずれている。つまり位相の存在であるらしく、人間が扱う武器は勿論、妖精達が操る力も殆ど受け付けないのだ。また、それぞれが『位相刻印』と呼ばれる印を持っており、その刻印を介して現世界に存在する者達に対し、強力なイーサ干渉を行う力を持つらしい。
「──で、そこから何がどうなったら、【NAME】の肩にその刻印ひっついちゃってるのよ……」
ごろんと首を捻ってシーツに顔をうずめ、深く溜息をつく。
ネレイド達にその話を聞いた時にはまだ『位相守護者』とニルフィエ、蒼穹艦隊の連合軍は交戦中の状態であり、結局その結末までは聞かずに宿へ戻ったのだ。いくらその化け物が強力だとしても、テュパンの軍船に南海のニルフィエ達が出張れば負ける筈はない、そう思い込んでいたのだ。
だが、【NAME】に刻まれていた印、あれは確かに守護者のもの。『観察者』の力を用いて戦いを覗き見たとき、『位相守護者』の身体には確かにあの印があった。
(どうしたものかなぁ)
まだ、【NAME】の刻印について、クォルルマルにある『聖域』には何の報告も入れていない。これは『観察者』として失格の烙印を押されても、文句は言えない行為ではあるのだが──
(言えないよねぇ……)
自分と繋がっている『源流』は、リトゥエ自身が報告したい、と決心するまで黙っていてくれるとは思う。しかし、この事が『聖域』のニルフィエ達に伝わったらどういう結果になるのか、考えたくも無い。
もし知られてしまえば、どう転んでも【NAME】は──
「はぁ……」
そのままリトゥエはもぞもぞと身体の向きを変えると、また大きく溜息をついた。
花々からの観察者 接触
──接触──
心に掛かった薄い靄を振り払い、私はゆっくりと目を覚ます。
小さく瞬く欠片に包まれながら、闇を掻くように、両手を虚空へと伸ばした。
十の指を滑らかに泳がせる度に、『皆』が在る世界の断片へと、その欠片が吸い込まれていく。
私はその心地よさに身を震わせる。
もうすぐ。
もうすぐ私は、私達は、『皆』とまた一緒に過ごすことが出来る。
でも。
何だろう、この感触は。
私達と『皆』とを繋ぐ十二の楔。そのうちの二つの感触が酷く鈍い。
何故だろう、何故だろう。
私は繋ぐ道を二つ手繰り寄せ、意識の欠片を指先にゆっくりと集中させて──

「──【NAME】!」
自分の名を呼ぶ声が、酷く遠い処から聞こえたような気がした。
貴方は何もかもがあやふやな世界の中で、薄く目を開く。眼前に映るのは──全てが横転した世界。重く鈍い頭を懸命に動かし、周囲の状況を把握しようと努める。垂直に近い形で伸びる石畳の道は視界の左半分を埋めている。そこから真横、右に向かって伸びる家屋と、疎らな人の足。そしてちらちらと動く小さな影。
(……つまるところ)
自分は街路の一角で、うつ伏せになって地面に倒れている、と。そう考えるのが妥当だろうか。
「ちょっと、【NAME】ってば! しっかりしてよ!」
再度響くリトゥエの声。先程とは違い、その声は酷く近い。まだ薄く曇った視界には彼女の小さな身体が周りの景色に滲んで見える。
身体に力を込める。どこか痺れるような感覚が身体に残っているが、動けない程ではない。ゆっくりと腕で身体を支え、身を起こした。
「ねぇ、大丈夫? まさかいきなり道端でぶっ倒れるなんて私もびっくりしちゃってもうホントに」
ばたばたと忙しなく周囲を飛び回るリトゥエ。本当に慌てているのか、喋っている内容が微妙におかしい。
しかし、いきなり倒れたとは。
その上、倒れた時の記憶が一切無い。確か、街に到着したあと手早く宿を取り、そこから食事を取る為に街の通りへと出たまでは覚えているのだが、そこから先の事がどうやっても思い出せない。
「別に、大したことしてないよ。宿を出て、こっちに歩いてたら、突然、ホントに突然、ばたって倒れちゃって……」
傍らに居たリトゥエに一体どうなったのか尋ねてはみたが、要領を得た答えは返ってこない。
単なる立ちくらみ、なのだろうか。それにしては、何か、違和感のようなものが身体に残っている。
貴方は両眼を閉じてその違和感の正体を確かめようとして──気づく。
身体に刻まれた二つの刻印。
未だ消えぬその印が、じりじりと、絶え間無く疼いている事に。
ふつり、と。
断片とを繋ぐ二つの道から、手ごたえが失せた。
何故だろう。
私は感覚の途切れた両の手を眺め、ほんの少しだけ、首を傾げる。
何故だろう。判らない。どうしてだろう。
でも、楔が無くなったわけじゃない。
それは今も、私の世界と、『皆』の居る場所への断片とを繋ぐ道。
だけど、どこかおかしい。何かが変わってしまった気がする。
私はもう一度、両手をゆっくりと前へ伸ばそうとした。
だけど、もう身体に力が入らない。ただ、痺れるような感触だけがある。
もう、眠ろう。
今は、眠ろう。
そして、目を覚ましたなら。
私は世界の要素を集め、断片へと注ぎ込む。
その時に、もう一度。もう一度、試してみよう。
そうすればきっと、元の楔に戻っている筈だから。
「では、ノイン・ヴァイヒュント副長殿。改めて、グラジオラス沖での作戦についての報告を」
深夜。商都テュパンにある館、現テュパン国主であるラナーン家の邸宅。館の主にしてテュパン国の主であるラナーン家の当主に呼び出され、彼女、ノイン・ヴァイヒュントはその一室で敬礼の姿勢を取る。
彼女は懐から羊皮紙の束を抜き出すと、豪奢な執務机にその書類を音もなく差し出す。通常ならば秘書を介して、部屋の主に手渡すのが筋というものだが、夜の闇も深くなるこの時刻ともなれば、秘書などが詰めている筈もなく。かわりに警備の近衛騎士が控えるのが筋というものだが、今は人払いが行われており、室内にはノインと、彼女の主である男の姿しかない。
硝子窓から南海を眺めていた青年はちらりと執務机に置かれた書類に目をやり、そのまま視線を部屋の扉近くに立つノインへと向ける。
「文章としての報告など不要だ。君の口から直接報告を受けようと考えたからこそ、今日ここに呼んだのだ」
男はゆっくりとした口調でそういうと、窓から身を放し、机の脇に置かれた椅子に静かに腰を下ろす。
窓から差し込む月の光に照らし出されたのは黒く長い髪と、夜の帳のなかででも判断できる褐色の肌。その容姿は、明らかに異国人の血が混じっている事を示している。
男の名はアルフレド・ラナーンという。彼女の主であり、テュパン国の王。
ノインは軽く息を吸うと、彼の問いに答えるためにゆっくりと口を開く。

「では、結果と損害のみを報告します。一言で申し上げますと、作戦は失敗しました。ニルフィエ達の助力もあり、二十五仕掛けた儀式印章魔術のうち、八つの印章刻印で何とか守護者を捕らえ、その身体の大半を崩滅させる事に成功しました。が、我が軍は十二隻の艦艇を失い、守護者は肝心の刻印部分を分離して逃亡。我々も懸命に追跡を続けましたが捕らえるには至らず、最終的には『第七位相守護者』を見失うという結果に終わりました」
そこまで表情という表情を一切見せずノインは言い切り、軽く視線で主の様子を伺う。まだ三十を過ぎたばかりの、青年と言っても良い年齢である男の黒い瞳は、相変わらず、何を考えているのかを他人に悟らせない。
ノインは小さく溜息をつくと、話を続ける。
「それ以後、『第七位相守護者』の所在についての情報は一切入っておりません。『陰翳の霧』の方から『忍』を幾人か借り受け沿岸周辺に放ちましたが、発見したという報告は受けておりません」
「なるほどね」
と、ノインの言葉を遮るように男は呟き、椅子から立ち上がる。
「ノイン・ヴァイヒュント。本日限りを持って、お前をテュパン騎士団副長の職から外す。異論は無いな」
「はい」
勿論、異論は無い。ノインは屹然とした返事を返した。
これはある程度予想していた事だ。これ程の損害を受けて作戦に失敗したとなれば任を解かれない方がおかしい。既に役職を後任の者に受け渡す手筈はある程度整えてある。あとは自宅謹慎か、禁固刑か。テュパンでの自分──の親の──位置付けを考えれば、斬首刑になる事はない筈だが。
「宜しい。では、お前に一騎士、いや、五王朝の一護法衛士として伝える。ノイン・ヴァイヒュント護法衛士。お前に『第七位相守護者捜索』の任を与える」
「……は?」
──予想外の言葉に、思考が一瞬固まる。
前に『護法』として任務を受けたのは一体いつの頃だったか。咄嗟に思い出せない。
「聞こえなかったか? お前が逃した位相守護者、それを探し出し、狩れと言っているのだ。お前はどうせ、自宅謹慎か禁固刑あたりを予想していたのだろうが、そうはいかない。『護法』を遊ばせておく程、我々には余裕はない」
「い、いえ! そんな……」
底意地の悪そうな男の言葉にノインは反射的に否定の言葉を返すが、自分でも情けなくなる程にうわずった声が出た。少しでも予想外の事が起きると、被っていた皮がすぐに剥がれる。彼女の欠点の一つだった。ノイン自身、直そう直そうと努力してはいるのだが、そう簡単に直る類のものでもない。
「とにかく、だ。刻印の崩滅を最優先に動け。だが、事は内密に運ぶように。人員は最小限に留めろ。今回の件はお前と、バリードに一任する。奴は数日中にはテュパンに帰還する筈だ」
「バ、バリード、と組むのですか?」
今度は別の意味で声が乱れる。
バリードと呼ばれる護法騎士に関する噂は、彼女もいくつか耳にしていた。そのどれもが、仕事の相棒とするのには難色を示したくなるようなものばかりだった。
「不服か?」
「いえ、そのような事は……。承知致しました」
頭の片隅で「不服に決まっている」と騒ぎ立てる小悪魔の声を黙殺し、ノインは一分の隙も無い敬礼を返し、部屋から退室した。
扉を閉め、身体を反転。音が響かぬように気をつけながら、ノインは扉に背中から持たれかかると、天井を見上げ深く息を吐く。
(……化け物退治の後処理が終わって、少しは都でゆっくりできると思ってたのだけど)
まさか、こういう展開になるとは思いもしなかった。
身を扉から放すと、館正面のエントランスへ向かって歩き出す。硝子の窓が並ぶ廊下には半円の月が生み出す光と、天井に刻まれた照明印章の生み出す光が二重に降り注いでおり、灯りを持たずとも廊下を歩くのに支障は無い。
「でも、なんだか厄介な事になってしまったかな……」
大体、その『位相守護者』に関しても、自分は殆ど説明を受けていないのだ。その上第七位相守護者と呼称されるそれは、今現在どのような形態をとっているのかすら判らないと来ている。その状況からどうやって守護者とやらを探せば良いのやら。
(部下を使う──わけにもいかなくなってしまったし)
これからの背負い込むであろう苦労に思いを馳せ、ノインは少々暗澹とした気分のまま館を後にした。
花々からの観察者 象形
──象形──
ホーヴローヴェ通りの北東、テュパンの師士団宿舎が密集しているクリアミネ区。そのとある宿舎の中庭で、五王朝護法衛士ノイン・ヴァイヒュントはある人物と待ち合わせていた。
待ち合わせていたのだが──。

「……来やしないし」
溜息混じりに呻く。ちなみに、既に約束の時刻から一時間は経過している。
(まさか、すっぽかされたとかじゃ無いでしょうね……)
自分が待ち合わせている人物についての様々な噂を思い出し、ノインはいらいらと爪を噛み──慌てて止める。子供の頃からの癖はそう簡単に直るものではない。
護法騎士バリード・ルッツ。
悪名高きミスフォーチュン──『不幸を招く者』と呼ばれ、その周囲の被害を考えない攻撃的かつワンマンな戦闘スタイルは、彼と行動を共にする者に過度の精神的負担を与える。
作戦成功率は非常に高く、護法師士達の中でも十指に入る。また、彼の作戦に参加した者の中では戦死者が殆ど居ないのも特徴だ。が、逆に負傷者の数は何故か非常に多く、そして当然ながら死者よりも生者の方が饒舌だ。これが彼の評判を悪くする原因となっている。
所謂、個人としての能力は高いが、団体行動には向かない類の存在。それがバリード・ルッツという男らしい。
と、その時。
視界の片隅に、こちらに向かって歩いてくる人影が一つ。
(すっぽかされた訳じゃ、ないようね)
少し安堵し、改めてその影を確認する。
身長は自分よりも大分高い──男としては平均的だ──中肉中背の男性。灰色に近い髪と、それと同色の眼。グローエスの師団構成員が着る制服と、手には大きな長槍。事前に聞いていた特徴と一致している。恐らく彼が自分が待ち合わせていた相手だろう。
数歩程の距離を残して男は立ち止まる。ノインは軽く身を正し、口を開く。
「まさか、顔合わせで一時間も待たされるとは思いませんでした」
皮肉交じりに言ってはみるが、己の外見を考えれば、どれほど皮肉気な台詞を口にしたところでそれ程意味は無い事は自分でも判っている。気持ちを一瞬で切り替え、男の眼を真っ直ぐに見据える。
「初めまして。私、ドゥヒス・ヴァイヒュント旧王領伯が三女、グローエス五王朝護法衛士ノイン・ヴァイヒュントと申します。テュパンでの所属は王国騎士団正騎士となっております。以後、お見知りおきを」
ノインはその男の前に立つと、息を継ぐ事無く一気に挨拶し、軽く目礼する。
しかし、反応は、無い。
ノインは訝しげに眉を顰める。まさか人違い、という訳でもないだろうに。
「貴方が、五王朝護法騎士バリード・ルッツ殿。で、間違いありませんね?」
男の灰色の両眼を真っ直ぐに見据えて彼女が念を押すと、男の顔が唐突に崩れた。
どう言えば良いのか、緩みきった──酷く、嫌な顔だ。

「かははッ!! こんな美人と仕事ができるとは、オレって幸せー!」
「な──」
突然、空を見上げ大声で絶叫する男に、ノインは絶句して固まる。
そして男は、呆然となったノインの目の前にまで一瞬で歩み寄ると、両手でノインの右掌を包み込む。
「ひゃ!?」
ぞわり、と鳥肌が立った。嫌悪感に頭がくらくらとする。
「ノイン・ヴァイヒュント殿、と申されましたかな? 私、バリード・ルッツと申す、しがない槍術者でございまして──」
「や、やぁ──や、止めなさいっ!!」
反射的に手が出た。空いた左の指が無意識のうちに空中に印を描き、その光跡が消える前に、芝居がかった口調で話し掛けてくる男の顔に向けて拳を振り切る。
淡い光を纏って高速で走った彼女の拳は、右手の甲に顔を寄せていた男の頬を殴打。
「げぼがいぃ!?」
簡易印章魔術を併用した拳を諸に受け、男の身体が真横に数メートル吹っ飛んだ。
「遊んでる、ような、暇は、無いんですよ、もう……!」
「す、すびばせん……」
闇夜の空に浮ぶ月は、煌々と満ちて美しい真円を描き、大地に横たわる者達を淡く、そして優しく包み込んでいた。そんな空の中を、小さな小さな人影が流れる風に支えられるように浮んでいる。
《これを──お使いなさい》
雲と大地の狭間に浮ぶその小さな影の更に上から。薄く目を閉じ、空を見上げている彼女の脳裏に直接響くような言葉が聞こえる。
身体が、酷く冷めていた。
リトゥエという名を持つその影は、思わず両手で己が肩を抱きしめようとして──自分の手の中に小さな輝きが灯っている事に気づいた。閉じた掌の隙間から淡く漏れ出す輝き。リトゥエはゆっくりと手を開き、己が手の内に輝く複雑な象形をじっと見据える。

「現世界という存在概念を強く付与する事による概念変質の抑制……それと、存在封縛、操作の象形──」
目線は外さぬまま、声を絞り出す。酷く掠れた音が、真夜中の空を小さく震わせる。
《私達『聖域』の結論は、その者を──『刻印者』を利用せよ》
厳格な言葉に、リトゥエは反射的に顔をあげた。
《私達や人間達の扱う力では、我らが守護する大地を侵食するあの者共を打ち滅ぼす事は出来ません。ですが、貴女と共に在る『刻印者』。あの者の相は私達よりもむしろ『守護者』に近い。貴女は『刻印者』を誘導し、我等の望む方向へと事を運ぶのです》
「……私は、【NAME】の身体に崩滅した筈の守護者の刻印が、継承され、刻み込まれていると報告しました。つまり、【NAME】では完全に位相守護者を消し去る事はできない、ただ、刻印の引き継ぎが行われているに過ぎないと、そう伝えた筈です」
《その為の象形です。貴女は、刻印者にその象形を刻み込みなさい。そして刻印者が位相守護者を倒すように仕向ける。それが今、貴女に課せられた役目。それ以外の事を考える必要は──ありません》
リトゥエは刺すような視線で薄い闇の中に浮ぶ月を睨む。
月は、悔しくなる程の真円。
《貴女の言いたい事は、私にも良く判っています。でも、それと同様に、私の心の内も、貴女には判るでしょう?》
響く声音に、寒々とした苦笑の色が混じる。しかし空を見上げるリトゥエは視線を緩める事は無い。
「判る、けど、判らない。駄目、納得できない」
《……人と共に生きてきたから? 貴女は、本当に変わってしまったのですね。もう私の面影すらない程に》
何かを振り払うように呟くリトゥエに、浮ぶ月から降り注いだ言葉は、諦めと、少しの困惑が混じっていた。
「違う。この私も、結局は貴女だもの。貴女の、忘れてしまった、私」
一瞬の沈黙。
《……どちらにせよ、貴女はその印を『刻印者』に刻むしかありません。既に、刻印者が呼び込む位相の気配に、貴女の身体も耐えられなくなってきているのでしょう? その象形を刻めば、刻印者が無意識に行っている概念干渉を抑えることもできるでしょう》
輝く月に満ちていた気配がゆっくりと遠退いていく。
リトゥエは、目を薄く閉じて月の光を遮り、細く、鳴くような小さな息を吐いた。
前に、【NAME】が街路で突然倒れたあの時。リトゥエは、その原因が【NAME】の身体に刻まれた刻印のせいだという事を直感的に感じ取っていた。
危険な兆候といえた。
大体、ニルフィエの女王達すらも警戒する程の力を秘めた刻印が、ちっぽけな人の身体に複数刻まれているのだ。普通に生きていける筈が無い。
しかし、小さな妖精の身でしかない自分には打つ手が無い。そこで彼女は、【NAME】の事をクォルルマルの『聖域』へ報告しようと決意した。自分の『源流』を通じ、彼女が他の女王達を説得してくれれば、と。
だが、その結果がこれだ。自分は『源流』という存在を信用しすぎていたらしい。
リトゥエは、【NAME】が滞在する街を目指し闇夜の空を駆けながら、掌に輝く小さな象形を見つめる。
【NAME】の身体に刻まれた印は、既に三つ。まだ、迷いはある。だが、もう迷っている余裕すら無いのかもしれない。
(たとえ、『聖域』に利用されることになっても──)
このまま、放っておく訳にはいかない。
強く、強く。淡く輝く拳を握り締めて、彼女は街を目指し、飛んだ。
街の外れにある小さな広場。朝食時には遅く、昼食時には早い、そんな時刻。
まだ中天にまで昇りきっていない太陽の日差しは、空に薄雲が掛かっているという事も相まってか、酷く弱々しい。周りを囲む風景達もどこか色褪せて見える。
貴方は広場の中央にある大きな樹の下に座り、無言のまま虚空を見つめていた、
じり、と。
身体に刻まれた印が、疼いている。
「【NAME】」
と、名を呼ばれ、そちらに振り向く。そこには一日ぶりに見る小さな人影があった。
「もう、探したんだよ! 宿の方に居ないしさ。私、朝頃に帰ってくるから待っててって言ったじゃない」
どうも怒っているらしい。空中に浮んだまま胸を張って器用に仁王立ちの仕草をしてみせる。何とも、芸の細かい妖精だ。
「──【NAME】」
だが、唐突にリトゥエの表情が変わる。その視線の先には、疼く感触を抑えるために何気なく右手を当てていた、【NAME】の左肩がある。
「身体の方、大丈夫なの?」
唐突な問いかけではあったが、取り敢えず大丈夫だと答える。
「【NAME】……その、辛くなったら、ね。……ちゃんと言ってね? 私に」
ぽつぽつと、俯いて呟く姿にいつもの快活な雰囲気は微塵も無い。
どうも、ここ暫くリトゥエの様子がおかしい。何かあったのだろうか。
だが、軽く首を捻りつつ記憶を探ってみるが、これといって思い浮かぶ事は無かった。
「とにかく、宿の方に戻ろう? そろそろお昼だし」
まだ少し震えが残っているリトゥエの声に同意の頷きを返し、貴方はゆっくりと立ち上がって──
(……?)
と、どこからか視線を感じた。
目を細め、周囲を見廻す。疼く刻印の感覚に従い、広場の外れ、街路沿いの茂みを見据える。同時に、小さくその茂みが揺れ、感じていた視線が消え失せた。
何者、だ?

「しかし、さっきは反射的に謝っちまったが、まさか伯爵令嬢に貴族流儀の挨拶して、術式併用のグーパンチ食らうとは思わなかったぞ。意外と冗談が通じないな、キミは」

「あの……御免なさい。私、他人に身体を触られるのは慣れてなくて……」
氷嚢を右頬に当てて呻く男──バリード・ルッツに、ノインは首を竦め、小さくなる。
(でも、美人と一緒に仕事、と叫ぶのが貴族の流儀なのかしら?)
とは思うが、いくら慌てていたとはいえ、一撃で大型ディオーズすら倒す程の威力がある拳撃を放つ自分もどうかしている。殴った相手が並の人間ならば顔ごと破裂させていた可能性もある。焦ると抑制が効かなくなるのも自分の悪い癖の一つだった。
「慣れてないってなぁ……キミ、晩餐会や舞踏会の時とかどうしてたんだ?」
呆れたような声音のバリードに、ノインは軽く指を組んで困ったように答える。
「いつも、そういったお誘いはお断りしていましたから」
「そんな無理が通るものなのか? テュパンの社交界ってのは。普通は爪弾きにされるぞ」
「それは──私の親の力かもしれませんけど」
「ああ、なるほどね。ヴァイヒュント伯といえば、テュパン貴族の中でもかなりの大物だからな」
バリードは軽く髪を掻くと、木製の粗末なテーブルに置かれていたジョッキに発酵酒を継ぎ足す。
ノインがバリードを鉄拳で殴り倒してからおよそ一時間後。二人はマリハンス繁華街の一角にある小さな店『カシム食堂』にやってきていた。バリードが宿舎の食堂を嫌がり、ノインが自分の屋敷に彼を招くのを拒否した結果がこれだ。
別に共に食事を取る必要もないのだが、親睦を深めるという点では食事は非常に有効な手段でもある。お互いそれは了解しているので、どうにか折り合いをつける為に、ノインが出した最低限のルールを前提としてバリードが選択した場所がここだった。
彼女の提示した条件は三つ。一つ目は内密の話が出来る、二つ目は師士団宿舎に近い、三つ目は美味しい葡萄酒がある場所。
このカシム食堂という店は少なくとも、宿舎に近い、美味しい葡萄酒という二つの条件を満たし、更にはヴァイヒュントのお抱え料理師を上回る程の料理を出してくれた。だが「内密の話が出来る」という点については──
「これだけ騒がしけりゃ、誰も他人の話してる事なんざ聞こえないさ」
(……確かに、話は聞かれないだろうけど……)
この無秩序な騒がしさは、秩序ある静寂を美徳とする騎士団で長い生活を送ってきたノインには少しばかり辛いものがあった。
「それで、あの……ルッツ、殿?」
「バドで良い。敬称は不要。つけないと気分が悪いっていうのなら、さん付けにしてくれ。で、何?」
初対面の男性を家名以外で呼ぶというのはノインにとっては酷く抵抗があることなのだが、何だかこの男にそう言われると、絶対にそう呼ばないといけないような気分になる。恐らくは先程容赦なく殴りつけた罪悪感が残っているせいだろうか。
「それでは、バド──さん。何だか、私達、酷く場から浮いているような気がするのですけど……」
言って、周囲を見渡すと、幾つかのテーブルから無遠慮な視線がこちらへ向けられているのが容易に感じ取れた。
バリードはノインの言葉を受けて、ふむと頷く。
「ま、確かに浮いてるな。だが、正確にはオレ達が、でなくて、キミだけが、だが」
意味が判らず、ノインは首を傾げる。
「……何故でしょう?」
「外見だろうな、やはり。まぁ、こんな下町の食堂にキミみたいなのを誘うオレもオレなんだが。っていうか断れよキミも」
「?」
なにやら歯切れの悪そうに呟く男に、ノインは首を傾げる。自分の着ている服はテーブルの向かいに座る彼と同じく、五王朝の師士団構成員が着る制服だ。護法師士用の特注品であるため細かいディティールは違うが、大まかな造形としては──性別による仕様の差こそあれ──同じな筈。五王朝では珍しい黒髪も、他国の者が多いこのテュパンではそれ程一目を惹くものではない。それで自分だけが目立つとはどういう意味なのか?
「まぁ、それはもういいだろう。それで、今回の仕事についての説明をしてもらえると助かる。なんせルアムザでは、テュパンでの待ち合わせ場所と組む相手だけしか知らされなかったものでね」
「ですが……」
やはり、理由は判らないにしても、注目を浴びているという事実だけは厳然としてそこにある訳で、その事にノインは言葉を詰らせる。
そんなこちらの様子を見て、バリードは「仕方ない」といった調子で壁に立てかけてあった槍を手に取ると、柄尻で軽く木製の床を叩いた。
坤、と。
軽く小さな音が響く。しかしその音は周囲の喧騒に紛れる事無く部屋中に木霊し、そして一瞬にして消えた。同時に、今までノインの方を眺めていた幾つかの視線がふっと逸れる。
「隠匿結界、ですか」
ノインは唖然として周囲を見渡す。事前に受け取った資料では、槍術師としか書いていなかったのだが。どうやらこの男、結界師としての訓練も積んでいるらしい。
「意外か? この程度はできないと、現役の『護法』としてはやっていけないさ。で、話の続き。もう周囲を気にすることも無いだろう?」
「……で、そんな化け物を二人で相手するのか? 無茶もいい所だ」
ノインがこれまでの顛末を一通り説明し終えると、目の前に座る男は呆れたような声音で呟き、軽く発酵酒を呷る。
それはノイン自身も感じていた事だ。グラジオラス沖で出会ったあの存在は、外見自体は従来の『現出』等により現れるディオーズ達と比べ、そう大きさは変わらないものの、振るう力は段違い。更に概念的な破砕を発生させるほどの威力をもつ攻撃でなければ自分達では傷一つつけることが出来ない。
自分と、そしてこの男が『位相守護者』を見つけることに成功したとして、そこからどうすればよいのか、それすらも判らない。対抗する手立ても、無いことは無いのだが……
「まぁ、それはいいとして。で、ヴァイヒュント嬢はその、あー、『第七位相守護者』とやらを探す方法は判っているのか? 一度は戦ったんだったか?」
「……いえ。私は団長と、ルアムザから来た術師からの指示を受けて守護者を追っていただけですので。戦ったといっても、後方で指揮をとっていただけですし」
「そりゃまた……どう言えば良いのか。今から守護者とやらを探す為の手段から考えんといけないのか? 効率悪い事この上ないぞ。もしかしてオレ等、暇でも出されたんじゃないかと疑いたくなるな」
「暇、ですか」
「良く言えば左遷か? オレも最近無茶ばかりやってたからなぁ。そろそろ干される頃だとは思っていたが」
「私も、干されてるんですか?」
何気なく問うてみたが、バリードは苦笑するだけで答えない。それはつまり、そういうことなのだろうか。今更、どうという気も起きないが。
ノインは軽くグラスを手に取り、葡萄酒を口に含む。比較的あっさりとした感触を舌で味わうと、少し気分が落ち着く。
「で、今後の方針とか、何か考えているか? 正直、人を使わないことにはどうにもならない気がするが。人海戦術だな」
「いえ、それはアルフレド様から禁じられています」
バリードの言葉に、ノインはきっぱりと言い返す。
「となると、オレ達二人で探すのか? それこそ不可能だという事くらい判るだろう、ヴァイヒュント嬢」
「勿論、判ってはいます。ですから、その前に少し……その『位相守護者』について、よく調べてみる必要があると思うんです。相手の特性を知れば、その痕跡を追う事も容易になると思うんです。それに、第七という事も気になりますし」
「第七、か。となると、少なくともその化け物は七体以上存在し、上の連中はその位置か──もしくは存在しているという証拠を掴んでいるということか」
バリードは軽く手に持ったフォークを廻すと、かつんと食器に押し当てる。
「だが、キミも判っているとは思うが、それを調べるのは手間だぞ」
テュパンの、いや、五王朝の上層に位置する人間達は、この『位相守護者』と呼ばれる存在について、かなりの情報を掴んでいる。それだけは判る。だが、下層──とはいえ、自分や、バリードもそれなりの地位にはある筈だが──の者達にはその情報は一切流れてこない。完全に隠蔽されている。
数日前までの彼女であれば──副長とは名ばかりで、実際は騎士団長の秘書兼護衛といった程度の扱いだったとしても──積極的に動いていれば守護者に関する情報を手に入れることが出来たかもしれない。しかし、人を指導し、統率する才能が自分には欠けている事をよく理解していた彼女は、秘書兼護衛という扱いを別段不服に思わず、与えられた仕事のみを律儀にこなしてきた。今は、そのことが仇となっていた。こんな事になるのなら、もう少し団長やあの怪しげな術師達を捕まえて話を聞いておけば良かった。一正騎士でしかなくなってしまった自分では彼らから事情を聞きだすのは不可能だろう。
「でも、そうするしかないと思います。闇雲に探しても無駄なのは判りきっていますし」
「それもそうだな。となると、あとはどう調べるかだが、そういう事に関してはオレにアテが無いわけでも──」
と、その時。唐突に、ノインの左耳に小さな鈴の音が聞こえた。彼女の纏う気配の質が変わった事に気づき、バリードは途中で言葉を止める。
「どうした?」
「……いえ、どうやら、調べる手間が省けたようです。出ましょう」
ノインは立ち上がると、足早に食堂の外へと向かう。結界の外に出たため、周囲の視線が自分に集まってくるのがはっきりと感じられたがもう気にする必要も無い。
槍を抱え後をついてきたバリードに、殆ど唇を動かさずに小さく言葉を続ける。
「私が副長を勤めていた頃に放った『忍』が、『第七位相守護者』の位置を掴んだようです。今から彼と落ち合います」
軽く、頭痛を抑えるように目を閉じ、息を吐く。そして告げた。
「どうやら、『位相守護者』は現在、人の姿をとっているようです」
花々からの観察者 護法
──護法──
護法衛士ノイン・ヴァイヒュントと護法騎士バリード・ルッツ。そしてごく普通の旅人といった風の男。三人はグローエス五王朝全域を隈なく結ぶウスタールの大街道を準駆け──グローエスの師士達の間で教えられる馬の歩法の一つ──で進んでいた。
ノインの左右を包む薄い緑が、多少上下に揺れつつ後方へと流れていく。石畳の街道に馬の蹄が打ち鳴らす軽い音が小気味良く重なっていく。

(あまり、馬達にこんなところを走らせてあげたくないのだけど……)
硬い路面をそれなりの速度で走らせるのは、馬の足にも負担が大きい。しかし、今は急ぎの旅だ。構ってやれる余裕は無い。

「で、あー、っと、名前なんだったか?」
「名はございません。便宜上どう呼んで頂いても結構です」
「そうだな……それなら忍、で良いか?」
「ご随意に」
「そうか。で、その『刻印者』って奴のところには何日ほどで辿りつきそうなんだ?」
「数日中には。『刻印者』の動向にもよりますが」
先頭を進む男からの素っ気無い言葉に、バリードは困ったように息を吐くと、目の前で手綱を握る騎士装束の小柄な娘に話し掛ける。
「……ヴァイヒュント嬢。『忍』って連中は皆こうなのか?」
バリードの小声に答えるように、声音を落としてノインは返事を返す。
「そうですね。彼らは個よりも全体を重視するように叩き込まれているそうですから。他人に本名を明かす必要は無いと考えているのか、それとも本当に名が無いのか──と、それよりも」
「それよりも?」
ノインは軽く眼を細め、半眼に近い形で背後へと視線を送る。
殆ど真後ろ、数十センチも離れていない位置に、灰色の髪の護法騎士の顔があった。その表情には多少の緊張がある。
「バドさん、馬に乗れなかったんですね」
言って、ノインは溜息。男はその仕草を見て、居心地悪そうに視線を逸らす。
「仕方ないだろう。ガキの頃に派手に落馬して足折って以来、こいつらは苦手なんだよ。意外か?」
「とっても。馬くらい操れないと、現役の護法としてはやっていけませんよ」
いつか聞いた台詞をそのままバリードに返してやると、男の眉が露骨に顰められる。
「……厭味か?」
「ええ、少しだけ。前にも言いませんでしたか? 私は他人に身体を触れられるのが酷く苦手だと」
「出来るだけ触れないように努力はしているつもりだが」
「それでも、イヤなものはイヤです」
「……左様で」
「──『第七位相守護者』が、他の守護者から、刻印を奪い取っている?」
テュパンの諜報師団、『陰翳の霧』に所属する『忍』であるその男からもたらされた情報は、ノイン達を絶句させるに十分値するものだった。
商都テュパンの師士団宿舎の一室。ノインとバリードの前には一人の男が立っている。一見何の変哲も無い商人風の服を纏った、無個性な顔つきの男。彼がテュパン諜報師団に属し、ノインが騎士団副長時代に師団から借り受けて放った『忍』の一人だった。
「位置の方は我々が完全に掴みました。ですからこうして、『神曲』のノイン・ヴァイヒュント様と『餓狼』のバリード・ルッツ様にご報告を」
「また、懐かしい名前を……」
バリードは呻き、ノインも久々に聞いた響きに目を丸くする。
神曲と餓狼。両方とも、自分達が護法の位を授かった時に同時につけられた通り名だ。
「しかし、何故、第七は他の守護者を襲っている? グラジオラス沖でやられた時に狂ったのか?」
バリードの疑問の言葉に、ノインも軽く頷き、男の表情を見やる。今回の話は、判らない点が多すぎる。
「いえ。現在、第七位相守護者は──我々はオルドリュードと呼称しておりましたが──存在しておりません」
男の言葉の意味が判らず、ノインは片眉を顰める。ちらりと視線をバリードに送ると、彼もこちらとまったく同じような表情を浮かべていた。確か、この『忍』は自分に「第七位相刻印を持つ存在を発見した」と、そう言った筈だ。だというのに、彼は第七位相守護者はもう存在しないという。
「どういう意味だ? 沖で刻印──本体か? それが分離した後、そのまま力尽きて死んだ、と?」
バドの問いかけに、男は無表情のまま答える。
「いえ、それは誤りです。オルドリュードはグラジオラスの沿岸部で何者かと接触し、その後、崩滅しました」
「それって……誰かが、倒した? あの、化け物を!?」
ノインの声に『忍』は小さく頷く。
「海都グラジオラスの岸でオルドリュードだったモノの欠片を手に入れています。既に概念的には完全に崩滅していましたが、我々が守護者の探索に使用した──グラジオラス沖で捕らえた第七位相守護者の身体の断片に、多少なりとも反応を見せましたので」
「少し、待ってください」
そこでノインは『忍』の言葉を強引に停めた。もう正直、何がなにやら良く判らなくなってきていたが、はっきりさせておかなければならない事が一つある。
「それなら、貴方達『忍』が見つけたというのは、いったい誰?」
「オルドリュードから第七位相刻印を受け継いだ人間の事です。どうやら、最近この五王朝にやってきた冒険者のようですが」
「……無茶苦茶だな。『位相刻印』が転移して、そのオルドリュードを倒した人間が新しく『第七位相守護者』になったっていうのか?」
男とバリードの言葉にノインは唖然とする。自分達が、あれ程の被害を出して捕らえられなかった存在を、ただの冒険者が倒したというのか?
(いや、違う?)
ニルフィエや蒼穹艦隊の攻撃を受けて身体が維持できなくなったオルドリュードが、刻印を他者に移植して延命を図った、そう考えるのが妥当か。
「正確には『第七位相守護者』ではなく、『第七位相守護者の位相刻印を持つ者』です。我々はその者を『刻印者』と呼称しています」
「その人、彼──か彼女は、何故他の守護者を?」
ノインの問いに、『忍』は両眼を閉じて答える。
「そこまでは私には。ただ、既に三体もの『位相守護者』が『刻印者』であるその冒険者に狩られており、彼らが所持していた刻印は、全て──」
「刻印者が継承している、と?」
「そのようです」
苦い表情で呻くバリードの言葉を、『忍』が短く肯定する。
三人、暫し沈黙し──ノインがゆっくりと口を開く。
「最後の質問。構いませんか?」
顔をあげ、『忍』を真っ直ぐに見据えて問う。
「何故、私に報告したのです? 本来ならば、まずテュパンの十副長に報告を行うのが筋というものでしょう?」
「我々もそう考えておりましたが、国主様からの勅命ですので」
「アルフレド様の……」
「貴方が本気で、周囲の被害を考える事無く『ソルモニアル』を放てば、たとえ位相の存在であろうと、崩滅させることは可能だと」
「…………」
「ノイン様。今後の行動については、如何いたしますか。刻印者の元へは私がご案内しますが」
黙り込んだノインを気にした風も無く、男は次の指示を待つ。どうやら、まだこちらの仕事を手伝ってくれるらしい。テュパン国主アルフレドからの命を受けているからなのかは判らないが、今のノインにはありがたい。
ノインは何かを振り払うように頭を軽く振ると、顔を上げて男と、そしてバドに向かい告げた。
「──判りました。私も、この五王朝を守る護法の一人。その為に己の力を惜しむ気はさらさらありません」
ノインは毅然とした調子で言い切る。
「一時間程、テュパンの外門で待っていてください。その間に諸手続きと、旅の準備を整えます。バド、貴方は大丈夫ですか?」
「オレは今日ついたばかりで、荷物も解いてないからな。いつでも出られる」
「ならば、彼と一緒に外門の方へ。私もすぐに向かいます」
迷っている余裕は無い。ノインは力強い足取りで部屋を後にした。
「で、アンタ」
「なんでしょうか」
「ヴァイヒュントのお嬢さんの役割はわかったが……オレに振られている役割はなんだ?」
問いに、男は間髪を入れず答える。
「彼女の補助。そして、もしもの時のための保険です。ノイン様が放つ『ソルモニアル』によって起きるであろう被害、その罪を肩代わりしていただきます。ヴァイヒュント旧王領伯に連なる方に悪評を背負わせるわけには参りませんので」
男の言葉に、バリードは軽く息を吐いた。
「薄々、そんな事じゃないかとは思ってはいたがな。しかし、被害が出るような場所でそんな危なそうなモノを使うとも思えないがね、あのお嬢さんが」
「かもしれません」
素っ気無く答える男を眺め、ふと、バリードは首を捻る。
「それ以前に、『神曲のノイン・ヴァイヒュント』のソルモニアルってのは、それ程のものなのか?」
「あの若さで、しかも女性。その上、あのような素直な気性の方が『護法』の地位にある。それは、家柄だけでは到底不可能な事だと推測できますが。貴方もある意味ではそうでしょう」
「……なるほどね。しかし、ヴァイヒュント嬢も何でこんな因果な仕事をやってるんだかな。伯爵令嬢らしく生きていれば良いものを」
言い捨て、バドは立てかけてあった長槍を手に取り、部屋の扉へと歩いていく。
「ま、仕事の内容は了解した。オレの方は汚れ役は慣れているから構わんが、あの人の良さそうなお嬢さんに悪評が立つってのは、確かにあまり宜しくないからな」
静寂に包まれていた夜の気配が遠退いて、空の色がゆっくりと変わり始める。それは緩やかながらも確実で、夜がもたらす微睡からうっすらと世界が目覚めていく。その流れは遥か昔から日毎繰り返されてきた他愛も無い出来事である筈なのに、どうしてこんなにも心を揺さぶられるのか。少し寒さを感じて、身体に掛けた毛布を軽く引き寄せる。
貴方は、ウスタールの大街道沿いに生えた大樹の根元でぼんやりとその様を眺めていた。街はすぐ傍という位置ではあるものの昨日は体調が優れず、結局街へ辿りつく前にここで一夜を過ごす事に決めた。
軽く視線を横へずらすと、こちらの身体の上で小さく丸まり、くぅくぅと寝息を立てている妖精の姿が映る。彼女は何やら酷く幸せそうな表情で眠っており、まるで悩みなど何も無いようなその姿が、何となく恨めしい。
──じり、と。
身体に刻まれた印が疼く。
何とも表現できぬ不快感が全身を包み、その感覚に耐えるために反射的に歯を食いしばる。汗が額ににじみ、そして頬を伝って顎から零れ落ちる頃には、その不快感、そして刻印の疼きは消え去ってくれた。
大きく息を吐き、大樹の幹に身体を寄りかからせて、ふと思う。
(限界、なのだろうか)
あの、奇妙な気配を持つ化け物達。まるで彼らが宿敵であるかのようにその気配を追い、狩っている自分。彼らの気配を無意識に感じる事ができるようにはなったが、そこへ赴き、狩っているのは自分の意思。しかし、何故わざわざ彼らの元へ赴き、倒して廻っているのか。自分でも良く判らなくなってきている。
そして彼らを倒す度に自分の身体に刻まれる印。既にその数は四つにまで増えていた。刻印が増える度に、明らかに身体の具合は悪くなっている。稀に身体の刻印から何ともいえぬ不気味な力が沸き起こり、そのお陰で何度か命を救われた事もあるが──それを差し引いても釣りが来る程に、普段の調子は最悪だった。発作的に訪れる、先程のような不快感、そして刻印の疼き。
まるで自分で自分を追い詰めているような感覚。
薄く苦笑し、軽く手を掲げて早朝の強い日差しに右の掌を透かしてみせる。
一瞬。ほんの一瞬。
文字通り、太陽の日差しが透けてみえた。
絶句する。たった一瞬き程の間ではあるが──自分の腕が霞み、まったく形を持っていなかったことに。
強く息を吐き、目を閉じる。
自分は一体どうなるのか。もうそれすらも判らない。街の施療院や解呪の術式などは役に立たない、それだけは確かだ。思考は堂々巡りで、出口は見えない。
ただ、このような身体になっても、あの位相の気配を感じれば、また自分はその気配を追い、そしてあの異形の存在を狩るのではないだろうか。そんな予感が、する。
貴方は目を閉じ、思い悩む。
その様を、貴方に気づかれぬよう、薄く眼を開けて見ていた小妖精の表情には、先程の幸せそうな気配など微塵も残っていなかった。
花々からの観察者 覚醒
──覚醒──
酷く──寒い。
身体の芯まで凍えていくような、際限の無い冷たさ。
眠りから覚めた私は小さく震え、両腕で抱えていた脚を離して、周りを見渡す。
意識がゆっくりと覚醒し、自分を包む様々な概念の輝きが様々な形を成していく。
黒の中に瞬く白の光点。
私の世界に在るのはそれだけ。
一体、眠りについてからどれ程の刻が過ぎたのだろうか。
目覚めている時と。
眠っている時と。
あの『皆』が在る世界の断片を見つけてから、その周期が乱れている。
頻繁に起こる意識の断絶。
理由は、判らない。
私は壊れ始めているのだろうか?
でも、私を治す役目を持っていた、もう一人の私は、ここには居ない。
では、どうすれば良いのだろう?
判らない。
…………。
──なら、判ることから始めよう。
私の世界を、『皆』の居る世界の断片へと注ぎ込む。
それが今の私がやらなければならない事。
私はゆっくりと両手を虚空へ伸ばし、楔への道を感じ取ろうと動いて。
……身体が、ざわりと、震えた。
『皆』の世界と私の世界。
それを繋ぐ道は確かにある。
だけど、私が楔へと送った声に、幾つかの楔が答えを返さない。
その楔達は、酷く、感触が鈍い。
在るという感触すら危うい、彼等の数は、五つ。
眠りに入る前より、更に増えていた。
呆然と考える。
私の眠っている間。
楔を打ち、放った概念達の身に何かが起きているのだ。
私は両の手を真っ直ぐに伸ばし、己が指先に意識を込めた。
そして、千々に乱れた心をまとめあげ、強く呼びかける。
ただ一心に──私の声に答えて、と。

「あれが、『刻印者』、ですか?」
街の近傍、ウスタールの大街道を見下ろす位置にある小高い丘の頂上付近。細い木々に紛れて街道の方向を見据える、三つの人影がある。
グローエス五王朝護法護士ノイン、同騎士バリード、そして、テュパンの諜報師団に属する『忍』。
彼らが見据えるのは、大街道を街に向かって歩く人影。
「ええ」
『忍』の返す短い返事を聞きながら、ノインは馬から降りて手綱を引き、目を凝らす。彼女の視力は正直なところ、あまり良いとは言えない。小さな頃に負った怪我が主な原因で、日常生活には支障はきたさない程度のものだ。普段は気にも留めないのだが、こういう時は少し損だ。噂の『刻印者』の姿も、ぼんやりとしか見えない。
何気なく視線を移すと、とうの昔に馬から降りていた──本当に馬が苦手らしい──バリードが、鷹のような目つきで街道の方を見据えている姿が映る。
「見えますか?」

「まぁ、そりゃな。……見えないのか?」
「ええ。朧気には見えますけど」
頷き、灰色髪の男に、『刻印者』とやらの特徴を尋ねてみる。が、ノインの問いにバリードは困ったように眉根を寄せた。
「普通、としかいえないな。ごく普通の、どこにでも居る冒険者に見える。あれが本当に、その位相守護者って化け物を狩ってる奴なのか?」
バリードは最後の言葉を、背後で細い樹に凭れかかり──丘に入る前に彼の乗っていた馬は別の『忍』らしき者に引き渡たされていた──じっと眼を閉じている男に向ける。
数秒の無言の後、男は目を開くと、細く細く口を開いた。
「今、見張りの者から報告が入りました。現在、『刻印者』が所持している『位相刻印』は、五つ、だそうです」
「それって……」
一瞬、ノインは彼が何を言ってるのか判らなかった。
「つまり、オレ達がテュパンからここに来るまでに、『刻印者』は更にもう一体『位相守護者』を仕留めたって事か」
軽く引きつった表情を浮かべるバリードに、男は無言で頷く。
「何者だ、あれは」
呟き、バリードは溜息。ノインも、殆ど同じような心境だった。実際、グラジオラス沖で行われた、海の妖精達とテュパンの蒼穹艦隊との合同作戦。そこで『第七位相守護者』の力を目の当たりにしていたノインにしてみれば、四体以上もの『位相守護者』をたった一人で崩滅させる人間など、一体どんな者なのか想像すら出来なかった。
(──あ)
そこでふと、思いつく。
「バドさん」
「なんだ?」
「その『刻印者』という方は──どういえば良いのでしょうか、えと、人間? なのでしょうか?」
「少なくとも、外見は、な」
バリードの言葉に軽く頷くと、ノインは少し考え込み、ぽつりと、独り言のように告げた。
「なら、少し、『刻印者』さんと話し合ってみましょうか」
場の空気が固まる。バリードは唖然と口を開いたまま固まり、常に無表情の『忍』ですら驚いた表情を浮かべる。
「──はぁ!? 正気か!?」
暢気そうな表情で街道の方を見据えるノインに、暫しの間固まっていたバリードが大声で叫ぶが、彼女の方はといえば気にした様子も無い。
「ええ、勿論正気です。相手が異形ならばともかく、『刻印者』は人間なのでしょう? でしたら、五王朝の護法として、こちらも卑劣な振る舞いは出来ません。まず礼節を持ってあたるのが筋でしょう」
ノインの言葉に、バリードは呆れを通り越して、憐れみに近い表情になっていた。
「人間ねぇ。話を聞いた限りじゃ、ありゃもう人間とは言えないんじゃないか? 甘すぎるぞ、キミは」
「私も同意見です」
珍しく、『忍』がノインの決定に口を出す。ノインとバリードは、若干の驚きを視線に乗せて彼を見る。
「あの者が街に辿りつくのを待ってから、街全体に閉鎖結界を敷き、住人を丸ごと『贄』として『ソルモニアル』を放てば──」
赦、と。
呟く『忍』の言葉を、酷く澄んだ鞘走りの音が遮った。
「…………」
男の喉元には銀色の刃がある。喉に触れるか触れないか、爪先程の距離も無い位置に、良く研がれた剣の波が揺らぐこと無く留まる。
「言った筈です。私は、この国の護法だと。私は己が持つ力を惜しむ気はありません。ですが、この国に暮らす民を犠牲にして力を得るつもりも毛頭ありません」
ノインは長剣に込める力を強くする。薄く、『忍』の喉に赤い点が生まれ、膨れ上がった。
「もう一度、私の前で先程の言葉を口にしたなら、その時は貴方の命の灯火が消える時。そう思いなさい」
「承知しました」
微動だにせず答える『忍』をじっと見据えた後、ノインは剣を瞬く間も無く鞘へと収める。その速度に、バリードは舌を巻いた。
「てっきり、キミは術士系の人間だと思っていたが」
思わず呻き混じりの声がでた。ノインは振り向かず、視線だけをこちらに寄越す。
「一応は、支神召喚師のつもりではありますけど。──話しませんでしたか? 私はテュパン騎士団長の『護衛』として、副長の任についていた者です。術式しか使えない者が、そのような役目を授かる筈もないでしょう」
ノインの声はバリードに対しても酷く硬い。どうやら完全に頭に来ているらしく、まだ気が収まっていないらしい。
「それに、この程度の事はできないと、現役の護法としてもやっていけませんから。今度、機会があれば結界術も学ぶ事にします」
「……意外と、根に持つタイプなんだな、キミは」
というよりも、八つ当たりだ。
「かもしれませんね」
バリードは困ったように頭を掻く。そこでようやく、ノインは薄く微笑んだ。
「──では、ノイン様、これを御受け取りください」
と、そこに喉元から細く走る朱の線を拭おうともせず、懐から黒色の小さな八角柱を一つ、取り出す。何かの鉱石を削って作られたと思しきその柱の表面には複雑な形状の大きな印が一つ刻まれており、淡い光を放っている。
それを見て、バリードは胡散臭げな表情で尋ねる。
「封縛……印章石? こんなもの、通用するのか?」
「判りません。『昂壁の翼』から送られてきた特注品ではありますが。話によれば『位相刻印』の封縛にのみ特化しているそうです」
「つまり、この石を使えば、あの冒険者から印を奪い取れるという事?」
「詳細までは私も存じませんが。ただ、現在はそれ一つしか御座いませんし、使えるのは一度切りです。その事をお忘れなきよう」
ノインは男から八角柱を受け取る。見かけよりも少しだけ、重い。バリードは横から手を伸ばし、軽くその表面に触れて呟く。
「失敗したら終りって事か。また役に立たんものを」
「無いよりはマシですよ。──ありがとう」
ノインの礼の言葉にも、忍は眉一つ動かさない。
「上から指示されたモノをコイツが渡しているだけなんだろうが、何故かコイツ自体が良い奴に見えてくるから不思議だな」
皮肉気なバリードの言葉に、男は彼へと視線だけ振り向き、平坦な声で告げる。
「先に断っておきますが、『刻印者』との戦闘には我々『忍』は手をお貸ししませんので、そのお積もりで。我々は、事の顛末を国主様に報告する義務が御座いますので」
「……前言撤回。お前最悪だ」
片手で頭を抱えてみせるバリードに、ノインは薄く苦笑する。彼女には『忍』達が守護者との戦いにまで手を貸してくれない事は、何とはなしに判っていたし、それはバリードも同様だろう。バリードは単に演技しているだけ。この灰色髪の男にはそういうふざけた部分があるのを、数日の旅で彼女は理解していた。
「では、私はここで」
『忍』は軽く一礼すると、自分の影の中に沈みこむように姿を消した。『忍』達が操る秘術のひとつ、影抜けだ。
男の気配が完全に消え去ると、バリードは改めて頭に手をやり、一息。呆れたような調子で小柄な娘の方へと振り向く。
「で、ヴァイヒュント嬢。その、本当に──行くのか?」
「ええ。せめて、名乗りくらいは挙げておきませんと。では、先に行ってますから、馬を樹に繋いでおいてくださいね」
ノインは自分でも理由は判らないが、少し気が急いていた。バリードにそれだけ告げると、街道に──『刻印者』が居る方角へと足早に歩いていく。
残されたのは、馬が苦手な男と、一頭の白馬。
バリードは深く溜息をつくと、引きつった表情で馬の手綱を握る。
「せめて不意打ちくらいはやらせてくれると思ったんだが。あそこまで『お嬢さん』だとはな……」
ウスタールの大街道を次の街目指して歩いていた貴方の前に、突然、何やら豪奢な服装の小柄な女が姿を現した。
「お初にお目にかかりまして。私、グローエス五王朝護法衛士、ノイン・ヴァイヒュントと申す者です」
十から二十歩程の距離を残して彼女は立ち止まり、こちらを真っ直ぐに見据えて軽く一礼する。
その礼の仕方がまた……明らかに、普通の仕草ではない。簡単に表現するならば上流階級者のそれだ。貴方は訝しげに彼女を見やる。
そして数秒。こちらの視線を受けて、彼女は小さく首を傾げ、唇を薄く開いた。
「不躾なお願いで申し訳御座いませんが、貴方のお名前、教えていただけると幸いなのですが」
固まっていた貴方を解き解すように、細く柔らかい声音が響く。確かに、名乗られたなら名乗り返すのが道理ではある。慌てて返事を返そうとして──

「この国の護法が、私達に何の用よ」
上空から、こちらの言葉を遮るように、小さな影が舞い降りる。リトゥエは【NAME】の肩ではなく、【NAME】と、ノインと名乗った女の間を遮るような位置に、音も無く留まる。
「──フェイアリィ! どうして小妖精が『刻印者』と一緒に居るの!?」
「尋ねているのは私よ、質問に答えて。……いや、そうね。聞くまでも無いよね」
すっと空中を滑るように移動し、視線は前方に立つ女の方を見据えたまま呟く。
「【NAME】、こいつ──敵だよ。武器を構えて、早く!」
「ち、違います!」
「嘘をつかないで。『位相刻印』を持つ【NAME】のところへ『護法』が来た。それだけで答えは明白じゃない。【NAME】の事、刻印ごと崩滅させようってんでしょう」
リトゥエの視線が一段ときつくなる。今まで貴方が見た事も無い程に、強く。
「させないから。絶対に」
「どういう事? どうして妖精である貴女が。ニルフィエ達は、いつから『位相守護者』側についたというの」
「勘違いしないで。別に、あの『芯なる者』の玩具達をかばっている訳じゃない。貴女達人間の知らないところで、色々な事が動いている。そういう事よ!」
「…………」
険のある声で叫ぶリトゥエに、騎士風の装束を身に纏った娘は、戸惑ったように押し黙ってしまう。
そこに、新たな影が現れる。
「ヴァイヒュント嬢、暢気に話し込んでる場合かよ。相手にこちらの話を聞く気は無い、それくらいもう判るだろうに」
ノインと同じような形状の服に身を包み、巨大な槍を携えた男だ。彼女の傍へと移動し、こちらを油断無く見据える視線の強さから考えるに、恐らくはノインの連れか。
「で、でも」
「いいから下がれ!」
しかし、何だか自分だけ話に取り残されているような気がするのだが。
槍を片手に、灰色髪の男がノインと『刻印者』との間に割って入る。
「……さて、ヴァイヒュント嬢。オレはまだキミの『ソルモニアル』とやらをよく知らんのだが。どうすればいい」
既に目の前に立つ男の気配は、戦いを前にした戦士のそれに移り変わっていた。ノインは慌てて叫ぶ。
「待ってください! そんな、勝手に!」
「これ以上は時間の無駄だ。いくらキミでも、それくらい判るだろう」
バリードの強い調子の声に、ノインは思わず黙り込んでしまう。ちらりと、『刻印者』へと視線を送ると、肩に先程の妖精を乗せて、戸惑ったような表情を浮べてこちらを見る冒険者らしき者の姿がある。あの者自身は、自分達に対して敵意を持っているようには見えないが──傍らに妖精が居る限り、まともな交渉はまず不可能なように思えた。無意識に、ノインは唇を噛み締める。
ノインは長く息を吐き、バリードに向かい不承不承頷いてみせる。しかし、まだ武器を引き抜く気にはなれない。
(あの妖精さえ居なければ、こうはならなかったのに……)
そんな気持ちだけが、先に出てしまう。
何故、あの妖精は『刻印者』と共に居るのか。そして、何故『刻印者』を護ろうとするのか。
妖精──ニルフィエ達の『位相守護者』に対する感情は、丁度今、ノイン達があの小妖精から受けているものとほぼ同等か、それ以上の敵意だった筈だ。それが何故、あの『刻印者』と──
「ヴァイヒュント嬢。戦いの場に迷いは禁物だ。意識を敵を倒すことのみに集中しろ。その程度のこと、習わなかったか?」
「まだ、敵と決まったわけではありません」
「いや、あのチビっこいのがこっちに敵意を持っている限り、説得なんか無駄だろう、恐らくな」
「どういう、意味です?」
「言葉通りの意味だ。あの小妖精が、いや、ニルフィエ達が『刻印者』を操ってるんじゃないかってな」
「そんな──」
ノインは絶句しつつも、同時にその言葉が事実を言い当てているようにも感じた。ニルフィエ達は『刻印者』を操り、『位相守護者』達を同士打ちさせている。つまりはそういう事なのか?
(ならば、自分達が彼らと戦うことは、間違っている?)
「今は深く考えるな。国主の勅命を思い出せ、テュパン国主はキミに何と言った、ヴァイヒュント嬢」
迷うノインを叱咤するかのように、バリードがこちらを振り向く事無く叫ぶ。
(……そうだ、今は戦うときだ)
バリードの言葉に小さく頷くと、ゆっくりとノインは口を開く。
「私の『ソルモニアル』は閉鎖領域指定後、その内部に局地的破壊をもたらす支神霊を連続召喚するものです。主に、遠距離からの大型建造物破壊や師団単位の部隊に対して使用します。これで『刻印者』を倒すことができるかどうかは判りませんが──無理だったとしても、『忍』から渡された石がありますから、何とかなると思います」
ふむ、と思案するようにバリードは一声唸る。
「で、欠点は?」
「加減が出来ない事と、詠唱に時間が掛かる事、この二点です。特に詠唱にはかなりの時間が」
「手加減は──キミの『ソルモニアル』がどの程度かしらんが、する必要はなかろう。問題は時間か。何秒かかる?」
「秒単位では無理です。三分……いや、二分半。その間、『刻印者』を食い止めてください。私は詠唱中は一切動けなくなりますから」
バリードは目線は『刻印者』に向けたまま、軽く頷いて返事をする。
「合図します。三秒以内に相手から五十メートル離れるか、私から半径一メートル以内に移動してください。できますか?」
「できなくても、やるしかないんだろう? 離れてろ、『眷属』を呼ぶ」
バリードの声に従い、数歩下がる。灰色髪の男は手に持った槍を軽く振り回し、己の影に向かって穂先を鋭く突きいれた。ずるり、と呆気なく槍がバリードの影の中に吸い込まれる。
そして数秒。抜き出した槍に巻きつくように、数匹の黒くしなやかな影が地上へと這いだす。
「狼……」
ノインはバリードの周囲を甘えるように廻る暗色の獣を見据え、呟く。具象化魔術の一つ、なのだろうか。だが、詠唱や魔術印章一つ使わずにこのような術式を操る者など、聞いたことが無い。
「それが、『餓狼』の由来、ですか」
「まぁな。オレの血筋は少々特殊でね、こういう事もできるのさ。だが」
と、その内の一匹の視線がノインの方へ向けられる。黒一色の身体の中に輝く朱色の両眼から感じる意思は、『餓』の一文字。同時に、その狼は瞬く間も無くノインに向かって跳びかかり──
ぎぎ、と。
ノインが長剣を引き抜く前に、バリードが無造作に突き出した長槍に身体を貫かれ、その黒狼は呆気なく四散する。
「こいつら、制御が殆ど利かないのが難点でな。よく仲間を襲って、恨まれた」
困ったようにバリードは告げてそのまま槍を一振りすると、黒狼達を率いて、ようやく武器を引き抜き構えた『刻印者』の方へと歩いていく。
「バドさん」
「?」
反射的に出た呼び止める言葉に、ノインは自分でも驚く。振り向いたバリードに何を言うつもりだったのか? ノインは視線だけで問い掛けてくるバリードに慌てて返す言葉を捜して──
「その、よろしくお願いします」
「……何だそりゃ?」
「ですから、お願いします」
ノインは自分でも良く判らないまま、繰り返す。
バリードは軽く首を傾げたまま──それでも、頷いた。
「ああ。じゃ、始めるか」
「だから、ぽーっとしてる場合じゃないんだってば! ちゃんと武器構えて、【NAME】、お願いだから!」
リトゥエは眉尻を下げ、今までに無い程に切羽詰った声音で貴方に訴える。
(とはいえ……)
理由も判らず襲われるというのは、正直気分が悪い。せめて、あの二人に理由程度は訊いておきたいのだが。
「そんなの決まってるじゃない! アイツ等、刻印を消しに来たんだよ」
叫ぶリトゥエに、貴方は訝しげな視線を送る。何故、彼等が自分の身体に刻まれた印の事を知っているのか、そして、何故リトゥエにそんな事が判るのか?
目の前に浮ぶ小妖精にそう問い詰めると、彼女は心底困ったような、殆ど泣きそうな顔つきで固まってしまう。
「それは、その……ごめん、今は聞かないで。お願いだから、黙って私の言うこと聞いて、【NAME】。ね?」
(駄目だ、これは)
内心呻いて貴方は空を仰ぎ、溜息をつく。
恐らくこれ以上尋ねたところで、彼女から実のある返事が返ってくる事はありえないだろう。視線をリトゥエから外し、先程の二人組を見やる。彼等の方も相談は終わったらしく、小柄な娘が後ろに下がり、いつの間にか現れた黒色の狼を引き連れて長槍を構えた男がこちらに向かってくる。どうやら、向こうは『やる気』らしい。
「【NAME】、今回は、私も手伝う。私達は、今やられる訳にはいかないんだよ」
どうも今ひとつ状況が掴めないのだが、だからといって、赤の他人に襲われて素直にやられてやる義理も無い。
リトゥエの声に合わせる様に貴方は武器を構え直し、散開して四方から迫る狼と、槍を構え突撃してくる男を迎え撃つ!
五王朝の護り手




長槍を持った男と狼達を蹴散らし、彼等から離れた位置で声高に謡う娘に渾身の一撃を見舞う。
「あくっ──!」
回避は勿論、防御の姿勢すら取る事無くまともにその一撃を受け、細い悲鳴と共に娘の小さな身体が吹っ飛んだ。先程まで彼女が呟いていた言葉は、明らかに魔術発動の鍵となるそれだ、強引にでも止めなければこちらが危ない。
(……さて)
これでひとまず落ち着いた訳だが。
男が落とした長槍を拾い上げて、軽く周囲を見渡してから貴方は小さく吐息。取り敢えず、相手の身動きを封じてから事情を聞いてみるのが先決か。
そう思い、地面に倒れ伏している娘に近づこうと一歩踏み込んで──眼前に現れた小妖精に道を塞がれる。
「【NAME】、油断しちゃだめだってば! 私が今から結界であいつの周りを塞ぐから、それまでじっとしてて」
そういうと、ゆっくりと身を起こそうとする娘の方へと両手を突き出し、短く声を出す。同時に、娘の周囲に虹色の靄が立ちこめ、彼女の動きが見る間に鈍っていく。どうやらリトゥエが彼女の動きを封じ込める結界とやらを敷いているらしい。確かに、離れた位置から相手の動きを封じる事ができるというなら、そうするに越した事は無い。
と、その時、どこからか力強い叫びが轟いた。
「ディエ・フェンリル、起動せよ! アグラクナ・マレーネ・クォウレ・レグェメトス!!」
先程打ち倒した男の声だ。貴方は慌てて武器を構え、そちらに振り返ろうとした瞬間。
「──ッ!?」
片手に握っていた、あの男から奪った巨大な槍の手ごたえが消え失せ、その姿が一瞬にして巨大な狼へと変化した。
「ガァアアァアッ!!」
驚きの声を上げる間もなく、猛々しい咆哮と共にその巨大な前脚が振るわれる。力強く振り下ろされた脚は、目を見開き固まっていたリトゥエを呆気なく弾き飛ばす。石畳の道に激しく叩きつけられ、身動き一つしなくなった妖精の姿を見届ける間もなく、巨狼はこちらの動きを留めるかのように襲い掛かってくる。
「ヴァイヒュント嬢! 今だ!!」
男の声に応じるように、リトゥエが生み出した虹色の靄を懸命に振り払った娘が、懐から掌大程の黒色の柱を取り出し、こちらに翳して叫ぶ。
「封じ、縛せよ!!」
瞬間、石の中から無数の光鎖が伸び、素早く身を離した狼と入れ替わるように【NAME】の身体を包み込む。光鎖の網が自分の身体を包むと同時に、全身に熱した鎖を巻きつけられたような強烈な激痛が走った。そして──
──どくん、と。
身体に刻まれた印が、強く、強く脈動した。
悲鳴をあげる間もなく、貴方の意識は一瞬にして暗転した。
その楔達へ呼びかけを始めてから、
一体どれほどの時間が過ぎただろう。
呼びかけて、呼びかけて、呼びかけて。
ようやく聞こえた、微かな声。
それは助けを求める彼等の声。
彼等の印は半ば眠っていて、その声は酷く弱々しい。
何故だかは、判らない。
でも構わない。
私は強く強く願い、そして彼等に訴える。
ただ一言、目覚めて、と。
きぃん、と。
細く甲高い音が響き、ノインの持っていた印章石が呆気なく、割れた。
殆ど砂粒のような細かさにまで一瞬にして砕けて地面に零れ落ちる石の欠片を、ノインは驚愕の視線で見据える。
それはあまりにも唐突な終りだった。
同時に、自分を包む全ての存在に、違和感のようなものを感じて、ノインは顔を上げた。
「あ、が、ギ、イあぎ」
その時響く、空間が歪み軋んで、その隙間から這い出してくるような不気味な音。
(……何、これ?)
それは音ではなく声だった。ノインは、聞く者の身体の芯まで凍りつかせる、呻きにも似た声をあげる物体へと視線を向けて──呆然と立ちすくむ。
自分の視線の先にある、その存在。つい先ほどまで、自分が『刻印者』と呼んでいた者が纏う気配は、明らかに尋常ではなかった。今、自分の目の前に立っている存在は、先程までのどこにでもいるような冒険者ではなく──人の形をした化け物。それ以外の何者でもなかった。
「ギ、ギ、ィ、ィ──!!」
化け物が、一際高い叫びを放った。
音が空間を走る軌跡に沿って、世界が異質なモノへと変貌していく。その流れは波紋状に広がり、立ちすくむノインを呆気なく包み込んだ。
──世界という色彩が、まるで万華鏡のように変化する。
天が歪み、地も歪む。
目に映る何もかもが霞み、自分を包む世界が際限なく歪んでいく。
そして現れたのは、異なる世界。
その世界では、自分は在り得ざる存在だった。
ならば、自分はここにいてはいけない。
そう思った瞬間、自分という存在が、概念が、揺らぐ。
何もかもが、あやふやになって、揺らいで、揺らいで──
意識を失う寸前。ノインは自分の身体が深い闇に取り込まれ、この世界から自分という存在が呆気なく消え失せていくのを、はっきりと感じた。
頬にあたる冷たい感触に、リトゥエはふと目を覚ました。まだ全身に痺れるような感覚が残っているが、動くには支障は無い。
「……どうして」
身体を起こし、呆然と呟く。
自分は先程、肉体的にも概念的にも致命傷となる一撃をまともに受けた筈だ。なのに、何故自分の身に傷一つ無いのか。リトゥエは自分の身を見下ろし、そして気づいた。身体全体を、淡く穏やかな光が包んでいることに。そして光は、両の掌を中心に広がっているように見えた。
無意識に、掌に刻まれた象形を見つめる。
(これの、力?)
「ギ、ギ、ィ、ィ──!!」
と、リトゥエの思考を遮るように、異質としか表現できないような音が響く。リトゥエは慌てて周囲を見廻して──絶句した。自分達の周りにある風景が、全てどろどろに溶けていた。自分達を襲ってきた護法達は影も形も無く、空と地面の境界すらあやふや。辛うじて残っているのはリトゥエがつい先程まで倒れていた石畳と、少し離れた場所に立つ【NAME】の姿だけ。
リトゥエは目を見開き、【NAME】の姿を呆然と見据える。【NAME】が纏う気配、それは今まで数度感じた、あの『位相守護者』達が纏っていた気配と完全に同質のものだった。
「ちょ、【NAME】!」
リトゥエは懸命に呼びかけるが、自分の声が【NAME】に届いていないのは明らかだった。既に、【NAME】に意識があるようには見えない。獣のようにただ叫ぶだけ。【NAME】が声をあげる度に、周囲の世界がどんどんと崩れ、代わりに、異質な世界の断片が崩れた隙間を埋めるように姿を現す。
つまり、これは『現出』だ。【NAME】に刻まれた刻印の力なのか、自分達の周りにある空間に、様々な概念が次々と『現出』を繰り返している。
「どう……しよう」
リトゥエは暫くのあいだ迷い、そしてある事に気づいて、再度己の掌を見据える。
(概念変質の抑制……存在封縛の象形──!)
この象形を身体に刻み込めば、自分達とは異なる、『守護者』に近い存在になった【NAME】を、元に戻すことができるかもしれない。果たして今の状態からこれが通用するのか、もう判らない。だけど今の自分にはこの象形を使う以外に手段が無い。
リトゥエは羽から淡い燐光を振りまいて空中へと浮かび上がり、【NAME】の方へと向かう。近づく度に自分という存在が歪み、崩れていくような感覚が襲う。象形の光に護られている状態でこれなのだ、象形が無ければとうの昔に自分は崩滅していただろう。
異質な叫びをあげる【NAME】の目の前まで辿りつくと、リトゥエは両の掌を、そっと【NAME】の身体の中心に押し当て、そして叫んだ。
「お願い、効いて──!」
瞬間。リトゥエの視界にあるものすべてが強烈な白光に埋め尽くされ、その余りの強さに、彼女の意識は瞬く間も無く遠退いた。
煌々と月が輝く夜の中。
貴方は疲れ切った身体を引きずりつつ、ようやく見つけたウスタールの大街道から、街の方へと向かって歩いていた。
ふと、今まで自分が居た場所へと振り返れば、そこには何とも形容し難い空間がある。簡単に言い表すならば特定の範囲に『現出』が何度も発生したような、そんな空間だ。見ているだけで頭がおかしくなりそうな程の、色々な地形の断片がそこで混じり合い、異様な形となって留まってる。
結局、あのノインと名乗った娘が放った光の網に捕らえられた後の記憶が一切無かった。貴方が目覚めた時には彼等の姿は既に無く、見えたのは奇怪極まりない周囲の風景と、あの男が持っていた巨大な長槍。そして足元に転がっていた小さな妖精の姿のみ。
槍を拾い、気を失っているらしきリトゥエを抱え上げ、滅茶苦茶としか表現しようの無い地形を歩き回る。ようやくそこから脱出した頃にはすっかり夜となっていた。
「──あ」
と、懐の中から細い声が聞こえた。見れば、小さな妖精が目を覚ましたらしく、ぼんやりとした表情でこちらを見据えている。
「【NAME】?」
見て判らないのだろうか。リトゥエの呟きに、貴方は軽く頷きで返してやる。
すると、リトゥエの表情がくしゃりと歪み、次の瞬間には懐から飛び出して、べたりとこちらの顔面に張り付いた。
「良かった……ホントに、良かった」
感極まったように呟くリトゥエに、貴方は彼女を引き剥がそうと伸ばした手を思わず止める。
(何やらよく判らないが──)
今は息苦しいのを我慢してでも、好きにやらせてやった方が良い。繰り返し呟くリトゥエの声を聞いて、何となく、そう思った。
花々からの観察者 幕間
──幕間──
酷く酷く澄んだ夜。深く高い黒の闇が覆う空には月の姿は無く、故に、普段は月が生み出す輝きに息を潜めている慎ましやかな星達も、今夜だけは自己主張に余念が無い。雲は無く、あるのは幾千幾億もの星の輝きのみ。空の中央を巨大な星の河が長く長く伸びて、南海の水平線に消えていく。
爽、と。
南海の方角から風が心地よく駆ける音が聞こえ、なだらかな丘に生える草々を順々に揺らしていく。その風は丘の頂上にある巨大な岩石の上に立ち、遥か天空に瞬く星々をじっと見据えていた少女の栗毛色の前髪を軽くそよがせる。
年の頃は九つ程だろうか。綺麗な螺旋を描く長い髪を大きな髪留めで止め、身の丈を優に越える巨大な杖を左手で構えたその少女は、まるでそれ自体が輝きを放っているかのような強い朱眼で空を見据え、小さく唇を動かす。

「東の空に、禍星が輝いているのが見えるな……」
呟く声音は酷く冷ややかで、声に色彩があるというならば、その色は褪めきった蒼が最も相応しい。
そのまま空を見上げ、数刻。
彼女はその大きな瞳を閉じ、細く小さく息を吐いた。
「波乱の示唆、か。……まったく、面倒な話だ」
彼女が言葉を紡ぎ終えると同時に、また強く風が吹き、丘を埋め尽くす緑が緩やかに流れる。
そしてその風に紛れるように、彼女の言葉とその姿が薄く色褪せて、夜の空に融けこむように消えた。

「ん? 目、覚ましたか。お嬢さん。良いタイミングだな」
すぐ近くに居る筈のその男の発した声は、酷く遠い処から聞こえるような気がした。

(……ここは)
どこだろう。
ノインはぼんやりと天井を見上げ、思う。見えるのは天井を構成する白い硬質の石と、その中央に打ち込まれた洋燈を吊り下げるためのフック、あとは、窓の外に広がる薄く雲の掛かった青い空。
苦労して横へと首を動かす。部屋の真中に置かれた小さなテーブルとその上に置かれた花瓶が見えた。花瓶を彩るのは美しい朱色の花々。彼女はその花を見つめ少し記憶を探ってみるが、花の名前までは判らなかった。まだ頭がぼんやりとしているせい……ではないだろう。元々、あまり花を愛でるような生活をしていない。
そして視線をゆっくりと滑らせると、丸椅子に座りのんびりとした調子でこちらを眺めている灰色髪の男が見えた。
どこかで、見たことのある顔。確か、自分は彼の名前を知っている。
(彼の名前は……そう、バド。バリード・ルッツ)
「────」
彼の名を呼ぼうとして、声が出ない事に気づいた。動揺する気持ちを落ち着かせ、今度はゆっくりと、言葉を紡ぐ。
「──バド、さん」
「ああ。気分の方はどうだ、眠り姫」
暢気そうな表情で言葉を返してくるバリードに、少しだけ、安心する。
「……なんだか、ぐらぐらして、ぼーっとしてます」
ノインは揺れる頭を右手で抑えて、寝台から半身を起こした。
「だろうな。どうもキミはまともに『刻印者』の干渉を受けたらしくてな、大変だったんだぞあれから。キミはどこまで覚えている?」
問われ、記憶を探る。しかしあの時の記憶はどうも断片的で、細切れにしか思い出せない。はっきりと思い出せるのは丘の上で『忍』から印章石を受け取ったあたりで、それ以降の記憶は酷くあやふやだった。
「そうか。なら、その後からの経過を話すぞ。あれから『刻印者』に接触したオレ達は、紆余曲折色々あって、何とか『忍』から受け取った印章石で『刻印者』を捕らえる事に成功したんだが──」
その直後に『刻印者』の所持していた刻印が力を発動し、周囲の地形に対して『現出』を発生させ、自分達はそれに巻き込まれたのだという。ノインは靄のかかった意識で懸命にその時の状況を思い出そうとするのだが、やはり、はっきりとは思い出せなかった。
しかし、『現出』の発生に巻き込まれて生き残ったという話は聞いたことが無い。自分達は一体どうやって助かったのだろうか?
ぼんやりと考えるノインの疑問に答えるような形で、バリードは話を続ける。どうも、自分達を『刻印者』の居る場所へと案内してくれた『忍』達が、『現出』に完全に巻き込まれる寸前、影抜けで自分達を『現出』の範囲外へと逃がしてくれたのだという。
(そうか……あの時の、闇は)
『忍』の影抜けは、己の影へと自らの身体を沈ませ、近隣にある別の影へと瞬間的に身を移す技だという。恐らくノインが気を失う前に感じたあの闇は、自分の身体が影の中へと入り込んだ時のものなのだろう。
「あいつらのお陰で何とか助かった訳なんだが……今でも、あの辺りには『刻印者』が『現出』させた滅茶苦茶の地形が残っててな。今、王朝の結界師が出向いてあそこを閉じてる真っ最中だとさ。途切れた大街道は現出地形を迂回して繋ぎ直すらしい」
「それで、あの『刻印者』は、どうなったんですか?」
「生きてるよ。『忍』が言うには、あの後、平気な顔して現出地形の中から這い出してきたらしい。なんつーか、滅茶苦茶だな」
ノインの問いに、バリードは小さく鼻を鳴らし、両手を挙げてみせる。
「そう、ですか……」
何ともいえない、よく判らない感覚がノインの心を占める。良かったような、良くなかったような。複雑な気分だった。
「ま、キミもあまり気にするなよ。あれは『昂壁の翼』の術者連中が悪いんだ。不良品寄越しやがって。あれがまともに動いてりゃ何とかなったかもしれんのに」
ぶつくさと愚痴めいた事を口にし始めるバリードを眺め──ふと気づき、ノインは慌てたように周囲を見廻した。そういえば肝心な事を聞くのを忘れていた。
「えと……それで、どこですか、ここは?」
「ラケナリアさ。アルマナフ大神殿にある外来患者用の宿舎。最初はテュパンに運ぼうって話だったんだが、キミの存在概念が結構揺らいでいてな。施療に関してはテュパンより聖アルマナフ大神殿の方が良かろうという事で、こっちに連れてきた。一応これでも最上級の部屋廻してもらってるんだがな。飾り気が全然無いせいか、どうにも殺風景で仕方ない」
バリード曰く、どうやら自分はあの場所から『忍』達に助け出される寸前、『刻印者』が発動させた力の直撃を受けて、かなり危険な状態に陥っていたらしい。身体ではなく、精神的、概念的な攻撃で負った傷を癒すにはテュパンよりも、ラケナリアのような大規模な施療院を持つところの方が確かに良いだろう。
「…………」
「どうした? 黙り込んじまって」
「──いえ、その……また、失敗してしまったなって」
言って、取り敢えず笑ってはみるものの。ノイン自身、その笑みが殆ど泣き笑いのようなものになってしまっているのがはっきりと判った。両手で顔を抱えて、その表情を揉み解す。
「さっきも言ったが、気に病んだところでどうなるものでもないさ。そろそろテュパンに報告にいった『忍』が帰ってくる頃だから、その間はほれ、ゆっくりしてな」
軽く頭を掻きながらバリードは呟くと、勢いを付けて丸椅子から立ち上がった。
と、その時。
バリードの影の中から、一つの人影がするりと這い出してくる。
「おわッ!」
その人影は仰け反るバリードを無視。寝台の上で目を丸くしたノインに深く一礼。
「お目覚めですか、ノイン様」
ノインもまだぼんやりとした意識の中で反射的に会釈を返す。バリードはその人影──『忍』を呆れたように眺め、呻いた。
「おいおい、エラく早いな」
「別に、私が直接テュパンまで赴いたわけでは御座いませんので。私自身は一時足りともこの都から離れてはおりません」
「……左様で」
抑揚の無い返答にバリードは素っ気無く呟くと、再度丸椅子に座り直す。
暫し、沈黙が続く。
身体がどうにも熱っぽく、ぼうっとした虚ろな視線で部屋の片隅を眺めていたノインは、バリードと『忍』の視線がこちらに集まっている事を感じ、ふと気づく。
(──あ、そうか)
二人とも、自分の言葉を待っているのだ。慌てて何か喋ろうとするのだが──何を言えばいいのか咄嗟に出てこない。
「それで、えと、すいません、まだ頭が良く廻らなくて」
ノインが誤魔化すような笑みを浮かべると、バリードは深く溜息をつく。
「んじゃオレが聞くよ。で、『忍』よ。テュパン国主は何と?」
「ノイン、バリード両護法は引き続き『刻印者』の監視を続けよ。以上です」
「引き続き、ね。いつからオレ達の役目は『監視』になってたんだ? ……まぁいい。それで、お前達『忍』は『刻印者』の位置を掴んでいるのか?」
胡散臭げなバリードの声に『忍』は小さく頷きで返す。
「一応は。しかし手出しする事は控えるようにとの厳命が。貴方がたにも同様の指示が降りています。これ以上『刻印者』を刺激する事なかれと」
「ふん。『刻印者』を刺激するな、でなくて妖精達と事を荒立てるなって事か?」
皮肉気にバリードは唸るが、『忍』の方は眉一つ動かさない。
「ったく、一体どうなってるんだか。国の方はニルフィエ達の動きを知っているのか? 大体、お前達『忍』が位置を掴んでいるなら、オレ達が『刻印者』を見張る理由も無かろう」
「もしもの時の抑止力として両護法を──」
「──待て待て。オレ達じゃ『刻印者』の相手にならん事を上に報告していないのか?」
バリードが『忍』の声を慌てて遮るが、『忍』は気にした様子も無く視線だけで頷く。
「しております」
「……なら、どういう事だ? それなら抑止力なんてもんがある訳ない事くらい判るだろうに。話が見えないぞ」
バリードが眉根を顰め、まるで咎めるような調子で呻くが、『忍』の方はといえば素っ気無いもので、
「私にもそこまでは。『刻印者』の居場所は判っておりますのでお二方をそちらまで案内する事は可能ですが、如何致しましょうか」
と、こちらの指示を求めるのみ。バリードはその様子にもう今日何度目かも判らぬ溜息を吐いた。
「オレに言われても知らんよ。オレはお守り役なんだろう? ヴァイヒュント嬢、どうだ、少しは頭がはっきりしてきたか?」
突然話を振られて、ノインはびくりと肩を震わせた。
「あ? え、えー、申し訳ありません。話を聞いていると、逆に頭がくらくらしてしまって……」
というより、どうにも頭がぼんやりとしていて、まともに物を考えることができない。バリード達の話も殆ど聞いていなかったのだ。
その様子にバリードはがっくりと肩を落す。
「──まぁ、キミの調子が戻るまで、ラケナリアでゆっくりしてるしかないか」
「い、いえ、もう身体の方は大丈夫です!」
バリードの言葉に慌ててノインは反論する。確かに調子は良いとは言えないが、自分が足手纏いになるのは堪えられない。だが、
「な訳あるかよ。キミは自分がどれだけの日数眠っていたか判って言ってるのか? 頭の方は暫くすりゃはっきりしてくるだろうが、身体の方はそうもいかんだろ。そろそろ施療師が来る時間だから、それまでじっとしてな」
その時バリードに告げられた日数は、自分でも驚く程だった。まさか、そんなに長い期間眠ったままだったとは思わなかった。
「……そう、ですね」
ノインは目を閉じて息を吐く。バリードはその返事に安心したように言葉を続けた。
「今は休むといい。頭の方がかなり鈍ってるのも──キミの外見を見てると一発で判るしな」
「? どうしてですか?」
何故外見でそんな事がわかるのだろう。きょとんとして首を傾げるノインに、バリードは眉を露骨に顰め、喉に何かが詰ったような表情で傍らに立つ『忍』を見上げる。
「あー。一応、言った方が良いのかね?」
「私は気にしませんが」
「いや、ヴァイヒュント嬢が気にするんじゃないか? 本人気づいていないようだし」
何やらひそひそと小声で会話する二人に、ノインは段々自分が苛立ってきているのを感じた。
「だから、何ですか? はっきり仰ってください」
少し前に身を乗り出し、強い視線でじっとバリードの方を見据える。
バリードはノインの方へ向き直り、上下へ数度視線を彷徨わせた後、深く深く溜息をついた。そして半ば自棄といった調子でぐいと身を乗り出すと、ノインの顔を真正面に見据えて口を開く。
「……だからだなぁ。キミは今寝台から半身を起こしているわけで、当然肩まで掛かっていた毛布がすっかりずり落ちてしまっているわけで」
「それが、何か?」
「キミ、自分が今裸だって事にそろそろ気づいた方が良いと思うんだがな、オレは。丸見えだぞ、色々と」
言われ、ノインは視線を男の顔から自分の身体へと移す。
「…………」
一瞬、世界が真っ白になった。
「どうだ、いい加減隠す気に」
「いぃぃいやぁああぁあああ──ッ!?」
あとは一瞬だった。悲鳴と共にノインの右手が上がり、五指が高速で動いて複雑な印章を空中に描く。そしてそのまま、目の前にある顔に向かって右拳が唸った。
「げぼがいぃ!?」
ごり、と酷く鈍い音が室内に響き、一拍置いて石壁に何かがぶつかり派手に砕ける音が、小さな振動を伴って宿舎中に鳴り響いた。
石壁に豪快にめり込んだバリードに軽く目を瞬かせて、『忍』はぽつりと呟く。
「身体の方は問題無いようですね。……お大事に」
言葉と共に、ずるりと『忍』の身体が影の中へと沈み込んだ。
身体が、震えている。
唐突に途切れた楔との関わりに、私は呆然と世界を漂っていた。
楔との繋がりはまだ残っている。
私の世界を『皆』の元へ届けることは出来る。
でも、もう楔達は私の声に答えてくれない。
自分の力が、徐々に失われていくを感じていた。
自分の意識が、徐々に世界に溶けていくのを感じていた。
もう、はっきりと判る。
私は壊れ始めていた。
本来の役目とは異なることを、無理に行っているせいだろうか。
何故こんなことをしているのだろう。
私は訪れる『皆』をこの世界で迎え、訪れる『皆』とこの世界で踊る。
その為の存在なのに。
何故私は『皆』が居る世界へ赴こうとしているのだろう。
判らない。理由は判らないけれど。
ただ、寂しい。
私の世界は暗すぎて、『皆』が居なければ堪えられない。
でも、私の世界には、もう誰も居ない。
もう一人の私すら。
私とは違う私すらも。
在るのは私と、世界の子たるただ一つの竜。
──そうだ。
あの子を、竜を呼ぼう。
今は世界の片隅で、すべてを護っているあの子。
あの子と一緒に居れば、私は寂しくなくなるかもしれないから。
花々からの観察者 妖精
──妖精──
そろそろ太陽が中天の位置に入ろうかという時刻。街の中心部近くにある食堂に入った貴方は、カウンターに近い席に腰を下ろすと、店員を呼び適当な料理を頼んだ。丁度昼食時という事もあり、食堂の中は酷く活気に満ちている。
かなりの時間を経て出された料理は、味はともかく量の方は流石なもので、単純に腹を膨らますことが優先されている。とにかく、出された料理をかき込んでいく。
今、あの小さな妖精リトゥエとは別行動を取っている。
「明日の晩には戻るから」
そう言って、昨日の深夜にふらりと出掛けたまま、まだ戻ってきていない。
近頃、リトゥエがふらりとどこかへ出掛ける事が多くなった。
別段、彼女のことを心配しているというわけでもないのだが、前まではこちらが嫌がっても延々引っ付いてきていたので、それに慣れてしまっている身としてはやはり気にしてしまう。
だが、安易に理由を尋ねるのも考えものだった。いざリトゥエに尋ねてみれば、
『いや、理由は別に無いんだけど……そいやそーだね。んじゃこれからはもっと引っ付いてる事にするよ』
などと薮蛇以外の何物でもない結果になる事も考えられる。あの妖精は居たら居たで鬱陶しいことこの上ないのだ。下手に口に出さない方が利口だろう。
軽く息を吐く。思考に沈んでいた意識を浅く目覚めさせ、木製のスプーンをゆっくりと動かす。器に盛られているのは羊肉のシチュー。味自体はごくごく平凡なもので、然したる感想も湧かない。量が多いのでなかなか無くならず、そろそろ冷めはじめているのが難点か。
貴方は顔をあげると何気なく視線を巡らせて、ふと、己の肩口あたりで止める。今は服に隠れ見えないが、そこにはグラジオラスの『大海神祭』で出くわしたあの化け物により刻まれた、不気味な印がある筈だった。今まで幾度となく疼き、痛み、己の身体を蝕む力を生み出す印。
──だが、近頃はこの刻印が疼く事は殆ど無くなった。
グラジオラスの海辺で出会った異形。あれと同種の気配を感じたときに鈍く疼く事はあるが、それ以外に、あの独特の感覚に襲われることは殆ど無くなっていた。
喜ばしいことではある。
しかし、何故いきなり刻印の疼きが無くなったのか、それが判らない。色々と考えてはみたのだが、思い当たるようなことなど欠片も無かった。
たが、いつから刻印の疼きが無くなったかは覚えている。『護法』と名乗った娘と青年、あの二人と戦ったあとからだ。
リトゥエに聞いた話によれば、『護法』と呼ばれる者達は、このグローエス五王朝を守護する職務につく衛士達や騎士達のなかでも、特に際立った能力を持つ者達に授けられる称号のようなものらしい。
その名の通り、五王朝の法を護する者。
また、彼ら自体が法であるとする考え方もあり、故に権限も大きい。『護法』と敵対するという事は、五王朝という存在に背くと同義。
だが。
(……一体、自分が何をしたというのか)
国の守護を務める『護法』に剣先を向けられる理由。そんなもの、皆目見当もつかない。
結局、あの戦いで貴方は倒れ、そして目覚めた時には周囲の地形は歪に変わり、二人の姿も無くなっていた。
一体、自分が倒れていた間に、何が起こったのか。
リトゥエはこちらが目覚めるまで気を失っていた筈だ。となれば、あの後のことを知るのは、『護法』の二人組だけだ。
「とはいえ……」
彼らが生きているのか死んでいるのかすら判らない。生きていたとしても、手がかりが無さすぎる。単純に探して見つかるとも思えないし、下手に『護法』の素性を調べようと国に近づけば、色々と厄介なことに巻き込まれる可能性もある。第一、『護法』に狙われているということは、五王朝に狙われているということだ。わざわざ自分から虎穴に飛び込むこともないだろう。
(どうせ、彼等が無事ならば……)
もし生きているならば、また自分のところにやってくるだろう。その時に聞き出せば良い。
そう結論づけ、貴方は目の前に置かれたスープの皿を更にかき回し、口をつけた。
【NAME】が滞在している街の外れにある小さな森。その狭間に、白、緑、茶の色、煌びやかな衣装を身に纏った妖精達がゆっくりと舞っていた。
彼ら……いや、彼女らは人間に近いディテールの身体を持っていた。だが、人と比べ酷く小さい。せいぜい成人男性の掌を少し上回る程度の大きさだ。髪の色は纏う服と同じでそれぞれ赤、青、白。そして背中には昆虫達が持つものによく似た細く薄い羽が二枚、柔らかな燐光を周囲に振りまいている。
彼女等は所謂、ミスティック──妖精と呼ばれる者達だった。人間などとは違い、肉体という物理的な要素ではなく、概念的な要素に比重を置いている存在。その中で、彼女等のような身体的特徴を持つ者達を『流翼種・フェイアリィ』と呼ぶ。
流翼種に限らず、妖精達は基本的に豊かな自然が残る地形で偶発的に生まれる。自然という概念が飽和し、現世界上で具象化されたものが妖精。そう言っても良い。そんな妖精達の長とされる、ニルフィエ──地母種と呼ばれる芯属も、元はそうして生まれた存在だとされている。また、妖精達は概念の飽和から生まれた存在であるがゆえに、既存の生物のような子を残し、己が種を増やすという構造は基本的に無い。彼らはあくまで自然が具象化した姿であり、厳密に言えば生物ではないともいえる。
だが、中には例外も存在する。
その代表的なものが、今ここで軽やかに舞う妖精達だった。
ニルフィエは、己の存在概念を分離し、自分の分身──とはいえ姿形は千差万別だが──ともいえる存在を作り出すことができる。そしてその力を用いて作り出されたのが彼女達だった。『分け身』と呼ばれる技で生まれた妖精は、現存する妖精種の特徴を持ちつつもそれらの者達とはかなり異なった存在となる。長い長い時を経て生き続けたニルフィエ達の存在概念を継承するからだ。故に個性もあるし、知識も並ではない。
また、同じニルフィエでもその個体の力により、分け身の能力や、妖精達のなかでの地位も変化する。
白の色彩を持つフェイアリィは、『風を仰ぐ女王』と呼ばれるニルフィエの系譜に連なる者。この女王は『南海』の方角から五王朝に吹く季節風を司るニルフィエ。故にその子である彼女は風の加護を得て操る力を持つ。
緑の色彩を持つフェイアリィは、『深緑に漂う女王』と呼ばれるニルフィエの系譜に連なる者。この女王は南オルスの平原から東にずれた位置にある大きな森を守護するニルフィエ。故にその子である彼女は木々の加護を得て操る力を持つ。
茶の色彩を持つフェイアリィは、『大地に寄り添う女王』と呼ばれるニルフィエの系譜に連なる者。この女王は『タラス山地』と呼ばれる地形から生まれたニルフィエ。故にその子である彼女は土の加護を得て操る力を持つ。
どの者達も、フェイアリィ種としては非常に強い力を持っている。当たり前だ。本来ならば流翼種は花の概念から生まれる存在なのだから。風や土の概念を秘めたフェイアリィなど本来ならば生まれることは無い。
踊る彼女等の中央に立っていたリトゥエは、心の中だけで小さく呟く。

(そして、私……か)
「久しぶりだな。色々大変だって聞いていたけど」
「でも、元気そうね。安心したわ」
「上手くやってるわね~。リトゥエ~」
リトゥエの周囲を囲う妖精達が、順々に口を開く。
白はアイネア、緑はオウル、茶はクリューネという名だ。リトゥエがクォルルマルの『聖域』で暮らしていた頃に知り合った者達。
「……別に、私は何もしてないよ」
明るい声音で話し掛けてくる妖精達に対して、リトゥエの表情はあまり冴えない。なにやら楽しげな彼女等の様子を見ていると、自分の気持ちがどんどんと落ち込んでいくのが良く判る。
実際、そういう気分になるのも当然といえば当然だった。
自分は『聖域』からの指示を半ば無視しているのだから。
本来ならば『刻印者』を操り、『刻印者』と『位相守護者』が争うよう仕向けなければならないというのに、アイネアやオウル達から今まで数度齎された『位相守護者』の居場所についてすらも【NAME】に伝えていない。今の状況は全て『刻印者』である【NAME】自身の意思と行動による結果だ。
リトゥエがやっている事といえば、自分の『源流』から授けられた象形──本来ならば『刻印者』を操る為の象形で、【NAME】が『位相刻印』から受けている概念的な侵食を、気づかれぬように押さえ込んでいるだけだった。
「いや、そう謙遜しなくてもいいだろ? 残る刻印は五つ。全ての刻印を集めさせたら、後はあの『刻印者』を封印してしまえば全てはお終い。もうちょっとだよな」
クリューネは軽い調子でリトゥエの肩を軽く叩くが、リトゥエは苦笑を返すことしか出来ない。
「それじゃ、用件を済ませましょうか」
リトゥエの正面に立ったオウルが、ゆったりとした口調で話し始める。その内容は、リトゥエの故郷である『聖域』からの指令だ。
彼女等はリトゥエに『位相守護者』についての様々な情報、そして『聖域』からの決定事項や今後の予定などを告げていく。彼女等に今割り振られている役目は、『刻印者』を操っている──とされている──リトゥエに『聖域』の決定を知らせるというものだ。リトゥエ自身、『聖域』に居る己の『源流』と繋がってはいるのだが、元々分身としての力は弱い『観察者』でしかない彼女には、遠くに居る『源流』と意識を通わせるには満月の夜でなければならない。故に普段はこうして繋ぎの者を立ててもらい、『聖域』からの情報を仕入れていた。
オウル達の話は続く。だが、正直言って、今のリトゥエにとってはあまり楽しい話とは言えなかった。
「リトゥエ。守護者が潜んでいると思われる位置は、先刻言った通りよ。元々は単なる『観察者』だった貴方には荷が重いかもしれないけど、しっかりね」
三人の小妖精達のなかでもっとも大人びた雰囲気を持つオウルが、話を纏めるようにそう告げて、ゆっくりと背の羽を振るわせる。用を済ませた彼女等は『聖域』へと帰るのだ。
「だよな。本当なら私等もついていけたら良かったんだけど。リトゥエも私等みたいな『守霊』ならもっと楽だったろうに」
顔をくしゃりとゆがめて笑うのはアイネア。空へと昇っていくオウルを追うように彼女の体もふわりと浮きがった。
「それじゃ、頑張ってね~、リトゥエ~」
最後に残ったクリューネは元気良くリトゥエに手を振ったあと、二人の後を追い、勢い良く飛び出した。
「……うん」
口々に激励の言葉を掛けて去っていく流翼種の妖精達に、リトゥエは小さく頷いて、手を振る。元々小さな三人の姿は見る間に遠退き、空の青の中に溶けていく。
彼女等の姿が完全に消えるまで振り続けていた手を下ろしたあとも、リトゥエはぼんやりとした表情のまま、彼女等が消えた方角を見上げていた。
「頑張れ、か」
現れたのは猛き竜。
私の世界を護る者。
傍らに寄り添うその子を優しく撫でると、彼は小さく喉を鳴らす。
竜はこの閉じた世界の扉を見張る力。
世界と世界の狭間に漂う『奈落』の者を退ける剣。
私は彼に話し掛ける。
いつか貴方も、違う私と同じように、『皆』の元へと運んであげる、と。
だけど、竜は答えない。
彼は単なる力の化身。
護りの竜以外の何者でもない。
でも、この子が居てくれるなら、私は少しだけ、強くなれる。
私の身体が溶けゆく前に、
私の心が砕ける前に、
今一度だけ、『皆』と一緒に踊りたい。
私は竜に身を寄せ、力を蓄えるため、ゆっくりと瞳を閉じた。

「本気か? ヴァイヒュント嬢」
ラケナリアの中央、聖アルマナフ大神殿の施療院にある一室。
その中にある硬い寝台の端に腰を降ろし、ノイン・ヴァイヒュントは真っ直ぐな視線で部屋の入り口に立つバリード・ルッツを見る。彼はどこか砕けたような印象を見る者に与える──着ているものの造り自体は他の護法達と同じであるのにだ──騎士装束に身を包み、呆れたような表情で見返してくる。
「監視命令を無視して、己の足で『位相守護者』や『刻印者』について調査したい? 今更?」

「はい」
こくりと頷くノイン。バリードは顔を片手で覆って視線を外し、息を吐いた。
「何故だ? キミはもう少し職務に忠実な人間だと思っていたが」
バリードのその言葉に、椅子に座る護法衛士は暫し視線を彷徨わせ、顔を伏せる。
「……自分でも、よく判りません。でも、今の私達では『刻印者』は止められない。ならば、違うアプローチで彼等について知り、干渉するしかないと思うんです。私は彼等について、あまりにも何も知らない。それにニルフィエ達の動向についても」
「オレ達の受けた指示は、『刻印者』を監視せよ、だ。止めることじゃないし、ニルフィエ達がどう動こうがオレ等には関係ない」
「判っています。ですが──」
ノインは顔を伏せたまま、少し言葉を詰らせる。
以前の自分ならば敵がどういったものだろうと気にすることは無かった。たとえ剣などでは敵わずとも、己の『ソルモニアル』を放てば必ず勝つことができると、そう信じていたから。
だがそれはもう過去の話。自分達は『刻印者』に敗北したのだ。
『刻印者』が発した、周囲の世界を作り替えるあの恐ろしい力。あの無秩序に発現される力は、酷く危険なものに思えた。到底、放置しておくわけには行かない。自分は、この国を守る『護法』なのだから。
「駄目、でしょうか? バドさん」
そこで視線をあげ、バリードの表情を盗み見る。
戸口にもたれかかり、こちらを見ている灰色髪の青年は露骨に面倒くさそうな顔。
「オレはこのまま『刻印者』を適当に追いかけて、のんびり監視していれば良いとは思うがな。それが一番楽できそうだし、第一キミは病み上がりだろ?」
言って、青年はひらひらと手を振ってみせた。ふざけたような彼の物言いにノインは反射的に顔を上げて睨む。
「冗談は止めてください。私は真面目に尋ねてるんです」
「……真面目に、ねぇ」
ノインの言葉に、バリードの表情がすっと冷える。
「別にどうでも良いさ。キミの好きにすれば良い。だが、問題は多いぞ。まずオレ達には『忍』がついている事を忘れるな。任務放棄など一瞬でばれる。そしてどうやって奴等についての情報を集める気だ? 恐らく守護者や刻印、位相に関する情報の殆どは国から規制され、表には出てきていない。書館や情報屋ごときを利用して情報を仕入れられると思っているなら、認識を改めた方が良い」
男は順々に指を立てつつ話す。
「そして最後に。アルフレドの奴は恐らく『刻印者に手を出す必要は無い』と判断したのだろう。オレ達が……いや、キミがこの任務を割り振られているのは、恐らく何らかの別の理由があるに違いない。だから、放棄するのは得策とは言えんだろうな」
バリードの言葉に、ノインは顔に疑問符を浮べ彼を見上げた。
「理由? どういうことです?」
「そこまでは知らんよ。極めて重大な事かもしれんし些細な事かもしれん。単なる推測だ。だが、ヴァイヒュント家のお嬢さんを国外へ出しておく、何らかの理由があるのだろう。あのテュパンの若君主にはな。ま、これは単なる当てずっぽうだし、その辺りはオレには関係の無い話だが、命令を破るつもりでいるのなら、取り敢えずキミはその辺りのことを確かめるために、一度国に戻ってみた方が良いんじゃないかとオレは思うがね。『刻印者』のことなどは忘れてな」
そこで話は終りとばかりに、バリードは部屋の壁に背を預けて腕を組んだ。ノインは視線を下ろし、両掌を小さく組んで俯いた。そしてそのまま数秒。
考えがまとまらない。
確かにバリードの言う通りなのかもしれないし、大体、何故に自分はこれほどまでに『刻印者』に固執しているのかすら、良く判らない。
しかし、自分は──
「──駄目です、帰れません。私は、『刻印者』を討つ手段を探します」
判らない、何もかもが判らない。だが、その言葉は何故かあっさりと口をついてでた。
彼女の返答に、バリードは深い溜息。
「頑固だな。あの刻印が生み出す、位相の力に惹かれたか?」
バリードの言葉に少し目を瞬かせ、そして俯く。
「そう、かもしれません。でも、あの力が見逃せないものであることは確かです。私達が護るべき国を、民を脅かす力だと。護法は国の法を護すると同時に、己が意思を国の法として動くことも許されています。ですから、国主の命に背き、あの『刻印者』を討つこと……いえ、あの人の力の源となるものを知ろうとすることが間違っているとは思えない。『忍』達が私の邪魔をしようとも、関係ありません」
顔を伏せ、まるで自分に言い聞かせるように言葉を継いでいく。
「先程も言いましたが、今の私には『刻印者』は止められない。ならば止めることができる方法を探さなければならない。ただ傍観しているだけなんて、私は堪えられない」
ノインは言い切り、顔を上げた。
視線の先には、両眼を閉じ壁に背を預けて立つ灰色髪の男の姿。視線を外す前とまったくの同じ姿勢。彼は気だるげに左眼だけを開けて、ノインを一瞥。
「馬鹿だな」
「ば……」
あまりの物言いにノインは面食らい、表情を険しくする。しかし、
「最初に会った時は、もう少し上手く立ち回れる類の人間だと思っていたが」
バリードはそこで言葉を切り、数度灰色の髪をかき回す。
「──だが、それでこそ『護法』だ。ならすぐに出るぞ。オレに心当たりが……まあ、無いことも無い」
そう言い、戸口に手を掛けて外へと出て行こうとするバリードにノインは慌てた。
「え? ち、違います! バドさんはこのまま『刻印者』の監視へ向かってください! 貴方まで任務を放棄したら『刻印者』の監視はどうするんですか!」
「うん? そんなもの『忍』の連中が居るだろうがよ。単なる尾行監視ならばあちらの方が専門だ。わざわざオレだけ残る必要も無いだろう、効率の悪い。大体キミ、『刻印者』とかについて調べるアテはあるのか?」
「あ、う」
勢い込んで立ち上がったところでバリードに釘を刺され、中途半端な姿勢で動きを止めてしまうノイン。
「で、ですけど、さっき私に『刻印者』をのんびり追いかけて、ゆっくりしていた方がいいって言ったのは貴方じゃないですか!」
「別にあれは、キミはそうすべきでないかと勧めただけだ。オレ自身がそうするとは言ってない。キミは病み上がりだし、のんびりしていた方が良いだろう? オレは元から命令に従う気は無かったしな。確かに、放っておく訳にはいかないだろう、あの力は」
(この人は……)
なんて勝手な人なのだろう。
私が素直に彼の言う事を聞いていたら、一人だけ置いていかれていたのだろうか?
そう思うと、ふつふつと怒りが湧いてくる。
しかし、バリードの方はと言えば、非難の眼差しを向けるノインのことなど気にした様子も無く、言葉を続けてくる。
「さて、オレにはアテあって、キミには無い。そしてオレが言うアテは、キミ一人が尋ねていったところで素直に言う事を聞く奴じゃないぞ」
嫌らしい笑いを浮かべるバリードの顔が、酷く癇に障る。ノインは何とか反論できるような事柄を探して──
「──あ、貴方の言うそのアテが、どれだけ信用できるかによります」
その言葉に、バリードは少々顔を顰め、髪を掻き揚げる。
「なに、ちょっとした古い知り合いだ。俗にいう『占い師』って奴が馴染みに居てね」
「う、占い!? そんなもので──」
訝しげに片眉を上げて文句を言おうとするノインを、バリードは片手で制止。
「馬鹿にしたものじゃないさ。ああいった異質な力を知るには正道よりも邪道を、ということだ。さぁ、どうする? どちらにせよオレは一人でも行くつもりだけどな」
ノインは頭を抱え、深く溜息を吐く。
暫しの間、黙考。頭の中に無数の案が浮び──ひとつを除いて全ての案が消去される。そこでまた、深々と溜息。
そして、寝台の脇に纏めてあった荷物を抱えて彼女はゆっくりと立ち上がると、戸口に立つ青年を真っ直ぐに、しかし恨めしげな目つきで見やり、一言。
「……意地悪」
「否定はしない。行くぞ」
花々からの観察者 娼館
──娼館──
副都オルノルンのフガー歓楽街。そこにリリィ・ネ・リネルと呼ばれる、大小様々な酒場、舞台、そして娼館が連なる大通りが存在する。護法衛士ノイン・ヴァイヒュントは、その通りの裏路地を奥へ進んだ処にある古びた館の前、広く開いた何も無い庭に立ち、呆然とそれを眺めていた。
高さ十メートル程。凹字の構造を持つ黒塗り煉瓦造りの館。正面にあるのは、館の規模を考えればあまり大きいとは言えない木製の扉。その上には流暢な文字で『キリネルアール娼館』と書かれた板が掲げられていた。
娼館。
テュパンに居た頃に何度か話には聞いていたが、実物を見るのは初めてだった。
そして、何故自分がこんな場所に足を運んでいるのかが、ノインは全く理解できない。自分の同僚が指示した通りの道を進んで、辿りついたのがこの館の庭だ。
(…………)
どうしたものだろうか。頭に血が上っている。完全に混乱していることが自分でも良く判る。
そこへ背後に人の気配。ノインは背後へ視線すら向けず、呟く。

「──不潔です」
その言葉に対し、彼女から数歩遅れて歩いていた護法騎士、バリード・ルッツは両眼を閉じて深々と吐息。

「何を勘違いしているのかは知らんが、今は単なるアパルトメントだ、ここは。この館の管理人は色々と頑固な奴でな。なかなか下げようとしないんだよ、この看板」
「え?」
片眼だけでこちらを見据えて告げる青年の言葉に、頭に上っていた血が一気に引いた。慌てたように視線を往復させるノイン。
「あ、私──」
「あと、先に言っておくが」
灰色髪の青年は片眼を閉じたまま、ノインの言葉を遮るように再度口を開く。
「中に入ったら『不潔』なんてのは絶対に口に出さないことだ。住人に袋叩きにされる──いや、キミならば返り討ちにできるか。なら、言うつもりならば、なるべく穏便に事を済ませてくれ」
バリードの言葉に、ノインはまたも言葉を詰らせる。つまり、この館には今でもそういった職につく人間が住んでいると。そういうことなのだろう。そして、それを悪し様に言うのは控えてくれとバリードは言っているのだ。
……確かに、それはそうだろう。
「その、ごめんなさい」
反射的についてでた謝罪の言葉に、バリードは更に苦笑の色を濃くした。
「オレに謝ってどうするよ。ここでぼんやりしていても仕方ないし、行くぞ」
街の外れにある宿の二階、階段を登ってすぐの位置にある一室。窓際に近い場所に置かれた寝台に貴方はぐったりと身を横たえていた。
感じるのは、筆舌に尽くし難い程の激しい痛み。
全身の神経を蝕むような痛みに意識は朦朧とし、目に映るものは全て翳み、歪んで見えた。
既に服も、そして寝台に掛けられていた薄布も脂汗でぐっしょりと濡れている。
丁度、次の街の手前近くへとやってきた時、それは唐突に訪れた。
──刻印の疼き。
しかも今までのような生易しい疼きでは無く、声を出すことも出来ぬほどの激痛を伴っていた。徐々に強くなる痛みに耐えながら、這いずるように街へと辿りついた貴方は、手近の宿で部屋を取り、そのまま寝台に倒れ伏した。それから既にどの程度時間が経ったのか、もう正直よく判っていない。余りの痛みに気を失い、つい先程目覚めたところだった。だが、痛みはやはり続いている。一時よりは幾分マシにはなってはいたが、到底起き上がれるような状態ではない。

「【NAME】……聞こえる?」
その時、傍らから声が聞こえた。
苦労して首だけを動かすと、歪んだ視界に紫の色彩が乗る。
「この宿の人が妖精嫌いじゃなくて助かったよ。水、貰ってきたんだけど……大丈夫?」
恐る恐るといった調子で尋ねてくるリトゥエに、この宿についてからどれだけ時間が経ったのかを尋ねた。
「えと、今は丁度、正午を過ぎた時分だよ。ここに来て三時間くらい、かな」
その答えに、貴方は両眼を閉じてぐったりと寝台に身を埋める。
「【NAME】、つらい?」
枕元に近い位置からそんな声が聞こえるが、もう答える余裕も無い。片目をあけてただ妖精の姿だけを見る。
「……そっか。そうだよね」
その視線だけで、彼女はこちらの意思をしっかりと汲み取ってくれたようだ。萎んでいく声と共に、リトゥエは顔を伏せる。近頃は、初めて出会った頃のような屈託の無い笑顔を見せることも殆ど無くなっていた。
暫くの間、室内を沈黙が包む。
「──ねぇ、【NAME】」
酷く真剣な声に、貴方は痛みに耐えつつ再度リトゥエの方へと視線を向けた。
「少しだけ目を瞑ってて。私が、何とかするから」
彼女の背の羽から燐光を散り、その小さな身体がゆっくりと空中へ浮き上がっていく。仰向けの貴方の眼前から指一本分も離れていない位置で留まり、うつ伏せとなった小さな妖精の両掌に、淡い光が灯ったように見えた。
同時に、彼女の顔が小さく歪むのも。
「瞑っててって言ってるのに……仕方ないなぁ」
リトゥエは苦笑しつつ、光を放つ掌を貴方のほうと伸ばす。
「【NAME】。なるべく、気を楽にして。逆らわず、受け入れるの」
彼女の小さな掌、淡い輝きを放つそれが、ゆっくりと貴方の眼前へと迫り、額に触れた。
酷く冷めた感触が身体を包み込む。
額から伝わる何かが全身へ走り、痛みも、疼きも、意識さえもが一瞬にして凍えていく。
急速に褪せて白に染まっていく視界の中で、目の前に浮ぶ小妖精が呟く声だけが、貴方の耳を打った。
「大丈夫。だから、今は何も考えずに休んで──ね?」
その声を聞き終えると同時に、貴方の意識は音もなく途絶えた。
商都テュパンにある国主館、その一室。
「そうか。あのノインがね」
「はい」
大きな硝子窓から差し込む光は太陽の輝きではなく月の瞬き。その白い光を見上げたまま、豪奢な椅子に腰掛けた青年──このテュパン国の主であるアルフレド・ラナーンは、部屋の扉付近に立つ影に尋ねる。
「バリードと組ませることで彼女も何か変わるかとは思っていたが、そこまでとはな。あの男が付いているなら大きな問題は無いとは思うが……行き先は?」
「ラケナリアからオルノルンへと向かったようです」
返答は瞬時に返って来た。微動だにせず戸口に立つ、白髪を長く伸ばしたその男は、まるで針金のような印象を見る者に与える。
アルフレドは彼の返答に暫し考え込むような仕草。
「ふむ。で、『刻印者』と彼女等の監視は?」
「『陰翳の霧』の者を差し向けてはあります。ですが、ヴァイヒュント王領伯のご令嬢ならともかく、彼等に『刻印者』相手は少々荷が重いと思われますが」
「構わんよ。あれは単なる監視、所詮は結末を知るためだけに付けているようなものだ。ニルフィエ達が『刻印者』を抑えた今、我等にとって奴の存在は然したる意味を持たない。今は彼女等も封じるに最も適した時期を待っているのだろうが、いずれ仕掛けるだろう。そうすれば『現出』も収まるだろうさ。『現出』から得られる他世界の力には魅せられるが、我等が制御できぬのなら致し方あるまい」
そこで戸口に立つ男の気配が微妙に揺らぐ。アルフレドはその気配に少し目を見張り、そして声も無く笑う。
「珍しいな。お前が言い淀むとは。言ってみろ」
対する男は、小さく咳払い。
「……差し出がましいとは思いますが、あのニルフィエ共をお信じになられるので? 所詮奴等は人ならざるもの。いつ確保した刻印の力を使い、我等に牙を向くか」
「いや、人と違い、彼女等の求めるものは酷く単純だ。故に行動を読みやすい。今回のような事ならば十分信じるに値するだろう。化け物は化け物同士、潰し合わせるのが楽でいい。第一、我等が表立って動くと事態がややこしくなる。この前のグラジオラス沖での海戦が良い例だ」
戸口の男から視線を外し、アルフレドは硝子窓を通して南海を見る。あの『第七位相守護者』を討つ作戦で、テュパンの主戦力である蒼穹艦隊はかなりの被害を受けていた。以前の戦力を完全に取り戻すにはもう暫く時間が必要だろう。だが、今の情勢はその時間を確保できるかどうかも危ういのだ。
「それに、我等には我等のやることがある。……セルマの話だが、ノティルバンの連中が密かにこの五王朝に兵を送り込んでいるらしい」
「──は? 彼等がこちらに密偵や傀儡を送るのは今に始まった事では……」
「違う。無論それもあるが、私が言っているのは密偵ではなく、兵の事だ。ノティルバンの虎の子である『神騎士』達が直接、こちらに入り込んできたという話がある。ウルトのうつけが奴等を秘密裏に通したらしい」
「なんと──」
「あの単細胞を騙くらかしたり、フォースやお坊ちゃん、そして私のところに傀儡を送り込んだりと、まったくお盛んなことだ。我等が判断を誤れば同士討ち、そしてノティルバンと直接剣を交える事無く敗北する可能性もあり得る」
「それでは、バリードやノイン嬢を早急にこちらへ呼び戻した方が宜しいのでは」
しかし、アルフレドは小さく首を横に振る。
「いや、必要は無かろう。この件に関しては、既に別の──カルエンスやクンアールに縁の無い護法が動いているからな。セルマもそちらを追ってくれるという話だ」
「セルマ様が……」
「それに、今回ノインにバリードの奴をつけたのは、研修の意味もある。あの娘は指示された事をこなすだけならひどく有用だが、柔軟性が微塵も無い。類稀なる力と家柄で『護法』の地位は得ても、あれでは使い物にならん。バリードのような男と行動を共にすることで、色々と学んでくれると良いのだが」
アルフレドは椅子に深く身体を沈め、軽く目元を揉み解す。
「さて、化け物退治は彼等や妖精共に任せるとして。我々は、我々に振られた役をこなさねばな」
縦横五メートル四方程度の部屋、その中央に置かれた天幕つきの豪奢な寝台に酷く気だるげな様子で身を埋めていた女は、幾ら扉をノックしても返事を返さぬ部屋の主に業を煮やして室内に踏み込んできた二つの影、ノインとバリードの姿を見やり、眼を丸くする。
「──バド?」

「正解。突然で悪いが、ちょっと占って欲しいことがあってな」
そう言って遠慮の欠片も無く部屋中央の寝台へと歩いていくバリード。ノインは彼についていこうとして、室内の様子に面食らったように立ち止まる。
彼女の知っている占い師という者達は大抵、仕事場どころか私室もどこか妖しげで、いずこから仕入れてきたのかも判らぬ珍妙な品が所狭しと置かれていたり、奇妙な香が焚かれていたりしたものだが、この部屋にあるものといえば、床や部屋の隅に配置された洒落た箪笥、他に寝台のすぐ傍に置かれた小さなテーブルなどに投げ捨てられた様々な衣服類と、部屋の大きさに比べかなり巨大な天幕つきのベッドだけ。
占い師の部屋というよりも、これは──
(衣装部屋みたい……)
「で、ヴァイヒュント嬢、こいつがオレの言ってた占い師で、名はナクルだ」
「え?」
意識が他のところへ行っていたノインは、バリードに声にはっと我に返る。見れば、バリードは寝台に掛けられていた幕をあげ、戸口に立ったまま室内を見渡してた彼女を待っている。ノインは慌ててそちらへ歩み寄り、寝台に寝そべる人影に小さく会釈する。

「はじめまして。ナクルさん、で、宜しいですか?」
「…………」
対する女性は未だ驚きの表情で固まったまま。だが、バリードはそんな彼女の様子にも気にした様子も無く、しかし何故か普段以上の顰め面で、彼女に向かって一気に用件を告げる。
「で、だ。詳しい内容は話せないんだが、今ちょっとオレ等、厄介な事件に絡んでいてな。正直先が全く見えん状態なんだ。だから、お前の占いと託宣で何とかならんかな、とな。オレ等が今後動く上での指針みたいなものが欲しいんだ。という訳で、一つ頼む」
言葉遣い自体はいつもと同じだが、どこかしら声色が硬い。そしてその言葉を受け取った女──ナクルは、そこでようやく反応を返す。
「はぁぁぁ~……」
細く、それでいて豊かという、完全に対照的な二つ要素を内包した身体。その半分以上を淡い紫色の寝台に埋めたナクルは、深く深く、まるで地の底にまで届けといった調子で重苦しい溜息を吐いた。
「ったく、久しぶりに帰ってきたと思ったら、いきなり女の子連れ。それで口を開けばそんなこと? 拗ねるわよ、私」
今度は冗談の色を塗せた声音で、ノインの一歩後ろに立つバリードに向かい薄く苦笑。そして一度寝台から身を起こした彼女は、今度は仰向けで改めて寝そべる。
「せめて、その子のお名前くらいは聞かせて欲しいところね。貴方、お名前は?」
「……ノイン・ヴァイヒュントと申します」
薄い笑みを浮かべたまま両肘をついて尋ねる口調は、明らかに小さな子供に対するような声音。ノインは反射的に眉根に皺を寄せつつも、とにかく名を名乗る。その返事に、寝台に寝そべる女は半眼に近い視線をノインの背後へと送った。
「ふ~ん、バドってこういう娘が趣味だったんだ。十年越しで明らかになる衝撃の新事実ってとこね」
ナクルの少しからかいの混じった言葉と視線に、バリードは捲りあげていた天幕を放し、一歩進む。
「……いい加減にしとけ。言っとくが彼女、オマエより年上だぞ? 大体、何が拗ねるわよ、だ。そういうタマかよオマエが。仕事中に尋ねていっても平気な顔しているヤツが」
「あぁら、そういう事言っちゃうわけ? バドの帰るところを用意してあげなきゃって、何年も何年も待っててあげてる私に向かって」
「阿呆か。オレ等が止めるのも聞かずに『ここが気に入ったよー』つって住み始めたのはどこの誰だよ。……大体オレみたいなのがこんなところで落ち着いてどうするよ。ここの連中の用心棒でもやるのか?」
「いいじゃない。過去はこの五王朝の法と秩序、国と民を護る護法騎士にして、現在は場末の娼婦のボディーガード。ははっ、なんだかお姫さまにでもなったみたい」
「あのなぁ。それ以前に舞踏で世界に干渉する『天舞姫』に護衛なんていらんだろうが」
心底呆れかえったように呟くバリード。そんな二人のやり取りを見ていたノインは、ぼんやりと思う。
(こういうのを、蚊帳の外っていうのかしら)
苦笑を浮かべながら二人の会話を傍観していたところに、
「ふ~ん。それじゃ、そこに居るお嬢様には、貴方みたいなのが必要ってことね。いいなぁ~」
「は?」
どこか面白がるような、そしてそれ以外の感情も混じっているような、何とも言い難い視線を唐突に向けられ、ノインは呆気に取られた声をあげて数度眼を瞬かせる。
(ええと……)
どう反応したものかと、視線だけで傍らに立つ灰色髪の青年に問い掛ける。彼はノインとナクルの間で視線を数度彷徨わせ、忙しなく己の髪をかき回した。
「──ああもう、ナクル、ややこしくなることは言うな。ほら、さっさと占ってくれ」
バリードの疲れ切ったような台詞にナクルは笑みを深くし、ひらひらと手を振ってみせた。
「はいはい。なんだか今日は余裕が無いわねぇ。まさか、本気とか? とか?」
「……いいから早くしてくれ」
「判ったわよ。そんなに急かさないで」
言って彼女が寝台の傍に置かれたテーブルの下から取り出したのは巨大な水晶だ。水晶球ではなく、水晶。一抱えほどもある巨大な結晶がそのままの形でテーブルに乗せられた。
「じゃ、始めましょうか」
ナクルは笑顔で告げて、薄布を絡めた両手を水晶へと翳した。
目を覚ました時。部屋は既に夜の帳に包まれていた。
見えるのは月の光差し込む窓辺の際のみで、他は淡い闇に閉ざされている。数度瞬きし、未だ強張っている身体を揉み解しながら貴方は寝台から身を起こした。眠る前にあれほど感じていた全身の痛みは既に無いが、それとは違う種の痛み──つまり、筋肉痛が全身を蝕んでいる。
鈍い痛みに眉を顰めつつ視線を動かすと、小さな小さな影が部屋の窓際の縁に背を預けて座っているのが見えた。両眼を閉じ、首を小さく傾げている姿から見るに、恐らくは眠っているのだろう。初めて会った頃は「眠る妖精」というのは珍しいとも思ったものだが、彼女曰く、そういう妖精も結構居るものらしい。
寝台から立ち上がり、何気なく窓際へと歩み寄る。
──ぢり、と。
身体に穿たれた刻印が疼いた。
しかし、痛みは無い。
右肩に穿たれた刻印を軽く指でなぞると、貴方は安堵の吐息。
リトゥエが一体何をしてくれたのかは判らないが……彼女の力であの痛みが治まったのは確かだろう。今度、礼も兼ねて彼女の好物である果実酒でも振舞ってやるのも良いかもしれない。
「…………」
この小さな妖精が、自分の身体に刻まれた印について何かを知っていて、そして隠している。それくらいは彼女の態度で判る。前に『護法』と戦った時の言葉などを思い起こせば、それは明らかだった。
しかし、それを教えろと無理に詰め寄ったところで、彼女は恐らく答えないだろう。何者かに口止めされているのか、彼女自身が自分に話さぬほうが良いと考えているのかは判らないが、どちらにしろ──
(待つしか、ないか)
彼女が自分からこちらに話してくれるのを待つしかない。
寄りかかり眠る小妖精の頭を指先でつつくと、彼女は眉根を寄せて煩わしげに身じろぎした。
貴方は声も無く笑うと、眠る妖精から視線を外し、窓を見る。
窓越しに映る月はそろそろ真円を描く頃合だ。見上げれば、煌々と白い輝きが夜の空を淡く照らしていた。
ナクルの占いによって出た結果は、
『西の丘に在る星視を求めるべし
その黒き狼の母は
遥か過去に全てを知り
そして関わったが故に
今は傍観者たり得ない』
彼女の言葉に、ノインは首を傾げる。有体に言ってしまえば、さっぱり意味が判らなかったのだ。しかし、隣に立つバリードにとってその言葉は十分に意味あるものであったらしく、彼は唖然とした表情で、寝台の端に座るナクルを見る。

「狼の母……星視だと?」
「お婆さんのことね、これ。あの人、知らないうちにこっちに帰ってきてたんだ……全然気づかなかった」
こちらも驚いた表情で軽く腕を組み、頷くナクル。バリードはがっくりの項垂れて、脱力しきった溜息を吐く。
「──マジかよ。いつの間にこっちに交わってたんだ? なんでナクルやエトエ、キールにレル、そして他の誰も気づかない?」
「無茶言わないで。ここ最近は『現出』のお陰か知らないけど、至る所で小さな『洞』が開きまくってるもの。その全てを把握できる筈無い。それ以前に、あの人の動きを追える人間なんて誰も居やしないわ。今回見つかったのだって、お婆さんじゃなくて貴方達の『縁』を追っていった結果なんだから」
困ったように言うナクルの声に、灰色髪の青年は伏せていた顔を唐突にあげた。
「それだ。なんで婆さんが俺達の運命に交わる? あの人は基本的にこっちには不干渉の筈だろう?」
バリードの問いにソファに座る彼女は片眉を顰めて唇に指をあて、思案するように目線を眼前の小さなテーブルに置かれた大水晶と向ける。
「判らない……けど、『傍観者たり得ない』と出てる。多分、お婆さんは貴方達が絡んでいる事柄について、何か直接的な繋がりがあるんだと思うわ」
「あの婆さんがか? 間接的に繋がっているというのならまだ判るが……あの人が直接的に関わるなんてのはどうも想像できんな」
「それは、確かに私もそう思うんだけど……」
そのまま己の考えに沈み込んでしまったように黙り込む二人。彼等が何を言っているのか判らないノインには口を挟めるわけも無く、暫しの沈黙が部屋を包む。
「まあ、とにかく」
数えて二十呼吸ほど過ぎたあたりで、バリードは灰色髪を軽く掻き揚げて、溜息。
「こちらに婆さんが居るのなら話は早い。あの婆さんがオレ等に手を貸してくれるっていうのなら、何もかも解決だ。あの人が知らない事は無い筈だしな」
「信じるの?」
「知らんが、オマエの水晶は婆さんを探すように言っているのだろう? なら、それを信じるさ」
その答えにナクルは数度目を瞬かせ、
「……うん」
淡い微笑みを浮べ、頷いた。
「じゃあ、決まりだな。ヴァイヒュント嬢、早速そこへ向かうぞ」
その言葉に、眼前で繰り広げられる意味不明の会話を呆と眺めていたノインは、はっと驚いたように振り返り、ナクルは今までの落ち着きようが嘘のような慌てぶりで、がばっと立ち上がる。

「あの、ちょっと待ってください! 私には何がなんだか──」
「え、ま、待って! バド!」
だが、それが聞こえなかったのか、それとも無視したのか。バリードの姿は部屋の戸口から呆気なく消える。
音を立てて閉じた扉を、呆然と眺める二人。
半分立ち上がった姿勢で固まっていたナクルは、そのまま糸が切れた人形のように寝台へと再度座り込むと、神経質そうな仕草で数度髪に手櫛を通す。
「行っちゃった……あの馬鹿、ホントにもう」
顰め面でぶつぶつと毒づく姿はかなり怖い。
(ええと……)
「あの、ナクルさん?」
そんな彼女に、ノインは恐る恐るといった調子で話し掛けた。遠慮がちな声に、虚空を見つめて何事かを呟いていたナクルが動きを止める。
「──ん?」
ノインの方へと視線を移し、小首を傾げるナクル。その表情は酷く静かなもので、感情の色というものが一切浮んでいない。
(さっきの話の解説は──してもらえそうにないなあ……)
能面のような顔で見返され、ノインは口元を引きつらせながら内心呻く。
「あなた……ええと、ヴァイヒュントさんだったかしら?」
問いに、ノインは頷きだけで肯定の意を返すと、ナクルはあっさりと視線を己の目の前にある水晶へと移した。先程まで彼女が持っていたものとは違う雰囲気に、ノインは思わず黙り込んでしまう。
だが、それも数秒。手を伸ばし、水晶を撫でていたナクルが再度口を開いた。
「もうアレ、行っちゃったわよ。ちゃんとついていかないと、本当に置いていかれるわ。アレ、そういう類の人だから」
その声音は酷く気怠るげな調子で、こちらの更なる問い掛けを拒絶するような雰囲気があった。ノインは彼女に先程のことについて尋ねようと暫し迷い、そして浅く頭を振った。
「判りました。では、ここで御暇させていただきます。……あの、ご協力感謝します。ナクルさん」
両の踵を鳴らして、胸に右の拳を軽く当ててみせる。王朝騎士団独特の礼。そしてノインは小走りに部屋から出ていった。
見るからにお人好しといった騎士装束の娘が、部屋の外へと出て行く。同時に、廊下あたりから子供や女達の間から嬌声があがった。黒髪の護法衛士など滅多に見れるものでもないし、本来ならば自分達が傍に近寄れる存在でもない。彼女等が騒ぐのも無理は無かった。
ナクルはその声を聞きながら、深く寝台に身を預ける。見上げた天蓋を染める深い紫に向かって彼女は何気なく手を伸ばすが、当然ながら届かない。ふらふらと左右に揺れた手をぱたりと降ろす。
「あ~あ」
溜息が出た。あれだけ舞い上がっていた気持ちが一気に冷める。
「……何だかホント、体の良い便利屋ね、これじゃ」
視線を虚空に彷徨わせたままナクルは小さく呟く。近頃、独り言が多くなったと自分でも思うが、こればかりは仕方が無い。
「でも──そうね」
こういうのも、悪くないのかもしれない。
少なくとも、彼は自分を頼りにして、ここへやってきてくれたのだから。
ならば自分は満足だ。
彼女はそのまま身体を丸め、柔らかな寝台の中央にまるで猫のような仕草で収まる。そしてこの気持ちを忘れぬよう、両手で己の身体を抱いてゆっくりと両の瞳を閉じた。
花々からの観察者 懇願
──懇願──
「──っ」
肺の中にあった空気が吐き出される。
唐突に襲ってきた、身体全体を鋭い針で突き刺されるような感触に、反射的に息を止める。無意識に身を折った貴方の視界に、身体に刻まれた刻印がほんの一瞬だけ輝くのが見えた。
そして次の瞬間、ゆらり、と。
貴方を包む景色、その片隅に波打つような揺らぎが走った。

「ああ……」
貴方の少し前方に浮んでいたリトゥエが、怯えの混じった声をあげ、身じろぎする。
かなり遠い位置。今貴方が居る場所から一つ山を越えたあたりで生まれた波紋は、ゆっくりとその範囲を広げ、衝撃となって周囲にある様々な存在の概念を揺るがせていく。
『歪の風』。
『現出』が発生する直前に生まれる激しい衝撃波のことを、五王朝の人間はそう呼んでいた。それは不幸を呼ぶ流れであり、不吉の象徴とされる風。この世界を構成する概念の揺らぎから生まれるその波動に晒された者は、己の存在自体がその揺らぎに巻き込まれ、消え去るという危険と立ち向かわなければならない。
揺らぎの走った位置から大地に生える緑が大きく撓んで、歪の風がこちらへと迫ってくるのが判る。
「来るか……」
舌打ち交じりに呟き、身構えたその時。
──ぢり、と。
身体に刻まれた刻印が疼き、そこから生まれた不気味な輝きが貴方の全身を覆い尽くした。視界に奇怪な色の幕が掛かる。
そして間髪入れず、風が来た。
轟音と共に、空が、木々が、大地が揺らぐ。周りに在るすべての存在が風の干渉に悲鳴をあげる。
「い──ったぁ」
風が鳴く音の合間に細い声。傍らで頭を抱えて苦しげに身をよじるリトゥエの姿が見えたが、貴方にはどうしてやることも出来ない。途方も無い力が激しく吹き荒れ、周りにある幾千幾億もの存在を揺らす。すぐ傍に立っていた一本の若木がその力に耐え切れず粉微塵となって砕け、そこに居たという痕跡すら残さずに消え去っていくのが見えた。
十秒、二十秒、三十秒。
六十を数えた辺りで、激しく吹きつけていた風がようやく収まっていく。
「……終わった、の?」
呆然とした調子で呟き、深く息を吐くリトゥエに、貴方は小さく頷きだけ返した。
既に、周りの風景は何事も無かったかのように平穏を取り戻している。しかし、先程の風が生まれた場所には、今まで見たことも無いような奇怪極まりない地形が新たに『現出』している筈だ。
「もう、今日で何回目、だっけ?」
貴方の肩の上に降り立ち、ぐったりと身を横たえるリトゥエの問いに答えず、貴方は『現出』が発生したらしき方向へ視線を向ける。
ここ数日の間で、【NAME】の近くで発生した『現出』の数は両の手では数えきれない程になっていた。明らかに、異常な数だ。
そして、その度に吹き荒れる『歪の風』。
刻印から生まれる力のお陰か、貴方にとってその風はどうというものでも無かったが、共に居るリトゥエにとって『歪の風』との戦いは酷く力を消耗させるものらしく、最近では風に抗するのに力を温存するためか、日の大半を眠って過ごしている。
「私、疲れたからもう休む……」
そう言って、彼女は貴方の背負っていた背嚢の中へと身体を潜り込ませた。
貴方は精根尽き果てたといった調子の小さな妖精が背嚢の中へ姿を消すのを見届けてから、先ほどの風が起こった方角を再度眺める。新たな『現出地形』。本来ならば喜び勇んでそこへ足を向けるのが冒険者というものなのだが。
「…………」
足がふらつき、視界が揺れる。滲んだ汗に湿った衣服のじっとりとした感触が酷く不快だった。リトゥエの入っている背嚢を取り落とさぬよう気をつけながら、おぼつかない足取りで街道を離れ、適当な樹の根元に腰を降ろした。
軽く目を閉じ、息を吐いた後。視線を身体に刻まれた刻印へと移す。
自分の周囲で最近頻繁に発生するようになった『現出』。それが発生する前後には必ずと言って良いほど、この刻印達に輝きが宿る。そして、『現出』後に襲ってくる激しい疲労感は、日に日に強くなっている。
単純に考えれば。
この刻印が、自分の周囲に『現出』を呼び起こしている、もしくは、それを誘発するか同調するような何かが、この刻印にはある。そう考えるのが妥当だろう。
貴方は樹の幹に身を預け、空を見上げる。目に映るのは茂る木葉とその隙間から差す青の空。
「……疲れたな」
思考がまとまらない。身体が睡眠を欲していた。誰に聞かせるでもなく呟くと、貴方は両眼を閉じる。
──眠りは瞬く間に訪れた。
グローエス五王朝テュパン国主領、その南部。南海の沿岸にある海都グラジオラスから暫く内陸へと進むと、柔らかな草が広がる丘陵地帯へと辿りつく。
大地を照らす太陽は西の地平に近い位置。夕暮れの朱色に染まる草原を歩くのは、ノイン・ヴァイヒュントとバリード・ルッツの二人。

「……本当に、こんなところにどなたかいらっしゃるのですか?」

「多分な。あの人がこっちに来ていた時、もっとも長い時間滞在していたのがここだった。『西の丘』ということなら、恐らくこの丘で間違いない、筈だ」
何とも曖昧な返事に、ノインは溜息をつきたくなるのを堪える。
先行して歩く灰色髪の男を、彼女は額に少しの汗を浮かべつつ追う。病み上がりである彼女には、旅の荷物はまだ若干重い。バリードが普段よりも歩を緩めているのが判るだけに、何とはなく悔しい気持ちになる。
暫く、無言のまま歩く。
「バドさん」
「うーん?」
平原の中央にある丘の頂上付近へと辿りついたその時、少し迷いの混じった声が、沈黙を破る。
「そろそろ、話して頂いても構わないと思うのですけど」
「何が」
ノインはそこで少し言葉に詰る。
「色々と、です」
歯切れの悪い返事に、バリードは小指で軽くこめかみを掻く。
「判るような判らんような……そうだな、これから会う人のことくらいは、言っておいたほうが良いかもな」
バリードは歩みを止めず、振り返らぬまま話を続ける。なだらかな丘の頂上を目指し歩く彼の背を見上げながら、ノインもついて歩いていく。
「『星視』というお婆さん、でしたか?」
「ああ」
オルノルンの元娼館での会話、それを思い出しつつ問うたノインに、短い返答。
あの時出会った美しい女性ナクルと、眼前を歩くバリードが話していた内容はノインにとっては殆ど意味の判らぬものだった。故に、ノインはその時の言葉一つ一つを忘れぬよう努めていた。先程の『星視』もその一つだ。
「星視ってのは、まあ、オレと──この前会ったナクルとかを育ててくれた、言ってみれば、養母みたいな人だ。あの婆さん、そのころ人を飼うのに凝っていたらしくて、世界中を旅しながら、目についた子供を適当に拾っては育てていたらしい」
「は?」
予想外の返答に、彼女は片眉を上げて立ち止まる。
「何だかそれって、人攫いみたいに聞こえるのですけど……」
「みたいじゃなくて、人攫いだったんだよ」
言って、くつくつと笑ってみせる青年を、唖然とした表情で見据えるノイン。人攫いに育てられた『護法』など聞いたことも無い。
しかし彼女のそんな反応など、灰色髪の男は気にした風も無い。軽く笑うと、さくさくと音を立てながら夕暮れの色に染まった平原を歩いていく。
「そうだな。善人か悪人かは置いておくとして、まあ、あまり常識が通用しない人だったのは確かだったな。……そういえば、本当に『人』かどうかもよく知らん。見かけは確かに人なんだが、十年以上一緒に居ても一向に外見が変わらなかったし。会って驚くなよ?」
「は、はあ……」
一体どういう人間なのか想像もつかなかったが、ノインは取り敢えず頷いてみせる。何だか、聞けば聞くほど良く判らない。
その時、爽、と。
朱に輝く草原に、一陣の風が吹いた。
そしてその風と共に、高い音域を持つ軽やかな声が響く。

「勝手なことを言うでないわ、バリード」
同時に、ノインとバリードが立っている場所から十数メートル程離れた丘の頂上に、高さ四メートル以上もある大岩が、何も無い空間から染み出すように現れた。
「相変わらず、口の悪さは直っていないようだな、貴様は」
声は大岩の頂点部から響いてくる。その声音に似合わぬ堅い言葉遣い。声の主を追ってそちらを見上げたノインの眼に映ったのは──
(子供……?)
己の身の丈ほどもある大きな杖を携えた、年の頃は九つ程度の少女。本来は紫である長衣と、長く編まれた髪が日没近い陽光に照らされて明るい赤へと色を変えている。
ノインの視線を追い、バリードがそちらへと顔を向けて、露骨に表情を歪めて舌打ち。
「……出やがったな、婆さん。ずっと盗み聞きしてたのか?」
嫌そうな声をあげるバリードに、彼女も眉を顰め言葉を返す。
「人を化け物みたく言うでないわ。親不孝者が」
「親ッ面するなよ。……でも、久しぶりだな」
笑いかけるバリードに、その少女は目を細めて頷いた。
「貴様の変わりようを見る限りでは、どうやらそのようだな」
呆然と大岩の上に座る少女を見上げていたノインが、傍らに立つバリードに小声で尋ねる。
「バドさん、もしかしてあの子が『星視』、ですか?」
対するバリードは小さく頷くだけ。呆気に取られた表情はそのまま、ノインは再度、岩上の少女へと視線を戻す。傾いた陽の光を浴びて赤く染まる岩に腰掛けてこちらを見下ろしていた彼女は、手に持つ杖をゆっくりと横に振る。それにあわせて、彼女の小柄な身体があっさりと空中に浮かび上がり、そのまま草原の上で音も無く停止する。
ついで、朱色の大きな瞳がノインの姿を捉えた。威圧するでもなく、ただこちらを見ているだけ。しかし、ノインはその朱色の瞳と視線を合わせただけであっさりと射竦められてしまった。
動けずにいるノインに、少女はゆっくりと話し掛ける。
「初見だな、娘。儂は『星を視る者』マレーネ・ウレフ。そこの馬鹿の親代わりだ」
更に理解し難い言葉が出てきた。
「……親代わり? 貴方が?」
「一応はな」
鷹揚に頷く少女。
ノインは唖然として草原に浮ぶ彼女を上から下へと眺める。その姿はどこをどうみても小さな子供のものだ。対してバリードは完全な成人男性。俄かに信じられるものではない。だが、その少女が生み出す雰囲気は明らかに老成し、長い年月を経て熟練されたもののそれだ。
「まあ、お互いの紹介は置いといて、だ」
そこへ、取り繕うようにバリードが口を挟む。
「婆さん。アンタならこちらのお嬢さんのことも、オレらが来た理由も、判ってるだろう? さぁ、教えてくれ」
単刀直入に告げるバリードに、マレーネと名乗った少女も短い言葉で答える。
「判らん」
「は?」
灰色髪の男は、素っ気無い少女の返答に間の抜けた声を返す。
「貴様等個人のことなど、儂が知っておるわけなかろうが」
「いや、だが、昔は──」
「あれは貴様等の思考を読んでいただけだ。今と違って、考えていることが素直に表に出ていたからな。特にバリード、貴様はな。キールやエトは早々に心を隠す術を覚えていたが」
「────」
ぱくぱくと口を動かすバリードに彼女は薄く微笑みながら、言葉を続けた。
「心を開けば、今でも読める。喋るのが面倒ならばそれで済ませろ、バリード。そこの娘もな」
遠くから獣が吼える声が響き、暗く澄んで褪めた空気をほんの一瞬だけ目覚めさせ、そして消える。
街道外れの森の中。周囲を埋めるのは夜の概念を秘めた闇と、それを照らし退ける炎の赤い光。樹齢十年程度と思われる若木に背を預けた貴方は、夜が深ける前に掻き集めておいた枝の小山から数本抜き取ると、少し離れた場所で燃え続ける炎の中へと放り込む。その拍子に炎が弾け、木々が小さく裂ける音が辺りに響いた。

「ねぇ、【NAME】」
唐突に呼びかけられた。何とはなしに見つめていた炎の揺らめきから視線を外し、その近くで小さく足を抱えて座っていた妖精の影へと移す。炎の朱色に照らされたその瞳は、先ほどの貴方のように目の前にある紅の揺らぎをただ追っているだけ。まるでこちらに意識が向いているようには見えないのだが、先刻の声は確かに彼女のものだった。
暫く訝しげにそちらを眺め、彼女の動きが無いことに「空耳だったのか」と首を小さく傾げた後、また焚火に枝を投げ込もうと枝の山に手を伸ばした時。
「話、があるんだけど……いい?」
そこでようやく、小妖精の瞳がこちらを捉える。昔のような真っ直ぐなものではなく、最近良く見せるようになった、どこか一歩退いた視線。貴方はそんな妖精を薄目で見返す。
「え、ええと、どういえばいいのかな」
こちらの視線を感じて、決心──それがどういう決心かは知らないが──が鈍ったのか。戸惑ったような声で顔を伏せ、思い直したように数度横に振ると、またこちらへ顔を上げる。
「その、貴方の身体にある……刻印のこと」
(やっと、か)
彼女のその言葉に、貴方は深々と息を吐く。
「え。なに、どうしたの……?」
そんな貴方の様子に小妖精は驚いたような表情。しかし、こちらにしてみればどうしたもこうしたも無かった。今の今まで我慢して、リトゥエ自身の口から彼女が知っている事を話してくれるのを待っていた身にもなって欲しい。そう彼女に告げる。
「あ……やっぱり、バレてた?」
あれだけ何か隠している風な態度をとっていれば、嫌でも何か知っているらしいことは判る。ウスタールの街道で『護法』と戦った時の例などをあげて、懇切丁寧に説明してやると、少し離れた位置からこちらを見上げる妖精の顔にはどこか引きつった笑み。
とにかく、漸くそちらが話してくれる気になったのなら話は早い。リトゥエに矢継ぎ早に尋ねる。刻印のこと、あの化け物のこと、そして『護法』のこと。しかし、返ってきた言葉は──
「──ごめん。言えないの」
流石に、苛立ってきた。
だが、彼女はこちらが癇癪を起こす前に、更に言葉を継いでいく。
「でもね、【NAME】。今の私は、貴方に何も教えることはできないけれど……忠告なら、できる」
そして、彼女はこちらを真っ直ぐに見据え、告げた。
「はっきり言うよ。貴方、これ以上あの印を持つ化け物達を倒せば、いつか死んじゃう」
その言葉に、リトゥエに詰め寄ろうと半ば腰を浮かしていた貴方の動きが止まる。
「もう、ダメなの……。貴方の身体に刻印が増えるごとに、位相と繋がる力は強まってく。今は私の力でその干渉を抑えてるけど、もう限界なの。このままじゃ、貴方の存在はあちらの世界に、位相の概念に侵されて崩れちゃう。だから、貴方の刻印があの化け物──『位相守護者』達の気配を感じても近づいちゃダメ。貴方も判ってるんでしょ? 自分の身体のこと。もうこれ以上は持たない、私の象形だけじゃ、これ以上抑え切れないよ」
言って、どこか虚ろな表情のまま、彼女は貴方に己の掌を広げてみせる。そこには淡い輝きを宿す複雑な形状の紋様──俗にいう『象形』が刻まれていた。それが彼女の言う、自分の刻印の干渉を押さえ込んでいる力なのだろう。
彼女の瞳と掌へと交互に視線を送って、戸惑った表情を浮かべる貴方に、リトゥエは喉の奥からどこか自嘲気味の声を立てて笑う。
「ホントはさ、貴方にこんなこと言うのもダメなんだよ? でも、でもさ、今まで【NAME】と旅してきて、色々あって、タイヘンなこととか一杯あったけど、楽しいことも一杯あって……だから」
声を紡ぐごとに彼女の声が細くなり、浮んでいた笑みが色を失っていく。
「だからお願い。もう『位相守護者』達に関わらないで」
酷く真剣な表情で見つめられ、貴方は心底困り果てた表情で視線を彷徨わせ──取り敢えず、頷いてやる。
「……ありがと」
それを見て、彼女は心底嬉しそうな表情を浮べ、笑った。殆ど場繋ぎ的に返答した貴方の心に、その笑顔が小さな棘となって突き刺さるが、今更取り消すわけにもいかない。
思わず視線を逸らした貴方を追うように、彼女の小さな身体がふわりと浮かび上がり、貴方のすぐ眼の前で止まる。細い両腕が貴方の頬に伸びて、ほんの少しだけ触れた。
「【NAME】……『位相守護者』の刻印に惹かれても、私の言ったこと、忘れないで」

「なるほどな。貴様等の事情は判ったが」
マレーネは小さく呟くと、音も無く空中を滑り、ノインとバリードに背を向けて黙り込む。

(ええと……)
その仕草が黙考なのか単なる拒絶なのかが判らず、ノインは反応に迷って困ったように傍らに立つ青年を見る。青年の方はと言えば、そんなノインの視線に気づく様子もなく、真っ直ぐに栗毛の少女を見据えていた。

「婆さんがこっちの出来事に大きく干渉するつもりが無いってのは知ってる。だが、ナクルはアンタのところへ向かえと、そう言ったんだ」
「…………」
バリードは背を向ける少女に話し掛けるが、それでも彼女は無言のまま。しかし、彼は気にした様子も無く言葉を続ける。
「アンタなら判ってるんだろう? 『虹色の夜』から続く、この五王朝の異変も、そしてあの『位相守護者』の正体ってのも。オレ達に力を貸してくれ、婆さん」
暫くの沈黙のあと、彼女は小さく溜息。
「正直、気が進まぬが……確かに、その刻印相手ならば、儂が出ぬ訳にもいかんか」
言ってようやくノイン達の方へと振り返る。その言葉にバリードはあからさまに安堵の表情を浮かべた。
「助かる」
彼が小さく言うと、マレーネは薄く微笑み、手に持った杖をくるりと転がす。
「……さて。貴様等の目的は、『刻印者』を討つこと、だったか?」
「そのつもりだったんだが。やはり、オレ達では無理か?」
問う灰色髪の青年に、少女は少し考え込むような仕草。
「いや、可能だ。貴様等の言う『刻印者』とは、つまり『位相守護者』の紛い物だ。相のズレを無視できる程の力を持つ攻撃を撃ちこめば、倒せなくもない。だが、あの類の象形刻印は触媒となる概念が消えれば、近くにある別の概念に寄生する。そしてそれを新たなる『刻印者』とし、上手く融合すれば位相の概念を自在に操る『位相守護者』となる。堂々巡り。倒したところで無駄だ」
「……つまり、オレ達がそいつを倒せば、今度はこっちに刻印が乗り移ってくるってことか?」
「そうだ。それに、あの刻印自体は単なる位相差を埋めるモノでしかない。元を断たなければ根本的な解決にはならんだろうよ」
少女の言葉に、ノインは戸惑ったように頬に手を当てる。
「元、と言われましても……」
そんなもの、欠片も心当たりが無い。だが、暫し己の記憶を遡った彼女は、はたと思いつく。
「そういえば、ナクルさんが言ってました。貴方は、過去に全てを知り、そして関わったと。あの『刻印者』と貴方は……何か関係があるのですか?」
「いや。無い」
「──え?」
素っ気無い返事に、ノインとバリードが同時に固まる。
「どういう意味だ? ナクルが占い損ねたって言いたいのか? アンタ直伝の占術を操るアイツが」
バリードはそこまで言ってから髪を数度掻き回し、普段の彼には珍しい真剣な表情で草原に浮ぶ少女へと問い掛ける。
「婆さん。できれば、もう少し詳しく話してもらえると助かるんだがな。端役は端役なりに、自分達が関わる事件の真相くらいは知っておきたいんだ」
「答えを急ぐな、バリード。儂は『刻印者』ともニルフィエ達とも全く……とは言えんが、係わり合いになってはおらん。元々、我等と地母共とは折り合いが悪い故な」
「なら──」
「貴様等が見た印に覚えがある。あの象形は確か……マウローゼに積まれていたもの、儂が考案し、あやつの創造主に提供した象形の亜流だ」
「マウ、ローゼ?」
鸚鵡返しに答えるノインに、少女は淡々とした調子で話し始める。
「架空・仮想事象発現管理構造体。遥か昔、我等がこの概念世界を己が家としていた時に作り出した玩具の箱庭。有り得ざる概念を具象し、それを楽しむ世界。マウローゼ系と呼ばれる構造体群。今、この概念世界に『洞』を開き、己が構造に格納された架空概念を呼び込んでいるのはそれの仕業だ。もっとも、やり方が杜撰すぎて、『奈落』や他の概念世界すらも巻き込んでいるようだがな」
「……どういうことです?」
ノインは眉を顰めて、傍らのバリードへと視線を送る。しかし、彼女の問いに男は小さく手を挙げて肩を竦めるだけ。仕方なく、ノインは疑問の視線をバリードから目の前に浮ぶ赤眼の少女へと移した。彼女はノインと、そしてバリードの無言の問いを受けて、手に持った杖をゆっくりとした動きで持ち替えたあと、ようやく口を開いた。
「古い話だ。貴様等が『芯なる時代』と呼ぶあの頃、我等は『奈落』の覇者である『外なる者共』につけ狙われておった。我等は己の故郷が奴等に汚されるのを嫌い、我等が居たという痕跡となるものを消し去り、この概念世界を去った。この世界に我等の遺産が殆ど残っていないのはその為だ。しかし、幾つかは崩滅させる余裕無く、そのまま残され、放置されたものがあった。内の一つが、そのマウローゼだ」
彼女は両眼を閉じたまま語り続ける。南の方角から絶え間なく吹く緩やかな風に煽られ、栗毛色の前髪が揺れている。
「残された遺産は、外なる者等を刺激せぬように我等の手で厳重に封じ、その封印の管理は貴様等、偽りの子等に任せたのだ。架空・仮想事象発現管理構造体は、今、貴様等が言うグローエス王家の祖先にあたる者に、その管理を任せた。だが……」
「その封印が……破れた?」
思わず出たノインの言葉に、マレーネは片眼を薄く開き、彼女を睨む。強い朱色に射竦められ、ノインは小さく身じろぎ。
「封が破れた程度ではこうはならん。恐らくは封が破れた上に、架空・仮想事象発現管理構造体自体が狂っておったのだろう。我等があの位相世界に配した『管理代行者』がな。マウローゼ達はその中枢管理体のデリケートさ故に欠陥品と呼ばれ、我等が去る以前から半ば放棄されていたシステムだからな」
「つまり、そのマウローゼって奴がオレ等の世界を滅茶苦茶にしているってわけか?」
「要約しすぎだが、強ち間違っているというわけではない。マウローゼとは様々な地形等の概念を圧縮し格納した、現世界とは異相となる世界。それ自体は本来無害な筈ではあるのだが──先程言ったように、管理代行者がその力を振るい、この世界に干渉しておるお陰で、今のような状況が生まれているわけだ」
なるほどな、と呟いたあと、何か気になることでも思いついたのか、バリードは眉根を寄せ首を傾げる。
「? そのマウローゼというのは、元々こんな事をするものだったのか?」
「狂っている、と言ったろう? 管理代行者は……確か賢人の改良種だったか。あの者達は決められたことをこなす象形という程度の存在では無く、自律した思考を持っている。だが、今回はそれが仇となったようだ」
どう言えば良いのか。既に自分の理解の範疇を超えている。
ノインは助けを求めるように傍らのバリードを見るが、彼も似たような調子らしく、まるで頭痛に耐えるように片手でこめかみを押さえている。
何とか混乱している頭を静めようとする。マウローゼ、管理代行者。それは取り敢えず後だ。自分が知りたいことは何だったのか。それを懸命に思い出す。
「では、結局、『位相守護者』や『刻印者』とは何なのです?」
問うたノインに、少女は間髪入れず答える。
「貴様等の言う守護者とは、この現世界とマウローゼが管理する位相世界とを繋ぐ道標を内に宿した者達だ。マウローゼには我等が術式の粋を尽くして作り上げた象形が幾つか載っておるからな。恐らくはそれに手を加えて、己が世界にある強い概念を持つ者に刻み、この概念世界へ送り込んだのだろう。それが『位相守護者』と『位相刻印』だ。貴様等が見た『刻印者』の力は、マウローゼが管理する構造体に収められた概念がこちらへ現出したものであろう。恐らくは管理代行者が『刻印者』に過度の接触を試みた結果、暴走したのだろう」
「『位相守護者』の持っていた刻印が、五王朝に『現出』を促す原因であると。そういうこと、ですか?」
マレーネの言葉をゆっくりと咀嚼しつつ、纏め、それを確かめるように尋ねるノインに、栗毛の少女は若干不満げな表情を浮かべつつも頷く。
「正確には違うが、そう理解しても問題はあるまい。推測の域をでんが、『管理代行者』は己が管理する位相の概念を全てこちらの概念世界へと送り込み、世界を一とするつもりなのだろう。何故そんなことをしようとしているのかは判らぬがな」
「つまり、その何たら構造体って所に居る『管理代行者』ってのを倒さなければ全ての解決にはならんと、そういうことか、婆さん?」
バリードの問いに、少女は小さく頷いてみせる。
「そんなところだ。そして、儂自身がそれの製造に関わっていた訳ではないが──今この世界に交わる『芯なる者』の一人として、己が同族が残した歪、それを正せと、星は言っておるのだろうな」
(……同族?)
どこか遠くを見据えつつ呟かれた言葉に、ノインは驚きの表情で固まる。
古の時を生き、この概念世界に存在する様々な芯属の頂点に立ち、一時はこの世界の全てを手中に収め、そして唐突に何処かへと去った伝説の種族、芯なる者。今、彼女の眼の前に浮ぶ少女は、自分がその『芯なる者』の一人であると、そう言ったのだ。
「ま、待ってください! 貴女、本当に──」
しかし、勢い込んで尋ねようとするノインを遮るかのように、栗毛の少女は音も無く空中を滑り、こちらに背を向けて告げる。
「暫し間を置こう。貴様等も疲れたであろう。ここで休んでいくが良い」
「でも、まだ話は……」
「それ以前に、こんな草原のど真ん中でどう休めっていうんだ?」
同時に不満の声をあげるノインとバリードに、彼女は少し気分を害したのか、輝く朱眼を細めて険のある声を二人に返す。
「何を言うか。この丘は現世界の中ではもっとも心休まる場所だぞ? 夜の訪れを待つがいい。今はまだ太陽が世界を照らす時分だ。星の声も翳み、道も揺らぐ。月が踊る時分になれば、道は確かに、星々の心も強く輝く。儂は、我等の行く末をもう少し見定めてくる。暫しの間、この丘で待っておれ」
強く強く、想う。
暖かく懐かしいあの頃のように、『皆』と手を取り、共に踊りたい、と。
そうして強く纏め上げた意思に、私の世界を形作る要素を乗せて。
『皆』の世界に開く亀裂目掛けて、一息に放つ。
私の指先から放たれた意識の槍は、世界の狭間に横たわる『奈落』を駆け、
世界と世界が混じる道、小さく開いた世界の『洞』に飛び込み、
そして刻印を介して、『皆』の居る世界へと送り込まれる。
『皆』の世界が小さく撓み、私の世界がゆっくりと交じり合う。
二つの世界の相が、徐々に近づいていく。
だけど、『皆』の世界と私の世界とを繋ぐ道は不確かで、
『皆』の世界へと送り込んだ刻印の意識も、欠片しか感じられない。
注いだ幾つかの概念が零れ、『奈落』に飲まれて消えていく。
誰かが、私の邪魔をしている。
刻印の輝きを揺るがせる何かが、彼等の近くに居るのだ。
私の心とはっきりと繋がっている印は、もう三つしか残っていない。
このままではいけない。それだけは判る。
でも、どうすれば良いのだろう。
──そうだ。
もし、最後の印の声が途絶えてしまったならば。
私は持てる力の全てを使い、『皆』の居る世界へ、護りの竜を送ろう。
彼ならば、私の眼となり、手足となってくれる。
彼の力さえあれば、途切れた印をもう一度繋ぐことなど、容易いこと。
彼がこの世界から居なくなってしまえば、
私は本当にひとりぼっちになってしまうけれど、
それでも私は、『皆』が暮らす世界をはっきりと感じたい。
そう、それははじめて見る世界。
生まれてから、延々とこの世界で『皆』の訪れを待っていた私にとって。
そう、それははじめて知る世界。
待っていてください、ファア。
私はもうすぐ、貴方の元へと参ります。
花々からの観察者 月下
──月下──
今宵は満月。宿の窓辺に椅子を置き、白く輝く月を眺める。窓枠に肘をつき、淡い藍色の天蓋を見上げつつ、ぼんやりと昼間のことを思い出す。
脳裏に浮ぶのは、殆ど半泣きの表情で約束を破ったことをぎゃんぎゃんと責めながら、つききりで刻印の侵食を抑えてくれた小さな妖精の姿。
無言のまま、室内へと視線を送る。しかし、夜の闇に包まれた部屋にリトゥエの姿は無い。満月の夜は月光浴に出るのが、彼女の習慣だった。それはこちらの治療で心身ともに疲弊しきっていたとしても、欠かすことはできないものらしい。
小さく息を吐くと、己の身体へ視線を移す。
刻まれた印はこれで十を数える。刻印の疼きや痛み、そして周りで起きる様々な異変にもすっかり慣れてしまい、もう何が起きても驚かなくなってしまったような気がする。
貴方は何を考えるでもなく、ぼぅ、と空を見上げる。
周囲を流れる時間は、酷く静かだ。
──何となく判る。
今は休息の時なのだと。
いずれ、自分は身体に刻まれた刻印と真っ直ぐに向き合わなければならない時が来る。その戦いに敗れれば、恐らく自分の命は無いだろう。今はその時の為の力を養う時だ。
両眼を閉じ、暫し背もたれに己の体重を預けた後、一呼吸。
(…………)
そして貴方は椅子から立ち上がり、眠りにつくため、寝台の上へと身を移した。
太陽は地平の彼方へと沈み、今は白く澄んだ色彩を纏う真円の月が、空と大地を統べる時。
丘陵の外れ、踝程度の草が茂る場所に一枚の厚布を敷き、そこに腰を降ろして既に一時間。深い藍色の染め上げられた護法師士の装束を身に纏った黒髪の娘、ノイン・ヴァイヒュントは飽きる事無く夜空を眺めている。
心を空にして、何も考えることなく、ただ満天に輝く星空を見上げる。満月の輝きと、そして星達の煌きが合わさり、空は夜とは思えぬほどの光に満ちていた。
こんな風にゆっくりとした時を過ごしたのは久方ぶりだった。
そういえば、前にこうして夜空を眺めたのはいつだっただろう?
ノインは瞳を閉じて、己の記憶を探る。
思い起こされるのは、質実剛健を絵に描いたような古い屋敷の一室と、今は亡き母の面影。
ほぅ、と空へ細く息を吐いた。
振り切るように、懐かしむように、心の中を通り過ぎていく色褪せた記憶を楽しむ。

「そういえば、お母様に幾つか星座を教えてもらった記憶があるのだけど……」
独りごちて、瞬く星々に目を向けてみるが、彼女が覚えているような星の並びは一向に見当たらない。というよりも、視力があまり良いとはいえない彼女にとって、星空というものは何を見るでもなしに眺めるには丁度良いが、何か一つの物に焦点を合わせようとすると途端に滲み、ぼやけてしまう。これでは見つかるものも見つからない。こういう時、眼が悪いというのはつくづく損だと思い知らされる。
(あの星の形は、確か猫座だったかしら。それとも山猫座だったかしら?)
他人から見れば至極どうでも良いことで、形の良い眉を寄せ、首を傾げていたところに、背後から人の気配。
気配の主が一体誰なのかは、見ずとも判る。
「綺麗なものですね」
ノインは含むように笑うと、空を見上げたまま、振り向く事無く背中ごしに話し掛ける。

「……まあ、確かにな」
ざっ、と。靴裏が土を噛む音が彼女のすぐ傍で止まり、同僚であるバリード・ルッツの声が返ってくる。
「あの婆さんは、どの概念世界に渡っても、ここみたいに星が良く見える場所でしか暮らさないって言ってたな、そういえば」
そこで声は途切れ、草と靴、そして土が擦れあう音が数回。闇と微細な光点に包まれていたノインの視界の隅に、灰色髪の青年の後ろ姿が映った。
「そういえば、マレーネさんは今どこに?」
ノインの問いに、灰色髪の男は半眼のまま上を、空の方向を指差してみせた。
どうやら、空の上という意味らしい。
「まったく、芯属ってのは便利なものだよな。空を飛ぶなんざお手の物らしい」
言って、芝居がかった仕草で肩を竦める彼に、ノインは小さく笑う。
そして暫く無言のまま、南海からそよぐ風を聴きながら、ただ空を彩る星々を眺める。
「あの」
「ん?」
「マレーネさんという方、本当に『芯なる者』なのですか?」
遥か古の時代からこの世界に存在する、驚異的な力を秘めた存在。それを芯属と呼ぶ。
その中でも『芯なる者』と呼ばれる芯属達は別格とされていた。
姿形は人間と殆ど変わらぬと彼等だが、内に秘めた力は尋常のものではなく、宙に描く象形一つで空を断ち、大地を裂き、この世のありとあらゆるものの理を操ったと伝えられている。
だが、『芯なる者』はある時を境に、一瞬にしてこの現世界から姿を消した。
以後、様々な歴史研究家が、古代から残された壁画や、彼等が生きた『芯なる時代』を語り継ぐディヒューム、ミスティック種達の話などから、『芯なる者』の消滅の理由を探っているが、未だこれはという話は出てきていない。
あのマレーネと名乗った少女の話したことが事実ならば、自分はその『芯なる者』と直接対面した人間ということになる。
問い掛けと共に見上げるノインの視線の先。護法の服に身を包んだ青年は、片手で顎を撫でつつ、小さく首を傾げてみせる。
「どうだろうな? まあ、実際がどうなのかは知らんが、あの婆さんが『芯なる者』と呼ぶに相応しい力を持っているのは確かだがね。ああも容易く他概念世界へ移動してみせる奴なんて、婆さん以外見たことも聞いたことも無い。というか、あれでも無用な混乱をこっちに呼び込まぬように力を抑えているらしいしな」
「はぁ……」
何とも彼らしいどちらともつかぬ返答に、ノインはつい気の抜けた声を返す。要は、彼自身もあのマレーネという少女のことをあまり良く知らないと、そういう事だろうか。
彼女は小さく息を吐くと、両手を前についてから腰を浮かし、折っていた足を前へと出してから一度伸ばす。そして今度は両の膝を立ててから腕で抱え込むようにし、座り直した。抱え込んだ膝に片頬を乗せて、横目でバリードを見る。
男は傍らに居るノインに気を配るわけでもなく──というより殆ど無視して──のんびりとした様子で立ち、浅く顎を上げて夜空を見上げている。
「あの、バドさん」
「んー?」
何気なく声を掛けると、顔と視線はそのままに、声だけがノインに向かって返ってくる。
「私達、こんなにゆっくりしていて良いのでしょうか? 私達がこうしている間にも──」
そこまで言ったところで、口を噤む。
先程から、なるべく考えるのを止めよう止めようと努めていたのだが、バリードの姿を一目見ただけで、すぐに目の前の現実に引き戻されてしまった。
あの栗毛の少女が語った、色々なこと。
マウローゼと呼ばれる存在と、それが統べる位相の世界。それを繋ぐ刻印と、位相守護者。そしてニルフィエと『刻印者』。あそこまで聞かされて、焦るなというほうがどうかしている。
だが、返ってきた言葉はノインにとってひどく意外なものだった。
「焦ったところで仕方ないさ。事態はそれほど切迫しているわけでもないしな」
「──え?」
己の膝に持たれかけていた顔をあげて数度瞼を瞬かせると、暢気な様子で空を眺めているバリードを見る。
「切迫して、ないんですか? この状況で」
「んー? んん、まあ、今回のことは少々異常ではあるが、この程度のことならば、オレだって今まで何度か関わったこともある。キミも『護法』ならば判るだろう?」
そこでようやっと、青年の視線がこちらに向けられる。
ノインはその視線を避けるように顔を俯かせると、ぽそりと答えた。
「……良く判りません。私、『護法』としての活動はあまり行ったことがありませんから」
何処かしら拗ねたような声音で呟かれた言葉に、青年は酷く納得したような声をあげて数度頷く。
「だろうな。言われてみれば確かにそんな感じだ」
その返答に、顔を伏せていたノインは反射的に顔を上げ、きっ、とバリードを睨んでみせる。
「なんだか、嫌な言い方」
呟き、また、つい、と視線を逸らす彼女に、バリードは肩を竦めて苦笑する。
「ま、仕方ないさ。『護法』への勅命は基本的に適材適所、『護法』個人の適性に重きを置いて下るからな。中には『護法』になって半年経っても全然勅命が来なかった奴も居たしな。そいつは今でも仲間内では良い笑いモノに──」
「…………」
「どうした?」
フォローの台詞を入れている筈が、草原に腰を降ろす黒髪の娘が明らかに困惑した表情でこちらを見上げてくるのに気づいて、彼は訝しげに問う。
その言葉を受けて、ノインはどこか迷うような色を己の黒瞳に宿らせてから、やはり少し戸惑ったような調子で尋ね返してきた。
「あの、バドさん。普通、『護法』になってからどの程度の間隔で勅命が下るものなのですか?」
「? それがどうしたという気もするが……あー、っと……大体は『護法』襲名から一月以内には大抵一つの仕事を任されて、そこからは適性によるが大体二月に一度程度だろう。オレは売れっ子でね、もう少し間隔が短い。さっきの半年っていうのは酷く特殊な例だ」
バリードの返事に、ノインはがっくりと肩を落す。
「私の時は一年でした。正確には、一年と二十二日」
ひゅう、と。
その言葉に合わせるように、南海から寒々しい風が彼等の間を吹き抜けた。
「あー」
「…………」
暫し無言。
草原に座る影はただ顔を伏せて落ち込み、傍らに立つ影は困ったように数度己の髪を掻き回すと、嘆息。
「悪い」
「──いえ、構いません。自分に『護法』としての適性が無いのは、何となく判っていましたから」
「ふむ」
自虐気味に言い放った言葉に奇妙な相槌で返され、彼女は訝しげに再度青年の方を見上げ、尋ねる。
「? 何です?」
「いや、意外と正しい自己評価ができているんだな、キミは」
片眼を細め、にやにやと笑う青年に、ノインは呆気に取られた表情を浮べ、そして見ようによっては泣き笑いとも取れるような複雑な笑み。
「少しくらい、慰めてもくれても良いと思うのですけど」
困りきったような声に、バリードは両眼を閉じて薄く笑みを浮かべつつ、淡々と答える。
「事実だからな。『護法』ってのは際立った力や知識、そして王朝への忠誠心などがその選出の条件だが、いざ『護法』となってモノを云うのは、その力をどう活用し事件を解決させるかという思考の柔軟性だ。キミの『ソルモニアル』は強力だが使いどころが難しいし、頭の方もひどく硬そうだったしな」
容赦の無い彼の言葉に反撥する気力も湧かないのか、ノインは立てていた己の両膝に、こてん、と頬を乗せる。
「……普通、そういうことって本人を目の前にすると言い辛い事ではありません?」
「これでも控えめのつもりだぜ? 大体、キミみたいな家柄の女性が『護法』を目指すなんて聞いたことも無い。ヴァイヒュント家の、王領伯爵家の令嬢ならば剣や術式を学ばずとも何不自由無く暮らせたろうに」
そこでバリードは言葉を切り、はて、と首を傾げる。
「……前から思っていたんだが、何故キミはこんな危険な職についてるんだ?」
不思議そうな声に、ノインはふと顔をあげ、きょとんとした表情で青年の顔を見る。そして次に見せたのが、心底戸惑ったような顔。
「ええと」
そして意味の無い声をあげつつ、忙しなく視線を泳がせてみせる。
訝しげにこちらを見下ろすバリードの視線に気づいて、黒髪の娘は照れたように薄く笑って、灰色髪の青年の顔から視線を外したまま口を開く。
「バドさんって、あまりテュパンの宮廷の方には出入りされていないんですね」
突拍子も無い言葉に、青年の眉根が更に寄せられる。
「? まあ、元は流れの人間だし、任務以外では近づかんが……何故だ?」
「宮廷の方では知られた話なんですけれど」
そう前置きして、彼女は抱えていた膝を離して、両掌をすっと前に伸ばした。
「私、本当はヴァイヒュント家の人間ではないんです。一応はお父様の、ドゥヒス・ヴァイヒュント伯爵の血を引いてはいますけれど、夫人のセレーニャ様の子ではなくて、家についていた異国の召喚師の娘なんです。ですから、『貴族の女』としては生きていけないんですよ、私は」
そのまま十指を組んで、ぐっと身体を伸ばしながら、彼女は何気ない風に言ってのける。
今度は、バリードが目を丸くする番だった。
「ほら、この髪」
固まってしまったバリードを気にした様子も──少なくとも表向きは──なく、彼女は組んでいた掌を解くと、己の黒髪を手櫛で梳いてみせる。
「この髪は母譲りなんです。お父様とセレーニャ様。二人とも髪は綺麗な金色。私の二人の姉もそうなんですよ」
それだけで、テュパンの社交界における彼女の扱いは容易に想像できた。
(……前に、晩餐会は断ると言っていたのは、そういう理由か)
バリードは己の迂闊さに数度舌打ちする。
「済まん。詮無いことを訊いた」
「構いません。知られて困るようなことでもありませんし」
くすくすと、鈴を転がすような軽々とした声音で笑うノイン。そんな彼女を眺めていたバリードが、思いついたように口を開いた。
「じゃあ、キミの『ソルモニアル』はその実の母親から、か?」
問いに、黒髪の娘は笑いを押さえ、頷く。
「ええ。剣都アサーン、ご存知ですか?」
知らぬ筈も無い。バリードは無言のまま首肯。
アサーンという都は、グローエス領内にあった『都』の規模を持つ大都市──だった。グローエスの首都であるルアムザの北に位置し、ヴォルガンディア闘技場と呼ばれる巨大な施設を都の中央に置いた『剣の都』。
だが、現在アサーンと呼ばれる都はこの五王朝には存在しない。『現出』の影響を受けて壊滅し、遺棄された都として、人々の記憶に残るのみだ。
「私は生まれてから十七の歳になるまで、生みの母と共にそこで暮らしていたんです。その都で私は母から召喚の術と、そして剣を学びました。いずれ、影ながら父の役に立てる時が来ることを夢見て、ね。母の夢もそうでしたから」
「……なるほどな」
ノインは両掌を後ろ手につき、力を込めて腰をあげた。敷いていた布を拾い上げて小さく叩き、埃を払う彼女を眺めながら、バリードはふと思いついた疑問をそのまま口にする。
「だが、貴族として育ってない割に、世間知らずなのはどういう訳だ?」
「お父様の口添えで、都を治める方の館に住まわせてもらっていましたから。母が亡くなってお父様に呼ばれるまで、館の外へ出ることも殆どありませんでしたし」
遠慮の無い問いかけに苦笑しつつ、布を畳んで手荷物を入れた袋に仕舞い込んだ。そしてどこか遠い視線のまま、話し続ける。
「何年か前に母が死んで、その時初めてお父様と会いました。あの人は周囲の反対を押し切って私をヴァイヒュントの家に呼んでくださいました。私は嬉しく思う反面、不安だった。本当にお父様のお役に立てるのかと」
そこで浮かべた苦笑を濃くして、深く息を吸い、吐く。
「テュパンに移ってからは大変でした。ヴァイヒュント家はグローエスに連なる血筋ですので、現国主であるラナーン家よりも家柄には伝統がありますから。義理の母であるセレーニャ様や二人の姉、それに宮廷の方で、色々と言われたものです。混じりの女、下賎な娘とね。私自身は堪えられましたけれど、宮廷ではそんな調子でしたし……到底『貴族の女』として父の役に立つことはできそうにありませんでした。ですから私は、母から受け継いだ召喚の術、そして剣の腕を磨くことにしたんです」
「それで、『護法』か」
「ええ。ヴァイヒュントの家からは、ずっと『護法』が出たことはなかったそうで。お父様はひどく喜んでくださいました。……その代わり、セレーニャ様や姉達の皮肉は一層酷くなりましたけどね」
くすくすとノインは一頻り笑ってみせ、そして深く吐息。ついていた膝を離して立ち上がると、両手を後ろに回して眼を閉じたまま、さくり、さくりと小気味良い音を立てて歩く。
「けれど、いざ『護法』になってみれば、この体たらくですから」
どこかさばさばとした調子で話しながら一歩、一歩と歩き、無言のまま彼女を見ていたバリードの隣で立ち止まると、小さな顎をあげて空へ視線を送る。
「テュパンの騎士としてもあまり優秀な方とは言えませんでしたし。……やっぱり、力や気持ちだけではどうにもならないのかも知れませんね……」
「大丈夫だろう」
殆ど独り言を話しているような気持ちになっていたノインは、間髪入れぬ否定に一瞬眼を白黒させ、声の主である傍らの青年を見上げた。
「?」
疑問の色を乗せて、少なくとも頭二つは高い位置にあるバリードの横顔を見る。そこにあるのは無表情と、片目だけでこちらを見下ろす灰色の眼。
彼女の問いかけの視線を受けて、彼は更に言葉を継ぐ。
「キミに足りないのは、経験だけだ。元々頭の回転自体は速いんだから、物事を判断するための材料となる経験さえ積めば、キミは今居る連中のなかでも一歩抜きん出た『護法』になれる。少なくともその力と気持ちさえ鈍らせなければ、いずれはこのオレより優秀にはなれるさ。保障するよ」
「…………」
絶句し、呆然とした表情を浮かべるノインに、バリードは居心地悪そうに顔を顰める。
「なんだよ」
「──いえ」
そこまで呟いて、ノインは言葉を切った。
口元にやった手の隙間から、嬉しそうな笑みが零れる。暫し顔を伏せたまま、喉の奥だけで声を立ててから、んっ、と小さく咳払い。そして青年を見上げる。
「ようやく、慰めてくれましたね」
にっこりと微笑み呟いた黒髪の娘に、男は更に顔を歪めて舌打ち一つ。
「……初めて会った時から思っていたが、意外と意地が悪いよな、キミは」
「お互い様です」
バリードは無駄に晴れやかな表情の彼女から視線を外すと、誤魔化すように周囲を見渡し、そして空の一点を見上げてその動きを止めた。
「婆さん、帰ってきたみたいだな。──じゃ、行くか、ヴァイヒュント嬢」
「はい」
翳る事無く輝く満月のおかげか、夜を覆う空は比較的淡い色に染まっている。仄かな光に照らされて、薄暗くも柔らかな色合いに染まる緑豊かな山の頂で、紫色の小妖精は一人宙を浮びつつ、白い円を描く月を見上げていた。
空を見る髪と同じ紫の瞳は、まるで満月のその向こう側を見透かすように遠くへと向けられている。実際、彼女は月を見ているわけではない。今、リトゥエは月という存在を介して、彼女の『源流』であるニルフィエの女王、『月夜に咲く女王』と呼ばれる存在と対話していた。
既に、彼女と彼女の『源流』が意識を繋ぎ合せてから半時間が過ぎている。いつもならば数分の定時報告で終わる筈なのに、だ。
彼女等の話は、既に佳境であるようだった。リトゥエは酷く静かな表情のまま、月を見上げ、言葉を継いでいる。

「その時は、私の身体を介して『刻印者』を──【NAME】を、止めてください。ニルフィエを統べる一人である貴女なら、出来る筈です」
《本気なのですか? 『観察者』の器でしかない貴女の存在概念を伝って、私が直接力を振るうには、貴女の存在自体を私と完全に一とする必要があります。それが何を意味するか、判らないわけではないでしょう?》
だが、リトゥエはくすくすと笑うだけ。
「こんなに月が綺麗な夜なのに、己の『分け身』が本気か本気じゃないかくらい、判りませんか? 私は、月夜様のコト、はっきりと判りますけれど」
《……理解できない。何故、貴女はそうも『刻印者』に固執するのですか?》
「判りません? 本当に?」
《…………》
月を介して伝わる気配は困惑。リトゥエは暫し困ったよう眉尻を下げた後、表情を引き締める。
「もう一度言います。私は、『刻印者』を操る気はありません。本当なら、守護者とも戦わせたくはない。でも、【NAME】がそれを望むなら、仕方ないと思ってる」
《──芯なる者の力を振るう位相の存在、それが伸ばした操り糸に『刻印者』の概念が飲まれれば、私達、地母の四女王すら上回る力を持つ『位相守護者』が生まれるかもしれません。それでも、貴女は──》
「うん。私は、この象形の本当の力を【NAME】に使う気はない。なんか、そういうのって嫌だし」
リトゥエはきっぱりと言い切り、笑みさえ浮かべながら、月越しに映る自分の『源流』を真っ直ぐに見据えた。
そして、お互い言葉を発せぬまま、無言の時間が、ゆるゆると過ぎる。
その沈黙を破ったのは、『源流』のほうだった。
《貴女は……》
どこか戸惑いを残した、呻きにも似た声のあと、深く溜息をつく。
《判りました。貴女の願い、聞き入れましょう。『聖域』のことも、私にお任せなさい》
「ごめんなさい、月夜様。あと、それと──」
《何です?》
「自分に素直にならないと、いつか疲れちゃいますよ? これ、貴女の子供からの忠告です」
《……貴女が、素直になりすぎるのです》
心底呆れたような声で返された。リトゥエは少し苦笑しつつも、空に映る『源流』の幻像に向かって呼びかける。
「でも、私はやっぱり貴女の『分け身』なんですから。そのことを、忘れないでください」
それが、彼女の本心だった。
基本的に、『分け身』とは『源流』が持つ要素を継承して生まれる。故に、『分け身』の思考や行動などは、本来『源流』が持っているものである筈なのだから。
暫しの無言のあと、月越しに浅い嘆息の気配。
《──私は、貴女が羨ましいわ》
どこか自嘲の陰り差す苦笑混じりの声と共に、繋がっていた意識が途切れる。月越しに見えていた『源流』の姿が、淡く輝く満月の空に霧散した。
「…………」
リトゥエは両眼を閉じて、空中で仰向けの姿勢になると深く深く息を吸い込み、そして吐いた。緊張で固まっていた身体がゆっくりと解されていく。
「あーあ」
一緒に、声も出た。自分でも判るほどの酷く気の抜けた声に何となく可笑しくなって、闇夜のなか、一人くすくすと笑う。
そして一頻り笑い、その衝動が収まった後、また息を吐いて、空を見る。
「これでもう、後戻りはできなくなっちゃったな」
星を視る丘の中央に置かれた巨岩。その上で、朱眼の芯なる者マレーネと、バリードは会話を続けていた。

「運命が歩む道筋は視えた、が──この事件を司る星の周囲に、貴様等の姿は殆ど見えぬ。この物語の主役は、貴様等が剣を交えた『刻印者』と地母の若き女王」
両眼を閉じ、小さく細い両腕を組んで浮ぶマレーネに、岩の上に立っていたバリードは疑問の表情を浮かべつつ己の首筋を数度撫でる。

「? あいつらが何だって言うんだ? あの『刻印者』は、ニルフィエ共に利用されているだけじゃないのか?」
「いや、彼等は彼等で、己の道を切り開くと。星は、そう言っている」
栗毛の少女と灰色髪の青年。二人の会話を心の中で反芻すると、一つの疑問が浮んだ。
話に割り込むように、ノインが口を開く。

「あの、マレーネさん。ニルフィエ達が何をしようとしているのか、判りますか?」
視線を岩の上に腰を下ろしているノインへと下げ、栗毛の少女は鷹揚に頷く。
「ある程度はな。地母共は『刻印者』の身体に『位相刻印』を全て集め、その段階で『刻印者』ごと存在を封縛するつもりなのだろう。『位相守護者』と同種の刻印を持つ『刻印者』ならば、通常の人間やニルフィエ達よりも相が近い故に、守護者を打ち倒すことも容易だ。全て集まったところで強力な結界で閉じ込めてしまえば、刻印を介して『現出』を起こすことも出来まい。ニルフィエ共は、少なくとも現世界上では我等をも上回る力を誇るしな」
「……でも、『刻印者』に印が集まれば、それだけ『刻印者』の力が強大に、そして封じるのが難しくなるのではありませんか?」
「いや、前もって『刻印者』の身体に仕掛けを施しておけばそう難しいことではない。貴様等の記憶にあった女王の眷属が、それを行う役目を持っていたのだろう」
「なるほどな」
少女の説明に、得心いったようにバリードは頷く。
「つまり、『刻印者』はニルフィエ共が仕掛けた、『位相刻印』を封じるための生贄であると、そういうことか。……あの『刻印者』も可哀相にな。グラジオラスで刻印を受け継いでしまったばかりに、こんな事に巻き込まれちまって」
「そうでもない。どうせ、地母共の策は無駄に終わるしな。あやつらは肝心なことを失念している」
「そう──なんですか?」
まるでこの先起こることが判りきっているかのような口調に、ノインは両目を瞬かせて少女を見る。
マレーネはノインの視線を真っ直ぐに受け、どこか冷めたような朱色の瞳で彼女を見返し、頷く。
「だが、その話は良かろう。貴様等には殆ど関係の無いことだ」
「またそれかよ……」
少女はバリードの呻きに答える事無く、口元に袖を当ててくつくつと笑うだけ。
彼女の笑いが収まった頃合を見計らい、バリードが話を纏めるような口調で尋ねる。
「で、結局、『刻印者』を──いや、『刻印者』に宿った印の力を完全に消し去るには、その『管理代行者』を何とかしなきゃならん。それは合ってるか?」
「大筋はな」
「じゃあ、『管理代行者』とやらを何とかするには一体どうしたらいい? オレ等にはそいつがどんな奴なのかもさっぱり判らんのでな、対策の立てようが無い」
「貴様等だけでは無理だ。まず他概念世界へと渡る力がなければ奴の元へと辿りつくことすらできん。そして辿りついたところで、貴様等程度の軟弱な存在概念では、容易に他概念の波に飲まれ、崩れ、跡形も無く消え去るぞ」
「なら、婆さんがケリをつけてくれるってのか?」
少し苛立ったような口調のバリードに、少女は小さく首を横に振る。
「そうしたいところではあるが……儂が表立って動くのはやはり危険でな。構造体が構成する位相世界へ移る程度なら容易ではあるが──我等と同等の象形を使う者が相手となると、手加減もできん。そして、我等『芯なる者』が本来の力を振るえば、それに『外なる者』が引き寄せられる可能性もある。それだけは避けたい」
「では、一体どうすれば……」
「だから、貴様等が何もせずとも全ては終結に辿りつくと、そうはじめから言っておろう。儂の役目も、後始末として少々力を振るうだけだからな」
淡々と、まるで目の前にある事実をただ告げるように喋るマレーネに、バリードとノインは言葉を挟めない。
「それが、先程星を視て得た結果だ。この物語は『刻印者』とニルフィエの女王、そして儂だけでも全ては決着する。貴様等は関わらずとも良い。わざわざ命を危険に晒す必要もなかろう」
栗毛の少女はそこまで言うとこちらに背を向ける。沈黙の帳が降り、海から吹く風の音だけが景色を埋める。
「……私達ではどうにもできない、そういう事ですか?」
ぽつりと呟かれた言葉に、背を向けた『芯なる者』は微かに振り返ると横目でノインを見やり、瞳の宿す色だけで肯定する。十歳にも満たないような少女の瞳に気圧され、ノインは怯んだように肩を震わせた。
しかし、視線だけは眼の前の少女から外さない。
「ふむ」
じっ、と。
無言のまま視線を交わしたあと。栗毛の少女が小さく吐息を吐くと、彼女には珍しい、どこか迷うような表情をノインの方へと向けた。
「……全くどうにもならぬ、という訳ではない。正直にいえば『刻印者』と『管理代行者』、どちらが勝つのか判らぬのだ」
「なら──」
「だが、先に寄るところがある。全てはそこへ赴いてから、だ」
喜色に染まりかけたノインの表情が止まり、戸惑ったようなものに変わる。
「寄るところ、ですか?」
眉を顰めて尋ねるノインに、マレーネは小さく頷いた。
「未だ道に揺らぎがある故はっきりとは言えん。だが、星のお陰で、『管理代行者』がこちらの概念世界へ流れてきているのは判った」
彼女の言葉に、岩上に座り込んでいたバリードは疑わしげな視線を少女に送る。
「──? どういうことだ? 『管理代行者』はこことは異なる概念世界に居るんじゃないのか?」
問いに、マレーネは微かに首を横に振ると、小さな唇をゆったりとした動きで震わせる。
「今、この世界に干渉しているマウローゼシステムは元々試作のものでな。管理は試験的に先行して作られた二体が、完成型の一体をサポートするという三体の『管理代行者』によって行われていた。恐らくはそのうちのどれかだろう」
マレーネは手に持つ巨大な杖を、くるりくるりと回す。
「儂はそやつに会いに行くつもりだ。休眠状態でこちらへ流れてきているのが気になるが……そやつに会えば、もう少し詳しい状況が判るかもしれん。そうすれば、儂が直接力を振るわずとも全てを決する策を思いつくかも知れんしな」
そこまで言うと、マレーネはその大きな朱の瞳を、戸惑ったように立つ黒髪の娘、ノインへと向け、
「さて、どうする?」
一言。そう問い掛ける。
その言葉に、ノインは一度両眼を閉じて浅く息を吸い、そして目を開き、答えた。
「どうするも何もありません、行きます。私はこの国を護る者として、今、この五王朝に混乱を巻き起こしているものの全てを、はっきりと知りたい。『護法』として見届けたいの。そして出来るなら、何かの役に立ちたいんです」
そこまで一気に言ってのけた彼女に、マレーネは冷めた両眼を向けたまま、改めて問う。
「貴様等、偽りの人には少々辛いぞ? 現世界上とはいえ『管理代行者』が眠る場所は、こことはかなり相を逸した地形に在るからな。儂がそれなりに守ってはやるが、それ程表立っては力を振るってやれん」
「構いません」
殆ど間髪入れぬ返答に、マレーネは軽く嘆息すると、視線をノインからバリードへと移す。
「貴様も来る気か、バリード」
問いに、いつの間にか岩上に胡座をかいて、片肘を突いて彼女等の様子を眺めていた男は、小さく肩を竦め、おどけたように笑う。
「オレの今の役目はこのお嬢さんのお守りなんでね。彼女が行くなら、オレも行くしかないだろう?」
「お守りって……」
「言葉のアヤだよ、アヤ」
情けない表情で呟くノインに、バリードは軽い調子で答える。そんな二人に小さく溜息をついたあと、栗毛の少女は視線を東の方角へと移し、誰に言うでもなく呟いた。
「ならば行くか。『管理代行者』が眠る地へ、ヴァドン絶界へな」
人間達がクォルルマル大森林と呼ぶ、その名の通りの巨大な森は、その全てが平地というわけではなく、幾つかのなだらかな山々も含めてクォルルマルと呼ばれている。その奥深くにある一山の内に『聖域』と呼ばれる場所がある。この世界の概念の化身ともいえる地母種、その頭達が集い、暮らす場所。
『聖域』の中心、鬱蒼と茂る木々の狭間に開いた空き地。大理石を思わせる光沢を放つ柱が八方に配置され、その中央には祭壇とも円卓とも取れるものが鎮座している。
その張り出した台座の片隅に腰を下ろし、空に輝く月を眺める、たおやかな人影が一つ。
彼女の姿形は殆ど人間と変わらない。背丈も、すらりと伸びた手足も、静かで、それでいてほんの僅か幼さを残した顔も。
しかし、根本的に人間と異なる部分が一つ。
その背には、柔らかな色彩に染まる薄羽が一対。仄かな輝きを放ちつつ衣服の隙間から伸びている。
彼女は、妖精達の間では『月夜に咲く女王』と呼ばれていた。
『地母の四女王』と呼ばれる、全てのニルフィエ達を統べる役割を持つ四人の地母種の一人。
そして、じっと空を見上げていた彼女が、ぽつりと呟いた。

「──私は、貴女が羨ましいわ」
呟き、嘆息して首を小さく振った。
「…………」
と、そこで彼女は、背後からこちらを見やる視線に気づく。
彼女は唐突に動きを止めて、振り返った。
「碧様、ですか?」
問い掛けの声を、彼女が座する位置から丁度真後ろに立つ柱に向かい、投げかける。

「お邪魔でしたかしら?」
暫しの沈黙の後、柱の後ろから柔らかく上品な声音が返ってきた。
声と共に柱の影から現れたのは、『月夜』と呼ばれた彼女とよく似た雰囲気を持つ女性だ。しかし纏う色彩は紫ではなく青。顔つきも少し異なり、より落ち着きを秘めた印象がある。
彼女の名は『碧の揺らぐ女王』。
月夜と同じ、地母の四女王としてニルフィエ達の頂点に位置する存在だ。
その女性の言葉に、月夜は一度だけ頭を振る。
「……いえ、お気になさらずに」
言葉少なにそれだけ言って、視線をまた空へと戻した。
碧と呼ばれたニルフィエは、そんな彼女に気にした様子もなく、ゆったりとした動作で歩を進めて、月夜の隣に音もなく立つ。
「『刻印者』は、順調に働いてくれていますか?」
「ええ、予定より二周期ほど早く。既に『刻印者』が屠った守護者の数は九つ以上。残る印は二つ」
そこで、暫し沈黙。
お互いがお互いの言葉を待つような空気が、二人の間を包んだ。
重苦しい空気が流れる。そして、そんな雰囲気に根負けしたという訳ではないのだろうが、碧が小さく吐息を吐いて、視線をそちらへ向けぬまま、再度隣に座る月夜へと尋ねる。
「我等四女王が作り上げた、『刻印者』を従えるための象形、問題ないようですね」
「そのようです」
短く、そしてどこか警戒するような声音に、今度ははっきりと溜息をつく碧。
彼女は、白の石段に座り、ただ空を見上げている月夜の方へと向き直り、はっきりと告げる。
「『深緑』の子から、わたくしの耳に報せが入っています。『月夜の分け身に不審な動き。刻印者に対する象形の拘束力について、内調の必要あり』、ということです」
「…………」
無表情のまま視線を向けた月夜に、碧は区切りを置くように細く吐息すると、改めて口を開く。
「さて。それでは、もう一度尋ねましょうか?」
凍っていた表情を少し解し、月夜は瞳を閉じて小さく首を振る。既に勘づかれているならば、これ以上しらを切っても無駄だ。
「敵わないわ、貴女には」
思わず呟いた言葉に、碧は唇に指を当て、くすりと悪戯っぽく笑う。
「あなたとは、名を受け継ぐ前からの仲ですもの。たとえ、それが偽りの人とはいえ、誰かに犠牲を強いるような手段をあなたが嫌うことくらい、判ります」
どこか澄ました調子で言う碧に、月夜は自虐的な笑みを浮かべつつ腰をあげる。空を眺めたまま、数歩、前へと歩いた。薄っすらと生えた草に素足が絡み、軽やかな音が短く響く。
「『月夜』を継ぐ時、そういう無駄な感情を捨てるために『分け身』を行った筈なのに……結局、こうですから。やはり、私は『月夜』の器ではなかったのだと、つくづくそう思います」
殆ど、彼女の口癖と言ってもいい言葉に、碧は苦笑する。
(相変わらずね……)
碧は内心溜息をつきつつ、そんな月夜の背中に、諭すように、それでいて叱咤するように話し掛ける。
「所詮、『分け身』は『分け身』です。望む部分だけ切り捨てるなんて、できはしません。それに、そういった部分も含めた上で、先代はあなたを選んだのです。あなたは、先代の決定が間違いだったと言うおつもりですか?」
碧の言葉に彼女は息を呑み、振り返る。
「そう、ですね。……ごめんなさい」
顔を伏せ、肩を落す月夜に、碧は柔らかく微笑んだ。
「お謝りにならなくても結構です。……本当に、『月夜』らしくない方ですね、あなたは」
言葉自体はきついながらも、どこか労わりを秘めた声。そして、一頻り笑ったあと、彼女は細く息を吐き、言葉を続ける。
「それで、どうされるおつもり? 今はわたくしが口を封じてはいますが、いずれは知られること。この事が皆に広まれば、気分屋の『粉雪』はともかく、『焔』はあなたを許さないでしょう。他のニルフィエ達も黙っていませんよ」
「先刻──」
「?」
「自分の『分け身』に説教されました。……もっと自分に素直になれ、と」
そこで言葉を区切り、月夜は複雑な笑みを浮べて見上げてくる。
「あの子の好きにさせてあげたいの。彼女は、『本当の私』といってもいい子だから。すべての責任は──私が負います」
「あなたは……」
呻くような声を残し、碧はそんな月夜を真剣な表情で見返す。
二人の妖精の女王が、暫し動きを止めて、互いを見る。
そのままどれだけの時間が経ったか。
空に浮ぶ星達の動きが目に見えてわかるほどの時間のあと、碧が深々と吐息。
「『焔』と『月夜』はわたくし達の長。『月夜』であるあなたが、わたくしにそう仰られるのでしたら、もう何も言いはしません」
音も無く踵を返し、月夜に背を向ける碧。視線だけで振り向く。
「ですが、『月夜』が『焔』を罰することができるように、『焔』は『月夜』を罰することができる。そしてわたくし達の主導は、月の概念を秘めた貴方ではなく、太陽の概念を秘めた『焔』にある。そのことをお忘れにならないでね」
それだけ言うと、彼女はゆっくりとした足取りでその場を去っていった。
後に残った月夜は、空に昇る白い円が完全に地平に没するまで、言葉も無く、それを眺めていた。
花々からの観察者 風羽
──風羽──
五王朝の主要都市を結ぶウスタールの大街道。石畳の道を歩く貴方の靴裏からは、石と靴の間で砂利の擦れる音が微かに響く。

「しっかし、最近イイ天気が続くよね~」
視界の片隅、歩く貴方の右斜め前といった位置で、浮んだまま大きく身体を伸ばしてみせる妖精の姿が映った。貴方は彼女の言葉に釣られるように空を見上げる。確かに彼女の言う通り、天気の方はすこぶる良い。雲一つ無い空と、燦々と照りつける太陽に眼を細め、思わず足を止めた。
と、青空の中に輝いていた太陽が、小さな影に遮られる。
「こら、何立ち止まってるのさ。もう疲れたの?」
わざわざこちらの真上、眼の前に移動してから、からからと景気良く笑うリトゥエを、貴方は半ば呆れにも似た表情で眺める。
どうも近頃のリトゥエは、この間までのどこか塞ぎこんだ、よそよそしい雰囲気が微塵も無くなり、丁度はじめて会った頃のような快活な小妖精に戻っていた。今まで貴方の周りで頻繁に起こっていた『現出』が最近はすっかり鳴りを潜めているせいなのか、身体の調子も酷く良いらしく、起きている間は常に喋り続けに近い状況だった。
正直な話、あまりの態度の急変ぶりについていけない。
この間までの陰鬱とした彼女よりは、付き合いやすいことは確か──と思いたいところだが、ひきりなしに喋り続けるため、非常に煩いのだ、この妖精は。その上、周囲を忙しなく動き回るので鬱陶しい。しかも彼女の話にいちいち返事をしないと「ちゃんと聞いてるの?」を連発してくる。生返事を返した時も同様だ。面倒なことこの上ない。
「ね、ね。【NAME】、あそこで一休みしてこうよ」
陰鬱とした表情で歩いていた貴方は、また眼の前に現れた妖精の姿をげんなりと見る。
彼女が示す方向には、小高い丘。その周囲を柔らかな色合いの森に囲まれ、頂上付近には一際巨大な広葉樹が一本、豊かに茂らせた葉で、空から降りそそぐ強い日差しを受け止めている。
まあ、否という理由も無い。
実際、街を出てからここまで歩き詰めで、休憩と呼べるようなものを一切取っていなかった。そろそろ身体を休めておいたほうが良いだろう。
貴方が軽く頷くと、小妖精は一際笑みを深くする。
「よっし、んじゃゴゥゴゥ!」
そして勢い良く片手をあげると、リトゥエはふわりふわりと背中の羽を揺らし、一人でさっさと飛んでいってしまう。
(加減というものを知らないのか)
暗と明、あまりにも両極端すぎる彼女の態度に、貴方は溜息混じりに肩を落としつつ、その理由について、何気なく考えを巡らす。
彼女を暗くしていた要因が無くなったから、元に戻ったのか。
それとも、その要因を忘れるために、ああして無理矢理明るく振舞っているのか。
あるいは……何もかも振り切って、自棄になってるか。
そこまで考えて──頭を振り、中断する。考えたところで詮の無いことだからだ。彼女がその事についてこちらに相談してこないということは、自分との関わり合いを拒絶しているという意味だ。こちらが幾ら気を揉んだところで、どうにかなるものでもない。
(だが……)
少し前までの彼女は、かなり思い詰めているようにも見えた。一人で何もかもを背負い込んでるような、そんな雰囲気。
(無理をしていなければ良いのだが)
そう考える貴方の視線の遥か先で、妖精が両手を忙しなく振って、早く来いと急かしている。貴方は片手を挙げて了解の意を伝えると、一度背嚢を背負い直してから、ゆっくりと歩き出した。
そこは深い深い漆黒の空間だった。瞼を見開いて周りを視ようとしても、映るのは斑の無い黒。上も下も左も右も、どこへ視線を送ろうと、目に入るのは光を拒む絶対の闇。己の手足や胴ですら、ノイン・ヴァイヒュントの黒瞳には映らない。
既にこの闇に包まれてどれだけの時間が経ったのか、見当もつかない。まだ数分しか過ぎていないような、それでいて何時間も過ぎ去っているような気もする。
五王朝の中心であるグローエス国の南、『黒の森』を更に南へと下った位置に、王朝の人々の間では名の知れた現出地形、『ヴァドン絶界』と呼ばれる場所がある。
『虹色の夜』の発生後、五王朝の空を舞う浮遊列島群、通称『セリテ天海』と共にいち早く『現出』したそれは、巨大なドーム状の領域。何人の侵入も拒む、絶対の闇が支配する空間だった。この直径数百メートル規模の空間に足を踏み入れ、生きて戻ってきた人間は誰も居らず、現在では王朝の護法結界師達が、黒の半円を取り囲むように敷いた障壁結界により、一般人は侵入することすらままならない。そんな場所に、彼女は足を踏み入れていた。

(ある程度は覚悟していたけど……こんな場所だったなんて……)
彼女の同僚である巨大な槍を携えた灰色髪の護法騎士バリード・ルッツと、彼の育ての親であり、伝説に云う『芯なる者』の一人だという栗毛の少女、マレーネ・ウレフ。この二人と共に、彼女はこの『ヴァドン絶界』へと入り込んだ筈だった。
だが、マレーネが護法結界師の敷いた結界を開き、黒の領域へと侵入した途端、五感全てが無に包まれたような感覚が彼女を襲い、踏み締めていた地面の感触すら、一瞬にして消えてしまった。常識的に考えれば、自分のすぐ近くに居る筈のバリードやマレーネの気配も微塵も感じられない。
心を埋め尽くすのは恐怖。
目を開いていても閉じていても、見えるものは全く同じ。そして、身体を支える大地と重力が存在しないというこの恐怖は、一度味わってみなければ判らぬ類のものだ。
だが、それ以上に彼女の心に影を差す、身の毛もよだつ奇怪な感覚。
(この感覚……いつか感じた……)
思い返し、彼女は身を震わせる。
そうだ、あの『刻印者』だ。『刻印者』が発した『現出』の力、あれをまともに受けたときに感じた、あの口には言い表せぬ感覚。
「あ、ああ──」
封じていた記憶が呼び戻され、あの時に心に刻み付けられた、より大きな恐怖。それが心の奥底から蘇えり、殆ど悲鳴に近い声が漏れた。
だが、ここで一度叫びはじめてしまえば、もう自分を維持できる自信は無い。闇に飲まれ、心は狂気に満たされるだろう。
喉まで出かけた悲鳴を懸命に噛み殺し、子供のように暴れ、泣き出したくなる気持ちを、深呼吸で沈める。しかし、努めてゆっくり吐き出そうとした筈の呼気ですら荒く、どくどくと脈打つ心臓の音が酷く大きく感じられて、なお恐怖をかきたてられる。
己の両肩を抱く掌の気配だけ頼りに、必死に恐れと立ち向かっていた彼女に、

「……ヴァイヒュント嬢、そこに居たのか」
凄まじく暢気な、というよりはどこか呆れたような調子の声が掛けられ、ノインはびくりと肩を震わせた。今まで完全に無音の状態にあった彼女にとって、その声はあまりに突然だった。
「バドさん! ど、どこですかッ!?」
反射的に、殆ど悲鳴混じりの声が出た。半ば恐慌状態になっている彼女の様子を察したのか、返ってきた声に、ほんの少しであるが真剣味が混じる。
「落ち着け、ヴァイヒュント嬢。ちと待ってな──婆さん!」

「聞こえている。叫ぶでないわ」
バリードが呼びかけると、ノインのすぐ真横の位置から、どこか幼く、不機嫌そうな声音が響く。
ひゅん、と。
何か細長い物が振るわれて空を裂く音が響き、それに合わせてノインを取り囲んでいた黒の闇が即座に払われた。直径数メートル程の範囲ではあるが、脆く乾いた土に薄く草の生えた地面が生まれ、突如生まれた重力に身体がそちらへと引き寄せられる。
「は」
思わず、安堵の吐息が漏れた。
「大丈夫か? そういえばキミ、結界術使えないんだったな。忘れてた」
「……は、あ」
上から見下ろしてくるバリードに、言葉を返すこともできない。ノインは比較的乾いた土の上に両手をつき、荒れた息を整える。地に身体がついているということが、これほど安心できることだとは。
「ちと、辛かったみたいだな。婆さん、もう少し相を合わせられるか? オレも結構ツライし」
気楽な調子で言うバリードに、傍らに無言のまま浮んでいた栗毛の少女が、半眼に近い眼差しを向ける。
「贅沢な奴だな。整調自体は容易ではあるが、正直これ以上力を振るいたくは無いのだがな」
「相変わらずシケてるよな、婆さんは」
「思慮深いと言え、馬鹿者。……だが、仕方あるまいな」
マレーネは空中を音も無く滑り、未だ苦しげな息を吐くノインに向けて、己の杖の先端を翳す。
「気を楽にせよ。貴様の概念、整えてやる」
言葉と共に杖に淡い輝きが宿り、ノインの身体へ伝播する。柔らかな波動が全身を満たし、感じていた異常なまでの恐怖と、何とも言えぬ独特の感覚が徐々に薄れていく。
そのまま浅く呼吸を繰り返し息を整えてから、土の固さを確かめつつ立ち上がる。
「マレーネさん、ここは……一体何なのですか?」
短く礼を述べた後、気味悪げに周囲を見渡しつつ尋ねるノインに、マレーネは「入るときに説明したろうに」といった表情を浮べつつも、言葉を繰り返す。
「この黒、いや、無色の領域は、現世界とマウローゼの管理する仮想世界との相の違いを緩衝させるための結界だ。この中心に、こちらへ流れてきた『管理代行者』が居る筈だ。……要は箱詰めのまま送られてきた荷物のようなものと思え」
最後に付け加えられた言葉に、バリードが口を挟む。
「待てよ。わざわざ『管理代行者』とやらがこっちに移動してきたっていうなら、何故こんな結界を張る必要がある」
「緩衝させているといったろうが? まだ外と内との相の違いが激しい故に、今この結界を解けば、恐らく中に居る存在はその位相差に耐えられまい。そのための結界だ──と、あれは」
そこでマレーネの視線が、ある一点で止まる。ノインとバリードは彼女の瞳が向けられた方向へと振り返り、
「黒い……玉?」
音もなく宙を浮ぶその物体に、警戒の混じった声をあげた。
それは大きさにして直径一メートル程であろうか。深い黒に包まれた景色の中でも、殊更色濃い闇色を持つ表面には、幾つか朱色の線が走っている。何の支えも無く、無の空間に浮ぶその物体は、ゆらりゆらりと左右に揺れながら、徐々にこちらへと近づいてくる。
「抗体か。狂っている割に用意周到だな。バリードよ、行けるか?」
一瞥すらせずに尋ねてくる少女に、男は眉を露骨に顰めて呻く。
「構わんが……まさか婆さん、手伝わん気か?」
「無論だ。何のために貴様等を連れてきたと思っている? これを使え。狼槍ガリア・クレンイだ」
いって、少女は己の袖に手を突っ込み、引き抜く。すると、肘から手首までせいぜい20センチといった彼女の袖の中から、長さ二メートル程の槍がずるりと這い出した。
そのまま、軽い動作で片手に持った槍をバリードの方へと投げる。少女と同じように片手で受け取ろうとして──がくん、と男の上体が泳ぐ。
「婆さん、重すぎだぞこれ!」
「身体が鈍っているな。だが、その程度の重量ならば、使いこなせるだろう」
冷ややかな視線を向けるマレーネに舌打ちし、慌てて両手で持ち直す。そして具合を確かめるように数度振り回してから、未だ額を抑えつつ荒い息を吐くノインに視線を移す。
「ヴァイヒュント嬢、動けるか? 辛いなら無理には──といったところで、キミが素直に『駄目』という筈も無いか」
「……ええ。少しきついですけど、やります」
一度深く吐息してから、意識にこびりつく異質な感覚を払うように数度頭を振ると、無理矢理笑ってみせる。
「オッケイ。じゃ、婆さん、照明ぐらいはちゃんと確保しといてくれよ」
「言われずとも、その程度ならやってやる。あれからどれだけ腕を上げたか、見せてみよ」
「そのつもりだが……影がでねえから眷属が呼べんな。面倒な」
面白くなさそうに呟き、槍を数度旋回させてから脇に抱え、徐々にこちらへ近づいてくる暗色の球体へと穂先を向ける。
ノインは素早く周囲へ視線を巡らせる。いつの間にか球体の数は増えており、ノイン達を囲むように八つ。球体の周りには怪しげな文字列が円を描くように周回しており、結界内に漂う歪なイーサをゆっくりと変質させていく。明らかに干渉系の攻撃を仕掛けてくる気配。
(待っていては不利、だけど)
こちらはマレーネの傍から離れてしまえば、視界はおろか足場すら確保することも難しい。となれば、引き寄せてから一気にけりをつけるしかない。
彼女は腰に吊るした長剣の柄に手をかける。このような不安定な空間で召喚術が使えるはずもない。剣を一動作で引き抜くと、片手で素早く印章を描き、刀身に力を宿す。更に数度印章を描き、自分とバリードの周囲に漂うイーサを整調し、簡略的に己の支配下におく。これでイーサ干渉系の攻撃は、ある程度中和できる筈だ。
細く息を吸い、吐く。そして両眉を引き締める。
「右は私が。バドさんは左をお願いします」
「ああ。──じゃ、行くぞ」
バリードが腰を落すと同時、周囲の球体から激しい干渉音が響く。その瞬間、二人は弾かれたように飛び出し、漂う球体に向かい、渾身の力を込めて己の武器を振り下ろした。
ウスタールの大街道沿いにある、なだらかな丘、その頂上に生えた一本の巨大な樹の下。ごつごつとした樹の幹に腰掛けて午睡を楽しんでいた貴方は、西から吹き込んだ一際強い風に、大樹の葉がざわめく音で目を覚ます。
薄っすらと開いた眼に映るのは、緑の葉に遮られて斑に差し込む太陽の日差しと、少し離れた位置で遥か遠方を眺め、ぼんやりと浮んでいる小さな妖精の姿だった。

「あ。起きた?」
こちらの視線に気づいたのか、彼女は振り返る。
と、普段から見慣れた彼女の姿が、どこかおかしいことに気づいた。
寝起きであるため頭が働かず、その違和感の正体を突き止めるために両の眉根を寄せて、数秒。
「あ……」
彼女の背から生えている、薄く半透明の羽。流翼種の特徴ともいえるその羽の片方が、半ばから見事に千切れていた。
驚きの表情を浮かべる貴方に気づいてか、彼女は一瞬だけ視線を己の羽へと移し、少し笑う。
「ああ、大丈夫大丈夫。ほら、これこれ」
言って、背後に回していた両手をひょいと前に出してみせる。そこには恐らく千切れた彼女の羽と思しき支脈の筋が入った薄羽が一枚。
非対称の長さとなった羽を揺らし、未だ幹に腰掛けたままである貴方の眼前にまで移動すると、彼女は手に持った羽を、ずいとこちらへ突き出した。
そのまま数秒、無言。
一体何なのか、と、視線だけで問い掛ける貴方に、彼女は小首を傾げ、答える。
「お守り。またいつか、どこかで出会えるように」
そう告げたリトゥエの表情は酷く静かで、まるで別人のようだ。
何を言っているのか判らず、訝しげに眉を寄せた貴方に、彼女は改めて声を立てて笑う。
「はははっ、なに難しい顔してんの! 単なるお守りだって言ってるでしょ? 持っててよ、ほら」
片翼となったリトゥエは満面笑顔のまま、動こうとしない貴方の片手に取り付くと、軽く握っていた拳を強引に開いて、その中に己の千切った羽を入れる。その薄羽の酷く頼りない感触に、貴方は握りこもうとした指の動きを慌てて止めた。
(お守り、ね)
二本の指で摘み上げ、軽く透かして見る。主の身体から千切られたそれは綺麗な半透明。未だに淡い燐光を放っている。そして透けた羽の向こうに、にこにこと笑いながら、片羽を半ばから失いつつも宙を浮ぶ妖精の姿がある。
少し心配になる。片方の羽を失っても、しっかりと空を飛ぶことができるのか、と。
貴方がそう尋ねると、
「ん? んー、ちょっと飛びにくいっちゃ飛びにくいけど、全然平気。ほら、ね?」
くるくると貴方の周囲を廻ってみせるリトゥエ。確かに大丈夫そうではある。
「じゃ、そろそろ行こっか。ほら、【NAME】!」
そのままこちらの返事も聞かずに、リトゥエはひらひらとウスタールの街道のほうへと飛んでいってしまう。
相変わらずの自分本位な行動に苦笑しつつ、貴方は手に収まっている一枚の薄羽へと視線を落し、掌の中で転がせる。その仕草に合わせるように、薄く草の生えた丘を柔らかな風が吹き抜けていく。
暫く何も考えるでもなくその羽を眺めた後、貴方は懐から布製の小袋を取り出し、その中へと羽を仕舞い込んだ。
遠くから、リトゥエが貴方の名を呼ぶ声が聞こえる。
貴方はその声に急かされるように、足早に丘の頂上、大樹の根から離れた。
花々からの観察者 虹色
──虹色──
周囲の闇よりも一際濃い黒の色をもつ球体、そこから細く伸びた触手を思わせるものが三本、ノインの側面を突くように滑らかに蠢く。
ノインは迫る鋭角の触手を一瞥すると、まず、眼前に浮ぶ球体に構えた長剣を叩きつけ砕いてから、振り下ろした剣の勢いを殺す事無く身を捻り、迫る触手を迎撃する。一本を斬り、二本を斬り、三本目は間に合わず、ぎりぎりまで引きつけてから身体を屈めて避けて、伸びきったところで斬りあげる。
彼女は崩れた態勢を一瞬で立て直し、疾駆。
こちらを襲った黒い触手が球体へ戻っていく前に己の剣の間合いへと踏み込み、印章により力を付与された黄金色に瞬く長剣を、左袈裟で一気に振り下ろした。球体の一つはその剣の一撃を受けて、真っ二つに分断される。
だが、球体の数はそれだけではない。すぐ近く、一踏み込みで届く間合いに一つ、少し離れた位置に二つ。その全てが、攻撃時に生まれた彼女の隙を捕らえ、触手を伸ばそうと動く。そして彼女は球体の攻撃を全て回避でるような態勢ではない。
そこへ鋭い声が響いた。

「ヴァイヒュント嬢、伏せろ!」
ノインは声のした方向を一瞥すらせずに、手近に居た球体に向かい、大きく踏み込む。それは踏み込むというよりは開脚にも近い動作で、上半身を屈めていることも相まって、殆ど地を滑るような動き。
そんな彼女の真上を薙ぎ払うように、印章の助けを借りた強烈な斬撃が、衝撃波を伴って吹き荒れる。離れた位置からバリードが放った槍の一撃は、半円状の刃となって闇の空間を滑り、ノインを狙っていた三つの球体のうち、離れた二体を飲み込んで破砕した。
そして、彼の放った衝撃波が突き抜けると同時、身を伏せるように踏み込んでいたノインが上体を起こしながら、槍の一撃から逃れた最後の一体に向かい、剣を振るう。
ほぼ真下に近い位置から振り上げられた輝剣は、何の迷いも無く黒色の球体を二分した。

「これで最後、ですか」
「多分な。──婆さん、こんなもんかね?」
周りを囲んでいた黒の球体を一通り打ち滅ぼした後。
ノイン・ヴァイヒュントとバリード・ルッツの二人は、軽く息を吐くと背後に控えていた少女の方へと振り返った。
そんな二人に、栗毛の少女マレーネ・ウレフは鷹揚な仕草で頷くと、

「ああ。あれを見るがいい」
手に持った巨大な杖で、ノインとバリードが立つ場所から、少し西側へずれた方向を指し示す。二人はそちらへと視線を走らせ──絶句し、固まった。
「なんだ、ありゃ」
呻き、露骨に眉を顰めるバリード。
マレーネが杖先を向けている方向には、黒く濃い闇が広がっている。だが、その只中に一点、粘質の黒とは異なる色が混じっていた。
だが少々位置が遠いため、バリードはともかく、視力の弱いノインにはその色の正体が何なのかがはっきりと判らない。殆ど藪睨みにも近い目つきで、暫くの間そちらを見やり、ぽつりと呟く。
「胸像……ですか?」
そう、それは人間の胸像に見えた。
頭部と胴──それも胸まで──しかない人間の姿。鋭い中に柔らかな曲線を帯びた顔は滑らかで、両眼は閉じられ、髪は肩上の位置で微塵の揺らぎもなく切り揃えられている。本来腕がある部分は、まるで無いことが自然であるように綺麗な丸みを帯びて、胸部より下も同様。遠目から見ているため、細かい部分は良く判らないが、かなり精巧な像のようには見える。
だが、隣でそれを眺めていたバリードは、少し掠れの混じった声で彼女の言葉を否定した。
「良く見ろ、ヴァイヒュント嬢。あれは像じゃない。生きてる」
「生きて──って、まさか」
続く言葉を飲み込み、改めてそちらを見る。像ではないということは。
「女性体か。ならば『ツヴァイ』だな。どうやら本当に休眠状態で送り込まれてきたらしい」
呻いたノインの言葉を継ぐようにマレーネは口を開き、一歩前に進み出て、携えた巨大な杖を持ち直す。
「やはり、あれが、『管理代行者』なのですか?」
問う声に、マレーネは無言のまま頷き、それを見たバリードは顰め面で己の髪を掻き回した。
「──確かに、頭と内臓さえあれば生きてはいけるのだろうが……婆さん、あれはちょっと、やりすぎじゃないか?」
「あれは元々ああいう生物だ。生まれてから手を加えたわけではない」
「……詭弁だ。生まれる前に手を加えてたら一緒だろうがよ。せめて原型と同じ身体にしてやれ。やりきれん」
「言うな。あれは儂が造り出したわけではない」
嘆息するように言い捨て、マレーネは己の巨大な杖を垂直に立てると、五つの指でそれぞれ別個の象形を描き、空中に杖を固定する。
「貴様等はここに居ろ。この杖が儂のかわりに貴様等の世界を確保してくれる。奴に近づくと、貴様等と奴の存在概念が反撥しあう。お互いの存在が崩れ、壊れるぞ」
言い捨て、闇の中に浮ぶ奇怪な人影に向かい、一人移動していく。
思わず後を追おうとしたノインだが、眼の前に槍を絡ませた腕が伸びて、歩みを止められる。
「ヴァイヒュント嬢、ここは婆さんに任せておけ。オレ等じゃどうにもならん」
「…………」
ノインは闇の只中へと進んでいくマレーネと、こちらを静かに見下ろすバリードとの間で、数度視線を彷徨わせてから頷き、一歩下がる。反射的に前へ動いてしまっていたものの、先程襲われたあの闇の感覚に再度身を浸す勇気は、今の彼女には到底無かった。
胸像、もとい、『管理代行者』のすぐ傍にまで闇を漂っていった少女は、暫くの間、何をするでもなく『管理代行者』を眺めてから、そして口を数度動かす。声は当然こちらには届くわけもない。
「何を為さっているのでしょうか」
眼を細めつつその様子を眺めていたノインが首を傾げて傍らの青年を見るが、こちらも肩を小さく竦めるだけ。
そこで、マレーネが新たな動きを取った。
やや顔を伏せ、小さく唇を開き吐息するような仕草。
その後、ゆったりとした己の服の袖に左腕を突き入れて、引き抜いた。入れる前は無手であった筈のその掌の内には、なにやら人型の物体が握られている。そして、左手にその物体を携えたまま、空いた右の手の指で『管理代行者』の眼前に、光り輝く象形を数度描いたと同時。
生白い肌を持つ『管理代行者』が、薄く瞳を開けて微笑み、
ぱん、と。
軽い音と共に、その顔が、身体が、破裂した。
遠目に、人と同じような赤い血が一瞬だけ弾け、砕けた身体ごと、闇に融けて消えるのが見えた。
「な──」
唖然とした表情で固まる二人を尻目に、栗毛の少女は血に塗れた右手を忌むように振り振り、行く時と同じ、ふわりふわりと漂うようにこちらへ戻ってくる。
「マレーネさん、どうしてあんな事を──」
地面すら無い闇の空間から、杖が守護する空間へと戻ってきたマレーネに、ノインは戸惑ったように問いかける。が、
「騒ぐな。どうせ、あの身では長くは持たん。だからこうして」
マレーネは左手をノインの眼前にまで上げて、手に掴んでいるものを見せる。黒瞳を数度瞬かせてから掲げられたものをしみじみと眺め、ノインは一言呟く。
「お人形……?」
それは、どこから見ても、ただの人形だった。細かい装飾が施された品の良い服を着込み、綿の身体を持つその人形の大きさは二十センチほど。栗毛の少女は血の払われた片手でその波打つ金色の髪を一撫でする。
彼女の言わんとしていることは判る。恐らくはこの人形に、先程破裂した物体の意識か、記憶が、それを継承させたのだろう。
人の概念を人形等へと移す術は、現在の人間が操る魔術でも可能といえば可能だ。人より遥かに強大な力を持つ芯属ならば、人形に存在を移すなど、極めて容易なものなのだろうと想像できる。
マレーネは慈しむように指に数度、その金色の髪を絡ませ、呟く。
「擬似的なものではあるが、完全に崩滅させるには不憫でな。生みだし育て、そして封じて放置し、彼女等を狂わせたのは儂等の罪だ。故に、せめても、とな」
「どうだかな。逆に弄ばれてるようにしか見えんぞ」
「……かもしれんな。だが、儂にはこういうことしかできん。力を持つ者の性、とでも言うのか」
皮肉気なバリードの言葉に、哀憫の色を漂わせた笑みで答える。そんな少女の返事に複雑な表情を浮かべつつ、バリードは人差し指で人形の頭を軽く突いた。
「──で、これが、さっきの管理代行者、なのか?」
「いや。貴様等も見ていたであろう、ツヴァイ自体は先程破壊した。これはその概念を移しただけだ。ツヴァイではあったが……器となるものが替わった今では、もう別の存在と言えるかもしれんな」
片手に人形を携えたまま、空いた右手を伸ばして、空中に浮んでいた長さ一メートル半程の杖をがしゃりと握り込む。
「もうここには用はない。ここを護っていた守護者も既に『刻印者』に狩られ、そして主までも失った今では、この結界も不要のものだな」
マレーネはそこまで言って、手に持った杖を軽々しい動作で大きく振る。次の瞬間、八方を包んでいた闇が杖の動きにあわせ、瞬く間に弾け飛び、連鎖し、そのまま『ヴァドン絶界』と呼ばれていた直径五百メートルは下らない黒の半球を、『護法』の構成した結界ごと、完膚なきまでに消失させた。
今までのどろりとした暗幕に閉ざされた世界から、青く爽やかな光が降り注ぐ場所へと引っ張り出され、ノインはその眩しさを避けるように、眼前に両手を掲げて光を遮る。
「凄い……」
漸く眼が慣れ、改めて周囲を見渡して感嘆の声をあげる。五王朝が誇る護法達の中でも名だたる結界師が敷いた印章結界すら、杖の一振りで払うその力。まさに人外の、芯属と呼ぶに相応しいものだった。
マレーネは身の丈ほどもある巨大な杖を片手だけで回して、担ぐように持ち直すと、左腕で抱えた人形に向かい話し掛ける。
「ツヴァイ、聞こえるか」
声に、人形の首がひくりと動き、緩やかな動作で捻られて、その硝子細工の両眼をマレーネに向けた。
「貴様の兄を殺した妹が漂う位置と相、貴様なら判るな」
相手は人形、しかも声を発するための口は、細い糸で紡がれた稚拙なものだ。返答など望むべくも無い。しかしマレーネは言葉を継ぎ、人形の両眼をただ凝視する。
そして数瞬の後、少女はまるで人形の発する無音の言葉を聞き取っているかのように、小さく頷いた。
「判っておる、言われるまでもない。閉じた世界で生きる孤独、儂もよくよく知っておるしな。だが、貴様の妹が為した所業は、我等『芯なる者』が『外なる者』より身を隠すために施した力、その全てを無にする可能性のある行為だ。裁かぬわけにはいくまいよ」
深い吐息の後、マレーネは己の袖に人形を仕舞い、携えていた巨大な杖も同じ仕草で袖の中へ。
「……で、婆さん。これからどうするつもりだ? もうこうなったら最後まで見届けさせてもらうからな」
一段落ついたらしき様子の少女に、傍らに立ってたバリードが問い掛ける。その言葉に彼女は浅く両腕を組むと、暫し思考。
「予想より状況が悪い。相と相が交わる場所、グローエスの封印が施されていた場所で、『刻印者』の訪れを待つ。星の示した運命が正しければ、必ず『刻印者』はそこへ現れる」
話が違う。ノインとバリードは疑問の表情で固まった。
星を視る丘での話では、直接『刻印者』とは争わず、奴の操る力の大元である、他概念世界に潜む『管理代行者』を討つ、そういう事ではなかったのか?
「ま、待ってください! 『刻印者』を待ち伏せてどうするんです!? 私達では、もし『刻印者』を倒せたとして……」
刻印自体がこちらに移り、新たな刻印者が生まれるだけだ。
そう叫ぼうとしたノインを、マレーネはその朱色の視線だけで留める。
「別に戦うわけではない。ツヴァイが言うには、『管理代行者』は世界守護のために積んでおいたシステムを、既に起動させ、それを操っているらしい。となれば、やはり貴様等だけで奴を屠ることは不可能だ。ならば……」
「だが、肝心の『刻印者』は、奴が起こす『現出』を止めるために、ニルフィエ達が特殊な象形で封縛してしまうっていう話じゃなかったか?」
訝しげに問い掛けるバリードにも、彼女は少し肩を竦めるだけで答えない。
闇が払われ、強い陽光が差し込む草原を、彼女は独りこちらに背を向けて歩いていく。
そして、未だ戸惑ったような二人へ視線だけで振り向くと、薄く笑みを浮かべた。
「なに、今は深く考えずとも良い。いずれは判ることだ」
その言葉に、二人の護法はお互い顔を見合わせ、一息。
「訊いても、答えてもらえそうにないですね……」
「だろうな。ま、婆さんがそういうなら、実際にそうなんだろうさ。今は、ついていくしかなかろ」
私は悲鳴をあげた。
今まで、どんなに遠く離れていても私の奥深くで繋がっていた、
もう一人の私の意識。
それが、呆気なく切り離される。
彼女の身体が壊れ、『奈落』の狭間へ融けていくのを感じる。
それは酷く耐え難いもので、
細く長く、掠れた声で私は鳴き、
既に触れているという感覚すら危うい、己の腕で震える両肩を抱く。
私と、違う私と、もう一人の私。
違う私は兄であり、もう一人の私は姉。
生まれた私を、『皆』と共に見守ってくれた、私とは別の私達。
だけど。
ファアから授けられた、全ての印との繋がりも既に薄れ、
壊れてしまった違う私を、私は屠り、
絶望し、眠っていた、もう一人の私すらも失い、
今、私の元に残るのは、この世界を孤独に護る猛き竜だけ。
世界を木霊していた私の悲鳴は遂に途切れ、
後には何も無い世界が残る。
もう、後戻りすることは許されない。
もう、残された道は一つしかない。
彼の力を借りて、すべての印を私の手中に取り戻す。
声と共に拡散してしまった意識を、私は必死で掻き集めながら、
彼を呼ぶ。
この世界を孤独に護る剣、猛々しい竜の御名を。
そう。彼の竜の名、それは──
叩きつけるような雨が通り過ぎ、ぬかるんだ土くれの道の只中で。雨水に濡れて湿りきった顔を上げ、いつの間にか過ぎ去っていった雨雲を見届けながら、リトゥエは安堵の吐息をつく。

「侵食が、止まった……」
現世界に流れ込んだ十二の位相刻印、その全てを刻まれて尚、【NAME】は『管理代行者』の束縛に屈せず、それを退けたのだ。
リトゥエの持つ、地母種の作り上げた象形で、『管理代行者』の干渉をいくらか遮ってはいるが、それはせいぜい【NAME】の背を頼りなげに支えてやった程度のことでしかない。【NAME】は全ての印を己の身体に刻み、それを己の力だけで押さえ込むことに成功したのだ。
「──本当に、お疲れ様。【NAME】」
疲労の色濃い顔に笑みを浮べ、彼女が【NAME】の頬を撫でた、その時。
何かの気配を感じ、片方を半ばから失った彼女の薄羽が、ぴんと張り詰める。
「……え?」
突如、明度を増した空に、リトゥエは戸惑ったような声と共に顔を上げ──絶句した。
先ほどまで大粒の雨を降らせていた雲が晴れ、大小様々に輝く夜空。それを覆うように、七つもの色を帯びた光彩が広がっていたのだ。
「虹、色の」
リトゥエは不気味な色合いに染まった空を見上げながら、擦れた声で呻く。
今、自分の瞳に映る空は、グローエス一帯に在る妖精達の間では悪夢の夜とされた、あの『虹色の夜』と同じものだった。
その正体は、彼女等妖精は既に知っている。
あの輝きは、強い位相の存在が強引にこの世界へ現れようとする時に、現世界というものを構成する根本的な概念達があげる悲鳴なのだ。
そして、次の瞬間。
筆舌に尽くし難い異様な気配が、遥か地平の彼方より、唐突に『現出』した。
視線を向けるだけで身体が痺れ、身動きが取れなくなるほどの強烈な気配。それが、こちらに向かい一直線に迫ってくる。
更に、その気配が漂ってくる方角から、現世界を構成する概念が凄まじい勢いで崩れ、弾け、悲鳴と共に滅されていくのが、はっきりと伝わってきた。
信じられない。
「──嘘でしょ? だってもう、位相守護者は【NAME】が」
そこまで呟いて、自分が至極単純な理屈をすっかり失念していた事に気づいた。
つまり。
位相守護者を現世界へ送り込んできた者が彼らの消滅に気づいたならば、その原因を探るために、新たな力を現世界へ送り込んでくるだろう、と。
新たに現れた気配は、恐らく、それだ。
あちら側に守護者以外の力があったとしてもおかしくはない──というより、これはある意味、当然の帰結だ。
(そんなことも、考えつかなかったなんて)
こちらの世界にやってきた十二の守護者を【NAME】が狩り、そして彼らの所持していた全ての印を押さえ込めば、何もかもが平和に収まる。
心のどこかでそんなことを夢想していた自分に気づいて、リトゥエは愕然とした。
そして、混乱した頭を整理する間も惜しむように、懸命に考える。
一体これから、どうすれば良いのか。
遠方より生まれた気配は、こちらへ向かい凄まじい勢いで近づいてくる。
そして肝心の【NAME】は、十二の刻印の干渉に抗うために力を使い果たし、今は完全に気を失って地に倒れ伏している。到底戦える状態ではない。
このままでは、【NAME】が今まで守護者から狩り歩いていった刻印は、全てあちら側の手に落ちることになってしまう。
そして当然──自分達が無事に済む筈もない。
「…………」
無言のまま、先程の雨のお陰で完全にぬかるんだ地面に、力無く腰を落とす。細い足に泥の飛沫が散ったが気にもならない。リトゥエは虚ろな瞳を虹色に染まる空へ向けた。
所詮『観察者』でしかない自分にできることは、もう何も無い。
少なくとも、自分の力だけでできることは。
「今が、その時──なのかな」
あの満月の夜に、己の『源流』と交わした言葉を思い出す。
身を起こす。
彼女は宛も無く彷徨っていた両の瞳の焦点を、虹色の天幕降りた空の狭間に浮ぶ、ほぼ真円に近い月に結んだ。未だ空に残っていた薄雲と、七色の輝きを帯びた不気味な帯にその姿を汚されてはいるが、リトゥエはそれに向かって迷わず両手を掲げ、心の中でただ一言、己の『源流』の名を叫ぶ。
そして、掲げた両手の掌を組み合わせ、ゆっくりと胸の前まで降ろしていく。組み合わされた掌の位置が下がっていくにつれて、彼女の身体の端から光がぽろりぽろりと零れ始めた。そして零れる光が彼女の存在そのものであったかのように、身体が末端部から次々と解け、宙に消えていく。足先が光となり、翼が光となり、腕が光となり、肩が、膝が、腿が、次々と光に包まれ、解けていく。
リトゥエは、己の存在というものを砕き、光として辺りへ散らしていた。
砕き、散らした彼女の概念、限りなく無に近く、限りなく『源流』に近い概念が濃厚に満たされた空間。
元々肉体にそれほど依存しない、概念上の存在に近い妖精達。それもニルフィエといった極めて上位の存在であるならば、場に満たされた己に近しい概念を利用することで、どんなに離れた場所からであろうと、一瞬にして己の身体をその場所で顕在化させることができる。
もっとも、それは二つの存在のうちの一つを砕き、それを触媒にしてもう一つの存在がそこへ実体化するということであり、そこで二つの存在は完全に混ざり合う。そして、元々存在していた二つの力関係に大きな差があった場合は。
「消えちゃうのはイヤだけど、何もかもなくなるわけじゃないし……仕方ないよね」
身体の殆どを光として周囲に散らし、残ったのは頭部だけとなった彼女は苦笑しつつ嘆息。その呼気すらも光となって漂う。髪が解け、頬が融けて、瞳を失い、そして最後に残った唇が言葉を紡ぐ。
「さようなら」
声と共に彼女の全てが光となり、淡く輝く霧がその空間に無音のまま漂う。
輝きは解ける事無く只々揺れて、暫くのあいだ、場にある全ての存在を淡く照らし続けた。
と、その時。
真円に近い月に掛かっていた薄雲がゆるりと動き。
煌々と輝く月光が、完全な形で地上へと舞い降りた。
同時に、空から降り注ぐ月の光を浴びて、【NAME】の周囲に漂っていた霧が、虹色に輝く空にも負けぬ程に煌きを放った。
霧は力強くも儚い輝きを放ちつつ徐々に集うと塊となり、その大きさを変えて、ゆっくりと人の形となる。大きさは丁度人間と同じ程度にまでなり、背と思われる部分からは細く長い羽が一対が伸びる。光の塊が作り出す輪郭は時間を経るごとに精密になっていき、手が、足が、胴が、髪が、顔の輪郭がはっきりと浮び、そして最後に、柔らかな光が何の前触れもなく消えた。
そこに立っていたのは、リトゥエと同じ、紫の髪と紫の衣服に身を包んだ女性だった。
リトゥエよりも遥かに大人びて整った顔と、細く伸びた四肢、そして快活さよりもたおやかさを印象づける衣服。背丈もほぼ人間と同じ程度であり、リトゥエを連想させる要素はせいぜい色と、背から生えた淡い燐光を撒く薄羽くらいしかない。
だが、若干呆然としつつ、己の掌を確かめるように覗き込む彼女には、明らかにリトゥエと同種の気配と呼べるようなものを、自然と身に纏っていた。
己の掌を試す眇めつするように数度動かしたあと、彼女は視線を周囲へと送る。髪と同じ色の瞳が映したのは、未だ微かに残るリトゥエと呼ばれた妖精の概念が作り出した光の欠片と、そして近づく位相の気配を感じてか、彼女の傍らに意識無く倒れ伏して、泥まみれのまま荒く息を吐く人間。
暫しの間、彼女は無言のまま立ち尽くし、両眼をきつく閉じて苦悶に近い表情を浮かべている『刻印者』を見詰めた後、嘆息する。

《……本当に、馬鹿な子》
呟き、己の胸に両手を当て、瞳を閉じる。
それだけで、リトゥエと呼ばれた小妖精が経験した大小様々な事柄が、まるで走馬灯のように彼女の心の内を巡る。自然と、胸に当てた手の力が強まった。
瞳を閉じたまま、胸の奥底から涌き出た熱い吐息を零して、ほんの少しだけ笑みを残した。
《でも──これも私。それで、いいのよね》
未だ顕在化が不安定であるため、呟かれる言葉は空気を震わせるというより、意思がそのまま空間を渡るような、振動というものを介さない声音。
紫の色彩を帯びたその女性は、閉じていた瞼を薄っすらと開くと、
《貴方を、運びます。私の──エルセイドのニルフィエが長、『月夜に咲く女王』の統べる、『聖域』へ》
恐らく、『刻印者』には聞こえていないだろう。
それでも彼女は告げて、ぬかるみに半ば身を埋めた形になっている【NAME】の傍で両膝をつき、未だ淡い輝きが残る掌を、そっと【NAME】の頬に触れさせた。
柔らかく、それでいてどこか褪めた光が【NAME】と彼女を包み、その輝きが残滓となって散る頃には、彼女等の姿は何処かへと消えていた。
虹色に輝く空を、一匹の巨大な竜が駆ける。
彼の身体を包み込む、全身の鱗から感じる気配は、『奈落』を泳ぐ時に感じるような刺激に満ちたものではなく、ただ、どこか纏わりつくような粘り気を帯びるだけのもの。彼に『大気』と呼ばれるものに対する知識は無く、単に己の飛翔を邪魔する感触という程度の認識。どこか満たされぬまま、彼は両翼から飛翔の概念を吐き出し、四方八方に漂う空気を思うままに破砕しつつ、空を駆ける。羽ばたきと共に砕かれた大気は強烈は衝撃となって周囲に飛び散り、竜が飛び去った後には強烈な爆風と、概念の揺らぎを生む波紋、つまり『歪の風』が吹き荒れる。
竜は空間の破砕を楽しみながら空を飛び、その感覚に満足の吼え声を上げた。その巨大な口蓋が限界にまで開かれると同時、『声』と表現するには明らかに異質な、例えるなら何かの爆発にも似た何かが放たれ、音の伝わるにも等しい速度で飛翔していた竜の何倍もの速さで前方へと飛んだ。やや下方へ向かい放たれた咆哮の弾丸は、己の前にある存在を概念ごと次々と破砕して飛び、地上に激突。八方にドーム状の衝撃波を放ったあと、中心に巨大なクレーターを残した。
だが、竜の吼え声一つで己が巻き起こした現象など全く気にも留めぬように、人の頭など遥かに超える大きさを持つ両眼は真っ直ぐに前を見据え、夜の空を駆けて行く。
彼は主の言いつけに従い、彼女が送り込んだ印の在りかを追っていた。
印の位置は、判る。彼の身体に刻まれた刻印──前もってこの概念世界へと送られた印よりも遥かに強力な、『芯なる者』が自らの手で作り上げた象形が刻まれている。刻印が発する位相の気配を読むなど容易いことだ。
彼は、急ぎ己の世界へ戻らなければならなかった。
己が生まれた理由は、彼女が統べる書割の世界を守護するため。彼はそれをはっきりと自覚していた。
しかし、主である彼女からの命であれば、それを曲げることも致し方ない。断れぬものならば、手早く済まそうとするのが道理。彼は己が住む世界と同一の相を持つ印の匂いを鼻で辿りつつ、全力で生温い何か──それをこの世界の人間は空気と表現するのだが──に包まれた場所を駆けていた。
己の鼻に頼らずとも、己と同種の相の気配をはっきりと感じる。彼は無心で空を駆け、距離にして、もうあと一羽ばたきというところで。
──唐突に。
刻印の放つ気配が微塵と消えた。
彼は慌てた。
最高速の状態から身体を起こすと、眼前に広がる大気に思い切り翼を叩きつけ、急制動を掛ける。凄まじい速度で空を駆けていた竜の身体が一瞬にして停止するのと引き換えに、殆ど爆音にも等しい音を立てながら数百メートル単位の空間が一気に破砕された。その波動に飲み込まれた地上の一部がごっそりと剥ぎ取られ、後に残ったのは滑らかに吹き飛ばされた曇りの無い地面。
しかし、被害はそれだけでは収まらない。
彼は突然の目標の消失に混乱し、激怒して、その場をのたうちながら憤怒の咆哮をあげた。
彼が宙でのたうち、咆声をあげる度に、周囲の空間に漂っていた大気が次々と破砕され、その衝撃で空に広がる薄雲や、地表に広がっていた森が次々と弾け、砕けていく。
だが、彼にとってみれば、この世界に在る概念がどれだけ砕けようと知ったことではない。彼が彼女から任された役目は、彼女が送り込んだ十二の印を回収することだ。
しかし、こうして悔しがっていても始まらない。竜は暴れるのを止めると幾度も首を巡らし、刻印が発する気配を追う。先程自分が巻き起こした騒ぎにより、周囲を漂う概念は無茶苦茶になっていたが、彼の鼻はそんな中でも的確に刻印の匂いを嗅ぎ取っていた。
そこで彼は鱗に包まれた鼻頭に皺を寄せ、不機嫌そうに小さく唸った。
刻印と共に感じた匂いは、世界の代弁者を主張する女共の匂いだ。彼の創造主である存在と非友好関係にあった女共。単純な竜の意識の中に憎悪の感情が生まれ、縦に切れ目の入った瞳を細く絞った。
そして彼は追跡を開始する。
己の鼻が感じる匂い自体を破砕させてしまわぬよう、今までとは全く異なるといって良い、ゆっくりとした動きで身体を翻し、空間と空間の狭間を点々と残された二つの概念の痕跡を追い始めた。
花々からの観察者 聖域
──聖域──
既に夜空に散った虹色は薄れ、浮ぶ月と星の青白い輝きが、柔らかく大地に降り注いでいる。
緩やかな傾斜を持つ山を吹き上げる風が、木々の合間を抜けて、微妙な距離を保つ彼女等の髪を撫でていく。
山の斜面を沿うように造られた、幾度も方向を変えて上へ上へと続いていく階段。白色の石階段の繋ぎ目に幾つか設けられた踊り場、その一つに四つの人影がある。

「裏切りか」
冷然とした声が、その緩やかな風を凝らせた。
その声の主は四つの影の内の一つ、髪も、衣服も、燃えるような赤に染まった女性。奇妙なほど整った顔には表情というものが無く、どこか周囲を威圧するような雰囲気がある。
彼女は『焔を纏う女王』と呼ばれる、太陽と炎の概念を秘めたニルフィエの長。

「そぉそぉ。ウラギリウラギリ」
ついで声をあげたのは、その影の中で一つだけ身体と影が接していない、つまり空中に浮んでいる女性。澄んだ色の髪と、他の者達よりは幾分幼い雰囲気を持つ顔には、酷薄そうな笑みが浮んでいる。
彼女は『粉雪に舞う女王』と呼ばれる、風と雪の概念を秘めたニルフィエの長。

「…………」
そんな二人と、彼女等の前に立つ一人の女性。その集団から少し離れた場所で彼女等三人を見詰めたまま黙し、複雑な表情を浮かべているのは、どこか達観したような色を纏う、淡い青色の衣服に身を包んだ女性。
彼女は『碧に揺らぐ女王』と呼ばれる、海と水の概念を秘めたニルフィエの長。
「何時まで沈黙を続ける気だ。答えよ」
焔が再度口を開く。彼女が答えを求めているのは、粉雪でも碧でもない。
森と月の概念を秘めたニルフィエの長。
焔と粉雪の正面で彼女等と相対するように立つ、紫色の髪と衣服に、空に輝く月と同じ淡い白の輝きを纏った女性に対して、だ。
彼女の名は『月夜に咲く女王』という。
裏切り。
確かに、彼女が行っていた事は裏切りと取られても致し方のない行為だった。
『刻印者』の存在概念を縛り、ニルフィエ達の指示通りに動く人形に仕立て上げる為の象形。彼女は、それを『刻印者』に刻み込まず、さらにその事を焔たち他の四女王に対して隠匿したのだ。月夜の巧妙な偽装に加え、『刻印者』が己の意思で、ほぼ『聖域』からの指示通りに動いたことが、発見を遅らせた。
月夜は閉じていた両眼をゆっくりと開く。

(……さて)
ここからが正念場だった。
心の内だけで小さく呟き、彼女は目の前に立つ二人──正確には焔ただ一人──に一度鋭い視線を向け、腹を括る。彼女を説得できるか出来ないかで、自分と、そして【NAME】の運命が決まるのだ。
月夜は自分以外の三人の女王、彼女と同じく、一帯のニルフィエ種を統べる『四女王』と呼ばれる彼女等を順々に見渡し、漸く、薄い紫の走った唇を開いた。
「否定はしません」
その返答に、彼女等は三者三様の表情を浮かべた。粉雪は愉悦、碧は沈痛、そして焔は細く瞳を細めるのみ。
月夜は彼女等が口を開く間を与えず、更に言葉を継いだ。
「ですが、事態は既に『刻印者』の所持する印を封じれば何もかもが終わるという段階ではありません。焔様も、それは判っておられるでしょう」
「無論。だが、だからと言ってお前の罪を見逃す気は無い」
言い切る焔に、月夜は薄く笑みすら浮かべ、答える。
「私をお裁きになりたいのでしたら、どうぞご随意に。ですが、それはあの『竜』と『刻印者』の処遇を決してから。構いませんでしょう?」
今まで表情らしい表情を見せなかった焔の眉が、微かに顰められる。
──『竜』。
それは『刻印者』と呼ばれる【NAME】が、十二の位相守護者全てを屠ると同時にこの世界に『現出』した存在だった。振るう力は位相守護者達の比ではなく、また、己の周囲の相をずらして自らの姿を隠し、内密に『現出』の発生を補助していた彼等とは違い、その巨大極まりない身体を空に晒して、周りにある存在を所構わず破壊し尽くしているという。
月夜のどこか挑むような態度に、両腕を組んだまま宙を浮んでいた粉雪は不満げに数度舌打ちする。
「……相変わらずナマイキ。あんた、あたしらの中で一番ガキだってこと、自覚してないんじゃない?」
見下したような表情を浮べて言い捨てる粉雪。
だが、その言葉に反論したのは月夜ではなく、別の者だった。
彼女等の話が始まってからずっと無言のままでいた碧。彼女が、一歩前に進み出て、口を開く。
「粉雪様。わたくし達にとって、名を継ぐ前に過ごした時など、何の意味もございません。そして『月夜』は『粉雪』よりも遥か古の時より連なる地母。勘違いしていただいては困ります」
「……ああもう、ったく、相変わらず鬱陶しいな、碧は」
今まで沈黙を保っていた碧の言葉に、粉雪は露骨に顔を顰めて鼻を鳴らし、黙り込んだ。
月夜はまた一歩下がり、傍観の姿勢に戻った碧に小さく目礼。今は時間が無いのだ。いちいち粉雪に混ぜ返されては話が全く進まない。
月夜は改めて焔へと向き直る。
「如何でしょうか。焔様が否と言われるのでしたなら、私はどのような罰も今すぐにお受けしますけれど」
告げて、焔の返事を待つ。
だが、焔は直ぐに答える事無く、暫しそのまま沈黙の時間が続いた。
普段ならば所構わず口を挟んでは皮肉を浴びせる粉雪も、焔の前ではあまり無茶はできない。今ばかりは無言のまま──しかし若干不満げに、焔の返答を待つ。
──彼女等四人は、地母種と、そしてそれに連なる妖精達の全てを統べる、いわばニルフィエの頂点に立つ者達といっても良い存在だ。だが、余人の目からは対等に見える彼女等も、実際には優劣というものが存在する。
太陽を司る焔と、月を司る月夜。
四人のうち、決定権を持つのはこの二人だ。粉雪と碧は発言権はあるものの、彼女等二人だけで物事を決めることは適わない。
そして決定権を持つ二人、焔と月夜の間でも優劣は存在する。夜と闇と月、物事の裏の概念を秘めた月夜は、昼と光と太陽の概念を持つ焔を補助する位置付けであり、故に、月夜は焔の決定に逆らうことは出来ない。逆らうには粉雪と碧、この二人の支持を受けることが最低条件だ。
(だけど……)
そこで月夜は内心苦笑し、子供じみた仕草で頬を膨らませている粉雪を眺める。
碧とは良好といっても良い間柄だが、月夜と粉雪との関係は、最低と言っても過言ではない。故に、現在の月夜に焔の決定を覆すことはまず不可能だ。
もし、ここで彼女が即座に自分を裁き、自分の崩滅、もしくは拘束を告げたなら全ては終りだ。だが、月夜は彼女がそうすることは万に一つも無いと読んでいた。
そして、どれだけの時間が過ぎたのか。
漸く、焔の唇が小さく揺れた。
「仕方あるまい。だが、覚悟しておけ。お前の愚かさが、この事態を招いたことを忘れるな」
大仰に告げる焔に、月夜は思わず漏れた苦笑を隠すように殊勝に頭を垂れた。
(手遅れになるまで気づかなかった癖に、良く言う)
内心ではそう思っていても、やはり彼女の判断に安堵する気持ちは隠せない。小さく吐息をつく。
そこで話が一段落ついたと察したのか、今まで一歩離れた位置で様子を窺っていた碧が、彼女等の傍へ進み出た。
「それで──焔様は『竜』と、そして『刻印者』をどうなさるおつもりなのかしら」
問いに、焔は小さく頷く。
「当初の予定通り、現世界より『刻印者』を放逐する」
「え──」
焔の言葉に、月夜は唖然として言葉を詰らせた。
「お待ちください。【NAME】は既に十二の印を己の力のみで──」
そこまで言って、周囲の女王達の訝しげな視線に月夜は言葉を途切らせた。
「……月夜。【NAME】とは?」
無表情のまま問い掛けてくる焔に、月夜は半ば呆然としつつ理解した。彼女等は、自分達が生贄にしようとした『刻印者』の名前すら覚えていないのだ。
(いや、生贄だからこそ……か)
無意識に握り締めた両の拳が震える。しかし薄い紫に彩られた唇が紡ぐのは、怒りの断片すら感じられぬ静かな言葉。
「──申し訳ありません。『刻印者』は、既に十二の印を己の力のみで押さえ込んでおります。ですので、もう『刻印者』が私達の世界を汚すことはないでしょう」
月夜の言葉に、焔は表情を動かさぬまま、しかし不快げに小さく鼻を鳴らす。
「ふざけるな。あの『芯なる者』が作り上げた印、たかが一人の人間が御せる筈もあるまい。それに、『竜』が追っているのが奴であるならば、あの者がこの世界にいるだけで災いを振りまくことになる。『刻印者』を現世界より移せば、『竜』はそれを追い、この大地を去るだろう。『芯なる者』の眷属が送り込んだ、頚木となる印。その全てを我等の大地より放逐し、奴等とこの世界との縁を断ち切ってから、我等自身の力で、『芯なる者』が残した世界の亀裂を塞ぐ」
「ですが、今更封じたところで、もう『竜』は私達の地へ舞い降りています。もし、刻印の気配が途切れれば、彼の行動はもう予測できません。この世界にある概念を根こそぎ破壊し尽くそうとする可能性も考えられます」
この状況にまでなって未だに護ることしか考えない焔に、月夜は苛立ちを隠せない。だが、焔はそんな彼女をどこか見下すように眺めるだけだ。
「あの『竜』の眼の前で『刻印者』を放逐する。奴の目的は明らかに刻印だ、眼前に餌を釣られれば否が応にも追わざるを得まい。そして、奴等がこの世界へ接触するために用いている『洞』さえ塞いでしまえば、もう我等の世界へ干渉する術は無い。これで全ては収まる」
「──また『刻印者』を生贄にするつもりですか。そんな、不確実な計画のために」
「たかだか人の子一人の命と、我等が長い時を経て慈しみ育てた大地。どちらが重いかは考えるまでもない。それに、『竜』と同じく『刻印者』という存在自体も危険なのだ。奴がこの世界に居る限り、亀裂を塞ぐこともできん。扱い辛い、邪魔な存在だ」
焔の言葉に、月夜の表情が変わる。その端正な顔を彩るのは明確な怒りの意思だ。
「そのような……犠牲など必要ありません。そして、憂いは完全に断つべきです。私達の大地に『芯なる者』達が刻んだ『洞』は、あれだけではない。今、彼等が用いている『洞』を閉じても、他の『洞』を利用してこの世界へ現れることが無いとは言えません。そんな方法では、いつまた同じようなことが起きるか」
そこで初めて、焔の表情に変化が起こる。深い苦渋に満ちた顔からは、彼女の内心の口惜しさを感じさせた。
「断てる筈も無かろう。我等地母種はこの世界の概念が生んだ大地の代弁者。故に、現世界では比類なき力を誇るが、他の芯属共のようにあの忌むべき『奈落』を渡り、他概念世界へ移る力など持たぬ。我等では、『芯なる者』共が作り上げた玩具の箱庭を討ち滅ぼす事はできぬのだから。それとも、お前にはその術があるというのか、月夜?」
「ええ」
間髪入れぬ答えに、焔の両眉が訝しげに寄せられる。
「──なに?」
「私が未だ『妖精騎士』となる者を傍に置いていないことは、焔様もご存知でしょう?」
その言葉に、月夜を除く三人の女王が唖然とした表情となった。
「……正気か?」
「無論です」
「ちょ、月夜! あんた何言ってるのさ!? 誰の犠牲を出さないとか言って、自分がそれになってたら一緒じゃんよ!」
昂ぶった声で詰め寄る粉雪に、月夜は意外なものを見るような視線を向けつつも、半ば笑みすら浮かべて答える。
「責任を取るとは、そういうことです。皆が持つ『妖精騎士』は現世の者故、私達とは相を逸したあの『竜』を完全に屠ることも、『奈落』を渡り箱庭を撃つこともできない。ですが、既にあちらの世界の住人に近い『刻印者』である【NAME】ならば、彼の者を討つことも適いましょう。そして、私と【NAME】が契りを結べば、私自身の相もそちらへ近づきます。私の力も、ある程度は通用する筈です」
「月夜様──あなた、ご自分がどういうことになるのか、本当にお判りになっていらっしゃいますの?」
堪らず、碧は口を開いた。
「わたくし達は、この世界の概念上でのみ在ることができる特殊な存在です。この世界の力と、『芯なる者』の象形の力を得た『刻印者』ならば『竜』も、そして他概念に潜む箱庭すらも破壊することは可能かも知れませんわ。ですけど、己が概念の相を他概念世界に近づけるということは、元々強くこの世界に依存しているあなたの存在自体を揺らがせて──」
碧はそこまで言って、己の言葉に改めて愕然とする。
この月夜と呼ばれるニルフィエは、半ば己の身を犠牲にして、あの『竜』と、『芯なる者』が作り出したという箱庭の世界を破壊すると言っているのだ。
「『刻印者』と共に、あなた自身も逝く、おつもりですか……?」
──今代の『焔』と、そして『月夜』は特異な存在といえた。
本来、『焔』の名を継ぐニルフィエは攻撃的で感情的、革新的な考えを持つ者が多く、替わりに『月夜』の名を継ぐニルフィエは受動的で保守的、冷静ではあるが、悪く言えば事なかれ主義な性質を持つ者となるのが普通だった。
だが、今代の二人は、その性質をそのまま反転させたような性格だった。
焔は常に冷徹で規律に厳格であり、月夜は酷く感傷的で、自然の理に離れた妖精達に対しても慈愛の念をもって接するような性格だった。焔はそのことを然して気にしている様子はなかったが、月夜は、自分が歴代の『月夜』らしからぬ性質を持っていることを酷く気に掛けており、己の心を殺して『月夜』として振舞おうと心がけるさまは、古くからの彼女を知る碧にとっては心の痛む光景だった。
ふと、碧はいつか聞いた言葉を思い出す。
『自分の「分け身」に説教されました。……もっと自分に素直になれ、と』
(これが……その結果?)
碧は諦観の混じった苦い笑みを浮べ、ゆるりと頭を振った。
そして、焔は真っ直ぐな眼を向けてくる月夜を無言のまま見返し、数秒。
浅く、吐息する。
「良かろう。だが『刻印者』が、我々の執り行う『騎士の審判』に合することができなかったその時は──」
「承知しております。『刻印者』の放逐、私も支持致します。そして──『月夜』の名も、他の者に譲りましょう。継承儀は碧様にお願いいたします」
その答えに、粉雪がつくづく呆れたように両手を挙げて首を左右に振ってみせる。
「……ホント馬鹿ね。それじゃ、どっちにしたってあんた、もう『月夜』じゃなくなっちゃうじゃん」
月夜はただ笑みを浮かべるだけ。
焔はその場に居る三人の女王をそれぞれ一瞥した後、
「幸いなことに『竜』の動きは鈍い。『騎士の審判』の刻限である、太陽と月の狭間の時までに奴が『聖域』に辿りつくことはなかろう。それまでは思うように時を過ごせ」
言って、両眼を閉じて背を向ける。
「──以上だ。皆、ご苦労」
彼女はそのまま、乳白に近い硬質の階段を屹然とした足取りで下りていく。
宙に浮んで両腕を組んでいた粉雪は、一度不機嫌そうに鼻を鳴らして、じっと立ち尽くしている月夜を睨んだ後、階段の脇に広がる木々の暗がりへと姿を消した。
彼女等より一歩離れた位置に立っていた碧は焔と粉雪を見送ったのち、何か言いたげに月夜に向かって数度唇を動かして──結局何も言わずに深い吐息。無言のまま、その場を去っていった。
最後に残ったのは月夜。
三人の女王が去って、彼女は漸く垂れていた頭を少し上げて、背後へ。山の頂上がある方角を見上げる。
その視線の先には、幾重にも折れ曲がる白の階段と深い緑を織り成す木々の狭間に浮ぶ、澄んだ水にも近い滑らかな色彩がある。【NAME】を封印している結界の上辺だ。
「……【NAME】と、話さないとね」
彼女はぽつりと呟くと、山の頂上を目指し、ゆっくりと歩き出した。
竜は苛立っていた。
彼が予想していた以上に、消えた刻印の痕跡を追うのは困難な作業だった。
世界に点々と残された刻印の気配は酷く微弱で、しかも残された気配の周囲には必ずといって良いほど、それを打ち消すほどの強大な力の痕跡が残されており、竜の鼻はそれに惑わされる。
しかし、竜は確実に追う。
彼は生粋の狩猟者だからだ。
無尽蔵の形態をもつ『奈落』の者の気配を感じて、彼女の世界を狙う者共を打ち滅ぼす狩人。それが彼だ。
竜は感覚を研ぎ澄まし、己と同種の気配を探す。
その時、彼の鋭敏な嗅覚が何かを捕らえた。鼻先が小さく揺れる。
中空に残された微細な刻印の気配。竜が浮ぶ小さな湖より遠く離れた、周りを囲む深く濃い木々の概念で巧妙に隠蔽されたその気配を、竜の鼻は逃す事無く感じ取る。
竜はその気配を破砕させぬよう、細心の注意を払いつつ翼を動かし、硬質の鱗で護られたその身を滑らせた。

「──【NAME】」
声がした。
何枚もの硝子を通したような、鈍い、歪んだ声。
「聞こえていますか? 【NAME】」
もう一度呼ばれる。今度は先刻の声より、確かに聞こえる。
貴方は、ぼう、としていた意識を徐々に覚醒させる。どうやら、いつの間にか気を失っていたらしい。
眼を開け、現状を把握しようと視線を動かし、そこで貴方は金縛りにあったように身を強張らせた。
全てが、薄い青の色に閉ざされていた。
全身に何か弾力のあるものが纏わりついており、身体を動かそうとしても直ぐに元の姿勢、両腕を左右に広げた十字を作る姿勢に戻されてしまう。どうやらこの視界を覆う青色が自分をその内に閉じ込めているらしい。
「動いてはなりません。無理に動けば、貴方の概念に傷がつきます」
そこに、新たな声。
貴方はそこから脱するのを諦めると、その声の主を探し、目を凝らす。周りを囲う青い色は薄く、外の景色を見通すのは容易だった。
白色の石畳らしき地面から少し浮いた位置に自分の身体があり、左右には傾斜のついた濃い緑が広がっている。そして眼の前には紫色のたおやかな影が立ち、柔らかな笑みを浮かべてこちらを見上げていた。
人間の成人女性とほぼ同程度の背丈。だが、常人には在りえぬ紫色の髪と、背から生えた二枚の薄羽が、彼女が人間ではないことを報せている。
(妖精……か?)
彼女が、先ほどからこちらに話し掛けている者。それは間違いないだろう。
貴方の視線に、「ここは何処なのか」と、そう尋ねようとしたのを察したのか、その女性は穏やかな笑みのまま唇を動かす。
「クォルルマル大森林はご存知ですね。ここはその南側、『非干渉域』の奥深く、決して人が立ち入ることの出来ぬ、私達ニルフィエの『聖域』です。貴方も、『聖域』という言葉なら、何度か聞いた記憶があるでしょう?」
外見通りの柔らかな声音は、青の色を通してでもはっきりと貴方の耳に伝わった。
「私は、『月夜に咲く女王』と申します。エルセイド──森と月の概念を司り、守護するニルフィエ。幾多のニルフィエを統べる四女王が一人」
浮かべた微笑には、こちらの緊張を瞬く間に解きほぐすような何があった。
貴方は彼女に問いかけようとして──口篭る。自分の周りを包んでいる青色越しに、こちらの声が彼女に届くのかどうか。向こうの声が聞こえるのだから、当然こちらの声も向こうに聞こえるはず、そう考えるのが普通だが……今の状況は明らかに普通ではない。
恐る恐る、貴方は眼前に立つ女性に話し掛ける。自分の声が、聞こえているのかと。
尋ねた貴方に、彼女は笑みを深くする。
「ええ、勿論。私、何も話せぬ方に一方的にお話して、それで満足してしまうような嗜好は持っておりませんから。安心してください」
だが、そこまで言ってから、彼女はその柔らかな笑みを翳らせた。
「──でも、事情はお話しなければなりませんよね」
そこで彼女は言葉を切り、小首を傾げて貴方を見る。
「どこから、お話しましょうか。今、何かお訊きになりたいこと、ございます? 私に答えられることでしたら、お答えします」
何もかも知っている。
そう言いたげな表情で微笑む彼女に、貴方は矢継ぎ早に質問を浴びせた。
刻印のこと、守護者のこと。大体、何故自分が今こうして捕らわれているのかもさっぱり判らない。
彼女はその一つ一つに丁寧に答えていく。
「刻印は、古の時代にこの大地を生きた『芯なる者』達が作り出した、宿主の周囲や宿主の相を操作する力を持つ印。そして守護者とはその印を操る者。相という言葉は、貴方には判りづらいかもしれませんけれど、貴方が今まで戦ってきたあの守護者達を思い出せば、判るでしょう?」
言われ、あの位相守護者達と戦ったときの事を思い出す。
彼等の周囲に漂っていた、あの独特の気配。それが、彼女の言う相を操るということなのだろうか。漠然とそう考えるが、確証がない故、断言は出来ない。
だが、鈍い表情で固まる貴方を気にした様子も無く、彼女は言葉を続ける。
「彼らは、この世界の者達とは根本的な相がずれている。本来ならば、貴方達人間ではその姿を見ることすら難しいのです。ですが、貴方はグラジオラスでオルドリュードの刻印を継いだせいで、彼らの姿をはっきりと捉え、崩滅させることが出来た。刻印が増える度に貴方の身体に負荷が掛かっていたのは、その印をこの世界へ送り込んだ者が、宿主である貴方に接触しようとしていたから」
視線だけ動かし、貴方は自分の身体に刻まれた刻印を胡散臭げに見る。最初は呪いのようにも考えていたが、どうやらそれ以上に性質の悪いものであるらしい。
「刻印は、『現出』を起こすための鍵。守護者──いえ、彼らを送り出した者の目的は、私達の世界にある概念を彼らの世界にある概念に摩り替えること。理由は未だ杳として知れません。ですが、彼らの行っている所業は、この大地と共に在り、それを慈しみ生きる私達にとって許されざることです」
彼女の紫の瞳のうちに、小さな怒りの火が灯るのが感じられた。
「今、貴方を包んでいるその結晶は、貴方の動きを封じると共に……完全とは言えませんが、その刻印の力も封じています。本当はこんなことしたくないのだけど……『芯なる者』の箱庭から新たに送り込まれてきた『竜』が、貴方の刻印を追っているのです。感じませんか? 貴方の刻印が」
言われてみれば、身体に刻まれた十二の刻印が、ぢりぢりと疼いている。
頷く貴方に、彼女も小さな頷きで返す。
「貴方をここへ運ぶ時に残した痕跡を追って、『竜』はこちらへ向かっています。リトゥエが私を呼ぶことを躊躇った故の事ですが……他のニルフィエならともかく、私は到底、あの子を責める気にはなれません」
眼を伏せて、沈痛な面持ちのまま告げる彼女の言葉に、貴方は、はたと気づく。
そうだ、リトゥエだ。
いつも自分の傍に居た、あの小さな妖精の姿がどこにも無い。
貴方は反射的に彼女の姿を探し、周囲を見回そうとするが、青色の弾力に阻まれ動くこともできない。
「リトゥエ、ですか?」
月夜の表情に、より暗が混じる。
「お話づらいことなのですが……もう『リトゥエ』という妖精は存在致しません」
唐突な言葉に、貴方は唖然として、眼の前に立つ月夜を見る。
自分が気を失っている間に、死んでしまった、のか?
困惑しつつ尋ねれば、月夜は少し迷うような、考え込むような雰囲気。
「死んだ──とは少し意味合いが違うのですけど。今は私の一部となり、その記憶が細々と受け継がれるのみです」
そこで月夜は何かを思い出したように、小さく微笑む。
「そういえば、『私』の事を詳しく貴方に話したことは、一度もありませんでしたね」
彼女の奇妙な物言いに貴方は暫し考え込み、そして頷く。
今まで長い間、あの妖精と共に五王朝中を旅して廻ったが、彼女自身の話を聞いたことは、数えるほどしかなかった気がする。
「リトゥエという流翼種の妖精は、私、『月夜に咲く女王』が生み出した『分け身』です。強い力を持つニルフィエは、自分の存在を複写することによって、個体を増やすことができます。リトゥエもそれによって生まれた妖精の一人でした」
月夜は貴方から視線を外すと、ゆっくりとした動作で歩き出す。石畳の上に結界で縛られた貴方の周囲を円を描くように。
「彼女は『観察者』という役目を持っていました。殆ど『聖域』を出ることは適わぬ私の慰めとして、森の外にある様々な物や出来事、そして貴方達人間の暮らし。そういった事を知るためだけに造られた子。だから、何かと戦うような力は殆ど持っていなかったし……貴方と居ても、あまり役に立たなかったよね」
時折、丁寧な彼女の口調が唐突に崩れ、いつも耳慣れた妖精のものへ戻る。その様に、何とも言い難い危うさを感じた。
彼女は貴方の一周し、また正面に戻ってくる。
「貴方と一緒に旅するようになったのは単なる偶然だけど、その後、貴方は『刻印者』となって──ほぼ同じ頃に、グローエスの人間達との情報交換でかなりの事実を掴んだ私達は、『現出』を留める為に貴方を利用する計画を練りました。──リトゥエの掌にあった象形、覚えていますか? あれは本来、貴方の概念を縛り、私達の思うままに操るためのものでした」
思わず頬が引きつった。
位相守護者を倒した後、リトゥエの掌に浮んでいた象形で何度か治療してもらった記憶がある。既に自分は彼女等に操られていると、そういう事なのだろうか。
愕然とする貴方の眼に、真剣な眼差しでこちらを見る月夜の姿が映った。
「大丈夫。彼女はそれを貴方の治療にしか使っていない。今、貴方の周囲に張られている結界がその証拠。貴方を操れることができるなら、そんな結界なんて必要ありませんから」
月夜の細い腕が伸びて、貴方を包む結界に触れる。
「でも、先刻言ったように、リトゥエは強い力を持っていなかったから。十二の刻印が貴方に渡ると同時に現れた『竜』。刻印を追って貴方に迫る『竜』から貴方を逃がすことは、彼女の力では到底不可能でした」
撫でるように柔らかく動いていた掌が、言葉と共に握られ、徐々に力が篭もっていくのがはっきりと見て取れた。
「ですから、彼女は私を呼んだのです。私と彼女は力の差こそあれ、基本的な部分では殆ど同じ概念を持っています。あの子は『リトゥエ』という存在を構成していた概念を砕いて、本来の『私』に近い概念を貴方の周囲に散らした。そして主を失った彼女の概念を使って、私が貴方の傍へと顕在化し、現世界の庇護篤い『聖域』へと運びました」
そこで彼女は言葉を切り、様々な色を絡めた複雑な表情で、笑う。
「判りませんか? 彼女は、自分という存在を無くして、今までの彼女を構成していた全てを、私に託したのです」
深々と、彼女は吐息。
「これで、お話はお終いです。貴方に内密で事を運んだこと、恨んでいただいても構いません。ですが」
そこで彼女は、浮かべていた笑みを潜め、真剣な眼差しで貴方を真っ直ぐに見る。
「『私』は、貴方と一緒に過ごせた時間を、とても大切に思っています。勝手な話だとは思います、でも──今だけは信じて」
貴方は困惑を隠せない。
こうして身体の自由を奪われた上で赤の他人に「信じて」といわれ、素直に頷くことなど出来る筈も無い。
だが、リトゥエとよく似た面差しを持つ彼女の懇願するような言葉を、無碍に拒絶することもできなかった。
沈黙の帳が降りて、ざわめく木々の音だけが辺りを埋める。
暫しの後、無言のままでいる貴方に、月夜は両の瞼を伏せて肩を落とし、細く息を吐く。
「早朝に、『騎士の審判』を行います。そこで貴方には、私を含めた四女王と戦っていただきます。……そしてその戦いに敗北すれば、貴方は私達の手によって、この世界から消し去られることになるでしょう」
顔を伏せたまま、とんでもない事を告げてくる。
「それが、私が他の女王達から引き出すことの出来た最大限の譲歩です。本来なら、貴方の刻印を追う『竜』の鼻先を逸らすため、貴方は問答無用でこの世界と他概念世界の狭間、『奈落』と呼ばれる場所へ投げ出される筈でしたから。でも『騎士の審判』を潜り抜ければ、その計画は取り消しになります。……単に取り消しになるだけで、それで一件落着となる訳ではないのですけどね」
絶句し、答えることも出来ない貴方を置いて、彼女は視線を合わせぬまま背を向けた。
「信じる信じないは、貴方にお任せします。……でも、私は貴方を信じてる。それだけは、忘れないで」
──審判──
全てを紅に染める朝日を背に浴びて、『焔を纏う女王』は厳かに告げる。

「これより、『騎士の審判』を執り行う」
太陽と月の姿が共に空に映る時。東の空から太陽が昇り、西の空へ月が落ちる、ほんの僅かな時分。
山の頂上に広がる白石が敷き詰められた空間。中央に配置された祭壇を思わせるモニュメントと、場の隅に配置された八つの柱。それ以外には何も無い。表面に微細な紋様が描かれた柱のそれぞれからは、薄く輝く幕のようなものが広がり、場の全体を包み込んでいる。
幕の内側には、幾つかの人影。
東側には四つの影。両腕を組み、無表情のまま立つ焔。宙に浮び、指先にまとわりつかせた冷ややかな風を弄んでいる粉雪。腰の前で掌を緩く組み、両眼を伏せて静かに時を待つ碧。そして一歩退いた位置に立ち、何とも言えぬ表情を浮べこちらを見る月夜。
そして西側、彼女等の対面には、封印を解かれ身体の自由を取り戻した貴方の姿がある。
「我等、地母の四女王のそれぞれに相応の傷を負わせることが出来たなら、お前をエルセイドがニルフィエの長『月夜に咲く女王』の『妖精騎士』として認めよう」
(またか……)
貴方は苦笑する。『妖精騎士』などと言う言葉、聞いたことも無い。認められたとして、それが一体何なのだというのだ。
次から次へと知らない言葉が出てきて、そしてそれに対する満足な説明も受けられないまま、事がどんどんと進む。いい加減慣れてきてはいたが、あまり気分の良いものではない。
「ただし、貴様の持つ位相の刻印は封じたままだ。故に、相を変質させることはできん。これは、『竜』にお前の所在を明らかにさせない為だ。もっとも、奴がこの『聖域』の位置を突き止めるのも時間の問題だろうが」
焔が、傍にいる三人の女王に視線だけで合図を送る。彼女等はそれを受けて、姿勢と位置を変えた。戦いの気配が場に満ちていく。
「以上だ。準備は宜しいか、『刻印者』よ」
正直な話、何故彼女等と戦わねばならぬのかも、よく判らない。
だが、戦わずして済む状況でもないのは、彼女等の緊迫した雰囲気で容易に知れた。
「…………」
やるしかない。いつものように貴方は武器を構え、順々に、相手となる者達へ視線を巡らせて、最後の一人で止める。
リトゥエとよく似た容姿と、そして同質の気配を持つ彼女は、貴方の視線を受けて、ふと目を逸らす。
だが、その仕草に何かを思う間もなく、焔が戦いの始まりを宣言する。
「では、行くぞ」
地母の四女王




「審は決した」
焔は、まるでそれが初めから決まっていたことのように、淀みなく告げた。
「我等、地母の四女王は、お前を『月夜に咲く女王』の騎士として、認めぬ」
一瞬、貴方は己の耳を疑った。
「な──」
どこか安堵したような表情で脇に控えていた月夜も、焔の宣告に唖然とした表情を浮かべ絶句している。
自分と彼女等は、少なくとも互角かそれ以上の戦いを繰り広げていた筈だ。そして、彼女等が示した条件は、相応の傷を負わせるということだったが、致命傷とまでは行かなくとも幾度か手応えのある攻撃があった筈だ。完全に無傷という訳でもあるまい。
貴方が困惑したまま立ち尽くしている間に、月夜が強い剣幕で焔に詰め寄る。
「何故です! 概念干渉を封じた私達『地母の四女王』に抗する事ができたなら、『妖精騎士』として承認される。それが『騎士の審判』でしょう!?」
昂ぶった声をあげる月夜とは対照的に、他の女王達の反応は酷く褪めたものだった。
「この程度の力では、芯属はおろか、あの『竜』にすら及ばん」
「そぉよ。今回は特別なんだから。こんなんじゃダメダメ、『奈落』を渡るのも無理なんじゃない?」
「月夜、判って。あなたをここで逝かせるわけには参りませんの。それがわたくし達の総意」
彼女等の返答に、月夜は心底戸惑ったように一歩下がり、
「何を言って──」
そこで、漸く彼女は気づいた。
他の女王達は、初めから【NAME】のことを『妖精騎士』として認める気はなかったのだと。
「貴女達は……」
「お前は下がっていろ。せめてもの情けだ。『刻印者』の放逐は我等が行おう」
月夜の言葉を遮るように焔は一歩前に進み出ると、右手を貴方へと向けた。
伸ばされた彼女の指先が数度踊り、そして次の瞬間、血飛沫が舞った。
「──【NAME】!」
月夜の悲鳴混じりの声が聞こえた。
身体の幾つかの箇所から鋭い痛みが走り、それが眼前に散った赤と繋がる前に、貴方の意識は途切れ、地に倒れる。
「位相よりの干渉に耐えようとしている分、我等、現世の力による干渉には存外弱いな」
呟き、倒れた『刻印者』へ近づこうとした焔の前を、何者かが遮る。
「何のつもりだ、月夜」
「…………」
問い掛けにも無言。しかし両手を広げ、『刻印者』を庇うように立つ月夜の表情は、今までになく厳しいものだった。
「ホントに、あたし達を裏切る気?」
それを傍から他人事のように眺めていた粉雪が、ほとほと呆れたような声音で呟く。その言葉に月夜は完全に激した。
「ふざけないで! 騙したのは貴女達もでしょうに!!」
語気荒く叫ぶ月夜を、三人の女王は複雑な表情で見やる。
と、そこに、歪な匂いが遠く風に乗って訪れる。
風と共に流れてきた奇妙な気配に気づき、その場にいる全員が、空の彼方を見据える。
「『竜』が……来る?」
粉雪が、ぽつりと呟く。
その言葉に我に返ったのか、焔が未だ気を失い倒れたままの【NAME】に向かい、歩き出そうとして──月夜に阻まれ、表情を歪ませる。
「予想より速い、先刻の戦いで感づかれた! 月夜、どけ! もう余裕がない!」
「──煩いッ!」
完全に昂ぶった声と共に、場の隅に建てられていた八つの柱が強烈な光と共に一斉に砕け、破裂した。
同時に、空中に現れた無数の光槍が月夜と焔の間に次々と落下し、彼女等の間を分かつ。
「月夜!!」
槍は次々と降り注ぎ、激しく耳障りな音と共に白色の石畳を次々と破壊していく。
弾けた光槍の飛沫と砕けた石片が飛び交う中、『刻印者』を抱えた月夜が森の奥へと姿を消すのが見えた。
焔は彼女の後を追おうとして──空の彼方より瞬く間にこちらへ迫る歪な気配に忌々しげに舌打ちする。
「……粉雪、碧。月夜は放置し、先に『竜』を留める。我等の『聖域』を冒させる訳には行かない!」
──騎士──
竜が猛る。
彼が追っていた刻印は、すぐ近くにある。
だが、彼の行く手を遮るかのように、竜の起こす破砕の吐息にも揺らがぬ強い概念の集まりがまとわりつき、彼の動きを止め、崩滅させようとする。
竜は、その概念達の名を知っていた。
ニルフィエ、地母の芯属。この世界という概念が自衛のために生み出した姿。
煩わしい。しかし、侮れぬ力を持つ者達。
竜は身体をくねらせて上空へと駆け、両翼を渾身の力を込めて叩きつける。竜の生み出す歪な力により大気が完膚無きまでに破砕され、次々と連鎖して、彼に追いすがろうと空を舞っていた概念達の一部を吹き飛ばす。
ニルフィエ達の間に動揺が走り、彼女等の強固な概念がほんの少しだけ、揺らぐ。
その感触の心地よさに眼を細め、竜は彼女等を破砕させるために動き出す。
彼の身一つでは、複数の芯属の相手をするのは厳しい。だが、今の彼には役目がある。ニルフィエ共の護りを掻い潜り、彼は刻印を手に入れなければならないのだ。
竜は硬質の鱗に包まれた巨体を反転し、鋭く翼をはためかせ、凄まじい勢いで降下した。
地が揺れるほどの強烈な重低音が響き、木々が激しくざわめく。

「今までの『位相守護者』とは、やはり一味が違いますね。相が完全にずれているお陰で、焔達もてこずっているようですし……このままだと、被害が広がるだけ、か」
山の中腹に広がる深い森の只中で、頂上付近で繰り広げられている『聖域』のニルフィエと『竜』との戦いを見ていた月夜は忌々しげに呟く。貴方の身体に触れていた手に微妙な力が篭もるのが感じ取れた。
先刻の焔達との争いの後、『竜』の襲撃のお陰で何とか彼女等の手から逃げ切った月夜と貴方は、適当な幹に身を預け、焔に負わされた傷の手当てを受けていた。
月夜の掌に灯る輝きが貴方の身体に染み、傷がゆっくりとではあるが癒されていく。
「これで大丈夫な筈ですが──立てますか?」
月夜が地についていた両膝を立てて、離れる。貴方も幹に手を付きながら立ち上がり、身体の具合を確かめる。筋肉や皮膚の強張りは無く、痛みもそれ程無い。
礼を告げた貴方に、彼女は数度頭を振る。
「いえ、構いません。それより……【NAME】、よく聞いてください。今から貴方を、私の『騎士』とします」
その言葉に、先刻戦った赤毛の妖精が言っていたことを思い出す。
確か『妖精騎士』、だったか。
そう、確かめるように呟いた貴方に、月夜は小さく頷く。
「ええ。ニルフィエである私と概念を混じり合わせれば、より現世界との繋がりが深まります。そうすれば、貴方は位相の者ながらも私達ニルフィエの助力を得て、身に刻まれた刻印を操り『現出』を止め、あの『竜』を打ち滅ぼすことも容易となる筈です。あの『竜』の目的は貴方の刻印です。逃げ切れぬなら、断ち切るしかありません」
そこで、真剣に見詰めてくる彼女の瞳に、迷うような色が一瞬混じる。
「ですが、一度契ればもう二度と結びが解けることはありません。貴方はいつか命の灯が消えて大地の欠片となって沈むまで、私と共に在らねばなりません。ですから、貴方が拒むなら、無理強いは致しませんが──構いません、か?」
今更な問いに、貴方は小さく嘆息した後、頷く。大体、拒めるような状況でもない。
「そう言ってくれると、思っていました」
貴方の返答に、月夜は柔らかく微笑んだ。
「前に、言ったでしょう? 私はあの子と──いえ、あの子は私そのものなの。だから、貴方のことも、良く知っている」
口調が、少しずつ変わっていく。
どこか落ち着いた雰囲気を持つ涼やかな声から、あの賑やかな小さな妖精を思わせる声音へ。
「大丈夫だから。私に、心を預けて」
月夜は貴方の背後へ動くと、両腕を伸ばし、その背を抱く。
『これは盟約でなく、契約でなく、遥か古より伝わる約束事。
だからこそ、存在の絆を結び、概念の繋がりを刻む、唯一にして無二のもの。
汝は我と共にあり、我は汝と共にある事を、ただ願う。
これは盟約では結べぬ絆、これは契約では記せぬ印。
思いだけが互いを紡ぐ、遠い古より受け継がれた約束事』
それは囁きにも似た声。
しかし、彼女の言葉は一言も宙に消える事無く貴方の耳に伝わり、彼女の魂、のようなものが貴方の身体と混じりあう感覚がはっきりと伝わってきた。
「貴方の中に、私の存在があること、判りますか?」
正面に回りこみ、こちらの顔を覗きこんでくる月夜に頷きで返す。確かに、今までとは違う何かが、身体の奥底に根付いたような、そんな感触がある。
「私の強固な概念を使って刻印の侵食を上手く捌いて、刻印が秘めた力だけを引き出して。ある程度は、感覚で判る筈です。刻印の力で、あの『竜』と私達の相を合わせて。そうすれば貴方と、そして私の力が直接『竜』に通じるようになる。……できる?」
そう言われて、出来ないといえる筈も無い。
理屈など欠片も理解できないが、確かに、どうすれば己の内にある刻印と、眼の前に居る彼女から齎される力を扱うことが出来るのかが、感覚的に判る。
顔を上げて、意思を込めて月夜を見れば、彼女は薄く微笑んでこちらに手を伸ばす。
「さあ、行きましょう。この『聖域』は私の力がもっとも高まる場所。だから、今の私と貴方なら、あの『竜』にだって負けやしない」
濃く茂った木々の隙間に見える空、その一角が強く輝く。同時に、激しい破砕音と『歪の風』が辺りを吹きつけた。
しかし、今の【NAME】や月夜にとって『歪の風』など微風にも等しい。瞬きすらせず、その風の先を睨みつける。
風を受けて周囲の樹木が根こそぎ消し飛び、空が開けた。
見上げた貴方の視界に、『聖域』に在るニルフィエ達の攻撃を振り切り、猛々しい吼声を上げながら真っ直ぐにこちらに向かってくる『竜』の姿が映る。
そして、傍らから声。
「──【NAME】、始めましょう」
眼前にまで迫った『竜』が、その巨大な顎を開く。
第十三位相守護者

山の中腹付近、相を操る刻印の力を使って『竜』の攻撃によるダメージを最小限に食い止めつつ、渾身の力を込めた攻撃を連続で繰り出す。それらを纏めて喰らい、『竜』がよろめき、怯む。
「月光よ、彼の者を封ず檻となれ」
間髪入れず、傍らに立つ月夜が涼やかな声をあげる。
『竜』に生まれた隙を突き、月夜が空から降り注ぐ月の輝きを集めた檻で『竜』の身体を捕らえ、地上に叩きつける。
轟音と共に地面が揺るぎ、光の檻や『竜』の身体に触れた幾つもの木々が瞬く間に弾けて宙を舞った。
光の檻に動きを完全に封じられた『竜』は、爆音にも等しい怒声を響かせ、檻を構成する光柱の一本に狙いを定めて強烈な雷弾を放つ。だが、柱に激突した雷弾は檻の内側で弾け、外には細い稲光が数度瞬くのみ。
どうやら、月夜が『竜』の動きをほぼ完全に抑えることに成功したらしい。
貴方は安堵の吐息をついて、一歩前に立つ月夜を見る。が、彼女はまだ力を抜いている様子は無い。
訝しげに眉を寄せて、まだ終わっていないのかと尋ねた貴方に、『竜』が檻の内でのたうち回るその様を無言のまま見詰めていた月夜は、振り向くこと無く告げる。
「【NAME】。今は──『竜』を逃がしましょう」
いきなりの言葉に、貴方は絶句して彼女を見る。
先刻、力を合わせて漸く捕らえた『竜』を、何故に逃がさねばならないのか。
語気荒く問い詰める貴方に、彼女は周囲に広がる森の暗がりに視線を走らせ、貴方にだけ聞こえるような小声で囁く。
「気づきませんか? 焔達が、私達を捕らえようと待ち構えています。『竜』を封じた檻の一部を解き、なるべく周囲に被害を与えぬよう、彼の力を放って、その隙を突きます」
貴方は改めて絶句する。この地母種は、己が暮らしていた森の一部をわざと『竜』に破壊させ、その隙にこの場を離れようと、そう言っているのだ。
唖然とした表情のまま固まる貴方を見て、彼女は自虐的に笑う。
「貴方を『騎士』に迎えた時点で、もう私は彼女達とは共に居られません。貴方に私の概念が混じったように、私にも貴方の概念が、この世界とは異なる位相の概念が混じってしまいましたから。もう──本当は『月夜』でも、ニルフィエですらないのかも知れない」
そして視線を外し、前を見る。彼女の視線の先には、光の檻に包まれ暴れる『竜』の姿。
「大丈夫。被害を大きくすることは私の本意ではありません。上手く『竜』を誘導して見せます。私が合図をしたら、全力で駆け出してください。混乱に乗じて、この場から逃げ出します」
有無も言わさぬ調子で言い切り、彼女は掲げた手の指を複雑に動かす。指先が空間を走る軌跡に沿って淡い光が走り、空中に微細な紋様を描く。
「今です!」
彼女の叫びと共に、『竜』を囲んでいた光の檻の一角が唐突に消え去り、檻の内部で飽和していた『竜』の力が堰を切ったように溢れ出した。『竜』が一際高く鳴く声が響き渡り、一瞬の内に空間を揺るがせ、森の一部を根こそぎ破壊するのが見えた。
ここにいては、どう考えても危険だ。
貴方は未だ複雑な象形を描き続けている月夜を反射的に抱えると、森の中へと身を躍らせる。
「ま、待って! 私なら一人で──」
月夜が戸惑ったような声をあげるが、無視。
背中に感じる激しい破砕音と、ニルフィエ達が上げる声を聞きつつ、貴方は抱えられたまま『竜』の誘導を続けようとする月夜と共に、無我夢中で鬱蒼と茂る森の狭間を駆け抜けた。
──哀愁──
数度、強烈な吐息を吐き出し、『聖域』を構成する森の一部を破砕したのち、『竜』がゆっくりと空へ舞い上がっていく。薄く紫の入った巨躯にまとわりつき散っていく光はニルフィエ達の攻撃によるものだが、『竜』はそれをものともせずに空へと駆け、そしてその姿が朝焼けに染まる空に溶け込み、消えた。
『聖域』の中心よりかなりの距離を置いたクォルルマルの森の外れで、月夜は消えていく『竜』を見上げ、呟いた。

「気配を消したのは、戦いでの負った傷を癒す時間を稼ぐため、か。……駄目です、完全に逃げられました」
立ち止まった彼女に合わせ、数歩先を進んでいた貴方も歩を休めて、振り返った。それに気づいて、月夜が視線を落す。
「参りましたね……。本当なら、少し『竜』を解放して『聖域』のニルフィエ達を牽制した後、直ぐに封じるつもりだったのですが……動きながら象形を描くのは無理があったみたい」
少し困ったような笑顔を浮べ、貴方を見る。
「──どうして、私を連れて逃げたのですか?」
貴方は返答に窮して、沈黙する。
あのような状況下での咄嗟の行動に、いちいち理由を求められても答えられるわけが無い。
無言のままでいる貴方に、月夜は浮かべていた笑みを苦いものへと変える。
「ああ……本当なら、まず先に礼を言うべきですね。……ありがとう」
面と向かって礼を言われると、それはそれで困ってしまう。
貴方は何か言わなければならないように感じて、適当に言葉を捜し、思いついた言葉をそのまま口に出した。
これからどうするのか、と。
そう、これからどうすれば良いのか。何やら凄まじく厄介なことに巻き込まれてる気がするのだが、話のスケールが大きすぎて、どうにもついていけない。
「……どうする、ですか?」
貴方の問いに、月夜は小さく首を傾げてほんの少し眉を顰める。微かに責めるような視線。
「そんなこと、決まっています。先ほどの『竜』、貴方に刻まれた刻印の侵食、そしてこの世界を侵食し続ける『現出』。それらを完全に止めるためには、元凶である『芯なる者』の眷属が潜む世界へ渡り、それを叩くしかありません。貴方が私の力を使って刻印を捻じ伏せれば『現出』はある程度抑制できるでしょうけど、刻印が『芯なる者』が作り出した箱庭の世界と繋がっている限り、私も貴方もこの世界にとって……邪魔者でしかありませんから」
言って、細く息を吐く月夜。
そして小さく嘆息した自分に驚いたように、少し眼を見開いてから、彼女は何かを振り払うように頭を振る。
「ですが、彼等の世界へ渡るには、この世界に開いている『洞』を通り抜ける必要があるのですが、位相の概念が私達の世界へ運ばれる時に使われている筈の亀裂、その位置が……判らないのです」
そこで貴方は首を捻る。
今まで端的に聞いた話では、自分が位相守護者達から受け継いだ刻印自体が『現出』を発生させているような事になっていたと思っていたのだが。
「いえ、貴方の身体に刻まれた刻印は、現世界に送られた位相の概念を、この世界にある概念と溶け込ませるために使われるもの。その刻印自体が『現出』を起こしているわけではありません。言ってみれば、概念の中継に近い役目を持っているのです」
月夜は歩き出す。殆ど人に近い動作だが、薄く草が茂る土を彼女が踏み締めても、物音一つ立たない。まるで草自体が彼女の足を避けるように動いている。
「まず『竜』を追い、徹底的に叩きます。身の危険を感じるほどに痛めつければ、彼は位相の世界──とまではいかなくても、世界と世界の狭間に広がる混沌の『奈落』へと逃げる筈です。その動きを追い、世界の亀裂、彼等が利用している『洞』を探します」
立ち止まっていた貴方の傍へと彼女は移動すると、少し見上げ、貴方と視線を絡ませる。
「でも、私では『竜』の気配を明確には感じ取れない。これは私よりも、同相の刻印を持つ貴方のほうが適任でしょうから。とにかく、色々な場所を虱潰しに巡って──」
そこで月夜は唐突に言葉を切り、鋭い視線を森の奥へと向けた。
釣られて貴方もそちらを見て、気づく。
人間とは異なる独特の気配が幾つか、こちらに近づいてきていることに。
「【NAME】、こっちへ。彼女等に気取られないよう、貴方の刻印の気配を抑えます」
ぐい、と予想以上の力で腕を引っ張られ、近くにあった樹の根元に身を隠す。月夜の唇から細く鋭い言葉が漏れ、それと同時に貴方と月夜の周りに薄い幕が掛かる。
視界の片隅に、無秩序に伸びた木々の隙間を高速ですり抜けていく小妖精達の姿が映る。彼女等は暫しの間探るように飛び回り、そしてこちらに気づく事無く離れていった。
「……案外と、動きが早いですね。当たり前といえば当たり前のことだけれど、それだけ向こうが私達を重要視しているということか」
消えていく妖精の影を見送りながら月夜が独りごちて、軽く手を振るう。ゆるやかな仕草にあわせ、周囲を包んでいた薄い幕が晴れていく。
月夜が先に立ち上がり、貴方の手を取り引く。細くたおやかな腕は様々な装備を身に付けた貴方の身体を容易く引き揚げた。どうやら、腕力のほうは見掛け通りというわけではないらしい。
だが、貴方を片腕だけで引き上げたあと、彼女は少し困ったような表情で己の掌を見る。
「──貴方から漏れる位相の気配と、刻印の侵食。その同時を抑えるためには、身体の顕在化に力を回すのも惜しい、か」
視線を虚空へ、そして考え込むように唇を指を当てて、数秒。
「【NAME】、少しだけ待っていてもらえますか? 今から、身体を変えます。これからのことを考えれば、力の浪費は極力避けねばなりませんから」
身体を変える。
さすが妖精、と言えば良いのか。止める理由があるわけでもないので、半ば呆れた表情のまま貴方は頷く。
その無言の返答に月夜は頷いて、一歩、二歩と下がり、胸の前で両掌を組み合わせ、瞳を閉じた。
ちり、と。
小さな虫が羽を擦り合わせたような音が響き、彼女の周囲を淡く輝く粉粒が舞い始める。
光の粒は徐々にその量を増して、月夜の身体を包み込むように螺旋を描き、廻る。響く音も釣られて大きくなり、耳障りと言うほどではないにしても、無視出来るほどでもない。
そして、螺旋の動きが変わる。
うねるように彼女の周囲を廻っていた光の帯は、ゆっくりとその幅を狭めて、月夜の身体を完全に包み込み始めた。両掌を合わせたまま立つ彼女の姿が光によって徐々に見えなくなり、淡く輝くだけだった光も強さを増して、月夜は間断なく明滅する巨大な白色の球体となって──
次の瞬間、強烈な閃光。
強烈な光を遮るために反射的に腕を掲げた間に、月夜の身体を包んでいた光の膜が解け、粒となり、ちりちりと音を立てながら消えていく。
三度眼を瞬かせる間もなく光は微塵と消えて、後に残ったのは──

「これで、どうでしょう?」
──リトゥエ、だった。
体長15センチほどの大きさの、男とも女とも取れる細身の身体。しかし、今ならばそれが彼でなく彼女であることが判る。
髪と瞳は紫。そして同色の布をぐるりと身体に巻いて、装飾の施された腰紐で縛った衣装。背中から伸びた薄羽が小さく震えるごとに、淡い燐光が零れ落ちた。
だが、どこかが違う。
姿形は、リトゥエと殆ど同じだ。違う部分を探すほうが難しい筈なのに、だ。
「うん、この姿なら、大分力を節約できますね。それに、身も軽いし」
嬉しげに微笑み、裾の短い衣服の端を摘んで、月夜はくるりと廻った。
「…………」
そんな彼女を、貴方は呆然と眺める。
リトゥエが居なくなったと聞かされたのはつい先刻の筈なのだが、何だか酷く長い間、その姿を見ていなかったような気がする。
ふと湧いた懐かしさに顔を綻ばせた貴方に、
「この姿、気に入ってくれていたんですね。あの子、内心色々気にしてたんですけれど」
月夜も口元に手をやって、くすくすと上品に笑ってみせる。
その何気ない仕草と口調、そして内面から滲み出る柔らかな雰囲気に、綻んでいた貴方の顔が少し、強張った。
「どうか、しましたか?」
貴方の変化を敏感に察して、リトゥエの姿をした月夜の表情も曇る。それが余計に違和感を感じさせて、貴方は戸惑ったように問い掛けた。
リトゥエは本当に消えてしまったのか、と。
月夜はその円らな瞳を見開いて暫し固まり、そして酷く寂しげな笑みを浮べ、頷いた。
「はい。もう、彼女は」
場の空気が、一気に暗く、淀んだ。
そして暫しの沈黙の後。
はぁ、と。
月夜が芝居がかった仕草で嘆息すると、にこやかに笑いながら顔を上げた。
「仕方ありませんね。では、あの子に合わせてみましょうか」
脈絡も無く言う月夜に、何を、と問い返す間もなく。
小さな妖精の姿となった彼女は、こほんと小さく咳払いして──
「でさ! 貴方、どこ行く予定なの? 私、何となく南の方行きたいなぁ~、って思ってるんだけど」
それは唐突な言葉で、唐突な口調だった。
「いやさ、貴方、こっちにきて間も無いんでしょ? だから私が色々手伝ってあげようかと思って」
貴方が声を返す間も与えず、彼女は言葉を継いでいく。
「……っていうか、私って人間の街中に一人で居ると結構目立っちゃてさ。なんか変な人が寄りついてくるし。だったら街に居なきゃ良いんだけど、『お役目』があってそういう訳にもね。だから誰か適当な人にひっついていけば大丈夫かなって──」
両腕を組み、顰め面で独りうんうんと首を振り、次の瞬間、その表情はぱっと明るくなった。
「ま、色々役に立つと思うからさ! いーでしょ?」
問い掛ける声は、いつか聞いた懐かしい口調。だが、どこか滑稽さを感じてしまうのは何故なのだろうか。
何も言えずにいる貴方の前で、その小さな妖精は優雅に一礼した後、真剣な表情で貴方を真っ直ぐに見据えた。
「私はエルセイドの『月夜に咲く女王』の系譜に連なる観察者、リトゥエ・アルストロメリア。見ての通り、流翼種・フェイアリィ ──貴方は?」
問う言葉に、貴方は何も声を出す事ができず、固まった。
暫し、無言のまま見詰め合う。
今、目の前にいる存在は、リトゥエではない。それだけは、はっきりと判ってしまう。
リトゥエの姿をし、リトゥエの口調で、いつか聞いた台詞を喋る彼女が、今どういう言葉を待っているのかは自明だった。
だが、言えない。
そのまま、無音の時間が過ぎていく。
貴方の瞳に映りこんだ小さな妖精の表情が、段々と崩れて、泣き笑いに近いものとなる。
そして彼女は、細く唇を震わせて呟いた。
「ダメ、ですか? あの子はもう、本当は居ないけれど、でも──」
酷く心細げに問い掛けてくる、リトゥエの姿を模した妖精に、貴方は頭を振った。
「なら、答えてください」
懇願するような声。その言葉に、貴方は反射的に自分の名を答えてしまう。
眼の前に浮ぶ、リトゥエであってリトゥエでない妖精の顔を、嬉しさと寂しさが綯い交ぜになった表情が彩った。
彼女は背から伸びた薄羽を震わせて貴方の肩に座ると、耳に身を寄せて囁くように呟く。
「これからは、リトゥエと呼んでいただいて構いません。私も、そのように振舞います」
そこで暫し戸惑った気配の後、今までよりも更に細い声で、ぽつりと言う。
「勘違いしないでくださいね。貴方のためを思ってこうしてるわけじゃない。これが……私の夢でもあったから」
視線だけで妖精へと振り返り、儚げな笑みのままこちらを見やる彼女と視線を絡ませた。
「──さあ、行きましょ、【NAME】!」
何かを振り払うように、景気良く叫ぶ妖精。
その言葉に、これまで様々な場所を共に旅した『リトゥエ』という小妖精が、本当にこの世から居なくなってしまった事を、強く、実感した。
花々からの観察者 破砕の護竜
──第十三位相守護者 破砕の護竜──
既に辺りは夜の色。
目指す街の面影が漸く視界の彼方に映った頃。
──ぢり、と。
身体に刻み込まれた刻印が、疼く。
久々の感触に、貴方は少し笑みを浮べる。少し前までは恐怖を呼び込むものでしかなかったこの疼きも、月夜と契ることにより得た力で刻印をほぼ完全に押さえ込んでいる今では、何ということもない。

「【NAME】? もしかして『竜』の気配、感じた?」
貴方の異変を敏感に察して、肩に止まっていたリトゥエ──いや、月夜が、顔を覗き込むように身を乗り出して、尋ねてくる。
問いに頷き武器を引き抜く貴方に、彼女も頷きで返し、ふわりと貴方の肩上から離れていく。
「そう。それなら、この姿では少々やり辛いですね」
月夜の身体の内側から強烈な光が弾け、それは一瞬のうちに等身大の光の球体となる。そしてその光が溶けて消えた後には、ほぼ人と同じ大きさとなったたおやかな影が一つ。細く伸びた美しい羽を震わせ、肩に掛かった後ろ髪を両手で流す。その仕草に合わせて、彼女の髪にまとわりついていた光の欠片が空中に払われ、消える。

「【NAME】。ここは『聖域』ではありませんから、前回のような力は、期待しないで」
警戒するように空を見上げたまま、月夜はこちらを見ずに告げる。
そんな彼女の横顔を眺めながら、貴方は旅の途中で月夜から聞いた話を思い出す。彼女等ニルフィエは己の生まれた故郷から離れれば離れるほど、その力が弱まっていくのだという。クォルルマルの『聖域』より生まれ出でた月夜ならば、前回の戦いよりも力が劣るのは致し方ない。
「──来る」
と、遥か上空を見上げていた月夜。
彼女の視線の先に、激しい光と歪の風を身に纏い、『竜』が中空から染み出すように姿を現した。
凄まじいまでの巨躯と、見る者の心を怯えさせる荒々しい炎を内に秘めた瞳。強烈な威圧感に、貴方は反射的に歯を食いしばる。
月夜が一歩前に進み出て、貴方の身を護るように仄かな燐光を絡ませた手を広げた。
「【NAME】。貴方も私も、ここで彼に負けるわけにはいかない。──必ず、倒しましょう」
第十三位相守護者

『竜』が、砕ける。
あの位相守護者達と同じように、その身体が末端部から徐々に砕けていく。
だが、宙に散った『竜』の欠片は空中で融けて消えず、仄かな輝きを残して宙を漂う。竜の身体が砕けるごとに舞い散る光の粒子は増え、緩やかな螺旋を描きながら空高い一点で集い始める。
「さて、何処へ逃げる気かな?」
貴方の隣に立ち、空の輝きを見上げながら酷く軽い調子で呟く彼女に、貴方は数度目を瞬かせ、その横顔を凝視した。
それに気づいて、月夜もこちらを見る。
「なに? 変な顔して」
見るからに快活な『リトゥエ』の姿でならともかく、淑やかという言葉をそのまま体現したような『月夜』の姿で気安げに話し掛けられると、何より違和感が先についてしまう。
言うと、彼女はどこか照れたような笑み。
「ああ──そう、ですね。……『聖域』を出て、色々しがらみが無くなったから、段々、素が出てきたのかも。ずっと、抑えてきましたから──と、そろそろ『竜』が動きます」
月夜は表情を引き締め、空へ視線を戻す。既に『竜』の身体は完全に光に砕けて輝く球体へと転じ、高い破裂音と共に放電の稲光を纏いながら、中空の一点に浮ぶ。
そして一際高い、空気が割けるような音が響き。
光の球体は、文字通りの光速で空を駆ける矢となって、空の彼方へと飛び去っていく。
「あの方角は──ストレリチア?」
月夜がふわりと空へ浮び、輝きが飛び去った方角を睨むように眺め、考え込むような仕草のまま眉を顰める。
「でも、そんな場所にあるなら、私達がそれに気づかない筈は……」
彼女は小さく独りごちてから、貴方の傍へと舞い降りてゆるりと頭を振った。
「【NAME】。とにかく、あの光を追いましょう」
花々からの観察者 終結
──再会──
もう、何もかもが判らなくなってしまった。
『皆』が居る筈の世界。そう信じていた世界。
だが、そこに『皆』は居なかったのだ。
誰も、彼も、私を造ってくれたファアも。
護りの竜の瞳を通して視えた者達は、
遥か昔に『皆』といがみ合っていた古の女達と、
『皆』に良く似て、それでいて何かが決定的に違う、出来損ないの者。
私は『皆』に逢う為に、全てを賭して世界を繋いだ。
なのに、その世界には既に『皆』が居ない。
……私の為していたことは、一体何だったのだろう。
後に残ったのは、もう殆どの力を失い、壊れ始めた私と、
出来損ないの者と女に傷つけられ、今は私の傍で眠り、傷を癒す護りの竜。
竜は深く傷つき、今は本来の役目である『奈落』の者を払う力も無い。
長い間、探して、探して、漸く見つけた希望の光。
しかし、その光の先に繋がっていたのは絶望の世界だった。
己の心が朽ちていくのがはっきりと判る。
自分を形作る概念が砕け、そこかしこに空隙が生まれていく。
だが、今の私には崩壊に逆らうための拠り処が無い。
打ちのめされた意識の拡散を留めることが出来ない。
だから私は、意識が崩れるに任せ、己の滅びを受け入れようとした。
──そう、受け入れようとしたが故に。
己の概念に空いた隙に、いつ間にか滑り込んでいた混沌の概念。
全てを冒し、混沌の一部とする『奈落』の子等。
護りの竜が眠るうちに、私の世界へ忍び込んできた歪な概念。
その者達の侵食に、私は抗うことが出来なかった。
祈りの街、ストレリチア。
大規模な測量機関を内包する五王朝の学士連盟、そしてグローエス王家の半直轄である『昂壁の翼』。その両者が一般市民に対して発行する地図。基本的に主要都市のみに絞った、簡略化された記述が多いこれらの地図、その全てに、何故かこの長閑な街ストレリチアの名がある。貴方は光となり飛び去った『竜』の後を追い、この街へとやってきていた。
街の様子は、一言でいえば大混乱の真っ最中だった。
少し前の『虹色の夜』の再来。
そして数日前の空の異変──遥か遠方から街上空に飛来した巨大な光と、爆発。
吉兆というにはあまりに物々しすぎる出来事に、街の住人達の間では、重苦しい不安の空気が漂っている。
そんな街の中央。ストレリチアの街で唯一舗装されている大通りを、貴方は硬い表情を浮べ、歩いていた。

「どう? 何か感じる?」
ふと。肩上に止まっていたリトゥエが貴方の頬に身を寄せ、囁くように尋ねてくる。
彼女の問いかけに、少し眉根を寄せる。別段、これといった感触は無いが──改めて、己の身体に刻まれた刻印に、意識を集中してみる。
「…………」
不快な、感覚。
今までとは全く違う、何処かに身体が引き寄せられていくような、そんな感触が鈍くある。それは気づくか気づかないかといった程度の些細なものではあるが、いざ気づいてしまうと酷く癇に障った。
その感触をそのまま言葉として答えると、リトゥエの表情が変わる。快活な小妖精から、森のニルフィエ達を統べていた女王の顔へと。
彼女は暫し唇に指を当てて、考え込むように小さく唸る。
「そう……。なら、どこへ引っ張られているのか、判る? ある程度で構わないから」
問いに、両眼を閉じて先刻よりも意識を集中し、もう一度刻印の感触を確かめる。
月夜の力を借りた今ならば、刻印の持つ力もある程度制御できる。その力を総動員し、引き寄せられていく方向を探る。意識を集中するうち、始めは曖昧だったその感覚は徐々に明確になっていく。
眼を開き、無意識にその方角をじっと見る。それに気づいて、肩上の妖精は何かを思い出すような仕草。
「──あちらは確か、街の中央。教会が、あるところでしたよね。……どういうことだろう。そんな場所に亀裂が開いているなんて、信じられない」
妖精の口調に困惑の色が濃くなる。
リトゥエの言う亀裂。『洞』と呼ばれる、現世界と『奈落』、そして他概念世界とを繋ぐ穴。彼女が言うには『洞』の存在は、傍に近づけば月夜のような芯属以外、人間や普通の動物達にも、その気配のようなものが容易に感じ取れるようになるらしい。そして気配を察した者達は、それを本能的に危険と判断して無意識のうちに近づかなくなるのだという。つまり人里、しかも街の中心に『洞』があるというのは、常識的には到底考えられないことだった。
自分の記憶違いだったのかと、改めてリトゥエに尋ねてみるが、彼女は戸惑いの表情を浮かべたまま貴方の疑問を否定する。
「いえ、確かにそう説明しましたし、事実、その筈なのですが……。私には直に感じられないから、何もいえないけど……そうですね、他に当てがあるわけでもありませんし、行ってみましょうか」
考えても始まらないなら、とにかく行動するしかない。
貴方は止めていた歩みを再開し、街の中央、『教会』へと足を向けた。
その敷地にある建造物群は、街の者達の間では一言、『教会』とだけ呼ばれている。だが、実際のところはかなり大規模なもので、教会という言葉から受けるイメージとは大分異なるものだ。敷地の内外を区切るために設けられた塀は高く二メートル半。西側にある正面門は開いてはいるものの、人の姿は無い。この教会を見物に訪れたと思しき者達は皆、『教会』の中に足を踏み入れる事無く、門の外から見える、漆喰で塗り固められているらしき建造物を眺めるだけで去っていく。貴方の眼からみれば、どこか不思議な光景だったが、周りに居る者達はそれが当然のような様子。
そして、教会の塀を囲む人々の中に、他の者達とは明らかに毛色の違う気配を放つ者達が数人。その姿はごく普通の旅人、もしくは冒険者といった風体だったが、彼等は『教会』ではなく、『教会』を見物に来た人間達に鋭い視線を向けていた。
リトゥエは周囲に鋭い視線を走らせつつ、囁く。
「どうやら、一般人に紛れさせた警備の人間が居ますね。あと……『教会』に結界が、敷いてあります。人の意識に作用して、無意識に門の内側へ入らないよう、ここから去るように仕向けてる。だから街の真中にあるのに、こんなにも人の気配が無い。──【NAME】、『教会』の内部から感じますか?」
貴方は暫し黙考し、頷く。月夜の力を借りた今の自分なら、刻印の微細な反応も逃さず感じ取れる。
この『教会』には、何かがある。
しかし、警備の人間が居るとなると、中に入るのは少々難しくなる。人垣に紛れて監視する類の連中が素直に侵入を許してくれるとは思えない。それに、結界とやらが敷いてあるならば自分たちにもそれが作用するのではないだろうか。
問いに、リトゥエは少し困ったような表情。
「私達は、普通じゃないから。それに警備の者を欺く程度なら私の力でも十分ですし──貴方も刻印の力を使って己の相を変えれば、直ぐに彼等には見えなくなりますよ?」
そう言われると、自分がいよいよ化け物じみて来たような気がして、貴方は苦笑した。
リトゥエの力により警備の者の監視をすり抜けて、『教会』の敷地内へと足を踏み入れる。
大きく開いた庭はどこか荒涼としており、人の気配は全くといって良いほど無い。見える建物は幾つかに分かれて、正面と左右にそれぞれ一棟づつ。正面の建物は屋根が低く、そのため裏には更にもう二棟ほど大きな建造物があるのが微かに判る。
取り敢えず、正面門から真っ直ぐに直進した先に建っていた建造物、その扉を開き、中を窺ってみる。窓から差し込む白い光が所々からみえるだけで他は薄暗く、開いた扉の勢いで舞い上がった埃で視界が霞み、喉が絡んだ。
貴方は不快感を押し込めて、刻印に意識を集中する。
──ここではない。もっと奥だ。
貴方は無言のまま扉を閉めると、建物の外周に沿って伸びる廊下を歩き、奥の建造物目指して歩き出す。建物の中を通って進んだほうが早いのかもしれないが、あの埃の中を歩いていくのは流石に遠慮したい。
濃い暗色の木板の上を歩く。軋みは無く、靴と板の擦れあう硬い音だけが響く。
靴音は人数よりも一つ少ない。貴方の傍らを歩く『月夜』からは衣装の衣ずれの音しかしない。この『教会』には明らかに何かが隠されていると感じた彼女は、『教会』に足を踏み入れる前に、既に『リトゥエ』の姿から『月夜』の姿へと戻っていた。
考え込むような表情で歩いていた月夜が、貴方の視線に気づいて口を開く。
「概念にほんの少しだけ歪みが残っています。人払いの結界の他にも沢山の種類の結界が敷かれているようですね。その中の一つが、周囲の概念の歪みを防いでいる……ような気がします」
この教会には、本当に『洞』があるのかもしれない。
言外に、彼女はそう言っているのだ。
幾つかの建造物を巡り、廊下を渡り、奥まった場所に建つ古ぼけた建物の前へと辿りつく。

「礼拝堂ですね。……【NAME】、ここであってる?」
月夜の問いに貴方は頷く。身体に刻まれた刻印が、この建物の中へと引き寄せられるような感覚が確かにある。この場所で、間違いない筈だ。
貴方は両開きの巨大な扉、錆の浮いた金属製のノブに手を掛けて、ゆっくりと押し開いた。耳障りな音が響き、開いた扉の隙間から差し込んだ光が貴方の影を床に落す。
そこで、違和感。
屋外の光で浮かび上がった床。本来ならば埃に埋め尽くされて、くすんだ白色となっている筈のその床に、本来の色である濃い黒の色が点々と残り、斑に近い模様を描いている。
足跡だった。真新しく、そして複数。
その事が示す事実に思考が辿りつく前に。
「どなたですか?」
突然の、声。
貴方は驚きの視線を声のした方向、薄暗い闇が広がる室内の奥へと向ける。
建物の天井付近にある細く小さな天窓から差し込む光は弱々しく、室内を照らすものはそこから届く点の白。そのため建物の中の全てに眼が届くことは無いが、簡単な構造ならば判る。
貴方が立っている建物の入り口から奥の祭壇らしき場所まで、中央に道を置いて、左右に一対づつ一定間隔で規則正しく並べられた長椅子。その最前列に、闇に紛れた人影が一つ、こちらを見詰め、立っている。
貴方はその人影が何者かを見極めようと、無意識のうちに眼を細めた。
と、その影に動きがあった。
人影の正面に細い輝きの軌跡が走り、それが奇妙な形の文字となって浮んだ。それはすぐさま蛍火を思わせる淡い光を纏った球体となって、室内の中央近くへ音も無く移動する。お陰で建物の中に立ち込めていた闇の気配が若干ではあるが晴れて、薄っすらとではあるが、貴方の眼にその人物の姿形が映る。
恐らくは成人女性、だろう。
にしては少々小柄なため、もしかすれば少年、未成年ということも考えられる。が、大仰な装飾が施された服の上からでも判る身体の線は、明らかに女性のものだった。無骨とも取れる手袋を填めた右手には、細く長い片手剣が握られている。剣は片手用にしては柄が大きいため、本来は両手持ちの剣なのかもしれない。だが左手はその柄には添えられておらず、照明の印章を刻んだあとのためか、胸の高さ。濃い青を主体とした衣服は、一般の人間が着るにしては造りが堅苦しく、国の騎士達が着る制服、礼服のように見える。
そして最も特徴的なのは。
──彼女の髪が、完全な漆黒の色、だったことだ。
その色は、どこかで見たことが、ある。
(彼女は──)
「【NAME】? どうしたの?」
扉を開け放ったまま、呆然と動きを止めてしまった貴方を訝しんだ月夜が、行く手を塞いでいた貴方の手を取り除けて、奥に立つその姿を一目見やり、眼を見開く。
「あの娘──前に私達を襲った『護法』?」
そう、そうだ。
ウスタールの街道で突然現れ、そして戦った後何処かへと姿を消したあの二人組。その片割れの女性。
彼女は扉を開け放ったまま固まる貴方に目を剥き、無意識にであろうが、左手を己の口に押し当てて隠しつつ、声をあげた。

「……驚きました。本当に『刻印者』、ですね。──バドさん、マレーネさん、来てください!」
入り口に立ち尽くす貴方や月夜から視線を外さぬまま、彼女はこの場に居らぬ誰かに呼びかける。
数える程の間もなく、礼拝堂の奥の左右にあった木製の扉、その片方が開く。
そして、そこから姿を現したのは、大きな槍を携えた灰色髪の青年と、濃い赤の長衣を身に纏った少女。
二人のうちの一方、槍を担いだ男はこちらの姿を確認すると露骨に顔を顰め、嫌々といった調子で呻いた。

「うわ、本当に来やがった……」

「貴様、儂の星視を信じておらなんだのか?」
青年の後ろに隠れる形になっていた少女が、立ち止まり槍を浅く構えた青年の脇を抜けて前へ進みつつ、何やら時代掛かった言葉を冷ややかな温度で投げる。
「い、いや、そういう訳じゃないが……信じるのと実際にそうなってみるのとじゃ違うってことだろ」
彼女の言葉に、青年は若干焦ったような声音で返すが、少女はそれを鼻で笑い、最前に置かれた長椅子の前に立つ黒髪の娘の隣まで歩を進める。部屋の真中に伸びた、長椅子と長椅子の隙間で造られた細い道に立ち、無言のままこちらを見上げている。
「何故こんな処に『護法』が……? 私達の動きを読んでいた、ということ?」
問い掛けるような、自問するような月夜に、黒髪の娘とは逆側の長椅子の前へと移動した男が「全くだ」といった調子で数度頷く。
「んで、オレ等も別に策とか練ってないし、どうすんだ、婆さん。まさか、正面切って『刻印者』と殴りあうのか? それはそれでなかなかストロングな選択だとは思うが」
「不要だ。バリード、ノイン、剣を引け。儂等は争うために『刻印者』を待っていた訳ではない」
「そう、なのか?」
男が半眼のまま尋ねるのは傍らに浮ぶ少女。しかし、その栗毛の彼女は男に気を向けることなく、まっすぐにこちらを、貴方と月夜を見据えている。
そこへ、貴方を押しのけるようにして、月夜が一歩前に出る。
目つきが、いつもと違う。
柔らかな面の筈の彼女の顔には、酷く険のある色が乗っており、その横顔に貴方は気圧されるように前を開けた。
「貴方は──『星を視る者』、ですか。昔、幾度か顔を合わせた覚えがありますね」
声色は酷く静か。しかし、今にも弾けそうな何かを無理矢理押さえ込んでいるが故の静けさだ。
マレーネはそんな彼女を常の半眼のまま眺め、何かを思い返すかのようにふむと息をつき、己の幼い輪郭を持つ顎を撫でる。
「月夜殿か。確かに、最後に会ったのはどれほど昔だったか。場所は確か……森の『聖域』で、だったか?」
「ええ。……ですが、そんなこと、今はどうでも良いのです。……何故、貴女がここに居るのですか。『芯なる者』である貴女がこの場所に居るということは、まさか、今回の件は全て貴女が──」
「先に断っておくが」
と、月夜の言を少女が遮る。
「今度のことは儂がやったわけではない。それだけは確実に言える。とはいえ、完全に責任が無い、とは言わんがな。だからこそこうしてわざわざ足を運んでおるわけだしな」
「──そんなこと、判るものですか!」
突然、激した。
あの月夜が、だ。
しかし、マレーネのほうは全く気にする様子も無い。身の丈を超える長さを持つ衣の裾を引きずりながら歩き、屋内の丁度真中あたり、黒髪の娘が放った光源の真下あたりで立ち止まる。視線は月夜ではなく貴方へ真っ直ぐに。
「初見、だったかどうかは忘れたが、儂の名はマレーネ・ウレフ。『芯なる者』達の間での名は『星を視る者』。そしてそこの二人はバリードと……ノイン、だったか。今回は、貴様がこれからやろうとしている事の手伝いをと思ってな、こうして待っていた。儂が直接手を振るえば早いのだが、そういう訳にもいかんので、あくまで手伝い、だがな」
その言葉に、貴方や月夜は勿論、少女の左右に控えていた二人の護法の表情も驚きの色に染まる。
「て、手助けをするのですか──?」
唖然とした黒髪の娘ノインに、マレーネは軽く頷いた。
「こやつらは、儂等と同じように『管理代行者』を討つためにここへ来たのだよ。そうだろう? 月夜殿」
話を振られても、月夜は無言のまま少女を睨むだけ。その顔は険しく、憤怒の形相、と言ってもいい。
「婆さん、まさか『刻印者』と一緒に『管理代行者』ってのを討つつもりか!? 『刻印者』はそいつから力を得てるんだろう、戦えるのか?」
「今、こうしてここに居るのが何よりの証拠だ。『刻印者』と月夜殿は、『管理代行者』の楔を断ち切り、地母種との絆を断ち切り、それ故にここに居る」
言って、そうなのだろう? と、マレーネは視線だけでこちらに問い掛けてくる。
「何故、それを……?」
貴方は頷くことも出来ず、ただ困惑。月夜も先ほどまでの怒りも忘れ、唖然とした様子で呻く。しかし、少女は判っていると言いた気な表情で、返事も出来ぬこちらを見返すと、改めて口を開く。
「だが、その人数で『リンドヴルム』、そして『管理代行者』とやりあうのは辛いであろう? 悪い話ではないと思うがな」
「馬鹿な事を──『芯なる者』と手を組むニルフィエなど、居る筈も無いでしょう!」
言い終わるか終わらないかというタイミングで厳しい声を返す月夜にも、朱眼の少女は動じた様子も無く、手に持った巨大な杖を軽く廻してみせるのみ。薄く笑みすら浮かべる。
「貴様が普通のニルフィエならば、そうだろうな。だが、今はもう違うだろう? それに、貴様等だけでは『奈落』を渡るのは難しかろう。貴様等は『位相領域』の詳細な位置を知らぬだろうし、それ以前に、ニルフィエが他概念世界に渡る手段を知っているわけもない。地母種は本来、この世界でのみ在ることができる存在だからな」
月夜は厳しい表情のまま、歯噛みする。どうやら、それは図星であるらしい。
「どうかね、『刻印者』殿。儂等の助力、欲しくないかね? 居ればそれなりに心強いとは思うがな」
「【NAME】、『芯なる者』を信じてはなりません。どうせ、今度のことだって、あの者達のせいに決まっています。こうして、『芯なる者』が直接介入してくるのがその証拠。彼女等は、己の種が関わらぬ事象には全く興味を持ちませんから」
「それは否定せんがな。だが、それが儂の申し出を断る理由にはならんだろう? 今ここで儂が貴様等を填めたなら、どうなるというのだ。それこそ益が無い。貴様等を滅するつもりならば、わざわざこんな風に、悠長に話などせんよ」
「──その『何者にも優る』という貴女達の慢心が、『外なる者』を呼び寄せ、この世界に混乱を招いたのでしょうが!!」
叫んだ月夜に、マレーネはその表情を暫しの間翳らせて、細く息を吐く。
「判っておるよ。儂等とて、儂等なりにこの故郷たる世界を愛している。だからこそ、儂には手が出せんと言っているのだろうが。『外なる者』共は儂等の力に敏感だしな。……さぁ、どうするね、『刻印者』殿?」
「…………」
真っ直ぐに尋ねられ、貴方は暫しの思案の後、小さく頷いた。
「【NAME】──!! 正気なのですか!?」
あまりの予想外の答えだったのか。
振り返った月夜が、彼女らしからぬ大声で叫ぶが、貴方は興奮した彼女を静めるように、一言一言区切りながら、言い聞かせるように話す。
これは月夜自身が言っていた事だが、彼女は己の故郷である『聖域』から離れれば離れるほど力が弱まるのだという。ならば、『竜』が逃げ込んだ完全な別世界らしき場所へ向かった時、彼女の力はどれほど弱まってしまうのか。それを考えれば、たとえどのような者でも助力を得ておくのが自分達の生還する確率を高める方法だろう。
「それは、そうなのですが……」
しかし、月夜は未だ戸惑うような表情のまま、貴方とマレーネへと交互に視線を泳がせる。その瞳に浮ぶ色から、理屈では納得できても感情では納得できない、という感情が読み取れ、貴方は少し嘆息。仕方なく、とっておきの言葉を引き出す。
これも前に月夜自身が言っていた言葉。
『私は貴方を信じている』
ならば、マレーネ達を信用しようとする自分を、月夜は信じてくれないのか。
「あ……」
問うた貴方を彼女は唖然として見詰め、次いでどこか諦めたような顔。
そして最後にゆっくりと笑みを浮べ、頷いた。
「……そう、ですね。判りました。貴方を、信じます」
表向き頷きを返しつつ、内心安堵する。
咄嗟にあの時の言葉を思い出さなければ、月夜を説得することは難しかっただろう。
「これで話は決まったな」
と、そこへ月夜と貴方の会話が一段落ついたのを察したのか、今まで黙していたマレーネが口を開く。
「ならば、ここにある『洞』を使い、『奈落』へ潜るぞ。あまり悠長にしている場合でもないしな」
「待ちなさい、『星を視る者』。まさか、ここに現世界の亀裂である『洞』があるというのですか? あるとすれば、私や……そしてこの街に住んでいる人間達が気づかぬ筈ありません」
「当然だ。人間は勿論、他の芯属ですら察知されぬように我等が死力を尽くして組み上げた隠匿結界、制御も完璧だ。元より場所をしっていなければ、我とて気づきもせぬよ。事実、貴様等はこの場所に『洞』があることを知らなかったろう? 別にこの『洞』を使わずともマウローゼの世界には渡れるが、縁の深い『洞』を使ったほうが楽だしな」
何気ない風に言ってのける少女に、月夜が悔しげに視線を外す。
「亀裂は──この教会の地下に隠された聖堂の最奥にある」
──封印──
礼拝堂の奥に在る扉は、地下深くへと続く階段へと繋がっていた。
遥か地中の底へ底へ。
延々と続く螺旋の階段を下る。
靴底が鳴らす硬質の音は、両腕を広げる程の幅もない階段の両の壁に反響し、果てしなく降っていく。
そんな中、狭苦しい階段の合間、湿り淀んだ空気の中を幼い声が通り過ぎる。

「──とまあ、そんな処だ。大体の事情は判ったか、『刻印者』殿」
振り向きもせず問うのは、集団の最前に浮び、下へ下へと降っていく栗毛の少女。階段を降りる間に、彼女は今回自分が関わるようになった顛末と、この事件についての情報を延々と話し続けていた。
『芯なる者』が作り上げた『位相領域』と『管理代行者』。
彼女の説明で聞いた限りでは、こちら、というより月夜の予想とそう差異は無い。つまるところ、この奥に在る異世界への入り口である『洞』とやらを通って、『位相領域』に居る『管理代行者』を倒せばよい、そういうことなのだろう。
貴方は納得顔で頷いてみるが、貴方のすぐ脇に居た月夜は、何故か頭痛を抑えるような仕草。

「やっぱり、根本は貴方達『芯なる者』のせいだったんだ……」
深々とした溜息と共に呟かれた声の調子は、どちらかといえばリトゥエに近いものだ。
「だから、初めからそう言っておるだろうに」
が、列の先頭からはにべも無い返答。認めている割に、まるで自分にはまったく責任が無いような、そんな調子。
だが、今彼女が話した内容が真実であるならば、確かに、マレーネ自身には殆ど咎と呼べるようなものは無いのだ。素っ気の無い反応になるのも当然で、こうしてわざわざ出向いているのも完全な義務感でしかないのだろう。
月夜は振り返りもしないマレーネをきつく睨んだ後、背後に視線を送り、浅く吐息。
「気は進みませんね。第一、私達は貴方が連れていた『護法』達に、一度死ぬような目に合わされているのですから」
月夜の視線の先、貴方と彼女の後ろには、巨大な槍を担いだ灰色髪の男と、グローエスの人間にしては珍しい黒髪の娘。
若干の不信を塗した視線を向けられ、まず反応したのは男のほうだ。心外だ、といった風に肩を竦めて見せる。

「ああ? それを言ったらお互い様だろう? こちらだって『刻印者』の起こした『現出』に飲まれかけて死にそうになってるんだがな。なあ、ヴァイヒュント嬢」

「え? あ……ええと、そう言われればそうなのですけど……」
唐突に話を振られ、何かの気を取られていたのか呆とした様子で『刻印者』を眺めていた娘は、びくりと肩を震わせて隣の青年を見上げる。そして数度視線を彷徨わせたあと、困ったような声。
そんな二人を眺めていた月夜は、どこか皮肉気な調子で息を吐く。彼女には珍しい仕草だ。
「貴方達は自業自得です。待ち伏せした上に問答無用で仕掛けておいて」
「あのなぁ──勝手に戦闘態勢に入ったのはそっちだろうが」
呆れ返ったようなバリードの言葉を無視し、月夜は見るからに不愉快といった表情のまま、彼女等から視線を外す。
貴方は意外な表情で、隣に居る月夜の横顔を眺めていた。出会った頃いつも柔らかな微笑を浮かべているだけだった気がするが、最近はこうして色々な表情──怒ったり、不機嫌そうといった類のものが多いが──を見せるようになっていた。違和感、というほどのものではないが、何となく、意外。
「あの」
と、そこで背後から戸惑いを残した声が掛かる。ノインの声だ。
「それよりも、何故貴女があの時のことをご存知なのかが気になるのですが……」
娘の問いに、
「判りません? あの時、【NAME】と共にいた小妖精は『私』でもあるのです。貴方達に容赦なく叩きのめされたことは、今でも鮮明に覚えていますよ」
「────」
青年と娘の顔が引きつる。
「おい、婆さん! 本当に大丈夫なのか? 寝首を掻かれるのは御免だぞ!?」
そんな最後尾からの呼びかけに、最前からあっさりとした返ってきた声が返る。
「知らぬよ。本人達に聞いてみたらどうだ」
「本人って……」
二人分の視線がじっと背中に注がれるが、貴方にしてみればどうにも反応しようが無い。振り返らず、先導するマレーネの小さな背中を追って黙々と階段を降っていった。
そのまま三十分ほど降り続けただろうか。
階段が途切れ、縦横10メートル程の空間へと出る。部屋の至る所に用途の知れぬ品、壁には複雑な印章がいくつか刻まれ、部屋の反対側には一際巨大な紋様、そしてその下には壁に張り付くように極彩色の渦が留まる事無く回転を続けていた。
「これが、『洞』……」
「そうです。そしてあのうねりの先が、『奈落』」
思わず出た呟きに月夜が硬い声で言葉を返し、睨むような視線でそちらを見る。
「『洞』自体は開いてますが、周囲に張った結界は生きていますね。だから、『奈落』の子も近づけないのか……」
周りの者に話し掛けているようにも、単に独りごちているようにも取れる調子で話しつつ、彼女は部屋の奥まで歩を進め、壁に刻まれた巨大な紋様、恐らくは何かの象形と思われるそれの中心を見る。
そこには、上から下へと真っ直ぐに走る、鑿かなにかで削り取ったような歪な線が一本。
「傷、ですか? まだ新しいようですけれど」
今度は明らかに問う声。月夜の振り向いた先には、室内の各所に刻まれている象形の具合を調べていたマレーネの姿がある。
「どこぞの馬鹿が封を解いた痕だ。まあ、こんなものは今更どうでも良い。問題は──」
そこで言葉を切り、マレーネは月夜と、その背後にあるものを流し見る。
うねうねと蠢く極彩の渦。
マレーネや月夜が『洞』と呼ぶ、現世界の弛みに開いた異界へと繋がる穴だ。
「あの、マレーネさん。この穴みたいなものを完全に結界で封じてしまえば、それで解決にはならないのですか?」
どこか戸惑いを残したノインの疑問に答えたのは、問われたマレーネではなく、じっと歪みを見詰めていた月夜だった。
「到底、成り得ません。この世界に開いている『洞』はここだけではないのです」
「え──そう、なんですか?」
意外なところから答えが返ってきたことに目を瞬かせるノインに、月夜は視線は渦へ向けたまま短く頷く。
「世界の至る処に『奈落』へ繋がる歪みは開いていて、この『洞』を閉じても、他の場所を手繰られてしまえばそれで終り。元凶を断たねば、解決とは言えません」
「…………」
はっきりと、己の意思を確かめるように言う月夜に、今まで壁に描かれた象形から視線を外しもしなかったマレーネが、見開いた赤の両眼に驚きの色を乗せて月夜を見る。
その視線に気づいたのか、月夜が訝しげにマレーネを睨む。
「何です?」
「貴様、本当に『月夜』か?」
マレーネの声音に、真面目に疑っている気配を感じ取ったのか、月夜の眼光が更に厳しくなる。元々柔らく優しげな雰囲気を持つ彼女だが、一度表情を引き締めればその雰囲気は微塵もなく消え去る。
「──侮辱しているつもりですか」
月夜の硬い声に、少女は軽く肩を竦めて視線を外した。
「いや。儂の記憶では、貴様はそういう強硬な質を持った存在ではなかった筈だが。元凶を断たねば終わらぬなど、到底貴様の言葉とは思えん。『刻印者』の概念に引っ張られているのか?」
「────」
「まあ、貴様のことなどどちらでも良いが、先刻そこの娘が言ったように結界で封じる、というのは悪くない。が、悪くないというより、今現在、この『洞』は既に結界で閉じられている状態なのだ。上の『教会』の気配を感じ取れるならそれも判るだろう」
ならば、どうして『竜』はこの街へ逃げ去り、そして消えたのか。
「『奈落』の接触は止められるが、『竜』達が持つ相を止める効果が無い、といったところか。応する相が違うのだ。元々この『洞』は奴等専用に開いたような場所だしな、致し方あるまいよ」
そこで、こつこつと神経質そうに地面を叩く音が響き、彼女の言葉を遮る。
音の主は槍の柄。その持ち主である灰色髪の男は、少女の長広舌にうんざりした様子で首を振った。
「婆さん。もう小難しい解説は不要だ。さっさと行って済まそうぜ? どうせ、『管理代行者』ってのを何とかすりゃもう用の無い知識なんだろう?」
「バ、バドさん、そんないい加減な──」
ノインが咎めるような声を出すが、マレーネは軽く笑うだけ。
「まあ、確かにな。では今からやることを順に説明する」
マレーネは手に持った杖を片手だけで廻し、弄ぶ。
「まず儂がその結界を暫くのあいだ弱め、その隙に『管理代行者』が在る世界の相を正確に掴む。『奈落』の内からでは察しづらいので現世界上から察知する。ある程度の位置はツヴァイに聞いておるからそれ程時間も掛からぬだろう。そして、それが終わり次第、眼の前にある『洞』を使い、儂等はそこへ向けて飛び立つ。先に儂がバドと娘を連れて飛ぶ故、【NAME】と月夜殿はその後についてくれば良い。以上だ」
ついてくれば良い、といわれ、貴方は困惑して朱眼の少女を見る。
自分は『奈落』とやらの渡り方など欠片も知らないのだ。ついてこいと言われても、一体どうすれば良いのか。
我ながら情けないと思いつつも、自分よりも遥かに背の低い少女にそう言うと、
「『奈落』の飛び方は貴様の刻印が教えてくれる筈だ。上手く相を整えてやらねば、貴様はともかく月夜殿が崩れるぞ。──いや、『妖精騎士』になっているのだったか? ならば二人で気をつけよ。……だがしかし、何だな」
マレーネは貴方と月夜を順々に眺め、突然くつくつと笑い出す。
月夜の表情が不愉快な色に染まる。少し頬が膨れているせいで、大人びている筈の彼女の顔が酷く幼く見える。
「何故笑いますか」
「いや、月夜殿の『妖精騎士』というのはどうしてこう、厄介な者が多いのかとな。前に会った時も──」
「う──煩い、黙りなさい!」
明らかにからかっている調子のマレーネと、律儀に怒る月夜。らしくないと言えばらしくないが、らしいと言えばらしい。
「『芯なる者』と『地母種』ってのは仲が悪いって聞いていたが……」
「なんだか、そうでもないみたいですね」
そんな二人に傍から見ていたバリードは肩を竦め、ノインもどこか愉快そうに笑った。
月夜との会話を打ち切ると、マレーネは手の持った巨大な杖でこつこつと己の肩を叩きつつ、周りの者達に告げた。
「では、今から結界を弱める。その隙を狙い、『洞』から『奈落』の者が這い出してくるかもしれぬが、それは貴様等で追い返せ」
壁に背を預けていたバリードの身体、ずるり、と滑る。
「な──!? そういうコトは先に言え先に!」
「次からは気をつけよう。さあ、始めるぞ」
「ま、待て! 先に結界を──」
止めるバリードを無視し、部屋の中央に立ったマレーネは杖を両手で水平に構え、両眼を閉じて動きを止める。
同時に、彼女の眼前に馬鹿でかい、としか表現の仕様の無い、縦横三メートル近い象形が一瞬だけ浮び、そして弾けた。
一瞬のうちに、周りの気配が、変わる。
バリードが殆ど反射的に張った結界が、その気配に抗し、ぎしりと現実的な音を立てて軋む。ギリギリのところでその庇護下に入っていたノインが、結界越しに感じる気配に悲鳴に近い声をあげた。
「な、何なんですか、これ──!」
「婆さんが結界を弱めたお陰で、『奈落』が本来持っている気配がこっちに流れ出てんだ──こんなに歪みがでかいと、黒狼も呼べんか。……流動結界に切り替えるから、キミも自分の結界を敷く準備をしろ!」
「私、単体では結界術使えませんっ!」
「──が~、仕方ない、領域結界のままやるか……ヴァイヒュント嬢、オレの傍から離れるなよ! 具体的に言えば半径二メートルと少し!」
「離れたくても離れられませんよ、こんなの!」
室内を埋め尽くすのは異質な気配と異質な色、そして異質な音。
微動だにしなくなったマレーネと、怒鳴りあいながら戦闘の準備を始めた二人の『護法』を眺め、月夜は浅く嘆息。
「……先に報せておいてあげれば、あの二人もあそこまで慌てなくて済むものを。『芯なる者』達は、どの者達も総じて自分本位なのですよね」
不思議なことに、月夜の周囲には『奈落』の渦から噴出する気配が入り込めないようだ。
まるで『奈落』の気配が、彼女の存在自体を恐れるような、そんな動き。
「ここは現世界ですからね。私の概念はそれを顕在化させたものですから。私が私の領域に居る限り、混沌の概念は私に近づくことはできません。私達ならば流れ込んできた概念を一瞬で整調し、この世界の一部とすることができますから。──それより、【NAME】は大丈夫ですか?」
いつもと同じような調子で尋ねてくる彼女の言葉に、貴方は己の身体を見下ろす。
身体に刻まれた十二の印が独りでに輝き、自分の全身を覆っていた。
貴方は軽く肩を竦める。月夜との契約のお陰なのか、勝手にこちらの身体を護ってくれるというのだから、全く、便利なものだ。
「大丈夫、のようですね。──『妖精騎士』としての私との繋がりより、『刻印者』としての力のほうが上、か」
そんな、どこか拗ねたような声を掻き消すように、広間に響く異音が更に高まっていく。
妖しく蠢き輝く『洞』から、何か、極めて異形の存在がこちらの世界に這い出してくる。月夜はそれを一瞥し、己の力を解放する。
「早速、来ます。【NAME】──構えて」
月夜の警告の声に、貴方は素早く武器を抜き放ち、その存在に立ち向かう!
奈落の子



異質。
その渦より現れる化け物達は、正に異質極まりない存在だった。
五感全てがその在り得ざる気配を感じ取り、無音の悲鳴をあげる。
常人ならば、数秒と持たずして発狂し、死に絶えるような、そんな空気が場に満ちている。
──しかし。
今の自分は、常人ではない。
本能があげる悲鳴を無視し、身体に刻まれた十二の刻印を無意識に操り、己の相をその混沌の気配に近づけ、そして叩く。
声とも呼べぬ声をあげ、化け物の身体がぢりと崩れる。概念の繋がりが解け、壁に開いた混沌の色渦巻く『洞』の中へと消えていく。
全身に漲らせていた力を抜くと、ひゅう、と栓が抜けたような吐息が出た。周りを見渡せば、貴方の傍らに居る月夜と、少し離れた場所で背中あわせのまま戦っていた二人の『護法』も、似たような様子で息をついている。
どうやら、一段落着いたらしい。
貴方の視線に気づいて、バリードがひらひらとこちらに手を振ってみせる。
「いやはや。流石だな、『刻印者』。この中を結界も無しに動けるか」
心底呆れたといった調子の声には、若干の疲れも混じっている。常時『奈落』から吹きつける異質な概念に抗するための結界を張り続け、更に這い出てきた異形と戦っていれば疲れもするだろう。
その背後には顔を伏せたノインの姿。青年の隣でなにやらぐったりと肩を落としているが、別に酷い怪我をした様子も無く、単に落ち込んでいるだけらしい。
「……私、この件が終わったら絶対に結界術を習うことにします……」
というような事を鬱々とした声で呟いているが、そこまで落ち込むようなことなのか、他人の眼からは今ひとつ理解できない。
「…………」
と、広間の中央で動きを止めていたマレーネの身体が揺れて、ゆっくりと眼を開いた。
「ご苦労。バリード、娘、こちらに来い。マウローゼの位置は掴んだ、さっそく『奈落』に降りる」
「あ、はい」
マレーネの言葉に、まずノインが慌てたように動き、その後ろからバリードが胡散臭げな表情のままゆっくりと歩く。
「しっかし、ホントに大丈夫なんだろうな、婆さん」
「儂の傍より離れなければな。貴様等が耐えられるように、概念の整調だけは行う。──『刻印者』、遅れるなよ」
ノインとバリードが己の傍に移動したのを確認した後、貴方と月夜を流し見てから、マレーネは手に持った杖を振るう。
彼女等が去った後、月夜の表情が冴えないことに気づき、声を掛ける。すると彼女は一瞬戸惑ったように眉をあげて、ついで苦笑。
「……少しだけ、怖い……のかもしれません」
怖い。
まさか、彼女からそういう言葉を聞くとは思わなかった。
貴方の率直な意見に、彼女は苦笑の色を濃くする。
「今はまだ現世界にいるから、先ほどのような『奈落』の混沌に己の概念が屈することはありません。ですが、前にも言った通り私の力は現世界にあってこそのもの。彼等の領域に飛び込んでしまえば、その限りではありませんから」
月夜のようなニルフィエ種は、この世界にある概念を力の源とする。故に、その庇護を受けられない、世界と世界の狭間である『奈落』へ移れば、その力は大幅に減退する。
月夜は心を落ち着けるように一度細く息をつき、目を伏せる。
だが、それも一瞬。
彼女が次に視線をあげたときには、その顔にはただ決意の色だけがあった。
「でも、ここで引き返すわけにも参りません。……【NAME】、貴方の中にある私の概念を含めて、『奈落』の相に抗えるよう、お願いできますか」
右の掌を両手で取られる。
貴方は彼女の声に答えるように、己の刻印に意識を集中すると、身体に一段と強い輝きが宿り、その光は月夜の身体にも伝染する。
幾度か具合を確かめるように掌を握り込んでみたりもしたが、正直なところ、これで大丈夫なのかどうかは良く判らない。今までの経験から、刻印に意識を集中し、漠然とした願望を思い浮かべれば、それが可能なものである限り刻印が反応し、勝手に『何か』を行ってくれるのは知っていたが……今纏った光の膜が、『奈落』とやらを渡る力となりえるのかどうか、それすらもはっきりと判らない。
「では、参りましょう」
だが、月夜は完全に信じ切った声で、そう告げる。
ならば、たとえ仮初めのものであれ、自分も自分の力を信じなければならないだろう。
眼前で渦巻く『奈落』への入り口を見る。先行したマレーネの気配は──何とか、感じられる。
貴方は意を決すると、月夜と共に『奈落』の中へと身を躍らせた。
──奈落──
視界の全てを埋め尽くすのは、無数の色彩が混じり合った混沌の風景。数え切れぬほどの色が重なっている故にそれぞれの彩は濃く、暗色混じりの世界はどこか毒々しく、熟れて腐った果実を思わせる。
重力は無く、まるで質量の無い水の中を泳ぐような感触。
──この『奈落』という場所を例えるなら。
世界という一つの場が生まれる前の、全ての概念が混じり合う極彩の場。
そう──始原だ。
始原の海。
それが最も相応しい。
明らかに異常な景色に包まれながら、貴方は混乱するでもなく、呆とした意識でそんなことを考える。
それぞれの世界はこの海より生まれ出でて、そして息絶えた時にこの海の中へと還る。
全ての始まりであり、全ての終り。
己の子たる世界を見守る、母なる混沌。

「普通に考えるなら、ある世界で生まれた存在はそこから外へ出る、つまり『奈落』を渡ることはできない。でも中には例外が居ます。それが先ほどの『星を視る者』のような『芯なる者』達。貴方達人間が芯属と呼ぶ者達も、その殆どは『世界』と言う檻に捕らわれません。例外は──私達ニルフィエくらいのものです」
説明する声は、貴方の耳ではなく頭に直接響くように伝わってくる。
いや──正確には、右の掌に感じられる暖かさから。
視覚は無数の極彩に封じられて己の身体すら見えず、他の感覚も殆ど役に立たない。生きているのは触覚と──刻印から伝わる、言うなれば『第六感』とも称することができる独特の感覚。
眼には見えないが、傍にははっきりと月夜の気配が感じられた。先行するマレーネ達の気配も直ぐ近くに在る。そして。
(……そして?)
先刻よりも強く、自身の身体に刻まれた十二の刻印に意識を集中する。
──ぢりぢりと。
十二の刻印が疼き、貴方の意識に警戒を促す。
『奈落』を泳ぐ自分達を追うように迫る、無数の概念。それは『存在』と呼ぶのも疑わしい、絶え間なく揺らぐ混沌の気配だ。ただ、周囲の『奈落』より、その濃度が強い故に感じ取れる歪。
そして、近づく気配には、覚えがある。
先ほど『教会』の地下に開いた『洞』で戦った、文字通りの化け物共と良く似た気配。マレーネが『奈落の子』と称していたあの存在達の気配だ。
気配はこちらに向かってぐんぐんと迫り、追いつかれるのは確実。
ならば迎え撃つしかないわけだが──今の自分は殆どの感覚は封じられ、あるのは刻印から伝わってくる気配と、掌にある月夜の感覚だけ。いつものように刻印が勝手に力を発して撃退してくれるなら良いのだが、そんな確実性の無いものに己の命を委ねきる気は無い。
無い、のだが……かといって、何か策が思いつくわけでもなく。
どうしたものかと暫し迷い、ふと、己の掌にある感覚を思い出して、その掌を介して月夜へと問い掛ける。彼女ならば、何か策があるかもしれない。
しかし、掌から返って来た意識は、どこか困惑したような感情。ついで、無音の声として貴方の脳に彼女の声が響く。
「ごめんなさい、今の私には、何も。私には貴方が言う気配すら感じられませんが──でも、貴方がそう感じるならば、きっとそうなんでしょうね」
そこで、月夜の意思は沈黙。微かな焦りの気配が掌から伝わってくるということは、彼女にも具体的な策が思い浮かばないのだろう。
そうこうしている間にも、こちらを追ってくる気配はどんどんと間を詰めてくる。物理的に距離が狭まる、というよりはその存在がどんどんと貴方の意識のなかで大きくなっていくような感覚。心が極彩の渦に掻き回されるようで、到底気持ちの良いものではない。
と、その時。
唐突に、視界を埋める極彩の色に包まれた領域、その一角が開けた。
毒花を思わせる『奈落』の只中に球状で現れたその空間は、中央に一枚の白板を思わせる平面があり、その上には三つの小さな人影が見える。
恐らくマレーネ達だ。
「…………」
考えるまでもない。
まるで、長い間海中に潜っていた者が酸素を求め、太陽の日差し揺らめく海面を目指すように、貴方は無心でそこを目指し、動いた。
今まで代わり映えの無い景色の中を延々と泳いでいたため気づかなかったが、『奈落』を泳ぐ自分達の速度はかなりのものだったらしく、かなり遠い位置に見えたその空間は瞬く間に近づき、五つと数える暇もなく、眼前にその健全な空間が広がった。

「来たな、『刻印者』」
『奈落』から、その空間へと移動する。同時に、全身を絶え間なく包んでいた圧迫感が消え去り、五感が戻ってくる。空間の中央に立つマレーネと、その脇で顔を真っ青にして偽の地面となる白色の床にへたりこんでいるノイン、若干呆れの混じった顔でそんな彼女の背中をぽんぽん叩いてやっているバリードの姿が視界に映る。
と、今まで常にあった掌の感触が途絶えた。見れば、月夜は貴方から手を離し、眉根を寄せたまま訝しげに周囲を見回している。
「……『星を視る者』。ここが『位相領域』なのですか? それにしては──」
そこで言葉を切り、視線だけでマレーネに問い掛ける。
彼女の仕草の意味は判る。明らかに、ここは狭い。狭すぎるのだ。広さで言えば、直径で五メートル程しかない、床以外になにもない世界。こんな人独り賄うこともできないようなちっぽけな場所が、あの『現出』を起こしている元凶の世界だとは到底思えない。
貴方と月夜の二重の視線を受けて、油断無く世界の縁を凝視していたマレーネが嘆息しつつこちらを流し見て、面倒そうに口を開く。
「馬鹿者。違うに決まっておるだろう。これは儂が『奈落』の概念を整調化して作り出した仮初めの世界だ。──『刻印者』よ。先ほどから『奈落』の者共が儂等に興味を示しておることに、気づいているだろう? このまま寄り付かれては邪魔だ。ここで迎え撃つ。準備せよ」
それで得心いった。マレーネもあの奇妙な気配に気づいていたのだ。
そして、それに抗する為に、戦いの場をこうして用意した、ということだろう。
「ですが、わざわざそんなものを相手している余裕があるのですか?」
と、月夜がどこか不機嫌そうな声を出すが、
「どうせ『位相領域』に進入する時に追いつかれる。ならば貴様等に有利な世界で『奈落』の連中とやりあったほうが良かろう? 『位相領域』侵入時に邪魔をされるのも厄介だしな。──バリード、貴様等の準備は?」

「だ、大丈夫、です」
マレーネの問いに、バリードでなく青い顔で屈み込んでいたノインが答える。なにやら酷く気分が悪そうだが、頭を振り振り、剣で体重を支えて立ち上がった。
そんな彼女を、バリードは困ったような表情で眺める。

「ヴァイヒュント嬢、あまり無理するな。前に『刻印者』の『現出』に飲まれ掛けたのがトラウマになってるんだろ。どうせ今から襲ってくる連中もああいう類のバケモノだから、大人しくしとけよ。──婆さん、そうなんだろ?」
問いに、マレーネは軽く肩を竦めるだけ。
「本来ならば形すらあやふやな者共だが、儂等を狙いこの領域に侵入してくれば、この世界の法則に則り、奴等が望むと望むまいと、その姿を顕にするしかない。故に、今まで貴様が相手にしてきた亜獣共とそうは変わらんさ」
「そう、ですよね……」
マレーネの言葉にノインは何とか笑みを浮べて、剣を構え直す。その仕草を見て、バリードは深々と吐息。
「婆さん……励ましてどーするよ」
「何を言っておる。この状況で戦力が下がるのはキツかろうが。それ、来るぞ?」
朱眼の少女が、手に持った巨大な杖の先で指し示した方向。混沌の『奈落』とマレーネの作り出した空虚の世界との縁に、あの『洞』で見た化け物と良く似た気配を持つ存在が、ゆっくりと染み出してくる。
「【NAME】。私達も、始めましょう」
月夜の声に頷き、貴方は己の刻印に意識を集中しつつ、手に持った武器を勢い良く振りぬいた。
姿無き存在




「まだ、来ますね」
「のようだ……ったく、切りがないな。──おい、『刻印者』は無事かー」
少し離れた場所で背中あわせに立つ二人の『護法』に、片手だけあげて返答。
「【NAME】、右から来ます!」
月夜の警告に身体が無意識のうちに反応する。
直径五メートルほどの世界の縁、絶えぬ虹色の向こう側から、こちらへと這い出してくる異質な存在に向かい、貴方は渾身の力を込めて攻撃を仕掛ける!
始原の水子





追いすがってきていた『奈落』の子を撃退した後、仮初めの世界を脱し、再度『奈落』の中へと身を投じる。
極彩の海を泳ぎだして、どれ程の時間が過ぎたのか。
時を示すような景色は一切無く、体内時計はとうの昔にあやふやで、既に何時間も過ぎたような、まだ数分しか経っていないような、そんな感覚。
と、唐突に。
何も無い筈の場所に、行く手を遮られた。
訝しげに動きを止めた貴方のすぐ傍へと、マレーネが無言のまま寄って来る。
「ここから先が、マウローゼの管理する架空世界。『奈落』の存在に気取られぬよう、こうして隠蔽──」
と、そこで彼女は何かに気づいたように視線を変えて、ぎゅ、と眉根を寄せた。
彼女の瞳が捉える先、マレーネが作り出した仮初めの世界から外れた『奈落』の領域の先には、奇妙な波があった。
濃度の高い色が渦巻く『奈落』にあって、他を拒む純白の粒子。それがある一点で渦を巻いている。
飛沫を散らす光の粒子を無言のまま眺め、唾棄するように呟いた。
「──されておらんな。しかも、あの残滓は既に『奈落』の子の侵入を許した証拠。……いよいよ、面倒なことになってきたな」
──第十三位相守護者 位相領域──

「綺麗な筈なのに……なんだか、怖いところですね」
それは酷く優しくて、そしてどこか物悲しい。
そんな淡い瞬きの光点が漂う、高く遠く深く遥かな藍色の空が視界の全てを埋め尽くす場所。

「あの星に似た輝きの一つ一つが、この世界に圧縮され、格納された架空概念達だ。『管理代行者』は、今まであの光の粒を懸命に懸命に、儂等の世界へと投げ込んでいたのだよ」
杖を肩に担いで仰ぎ見て、マレーネは誰に言うでもなく話す。ここは漆黒の空の中を、結晶化された様々な存在概念が星のように瞬き流れる、ある種、幻想的ともいえる世界だった。
「あとは、この世界のどこかにいる『管理代行者』を探すだけ、か」
「そういえば……探せるの、ですか?」
若干不安そうなノインの声に、少女は小さく肩を竦める。
「無論。元々この世界は儂等自身が扱うために作り上げたものだからな。ここまでくれば、後は簡単なものだ。……『我と我等は芯なる血族。我は求める、偽りの現出。世界が主の元へ繋がる幻想にして架空の道を、今ここへ示せ』」
口早に言って、マレーネは手に持った杖の先で空中に象形を書く。微細な紋様が空間に浮んで消えると同時、周囲の空間が、きしりと鳴いた。
次の瞬間、マレーネが浮ぶ丁度真下の位置に、すぅ、と淡く光るブロック状の網目が走り、次の瞬間、その網は赤茶けた煉瓦で構成された果ての見えぬ一本の道となった。
薄闇の中空に浮ぶ、厚み十センチも無い細い煉瓦の道。まるで冗談のような光景だ。貴方は若干呆れの混じった表情のまま、己の刻印の力を操り、マレーネの隣に音もなく着地する。途端に靴裏が道に吸い付くような感触。律儀に重力まで働いているらしい。
「この道をただ進めば、『管理代行者』の漂う場所へと辿りつく筈だが」
そこで言葉を切り、マレーネはふと首を傾げる。
「──奇妙だな」

「そりゃ確かに奇妙だよな。先刻の『奈落』ってとこも凄かったが……ここもなかなかに奇怪な──痛っ!」
ご、と。
バリードの後頭部にマレーネの持っていた杖の先端がめり込む。
「馬鹿者が。それとは意味が違う。──どうも、この世界の根本となる部分の相が淀んでいる。これでは、この世界の本来の役目である仮想概念の具象化も満足に行えまい」
「……確かに、『奈落』じゃない筈なのに、『奈落』と同じ気配がします。まだ全体に染み込んではいないけど──」
「先程の残滓の事もある。恐らくは侵入した『奈落』の子からの影響を受けているのだろう。……が、どうも解せぬな。『奈落』の存在に対する防御策なくして世界の構築は有り得ん。この構造体にもそれ相応のシステムが備えてある筈──と、そうか」
マレーネは言葉を切り、忌々しげに吐き捨てる。
「『管理代行者』は護りのリンドヴルムを儂等の世界に寄越していたのだったな。その隙を『奈落』の子に突かれた、か。『奈落』の覇者たる『外なる者』相手ならまだしも、混沌の概念の飽和により生まれた意思なき『奈落』の子如きに汚染されるとは、ファアの奴も詰らぬものを作ったな」
そして先導するように足早に歩き出す。とはいえ、元々の体躯が女性の中でも小柄の部類に入るノインの半分も無いため、追いつくのは容易だ。十歩も歩かぬうちに追いつく。
彼女は隣にきた貴方を一瞥すると、不機嫌な声音のまま、告げた。
「急ぐぞ。『奈落』の子が全てを喰らう前に、ケリをつける」
唐突に。
薄闇の彼方からこちらへと迫る存在を感じ、道の果て、『管理代行者』の居る場所を目指していた全員の足が止まる。
「──っ、何、これ……バドさん、何かがこっちに来ます」
眉を顰め、頭痛に堪えるように頭を抑えたノインの声に、バリードが苦々しく頷く。
「らしいな。しかも、気配が並じゃない。婆さん、なんだ、これ」
「噂をすればなんとやら、だな。『護りの竜』が来る」
両眼を細め、栗毛の少女が呟いたその時。
轟、と。
マレーネが作り出した遥か遠方に繋がる道を遡るように、薄紫に染まった硬質の鱗を身に纏った巨躯が姿を現した。
──『竜』。
朱眼の『芯なる者』はリンドヴルムと呼んだ、巨大極まりない破砕の力を操る竜。
その姿はクォルルマルの『聖域』などで戦った時とは明らかに違う、凄まじいまでの圧迫感を放つ存在となっていた。巨大な両眼は爛々と輝き、こちらを威嚇するようにはためかせた翼からは絶え間なく『歪の風』が巻き起こり、周囲の概念を圧迫している。
完全に刻印の力を御した今の貴方と月夜、そして『芯なる者』であるマレーネとその庇護下にあるノインとバリードには、『竜』の起こす『歪の風』に耐える事など容易だが、それでも彼の巻き起こす破砕の力が前回よりも数段上なのははっきりと感じられた。
「あれが、リンドヴルムの本性だ。本来は己の概念世界上で外敵を払うのが役目だからな。月夜殿がこちらに渡れば力を削がれるように、『竜』も他概念世界に渡ればその力も鈍る。……さて、後は任せる。儂は『道』の維持と相の整調に力を注ぐ」
一歩下がり、杖を道に対して垂直に構え直したマレーネを呼び止めるように、呆けた様子で『竜』の姿を眺めていたバリードが声を出した。
「おい、婆さん……。もしかして、あれとやりあうのか?」
「無論だ。儂もある程度は奴の動きを鈍らせてやる。その隙に貴様等が何とかしろ。『刻印者』と『地母種』の力があれば、そう難しいことではあるまい」
マレーネの視線が一瞬だけ貴方と月夜に向けられる。が、こちらとしても確実に勝てるかどうかなど判るわけも無い。
「っかー。ニルフィエ付きの『刻印者』ならともかく、オレ等は滅茶苦茶凡人なんだぜ? あんなの相手にしてたら死ぬぞマジで」
ほとほと疲れたといった調子で片手で頭を抱えたバリード。
「大丈夫ですよ、バドさん」
そこに、どこか余裕のあるノインの声が被る。バリードは手に持った槍を軽く肩に担ぎなおし、見上げてくるノインを胡散臭げに眺めた。
「大丈夫──って、虎の子のソルモニアルも封じられてるってのに、エラく楽観的だな、キミは。大体、キミってこういう処は苦手なんじゃないのか?」
「ええと、ここは『奈落』みたいに滅茶苦茶でありませんし、星もあって明るいですから。それに、先刻の化け物や『ヴァドン絶界』の時にも感じてたんですけど、バドさんと組んでると何だか安心して動けるんです。合図なんか無くてもお互いの息が合ってるっていうか……」
バリードは苦虫を噛み潰したような表情になる。
「……まあ、やりやすいのは確かだが、どうも引っかかるな、その言い方。なんかアテられたのか?」
「そうですか?」
「そうですよ……まぁいい。そうまで言われちゃ、一人で逃げるわけにも行かんか。大体逃げ場所も無いしな」
「ええ。──と、『刻印者』、【NAME】さん達の方も、大丈夫ですか? そろそろ、あちらも痺れを切らしてきたようですし」
彼女の視線の先には、周囲の概念を吸い込み、喉元を膨らませ始めた『竜』の姿。
貴方は傍らの月夜と一瞬だけ視線を交わし、そして頷きで返す。
「では、始めましょう」
第十三位相守護者

致命傷となる一撃を受けて、『竜』の身体がゆっくりと崩れ始める。あとは全てが塵となり、消え去るのを見届けるだけ。
──の、筈だった。
だが、『竜』の身体の末端が砕け始めた矢先から即座に修復を始め、崩壊と同時に再生していく。一瞬だけ形を失った手足がすぐさま元の姿に戻り、傷一つない『竜』の巨躯が眼の前で復活する。
「あの回復力は異常ですね……」
呟くノインの息は荒い。いい加減体力も尽きてきているところで、こちらの努力を完全に無視するようなあの回復力を見せ付けられては、流石に意気も消沈しようものだ。
このままでは、いずれ負ける。
脳裏にそんな言葉が浮ぶ。貴方と月夜、そして『護法』の二人は、決定打を与えられない自分達に歯噛みしつつ、『竜』が復活していく様を見届けるしかない──
「──仕様もないな。二手に分ける」
と、はっきりと告げたのは、背後に控え様子を見守っていたマレーネだ。幼くも威厳に溢れた声は、どのような場でも良く通る。
「リンドヴルムは儂等が引き受ける。『刻印者』と月夜殿は『管理代行者』の始末に廻るがいい。リンドヴルムより、『管理代行者』の方が倒すのは容易な筈だ。儂とバリード、そしてそこの娘がこやつを抑えている間に、『管理代行者』を討て」
「……しかし婆さん、皆で『竜』をブチ倒して、その後に『管理代行者』を全員で倒すほうが確実じゃないか?」
苦々しい表情のまま『竜』を睨むバリードの言に、マレーネは小さく鼻を鳴らした。
「屠れんよ。リンドヴルムの力の源はこの世界そのもの、つまり『管理代行者』そのものだ。この『位相領域』におけるニルフィエ、といえば話は早いか?」
言って、貴方の傍らに立つ月夜を見る。彼女はマレーネの朱眼を受けて、小さく溜息。
「力の源との繋がりを断ち切らぬ限り、永劫に息絶えることは無い、ということですか」
「ああ。そろそろ、先程の攻撃で受けた傷が癒える。『刻印者』、リンドヴルムが動き出す前に、行くがいい」
マレーネの言葉に、貴方は困惑したように視線を彷徨わせる。今更、彼女等を置いて先に進むというのは、あまり楽しい選択肢とは言えない。
しかし、そんなこちらの心情を察したのか、マレーネの隣に立っていた『護法』の一人、灰色髪の男が貴方に声を掛ける。
「こっちを気にする必要も無い。さっさと行っちまえ。どちらにしろ、オレ等は婆さんの傍から離れられん訳だし。この人がそう決めたのなら、従わないわけにもいかんさ。……ヴァイヒュント嬢も、構わんよな?」
バリードに話を振られ、その横に立つ黒髪の娘ノインは小鳥を思わせる仕草で小首を傾げ、どこか愉快気な表情のまま、言葉を繋げる。
「そうですね……。ここまできて結末を見られないのは癪ですけど、ここを貴方達に食い止めてもらって私達が『管理代行者』を倒すという図は、どうも想像できませんし。──全ての幕引きは貴方達の手で行うべきだと、私はそう思います」
「…………」
彼女等の言葉で、こちらの意思は決まった。
未だ戸惑いを残す月夜の腕を取り、遥か先へと伸びた中空の街路を走る。
背後からは『竜』の咆声と、『護法』達が操る印章が導く、強烈な干渉音。
マレーネの言うとおり、『竜』が無限の再生力を持つというのなら、自分達が『管理代行者』を屠らぬ限り、彼らが生き延びる術は無い。
赤の他人の為に懸命になる義理も無いが、かと言って赤の他人が命を張っているのを傍観する趣味も無い。
位相の世界の果てまで続く煉瓦の道。その先に、『管理代行者』が居る筈だ。
全ての決着をつけるため、ただ、走る。
──位相管理代行者──
道が途切れる。
中空に道を形成していた茶色の煉瓦が崩れて、その先端にはまるで胎児のように身体を丸め、宙に浮び眠る女の姿。
淡い、淡い黄金の髪。
八方に輝く星の仄かな光を受けて、柔らかく波打つ黄金の糸は中央で蹲る彼女の身体を包み込むように広がり、風も無いというのにゆっくりとそよいで、揺れている。崩れ砕けた煉瓦は、彼女の周りを無言のまま漂い、まるで眠る彼女を守るかのよう。

「彼女が『管理代行者』、ですね」
硬い声で呟いた月夜に、貴方は首肯。身体に刻まれた刻印の全てが、眼の前に浮ぶその存在と共鳴しているのが判る。
(さて……)
どうしたものかと、ふと、迷う。
眼前に漂うその存在からは、害意などが全く感じ取れないのだ。
両眼を伏せた彼女の顔は心なしか眉根が寄せられてはいるものの、際立った険はなく、強いて言えば柔らかな眠りの表情。
正直な話、今まで自分達が出会ってきた位相の、そして『奈落』の存在は皆こちらに対して酷く攻撃的で、戦わずに切り抜けることなど明らかに不可能だった。彼等を取り巻く空気、気配が既に敵意と害意に満ち満ちていて、こちらの言葉など一切聞く耳も持たぬような、そんな者達。
だが、今この場所に漂う気配に張り詰めたものは一切無く、ただ、緩やかな雰囲気だけがある。刻印から伝わってくる周囲の存在概念の中で、緊の概念を表に出しているのは、自分と、そして月夜だけ。
こんなにも気配が柔らかいと、
(話し合いも、できるんじゃないか?)
そんな風な、馬鹿なことも考えてしまう。
だが、浮ぶ彼女へ近づこうと、改めて一歩足を踏み出したその時。
薄闇と黄金に護られた女の閉じられていた両の瞳が、ゆっくりと開かれた瞬間。
──全ての気配が、変質した。
総毛立つ。
見開かれた女の両眼に、正気の色は微塵も無い。
緩やかだった周囲の気配が一気に凍りつき、そして過熱する。
それは眩暈を呼び、吐き気を催すほどの敵意と害意。
その意思が力となり形となり、陽炎を思わせる揺らぎとなって、迫る。
「!? 【NAME】、逃げて──!」
月夜の言葉を最後まで聞く前に、一足で飛び退く。一瞬前まで貴方が立っていた場所が耳障りな音を立てて震え、赤茶けた道を粉々に砕いた。
強引な動きで態勢を崩した貴方には、次の攻撃を避ける余裕が無い。薄闇の空間に走った波紋が自分に収束してくるのを見て歯噛みする。
と、波紋と貴方との間に、一つの影が割って入る。
淡い燐光を纏ったその影は月夜。迫る破砕の波動を最小の力で受け流すと、貴方の身体を抱えて飛び退り、更に距離を取る。
「無事、ですか?」
気遣わしげに問う月夜に頷き、彼女の手を借りて立ち上がりつつも、眼は中空に浮ぶ女に向けたまま。
月夜も貴方の視線を追ってそれを見て、呆然と呟く。
「彼女の発する気配……あれは」
そう。
先刻自分達が死闘を繰り広げた、混沌の『奈落』に住まう者達。
彼らが発していた異質な気配と全く同質の、モノ。
「『奈落』の子に、寄生されてる」
ぶわ、と黄金の髪が広がる。
見開かれた両眼には正気の色は微塵もなく、その細い身体の至る所より噴出する混沌の概念は周囲に満ちる薄闇という至極希薄な概念すらも揺るがせる。
真紅と呼ぶに相応しいその唇が薄く開く。
「ァ──ギ──ィギ──!!」
発せられるのは、声ならぬ声、言葉ならぬ言葉。
耳障り、を通り越して、こちらの存在概念を直接捻じ曲げてくるような、そんな歪な音。
それと同時に、彼女の周りを漂っていた道の残骸、マレーネの作り出した赤茶けた煉瓦に変化が起こる。
繋がりを解かれ、ブロック単位で宙に舞う煉瓦が、一つずつ、一つずつ、光の粒子と変じ、黄金の色を纏う女の周囲に集まり始める。集う粒子は他の輝きと混じり、その身を大きく、強いものへと変えていく。
そして、数メートル程の大きさとなった、黄金の女の傍に浮ぶ球体に、無数の亀裂が走った。
まるで孵化。ひび割れた光の球体が高い音をあげて弾け、そしてそこから現れたのは──
「まさか……『竜』?」
唖然として月夜が呟く。
煉瓦から作り出されたのは、そう、今はマレーネ達が食い止めている筈のあの『竜』。
大きさ自体はそれ程ではないものの、姿形はあの『竜』そのもの。まるで精巧なミニチュアを思わせるそれは、血走った瞳や、薄紫の鱗の隙間から漏れ出す歪な概念は、こちらの警戒心を呼び起こすに十分な代物だった。
漂っていた煉瓦が次々と砕けて集まり、鈍く輝く球体となって、そして新たな『竜』が誕生する。『管理代行者』が一声鳴くごとに、煉瓦が動き、光が生まれ、新たな球体──卵を作り出す。
「【NAME】! このままでは──」
拙い。
向こうが無尽蔵に『竜』を造ることが出来るなら、こちらが明らかに不利だ。
素早く視線を走らす。
周囲に浮ぶ鈍色の卵は既に六つ、そしてどんどんと増えていく。しかし、そこから孵った『竜』の数は未だ二つ。
今、仕掛けねば、こちらがやられる。
貴方は武器を構え、そして一瞬だけ、傍らに居る月夜を見る。
「…………」
無言のまま、彼女は頷きを返してきた。
──場に、戦いの気配が、満ちる。
管理代行者



黄金の髪に守られた『管理代行者』の繰り出す様々な攻撃を紙一重で掻い潜り、渾身の力を込めた一撃を、至近距離から彼女の頭部目掛け、放つ。
──ぐしゃり、と。
鈍い音と共に、黄金の髪が弾ける。
貴方の一撃を受け、整った顔に狂気の色を滲ませて狂う『管理代行者』の頭部が、まるで何かの果物を叩き割ったかのような音を立てて弾け、あっけなく飛び散った。頭を失った身体は受けた衝撃を殺すこともなく、無重力の中を滑るように、緩慢な動きでこちらから離れていく。力無く弛緩した四肢に生気は無く、流されるまま、薄闇の世界の彼方へと漂っていった。
は、と。
無意識に天を仰ぎ、息を吐く。
見えるのは無を示す薄闇と、格納された仮想概念の存在を示す光点が無数に浮んだ、酷く異質な空間。だが、ほんの一瞬、己の世界にある満天に星散る夜空と錯覚し、独り苦笑する。
そこへ、両肩と背に細い身体が乗った。
「……お疲れ様、【NAME】」
耳元で月夜の声。
言葉では応えず、貴方はただ笑みだけを浮かべた──その時。
──ぢり、と。
身体に刻まれた刻印が、疼いた。
反射的に身体を強張らせる。
「まだ、終わってない」
無意識に呟いた貴方に、月夜がびくりと身体を震わせた。そして正面、星を思わせる光点の散る闇の奥へと顔を上げる。
何も無い薄闇、『管理代行者』の亡骸が漂っていった場所から、虹色が伸びた。
八方の闇空に散っていた光点が、瞬く間にその数を減らしていく。
光が消えるごとに、奥に見える虹色が力強く鳴動し、禍々しく脈動した。
虹が、輪郭を描く。
その姿を取る為に、光点はおろか、世界を漂う薄闇すらもそれは喰らい始める。
輪郭が、質量を持ったカタチとなる。
貴方と月夜は、呆然と、それを見た。
巨大で、尊大で、荘厳で、
そして言いようのない恐怖と混沌を身に秘めた、
ソレはただ、世界という概念を飽く無く喰らう存在。
──位相世界──
自分を包む世界が、酷く嫌な音を立てて軋む。
眼の前に漂うのは、既に異形としか表現できぬ存在。
ソレは『奈落』で見たものと良く似た虹色の影を広げて、八方を囲んでいた薄闇の空間すらも喰い始め、肥大化していく。
既にマレーネが作り上げた道も、その存在に取り込まれた。
まだノインやバリード達が戦っている筈の場所までソレの侵食は及んでいないが、放っておけばいずれはそこも虹色に取り込まれるだろう。
自分は月夜を抱えて早々に道から離れ、空間を縦横無尽にのたうつ極彩の影を避けながら様子を伺う。
──『管理代行者』に寄生した『奈落』の子が、宿主と世界を食い尽くそうとしている。
月夜は言う。
あの『奈落』の者達は皆、ああして寄生した存在を利用して身を変え、世界を喰らい、『奈落』という始原の海に帰す事が役目。故に『奈落』の子は、存在するありとあらゆる世界の敵なのだと。
彼女の言葉を証明するように、ソレから伸びた虹色の影に触れられたものは、何の抵抗もなく取り込まれる。
それは相手がどんなモノであろうと同じ。
いや、モノではない。それは概念を取り込む動きだ。
『奈落』で見た極彩の侵食よりも、一際強い混沌の力。
あの虹に捕まれば、刻印の加護があるこちらでも一溜まりも無い。
が、ソレから伸びた虹色の流れは既にこちらの退路を塞ぎ、徐々に、徐々に、その包囲を狭めてきている。
『逃れられぬならば、断ち切るしかない』
──あれは誰が言った言葉だったろうか。
これで、最後だ。
あの異形を打ち倒せば、全てが終わる。
身体に刻まれた刻印の力をゆっくりと解放する。
『管理代行者』が『奈落』の子に喰われた後も、刻印の力が失せていなかったのは不幸中の幸いだった。
貴方は武器を構え、真っ直ぐに、ソレを見据えた。
同時に、そっと、何かが寄り添う感覚。
傍らで月夜が何事かを囁く声がした。
「────」
その言葉は励ましか、労わりか、謝罪か、感謝か。そのどれでもあったのか、どれでもなかったのか。
だが、何であったとしても構わない。
それは必ず、今までの全ての事に決着をつけるための合図として、相応しい言葉である筈だから。
一瞬だけ月夜に目配せし、また視線を戻す。
さあ、始めよう。
全ての決着が、ここで決まる。
──後は、自分の力を信じるのみ。
管理代行者
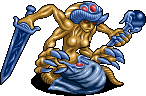
止めを刺す為、巨大極まりないソレの懐へと一気に飛び込み、全精力を込めた一撃を叩きつける。
明確な手応え。明らかに致命となる一撃。
……だが、その一撃を放った直後。
こちらにも、致命的な隙が生まれた。
「────」
それを逃さず、今まで何があろうと確実に回避してきた虹色の触手が、獲物を狙う蛇を思わせる動きで伸びてくる。
不意打ちにも似た、真横から一撃。
反射的に思考。
避けることは適わず。ならば、防ぐしかない。
己の内に在る刻印の力を総動員して、虹色の干渉に耐えようと身体を強張らせた。
そして、極彩の触手が己の身体に触れた瞬間。
飲み込まれる。
まず真っ先に、身を守るために操っていた刻印が飲まれた。
一つ、二つ、三つ。
身体にあった刻印の持つ概念が、次々と解体され、取り込まれる。
しかし、触手の本体は既に叩いた。崩壊は始まっており、こちらに侵食してきた虹色の触手が塵と消えるのも時間の問題。
中心部から始まった崩壊が、末端である触手まで達するのが先か。それともこちらの概念が解体し尽くされるのが先か。
圧倒的な力で捻じ伏せ、全ての繋がりを解いてくる虹色に、貴方は懸命に抵抗する。
四つ、五つ、六つ。
三つの刻印を犠牲にして得た時間を使い、生き残った刻印に対する支配を強化する。
七つ、八つ、九つ。
が、こちらの意思による束縛など全く意に介さず、更に三つの刻印が瞬く間に制される。
そして、十、十一。
残り一つ。これを解かれれば、後に残るのはちっぽけな人間一人。抗する間もなく取り込まれる。ここが最後の一線。
──その時だ。

「【NAME】ッ!」
声と共に、貴方の存在概念は、虹色の侵食から解放された。
そこからは、全てが一瞬の出来事。
突き飛ばされたこちらの身体が虹色の触手から離れ、替わりに月夜の身体が触手に飲み込まれる。
彼女の胴が上下に二分。そのまま下半身が取り込まれ、呆気なく砕けた。
同時に、ソレの中央部から伝わってきた崩壊が、漸く末端にまで届く。
残った月夜の上半身が完全に解体される前に、伸びていた虹色の触手が音も無く霧散した。
月夜は、どこか他人事のような目で、己の身体を見る。
胸より下が、無い。
千切られたような傷などではなく、『月夜に咲く女王』という存在を構成する概念自体が、半ばまで解けたような、そんな痕。
「ぁあ……」
月夜の唇から、細く、虚ろな声が漏れて、そして一度だけ貴方の顔を見て。
笑ったように、見えた。
「────」
崩壊が連鎖する。
存在を維持できず、残った半身も、崩れ去った。
満ちた月が纏うような仄白い燐光を残して、何の余韻も残さずに、こんな位相の世界の片隅で消えていく、存在。
世界が軋む音が、大きくなる。
『管理代行者』だった存在が喰ったこの世界の概念は、その主が崩滅すると共に砕け、消滅したまま。世界に開いた穴を埋めるものはなく、世界は世界としてのカタチを維持するための要素を失い、己を失う恐怖に悲鳴をあげる。
崩れる世界の合間、軋んだ世界の隙間から、『奈落』の極彩が染み出してくる。
貴方は呆然とその様を眺め、そして己の存在概念があげる警告の声に気づいた。
酷い、悪寒がする。
自分という存在が危機に瀕している。無意識の、警告。
『奈落』の混沌に抗するための力が、刻印の力が足りないのだ。
十二あった刻印のうち、十一を完全に解体され、最後に残った印も殆どの存在概念を喰われ、その力を失っている。いずれ己の存在を維持できずに消滅するだろう。
世界の崩壊が進む。
開いた世界の隙間、あちこちから染み出してくる『奈落』の混沌。
今の貴方には満足に己の概念の相を整えることも出来ず、この状態で世界が完全に砕けて『奈落』に飲まれたなら、恐らく自分の概念は『奈落』の生む混沌に飲まれ、あの極彩の海に帰るだろう。
先程の、月夜と同じように。
「…………」
足掻く気力も失せた。
それに今までの無理が祟ったのか、もう身体を動かすことすら億劫だ。刻印が無事だったとしても、恐らくは『奈落』を渡る前に力尽きるだろう。
呆、と薄闇と極彩が混じりあう中を漂う。
視界を埋める色の比率はどんどんと『奈落』の側へと傾き、もう間もなく、世界が始原の海に還る。
身体の末端から、段々と感覚が失せていく。
全身の力を抜いた貴方は、全てを受け入れようと両の瞼を閉じようとして──
「月夜殿の想いを無にする気か。愚か者が」
──暗転する意識の間際。
そんな不機嫌な呟きが聞こえた気がした。
──終幕──
ふと、気づけば。
私は全てから隔離されていた。
自分の管理する世界とも、護りの竜との繋がりとも、己の身体の感覚からすらも隔離され、ただ、何もない無色の世界に心だけが取り残されている。
そこで暫しの間、呆として。
ああ──そうか、と。
もう、私は駄目なのか、と。
漸く気づいて、私は苦笑する。
だけど、それも身体という感覚も無い今では、心の中でだけ。
そうしている間にも、自分の意識がどんどんと崩れていく。
──でも、もうそれを食い止めようとする事すら、億劫だった。
今までの私を支えてくれた、色々なモノ。
その全てとの繋がりが絶たれて、欲したモノを手に入れることも出来ず、こうして独り、消えていく。
別段、何の感慨も沸いてこない。
もう、当の昔に何もかもが終わっていたのだから。
自分は在る物全てから忘れさられ、こうして独り、朽ちていこう。
目覚めた心を、ゆっくりと眠らせる。
もう、目覚めることは無いだろう、永久の眠りへと。
──赴く間際。
何かが、私の心に、触れた。
声も、出ない。
微かに触れたその感覚は、確かに。
確かに、今まで私が待ち望んでいた『皆』の気配。
どうして。
何故。
そんな疑問の意思が私の心を埋め尽くし、そして一瞬で消える。
理由など、どうでも良い。
酷く近い、すぐ傍と言っても良い場所に、その感覚はあるのだ。
それだけで、それだけで私は──
でも。
だけど。
今の私はもう意識の塊でしかなく。
その人を見ることも、出来ない。
見ることも、出来ない。
出来ない。
「────」
そんなことは、許せない。
もう無いと諦めていた己の感覚を取り戻すため、私は己に残った全ての力を集中する。
ある筈の無い右腕の感覚が蘇る。
ある筈の無い右足の感覚が蘇る。
ある筈の無い左腕の感覚が蘇る。
ある筈の無い左足の感覚が蘇る。
──ある筈の無い全ての感覚が、一瞬だけ蘇る。
閉じていた両眼を開く。
仄白い世界。
眼の前には、一つの人影がある。
私はその人の顔を見た。
綺麗な、綺麗な、朱色の瞳。
ああ、そう。
この人だ。
無意識に、心が躍る。
私は定められた歓迎の姿勢を取ろうとして、右の腕以外の部位を本当に失っていることに気づいた。
少し、当惑。
何故身体がなくなっているのだろう。感覚が蘇えっても、身体がなければどうしようもない。
仕方なく、意識の内に残っている感覚だけで四肢を動かしてみる。
不恰好な気もするけれど、今の私にはこれが精一杯だ。
あとは、声を──
「ようこそ、マウロー、ゼシステム……へ。私は、当……構造……」

「止めよ」
私の意識に届くのは、幼くも超然とした声音。
「無駄なことに労力を使うでない。──『星を視る者』の名において、貴様の『役割』を解除する」
その人の一言で、私という存在概念の一番奥深くに刻まれていた何かが、一瞬で消し飛んだ。
「──あ」
深く重く、私の心を縛っていた何かが弾け、私は浅く声を震わせた。
そして、生まれてから今まで背負ってきた役割から解放された私の眼の前には、ずっと夢見てきた朱色の両眼がある。
その瞳を、私はずっと長い間、待っていたのだ。
彼女は小さく吐息をついた後、感情を見せぬまま、私に向かって話し始める。
「マウローゼ・ディーファ。役割は『構造体管理補助』。創造主は『虹色のファア・シノウ』。相違は無いな」
己の名を、誰かから呼ばれるという幸せ。
私は歓喜に震えながら、たどたどしく頷く。
「……今更、何故このようなことをしたのかは問わん。用件だけを単刀直入に言う。既に判っているとは思うが、貴様の身体はもう持たん。『刻印者』が貴様に寄生していた『奈落』の子を打ち滅ぼしてはくれたが──自分でも判るだろうが、もう貴様の身体はボロボロだ。そして貴様が任されていた位相の世界も『奈落』の海に溶けて、最早その残滓すらない。帰る家もなく、貴様はこのまま混沌の海に飲まれ、消えるだろう」
冷然と見下ろす彼女の言葉を、私は酷く満たされた気持ちのまま聞いていた。
その人の言葉は、もう殆ど理解できなかった。判ったのは、私の命はもうあと僅かだと、その人が言っているということ。
「構いま、せん。私はただ、あなた達『芯なる者』と、もう一……逢う為……どれ程のこ……い残す……」
言葉も、満足に生み出せない。
ただ泡のような意識の中に浮ぶのは、得もいわれぬ幸福感だけ。
もう、ここで息絶えようと、私には思い残すことなど──
「──ああ」
ああ、でも。
少しだけ、心残りが在る。
ファア。
あの人に、会いたい。
そのことを伝えようと、私は崩れていく心を懸命にまとめあげようとする。
だけど、その思いはまるで掌で水を掬い上げるよう。音も無く、手応えも無く、指の合間からすり抜けて行ってしまう。
「あ……あ」
細く擦れた声だけが出た。もう、声を発する力も残されていない。
昂ぶっていた身体モどんどんと褪めて、蘇えっていた四肢の感覚が凍えていく。
そして、私というイ識も、加速度的にコわれ始める。
「……無理はするな。言わずとも判っておるよ。だが、意識のほうも既に危ういか」
私を見下ろすその人の瞳に真剣味が増シた。
「良く聞け。今から貴様の存在概念を、儂の所持している人形の一つに複写する。そして、儂が直々に貴様の創造主であるファアの奴に届けてやろう。あやつは今なら確か、パンデモニウムの最下に居る筈だ。……本来ならば、貴様を届けてやる義理などないのだが、貴様の姉が、どうしてもというのでな」
姉……? という私の疑問の意志ニ答えるように、その人の長い袖の中カラ、髪ノ長い人形が顔を出した。
「────」
声を出そうと唇を開くが、声にならない。
ソの人形の円らナ瞳が、どこか恥ずかしがるヨうに、私に向けられている。
それだけで、私ニハはっきりと判った。
あの子は、もうヒトリの私だ。このヒトは、あの子も助けてくれたのだ。
嬉しくて、ウレしくて。
なみだが、あふれる。
「……だが、これはあくまでも概念の複写でしかない。貴様から分かれたもう一人の貴様はファア・シノウと出会うことができるが、本来の貴様はこのまま死に絶える。概念を複写したところで、その存在は既に貴様とは別個のもの。貴様がここで死ぬことには、代わり無い」
よく、ワカラない。
だけど、自分ではナい自分が、ファアに会うことが出来る。それだけはワカル。
なラ、私は満足。少し妬まシイけれど、このまま消えてしまうより、ずっと。
「そうか。……貴様は根が素直なのだな」
そのヒトはそういって、少しだけ笑う。どういう意味なのかがワカラナカッタケレド、もうソレモどうでも良いことに思えた。
ヒドク、眠い。
今にモ途切れそうな私ノ意識に、ナニカが撫でてイク感触。
そして、ヒドク朧な景色、朱眼のヒトの腕のナカに、新シい人形ガ、ヒトツ。
──アあ、あれが、ワタシ、なのカ。
あのヒトが、ナニカ、私ニ呼びかけテイル。
ダケド、もう、ヨク、キコえナイ。
わたしが、答エナイのをサトると、あのヒトは、ワタシに背ヲムけ、サッテいく。
イシキが、溶けていく。
フウケイが、キえる。ナニもカモガ、トオくナる。
スベテガ、トケテシマウマエニ。
ワタシハ、モウイチドダケ、アノヒトノ。
ファアノオモカゲダケヲ、オモイウカベ──
ただ、遠い昔に確かにあった幸せな日々に、彼女は柔らかく笑みを浮かべた。
低い山々が連なる場所に、その隙間を縫うように走る細い街道が一本。
アントハイン・バーニェンタ街道。
街道の所々に生えた標識には、そんな文字が書かれている。その下には、フィーエル国認可のニ級街道を示す朱線が一本。
だが、アントハイン・バーニェンタなどといった大層な名前のわりに、その街道は幅二メートルあるかどうかも怪しい畦道。道に走った二本の轍も浅く、この道を利用している者が少ないことを示している。
そんな山間の田舎道を、なにやら場違いな服装の二人組が進んでいる。
一人は女。
一人は男。
女は明らかにくたびれた風の老馬に跨り、男はその手綱を引いて先導するように歩く。
歩みは到底速いとはいえず、どこか散歩をするような緩やかな動き。ぽっくりぽっくりと、老馬の蹄が地面を小さく削っていく。
女はこの地方では珍しい黒髪。すっきりと整った顔に品の良い騎士風の装束はよく似合っているが、縫い付けられた装飾の一部が剥げているのが難か。名をノイン・ヴァイヒュントという。
男はざんばらの灰色髪を背で浅く纏め、衣服は女とほぼ同じ装飾を施されたもの。右手には手綱、左手には大きな槍。そして浮ぶ表情は顰め面。名をバリード・ルッツという。

「で、ヴァイヒュント嬢」

「はい、なんでしょう?」
男は手に持った綱をぐいと曳く。その動きに驚いた老馬が少し不服そうに鳴いた。
「なんでオレが馬引きなんかやってんだ?」
女は小首を傾げるだけで応えない。男は構わず続ける。
「キミの槍持ちかなんかか、オレは? てか、それ以前にオレが馬苦手なの知ってるだろうに」
「…………」
言葉に、女はぷらぷらと片足を振ってみせる。鞍に巻き込まれて少しずり上がったスカートの裾からは、白布に巻かれた細い足が見えた。
「怪我ってのなら休めば良いだろう休めば。さっきの爺さんとか、親切そうだったし。あれなら、タダで暫く泊めてくれそうだったが」
「お断りです」
巻き込んでいたスカートを引っ張り出して足を隠してから、ノインは澄ました調子で一言。
「何で」
「……理由など、ありません」
「ふむ」
そこで顎を撫でて、一息。
「ああ。村の連中に言葉が通じなかったこと、気にしてるのか?」
「──ち、違います!!」
思わず叫んで、慌てたように視線を外したノインの耳に、押し殺した笑いが響く。
「くくっ、皆まで言うな。判ってる判ってる。まぁ、自分の国以外の言葉が話せなくても恥じゃないさ」
「話せますってば!」
「そうか? 見たところ、村の連中に話し掛けられるたびに混乱してたみたいだったが」
「それは──その、だって、私が教わってたフィングールとは全然──ああもう、意地悪ですね! 大体なんでバドさんが話せるんですか!?」
勢い込んだノインの言葉に、ふん、と鼻を鳴らす。
「こちとら、グローエスが誇る『護法』の一人だぞ。同盟国の言葉くらい話せるに決まってるだろう?」
「~~~~!」
血が上る。
そんなノインをくつくつと一頻り笑ったあと。
「ま、判らんでもないがな。……あそこまで訛ってると、実際にその言葉を使って生きた経験の無い人間じゃ、そう直ぐには対応できんさ。オレだって、何度かフィーエルの都のほうに行ったことがあったから、何とかついていけたようなものだしな」
バリードは振り返らぬまま、そう続ける。彼の言葉にノインは暫し考え、
「……慰めは要りません」
言って小さく嘆息。初めは、村の者達が話している言葉が、国で習っていたフィーエルの公用語『フィングール』だと気づかなかったぐらいなのだ。ついていける、ついていけない以前の問題だった。
むくれたまま視線を巡らせ、午前の日差しに染まる空を眺めた。
空高くに大鳥が何匹か舞っているのが見えた。甲高い鳴き声が、時折高い空に響く。
「でも、本当にフィーエルなんですね、ここ」
「ああ、恐らくな。……ったく、あの婆さんも滅茶苦茶やってくれたもんだが。いくら急ぎとはいえ、位置がズレ過ぎだ」
そう。
あの竜、リンドヴルムを屠った後で起こった位相領域の崩壊。全てが崩れ、『奈落』へ放り出される間際に、マレーネの力で強制的にこちらの世界へ転移してもらったまでは良かったのだが、
「済まんが、時間が無い。座標に誤差が出るが、死ぬことはあるまい。自分達で何とかしろ」
杖が振るわれる間際に響いた、マレーネの無茶苦茶な言葉。
次の瞬間に彼等が立っていた場所は、『奈落』へと続く『洞』があったストレリチアの『教会』ではなく、何故かどことも知れぬ深い森の奥深く。『奈落』の子や『竜』と戦った疲労を引きずったまま森を歩き回り、漸く人里らしき所へ辿り着いた頃には既に半日。
そこで一度安堵したノイン達であったが、現れた村人に話し掛けようとしてまず絶句。
言葉が、違ったのだ。
当惑したノインに代わり、バリードが会話を引き継ぐ。ノインには殆ど理解できぬ言葉でやりとりしたあと、バリードは嘆息しつつ告げた。
「どーもここ、グローエスじゃ無いらしい」
グローエス五王朝の南東部に接した大国フィーエル、その中でも更に南の位置にある、山間の小さな村の外れ。それが、彼女等の居る場所だった。
北から南と縦に長い国土を持つフィーエルの南部地域となれば、隣国であるグローエス五王朝までの距離は途方も無い。
『竜』との戦いでノインが足を負傷していたこともあり、数日の間その村に滞在して知ったことと言えば、村人達の人の良さと、好奇心の旺盛さ。
ノインが今跨っている馬も、村を出るときに餞別にと頂いたものだ。とはいえ、数日傷の治療や食事などの世話をしてもらった上に、馬までタダで貰うわけにもいかなかった。が、代金を払おうにも、ノイン達が持っていた貨幣はこんなところでは単なる塊でしかない。通貨が違うのだ。
金で払うのが無理ならば、後はモノで払うしかない。ノインの服の幾つかに残った、装飾を引き千切った痕はその結果だった。
「大体、これくらいの怪我で、休んではいられませんから」
突然の声に、青年はノインを訝しげに見やり、数瞬。ああ、と一度生返事。どうやら、自分が何故急ぎ村を出たのかとノインに問うたことを忘れていたらしい。
軽く首を捻って一拍置く。
「そんな気張ってやるもんかね。もう一段落ついたんだし、後は単なる事後報告だろう? 骨休めってことでゆっくりしても良いと思うんだが」
「単なる……って、そんな簡単な話ですか」
自分達が関わった事件は並ではない。
だが、バリードの方は気楽なもので、時折老馬に繋がれた綱を引きつつ、軽く肩を竦めて見せる。
「ま、大丈夫だろ。グローエスの上の連中ってのは、何でかそういう話に強いしな。今回の事だって、既にある程度は掴んでいる筈だし」
「それは……そうかもしれませんれど」
ノインは眉根を寄せて言葉を濁す。
そこで会話が少し途切れた。弛緩した沈黙の隙間を西からの風がゆるゆる流れていく。
「──そういえば、マレーネさんはどうされたんでしょう」
ふと、思いついて発せられたノインの言葉に、
「そりゃ無事だろうさ」
答えは間髪入れず返って来た。
「オレ等にとっちゃ大層な出来事だったが、婆さんにしてみりゃ暇つぶしの座興のようなものだろ、あんなのは。どうにかなる筈も無い。むしろヤバいのは婆さんでなくて──」
「あの人達、ですね」
彼の言葉を受け継ぐように、ノインは呟く。
思い浮かべるのは、身体に無数の象形を刻んだ『刻印者』と、その傍らにあった地母の女王。
「あの人達は、ちゃんと目的を果たすことが出来たんでしょうか──?」
まるで独りごちるような問い。
「……そうだな」
バリードは考え込むように唸る。
「だが、オレ達が『竜』を屠ることが出来たと言う事は、アイツ等は『管理代行者』を倒すことに成功したんだろう。倒した後、アイツ等がどうなったかは知らんがな」
暫くお互い無言。
殆ど断片的な記憶でしか無い、彼女等の姿を回想する。
それは奈落で、そしてあの領域で。
襲い掛かってくる、明らかに異質な存在達との戦いで見せた、彼らの力と意思。
「──そういえば、なんだか強い人達でしたね」
「ああ。それに、ニルフィエってのがあんなに綺麗なものだとは想像もしてなかった。同じ芯属でも、ガキのまんまな婆さんとはエライ違いだ。眼福眼福」
「…………」
「……済まん。続けてくれ」
後頭部に刺さる鋭角の視線に、バリードは咳払い。ノインは責めるような表情を緩め、苦笑しながら続ける。
「でも、そうですね。力だけでなく、意思も、そして想いも強い。──ああいう人も、居るんですね」
ああいった場にあっても、己を見失う事無く、ただ突き進むような強さ。
(少し、羨ましいな)
自分もそうあれたら良いと、思う。
「本当なら、もっと話したかったけれど……結局色々あって、まともに話せるようなこともありませんでしたし、なんだか、残念ですね」
実際、ノインはあの『刻印者』がどういう人だったのか、何も知らない。
少しの間、出会い、共に戦って、そして別れた。それだけの関係。
どこか気落ちしたような声を出すノインに、バリードは軽く笑う。
「ま、アイツらが無事にこっちに帰ってきてるなら、またいつかどこかで会えるだろうさ」
ノインは数度目を瞬かせた。
「……会える、のでしょうか?」
問いに、青年はなぜか自信ありげに答える。
「会えるさ。縁があれば、な」
ノインは暫し無言の後、薄く笑みを浮べて、そうですねと呟き、空を見る。
あの『刻印者』がこの世界へと戻ってきているのなら、どこかでこの空を眺めているのだろうか。
「同じ空が見える場所に居るのなら、きっとまた、会えますよね」
見上げた空は高く遠く、どこまでも続いている。
遥かの青よりも、輝きの白が強い空の下。
喧騒がある。
騒がしく、雑多で、耳障りなようでどこか心地良い、様々な音の重奏。
瞼の裏が熱い。
日差しに、身が焼ける感覚がある。
薄っすらと、眼を開いた。
桟橋の縁で大の字になり、倒れている己の身体。
当惑した表情のまま身を起こし、辺りを見渡す。
接舷している船も無いため、人の影も無い桟橋の先端。
鼻先を擽るのは潮の色濃い海の匂い。
広がるのは白色を基調とした雑多な街並み。
その街の名前を思い出す。
そう、ここは商都。商都テュパンだ。
「……なんで」
こんな、場所に。
状況が理解できない。
慌てて月夜に問いかけようと、反射的に背後へと振り返り。
「────」
脳裏を一瞬だけ横切った彼女の最後の姿に、無言のまま空を見上げる。
自分は生きて戻って。
彼女は死んで消えた。
──つまり、そういう事だ。
何気なく、己の右肩に手をやった。
ぢり、と。
最後に残っていた刻印が小さく疼く。
だが、それも一瞬。
今まで解けるのを待っていたその概念が、跡形も無く霧散する。
もう、何の感触も残さない肩。
一度だけ撫でて、貴方は深く嘆息した。
何もかも失ったような、空虚な感覚。
それを持て余すように、貴方は頼りない足取りで歩き出した。
何処に行こうなどという考えは欠片も浮ばない。
ただ、何かを探すように、歩き出す。
花々からの観察者 月夜に咲く an epilogue
──月夜に咲く an epilogue──
美しい真円を描く満月の下で。
貴方は街道を少し外れた場所にある丘、その頂上に生えた大樹に背を預け、無言のまま空を見る。
時は真夜中。
周りには誰も居ない。人は当然、丘を埋める草原の狭間には小さな獣達の気配すら無い。
うつろう景色は静寂に満ちて、吹き抜ける風と、それにあわせて揺れる草葉の擦れ合う音だけが、それでも静々と辺りに響く。
丘は月の仄白い光に照らされ、本来は色濃い緑である筈の草木も、今はどこか褪せて見える。
傍らに『月夜』は居らず、増してや『リトゥエ』も居らず。身体に刻まれていた印も失せて、全てはあのテュパンの桟橋を踏み締めた時のまま。
『奈落』に取り込まれる間際。どこからか響いたあの声を思い出せば、自分を助けてくれたのは恐らくマレーネだろう。
あれだけの戦いをこなして、自分はこの世界へと戻ってきた。
だが、変化と言える変化は、せいぜいこの五王朝で『現出』が発生しなくなった程度。
既にこの国の人々は『現出』などという現象は過去のものと受け止め、忙しなく日々を生きている。
貴方は思う。
何とも、逞しい限りだ、と。
未だ、あの時のことを引きずっている自分などとは比べ物にならない。
貴方は、改めて大樹の幹に己の体重を預けて、浅く、嘆息。
目を閉じて。
そして開く。
夜に紛れた景色は淡く、まるで今までのことが全て夢であったようで、何もかもが胡乱だった。
「…………」
ふと気づいて。
懐の奥に仕舞っていた布の小袋を取り出した。
幾度か振った後、手探りに動かし、引き抜いたのは一枚の薄羽だった。
折れ曲がっている痕も無く、千切れた部分だけは少々生々しいが、それ以外は美しく透き通った一枚の羽。
結局、あれだけ長いあいだ共に旅をしていたというのに、あの小妖精がここにいたという証明となる品は、これだけしかなかった。
茂る枝葉の合間から見える月にその羽を透かして、その仄かな輝きが、最後の戦いでの月夜との別れ際に見たあの微笑に重なって、沸き起こる懐かしさに一人苦笑する。
そして、全てに別れを告げるように。
指先だけで、その羽を弾いてみせた。
薄羽はひらりひらりと夜の闇を舞って、風に吹かれて空の高みに昇る。
と、その時。
唐突に、異変が起きた。
無音のまま空を舞っていた羽が、月の光を浴びて強い輝きを放ち。
そして、まるで花咲くように弾けて──

「っぷはぁああ!!」
絶句した。
弾けた後に現れたのは、15センチ程の大きさの細い身体と、紫色の髪と瞳。同色の衣服に身を纏い、背からは細く伸びた薄羽が一対。淡い燐光をまとったまま空中で制止し、苦しげに息を吐いている。
つまり、リトゥエだった。
「────」
思考が固まり、動けない。
暫くぜぇはぁと荒い息をついた後、その妖精は突然のことに反応できない貴方を指差し、怒り心頭といった様子で、
「っああああ、【NAME】~ッ!! 貴方、いつまで私をあんなトコに閉じ込めとく気だったのさ!! 狭いわ暗いわ月の光は届かないわで、いっつまで経っても元の姿に戻れなかったでしょうが──ッ!!」
と、そこまで叫んでから。
唖然としたまま固まり続けている貴方を見て、リトゥエも意気を殺がれたのか、表情に険が抜けて何やら困ったような顔になる。
「……って【NAME】、今、なんか凄い呆けてるっていうか、ヘンな顔だよ? 大丈夫?」
彼女の言葉に、深々と溜息。驚くな、という方が無理があることくらい判りそうなものだ。
そう考えた貴方を見透かすように、紫色の小さな妖精は溜息。
「うーん、そんなに豪快に驚かれても困るんだけど。っていうか、相変わらずニッブイよね、私が何のために羽を千切って渡しといたと思ってんのさ」
言われ、あの羽を渡された時に彼女が告げた言葉を思い出し、苦笑する。そういえば、そんなことも言っていた気がするが、あんな些細なこと、いちいち覚えているわけが無い。
「まぁ、ホントは私もこういうコトになるのを読んで渡したワケじゃなかったんだけど、結果オーライってことで、ね」
にこにこと屈託無く笑うリトゥエに、ふと、疑問が湧く。
果たして、今、眼の前でふわふわと浮んでいる彼女。
これは『リトゥエ』なのか。
あるいは『月夜』なのか。
「…………」
貴方の問いに、彼女の笑みが変化する。
「さあ? どうでしょう?」
それは貴方の知る『月夜』が良く浮かべていた、淡い笑み。
「──でも、ホントはそんなの、どちらでも良いんじゃない?」
言われ、貴方は暫し目を見開いて彼女を眺めた。そして、ふと、息を吐く。
(……それも、そうかもしれない)
深く吐息する貴方を尻目に、リトゥエは大仰な仕草でぐるぐると肩を廻してみせた。
「あー、肩こった。ったく、しっかしエラい目にあったよ、ホント。今日くらいはベッドのあるとこで寝たいわ」
羽から細かな燐光を零しながら、リトゥエは貴方の眼の前をひらりひらりと舞う。
「取り敢えず、街行きましょ街。っていうか、なんでこんな辺鄙なトコにワザワザ来てるかなー【NAME】も」
確かに、夜中に月を見上げて黄昏ている気分ではなくなった。貴方は背嚢を抱え直すと、幹から腰をあげようとして、ふと、訝しげに眉を顰める。
──この妖精、やはりまだ自分にひっついてくる気なのか?
「仕っ方無いでしょ? 刻印は消えても、私と貴方が結んだ『騎士』の繋がりは、まだ生きてるんだし。離れらんないんだもん」
問いに、どこか愉快な調子で振り向きながら笑うリトゥエ。そして人差し指を立てて、ちちっと左右に振ってみせる。
「それに、まだ貴方を案内してないところだって一杯あるんだから。エルセイドのニルフィエが長、『月夜に咲く女王』に連なっていた『観察者』のエスコート、まだ五王朝で冒険続けるつもりなら、あった方が色々便利じゃない?」
彼女はその小さな掌を貴方に向かって差し出して、零れるような笑顔のまま、告げた。
「【NAME】──ほら、行きましょ?」
──fin──
本サイト内コンテンツの一切の転載を禁止いたします。