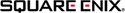![]()
みんなdeクエスト 那由多の道と異界の扉
- 四大遺跡 始まりの烽火
- 四大遺跡 彼方の見定め
- 四大遺跡 双頭四腕の鬼
- 四大遺跡 幽かなる彼女
- 四大遺跡 救いの道先
- 四大遺跡 絶対の大禍鬼
- 四大遺跡 物語を綴じる紐
- 四大遺跡 予期せぬ再会
- 四大遺跡 女賢者の示唆
四大遺跡 始まりの烽火
――始まりの烽火――
「いやはや、時が来たというべきでしょうな。動くならば今であると、ワタクシは考えますがね」
窓から見える外の景色は夕暮れの色に染まっていた。
ポロサ近郊にある、アノーレにおけるアラセマ常駐軍駐屯地本営。師団長であるカナード・フハールが居するその部屋には、長杖を手にした小柄な男、召喚司イルギジド・マイゼルの姿があった。
「…………」
イルギジドの言葉に、椅子に腰を降ろしたまま、部屋の主たるカナード・フハールは黙し、思考する。
彼が話すノイハウスでの顛末。遺跡についての情報。そして噂として軍の間に広がっていた神形器の実在と、その使い手が何故かレェア・ガナッシュと共に居た事。
使い手とレェアが組んでいるなら、既に状況はこちらが後手に回っている。遺跡を占領している者達がやろうとしている事がイルギジドの調査通りなら、彼等が実行する前にこちらから仕掛けねば時間切れ。
否と答える理由が無い。カナードは閉じていた両眼を開くと、宣言する。
「……判った。ならば始めるぞ」
言葉に、イルギジドは仰々しく頭を垂れて、
「了解です、師団長殿。では参りますか」
上げ様、とんと杖で床を叩くと、何らかの技法を併用したのか、廊下へと続く扉がキィと音を立てて開く。カナードは脇に掛けてあった外套を羽織ると立ち上がり、イルギジドを見ずに声だけで問う。
「兵の具合はどうだ?」
「実は既に指示済みでしてな。今駐屯地に詰めている部隊のうち四つ──そこそこの数は動かせましたかね。後はガレー駐在の兵を幾らかか足せば、“贄”の数としては十分ですな。やはり、師団長直接の命令というのは聞くようで。難を示していた二つが渋々指示に従ってくれるようになりましたよ」
既に指示済み。イルギジドのその言葉は、暗にカナードの決断など端から無視していたとも取れた。
「ならば支障はなし、か」
だが、カナードは兵がどの程度動かせたか判ったのならもう聞く事は無いとばかりに、素っ気無く呟くと部屋の外まで歩き、廊下へ。その後ろにイルギジドが続く。
夕日差し込む廊下は赤く染まっている。大草原にかなりの人員を割いている上に、残った者達もこちらに付いてくるために既に準備に入っているのか人は少なく、響く足音は二つだけだ。
「……しかし、ナンですな」
「何だ」
背後からの呟きにカナードが律儀に返事してやると、イルギジドは珍しく逡巡したのか僅かな沈黙を挟んでこう問うてきた。
「本当に宜しいのですかな? ワタクシとしては、貴方の“血脈”を借りたいのであって、わざわざ“同加”していただく必要はないのですが」
「勘違いするな、それこそがオレの望みだ」
「人と鬼では基が違いますので、同加の際に師団長殿の意志が残る保障はできませんし、何より私の僕として扱われる事になりますが、宜しいので?」
カナードはそこで足を止めて、ふと思案するように窓の外の赤く染まった空を見る。数秒ほどの沈黙を挟んで後ろを振り返ると、言葉通りの怪訝そうな顔をしたイルギジドの顔がある。この魔術師にこういう顔をさせることが出来たのは中々痛快な事であるなと、カナードは内心笑いつつ答えた。
「鬼の果て無き生の内では貴様に使役される時間など些細なものだろう。駄賃とでも考えるがいいさ」
イルギジドの顔が一度大きく驚きに揺れて、そして何が気に入ったのかは判らないがにんまりと笑い頷く。
「……ふむ。仕掛けを施したあなたが混ざってくれるなら、よりワタクシが御しやすくなるのは確かですし。当人がそう仰るのでしたら構いはしませんがね」
カナードは肩を竦めて軽く笑う小男に一瞥をくれて、直ぐに視線を前に戻して歩き出す。
廊下を軋ませながら、何とは無しに考えるのは後ろを歩く魔術師の事だ。
イルギジド・マイゼル。
この男は、召喚師だという。しかも“司位”と呼ばれる極めて優秀な術士であると言い、彼が術を操る処を幾度か見かけた限り、その話は確かな物であるとカナードは判じていた。
司位といえば、アラセマの国でも100人と居ない大術士の類である。その才能と力は計り知れないだろう。
同時に聞かされた彼の目的も、己が限界を見極める為といった要素も隠れ見えた。
(才ある人間、か)
だが、そんな彼を見ても、カナードにはイルギジドを妬む、羨むという気持ちは微塵も沸いては来なかった。遥か昔に様々な事に妬みすぎて、今ではそういった感情は殆ど枯れてしまった。
──例外は、クスィークくらいだ。
あの女が癪に障るのは、個人としての能力が何もかも自分より上な癖に、奇妙なまでに自分と関わりを、それも下の人間としての関わりを求めてくるからだ。
立場という表向きの理由だけならこちらも気にする必要もないのだが、引け目から他人の眼を気にして生きてきたカナードには、他人の表情や態度から何を考えているかある程度読み取れる。そしてその感覚が告げるのは、あの女は本心からそういった行動を取っているという事だ。
カナードには、何故彼女がそう考えられるのかが理解できなかった。
多かれ少なかれ人の関係はギブアンドテイクで成り立つ。フハールの侍従を生むカナルの家の人間である彼女が、フハール正家の人間である自分に従おうとする行動自体は判りやすいものだ。例えば今の自分の侍従を務める少年カユリ・イムカは、イムカ家から課せられた責務として自分の下につき、行動しているという態度を崩さない。こういった人種なら安心できる。何を基として動いているのか明確で、理解しやすい。
だが、どうもあの女は義務感のみで動いてる風には見えず、真心で自分に接し、仕えようとしてくる。そしてその理由がカナードには全く判らなかった。
行動原理の判らない存在が、自分に懸命に関わってこようとする。これ程気味の悪い物は無い。それ故の嫌悪であり、苛立ちだ。嫉妬といったモノとはまた別の次元の心の動きである。
──とはいえ、やはり召喚師という言葉には多少の感慨もある。
幼き頃の調べで、自分が異質存在と連結するという召喚師としての素質は類稀なるものを持っていた事が判った。だというのに、彼らと契約を交わす為に使う技を含めた、技法というものを扱う資質が徹底的に欠けていたとは何とも皮肉な話だ。
西大陸は召喚術が極めて盛んな地であり、アラセマの第一貴族である『六家』もその多くが召喚専家である。傍流の家ならば異なるが、正家となると召喚士としての能力がその立場に作用する。とはいえ、これも然程高い技量が必要という訳ではなく、一定の水準以上の才能を示せれば問題は全く無い。
だが、カナードはその水準は愚か、技法すら満足に扱えない身。
一定の枠からはみ出した──それも、下の方向へとはみ出した人間に対する、上流世界という閉鎖空間での扱いは酷いものだった。
「…………」
軋む廊下を渡りながら、カナードはもう一度外を見る。
己の器という限界を捨てれば、自分は、一体どこまでいけるのだろうか。そんな事を考えながら。
日は完全に沈み、空に浮ぶは月と星。
既に夜は深けて、ノイハウス近傍に建つシニの設営地に暮す者達も大半は眠りについている。
この場に居する彼等は元はアラセマ常駐軍所属ではあったが、遺跡研究の為の学士が殆どであるため本来夜には強い存在だ。普段の生活を送っているならばこの時刻でも起きている者は多い。
しかし、今は慣れぬ戦いをこなさねばならず、しかも以前の同僚と戦う身である。
精神的な疲労は肉体の疲労にも繋がり、今起きているのは夜番の者と、そして彼等の指導者のみだった。
天幕と天幕の間に開いた小さな広場。石が点々と椅子代わりに置かれ、中央には簡単な竈が備え付けられている。
そして広場に並ぶ石の上には人影が一つだけ。
石に座り込んだ彼女は、地面の上に投げ置かれた円状の鏡のようなものからぼんやりと浮かび上がった透き通る幻に向かって話しかける。
「なるほどねぇ。あの召喚師──イルギジドだっけか。あいつが自称私の後釜に入った準軍師殿だったとはね」
『お前の話を聞いた限りでは、恐らく同一人物と考えて問題ないだろうな』
石の上に座るのは、ノイハウスを占領する者達の長である“女賢者”レェア・ガナッシュ。
対して、鏡から奇妙に浮き上がった透き通る影は、幼いながらも妙な威厳を秘めた立ち振る舞いをする少年。ヴィタメール遺跡を占領しているキヴェンティ達を率いる“杜人”のリゼラ・マオエ・キヴェンティだ。
『どうするつもりか。あの男が我等の障害となる可能性は高いだろう』
幻の唇が動くが、声として周りには伝わらない。少年の言葉が届くのは白の小さな飾りを右耳につけたレェアだけだ。
これらの品は元々レェアの持ち物であり、ヴィタメール遺跡に居るリゼラも似たような石と鏡をもっており、それで二人は細めに情報交換と打ち合わせを行っていた。そしてお互いの情報を交換した際、レェアは遺跡で遭遇し争った魔術師がヴィタメールにも姿を現していたのだと判った。あちらでは名と立場を名乗っており、そのお陰でレェアはあの男が軍の所属であることを知ることが出来、逆にリゼラはイルギジドが召喚司である事を知っていた。
「確かにね。イルギジドの狙いは恐らく遺跡だろう。その芯形機構としての力か、それとも別の何かを求めてるのか。ああいや、召喚司って処から考えりゃ、ある程度は何するつもりか読めるけど……ホントにやるつもりなのかね」
がりがりと雑に頭を掻くと、レェアは苛立ったように舌打ちする。
レェアはてっきり奴が単独で行動しているものだと思っていたが、組織に所属して動いているとなると話は別だ。しかも常駐軍に所属となれば、ヴィタメールとノイハウスは兎も角、ガレー遺跡に侵入するのは容易い。イェアの管理下にあるといっても、同じ所属の人間にそれ程注意は払うまい。
単独でか集団でかは判らないが、あの男はガレーに対して入念な調査を済ませている筈。奴がアノーレの“四大遺跡”についてそれなりの造詣があるように見えたのはその為か。
「となると、拙いなー。最初の標的は私達じゃなくてイェアの居るガレー? あー、もうミスったなぁ」
『レェア。一人で盛り上がるのは勝手だが、我の事を忘れてはいまいか。どうするつもりかと聞いている』
「ああ、御免。ついね、あの捻くれ気味な召喚司のせいで色々ぶち壊しになりそうだと思うと」
『ならばぶち壊しにならぬようにすれば良かろうが』
「そうはいっても、ね。私と君は元より遺跡から動けないんだから、向こうからこっちに来てくれないとどうしようもないわ。多分ガレーだと思うけど、ヴィタメールの方に来る可能性も無いわけじゃない。気をつけてね、リゼラ君」
『致し方あるまいな。待ちの戦は正直好まぬが、既に我等の動きも変更できぬ段階にまで来ているのも確かだ。もしこちらに来る事があらば、我の剣に賭けて全く斬り捨ててみせよう』
「はは、勇ましいね」
澄ました顔で告げるリゼラに、レェアは笑みと皮肉の色無い口調で答える。
実際、リゼラは勇ましい人間であった。
少年らしい真っ直ぐな性格と、少年らしからぬ類稀なる能力を持っていた彼は、ある意味アンバランスな存在といえた。彼は子供らしい純情な正義感、本来ならば周囲の環境や上の人間などに押し潰されてしまう筈のものを、そのまま押し通してしまうだけ力を持っていた。
遠まわしに言えば、それが今自分と共に彼が行動している理由である。現代ではキヴェンティ達の中でもそれほど重要視されていない教えを守るため、こんな自分と一緒に、こんな事をしている理由──。
(……なんて。責任逃れな考え方よねぇ、これ)
僅かな嘆息と共に、レェアは苦笑しつつ空を見る。
判っている。
あの子がこんな事をしているのは勿論、それだけではないのだ。
この占領事件を起こす以前。キヴェンティ達の里へと赴いたレェアは彼等に協力を求めて、そして断られた。 元々レェア自身も殆ど当てにはしていなかった。正に頷いてくれたら儲け物といった程度の気分で、取り敢えず話を持ちかけてみたというだけの事。
だが、交渉を終えて里を出るレェアの後をわざわざ追いかけ、協力を申し込んできた者が居た。それがリゼラだった。
少年がキヴェンティの信仰に殉ずる気持ちの他に、レェア本人に対する気遣いにも似た気持ちを持って、そう申し出てきた。その事は初めから理解していた。
そんな彼の気持ちを利用して、レェアはまだ幼いという他無い少年を自分の仲間に取り込んだ──といえばそれなりの悪役らしい格好はつくのだろうが、実際の処はレェアの方が彼の心に打たれてしまって、只嬉しくて今後のリゼラの立場も考えずに彼の提案を受けてしまったというのが正解だった。
そのせいで、リゼラはアノーレにあるキヴェンティの一団からはほぼ離反したような形で、自分に付き合ってくれている。
(……全く、いい子だよね)
何で自分のような人間を彼が気に入ったのか。
そんな事をふと考えて──幾つか思い当たった事柄を脳内で反芻してしまい、レェアは空を見上げたまま「うっ」と唸る。
『どうかしたか、レェア』
訝しげなリゼラの声。確かに、空を見上げたまま突然唸りだした自分はかなり奇妙な様に見えただろう。レェアは誤魔化す為に慌てて適当な言葉を紡ぎ足す。
「いや、月があんなに高いなって。そろそろ深夜だし、今日はこんな処で締めようか。リゼラ君はもう寝る時間かな?」
レェアがわざとおどけて言うと、幻の少年は表情を変えぬまま、しかし「ふん」と僅かに鼻を鳴らすと、
『全く、我を子供扱いして無傷で済むのはお前くらいのものだぞ』
機嫌を損ねたような、単に呆れているかのような、どちらとも取れる調子で返してくる。
確かに年齢自体は子供であるリゼラであるが、主氏族マオエに連なる“杜人”の二つ名の持ち主であり、剣技に置いてはこの年で正に神域。大陸での“天剣司”にも匹敵するであろう彼はキヴェンティ達の間でも極めて丁重に、半ば怯え混じりに扱われていたのを覚えている。
「ふぅん、そうなの。まぁそれだけ君が私の事特別に思ってくれてるって自惚れちゃってもいいかね?」
言ってにんまりと笑えば、少年の顔が渋面になる。それがこの子の照れた表情である事をレェアは知っていた。
『……我をからかって無傷で済むのもお前だけだ』
しかめっ面のまま、リゼラは拗ねたような口調で呟く。その様子を見たレェアの感想は、何というか。この一言に尽きた。
彼女は含むように笑いながら、素直にその言葉を口にする。
「くく、なんつーか、可愛いね。君は」
『──勝手に言っているがいい』
今の一言で完全に臍を曲げたか、リゼラはふいと顔を背けると、そのままこちらを見ようとしない。レェアは笑みを完全に殺せないまま、謝る。
「御免。悪かったよ」
『…………』
反応が無い。
「ねぇ、リゼラ君」
『…………』
「ねぇったら。返事しないか」
『何だ』
「怒ってる?」
『怒りはしていない。ただ呆れていただけだ』
「左様で」
どうやら少しだけではあるが彼の機嫌は直ったようだと判断し、ひょいと肩を竦めて軽く笑って見せるレェア。が、リゼラはそんなレェアの雰囲気には乗らず、表情を正してレェアを真っ直ぐに見据えた。
『だが、言っておくことはある』
「なぁに」
『今回の、翆脈顕現[ヴォルベイズ]についてのことだ』
その言葉に、レェアの表情もすっと引き締まる。
『我は自分の部下と共に“命脈”に還れない。お前が止めたからだ。だが、あの時は言い争ったが、我を翆脈顕現[ヴォルベイズ]の担い手から外すというお前の意見は確かに正しい。余程絶対の理由がないのであれば、集団を束ねる者が真っ先に死を選ぶような選択は好ましくない。ただ』
「ただ?」
『それはお前にも言える事ではないか?』
「ああ、まぁそうなんだけどねぇ」
ぽんぽんと己の首筋を叩いて、レェアは周りを見る。
幾つもある天幕で眠る彼らの中には、彼女が“螺旋の理”からこの島へやってきた当時の部下も多く混じっている。自分が居なくなった後、彼等にはレェア・ガナッシュが扱った遺跡の力で操られていただけだったというような言い訳と共に、常駐軍へ下るように指示してはある。
何とも無責任な物言いである事はレェア自身も自覚していたし、部下達からもそう言われたが。
「駄目なのよ。貴方達固有の技である命脈操作の技法。結局あれを教わったのは私だけで、やっぱりそれを他の者に教えるわけには行かないし、第一理屈が判っても多分無理よ。あれは貴方達キヴェンティにしか出来ないわ」
レェアの答えに、幻のリゼラの顔が険しくなる。
『それはどういう事か。お前はあの時“出来る”と言った筈だぞ』
「こう言わなかったかしら。“翆脈顕現[ヴォルベイズ]らしき事が出来る”って」
らしき、という部分に力を入れてレェアは答えた。
「完全には無理よ。でも私が持つ知識と技術ならば近いことは出来る。なら私自身と“現創”の力で作った私の形代でなら、貴方達がヴィタメールでやる翆脈顕現[ヴォルベイズ]の真似事くらいはできるという事よ。それにまぁ、“命脈”と交わってみる事は私の前々からの目的であったわけで、昔から色々と下準備はしてあるのだよ。だからただ死ぬわけじゃない」
そこまで言って、レェアはふと表情を変える。
「……それより、貴方の方こそ良いの? 私、貴方達キヴェンティの源とも言える“命脈”を多少たりとも汚しちゃう事になるんだけど。私、翆獣種の眷属って訳でもないのに」
『良い事ではないな』
即答だった。リゼラは表情を変えぬまま、淡々と言葉を続ける。
『我等キヴェンティが翆なる獣から課せられた使命は、この島に在る鬼種を全て打ち払う事。それは絶対でなければならず、それを遂行するのに枷となるようなものは全て払い、無視して構わぬ。我はそう考えるからこそ、お前に翆脈顕現[ヴォルベイズ]の理を教え、共にこのような事をしているのだ。何度も言わせるな』
責める様な口調に、レェアは軽く頬を指で掻いて困ったように笑う。
「……む、御免。ってなんかさっきから謝ってばっかだね、私」
『それだけお前が迂闊なのだ。猛省するがいい』
「酷いな。一応、私“女賢者”とか言われてチヤホヤされてるくらいの実力はあるんだけど」
『己が名を汚されたと感じるならば、他の者からそのような言が出ても一笑に伏せる振る舞いを心がければ良かろう。お前にはそういった心構えが欠けていると、以前にも忠告した筈だが』
「はいはい、君には負けるよ。──じゃ、そろそろ終わろうか。リゼラ君、取り敢えずあの召喚司の事、気をつけなさい」
『言われるまでも無い。お前も……』
そこで口を噤むと、彼は僅かに逡巡。そして。
『お前も、無理せぬように、な』
「…………」
眼の前に浮ぶ幻の少年。彼の表情と声音に、素直に不意をつかれた。
レェアは完全に顔を硬直させて暫く凍り、あー、と混乱する頭を整理するために顔を空に向けて惚けた声を出す。
この少年は色々と賢く聡く、まるで大の大人のようなしっかりと根を張った精神を持っている癖に、子供らしい純真さが抜けていない。唐突に姿を現すその部分に、毎回自分は不意をつかれている気がする。
──いや、無理するも何ももうそろそろ死ぬんだけどね、私。
翆脈顕現[ヴォルベイズ]とは、キヴェンティ達が使う翆霊、その発現方法をより推し進めたもので、己の存在概念の一部ではなく、命全てを“命脈”へと還す事によって、その反動によってこちら側の世界へ溢れ出た“命脈”の飛沫を奇跡と言う力に変えて発現させる技である。つまり、死を賭した物であり、彼もその事を理解している筈だが、そんな人間に向かって無理をするなと彼は言う。
──全く。
心底からの笑みと共に、レェアは眼の前の幻を真っ直ぐに見据え、
「ホンット可愛いね、君。喰っといたのは正解だったとここで宣言しちゃうよ私は」
『……ッ!?』
「いやー、こっちも初が君みたいな子で良かった。じゃあね」
『お前、ま──』
極めて彼らしからぬ調子の思念が最後まで言葉を伝えてくる前に、接続を切る。茫然とする相手の顔が易々と脳裏に浮んで、レェアは堪えきれぬように声を漏らして笑い、暫く。
あの召喚司がどう動くかはある程度は判るが、それを阻止する為にこの場を離れる訳にも行かない。自分達は自分達のやる事を。それを邪魔しに現れるならその時に相手をする。邪魔をしに来る前にこちらの用件が済ませられたら一番なのだが。
そこまで思うと一息。レェアは片手を軽く翳し、空に曲がり輝く白を見上げた。
「ホント──月が綺麗ね、今夜は」
東に聳えるカンクゥサ山脈の向こうから朝の日が上り、草原はゆっくりと光に包まれていく。
アノーレ中央より僅かに西、大草原南の一角に、大き目の天幕が無数に張られた陣地がある。
先の大草原での戦に参加したアラセマ常駐軍の部隊が拠点として建てた仮設の陣である。アラセマの軍は先の戦闘で制圧した大草原に陣取りつつ、ノイハウスへと攻め込むための態勢を整えている最中だった。
その部隊を率いるのは、アノーレに詰めるアラセマ陸軍第十二師団の副団長を務めるクスィーク・カナル・フハール。兵の再編と補給、負傷者死傷者への対処、戦況把握を終え、今日にでも方針を決めてノイハウスを叩く。
そんな意気込みと共に、身だしなみを整えて天幕の外へと出た彼女を迎えたのは、数人の副官と、一人の伝令。ポロサより伝わってきた情報──師団長カナード・フハールがポロサの駐屯地に残っていた兵を率い、ガレー遺跡に向かったという情報であった。
「なん、ですって?」
唖然とする。師団長が行動する──しかも兵を率いて大々的に動くなど今まで一度も無かった事。しかも、意図が全く読めない。既に常駐軍が占拠しているといっても良いガレーの遺跡に、わざわざポロサに残っていた兵を引き連れて何故向かう必要があるのか。一体何をするつもりなのか。
疑問だけがクスィークの頭の中を駆け巡り、自分の主が何故突然こんな行動に出たのか。その理由だけを考え──そして一つの人物の顔が浮ぶ。カナードのお気に入りである小柄の魔術師の引きつった笑みを浮かべた顔。
(まさか……)
思い伝令の者に詳しく問えば、出立するカナードの隣には確かにイルギジドの姿があり、カナードが引き連れた兵士達もイルギジドが根回しをしていたものであるらしい。
「──あの男! 一体、カナード様に何を吹き込んだ!?」
イルギジドがカナードを唆し、何か良からぬ事を企んでいる。そうとしか考えられない。
叫び、頭を振ると早足で伝令に背を向けた。副団長どちらへ、という声に、クスィークは滅多に無い怒鳴り声で返す。
「私の隊がガレーへ向かう! イーザ、至急出立の準備をさせろ! 残った部隊の指揮はワベル、ノクトワイ連隊長が引き継ぎ、私が戻るまでたとえどんな事があっても戦線を維持しろと伝えておけ!!」
は、と横に控えていた数人が陣の彼方此方へと散る。それを見届ける事無く、クスィークは自分の馬が繋がれている場所へと逸る気持ちを押さえて歩く。
他の者達の準備が整うまで待っているなんて出来ない。一人ででも一刻も早くガレーへ向かい、イルギジド──あの男をカナードから引き離す。それだけしか考えられなかった。
「カナード様……どうか……」
無意識に空を見上げる。ガレー遺跡のある西の空は、気のせいか徐々に雲が増え、暗く翳りだしているように見えた。
四大遺跡 彼方の見定め
――檻の囲い手――
ポロサ北、森の中に開く平地に残る建造物群。ガレー遺跡と呼ばれるその場所の周りに建てられた幾つかの家屋は、アノーレの“四大遺跡”とも称される貴重な遺跡であるこの地を調査する、アラセマ常駐軍の学士と警護の兵士達が暮すためのバラックだ。
常ならそれなりの活気を持つバラック群だが、今、その家屋の殆どはしんと静まり返っている。
喧騒があるのはその内の一角のみ。それも、賑わいではなく多数の人間が無言の行動を取る事により生まれた不自然なざわめきだ。
それぞれ軍の正式な装備を身に纏った者達が、同じ服装の者達を捕え、東にある一際大きな建物へと押し込んでいた。
前者がカナード・フハールとイルギジド・マイゼルが連れてきたポロサ駐留の兵士達。後者が、ガレー遺跡の調査を行っていた学士と遺跡の警護についていた兵士達だ。ガレー駐留の者達の殆どは既に建物の中へと押し込められている。
それを馬上から眺めていたカナードとイルギジドは、最後に兵達に連れられた一人を見て、僅かに表情を改める。
周りを囲む兵士達に自分に触らぬよう視線で牽制しつつ歩いてくるのは、このガレー遺跡の調査を任されていた“先生”ことイェア・ガナッシュである。
「……あら。そちらにいらっしゃるのは師団長様に準軍師様ですの?」
イェアはカナード達の姿に気付くと、にこやかに微笑んで訊ねてきた。
「ということは、この唐突な拘束は本当に師団長様の指示があっての事なのですね。……師団長様。一体、何を為さるおつもりですの? どういった経緯でわたくし達はこうして閉じ込められねばならないのです?」
このような場にあって普段の口調を崩さぬ彼女に、カナードは僅かに感嘆しつつも皮肉気な調子は忘れぬまま答える。彼女に対する持ち駒は多い。
「ふん、ちょっとした用件だよ。お前が今の今まで報告もせずに隠していたとある事実。遺跡の奥に封じられた“大禍鬼”に用事があってな」
微笑んでいた彼女の表情がそのまま固まった。カナードは愉快気に笑みを濃くしながら更に告げる。
「まぁ、自分が捕えられた理由がそんなに聞きたいのならば幾らでも提示できるが。イルギジド」
声を掛けてやると、隣の馬に跨っていた小柄な召喚師は、にやにやとした笑みを浮かべたまま言葉を引き継ぐ。
「ええ。実はワタクシ、ヴィタメールやノイハウスに様子見という事で幾度か出向いた訳ですが、その時、軍装に黒い銃を持った少女を見かけまして。当然、ワタクシ達常駐軍の陣内ではなく、遺跡占領を行っている者達の処でですが」
「…………」
イェアの顔が笑みの硬直から無表情なモノへと変化していく。
──全く、楽しい。
こういうタイプの女が余裕を失っていく様ほど見ていて楽しいものはない。カナードは唇の端を歪めながら彼女を見下ろした。
そしてイルギジドの話は続く。
「それでですな。ワタクシ、彼女と全く同じ外見の人物を、このガレー遺跡のバラックで見た記憶があるのですよねぇ。それも、あなたの部下として、ね。はてさて、ノイハウスやヴィタメールといった入り込む事すら困難な場所に彼女の姿があった。これは一体どういう事でしょうね?」
「……人違いだと断言しますわ」
少しの沈黙を置いての答えは、対応としては妥当なものだ。上手く開き直ったかとカナードは小さく鼻を鳴らし、イルギジドは笑みを変えぬまま言葉を続ける。
「まぁ、人違いなのかもしれませんが、当人であるかもしれない。確証はありませんが、疑いは残る。それで、取り敢えずの拘束と。理由付けとしてはこんなもので宜しいのではないでしょうかね」
イェアは厳しい表情の中にも徐々に余裕を取り戻していく。
「圧倒的に不足ですわね。でも、理で説いても既に無駄な状況でもあるようですわね、あなたや師団長様がここまでいらっしゃっているという事は。……でも、本当に何をするつもりですの? “大禍鬼”は人の手には負えない存在であるなんて、それくらいご存知でしょう?」
カナードとイルギジドはお互い僅かに顔を見合わせ、イルギジドは苦笑。カナードは表情を変えぬまま視線を外す。
そんな思わせぶりな態度に、イェアは一瞬怪訝そうに眉根を寄せ、そしてはっと何かに気付いたかのように目を見開く。
「……あなた達、まさか」
イェアは顔色を変えて更に言い募ろうとするが、
「ま、それは後で見てのお楽しみですなぁ。ではそろそろここいらで。連れて行ってくださいな」
「お待ちなさい、まだ話は──っく」
イルギジドの合図に合わせて、囲む兵士が一歩、手にした武器を構えて自分を威圧するように近寄る。
周りの兵達の数を考えれば、ここで争っても脱出は不可能と考えたのだろう。イェアは口惜しげに言葉を止めて、兵達の指示に従い、建物の中へと消えていった。
「では、ごきげんようイェア・ガナッシュ。そして後の始末は宜しくお願いしますよ」
背に掛けられた言葉が彼女に聞こえたかどうか、それを判断する間も無く。
扉は、重い音と共に閉じられた。
「さてと。それではここの番はどうしましょうかね、師団長。兵をこちらに割くと“贄”の数が少々心許ないですが」
「それならば適任が居る。カユリ、来い」
カナードが僅かに声を張ると、いつの間にか彼の馬の足許には全身を濃い色の布で包んだ小さな影が片膝をつき畏まっていた。
「合意。ここに」
短くそれだけいって、カナードの命令をただ待つ。その正体は現在のカナードの従者を務めるカユリ・イムカと呼ばれる子供である。顔は伏せたまま固まるカユリを見て、イルギジドはイムカ家に関する情報を頭の中から引きずり出す。
イムカ家は、クスィークのカナル家と同じくフハール正家の人間に仕える者を生産する従者の家である。だが、同じ従者の家と言えど、その役目、性質は異なる。カナルの家が表向きにフハールの家の人間を支えるのとは逆に、イムカ家は裏の面でフハールの者を支える者を輩出していた。その役目の最たるものが暗殺といえば、判りやすい。
本来ならばこうして人前に出る事などありえぬ存在であるのだが、カナードはフハールの家の者であるクスィークを遠ざけ、イムカの家の人間であるカユリを自身の正式な従者とした。お陰で、この子供は表に顔等が知れて、暗殺等の裏の能力はほぼ死んだも同然となったようだ。
何故カナードがそのような事をしたのか、そしてカユリ・イムカ自身は今の扱いをどのように感じているのか。
興味は無くもないが、この大事を前にしてそのような瑣末な事に気を取られている場合でもない。イルギジドは己の好奇心を簡単に殺してカナードの言葉を待つ。
カナードがカユリに指示したのは、自分達が事を成す間、彼女等が外へと出ぬよう。そして建物に近づく者を阻むよう。最後に、事が終われば彼女等を解放するように。
「殺さぬのですか」
表情を変えぬまま淡々と物騒な言葉を吐くカユリに、カナードは素っ気無く頷く。
「ああ、殺してしまうと後処理が面倒なのだそうだ。彼女等は、色々と今まで研究と準備を進めて、この遺跡周辺に専用の印章陣を作り上げているのだと。そうだな、イルギジド」
「ええ」
どこか投げやりな調子で話を振られたイルギジドは、頷きと共に答える。
イェア・ガナッシュを筆頭とするガレー駐留の者達が、いつガレー遺跡が大規模な概念変質を起こし土地概念ごと崩滅を始めても対処できるよう、こつこつとバラックをなぞる円の印章陣を仕込み続けていたのは幾度かの下調べを経て知っていた。
レェア・ガナッシュが行うつもりであるらしい他遺跡に対する破壊か、封印のアクションがガレー遺跡に何らかの影響を与え、暴発する可能性を考慮していたのか。それとも初めからレェア・ガナッシュが自身の妹にそういった知恵を授けていたのかは定かではない。
が、イルギジドにしてみればどちらでも良い事だ。
自分達の行動によってここ一帯が消滅する程度なら放置もするが、その異変が周辺に波及し、諸島全体のバランスを崩して全ての崩壊へと導くシナリオは流石に困る。せめて、自分がこの島での用事を全て済ませ、脱出する程度には持っていてもらわねばならない。
「ワタクシ達の作業の後は彼女達に任せるということで、解放してあげてください」
そうカユリに告げたイルギジドだが、当のカユリは彼の方などには目もくれず、じっとカナードを見上げたまま。
「ご主人様。それで宜しいでしょうか」
「ああ」
カナードの短い言葉に、カユリは素直に頷く。
自分はカナードの命令しか聞かない。
そんな態度の露骨さにイルギジドは苦笑して小さく肩を竦めるが、カユリはイルギジドの事など気にもかけずに、カナードに向けて言葉短く問いを続ける。
「では、こちらではなく遺跡の方へと向かう者については、どうされますか」
カナードは僅かに考え、
「無視して構わん。来たとしても、イルギジド。良いのだろう?」
イルギジドは己の顎を軽く撫でつつ答える。
「ええ。ガナッシュのお二方はこれで動けませんし、“杜人”殿もヴィタメールです。他に障害となりそうな者は一人おりますが──来たとしたら殺してもらえると楽ですね。黒銃を抱えた軍の娘が付いている筈です。それ以外の方々ならば、どれだけ来ようが逆に“贄”の一つとして使わせていただきますよ」
「だそうだ」
カユリは暫し黙考するように顔を伏せて、直ぐに上げる。
「……つまり、その黒銃を持った者ならば殺してよいと」
「殺せるなら、な。無理なようならば退け」
「承りました。では外敵に対する罠を張りますので、早々に人払いをお願いいたします」
深く一礼。そしてじ、という地面を削る音一つ残して、一瞬の内にこの場から消え去った。イルギジドはほうと唸り、顎を軽く撫でてカナードを見る。
「速いですな。扱う技法も身体能力も高い」
「カナルと違って、イムカの家は優秀だと言うことだろう。オレに対する文句も溢さんし、良い犬だ。使っていても不快感がない。あの家の指示故に従っているという態度が特に良いな」
「くく、師団長殿も奇妙な方ですな。まあ、ですがあの調子ならば問題ないでしょう。では、そろそろ本番と参りますか」
「ああ、どうすれば良い?」
「事前に描いておいた“贄”喰いの印章陣を“閉ざされし扉”の前に召喚しますので、ワタクシは先に入ります。師団長殿は兵を纏めてワタクシの合図の後、彼等を指定の場所へ」
「判った」
カナードは小さく是の答えを返してくる。
覚悟というものが出来て何かが変わったのか。カナードはここ数日で不思議なまでの落ち着きを身に付けたようにイルギジドには思えた。それは恐らく達観から来るものか、それとも別の何かか。どちらにせよ、この正念場でぐだぐだとごねられるような状況にならなかったのは有り難い。彼を無理矢理従わせるようなことは容易にできるが、これからの大仕事を考えると無駄な負担を背負いたくないと言うのは紛れもない本音だった。
「さて」
これで、ほぼお膳立ては整った。
後は行けるところまで行くだけだ。自分と、カナードの──いや、フハールの召喚師としての血の力によって正否は決まる。
自身の中でふつふつと湧き上がる何かを押さえて、イルギジドは馬の腹に蹴りを入れた。
「では、参りますか。全ては我等のささやかなる目的の為に」
呟きと共に見上げるのはガレー遺跡。その奥に封じられた“大禍鬼”に対する、それは宣戦布告であった。
アノーレの南西にあるポロサの街から北へ。“四大遺跡”の一つであるガレー遺跡へと至る道程に、【NAME】とノエルの姿があった。
ガレー周辺に滞在しているイェア・ガナッシュに、ノイハウスでの顛末を伝えるためである。
今歩いているのは、過去に大鬼と戦い、今は何も無い更地となってしまった場所である。これより北へ進めば大鬼の起こす概念変質からから逃れた濃い森があり、その向こうにガレーの遺跡がある。ポロサとガレーのほぼ中間の位置、といったところか。
ガレーとポロサの間は正式な道はないものの、常駐軍兵士が頻繁に行き来する為に危険な亜獣等はその過程でほぼ掃討されており、安全な旅路といって良いだろう。のんびりと──というには、ノイハウスで起きた事件は生温いものではなかったが、しかし切迫した状況という程でもない。殊更急く事も無く道を歩く。
あの遺跡で出会った魔術師も、素性は知れず怪しげではあったが軍やリゼラ、レェア達が守る遺跡を狙ったとて単独ではそう何か事件を起こすというのも難しかろうと。イェアの元に着いたら、ノイハウスでの顛末と一緒に取り敢えずは伝えておくかと、その程度に【NAME】は考えていた。
「ん?」
ふと。
【NAME】は小さく唸って、思考を打ち切ると視線を上へと移す。
見えたのは、白い点だ。
前方の空から小さな白い点が一つ、ぽつんと生まれ、こちらへ向かって飛んでくることに気付いた。
点は徐々に近づき一羽の鳥の姿へと変わる。
空を見る【NAME】に気付いて、ノエルも同様に両目の焦点を遠くの空へと飛ばす。
「あれは──恐らく鳩であるとわたしは考えます。それに、見覚えがあるようにも感じます」
ノエルがそう淡々と告げる間に、鳥は【NAME】の上空を飛び去る事無く、真上付近で突然動きを変えて急降下してくる。
何事かと身構えた【NAME】とノエルの周りを、降下し終えた白鳩はばさばさと回り始めた。
意味が判らず首を傾げる【NAME】だが、ノエルは白鳩をじっと眺めて、そして僅かに顔を強張らせる。
「……これは、イェアが使う緊急連絡用の白鳩だとわたしは推察します。証拠に、足首のところに手紙が。ほら、おいで?」
ノエルが左腕を差し出すと、二の腕を支えにして鳩が止まる。空いた右手で鳩の足に括りつけられていた文の結びを解くと、それをそのまま【NAME】へ渡す。
【NAME】は無言で受け取ると、手早く包みを解いて開き、目を通す。
「如何でしょうか、【NAME】。この鳩がわたし達を見つけて近寄ってきたという事なら、その文はわたし達宛てである筈ですが」
内容を訊ねてきたノエルに、【NAME】は険しい表情を浮かべてそのまま文を返す。腕に止まる鳩を一撫でして離し、ノエルは手紙へと視線を落す。
「……何ですか、これは」
読み始めたノエルが呻くように呟く間に、白鳩は羽ばたきで持って空へと上がり、【NAME】達を促すように旋回する。
白鳩が運んだ文に書かれていた内容は、アノーレ常駐軍の頭であるカナード・フハールがポロサに駐屯していた兵士達を連れてガレー遺跡へと直接赴き、突然自分達ガレー遺跡での警備調査を行っていた者達を拘束し始めた事。そして、カナードが部下のイルギジドと共に遺跡で何かを起こすつもりである事。カナード達による拘束が始まってから自分に手が伸びてくる間に急ぎで書かれた物であるようで、筆はかなり乱れていた。
「状況が掴めません。何故師団長が、こんな。これはどういう事なのでしょうか」
顔を上げたノエルは至極難しい表情をしていたが、恐らく彼女が見た自分の顔も全く同じ表情をしていたことだろう。
イェア・ガナッシュの所属は常駐軍にあり、今ノイハウスを占拠するレェア・ガナッシュとは血縁であるもののほぼ彼女との繋がりはゼロだ。確かに、外から見れば完全な白とは言い難いだろうが、それでも師団長直々に出向き更迭するという流れは完全に想像の外にあった。
「兎に角、何か異変が起きたことは確かです。急ぎましょう、【NAME】。あの白鳩はイェアによる手が加えられていますから、鳩の先導に従えば彼女が何処に捕らえられているか判る筈です」
ノエルに釣られて空を見上げれば、先刻の鳩は飛び去る事無く【NAME】達の上を旋回し続けている。
──何やら、また厄介な事になってきたようだ。
【NAME】は溜息をつきつつも、意識を高める。
一体どうなっているのかは判らないが、兎に角イェア・ガナッシュに会うのがまず先。【NAME】が前へと踏み出すと、鳩はそれに合わせて旋回を止めて一直線にガレーへと飛び、後方の【NAME】達が来るのを待つようにまた旋回を始める。なるほど。確かに道案内らしい。
あの鳩が居るなら迷う事は無さそうだ。【NAME】とノエルは歩く速度をあげながら、前を飛ぶ白鳩を急ぎ追いかけた。
――目覚める時――
鳩は森の上空から【NAME】達が見える位置を飛び、【NAME】達は空に浮ぶ白を見失わぬよう追う。
地面を走る巨樹の根を飛び越え、腰まで届く雑草の繁みを強引に抜ける。普段はガレーとポロサを行き来する者達が使うある程度手の入った道を通るのだが、鳩は一直線にガレーを目指すため、そちらの道を通っていては見失ってしまう。実際、手紙から状況を察するならばあまり悠長にしている余裕はなさそうであるのは確か。【NAME】は半ば意地になって森を突き進んだ。
最後の大きな繁みを突き抜けると、視界を蔽っていた木々は晴れ、平野が大きく広がった。先行する白鳩を追い草の原を更に進めば、二つの塔を備えた黒い壁面を持つガレーの遺跡と、それを囲う常駐軍のバラックが視界に入る。だが。
(なんだ、これは)
走りながら、【NAME】は内心呻く。
外見に何ら変化はない。だが、遺跡の奥より漂う気配が、明らかに異質だ。以前、ガレー遺跡の地下へ降りた際に、大扉の前で行った戦闘。あの時と、そして終わった後に扉奥から感じた雰囲気に似ているが、それとは比べ物にならぬほど気配が大きい。
「……【NAME】、鳩が」
遺跡が放つ気配に飲まれているのか、片手で頭を抑え顔を顰めながらのノエルの注意に、【NAME】は遺跡に釘付けになっていた視線を戻し、慌てて空の白鳩を探す。
鳩はガレー遺跡の方へは向かわず、常駐軍が使っているバラック群の奥へ向かって飛んでいた。あの鳩はイェアの元へと自分達を誘うのが目的であり、遺跡の異変など関係ないということなのだろう。
遺跡と鳩。視線を彷徨わせ、どちらを追うか【NAME】は迷う。
だが、その逡巡も一瞬の事だ。
自分のような“四大遺跡”についての知識がそれほど無い者が迂闊に遺跡へと近づくより、イェア・ガナッシュを解放し、彼女の知識を借りる方が良手であろう。
──と、遺跡から視線を外そうとした【NAME】だが、その隅に凄まじい速度で地を駆ける一頭の馬の姿が入る。馬は遺跡傍まで走ると力尽きたかそのまま横倒しになり、馬を操っていた者は投げ出されつつも地に転がって勢いを殺すとすぐさま立ち上がり、遺跡の中へと走っていった。
(……何者だ?)
残され倒れた馬の装備を遠目から見るに、恐らく常駐軍の者だと推測できるが、一人で遺跡へと飛び込んで一体何をするつもりなのか。
「【NAME】、どうしましたか。このままでは鳩を見失います」
まあいい。ノエルの声に、【NAME】はああと答えて意識を切り替える。
兎に角、今はイェア・ガナッシュの救出を急ぐべきか。【NAME】はノエルを後ろに従え、白鳩が消えたバラック群へと足早に駆け出した。
二つの螺旋階段に挟まれた道を抜け、砕かれた四枚の隔壁など見もせずに彼女、クスィーク・カナル・フハールは遺跡を進む。
遺跡から発せられる異様な気配に、生死に関わる戦いを幾度も越えてきた彼女の本能が激しい警鐘を鳴らしてはいるが、それ故に止まる事など出来やしない。カナード・フハールがその気配の中心に居る。そう考えるだけで躊躇いなど跡形も無く消し飛ぶ。
壊れた隔壁の合間を抜け、中央を大きく削り取られた広間の階段から下へ。下れば下るほど気配は大きく、内にある不安と焦りはもうこれ以上は増しようも無い程。
早く、早く。
荒れ狂う内心に後押されるように、クスィークは正に飛ぶが如き勢いで階段を下りきり、巨大な通路へと辿り着く。
──そして、
「……何だ、これは」
彼女が奥で見たものは、大きく開かれた道に転がる、凄まじい数の服と武器だった。
百を優に超える程の武器と衣服だけが、ただ地面に放置されているその異様さ。クスィークは唖然として固まった。
手に取り、服と武器、防具を調べる。それが常駐軍兵士の装備である事は判るが、何故こんな処にこんな状態で転がっているのか。
──と、服の下、硬質の床に何か紋様が書き込まれている事に気付く。
よくよく気をつけて見れば、床全体にびっしりと紋様は書き込まれており、奥にある開かれた扉らしきものの前まで広がっている。同時に、衣服と武器が転がっている範囲もそこまで。
「印章陣、か? かなり巨大なものであるようだが……」
地面に書き込まれた印章陣の意味は、内容が高度すぎて専門的な知識の無いクスィークには判らなかった。だが、恐らくその陣が発動させた術式により、この場にあるような状況が生まれたのだろうとは察せられる。
察せられはしたが、一体これはどういう意味があるのか。それとも、この場にある結果はあくまで副次的なモノであり、印章陣が起動させた式にはまた別の目的が──。
「おやおやおや。これは副団長殿。えらくお早いお着きですな」
正に唐突。
虚を突かれる形でクスィークは慌てて顔を上げて、声の主を探す。
「──イル、ギジド!?」
長衣に身を包んだ小柄な魔術師。イルギジド・マイゼルの姿は、すぐに見つかった。
彼は通路の奥、開かれた巨大な扉の向こう側に、殆ど闇に紛れるような形で、じっとこちらを見ている。
男は元々、何処かしら怪しい雰囲気を漂わせていたが、今の彼は以前とは比にならぬ程強大、かつ異質な気配を発していた。重苦しい、というべきか。何か、尋常ではないモノを身に担っているかのようなその姿。
クスィークは一瞬その雰囲気に飲まれて息を呑むが、しかし己の内にある疑問を叫ぶ心がそれを振り払い、言葉となって発露される。
「貴様、どういうことだ!! ポロサの兵を勝手に持ち出し、一体こんな処で何を、それに、この状況は──」
混乱を如実に表したクスィークの叫びに、イルギジドはくつくつと笑う。その様に神経を逆撫でされて更に声を上げようとするクスィークを遮り、小男はゆっくりと声を放つ。
「ああ、それですか。ガレーが誇る“閉ざされた扉”を開くためには、ワタクシでもまあちょっとばかり力が不足しておりましてな。で、その補填としてポロサから連れてきた兵士の方々を“贄”として利用させていただきました」
「“贄”、だと?」
ええ、とイルギジドは頷き、おどけるように両腕を広げてみせた。
「“犠牲の転換[サクリファイス・チェイン]”。要するに彼等の命、存在する力をワタクシが使用できる形に変換させていただいたのですよ。ほら、ワタクシが持つ杖の先端に宿るこれですな」
そして手に持っていた長杖を大きく振る。
──ぼう、と。
動作と共に、イルギジドの持つ長杖の先端に、朧な影が宿る。
それは巨大な緑色の火の玉という表現が確かか。軽く振るたびにゆらりゆらりと怪しげに揺れる。その様は一見頼りなげであるが、玉が放つ気配は尋常ではない禍々しさを宿しており、直視し玉の存在を意識したクスィークは、自身の肌が泡立つのをはっきりと感じた。
そして、気付く。
「ではまさか……この床にある武器と服は」
クスィークは驚きの為か一歩後ろへと下がり、地面に捨て置かれた無数の衣服と武器を見る。
イルギジドは兵達を命を吸ったと言い、この場には複雑かつ高度な印章の陣と、そして兵達の服と武器がある。
──それは、つまり。
動きを止めたクスィークを見て、イルギジドは笑みのまま小さく鼻を鳴らす。
「いやはや、ご明察。今貴女の周りに転がっているそれらは、存在を吸われた兵士達のものでしてな。生命を吸う式である故、生きている有機物は完全に喰えても、無機物はそのまま残ってしまうのがこの術式の欠点でして。まぁ無機物に命など有りませんから吸い様も無いのですがね」
だが、イルギジドの言葉はクスィークには殆ど届いていなかった。
彼女はゆっくりと顔を上げた。自分の思いつきに心底恐怖する表情で、暗闇の中に半ば沈む魔術師の姿を見る。
「……貴様、師団長をどうした?」
「はて?」
「とぼけるな!!」
首を傾げて恍けるイルギジドの態度に、クスィークの様子が唐突に一変した。
「カナード様はどうしたんだと言っている!!」
生気を失っていた眼には異様な気迫が宿り、表情は完全な怒りと焦りに塗れたものへと豹変する。
兵の生き死になど、今はどうでもいいのだ。ただ知りたいのはカナードの安否。それだけだ。
イルギジドへと詰め寄りながら、クスィークは更に問いの叫びを放つ。
「共に居たのだろう!? 貴様が唆して、ここへカナード様を──まさか、この中に」
「おや、らしくない」
だが、そんな彼女を眺めて、小男は肩を小さく竦め首を振る。
「アナタなら直ぐ判るかと思ったのですがねぇ」
ふざけている。
完全に頭に血が上ったまま、勢い良くイルギジドへと迫るクスィークだったが、
「何が判ると──ひッ!?」
引きつるような声を洩らし、ぴたりと足を止めた。
いや、止めたではない。止められたと言うべきか。
人を“贄”として吸って邪な命の力を宿し、常とは異なる強烈な気を放つイルギジドの背後。暗闇の向こうに彼とは別の、そんなものなど比べ物にならぬ程の異様な気配を感じた。
その気に当てられて、意志でなく本能が彼女の足を引き止めたのだ。
「何、だ、これは」
そんな呟きが自然と漏れる。
顔を引きつらせて固まってしまったクスィークを心底愉快そうに眺めて、そして男は口を開く。
「ナニも何もないでしょうが。ほら、だってここに居るではないですが。アナタの愛しの主殿が」
イルギジドが杖を前へと一度振る。
ゆっくりとした仕草に合わせ、召喚師の背後から、気配の主──今まで闇に隠れていたその存在が姿を現した。
不気味な体色。所々に鋭角を持つ硬質の身体。背には二枚の大翼を備えたソレは、凄まじいまでの巨体を揺らし、一歩踏み出す。
僅かに動く度に発せられる凄まじいまでの破気。歪み。その全てに本能が警鐘を鳴らす。
──尋常ではない。
今まで幾度も鬼種と相対し打ち滅ぼしてきた彼女だが、これ程の存在を見た記憶は一度も無かった。
「馬鹿な……こんな、これは」
うわ言のように呟き、身を凍らせる彼女に、イルギジドはまるで歌うように語る。
「“鬼喰らいの鬼”と過去に呼ばれた大禍鬼、シンラ。これがまぁ、今のあなたが言う処の“カナード様”と言う奴ですよ」
「……え?」
完全に惚けた声が出た。
イルギジドの背後にある存在に完全に気圧され、茫然となっていた処に差し込まれたその言葉を、クスィークは何の心の準備も出来ぬまま受け取ってしまう。
「尤も、もう自身がカナード・フハールであったなどという意識は殆どないでしょうがね。シンラが持つとされていた“同加”によって身体は全て飲み込まれ、死んだも同然といった処なのですが……と、いやはや。副団長殿には少々ショックが強すぎましたかな」
両眼を見開き、動こうともしないクスィークを眺め、イルギジドは一つ笑う。
「どうせですし、貴女が落ち着くまでお話でもしてあげましょう。そもそもワタクシが軍に居た理由は、この遺跡奥に封じられた大禍鬼なのですよ。ガレーには“同加”の大禍鬼シンラ。ノイハウスには“現創”の大禍鬼シルイーヌ。ヴィタメールには“百封”の大禍鬼ヴァイオラ。そしてゴディバには“天従”の大禍鬼ウィースルゥインの四体でしたかな。調べた結果、そのどれもが強大な力を持ち、そしてワタクシの力では本来ならば従える事適わぬモノ達でした。いやはや、やはり血による素質と言うのは中々自力では抗い難いモノがありましてな。召喚の技を磨けばどうにかなるというレベルではありませんでして。正直諦めようかとも思っていたのですが、幸いな事に、丁度この島で良い逸材が見つかりましてな」
びくりと肩を震わせ、イルギジドを見る視線には、もう普段の毅然とした調子など欠片も無い。ただカナードの事を指しているのだという事実だけで反応したかのような態度だった。
まるで犬だなとイルギジドは内心呟き、笑みのまま告げる。
「ええ、貴女が思っている通りの方です。召喚師としての血統は正しくも、技法が使えぬという欠陥を持つ師団長殿にワタクシが操る為の様々な技法、仕掛けを施した上で“大禍鬼”に取り込まれていただいて、それを媒介として“大禍鬼”をワタクシの支配下に置く。そんなカタチを作り上げてみたのですよ。いやぁ、我ながら会心の策でありましたな、これは。師団長殿が優秀であるのか、ワタクシが優秀であるのか。多分、その両方でしょうなぁ」
とんとんと杖で己の肩を叩きながら、クスィークの反応を待つ。固まっていた彼女だが、わなわなと唇を震わせると。
「……そんな、その為だけに、そんな事のために」
「お、喋れる程度には回復しましたか」
辛うじて小さく呻くことしか出来ない彼女に向かい、イルギジドは更に言葉を続ける。
「まぁ、あくまで同意の上ですがねぇ。師団長殿に直接会いに行ってワタクシの目的を話した際に、ワタクシが動きやすくなるようにと偽の辞令を作り上げて、軍での地位を作ってくださったのも師団長ですし。正直あの時はワタクシも驚きましたがね。彼を操り攫おうと準備していたモノが無駄になって困ったものでしたなぁ」
「────」
「副団長殿がワタクシの身分についての見当外れな憶測を、辞令自体を作成した師団長殿に述べる場面、ワタクシも陰で聞いておりましたが、あれは何とも……愉快な場面でしたなぁ。笑いを噛み殺すのに必死でしたよ。師団長殿も似たような気分で聞いていたんじゃ無いですかねぇ」
もう反応する気力も無いのか、茫然としたまま動きもしない。
イルギジドはそんな彼女の様子をじっくりと眺めて満足の溜息を一つ溢すと、さてと呟く。
「では、そろそろお暇させて戴きますよ。“贄”の魂が尽きる前に四つの遺跡全てを巡る予定でしてな。今アナタのお相手を長々としている余裕はないのですよ」
「ま、待て。待って……待って!!」
と、去ろうとしたイルギジドに、クスィークは必死の声を上げた。
まるで今ここで彼を逃せば全てが終わってしまうかのような、そんな声だ。
「いや、いやよ、こんなの。こんなのいやなの!! ──カナード様、お願いだからカナード様を返して!!」
正に悲痛。外面の何もない、心からの懇願の叫び。
それを両眼を閉じ、味わうように聞いていたイルギジドは、目を開くと正に満面の笑みを浮かべた。心底意地の悪い、悦楽極まった笑みと共に告げる言葉は。
「それは出来ない相談というものですな。悔やむならば、彼の心を退廃から救えなかった過去の自分を恨むと宜しいでしょう。カナード・フハール殿の前従者、クスィーク・カナル・フハール殿」
「ぁ、あ」
その言葉が止めとなったのか。
クスィークはがくり、膝を折り、喘ぎともつかぬ声を上げた。
もう焦点も合わぬ両眼を天井へと向ける彼女を暫し眺めて、そして開かれた大扉の奥へとイルギジドは視線を移す。
奥からはいつの間にか白色の強い光が灯り、徐々にその大きさと、莫大なまでの力の気配を拡大しつつあった。
「……と、そろそろ留め金を失った“命脈”が遺跡を介して暴れ出してくる頃か。後は“先生”殿が適当に処理してくれるのを期待するのみですが、はてさて、どうなるやら」
そしてイルギジドはもう一度クスィークを見る。
「しかし、これでお別れというのも不憫ですかね。せめて手向けは、アナタの主の名残を残す彼から受け取ると良いでしょう」
イルギジドはその場から背を向け、そして翼の大禍鬼が彼女へ向けて動く。イルギジドはふんと笑い、ただ一言呟いた。
「では、さようなら」
その間にも、扉の奥の輝きは加速度的に大きくなっていった。
「む」
鳩を追い、バラック群の一角へと辿り着いた【NAME】は、何も無い場所で足を止めると、眉根を寄せてバラックの奥を見据える。
「どうしましたか、【NAME】。鳩は奥へ進んでいきましたが」
唐突に立ち止まった【NAME】を不審に思ったか、後ろを付いてきていたノエルも足を止めて訊ねてくる。その彼女に、【NAME】は無言で眼前、草禿げた土の上を指し示す。
そこには、胸を短剣で貫かれた白鳩の亡骸があった。
「……何者かの投擲術によるものとわたしは考えます」
ノエルが背の黒銃を腕の中へと回すのを見ながら、【NAME】も武器を手に取る。
無言のまま数刻。耳を澄まし、感覚を研ぎ澄ませて周囲の空間を探るが、何の気配も感じ取れない。余りにも静かな沈黙。恐らく何者かがどこかに潜んでいる筈だが、全くその場所がつかめず、そして仕掛けてくる気配もない。
遺跡から漂う異様な気配は、その間にもどんどんと増しつつある。
(……ええい)
埒があかない。相手の狙いはこちらの足止めか何かか。ならば、このままでは事態の悪化を招くだけだろう。
【NAME】は意を決すると、一歩、一歩と用心深く、地に伏せた鳩の亡骸に近づくように進んでいく。進めば危険であるのは判ってはいるが、この状況では、こちらから行動して相手の動きを誘発し、対処する以外無いからだ。
そして、鳩の傍まであと数歩、という処で、靴先に何かが触れる感覚。
「ッ!?」
がん、という独特の音と共に、地面に仕掛けられていた何かが起動した。両脇から迫るのは鉄製の鉤爪。【NAME】は背後への大跳躍という形で冷たき死の腕を回避する。
だが、そんな【NAME】の動きを読んでいたかのように、バラックの影から凄まじい速度で飛来する無数の短剣。予想はしていても避けきれるタイミングではない。
──とはいえ、避ける必要が無い状況を作っていれば問題の無い話だ。
「そこですか!!」
背後からのノエルの声と、走る閃光。飛来する短剣は悉くその輝きに打ち飛ばされ、そして次の一撃で、短剣が投げつけられてきたバラックに黒銃による一撃が入り、派手に爆発する。
吹き飛ばされたバラックの影から出てきたのは、濃い色の衣服で頭まですっぽりと蔽った小さな人影だ。
身軽な動きで態勢を整えると、身を隠す事を諦めたのか、ゆらりと揺れるような動作で【NAME】達の方を見る。
「事が終わるまで、この先へ進もうとする者は全て阻み、中の者も外へは出すなと命令を受けております。また、あなたがたに関しては、ここで死んでいただくようカナード様より仰せつかっています」
まだ高い、幼い子供の声で呟かれるのは酷く物騒な内容の言葉だ。
「では、任務を遂行させていただきます。お覚悟を」
影は一方的に言い切る。
そして、じ、という地面を削る音と共に、その人物は僅かな残像と共に一瞬で姿を消す。
技法による高速移動。しかし完全に追えぬ訳ではない。
じっと見つめていたお陰で、どの物陰に身を隠したかを何とか知覚することが出来た【NAME】は、一撃を加える為に全力で踏み込み、
「──【NAME】、迂闊です!!」
ノエルの警告と共に、何か糸のようなものを引っ掛ける感触。
同時に、直ぐ傍の建物の壁から無数の槍が突き出されるのを寸での処で回避しながら、自分が先刻とはまた別の罠を踏んだ事を知る。
そして、強引に回避した処を強襲する短剣。
「くっ」
武器で弾き返しながら、この場が敵によって仕掛けられた罠が無数に存在する、正に敵地である事を理解する。
しかし、イェアを解放するにはここを抜けるしかない。
【NAME】は覚悟を決めて、己が武器に力を込めた。
[BossMonster Encountered!]
裏家の暗殺者



戦いはほぼ一進一退の状況で進んでいた。
攻めようと動いたところで罠が発動。それと共に飛来する短剣の二重攻撃を何とか回避して、また次の機会を待つ。その繰り返しだ。
そんな均衡を崩したのは、二次的な要素によるもの。
ガレーの遺跡から響いた凄まじいまでの激音と地響き、そして遺跡から空へと貫かれる一条の黒線だ。耳障りな異音と共に、太さ数メートルはあろうかという暗色の柱が、遺跡から一直線に空へ向かって突き抜けていく。
更に、
「な、これは──あ、ぅ」
空に黒色の線が穿たれると同時に、ノエルが唐突に頭を抑え、身を折った。
拙い。【NAME】は慌てて動く。
隙を逃さず、家屋の影から短剣が数本列をなして飛ぶが、それを予測していた【NAME】が武器を振るい弾き飛ばすと、伏したノエルを護る様に位置を取る。
敵は己の位置を知られぬように素早く移動を開始するが、そろそろこちらの眼も慣れてきている。どの家屋の影へと身を移したのかは何とか追う事が出来た。
それに気付いたのか、敵は幾度も移動しながら短剣をこちらに投げつけるが、【NAME】はその悉くを弾き飛ばす。
【NAME】は未だ苦しそうに伏せるノエルの傍から離れられず、敵は【NAME】の視線を振り切る事が出来ずに大きな攻撃に入ることが出来ない。
生まれるのは先刻以上の硬直だ。互いに動かぬまま、じりじりと時が過ぎる。
(……どうする)
遺跡の異変。空に走った黒い輝き。気になる事が多すぎる。何とか奴を退けてイェアの元か、もしくは遺跡に直接向かうかしたいところだが──この状況を打破するには一体どう動けば良いのか。
良い策が浮ばず、【NAME】は睨むように敵の影を見据えていたが、ふと、視線の先にある影が身構えを解いたように思えた。
(──好機、だが)
しかし、何らかの罠という可能性もある。結局動けずにいる【NAME】に向けて、影から声が届いた。
「現状ではあなたがたを殺傷するのは不可能のようです。それに、先刻の遺跡から飛び出した影と、そして今遺跡全体に広がっている異様な気配から察するに、私の役は無事果たされた。この場から離脱させて戴きます」
言葉の意味を理解するのに数瞬の間を要した。
そしてそれが致命的だった。慌てて追い縋ろうと動く【NAME】の前に投げ込まれたのは、印章が刻まれているらしき石の礫が数個。礫は【NAME】がそれに気付いたとほぼ同時のタイミングで、強烈な光を放ち、周りを完全な白へと染める。
(しまった!!)
視界を殺されたこの状況で、投剣に狙われれば回避の仕様が無い。
己の迂闊さに歯噛みしつつ、【NAME】は急所となる箇所を手や武器等で庇いながら全力で後ろへ飛び退き、物陰へと入り込む。
閃光は三秒ほど続いた後、唐突に消え去った。
陰を作る壁に背を預けて、【NAME】はそのまま大きく吐息。
どうやら先程の光は印章石による目暗まし。まともに引っかかってしまったというのに敵の攻撃が一切無く、無傷で物陰に入る事ができたのを考えると。
「本当に逃げた、か?」
あの小さな影は、今の光に紛れてこの場から離れたとするのが妥当。実際、物陰から出て周囲を窺ってみるが、敵が潜む気配は全く無い。場に流れていた張り詰めたような空気が全く消え去っている。
取り敢えず、障害は去ったようだ。
【NAME】は頭痛を堪えるように顔を顰めるノエルに肩を貸すと、未だ残っているであろう罠に気を払いつつ、バラック群の奥にある一際大きな建物を目指した。
――彼方の見定め――
暗雲立ち込めるガレー遺跡の周辺に建つバラック群。その一角を早足に歩く集団がある。
その先頭に立つのは三つの影。【NAME】、ノエル、そしてガレー遺跡に駐屯する調査部隊を纏めていた軍属の学士、“先生”ことイェア・ガナッシュである。
先頭を大股で進むのは白衣のイェアだ。暫く時間をおいてノエルの復調を待った後、【NAME】達が救出の為にイェア達が閉じ込められていた扉を吹き飛ばすと、すぐさま中から出てきたのが彼女だった。
顔を合わせた【NAME】から大まかな状況──とはいえ、【NAME】が語れたのは遺跡から伸びた奇妙な黒線や、気配の変化等とたいした事ではなかったが──を聞いたイェアは、酷く慌てた様子で建物の中に戻ると、縛られていた他の者達を大急ぎで解放。そしてすぐさま外へと出ると、何処かへ向かって歩き出す。
「まったくこんなの、無茶苦茶ですわ! 遺跡の封印を解いて“大禍鬼”だけを連れ出し、それを己の召喚獣として支配下に置くなんて、しかもそれが成功するだなんて!! 幾ら司位でも有り得ませんわ! 召喚師の範疇を越えてます!!」
何やら気が昂ぶってるのか、誰に話しているともつかない事を喋りながらずんずんと歩くイェアの後を、【NAME】とノエルは訳も判らず慌てて追い、拘束されていた他の者達はどこか決意を秘めた表情でついてくる。
「落ち着いてくださいイェア。それよりも一体」
何処へ向かっているのですか、と続けようとするノエルだが、イェアはテンションを下げる事無く遮る。
「判ってます。判っておりますわよ。でも落ち着いていられる状況でもありませんわ。こんな事態、まったく有り得ませんわ!!」
「ですが、イェア。現実にそうなってしまったのですから、有り得ないという事はないのではとわたしは考えますが」
冷静に冷静に訂正を入れ続けるノエルの物言いが、いい加減効いて来たのか。イェアは大きく溜息をついて幾分声のトーンを落す。
「ああもう、そんな事判ってますわ。ちょっと気を紛らわせる為に言ってるだけなんだからそんないちいち反応しなくてもいいの。ノエルはホントにこういう会話は駄目ですのね、プンプン」
ぶつぶつと小声で呟くイェアだが、意味が判らないのか、ノエルは小首を傾げて眉根を寄せる。
「……何故非難されているのか理解できませんが、それよりイェア。今のこの状況の説明をお願いします。先刻、“大禍鬼”を支配下に、と仰っていましたが、それは確かな事なのですか?」
「簡単な事ですわ。師団長様とイルギジドさんという組み合わせ、そして今遺跡の奥から感じるこの莫大なまでの力の気配。この二つの要素から推測するなら、イルギジドさんが遺跡最奥にある“命脈”の弁として封じられていた“大禍鬼”を解き放ったとしか考えられませんもの」
イェアは足を止めぬまま睨むようにガレーを見る。遺跡からは、どんどんと高まる強い力の気配に重く響く振動音が加わり、異様さを増していた。イェアはこの状況を“四大遺跡”が持つ芯形機構、その要である封じられた“大禍鬼”が失われたせいだと結論付けているらしい。
「そして召喚師であるイルギジドさんが“大禍鬼”の封印を解く理由といったら、ガレーに封じられていた“大禍鬼”を自身の支配下に置こうとする以外に思いつきませんわ。今はもう鬼の気配がここには無いという事を考慮すると、【NAME】さん達が見た黒の光。あれで遺跡に穴を開けて脱出し、ここから去ったのでしょうね」
「……もういないのですか?」
「え?」
ノエルの問いに、イェアが驚いたような顔で彼女を見る。
「ノエル。環境の概念的な変移に敏感なあなたなら気付いていると思っていたのだけど──もう、位の高い鬼種が発するような規模の陰性概念はこの場にはありませんわよ?」
ノエルは少し困ったように表情を曇らせる。
「申し訳ありません、先程から遺跡の方で漏れ出してきている気配の質が濃厚すぎて、感覚が半ば麻痺してしまって」
「んー、感度高いというのも困りものですわね。あ、そうだ、あなたが出ている間にちょっと面白いもの作ったから、後でそれをあげますわ。──と、それでええと何のお話でしたっけ?」
何故異常を見せる遺跡に向かわず、かといってポロサ方面へと逃げることも無く、こんな早足でバラックを歩き回っているのかという話。
【NAME】が脇道に逸れていないで早く話せという憤りを込めて答えると、あぁあぁと首を二度縦に振るイェア。本気で言っているのか判断に困る態度である。
「あらあらそうでしたわね。で、今のこの状況ですけれど──“大禍鬼”という弁を外せば、当然塞がれていたモノが外へと出てくる。簡単に表現すると、それは凄まじい迄に純粋な力の塊で、放置すれば周辺丸ごと飲み込むか、それに似た被害を出すのは必至ですわ。なのに、それに対する施しを何もせぬままこの場所を去ったという事は……取り敢えずイルギジドさんは“大禍鬼”を遺跡から引き抜いた後の処理なんてどうでも良い、全く考えてなかったのでしょうね」
無責任な話である。化け物を自身に従えさせようとするのは勝手だが、周りに迷惑をかけずにやって欲しい処だ。
【NAME】の半ば苦笑しつつの意見に、イェアも小さく笑って同意する。
「そうですわね。でも、自分では何もしていかなくとも、他に何とかするアテはあった。わたくし達、ガレーに詰めていた学士を“贄”として使わずにここに軟禁し、見張っていた方が【NAME】さん達との戦闘の途中で引き揚げたのもその為、ですわね。……仕方ないとはいえ、掌で踊らされているみたいで気分がよくありませんけどね、全く」
言って、彼女は最後に溜息。
【NAME】は彼女の言葉に少し驚く。つまり、イェア達は遺跡から漏れ出すであろう“命脈”の力とやらを、自分達でどうにかする手立てがある、という事か?
【NAME】がそう問い質そうとする前に、イェアが唐突に歩みを止める。距離自体は遠く離れているが、ガレー遺跡正面の入口となる大扉を前方に置いた位置。彼女はそこで二つの塔が左右から伸びたガレーの威容を見据え、そして後ろからついてきていた学士達に向かって声を張った。
「皆、事態を収拾しますわ。印章陣“エファ・リス・シー・イル”を駆動させて、場を一気に調律します。自動制御の為の式が未完なのは皆の知っての通りです。だから、わたくし達自らがリアルタイムで式を弄り、場を調律します。長い戦いになるけれど、成功する以外にわたくし達が生き残る術はありません。皆、気合を入れて事に取り組んでくださいな」
返答は行動だ。学士達は無言のまま四方へと散り、それぞれの準備を始める。何人かがイェアや自分達を中心に置いて円を描くように立ち、残りの者はその外にもう一つの円を作る。更に余った者達は今まで歩いてきた方角とは逆へ向かって走っていった。
「じゃ、行きますわよ!! “鍵は我が腕の中に、ローデルン・エファ・リス・シー・イル!!”」
イェアが両手を前へと掲げて叫ぶと、強い輝きと共に彼女の手の中に光る槍のようなものが現れる。彼女は躊躇う事無くその白い棒を掴むと、大きく振りかぶって、勢い良く地面へと突き刺した。
瞬間、地面から青白い光が生まれ、天へ向かって立ち上がる。
「なっ」
【NAME】は驚きと共に白色に包まれた周りを見回し、そして下を見る。地面に浮かび上がったのは極めて複雑な構造を持つ巨大な紋様。紋様は前後5メートル程の幅を持ち、左右は僅かに前へと曲がりつつ遥か遠くへと伸びている。その軌跡に沿って光は空高く伸びており、遺跡全体をぐるりと一周して、まるで遺跡を包み込む城壁のようにそそり立っていた。
イェアの傍に残った者達がそれぞれ膝をつき、独特の韻を含んだ言葉を告げて地面に両手をつく。同時に、輝きの壁が力を増して、紋様の上を離れて徐々にその円の幅を狭め始める。
「イェア──これは」
じりじりと遺跡へ向かってにじり寄る蒼白の光壁。ノエルの問いに、イェアは手にした光の槍をがっちりと握り、両眼を強く閉じたまま答える。
「……だから、印章陣“エファ・リス・シー・イル”ですの。こんな事もあろうかと、事前に組んであった対概念変質障壁・調律用閉鎖結界形成印章陣。まだちょっと足りない処があるんですけれど、悠長なことを言っている場合ではないですもの。ノエルと【NAME】さんは少し下がっていてくださいな、わたくし達は暫くこの結界の調整に掛かりきりになりますので……」
そう呟く間にも光の壁はどんどんと動き、イェアの足許に広がる紋様と、手の槍が放つ光の強さは激しく変化する。
確かに、この結界とやらの知識は【NAME】には無い。彼等の手助けができそうにないのなら、邪魔をしないように取り敢えずこの場から離れておくべきか。
輝きは暖かで、それに身体全体を包まれる感覚は何ともいえず心地が良い。僅かに名残惜しいがそのような理由で居座る訳にも行かない。【NAME】はノエルに無言で促すと、地面に手をつき集中する学士達の間を静かにすり抜けて、紋様の上から外へと出る。
紋様より沸き立つ光の奔流。その外側へと離れた【NAME】は小さく息を吐いて、暖かな光の感触に馴らされた身体を改めるように軽く肩を回す。
──閉じるのはキライ。
唐突に、それは来た。
「……ッ!!」
耳を擽る少女の声に、【NAME】は己の懐にある首飾りを慌てて掴む。
今は首飾りに姿を変えた神形器。その意思のようなモノが紡ぐ、【NAME】にしか聞こえない声無き声だ。
しかし、今のこの状況で、閉鎖を拒む力、流転の象徴たるゼーレンヴァンデルングに起きられては困る。神形器の破壊の意志に乗って結界を壊してしまえば、破滅するのは自分達だ。
全力の意志を込めて首飾りを握り、眠っていてくれと懇願する。
──壊したいのに。
何処か拗ねた様な感触が【NAME】の心を撫でて、そしてゆっくりと離れていった。
「……全く」
どうやら、見逃してくれたらしい。
【NAME】が人知れず安堵の吐息をつく間にも、イェア達の発動させた印章陣から生まれた光は更に範囲を狭め、既に遺跡の殆どをその輝きで包んでいた。遺跡中央から生み出される力は順調に押さえ込まれているらしく、徐々に安定した形へと変化し始めているように見えた。
意外と簡単に片付くものかとも思えたが、しかし時折中央から漏れる完全な白。“命脈”からの流れが光の壁を押し戻し、イェア達が慌ててそれに対抗する為に動き始める様を見ていると、そう簡単に終わるものでも無いらしい。
その場から離れる気分にもなれず、【NAME】は近くにある建物の手頃な縁に腰掛けると、最後まで見守る態勢を整える。
「無事に終わると良いのですが」
そう呟いて隣に座り、紋様の上で作業を続けるイェア達を真剣に見つめるノエルに、【NAME】は無言で頷く。
結局、結界となる光壁の場が完全に安定するまでに五時間という時を要した。
ガレーとノイハウスの間となる空の上を、高速で飛ぶ影が二つある。イルギジド・マイゼルと、そして大禍鬼シンラである。
向かう先は当然ノイハウス。彼の地に封じられた鬼を起こし、そして従えるか、“喰らう”か。どちらにするかは状況次第だが、イルギジドはどちらでも良いと考えていた。兎に角、力の種として使えれば良い。
何より先に、ノイハウスにいるレェア・ガナッシュが遺跡に眠る封印された鬼を殺す為の行動に出る前に、彼女を拘束するか、殺さなければならない。ヴィタメールとノイハウスの双方を調査した際、より準備が整っているのがノイハウスだった。
鬼を先に殺され、消されてしまえば元も子もない。あれは、自分のモノだ。急ぎ向かい、レェアの行動を阻止する必要がある。
イルギジドは己の後ろを付き従うように飛ぶ鬼に一瞬視線を向けて、先刻のあの鬼の行動を考える。
イルギジドはガレー遺跡の中でクスィークを言葉で弄った後、そのままシンラに殺させるつもりで指示を出し、そして遺跡を一足先に出た。
そしてシンラ自身が放ったであろう破壊の一閃により開いた穴を飛び抜け、僅かに遅れて遺跡外へと出てきた巨体を見て、イルギジドは唖然とした。
その腕の中に、気を失ったクスィーク・カナル・フハールの姿があったのだ。
(……何故ですかねぇ?)
イルギジドは黙したまま考える。シンラと自分に結ばれた、召喚師が良く使う主従の概念。これはしっかりと生まれている。なのに、何故こうなったか。クスィークを殺すという指示が守られなかったという現象に対する答え。考えられるパターンはそれほど多くは無い。いや、一つか。
(カナード・フハールの意志が残っていた、という事ですかね。それも、彼の意志の表層ではなく、根元というべき部分が)
意外、という他無いが、彼の意思が残っていたとするならば先刻の行動にも納得がいく。
極めて存在としての格が上である“大禍鬼”との契約は、かなり危うい位置で結ばれたものだ。完全な契約ではない今の状況であるなら、鬼の意志によってこちらの指示した行動が成されないという可能性は十分にあった。
尤も、明確な反抗の意思があったのなら、主であるイルギジドも感じ取れ、それを捻じ伏せることもできたが、鬼自体が意識せずに行われた場合は補正の仕様も無い。
「いやはや、厄介なことですなぁ」
イルギジドは独りごち、そしてくつくつと笑う。
この、まるで綱渡りをしているかのような感触。
やはりこうではなくては、折角あの“大禍鬼”を従えたという実感が沸かない。
「とはいえ、これだけでは物足りない。もっと、もっと上の存在へと近づける筈だ。そうすれば──」
まだ見えぬ程遠くにあるノイハウスの遺跡。イルギジドはそこにある者と、そして敵の存在に心を振るわせた。
「副団長、が?」
「ええ、結界がある程度安定化した後、状況を調べる為に遺跡の近くへ向かった時に、直ぐ傍の壊れたバラックの隅で見つけたんですの。地面にぺたんと座り込んで、わたくし達が話し掛けても何の反応も示さなくて。今、施療師の方に見てもらっていますけれど、外傷は然程無いようでしたから……一体何があったのか。多分、師団長様を追ってこられたのでしょうけれど」
【NAME】は記憶を掘り起こす。確か、自分達が鳩に導かれてガレー遺跡にたどり着いたとき、一頭の軍馬が遺跡に向かって駆けていったのを見た。恐らくそれが彼女だったのだろう。
今【NAME】とノエルが居るのは、ガレー近傍に建つバラックの一棟。イェア・ガナッシュの居室である。“大禍鬼”の消失による“命脈”の流出、その他諸々の現象を押さえ込むための印章陣が一先ず安定するのを見届けた後、イェアは【NAME】達にこの部屋で待つように伝え、自分は現状の把握の為に部下を引き連れてその場を去った。
そして、彼女の部屋で待つ【NAME】達の前にイェアが姿を現したのは、彼女の指示からおおよそ三時間程過ぎた後。そこで漸く、【NAME】は最初の目的であるノイハウスでの顛末を彼女に伝え、イェアは数時間の調査で判った事を【NAME】に伝えた。その内の一つが、先刻の副団長についてである。
一通りの情報交換を終えると、椅子に腰掛けたイェアはふぁ、と息をついて、座ったまま軽く身体を伸ばしてみせる。
「──はぁ。色々と厄介な事になってしまいましたわね。特に、わたくし達軍の側が」
イェアの苦笑に、【NAME】は小さく頷く。
アノーレに常駐するアラセマ陸軍第十二師団のトップである師団長、そしてその補助である準軍師が共に行方不明となり、実質的な長でもあった副団長は完全に自失の態。となると、今まで師団を引っ張ってきた者達はほぼ全滅に近い形といって良いだろう。
【NAME】はそこまで考えて眉を顰める。
軍離脱組とキヴェンティ達によるノイハウス、ヴィタメール占領という状況はそのまま、新たなる問題としてガレーからの“命脈”の発現と、カナード・フハールとイルギジド・マイゼルの失踪という二つが追加された。
前者は一先ずイェア達が結界によって押さえ込んでいるようだが、完全な封印には程遠いものであり、印章陣の効力が失われる前に何か更なる手を考えないとならないらしい。
後者については、カナード・フハールがどうなったか明確な結論は出せないが、既に亡くなっているか、イルギジドと行動を共にしていると考えて問題ないだろう。彼の個人としての能力は噂を聞く限りたいした物ではないらしいのでそれ程重要ではない。
問題なのはイルギジドの方である。
元々がノイハウスでの骨竜のような異質な存在を使役する極めて有能な召喚師である上に、イェアの憶測では“大禍鬼”という驚異的な存在を自分の支配下に置いているらしく、その力は計り知れない。
軍を利用し、そして姿を消した彼。その目的、今後の行動についてははっきりとした事はいえないが、予想くらいは出来る。
「ガレーの“大禍鬼”の掌握に成功したというなら、更に他の遺跡に封印された“大禍鬼”を狙って動くつもり、という予想が一番迷惑かつ妥当なものですわね」
イェアの意見に、【NAME】も同意の頷きを返す。
ノイハウスで彼と戦った際に、あの召喚司はレェアと戦う為の仕掛けなどを遺跡に仕込むといった行動を取っていた。つまり、ノイハウスでの彼女との戦闘を元々考えて行動していたという事だ。ガレーの“大禍鬼”を解放した今、次はノイハウス、ヴィタメールへ向かう可能性は高い。
彼が遺跡へ辿りつけばレェア達と激しい戦いとなるであろうし、イルギジドが勝利した際はガレーで起きたような“命脈”の流出、土地概念の変質現象が他の遺跡でも発生するかもしれない。
ガレーのような結界が事前に用意されているかどうかなど判りようも無く、イルギジドが遺跡へと辿り着く前に見つけ出し、倒すことが行動としては最良であろう。が、ガレーに残された部隊、各駐屯地の部隊、そして大草原に展開している部隊。それらを指揮する者が軒並み失せた今、軍部隊の迅速な行動は望めない。
せめて副団長が動けるのならば、もう少し状況はマシになるのではないか。
そう【NAME】は呟くが、イェアは痛ましげな表情で首を横に振る。
「副団長様は暫くは駄目ですわね。あれは、とても正常な精神状態とはいえませんわ。あのような痛々しい姿で人を率いて、増してや以前師団長様であったモノと戦うなど、決してあってはならない事です」
師団長であった、モノ?
「ええ。“大禍鬼”程の存在を支配下に置こうとすれば、余程高い位の召喚師としての素質──つまり“血脈”を持っていないと不可能ですわ。イルギジドさんが師団長様に取り入ったのはフハール家という召喚師の血を利用する為のものでしょう。ガレー遺跡の“大禍鬼”であるシンラは他存在を取り込む力を持っていた。イルギジドさんはそれを逆手に取って、技法によって己の手を加えた師団長様をシンラに取り込ませ、それを基点として鬼を支配下に置いたのだと推測しますわ」
彼女の言い分が正しいのであれば、イルギジドが連れた“大禍鬼”は、広義で言えば鬼であると同時に、カナード・フハールでもあるという事か。
腕を組み、ふむと息を吐く【NAME】。と、そこで今まで黙って話を聞くだけであったノエルが小さく手をあげ、イェアの注意が自分に向くのを待ってから口を開く。
「イェア、改めて訊ねておきたいことがあります。“師団長であったモノと戦う”ということは、常駐軍はイルギジド準軍師とあの鬼──大禍鬼シンラとの戦闘を考えているということでしょうか。つまり、彼等の行動を止めると?」
「一応はそのつもりのようですわね。でも、副団長様があんな調子で、師団長様と準軍師様が失踪ですから、もう混乱の極みという感じでね。本当なら大草原に常駐している軍を早急に動かせれば良いのだけれど、今のままではイルギジドさんが他の二つ、いえ、もしかしたら三つの遺跡に眠る“大禍鬼”と接触する為に、姉やキヴェンティの“杜人”と激突するのは止められないでしょうね」
イェアは、はぁ、と疲れの色濃い溜息をつく。
「……しかし、イルギジドさんが他の遺跡へ忍び込む程活発に動いていた事を気付いていなかったのが正に痛恨、ですわね。こうまで後手となるとは」
舌打ちしかねない後悔の強い調子で彼女は呟き、そして顔を伏せたまま呟く。
「イルギジドさん達がどちらの遺跡に向かうか判りませんが、その一つを落として、もう一つへと移動する間。わたくし達の準備が整うとしたらそこが最速でしょう。私も動ければ良いのですが、ガレー遺跡周辺に描いておいた、この土地概念を調律する印章陣の微調整という最重要の仕事からは抜けられませんし」
そこで言葉を切り、イェアは【NAME】を真っ直ぐに見る。
「でも、【NAME】さん。貴方なら、何とかできるのではありません? 大禍鬼殺しの貴方なら」
馬鹿な、と【NAME】は呻いた。
コルトレカンの大禍鬼の死に関わった者ではあるが、自分ひとりで倒せたとは考えていない。不可能だと【NAME】は呟く。が。
「でも、今の貴方には神形器がありますわ。ノイハウスで、力を貸してくれたのでしょう?」
イェアの言う事は確かだが、しかし、確実に扱えるものだとは到底思えない。
いざ対峙した時に神形器が沈黙したままならば、単なる犬死となってしまう。そんな結末は【NAME】としては遠慮したい処だった。
「それは、そうなのですが……この状況ではもう宛てになる方が貴方しか居りませんの。出来れば姉の行動も止めたいのですけれど──姉は相応の覚悟を持って行動しているようですし、後のフォローもあの人なりに考えてはいるようですから、そちらまでは無理にとは言いませんわ」
イェアは己の懐に手を入れて何かを取り出すと、【NAME】の手を取りその掌に硬い結晶のようなものを握らせる。
「報酬としてこれをお渡ししますわ。兎に角、イルギジドさん……あの方を止めてください。ガレーでの行動を見る限り、彼の行動は自身の目的達成以外の部分に対する配慮が欠けていると言わざるを得ません。ガレーで行ったような荒っぽい手段をとるなら、“命脈”は問答無用で溢れ、周囲を圧倒し、壊すでしょう。その力は伝播し、下手をすればこの島全体を飲み込みかねない。だから、お願いします」
【NAME】は嘆息と共に頷く。そこまで言われては断れない。
「ありがとうございます、【NAME】さん。──なら、ノエル?」
「はい」
「あなたも、この人を助けてあげて」
「……ですが、わたしは」
ノエルは感情の宿らない声を僅かに掠らせる。拒絶、とまでは行かないが、明らかに逡巡しているように見えるその様子に、イェアは小さく頷いて彼女の傍へと寄った。
「“大禍鬼”に近づくのが不安ですのね。ならノエル、こっちにいらっしゃいな」
「?」
小首を傾げて歩み寄ってくるノエル。イェアは袖から抜き出した小さな白羽根を彼女の耳上に刺す。
「印章で術式を組み込んだ飾りですわ。これであなたの能力は少し抑えられてしまいますけど、その分概念に纏わる感度も低下して防御能力も上がります。結構色々考えて頑張って作った特注品ですのよ?」
ノエルは目をしばしばさせて己の左耳上に飾られた羽を触る。そんな彼女の様子を見て、イェアは窘めるような表情で小さく首を傾げる。
「ほら、人に何かをしてもらったときは?」
「ありがとう、ございます」
ノエルの言葉に、イェアの顔がぱっと綻ぶ。
「よし、良い子! じゃ、【NAME】さん、ノエル。申し訳ないけどお願いします。急げば、もしかしたらノイハウスにも間に合うかもしれません」
悠長にしている余裕は無い、か。
【NAME】はイェアに頷き、そして自分の隣に来るノエルに視線だけで合図すると、部屋の外を目指し歩き出す。
急ぎ、ノイハウスへ。イルギジド達が一直線に向かっていったならば間に合う筈も無いが、レェア達と戦闘になり、それが長期戦にでもなっていれば、もしかしたらという可能性もある。
“大禍鬼”相手に戦えるのかどうか。不安は残るが──兎に角、やるしかない。
四大遺跡 双頭四腕の鬼
――潰えぬ影者――
暗闇に閉ざされた黒色の城塞の中。【NAME】とノエルはノイハウス遺跡の内部をただ走っていた。
意外なことに、ノイハウスを占領していた者達はレェア以外既に軍に投降した後で、遺跡に人気は全く無い。
【NAME】達が大草原に展開された常駐軍の陣地に到着した時には、彼等は投降者の対応を終え、ノイハウスへと攻め込むべきか、それともポロサの本営から入った情報を考慮してノイハウスからヴィタメールへと至る直線の上に部隊を配置するかで揉めに揉めている最中。【NAME】達はその隙を利用して彼等の展開する網をすり抜け、遺跡へ辿りつく事が出来た。軍上層部の混乱による行動の遅れが生み出した恩恵だ。
遺跡は既に“現創”による罠等は動作していないらしく、亜獣の気配も無い。遺跡を正面から探索するのは今回で初めてとなるわけだが、構造はいかにも単純で危険も無く、【NAME】は地下へと伸びる大階段をあっさりと見つけた。階段の下からは何ともいえぬ異質な空気が漏れ出しており、その感覚はガレー遺跡で漂っていた気配に近い。この下かと【NAME】は急ぎ階段へと駆け寄る。
その時、階段の手前に何か奇妙なものが転がっている事に気付き、足を止めた。
闇の中、じっと目を凝らす。
「…………」
目前に転がっているのは、恐らく人らしきモノの亡骸。
──何故こんな場所で。
【NAME】は慌てて近づこうと数歩駆け出して、
「【NAME】、あぶな」
背後にいたノエルの声を最後まで聞くこと無く、【NAME】は大きく背後へ跳躍。その動きを追うようにして死体が凄まじい爆発を起こした。
だんだんと数度床に叩きつけられ、しかし【NAME】はそこで動きを止める事無く地面を蹴り、飛び退る。
「──ッ」
一瞬前まで【NAME】が居た場所に響く、鉄のぶつかる音。
か、という硬い音を響かせて弾かれたのは、投擲用の短刀だ。
この刀を使う者を以前に見た。ガレー遺跡で戦い、去っていった謎の人物。
答えを期待せずに【NAME】は誰何の声をあげ、その間に態勢を整え武器を手に持つ──と。
「何者……そうですね」
意外な事に、返答が来た。
【NAME】が慌てて声がした方を向くと、そこにはガレーで見た小さな影が立っていた。
目元を覆う布は外されており今は顔を隠していない。見える顔立ちからは、しかし少年か少女か判断できない。声と同じ幼くも整った顔が、無表情にこちらを覗いている。
彼、もしくは彼女は自身を晒す様に悠然と立つと、身構える【NAME】とノエルを見据えてゆっくりと言葉を放つ。
「私はフハールの従家を務めておりますイムカの者。カユリ・イムカ・フハールと申します。これ以上先へ貴方がたを進ませる訳にはまいりません。ここで私が相手をいたしましょう」
同時、輪郭が揺れて、その姿が一つ二つと数を増やす。
幻であって幻でない、正に分身。
それらを従え、カユリは一度身を伏せ、反動として凄まじい速度で跳ね上がると【NAME】に向けて音速の刀を放つ!!
[BossMonster Encountered!]
裏家の暗殺者



──獲った。
確信と共に放たれた【NAME】の一撃が、小さなカユリの身体に叩き込まれる。明確な手応えと共にカユリは吹き飛び、壁際へと激突。その身を折って倒れ伏した。
【NAME】は大きく息をつくと、一度武器を振って間を取り、意識を切り替えようとして。
「【NAME】、それは偽物です!!」
ノエルの叫びに、【NAME】は驚きと共に吹き飛ばしたカユリの方へと視線を向け──咄嗟の判断でそれを中止。その場から横へと全力で転がる。
そして何処からか飛来する短刀の群れ。
空気を裂く音を携え飛び来る短刀を寸で避けてから壁際を見れば、そこにはカユリとは似ても似つかぬ丸太が一つ。真中に大きな印が刻まれているのを見ると、どうやら何らかの術式が施されたものらしい。
(……幻術の一種か)
なるほど、カユリがわざわざこちらの前に姿を現して名乗ったのはこれの為か。
舌打ちする間もなく【NAME】は身を動かし、追撃してくる短刀を構え直した獲物でもって叩き落す。
──となると、もう一度、か。
連戦となるが仕方が無い。【NAME】は意識を集中し、近くに居るであろうカユリの気配を探った。
[BossMonster Encountered!]
裏家の暗殺者



「──かっ、ふ」
肺に溜まった空気を強制的に押し出され、カユリが小さく声を吐いて震え、その場に倒れる。高速で動くカユリの位置を読み、放った【NAME】の一撃がカユリの胴を捉えたのだ。
込めた力は全力のもので、喰らえばまず行動不能に陥る筈だ。【NAME】は完全に力を失ったカユリを暫く観察し、動きが無いのを確認してから武器を収める。
「【NAME】、終わったのですか」
僅かに離れた位置で援護を行っていたノエルが、銃を構えたままとことこと近づいてくるのに【NAME】は頷き、カユリから距離を取る。面倒を排除するならこの場でカユリを殺すか縛るかするべきなのだろうが、下手に近づくともし今のカユリの仕草が演技だった場合に虚を突かれる形となるし、時間もない。放置して先へと進むべきか。
【NAME】はノエルの方を向いて彼女に先を急ぐ事を伝えようと動く、その時。
じゃ、という地面を削る音と共に、視界の片隅、倒れていたカユリの身体が跳ね上がり、猛然と自分の方へと向かってくるのを見た。
馬鹿な、と呟く言葉も声にならない。
攻撃の動作も無く、懐に手を入れて、ただ体当たりしてくるような仕草で迫るカユリに、【NAME】は慌てて反応して、
「──【NAME】!!」
視界を横切る閃光。黒銃から放たれた一撃に真横より貫かれ、吹き飛ぶ暗殺者の姿を見た。
続けて、数撃。空中に浮ぶその身体を光が連続で打ち据え、分解する。
音を立てて砕けた身体が床へと落ち、既に物言わぬ存在となったモノを半ば茫然としながら【NAME】は見届け、そして射手の方を見る。
「……【NAME】。急いでいるとはいえ、油断です」
ノエルの無表情には僅かな憤りの感情が混ざっていた。
彼女は黒銃に纏わりつく熱を払うように一度振って、【NAME】の隣に立つ。床に転がる物体、自分の手によって息絶えたそれを僅かに見据える。
「最後、【NAME】に襲い掛かった際に、あの人の内部に強烈なイーサの変動を感知しました。恐らく、自爆するつもりだったのだとわたしは考えます」
だから躊躇無く、殺すために撃ち、そして追い打ちまでかけた。言外にそう言っていた。
【NAME】は難しい表情で黙り込む。
彼──か彼女かを自爆にまで駆り立てるものは一体何だったのか。受けた教育に従っての行動であるのか、それとも既に化け物と化した主に対する忠誠心故なのか。【NAME】は転がる亡骸を見据え、答えの無い問いを呟く。
僅かに目を伏せ、ノエルは小さく息を吐いた。
「どうでしょうか。でも、あの人の心情がどのようなモノであったとしても関係ない」
そして、【NAME】を真っ直ぐに見上げる。
「あなたが無事で、良かった。──わたしはそう考えます」
全く偽りの無い素直な言葉は、言った当人以上に言われた者を動揺させる。両眼を瞬かせて固まった【NAME】を、ノエルは不思議そうに首を傾げて見た後、視線を階段に移す。
「行きましょう、【NAME】。あの人がわたし達をここで留めようとしたのなら、まだ急げば間に合うのかもしれません」
確かにそうだ、呆けている場合ではない。
軽く頭を振って【NAME】は意識を切り替えると、ノエルの視線を追うように大階段を見る。その下方からはガレーで感じたものとよく似た強い不快感を伴う、何ともいえぬ歪な気配が漏れ出していた。
――双頭四腕の鬼――
ノイハウス遺跡の真中より地下へと伸びる大階段の最下。
中央に祭壇らしきものを配した、六角の大広間に辿り着いた【NAME】とノエルが見たもの。それは先端に朧なる気を宿した長杖を担ぎ、祭壇の横で悠然と立つイルギジドと、レェアとレェアに良く似た姿をした者達が、それぞれ致命傷を受けて力無く倒れ伏している場面だった。
レェアらしき者達は広場に十人ほどおり、彼女等は皆どこか色が白く全裸に等しい格好をして、まだ生きてはいるようだが動きは殆ど無く、ぐったりと身を横たえている。まるで糸の切れた人形のような印象だ。
しかし、そんな彼女らの中で一人だけ、硬い衣服を纏い傍に大銃を置いたレェアは、歯を食いしばり、己の傷が齎す痛みに逆らうように顔を上げ、イルギジドを睨んでいた。
「“先生”!!」
ノエルの悲鳴というものを、【NAME】は初めて聞いた。
彼女の声に反応し、イルギジドを睨んでいたレェアが血まみれの顔を大広間の入口に立つ【NAME】達に向ける。
「……ノエル? 駄目、退きなさい──!!」
叫ぶ声は掠れて細く、彼女の眼の焦点は既に合っていない。右胸に開いた大穴から漏れ出す血が彼女の感覚全てを奪っているようだった。
明らかに、致命傷に見えた。
イルギジドもゆっくりと視線を移し、口を半月に逸らせて笑った。
「いやはや、もうこちらへ来ましたか。カユリ殿も長い表暮らしで腕が鈍っていたようですなぁ」
既に語るべき事も無い。【NAME】は武器を抜き、ノエルも銃を構えてレェアを庇うべくじりじりと彼らに近づき始める。
「“先生”、今すぐに、助けます!」
「馬鹿、逃げなさい!! 擬似的な翆脈顕現[ヴォルベイズ]の為に呼んだ“現創”の私を使っても、奴を止められなかった……もうノイハウスの“大禍鬼”は、シルイーヌの鬼封は解かれ、目覚めている。……でもまだ手はある、だから早く逃げ──がッ!?」
「なかなかしぶといですな、“女賢者”殿」
先端に朧な影を宿した杖。それを携えたイルギジドの右手が振られると同時、突然レェアの身体が跳ね飛ばされ、無形の手によって広間の壁に張りつけられる。
「か、は」
胴に開いた穴から鮮血が吹き、レェアの顔色は既に蒼白を通り越してどす黒いものになりつつある。
「だが、これで終わりです」
イルギジドが醜く捻じ曲がった指を鳴らすと、ぢり、と空間が爆ぜる音が響く。
次いで生まれた歪みの奥から、二つの頭と四本の腕を持つ不気味な巨体が悠然と立ち上がる。今までは然程漂っていなかった鬼種特有の重く捻れた気配が増し、周囲の空間を侵食するかのように膨れ上がった。
「シルイーヌ、やりなさい。“飲み込め、邪なる力[ブラッディアーム]”」
イルギジドの淡々とした指示に、鬼の表情は愉悦の色に染まり、歯の隙間から毒々しい吐息が漏れた。
そして、【NAME】やノエルが行動に移す前に、鬼がありえない速度で動き、その四本の腕を壁に貼り付けられたレェアの身体に叩きつけた。
「────」
音も無く。
揺らぐような黒光りする輝きを纏った四つの拳が触れると同時に、レェアの身体は背後の壁ごと捻じ曲がる。
「レェア!!」
ノエルが上げる悲鳴すらも吸い込むように、拳から広がった輝きは打撃点に向かって一瞬にして収縮し、壁の破片やレェアの身体を巻き込みながら、この場から完全に消滅した。
「──そん、な」
呟くノエルの手が緩み、下がった黒銃の先端が床を打った。【NAME】も息を呑み、固まる。
眼の前で起きた事とはいえ、余りにも短い時間での出来事に思考が麻痺する。彼女の実力は前にノイハウスを訪れた際──イルギジドとの戦闘時に確認済だ。大銃から放たれる一撃は凄まじく、扱う技法や術式の技量も極めて高い位置にあった。その彼女がああもあっさりと、跡形も無く消し去られる。“大禍鬼”という存在の力を改めて感じさせられ、背筋に震えが走る。
そんな【NAME】の硬直を解いたのは、イルギジドの淡々とした言葉だ。
「ふむ、意外と呆気ない最後ですな、“女賢者”殿。もう少し粘るかと思っておりましたが、所詮この程度の雑魚ということですかね」
言って、イルギジドがゆっくりとこちらへと向いた。
杖から溢れ出る、不自然なまでに強い負の波動が【NAME】の全身を打ち、【NAME】は小さく首を振って瞬時に意識を切り替える。
固まっている場合ではない。今から自分は、彼らと戦わねばならないのだ。
惚けていても、熱くなっても駄目だ。迂闊な行動は即座に死に繋がる。冷静に、慎重に対応しなければ、今のこの状況で勝ちを拾う事などできないだろう。
困惑、恐怖、怒り、その全てを押さえ込み、【NAME】はイルギジドと四つ腕の鬼の姿を静かに見据える。
が、明らかに冷静ではない者がいた。
「──今の言葉、取り消しなさい」
そんな震える声を放ったのはノエルだ。
「“先生”の侮辱は、許しません」
普段ならば冷静に判断を下し、動く筈の彼女の背中からは、明らかなる怒気が立ち昇っていた。表情は常の無表情ではなく、眉を引き絞り、歯を噛み締めたもの。黒銃をしっかりと構え直し、祭壇の横に立つイルギジドを睨み上げるその様は、激昂という表現が一番的確だろう。
彼女が“先生”と慕っていたレェアの消滅。それがノエルの冷静さを完全に奪っていた。あの様子では、銃を抱えてイルギジドに殴りかかるような事もやりかねない。慌ててノエルの傍へと動きかけた【NAME】だが、
「ほほう。では、どう許さないのか、ゆっくりと見せていただきましょうかね」
【NAME】の行動を遮るかのようにイルギジドが杖を振ると、四腕の鬼は【NAME】達の方へ向かい大きく踏み出す。その仕草にあわせて広間全体が大きく揺れ、空気が熱く軋んだ。
かぁ、と濃い吐息を二つの頭が吐き出すと、同時に巨体の左右に直径3メートルはあろうかという歪みの渦が湧き上がる。生まれた二つのどす黒い渦から外へと這い出してきたのは、それぞれ奇怪な形状の身体を持つ大鬼。恐らくシルイーヌと呼ばれる四腕の“大禍鬼”の眷属たる存在であろう。
状況の更なる悪化に、【NAME】は舌打ち。
──しかし、どういう事だ、これは。
内心の疑問を口の中で転がす。
「おや、何やら不思議そうですな、“神形の操手”殿」
表情に出たか、余裕の笑みで見下ろすイルギジドの言葉に、【NAME】は僅かに思案の間を置いた後、問いの言葉をゆっくりと放つ。
レェアが部下達を軍に投降させた後、以前言っていた遺跡停止の儀式とやらを行っている最中──もしくは準備中の段階でイルギジドが現れ戦闘となり、そしてレェアが敗れた。
ここまでは、現在の状況を見れば納得できる流れだ。
しかし、一体イルギジドはどうやってノイハウスの“大禍鬼”、シルイーヌを己の支配下に置いているのか。これが判らない。
話しながら、【NAME】はさり気ない動きでノエルの傍へと近寄り、彼女を斜め後方に置いた位置に移動する。この会話は自身の疑問を晴らす為の行為であると同時に、いきり立つノエルを静める間を作るためのものだ。ノエルの前に立って一瞬だけ視線を送り、こちらの意図を何とか把握させてから、【NAME】は問いを続ける。
ガレーの“大禍鬼”シンラを支配下に置いた際は、カナード・フハールという触媒をシンラが持つ“同加”を利用して取り込ませ、それを介してシンラの存在概念を掌握したとイェアは考えていた。この推測が正しいのであれば、“同加”という他存在を取り込み力とする能力を持たない他の“大禍鬼”を掌握する為には、また別の方法を取らねばならないのではないか。
ならば、イェアの立てた推測は間違っていたのか。しかし、幾ら召喚の司であろうと“大禍鬼”を独力で従えたというのは俄に信じ難い。他に一体どんな手法があったのか?
イルギジドは【NAME】の意図など気付いていたのだろうが、しかし余裕故かノエルを庇うように動いた【NAME】を阻止するでもなく、話を最後まで聞き終えて一つ頷く。
「ふむ。まぁその疑問は尤もですな」
小男はにんまりと笑みを見せて、手にした朧を纏う杖を僅かに浮かせた。
「答えは簡単ですよ。全てはワタクシの力ではなく、カナード・フハール殿が持っていた“血脈”の力のお陰という奴でして」
イルギジドがとんと杖を床につくと、小柄な召喚師の背後に二枚の大翼を広げた巨体が染み出すように姿を現した。
「──ッ」
纏う形無き力に気圧される。【NAME】はぎりと歯を鳴らし、その存在を計るように睨み据える事で抗う。
放つ気配は四腕の鬼と同等か、それを上回るか。規模が大きすぎて、計る事すら難しい。恐らくあれが、ガレーに封じられていた“大禍鬼”シンラなのだろう。
イルギジドはそんな【NAME】の様子を満足げな表情で見下ろす。
「この“鬼喰らいの鬼”に仕込んだ仕掛けを使って、コレを媒介として経由しシルイーヌを従えているのですよ。ワタクシが“鬼喰らいの鬼”を従え、“鬼喰らいの鬼”が“双頭四腕の鬼”を従える。こういう構図ですな。いやはや、シルイーヌはヴァイオラやシンラ、ウィースルゥインより一段格の低い“大禍鬼”である故とはいえ、我ながら上手く行ったものだと自賛したい処ですが」
イルギジドとシンラの身体がふわりと浮び、祭壇の奥へと飛ぶ。逆に、シルイーヌとその眷属達が前へ、【NAME】達の方へと動いた。
「【NAME】、もう、大丈夫です」
背中からの声に一瞬だけ振り返れば、常の無表情にはほど遠いながらも、ある程度冷静さを取り戻したノエルの顔がある。【NAME】は頷き、そして武器を新たに構え直しながら、懐に下がる首飾りを一度触れる。
流転の神形ゼーレンヴァンデルング。
ただの人の身である【NAME】が“大禍鬼”と互角に相対するには、この器の力を借りねば不可能だ。
祈るような気持ちで握り込み、そして全力を込めて訴えかける。
果たして、答えはあった。
──斬りたいの?
神形の意志が今の状況に感じる興味の度合いを示すかのように、ちりん、という鈴音は酷く小さく、響く声もコルトレカンで聞いたものと比べて遥かに弱い。
だが、確かにその音は【NAME】の耳に届き、慌てて肯定の意を返す。
──だけど、あれは駄目。
予想外の言葉に、【NAME】は息を詰まらせる。
【NAME】の戸惑いを察したように、少女の声は更に響いた。
──だって、私は留める鎖を、断つモノだから。
そうか。神形器ゼーレンヴァンデルングは流転の象徴。停滞を促すもの、永遠を計るものを壊す役目を担った器だ。故にそれ以外の存在に対して絶対の力は望めない。“大禍鬼”は長き寿命をもつ存在と言われるがそれも完全な無限ではなく、故にゼーレンヴァンデルングが完全な対象とする存在ではないらしい。
絶望しかけた【NAME】であったが、しかし。
──でも、壊すのは好き。
りん、と一際大きく鈴音が響き、背筋に熱い何かが差し込まれる感覚。
──だから、手伝ってあげる。
そして次の瞬間、全身が白い輝きに覆われた。輝きの中心は首に掛かった飾り。半ば浮き上がるようにして輝くそれからは、凄まじい力が満ちて、周囲の空間に伝播する。
その様を見据え、空中に浮ぶイルギジドがふんと鼻を鳴らす。
「ほう。前回と覚醒式が違うようですが──まあ、そちらの準備は整ったようですな」
イルギジドの細い両眼が、昏い喜悦と共に輝く。
「では参りましょうか。何処まで出来るのか見せていただきますよ。“神形の操手”殿」
言葉と同時、四つ腕の“大禍鬼”の右上腕が振りかぶられ、前へと突き出された。鉄を打ち出すような腹に響く音が響き、拳が撃った空間を中心に強烈な波が生まれた。無形の揺れは一瞬にして【NAME】と、傍に居るノエルの方へと迫る。
「────」
正体は判らない、しかし危険。それだけは理解できる。
【NAME】は大きく左へと回避しようと飛び、ノエルは黒銃による射撃を行いながら右へと飛ぶ。
ノエルのフォーレミュートから放たれた光は、鬼の拳が打った形無き波動と干渉し、光はあらぬ方へ、波動は僅かに左へとずれてノエルと【NAME】の間を通過。【NAME】が背にしていた広間入口に激突し、周囲の壁が豪快にひび割れ、砕け散り、そして収縮して消滅する。
──直撃を受ければ一体どうなるやら。
内心の冷や汗を隠して【NAME】は鬼の脇へと回りこみ、技法を放つ。
ゼーレンヴァンデルングの加護の為か、動きは常よりも数段速い。放った技法も一度鬼の身体へと届く寸前、見えぬ殻のようなものに一瞬阻まれ、しかし全身を包む光が輝きを増すと同時に突き抜けて、鬼の肉を削る。
(……いける)
両脇から来る攻撃を避けきり、その確信と共に距離を取る。鬼が放つ威圧の気に身体が怯えることが全く無い。この輝きが身を覆っているならば、たとえどのような力にも縛られる事はない。そう信じる事が出来た。
──あとは、自分の力次第か。
神形が力を貸してくれているとはいえ、相手は“大禍鬼”とその眷属。イルギジドと“鬼喰らいの鬼”が高みの見物を決め込んでいるのが気に掛かるが、同時の相手となればそれこそ勝機は無い。
まずは眼の前の敵を全力で倒す。それしかない。【NAME】は地を蹴り、四腕の鬼に向かって渾身の技を繰り出す!!
[BossMonster Encountered!]
現創の大禍鬼



「ほう、やりますな」
ゼーレンヴァンデルングの助力故か。【NAME】の放った一撃を受けて四つ腕の“大禍鬼”が砕かれ、再生する事も適わず朽ちていく。鬼が自身を維持するために持っていた陰性の概念が広間に撒き散らされ、ずしりと空気が歪み、重くなった。
その粘るような感触を振り払い、【NAME】は疲労を訴える身体に鞭打って武器を構え、空中に浮ぶイルギジド、そしてシンラを睨んだ。
長杖の召喚師は、その視線を小さく首を捻って受け流す。
「本来ならば鬼を斬る為の役を担った武器ではないでしょうに、“大禍鬼”を打ち滅ぼす程の力を所有者に与えるとは。余程格の高い神形のようですな」
崩滅した“大禍鬼”を見届けても、しかしイルギジドの余裕は崩れない。それも当然だ。彼の背後には別の“大禍鬼”の姿があるのだから。
手に持つ杖をくるりと回してから、小男は僅かに思案するように顎を撫でると、何かに納得するかのようにふんと一息つく。
「ま、良しとしましょう。今は概念の回収を優先しましょうか。“一と加せ、同加[エクストゥルース]”」
最後に呟かれた文句に合わせて、イルギジドの背後に浮んでいたシンラが天を見上げて両腕を広げ、大きくその口蓋を開く。
何をするつもりか。警戒に身を引き締める【NAME】が見据える中。
──雄々、と。
シンラが放った太く強い咆哮が広間全体を大きく震わせ、同時に空間に散り漂っていた重苦しく歪んだ気配が、空中に浮ぶ“大禍鬼”に向かって凄まじい勢いで収束し、吸い込まれていった。
空間を埋めていた重い空気が薄れていくのに反比例して、浮ぶシンラが放つ力の気配がどんどんと高まっていく。
「……これは、まさか散った“大禍鬼”の力を、取り込んでいる?」
茫然とするノエルに、イルギジドは軽く頷いてみせる。
「正解ですよ、お嬢さん。これが“鬼喰らいの鬼”と古に呼ばれたシンラの力。他存在はおろか、同族である鬼種すらもその身の力に変換する喰らう者ですな。尤も、“大禍鬼”クラスとなると、存在が完全に砕けた状態でなければ喰らうのは不可能ですがね。しかし──シルイーヌは兎も角ヴァイオラはどうするべきか迷っていたのですが……手間も掛かりませんし、あちらでもこの方法を取るのも悪くないですかねぇ」
とんとんと、正に悠々と杖で己の肩を数度叩いて、【NAME】達の方と、そして真下にある祭壇の中央へと視線を走らせ、彼はふむと一息。
「さて。では、ワタクシはこの辺でお暇させていただきますか。ヴィタメールの“杜人”殿が行動を起こす前に着く必要もある事ですし」
「な──逃げるつもりですか!?」
ノエルの叫びは尤もだ。自分達は辛うじて“大禍鬼”を倒す事に成功したが消耗は激しく、対してイルギジドはただ傍観していただけ。戦力比は圧倒的なままで、それなのに自分達を無視してこの場から去るという。理解できず、【NAME】も唖然とイルギジドを見上げる。
だが、イルギジドは真面目な表情で首を横へと振って否定する。
「いや。逃げる、というより、無駄な労力を使わずにあなた方に死んでもらおうと考えているのですよ」
「……?」
更に意味不明な言葉に、【NAME】は眉根を寄せて呻く。どういう意味なのか見当もつかない。
「ふむ?」
イルギジドはそんな【NAME】達を怪訝な表情で眺めて、何かに気付いたかにやりと笑う。
「ああ。強い神形の力に覆われているせいで、知覚できてないのですか。そちらのお嬢さんは……その頭に差した飾りのせいですかね。では、ヒントを差し上げましょう。“命脈”と“大禍鬼がここに封じられていた意味”。この二つです」
「…………」
答えは直ぐに出た。
【NAME】は慌てて自身を覆う神形の力を拒む。その意志を敏感に察知したか、首飾りから放たれていた輝きは一瞬にして失せて、替わりに周りの空間全てを圧倒する強烈な力が、遺跡の底から盛り上がってくるのをはっきりと感じた。
「“大禍鬼”という弁を失ったが故の、“命脈”の氾濫、ですか」
同じ結論を呟くノエルに、イルギジドは大きく頷く。
「大正解。上に浮いているワタクシの眼には、祭壇の真中に開いた大穴の底から、今にも噴き出そうとする力の気配が見えている訳でして──まあ、命が惜しいと言いますか。ここで争っている暇はないと、そういう事ですなぁ」
ガレーではイェア達が事前に印章陣を敷いており、ここノイハウスではレェアが何らかの策を施すと同時に遺跡停止、“大禍鬼”の排除を同時進行させるような話を聞いていたが──この広間に入ってきたときの事を思い出すと、その策とやらを施す前に彼女はイルギジドに消されたように見えた。
ノイハウスの要となっていた鬼はイルギジドによって解放され、そして【NAME】によって崩滅している。既に蓋は無く、一過性のものながら“命脈”の乱流はこの遺跡より世界へと漏れ出し始めているという事だ。このまま広間に留まっていれば、その力の乱流を真っ先に受けて、逆らう事も出来ずに己の存在概念ごとあっさり消し飛ばされるだろう。
「では、ワタクシは退くための道を開く事にしましょうかね」
云いつつ、イルギジドが杖持つ腕を一つ振る。
その動きに合わせ、背後を飛ぶシンラがその両腕を高く掲げて、お、と深く響く単音の咆哮を吐いた。
鬼の掌に正に漆黒と呼ぶに相応しい円が浮かび上がり、次の瞬間、空気が裂ける音と共に、太さ数メートルにも及ぶ黒線となって天へと向かい突き抜けた。
「さて、“命脈”の流出を防ぐ手段があるならば使っていただいて、その後にワタクシがあなた方の止めを刺そうかと考えていましたが……無さそうですな」
苦虫を噛み締めたような表情で黙り込んだ【NAME】を見て、イルギジドは肩を竦めた。
「ならば、諦めるのが宜しいでしょう。今から階段を使って地上へと駆け戻ったとしても、“命脈”流出による概念飽和範囲から逃れるのは至難でしょうからね。──では、ワタクシはこれで」
天井に開いた大穴から、イルギジドとシンラの姿がするすると消える。残されたのは、【NAME】とノエル、そして戦いの余波でぼろぼろに崩れたレェアらしきモノ達の残骸だった。
「…………」
【NAME】は無言のまま、広間中央に配置された巨大な祭壇に近づく。
祭壇は中央部が空洞になっており、【NAME】がそこから下を覗き込めば、遥か遠く地の底まで刳り貫かれた穴の奥から、ガレーに居た時に感じたあの圧倒的なまでの力がどんどんと迫り上がってくるのが判る。栓を抜かれた“命脈”が現世界へと噴き出そうとする流れだ。
「……どうされますか、【NAME】」
隣へと寄ってきたノエルの言葉に、【NAME】は穴奥に見える白き輝きを睨む。
“大禍鬼”を失った事による“命脈”の流出。それを止めようにも、【NAME】には何の案も無かった。
反射的に懐の首飾りに手をやるが、力を発現させた反動で休眠に入ったか、それとも自分の領分にかすりもしない現象には反応する気も無いのか。今はもう全くの無反応。
となれば、後はもう全力でこの場から離れ、噴出した“命脈”という乱流の範囲外へと脱出する以外ない。イルギジドは間に合わないと云っていたが、ここで茫然と立ち止まっているよりはマシだ。
【NAME】は急ぎその場を去るために、ノエルへ促しの言葉をかけようとして。
「…………」
彼女が広間の一点。大きく崩れ剥がれた壁の一角をじっと見つめているのに気付いて、言葉を詰まらせる。
その場所は、レェアがシルイーヌの一撃を喰らい跡形も無く消え去った場所だ。
──と、【NAME】の視線に気付いたか、ノエルの両肩が揺れてこちらへと振り向く。
先程の戦いにより煤けた顔はいつもの無表情に戻っているが、その奥に揺らぐものを見逃すほど【NAME】の目は甘くは無い。甘くは無いが──しかし、掛ける言葉は思いつかない。
そんな【NAME】に、ノエルはほんの僅かに相好を崩してみせる。
「……申し訳ありません。大丈夫です、【NAME】。行きましょう」
振り切るように、外へと続く階段へと駆け出すノエル。【NAME】も後を追う形で走る。
祭壇奥から感じる気配は加速度的にその大きさを増しており、地響きにも似た振動が遺跡を支配しつつある。
果たして間に合うか。
【NAME】とノエルは、全速で持って地上へと続く大階段を駆け上がった。
「く、っ」
戦いで痛む身体を引き摺りながら、【NAME】とノエルはどうにかノイハウス遺跡の外へと飛び出す。
地響きは既に轟音にも等しい音で、遺跡だけではなく地面全体が激しく揺れる。真っ直ぐ走ることもままならぬ状況で、しかし【NAME】とノエルは懸命に遺跡から離れるべく走る。こんな処で何も解決せずに終わらせる訳には行かない。
遺跡の周囲に作られたシニの設営地は、あまりの揺れに建てられていた天幕の殆どが潰れてしまっている。【NAME】とノエルはその合間を抜け、折れた支え木を避けて南へと走る。そろそろ設営地を抜けて森へと入る。
そんなタイミングで、後方で強まっていた力の気配が一気に膨張した。
遺跡とその周囲諸共、眩い光で包み込む。森に入った【NAME】達も例外ではなく、全身を輝きに包まれた瞬間、光に接する部分全てが泡立ち、弾けるような感覚に襲われる。
そして訪れる、凄まじいまでの圧迫感。
力の奔流に、全てが飲み込まれる。
そう思った瞬間。
「──あ、つ?」
突然、辺りを埋める輝きが急速に弱くなっていく。
何故。そう思う間にも光はどんどんと弱まり、森を覆うほどに広がっていた輝きの領域は一瞬にして萎み、遺跡を覆う程度にまで収縮していった。
「……【NAME】?」
いつの間にか蹲っていたノエルが苦しげな顔のまま【NAME】を見上げてくる。先刻の光に包み込まれたのが余程効いたらしい。ノエルは普通の人よりもこう言った概念的な圧力に弱い。レェアが言っていた事を思い出しながら彼女を助け起こすと、様子を伺うようにノイハウスの遺跡を見る。
遺跡を何とか包む程度にまで収縮した力の光であったが、そこからは縮む事も無く、かといって拡大する事も無く。ただただ周りの存在を圧倒する気配を放ちながら留まっている。たまに揺らぎ、外へと向かって光が伸びようとして、何かに引き寄せられるかのように遺跡の内へと引っ込むのを見ている限り、何か外的要因によって力の流出が抑えられているように見えるが──しかしその要因とやらが何なのかが判らない。
「もしかして、レェアが事前に対策を施していたのでしょうか?」
どうだろうか。強引に推測するならばその辺りの答えが一番妥当であろうが、詳しい知識の無い自分達では結論は出せず、そしてここで出来る事ももうない。
ならば、どうすべきか。
答えは直ぐに出る。イルギジドを追うことを優先するべきだ。今回の戦いで、神形ゼーレンヴァンデルングの力を間借りすれば、“大禍鬼”にも拮抗する事が可能なのは判った。ならば、今島に居る人間のなかで最も勝率の高いのが、自分達の筈。
既にイルギジドはヴィタメール遺跡に向かったはずだ。奴がヴィタメールに封じられた“大禍鬼”を解くまでに、自分達も追いつき、止める必要がある。
「【NAME】、大丈夫。立てます」
ふらつきながらも【NAME】から身を離すノエルを軽く支えながら、【NAME】は南へ。一先ずティネの村を目指して歩き出す。
遺跡を占領するキヴェンティ達、もしくはその手前に張られた常駐軍の部隊をイルギジドが突破しきる前に、ヴィタメールに辿り着かなければ──。
四大遺跡 幽かなる彼女
――百封の遺跡――
「三、七の部隊を一時的に前に出せ!! その間に二を回収、終わり次第三と七、五も退かせろ!! 一度撤退する!!」
深い森の中では馬は使いづらい。ノクトワイは地面に立ち、近くの伝令に大声を張りあげる。
ヤムールと大草原の間、ノイハウスとヴィタメールの直線上に広がる大きな森。そこでノクトワイ率いる常駐軍の部隊は、本来ならば同じ常駐軍の者であるイルギジド、そして彼に付き従う“鬼喰らいの鬼”と相対していた。
まだ戦いが始まって然程の時間も経っていない。しかし常駐軍側は、既に劣勢という他無い状況に陥っていた。部隊を二つに分けての挟撃、奇襲をかけたにもかかわらずだ。
イルギジドが放つ、魔術司にも匹敵するかという強大な威力の術式と、有り得ない程の強度を持つ障壁。召喚される獣の異様なまでの強さ。そして彼に随伴する“大禍鬼”の圧倒的な力。
そのどれもが、然したる前準備も出来ず、専用の武具も罠も仕掛られずに戦う事になった常駐軍の人間を打ち据える。
「隊長、ですがそれは!!」
「仕方ないでしょ! これじゃ足止めにもならないわ!」
止める部下に怒鳴りで返して、ノクトワイは歯噛みする。
イルギジド・マイゼルと彼が操る“大禍鬼”を打ち倒すべく待ち伏せを仕掛けた訳だが、このまま対峙し続けたところで、どう考えても無駄死にになるのは目に見えていた。
それ程までに、状況は悪い。
単なる召喚師という枠を明らかに超えたイルギジドの力と技。そして“大禍鬼”が放つ圧倒的な力は、常駐軍の兵士達が放つ集団技法すらも全く寄せ付けない。特に“大禍鬼”は、その凝固しすぎた陰性概念のお陰か、並の武器では皮膚に刃を届かせることすら出来ないようだ。
常駐軍内では幾つか“大禍鬼”クラスの存在と交戦した記録が残っているが、通常の武器、術式では傷一つつけられなかったという報告は多い。念入りに敷かれた大規模な印章陣や、特殊な封印結界術。または強い力を持つ魔導器、神形器の力を借りて何とか相手になる。“大禍鬼”とはそんな相手だ。今のように数に任せた人対人のような戦法は正に愚の骨頂──判っていた事だが、眼の前で改めてその事実を見せ付けられると、やはり苛立ちは隠せない。
「見てみなさい、あちら側の部隊も後退を始めているでしょ? ワベルもアタシと同じ考えなのよ。だってイルギジドの奴、遊んでるわ。多分。アタシ達を餌にしてるのよ」
「…………」
黙り込む部下を放置して部隊を退かせる指示を飛ばしながら、ノクトワイは恨めしげに森の向こうに見える巨体を睨む。
集団の頭とも云うべき者達を失ったアノーレの常駐軍は、兎に角まとまりを欠いていた。今こうして鬼を倒す為に出てきたのも、大草原を任されていた部隊の約三割。あとは初期の命令を頑なに信じて大草原に居座る部隊。ノイハウスへと進攻していった部隊。勝手にポロサへと撤退していった部隊など、それぞれの部隊長が好き勝手に動いている。
軍の象徴たるカナード・フハール、実際に統括していたクスィーク・カナルとイルギジド・マイゼル。その内二人を同時に失い、更にクスィークは自失状態で軍務遂行不可能。上という抑えを失った状態でのこの異常事態に、各部隊の長達も混乱し、右往左往してるというのが現状だ。
「ったく、参ったわねぇ」
既にノクトワイの預かっていた部隊は半ば戦闘力を失っていた。これ以上の戦闘続行は不可能だ。逆側から攻め込んだワベルの部隊も同様か、更に消耗しているだろう。
常駐軍部隊が自分達の方へと突撃してくる気配が無いことを悟ったか、小柄な人影と翼を持つ巨体がふわりと空へと浮かび上がり、ヴィタメール側へと飛び去っていく。
ノクトワイとワベルが率いる部隊には、上空の敵を叩く手段を持つ魔術士は少なく、弓兵も居る事には居るが、何の加工もされていない矢では足止めにもならない。
「打つ手なし、か」
ヴィタメールの方角へと消えていく二つの影を眺め、ノクトワイは深々と嘆息をつく。
イェアから貰った伝え鳩で、【NAME】達が彼らを止める為に動いている事は知っていた。その為の時間稼ぎと気張ってはみたものの、役に立ったのかどうなのか。それは今の彼には判断しようもない。
あとは、ヴィタメールを占領するあの“杜人”たる少年がどの程度粘ってくれるかだが、彼は彼で何やらロクでもない仕掛けを行っていたようでもある。
「全く、面倒な状況だこと……。報告書、大変だわ」
ノクトワイは改めて大きく溜息。そして自分の部隊を一先ず駐屯地へ撤退させる為、伝令に新たな指示を飛ばした。
ヴィタメールを囲う森に展開していた常駐軍の部隊の姿も既に無く、同様にヴィタメール近傍に張られているキヴェンティ達の野営地にも人影は無い。
前者は恐らく大草原での戦闘の際にそちらに召集されてそのまま、という事なのだろうが、キヴェンティ達の姿が野営地に一切無いというのはどういう事なのか。空っぽの大天幕の一つを覗き込んだ【NAME】は、訝しげに首を傾げる。
「ですが、【NAME】。この状況は好都合だとわたしは考えます。遺跡に忍び込むまでの手間が省けました」
背後、天幕の外で用心深げに首を巡らせていたノエルの言葉は、確かに頷けるものだ。この急ぎの状況でキヴェンティ達と遺跡に侵入する手前から大立ち回りを繰り広げていては、イルギジドと彼が従える“大禍鬼”の相手などできやしない。
天幕を出た【NAME】は、北方向に聳えるヴィタメールの遺跡へと走り出す。半円、ドーム状のその威容は、今まで見てきた二つの遺跡、ノイハウスとガレーとはまた別の、奇妙な形状の建造物。イルギジドは自分達より先にノイハウスの遺跡を脱していた。既にこの遺跡に到着していても可笑しくない。野営地にキヴェンティ達が居ないのは、彼のせいであるという予想もできる。
「急ぎましょう、【NAME】。わたしは、あの男が許せない」
薄い表情のまま告げるノエルに後押しされ、【NAME】はヴィタメールの遺跡内部へと続くと思われる巨大な横穴へと向かう。以前に訪れた時に、このような横穴が遺跡の側面に開いていただろうかとも思ったが、今はそんな事を気にしている場合でもない。【NAME】は天幕の合間を抜けるように、その横穴へと駆け出した。
――ヴィタメール遺跡――
遺跡に足を踏み入れると同時に、周りの景色がずるりとずれて、全く別のものへと変化した。
「ヴィタメールの遺跡については──」
隣に立つノエルが、移り変わる景色をじっと眺めながら小さく唇を動かす。
「“先生”に様々な事を教わっていた頃、まだあの人が島の調査を始めて間もない時にここへ入った事のお話を聞いたことがあります」
景色の流動が不意に止まった。眼の前に広がるのは石造りの小さな部屋と、中央に微細な刻印が施された巨大な石版。そして古ぼけたレバーが一つ。
「その時は、最奥にたどり着けぬまま帰還したそうですが、中では“過去に存在した何処かの空間”をそのまま再現させる機能が発現しているそうで、内部に複数設置されたレバーでそれを制御するという話です」
これか。【NAME】は古ぼけたレバーの取っ手を握りこむ。
「それぞれの地点は全て現実の存在ではなく、その辺りの仕組みはノイハウスのものに近いと。レバー自体も単なる機能を示す“シンボル”として、わたし達に知覚させるためのものだと云っていました。あと、レバーの近くの床に刻まれた刻印があって──」
云われて下を見れば、確かにそれらしい紋様が床に刻まれている。
「転送の力を秘めているらしく、それを使えば即座に遺跡の出入口に戻ってくることができるという事でした。わたしが聞いたのは以上の事です」
ふむ、と【NAME】は唸り、そしてレバーの下部を見る。
レバーは刻まれた十字の溝の中央にあった。前へ倒すか後ろへ倒すか、それとも左右へ倒すかは自分次第だが。
――翆の杜人――
レバーを動かすと、周りの景色が一気に変化する。
(……次はどんな世界だか)
いい加減慣れてきた【NAME】は、レバーを握ったまま周囲の変化をじっくりと見定めながら──握っていたレバーがいつまで経っても消え去らないのに首を傾げた。その間にも風景の変化は終了し、包む世界が固定化される。レバーを握り締めたまま【NAME】は周囲をぐるりと見渡して、今までとは一風変わった景色が広がっている事に気付く。
直径数100メートルはあろうかという巨大な建造物の中。天井はなだらかに傾斜するドーム状で、下も同様。床も天井も凹凸は無く、ただ楕円の空間が広がる。
そんな中、天と地の中間、楕円の縁とも言える位置から、建物中央にまでするりと、平らな板状の出っ張りが一本伸びており、【NAME】は幅3メートル程のその道が遺跡の壁と接する場所に、レバーを掴んだまま立っていた。
背後を振り返れば、斜め上方へと続く大通路。見上げれば、道の先に外から差し込んでいるであろう光が見えた。恐らくヴィタメール遺跡に侵入する際に使った横穴へと繋がる道であろう。
──つまり、今眼の前に広がるこの風景が、本当のヴィタメール遺跡の姿ということか。
思い、前方へと視線を戻す。遺跡中央にまで伸びる道の先に、巨大な光の球体が何の支えも無く浮んでいるのが見える。光る網を何枚も何枚も重ねたようなその球体が放つ気配の質から察するに、あれはノイハウスやガレーで感じた“命脈”だ。“命脈”とこの世界を繋ぐ孔のようなものが、あの空中の一点に開いている、という事だろう。
イルギジドらしき姿も、気配も無い。理由は判らないが、先にノイハウスを発った筈のイルギジドよりも先にこの場へと到着する事が出来たらしい。
そして──。
「先にお前が来たか、神形の使い手」
遺跡中央の光球と、遺跡の縁に居る【NAME】達。二点を繋ぐ細道の中間に、一人立つ幼き影。
手に一刀、腰にもう一刀を提げて立つ少年は、“杜人”のリゼラ・マオエ・キヴェンティ。
少年は【NAME】とノエルを順々に見据え、良く通る声を放つ。
「アレから──レェアからお前の事は聞いている。人による人為らざる力持つ器、神形を操る旅人。そして鬼の概念を受け入れて操られることで強き力を保つ、呪われの申し子、とな」
彼は右手に柄、左手に鞘を持って剣を抜き放つと、左手の鞘を投げ捨てて肩の高さにまで掲げる。
袖からそろりとまろびでたのは、丸まった緋色の糸。
「いでませい、我が孔より生まれし翆の顕『九継』よ」
言葉と共に真横へと腕を振れば、小さい蛇は一瞬にして膨れ、九つの首持つ巨大な炎蛇へと変化する。炎の粉を散らしながら悠然と宙を泳ぎ、少年の背後へと廻った炎蛇は九つの顎を大きく開き【NAME】達を貫くように睨み据えた。
「では、始めるか。“迷の民”よ」
少年が、また一歩踏み出す。
彼の動きはゆったりとしたものでありながら、纏う気配は張り詰めたもの。その姿は闘いを迎える戦士のそれだ。
半ば少年の生み出す雰囲気に飲まれかけていた【NAME】とノエルは、はっと我に返る。
「待ってください! わたし達は戦うつもりは──今は、ここへやってくる召喚師と、彼が従える“大禍鬼”を」
慌ててノエルが訴える。
そう。自分達はヴィタメールへ向かっているであろうイルギジドを止める為に来たのだ。彼の従える“大禍鬼”との戦闘の為に無駄な消耗を避けねばならぬ身としては、出来ればキヴェンティ達との戦いは回避したい。寧ろ共同戦線を張りたいというのが本音だった。あの召喚師と“大禍鬼”を同時に相手にする事を考えると、正直自分達だけでは心許ない。
──だが。
「いや、お前達は我と戦わねばならない」
少年は断言するように告げる。
「眼を見れば判る。お前達の瞳は死にに来た者の眼ではない。ならば、我と戦う為にここへ来たという事だろう?」
「……?」
少年の理屈が理解できない。【NAME】とノエルは怪訝な表情でお互い顔を見合わせる。
そんな【NAME】達を見て、少年の足が止まる。幼き両眼は見定めるように【NAME】とノエルを暫し見据えて、溜息一歩手前の息をついた。
「成程な。今からここで何が行われるのか──それを理解していないのか、お前達は。ならば見るがいい、あの者達を」
リゼラは手に持つ剣の先端で、すり鉢状となっている遺跡の下部を指し示した。
そこには、白を基調とした衣服を纏った男女が円を描いて並び、中心に向かって一心に祈りを捧げている。その人数はかなりのもので、外の野営陣に詰めていた者達の三割程があそこに集まっていると考えて良いだろう。
「何を、されているのでしょうか。彼らは」
ノエルの自問のような呟きが聞こえたのか。リゼラは視線を下方へと向けたまま、淡々と答える。
「翆脈顕現[ヴォルベイズ]の儀式だ。己が存在の一部を翆なる“命脈”へ還し、力ある翆の眷属を起こす翆片憑依[ティルベイズ]を更に推し進め、存在全てを翆なる“命脈”へと反転させ、その際に漏れ出した“命脈”の飛沫を力として用いる、我等キヴェンティが秘儀の一つ。今から彼らは祈りと共に自身を殺し、その犠牲より生まれる力で持ってして奇蹟を──封じられた“大禍鬼”を遺跡ごと消滅させる」
淡々と、彼は自分に従う者達が今何を行っているのかを告げる。
「その破壊は遺跡のみでなく、この場所により近い、お前達“迷の民”の里すらも飲み込むだろう。あの召喚司──イルギジドといったか? 奴がここへと向かっているというのなら、その破壊に巻き込む事もできる。そして我は長の務めとして、無防備となる彼らを護る者として、こうして一人残っている」
「な……」
【NAME】は驚愕の瞳で彼と、そして遥か下方で一心に祈りを捧げるキヴェンティ達を見比べた。
狂信的な殉教者。そんな言葉が脳裏に浮ぶ。
まだ幼さを残した顔に不相応な大人びた眼で【NAME】を見据えるリゼラは、そこで小さく笑みを見せる。それは促しの、挑発とも取れる不敵な笑みだ。
「理解したか、神形の使い手。儀式は間もなく終わる。そうすれば、お前達はこの遺跡に封じられた“大禍鬼”や、供物となる者達を護る我と共に、翆脈顕現[ヴォルベイズ]による破壊に巻き込まれて死ぬ事になるだろう。つまり、お前達はこのままでは死に、死にたくないのならば我を討ち、我が同胞が儀式を終える前に根こそぎ斬り捨てるしかないという事だ」
「…………」
──勘弁してくれ。
【NAME】は呟き、苛立ち混じりに舌打ちする。
彼らだけで死ぬつもりなら兎も角、近くの人里、ノスキスやティネで何も知らずに暮らす者達すら巻き込んでの破壊活動など、見逃せるものではない。もっと良い解決手段があるのかもしれないのに、このような処で彼らの犠牲だらけの計画に乗せられ、殺される訳には行かないのだ。
【NAME】の呻きに、ノエルも大きく頷く。
「その通りだと、わたしも考えます。そんな犠牲を強いる選択を取らずとも、もっと良き流れへと至る道はあるとわたしには思えます」
【NAME】は武器を構え、隣でそう呟いて黒銃を持ち直すノエルを横目で確かめて、前方へと視線を移す。
リゼラは【NAME】達が戦いの構えを取るのを見届けてから、「そうか」と短く呟いた。
「お前達の選択に我は干渉する気は無い。だが、お前達が我の選択に干渉するつもりならば」
少年がゆっくりと構えを取る。独特といって良い、前傾の姿勢。両の足底からじり、と音が漏れ、小さく振動しているのが判った。軽く掲げた剣先には尋常ならざる気配が宿り、全身からは今までとは比べ物にならない圧倒的な破気が放たれる。
以前、野営地で戦ったときとは明らかに異なる、“杜人”の全力となる構え。
息を呑む【NAME】を見て、少年の唇が小さく笑みを作る。
「手加減はせん──剣技を超えた剣技、我が古の月を見るがいい」
言葉と共に少年の姿が掻き消え、次の瞬間、眼の前に現れた白色の衣装を纏った影が、残像すらも残さぬ速度で逆袈裟に剣を振るう!!
[BossMonster Encountered!]
翆獣の杜人


「我が剣筋を捉え見切るか、神形の使い手。──だが」
剣を構えたリゼラの手が霞む。
「……ッ!!」
一足四斬。
【NAME】は思考ではなく経験と反射による動きだけで、眼では追いきれぬ少年の連斬を凌いだ。
そしてリゼラが最後の斬撃で崩れた態勢を補う為に放った回し蹴り。唸りを上げて迫るリゼラの右脚を掻い潜りながらの【NAME】の反撃は、蹴りを放った勢いを殺さず、そのまま後方へと飛んだ少年の体を捉えられずに空を切る。
同時に、【NAME】とリゼラの距離が離れたのを機と見てか、脇からノエルのフォーレミュートによる射撃が飛ぶ。だが、リゼラは左右に跳ねながら下がる事で光弾を避け、着地点を狙った一撃は少年の剣が真っ二つに断ち割った。
僅かな静寂。
少年は場を仕切り直す様に剣を一度払って、【NAME】を真っ直ぐに見る。その表情は透明で、何を考えているのか読み取る事は出来ない。
「互いに決め手に欠ける、といった処だな。しかし、判ってるだろう。このままではお前達の敗北となるぞ」
彼の淡々とした言葉に【NAME】は無言で歯噛みし、僅かに距離を取って立つ小さな剣士を睨んだ。
確かに、彼の言う通りなのだ。
リゼラはあくまで翆脈顕現[ヴォルベイズ]の儀式が終わるまでの時間を稼げば良い訳で、こちらは彼を倒した後、儀式が完遂される前に妨害しなければならない。こんな調子で彼との戦闘に時間をかけていけば、最終的に自分達の負け。彼らの儀式により生まれる破壊に巻き込まれて死ぬ事になる。
(だが、どうすれば良い)
彼の翆霊である『九継』を何とか戦闘不能なまでに破壊し、彼の袖内へと退かせたまでは良かったが、リゼラ自身が手強すぎた。
リゼラの剣技は前にキヴェンティ達の野営陣で戦った時よりも更に苛烈で、凌げはすれども渾身となる反撃を繰り出す余裕は無く、戦いを決するような一撃を入れるのは正に至難。本来ならば長期戦の中、どちらかが冒した小さなミスを突く事によって勝負がつく──そんな状況だ。
だが、時間をかけて彼のミスを待つ等という選択肢は、時間の無い今は取れない。
ならば一体どうすれば良いのか。この場面を打開する為の方法を焦る頭で考え始め、そんな都合の良い方法などこの切羽詰った戦闘中に思い当たる訳もないと絶望しかけた、その時。
──突然、天が崩れた。
遺跡上部。中央に浮ぶ光球を挟んだ逆側の天井を突き破り、遺跡の内部へと突き入ってきたのは黒色の閃光。幅10メートルはあろうかという極大の一閃は、その幅以上に天井を砕き、崩れさせる。そして耳をつんざく轟音と共に、黒の閃光は遺跡下部へと突き抜けた。地に刺さった閃光は床を削り取るように弾けて大穴を穿ち、散り飛んだ黒色の飛沫が無防備に祈りを捧げるキヴェンティ達の身体を無差別に消し飛ばす。
「な、上からだと!?」
少年が驚きの叫びをあげる中、上方から更にもう一閃。
轟音と共に砕かれた天井が瓦礫となって降り注ぎ、下方に居るキヴェンティ達を次々と押し潰していく。
そして少しの間。破壊によって起こった天井部の崩落がある程度収まったところで、光球を挟んだ向こう側に開いた空から、ゆっくりと舞い降りる二つの影。
その正体は言うまでも無い。
朧な影を纏う大杖を携えた召喚司イルギジド・マイゼルと、背より一対の大翼を生やした“大禍鬼”──“鬼喰らいの鬼”シンラである。
空中に浮んだまま、イルギジドは己が巻き起こした惨状を見下ろし、おどけたように笑った。
「いやはや、危ない危ない。もう少しの処で翆脈顕現[ヴォルベイズ]が発動する状況だったようですなぁ……と、殺り残しがまだ居ますな。シンラ、もう一度どうぞ」
大翼をはためかせて飛ぶ“大禍鬼”が大きく口を開き、そこから黒色の波動を吐き出した。
噴き出された闇色の一閃が遺跡下部を一掃するように舐め、先程の攻撃と崩落から逃れることが出来ていた者達の身体も、一瞬にして黒に飲まれ、次の瞬間には跡形も残らず消滅した。
「──術士、貴様ぁ!!」
同胞が声も無く消し去られる様に、リゼラが怒りの叫びをあげた。
そして、白の少年の姿が霞んで消えた。ノエルが使う銃の弾丸をも上回るかという勢いで地を蹴り走ったリゼラは、道の途切れるぎりぎりの処まで踏み込んでから、有り得ない速度で跳躍する。
技法併用によるものか、凄まじい速度で跳躍した少年の身体は一瞬にして空中に浮ぶイルギジドへと迫り、
「“翳ろ、古の月[エンシェントムーン]”」
一閃。
常人には決して見えぬ速度で真横へと振るわれた剣筋は、半月の刃と化してイルギジドとの距離およそ10メートルを一瞬で埋める断層となる。
そして、更に一閃。
翆霊を喚ぶ力を流用したものなのか、衝撃波すら放ちつつ突き出された剣が、儀式魔術による一撃すら上回るような強烈な光撃を吹いた。
線と点の交撃。
二つの連なる破壊は宙に浮ぶイルギジドを音速で捉えようと動き、
「……く」
光撃の反動によって後方へと打ち出され、踏み切りを行った場所へと着地したリゼラは、己が放った一撃の結果に小さく唸る。
イルギジドの楯となる位置に一瞬で移動していたシンラ。彼の右腕を僅かに裂く横線と、肩口を大きく抉った突き穴だけが、先程のリゼラが放った技の成果だった。
「我が古の月を持ってして、腕一本すら取れぬか……化け物が」
シンラの背後から前へと出たイルギジドは、シンラが受けた傷と、歯噛みしながらこちらを睨んでいるリゼラを順々に見て、やれやれといった調子で溜息をついた。
「ふむ。困りますなぁ、リゼラ・マオエ・キヴェンティ殿。相手が違いますよ。あなたがまず剣を向ける相手は──」
イルギジドの杖の先端に宿る朧な影、その三割程が振られた杖に勢いに乗って、遺跡中央に浮く巨大は光の玉へと纏わりついた。
「こちらですよ。とはいえ、少々お待ちいただきますがね」
球体の表面を覆う網の輝きは次々とその影に喰われて解かれ、周囲に小さな象形の連なりという形で浮遊する。影はどんどんと光の網を引き剥がし、食い千切り、球体の形を歪にし、そして中にあるモノを露出させていく。
「貴様、一体何を──あのままでは、封じられた鬼種が何の制約もなく目覚めるぞ!!」
リゼラの叫びに、イルギジドは剥がれていく光の球から視線を外さずに答える。
「ああ。まぁ、そうでしょうな。その為に“贄”の力を解放してアレに嗾けた訳ですし。今回のワタクシは、ただヴァイオラを目覚めさせるだけでして、後はあなた方にお任せしようと考えてましてね」
(……どういう意味だ?)
【NAME】が首を傾げる間にも、光の網はどんどんと解れ、遂に最後の網が取り払われる。
「ほうら、目覚めますよ」
光の網が全て剥がれた後に残ったのは、より強い輝きを放つ水のような球体だ。先刻までの硬質な雰囲気とは異なり、それは球という形態を維持しつつも、何処か柔らかなモノへと変化していた。
そして、光の水球の中に一つの影があった。シンラを主に横方向で上回る歪な巨体。光の鎖という形で括られていた封印結界を解かれた今、その存在が持つ歪な気配は、何の遮るものもなく周囲に発散されている。
周りを急速に汚染していく気配の質──それは明らかに“大禍鬼”のものだった。
――百封の大禍鬼――
光の水球から飛沫が上がる。同時に、球の中に閉じ込められていた巨体が外へと飛び出し、【NAME】達の居る道の先端へと降り立つ。
放つ気はノイハウスで出会った“大禍鬼”よりも遥かに無秩序なモノで、獰猛な輝きを放つ両眼は血走り、自分以外の存在を無秩序に破壊しようという意識に染まっている。これがヴァイオラという“大禍鬼”本来の性質なのか、それとも封印を解かれて直ぐという状況が影響しているのか。どちらにせよ、危険である事には変わりない。
「【NAME】」
と、傍に寄ってきたノエルが小さく声を掛けてくる。
「わたしには準軍師の意図が理解できません。あの“大禍鬼”は制御されていない。あれでは準軍師も鬼の攻撃対象に含まれる筈。なのに何故、あんな強引に封印の解除を?」
言われて考え、数拍。
「ああ」
思い当たった。奴がノイハウスで呟いた言葉が【NAME】の脳裏に甦る。
『ヴァイオラはどうするべきか迷っていたのですが……手間も掛かりませんし、あちらでもこの方法を取るのも悪くないですかねぇ』
【NAME】がシルイーヌを倒してその存在を砕き切った時、イルギジドは、控えさせていたシンラにシルイーヌの残滓を吸い取らせながら、そう言ったのだ。
(……という事は)
イルギジドは、ヴァイオラという鬼を直接支配下に置くつもりはなく、【NAME】かリゼラか、第三者の手によって一度ヴァイオラが殺されるのを待ち、その時生まれる意志を失い砕け散った力の概念をシンラに吸収させようという腹積もりなのだろう。
──だが。
「おやおや」
イルギジドは小さく肩を竦めて、光の球より外へと脱出した“大禍鬼”を見る。
薄板状の通路の上に降り立ったヴァイオラは、周囲の己の眷属を呼び出した後、【NAME】やリゼラが居る方向ではなく、逆側。イルギジドとシンラが浮ぶ方向へと振り向くと、威嚇とも取れる咆哮を上げて身構えた。
リゼラはその様を眺め、小さく鼻を鳴らす。
「術士よ。封印を解いたは良いが、奴にとってお前達が最も注意しなければならぬ敵であるらしいな」
イルギジドはリゼラと【NAME】達が立つ方を見下ろすと、「確かに確かに」と口元を歪めて笑う。
「ですが、ワタクシが相手をしていては、封印を急ぎ解いた意味がないのは確かですな。という訳で、ワタクシ達は高みの見物と洒落込む事にいたしましょう。後は宜しくお願いしますよ、“杜人”殿に、“神形の操手”殿」
「何?」
彼の物言いに訝しげに片眉を寄せるリゼラを無視して、イルギジドは杖を両手に構え持つ。
「“我が身は無へ、完全なる密偵[パーフェクトステルス]”」
そして最後の呟きにあわせて大きく杖を横へと振った。
「──いけない。【NAME】、あの術式は」
ノエルの呟きが最後まで紡がれる前に、空中に浮ぶ二つの影、イルギジドとシンラの姿は空間に溶けるように消えて、同時に彼らが放っていた強烈な気配も一瞬にして消え去った。
「召喚師が使う“不自然なる密偵[フォースドステルス]”の亜流──停止型完全隠匿結界の一種です。あれではいくら“大禍鬼”でも完全に対象を見失う筈です。そうなると……」
ヴァイオラは突然消滅したイルギジドとシンラに戸惑うような動きを見せるが、それも一瞬だ。
鬼は何かを感じたように素早い動きで【NAME】とリゼラが立つ側へと身を返すと、先程イルギジドに浴びせたモノと似た威嚇の咆哮を上げて、大きく身構える。
「……成程な。興味の対象から自分達を消せば、あとは我や神形の使い手にその矛先が向くという仕組みか」
リゼラが己の剣を一度大きく振り、悠然とした仕草で構え直す。
「気に食わぬが、まぁいい。我らキヴェンティの目的は“大禍鬼”を片端残らず討つ事。やる事は変わりはせん」
言い切った少年の視線が、ふと【NAME】の方へと向く。それに気付き、表情だけで何用かと問えば。
「神形の使い手、お前も手を貸せ」
わざわざ言わずとも良い言葉を言う彼に、【NAME】は小さく苦笑。
どうせ“大禍鬼”に眼を付けられたこの状況では、鬼と戦い退けるという選択肢しかなく、しかも相手は人では到底太刀打ちできぬ程の力を持つ相手だ。生存率、倒せる確率を上げる為には協力関係を結ぶのが得策。わざわざ口に出す必要もない自明の話といえた。
【NAME】は小さく頷いてから、首から下がったゼーレンヴァンデルングに心の中で訴えかける。反応は早く、一呼吸も置かずに飾りがゆっくりと輝き始め、【NAME】の全身を包んだ。
「【NAME】、来ます」
脇に立ち、険しい表情で鬼達を見据えていたノエルの言葉に頷きながら、【NAME】は両脇から挟み込むように襲い掛かってきた二つの影と、中央から距離を詰めてくる巨体を順々に見据え、己が身体を包む力を解放しながら大きく床を蹴った。
[BossMonster Encountered!]
百封の大禍鬼



右と左。両手に剣を持ったリゼラが大きく踏み込むと同時に鬼を斬る。
音すらも絶つ速度で放たれた六つの剣線を寸断無く身に受けたヴァイオラだが、“大禍鬼”を構成する存在概念の強固さが物理的強度にも影響しているのか、細い切り傷程度しかつかない。
だが、鬼の気を引き付ける効果は十分にあった。
そこへ横からのノエルの射撃。黒の銃口から放たれた光の奔流が鬼の側面、リゼラが斬った六つの剣線の内の一つを的確に打ち、爆音と共に弾けた。着弾したヴァイオラの上腕部にあたる肉が飛び散り、衝撃に耐え切れずに鬼の膝が落ちる。
「【NAME】、今です!」
ノエルの声を聞く前から、既に【NAME】は行動を開始していた。
完全に動きの止まった鬼の傍へと駆け寄ると、身に宿るゼーレンヴァンデルングの力を混ぜ合わせるように気を込め、至近の位置から全力の技法を放つ。
──これ以上無い、会心の手応え。
打ち抜くような感覚と共に、ヴァイオラの巨体がその一撃に貫かれ、纏う神形の力が一瞬にして鬼の身体へ浸透。そして次の瞬間、大きく弾け飛んだ。
散った肉片達は、元の形へと戻ろうと一瞬ぶるぶると震えるのだが、打ち込まれた技法に乗った神形の輝きに阻害されるように動きを縛られ、そして次の瞬間には音を立てて腐り果てて、そのまま空間に溶けるように消えていった。
(……何とかなった、か)
その様を見届け、【NAME】は肩の荷が下りたような気分になって、大きく息を吐いた。
──しかし。
「いやはや、終わりましたか」
響いた声に、【NAME】ははっと顔を上げる。いつの間に身を隠す結界を解いたのか。そこに浮ぶのは小柄な術士と翼持つ大鬼、イルギジドとシンラだった。
――幽かなる彼女――
イルギジドは【NAME】達の視線を受けて一つ笑みを作ると。
「ご苦労様ですな皆様。では早速、概念の回収をさせていただきましょうか──“一と加せ、同加[エクストゥルース]”」
【NAME】やリゼラが立つ厚みの無い床の通路上に着地したイルギジドは、呪文と共に何かを促すように杖を振る。
それにあわせてシンラが高々と吠え声を上げれば、散り飛んだヴァイオラの気配がシンラの身の内へと吸い込まれ始める。
「【NAME】、止めなければ──!」
ノエルの言葉に頷き、【NAME】は武器を構える。既にシンラはノイハウスの“大禍鬼”を喰らっている。これ以上“大禍鬼”を喰わせて力をつけさせる訳には行かない。
【NAME】は素早く己が身に宿る神形の力を解放しようとして──その動きを上回る速度で【NAME】の横をすり抜け、イルギジドの元へと向かい飛び出す影があった。
「ぬかせ術士、次は貴様だ!!」
そう叫び、駆けるのはリゼラだ。
彼は己の袖内より『九継』を出しながら、イルギジドに向かい一瞬で間合いを詰める。床を蹴り飛ぶように走る速さは、荷を背負わずに全速で駆ける軍馬をも上回る程だ。
だが、それでも接近しきるまでに、イルギジドが一動作を取る程度の間はかかる。
「いやいや。邪魔は無しですよ、“杜人”殿」
腕を振る動き一つ。イルギジドが杖に宿った奇妙な力を、場へ大きく解放させるのが見えた。
「“喰らいつけ、不吉なる横笛[イヴルフルート]”」
更に、杖から離れた力がイルギジドの言葉によって異質な気配を増し、目前にまで迫ったリゼラに収縮する。
その力は彼が喚び出しかけていた『九継』の炎身を一瞬にして砕き、強烈な波動となってリゼラの小さな身体を呆気なく吹き飛ばした。
少年の身体が凄まじい速度で空中を滑り、彼方の壁面に叩きつけられ、転落する。
「──っ、は」
落ちた地面の上で、呻きの声と共に何とか起き上がろうとリゼラはもがく。意識はあるようだが、しかし受けたダメージの大きさは隠しようが無いのか。僅かに身を起こす事すらままならないようだ。
「はは、いやはやいやはや」
ほんの少しの力も入らず震える彼を遠く眺め、イルギジドは驚きの表情のまま拍手した。
「流石流石。残る“贄”の力三割を解放しての一撃を受けて、まだ意識を保ちますか。全く、その年でその精神力の強さは、正直驚嘆する他ありませんな」
「……く、きさ、ま」
顔だけを何とか上げて、リゼラは凄惨な形相でイルギジドを睨む。だがイルギジドはにこやかな笑みすら浮かべてその視線を受け流した。
「だが、身体は持ちますまいよ。散った翆霊とてその身では掻き集められぬでしょうしな」
正に余裕、といった態度でイルギジドは告げると、今度は【NAME】の方へと視線を移す。
「さて、次はあなた方ですが」
同時に感じる、何とも表現し難い厭な気配。
「────」
身体が無意識に動いた。
【NAME】は反射的に斜め前方へと飛び、彼の視線を避けつつ近づこうとしかけて、
「“それは何物も拒む境。絶対領域[フォースフィールド]”」
一瞬での術式の構築。【NAME】が動きを開始する前に、その周囲を輝く壁が塞ぎ、閉じる。
絶対領域[フォースフィールド]。
主に召喚師達が対象の束縛若しくは防衛のために使う、世界を断絶する結界術の一つ。効果時間は短いが、破る事は決して出来ないとされるものだ。
──だが。
「【NAME】、今のあなたならこの壁を破る事は容易い筈です!!」
判っている。背後からのノエルの声に、【NAME】は頷きだけで返すと、片手を大きく掲げる。
身に宿る神形の輝きが一際増した。自分を包む環境。強い“留める力”に反応して、器に宿る神形の意識が沸き立ってる証拠だ。
躊躇う間もなく、【NAME】が振り上げた武器を払い撃てば、囲っていた絶対領域の境界は熱に溶けるバターのように呆気なく消え去る。結界の形成から消滅させるここまでの動きに、まだ三秒と掛かっていない。
しかし、その僅かという他無い間を、イルギジドは有効に活用した。
「“開け、封印の檻[シールドケイジ]”」
イルギジドの力持つ言葉と共に空中に浮ぶのは、召喚の為の印章の輪だ。彼は【NAME】が結界を抜けるための動作を取る間に、召喚術を扱う為の輪を作り上げていた。
数は無数。本来ならば有り得ぬ技であるが、あの杖に宿った奇妙な力がそれを可能にするのか。紡がれた円の間から様々な召喚獣が吐き出され、【NAME】へと殺到した。
舌打ちしつつ、迎撃を開始する。
一撃、若しくは二撃。神形器の力を借りた【NAME】は群がる獣達を一瞬で屠っていく。
だが、その間にもイルギジドの後方に浮ぶシンラは、周囲の空間に散った陰性概念──“大禍鬼”の残滓を啜り上げ、己の力へと変換していく。
「【NAME】、これでは──」
ノイハウスの再現だ。判っているが、しかし召喚獣の相手をしない訳にも行くまい。
最後の獣を消し飛ばし、【NAME】はそこで漸くイルギジドの方へと向くが。
「惜しい。もう少しでしたな。既にこちらの作業は終了です」
「────」
イルギジドの後ろに控える“大禍鬼”は同族を二度も喰らった影響か、もうシルイーヌやヴァイオラとは全く別次元の存在であるかのような雰囲気を漂わせていた。翼持つ巨体という姿はそのまま、最初にノイハウスで見た時より、二回りはその身を大きくさせているように見えるのは、単なる纏う気の強さによる錯覚であるのか、それとも。
「さて、用も済んだ事ですし、そろそろワタクシはお暇──と行きたいのですが、どうしましょうかね。あなた達がどうやってノイハウスの“命脈”流出から逃げ切ったのか、少し興味があるのですが」
イルギジドは伺うようにこちらを見る。
だが、【NAME】には答える気など全く無い。そもそも【NAME】はあの遺跡から溢れ出ていた力の流れが急速に萎んだ原因など知らなかったし、知っていたとしてもこのふざけきった男にどんな小さな情報でもくれてやる気は無かった。無視したまま、自身を覆う神形の力を溜め込むように身構える。
そんな【NAME】達の様子を見て、イルギジドは顎を軽く撫でて苦笑。
「当然と言えば当然ですが、嫌われたものですなぁ。では、致し方ない。答えを聞くのは諦めて、憂いを断つ為にここで死んでいただきましょう。シンラ、行きなさい」
一歩。大きな歩みでこちらへと進むシンラ。ただそれだけで周囲の空間が震え、【NAME】の肌上をびりびりと痺れが走る。
「【NAME】、来ます……っう」
呻きと共にノエルが頭痛を堪えるように顔を顰め、僅かに膝を崩す。シンラの生み出す威圧力が、彼女の耳上に飾られた羽──イェア特製のアクセサリが持つ護りの力を上回っているのか。
【NAME】は反射的に彼女を庇う位置へと移動すると、また一歩、前へと踏み出した“大禍鬼”を睨み上げ、そして素早く視線を移す。
イルギジド。彼は最初見た時より半分程度の大きさとなった朧な輝きを纏う杖を肩に当て、ゆるりと後ろへと下がる。戦いを傍観するつもりか、それともこちらの隙を狙って攻撃を仕掛けてくるつもりか。
次に、鬼の背後を見る。シンラが放つ凄まじい破気に紛れて感じ取り辛いが、遺跡中央に浮ぶ光の球体、ヴァイオラを閉じ込めていた力の輝きは、制する為の蓋を失ったことにより徐々に強くなり始めている。“命脈”から漏れ出す力の氾濫。それから逃れるには、シンラとイルギジドを早急に片付ける必要がある。
──しかし。
厳しい視線のまま、【NAME】は一瞬だけ背後を見る。遠く遺跡の壁際には、倒れ伏したままのリゼラ。まだ先程イルギジドから喰らった衝撃が抜けないらしく、漸く半身を起こした程度。戦闘など不可能だ。
そして【NAME】の直ぐ背後に居るノエル。銃を構え、戦う意気は見せているものの、顔は顰められたまま。イェアから貰った羽飾りでも、鬼が放つ陰性概念を完全に遮断する事ができてないようだ。
【NAME】とて、既にリゼラと一戦、“大禍鬼”と一戦と、激しい戦いを二度も超えており、完調とは言い難い。急いで倒さねばならないどころか、まともな戦いになるのかどうか。それすらも判断がつかない。
いっそ、今は全力で退くべきか。真正面から戦うより生き残る確率はまだ高いかも知れない──そんな事すら考え始めた、その時。
『その辺にしときなさい』
──何処かで聞いた声が、戦いの場である遺跡全体を木霊すように響いた。
「その声──“先生”!?」
背後からのノエルの叫びに、【NAME】ははっとする。
そう。今響いた声の質は、明らかに彼女、ノイハウスの遺跡でシルイーヌの拳によって消し去られた“女賢者”レェア・ガナッシュの声だ。
『はぁい、せーかい。相変わらず優秀だねノエル。……さて』
同時、ドーム中央に浮ぶ光の球体──“命脈”へ繋がる空間から、槍のような光が曲線を描くようにして無数に飛ぶ。幾本もの光は【NAME】やシンラ、イルギジドにリゼラと各々の間を力の格子となって遮った。
「これは、翆霊? いや、“命脈”の力か?」
己の長杖を構えて目を細めたイルギジドに、響く声が答える。
『ご名答だ、“召喚司”。ここでうちの生徒とその連れをやらせる訳にはいかないんでね』
そして、身構えたままの【NAME】とノエルの丁度中間の位置に、ぼんやりと輝く白色の人影が浮かび上がった。
ディティールは酷く曖昧で、輪郭も半ば周囲の空間に溶け出している。しかし、それは確かに、あの“女賢者”レェア・ガナッシュの姿だった。
「せ、“先生”──」
手にした銃を放り出しかねない勢いで、彼女の傍へ駆け寄るノエルだが。
『っと、ととストップストップ! 触っちゃ駄目だよノエル!』
慌てた様子のレェアに、ノエルは顔中に疑問を浮かべて立ち止まる。
『この身体、“命脈”の──飛沫の一滴みたいなちっさい力を捏ねて作ったモノだから、触っちゃうと形を維持できなくなる。だからストップ』
目を瞬かせながら頷くノエルに、レェアは笑みを一つ送ってから表情を改め、イルギジドの方へと振り向く。
「いやはやいやはや、何とまぁ。はは、ははは」
イルギジドは驚きと愉悦。その二つを大きく表した表情で一頻り笑った後。
「──驚きましたな。確かに殺した筈でしたが……どういう事ですかね、その身体は?」
問いに、レェアはふんと鼻を鳴らす仕草。
『簡単な事よ、召喚司。あの鬼に殺される前に、貴方が来る前に駆動寸前にしてあった“命脈”に存在概念を写す式を動かしたの。不完全もイイトコ、サポートの人形も全部壊された状態で起動した上に、即座にノイハウスから漏れ出す“命脈”の押さえ込みに入ってたから、今の状態になるのにかなり時間食ったけどね』
「精神の“命脈”への転写、ですか。召喚士のワタクシからしますと、到底ありえぬ技に思えますが──」
『“大禍鬼”従えてるあなたに言われたかないがね。それに“命脈”自体へ転写したって訳じゃない。長年の研究と、引いた“命脈”の規模が枝の枝、極めて末端のソレだった事。あと、行った環境が“命脈”への概念的距離がほぼゼロに近い状況だったってのが成功の要因かしらね。色々と“欠けた”けれど、予想以上に上手く行ったわ』
レェアの形をした何かは、揺らぐ両腕を器用に組んで見せると、僅かに首を傾げた不敵な態度で問う。
『さぁて、召喚司。ずいぶん派手にやってるようだけど。来る途中、軍の部隊も幾つか潰してきたみたいね』
「彼等が突っ掛かってきましたのでお相手していただけですが……よくご存知で。それも“命脈”と繋がった恩恵ですかな」
『まぁね。といっても大して融通は利かないけど。で、どうする? この場でやるか?』
「────」
イルギジドは僅かに眉根を寄せて周りを見回すように視線を動かす。
自身の杖。イルギジドの意志を受けて、大翼を広げたまま光の格子の前で止まっているシンラ。その向こう側に立つ神形の使い手と、特殊調整された古代亜人種。そして“命脈”の末端、半ば概念の存在と化した女賢者。最後に、遺跡中央に輝く光の球体。球から漏れ出る力の気配は、ヴァイオラ顕現後から加速度的に大きくなってきている。
それらを見届けた後、イルギジドは【NAME】達を見て、力を抜くように小さく吐息。僅かに笑みを見せた。
「……止めておきましょうかね。この光の檻が、扱える“命脈”の力の限界であるならば大した事はなさそうですが、実際の処は未知数ですし……無駄に突ついて“命脈”の力を暴走されては逃げ切れない。退かせていただけるならばそうしたい処ですが」
『なら退きなさい、追いはしない。【NAME】達も消耗激しいだろうし、これ以上の戦闘は無理でしょ?』
厳しいのは確かだ。だが、ここで奴を逃がして良いのか? 既に二つの遺跡に封じられていた“大禍鬼”を取り込み終えたイルギジドが、次にどう動くつもりなのか。それが一切判らないというのに。
「“先生”──ですがそれは」
ノエルが戸惑うように呟き、格子の向こうに見えるイルギジドも僅かに驚いたような表情を浮かべる。
「宜しいのですか? 推測ですが、貴女は“命脈”と概念的位置が近い場所でなければこちらへ現れる事も出来ないでしょうに。貴女の事です、次のワタクシの狙いも読めているのでしょうが──あそこは特殊だ。その身では顕現できますまい。それでも今を逃すつもりですか」
『判っちゃいるけどね。でも、今からここでドンパチやられて理粒子[イーサ]を乱されると、ヴィタメールに連結している“命脈”が抑え切れない。だから早く静かにしてほしいのよ。もうここでの用は終わってるんだろう、召喚司』
イルギジドはふむと一つ唸り、思案の間を開けた後。
「確かに、あなたの“命脈”の流出防止を邪魔をして被害を拡大させても、大した意味はありませんしな。利のある悲劇を呼び起こす事には躊躇いませんが、意味の全く無い悲劇のお手伝いをわざわざする程、良い趣味はしておりませんし」
長杖を軽く横へと振って、小男は口元だけを歪めた笑みを作る。
「──宜しいでしょう、今日のところはここでお暇しましょう。“繋げ、境界[スレショールド]”」
イルギジドが最後に紡いだ言葉は、召喚士達が召喚獣を自分が所有する閉鎖領域へと還すもの。シンラの身体が煌く虹の色に包まれて、空間に溶けるように姿を消した。
同時にレェアが右手を掲げれば、光の球体から伸びていた檻も消え去る。消滅したのはイルギジドを囲っていた光のみで、【NAME】達の前にはまだ光の格子が組まれたままだ。自分やノエルがイルギジドに手を出して場をややこしくするのを防ぐためか、それともイルギジドの不意の攻撃に対応するための壁として残しているのか。
イルギジドは杖を構えたまま、レェアに定めていた視線を僅かに左右へとずらした。
「しかし……貴女が来ないとなれば、来るのはそこの方々ですか?」
『んー、どうかな。正直、あなたの次の目的地は判るけど、そこで何をして、その後どうするつもりなのか。そこがいまいちはっきりしなくてね。だから、下手にちょっかいを出すか出さざるべきか、迷う処なんだが』
答える気はあるのか。そんな視線を向けるレェアに、イルギジドは薄く浮かべていた笑みを消す。
「ワタクシの目的、か。……まぁ、大したものではありませんよ。一つは単なる欲求であるし、もう一つも感傷に近いもの。半ば諦めてはいるのですが、これだけの力があればもしやという事もある。やれる事はやっておきたいと、そういう訳でして」
『判り辛いね。もう少しはっきり言えない?』
「ワタクシにも恥じらいというモノがありましてな、この辺りでご勘弁を」
レェアの言葉をイルギジドは軽く肩を竦めて受け流すと、
「さて、ではまた──次に会う機会がありましたら、決着でもつけましょう、“神形の操手”殿」
大仰に一礼。そして杖を大きく横へと振れば、彼の身体は一瞬にして速度を増し、半ば崩れた天井の大穴から、遥か北の向こうへと飛び去っていった。
「“先生”……」
イルギジドが消えていった方向を睨んでいたレェアは、恐る恐る、といった風に見上げ呟くノエルに、にこやかな笑みで振り返る。
『ノエルに【NAME】。無事で良かった、何とか間に合ったね』
そんな事よりも、今の彼女の状態の方が気になった。一体その姿は何なのか。
【NAME】が半ば顔を引きつらせて問えば、レェアは自身の身体を見下ろして、小さく苦笑。
『これか。ま、簡単に云うと、実際の私はもうあの時に──ノイハウスで死んでるの。今のこれは、寸前の処で“命脈”の細い細い支流。そこに自分の存在概念を強引に転写して焼きつけた結果。その形をなぞって発現してるのが今の私のこの身体ー……って判り辛い?』
判り辛い。頷く【NAME】に、朧な彼女は小さく苦笑する。
『まあ、亡霊みたいなモノって思ってもらえば良いよ。といっても、アノーレの“命脈”が近い部分でしか出て来れなくて、少しだけ“命脈”の力を間借りできるヘンな亡霊だけど、ね』
言って彼女が掌を【NAME】達の方へと掲げれば、確かにそれは輪郭もぼやけ、僅かに透けている。レェアの姿を模ってはいるが、その身は既に明らかに人外のものだった。
「でも、“先生”」
ノエルが、その掲げられた掌を、両手で柔らかく包むような仕草で取る。感情の薄い表情と瞳が、しかし精一杯の心を込めてレェアを見据えて。
「そんな姿でも、もう一度あなたに会えて嬉しい。わたしはそう思えます」
『……うん。ありがと』
触れないように、それでいてしっかりと掴むように掌を包んだまま告げたノエルに、レェアは顔をくしゃりと歪めて頷いた。
『──さて、“命脈”を押さえ込みますかね』
レェアは周囲に刺さった光の格子を全て浮ぶ球体へと引き戻させてから、気合を入れるように声を張った。
『ノエルと【NAME】はまず遺跡の外へ出なさい。多分その辺りまでで流れを押さえ込めると思うから。後の事はこっちに任せて、あなた達は……』
と、そこでレェアは一度言葉を止めて【NAME】達を見て、少し間を置いてから続ける。
『これからどうする気なの? イルギジドは多分カンクゥサの北、既に原因不明の爆発で吹っ飛んだゴディバ遺跡へと向かうだろう。多分そこで、ゴディバに封じられた“大禍鬼”の存在確認と、そして居た場合はその鬼──確かウィースルゥインっていう“大禍鬼”を支配下に置くか、シンラに食わせるかするつもりでしょうけれど』
先刻イルギジドとレェアが話していた目的地とやらはそこであるらしい。納得する【NAME】を横目に、レェアは話を続ける。
『その行動自体は、もう別段問題にはならないのよね。既にあの遺跡は暴走し終わった後で周りの地形は無茶苦茶だからね。要の“大禍鬼”が存在して、それを取り外したとしても被害は今と変わらない。彼を放置しても結果は同じなの。なら』
「同じであるなら、無駄に関わり危険を冒すよりは放置したほうが良い、と仰りたいのですか?」
口を挟んだノエルに、レェアは難しい表情で小さく唸る。既に音声として伝わらない彼女の唸りは、頭の底に重く響く振動となって響いた。
『どうだろうね。奴がゴディバでウィースルゥインを得る得ないに関わらず、そこから先の行動が読めないから何とも言えないのよね。既に“大禍鬼”としては破格の力をつけつつあるシンラを連れてアノーレを──いえ、フローリア中を壊しまくるつもりなのかも知れないし、何の害も出さずにこの諸島を去るつもりなのかもしれない。前者ならゴディバでウィースルゥインと接触する前に止めたほうが良いし、逆なら無駄に手を出して被害を出すより放置してもいいかもね。まあ、私の予想だと意味も無く暴れ回るって事は無いと思うが』
言って、彼女はくすりと笑って肩を竦める。その雰囲気から察するに、彼女自身はどちらでも良い、若しくは面倒な手間とならない後者の選択が良いと考えているように見えた。
「ですが、レェア」
と、そこで僅かに非難の色を滲ませた口調でノエルが言う。
「その理屈でしたら、意味が有れば暴れるという筋も成り立つ筈です。それにイェアからの指示という部分もありますし、準軍師はポロサ駐屯の部隊と、そしてカナード・フハールを殺害した疑いがあります。軍という立場から考えるなら、見過ごすわけには行かないと考えます。【NAME】にも、強制できませんが、準軍師の件について協力は求めたいと思っています」
淡々と告げるノエルをレェアは困ったように見て、次いで【NAME】の方へと視線を送る。その目が訴えるのは、あなたはどうするつもりなのか、という問いだ。答え辛く、【NAME】は口を噤む。
【NAME】としては、イルギジドを追うつもりだった。まず、イェア・ガナッシュから受けた彼を止めろという依頼がある。更にあの召喚司は倫理といったものを然して重視しないような気配も感じ取れたし、幾度かしてやられ、その借りを返したいという思いもある。
しかし、本音を言えばノエルはこれ以上付き合わないほうが良いのではないかとも考えていた。先程シンラと対峙した際に、奴の放つ強烈な概念的な威圧がイェアの持たせてくれたアクセサリの護りを上回る様を見ていると、少しばかり心配になる。
直ぐには答えられずに困った表情で首を傾げて見せた【NAME】に、レェアは溜息──実際はそんな仕草を見せるだけだが──をついて、何やらいつに無く硬い表情を見せているノエルへと視線を戻す。
『まぁ、私も強制するつもりは無いけれど……軍っていっても、あなたは本当は軍人でも何でもないでしょうに』
む、と黙り込むノエルに、レェアは言い聞かせるように言葉を続ける。
『あなたが軍属扱いなのは、あくまで私やイェア達と一緒に居る為の隠れ蓑みたいなものだったでしょ? 別に私も妹もあなたを真っ当な軍人に育てる気なんてないよ。あなたとあいつは──“大禍鬼”は相性が悪い。だから無理に追う必要は無いと思うけれど』
だが、ノエルは小さく首を振った。
「そういう訳にも行きません。今の軍ではこの情報を伝えたところで実際に動き出す頃にはもう手遅れになっていると考えます。間に合うのはわたしと【NAME】だけです。あの人には罪がある。償ってもらわなければなりません」
『珍しいね。そうやって感情的になれるのは、昔と比べれば良い傾向だとは思うけど……どうして、そんなに必死になるの?』
呆れと戸惑い半々の苦り顔で訊ねるレェアに、ノエルの顔が崩れた。
何故判ってくれないのか、そんな表情と共に呟かれたのは。
「……だって、彼は貴女を殺しました。許せる筈、ありません」
『────』
レェアは両眼を見開いて固まり、数拍。
『あー、そう来たか』
彼女は燐光を放つ髪を軽く掻いて苦笑すると、小さく頷く。
『……となると当人の私が幾ら言っても止められない、か。なら急ぎなさい、ゴディバへ。この混乱状態なら、カンクゥサを番していた軍の連中も引っ張り出されてるでしょ。抜けるのは容易い筈だけど、三つの遺跡で大きな概念変動があったせいで、島全体の土地概念がバランスを欠いてる。鬼種が発生しやすくなってるから気をつけなさい。──あと、【NAME】』
名を呼ばれ、【NAME】はレェアと視線を絡ませる。彼女は【NAME】の首に掛かる飾りをじっと見つめてから、顔を上げて【NAME】を真っ直ぐに見る。
『冒険者のあなたに依頼。この子の事、守ってあげて。イルギジドとケリをつけられたら、私が替わりに報酬をあげるから、無事に帰ってきなさい』
【NAME】は無言のまま、頷きで返す。その力強い返答にレェアは大きく笑って、軽く手を振った。
これ以上、ここに居ては邪魔になるか。
【NAME】はそう判断して、動く気配の無いノエルの手を引く。だが、彼女は逆らいはしないまでもレェアの方を見たまま首を動かさない。
そんな彼女に、優しい表情でレェアは呼びかけた。
『ノエル』
「はい」
『全部終わったら、ノイハウスへいらっしゃい。前に、約束しただろう? また、あなたの“先生”に戻ってあげる』
「──はい」
そこで漸く、吹っ切れたような返事と共に、ノエルは自分の力で外へと向かって歩き始めた。
その様を見届けた【NAME】は自分も遺跡の外へと急ごうとして、レェアが自分を見ている事に気付いて視線だけで何かと問う。
彼女は小さく手を振って、
『【NAME】。申し訳ないけど、その子をお願いね』
自分の妹を託す姉のように、そう告げた彼女に、【NAME】はもう一度大きく頷いて、遺跡の外へと走り出した。
「……全く、はじめは戯言だと思ったものだが、本当に我等が崇める翆なる力の化身となったか、レェア」
【NAME】とノエルが去った後。レェアが向かったのは“命脈”の孔の傍ではなく、遺跡内壁の際だった。彼女は眼の前に座る影──上半身を起こし、しかし立ち上がれずに壁を背にして座り込んでいた少年の顔を覗き込む。
『御免ね、ホント。あなた達の信仰対象を汚しちゃったみたいで。それより、大丈夫?』
「……死んだお前よりは、大したことは無い」
『ま、そりゃそうでしょうけど。……どれどれ』
レェアは己の右手を伸ばし、少年の額に添える。同時、彼女の手が砕けて、散った光がリゼラの身体を覆い、這い回る。
「──ッ!? お前!」
全身を弄られるような感覚に、リゼラは僅かに声を上擦らせて抗議するが、レェアは驚きの表情で彼の文句を無視。
『身体中ボロボロじゃない! それにイルギジドの“贄”の気がまだ身体に食い込んで……何で意識あるんだ、こんな状態で。待って、侵食だけは何とかするから』
リゼラを覆う輝きが増し、鍛えられてはいるもまだ小さな彼の身体からどろりと黒い染みが浮き、光に溶けて分解されていく。
痛みを伴うのか、リゼラは眉根を強く寄せながら己の身体から抜け出ていく染みを見る。
「たとえどのような一撃を受けたとて、気絶する訳には行くまい。我の下についてきてくれていた者達を志半ばで皆殺しにされたというのに、気を失って寝ていろというのか、お前は?」
言い捨てるリゼラの顔は、悔恨の情に歪んでいた。彼の心情はレェアにも理解できる。だが、彼女は睨むように少年を見据えて告げた。
『そうよ。今は寝てなさい。そんな身体で起きていたって、何の意味も無いわ。戦士ならそれくらい判るでしょう?』
「……判らいでか。だが、それでも奴を斬りたかった。恨み、という言葉に動かされる程に我等は愚かな存在ではないが、けじめはつけねばなるまい」
『気持ちは判るけれど、今回はあの子達に──“神形の操手”に任せて、兎に角じっとしていなさい。“命脈”を押さえ切ったら直ぐにちゃんとした手当てするから』
言って、一通りイルギジドが放った“贄”による侵食を取り除いたレェアは砕けた右手を引くと、くるりと少年から背を向ける。
彼女の向く先には、先程から徐々に発する力を増し始めた“命脈”の孔たる光の球体がある。球体の大きさはイルギジドが封印を解いた時と比べ既に三倍近い大きさとなっており、漏れ出す力も危険な域に達しつつある。球の周囲の空間が力に飲まれて歪み、泡立つように揺れているのが判った。
レェアは崩れた片手を気にする様子も無く、両腕を広げて肩に力を入れつつ後ろへ声を飛ばす。
『さて、リゼラ君は大丈夫なのかな、こういうの。キヴェンティ達は翆霊があるから“命脈”の力には耐性がありそうだけど、どれくらい強いのに呑まれても平気?』
「お前がどれだけ“命脈”を押さえ込めるのか判らんから答えられんよ。とはいえ、まともに呑まれれば耐え切れまいな」
『……なら、外で待っていてもらうべきかな』
僅かに振り返り、少し迷うように呟いたレェアに、リゼラは小さく首を振った。
「いや、我はここで見届けさせてもらう。外へ運ぶなどと、そう悠長にしている時間も無かろう? なに、我を死なせたくないと思うなら、完全に“命脈”の氾濫を抑えてみせれば良いだけだ」
『気安く言ってくれるね。そんな簡単な事じゃないんだよ?』
【NAME】やノエル達の前では出さない、何処か拗ねたような声で言うレェアに、リゼラは不敵な笑みと共に告げた。
「我はお前を信頼している。それが全てだ」
『────』
レェアの背中が一瞬びくりと震え、暫しの間。そして張っていた力が抜けたように柔らかくなる。
『……君のそう言う台詞を臆面無く言えてしまう処、直したほうが良いと思うんだけど、どうだろう?』
「駆け引きの場以外での正直は美徳だ。それより急げ。そろそろ孔の臨界を越えて一気に漏れ出してくる」
『──判ってるよ、もう。黙って大人しく見てなさい』
言葉と共に、レェアは己という存在のシンボルとして発現させていた輝く身体を消滅させる。このようなものの顕在化に力を回している余裕など無いからだ。
果たして抑えられるか。そんな不安は当然ある。【NAME】達やリゼラの前では余裕の態度を見せてはいたものの、本当はノイハウスの時だってぎりぎりだったのだ。確実に出来るという自信など全く無い。
だが、ノイハウスではノエルと【NAME】の。今はリゼラの命を背負っている。
しくじる訳には行かない。見守るリゼラの意識を支えに、彼女は膨れ上がる“命脈”の力に己の存在を溶け込ませ、全力での制動に入った。
四大遺跡 救いの道先
――救いの道先――
ポロサ近傍に敷かれた、アノーレに置けるアラセマ常駐軍の本営となる駐屯地。
駐屯地を構成する、北の森から切り出された木々で組まれた木造建造物群の中の一室。第十二師団副団長の居室であるその部屋には、二つの人影があった。
一つは、窓際の寝台に両膝を抱えるようにして座り、焦点の合わぬ両眼を茫と外へと泳がせた妙齢の娘。この部屋の主である、クスィーク・カナル・フハールだ。
銀鎖で仕立てられた鎧と剣、隙無い軍服で固められていた身体は、今は白一色の施療服が覆うのみ。本来ならば凛と張った気を常に放っていたその肩は細く小さく、表情は虚ろという他無い。
額や腕には包帯が巻かれてはいるものの、ガレーで起こった遺跡暴走の際に負った傷であるそれは既に癒えており、身体には何の問題も無いという。
だが、眼に見えぬ傷というものも世の中には確かに存在する。
身体ではなく心。外側ではなく、内側に大きな傷を負った──彼女を診た施療師は、そう診断して切り上げた。神蹟による治療は、外的な損傷や術式による精神干渉を排除する手段は持つが、既に心に傷を負ってしまった者を癒す事は出来ない。時間と、周りの協力以外に治癒を手助けすることは出来ないという。
ここへ来る途中に聞いたそんな話を思い出し、部屋の出入口となる扉を背に立つもう一つの影。長い髪を後ろで結い上げた彼女──“先見のエリンベル”とも呼ばれる予言者、マリカは苦々しげな表情を浮べ、寝台で縮こまる娘の姿を見ていた。
象徴のみの存在ではあったが、公式ではアノーレ駐屯の常駐軍の頭である師団長カナード・フハールと、クスィークと並ぶ力で軍部隊を纏めていた準軍師イルギジド・マイゼルを同時に失い、第十二師団の上位指揮権を持つのは現在彼女だけである。普段通りのクスィークであればそんな状況など物ともせず、今起こってる変事への対処も的確に行っている筈だった。
だが、今の彼女は外部からの言葉に反応を殆ど返さず、ただこうして寝台の上で丸まっているだけ。食事も殆ど取っていないらしく、青白い顔には以前までの力強い凛々しさなど欠片もない。
指導者全て失った形となった常駐軍は完全な混乱状態にあり、各々の部隊の長達が自己判断で事態を収拾するべく走り回っているが、当然そのような形では満足な連携が取れるはずも無く、成果は芳しくないと言う。
幾度か彼女の部下となる部隊長達が今後の方針を伺う為に訪れたようだが、自分の眼で見た彼女の様子と施療師の言葉に、落胆の色を隠さず去っていったらしい。
彼等が落胆するのも判らなくもない。今、眼の前に居るクスィークはまるで抜け殻のようだ。気力というようなものがその瞳から全く抜け落ちていた。現在の軍を纏められる唯一の存在がこんな有様ではどうしようもない。
──まぁ、軍がどうなろうと関係無いけどね。
疲れの混じった吐息をつきながら、マリカは両腕を組んだまま扉の横の壁に背を預ける。
マリカは、軍がどうこうという理由でここに訪れたわけではない。単に、自分が視た彼女に纏わる道筋を、当人に伝えようと思っただけだ。
「くーちゃん、聞こえてる?」
ただ声を掛ける。当然、というべきなのか。寝台に丸まるクスィークは何の反応も示さず、茫と外を眺めるだけ。開かれた窓からは緩やかな風が流れ込み、カーテンを小さく揺らしている。
マリカはもう一度溜息をついて、僅かに思案する。
言うべきか言わざるべきか。いや、それは決まっている。本当に決めなければならないのは、どう言って切り出せば、完全に沈み切ってしまっているクスィークの意識を揺り動かせるのか。それだけなのだが。
「…………」
どうしたものか。迷って、しかし苦笑する。単刀直入に言ってしまえば良い。その後の彼女の行動に自分は責任などもつ必要はない。むしろ、何の反応も無いほうが平和で良い気もしていた。マリカはただ、自分の視た道を彼女に伝えれば良い。所詮は部外者なのだから。
壁から背を離すと、彼女は寝台の横に歩み寄り、告げた。
「“先見”を視たよ、くーちゃん。貴女と、師団長の──カナード・フハールの事」
カナード。その響きに、ふるりと彼女の首が動いた。
虚ろな視線がマリカの顔を捉え、大きく見開かれる。マリカは間近で見た彼女のやつれたの顔にほんの一瞬痛ましげな表情を浮かべて、言葉を続ける。この“先見”は、少なくとも彼女の心にとっての強壮剤となる筈だから。
「ガレーに向かった連中や、大草原の連中が見かけた“大禍鬼”の縁を追って、昨日視てみたのさ。そうしたら、二つの道が視えた。一つは貴女が死ぬ道。もう一つはカナード・フハールが死ぬ道。指された場所は雪の廃墟。分岐点は貴女の行動」
「──ッ、こほ、こ、ほ!」
クスィークの身体が揺れて、激しく咳き込む。声を出そうとして、その出し方を忘れていた。そんな音。
錆び付いた声帯を動かす為か、彼女は何度も咳をした後、先刻までとは質の異なる茫然の顔でマリカを見上げ、
「でも──でも、カナード様は、もう」
うわ言のように呟いて、そしてぶんぶんと思い浮かんだ記憶を振り払うように彼女は首を振る。
クスィークがガレーの遺跡で何を見たのか。それはマリカにも知れない。だから、彼女は自分が見た“先見”だけを伝える。
「少なくとも、死んではいないみたいよ」
「……え?」
顔を上げたクスィークに、マリカは両腕を組んだまま淡々と続ける。
「先見のヴィジョンによると、ね。あの馬鹿でかい鬼に取り込まれてるけど、イルギジドが施した式かなんかのせいで、完全に溶けてないみたいだね。片方のヴィジョンで、その結びが解ける場面が見えたから。上手くいけば、助けられるかも知れないよ」
「嘘、そんな……」
未だ衝撃覚めやらぬといった風に揺れる彼女は、もう完全に混乱しているように見えた。
マリカは他に彼女の思考を補助する話題は無かったかと、とんとんと何か思い出すように自分のこめかみを叩く。
「──そうだわねぇ、ならもう一つ話そうか。前に……いつだったかな。そう、貴女がノイハウスを攻めるためにポロサを出た時。あたし、ちょっと気になったから貴女に関する“先見”をしたのよ。その時あたしが見たのが、貴女を大事そうに抱えてどこか暗い建物の中から外へと運び出す大鬼の絵。内容が滅茶苦茶だったからすっかり忘れてたけれど……貴女はガレー遺跡でイルギジドと彼の“大禍鬼”と遭遇して、それからどうやって助かった? それを思い出してみなさい?」
「……え、あ」
クスィークは少し俯いて、自分の肩を両手で抱くようにして動きを止める。そして少しの間の後、一度強く、両肩に指が食い込むほどに強く自身を掴んだ。
「そう、そうだ。私、私はあの時みたいに、手を引かれて」
呟きと共に、彼女は勢い良く顔を上げる。
「それなら……それなら、教えて、マリカ。私が死んで、カナード様が生きる道。たとえどんな姿でも、あの人は私の──」
「…………」
見上げてくる彼女の痩けた顔に宿る決意の気配、両眼に灯る強い意志の色に呑まれて、マリカは僅かに黙り込む。
「マリカ、お願い」
必死の懇願。身を乗り出すようにしてこちらを見上げる彼女に、マリカは何とも居心地に悪い気持ちで視線を外した。
(なんだか、馴れないわねぇ)
何もない天井を見上げて間を作りながら、内心苦笑する。
違和感の理由は簡単なもの。彼女の言葉遣いだ。
今までクスィークにこんな口調で話された経験など一度も無かった。普段の彼女は常にどこか堅苦しくも素っ気無い男言葉でマリカや部下達に接していた。
だが、先程からの彼女はどこか気弱げな風すらある子供のような口調。覗いてくる瞳には強い力が込められているものの、それは藁にも縋る様な必死という意志。
そんな彼女の態度の裏から透けて見えるのは、小動物を思わせる弱々しさだ。
これがクスィーク・カナルという人間の何の偽りもない素の形であるとするならば、今までの彼女の副団長としての生活、軍人としての生活は酷く辛い物であったのではないか。
ほんの僅かに、マリカは夢想する。
この“先見”の事を知らなかった彼女ならば、もう仕える者も無い軍に固執する事はなかっただろう。体面を気にして常に気を張るような生活を止める選択肢だって見出せたのではないか。客観的な視点で彼女の為を思うのならば、ここで“先見”のことを話さなければ、もしかしたら──。
「…………」
──しかし、マリカはそこまで考え、内から生まれた誘惑に小さく首を振る。彼女は生粋の予言者であった。
「あたしが見たのは殺される貴女と、鬼から切り離される師団長の場面。もう一つは鬼と誰かが相打ちになって消える場面。貴女が望む未来を得たいと思うなら、まず急ぎなさい。北のゴディバへ。ガレー、ノイハウス、ヴィタメールと辿って最後が雪の降る廃墟というなら、そこしか有り得ない。細かくどうすれば良いかまでは判らないけど、そこで貴女が望むように動けば──変わる筈だよ」
「……そう」
そしてクスィークは立ち上がる。両眼には強い意志が宿り、身体からは痩せたその身を補うかのように強い気迫が溢れている。
「ありがとう、マリカ」
普段の彼女が纏う凛とした清廉さとはまた質の異なる、死地へ向かう覚悟を決めた者独特の気配だった。
多少覚束ない足取りで、彼女は準備を始める。北へと向かう準備。弱った彼女の身体で果たしてもつのかどうか。武術技法の他にも様々な術式や召喚術を扱うことの出来る彼女なら無理は出来るだろうが、適う限り全力での旅路となれば、やはり過酷なものとなる。
──それでも、この子は行くのだろう。
マリカは溜息と共に彼女の傍へと寄ると、無言で彼女を手伝う。
脱ぎ捨てた衣服はそのまま、久々に動かす己の身体を確かめるようにゆっくりと軍装を纏っていく。
クスィークはマリカの方を見ぬまま、まるで独りごとのように呟いた。
「ガレー遺跡での事、思い出したの。あの鬼は確かに、私を救いあげてくれた。もしかしたらそれは、自分で生み出した幻だったのかもしれない。だけど、それでもいい。今更、今更迷いはしない」
マリカは彼女の言葉には何も言わず、別の問いを作る。
「一応聞くけれど、軍のことはどうするの? 色々と無茶苦茶になってるみたいだけど」
普段着込む鎖鎧は手に取らず、服だけを整えていく。つける防具は手甲のみだ。己の体力を把握した上での選択。腰に提げるは銀の長剣。留め金全てを調節し終えてから、彼女はマリカの方へほんの僅かに視線を向けると、
「知らない。今の私にはそんな事考えられないもの。残った人が好きにすればいいわ」
きっぱりと言い切る。その潔さに、マリカは思わず声を出して笑い、そして「そう」と気持ちよく頷いた。
最後に上着となる軍套を纏い、クスィークはマリカの方へと改めて振り返ると深々と一礼。
そして挙げた顔に浮ぶのは今までマリカが見たこともない、清々しい笑顔だ。
「行きます、マリカ。……今まで本当にありがとう」
マリカは言葉として答えを返さず、ただ小さく手を振る事で別れを告げた。
クスィークはそれで満足したのか、踵を返すと小走りに近い足取りで部屋から姿を消した。
「……さて」
クスィークの面影を追うように誰も居ない扉前を眺めていたマリカは、区切るように呟いて、傍にある──クスィークがつい先程まで蹲っていた寝台へと手を置き、そしてゆっくりと腰を降ろす。
「一つは貴女が死ぬ道、もう一つが師団長が死ぬ道、か」
独りごちて、マリカは小さく苦笑する。
本当はもう一つ、別の道を見ていた。
一番欠けて、一番淡い。しかしクスィークには幸ある未来。しかしそれを教えればその道は閉ざされる。故に伏した。教える事で可能性を完全に摘まれる選択肢は、予言者が告げる事はない。何故なら告げるという事でその予言は既に意味を成さなくなるからだ。
「上手く、その道を選び取れれば良いのだけどね、あの子も」
寝台に座り、窓際から外を見る。まどろみを誘う暖かな日差しにマリカは眼を細めて、そして空が掲げる太陽の輝きが、彼女の道行を明るく照らすことを祈った。
カンクゥサの山脈を越えた【NAME】を包むのは、北方からただ吹きつける凍えた寒風だ。
空は高く清んで太陽も大きく空を照らしているにもかかわらず、漂う空気は触れれば切れるような鋭い冷たさを帯びていた。
【NAME】は山の麓に立ち、遠く見える集落の影、コートニーの村を眺める。
アノーレの島にアラセマ移民達が作り上げた集落は大きく括れば五つ存在するという。
他島との交流の要たる港を持ち、アノーレ島に詰める常駐軍の本営があるポロサ。
四つの芯林に囲まれ、その林での狩猟によって生計を立てるティネ。
カンクゥサの山脈から取れる鉱物を加工する施設を備えた鍛冶の村、ノスキス。
この三つがアノーレの南部にあるのに対し、他の二つ、コートニーとハザムはカンクゥサを挟んだ島北部に存在する。
北部は亜獣の数が多く、カンクゥサという難所を抜ける必要があったため、そもそも人口も少なく、開拓者達の暮す集落という意味合いが強い。コートニーの場合は島北部の鉱石及び、カチトの平原に生息する珍しい動植物の狩猟、収穫。そして幾つかの遺跡に残った“機甲”の部類に属する品々を得る者達が暮す村だった。
再度凍えた風が吹き、思わず身を震わせた【NAME】の横に、ノエルが吐く息を白くさせながら並び立つ。
「【NAME】、アノーレ北部の情報は不明な点が多い。カンクゥサの存在と、そしてゴディバでの爆発の影響による土地概念の変動。前者は兎も角、後者の影響は大きいはずです。コートニーにも常駐軍の駐屯地は存在しますが、本営からここまでは遠い。わたしが持っている情報もガレーに居たお二人から教わったものが殆どですから、食い違いも多いでしょう」
言いたい事は直ぐに判った。まずコートニーで情報収集を行うべき、という事だろう。
それには【NAME】も異論は無かった。元々アノーレで暮していた訳ではない【NAME】にとって、南部では殆ど話題にも上らないアノーレ北部の事柄については殆ど知識が無い。目的地である“四大遺跡”、ゴディバについても詳しい位置は知らず、至る道筋についても同様だ。急ぎ、その辺りの情報を仕入れる必要がある。
【NAME】の呟きに、ノエルは無表情のまま小さく頷く。
「【NAME】は村の方へ向かってください。わたしは軍の駐屯地の方でそちらに詰めている兵士の方からお話を伺ってきます、【NAME】は村の方達から周辺地域や、ゴディバまでの道筋の現状等の情報収集をお願いします。コートニーには“先生”とイェアが共同で作成した特殊結界を構成する印章機構が運び込まれています。“灯火の座”という名のその器が置かれた建物は、村人達の憩いの場となっていると聞いていますので、そちらで彼等から情報を集めるのが良いかとわたしは考えます」
【NAME】の頷きを見届けてから、ノエルは坂を早足で下っていく。
「では先に行きます。印章機構“灯火の座”で落ち合いましょう」
数時間の後。【NAME】はノエルの言っていた“灯火の座”が安置されている、村の中心に建てられた建物の中に居た。
“灯火の座”を設置するためにわざわざ造られたのであろう、白色に染め抜かれた建物の中央。祭壇を思わせる台座の上に置かれるのは、暖色の輝きに包まれた大きな洋燈を思わせる硝子の細工だ。表面に刻まれた無数の印章と、真中に印章を刻む事で加工された理石──つまり印章石を三つはめ込まれたその品が、所謂“灯火の座”という奴らしい。
【NAME】が村に入った時、驚いたのは村の外との気温差だ、中心に近づくほど気温は増して“灯火の座”の直ぐ傍となる建物の中に入れば他の地域とほぼ同等か、むしろ少し汗ばむ程の暖かさへと変わる。“灯火の座”が構成する圏が村全体を大きく覆っており、外からの冷気を遮断する仕組みになっているのだという。
そんな暖かな空気が漂う建物内部の一角。白色に染められた壁に背を預け、【NAME】はノエルがやってくるのを待ちながら、村人達から仕入れた情報を頭の中で纏めていた。
数ヶ月前からフローリア諸島一帯で発生した、常駐軍の派遣理由ともなった土地概念の異常と鬼種の発生増加。はじめ、【NAME】はコートニー──というよりカンクゥサ以北の異常気象とやらは、その流れによるものなのかと想像していた。だが、村人の話を聞いていると、この地方が今のような極寒の地となったのはその事件より更に昔、コートニーよりも更に北にあるというゴディバの遺跡で起こった謎の爆発と、それによって発生した大規模な土地概念の変質が原因であるという。
元々はアノーレ北部も現在の南部一帯の気候と殆ど変わらない地域であったらしく、コートニーのすぐ北に広がっているカチトは昔は土地豊かな平野として村人達の狩猟場として使われていたようなのだが、今では風雪渦巻く雪原となって侵入者を拒む異質地形へと成り代わっているという。カチトを越えた先にあった幾つかの地形とアノーレ最北の村とされたハザムは、その雪原に遮られ、今はどうなっているのかコートニーの村人達も確かな事は知らないらしい。
土地概念が変質した地形では常識外としか言いようの無い現象に見舞われる事もあるため、知識の無い者、準備の無い者、覚悟の足りない者がそれらの地形に足を踏み入れるのは極めて危険だ。村人達がカチトの向こう側について殆ど何も知らないというのも致し方ない事ではあるが、これよりカチト雪原を渡り北へと向かう身である【NAME】としては、もう少し彼等が踏み込んだ情報を持っていてくれれば、と落胆する気持ちは隠せなかった。
ゴディバの遺跡。そこへと至るには、カチトを抜けてハザムの村へと向かい、そこから西へと進むのが定番のルートだという話だったが、この状況では易々と辿れる道筋ではないようだ。
「……しかし」
彼等の話を聞いていて、ふと疑問に思ったことがある。
村の者達含め、ポロサやティネ、軍駐屯地で過去のアノーレを聞く時に良く話に上る、ゴディバで起きた謎の爆発。これが一体何なのかが判らない。
何が原因で起きたのか。そもそも、その現象は本当にゴディバで起きた爆発なのだろうか。一度も踏み込んで話を聞いた事がなかったが、目的地としてその場を選び、コートニーまできてこの異常気象を目の当たりにすると、発端となったであろうその事に意識を向けずに居られない。
──と、そんな事を考えて。
「“しかし”……どうされましたか。【NAME】?」
すぐ傍から唐突に掛けられた声に、【NAME】はびくりと肩を震わせて声のした方を見る。いつの間に来ていたのか。黒銃を背負ったノエルが首を傾げて立っていた。
【NAME】は何でもないと首を振る。口に出すほどの疑問でもないし、出したところでノエルが答えられる類の問いでもない。
素早く意識を切り替えると、【NAME】はとりあえず村で仕入れた情報をノエルに話す。
「そうですか。やはりカチトより北は実際に足を運んでみないとはっきりとはしませんね」
ノエルは【NAME】に並ぶように立つと背負った銃を地面に下ろし、【NAME】を真似するように背中を壁に預ける。
「カチトについては、軍の方でも同様の話を聞きました」
ノエルの言葉に、【NAME】は意外という表情を作る。軍もカチトより北の調査を行っていなかったのだろうか?
問いに、ノエルは一度首を横へ振る。
「いえ。カチトの北にはハザムという村もありましたから、村の安否を確認する為にコートニー駐在の部隊も何度か斥候を派遣したそうなのですが──一応村の存在は確認できたらしいのですけれど、どうしても確定したルートを作る事ができないそうです。物資を持ってハザムを目指した部隊も、時によって辿り着けたり辿り着けなかったりするだとか」
一体どういう事かと、【NAME】は首を捻る。カンクゥサで展開されていたような特殊な場が形成されて、土地と土地の繋がりが不安定になっているとか、その辺りだろうか。
「近いです。兎に角、雪原の土地概念の歪みが酷くて、それの影響で技法の発現にも支障を来す程だそうです。特に術式技法の効力が格段に弱まってしまうとか。技法による地図作成も妨害されてしまうそうです」
技法の効力が弱まるというのは初耳だ、【NAME】はげんなりと顔を顰めさせる。
「そしてそんな中を、周期的にくる吹雪を避けながら進まなければならない。そのような不安定な状況では大部隊も派遣し辛く、それにコートニーの維持にも手一杯という事で、カチト雪原以北は、半ば放置の状態にあるとの事です」
そんな事で良いのだろうかと、【NAME】は思わず呟く。
コートニーの村で聞き込んだ時に耳を挟んだのだが、ハザムの村ではアラセマ常駐軍の駐屯地は存在しなかったと聞いた。護ってくれる者達もおらず、コートニーの村からも寸断され、更には遺跡の概念異常に巻き込まれたハザムを捨てて置くというのはどうなのか。
「それは、既にハザムが壊れた村だからとわたしは推測します」
──壊れた?
【NAME】は訝しげにノエルを見る。ついさっき彼女は『村の存在は確認できた』と言わなかっただろうか。
ノエルは無表情のまま、どう答えるべきか迷うように暫し視線を泳がせて、祭壇の“灯火の座”を眺める形で固定し、その間に頭の中で纏めた言葉を口にする。
「【NAME】には判り辛い表現かもしれませんが、ハザムの村は現在、存在はしていますがそれは幻のものであるというのが、コートニーの駐屯地に詰める方達の結論だそうです。ゴディバから波及した土地概念の変質に取り込まれて、村の人々は既に生物でなく、ハザムという土地が持つ大きな概念に飲まれた、現象の一部と化したと。ハザムに辿り着いた軍の方達の話を聞くと、村の方々はその出来事より以前の生活そのまま、普通に暮してらっしゃるそうです。けれど、村の外には出られず、身体が変化する事もない、殆ど人ではない別のモノとなっていると、わたしはそう伺いました」
「…………」
なるほど、確かにそれは、壊れている。
【NAME】は顔を顰めて黙り込む。ノエルも口を閉ざし、暫しの沈黙が降りた。
暖かく輝く“灯火の座”を何とはなく眺めて、小さく息をつくことで沈黙を破ったのはノエルの方だ。
「……ハザムについては、今のわたし達に出来る事はありません。ですので、気持ちを切り替えましょう。今のわたし達がやらねばならぬことは、ゴディバへと辿り着く事。幸い、カチトの土地概念が及ぼす影響は準軍師にも出ている筈。技法による飛行は適わず、足は遅くなっている筈です。先行する事は適わずとも、距離を詰める程度は出来るかと考えます」
ノエルは壁から背を離すと数歩前へと進み、そして振り返る。
「急ぎましょう、【NAME】。北の果て──“凍え穢れし”ゴディバへ。そこで、全ての決着を」
四大遺跡 絶対の大禍鬼
――天従の遺跡――
ちらちらと降る雪の中。白色に包まれた林の合間を、【NAME】とノエルは急ぎ足で進んでいた。
ハザムの村付近では激しい豪雪に見舞われ手間取ったが、運が良いのか、村を離れて西に広がる大林に入ってからの天候はそう酷くない。
アノーレ北部を覆う異常気象の中心である筈のゴディバ遺跡へと近づく程に、何故か風雪の勢いは弱まり、時折吹く風は冷たいが降りる雪の動きは緩やかで、空も薄い雲が張るだけとなっていた。
地を踏み締める靴も、曇りない雪の白の中へと完全には埋まらない。この程度ならば歩みを阻む要素とはなりえず、【NAME】達は林を西の方角へ──ゴディバの遺跡があるという方へと速度を上げて進んでいた。
既に半ば人外となりつつあるハザムの村人達は現在のゴディバの様子を殆ど知らぬようであったが、異常気象が始まる以前の情報は何とか聞き出す事ができ、それによって遺跡の大まかな位置は把握することができた。
道中の地形自体も吹き荒ぶ風雪によって大きく景色は変わっているものの、大元の部分での変化は無く、以前は緑に、今は白に覆われた大林を西へと突き抜けた先。なだらかな丘の上を埋めるようにゴディバの遺跡はあるという話であったが。
そこまで思い、視線を前へと向ける。冷えた風が木々の間を吹き抜けて、微かに枝に積もる雪を落すのが見えた。それなりの時間を前へと進むことに費やした筈だが林の切れ目は未だ見えず、辺りを包むのは無数の木々と白の雪、そして薄曇の空だけである。
小さく、【NAME】は溜息とも取れる息を一つ吐く。
そもそも土地鑑のまったくない場所だ。一体何処まで進んだのか、遺跡まであとどの程度の距離があるのか。そもそもこの方角へ進むのが正解であるのか。それすらも実際は未知数だった。
無事に辿り着けるのかという不安もあるが、しかし急がなければ先行したであろうイルギジドに追いつけない。既にイルギジドは遺跡へ到着し、用件を終えて立ち去っているという可能性も考えられるが、それが足を緩める為の理由にはなり得ない。最善を尽くすならば今は遺跡へと一刻も早く向かい、既にイルギジドが立ち寄り、去っているようであれば別の方策を練るか、それとも諦めるか──その時に考えれば良い。
今は兎に角、遺跡へと急ぐのが優先事項だ。凍える風に歯向かうように、【NAME】はまた一歩前へと進む。
──と。
「……?」
露出した皮膚、右側の頬に走ったぴりりと微かに痺れるような感覚に、【NAME】は足を止めた。
無意識に手をやって、そしてふと、周囲の空気が先刻までとは微妙に異なっている事に気付く。意志無き木々や風すらも緊張しているかのような、何処か張り詰めた気配がゆっくりと、しかし確実に周囲に立ち込めつつある。
「【NAME】? どうされましたか」
唐突に立ち止まった【NAME】を訝しむように顔を向けてきたノエルに、【NAME】は何か変な感じがしないかと、曖昧な言葉を呟く。
「変な感じ、ですか? ……少しお待ちください」
ノエルは己の耳上に刺さった羽飾りに手を伸ばす。イェアから貰ったその飾りは、彼女が持つ不思議な──大した知識の無い【NAME】にしてみれば不思議としか言いようの無い能力を押さえ込むものであるという。彼女はそれを外し、自身の持つ特殊な力で持って周囲を探るつもりなのだろう。
だが、彼女が飾りを外して自身の力を解放するより早く、より明確な形で異変が生じた。
──轟、と。
【NAME】達が進む遥か先。白の林が埋める西の地平の端に、凄まじい勢いで輝く柱が立ち昇り、薄く曇った空を白く染まる光が大きくかち割ったのだ。
光の太さはどれ程のものか。距離は遠く、目測では判断し難いものの、100メートルは下るまい。
同時に、光柱の根元に揺らぎが生まれ、それが放射線状に広がる。揺らぎはまるで空気を伝う波のように一瞬にして【NAME】達の所まで押し寄せ、そして徐々に振幅を狭めながら背後へとすり抜けていった。
「……いけない。【NAME】、急がないと。何かが、始まっています」
波に飲まれると同時に頭を抑え顔を顰めたノエルが、絞り出すような声で呻いた。
言われずとも判る。【NAME】は短く頷いた後、未だ眉を寄せて動きを止めていたノエルに、【NAME】はここに残るように告げた。光柱の根からはまだ遠いこの場所に居る時点で調子を崩しているようでは、この先どうなるか。
だが、
「……【NAME】、あなたは馬鹿であるとわたしは結論付けます。ここで、このような場所まで来て、今更退けると本当に考えているのですか?」
無表情のまま言われ、【NAME】は彼女の物言いに一瞬目を瞬かせて驚き、そして苦笑する。
確かにそうだ。こんな場所までついてきて、いざという今になって置いていかれては堪らない。自分が逆の立場ならそう思う。
しかし、あれは一体何なのか。今までの“大禍鬼”開放とは趣がかなり異なっている。“命脈”の解放にしては漂う気配が違う。
「判りません。ですが、軍や近隣の村人の誰かが遺跡へ向かったという話は一度も聞いていませんから、恐らくイルギジドが遺跡で何かを行った、若しくは今も行っているせいと考えるのが妥当だとわたしは推測します」
ノエルは顔に微かな緊張を走らせて、未だ天に向けて立つ柱へ向かって一歩踏み出すと、【NAME】の方を振り返り、告げる。
「急ぎましょう、【NAME】。まだ、まだ間に合うかもしれません」
【NAME】は無言のまま表情に力を込めて頷く。あの光の根元に遺跡が、そしてイルギジドが居る筈だ。
背後からついてくる雪蹴る音を聞きながら、【NAME】は林の彼方に立つ光柱へと向かって駆け出した。
――四界の召喚司――
林を抜けた先に広がったなだらかな丘は、立ち昇る光に包まれ黄金色に輝いていた。
丘の地面に浮かび上がるのは複雑な印章が刻まれた陣。輝きによって構成されたそれは、己が生み出す光を上方、空へと高く伸ばして自己主張していた。
そしてその輝きの陣の中央。遺跡の残骸が至る所に散らばり、まさに廃墟といった丘の頂には、二つの影があった。
一つは横向けに倒れ、半分を地に埋めた楕円の物体の上に立ち、もう一つは更に奥で片膝をつき、蹲るような姿勢で動きを止めている。
「──イルギジド・マイゼル!」
銃を構えたノエルの叫びに、楕円の物体の上に立っていた影。背を向けていた小男が、ゆっくりとこちらへと振り返る。
「ふむ。やはり来ましたか。“神形の操手”殿」
男の後方には、地面に書かれた印章陣から伸びる光の鎖を全身に繋いだシンラの姿がある。
一体、何をしているのか。【NAME】は身構えながら、両手に杖持ちこちらを眺める小男に声を飛ばす。
今までの二つの遺跡で見た“大禍鬼”解放の様子とは周囲に漂う気配が明らかに違う。丘全体に記述されたこの印章陣は何のためのものなのか。これだけの規模の印章陣だ、まだ完全に駆動していないようだが、効果が発現すれば一体どれ程の力を発揮するのか想像できない。
そんな緊張を孕んだ【NAME】の問いに、
「いやいや。これはここの土地概念と鬼との同調の為に少々大きな記述が必要だっただけの話で、やってることは大した物ではないのですよ」
言って、イルギジドは僅かに肩を竦めて苦笑を見せる。
「薄々は予感していた事だったのですが、やはりこの遺跡には既にウィースルゥインはいないようでしてな。ですが、折角やってきてこのまま立ち去るというのも何ですし、鬼とこの場の脈を利用しまして、少しばかり島の奥を探らせていただこうと」
「……奥? あなたは一体、何を」
「簡単な事ですよ。この島が作り出す檻の奥に秘された存在。その現状とやらを調べているだけでしてな。ついでに、同調した脈を使ってウィースルゥインの痕跡を追うつもりではありますが、さて」
区切り、イルギジドは引きつるような笑みを造り、【NAME】達を見た。
「ワタクシは今この場から離れられませんし、その間あなた方のお相手くらいはしてあげても構いませんが、どうされますかね?」
その言葉に答えたのは、【NAME】の隣に立つ軍装の娘だ。
「──“先生”の仇は、討たせてもらいます」
手にした黒銃を構え、ノエルは強い意志を込めた声でただ告げる。
【NAME】にしても同様だ。この場から奴を逃すつもりはない。武器を構え直すと、一度僅かに身体を沈ませ、筋肉のバネでもって跳ねるように地を蹴る。イルギジドは召喚士であり、今はまだ使い魔となる獣を呼んではいない。その間に僅かでも距離を詰め、攻撃を叩き込むつもりで一直線に走る。
「ふむ」
しかし、イルギジドの動きは【NAME】の予想を上回った。
手に持つ杖から昇る莫大な力故か、一瞬で空中に記述される無数の印章。描かれた文字は巨大な輪となって留まり、力を込められ、文句を紡がれると同時に高速で回転しはじめる。
──間に合わない。
そう思う間もなく、イルギジドが締めとなる言葉を飛ばす。
「“開け、封印の檻[シールドケイジ]”」
印章の輪の間に大きな歪みが生じ、そこから吐き出された二つの影が【NAME】とイルギジドとの間を塞ぐ。
現れたのは巨大な樹木と恐竜。竜はこちらの存在にすぐさま反応し、走る【NAME】の眼の前を塞ぐように尾を飛ばす。
「──ッ!!」
全力で上へと跳躍し、轟音をあげて迫る尾の一撃を避けた。が、続けて伸びてきた大樹の鋭い枝が【NAME】の着地を捉えるように迫る。回避の仕様も無いタイミング。
そこへ走る光の閃。
身体を貫かれる衝撃に身体を強張らせていた【NAME】の眼の前で、枝が後方より飛んできた銃撃によって払われる。
ノエルか──そう思考する間にも【NAME】は全力で後ろへと飛び退り、恐竜の更なる一撃を回避する。
「では、自然の者達らしくこの術式で参りますか。“咲き誇れ、大自然の力[ナチュラルパワー]”」
イルギジドの更なる詠唱。杖から剥離した概念の欠片が術式として力となり、大樹と恐竜の身体に宿る。
そしてイルギジドが愉悦の表情で手にした杖を大きく振るえば、それを合図に、二体の使い魔が一斉に【NAME】へ向けて動き出す。
男は満足げにその様を眺めると、舌なめずりを一つして、呟いた。
「さてさて、では祭りの始まりと参りますかね」
[BossMonster Encountered!]
現世の召喚司



イルギジドが呼び出した二つの力。生きる大樹の幹を【NAME】は圧し折り、返す刀で恐竜の身を両断する。
地に転がり止まる音二つを背景に【NAME】がイルギジドを見れば、彼はその隙に【NAME】達の手の届かぬ位置へと身を移して、口元だけ歪めた笑みでこちらを見ていた。
戦いはこれから。そんな表情を顔に貼り付けて。
「──ッ!!」
無音の気合と共に一瞬身を沈め、それを反動としてイルギジドへ向かって駆け出そうとする【NAME】。
だが。
「ふむ、自然を克しましたか。ならば次はこれで参りましょうかね」
その出鼻を挫くように、距離をとった召喚司は一瞬にして文句を継ぐ。
「“開け、封印の檻[シールドケイジ]”」
間に合わない。有り得ない速度で描かれた印章の輪が、瞬く間に二つの門となり、新たな召喚獣が吐き出される。空間が裂ける轟音と共に歪んだ輪の間から現れたのは、
「機種──!?」
強い疑問の声を上げたのは、【NAME】の斜め後ろで銃を構えるノエルだ。
彼女の言葉の通り、召喚の門から現れたのは二つの鉄の塊。人型を模したその機械は地に降り立つとぎりぎりと独特の音を立てて跳ね動き、それぞれの戦闘の姿勢へと移行する。
「有り得ないと、考えます。基礎専科となる分派四門、自然、機械、神魔、外来の枠に捉われない召喚術──幾ら外法とはいえ、こんな……何者なのですか、あなたは」
「何者といわれましても──成程、貴女の知識は“女賢者”殿に由来するもの。ならば知らぬのも理解できますが」
イルギジドは杖を弄びながら僅かに苦笑する。
「単純な話ですよ。世の中には四聖地を基盤として発展した西大陸由来の召喚術の上澄みだけを掬った、系統の異なる召喚術が存在するという事ですよ。聖地の力を満足に得られぬ土地では、それを補う為の相応の技術が発達しうる──後は、少し想像力を働かせれば判るものだとは思いますがね」
「つまり、あなたは……」
奴はアラセマのある西大陸ではなく、別の大陸からやってきた召喚士ということか。
【NAME】がそう推測する間もなく、イルギジドは笑みのまま言葉を継ぐ。
「ほらほら、思案している場合ではないでしょう? “振り絞れ、超過駆動[オーヴァードライヴ]”」
構えた杖から“贄”の力が剥がれ、それが術式の触媒となって空に散る。同時、眼前の機械人形二体から耳障りな高音をあげる。それは付加された術式によって彼等の動力部が限界を越えた出力を出し始めた証拠。
「まだまだ先は長い。この程度で力尽きてもらっては楽しめませんよ、“神形の操手”殿」
そんなイルギジドの呟きを合図として、地を抉りながら二つの戦闘機械が【NAME】へと迫る!
[BossMonster Encountered!]
機甲の召喚司



打ち出される鉄の拳を掻い潜り、技法を一撃。吹き飛ぶ硬質の頭部を見届ける事無く後方へと飛べば、攻撃の隙を狙って蹴り込まれた別の機械人形の脚が【NAME】の鼻先を掠める。
己の攻撃が空を切ったのを悟り、次なる攻撃を放つ為に体勢を一瞬で整える人形。だが身構えから実際の動きへと移る前に後方から飛んできたノエルの銃撃が胴に刺さり、人形は鉄の部品を撒き散らしながら動きを止めた。
──次は、召喚士。
思い、動こうとした矢先に降り注ぐ無数の雷槍。避けるために飛び退れば、既にイルギジドは次の術式の準備──更なる召喚術を行使するための印章記述に入っている。
(……くそ)
この距離と、奴の術式構成の速度を考えるとそれを阻止する事は難しい。【NAME】は歯噛みしつつイルギジドを睨み、武器を改めて構え直した。
正に悠々といった風に、イルギジドは杖を一度大きく振るう。
「いやはや、次は他概念世界の一つを統べる神の使徒と参りましょうか。ついでに芯属の模倣者も呼びますかね」
「──く、させません!」
言葉と共に放たれたノエルの銃撃は、しかしイルギジドの杖を中心に形成された無形の殻に弾かれ、空しく横へと逸れる。その間にイルギジドは動作を終えて、くつくつと肩を揺らしながら笑い、そして告げた。
「甘い甘い。貴女のその銃では対概念障壁用の準備を行った射撃でなければ、この杖が常に生み出す殻すら抜けられませんよ。──では参りますか、“開け、封印の檻[シールドケイジ]”」
浮ぶ印章で組み上げられた輪が高速で回転し、その内側に歪みが生じる。召喚の門が通された証だ。
そして空中に開かれた二つの印章の輪からこぼれ落ちるのは輝かしい光の羽と、鱗を燃え盛る火の赤に染めた巨体。
羽の主は背に一対の翼を供えた白色の弓持つ女で、凄まじい音を立てて地に降り立った巨体は炎を身に纏って全てを紅に染める巨大な火竜だ。
「そして彼等に相応しいのはこの術式ですかね。“貴く宿れ、聖なる力[ホーリーアーム]”」
同時、竜と白天。両者の爪や武具に仄白い輝きが灯った。それを見て、隣に立つノエルが両眉を寄せる。
「神聖の追撃……あんな術まで使えるなんて。【NAME】、気をつけてください。彼等の攻撃を受けると同時に、聖なる概念での追加攻撃が来る筈です」
先刻までもそうだが、呼び出す召喚獣の強さも然ることながら、イルギジドが彼等に付与する補助の術式が兎角厄介だ。空に浮び弓に矢を番える女と、地響きを立てつつゆっくりと歩いてくる巨竜を見据え──竜の喉仏が大きく膨らむのを見て、【NAME】は舌打ちしながら横へと飛ぶ。
「では、第三戦と洒落込みますか」
そして呟かれたイルギジドの言葉は、横へと駆ける【NAME】を追うように竜が吐き出した極炎の吐息が紡ぐ轟音によって遮られた。
[BossMonster Encountered!]
神禮の召喚司



竜を屠り、飛天する女を落す。
しかしその間にもイルギジドは更なる召喚の態勢へと入っており、奴を追い詰める隙が無い。
「【NAME】、このままでは──」
ノエルの言いたいことは最後まで聞かずとも判った。イルギジドと自分達。まったく動かずにただ後方から術を飛ばすイルギジドと、全力で走り回り攻撃と防御、更には回避をこなすこちらでは、疲労の度合いが段違いだ。このまま戦っていては拙い。
だが、どうすれば。
解決する策を模索する間も与えず、イルギジドの描いた新たなる召喚の門が開く。
「“開け、封印の檻[シールドケイジ]”」
新たな二つの輪より生み出された存在は、今までのモノとは一線を画していた。
「外来種──“奈落”の者達ですか」
ノエルが小さく息を呑む。【NAME】も、現れた存在のあまりの異質さに、反射的に眉を顰めた。
出現した二つの存在のうち、片方は異様なほどに長い鼻を持つ双腕双足の存在。紅色の宝石が如き両眼からは凄まじい熱の気配を感じる。
もう一方は、ドロドロに溶けた不定形の物体。地面に落ちた際に水っぽい音と共に身体の一部が弾け、地面に触れた部分は煙を上げて異臭を放つ。
「彼等に似合うのはこの術式でしょうな。“喰らいつけ、歪なる横笛[イヴルフルート]”」
文句と共に、眼前の異形二つの身体から鳴り響く奇怪な笛の音。きんと耳鳴りのような音が頭の中に深く響き、【NAME】は舌打ちと共に頭を抑える。
「西大陸に伝わる召喚四門のうち、最後の分類に属するのが彼等ですな。そちらの銃使いのお嬢さんには少々厳しい相手でしょうが、まぁ頑張って戴きましょう」
[BossMonster Encountered!]
外空の召喚司



その存在に近づくだけで、肌が焼けるように痛む。長鼻の先端から吹き出される炎は現実のものとは思えぬ程の力強さで、直撃を貰えば消し炭すら残さず消し飛ばされるだろう。凄まじい勢いで吹いた極炎の波を寸でのところで避けると、【NAME】は笛の音による頭痛を堪えるように歯を食いしばりながら化け物の懐へと飛び込み、一撃を放つ。
まさにこの世のモノとは思えぬ絶叫を放って長鼻の異形は仰け反り、元々この場に存在する事自体が許されぬものであったかのように、全身が押し潰されるように縮み、消滅した。
「いやはや、流石と申しましょうか」
ぱんぱんと、声と共に拍手の音が響く。
当然、その音の主はイルギジドだ。
余裕を見せ付けるように、小男は肩で息する【NAME】達を眺め、にこやかに微笑した。
――天従の力――
「では、次は少しばかり趣向を変えてみましょうか」
言って、イルギジドは数歩後ろへと下がり、楕円の物体の上から離れる。次の瞬間、その物体の側面に筋が入り、中に溜まっていた空気が押され噴き出すような音と共に、物体の上部が弾け飛んだ。
「それでは、参りますかね。そちらのお嬢さん、諦めて従わなければ壊れますので、注意なさい」
向けられた視線と言葉に、【NAME】の右隣に立っていたノエルは驚きで表情を揺るがせる。
「それは、どういう──」
「“率いるは力の眷属、天従[オールズワン]”」
ノエルの疑問の声を遮るように呟かれた、イルギジドの言葉。同時に、彼女はがくりと突然両膝を着き、力を失ったかのように顔を伏せた。
一体どうしたのか。
【NAME】は慌ててノエルに駆け寄ろうとして、
「……【NAME】、駄目です!」
声と共に彼女の片腕がありえない勢いで跳ね上がり、手の先から膨れ上がった人為らざる力の波動が近寄りかけた【NAME】に襲い掛かる。
「!?」
反応しきれず、力の波が全身を打ち、【NAME】は大きく後ろへと飛ばされた。一度地面にバウンドしてからその反動を利用して態勢を整えて立ち上がった【NAME】は、痛みを堪えてノエルを見る。
彼女はまるで後ろで糸を曳かれる人形のような不自然な動きで立ち上がると、驚きと恐怖で固まった表情を【NAME】に向けて、ゆっくりと右手をこちらへと挙げた。
──どういうことだ、これは。
そんな【NAME】の疑問に対する答えは、左手から来た。
「驚かれているようですな、“神形の操手”殿。どの程度そのお嬢さんの事を知っているのかは判りませんが……元々彼女はこの遺跡の“天従”となる鬼の力によって操られ、その真価を発揮する端末となる存在なのですよ。今、敷いた印章陣はこの地の脈……つまり、過去に“天従”の力の根元となっていたものと繋げる為の式。それを少しばかり利用させていただいて、そこのお嬢さんを使わせて戴いているという訳です。ついでに──」
イルギジドの傍らには、ノエルと良く似た造形の人影が立っていた。しかし纏う衣装はまったく別のもの。赤色に染まった衣服と鎧、兜は揺らめくような力を纏い、亜人というよりはまるで妖精にも近い存在に見えた。
「こちらの殻で保管されていた彼女も使わせていただくことに致しましょう」
イルギジドが杖を振ると同時に、彼の隣に立っていた娘がふわりと宙に浮び、手にした武器に力を込める。それと同時に、
「だ、駄目」
ノエルがこちらに向けていた掌から、また強い力が収縮するの感じた。
──全く。
舌打ちと共に【NAME】は大きく横へと跳躍してノエルが放った波動を避け、そして空中からこちらに向かって飛び掛ってくる娘に対してカウンター気味に技法を放つ。確実に当たるタイミングで放たれたその一撃は──。
「“巡り駆けよ、運命の輪[ホイールオヴフォーチュン]”」
イルギジドが二人に付与した追加の術式によって、彼女等の動く速度が唐突に二倍となり、胴を凪ぐ筈であった一撃は容易に回避される。
回る視界の片隅に一瞬映ったイルギジドの顔は、完全な愉悦の色に染まっていた。
「さぁ、頑張ってくださいよ、“神形の操手”殿」
[BossMonster Encountered!]
現世の召喚司



鎧の娘を打ち倒し、ノエルの動きも何とか封じる事に成功するが、しかし既にイルギジドは更なる召喚の姿勢へと入っていた。
──まだ呼べるのか!?
【NAME】はその様を見て愕然とする。
奴の魔力は無尽蔵なのか、それとも杖に宿る“贄”の力なのか?
そのどちらだとしても、この調子で決め手を欠いた状態で戦っていては体力が持たない。このままではいつか奴が次々と呼び出す召喚獣に押し切られてしまうだろう。
一体どうすれば。しかし考える間もなく、イルギジドは素早く印章の輪を造り、
「では、次はこの世界に在りし亜人の種を呼びますかね。“開け、封印の──」
「“巡り駆けよ、運命の輪[ホイールオヴフォーチュン]”!!」
イルギジドが放つ召喚の言葉を遮るように、一際高く場に轟いたのは凛と響く女性の声。
次に響くのは【NAME】の真横から突然生まれた地を蹴る馬の蹄の音だ。反射的に振り向けば、【NAME】の斜め前方、何も無い筈の空間から染み出すように生まれる六本の足持つ馬と、その背に跨る軍装の女の姿。
「はぁああああ!!」
淡い輝き──“運命の輪”による時間加速を示す輝きに包まれた六足の馬は音速に等しい速さでイルギジドとの間合いを一瞬で詰め、そしてその背から飛び降りた女が唖然と固まるイルギジドの懐へと飛び込む。
閃光と激突。
技法と術式の交差。
一瞬、時が止まったかのように二つの影が重なったまま止まり、そして。
「──ッ!?」
女が突撃の勢いをそのまま返されたかのように真後ろへと弾き飛ばされ、【NAME】達の直ぐ傍にまで地面を転がる。
イルギジド本人と、彼が持つ杖が展開する二つの対物理障壁にその勢いをまともに跳ね返されたせいだろう。彼女は仰向けに蹲り、己が身に返って来た激突の衝撃に全身を震わせながら、しかし懸命に顔を上げた。
【NAME】はその横顔を見て、己の記憶から二つの事柄──第十二師団副団長という肩書きと、クスィーク・カナル・フハールという名を思い出す。
「……あなたは、副団長!? 何故、ここに」
ノエルの驚きの声に、彼女は振り向かないまま、
「茫とするな、この隙を使え!!」
叫びに、【NAME】ははっとイルギジドの方を見て、そして迷わず全力で駆け出す。
イルギジドもクスィークと同様にかなりの距離を弾き飛ばされており、その肩には彼女の一撃によるものか深い斬撃による傷が。そして、その手にあった筈の杖は彼の手元を離れ、薄く積もった雪に埋もれるように転がっている。
──今ならば。
傷を負い、杖が持つ“贄”の力を得られぬ今ならば即座の召喚などは行えない筈。
「ぬぅ……!!」
イルギジドが肩の傷を物共せずに印章を空中に描きつつ、杖へと手を伸ばす。
杖を取ると同時に、その力を描いた印章に乗せて、何らかの術式を駆動させるつもりか。
【NAME】は前へと身を折り駆けるが、しかしその距離はクスィークの一撃によって先刻よりも離されている。イルギジドの動きが傷によって鈍っているとはいえ、彼の手が杖を捕まえるより早く自分の技法の射程へ入るのは不可能。一瞬そんな考えが頭を過ぎる。
技法の射程まであと十歩。しかしイルギジドと地面に転がる杖との距離は既に一歩の幅も無い。小男が一歩前へと進み、残り九歩。杖を拾い上げる為に身体を前へと倒し、八と七歩。最後の印章を空中へと刻み、六歩。地面に転がる杖へと手を伸ばして、五歩。節くれ立った指が杖に触れる間際、残り四歩。
──やはり、駄目か!?
だが、この機を逃せば後は無く、今更動きを止めたところでこの勢いではイルギジドの放つ術を避けられまい。覚悟を決めて【NAME】は身体を来るであろう衝撃に供えて硬直させる。そして開かれたイルギジドの五指が杖を捉え──。
「……当たって!!」
【NAME】の直ぐ真横を掠める光の一閃。
身体の自由を取り戻したノエルの黒銃、フォーレミュートによる一撃が、今まさに掴まれようとしていたイルギジドの杖を空へ向かって跳ね上げた。
「な……!」
空を切る己が手にイルギジドは驚愕の呻きを発し、そして茫然と顔をあげて、眼前まで迫った【NAME】の姿を見て動きを止めた。
迷うことは無い。
【NAME】が放った渾身の技法は、小柄な召喚司の身体をまともに打ち据え、吹き飛ばした。
「か、は、く──いや、はやこれは……」
呟きと共に、口端から血が上った。大の字に倒れ、ただ虚ろに空を見上げている小男の傍に、【NAME】は無言のまま近づく。
「は、ははは。まったく、派手にやられた、ものですな。まさか、この場面で、あなたが来るとは」
イルギジドの視線は【NAME】の背後。欠けた銀の剣を杖として揺らぐ体を支えながらこちらへと歩いてくる女騎士へと向けられていた。
「……六脚の幻獣エクウスを駆って、不自然なる密偵[フォースドステルス]を維持したまま全速で近づき……そして術を解くと同時に運命の輪[ホイールオヴフォーチュン]でもって、こちらの反応が間に合わぬ速度でもって突撃。その突進力と、事前に付与した銀の力で障壁を崩すとは……。いやはや、お見事ですな、副団長殿」
クスィークはイルギジドの傍へと立つと、表情を見せぬまま淡々と告げた。
「お前の負けだ、イルギジド・マイゼル。その傷ではもう長くはあるまい」
彼女の言葉に、イルギジドは引きつるように身体を震わせ、喉を鳴らした。
「く、くく……仕方ない。仕方ない。ああ、仕方ない。死ぬ、ここで死ぬ、くらいならば、ああ、全く」
にぃ、とイルギジドの顔がいやらしく歪んだ。そして開かれた口、覗く彼の歯の一本が強く、印章石独特の輝きを放つのが見えた。
「な、しまっ──」
歯に仕込んだ印章石を媒介とした無詠唱無記述での術式起動。
「“蠢け、幾重もの蔓[アンシードヴァイン]”」
同時、イルギジドが着込んだ長衣の裾から無数の蔦が伸びる。先端を鋭く尖らせた三本の蔦を【NAME】は後方へと飛び退る事によって回避し、続いて追って来た五本を技法によって撃ち払う。イルギジドの傍へは近づいていなかったノエルも下がりながら銃によって蔦を狙い撃ち、その身を安全な場所へと移していた、が。
「……くっ」
先程の全速での体当たりが身体に響いているのか、クスィークの動きは鈍く、蔦の作り出す網に足止めされる形となる。
そしてイルギジドは蔦を己が身体の支えとして宙に浮ぶと、胴から血を滴らせながら、ゆっくりと後ろへと下がっていく。
半ば虚ろとなったイルギジドの視線の先にあるものは。
「シンラ──ワタクシの身体も、何もかも、全て、全てを喰らってしまえ」
操る蔦によって、“大禍鬼”シンラの肩上へと移動した小男は、血の混じった吐息をひとつ吐くと、笑みのまま空を見上げて小さく呟いた。
「“全てを一に、統一世界[オーヴァーワード]”」
イルギジドが発した一つの言葉。それが契機だ。
地面に書かれた巨大極まりない印章の陣。その式が止まり、まず光が失せる。身体の各所に生えた硬質の突起部──角とも呼べる部分が展開、そこからどす黒い靄が生まれ、それが鬼の巨体をゆっくりと覆っていく。
黒色の影を纏い終えたシンラは、ゆっくりと左右に深く裂けた口蓋を開き、
『────!!』
言語として表現できぬ、まさに力の表現とも言うべき圧倒的な破の声を放った。
周りに存在するモノ全てがその声に叩き伏せられ、捻じ伏せられ、屈服せざるを得ない。そんな力の叫びだ。そして叫びを終えた鬼は、己が両手を組み合わせると一際強く握り締め、そして。
『統一世界[オーヴァーワード]』
声としての形を持たぬ、この場に存在するあらゆるものに届かせる意志の言葉が響く。
──瞬間、世界全てが鬼に吸い寄せられた。
「【NAME】、これは」
そんなノエルの叫びすらも、鬼の方へと引き寄せられて半ば途切れて聞こえる。【NAME】から見える鬼の周りは奇妙な形に歪んで、ゆっくりとその全てを己の中へと吸い込んでいた。
その歪みの景色は、一つ穴を開けた板の上に紙で描いた風景画を置き、穴から板の裏側へと紙を引っ張った様に良く似ていた。まるで“鬼喰らいの鬼”という穴に向かって、世界という風景が落ち込んでいくようだ。
肩上に居た筈のイルギジドの姿はもう既に無く、鬼の中へと吸い込まれた。風も雪も土も、何もかもがゆっくりと鬼へと向かって引き寄せられ、取り込まれていき、逆に鬼の力はどんどんと増していく。吸い込む存在の量が多すぎるのか、先刻から鬼の身体の輪郭が徐々に崩れ始め、何やら別の存在へと変わりつつあるようだ。
──無茶苦茶だ。
呻く間にも、周りの存在がどんどんと喰われていく。遺跡の残骸である岩が食われ、地に描かれていたイルギジドの印章陣が食われ、残されていた蔦の欠片が食われ、そして朧に輝くイルギジドの杖すらも飲み込まれる。杖を取り込んだ際に鬼の身体は大きく膨れ上がり、あの杖が持つ潜在能力がそれだけで知れた。
どうするべきか。その様を見据えて【NAME】は迷う。後ろを見れば既にノエルは膝をついている。先刻イルギジドに操られて消耗しているところに、今までの“大禍鬼”二体とは比べ物にならない程の圧倒的なこの気配だ。耐えられる訳も無い。戦うにしても彼女の手を借りるのはもう難しく、逃げるにしても人一人抱えてはこの状況は厳しい。
迷う間にも、どんどんとシンラに向かって吸い寄せられる。【NAME】は武器を地面に刺して踏みとどまろうとして、その地面自体もあの鬼に引き寄せられている事に気付いて舌打ちし、そして顔を上げて──息を呑んだ。
軍の服に身を包んだ女性が、祈るような仕草で“大禍鬼”の眼の前に立っていた。
クスィーク・カナル・フハール。
そうだ、彼女は、イルギジドが操った蔦に囲われ下がれなかったせいで、自分やノエルより鬼との位置が近かった。
あの位置では、もう助けにいこうにも間に合わない。ぎり、と【NAME】が歯を鳴らす間にも、彼女と鬼との距離は近づいていく。
「…………」
彼女は既に覚悟を決めているのか。逃げようとする様子も無く、ただ真摯な視線を鬼へと向けて見上げて、何気ない動作で片方の掌を鬼の方へとそろそろと伸ばす。
クスィークの手が、鬼の身体に触れる。どろりと彼女の手先が鬼の身体と溶け合い、その境界を無くした。
「……カナード様」
しかし、それはほんの一瞬の事。
溶けたはずの彼女の手が本来の形へとゆっくりと戻り始め、そして同時にシンラの動きが、世界を食い尽くす動きが僅かに鈍る。
『────』
幼子がむずがるような意志が周囲に伝播し、鬼の身体が小さく揺れた。クスィークは半ば腕を溶かされた状態のまま、ただただ真っ直ぐに遥か上にある鬼の顔を見つめている。
一体、何が起こっているのか。
【NAME】は両眼を細めて動きを止めた鬼と、目前に立つ娘とを交互に見比べ──と、その時。
──拒んでるのね。
ちりん、と鈴鳴る音を聴いた。
――絶対の大禍鬼――
──飲み込もうとするもの。
──飲み込まれようとするもの。
──お互いがお互いの消滅を拒んでる。
どういう意味か。そう呟く間にも、声は更に響く。
──拒んでいるのに、理に縛られてる。
──意志を縛って、絡める為の鎖が見える。
──一杯の心が、一つになるのを拒んでる。
そして一つ、強い意志が来る。
──私が望まれてる。今なら、斬れる。
胸元に浮ぶ首飾り。
【NAME】は無言でそれを掴み、強く握りこむ。
輝きはそれに答えるように光を増し、嬉しさのようなものが篭もった擽るような感触と、囁く声が【NAME】の耳に届く。
──ねえ、唄って?
──私を紡ぐ、流転の詩。
声と共に脳裏に浮ぶのは、いつか誰かが唄った美しい詩。
その記憶に後押しされるように、【NAME】は息を浅く吸い、流れるように言葉を継いだ。
回れ、運命の糸車
絡まる呪縛を切り
連なる劫罰を断ち
儚き泡沫と散る
贖え、
其の身解くるまで
手の中にあった首飾りが弾け、両手でも抱え持つのが難しい程の巨大な白剣へと変化した。
浮ぶ剣の柄を片手のみで握れば、しっくりと掌に馴染むような感触と、その大きさからは想像も出来ない適度な重みが返って来る。
そして剣が宿す意志が操り手である【NAME】の意志と混ざり合い、五感も特殊なものへと変化する。前方に立つ“鬼喰らいの鬼”の巨体に奇妙な線が三本と、それを縫うように張られた無数の鎖の姿が見えるのが、その最たるものといえた。
鬼に引かれた三つの線は、それぞれ鬼の中で大きな別要素として存在し、まだ完全に溶けきっていない存在概念それぞれを分かつ境だと、混ざり合った意志が教えてくれる。
一つはヴァイオラ、一つはシルイーヌ、そしてもう一つは様々な式のしがらみで縛られ、ある意味護られた人の存在概念。
最後の一つが強硬に拒み、鬼の中にある幾百幾千もの存在概念の足並みを乱しているが故に、本来なら見える筈の無い線と、そしてそれぞれを繋ぎとめる鎖がはっきりと見えていた。
(……いける)
神形器と同調した意識が高揚する。
──振りかぶり、払った剣の動きは三度。
莫大な光の奔流として放たれた神形の斬撃は、その直線上に居たクスィークの身体をすり抜けて、鬼の巨体の表面に浮ぶ線をなぞる様に突き刺さり、切り裂いた。
鬼の身体が吹き飛び、近くに居たクスィークも斬撃の勢いに押されて後方へと飛ばされる。
断たれた鬼の身体は三片、二つは空中に飛ぶと同時に砕け、鬼が持つ強い陰性概念をあたりに散らせて形を失う。シルイーヌ、そしてヴァイオラの存在概念の残滓だ。
そして残った一片は地面に転がると、ゆっくりとその姿を人の形へと変え始める。
「あ、ああ……!」
声にならない震えるような息を吐いて、クスィークは変化する欠片の傍へと半ば這うように急ぐ。
その背を横目に、【NAME】はシンラへと一気に駆け寄る。鬼は斬り飛ばされた部分の殆どを既に修復していたが、その替わりに、二回りほどその巨体が縮んでいる。無事な部分を使って、斬り飛ばされた部分の存在概念を補填したが故だろう。
しかし、縮んだとはいえ斬り飛ばしたのはあくまで二体の“大禍鬼”の残滓と、イルギジドが操りの為の要として使っていた人間一人の概念。先程吸った様々な存在は既に鬼の身体と同化しており、宿す気配はシルイーヌ、ヴァイオラの比ではない。
……果たして、勝てるのか?
自問したところで、声が来た。
──大丈夫。
神形の意志たる少女の声が告げるのは鮮やかな断言。【NAME】は一瞬苦笑し、そして決意を込めて前を見据える。
イルギジドがシンラに取り込まれて消えた今、あの“大禍鬼”さえ砕けば全ては終わる。
ここで、ここで負ける訳には行かない。
『────!!』
シンラのあげる咆哮が破壊の力となって駆ける【NAME】へと迫る。【NAME】は手にした白剣を右肩の高さへと引き、剣の平は地面に水平に、切先は鬼へと向けて、迫り来る力の波と相対する。
──だって、あなたの運命はもっと先へと続いているから。
ちりんという鈴音と共に響いた、そんな言葉を聞きながら。
[Shape Your Own Destiny!]
絶対の大禍鬼

一撃。
零距離から放った技法がシンラの巨体を打ち、僅かに空中へと浮かせる。
そして【NAME】は手に持つ神形の剣を握り直しながら跳躍、大きく振りかぶり、剣身を鬼の右肩へと斬りつけた。
鬼の身体に触れると同時に、剣が黄金の火を噴いて地面へと叩きつける。本来、ゼーレンヴァンデルングが斬る対象とする存在からは既に外れているため、その威力は神形が持つ全力とは程遠いが、しかしその一撃の手応えは確かなもの。反動を利用して大きく飛び退き、着地した【NAME】は、膝をつき地に伏せるシンラの姿を見た。
『────』
シンラは一度無音の叫びをあげると、肩口から黒い粒子のようなものを散らしながら、力尽きたように身を投げ出して倒れる。
力を失った身体はゆっくりと雪の白と地の茶が混じった地面の中へと沈んでいき──そして完全に、その姿を消した。
手が交じり合ったとき、懐かしい夢を見た。
幼い頃。何もかもを知らずに居た頃の一つの出会い。
その時、自分は目の前で泣く彼女をどのように思ったのか。
忘れていた。
不全。欠陥。無能。
幾つもの柵が自分を縛り、もう一度出会った時には何もかも色褪せていた。
だから、何故彼女が自分に拘るのか判らなかった。
ああ。
──でも、今は思い出せる。
自分を見下ろす泣き顔。
「カナード様ぁ……!」
呼ばれる声。
それに、今なら答えられる気がした。
殆ど動かぬ、既に自身のものであるという感覚すら薄い身体を震わせて。
ただ一言。
泣くなと、ただそれだけを告げた。
返された微笑は──初めて会った頃の笑顔に良く似ていた。
「は、ぁ──」
大の字に倒れ、【NAME】は全身の力を抜いて動きを止めた。
まさに全力。
全てを出し切った身体は、もう動く事を拒否している。
視界の右隅に刺さり立つのは一本の白剣。その一点を覗けば、目に映るものは一面の空だ。イルギジドの張った印章陣は既に効力を失い、しかし立ち昇った光の柱が割った空はそのまま。本来ならば薄雲に閉ざされている筈の空は遺跡の真上となる位置だけ大きく開き、純粋な青の空が見えた。
「【NAME】」
呼ばれ、声のした右側へと視界だけを巡らせれば、そこには全身ぼろぼろとなったノエルが立っている。
彼女の顔に浮ぶのは、心の底からの安堵の微笑み。
「……本当に、お疲れ様でした」
言って、傍に両膝をついて座り込む。ノエルも体力の限界であるらしく、【NAME】と同じようにごろんと身体を寝そべらせ、空を見上げる姿勢で動かなくなる。
空に開いた青色の穴は、ゆっくりとであるが周囲を埋める薄雲によって閉じられつつある。然したる間も無く、この場は濃い風雪の檻に閉ざされる事となるだろう。
──だが、今だけは。
せめて自分達が動ける程度に体力が回復するまでは、待って欲しい。
目を閉じて、差し込む暖かな日の光を浴びながら、【NAME】はただそれだけを願った。
四大遺跡 物語を綴じる紐
――物語を綴じる紐――
──以後の出来事をここに記す。
ゴディバ遺跡での戦闘に参加した者達はハザム、コートニーの村を経由し、無事常駐軍の駐屯地へ帰還した。これには準軍師イルギジド・マイゼルが従えた“大禍鬼”シンラに同加されていたらしい第十二師団師団長、カナード・フハールも含まれる。
対し、準軍師イルギジド・マイゼルはゴディバ遺跡跡にて“大禍鬼”シンラに同加され、以後行方不明。彼の従えていた“大禍鬼”シンラも、その最後を見届けた者は居ないものの、まず死亡、崩滅したとわたしは判断する。
これにより、アノーレで起きた“四大遺跡事変”は一応の決着を見た事となる。
そもそもの発端である“女賢者”レェア・ガナッシュは、準軍師イルギジド・マイゼルがノイハウスに乗り込んだ際、彼によって殺害されたと──表向きの話ではあるが──され、軍離反、遺跡占領の罪を問う事は出来なくなった。
もう一人の首謀者とされた“杜人”のリゼラ・マオエ・キヴェンティはヴィタメール遺跡の安定化以後、軍に対して正式に謝罪。多数の寄贈品と合わせ、他のキヴェンティ氏族との仲介役として、そして土地概念の変質による鬼種多発における軍の助力者として武力を発揮すると表明した。
無論、軍の間で彼に対し反感を持つ者は多数居たが、彼の提案、特にアノーレに置けるキヴェンティ氏族と交渉を行う際の確かなルートの開拓という点においてはその有益性は計りようも無く、更には軍自体も上層部の要となる人物を失った状態であった為に明確な姿勢を出せず、なし崩しという形で彼の提案を受け、その罪を水に流すという形となったようだ。
次に、常駐軍についての事を書く。
とある冒険者が所持していた神形器ゼーレンヴァンデルングの斬撃により、“大禍鬼”シンラからカナード・フハール師団長の存在概念が切り離され、それによって彼は生還する事ができた。だが、カナード・フハールと同様にガレー遺跡で行方不明になった筈の兵士達が、それによって元の姿を取り戻す事は無かった。
これには、軍属である学士イェア・ガナッシュによる見解として、ガレーの兵士達はシンラが持つ特性“同加”によって取り込まれた訳ではなく、イルギジド・マイゼルがガレー遺跡奥の“閉ざされし扉”を開くために用いた代償魔術の生贄として使われたためではないかという推測がある。つまり、カナード・フハールの場合とは異なり、大禍鬼シンラの同加によってではなく、イルギジド・マイゼルによる術式によって殺されたため、シンラを神形器で斬ったところで生き返る筈も無い、という事らしい。
合わせて、カナード・フハールにはイルギジド・マイゼルが多種の術式を施していた為にその存在概念が完全に鬼とは交わっていなかった事も、カナード・フハール生還の要因の一つとしても考えられるとのことだ。
現在の軍は、ノクトワイ・キーマに代表される副団長の下についていた数名の部隊長と、そしてガレーのイェア・ガナッシュが動かしている。指揮層を形成する者達の数が多く、その立ち位置も明確ではない為いざこざは多いと聞くが、内側以上に外側──三遺跡の“命脈”流出による島全域の土地概念不安定化、それによる鬼種の発生増加と問題が多発している為、致命的な亀裂が生じるには至っていないようだ。
イェア・ガナッシュはガレーを拠点としつつヴィタメール、ノイハウスを回り、それぞれの土地概念を調べ、調整を行っている。彼女は現在は既に死去して肉体を失い、完全な概念のみの存在となったレェア・ガナッシュとも密かに交流をもち、島全体の土地概念の安定に力を尽くしている。
本来ならば彼等を統べる立場に居る師団長カナード・フハールは、生還はしたものの健康とは言い難く、未だ床から背を離せぬ身である。実質の長であった副団長クスィーク・カナル・フハールは、その地位と課せられた軍務全てを放棄して、彼の付添として看病にあたっているという。
カナード・フハールの方は兎も角、クスィーク・カナル・フハールに対しては彼女の部下達が幾度も訪れ、今だけは軍務へと戻るよう懇願したというが、クスィーク・カナル・フハールはその全てに対し無言で首を横に振ったのだと聞いた。
既に半ば専用と化した治療の為の一室。窓際の寝台に横たわり外を見るカナード氏と、その傍に置かれた椅子に座って穏やかに彼を眺めるクスィーク女史の姿は、今まで二人の間にあったという溝のようなものが失せて、二人が本来の関係に戻った事を示す一つの形なのではないかと、駐屯地の食堂に詰めるとある女性は、様子を伺いに出向いたわたしに嬉しそうな表情で話してくれた。
カナード・フハールという人物が、今回の件に対してどのような関わり方をしたのかはわたしには判らない。
単なる被害者であったのかもしれず、イルギジド・マイゼルの共犯者であったのかもしれない。
だが、そのどちらであろうと、あのクスィークという女性は彼を護るために動くのだろう。そういった気持ちはわたしにはまだ理解できないものであるが、だからといって拒絶するような思考は持ち合わせてはいない。ただ、彼等がこれからも心安らかな日々を過せる事を願うのみだ。
“大禍鬼”シンラの討伐に多大な貢献を成した冒険者は、ゴディバでの戦い以後もフローリア諸島での活動を続けている。神形器ゼーレンヴァンデルングの所持、コルトレカンやアノーレで“大禍鬼”と戦いを繰り広げた事等は一切公にはしていないが、その腕は確かであり、常駐軍やアラセマ移民達からは勿論の事、キヴェンティ達や果ては亜人の者達から仕事を依頼されることもあるという。
──そして、わたしは。
いつかの約束の場所で、こうして物語を綴じるための手を動かしている。
既に例えるまでも無い話。
どことも知れぬ島の只中、小さな小さな森の奥に、こじんまりとした一つの家があったとする。
その家の中央には古めかしい木彫りの机があり、その脇には小さな椅子が二つあるとしよう。そして椅子の上には二つの人影がある。
一つの影は教師であり、一つの影は教え子だ。
教師は朧な身体を持つ妙齢の女性。椅子にゆったりと腰掛けて、眼の前に座る教え子を眺めている。
対するもう一つの影は、小柄な──少年と呼んでも通じそうな曖昧な身体を持つ娘。彼女は視線を机の上に置かれた紙に落として、黙々とペンを走らせている。
走るペンは紙の最下部へと進み、最後の文字を書く。娘が表情の変化が乏しい顔に僅かな満足感を浮かべて小さく息をつき、面を上げるのを待ってから、対面の教師は笑みで声をかける。
「できたかね? ノエル」
「はい。終わりました、“先生”。ですが」
「ですが?」
ノエルは最後の一枚となる紙を手に取り、小さく首を傾げて眼前に座る教師──つまりレェア・ガナッシュに問う。
「このようなもの、記述する意味はあるのでしょうか。わたしは一度得た情報を失う事はほぼありませんし、この記録は今わたし達がいる“現創領域”の外へ出す事はできないのでしょう?」
今自分達が居るのは以前ノイハウスに訪れた時にレェアと話した、彼女の私的な仮想空間だ。既に要の“大禍鬼”を失い、現創の力を扱う事は不可能であるのだが、繋がった“命脈”と遺跡の力、そして代わりの要となったレェア自身の力で、何とかこの場所だけは護ったのだと聞いた。
だが、辛うじて場所は護ったものの、現創の力自体は失われている。つまり、この場所にあるモノを現世界へと発現させることはできず、当然、今彼女が書き記した書物も同様だ。
「うーん、そうだな。まぁ、何故書かせたかっていうと」
「いうと?」
「私が読んで暇つぶす為──っていったら怒る?」
「…………」
「嘘よ」
「……………………」
黙り込んでいると、レェアはくすくすと笑って手を上下に軽く振った。
「怒らない怒らない。記憶は形にしておくことが大切なんだ。たとえ貴女の頭の中からその記憶が消えていないとしても、その記憶を想起するための切っ掛けが必要ってこと。それにそれ、外へ持ち出せるわよ?」
「え?」
「もう“現創”の再現は殆ど無理だけど、その紙が現世界からこちらへと運び込まれたものであるなら別ってこと。時がきたら貴女に渡すから、もっていきなさい。まぁ、暫くは私の暇つぶしとして役立ってもらう予定だけど」
「…………。先生、あなたのその性格はもう少し何とかならないものかとわたしは考えるのですが。非常識です」
「はは。非常識──つまり常識的な人間がどんな連中かがわかってきたわけだ。良い事だね、ホントに」
「……わたしについてではなく、あなたについて話しているのですが」
「まぁ、その辺の小言はまた来た時に聞くよ。そろそろ【NAME】がこっちに来てるみたいだから」
「あ、そうでした」
言って、ノエルは席を立つ。
「じゃ、私は【NAME】をこっちに呼び込んでくるとしますか。ノエル、貴女はその間に準備済ませてしまいなさい」
ふつ、と溶けるように椅子の上から消えるレェアに頷きだけで返し、ノエルは隣室に置かれた自分の荷物を取りに戻る。愛用の黒銃を手にしつつ考えるのは、【NAME】と、そして自分の事だ。
冒険者である【NAME】には、現在もイェアに極めて曖昧な条件で雇われるという形で、土地概念の不安定化に伴って発生する鬼種の討伐を手伝ってもらっている。ノエルは【NAME】がアノーレに居る間だけだが今までと同じように付き添い、力を貸していた。今回は、【NAME】がティネの村に滞在する期間だけ、無理を言ってノイハウスのレェアの元へとやってきたのだ。
あの海向こうから来た冒険者が、島で起こる様々な面倒事にふらふらと要らぬ首を突っ込んでいるのも相変わらず。
お陰で付き添うノエル自身も色々ととばっちりを受け続けている気もするが、それはそれで良いような気も多少してきたのは、【NAME】が持つ不思議な雰囲気に感化されたのか、それとも堕落したのか。堕落だとしても別に構わないかなと思い始めてるあたり、いよいよ問題があるのかもしれない。
旅を始めた当初は気付かなかったが、自分は外を出歩き、様々なもの、様々なひと、様々なことに出会うのを楽しいと、そう感じ始めていると知った。それがこの想いの原因なのだろうか。
荷物を纏め終えると、家の扉を開き、外へと出る。
幻の陽光。幻の微風を浴びて小さく一息つけば、森向こうに広がる果てない平原の彼方から、誰かがやってくるのが見えた。
「────」
自然、足が急く。
彼女は半ば駆け出すような勢いで小さな森を抜けて、今では意識せずとも浮かべられるようになった笑みの表情と共に、大きく手を振る。
自分を含め、数人しか知る事の無い──この芯海の島に生まれた英雄へと向けて。
Fin...
四大遺跡 予期せぬ再会
――予期せぬ再会――
ポロサに立ち寄ったついでに、ガレー遺跡にいるイェアを訊ねてみよう。そんな風に考えたのは単なる気まぐれだ。
イルギジドを倒し、“四大遺跡事変”が収まってから暫く経つ。それぞれの遺跡に封じられていた“大禍鬼”を彼が開放した事によって起きた“命脈”の力の流出は、ガレーを拠点として活動するイェア・ガナッシュと──公にはなっていないが、既に自身の身体を失い半ば亡霊のような存在と化したレェア・ガナッシュの力によって、何とか安定した状態に移行しつつある。
尤も、流出を食い止められるようになったとはいえ、やはりその影響を完全に封じ込められたとは言い難く、安定化する前までに流出の影響を受けた土地はそれぞれが持っていたカタチを歪められ、異常気象や鬼種の増加としてその歪を表していたが。
以前は他の場所に詰めていた兵士達が押し寄せ警護に当たっていたガレーも、今では事変前からガレーに詰めていた学士や兵士達しか残っていない。既に馴染にすらなった彼等に軽く挨拶してからイェアの所在を問えば、彼女は珍しく自室にいるという。
「少し、イェアも余裕がでてきたということでしょうか」
ノエルの呟きに、【NAME】は僅かに表情を緩めることで答えとする。
ガレー周辺に描かれた印章陣でもって遺跡を押さえ込み始めて数日は、殆ど眠らずでその維持調整を行っていたという。
それが終わった後も、頭を失った常駐軍の中で精力的に働き、芯形機構についての第一人者という役目からか他の者達から様々な形で助力を請われる事にもなり、最近までの彼女の忙しさは少々常軌を逸していたようだが、それも漸く一段落着いたという事らしい。
煌々と輝く印章陣の上を歩いてバラックの合間を抜け、イェアの居室がある建物へと辿り着いた【NAME】とノエルは、木造の扉の前に立つ。
数度扉を軽く叩き、中からの「あらあら、どうぞー」という何処かぬくぬくとした感触を聞く者に与える返答を待ってから【NAME】は扉を開いた。
──と。
相変わらずの乱雑極まりない部屋の中央、置かれたテーブル傍にはイェア・ガナッシュともう一人の人影。つまり、先客が居た。
先客は、探検家の装束を身に纏い、腰に肉厚の小剣を差した力溢れる顔つきの男。
このフローリアへと初めてやってきた時に出会った男。ハマダン・オリオールだ。
室内の二人は、戸口に顔を出した【NAME】の方を同時に見ると。
「おや、【NAME】?」
「あら、【NAME】さん?」
そう声を揃え、
「「え?」」
そしてお互い驚いたように顔を見合わせた。
イェアとオリオール、そして【NAME】。お互いの関係を簡単に話し合う。
「……そういうことでしたの。コルトレカンの方へ渡る以前にお知り合いになられたのですね」
「そうなる。あなたと【NAME】は、アノーレで最近起こっていた四大遺跡の事件で知り合ったと。しかし、前にガレーに来る途中の森で【NAME】に会った時、何故ゼーレンヴァンデルングを持っているのか不思議だったのだけど、コルトレカン駐在の常駐軍の長がね。……あの人もいい加減なものだな」
苦笑するオリオールの言葉からは、彼がネスカートと何らかの親交があるものと察せられた。
「それにしても──」
と、イェアがにこにこと笑いながら【NAME】の方を見て口を開く。
「相変わらず【NAME】さんは良いタイミングでわたくしの処へ来てくださいますわね」
【NAME】は僅かに厭な予感を覚えながら、一体どういう意味かと問えば。
「ええ、実は少し前からいくつか有益な情報を手に入れまして、ノクトワイ様と色々と準備を進めてますの。で、今からその関係でポロサの方へと出向く必要がありまして──【NAME】さんに一つを頼まれていただけないかな、と」
「? 有益な情報、ですか?」
ノエルの素朴な問いに、イェアは「ええ」と頷く。
「姉から伝わった情報、軍から回ってきた情報、最後にハマダン様──いえ、オリオールさんから戴いたちょっとした情報。どれも興味深く、そして動くに値する情報でしたの。だから、本格的に事を進めちゃいましょうかと」
動く、そして事を進めると彼女は言った。
一体、何をするつもりなのか。疑問の顔を浮かべたままの【NAME】に、イェアは自分の用件だけを告げる。
「それで、ですね。わたくしはポロサに直ぐに向かいますので、申し訳ないですけれどオリオールさんを姉の所へ案内して戴きたいんですの」
「姉──“先生”のところへ、でしょうか?」
ノエルが僅かばかり目を見開き、驚きの表情で問い掛ける。
【NAME】も素直に驚いた、イェアの姉、レェア・ガナッシュが半ば亡霊に近い形で未だ意思を持って存在し、ノイハウス遺跡を拠点として活動していることは極秘中の極秘といってもいい。それなのに、正体も半ば知れぬ探検家である彼を連れて行って大丈夫なのだろうか。
そんな【NAME】達の様子を眺め、オリオールは己の顎を一撫でして口を開く。
「うん、【NAME】達が戸惑うのも判るよ。僕はいってみれば完全に部外者であるわけだし。でも取り敢えず、レェア・ガナッシュ女史についての簡単な話を、僕はイェア嬢から既に聞いてしまってる。だから、その辺りの事は気にしなくて良い、と思う。──正直、何故話してくれたのか僕にも良く判らないけれど」
苦笑するオリオールに、イェアはくすくすと笑ってみせる。
「単純なお話ですわ。オリオールさんから先に手札を開いてくださったから、そのお返しに、と言うだけの話です。ワイゼン正家の方を無下に扱うわけには参りませんもの」
ワイゼン正家。アラセマ第一貴族である『六家』に連なる人間、ということか。
彼女の言葉と驚きで表情を変えた【NAME】に、オリオールは浮かべていた苦笑をより苦いものとする。
「……開こうと思って開いた訳じゃないんだが。誘導尋問はどうかと思うよ、僕は」
どうやら、自分達がここへ来る前に二人が中々楽しい会話を繰り広げていたらしい。
「いや、そんな目で見られると逆に惨めになるから」
【NAME】の気の毒にと同情の混じった視線を、オリオールは小さな吐息と共に払う。
「まあ、それはそれとして……僕としては探し人と“杖”の所在についての話を聞かせてもらうだけで構わないのだから、あなたが先刻言っていた情報とやらを教えてもらえるなら、別段レェア・ガナッシュ女史に直接会う必要もないと思うのだけれど──」
言って、オリオールは伺うようにイェアの方を見る。どうやら、オリオールはイェアに彼の“探し人”とやらについてを訊ね、イェアはそれに思い当たる事がある風な返しを自分達が来る前に交わしていたようだ。
──口出しは不要か。
そう結論づけて、【NAME】は静観を決め込む。その間に、イェアは渋い顔で小さく唸り、
「んー、ちょっとわたくしも急ぎたいですし、大きな視野で見ればそう時間の無駄になる事ではないですから……申し訳ないですけれどやはり姉から話を聞いて、あと姉にもオリオールさんの持ってる情報を直接話してあげてくださいませんか? オリオールさんの目的を果たす為の情報は、殆どが姉から齎されたものですから」
オリオールは顎に当てた親指をとんとんと三度揺らすだけの間をあけて、吐息。
「……了解した。元よりこちらは無理を言って話を聞いてもらっている立場だから、そうまで言われてはこれ以上押せないな。【NAME】達のほうはそれで構わないか?」
話を振られ、【NAME】は少しばかりの思案。四大遺跡に関する事件も一段落つき、急くような用事もこれといってないのは確かだ。報酬がしっかりもらえるのであれば異論は無い。
そう返せば、イェアはにこりと笑って頷く。
「良かった。でしたらお願いしますね? 報酬の方は──そうですわね。いくつか予備の」
言って彼女がごそごそと出してきたのは丁度掌に収まる形の鉄塊。
「これをお譲りします。機甲技術による短銃ですわ。お金が宜しいという事でしたらこれを売り払ってくださっても構いませんわ。【NAME】さん達が姉のところへ行っている間に準備は進めておきますから、ゆっくりしてらしてください」
「あの、イェア」
と、小さく手を挙げて呼びかけたのは脇に控えて殆ど無言のままいたノエルだ。
「先刻から幾度か仰っている“準備”とは何を行う為の準備なのでしょうか?」
「それは今はヒミツですわ。といっても、どうせ直ぐに知れる事になるでしょうけど。──あと、その流れで姉から【NAME】にも話があるでしょうから、ちゃんと詳しく話を聞いておいてくださいな」
言われ、首を捻る。“その流れ”とやらは自分にも関係する事なのだろうか。
何とはなしにきな臭い気配を感じ顰め面になる【NAME】に、
「それはお楽しみという事で。期待しておいてくださいな」
などと厭な台詞を寄越したイェアは、軽く微笑んだ後ゆっくりと席を立つ。
「では、わたくし、そろそろ出ないといけませんので」
どうやら、彼女は本当に今直ぐポロサへ向けて旅立つつもりらしい。
その言葉を受けて、【NAME】とノエル、そしてオリオールも立ち上がると部屋の外へと出る。
「では、申し訳ありませんけどお先に失礼しますね。【NAME】さん、ノエル。オリオールさんの案内の方、宜しくお願いします」
イェアは小さく一礼すると、バラック群の一角にある小さな厩舎へ向かい歩いていった。
バラックで馴染の兵士にイェアが自室に居ると聞いた時は、漸く彼女の忙しさも一段落着いたのかと思っていたが、休む間もなく既に次の仕事の下準備に入っているらしい。
「自身の健康についてあまり気を配らない方ですし、身体を壊さなければ良いのですが」
普段の無表情に少しばかりの心配を乗せたノエルの呟きに頷きながら、【NAME】は足早に去っていった彼女を見送った。
「さて」
白衣の背中が完全に消えるのを見届けてから、【NAME】は一息ついて隣のオリオールを見る。
(そういえば……)
先刻のイェアを含めて話した内容を思い出す。
アラセマ『六家』の一つ、ワイゼン正家の人間。もしそれが本当ならば、アラセマ皇国の中ではかなり高い地位にある筈だ。それが何故、探検家などという立場でこのような場所に居るのか。
オリオールは【NAME】の計るような視線を受け流すように、軽く肩を竦めてみせると。
「まぁ、よろしく頼む。下手に手を出すと邪魔になるかもしれないから、道中での厄介事はすべて君に任せるよ、今回は」
言って、彼はひらひらと手を振った。
「宜しいのですか、【NAME】?」
無表情のままこちらを見上げ伺うノエルに、【NAME】は少しばかりの思案の後、頷く。
護衛対象に戦いの先頭に立たせるというのもよく考えれば変な話であるし、ノイハウスまでの道程であればオリオールの手を煩わせる必要もないのは確かだった。
──しかし。
小さく呟いて、【NAME】は頭を掻く。
イェアが何の準備をしているのか。オリオールは何を求めて動いているのか。そしてレェア・ガナッシュがそれにどう関わるのか。
どれも現状ではいまひとつ良く判らないが、それもノイハウスに居るレェアに会えば解決するのだろうか?
視線だけでオリオールを促した後、【NAME】は先導するようにポロサの町へと向かって歩き出した。
四大遺跡 女賢者の示唆
――女賢者の示唆――
大草原を北へ抜けた先に広がる森の中。
城塞が如き威容を誇る建造物、アノーレ四大遺跡の一つに数えられるノイハウスの遺跡がある。その正面門前に【NAME】とノエル、そしてオリオールは立っていた。
遺跡の扉は常駐軍の術士達が様々な方法を用いた封印結界が幾重も張られ、一度触れれば警告となる小さな電撃が、再び触れれば死すら齎す強烈な対抗術が駆動する筈。
つまり、現在は何人も遺跡の中へ入ることは出来ないといって良い状況にある。
「さて、ここからどうするつもりだ、【NAME】君? 到底中には入れそうに無いが……」
既に軍の兵士達も去り、すっかり人気の失せた遺跡とその周辺をぐるりと見渡して、オリオールが問うてくる。
「問題ありません。そもそもこの遺跡の中へと入る必要はありませんので」
と、答えたのはノエルだ。
続けて、ノエルがオリオールが関係者であることを告げてレェアの名を呼べば。
「はいはい、ちょっと待ってなさいなぁ」
という声と共に輝きが生まれ、そこから長髪の女の影──レェア・ガナッシュの姿が現れた。
その様は以前ヴィタメールでイルギジドと争った際に出現した物より揺らぎは少なく、微細な部分も明確に存在する。
各遺跡での“命脈”の流出とそれに付随する土地概念の異常も何とか一段落つき、彼女が自身という存在を現世界に現す際に、より元に近い身体を写す事に力を割ける程度の余裕が出てきた、という事らしい。響く声も肉声に近く、殆ど生身の人間と変わりが無いようにも見えた。
レェアは輝きを纏った髪を一度払って地に足をつくと、【NAME】達を順々に見回す。
「お久しぶりだ、【NAME】、ノエル。それで貴方が、えーっと、ハマダン・オリオールさん──で良いの?」
「そうだが……しかし、驚いたな。型を作る器を持たない概念のみの存在か、君は」
「あら、私を見てその程度の反応って、貴方頭がかなり柔らかいのね」
目を瞬かせたレェアに、オリオールは軽く笑う。
「まあ、似た存在は昔に幾度か見たことがあるからね。それより、僕の名を知っているという事は君の妹さんから話は通っているのかな?」
「大まかにはね。取り敢えず私の家に引っ張り上げるからそこで話しましょ? ──っと、ちょっと待ってて」
何かに気付いたか、慌てて彼女は一度姿を消した。
一体どうしたのか。ノエルとオリオールと共に【NAME】は顔を見合わせる。
そして一分も経たずにもう一度姿を現した彼女は、後ろに一人小さな人影を引き連れていた。
僅かに地面から離れた位置に出現したその影は音も立てず着地すると、自分を覗き込むように見る【NAME】達へ向けて鋭い面を上げる。
影の正体は、全身を白の装束に身を包み、腰に二本の刀を差した大人びた瞳の色を持つ鋭利な少年。
「あなたは──」
驚きで言葉を詰まらせたノエルとその隣に立つ【NAME】を一瞥して、彼──リゼラ・マオエ・キヴェンティは淡々と呟く。
「成る程。新たな客とはお前達か、神形の使い手」
──何故彼が。
【NAME】は目を瞬かせて固まり、ノエルは詰まらせていた言葉を漸く続ける。
「どうして、あなたがここに?」
その問いに答えたのは、
「あら。ノエル気付いてなかったの? リゼラ君、前から結構ここに来てるけど」
「え?」
あっけらかんとしたレェアの言葉に、ノエルが驚きで目を見開く。
「…………」
彼女は僅かな沈黙を置いて、深々と溜息をついた後。何処か言い聞かせるような調子で話し出す。
「レェア、それはあらゆる面で見てあまり宜しくない行為なのではとわたしは考えます。あなたと彼は、遺跡占領の事件の首謀者です。ただでさえ警戒されて然るべきだというのに、その二人が今も内密に会っているなど」
「確かにな」
そんなノエルの忠言に答えたのは、レェアではなくリゼラだった。
彼は軽く己の腕を組むと、
「我としても、お前たち“迷の民”の戦を司る集団──“常駐軍”であったか。それらの警戒を無闇に煽る真似は控えたいのだが」
「うぅ」
言って、半眼にも似た視線をレェアに向ける。レェアは怯んだような怒ったような、何とも言い難い表情で睨み返した。
「……何よ。私のせいだって言いたいのか?」
「そうだ。今回のような件での呼び出しならば致し方ないとは思うが、暇だから、退屈だからといって我の“孔”を使って自分の処へ来い来いと喚くな」
「ううぅ」
【NAME】は素直に苦笑し、ノエルは小さく首を傾げる。
「喚いていたのですか、レェア?」
「うううぅ」
以前レェアに聞いた話であるが、彼女は“命脈”と繋がりを持ち、尚且つ外的影響が少ない地域でなら己の身体を今のように実体化させることが出来るらしい。そして、彼等キヴェンティは『翆霊』という“命脈”の化身とも呼べる存在を操る“命脈”に近い存在だ。恐らくは彼が持つ“命脈”の繋がりを使って幾度もリゼラとコンタクトを取っていたのだろう。
多重の呆れの視線を受けて、レェアはうぅうぅと暫く唸っていたが。
「──ちぇ。もう良いわ、そうまで言うならさっさと帰っちゃいなさいよ。リゼラ君、これから色々準備があるでしょ?」
ある程度まで到達すると開き直ったのか、燐光を纏った髪を払うと半分拗ねたような口調でリゼラに言う。
少年は頷くとレェアへの視線を切った。
「ああ、それについては感謝する。急ぎ、用意を進める事としよう。ではな、レェア」
短く告げて、白衣の少年は遺跡を囲う森へと向かって歩みかけ──足を止めると浅く振り返り、【NAME】に向けてこう告げた。
「そして“真なる亜獣達の楽園”でまた会おう、神形の使い手よ」
「……?」
意味が判らず、怪訝な表情となった【NAME】を無視して、リゼラはそのまま去っていった。
少年の小さな背が森の向こうへ消えるのを見届ける間に訪れた沈黙。それを破ったのは、今まで傍観に近い形で黙っていたオリオールだ。彼は軽く手を挙げると苦笑のまま、
「あー、と。それで──あの小さな子は何者なんだろうか?」
と、彼からしてみれば尤もな問い。あれだけ話に置いていかれていても文句一つ言わない彼は人が出来ているという他無いだろう。
何処から話したものかと僅かに考え込んだ【NAME】を制する様にレェアが自身の髪を軽く梳くと、オリオールを微笑のまま見て一つ指を鳴らす。
「その辺りのお話も含めて、私の家で話すわ。取り敢えずあまりこの身体を人に見られると拙いし、早いところ場所移しましょ?」
その音と言葉が合図となったのか、【NAME】達を包む周囲の景色がずるりとズレる。
城塞が如き遺跡とそれを囲う森、以前に使われていた天幕の残骸などが視界から消え去り、一片も曇りのない青空と、ただただ遠くまで果てなく続く草原が【NAME】達の眼の前に広がった。
ノイハウスの力で造られた様々な現創領域の名残。レェア・ガナッシュの私的空間として作られた大きな野原の一角に、小さな小さな森がある。
森を形成する木々の中で、真中に生えた一際大きな樹の根元に作られた木造の家。それがレェア・ガナッシュの居室である。
既に生身というものを失い、一応は食事も睡眠といった生理現象から無縁の存在、人の体すら維持することも不要となった筈の彼女であるが、【NAME】が何度かこの地に訪れ彼女の様子を見ていた限りでは、レェアは普段はその小屋の中で人の形を保って暮らし、仮初めの食事を取ったり、定刻での睡眠を取ったりしている。
その事について以前訊ねてみたところ、
「なるべく人としての生活を崩さないようにしないと、“レェア・ガナッシュという名の人間”って要素がどんどん希薄になって、最終的には自分を維持できなくなってしまうんだよ」
という答えが返ってきた。
つまり、人としての生活を固持する事によって、既に人外となった自分を人に近いもの、人に等しい形に留まらせる助けとしているらしい。
「で? 取り敢えず私、ハマダン氏のことは大まかにしか聞いてないから、もう一度しっかり話を聞いておきたいのだけど──宜しい?」
ノエルが淹れてきた茶が全員に回ったことを確認して、椅子に腰掛けたレェアが対面に座るオリオールを見る。
「構わないが、貴女が本当に僕の用件に関わる事を知っているのか?」
「それは、あなたが今から話してくれる内容次第。まぁ、イェアが聞いた限りでは関係あるみたいだけれど」
「……判った。少し長話になるが、構わないだろうか?」
「勿論。暇はあるしねぇ私は」
笑みを見せつつレェアは首肯。オリオールは次いで【NAME】とノエルを見る。ノエルは自分の意見など無いように無言のまま両目を閉じ、【NAME】も軽い頷きをオリオールに返した。彼の目的というものには多少の興味があった。
皆の反応を見届けてから、オリオールは一度咳払いして喉の調子を整えると、ゆっくりとした口調で話し始める。
「僕は元々、二つの役目を持ってこの諸島に来たんだ。一つは、今は【NAME】が持つ神形器ゼーレンヴァンデルングをフローリアへと運ぶ仕事。本当ならもう捨てた名だけれど、それでもワイゼンの血に連なる人間である事は変わりない。ベルトーチェ様直々の指定となると、流石に断るのはね」
レェアはふむと小さく鼻を鳴らす。
「だけど、そのお役目の方はコルトレカンでの顛末を聞く限りでは既に終わってるのだろう? ということは、もう一つの役目の方が私の処に来た理由ってこと?」
挟まれた言葉に、オリオールはゆっくりと頷く。
「そういう事になる、のかな。僕のもう一つの目的は──東大陸にある国の一つグローエスにある魔術学院『昂壁の翼』に所属する人間から受けたもの。ギンナム・ラシャ・オルシスという名の人物の捕縛と──彼が持ち出した魔導器の奪還若しくは破壊だ」
グローエス、という国については【NAME】も知っていた。五つの国を統合するグローエス五王朝では半年以上前に『現出』と呼ばれる異常現象──他概念世界からのものと思われる地形、生物などが現世界に無差別に実体化若しくは融合する現象が発生し、極度の混乱に陥った。その事件は既に沈静化したものの傷痕は未だ深く、また北西のノティルバン教国との関係悪化も懸念されている、色々と話題に事欠かない国の名だ。
そして魔導器。
こちらも多少の知識はあった。神形器が神の力を模して作り出された器であるのに対し、魔導器は魔の理を器に導く事によって力を振るう品だと。
神形器が主に過去の力ある聖職者達の奇蹟によって作り出されたとされる品であり、魔導器は起源の魔術師、“芯なる者”直々の教えを受けた人間達が己の持つ理の全てを費やして作り出したものであるという。
神と魔という名称の差こそあれ、実体には差異は無く、人の手に溢れる凄まじい力の器であることは変わりもない。故にそれらは扱い手によって善を為す品にも悪を憚らせる品にもなりうるものとされ、扱いには細心の注意を払う必要があるとされた。中には仮想の意識を付与して器自体に所有者を選定させる構造を持つ者もあり、神形器ゼーレンヴァンデルングはその一例としてあげられるだろう。
【NAME】がそれらの記憶を思い起こす間にも、オリオールは話を続けていく。
「ギンナム・ラシャ・オルシスは『昂壁の翼』に数年程所属していた召喚師なんだ。彼は半年程前に『昂壁の翼』に安置封印されていた“四界の杖”と呼ばれる魔導器の封印を解くとそれを奪い、そのまま西へと逃亡した。“四界の杖”は召喚術を補助する魔導器であり、固有能力として杖に宿らせた人の存在概念を力として転換する品だ。杖の内には生物を犠牲にして力を得る為の危険な式が内蔵されているという話で、禁忌の品として翼の方で封じられていたらしい。あと、ギンナム自身も“司位”に匹敵する召喚師と、レリエルから──僕の依頼主から聞いている」
「…………」
【NAME】は眉を顰めて、ノエルは僅かに目を見開いて顔を見合わせる。
“司位”に匹敵する召喚師であり、犠牲にした生物を力に変える特異な能力を秘めた杖を持つ人物。
【NAME】が思いついたように、ノエルにもオリオールが言う人物に思い当たる節があったらしい。
──つまり。彼が探しているのは、このアノーレではイルギジド・マイゼルと名乗っていたあの小男なのではないだろうか?
レェアもその事には気付いているだろうが、彼女は黙ったまま、オリオールが最後まで話すのを待っている。【NAME】とノエルは口を挟むかどうか暫し迷ったが、この件ではあくまでオリオールがレェアに意見を聞きに来ているのだということを思い出し、レェアに倣って口を噤むことにした。
オリオールの話は続く。
「『昂壁の翼』はそんなものを持ち出した彼を捕える為に人を動かしたけれど、彼が西の海を渡ったところでその追跡をやめた。労力に対して得られる価値がないとか何とかそういう話だったと思うけれど、単に自分達の縄張りで大事を起こすつもりがないと判ったから放置したというのが本当の理由だろうね。神形器と同等である魔導器という力を持ち、ギンナム自身も極めて優れた召喚師だった。そんな彼に突っ掛かり無駄な痛手を負うならば、という事だね」
「でも、あなたの依頼者はそれを善しとしなかった訳だ」
そこで漸く、レェアが口を挟む。オリオールは懐に手を入れながら彼女の言葉に頷くと、
「僕がここに居る事を考えてもらえれば直ぐに判る話だけれどね。これを見てもらえるだろうか」
言って、彼が懐から取り出したのは微妙に黒が濃い灰色に輝く宝石の欠片だ。
「これは“四界の杖”の欠片でね。本体との距離が離れていると真っ白、完全に一つになれば真っ黒に、破壊されれば色を失い不透明な石ころに変わる。東大陸に居た頃はこれは白く、ゼーレンヴァンデルング運搬の際に一度西大陸のアラセマに戻ったときも白かった」
立ったままでいたノエルがオリオールの手元で輝く宝石を覗き込むと、少し考え込むように眉を寄せる。
「……ですが、今は灰色に見えるとわたしは考えます。そこから推察するならば」
「そう。フローリア諸島へとやってきた時、石はこの色に変わった。なら“四界の杖”とその持ち主はこの諸島の何処かに居る筈だ。そう考えて色々と探してはみたのだけれど──なかなか上手く行かなくてね。それで、以前から島に住んでいて術式や理粒子、概念変質に詳しい人物に話を聞いて回っているという訳だ。ここに来たのもその流れ、という事なんだが……」
一通りの話は終わったという事なのだろう、オリオールはそこで言葉を切ると、伺うように対面に座る女性を見る。
「成る程ね。大体話は判ったよ」
レェアが一つ頷くのを見て、オリオールは表情を改めると彼女の発言を待つ。レェアの表情に真剣の色が濃いのを見て取った故だろう。
レェアは考えを整理する為かほんの少しだけ部屋の天井に視線を移した後、
「まず聞くけど。その人物と魔導器がそれぞれ既に失われていた時、一体どうするつもりなの?」
と、彼に尋ねた。
オリオールは「んー」と自身の頬を掻いてどう答えるかと間を置いた後、
「……難しいね。さっきは僕の依頼者は“四界の杖”が持ち去られるのを善しとしなかった、とは言ったけれど、実際はそれ程重要視している訳でもなくてね。ギンナム・ラシャ・オルシス自体は出来るなら捕縛、無理ならば放置しても構わないという程度。魔導器“四界の杖”については──神形や魔導器は特化された目的を果たす事による充足消滅以外で破壊されることは殆どないし、失われているかどうかは僕が預かっている石で判るからその限りじゃないだろう。今も現存していると、この石が報せてくれる」
「そうか。……ハマダン氏が持つその石の存在は、私達にとっても有益な情報源と言えるだろうな。その情報を対価と考えて、こちらの情報も明かすべきだな」
レェアは己の言葉に一度頷いてから、対面に座りこちらを見るオリオールへゆっくりと話し始める。
「……簡単に言うとね。“四界の杖”を持っていた男、ギンナム・ラシャ・オルシスだっけ? そいつはこっちではイルギジド・マイゼルと名乗っていて、あなたも多少は知ってるでしょうけど、アノーレのアラセマ常駐軍に紛れ込んだ後、大きな騒ぎを起こして──そこの【NAME】の話を聞く限りでは“鬼喰らいの鬼”に杖と一緒に飲み込まれたらしいね」
「────」
オリオールは大きく目を見開いて固まり、そして次の瞬間小さく舌打ちして毒づく。何故気付かなかったのかと自身の愚かさを呪うものだ。
「……成る程、な。あの準軍師は魔術師でなく召喚師だったのか。なら確かに、符号としては一致する」
「あの」
と、そこで手を挙げたのはノエルだ。彼女は盆を抱えたまま視線で皆を伺い、沈黙という許可を得て話し始める。
「その推測には矛盾があるとわたしは考えます。何故なら今オリオール氏がお持ちになっている宝石。それが示している事実はどうなりますか? もしイルギジド・マイゼルがギンナム・ラシャ・オルシスであり、彼が持っていた杖が“四界の杖”であったとしましょう。ですが、もしそうならばオリオール氏が持っているこの石は完全に輝きを失っている筈だとわたしは考えます。イルギジド・マイゼルと杖を取り込んだ“鬼喰らいの鬼”は【NAME】の手により滅しました。でも、まだこの石は透明で力の輝きに満ちている」
それもそうだ。成る程と【NAME】は内心呟き納得する。オリオールも「確かに」と呟いて、考え込むように視線を下へと向けた。
「なら……別人という事になるのだろうか?」
暫しの沈黙の後、ぽつりと呟かれたオリオールの言葉に、
「いや、それはない。恐らく同一人物だろう」
両腕を組んで黙っていたレェアが、淡々とした調子でオリオールの言葉を否定した。
「──?」
レェア以外の者達が目を瞬かせて彼女を見る。何故彼女が断言できるのか、その理由が判らなかった。
「どういう事でしょうか“先生”。わたしの考えに何か間違いが──」
「ううん。ノエルの思考は間違っちゃいないよ。でも、前提となる条件が崩れてるかもしれないってこと。“鬼喰らいの鬼”──大禍鬼シンラがちゃんと消滅していたなら良かったんだけど……実は、そう上手くいってないみたいでね」
思わせぶりなレェアの言葉と、こちらを見る視線。それが指す意味は──。
「まさか、“鬼喰らいの鬼”がまだ存在している、と?」
【NAME】の替わりに、ノエルが普段の無表情に僅かな憤慨の色を乗せた。
「ですが、わたしと【NAME】は確かに」
「【NAME】、貴方が“鬼喰らいの鬼”を倒した場面、もう一度詳しく話してくれる?」
だが、ノエルの反論を封じるようにレェアが言葉を継ぎ、【NAME】は改めてあのゴディバでの戦いを思い出す。
召喚師である小男が呼び出す四界の獣達。ゴディバ遺跡の残骸に葬られていたノエルと同型の存在。最後に、全てを取り込み同化しようとした大禍鬼シンラとの戦い。
自分と神形のゼーレンヴァンデルングの力によって断たれたシンラは、身を折り、雪積もる地に倒れ伏せた。
「そう、その最後の所。鬼が地面に倒れて、そして沈むように消えたって君は言ったでしょ?」
「…………」
レェアの言葉に厭な予感を覚える。
ノエルも同様だったようだ。内の驚きを表すかのようにノエルの口調が速くなる。
「──まさか、あれは消滅したのではなく、地の内へと沈んでそのまま別の場所へと逃げ去ったとおっしゃりたいのですか?」
「……私としてもそう考えたくはないんだけどね。でも、四大遺跡に繋がった“命脈”を弄るために少し深いところまで脈を遡って調べてみたら、あの“鬼喰らいの鬼”と、イルギジドが持ってた杖が漂わせてた厭な気配を脈の末端から感じたのよ。あれは確かに、シンラとイルギジドが持ってた杖──そこのハマダン氏の言う処の“四界の杖”の気配。末端の大まかな位置はアノーレ北部から更に北、って言って判るかな?」
アノーレの北。
言われ、【NAME】はフローリア諸島に点在する島々のことを思い出す。
フローリアは主に四つの島によって構成されている。
諸島南西、他の島々より離れた位置にある小島ランドリート。アラセマ移民達の数が最も多い、諸島西部を占める大島コルトレカン。コルトレカンの東にある三日月にも似た形の大島が、今自分達が居るアノーレ。
そしてアノーレの北にある島、常駐軍の手も殆ど入っていない“真なる亜獣達の楽園”とも呼ばれる──。
「……レェア、貴女が言いたいのはまさか──エルツァン島のことですか?」
ノエルの言葉に、レェアは笑みで答える。
「大正解。あの鬼、エルツァンの大奥にあるでかい脈……多分あっちの島にある“檻の柱”近くに陣取って、何かやってるみたいなのよ。で、ハマダン氏。ここで先刻私が訪ねたことが効いてくるのだけど、判るだろうか」
問いに、オリオールは詰まった気を抜くように一つ息をつき、そして鋭い視線を正面──レェアに向ける。
「ギンナム・ラシャ・オルシスという人物は既に存在しない。だが、その人物が交じり合った存在はまだ何らかの形で生きており、そして“四界の杖”もその鬼が持っていると?」
「“四界の杖”の方ははっきりしないけどね。あの杖の気配が大きな形質の変化も無く感じ取れたということは、シンラと完全に“同加”しているということは無いだろうが、それも実際どうなってるかなんて判らないよ。──それで、オリオールさんはここまで話を聞いて、どうするのだろうか」
「どうする、と言われてもな……。人の手が入っていない場所へ分け入るのは慣れてるが“大禍鬼”相手となると、流石にどうしたものかと言うしかないな」
オリオールは苦笑して顎を撫でた。見た処、オリオールは冒険者としての技量は高いものの、超常的な力を持った人間という風には見えない。“大禍鬼”と聞いて戸惑うのも無理からぬ話だろう。
「まあ、尤もだ。で、少しばかり話は変わるが──エルツァンでの“大禍鬼”シンラの怪しい動きやその辺りの情報は、イェアを通して常駐軍に回してあるんだ。それで今、イェアとノクトワイ・キーマ辺りが動いて早い段階でエルツァンへと入る部隊を編成するとか言ってたかな。【NAME】、イェアに私から“詳しく話を聞いて来い”と言われたろう?」
イェアとの別れ際辺りでそんな事を言われたような記憶があるような無いような。曖昧な表情で首を捻った【NAME】に、レェアは喉を鳴らすように笑う。
「イェアとしては君にもエルツァンへ向かう部隊に同行してもらうつもりだろうから、これはその前説という奴だよ。“鬼喰らいの鬼”の調査と、エルツァン島の調査を同時に行う腹積もりらしいから人は多ければ多いほど良いとか言ってたかな。【NAME】も今は暇だろうし、丁度良いんじゃない?」
そんな勝手な、とげんなりする【NAME】だが、レェアは笑みを濃くするだけだ。
「人気者は辛いという事だね。まぁ、私個人の考えだと、イルギジドが絡んでないならもうあの鬼も放っておいても大丈夫じゃないかって気もするんだけど、イェアは心配性だからね。憂いとなりそうなコトは手早く処理したいんでしょ。……で、まぁそんな流れで近々エルツァンへと向かう探索隊が編成されて、出発する筈なんだけど──」
そこで言葉を区切ると、レェアは意味深に机を挟んだ向こう側に座るオリオールを見る。その視線の意味を察して、オリオールは小さく唸るとこう言った。
「む……つまり、その軍の部隊に同行しろと?」
「しろ、という訳でもないけどね。ただ、貴方が自分の目的を果たしたいと考えるなら、彼等に同行するのも悪い選択ではないんじゃないかって言いたいだけだけど、どう?」
オリオールは暫く考え込むように天井を見上げて、渋い表情と共に面を下げる。
「確かに……ギンナム・ラシャ・オルシスが鬼に取り込まれ、その鬼が“四界の杖”を所持しているのが本当であるなら同行する他無いけれど──真実という証拠も無いね」
「まぁ、それはね」
レェアは苦笑しながら自分の髪を一房つかみ、くるりと巻く。
「それ言われると何とも答え辛いけど。私達が提供できるのはあくまで先刻の情報と、あなたがエルツァンへと渡る権利くらいよ。それを行使するか無視するかは貴方自身が決めると良い。イェアは今ならポロサの駐屯地に居る筈だから、同行するつもりなら声を掛けてあげて。東大陸では名高い冒険者であるあなたならイェアが拒む事は無いだろう」
「…………」
そこで、少し会話が途切れて沈黙が降りる。レェアはオリオールの返事を待ち、オリオールは顔を僅かに伏せて頭の中で情報を整理し、どうするかを検討しているのだろう。ノエルは盆を抱えたままじっと二人の様子を眺めたまま動かず、【NAME】にしても今自分が口を出す状況ではないのは弁えている。
そのまま二十呼吸程の間を置いただろうか。
オリオールが伏せていた顔を上げると、前に座るレェアを見て表情を少しばかり緩め、告げた。
「……了解した、そこまでお膳立てしてくれたとなれば断る謂われも無い、か」
「それは良かった。人手が足りないから、イェアも喜ぶだろうね。──あと、【NAME】の場合は“あの方は強制参加です!! して戴かないとわたくし達ホント困りますぅ!!”て言ってたから拒否権無しね」
むぅ、と唸る【NAME】。替わりに、軍服の娘が無表情のまま口を挟む。
「……“先生”、それは流石に強引すぎるのではないかとわたしは思いますが。【NAME】の意志の尊重が全くされていないように思えます」
ノエルの淡々とした抗議を、レェアは苦笑しつつ受け入れる。
「それは判ってるし、無茶を言っているのも判ってるけれどね。でも【NAME】が持ってる神形器が無いと“大禍鬼”の相手は厳しいし、それ以前に島全体が侵入者を拒む結界みたいなので覆われているって話だから、ゼーレンヴァンデルングの力が無いと始まらないんだよ」
そこまで言って、レェアは憂鬱そうな表情を浮かべて溜息の仕草──実際息をしている訳ではないので単なる癖なのだろう──をする。
「……私もお手伝いできたら良かったんだけど、エルツァンの島は兎に角、土地概念の歪みが並じゃなくて、私みたいなのが外側から干渉するには厳しい場所でね。あの中では時の歩みや因果すらも歪むっていう話で、身体の顕現が出来る出来ない以前に、意識を向こうへ繋ぐのも不可能なのよ。だから、残念だけど今回はお留守番。──それに【NAME】だって、行ってみたくないか? フローリア諸島にある大島の中で、最も特異な場所と言われるエルツァンへ」
「…………」
言われ、【NAME】は自分の意志を改めて確認する。
エルツァンに対する興味が無い、といえば嘘になる。未だ殆ど未踏の島であるエルツァンへと渡れば、今までに無い何かを見つけ、手に入れられる可能性も、誰もが知りえない何かを知る事ができるかもしれない。
だが、同時に極めて危険な旅となるのは確実であり、尚且つあの“大禍鬼”シンラとの再戦も有り得るとなれば少しばかり躊躇いが出来るのも仕方が無い。
少々深刻に考え込んでしまった【NAME】の様子を見て、レェアは席からふわりと腰をあげると、【NAME】の肩をぽんと軽く叩いた。
「ま、あまり深く考えないで、気軽なおまけ、事後処理みたいなものって考えて良いんじゃないかと私は思うけど──行く気になったら、ポロサのイェアの処へ行ってあげて」
本サイト内コンテンツの一切の転載を禁止いたします。