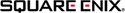贄の聖女 凍える大地
──凍える大地──
五王朝属国クンアール。王朝の北東に位置するこの一帯は元々他概念世界への『門』が開きやすい地域として知られており、『虹色の夜』以後発生し始めた『現出』の影響を最も大きく受けたのがこの国といわれている。
しかし、当初こそ領土内に発生した様々な現出の影響により極度の混乱状態にあったクンアールだが、丁度『虹色の夜』以後一ヶ月ほど過ぎたあたりから急速に『現出』の発生率が低下しはじめた。増加傾向にある他四国とは異なり、今現在、この国での現出発生率は隣国オルスやカルエンスなどを10とするならば、1、または2の割合といったところで落ち着いているという。
これにはグローエスの支都ルアムザにある魔術学院『昂壁の翼』や、アグナ・スネフの王宮所属の学士連盟、更には預言者ギルド等から様々な仮説が立てられているが、いまだ定説となりえたものは存在していない。それも『現出』の理屈が完全に解明されていない現在の状況では仕方ないといえば仕方ないのだが。
そんなクンアール国のなかで、代表的な『現出地形』として挙げられるものは三つある。どれも元々その場所に存在していた地形に混ざり合うように現出した、俗にいう『概念現出』と呼ばれる類のものだが、規模が大きく、住み着いている亜獣達も通常の現出地形などと比べても優るとも劣らない。
一つは『クォルルマル大森林』の北部、通称『干渉域』。
一つはカルセオラリアとアグナ・スネフを最短のルートで結ぶサーンナル第五街道の北東に広がる『朱色の湿原』。
そして最後が、今貴方が辿り着いた場所。サーンナルの街道を南東に進んだ地域にある広大な寒冷地、通称『凍える大地』だ。
・
「んでだね。一応この辺りはパラーシェ副伯家の領地だったらしいんだけど、今となっては他の四国と同じようにそういったのは名前が残ってるだけで、実質的にはクンアール王家の直轄地って事になってる筈なの」
【NAME】の頭の上に座り、得意げに解説を続けるリトゥエの声を右から左へと聞き流し、貴方は両脇に針葉樹がすらりと立ち並ぶ森の小街道を歩いていた。サーンナルの第五街道をはずれ、南東へと続く道。一応既に『凍える大地』の範囲内に入っているはずだが、まだ街道を吹き抜ける風は「少々肌寒い」という程度で済んでいる。しかし、もう暫く進めば、すぐにその風は轟音を伴う強烈な冷風へと変化する筈だ。
貴方は更にどうでもいい事を喋り続けるリトゥエを軽く突いて窘め、『凍える大地』についての情報──先程のような領地がどうとかという話ではなく、もっと実用的な情報──を求める。
「うぅ、折角ノッってきたのに。まぁ、いいけどさ」
頭の上でリトゥエがくるりと身体の向きを変えたのが判る。髪が引っ張られ、【NAME】は小さな痛みに顔を顰める。
「冒険に役に立ちそうな噂となると……うーん、三つくらいあるかな」
どうやら座りながら背中の羽をひこひこと動かしているらしく、眼前に彼女の羽が零す小さな燐光がちらつく。綺麗ではあるが少々鬱陶しい。
「凍える大地のどこかの森に大きな氷竜が住んでいて、そいつを狩れば良い金になるんじゃないかなーって話とか、南で起きてる猛吹雪は、吹雪を操る巨人のせいだとか。あと、大きな洞穴が現出してて、その奥には訪れた者に幻を見せる氷の祭壇があるとかないとかいう噂もあったよ」
そこまで言って、うーんと軽く唸る。
「……私が知ってるのはこんなところかなぁ。個人的には、竜の話が一番信憑性ありそうだったけど。確かに竜の鱗とか爪とか、結構高く売れるもんね──っと」
途中で言葉を切り、リトゥエが空中に浮かび上がる。
「亜獣、だね」
battle
白い恐怖


襲い掛かってきた亜獣を倒し道を進んでいくと、突然風の気配が変わる。露出した肌を掠めていくそれは身を切るような冷たさを秘めた鋭利な風だ。
「さ、さむっ~!!」
リトゥエが情けない悲鳴をあげ、【NAME】の懐に潜り込む。頭から飛び込んだ為、ばたばたと振られる足が貴方の視界のなかで左右に揺れた。どう言えば良いのか。酷く邪魔だ。
というよりも、それ以前に彼女のようなミスティック、妖精は寒さなど感じないものと思っていたのだが。
「いや……まぁ、凍え死んだりはしないんだけど……こう、『寒』って概念を叩きつけられちゃうと、自分の存在概念自体が冷えちゃってさ。居ても立っても居られなくなるのよぅ」
情けない調子で呻くリトゥエ。良く意味はわからないが、要するに彼女達も人間と同じように熱いだの寒いだのという感覚があるということなのだろうか。
・
貴方はようやく本性を現し始めた『凍える大地』の奥を目指し、どんどんと先へ進んでいく。
さて、今回はどこを目指すか。目指すルートとしては、氷の竜が住むという森があると噂の氷原へと続く道筋と、強力な吹雪が渦巻いているという凍える大地の南部へと続く道筋との二つがある。
残念ながら、この寒冷地のどこかにあるという洞穴への道筋は未だ不明のままだ。
轟、と一際風が強く唸り、周囲に降り積もっていた雪が激しく舞い散り視界を塞ぐ。一時間程前から降り始めた雪は既に豪雪といっても差し支えの無いものとなっており、吹き荒ぶ強烈な風と相まって、現在の天候を一言で表すならば、
「吹雪! 吹雪すぎる!! も、帰ろーよぉ!」
風に負けぬよう大声で叫ぶリトゥエの言葉が全てを現している。防寒具を持ってきて居なければとっくの昔に行き倒れていただろう。
だが、そんな豪風吹き荒れる中でも、まったく平然とした様子で宙を遊泳する連中がいるのだから閉口してしまう。
白い網にも見える雪の流れの中、貴方は苦労して武器を構え、襲い掛かってきた化け物と相対する。
空中に漂っていた化け物を打ち倒した後も、吹雪は更に強くなっていく。と、その時──
「……?」
ふと、視界の片隅に、微かに人影のようなものが映った気がした。
「【NAME】? どしたの?」
訝しげなリトゥエの問いを無視し、先程ちらりと人影が見えた方向へと目を凝らすのだが……唸る雪風が邪魔をしてよく判らない。人影のようでもあるし、雪面についた只の陰影のようでもある。
(近づいて、確かめてみるか?)
だが、もし人だったとしても、この吹雪の中だ。生きているという可能性はこの上なく低いだろう。それに、いざ近づいてみたら亜獣だったという場合も考えられる。
気になった場所へ近づいてみると、そこにはひとりの青年が雪の上で大の字になって豪快に倒れていた。雪で半ば埋もれた彼の髪が醒めるような青だったため、それが偶然目についたのだろう。
どう考えても凍死していそうだったが、せっかくだからと掘り出してみると──
「……いやぁ、誰だか知らないけど、助かりました」
「うわ、びっくりした!」
唐突な声に仰け反るリトゥエ。
白を通り越して青に近い顔色になっているにもかかわらず、青年は緊張感の無いのんびりとした声を出す。
生きているのならば、やはり助けなければなるまい。
殆ど氷のような冷たさの青年を肩に担ぎ、何とか歩き出す。とにかく、この吹雪の外へと連れ出さなければ話にならない。思い、来た道を戻ろうとして──
「いやはや……普段ならこの程度の吹雪はどうという事もないのですが、運悪く氷結の乙女達がこの辺りまでやってきていたようで。
まったく、うつつの身体というのは面倒なものでして……」
青い顔に笑みを浮かべ、とつとつと喋る青年の言葉に貴方は露骨に眉を潜める。懐のリトゥエの表情も一気に引きつった。
「氷結の乙女の──住処?」
思わず鸚鵡返しに呟くと同時。周囲の気温が一気に低下し始めた。
耳の奥に鈍い痛み。そして風が唸る音が聞こえる。
「【NAME】、もう囲まれてる! 来るよ!」
リトゥエの声に青年を雪の上に投げ出し──乱暴だなぁと呟く声が聞こえたが無視──疼く痛みをこらえつつ武器を構え、周囲の気配を探る。
──氷結の乙女。それは寒冷地を渡る人々に死を呼び込む精霊達だ。彼女達の凍える吐息をその身に受けたものは一瞬にして凍りつく。
そして、彼女達は目に見える存在ではない。実体は無く、その存在は限りなく無に近い。乙女という名称にしても単なるイメージからつけられた名称であり、実際に彼女等がそういった姿をとっているのかはまた別の問題だ。
風の流れ、雪の流れを追って彼女等の位置を掴み、そして魔術などの力を借りた攻撃を仕掛ける。氷結の乙女達を撃退するにはその方法しかない。
射、と空気が流れる。頬を掠める鋭い凍風を寸でのところで回避し、そして風が襲い掛かってきた場所──乙女達の居ると思しき場所へと間髪入れず攻撃を仕掛ける!
無形の乙女達を退け、青年を抱えて彼女等の住処から逃げ出す。しかし方角などを考えずにがむしゃらに逃げ出したため、吹雪の中からは未だ抜け出せないでいた。
「……あの」
いい加減焦り始めた貴方の肩に捕まっていた青年が、おずおず、というよりはのんびりといった風な声で切り出す。
彼曰く、ここから東の方向──彼はしっかりと方角が判っていたらしい──へ少し進むと、彼が世話になっているという人が住む小屋があるという。小屋周辺の地域は吹雪に襲われる事も無いという話だったので、その小屋で少し休んでいかないかという話だった。
確かにこちらも先程からの戦闘や、吹雪の中を延々と強行軍で進んできた為、休めるというのならどこででも休みたい心境だった。小屋が近いというならば、彼の言葉に甘えさせてもらっても構わないだろう。
そう考え、貴方は青年の案内を頼りに吹雪の中を進んでいった。
青年の案内どおりに進むと、半時間も歩かぬうちに吹雪は晴れて、細い針葉樹が並び立つ小さな林の中へと辿りつく。殆ど誰もやってこないように見えるその森には、明らかに人が雪を掻いて作ったと思しき小道が一本伸びていた。
「この道を辿っていけば、今、私が居候させてもらっている家につくはずですよ」
相変わらずガチガチに凍りついたままで、殆ど死人のような顔色の青年だが、声だけはえらくしっかりとしている。
「……ねぇ、それより貴方、あんなところで何してたの?」
「いやぁ、家主の方に街へ買い出しを頼まれまして。それで近道をとあの道を通っていったのですが」
リトゥエの問い掛けに、青年は視線だけを──首が動かないらしい──彼女へ向けて答える。
「運悪く彼女達に捕まってしまいまして。いつもならばもう少し南の方にいる筈なんですが、何故か今日に限って北の方に来ていたようで」
そこで少し安心したような吐息。
「いやぁ、買いだしの帰りに捕まらなくてよかった。そうなれば買い出してきた品は皆おじゃんですから。またどやされるところでした」
安心したように笑う。「またどやされる」という事は、普段からあんな風に行き倒れているのだろうか、この青年は。
「……でさ」
そこで少し神妙な顔つきとなり、リトゥエが改まった声を出す。
「貴方、何者?」
唐突な問いかけに、青年は首を捻ろうとして顔を顰め、動きを止める。
「何者……と言われましても、答え辛いものがあるのですが」
「まず、人間じゃないでしょ、貴方」
リトゥエはさも当然といった風に人差し指をぴっと立ててみせる。
「フツー、あんな状態ならどう考えたって死んでるもん。それに貴方、見かけは人だけど、存在概念のカタチが全然人間と違うもの。私達みたいな妖精とも、鬼種とも違う。『ここ』の存在じゃないんでしょ? 貴方の『家主』って人、召喚師か何か?」
「ふむ」
青年は一声唸り、言葉を続ける。
「では、『私は神です』と。そういえば、貴方は信じますか?」
ぶっ、とリトゥエが吹き出した。
「……いきなり大きく出たね、貴方」
「他概念世界や、私が本来在る世界では『悪魔』と呼ばれる事の方が多いのですが、この世界では神──というよりは使役精霊の一つとして位置付けられているようですね」
そこで言葉を区切る。
「アレイスタの支神霊。ご存知ですか?」
「う、うそ!?」
青年の言葉に、リトゥエの顔が露骨に引きつる。
──アレイスタの支神霊、と呼ばれる存在がある。
彼等はこの世界の魔術の基礎ともいえる『印章』と呼ばれる魔術技法を作り上げた大魔術師、アレイスタ・クラウリーが用いたとされる七十二の使役神達だ。
それぞれの神霊は本来人の存在など歯牙にもかけぬ強大な力の持ち主であるが、現世界においてはその存在顕現度が弱く(つまり彼らが本来在る世界と現世界とでは世界固有の概念構成に大きな隔たりがあるという事)、逆に現世界内でも比較的強い存在顕現度を持つ四柱神などから強制力を行使されると、彼らはそれに抗うことは──少なくとも表だっては出来ない。
こういった関係は一つの概念世界での存在顕現度による力差で生まれるものである。なので、支神霊達の存在顕現度が強く、四柱神の存在顕現度が弱い概念世界では、当然ながらこの上下関係は完全に逆転する事になる。
アレイスタはこの法則を利用して、現世界側に漏れだしてる支神霊達の存在を擬似的に顕在化させ、四柱神などの名を借りて彼らを使役し、己のイーサ同調力を上回る強力な魔術を操ったという。
一般には『ソルモニアル』と呼ばれるこの術式は非常に難易度が高く、後世にもわずかにしか伝わっていない。
「正確にはもう違うのですが、一応、アレイスタ支神霊72柱の一柱──そのカケラ、とでも申しましょうか」
青年の言葉に、リトゥエが呆れきった表情を浮かべる。
「……神様が行き倒れってのもまた何ともアレねぇ。で、その『カケラ』とか、その辺の事情はどうなってるの? 神様って割には、こう、存在概念が弱いというか、固まってないっていうか」
リトゥエの言葉に、青年は困ったような表情で固まる。
「んー、あまり言いたくは無いのですが、そんなに聞きたいですか?」
「すっごく言いたくない、って事なら無理には聞かないけど、教えてくれた方が嬉しいといえば嬉しいかな。【NAME】もそうだよね?」
言われ、貴方は肩を竦めた。大体、彼女達が何について話しているかもよく判らないのだ。答えようが無い。
「別に構わないといえば構わないのですが……そうですね、取り敢えずあそこに着いてからにしましょう」
青年がリトゥエから視線を外し、正面を見る。その視線の先を追うと、雪に彩られた白色の屋根を持つ木製の家屋が、木々の隙間からちらりと見えた。
・
その木造の建物は、小屋、というには若干大きすぎる代物だった。高さはそれ程ではないが、縦横はそれぞれ十五メートル程あるだろう。
家屋の周囲には割り積み上げられた薪や除雪用の器具。窓に填め込まれている硝子は、都市の家々でもそう使われることは無い貴重品だ。
「エトエ、いま帰りました。扉の方、開けてくださると幸いなのですが」
青年が戸口に向かって声を掛けると、屋内から「はい、はい、はーい」と扉の方に誰かが駆け寄ってくる気配。
そして、ばん、と勢い良く扉を開いて出てきたのは、幾重にも服を重ねた独特の衣装──リカステ等の寒冷地で良く見られる類の民族衣装だ──を着込んだ、どこかしら子供めいた雰囲気を持つ金髪の女性だった。
身体の造形自体は完全に大人のそれであるのに、何故子供じみた印象を見る者に与えるのかは、恐らく満面の笑みを浮かべたその屈託の無い表情にあるのだろう。
「お帰りなさ──い?」
だが、【NAME】の肩で半分凍りついている青年の姿を見て、その表情が瞬きする間もなく180度反転する。
「ちょ──オーベン、オーベン! しっかりして!!」
「あ、あ、あ、ゆら、ゆらさないで」
一瞬にして今にも泣きそうな顔になった女性が、青年を掴んでがくがくと揺らす。その仕草に合わせて青年の首筋が嫌な音を立てる。
「ああーん、また真っ青になっちゃってるぅ!! もぉこの人は、何回行き倒れたら気が済むんですかぁ!!」
そのまま【NAME】から引っ手繰るように青年を抱え込むと、家の中へと飛び込み──唐突に急停止。足踏みしつつこちらに振り向き、
「あ、えと、どちら様かは存じませんが、わざわざこんな所にまで運んできてくださって有難うございます! 取り敢えず、あたし、この人元に戻してきますから、家の中の、えと、あっち。あっちの方に座っててください!」
視線だけで「あっち」とやらを示すと、そのまま家の奥へと駆けて行った。
「何だか……忙しない人だね」
少々呆気に取られた表情でリトゥエが呟く。全く、その通りだった。
貴方は戸口から屋内へと入り、彼女の示した「あっち」とやらを覗く。そこには様々な装飾品──といっても到底売り物にはなりそうにない手製のものだ──や小さな鉢に咲く花々などに埋もれるように、木製のテーブルと幾つかの椅子がある。部屋の隅には暖炉らしきものが設けられており、そこからは薪が弾ける独特の音が断続的に漏れている。
あの青年ほどでは無いにしても、身体が冷え切っているという事ではこちらも同じだ。遠慮なく暖炉の火にあたらせて貰うことにする。
「だ、か、らぁ! あの道は通っちゃ駄目だっていったでしょーっ!!」
「す、すいません、すいません!」
と、家の奥から何やら怒鳴り声などが聞こえてきたが、下手に首を突っ込まないほうが良いだろう。
・
「いやはや、助かりました」
「全く、いっくら言っても懲りないんだから……」
数分後。すっかり元の状態に戻った──たった数分であの状態からどうやって復活したのかは謎だが──らしき青年が、家の奥へと続く小さな廊下から、【NAME】達の居る部屋の方へと顔を出す。手にはリトゥエを含めた人数分のカップが乗った盆。カップの中からは白い湯気が立ち上っている。青年の背後からは疲れ切った表情を浮かべた女性が顔を出す。
「あの、わざわざ有難うございます。この人、本当に、何回も何回もあの辺りには近づいちゃ駄目だって言ってるのに」
彼女はこちらの姿に気づくと、べちんべちんと青年──彼女はオーベンと呼んでいたか──の背中を叩きながら【NAME】に礼を言う。
青年がカップを全員に手渡し、リトゥエの分をテーブルに置く。女性は窓際の長椅子、青年は少し離れた壁に軽く寄りかかるように立つ。
「それで、えと、自己紹介がまだでしたね。あたし、エト。エト・ミュルエって言います。エトエって呼んでもらえると嬉しいです。それで、あの人はオーベンさん。数ヶ月か前に、近くの氷原で行き倒れているの見つけて、行くところが無いからってここで色々力仕事とか手伝ってもらってるの。……それで、えと、貴方がたのお名前は?」
手すりに掛けてあった毛布を膝上にかけて、にこにこと問うてくる。
ここでだんまりを決め込んでも意味は無い。貴方は素直に名前を答えた。
「【NAME】さんですか。綺麗な響きのいい名前ですね」
そこで軽く首を捻る。
「それで、そちらの妖精さんは?」
「ふぇっ!?」
暖炉の前でぬくぬくと幸せそうに火にあたっていたリトゥエが、びくりと肩を揺すらせる。
「あ、あれぇ? 私、隠匿結界張ってなかったっけ?」
リトゥエは首を傾げつつひらりと空中へと浮かび上がると、テーブルに一つ置かれたカップの近くに着地して「リトゥエっていうの」と短く名を告げる。
「リトゥエさん、か。地母の分け身の妖精さんが、人と一緒にこんな場所まで来るのってなんだか珍しいですね」
そういってくすくすと笑うエトエに、リトゥエは気味悪そうな視線を向ける。
「……なんでそこまで判るの、貴方」
「ふふ、秘密です」
全く答えになっていない言葉を返すと、エトエは改めて【NAME】の方へと向き直る。
「それで、【NAME】さん達はどういったご用件でこちらの方までいらっしゃったんですか?」
問われ、この『凍える大地』の南部で発生している大吹雪の原因とも言われる巨人を狩りに来たことを話す。
「ああ、無駄ですよ」
と、話を聞いていたオーベンが途中で口を挟む。
「無駄って……どういうことよ」
リトゥエが言うと、オーベンは軽く人差し指を立ててくるりと回してみせる。
「んー。あの巨人が吹雪を起こしている、というのは正解ですが、彼等を倒したところで吹雪は収まりませんよ。あれはこの土地に根付いている凍えた概念が、開いた『洞』を使って他概念世界などから呼び出している存在ですから。倒しても倒しても、その度に巨人はこの世界に呼び出されます。堂々巡りです」
くるくると指を回しつつ説明するオーベン。あの動きは循環を示しているのか。
「でも、それなら巨人っていう存在をこの世界から崩滅させれば、この土地の概念にもちょっとくらい影響出ない?」
「それはそうなのですが、この土地自身が化身として巨人を作り出しているわけではありませんから。巨人を倒したところで、その土地の概念の表層を削っているに過ぎません。恐らくは殆ど影響はでないでしょう」
「なるほどね……」
うーん、と黙り込んでしまうリトゥエ。どうやら、話を聞く限りでは巨人を倒したところで『凍える大地』の吹雪が収まる事はないらしい。
要するに、今回は無駄足を踏んでしまったと、そういう事か。
・
「えーっと、と、取り敢えずほら、冷えてしまう前にお茶飲んで、ね?」
何やら場が暗くなってきたことを悟ったのか、エトエが取り繕うように明るい声を出す。声に釣られて、軽くカップに口をつけると、濃厚な味わいが口内に広がった。
「あ、そうだ」
ひょいとカップから身を起こした──彼女の場合、カップを持ち上げる訳にも行かないので──リトゥエが、オーベンの方へと顔を向ける。
「貴方、ほら。約束したでしょ、家に着いたら『カケラ』の事について話すって」
言われ、オーベンはカップを口にくわえたまま。ぽん、と器用に手を叩いてみせる。
「ほーれひた」
「御下品──って、『カケラ』って何の話ですか?」
顔を顰めて呻くエトエ。
「いや、どうせならエトエも一緒に聞いてもらったほうが早いと思ってね。彼女にも、まだ話していなかったし」
「?」
「私の身の上話。貴方には何と言いましたっけ?」
問われ、エトエは軽く両目を閉じ、思い出すような仕草を数秒。
「確か……記憶喪失。それを全面的に信じてるっていっちゃうと嘘になっちゃいますけどね。名前も覚えてないというから勝手にオーベンってつけちゃいましたけど、それで良かったの?」
「ええ、私は貴方のつけてくれたこの名前、気に入っていますからね」
くすくすと笑う。
「え、ちょっと待って。貴方ってエトエに呼び出されたんじゃないの?」
リトゥエの問いにオーベンは左右に首を振る。
「いえ、違います。先程彼女が言った通り、私は行き倒れていたところを彼女に拾われただけなのですよ。……こう、どう言えばよろしいのでしょうね」
そこで青年は考え込むように首を捻る。
「貴方がたも『虹色の夜』はご存知ですよね。エトエも、大丈夫?」
「ええ、知ってます。その翌日あたりから、ここ一帯の気候が突然変わってしまったの、覚えてるもの」
「あの夜を境に、この世界は酷く不安定な状態になってしまったんですよ。
リトゥエ。貴方がた──ニルフィエに連なる者達はどの程度、『現出』についての情報をつかんでいますか?」
その問いかけに、リトゥエは小さく唸る。
「あまり部外者に言うことじゃないんだけど、貴方、色々知ってそうだし、まいっか。【NAME】にも話しておいた方が良さそうだし」
ふわりと空中に浮かび上がると、室内に居る全員を見下ろし、リトゥエは口を開く。
「つまるところ。『現出』とは、過去にこの現世界に存在していた、人間達の芯種である『芯なる者』達。彼等が遊戯として作り上げ、放置した架空の擬似世界──私達ニルフィエは位相領域って呼んでるけど──、言ってみれば『玩具の箱庭』を構成していた要素が、何らかの原因でこの現世界に接触し、干渉してる。その結果が今、この五王朝内で起こっている『現出』の正体。どう、あってる?」
リトゥエの問いに、オーベンは頷く。
「流石ですね、多少は事実と食い違っていますが、ほぼ正解です。もう、地母種達はそこまで探り当ててますか」
「理屈はね。でも、何故そうなったかっていう原因も、『現出』を止める手立てもまだ判ってないの。元々私達と芯なる者は敵対──とまではいかなくても、お互いいけ好かない相手と思ってて、殆ど交流が無かったから。それに理屈だけ判っても、それを止める方法が判らなければ意味がない」
お手上げ、といった調子で肩を竦めるリトゥエ。
「まぁ、そうでしょうね」
オーベンは軽く頷くと、話を続ける。
「どうもこの世界には、その位相の世界と現世界とを結びつけている頚木となるようなモノがどこかに穿たれているようなのです。それを基点として、現出を発生させる範囲を決定し、その範囲内にある現実世界の構成要素と、架空世界の構成要素を強引に入れ替えている。これが、この五王朝内でのみ『現出』が発生しているという理由です。
それで、ですね。ここからが重要なのですが──」
青年は軽く咳払いを挟む。
「この領域によって形成されている力場は、あくまで位相領域に存在する要素を現世界に顕在化させるためだけに作用するものでなく、他概念世界や、『奈落』──つまり、概念世界と概念世界との狭間にある混沌の領域に住む驚異的な存在までをも、まとめてこの現世界に顕在化させる力を持っていたのですよ」
「──えと、それじゃ、オーベンは……?」
「私はその時、運悪くこの世界に呼ばれていたので。お陰で力場の影響をまともに受けて、私は完全にこちらの世界に顕在化してしまいました。本来存在する概念世界に在る私と、現世界に呼ばれていた私とを繋ぐ線のようなものが、こう、切り離されてしまったというわけです。
本来の私の名はマルコシアス。万魔殿に居を構える侯爵にして、三十の魔軍を統べる力強き翼狼……なのですが」
溜息混じりに、己の身体を見下ろす。
「人の形をとっている時に影響を受けましてね。現在ではこの通り。完全にこの形で固定されてしまいまして。マルコシアスであってマルコシアスでない。その半端なカケラであるオーベンとしてここに居候してるわけなんですよ。まだ本調子に戻ってないという事もありますが、力も殆ど使えなくなってしまいましたし。下手に生身がある分、やりづらくて仕方ない」
苦笑し、そこで話は終り、といった調子でオーベンはもう湯気も立たなくなったカップを軽く傾ける。エトエは深く得心いったように数度頷き、リトゥエの方も「なるほどね」といった調子で息を吐く。
どうも、何を言っているのかさっぱり判らなかったのは自分だけのようだった。
「……ねぇ、オーベン。ちょっと聞きたいんだけど」
と、じっと腕を組んで考え込んでいたリトゥエが声をあげる。
「さっき、頚木がどうとかって言ってたよね」
「ええ」
「それって、どんなものか……判ってる、よね?」
恐る恐るといった調子のリトゥエの言葉に、オーベンは軽く視線をどこかへ走らせ、またリトゥエを見据え、言う。
「貴方も、気づいてはいるようですね」
「はっきり誰かの口から聞きたいのよ。答えて」
「……判っているなら、わざわざ言う必要も無いで──」
がっ、と。
オーベンが言い終える前に、猛烈な速度で部屋を移動したリトゥエが青年の襟首を掴み、
「言いなさいよっ!!」
叫ぶ。が、青年はまったく動じず、彼女を真っ直ぐに見据えて言葉を返す。
「それは、貴方が伝えなければならない事ではないですか? 私よりも、貴方が」
「──っ」
青年の声に、リトゥエががくりと肩を落とし、項垂れる。ゆっくりと床に降り立ちへたり込む彼女を、長椅子からいつの間にか立ち上がっていたエトエが優しく抱え上げた。
「【NAME】さんに、リトゥエさん。今日はもうお疲れでしょう? 寝床を用意しますから、今日はここでお休みになっていって」
そろそろ、窓辺から差し込む日差しは夕暮れ時のそれになっている。ここは、彼女の申し出に甘えさせてもらうのが得策だろう。
・
「それじゃ、【NAME】さん、お元気で」
翌日。エトエとオーベンに見送られ、小屋を後にする。軽く手を上げて彼等に返事を返す【NAME】に対し、リトゥエは拗ねたように両足を抱えて無言。その仕草に、エトエとオーベンが苦笑する。
「あと、これを。助けていただいたお礼です」
オーベンが湾曲した刀身を持つ小さな小刀を手渡してくれる。
「リトゥエさん。誰も、貴方を責めはしませんよ。貴方に、一欠片の勇気を」
贄の聖女 小さな訪問者
──小さな訪問者──
噂の巨人を倒す事に成功し、吹雪も収まった。今なら然したる苦も無く、この凍えた氷原を脱する事ができるだろう。
──と、安易に考えていたのだが。
「ねぇ、【NAME】」
貴方の胸の上、着込んだ防寒具の襟元からひょいと顔だけだしたリトゥエが、視線は空へと向けたまま、気難しげな顔で貴方の名を呼んだ。
リトゥエが何を言いたいのかは判っている。恐らく彼女と同じような表情を浮かべているであろう顔を下へと向けると、
「なんかさ。天気がまた悪くなってきてない?」
「…………」
返事はせぬまま、貴方は彼女の視線を追うように顔を上げて、空を見る。
上空は濃い雲の幕にすっぽりと覆われて、今にも白の礫が零れ落ちそうな空模様。氷の巨人を倒した時には晴れ間すらも見えるような天気だったというのに、あれから一時間と経たずにこの状況である。
以前、この凍える大地を訪れた際に出会った人物が言っていた言葉が思い出される。曰く、巨人が周辺地域に吹雪を巻き起こしているのは確かだが、それを倒したところで、この土地の存在概念自体に根づいた凍えた力が完全に払拭される訳ではないと。倒して、それによって天候が回復したとしても、それはあくまで一時的、局地的なものにしか過ぎないと。
はぁー、とがっくり肩を落とし、地面に重い息を吐く。
言われ、その時は一応納得してはいたものの。こうして実際に、あの巨人を倒した処で殆ど意味が無かったという状況を目の当たりにしてしまうと、流石にげんなりとした気分になってしまうのは避けられなかった。
「……うーん。気持ちは判るけど、取り敢えず過ぎた事は気にしないのがいいんじゃないかなぁ」
リトゥエは苦笑しつつそんな事を言うが、猛吹雪の中あそこまで辿り着き、そして巨人を倒すという手間を思い出せば気分が萎むのも致し方ないのではないか。
「言いたいことは判るけど、ほら。とぼとぼ歩いてたら、帰り道も猛吹雪のなかを進むことに……ていうか、降って来た」
彼女の言葉にのろのろと顔を上げると、確かにぽつぽつと曇天模様の空から白い塊が揺れながら降りてきている。更には、
「それに、なんか風も──」
降って来る雪が、ゆらゆらと大きく揺れている。その動きに合わせるかのように貴方の前髪が揺れて、頬を凍えた気配が撫でていく。その感触に、酷く嫌な予感が貴方の背筋を撫でる。
「ねぇ、【NAME】。これって、アレだよね?」
似たような事を感じたのか。酷く嫌そうな顔で抽象的に訊ねてくるリトゥエに、貴方は無言のまま頷きを返す。
──これは、明らかに吹雪く気配だ。
それも激しく。今直ぐにも。
「【NAME】、【NAME】! 荒れてくる前に急ご! これはのんびりしていると本格的にヤバくなるかも!」
行きの道程からして吹雪の中を突き進むような行程だったというのに、帰りの道すらそれではげんなりする処の話ではない。本格的な吹雪になる前に、この凍える大地を脱しなければ。
「ほら、いっそげ! いっそげ! いっそ──って痛ぁ!? なにすんのー!」
顎の下で騒ぐ妖精を指で弾いて黙らせながら、疲れた身体に鞭打ち歩く速度を上げる。
だが道行を急ぐ貴方を嘲うかのように、つい先刻まではちらちらと降っていただけの雪は既に途切れない勢いで空から注ぎ、吹き抜ける風もどんどんと勢いを増していった。
・
そんな貴方の慎ましい努力も虚しく。
予想通りというべきか、一時間と経たずに辺りは視界の確保すら難しい猛吹雪となり、環境の悪化に貴方の意思に関係なく足取りは鈍る。そして時間はどんどんと過ぎ去って、結局外までの行程の丁度中ほどに至る辺りで、空は日暮れの気配を見せ始めていた。
「やばいよ【NAME】。これで夜になっちゃうといよいよ拙いよ!」
そんなこと言われなくても判っている。日が落ちれば気温は更に下がり、視界も今以上に悪化する。そんな中を歩き回るなど正に自殺行為だ。だが、かといってこの極寒の中を野宿するという展開も出来れば遠慮したい。
「と、とにかく急ご! 頑張って【NAME】!」
等と励まされるままに、貴方は出来うる限界まで速度を上げて氷原を歩いた。
唸る風と、吹きつける雪。
深く沈む足を強引に引き抜き、内の熱を篭めて吐いた息は外の大気に触れると同時に瞬く間に凍る。
視界はいよいよ悪くなり、正直この方向へ進んでいるのが正解なのかどうなのかも良く判っていない。リトゥエの補助が無ければ確実に遭難しているだろう。
「【NAME】、そろそろ氷結の乙女達の住処だよ。気をつけてね」
そんなリトゥエの声に、貴方は半ば飛びかけていた意識を慌てて覚醒させる。
(氷結の乙女の住処?)
「うん。ほら、前に凍える大地に来た時さ、オーベンがこの辺倒れてて、それ助けたじゃない。その時に『このあたりは氷結の乙女達の住処』だって言ってたのを思い出して」
あの時の場所がこの辺りなのか。全く気づかなかったというか、目印になるようなものがないので気づきようがない。リトゥエは恐らく場に漂う概念的な差異を視てそれで区別しているのだろうが。
「…………」
と、そこまで考えて、ある事に気づいた。
「ん?」
足を止めて固まった貴方を、リトゥエがいぶかしむ様に見上げてくる。
「どしたの【NAME】」
いや、オーベンが倒れていた場所がここだというなら、近くにあの金髪の娘が住む家があるのではないかな、と。
「あ」
言われて気づいたのか。リトゥエがぽかんと声をあげた。
「それもそっか、ごめん私呆けてた。そうだよね、傍に──ええと、エトエだっけ。あの人の家があるなら、日が完全に暮れる前にそっちに寄せてもらえば」
取り敢えず今日の安眠だけは確保できる。
「でも、ここからだとエトエの家は住処の反対側になるかな……。突っ切ることになるけど大丈夫?」
大丈夫ではないかもしれないが、吹雪の中を野宿よりはマシである。何とか氷結の乙女達に見つからないようにしながら進むしかない。
ざくざく、と雪を踏み締めつつ真っ直ぐに進む。吹雪の勢いは多少収まったものの気温は更に低下し、顔の皮膚にちくちくと刺すような痛みが走る。氷結の乙女達の住処だけに、この場では雪よりも冷気が強まるようだ。
用心深く氷原を歩き、それらしい気配。例えば強い凍風が吹いてきた方向や、何かの粒が光を反射している奇妙な瞬きが見えた場所は避けるようにして歩く。10分、20分と歩き、幸い乙女達に見つかる事無く半時間経過。「そろそろ住処を脱する辺りかも……」と、リトゥエが安堵の息と共に呟いたその時。
(……?)
視界の片隅。僅かに傾斜し小さな丘のような形になっている場所の頂上部辺りで、今までにない程にきらきらと瞬く光の粒と、半透明の影の大群がひらりひらりと舞っているのが見えた。
「氷結の乙女──しかも天候のせいかな。カタチがちゃんと見える程に現れてる」
ここまで気配だけは感じていたものの、氷結の乙女の姿を目で確認したのは今が初めてだった。
白と薄い青の陰影だけで彩られた身体で宙を舞う彼女達は、丘の頂上付近に近づいては離れ、風を起こしてはまた近づきを繰り返しているようだ。
何か、乙女達を惹きつけるようなモノがあそこにあるのかは知らないが、彼女等の気がそっちに集中しているのなら好都合だ。その間に、さっさとこの危険な場所を抜けてしまう事にしよう。
そう考えた貴方は、最後の一息と歩く速度を上げようとして、
「ちょいまって【NAME】! あれ、良く見て!」
言って、リトゥエが下から貴方の顎を掴んでぐいと乙女達の方へと向ける。首がぐきりと音を立てた。
「~~!」
何をするのか、と懐からリトゥエを掴んで引きずり出してお仕置きとばかりに額を指で弾こうとして、
「私じゃなくてあっち! あいつら、人を──子供を襲ってる!」
(子供?)
慌てて丘の方を振り返り、じっと目を凝らす。
「…………」
氷結の乙女達は単にひらひらと舞っている訳ではなく、丘の頂上付近に突撃すると同時に何かの光の殻が一瞬だけ生まれ、乙女達が弾かれているのが判った。彼女等が起こす凍えた風もその光の殻とやらに防がれ阻まれているらしく、その事が更に乙女達の関心を惹いているようだった。
そんな彼女達を今は無視して、更に目を凝らす。見据える先は、光の殻の中心だ。
──瞬く光の粒と、完全には止まぬ雪の嵐。舞い踊る氷の乙女と乙女の間から辛うじて見えた。
光の殻の真中に居たのは、まだ幼い体つきの少年と少女だ。彼等は己の周りを飛び回る乙女達を絶望的な顔で見上げて、抱き合うように雪の中に膝をついている。その彼等の中心でふわふわと浮んでいる丸い玉のようなものが、氷結の乙女達の力を拒む光の殻を作り出しているのだろうが、その輝きはくすみ、不安定な明滅を繰り返している。
「ええい」
年端も行かない子供をまるで囮のように見捨てて、自分達だけ乙女達の住処を脱出するというのは流石に寝覚めが悪くなりそうだ。貴方は小さな舌打ちと共にリトゥエを己の懐に突っ込み直してから武器の柄を取ると、
「ちょ、苦しい苦しい! 乱暴すぎるよ!」
というリトゥエの悲鳴など無視して、丘を目指して全力で駆け出した。
飛ぶ視界の中。乙女の一人が放った冷風の槍が光の殻に突き刺さり、遂にはその壁を突き崩す。浮んでいた光の玉は輝きを完全に失って砕け、子供達が悲鳴を上げた。
(間に合うか!?)
兎に角、気を逸らさなければ。走る速度は落とさず、武器に力を篭めて技法を放つ。本来の射程の外から放たれた技は満足なダメージなど与えられる筈もないが、突然の攻撃とそれによる理粒子のうねり、そして走ってくる貴方の姿に、乙女達の動きが変化する。
射、と風が鳴る。彼女等の唇から紡がれる、触れれば瞬く間に死に至る程の凍えた気。それを半ば勘だけで回避しつつ、彼女等の只中。二人の子供が肩寄せ合って膝をついている場所に無理矢理飛び込んだ。
「……ぅ」
いきなり自分達の前に現れた貴方に、子供の片割れ、少女の方が驚きと疑問に引きつった呻きを漏らす。上げられた顔はかちかちに凍えた涙で濡れて、緊張と疲労によるものか顔色は酷く悪い。
「なん──誰? って、人間!?」
対する少年の方はまだ多少は元気が残っているようだ。少女の身体を護るように抱くと、警戒と困惑が入り混じった声を上げた。
(誰だ、と言われても)
元々赤の他人である。ここで普通に名乗ったところで本当の意味で彼の疑問を解消する事は出来ない。だから端的に告げる。助けにきたのだ、と。
「助け、って何で……。それ以前にこいつらに勝てるの!? 氷結の乙女は身体が無いから、普通の手段じゃ傷一つつけられないのに!」
勝てるかどうかは判らないが、そういう事を考えていてはこういう場での人助けは出来ない。貴方は少年の声を無視して武器を構え直し、周囲を舞い踊る半ば実体を得るほどに力を秘めた乙女達を睨みつける。
乙女の一人が、音も無く手を振る。
ゆるゆると後ろから前へ。その他愛のない仕草に沿って大気が唸り、凍えた概念の力が貴方の身体を串刺しにする勢いで迫る。
しかし、手の動きを見ていたならば風の流れを読むのは容易い。ご、と独特の音を立てて走る風を、一歩大きく横へとズレる事で回避。更に避けた勢いで近くに居る乙女に一撃を加えようと技法を練り上げて、
「きゃああああ!」
聴こえた少女の悲鳴に、その動きを止めて振り返る。
映ったのは、凍えた両手を今にも子供達へと伸ばそうとする、別の氷の乙女の姿だ。
いつのまに近づいていたのか。貴方は強引に方向転換すると、子供と乙女の間に滑り込むように身を割り込ませる。
「────」
氷結の乙女の手が、貴方の身体に触れた。
瞬間、その手先から伝わってくる異質な感触。自身の色、氷結の概念に固められた己の色に、触れたものを染めようとする浸食の力だ。防寒具等易々と突き抜ける程の単一化された冷気が身をなぞり、痺れるような感覚が走るが、ここで怯めばそのまま全身が蝕まれ、死した氷像が生まれる事になるだろう。
「っぁあああ!」
気合の声と共に、練り上げていた技法を眼の前の半透明の影に叩きつけ、吹き飛ばした。
(これは拙いな……)
二人の子供を護りつつ、この数の乙女を相手にする。課せられた二つの難題に貴方は一度歯噛みし、だがすぐさま打開策を思いついた。
そこから貴方が取った行動は二つ。
まず懐に空いた手を突っ込み、中に居る者を引っ張り出す。
「ちょ、いきなり何!?」
そして唐突に外に出されて目を白黒させている彼女に、一つの指示を出した。
内容は簡単な物だ。自分が乙女達と戦う間、この二人を護れという極単純かつ真っ当なモノ。
リトゥエは素早く貴方と周囲の乙女達、そして二人の子供へと視線を走らせてから、
「この状況ならそれしかないとは思うけど……私の力じゃ護りきれるかどうか自信ないよ? それでも良い?」
他に手がないのだから仕方がない。
返事の変わりに、掴んでいたリトゥエをそのまま直ぐ傍にいた二人の方へとぽいと投げた。
「うわわわ──」
「ふわ」
飛んできた妖精に、少女が反射的な動きで手を差し出す。
「ぅぶ! ……って、ぃたたたぁ」
「ご、ごめんなさいです」
べちゃ、と少女の掌に顔面から突っ伏して、顔を擦りつつ起き上がるリトゥエに、少女が怯えた声で謝った。
「へ? あいや、気にしないで気にしないで。大丈夫」
自分の発言に少女が罪悪感を覚えたのかと、リトゥエは慌てて顔を抑えていた手をなんでもないとばかりにぶんぶん振ると、
「悪いのは【NAME】だから。っていうかホント何すんのもー!」
がー、と毛を逆立てて怒る。
その血の昇り具合なら、氷結の乙女の一人や二人は平気だろう。貴方はそう笑っていうと、後は任せたとばかりに彼女から視線を切る。
「……ええいもう、仕方ないな。ちょっと貴方達、一歩も動いちゃダメだからね。今から私が超小規模の結界を作るから」
「わ、判った」
「…………」
「大丈夫。兎に角規模を小さくして、その分概念的に区切る力を限界まで強くするから、少々一杯来ても平気。安心して」
そんな声を背に、貴方は武器を構え直して乙女達の出方を伺う。これで二つの問題の内の一つ、子供達を護りながら戦うという部分は、多少ではあるが解消された。後は、自分が氷結の乙女達を何とかできれば解決なのだが──。
「【NAME】!」
と、そこへ背後から声が飛ぶ。
「兎に角、逃げる隙を見つけて! ただ倒してるだけじゃ、いつかどうにもならなくなるから!」
(倒しているだけじゃ、駄目?)
一体どういう意味なのか。思わず振り返りそうになって、しかし辺りを囲う乙女達の気配に攻撃の色を感じ、その衝動を押さえ込む。
──凍えた風がうねりを見せた。
悠長に会話をしている間はもう無いようだ。次の瞬間放たれるであろう氷風の流れと、その隙に乗じて如何にして彼女等に攻撃を加えるか。疑問には蓋をして、意識を集中。思考を戦闘に特化する。
貴方の放った技法が半透明の娘達の中心で炸裂し、彼女等の身体を概念的に砕いて空に散らす。倒した数は五。これで最初に居た乙女達の約半分を倒した事になる──筈なのだが。
「な、何なんだよこいつら! やられてもやられても全然減らないなんてずるい!」
幅1メートルも無い小さな円柱型の結界。淡い輝きを放つそれに護られながら貴方の戦いを見守っていた少年が、何かに抗議するように声を上げた。
──そうなのだ。
最初は十人程の乙女達がこの場に居て、今の攻撃で五人目を倒した。なのに、今貴方達を囲んでいる氷の乙女達の数は残り五つまで減ったどころか、寧ろ十人以上に増えているようにも見える。
(どうなっている……?)
溜まる苛立ちと疲れに、舌打ちしつつ忙しなく辺りを見渡す貴方に、背後からリトゥエの鋭い声が届く。
「【NAME】、ここは彼女達のテリトリーって事忘れないで! アレだけの数が集まってるとなると、場の概念が冷の気に偏りすぎて捻じ曲がり始めてるかも。もしそうなってたら、元々歪みから生まれる彼女達はほぼ無限の存在よ。倒しても倒してもまた新しい乙女達がやってくる!」
──つまり、倒すだけ無駄という事か?
「そう! だから、何とかここから逃げ出せる隙を作って!」
隙といっても、どうやって作ればいいのか。迫る乙女達の腕を懸命に捌きつつ考えるが、良い案が浮ばない。
「取り敢えず、びっくりさせたり動きが止まってくれたらいいの。ええと、例えば──」
「……あの。お父さんがときどき使ってる、あつい石みたいなの、とかかな……?」
「へ?」
「ミロウ、それじゃ判らないよ。ええと、父さんが鍛冶の材料に使う素材で、炎の概念が残った結晶っていうのがあるんだ。こいつら、氷の化け物だから、熱い物にはびっくりすんじゃってことだろ?」
「そ、そう。それですお兄ちゃん。……えと、あってるですか?」
「うん。要は氷の概念で偏った連中だから、その反属性の性質を持つ品を放り投げでもしてやればいけるかも。もし貴方達が言ってるその品があるなら、私がちょっと干渉してあげるだけで──という訳で【NAME】! そんな感じなんだけど、何か無い!?」
などと、なにやらごちゃごちゃと後ろで聴こえてくるが、貴方にはそれに言葉を返す余裕もない。取り敢えず、戦闘の邪魔になるからと地面に投げ捨ててあった背嚢を、タイミングを見て彼女等の方へと蹴り飛ばした。
「ナイス! よし二人とも、探すから手伝いなさい!」
そんな声と共に、リトゥエと子供二人がわさわさと背嚢に首を突っ込んでいるのが視界の片隅に映る。
出来れば、こちらが力尽きる前に何か見つけて欲しい処だが──。
・
乙女の一人を打ち崩してから大きく跳躍。何とか距離を取って態勢を整えた貴方の傍に、
「あったよ! これでいける!」
いつの間にかやってきたリトゥエは、手に抱えた石を振り上げて叫ぶ。
彼女が手に持つその石は、
(炎の残石か)
理石とも呼ばれる、属性概念を大きく秘めた石である。だが、しかしこんな石ころが一つあった処でどうにかなるものなのか?
貴方の疑問に、リトゥエはぽんと小さな胸を叩く。
「任せて。これって上手い事やると面白い風に変化するの。【NAME】、今から結界解くからあの子達の傍へ──あと、私が合図したらあっちの方角へ走って」
その言葉に頷く間もなく、子供達を包んでいた結界が消える。慌てて貴方が彼等に駆け寄ろうとした瞬間、背後で濃い熱を感じた。
(……何だ?)
生まれた熱は、熱いというよりは暑いという類のもの。氷点下にも悠々届く程の気温が、なにやらぐんぐんと温度を上げていく。それにあわせて、辺りを舞っていた氷結の乙女達が甲高い、ぎぎききと軋むような音を立てて身を捩じらせている。
ふらふらと空中を漂い、今にも消えそうな乙女達を唖然と見上げていた貴方の肩上に、リトゥエがひらりと着地する。
「ふふん。ほら上手く行った。ね、ね。褒めてよ【NAME】」
一体何をしたのか。その問いに、リトゥエはにやりと微笑み、
「残石の中に秘められた火の概念を、場に開放するんじゃなくて、ここの土地概念に直接流し込んでやったの。所詮残石一つだから範囲も狭いし、効果時間も短いけど、一時的であれ今この場所は極普通か、少し暖かいくらいの気候を持った土地に矯正されてるの。だから冷気や雪みたいな属性が存在概念に大きく関わってる氷結の乙女にとって、今この場所は正に地獄の筈──といっても、二分も持たないから、今のうちに逃げよ!」
言われるまでもない。貴方は子供達のそばへと駆け寄ると、二人の身体を強引に抱え上げる。
「ひゃ!?」
「う、うわ! 何を」
何をも何も無い。リトゥエが使った策の効果が二分と無いというならぐずぐずしている暇は無い。子供の歩幅ではロクに距離も稼げないだろう。となれば自分が抱えて走るしかない。
貴方は技法を併用しつつ二人の身体の位置を軽くずらして整えると、出来うる限り速度を上げてこの場から脱出を図る。
目指す先は、エト・ミュルエと名乗ったあの娘の家。既に日は暮れて、かすかな赤色の残滓が空の彼方に見えるだけ。この先は闇の中の逃走劇となるが、朧な記憶によれば大した障害も無かった筈だし、リトゥエの助けもある。
(何とかなる)
楽観極まりない結論だが、悲観したところでどうなるものでもない。そんな事を考えながら、貴方はもう熱を失って元の極寒の地に戻り始めている氷原を、全速力で駆け抜けた。
・
「はぁ、はぁ──」
乱れた息を整える間も無い。荒い呼吸を続けながら、貴方は既にとっぷりと暮れた夜の凍土を走り続ける。
既にあれから小半時。
氷結の乙女達の住処である筈の氷原は突破し、辺りは針葉樹が並ぶ森の景色に変化している。以前訪れた時と同じよう、森の中に入ると同時に吹き荒れていた風雪は途端に弱まり、まるでここだけは別世界であるかのような静かな佇まいをを見せている。
だというのに、その森を走る貴方の背後には、未だ十を超える数の氷結の乙女達が、逃げるその背に手を伸ばそうと迫っていた。
「つーかなんでこんなとこまで追ってくるの! ちょっと執念深すぎるんじゃない!?」
先程リトゥエが使った策が余程彼女等の逆鱗に触れたのか、それとも何か別の要因でもあるのか。理由はさっぱり判らないが、判ったところで今自分たちが追われている事には変わりなく、かつ解決法への手掛かりにもなりそうにない。考えても無駄だと、貴方は兎に角逃げ切る事に意識を集中しようとして、
「────」
前方に、三体。
どうやらこちらの逃走経路を読んでいたのか。貴方の進む道を塞ぐように、氷結の乙女達がふわふわと漂っている。
本来ならばあの程度の数なら牽制の技法でも放ち、その隙に上手くすり抜ける事も出来るのだが、今はあいにく両手がそれなりの重量を持った荷物で塞がっており、そんな器用な真似ができるような状況でもない。
迷った貴方は、反射的に傍を飛ぶリトゥエを見る。彼女もその視線と込められた意味に気づいたのか、
「う、うーん。取り敢えずやっているけど……」
ひらりと揺れるように瞬く羽を一度震わせて速度を上げると、前方を塞ぐ乙女達に向けて両手を掲げる。リトゥエの身体と羽から光の粒子が噴き出して、そして次の瞬間。三体の乙女達の中央に凄まじい光の炸裂が起きた。
だが、その光が生まれたのはほんの一瞬で、しかも氷の乙女達は光の炸裂など無かったかのように何の損傷もなくその場に存在していた。
身体に纏わりついた輝きを払ってから、リトゥエが貴方の肩上に着地する。
「御免」
その顔には申し訳無さそうな表情が浮んでいた。
「やっぱこの身体じゃ無理みたい。目暗ましがせいぜいで、しかもあいつ等目なんか飾りだから全然意味が無い……」
そうする間にも前方に浮ぶ乙女達との距離は縮まって、もう立ち止まるしかない。しかし背後からも十を超える数の乙女達が押し寄せてきており、足を止めてしまえば直ぐに追い着かれてしまうだろう。既に氷結の乙女達の縄張りではないここでなら、彼女達が次々と数を増やしてくる事もないだろうが、先程の戦闘と、そしてここまでの逃走劇のお陰で殆ど力を使い果たしている。今戦えばロクに身動きも出来ずに瞬く間に凍らされる事だろう。
(ここまで、か?)
そう、貴方が諦めかけた瞬間。
『"聖女"の元へ来たれ、天啓の"聖騎剣"よ。
その剣の前に立つ者は皆、神の御力を知る』
「伏せなさい──斬り捨てます!」
凛と張った声が場を貫き、貴方は反射的にその場に身を投げ出した。
まず身体が雪に埋もれる感触が来て、続いて己の背中の僅か上辺りを、凄まじい力の奔流が駆け抜けていく感覚。一体何が、と顔を上げた時には既にその奔流は消え去り、それと同時に。
「氷結の乙女達が、消えた?」
前と後ろを交互に見て、呆然と声を上げるリトゥエ。
そう。つい先刻までこちらを追いかけてきていた、10を超える数の氷結の乙女達の姿が、今はもう何処にも無かった。
狐につままれたような気分できょろきょろと辺りを見廻していた貴方だったが、
「お久しぶりですね、【NAME】さん」
──声を掛けられたお陰で、漸く彼女に焦点が合った。
先程前方を塞いでいた氷結の乙女達が居た場所の更に向こう側。森の中に作られた細い畦道の終端に、木造の小屋がある。その貴方の目的地であった小屋と、今貴方が倒れている場所の丁度中間となる位置に、一人の女性が立っている。正式な名は、確かエト・ミュルエと言っただろうか。
小屋から漏れ出している淡い照明を御光のように背負い、その小さな身を覆う長い金髪が、後ろから射す光と彼女の境界を曖昧にして、一種幻想的ともいえる雰囲気を醸し出している。だが、手に持っている──いや、脇に挟み込んで抱えているというべきか。全長2メートルは優に超える凄まじい大きさの長剣が、その雰囲気をぶち壊しにしていた。
「食事の準備をしていた時に、ちらと外で害意に偏った概念存在の気配を感じて出てきたのですが、間に合って良かった。大事はありませんか?」
先刻からずっと戦いっぱなしだったのだ。怪我が無いとは口が裂けてもいえないが、しかし命に関わるような傷は無いのは確か。貴方はそう答えようとして、
「「魔女お姉ちゃん!」」
自分の両脇から上がった突然の叫びに口を噤む。
「ちょ、いきなり何!?」
大声に驚いたのか貴方の肩上でぴょんと僅かに跳ねたリトゥエの事など気にもせず。貴方の両腕に捉まれていた二人がもぞもぞと動いて飛び出すと、少年は全力で、少女の方は足を引き摺りながらだが駆けて行き、そのままの勢いでぼん、とエトエの胸に飛び込んだ。
「……え?」
自分の身体に抱きついてきた二人の子供を見下ろして、エトエは数度眼を瞬かせる。
「──クオウ? それにミロウも……貴方達、どうしてこんな処に?」
「魔女お姉ちゃん、魔女お姉ちゃん! ねぇ、助けてよ! 大変なんだ!」
顔をあげ、切羽詰まった声を出すのは彼女の胸にしがみついている少年だ。少女の方はエトエの身体に顔を埋めるように強く抱きついて、唸るような泣き声を零している。
「大変って、何かあったんですか? それにあなた達だけでこんな時間にここまで来るなんて──お父さんや、お母さんは?」
「だから、父さんが──くしゅん!!」
「あらら。少し落ち着いてクオウ。大丈夫、あたしは逃げないから。ミロウも泣き止んで、ね? ……って、ミロウ?」
自分に抱きついたまま声も上げなくなったミロウの顔をエトエは訝しげに覗き込み、そして彼女が単に眠ってしまった事を確認して小さく苦笑。苦労しつつ少女の身体を何とか抱きかかえると、
「一先ずお家に入りましょう。このままじゃ風邪引いちゃいますから。──【NAME】さんも、遠慮なさらず。歓迎します」
言って、彼女は眼を細く柔らかい笑みを作り、漸く疲れた身体に鞭打ち身を起こした貴方を見る。
その申し出は有り難いと、素直にそう思う。正直、ここまでの連戦と無理を押しての逃亡劇、その疲労により既に立ち上がる事すらも億劫な状況だったのだ。
貴方が僅かに頭を下げると、エトエは一際笑みを強くして頷き、そして貴方の背を向け歩き出す。
ミロウという名の少女を胸に抱え、大変大変と支離滅裂な言葉を話す少年クオウに一つ一つ頷きで返しながら、黄金色の髪がゆらゆらと歩いていく。
そんな彼女の道先には、窓から淡い照明の輝きを零す木造の小屋。
家の扉は既に開いており、その傍には主達の帰還を待っている長身の男の姿があった。
「はい、どうぞ。疲労回復と強壮の力を持つ特製の根を入れましたから、これを飲めばかなり楽になると思います」
この小屋に暮らすもう一人の人物。長身の青年オーベンから木製の器を渡され、貴方は礼と共にそれを飲み干す。適度な温かさと、少しの苦味が喉を過ぎて胃に下り、疲れ果てていた身の奥を癒すように染み渡る。その感触に、貴方は思わずほぅと深く息を吐いた。
部屋に居るのは貴方とリトゥエ、オーベンにエトエ。そしてクオウという名の少年だ。ミロウという少女の方は別室の寝台で今は休んでいるらしい。エトエが言うには身体に問題は無く、ただ疲労で眠っているだけだという。
ぱち、と暖炉の中で薪が弾ける音がする。場は静かで、オーベンが煎れた茶を皆に配るために動く音がよく響く。暖炉の火と部屋の各所に置かれた洋灯の光がちらちらと部屋に居る者達の顔を照らすが、その誰も表情に笑みはなく、神妙な顔を浮かべている。
その理由は、先程からこの場で交されている会話の内容故だ。
既に貴方がこの家へと訪れた理由はエトエ達に話し、宿泊の許可は取ってある。貴方と子供達、クオウとミロウと出会ってからここまでやってきた経緯も同様。
──問題はもう一組。クオウとミロウ達が、たった二人きりで夜も近い凍土の中をエトエの家までやってきた理由だった。
「さて、失礼しました。クオウ、お話の続き、お願いできますか?」
茶を配り終えたオーベンが、自身の杯を片手に、床に広げられた毛の敷物の上に腰を降ろす。その促しに頷くと、ソファに座るクオウが話を再開した。
・
クオウとミロウの二人は、凍える大地にある数少ない村。小人種達の集落に暮らす子供である。
小人種は成人しても人間の半分と少し程度の身長しかなく、長寿ではないが老い自体は非常に緩やかと言われる種族だが、この二人はまだ外見通りの年齢であるという。
そんなまだ幼い彼が、妹であるミロウと共に氷結の乙女達の住処を突き切るという、最短ではあるものの同時にとても危険なルートを抜けてエトエの家にやってきた理由はこうだ。
彼等の父親は村一番の鍛冶細工師であり、特に属性概念の付与に関わる細工を専門としていた。
その父親が、最近小人種達の村に訪れたエトエが、「決して足を踏み入れないように」と警告したとある谷に、鍛冶細工のための品を採りに降りてしまったのだという。
父親は無事に帰ってきたものの、以後酷く体調を崩してしまった。村の医者は風邪の一種だと言うのだが、それにしては直りが悪い。だからこうして「魔女お姉ちゃん」に助けを求めに来たらしい。
「にしても、『魔女お姉ちゃん』ってずいぶんな仇名ねぇ」
「あはは……。一応名前はちゃんと名乗ったんですけれど、どうもあそこの村だとそっちの名前の通りが悪くて……」
リトゥエの呆れたような呟きに、エトエは苦笑しつつ頬を掻いて誤魔化す。
そして表情を改めるとソファに座るクオウの前に膝をつき、俯き加減になっている少年の顔を覗き込むようにして話し掛ける。
「それにしても、無茶をしたものですね。貴方達二人だけでこの現出地形を抜けてくるなんて。お母さんはどうされたの? 村の人たちは?」
「母さんは父さんの看病で疲れてるし、無理させられないよ。……それに、村の人達は」
そこでクオウは言葉を区切ると、顔を僅かに歪め、口を浅く開いては閉じを繰り返して。
「あの『魔女』には近づくなって、爺ちゃん達に言われてるからって」
「……っ」
すぅ、と。
エトエが目を僅かに細めると、薄く息を吐いた。
クオウはそんな彼女の様子にも気づかず、半ば泣き出すような声音でただ言葉を続ける。
「みんな言うんだ。今度の事だって、父さんが魔女お姉ちゃんの言いつけ破って、細工に使う結晶が欲しいからってあの谷に入るからこうなったのに、『あの気味の悪い人間の女のせいだ』って。魔女が結晶を独り占めするために、『谷』に呪いを掛けたんだって!」
そこまで一気に喋ると、クオウは漸く面を起こし、そして自分の目の前に居る黄金色の髪の娘に縋るように声を上げる。
「ね、魔女姉ちゃん。違うよね? 魔女姉ちゃんはそんなことしてないよね?」
少年の必死の声。
それに対し、エトエは少し間を置いて、大きく。自分を信じてくれている少年の意気に答えるようにしっかりと頷く。
「──ええ。していません。貴方のお父さんを苦しめるような事は決して」
「でも、俺やミロウがどれだけ言っても、爺ちゃん連中は信じてくれないんだ」
「……それは恐らく、私のせいでしょうね」
そこで言葉を挟んだのは、床に座したまま決まりの悪そうな表情を浮かべるオーベンである。
「どゆこと? 貴方、何かしたの?」
貴方の疑問をそのままリトゥエが声に出すと、オーベンはいよいよ表情をゆがめて、
「エトエがあそこの村と関わりを持った直接の要因が私でして。その時のいざこざで、あそこの村の方々との第一印象が最悪だったんですよ」
「どう思われようと、あたしは構いません。あちらの御爺様方には、また後日誤解を解きに伺います。──それよりも、クオウ。これはとても大事な事なんだけど……お父さんが谷から帰ってきたのは何日前なの?」
「ええと、一週間前、かな」
「体調を崩したのは何時?」
「谷から戻って、四日後」
その答えに、エトエは口元に軽く握った手の親指部を宛てて、じっと考え込む。
「……発症が遅い。直接視られた訳じゃないのね。それなら、助かるかもしれない」
「魔女姉ちゃん?」
小さく呟かれた声に、クオウが少し不安げな声を出す。そんな少年を安心させるように、エトエはにこりと表情を変えた。
「安心してください、クオウ。お父さんは大丈夫。今からお薬の材料を取ってくるから、ここでミロウちゃんと、あと妖精さんと一緒に待ってて。出来る?」
「う、うん!」
「ぅえ、私も?」
エトエの力強い笑みに押されるように、クオウは大きく頷く。
対して突然話を振られたリトゥエは、貴方の肩上で己の顔を指さして素っ頓狂な声を上げたが、
「お願いします、あたしもオーベンさんも、これから家を離れないといけないし」
「んー。まぁやる事も無いし、いいけどさ」
リトゥエは不承不承といった様子で髪に指を絡める。エトエはクオウに一度微笑んで頭を撫でて、リトゥエには両眼を閉じて静かに頭を下げた。
そして勢いをつけて立ち上がると、まるで彼女から声を掛けられるのを待つように、いつの間にかエトエの傍に控えていた青年に声を掛ける。
「オーベンさん。今、元の姿に戻れますか」
「……それは難しい、かな」
「なら、移動速度だけでも上げられます?」
「何処かへ走れと?」
「テュパンの南、ターナス平原の近くに、とても星が良く視える場所があります。そこで一番初めに出会った女の子に」
彼女はテーブルに寄ると、備え置かれていた厚い紙片にさらさらと文字を書くと、それをオーベンに手渡す。
「これを渡して、その結果を問わず半日以内に戻ってきてください」
「行き来だけなら今まで蓄えていた力を解放すれば可能だけれど、その曖昧な目標指定では、時間内に確実に戻れるかどうか保障しかね──」
「戻ってきて」
「──了解しました、我が主殿」
おどけた調子でそう言って、長身の男は外套も手にせず玄関の扉に手をかける。開き、吹雪が荒ぶ夜の中へと身を躍らせた彼は、風に押されて扉が閉じる前に、その姿を闇の中へと溶かしていった。
「あとは、あたし達か」
エトエは大きく息を吸って吐くと、ぴしりと自身の両頬を張る。そして引き締まった顔を貴方へと向けると、有無を言わせぬ調子で告げた。
「【NAME】さん、手伝ってください。──今から谷に降りて、幻獣ヤムサと戦います」
普通に考えれば、風雪が荒ぶ真夜中の氷原を歩き廻るなど、文字通り自殺行為である。
そんな中を先導するように歩くのは、全身を水色の奇妙な衣服に身を包んだ黄金色の髪の娘。吹き荒れる風に長い髪を乱しながら、しかし彼女は黙々と。全く緩まぬ危なげの無い足取りで、踏み込めば膝上まで埋まろうかという雪の中を歩いていく。彼女の身体から零れる淡い光の輝きが後に続く貴方の身体をも僅かに包み、不思議と周りの風雪が僅かではあるものの脇へと避けていく。しかし、それでも厳しい旅路である事は変わりない。冒険者としての豊富な経験を持ち、悪路での旅にも慣れた貴方でも、その背を追うにはかなりの努力を必要とした。
「【NAME】さん、そろそろ気を引き締めてください。谷に着きます」
この周囲を白と黒に閉ざされ、足場すら定かではない中での強行軍の一体何処に気を緩めるような余裕があったのか。そういう文句すら言う気力も無い。エトエが右の脇に挟んだ巨大な長剣の刀身が放つ光を頼りに、貴方は無言で彼女の背を追った。
・
彼女が言う『谷』とは、今日の昼間に氷の巨人を倒した後で危うく転落しかけた大溝の事であるらしい。とはいえ、辿り着いた場所は貴方が氷の巨人と戦った所ではなく、普通に歩いて侵入できる程度の傾斜しかない谷の始端であるが。
谷の幅は10メートル程。溝故に外で荒ぶ強風からは護られているものの、降り積もった雪が醸し出す一種病的なまでの白さ、谷底全体に漂う異質な気配に、貴方は歩を止めて息を呑む。一見静かで、安全なように見える。だが、何かが違う。何かがズレている。ここに足を踏み入れるのは危険だと、冒険者としての貴方の勘が告げている。
「けれど、ここに住むあの子達の存在概念を少しでも貰わないと、お薬が作れない。だから、止まれないの」
立ち止まった貴方を励ますように、隣に立つ彼女の髪の色が周囲の闇を払う。
一歩、前へと踏み込んだ彼女は、空いた左手で己の奇妙な服の懐を探り、一つの丸い物体を取り出すと、貴方へと差し出す。
光源が彼女の右手に携えられた大長剣しかない関係上、彼女の身体が陰となり、左手の中にあるものが良く見えない。取り敢えず手を差し出して受け取り、位置を移して光を得、その物体を確かめる。
それは小さな硬貨だった。中央に描かれたのは不思議な形の樹と、それから伸びる一本の剣の装飾。
(これが……?)
一体何なのか。貴方が顔を上げてエトエに問うと、彼女は手にした長剣で貴方の手の中にある硬貨をゆっくりと叩く。すると、硬貨に淡い輝きが灯り、それが貴方の身体をも包んでいく。同時に、辺りに漂う異質な気配と自分との間に境が生まれて、身体の硬直が解ける。
「そのメダルに『祝福』を与えました。貴方が私の傍に居る間は、ある種の加護を得る事ができます。これで、貴方の身がこの谷の概念に冒される事は在りません」
短く、必要な説明だけを告げて、彼女は谷の中へと入っていく。貴方はメダルを握り締めたまま慌てて彼女の背を追った。
・
谷の中で兎に角目についたのが、壁や地面の隙間から無秩序に生えた、独特の薄い靄を被った白色透明の結晶体だ。
「氷霧芯結晶体。それが、クオウのお父さんが欲しがっていたものです。高い同調能力と冷気の概念を秘めた結晶で、希少価値がとても高く、鍛冶等の素材として扱えば際立った力を発すると聞いています」
それ程のものなのか。
エトエの説明に興味を惹かれ、何となくその一つに触れてみようとするが、エトエの手がその動きを止める。
「止めておいた方がいいです。ちゃんと備えをして、専用の技法を使わないと、力を損なう事無く採掘することはできないの。力が漏れて、単なる結晶体になるだけ」
貴方が手を引いたのを確認してから、エトエは剣を明かりに谷を進む。谷は静かで、生き物の気配は微塵も無い。上空で吹雪く風の音がたまに聞こえるだけだ。
さく、さく、と。
エトエの足跡が、白雪の中に残る。
「──そういえばこの事、話してましたか?」
ふと、思いついたかのようにエトエが言う。一体何の事かと貴方が訊ねれば、彼女は、
「今から戦う相手の事です」
と、振り返る事無く淡々と話し出す。
「属性概念と高同調能力を持つ結晶が生まれる場所では、ある幻獣種が姿を現す事が多いの。その幻獣は芯結晶で身体を覆う八本腕の獣で、名はヤムサ。彼が誕生すれば、その場所では芯結晶が更に生まれやすくなります。けれど」
谷底は僅かに傾斜を持っており、徐々に徐々に、下へ下へと下っていく。
「それは、その幻獣が自分の暮らす土地の概念を浸食して、含まれる属性概念のバランスをより強く崩そうとするから。だから、その幻獣の住む場所に人が足を踏み入れれば」
ふと気づくと、進むごとに僅かにではあるが谷の幅が広がっていっているようだ。
「幻獣の力に冒されて、身を創るための概念が暴走してしまう。炎の芯結晶が生まれるような場所なら、高熱を発してやがて燃え尽きて、氷の芯結晶が生まれるような場所なら、徐々に体温が低下して最後には氷像となって砕けてしまう。クオウのお父さんは、後者の類ですね」
幅は10から15メートルへと広がり、更にその先には大きく円状に広がった空間があった。
「その病を癒すには。影響を与えた幻獣の概念を秘めたモノと、その力を逆転させるための術式と薬草がいくつか。術式と薬草はオーベンさんにお願いしましたから、あとは」
谷底に拓いた広場の中心には、一匹の獣が居た。
硬質の、青い透明な外皮に覆われた八本腕の獣。
「芯結晶が生まれる場所に現れる幻獣──ヤムサを倒し、場所を問わずその身の欠片を得る事が出来れば、クオウのお父さんは救われます」
エトエが己の身長を優に超える大長剣の柄に両手を添えて、身構える。細い娘の身体から濃い光の粒が零れて、黄金の髪が独りでに渦を巻くように踊り出す。
己が住処に現れた闖入者の姿を確認したのか。身を折り寝そべっていたヤムサが立ち上がり、ゆっくりとこちらに向かってくる。八本の腕が広がり、幻獣の周囲に漂う空気が一段と凍えていく。
「謝る言葉など持ちません。あたし達の心と命を護る為に──ヤムサ。貴方の身体、貰い受けます」
battle
谷奥の幻獣

「…………」
光の礫が辺りを照らし、振り切られた長剣の切先に沿って雪が音も無く舞い上がる。
膝を折るヤムサ。蠢く八本の腕の一つ目掛けて打ち込まれた貴方の技法は、エトエの剣により傷ついた部分を的確に打ち、斬り飛ばした。
幻獣の叫びが谷を木霊す。腕を失い戦意を喪失したヤムサはこちらに背を向け、谷の奥へと消えていく。その動きは鈍く、追い縋れば止めを刺すのは容易。
反射的に武器を構えてその背を追おうとした貴方の肩を、細い手が押し止める。
「私達の目的は、ヤムサの存在概念を得ること。目的は既に達しています。これ以上は」
しかし、あの小人種の子供の親が病に倒れたのは、あの幻獣のせいではないのか。倒せるときに倒しておかねば、また被害者がでる可能性もある。
そう言う貴方に、エトエは小さく頭を振る。
「芯結晶が生まれる場所である限り、彼等の存在が完全に絶えることはありませんから。それに、ヤムサは自分の縄張りを侵した者にすら全力を振るう事を躊躇うような獣です。そんな子の命までも殺めるのは気が咎めます。ただでさえ、こうして自分達の都合で彼を襲って、腕をもぎ取ったりしているのに、ね」
エトエは溜息と共に地に転がっていたヤムサの腕を抱え上げる。自身の胴回り程もあろうかという巨腕を容易く抱え上げるその姿は正に異様という他無く。クオウの親達が彼女を恐れ、そして『魔女』と呼ぶ理由を垣間見たような気がした。
「【NAME】さん、戻りましょう。クオウが話してくれた発症からの日数を考えると、もう猶予は一日あるかないかなんです。今から急いで戻っても、薬を作る時間を考えれば間に合うかどうか……」
だが自分を恐れて蔑む者をも彼女は助けたいと、そう考えているらしい。
──正直なところ、理解し難い。
一体どういうつもりで、クオウの父親を助けようとしているのか。急ぎ戻る道の途中、そんな事を明け透けも無く訊ねてみると、彼女はこう返した。
「本当は、私が忌むべき者だって、呪いの魔女だって。そういわれる事、私自身は別に構わないんです。慣れてますから。でも、クオウとミロウ。あの子達が私の事を『良い魔女さん』だって思って、魔女お姉ちゃんって言って慕ってくれて。でも、その事を自分の親に言っても信じてもらえない。自分がそうだって信じる事を、親が認めてくれない。それだけが、悲しいって。そう思うんです」
ざくざくと雪を踏み締め、吹雪を物ともせずに歩きながら、彼女は真っ直ぐ前へと見据えたまま言葉を紡ぐ。
「だから、クオウのお父さんは死なせません。そして私も努力します。クオウとミロウの魔女お姉ちゃんが、誰も呪ったりしない、誰も不幸にさせない良い魔女なんだって。その事を認めてもらうまで、ね」
そろそろ夜が明ける。
吹雪も徐々に終わりの気配を見せ始め、空の端がゆっくりと赤く染まり出す。その朱色の向こうに、彼女の家が。彼女を信じて帰りを待つ二人の小人達が待つ家が見えた。
ぎしり、と音を立てて扉を開けば、部屋の隅に置かれたソファに並んで眠る三つの影。クオウとミロウ、そしてリトゥエの姿があり、そしてその直ぐ傍の暖炉前には、
「お帰りなさい、エトエ。それに【NAME】さん。存外時間が掛かったようですね」
既に燻り消えかけていた火を起すべく薪を片手に持ったオーベンの姿があった。彼は家に入ってきた貴方達に気づくと小さく目礼。エトエは彼の姿を認めて一、二度目を瞬かせた。
「あ、オーベンさん? もしかして、もう終わったんですか?」
「ええ。紅目の方から頂いた品はそちらに。一応伝言もいくつか頂いてるけれど、今聞くかな?」
「お婆様のお話は是非伺いたいですけれど、それは一仕事終えてからにします。今から早速作業に入りますから、オーベンさん、手を貸してもらえます?」
オーベンは軽く指を鳴らして薪に火を付けると、暖炉の中に放り込んで立ち上がる。
「勿論。人使いの荒い主に仕えるのは、従者としては幸せな事だね」
「貴方の主になった覚えはないんですけれど……まぁいいです。──っと、えと、【NAME】さん?」
と、漸く雪風から遮られた場所に辿り着き、気が抜けていたところに唐突に名前を呼ばれ、貴方は反射的に背筋を伸ばして顔を上げる。その過剰な反応に名前を呼んだエトエの方が驚いたらしく、彼女は眼を数度瞬かせると、
「ああ、いやその、ええと今から私、薬を作る作業に入りますから、取り敢えず【NAME】さんはここで十分休んでいってください。本当に、その、助かりました。有り難うございます」
言って深々と頭を下げる。しかし正直な話、自分がついていく必要があったのかどうか首を傾げざるを得ないのだが、ここであれこれと言っても仕方が無い。貴方は彼女の感謝を受け入れると、兎に角疲れた身体を空いていたソファに横たえる。
そこで一気に疲れが来た。瞬きの間すらなく落ちていく意識の片隅。閉じる視界の間際を、仲良く並んで眠るリトゥエ達と、氷原を抜ける際にがちがちに固まった巨腕を抱えながらオーベンと共に家の奥へと消えていくエトエの背中が掠めていった。
・
目覚めた時には、既に小屋に残っているのは貴方とリトゥエだけだった。
「薬が出来たから、クオウ達を送っていくついでに届けてくるんだってさ。ホント面倒見が良くて──あと、無用心だよねぇ」
確かに、殆ど面識のない自分達を家に放っておいてさっさと出かけてしまうというのだから、相当なものだ。
貴方は苦笑と共にソファから身を起こすと、いつの間にか掛けられていたらしい毛布を軽くたたんでソファに掛けて、簡単に身支度を整える。氷原での旅や谷での戦いの中で垣間見た、あの娘の人外の域と呼んでも良い力を思い出してしまえば、家の品をちょいとばかり拝借しようなどという気も起こらない。あまり長居するのも悪いし、クオウの親が助かったかどうかはまた今度訪れた時に訊ねるとして、今日はさっさと御暇するとしよう。
家を出た後、鍵はどうしたものかと暫く迷って、諦めて背を向けた。空を見上げれば今朝方までの吹雪の気配はもう無く、熱さを感じさせない太陽は既に中天を過ぎて半ばまで降りてきている。あまりぐずぐずしていると、街に戻る前に日が暮れそうだ。
「あ、そうだ。伝言貰ってたんだ」
歩き出した貴方の肩にいつものようにリトゥエが着地して、ふと思い出したように呟いた。
「ええと、『谷でお渡ししたメダルはもう私の加護を失っていますけれど、メダル自身が持っている力は健在です。それを今回の件のお礼にさせてください』だってさ」
そりゃわざわざご丁寧にどうも。
贄の聖女 氷源の秘境
──氷源の秘境──
「戻りました。何とか、一通り終わりましたよ」
小屋の屋根の雪下ろしを終えたらしいオーベンが、ばさばさと羽織った服に付いた雪を払いながら小屋に入ってくる。
「あ、オーベンさんお疲れ様。はい、暖かい御茶です」
こんな辺境の小屋には少々不似合いな、美しい模様の入った陶磁器をエトエから受け取り、青年は一口。そして浅く息を吐く。
「いや、生き返ります。はは、たかがこの程度で動きが鈍くなるとは、全く完全な肉の身とは不便なものです」
オーベンは己の肩をとんとんと叩いて、ソファに座る貴方に小さく苦笑を見せた。
・
凍える大地に足を踏み入れ、さてどうしようか。そう考えた時にふと思い出したのだ。黄金色の髪の娘と長身の青年の事を。
以前、あの小屋を訪れた時は、丁度同じ時期にやってきていた小人達の件もあり、別れの挨拶も無しと言うそっけない結末となってしまった。
あの小人の兄妹達の親がどうなったのかも気になった貴方は、普段よりも激しい風雪を乗り越えて、あの二人が暮らす小屋へと足を運んだのだ。
・
「【NAME】さんも、身体の方、あったまりました?」
ひょい、と貴方の肩越しに黄金色の髪が掛かる。覗き込んできたエトエに貴方は礼を告げて、手にしていた空の器を手渡す。エトエは笑みでそれを受け取ると、視線を少しずらす。
「リトゥエさんも、どうです?」
「……あー、うん。大分マシになった、かも」
ソファの前に置かれていた小さなテーブルの上で、小さな毛布に包まっていた妖精がもこりと顔を出す。その面はまだ白い。リトゥエはこの小屋までやってくる間に出くわした大吹雪に中てられて、少しばかり調子を崩していた。
「……にしても、凄い雪だよねぇ。私達がこっち来るときもさ、道中大荒れだったもんね」
毛布をしっかりと首元まで被ったまま、リトゥエが視線を窓の外へと向けて疲れた声を出す。
確かに、大変だった。この地域で吹雪に出くわすのはいつもの事だが、今回は何時にも増して酷い吹雪で、視界は雪に塞がれ、歩みは風に押し返され、全く酷い状況だったのだ。下手に『凍える大地』の奥地を目指さず、比較的近場にあるこのエトエの小屋を目指していて良かったと思う。
「どうやら『凍える大地』全域でこんな調子らしいですね。小人種の村でもこの雪と風には難儀していると聞きました」
この家に訪れた時に直ぐ聞いた話だが、前回の件で出会った小人の二人、クオウとミロウの兄妹の親は、何とかエトエの作った薬で事なきを得たらしい。が、それだけやっても、未だ村での彼女等の扱いは酷いままだとか。一体、初遭遇の時にどんなヘマをしたのか気になる処である。
「そーいえばさ。この家の屋根にまでずんどこ雪積もってるって珍しいね?」
エトエが新しく淹れてくれた茶を、器にしがみつく様な姿勢で口に含んでいたリトゥエが、ふと思いついたように言う。
(言われてみれば)
初めて訪れたときも、次に訪れたときも。辺りがどれだけ大吹雪になっていようと、この家と家を包む一帯の森だけはちらちらと雪の粒がかすかに視界を掠める程度で、今日のようにオーベンが器具を担いで辺りをがっさがっさと掻くような場面を見たのは初めてだ。
「んー、そうなんですよねー。ちょっと概念の偏りが危ない処まで来ちゃってるのかも。そろそろ動かないと駄目かなぁ? どう思います、オーベンさん」
「頃合──いや、いつもよりは既に遅い時期かもしれない。やるなら早めに動かないと、後に響くかもしれませんね」
「むむ。なら今日明日中に何とかしちゃいましょうか」
ん、と気合の声と共に両腕をぐっと持ち上げてポーズを取るエトエに、貴方は目を瞬かせる。
何やらやる気になっているようだが、何をするつもりなのだろうか。
「簡単ですよ。この辺りで土地概念の歪みが一番酷い場所まで出向いて、場を整調してしまえばいいんです」
(整、調……?)
貴方は眉間に皺を寄せて唸る。恐らくは偏った氷の概念を抑えるとか、そんな事だろうというのは判るが──しかし、一体どうやって。
「ええと、どう説明したらいいかなぁ? あたしも結構感覚でやってる事だから……」
うにゅう、と困った顔で言い淀むエトエに、漸く濡れた髪と服を調え終えたオーベンが助け舟を出す。
「【NAME】さん。以前、私がした話を覚えていらっしゃいますか? 貴方が氷原の方に巨人を狩りに来ていた時ですが」
はて、とその時の会話を思い出そうと首を傾げる。
確か、あの時は凍土の奥で大吹雪を巻き起こしているという巨人を狩りに来たのだが、それは効果が薄いとオーベンに止められたのだったか。あの巨人は土地概念の偏りから呼び寄せられた存在で、狩っても狩っても復活するとか何とか。
「大筋には間違いありませんね。それでですね、今から彼女がしようとしてる事は、基本的にはあの時【NAME】さんがしようとしてた事と変わりはありません」
「……?」
それで解決するならば、以前のオーベンの言とは矛盾するではないか?
貴方のそんな呟きに、しかし長身の青年は首を振る。
「いえいえ。基本は同じなのですけれど、対象と、規模が異なるのです。実は前に【NAME】さんとエトエが向かった処よりも更に奥に、別の大きな峡谷があるのですが、そこがこの『凍える大地』で一番概念変質が大きな場所なのです。それでですね。この家の周辺にまで影響が出る程に土地概念が偏ってきてるという事は、恐らくその峡谷の方で『概念結晶体』が発生している筈ですから、それをエトエの持つ力で叩いて砕いて調整してしまおうと。これなら、ある程度ですが土地概念に直接干渉ができますので、『現出』前の状態に戻すというのは到底無理ですが……そうですね。初めて【NAME】さんと出会った時くらいの状況くらいにまで戻せる、という事です」
「…………」
んー? と首を傾げる。概念がどうこうという部分に関する知識があまり無いせいか、中盤の彼の説明から、最後の結論までの流れがどうも把握できない。そもそも、『概念結晶体』というのが何なのか。
「あー、それはね」
と、そこで口を挟んできたのが、漸く血色の戻ってきたリトゥエだ。
「概念結晶体ってのは、概念飽和によって現世界に実体を持った根源的概念存在──要するに、私達妖精の原始的な姿というか、もっとプリミティブな状態の形だよ。といっても、ここの土地概念の偏りは『現出』の影響で不自然に歪んだ結果生まれたモノだから、生まれてくる概念結晶は陰性質を持つモノ──中位か上位鬼種の種になるモノである可能性が高いけど」
「…………」
「……えーと、【NAME】? 無理に頭捻らなくても、取り敢えず結果の部分だけ押さえときゃいいと思うよ? 要するに、その峡谷行って、何か胡散臭い塊みたいなのを壊しちゃえば万事解決! って感じで。ね?」
ええい、若干憐れみのこもった目で見るでない、と貴方はひらひら寄ってきたリトゥエを適当に叩く。
エトエはそんな貴方とリトゥエの様子を微笑ましげに眺めていたが、
「じゃ、取り敢えずそんな感じで私達は早速出かけますけれど。【NAME】さんはどうされます?」
「え」
突然の発言に、貴方は思わずリトゥエを苛める手を止めた。
まさか、今から出掛けるというのだろうか? 流石にそれは急な話という他無いが。
「まぁ、大した準備が必要って訳でもありませんから。私達だけでささっと片をつけてきても良いんですけれど、冒険者な【NAME】さんなら『概念結晶体』の討伐は興味あるかなって。結晶体の破片は結構価値があるものと聞いていますから」
──金目のモノ。
覿面に目の色を変えた貴方に、エトエは小さく微笑む。
「一緒に来られるならちょっとお得かもしれませんよ? 勿論、無理強いするつもりはありませんけれど」
勿論、行かせていただきます。
「【NAME】は元気だなぁ」
間髪言わずに答える貴方を、リトゥエは呆れたように見上げて、
「……私は、ちょっと止めとこうかな。ここで留守番してたいんだけど、エトエ、良い?」
「それは、あたしとしても助かります。誰も居ないのは少し無用心ですから」
「ん。じゃ待ってるね」
言って、こくりと茶を飲むリトゥエを、貴方は意外な顔で見下ろす。
てっきり、いつものように付いてくるものだと思っていたが。
「……いや、さ。どうもオーベンの話からすると、そこって土地概念が凄い偏ってる場所なんでしょ? 【NAME】も知ってるかも知んないけど、私ってそういう場所はちょっと苦手なのよ」
そんなリトゥエの言葉に、ふむと納得顔で頷いたのはオーベンだ。
「つまりこうですか。実体持つ肉を従、魂たる概念を主とする貴方達地母の眷属には、強い歪みを持つ概念に終始晒される事は、己の根、存在概念の変質にも繋がる可能性がある、と」
「うん、そんな感じ」
オーベンの呟きにリトゥエは頷いて、少し済まなそうな表情で貴方を見上げる。
「だから付いてけないけど……ごめんね【NAME】?」
いや、別に謝られても困るが。元々居ても居なくてもあんまり変わらないし、普段の戦闘にも手を貸してくれないし。
「ぶぅ」
・
エトエの先導に従い、吹雪く凍土を進む事暫く。
前を行く娘の背が止まり、その仕草に合わせて辺りを柔らかく包む黄金の光が揺れる。何らかの技法の一種なのか、彼女の身体より広がるこの黄金色の光は吹き荒ぶ極寒の風を遮り、お陰でここまでの道中は至極順調だった。
「着きました」
振り返ったエトエが、前方を指差す。
そこは、以前に幻獣退治に向かった谷とはまた別の、もっと大きな峡谷の底だ。
左右に伸びる細道は崖を沿うようにうねうねと斜め上へ伸びている。話によればこの道は崖の中腹を通る棚になっており、崖に穿たれた幾つかの横穴へと通じる唯一の道となっているらしい。開いた横穴の洞窟は、特に氷の概念が溜り易い場所らしく、エトエ達の今までの経験では、その幾つかある洞窟の何処かに、目的の『概念結晶体』が生まれている筈だという。
「問題は、どこの洞窟に『概念結晶体』が在るのかがさっぱり判らないって事なんですけど……」
となると、ここが最初の分岐点。右手、東側の崖道を登っていくか、それとも左手、西側の崖道を登っていくか。間違えればかなりの時間のロスになるが、判断基準が全く無いため殆ど運試しの域だ。
「ですので、あたしに一つ提案が。これだけの人数ですし、二手に分かれません?」
悪い案ではない。エトエの発言に貴方は同意。オーベンも同様の意となる頷きを返す。
(……しかし)
問題は、どう分けるか、か。
そんな貴方の呟きに、エトエは少し驚いたように目を瞬かせ、
「え? そんなの、あたしと、あたし以外の人達の二手で良いんじゃ?」
エトエは自分をぴっと指差しながら、貴方とオーベンを見る。
「…………」
それで良いだろうか? 何だか凄く歪な分け方であるような気がするのだが。
渋い表情で首を傾げた貴方に、エトエは戸惑いの混じった笑みを浮かべる。
「え、でも、多分これが最善だと思いますけど。【NAME】さんはここに来るの初めてでしょうから単独行動って訳には行かないし、オーベンさんは何か身体があまり上手く動かないから戦いは得意じゃないって言ってたでしょ?」
話を向けられたオーベンは、少しばかり視線を外してから、こくりと頷く。
「正確には違うのですが──そうですね、結果的には似たようなものです」
「うん。なら【NAME】さんとオーベンさんに組んでもらうのが一番だと思います。私は一応ここに入った経験はありますし、それにこの辺りにでる亜獣くらいなら」
彼女はぽんぽん、と細い腕を叩いてみせると、
「何十匹襲ってこようとも、一発で薙ぎ払っちゃいますから全然平気です!」
「…………」
そうですか。何十匹来ようと一発ですか。
「じゃ、あたし東側の崖見てきますから、【NAME】さん達は西をお任せしますね。オーベンさん、【NAME】さんの事、宜しくお願いします」
貴方の頬が僅かに引きつっている事にも気づかず、エトエは両手で持った大長剣をよいしょっとばかりに振って肩に担ぎ、てくてくと歩いていってしまった。
「相変わらずマイペースな人だ」
そう呟いたのは貴方の隣に残ったオーベンだ。貴方が視線を上げると、彼は小さく目礼した後。
「では、【NAME】さん。私達も行きましょう。先導は私がします」
言って、凍えた風とちらつく雪の中を西へと歩き出す。貴方ははぐれぬよう、その長身の背を追った。
・
崖に沿って伸びる幅二メートル程の坂道を暫く登っていくと、崖の中腹辺りでその傾斜が無くなり、平坦な棚へと変化する。
「見えました。あれが洞窟です」
オーベンが指差す先。今歩いている道の左手側の壁が一部、ぽっかりと穴を開けている。
「取り敢えず手近な洞窟から調べていく事にしましょう。──と、そうだ」
ふと何かに気づいたようにオーベンは足を止めると、貴方のほうを振り返る。
「一つ注意を。崖に開いた洞窟は、どれも氷の概念の溜り場です。『概念結晶体』が発生する程に歪みが生まれていなくとも、場には極めて濃い単一概念が留まり、うねっています。そしてこれが問題なのですが──この概念の溜りは、一定の域に達すると零れ落ち、破裂します」
「……?」
溜った概念が零れ落ち、破裂する。
その言葉がどういう現象を示すのがどうのも理解できず、貴方は渋い顔で唸る。そんな貴方を、オーベンは少し困ったように見て、
「私としても聞くだけでは理解しづらい話をしているというのは判っているのですが、これが中々適切な言葉が……そうですね。発生する現象だけを話した方が判りやすいかもしれませんね」
ふむ。と彼は自分の発言に納得するように一つ頷き、そしてこんな事を話し始める。
「各洞窟では一定の周期で爆発的な概念の奔流──一種の衝撃波が吹き出します。この衝撃波はかなり強烈なモノで、もし洞窟内でこれに飲まれた場合、恐らく洞窟の入り口まで戻されるどころか、そのまま谷の方まで容易く吹き飛ばされる事でしょう。こうなれば」
貴方は反射的に視線を右手側。谷の方へと向ける。
谷の規模は大きく、崖の中腹付近である現在地から谷の底までの距離は、ざっと見積もっても数十メートル。もし吹き飛ばされ、落ちてしまえば、
(……命はない、と)
「でしょうね。衝撃波の威力は兎に角凄まじいですから、勢い余ってそのまま向こう岸にまでいってしまうかもしれませんが」
などとオーベンは冗談めかして肩を竦めるが、全く笑えない。
兎に角、洞窟を覗く際にはその衝撃波とやらにも注意しろ、という事らしい。
「とはいえ、そう心配する事もありません。概念の飽和による現世界に対する干渉現象──要は今話した洞窟奥で生まれる衝撃波ですが、それに関しては私がある程度事前に察知できますので、ご安心を」
オーベンの言葉に、貴方はふむ、と頷く。
要は彼が警告を出したときだけ、その洞窟に近づかなければ衝撃波に飛ばされる事は無い、と。
「そうなります。では、早速探索を始めましょう。それぞれの洞窟は広くはありませんし、問題が無ければ調査は直ぐに終わる筈です」
その洞窟の最奥まで辿り着いた貴方とオーベンの目の前に現れたのは、渦巻く氷の風を幾重にも纏った、きらきらと輝く蒼白の結晶だった。
「見つけました。あれが概念結晶です」
オーベンが呟き、目を鋭く細める。
「出来ればエトエが見つけて欲しかった処ですが──見つけてしまったのなら仕方がありませんね、私達で何とか破壊しましょう。【NAME】さん、戦いの準備を」
その言葉に、貴方が慌てて武器を構えると同時。氷の渦が大きくその半径を広げ、青色に染まった風が全てを切り裂く氷の刃となって貴方とオーベンに襲い掛かる!
battle
凍る大地の中心

凍てつく風の刃、弾ける氷礫の嵐を強引に突き抜けて、その中心。浮かぶ蒼白の結晶に向けて放った一撃は正に会心。
「お見事」
貴方の技法を受けて結晶が砕けて散るのと、オーベンが小さな笑みと共にそう呟くのはほぼ同時だった。
「では、後は彼女に任せましょうか」
言って、オーベンが洞窟の入り口方向を見る。
「──う」
そこには、
「……一応、気配を感じて全力で走って来たんですけど……もしかして、間に合いませんでした?」
片手に大長剣を担ぎ、少し困り顔のまま頬を掻くエトエの姿があった。
・
エトエが力を振るい、場の概念を整調する様は中々に圧巻だった。
洞窟内に砕けた概念を一度手にした剣に取り込み、剣舞と共に概念を加工。それを洞窟に突き立てて土地に直接流し込む事によって、周辺一帯は愚か、『凍える大地』全体にまで影響を及ぼす程の大干渉。洞窟の外に出たときに、空が雲一つ無い快晴になっていた時は驚いたものだ。
「ふーん。……で、今回の手伝いで手に入れた品ってのがそれ?」
凍える大地から街へと戻る道すがら。今回の冒険についてお留守番だったリトゥエに話していた貴方は、彼女が自分の手の中にあるこぶし大程の青白い結晶を指差しているのを見て、軽く頷く。あの時戦った概念結晶体の欠片の内、エトエの大長剣に取り込まれ損ねたものを、拾って持ち帰って来たのだ。
リトゥエは暫くその塊をじーっと見つめた後、うんうんと頷く。
「私が見た感じだと、まだかなり強い概念的な力が中に残留してるっぽいし、お宝としては結構いいものかな? 多分、力を解放すれば辺りを強い氷の力で満たす事が出来ると思う」
どうやらリトゥエの目から見ても結構良い品であるらしい。
「といっても、あんまし長持ちはしなさそうだけどね。──にしても」
そこでリトゥエは言葉を切ると、腕を組んでうーんと考え込むように首を捻った。
「私も小屋の中で、ここ一帯の土地概念から凍結の因子がどんどん小さくなってくのを実際に感じたけどさ。普通、こんな事って自然と大きく繋がりを持ってる妖精種でも難しいんだけど……あのエトエって子、ホント何者なの?」
それはこっちが聞きたい。概念結晶を破壊し、土地を整調した後。彼女は『凍える大地』内にある亜人の集落にその事を伝えに行くと言い出し、そのまま別れてしまった。本当なら少し話をしたかったのだが。
貴方がそう零すと、リトゥエは少しだけ間を置いてから、何故かこう呟いた。
「まぁでも……もしかしたらそれで良かったかもしれないね」
一体何が良かったというのか。貴方が目を瞬かせてリトゥエを見ると、彼女は視線は貴方に合わせぬまま、迷い迷いといった調子で言葉を続ける。
「何となくだけど、あんまり深入りしない方が良い気がする。あのオーベンの素性もそうだけど、エトエの持ってるあの力は正直異常だと思う。技法を扱うのが上手いとか、身体を鍛えてるとか、そういうのとはちょっと次元が違う雰囲気があるもん」
それはオーベンも言っていたか。確か、『芯属』の概念がどうとか、直系がどうとかと。
曖昧に呟いた貴方の言葉に、リトゥエは真剣な顔で頷く。
「ああ、ありそうかも。先祖に『芯属』の祝福か身を宿した者が居たとか、もしくは直接の血を引いてるとか。少なくとも生粋の人じゃないと思う。『地母種』の眷属なら私には直ぐ判るし、人の姿を維持してるとなると──『芯なる者』か『古賢属』の一氏か。『象神種』や『翆獣種』って可能性もあるけど」
そこまで一気に喋って、リトゥエは大きく一つ息を吐く。
「何にせよ、色々と事情がある子だと思う。もし【NAME】があの子に深く関わるつもりなら、それなりの覚悟を持って付き合ってあげた方が良いと思うよ?」
──とはいえ、次の機会などあるのかどうか。
などと話している間に凍土は終わりを告げて、遠く地平の向こうに街の影が映る。
「お、見えてきたー。ほら、暗くなる前に、急ぎましょ?」
急かすリトゥエに視線だけで了解と答え、貴方は背嚢を軽く背負い直すと歩みの速度を少しばかり上げた。