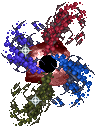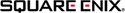礎の王格 箱外の彼女
──箱外の彼女──
場所は支都ルアムザの大通り。時刻は早朝を過ぎて、太陽が徐々に位置を上方へと移し始めた頃。朝の諸事を終えた都の人々が、本格的に今日の活動を開始し、道は結構な人通りである。そんな中、貴方は前方四、五歩ほど先行して歩く数人の背中に付いていく形で、彼等が割る人波の間をゆっくりと歩いていた。
前を行くのは二人とおまけ。獣神の神官であり宝精召師でもある少女リヴィエラと、その従者であるシモンズ、そして妖精のリトゥエである。ルアムザの都を出る事にした貴方は、丁度同じ頃合いでテュパンの常駐宿へと戻るというリヴィエラ達と、暫し歩みを共にする事となったのだ。
その距離は、同宿していた都内の宿屋から都の外までの間と短い。五王朝の要、グローエスの首都たるルアムザの都は五王朝でも指折りの巨大都市であるが、それでも端から端までを横断するのに30分。貴方が寝泊まりしていた宿から都の外縁までとなれば、10分も掛からない。連れ立って歩く事に意味を見出せる距離ではないが、しかしわざわざ別れる程の理由も無い。そんな距離であり、半ば惰性に近い同行である。
以前までは、リトゥエとマヒトやシモンズとの関係はとても良好とは言い難いものだったが、現在はテュパンでの話し合いを経て、双方悪感情は残りつつも強い嫌悪という程では無くなっており、マヒト等が貴方に向ける感情も同様に軟化していた。故に“わざわざ別れる程の理由”ともなり得ず、今も前方では、リヴィエラを中央に挟み、左方空中に隠匿結界を敷いたリトゥエ、右方にシモンズが付いて、何やら話をしている。
主に口を開いているのは左右の二人で、時折漏れ聞こえる内容は、テュパンとルアムザでの食糧事情の話であるようだ。テュパンは大港を持つ沿岸都市故、魚介類や異国文化の食材、料理が豊富だとか、ルアムザではグローエス北部の大農耕地で採れた穀物や、南方オルス国境の山脈付近にある果樹園産の果実が美味しいだとか。あれが美味しい、これが不味い。そんな話をリトゥエとシモンズが交互にしているようだが、間に挟まれたリヴィエラがそれに反応している様子は無い。うつむきがちに、肩を落として歩く後ろ姿からは、内に籠もって何か考え込んでいるようにも見える。左右のリトゥエとシモンズが先刻から活発に喋っているのも、そんなリヴィエラに気を回しての事なのだろう。だが、後ろから見ている限りでは、残念ながら彼等の努力は実を結んではいないようだ。
とはいえ、先のアサーンにて自分達が経験した一連の出来事。それを考えれば、リヴィエラが未だふさぎ込んでいるのも無理からぬ事だ。貴方にしても、あの最後に見た惨烈たる光景は、未だ脳裏に焼き付いたままで、こうして僅かに思い出すだけで気が沈む。実際に見ていないリトゥエは兎も角、共に見た筈のシモンズがああして全くの普段通りに振る舞っているのには、感心すらしてしまう程だ。
「…………」
だからこそ。
今朝方、出立準備中であったリヴィエラ達と顔を合わせた際、真剣極まる表情を浮かべた彼女に告げられた申し出は、貴方からすれば困惑すらもたらす程に意外なものだった。
曰く。
貴方の、協力をさせて欲しい、と。
・
半ば、彼女の協力を得るのは諦めていたのだ。
最初の想定では、今回のアサーンでの“異象”処理はこちらの言の証明となるものをリヴィエラ達に見せると同時に、軽く彼女の危機感や義務感、使命感等を煽り、自分の仕事に協力して貰う足がかりを作ろうと、その程度のつもりだった。
しかし、油断とまでは言わないが、これまで通りの“異象”対応の仕事のつもりで足を運んだ貴方を待っていたのは、自分と同じ“同化者”と、術技を操る侍従、そして彼等の手による“擬象”との戦いだった。
結果は完敗とも言えるものだった。こちらは早々に戦闘不能となり、リヴィエラ達は命からがら逃げ出して、敗北の尻ぬぐいは軍の部隊に丸投げする形になってしまった。その後も、軍の者達が対処出来ていたならまだ救いがあったのだが、軍部隊すら彼等に全滅させられてしまう。
正に手も足も出ない、そんな結末だったのだ。
自分達では手に負えない、逃げるしかない――そんな風にしか思えない存在が敵だと判って、その上でどうして協力をする気になるだろうか? 軽く危機感を煽る程度のつもりが、これでは逆効果にしかならないだろう。
せめて、自分があの“擬象”を討伐するなり互角に戦うなりが出来ていれば、「リヴィエラが協力してくれるならあいつ等もどうにか出来る」といった風な大言も吐けたのだが、真っ先にやられてしまった事実を前にしては戯言でしかない。
更に言えば、これでリヴィエラがアサーンでの件に対して然程ショックを受けていなかった、という事であったならば、まだ遣り様はあった。短い付き合いでも、何処か脳天気な雰囲気を持っているのは感じ取れた程だ。今回も都合良くその脳天気さが発揮されていればと、僅かに期待はしていたのだが、リヴィエラが見せた反応は真逆と言えるものだった。
あの惨劇の後、アサーンでの合同調査は団長副長が揃って死亡した為、これ以上の続行は危険として、捜索隊を率いた大柄の騎士と衛生班の長であった女性が指揮者となり、早々に撤収した。団長であるベリーナの部隊を最後に見たマヒト達は、騎士からかなり厳しく問い詰められていたようだが、マヒトもシモンズも詳しい事情を一切話す事は無く、マヒトは怒るように、シモンズは下手に出るようにしながら、最小の情報だけをただただ繰り返し答えていた。
その遣り取りから、マヒトとシモンズが普段見せる態度は、差し迫った場面では己の真意を隠すための仮面ともなるのだと気づいたが、リヴィエラの方は当然ながらそのような器用さなど持ち合わせてはいなかったようで、顔面蒼白のまま、“光”が形になって襲いかかってきた等と、あの騎士には到底理解できない言を撒き散らしていた。
騎士からすれば苛立たしい事この上ない受け答えであっただろうが、しかしそんな彼が大した罵倒も無くリヴィエラ達を早々解放する程に彼女の顔色は悪く、下方を向きつつ不安定に揺れる瞳、時折嘔吐くように背中を震わせる様は、彼女が受けた精神的衝撃の程を報せてくれた。
宿に戻った後もリヴィエラは暫く部屋から出てこず、その後も表情は晴れないままで、マヒトやシモンズがあれこれと気を回している様子を時折見掛けていた。貴方も顔を合わせる度に声を掛けてみてはいたのだが、反応は鈍く、こちらを見ては何か考え込むように黙ってしまうのが常だった。
テュパンでの話し合い以後とはまた別種の硬い雰囲気に、貴方とクーリアはリヴィエラの説得を諦めて、別の方針の模索や、代替の協力者を探す事も考えていたのだ。
そんな中で、突然のリヴィエラからの申し出である。
一体、どういう思考の末に、その結論に至ったのか。驚きの中、それを問おうとした貴方であったが、しかし結局は飲み込んだ。相手がこちらの希望に添う結論を出してくれたのだから、下手に藪を突く必要も無いだろうと。そう考えたのだ。何より、自分を見るリヴィエラの顔から、彼女の考えが全く読めなかった、というのもあった。普段の彼女や、これまでの彼女が見せていた表情とは違う、初めて見る類の真剣さ。意気込む、思い詰める。そんな言葉が浮かんだが、しかしそれは正しくはあれど、芯を捉えていない。そんなしっくりとこない感触があった。だからこそ、彼女の真意を問い詰めるのに躊躇いが生じた。時間を置いて、あの場面での自分の心理を分析すれば、そういう事になるのだろうか。
「どうしたよ、【NAME】」
そんな事を考えながら、難しい顔で先行く三つの姿を追いかけていた貴方は、横からの声にそちらを振り向く。
何時の間にか、リヴィエラ達三人組の残る一人、マヒトが貴方の隣にやってきていた。所用があると宿を出る時に一度別れた筈が、もう追いついてきたらしい。
用事とやらは無事終わったのだろうか。そう訊ねた貴方に、マヒトは息を抜くように軽く笑い、
「嘘に決まってんだろ。ちーとばかし、お前とサシで話しときたいと思ってな」
マヒトが前方へ視線を向ける。釣られてそちらを見れば、前行く三人の内、シモンズが一瞬こちらを振り返って目配せしてきた。どうやら、シモンズがああしてリヴィエラに話し続けているのは、単にふさぎ込み気味な彼女を気遣ってというだけではなかったらしい。
納得した貴方は、改めて隣の男に意識を向ける。リヴィエラの付き人であるこの男が、こちらと一対一で話したい事となると、そう多くはない。最初に思いつくのは、宿で受けたリヴィエラからの申し出についての話だ。あの件についてマヒトがどう考えているのかは、貴方も多少興味があった。また、リヴィエラの連れである彼ならば、リヴィエラの予想外の変心についても相談を受けている可能性が高い。彼女が今、何を考えているのか。本人を刺激せずに聞き出せるならば、それに越したことは無い。
「はは。お前の方もやっぱ戸惑ってるみてーだな」
そんな貴方の思考は、わざわざ言葉にせずともマヒトに伝わったらしい。僅かに身を折って、こちらの顔を覗き込むようにしてマヒトは笑い、
「ま、色々戸惑ってんのはこっちも同じではあるんだが……それでも、今回の御嬢の決定にゃあ、表立って反対するつもりはねーんだ」
そうなのか、と貴方は目を瞬かせる。マヒト達からすると、こちらの事情に強引に巻き込まれたような形だ。乗り気で無いのが当然と思ったのだが。
思ったままを口にすると、
「乗り気じゃねーよ」
はん、と鼻を鳴らされた。
「特に、俺が最初に思ってたよりもどうやら事がヤベーっぽい点が問題だな。軽いお遊びや寄り道じゃ済みそうにねぇ。本音を言えば、御嬢を止めたい気は今も結構ある」
では何故。
素直に問えば、マヒトは機嫌が悪そうに眉をしかめる。
「……お前、結構サクサク突っ込んでくるよな。話進めやすくて有り難いっちゃ有り難いが。で、ええと、何故か、か。それ答える前に、先にこっちの話、いいか? その方が、多分判り易いしよ。それに、御嬢にあんまり聞かれたくない話でもあるから、ささっと終わらしてぇ」
リヴィエラに聞かれるとまずい、という言葉には驚いた。
互いに秘密など無いような、相応の信頼関係を築いている三人組だと思っていたのだが。
「秘密と信頼は別だろ。御嬢はどうかはしらねーが、俺とシモンズは秘密ありありだよ。んで、話しときたいってのはそれを含めた俺等の素性だ。取り敢えず、要点だけ簡潔に行くぞ――」
と、そう前置いてのマヒトの話は、本当に端的な事実だけを語ったものだった。
獣神の神官としてグローエスにやってきたリヴィエラが、実は隣国ラカルジャの“円卓十氏”に連なる人間である事。
彼女が持つ“眼”と、それに関係する幾多の出来事の伝聞。最終的に、リヴィエラはベルモルトという神を崇める教団に入った事。
リヴィエラのグローエスへの旅は、ラカルジャ内で氏族内外にて揉め事が起きる前兆をかぎ取った親族筋が、教団に働きかけた事によって決まった、厄介払いかつ緊急避難的な処置である事。
マヒトとシモンズは、リヴィエラの氏族内から指令を受けて派遣された、氏族の息女専属の護衛である事。
そしてリヴィエラ本人は、マヒト達の事情や氏族の思惑など一切知らされておらず、自分が家を離れてしっかり独り立ち出来ていると考えている事。
淡々と、マヒトはそれらの話を手短に語っていった。
「――とまぁ、こちらの事情としちゃこんなとこか。……なんか判りづらかったところとか、感想とか、あるかよ?」
感想。
鸚鵡返しにそう呟いて、貴方は僅かに思考し、そして思いついた事をそのまま口にした。
――そんな事情があるのなら、尚更こっちの厄介事に首を突っ込むのはまずくないだろうか?
なにせつい先日、アサーンの都で正に生死の境目に立つような体験をさせてしまったばかりだ。途中、無数にあった選択肢の内、その幾つかを選び間違っていたならば、自分は勿論の事、共に居たリヴィエラやマヒト達も、あの軍部隊の者達のような――人の死に様とも思えぬ無残極まる姿を晒していた可能性があったのだ。
マヒトの言う“円卓十氏に連なる者”とやらが、どれ程の地位を示すものなのか。貴方にははっきりとしたところまでは良く判らなかったが、しかし少なくとも一族内で揉め事が起きたり、護衛が二人も専属でつけられたりする程の、高貴かつ重要な身分なのは理解出来る。
ならば、だ。
そんな人物を、ひとつ間違うだけであっさりと命が失われるような事柄に関わらせるのは――、
「まずいな。当たり前だがよ」
あっさりとそう返されて、貴方は逆に面食らう。
まずいなら、なぜマヒトはリヴィエラの決定に反対しないのか。こちらにとっては至極有り難い事ではあるが、全くもって理解が出来ない。
そんな貴方の内心は、マヒトの方も察しているらしい。どう説明したものかな、とマヒトはばりばりと後頭部を掻きつつ、
「……端的に言っちまえば、これも、良い機会だから、ってとこかね。本当ならもうちょっとヌルい話が良かったんだが、御嬢の目が持つ力に、冗談抜きで絡んでくるようなネタとなると、早々あるもんでもねーしな」
マヒトは、とんとん、とこめかみを叩いてみせる。
リヴィエラの眼。
それはつまり、リヴィエラが持っているアエルを“光”として捉える力の事か。
「そ。あのお嬢ちゃん、ずっとその力のせいで悩んでたみてーだからな。ラカルジャに居た頃は、もうあの力は完全に意味不明な扱い受けてたらしいし。色々と期待を掛けられたり、騙されたり、疑われたり、あったんだとよ。で、それから逃げるためか教団に入って、宝精とも縁遠いグローエスにでまでやってきて。昔のことも、ようやく気に掛ける事もなくなってきたかってところに――」
一拍、マヒトが言葉を切る。貴方は横から鋭い視線が飛んでくるのを感じた。
「――お前が現れたんだ。今までずっと意味が判らなかったものに意味を与えて、しかも自分もその“光”とやらを感じ取れるらしいお前が、な」
ここ最近は、『礎の世』からの干渉のせいかグローエスの方でも“光”を認識する事が増えていて、リヴィエラの気もそちらへ向きがちになっていたらしい。
そんな彼女のところに、正に折良く、貴方がやってきた。
貴方が自分の目的のために話した事柄は、リヴィエラにとっても至極重要な、信じられるか信じられないかで、彼女の根の部分が大きく変わるような代物で。
「御嬢がお前の事を気に掛けるのも、わかんだろ? これでお前が、御嬢のその辺の心をくすぐって騙して利用しようってつもりだったならぶっ殺してるところだが、これまでの流れを見るに、そんな風でもねーみてーだし」
この間まで半ば敵対に近いような間柄だったマヒトから、妙に持ち上げるような発言をされたせいか、背筋にむず痒さのようなものが走る。正直薄気味が悪い。
というか、騙すつもりは一切なかったが、心をくすぐり、利用しようとしている部分については、意図していなかったものではあったが実際それに近い形になってしまっているような気がするのだが。
「別に狙ってやったんじゃねーってんならあーだこーだと言うつもりはねーよ。巡り合わせ、でカタがついちまう話だ。それに、これまでのお前の態度から、読み取れる事もあるしな」
そんな事を言われて、貴方は首を捻る。自分が他者からどう見られているのか。他者が自分の振る舞いに何を見出すか。それを把握するのは、中々に困難だ。
戸惑う貴方の様子に、あー、とマヒトは言葉を探すように少し間を置き、
「例えばお前、御嬢を危険に晒す気、あったかよ?」
無かった。
何故ならば、あくまで協力者という程度のつもりであったからだ。“異象”のような相手との戦いに加わってほしいのではなく、もっと別種の、自分の事情を知るこの世界の人間という立場の、補助的な助力として当てにしていたのだ。クーリアから話を聞いたときもそういう認識だった。
アサーンへの同行も、正直な話“異象”相手ならばどうにか出来るという自信があったからこそだ。アサーンの亜獣も強力だという話は聞いていたが、それ程意識してはいなかった。
「だろうな。で、もし俺等を盾にとか、自分だけ助かりたいとか、そういうのを考えてんなら、アサーンの闘技場であの化け物共と出くわしたとき、一人だけで前に出て、あいつらを相手しようなんて真似はしねーだろうしな」
彼の言に、成る程、と貴方は納得する。どうも、これまでに自分が取った行動が、知らぬ間にマヒトの信頼を勝ち取っていたようだ。
「信頼っつか、あくまでお前からすりゃ、俺等は外方だと割切ってるってのが判るだけなんだがな。……んで、まぁ、そんなお前だから、特に今回のような事があった後じゃ、御嬢を早々危ない状況に引っ張りださんだろって読みがあっての黙認ってこった」
俺が今、一番お前に話しておきたかったのはな、とマヒトは言葉を挟み、
「簡単に言っちまえば、こっちの事情をある程度弁えて、御嬢にゃあんま危険な真似はさせないで欲しいっていう、釘差しだ。真面目な話、御嬢の無事にゃ俺やシモンズの命が掛かってる。比喩じゃなくて、本当にな」
念押すマヒトに、貴方は判っていると頷く。
これまでの話に従うならば、いわば彼等は、姫に付けられた護衛の騎士だ。それが守護対象を守りきれなかったとなれば、処分は免れまい。
「だから、その辺りを考慮して、御嬢の事を宜しく頼みたい。……けれど、【NAME】よ」
マヒトの口調が、少しだけ変化した。その変化が、どういう質を持つものなのかまでは察する事が出来なかったが、変化だけは感じられた。だから貴方は窺うように隣に視線を送る。長身の男は笑みの無い顔で、こちらの視線を真っ直ぐに受け止め、
「考慮しながら、出来れば御嬢に見せてやって欲しい。お前の事情や、お前が持つもの、お前が持ってきた世界を、見せてやって欲しいんだよ」
「…………」
ややこしい要望だった。
自分なりに受け止めれば、“異象”のような危険や荒事からは遠ざけつつ、しかし『礎の世』に関する事情は極力見せて、絡ませてやって欲しい、という事だろうか。
こちらが欲するときに、都合良くリヴィエラの“眼”や、彼女が持つというアエルに対する適性を利用させてもらうのではなく、『礎の世』に関する問題が起きれば常にリヴィエラ達と状況を確認しあうような関係。そして、そんな密な関係を保ちつつ、いざ危険が迫れば彼女等は確実に安全となるようにする。
そのように出来るのならば、確かに理想的な関係ではあるが、しかし現実的には些か厳しいように貴方には思えた。
何せ、アサーンではこれを意識せずにやろうとして、正に間一髪の状態に陥ったのだから。だからこそ、リヴィエラの協力を得られたとしても極力接点は減らそうと考えてもいたのだ。そこに、マヒトからのこの要望である。貴方は明確な反応を返せず、小さく唸るような声を上げて黙り込む。
「結構無理言ってるってのは、俺も判っちゃいるがな」
そんな貴方の様子に、マヒトは苦笑いと共に口調を少し緩めて、けれども直ぐにまた引き締める。
「先刻話した通り、本人がどう考えてるかは別にして、御嬢はまだ親連中の用意した箱から出られてねぇんだ。この旅だって、結局は箱の内だ。俺等みたいなお目付がついてるのも含めて、な。そんな、お目付の俺が言う事じゃないんだろうが――」
言葉が途切れて、歩みを止める気配。
数歩先行く形で貴方も立ち止まり、背後を振り返る。
「――多分お前は、御嬢にとって初めての奴なんだよ。初めての、箱の外に居て、御嬢が気を惹かれた奴だ。……そういや、さっきからお前に聞かれてる問いに答えるか。御嬢が危険な事に首突っ込んでんのに、俺が何故止めないかって?」
マヒトは、戯けたように肩を竦めてみせて、
「雛がようやく、分厚い分厚い卵の殻を割って外出てこようって頑張ってんだ。なのに、それを邪魔するってのは無粋でしかねーだろ?」
「…………」
その言葉を聞いて、ようやくマヒトがリヴィエラという存在をどのように定義しているのかが理解出来た気がする。
マヒトにとってリヴィエラは、主や護衛対象というよりも、妹や娘、庇護すべき子供に近い扱いなのだ、と。
ならば成程。マヒトの何処か矛盾しがちな態度も腑に落ちるような心地となった。目の前の目つきの悪い男が、リヴィエラをそのように認識しているのかと考えると、微笑ましくさえある。貴方が思わずにやにやと笑ってしまうと、それを見たマヒトは居心地悪げに視線を彷徨わせて、
「第一、お前もある意味光栄に思えよ? 幾ら初心だっつっても、あんだけ気に掛けられてんだから。せめて、自覚くらいはして、上手くあしらってやってくれ。面倒だろうが、お前だっていざって時に裾掴まれても困んだろ」
と、そう続けたが、貴方はいまひとつその言葉の意味を掴みきれず、笑みを引っ込めて首を捻る。
彼が言っているのがリヴィエラの事であるのは判るが、気に掛けられている、というのはどういう意味だろうか。自分が彼女に興味を持たれているのは、貴方も流石に理解は出来ていたのだが。
「……お前、御嬢がなんでいきなり協力するって言い出したか、想像ついてるかよ?」
どうせ判ってないんだろう、とも言いたげな口調。つい反論したくなるが、実際に判っていない訳で、ここで意地を張っても仕方無い。
否、と素直に首を振ると、マヒトは心底呆れたとばかりに深々と溜め息をついた。芝居がかった態度は癪に障る事この上ないが、貴方はどうにか堪える。
「そういやお前。最近聞いた話なんだが、少しばかり前に、テュパンの地下かどっかで化け物退治をやって、御嬢にかっこいいとこ見せたんだっけ?」
見せたというか、見られたというか、そんな感じだったが。恰好が良かったかどうかは客観視出来るものでもないので答えようがない。
貴方がむにゃむにゃと形にならない言葉を呟いていると、
「どうやら御嬢、そんときの印象で、お前が本当はすげー強くて、どんな相手にも負けないみたいなイメージがあったらしいのよ。だから食堂で最初に話聞いたときも、教義がどうだの、信じられないだの、上辺の部分だけで考えて、するっと流すなり、拒否できた訳だ。けれどよ」
「…………」
何となく、貴方は話が読めてきた。
つまりあれか。
リヴィエラはこちらに対してそんなイメージを持っていたのに、アサーンであっさりと“擬象”に敗北し、あと一歩で死ぬ。そんな状況に追い込まれる自分の姿を目の前で見せつけられたから、
「お前の事が心配になって、教義がどうとか、信じる信じられないとか、自分の命も危なくなるとか、そこんとこが全部すっとんで、ただお前を助けないとってなっちまったんだろうよ」
うわぁ。
と、貴方は思わず自分の顔を掌で覆う。
内心を過ぎるのは、情けなさ半分、恥ずかしさ半分だ。失礼極まりない話なのだろうが、感覚としては犬や子供に守られたような心境に近い。
思い起こすのは、自分に協力すると言っていた時の、こちらを真剣に見るリヴィエラの顔だ。
あれは要するに、「この人は実は危ないっぽいんで何とか助けるために頑張ろう」というような、そんなつもりの顔だったのだ。
まさかリヴィエラがそのような気持ちでいるなどと全く考えていなかったから、その時には全く思い至らなかったが、今なら判る。
あれは誰かを心配し、そして自分が何とかしようとする者の顔だ。
(……だが)
正直な話、戸惑うしかない。リヴィエラが、こちらの何を守るつもりなのか。
自惚れ抜きで、自分とリヴィエラには大きな戦闘能力の差があると貴方は認識していた。冒険者としての経験に加えて、“同化者”である事により得られた様々な特性は、貴方を高域の戦者へと押し上げている。対し、リヴィエラは宝精召術と神蹟を操るとはいえ、戦種傾向は後衛専門であり、実戦経験は少なく、更には気性も戦いに向くタイプとも思えない。それで一体どうする気か。一瞬の気恥ずかしさが引いて、後には現実的にはどう対処すべきかという悩みだけが残った。
「まぁ、【NAME】が何考えてるかは判るけどよ。でも、恐らく御嬢からするとそんな気持ちっぽいんだよ。んで、さっきの話に戻る訳だ」
マヒトの言葉は続く。
「御嬢はお前のやばいところ見て気が変わった。だから、お前の事を、戦いの面でも助ける気になってる可能性が高い。でも、お前はさっき言ったよな?」
彼が何を問うてきているのかは、流石に判る。
それは、再確認の言葉だ。先刻まで貴方が話していた事を、改めて確かめる問い。
こちらがリヴィエラに望んでいたのは、共に戦う者ではなく協力をしてくれる事。助力者としての立場だ。しかしどうやら、リヴィエラは戦いの部分でも、協力者としてこちらを守ろうとしてくれているつもりらしい。
「ってな訳でだ。お前にゃ色々と上手く立ち回ってくれってのが、御嬢抜きで、俺がお前に言っときたかった事だ。判ったか?」
善意であるが故に厄介だ。強く拒絶すれば、根元である協力態勢にもヒビが入りかねないが、しかしだからと弱い拒否ではリヴィエラが抱いてしまった不安、心配を抑えられるかどうか危うい。そして押し切られてしまえば、それこそマヒトが先程言ったように、いざという場面で裾を引かれて、互いに致命的な状況に陥ってしまう可能性もある。
加えて、リヴィエラが持つこちらへの興味。マヒトからの要望。それらを合わせて考えれば、
(厄介な……)
頭痛がしてきた。思わずこめかみを押さえる貴方に、マヒトが苦笑しながらも何かを言おうとして、
「ちょっと、【NAME】~!? 何立ち止まってんのさーっ! ってあれ、ひょろながもう戻ってきてる」
「……っと、ほれ。お前のちびっ子が呼んでんぞってかひょろなが言うなや!」
騒がしい声と共に、足を止めていたこちらに気づいたらしいリトゥエが、ひらひらと貴方の傍に戻ってきた。小さな妖精は、隣に立つマヒトを認め、早速口論を始める。少し前までは真面目に話をしていたマヒトが早々に沸騰していく様子を眺めながら、貴方は僅かに視線を移す。
前方。人波の中にて、こちらへ振り返っている二人の姿が見えた。
苦笑を浮かべてリトゥエとマヒトの遣り取りを見ているシモンズはある意味何時もの顔で、そして隣のリヴィエラは笑みの無い顔で、アサーンへ入る前と似ていて、けれども少し違う。そんな様子で、じっとこちらを窺っていた。
そこから透けて見えるのは、確かに心配の意思だ。良く良く考えてみれば、つまり自分は、相当のショックを受けた彼女が不安になり心配する程に、アサーンの後の態度が沈んでいた、という事なのかもしれない。
「…………」
少しの思案。
試しに、貴方は意識して表情を緩めて、自分を見ているリヴィエラに笑いかけてみた。
すると、彼女はきょとんと眼を瞬かせて、一拍。小さく淡いものでありながら、微笑みに近い表情を返してくれた。
まるで鏡だ、と思う。そして、どうやら自分が思っていた以上に、アサーンでの敗北がリヴィエラだけでなく、自分自身にも影を落としていたらしい、とも。
そうだ。暗くなっていても仕方無い。いや、落ち込むのは勝手だが、それを隠しきれずに周りに心配されるなど、全くもって情けない話だ。
貴方は自嘲の笑みを一つ零して、そして軽く頬を打った。それで気持ちを切り替えると、未だ口論を続けるリトゥエ達を置いて、リヴィエラが居る場所へと軽い気持ちで歩み寄る。見れば、頬打つ動作に驚いたのか、リヴィエラは面食らったような顔で完全に動きを止めていた。その表情のおかしさに浮かんだ貴方の笑みは、先刻のものとは違う、自然なものだった。
・
『あのー』
と、そろそろリヴィエラ達とも別れようかという、ルアムザの都の境付近に差し掛かった時。内側から響いた声に、貴方は反射的に足を止めた。
「……っと。どしたの?」
突然の停止に、貴方の肩上に戻っていたリトゥエがつんのめるように身を揺らし、傍を歩いていたリヴィエラ達三人も怪訝と振り返る。
だが、そんな彼等の動きに貴方は気づかない。その時には既に、己の内に意識を向けていたからだ。先刻の声は、外からではなく内からのもの。ならばその主は、
『あ、私です私、クーリアです。ちょっと良いですかね? リヴィエラさん達と別れる前に、話しとかないとまずい事がありまして』
何だろうか、と思い、そこでようやく、周りの反応に気づく。貴方は少し考えて、クーリアに以前のテュパンでの時のように声を外に出せないかと伝える。内心での会話は意思伝達が速くて良いが、周囲に人が居る状態ではかなり訝しげに見られる。ならば既に事情をある程度察している者達しかいないこの場では、クーリアの声を音声としてもらった方がリヴィエラ達にしても状況を把握しやすい筈だ。
もっともそれは、彼等に聞かれても構わない話であるならばという前提あっての話だが。
『それについては大丈夫です。単に、協力を得られるという話になったからには、もう一方の――フローリア側での話もしないとってだけですから』
……ああ、と思い出す。
言われてみれば、フローリアでの彼女達にも協力してもらうには、“分離同化”を含めたもう一人の自分とも言うべき存在についての説明をし、リヴィエラ達に理解してもらわねばならないのだ。そういえば、その辺りの説明は一切していないのだった。
『と言う訳で、ええと、こほん。聞こえますかね?』
「お、おぅ? クーリア?」
『そうですそうです。どうもリトゥエさん。それでですね。今回リヴィエラさん達に協力してもらうのが一応決定したという事で、改めてお話ししておきたいことがありまして』
「……まだ何かあるッスか?」
『はい実は。これはいちいち釘を刺す必要も無いことかもしれませんけど、私達が一緒に居ないときに、“異象”とか、大規模なアエルの反応とか、そういう気配を感じたときは、なるべくそこから離れるようにしてください。端的に言って、非常に危険ですから。これはもう、三人とも理解されてますよね?』
「当たり前だ。誰が好き好んであんな化け物とか相手にしたいと思うかよ」
「でも、そんな気配どうやって感じれば……って、ああ」
途中まで喋ったところで、シモンズは言葉を切ってリヴィエラを見た。その視線に、彼女はこくりと頷いて返す。
「私の“眼”なら、視えますから。……大丈夫です。あれがどういうものなのか、もう判っています。だから、無闇に近付いたりは、もうしません」
リヴィエラの真剣な答えに、クーリアは結構、と短く返し、
『あと、もう一つ。こっちははっきり言いまして、貴方がたからすると更に判りづらい話になると思いますんで、出来れば頭空っぽにして、夢詰め込むくらいの心持ちで聞いていてくださると有り難いです』
そんな前置きの後に繰り広げられたクーリアの説明は、裏事情などを割愛した、結果だけを大雑把に説明したものだった。
端的に言えば、今から結構後に、あなた達の前に別人の姿をした【NAME】が現れるので、その時にも今と同様にこちらのやる事に協力してくれないか、などという話だ。
大雑把かつ、理解しがたい話である。当然反応の方は、
「結構後っていつだっての」
「別人の姿をした【NAME】さんってのがまず意味不明なんッスけど」
「ってか、それって私は関係ないのよね?」
という、突っ込みと疑問符が入り交じるもので、もう少し『礎の世』側の事情も交えた詳しい説明をした方が良かったんじゃ、と貴方がクーリアに内心で苦言する程であったのだが。
「……あの、良く判りませんでしたけれど、判りました」
『え、どっち?』
「あ、すみません。話は判りませんでしたが、クーリアさんが望まれてる事は判りました、という意味です。――はい。その時にも、私は【NAME】さんに協力させてもらいます」
というリヴィエラの発言で、話はあっさりと片付いてしまった。
「……おい御嬢。流石にその、躊躇いなさ過ぎじゃねーか?」
と、場に居た皆の心境を代弁するようなマヒトの突っ込みが入ったのだが、
「どうしてですか? 【NAME】さんの協力をするというのは、もう決めていた事ですし。ただ、後でもう一度、別の方のお姿で、というだけの話でしょう?」
不思議そうな顔と共にそう返されて、マヒトがむぅ、と唸る声と共に沈黙する。論破されたというよりも、反論の意気が萎えたらしい。貴方はマヒトとの話を終えた後、ここまで歩く道すがら、少し意識しながらリヴィエラと話をしていた。その結果、彼女の気分は先刻までとは大分変化しているようだ。そのせいか、リヴィエラが元々持っている何処か抜けている、脳天気な気質が前に出てきているように見える。
「後でもう一度、というのも結構大概だとは思うんスけど、別人の姿ってところは気になんないんスか……?」
「? 【NAME】さんなんですよね? なら良いんじゃないでしょうか? 後で、というお話は気になりますけど」
「…………」
一同沈黙する。想像していた以上に、リヴィエラという少女は感性が普通と違っている。実際に“分離同化”している貴方からしても異質に見える程だ。マヒトやシモンズ達ですら若干引いているところから察するに、ラカルジャでは皆こういう考え方をするという訳ではないようで、若干安心する。
「ただ、姿が別となると、私達には見分けが付かないと思うのですけれど。その点についてはどうされるのですか?」
『……え? あ、ああ。ええと、どうしましょうかね』
考えていなかったのか、クーリアが迷うように口篭もる。
姿形が別人となっているのならば、中々それが“【NAME】”である証明というのは難しい。
貴方は少し考えて、そういえばと思いつく。
自分は“同化者”だ。ならば、リヴィエラからは普通の人とは違う“光”を纏っているのを見分ける事が出来るのではないか。ならば、その確認がそのまま証明にも繋がるのではないか、と。
しかし、そんな貴方の提案には、二方から懸念の言葉が来た。
「出来る、とは、思います。けれど、でも、あの都での事も、ありますし」
『彼女の“眼”で視るとするなら、“同化者”ならみんな同じに見えると思いますから。アサーンでの件で、同じ“同化者”と遭遇したことを考えると、それだけで貴方と特定するのは危険かもしれません』
言われてみれば、あまり良い手ではないかもしれない。となると他の案を考えなければならないが、
「まぁ、無難なのは合い言葉とかじゃないッスかねぇ」
シモンズの意見はかなり投げやりな調子で述べられたものだったが、妥当なものでもあった。
「合い言葉ねぇ。良いんじゃない? とは、思うけど……」
リトゥエが首を捻り、他の皆が顔を見合わせる。その間で行き来するのは、どういう合い言葉にする? というものだ。
別段、凝ったものにする必要は無い。さっさと決めてしまおうと貴方が適当な言葉を口にしようとした、その寸前。
「それなら私、良い言葉を知っています!」
と、遮るようにリヴィエラが手を挙げる。その妙な勢いの良さに、貴方は理由も無く嫌な予感を覚えたが、しかし理由が無いだけに彼女を遮れない。
「イーマ教団で定番化している伝統の合い言葉で、私、これ好きなんです。ええと――」
続けて放たれた言葉と、それに合わせてリヴィエラが取った動きを見て、全員脱力する。
一仕事終えたとばかりに良い笑顔でこちらを見たリヴィエラは、皆の反応に首を傾げて、
「――あれ、ダメですか? 判りやすいと思うんですけど」
「……ああ、うん。確かに判りやすいこたぁ判りやすいかもしんねーなぁってか、何語よそれ」
「突っ込んだら長くなるッスよアニキ。取り敢えず、【NAME】さんは、別人になった時にさっきの合い言葉でも言ってみて欲しいッス。別人になったらってのも全く意味わからんッスけど……」
もう色々と面倒くさくなったのか、マヒトとシモンズが疲れ切った声でそんな事を言う。
というか、今の合い言葉で決定なのか、と貴方はげんなりと肩を落とした。
隣には、自分好みの合い言葉が採用されて、どこか嬉しそうなリヴィエラの顔がある。
テュパンからアサーンを経て、真剣な様子の彼女を見てばかりであったが、やはり元は元であるようだ。
そして、
「…………」
きっと、そんな様子を覗かせる彼女の方が、先刻までよりは健全で、正しい状態なのだろうと、貴方は思った。
礎の王格 両人の統一
──両人の統一──
『……それにしても、やっぱり少し、不安になりますよね』
ランドリートの都内。大通りを一人歩いていた貴方は、心に届いたクーリアの言葉に短く頷く。
“異象”への対処や、“王格”の探索。それを効率よく行うための、現地での協力者の確保。その最有力候補であった宝精召師リヴィエラとの交渉は、途中紆余曲折あったものの、一先ずグローエス側では協力を得る約束を取り付ける事は出来た。
だが、残念ながらそれで終わりとはならない。残る、もう一方。今居るフローリア側でも、彼女等の協力を得なければならないのだ。
一応、過去となるグローエス側で一通りの事情は話しており、更には別れ際、“分離同化”についての遠回しな説明と、後の打ち合わせはしておいたものの、不安は大きい。
何故なら、
『私達からすると殆ど時間が経過してませんけど、リヴィエラさん達からすると、かなり昔の話になるでしょうし……』
グローエスにて“虹色の夜”が発生し、続いて発生した多種の異常現象と、それに関わる諸々の出来事にある程度の収拾がついたのが、今居るフローリアの時間を基準にして、大凡半年ほど前と聞いている。つまり、グローエス側でリヴィエラ達と約束を取り付けてから、少なくとも半年以上が経過している筈。綺麗さっぱり忘れ去られている事も十分に有り得る程の時間が過ぎているのだ。
「…………」
改めて考えてみると、過去での自分の行動は未来となる今の状況に大きな影響を及ぼしてしまっている気がする。その事に思い至って、貴方は何だか落ち着かなくなる。
例えばこれまで、フローリアでもリヴィエラ達と出会い、あれこれと事件を起こしていた訳だが。もしあの時、アサーンでの戦いでリヴィエラ達が命を落としていたならば、フローリアで自分が体験した彼女達との出来事は、一体どういう形になるのだろうか?
そんな貴方の疑問を感じ取ったのか、クーリアが僅かに思考するような気配を挟み、
『そうですね……。もしアサーンでの件でそういう結末になっていた場合は、リヴィエラさん達がフローリアに居たという可能性事象は、実事象から擬事象へと変化する事になり……要するに、それが確定した現実、という事になってしまいます。ですので、貴方がフローリアでリヴィエラさん達と体験した出来事は貴方の記憶には残りますが、現実としてはそのような出来事は無かった時間点が採用されて――言ってみれば貴方が見た夢幻、という扱いになるでしょうね』
やはりそうなるのか、と貴方は呻く。
過去の行動によって、未来が容易く変化していく。当たり前の事ではあるが、同時に空恐ろしさも感じてしまう。それはきっと、本来ならば見えない筈の未来を、“分離同化”によって己の眼で確認した事で得た実感故のものなのだろう。時間というものを飛び越えて、物事に干渉する。侵してはならぬルールを破っているような、嫌な感覚があった。
しかし、ルールを破っているからこそ。
本来ならば不可能である事も、容易く可能にする事も出来るのではないか。
例えばそう。先刻の話であるならば、命を落としたリヴィエラを助けるために、更に過去に干渉してしまえば、とか。
だが、そう考えた貴方を遮るように、否定的な意思が届く。
『……うーん。実事象を更に変化させる事自体は可能でしょうが、それを私達が行うのは難しいですね』
無理、なのか。
『はい。この話は前にもしたと思いますけど、何せ、私達が干渉可能な時間点は、流動性が発生し、広がった干渉幅の両端に限定されています』
そういえば、以前そんな話を聞いたような記憶がある。
確か、こちらが現在可能なのは、“王格”が存在すると思しき時間点二つに対し、どうにか干渉する程度だと。
『だからグローエスにて貴方が体験したあの時間が、私達が干渉出来るもっとも過去の時間となります。ですので……』
成る程と理解し、同時に気を引き締められる。
あのアサーンでの事件は、綱渡りの連続だった。自分か、リヴィエラ達。どちらかが命を落としていてもおかしくはなかった。そして、もしそんな状況になってしまった場合、取り返しはつかないのだ。二つの時間に干渉し、大袈裟に言えばこの世界の歴史を変える事は出来る立場ではあるが、それは絶対の力ではなく、やり直しが効くものでもないのだ、と。
『とはいえ、そちらの現実を意識無意識関わらず変化させる力があるのも確かですけれどね。例えば、貴方がグローエス側で色々とリヴィエラさんと関わりを持った結果、彼女達がフローリアにやってこない可能性事象が実事象になる場合も有り得るわけでして』
「…………」
え、それまずくない? と貴方は思わず足を止めてしまう。
実のところ、貴方は今、リヴィエラ達を探してランドリートの都にある宿をしらみつぶしに回っている最中だった。グローエスの時と違い、フローリアでの彼女達が何処を行きつけにしている等といった情報を持っていなかったため、こういう方法を採るしかなかったのだ。
だが、ここまでリヴィエラ達の姿を見つけられなかったのは勿論、彼女等がどこそこに泊まっているという話も得られず、回った宿は既に十数軒。ボーグボーデン港付近のめぼしい宿は巡り終えて、後は可能性の低い新市街を回るか、それとも外街の治安の悪い区域に足を伸ばすべきか。歩きながら迷っているところに、このクーリアの衝撃発言である。
少なくともランドリートの都にリヴィエラ達が居るだろうと、そう考えて、こうして足を使って探していたのだが。もしかしてその前提すら間違っていたのか。
というか、そういう可能性があるのならもっと早く言って欲しい。クーリア目掛けて怒りの感情を込めると、
『ああ、いえ。そこについては大丈夫だと思います。あくまで可能性の話でして。リヴィエラさん達がフローリアに渡らないという事象は、時間断面上の近似域には殆ど存在していませんので。余程の事がない限り、リヴィエラさん達は少なくともフローリアの何処かにいる筈です』
だったらそんな例え話を出さないで欲しい。無駄に焦ってしまった。
貴方の抗議に、触れていたクーリアの意識が小さくなる。
『す、すみません。全くもってその通りで。取り敢えずほら、話を戻しましょう話を』
明らかに話題逸らし目的の言い様ではあったが、別段引っ張るようなネタでもない。貴方はクーリアの言葉に素直に従い、意識を少し前に戻す。確か、リヴィエラ達に上手く話をつけられるかどうか、だったか。
『です。時間についてもそうですけど……貴方の姿も、気になるところではありますね』
言われて、貴方は己の身体を見下ろす。
クーリアの言う通り、今の自分は姿形からして別物だ。この点については一応リヴィエラ達に伝えた覚えはあるが、細かく説明をしても混乱を招くだけだとクーリアが至極大雑把に話をしただけだった気がする。リヴィエラ達がしっかり理解してくれたのかどうかも正直はっきりとしておらず、加えて半年という時間の経過もある。こちらとの約束は覚えていてくれていても、この辺りの話はすっぱりと忘れ去られている場合も勿論あるだろう。
こうして考えると、不安要素だらけだ。リヴィエラ達を無事見つけられても、話がスムーズに進むかどうか。
『ですねー。……あ。でも、ほら。アレがあるから、結構大丈夫なんじゃないですか?』
と、クーリアが突然そんな事を言い出した。
アレだの何だのといわれてもさっぱり判りません。貴方が淡々と切り返すと、
『ほらアレです。リヴィエラさんが教えてくれた、“合い言葉”!』
「あー……」
言われて、思わず肉声が溢れた。道をすれ違っていた幾人かが、いきなり声を発したこちらに怪訝な顔を向けてくるが、貴方は構うことなく内心の会話に意識を戻す。
リヴィエラが教えてくれた“合い言葉”。
覚えてはいる。リヴィエラが嬉しそうに見せてくれた仕草と言葉が脳裏に蘇る。リヴィエラはお気に入りと言っていたが、
『今思い出しても疑問に思うんですが、本当になんなんでしょうねあれ』
「…………」
判らん、と返す他無い。
少なくとも、貴方が知っている言葉ではなかった。擬声語に近い音の羅列と、それに併せた謎の仕草。印象としては奇怪。全くもって理解不能な代物だったが、だからこそ使いやすいものなのかもしれない。ただ、“合い言葉”なのに踊り有りというのはどうなのだろう。
『まぁ、リヴィエラさんから提案してきたものなんですし、アレをやれば一応信じてはもらえるんじゃないでしょうかね。というわけで、実践頑張ってください!』
やるのか、あれを。自分が。
『頑張って!』
完全に他人事といった体のクーリアに、貴方は刺々しい感情を向ける。
とはいえ、肉体を持たないクーリアが替わりにやれる筈もないのだから、実際他人事なのは確かである。自分がやるしかないのだ。
もういっそ、リヴィエラ達がこのまま見つからなくてもいいんじゃないの? と、貴方がくさくさした気分で歩いている内に、大通りが終わりを迎える。辿り着いたのは新市街の中央となるガーナ・ニレンの大広場だ。多角の大きな広場の真中には噴水と彫像。その周囲には花樹が植えられ、内縁と外縁にそれぞれ長椅子が配置されている。その造りは、単なる広場というよりは公園に近い。馬車等は広場の外側に用意された円状の道を通るよう決められているため、広場の中と外ではまるで時間の流れが違うかのような、隔絶の気配があった。
ここまで宿を巡って歩き続けていた事に加え、先刻の話で受けた精神的な傷もあり。公園で軽く休んでいきたい誘惑にも駆られたが、ここで一度休憩を入れてしまうと、そのまま気分が完全に萎えて今日の捜索を切り上げてしまいそうだ。
貴方は浅く首を振ると、今度は新市街の宿巡りを始めるべく、広場沿いの道を辿って手近な大通りへと入ろうとし、
「…………」
視界の片隅。広場外縁の長椅子の一つで、大勢の子供達を相手に木板を捲り、声を張る小柄な人影が映った。
足を止めてその人影を確認し、浅く嘆息。よくよく考えてみれば、そうおかしな話ではない。
『そういえば、リヴィエラさん達、前にもここで絵語りをやってましたっけ』
そうなのだ。先刻、彼女等が行きつけにしている場所の情報は無いなどと考えていたが、大きな間違いだった。前にこの広場でリヴィエラ達と出会った時、言っていたではないか。熱りが冷めるまでは、大人しく布教活動に専念すると。ならばわざわざあちこちを歩き回らずとも、ここで彼等がまた絵語りをするのを待っているだけで良かったのだ。
気づいた事実が、これまで無駄に歩き回った疲労を倍増させる。そして、この疲労感の中であの“合い言葉”をやらねばならない事にも気づいて、全身を覆う倦怠感が尋常じゃないまでに増していく。
『……取り敢えず、行きましょうか』
促しに、深く溜め息をつく。正直帰りたいが、そういう訳にも行くまい。
貴方はまるで身を引き摺るような鈍い動きで道を横切り、のろのろと広場の中へと入っていった。
・
絵語りが終わり、広場の長椅子前に残っているのは貴方とリヴィエラ達三人。
貴方は彼女達が無言で注目する中、全力で“合い言葉”を実演していた。
「いん、いん、いんぱらぷ」
自分でも理解出来ていない言葉を呟きながら、貴方は肩を怒らすように振りつつステップを踏む。
「おっぽんぽっぽ。おっぽんぽっぽ」
足を開き、身体を左右にスイング。端に至ると同時に伸び上がるように身を伸ばし、しかし両手は腰前で合わせる形でまっすぐ真下を維持。
『……本当にきついですねこれ』
判ってるから言わないで欲しかった。途中で挫けそうになる。
「ぷぎっちょぽぎっちょ、ぱんぽるぱ。まるっぱむるっぱ、しんこるちょ」
本当にどういう意味があるのかこの言葉。我ながらよく覚えているものだと感心しながら、下ろした手を右に左に振りつつその場でくるくると二回転。そして、
「いん、いん、いんぱらぷーっ!」
最後の叫びに合わせるように、掌を上に掲げるような形で、全力で両腕を上げて停止した。
「…………」
暫し、嫌な沈黙が場を支配するが、やりきった貴方はもう殆ど気にならない。
思うのは一つ。
如何か、と。そんな、相手に「どうだ」と見せつけ、問う意思だ。
自信はあった。リヴィエラが見せてくれた仕草と声。それをほぼ完璧に模倣出来た筈だ。後は、相手の反応である。
対する三人。左右二人の男は、完全に真顔でこちらを見返し、
「どうした【NAME】。完全に気が狂ったか」
「最近暑いッスからね。気持ちはわからなくもないッスけど、ちょっとそこの噴水で顔洗って来た方が良いんじゃないッスかね」
「…………」
何となく判ってはいた。こいつらは駄目だと。
だが、最後の望みが居る。この意味不明としか言いようのない“合い言葉”を決めた張本人が。
彼女ならば、と。その期待を胸に、貴方は真っ直ぐ正面、驚いた顔で眼を瞬かせるリヴィエラを見る。
そんな貴方の視線に対し、リヴィエラは、ぽん、と両手を合わせてふんわりと笑い、
「お上手ですね、【NAME】さん。私の教団の子供向けの御遊戯、一体どちらでお知りになったんですか?」
「…………」
天を仰ぐ。
望みは絶たれた。この人達、完全に忘れています。まず何より、これ“合い言葉”じゃなかったんですか? 子供向けの御遊戯だったんですか?
『っていうか、何の挨拶も前置きもなしでやったのは流石にどうかと思うんですけれど……。ええっと、あー。あー。あの、聞こえますかー?』
途中から、クーリアの思考が声音となって鼓膜を震わせる。同時に淡く感じるアエルの反応。クーリアが術技を使って、意思を音声へと変換させたのだ。
「ん?」
「お」
と、突如響いた声に、左右男二人が反応した。
「……その声、聞いた事あんぞ」
え? と貴方が驚くが、クーリアはその様子に手応えを感じたのか、素早く言葉を繋げた。
『あ、私の事は覚えてます? どうもどうも、クーリアです。えっと、大体半年ぶり、くらいになるんでしょうか?』
「…………」
マヒトとシモンズ。二人の顔が怪訝な表情で歪み、どうもしっくり来ないという風に、貴方の顔を何度も見る。
彼等が何を考えているのかは、何となく判った。それはクーリアも同様であったらしく、
『ええっと、多分最後に私達がお話をした時、説明しませんでしたっけ? ほら、別人になって、後で貴方達に会いに行くって』
「……あー。あーあー! はいはいはい、思い出した思い出した。ってか、え? マジで? 【NAME】なのかよ?」
唖然と声を上げるマヒトに、貴方が無言で頷く。シモンズはぽかんと口を開いて、貴方の顔をまじまじと眺め、
「た、確かにそんなような事、言ってた気はするッスけど……いやホントに別人じゃないッスか。比喩とかそんなんじゃなくて」
比喩を言ったつもりではなかったのだから当然なのだが、その言葉から察するに、どうやらシモンズはこちらの別人という言葉を何かの比喩と捉えていたらしい。
だが、マヒトとシモンズ、二人から向けられる視線は、既にグローエスでのものと変わらなくなってきていた。それは彼等が自分を同一の存在であると信じてくれた証拠だった。
それは良かった、のだが。
「…………」
クーリアが声を出すだけで話がつくのならば、先刻自分が見せたあの“合い言葉”には何の意味が。
釈然としない気持ちでぐったりと肩を落とすが、マヒトとシモンズは驚きの事実にそれどころではないらしく、貴方の様子など気にせず話しかけてくる。
「ってか【NAME】? で、本当にあってんのかよ? いやだって、今の今までお前、そんな素振りひとっつも見せてなかったじゃねーか」
「そッスよ。一体また、何で今頃になってそんな話を?」
そう言われて少し戸惑い、そして貴方は彼等の発言が正しくどういう意味なのかを理解する。
グローエスで彼等と出会った自分と、フローリアで今こうしている自分。
これが同一の存在であるならば、彼等からしてみれば、貴方はランドリートの酒場にて喧嘩をし、都心大路でやり合い、中央広場で話をするその間、ずっとグローエスでの件を黙っていたという事になる。勿論、こちらからすれば当時はリヴィエラ達と約束をしていなかったという至極明快な理由がある訳だが、それを話して彼等に理解してもらうのは難しいような気もする。
と、貴方が迷っている間に、
『それは単純な話でして、私達からすると貴方達と約束した半年前が、実はついさっきの事なんですよ。えっと、事実を判りやすく解釈して説明しますと、私達は半年前と今とを意識のみ、好きなように行き来する事ができまして。それで先刻、ルアムザで貴方達とお別れしてこちらに戻ってきたばかりという訳です』
などと、クーリアがかなり直球の説明を繰り出した。
大雑把であるが、確かに本人が言う通り判りやすい説明だ。理屈などは一切省いた、事実のみの言葉。勿論、それに説得力があるかどうかはまた別問題で、
「……お前、それを他人に納得しろって言う方が無理ねーか?」
「普通なら妄想癖もいい加減にしろって言われるッスよ」
二人からは当然とも言える反応が返ってくる。
しかし、クーリアの方もそれを予期していたのか、続ける言葉に全く揺らぎがない。
『そう言われましてもこれが事実ですので、まぁ、単純にそういうものなのだと受け取っていただければ、と。残念ながら証拠となるようなものが示せる訳ではありませんし、知識という下地が無い方々に理論的な話を長々と説明しても精々煙に巻かれていると感じるだけでしょうし。ですので納得できないという事でしたら、お二人が好きなように、辻褄の合う理屈をでっち上げていただければそれで良いかと思います』
「…………」
それはどことなく突き放したような、理解してもらう事を諦めたかのような物言いだった。
あまり、聞いていて気持ちの良い発言ではない。マヒトとシモンズの不信感を煽る形になるのでは、と貴方は少しばかり不安になったが、二人は黙って数度視線を交わした後、気を抜いたように深く息を吐く。
「わぁーったよ。全面的に信じるつもりはねーが、少なくともこいつがグローエスでのあいつと同一人物だってのは了解した」
「説明する気は無いかわりに、どう思われる覚悟もあるって事ッスよね。なら、その意気を買うッスよ」
『そう言ってもらえると助かります』
二人の発言に、若干満足げなクーリアの声が返る。結局、こちらが何か口に出す必要もなくマヒト達からの理解が得られたようだ。若干放っておかれたような感覚がないでもないが、未だ“合い言葉”の実演によって受けたダメージが抜けきっていない貴方からすれば、むしろ有り難い展開であった。
「で、まぁそいつぁ判ったけどよ」
と、マヒトが仕切り直すように話しはじめる。
「今、グローエスでしてた話を蒸し返すって事は、つまりアレか? フローリアでもお前等の……あのクソヤベェ化け物の処理を手伝えって事かよ?」
『そういう事です。正確には、処理ではなく探知といった補助的な作業を、それも“異象”だけではなく、“王格”も含めたアエルに関わる理粒子変移探知をお願いしたという話ですけれど――』
どうでしょうか。
回答を窺うように言葉を切るクーリア。対し、マヒトとシモンズは何とも言えない渋い顔を貴方へと向けてきた。
その表情と態度は、まるで約束に遅れてやってきた場違い者にどう対処をするか迷っている。そんな印象を与えるものだった。
しかし、何故そんな反応なのかが判らない。貴方が怪訝と見返すと、マヒトは不機嫌そうに目を眇めながらも貴方から視線を外さず、逆にシモンズは逸らすように後方を振り返った。
「……という事らしいッスけど、リヴィエラ様、どうされるッスか? ……ってか、リヴィエラ様?」
シモンズの振りに、マヒトとシモンズの二人から数歩下がった位置に立っていたリヴィエラへと視線が集まる。
「はい?」
「さっきから黙りっぱなしッスけど、話ついてこれてます?」
「っつか、御嬢よ。今ここに居るこいつが、グローエスで御嬢がご執心だったあいつと同一人物らしいって話、ちゃんと判ってる?」
どうせ判ってないだろう。そんなニュアンスを込めたマヒトの発言に、
「はい、大丈夫です。だって、始めから、判ってましたし」
「「え、判ってたの?」」
「ひゃっ!」
と、余りの予想外の答えに、場に居る全員が驚きの声を上げ、それに驚いたらしいリヴィエラがびくんと身体を跳ねさせる。
というか、判っていた? つまりリヴィエラは、最初にフローリアで自分と会ったときから、グローエスでの自分と同一の存在であると判っていたというのか?
「いやいや、リヴィエラ様? 自分ら、リヴィエラ様がそんな素振り見せてたの、一度も見たことないんスけど?」
シモンズの突っ込みに、リヴィエラは少し困ったように首を傾げて、
「え? だって、“光”の感じが【NAME】さんだったから。でも、ええと、“同化者”さん? そういう人は、みんな【NAME】さんみたいに見えるって話も聞いてましたから、違うかもしれないし、言わなくてもいいかなって」
「……なら、本人に確かめりゃよかったんじゃねーか?」
「で、でも確かめたら、答えてくれなくて。意味が判らないって言われて、それで困っちゃって……」
何処か恨めしげにこちらを見るリヴィエラに、貴方は「え?」と固まった。
何故なら、そんな問答をした記憶は、貴方の中に一切無かったからだ。
貴方が慌ててリヴィエラにそう言うと、彼女は不思議そうにこちらを見て、
「寺院の屋上で、話したじゃないですか。私には同じにか視えませんでしたけど、【NAME】さんが誤魔化すのなら、今はその方が良いのかなって思って」
先刻の“合い言葉”についても、どうやらそれを気にして知らない振りをしたらしい。
しかし、おかしい。
彼女が言う過去。彼女の中で対峙する自分。その姿が、貴方の中の記憶とは明らかに違う。
これはどういう事だ。貴方が難しい顔で自問していると、
『記憶違い――というよりは、どちらも本当の事を話しているだけですね、恐らく』
声音ではなく、貴方の内心にだけ響く声で、クーリアが呟く。
どういう意味だと問い質すと、
『簡単な話です。貴方の過去の行動により、今に至るリヴィエラさんの行動も変化した訳ですが、その変化には当然貴方との交流時のものも含まれるんです。つまり、リヴィエラさんが過去に貴方と対峙した時の態度が、貴方が体験したものと変わっている可能性がある。擬事象であった時間点が実事象へと変化した際に、その可能性事象軸線も纏めて実事象へと変化したという話です。……まぁ、“過去の実事象”というものは他の時間点と区別できないんで、厳密には存在しない定義ではあるんですが、判りやすく言うとそうなります』
全く判りやすくなかった。
『……要するに、過去が変わったのでその後起きた出来事も変わり、それには既に貴方が体験した出来事も含むという話です。そして、この世界の時流からは離れた存在である貴方には、変化した自分に纏わる過去の出来事を認識する事が出来ない、という事です』
多少、判りやすくなった気がする。
貴方は理解した内容を先程のリヴィエラの話に当てはめてみた。
自分がグローエスにてリヴィエラと接触し、“異象”やアエル、“光”についてを話し、彼女に知識を与えて、加えて自分という存在を彼女に強く認識させた。
結果、リヴィエラはフローリアにて別の被同化対象と同化している自分を見て、直ぐにグローエスでの貴方と同じ存在だと認識するようになった。
当然、そうなればリヴィエラは相応の態度を、当時の自分に対して向けていた筈だ。それに対し、自分は恐らく何らかのリアクション――リヴィエラの言を信じるならば誤魔化しを行い、話を先送りにしたらしい。
しかし、その自分が行ったとされる行為を、貴方は一切思い出すことが出来なかった。貴方にあるのは、全く別の、リヴィエラとはそんな話を全くしていない記憶だけだ。
今ここに居る自分と、リヴィエラが貴方の事を正しく知った後に出会った過去の自分、そして貴方が実際に体験し記憶として持っている過去の自分。
この三つは切り離されており、孤立しているのだ。
前者の過去は現実としては繋がっているが今の自分とは繋がらず、後者の過去は自分としては繋がっているが今の現実とは繋がらない。
今の自分は、記憶に無い現実を過去に持ち、過去に無い現実を記憶として持つ、中途半端な存在。
(……これは)
薄ら寒い、背筋が凍るような感覚に襲われる。
過去を変化させる事に対しての恐ろしさはつい先程も考えていたものだが、これはまた別種の恐ろしさだ。
何せ、過去に自分がこの世界で取ったという行動が、記憶とは別のものにすり替わっているのかもしれないのだから。
自分が記憶に無い行動を、紛れもない自分が取ったという形で世界の認識が書き換わる。それは中々に空恐ろしく、そして厄介と感じさせる代物だった。
しかもその変化した状況に、自分は順応する事が出来ない。その事実は、世界の変化に巻き込まれない不変の証であると同時に、この世界にとって自分はやはり異分子なのだと、そう再確認させてくれた。
『一応、私の“本体”の方で貴方を要に事象観測を行えば、どういった行動を取ったことになっているかの確認は可能な筈ですけど、二時間点の間の状況については観測干渉を阻害する要素が多すぎて、精度、所要時間共に実用のレベルには辿り着けないでしょう』
ならば、どうすればいいのか。
『割り切って、大らかに受け止めるしかないでしょうね。後は、極力状況を未来時間点――フローリア側で片付ければ、事象変化に惑わされる状況も減るとは思います。でも、“虹色の夜”の影響もあってか、現段階での観測結果では過去時間点側の方が色々と問題が起きやすい状況なので……』
それも難しい、と。
『極力、フローリアとグローエスで共通して関係を持つ相手とは、“異象”や“王格”に関する、要するに私達の事情に絡んだ物事には巻き込まないようにすれば、それ程気になるような展開にはならないとは思いますけど……うーん』
そこまで伝えて、クーリアは小さく唸るように思考の尻を濁す。
クーリアが何を言いたいかは判る。フローリアとグローエス。共通して行動を共にするような相手はリヴィエラ達しかおらず、そして彼女達は既にこちらの事情に巻き込んでしまっている。そうなればもう、この先互いの関係はどんどんと変化し、それがグローエス側の事であれば未来となるフローリア側にも影響を及ぼし、一度変化した過去、つい先程リヴィエラが語った知らない貴方の態度もまた、それに応じて貴方の知らぬ間に変化していくのだろう。
本当に、割り切るしかないのだろう。
「えっと、あの……【NAME】さん?」
と、頭を下げた状態で黙考していた貴方は、リヴィエラの戸惑ったような声に顔を上げる。内心でのクーリアとの会話に意識を取られて、外の事を完全に忘れていた。
何だろう、と視線で問うと、
「半年前。私に、協力してほしいと言ってくれたこと。覚えてます。そして、【NAME】さんが今、こうして私達に話をしにきてくれたという事は」
じっと、貴方を見つめてくる。その視線は、グローエスで彼女から向けられていたのと近しいものだ。何かを乞うようで、同時に求められる事を期待するような、不思議な視線。
「私はやっと、貴方に協力できるんですか?」
「――――」
言われて、貴方は気づく。
恐らく、今ここに居るリヴィエラは、自分が半年前に協力を求めて、一度は拒絶し、けれども改めての答えに迷い、アサーンでの出来事を経て応じる事に決めて――その後、半年の間貴方に放置されたリヴィエラなのだ。
証拠に、視線に込められた意志はグローエスより濃く、しかしあの時には欠片も無かった他の感情も同時に透けて見えた。それは不安であったり、憤りであったり、疑いであったり。ほんの僅かではあるものの、そんな複数の感情の色が絡まっているのが判る。
そして彼女の左右。マヒトとシモンズが先程から貴方に向けていた態度の理由も、ようやく理解出来た。成る程、リヴィエラが相応の決意を持って協力を決めたというのにその後半年間放っておき、そして今頃になってのこのこと現れて改めて協力を申し出ている。そんな輩を前にしては、今更約束を持ち出す場違い者と、そう映っても仕方無いだろう。
何とも居た堪れない気分が貴方を襲うが、それは受け入れるべきものとして貴方は耐え、そして真っ直ぐに自分を見てくるリヴィエラに、答えを返す。
――改めて、宜しく、と。
「はい。こちらこそ」
薄く。リヴィエラは目を閉じて微笑み、頷く。
左右の二人は、そんな彼女を軽い笑みで見守り、そして貴方も、無事彼女とこちら側で協力関係を結ぶことが出来た事に、深く安堵の吐息をついた。
・
――今後の具体的な行動については、また後ほど連絡する。
貴方は互いの居所の情報を交換した後、彼女等にそう告げて一旦別れた。広場を離れて大通りへと歩く間、リヴィエラから教えられた住所を確認し、宿を探し回っても見つからない訳だと納得する。どうやら今は孤児院の一部屋を借りて暮らしているらしい。
軽く、息をつく。
取り敢えず、これでリヴィエラ達の協力を得るという目的は無事達成する事が出来た。
グローエス側でも色々と大変であったが、こちらはこちらで色々とあった。特に過去への干渉による現実の変化がこういう形で現れるとは思っていなかっただけに、中々感慨深いものだった。また、リヴィエラ達の事を実質半年以上放置する形となっていた事も、グローエスとフローリア、二つの時間点を自由に行き来できる身からすれば、理解はしていても実感としては捉え辛いものだった。こうして考えてみると、フローリアでの彼女達からすれば正に今更と、そういう他無い求めによく頷いてくれたものだ。ばっさりと切って捨てられていても全くおかしくはなかった。
しかし、おかしくはないからこそ。
リヴィエラがああして険も無くこちらの求めに応じてくれたのは、素直に嬉しく、有り難いものだった。
先刻のリヴィエラの返事と、表情。それを思い返して、貴方が一人頷いていると、
『……まぁ、冷静に考えてみますと、さっきの出来事もまた、これから過去で行うあれこれの影響を受けて変化して、私達とあの人達とで、別々の思い出になってしまうんでしょうけどね』
何故ここで水を差すかな。
少々本気交じりの苛立ちをクーリアにぶつけるが、しかし返ってきた反応は笑みすら含んだもので、
『だって、半年間放置してしまったという事実をひっくり返してしまったほうが、きっとリヴィエラさん達にとっては良いことだと思いますし。この思い出は、私達だけのものと。そうしてしまった方がいいんじゃないかなー、と』
「…………」
それは全く、その通りだ。
『と言う訳で、グローエスに戻りましょう。まずはリヴィエラさんに“王格”探査に使える術技等を習得してもらわないといけないんですけど、それはこちらじゃなくあちらでやっておいた方が、結果が未来に反映される分、二度手間になりませんからね』
了解、と返しかけて、ふと気づく。
それなら別に、今こうしてフローリア側で今すぐに協力を取り付ける必要などなく、グローエス側でやれることを全て終えてからでも良かったのでは?
そうすればきっと、自分と協力を取り付けた後に音沙汰が無く、そのまま半年放置されたというリヴィエラと、こうして顔を合わせることも無かっただろう。
そんな貴方の疑問に、クーリアは、んー、と迷うような間を置いて、
『理由は二つあって、一つは単純に、グローエス側でのリヴィエラさんは結構ショックが大きくて、気負いすぎてるみたいでしたから。少し間を置いた方が良いかな、と。そう思ったからです』
なら、もう一つは?
問うと、小さく笑みが届き、
『多分、あの後グローエス側でそれなりの関係を築いてしまった後だと、“合い言葉”の出番が無くても話が通ってしまいそうだったので。貴方がやる姿を見るなら今のうちだ、って』
「…………」
――最低。この人最低です。
既に入っていた都心大路。そのど真ん中で立ち止まってしまったが、周りの迷惑げな様子も全く気にならない。
『いん、いん、いんぱらぷー』
止めてください。
『貴方が取ってた最後のポーズ、凄く似合ってましたよ。それにしてもあれ、本当に何の意味があるんでしょうね? 気になりません? ねぇ?』
本当に止めてください。
そうして懇願するも、クーリアの楽しそうな“合い言葉”談義は中々終わらず、結局宿の扉を潜るまで続いた。
礎の王格 転変の来訪
――転変の来訪──
場所はグローエス五王朝内。
テュパンの都の都市門から各都市へと続く大道より離れ、暫し北東方向へと進んだ先にある小高い丘の中腹にて。向かい合って立つ、二つの影があった。
「…………」
繋いでいた両の手を、貴方は無言のまま解く。正面。長衣のフードの裾から溢れる髪が少し揺れて、事前に指し示していた通り、一歩、貴方から距離を取るように離れた。
長衣を纏った娘の身体から、服を突き抜けるように感じられる力は、この世界には本来有り得ざる力。アエルに由来する力の波だ。
手を繋ぎ、先刻まで貴方と彼女が行っていたのは、貴方が所持し管理していたアエル、その一部を、彼女――リヴィエラ・シオレの管理へと移すための術技である。
「……ふぅ」
自身の身体に満ちる異質である筈の力。今にも溢れそうなそれを、リヴィエラは深い吐息一つであっさりと抑えていく。もう見慣れた光景である筈なのに、貴方は内心に驚きを得てしまう。
既にリヴィエラはアエルというものを捉え、操り、管理し、利用する為の術を、基本的な手法ながらもほぼ習得しつつあった。これは、貴方にとって、そして自分達に対し術技の指導を行っているクーリアにとっても想定外といえる成長ぶりであり、この事実はリヴィエラ本人も含めて、かなりの当惑を伴って周囲に受け止められていた。
そんな事を考えている内に、貴方から移されたアエルをもう制御下に置くことに成功したらしいリヴィエラは、更にととんと短い動きでステップを踏むと、貴方との距離を更に離す。
今から二人の間で行うのは、アエルの力を利用した模擬戦闘である。
前回、“擬象”とそれを従える術技の使い手に敗れた経験を踏まえ、貴方は実践的なアエルの利用方法を習得するために。リヴィエラは“眼”の力を活かした探知能力の向上と、基本的なアエルの扱い方を覚えるために、クーリアから指導を受けていた。
高水準のアエルの集合体であるところの“擬象”や、術技により存在の在り方をズラしてくる彼女達の戦いぶりから、アエルを使った攻撃、防御方法を覚えなければどうしようもない、という話になったのだ。
実際、当時の貴方はアエルの使い方など漠然としたものであり、何となく力を集めてみたり、広げてみたり程度の事しか出来ず、宝の持ち腐れに近い状態だった。そしてリヴィエラの方も、ただアエルを“光”として捉えられるだけで、それを力や、自分の能力を高める方向へ利用するという考えなど微塵も無かった。
しかし、既に三桁近い回数、【NAME】とリヴィエラ、そしてクーリアの間で行われた訓練によって、貴方とリヴィエラ、二人の力はかなり大きな変化を見せていた。
証拠に、【NAME】の正面で真剣な面持ちのままこちらを見るリヴィエラの身体は、既に彼女が操作し始めたアエルによって、覆われ始めている。長衣から沸き立つように、うねり、渦巻く力の気配が外へと溢れ出ていた。
対し、貴方が操るアエルは、手にした武器と身に付けた防具に、ちらちらと明滅するように宿るだけである。リヴィエラが全身を覆うようにアエルを広げているのに対し、貴方は点、主に装備に集中させる形でアエルを操っていた。
この二人の差は、指導役を務めるクーリアが意図したもので、戦闘に於ける貴方とリヴィエラの方向性の違いによるものである。
既にアエルというものをある程度認識し、そして幾多の技法、術式を習得している貴方の場合は、一からアエルのみを使った攻撃や防御、その他の行動を行う術技を習得するより、既に覚えているイーサを使って駆動させる技法や術式にアエルを取り入れることで、イーサとアエルによる両面の攻防を行えるようにしたのだ。この方が習得が速く、戦闘方法を大きく変える必要もない為、より実践的であるとクーリアは考えた結果である。実際、この手法を取り入れる事で、対“異象”といったアエル由来の敵に対してはこれまでとは比べものにならない程の攻撃、防御力を得られたのは既に確認済みである。
そして、貴方が取った手法とは真逆の方針で訓練をしていたのが、リヴィエラである。
リヴィエラの場合、長年“眼”によりアエルを捉え続けていた事からくる親和性なのかは判らないが、この世界の人間として考えると規格外とも言える程に、アエルを操り望む現象を呼び込む――術技に対する適性が高かった。
その事を把握したクーリアは、アエルについての扱いをリヴィエラに一から指導し、イーサを使わずアエルのみを使った様々な術技を、貴方を経由する形で彼女の身体に刻み込んでいった。術技はこの世界に於ける技法や術式とは若干趣が異なり、アエルに対する認識や、起こす現象に対するイメージ、それらを明確に発現させる為の心的象徴となる条件鍵の構築が重要になる。クーリアは貴方を経由してまず様々な術技の条件鍵をリヴィエラの心に片っ端から焼き付け、そこからリヴィエラの“眼”を利用したアエルの認識、そして術技のイメージを想像させる指導を行った。
その結果は上々という他無く、リヴィエラは貴方も知らない様々な術技を、自在に操るレベルにまで一気に駆け上がり、また、アエルというものを身近に捉え扱えるようになった事で、宝精召術に関する腕前も飛躍的に上昇した。これまで何となく感じていた“光”でしかなかったものに、宝精と繋がり得る理屈と仕組みがあると知った事で、彼女の中で明確な線として繋がり、それが彼女が本来持っていた宝精召士としての才能を開花させる大きな要因となったのだ。
故に。
今、模擬戦の相手として立つ彼女は、少し前までのリヴィエラとは大きく違う。
勿論、世間知らずで何処か控えめな娘という部分に大きな変化は無いが、精神面ではなく戦闘能力という面で言えば、大幅な向上を見せている。
油断出来る相手では既に無いし、だからこそ訓練の相手として成り立つとも言える。
「それでは」
相応に距離を取った彼女が、杖をくるりと回してその先端をこちらに向けつつ、小さく呟く。
瞬間、リヴィエラの全身に薄い輝きが走った。貴方にとっては見慣れたその輝きが示すのは、アエルを使った身体能力強化の術技に加えて、自身の存在状態を僅かに不定とし、物理攻撃や理粒子を使った攻撃によるダメージを大幅に軽減する術技が駆動した事。それは彼女の最低限の戦闘準備が整った合図だ。
「……行きます!」
眉を引き締め、真剣な表情でこちらを見つめて告げるリヴィエラの言葉。
それを聞き届けてから、貴方は上体を前へと伏せると、彼女との距離を一気に詰めるべく全力で地を蹴った。
・
「うぃーっす。帰ったッスよアニキ」
丘の頂上付近には一本の大きな巨樹が立っている。横へ広がった枝葉は下方へと大きな影を落とし、そろそろ昼時に入り強くなった太陽の光を遮ってくれる。
その幹に腰を下ろし、丘の下方を眺めていたマヒト・クーゲンは、背後からやってきたシモンズ・カプレへとちらりと視線を移し、
「ご苦労さん。で、収穫の方は?」
「問題無く。ほい、カシム食堂の弁当五人前」
どん、と横に置かれた包みからは少々中身がはみ出て見えて、中に詰まっているのが白パンに様々な具材を包んだものであるのが判る。
マヒトは包みを軽く解いてひょいと覗き込み、
「お、肉詰め多いな。今日はアタリか」
「前日に亜獣の肉の持ち込みが多かったらしくて、肉モノ多めの配分になってるって聞いたッス。お値段変わらずで」
「って亜獣の肉かよ。亜獣って肉食多いからイマイチなのが多いのによ」
「カシムさんとこの旦那なら、そのあたりは上手いこと調理してるんじゃないッスかね? 少なくとも材料が余ったからって不味い代物を客に平気で出すような店じゃないですし、もし出してるならあんな人気な訳ないでしょうし」
「……ま、それもそうか」
「で、一応まだ温かいんでさっさと手をつけたいところなんスけど……あっちの方は今何本目で?」
「んー?」
シモンズが見るのは、先刻までマヒトが眺めていた丘の下方。自分達が居る頂上から大凡百歩の距離を置いて戦う二人――【NAME】とリヴィエラ・シオレの姿である。
マヒトとシモンズはリヴィエラの護衛役。それ故、リヴィエラが少し前から【NAME】という名の冒険者と行うようになった訓練にも全て同行している。
訓練を行う日は、大抵丸々一日使って行われるのが常だ。最初の頃は互いに両手を繋ぎ、クーリアという姿の無い何者かの指導を受けながら延々ろくに身動きもせず半日潰すなどザラであったが、最近は完全に実戦形式の戦闘訓練ばかりである。
武器防具はそのまま利用した、殆ど制限のない一対一の戦闘。
十戦を一単位として行い、間にアエル補充を兼ねた休憩を挟む。それを何度も繰り返して、習得した様々な技の使用感を覚えていくという手法らしい。
その段階に至るまでの時間はマヒトが想定したよりも遥かに短く、最初は大丈夫かと止めようとした事もあったが、クーリア曰く「リヴィエラさんは誤解を気にせず言えば化け物」であり、実際今、彼女が【NAME】と戦う様子を見ているマヒトからしても感想は似たようなものとなっていた。
「確か七本目だったかな――っと、今丁度八本目になった」
【NAME】が対亜獣などで見せる動きとほぼ変わらぬ本気の速度、強さで打ち込んだ技法を木の杖の払いで易々と払ったリヴィエラは、その動きに宝精を呼び出すための石の打撃を絡めており、至近にて宝精――それも殆どクズ石に近い石から中位級の宝精を呼び出しての突進を受けた【NAME】は堪えきれず、十数メートル程吹き飛ばされたのだ。その時に【NAME】は完全に地面に倒れた上、武器が手元から飛ばされていた為、リヴィエラが一本取ったという判断になるのだが、
「……まさかこの短期間で、【NAME】と良い勝負出来るくらいまで腕が上がるとはなぁ……」
我知らず、呆れたような声が漏れる。
あの戦いについてはド素人、普段の鈍臭い動きに、失敗宝精であるプリュクルを召喚しまくるリヴィエラを見慣れていた身からすると、もう別人じゃないのかという感想が沸いてくるのも仕方無かろう。
「今のリヴィエラ様、動きは殆ど超人並で、宝精召喚も完璧どころか質の悪い石からでも確実に一段上の宝精を呼び出せるようになったんでしたっけ」
「まあ、宝精召術の方は才能が別の観点を得た事で開花したって話だから、あれが素の実力って事らしいけど、他の部分に関しちゃ【NAME】からアエルってのを分けて貰ってそれ全力で注ぎ込まないと無理らしいからな。普通にしてるとアエルなんて然う然う溜められないって話だし」
「それを考慮しても、無茶苦茶な話ッスよねぇ……。棒術とか体術なんて全然修めてないのに、【NAME】さんと互角に殴り合ってるッスよ」
確かに、今視線の先では起き上がった【NAME】との八本目が繰り広げられている訳だが、マヒトとシモンズの目からは何やら全身や手にした棒から得も言われぬ不気味な気配を纏ったリヴィエラが、【NAME】の振るう武器の直撃を受けても傷一つ受けないまま、逆に反撃まで繰り出している異様な流れが展開されている。
以前に説明された話を信用するならば、【NAME】が使う技法術式もアエルが織り交ぜられているため、あれでもアエルを使った防御法を習得したリヴィエラにも相応のダメージを与えているらしい。ただ実体ではなく、先に彼女が管理するアエルの方が消費される事から、見た目何のダメージも受けていないように見えるだけ、との事だ。
そんな事を思い出しながら眺めている間に、戦況も変化する。
近接の距離へと近付こうとした【NAME】に向けてリヴィエラが杖を翳し、何か強い気合の声を発すると同時。無形の力が先端から弾け、空間が歪に破裂していく。マヒトからすると無秩序な破裂の連続に見えるそれを、【NAME】は勘か何らかの感知かによって捌き、回避し、距離を大きく取り直すことでどうにかやり過ごしてみせる。あれはアエルを使った純攻撃術技の一つで、同じアエルを使った防御を行わずに直撃すると、複数の破裂の内の一発を貰うだけでも致命傷になりかねないという。
そんな激しい攻防を繰り広げる二人を、マヒトとシモンズは何とも言えない表情で眺める。
「……何かこう、アレ見てると自分達、護衛役としての存在意義がちょっと揺らいできてるように思えるッス」
「起請術式使ったオレ並の速度出しながら立ち回ってるしなぁ、御嬢」
【NAME】が完全な本気で相手をしているかというと否ではあるだろうが、しかし手を抜いているかというとそれも否。冒険者として相当な経験を持ち、マヒトからしても自分より遥かに上の実力を持つと認めている【NAME】と正面切ってやり合えている時点で、今のリヴィエラの戦闘能力は自分達よりも上であると判断するしかないだろう。
「……つっても、いくら【NAME】に揉んで貰ってるとはいえ所詮は付け焼き刃だから、本当の殺し合いでどこまで動けるかってのはまた別の話ではあるんだけどな」
「そこはもう経験と本人の性根が効いてくるッスからねぇ……。まぁ、その時どうなろうと、今やってる事が無駄になるって訳じゃないッスから、やらないよりはマシじゃないッスかね」
「妙な自信付けて、迂闊な真似しないでくれりゃいいんだが、この先どうなるかがはっきりしねーから何ともなぁ……お? 【NAME】が取り返した」
巧いな、とマヒトは小さく唸るように溢す。
攻撃と攻撃の間に割り込むようにして一気に詰め寄り、甘い動きで武器を突き出して誘いを掛ける。対してリヴィエラが防御の為に杖を向けてくるのを待ち構え、そこから瞬時に動きを早めて絡め取ったのだ。
そのまま杖を跳ね上げた動きで彼女の上体が反り、がら空きになった胴部に【NAME】の遠慮の無い蹴りが叩き込まれる。
体術絡みの技法を使ったのだろうそれは、リヴィエラの小さな身体を面白いように吹き飛ばした。
以前までのマヒトとシモンズなら大慌てで走り寄っている所だが、今のリヴィエラであれば、少なくともアエル切れしていないならあの程度はどうという事は無いのは判っているので涼しい顔だ。実際、十メートル以上は飛んでごろごろと地面に転がったリヴィエラであったがそのまま平気な顔して直ぐさま立ち上がっている。但し、武器として使っていた杖は【NAME】に取り上げられているのでこれで一本。
現在の成績は【NAME】が六に対し、リヴィエラが三である。
直近の十本戦の戦績は大凡九対一から五対五あたりをふらふらと行き来するような状態なので、まだまだリヴィエラが【NAME】に追いつくのは難しいようだが、現状でも破格の成長と言ってしまって良いだろう。
リヴィエラが多少距離を詰め直し、【NAME】が手にしていたリヴィエラの杖を彼女へ投げて返して、さて最後の十本目が始まる――かと思ったのだが。何やら二人はその場で棒立ちのまま言葉を幾度か交わすと、連れ立って自分達の居る大樹の木陰の方へと歩いて戻ってくる。
「あれ。もう一本あるんじゃないんスか?」
「の、筈なんだがな」
首を捻るが、防御失敗による負傷やリヴィエラのアエル切れ。クーリアの途中指導が入ったり、或いは武器防具の不具合などで、十本戦の途中で切り上げというのは偶にあるのだ。
「まぁ、こっちとしてはメシがこれ以上冷めなくて有り難いッスけど」
それについてはマヒトも同意見な上に、どうせ自分達は単なる見物者だ。訓練を行う当人達が終いということならそれで良かろう。
近付いてきた二人に、昼飯あるぞーとばかりに包みを掲げてみせると、歩いてきた二人の顔が露骨に綻ぶ。包みの柄からカシム印の弁当であるのが判ったからだろう。もしオレが逆の立場でも同じ顔をすると頷き、包みを広げて昼食の準備を進めながらやってきた二人を迎え入れる。
「マヒトさん、シモンズさん、いつもお昼の用意、ありがとうございます」
リヴィエラがふわふわと笑いながら頭を下げて、隣の【NAME】が礼の代わりに貨幣を投げ寄越してくるのを受け取りながら、
「お前等、もう一本はどうしたよ。何か問題でもあったか?」
と、マヒトは何となく先刻の疑問を口にする。すると、返事は意外なところからきた。
『ありましたよ問題! もー問題も問題。大問題が!』
何も無い空間から、弾けるようなそんな声。【NAME】が連れている妖精とはまた別の、姿の無い何者か。本人曰く、クーリアという名を持つ存在の声だ。
「こいつ、戦いの訓練始める前からずっと反応なくてさ。やっと喋りだしたと思ったら『大問題です! 大問題が発生しましたから、即刻訓練中止してくださいっ!』とか言い出して」
ぴょこんと、【NAME】の後ろから小憎たらしい顔の小さな妖精が呆れたような声音で笑う。
『いやでも、実際大問題なんですからしょうがないじゃないですか! さっきまで“本体”の方でもてんやわんやで、“私”の方にもなかなか正確な形で情報が伝わってこなくて、さっきからじっと意識集中し続けてたんですよ!?』
「取り敢えず、大変だったのは判ったッスけど、何がどう大問題だったんッスか?」
包みの中に入っていた長筒を取り出して、小さな杯に飲み物――筒に茶葉を入れ、適度に温かくしたものを淹れて回っていたマヒトの言葉に、クーリアは『それなんですよ!』と叫び、続けてこう宣ったのだ。
『なんとびっくり! 『礎の世』の方で、“王格”誘拐に絡んだ一連の事件に対する“犯行声明”が行われたんですよっ!』
・
いつもの戦闘訓練を途中で強引に切り上げられる形となった貴方は、リヴィエラ達と共に昼食を取りながら、興奮した様子で話すクーリアの言葉を聞いていた。
それは『礎の世』に於ける最大規模の反“派閥”組織――エギアクルスと名乗る集団から、所謂犯行声明とも取れるものが発せられたという報告だった。
その声明曰く。
彼等は自分達が『礎の世』に於いて世界の理を司る“王格”達の一部を異世界へと送った張本人であると名乗り、更に移動した先の異世界にて大規模な術技を行い、『礎の世』の世界法則を宿す“王格”を存在ごと解体、浸透させる事で異世界を基盤ごと変質させ、そこを新たな『礎の世』とするのだという。
そして最終的には異世界への移住を行い、現社会体制――つまり“派閥”による支配からの脱却を目指す、と謳ったらしい。
「――んで? それって現実的に可能な話なのかよ」
『出来る出来ないで言えば出来なくもない……ですけど、少なくとも『礎の世』の在り方は何もかもひっくり返す必要がありますねぇ。で、それが現実的に受け入れられるものかというと、まず無理としか言いようが無いくらいのひっくり返し方になります』
「具体的にいうと?」
マヒトが続けると、貴方の肩上、リトゥエが座る逆側で空気が振動し、新たにクーリアの声が生まれる。
『こっちの世界は基本となる世界法則が大きく乱れて、まあ色々ろくでもない状況になると思います。これまで当たり前に存在していた法則に例外が紛れ込むんですから、異常現象の多発、天変地異、下手すると世界自体の欠損や崩壊が起きる可能性もあるでしょうね。『礎の世』の方はもっと致命的です。世界の基盤法則自体が余所の世界に移植されてしまうんですから。元々存在していた法則が『礎の世』上から完全に失われてしまう形になります。こうなるとエギアクルスの思惑にのって全“王格”がこちらの世界へ渡り乗っ取りを行うか、あるいは元の世界で残された“王格”によるギリギリの世界維持を行うかの二択になりますが……』
クーリアの言葉が憂鬱そうに一度途切れる。
『……元々衰退の方向に進んでいた『礎の世』ですから、後者を選べば世界の寿命が一気に縮む形になるでしょう。かといって前者を選んだ場合も、全ての“王格”が異世界に渡って、そこの世界の法則に干渉なんてすればもう滅茶苦茶になるでしょうし。もしそれが成功したとしても、そこから“人の形”を保ってこちらの世界に渡る事が出来る者なんて、果たして何人いるか――みたいな状況になるでしょうね』
どちらに転んでも末世ですよ末世、と心底疲れた声音でクーリアは語る。姿があれば、肩を竦めて首を横に振っているような調子だ。
ここまで一切口は挟まないまま、包みの中に詰め込まれていたパンをもぐもぐと口に突っ込んでいた貴方は、うーんと首を捻った。
結局のところ、エギアクルスという連中がやろうとしている事を一切成功させず、完全に阻止しない限り、状況の平和的な解決とやらは不可能であるようだ。
これまでの“王格”を探し元の世界へと戻す、という大目標自体に大きな変化はないのだが、それに至るまでの制限が一気に厳しくなった、と認識すれば良いのだろうか。
(に、しても……)
そもそも最大規模の反“派閥”組織の名前どころかその存在すら、自分は今初めて聞いた程なのだが。本当にそんな組織あるのだろうか。
思ったままの感想を口にすると、クーリアからは『貴方がそう考えるのも、別におかしな話でもないですよ』との返事。
『そんなものが存在している事自体、“派閥”の中で暮らしている末端の人々には隠されてますから。そんな連中が居るのを知られる事自体が、“派閥”の管理態勢に揺らぎを生じさせる事になりますし』
それもそうか、と貴方は納得する。
“派閥”は一つの集合体の中であらゆるものを補い、満たそうとする為の集団だ。国家等よりも概念としては上に属し、在り方としては社会概念に近い。故に、自分が所属する“派閥”の外についての情報は極端に手に入りづらくなる。
例外は“派閥”の上層や外交を受け持つ者達か、あるいはクーリアの所属するマウスベンドールのような“派閥外”に身を置く存在と接点を持っている者くらいだろう。
『まあ、そもそも各“派閥”の力が強すぎて、反“派閥”組織なんてあろうがなかろうがどうでもいい烏合の衆――みたいに考えられてましたし』
「でも、その烏合の衆と思ってた連中が、今回こんな大事を起こしたって言ってきたんッスよね? つまり、“派閥”って連中がエギアなんとかの力を見くびってたって事ッスか? それとも完全なブラフとか?」
シモンズの言葉に、確かになぁと貴方も頷く。
そもそも犯行声明とはいうが、その発言の信憑性というのがどの程度あるものなのだろうか?
クーリアの言う力関係から考えれば、そんな大それた真似を“派閥”を出し抜いて出来るものなのか、という疑問が先に付くのだが、しかしクーリアがこれだけ慌てた様子で話を持ってきたということは、少なくとも元の世界『礎の世』ではそう捉えられてはいない事になる。
対して、クーリアの方は少し口篭もるような間を置き、
『普通なら、こんなの即黙殺されるような代物なんですけれど、問題はその声明を行った……というか時限式で残していった人物に問題がありまして』
「なんかマズい感じの人だったの?」
リトゥエの問いに、クーリアは『大正解です』と短く返し、
『なんと“王格”本人。しかも非常任ではありますがかなり大きな“派閥”の上層を務めていた、数少ない“派閥”の政治に関わっていた“王格”からの声明なんです、これ。立場ある彼の手によるものだから、各“派閥”に反“派閥”勢力発の声がしっかりと届けられたんですよ。普通なら届きすらしません』
「……つまり、アレかよ。二重スパイとかそういう?」
『スパイ……といって良いものかは判断に迷いますが、事実として言えるのは、その“王格”の方が“派閥”の上層部に在籍すると同時に、反“派閥”組織に属する存在でもあった、という事ですかね。後、この人物が他の“王格”達に色々と勧誘を行っていた事も既に掴んでます』
そう言えば、以前にクーリアから“王格”の話を聞いたときに、何やら他の“王格”を口説いている者が居たとか、そんな話を聞いた覚えがある。その人物がつまりは犯行声明とやらを残した当人であったと、そういう話か。
しかし、クーリアから聞いた声明からすると、“王格”は存在自体を術技によって分解し、この世界に解け込んでしまうとか、そんな話だった気がする。つまり、その“王格”は自らの人としての生を投げ捨てても構わないと、そう考えて今回の件に臨んだのだろうか?
『残念ながら、そのようですね。元々、我が身を省みず誰かの為に事を為そうと考える傾向があった方だそうですし。因みに、こっちの世界へと移った他の四人の“王格”達が彼に同調していたのか、それとも望まざる形で巻き込まれたのかは、今となってはもう判りません。“王格”達はどうやら世界を転移した時点で、既に人としての在り方を失っているそうですから。本人達から聞き出す事はもう不可能である、と考えられます』
「……それも、声明からの情報なのですか?」
リヴィエラの問いは、恐る恐るといった調子だ。純粋に、話の内容に恐怖を感じているようだった。
『その通り――というか犯行声明とは言いましたけど、件の“王格”が残したメッセージは、殆どネタ晴らしのようなものですね。既にあらゆる準備を整えて、“派閥”が手を回しても間に合わない段階にまで来たところで、勝ち誇るために残した伝言……と言いますか。声明とほぼ時を同じくして、未来のフローリアと過去のグローエス、その二点にてアエルの量が急速に増大していくのが観測されています。恐らく声明と同タイミングで、話にあった大規模術技の行使を始めているんだと思います。加えて同時に、『礎の世』側でも世界間転移や観測に対して、大規模かつ多面的な妨害工作が行われていて、正直な所、かなり不味い状態です。私の“本体”も、今はそっちの対処と情報収集に掛かりきりで、お陰で“私”に入ってきている情報は、大分頻度と精度が下がっていますが。……取り敢えず、現状判っているのはこんな所ですね』
「…………」
貴方達は一様に黙り込む。
クーリアの話から判るのは、兎に角状況は芳しくなく、解決には早期の行動が必要であるという事だった。
エギアクルスとかいう集団が行うと宣言した方法。もしそれが成功したならば、『礎の世』の人々は確かに緩慢な終わりが近付く世界を捨て、未来ある新天地を手に入れる事が出来るかもしれない。
だが、その結果に至る前の段階で、既に凄まじいまでのリスクとデメリットが生じるであろうし、万一成功したとしても取り返しがつかない形となるだろう。
――あらゆるものを捨てて異世界へと渡る。
それは、今の『礎の世』を構成している社会は疎か、『礎の世』で暮らす人々の姿形すら失われるものの筈だ。果たしてそうまでして望むに足る事であるのかどうか。貴方からすると、判断しがたいものだった。
「……まぁ、大雑把な話は判ったが、そんで、お前達は具体的にはどうするつもりなんだ?」
ぺろりと、手にしたパンを食べ終えて、指を軽く舐めたマヒトの視線は、貴方と、そして見えないクーリアへと向けられていた。
――どうするか、か。
問われて、独りごちる、
“派閥”からの指示、のようなものは来ているのだろうか? 内心でクーリアに問うと、返事は音声として返ってきた。
『現在の秩序の維持者、社会の支配層である各“派閥”上層部は、この行為の阻止のために全力を注ぐと宣言してします。既にエギアクルスに対しては全“派閥”総出での掃討作戦が始まっていますし、テロ的に仕掛けられた妨害工作に対しても、急ぎ対応を行っています。が……』
そこで一旦、口篭もる。
『……状況は既に『礎の世』側でどうにかできる段階ではなく、こちら側の世界で“王格”を分解浸透させる大規模術技を阻止し、“王格”を確保出来るかに否かに掛かっています。当然、私達にもそれを為すよう最上級の命令が出ていますね。ただ問題は、エギアクルス側が行った妨害工作の部分で、これのお陰で『礎の世』側からの援護や増員がほぼ望めない状況になっています』
つまり、現状の戦力のまま、新たな情報や補助も満足に受けられない状況で、早急に全ての“王格”の場所を掴み、今まさに行われているであろう大規模術技が完成する前に事態を収拾せよ、と。
『そう、なります』
「無理じゃねーの?」
苦しげなクーリアの声に、簡潔なマヒトの言葉が場の空気を凍らせる。
しかし、それが全くの正論であることは、この場に居る全員が理解していた。
『……“王格”は世界の理を具現した存在です。それを解体する術技となると、終了までに相応の猶予が存在する筈です。それまでにどうにか、“王格”達の場所だけでも判れば良いのですが。――リヴィエラさん、今の貴女なら、どうにか判りませんか?』
話を向けられたリヴィエラは、困り顔で眉根を寄せる。手にしたままのパンは未だ一つ目で、それもあまり減っていない。
「クーリアさんから色々教えて貰って、“光”は凄く遠くまで感じられるようになりました、けれども……まず“王格”……? それが、どんな“光”を持つものなのかが判らないから、探そうにも……」
『ですよねぇ』
予想していた返答なのか、クーリアは然して気落ちした感じも無く返す。それに、リヴィエラは考え込むように空を見上げて、
「一応、ここ最近、広く“光”の動きが変わってきたっていうのは、感じます。だから、これがクーリアさんの言っていた事の兆候なのかな? とは思うんですけれど……でも、その大元が何処か、みたいなのはちょっと……」
「リヴィエラ様がダメとなると、後何か方法はあるんスか?」
食欲無さげなリヴィエラとは逆に、もっしゃもっしゃとパンを貪るシモンズがそう訊ねるが、対する声は至極鈍い。
『うーん……。悠長に探索などしている時間は無くなりましたけど、かといって新しい手掛かり等があるわけでもない。タイムリミットは突然で、そして『礎の世』からの補助は以前よりも難しくなっていて“派閥”側は具体的な指示を出せない状態。マウスベンドールでも色々動いてはいますけど、結局妨害工作の影響は『礎の世』全体に出てるから、状況はうちも“派閥”と大差なし……となると』
一拍置いて、結論を呟いた。
『……手詰まりですね』
誰も反論出来ず、暫しの静寂。
丘に吹く小さな風の音だけが、暫く場にゆるゆると響いて、
「――君達が手詰まりという事ならば丁度良い。我々からの誘い、受けてはいただけないでしょうか?」
「!?」
そして突然割り込んできた男の声に、何処か弛緩していた空気が、一気に緊迫する。
ほぼ全員が立ち上がり、身構えながら視線を声が生まれた先。ほんの少し前まで何も存在していなかった場所に向ける。
丘頂上、大樹が生み出す影から数メートルほど離れた場所に、一つの人影が誰も気づかぬ内に立っていた。
黒の侍従服に身を包んだ、褐色の肌に波打つ髪を後ろに流した青年。それが、影が保つ姿だった。
「……一体いつの間に来やがった、こいつ」
「つーか、どっかで見たッスね、この人」
槍を脇に挟み、斧を両手で構えながら、マヒトとシモンズが呟く声に、貴方は記憶を探る。
思い当たる姿は――あった。
「あなたは……アサーンの都に居た人?」
そうだ。剣都アサーンでの、あの地獄のような出来事。その中で、ヴォルガンディア闘技場にて対峙した“同化者”の老人が連れていた者達の一人だ。
リヴィエラが緊張に満ちた声で問い質せば、青年は浅く首肯する。
「ええ。自分の名はラバナと申します。我が師にして主、シバリスより伝言を託され、こうして貴方達の元に足を運んだ次第です。己が残した術技の後継者である“派閥”の“同化者”に対し、師から一つ提案がある、と」
『……提案、ですか?』
ラバナは細い目で場に居る者達を順々に、見定めるように眺めて、そして最後に貴方の顔で視線を止めると、頷く。
「提案ですね。“派閥”に所属する“同化者”と、彼と行動を共にする者達であるならば、既にエギアクルスによる声明は把握しているでしょう? 状況は切迫していて、そしてそれは我々にとってもあまり良い形であるとは言えない。だからこそ」
貴方を見る視線が、細く、鋭く。内心を図るように絞られる。
「我々と対話し返答を問う場へと君を招待します。我が師の屋敷にね。そこで師が直々に、手詰まりだという君等へ、現状を打開するための術を授けて下さるでしょう」
「随分とまぁ……こちらに都合の良い話だなおい。一体何企んでやがる」
マヒトの煽るような物言いに、しかしラバナは眉一つ動かさない。
「勿論、我々にも企みや都合がある。警戒するのも当然でしょう。ですが、君達にはこの提案を断る余裕は無いでしょう? 最低でも、今以上の情報を得るためには、このシバリスからの誘いに乗らざるを得ないのですから」
その言葉に、黙るしかない。
それを見届けて、ラバナは小さく鼻を鳴らす。
「勿論、それでも受けるか否かを選ぶ権利は君達にもあります。もっとも、闇雲に彷徨い何もかもが手遅れになる前には、我が師の所を訊ねてくれると我々としても助かるのですがね」
告げて、ラバナはこちらに背を向けると、最後に一度、目線だけ振り返り、
「――支都ルアムザ、シバリス・カーライル邸。そこで我々は待っていますよ」
そしてアエルに由来する無色の力が男の全身を包むと同時。泡となって弾けるように、ラバナの姿はこの場から消えていった。
礎の王格 同者との交渉
――同者との交渉──
過去には珍しい名を持つ彫像を高額で買い取る奇特な貴族として、冒険者達の間で広く知られていたシバリス・カーライル氏であるが、今ではそれも昔の話。彼の名前が冒険者達の間で上がらなくなって久しい。
ここ最近は固く閉ざされたままであったというカーライル邸正面の門は、今は浅く開かれた状態であった。貴方はそこをすり抜けるようにして邸内へと入り込む。
「なんというか、何処か胡散臭いというか……嫌な感じがする家よね」
『入ってみて判るんですけど、イーサの方では殆ど術を施されてない代わりに、アエル関係の術がかなりの量仕掛けられているせいで、リトゥエさんからはそう感じるのかもしれないです。……なんというか、内から外に色々なモノが漏れ出さないようにする類の結界が、多重で敷いてありますね』
「何それ怖い。入ったら出られなくなるような?」
『いえ、リトゥエさんのようなこちらの世界の人達用じゃなくて、アエル絡みの人達向きの結界です。この屋敷の中でのアエルの動きを外から感知されないようにするとか、そういう類の。リヴィエラさんが居れば、アエルがどんな感じで塞がれたり隠されてるのかが“光”で見えたとは思うんですが……』
貴方の肩に腰掛けて、気味悪げに辺りを見回しながら話すのはリトゥエだ。対して、空間のみを震わせて声を生み出すクーリアの方も、何処か警戒感の濃い声色を作っている。
今回、シバリス・カーライルの屋敷にやってきているのは貴方とリトゥエのみである。純粋な戦力として考慮するなら今のリヴィエラは当然として、マヒトやシモンズ達ですら居てくれると有り難い存在ではあるのだが、今回は以前アサーンで対峙した相手――“擬象”のような凶悪な代物を生み出して、生死の遣り取りにまで至った相手の本拠地へ赴くという、正に虎穴に飛び込むような行動である。そんなところにリヴィエラを連れて行くのは、以前マヒトと約束した「リヴィエラを迂闊に危険な目に遭わせない」という項目に反するように思えたが故だ。
勿論、どうしようもない程に追い詰められ、切り抜けるための戦力が必須となる場面ならば、危険であろうともリヴィエラ達に助力を乞うのも致し方なしと考える事も出来たが、今回についてはあくまで話を聞きに行くだけである。正面切って戦うという予定ではなく、いざとなれば早々に逃げ出すという選択肢も取る必要が出てくる場面だ。ならば大人数で赴き相手を刺激したり、逆に身動きが取りづらくなるよりも、ほぼ単独行の方が身軽な立ち回りが可能となり、こちらの方が逆に良いと判断したのだ。
リヴィエラ達は支都内で取った宿のほうで、自分の帰りを待ってくれている。別れ際の、心配のし過ぎで顔色をかなり悪くしたリヴィエラの様子を思い出すと、早めに話を終えて帰ってやりたいところだが、果たしてそう上手く行くのかどうか。
『そもそも、一体あのお爺さんに“同化”した奴は、私達に何を言ってくるつもりなんでしょうね』
「えーっと。例えば、あの人が何処かの“派閥”ってところの“同化者”だとしたら、今の【NAME】やクーリアとは、あんまり変わらない立場なのよね?」
『の筈ではあるのですが……この世界に於ける貴族階級の者と“同化”しているなら、そちら経由のコネクションから私達が得られないような情報を仕入れているという可能性もありますし。それに前回の彼――ラバナさんでしたか。彼の物言いにも少し引っかかる所がありましたから、もしかすると』
と、そこで庭が終わり、屋敷の入り口に辿り着く。どうやら無駄話の時間は終わりのようだ。
備え付けられていた呼び鈴を鳴らし、待つ事暫し。扉が開き、顔を出したのは、
「あ、兎の人。いらっしゃい」
「――――」
忘れようとしても忘れられない、侍女服に身を包んだ小柄な金髪の少女の姿だった。
確か名前はメリシェン。“兎”という言葉にアサーンでの出来事が蘇り、思わず息を呑んで固まってしまう。
確かあの時は、こちらを狩り手から逃げ惑う“兎役”として定めて、躊躇無く自分達に“擬象”を差し向けてきたのだ。当時の敗北の記憶は、未だ色褪せてはいない。
だが、相手の方はそんな事に頓着している様子は無く。【NAME】の顔を暫し眺めた後、その視線を横へとずらす。
「わ。妖精さんね。こんにちは」
「ん、えっと、こんにちは?」
リトゥエは困惑気味に言葉を返す。一応張っていたらしい隠匿結界はあっさりと素通りされたようだが、貴方のように彼女に対するトラウマ染みた経験が無いリトゥエは、そのまま少女との会話を続行する。
「それで、ええと、私達、ここのお家の当主様に呼ばれて? 一応やってきたんだけど……話ちゃんと通ってるかな?」
「……?」
茫洋とした視線のまま、彼女は小さく首を傾げる。
話通ってないのかよ大丈夫か、と一瞬その場から逃げ出したくなった貴方だったが、
「……思い出した。聞いてる。来たら主のところに連れてけってラバナ兄ぃにいわれているわ。だから、入っていいよ」
少女はそのまま引っ込んで、以後反応はない。
恐る恐る開いたままの扉から中を覗き見れば、既にメリシェンはこちらに背を向けて、まるでこちらが付いてきているのが当然とも言うべき足どりでとことことエントランスを歩いていた。
「……入っていいのかな」
『むしろ後を追っていないと逆に怒ってきそうな気すらしますね』
正直、屋敷の中から噴き出した色濃いアエルの感覚に怯みすら覚えていた貴方だったが、ここで立ち止まっていても仕方が無い。
貴方は意を決し、既にエントランス奥から繋がる通路の向こうに消えようとしているメリシェンの背中を追い掛けた。
・
「主。お話の兎さん達、連れてきましたー」
声は掛けているものの、ノックどころか返答すら待たずに扉を開けて中に入っていくメリシェンに驚愕の視線を向けながら、貴方もその後に続いて部屋の中へと入った。
場所は屋敷の地下にある一室だ。途中でメリシェンから聞き出した内容が真実であるならば、ここは屋敷の主であるシバリスの研究室の一つ、であるらしい。
中に入ると、成る程と頷けるものだ。
乱雑に紙束が積み上げられた机に、壁際には全て大きな棚。そこには様々な形状の彫像が置かれて、そして広く空けられた中央の空間、石畳の床の上には、染料と思しきもので、複雑な陣が描かれている。それは一見してこの世界で使われる印章陣とは異なる形式によるもので、クーリアからある程度の術技を学んだ今の貴方ならば、それが術技を描画して陣と為して発動させる術技陣の一種である事が理解出来た。
しかし、判るのはそこまでだ。複雑に描かれた陣の紋様から、その効果を読み取る事は欠片も出来ない。所詮は術技を付け焼き刃で習得したこちらとは、そもそもの土台が違うのだ。ここに描かれている術技陣は、極めて高等な部類の代物であると思われた。
そしてその陣の中央には、片手に杖を持ち、床に置かれた一つの像に向かってしゃがみ込んでいた老人の姿があった。
ヴォルガンディア闘技場で、刃を交えた自分と同じ“同化者”、シバリス・カーライルだ。
彼は入室者に気づいて、ゆっくりと振り向き、そして貴方と眼を合わせると、深く、にやりと、口元を歪めて笑ってみせた。
「やあやあやあ。どうやら僕の弟子達は無事君を見つけ、伝言役をこなすことに成功したようだね。ただし、メリシェンよ。客をそのまま僕の居る場所まで連れてくるのは頂けないな」
「そうなの?」
「そうさその通り。普通は応接室で待たせておくものだよ。ま、別にここでも構いやしないし、君にこういう事への真っ当な働きを期待してもいないがいね。どれ、少し待つといい」
老人は床に置かれた像を棚の空いた場所に突っ込むと、部屋の隅に詰み置かれていた椅子を数個、杖先で引っかけ、そのまま跳ね上げる。
くるりと空中で回転した椅子達が三つに離れ、それぞれシバリス、貴方、メリシェンの傍に足から落下する。シバリスとメリシェンは遠慮無く腰を下ろし、そして視線で貴方にも着席を促す。
「…………」
一瞬迷うが、しかし今回は彼から話を聞きに来た身。あまり露骨な警戒心を見せるのも不味いかと、視線や意識はシバリスやメリシェンから外さぬまま、浅く腰を掛ける。
「さてとさて。ではまず最初にこちらの招待を受けてくれた事に礼を言おう、少年。……そして、間の抜けた話ではあるが、僕と君は、まだまともな自己紹介すらもしていない事に気づいたよ。恐らく、僕のここでの名は既に君は知っているだろうから……先に、君の名前を聞いても良いかね?」
別段、否という必要もない。
貴方はこのグローエスで冒険者で活動している人物の名、【NAME】と名乗り、そして僅かに迷った後、自分が主権派に属する“派閥”に在籍している事を伝える。
続けて、リトゥエが名乗り、そして最後に、クーリアが己の存在を音声として明かす。最初はクーリアは存在自体を隠すかという選択肢もあったのだが、いざ対話となった際に、【NAME】が正面切って話すかクーリアが表に出るかで、得られる情報量等に大きく差が出る可能性も考え、早々に存在を明らかにする事にしたのだ。
対し、老人はにこやかな笑みを浮かべて数度頷き、興味深げにリトゥエと、そして貴方の内側に寄り添うように存在するクーリアを見通すように眼を細めてみせる。
「ほうほうほう。妖精殿に、マウスベンドールの末端の子か。こちらの世界の妖精というのはあまり見ぬ存在であるし、そしてマウスベンドールの子が直々に付くとなれば、【NAME】。どうやら君は、僕の予想通り、“派閥”から相応の価値を見出されてこちらの世界へやってきた存在であるようだね」
「…………」
シバリスの反応に、貴方は少し情報を出し過ぎたか? と焦る気持ちが生まれる。
しかし、そんな心の動きも老人はお見通しであるようだった。彼は微かに苦笑をしてみせると、僅かに居住まいを正し、貴方を正面に捉える形で背筋を伸ばすと、
「どれ、ではそちらが見せてくれたものに、ある程度は応えてあげよう。――僕のこの身の名はシバリス・カーライル。立場はグローエス旧貴族に連なるもの、という事になっている。そして『礎の世』での立場を語るなら――」
ふ、と鼻から抜けるような笑みの音が聞こえて、
「――反“派閥”組織エギアクルスの術技顧問、というのが恐らくは最も正しい表現であろうね」
ある意味、爆弾にも近い情報をこちらへ叩き付けてきた。
・
「さてさてさて。君達も当然把握しているだろうが、今は正直時間が無い。だから、手短に、僕から君に対する提案を行っていきたい。故に質問は話の後で、最小限に留めて貰えると助かる」
貴方やクーリアが反応を示す前に、老人は一気に言葉を続け、それを封殺してきた。
『……随分と、上から目線で語ってくれますね』
「うんうん。それについては、君達に対してそれだけの材料というものを僕が持っているという自信があるからと、そう思って貰って構わないよ。その証拠に、そうだねぇ」
シバリスは少し視線を虚空にやると、こう続けた。
「僕は、この世界に転移してきた五つの“王格”、その所在をほぼ把握している」
「……!?」
「どうだいどうだい? もうこれだけで、君達とは立っている舞台が違うのが判るだろう? 先刻言ったと思うが、僕はエギアクルスという組織の中でそれなりの地位に居た。だから、君達“派閥”側が把握していない情報を、数多く持っている、という訳なんだな、これが」
「……えっと。ちょっと待って。質問ダメって話だけど、これだけ聞かせて?」
「ふむ、何かな妖精殿?」
「つまり、お爺さんは結局私達の敵なの? 話聞いた限りだと、完全に所属が敵味方に分かれてるんだけど」
小さな妖精の恐る恐るの問いに、老人は二度三度と頷き、
「それについては、現状を最も的確に表現するならば“敵ではあるが味方ともなりうる”というのが近いだろうかなぁ? まあ、その辺りの疑問の解消にもなるから、僕から君達への“提案”を少しばかり黙って聞いてくれると助かるな。何、直ぐに終わる話だから、少し待ってくれるだけで良い」
「…………」
貴方とクーリア、そしてリトゥエが沈黙したのを確認して、シバリスは何処か楽しげな調子で話し始める。どうもこの男、単に話すという行為自体が好きなようだ。
「物凄く簡潔に言うと、僕は確かにエギアクルスに在籍していたのだけれども、別にエギアクルスの理想とか、目的にとかに感銘を受けて所属していたという訳じゃない。単に自分の“実験”に都合が良い環境であったから、そこに居ただけなんだ。そして、僕の立場からすると、あのエギアクルスに荷担していた“王格”がやろうとしていた計画が実行されると、少しばかり困ってしまうんだよ。……“王格”を、そんな無駄な事に消費されるのは忍びない」
であるのでね、と彼は間に挟み、
「僕はそれを阻止しようと考えているんだが、しかし情報や方法はあれども、残念ながら少しばかり手が足りなくてね。どうしたものかと思った時に、丁度君の事を思い出したと言う訳だ。つまり、僕が言う“提案”とは――【NAME】、僕達に手を貸して、エギアクルスの計画を阻止するのを手伝ってくれないか? というものだよ」
「……確かに、簡単な話ではあるけど」
『疑問が全く無いかというと、そうでありませんね。そもそも、貴方の目的は何なのです?』
「それは秘密。だって、自分のまだ成し得ていない“実験”は、おいそれと他人に語るものではない――というのが僕の美学でね。ただまぁ、君達にとってあまり利になるものではないのは確かだ。つまり、最終的には僕と君達では利害は一致していない」
しかし、そういう物言いをするという事は。
『ですが、途中までの利害――エギアクルスの計画を阻止し、“王格”がこの世界上で分解され、浸透されては困るという部分は一致している、と』
「そう! だから、少なくともそこまでは、僕と君達は共に力を合わせられると、そう思うんだよ。……そして勿論、それが終わった後はその力を互いに向け合う事が当然だともね!」
朗らかにそう語る老人に、貴方は僅かな畏怖すら覚えた。目的を果たした後は敵対する事になると、そう堂々と言い切ってみせる。恐ろしいまでのクレバーさだ。
「ちなみに言うとね、こちらから提供できるものはかなり多い。だから、この話ははっきり言ってしまうと君達が得られる利の方が遥かに多いと思うよ。だから最初から“交渉”とか“取引”とは言わずに、“提案”と言ってたんだけどね。まずこちらからは、“王格”の居場所についてと、そして“王格”を一時的に封じる手段が提供できる。今はもうエギアクルスが“王格”を捕らえ、大規模術技を行っている最中だからね。場所は動かせないから、居場所についての情報はほぼ確実だ。加えて、大規模術技を破壊した後に残された“王格”をそのまま放置する訳にもいかないから、その為の封印具も用意してある」
老人は思わせぶりに、先程まで部屋の中央に置いてあった像に視線を向ける。
『もしかしてその封印具って、“擬象”の核に使ってた……』
「大正解! さすがマウスベンドールの子だね。察しが良い。もっとも、そのままあの像じゃなくて、専用に調整を施した像だけどね。だから君達がやることは、僕が指示した現場に行って暴れ回って儀式をブチ壊した後、像に“王格”を封じてくれるだけで良いって訳だ。まだエギアクルスの世界間妨害工作の影響で、“派閥”側が“王格”を丸ごと元の世界へ戻すってのは無理な状況だろう? だからその間は像を使って“王格”を封じておけば安全という訳だね」
「……えーっとその、なんか話聞いてると、それお爺ちゃん達が全部やっちゃっても問題なさそうなんだけど。なんで【NAME】の事呼んだの?」
リトゥエの疑問はもっともだった。
話を聞いていると、シバリス達だけで捜索、処理、封印、全てをこなせるように思える。自分がわざわざ呼びつけられ、協力を仰がれている理由が判らない。
「勿論、それについては理由はあるよ。第一に――少年が“分離同化”をしている点だ」
その言葉に、流石に貴方とクーリアは揃って絶句した。
一体何故“分離同化”の事を、この“同化者”は把握しているのか。
混乱し、言葉に詰まる貴方達に、老人は悪戯が成功したかのような稚気溢れる目つきで笑い、
「そりゃ判るさ、少年。何せ、その“分離同化”の素案を“派閥”に残していったのはこの僕だからね。君の存在概念の在り方を見れば、その程度読み解けるに決まっている。全く、結局秘奥として封印したモノを表に引っ張り出すのなら、最初から公開して発展させれば良かっただろうに。だから今のように後手後手になるんだよ、“派閥”は」
「…………」
老人の言の真偽が判断出来ず、無言を返すしかない貴方達を気にせず、シバリスはまた朗々と言葉を続ける。
「そのへんは今はどうでもいいとしてね。問題は、五つ存在する“王格”の内、二つが今の時間断面上ではなく、半年後のフローリア諸島にあるという事なんだ。で、第二の理由として、残念ながら、僕の“同化”は“分離同化”の手法を使った物ではなくてね。一応、無理矢理“管”を伸ばして、あちらの時間でのフローリアで最低限の活動が出来るよう手を回してはいたんだが、主体として動くのは少しばかり難しい。そこで、介入できる時間軸の最も未来に“同化対象”を置いているらしい君に、そちらでの“王格”の確保をお願いしたい、という話なのさ」
このシバリスの言で、大分理解が出来るようになった気がする。
要するに、グローエスに居るシバリスであればこの時間上に存在する三つの“王格”に対し介入は出来るが、半年後のフローリアに存在している残り二つについては少し手を伸ばすのが難しい。だから、そちらに“身体”があると推測した貴方に、フローリア側での“王格”の対処を依頼してきた、という事か。
「ただ、像の扱いは恐らく今から君に教えたところでまず習得はできないだろうから、半年後のフローリアへ、僕の弟子を派遣する。だから君には彼女達と一緒に“王格”の居場所へと向かって、エギアクルス達が行っている術技を阻止し、像に“王格”を封印し、持ち帰って欲しい。……これが、僕から君への“提案”なんだが」
そこでようやく、シバリスは流れるように動かしていた口を閉じて、少しの間を作り、訊ねる。
「さてさて、どうだろう、少年。この話、受けてくれるかい? それとも、断るかな?」
「…………」
貴方は内心でだけでクーリアに問う。
――この話、受けずに済むという選択は有り得るのかと。
対する答えも、心の内だけに響くものだった。
『無いですね。現状、“派閥”は五つの“王格”の所在を一切掴めていない。この点だけでも、彼からの提案は破格の代物です。更に、彼は儀式の阻止すらも目的としている。ここまで御膳立てされては、シバリスさんの言う通り、共闘する以外の選択肢はないでしょう』
しかし、問題はその儀式の阻止をしてからなのではないか。
『彼も言っている通り、それすら踏まえた上での提案でしょうね、これは。つまり、トロフィーとして得た“王格”を封じた像を、私達としては自陣に確保したい訳ですが、向こうもそれは判っているからこそ、フローリア側で像を操るための従者を用意する、と言っているのでしょう。つまり、術技を阻止した上で、私達と従者達の間で像二つの取り合いが発生する事を前提とした提案です』
そう考えると、あまりにもこちら側に配慮というか、有利な条件の提案にも思える。わざわざ、こちらに“王格”を手にする好機を与えてくれているようなものなのだから。
その辺り、警戒すべき要素となり得るのかどうか。
『シバリスさんの目的が読めないから何とも言えませんが、結局、私達は“王格”を一つや二つ確保出来たところで、シバリスさんは三つの“王格”を確実に確保している事になります。そしてシバリスさんは“王格”を“実験”に使うと言っている。それは“派閥”の目指す“王格”の全奪還に反する行為です。結局彼との戦いとなるのは避けられないでしょうし、そして“王格”を保有している相手と戦うのであれば、こちらも“王格”の存在が無ければ厳しい。そしてシバリスさんはその辺りも織り込んでの提案、という事なのでしょう』
「…………」
少し話の流れが判りづらい。
もう少し詳しい説明を要求すると、こう返ってきた。
『自分と対抗するために、もし【NAME】さんが“王格”を確保したとしても先に『礎の世』に帰還させる事は無く、自分の所に持ってきた状態で戦いを挑んでくると、そう読んでいるのですよ、シバリスさんは。だからどういう経路を辿ろうと、最後には自分の手元に、全ての“王格”は集まる、と』
成る程、という他無い。
ただ、そういった流れを考慮しても、この提案を蹴るという方向は無いと、そういう話で良いのだろうか。
改めての確認に、クーリアは『受ける形で構わないでしょう』と肯定してくる。
『まず今絶賛進行中のエギアクルスの計画を止めるのが最優先ですからね。これはたった一つでも成功してしまうと、もう後戻りが聞きません。だから腕の立つ“同化者”であるシバリスさんと、二手に別れて急ぎ阻止していこうという提案は、正に願ったり叶ったりです。諄いようですが、本人も言っている通り、これを蹴る選択肢は有り得ないとまで言えるでしょう。例え罠の可能性があったとしても、乗った方が遥かにマシです』
「おやおやおや。随分と考え込んでいるようだが、そこまで難しく悩むような提案であったかな? はっきり言わせてもらうと、これ以上そちらに譲歩を見せた提案など思い付かぬ程なのだがね」
だからこそ、ここまで警戒している訳なのだが。上手い話程、怪しい話もないのだ。
しかし、クーリアとの相談の中で腹も決まった。後、問題と言えるのは、
『シバリスさんの方から従者を付けるという話でしたが、一体何方がその役を?』
「そこに居るメリシェン。あと、ヴィータの二人を寄越すつもりだ。……フフ、二人とも、未熟なところはあるが、見所も大いにある。頼りにするといい」
そう言いながらも、老人の顔は何処か厭らしい笑みを浮かべている。
彼も当然、判っていて言っているのだ。途中までは“頼りになる相手”だとしても、二つの“王格”を像に封じた後、その評価は“手強い相手”へと変化する事に。
「ではではでは、だ。これで僕の提案を君が呑むという形で話は無事終了、という事で構わないかね?」
杖を突き、立ち上がったシバリスに、貴方も頷きながら席を立つと、老人が差し出した手を握り返す。
返ってきたのは、しわがれながらも、所々の皮が硬くなった手肌の感触。
対話の終わりを示す握手の中で、貴方は最後に、シバリスという人物の印象を元道楽貴族というものから、相応の戦士として訓練を積んでいた存在として認識し直す事になった。
・
「そりゃまたなんとも……予想外な展開になったな」
支都ルアムザの外輪部にある場末の宿。
その一室にて集まった貴方とリヴィエラ達三人は、貴方からカーライル邸での提案とその結果についてを説明していた。
「つまりもしかしてアレッスか? 自分達、半年後にそのフローリアって島で、あのマイ天使ちゃん達と一緒に“王格”を追い掛ける旅に出るって事ッスか? 最高じゃないッスか!!」
「あの子と……一緒に……?」
異様に興奮しているのはシモンズくらいで、マヒトには困惑と警戒の色が濃く、リヴィエラの顔は緊張で引きつっている。
その反応は判らなくもない。彼等三人は、“擬象”を引き連れたメリシェンに追い掛けられ、死に物狂いで逃げた経験を持つ。幾ら彼等からして半年以上後の事とはいえ、そんな相手と共闘することに複雑な気持ちを抱かない筈も無かった。しかも、途中まで共闘するとはいえ、最終的には敵対することが確定しているのだ。
「にしても、半年後か。一応説明自体は聞いていたが、中々信じられるもんじゃねーな。俺達が未来で、そんな場所に居るって流れが【NAME】に知られてるって状況が。まぁ、今更疑うもんでもないんだがよ」
正直な所、リヴィエラ達にこれ以降の旅での助力を頼むか否かは迷った。
しかし、エギアクルスによる“王格”に対する大規模術技行使の阻止、そしてその後に行われるであろうシバリス一派との戦いを考えると、どうしても自分一人で切り抜けられるイメージが沸かなかったのだ。
少なくとも今の様々な力を付けたリヴィエラ、出来ればマヒトとシモンズの二人にも、力を貸して欲しいところだった。
貴方が素直にそう告げ、そしてマヒトに頭を下げる。彼には以前に釘を刺された事がある。リヴィエラをあまり危険な事に巻き込むなと。しかし、状況がここまで切迫してしまうと、悠長な事も言っていられなくなる。
そんな貴方に、マヒトは小さな舌打ちを一つ溢し、
「いちいち謝んなよ。こっちだって、もう状況は判ってんだ。今更あーだこーだと口出しするつもりはねーよ。大体、御嬢をあれだけ鍛えちまったのもお前の力あってこそだしな。もうここまでくりゃ、腹括って最後まで付き合ってやるさ」
マヒトの言葉に、貴方は内心の安堵と共に礼を告げる。「だからそういうのやめろってんだろうがよ!」と叫ぶマヒトに他の皆が笑みを溢した。
そして貴方はマヒトとシモンズの二人に、少しばかり考えていた“策”を話す。対する反応は、マヒトの方は渋く、そしてシモンズの方は何故か彼らしくない妙な笑みを浮かべてはいたが、
「……ま、確かに今のままじゃ、“その時”にゃ役立たずだ。だからダメ元でも備えるってなら、断る理由はねーけどよ」
「いやぁ! いいッスね! マイ天にお近づきになれる機会! 俄然やる気ッスよ自分! 自分俄然やる気ッスよ!」
案外と悪くない反応が返ってきた。貴方は二人に今後の予定を簡単に話し、協力の約束を取り付ける。既に状況は始まっている。時間は少なく、付け焼き刃には違いないが、使い所を間違えなければ、その刃は確かな“奥の手”になり得る筈だ。
と、話が一段落したところで、リヴィエラがおずおずと手を挙げる。
「あの、取り敢えず半年後にフローリアという場所で重要な戦いがある、というお話は判りましたけれど、その時の具体的なお話というか、何をどうするかの手順みたいなものについては打ち合わせされたんですか?」
『それについては、改めてあっちで説明するって事になってます。今説明を受けても、“同化者”である【NAME】や付き添いの私はともかく、他の方々は記憶が薄れてしまうでしょうし、向こうも向こうで、どうもフローリア側に手駒か、あとシバリスさんの“管”っていっていたかな。そんなものを手配するみたいだし』
「にしても、フローリアといっても場所は色々あるッスよね。結局、自分達は何処で合流して、件のシバリスさん達の集団と落ち合えばいいんスか」
それについては、別れ際にシバリスが言っていた言葉を、【NAME】はそのまま口にした。
――場所はフローリア諸島を構成する島の一つ、ランドリート島の北の街ラースナウア。
そこでシバリスは、“別の姿”で待っている、と。
礎の王格 苟且なる貴女
――苟且なる貴女──
ランドリート島北端の街、ラースナウアに到着した貴方は、早速そこで待っていたリヴィエラ達と合流した。
グローエスとフローリアで別人の姿をしている【NAME】であるが、より正確に“光”を見分ける事が出来るようになったリヴィエラからすれば、二人を同一人物として認識するのは至極簡単な事だった。
「丁度、面白いタイミングで来たな、【NAME】」
貴方にとっては殆ど間を置かず、しかしリヴィエラ達にとっては暫くの間を置いての再会を祝して、宿屋兼酒場となっている店の一階で軽く食事を取っていた貴方とリヴィエラ達だったが、貴方が街全体の妙に浮ついた雰囲気を察して落ち着かない気分になっているのを察したか、何処かにやにやとした笑みを浮かべてそう話を振ってくる。
何かあるのか、と素直に貴方が問うと、フォークで細かく割いた熱した芋の塊を小さな口でちまちまと食べていたリヴィエラが、思い返すように首を傾げながら応えてくれた。
「なんでも、アラセマ本国の方から、“六家”の一つの……ええとワイゼン? イーディスだったかな? えと、とにかく“六家”の正家に連なる令嬢様がラースナウアに軍人として派遣されてくるそうなんです。そろそろその方を乗せた船が港に到着するそうで、そのまま馬車で街の大通りをパレードされるそうですよ」
凄くどうでもいい話だった。
そんな事より、シバリスやその従者達の姿を見掛けなかったかを訊ねるが、リヴィエラ達は揃って首を振る。
「そもそも今はさっきの令嬢殿の件もあって見物客が多くてな。そんな中で人探しとなると、正味な話かなりきつい」
「一応、リヴィエラ様が街の彼方此方で“光”の具合を追って、アエルを強く宿している人を探したりとか、溜まっている場所を巡ったりとかしてはいたんスけど……」
「ごめんなさい、【NAME】さん。私の方でも、出来る限り探してはみたんですが、あの人達――シバリスさんの従者の“光”も、シバリスさんのような“光”も、上手く見つけられなくて」
申し訳なさ気に謝られるが、彼女等に責任がある話でもない。気にしないで良いと首を振って、しかしさてどうしようと腕を組む。
『改めて考えてみると、結構雑な合流計画でしたよね……。もう少し、ちゃんと詰めておいた方が良かったのかも』
とは言うが既に後の祭りという他無い。
取り敢えずは多少目立つ行動を取りながら暫くラースナウアに滞在し、シバリス側から接触してくるのを待ち、それでも駄目なようならばこちらから探し、最終手段としては一度グローエス側に戻ってシバリスと話を付け直すという方法を採るしかないだろう。
そう結論付け、更に残った最後の肉の塊を放り込んだところで、何やら酒場の外が一段と騒がしくなった。
「どーやら、噂の令嬢様の馬車がやってきたんじゃねーか?」
成る程、それならば外の大騒ぎも頷ける話ではある。
「で、その偉いところの娘さんって美人さんなんッスかね? なんか軍人の娘っていうと、女だてらにムキムキマッチョの男女みたいなイメージが自分あるんスけど……」
「でしたら、丁度今からいらっしゃるようですし、直で見てみれば判るんじゃないですか? ……私もちょっと、興味あったりします。こう、男装の麗人、みたいな感じだったりするかもしれませんし!」
シモンズの予想も、リヴィエラの推測も、どちらもありそうなタイプではあるが。
兎に角、正解は実物を見てみれば判るのだ。丁度皆の食事も終わったことだし、軽く見物していくのも悪くないだろう。
そんな貴方の提案に皆異論はないらしく、金を払って酒場を出ると、人の列を割り裂くようにして道を進み、どうにかやってくる馬車の中が捉えられそうな場所にまで移動する。
そこで待つ事暫し。港の方から件の馬車がやってきて、【NAME】達の前を通り過ぎていった、のだが。
「ちょっとビビったな。一応常駐軍の士官扱いで派遣されてきたって話だが、まさかあんな可憐な感じのお嬢さんだとはなぁ……」
「確かに美少女ではありましたッスけど、正直自分の好みからはちょーっと外れてる感じッスねぇ。もっとこう、他人に対する嗜虐性みたいなのが感じられないと」
「相変わらずお前の趣向は終わってんな」
などとたわいもない遣り取りを繰り広げるマヒト、シモンズの二人に対し、
「…………」
「…………」
『…………』
貴方とリヴィエラ、そしてクーリアという、方式は異なるものの総じてアエルを何らかの形で認識出来る者達は、何とも言い難い気分で、通り抜けていった馬車の後ろに意識を向けていた。
「……? おい、御嬢。それに【NAME】も、どうかしたのかよ?」
そんな貴方達の奇妙な態度に気づいたのだろう。マヒトが怪訝と声を掛けてくるが、そんな彼に、貴方は端的に先程見た現実を教える。
先程、馬車に乗っていた可憐な容姿の娘。
その身体から漂っていたアエルの気配が、規模自体は数段小さいものながら、その形や質が、あの年老いた老人貴族シバリスが放っていたものと同一であった、と。
「それってつまり……」
「あの良い所出のカワイイ御嬢様に、爺さんの精神が……?」
少し違うのだが、大凡としては間違っていない気もする。
貴方の返事に、マヒトとシモンズが「……マジかー?」とばかりに既に姿も見えなくなった馬車の消えた方へと視線を送り、恐々とした声を出す。
けれども、貴方としてはこれで一つの懸案は解決した事になり、安堵の吐息をつく。
あとは、先刻の彼女と接触すれば良いだけ、なのだが。
「でもあれ、どうやって接触すりゃいいんだ? 当然事前に約束とかとってないと会えねーよな?」
「…………」
マヒトの言葉に、貴方は思わず黙り込んでしまう。
しかもよくよく考えてみると、彼女が何処へ向かっていったのかすらよく判らない。常駐軍駐屯地だろうか? それとも街の有力者の邸宅だろうか? あるいは空いている屋敷で暮らす予定という可能性もあるし、下手をすれば新築の家を建てるという可能性もある。
思ったより前途多難か、と貴方が固まったところで、背後からあまり聞き慣れない女の声が掛けられた。
「……あんた達、どっかで見た事あるね」
振り返ると、長い赤毛で顔の半分を覆い隠した侍女服姿の女が、どこか下から睨み上げるように自分達を眺めていた。
貴方も反射的に彼女の姿を眺める。見覚えがあるような気もするが、具体的に何処で出会ったか、というのがぱっと出てこない。
互いに、怪訝とお互いを眺め合う状況が少し続き、
「わかんねー。あ、おいそうだメリシェン!! ちょっとこっち来な!」
「なんなのよ、ヴィーお姉ちゃん。――ってあ、兎さん達だ!」
赤毛の女に呼ばれて、人込みの中から小さい黄金色の影がするりと出てくると、貴方と、そしてリヴィエラ達を見て素っ頓狂な声を出す。
「うわぁ。出た」
「来たっ、マイ天来たッスよ!」
げぇ、と顔を顰めるマヒトと、逆に歓喜の声を上げるシモンズ。
対照的ではあったが、しかし新たに現れた人物は、貴方もリヴィエラ達にも既知の人物だった。
シバリスの従者であり、無邪気な残虐さを持つ金髪の少女、メリシェン。半年という年月を経て、少し変化はあるものの、大きな印象の変化にまでは至らず、見分けは容易についた、
その彼女と同行しているという事は、この赤毛の女も同様、シバリスの従者であるのだろう。
「ってことはー……、あんた達が、シバリスの言ってたあたし達の協力者って事でいいの?」
「多分そうだろうとは思うがよ、そもそもアンタこそ何者だよ?」
馴れ馴れしい態度に合わせるように、マヒトが砕けた調子の疑問で言葉を返す。
「そーいや、顔合わせたのも大分前に一瞬だけだったっけか。あたしはヴィータっていうの。そっちのメリシェンと同じ、シバリスの従者兼弟子よ。ま、取り敢えずこの街に入って早々、あんた達を見つけられたのは幸いだったわ」
言って、彼女は貴方達の横を通り抜けると、一度視線だけで振り返り、
「付いてきな。今、ここでのシバリスの“管”役に会わせたげる。そこで、今後の事を詳しく詰めるから」
・
ラースナウアの中心部に並び立つ屋敷の中には、所有者の居ない空き屋敷がそこそこ存在する。都市建設時に一応用意はされたものの、屋敷の規模に見合うような立場の人物が居らず、そのまま管理だけは続けられていたが実質放置されていたものだ。
そんな屋敷の一つに、今日、新たな主が誕生した。建物の中に運び入れられていく、立場の割りには少ない荷物を腕組みしつつ眺めていたのは、年の頃十代も半ば程度の、飾りの多い軍装を纏った娘だった。
小柄な体躯に、愛らしい面立ち。その中で、目の奥にちらちらと、見る者が見れば漸く垣間見える程度の異質さが宿っている。底知れない黒の色は、本来の彼女が持つものではなく、彼女を操っている“管”によって齎された闇であることを知るのは、当人と、そして彼女がフローリアへとやってきた際に雇い入れた異大陸の侍女達のみであった。
「おーい、シバリース」
と、遠くから掛けられた声に、娘は露骨な顰め面を浮かべて然程大きくもない庭を視線で跨ぎ、門前にて気怠げに声を上げた女の方を見る。
「これこれこれ。ヴィータよ。今はその名で呼ぶではないと僕は注意したと思うのだがね」
「だったらそのしゃべり方ももうちょっと矯正したほうがいいんじゃないの? エルテミシア様」
「ま、もうどうせ直ぐに離す身体だ。然程立場を意識し繕う意味もありはしないがね。それで? どうやら無事に見つけてきたようだね」
娘の視線が横へとズレると、彼女――いや、彼にとっては既に見慣れた者達が、何とも曰く言い難い顔つきで自分の事を見ていた。
「やあやあやあ。この姿と、そしてその姿ではお初にお目に掛かるね、少年。そして後ろの連れの者達は変わらぬ顔ぶれのようで何よりだ。残念ながら、妖精殿はいないようだが」
気軽に話しかけながら彼等に近付くと、彼女は優雅に一礼し、娘らしい微笑みを浮かべてみせた。
「では一応、こちらでの僕も名乗ってみせるとしようか。――初めまして、皆々様。わたくしはエルテミシア・ワイゼン。ワイゼン正家に連なる三人目の女子にて、今はアラセマ常駐軍第三師団の客将という身分を得ております。以後お見知りおきを――なんてね」
最後に、くくと喉を鳴らして笑う態度は、完全にあの老人、シバリス・カーライルが見せていた仕草だった。
・
「それじゃそれじゃあ、無事にフローリアで合流できたようだし、具体的にこちらで何をどうするか、話していこうか。時間の余裕もどの程度あるか判らないし、急ぎ説明して、君達には早々に出発して貰う事になるだろう」
未だ荷ほどきも済んでいない屋敷の中。急遽間に合わせで用意された応接間に、今回の件に関わる全員が集まっていた。
【NAME】達の側からは貴方とリヴィエラ達三人。シバリス側からは、今は六家の令嬢エルテミシアの姿を持つシバリスと、彼の弟子兼従者と名乗る女と少女の計三人だ。
「今、フローリア諸島に存在している“王格”の数は二つ。一つはこのランドリート島の沿岸にある孤島。もう一つはアノーレ島の中部にある森の中に存在している。どちらも、既にエギアクルスの工作員が現地民を煽動し、大規模術技を行使するための手足として操っている状態だ。【NAME】達はヴィータ、メリシェンと共に、この二つの場所で行われている儀式を急ぎ阻止し、用意してあるこの像に“王格”を封じて貰うというのが今回の……まぁ、任務のようなものだな」
エルテミシアの両隣に座る二人の従者達の手の中には、一抱えほどの巨大な像がある。あれが、“王格”を封じるための像らしい。
「像の操作についてはかなり繊細な作業が要求されるから、その間、ヴィータとメリシェンの戦闘参加は難しくなる。だから【NAME】。術技阻止の方は兎も角、術技によって状態が不安定になっている“王格”を鎮める作業は君達の仕事になるだろうから、そのつもりで頼む。後、ゴーシェ島と呼ばれる沿岸の孤島、そしてアノーレ島へと向かう足は、僕の伝手で用意してある。港の一番端に停泊している小型の軍船に、この証書を見せれば乗せてくれる筈だ。証書自体はヴィータに渡しておくから、乗るときは彼女と一緒に居るように。……あと、何かあるかい?」
「……具体的に、どういう奴等が敵になってるかってのは、判ってるんスかね?」
シモンズの問いに、少女は端正な表情をむむむと歪ませる。
「正直、僕もこちらに来たばかりだから情報収集はあまり出来ていないのだけれどもねぇ。……まず、近場のゴーシェ島の方では、元々島を根城にしていた海賊達が居て、あと“藍の淑女”という人魚達の集団の縄張りの内でもあるという話だよ。エギアクルスの連中は確か海賊達を手駒にしているようだから、船でそちらに向かうなら、まず“藍の淑女”達を相手して、その後海賊達、そして術技によって不安定になっている“王格”の対処という流れになるだろう。アノーレ島の方は……悪いがあそこは情報が殆ど島内で完結していて、外に殆どでてこないから判らないんだ。一応、余所の土地で暮らしていた翼人達を洗脳して、“王格”があったっていうラノフ芯林の奥に連れ込み、兵や端末、生贄の代わりにしている……みたいな話を聞いた覚えがあるが、当時は然程気にしていなかったから空覚えだ。あまり当てにはしないでくれ」
そこまでいって、「僕が言えるのはまぁこんなところかな」と、少女は軽く吐息をつく。
「悪いが、このお嬢さんの身体をシバリスから伸ばした“管”で操るのは結構力が必要でね。あと、僕の方でもグローエスの“王格”の対処を進めないといけないから、あまりこちらに構えない。状況が理解できたようなら、早速作戦を進めてくれると有り難い。後は、宜しく頼むよ」
と、これで話を締めようとしているシバリスに、短く制止の声が入った。
『ああ、一つ待ってください』
「……何かな?」
問い掛けに、少し、迷うような間を挟んだ後。クーリアは慎重な声音で、シバリスを窺う
『“王格”二つを無事像に回収出来た後。貴方はその像はどうしてほしいと考えているのですか? 当然あなたの侍従達にそれを伝えてはいるのでしょうが、私達は聞いてはおりませんでしたので』
「そうだねそうだね。……可能であれば、“この”僕のところまで届けてくれると有り難いけれど……こういっては何だけれども、君達がそれをする理由というのは、無いよね?」
『そう、ですね』
「うんうん。それならそれで、別に構わないよ。ヴィータやメリシェンにも、この辺りの事はしっかりと伝えてあるからね。だよね、二人とも?」
「判ってるよ。ちゃんとね」
「うん! また兎ちゃん達と、今度は自分で戦うの、楽しみなの!」
「だ、そうだよ?」
『…………』
判っていた事であるが、ここまではっきりと、共闘関係でありながら敵対関係でもあるという割り切りを見せられるのは、ある意味清々しくも感じた。
傍にいるリヴィエラが、浅く息を飲み込むのが判る。今の彼女であれば、シバリス、ヴィータ、メリシェン。彼女等の術技使いとしての強さがどの程度であるのか、理解出来ている筈だ。それ故の緊張だろう。
「さてさて。取り敢えず、話は以上だよ。後は我が弟子達の吉報――あるいは君達の勝利の声のどちらかが届くのを……わたくしはこのお屋敷で、待つといたしましょう」
最後に言葉遣いを変えて、エルテミシアは部屋から出て行く。その立ち姿から、ゆっくりとアエルの気配が抜けていくのが見えた。
「じゃあ、さっさと屋敷を出ようかね。シバリスの“管”が抜けると、エルテミシア様は“元に戻ってしまう”から。その前に、あたし達はここを出ておかないと不味いことになる」
「……はーん。そういう構造になってんのな」
それは確かに、長居していると宜しくない流れになりそうだ。
席を立ちながら、納得したような声を上げるマヒトに続き、全員が席を立ち、屋敷の外へと早々に退散した。
・
「それじゃ、まず最初は近場のゴーシェ島の“王格”から行くけれど、異論ある?」
わざわざ遠くのアノーレから始める意味もない。全員が首を振ると、ヴィータは軽く頷いて、港の方へと歩き出す。
「一応、聞いておくけど、あんた達、戦いとかどの程度出来んの?」
街の通りを先導しながらヴィータの問いに、後方に続いていたマヒトは僅かに目を細めた後、自嘲するように肩を竦める。
「……オレとシモンズは精々並程度だと思え。まともにやれんのは【NAME】と、あとは本領発揮できりゃ御嬢だな。因みに、オレとシモンズはお前等みてーなヘンな技使えねーからな」
「マヒト、シモンズ、役立たず。やっぱり兎ね」
「おうふ。天使様の鋭いナイフが自分の贅肉に鋭く突き刺さるッス……」
ヴィータの直ぐ後ろを行くメリシェンが振り返り見せるのは白けた半眼。シモンズが苦しそうに胸を押さえて悶えるがあまり構いたくない。というより、彼女が二人の名前を覚えていたのが少し意外だった。
そんな彼等の様子を、貴方を通して眺めていたのか。肩上辺りから呆れたような吐息の音がこぼれる。
『巫山戯ている場面でもないと思いますけど……。一応、最後は不安定になっている“王格”を収める事になる筈ですから、マヒトさんとシモンズさんは、何だか知らない間に存在ごと消えてたとか普通に起きかねないんで、良く良く注意して動いた方が良いかと思います。一応、私の方から防御用の術技を飛ばしておきますけれども』
「……寧ろ俺達、付いていかない方が足引っ張らなくていいかもしらんね」
「でも起請術式が自分達を縛るッス……」
言って、マヒトは半笑いで掌を上に掲げみせ、シモンズはしくしくと泣いてみせる。
だが、そんな冗談染みた態度を見せる二人に、ヴィータは醒めた目を向けて足を止めると、
「なんでも良いけどさ。今回の仕事、あたし達の足引っ張るような真似をしたら、遠慮無く殺すから。そこだけは理解しておきなさい」
「この間の子達みたいに、おもちゃみたいにひっつけたり剥がしたり、してあげてもいいよ?」
赤毛の女は気怠げに。金髪の少女はけらけらと笑いながら。
貴方やリヴィエラ達を、路傍の石か目新しい玩具を見るような目つきで眺めていた。
「…………」
そんな彼女達に対し、マヒトとシモンズは戯けた態度を引っ込めて、今度は浅く、鼻を鳴らしてみせる。
「ま、その時はこちらも遠慮無く、出来る事をやらせてもらうまでよ」
「相応に、対処させていただきまッス」
そして、リヴィエラは一気に緊迫した空気に呑まれぬよう、ぎゅっと両の手を胸の前で握り締めて、
「今度は、逃げません。もう誰も、あんな姿になんてさせない。……メリシェンさん、私は、貴女に、負けません」
「……そう。兎さんは兎さんらしくしていれば、幸せなのにね」
ヴィータとメリシェンが、貴方達から視線を外し、先を歩いて行く。
その背中を、貴方達は険しい眼で睨み付けた後。荒れた心を静めてから、彼女達の後を追い掛けた。
今は、彼女達と戦う時ではない。
そう、少なくとも今は――。
礎の王格 波濤の先を越えて
――波濤の先を越えて──
空に暗雲が立ち込める中。操舵をヴィータに任せた一行は、船の各所で警戒の為の配置につき、海からの襲撃に備えながら、ランドリート島沿岸に浮かぶ小島――ゴーシェ島を目指していた。
エルテミシアから貴方達に提供された船は、乗員上限が十数人程度の小型なものながら、機関動力部に印章術式機構を搭載し、多少の陸上走行機能すら持つ高価な魔導船だった。流石“六家”の御嬢様を乗っ取っているだけある。金に糸目を付けない代物を、遠慮無く寄越してくれた。この魔導船の存在は、この付近の海域に棲む凶暴な人魚達“藍の淑女”達の縄張りを少人数で突破し、孤島上陸を成さねばならない貴方達からすると至極有り難い代物だった。
まず、出せる速度が、他の形式の船とは根本的に違う。“藍の淑女”達が水中を泳ぐよりも速く、しかも環境条件による減速が殆ど生じないのだ。無風であろうが、大波が来ようが諸共しない。このお陰で、今のところ彼女達に発見されたとしても集団で囲まれたり、あるいは追跡されて攻撃を受けるという状況を避ける事が出来ていた。これが普通の帆船やガレー船であったなら、一体どれ程の苦労が必要であったか。想像もつかない程だ。
今の船の速力は、ほぼ術式機構が出せる限界に近い程。高速故に海を割り裂き進む際に生じる波飛沫は激しく、船上に居る貴方達に容赦なく降りかかる。しかし、のんびりと進んでいては“藍の淑女”達に瞬く間に囲まれ、彼女等が操る水や雷の力で滅多打ちにされてしまうだろう。
何せ、これだけの速度を出しているというのに、“藍の淑女”達はこちらの船目掛けて、既に幾度も襲撃を仕掛けてきているのだから。
「2時より警戒! 10匹ほど待ち伏せしているのが見えます! ヴィータさん、10……いえ、9時方向に舵を!」
「遠回りすぎる。直進して抜けるから、あんた達迎撃なさい」
「10相手は流石に多くねーか!?」
「宝精使い。あんたなら、ここから宝精で大半吹っ飛ばせんでしょ。やんな」
「そんな、無……いえ、やってみせますっ!」
「リ、リヴィエラ様、大丈夫ッスか!?」
焦るシモンズの声にも耳を貸さず、リヴィエラは懐から燦めく宝石を取り出す。最近では珍しい、精錬研磨された純粋な宝石だ。彼女は石を素早く前へと放り投げると、宣言句すら唱えずに、手にした杖で宝石を打撃する。
瞬間、強烈なアエルの流れが宝石を中心にして生じ、その内側から異界の法則により導き出された力が溢れ、形を成す。
水色の蛇を模し、全身から無数のヒレを生やした化生は、まるで己の身体を槍の穂先のように尖らせて、海面に揺れる波紋、海中に浅く潜り襲撃の機会を窺っていた“藍の淑女”達目掛けて飛翔していく。
空を切るのも無音なら、巨体が海中に潜り込む際も無音。
しかし、効果は確かだ。立ちのぼる水柱。蛇を象っていた水と海水が混じり合って生じた破裂の中、ちぎれた人魚達の部位が四方八方へと飛び散るのが見えた。
「ははっ上出来。才能あるよあんた。敵を殺す才能がさっ!」
「――な、あっ!?」
リヴィエラが反射的に反論の声をあげようとするが、しかし船に更なる加速が加わった事で、その言葉は形になることなく彼女の中に飲み込まれていく。
船は直進のまま、ただ速度だけを上げて海面を突き進む。
リヴィエラの宝精召術により斜め前方に潜んでいた“藍の淑女”達の殆どは爆散していたが、それも全てではない。
一部の人魚達は難を逃れており、仲間を殺された恨みにより、狂気に犯された眼を貴方達に向けて、高速で迫る船目掛けて、捨て身の突貫を掛けてくる!
「いよっし! 最後のラインは抜けた! 後は、島に逃げ込んじまえば追ってこれねぇ筈だ!」
槍を手に船上へと躍りかかるように飛び上がってきた“藍の淑女”。彼女と打ち合い、逆に海へと叩き落としたマヒトが歓声を上げる。
最後の“藍の淑女”達を振り切った貴方達の眼前には、既にゴーシェ島の姿が見えていた。後方から“藍の淑女”達が追い縋ってくる様子は無い。こちらの船の速度に追いつけないというのもあるが、
「……凄い、アエルの量。島の奥から、眩しいくらいに溢れてます……」
目を細めて呟くリヴィエラの言の通り、島は既に強烈なアエルに満たされている。貴方の経験からすれば、いつ置換現象が発生してもおかしくない程の飽和状態にあった。
それでも“異象”が発生している兆候が見られないのは、単なる偶然か、それともこれが“王格”を解体浸透させるという儀式によるものであるせいなのか。
何にせよ、島から伝わる異質さは、アエルを感知出来る【NAME】やリヴィエラ、そして術技に長けたヴィータやメリシェンは当然ながら、アエルを感じ取れない者達からしても何らかの異変として伝わるものであり、
『先刻の人魚達も、これだけ膨大な量のアエルに満ちた場所に近付く気にはならないでしょうね。五感で捉えられなくても、“何かが違う”……雰囲気のようなものは感じ取れるでしょうから』
「人の姿を一部模しちゃいるけど、所詮化け物だからね。その辺りの感覚は、普通の人間よりも遥かに鋭いでしょうよ。……取り敢えず、とっとと上陸しちまうよ。海賊連中の拠点として使われてたなら、船を泊められる場所がある筈だけど」
舵を取るヴィータが、島の沿岸を巡るように船を動かす。遠く、“藍の淑女”達がこちらを窺っている気配を感じるが、やはり近寄ってくる様子は無かった。それ程までに、彼女達にとっても今のこの島は危険を感じさせる状態なのだろう。
暫く島の周囲を巡っていると、湾の形状になっている場所が見つかり、そこに幾つかの船が停留しているのも見えた。
「……で、ここからの相手は海賊って訳か」
『エギアクルスの連中が支配した海賊達全員をどのように使ってるかまでは判りませんけれど、普通に考えればある程度の数は防衛に割いているでしょうね……ほら』
見れば、天然の港となっているその場所では、幾人かの男達が武器を手にし、まるで屍人のような覚束無い動きで、何かが来るのを待つように徘徊している姿が見えた。
島に上陸した貴方達は、次から次へと襲い掛かってくる海賊達の相手を続けながら天然の港を通り抜け、今は濃い木々に覆われた森をひたすら突き進んでいた。
アエルを感知出来る才能を持つものならば、例え密林であろうと行き先を迷う事は無い。それ程までに強いアエルの気配が、前方から吹き付けてくる。
そして道行く先からは、目を虚ろに濁らせた海賊達が貴方達の接近に反応してぎこちない動きで近寄ってくる。
「ったく、しつこいくせに、正気ですらねぇってんだからたまんねーなオイ!」
マヒトが忌々しげに叫びながら、横合いから襲い掛かってきた海賊を、槍の石突きで弾き、距離を稼いでから回転させて穂先で薙ぐ。縦に血飛沫が走り、海賊は仰向けに倒れ臥した。その動きに容赦はない。完全な致命傷でも与えなければ戦闘を続行してくるからだ。少数であれば取り押さえ捕縛するという穏便な手もないではないが、如何せん数が多く、悠長にそんな事をしていられる状況でもない。
「遠慮無く殺せていいじゃないの。ま、メリシェンなんてそもそも誰相手でも遠慮なんてしないけれどさ」
「殺しやすいけど、この子達あまり殺しても面白くない。鳴かないから」
先頭を行くシバリスの侍従二人は、全く躊躇のない術技をぶつけて、生い茂る草木を払うと同時に海賊達を殺害していく。斬殺、殴殺、圧殺、爆殺。海賊達はまるで踏みつぶされていく蟻のように殺されていくが、しかし彼等が怯み、逃げ出す事は無い。
「……完全に、操り人形みたいになってるッスからねぇ……」
斧を横に振って両足を飛ばし、動けなくした海賊から離れながら、マヒトが辟易したように呟くのが聞こえた。
相手をしてみれば判るが、立ち塞がる海賊達は、まるで意志の無い肉の塊に武器と防具を身に着けさせただけのような不気味な相手だった。
元は海賊、であるのだろうが、その瞳には自由意志というモノは一切感じられず。ただ奥地を目指して進む貴方達を食い止め、殺すために派遣された人の姿をした何か。先刻から襲ってくるのはそんな存在だ。
クーリアやシバリスの侍従二人が推測するに、彼等は術技によってまず人格を消失させ、そこから洗脳によって、後から植え付けられた単純な命令をこなすだけの存在に変えられてしまっているらしい。しかも初手の段階で思考が破壊されている為、もし洗脳を解いたとしても廃人が一人出来上がるだけ。救いは既に無い、とも。
侍従達のように嬉々として人を殺す趣味はないが、貴方も遠慮無く向かってくる敵に手加減をする程優しくはない。既に痛みを得る事も無く、だが命ある限り向かってくる相手故、極力手短に命を絶つ事を心がけながら武器を振るう。
「――っふ」
短い吐息と共に、正面から何の小細工もせず襲い掛かってくる海賊相手に、貴方は遠慮無く技法を連続で叩き込む。やや過剰気味の攻撃を受けて、男は全身から血を噴き出し頽れた。
襲ってくる海賊達は、戦闘力という面で見れば手強い相手ではないが、兎に角タフなのだ。そして痛みを感じないためか、関節の可動域を度外視した動きを見せる事があり、更には意識がない故殺気を一切発揮しないといった特徴がある。これらを頭の隅に留め置いて相手をしないと逆に痛い目を見かねない、手強くは無いが面倒ではある相手と言えた。
「【NAME】! 後ろから追加で来てる、御嬢のフォローをしてやってくれ!」
新たな海賊数人と切り結んでいたマヒトの言葉に、貴方は頷きすらなく、動きだけで返事とする。
場所が木々の密集する場所故に不意に近付かれてしまっている事が多く、本来は敵とは距離を置いた状態を得意とするリヴィエラも近接戦闘を行わねばならない状況が頻発していた。宝精召士――つまりは術士系統の戦種である彼女からすると、この地はあまり戦いやすい場所ではない。
もっとも、今の彼女は貴方との実戦訓練を経て、相応のアエルさえ管理下にあれば近接戦闘に於いても相当な戦闘能力を発揮する。そう危険な状況に陥る事も少ないのだが、万が一という場合も有り得るのが戦場という場だ。
杖の先端にアエルを纏わせ、次々と海賊達を弾き飛ばしていくリヴィエラの隣へと貴方は移動すると、彼女と共に後方から迫る海賊の掃討に移る。
侍従達の先導に従い、海賊達を倒し続け、森の奥へ奥へと進み続けて数時間。
そうして辿り着いたのは、島の中央付近に存在していた山の麓。露出した岩肌、急な斜面に喰い込むようにして、巨大な石材が突き刺さり、支えられ、一つの建物となっていた。苔むした石材は時代を感じさせるが、しかし“芯形機構”のような異質な素材で造られたもののようには見えない。旧時代のフローリア諸島原住民か、あるいは亜人が建てた建物と考えるのが妥当な線か。
見て受ける印象としては、神殿か遺跡か。広く、横数十メートルの幅で山を抉る石造りの建物の奥は濃い暗闇で覆われているが、その奥からは野太く怪しげな、唸りとも祈りとも取れる重声が僅かに届き、そしてその音の波の強弱に乗るようにして、アエルが強く噴き出しては弱まるのをまるで呼吸のように繰り返している。
「やっと着いたか。この奥で“王格”への術技が行われてる。感じたところじゃ、まだ全然大丈夫そうだね」
「全然、理が広がってる感じ、しないもの。これなら一週間くらい、余裕あったね」
『これだけのアエルが溢れていて、ですか……?』
クーリアが唖然と声を上げるが、侍従二人は訝しそうに視線を寄越し、
「この感じだと精々、“王格”の殻が綻び始めてる程度の進行具合でしょ? 今漂ってるアエルはソレだし。“王格”自体が宿す理がこの世界に解け込むような段になってたら、アエルの気配だけじゃ済まないさ」
「まだ何も変わってないもの。だから、まだ“王格”はそのまま残ってる筈だから、わたし達の像で全然封じ込められる」
「もう“王格”が解体されてて、こっちの世界に浸透し始めるってんだったら大仕事になるんだがね。……これなら、軽く“王格”の殻からはみ出した部分を叩いて引っ込めりゃ、いけるでしょ」
軽くそう言うと、彼女達は更に数を増して襲い掛かってくる海賊達を皆殺しにしながら、山の裾を掘り進んで造られた建物の中へと入っていく。
「――ほら、とっととついてきな。あんた達の仕事はあたし達のケツにひっついてくる事じゃないでしょ? こっからがあんた達の出番なんだから、しゃんとしな」
言い捨てて、どんどんと進んでいく二人を、貴方達は突っ掛かってくる海賊達を遇いながら慌てて追い掛けた。
入口部分は広く取られていた建物であったが、中へと入ると幅は一気に狭まり、横五メートル程度の一本道へと変わる。ここまで来るともう海賊達の姿は無く、ただ通路の奥から不気味な声だけが石畳の通路を反響するだけだ。
「にしても、あいつ等好き勝手言いやがって……」
「でも、最初からあの人達が像で“王格”を封じるための時間稼ぎ? みたいなのが自分達の役目って話ッスから……」
シモンズがそう言うと、貴方の横にいたリヴィエラが緊張した表情で呟く。
「奥から、物凄く強くて濃い“光”が視えるんですが、あれが“王格”なのでしょうか? もしそうなら、一体どれだけの力を持っているのか、想像もつかないんですけれど、本当に戦ったりとか、封じたりなんて、出来るんでしょうか……? クーリアさんなら、判りますか?」
問いに、気難しげな唸り声が貴方の傍から溢れる。
『んー。確かに、“王格”という存在自体は凄い力――というか、世界の基盤の一つになり得る力を持っていますけれど、それが全て戦いに使える力なのかっていうとそうでもありませんから……現在の“王格”の状態次第では、案外あの像でも一時的になら封じ込められる可能性もあるんですよね』
「……実は大した事無いって事かよ?」
『大した事は凄いありますけれど、結局は状態次第という話です。さっき彼女達が言っていた通り、大規模術技の影響が少ない程、“王格”は安定した状態のままでしょうから封じるのは難しくない筈ですし、そもそも“王格”は単なる世界の理を宿した一つの概念存在でしかありませんから、既に『礎の世』で取っていた人の形を失って、唯の理の塊という存在になっているなら、自己防衛行動すら取らないモノになっている場合も十分考えられるんですよ』
「だとしたら、楽そうなんッスけどねぇ……」
建物の中に入り、闇の奥に消えそうになる二人を追いながら、貴方は結論を述べる。
――結局は、実物と相対してみなければ判らない、と。
『そうなります……。あれこれ考えたところで、“王格”はもうすぐそこに居る筈ですから。覚悟だけ決めて、突撃するしかありませんね』
クーリアの言葉に嘆息を付く前に、先に進んでいた侍従二人の足が止まる。彼女達の前方では通路が途切れて、その先には薄暗い照明に照らされた大きな空間が存在しているのが見えた。
――陰霖の王格──
「こりゃまた、気味悪いッスね……」
「完全に邪教の儀式って感じだなこりゃ」
通路の終端。広がるのはドーム状の天井を持つ空間だ。広間の中央には一段高い祭壇となっており、そこには長衣に身を包んだ人影が、両手を広げて朗々と呪文を唱えていた。
そして祭壇を中心にして、広間を埋め尽くすように身を折り、頭を垂れて地面にこすりつけるような姿勢で、数百もの人影が蹲り、中央に立つ人物が唱えるものと同じ文句を口ずさんでいる。先刻から聞こえていた不気味な声の正体はこれだ。見たところ、彼等の多くは先刻貴方達が打ち倒してきた海賊であるようだが、中には平民や兵士のような外見の者達も居る。しかし総じて、同じ姿勢を取り、唯一心に呪文を唱え続けているのは変わらない。
そして祭壇の上方には、直径にして優に十メートルは超える巨大な光の塊が、強い輝きを放って明滅している。浮かぶ光の玉から放たれるのは強大極まるアエルの波だ。知覚全てが押し流されそうな程に、その光る玉から力が外へと漏れている。球体の一部に穴が空き、中身が外へと噴き出しているようだ。
そんな広間の様子を茫然と眺めていた貴方であったが、しかしシバリスの侍従達はこの場の光景には然程の感慨も浮かばないようだ。
「じゃ、さっさと片付けるよ。今回はあたしの像使うから、メリシェン、あんたは取り敢えず“端末”にされてる連中を殺して術技陣を破綻させて」
「壊れたオモチャじゃ遊べないから、つまらないわ」
「そこは諦めな。で、【NAME】? あんた達はまずあの中心に居るエギアの術技士殺して。その後、術技陣で壊された“王格”の殻を殴って、溢れてるのを押し込めな」
押し込めろと簡単に言うが、具体的にはどうしろというのか。
「術技陣が停止してりゃ、空いた穴目掛けて適当にアエル使って攻撃すればいい。“王格”が勝手にあんたが使ったアエルを吸い取って、殻を再生させて安定しようとする筈だよ。うだうだ言ってないで、全力で殴ってりゃそれでどうにかなるから大人しく言う事聞きな。――じゃ、とっとと始めるよ」
ヴィータは言いたいことだけ告げて、手にした長鞭を高速で振る。
通路への出入口から中央の祭壇まで、走り抜けたのはモノクロの炎の舌だ。鞭の長さは精々三、四メートル。対し、伸びた単色の火線は距離にして数十メートル程。その間に蹲り、頭を垂れて声を上げていた者達が、炸裂する無色の炎の破裂に切り裂かれて、左右へと散り飛ばされる。鮮血が弾け、手足や臓物が撒き散らされるが、悲鳴一つ上がらない。彼等は彼等は存在を支配され、ある意味存在としては死んでいるのだ。己の身がどうなろうと、それを認識する事すらできやしないのだろう。全身に焼痕を刻まれ、頭と胴のみを残して近くに転がってきた一人が、未だに朗唱を続けているのがその証拠だ。
兎に角、“王格”までの道はこれで開かれた。走り出すヴィータに続き、貴方達も後を追う。リヴィエラ達が真っ青な顔で周囲の様子を見回しながら付いてくるが、正直フォローの言葉も思い付かない。何も考えず、やると決めた事だけを考えて、早々に終えてしまうのが現状最良の行動だろう。
「ふふ、ふふふっ! でも、これはこれで、気持ちがいいわねっ!」
後方では、メリシェンが愉しげな声と共に近場に伏せる者達から順々に殺して回っているようだが、そちらに視線を送る気にもなれない。貴方はただこの狂気染みた場からいち早く脱出するべく、中央の祭壇を目指す。
「――――」
ようやく場に生じた異変を察したのか。“王格”を見上げ、声を張っていた長衣の人影が貴方達の方へと振り返った。髭面の、中年の男だ。驚きの表情と共に何事かをわめき散らす。
しかしその言葉は明確な言葉として貴方には届かず、そしてわざわざ聞き返す必要性も感じなかった。あの男がこの場を整えたのは明白だ。可能な限り早く倒し、急ぎ“王格”をどうにかせねばならない。
走るヴィータの速度が落ち、貴方達はその横を通り過ぎて前へと出る。宣言通りヴィータは戦闘には参加せず像の準備を始めるようだ。後は、自分達が長衣の男を叩き潰し、“王格”を鎮める必要がある。祈りを捧げる者達をメリシェンが片っ端から殺して回っているため、この場に構築されている大規模術技陣の力が徐々に弱まっていくのを感じる。この調子であれば、“王格”の状態が今以上に悪化していく事は無いだろう。
武器を引き抜く。突撃してくるこちらを見定め、長衣の男が杖を手に身構えた。彼に寄り集まるのは無形の力。イーサではない。アエルによる術技の前兆だ。相手もどうやらこちらと“同類”であるようだ。これまでの情報と、姿が完全にこの世界の人間であるところから推測するならば、反“派閥”組織に属する“同化者”といったところか。
とはいえ、あのシバリスのような強烈な威圧感はない。彼の手の内で展開されていく術技も遅く、恐らく戦闘能力自体はシバリスどころか、その従者達にも大きく劣るレベルだろう。
であるならば、奴は前座だ。早々に片付け、“王格”を鎮める作業に入らねば。
貴方は更に加速すると祭壇を蹴るように駆け上がり、術技を放とうとする長衣の男と――そしてその上方に浮かぶ“王格”に対し、アエルを織り交ぜた攻撃を仕掛ける!
battle
陰霖の王格


「全部殺したよー」
そういって、祭壇の上に上がってくるメリシェンの姿は真っ赤に染まっていた。
見下ろせば、広間に居た数百の人々はその全てが死に絶えて、血の臭いがむせかえるほどに蔓延している。メリシェンが祈りを捧げていた全ての人間を殺したが故か、それとも貴方が長衣の男を倒したお陰か。広間に仕掛けられていた大規模術技はその効力を既に失っており、そして事前にヴィータが言っていたように、貴方とリヴィエラのアエルを交えた攻撃を受けた“王格”は、その力を吸収して取り込み、大規模術技により揺らぎ、穴が空いていた己の殻を修復。安定した状態に戻っていた。
「……う」
眼下の光景に口元を抑え、顔を青くしているリヴィエラの隣を悠々と金髪の少女は通り過ぎて、浮かぶ“王格”の下に像を設置しているヴィータの傍へと寄っていった。
ヴィータは貴方の手により命を落とした長衣の男の血を使って描いた陣の中央に像を置き、その前に座すると術技を使う準備を行っている。
「ヴィー姉。何か手伝う事、ある?」
「無いよ。黙って見てな。ってか、次はあんたがやんだから、よく手順見ときなよ。なんか忘れてそうで不安になるし」
「あー、言われてみればあんまり覚えてないかも」
「はぁ? このバカ妹弟子、頭空っぽ過ぎない? ホントになんであんたみたいな子をシバリスは弟子に取ったんだか。やる気がないってのに才能の方も微妙だし」
「確か、面白いからって言われたわ。術技の才能は無いが人を弄ぶ才能はあるって」
「……納得出来ちゃうから厭だわ。シバリスの物好きも何とかなんないもんかねぇ」
「漫才してる場合かよ。像への封印ってのはどうなってんだ? こんな場所、正直長居したくねぇんだ。さっさとしてくれ」
イライラとした様子でマヒトが口を挟むと、ヴィータは像へ向けていた視線を僅かに外し、
「魚の糞が生意気な口利くんじゃないよ。今からやる。直ぐ終わるから見てな」
血で濡れた指先で数度空中を切り、そしてヴィータは像の頂点部分に二本の指を添えて、一度呼吸を止める。
瞬間、空気が変わる。アエルに対する感知能力を持つ貴方とリヴィエラは、ヴィータが己の内に溜め込み圧を増したアエルを像に叩き込んで、その中に組み込まれていた複数の術技陣を駆動させたのが判った。
像に内蔵された術技陣達が外の血で描かれた大型の術技陣と繋がって、更に大小組み合わさった一つの巨大術技陣となって駆動する。像から噴き出すように伸びたアエルの手が、無数に“王格”に絡みつき、食らいついていった。
像が精々一抱え程の大きさであるのに対し、“王格”は直径十メートル強の光の塊だ。そのままのサイズでは到底像に封じ込められるものではないが、血の陣からも伸びた手が“王格”を包み込むように動き、握り潰すように光りの玉を凝縮して、“王格”を像の中へと引き摺り込む。
そうして後に残ったのは、内側から強い光を発し続ける一つの像。先程までの、島全体を覆うような強烈なアエルの波動は生じなくなったが、代わりに、像の内部には凄まじく凝縮されたアエルの塊が宿り、その存在感を周囲に撒き散らしているのが判る。アエルに対する探知の能力を持つ者ならば、例えばここからランドリート島程の距離があろうとも、その所在を突き止められる程の濃厚かつ明確な気配だ。これが、本来の“王格”が持つ気配の強さであるのか、それとも像に封じられたからこそこうなっているのか。判らないが、どちらにせよ目立つ事この上無い。これはかなり不味い状況ではないだろうか。
しかし、ヴィータはそんな懸念を小さく笑い飛ばす。
「どうせ、今こっちの世界に居る『礎の世』の連中なんて、あんた達を除けばカス揃いだ。妨害工作の影響がまだ残ってるから“派閥”は本格的な戦力をまだこっちには寄こせないだろうし、エギアの連中もシバリス以外はそこの雑魚みたいなのが主力だよ。見つかったところでどうでもいいし、寄ってきてくれたならそれはそれで」
「わたしが愉しいよ?」
「って訳だ。あんた達が気にする事じゃないさ」
そう軽く言って、ヴィータは像を抱えると、横目で貴方達を見る。
「で? まず一つ“王格”を手に入れた訳だけど……ここで“仕掛けて”みるかい?」
「…………」
貴方は目を僅かに細める。
それは誘いの問いだ。この像を、自分達から奪ってみるか、という。
だが、ここで決裂すればこの世界に存在するというもう一つの“王格”の正確な行方が判らず、そして貴方には彼女等の像へ封じるような“王格”の対応策がまだ無い。
『もう少し時間が経てば、妨害工作の効果がある程度押さえ込めます。そうすれば、私の“本体”の力を借りて、どうにかこちらで処理するという方法が採れなくもないのですが……少なくとも現状では試す事すら不可能です……』
今はまだ無理となれば、このタイミングで仕掛けるという手は有り得ない。
無言で首を横に振った貴方に、「そうかい」とヴィータは笑い、
「じゃ、ここでやる事はもう無いね。さっさとこんなカス共の血で生臭い場所からおさらばして、次の“王格”を目指すとするよ。エギアの術技士も殺したから、こいつが操ってた海賊連中がまだ外に残ってようが全部廃人だし、アエルを無遠慮に撒き散らす像もあるから“藍の淑女”も寄ってこなかろうよ。喜びな、あんた達。帰りは楽だよ」
「つまんないけどね」
「木偶の坊や気狂いの人魚共をいちいち相手する方がつまらんさ。この像もシバリスが特注で造ったもんだけど、どれだけ持つかは怪しいしね。限界が来る前に、とっとと次回収するよ」
「って、オイオイ。持つか怪しいってんなら、一度像はあの……エルテミシアだっけ? 貴族のお嬢ちゃんに預けてったほうがいいんじゃねーの?」
「予定にないわ。シバリスの“管”は長く繋がれないし、一度切れたら暫く無理だもの」
「次に“落ち合う”タイミングはまだ暫く先でね。……ま、あんた達が気にする事じゃないよ」
「それに、兎さん達にとっては、この方が都合良いでしょ?」
赤い女は気怠げに、金の少女は醒めた笑みと共にそう言い捨てて、二人は祭壇を降りて、さっさと建物の外へと歩いて行く。
貴方達はその背中を暫し見つめた後、互いに顔を見合わせる。
何というか、あの侍従二人は、本当に遠慮が無い。邪魔をする存在は本当に皆殺しにしていくし、そしてこちらに対しても本当に利用するだけの、ドライな態度を見せつけてくる。
『こう言っては何ですが……やはり彼女達とは相容れないものを感じます、ね』
「容赦なさ過ぎだろ。無抵抗で、もう手遅れだとしても、そんな連中をまるでゴミ掃除みたいに殺していきやがる」
「それってつまり、自分達もあの人達の邪魔になればそういう扱いを受けるって事ッスよねぇ……」
本人達が事前に言っていた通り、といえばその通りなのだが。
実際に目の当たりにした、彼女達の情を全く感じさせない割り切りが、こちらの認識の甘さを指摘してくる。
『彼女達が持つ“王格”を封じた像。あれは何処かのタイミングで、何としても奪い取らなければなりません。主であるシバリス・カーライルの思惑はまだ掴めていませんが、まさか確保した“王格”を素直に『礎の世』に戻すなどという真似は決してしないでしょうし』
だから、後々戦いになるのは避けられないだろう。それはいい。しかし問題はその先だ。
「あの人達、先刻気になる事を言っていませんでしたか? 像が、どれだけ持つか怪しいって」
「言われてみりゃ、そりゃそうだわな。あんな像一つで、別の世界の……なんだ、理? そんなもん抱えた存在を延々封じ込められる訳がねーわ」
「つまり、奪い取った後それをどうするかの策を自分達が持ってないと奪い損、って事になるんスかね? そこんとこ、どうするんッスか? クーリアさん」
問いに、悩ましげな唸り声が挟まる。
『さっきも言った通り、妨害工作の影響次第です。この影響が無くなってくれれば、一応マウスベンドールの方で考えた方法を試して、どうにか【NAME】さんの存在概念に一度“王格”を移して、そこからの繋がりを利用して『礎の世』側に“王格”の理だけでも戻す事は出来るとは思うのですが……』
「そんな事して、【NAME】さんは大丈夫……なんですか?」
リヴィエラの表情が心配の色に染まる。貴方としても、先程見せられた“王格”が放つ枠外の力を思い出すと、不安しかない話だ。
そんな問いに対するクーリアの答えは、どうにも苦しげだ。
『……私含めて、大分キツい事になると思います。時間を掛けてやればリスクはかなり抑えられるとは思うんですが、やはり人一人の存在概念に一つの世界の理を乗せてどうにかするっていうのは中々に無理が……』
「でもよ、“王格”ってのも元々は一人が一つ背負うみたいな構造だったんだろ? ならいけんじゃねーの?」
『それは『礎の世』の世界側で、最も適性のある存在に“王格”を移していく手法だからどうにか成り立ってるんです。【NAME】さんにいきなり関係ない“王格”の理を移して大丈夫なのかどうかは、正直よくわからないんです。だってそんな事、誰も試したことありませんから。理論上はそこそこ行けそうでも、実際にやってみた場合、果たしてどうなるか……』
――とはいえ、現状の私達の手となると、それくらいしか残っていないのですけど。
そう、疲れの濃い声でクーリアが呟きを終える。
何とも厄介な話であるが……それが現状の最善というのならば、ある程度の覚悟をしておかねばならないだろうか。
「と、取り敢えず、ヴィータさん達を追い掛けましょうか。置いていかれたら大変ですし」
彼女達の事だ。こちらが付いてこないと、待つ事もせずにさっさと船を動かして帰ってしまいそうだ。そうなると島からの脱出は一気に大仕事になる。
「……にしてもあのチビっ子、服がすげー事になってっけど、ランドリートに戻ったら捕まらんのかね……」
術技陣の補助要員として利用されていた海賊達を皆殺しにしたメリシェンは、全身血まみれだったのだ。
「どうなんスかね。海賊退治をしていたとでも言えばどうにかなるんじゃないッスか? 実際、殺してたのは海賊ばっかだし。……まぁ、その辺はあちらにも考えがあるんじゃないッスかね」
話しながら、貴方とリヴィエラ達は急いで死体が無数に転がる広間を駆け抜け、先行するヴィータとメリシェンの背中を追い掛けた。
次の目的地は、フローリア諸島の代表とされる四島の内の一つ、アノーレ島だ。
エルテミシアの情報によれば、その中部にある森、ラノフ芯林の奥に“王格”が存在している、という話だが――。
礎の王格 翼人の秘を砕いて
――翼人の秘を砕いて──
ラースナウアの都で一度補給を済ませた後。貴方達は魔導船で海を渡り、直接アノーレ唯一の港を持つ町ポロサへと入港する。
まだアノーレは渡島規制が施されているため、港で警備を務める常駐軍の兵士達と一悶着ありつつも、エルテミシアの威光でどうにか切り抜けて、貴方とリヴィエラ達、そしてシバリスの従者二人はシベツの街道を通り、無事第一の目的地であるティネという村に辿り着く。
村の各施設や店などとを巡り、簡単な情報を仕入れて回ると、現在の村の情勢と、そしてティネの村の北東に位置する森で起きている異変が知れる。
「亜獣の動きの活発化と、その裏に最近森に移ってきた有翼種の存在、か。表面上に情報は出てきてはいねーが……」
「ふん。シバリスの情報と組み合わせれば自明に近いさ。この前の島同様、ラノフ芯林でエギアの術技士が亜人を使って儀式の行使と、あと人払いでもやってんでしょ」
「ですけど、この前のゴーシェ島の時と違って、アエルの“光”はあまり広がっても、強まってもいないように見えますが……」
リヴィエラが目を凝らすようにして森の方へと視線を向けるが、どうも彼女から見ると、前回のようなアエルの気配を感じ取れてはいないようだ。そしてそれは貴方から見ても同様だった。
『という事は、こちらの“王格”に対する術技の進捗は、ゴーシェ島の“王格”よりも遅れていると見る事もできますが……どうでしょうね』
推測を述べるも、クーリアは断定を避ける。
今自分達に見える単純な事象だけで推測するのならばそうなるが、
「同じエギアクルスに属していて、同じ大規模術技をやるにしても、そこまでの過程や何をどう使うかは担当してる術技士それぞれだからねぇ。こっちの術技士は周りにバレないようにしっかり対策を施してるって可能性もある。甘く見るのは避けるべきだわね」
「そういや、森の奥に翼人の連中が何かの結界を張ってるって話もあったッス。村人達は自分達の進入を避けるためのものだと考えてたみたいで、実際隠匿結界としての効果も確認済みらしいッスけど」
『同時に、中で起きている状況を外に漏らさないための結界である、という事も十分考えられますか』
クーリアの言葉に、腕組みしていたヴィータが舌打ちと共に浅い嘆息を漏らす。
「確かに、前と違って大きなアエルの波みたいなのが出てないから、明確な位置の特定が出来てないんだよねぇ。……ま、兎に角森の奥に入って、翼人連中の住処まで辿り着けりゃ、解決する話だ。無駄話で時間を潰すのも飽きたし、今から森に入るよ」
ヴィータの言葉に異論は無い。貴方達は自分の荷物を担ぎ直してラノフ芯林目指して歩き出そうとし、
「あの。私達が森に入る事、村の人達に……教えておきますか?」
「はぁ?」
おずおずとリヴィエラが切り出してきた問いに、ヴィータは凶相を見せる。
「教える意味なんて何も無いどころか、逆に変に干渉されたらたまったもんじゃない。ネタはほぼ割れてるようなもんなんだ。とっととラノフ芯林に潜って、“王格”を確保するよ。どうせ亜獣も亜人も、エギアの術技士が操ってんだろうから、そいつやっちまえば話は終いだろ」
「お前達みたいな人の命を何とも思ってない奴等からすりゃ、村人使って亜人達とつぶし合わせてその隙に悠々と……みたいな印象があっけど、そういうのはやんねーのかよ?」
何処か挑発するような笑みを浮かべて言うマヒトに、赤毛の女は気怠げな視線を向けて、
「なんか勘違いしてるようだけど。そういうクソ面倒臭い手回しして逆に手間掛けるくらいなら、自分達で動いて片付ける方が早いし楽なんだからやるわけねーでしょ。……ま、人の命なんて何とも思ってないってのは正解だけど」
「勘違いってそっちがかよ……」
「第一、そういう障害をあたしが頑張らずにどうにかさせるために、あんた達を連れてきてるようなもんだし。ウダウダ口動かしてないでキリキリ働きゃいいのさ。もっとも、メリシェンのお馬鹿は随分とやる気があるみたいだけど」
視線を移すと、ヴィータの横に立っていた金髪の少女は、深く深く笑みを作り、
「亜獣に、亜人でしょ? 亜獣は痛みや苦しみを声でくらいしか出さないから面白くないけれど、亜人をオモチャにするのは愉しそう。ふふ、どんな声をあげて、どんな顔を見せてくれるのかな?」
くすくすと愉快そうに笑う小さな子供。口持ちを大きく横へと引き延ばした顔つきは、元の造形の美しさもあって不気味な印象をより際立たせていた。
「…………」
その態度を、貴方やリヴィエラ達は眉を寄せて不快を表しつつも、しかし眺めるだけに留める。
口を出したところで、どうなるものでもない。所詮は一時の共闘であり、何れの決別は見えている関係だ。そしてその時には、互いの命すら賭け合う戦いとなるだろう。
相手への悪感情は、容赦無くその時ぶつければいい。迂闊な交流で情が生まれ、躊躇や油断に繋がる事が無いように。
少なくともシバリスの従者二人は、如何な交流を経ようとも、自分達を殺す事に一切の迷いを持たないであろうから。
・
簡単な準備を整えて、貴方達はラノフ芯林へと突入する。
村人達が言うには、現在の芯林は既に翼人種達の勢力下に置かれており、芯林外縁ですら彼等の眷属となった亜獣達が侵入者を警戒するように徘徊していて、森に入り込んでくる人間を見つければ即座に襲い掛かってくるという。
とはいえ、そもそも人と出くわして襲いかかって来ない亜獣の方が珍しく、加えてこちらとしても邪魔する者は全て叩き潰すというスタンスだ。それを考えれば比較的どうでも良い情報ではある。出てくるならば一切の躊躇無く打ち倒して進む。ただそれだけの話だ。
「あー、なんかガサガサ音がするッスね」
「入って百歩も進まずかよ。村見張ってたのかこれ?」
何にせよ、先に進むには倒して行くしかない。貴方が武器を構え、それに遅れてリヴィエラ達が身構える。
「んー。なら、わたしは別のと遊んでくるね」
「あたしも上の方が立ち回りやすいし、付き合うかねぇ」
と、メリシェンとヴィータがととんと周囲の木々を蹴って森の上方へと飛ぶ。見上げれば、幹を蹴られて揺れる草葉の隙間から、上空を飛行する何者かの影が見えた。
「空の相手は任せてもよさそうですね」
『なら、私達は下ですね。相手からは……アエルの気配も感じませんし、普通の亜獣のつもりで倒してしまいましょう』
異論は無い。
茂みから飛び出す獣。木の枝や葉に擬態する虫。そして自ら動き捕食しようとしてくる植物の亜獣。
多彩な亜獣相手に、貴方達は森の奥目指して進軍を開始する。
「ぎ」
短い絶叫と共に、何かが森の上から叩き落とされてくる。
一通り亜獣の処理を終えていた貴方達が振り返ると、そこには四肢をもがれ血を噴き出した男が、仰向けの形で転がっていた。叩き堕とされた衝撃によるものか、意識は既に無いようでもしかすると死んでいるのかもしれない。どちらにせよ、今死んでいなくとも何れ死ぬ事には変わりない。そんな重傷だ。
「……あっ、治療をっ……」
反射的にリヴィエラが神蹟による治療を行おうとして、しかし倒れ臥す男の背中を踏みつけるようにして落下してきた赤毛の女がそれを制止する。
「やめときな。手遅れだ。ってか、こいつ、敵だからね」
ヴィータは男を踏みつけたまま、嘆息混じりに背中に視線を向ける。
彼の背中、両の肩胛骨あたりに、えぐり取られたような大きな傷がある。骨まで露出するようなその痕は、よくよく見ると人のものと構造がすこし違っていた。
どうやらこの半死体は翼人であるようだ。背中の傷は、つまり翼をむしりとられた痕なのだろう。誰がやったかは――直ぐに想像がついた。
「ったく、どうも前の島にいた海賊共と違って、人格自体を破壊して洗脳まではしてないみたいだから、こいつを生かせりゃ先進むのが多少楽になったんだがねぇ。――メリシェン! この落とし前、どう付けんだい!」
「先に言ってくれないと無理よ、そんなの。だってこの子、良い声で鳴いてくれたし」
木々を裂く音が響いて、最後に金色の影が空から落下してくる。どん、と踏み抜いたのは翼人の頭部だ。弾けるような音と共に、脳漿が飛び散る。その進行方向に誰も立っていなかったのが幸いだった。
「でももうそれもダメそうだし。壊しちゃうわ。これで落とし前」
「全く、言葉の意味も理解できないお馬鹿には何を言っても無駄かねこれは」
「……ぅ、ぐ」
それを見ていたリヴィエラが、えづくように声を漏らして口元を抑える。メリシェンの躊躇の無い残酷さは、何度見ても慣れる事が無い。特にリヴィエラのような元々の性根が真っ直ぐで優しい人間には、彼女の振るまいに耐えるのは厳しいものがあるだろう。
「まぁ、そんな訳で、残念ながら案内役はお亡くなりだ。取り敢えずはあたし達だけで森を進んでくしかないね」
「元からその予定だっつったらそうだから、何か方針に変わりがある訳でもねーけどな。結局の所、森の奥に進んできゃいいんだろ?」
「村の人達は有翼種の張った結界が森の奥にあるって言ってたッスから。まず探すとするならそれッスかね。結界さえ見つけりゃ、後はトントン拍子で見つかるとは思うッスけど」
『前の島と違って凄く薄くなってるけど、似たようなアエルの流れ自体が存在しているのは私――というか【NAME】さんの感知でも捉えられていますから、それを辿れば、何とかなるでしょう』
クーリアの言葉に、リヴィエラは僅かに頷き、侍従二人も何も異論は出さない。アエルを感知できる者達は皆、クーリアの言うそれを掴めているのだ。
「なら話は早ええ。次の亜獣か、翼人共が寄ってくる前に、さっさと距離を詰めちまおうぜ」
マヒトの言葉に、誰も声は返さず、ただ行動――森を歩き始めるという動きだけで応えた。
頻繁に襲ってくる亜獣達を蹴散らしながらラノフ芯林の奥へ奥へと進んでいくと、途中、妙な違和感に襲われて立ち止まる。他の皆も、それぞれ千差万別ながらも何らかの形で表情を変化させ、動きを止めた。
様々な冒険をこなし、経験を積んだ貴方には、覚えのある感覚だ。探知と人払いを絡めた結界の縁に触れたのだ。
可能であれば、結界が持つ探知の機能を誤魔化して結界の主にこちらの存在を知らせないまま、内側へと滑り込むのが最良なのだが、
「……何これ。鬱陶しいな」
「壊しちゃえばいいんじゃない? なんとなく、あのへんからやな感じなのが出てるの判るし」
と、シバリスの侍従達は躊躇無く術技を駆動させ、強烈なアエルの嵐を叩き付けて、林の各所を結界ごと吹き飛ばしてしまった。
すると同時に、膨大な量のアエルの奔流が辺りに吹き荒れ、芯林を覆い、外の村にも届こうかという勢いで広がっていく。どうやら先刻の結界は、内部で生じたアエルを外に漏らさない為の結界でもあったようだ。
「成る程ねぇ。どうもここで“王格”を解かしてるエギアの術技士は、島に居た奴よりも随分慎重というか、丁寧な仕事をしてるみたいねぇ」
「どうせバレてるのに。馬鹿みたい」
「結局漏れてたしねぇ。シバリスの言うとおり、エギアクルスの連中の質なんてこの程度って事なんじゃない?」
好き勝手に感想を述べる二人だが、芯林で“王格”に術技を施しているであろうエギアクルスの者からすれば、文句の一つも返したくなるような言い様だった。貴方や侍従達がこうしてラノフ芯林に当てをつけてやってきたのも、事前にシバリスが情報を仕入れていたからこそだ。もしそういった裏の情報が無い相手に対してならば、先程の結界もかなり有効に働いていた事だろう。
「しっかし、無茶苦茶しやがんなこいつら……」
「まぁ、常識とか損得とかそういう考えが全くなさそうッスからしゃーないんじゃ……」
後方で先行く侍従二人に聞こえないようにマヒトとシモンズがぼやくのが聞こえたが、あまり仕方ないで済ませて良い行為でもない。
何故なら、結界が破壊された事が知られれば、当然ながらそれに反応してやってくる者達が居るのも道理だからだ。
結界があった方角。森の奥が騒がしく蠢き、更には上方からも独特の物音が響いてくる。見上げれば、翼を背から生やした人影が複数、既に貴方達の真上を周回しており、
「我等が森を、守りを破壊しているのは貴様等か! この大地の恩恵を敬わぬ不心得者どもがっ!」
「お、今度はどうもちゃんと喋れるみてぇだな」
「この前の屍人みたいな相手なら倒すのも楽なんッスけど、こっちの人達は一応まともに動いてるっぽいッスね」
マヒトとシモンズがそれぞれ武器を構えながら、空から響いてきた声に感想を漏らす。
「どちらにせよ殺すだけだから、どちらでも一緒だけどねぇ」
「それでも、やっぱり反応があった方が、遊び甲斐があるわ」
侍従二人の相変わらずな言葉に貴方は呆れ顔を浮かべるが、しかし地上の方でも周囲に無数の気配が生まれ、高速で接近してくるのを感じて口を噤み武器を引き抜く。
ヴィータ達の術技により大きく破壊された森の残骸を飛び越えてくる形で、低空を高速で飛行してくるのは、上空に居る者達と同様の翼持つ亜人だ。彼等は正に問答無用という調子で貴方達目掛けて殺到してくるが、するりと前へと出た侍従二人は緩慢な動きで手を翳し、術技を繰り出すだけで瞬く間に翼人達を血祭りにあげていく。
「あたし達だって、こんなゴミの相手をしてる暇はないってのよ」
「そう? でも愉しいよ?」
「遊びじゃないのよおバカ。……あんた達も、ぼさっとしてないてとっとと片付けておくれよ」
勝手に派手に動いて翼人達を呼び寄せておいて、と貴方は口元を引きつらせるが、しかし襲ってくる翼人達からすれば彼女等と自分達に区別などない。
側面や後方、そして上空から降下し襲い掛かってくる翼人達との戦いは避けられそうに無かった。
次々とやってくる翼人達を蹴散らしながら、貴方とリヴィエラ達は翼人達がやってくる方向を遡るように進む二人――ヴィータとメリシェンの後を追う。
彼女等の進む方向自体は恐らく間違ってはいない。
目指すは翼人達の本拠地。ならば、彼等がやってくる方向がその場所である筈だからだ。既に森全域を包むほどに強く感じられるようになったアエルの波動も、その中心点が翼人達が来る方向と同一である事を示している。
既に戦況は一方的である。赤毛の女が振るう緋色の鞭、金髪の少女が操る黄金の飾刀。鞭が空間を叩くと同時に、彼女の制御下にあるアエルがモノクロの炎の渦という現象を巻き起こし、それに巻き込まれたあらゆるものが、漆黒の焼痕を刻まれて命を奪われる。そして二刀の刃が閃く度に、放たれたアエルによって場が大きく切り裂かれて歪み、世の隙間を切り裂いてその断面に巻き込まれた存在を二分する。どちらも、イーサのみによる防御は不能だ。不定という概念に喰い込まれた理粒子は、その在り方を大人しく歪ませるしかない。それは全ての存在がイーサによって形作られているこの世界に於いて、彼女等の攻撃が生半可な方法では防げない程の圧倒的な力を持つ事を示す。唯の亜人でしかない翼人達は、二人の放つ絶対の攻撃に、為す術無く殺され続けるしかない。
翼人達は島の海賊達と違い、人格までは破壊されている訳ではないようだが、しかしこのような一方的な状況になっても、退くことを知らぬかのように襲い掛かっては屍を晒していく。その様は、後方や側面から来る敵を捌きながら様子を窺っていた貴方達からすると、異様という他無い光景だった。
そこへ、少し調子を落としたクーリアの声が響く。
『……僅かながら、亜人達の身体にアエルによる干渉の痕跡が見られます。恐らく……人格はそのまま残して、術技によって思考を誘導操作しているのでしょうね』
「島の海賊連中と比べりゃこっちの方が遥かにつえーし、島で海賊を洗脳してた奴より、こっちの森で動いてる奴の方が頭が回るっつーことかね」
「といっても、戦力差が圧倒的なのは変わんないみたいッスけど」
前方にて好き放題に敵を蹴散らしていく二人を眺めて、シモンズは溜息まじりに呟く。
「ここで“王格”を像に封じたら、自分達はあの二人と戦う事になるんッスよね。ホントに勝ち目あるんスか?」
「…………」
問われて、【NAME】は鈍く唸る。
リヴィエラと共に相応に修行を行い、更に小手先ながらも一応の策のようなものは練った。が、あの様子を見ていると、勝ち目自体はあるだろうが、勝てると断言は出来ない相手。そんな、曖昧な言いようしか出来ない。
貴方が素直に心情を応えると、シモンズは引きつり気味の笑みを浮かべ、リヴィエラは「……頑張ります」と貴方を真っ直ぐ見つめ、短く心を込めた言葉を紡ぎ、そしてマヒトはがりがりと頭を掻き毟ると。
「まぁ、俺等としても御嬢を殺される訳にはいかねぇ。――言われた通り、やるだけやらせてもらうさ」
――万籟の王格──
襲撃してくる翼人達の勢いが少しずつ減り始め、そして遂には向かってくる者が全く居なくなった頃、貴方達はようやく芯林の最奥に到着する。
そこに広がっていたのは、前回の島の遺跡で見たものとほぼ変わらぬ光景だった。
中央には祭壇。地面に描かれた巨大な術技用の陣の上には、頭を垂れてひれ伏す翼人達。祭壇の直ぐ傍には長衣を着た何者かが立ち、宙に浮かぶ光の塊に祈りを捧げている。
森の木々はほぼそのまま残されており、上方を見れば小さな家屋らしきものが木上に立てられているのが見える。翼人達の住処なのだろう。術技陣は木々を器用に避けるように描かれているが、一部邪魔だったのだろう木は根元から抜き出された跡がある。あくまで優先は術技陣ということか。
「……島の時はまだ余裕あったけど、こっちは結構まずいわねぇ」
貴方達が近付いた事にも気づかず、頭を垂れている翼人の一人を仰向けに蹴飛ばしながら、ヴィータが僅かに声音を落として呟くのが聞こえた。
ごろんと仰向けに倒れた翼人は抵抗どころか、元の姿勢に戻ろうとする仕草すら見せない。頬は痩け、腹はへこみ、脱力して倒れ込む様は半死人のそれだ。翼人が伏せていた場所にはその場で垂れ流したのであろう糞尿の痕があり、臭いが鼻に突き刺さる。
『既に大規模術技を始めてかなりの時間――少なくとも数日は経過しているのでしょう。それに最初から、強制的に参加されられているのだから、こうなるのも仕方無いでしょうね』
「当然休みも無し、交代も無しか」
「当然でしょ? だってその鳥さん達、餌の役割も兼ねてるもの。最後には死んでくれないと逆に困っちゃうでしょ?」
苦々しく呟いたマヒトの言葉に、メリシェンは馬鹿にしたような態度で返す。
「それでヴィー姉。今日は私が封じる役でいいの?」
「そうなるんだけど、術技がかなり進んでるのが心配だねぇ。前のは“殻”が大分残ってたからアエルを注ぎ込めばそれが修復されたけれど、あの“王格”はもう“殻”が殆ど残ってないわ」
ヴィータの視線の先。木掘りの祭壇の上に浮かぶ光の塊は、前回のような球体の“殻”のようなものが殆ど失われており、円形という形を殆ど失って揺らぐ光の塊になっている。波打つように光度を変化させるそれからは強烈なアエルの気配が染み出し、徐々に塊という形すら失おうとしているのを感じる。猛烈な光が、少しずつ周囲へと広がっていくような感覚。更には時折“王格”の周りの風景が色を失い、そしてまた元に戻るという現象を繰り返している。
『中々不味い状況ですね、これ。“王格”という形を崩す作業はほぼ終了していて、次の段階――崩したそれをこの世界に移し込む作業に移ろうとしているようです』
「ってこたぁ、とっとと止めないとやべぇって事かよ」
「あの状態だと、もう“殻”を戻してからとか悠長な事言ってられないねぇ。取り敢えず急ぐよ。あたしが陣と生贄の方潰していくから、メリシェンは像の準備。あんた達は兎に角“王格”が広がって散るのを防ぎな」
「防ぐって……具体的にどうするんスか!?」
「アエル込めてぶん殴りな。もう“殻”を再構成は出来ないけど、術技陣を破綻させた上で、別管理のアエルを“王格”にぶつければそれに誘き寄せられる形で広がるのを止めて、集まってくるから。それを利用して集められるだけ集めて、メリシェンの像に可能な限り封じ込む。時間が経てば経つほど状況が悪くなるし、さっさとやるよ」
ヴィータはそれだけ告げて、鞭を振るう。蛇のようにうねる縄の先端は強烈な衝撃波を放ちながら暴れ回り、地面を抉って術技陣を削り、その上で蹲る翼人達ごと容赦無く破壊していく。次々と生じる血煙が、辺りを濃い赤色へと染めていく。立ち込め始める血の臭いに貴方は顔を顰めるが、確かに彼女の言うとおり、立ち止まっている場合ではない。
「それじゃ、私も行くわ。兎さん達、ちゃんとお仕事してね」
と、貴方の隣で金色の影が前へと飛び出していくのが見えた。構えた両刀が振るわれる度に前を塞ぐように蹲る翼人達が切り裂かれ、細切れになって道を開く。彼女が走るのは一直線。術技陣の中央に存在する祭壇だ。その隣に立ち儀式を進めていたエギアクルスの術技士は、侍従二人の動きに気づいて慌てて向き直り、こちらに対抗するべく術技の準備を始めている。その標的は先行くメリシェンのようだが、彼女は“王格”を封じるための像の準備がある。術技士と戦うのは、
「お仕事ねぇ……。まぁ、しゃーねぇよな。【NAME】、とっとと行くぜ」
「兎に角、“王格”をなんとかしないと……」
自分達の役目である。リヴィエラ達の言葉に頷いて、貴方はメリシェンの後を追うと、途中で減速した彼女とすれ違い、道を開く作業を交代する。
無抵抗な翼人達を切り伏せるのはあまり気持ちの良いものではないが、状況が状況だ。道を塞ぐ彼等を排除しながら、祭壇への距離を一気に詰めていく。
正面では膨れ上がるアエルの気配。エギアクルスの術技士が自分達目掛けて術技を放とうとする気配を感じるが、
「行って!」
リヴィエラの短い合図と共に、杖の打音が響く。詠唱や宣言句すら無く宝石から導き出されたアエルの獣が貴方を追い越して空を走り、その身に術技を喰らいながらも、エギアの術技士に食らいつく。術技士が焦りながら更なる術技を行使し、近接距離からそれをまともに受けた宝精はその形を失って消滅していくが、稼いでくれた時間を生かして、既に貴方は術技士を己の間合いの内側に捉えていた。
「――――」
音の無い、短い呼気を吐きながら、貴方は一気に速度を上げて、己の管理下にあるアエルを練り上げる。
術技士と塊という形すら失い始めた“王格”目掛けて、技法という形でそのアエルを解き放った!
battle
万籟の王格


まずは術技士を落としに掛かる。然程難しい事ではない。所詮は大規模術技を行使するために力の多くを費やしていた相手だ。漂う気配は“同化者”としては曖昧で薄く、殆ど被同化者との間に“道”を繋げられていない。要は全くの雑魚で、戦闘時のアエルの使い方も拙い。これならばそもそも“同化者”ですらないヴィータやメリシェンの方が、アエルの扱いを遥かに心得ているだろう。
あくまで、今回の“王格”に対する大規模術技を問題無く行使するためだけに用意された者でしかないのだ。翼人達を洗脳したり、森の奥に結界を敷くなど、色々と策を用意してはいたようだが、術技士自身の戦闘能力はゴーシェ島に居た術技士と同等程度のものだった。放った連撃を受けて堪らず膝をついた術技士を横から蹴り倒し、祭壇の傍から引き離す形で戦闘不能にする。
問題は、“王格”の方だった。
“殻”という形を失った光の塊となった“王格”は、急速に実体を失おうとしていた。ヴィータの作業染みた虐殺により、術技陣は既に効力を失っている。だが、しかし一度解け始めた“王格”という存在は、放置すればそのままこの世界に対して浸透を始めてしまう。しかも、制御されていないそれは、膨大なアエルと異世界の理を秘めた、異質と言うほか無い代物だ。このまま放置すれば、“異象”顕現から消滅時に生じるものを遥かに上回る“置換”現象――大災害をこの世界に巻き起こすだろう。
「――――」
一つ大きな呼吸を置いて、標的を“王格”へと切り替える。
振るう技法、放つ術式に己の管理下にあるアエルを練り込む。クーリアと二人で考えた、この世界に於いてもっとも最適と思われる“同化者”としての戦闘方法だ。それを次々と光る塊の中央へと叩き込むと、周囲に広がろうとしていた光が中心に引き戻されるように集まってくる。理由は比較的単純だ。こちらが管理し放ったアエルに惹かれて集まっているだけである。他人の管理下に置かれたアエルを、自分達と同種のアエルへと変換しようとしているのだ。元々が“王格”――世界の理を象徴する存在であるが故、未管理や他者の管理下にあるアエルを自分の管理下に置こうとする習性がある。“王格”自身が持つ理を正常に行使するために必要なアエルを確保しようとするためだ。これは『礎の世』に存在していた頃の“王格”達が持っていた能力でもあり、それ故彼等の多くは他者の管理下にあるアエルを無意識に吸い取ることを避けるため、人里を離れ、単独或いは少数での行動を取ることが多かった。
貴方はその性質を利用し、己の内のアエルを全力で振り絞って“王格”に叩き付けていく。戦闘開始時には塊という状態すら維持出来なくなり、周囲に強烈な光を広げ始めていた“王格”だったが、今は貴方の手によりその姿を縮小させ、以前ゴーシェ島で見た“王格”程度の、光の球体程度の大きさで維持させる事に成功していた。
後は、彼女の作業が終了するのを待つだけであるが、出来れば早く済ませて欲しいというのが本音だ。攻撃を放つ度に、これまでの“同化者”としての生活で得たアエルが加速度的に減っていく。この先の事を考えれば、そろそろ終わらせてくれないと今後の戦いに支障が出る。
「んー。これでいい、かな。兎さん、離れていいよ?」
と、祭壇の傍でしゃがみ込み、台座の上に置いた像相手にごそごそとやっていたメリシェンからようやくのお許しが出て、貴方は遠慮無くその場から離脱する。
次の瞬間生じたのは、以前にヴィータが“王格”を捉えたのと同様の現象。像から伸びた無数の手が、上方に浮かぶ“王格”に絡みつき、凝縮し、身の中へと収めていく。抵抗は殆ど無く、光輝く塊は呆気なく像の中へと押し込まれた。
ただ、全く前回と同じ、という訳ではない。
メリシェンが持っていた像は強烈な光を放ったままの状態で、がたがたと振るえるように震動しているのだ。内から漏れ出すアエルの気配もかなり濃い。前のゴーシェ島で捉えた際には、像に外見上の変化は無かったのだが。
『“王格”の“殻”がもう壊れてしまっていたからでしょうね。この像に施された術技では完全に抑え込むのは難しい、ということなんでしょう』
「大正解だよ」
言って、鞭を大きく払って血まみれの鞭から血を払いつつ傍にやってきたのはヴィータだ。辺りに居た翼人達は皆殺しにされており、凄惨という他無い光景が広がっている。
「見て判るとおり、この像であそこまで崩れた“王格”を封じ続けるのはちょいと厳しい。けど、あたし達に任されてた二つの“王格”を確保するという仕事は終わったんだ。後はどうにか、像が限界を迎える前にシバリスと合流すれば何とかしてくれるだろうさ。……具体的にどうするかまでは知らないが、その辺りはあたしにとっちゃ知ったこっちゃないがね」
「取り敢えず、早くランドリートに戻った方が良さそうね」
像を抱え上げたメリシェンに、ヴィータは頷く。
「そうなるねぇ。もっとも――先に一つ、やることが残っているけれどもね。まぁ、それをどうするかは、あたし達には関係ない話だけどさ」
「…………」
にやりと、口元を歪めてヴィータは貴方達を見るが、無言で視線だけを返す。
『……さて、ここからがいよいよ本番です。彼女達に二つの“王格”を持ち帰らせる訳には行きません。だから前からの話の通り、船に乗る前――アノーレ内で、仕掛けましょう』
貴方だけに聞こえるよう、声無き言葉でそう呟いてくるクーリアに、貴方は頷きだけを返し、リヴィエラ達にも目配せする。
厄介なのは、相手もこちらが像を奪いに来るのを当然と想定している事だ。不意打ちはまず無理。正面から殴り合う事になるだろう。
「…………」
リヴィエラ達三人も、それぞれ千差万別ながらも覚悟した顔を返してくる。
事前に打ち合わせと覚悟は済ませてあるのだ。だから後は、実際に刃を交えるだけである。
「じゃ、まずはポロサを目指すよ。そこから船でラースナウアへと帰還する。――行くよ」
ヴィータが告げて転がる死体の中を歩き出し、メリシェンがその後に続く。くるくると踊るようなメリシェンの瞳がこちらに向けられら時に愉しげに歪むのが見える。ヴィータは兎も角、メリシェンの方はどうやらいつこちらが襲い掛かってくるのかを期待しているようだ。
『……あちらの方向……ティネに寄るつもりはないようですね。なら、仕掛けるのはあの場所で』
既にラノフ芯林に移動する前から、幾つかの戦いに向く場所の選定を行っている。クーリアの言葉に貴方は了解と短く返し、先行く二人を追い掛ける。
芯林を離れ、街道へと出る間に広がる、名も無き草原地帯。
――そこが、彼女達二人と決着を付ける場所になるだろう。
礎の王格 深緋と黄金の舞
――深緋と黄金の舞──
――そして、いよいよ対決の時が来る。
場所はティネの森林地帯を西へと抜けてシベツ街道へと合流する手前。膝丈程の草が揺れる以外何も無い空白地域だ。
このままシバリスの侍従二人に、“王格”が封じられた二つの像を持ち帰られる訳には行かない。彼女等の主が像をどのように扱うかは判らないが、過去での出来事から推測するに、単純な『礎の世』への返還などは望めないだろう。何か碌でもない事に使うに違いない。
草原の中。彼女等の行く手に回り込むように動いたのは貴方とリヴィエラの二人である。シバリスの侍従達が術技を操り、アエルによって自分達の存在を変化させ、この世界で一般化されているイーサによる技法、術式を軽減、無効化させることは、以前の戦いの様子や、これまでの“王格”回収の旅の間で判っている。 それ故、彼女達と正面切って戦えるのは、技法術式にアエルを混ぜ込み操る術を学んだ“同化者”である貴方と、『礎の世』より招かれる宝精を操り、そして幾つかの基本的な術技も習得したリヴィエラのみ。マヒトとシモンズ達が表立って戦うには、この場は荷が重い。それが判っているのか、二人は心配げな表情を隠さず、しかしそろりそろりと、これから発生するであろう状況に巻き込まれぬように動き始めている。
対し、突然行く手を阻まれる形となった二人の侍従の表情に驚きの色は当然無い。彼女達もいつ頃仕掛けてくるのかと待ち構えていたのだから当然だ。
二人は浅い身構えと共に、笑みすら浮かべて貴方とリヴィエラを見返す。
「ま、この辺りが潮時だろうしねぇ」
「随分待ったわ。あなた達と、また遊べるの」
ヴィータとメリシェン。彼女等の手元に“擬象”を呼ぶための像は無く、逆に“王格”を封じた像がある。彼女等はそれをこちらに奪われる訳には行かない。文字通りのお荷物である。それでも、手強い相手なのは変わらない。
「…………」
その言葉に、貴方とリヴィエラは何も言葉を返さず、己の武器を強く握り締める。視界の片隅、リヴィエラの表情は硬く強張っており、呼吸も浅い。強く緊張しているのだろう。当たり前だ。元々戦闘経験はあまり無く、自分とクーリアの指導により戦闘能力自体は飛躍的に上昇したが、それも実戦を経て身についたものではなく、詰め込みの訓練によるものである。今回のような正面切って、命を賭けた決闘を経験した事など一度もないだろう。
加えて、リヴィエラは過去にメリシェンと“擬象”という組み合わせに追いかけ回された過去を持つ。そんな相手に、生死の境を幾度も乗り越えてきた自分のように全く緊張しない方がおかしい。
しかしこの場において、リヴィエラの助力はどうしても必要だった。自分一人で、ヴィータとメリシェン、二人の卓越した術技使いと戦うのは正直厳しいという他無かった。例え多少劣った戦力であろうとも、援護してくれる者が一人いるかいないかで、状況は大きく変わる。勿論リヴィエラが負う危険は相当なものとなるが、それでも、ここが一つの分水嶺だ。もし敗北し、全ての“王格”がシバリスという底の知れない男の元に渡ってしまえば、この先の展開が全く読めなくなる。持てる戦力は、可能な限りここに注ぎ込むしかなかった。
お互いが、お互いを殺す気で掛からなければ、勝つことは難しいだろう。
【NAME】とリヴィエラ、ヴィータとメリシェンの間で、緊張が極限にまで高まり、そして。
「――ッ!!」
戦いが始まった。
battle
深緋と黄金の舞


アエルを一度に込められる限界まで込めた技法を、横薙ぎに大きく振り払う。
大きく広く、空間をモノクロームに染める力の波が、ヴィータとメリシェン、二人の術技使いの身体を後方へと押し流す。黄金と緋色。二つの色がその力に反発するように輝くが、しかし押し切られるようにして双色の光は途切れ、二人は力の波に呑まれぬように高く大きく飛び退って逃れようとする。
そこへ、
「オフィエル! ファレグ! ピュレ! 行きなさいっ!」
短く叫ぶ声が走り、連続で響く打音。複数の宝精が、宝精召術の常識からすれば有り得ない速度で喚び出され、貴方の放った一撃を飛び越すような軌跡を描きながら、宙に浮いた状態の侍従二人目掛けて襲い掛かる。
これが普通の術式や、召喚術により喚び出された存在による攻撃であるならば、彼女達は対応の姿勢すら取る事無く、独自の回避法でもって容易く捌いてしまっただろう。
彼女等――シバリスとその従者達が使っている回避法。彼等と始めて相対したアサーン戦後、クーリアと幾度も意見を交わした結果、推測ではあるがその種はもうほぼ割れていた。それはアエルを使い、己の存在をイーサではなくアエルにより形作られたものへと一瞬だけ変化させて、イーサによる攻撃を無効化しているのだろう、と。
この世界には基本的にイーサしか存在しないが故、あらゆる攻撃はイーサに基づいた現象を由来とする。それ故に、アエルというイーサとは違う理粒子を基にした存在へと己を変質させる事で、互いに干渉できない状態にして、受ける攻撃を無視しているのだ。
この手法の効果は絶大と言っても良く、理論上ではどれほど強烈な攻撃であろうともイーサが起こした現象であれば回避可能という、半ば詐欺じみた効果を持つというのがクーリアの結論だった。
しかし、この相手が宝精となると話が違ってくる。宝精は『礎の世』より石を渡って招かれた、アエルの力を帯びて仮の実体を持つ存在だからだ。彼女等はイーサによる攻撃に対しては絶対に近い回避法を持つが、しかし技法や術式にアエルを織り交ぜた貴方の攻撃や、アエルそのものを形とする宝精による攻撃にそれを使うと、無効化どころか通常時よりも大きなダメージを負ってしまうのだ。不定理粒子というだけあって、アエルはそもそもが理粒子よりも不安定な存在である。己の存在をそんな理粒子へ変質させた所で「相を合わせた」攻撃を受けると、その影響は、より安定しているイーサという理粒子で身体を構成している時よりも崩れやすくなってしまうのだ。
故に侍従達は飛来する宝精に対し、まともに受けるか或いは避けるか、何らかの守りの行動を取る必要があった。
「っち」
短い舌打ちの音。
ヴィータは空を更に蹴って宝精の追撃を飛び越えて回避すると、更なる追撃の構えを見せていた貴方へ鞭を振るって牽制を入れ、逆にメリシェンは黄金の刀を振るって宝精を切り捨て、身体を上下に反転させて空を踏み、素早く地面へと着地する。そこへ、貴方とリヴィエラは更なる追撃を準備し、放っていく。
現在の戦況は、貴方とリヴィエラがヴィータ、メリシェンの二人を順調に追い込み、有利を維持して攻め続ける形で進行していた。
その理由は、貴方とリヴィエラの二人がアエルを使った攻撃方法をそれぞれ習得し、力を伸ばしたというのが一番だが、所有しているアエルの総量と、攻撃方法の相性。更には侍従二人が像という「守らねばならないもの」を所持しているのも大きかった。
前回は“擬象”という膨大なアエルを秘めた化け物が居たが今は無く、彼女達が個人で管理下に置いているアエルは、“同化者”として活動する生粋の『礎の世』の住人である貴方よりもかなり少ない。術技の技量については相手のほうが上だが、所詮彼女等はこのイーサが全てを司る世界にて生まれた身である。純粋な素養の面では貴方どころか、特殊な体質を持つリヴィエラにすら大きく劣る相手だった。
加えて、リヴィエラが宝精召術というアエル戦において大きなアドバンテージとなりうる術式を習得しているのが更に効いた。ヴィータ、メリシェンの戦闘方法が貴方に近い、技法にアエルを注ぎ込む類が多いのに対し、リヴィエラの宝精召術はそのまま使うだけで純粋なアエルを用いた攻撃となる。しかも、『礎の世』の知識とクーリアの指導によって、その威力は通常の宝霊召術より大幅に増し、召喚速度も比べものにならない。貴方が前衛を務めてヴィータとメリシェンの動きを止め、後方からリヴィエラが宝精召術を使い遠隔攻撃を仕掛ければ、それだけで相手はほぼ一方的に叩かれる状態に持ち込まれるのだ。
当然、この状況がまずいのは敵二人とも理解しているのだろう。大きく距離を取ったヴィータとメリシェンは、
「メリシェン、このままじゃ押し切られる。相手を割るよ。あんたのが足がある。後ろ回りな」
「いーよ。私が“攻め”でいいよね」
「好きにしな。けど、早めにケリつけないと後でお仕置きだからね」
「怖いわね。でも相手があの子なら、寄ってしまえばそんなに掛からないわ」
短く言葉を交わし、その動きを変えた。
メリシェンが草原を抉るように走り出すと同時に、ヴィータの鞭が貴方目掛けて放たれる。こちらの身体を真正面から狙うのではなく、僅かに角度を付けた一撃。地面の土を容易に陥没させる鞭の連撃は、走るメリシェンへ介入を出来ないように、貴方の行く手を遮る壁を作るような攻撃だった。
「――ッ」
それだけで、相手の思惑が読めた。それを覆すべく、貴方は素早く下がり、後方にいたリヴィエラとの距離を何とか縮めようとするが、
「駄目だっての」
声と共に、ヴィータが大きく前へと真っ直ぐに、躊躇う事無く前進してきたのだ。
その動きに意表を突かれる。彼女が持つ鞭は中距離の武器であり、アエルを織り交ぜた技法でもって遠距離にも対応している。だが、構造上ある程度の間合いを保たねばならない事には変わらない。近距離はどうしても不得手となる。そんな彼女が、全速で貴方との距離を詰めてきたのだから。
同時に、燃えさかる鞭が後方へと下がろうとしていた貴方目掛けて次々と放たれる。下がる速度が追いつかず、かといってこの状況から鞭を封じる為に懐へ飛び込む訳にもいかない。受けるか、まだマシな左右へと回避するか。しかし鞭相手に受けの選択肢は良手ではない。貴方は仕方無く横への回避を選び、続けて放たれる鞭によって移動方向を誘導されて――結果、リヴィエラと合流する機会を逃してしまう。
「【NAME】さんっ!! あっ、く」
「余所見している場合かしら? 兎さん」
視界の隅で、リヴィエラが駆け寄られたメリシェンに鋭く斬り付けられるのが見えた。間に合わなかった。そう思う間に、ヴィータの鞭が更に貴方とリヴィエラ達とを遮るようにして放たれる。
二対二で不利ならば、一対一を二つ作る。
ヴィータ達が狙った構図が完全に成立してしまい、思わず歯噛みする。
しかも、この形は非常にまずい、と貴方は呻く。ヴィータと自分の方は兎も角として、メリシェンとリヴィエラの相性が壊滅的なのだ。
両の手に黄金の刀を携え、近接距離を得手とし手数重視の型を持つメリシェンと、手持ちの宝石から宝精を召喚する事でようやく攻撃の形を作るリヴィエラでは、速度負けするのは目に見えている。実際、ヴィータと打ち合う間、隙を見てリヴィエラ達の方へと視線を飛ばせば、愉しげな笑い声を上げるメリシェンがリヴィエラを両の刀で追い詰めていた。リヴィエラは相応の杖術に神蹟、そしてアエルを使った初歩的な純粋な術技も習得してはいるが、それが実戦でどれだけ役に立つのかと言われれば未知数という他無く、やはり寄られてしまえば二刀を操る近接の名手を相手にいくらも持たせられるものでもない。どうにかリヴィエラを援護するため攻撃をメリシェンに飛ばそうとするが、
「だーめよ」
近距離まで詰めてきたヴィータが手を素早く振る。袖口からこちらの首を薙ぐように払われたのは緋色の鞭ではなく、細い鉄鎖だ。近接用の副武器。持っていてもおかしくないどころか当然とも言える。喰らったところで致命的な手傷を負うものではないが、何らかの隙が生じるのは確実で、そこへアエルを込めた鞭で打ち据えられれば勝負は即座に決まってしまうだろう。
この状況を自分の力で打開するには、リヴィエラがメリシェンに斬り殺される前に目の前のヴィータを排除し、リヴィエラの救援に向かうしかない。
貴方は意識を切り替えると、間合いを詰めていたヴィータ相手に一気に踏み込み、距離を徹底的に寄せて鞭を封じた上で、短時間での決着を狙う。
だが、その動きを読んでいたかのように、ヴィータは鉄鎖と術技を使って貴方の動きを牽制すると、素早い動きで貴方の傍から大きく後方へと飛び退り、後は下がりながら誘うように鞭を振るって、自分とリヴィエラ達との距離を離そうとしてくる。
放ってくる鞭の動きにはこちらを倒そうとする意気は弱く、完全に時間稼ぎを目的とした動きであるのは明白だった。故に、浅いが隙が無い。
「く」
そんなヴィータの動きを見て、短い声が漏れる。
徹底している。あくまでヴィータは、メリシェンがリヴィエラを殺すまでの足止め役である。彼女からすれば、別に今貴方を倒す必要は無いのだから守勢で牽制重視の立ち回りとなるのも当然だ。メリシェンがリヴィエラを処理した後に、二対一の構図でこちらを嬲れば良いだけなのだから。
こうなってしまうと、少なくともこちらからのアクションで逆転の目をたぐり寄せるのは難しい。
しかし、他にやりようもない。貴方は状況の悪さを自覚しながらも、回避と牽制、守りと足止めに終始するヴィータに対し如何にして距離を詰め、打ち倒すか。それを懸命に考え続けた。
・
こういう展開になる可能性は、実の所、事前に予想はしていたのだ。
左右から走る黄金色の刃を懸命に凌ぎながら、リヴィエラは過去の記憶を思い出す。
シバリスの侍従二人と共に“王格”確保の旅に出ることが決まった段階で、彼女達と最終的に戦闘になるのも規定路線となっていた。だから、リヴィエラ達は彼女達二人に気づかれないタイミングで、幾度も今回の戦いについての打ち合わせを行っていた。
その中で、【NAME】と自分が分断されるという予想も当然ながら行われており、その時どう動くべきかという点に於いてもある程度打ち合わせていた。
最良の展開は、そういう形に持ち込ませないこと。そしてもしそうなった場合、多少強引であっても無理矢理合流を目指す、という事になってはいた。
しかし、いざメリシェンという少女を前にすると、そのような行動をする猶予はないとリヴィエラは判断するしかなかった。メリシェンの攻撃は苛烈という他無く、特に速度の面では目で追うのも難しい程だ。【NAME】との訓練で彼の動きを目の前で見続けてきた今のリヴィエラでも、メリシェンの攻撃を捌くのは半ば勘頼みに近く、その手から逃れつつ【NAME】との合流を目指すのは不可能と言う他無かった。宝精召術用の杖がアサーン戦前に使っていた木製で無かったのは幸いだ。もし木製のままであったなら今頃メリシェンの刀に切り刻まれ、杖の体裁すら保て状態になっていたに違いない。
右、左、回転からの更に左、左、そして右。
流れるような攻撃を、鳴銀製の杖で受け流す。甲高い音と共に杖が火花を放ち、刃の痕が杖に刻まれていく。鳴銀は同調誘導器の素材として優れ、リヴィエラでも扱えるような比較的軽い金属であるが、しかし金属としての硬度はそれなりだ。メリシェンの一撃には重さはない故にどうにか破壊されずに済んではいるが、刻み込まれた刃の一撃は杖の形状をどんどん歪なものへと変えていく。同じ場所へ数度、刀を打ち込まれれば恐らく杖はそのまま斬り断たれてしまうだろう。
それでもどうにか凌ぎ切れているのは、偏にメリシェンの動きが加減されたものであるからに違いない。相手をしているリヴィエラは、それを恐怖と共に理解していた。要は、遊んでいるのだ。
自分よりも背丈の低い少女が放つ刃の群れに、リヴィエラは必死に杖を合わせる。刃を振るう度に踏み込んでくるため、リヴィエラは後ろへと下がりながらの防御行動だ。走る金閃の間に見える少女の顔には、にんまりとした笑みが浮かんでいる。目の前の獲物を弄び愉しむ狩猟者の眼が、自分を見ている。同じ人間、同じ性別、歳は同じ処かかなり歳下。そんな者が自分に向ける瞳に、リヴィエラは不気味さと恐ろしさしか見出せなかった。【NAME】との訓練を経て、多少なりと身体が自然に動いてくれているからどうにかなっているが、いつ自分の手が、足が、首が飛んでもおかしくない、そんな紙一重の危うさの上に自分が立っている事は十二分に理解していた。心臓が激しく脈打っている筈なのに、頭はまるで血が足りないみたいに上手く働かず、視界が狭まり全身が重くなっていく感覚が収まらない。
――怖い。
下がる。下がる。目を離してはいけない。けれども、救いを求めて視線が動く。片隅、ヴィーラと相対している【NAME】の姿が目に映る。その距離は先程までよりも開いている。モノクロの炎が舞って、弾ける土と草が、【NAME】との距離を更に離していく。それを掻い潜り、どうにかこちらへと近付いてきてくれる【NAME】の姿が見えるが、彼が自分の所に辿り着くより先に、メリシェンの刃が喰い込む方が早いだろうと、リヴィエラは鈍く回転する頭で理解する。
――怖い。
それを理解して、心が強く震える。【NAME】の助けはない。つまりそれは、今目の前に居る少女の姿をした化け物を、自分達だけでどうにかしなければならない。
少女の二本の腕が跳ねて、刃が左右から同時に来る。自分の杖術では捌ききれない。半ば転ぶように腰から後ろに尻餅を突いてその刃を潜り、下方から突き上げるように杖を放つ。踏み込みながら両の刃を放った後、という明確な隙に対して放った一撃は、リヴィエラにしてみれば起死回生を狙った渾身の突きだ。しかしメリシェンは前に踏み込んだ勢いなどまるで無かったかのように、一瞬で体重を後ろへと移して、身を逸らし、くるりと後転してその突きを回避した。
距離が僅かに離れる。そして空中から着地へと続く明確な猶予の時間。リヴィエラはその貴重な間を利用して攻撃――ではなく、半ば這うようにしながら立ち上がると、全力で彼女から離れるように走り出した。
――怖い。
背を向けて、逃亡する。後ろを全く確認せず、ただメリシェンから離れるだけのその行為は、普通に考えれば自殺行為に近い。何故なら、リヴィエラの身体能力は以前より向上しているが、メリシェンの速度には到底及ばないものだからだ。例え全力で逃げ出そうとも、大した時間も掛からず追いつかれる。しかもリヴィエラが走る方向は【NAME】が居る場所とは逆だ。つまりもう【NAME】の助けは殆ど望めない状況に、自分から飛び込んでしまっていた。
「あははっ! 本当に貴女って兎さんみたいね!」
着地したメリシェンが、喜色の声を上げてリヴィエラを追う。
速い。後ろを見ずに走るリヴィエラは、後方から迫る気配の速度に絶望する。これでは“決めていた場所”にまで逃げ込めるか、それすら判らない。
――怖い。でもっ!
諦める訳には行かない。リヴィエラは自分が出せる限界の速度で走り、どうにか追いつかれる前にその場所を通り過ぎる。
後は、ここで決めるだけだ。
思い、リヴィエラはこれまでの逃走から一転、袖口から一際大きな宝石を握り締めて、決意を秘めた顔つきで足を止めて振り返る。
――これ以上、足手まといになんてならないっ!
「あら、諦めちゃったの? そんなのつまらないわよ?」
視界に映った、高速でこちらに迫るメリシェンの姿が自分の元へと到着するのに、残る歩数は大凡五歩程。時間にして二秒も無いだろう。振り上げた刀が薄く陽光を浴びて燦めく。
それでも、ここが勝負所だった。
リヴィエラは手にした宝石を眼前へと放り投げ、幾度も刀を受け止めてボロボロになった杖を大きく振り上げる。
「覚醒せよ! 宝たる石に宿る精霊よ!」
今のリヴィエラであれば、中位までの宝精ならば宝石を杖で叩くだけで召喚出来る。しかし、それでは力が足りない。故の、宣言句を用いての宝精召喚。
「あはっ残念! それじゃ、間に合わないわ!」
振りかぶった刃をメリシェンが振り下ろす。既にリヴィエラの身体は射程内。これまで彼女が防御に使っていた杖は、宝石を叩くために振り下ろされている最中だ。今更その動きを変化させることは出来ない。
黄金の軌跡が空間を走り、リヴィエラの肩口から腰上を斜めに薙ぐ。その直前――
「させないッスよ」
ざっ、と草原の中から小柄な男が立ち上がり、その軌跡に合わせて斧を掲げ、刀の一撃を受け止めようとする。
メリシェンは突然姿を現した男に眼を見開き、そして一瞬で気づく。リヴィエラがこちらに背を向けて逃げ出し、しかし唐突に振り返って自分に攻撃を仕掛けてこようとした。それはつまり、この場所でならば宝精召術を使うことが可能と考えていたということで、
「あら、伏兵? でも、アエルも使えない貴方達が立ち塞がったところで――」
メリシェンは黄金の刃にアエルを通し、掲げられた斧に触れる瞬間、その存在全てをアエルへと変換する。普段使っている回避術を武器に転用したのだ。これでイーサで形作られた武器を一瞬透化させて、直ぐに元に戻してリヴィエラを切り裂く。そのつもりで、彼女はそのまま刃を振り下ろし、
「――っ!?」
きん、と金属が噛み合う音が響き、振り下ろしたメリシェンの腕が弾かれて浮かぶ。メリシェンの顔が驚愕に歪み、その動きが停止する。無理からぬ事だろう。己の攻撃が斧を擦り抜けて人の肉を裂くと、そのつもりで振り下ろした武器が、途中で硬い金属にぶち当たって止まったのだ。力の入れ方も当然そのつもりで行っており、故に想定外のところで重い金属にぶち当たった反動で、腕は跳ね上がり、身体は動きを止める。
「何故!?」
「何故ってそりゃ、自分の武器にもアエルを宿らせておいたからに決まってるじゃないッスか」
簡単にそう告げる小男――シモンズに、メリシェンは唖然と表情を固まらせる。
これまで、この男がアエルを使う様子など一度も見た事が無かった。彼等自身も、自分達はアエルを使った戦いでは役に立たないとずっと言っていた筈だ。なのに、
「そん――」
「な馬鹿な、と言いたいところだろうが、まぁいつか戦う可能性のある相手に、手札全部晒すわけねーだろ?」
「――あ」
声をした場所。傍の草むらの中に、長身の男が伏せているのをメリシェンの眼が捉えた瞬間、彼――マヒトが槍を斜め上へと突き出し、少女の身体を横から貫いた。
「い、いた……たい……なん、で? どうして、刺さってる、の?」
「どうもこうも。要するに、アエルってのが混ざってりゃ、お前等避けられないんだろ? いやまったく、苦労したんだぜ? 【NAME】の奴にかなりハードに鍛えられて、あいつが持ってるアエルをちょいっとばかし事前に分けて貰って、ようやく攻撃一度分のアエルを使えるようになった程度だからな」
そのまま、マヒトは槍を両手で持ったまま立ち上がると、突き抜けた穂先を地面に刺す。貫かれたままのメリシェンの身体が、大きく傾いた姿で地面に打ち立てられる。少女の長い髪が地面に垂れ下がり、口の端から血が溢れ落ちる。
「そんな……の、おかしい……だって、あなた達は、兎さん……なのに。それで……わたしは狼で……」
「そんな兎さんでも、狼を殺すくらいの歯は持ってるってこった。甘く見たお前の負けだよチビっ子。取り敢えず御嬢、動きが止まってる内に、とっととそいつを打つけちまってくれ。いつ正気に戻って逃げ出そうとするか判らん」
「……はい」
そして串刺しとなったメリシェンの前では、先刻より十数歩程距離を取った上で巨大な宝精の召喚を終え、翼持つ鯨のような外見の存在を上空に浮かべて制御するリヴィエラの姿があった。
「――さぁ、行きなさい、オブシダンファレーグ!! この者の全てを消し去ってっ!」
言葉と共に、彼女が掲げていた杖が振り下ろされる。
その軌跡に沿って、一度ぐるりと空中で身を回した大宝精が、距離を取ったマヒトとシモンズと入れ替わるように、小さな少女の身体を飲み込むようにして突撃し、破裂した。
・
「これは……想定外だわ」
相対していた女が舌打ちと共に呟きながら、腕を独特のしなりを持たせながら振る。
緋色の鞭が不可思議な曲線を描いて唸り、噴き出したアエルが周囲をモノクロームの炎となって荒れ狂う。その半ば面に近い攻撃の隙間をどうにか潜り抜け、体勢を立て直した貴方は、開いた間合いに隙を見出し、彼女が向ける視線の先を見る。
「…………」
光景に息を呑む。
そこでは、リヴィエラの放った巨大な宝精が破裂し、草原をえぐり取るように地面に大穴を空けていた。リヴィエラ、マヒト、シモンズの姿があるが、彼等の視線の先には何も無い空間しかなく、そしてつい先程までリヴィエラを追い詰めていた少女の姿は跡形も無い。
「あのお馬鹿、ホントに死にやがった。しかも“像”ごと潰されるとか……」
鞭の動きが変わる。地面を薙ぐように払われた緋色が垂直に火の柱を立ち上げて、長大な炎壁を打ち立てる。ヴィーラが管理しているアエルの内、かなりの量を注ぎ込んだと思われるその炎の壁は厚く、それを貫くべく放った貴方の攻撃も、炎の圧力に呑まれて押し返されてしまう。
「悪いけど、ここは退かせてもらう。最低でも一つは持ち帰らないと、シバリスに顔向けできないからねっ!」
そうしている間に、炎の向こうでは、“像”を手にした女が遠くこの場から離脱すべく走り去っていく。
その様を見て、貴方は内心に焦りを得る。この炎壁が消えるまで待っていては、確実に追いつけなくなる。
貴方は先刻の一撃よりも管理下のアエルを多く注ぎ込み、大規模技法を放つために力を溜める姿勢に入り――
「あ、あのっ、【NAME】さんっ! 出来れば、すぐこっちへ来て下さいっ!」
遠くから聞こえる悲鳴染みた声に、貴方は思わず意識をそちらへと向けてしまい、その拍子に注ぎ込もうとしていたアエルが管理下から離れ、溜めていた力が散ってしまう感触に、思わず舌打ちする。
だが、声のした方を振り返った貴方は、その事も直ぐに忘れて、視線の先に見えたそれを唖然と眺めた。
リヴィエラが叩き込んだ大宝精の一撃により地面に空いた大穴の上に、巨大な光の塊がふわふわと浮かんでいたのだ。
その存在は、貴方にとってはもう見慣れたといってしまってもいいものだ。
『あれは……“王格”?』
そう。つい先程、ラノフ芯林にて確保した“王格”である。
何故あれがいきなりこんな所に現れているのか。突然の事に、貴方は一瞬眉をしかめて考え込んで、
『……って、そりゃそうか! “王格”を封じていた“像”ごと破壊しちゃったら、そりゃ中身出てきちゃいますよっ!』
クーリアの叫びに、ああ成る程と得心する。考え込むほどの話ではなかった。が、しかしこの状況自体は至極不味い。
「おい、【NAME】、クーリア! これどうすりゃいいんだっ!? このまま放置してて大丈夫なのかよ!」
『大丈夫じゃないです! メリシェンさんが封じた“像”に入っていた“王格”は“殻”が破壊された状態でしたから、そのままだと“異象”みたいに辺りを巻き込んで“置換”を発生させるか……もしくは近くに居る適合者を宿主にして……リヴィエラさんっ! 下がって!』
「え? あ、きゃ、っ」
クーリアの警告の声とほぼ同時。ただ穴の上で停止していた“王格”が、ゆらゆらとリヴィエラの方へと近づき始め、それに気づいた彼女は慌てて距離を取ろうとする。
「ったく、何だってんだ! おい、それ以上行かせねぇぞ!」
慌てたのはリヴィエラの護衛達だ。いつもの槍を失ったのか、素手の状態のマヒトがリヴィエラへ向かって移動していく“王格”に突っ掛かるが、光の塊は全く見たまま、実体の無い光の塊でしかないように、立ち塞がったマヒトの身体を擦り抜けてしまう。
「こいつ、オレ達は素通りしやがるっ! 御嬢、もっと退け!」
「は、はいっ! っと、あっ」
迫る“王格”は、リヴィエラから見れば目も眩む程に輝く“光”である筈だ。そのあまりに濃厚なアエルの気配から目をそらせなかったのか、彼女は視線は“王格”へと向けたまま後ずさるように下がっており、そのせいか踵を地面の凹凸に引っかけたらしく、ころんと尻から地面に転んでしまった。
貴方との訓練前にはよく見た姿だったが、今、この場でそれが発生するのは至極不味い。ふわふわとリヴィエラに近付き、光の帯のようなものをリヴィエラへと向けて伸ばしていた“王格”の動きが、標的が地面に倒れ込み動きを止めたことで、一気に加速する。
慌ててマヒトが壁になるように割って入るが先程と同様、光は擦り抜けるようにしてマヒトの身体を通り過ぎ、
「なら、これはどうッスか!」
アエルの気配を纏わせた斧を光の塊目掛けて振り抜いたシモンズだったが、斧は僅かに光の塊の手前で止まった後、直ぐにするりと通り抜けてしまう。纏わせたアエルが一瞬の接触で飛び散ったのだ。
光の塊は、地面に倒れ込んだままのリヴィエラをまるで取り込むかのようにその輝きを広げていく。
そうしてついに“王格”がリヴィエラに触れようとする、その間際。
『仕方在りません、このまま突っ込んで!』
「――っ」
クーリアの指示が届く前に、貴方は体当たりするように、光の塊という姿を取る“王格”に飛び込んだのだ。
瞬間、光の塊が、貴方の身体の中へと吸い込まれるように入ってくる。
より正確には、身体ではない。その奥にある、“同化者”という自分の存在概念に取り憑くように、だ。
そして次の瞬間には、強烈な意識の混濁が襲ってくる。視界が無茶苦茶に歪み、外部の情報がまともに手に入らなくなる。身体の感覚も失われて、ぐねぐねとうねる視界が横倒しになるのが辛うじて判った。
『私の術技が直接発揮出来る分、リヴィエラさんが“王格”に取り込まれるよりは余程マシです! 【NAME】さん、聞こえますか!? 今から私が制御して、どうにか“王格”を貴方の存在概念の制御下に置きます! どんなに気が遠くなっても、絶対に意識だけは失わないで下さい! 貴方が気を失ってしまうと、私が休眠状態に移行しちゃって、どうしようもなくなっちゃいますから! ……ああもう! “私”じゃなくて、“本体”が出張れたら、こんなにギリギリになんてならないのにっ!』
無茶を言ってくれる、と心の中でそう返す事すらも難しいが、こうなってはもう、頼れる存在はクーリアしかいない。
朦朧とした意識の中。貴方は己の根本に入り込んできた“王格”の力に、正に死に物狂いで抗い続けるしかなかった。
礎の王格 究者の矜持
――究者の矜持──
「……ぐ」
鈍く、自分が声が漏らしたことを自覚する。
きつく閉じていた目を開けば、随分と周りがまともに見えるようになっていた事に驚いた。先刻までは様々な色彩が捻れた渦しか映らなかったというのに、今はぼんやりとだが、周囲の風景が色の塊として捉えられるようになっている。
『――そ――定――と、思――か?』
「目――それ――で――う!」
わんわんと頭の中で鳴り響く音の合間合間に、飛び飛びの思念と声が届いてくるのを感じ取る。これは何だったか、と思っているうちに、長い間完全に停止していた“考える”という力が戻ってきているのを感じた。震える手で、バラバラになっていた意識の歯車を組み合わせて、ゆっくりとそれを動かしていく。それによって、考える。思い出す。状況を把握する。そうしようとする意志が戻ってきた。
そうすると、加速度的に五感が戻ってくる。どうやら自分は今何処かに寝かされているらしい、背中に接する触感からそれを判断する。
視覚も、先程までの色の塊ではなく、明確な形として捉え、それが何らかの物体であるのかを認識できるようになっていた。
止まっていた頭が動き始めたお陰で、物体が何であるのかも、徐々に判るようになってくる。
頭の中に鳴り響いていた音も次第に収まり、澱んだ空気の臭いが、ここが室内であることを教えてくれた。
「【NAME】さん、大丈夫ですか? 私の声、聞こえますか!?」
「おい御嬢、あんまがっつくなっての。クーリアが言うには、まだかなりキツイ状態なんだろ?」
『どうにか、“王格”の力全てをこの人の存在概念に抑え込んで、擬似的な“王格”へと仕立て上げる事には成功したとは思います。負担の方も、時間が経てば馴染んである程度収まるとは思うのですが……』
響く声の意味も、何とか認識出来ている。それに安堵しながら、貴方はどうにか身体を起こそうとする。四肢は鉛のように重く、しかし自分の内側からは焼けるような熱が満ち、力が溢れて身体が破裂しそうにも感じる。
身体――いや、この身体に同化している自分という器に、恐ろしいまでのアエルと、自分ですら理解出来ない何かが宿っているのが判る。判るが――しかしそれだけだ。自分には、“王格”として宿る『礎の世』の理に手を出す才がないのも感じ取れてしまう。扱えるのは、“王格”が秘めていた莫大な量のアエルだ。それが自分の管理下に置かれ、自在に使えるのだけは判る。
苦労して半身を起こし、深く一息。取り敢えず、自分は像から解放された“王格”をどうにかする事が出来たと、そう考えても良いのだろうか?
『出来てはいますが、完全な適格者ではありませんから、負担は常に掛かると思って下さい。本来なら、貴方を経由して直ぐにでも“王格”を成していた要素全てを『礎の世』側に送るのが良いのですが――まだ障害が完全に復旧できていない上に、ヴィータが持っていった“王格”の件もありますから、それは早いかと。……貴方にも、“王格”が持っていた巨大なアエルの力は把握できているでしょう?』
確かに、このアエルは今後どうなるか判らない所を考えれば有り難いものだ。
『結局、あのシバリスという“同化者”が“王格”を回収した後どうするつもりなのか判然としていませんから、こちらも同じ“王格”を対抗手段として残す必要があるんです。例え“王格”の理に触れられずとも、膨大なアエルは確かな力となりますからね』
頷いて、貴方は足を着いて周囲を見渡す。どうやら場所は宿の一室であるようだ。先刻まで寝台で寝かされていたらしい。まだ完全に復調したとは言えないが、大分調子は戻ってきた。貴方は顔を上げると、室内に居た三人――直ぐ傍で心配そうな顔でこちらを見ているリヴィエラと、別の寝台に座っていたシモンズ、そして戸口近くの壁に背を預けているマヒトを順々に見る。
彼女等にどうにか落ち着いた事と、“王格”を一応抑える事に成功した事を伝え、表情が和らいだ三人に改めて自分が倒れた後の事を問う。
すると、リヴィエラは眉根を寄せて、
「ここはポロサの宿屋です。ヴィータさんとメリシェンさん。あのお二人と戦ってから……もう三日過ぎていますね」
窓辺から入る日差しは僅かに赤い。外の喧噪も合わせて推測するに、今は夕の刻といったところだろう。
「あれからぶっ倒れたお前担いでポロサまで急いで移動したんだが、オレ達がここに来たときに使った船はもう港に無かった」
そう不機嫌そうにマヒトは告げてくる。
つまり、ヴィータは一人で魔導船を使ってラースナウアに戻ったという事か。
「だと、思います。あの独特の“光”が、ランドリートの方に遠ざかっていくのが視えていますから」
視えている?
「えっと、はい。像に封じられた状態ですから大分弱まってるんで、ちょっと見づらいですけど。何度も“王格”を視たせいか判りませんけれど、“王格”の“光”は独特の癖……みたいなものがあるみたいで、普通のアエルとは見分ける事が出来るんです。……【NAME】さんの中にある“王格”も、ちゃんと視えてますよ」
眩しそうに目を細めてこちらを見るリヴィエラに、成る程と貴方は頷く。ヴィータは自分がもっていた像を抱え、エルテミシアに届けに向かっているのだろう。
「距離までははっきりしませんけれど……」
「今頃はまだ海の上じゃないッスかね。とはいえ、今から追い掛けるには……」
「港で常駐軍と交渉してコルトレカン行きの船にどうにか乗り込ませて貰って、そこから更にランドリートへの定期船っつー流れになるから……まぁまず追いつけねーな」
既に三日というアドバンテージから移動経路の差を含めれば、マヒトの考えには同感としかいいようがない。
『とはいえ、そもそもあの人達が“王格”をどうするつもりなのか。それを問い詰めないとならない事を考えれば、一先ず追うという選択肢しか無いと思います。まぁ、でも……』
そこまで呟いて、クーリアから考え込むような間が入る。
『実は、“王格”を抑えている途中から私の“本体”の方からあれこれ補助をしてもらっていたんですけど、その時にいくらか向こう――『礎の世』側の情報も仕入れる事が出来たんですよね』
「良くわかんないッスけど、そっちはそっちで大騒ぎになってるって話なんッスよね」
『正確にはなっていた、ってところでしょうか。あんな宣言されたもんだからもう全“派閥”が完全に怒っちゃいましてね。各“派閥”は全力で以てエギアクルスなる反“派閥”勢力に対して攻撃を仕掛け、施設含め、属する者達全てを殲滅させたそうです』
「……え。もうやっつけちゃったんですか?」
『こっちの世界での“派閥”という存在の規模を舐めてもらっちゃ困ります。普段は方針の違いやらで牽制しあってる各“派閥”が一丸になって殺しに行きましたからね。木っ端の秘密組織なんて相手になりません。末端まで皆殺しな上に“派閥”内部でも魔女狩り染みたエギアクルスの関係者捜索が行われてる最中です。そんな感じなんで――少なくとも、シバリスはこちらの世界で完全に孤立した存在……最低でも“礎の世”から彼の味方が新たに現れる可能性は低い、という理屈になるのですが……』
そこでクーリアが声を途切らせる理由は判る。
そもそも、あの男はエギアクルスに所属していたとはいえ、既にそこからは縁を切っているような動きを見せている。何より、自分達にエギアクルスが行っていた“王格”に対する儀式の妨害協力を申し込んできた時点で、彼とエギアクルスは終わった関係と考えられた。
『なので余計に動きが読めないんですよね。まさかあの胡散臭い“同化者”素直に“王格”を『礎の世』へと戻すために回収しているとか――そんな風に考えられたりします?』
恐る恐るという風に聞いてきたクーリアに、貴方とリヴィエラ達はそろって首を横に振った。
『本当なら、“派閥”側からの援軍を待ってから彼の思惑を暴きたい所なんですけど、エギアクルスが行った妨害が未だ影響残してまして』
「ん? そのエギアなんたらってのは全滅させたんじゃねーのかよ?」
怪訝と眉を寄せるマヒトに、クーリアは小さな溜息のような音を挟み、
『全滅はさせましたが、彼等が妨害の為に仕掛けた術技の対処はまた別、という話です。傷をつけた輩を殺しても、つけられた傷が即座に癒えるという訳じゃないでしょう? こちらは時間を掛けて地道に復旧させていくしかない、というのがうち――マウスベンドール側も含めた見解ですね。“王格”が五つも欠けているというのも長引く原因の一つではありますけど』
となると、相手の増援もないが、こちらの援護も期待できない。これが現状という事か。
貴方は未だ不調を抜け出せない身体を動かし、寝台からどうにか起き上がる。
「だ、大丈夫ですか?」
軽くふらつき、慌てたリヴィエラに支えられるが、大丈夫と短く返して彼女から離れる。あまり悠長にしている暇は無いのは確かなのだ。
既にフローリア諸島に存在する“王格”は全て処理され、一つはほぼ確実にシバリスの側に渡る。残るグローエス側三つに関しては不明であるが、そちらはシバリス本人が従者達と共に出張っている筈だ。フローリア側でのシバリスの侍従二人の動きから考えれば、グローエス側での“王格”の確保に失敗している可能性は低いだろう。
ただ、ここで注目すべき点は、フローリア側ではシバリス本人ではなく、エルテミシアという娘がシバリスと共に在る“同化者”の手先として扱われている事だ。思い出すに、あの娘は自分のような“分離同化”の対象としてではなく、あくまで一時の操り人形のような、そんな扱いを受けているように見えた。
そんな彼女にヴィータは像を渡して、そこからどうするつもりなのか。それが読めない現状、例えヴィータがラースナウアに到着するまでに間に合わずとも、彼女を追い掛けてエルテミシアの元へ向かうというのはそう悪い手ではないように思える。少なくとも、エルテミシアがあれをどうするのか。それを確認する必要はあるだろうし、もし何もしていなかったならば、そこでもう一度奪い取るという手も選べるのだ。もう彼等と結んだ協力関係は終わっているのだから。
貴方がそう話すと、リヴィエラ達三人はそれぞれに思案するような表情を浮かべ、
「……それを考えれば、まだ完全にチャンスが失せた訳でもねーのか。上手くすれば、あの赤毛の女が持ってた像も奪い取ることが出来るかもしれねーし」
「といっても、相手が向かってるのは常駐軍……というか“六家”に連なるお偉いさんの屋敷ッスよ? そこでドンパチやる羽目になったら冗談じゃなく賞金首になるような……」
「それもありますけれど、他にも今度は像を破壊しないよう気をつけないといけないでしょうね。これ以上、【NAME】さんに負担を掛けさせる訳にもいきませんから……」
『ああ、そこは結構本気で気をつけてください。“王格”っていうのは大体一人一つが原則ですから、一人の存在概念に二つ以上宿らせるのはかなりのリスクになります。直ぐさま『礎の世』への転送を行うというのなら別ですが、妨害の影響がまだ残っている状況ですと大分問題ありですね。特に今回みたく事前準備とか無しの状態で“王格”を捕らえようとするのは結構洒落にならないんで、像は極力破壊せず確保する方向で動いて下さい。まぁ、それについても、私達が到着するまでシバリス――いえ、エルテミシアさんが何もしていなければ、という前置きがつきますが』
「……つーかまぁ、ここであーだこーだ言っててもしゃーねぇだろうよ。【NAME】が大丈夫だってんなら、取り敢えず動いちまおうぜ」
マヒトの促しに頷き、貴方は未だ馴染まず違和感の強い身体の感覚に戸惑いながら、部屋を出る。
目指すは港。常駐軍の管理する船舶が停泊している区画だ。そこでまず、アノーレからコルトレカンへと向かう船に乗せて貰う交渉をしなければならない。
既に時刻は夕方。今からうまく話をつけたとしても、恐らくは明日出港の船になるだろう。そこからコルトレカンでまた船に乗り、ラースナウアを目指す。
――さて、そうして自分達が到着する頃には、果たしてどういう状況になっている事やら。
貴方は未だ残る身体の違和感も相まって、陰鬱とした気分のままそう考えた。
・
そして更に数日の後。
“王格”を封じた像を所持したヴィータは、ラースナウアにあるエルテミシアが滞在する屋敷に帰還していた。
「成る程ね。メリシェンは死んだのかい」
エルテミシアの私室にて一連の報告を聞き終えたエルテミシアは、軽い調子でそう呟く。そこには己の侍従の死を嘆くような態度も、“王格”を一つ手に入れ損ねた事に対する感情も見えない。口元だけを歪めるような笑みを浮かべて、手の中にある、ヴィータが持ち帰った像を、まだ幼さの残る手で撫で続けるだけだ。
その様子を、ヴィータは全く普段のままの調子で眺めつつ言葉を返す、
「ええ。けれど、別に大きな問題はないのでしょう?」
「寧ろ寧ろだ。彼等の手にあった方が、僕の作業は楽になるともいえるかもしれないねぇ。どうせあちらも、僕に対抗するために“王格”はこちらの世界に残そうとするだろうしね。直ぐに手に入るか、何れ手に入るかの差でしかない。気にする必要はないよ。丁度良い。これも、一つの実験になるさ」
それで、とエルテミシアは視線をヴィータへと移し、
「こちらの時間での用事は終わった。僕はこれから“管”を通してこの“王格”を回収するつもりだけれども……ヴィータ、君はいつまでここに居るつもりかね?」
「折角の機会ですから、その様子を見物させていただこうか、とね。……どうせ、この今は無かったことになるのよねぇ?」
「無くなる、とは少し違うが、別の軸線へと移るのは確かかなぁ。でもだね、君は僕のような“同化者”とは違うのだから、ここで見ていた事自体も無になるから大して意味がある事には思えないがね?」
「別にいいさ。全部意味がないのなら、あたしが死んだって同じなんでしょ? いちいち離れるのも面倒だし。あたしの役目はもう終わったんだから」
「……君がそういうのなら、こちらも構わんがね。では、行くよ」
エルテミシアは像を室内の中央に置き、アエルを床全体に注ぎ込む。すると、うっすらと床面に描かれていた術技陣が輝き始め、記述者の望み通りの力を発揮しようとする。
そして、彼女は顎に手を当ててその術技陣の輝きと、刻まれた陣の内容、そして像の中に封じられている“王格”を暫し見やり、
「案外とはみ出るが、今更不要な縁だ。どうなっても構うまい。――では、行こうか“陰霖の王格”。君を僕の元へ案内しよう」
像が勢い良く踏み抜かれると同時。噴き出した光の塊が、陣より染み出し膨れ上がった無色の群れによって取り囲まれ、沈み込んでいく。
そのまま暫しの拮抗の後、術技陣から立ちのぼるアエルの量が加速度的に増していく。吹き荒れたアエルの嵐は無色の球状となって屋敷全てを飲み込むまでに膨れ上がり、そして膨大なアエルは屋敷共々、フローリア上から忽然と消滅する。
まるで、何処か別の空間、別の時間に存在する何者かへと、丸ごと吸い込まれたかのように。
礎の王格 名残より知る
――名残より知る──
しとしとと小雨が降る中。貴方は、街の中心にて唐突に出現したという何も無い空間を、ただじっと眺めていた。
ヴィータの後を追ってアノーレからコルトレカンを経由し、ランドリートの街ラースナウアに到着した貴方は、急ぎエルテミシアの居所へと急行し――以前は相応の庭と屋敷があった筈の場所で、暫し茫然と立ち尽くす羽目となったのだ。
その後、街の人々に聞いて回ったところによると、貴方達がラースナウアに到着する少し前に、突如無色の球体が屋敷を包み込むように生じ、それが消えた後には今貴方が目にしている、まるで土ごとえぐり取られたかのような半円の痕を残すだけとなっていたらしい。
そして推測の範疇を出ないが、この屋敷を職場、あるいは住居としていた多くの召使い達と共に、つい最近屋敷の主となったばかりのアラセマ“六家”から来た少女も消滅したのではないか、とも。少なくとも、事件の後に彼女の姿を見た者は誰一人としていないとの事だった。
現場に漂っていたのは、強いアエルの残滓。
しかし、“異象”が起こすような置換現象の跡は無く、ただここで何かが起きて、そして消え去った事だけしか、貴方達には判らなかった。
――ここで一体何が起きたのか。
貴方は少しの間考えて、そして思考を放棄する。
それはもう、少なくともこの時間に存在する誰にも判らない事であるように思えたからだ。
同時に、フローリアにて出来る事は、もう何も無いのだ、とも。
その判断は、ヴィータが持つ像に封じ込められていた“王格”の“光”が少し前から見えなくなった、というリヴィエラの言も後押ししてくれた。
「…………」
雨に濡れ、額に張り付いた前髪を払いながら、貴方は空を見上げて息をつく。
エルテミシアは、恐らくもう居ない。ならば、
――どうやら、決着はグローエス側でつける。そういう事になりそうだ。
先の見えない曇天の空は、これからの自分の道行きを暗示しているかのようだった。
礎の王格 末世の風光
――末世の風光──
「……これは」
焦点を移し、フローリア諸島からグローエス五王朝へと舞い戻った貴方は、世界に満ちていく異変に呻きに近い声を漏らした。
以前の段階でも、エギアクルスが行っていた大規模術技のせいか世界中に薄く広がり始めていたアエルの気配が、今では強く濃厚な、流れを持つものへと変化していたからだ。貴方の目から見ても捉えられるほどのアエルが、地を、空を、緩く渦巻くように広がっていた。
有り体に言えば、状況が悪化している。この世界に暮らす人々の間ではまだ気づかれてはいないだろう。しかし貴方のような『礎の世』を故郷としアエルを近しいものとして感じ取れる人間からすれば、激変とも言える変化であり、そしてそれは今にも破綻を見せる間際であるようにも感じられた。
「【NAME】……そんな筈ないのに、何だか、凄く寒い気がするの。なんだろ、これ?」
傍に居るリトゥエは、今のこの状況を、そんな風に捉えているようだ。雨ざらしのまま放置した後のように、両肩を抱いて不安げに震える小さな妖精にとって、この強烈なアエルの気配は感じ取れぬ毒にしかなるまい。
目に見える世界全てに広がるアエルは、まるで脈動するように、一方向から全域へと広がっていっているようだ。貴方は空を仰いでその様子を感じながら思考する。
――シバリスが儀式の阻止に失敗したのだろうか? それとも、まったく違う、想定外の状況が生まれているのか?
貴方は状況を確かめるべくカーライル邸に向かうも、そこは全くの無人であった。生活の気配は微塵も無く、シバリスが好んだ像や、“実験”で使っていそうな特殊な品も全ては影も形もなくなって、まるで屋敷自体を手放したかのような状態で放置されていた。
邸宅での情報収集を諦めて門扉より敷地の外へと出た貴方は、そこで三つの人影が近付いてくるのを見る。
「良かった! やっと会えましたっ!」
そういって近付いてきたのはリヴィエラだ。後ろには硬い顔つきの二人組が付き従っている。
話によるとリヴィエラ達はルアムザでカーライル邸や都市の出入り口などを幾度も確認し、貴方の姿を探していたのだという。【NAME】ならば、きっと未来での事を終えた後にルアムザのカーライル邸にやってくる筈だ、と。
リヴィエラは、貴方が居ない間、彼女の“眼”が捉えていた五王朝各地での“光”の変移から、シバリスが三つの“王格”を像に封じ込める事に成功した後、それを使って改めて何か――自分達には与り知らぬ真似をしようとしているのではないか、と推測を述べる。既に三つ――リヴィエラが言うには何故か四つの“王格”の気配を携えたシバリスが向かった先も、彼女ははっきりと掴んでいた。曰く、「いきなり独特の“光”を持つアエルの塊が視えるようになっていった」らしい。推測するならば、シバリス達が“王格”をエギアの術技士から解放した際に、彼等が施していた隠蔽が解かれたから視えるようになったのだろう。更に言えば、“王格”を実際に目にしたことがない今のリヴィエラが“王格”の“光”を過分無く補足出来ているのは――シバリスたちが“王格”をフローリアの時のように像の中に封じてはいないからだ。
隠す気が無い、というのはつまり、彼等にとってそれは隠さなくても問題が無い状況であると言える。
「…………」
彼等の目的は未だ見えていないが、あまり、いや、かなり、宜しくない事になっているように思える。
リヴィエラも不安を感じていたようなのだが、しかし自分達だけで動くのは危険と、貴方が帰ってくるのを待っていたらしい。
『あーっと、ちょっと良いですかね?』
そうして貴方がリヴィエラ達の話を聞いている間に、クーリアが声を挟んでくる。
『今“派閥”とマウスベンドールの方から追加報告が来ました。聞いておきます?』
否も無く頷くと、クーリアは自分の“本体”経由で齎された情報を話し出す。
壊滅させたエギアクルスの拠点から、シバリスとエルテミシアに“同化”していた者についての情報があったのだ。
どうやらあの人物、元は“派閥”の世界学に纏わる研究者であり、編み出した術技“同化術技”を“派閥”秘奥禁術扱いとされ研究が禁じられた事で離反。その後幾つかの下位“派閥”を点々とした後、エギアクルスの学士として腰を落ち着ける事になったらしい。
成る程ね、と貴方は得心する。これまでの言動や行動を見ていると、確かに研究者のそれだ。それも、倫理観が外れた類の。
こちらの世界と『礎の世』、どちらのエギアクルスとも既に接点を見出せない行動は、やはり本人が言う通り、彼には“派閥”とも反“派閥”組織とも違う目的があるようだ。
そんな話を聞きながら、貴方は急ぎ移動を開始する。
シバリスが居ると思われる場所は、リヴィエラにわざわざ訊ねる程でもない。多くの“王格”を手中に収めることに成功したというのならば、その居場所を追うのは貴方にとっても既に容易だった。今、グローエスすら越えるように噴き出しているアエルの中心点は、貴方にも感じ取れるものなのだから。
貴方とリヴィエラ達が向かうのは剣都アサーン。
その中心に位置する、ヴォルガンディア闘技場だ。
礎の王格 礎の王格
――黄金の従者──
あまり悠長にしている余裕が無いのは、漂うアエルの加速度的な変化で判っていた。
だから貴方達は支都ルアムザで馬を調達し急ぎ北へと走らせて、馬達が目的地から漂う異質な気配によって怯え始める限界まで移動する。
遠く、都の姿が確認できる辺りで、貴方は馬と、そしてリトゥエと別れた。リトゥエからはあれこれと文句を言われたが、あの都が小さな妖精である彼女と相性が悪いことは既に判りきった事である。リトゥエにはここで待機して貰うしか無かった。
そして剣都アサーンへと近付いた貴方達は――まず、都を覆うように存在していた筈の結界が消滅している事に気づいた。都からは猛烈な勢いでアエルが外へと噴き出しているのが確認出来、シバリス達がここで何かしていると、ほぼ断言できる状態でもあった。
「前の時は、結界は確かそのまま、でしたよね……?」
『結界を擦り抜ける技術はある筈なのに、今回はそれを丸ごと破壊した、という事でしょうか』
勿論、別の要因によって結界が消滅したと考える事も出来るが、もし国がそういう方策を採る予定であったなら告知がされているだろうし、何らかの問題が生じて結界が消滅したというなら、それはそれで騒ぎになっているだろう。なにせ、アサーンの内部は亜獣達の巣窟となっていたのだから。
だが、ルアムザでそんな話は一つも聞いてはいない。そうなると、この状況は極々最近生じ、まだ誰も認識されていないという事なのだろう。
「あいつ等が結界を壊したとそう考えるなら……要は、前は隠れてあれこれやる必要があったが、今はもう、そうする必要も無いってこったろうな。つまり」
「そんなのは些細な事ってなるくらいのえらい事をやるつもり……って事なんッスかね?」
「あるいは、後の事なんて知ったこっちゃねーと思ってるか。まぁ、どっちにせよ禄な話じゃねーけどな。……で? 【NAME】よ。こっからどうする?」
どうもこうもない、と貴方は短く返す。
結界が無いなら好都合だった。このままアサーンへと入り込み、襲ってくるであろう亜獣を薙ぎ払って渦巻くアエルの中心を目指す。前回のアサーン攻略の焼き直しだ。
「その結末の方も焼き直しにならねーよう、気張るしかねーか……」
溜息をつきながらのマヒトの言葉に頷きながら、貴方は皆を先導するように遠く見えるアサーンへ向かい走り出した。
・
亜獣達に占領されていたはずの剣都アサーンは、過去とは全く異なる様相を見せていた。イーサではなくアエルに置換された都市と、その影響を受けて存在を崩されアエル化した亜獣達の残滓が猛烈な勢いで渦巻く異界。それが現在のアサーンだった。
都の入り口。破壊された都の大門に立った貴方達の前に広がるのは、動く者の無い、残骸のみの大通りが真っ直ぐに一本、都の中央へと伸びており、その先にはアサーンの代名詞とも言える闘技場ヴォルガンディアの姿が見えた。
「あの亜獣だらけの地獄の街が、こうも殺風景になっちまうなんてな……」
「それもあるッスけど、時々こう、視界の色が全部消えたりするのがめっちゃ怖いんスけど、何なんスかこれ?」
『普通の“異象”であるなら、土地に対する存在置換の前触れ、なんですけど、そもそもここから噴き出してるアエルは集まるんじゃなくて、外へ噴き出してる感じですから、実際にそうなるかどうかというのはちょっと判らないですね』
「兎に角、ここでじっとしていても状況は悪くなるだけ、ですか」
都に渦巻く異質なアエルを“光”を捉えているせいか、目を眇めながら呟くリヴィエラに、貴方は短く頷く。
都の中心に存在する闘技場から、自分の中にある“王格”と似た気配がのたうち、暴れるように辺りにアエルを振りまいているのは既に貴方にも感じられていた。
ヴォルガンディア闘技場で、グローエスに存在した全ての“王格”――いや、フローリアでヴィータが持ち去った“王格”までもが揃っているのは判っている。ならば後は、急ぎどういう状況になっているのか。それを確認せねばなるまい。
貴方達は大門を潜り、通りへと出ようと走り出したところで――、
「あら、本当に来たのね、兎さん達」
――上方。門上から響いた声に、全員が反射的に動きを止めて上を見上げる。
そこからふわりと、貴方達の前方を遮るように現れたのは、手に像を持った黄金色の髪の少女だ。
シバリスの侍従の一人、メリシェン。
彼女が現れた事で、このアサーンの異常と集められた“王格”の異様な挙動はシバリスの仕業であると確定出来た。
が、ほぼ確定が確定になったところであまり意味は無く、明確な自分達の敵対者が現れた事の方が厄介だ。
貴方の記憶の中では、既に一度死んでいるメリシェンであるが、当然ながらこの時間平面上では傷一つない。そして彼女の命を奪ったリヴィエラ達にとってもその頃の記憶がある訳もなく、リヴィエラ達は緊張と共に身構える。
「貴女は――この前の」
「性懲りも無く、またやってきたのね。前はただただ逃げるかわいい兎さんでしかなかったのに」
「……あの時とは、もう違います」
「そう? まぁ、師たるシバリスの予想通り、やってきてくれて助かったわ。亜獣も皆死んでしまったし、このままだと私、暇で暇でどうにかなってしまいそうだったから」
そして少女は花咲くように微笑むと、手にした像を宙へと投げる。
「――さあ、私の“擬象”。一緒に狩りを始めましょう?」
彼女が像へとアエルを注ぎ込むと、周辺に漂っていた濃厚なアエルもその動きに従って、像を核として急速に塊を成し、そして一つの形を得ていく。
早い。以前見たシバリスが生み出した“擬象”と根本的な部分は同様ながら、他はもう別物だ。あれから様々な改良を施したのだろう。大型の術技陣ではなく像に刻んだ小型の術技陣を使い、至極短い時間で、前回の“擬象”と同等に近い存在を生み出そうとしている。
そうして瞬きを数度もせず内に、像は貴方達が以前戦い敗れた“擬象”の姿を取る。
傍に生じた巨体をいとおしげに一撫でしてから、メリシェンは両の腰に下げた黄金の刃を抜き放った。
「貴方達が前とは違うのは聞いているわ。だから、遊びは抜きよ。私とこの子の爪の前に、その身を大人しく捧げなさい」
battle
黄金の従者


「何故……?」
呻くように呟くメリシェンに対し、複数の宝石を打撃して宝精を召喚したリヴィエラは、眉根を詰めたまま答える。
「以前とは違う、という事です。私も、そして【NAME】さんも」
合計にして六つ。矢のように飛んだ宝精をメリシェンは両方の刃で辛うじて捌き、しかし。
「――嘘」
その隙に真横へと寄った貴方の一撃に、メリシェンは軽々と崩れた家屋に叩き付けられた。込められた圧倒的とも言えるアエルは、今のメリシェンが管理下に置いているアエル如きでは堪える事すら出来なかった。
既に“擬象”は消滅している。強大な力を持つとは言え、所詮は溜め込んだアエルを使って動く魔導生物のような存在だ。“王格”を身の内に取り込んだ貴方のアエルとは質も量も大きな差がある。最初は“擬象”をある程度自由に行動させてアエルを消費させてから、隙を見て逆に貴方が有り余るアエルを注ぎ込んで叩き付けてしまえば、“擬象”は耐えきれず崩れ去るしかなかった。
衝撃により、木壁に貼り付けにされたメリシェンは、衝撃が抜けるまで身を硬直させた後、瞳に狂気を走らせて、背の木壁を蹴って正面の貴方とリヴィエラへ襲い掛かろうとして、
「そこまでだ。おチビさん」
声と共に、脇から一人の男が前に出てくる。手に持つのは槍。穂先は少女の身体を捉え、今にも放たれようとしている。
しかし、メリシェンからすれば注意すべきは【NAME】とリヴィエラの二人だけ。他の者達の攻撃など、受ける際に己の存在をイーサからアエルへと瞬間的に切り替えれば無効化出来る。メリシェンは素早くそれを行いながら、壁を蹴って前へと飛び出し――、
「え?」
すこん、と抜けるような音と共に、今まさに飛び出そうとしていた少女の身体が、木壁に縫い付けられた。
それを成したのは、長身痩躯の男が放った槍の一撃だ。メリシェンの腹を貫くように放たれた槍が、木壁を貫いて刺さっている。
「……あれ、どうして? これ、アエルが」
見下ろすメリシェンの視界の中で、己の身体に穴を空けた槍から、淡い無色の影が揺らめく。それはアエルが込められた一撃。だからこそ、彼女の身体は完全に木壁に縫い付けられて、身体の芯から猛烈な痛みが生まれ、同時に虚脱感が襲う。
「が、ふ」
熱い塊が迫り上がり、口から吐き出す。血の波が吹き出すように溢れて、少女の身体と、そして未だ身体に突き刺さったままの槍を濡らした。
自分の内から溢れ落ちる赤い飛沫を見届けてから、彼女はゆっくりと顔を上げようとするが、しかし視界が急激に霞み、周囲の音が遠ざかっていくのをメリシェンは自覚する。
目の前に立っていた男は槍から手を離すと、少女へ向けて複雑な視線を向けると、
「こいつらは得体がしれねぇ。もしかしたらまだ動き出すかもしれん。槍はこのまま置いていく」
「……それだと、マヒトさんの武器が無くなりますけど、良いんですか……?」
「よかねぇが、仕方ねぇだろ。徹底的に切り刻むって手もあるが、悠長にしてる時間もなかろうが。こいつが居るってこたぁ、他の二人も居るって事だしな」
「ちょっと勿体ないッスけど、状況考えるとやむを得ないッスね。自分もここは一時執着捨てるッスよ」
「……止めろよ気味わりぃ。ほれ、【NAME】、御嬢。さっさと先進むぞ」
そして声が遠ざかり、気配も消えていく。
一人串刺しにされたまま取り残された少女は、顔をふせたまま、数度血を吐き、
「……兎如きが……狼に情けを掛けるというの……? そんなの許さない……許さないから……」
囀るような声と共に、未だ握り締めたままであった刀二本を手放し、彼女は己を縫い止める槍の柄に手を伸ばしていく。
その少女の動きを目に留めるものは、もうここには誰も居ない。
――深緋の従者──
メリシェンを下した貴方達であったが、油断出来る状況ではなかった。
シバリスの従者は合計三人。門上にメリシェンが居たのであれば、後の二人も何処かにて闘技場へと目指す者を排除しようと待ち伏せているのは道理である。
「大通りをこのまま真っ直ぐ行けば闘技場には早く着くのは確実ですけれど……」
「当然、そのルート上で待ち伏せされている可能性はたけぇよな。どうする、【NAME】。裏路地でも回ってくか?」
マヒトの言葉に、貴方は僅かな逡巡の後、首を横に振った。何らかの感知の仕掛けが全方位に張り巡らされている事も考えられるし、細い路地へと入れば不意打ちを受ける可能性も大幅に高まる。
ならば、最初から広く空いた大通りを警戒しながら全力で進み、相手から襲われるのは前提で、少しでも闘技場との距離を詰めていくのが得策だろう、と。ここで亜獣達が居るならばかなり苦労したのだろうが、幸い亜獣の気配は完全に消滅している。自分達目掛けて放たれる殺気を察知するのは、そう難しい事ではない筈だ。
その方針に異論が出る事はなく、貴方達は全力で大通りを走り、闘技場への距離を詰めていく。
時折、ノイズのように視界全てがモノクロになる。飽和したアエルの気配。そんな中で、通りの端に大きく焼け焦げた痕が残っているのが視界に一瞬映る。あれは確か、と意識が一瞬過去に飛んだ。前回のアサーン戦の際、自分達の代わりにメリシェン達と戦い、弄ばれた亡骸を焼いた痕だ。遺骨や装備などは持ち帰った為、後に残ったのは遺体を焼いた焼痕のみで――、
『【NAME】! 気を抜かないでっ! 来ます!』
鋭い警告と共に、周囲の空間に無形の破裂が複数生じる気配を察知する。
術技による遠隔攻撃。場に居る全員に散開の指示を出し、その範囲外から這々の体で脱出した貴方は、更なる追撃の気配に、不完全な姿勢で更に大きく飛び跳ねた。
数瞬前まで貴方が居た場所を、モノクロームの炎が縦列となって走り、地面に独特の焼痕を残して通り過ぎていく。
着地した貴方が、その炎が放たれた方向へと視線を向ければ、大通り沿いに立ち並ぶ半ば崩れた建物の屋根の上に、片手には緋色に染めた鞭を携え、もう片手には人の頭部ほどの大きさの像を抱えた赤毛の女が立っていた。
「おや避けた。この場所で狙っちまえば、あんた達なら上手いこと油断して喰らってくれるかと思ったんだがねぇ」
口を半月の形に歪めて笑う女。その姿は、フローリアでの一連の出来事の間にすっかり見慣れたものであった。
シバリスの従者の一人。名はヴィータである。
「まぁ、いいさ。ここに居るってことは、メリシェンのお馬鹿とはしっかり遊んでやったんだろう? なら次は、あたしと遊ぼうか」
彼女は手にした像に十分なアエルを注ぎ込んでから放り投げると、素早く術技を駆動させる。像に施されていたのだろう術技陣を展開し、注がれたアエルを核として周囲のアエルを吸い集め、巨大な“擬象”を造り出した。その姿形は像自体の形状がほぼ変わらぬものであったからか、メリシェンが喚び出した“擬象”とほぼ同様で、多少色が異なる程度だ。
「さて、こちらの準備は終いだ。正直あたしからすりゃどうでもいいんだが、ラバナの奴が煩くてね、悪いが、闘技場に顔を出すのは諦めてもらうよ!」
battle
深緋の従者


「なんだって、こっちの手の内がそんなにバレてんのさっ!」
焦った声を漏らしながら鞭を振るい、貴方を近づけないようにするヴィータに、貴方は無言で突っ込んでいく。
撓る鞭の軌道。それを読み切った貴方はその合間を潜るように彼女へと距離を詰める。結果、間合いは近接の位置。既に鞭が十全な力を発揮出来る間合いではない。
しかし、貴方はここで勝機と攻撃を仕掛けずに、彼女が更に動くのを待つ。
何故なら知っているからだ。ヴィータが接近専用に、服の袖の内に鉄鎖を仕込んでいる事を。
「――っ」
貴方の予想通り、彼女が袖口に手を引っ込めた後、ぶんと横へと振る。飛び出した鉄鎖は、直撃すれば身体を巻き取られ、身動きが封じられてしまうだろう。宿るアエルの気配を考えれば、単に巻き取られるだけでは済まず、そのまま刃となって断ち切られるものなのかもしれない。
だが、判っていれば当たるものではない。貴方は悠々とその鎖を潜ると、己が内に宿る膨大なアエルを注ぎ込んだ技法を、一切の遠慮無く彼女の身体へと叩き込んだ。
シバリスの侍従達がどれ程危険で厄介で、そして人を殺すことに躊躇しない存在か。それを理解していた貴方は、手加減をするつもりは全くなかった。完全に殺すつもりで放たれた一撃は、彼女等が使う回避法を完全に無効化して、女の細くくびれた腰の中央に大穴を空けた。
ど、と内臓が後方へと飛び散り、薄く残った脇が、落下する上半身の重量に負けて千切れ、ヴィータの身体は二つに分かれ、地面に力なく転がった。
「ひ、ひゅー、ひゅ、ひゅ」
驚愕に染まったヴィータの顔が、ごろりと貴方の方を向く。引きつった呼吸が数度続いた後、彼女はこちらを凝視したまま、その呼吸を停止した。
「…………」
それを見届けて。貴方は一度大きく深呼吸を挟み、意識を切り替える。
殺すべき相手であった。その筈だ。しかし本当に殺して良かったのか。それは、誰かを、何かを殺したときに、常に過ぎる問いだ。
そして、取り返しのつかない行動をした後にそんな事を考えても全くの無意味でしかないと、そう結論付けることも。
貴方は血の付いた武器を軽く払う事で散らすと、死体となって転がる女の傍を通り抜けて、リヴィエラが追い込んでいる“擬象”の手助けに向かう。
既にリヴィエラとの戦いで殆どのアエルを使い切っていた“擬象”は、横から突然に襲い掛かってきた貴方の一撃に不意をうたれ、その主であった女と同様、あっさりとこの世から姿を消した。
――烏羽の従者──
都の中心に聳える一大建造物、ヴォルガンディア闘技場。
大通りより繋がる闘技場の正面入り口の前にて、手に一体の像を抱えて立つ一人の男が居た。
都の入り口、そして大通りにて襲い掛かってきた二人の侍従達と比べると接点は薄いが、しかしその存在自体は辛うじて覚えていた。
前回のアサーン戦の際、闘技場で“擬象”召喚の術技を手伝っていた、シバリスの三人の従者の内の一人、唯一の男の従者だ。
浅黒い肌に、この辺りでは珍しい波打つ黒髪を後ろへ流した彼は、警戒するように足を止めた貴方達を一瞥し、
「やはり来ましたか。シバリスとは違う、もう一人の“同化者”殿。我が師シバリスの予想通りだ」
彫りの深い顔に、薄い笑みを作り、男は優雅に一礼する。
「そして申し訳ないが、貴方がたをこれ以上先に行かせるわけには行かない。今、シバリスはこれまでの実験の集大成というべき作業の最中。それが終わってからであれば寧ろ望むところであるけれど、今、彼の元に君達を向かわせ、実験の邪魔をされては困る」
男が手にした像を投げると、貴方と男の中間の位置で静止し、込められたアエルが四方のアエルを吸い込みながら、一つの“擬象”となって顕現していく。
「貴方がたには可能な限り、私――ラバナの時間稼ぎに付き合って頂く事になる。“王格”を宿す貴方と、そちらの有能な宝精召師のお嬢さんに勝てるとは思えないが、けれども道行きを遮る程度ならば、私にも出来なくはないだろう」
ラバナが背からくるりと回して両の手に構え直したのは長大な錫杖。放つ気配、漏れ出すアエルの量は、メリシェン、ヴィータよりも一段上だ。油断出来る相手ではないだろう。
そして以後は動き無く、こちらが来るのを待ち受けるように、視線だけは鋭く貴方達を見据えてくる。これまでの二人とは明らかに違う、正に守り、時を稼ぐのを目的とした態度だ。
「…………」
彼を打ち破らねば、闘技場の中に居るであろうシバリスの元には辿り着けない。
貴方は傍のリヴィエラ達に一度目配せし、無言で武器を構える。リヴィエラ達も、それぞれが身構える気配を感じた。
そして静かに、戦いが始まる。
battle
烏羽の従者


実際に戦い始めても、彼とその“擬象”の動きは、メリシェンやヴィータ達のそれとは明らかに違っていた。
ラバナは最小のアエルを用いて最大の障害を成す事を第一として術技を行使し、牽制と補助を徹底。無理な攻めは一切行ってこず、彼等を擦り抜けて貴方達を闘技場へ向かわせない事を最優先に動いてくる。
そして彼の制御下にある“擬象”は、その巨体に見合わぬ敏捷さでこちらの攻撃を回避し、じっくりと隙を狙う、まるで狼のような動きを見せていた。油断を見せれば即座にアエルを大きく注ぎ、最大威力の攻撃を仕掛けてくるのだ。
一人と一体の動きは完全に連携しており、そして分断しようとしても巧みな動きでそれを阻害してくる。隙が無く、手強いという他無い相手だった。
が、こういう相手の崩し方というのは心得ている。
小手先に頼ること無く真正面からブチ当たる、圧倒的な力量差を活かしたゴリ押しである。
今のリヴィエラがあまり使うことのない宣言句と高級な宝石を併用した上位宝精による一撃と、貴方の取り込んだ“王格”から継承した膨大かつ上質なアエルを遠慮無く注ぎ込んだ一撃を、回避不能な状況に追い込んだ後、真正面から叩き込む。
“擬象”と同等近い大きさの宝精が突撃し、破裂。炸裂したアエルの力が“擬象”を呑み込み、分解していく。
その中を突っ切るように飛び込んだ貴方が、“擬象”を盾にするように立ち回っていたラバナ目掛けて、渾身の技法を放った。
「――ぐっ」
防御に使った彼のアエルを纏う錫杖が半ばから折れて、胴を打たれた男の身体が、闘技場の入り口を越えて石畳の上を滑っていく。
闘技場の中へと踏み込み、慌てて身を起こそうとするラバナ目掛けて更に武器を振るい、釣り上げて、更に叩き堕とす。その衝撃で息が詰まったのか、硬直して身動きを止めた一瞬を狙い、貴方は馬乗りになると服の襟を使って首を絞める。上手く入れば、アエルを消費して相手が倒れるまで攻撃し続けるよりもよっぽど効率良く相手を無力化できる。思惑通り、完璧に首を絞められたラバナは一分と掛からず気を失った。
「流石手際がいーな。んで、そいつどうすんだ? 殺すのか?」
槍をメリシェンに突き刺したまま放置した為、副武器の短剣だけを持ったマヒトが背後から訊ねてくるが、貴方は少しの思案の後、彼が着ていた服を縄代わりにして、ラバナを身動きが取れない状態にして転がす。
「大丈夫なんスかそれで? この人、術技っての使うんスよね? こんなの直ぐにどうにかしちゃうんじゃ」
確かにそうだが、どうせ目指す場所はすぐそこだ。彼が気を取り戻す前に、恐らくは全てが終わるだろう。ならばいちいち殺す手間を掛ける必要も無い。
何より、目的があったが故とはいえ、ラバナという男が積極的にこちらを殺す目的の攻撃を放ってこなかった事が、彼の命を奪う事を躊躇わせた。
「なら、早く奥へ向かったほうがいいと思います。 さっきから、闘技場の奥から溢れてくる“光”の様子が、前までとは変わってきてて、凄くいやな予感が――」
最後尾で不安そうにそう呟いたリヴィエラの方へと振り返った貴方は、目を見開くと全力で床を蹴った。
「――ひぅ!」
そのまま、リヴィエラを押し倒すように床に伏せる。身体の下から奇怪な声が聞こえたがそれどころではない。何故なら、伏せた貴方とリヴィエラの真上を、投擲された槍が凄まじい勢いで通り過ぎていったからだ。
マヒトとシモンズも、自分達の直ぐ傍を掠めるように飛び、耳障りな音と共に闘技場の支柱に突き刺さった槍を暫し茫然と見て、それがマヒトの愛用していた槍である事に気づき、そして視線を闘技場の外へと向ければ、
「おまえは、メリシェン!?」
「……よくも、やってくれたわね。兎さん達……」
半身を血で染めた少女が、槍を投げた体勢からゆっくりと姿勢を戻していく。僅かに伏せられた顔、赤く濡れた口元、乱れた髪の合間からこちらを覗く視線は、射殺すような厳しさを宿していた。
「……っは、あの程度じゃ駄目だったか。やっぱこいつら、殺した方が良いぜ、【NAME】よ」
引きつった笑みで一瞬ラバナの方へと視線を向けながらマヒトは言うが、鬼気を秘めて両の刀を抜き放つメリシェンを目の前にしながら、ラバナの止めを刺している余裕は無い。
ここから、更に彼女ともう一戦か。そう覚悟を決めて起き上がろうとした貴方の手に、別の手が重なった。
「【NAME】さん」
名を呼ばれ、正面に意識を向けながらも視線を僅かに下へと落とす。貴方に押し倒される形になっていたリヴィエラが、手を重ね、真剣な表情で貴方の顔を見上げていた。
「ここは、私達だけで彼女と戦います。【NAME】さんは、奥へ先に向かって下さい。多分、ここで時間を取っていたら、間に合わなくなる」
何が、とそう問う為に口が僅かに動いて、しかしそれは形にならず消える。
貴方も感じていたのだ。闘技場の中心で起きている事象に、大きな変化が起きようとしている事を。
ならば彼女の提案は、現状では最善のものだろう。
刹那の黙考を経て、貴方は跳ね上がるように立ち上がると、闘技場の中央目掛けて走り出す。
「貴方達、誰一人――」
背を向け走る貴方を追うべくメリシェンが動き出すが、それを制するように、長衣の娘は立ち上がり、両の杖を構えて声を張った。
「申し訳ありませんが、あなたはここで私達の相手をして頂きます! マヒトさん、シモンズさん、どうか、力を貸して下さい!」
「……ったく、槍が戻ってきたのは幸いだが、今度はそう上手くはいかねーぞ?」
「でも、マイエンジェルとこうして正面からやりあうってのもちょっと素敵ッスよね……」
そんな声を背に、貴方はこの場の全てを彼等に任せて、一人闘技場の廊下を走る。
――目指す場所は、もう直ぐそこの筈だ。
――礎の王格──
そうして遂に辿り着く。
ヴォルガンディア闘技場の中央、本来ならば闘技の試合を行うために設けられた広い空間。
そこには、まるで過去に見た光景を再現するかのように、地面に巨大かつ精密な術技陣が描かれており、そして真中には一人の老人の姿があった。
違いは、三角形を描く術技陣の頂点それぞれに置かれているのが彼の侍従達ではなく、三つの“王格”を封じた像である事。
そしてシバリスの身体からは、貴方と同様、“王格”を宿している事を示す、異様な気配と膨大な量のアエルが纏わり付いている事だ。
「やはりやはり、やってきたようだね、僕と同じで、そして異なる者。君が見届けに来てくれたのは僥倖といってしまっても良い事だろうね」
貴方を見据え、そう呟くシバリスから漂う気配は、貴方のものとは少し様子が違っていた。
術技によってどうにか制御下に置き“王格”と“宿主”という二つに一応ながら分かれている貴方とは違い、シバリスは自身の身体を同化している存在ごと“王格”で貫き、抉る事で、“王格”と一体の形となっていた。
貴方は己の武器を握り直し、身構えを整えながら、シバリスにこういう状況に至った経緯と、そして目的を尋ねた。正直、今更の疑問であったが、しかし今でなければきっと、今後知る事は出来ない問いでもあった。
「……然程、突飛な“実験”ではないよ。誰もが思い付く事の、延長のようなものさ」
そう前置いてのシバリスの答えは、極めて簡素なものだった。
――既に身に宿した一つの“王格”の力を利用し、更に封じた三つの“王格”を己の身体に宿し、更には“王格”それぞれが持つ理の制御にすら手を伸ばす事。
一体ですら怪しい状況で更に複数の“王格”を宿すなど貴方やクーリアからすると有り得ないとしか言えないが、しかしシバリスは逆に複数の力を拮抗させる事で状態の安定を狙うのだという。制御のためにあらゆる手を尽くした核を己の内に埋め込み、計四つの“王格”全てをそれで管理してみせると。
彼が既に宿す“王格”はエルテミシアとの繋がりから得たものだ。今の不安定さは、備えの甘い状況で宿した事が悪しき影響を及ぼしているのだと推測しており、シバリスが長く研鑽を積んできた術技の腕があれば、更なる“王格”の力で制御し、より己を高い水準の存在へと変質させ得る事も可能であると考えているようだった。因みにその対象は、今貴方の中にある一つの“王格”の力も含んでいると。
そして彼は、母体としていた反“派閥”組織が壊滅していることも知っていたが、やることには変わりは無いとも断言した。
元々判っていた事だが、彼にとってのエギアクルスとは、あくまで利用するだけの存在でしかなく、組織が求めた理想などに心を寄せるところなど一片も無かったのだろう。
「……さて、もう話は良いだろう。実験もそろそろ佳境だ。僕は先にお暇させて貰うよ。“実験”の結果については――君の好きにしたまえよ」
渦を巻く四つの帯の中央で、どんどんと人の形を失い、黒き輝きの塊へと変じていく老人が告げた終わりの言葉を聞き終えて、【NAME】は微かに嘆息する。
シバリスの目的は、ある意味単純だった。
この世界へと移った“王格”全て――貴方が抱えたものも含めて己に宿し、そして最高の“擬象”を生み出す。
これまで使われていた像を用いた“擬象”は実験用の仮初めの素体として選ばれたものであり、最終的な目的は、術技を極めた人の身たる己にアエルを集め核となって、目指す極地の存在へと自らを昇華するためだ。
あくまで己の目指す地へと至る事だけを考え、ただそれだけを希求する魂の在り方は、ある意味美しいとも言えたが、同時に貴方にとって許容出来るような姿でもなく。
結局の所、貴方とシバリスの目的は全く相容れず、妥協する余地も見出せなかった。
既に得た一つに加え、像から解放された三つの“王格”の力を受け止め、それを術技陣にて“擬象”として纏めて『礎の世』の理を宿す、世界の一部の化身となったシバリス。
これを放置する事は到底出来るものではなく、戦いは避けられない。
「――――」
貴方は己の内側からあふれ出す膨大な“王格”の力を制御しながら、『礎の王格』となったシバリスに己が持てる力全てを持って立ち向かう!
battle
礎の王格
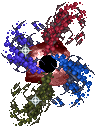
貴方が選んだ解法は、そう難しいものではなかった。
今ここでシバリスの術技によって取り込まれ、荒れ狂っている“王格”達は、結局のところシバリスが己の身を黒色の核として存在しているからこそ成り立っているものである。
ならば、“王格”達を従え、制御し、その理にまでも手を伸ばそうとしている術技が詰まった核目掛け、鋭く、硬く、細く、極限にまで高めたアエルを叩き込み、破壊してしまえば良いだけなのだ。
そして弱点ともいえる核は、四色の“王格”の帯に守られるような姿ながらも、黒色の塊の塊としてその中央に存在している。ならば、後はそこ目掛けて己が持てる力全てを注ぎ込めば良いだけの話だった。
戦い自体は死力を尽くしたものとなった。うねるアエルの帯は一つ一つが“王格”の膨大なアエルを宿したもの。守りも無く受ければ一撃で存在自体を消し飛ばされかねないもの。それを避け、潜り、飛び越えながら、貴方は渾身となる攻撃を放ち続けた。
一つ。
二つ。
三つ。
四つ。
貴方が攻撃を放つ度に、核が削り取られ、“王格”を制御する要素が失われ、シバリスが命を賭して変化した塊が消失していく。
そして最後の一撃を放った瞬間。黒色の核が消え去った後には、四色の光を放つ巨大な球状の塊――“王格”だけが残されてる事となった。
「……これで」
シバリスという“同化者”が、複数の“王格”を従え、その力を思うままに振るうという未来は打ち破ることが出来た。
だが、問題はまだ残っていた。
シバリスから解放された四つの“王格”の力が、すぐ近くに居る“同化者”である貴方に殺到してきたのだ。以前、フローリアで見た現象。自分が“王格”を宿す事になったあの時と同じものだ。“王格”は人に宿る事で安定する存在。故に、今の“王格”は最も近くに居る“適合者”に宿ろうと自然に動くのだ。
「――っ」
逃げるという判断が一瞬浮かぶが、少し離れた場所にリヴィエラが居る事を思い出し、甘んじて近付いてくる“王格”を受け止めた。
既に一つ“王格”を抱えている状態で、更に四つ。合計五つの“王格”の力を抱える事になったのだ。貴方の心身に、筆舌に尽くし難い苦痛が走る。
クーリアから直ぐさま警告が飛び、彼女は今すぐ『礎の世』へ帰還するべきだと貴方に告げる。ようやっとではあるがエギアクルスが施していった妨害も八割方対処を終えており、存在概念の帰還程度であれば可能であると。
『戻ったところでどうにか出来るかは断言しませんが、しかしこちらの世界で処置無しのままでいるよりは遥かにマシな筈です! 今の“私”の処理能力と術技じゃ、とてもじゃないけど追いつかないです!』
兎に角『礎の世』へと戻らねば、所詮ここにいるクーリアは断片でしかなく、やれる事は少ない。早急に帰還し、“派閥”やマウスベンドールの手による処置を受けるべきだった。
だが、それは同時に、グローエスとフローリアで“同化者”として生きてきた「二人の自分」から離れる事を意味していた。
一度戻れば後はどうなるか本当に判らず、改めてこの世界に“分離同化者”としてやってこれるかどうかも一切不明だった。
もし“同化者”として戻れなければ、果たして今ここにいる「【NAME】」はどういう存在になるのか。クーリアの推測では、“同化”した時点から今までの記憶がすっぽり抜けた二人の人間がグローエスとフローリアに残されるのかもしれない、と。
「【NAME】さんっ!」
そこへ叫ぶような声が響いた。リヴィエラと、そしてマヒトとシモンズ。三人とも無事だ。どうやらメリシェンを殺すか、或いは無力化する事に成功したのだろう。
状況の一応の解決に喜ぶも、苦しげな貴方とクーリアからの説明に、リヴィエラ達は絶句する。特にリヴィエラは駄々に近い態度を見せるも、結局他に方策は無く。
「…………」
たった数拍程の間であった筈なのに、その迷いの時間は非常に長く感じた。
そして貴方は、苦渋とも言える決断をする。
傍の彼女に、さよなら、と。
一先ず別れの言葉だけを告げて、貴方はクーリアの指示に従い、己の“同化”を解いていく――。
礎の王格 さよならの再会
――さよならの再会──
その日
私達が辿り着いたときには、もう殆どの事は終わってしまっていた。
後に残されたのは、目も眩む程のアエルを溜め込み動きを止めた彼だけで、アサーンの都は疎か、グローエス中に広がっていたアエルの気配は一切消滅し、元の世界の姿を取り戻していた。
その後、私達は動かなくなった彼を連れてアサーンを脱出し、ルアムザに戻ると、幾つかの施療院を巡り、彼の事を看てもらった。
けれど、その全てで芳しい答えは返ってこなかった。何せ、呼吸も心の臓も止まっているというのに、体温は下がらず、身体の硬直も始まらないという不可思議という他無い状態を維持しているのだ。
しかも、私自身も幾度か試したことだが、神蹟による干渉を一切受け付けないのだ。それを治療の主として扱う施療院の者達からすれば手の施しようが無いというしかないだろう。それが判っていて、彼を連れ回した私達も、当時は相当に混乱し、焦っていたのだろうと今なら判る。
神蹟が効かない理由については簡単だった。彼の身体を覆う、濃密なアエルの膜。それが外部からのイーサを使った干渉を阻害するのだ。
問題は、この膜が何の役割を果たしているのかが正確に判らないのだ。それが判明していたなら、今自分を襲っている心労の何割かは軽減されていただろう。
結局、その日は施療院で無駄な時間を過ごし、宿に戻るだけで終わってしまった。
戦いには勝った筈なのに。私も、マヒトさんも、シモンズさんも。碌に会話も無いまま、彼を部屋の寝台に寝かせた後、それぞれの部屋に戻る。
もしかしたら、明日にはあの人はあっさり目覚めて、自分達に朝の挨拶をしてくれるかもしれない。
その日は、そんな事を思いながら苦労して眠りに就いた記憶がある。
追記すると。
それが、どんなに楽観した考えであったのか。私はこの日記を読み直す度に見せつけられ、幾度も幾度も、やるせない気持ちを持て余す事になった。
二日目
曇天だったと思う。この頃の記憶はよく思い出せない。
朝から今後の方針についてマヒトさん達と話し合ったのは覚えている。
あの人の目が覚めるまで私が面倒をみたいというお願いを、二人は渋々ながらも受け入れてくれた。
その後、私は一日中彼の傍にいて、ただ目覚めるのを待っていた気がする。
後で聞いた話によれば、その頃マヒトさんは都に出て、色々な事についての情報収集を行っていたらしい。
日が暮れる頃に戻ってきたマヒトさんと入れ替わるように、今度はシモンズさんが宿から出て行った。
こちらは泊まりがけで、アサーンへの再調査に向かったそうだが、当時の私は話半分しか聞いていなかった気がする。
何にせよ、この頃の私はいつにも増して視野が狭くなっていて、どうしようも無かったと思う。
三日目
強い雨が降っていた気がする。
昼頃。濡れ鼠になったシモンズさんが戻ってくる。
シバリスさん達との戦いの後、彼の状態の事もあり、状況を碌に確認もせずルアムザに向かった件が気になっていたそうで、改めてアサーンの状況を調べてきたのだそうだ。
そしてシモンズさんが見た限りでは、メリシェンさん、ヴィータさんという二人の従者の遺体は確認出来たが、拘束したまま放置したラバナの姿が無くなっていたという。
今のアサーンにはもう亜獣は存在しない為、都に巣くう亜獣に喰われたという線は薄く、都に入り込んだ賊にそのまま浚われたという可能性もあるが、普段のアサーンが結界により進入不能であり入れたとしても亜獣の巣になっている事を考えれば、そちらの線も薄いという。
結論としてはラバナさんは私達が去った後あの拘束を地力で抜け出し、アサーンを去ったという事になる。
自分達を恨んで襲撃を仕掛けてくるかも知れないから、外出時等は十分に気をつけるように。特に御嬢は、とマヒトさんに釘を刺されるが、彼の傍で目覚めるのを待つ事を優先していた私は、そんな忠告なんて全く無意味と聞き流していたように思う。
七日目
晴天のち通り雨。
あれから一の巡りを経た事を思い出し、ふと、日記でも付けてみようと思い立つ。
なので、実は一日目から三日目については、後から思い出した事を今書いてしまったものである。
早速のズルに先が思い遣られるけれども、元々ラカルジャに居た頃は日記をつけていたのだから、いざ始めてしまえばそうそう途絶える事もあるまいと楽観している。この楽観が後の後悔に繋がらない事を祈る。
この事をマヒトさんとシモンズさんに話すと、何処か安心したような、不思議な顔で見られた。戸惑っていると「ようやく御嬢も落ち着いてきたみたいだな」と言われた。
言われてみれば、日記としてあの日からの事を思い返すと、自分が一体何をしていたのか、それを細かく思い出せない事に気づいた。
それだけ自分は、あの人が居なくなってしまった事に。眠りについてしまった事に。取り乱していたのだろうと思う。
既に今日で、日の一巡。
ただ、早く目覚めてくれることを。早く声を聞かせてくれることを。
願う事しか、今の自分には出来ないのだろうか。
何だか、泣き言を綴ることしか出来ない日記になりそうで、初日から陰鬱とした気分になる。
もう早く寝てしまおう。どうか、明日は良い日でありますように。
八日目
朝より雨。後に曇り。
一巡が過ぎ、ルアムザの宿に滞在し続ける意味を見出せなくなってきた私達は、宿を引き払い、元々拠点としていたテュパンへの移動を行う事にした。
何時もであれば徒歩か相馬車、あるいは各首都に設けられた転移陣を使うのだが、全く身動きの取れない彼を連れた今では徒歩や相馬車という手段を取るのは難しく、転移陣に関しては彼を包んでいるアエルが転移に際しどのような悪影響を及ぼすのか判らず。
結局、馬と格安の荷車を購入してどうにか運ぶ事を選ぶ。
目が覚めたら真っ先にこの金を請求してやるとマヒトさんは息巻いていた。
彼の借金が勝手に増える前に、早く起きて欲しいと願う。
夕刻。旅立つ準備を進めていると、リトゥエさんから暫く単独での行動をしたいという申し出をされる。その間、彼の事を託したい、とも。
彼女は妖精という自分の立場を活かして、あの人を元に戻すための方法を探したいのだと言う。ただ待つだけなのはつらいと。
確かに、何の解決法も思い付かず、出来ることと言えば我が神に祈るだけである自分と違い、妖精の彼女ならば独自の伝手というものがあるだろうし、こういった状況をどうにかできる方法を見つけられるかもしれない。
それに、彼の面倒を見る事については、リトゥエさんに言われるまでもなく、私が受け持つとそう考えていたから、別に問題は何一つなかった。
彼女の旅が上手く行く事を祈り、旅立ちを見送る。
どうか、無事に旅を続けられますように。
そして、彼女の目的が果たされますように。
九日目
通して晴れ。朝晩冷え込む。
旅の一日。問題無く街道を進む事が出来れば、予定では翌日中にはどうにか目指すテュパンへと到着する予定だ。
時折亜獣などの襲撃を受けたが、今の私達にとっては街道で出てくるような亜獣など相手にもならず、躊躇無く蹴散らして進む。
野営の準備を終え、天幕の中でこの日記を書いているが、今日は妙に夜が冷え込んでいる。
隣で眠る彼にも毛布を掛けてはいるが、果たして今の状態のこの人に毛布が必要であるのか。必要ならばどの程度必要なのかがさっぱり判らないのがとても困る。
彼の横顔を見ながら眠りにつく。これも旅中であるが故に許される特権と言ってしまっても良いのだろうか?
十日目
寝覚めは最悪だった。
彼の傍で眠ったのがいけなかったのか。酷く厭な夢を見た。詳細が思い出せないのが逆にもどかしい。
ただ、夢の中で彼に「さよなら」と告げられた事だけが、明確に耳の奥にこびり付く。多分、現実にあの人が最後に伝えた言葉がそれだったのが原因なのかなと考える。
せめてその言葉が、再会を約束してくれるような、そんな言葉であったならと思いながら、馬に揺られ続けた。
道中は問題無く、テュパン到着後も、以前に借りていた部屋はそのまま問題無く入れるようで一先ず安堵するも、夢の件もあり気力を削られ、宿から出ずに一日を過ごす。
ただ、あの人をどの部屋で扱うかで少し揉める。追加で部屋を借りる案も出たが、私が自分の部屋で預かることを主張し、難色を示す二人を強引に押し切って認めさせる。
元々あまり大きくない部屋に、寝台を二つ入れると大分窮屈になったが、別に物にも部屋の広さにも拘るような質は持ち合わせていない。
未だ身動きしない彼を覆うアエルの光を目で捉えながら、眠りに就く。
明日から新たな日々の始まり。
けれども、心が華やぐこともなく、じっと海底で蹲り、何かに耐え続けるような。そんな未来しか思い描けなかった。
彼が目覚める気配は、微塵として無い。
・
三十日目
夕刻に強風。空の気配危うし。
その頃には、時折、マヒトさんがふらりと一人いなくなる事は、何時もの習慣の一つとして、何ら気にしなくなっていた。
何をしているかは少し気になってはいたのだけれども、大人の男の人だし、一人で何かしたい時間も必要なのだろうと、そんな風に簡単に考えていたのだ。
けれど今日、いつもの日課から帰ってきたマヒトさんは、顔に厳しい表情を浮かべて、一人になっていた時間に一体何をしていたのかを教えてくれた。
マヒトさんは定期的に故郷――ラカルジャの者と連絡を取り、向こうの情勢など様々な情報を仕入れていたのだという。
そして、今回の情報交換で、どうやらラカルジャで表立った抗争と、それに伴う政変が発生し、そして私の実家、シオレの氏族もそれに巻き込まれ、窮地に陥っているのだという。
もっとも、今の私は家を出た身であり、出来る事など何も無い。ただ家族が無事であるようにと、そう祈るくらいしか出来ない。
そんな風に、その話を聞いたときは思っていたのだが、どうやらマヒトさんの言いたいことは違うらしい。
マヒトさんが懸念しているのは、私が全く想定していなかった展開。既に家を出た筈の自分――リヴィエラ・シオレに対して刺客が差し向けられる可能性、というものだった。
グローエスに潜んでいるというラカルジャの連絡員から仕入れた情報は、本国内の激しい混乱により、真偽定かでない情報が錯綜していてはっきりとしないそうなのだが、シオレの氏族の代表者――つまり私の血縁者の多くが、他氏族から差し向けられた刺客に襲われ、現状死者も何人か出ているという。
けれど、私としてはそんな話をされても困るしかない。彼の事と同じだ。不安で、心配だけれども、遠く離れた隣国に居る自分に、出来る事など何も無いのだから。
そんな私の態度に、マヒトさんが「そういう事が言いたいんじゃねーよ」と苛ついた様子で言われて、私は身を縮めてしまう。
どういう意味で言われたものであろうと、今の自分に出来るのは、ただ自分の神に祈りを捧げ、皆の無事を願うだけでしかないように思えた。
話を切り上げ自室に戻ると、何時もの祈りを彼の傍で捧げた後、自分の髪をほんの少しだけ切り、それを香に巻き付けて燻し、また祈る。
テュパンに来て少し経った頃、カシムの食堂で知り合った老婆に聞いた、願掛けのおまじないだ。
話を聞いてからずっと続けているが、出来れば内心自慢であった長い髪が完全に短くなってしまう前に、彼には目覚めて欲しいと、そう願う。
三十一日目
暗雲濃く、雨の気配。まるでこれからの未来を示すようで暗澹となる。
朝から公社での仕事を三人でこなし、夕前に戻ると食事を取り、それぞれの部屋へと帰る。
日が暮れた頃から、何だかぴりぴりと、部屋の周囲に厭な気配が漂っているのを感じ取る。
あの人やクーリアさんと訓練してから、そういった形の無い気配のようなものを察知する力も格段に上がった。今回感じた気配は、その感覚にひっかかった。アエルに関わるものではなく、純粋な危険察知の技能によるものだ。
マヒトさんとシモンズさんの部屋へと向かい、その事を伝えると、マヒトさんは気難しげに考え込んだ後、暫く全員で一つの部屋に泊まった方が良いかも知れないと告げ、シモンズさんも同意する。
案外と言っては失礼かもしれないが、女性である私に対して相応の配慮を見せてくれる二人がこういう提案をしてくるという事は、どうやら本当に自分は刺客に狙われているのかと、この時ようやく実感する。
彼を動かすわけにもいかないので、毛布などを運び込んで私の部屋で無理矢理四人で眠る。
強い風が吹く度、がたがたと音を立てる戸に妙な恐怖を煽られて、なかなか眠りにつけず難儀する。
三十二日目
初めて、自分の手で人を殺した。
三十六日目
終始雨強し。
ようやく、状況が落ち着いてきたので、今日までの経緯を記しておく。
四日前。夕食を終えて部屋に戻ると、部屋の中に刺客が待ち伏せていた。マヒトさんとシモンズさんも一緒に居た上に、私自身も自画自賛ではないがそれなりの力を持っている。室内室外合わせて倍の人数に襲われようと、そう不覚を取ることは無く、私達は冷静に彼等を無力化していた。
けれど、状況の不利を悟った相手が、あの人を人質に取ろうとしている事に気づいた私は、完全に我を失ってしまった。
だから、あのアサーンでの戦いの前に、彼から譲り受けていたアエルの残りを注ぎ込んで全身を強化し、手にした杖を全く加減すること無く振り抜いてしまったのだ。
結果、その刺客の頭部はまるで壁に叩き付けた柔らかい果物のように破裂して、私は初めての殺人というものを経験する事になった。
私は暫くその事で自失してしまい、後の処理はマヒトさんとシモンズさんが行ってくれ、私がどうにか気を持ち直した頃には、刺客に関する件は大体の始末が付いてしまった後だった。
確かにショックな出来事で、シモンズさん等は気を遣って何度も声を掛けてくれたが、しかし改めて自分の心の弱さのようなものがさらけ出された気がして、堪らなくなる。
本当に、私は一人では何も出来ないまま。
いつまでも、変わっていないのだ。
三十八日目
漸く晴れ間が見える。長く続いた雨で鬱々とした気も少しは晴れてくれると良いのだけれど、そう上手く行かない。
ここ数日、目覚めた後、時間が経ってもふわふわと身体が浮遊しているような感覚が纏わり付いて、上手く物を考えられない状態が続いている。
眠りも浅く、眠れたとしても刺客の頭を砕いた感触と、彼が眠りについた時の光景が混じり合い、偶に刺客の頭を砕いた筈があの人の頭を砕いていたなんて、悪夢という他無い夢を見て飛び起きる事もあった。
眠るのが怖くなり、けれど眠らなければ身体の調子が良くならないのも判っていた。何だかあの日から、相反する事象に挟まれ、身動きが取れずに何もできなくなる事がどんどん多くなっている気がする。
誰かに相談した方が良いかも知れないと、そう思うのだけれど、マヒトさんもシモンズさんも、今はテュパンの都に忍び込んでいるラカルジャの手の者達の動向を追うのに必死らしく、それを邪魔するのはどうにも気が引けてしまう。二人が頑張ってくれているのも、結局は狙われている私のためなのだから。
ふわふわとした頭を動かして、眠る前に何時もの儀式をして床に付くことにする。
鼻につく焼けた髪と香の匂い。
私は、今日は眠れるだろうか?
四十二日目
雨のち曇り。
マヒトさん達から言い渡された外出禁止令は未だ続いている。
私はやることもなく終日を彼を眺めながら無為に過ごし続けている。
この日記を読み直して思うのは、もう彼が今の状態になって一月半近くが経過しているという事だ。
未だに彼はアエルの輝きに包まれて、目覚める気配は無い。状態が良くなることもないが、悪くなることもない、制止した状態。
あの人との別れ際。クーリアさんや彼が手短に説明をしてくれたのは覚えているのだが、あまりにも状況が急いていたため、その時の言葉が、あまりはっきりと思い出せない。
恐らくこの輝きが、彼の状態を静止させているのだろうが、もしこの輝きを消してしまったならどうなるのだろう、とふと考える。
そうしたら、あの人は目覚めるのだろうか。
それとも、私の知らない別の人が目覚めるのだろうか。
もしかしたら、呼吸も鼓動も止まったまま、目覚めないという事も、有り得るのだろうか。
そんな結末を迎えるくらいなら、このままずっと、制止したままでもいいのではないかと、一瞬私は考えて、笑う。
無理矢理浮かべた笑みは、自分でも酷く乾いているのが判った。
だって、このままずっと、こんな散り散りの気持ちを抱えて生きていくなんて、耐えられる筈無いと知っていたから。
四十三日目
薄曇り。
一先ず状況は落ち着いたと判断したのか、マヒトさんから言い渡されていた外出禁止令が解かれた。
といっても、今の私に外へ一人で出かけるような元気さは失われていた。自室で簡単に彼の世話をしながら、無為であると自分でも思う時間を淡々と過ごす。
彼の身体は生理現象が全て止まっているため、食事は疎か下の世話や身体を清める事すら不要で、恐らくは床擦れすら起こさないように思えた。
それでも、私は時折あの人の四肢を掴んで動かしたり、姿勢を変えたりしている。
こういった事が、彼の正常な目覚めを促すと信じているのか。それともただこの人に何らかの形で触れて、何故か維持されている体温を感じたいだけなのか。
自分の心である筈なのに、それすらももうよく判らなくなっていた。
変化のない日々は、心をどんどんと摩耗させていくような気がする。
これならばいっそ、定期的に刺客が訪れてくれた方が良いのかも知れない、などと食事の席で口にしたら、マヒトさんに本気で怒られた。
そんな軽率な言葉がふと転び出てしまう程、どうやら私の心はおかしくなっているようだ。そしてそれが判っても、自分では解決する方法が全く思い浮かばない。
堂々巡りの思考の中、床に入る。
こういう日の夢は期待出来ない。果たして明日はどんな悪夢を見て飛び起きるのか。
我が事ながら、泣きたくなった。
・
五十九日目
日中晴天。夕に時雨。その後曇り。
近頃は以前よりも多少ながら心が落ち着いてきた気がする。あの夢を見る頻度も減った。
けれど、昔のような自分に戻れたかといえば、程遠いとしか言いようのない有り様なのは変わらず。
もう原因が解消されてもこんな性格のまま治らないのではないかと、自分でも薄々感じ始めている。
その予想が外れている事を祈りたいが、当たり外れという結果すら何時得られるか判らないのだから堪らない。
日中。円卓十氏の連絡員と会いにいっていたらしいマヒトさんが、渋い顔で返ってくる。
ラカルジャの政変はいよいよ悪化し、シオレ氏はかなり危険な立場に立たされていると聞く。
自分達がテュパンに滞在している事は既に完全に十氏側に割れている為、よりラカルジャより距離を離したグラジオラスへの移動を提案される。
このテュパンの部屋で暮らした時間は長く、すっかり馴染んだ部屋を離れるのは惜しいけれど、状況を考えれば可能な限り危険の少ない場所へと向かうという案は否定出来ない。
特に、全く身動きの出来ない無防備なあの人が居る自分達にとっては、襲撃という危険はなるべく避けたいファクターだった。
手早く荷物を纏め、宿を引き払う。久々の馬と荷車の出番と相成る。
グラジオラスで取れる部屋はテュパンの頃より格が落ちる事になるだろうが、そう酷い部屋でなければ良いのだけれども。
六十二日目
雨。時に猛雨となる。
夜の入り。ようやっと新しい住居にも慣れてきた頃に、突然、一人の男性が私達を訪ねてきた。
あの老人の侍従を名乗っていた三人のうちの一人。行方不明になっていた、ラバナという名前の人だ。本人が言うには、どうやら私達がグラジオラスへと転居した際に、こちらの居所を偶然知られたらしい。
あまりの唐突な来訪に、私達は皆武器を手に取ったが、曰く戦う気などさらさらないという。確かに、彼は武器も手にしておらず、管理下に置いたアエルも極僅かでしかなかった。服も侍従服から旅装へと変わっていた。今は旅商に近い事をして暮らしているという。
こちらの事についても、彼が知る私達に良く似た恰好の者達について、近くの酒場兼食堂で店の常連達が話しているのを聞いただけとの事だ。ラバナ曰く、自分達三人は結構この辺では浮いてしまっていたらしい。
彼と同じ侍従の仲間や、その主を実質殺した私達に対して、ラバナは少なくとも私が判る範囲では、なんの隔意も抱いていないようだった。
それが酷く不気味で、怖く感じたけれど、結局彼は何をする訳でもなく。こちらの近況と、そしてあの人の事を訊ねてきた。その問いの意図を正せば、ただどうしているのかと懐かしくなっただけだという。
それが本当か嘘なのか。未熟な私には判別出来なかったけれど、でも彼は“同化者”であったシバリスの弟子だ。もしかしたら、今の彼の状況について何か判る事があるかもしれない。私は悩んだ末、眠る彼と彼を会わせる事にした。
これは後で迂闊すぎるとマヒトさんに酷く叱られる事になったが、結果としては問題はなかった。
ラバナは眠るあの人を暫く眺めて、一つ。首を横に振るという仕草をするだけだったから。
彼が言うには、全ての問題が、既に『礎の世』側に移ってしまっているから、結果は向こうの処置次第。こちらから出来る事は、せいぜいが無事を祈るだけだろう、と。
そんな事、私はあの日からずっと、続けているのに。
七十日目
晴れるもあまり暖かくならず。
またラバナが訪ねてきた。何でも、あの人の事で幾つか調べてきた事があるからそれを伝えにきてくれたらしい。
ラバナが調べてくれたのは彼を包むアエルの構造だ。やはりこれが、今の彼の身体を保護するための防御膜のようなものなのだという。内部の時間を部分的に停止させ、維持する。膨大の量のアエルが注ぎ込まれた、そんな術技であるらしい。
そんな事をわざわざ調べ教えに来てくれるなんて、アサーンでは喧嘩した仲だったけれども、本来のこの人は案外良い人なのだろうか。
そう考えるが、「単にこいつ、【NAME】を調べてあっちの世界の術技の知識を掠め取りたいだけだろ」とマヒトさんに言われて気を引き締める。
といっても、以前本人が言っていた通り、私達に何か嫌がらせをするようなつもりも無いようで、他にも色々とためになるようなならないような、そんな話をして帰っていった。
ただ、別れ際ラバナさんは最後に彼の事を見て、前に訪れた時よりも、覆われているアエルが減っていると言っていたのが心に引っかかった。
殆ど離れずこの人と一緒に居たせいか気づかなかったけれども、言われてみれば確かに、最初の頃と比べると彼の身体を包んでいる光が、かなり弱く、薄くなっていっている事に気づいた。
これが良い変化であるのか、それとも悪い変化であるのか。
それすらも判らない事がとても怖くて、中々寝付けず。今のように日記に追記したり、刺繍をしたりして眠気が訪れるのを待つ。
七十九日目
終日小雨。
リトゥエさんが戻ってきた。彼女は色々と伝手を辿り解決の方法を探し回っていたそうだが結局当てはなく、最後の手段として海の地母種との繋がりを使うという。
芯属であればと希望を持ち、彼女と謁見すべく明日からあの人も連れて皆で旅に出る事になった。
どうか、実りある旅となりますようにと、我が神に祈るも、ベルモルト神の由来を鑑みるに、地母の種とは相性が悪そうにも思え、祈り伝えたのは失敗であったかなどと、神職ならぬ思いが過ぎる。
判っていた事だが、私はいよいよ、我欲に塗れた情けない神官であるらしい。それでも、神蹟を授けてくれる我が神には、感謝と崇拝の念しかない。
だが、もし目覚めることがあれば。
果たして帰ってきた彼が“どちら”であるのか。それを私は知ることになる。
未だにその恐怖は薄れないが、しかしこれまでの日々の中でもっとも信の置ける話でもあった。
不安よりも喜びを胸に、旅に出るのがきっと正しいことなのだと。そう信じて筆を置く。
・
百日目
本日戻る。取り急ぎ旅具だけを解いて、今筆を取っている。
結論から書けば、駄目だった。
この世界に於ける十三の偉大種とされる地母の芯属ですら、迂闊に手を出すことすら適わない、という。
その事実に、自分が酷く打ちのめされているのが判る。今も、それを考えると息が苦しくなる。
地母の芯属からその答えを聞いたとき、私はリトゥエが世も終わりかという表情で天を仰いでいたのを、茫然と眺めていた気がする。
帰りの道の間、皆と何を話したか。どう歩んだかさえ、はっきりと思い出せなかった。
とにかく疲れた。身体もそうだけれど、心の方も。
今日はもう、何も考えず眠ってしまう事にする。
でもその前に、あの人の寝床だけは整えておこうと思う。
百一日目
雲厚く、雨音強し。
遂に昨日で、あの人が眠りについてから百日が過ぎた事に驚いて、続いて強い虚しさが胸に過ぎる。
もうあれから三ヶ月と少しが経過したのだと、そう考えると何だか夢みたいだと感じる。
実際、あの出来事から今日まで、私の心はふわふわと、まるで夢の中にいるかのように曖昧だ。その曖昧な感覚は時を経る毎に強くなっていて、時折そのまま気すら失ってしまう事もある。最近では街中を歩く事すら危ういような有り様だ。
リトゥエと共に地母種へと会いに行く旅が終わってからは、特にその感覚が酷くなった。一縷の希望を託し、一縷である事を理解していたつもりでいたのに、その希望が断たれた結果の影響が出た。情けない話だけれども、そう考えるしかなかった。
マヒトさんはシモンズさん、そして今はあの人の傍で尽きっきりのリトゥエさんにも、もう私の異常は気づかれていて、色々気を遣ってくれているのを感じる。だけど、それが自分の中で更なる重みになってしまっていると自覚出来てしまって、尚更罪悪感に押し潰されそうになる。
もう食事に出る事も、彼の顔を眺める事も、段々怖くなってしまって。
私はこの日記を書き終えたら直ぐに毛布に潜り込んで、じっと縮こまる事しか出来なくなっていた。
百十四日目
終日晴れ。暖かく過ごし易し。
ここ数日。続けて「さよなら」の夢を見る。
あの夢を見た日は、目を覚ましても身動きすら取れず、暫く嗚咽を溢すしかなくなってしまう。それが収まっても全身に酷い倦怠感が残り、午前は碌に動けずに終わってしまう事が殆どだ。
最近は生活費を稼ぐための斡旋公社への通いも、マヒトさん達に任せきりで、彼と一緒にリトゥエさんが私の面倒もしてくれた。手間の掛かる病人と手間の掛からない病人が二人いるような状態だ。
今日は天候が安定して、どうにか午後には寝台から離れ、軽く家の仕事をこなす事が出来たが、自分の身体も心も、もうどうしようもない程に弱ってしまっている事を自覚する。
正直な話、何故自分がここまで堕落してしまったのか。それすら良く判らない。
あの人の事は、自分に指導してくれたり、一緒に戦っていた時はとても強くて頼りになる尊敬出来る人という位置づけで、重要な人ではあったけれど、そこまで自分の心を占めるような扱いではなかった筈なのに。
さよならを告げられて、こうして抜け殻となってしまった後。何がこんなに、私の心の根っこに突き刺さるような扱いへと変わってしまったのか。
どちらにせよ、もう遅い。
原因がなんであれ、ここまでおかしくなってしまったのなら、もう彼にどういう形であれ変化が起きるまで、このまま流されてしまおう。
百二十二日目
朝方に濃く霧が出る。
一週間程前の覚悟が、試される時が来てしまった。
真剣な顔つきのマヒトさんが、全員を集めて語るには、ついにラカルジャの政変は最終局面を迎え、そしてシオレの家はほぼ破滅し、今は血族全てを狩り出し、皆殺しにするという段階にまで至ってしまったそうなのだ。
つまり、それは私の家族がもう既に殆ど死に絶えているという事を示していた。
過去の私であれば、その事に深いショックを受けて、半狂乱にでもなっていたのかもしれないが、今の私はもう既に半分狂っている。流石に平然とではないが、そうなってしまったのだなと、ぼんやりとではあるが受け止める事が出来た。
問題は、ここからだ。
そういった事情から、私に対して更なる刺客が派遣されてくるのは明白だ。テュパンと比べラカルジャから更に遠いグラジオラスに逃げ込んだとしても、距離としてはそう大きな差は無い。そう時間を掛ける事無く刺客は私達の居場所を捉え襲撃してくるだろう。
その対抗策としてマヒトさんがぶち上げたのが、何と海を渡るという方法だった。
彼の言う事は判る。このままグローエス内を逃げ回るか、更に南の国であるフィーエルに逃げ込んだとて、ラカルジャの手から逃れられる気はしない。
しかし、流石に芯海を渡れば話は別だ。ラカルジャの連絡網は東大陸に集中しており、海向こうに対しては殆ど影響力がない。西大陸か、あるいはその中間に存在するフローリア諸島辺りに逃げ込めば、ラカルジャの刺客といえどそう簡単に追ってこれないように思える。逃亡先として考えるなら、これ以上無い選択肢だと思う。
ただ、問題が一つ。
【NAME】だ。意識を失い人形のようになった彼を連れて船旅に出るのは難しいと、マヒトさんは断言した。
だから決断をして欲しいと、彼は私に告げる。
あの人を残して芯海を渡るか。それとも意識の無い彼が巻き込まれる事も覚悟で、東大陸に残るかを。
こうして、日記を書いている今も、私は迷っている。
視界の隅には、あの人が眠る寝台がある。
あの人を覆う光は至極薄くなり、もう殆ど見えなくなっていた。
百二十五日目
薄曇り。
泣きたくなるほど、嬉しい夢を見た。
あの人が目を覚まして、私の名前を呼んで、静かに二人だけで、言葉を交わす。そんな馬鹿みたいな夢だ。
何を話したのかなんて覚えていないのに、楽しくて、嬉しくて、そんな感情だけが残る夢。
だから目を覚ましたとき、「さよなら」の夢を見た時以上に、泣きたくなるほど悲しくなった。
楽しくて嬉しかったその感情が、全部反転して自分を苛むのだ。
あまりの辛さに、こんな朝早くから夢の事を書き記しているなんてどうしようもないが、それだけ辛くて、こうでもしないと暴れ回りそうだったのだ。
自分がもう、限界であることを薄々感じる。幻聴、幻覚。そんなものも時折感じるようになった。
今だってそうだ。
振り返れば傍の寝台で、起き上がる筈の彼が上体を起こして私を真っ直ぐにみ
・
目覚めると、見知らぬ場所で横になっていた。
けれど、四肢の感覚、五感の働き。それらは自分にとってはしっくり来る、慣れた感触ともいえるもので、どうやら“この世界”の“この人物”に、上手く焦点を定める事に成功したのを確信する。
寝台から半身を起こす。恐らく長い間放置されていた身体の筈だが、まるであの時離れてからそのまま時が止まっていたかのように、全く身体が鈍った感触無く動かす事が出来て、逆に驚いてしまう程だ。
取り敢えず、誰かいないかなと貴方は首を捻ると、寝台の傍で、茫然と自分の顔を見つめている娘と目が合った。
髪はぼさぼさに乱れて、頬も目元も赤く、まるでついさっきまで泣いていたかのように、両の瞳は揺らぐように潤んでいる。
そんな有り様ではあったが、貴方にとっては懐かしく、そして忘れがたい人物だった。
リヴィエラ・シオレ。
彼女が、丁度目覚めたタイミングで傍に居てくれたのは運が良かったと、貴方は素直に思う。訊ねれば、今自分が置かれている状況が直ぐに判るからだ。
そんな事を考えながら、貴方が眼前に近い位置に居る彼女を見つめてみると、
「……あ、の、……えっと、は……じめまし、て?」
予想外の事を言われ、貴方は怪訝と首を捻る。
何故ここで「はじめまして」となるのか。
問うと、彼女は口元を戦慄かせて
「でも、さよならって、あの時、だから、それに……【NAME】、さん? 【NAME】さんで、いいの? 私……判ります、か?」
混乱しきった言葉から、貴方は意味の把握に戸惑う。
だが、取り敢えず、自分は【NAME】だと返し、そして君はリヴィエラであると告げれば、
「【NAME】さんっ!!」
叫びと共に、彼女の身体が飛び出して、貴方の正面から絡まると、思い切り抱きしめられた。
――そうして貴方達は無事、さよならからの再会を、果たしたのだ。