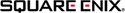四大遺跡 陸の海月
――陸の海月――
深夜。ティネとノスキスという二つの村を繋ぐ街道、ユウベル街道の北部に、深く濃く広がる森がある。アノーレ島の“四大遺跡”の一つに数えられるヴィタメール遺跡を内包する巨大な森林地帯だ。
その森の端から西へ、少しの距離を置いて広がる平地の一部に、人々が過ごす気配があった。占領されたヴィタメール遺跡を奪還するために編成された常駐軍の部隊、その宿営地だ。
平原に幾つも張られた天幕のうち、中央に建つ一際大きな天幕。その中には腰から細く長い半身剣を提げた男が一人。彼は地面に腰を降ろして、携帯用である組み立て式の木机に乗せた小さな洋燈の灯りを頼りに、きつい折り目の残る紙へと視線を落としている。
彼は片眉を曲げつつその紙を暫し眺めた後、空いた手で己の顎を撫でる。いい加減に剃られた髭の残る顎がぞりぞりと音を立て、男はその感触を楽しむように一通り撫で回した後、嘆息。
「相変わらずアホね、あのコ。こんなことしてちゃ、ホントに共犯とかで捕まるわよ」
誰に聞かせるでもなく男は呟いて、軽く頭を掻く。そして紙をおざなりに畳んで懐へ仕舞うと、勢いをつけて立ち上がり、天幕を出た。
「……とか言いつつ、協力しちゃうアタシもアホねぇ」
独りごちつつ何気なく振り返ると、天幕の頂点に一羽の白鳩が止まっていた。男の視線に気付いたのか、鳩は首を傾げて彼を見下ろす。
「了解したっつっといて」
男が告げると、鳩は一度喉を鳴らすような音を立てて鳴き、次の瞬間、夜闇に染まった空を西へ、何の躊躇も無く飛び去っていった。上空に広がる黒色の中で、ぽつんと残った白の一点を見上げて、男は少し驚いた表情。
「呆れた。こんな暗い夜なのに平気で飛んでっちゃうし。流石“先生ちゃん”のトコの鳩……っつーか、そもそも鳥目云々以前に本当に鳥なのかどうかも怪しいわねん、あれ」
「──ノクトワイ隊長? どうかされました?」
と、天幕から出てきた彼に気付き、外で動いていた兵士の一人が声を掛けてきた。ノクトワイと呼ばれた男は振り向かぬまま少し間を置く。
「ん? いや、何でも。雨は暫く来ないわねとか、そんな事考えてただけ」
そこまで言って、ノクトワイは顎に手をやり、少し考え込む。
──手紙に書かれていた日付からして、彼らがやってくるタイミングとしてはそろそろ。気分転換、散歩がてらに探してみるのも悪くは無い。
そう判断し、ノクトワイは一つ頷き。振り返らぬまま背後へと声を掛けた。
「でさ、ちょい今からアタシ出かけてくるわ。他の連中にもそう言っといて」
「は?」
理解しているのかいないのか判らない惚けたような声が返って来たが、ノクトワイとしてはその方がありがたかった。
「んじゃま、あとよろ」
告げて手を振り、一拍。
後ろで「ちょ、ちょっと待ってください──本営への戦闘の報告書、まだ貰ってませんよ!?」やら「うわ、負け戦の処理こっち任せで逃げる気だぞあの人!!」やらと兵士達が騒ぎ出すのを無視して、彼は全力で駆け出した。
・
狩人の村ティネと産み出す村ノスキス。この二つの村を繋ぐユウベル街道の中間点、その北側には黒々とした葉々を茂らせた木々が乱立する大森林が広がっている。
ユウベルの街道からほんの少しだけその森へと分け入った位置。【NAME】とノエルは用心深く歩きながら、森の奥の様子を慎重に観察していた。
「それで、【NAME】」
そう声を掛けてきたのは、【NAME】の隣をついて歩いてきていたノエルだ。
「これからどうされますか?」
素朴極まりない問いに【NAME】は直ぐ返答することができず、難しい表情のまま森の小径で立ち止まる。
今【NAME】達が居るヴィタメール遺跡を囲う大きな森には、遺跡攻略側と占領側のニ陣営の斥候の姿が頻繁に行き来して迂闊に奥へ足を踏み入れることも出来ない状況にあった。
先刻ティネの村で伝え聞いた戦闘の影響なのか、森全体が何処か殺気だった気配に包まれており、森の中を動く兵士達の数もかなりのものだ。【NAME】の今の目的を考えるに、兎に角ヴィタメールの遺跡に近づかなければ話にならないのだが、途中どちらの陣営問わず斥候や警邏の者に見つかってしまうと、色々とややこしいことになるのは目に見えている。森を徘徊する彼らを完全に避け切り、森の奥にあるヴィタメールの遺跡へ辿り着く程の自信は【NAME】には無かった。
(となると、一体どうすればいいんだ?)
考え込むが良い案は浮ばない。そこへ──。
「いやいや、ホント探したわよん」
背後から唐突に響いた声。人の気配など微塵も無かった筈と驚きつつも、ノエルは背の黒銃フォーレミュートを手元へ手繰り、【NAME】も己の武器の柄に手をやりながら素早く振り返る。
黒い葉々に遮られて暗く閉じた木々の合間。微かに届く陽光の中に浮んだ人影は、そんな落ち着いた風景から激しく遊離する派手な色彩を持っていた。目に鮮やかな青色の衣服を着込み、腰に微細な彫刻が施された剣の鞘を提げた偉丈夫。背は高く、男らしい彫りの深い顔に手入れされた立派な口髭が良く似合っていた。
(……だけど、何者だ?)
その形から素性が掴めない。キヴェンティでは勿論無く、兵士のようにも見えず、そこらの村人という風にも見えない。
男は【NAME】達の鋭い視線を悠然と受け止めて、軽く片手を上げると挨拶。
「はぁ~い、おこんばんわぁ。初めましてねん」
「────」
視界の隅、横で身構えていたノエルがびくりと驚きで身を強張らせたのは、恐らく【NAME】と同種の悪寒が背筋に走ったからに違いない。
(なんだ、こいつは)
ダンディズム全開のバスの効いた深みある声音、しかし口調は極めて軽く異様に馴れ馴れしい。そのギャップにより生み出される感覚を一言で表すなら、兎に角“気色悪い”だ。
男はそのショックで固まってしまった【NAME】達を何とも云えぬ粘ついた視線で順々に眺めた後。最後の一人──ノエルを眺めて小さく頷き、唐突にこう云った。
「で、アナタが話のノエルちゃん? ってことは、そっちのコは噂の冒険者君かしらん」
「────」
今度は緊張で【NAME】達の動きが止まった。
(どうしてこちらの事を知っている……?)
【NAME】がどう反応するべきか迷っていると、横に居たノエルが一歩前に出て口を開く。
「……どういったお話を聞かれているのかは存じませんが、わたしがノエルという名なのは確かです」
そしてノエルは警戒を解かぬまま、硬い表情で問うた。
「それで、あなたは何者でしょうか」
「んー?」
その問いに、男は不思議そうに目を瞬かせて数秒。
「ああ、えーとそーいや名乗ってなかったわねん、アタシ。いやぁゴメンゴメン」
云いつつ、男はごそごそと自身の懐に手を突っ込むと、仕舞っていた金属製の印を取り出す。
「アタシはアラセマ陸軍第十二師団第二兵士団長で、今ヴィタメール占領しているキヴェンティ連中を張り切って全滅させようと頑張ってる部隊の隊長、名前はノクトワイ・キーマ・フハール。これでイイ? ほら、証拠の階級章」
ノクトワイと名乗った男は、手に持った印を【NAME】達に見えるようにふりふりと数度振ってみせた。
(……本物、なのか?)
殆ど軍の外の人間である【NAME】には判断できず、反射的に軍人であるノエルを見ると、彼女は表情を崩さぬままこくりと頷いてみせる。つまり、男が見せたあの印はどうやら本物であるらしい。
だが、本物だとしたら何故こんな場所を一人でひょこひょこと歩いているのか。
「あれ、まだ信用してない?」
己の身分を明かしたにもかかわらず、より疑念の色を濃くして自分を見ている【NAME】達の様子を見て、ノクトワイと名乗った男は少し困ったような表情を浮かべて己の髭を摘んでみせる。
「そんな警戒しなくてもダイジョブよん。ああでも……ウフ、可愛らしいわねアナタ」
云って、ノクトワイは【NAME】の隣に居たノエルの方へと妖しげな視線を送る。途端、ノエルの肩がびくりと震えた。
「なんつーかこう、その“中途半端”なところがタマンナイわ。ウフフ……」
「────」
男の気色悪い視線を避けるように、ノエルはさりげなく【NAME】の背後へと隠れる。そんな彼女の様子に、ノクトワイはケタケタと笑った。
「だーかーらー、そんな怖がんなくてもダイジョブだってば。種を明かすとね、アタシ前もって“先生ちゃん”──イェア・ガナッシュからお手紙貰っててねー。それでアナタ達のコト知ってたって訳。はい、これ証拠品」
男は自分の懐に再度手を突っ込むと、今度は一枚の紙を取り出してひらひらと振ってみせ、筒状に丸めて投げられるようにしてからひょいとノエルへと投げて寄越した。
ノエルは片手でそれを受け止めると、警戒を解かぬまま素早く紙に視線を巡らせて数秒。
「イェアが、あなたを?」
「そそ。アナタ達のこと手伝ってあげてって。先生ちゃんって文章でも“ですわ調”なのよねーってまぁ、それはどうでも良くって。アタシもアイツ等が何考えてんのか前から結構興味あったし、だから私的に手を貸してあげてもイイかなーってね。言うなれば“お仲間”よ、アタシ達」
「……お仲間、ですか」
「何よその厭そーな言い方」
気持ち眉を顰めてのノエルの言葉に、ノクトワイはいかめしい顔の癖してぶぅぶぅと子供っぽい仕草で抗議。何というかとにかく気色が悪い。
(だけど、取り敢えず味方とみて良いか)
依頼主のお墨付きなら大丈夫だろう──と、【NAME】が安心しかけた矢先。
「でもま、その辺の話は一旦横に置いとくとして──実はアタシ、先にやるコトが一つあるのよねん」
(……は?)
やる事とは何だろうと首を捻る。そんな【NAME】の仕草を見て、ノクトワイは極めて馴れ馴れしい調子でこう言ってのけた。
「ああ、ほらアタシさぁ、一応曲りなりにも常駐軍の人間で、しかもそこそこ立場のあるニンゲンな訳じゃない? で、先生ちゃんからアナタ達に協力してあげてーっていうお願いも聞いてる事には聞いてるんだけど、遺跡に近づくお馬鹿な部外者ちゃんは丁重に追っ払わないとダメっていう義務、つまりオシゴトがある訳よ。こっちが作戦するにも邪魔だし」
「…………」
何となく、彼が言いたいことは読めた。
【NAME】は何も云わずに心底呆れた表情でノクトワイを眺め、ノエルの顔にも一時薄れていた警戒の色が戻る。
「だからまぁ、判るわよねん? 本音としてはアナタ達と一緒にとっとと行きたいトコなんだけど、一応形だけでも職務は果たさないと。いやホント、オシゴトって大変だわぁ」
べらべらと喋り続けるノクトワイを無視して【NAME】は無言のまま武器を引き抜き、ノエルも手にした黒銃を抱え直すと淡々と呟く。
「──イェアは協力を仰ぐ相手を間違えたと、わたしはそう判断しました」
その言葉に、ノクトワイはわざとらしくさも心外とばかりの表情。
「あら、いやぁねぇ。ちゃんとアタシに勝てたなら、こっちのオシゴトは失敗でアタシの中での優先順位は大低下。順位変動下克上ってことで、アナタ達を個人的に手伝ってあげてもいいわよん」
そして鞘に収めた剣を後ろへ引き、右手を柄、左手を鞘に添えて腰だめで構えるノクトワイ。遥か遠方の“環の国”に伝わる、独自の形状を持つ片手半剣を用いた特殊剣技の構えだ。
(……つまり“力を示せ”ということか)
それならば慣れた物だ。軽く笑みさえ浮かべて戦闘態勢へと入る【NAME】を見て、ノクトワイもどこか楽しげに笑う。
「フフッ──アナタってあの“コロちゃん”を倒した冒険者ちゃんなんでしょ? さぁて、一体どの程度のものか──手は抜かないから、覚悟してねん」
“コロちゃん”って何、と問う前に、ノクトワイが動く。腰に提げていた剣の柄に添えられた片手が閃き、同時に走った銀光が【NAME】の喉元へと迫る!
battle
奇妙な男

男は【NAME】の補助を受けて放たれたノエルの銃撃を器用にいなし、驚きの表情を浮かべつつ間合いを取った。
「へぇ、アタシの“心眼”を越えるとは──うん、合格よん。イイわ、アタシも力を貸してあげましょ」
四大遺跡 ユウベル街道
――ユウベル街道――
ノクトワイと【NAME】達はお互い武器を収め、改めて向かい合う。ノクトワイの言動から察するに、どうやら自分達に力を貸してくれるつもりらしいのだが──はて、具体的にどう手伝ってくれるのか。【NAME】は黙したまま男の出方を窺った。
「それで、どうしましょうかね」
手にしていた刀を納めた髭の男は、まだ緊張を帯びた眼差しで己を見る【NAME】とノエルをしげしげと眺めて「んー」と唸る。
「今の状況だと、キヴェンティ達の陣地に潜入して向こうの頭と直接接触するくらいしか無い訳なんだけど──でもま、そんなカッコじゃ潜入も何もないわねん。大体、ノエルちゃんなんてそれ、一応平服だけどモロに常駐軍のモノじゃない」
そんなノクトワイの言葉に、【NAME】とノエルは困ったように自身の姿を見る。確かにキヴェンティ達の中に紛れ込むのに向いた服装とは云い難い。
ではどうすれば良いのかとノクトワイの方を見ると、男はニマニマとした笑顔を浮かべた。
「やっぱこういう時はヘンソーよん。それしかないわん」
(変装……なるほど)
理に適っている。が、問題は──。
「ですが、キヴェンティ部族の服装をどこで用意されるおつもりでしょう?」
と、【NAME】の代わりにノエルがその疑問点を問うた。キヴェンティ達の衣服は独特で、大陸の移民であるアラセマの民の町や村で扱っている衣類とは様式がかなり異なる。つまり手に入れるにはキヴェンティ達と直接接触し、取引するしかない。
ノクトワイの方もそれは心得ているようで、難しい表情で小さく頷く。
「まぁ、確かにお店で手に入る類でも無いのは確かなんだけどねぇ。それに、アタシ達じゃ服替えたくらいでキヴェンティ連中に混ざり合うのはちょーっとばかしムズカシイわねん。多分バレバレ」
ノクトワイはそこまで言って、気楽な調子でからからと笑い、一息。
「とかいいつつ無理でもやるんだけど。ウフ」
「やるんですか」
やるのかよ。
「つってもほら、近いと即アウトだろうけど、遠目からだとそれなりにバレないと思うし、それならそれでイイんじゃないの? 要はキヴェンティのお頭に会うまで誤魔化せればいいんだから」
ノクトワイはそこまで言って、気楽な調子でからからと笑い、一息。
「あとアナタ達のお着替えも手伝いたいし。ウフ」
「それが本音ですか」
それが本音かよ。
「ウフフフ。若いコのハダってイイわよねー、ハリがあって。羨ましいわ、ホント」
「…………」
【NAME】はノエルと共に無言のまま、じとり、と褪めた視線をノクトワイへと向けるが、ノクトワイはウフウフ笑ってその視線を受け流すと、
「──いやまぁ、冗談は置いとくとして」
到底冗談を言っている様子には見えなかったが、ノクトワイは場の空気を変える為か取り敢えずそう言って、軽く咳払いを一つ入れた。
「で、ホントどうしましょうかね。取り敢えず連中の陣に近づいて、その辺うろうろしてる見張りを繁みに引き摺り込んでから、ばばっと身包み剥いじゃうのが簡単かしらん」
(それ、簡単か?)
とは思うが、代案になるようなものも即座に思いつかない。隣に居たノエルも同様らしく、【NAME】とノエルはお互い気難しげな表情で顔を見合わせる。
そんな【NAME】達の様子を同意と解釈したのか。
「じゃ、この作戦でいきましょ。キヴェンティ達の陣地はこの大森林の奥、ヴィタメール遺跡の手前にある筈よん。先にいって適当に準備してるから、暫くしてからおいで。それじゃね」
云って、ノクトワイはさっさと森の奥へ向かい歩き出していってしまった。
(……どうしたものかな)
取り敢えず、彼に任せてみるべきなのだろうか?
四大遺跡 キヴェンティ野営地
――キヴェンティ野営地――
世界を力強く照らしていた陽の円は地平の彼方と沈み、その残滓とも云える仄かな輝きが空の端に僅かに残る。夕から夜へと移り変わる最中──そんな時分。
用心深く森を進み、キヴェンティ達の陣地があるという遺跡近辺へと足を運んだ【NAME】達は、先行して森へと入っていた口髭の男、ノクトワイ・キーマ・フハールの背中を木々の合間に見つけた。
「あら、もう来たのん? 早いわねぇ」
【NAME】の存在に気付いたのか、振り返ったノクトワイは緩んだ表情を浮かべてひらひらと手を揺らす。
(準備とやらをする為に、森へ先へ入っていった筈だが……)
その準備とやらはどうなったのか。彼の傍へと移動した【NAME】がその事をノクトワイに問うと、
「あー、あれね。取り敢えずアタリはつけといたわん。ほら、あそこ。見える?」
ノクトワイの指差す先には、キヴェンティと思しき独特の衣服に身を包み、武器を手に携えた男が数人、灯りを手に立っていた。恐らくは彼らの陣地に近づこうとする軍のものを警戒して配された見張りだ。
「んじゃま、ちょいと行ってくるから。ここで見てなさいな」
へらへらと笑いつつ。ノクトワイは散歩にでも出かけるような気軽さで、しかし確実に夜の闇に身を潜めながら森を進み、灯りを抱え退屈げに立つ男の背後へと事も無げに身を移す。
要するに、あの見張り達を襲って身包みを剥ぐつもりらしい。
「大丈夫でしょうか?」
横で見ていたノエルが小さく首を傾げて呟くのが聞こえたが、闇に動くノクトワイの身のこなしは一見いい加減なように見えて、しかし何故か隙が無い。あの調子なら大丈夫だろう。そう返答しかけたその時。
「誰だッ!!」
──と。
ノクトワイの居る位置からではなく、【NAME】の背後から誰何の声があがった。振り向けば、そこには先程見たキヴェンティと良く似た服を身に纏った数人の男が立っていた。どうやらノクトワイに気を取られて、別の見張りがこちらに近づいてきていたのに気づかなかったらしい。
(……油断した)
思い、舌打ちする。完全にこちらの失策。ノクトワイの事を心配している場合ではなかった。
「【NAME】、いきます」
──と、傍らに居たノエルが短く呟き、背負っていた黒銃を素早い動作で持ち直すのが視界の隅に見えた。
ともかく、敵にこちらの存在を知られる訳にはいかない。【NAME】も己の武器を引き抜き、今にも仲間を呼ぶため大声を上げようとしている男達に全力で攻撃を仕掛ける!
最後の一人を打ち倒し、【NAME】は小さく安堵の息を吐く。何とかキヴェンティが他の仲間を呼ぶ前に仕留めることに成功したようだ。
武器を収めて視線を移せば、ノクトワイが手際よく見張りを気絶させ、彼らの着ていた衣服を片手にこちらに歩いてくるのが見えた。彼は【NAME】の視線に気付くと、へらへらとした笑顔でこちらに手を振り、次いで【NAME】の足元に転がっているキヴェンティ達を見て少し目を見張る。
「あら。そっちでもやっちゃったの? ちゃんと人数分確保してきたから大丈夫なのに。ほら」
ばさばさと持っていた服を地面に投げたノクトワイに、【NAME】とノエルは返す言葉も無くお互いの顔を見合わせた。ノクトワイが出向いている間に他の見張りに見つかってしまったと言うのも間抜けな話で、あまり進んで話したい内容でもない。
黙り込んだ【NAME】達に、ノクトワイは軽く肩を竦める。
「んー、まぁいいわ。じゃ、取り敢えず上着だけでもひっかぶっときますかね。ノエルちゃん達はそっちのヒトの服でよろしくねん」
ノクトワイの言葉に【NAME】は頷きで返すと、気の失ったキヴェンティ達の衣服を手早く剥ぐ。あとはこれに着替えれば良い訳だが──。
「…………」
何処からか「じぃ」と音が聞こえてきそうな程の熱いノクトワイの視線。
その矛先となっていたノエルは、表情は一切変えず、しかし服を手にしたまま動きを止めてしまっていた。
「ほら、どうしたの。着替え着替え」
「…………」
促すノクトワイと、黙ったままノクトワイを見返すノエル。そのままお互い睨み合い、動かなくなる。何ともいえぬ緊張感が場を支配した。
何をやっているのやら、と呆れの感情を小さな溜息として吐き出す。
この先どうなるのか黙って見物するのも一興ではあったが、今はそんな場合ではない。【NAME】はノエルを適当な木陰に放り込むと、何だかんだと喚くノクトワイを捕まえ、一旦その場から離れる。
「──う、うううぅ。折角のお着替え──スベスベ──」
既に敵陣近く、キヴェンティ達の新手が現れる可能性もある為、あまり大きく距離を取る訳にも行かず。【NAME】はぶつぶつと何やら呟いているノクトワイを両腕で捕まえたまま、さてどうしたものかと考えていると。
「【NAME】、おまたせしました」
背後からの声に振り向けば、キヴェンティの衣装を身に纏った小柄な人影が立っていた。それを見て、ノクトワイががっくりと肩を落した。
・
正に意気消沈といった態で、もそもそと着替え始めるノクトワイ。
(というか、そこまでがっくりする程のことか?)
そんな彼の様子を半眼で眺めながら、【NAME】もキヴェンティ達の上着を羽織る。ノエルと違い、装備している防具との関係もある為、普段の装備の上から被る程度しかできない。だが、真面目に着込んでみた処で、彼等は所謂“閉じた部族”だ。外部の者を嗅ぎ分ける鼻は並ではなく、どうせ近づかれれば一目で余所者と看破されるだろう。ならば戦う力を捨ててまで形を変える必要も無い。
重ね着によりごわごわとする衣服を整え、襟を両手で数度引く。服の感触に馴れたところで隣を見れば、既に着替え終えていたノクトワイが、【NAME】の視線を受けて疲れたように溜息をついた。
「はぁ……。なんか一気にやる気なくなっちゃったけど、ここで帰る訳にもいかないわよねぇ」
などと云いながら、極めて気怠げな調子で己の首に手をやり、軽く揉み解す。態度といい、口調といい、冗談ではなく素でそう考えてそうな処が恐ろしい。
そんな彼の様子に危機感を覚えたのか。一歩前に進み出たノエルが、頭二つは上にあるノクトワイの顔をじっと見つめて小さく口を開く。
「あの、失礼な物言いかもしれませんが、もう少し真面目に取り組んでいただけるとありがたいと、わたしは思うのですが」
それに対し、ノクトワイは爽やかな笑顔を浮かべて片手を上げ、へこへこと前後へ。
「いやぁねぇ~。マジメもマジメ、いつでもどこでも大真面目よアタシ。例えばアナタのお肌をジカに拝見したいなーとか思ってたトコなんか特に」
「…………」
表情は硬いまま、しかし瞳だけで至極不信気な様子を伝えてくるノエルに、ノクトワイは上下に揺らしていた手を下ろし、それを受け流すように軽く肩を竦めてみせた。
「……まあ、気が進まないってのはマジだし否定しないけどさ。でも、今回のコトはアタシとしてもやっとかなきゃならない事だから、逃げやしないわよ。だからほら、さっさと済ませちゃいましょ」
告げて、ノクトワイは森の奥へと軽い調子で歩き出す。唐突な動きに反応が遅れた【NAME】とノエルは、お互い顔を見合わせた後、慌てて彼の後に続いた。
・
キヴェンティの衣服を纏ったノクトワイは、夜と茂る葉々によって生み出された二重の闇の中を、灯りも無しにするすると。一片の迷いも見せずに進んでいく。その後ろを【NAME】──そしてノエルが遅れないように続く。ノクトワイの歩みは一見のんびりしているようで、実の処は驚く程に速く、【NAME】は見失わぬよう懸命にその背を追った。
そのまま小半時ほど森を歩いただろうか。殆ど走るにも等しい速度で森を進んでいた【NAME】達の前方が、唐突に晴れた。
森を拓いて作られた平地に、獣の皮などを材料とした六角形の天幕が幾つも並ぶ。それらの群れの遠く向こうには、既に夜の暗闇に包まれているにもかかわらず、その存在を視認出来る程の威容。“四大遺跡”の一つであるヴィタメール遺跡の姿が見える。
「着いたわね。ここがキヴェンティ達の野営地よ」
ノクトワイはそのまま森の外へと踏み出しはせずに、脇に生えていた一際大きな樹の影へと身を移した。彼に習い、【NAME】とノエルもその後ろへとつく。ノクトワイは傍へとやってきたこちらに顔を向けず、視線は慎重に野営地の中を見据えながら、しかし声だけは【NAME】達へと向ける。
「キヴェンティの陣は複数の天幕で構成されてるわ。で、ここに居座っている連中を束ねているマオエ氏族の若長──リゼラ・マオエは、北東の大天幕に居るってのがウチの連中の結論。そいつに会いに行くなら陣地を通ってそっち目指すしかないんだけど──」
「あの、一つ宜しいですか?」
調子良く話していた男の言葉をノエルが遮る。ノクトワイは野営地へと向けていた視線を、背後の黒銃を抱えた少女へと移した。
「何?」
「先刻抜けてきた森と同じように、野営地の中にもキヴェンティの警邏の者が多く配置されているとわたしは予想します。迂闊に足を踏み入れるのは危険と判断しますが、如何でしょうか」
ノエルの言葉に、ノクトワイは片眉を顰めて「んー」と唸る。
「とはいえねー。確かに森を回り込んで北東へ移動するのが常道なんでしょうけど、前情報だと野営地近辺の森は南西のこの位置くらいしか警備がヌルい場所ないのよ。だからまぁ、ここから中に入って、野営地内を巡回している連中を上手く避けて進む方が無難かなってね。外よりも中を警備している連中の方が油断してると思うし」
そこで言葉を切って一息。首を捻ってこきりこきりと鳴らす。
「一応、アタシ達のナリもキヴェンティのモノになってるから、遠目からならバレないと思うわ。でも、近づかれたら多分ダメ。その時は──」
「その時は?」
鸚鵡返しに問うたノエルに、口髭の男はおどけた様に肩を竦めて、
「ま、ノリノリで一発殴ってから即逃げかしら。仕切り直しってことで」
「…………」
行き当たりばったりにも程がある。【NAME】は細く溜息をつき、ノエルは眉根を寄せてだんまり。だが、ノクトワイはそんな【NAME】達の様子は全く意に介さず、
「取り敢えずそーゆーことで。んじゃま、行くわよん」
などと言うだけ言って、彼は木陰から身を起こすとキヴェンティの野営地──敵地の只中へと飛び込んでいく。
天幕と天幕、樹と樹の間に点々と配置されたかがり火の列。それ等から生み出される光の影響が最も少ないであろう場所を選び、影から影へと飛ぶように動く。その隙のない動きを、【NAME】は感嘆の表情で見送った。
「【NAME】」
と、直ぐ脇からの声。反射的にそちらへ振り向くと、
「お先に失礼します」
それだけ言って、【NAME】の隣に控えていた少女が木の裏からするりと抜け出す。こちらもそつ無く闇から闇へ。白を基調としたキヴェンティの衣装に包まれた小さな体が敵地を身軽に疾る。しかし、そんな彼女の背中を見た【NAME】は思わず苦笑。
(……あれでは、着替えた意味も無いな)
幾ら服をキヴェンティのものに替えていても、彼女の背中で鈍く輝き揺れる長大な黒銃は、キヴェンティ達が使うものでは明らかに無く。全く、怪しい事この上ない。
去り行く彼女を見送りながら、一頻り笑い終えた【NAME】は「さて」と一息。
(では、行きますか)
内心呟き、意を決する。
野営地を巡回しているであろう見張りの者達を避けつつ、何とか北東にあるという大天幕とやらへ辿り着かねばならない。今の自分の着膨れした姿と、先程のノエルの後ろ姿を考えれば、少しでも見張りの気を引いてしまえばそこで終了。これは確実だ。ならば兎に角、出来うる限り身を隠して進むしかない。
【NAME】は周囲に鋭く視線を走らせて、近くにキヴェンティ達の気配が無いことを確認。素早く木陰から飛び出すと、極力身を屈めたまま、先行したノクトワイ達の後を追った。
四大遺跡 暗躍の翳
――剣の杜人――
「まずは……あそこの見張りね」
リゼラが居ると思しき大天幕の入口前には、数人のキヴェンティ達の影。避けられる位置ではない。──ならば、騒がれる間を置かず、一瞬でケリをつける他無いか。
battle
芯獣の下僕


大天幕の入口前に立っていた見張り二人を手早く昏倒させると、【NAME】達はそれぞれ身振りだけでタイミングを計り、そして同時に天幕の中へと踏み込んだ。
緩い円形を描く直径10メートル超の天幕内は、入口より中央付近までは地肌が剥き出しになっており、それより奥は膝丈ほどの高さの木製の段が床として配置されていた。天幕の形状に合うよう半円で造られた木製の段上には、天幕の内を仄かに照らす灯火が二つと、それに挟まれた形で床に座した人影が一つ。姿勢良く胡座を組んだ影の隣には、細枝を合わせて造られた台座があり、その上には微妙に拵えが異なる二本の長剣が置かれていた。
二つの灯を左右に置いた影は小柄な少年だ。
両側の灯を受けて赤みがかった黄色に染まった彼は、いきなり自身の居所へ侵入してきた【NAME】達に驚いた様子も無く。ただただ静かな表情でこちらを見据えている。肩も腕も細身で、金の髪が乗る顔の造形もまだ幼さを残したもの。しかし、その両眼の奥に宿る年齢不相応な鋭い輝きは、彼が只の子供ではない事を示していた。
(この子が、ヴィタメールを占領するキヴェンティ達の長、リゼラ・マオエ・キヴェンティ……)
──そう【NAME】が認識する程度の間を置いて。
少年は胡座を組んだまま、突然の闖入者である筈の【NAME】達に向かい、慌てた様子も無くゆっくりと言葉を放つ。
「漸く我の元へと参ったか。羽虫の如くちょろちょろと──煩わしい」
(……既に気付かれていた、か)
心中で呻き、より表情を硬くした【NAME】達に対して、少年は床に座したまま小さく鼻を鳴らし、
「先刻からヴィタメール遺跡の周りを色々と嗅ぎ回っていたようだが、そう易々とは近づけるものではあるまい。守りの民たる我等キヴェンティの──」
彼はそこまで言って言葉を切ると、そこで初めて視線に薄い驚きを乗せて【NAME】達を見据えた。
「……いや、気配が違う? 先程からうろついている輩とは別口か──何者だ、お前達」
(は──?)
言葉の意味が理解できず、【NAME】は眉根を寄せて反射的に疑問の表情を作る。
一体、この少年は何を言っているのか。自分達が野営地へ侵入していたのを気付いていた訳ではないのか?
そして兎に角何か言葉を返そうと、【NAME】が一歩前に出たその時。
「ちょい待ち」
囁きに近い声と共に肩を掴まれ、留められる。振り返れば、不敵な笑みを浮かべた口髭の男の姿。
「ここはアタシに任せてもらっていい? 上手くやってみせるからさ」
彼は【NAME】とノエルにだけ聞こえる程度の声量でそう囁くと、そのままこちらの前へ出ようと動く。
大丈夫なのかと一瞬思うが、【NAME】も己がキヴェンティという者達について疎いことは自覚している。ならば、彼等と争い、そしてその過程で様々な情報を仕入れているであろうノクトワイが前面に出て交渉する方が自然かと、【NAME】は素直に位置を譲る。
【NAME】の動きに、ノクトワイは手振りだけで【NAME】に一礼。
「我は、何者かと問うている」
そこへ響く再度の問いに、ノクトワイは口元に余裕を持たせたまま軽く咳払いを挟むと、
「失礼。アタシはアラセマ陸軍第十二師団第二兵士団長。第二級貴族ノクトワイ・キーマ・フハール。アナタに判りやすく説明するなら、そこの森を隔てた反対側に陣張ってる連中の大将よ。わざわざお忍びでお邪魔させて貰ったの。出来れば人を呼ばないでいただけるとありがたいんだけど、どうかしらん? “杜人”のリゼラ・マオエ・キヴェンティ殿」
「つまり、我等と争っている“迷の民”の戦士達の長か」
「そうなるわねん」
へらへらと笑って告げるノクトワイ。それを見て少年の表情が呆れの混じったものへと変わる。
「確かに、お前達の陣に近づいた我の民から伝え聞いた容姿と一致するが──そのような立場にある身で、我等が陣の奥までよくものこのこと」
「ま、長つっても士団長程度だからそんな大したもんでもないんだけど、でもアナタ達の当面の敵将であるってのは確かかな。──んで、どうかしら。ちょっとお話したいんだけどね。勿論、タダって訳じゃないわ。ヴィタメール奪還部隊の布陣と今後の大まかな作戦方針。この辺のこと、先に教えてあげるわ」
「ノ、ノクトワイ様!?」
その言葉に慌てたのはノエルだ。珍しく上ずった声をあげる。彼の言葉の内容を考えればそれも当然だが、しかしノクトワイはというといつものへらへらとした調子で、
「やっぱほら、提案した方から手札を開くのが礼儀だしねー」
などと暢気な台詞を吐く。
【NAME】はそんな男の様子に軽い溜息を溢して一拍。そしてリゼラの反応を窺うように視線を正面へと戻すと、座してこちらを眺める少年の口元が小さく緩み、そこから軽く息が漏れるのが見えた。
「──良かろう」
そう呟いた少年が浮かべる表情。それは僅かな、ほんの僅かな笑みだ。
「その愚かさ加減が気に入った。聞くだけは聞いてやる」
続く言葉を聞いたノクトワイは、浅い安堵の吐息。
「そりゃ助かるわ。んじゃ、提案したのはこっちだし、先にウチらの配置について話しとくけど──」
「不要だ」
「……は?」
疑問の声と共に片眉を寄せたノクトワイに、少年は淡々と言葉を継ぐ。
「不要だと云った。我はお前の愚かさが気に入ったと、そう告げた筈だ。お前の齎す情報などどうでも良い──それより、お前の後ろに居る者達は何者か。お前の従者か」
リゼラの視線が、ノクトワイの斜め後ろへと流れた。それに気付いたノクトワイは小さく頭を振ると、軽い調子で声を出す。
「んにゃ。アナタもご存知の“女賢者”、レェア・ガナッシュの親族さんと、その付き添いね。そこのちっこい子が親族さん」
問うようなリゼラの視線を、所詮は雇われの冒険者であり名乗る程でもないと【NAME】が無言で受け流したのに対し、ノエルの方はほんの僅か動きを止めた後、リゼラに深々と御辞儀。
「ノエル・ガナッシュと申します」
「────」
と。そこで顔を上げたノエルが、リゼラが睨むように自分を見ているのに気付いて、僅かに身体を強張らせる。
ノクトワイより伝え聞いた年齢からは不相応とも云える鋭い眼光を更に鋭角なものにして、まるで何かを見定めるようにノエルを見るリゼラ。
(何、だ?)
【NAME】は少年が何に気を取られているのか理解できず、内心首を傾げる。
衣服? 容姿? 武器?
それとも、こちらが気付かない全く別の──。
「……あの、どうかしましたか?」
と、そこで視線に耐え切れなくなったらしいノエルが、小さく問いの声を上げた。
その声が拍子となったのか。
少年の両眼に宿る鋭さがふと緩まる。彼は一度頭を振ると、
「いや、まあ良い。──して、何用だ。用件を告げよ」
云って、リゼラは視線をノエルからノクトワイへと戻した。硬い表情でノエルを凝視していた少年の様子を、訝しげな顔で眺めていたノクトワイは、彼の言葉に数度瞬きしてた後、気を取り直して話し出す。
「ああ、まぁ、先刻も云ったけど、ちとアナタに聞きたい事があってね。それを直接訊ねにきたってだけ。ホントそれだけなのよ」
そう前置きして一息。
「“女賢者”レェア・ガナッシュやアナタ、主氏族マオエの若長であるリゼラ・マオエが、何故こんな事をしているのか。ただそれを訊ねに来たのよん」
言葉に、少年は呆れ混じりの苦笑。
「奇妙な話だな。同じ“迷の民”であるアレではなく、キヴェンティである我の元へそれを訊ねに来るか」
「だってアタシの受け持ちはこっちだったし。それにレェアちゃんがいるって話のノイハウスはまだ遺跡の周辺にすら近づけないのよ。遺跡の持ってた“現創”の力だか何だかしらないけど、それのせいで大草原あたりで完全に足止め喰らっちゃっててねー」
気楽な調子で話しながら、己の口髭を指で摘むとくるくると廻してみせる。
「それに、アナタとも少し話してみたかったし。今回のこの事件、アナタが四主氏族の長老達からの指示ではなくて、完全にアナタの独断で、配下の従氏族を率いて動いてるって、そういう噂があってね」
「…………」
「正確には、主氏族の各長老達は“迷の民”である女賢者から齎された話を無視し、切り捨て、彼女に手を貸さぬよう下々の長に指示した。それにアナタは堂々と反対し、己が扱える権限を最大限に使って女賢者に力を貸している──ていう、そんな話。それをね、ホントかどうか確かめておきたかったの。ま、殆ど確定情報なんだけど、直接アナタの口からの話も聞いておきたいかなってね。それに、一番カンジンなとこだけまだはっきりしていないのよ」
そこでノクトワイは髭を摘んでいた指を離す。
「“女賢者”レェア・ガナッシュは──アナタ達キヴェンティの長達にいったい何を話し、何をする為にアナタ達に協力を求めたのか。彼女がこういう事件を起さざるを得なかったその背景。それを教えて欲しいのよ」
暫しの沈黙を置いて、座していた少年はゆっくりと口を開いた。
「それを聞いて何とするか、“迷の民”の男よ」
少年の言葉に、男はふと詰めていた力を抜いて、返答。
「ただ、知っておきたいのよ、色々と。アナタには関係ない話だけど、アタシは記録係だから。そのためにこの島にいるの。この島で起きる事、起きた事。それを知るためにね」
「…………」
「レェア・ガナッシュ。彼女がアナタ達に何を話したのか、それを教えてくれるだけでいいのよ。アナタだってレェアちゃんから直接話を聞いてるんでしょう?」
「アレがお前達にその話をしなかったのなら、我の口から伝えてやる義理もあるまいな。──だが」
「だが、何?」
「アレが何故、自らと同じ故郷を持つお前達にあの話を伝えず、我らキヴェンティにのみに聞かせ、助力を求めたか。その理を解せば自ずと事の断片も掴めよう」
少年の言葉にノクトワイとノエルは同時に視線を彷徨わせ、数秒。
「──つまり、わたし達常駐軍の人間に彼女が自身の考えを話した場合、何らかの問題、もしくは彼女が行おうとしている事に対して障害となりうる。そうレェアは判断したという事でしょうか」
呟くノエルに【NAME】は無言で頷き、ノクトワイはおどけた調子で肩を竦めた。
「……んー、そうなるかしら。あらあら、信用されてないのねん、アタシ達って」
リゼラはそんな【NAME】達の様子など構いもせず、視線を僅か外し、どこか遠くを眺めるよう目を細めて言葉を続けた。
「アレが我に示した話はお前達には到底信じられぬ類の、いわば世迷言だ。だが我らは地の脈より連なる翆なる方から、この“古戦場”の守護を託された身。たとえアレが“迷の民”だとしても、彼女が齎した話にたった一片でも真実があるというなら、我は──いや、我らはアレに力を貸さねばならぬ筈。我は翆獣の僕として最善とする道を選んだだけだ」
「だから。その世迷言とやらの詳細を教えてもらえると助かるんだけど」
呆れと苛立ちが半々に混じったノクトワイの声に、少年は皮肉気に口端を歪めてみせる。
「先程云ったであろう。我の口から伝えてやる義理もないとな。手掛かりはくれてやった。これ以上話す気はない」
そんな会話の終了を示す少年の言葉に、ノエルが細い眉を顰めて小さく呻く。
「ですが、これでは……このような話では」
何の役にも立たない。そう続く筈のノエルの言葉は、少年の動きによって途切れた。
「──さて」
声と共に、今まで木製の床に座していた少年が、流水を思わせる滑らかな動きで音も無く立ち上がる。そして【NAME】達を真っ直ぐに見据えると、浅く口元を釣り上げこう呟いた。
「話はこれで終わりだ。では、我は敵であるお前達を排除する事としようか」
――焔たるは九継――
少年が言葉を放つと同時。大天幕の中に漂っていた気配が、ぴんと張り詰めたものへと変わる。
「あら。結局やるってのん?」
ノクトワイの眼がすっと細まる。腰に下げた片手半剣の柄に手をやる動きに合わせて、かちりと鍔が硬い音を立てた。
「色々疲れるし、出来れば今日はやり合いたくは無いんだけど」
声音だけはふざけた調子の男の問いに、険しい目つきの少年は僅かな動作で首を浅く振り、
「そうも行くまい」
呟いて、リゼラは横の台座に置かれていた二本の長剣の内、より鞘の長い一本を手に取る。
「アレには恩もある故、義理は果たさねばな。アレの身内というそこの者は兎も角──」
子供のものとは到底思えぬ、無機物さえ貫くような鋭い視線が【NAME】とノエルへと一瞬流れ、そしてノクトワイへと戻る。
「我等と争う小さき集いの長。その役を務めるというお前を捕え、それを謀の素として使えば、アレの猶予となる時間もそれなりに稼げよう。些細なものとはいえ、土産話はしてやった。それを持ち帰ることができるかどうかは、お前達次第だ」
少年が軽く右手を振るう。と同時に、その袖の内より細い糸のようなものがするりと宙を泳ぎ出た。
「いでませい、我が孔より生まれし翆の顕『九継』よ」
緋色の糸はリゼラと【NAME】達の丁度中間にあたる位置をゆらりゆらりと漂うと、少年が紡いだ言葉が空間に染み込むと同時にその姿を変化。一瞬きする間に、細く短い糸屑は九つの頭を持つ巨大な炎蛇へと化けた。
炎纏う鱗を具えたその蛇達はそれぞれ大熊の腕程の太さがあり、熱く猛る十八の眼が【NAME】達を強く威圧する。宙をうねる蛇から発せられる力の波動は、今まで相対してきた翆霊達の比では無い。
「翆霊? でも、これは──」
ノエルが彼女らしからぬ揺れた声音で呻く。だがそれも無理はない。眼前に浮ぶその蛇は翆霊の常識を超えていた。【NAME】も宙を浮ぶその威容に気圧され、我知らず後ろへと下がる。
「……流石。キヴェンティの戦頭ともされる主氏族マオエの若長。噂通り、遣う翆霊も並じゃないわね」
口髭の男は不敵に笑うと、自身の剣の柄に置いていた手に力を込め、そして残った手を鞘の腹へと添えて僅かに腰を落した。
その仕草に、九頭の蛇が放つ強い気配に圧倒されていた【NAME】も慌てて己の武器に手を掛けた。
同時に蛇の気配が動き、そして少年も動く。
「──では覚悟せよ、“迷の民”の戦士よ」
[BossMonster Encountered!]
battle
主氏族の若長


「あ~、ったくも~」
轟炎を纏う蛇が、豪快な動きで【NAME】達の目前に迫る。鋭く立てられた無数の牙。【NAME】がそれを避けようと動くのを制する様に、ノクトワイが気だるげな仕草で一歩前に出る。
「ったくだるいわぁ。なんでアタシがこんなに頑張んなきゃだめなのかしら」
投げやりな台詞と共に彼の右腕が数度瞬き、鋭く大気を裂いた。走る右腕の動きに沿って煌く銀閃が、リゼラの操る炎の蛇の頭を二つ程切り飛ばす。首から離れた頭は地に落ちる前に爆ぜて、中空に赤い飛沫となって消えていった。
「……ふむ。我の『九継』を退けるか」
それを眺め、リゼラは幼い顔に年齢不相応な感情の薄い笑みを浮かべる。対し、ノクトワイは不敵とも取れる表情で軽く己の髭をなでてみせた。
「フフン。ま、あれよ、アンタ達の“翆霊”を相手にすんのは結構慣れてるからね、アタシ。そう簡単にゃ、遅れはとらないわよん」
「の、ようだな」
挑発とも取れるノクトワイの言葉。しかし幼き若長は軽く苦笑するだけでそれを受け流す。
「──だが、そろそろ潮時であろう。今の騒ぎを聞きつけて外の者達が動き出す頃だ。それに、我の翆霊もこれで終わりではない」
リゼラがゆっくりと手をあげると同時に、幾つかの頭を飛ばされ力を失っていた筈の翆霊が、一瞬にしてその欠けた頭部を再生させた。
「な……」
思わず呻き、舌打ちする【NAME】。これではキリがない。
そんな【NAME】達の様子を一瞥し、そしてリゼラは表情も変えず短く問う。
「さぁ、どうする“迷の民”よ。まだ続けるか? それともここで剣を捨てて大人しく囚われるか?」
その問いかけに、ノクトワイはただ小さく肩を竦めた。
「どうするって、決まってるじゃない。もう用事は終わったから、さっさと帰らせていただくわん。──ほい、じゃじゃーん」
気の抜ける擬音を呟きつつノクトワイが懐から取り出したのは、無数の石つぶて。石の表面には微細な凹凸があり、それに沿って複数の染料が塗りこまれて殆ど斑に近い。
ノクトワイはまるで手品師のように己の指の間に石をそれぞれ挟み込むと、にんまりとした笑みを浮べ、
「それじゃ、いってみましょー」
軽い声と共に、その石を纏めて投げつけた。
『瞬く満ちて、瞬く光れ。総て切り裂く白となれ』
男が文句を紡ぐと同時。放り投げられた石の塊から強烈な閃光が走り、天幕内を包む闇を切り裂いた。発光の印章石だ。
「──ッ、目くらましか!?」
そう叫ぶリゼラの姿も、弾けた光に包まれて殆ど見えない。と、動きを止めた【NAME】の腕を誰かが引く。薄目を開けてそちらを見れば、既に天幕の外へと走り出しかけたノクトワイの姿が映る。
「ほら、アナタ達も! この隙に逃げるわよ!!」
――暗躍の翳――
キヴェンティの野営地を囲む森を南へと走るノクトワイとノエル、そして【NAME】。遠く後方、北の方角には喧騒がある。自陣に忍び込んできた賊──【NAME】達を探すキヴェンティ達が互いに掛ける声の重奏だ。
背後の騒ぎからはある程度の距離が開いたことを確認して、先行していたノクトワイが漸く足を緩める。
それに合わせて【NAME】と、そして少し遅れていたノエルも走から歩へ。
「はぁ~~、なんとか撒いたわねぇ──と、みんな大丈夫?」
振り返り、【NAME】達が近づいてくるのを待っていたノクトワイは、【NAME】の背中でやや顔を伏せて歩く少女を見て、ふむと一息。
「浮かない顔ねぇ」
その言葉が己に向けてのものと気付いたノエルは、視線を下へと向けたまま、ゆるりと首を横へ振った。
「わたし達の目的はレェアの事情を知り、そして和解の手掛かりとなる情報を探ることです。ですが、リゼラ・マオエの語った内容では、到底──」
そこまで呟いて言葉を切ったノエルに釣られて、【NAME】も浅く溜息をつく。
確かにノエルの云うとおり、あのマオエの若長が語った話は至極曖昧なもので、交渉の材料に使えるようなものではない。たとえイェア・ガナッシュに一語一句間違いなく伝えたとしても、大して彼女の役には立たない事は明白だった。
やる前からある程度は予想できた事だが、今回の件はリスクの割には──全く、見返りが少ないとしか言いようが無い。
そんな【NAME】達の様子を眺め、ノクトワイは気を抜いた軽い声を上げた。
「ま、あんませかせかやっても仕方ないわよ。それに──和解なんて無理よ多分」
「どうして、そう思われるのですか?」
疑問符を乗せたノエルの声に、ノクトワイは小さく肩を竦める。
「どうしてもなにも。話し合いで済むようなら今こんなことになってないわ。先生ちゃんって頭良い割にアマイからこんなことをアナタ達に頼んでるけど、本人だって本当は無理なことくらい判ってる筈よ。アナタだって、そうでしょ?」
ノクトワイの視線に促され、【NAME】は暫し迷った後、頷く。イェアには悪いが、キヴェンティにまで協力を仰いでここまで派手に軍とやりあってしまっているこの状況から、平和的な解決を望むというのは些か無理がある。万が一成立したとしても遺恨は深く残る事となり、それが後の争いの火種となりうるのは容易に想像できる。そしてその状況がイェアの望むものとは到底思えなかった。
ノエルはノクトワイと【NAME】の表情を交互に見やり、僅かに押し黙ったあと、言葉を紡ぐ。
「では──それでは、どうしてイェアはわたし達に」
「判っていても、手は打っておきたいんでしょ。自身が望むコト、願うコトが到底叶わないものと薄々判っていても、ほんの僅かでも可能性があるなら、それを捨てずにいたい。そんなトコじゃないかしらね。──ほら、あの“コロちゃん”倒した冒険者とかなら、やっぱ期待しちゃうじゃない?」
茶目っ気たっぷりに片目を瞑ってみせる口髭の男に、【NAME】は小さく苦笑してから──そして突っ込む。だから“コロちゃん”って何と。
「ああほら、“殺すことのできない獣”だから、頭文字二つ取ってきて“コロちゃん”よ。どう? 可愛いっしょ?」
「…………」
あの常識外の化け物を“コロちゃん”と呼べるのは、やはり直にアレとやりあってないからだろうな、と【NAME】は引きつった笑みを返す以外になかった。
・
そこで言葉は途切れて、【NAME】達はそのまま黙々と森を歩み続け、数分。
「っと、見えたわ」
ノクトワイの声に視線を上げれば、森の遠くに拓けた細い線。ティネとノスキスとを結ぶユウベルの街道が見えた。ここまで来れば一先ずは安全と、【NAME】は漸く一息つく。
と、僅かに遅れてついてきていたノエルが追いつき、【NAME】の横に立った。彼女はこちらに背を向けて少し前方に立つノクトワイの方を見上げ、小さく口を開く。
「ノクトワイ様はこれからどうされるおつもりですか?」
街道の走る方角を眺めていたノクトワイは振り返り、視線を問うてきたノエルに移してとんとんと、軽く己の肩を叩いた後。
「んー、アタシはそろそろ部隊の陣に戻らせてもらうわ。“女賢者”殿のほうはともかく“杜人”クンの考えは何となく判ったし」
その言葉に、【NAME】は目を瞬かせる。ノクトワイは、たったあれだけの話でリゼラの考えが掴めたのだろうか。見れば、隣に立っていたノエルも、表情は変わらないまでも僅かに目を見開いてノクトワイを見上げていた。
【NAME】とノエルの様子を順々に眺めてその心中を察したのか、ノクトワイは言葉を続けた。
「そりゃ詳しいトコまではわかんないけどね。でもま、アタシらアラセマからの移民を狙った悪巧みってなコト考えてるわけじゃなさそうだし、それが判ればまぁいいわってトコで。アタシはアタシで、のんびりと調べさせてもらうわ。アナタ達は先生ちゃんのトコに一旦戻るんでしょ?」
無言のまま【NAME】は頷く。役に立ちそうに無いとはいえ、取り敢えず雇い主に結果を報告する義務はあるだろう。
そう告げた【NAME】にノクトワイは一つ頷き、
「そ。じゃ、気ーつけてね。またどこかで会えたなら──いえ、きっと会うでしょうね。その時はま、宜しくねん」
ひらりと手を振り、男は去っていく。ノエルがその背に向けて一礼すると、
「ノクトワイ様。今日は本当に、ありがとうございました」
掛けられた少女の言葉に男は振り向かず、ただもう一度だけ手を振って、そしてそのまま街道の向こうへと消えていった。
ノクトワイの姿が完全に失せるのを見届けてから、【NAME】はふと息をつき、何気なく空を見上げる。既に空からは夜の気配が去り始めており、東の果てには日の登りを示す白光の色が見える。長い一夜が漸く終わろうとしていた。
(結局……今回の事は)
自問。その答えは明確だった。【NAME】は再度、疲れの混じった吐息を吐き出す。
「【NAME】。わたし達も参りましょう」
その声に我に返れば、ノエルが色の薄い顔をこちらへと向けている。
(うじうじしていても仕方が無い、か)
兎に角、次の指示を仰ぐためにイェア・ガナッシュの元へと戻る必要がある。
【NAME】は彼女に了解の頷きを一つ返すと、街道を西へと歩き出した。
・
森の彼方に上る太陽を眺めつつ、配下の者達の報告を聞いていたリゼラ・マオエ・キヴェンティは、彼らの報告全てを聞き終えてから、一拍。視線を東の空から、自身を囲む戦士達に移す。
「つまりは、逃がした──ということか」
リゼラの呟きに返る言葉は無く、キヴェンティの戦士達はただ深々と頭を垂れるのみ。リゼラは暫し無言のまま彼らを眺めた後。
「ご苦労だった。夜番の者は休ませよ。他の者達は常の仕事に戻れ。朝餉の後、夜の配置について話し合う故、頭の者は我の天幕へ来い」
リゼラが告げると、彼の周囲に集まっていた者達は再度深く身を折った後、それぞれの役目を果たす為に散っていく。そんな彼らを見送ってから、リゼラは一人、自身の天幕へ戻るために歩き始め──。
「そろそろ、姿を現したらどうだ」
立ち止まり、視線は虚空へと向けたまま、声を僅かに後方に建つ天幕と天幕の狭間──何も無い薄闇の内へと飛ばす。すると、そのぼんやりとした闇が不意にゆらりと揺れて、そこから人の気配が一つ、唐突に生まれ落ちた。
「こりゃどうも。バレておりましたかな」
生まれた気配からは、少し擦れの混じった男の声が響いた。しかし、その伝わりは周囲の空間を介したものではなく、直接耳に響くような、そんな感触を持った声だ。
リゼラはそちらへ顔を向ける事無く、ただ淡々と呟きの声だけを気配へと飛ばす。
「無論だ。上手く概念を偽装していたようだが、それを行う為の理の流れを消すことはできまい。それに先刻、我の天幕の裏にまで来ておったであろう。あそこまで近づかれては、気付くなという方が難しい」
そこで少年は言葉を切ると、浅く嘆息。そして僅かに怒を混ぜた声を放つ。
「──全く、半端に留まりおって。お陰で、あの者達に隙を見せたわ」
少年の言葉に、天幕の狭間にある気配が僅かな笑みの動きで揺らいだ。
「いやはや。ワタクシとしても、そのまま天幕の内にいる貴方に会いに行くつもりだったのですが──ほら、予想外のお客様がいらっしゃっておりましたのでね。ですので、まずは彼らに順番をお譲りして、お引取りになられるのを待ってから、またこうしてお話にと参った次第で」
そこで気配は言葉を切ると、少年の反応を窺うように待つ。だが、少年が背を向けたまま微動だにしないのを見届けてから、改めて声ならぬ声を伝える。
「ふむ。では一応名乗りましょうかね。“女賢者”レェア・ガナッシュの後任としてアラセマ陸軍第十二師団の準軍師としてこの島へと参りました、イルギジド・マイゼルと申します。以後お見知りおきを、リゼラ・マオエ・キヴェンティ殿」
「……意外だな。先刻の者達と同じ口か。あの者達は、お前ほど歪なカタチはしていなかったが」
「さぁて、どうでしょうかね? 確かに、同じ組織に属していることは確かですが」
くく、と喉を鳴らすように笑い、少し間をあけた後。気配は僅かに纏う色を変えて、どこか挑むような、反応を窺うような調子で話し出す。
「ヴィタメール遺跡の方、見させていただきましたよ。──いやはや、驚きました。まさか既にキヴェンティが秘儀、翆脈顕現[ヴォルベィズ]による遺跡破壊の準備に入っていたとは」
「──我らの結界を抜いたか、お前」
呟かれたリゼラの声は堅い。微細な驚きと、そして緊張に染まった少年の声は鋭く走り、対して暗がりに潜む何かからは慌てたような気配が返る。
「とと、勘違いなされぬよう。儀式のお邪魔などしておりませんよ。少なくとも、今回はね」
「…………」
囁かれる言葉に、少年は無言。しかしその手は腰に提げた長剣の柄へと廻された。
だが気配はそんな彼の仕草を気にした風も無く、話を続ける。
「しかし、これは困るのですよねぇ。今のワタクシの主は、あの遺跡が持つという力に興味を持たれているわけでして、それを壊されてしまうのは、いやはや全く、困りますなぁ」
はは、と笑う気配に、少年は両眼を閉じて一つ息をつく。
「去るがいい、“迷の民”の術士よ。ヴィタメールの遺跡はお前達には渡さん。我等が力を以って、必ず跡形も無く消してやる。いいか、必ずだ」
そして静かな中に強い力を込めて、少年は言葉を放つ。だが、気配から漂う笑いの色が更に強くなるだけだ。
「はは。いやはや、良い啖呵ですな。美しい」
漂う気配は、どこか茶化すような調子で一頻り笑い、
「ですが、なるほどなるほど。フローリアの護り手を自認する貴方がたキヴェンティが、それ程に力を入れて動くとなると、やはり“四大遺跡”の力の源はアレですか? 鬼芯の欠片たる大──」
「黙れ」
──斜、と。
気配が続けようとした言葉。それすらも切り裂くように、長剣の柄に添えられていた少年の腕が閃き、鋭い銀光が飛んだ。
鞘より跳ねた一閃は正に神速。天幕の狭間に漂う気配を、瞬く間も置かずに両断──する寸前。
「──っと」
気配が揺らぎ、瞬時に位置を天幕の狭間からその斜め上方、脇に建つ天幕の上へと移した。
「はは、危ない危ない」
同時に響いた声は先刻までとは違い、明らかな肉声だ。天幕の上へと移った気配は、既に単なる気配ではなく、確固たる人の身を持った存在となってそこに居た。
姿を顕にした気配の主は、濃い色に染まった長衣に身を包む痩身の男だ。年の頃は四十を過ぎた程度で、背は低い。彼は右の脇に大棒杖を挟んだまま、己の左腕を眺めてひらひらと具合を確かめるように腕を振っている。その動きに合わせて揺れる袖には、縦の切れ筋が一線。
「いやはや、流石ですなぁ、リゼラ・マオエ・キヴェンティ殿。袖をちょっとばかり持っていかれましたよ」
そこで初めて、少年の眼光が後方の天幕上に立つ男へと向けられる。リゼラは強く鋭い、正に刺すような視線で男を睨みつけ、そして告げる。
「次は加減せん。去ねよ、術士」
強い威圧を込めた言葉。しかし、男は口端を一度釣り上げて笑い、それをするりと受け流した。
「ははぁ、いやはや。了解しましたよ。ワタクシが見たところ、翆脈顕現の準備はまだまだ掛かるようですし、今日のところは一先ず退散いたしましょう。何れまた──ええ、何れまたお会いすることとなるでしょうが、それまでどうか、健やかに過ごされますよう」
そして、瞬きもせぬ間に消える気配と姿。余韻は無く、既に天幕の上に何かが存在したという痕跡も微塵も無い。
「…………」
それを無言で見送った後、リゼラ・マオエは浅く息をつくと首を左右に振り、そして視線を空へと向けた。
「まさか、あれ程の者が居るとはな。──気付いているのか、レェア。己の道行きの、危うさに」
四大遺跡 芯なる遺産
――芯なる遺産――
ガレー遺跡を包む軍駐屯地の一棟。“四大遺跡”の一つであるガレー調査団の長である学士、イェア・ガナッシュの居室であるそこへと足を運んだ【NAME】とノエルは、ヴィタメールでの顛末を部屋の主に話した。口を開くのは主にノエルで、【NAME】はその補足を少々。とはいえ、ノエルの説明は些細な事でも省かずに話すため、補いが必要な場面など殆ど無かったが。
長々とした話を終え、ノエルが無表情のまま細く息を吐く。それを見届けてから、部屋中央の椅子に座してノエルの報告を黙ってきていたイェアは、軽く首をかしげてみせて、
「確かに、些か心許ない内容ではありますわね」
云って、くすくすと笑う。自身でも感じていた事を直接的に告げられて、ノエルは僅かに顔を伏せて小さくなり、【NAME】も肩を竦めて薄く苦笑した。
そんな【NAME】達の様子に、イェアは僅かに慌ててみせた。
「──ああ、御免なさい。あなた達に落ち度があったという訳ではありませんから、お気になさらないでくださいな」
明らかに繕いと判る言葉に、【NAME】は苦笑を深くする。無茶な依頼であったとはいえ、受けたからには相応の結果を残せなければ冒険者としては失格だろう。
だが、イェアは【NAME】の表情を解く為に、ゆっくりと間を置いて首を左右へと振った。
「勘違いしていただいては困りますわ。ちゃんと有益と思われる情報はありますもの。リゼラ・マオエが己の属するキヴェンティという部族の間で“四大遺跡”に固執せねばならない何らかの理由。それも、恐らくは彼らの底に根づく宗教的な部分に由来する理由がある、ということなのでしょうね。──尤も、それが何なのかが判らないのですけれど」
ふ、と息を吐いて背を椅子に預けるイェアを、【NAME】は若干意外な心持ちで眺める。
確か、ヴィタメールに展開している常駐軍部隊を束ねていたノクトワイ・キーマ・フハールは、リゼラ・マオエが持つ理由について取り敢えずの見当はついていると云っていた。が、単なる騎士でしかないノクトワイには判り、知識の探求を主とする学士である彼女には判らないと云うのはどうなのか。偏見にも近い考えではあるが、単に意外だと思う事に罪はあるまい。
と、そんな【NAME】の視線に気付いたのか、イェアは恥かしげに肩を竦めると小さく笑う。
「わたくし達のような人種は、自身の専門分野以外の事、特に噂話やそういう類のものには結構疎くなっちゃうものなんですの。それに、あの人はあれで結構博識といいますか、色々な事情に通じている方ですから」
云われて、【NAME】はヴィタメールで会ったノクトワイの様々な言葉を思い起こす。確かに、頷ける点も多いように思えた。というより、リゼラの思惑などより寧ろ、あの奇妙極まりない男の素性の方が気になった。
(もう一度会えたら、色々と問い詰めてみるのも良いか……?)
そんな【NAME】の思考には気付かず、イェアは両眼を閉じて天井を仰ぐと、目元を二つの指で解しながら細く上へと溜息を吐いた。
「わたくしの方でもキヴェンティ達の習慣や伝承、このあたりを洗ってみますが──宗教的な事が絡んでくるとなると、それを理で持って翻意させるというのは正直難しいでしょう。……リゼラ・マオエに対するアプローチは一先ず保留とした方が良いでしょうね」
結局、結論はそうなるか。三人は互いに顔を見合わせ、改めて溜息をついた。
・
「【NAME】さん。引き続き、お仕事のほうお願いして宜しいでしょうか?」
と、イェアが切り出したのは、長い長い沈黙を置いた後の事だった。
【NAME】は内心小さく嘆息。前回のヴィタメールでの騒動を考えれば、また色々と面倒な事になりそうな気がする。
(……だが)
ここまで付き合っておいて途中で放り出すのは無責任──というほどでもないが、決まりが悪いのも確かだ。
【NAME】は暫しの間を置いて、縦の頷きで返答した。
対し、イェアは僅かに安堵の表情を浮かべて、そして直ぐに引き締め、言葉を続ける。
「既に予想はされているでしょうが、次の目的地はノイハウス。アノーレが誇る“四大遺跡”の一つ、ノイハウス遺跡です。そこは恐らく姉が──レェア・ガナッシュが居る筈ですわ。あなたにはそこへ向かい、彼女が事を起した理由と、最終的な目的を探ってきていただきたいの」
(ノイハウス遺跡、か)
どの辺りにあったか、と【NAME】は己の記憶を漁る。ガレー遺跡はポロサの北、ヴィタメール遺跡はティネとノスキスの狭間に広がる森の中、そして既に消滅したとされるゴディバ遺跡は今は往来を禁じられているアノーレ北部に在ったという事だが、確かノイハウスは──。
(……どこだったかな?)
眉根を寄せて、かくり、と首を傾げた【NAME】を見て、イェアは僅かに笑みを浮かべる。
「ノイハウス遺跡はですね。ティネの村の北方に広がる“大草原”を抜けた先にありますの。ですけど、キヴェンティ達が遺跡周囲に陣を張って防衛しているだけのヴィタメール遺跡とは違って、ノイハウスは姉が何らかの技を用いて遺跡の力を駆動させているそうでして、遺跡占領側の部隊の殆どは──遺跡の力で生み出された亜獣の群れで構成されていますの」
(亜獣の……部隊?)
【NAME】は驚きで目を見開く。
何かの勘違いではないか、とも一瞬思う。亜獣などを含めた動植物を使役する者達が相手側に居るならば、敵の部隊に亜獣の姿があってもおかしくはないからだ。だが、そういった者達が使役できる数はたかがしれている。部隊を構成できる数の亜獣、というのは流石に異常か、と思い直す。
動きを止めた【NAME】に、イェアは小さい頷きを挟んで話を続ける。
「この亜獣達のことについては、前々から遺跡調査を行っていた者達の間で噂にはなっていたそうなんですの。ノイハウスが持つ力は“現創”──つまり、亜獣といった本来の自然体系から多少なり逸脱した存在を、現実に創造する力だと。……亜獣を生み出し、それを自在に操るなんて、とても──そう、とても危険なもの。姉はあの力が軍の手に落ちるのを恐れたんじゃないかって、わたくしは考えておりますの」
イェアは疲れたような息を吐いた。
(だが、本人が好き勝手に使っていては世話ない)
【NAME】は皮肉げに笑った。
と、その間を見計らったように、隣の席に座っていたノエルが小さく、肩上程度の高さに掌をあげる。
「イェア、一つ宜しいでしょうか?」
? と疑問符を乗せてイェアが見ると、ノエルは掌をあげたまま、抑揚のない声で続けた。
「レェアとの対面を──いえ、ノイハウスへの潜入を容易なものとする為の何らかの手順、もしくは計画のようなものは立てていらっしゃるのでしょうか。僭越ながら言わせていただきますと、前回のようなお粗末極まりない計画と同水準のものでしたなら、今回は依頼自体を取り下げるべきだ、とわたしは考えます」
「……ひど」
「イェア、如何でしょうか」
意思の色なくただ問うノエルに、イェアは殆ど半泣きな表情。ノエルと【NAME】を順々に見つめた後、彼女はぼそぼそと云った調子で口を開く。
「……常駐軍のほうで、ノイハウス占領組に対する大規模な侵攻作戦が近々行われると聞いています。何でも、師団副団長自らが部隊を率いて大草原に展開された“現創”の獣を討つという話になっているそうですわ。だから、それの騒ぎに乗じれば、上手く大草原を抜けてノイハウス遺跡まで辿り着けないかな? とか」
「…………」
「…………」
「…………」
「……何か云ってくださいなぁ~」
「もう一度進言します。今回は依頼自体を取り下げるべきだと」
寒々しい色が混じったノエルの声に、あふん、といった調子でしょぼくれた表情を浮かべるイェア。
「そうは云いましても……わたくし、元々立場ある人間ではない一介の学士ですし、裏から手を廻そうにも先立つものがありませんもの。今回の侵攻作戦に協力者として【NAME】さんとノエル、あなたを裏から捻じ込むくらいがせいぜいですわ。それだって、ノクトワイ様の厚意に甘えているようなものですの。……でも、他に幾つか策を思いつかないでもありませんでしたけれど、大草原を突破するという点のみ考慮するなら、これが一番成功率が高い筈です!」
と、最後だけ勢い良く言い切ったイェアだが。
「点のみを考慮、ですか」
「そう。点のみを考慮ですわ!」
淡々としたノエルの問い返しに、何やら清々しさすら感じる程の勢いで「ですわ!」と叫んだ後。
「……だって仕様がありませんもの」
暫くの間を挟んで、イェアはがくんと首を落す。
「ノイハウス遺跡に限らず、“四大遺跡”に纏わる資料は全て姉が持ち出していて、そして主に遺跡の調査を行っていたのは、現在遺跡占領組となった姉の配下の者達と、そして姉自身ですの。なので、資料が無い以上、ノイハウス遺跡についてわたくしが知りえる情報の殆どは、伝聞によるものとガレーから得た間接的な知識だけでして。わたくし、ノイハウスの遺跡なんて直に見たこともありませんし」
なるほどね、と【NAME】は溜息混じりに小さく呟く。
つまり、細かい部分も考慮した策を練ろうにも、そうするための情報が足りない、という事らしい。
「“鳩”を飛ばして得た情報として、ノイハウス遺跡調査のために設営された駐屯地、シニが占領軍の陣に使われているくらいしか、わたくしには判りませんわ」
と、やや視線を下げて話していたイェアがそこで顔をあげ、【NAME】の方を真っ直ぐに見る。向けられた彼女の顔に浮ぶのは真剣な──謝罪と懇願の表情だった。
「こんなあやふやな情報ばかりで御免なさい。でも──お願いします、【NAME】さん。ノクトワイ様を通じて、あなたが侵攻作戦の部隊に紛れていても問題の無いよう、話を通しておいていただきますからご心配なく。あと──」
そこで言葉を切ってイェアは立ち上がると、部屋の隅に置かれていた木机の上、そこに積み置かれた山場から一つの布袋を引き抜き、【NAME】達が囲むテーブルの上へと置く。
「ヴィタメールの件での報酬と、今回の前金。合わせて2000zid、お渡しします。それで相応の準備をお済ましになられましたら、ティネの村の北に広がる『大草原』の方へ向かってください。そこの中心あたりに、常駐軍の陣がある筈ですから。ノエルもこのまま、【NAME】さんのサポートをお願い。──遺跡の奥にあなたを向かわせるのは少し不安ですけれど、多分あなたが居た方が姉も話しやすいでしょうし」
ノエルは無言のまま小さく頷き、それを見届けてからイェアは視線を【NAME】へと戻す。そしてじっと顔を見つめてから、頭を深く下げた。
「改めて……宜しくお願いします、【NAME】さん」
四大遺跡 二人の昔日
――二人の昔日――
それは彼女が幼い頃の話。
クスィークという名を持つ彼女はその日、家を逃げ出して泣いていた。
都の郊外にある緩やかな丘の頂きに、彼女の家はあった。屋敷と呼べるほどの大きさを持つその家の周囲は森が包み込んでおり、浅い風に揺れる木々の群れは、夕刻の赤い日差しを横より受けて、色濃い陰影を持って広がっていた。
その陰影の中に埋もれるように、膝を抱え込んだ少女の姿が一つ。
彼女が座るのは、森の中程に生えた樹齢数百にも及ぶ大きな樹の根元。そこが彼女の“隠れ家”だった。彼女自身が懸命に両の腕を伸ばしたとしても、到底抱え込めない太さを持った幹に背を預けたまま。クスィークはただぐずぐずと泣き続けている。
彼女の家は、従う者を生む家──より正確には、従う者を育てる家だった。家で行われる“訓練”はその為のもので、修錬内容は厳しく、礼儀から家事、武術に算術、交渉術と多岐に渡った。
養われる立場の自分にはそれを拒絶する事はできない。支えるものも無く、信じる道も無く。理由も判らぬまま“訓練”を施されて、赤の他人に囲まれて日々を過ごす。
──辛い。そう感じる。
生活自体は孤児院に居た頃よりずっと楽になった。子供達同士で行われる醜い争い、大人から振るわれる様々な暴力の形。そのようなものはカナルの家にはなく、ただ淡々と修錬が行われるだけ。なのに何故、このような陰鬱な気持ちになるのか。
「何故……?」
その理由は、何とは無く想像はついていた。
ただ“訓練”という過程だけがあり、過程の先にある目指すものが見えない。進む道は用意されていても、追い求める標が無ければ迷ってしまう。そして迷いは憂いとなり、心の底に沈殿する。
己というものの支えとなる何か。それが自分に欠けていた。
昔の生活に比べれば、と思う。だけれど、それが今の辛さを紛らわすものにはならない。大きな心痛が取り除かれれば、今まで気も止めなかった筈の小さな痛みも、己を苛む棘となる。
じっと堪えることには慣れていたが、それで痛みが消え去るというものでもない。だからこうして、偶に自分の“隠れ家”へと逃げ出して、そして気の済むまで泣く。それが彼女の習慣になっていた。
──と。
「そんな処に居たのか」
高い位置から声がして、クスィークはその時初めて、自分の眼の前に誰かが居る事に気付いた。泣き腫らしてぼやけた視線を上げると、そこには一頭の馬の姿。こちらを覗きこむようにしていたのか、視界が馬の顔で埋まる。
「!?」
素直に驚くクスィークの頬を、長い顔の先端となる鼻先が突き、そのお陰で馬の顔に隠れていた人影が見えた。
「探したぞ。お前がカナルの養い子か?」
少年の声に頷きつつも、クスィークは混乱した視線を馬上へと投げかける。
声の主は馬上の人。夕の日差しに染まったその人物はどうやら自分とそう年齢も変わらない少年だった。孤児院に居た頃には到底お目にかかれなかったような装飾の多い衣服を着込み、腰には小剣を差しているが子供の体躯ではそれも立派な長剣にも見える。
問いたくても声がでない、そんなクスィークの様子に気付いたのか、少年は未だにつんつんとクスィークの頬を突く馬の手綱を引いて収めると。
「僕はカナード。カナード・フハール。父様が言うには、僕は将来、お前の主になるらしい」
そう言った。
呆気に取られ、クスィークはぽかんと少年を見る。しかし彼はクスィークの疑問の意思など気にした様子も無く、どこか困ったような表情で言葉を続けた。
「立てるのか、お前。何を泣いている?」
言われて、え、と自分の頬に手を当てた。既に先刻の驚きで涙など止まっていたが、しかし拭う事もせずに放置していたため、まだ瞳には涙が溜まっている。
「兎に角、立てよ、みっともない。あと、泣くな」
もう泣いている訳ではない。そう言いたいのだが、派手に声をあげていたため喉の具合もおかしく、しゃくりあげるような動きしかしない。
取り敢えず立ち上がってみるもそれは止まらず、替わりに瞳に溜まっていた涙の残りがまた零れる。それをみて、少年は困ったような声を上げた。
「泣くなといってるだろ。──仕方ないな」
そう言って少年は溜息一つ。馬から身軽な動作で降りてクスィークの眼の前に立った彼は、片手は手綱にやったまま、もう一方の手で乱暴にクスィークの頬の涙を拭い、握った拳の先で額を小突いた。
「判るか。お前は僕の付き人になるんだから。だから、泣くなよ。これは命令だ」
確かに、泣いていても仕方が無い。
こくこくと、ひくつく喉を押さえながらクスィークは頷く。その様子に、少年は再度溜息をついた。
「ったく……そもそもお前、何で泣いてる?」
そういえば、何故泣いていたのか。今日のきっかけは確か、修錬での些細な失敗だった気がする。その事をクスィークは素直に話した。誰かと普通に話をするなんて、カナルの家に来てから初めてだと、そんな事を思いながら。
枯れた声で紡がれる拙い話を聞いて、少年は僅かに眉根を寄せつつも、しかしうんと頷いた。
「そうか。なら、僕が教えてやる。……そうだな、ピアノとか宮廷の事とか。最近は剣だってやっている。だからもう泣くな。ほら、返事をしろ」
“修錬”についての詳しい話はしなかったため、返って来た言葉は僅かに的外れのもの。
だが、少年の不器用な言葉から伝わってくる彼の意思はしっかりと受け取れた。言葉だけの、カナルの家にいる養父や指導士官達と違って。
クスィークは涙の跡の残った頬を拭うと、改めて顔をあげ、枯れた声を絞った。
「──はい」
自分の言葉に、少年の顔に純粋な笑みが浮ぶ。
「よし、いい子だ。後……お前、名前は?」
問われて、クスィークは目を瞬かせた。カナルの家に居るという事を知っていて、名前は聞いていないなんて。
きょとんとしたクスィークの視線に、少年は拗ねたように顔を顰めた。
「悪かったな。カナルの屋敷で父様とお前の親が話しているのを立ち聞いただけだから、名前までは知らないんだよ」
そんな少年の仕草に、クスィークの顔に知らず笑みが湧いた。すると、今度は少年の方が目を瞬かせる。
「何だ。お前、ちゃんと笑えるじゃないか。で、名前」
「……クスィーク。クスィーク・カナル」
自分で呟いた家名に、酷い違和感。しかし、当然少年は全く気にした風も無く、納得するように一つ頷くだけだ。
「うん、そうか。では、これから宜しく頼む、クスィーク」
「はい。──その、ご主人様?」
そういえば、彼は自分の主人となるらしい、という事を思い出し、クスィークはそう呼んでみる。カナルの家は従者の家。自分が従う事になる人間が既に決まっていてもそう驚くことではない。
だが、その呼び方はお気に召さなかったのか、少年は眉根を寄せて小さく唸る。
「ご主人様はどうもな。あまりそういうのは好きじゃない。名前でいい。それがお前の権利だ」
「……権、利?」
「そう。三位のカナル家であるお前が、一位“六家”のフハールの人間を名で呼ぶ。これが僕の付き人となるお前の権利だ。ほら、呼んでみろ」
促され、クスィークは迷うように数度口を開いては閉じ、そしてゆっくりと。
「カナード様?」
「──様?」
「カナード……様」
言えない。堪らず、クスィークは顔を伏せた。
対する少年は眉を顰めてうーと唸ったが、一つの吐息と頷きで表情から険を抜く。
「んー、まあ今日のところはそれでいいか。──さ、乗れよ、クスィーク。カナルの屋敷に帰るぞ」
言って、さっさと少年は馬上の人となるとこちらに手を差し伸べる。だが、クスィークは困った表情でその手を眺めるしかなかった。従者であれば手綱を引いて先導するのが当然と教わった。主の馬に乗るなど到底考えられぬ話。
「お前を歩かせると日が暮れてしまう。そうなればどちらにしろ大目玉だからな、いいから乗れよ、ほら──」
「あ……」
手を掴まれ、強引に引き上げられる。鞍の後ろに座らされれば、もう降りる訳にも行かなくなった。
「よし、じゃ掴まってろ。行くぞ、マクス」
両側の鐙で腹を蹴り、手綱で馬の向きを変える。派手な動きに、クスィークは慌てて少年に掴まった。
馬は森を進む。
少女の前には、幼い彼女と殆ど変わらぬ、小さな背中。
でも、その背中と、馬上から広がる朱に染まった美しい風景。そしてまだ拙い術で馬を操る少年を掴んだ手の温もり。
それは遠い年月を経た今でも、クスィークの心の真中に根を張って残っていた。
・
結局、きっかけはそれだったのだと。クスィークはあの時の事を想う。
あとは簡単だ。幼い頃は兎に角、不器用で、何をやっても駄目で常に叱られる毎日だった。だが、それでもそれまでの自分の中に無かったもの。目標ともいえるべきものが生まれ、辛いと感じる事は無くなった。自分の前に引かれた線路の先に、あの少年が居るのだと。
その日からクスィークは、アラセマの中枢を占める六家の人間に仕える者として相応しくなろうと、カナルの家で行われていた“訓練”から様々な事を正に死に物狂いで学んだ。
自分には無理だと半ば放棄していた事も積極的に挑んでみれば、不思議と苦手であった筈のそれらも容易に克服する事ができ、結果何とか彼の従者が務まる程度には成長したという自負はあった。
──だが。
年月を経て、落ちこぼれだった自分が徐々に力をつけ始めた頃から、主人となる筈のカナードとの仲は徐々に良くない方向へと進んでいった。
理由は今でもはっきりとは判らない。
カナードと、自分。二つの歯車がどんどんと噛み合わなくなっていく事だけは理解できたが、それを正すやり方など彼女は教わらなかった。カナルの家で教わったことは、主人に心から尽くし、主の利となる事をこなすこと。それだけだった。
「その為に、ずっと、頑張ってきたのだから」
何気なく出た自身の呟きに、クスィークはふと物思いから覚めた。
息を吐き、そして見る。己の身は既に大人のもので、軍の服に身を包み、そして腰には剣が見える。広がる景色もあの時のような斜陽の森ではなく、乱雑に組み上げられた野営地の棟の廊下。進む先には、自分の主人である筈の彼がいる部屋へ通じる扉がある。
「…………」
何故、今のような拗れた関係になったのか判らない。
判らないが、でも──いや、だからこそ、たとえその人から嫌われようとも恨まれようとも、離れる気はクスィークにはなかった。
それはもう。
あの夕焼けの日に彼の背を見た時から、決めたことだから。
・
カナードは、身の内に徐々に苛立ちが募っていくのを感じていた。それはまだ己の中で明確に形にならぬ、曖昧な何かから生まれたもので、故に正体が掴めず、そのせいでより苛立ちが増す。悪循環だと思いつつも、しかし容易に払うことの出来ない不快感に、彼は一度音となる程に呼吸を大きく取り、僅かに座していた木椅子の背凭れに身を預けた。
「お疲れのようですな」
視線だけを声のした方へと投げて、掌で机上を指し、カナードは小さく鼻で笑った。
両の肘をついて掌を組み合わせ、そこに額を当てるようにして顔を伏せていた彼は、部屋脇に立つ小男へ視線だけを向ける。
彼らの居る場所はポロサ近傍に建つ常駐軍の駐屯地。アノーレにおけるアラセマ常駐軍の拠点とも言うべき建造物群のうちの一棟だ。アノーレ島に派遣された第十二師団の中で上層の立場にあるもの──より具体的に云えば、師団を束ねる長たる彼、カナード・フハールが居する場所。その棟の一室、執務室にあたる部屋に彼と小男は居た。
人払いは済ませてあり、部屋の中に他の人間の気配はない。尤もカナードは普段からあまり人を近づけぬ性分なのでわざわざ掃う必要もないとは言えた。好き好んで彼の居室に詰めようとする物好きも──何人かはいたものの、一人を除いて既に払った。彼が唯一許す付き人たるカユリ・イムカも、今は厨房の方へと向かわせてある。
「皮肉か? この机の上を見てそう取れるなら、お前の評価を改める必要があるけどな」
「これは失礼」
声の主は、短く謝罪の言葉を口にして、横に細い眼差しをカナードの掌が指し示す方へとなぞらせる。
それを追い、カナードも視線をそちらへ移した。
机の上には、何もない。使われた跡も殆どない真新しささえ漂う木机の上は、ただ平らな面が広がっているだけ。本来ならば師団長としての務めを果たすために必要なものは何一つ置かれていなかった。
──それは自身が望んだ結果であり、そして他人が望んだ結果でもあった。
自然、自嘲に顔が歪むが、それが表に出るのを押さえようとも思わなかった。今更繕う必要のある外面などありはしない。
「さて、行ってきたんだろ、ヴィタメールに。話を聞かせてくれるか。我が軍師イルギジド・マイゼル殿」
言って、カナードは扉近くに立つ小男へと視線を戻す。
イルギジドは“女賢者”が離反した後、その後を引き継ぐように一人やってきた魔術師だ。“女賢者”は遺跡の研究を主とし、軍の仕事は専門外ながらも何とか、という形でこなしていたのに対し、イルギジドは軍の仕事を主とし、遺跡関連の事柄には表向き干渉するような素振りは見せず、短期間で“女賢者”が抜けた穴を埋め、アノーレの常駐軍内での己の足場を固めていた。
そして彼は何故か自分に近づき、様々な情報を提供してきた。最初は今後フハール正家つきの魔術師にでもなりたいのかと思い、自分にそのような真似をしても無駄だと皮肉交じりに言い捨てれば、彼は違うという。
理由を問えば、
「ま、必要あってのことでしてな。師団長殿に色々と考えて行動していただけると、こちらも色々と動きやすくなりますので。その為の判断材料としての情報を提供しているだけのことでして」
そして、何故自分に近づいてきたのかをあっさりと話してきた。
腫れ物のような扱いか、自分には理解できぬ盲従か。その二つに囲まれていたカナードに取って、小男の己が利益の為に他を利用するという態度は酷く納得できるもので、素直に気に入った。
更にクスィークと犬猿の仲らしいことを聞き、カナードは更にこの男が気に入った。
自分がイルギジドと会っている事を仄めかすと、あの普段は堅い表情のままに淡々と仕事をこなす、何を考えているか全く判らない女が途端に慌てる。こちらが彼女の存在を疎むような辛辣な言葉を吐いても動じる素振りを見せないクスィークが血相を変える様は兎角愉快であり、カナードがイルギジドを頻繁に部屋へと呼ぶ理由の半分はそれであり、そして残りの半分は彼が齎す情報。主にアノーレにある“四大遺跡”についての情報だった。
「承りましたよ。師団長殿」
長衣を着込んだ小男は、カナードの呼びかけに口元だけの笑みを浮べて一歩前へと進む。動きに釣られて、彼の衣の下からちろちろと鱗粉のようなものが零れ、どこか甘い香りが部屋に広がる。それを認識しつつ、カナードは男の話に耳を傾ける。“四大遺跡”が持つ力と、その現状についての話を。
・
僅かに迷った後、クスィークは扉に手を掛けゆっくりと押し開けた。
室内には、部屋の主であり自分の主でもあるカナードが一人。椅子に腰掛けて、何かを思案するように目を閉じている。
「師団長? 宜しいですか?」
扉を閉めた後、クスィークはカナードへと話し掛け──ふと怪訝に思う。
室内に僅かに漂う、独特の残り香。
(……この匂い)
内心呟き、思考を巡らせたクスィークだったが、香りについての記憶を呼び起こす前に、カナードがゆっくりと顔を上げてこちらを見た。
「まだ居たのか、お前。大草原の作戦の準備が整ったから今日からお前も行くんだろ。ノイハウス遺跡、だったか。あの“螺旋の理”の学者が占領したって処。そこを攻める作戦の指揮にさ」
「…………」
彼の発言に、クスィークは驚きと、そして違和感を得る。
何故彼がそのことを知っているのか、という疑問だ。
今回の作戦については、まだカナードに概略すら話せていなかった。別に内密に進めるつもりだったという訳ではなく、意見を聞くためにイェア・ガナッシュの元へと赴いたり、ヴィタメール奪還失敗の後処理などをしている間に、クスィークに報告を入れる前に部隊の布陣が終わってしまったと言うだけの話だった。それなりの期間があり、カナードが作戦の事を知っていたとしてもおかしくは無い。
だが、今日準備が整ったこと、そして自分が攻撃部隊の指揮をするという事を彼が知っているのは意外という他なかった。それらが決定したのはつい先程だ。誰かが彼に話したのだろうが、しかし、遠く大草原付近に布陣した部隊の準備が今日整った等という情報を知るのは、この駐屯地いる者の中でほんの一握りの筈で、しかもカナードとは縁遠い人物ばかりだ。
(一体、誰が)
クスィークの脳裏に何人かの顔が浮ぶが、そのどれもが可能性としては低い。
──と、そこでふと思い出す。
先刻から室内に漂っている甘い残り香。それを普段纏っている、小柄な魔術師の顔を。
心の内で舌打ちしつつ、クスィークは表情を引き締めて椅子に座るカナードを見る。
「……はい。ティネ村北の草原地帯制圧の部隊編成、出撃準備が整いましたので、今回指揮を取る事となりました私がご報告に参りました。──ですが、既にご存知だったようですね」
そこで一度口篭り、彼女は続ける。
「イルギジド、ですか」
「だから何だ?」
笑みすら含んだカナードの声色にクスィークは僅かに迷い、しかし歪めていた顔を正すと諭すように告げた。
「師団長。彼に心許すのは危険です。──イルギジド・マイゼル。彼の素性は知れない。あのような人物がアラセマ陸海軍に居た記憶は私にはありません。魔術師のようですが、稀に軍に術師を貸し出す“螺旋の理”にも彼の名前は名簿に無い筈です。こちらへ来る前、一度目を通したことがありますから。魔術師で軍の術士団の内におらず、“螺旋の理”にも属さない。そんな者が突然準軍師として着くなど──」
「はん。俺達がここに来た後に入ったのかも判らないだろう。それに、“六家”のどこかが囲い込んでた術師を出してきたのかもしれん。これなら、全てはコネだ。軍に所属していようがいなかろうが関係ない」
「はい。その判断は正しい。ですが故に危険なのです」
クスィークは、己がイルギジドを忌避する理由を素直に伝える。
「そもそも“女賢者”レェア・ガナッシュが軍の指揮を手伝っていたのは正式の指令を受けてのものではなく、言い方は悪くなりますが成り行き上のものです。なのに、彼女が離反するのにあわせたように、本国からその後任に着くなどという辞令を持って現れるのは、明らかにおかしい。他の“六家”から送られた、フハール正家の者である師団長の監査役か、諜報員という可能性があります。内密に本国の方へ問い合わせておりますので、その結果が出るまでは、彼との接触はなるべく抑えて下さい」
言い終えて、クスィークはカナードを見る。納得してくれただろうかと、そんな期待を込めて。
しかし。
「く、はは、はははは」
カナードは肩を震わせて笑い出す。
「はははっ。……馬鹿かお前は。監査役か諜報員か知らんが、そんなのをこんな辺鄙なところにトバされてる奴の処へ廻してどうするってんだ。そういうのは皇都イゼルアネッサにいる連中の処へ行かせた方が無駄が無いってものだろう」
「師団長。確かにフローリア諸島は辺境の地ではありますが、陸軍3師団、海軍2師団もの人員が回されているのは、軍最上層部がこの任務を極めて重要視している証です。その一員として選ばれた事は不名誉な事ではなく、師団長が軽んじられているという事には繋がらないでしょう」
クスィークは思った事を素直に述べる。
事実、フローリアへの軍派遣の人選にカナードの立場が考慮されている可能性はまずなかった。能力がどうこうという事より、決定時に比較的余裕があった師団がそのまま廻されたというのが真相だ。カナードが“六家”が一つ、フハール家の人間であるというのは変わる事の無い事実であり、彼が本国から離れていようとも、フハール正家の者であるという重要性が変わる訳ではない。
だが。
「──だから馬鹿かと言っている。そんな表面的な話じゃないんだよ、これは」
カナードは苦々しい表情のまま刺す様にクスィークを睨み、そして、は、と息を抜くと椅子から勢いをつけて立ち上がる。
「まあいい。取り敢えず言っておくか。俺はイルギジドと手を切るつもりはない。あいつの情報は……そうだな、色々と有り難い。そういう情報だ。お前のものと違ってな」
「師団長!!」
反射的に叫ぶが、しかしカナードはクスィークと視線を合わそうともしない。
「さぁ、もう行けよ。──いや、俺が出て行くべきかな? お前の事だ、俺が出て行けと命じてもしつこく食い下がってきそうだしな」
「…………」
カナードは大きな歩幅で扉前に立つクスィークの傍まで歩くと、皮肉気な笑みを浮かべて彼女の眼を見て、
「じゃあな。健闘を祈るよ、副団長殿」
扉が開き、そして閉まる。
後に残されたのはクスィーク一人。部屋に残っていた甘い香りは既に消え、ただ空虚な静寂だけが空間を埋める。
「……は、ぁ」
──どうして、こんな風に。
過去の思い出と、今ある関係との差。それが酷く心を締め付ける。
もう溜息も出ない。彼女は喉の奥に小さな呻きを残し、何かを堪えるように顔を伏せた。
四大遺跡 死線
――前哨――
薄く細い雲が延びる空の下。緑色に彩られた絨毯を大きく広げた平地がある。
アノーレの島にしては珍しく、場所としての名を持たぬその平野は、ただ“大草原”と通称されるのが常だ。穏やかな草原は、島の中央を南北に分かつカンクゥサの山脈から西へ、ティネの村からは北へと進んだ先に位置する。開拓に適した地ではあったが、生息する大型亜獣の多さと、それらを食料にと山脈より飛来する更に大型の飛行亜獣のお陰で、移住開始からかなりの期間を経た今でもほぼ手付かずと言っていい状態で放置されている。
そんな大草原の南端。ティネを囲う四つ林すら見える位置。鉄の帷子を纏う馬の背に跨ったクスィーク・カナル・フハールは、馬上からゆっくりと辺りを見渡す。
彼女の周囲ではアラセマ陸軍の装束に身を包んだ者達が多数、急がしく動き回っている。手に武器を抱えて走る者、複数の馬を連れて進む者、仮設の天幕を立てる者、部下を従え指示する者。
彼らが行っているのは戦の仕度だ。
大草原を北へ抜けた先にある“四大遺跡”の一つ、ノイハウスへと至る為の準備である。
ガレー、ヴィタメール、ノイハウス、ゴディバ。このアノーレに点在する四つの巨大遺跡のうち、二つ。ヴィタメール遺跡とノイハウス遺跡が、“女賢者”レェア・ガナッシュを中心とした一派と“杜人”のリゼラ・マオエ・キヴェンティを中心とした一派にそれぞれ占拠されてから、もうかなりの時間が経つ。ヴィタメール側がリゼラ配下のキヴェンティ達が周りを囲うように陣を敷いて他者の侵入を拒んでいるのに対し、ノイハウス側ではそこへと至る唯一の道である大草原の北部に遺跡の力を借りたと思しき亜獣の隊を配置して、アラセマ常駐軍の侵攻を食い止めている。
ノイハウスの東西北三方は起伏の極めて激しい地形で大人数での侵入はほぼ不可能であり、攻める側としては大草原に張られた陣を抜けるしかない訳だが、ノイハウスが持っていたという“現創”の力を用いて生み出された亜獣達の群れは手強く、数度か行われた侵攻作戦は全て失敗に終わっていた。
クスィークの視界に映る常駐軍兵士達の数はかなりのもので、今回の作戦の肝とも言える儀式印章魔術に使われる巨大な印章石が並べ置かれているのも見える。
今回、大草原に動員されたアラセマ常駐軍部隊の数は、今までの作戦とは比較にならない程の大規模なものである。
ヴィタメール遺跡を占拠するキヴェンティ達はただ遺跡を占拠して侵入者を排除するだけで、ある意味放置しても問題ない行動しか取っていないのに対し、ノイハウスを占拠する“女賢者”は遺跡の力、それも軍には秘匿していた機能を用い、事もあろうに亜獣を量産するなどという暴挙に出ており、早急にノイハウスを落し、彼女を拘束する必要があった。それ故の今回の大作戦であったが。
──遺跡の力、か。
内心呟き、クスィークは沈思する。
西大陸では聞いたことも無い力。亜獣を生み出す──もしくは操る力が存在し、尚且つ自分達の手に届く場所にある。常駐軍としての役目をこなすならば、明らかに危険であるこの遺跡は即刻破壊すべきだ。
だが、これは好機ではないだろうか?
ノイハウスを制圧し、遺跡制御の方法を聞き出すか、調べるか。その後、本国へと報告すればカナード様の大きな手柄となる筈だ。遥か古代の芯形機構に手を出すのは極めて危険な行為ではあるが──しかし、カナード様の評価に繋がるならばそれも、
「何やら心ここにあらず、といった様子ですなぁ、副団長」
「っ!?」
と、そこで背後からの声。
クスィークは驚きで小さく肩を揺らし、そして揺れた意識が収まるのを待ってからゆっくりと振り返る。
声の主は黒馬の背に跨り、腰に奇妙な形状の長剣を腰に差した口髭の男だ。
「──ノクトワイ様、ですか。到着されていたのですね」
こちらの言葉に、髭の男ノクトワイ・キーマ・フハールはどこか困ったような風に苦笑する。
「……うーんむ。前々から思ってたんですが、ウチの軍のこういう傾向、良くないと思うんですがねぇ。確かにワタシは第二貴族、貴女は第三貴族と位はワタシの方が上ではありますが、軍内での立場は貴女の方が上でしょう。もっとこう、ビシビシっとほら。ヴィタメール攻略失敗の件もあるでしょうに」
「確かに問題はあるでしょうが、しかし貴人としての立場はどこであれ重視されるべきでしょう」
そこまで言って、クスィークは僅かに俯き、眼を伏せる。
「それに、ヴィタメールの件ではノクトワイ様に落ち度はないと考えています。私の作戦通りにノクトワイ様は動かれ、しかしキヴェンティ達に読まれて裏をかかれ、しかし被る筈の被害を最小に抑えた。評価されるべきはあなたで、罰せられるのは私でしょう」
ノクトワイは髭を軽く撫で、呆れ半分といった調子で笑った。
「ふむ。あなたが問題ないというならこれ以上は言いませんがね。しかし──はは、上層の人間が内罰的傾向というのは正直どうかと思いますが。出世に響きますよ」
「構いません。現在の地位以上に出世する必要は、今のところありませんから」
「ま、確かに。今の地位より上に行くわけにはいかんでしょうな。カナルという家柄を考えるならフハール正家の仕えるべき人の上に立つのは何でしょうし。たとえあんな──」
と、そこでノクトワイが言葉を切り、反省するかのように表情を改めるのを見て、クスィークは彼を見る己の眼光が酷く危うくなっている事に気付く。
「──と失礼。それより、今回の作戦についての詳細、教えていただけますかね。召集の命のみで、具体的な事はさっぱりでして」
「……判りました」
さっぱりと話を変えてくるノクトワイに、クスィークは僅かな間を置いて、ふ、と息を抜いた。
ノクトワイを相手に熱くなるべきことではない。小さく首を振って無駄な思考を振り払い、彼女は懐から資料を取り出し、説明を始めた。
・
「──以上、配置を終えています。作戦開始につきましてはノクトワイ様にお任せします。時刻等に関しましては後ほど配置の進行状況を見ながら話したいと考えていますが、如何でしょうか」
一通りの説明を終え、クスィークは資料から目を離して顔を上げると、隣に馬を並べていたノクトワイを見る。
「ふぅんむ。大草原各所に鍵となる印章石を配置し、それを基とした儀式印章魔術を大草原全体に発動、亜獣達の動きを一定時間束縛し、その隙に殲滅する、って処ね」
「ええ。印章魔術は自然存在と比べ概念的に欠けた要素を持つ者達、つまり亜獣や亜人のみを対象とし、効果を発揮するという記述になっています。私たちには影響せず、相手が操る亜獣にだけ効果を及ぼす筈です」
ノクトワイは数度頷いて、視線を遠く、草原の北へと向ける。
「で、問題は印章石の配置ですか。印章石で陣の縁を指定する構造なら、大草原全てをカバーするには占領派の勢力圏でもある大草原の北部にも印章石を配置する必要がある、と。ちょっとばかし手間よねぇ、相手の中央を突破して印章石を配置するってのは。これ、ウチの連中がやるってことで宜しいので?」
そこでクスィークは僅かに口篭る。
「──申し訳ありません。危険な任務となりますが」
しかし、ノクトワイは気にした風も無くひらひらと手を振ってみせた。
「ま、それはヴィタメールでの失敗の責ってことで。……ああでも一つ宜しい?」
何だろうか、と改めてノクトワイを見たクスィークに、口髭の男は視線を合わせると、
「前回の戦闘でちょっと人員に不足が出てましてね。何人か部外の人間を組み込みたいんだけど、構わない?」
クスィークは僅かに視線を外し、思案する。部外の者とはいえ、渡島規制により怪しい者がアノーレに入ってきているという事は無い筈。今回ノクトワイが行う任務は多分に危険なものではあるが、軍の中枢情報に触れられるようなものでもない。部外の者が紛れ込んでいようが問題は無いだろう。ノクトワイも、裏切る可能性のある人員を入れれば危機に陥るのは彼の部下であることを考えれば迂闊な人選はするまい。
「構いません。あまり大人数を引き入れられると流石に困りますが、少数であるのなら許可します」
「あ、それなら大丈夫。五人も越えない程度ですんで。じゃ、連れて来た連中と打ち合わせてくるから、この辺りで」
「判りました。では半刻後に指揮天幕へいらしてください。もう少し細かく作戦を詰めますので」
了解とばかりにひらひらと手を振り、ノクトワイは笑みのまま馬の手綱を引いて頭を巡らせ、鐙で馬の腹を打つ。
去っていく男の背を暫し眺めて、そしてクスィークは改めて草原を見渡す。
──上手くいくだろうか。
少々強引な作戦ではあるが、多数の亜獣を生み出し戦力として組み込んで数を補うという相手側の戦法は、ある意味反則といっても良く、まともにぶつかれば、たとえ勝利したとしても大きな損害は免れない。搦め手を用いて有利に事が運べるならばそうすべきであるが、しかしそれも上手くいけばの話。失敗してしまえば元も子もない。
僅かな不安を残したまま、クスィークは戦の準備進む草原をただ眺めていた。
・
「──以上がノクトワイ様から窺った作戦の概要です。何か質問などはありますでしょうか」
ノエルの問いに【NAME】は軽く横に一度首を振って、彼女から受けた説明を反芻する。
大草原南部に集結したアラセマ常駐軍部隊。その内、ノクトワイ指揮下のヴィタメール攻略部隊から派遣された面子に紛れた【NAME】は、ノエルから自分が潜り込んだ部隊がこなさなければならない任務についての話を聞かされた。
軍勢は大きな視点から見れば大草原南部と呼べる位置だが、実際の処は既に大草原の中央に近い位置へと進軍しており、遮蔽物の無い平野では敵方に知られぬ行軍など有り得る筈も無く。遥か前方、大草原の北側からは先程からノイハウスを占拠する者達と、彼らが従える多数の亜獣達が集結しているのが見えた。
【NAME】は目を凝らし、敵となる彼らを観察する。
亜獣という異質な獣達を内に配しているにもかかわらず、対面に集結する集団が、通常では到底有り得ぬ統率を保っているのは遠目からでも知れた。容易に下せる相手ではない。元来只の冒険者であり、こういった大人数の集団戦には不慣れな【NAME】にもそれだけは理解できた。
そして【NAME】は、自分達のすぐ横の荷台に乗せられた巨大な印章石へと視線を移す。
今回の作戦は、この印章石を大草原の各地に配置し、それを基盤とした大規模な儀式印章魔術を使って敵軍の使う亜獣達の動きを妨げ、その隙に一気に攻勢を掛けるというものだ。印章魔術は特殊な式を組み入れることによって人には作用せず、亜獣にのみ効果を及ぼすように記述されていると聞いた。
彼らの言が確かならば、この魔術の起動に成功すれば確かに勝ちは決まりなのであろうが、しかし問題があった。印章石の配置位置である。
魔術の範囲を決める縁の五つと要の中央となる一つ。合わせて六つを大草原の各地に配置せねばならない訳だが、相手側をその効果圏内に引き入れるには最低縁一つの印章石は彼らの陣の真中──より効果的な状況を作るならば、ほぼ背後に近い位置まで印章を運び込む必要があるのだという。
上からの指示では、取り敢えず敵陣中央まで印章石を運び込めば、ある程度の効果は得られるので無理はせず、まず印章石を傷つけられずに運ぶことを至上とせよ、という話らしいが。
そこで改めて【NAME】は視線の先にある印章石を眺める。
大人が漸く抱え込める程度の大きさの石を複数、幅を置いて輪状に繋ぎ、その輪の中央に長さ2メートル程の棒を差したような形。石と棒は接してはいないが、まるで見えない何かでつながれているかのように、石を動かせば棒が動き、棒を動かせば石も動く。そんな巨大な運搬物を眺めながら、
──無茶だな。
【NAME】はそう結論付けて苦笑する。
印章石に付加された術式により重さは無く、石と棒はふわふわと浮遊しているため運ぶ事自体は楽であろうが、石自体が高く低くと波のある唸りを上げ、更には黄金色に明滅すらする為、兎に角、目立つ。いかにも何かありそうで、こんなものを曳いて敵陣に突っ込めばまず集中打を受けるだろう。
だが。
(面倒だが……やるしか無いか)
ノイハウスに辿り着かなければ何も始まらない。ならばこの作戦を成功させるか、少なくとも自分達だけでも大草原を抜けて北へと進む必要がある。
【NAME】が複雑な表情で溜息を吐くと同時、作戦開始を告げる鼓の音が響いた。鳴り響く音を追ってそちらを見れば、部隊指揮を取る馬群の中にノクトワイの髭面が遠く見える。男は丁度こちらを見ていたようで、視線に気付いたか軽くウィンク──したように見えて、【NAME】はげんなりと顔を歪ませた。
「【NAME】」
と、動きの止まった【NAME】を呼ぶ声。
見れば、傍らに立っていたノエルが背の黒い大筒を手元へと廻してこちらを見ている。戦いの準備を促す目つきに、【NAME】は軽く頷いて面を前へ。
──行こう。
【NAME】は深呼吸を一つするとゆっくりと武器を引き抜き、そしてもう一度印章石を見る。
大草原北部、敵陣只中へと破壊されずに運ぶ必要のあるその印章石。炎氷雷光闇の五つのうち、今回運ぶのは──。
――第二次防衛線――
打ち鳴らされる武具の火花と、術式が裂く空気の音色。そして獣達が放つ高き咆哮が草原を埋め尽くす。
──これが戦場か。
今まで冒険者として過ごしてきた【NAME】にとって、こういった戦の場は新鮮に映る。僅かな感慨を表情に乗せて【NAME】は頭を巡らせる。
幾分離れた場所で爆発音にも似た物音が響き、遠く【NAME】の視界の片隅を味方が数人、空中に高く吹き飛ばされる姿が掠める。別の場所では敵の大型亜獣が馬上槍による連携吶喊を喰らい、為す術も無く屠られる様も見えた。派手なものだと、【NAME】は半ば傍観者気分でそれらを眺めていたが、自分もその戦闘に組み込まれ、そういった戦場独特の技を喰らい喰らわせる側に回っていることに気付いて、厄介な事になったものだと苦く笑う。
未だ敵の本陣は遠い。
亜獣を操る遺跡占領側の抵抗は激しく、攻め手である常駐軍の動きは鈍い。敵は三本の防衛線を構築しこちらと対峙しているようだが、軍はその最前の防衛線すらまだ突破できていない。【NAME】達の所属する部隊は、ある程度本軍が敵と交戦し道を開いた後、相手の中央へと少数で突撃して印章石を配置し、離脱するという役目を持つ。故に序盤は陣の半ばか後方で待機していれば良い──筈であったが。
「【NAME】」
と、部隊の者達と何やら話をしていたノエルが、北の一点を気にしつつ足早に【NAME】の方へと戻ってくる。何かあったのかと問えば、
「敵の最前衛を構成していた一部がこちらへ向かっているとの事です。恐らく、ここにある印章石に目を付けての行動とわたしは考えます」
言って、彼女は己の視線の先を指で差し示す。それをなぞる様に見れば、なるほど。先刻味方が吹き飛んでいた辺りの陣が崩れ、そこから亜獣の群れを先頭に置いた一団がこちらへと向かってきている。
浮遊する巨大な印章石の外見、発光をいぶかしんでの突発的な行動か、それとも軍の作戦を事前に察したのか。
どちらにせよ、少しばかり早く出番が回ってきたのは確かなようだ。
【NAME】は一歩前へと進み出て、己が武器に力を込める。
「では迎え撃ちます。【NAME】、印章石を破壊されぬよう、常に警戒しつつ戦闘を」
すぐ隣で銃を構えるノエルの言葉に【NAME】は黙って頷くと、武器の握りを今一度確かめ直してから、高速で迫る敵達を見据え迎撃する。
──奴等が印章石に近づく前に、仕留める。
battle
現創の亜獣

目の前の亜獣を仕留め、息を吐いて辺りを見渡すと同時。部隊進軍開始の笛が鳴る。軍の本隊が敵の第一陣を撃破したことを示すものであり、以降は本隊と合同で【NAME】達も敵の第二陣、二番目の防衛線を叩くために前へと出ることとなる。
「【NAME】、行きましょう」
戦闘を終えたばかりだというに涼しげな表情で告げてくるノエルに、【NAME】は短く頷く。
ここからが本番だ――【NAME】は自分に喝を入れ、未だ前方に広がる戦線を見据えた。
敵陣深くの所定位置に辿り着くにはまだ遠い。左右へ回り込むか、それとも直線で突き進むか。
――第一次防衛線――
突然、激しい血飛沫が【NAME】に降り掛かった。
一瞬自分の血かと錯覚もしたが、寄り掛かるように倒れて来た味方の身体に、それが勘違いだとすぐに分かる。
進軍するに連れて亜獣の数は増え続け、同時にその出現する間隔も次第に短くなっていった。
「【NAME】、左前方から次が来ます。迎撃に向かいますか?」
ノエルの声にそちらを見遣れば、確かに彼女の云う方角から敵の新たな部隊がこちらへ向かってきていた。どうやら術式による攻撃を主とした部隊らしく、集団に亜獣の姿は少なく、かわりに術士と思しき衣服を纏った兵の姿が見える。
【NAME】は忌々しげに顔を顰め、次いで周囲の味方の様子を確かめる。既に印章石護衛の兵達も脱落者は少ないが疲弊の色は少なからず見える。そしてそんな彼等の中央で護られた印章石。少々傷付いているものの、致命的ともいえる損傷は見当たらない。
だが、間近に迫るあの部隊の攻撃に耐えられるかどうか。
(──やるしかない、か)
あの部隊がこちらへ辿り着く前に、単身で突撃し、叩く。これしかない。
【NAME】は舌打ちを一つ残すと風の様に駆け、敵部隊へと向かう。
気付いたノエルがそれに続き、すぐ傍に居た数人の味方兵士が更に二人を追った。
battle
理の力操る者


手近な最後の敵を打ち倒し、再び辺りを振り返る。
「【NAME】、無事ですか」
ノエルの声に彼女の姿を確認し、無言の了解だけを返した。
まだ軍の本隊は敵の防衛線に遮られたままであるが、ここから先は自分達の部隊だけで敵陣奥へと強攻し、一定の距離まで進み込んだ上で印章石の中央に浮ぶ棒を地面に差し込み、術式の基としなければならない。中央と【NAME】達が担当する印章石以外の四つは作戦開始前に配置済み。そして中央の一つは先刻の一番目の防衛線を突破した位置に配置された筈で、あとは自分達が印章を運び設置すれば術は駆動する。
この行軍は速度が勝負だ。突っ込み、敵を混乱させ、足を決して止めずに常に前進する。留まれば囲まれて八方より攻撃を受ける事になる。自分達の位置を認識させないよう、全速力で一気に疾駆するのが最良だが──しかし、【NAME】達には印章石という足枷がある。内に組み込まれた補助の印章術式により石の重さはほぼ零に等しいため、縄を掛けて引くことで速度という面での問題はでないが、やはり縦横共に3メートルはある物体を無傷で曳きながら敵陣を突破、というのは至難という他無い。
至難という他無い、のだが、作戦上やるしかないのは確かだ。
印章石が専用の台座から外され、一人の兵士が輪を描く石に綱の一方を掛けてその逆側を肩に巻く。
そして部隊は始めはゆっくりと、次第に速度を上げて進軍を開始する。
幾多の亜獣犇く敵軍の只中。正に“死線”へと。
――死線――
不意を突かれた。背後、真後ろで上がった咆哮に背筋が凍る。
つい先刻まで戦っていた大蛇の死体を蹴り飛ばすと半身で振り向き、【NAME】は勘のみで武器を振るう。
【NAME】の首筋に迫っていた四足獣の牙と武器が交差し、次いで衝撃。獣を振り払うことには成功するも勢いは殺せず、草原の土へと弾き飛ばされる。
「──ッ」
舌打ち。地に背中が着くと同時に素早く後転し、位置を動かす。縦に回る視界の端に、【NAME】が倒れた隙を狙って放たれたと思しき敵の術式が弾けるのを見届け、そして何処から狙ってきたのかを一瞬で確認する。
──そこか。
獣の右斜め前10メートル程の位置にそれらしき姿。まだ術式を放った姿勢のまま固まっている。
こちらの動きに対する反応は鈍い。ならば獣よりもまず術士か。
【NAME】は弾いた獣が態勢を整えてこちらに向かってくる前に、術を放った敵軍の術者の傍へと瞬く間も与えず踏み込む。
「がっ!?」
鎧越しからでも、攻撃をまともに受ければ少なからず衝撃は残る。胸に入った一撃に驚きと苦痛の混じった声を上げて吹き飛ぶ術士を横目で見届けつつ、【NAME】は先刻の獣と対峙するために振り返った処で、じ、と空気が熱く焦げる音が響く。【NAME】に襲い掛かろうとしていた獣の頭部が、何処かより飛来した光の一閃を喰らって弾け飛び、首より上を失った巨体がゆっくりと頽れる。この攻撃手段は、
「……ノエル?」
【NAME】の呟きに答えるように、倒れた獣の向こう側から黒銃を手に持った軍服の娘がこちらへと駆け寄ってくる。戦いにより衣装も血や埃に汚れており、表情は何時もの静かな様子ながら血の乗った顔の色は青白く、激戦を経た疲れを感じさせた。
「【NAME】。印章石の方は」
彼女の言葉に、【NAME】は後方を見て──慌て全力で駆け出し、咄嗟の動きで技法を放つ。放った一撃は印章石の曳き手に襲い掛かっていた亜獣の背を撃ち据えるも、曳き手であった兵士は既に亜獣の一撃を受けて身を折り、地に倒れ伏している状態だった。勢いだけで乗り込んだために全体的に散らばる形となっており、故に周囲に味方の影は殆ど無く、曳き手となるのはこの状況では自分しかいない。
──くそ。
内心毒づき、離された印章石の綱を手に取ると【NAME】はノエルを一瞥。彼女が頷きを返してくるのを見届ける事無く走り出す。
前を塞ぐ敵兵、亜獣。双方の合間をすり抜け、時には叩き、時には防いで更に進む。
紙一重といって良い進軍を続けてどれだけの時間が経ったか。
唐突に敵の影が作る森に小さな抜け道が生まれた。ぎりぎりの戦闘を続けていた【NAME】は現在の状況から脱するのに必死で、何故隙間が生まれたのか等という事など考えられずそこへと飛び込む。
幾多の兵の剣と獣の爪を掻い潜り飛び出した先は、敵のいない大きな空間だ。何故かそこにだけ敵兵がおらず、正に空白。確かに数瞬とは言え息をつくことが可能な場所ではあったが──しかし敵陣只中にこのような場所がある事が不気味で、その事に【NAME】は素直に戦慄する。
まだ敵軍の背後へと出るような地点ではない。ならば一体なんだ、と思う暇無く、眼前に、いや、場に立つ【NAME】を含んだ空白地一帯に巨大な影が差す。
「……!?」
影──影? 影ならそれを作り出す物体、日の光を遮る何かがある筈。しかしこの巨大な影と身を接するものはその場には居ない、ならば。
「【NAME】、上です!!」
見上げれば、そこには大翼を広げた不気味な姿の奇鳥が、【NAME】へ向けて両足の鋭い爪を繰り出そうとする姿があった。
[BossMonster Encountered!]
巨大な怪鳥を辛うじて退けるも、
「【NAME】、もうこれ以上印章石を牽引しての進行は不可能とわたしは考えます。印章石の損傷も危険域に達しつつあります──お早く!」
位置としてはもう問題無い筈だ。ノエルの声に急かされるように【NAME】は印章石の軸棒を手に持ち、そして勢い良く地面に突き刺した。
きん、と。
甲高く何かが弾ける音と共に、世界が白色に染まった。
次いで各所で巻き起こる亜獣達の咆哮。【NAME】の視界内でも、こちらに向かい牙を向けてにじり寄っていた亜獣達が身を地に伏せて唸るのみとなっていたり、何かに堪えるように高く叫びを上げてのた打ち回っていたりと、理屈は判らないが事前の情報通り亜獣の殆どが無力化している。
──やった、か。
【NAME】は安堵の吐息を一つついて、そして眼差しを新たに草原北、ノイハウスへ向かい走り出す。
亜獣達の制御を失い、兵士達の方も混乱している。軍の方はこの隙を狙って一気に攻勢へと出るのであろうが、こちらの目的はノイハウスへと辿り着き、レェアと対話すること。軍と違い、彼女と戦う為に向かう訳ではないのだ。出来れば軍がレェアを抑える前に会っておきたい。
と、走る【NAME】の隣に黒銃を背負った小柄な影が寄り沿う。
「【NAME】、ここからはわたしが先導します。ノイハウス遺跡前に存在した研究用の軍駐屯地、シニ設営地へと案内します」
ちょっと待った、と【NAME】は問う。シニ設営地とやらはノイハウス遺跡占領側の基地になっているという話ではなかったか。そんな処へ向かって大丈夫なのか?
「大丈夫かどうかは判りませんが、シニへ向かうということはノイハウスへ向かうと言う事と同義だとわたしは考えます。先日のヴィタメール遺跡とキヴェンティ達の野営地、ガレー遺跡と周辺天幕群。ノイハウスとシニはその二つの組み合わせと酷似した配置にあり、避けて通ることはできないと、わたしは考えます」
なるほど、と暴れたり蹲ったりと忙しい亜獣達の隣をすり抜けつつ【NAME】は頷く。
どうにせよ、こちらには土地鑑がない。ならばある程度は詳しいらしいノエルに従うのが妥当。そう判断し、【NAME】は僅かに速度を落すとノエルを先行させ、その小さな背中を追った。
四大遺跡 向かい行く城
――向かい行く城――
輝きが満ち、そして一変した戦場。
その中を、切れ味を重視の連戦には向かぬ片手半剣で器用に敵を叩き伏せつつ、ノクトワイは駆けていた。
馬上。高速に流れる視界に映る無数の敵達の内、亜獣は斬り捨て、人は叩き捨てる。たとえ敵に回ったとはいえ、元は同じ組織の人間。しかもレェア・ガナッシュと共に離反した面子の大半は本来軍人ではない外部からの術者学者連中が多い。彼等は貴重な人材だ。気軽に失って良い者達ではない。
先刻大草原全体を対象に起動した印章魔術は、ほぼこちらの意図通りの効果を発揮し、敵の亜獣は制御を失って暴れ、部隊としての統率をほぼ失っている。
──勝ち戦、ってトコね。
部下達に素早く指示を出しながら、ノクトワイはそう結論を出した。
元々敵の主力は亜獣にある。術による意識混乱でその制御の阻害に成功した時点でこちらの勝ちは確実だ。後は統率を失った亜獣を各個撃破していくのみだ。印章石による儀式魔術の効果時間はまだ暫くはある。焦る必要はない。こちらの被害をなるべく抑えつつ、手駒ではなく只の猛獣となった亜獣を慎重に撃破していけば良いだけだ。
周囲に敵影が無くなったところで、ノクトワイは馬の歩を緩め、戦況を見極めるように視界を廻す。
敵側は亜獣の制御や自陣を保つ事に懸命になっており、味方は混乱した敵にここぞとばかりに攻撃を仕掛けている。クスィークの指揮はメリハリが利いており、今までの何処か堪える処のある進攻から一転しての怒涛の如き攻めは、彼女が上手く主戦力を温存していたが故に生まれた勢いだ。
しかし、予想外に上手く行ったものだ。
クスィークの前では口には出さなかったが、この作戦が上手く行くかどうか。ノクトワイ自身の予測では、成功率はせいぜい五割程度だろうと考えていた。特に、敵陣内に印章石を運び込むという部分は失敗の可能性が大きすぎる。作戦手順を聞いた時には何と言う無茶をと内心呆れていたものだが、こちらが寄越した連中がどうやら気張ったらしく、無事に石を所定位置まで運び込んでしまったらしい。運が良かったのか、自分の部下が想像以上に張り切ったのか。はたまた、彼等に同行した、あのキヴェンティの野営地へ共に向かった冒険者の力なのか。
(……そういえば)
あのイェアが使っている冒険者と補助役らしき奇妙な雰囲気の銃士は、上手くノイハウス遺跡へと近づくことが出来たのだろうか。
ノクトワイ自身は彼等に遺跡へ近づくためのチャンスを提供したに過ぎず、表立って力を貸した訳ではない。が、やはり結果くらいは気になる。
印章石が起動したということは、少なくとも敵陣の最奥までには辿り着いただろうか。しかし、石が起動したからといって、あの二人が無事に突破できたという証明にはならず、そもそも彼等が最後まで印章石と共に行動していたかどうかも、錯綜した戦場にあっては判然としない。
「ま、上手くやってくれてると良いんだけどねぇ。カナルのあの子だと、“芯形機構”を使う女賢者様の相手は無駄に時間がかかりそうだし」
何処か投げやりな調子で独りごち、ノクトワイはこきりと一つ首を鳴らす。
──と、その時。
空から細く高い、奇妙な音が微かに聞こえた。
「……何?」
この戦場の喧騒の中にあってその音が聞こえたのは偶然以外の何物でもないだろう。
本来ならば別に気にする必要もない、空の唸り。しかしノクトワイは目つきは厳しく、顔を空へと、音が響いた方角へと向ける。
その視界に映ったのは数条の光の線だ。
大草原を越えた北の先。ノイハウスと大草原の合間に広がる森から空へと伸びた輝きは、美しいアーチを描きつつ緩やかに空を曲り飛ぶ。この時点で空から届く唸りは耳障りな高音へと変わり、戦場に居た者達の殆どがその音に吊られて空を見上げた。
森より放たれた光は六発。六つの軌跡は大草原で戦う者達の頭上を飛び越えて、五発は草原の隅へ、一発は草原の中央へと走り、
「あら」
と、何処か惚けたようなノクトワイの声にタイミングを合わせるかのように、大草原の各地に配置された六つの印章石を正確に射抜いた。
──ど、と響き渡る激音。
地を打ち弾ける光の奔流は土を激しく盛り上げて腹に響く音を上げ、しかし同時に、ぱりん、と硝子の砕けるような高い音も戦場に響き渡った。
そして、要の印章石を失い、草原に展開されていた儀式魔術の光がゆっくりと失せ始める。突然のことに敵味方問わず動きが止まり、術が効力を失ったことにより亜獣達の暴走も同時に停止する。
「あー、マズイわねこれ」
まだ予定効果時間の半分も経過していない段階で、六つの印章石が全て破壊されるという展開は明らかに想定外だ。作戦立案の段階で考えられていた行動指針は、術の発動自体が失敗した場合と成功した場合の二つのみで、印章魔術の効果時間中に印章石がすべて破壊され、術が消滅するなどという展開は想定されていない。術は起動してしまえば六つの石全てが破壊されない限り最低限効果を発揮し続けるという事になっており、亜獣の制御を失った敵側が印章石全てを破壊することなど不可能と結論づけていたからだ。
そして想定外の出来事に、集団というものは弱い。
「ったく、仕方ないわねぇ」
ノクトワイは逡巡は僅かに、素早く部下達に突撃の命を下す。
悠長にしている場合では無くなった。眼前の敵、印章の力により混乱していた亜獣達が落ち着きを取り戻し、敵の制御下に戻りつつある。これでは元の木阿弥となってしまう。せめて敵が完全に立て直す前に最大限の損害を与えておかなければならない。まだ敵側の亜獣は半分も削ってないのだ。
鐙で馬の両腹を打ち、手綱は左手に。空いた右手には剣を握る。
──敵軍の完全撃破は無理としても、大草原を制圧できるくらいにはもってきたいところだけど。
未だこちら側が優位であることには違いないが、予想外の展開となった故に自軍の内にも少なからず混乱もある。ある程度は敵を詰められるだろうが、こうなってしまっては最終的には膠着状態となる可能性が最も高いだろうか。
それに先刻の光の一撃。あれは恐らく“女賢者”によるものだろう。彼女がそれらしい“武器”を持っていることは噂には聞いていた。
こちらが打った術の質を見抜いての、遠距離からの狙撃。あれ程の威力と精度ならば、こちらの本陣を狙い打ちにすることすら可能な筈だが、第二射が来ないのは手を抜いているのか、手を抜かなければならぬ理由があるのか。どちらにせよ、
「全く、ヤッカイな話よねぇ……」
そう嘆息しながらも、ノクトワイは最善を尽くすために部下に素早く指示を出しつつ、己が馬の脚を速めた。
・
──草原に打ち込まれた光の射撃。遥か遠方から、六つの印章石を過たずに射抜いた強烈な輝きが生まれた場所。
緑と茶の色が織り成す空間、戦いの舞台である“大草原”から北へと抜けた先に広がる森。木々の狭間に置かれた、小さな陣地の一角に、一人の女が居た。
年の頃は二十を既に過ぎて、しかし三十にはまだ届かないといった処。鋭いながらもどこか気の抜けた風な雰囲気を纏い、柔らかな生地ではなく、しっかりとした硬い素材で造られている珍しい形状の衣をいい加減に身につけた彼女は、己が放った光の威力を、術式により作り出した半透明の円盤より知る。
遠見の術式によって生み出された架空の円の中では、空より飛来した光の狙撃により巨大な印章石が砕かれ、次いで要が破壊された事によって草原を包んでいた印章魔術の力が消え、亜獣達が落ち着きを取り戻していく様が写る。常駐軍が仕掛けた印章魔術の起動から印章石の破壊まで、時間は然程経っていない。味方の被害は免れぬだろうが、しかし致命的な事態にまでは至っていない筈だった。
──こんなもの、かな。
思い、ふむ、と小さく息をついて彼女は両手に握っていたグリップから手を話すと、担いでいた物体を地面へと置く。同時、周りを取り囲んでいた部下達が自分達の上司が放った力の凄まじさに喝采を上げた。
そんな彼等にノリの良い連中だと苦笑を向けながら、彼女──アラセマでは“女賢者”の二つ名で呼ばれる魔術司にして機甲師であり、アノーレ四大遺跡が一つ、ノイハウス遺跡を占拠する者たちの長である女性、レェア・ガナッシュ──は地面に降ろした己の武器を見る。
ずしりと。沈むような重みを持って、疎らに草生える土の上に置かれたそれは、長細く巨大な鉄塊だ。
曲線と直線を組み合わせた奇妙な形状。黒く輝くそれの先端部周辺の空間が淡く歪んでみえるのは、そこから放たれた光の力が影響してのものだ。レーゼラーファールという名を持つこの巨大かつ奇怪な形状の“銃”は彼女の愛銃であり、機甲と術式を組み合わせた特殊な分類に位置する銃でもある。
ノイハウスの深部にある“現創空間”で遺跡の調査と“これからの準備”とを進めていた彼女は、大草原に集まったアラセマ常駐軍の部隊の中に、奇妙な形状の物体がいくつか確認されたという報告を部下から受け、己が武器を携え急ぎ遺跡から部下達の駐屯するシニ設営地へとやってきたのだ。
報告にあった物体とやらが一体何であるのかは、受けた報告があくまで第三者が遠目から確認したという曖昧な話であった為にノイハウス内に居た時点では判らなかったが、念のためにと外に出て遠見の術式を使った結果、その物体が大規模な儀式魔術のための印章石だと認めて、レェアはレーゼラーファールを持ってきたのは間違いではなかったと己の判断の正しさを再確認した。
──クスィーク嬢もそろそろ痺れを切らしてきたってところか。
思い、薄く笑う。人対人、正攻法による部隊運営、戦術構成しか経験が無いであろう彼女には、召喚術などによる局地的、限定的な人外生物の対処ではなく、恒常的に存在し、戦闘部隊として組み込まれた多数の亜獣に対する術を思いつくのは難しい筈だ。そんなクスィークが儀式印章魔術を絡めた大規模な作戦を練ってきたということは、相手もこちらの戦力を過小評価せず見極めて、本腰を入れて攻略に掛かってきたと考えて良いだろう。
──時間稼ぎ、考えないと駄目かねー。
こちらの戦力は言ってみれば急造、場凌ぎのものだ。全力になった相手と長期に渡り合える程のものではない。“準備”にはまだ暫くの時間が掛かる。ならばその間を繋ぐ方法を考えないと。
そう思ったところで、傍らに置いた黒銃から熱気が来て思考が中断される。
地面の上に置かれた黒銃は、全力射撃の形状から排気放熱の形状へと変形している。レーゼラーファールの各所より突き出た廃熱角と展開した外殻の隙間からは熱の篭った気が勢い良く吹き出て、己が身に宿った熱を懸命に逃している。
先刻の誘導の概念を付与した全力による連射撃は、自分の弟子に預けたフォーレミュートより遥かに高い性能を持つこのレーゼラーファールでもかなりの負荷が掛かる。一度使えば放熱等の為に暫くの待機時間をとる必要があり、砲自体のバランスにも多少ズレが生ずるため再調整も欠かせない。できれば今からでも調整をやってやりたい処であるが、そんな余裕もないか、と女は苦笑しつつ顔を上げて、彼女の射撃を見物にと、自分達の仕事を適当に切り上げて未だ騒いでいる部下達に声をかける。
「こらこら、盛り上がってる場合じゃないでしょが。くじ引きで負けた連中はまだ大草原のほうで頑張ってんだから。取り敢えずアンタらも援護、いってきて」
レェアはそう指示を出すが、しかし部下たちはぶーぶーという抗議の声を上げる。どうしてくじ引きで勝ったのに戦いに行かないとならんのですか面倒くさ──もといそんな余裕はありませんよ、やら、厳選なくじ引きの結果を覆す行動はくじ引きの神に対する冒涜ですよ冒涜、いけません、許せませんね全く、やら。
ああもう何でこんな餓鬼っぽいのかと、レェアは細く癖のない髪を荒っぽい手つきでがりがりと掻いて乱すと、
「ふぅん、そりゃ残念ね。ちゃんと大草原の方で働いてきたらノイハウスでの助手に回ってる連中と配置入れ替えてやろうかとも思ってたんだけど」
そう彼女が告げれば、わーい、と今までの態度はどこへ行ったのか嬉々として出撃準備を始める部下達。
ぶん殴ってやろうかと心の隅で思いつつ、レェアは準備の為に散っていく彼らを見届けた後。放熱を終えて通常形態へと戻った黒銃の側面に刻まれた印章刻印をなぞり、重量軽減の術式を起動させる。低く唸るような音が一度響き、平均的な大人の男とほぼ同等の重量を持つ黒の塊が、赤子の身体程度の重さへと僅かな間を置いて変化した。
「さて」
一つ声を置いて、レェアはひょいと黒の銃身を持ち上げて陣地を北へと歩き出す。
「大草原の方はもう暫く持たせられるだろうから、準備の方、急がないとね……」
ひとり呟いた彼女が目指す先には、城の如き外観を持つ黒色の巨大な建造物。ノイハウスと呼ばれる“生きた芯形機構”があった。
・
大草原を抜けた先に広がるのは針葉の森。木々の間を飛ぶように走っていた【NAME】は軽く振り返り、大草原からの追手が居ない事を確認し、安堵と共に走る速度を緩める。
どうやら、印章魔術起動によって生まれた混乱に乗じてはあるものの、敵本陣を堂々突破することに成功したらしい。
──ここまで距離を稼げばもう問題ない。後は難なく遺跡へと辿り着けるだろう。
そう、軽い笑みも交えながら、隣を走っていた筈のノエルに話し掛ける、が。
「…………」
居ない。
つい先刻まで隣を走っていた筈だと、疑問の意志と共に【NAME】は改めて背後を振り返り──かなりの後方、傍の木に肩を預けて、半ば寄りかかるようにして立つ小さな影を見つけた。
(……な)
【NAME】は慌てて彼女へと近づき、様子を改める。
「あ、【NAME】……?」
傍へ来た【NAME】に気付いたのか、ノエルが半ば閉じかけていた瞼を開き、面を上げた。
相変わらずの無表情ながらも、常より白く、寧ろ青いと表現しても良い顔色。見た限り、大草原を抜ける際に致命的な傷を負ったという訳ではなさそうだが、体調の悪さは隠せない。
──だが一体どうしたのか。大草原での戦闘の疲れが出た、というのが理由としては一番尤もらしいが。
しかし訊ねた【NAME】に、ノエルは首を僅かに左右へと振る。
「……いえ、これは疲労ではなく、大草原に張られた印章魔術の影響を受けたのではないかとわたしは推測します。……理由のない不快感と、自律神経の失調による身体の異変、思考能力の低下。……別にもう一つ、原因となるものも考えられますが、それが作用するにはまだ距離がある。ですので、恐らく先刻の術の影響を受けたというのが正解だとわたしは考えます」
細い息を途中に挟みつつ、ノエルは平坦な調子で語る。
だが、それは少しおかしい。【NAME】は片眉を寄せて疑問を口にした。
作戦前の説明では、大草原に展開する術式は人体に影響はないと言っていた。亜獣等の存在概念に一定以上の異質な要素が含まれている者を対象にして効果を発揮すると。実際【NAME】も印章魔術の起動後に別段異常を感じる風なことは無かった。なのに、何故彼女に影響がでるのか。
「……単なる予想となりますが、印章石に刻まれた式に何かの不具合──途中、印章石が受けた損傷等が原因となって動作に僅かな異常が出たのではないかと、わたしは考えます」
淡々と答えながら、ノエルは身を寄せていた木に手をつくとゆっくりと押し、身を立てる。どうやら動くつもりらしい。
暫く間を取り、一先ずの休憩を入れた方が良いのではないか。【NAME】はそう提案するが、ノエルは首を横に振った。
「大草原を抜けはしましたが、まだこの先には本拠とも言えるシニ設営地があります。今わたし達が居る場所は、前と後ろを敵に挟まれた極めて危険な場所だと考えます。もし大草原にいる敵部隊が敗走したなら、当然ここを通過しシニへと戻る筈です。そんな場所で悠長に休息を取っていれば一体どうなるか」
確かに、彼女の言う事には一理ある。しかしここは深い森の中だ。場所さえ上手く考えれば見つからずに休息を取る事は可能だろう。
しっかりと場所を考えて隠れればそう問題はないと判断できたが、しかしノエルは、
「この状況で無駄なことに時間をかけるのは良策とはいえないとわたしは考えます。大草原へと人が出払っている今の内に急ぎ進むべきです」
と、強硬に主張する。
どちらもある意味正論である。【NAME】は小さく唸って頭を掻いてから、軽く吐息。
──こういう時は妥協案か。
取り敢えず、速度を緩めつつも森を進む方針をノエルに提案してみる。今の彼女の状態ではそれも辛いのではないかと想像できたが、大草原での術式に当てられたというなら、身体を完全に休ませずとも時間さえ過ぎてくれれば復調するかもしれない。
「…………」
彼女は何時もの無表情で暫く黙るが、渋々といった調子で頷いた。
自分が足手纏いになるのが気に入らない、という面もあるのだろうが──全く、面倒なことだと、ノエルに見えぬように小さく溜息をついてから、【NAME】は未だ足許が定かではないノエルを気にかけつつ、森を北へと歩き始めた。
・
緩やかな歩みで二時間程北へと進んだ頃だろうか。【NAME】の視界に、森を削って作られたアラセマ軍の駐屯地に良く似た構造の建物が並ぶ広場が映る。恐らく、ここが件のシニ設営地だろう。
シニ設営地は元々ガレー周辺のバラック群と同じく、遺跡研究を行う者達の拠点となる場所として作られたものであり、それをレェアと彼女に従う一派が占拠し、現在は彼女等の基地として使われているとの話だった。
いわば、敵の本拠地である。となれば、そこを突破してその奥に建つノイハウス遺跡へと辿り着くのは容易では無いのではなかろうか。
そんな予想と共に、【NAME】がシニへと入る手前。森の合間に張られた手製の柵越しに設営地内部の様子を覗き見たのだが。
「……?」
素直に首を傾げた。
【NAME】の眼前に広がったシニの設営地は、殆どもぬけの殻であるように見えたからだ。
陣地の所々に漂う気配から、恐らく【NAME】達とすれ違いに、シニに駐屯していた遺跡占領側の者達が大草原へと向っていったらしいことが察せられた。
そこに、まだ気怠げな雰囲気を漂わせたままのノエルが顔を出す。
「……【NAME】、これは好機であるとわたしは考えます。今ならシニを抜けられる。大草原での戦闘の結果がどちらの勝利に終わったのかは判りませんが、たとえどちらの結果になったとしても、わたし達が先生と単独で対話する機会は今しかないと考えます」
先生、という単語に【NAME】は軽く首を捻る。二つ名で“先生”を持つのはレェアでなくガレーに居るイェア・ガナッシュだ。しかしそれでは話が繋がらず、彼女の言葉の意味が判らない。
「──ああ」
疑問をそのまま口にすれば、ノエルは目を一度瞬かせ、僅かな間を挟んで小さく声を漏らすと、小さく頭を左右に振ってから下げる。
「……申し訳ありません。わたしが言いたかったのは二つ名としての“先生”ではなく、わたし個人としての先生という意味です。わたしにとってレェア・ガナッシュはこの世界にある様々な事に対する“先生”であったのです。あなたとの会話で使う呼称としては不適切でした」
謝罪を経て上げられる面に浮かぶ表情の暗さは、体調の悪さによるものだけではないだろう。どうやら、ノエルとレェア・ガナッシュには浅からぬ関わりがあったらしい。
【NAME】はその事について深く触れるか、さらりと流すかの二択に迷う。もう目前といって良い場所にレェア・ガナッシュが居る事を考えれば、なるべく彼女についての情報を得ておくべきかもしれないが、しかし今のノエルの様子と先刻までの体調を考えると深入りする問いを放つのも躊躇われる。
【NAME】は一息の間を挟んだ後、
(今は話し込んでいる場合でもない、か)
そう判断し、視線をノエルから再度シニ設営地のほうへと向ける。
よくよく観察すれば何人かの兵──というよりは盛んな都等に良く居るような学士の格好をした、到底兵らしく見えない者達の姿があったが、気をつけて進めば彼らに見つからずに設営地の中を抜け、北に見える建造物へと辿り着くことはできそうだ。
思い、【NAME】は改めて視線を北へ。無数に経つ天幕の向こうに聳える黒の建物を眺める。恐らくはあれがノイハウス遺跡、である筈だ。ガレーのどこか朽ちた廃墟めいた外観から受ける寂れた雰囲気とも、ヴィタメールの半円ドーム状という形状が醸し出す奇妙な雰囲気とも異なり、まさに城塞。現代の建物に近い外観と、堅牢の印象を秘めるその遺跡を暫し眺める。
「【NAME】、行きましょう」
告げるノエルの顔色を【NAME】は確かめる。まだ血の気は引いたままで多少動きも頼りないが、しかし先刻よりは確かに状態は良くなってきているようだ。
【NAME】が走れるかと訊ねれば、ノエルは面を上げて小さく頷く。その眼に偽りの色は無く、【NAME】はそれを信じて視線を前へ。タイミングを計り、人の気が最も失せた処で勢い良く飛び出す。
建物の影から影へとを渡り、目指す先は北に聳える城だ。何とか遅れずに追走してくるノエルの様子に気を配りつつ、【NAME】はシニを飛ぶように駆け抜けた。
四大遺跡 芯海の物語
――幻の庭の女賢者――
そこは奇妙な世界だった。
上へ下へと起伏しながら延々と、文字通り果てしなく広がる緑の草原がある。空は晴天ながらも太陽はなく、雲は見えども動きはしない。そよぐ風も、地に生きる動物達の気配も無い。
そんな平穏な、ある種異質な草原の只中に生まれたたった一つのアクセント。ぽつんと生えた大樹と、それに寄り添うようにして広がる、小さな小さな森があった。
緑の葉を一杯に纏った大樹の根元には、こじんまりとした木造の家があり、【NAME】と彼女は、その家の真中に置かれた木机に、向かい合って座っていた。
・
【NAME】は諸島へ渡ってからノイハウスの遺跡へとやってくるまでの事──神形器の所在のみをぼかして──を漸く話し終え、一息つく。対する女性は、己の前に置かれたカップを手で弄びながら、うーんと小さく唸った。
「成る程ね。イェアの遣いであの子──ノエルと一緒にこんなとこまで、ね。そりゃまたメンドクサイコトに巻き込まれたもんだね、君もさ」
銀の髪を軽く横に流した彼女は、苦笑交じりにそう言う。彼女がレェア・ガナッシュ──ノイハウス遺跡を占領する者達の頭であることは、平原の只中で気を失っていた【NAME】を連れてこの一軒家へと辿り着く間に聞いていた。
メンドクサイコト。確かにそうだ、と【NAME】はレェアの浮かべた苦笑に釣られて笑い、軽く息をついた。ガレーでのイェア・ガナッシュの探索やヴィタメール前でのキヴェンティ野営陣への潜入劇。ノイハウスへは大草原での大戦を経ての先刻の現創領域での闘い。それらは文字通り、面倒極まりないものだった。
そんな仕草に、レェアは笑みの色を濃くする。
「くく、全く面倒事だと思うよ。コルトレカンに出たっていう大禍鬼の討伐に関わっただけでイェアに目をつけられて、常駐軍と正面切ってドンパチやってる連中の本拠地に、こうやって単身潜入する羽目になったっていうんだから。いやもういつ死んでもおかしくないって処?」
冗談めかした言葉に、釣られて苦笑。だが、レェアはそんな【NAME】の態度に笑みを引っ込め、少し真剣な表情で忠告する。
「……ホントに判ってる? 先刻だって、対侵入者用の“現創領域”が壊れて、元の空間へと整調化する時に起きる揺り戻しに飲まれかけてた貴方達をここに──私が個人的に使ってる“現創領域”に引き摺りあげて、こうして匿ってあげたから良かったけど、あのままだと存在概念が変質してカタチを維持できなくなって砕けて死ぬか、それとも精神が壊れるか。運良く無事に空間の揺り戻しから抜けられたとしても、出る先は私の部下連中が作業してる処のど真中だ。どう転んでも、貴方にとっては楽しい結末じゃなかろうね」
「…………」
言われて、流石に背筋が薄寒くなってきた。顔色を変えた【NAME】を見て、レェアは満足気な顔になる。彼女の意地の悪さが顔の裏に透けて見えた気がした。
「まあ、確率的に脱出する可能性は一番高かったんだろうけど、ノエルも無茶な提案したものね」
彼女は肩を竦めて、部屋の北側にある扉を見る。扉の向こう、隣の部屋に置かれた寝台では、ノエルがまだ眠りについている筈だ。
(そういえば)
ふと、思いつく。
この遺跡へ入ってのノエルの不思議な力。それに、大草原を抜けて直ぐの唐突な体調不良。遺跡に入る直前、ノエルはレェア・ガナッシュの事を“先生”と呼んでいた。浅い間柄と言う訳ではないだろう。ならその事について──彼女が持つ何処かしら異質な雰囲気の根について知っているのではないだろうか。
強いて知りたい、と言う訳ではなかったが、想定外の事柄でこちらに不利な問題を引き起こす可能性も考えれば、少々詳しく把握しておきたい部分ではあった。
【NAME】の問いに、レェアは眉を顰めて首を傾げる。
「うん? あれ、イェアから聞いてない? あの子の事」
聞いていない。
あくまで彼女の部下、しかも同じ家名を持つ部下であるというだけしか知らされていなかった。
「ふん。“四大遺跡”にノエル連れてくるなら話しとかないとアブナイでしょうに、ったく相変わらず抜けてるな、我が妹は」
レェアは呆れ混じりに肩を竦めると、仕方ない、といった調子で口を開く。
「あの子は“亜人”なんだ。いや、こういうと勘違いさせるか。亜人は亜人でも一般で言う亜人でなくて、もう少し括りの大きい亜人というか──要するにあれよ、人じゃないの」
(……人では、ない?)
しかし、今まで彼女と一緒にそれなりの期間旅をしてきたが、不自然な処は多少あれど、人間の範疇から外れる程のものではなかったような気がする。
いまいち納得できず首を傾げる【NAME】に、レェアは笑いながら言葉を続ける。
「ああ、まぁ人じゃないっていっても、細かい部分で見た話だよ。あの子は、今はもう無いんだけど、“四大遺跡”の一つに数えられるゴディバ遺跡。常駐軍が来る以前に島中の遺跡を調査してた時に見つけたのよ」
ゴディバ。確か、アノーレの北部にある遺跡で数ヶ月前に謎の爆発があって消滅した場所だと、何処かで聞いたのを思い出す。
「アノーレの“四大遺跡”は、それぞれ独自の研究を行っていた施設でね、ノエルはゴディバで行われていた実験研究の一環で創られた“端末”というか“手足”みたいなもので──っと、この辺は知識がないと判りにくい話だな。どう説明したものか……ああ面倒臭いな!」
何やら勝手にテンションが上がって来たレェアを何とか諭して、専門的な部分を省いた説明を頼む。彼女は「判っている」という風に手を振った。
「──つまりだね。ノエルは遥か過去に遺跡を作った連中、“芯なる者”っていう奴等が研究用に作成していた人間なんだ。だからあの子は普通の人には無い能力を幾つも持ってるし、逆に本来なら持っている筈の能力が無い。例えばあの子の知覚は特別で両眼は概念的な歪みを直視できるし、身体に概念を取り込んで内部処理を行ったりできる。替わりに、心に影響を与える精神的な概念干渉には人よりも弱かったり、内部骨格とかは女性のソレなんだけど性徴は殆ど無い、無性別と言って良い身体だったりする。そんな子なの」
彼女の特殊性。それは過去に手を加えられ創られた存在であるという部分から来ているのか。
独りごちるように呟いた【NAME】に、彼女は頷く。
「そうなるね。ゴディバの遺跡の奥のほうで、“停滞殻”っていう、遺跡に良くある保存用の棺みたいなのに入っててね。私が調査した時に殻を開くまでずっとずっと、長い間眠ってたのさ。最初は、遺跡が造られた時代の話を聞けるかと期待したんだけど、どうも創られて一度も目覚めずに今まで放置されてたらしくって全然ダメでね。まあだからといって捨てるのも何だし、私が連れ歩いて色々教えて育ててたという訳」
だから、“先生”という訳らしい。
「あの子、元々ゴディバ遺跡の基幹を中核とした連動操作機構の一端末として組み込まれるために作られてたらしくてね。機構自体は吹っ飛んだ今でも、“四大遺跡”の奥とか、概念的に強い存在の傍に近づくと精神が不安定になって、多分下手すると自我崩壊起こす。だから一緒には連れてこなかったんだけど、まさかイェアがあの子を遣いに出してくるなんてね。やられたわ──」
そこまで言って、レェアは何かに気付いたかのようにはっと顔を上げて、そして心底可笑しそうにくくく、と笑い出した。
「……そうか。こうなる事を予想して出してきたんでしょうねー。こっちが気になって手を出してくるだろうからって、あの狸め。人は良い癖に妙なトコで腹黒いんだから」
ガレーでのイェアの態度を思い出すに、そういった思惑は無しでノエルを遣いに出したような風ではあったが、何やら酷く楽しそうに笑うレェアに水を差すのも何なので、訂正はせずに苦笑いで流す。
と、そこで。
「──ぁ、う……あ?」
「お?」
隣の部屋から小さな物音と共に、どこか寝惚けたような気の抜けた声がした。
「ノエル、起きたみたいだね」
レェアは「よっこいしょ」と年齢に似合わぬ年寄り臭い声と動作で席から立つと、ノエルの居る隣室の扉へと歩きながら、【NAME】を見てこう告げた。
「じゃ、あの子の様子を確かめてから、改めてお話と参りましょ」
・
「先生。冗句の類は無しでお答えください」
一つのテーブルを囲む、【NAME】、レェア、そしてノエル。ノエルの体調は未だ良好とは言い難く、顔色は青く椅子に腰掛けた身体も時折左右に危なげに揺れる。目を覚ましたノエルを簡単に調べたレェアはノエルの不調を考え、もう少し寝台で休んでいるよう告げたのだが、しかしノエルは強硬にそれを拒み、こうしてレェアとの話し合いの席に身を置く事を選んだ。
「何故、このような事をしたのですか?」
普段はどこか茫とした気の無い風に話すノエルの、いつに無く気合の入った真剣な調子の問い。それを受けて、対面に座るレェアは、一体何を言われているのか考え込むかのように小首を傾げ、一拍。
「何故って、自分の弟子が今にも結界消滅の余波に巻き込まれそうだったから、慌てて助けに入ったんだけど、拙かった?」
おどけた調子のレェアにじっとりとした半眼の視線を暫く寄越してから、彼女には珍しい強い不機嫌という感情を乗せた声音で、もう一度ノエルは言葉を紡ぐ。
「……先生。何故、このような事をしたのですか? それに──イェアに何も告げずに、こんな。とても、とても心配していました」
言われて、レェアは、あー、と気の抜けた逡巡の後、正に苦笑いといった表情で軽く自分の髪を弄る。
「イェアに云わなかったのは、単に巻き込みたくなかったからなんだけど……こうも積極的に関わってくるなら素直に話しとけば良かったかもね。あなたにも」
す、とレェアの手が伸びて、対面に座るノエルの頭をぐりぐりと撫でる。ノエルも僅かに怒ったような顔で小さく唸りのような声を出しつつも拒絶しない辺り、二人の間にはそれなりの絆というものがあるらしい。
そのまま自分の気が済むまでぐりぐりと続けると、レェアは姿勢を正して【NAME】を正面に見た。
「さてと。じゃ、さっさと本題に入りたいとこだけど、直ぐに言っても理解できないだろうから、まず前説だ。君の素性が単なる冒険者だとすると、“四大遺跡”の特殊性、それにアノーレ──フローリア諸島の歴史とか、この辺の知識が全然無いだろう。ノエルには一度簡単に話したか?」
「酷く曖昧かついい加減にではありますが、覚醒初期に一通り教わっています」
「何気に酷い言われ方をされている気がするが無視して行くわね。なら復習がてら、疑問点やら補足やらを思いついたら入れていきなさい」
ノエルがこくりと頷くのを見て、カップに一度口をつけた後、レェアは表情を改めると【NAME】の眼を真っ直ぐに見据えて、
「じゃまずノイハウスとヴィタメール、この二つの遺跡をどうして占領しようとしたのかっていうとね。“四大遺跡”が持ってる芯形機構としての力、過去に起きた“鬼芯属”との戦いの為に利用し──いや、それよりも先にフローリアの歴史辺りから話したほうがいいのかね、この場合?」
と、一瞬前まで真剣味に溢れていた顔から急に力が抜けて、隣のノエルを窺うように見やるレェア。
「…………」
聴く態勢に入っていた【NAME】は、肩透かしにあった形で僅かに姿勢を崩す。
そんな二人の様子を見て、ノエルはやれやれといった調子で吐息をついた。
「どういった結論に持っていきたいのか推測できませんのでわたしに聞かれても困りますが、まず“芯形機構”についての説明が必要ではないでしょうか」
「ん? 芯形機構くらいはわかるでしょ。“芯なる者”が残した大規模象形式駆動機構。建造物自体が式としての機能を持って、特異かつ強大な力を発する事が出来る。古代に造られ今に残る遺跡の殆どがこの芯形機構なんだから、遺跡に触れる機会の多い冒険者なら──む?」
レェアとノエル、二人の視線を受けて、【NAME】は「うう……」と肩を竦める。そういえば、はっきりとした知識は持っていなかった。
「あー、ごほん。まああれだ、大抵の遺跡は既に芯形機構としての力を発揮できなくなったものばかりであるから、知らなくても可笑しくない、気を落す必要は無いよ」
そんな【NAME】にレェアは半分笑いながらフォロー。余計惨めな気分になったが、口出しすると更に泥沼になるので何も言わずに彼女の話を聞きに入る。
「で、当然私達が今居るノイハウスや他の四大遺跡も芯形機構であって、それも機能を失っていない、“生きた芯形機構”であり、そして極めて特殊な能力を持つ遺跡でもあった。ま、芯形機構についてはこんなものだが、判ったかね?」
問いかけに、【NAME】は今までの彼女の言葉を懸命に頭の中で処理しつつ、【NAME】は取り敢えずこくこくと頷いてみせる。
「そ。なら改めて、コルトレカンやアノーレに暮らすキヴェンティ達や島中の遺跡から集めた様々な伝承、記録。その全てを纏めた上での、私が考えるフローリアの歴史、行ってみようか」
――芯海の物語――
「フローリアの始まりは、鬼の芯たる存在と、他の芯なる属との戦いにあるんだ。はるか昔。まだ人が歴史を作り出す前の、“芯属”と呼ばれる強大な力を秘めた種族群が世界の表側で生きていた時代があった。その頃に、起きた一つの大きな争い。“鬼芯”という、今私達の世界に蠢く鬼種達の元となる強大極まりない存在と戦う為に、“芯なる者”と呼ばれる私達人間の祖を導いていたとされる芯属は、何も無い海から“鬼芯”との“戦場”として特化した専用の場を作り上げた。それが、このフローリア諸島なのよ。要するにこの島、作り物なんだよね」
あっけらかんとそう言って、レェアはずずずとカップに注がれた茶を啜った。
「…………」
対する【NAME】は沈黙。
何というか、突拍子も無い話としか言いようが無い。
半ば茫然としていた【NAME】に気付いて、にやりと笑みを浮かべた。
「あ、呆気に取られてる? でも、【NAME】。先刻君が話してくれたコルトレカンでの出来事から推測すると、君は見たんじゃないか? 私の話の証明となる事。そう、例えば“鬼芯”を封じていた、檻の一部を」
言われ、【NAME】の脳裏を過ぎるのは、あの“黒い切り株の向こう”でのユーリの言葉だ。
『フローリアの島々が“鉄格子”だとすれば、ここはさしずめ“檻の中”』
息を呑んだ【NAME】に、レェアは更に笑みを濃くした。
「思い当たる事があったようだね。“大禍鬼”が極めて上位に位置する鬼種と呼ばれるのは、他の鬼種のように陰性概念飽和による自然発生や、存在概念を汚染されることで“堕ちる”妖魔化でなく、“鬼芯”から直接生まれ落ちる“生粋の鬼”が多いという点が大きい。コルトレカンの“大禍鬼”は、多分自身を生み落とした存在に惹かれたんだろうな」
──どうだっただろうか? 【NAME】はあの時のユーリの台詞を思い出そうとして、
「ああ、その“大禍鬼”は今の話には直接的に関係ないから、そんな考え込まなくても良いよ」
それをレェアの声に遮られる。
「で、そういった事実が示すように、“鬼芯”と他の芯属との戦いは、芯属側の勝利で終わったんだ。芯属達はその持てる力を発揮して“鬼芯”を打ち倒した。そして、この諸島の土地概念と、地に通る魂の源たる“命脈”を結びつけて檻として、フローリアという土地の根元へ彼の存在を封じ込み、“鬼芯”が持つ陰性概念を徐々に浄化させる事にしたらしい。フローリア諸島が見つかったのはここ10年程前の事だけど、それまでこの諸島が見つからなかったのは、“鬼芯”の浄化が完了するまで島全体に敷かれていた隠匿結界のせい。それまでは、この島はほぼ完全に外から遮蔽された世界となっていた。──因みに、この島の原住民であるキヴェンティ達は、その頃に芯属の一つである“翆獣種”の眷族として連れられてきた者達の末裔、という事らしいね。彼らの残した伝承からすると」
一気にそこまで言って、ふぅ、とレェアは一息つくと、喋り続けて乾いた喉を癒す為か、カップを手に取り中身を口に含み、もう一度吐息。
「まあ、そういった経緯で“戦場”として造られたこの島には、“鬼芯”に対抗するための仕組みが幾つも作られていた。その代表が芯形機構。私がフローリアを調査して、まず驚いたのは遺跡の多さね。そして大抵の遺跡は戦闘か、それに補助する芯形機構を備えていたのが調査で判った。尤も、見つかった遺跡の殆どは壊れていたけどね」
と、レェアは何かを思い出したように苦く笑う。
研究者として調査を行っていたならば、遺跡の殆どが壊れていたと知った時の落胆は大きかった、と言う事だろう。
「まぁそれでも、“生きた芯形機構”の数は他の地域よりは圧倒的に多かった。そんな遺跡群の中で、アノーレの“四大遺跡”は更に特殊で、“鬼芯”との争いが始まる間際に創造された、それぞれ独自の研究実験を行う為の施設であり、他の遺跡──“芯形機構”とは大きく異なる点が一つあった。ここ、ノエルは覚えてる?」
「はい」
突然話を振られたノエルだが、しっかりと流れについてきていたらしく淀みなく答える。
「その特殊さは発現する能力ではなく、遺跡が生み出す力の属性、質、基点にあった。“鬼芯”より生まれ、近しい相の存在概念を持つ“大禍鬼”。彼らを捕らえ、その存在概念をフィルタとして発揮された力は“鬼芯”に対する親和性が高く、うまく調整すれば通常の手段より効果的な攻撃が可能となるのが“芯なる者”達の間で知られていた。四大遺跡は、それと“命脈”を組み合わせる研究の為の施設であったと、私は教わりましたが」
「うん、合格だな。相変わらず優秀な生徒だね」
レェアは満足げな笑みと共にノエルを一瞥してから、【NAME】へ視線を戻す。
「アノーレにある四つの遺跡では、それぞれ別の“大禍鬼”を封じ、別のアプローチによって研究、調整が行われたんだ。各遺跡に残された断片的な資料によれば、四大遺跡で行われていた研究物は“鬼芯”との決戦には間に合わず、用を失った四つの施設は途中放棄という形で捨て去られたものの、遺跡深部に封じられた“大禍鬼”はそのまま放置され、フローリアは結界によって閉じられた」
──それは、危険ではないのだろうか。
【NAME】の独り言のような呟きに、レェアは大きく頷いた。
「根本に鬼種という陰性概念の結晶のような存在を配置して“命脈”の力を引き出すような機構が、生きたまま放置されていた。これだけでもかなり危険だったんだけど、遺跡の機構が完全に眠っていたお陰で、最近までは大きな問題にはなっていなかった。……でも」
「でも?」
ノエルの促す鸚鵡返しに、レェアは一つ大きな溜息を挟んでから続ける。
「ゴディバが原因不明の爆発で吹き飛んでから、それの影響が同じ“命脈”を使う機構である残りの三遺跡にも出始めたの。奥に封じられてた“大禍鬼”と、遺跡の機構が徐々にであるが活性化を始めたのよ。で、そのせいで遺跡奥の陰性概念が外へ漏れ出して、周りの土地概念を汚染し始めたりと、拙い事が色々と起き始めたんだ。でまぁ、色々考えて、これは私だけで原因を無くしてしまう事にしたの」
それは、つまり。
「そうよ。私は、アノーレの“四大遺跡”の機能を止めるつもりで、ここを占拠したの」
・
「判らない。理解できません」
「何が?」
硬い表情でレェアをじっと見るノエルだが、対照的にレェアは楽しげな笑みを作る。ノエルはその態度に苛立ったように顔を顰める。
「あなたが所属していた組織、アラセマ常駐軍こそ、そういった危険な遺跡を破壊封印する事を己が任とした組織でしょう。なのに何故あなたはそこから離れて、こんな事を」
それもそうだ。遺跡の破壊が目的ならば、常駐軍という集団からわざわざ離れ、しかも彼らと敵対までするリスクを背負う必要は全く無い筈だ。
だがレェアは、ノエルの言葉を理解できないというように眉を寄せる。
「そんなの、少し考えればすぐ判るでしょうに。簡単に云ってしまうと、私は常駐軍が信用できなかったのよ。ちょっとね、遺跡の力が魅力的過ぎると思ったのよ。アノーレに来てるアラセマ常駐軍──第十二師団の上二人、カナード・フハールはどうも退廃的で何するか判らないところがあったし、クスィーク嬢のほうも方向性は違うけど結構似たような感じでね。ちょっとモラル的に壊れた処がたまに見えたから。遺跡の力を自分の利のために利用しようとするかもしれない。知ってる? 彼女、カナード・フハールの為なら何でもやるタイプだよ」
と言われても、【NAME】にはアノーレの常駐軍上層の位置する二人のひととなりなど知る筈も無く、答えようが無い。
仕方なく、こちらよりは知識があるであろうノエルに視線を送る。彼女の顔に浮んでいた表情は、疑問のそれだった。
「先生? カナード団長の事は殆ど存じませんが、副団長は誠実かつ公正な方であると、ガレーの人々の間では噂されておりましたが、違うのでしょうか?」
対して、レェアは軽く片手を広げて肩を竦めた。
「外面はねー。あいつ、私の勘だと結構捻れてると思うよ。──まあ、軍に任せられない理由が他にもあるのは確かなんだ。今、アノーレの土地は、それぞれの四大遺跡の奥に封じられた“大禍鬼”と、島の地底を幾つか通る魂の根元たる力の地脈、“命脈”とが深く繋がって、ゴディバの消滅で揺らぎはあるけど、一応バランスが取れている状態。ここから三つの遺跡を更に壊したら……ノエル、どうなると思う?」
「“大禍鬼”ごと崩滅させることで、鬼というフィルタを通して陰性へ変質した“命脈”の力の漏れ出しは収まりますが、“大禍鬼”を含めた形で均衡を保っていた島全体の土地概念のバランスが、消滅という形でパーツを失うことによって──崩れる、という事でしょうか」
「そう。遺跡の破壊は、言ってみれば“命脈”という水の入った容器の口を壊してしまうようなもの。封を失い、地表に吹き出る力の乱流は土地概念の安定を乱す。一時的にだけど概念の歪みは増して、多分今以上にアノーレは危険な場所になる。気候が安定しなくなって天災が当然増えるし、中心となる遺跡周辺の土地は完全に安定を欠いて異質地形に変貌するか、下手したら完全に“壊れる”かもしれない。鬼種の発生も増えるだろうし、もしかしたらアノーレの外へ、他の島々にもその影響がでるかもね。そんなリスク、軍が背負える訳がない。でも、私とリゼラ君にはちょっとした策があるし、それに失敗したとしても組織を離れてやるなら、全部の責任は私に回ってくるからね、それなら問題ないじゃない?」
それは、詭弁だ。取れない責任を負ってどうするつもりか。
「ま、ね。でもたとえ詭弁でも、完璧に押し通してしまえばそれで世界は動くものだから。それに今の状態で放置していたら遺跡を中心とした地点からどんどん土地概念が汚染されていく。一年もすれば均衡を保てなくなって、一気に島中が汚染されるわ。そうなれば結果は私達が失敗した時と同じ──いえ、もっと酷い状況になるかもね。だからさっさとカタをつけるために、私は行動したって訳だ。……まあ、私が常駐軍を退ける為に“現創”の力を借りてるのもあんまり良くないんだけど」
レェアは茶を飲もうとカップを手にとって、それがもう空だと判ると思い切り顔を顰めると、全く手の付けられていなかったノエルの前に置かれたカップをひょいと奪う。そんな彼女の行儀の悪い行動など目に入らぬようにレェアの顔を眺めていたノエルは、レェアがもう冷えた茶をずるずると飲み始めたところで漸く口を開いた。
「あなたと、そしてヴィタメールに居るキヴェンティ達はそのために動いているのですか」
「む?」
レェアの動きがぴたりと止まり、眼を数度瞬かせた後、ああ、と何か思いついたような声を出す。
「キヴェンティ──リゼラ君と私はちょっと目的違うけどね。遺跡の奥には“大禍鬼”が眠ってるっていったでしょ? あの子はキヴェンティの中でも原理主義というか、遥か昔に“翆獣種”が直々に自らの眷属たるキヴェンティの先祖に残したらしい“鬼の存在を見つけ次第、何物にも優先して断て”っていう言葉を第一にして動いてるの。……まあ、ちょっとしたことで知り合って、その時の出来事を恩に感じて私に付き合ってくれてるのかも知れないけれどね」
そこまで言って少しの間の後。レェアはふぅと長く大きく息をついた。
「取り敢えず、私達が何をするつもりか、っていうのはこんな処ね。イェアがこれ聞いてどんな反応するかはちょっと興味あるけど、一緒に見にいく訳にも行かないから諦めるわ」
ひらりひらりと手を振って見せたレェアからは、己の妹とはもう会えないかもしれないという悲壮感などは一切無かった。そういった感傷とは無縁の人物であるらしい。
(……ふむ)
話が一段落したと見て、【NAME】は今までのレェアの長話を整理する。
大筋の流れは掴めたが、幾つか疑問に感じた事がないでもない。
まず、彼女達はノイハウス、ヴィタメールという二つの遺跡を今占領しているが、残されたガレーはどうするつもりだったのか。
そして、遺跡破壊後の土地概念の均衡の崩れとかいう、【NAME】にはいまひとつ理解できなかったが何となく重大そうな件に関する手立ては考えてあるのかどうか。
「あー、その辺か」
訊ねると、彼女はがりがりと頭を掻いて照れ笑い気味の顔を作る。
「ガレーは封じられた“大禍鬼”がかなり危ない奴だったのか知らないけれど、奥の方に“閉ざされた扉”っていうすごい強烈な封印が施された扉があってねー。私やリゼラ君の力ではどー頑張っても開けられそうに無いから、搦め手で行く事にしたんだ」
「搦め手、ですか?」
ノエルの言葉に、レェアはああと頷く。
「ノイハウスとヴィタメールを破壊した後、地の底に流れる“命脈”を私が何とか操作して、ガレー遺跡との“命脈”の連結を解いてしまおうってね。そうすればあの遺跡に残るのは封じられた“大禍鬼”だけってことになって、外に何かが漏れ出してこなくなると思うから」
は? と【NAME】は首を傾げる。そんな事、本当に出来るのだろうか?
「理論上はね。実は遺跡破壊による土地概念の不安定化は、解決法はもう考えてあるの。例えば、今ノイハウスは“大禍鬼”という存在を中核に置き、底の“命脈”と繋がって、遺跡は“現創”という力を発現させている。この“大禍鬼”が行っている部分。ここを私の存在概念を丸ごと使って肩代わりしようって考えてる。陰性概念の塊である“大禍鬼”でなく、ニュートラルな人間の概念を使うなら、キャパシティは格段に落ちるけれど“命脈”から吸い上げる力が偏った方向に変質することはないから、問題は解消される」
「……先生、それは」
と、表情をいつに無く険しくして、ノエルが言葉を詰まらせた。
「あなた自身が肉体を完全に捨てて、己という概念全てを“命脈”と交わる──つまり、死んだ自分の精神を遺跡の一部として変質利用する、という事ですか」
「正解。貴女は時々妙に察しが良くなるね」
冗談じみた言葉で返すレェアを意に介さず、ノエルは真剣な表情のまま、問う。
「本気ですか?」
「うん。ま、個としての性質を残したままでの、“命脈”との同化。これは元々私の目指してたことなのよ。元々こっちに来てたのも“命脈”の研究が主だったし、望む処でもあるのだよね。丁度良い踏ん切りがついた。これに成功すれば、この生の身体は死んだとしても意識として何とか残ることが出来る。だから問題ないわ。これやらないと、ノイハウスの“大禍鬼”も吹っ飛ばせないし」
「…………」
ノエルは両眼を閉じて暫し無言。そして、
「……当人がそう言うのでしたら、何ら問題はないと私は考えます」
テーブル上の空白へと視線を落とした彼女を、レェアは困ったような顔で見てから、【NAME】へと視線を移す。
「で、その状態で私から“命脈”に接触して微弱ながら制御を行って、ヴィタメールとガレーの土地に繋がっている流れをほんの少し曲げる。これくらいは出来ると思うし、ガレーに残る“大禍鬼”は“命脈”との連結を切れば何とかなるでしょうから、残った人たちに任せるわ。まあリゼラ君が動いてくるかもしれないけど。──他には?」
専門的な知識の無い【NAME】にはこれ以上聞くべき事は何も思い浮かばない。ノエルを見ると、彼女も僅かに顔を上げてこちらを見て、小さく首を横に振った。
・
「なら講義は終わりね。さて、君達の目的は“調査と調停”だったか? これで前者は達成されて、後者は私達がそれを受け入れる気は毛頭無いって事を理解して欲しいのだけど、どうする? 戻るなら、私が内緒で遺跡の外へ──、ッ!?」
と。
突然、がたん、と椅子を蹴倒しながらレェアが立ち上がり、じっと何もない方向、木製の屋根の一角を見つめて動きを止める。
「先生? どうされました?」
ノエルが怪訝な顔で立ち上がったレェアを見上げ、訊ねる。
「……遺跡内に張った印章での警戒網に何か引っかかった」
レェアは彼女を見ず、小さく舌打ち。
「君達とは別口の侵入者が来てる。話していて気付くのが遅れたな。それに、先刻から視てると、“現創”の結界を器用に避けて、遺跡内に配置した亜獣は一瞬で滅ぼし、しかもそれが判らぬように替え玉まで用意してる──これは、まずい。何者?」
最後はまるで独り言のような調子で呟く。何やら事件が起きているらしいことを感じ取り、腰を浮かせる【NAME】。
その仕草に反応したか、虚空を見つめていたレェアが唐突に【NAME】達の方へと視線を落す。
「御免、私ちょっと行ってくるわ。出来れば、君達も手伝ってくれると嬉しいんだけど……どう? 侵入者が常駐軍の奴なら裏切りって事になっちゃうけど、あの風体はどう見ても軍人っぽくないし、多分大丈夫だろうと思う。さっき“現創結界”から拾ってあげた恩返しって事で、ね」
反射的に隣に座るノエルの顔を窺うと、彼女は判断を任すという表情でこちらを見ていた。
【NAME】は視線を外して少し逡巡する。が、迷いは一瞬だ。確かに先程助けてもらった恩があるし、第一ここで彼女の機嫌を損ねたらこの草原の空間の外へも出れなくなってしまう。彼女の要請を是とする以外あるまい。
【NAME】が短く頷くと、ノエルはそれを見て僅かに嘆息。
「……判りました、お供します」
云って、ゆっくりと立ち上がった。そんな二人を見て、レェアは難しい表情の中に一瞬だけ笑みを混ぜつつ右手を大きく掲げた。
「よし、助かるよ。じゃ、少し急ぐから荒っぽいけど許してね」
ぱちん、と高く上げた手の指を鳴らす。
──同時、周りの風景がまるで鉄の一撃を受けた硝子細工のように、甲高い音を立てて砕け散った。
四大遺跡 灰色の闖入者
――灰色の闖入者――
突然の景色の破裂に【NAME】は反射的に目を閉じて、開いた時には周囲の風景は青と緑に囲まれた草原から、硬質の黒を纏った鉄壁に覆われた長方形の大広間へと変化していた。
広間の中央に立つのは、レェアとノエル、そして【NAME】。草原の小屋に置いてあった荷物はそのままこの場に移動されており、ノエルの手には彼女愛用の黒銃が収まっている。レェアの方も、ノエルの銃に良く似た──しかし二回りは巨大な大銃を自身の足許に置いていた。
レェアは肩に掛かった自身の髪を弾くと、【NAME】達の方を向く。
「最後に視た位置から推測すると、侵入者はもう直ぐここへやってくる筈だ。待ち伏せて叩く。良い?」
状況に流されている気がして仕方ないが、協力すると言ったからにはやるしかない。【NAME】は沈黙のまま頷きだけで答える。
「そう。ならまず見つからないように隠れるか。私が隠匿結界を形成──」
「──しなくても構いませんがね。もう到着済みですので」
「!?」
広間の一角。通路の入口から姿を現したのは、灰色の長衣に身を包んだ小男だ。手に持つ歪んだ長杖から察するに、恐らくは魔術師。状況から察すれば、こいつがレェアの言う侵入者だろう。
「いやはや、恐ろしい処ですなぁここは」
小男はゆっくりとした動きで完全に広間の中へと入ると、ある程度の距離を開けて【NAME】達と対峙する。
「幾多に張られた固有の閉鎖領域へ送り込む罠と、各所に配置された亜獣。それらを避けるために術式を使ったせいで、用は一通り済みましたが、予想より早くばれてしまった。……あなたが、レェア・ガナッシュですかな?」
「貴方、何者?」
レェアは険しい表情のまま、男の問いを無視して逆に誰何する。男は気にした風も無く、自らの顎を軽く撫でた。
「ふむ、どうしましょうかねぇ。名乗っても何ら構わないのですが、そうですなぁ」
「……いや、もう誰でもいいわ」
と、飄々とした調子の男の喋りが癇に障ったか、レェアは不快げな舌打ちを絡めて彼の言を遮る。
「だって、私の敵って事だけは判るから。ここで済ませた用ってのも、今から吐かすよ、“魔術師”」
レェアが地に置かれていた大銃の上部を手で触れる。銃各所から伸びた筒から白い蒸気が吹き、低く唸る音と共に何の支えも無く浮かび上がって、彼女の両腕の内に納まろうと動く。それに合わせて、【NAME】とノエルも己の武器を手に取りゆっくりと身構える。
対する小男は、おどけた様な軽い笑み。
「はは、いやはや。流石は“女賢者”殿、大した自信で。しかし、一つゴカイがあるようですなぁ」
小男の手が大きく動き、杖が大きく振るわれる。
その軌跡に沿って中空に穿たれるのは無数の印章。浮ぶ印章は繋がり動くと、空中に巨大な輪を作った。
「──ッ!? お前、それは」
「ははは、気付いたようですな。だが遅い」
驚きの声を上げるレェア。男はその声に小さな笑みを浮べ、更に杖を振る。
杖の動きを合図にして、輪の間には輝く無数の格子が浮び、その隙間を埋める空間の色が黒へと変化。黒の平面はぼこぼこと奇妙な泡を立てて、見るものに異質な気配を感じさせた。
「“開け、封印の檻[シールドケイジ]”」
言葉と共に、小男が杖を振る。
同時、輪の間を縫っていた光の網は消え去り、その奥から凄まじい闇の霧を纏った何かが弾けるように飛び出す。
飛び出してきた物は巨大な骨。頭部、頚部、腕部等と、細かに分けられた骨がそれぞれ飛び出して空中を漂うと、纏う黒い霧がそれぞれを結びつけ、一つの獣の姿を再現する。
大きく取られた広間の天井に達するかとも思われる巨大竜。飛び出した骨が作り上げたのはそんな化け物だった。
小男の身体が奇妙に揺れて、次の瞬間には骨竜の頭頂部に着地。【NAME】達を見下ろすと、にやりと笑う。
「という訳で、実はワタクシ、“魔術師”ではなく“召喚師”なのですよ」
そんな男を見上げ、レェアが忌々しげに鼻を鳴らした。
「……迂闊だったな。召喚師だとハナから判ってたら、ちんたら召喚する余裕なんか与えなかったんだけど。で、そんなの呼んでどうする気?」
「ま、そうですなぁ。最初はその気は無かったのですが、今の状況は都合が良い。“女賢者”殿が邪魔である事には変わりありませんし、ここで殺せるならば殺しておきましょうかね」
小男が手を掲げ、ぱちんと指を鳴らす。同時に浮いた小さな印章が空間に散り、そして。
「──ッ!?」
ど、と腹に響く音と共に、遺跡全体が一度振動する。そして完全な黒色であった筈の壁に、白い斑点が浮び、その領域を急速に広げ始めた。
「先生、これは──」
白の領域拡大は直ぐに収まるも、壁は斑模様に染まったまま。突然の異変に警戒心を強くするノエルに、レェアはぎしりと歯を鳴らし、答える。
「……遺跡との簡易連結が、“現創”の力が途絶えた」
そして凄みのある笑みを浮かべて、竜骨の上に立つ灰色の小男を睨み上げた。
「“現創”の効果を一時的に鈍らせる仕掛け──先刻の用ってのはコレ? あの野郎、始めっから私とやる気満々じゃない」
しかし男はそんな視線などものともせず、わざとらしい仕草で両手を振ると、
「いやいや、この仕掛けは後でコトを起こす時に使えるかと、物のついでに仕込んでおいただけでして、まさか今使うことになるとは夢にも。ま、面倒ですし言ってしまうと、あくまで今回の目的は調査。奥に在る“大禍鬼”の状態を確認しにきただけでしてな、今日争うつもりはなかったのですが」
「────」
レェアの視線が更に殺気立つ。
「お前、遺跡に“大禍鬼”が封じられている事を」
「無論ですな。その程度の事、判らぬ訳が無いでしょう」
「……何者だ、貴様」
「おやおや。先程ワタクシが名乗ろうとしたところ“誰でも良い”と仰られた記憶がありますが、気のせいですかね?」
心底可笑しげに笑う小男に、レェアが無言で両手の大銃を向けると、
「私の銃、“レーゼラーファール”が全力射撃可能状態になるまであいつ等の気を引いて。一撃で決めるから」
【NAME】とノエルに聞こえる程度の小声──しかし明らかに怒気を無理矢理押さえ込んだ風な奇妙な声音──で呟く。【NAME】とノエルが頷くと同時に、頭上から小男の宣言が届いた。
「それでは、開戦と参りますかね」
言葉と共に振り下ろされる長杖。骨の大竜が顎を大きく開き、身構えた【NAME】達に向けて凄まじい勢いで迫る!!
[BossMonster Encountered!]
battle
灰色の闖入者


「退きなさい、【NAME】!!」
背後からの声。聞くと同時に横へと飛び退き振り返れば、レェアの抱えた大銃の先端から空浮ぶ太陽をも上回る凄まじい光が灯り、極太の熱線となって竜へ向かって放たれる。
か、と甲高い音と共に、輝きが全てを貫いた。
「やったか!?」
広間が白一色に染まる程の強烈な光撃。その一撃は大竜を構成する骨の大半を蹴散らし、斑色の壁に当たると飛沫となって散り消える。
この一撃で、竜は墜とした。後は召喚師である小男に止めを差すだけだ。
「──いやはや、流石ですな」
しかし、消滅していく竜の姿を眺め、後退していた小男は杖は手にしたまま拍手。
(……まだ、余裕があるのか?)
召喚獣は倒した。男が再度大召喚を放つ間など与えるつもりは無く、相手もそれは理解している筈。なのに何故。
訝しげな【NAME】達を見て、男はふんと笑うと、
「だがそれでは勝てはしませんよ。“虚より吸え、黒の波動[ダークエナジー]”」
杖を大きく横へと振る。
その仕草に合わせ、散り飛んだ筈の闇の霧が唐突に濃さを増し、元の位置へと収縮。同時にその闇の中へと砕けた竜骨の粒が集まり、光撃を受ける前の姿へと瞬く間に戻っていく。
──身体を、修復させた?
唖然として呻く【NAME】に、隣に立つノエルが目を眇めて竜を見る。
「いえ、修復というより、元の状態まで“巻き戻った”ように見えましたが」
ノエルの呟きに、レェアが大きく舌打ちして頷く。
「ああ。恐らく纏わりついている黒い霧が特殊な付加式なんだ。あの骨、“死して生きる”という矛盾の状態で既に存在が固められていて、壊せない。骨と霧と召喚師との間の結びを解かないとダメだが……現状手が無い」
策を練る間も無く巨大な竜が顎を開き、その内側にどす黒い渦が宿る。黒色の吐息の前動作。避ける間は無く、避けたとしても倒す術を思いつかない、
ならば。
ならば、どうすれば。
──壊したいの?
その時、ちりんと。
鈴音と共に響く、いつか聞いた少女の声。
──死を生とする、あの止まった存在。
【NAME】はびくりと肩を震わせ、そして声の出所を見る。
──私も、あれはキライ。だから壊そう?
そこにあるのは首飾り。
流転の象徴、停滞を払う為に作られた神形器の眠る姿だ。
「…………」
壊そう? あの、竜の事か?
──うん。なら、私のカタチを望んで?
形。
言われて思い起こすのは、あの“黒い切り株の向こう”
──拘るモノを解す力。
ドレス姿のユーリが手に携えた、白色の輝きを纏う美しき剣身。
──縛るモノを解く力。
思い描いたイメージが、ふわりと浮んだ首飾りの形を崩す。
──留まる運命を動かす力のカタチを。
「【NAME】、それは」
ノエルの驚きの言葉に気付けば、自分の手の中には煌々と輝く剣身を備えた巨大な長剣、ゼーレンヴァンデルングがあった。
「まさか、神形器──君が持っていたのか!?」
叫ぶレェアの声もどこか遠い。今の【NAME】の意識を埋めるのは、
──さぁ、壊そう?
鈴音と共にそう促してくる少女の言葉だけ。
頭に響く言葉に、意志とは無関係に身体が動く。両手を柄に添えて、大上段に構えたゼーレンヴァンデルングを振り下ろす。
その軌跡に沿って光が爆発し、奔流となって前方へ。
「なんと──!」
竜が吐き出した闇色の吐息ごと、骨の竜を構成する何もかもを淀み無く消し飛ばした。
「……いやはや。驚いた」
闇の粒子となって跡形も無く散り、空間に溶ける。その中を、寸でのところで避けた小男は目を見開いて【NAME】が持つ白剣を凝視する。
「“流転の神形”ですか。あなたが何者かは知りませんが──そのようなモノがこの島にあるなら、あまり悠長な事はしていられませんな。早急に“始める”事にしましょう」
「待て、逃げるか!」
レェアの叫びに、小男は笑みのまま半歩引く。
「ええ、逃げさせていただきますよ。まあ、どうせ直ぐに会う事になるでしょうが、そろそろ“現創”を封じる仕掛けも時間切れですし、今日はここで」
「逃がしません」
と、そこで一歩前に進み出たのはノエル。腰だめに構えられた黒銃からは目で追えぬ速度で光の線が打ち出され、小男の身体を叩く。だが、
「──当たらない?」
男の身体が上下左右へと揺らぎ乱れ、光撃は何の障害も無く背後へとすり抜けてしまう。
「技法による完全回避、とわたしは推測します。逃げられます」
ノエルがそう呻く間にも男の姿は更に揺らぎ、ゆっくりと周囲の空間に溶けて消えていく。
そして完全に消え去る間際。悔しげに顔を歪めるレェアと、【NAME】とを順々に見て男は小さく笑い、
「では、ごきげんよう。“女賢者”殿に……“神形の操手”殿」
その言葉と共に、灰色の召喚師は【NAME】達の前から完全に姿を消した。
・
「参ったな」
レェアは大銃を地面に置いて、疲れの混じった吐息と共に呟く。疲れたのはこちらも同様と、ノエルは銃を引き、【NAME】も鈍い動作で武器を収める。
召喚師には逃げられた。あの人物が何者かは知らないが、先刻の会話から察するに、何やら大事を仕掛けるつもりらしいのは判った。が、実際どう動き、何を成すつもりなのか。
「取り敢えずだな」
重い沈黙を破るように、レェアが力を込めて声を出す。
「【NAME】、ノエル。君達は早くイェアの元へと戻りなさい。厭な予感がする。【NAME】の神形器は気になるけど、引き止めてのんびり調べさせてもらうような状況でもないし」
と、既に首飾りの形に戻ったゼーレンヴァンデルングを少し物欲しげに見るレェア。
「厭な予感とは、先程の男ですか?」
ノエルの問いに、首飾りに持っていかれていた意識を引き戻しつつレェアは頷く。口元に手をやり、考えながらといった調子で話し出す。
「ええ。あいつ、早急に始める、とか言っていたからね。ノイハウスの“大禍鬼”を調べて、そして今ここから撤退して何かを始めるというなら、四大遺跡に纏わる事……ガレーかヴィタメールのどちらかで何かをやるつもりなのだろう。だから、君達は急いでガレーへ戻りなさい。ヴィタメールのほうは私から警告を飛ばす。あいつ、恐らくは“師位”ではなくて、更に上位の“司位”クラスの術士──召喚司よ。しかも外法。多分、ロクでもない事をやるつもりだ。イェアのところへ、なるべく早く戻ってあげて」
今回の件についての報告もある。言われるまでもないと、【NAME】は小さく頷く。
と、遺跡全体からごぅんと鈍い音が一つ響き、斑状になっていた壁が黒一色へと変化した。
それを見たレェアの顔がぱっと晴れる。
「遺跡との連結障害が直ったわ。なら──そうだな、ティネ辺りまで飛ばす。ウチの連中が頑張ったせいか、常駐軍の連中は結局大草原辺りまでしか確保できてないから、ティネ近くまですっ飛ばさないとヘンなのに絡まれるかもしれないしね」
「あ……」
と、ノエルが何か言いたげに動いて、しかし何を言いたかったのか自分でも判らぬかのように言葉を詰まらせた。
そんな彼女を見て、レェアは数度瞬き。そしてふと笑うと、背の低い彼女に合わせるように僅かに腰を折ると、戸惑った顔で固まるノエルの顔を覗き込むように見る。
「ノエル、どうしたの?」
「あ、いえ、その……」
結局、言葉が出ずに口ごもってしまうノエルに、レェアは無言で笑みを濃くする。
そして彼女の手が伸び、ノエルの頭をくしゃくしゃと撫でた。
「大丈夫。きっとまた会えるから、安心なさい。今度の事が一段落したら、また貴女の“先生”に戻ってあげるよ。だから今はお別れね」
「……はい」
暫く成すがままにされたあと、ノエルは小さく呟いて下がり、【NAME】の隣に立つ。その様を見届けてレェアは一つ笑い、
「行きなさい、ノエル。そして【NAME】」
言って、ぱんと両手を叩く。
乾いた音が空間に弾けるのに合わせて光が瞬き、【NAME】の視界を一瞬にして白一色へと変化させた。