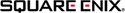四大遺跡 女賢者の弟子
──港にて──
フローリア諸島を構成する四つの大島の内のひとつ、アノーレ島。
コルトレカン島から南東へ進んだ先にあるというその島へ渡るため、【NAME】はリコルスの港に停泊する船舶を巡り、アノーレへと向う船を探した訳だが……。
・
【NAME】は港を巡り、三隻、四隻と島間航行が可能と思われる規模の船を回ってみる。が、その内のどれからも良い返事がかえってくることは無かった。
何れもコルトレカンとランドリートを結ぶ船であり、アノーレへと向かう予定は無いという。
コルトレカンとアノーレ、この二つの島は然程離れているわけではない。寧ろ距離だけで言えばランドリートよりもアノーレ島の方が近く、当然船の往来があってもおかしくは無い筈だ。
なのに、アノーレへと向かう船が全く見つからないというのは。
(──何か、裏があるのか?)
そう考えた【NAME】は再度港を回り、辺りに屯していた船員の一人を捕まえ、もう少し突っ込んで話を聞いてみることにした。
すると、
「アノーレ? ……ああ、知らないのかあんた」
そんな半ば呆れたような調子の声が返ってきた。
どういうことかと【NAME】が更に問えば、船員は面倒臭そうな様子ながらも話し始める。
「ランドリートとコルトレカンの間の海上封鎖が最近解除されたってのは幾らなんでも知ってるよな? だけど、実はアノーレとの間の封鎖はまだ解けてないんだよ」
初耳だった。
「だろうな。ま、完全封鎖って訳でなくて、今んところあっちへ行けるのはアラセマ軍の方から渡航の認可受けてる船だけなんだが、その許可ってのを取るのが結構面倒でな。審査もキツイ。だから今アノーレへ向う船なんか滅多にないし、あったとしても、あんたみたいなどこの馬の骨とも知らんヤツをわざわざ乗せてくれる訳は無いってことだ」
そこまで長々と話して、船員は【NAME】を見てきっぱりと告げる。
「要するに、諦めなってこった」
──はてさて。どうしたものだろうか。
・
アノーレ島へと渡ろうにも、肝心の船が見つからず。港に積み置かれていた木箱の上で、【NAME】は途方に暮れていた。
と、そこへ──。
「少し、宜しいでしょうか」
【NAME】の後ろから、細い声が掛けられる。
「……?」
無言のまま振り向けば、そこには一つの人影があった。
小柄な身体を仕立ての良い格式ばった服で包んだ、くすんだ金髪の──恐らくは娘か。造形に一分の隙も無い顔は全くの無表情で、整った服装や細い四肢も相まって、まるで品の良いお人形、といった雰囲気があった。
尤も──そんな上品な雰囲気は、彼女が背負う身の丈の半分ほどもある無骨な“大筒”が、見事なまでにぶち壊していたが。
(機甲師[マシーナリィ]……いや、銃士[ガンナー]?)
胡散臭げに、探るような視線を向けた【NAME】を、その娘は色の薄い両眼で真っ直ぐに見返してくる。
そして暫しの沈黙のあと、娘は小さく唇を開いた。
「突然申し訳ありませんが、あなたのお名前を、お聞かせくださいますか」
(──いきなり“お名前は?”と来たか)
【NAME】は素直に呆れた。物言いは丁寧だが、会話の基本というものがなってない。本来ならば無視するところだが──暇つぶしに相手をするのも悪くない。そう考え、【NAME】は彼女に短く名乗る。
「【NAME】。間違いありませんね?」
反芻するように呟く彼女に【NAME】が頷くと、娘は一度深く頭を下げた。
「申し遅れました。わたしは、アラセマ陸軍第十二師団に属する次階士位、ノエル・ガナッシュと申します」
アラセマ陸軍所属。それはつまり。
(……常駐軍の人間か?)
こんな小柄な娘が軍人だというのだろうか。【NAME】は胡散臭げに彼女を見る。大嘘だと切って捨てるのは簡単だが──しかし嘘にしては、相手に“それが本当だ”と思わせるための真実味というものがなかった。
【NAME】は暫し迷った後、その事には触れずにただ「何用か」と問う。単に名前を聞きたかっただけ、という訳でもあるまい。
「わたしの用件は一つです。わたしと共に、アノーレ島へと渡っていただけませんでしょうか」
若干の警戒の色が混じった【NAME】の声音に、ノエルと名乗った娘は淡々と答えた。
いきなりの──しかもこちらにとって至極都合の良い言葉に、【NAME】は片眉を顰め、無言のまま彼女を見返した。そのタイミングの良さも然ることながら、意図がまったく読めない。警戒するな、という方が無理がある。
不審げな【NAME】の表情に気づいたのか、娘は少し考え込むように視線を虚空へと移した後、改めて言葉を継ぐ。
「わたしの──そうですね、上官にあたる方。その方が、あなたのコルトレカンでの活躍を耳に挟まれまして。曰く、あなたはあの“殺すことのできない獣”をお斬りになられたと」
「…………」
どうやら、彼女が軍の人間だというのは間違いないらしい。
理由は簡単。あの事件はアラセマ軍の人間か、キヴェンティ達にしか知りようのない出来事だから。そして自然と共に生きるキヴェンティ達が、文明の結晶たる“大筒”を使うわけがない。
ノエルは、更に続ける。
「彼女はそんなあなたの力を、是非お借りしたいのだそうです。わたしは彼女の遣いとして、あなたの意思確認と、そしてアノーレへとお送りする任を受けてこの島へとやってきました」
力を借りたい。
それはつまり“仕事の依頼”と、そういうことか。
「そうなります。……ですが、その詳しい内容について、今ここでお話をすることはできません。依頼を受けるか受けないか。それだけをお答えください」
……仕事の内容が判らなければ判断の仕様が無い。どうやらこのノエルという娘、なかなか無茶苦茶な事を平気で言う人間であるらしい。
【NAME】は半ば呆れ顔で彼女に文句を言うが、
「申し訳ありませんが、部外の方にお話できるようなことではありませんので」
ノエルは酷く素っ気無い声で、そう返してくるだけだった。
「仕事を引き受けていただけるというのなら、港の方に軍の船がありますので、それで今直ぐにでもわたしとアノーレへ渡っていただきますが。どうされますか、ご返答を」
──女賢者の弟子──
ノエルの話に乗ることにした。
・
「判りました。では、こちらへ」
ノエルの先導で向かう先は、港より少し離れた薄暗い路地の奥。どう考えても、その先に軍の船がありそうな様子ではない。
(一体、どこに連れて行かれるのやら)
気楽にそう考えつつ、【NAME】は己の武器の柄に手を置く。添えるだけで、握ることはない。それ程気を張る必要も無いだろうと判断したからだ。
この先で何が待ち構えていようと、切り抜ける自信はあった。それだけの経験を、【NAME】は既にこの島で積んでいる。寧ろどこかワクワクと。一体“どの程度のモノか”と内心期待すらしているのだから──。
「度し難い」
「……何か仰いましたか?」
振り返るノエルに、【NAME】は無言で首を横に振った。
・
路地の終着は袋小路。前方を歩いていたノエルが、壁を背にゆっくりと振り返る。こちらに向いた彼女の無表情な顔。その奥に、僅かながらの緊張が見て取れた。
「アノーレへあなたをご案内する前に、ひとつ試しておかなければならない事があります」
ノエルは深く一礼した後、携えていた黒い大筒を一度地面に降ろし、改めて両手で持ち上げる。彼女の持つ鉄製の筒は俗に『銃』と呼ばれ、機械仕掛けの兵器を操る『機甲師』や、その中で銃術にのみ特化した技能を持つ『銃士』達が扱うものだ。そこから走る火線は目で追う事など適わぬ速度。技法以外での回避を許さない絶対の攻撃。
「あなたがわたし達の助力者足りうる力を、本当にお持ちなのかどうか。アノーレへと渡る前に、それを計らせていただきます。申し訳ありませんが、お付き合いください」
ノエルが軽く筒の側面を撫でると、その片側の先端に取り付けられていた二つの白い球体が音も無くふわりと浮びあがり、彼女を守るかのように旋回を始めた。
【NAME】を見据えるノエルの両眼が細く絞られる。
「手加減は、いたしません。“駆除”するつもりで行きますので、そちらも相応の覚悟を、お願いいたします」
どうやら、彼女は“やる気”らしい。
「…………」
自然に浮んできた笑みを、【NAME】は軽く掌で撫でて消した。
──全く、度し難い。
今度は心の内でだけ、そう呟く。呆れたことに、自分はこの状況を密かに楽しんでいるらしい。
一切言葉を発する事無く、【NAME】はただ己の武器を構えた。それを了解の意と取ったのか、ノエルは小柄な身体に合わぬ巨大な鉄筒を一度持ち直し、軽く腰を落とす。
「では、参ります」
[BossMonster Encountered!]
「流石、ですね」
軽い戸惑いを乗せた声と共に、ノエルは武器を引いて真っ直ぐに【NAME】を見る。
「申し訳ありません。正直、ここまでとは思っていませんでした。わたしは、あなたを過小評価していたようです」
云って、そのまま深々と頭を下げる。一つ一つの動作がどうにも大袈裟で、何だか馬鹿にされているような気がしてくる。だが、漂う気配や表情の色などから、彼女にこちらをからかうつもりなど毛頭無いのは容易に知れた。
(素でこういう子なんだろうな……)
そんな風なことを考えつつ眺めている間に、彼女はくるりと背を向けると船と港を繋ぐ桟橋へと歩き出す。
「では、参りましょう。詳しいお話は、アノーレの方で行います──あ」
と、感情の色が浮いた呻きと共に、歩くノエルの背中がぴたりと止まり、そのまま【NAME】の方へと振り返る。
「今から直ぐにアノーレへと向かいたいのですが、用意の方は宜しいですか? 問題があるようでしたら、一度お戻りになられても、構いませんが」
四大遺跡 船上の夜風
──船上の夜風──
今すぐアノーレ島へ向うことにした。
・
月は無く。
星すらも鱗雲に隠されて、黒く暗く沈んだ夜空。
風の流れが絶えた海上を、一隻の大型船が往く。
フローリア諸島を行き来する船舶の大多数は、海風を利用して進む帆船、大人数が櫂を使って動かすガレー船、そして極めて強力な印章石を動力として航行する魔動船という三種の何れかに分類される。
現在主流となっているのは人手、費用共に大して掛からぬ帆船──ガレー船は衛生面や効率性、魔動船は術式機構や心臓となる印章石の高価さに難がある──であるが、軍で利用される船舶の場合、帆船最大の弱点となる無風時の対策として、風受ける帆以外に何らかの補助的な動力を用意するのが普通だった。大抵は乗り込んでいる兵士の一部を臨時の漕ぎ手に回したりして補うのだが、中には短期間の駆動に限定した簡素な術式機構を積み込んでいる船も存在する。丁度【NAME】の乗り込んだ船が、それだった。
・
潮の匂いすら運ばない凪の海を、術式機構の力によって緩く波割る音だけを残して進む船。【NAME】はその船の甲板の縁に立ち、無言のまま空を眺めていた。
(……はてさて)
茫と黒色の空を眺めたまま。【NAME】はつらつらと思考を巡らせる。
あの港で出会った女──というより、少女と表現したほうが近いか──の誘いに、取り敢えず乗ってはみたものの。どうにも、そこからの展開は急としか言いようがなかった。
あれよあれよという間に船に乗せられ、間髪入れずに船はそのまま出航。気づいた時には既に大海原の上と来た。
そもそも、この誘いに乗って良かったのかどうか。それすらもまだ判然としない。
なにせ、あの“殺すことのできない獣”の件を聞いてのこの依頼だ。ロクなものではないのは明白。考えるまでもなかった。
(……なのに、ほいほいとついてきてしまっているのだから)
全くもって処置無しだった。
危険を避けず、寧ろ危険に身を委ねるようでは、この先、長生きできそうにない。できそうにないが──しかし、ただ単に安穏な生活を送るつもりなら、冒険者になどなりはしないのだ。
(まあ、一度受けると言ってしまったからには、腹を括らなければならないか)
そこまで考えてから、【NAME】は一度両眼を閉じて深く息をつく。肺に詰まった空気を全部吐き出したところで一拍。そしてゆっくりと海の空気を吸い込む。
「……兎にも角にも、まずもう少し詳しい話を聞いておかないと」
ぽつりと。そんなふうに、何とはなしに呟いた独り言に、
「そうですね」
背後から硬い、無感情な声が掛かった。
微かに生まれた動揺を殺しつつ、【NAME】は視線だけで振り返る。その視線の先には、長めの金髪を夜闇に梳かして立つ小柄な人影──ノエル・ガナッシュの姿があった。
・
「わたしも、もう少しあなたにお話した方が良いと、そう考えて今まで探していました。ここに居られたのですね」
言葉と共にノエルはゆっくりと歩み寄り、【NAME】の隣に並び立った。甲板の縁に身を預けることは無く、ただどこか茫とした表情を【NAME】に向けてくる。
「…………」
無言のまま立つノエル。そんな彼女を眺めていた【NAME】は、何とも言い難い気分になった。
こうして軍の船に乗っている自分達のことを考えれば、彼女が自らを軍人と言ったことは信じても良いと──少なくとも軍の人間か、それに近しい者であることは取り敢えず納得できた。そして、彼女が『機甲師』だという事も、あの港での戦いと、いま隣に立つ彼女の背に提げられた黒色の銃身が証明している。
軍人であり、そして機甲師でもある。
この二つの組み合わせ、それ自体は別段おかしくはない。アラセマ皇国からフローリア諸島に派遣されている幾つかの師団の中には、機甲師達を集めた部隊も存在する。寧ろ、より納得しやすい、信憑性の増す取り合わせといって良い。
──しかしだ。
その二つの要素に、『未成年の女性』という要素が加わると話が違ってくる。
実際の年齢を知っている訳ではないが、身長や体格を見る限り、彼女はどう贔屓目に見ても大人にはみえなかった。表情に乏しい、あまり感情の色が見えない顔のお陰で、纏う雰囲気自体は落ち着いてみえる。だが、それでも成人女性と呼ぶのは躊躇われる程なのだから、実年齢が一体いくつなのかは想像もつかない。
そんな少女が、フローリアに巣食う亜獣達を相手にするアラセマ常駐軍の人間で、しかも一撃で大型亜獣を屠る程の威力を具えた黒銃を操る機甲師なのだという。
何といえばいいのか。アンバランス極まりない。
「では、何からお話しましょうか」
──と。
無言を保っていた【NAME】に業を煮やした──という訳ではないだろうが、隣に立つノエルの方から声が掛けられ、【NAME】は実のない思考を途中で止めた。彼女の素性より何より、まず知っておかなければならない事がある。
そう。今回の仕事について。
まず知らなければならないのは、仕事の内容についてだった。これが判らなければどうしようもない。
そう告げる【NAME】に、ノエルは了解の頷きを一つ。
「これはリコルス港で申し上げた通り、詳しいお話は後ほど依頼者本人からという事でお願いしたいのですが、わたしが聞いている程度の事でしたら、今ここでお伝えします。今回、あなたにお願いするのは、内々での“調査”及び“調停”になります。改めてする程の話では無いのですが、現在アノーレでは、わたし達アラセマ常駐軍からの離反者が徒党を組み、“四大遺跡”の幾つかを占拠しているのはあなたもご存知かと、わたしは思います。それについてわたしの上官──」
(……?)
はい? と【NAME】は首を傾げる。ノエルは「あなたもご存知」とそう言うが、【NAME】にしてみればさっぱりご存知ではない話だった。
沈黙したまま、何とも言えぬ表情を浮かべた【NAME】に、ノエルは若干不信気な目つきを向ける。
「──【NAME】。あなたはアノーレ島の現状について、どの程度の知識をお持ちでしょうか」
全然。
「全然……とはつまり、アノーレ島についての知識は何も持っていない、ということですか?」
頷く。
「…………」
困った顔で黙り込まれてしまった。
暫しの沈黙のあと、ノエルはわかるかわからないか程度の小さな息をついた。
「判りました。では、アノーレ島についての基本的なお話と、そして現在の状況について。それだけをお話させていただきます」
そこで少し自分の考えを纏めるように少しの沈黙。
「──アノーレについてを一言で云い表すなら、そうですね。“危険な島”というのが比較的適切であると、わたしは思います。亜獣や妖魔は云うに及ばず、幾多の亜人種、そしてあの忌むべき鬼種も島の至るところに数多く潜んでいます。未だ軍の手すら入っていない、“真なる亜獣達の楽園”であるエルツァン島とは比べるべくも無いですが、しかしランドリートやコルトレカンの島と比較すれば、やはり危険な島であると、わたしは考えます。また、アノーレには多くの遺跡が点在することでも知られています。特に“四大遺跡”と呼ばれる遺跡群の内の三つ、ガレー、ヴィタメール、ノイハウスの三遺跡は、その規模も然ることながら、未だ遺跡それぞれが具えていた“芯形機構[グリフコンバータ]”の機能が停止していないという点で、非常に稀少かつ価値のある遺跡だと云えるでしょう」
このあたりの話は、実際に島を歩き回ってみれば直ぐに実感できることだとは思いますが──と、ノエルはそこまで言ってから一息。そして少し真剣味の混じった表情を浮かべ、改めて話し始める。
「では、次にアノーレの情勢についてお話しましょう。現在、アノーレは『戦争状態』と呼んでも差し支えない状況にあります」
黙って聞いていた【NAME】は、思わず、ぶ、と噴き出しかける。物騒なことこの上なかった。
「数ヶ月程前の事になるのでしょうか。アラセマ常駐軍に籍を置いていた者の一部が、島の原住部族たる“キヴェンティ”達と共に、先程述べた“四大遺跡”を調査していた軍の人間を襲って蹴散らし、内の二つの遺跡を占領してしまったのです」
キヴェンティ──その言葉を聞き、【NAME】は無意識に眉を顰める。“殺すことのできない獣”での件でも、キヴェンティと名乗るあの者達は深く関わっていた。このフローリアで起こっている厄介事には、全部首を突っ込んでいるのだろうか、あの連中は。
「彼等の目的ははっきりしていません。ですが、常駐軍に所属していた一部の人間が離反して“四大遺跡”の幾つかに乗り込み、既に数ヶ月は経った今も尚、軍が編成した鎮圧部隊を幾度も退けながら、遺跡の占領を続けているというのは厳然たる事実です。そんな状況ですので、軍も本来の役目である亜獣討伐が疎かになっておりまして、各地の亜獣達の動きも活発に。それに伴い、島に点在する街や村でも大なり小なりの混乱が起き、治安はより悪化する──あまり好ましい状態とは言えないでしょう」
【NAME】は、なるほど、と半ば呆れ混じりに頷く。なかなか楽しそうな状況にあるのは理解できた。何故だか頭も痛くなってきたが。
「今、わたしがお話できるのは以上です。それを踏まえての、先程の“調査”と“調停”というお話になります。わたしがお話できるのはここまでとなりますが、今回のあなたへの依頼がどういった内容であるかは、ある程度理解していただけたかと、わたしは思います。……如何でしょうか」
彼女は言外に、“話は終わりだ”と告げていた。更に詳しい話はノエルが言う処の“依頼者”に聞け、という事なのだろう。
これ以上彼女に何かを尋ねたところで、良い返事はかえってこない──そう判断した【NAME】は無言のまま、取り敢えず小さな頷きだけで是と返す。
ノエルは【NAME】の頷きを確認して一拍。視線を外すと、軽く己の前髪に手をやった。
「風が、でてきましたね」
ふと気づけば──確かに彼女の言う通りに、甲板の上を疾る海風は徐々に強くなり始めていた。それに合わせて、船員達の動きも慌しくなる。術式機構を停止させ、帆による操船を行う為だ。
ノエルは暫くの間、茫と風上の方角を眺めた後、視線を【NAME】に戻す。
「今日はもう眠った方が良いと、わたしはそう思います。日が昇る頃には、アノーレへ着いていると思いますから」
四大遺跡 力の象徴
――力の象徴――
意外、といえば良いのか。
昨夜、船上でノエルが言った通り、夜が明けて空の東端に日が昇り始める頃には、船は何事もなくアノーレへと辿りついた。
てっきり、いつものように航海の途中で亜獣なり何なりが大登場なされて、平穏無事にアノーレへ到着する事など在り得ないのだろうなぁ、などと内心考えていただけに、【NAME】は何やら拍子抜けしたような面持ちのまま船を降り、アノーレ島の土を踏む。
ぐるりとあたりを見渡す。
港と、それを中心にして広がった街並みは、“沿岸の町”の基本に忠実な、フローリア諸島では良く見られる構造だ。街の規模の方はといえば、ランドリートの都に匹敵する大きさはないがリコルスやラースナウアに劣る程ではない、といった処だろうか。
などと考えていた自分に続いて、格式ばった服を着込んだ小柄な娘が船から降りてくる。彼女──ノエルは一度身体を揺らして“大筒”を背負い直した後、相変わらず無表情のまま、唇だけを僅かに動かした。
「この街は“潮風の港”──ポロサと呼ばれています。アノーレにおける常駐軍の本営もこの街に置かれていますし、アノーレ島では最も大きな街だと、そう聞いています」
そのままノエルはコツコツと踵を鳴らして前へ回り込むと、一度顔を上げて【NAME】と視線を合わせてから、小さくお辞儀してみせた。
「ようこそ、アノーレへ」
・
「ガレー遺跡。まずそちらへ向かっていただくことになります」
ポロサの町を通る街路。隣を歩いていたノエルの言葉に、【NAME】はうん? と眉を顰めて疑問を口にする。
そんな処に行くよりも、まず彼女が言っていた“上官”とやらに会うのが先ではないだろうか?
その問いに、ノエルは一瞬理解できないという風な表情を浮かべた後、いえ、そうではなくて、と続ける。
「彼女はこのポロサにも、この町の近くにある軍の駐屯地にも居りませんから。あなたの依頼主となるイェア──イェア・ガナッシュは“ガレー遺跡”の周辺に張った軍の野営地に居ます。そこが彼女の“庭”です」
【NAME】はその言葉に、なるほどと頷く。つまり依頼主に会う為にはガレー遺跡へと足を運ぶ必要があるということか。
しかし、ガレー遺跡というのは確か……。
「はい。アノーレの“四大遺跡”の内の一つです。イェアは今では軍属ではありますが、元々は学士です。常駐軍が派遣される際に、出向という形で第十二師団に付いてきたと聞いています。“芯なる時代”に造られた建造物──正確には、芯形機構[グリフコンバータ]の研究が専門でして、遺跡周辺に敷かれた仮設の野営地の外に出られるのは稀ですね」
ふむ、と【NAME】は小さく唸る。
・
軍隊付きの学者。
そのような人物が自分に対して“調査”と“調停”を依頼する。
調査だけなら、危険な遺跡への単独潜入に冒険者を雇うというのも判る。だが調査と調停となると──はて、一体どんな依頼なのかと首を傾げてしまう。
調停という要素がある以上、少なくとも遺跡に潜ってはい終了、という類のものではないだろうが。
・
「ガレー遺跡はポロサからそう離れてはおりません。ですので今すぐポロサを出れば今日中にでもガレーに──」
──と、ノエルは何かに気づいたように唐突に言葉を切り、足を止めた。
立ち止まった彼女に気づき、一瞬遅れて【NAME】も歩を止める。
己の意識を内から外へと切り替え、ノエルの視線を追って街路の先に目を凝らせば、そこには物騒な武器と硬質の防具に身を包んだ兵士達の一団があった。
(……常駐軍の部隊、か?)
旗兵の掲げる軍旗の紋と、集団の一部の人間がノエルの服とよく似たものを着ていることから、彼等がアラセマ常駐軍の人間なのは判断できた。
兵士達は速くもなく遅くもなく、規則正しく街路を歩いてくる。集団の中にはフローリアでは珍しい生粋の馬と、それに跨る騎士の姿も見えた。
その騎士達の中に一際目立つ影が一つ。
部隊の先陣を切るのは、軽量の鎖帷子に身を包んだ女性だった。
その表情は遠目からでも判るほどに凛として、頑なさが際立ってみえた。
【NAME】が誰を見ているのかに気づいたのか、ノエルが補うように口を開く。
「あれは──クスィーク・カナル・フハール様ですね。彼女は、アノーレを統括するアラセマ常駐軍の実質的な長です」
(……実質的?)
実質的とはつまり、実際に彼女が軍の長ではない、形式的な長が別に居ると言う事だろうか。
「そうなります。クスィーク様はアノーレ島に常駐する第十二師団の副団長です。師団長はカナード・フハール様という方が務めていらっしゃるそうですが、あまり表にお出にならない方のようで、代わりにクスィーク様が師団を仕切っておられると、そう聞いています」
そして「行きましょう」とノエルが呟く。
確かに、あまり立ち止まってじろじろと眺めるのは良い選択とはいえない。【NAME】は彼等から視線を外し、舗装も不十分な道を歩き出す。
「武装と編成を見る限りでは亜獣討伐のようですね。恐らく、駐屯地の本営へ帰還する途中なのでしょう」
隣に居る【NAME】に聞こえる程度の小声で呟かれるノエルの言葉を聞きながら、【NAME】達は彼等とすれ違う。鉄の踵と馬の蹄が鳴らす重奏が近づき、そして遠ざかっていく。
そして数拍。
ふと気づけば、いつの間にか足を止めていたノエルが、黙したまま、じっと去っていく彼等の背中を見詰めていた。
暫しの後、【NAME】の視線に気づいたノエルは、止めていた足を動かして【NAME】の隣に並ぶと、
「……いえ、単なる亜獣討伐の部隊をクスィーク様がわざわざ率いられるのも珍しいと、そう思っただけです」
まるで独りごちるように呟いて、表情の色薄い顔を上げて【NAME】を見た。
「参りましょう、【NAME】。できれば日が沈む前にガレーに辿り着きたいですから」
四大遺跡 虚木瞑々
――枯渇樹林――
ポロサの町から北にあるという遺跡、ガレーへと続く道筋を【NAME】とノエルは進む。
高台を抜ける、腰丈ほどの雑草に半ば隠された小道。途中、急いでください急いでくださいと無表情のまませっついてくるノエルを宥めすかして幾度か休息を挟んだ為、既に周囲は夜の闇に閉ざされつつあった。
少々傾斜のきつい坂道を足早に登る。ノエルが言うには、今いる高台を抜けて林に入り、そこから一時間程北へ向かえばガレーに辿り着くという。
黙々と坂を歩き続けて暫く。ようやく高台を登り切った【NAME】の前に姿を現したのは、身に纏う筈の緑の葉をすべて失った木々の群だった。
(……何だか)
薄ら寒い。生気の感じられない──“死んだ”というよりは“壊れた”という表現が似合う。そんな場所だ。恐らくあれがノエルの言っていた林なのだろうが──正直云って、あまり近寄りたくない。そう感じた。
そこへ、数歩遅れて付いて来ていたノエルがやってくる。
彼女は高台から見下ろす光景に無表情のまま一瞬固まり、
「────」
小さく首を傾げた。
「不可解です。ガレーとポロサを繋ぐ道筋に、このような枯れた林など無かった筈なのですが」
そりゃ単に道を間違えたんじゃないの、と【NAME】は呆れ混じりに言う。
「そのような事はありえません。わたしの記憶は確かです」
ノエルはきっぱりと断言してきた。しかし、
「ですが、この林がわたしの記憶に無いのも確かです。……矛盾していると、わたしは思います。ですので」
──少し調べてきます。
彼女は【NAME】にそう告げて、眼下に広がる寒々とした林へ向かってとんとんと降りていく。足場が悪いせいか、背負った“大筒”に小さな身体が振り回されて、偶に体勢を崩しかけるのが危なっかしい。
「…………」
【NAME】はげんなりとした表情で遠退く背中を眺めた。
今までの経験上、こういう状況になると大抵ロクな事がないのだ。今回もとてもとても厭な予感がしてならないのだが──しかし、案内役殿が居なければガレーへ辿り着けないのもまた事実。放っておく訳にもいくまい。
結局付き合うしかないのだなぁと、自然ついて出る溜息を噛み殺しつつ、【NAME】はノエルの後を追った。
・
殆ど崖と呼んでも良い急な斜面を降りきり、【NAME】は林の中へと入る。警戒しつつ林を進んでいくと、程なくして二股に分かれた幹を持つ巨木、その根に膝をつくノエルの姿を見つけた。彼女は幹に掌を添え、表情の薄い顔をじっと樹に向けている。
(……何をやっているのやら)
不思議に思いつつ【NAME】が近づくと、ノエルは隣に生えていた背の低い若木から枝を一本折って、それを【NAME】に見えるように差し出してみせた。
「見ていてください」
手の中にある折った枝を、ノエルは親指で軽く撫でる。すると枝は何の音も発さずにぼろぼろと崩れ、淡い粒子となって空気に溶けてしまう。広げられたノエルの掌には、その欠片すらも残らなかった。
「生命ではなく、樹が持っていた根本概念が崩れています。樹の形を辛うじて保っているのは、まだ概念を奪われて間も無いからです。あと数刻も経てば、この樹も先程の枝のように跡形も無く消え去るでしょう」
「────」
明らかに尋常じゃない。驚きと疑問で固まってしまった【NAME】だが、ノエルは更に説明を続ける。
「これは恐らく“鬼”の仕業と、わたしは判断します。その証拠に【NAME】、あちらを見てください」
いつの間に現れたのか。ノエルが指差した先には、白色の炎の塊が複数。黄昏に染まる風景に紛れるように、枯れた木々の間を音も無く浮遊していた。
死した林を舞う火の魂は、ゆらりゆらりと見る者の気を殺ぐように、しかし確実に【NAME】達との間を狭めつつある。
「あれは比喩ではない、正真正銘の“鬼火”です。力ある鬼種達が操る、破壊概念の断片。どうやら鬼は林に在った概念を根こそぎ破壊して奪った後、ここを己の縄張りと決めたようですね」
ノエルは背負った“大筒”を一度地面に降ろしてから、両手でしっかりと構え直した。側面についた折込式のレバーを延ばして掴むと勢い良く引き、放す。それに合わせて鈍い機械音が生気の無い林に響いた。
「【NAME】も準備を。今は自分達の身の安全を確保した方が良いと、わたしは考えます」
battle
鬼種の御使い


【NAME】が最後の鬼火を破壊した瞬間。
ぐねり、と。
目に映る風景の全てが渦を巻くように捻られ、次いで逆方向へと高速で回転した。
息が詰まる。その現象は一瞬で収まったが、【NAME】はその奇妙な感覚に堪えきれず片膝をついた。
「……これは」
顔を顰めて座り込む【NAME】の耳に、抑揚のない呟きが届く。顔を上げれば、黒銃を構えたままのノエルが、小さく眉を顰めて空を見上げていた。
枯れた枝木の隙間に見える空は、先刻までの昼と夜の狭間にある黄昏の赤ではなく、暗く昏く閉じた闇の黒。周囲に漂う気配も、どこか異質なモノへと変化していた。
「世界を“括られ”ました。結界に閉じ込められたようですね」
この林を枯れ果てさせたであろう存在。どうやら自分たちはソレに目をつけられてしまったらしい。
「張られた結界をどうにかしないと林の外には出られそうにないと、わたしは思います。困りましたね」
などと、さっぱり困ってなさげな口調で言うノエル。傍目、全くどうという事も無さげな彼女だが、表面に出ないだけで実際に困ってるのだろう。感情があまり表に出ないというのも考えものだ。
──しかし、結界か。
無意識に、【NAME】は首から提げた飾りを指先で弄る。それはあの“殺すことのできない獣”の事件で手に入れた品。とある神形器の変化した姿だ。
閉じ込める。
束縛する。
停滞させる。
正常なる流れを阻害する。
そんな概念を断つための力。
流転の象徴たる神形器ゼーレンヴァンデルング。
ならば、この林に張られた閉鎖結界に対しても効力を持つ──筈なのだが、神形器は未だ何の力も発さず、只の首飾りとしての己を維持している。
それは何故か。考えられる答えは──
(この程度の結界相手に“出る”つもりはない、ということか)
──全く、扱い辛い事この上ない。
「それで、どうされますか。【NAME】」
ノエルの問いに、【NAME】は小さく肩を竦める。どうするもこうするもない。要は結界を形成した張本人を叩けば良いだけのことだ。
だが、問題はある。まず結界を作り出した存在を如何にして見つけるかだ。闇雲に走り回るのは好きではないが、受身に回って好転するような状況でもない。
兎に角動くべきだが、果たしてどう動くべきか。
――虚木瞑々――
「何だろな、あれは」
既に日も落ちて完全な夜の闇に包まれた高台の上に、一人の男の影があった。
「メチャクチャ雑だが“閉鎖”と“円環”を含んだ結界か、一応。“隠匿”の概念が混じってないって処を見ると……」
眼下に形成された黒の巨大な半円の中で、ちかちか何かが瞬いた。それを見て男はうむむと眉を顰めた。
「やっぱり。誰か中で頑張ってるのか」
男はうむむと唸りを深くする。顎に手をやり、無精髭を数度撫でた。
「……本音を言うと無視して通り過ぎたいところだけど──まぁ、様子だけでも見にいくべきか」
懐から紋様が刻まれた石を取り出すと、男は軽い足取りで結界へと近づいていった。
・
林の奥、然して深くも無い窪地の底にその樹は在った。枝の末端まで歪な生命力に満ち満ちた大樹。その幹には不気味な人面──いや、鬼面が浮んでおり、どくどくと脈動する根と枝が酷く禍々しい。
──恐らく、アレが結界の主か。
数歩遅れて【NAME】の傍に来たノエルはそれを見て、理解しました、と一人呟き、頷く。
「最初は、他方に棲んでいた鬼種がこの林へ流れてきたのかと考えていたのですが、それは不正解だったようですね」
彼女の言に【NAME】は考え込むように小さく唸った後、こう訊ねた。
それはつまり、あの巨大な鬼面樹はこの土地で生まれたものだと?
「はい。恐らく、この土地に蓄積していた“歪み”を受けてごく最近──推測では数時間前に鬼種としてのカタチを持ったのではないかと思われます。樹の形態を取る鬼というのは珍しいですが、討伐例はいくつか存在します。見たところ歩行樹の類ではないようですし、深く広く根を張って周辺地域を土地ごと喰らうのでしょう」
ノエルは話しながら背負った黒銃を前に回し、構えた。閉ざされた空の暗闇に紛れて半ば形を失っている黒の銃身に、白く細い指が添えられる。
「では“駆除”に入りましょう。完全に崩滅させるか、それが出来なくとも結界を維持できなくなるまで弱らせることが出来れば良いのですが」
[BossMonster Encountered!]
「邪魔です」
じ、と空気が熱く爆ぜる音と共に、ノエルの構えた黒銃の先端から凄まじい光が吹き出し、わさわさと蠢いていた無数の枝木をたった一射で焼き払う。
「──【NAME】、とどめを」
言われるまでも無かった。身体の一部を失って動きの止まった鬼面樹の懐に飛び込むと、【NAME】は裂帛の声と共に武器を振るい、幹の中心に必殺の一撃を入れる。
みしりと鈍い音が走る。木の表面に無数の罅が入り、そして次の瞬間、巨大な樹が粉々に砕け散った。同時に、林全体を包んでいた奇妙な気配も払われていく。
(やった、か)
崩壊し、砕け散った鬼面樹の木片に埋もれながら、【NAME】は安堵の吐息をついて座り込んだ。
その傍へ、先程の射撃で熱を帯びた銃身を持て余しながら、ノエルがとことこと歩み寄る。
「ご苦労様です、【NAME】。これで漸くガレーへ向かうことが出来ますね」
まったく、ある意味予想通りとはいえ、やはりロクなことにならなかった。【NAME】は疲れの溜まった身体を起す。何かまたヘンな事に巻き込まれないうちに目的地へ向かう事にしよう。
確か林を北へ抜ければガレーだったか、と気だるい身体を引き摺るように歩き出して十数歩。
──ノエルがついてきていない。
はて、と後ろを見ると、茫とした様子で窪地の真中を眺めているノエルの姿があった。
「──いえ」
視線に気づき、ノエルはどこか迷うような調子で呟く。
「正直に申しますと、これだけの力を持つ鬼種が生まれる程の“歪み”が実際にこの林にあったとは、わたしには思えなくて」
ノエルはあの鬼面樹の存在に何らかの違和感を感じているようだった。
だが、その辺りの事情など、一介の冒険者でしかない【NAME】にはどうでもいい事だった。【NAME】は黙り込んだまま動かないノエルを促し、さっさとガレーへ向けて出発することにした。
四大遺跡 夜の邂逅
――夜の邂逅――
鬼を討ち、危険の去った林の中を黙々と歩く【NAME】達。
「…………」
──と。
突然、隣を歩いていたノエルが、表情をいつも以上に硬くして立ち止まった。
「そこの方。出てきなさい」
彼女は背負っていた大筒を素早く構えると、近くに立っていた枯れ木に向かって、ばんといきなり発砲した。
すると。
「だああ──!?」
驚いたことに、上半分が吹っ飛んだ枯れ木の陰からごろごろと一人の男が転がり出てきた。
「──ちょ、待て待て! 撃つな、僕は敵じゃない!」
濃い青色に染まった衣服と大型の背嚢。両手をぶんぶんと振って慌てて叫ぶ男の姿を、【NAME】は首を傾げて見やる。
(……どこかで見たような?)
むむ、と【NAME】が記憶を探っている間に、ノエルは男に銃口を向けて淡々と言い放つ。
「物陰に隠れてわたし達の様子を窺うような方が、敵ではないとは思えません」
ばんばん。
音に合わせて男が器用にダンスを踊る。
「だから、違うって云ってるだろう! どうすれば信じてくれるんだ!!」
「当たっていただければ信じます」
ばんばんばん。
段々ダンスというよりアクロバットに近くなってきた。
「危なっ、【NAME】! 君からも云ってやってくれ!」
「……?」
ばんばんばん、じゃこん。
そろそろ当たりそうだ。
「判らないのか! オリオール! ハマダン・オリオールだ! ほら、ランドリートの島で君と旅しただろう!?」
(……ああ)
言われて漸く思い出した。ぽんと手を鳴らす【NAME】。しかし。
「知りません」
ばんばんばん。
「いや、そちらのお嬢さんではなくて──ってあああっ!」
・
「──と言う訳で、理解してもらえたかな」
「了解しました。【NAME】の知人の方だったのですね。でしたら初めからそう仰っていただければ宜しかったのに」
「だから……いやもういい」
ノエルと会話するのを諦め、オリオールは【NAME】へと視線を移す。
「しかし、【NAME】がアノーレに来ているとは思わなかったな。何だってわざわざこっちに? 島に入るのも手間だったろうに。てっきりコルトレカンに居着くと思っていたよ。あそこは冒険者には過ごしやすい島だからね」
言葉に詰まる。答えようにも、【NAME】自身も何のためにこの島へ呼ばれたのか、詳しい話を聞いていないのだ。説明の仕様がない。
黙り込んでしまった【NAME】に、オリオールは軽く肩を竦めてみせた。
「云えない事情でもあるのかい? なら、こちらも別に無理には訊かないけど、先刻のアレが何だったのかくらいは教えてもらえると助かるな。外から見ていたらなかなか派手に“括られ”てたみたいだけど」
先程の鬼面の大樹との戦いは、完全に偶発的なもので別段隠す必要のある事柄も無い。【NAME】は簡単に話す。
「ふぅん……?」
話を聞いて、オリオールは真剣な表情で黙り込む。
(何か気になる点でもあったのだろうか?)
【NAME】が怪訝な顔で自分を見ているのに気づいたのか、オリオールは「いや、何でもない」と首を振る。
「しかし災難だったな。というか、状況が状況とはいえ無茶をするな君も。ランドリート辺りの鬼種なら個人でもどうにかなるけど、この島の鬼はそんな生易しいものじゃないぞ。ある程度以上の等級の鬼は下手に欲を出して挑むより、この島のアラセマ常駐軍に任せるのが得策だよ。元々、彼等はその為に居るんだから」
──この島のアラセマ常駐軍。
そう言われて思い出すのは、ポロサの町ですれ違った兵士達と、それを率いていた女騎士の姿。
「【NAME】」
と、思考に割り込むようにノエルが名を呼ぶ。
「そろそろガレーへ参りたいと思うのですが、宜しいでしょうか」
ノエルの言葉に、ついつい暢気に話し込んでいたことに気づく。オリオールも同じだったらしく苦笑いの表情に変わった。
「ああ、済まない。急いでいる処を引き止めてしまったみたいだな。行ってくれて構わないよ。また何れどこかで会おう」
軽く手を振って見せるオリオールに挨拶を返して立ち去りかけて、【NAME】はそこで動きを止めて、先程訊きそびれた事を口にする。
──何故、貴方はこの島に居るのか、と。
その問いに、オリオールは小さく笑ってこう答えた。
「前に言わなかったかな。僕がこの島へ来たのは“もう一つの用事”を済ませるためさ」
・
同日同刻、アラセマ常駐軍駐屯地。
アラセマ第一位貴族の一員であり、同時にアラセマ陸軍第十二師団長を務める男の私室に、二つの影があった。
一つは、部屋の主であるカナード・フハール。彼は机に肘を突き、陰鬱な表情を浮べて椅子に腰を降ろしていた。色の薄い両眼は、机ごしに立つもう一つの影を煩わしげに見据えている。
彼の眼前に立つ影の名はクスィーク・カナル・フハール。第十二師団の副団長であり、カナードの副官の位置にある人物。師官用の軍服に身を包んだ彼女は、手にした皮紙の束を捲りながら延々と喋り続けている。
「──の件ですが、65時間前に出現を“予知”されていたユウベル北の平原、ガレー南の森林地帯、ノスキス南東の峡谷の三つの地域のうち、本日早朝にユウベル北で禍鬼クラスの陰性存在概念発生を把握。私自身が部隊を率いて当該地域へと出向き、現地到着2時間後に対象と交戦。その15分後に対象の崩滅に成功しました。被害人員は死傷0、重軽傷8。エリンベルの“先見”の通り、アノーレ島に限らずフローリア全域で概念的な“歪み”がより強くなっているのは確かかと思われます。また、交戦時に0.5戦術単位評価の攻的印章石を二つ使用しましたので、明日までに使用分の補充手続きを行っておきます」
「…………」
「次に遺跡占領組の対応についてですが、ノクトワイ様の方から、前回ヴィタメール攻略作戦に使用するとお知らせした儀式印章魔術の作成に人手が足りず、今の進捗状況では決行日時に間に合いそうに無いという報告が入っていまして、予定の期日を数日ずらす事になりました。これは後ほどノクトワイ様の方から正式な書類で師団長に詳細報告が届くと思いますのでそれを参照してください。──次に“四大遺跡”の活発化の件ですが」
「クスィーク」
「我々が唯一掌握しているガレー遺跡については、例外処置として謹慎中のイェア・ガナッシュに対して調査に赴くよう指示を出し──」
「クスィーク!」
「──はい」
「……お前もしつこいな。師団の運営に関する事は全てお前に任せてある、その詳細をわざわざ俺に報告する必要は無い──これ、お前に言うのはもう何度目だ?」
「一語一句での差異を省くなら57回目になります」
「覚えてるなら、いい加減言う事を聞けよ」
カナードは頭痛を押さえるようにこめかみを指で揉み解しながら、投げやりに呟く。見るからに嫌そうな、辟易している仕草。
だが、そんなカナードの態度も、彼の眼の前に立つ人物は全く通じないようだった。
「貴方様はこの師団の長です。師団長に対して軍の活動内容をご報告するのは当然と考えます」
「お飾りの長に、か?」
生真面目な答えを返すクスィークに、カナードは両手を広げ大袈裟に肩を竦めてみせた。
「剣もダメ、技法もダメ、術式もダメで人を従える力も技能も無い。出来ることといえば御婦人方のダンスのお相手に算盤勘定程度か。そんなもの、この辺鄙な島じゃカケラも役に立ちゃしない」
自分で言っていて情けなくなるがな──皮肉に満ちた口調でそう言って、カナードは苦笑のまま……しかし目つきだけは真剣味を帯びてクスィークを見た。
「で、それを踏まえて質問だ。そんな俺にお前は何を報告してるんだ? そんな事はお前が理解し、お前が指示を出せば済むことだろう。この師団を動かしているのはお前なんだからな」
対するクスィークは何も言わない。
ただ物静かな瞳が、椅子に腰を降ろしているカナードをじっと見つめてくる。
「…………」
凛とした、揺るぎの無い瞳。
──昔から。
この眼に見つめられるのが苦手だった。
「何か言いたそうだな。言ってみろよ」
堪え切れず、自棄気味に突っ掛かる。しかし、クスィークは真っ直ぐ視線を外さぬまま、真摯な面持ちで口を開いた。
「……あまりご自分を卑下なさるのはよろしくないと考えます。師団長は本来優秀な方です。ですが、ご本人の口からそのような事を仰っていては、現実もそちらへ引き寄せられてしまいます」
それは模範的で優等生的な。
──本心からのものとは到底思えぬ言葉。
癇に障る。
感情がささくれ立ち、何とも言えない苛立ちだけが募ってくる。
「ああ、そうだ。そうだそうだ尤もだな。いつもお前の言う事は尤もだよ。至極尤も。尤も過ぎて些か飽きてきた」
だん、とカナードは勢いをつけて席を立った。
「判った。なるべく善処する。するからもう出て行ってくれ」
カナードは切り捨てるように言って視線を逸らすと、そのまま窓辺へと寄った。もう会話を続ける意思はないと、露骨な態度で示してみる。
しかしクスィークは動かず、先程と同じ瞳でただじっとカナードを見つめ、立ち尽くすだけだった。
お互い喋らず、じりじりと時間が過ぎていく。
「……クソ」
やはり、先に根を上げたのはカナードの方だった。苛立たしげに舌打ちし、無言のクスィークを睨みつける。
「聞こえなかったか? 出て行けと俺は言ってるんだ。──おい、カユリは居るか!」
カナードが部屋の外へと聞こえるように声を張ると、間髪入れずに扉が開き、小柄な人影が室内に入ってくる。まだ幼いといって良い少年はカユリと言い、カナード付きの従者の一人だ。
「参りました、師団長。御用でしょうか」
「イルギジドを呼んで来てくれ。また大陸の話を聞きたいと──」
「──師団長!!」
かっ、と。
クスィークが今までの物静かな調子が嘘のような、強く高い声をあげる。表情も先程までとは打って変わり、怒気を孕みつつもどこか不安げな、頼りないものになっていた。
「あの男とお会いになるのはお止めくださいと幾度も申し上げてますでしょうに!」
その慌てぶりに、少し溜飲が下がる。クスィークは何故か自分とあの男が会うのを止めようとしていた。理由など知らない。知らないが、あの普段冷静な彼女が取り乱す姿はカナードにとって酷く愉快な光景だった。
カナードは彼女を一瞥しただけで無視し、先程の声に驚いたのか扉の前で固まっていた少年に短く命令する。
「カユリ、行け」
カナードの声に、カユリと呼ばれた少年は深い一礼を残して部屋から消える。それを見届けてから、気だるげに息を吐いた。
「全く……くどいんだよクスィーク。お前を真似て言うなら“一語一句での差異を省くなら25回目になります”だな。……はは、それでも半分くらいか。お前の頑固さには全く恐れ入るよ」
軽い調子で笑ったカナードに、クスィークの表情はより険しくなる。
「おふざけにならないでください。それとこれとは話が別です。イルギジド・マイゼル、あの男は明らかに──」
「黙れよクスィーク。もういい戻れ。これは命令だ。お前が言うには俺はこの師団で一番偉い人間なのだろう? ならその命令は聞くべきだ。尤も、お前が実際にそう思っていないと言うのならその限りじゃないけどな」
「────」
痛い処を突かれたのか、クスィークは喉を詰まらせる。そして一瞬恨めしげな顔を見せた後、何かに堪えるように顔を伏せた。
「……畏まりました」
顔を伏せたまま搾り出すように呟かれる声。そのまま背を向け立ち去る彼女の身体は、先程と比べ一回りほど小さく見えた。
カナードは何も言わずその背中を一瞥した後、視線を窓へと戻す。少しの間を置いて扉が軋む音が響き、そして。
「では、失礼いたします。……おやすみなさいませ、カナード様」
力ない、囁くような声を残して、ぱたんと扉が閉まった。
黒く染まり、見通すことすら難しい闇夜。窓辺からそれを眺めつつ、カナードは彼女が最後に残した言葉を喉の奥でなぞる。
「……カナード様ね」
──昔から、苦手だったのだ。
あの頃は、まだ堪えられた。
だけど、今はもう堪えられそうにない。
四大遺跡 先見の者
――先見の者――
夜が明けてからまだ一刻も立たぬ時分。
ポロサの外れに建てられたアラセマ常駐軍の駐屯地では、僅かではあるがそんな早朝でも人の動く気配がある。
夜警から宿舎へ戻る兵士達。そして、朝の食事の仕込を始める町から雇われた賄いの者達だ。
元々は仮設にも近い駐屯地。ポロサにある駐屯地はアノーレにおける常駐軍の本営とはいえ、厨房なども人数の割にはお粗末な物だ。工兵達が基礎を組み上げたそれらの厨房は簡素で使い勝手は良いものの、必要最小限のもののみで構成されているため汎用性に乏しく、近隣の町から雇われてここへ出張ってきている者達には不評。彼らは厨房を自分たちが使いやすいように好き勝手に弄り、今の厨房は殆ど原型を留めない程にまで変形している。
その厨房の裏手。
無計画な拡張のせいで酷く凹凸に富んだ壁の陰で、大き目の桶に歪な球状の物体を入れて、それをがしゅがしゅと掻き回している人影が一つ。
人影は、町で雇われた人間そのものといった雰囲気を持っていた。極々ありふれた女物の衣服に身を包み、髪を後ろに纏めたその背中は手の動きと連動して左右に揺れている。
その背中を暫し眺めた後。少し離れた位置に立っていたクスィーク・カナル・フハールは、短く彼女に呼びかけた。
「マリカ」
それが彼女の名だった。呼ばれた女は動かす手を止める事無く、笑みを含んだ視線だけでクスィークを見た。
「あら、くーちゃんかね。毎度毎度こんな朝っぱらからご苦労さんね」
「表立って会いに来ては貴女が困るだろう。人目の無いこの時刻に足を運んでいるのは、貴女の意思と私達の状況、立場を考慮した結果の上だ」
気楽な調子の言葉に、クスィークは硬く返す。それを見て、マリカはけらけらと心底面白そうに笑った。
「貴族さんで軍人さんのクセに義理堅いよねぇ、くーちゃんって。あんたはそういうけど、実際あたし等みたいな人間の立場なんて考えてくれる人いないよホント」
「そういう貴女は、他人はおろか自分の立場すら考えない人間だ。その『くーちゃん』と呼ぶのを止めろと何度言ったか知れない」
「何いってるかね、ちゃんと考えてるさ。あんたはそう呼んでも大丈夫な人間だからそう呼ぶのさ、それなりの親しみを込めてねー。それとも、不敬だ何だってケチつけてあたしを斬るかい?」
肩を震わせて笑うマリカに、クスィークは息をついて苦笑。暫しの間、ごろんごろんと硬さを感じさせる何かが桶の中を回る音が響いた。
そろそろ本題に入ろうか、とクスィークが改めて口を開きかけた時、
「あ、そーそーくーちゃん。昨晩あんた、また師団長殿と喧嘩したんだって?」
──何故それを。
驚きで固まり、次いで喉が詰まった。クスィークは身を浅く折り、小さく噎せてこほこほと咳払い。
「はははっ、相変わらず判り易いねぇ、あんた」
自然伏せる形となった顔を上げてマリカを見ると、彼女はいつにも増して深い笑みを浮かべてこちらを見ていた。
「……どこでその話を?」
「カユリちゃん。夜中に偶然会ってね」
「な──」
「夜中とか、結構こっちへ師団長殿の軽食つくりに来るからね、あの子。偶に顔会わせた時に色々とお話聞いてたんだけど」
楽しげに語るマリカに、クスィークは本気で顔を顰める。
「無用心な。あの者の素性は──」
「知ってるよ。けど別に構いやしないさ。その剣の先があたしに向く訳でもなし、誰だって事情はある。──そんなことより」
マリカの声に常に含まれていた軽い気配が、僅かに薄れる。
「本音を言っちゃうと、何であんたのような優秀な子があんな駄々っ子みたいなのを気にしてるのか、あたしにゃ全然理解できないんだけど。師団長殿が何やろうが何言おうが、別に放っておきゃ良いんじゃないの。どうだろうと実際軍動かすのはあんたなんだろ?」
「…………」
「あたしにゃよく判んないけどさ、結局あの師団長殿がお飾りってのは本当なんだろ? 昔の軍はあんたと“女賢者”のレェアのお嬢ちゃん、今の軍はあんたと新しく来た魔術師の人。これで動いてるってのはここに詰めてる人間なら誰でも知ってる事だし、事実でもあるわけじゃない」
「──マリカ」
「それなのに、あんたはあのフハールのお坊ちゃんを気にする。無視しときゃいいのにさ。そんなにフハールの姓てのは重いものなのかい? それとも、別の何かがあるとか?」
「……貴女のそのずけずけと物を言うところは直した方が良い。いくら私でも、許容できるものとできないものがある」
「はん、あんたは溜め込みすぎなんさ。一度吐き出しちまった方が良いと思うけど。あたしで良ければ相手してあげるよ」
お互い、そのまま無言で睨み合うこと数分。
折れたのはマリカの方だった。息をつき軽く肩を一度竦めてみせただけで、まるで魔法のように彼女の纏う気配が軽くなった。
「ふん、悪かったよ。あんまり話したいことじゃなさそうだね。いいよ、それよりそろそろ本題に入らないかい」
マリカの催促にクスィークは頷き、溜まった怒気を逃がすように細く息を吐いた。
「前回、貴女より受けた“先見”の結果を報せに来た」
彼女の言葉に、マリカは呆れたような顔になる。
「相変わらずマメだねぇ。そんなこと別に知らせなくてもいいのに。あたしはただ自分が“見たモノ”をあんたに報せただけじゃないか。“先見のエリンベル”って言ったってそんな大したもんじゃないよ。起こるのか起こんないのか良く判んないビジョンを予知できるだけじゃないのさ」
「貴女の“先見”は流動的であり不安定だ。だから、それを今後に役立てるようにするためには、見る者と動く者、相互の理解は不可欠だと思う」
「まぁ、あんたがそういうなら良いけどね。で、結果の話だけど──悪いけど、実はもう知っててね。さっきその辺に居たヒラの兄ちゃんに聞いたよ」
クスィークは僅かに目を瞬かせ、そしてふと表情を緩める。
「そうか。──なら今更告げるまでも無いかも知れないが、今回も貴女の“先見”は当たりだ。そのお陰で、大きな被害が出る前に何とかすることができた。礼を言う」
「止めなさいな、照れるだろ? ……でも、三つの“先見”の内の二つが現実になるって珍しいんだよ。あたしはてっきり、あの中のどれか一つだけが本当だろうって勝手に思ってたんだけど。あんたも良く気を抜かずに見張ってたね」
「──え?」
クスィークの声色が変わった事に気づき、マリカはそこで初めて手を止めて立ち上がると、戸惑いの顔で振り返る。
「違ったのかい? 昨日の夜中にガレーへ向かって部隊が出て行って、さっきその連中の一部が帰ってきたんだよ。で、どこ行ってたのか聞いたら、イルギジド軍師の指揮でガレー南の森林地帯に出た禍鬼の討伐にって──てっきり、あんたがあの魔術師に指示を出してたんだと思って感心してたんだけど」
クスィークは短く左右に頭を振った。
「……少なくとも、私はあいつに何も教えていない」
「師団長殿には?」
「無論、お伝えしてある」
「なら、そこから漏れたんじゃないかね」
「…………」
むっつりと黙り込んだクスィークを、マリカは困った表情で見た。
「あんたが師団長殿に拘る理由は何となく判るんだけど、あの魔術師──イルギジド・マイゼルだっけ? あいつを嫌う理由の方はよく判んないねぇ」
「……そんなこと、貴女には関係無い」
溜息と共に言い捨て、そして数瞬の躊躇いの後、クスィークはマリカに背を向けた。
「──用事が出来た。今日は失礼する」
「現場調査かい。……ま、あまり無理しないようにね」
言葉と、桶の水を地面に捨てる音を背中で聞きつつ、クスィークは厩舎へ向かい歩き始めた。
・
オリオールと別れた後、【NAME】とノエルは改めてガレーへ向かい旅立った。
鬼面の大樹の勢力圏であった事を示す死んだ樹林を抜けて、更に北へ北へと進んでいくと、徐々に木々の数が減り、周囲の景色は丈の低い草に覆われた原へと変化した。幾度かの休息と仮眠を挟みつつ、踝程の高さしかない緑を踏み締め歩むこと数刻。原の先に点々と、緑以外の色彩が混じり始める。歩を進めるごとに緑以外の色彩は面積と数を増し、次第に明確な形となって【NAME】の前に姿を現していく。
色浅い緑の上に建つそれは、遺跡というよりは“城塞”に近い雰囲気を持った建造物だった。
敷地にある建物の壁面はほぼ全て濃い黒で、“城塞”の左右から突き出た二本の塔がいやに目立っていた。また、その建造物を護るかのように、周囲には小振りな建造物や柱、壁の残骸などが無秩序に散乱して、そこへ至るまでの道を汚していた。
そして、そんな鋼色の遺跡群を取り巻くように小さなテントやバラックなどが建ち、近くでアラセマ常駐軍の人間と思しき者達が忙しなく動く姿が見えた。
「漸く着きましたね、【NAME】。ここが──」
──ガレー遺跡か。
四大遺跡 ガレー遺跡
――ガレー遺跡――
ガレー遺跡に到着したは良いものの。
遺跡の周囲に建てられた常駐軍のバラック。そこに詰めていた常駐軍の人間を一人捕まえたノエルは、一人の人物──イェア・ガナッシュの名を告げて所在を尋ねたのだが、返って来たのは「彼女はここに居ない」という答えだった。
「イェアは居ない?」
ノエルの問いに、兵士は眉を寄せる。
「んー。すぐ近いところに居る筈なんで、実際には“居ない”というよりは“居る”、といった方が良いのかなぁ」
兵士の曖昧な呟きに、ノエルは小さく首を傾げ、数瞬。
「つまり、イェアはガレー遺跡に入ったのですか」
そう、と簡単に頷く兵士。どうやらノエルが会わせたがっていた人物は、現在ガレー遺跡の奥へと赴いているらしい。
「どうしてです。彼女の“謹慎処分”はもう解けたのですか?」
(謹慎……?)
何やらあまり世間的に好ましくない単語が聞こえ、【NAME】は訝しげにノエルを見た。が、ノエルも兵士もその様子には気づかず会話を続ける。
「特例処置だ。最近の“四大遺跡”の活発化は知ってるだろ? で、その影響で遺跡の内部から周辺地域に概念汚染が始まっているんじゃないかって話が上で出てな。それの調査に。“女賢者”がほら、ああなっちまったから、遺跡関連だと“先生”くらいしか出せる人がいないんだよ。それに先生の謹慎は別に本人に問題があった訳でもないしな。体裁繕うためのものだろ、あれは」
「……そうですか。判りました」
ノエルは小さな嘆息を挟んで、足早にバラックを後にする。【NAME】が慌てて彼女に続くと、ノエルは顔だけを向けて手短に告げた。
「追いましょう。本来ならば待つべきなのですが、一度調査に入ればいつ出てくるのか判りませんし、その間ここで待つのは非効率です」
彼女の足が向く先には、ガレー遺跡の中心に建つ巨大な建造物があった。
・
ガレー遺跡を包む常駐軍のバラック群。それらが形成していた輪の内側へと侵入する。材質も不明な柱や砕けた壁などが散乱し、行く手を阻んでいる。それらを避けて時には乗り越え、【NAME】とノエルは進む。
「【NAME】、中央にある建物が見えますか」
ノエルの言葉に彼女の指差す方向を見ると、その先に左右に二つの塔を備えた一際大きい建造物が見えた。
「あそこへ向かいます。ガレー遺跡で調査の終わっていない場所はあそこだけです。いえ、正確には、あの建物のみが調査対象である、というべきでしょうか」
そこまで言って、ノエルがふと動きを止める。それに気づき、【NAME】も足を止めた。
「あの建物以外はただの飾りです。ですが、一部の建造物には亜獣等が棲みついているそうで──」
──がらり、と。
唐突に【NAME】達の脇に転がっていた瓦礫が崩れ、その影から“凶暴”を体現する大型の獣が飛び出し、襲い掛かってきた。が、【NAME】とノエルは難なく獣の不意打ちを避けて、距離を取る。
「──このように、偶に屋外に出てきて襲ってきます。【NAME】、戦いの準備を」
battle
遺跡の猛虎

徘徊する亜獣との戦闘を切り抜け、【NAME】達は何とか中央に建つ建造物の入口に辿り着いた。
浅い黒色に染まるその建物には扉などなく、ただ暗い口を開く門が一つあるだけだ。
【NAME】達が遺跡の内部へ足を踏み入れると、それに合わせてごうん、と奥から鈍い振動音が一度響く。
同時に、遺跡の壁面に一瞬だけ紫色の筋が走り、そして消えていった。
(……なんだ?)
反射的に身構え、何が起こっても即座に対応できるように腰を若干落す。が、待てども待てどもそれきり何も起きない。【NAME】は拍子抜けしたように身体の緊張を抜いた。
隣を見ると、ノエルは先ほどの異常も別段気にした様子はなく、ただ茫と立っていた。
(そういえば、ノエルは軍の人間か)
遺跡の周囲に陣を張るくらいなのだから、軍はこの遺跡の調査も積極的に行っているのだろう。ならば彼女も、この遺跡の構造を熟知──とはいかないまでも、それなりの情報を所持しているのではないか?
試しにそう訊ねてみると、ノエルは顔を上げて【NAME】を見て、しかしふるふると首を振った。
「詳しくは聞いておりません。わたしは『遺跡には極力近づかないように』と言いつけられていましたので、遺跡奥への侵入方法について興味はありませんでしたから。ですが、この施設は侵入者を感知すると先刻のような動作をする程度の事でしたら、噂話の範疇ですが聞き知っていました」
つまり、先程全く動じなかったのは前もって知っていたからか。
だが“近づかないように”と言われていたのならば、今のこの状況は一体どういう事なのか。【NAME】が呆れながら問うと、
「わたしは私的に『遺跡には近づかないように』という“要請”を受けていただけです。公的な“命令”を受けた訳ではありません。そして、今のわたしには“命令”により生まれた役目があります。それは“要請”よりも優先されるべき事柄だとわたしは判断します」
との返事。
言いたいことは判るのだが、その堅苦しい事この上ない口調は何とかならないのか。内心そんな事を考えつつ、【NAME】は遺跡の奥へ、なだらかに下方へと傾斜する通路を進んでいった。
・
通路を抜けて、円形の大広間へと出る。
「あるのは……台座ですね」
大広間の上の中央には巨大な台座があり、その右側に掌程の大きさの窪みがある。部屋の隅には円盤状の巨大な石板が寝かされており、その表面には微細な刻印が施されていた。
取り敢えず円盤は無視し、真中に鎮座する台座を調べてみる。台座の脇に不思議な色に染め抜かれた七つの石が置かれているのを見つけた。恐らくはこれを窪みにはめ込めば良いのだろうが。
・
鈍い音と共に台座が振動し、横にずれていく。台座の下から現れたのは地下へと続く階段だった。どうやらこの遺跡にはまだ先があるらしい。
今まで自分達が通ってきた道に目的の人物の死骸が無かったところを見ると、遺跡の更に奥──つまりこの階段の下に彼女は向かったと予測はできる。
(となると、行くしかないか……)
【NAME】は足元に開いた階段の口をげんなりと眺めた。
「どうされましたか」
階段を前にして動く気配の無い【NAME】に、背後からノエルの声が掛かる。【NAME】は何でもないと首を振って軽く溜息。
この先に今まで以上の化け物が出てこない事を祈りつつ、【NAME】は階段を下り、遺跡の奥を目指して歩を進めた。
・
台座の下に隠されていた細い階段を降り切った【NAME】達の前に広がるのは、幅15メートル、奥行きは100メートル程の長方の大部屋。最初、【NAME】はそう判断した。
──が、何処か違和感が残る。
(……何が違う?)
内心呟き、目を細める。若干遠いが、それでも【NAME】は違和感の原因であろう幾つかの事柄を発見した。【NAME】達が降りてきた位置の対面に聳える壁は、両側面にある壁とは色合いや材質などが微妙に異なっていた。そして壁の真中には垂直の細い溝が一本、まるで区切り線のようにつけられている。
以上の事から推測するに──
(扉か、あれは)
どうやら対面にある壁は、15メートルの幅をみっしりと埋める程の大きさを持つ、両開きの『扉』だったようだ。大部屋というより、ここは巨大な通路の縁であるらしい。
そこへ、背後に人の気配。後方を歩いていたノエルだ。彼女は前方の大扉へと視線をやり、無表情のままこくりと一つ頷く。
「お疲れ様です、【NAME】。無事に追いつけましたね」
意味が判らず、疑問の視線でノエルを見ると、彼女はすっと己の細い指で大扉の下部を指し示した。
「見えませんか? 部屋の奥に軍の調査団とイェア──あなたの依頼主の姿があります」
言われて、慌てて彼女の指が示す先を見ると、確かに扉の下部──というよりは大扉の前で、疎らに動く人の姿が見えた。どうも扉のスケールに目が行ってしまい、そちらに気がつかなかったらしい。
「では、参りましょう。イェアは右から三番目の白い上着を──」
ノエルが説明を続けながら大扉の元へ歩き出したその時。
どくん、と。
「──ッ」
腹に響く、しかし大気の震えを介さぬ無音の鼓動が一つ。
それと同時に、辺りに漂う空気が急速に濁り、腐っていくような感触。際立った──明確な異常ではないが、通路に漂う気配のようなものが、先程の鼓動を境に切り替わった。そんな感じだ。
突然のことに動きを止めた【NAME】達の耳に、
「……あら?」
場違いとも思える、柔らかな声が届いた。
四大遺跡 白衣の学士
――白衣の学士――
無意識に伏せていた顔を上げ、声のした方向──大扉の手前を見れば、そこに居た常駐軍の人間と思しき者達の一人。白色の上着を羽織った女性が【NAME】達を驚きの表情で見ていた。
「あら。あらあらあら」
彼女はあらあら呟きつつ小走りでこちらに駆け寄り、【NAME】の隣に居たノエルの前に立つと、ぽんと両手を合わせる。
「あらやっぱり。──人違いではありませんわね。もしかして本当にノエルですの?」
「はい。イェアもお元気そうで何よりです」
こっくりと頷くノエル。驚きに染まっていた女性──イェアの顔が、次第に怒りと心配が綯い交ぜになった微妙な表情に変わる。
「はい──ってあなた、何でまたこんなところまで。芯形機構を内包すると考えられている遺跡、特に“四大遺跡”には近づかないようって、あれだけ言っていたでしょうに」
「駐屯地であなたの帰りを待つのは非効率的であると、わたしは判断しました。あなたやレェアの言いつけを破ることになってしまい、申し訳なく思っています」
淡々と、【NAME】が傍から見ている分には、全く心が篭もっているように見えない謝罪。イェアは嘆息しつつ、心配げにノエルの顔を覗き込む。
「ああもう、判りました。それについてはもう咎めませんわ。それよりあなた、大丈夫? なにかヘンなところとか、ありません?」
「──? これといって、別に」
「そう。……ならいいの、良かった」
イェアは心底安心したように息を吐き、ぽんぽんとノエルの頭に手を置いた。傍から見ていた【NAME】には、その様はまるでノエルの母か姉のようにも見えた。
頭の上に乗せられた手が降ろされるのを見計らい、ノエルが口を開く。
「それよりイェア。曖昧な表現になりますが、先程この辺りに漂う気配の──質、のようなものが……変わったと、わたしは感じられたのですが」
普段感情の色が無い彼女にしては、揺らぎの多い声音。イェアは彼女を安心させるように、一度大きく頷いて返した。
「ええ、把握しています。それについては順を追って説明しますわ。でも、まず」
イェアの視線がノエルから【NAME】の方へと移る。
「先にこちらの方の話をお聞きしたいのですけれど──ノエル、この方が?」
主語が曖昧なイェアの質問に、ノエルはきっぱりと頷いた。イェアはほぅと何処か陶酔したような目つきで【NAME】を見た。
「貴方があのコルトレカンの伝承にある“殺すことのできない獣”を斬った方ですのね。……ふふ。そうですかそうですか。本当に、丁度良かった。これをグッドタイミングと呼ばずして何と呼ぶのか、ですわ」
酷く気に掛かる物言いだった。
(……何だか、凄く厭な予感が)
が、【NAME】が彼女の呟きの真意を問い正す前に、イェアは「こちらにいらしてくださいな」とだけ言って、大扉の近く、調査団の面々が居る場所へと歩いていく。問うタイミングを逸した【NAME】は、仕方なく彼女の後を追った。
・
先行くイェアの後に続き、【NAME】達は調査団の人間が屯している大扉の前へと歩く。
イェアが連れていた調査団は全部で十数人程の小さな集団であるようだった。調査を目的とした編成の割に、自らの傍に武器や同調誘導器、機甲兵器などを置いている者達が多く見える。彼らはそれぞれ一箇所に固まる事無く、しかし距離を取ることも無く。満遍なく散って、何も無い筈の中空の一点をただじっと、何かを待つように見つめていた。【NAME】達が傍に近づいても、彼らは然程気にした様子も無く、ちらりと見るだけで視線をまた戻す。
傍へ移動して初めて気づいたことだが、大扉前の床には特殊な染料による真新しい印章が一つ大きく書かれ、その周囲に補助用らしき印章石が幾つか、小規模の印章と共に設置されていた。印章と印章石はそれぞれ固有の色の輝きを発しており、既に印章が持つ力が駆動している事が知れた。そしてどうやら調査団の面々が見据えているのは、中央に書かれた巨大な印章のほぼ真上の位置のようだった。
「この印章は一体何でしょうか」
ノエルの素直な問いに、イェアは自らの顎に細指を添えて、うーんと小さく唸る。
「ノエル、わたくしがどういった目的でこの遺跡へ潜ったか、もう聞いてます?」
「はい。“四大遺跡”の活性化──正確には、遺跡周辺地域で発生している原因不明の概念汚染現象、その原因特定の為の予備調査。わたしはそう聞いていましたが」
詰まりの無い回答にイェアはうんうんと二回頷き、しかし「でもね」と続ける。
「大筋は正解ですけれど、実は原因の見当くらいは初めからついておりましたのよ。これは──【NAME】さんもご存知のとある事件、その余波で一時的に“世界の澱み”が増加しただけだと思いますの」
そう言って、イェアは思わせぶりな視線を【NAME】へと投げかけた。
“殺すことのできない獣”ギ・ロ。
檻を断つ流転の神形ゼーレンヴァンデルングと、黒い切り株の向こう。
そしてユーリ、マギサ。
イェアがあの件についてどの程度知っているのかは判らないが──何とか阻止したとはいえ、フローリアのどこかであの事件の影響が出ているというのは、考えられない事ではない。
「“四大遺跡”はフローリア上での異常に敏感ですから。本当なら、この『扉』を越えた先へ移動することができたなら良かったのですけれど、わたくしの力では無理ですし。それに、あまり迂闊に深層に近づけば、下手をすると手におえない事になるかもしれませんから。妥協してここで“式”を打ったのは、大きな視点で見ても最善手かもしれませんわね」
「……良く理解できませんが、つまりこの印章があなたの言う“式”ですか?」
床に書かれた印章を指差すノエルに、イェアは大きく頷いてみせる。
「ええ。今は徐々に染み出してきている“世界の澱み”を、人為的にぐーっと纏めてこの場に搾り出しちゃいますの。そうしますと、一箇所に集められて凝縮されたそれは、相応の『鬼』という形を持って実体化する筈ですの。滞った歪みを放置すればどこで何が起こるのか判りませんもの。それなら、こうやって“鬼”の出現場所を特定してしまった方が、色々とやりやすいというものですわ」
やりやすい。
(……一体、何がやりやすいんだ?)
【NAME】が思わず口を開きかけたその時。
「────」
突然、イェアの表情に緊の色が浮び、大扉前の床中央に書かれた印章の上を鋭く睨みつける。
釣られて【NAME】がそちらを見ると、つい先程までは何も無かった筈の空間に、黒い靄のようなものがぽつんと、小さな点として空中を汚していた。
「さぁ、出ますわよ──みなさん、油断せぬよう。気をつけなさい」
周囲の人間に対して警戒を喚起するイェアの声が響く、と同時に。
──どくん!
先刻のものとは比べ物にならない、強い鼓動。辺りを漂う気配が急激に澱み始め、床に書かれた印章の輝きがどんどんと強くなる。その輝きに照らし出されて、中央の印章の上に生じていた黒色の靄もその大きさを増し、直径数メートルの球状へと変化しているのが見えた。
ぱりんぱりん、と。
中央の印章を囲むように配置されていた印章石が、軽い音を立てて次々と割れて、浮ぶ靄は更に大きさと濃度を増す。
そしてもう“靄”と表現するのも躊躇われる──固体と呼んでも差し支えない程にカタチを持ったそれの内から外へと、ゆっくりと這い出してくる人型の何か。
──ずるり、と。
凶暴を体現したような四肢と猛々しい鬼面を具えた巨躯が、染料による印章が書かれた床に重々しく着地する。同時に印章の輝きが失われ、中空を渦巻いていた黒の靄も消え去った。
最後に残ったのは一匹の鬼、鬼種の中でも大型に属する喰人鬼[オウガ]を、更に一回りほど大きくしたような大鬼だ。両の腕の外側より飛び出し、今は手の届かぬ高さで不気味に浮ぶ一対の歪な大鎌が、鬼の纏う禍々しさを増している。
「これはなかなか。澱みの総量から考えれば、妥当な等級の鬼種ですわね」
腕組みしつつ眺め、不敵に笑うイェア。
「イェア」
そこへノエルの声。イェアは視線は鬼に向けたままノエルに問い返す。
「なんです?」
「澱みを集めて形とする、これは判りました。ですが、そうして生み出した鬼を、イェアは一体どうされるおつもりなのでしょうか」
それは【NAME】も是非聞いておきたい事柄だった。鬼の動きを注視しつつイェアの話に耳を傾ける。
「簡単なことです。生まれた鬼をわたくし達が討つことで、その歪みは破壊されて健全な物として世界へ還る。元々己が溜め込んだ歪みに耐え切れなくなった世界が、それを凝縮して産み落とすのが鬼。歪みに形を与えて、世界の子であるわたくし達にその処理を託すんですの」
(……ああ)
横で聞いていた【NAME】は、彼女の言葉にいよいよ不穏な気配を感じ取る。ノエルも同様だったのか、
「……つまり、わたし達があの鬼を倒さねばならない、ということですか?」
そう眉を顰めて問うた彼女に、イェアはわざとらしい驚きの表情を作ってみせた。
「あらあら。それは助かりますわね。あなたがそういってくれるのならその意思を尊重いたしますわ。さぁどうぞ。遠慮なく始末してくださいな」
「──いえ。わたしはただ、イェアを含めたわたし達があの鬼と戦うのですか、と尋ねただけなのですが」
すると、イェアは口元に手を当てて大袈裟な仕草。
「あらあらあら。駄目ですわよノエル。一度口に出したことを曲げるなんて、わたくし感心しませんよ? 『有言実行、女に二言は無い』と姉に教わりませんでした? わたくしは教わりましたけど」
「…………」
困惑した表情のまま固まり、黙ってしまったノエルに、くすくすと白衣の女性は軽く笑う。
「冗談ですわよ、ノエル。でも、あなたがアレと戦うのは本当。【NAME】さんの腕前を見せていただく、というのも兼ねてね。ここまで平気で来れたのなら、あなたがあの鬼に“干渉”される事は無いでしょう。本当でしたら、わたくしと軍の皆さんでその鬼を退治するつもりだったのですけれど、ここに【NAME】さんが来ていただけたのは幸いでしたわ」
言って、イェアは含みのある視線を【NAME】へと投げかけた。
「さぁ、あの“殺すことのできない獣”すら滅したと言う貴方の力、わたくしに見せてくださいな」
[BossMonster Encountered!]
ノエルの支援を受けつつ、【NAME】が全力を込めた一撃を放つ。その直撃を受けた大鬼は膝を突き、そしてゆっくりと倒れ伏した。
鬼は打ち倒されると同時に砕け、跡形も無く消えていく。辺りに沈殿していた澱んだ気配も瞬く間に清浄な物へと戻り、いつフォローに入るかと【NAME】達の戦いを見守っていた調査団の面々は、その結末にどよめきの声をあげた。
疲労からその場に座り込んだ【NAME】の傍へ、ゆっくりとイェアが歩み寄ってくる。【NAME】がそれに気づいて顔を上げると、イェアはにこやかな笑みを浮かべた。
「ご苦労様でした、【NAME】さん。これでわたくしも大手を振って帰れますわ。詳しい話は、ここを出てからにいたしましょう」
これで漸く一区切りか、と【NAME】は息をついて──
──ちりん。
幻聴。
唐突に響く、鈴鳴りにも似た音。
同時に、身近に眠る強い破壊の質を秘めた“何か”が、深い眠りから僅かに浮上する気配。
「────」
反射的に、【NAME】は首から提げた飾りを、ぎ、と強く掴む。“目覚めるな”という意思を込めて。その仕草に応じてか、気配は完全に浮びあがることなく、眠りの底へと降りていった。
幻聴はもう、聞こえない。
【NAME】が顔を上げれば、視界の一辺を完全に埋めるほどの『大扉』が、ただ静かに聳えていた。
四大遺跡 争いの図式
――争いの図式――
「おまたせしました、【NAME】さん」
ガレーの周囲に点々と建つ常駐軍のバラック。その一室で柔らかな質の声が響いた。
遺跡帰還後、イェア・ガナッシュの私室に通されていた【NAME】とノエルの前に、部屋の主である白衣の女性が姿を現したのは、かれこれ数時間以上経った後のことだった。
扉を開けて入ってきたイェアの手には小さめのバケットがあり、中には木製の杯と赤い──恐らくは葡萄酒と思しき液体の入った瓶が入っていた。
「御免なさいね、少し、先刻の鬼種に関する後始末で手間取ってしまいまして。でも本当、先刻はお見事でした。流石は大禍鬼殺しの冒険者殿ですわね」
ノエルが椅子から立ち上がり、喋る彼女の手からそのバケットを受け取ろうとするが、イェアは「いいのいいの」と彼女の背を押して再度椅子に座らせてしまう。
「んー、汚くって御免なさいね。ノエルも居なかったし、最近篭もってばっかりだったからついついお掃除が面倒くさくなっちゃいまして。──えいえい」
部屋の隅に置かれていた小机、その上に山と積まれていた得体の知れない物体を、イェアは気の抜ける掛け声と共に無造作に払う。重苦しい音を立てて落ちていく荷物を彼女は完全に無視。机を持ち上げると、【NAME】とノエルが座っていた丸椅子の前にどかんと置いた。ぱんぱんと二度ほど手を叩いて埃を払うと、床に置いていたバケットを持ち上げて机の上に。手早く杯を並べて、それぞれに瓶に詰められていた液体を注ぎ込む。更にバケットの奥から果実と何かの動物の燻製らしきものを幾つか取り出すと、手近な場所から自分の椅子を引き寄せてぽすんと座って準備万端。
「はい。かんぱーい」
イェアは自分の前に置いた杯を掴んでにこやかに宣言。そう言われれば付き合うしかない。【NAME】も杯を取り、そして座ってじっとイェアを眺めていたノエルも、ゆっくりとした動作で杯を持ち上げて、それぞれの杯を軽く打ち合わせた。
全員一息ついたところで、イェアは杯を置くと改まったように姿勢を正し、【NAME】を真っ直ぐに見た。
「改めて初めまして。わたくし、アラセマ陸軍第十二師団付きの学士イェア・ガナッシュと申します。宜しくお願いしますわね、【NAME】さん」
座したままながらも、イェアは行儀良く頭を下げてみせる。【NAME】も反射的に会釈で返すと、彼女は一度にこりと笑ってから、視線を隣に座っていたノエルへと移した。
「さて──ノエル、【NAME】さんにはどの辺りまでお話を?」
両手で杯を持ち、どこか舐めるような仕草で口をつけていたノエルが、イェアの質問に顔を上げる。
「詳細は伏せろとの指示を受けておりましたので。“貴方にお願いする役目は、調査と調停の二つだ”と。これ以上の話はしておりません」
そう、とイェアは頷くと視線を【NAME】へと戻す。
「では、確認の意味も含めて──現在、アノーレに点在する“四大遺跡”の内の二つ、ノイハウスとヴィタメールの遺跡を、アラセマ常駐軍の離脱者と一部のキヴェンティ達がそれぞれ占領しているというお話。これはご存知ですよね」
【NAME】は無言で頷く。その話は確かアノーレへと向かう船上でノエルから聞いたような覚えがある。
「ガレーは見ての通り、わたくし達アラセマ常駐軍が掌握しています。残った最後の一つ……ゴディバ遺跡は、詳細は不明ですが、常駐軍がフローリアへと派遣される前に起きた爆発事故──恐らくは内部の芯形機構の起動によるものの暴走で、完全に消失しています。ですから、単純な数でいえばわたくし達よりも占領組の方が、遺跡をより多く占拠していることになりますわね」
話を聞きつつ、【NAME】は葡萄酒の入った杯を軽く仰ぐ。駐屯地の倉から無造作に引っこ抜いてきたものなのか味は極々平均。至極上等な物か、葡萄酒とは名ばかりの水のような物のどちらかを想像していた【NAME】は少し拍子抜けだった。
イェアの話は続く。
「それでですね。遺跡占領組を率いている人間、つまり今回の件の主犯と目されている人物は二人いるんですの。一人は“杜人”のリゼラ・マオエ・キヴェンティ。フローリアに暮すキヴェンティ達を束ねる主氏族、マオエ、シギナ、センテ、ラカカスマ、その内の一氏族であるマオエ氏族の若長ですの。彼は自身の氏族であるマオエの者と、その下につく幾つかの従氏族の人間を集めてヴィタメールの遺跡を占拠しています。そしてもう一人が──」
そこでイェアは言葉を切り、少し黙る。いつの間にか、彼女の表情が複雑なものへと変わっていた。
「──異変発生前までは、“螺旋の理”学院からフローリアに派遣されていた遺跡調査団の長であり、フローリアへの常駐軍派遣後は、アラセマ陸軍第十二師団所属の軍師を務めた“女賢者”。魔術司にして機構学者[グランコレクター]である──レェア。レェア・ガナッシュですの。“四大遺跡”に関する研究の第一人者であり、彼等の占領計画はレェア・ガナッシュが立案し、リゼラ・マオエがその話に乗ったと言われていますわ」
(レェア……ガナッシュ?)
その名を聞き【NAME】は訝しげに首を傾げ、白衣の学士と、その隣に座っている少女を見る。
今、眼の前で話すこの女性。彼女は自分の名をイェア・ガナッシュと名乗った。そういえばノエルも同じガナッシュの姓だったか。
(ということは──)
【NAME】が何を考えているのか察したイェアは、小さく頷いて肯定の意思。そして改めて話し始める。
「貴方のご想像の通りですわ。遺跡占領軍を率いる“女賢者”レェア・ガナッシュは、わたくしの親類──正確には姉にあたりますの。お陰でわたくしも共犯ではないかと疑われて、証拠も無いのに謹慎処分ですのよ。……そう言えば、ここ暫くはガレーの駐屯地から一歩も外に出ていませんわね、わたくし」
笑って、何処か疲れたような吐息。
「本当、何故こんな事になってしまったのか、わたくしにも良く判らないんですの。本当に突然、何の前触れも無くあの人は事を起されて。顔を会わせる事は少なくても、一緒の組織に居て、たくさん話をしていたのに──わたくしには、裏で姉がこんな事をしようと考えていたなんて、全然」
肩に掛かった髪を指で弄びながら、彼女は話を続ける。
「……元々、姉は人と付き合うのを好まないような処があって、わざわざ赤の他人を巻き込んでまで、こんな大事を起すような人では無かった筈なんです。面倒臭がり屋でもありましたからね」
そこでイェアはくすりと笑ってみせるものの、それも長くは続かない。
「でもそんな姉が自ら動いて、あの排他的なキヴェンティ達がそれに力を貸す。……もう、この流れはわたくしに想像できる範囲の外にあります」
伏せられる顔。共に、声の調子も沈む。
「軍は彼等が何故遺跡を占領し立てこもっているのかなんてお構い無しに、ただ兵を派遣して彼等を駆逐するつもりです。彼らが一体どういう思惑を持って事を起こしたのか。そんな事、考えもしないで」
彼女はそれを拒絶するように頭を振った。
「何か、訳がある筈なんです。だから、これは私的な──ごく個人的なお願い。遺跡の占領軍を率いているわたくしの姉──レェア・ガナッシュと、彼女に力を貸しているキヴェンティ達の真意。そして出来るなら、常駐軍と遺跡占領軍との対立が、平和的に解決できるような──交渉の余地が生まれるような何かを、貴方に探って欲しいんですの」
イェアは伏せがちになっていた顔を上げ、【NAME】を見る。
「──如何でしょう。引き受けてくださいます? 勿論、相応の報酬はお支払いさせていただくつもりですわ」
言われ、【NAME】は迷うように腕を組み、一度彼女から視線を外した。
正直に言えば引き受けたくは無い。引き受けたくは無いのだが──。
(……一度“受ける”といってしまったしな)
思い出すのはリコルスの港でのノエルとの会話。あんな条件での約束を律儀に守る必要は無いのも事実だが、それでも約束は約束だ。【NAME】はそう結論を下し、イェアにはっきりと頷いてみせた。
「──ありがとう」
【NAME】の確かな答えに、イェアは安堵したように細く息を吐き、そして硬さの取れた笑みを浮かべた。
「助かります、助かりますわ。本当ならわたくしが直接向かえば良い話なのでしょうけど、あまり派手に動ける立場でもなくて。わたくしが姉に会いに行くなどといえば、“謹慎処分”どころでは済まないでしょうから」
呟きの中、笑みが苦笑に変化。そのまま彼女は机上に置かれた杯を手に取り、中の葡萄酒を口に含んだ。
・
常駐軍の建てたバラックの外れ。丈の短い草がそよぐ野原の上には、イェアとノエル、そして【NAME】達の姿だけがあった。
「【NAME】さん。まず、ヴィタメールの遺跡へ廻ってください。近々、あの遺跡には軍が攻め入ることになっています。それに便乗しつつ上手く出し抜けば、彼らより先にキヴェンティ達の頭と会うことも可能だと思いますわ」
なかなか無茶な彼女の言に、【NAME】は呆れたような顔をイェアに向けた。そんな状況では、話し合いも何もないような気がする。
「戦いとなるかならないかは、貴方の立ち振る舞いによると思いますわ。それに貴方は大禍鬼すら屠る冒険者なのでしょう? でしたら、彼らの相手など造作ないのではありません?」
どこかからかいの混じった声音に、【NAME】は少し視線に力を込めてイェアを睨む。彼女はそれを避けるようにくすくすと笑った。
「前金として800zidをお渡しします。あと、貴方にはこの子を、ノエルをつけますわ。ここまで一緒に旅をされた【NAME】さんなら既にご存知でしょうが、戦いに関してはそれなりの腕前ですので、お役には立てると思いますわ。──ノエル、構いませんか?」
問われたノエルは無表情のまま暫しの間。そしてこくりと小さく頷くだけ。そんなノエルに苦笑しつつ、イェアは【NAME】に向かい一度小さく頭を下げてみせた。
「では、お願いしますね、【NAME】さん。ヴィタメールで事が済んだなら、一度こちらへ戻ってきてくださいな」
四大遺跡 騎士と学士
――騎士と学士――
ガレー南に出たという鬼種の発生現場を検分した後、アラセマ常駐軍第十二師団副団長であるクスィーク・カナル・フハールが足を運んだのは、ガレー遺跡調査と警備の任を帯びた部隊の駐屯地だった。
近隣の森から切り出した木材を用いて建てたという、仮組みの粗末な平屋。立てつきの悪い扉を開き、中へと入ろうとしたクスィークは、
「これは……」
室内の様子を見てそう呟き、思わず足を止めた。
「あらあら。ようこそいらっしゃいました。カナルの方」
と、眉を顰めたまま固まってしまった彼女を促すように、室内から柔らかな声が届く。
「汚い部屋ですけれど、突然のご訪問でしたのでお片付けしている時間が取れなくて。ご容赦していただければ幸いですわ」
言って、響く女の声に軽く笑いの粒子が混ざる。
汚い──と言えば確かに汚いが、それよりクスィークを圧倒したのは、置かれている物の多さとその無秩序極まりない配置にあった。まるで室内で竜巻でも発生したかのような滅茶苦茶さ。
無事なのは、部屋中央の一抱え程のバケットが置かれているだけの円机と椅子が何脚か。部屋の隅などに別の机が置かれているように見えるが、それはクスィークには価値の良く判らないガラクタなどで埋め尽くされており、机の脚らしきものが二本程、ガラクタの隙間から斜め上に伸びているのが辛うじて見えるだけ。
声の主は、無事な椅子の一つに腰掛けて、戸口に立ち止まっているクスィークをにこやかに眺めていた。
この部屋の主であり、このガレー遺跡に駐屯する調査団の長でもある学士イェア・ガナッシュである。
数ヶ月前。ヴィタメール、ノイハウス遺跡占領の件で、首謀者である“女賢者”レェア・ガナッシュとの関係から、クスィークは彼女には謹慎処分を与えたが、それでも彼女が今もここに駐屯している部隊の長であるのは変わりない。レェア・ガナッシュが去った現在の第十二師団で、“四大遺跡”を代表とする古代遺跡群に纏わる深い知識をもつのは彼女一人だ。例えイェア・ガナッシュが、姉であるレェア・ガナッシュと本当に繋がっていようとも、今の軍はイェアの知識無くして島に点在する遺跡群の調査は行えない。遺跡で何らかの問題が発生した場合もその対処策を練ることができるのは彼女のみだった。故に余程決定的な証拠でも無い限りは、調査団の長という役から外す訳には行かない。レェア・ガナッシュがヴィタメール、ノイハウスの占領を行ってから、アノーレ島上での概念汚染拡大とそれに伴う『鬼種』の発生も増加している。“四大遺跡”以外の遺跡でも大なり小なりの問題が起きることもあり、更にはノイハウス遺跡を占領したレェア・ガナッシュは遺跡の『芯形機構』を駆動させているという情報まで入っていた。それらに対応するには、イェアの存在は不可欠だった。
「クスィーク様? どうされました?」
再度の声に、クスィークは我に返る。見ればイェア・ガナッシュが若干不審げな表情でこちらを見ていた。
「いや、何でもない」
クスィークは鬱々とした思考を一度首を横に振って払うと、ガラクタの海へと一歩足を踏み入れた。
・
円机の傍に置かれた椅子の一つにクスィークは腰掛けて、ふと、机の上に置かれていたものに視線が行った。
(……ん?)
内心、首を傾げる。相手の出方を窺うように机を挟んで座る女の顔を覗き見ると、どうやらイェアの方もなにやら不思議に思うことがあるようで、どこか物問いたげな表情。
「どうかなさいまして?」
お互い少し迷い、取り敢えずイェアが水を掛けてくる。クスィークは机の上に置かれていたバケットの中身にじっと視線を向けたまま、口を開いた。
「私が来る前に、誰か来客があったのか?」
「は?」
一瞬意外そうな表情。次いで、クスィークが机上のバケットに目をやっていることに気づき、イェアは「ああ」と少し笑う。
「──いえ、どなたも。これは先刻ガレー深部で行った作戦の後始末を下の者と話し合った時に、彼らが持ち込んできたものなんですの。まったく、自分達が持ち込んだ物の始末もしていかないなんて、困ったものですわね」
さらりとそう言って、指で葡萄酒を入れた瓶を弾いてみせ、バケットの奥から未使用らしき杯を取ってさっさとその中に液体を注いだ。
「それで、本日のご用件は? わざわざ副団長殿が直々にこちらへ来られるくらいですから、何か厄介事でも起きたのかと少し心配ですけれど、わたくし」
イェアにそう続けられ、クスィークも思考を切り替える。
「厄介事が起きていない時などありはしない。単に別件でこの近くに用があって、そのついでに状況確認を兼ねて馬を走らせただけだ。“四大遺跡”の活性化について、貴女から直接話を聞こうと」
「その件でしたら、ええ、ガレー遺跡に限って言うなら無事カタをつけましたわ」
視線だけで話の続きを促すクスィークに、イェアは一度杯を手に取りその中身で唇を湿らせて間を置いた。
「……あれは正確には“四大遺跡”の活性化というより、遺跡深層に滞った陰性概念が地表に染み出した事による周辺地域の概念汚染、ですわね。恐らく、他島でのイザコザや一部の“四大遺跡”の芯形機構駆動による島の土地概念の歪み。これらの要素が“四大遺跡”に何らかの影響を与え、概念的な澱みの溜まり場を生み出す原因になったのではないかと、わたくしは考えています。遺跡自体が活性化し、内に秘めた効力を発揮した結果ではなく、単なる外的要因の影響を受けて発した副次的な現象、というのがわたくしの予想ですわ」
話していていつも思うことだが、どうも彼女の言い回しは勿体ぶっていて判り辛い。クスィークにとって、イェア・ガナッシュはイルギジドとは別の意味で苦手な種の人物だった。
「判らないな。その、他の島のイザコザに土地概念の歪み? それが何故“四大遺跡”に影響を及ぼす?」
「詳細までははっきりしていませんから、単なる憶測になりますけれど、“四大遺跡”──少なくともガレー遺跡には、そういったモノを引き寄せて溜め込んでしまうような“特性”のようなモノがあるようなんですの。そのせいですわ」
「……で、どうしてそんな“特性”が?」
クスィークは眉を顰めたまま問うと、イェアは軽く肩を竦める。
「さぁ? ──きっぱりと申し上げますと、今のわたくしの知識や所持している文献のみでは“四大遺跡”の構造や、遺跡それぞれが持つ芯形機構の機能について判ることは殆どございません。このガレー遺跡の奥にある“扉”の先についても──そして、他の遺跡にもガレーのような扉があるのかどうかも同様ですわ。常駐軍が島へ渡る以前からこの島で研究を続けていた姉なら、もっと詳しく知っているのでしょうけれど」
クスィークはふむと唸り、暫し自分の考えを纏めるように沈黙した後、ふと何かに気づいたように顔を上げた。
「──それで、ガレー遺跡に限ってはカタをつけたと言ったな。それはどういう意味だ?」
イェアはそこでくすりと笑ってみせる。
「どうしたもこうしたもありませんわ。式で“歪み”に鬼というカタチをつけてからぼかんと一発張り切って殴れば、はい、お終い、ですもの。鬼さんも清々しく崩滅なされて歪みも矯正、今ではすっかり健全になってますわ。先程言った“特性”は消えておりませんので期限はありますが、暫く──そうですね、数ヶ月は安全だと思われますわ」
「……無茶をする。人工的に鬼を作ったのか? 等級は?」
「確か大鬼級でしたわね。前準備はしっかりとやっておきましたので、大した力は持っておりませんでしたけど」
そこまで聞いて、クスィークはイェアの部屋に訪れる前に立ち聞いた話を思い出した。
「しかし、大鬼級の鬼種を単独で打ち滅ぼす冒険者か。初耳だが、一体どこで雇った者達だ? 遺跡に部外者を無断で招き入れるのは問題だぞ」
そう、少し咎めるように告げると、
「──え?」
惚けたような声が返ってきた。
「あの、冒険者、とは?」
(……?)
イェアの態度に奇妙なものを感じつつも、クスィークは答える。
「ここへ来る途中、先生殿についてガレーへ潜ったという者達から話を聞いた。遺跡の奥で出た鬼種を、学者先生が前もって呼び寄せていた冒険者達が自分達の助けも借りずに戦い、倒したと。何者だ?」
イェアは一瞬無表情のまま固まった後、今度は考え込むように眉を顰めて首を傾げてみせる。
「──と申されましても、詳しい素性は知りませんわ。部下の者に街へ行かせて、腕の立つ人間を連れてこさせただけですから。……確かにクスィーク様の言う通り、この事に関しては、わたくしが少し迂闊でしたわね。申し訳ございませんでした」
深々と殊勝に頭を下げてみせるイェア。そしてクスィークが何か言葉を発する前に、
「それで、クスィーク様。先程仰っていた“別の用件”と言うのが、わたくしは気になるのですけれど。ここの周辺地域で何か問題でもありましたの?」
するりとそう繋げた。
「…………」
クスィークは眉根を寄せて対面に座るイェアを見る。
(……どうも引っ掛かるけれど)
正直、あまり下手に追求したくはなかった。もし彼女が何かを隠しており、それが軍に対する明確な裏切り──最悪、遺跡占領組に与するような行為であると判れば、自分は彼女をどうするのか。謹慎などでは済ませられまいが、だがしかし彼女の知識無しで、“四大遺跡”の力を操るレェア・ガナッシュに対抗できないだろう。
自身の心の隅に留まる恐れにも似た小さな感情が、それ以上の追求を無意識に押し止めて、イェアの問いに対する返答に変化する。
「この近くで鬼が出た。昨日の話だ」
「あらあらあら。場所はどの辺りですの?」
口元に手をやり驚きの表情を見せるイェアに、小さな溜息を溢しつつクスィークは説明を続ける。元々、クスィークは彼女にその“別の用件”についての意見を求めにここまで来たのだ。
「ユウベル北の平原と、ガレー南の森林地域の一角だ。前者は発生と同時に崩滅させたので大きな害は無かったが、後者は私が現場についた時には森の一部が概念を食われて更地になっていた」
イェアの表情に、より驚きの色が強まった。
「それはまた、派手ですわね。等級は?」
「ユウベルに出た鬼種は禍鬼級だった。ガレー南の鬼種は、我々が現地に到着した時には既に崩滅した後で詳細は不明だが、恐らくはこれも禍鬼級だろうと、あの魔術師は言っていた。奴の言を鵜呑みにするならば、だが」
イェアが不審げな表情となってクスィークを見る。
「──既に崩滅していた? どう言う事ですの?」
「簡単な話だ。我々アラセマ常駐軍が現場に向かう前に、別の何者かがその鬼を倒しただけ。それだけの事だ」
「本当、簡単に仰いますわね。禍鬼級ですのよ?」
「つい先刻、似たような話を聞いた気がする。大鬼を討った冒険者の話を。……まあ、その事は良い。それよりこの状況の原因は判るか?」
口元を覆うように手をやって、天井を見上げること数秒。イェアは視線をクスィークに戻して答える。
「……そうですわね。アノーレでの上級鬼種頻出の原因について──その事でしたら“四大遺跡”の件と繋がるお話ですわ。ガレー南やユウベルで鬼が出たのは、近隣にある“四大遺跡”から漏れでた陰気が周囲の同属を取り込んでその場に滞り、飽和した結果であると推測できますわ。そしてガレーは先程お話した通り。ノイハウスに関しては姉がその辺りの事は完全に調整しているでしょうから、問題はヴィタメール周辺のみとなりますわね──と、そういえば、カンクゥサを越えた先ではどうなっておりますの?」
問われて、クスィークは反射的に眉を寄せる。
「殆ど手付かずだ。カンクゥサ山地自体も土地概念の歪みが大きくなっていて、今ではカンクゥサ以北へ渡るのも容易ではない。コートニーに置いた駐屯地からの現状報告によれば、殆どの土地が氷系属性に偏って、氷雪に閉ざされた極寒の地となっているそうだ」
「……ゴディバの影響がまだ残っているんですのね」
イェアの呟きに、クスィークは細い嘆息だけで肯定を返す。全く、厄介な事だらけだが、短期間ながら鬼種の出現地域を特定できただけでも僥倖とするべきかもしれない。これでもう少しは手早い対応を──とそこまで考えて、自分が本営を出てから結構な時間が流れていることに気づいた。
椅子から立つ。
「そろそろ戻る事にする──ヴィタメールでの作戦報告がそろそろ入っている頃だろう。邪魔をした、“先生”殿」
「…………」
形式的な答えが返って来る前に空いた、ほんの少しの間。
「いえ、カナルの方。然程お役に立てず、申し訳ありませんでした」
それに気付かず、クスィークはイェアの言葉に見送られて部屋を後にした。
馬の番を任せた兵士の元へと早足で歩く。
この程度の時間本営を離れたところで問題がでることはないだろうが、時が経つほどに自分がやるべき仕事が机の上に溜まっていく。明日の自分のためにも、翌日に影響が出る程の量になる前に本営に戻らなければ。
──と。
歩くクスィークの耳に、どこからか羽ばたきの音が響いた。
音に釣られてクスィークがそちらへ顔を向けると、背後、薄く鱗状の雲が出始めた空を真っ白な鳩が一羽。東に向かって飛び去っていく姿が見えた。
・
四つの林に囲まれた狩人達の村ティネ。宿──というより単なる民家の前で、茫と壁に背を預けていた【NAME】は、道の向こうから歩いてきた小さな影に気づいて壁から身を離す。
「お待たせしました」
短くそう言って【NAME】の前で立ち止まったのはノエルだ。ティネの村と近隣にある軍の駐屯地、この二箇所から情報を収集するため、一時二手に分かれていたのだ。
「【NAME】、駐屯地で聞いた話なのですが、ヴィタメールでの戦闘について既にご存知ですか?」
然したる間も開けずに訊いてくるノエルに、【NAME】は苦い表情で頷いた。
「困りました。まさか、既に軍の作戦が終了した後だとは。これでは紛れて忍び込むも何もありません。曖昧で不確かな指示だったとはいえ、その第一歩で躓くとは思いませんでした」
そう。ガレー遺跡を出る時、イェア・ガナッシュは近々軍がヴィタメール遺跡に攻め込む計画がある、それに乗じて動けと、【NAME】達に告げていた。だが肝心の軍の遺跡攻撃作戦とやらが、【NAME】達がヴィタメールへ到着する前に既に実行されてしまっていたのだ。
【NAME】が村を回って仕入れた噂話によれば、常駐軍側は大規模な儀式魔術による敵の一掃を計ったらしいが、駆動前にキヴェンティ側に察知されてその殆どが失敗。無事だった幾つかの儀式魔術によるキヴェンティ側の被害を考慮に入れれば、戦い自体は痛み分け。遺跡奪還に失敗した事を考えれば、実質的には常駐軍側の敗北と言っても良い結果に終わったらしい。
これで、騒ぎに乗じて忍び込むという線は失せた。が、自分達の目的は暗殺やらではなく、あくまで話を聞くためのものだ。そんな状況でキヴェンティの頭とやらに会ったとして、友好的な会話は難しいだろう。ある意味、やらずに正解という類の選択だ。
「【NAME】、どうされますか?」
ノエルの問いに、【NAME】は腕を組んで小さく唸る。こうなると、後は闇夜に紛れて陣地に忍び込むか、真っ当に正面から話し合いを申し込むかくらいしか浮ばないが、後者の手段が通るほど長閑な状況でもあるまい。
(厳しいな……)
呻き、溜息。
【NAME】のそんな様子を見て、ノエルが口を開く。
「──【NAME】、今日は休んだ方が良いと、わたしは思います。ヴィタメール遺跡はティネの村から東へ伸びる道、ユウベル街道の北の森にありますので、明日に状況確認を兼ねて、一度そちらへ足を運んでみるというのはどうでしょうか。何かいい案が思いつくかもしれませんから」
言われ、【NAME】は肩の力を少し抜いて、ノエルに頷いた。
確かにあまり根を詰めて考えても仕方が無い。今日の処は、ゆっくり身体を休める事にしよう。